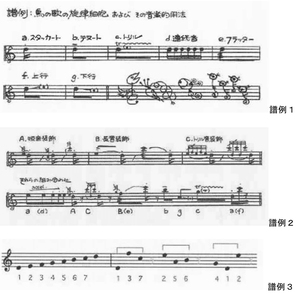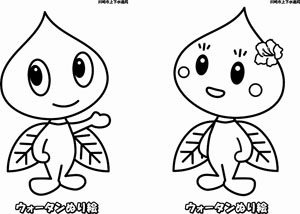演奏会データ
レスピーギ:交響詩「ローマの松」
「変わり種」としての標題音楽
「ローマの松」と聞いて、あなたは何を思い浮かべるだろうか。これが音楽作品の題名だと知らなければ、「高級家具に使われる木材としてローマの職人たちの手に渡るローマ産の松の木」を想像するだろうか。反対に、これが音楽作品芳賀 大夢(トロンボーン)題名だと知っているならば、この作品はおそらく「標題音楽」の類なのだろうと思索をめぐらせるのは難しくない。初めは私も同様のことを考えており、ローマの松の木とは一体どんな姿形をしているのだろうと、インターネットで画像検索をしてみたりした。すると、盆栽に代表されるような枝と葉とが鈍角な三角形をなしている日本の松と比べて、ローマの松は、樹高や葉の位置が高く、すらっとした印象を受ける。これを見て何を思うかは十人十色だが、私の正直な感想は「思ったよりショボいな」である。幹がとても太いとか、枝ぶりが非常に良いとか、神秘的な自然を目前にして畏敬の念を抱かずにはいられないようなスケールの松の木を勝手に想像していた私が悪いのだが、これに共感する人は決して少なくないだろう。
題名が付いていれば標題音楽になる、というのはいささか安直な思考だが、決して間違いとはいえない。標題音楽の代表作ともいえるベルリオーズの「幻想交響曲」は、ベルリオーズ自身の失恋体験を元にしたストーリー仕立てであるし、ムゾルグスキーの組曲「展覧会の絵」は、彼の友人が遺した絵を音楽で表現したものである。標題音楽の大家ともいえるリヒャルト・シュトラウスの「英雄の生涯」や「アルプス交響曲」をはじめとする数々の交響詩も忘れてはならない。いずれの作品も、題名と内容とに直観的な相関がみられるが、一方でレスピーギの「ローマの松」はそう一筋縄にはいかない。この曲目解説では、彼がこの作品で何を試みたのか、彼の来歴や彼が遺した言葉を参照にしつつ明らかにしたい。
人物
オットリーノ・レスピーギ(1879-1936)は、イタリアのボローニャ地方に生まれ、幼少期から、音楽に限らずあらゆる分野に興味や関心を示し、弦楽器全般の優れた演奏技術はもちろん、好奇心旺盛で博学で、語学力にも長けた人物だった。ボローニャの市立歌劇場オーケストラでヴァイオリン奏者を務めたのちに、帝政ロシアの首都サンクトペテルブルクの歌劇場の第1ヴィオラ奏者を務め、そこでリムスキー=コルサコフと出会い、彼の色彩的な管弦楽法の指導を受ける。その後ベルリンで唱歌学校のピアニストを務め、声楽について深い知見を得る。やがてローマの国立サンタ・チェチリア音楽学校の教授および校長の任を受けてローマに移住したのちに、「ローマの噴水」「ローマの松」「ローマの祭り」からなる、いわゆる「ローマ三部作」を世に出す。
彼がイタリア出身であることから、当時のイタリア音楽の芸術的地位、ひいてはイタリア出身の作曲家の系譜を思い浮かべてみると、18、19世紀こそジュゼッペ・ヴェルディやジャコモ・プッチーニ、ジョアキーノ・ロッシーニといった優れた作曲家らによりオペラ音楽において興隆をきわめたものの、19世紀にドイツを先頭にフランス、ロシアその他の国から続々と純粋器楽の作曲家が生まれたなかで、イタリアはそうではなかった。この状況を打開すべく、「輝かしい18世紀の末以来今日まで、わずかの例外を除いて、商業主義と俗物主義のために低められ、矮小化されてきたイタリア人の、われわれの真実性のある偉大な音楽の復興を成しとげる」ことを趣旨として、「イタリア五人組」が結成され、レスピーギはその一員だった。このグループは短命に終わったが、それぞれ前期バロックからルネサンス音楽、グレゴリオ聖歌、古代ギリシャ悲劇の形式にまでさかのぼってその憧れを打ち出し、イタリア音楽復興の旺盛な活動を展開した。この集大成こそが、レスピーギの「ローマ三部作」の絶大な人気だった。
作品
ローマを題材にした音楽作品は、ベルリオーズの序曲「ローマの謝肉祭」、ビゼーの組曲「ローマ」などがあるが、やはりこの「ローマ三部作」が一番の大作であることに間違いはない。初めに述べたように、「ローマの松」と聞いて、これはおそらく「イタリアの都、二千年来の歴史を持つローマの町のあちこちに見える松の木の姿」を描いた作品なのではないか、と想像するのは難しくなく、むしろ自然なことである。しかし、1926年にレスピーギ自らフィラデルフィア管弦楽団を指揮してこの曲を演奏した際、彼はプログラムに次のように書いている。
「『ローマの松』では、私は、記憶と幻想を呼び起こすために出発点として自然を用いた。きわめて特徴をおびてローマの風景を支配している何世紀にもわたる樹木は、ローマの生活での主要な事件の証人となっている」
つまり、この作品は単に松の印象を描いたものではなく、松が象徴するローマの自然の奥にある精神を描こうとしたものであり、換言すれば、各楽章に題名こそ付いているものの、これは単なる描写音楽ではなく、自然に対面した作曲者自身の内面的世界の表現であるといえる。最初の問いに答えるならば、松の忠実な姿そのものは、雰囲気以外にはここではほとんど問題にされていない。「記憶と幻想を呼び起こす」とは、彼の個人的な追憶ではなく、「何世紀にもわたる樹木」の追憶、つまりローマの歴史であり、それは古代ローマにまで遡る。そのため彼は作中でグレゴリオ旋法を効果的に用いており、これは先に述べたように、先の時代の音楽に学びイタリア音楽復興を成し遂げんとする当時のイタリア音楽の潮流とも一致する。
これは「ローマの松」に限られたことではなく、彼はローマに寄せる深い愛着から、「ローマ三部作」を手掛け、そのなかで単なる風景の描写ではなく、「ローマの噴水」では教皇庁の都としてのローマを、「ローマの松」では古代ローマ、ルネサンスのローマへの郷愁を、「ローマの祭り」では民衆生活の中に伝統的に受け継がれた生命力を謳った。
曲ごとに彼自身による説明が付されており、彼がそれぞれの松の木からどのようなローマの歴史を追憶したのかがうかがえる。なお曲の順序に物語的な意味はみられず、強いていえば、急緩緩急という音楽的な流れを重視したと考えられる。
第1曲「ボルゲーゼ荘の松」
ボルゲーゼ荘とは、ローマの北の町外れに位置するボルゲーゼ家の別荘のことであり、そこには古い立派な建物と広い庭があり、レスピーギが27歳の時に一般市民に開放され、今なお残るローマ市の公園である。日本でいうところの、恩賜公園にあたるだろうか。ここには背の高い松の木が何百本もそびえている。
「ボルゲーゼ荘の松の木立ちの中で、子供たちが遊んでいる。彼らは輪になって踊り、兵隊の真似をし、行進したり戦争ごっこをしている。彼らは夕暮れの燕のように自分たちの叫び声に興奮し、群れをなして往き来している。突然情景が変わる。」
たしかに、冒頭のヴァイオリンとオーボエのトレモロやフルート、クラリネット、トランペット、チェレスタ、ピアノの細かい連符、ハープのグリッサンドなどから、子供たちが軽快にはしゃいでいる様子を、その直後のチェロとコールアングレ、ファゴット、ホルンの弾むような旋律から、子供たちのみならず、周囲の大人や、松の木々までもが、胸を高鳴らせている様子を想像できる。曲の中盤のおもちゃのトランペットのようなかわいらしい行進曲風の旋律は、子供たちの行進や戦争ごっこを、曲の終盤の細かい連符にかぶさるようなトランペットのやや長めの音は、子供たちの叫び声を表現しているのだろう。彼らは遠いローマの地の子供たちだとはいえ、我々が子供だった頃の記憶とかけ離れているものではないだろう。
第2曲「カタコンバ付近の松」
カタコンバとは、3、4世紀にかけてローマ帝国下で弾圧されたキリスト教徒が、秘密の礼拝所とした地下墓所のことである。ローマ帝国がキリスト教を国教化する以前に、弾圧下で信仰を守り続けた人々を、彼はここで追憶する。
「カタコンバに入る道の両側に立ち並ぶ松の木陰。墓地の奥底から悲しげな歌声が上がってきて、荘重な聖歌のように広がり、しだいに神秘的に消えてゆく。」
第1曲とは対照的なゆっくりとしたテンポとフレーズ、低音域へのシフトから、第1楽章よりもずっと古く、長い歴史を想像できよう。ホルンや、後に続くフルートとファゴットに続く旋律が墓地の悲しげな歌声を、その後のバンダのトランペットの清らかなソロが聖歌を提示する。やがてトロンボーンとホルンがその荘重な歌声と聖歌をより壮大に表現する。木管楽器と弦楽器の独特な5拍子のリズムは、当時の重く痛々しい雰囲気を見事に醸し出している。
第3曲「ジャニコロの松」
ジャニコロとは、テヴェレ川を見下ろす山の手の丘である。時間は夜。
「風が走り大気が揺らぐ。ジャニコロの丘の松が清らかな満月の光にくっきりと浮かび上がる。ナイチンゲールが鳴く。」
第2曲とテンポはさほど変わらないものの、中音域と高音域へのシフトから、雰囲気はがらっと異なっている。冒頭のピアノから風とそれに揺らぐ松の木が脳裏に浮かぶ。視野は第2曲よりずっと開けている。クラリネットのソロが満月のやさしい光となって松の木を照らし、鼓動を落ち着かせる。松の木と満月との逢瀬はこれまでに数えきれないほど重ねられてきただろうに、毎度のように息をのむほど美しい情景がそこにあることをしみじみと感じ入る。西洋のウグイスともよばれるナイチンゲールという鳥の美しい鳴き声が響き渡る。
第4曲「アッピア街道の松」
アッピア街道とは、ローマから東南に走る、二千年の歴史をもつローマ帝国の幹線道路で、今では部分的な遺跡として残っている。レスピーギは朝霧のなか、この長い街道のどこかを訪れる。
「霧に包まれたアッピア街道の夜明け。松並木の影に、静かな平原の景色が見える。突如として、多数の兵士の足音の響きが絶え間ないリズムをとって聞こえてくる。古代の栄光が詩人の幻想によみがえる。ラッパの音が轟き、太陽の光が射すとともに執政官の軍隊が現れ、聖なる街道を行進して、首都へ凱旋してゆく。」
ティンパニやチェロ、コントラバス、ピアノの低音の刻みが、ローマ兵の足音を想起させ、曲が進むにつれてその音は大きくなり、最後には地響きの如く空間全体を支配する。コールアングレの吟遊詩人の語り口のような旋律は、何かの前兆を説いているかのようだ。バンダの金管楽器と舞台の金管楽器とが互いに呼応しあうように爆音を鳴らす。当時のローマ兵の凱旋を目の当たりにしていたら、このような大迫力だったのだろうか。
初演:1924年12月14日 ベルナルディーノ・モリナーリ指揮 アウグステオ楽堂(ローマ)
楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トライアングル、シンバル、小シンバル、タンブリン、ラチェット(木製の回転式楽器=ガラガラ)、大太鼓、タムタム(銅鑼)、グロッケンシュピール、水笛等(楽譜には「ナイチンゲールの声の録音盤」と指定)、ハープ、チェレスタ、ピアノ、オルガン、弦五部、ブッキーナ6(トランペット4、トロンボーン2)
参考文献:
井上和男「レスピーギと近代イタリア音楽」『フィルハーモニー』 第51巻第3号 NHK交響楽団 1979年
音楽之友社 編『最新名曲解説全集』第6巻 (管弦楽曲 3)音楽之友社1980年
寺本まり子『交響詩ローマの松』スコア解説 音楽之友社1992年
溝部國光『交響詩《ローマの松》』スコア解説 日本楽譜出版社
属啓成「ローマの松と噴水 レスピーギの名曲モデルめぐり」『音楽の友』 第14巻第8号 音楽之友社1956年
芳賀日出男「ローマの噴水、ローマの松」『フィルハーモニー』第51巻第3号 NHK交響楽団 1979年
橋本エリ子「演奏家の立場における『近代イタリア歌曲』の演奏解釈論 : オットリーノ・レスピーギの作品を中心に」1995年
堀内敬三『音楽の泉 名曲解説』第4巻 音楽之友社1954年
丸山和平『海員 全日本海員組合機関誌』第14巻第2号 全日本海員組合本部 1962年
吉田秀和『音楽家の世界』創元社 1953年
ラヴェル:高雅で感傷的なワルツ
「親当てクイズ」が物語るもの
1911年5月9日、パリ8区ラ・ボエシ通りにあるコンサートホール「サル・ガヴォー」で開かれたさる会合で、8曲からなる15分ほどの新作ピアノ曲が発表された。ワルツ集「高雅で感傷的なワルツ」が生を享けた瞬間だったが、作曲者名は「X」とされて演奏後にそれを当てる趣向が採られた。生まれたての子の顔を見て父親を当てろということだ。あまり良い趣味ではない(笑)。この会は「独立音楽協会」といい、ラヴェルが前年に組織したもの。その時の第1回演奏会ではピアノ連弾曲「マ・メール・ロワ」が同じホールで初演されている。当然彼と彼の作品にはなじみの深い人々が——批評家や演奏家も含め——当日集まっていた。が、そうしたメンバーを以ってしてもこの「親当てクイズ」の成績は芳しいものではなく、ラヴェルの作品と言い当てたのは諸説あるが半数前後。サティやコダーイの名まで挙がって、演奏者のルイ・オベールをして失望も憤慨もさせた(ラヴェル本人の反応は記録されていない。サティは自分の名が出たことを知って立腹し、意趣返しの作品を後に発表した)。
この結果を意外に思うかも知れない。が、同時代作曲家の最新作を受け入れる機会の少ない現在の基準で捉えては、事の本質も見誤りかねない。いま我々はこの作曲者の生涯を俯瞰し、全作品を知ることで彼の作風やその変遷を念頭に全てを判断できる立場にある。もしこのワルツ集を初めて耳にしたとしても、一聴して「ラヴェルの作品だ」と判断できる可能性は高かろう。初演に居合わせた100年以上前の人々と同じ意識の次元に立つことは難しいのだ。例えばこのワルツの中には彼の代表作のひとつである「ラ・ヴァルス」を思わせる動機が現れる。未知の作品の作曲者を導き出す大きなヒントになり得る要素に違いない。だが、この大規模なワルツが完成するのは1920年。9年後のことで、ラヴェルにとってさえ未知というべき情報なのである。生きている限り、人は自己の置かれた時空に限定された、過去からいま現在まで以上の何ものをも経験出来ない。1911年5月時点で「高雅で感傷的なワルツ」を聴いた人々に与えられた判断材料はそれまでに創造された作品の情報しかあり得ず、しかも同時代に生きる作曲家たちが、これまでとは一転した作風をにわかに打出してくる可能性も想定しなければなるまい。となればこのクイズは結構な難問に思えてくるのだが如何であろうか?
バレエ隆盛のパリで
この作品を書いた時点でラヴェルは36歳。ディアギレフ率いるバレエ団(バレエ・リュス=ロシアバレエ)の為に「ダフニスとクロエ」の仕上げに追われていた。前年に上演する計画がディアギレフとの意見の齟齬によって改作を余儀なくされていたためである。更には「マ・メール・ロワ」もバレエ用管弦楽版に改編するという多忙の渦中にいた。1910年から1913年までの4年間だけでもこのバレエ団は、ストラヴィンスキーの三大バレエとラヴェルの大作のような、20世紀を代表する作品を次々に毎年上演している盛況を示しており、「ペトルーシカ」が上演されたのは例の親当てクイズから僅か1か月後。当時のパリに於けるバレエ隆盛の空気を想像するのは難しくない。
「サル・ガヴォー」で初演を聴いたバレリーナ、ナターシャ・トルハノーヴァ(キーウ出身という)の委嘱によって、ワルツ集がバレエ音楽として管弦楽曲に改編される運びとなったのもその反映と見るべきであろう。ラヴェルはこのオーケストレーションを初演翌日から僅か2週間ほどで完了させる。更にそれに飽き足らず、「アデライード、または花言葉」と題して自らバレエの台本を書く頑張りを見せる。ラヴェルにとっても例が無いが、その意図はいまわからない。このバレエは翌1912年4月22日にトルハノーヴァが主宰するバレエ団によって上演されたが、指揮は作曲者自身が行っている。これが前述した「ダフニスとクロエ」上演の僅か2か月前。「手あたり次第」にバレエの興行が行われていた印象で、またその為の音楽がどれほど渇望されていたかを垣間見る思いがする。
さて、ラヴェルがその折にものしたその台本だが作品への理解の為、以下に曲ごとの情景とストーリー概要を示しておこう。
高級娼婦のアデライードを巡る、なじみの「男爵」と新参者のロレダンとの、花言葉を介した恋の駆引きがテーマ。花言葉がストーリー展開のキイとなっているが、同じ花に関するそれにも、正反対ともとれるような複数の内容を含む場合がある。ここではストーリーの展開に沿った意味の花言葉を選んで示すことにする。
1820年前後のパリにあるアデライードの館が舞台。ステージの背景には窓があり夜の庭を望む。舞台両袖には様々な花を活けた花瓶が円卓上に置かれる。
1:Modéré(中庸の速さで)*オランダ水仙⇒花言葉は危険な快楽
館での夜会。踊る男女や会話を愉しむ人々など大勢が集う。その間を巡った後アデライードはオランダ水仙の香を嗅ぎ、胸に吸い込む。
2:Assez lent(充分に遅く)*きんぽうげ⇒名誉
客のひとりである陰気な印象の男ロレダンが、アデライードにきんぽうげの花を捧げる。愛情を示された彼女は妖艶な姿態を彼に見せ、男女の駆引きが展開される。
3:Modéré( 中庸の速さで )
彼女はきんぽうげの花びらを1枚ずつちぎって花占いを行い、ロレダンの愛情の真摯さを知る。ロレダンも同様の占いをすると反対の結果。アデライードはいま一度やり直しをロレダンに求める。今度は望みどおりの見立てとなる。
4:Assez animé(充分活発に)
花占いの結果を受け、アデライードとロレダンは親密に踊る。そこに男爵が入って来る。彼女は動揺を露わにする。
5:Presque lent(ほぼゆったりと)*ひまわり⇒貴方を幸せにしよう
男爵はこの娼婦にひまわりの花束と、ダイヤを散りばめた首飾りを贈る。
6:Vif(活発に)
男爵がアデライードに示した姿勢にロレダンは絶望し、アデライードに翻意を迫るが拒絶される。
7:Moins vif(活発過ぎずに)
男爵は退出前にワルツを踊ることを彼女に申し入れるが、アデライードは拒絶し、当てつけるようにロレダンを誘う。最初は及び腰のロレダンも最後はアデライードの誘惑に屈し受け容れる。
8:Épilogue: lent(終曲 緩やかに)*アカシア⇒友情 *白い芥子⇒忘却 *赤い薔薇⇒貴方を愛する
宴は果てて客はみな退場。3人だけが残る。そこで男爵は再びアデライードに迫るが、彼女はアカシア(お友達でいましょうの意)を男爵に手渡す。ロレダンには白い芥子の花を示す。男爵は立ち去り、一方のロレダンは悲嘆にくれて「忘却」を示す花を受け取らずに退出。
その後アデライードはバルコニーに出て再び水仙の香りを吸う。そこにロレダンがよじ登ってやってくる。彼はアデライードに駆け寄るとその足元に伏して拳銃を自分のこめかみに押し当て、彼女への想いのたけを示す。
アデライードは微笑んで胸元から赤い薔薇を取り出す。意に気づくロレダン。二人は抱擁し合い、静寂の中でこの短い物語は終わる。
本質の変容か?
ラヴェルがこの作品を創作するに当たって念頭に置いていたのは、シューベルトが遺したピアノのためのワル ツ集だった。この夭逝した作曲家は仲間の集う場で即興的に短いワルツ(ウィーン発祥のレントラーというべきだろうが)を弾くことを常としていた。そうした結果として彼の遺した作品集に「感傷的なワルツ集“Valses sentimentales”」(D 779 1823-1825年)や「高雅なワルツ集“Valses nobles”」(作品77 D 969 1824年)と題されたものが含まれている。「高雅で感傷的なワルツ」という曲名の由来はここにあり、且つシューベルトの作品のモチーフに基づいた展開を示している部分も見受けられる。とすれば、この偉大なる先達の作品に対するオマージュ(敬意)とさえ言えるのではあるまいか。
だがこれがバレエ音楽としてストーリーが付帯された時点で、その性格は大きく変貌したように思えてしまう。歌曲に譬えれば詞(詩)が先にあってそれに合致するメロディを創るのに対し、この場合はある意図を以って既に出来上がった旋律に、本来関係性のない詞を当てはめる形にあるということだ。いわば作品の「転用」であり、もはやシューベルトとの関連は希薄な上にも希薄である。とすれば「高雅で感傷的なワルツ」の曲名はあくまで当初のピアノ作品に対して付されたものであって、その後の改編によって生み出された管弦楽作品名としては作曲者本人が改めて題した「アデライード、または花言葉」こそが本来ふさわしいように思えてくる。
実は初演時の曲名には「アデライード」の副題がつけられてはいる。これを以って作曲者が当初より既にバレエ音楽へのストーリー展開を構想していたとの見方もあるようだが、それがどの程度の具体性を伴っていたかは全く不明。副題は所詮副題に過ぎぬ。事実ラヴェルが遺した他のバレエのための作品は「ダフニスとクロエ」のように台本に沿って当初より作曲されるか、もしくは「マ・メール・ロワ」のごとくそもそもストーリー性を以って創作された音楽に合わせてバレエの振付が行われており、この曲のような曖昧さを含む例はほかに無い。
管弦楽で聴くこの作品が、こうした異例と変容の果てにいま我々の前にあるという事実を、或いは心にとめおくべきなのかもしれない。
初 演:1912年4月22日 作曲者指揮 シャトレ座(パリ)
管弦楽のみ1924年2月15日 ピエール・モントゥー指揮サル・デュ・カジノ・ド・パリ
楽器編成:フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、
ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、
テューバ、ティンパニ、トライアングル、小太鼓、タンブリン、シンバル、大太鼓、グロッケンシュピール、チェレスタ、ハープ2、弦五部
主な参考文献
平島正郎『音楽大事典』「ラヴェル」の項 平凡社 1983年
三善晃/石島正博『ラヴェルピアノ作品全集』第3巻 全音楽譜出版社 2007年
真田千絵「M.ラヴェルの『高雅で感傷的なワルツ』の研究
『こども教育宝仙大学紀要』2012年
野平多美「優雅で感傷的なワルツ」スコア解説 全音楽譜出版社 2024年
「高雅で感傷的なワルツ」Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki
「音楽図鑑Clssic 高雅で感傷的なワルツ」https://www.asahi- net.or.jp/~qa8f-kik/Ravel/Analyze/08_Valses_ nobles_et _sentimentales/index.html(アクセス日はすべて2024年2月15日)
デュカス:交響曲ハ長調
人と作品
ポール・アブラアム・デュカスは1865年10月1日にパリのコキリエール通りでユダヤ人の家庭に生まれた。ミドルネームのアブラアムや苗字の発音はそのためと思われる。父ジュール・ジャコブは銀行家、母ウジェニーはピアニストであった。ウジェニーはポールが5歳の時にピアノのレッスンを受けさせたが、14歳の頃まで特に才能は現さず、1881年の終わりに16歳でパリ音楽院に入学するまで特筆すべきエピソードは残っていない。
パリ音楽院では作曲をエルネスト・ギローに師事する。ギローはビゼーの「アルルの女」の編曲で知られた作曲家である。そこで、生涯の友人となるクロード・ドビュッシーに会う。ドビュッシーとの親交は彼の死に際して「牧神の遥かな嘆き」を追悼に捧げるほどであった。音楽院時代にはカンタータ「ヴェレダ」でローマ大賞の2位となるが、翌年には賞を取ることができず、失望したデュカスは音楽院を退学してしまう。
デュカスは後年、教育者、批評家としても活動した。そのためか厳しい批評の目を自らにも向け、その多くを破棄してしまったために現存する作品は20ほどである。
1907年初演の歌劇「アリアーヌと青ひげ」は、同じくメーテルランクの戯曲によるドビュッシーの「ペレアスとメリザンド」と並んで20世紀初頭のフランスでもっとも重要な舞台作品として同時代の作曲家の称賛を浴びた。この中にはツェムリンスキー、シェーンベルク、その弟子のアルバン・ベルクとアントン・ウェーベルンも含まれ、ウィーン初演に際して祝辞を贈ったほどであった。
デュカスの弟子にはオリヴィエ・メシアンやホアキン・ロドリーゴなど高名な作曲家がいる。先日の練習でトレーナーの先生に鳥の声を思わせる表現が今回の交響曲にあると指摘を受けた。直接の繋がりはないようだがメシアンは鳥の鳴き声を曲に使うことがよくある。
批評家としての活動は1892年から1905年まで続き、自身の音楽を作ることを妨げたように思われる。1912年にバレエ音楽「ラ・ぺリ」の初演が行われた後は1935年5月17日に死を迎えるまで一切の楽曲の出版は行われなかった。
フランスの「交響曲」
あくまでも私論であるが、フランスの作曲家は交響曲という堅牢な構造を持つジャンルには向かないのか、知る限りでは複数の交響曲を作っている作曲家はほとんどいない。現在よく演奏され、重要なレパートリーとなっている曲としては、ベルリオーズの幻想交響曲、フランクのニ短調、ダンディの「フランスの山人の歌による交響曲」、当団でも過去に演奏したショーソンの交響曲、例外的に複数作曲しているが「オルガン付き」以外は滅多に演奏されないサン=サーンスあたりが有名である。ベルリオーズは他にも交響曲と名のつく大作を残しているが果たして交響曲として扱っていいものかわからない破格の作品ばかりである。型破りといえば、弟子のメシアンの手になる「トゥーランガリラ交響曲」もあげておこう。
これらは意表をついたものでなくても、どの曲もいわゆる一般の考える交響曲とは大いに異なる。一般的には交響曲とは第1楽章にソナタ形式、中間楽章となる第2楽章、第3楽章で緩徐楽章とメヌエットやスケルツォなどの舞踊曲、終楽章となる第4楽章では再びソナタ形式か変奏曲形式を取った早いテンポの楽章からなる。
ここであげたフランスの交響曲は一般的なフォルムは全く採用していない。ほとんど3楽章構成、編成にもピアノやオルガンを含んだ協奏曲風であるもの、多楽章でどこが交響曲なのやら見当もつかないものまである。
その意味では今回取り上げるデュカスはフランス人の交響曲としてはかなり形式張った曲と言えなくもない。とは言え、至る所でフランス的な響きを感じることができるやはり「フランスの交響曲」であることは疑いがない。
本日どんな演奏をお届けすることができるか楽しみでもあり、期待に背かないか不安でもある。
第1楽章 Allegro non troppo vivace, ma con fuoco
ハ長調。ソナタ形式、8分の6拍子
弦楽器で演奏される活発な第1主題で始まり、どこか哀調を帯びた第2主題が同じく弦楽器で演奏される。様々に展開された後、圧倒的なエネルギーをもってこの楽章は終わる。
第2楽章 Andante espressivo e sostenuto
ホ短調。ソナタ形式、8分の4拍子
心に染み入るような主題がホルンの特徴的な音型を伴って開始され、自然を表すような優美な伴奏とともに緩徐楽章は進み、コラールが幅広く鳴り響いた後、静かに幕を閉じる。
第3楽章 Allegro spiritoso
ハ長調。ロンド形式、4分の3 = 8分の9拍子
2種類の拍子が組み合わされて歓喜に満ちた雰囲気で自由なロンドが繰り広げられる。次々に新しい楽想が現れては消え、再び華やかなフィナーレとなる。
初 演:1897年1月3日パリ・オペラ座にて ポール・ヴィダル指揮
楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2(1番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、ピッコロ・トランペット、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、弦五部
参考:
「フランス語版ウィキペディア」https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Dukas#Biographie
「ベルリンフィルハーモニー管弦楽団」https://www.berliner-philharmoniker.de/en/stories/paul-dukas/
「ブリタニカ」https://www.britannica.com/biography/Paul-Abraham-Dukas (アクセス日はすべて2024年2月24日)
第265回演奏会のご案内
「ローマの松」とローマ街道1号線
オモテ面の地図はローマのアッピア旧街道に沿って地形図を切り抜いたものである。1km方眼の傾きは南東を向いた街道に合わせたためだ。古代ローマ帝国(共和制を含む)が広大な版図に張り巡らせた街道は10万kmにも及ぶ。構造はこぶし大の礫から砕石、セメントに至る何層にも重ねられた上に石畳で舗装した2車線の車道と、両側の歩道を備えていた。コースは地形をほとんど顧慮することなくどこまでもまっすぐなのが特徴だが、アッピア街道はその最初期に建設されたものである。その名はローマのケンソル(高位政務官)であったアッピウス・クラウディウス・カエクスに由来する。ローマの城門を出た直後から20kmほどひたすら直線コースが続く。
レスピーギ(1879-1936)の代表作「ローマの松」は4部に分かれ、それぞれ「松のある古代ローマの風景」を描いている。ボルゲーゼ荘の松、カタコンバ付近の松、ジャニコロの松、そして終曲がこのアッピア街道の松である。1924年の初演から今年でちょうど100年、「1号線」たるこの街道の開通からはすでに2300年以上が経過した。現在も古代さながらの石畳道を、馬車ならぬ自動車が行き交っているが、レスピーギは「別働隊」のラッパとオルガンが鳴り渡る壮大な音響で、遙か昔の世界帝国の空気を描いている。
ラヴェルは当時の「前衛作家」だった
ラヴェルの「高雅で感傷的なワルツ」はサル・ガヴォーというピアノ製作会社の名を冠した小ホールでピアノ曲として初演された。「独立音楽協会」の催しで、誰の作品か事前に知らされない聴衆が作曲者を当てるという趣向。正解者は多かったものの評価は今ひとつだったという。「正統派」であった国民音楽協会を脱退して「現代的な音楽の創造」に寄与すべく立ち上げられた独立音楽協会のコンサートで、耳の肥えた聴衆が多かったとはいえ、その前衛ぶりについて行けなかったのかもしれない。曲は緩急8つのワルツからなり、翌年にはバレエ音楽としての依頼によりわずか2週間でオーケストラ用に編曲されたという。色彩感溢れる表現が聴きどころである。
最初に取り上げるのはデュカスの交響曲。この人の作品で最も知られているのは「魔法使いの弟子」だろう。生涯で1つだけとなった交響曲はその前年に書かれたものである。印象としては同じ作家とは思えないほど古典的で堅固な構成だが、その中に華やかな響きを併せ持った作品で、演奏機会はそれほど多くはないが佳品である。
最後にクイズ。地図の最上部にDomine Quo Vadis ? とあるのは何を意味しているだろうか。地図に疑問符が印刷されるなど他で聞いたこともない。「主よ、何処へ」を意味するこのラテン語、実はそのまま小さな教会の名前であるが、なるほどあるべき所に位置している。意味深長なこの言葉を数行で説明するのは無理なので、気になる方は検索してください。(K.I.)
「マーラーブーム」の頃
今を去る30年以上むかし、わが国にマーラーブームが起こった事があった。それはバブル期に突如起こり、極めて短期間に終わりを遂げた。今ではその残滓を見出す事も困難といえる当時の状況を、その時代に深く関わったひとりとして記録しておきたい。今回「クック版」の全曲演奏により、マーラーの交響曲全てを演奏した事になるので、その記念としても。
◆新響<マーラーシリーズ>の軌跡
かつて新響は10年に亘ってマーラーの交響曲の全曲演奏に挑んだ事があった。指揮は山田一雄氏による。ひとつのオーケストラが同一指揮者によるマーラーの交響曲全曲演奏を果たした例としては先駆と云うべきで、その後40年もの時間を経ても、その例は余り多くはない。
その軌跡を新響の演奏記録から改めて抜き出してみた。
① 1979/12/1 第86回 交響曲第5番
(+花の章)
② 1980/11/20 第90回 交響曲第6番
③ 1981/9/19 第93回 交響曲第7番
④ 1983/1/23 第98回 交響曲第9番
⑤ 1983/11/1 第101回 交響曲第2番
⑥ 1984/9/26 第105回 交響曲第3番
⑦ 1985/7/20 第108回 大地の歌
⑧ 1986/4/6 第110回 交響曲第8番
⑨ 1987/6/21 第116回 交響曲第10番
(第1楽章のみ)
⑩ 1988/1/17 第118回 交響曲第4番
⑪ 1988/7/31 第120回 交響曲第1番
(+さすらう若人の歌)
1回1曲(まぁ当然か)で『大地の歌』を含めた11曲をまる10年かけての「マーラーシリーズ」と銘打った演奏会が、年によっては2回行われていた事に、今更ながら驚きを禁じ得ない。1月の年明けに第9番をやり終えて、10か月後に第2番『復活』を取り上げる(上記④と⑤…しかもこの間に2回の演奏会を挟んでいるのだ)というのは、現在の新響でも二の足を踏んでおかしくない。よほどの執念と情熱と勢いと、そしてある種の諦め(笑)が無ければなかなか通らない企画だろう。
もっとも……当時の新響は今と練習量が違った。演奏会が終わればその週末から次シーズンの練習が始まった。5月連休と秋には2泊3日の合宿。文字通り盆と正月以外の週末は練習が入っていたから、1シーズンの練習は15~18回程度(現在は演奏会翌週は休みで、初回練習に備えて個人練習に充てる。全体で11~13回ほど。「働き方改革」の波は新響にも及んでいる)。個人の技量レヴェルをオケ全体の練習量で補っていた感はある。そのようにして大抵の「無理」を乗り越えたのである。
新響のマーラーシリーズが始まったのは、マーラーの作品が一般の音楽愛好家の間に広く浸透しつつあった時期であったように感じている。いくつもの要因があろうが、デジタル化が進行によるコンパクトディスク(CD)の普及というハード面に於ける革新要素は意外と忘れられているのではないだろうか?この出現が、初めて彼の長大な交響曲は切れ目無く、手軽に再生することを可能にした。ベートーヴェンの『第九』をそっくり納める事がCD 1枚の収録時間の条件とされたとの話を当時何度も耳にした。それまでのLPレコードではこの大作は楽章毎に盤面を返す必要があって興を殺がれること甚大だったので(当時はその方法しか無かったから、ある種の儀式と割りきってもいたが)、これは画期的というにも余りあった。
収録時間だけではない。デジタル化によって各楽器各パートの音がより明確になった。例えばマーラーの作品には、同じ旋律を受持つ複数のパートに片やクレッシェンド、片やディミヌエンドを求め、旋律の音色の変化を意図する箇所が多々出現する。或いはなかなか生演奏でも聴き始分けられない舞台裏からの演奏音や特殊楽器の音質感……新技術によってこうした音の再現効果は一挙に増大したのだ。こうした事は改めて思い起こさないと何も感じぬ程に当たり前になっている。だが、大雑把に言えばマーラーの、特に交響曲はデジタル時代に合致した音楽だったのだと思わざるを得ない。音楽ソフトとしてのCDが従来のレコードの販売枚数を超えたのが1986年というから、これが彼の作品を浸透させる結果となり、来るべき「ブーム」を形成する為の基盤となったと実感している。本来これは従来の愛好家の間に生起した、穏やかなそれとして終わる筈だったのだが。
当時の新響はその流れを先見して感じとり、交響曲全曲の演奏をシリーズ化させて、10年かけて実現(ここが重要である)した。後述するマーラーブームが過熱しつつあった時点でシリーズを終えた点は注目されるべき点だと考えている。
今から40年以上前といえば、マーラーの交響曲を単発でもプログラムに載せられるほどの規模と技量を備えたアマチュアオーケストラは数えるほどしか無かった、と記憶する。例えば第8番『千人の交響曲』は新響の他には、早稲田大学交響楽団が、大学の創立百周年を記念して学内の合唱団を交えて全学を挙げて演奏(指揮は岩城宏之氏)したくらいで、この記録は今もってほぼ変わっていないのではあるまいか。
マーラーシリーズは「邦人作品展」と同時並行で行われていた。この二枚看板が新響の一時代を作り上げたのだから、先人たちの功績への驚異と敬意はもっと大きくあって然るべきである。
私は1982年に新響に入り④の交響曲第9番の演奏から加わった。とはいえいくつも理由はあるが、シリーズの間に上記のうちまともに演奏したのは結局④・⑧・⑩のみ。このように新響に入団する前は如何ともし難く、且つ入団後も演奏の機会を持てぬ交響曲の方が多かったのだ。そもそもマーラーの作品にさほどの拘りもなく(どちらかと言えば嫌いだった)、演奏機会を得られない事を不満とも思わなかった。 が、1988年7月、シリーズ最後の演奏会(⑪)終演後のレセプションで、このシリーズに皆勤した団員・・・・20名ほどいたろうか・・・・に対し、山田一雄氏から銘々に自筆の色紙が贈られるのを目の当たりにして、流石に心穏やかではいられなくなった。演奏者にとって得難い体験であった事は間違いない。そして色紙というモノの存在が、逃してしまったマーラーの演奏機会への気づきにつながったというのだから、我ながら現金なものである。さほどの執着もないくせに欠如感があったとしか思えない。そうでない限りその後に自分がとった行動に説明がつかないからだ。
その欠如感を埋める機会は「マーラーブーム」の到来によって突如もたらされる事になったのである。
◆空前のマーラーブームとその土壌
その「ブーム」は1本のTV-CMによって突如起こったように今も感じている。
https://www.youtube.com/watch?v=3-h_kaEnNKg
このCMが初めて電波に乗ったのは1986年という。ご記憶の方もおいでかもしれない。使われているのはテロップにもある通り『大地の歌』。彼の作品に接していれば、ここで使われている部分がどんな作曲者の思考の果てに創作された音楽であるか、についての知識もある。だが、全く予備知識なしにこのCMから流れる音楽とナレーションで、初めてマーラーなる人物と「作品」を知った人にとってみれば、「東洋的なメロディを書く、ちょっと風変わりな作曲家」程度の認識しか持てないだろう。そしてこうした認識の人々が前代未聞の「マーラーブーム」を現出させたのである。謂わばマーラーの「大衆化」で、今考えると不思議としか言いようがない。それまで限られた?愛好家でしか知られていなかったマーラ実はこの会社は同工異曲のCMをあと二つ制作して流している。ランボーとガウディがモデルだ。
実はこの会社は同工異曲のCMをあと二つ制作して流している。ランボーとガウディがモデルだ。
https://www.youtube.com/watch?v=3Hbf4LGmrf8
https://www.youtube.com/watch?v=NPZlOzrtTSk&t=1s
だがこれらによってランボーの詩集が発的に増版を重ねたとか、サグラダ・ファミリアに日本人が以前に増して押しかけたとかいう現象にはつながらなかった。ひとりマーラーだけがもてはやされるに至った。 受け入れるに足る社会の下地が醸成されていなければ、落ちた種は発芽も況して開花もしない。事実この1分に満たぬCM がマーラーブームへの発展に至るには、当時の社会状況が大きく反映していた。その社会の下地とは所謂「バブル景気」であった事を改めてここで述べる必要があろう。既に人々の記憶から遠ざかってしまっているのだから。
1985年から91年までの6年ほどの期間が一般に「バブル時代」と位置付けられているようだ。1981年入社組の駆け出し社会人として、また給与所得を経済的基盤とする生活者としての実感はもう少し狭い時間だったように思うが、いずれにせよこの時期、戦後の日本経済の繁栄を牽引し続けてきたモノづくりから離れて、不動産や株が更なる富をもたらす源泉となるとの信仰に個人も企業も浮かれた。そしてそれが実際カネになった(個人的には全く無縁だったが)事で更に信仰が深まるという循環が出来上がっていたのだ。挙げ句にそのようにしてもたらされた、日頃持ち慣れない大金の使い途に迷った事については、企業も個人も区別がなかったのである。要するにアブク銭。まさにバブルだったし、この風潮にどっぷり浸っている人々も、こんな景気がいつまでも続こうとは考えていなかった。故に余計に刹那的な消費につながった感を拭えない。
音楽に関連する「消費」に目を向けても、まず各地に立派なホールの建設ラッシュが起きた。思わぬ税収の伸びに浮かれた自治体もこの有り様で、建てたはいいがその使い途は地元敬老会のカラオケ大会・・・・という、笑えぬ状況が現出した。企業は揃って「メセナ活動」に注力し、芸術に対する理解・愛好度合いを、その助成金額を唯一の尺度にして競った。その恩恵によって得体の知れぬ「著名な」海外演奏家が法外なギャラで招かれる事も頻繁に起きたし、1000人ひいては5000人というやたら合唱人数の多い『第九』の演奏会(向島の芸者衆を集めて歌わせた趣向すらあった)が各所で開かれた。確か東京ドーム行われた『アイーダ』の公演では、生きた像を何頭も登場させた記憶がある(2013年にも同様の企画があったが中止)。
新設の大ホールという「器」があって使途に困るほどの「カネ」がある・・・・となれば大編成のマーラーの交響曲がそこに根付く土壌は充分過ぎるほどに形成されていた。挙句に全国のホールにて玉石混淆レヴェルの演奏で、マーラーの交響曲が鳴り響く事態が起こっていった。
◆東京マーラー・ユーゲント・オーケストラ(TMJ)
こうした状況を冷めた目で見ていた1987年の夏、新響を含めた複数の音楽仲間から「マーラーの交響曲第9番を山田一雄氏の指揮で演奏しないか」との声がかかった。会場として翌年2月のサントリーホールを押さえたという。このホールはこの前年1986年10月に竣工したばかりだった。曲目・指揮者・会場いずれもこれ以上望むべくもない条件だ。曲自体は新響入団後初のコンサートで演奏してはいるものの3番フルートの席で、且つ演奏自体、合宿での練習をも経ていながらあまり完成度の高いものではなかった。本番中ヤマカズ氏がオケに向かって何度も叱咤の声を上げている(!)のを耳にして驚いたほどのものだった。要するにその時の演奏の出来と、それを自分の力では如何ともし難いポジションにあった事への満たされぬ思いがずっと燻り続けていたのだった。それから4年、マーラーの作品を取巻く環境もこれまで述べたように激変しており、言うなれば意趣返しの機会を得た心境で話に飛びついた。
名称を『東京マーラー・ユーゲント・オーケストラ(TMJ)』として、秋口より開始予定の練習に向けて、主に東京で活動するアマチュアオーケストラからこれぞというメンバーをほぼ一本釣りで集める。並行して運営メンバーも徐々に絞られ、私はこの一期一会といえる一発オーケストラの代表者に祭り上げられた。当時新響でインスペクターを務めており、山田一雄氏とのコンタクトの利便性がその一番の理由だったのだろう(それが災いして巨匠に新響とTMJ を混同させる弊害も招いたが)。
ここでこのオーケストラが果たした演奏についての詳述する紙幅は無く、本稿の目的でもないので避けるが、当時のアマ・オケとしては突出した水準に達していた事だけは明記しておきたい。当初TMJ なる団体について半信半疑だったヤマカズ氏も、我々の想定を超える注力振りを見せた。1988年2月に行われた演奏会は成功だったのだ。
だが、特筆すべきはこの演奏会を運営するに際して直面した当時のマーラーブームの異常さにこそある。
そもそも何の実績も信用もない、従ってカネもない「一発オーケストラ」がサントリーホールを確保できた事自体が既にして不思議だった。当然予約に当たっては前金を支払う。だがそもそも未だメンバーも揃っておらず、経済的基盤も曖昧と来ている。どうしたか?参加者からの出費ももちろん充てたが、結局そのカネの大半は、核となったメンバーが心当たりの企業から協賛として集めたのである。サントリーホールの使用料は当時でも200万円ほどの額だった筈で、有り体に言えばそれ賄うに足る金額が集まった(因みに言えば新響が毎回のコンサート会場としている東京芸術劇場の使用料は、現在でも100万円に届かない)。それも極めて短期間に先にも触れたが各企業は「メセナ」の美名の下に、競って協賛先を求めていたのだ。
マーラーの名を冠したオーケストラが、マーラーの権威たる山田一雄氏の指揮で、マーラーの交響曲をサントリーホール(例のCM の威力がここで遺憾なく発揮される)で演奏する……となればカネ余りに苦しむ企業は狂喜して飛び付き、ひれ伏して惜しまずカネを差し出すという構図が出来上がっていたのである。演奏会を開こうとした我々の動機は純粋そのもので、決して増長していた訳ではなかったが、この時流に結果として(上手く)乗った事になる。
現在新響が音楽振興に理解ある財団から助成金(最大でも100万円だ)を申請するために費やす知恵と努力と比較すると、まさに隔世の感を禁じ得ない。
メディアにも数多く取り上げられた。『朝日新聞』に我々運営陣のインタビュー記事が載ったその日、代表者たる自分とコンサートマスターがそれぞれ属する企業(いずれも一部上場の大企業である)のトップ同士が会うという偶然が重なった。会談の冒頭、両者間でこの記事の件が話題になり、円滑に事が運ぶ一助になった・・・・と後に秘書室からわざわざ上司経由で連絡があり、暫くの間は有名人の地位を得た(昇進とは全く無縁だったが)。無教養で反知性的な社員ばかりだ!と日ごろ反感を持っていたが、そのわが社内でもこの時期はさすがにマーラーが浸透していたのだ。
日頃よほど著名な演奏家のコンサートしか取り上げない『週刊新潮』の“Tempo”欄に我々TMJの演奏会の告知が載った事には心底驚き、少し怖くさえなった。我々からダメ元で情報をバラまいた結果とはいえ話題性があったのだ。
演奏会終了後には、代表者として『週刊文春』の取材も受けた。この団体の杜撰な経理状況(これは後に事実とわかり、処理に苦慮した)や代表者の乱倫な女性関係(そんなものは幸か不幸かなかったが)を「文春砲」によってスクープしようとの意図ではなく、コンサートの盛況に対する取材との話だったが、相手の意図は次第に判ってきた。要するにこの皮相なブームを、マーラーの名を冠したオーケストラの代表としてどう見ているか?を確認したいという事なのだった。「マーラーを初めて聴く人が多くいたようですね」「寝ていた客も目立ちましたが・・・・」との形で水を向けてくる。こちらにしてみれば初めてだろうが寝に来ようが客は客なので、当たり障りのない真面目な答えに終始した。そうしたコメントが決め手に欠けたのだろう、結局その原稿はボツになったとの通知があり、掲載用の写真だけ後日送られてきた。
記事はボツになったが、この記者の眼はブームの一面を確実に捉えていたと感じる。確かに2000人余りを収容するサントリーホールはほぼ満席になった。新響がここで行った数々のコンサートでもこれほどの入りは目にした事はない。だがこの時の来場者の大半は初めてマーラーの交響曲を聴きに足を運んでいた。今ならさしずめ「にわか」と呼ばれるファン、要するに例のCMのイメージを唯一のよすがとして作品に接しようと足を運んだ善男善女だった。
だが日頃クラシック音楽とは疎遠で、『大地の歌』の、殊更に東洋風の1分ほどの部分をもってそれをマーラーの音楽と考える人が、いきなり90分にも及ぶ交響曲に接した。そのイメージとの落差・隔絶は察するに余りある。
「こんな長い曲だとは思わなかった」「退屈で眠くなった」などなど、通常のコンサートではまず目にしない呪詛の言葉がアンケートに多く見られた。我々は苦笑する他はなかったがブームを思うと象徴的である。しかもこの時の前プロがベルクの『6つの小品』とくれば、悲劇でさえあったろう。気の毒と思う他はない・・・・。
◆ブームの退潮=TMJと新響=
こうした人々がその後同様のコンサートに足を運ぶことはなかったろう。もうマーラーは懲り懲り、そう考える人がいて普通である。そして現実ににわかファンは急速に退場して、ブームは急速に退潮に向かう。一方で「そういうものだ。マーラーの音楽が『ブーム』になるなんて異常そのものだ!」と考え、にわかファンと席を同じゅうせず、そうした連中を相手にした低レヴェルの演奏など聴きたくないとの矜持を示す、従来からの愛好家も離れていったから、更に凋落には拍車がかかった印象がある。
TMJはそうした動向に鈍感に過ぎた。一回限りの前提を覆して「次」に挑んだ。従来の成功体験そのまま意識で運営が継続されたが、山田一雄氏が死去した1991年(バブル終焉の年だ)を境に、その後は演奏会を重ねる毎に財政的に窮乏が進行していた。企業は既に一斉にメセナから手を引いていた。恒久的な資産がある訳でもない。それでも海外公演まで企画をし、代表者も知らぬ間に一部メンバーは実行に移そうとしていたのである。当然頓挫する。これが1994年の事で、これでTMJは解消した事になるが実質的にはもっと早い。
こうして見返すとマーラーブームの真只中にあった1988年という年の、新響と東京マーラー・ユーゲント・オーケストラというふたつの団体の活動は極めて対照的だった事に気づく。片やその年の夏に10年続いたシリーズを完結した。一方はブームの波に乗り、瞬時の大成功を収めた事で、時代の下降に気づかず凋落を免れなかった。
双方のオーケストラに関わった身としては、単純に新響の先見に軍配を上げる気にはなれない。今は関係者からさえ語られる事の殆どないTMJが、あのバブル時代に束の間開花したブームのあだ花のひとつの様に、後に伝えられてしまう事だけは避けたい、と切に思うのである。
マーラー:交響曲第10番
■はじめに
交響曲第10番は、グスタフ・マーラー(1860-1911)の死によって未完のまま残されることとなった、彼の生涯最後の作品である。全5楽章からなり、作曲者自身がほぼ完成の状態までスコアの草稿を書き上げていた第1楽章のみが単独で演奏されることも多いが、残りの部分を後世の人間が補筆して、全曲を通して演奏できるようにした「補作版」もいくつか存在する。本日は、こうした「補作版」の中から「クック版第3稿」を演奏する。
■交響曲第10番の概要
生前のマーラーは作曲家である以上に、当時の楽壇におけるトップ指揮者であり、秋~翌春にかけての楽季中はオペラやオーケストラの指揮者業で多忙を極めていた。3日に1回ペースで本番をこなすこともしばしばであったという。彼が作曲に取り組めたのはオフシーズンである夏の間だけであり、オーストリア近郊の自然豊かな別荘で「作曲小屋」に籠って集中的に作品を書くというスタイルであった。
1907年、マーラーは10年間君臨していたウィーン宮廷歌劇場(現ウィーン国立歌劇場)総監督の座を辞し、妻アルマ(1879-1964)と共にニューヨークへ渡ってメトロポリタン歌劇場の指揮者に就任する。この年は長女マリア・アンナの急逝(享年4歳)、マーラー自身の心臓疾患の発覚という不幸が重なっており、さらに「ユダヤ排斥の気運に押され心身共に絶望した状態で、ウィーンを半ば追放された」とマーラーのアメリカ行きが悲劇的に語られることも多い。しかしマーラー本人は若いころから各地の歌劇場を転々とする生活に慣れていたことに加え、新天地での仕事も非常に精力的にこなしており、当時の書簡の内容等からも悲愴感はさほどうかがえない。逆に妻のアルマは生粋のウィーンっ子で英語もあまり喋れず、忙殺される夫を支えようとしつつもアメリカで孤独感を深めていたようである。このように1908年以降は、マーラーは楽季の活動を主にニューヨークで行い、ヨーロッパでの単発の仕事もこなしつつ、夏には南チロル(現在はイタリア北部)トープラッハの別荘で作曲を行うというサイクルで生活していた。以上の前提を踏まえ、実際に交響曲第10番が作曲された1910年夏からマーラーの死去までを、まずは時系列でみてみよう。
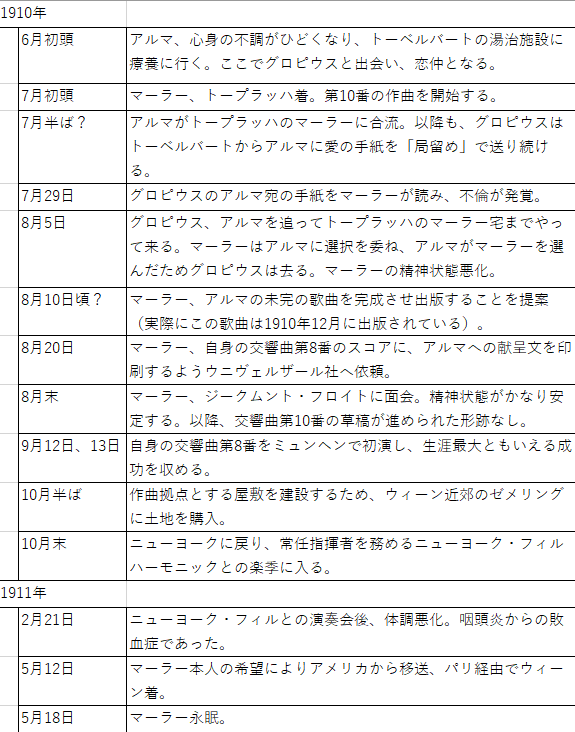
1910年夏ごろのアルマは、先述の通り鬱積したストレスや孤独感により、本人の回想録の言葉を借りれば「ひどいヒステリー」状態であったらしい。見かねたマーラーは彼女をしばらく休ませるため、当時評判だったトーベルバートの湯治施設に送り届けたのだが、そこでアルマは建築家のヴァルター・グロピウス(1883-1969)と出逢ってしまうのである。当時アルマは30歳、グロピウスは27歳で、後のモダニズム建築の巨匠は、この時は新進気鋭の魅力あふれる青年であった。2人はアルマのトーベルバート着後すぐに知り合い、1か月あまり激しい恋の日々を過ごす。その後アルマはトープラッハの別荘に居るマーラーと合流したが、グロピウスとは頻繁な手紙のやり取りが続いていた。そのうちの1通が手違いで(そうでないという説もあるが)マーラーの手に渡ってしまい、2人の不倫関係が表沙汰になる。
マーラーはアルマの自分に対する忠誠と貞操を疑っていなかっただけに、グロピウスからの手紙を読んだ時、またそれをきっかけに妻から吐露された積年の不満を知った時には大変な衝撃であったようだ。8月5日にグロピウスが直接訪ねてきた際、アルマはマーラーを選んだが、その後もマーラーは、いつ彼女が自分のもとを去ってしまうか分からないという強迫観念に囚われていたらしい。マーラーはアルマと結婚する際の条件として彼女が作曲することを禁じているが、ここにきて急に彼女の未完の歌曲を褒めだし、これを完成させて出版することを提案したり、初演を秋に控えた自身の交響曲第8番をアルマへ献呈することにしたりと、妻への愛情を示そうと躍起になっている様子がうかがえる。8月末には精神学者のジークムント・フロイトを訪ねており、様々なアドバイスを受けて精神状態は大分回復したようであるが、そうこうしているうちに1910年の夏は終わり、結局この「グロピウス事件」のせいで交響曲第10番の作曲は中途半端なところまでしか進まなかった。そして次の夏を迎えることなく、マーラーは死んでしまったのである。

トープラッハを散歩するマーラーとアルマ(1909年)
■クック版について
マーラーは交響曲の作曲において、おおむね以下の3段階の過程を経て作品を作り上げていた(各過程における細かい修正や楽章順の入れ替え等はあった)。
①パルティチェル(3段か4段の譜表に、おもな楽想だけを書き込んだ略式のショートスコア)を書く
②パルティチェルをもとに全体のオーケストレーションをつけ、スコアの草稿を書く
③草稿を清書して完成
マーラーが死んだとき、交響曲第10番は全5楽章のうち第1、2楽章と第3楽章の冒頭30小節目までは②草稿の段階までざっくり出来上がっていた。しかし第3楽章の31小節目以降は①パルティチェルの段階であり、強弱記号や楽器の指定などはところどころにしか記載されていない(第3楽章のスケッチを書き始めたあたりで「グロピウス事件」が勃発したと分析する研究者が多い)。とはいえパルティチェルは第5楽章の最後まで繋がっており、曲としての要素は不完全ながらも揃っているという状態であった。
マーラーの死後、妻アルマの手元に遺された交響曲第10番の草稿は、アルマの10年以上の逡巡を経て1924年にようやくファクシミリの形で出版される。並行して、アルマは近しい作曲家(娘婿のクルシェネク)らに第1楽章と第3楽章の演奏可能な譜面の作成を依頼し、この演奏譜を用いた部分初演が1924年10月にウィーンで行われた。これらのきっかけによって、世界各所でこの幻の傑作の補筆作業が検討され始める。
デリック・クック(1919-1976)はワーグナーやマーラーを専門とする音楽学者・評論家で、BBC(英国放送協会)の音楽部門で放送作家をしたり、フリーの評論家として活動した人であった。1960年、BBCではマーラー生誕100年を記念した特別番組を企画しており、クックはこの番組でのレクチャーを依頼された。そこで出版済の交響曲第10番の自筆譜ファクシミリを研究し始めたクックは、それが「スケッチとしてほぼ完成した作品」であることに驚き、すっかりのめり込んでしまう。結局第2、4楽章に部分的な欠落を残しながらも、その他の部分は網羅された「クック版第1稿」が1960年に放送初演された。妻のアルマは、事前にBBCから「レクチャーのため部分的に演奏したい」旨の申し入れがあり許諾していたものの、まさか全5楽章が演奏されるとは思っていなかったらしく、当初は怒ってこの「クック版」を今後演奏することを禁じてしまった。しかし数年後、説得に応じてこの時の演奏テープを聴いたアルマは「ここ(クック版)にどれほど『マーラーが居る』のか、解ってなかったわ」と涙を流したといい、以降はファクシミリ版に含まれていなかった未発表草稿を提供するなどクックに協力している。
こうした新たな素材も活用しながらクックは補筆作業をさらにすすめ、1964年には第2、4楽章の欠落も補われたフルバージョン「クック版第2稿」が初演。さらに1976年には「演奏可能版(a performing version)」という名目でスコアが出版されており、これが「第3稿」ということになる(クックはこれを「最終稿」としている)。クック自身はこの出版の直後に死去しているが、生前からの協力者であったコリン&デイヴィッド・マシューズ兄弟とゴールドシュミットがこれを引き継いで若干改変を加えた「第3稿第2版」というのを1989年に出版している。本日の演奏会で演奏する譜面は、この「第3稿第2版」となる。このあたりは英語と日本語でバージョンのナンバリングが異なったりしてややこしいので下表も参照頂きたい。
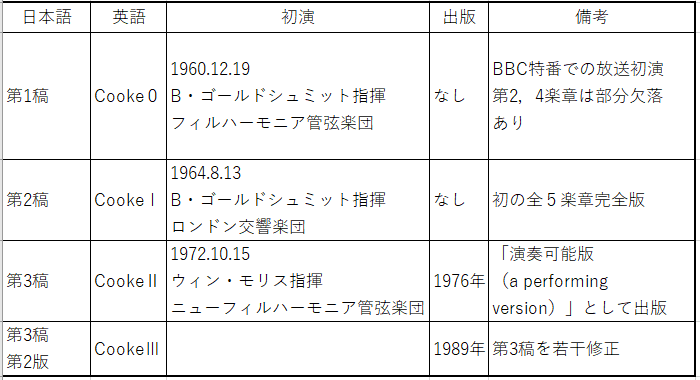
クック版の特徴として、第3稿が出版された際の「演奏可能版」という標題からも判る通り、実際に演奏するための必要最低限の補筆しかなされていないことが挙げられる。クック自身の言葉がそれを明確に説明している。
「…私の仕事の狙いは、作曲者が遺した段階における作品を実際に演奏可能な版として再現することにある。…目の粗い織物としてであれ、マーラーの特徴が保存されている限り、この音楽は他人のオーケストレーションのなかでも生きて、魅力を保っている。…」
つまりマーラーの作品を補筆によって「完成させる」という考え方ではなく、あくまで実演の際の叩き台となるオーケストレーションを整えただけ、というスタンスである。クックが補った音符はマーラー自身が書いた音符よりもスコア上で小さく記され補筆部分が瞭然としていること、第3楽章以降はパルティチェルも並行して印刷されており比較が容易であること、校訂報告が非常に詳細で補筆の依拠が明瞭であることから、信頼性が高く、今日存在する交響曲第10番の補作の中では最も広く受容されているといえる。
そもそも未完作品の補作自体が許される行為であるのか、という創作倫理上の議論はあり、事実、作曲者以外の譜面への関与に否定的な国際マーラー協会の「全集版」においては、交響曲第10番は(ほとんど完成していて第三者の補筆が不要な)第1楽章しか出版されていない。それでも補作をすることで初めて全5楽章の実演が可能になるわけで、曲の全貌を実際に演奏することでしか得られない新たなマーラー体験は確かにあるはずである。我々も、まだ見ぬマーラーの世界を少しでも感じ、演奏を聞いて下さる皆様と共有してみたいという欲望に抗えず、クックの偉大かつ謙虚な仕事に対峙させてもらうのである。
■楽曲解説
交響曲第10番については、大作曲家マーラーの最後かつ未完の作品だということもあって、多くの深遠・哲学的かつ当時のマーラーの感情や精神の状態にまで憶測を拡げた分析がなされてきた。この作品と「グロピウス事件」、そしてマーラーの人生自体の終わりとを3点セットにして関連付ける解釈も比較的多くみられる。その依拠の1つとして、「グロピウス事件」の後に書かれたと推測される第3楽章以降、スケッチのところどころにマーラーの感情的な走り書きがなされていることがある。例えば
「憐れみたまえ!わが神!わが神!どうして私をお見捨てになられたのですか?」(第3楽章後半、マタイ福音書による十字架上のキリストの言葉を引用している)
「悪魔が私と踊る…狂気よ、私を捕らえよ、この呪われた者を!…」(第4楽章タイトル部分)
「ああ、ああ、ああ! さようなら、私の竪琴よ! さようなら、さようなら…」(第4楽章ラスト)
などなど。実際、この曲を聴いていると、一人の人間の内面をずっと覗かされているような、こんな個人的なことまで追体験してしまってよいのだろうか、という一種の罪悪感さえ生まれるような感覚に陥る。マーラーの人生におけるこれまでのこと、これからのこと、アルマのこと、子供の頃に聞いた軍楽隊の音楽、文学と自然、宗教、世界と宇宙…こうした要素が混然一体となって、波のようにぐっと高まっては急に寸断されたり、爆発したり、そして最終的には救いを得て安らかに消えていくところまで、我々はマーラーの剥き出しの心に肉薄させられ、揺さぶられ続けてしまう。
ただマーラーが1910年秋には自身の交響曲第8番初演を金字塔的な成功に収め、さらにウィーン近郊に今後の作曲拠点とする屋敷を建てるための土地を購入していることなどを考えると、マーラーが「グロピウス事件」によって人生そのものに決定的に絶望したとか、交響曲第10番の全てが「グロピウス事件」やそれ以前の負の出来事から生み出された死の影漂う作品であり、マーラーが案の定その影に押しつぶされてしまったがために未完なのである、とかいうのは、やや感傷的な解釈という印象がある。マーラー自身は重なる不幸や私生活における大きな危機に直面しながらも、自らの使命に今後一層全力で挑もうとしていた矢先に突然死んでしまったという方が真相に近いのではないだろうか。ということで、この曲の結論としては、苦悩と歓喜、愛と絶望といった相反する要素が全て綯い交ぜになった「人生自体の肯定」であってほしい、というのが筆者の思いである。
<第1楽章>アダージョ(約20分)
長大な緩徐楽章だが、主要な主題は2つ。1つめの主題は、曲の冒頭からヴィオラによって奏される。
<譜例1>
交響曲第10番は「嬰ヘ長調」(シャープが6つ!)とされているが、この主題は調性もあいまいで、かつて聞いたことのない虚無感と諦念を孕んだメロディである。生きているのか、悲しいのか、どこへ行くのか、全てわからない不安感がある(最も不安なのは、この音程を取りながらどソロを弾かねばならないヴィオラパート諸君であろう)。この調子でずっと続いたらどうしよう、と心配になるものの、続く第2主題はマーラー一流の実に幽玄で嫋やかな美しさにあふれている。
<譜例2>
中間の展開部にはおどけたアイロニックな調子を挟むものの、全体的には2つの主題を繰り返しながら弦楽器が半分夢遊病のようにあてどない動きで漂い続ける。特筆すべきは、クライマックスに近い部分で突如出現する凄まじい不協和音(通称「カタストローフ」)。オーケストラ全体が9個のぶつかり合う音を ff で奏し、現代音楽でいうトーン・クラスターにも近い衝撃が響き渡る。まさに心がぐちゃぐちゃになって「わーっ!」と絶叫しているかのようである。これを貫くようにトランペットだけがAの音を伸ばし続けるが、これがアルマ(Alma)の頭文字であることを指摘する研究者も多い。その後は主題も次第に切れ切れになり、消え入るように終わる。
<第2楽章>スケルツォ(約12分)
激しい変拍子の嵐となる攻撃的な主部と、ゆったりしたレントラー風の3拍子のトリオが交互に現れる。主部はほとんど1小節ごとに拍子が変わり、しかもわざと小節線をずらしたような変則的な拍の踏み方なので一瞬たりとも油断できない。この変拍子は、1910年当時にはかなり前衛的であったと思われ、マーラー自身もスコアの草稿に「3/4は1小節1つ振り、4/4はアラ・ブレーヴェ(2つ振り)で」などと指揮の振り方の指示を書き込んでいる。しかしこの鬼のようなスコアを解読・清書していったクックの苦労は如何ばかりだったかと思うと、我々は文句を言わず演奏せねばならない。トリオはずっと3拍子なので精神的にものんびりと表現できる。ラストは主部とトリオの両主題が一体となって輝かしく終結する。
<第3楽章>プルガトリオ(煉獄)(約4分)
5分にも満たない、マーラーの全交響曲の中でも最も短い楽章。「プルガトリオ(煉獄)」とは、文学オタクだったマーラーがダンテの『神曲』から引いたであろうキーワードで、地獄から天国に至る道の中間にある浄化(清め)の苦しみを受ける場所という。交響曲の構成から見ても、第1、5楽章は長大なアンダンテ、第2、4楽章はスケルツォと対象に配置された真ん中に挟まる、ちょうど中間軸のような位置づけである。歌曲的な要素が非常に強く、無機的な16分音符の繰り返し(オスティナート)音型の伴奏に乗って、もの悲しくも魅力的なメロディが歌われていく。特にマーラーが1893年に作曲した歌曲「子供の魔法の角笛」の「この世の生活」が、この楽章との近似性を指摘されている。「この世の生活」の詩の内容としては、パンを欲しがって叫ぶ餓えた子どもを、母親が繰り返し待てとなだめながら麦を刈り、粉を挽き、生地をこねる。しかしようやくパンが完成したときには、子どもは餓死していたというもの。マーラーは「この世の生活」について、「人間の生とは、この子どものパンのように、最も必要なものが手遅れになるまで与えられないものだ」という旨の言葉を残している。このように「この世の生活」に由来した主題が「煉獄」と題された楽章の中で登場するというのは、確かに「グロピウス事件」との関連性やマーラーの人生観を象徴している側面があると思われる。
<第4楽章>スケルツォ(約12分)
マーラーの交響曲の中で1曲のうちにスケルツォ楽章が2つ存在するのは、交響曲第10番のみである。第2楽章に比べると、主部は拍子こそ3拍子で一定なものの、曲想はより劇的・悲愴的で、テンポも目まぐるしく変わる。トリオはこちらもゆったりとしたレントラー風ではあるが、ヴァイオリンやヴィオラのソロのみによってノスタルジックに奏される部分なども挟まり、遠い日々を懐古するような、どこか寂れたもの悲しい空気を醸し出している。主部とトリオの雰囲気の落差は非常に効果的であり、急激なテンポの変化の連続も相まってマーラーの情緒に振り回されっぱなしである。ラストは多様な打楽器が登場し、影がうごめくような、静かだが不穏な雰囲気となり、最後は「完全にミュートした軍楽大太鼓」の一発で閉じる。
余談だが、本日演奏する第3稿第2版(1989年出版)はほぼ第3稿(1976年出版)を下地にしており、大きな変更点は無いのだが、目立つところでは第4楽章の木琴とスネアドラム(小太鼓)が削除されている。クック版の演奏においては特に打楽器の取り扱いが指揮者によってかなり異なり、第3稿と第3稿第2版の「良いとこ取り」をするパターンも多いようである。本日の寺岡先生の指揮ではスコア通りの編成で演奏するが、個人的には「木琴あり」のパターンも捨てがたい魅力があると思っており、ぜひ様々な演奏を聴き比べてみて頂きたい。
<第5楽章>フィナーレ(約20分)
第4楽章ラストからの軍楽大太鼓の打撃に引き続き、テューバ、2台のコントラファゴットなどが重苦しく響く。草稿スケッチには、ここに「君だけがこの太鼓が何を意味しているのかを知っている…」 とマーラーの走り書きがある。「君」とはほぼ確実にアルマのことであり、彼女の回想録によると、これは1908年冬にニューヨークでマーラーとアルマが目撃した、消防士の葬儀の印象に基づいているらしい。以下少し長いが回想録を引用する。
…セントラル・パーク沿いの広い通りで騒がしい音がする。窓から身を乗り出して見ると、下は黒山の人だかりだ。葬式だった-葬列が近づいてくる。…それは火事の際に殉職した消防士の葬儀だった。行列が止まる。代表者が進み出て、短い挨拶をするが、12階にいる私たちには、何かしゃべっているという以上のことは分からない。挨拶の後、ちょっと間をおいて覆いをかけられた大太鼓が1つ、鳴った。一同は音もなく、直立不動のまま-それから葬列は動き出し、式は終わった。この風変わりな葬礼は私たちの涙を誘った。おそるおそるマーラーの窓の方を見やると、彼も大きく身を乗り出しており、その顔には涙があふれていた。…
太鼓の鈍い衝撃と、引きずるような低音楽器の響きは、まさにこの葬列とそれを見るマーラーの心情を表しているのだろう。フルートによる痛いほどに清冽なメロディがつと表れ、盛り上がりながら発展して救われるかと思う場面もあるが、再び太鼓の「死の打撃」に遮られてしまい、結局導入部は葬送の音楽のまま消えていく。
その後アレグロ・モデラートの中間部となり、これまで演奏してきた各楽章のモチーフが代わる代わる引用され、戦い合う激しい展開となる。第1楽章で登場した「カタストローフ」の不協和音が再び鳴り響き、続いて第1楽章冒頭のヴィオラの主題がホルンに戻ってくる。この回帰を経て、曲は最後の終結部へ向かう。幅の広い7度跳躍が印象的な、穏やかなメロディが延々と重なりながら発展していき、クライマックスは確信に満ちた非常にドラマチックな盛り上がりを見せる。ここまでの過程を思うと、こんなに順当に幸せになって良いのだろうかと要らぬ不安に駆られなくもないが、もはや純粋に胸を打たれる。そこから次第に感情は緩やかになってゆき、遠くで微笑むようなコーダでついに曲が終わったかと思いきや、ラスト7小節で突如、弦楽器が再び湧き上がるのである。
<譜例3>
13度のグリッサンドで ff に到達し、最後の輝きを見せた後、ゆっくりと安らかに消えていく。この部分にマーラーが書き込んだ言葉は、
「君のために生き!君のために死す!アルムシ!」。
「アルムシ」は「アルマ」の愛称である。結局これが、交響曲第10番におけるマーラーからの最終的なメッセージであったということになる。それは決意と勝利の雄叫びなのか、はたまた絶望と諦念からくる遺言なのか。この曲においては、もはやそのどちらかに帰結させようとすること自体がナンセンスなのかもしれない。
初演:
(クック版第3稿)1972年10月15日、ウィン・モリス指揮、ニューフィルハーモニア管弦楽団
楽器編成:
フルート4(4番はピッコロ持ち替え)、オーボエ4(4番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット3、Esクラリネット(4番クラリネット持ち替え)、バスクラリネット、ファゴット4(3番、4番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット4、トロンボーン4、テューバ、ティンパニ(奏者2人)、大太鼓、軍楽大太鼓、シンバル付き大太鼓、シンバル、タムタム、トライアングル、グロッケンシュピール、ルーテ(むち)、ハープ、弦五部
参考文献:
前島良雄『マーラー 輝かしい日々と断ち切られた未来』アルファベータ 2011年
アンリ = ルイ・ド・ラ・グランジュ(船山隆・井上さつき訳)『グスタフ・マーラー 失われた無限を求めて』草思社 1993年
コンスタンティン・フローロス(前島良雄、前島真理訳)『マーラー 交響曲のすべて』藤原書店 2005年
村井翔『作曲家 人と作品 マーラー』音楽之友社 2004年
アルフォンス・ジルバーマン(山我哲雄訳)『グスタフ・マーラー辞典』岩波書店 1993年
船山隆『マーラー カラー版作曲家の生涯』新潮社 1987年
吉田秀和『決定版 マーラー』河出書房新社 2019年
シュレーカー:あるドラマへの前奏曲
■埋もれてしまった作曲家、フランツ・シュレーカー
フランツ・シュレーカーの作品は、オペラを中心に、このところ少しずつ演奏される機会が増えているが、それでもシュレーカーは、現在、誰でも知っているような作曲家というわけではない。しかし、シュレーカーが名声の頂点にあった1910年前後から1920年代前半にかけてのウィーン、ベルリン等では、彼のオペラはリヒャルト・シュトラウスに次いで数多く上演されるほどの人気だった。
1878年に生まれたシュレーカーは、4歳年上のシェーンベルクやフランツ・シュミットと同じ時代にウィーンで、またその後ベルリンで活躍した作曲家である。「グレの歌」のウィーン初演(1913年)を指揮したのもシュレーカーであった。同じ年のうちに本日演奏する「あるドラマへの前奏曲」が作曲され、翌1914年の2月に、フェリックス・ヴァインガルトナーの指揮、ウィーン・フィルのコンサートで初演されている。そのことだけをとっても、1912年にオペラ「遥かなる響き」(フランクフルトで初演)で大きな成功を収めていたシュレーカーが、ウィーンの音楽界でどれほどの地位にあったかを如実に示すものであったといえるだろう。その実力を買われて、1920年にはベルリン音楽アカデミー(現在のベルリン芸術大学)の校長に就任している。
そのように20世紀初頭のウィーンとベルリンで活躍し、高い評価を受けていたシュレーカーが、なぜいまでは一般的にあまり知られることのない作曲家になってしまったのだろうか。一つには、オペラを中心に活躍してきた作曲家にとって、20世紀に入って新作オペラの発表という意味が、19世紀のように市民の娯楽として広く期待されるようなものから変質してきたということもあるだろう。とくに第一次世界大戦以降、都市大衆社会が求めるものが大きく変化し、伝統的な音楽とあらたな音楽の潮流のせめぎ合いの中で、自分自身の芸術の立ち位置を強烈に示すことが困難になっていた。しかしそれとともに、ユダヤ人であったシュレーカーにとって大きな打撃となったのは、ナチスによって彼の音楽が「退廃芸術(音楽)」とされたことである。そのためにシュレーカーは音楽の表舞台からいったん姿を消すことになり、それが後世のシュレーカーの受容にとって障害となり続けた。
ナチスのいう「退廃芸術(entartete Kunst)」というのは、デカダンスの芸術ということではなく、ドイツ民族の人種的な優越性を掲げる人種理論から、モダニズムの芸術、社会主義的な思想をもつ芸術、ユダヤ人による芸術等を否定するために公的に用いられていた言葉だった。美術の分野では、「退廃芸術」とされた表現主義、シュルレアリスム、キュビスムなども、今日では誰もがこの時代の傑出した芸術の潮流として認めている。音楽でも、例えばシェーンベルク、ヒンデミット、ストラヴィンスキーなど、「退廃音楽」というナチスのレッテルとは無関係に、音楽史のうちに不動の地位を獲得している作曲家もいる。しかし、シュレーカーにとっては、このことは後の時代の受容にとって大きく作用することになった。時代の流れからすると、シュレーカーはかなり運の悪い作曲家といえるかもしれない。作曲家として実力が認められたときに第一次世界大戦が始まり、20世紀初頭(とりわけ戦後のワイマール時代)にはあらたな音楽の潮流に翻弄され、そしてナチスの「退廃音楽」というレッテルによる否定のさなか1934年にこの世を去って、その後、長い間そのまま顧みられることがなかったからである。しかし、生前のシュレーカーの名声はダテではない。いま、彼のオペラ等の作品をあらためて聴くと、シュレーカーがいかに傑出した作曲家であったかということを強く感じざるを得ない。
■オペラ「烙印を押された者たち」の「前奏曲」
「あるドラマへの前奏曲」は、第一次世界大戦後の1918年になって初演された彼のオペラ「烙印を押された者たち」のための「前奏曲」という位置づけの作品である。しかし、オペラで用いられている前奏曲は、この「あるドラマへの前奏曲」そのものではない。この作品は、オペラの実際の前奏曲として使われている部分を含みながらも、それをはるかに拡大した形式を備える独立した管弦楽曲となっている。時間で言えば、オペラの前奏曲よりも3倍の長さをもつ。
「あるドラマへの前奏曲」は1913年に作曲が完成しているが、オペラが作曲されたのは1913年から1915年にかけてである。シュレーカー自身による台本(リブレット)は1911年かそれ以前には書かれており(そもそものきっかけは、ツェムリンスキーが「醜い男の悲劇」を自分のために書いて欲しいという依頼であったようだ)、主要登場人物や場面のための音楽上の主題は、この「前奏曲」の作曲の時点でかなりの程度出来上がっていたにせよ、ともかくオペラそのものはそのあとになって完成されている。この「前奏曲」が「あるドラマ」のためのものとされているのは、オペラができていないこの時点では、あくまでも自分が書いた「戯曲(ドラマ)」のためのものであるという意味合いがまずあるだろう。それとともに、実際のオペラの前奏曲そのものとはならないという含みを、「あるドラマへの前奏曲」というタイトルのうちにもたせていたのではないかとも想像される。ちなみに、シュレーカーは自分のオペラの台本は、ヴァーグナーのようにすべて自分自身で書いており、その意味でも彼のオペラ創作は、オペラ史の中でも特別の位置を占めているといえる。
オペラがまだ発表される前にその「前奏曲」をウィーン・フィルの演奏会で初演するという状況にも興味深いものがある。上流階級の社交の場でもある新作オペラ発表に先立つこの「前奏曲」の披露は、今でいえば、新作映画を公開する前に作成されるトレーラーのような宣伝効果をもつものであったかもしれない。たしかにこの「前奏曲」では、まさに映画の「予告編」のように、オペラの話の筋の展開とは無関係に、印象的な主題が散りばめられ、独自の配置を与えられて構成されている。
前奏曲や序曲は、オペラの内容を予示するものとして、オペラの中のさまざまな主題を用いることが多い。「あるドラマへの前奏曲」も、できあがったオペラ「烙印を押された者たち」を聴くと、主要登場人物の主題や特徴的な場面の音楽がそこに縮約されていることがわかる。しかし、それとともに、この曲は、独立した管弦楽曲として独自の形式性を備えたある種の絶対音楽のような作品として作り上げられていることが、一般的な「前奏曲」とは大きく異なる。さて、そのオペラ「烙印を押された者たち」の中身だが、次のようなかなり強烈な内容のものである。
■オペラ「烙印を押された者たち」のあらすじ
イタリア北西部の港湾都市ジェノヴァ。町の有力な貴族の一人であるアルヴィアーノは、美と女性への強い憧れから、自らの財産をつぎこんで海に浮かぶ島を、噴水や彫刻を備えたすばらしい庭園「楽園(エリュージウム)」に作り上げている。だが、彼自身は背中が曲がり醜い容姿であるため、女性からは離れ、その島に足を踏み入れることもない。実は、この島の地下の広間には、性的狂乱(オルギア)のための洞窟(グロッタ)が作られており、貴族の友人たちはジェノヴァ市民の娘たちを誘拐してはそこに閉じ込めていた。この「楽園」は、もともとアルヴィアーノが考え出したものではあるが、彼は友人たちの目にあまる行状に我慢できず、この豪華な島をジェノヴァ市民に寄贈しようとする。悪事の露見を恐れる貴族たちは思いとどまらせようとするが、アルヴィアーノの考えは変わらない。相談している貴族たちのところに、美男子の貴族タマーレが遅れてやってくる。彼は、途中ですれちがった淑女を一目見て、恋の虜となっている。
島の寄贈の意向を受けて、ジェノヴァ市長が娘のカルロッタを連れてアルヴィアーノの邸宅にやってくる。このカルロッタこそ、タマーレが一目惚れした女性であり、彼は情熱を込めて愛を伝えようとするが、カルロッタは手玉に取るように言葉を交わしながらも、タマーレをまるで相手にしない。アルヴィアーノの邸宅での食事のあと、カルロッタはアルヴィアーノと二人だけになったときに、自分は絵を描いており、とりわけ魂を描こうとしているのだと語る。そして、実はそれまでにすでにアルヴィアーノの絵を途中まで描いており、欠けている顔と眼を完成するために自分のアトリエに来てほしいと願う。最初は障がい者である自分をからかっていると憤っていたアルヴィアーノも、本気だとわかり承諾する。(第1幕)
タマーレは、街で一番の有力者であるアドルノ公爵にカルロッタへの求婚の助力を求め、アドルノもそれに力を貸すことになる。タマーレは、求婚を断られた場合も、カルロッタを力でものにすると言う。
一方、カルロッタは自分のアトリエでアルヴィアーノと二人きりになり彼の絵を描いている。カルロッタの話から、彼女は心臓を患っていること、そのために愛(官能の力)を抑えているということも明らかになるが、カルロッタは自分が描いているアルヴィアーノに対する愛の言葉を口にし、はじめはなかなかそれが理解できないアルヴィアーノもついにそれを受け入れて、二人の情熱はたかまる。しかし、それでもアルヴィアーノは最後の一歩を踏み出すことができない。(第2幕)
「楽園」が開放されて、市民が島にやってくる。「楽園」は、古代ギリシアを思わせる牧神(パン)やバッカスの巫女など異教的でエロティックな雰囲気に満ち、信心深いまじめなキリスト教徒の市民たちにとっては受け入れ難いものに溢れている。市長とともにやってきたアルヴィアーノは、婚約したカルロッタの姿が見当たらないため落ち着かない。島を市に寄贈するということは、アルヴィアーノ自身の罪(地下洞窟のアイディア)を露呈させることにもなるが、自分自身は悪行に関わっていないので市民と市長の理解は得られると思っている。カルロッタは、絵を完成させて以来、自分に必要なものはアルヴィアーノからすでに与えられたと感じ、彼に以前のような魅力をみてとれない。彼女はそんな自分を忌まわしい存在だと感じている。島での祝祭の興奮の中で、タマーレはそのようなカルロッタをつかまえる。カルロッタは、タマーレに惹きつけられるように、二人だけの場所を求める。
一方、アルヴィアーノのところには、タマーレの計略による告発で司法警察がやってくるが、島の寄贈により英雄視されているアルヴィアーノに対する市民の信頼は揺るがない。アルヴィアーノは、司法警察とのやり取りで事の次第を察し、市民を引き連れて地下の洞窟に向かう。カルロッタは意識を失ってベッドに横たわっており、その横にとらえられたタマーレがいる。カルロッタが自らの意志で身体を捧げたというタマーレの言葉をアルヴィアーノは「嘘だ」と否定しようとし、タマーレの言葉によって激情にかられたアルヴィアーノはタマーレを刺し殺す。タマーレの叫びで意識を取り戻したカルロッタに、アルヴィアーノは「愛する人よ」と声をかけるが、カルロッタはそれを退け、タマーレの名前を呼びながら息絶える。アルヴィアーノはそれを聞き、狂ったように呆然とした言葉を発しながら去ってゆく。(第3幕)
■作品の構成
「あるドラマへの前奏曲」は、オペラ「烙印を押された者たち」の登場人物や物語の設定を表現する音楽であるとともに、実は全体がソナタ形式のような構成を備えた音楽として作り上げられている。
作品の冒頭、神秘的で繊細な伴奏音形(2台のハープ、ピアノ、チェレスタ、ヴァイオリンが二つの異なる調性で奏でる)にのって、ヴィオラ、チェロ、バスクラリネットによる瞑想的な旋律が始まる。この音楽は、オペラでは第2幕後半で、カルロッタがアルヴィアーノに愛を告白した後、彼に催眠術をかけるかのように語りかけ、絵の制作に没頭するときに使われている。二人とも、肉体的な制約にはばまれた、強い憧れと愛欲の力を暗く秘めている人物であり、その抑えられた強い感情が、付点を伴う跳躍の音形や、続くホルンの強奏(アルヴィアーノの主題)によって繰り返し表現されている。この部分が全体の導入部となっている。
続いて、突然アレグロ・ヴィヴァーチェの早いテンポとなり、ここからがソナタ形式の提示部にあたる部分となる。最初の少しばかりおどけたような、しかし華やかな音楽は、オペラでは第3幕で楽園島がジェノヴァ市民たちにも公開され、そこで異教的な仮装行列による祝祭が繰り広げられている場面で使われているものである。そのあと、シンバルも伴う非常に晴れやかで情熱的な音楽となる。これは、輝かしく生命力に満ち溢れた若い美男子の貴族タマーレの主題である。これがいったん収束するところまでが、オペラの実際の前奏曲として用いられた部分にほぼあたり、そしてまた、この作品にとっては提示部の終結するところとなる。
引き続き、展開部にあたる部分がはじまるが、ここでは提示部で現れた主題の展開だけではなく、あらたな不気味な音楽も現れる。ここは、第3幕の終盤、アルヴィアーノがジェノヴァ市民を地下洞窟に案内する舞台転換で用いられているスペクタクル的な音楽である。そこには、アルヴィアーノの暗い情熱の主題も絡み合っている。
このあと再びアレグロ・ヴィヴァーチェの音楽が始まり、ここからが「再現部」となる。かなりの程度、「提示部」と対応した音楽のあと、冒頭の主題が現れるコーダとなり、全曲が静かに締めくくられる。
初演:1914年2月8日、ウィーン楽友協会大ホール、フェリックス・ヴァインガルトナー指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
楽器編成:
ピッコロ、フルート3、オーボエ3、コールアングレ、クラリネット4(4番はE♭クラリネット持ち替え)、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン6、トランペット4、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ(奏者2人)、シンバル、シンバル付き大太鼓、小太鼓、トライアングル、タンブリン、カスタネット、グロッケンシュピール、木琴、タムタム(銅鑼)、低音の鐘(テューブラーベル)、ハープ2、チェレスタ、ピアノ、弦五部
主要参考文献:
Christopher Hailey, Franz Schreker 1878-1934: Eine kulturgeschicht-
liche Biographie. Böhlau, 2015.
David Klein, „Die Schönheit sei Beute des Starken“. Franz Schrekers
Oper „Die Gezeichneten“. Are Musik Verlag, 2010.
Rudolf Stephan, „Zu Franz Schrekers Vorspiel zu einem Drama“, in: Otto Kolleritsch (Hrsg.), Franz Schreker. Am Beginn der neuen Musik,
Universal Edition, 1978.
Th. W. アドルノ(岡田暁生・藤井俊之訳)『アドルノ音楽論集 幻
想曲風に』法政大学出版局、2018年
*シュレーカーを研究している声楽家・田辺とおる氏との対話、論文から、多くの教示・気づきを得た。また、多くの貴重な文献についても協力いただいた。
第264回演奏会のご案内
マーラー 9つの交響曲のその先へ
マーラーは交響曲に革命を起こした作曲家です。1860年に生まれドイツ後期ロマン派の最後の方で活躍しました。主要な作品は交響曲ですが、その規模や表現方法において革新をもたらし、9つの交響曲(「大地の歌」を入れると10曲)を完成させました。今では多くのクラシック音楽愛好家に支持され、どの曲も人気があると言ってよいでしょう。
マーラーはウィーン音楽院に学んだ後、指揮者としてのキャリアを積み、37歳にはウィーン宮廷歌劇場(現在のウィーン国立歌劇場)の芸術監督となり絶頂期を迎えます。49歳でニューヨーク・フィルの指揮者となり、交響曲第9番を完成させた後、さらにその先を行く交響曲第10番の構想を描き始めます。しかし咽頭炎を患い敗血症で亡くなりました。51歳でした。
未完の交響曲第10番は、第1楽章がほぼ完成しているものの第2~第5楽章は大まかなスケッチとして残されました。国際マーラー協会は第1楽章のみを出版しており、第1楽章単独で演奏されることが多いのですが、補筆によるいくつかの全曲完成版が存在します。中でもイギリスの音楽学者デリック・クックによるものが広く受け入れられています。
そもそも、マーラーは第10番のスコアを焼却するように妻アルマに言い残したらしいのですが、形見として残し自筆譜のファクシミリを出版しました。アルマの娘婿であるクルシェネクに補筆を依頼し、ほぼそのままの第1楽章と途中までオーケストラ譜ができていた第3楽章を補筆して完成させ、ウィーン・フィルにより初演されました。ファクシミリ版を見た何人かの人は、その音楽が感動的でかつ補筆可能と判断し、全楽章をオーケストラで演奏することを目指しました。その一人がクックで、1960年にBBC放送のマーラー生誕百周年を記念する特別番組で演奏され放送されました。それに激怒したアルマは演奏を禁止したものの、演奏テープを聴いたアルマは感動し禁止を解除、その後もクックは補筆作業を続け、非常に信頼性の高いものとして認められるようになりました。
シュレーカー ドイツロマン派のその先へ
シュレーカーは1876年生まれ、マーラーと同様にユダヤ人でウィーン音楽院に学び、指揮者をしながら作曲を行いました。
基本的に調性があるが高度な技法を取り入れた独自の作風で、指揮者エッシェンバッハは「マーラーの交響曲作りの書法を丸ごと新しいレベルに引き上げた」とも言っています。
主にオペラを作曲しており、その代表作が『烙印を押された人々』で当時は大変ヒットし、シュレーカー自身もウィーン音楽院の教授に任命され影響力を持つ作曲家になったものの、ナチスの弾圧にあい、失意の中脳梗塞で亡くなりました。55歳でした。
今回演奏する「あるドラマへの前奏曲」は、歌劇『烙印を押された人々』の完成前に、この歌劇の前奏曲に他場面の音楽を書き足して編纂されたものです。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
追悼 飯守泰次郎先生
飯守泰次郎先生が2023年8月15日に享年82歳にて逝去との訃報、あまりにも突然のお知らせでした。
最後にご一緒したのは、昨年4月29日の第257回演奏会でのブラームス交響曲第4番でした。そして2026年新交響楽団創立70周年に向けて、ご体調に配慮しつつ更なる薫陶を賜りたく、演奏会の機会を検討していたところです。
飯守先生とのお付き合いは、第193回演奏会(1993年4月24日)に始まります。当時、飯守先生はオランダ在住にて日本と行ったり来たりという状況でしたが、その後30年もの長きにわたり、自主演奏会で30回(コロナ過のため中止となった演奏会も含む)、芥川也寸志没後10年として埼玉県松伏町や上野の奏楽堂での演奏会2回含めて、数多くの演奏会でご指導いただきました。
飯守先生と演奏した曲は、ドイツ・ロマン派が多く、ワーグナー・ブルックナー・マーラーそしてシューマン・ブラームスとベートーヴェン、時々ドビュッシー・ラヴェルなどのフランス音楽、スクリャービンやヴィラ=ロボス、芥川也寸志をはじめとする数多くの邦人作品、現代の湯浅譲二など、多岐にわたります。
あらためて振り返ると、新響の節目、例えば創立40周年、50周年、60周年などの演奏会には必ず飯守先生がいらしてくださいました。特に芥川也寸志没後10年のオール芥川プログラム(第166回演奏会)をはじめ、ワーグナー楽劇「ワルキューレ第1幕(第151回演奏会)、「トリスタンとイゾルデ」(第195回演奏会・第244回演奏会)、「ニーベルングの指輪」ハイライトを含むワーグナーの諸作品や声楽を伴う大規模且つ意欲的なプログラムは、忘れることのない名演として練習の体験と共に私たちの記憶に残っております。
飯守先生は、故芥川也寸志が提唱された「音楽はみんなのもの」という理念に支えられた団員の自主運営と発想による活動に深い共感を示され、妥協することのない厳しい練習の中、深い愛情を持って真摯にご指導してくださいました。充実した練習の中、「自由を最大限に使いこなすこと」すなわちオーケストラ自身が一つの有機体となって高い音楽技術を持って音楽を創っていくことの重要性、音程・ハーモニー・フレーズ・調性の持つ意味合いを常に意識して「音を出す前に自発的な意思とイメージを持つ、新響はそれができると信じている」、と常にお話しされていたことを思いだします。ブルックナーの交響曲第7番の練習で、冒頭のヴァイオリンによる最弱音のトレモロだけで30分近く費やしたこともありました。
また、深い理解と共感を持って曲に臨むべく、数多くのインタビューを通して、修行時代からのご経験や、洞察力に充ちた音楽全般にわたる貴重なお話をお伺いいたしました。時には飯守先生との初リハーサルの前に先生自らピアノを弾きながら解説していただいたこともあります。
飯守先生の残されたメッセージは新響の大切な財産であり、今を活きる新響の演奏活動の根幹として私たちの心の中に活き続けております。
新響にとって「芥川也寸志」が生みの親、「山田一雄」が成長期の恩師であれば、「飯守泰次郎」は成長から成熟に向かう中での指導者で育ての親ともいえる存在です。先生のお名前は、ご指導いただいたことへの誇りと共に、永遠に刻まれていくことでしょう。
「ワルキューレ」のブリュンヒルデの如く、音楽という魔の炎に包まれて永遠の眠りについておられる飯守先生。生前のお姿を偲び、あらためて長年に亘るご貢献とご指導に心から感謝を捧げます。
安らかにお眠りください。

「ウィーン・楽友協会にて。飯守先生の指揮でチェロを演奏しました。」写真:坂入健司郎氏提供
ショスタコーヴィチ:交響曲第12番「1917年」
十月革命について
最初に、この曲の標題となっている「1917年」に起こったソ連の十月革命とその主導者レーニンについて、歴史的な背景とともに触れておきたい。以下にロシア革命に関する簡単な年表を記す。
| 1905年 | 血の日曜日事件: 交響曲第11番の題材、ペテルブルクで労働者の請願に対して軍隊が発砲。 第1次ロシア革命勃発。 |
| 1917年2月 ※グレゴリオ暦では3月にあたる | 二月革命: ロシア帝政の終焉。ブルジョワ立憲主義者を中心とした臨時政府と各地の労働者・兵士のソヴィエト(評議会)が成立する二重権力状態へ。 |
| 1917年10月 ※グレゴリオ暦では11月にあたる | 十月革命: 臨時政府消滅。史上初の社会主義国家であるソヴィエト政権樹立。 |
若き日のレーニンは社会主義革命の実現を目指すべく活動していたが、厳しく弾圧され国外に亡命していた。二月革命後の1917年4月に亡命先のスイスから帰国すると、ペトログラード(のちのレニングラード、現サンクトペテルブルク)で「4月テーゼ」を発表し「すべての権力をソヴィエトへ」という指針を提起した。その後、ロシア社会民主労働党のボリシェヴィキ派の指導者として兵士や労働者の支持を獲得し、1917年10月25日、ペトログラードの主な輸送機関や通信機関などを武力で制圧。さらに、臨時政府が置かれていた冬宮殿を占領して権力を掌握することに成功した。のちに全ロシア=ソヴィエト会議を開催し、臨時政府打倒とソヴィエト政権の樹立を宣言する。
補足になるが、ショスタコーヴィチの生きたソ連時代の社会主義体制にとって1917年の十月革命とは1991年まで続いた体制の発端であり、きわめて神聖にして汚すことのできない一種の「建国神話」だった。革命後、芸術のプロパガンダ的機能が重視されたこともあって、十月革命はソ連時代には芸術のテーマとして繰り返し用いられることとなる。ショスタコーヴィチも革命10周年を記念して交響曲第2番『十月革命に捧げる』(1927年)を作曲している。
作曲の経緯
十月革命が起きたときショスタコーヴィチは11歳だった。革命を導いたレーニンが亡命先からペトログラードに到着したときに行った演説を幼い作曲家が聞いたともいわれているが、真偽を巡っては今も議論が続いている。
この曲の構想が練られたのは古く、ショスタコーヴィチは1930年代には「レーニンに捧げる交響曲」を書きたいと発信していた。作曲の背景については諸説あるが、1960年の共産党入党が関連していると考えられる。
無論、作曲家自身が入党を望んだのではなく、党官僚の執拗な勧誘にやむなく屈した形だが、その忠誠の証にレーニンに捧げる交響曲の作曲を余儀なくされたというわけである。ショスタコーヴィチが1960年10月にラジオ放送にて発表した内容は以下の通りである。
「第1楽章では、1917年4月のウラジーミル・レーニンのペトログラード到着、苛酷な労働に従事する労働者階級との出会いを、音楽で表現するつもりです。第2楽章では、11月7日の歴史的事件を再現します。第3楽章では国内戦、第4楽章では大十月社会主義革命の勝利を描きます」
初演当時、入党したばかりの世界的な作曲家が十月革命とその主導者であるレーニンについての交響曲を書いたということで、聴衆の期待は高まり、大々的に宣伝された。しかし、ソ連の最高国家賞のレーニン賞を受賞した前作と比較して標題も抽象的だったせいか、初演時の評価はあまり芳しくなかった。
交響曲第11番(1957年作曲)との共通点は多い。作曲年代が近いこと、全楽章がAttaccaで切れ目なく演奏されること、革命の歴史と深く関連があり、ともに標題を持っていることなどである。
この2曲の大きな違いは時間的・編成的な規模にある。第11番は60分程度であるが、第12番は40分程度と短い。また、第11番は特殊楽器が多く使われている(ハープ、シロフォン、チェレスタ等)が、第12番はそのような特殊楽器は一切使われておらず、比較的編成は小さい方である。一見ブラームスかと思われるほど地味な編成のため、ショスタコーヴィチ特有の反骨精神に満ちた音が聴こえないのはかえって不気味な感じでもある。
交響曲第12番は、表向きには十月革命を記念しレーニンの偉業を称える交響曲であるということになっている。そのため,かつて西側諸国では,ショスタコーヴィチが体制に擦り寄って書いた駄作(!)という評価が支配的だった。音楽学者のレベディンスキーによれば、ショスタコーヴィチはこの曲をレーニンのパロディとして作曲していたが、直前になって考え直し、急いで書き直した結果、不本意な妥協作が出来上がってしまったという。作曲経緯については事実と虚構が入り混じって伝えられてきており、作曲家本人の真意が見えにくい状態である以上、解釈が分かれてしまうのもやむを得ないと考える。
これに対し「ショスタコーヴィチが体制に迎合する交響曲を書いた」ということを認めないファン心理が無意識に働かなくもないが、この曲は当初の作曲家の構想通り、レーニンの社会主義革命によってもたらされる「人類の夜明け」までを一息に描く、実は何の裏もない曲なのではないかと考えることもできる。
また、この曲の第1楽章の後半で暗示的に示され、第4楽章の終わりで反復されるEs(ミ♭)→B(シ♭)→C(ド)の音型についても諸説ある。これは終盤にベートーヴェンのごとく執拗に果てしなく繰り返され、そのたびに音楽が止まるため、演奏する側には体力と気力のコントロールが求められるものでもある。
ロシア音楽研究者の一柳富美子氏は、この音型がヨシフ・ヴィサリオーノヴィチ・スターリン(Иосиф Виссарионович Сталин)のイニシャルであるとの説を提唱している。また、ロシア文学者の亀山郁夫氏の解釈はさらに興味深い。
スターリンのEBのイニシャル、このラテン文字をキリル文字に置き換えたとき、EB(イョーブ)!—「糞食らえ、スターリン」の罵倒語になるというものだ。もしそうであるなら、やはりショスタコーヴィチは「二重言語」の作曲家であった、と妙に安心するような気持ちも生まれてくる。
楽曲解説
4楽章がそれぞれ標題をもち切れ目なく演奏される。
第1楽章 革命のペトログラード モデラート ニ短調
序奏部つきのソナタ形式。序奏部はモデラートで、悲壮感をたたえた低弦のユニゾンから始まる。やがてファゴットがアレグロで、発達した序奏旋律を出す(第1主題)。第2主題はベートーヴェンの「歓喜の歌」にも似て、低弦から各声部に歌い継がれていく。終盤で弦楽器のピッツィカートにより、新しい3音の動機(Es(ミ♭)→B(シ♭)→C(ド))が紛れ込んできて、交響曲の最後に重要な役割を果たす。
第2楽章 ラズリーフ アダージョ
三部形式。「ラズリーフ」はロシア語で「氾濫」という意味であり、レーニンがスイスから帰国後、革命のプランを練るべく潜んでいたといわれる近郊の湖の名前である。主部には、オスティナート風の旋律でショスタコーヴィチの音名象徴に基づく動機が現れる。弦楽器の澄んだ響きで始まる中間部の旋律は、将来の革命を暗示するかのように次の第3楽章の主題を先取りしている。
第3楽章 アヴローラ アレグロ
三部形式。巡洋艦「アヴローラ(オーロラ)」はネヴァ河から空砲で革命の合図を送ったと言われる。弦楽器のピッツィカートで奏でるのは「アヴローラの主題」である。それは描写音楽のようで、川面のさざ波を思わせる弦と打楽器のppをバックに第1楽章第2主題が現れ、アヴローラ号が人々の前にその姿をあらわす。音楽がfffのクライマックスを形作るとき打楽器が刻むリズムはアヴローラの号砲であり、ここからアヴローラのテーマの展開による力強い前進が始まる。
第4楽章 人類の夜明け リステッソ・テンポ ー アレグレット
まずホルンの燦々たる第1主題で始まる。これまでの主要主題がメドレーのように回想されるが、悲劇的な第1楽章の第1主題によって断ち切られる。フィナーレでは交響曲の主要なテーマが終極的には一つの多声合唱のようになり、朗々たる展開のなか、華やかに楽章を終える。
今回の演奏会は、録音や演奏機会のさほど多くない交響曲第12番を含めオールショスタコーヴィチで揃えられており、演奏者から見てもまたとないプログラムと感じている。この原稿を書いている8月9日(ショスタコーヴィチの命日である)時点ではまだ指揮者練習は行われていないが、新進気鋭の坂入氏がどのようなアプローチでこの3曲に向き合うのか、それによってどのような音楽が生まれるのか、今から大変楽しみにしている。
初演:
世界初演:1961年10月1日 エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮
レニングラード・フィルハーモニー交響楽団
日本初演:1962年4月12日 上田仁指揮 東京交響楽団
楽器編成:
フルート2、ピッコロ(3番フルート持ち替え)、オーボエ3、クラリネット3、ファゴット3(3番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ1、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、タムタム、トライアングル、弦五部
参考文献:
亀山郁夫『ショスタコーヴィチ 引き裂かれた栄光』岩波書店2018年
梅津紀雄『ショスタコーヴィチとロシア革命 ― 作曲家の生涯と創作をめぐる神話と現実 ―』総合文化研究所年報 第18号 2011年
梅津紀雄『ショスタコーヴィチ(作曲家別名曲解説ライブラリー)』音楽之友社 2005年
千葉潤『作曲家◎人と作品 ショスタコーヴィチ』音楽之友社 2005年
ショスタコーヴィチ:交響曲第9番
決死の皮肉とユーモア
ナチスやソ連当局による規制や弾圧を受け、道を断念したり活動の拠点を国外へ移したりした芸術家は数知れないが、そんな中ショスタコーヴィチは祖国に残り、スターリンや当局が掲げるイデオロギーに翻弄されながらも気丈に音楽活動を続けた。
19歳のときに作曲した交響曲第1番はソ連のみならず、海外の一流オーケストラや指揮者に取り上げられ、その後もレニングラードの誇りとして着実に名声を築いていったが、「プロレタリア文化協会(通称プロレトクリト)」の関係者などの嫉妬を買い、若くして異彩を放つショスタコーヴィチに対して嫉妬心を持つ関係者も一定数いたようで、平等を掲げる社会主義において一人が目立ちすぎるのはイデオロギーに反するといった声もあったとされる。
1930年代半ばにショスタコーヴィチの大ヒットオペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人」が各地でロングラン公演を続ける中、モスクワのボリショイ劇場にてスターリンが当作品を観劇するものの途中退席し、2日後にソ連当局の機関紙『プラウダ』にて「音楽の代わりの支離滅裂」と題する記事が掲載され、作品を痛烈に批判されてしまい、しばらく音楽活動の危機を迎えた(※1)。
1939年には第二次世界大戦が勃発し、この間もショスタコーヴィチは1941年に交響曲第7番、1943年には交響曲第8番を作曲している。1944年、ソ連が加わっていた連合軍側の戦況が良くなり、勝利が確実視されてきたころ、彼は勝利をテーマとした合唱付きの壮大な作品の創作を示唆する。当局や周囲の人々も、ベートーヴェンの「第9」に比肩するような華々しい作品を期待していた。友人の批評家に披露した1楽章のスケッチ(※2)もそのような期待に応えそうなものであったという。ところが、作曲を中断し、一から書き直して出来上がった曲は周囲の予想や期待とは大きく異なる、コンパクトな曲であった。全楽章を通しても30分に満たず、第7番や第8番の第1楽章と同等の長さでしかない。曲想も感動的というよりは、ユーモアがだいぶ溢れている。『プラウダ』紙上での批判を経験しており、この状況で茶目っ気を披露したら自分の身に何が起こるか、想像していなかったとは思えない。
世界的チェリストである夫・ロストロポーヴィチとともにショスタコーヴィチと親交が深かったソプラノ歌手・ヴィシネフスカヤの解釈としては、ショスタコーヴィチは自身の芸術家としての唯一の生存戦略を欺瞞に見出した。交響曲第5番の初演時も、作品があたかも社会主義的精神に基づく明るい未来を示しているかのように振る舞い、ソ連当局を満足させたという。
いくら皮肉屋であったショスタコーヴィチとはいえ第9番の創作においてなぜわざわざ音楽家人生を危機に晒すような選択をしたか、答えは本人のみぞ知るが、敬愛していたマーラーが恐れたように、ベートーヴェンから続く「第9」のジンクスを恐れたのだろうか。
案の定、1948年には交響曲第8番を中心に、第9番とともに、芸術分野での思想統制「ジダーノフ批判」の標的となり、『プラウダ』紙上での批判に続いて苦境に立たされるも、1953年のスターリンの死後、ショスタコーヴィチは不死鳥のごとく息を吹き返し、結果としては生涯で15曲の交響曲を残すこととなった。
第1楽章 アレグロ 変ホ長調 2/2拍子
「さながらハイドン」「新古典主義」といった言葉がつい浮かぶ、軽妙な楽章。不穏な和声や変拍子を挟むなど、ショスタコーヴィチらしい筆跡を随所に感じるが、構成としては提示部・展開部・再現部が律儀に登場する昔ながらのソナタ形式となっている。
戦争を抜きにして聴けば、トロンボーンの「ぱっぱーーーーぁぁぁぁ(スビト(急に)ピアノ)」といったとぼけたファンファーレに導かれるマーチ部分におけるピッコロの可愛らしい主題、後に幾度となく主題を再現しようとファンファーレを試みるも他の楽器群に「妨害」されながらなんとかヴァイオリンソロに繋ぐ様子など、喜劇を見ているかのような気持ちになる愉快な曲である。拍子が入り乱れて混沌とした状況を払拭すべく打たれる、大太鼓によるこの曲唯一にして渾身の大砲のような一撃も注目に値する。
長く続いた大戦を回想したり、膨大な数の犠牲者を弔うような感動大作を期待していたところ、戦争に勝っているのか負けているのか、そもそも戦っているのかすらよくわからない1楽章を聞いてソ連当局が大いに困惑したことは想像に難くない。
第2楽章 モデラート ロ短調 3/4拍子
ABABA形式。不規則に4拍子を挟みながらクラリネットが怪しげな主題を提示し、フルートとファゴットに移る。B部分では弦楽器がより規則的なひっそりとしたワルツ調の旋律を奏でる。楽章の締めくくりはピッコロがもの悲しげに旋律を吹いて終わる。
第3楽章 プレスト ト長調 6/8拍子
速く短いスケルツォ。またもやクラリネットが活躍し、1楽章の冒頭の下降系の分散和音を彷彿とさせる技巧的な主題を提示、中間部ではスペインの民族舞踊のような弦楽の伴奏の上でトランペットがソロを吹き、最後は楽器が減っていき収束する。
第4楽章 ラルゴ 変ロ短調 2/4拍子
3楽章から続けて演奏される。ABAB形式の単純な構成ながら、A部分における低音金管楽器の咆哮と、B部分ではファゴットによる祈りや弔いとも取れる長大なカデンツァとの対比が目覚ましい。
第5楽章 アレグレット 変ホ長調 2/4拍子
ソナタ形式。4楽章から続けて演奏され、ファゴットのさっきまでの深刻さはいずこへ、おどけた調子の「上がって下がる」第1主題を提示する。変ホ長調で始まり、愉快かと思わせ、すぐにハ短調で繰り返し、どことなく哀愁を帯びている。オーボエが提示する異国風情漂う部分に続き、ヴァイオリンが下降系のマーチ風な第二主題を提示する。展開部では急に加速したり、シンコペーションを交えて盛り上がり、減速して再現部に入りタンブリンも加わる。金管楽器が第1主題を華やかに吹き、続いてヴァイオリンと木管楽器が第2主題を朗々と、勝利のパレードのように再現する。コーダ部分ではまたテンポが急に上がり、そのまま駆け抜けるように文字通り「チャン、チャン」とあっさり終わる。
※1 この時期に作曲された交響曲第4番は新交響楽団が日本初演を果たしている。
※2 2003年に手稿の中から中断された第9番の初稿と思われる断片が発見されており、現在では録音も存在する。
初演:1945年11月3日レニングラードにてエフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、トライアングル、大太鼓、小太鼓、タンブリン、弦五部
参考文献:
千葉潤『作曲家◎人と作品 ショスタコーヴィチ』
音楽之友社 2005年
Hurwitz, D. Shostakovich Symphonies and Concertos – An Owner’s Manual. New Jersey: Amadeus Press. 2006
Vishnevskaya,G. Galina: A Russian Story. London: Hodder & Stoughton. 1985
ショスタコーヴィチ:バレエ組曲「黄金時代」Op.22a
1.芥川也寸志とショスタコーヴィチの出会い
新響が創設される2年前の1954年、ソ連の芸術をこよなく愛していた芥川也寸志は自作のスコアを携えて国交のなかったソヴィエト連邦へ密入国した。現代なら大きな社会問題になりかねない29歳の若者の大胆な行動は、なんとソヴィエト政府から歓待を受け、敬愛するショスタコーヴィチやハチャトゥリアンらと親交を結び凱旋帰国することとなる。
その時ショスタコーヴィチは、スターリン賞第1席やソ連人民芸術家の表彰を受けるなど、ソ連を代表する大作曲家となっていた。しかし、芥川が受けた印象は偉大で英雄的なイメージとは正反対に、絶えず周囲を気にする神経質で気の弱い感じだったという。
それは無理もないことで、彼が30歳の時に大好評を博していたオペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人」が、共産党機関紙『プラウダ』により批判され、さらに42歳の時には作品の内容が、社会主義リアリズム(社会主義を賞賛し、人民に革命意識を持たせるべく教育する目的を持った芸術)に合致していないというジダーノフ批判を浴び、レニングラード音楽院やモスクワ音楽院の教授職を解任されるなど作曲家生命の危機に陥っていたのである。
芥川に出会ったその時期は、スターリンを讃えたオラトリオ「森の歌」などの発表によりやっと社会的に復活を遂げた頃であり、オドオドした態度は偉大な作曲家という称号を得ながらもソ連という国で芸術家として生き抜くためには仕方のなかったことなのかもしれない。
2.若き日のショスタコーヴィチ
ショスタコーヴィチの父ドミトリィは度量衡検査所の技師であったが音楽好きで、音楽院でピアノを学んだ母ソフィアの伴奏でよく歌を楽しんだという。
そんな家庭環境に生まれたショスタコーヴィチは、9歳からピアノを始めたものの当初は商業学校へ通っていたが、いち早く彼の音楽的才能に気づいた母は11歳で音楽学校に入学させた。
彼はピアノのレッスンの傍ら作曲もはじめ、13歳で初のオーケストラ作品を作曲し、19歳で交響曲第1番を発表するなど、音楽院長であったグラズノフが「モーツァルト的才能」と絶賛するほどの天才ぶりだった。
さらに、1927年、20歳の時にはピアニストとして第1回ショパン国際ピアノコンクールにソ連代表として派遣され、その後も、交響曲第2番、第3番などの大曲を立て続けに発表するなど、20代前半にしてすでにソ連を代表する音楽家として順風満帆な道を歩んでいた。その後すぐに作曲家生命が危ぶまれることになることも知らずに。
3.バレエ音楽の依頼
1920年代の終わり、ソ連の劇場では古いレパートリーを更新する傾向が現れ、1929年レニングラード国立劇場は「ソ連の生活を称賛する新しいバレエ」の台本コンクールを開催し、映画監督A.イワノフスキーの「ディナミアーダ」(黄金時代)が入選した。
それまでのロシアバレエは、民話やおとぎ話を主題とする抒情的なものが多かったが、この台本は、勇敢なソ連のサッカーチームとそれを妨害しようとする西側のブルジョワ(ファシスト)の対峙という現代的な内容であった。
音楽は、すでに有名な作曲家であり、3つの交響曲やオペラ、数多くの器楽作品や映画音楽を作曲していた23歳のショスタコーヴィチに依頼された。彼は公式審判員の資格を持つほどの熱烈なサッカーファンでもあったため、サッカーを台本にした内容に戸惑ったものの夢中になって仕事に取り組んだという。
4.バレエ組曲「黄金時代」
新しいバレエ「黄金時代」は、ロシアバレエを見慣れていた人々を大いに驚かせた。
体操、アクロバットなどの奇妙な動きやボクシング、トランプ、サッカーなどのシーンがあったほか、カンカン、フォックストロット、タンゴ、タップダンスなど西洋音楽が盛り込まれ、お祭り騒ぎのようなバレエだった。
「黄金時代」は、観客には大いに受けたものの、ブルジョア風の気取った歩き方や振付けのけばけばしさが批判の対象となり、2年間でたった18回上演したのみで幕を閉じることとなった。
ストーリーは、1920 年代のヨーロッパの政治的および文化的状況を風刺的に描いたもので、ソ連のサッカーチームが西側の都市で開催された産業博覧会「黄金時代」に招待され、労働者たちに人気となるが、西側のファシストたちは彼らに八百長試合を持ちかけたり警察による嫌がらせをしたり邪悪な陰謀をめぐらす。ミュージックホールでの奇妙な踊りやスポーツ競技の光景などを織り込みながら、黒人のボクサーや地元の労働者たちとソ連サッカーチームは正しい思想に基づいて友情を築き、最後は、地元の労働者がファシストたちを打倒して、バレエは労働者とサッカーチームの力強い団結のダンスで終わる。
もともとバレエ音楽「黄金時代」は、37曲から構成される2時間余りの曲だったが、全曲版の演奏に先立って、作曲者自らその中の「序曲」「アダージョ」「ポルカ」「舞踏」の4曲をバレエ組曲「黄金時代」(作品22a)として再編し、初演した。
第1曲 序曲
幕が上がる前の序曲と、博覧会の見物客の入場。ショスタコーヴィチの典型的な作風である早いテンポのフーガと目まぐるしく変わるワルツやマーチにより、博覧会場の活気やさまざまなアトラクションが表されている。まるで映画音楽のような情景描写がショスタコーヴィチらしい。
第2曲 アダージョ
ファシストの美人ダンサー、ジーヴァが男たちを誘って舞う妖艶で官能的な踊り。ソプラノサックス、ヴァイオリン、フルートのソロが、いかがわしさたっぷりの頽廃した色っぽさを描写している。カデンツァを含む長大なバリトンのソロは、歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」のベッドシーンの音楽を思い起こさせる。
第3曲 ポルカ
ミュージックホールでの余興として披露される踊りの一つ。一向に進まない1927年のジュネーヴ海軍軍縮会議を風刺した踊りで、「間違った音によるポルカ」との異名を持ち、常に調子はずれの音が混じっているのが特徴的。「平和の天使」と名付けられている。
第4曲 舞踏
ソ連サッカーチームのキャプテンを誘惑しようと妖艶なダンスを踊るが、健全なソ連サッカーチームのメンバーは健康的で陽気な踊りを踊る。ハルモニウム(足踏みオルガン)と弦楽器によって団結した労働者とサッカーチームの踊りが元気なシンコペーションで奏でられる。

黄金時代初演の際のポスター(サンクトペテルブルク演劇音楽芸術博物館提供)

歌姫(ジーヴァ)とファシストのダンス(サンクトペテルブルク演劇音楽芸術博物館提供)
組曲版初演:
1930年3月19日 レニングラードにて アレクサンドル・ガウク指揮 レニングラード・フィルハーモニー交響楽団
楽器編成:
フルート、ピッコロ、オーボエ、コールアングレ、クラリネット、Esクラリネット、バスクラリネット、ソプラノサクソフォン、ファゴット、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、バリトン、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、タンブリン、タムタム、トライアングル、ウッドブロック、木琴、ハルモニウム、弦五部
参考文献:
レフ・グリゴーリエフ、ヤーコフ・プラデーク『ショスタコーヴィチ自伝』ラドガ出版所 1983年
ドミートリイ&リュドミラ・ソレルチンスキイ(若林健吉訳)『ショスタコーヴィチの生涯』新時代社1984年
森田 稔『ショスタコーヴィチ大研究』よりⅠ生涯とその時代 春秋社 1994年
千葉 潤『作曲家◎人と作品 ショスタコーヴィチ』音楽之友社 2005年
梅津 紀雄『ショスタコーヴィチとロシア革命 ― 作曲家の生涯と創作をめぐる神話と現実 ―』総合文化研究所年報 第18号 2011年
亀山郁夫×吉松隆『ショスタコーヴィチの謎と仕掛け』岩波書店WEBマガジン「たねをまく」
森田 稔 ONTOMO作曲家辞典 ショスタコーヴィチの生涯と主要作品」
黒くないクラリネットのおはなし
1.はじめに
タイトルの通り黒くないクラリネットのおはなしをします。クラリネットとオーボエは本体が黒くて、たくさんの銀色の金具(=キー:指が届かないところの孔を開閉できるようにすることで音域を広げたり♯や♭が多い曲の演奏を容易にしたりするメカニズム)がついている楽器というのが一般常識だと思いますが最近は本体が茶色や明るい黄色の楽器も見かけるようになってきました。新交響楽団の’23年4月のコンサートでドヴォルザークの交響曲第7番において本体が明るい黄色でキーは金色のクラリネットを私が使用したところ、団員と一部のお客様からあの黄色い(または白い)楽器はなんだろう?という声があったとのことなのでその楽器について書いてみようと思います。
2.古典クラリネットについて
最初に答えを書いてしまうと、黄色い木材であるボックスウッド(西洋柘植)(※1)で管体が作られているので黄色いのです。実は100年以上昔のクラリネットは主にこのボックスウッドで作られていました。その理由は、当時ヨーロッパで入手できた木材の中では特に組織が緻密で気密性が高く管楽器に最適だったからだそうです。(ザ・クラリネットClarinet Vol.77 P45) 。少なくとも19世紀後半まで、つまりロマン派の中頃までのクラシック音楽は主に黄色いクラリネットで演奏することを想定していたということになります。ちなみにブラームスが晩年にクラリネットの名曲群を作曲するきっかけをつくり、それらの曲を初演した名クラリネット奏者のミュールフェルト(1856-1907)もボックスウッドの楽器を愛用していたようです(https://oehler-spieler.jpn.org/akaiharinezumi.htm)。
右の写真3枚は私が所有する、モーツァルトが活躍した頃の楽器二種類とウェーバーが活躍したころの楽器です。いずれも現存する当時の実物や当時の文献を参考にして現代の工房で製作された複製品です。モーツァルトの時代の楽器(写真1)はキーの数が5個、また有名な五重奏曲や協奏曲などを吹くために普通のクラリネットよりも3度または4度低い音まで出せるよう音域が拡張されたいわゆるバセットクラリネット(※2)(写真2)では拡張低音域用の4個のキーが追加されています。またウェーバーの時代の楽器(写真3)は、キー5個の楽器と音域は同じですがキーが増えて11個になり半音階やトリルが演奏しやすくなっています。どれも本体はボックスウッドでできていて、キーは無垢の真鍮です。ちなみに現代の一般的楽器はリングキー(※3)もいれるとキーの数は20個以上にもなります。この古典バセットクラリネット(写真2)を9月17日の新交響楽団室内楽演奏会で演奏しますので興味のある方は是非お越しください。

3.グラナディラ材による現代の黒いクラリネット
現代の一般的な黒いクラリネットはアフリカ産のグラナディラという木材を使って作られています。素材の色はかなり黒に近い濃い茶色で黒に染色することも多いです。この材料でクラリネットが作られるようになったのは19世紀後半ころのようで、広く使われるようになったのはアフリカの植民地から多くの木材がヨーロッパに多量に入ってくるようになった20世紀にはいってからとのことです(ザ・クラリネット Clarinet Vol.77 P44、https://clarinetto.exblog.jp/i57/ など)。グラナディラはボックスウッドよりさらに密度が高く気密性も非常に高いので管楽器の素材として理想的だったのです。そんなわけで20世紀に入ってからはほとんどの中級機種以上のクラリネットは(オーボエも)グラナディラで作られるようになり100年以上が経過しました。ところが、このままの勢いで伐採していくとグラナディラは絶滅する可能性が高いということが判明し、国際条約で取引に一定の制約が課されるようになりました。とはいっても象牙のように新しい材料の取引は一切禁止というわけではないのでまだグラナディラの楽器は大量に製造されてはいます。でも多くの楽器メーカーがこのままグラナディラ一辺倒ではまずいと考えたのでしょう。最近他の木材によるクラリネットを販売するようになってきました。先祖返りともいえるボックスウッド材だけでなくモパネ材、ローズウッド材、ココボロ材などです。ただモパネ、ローズウッド、ココボロなどは希少な木材だそうでいくらでも取引できるわけではないのはグラナディラと同じそうです(ザ・クラリネット Clarinet Vol.77 P47)。世界最大のシェアを持つフランスのビュッフェ・クランポン社、ドイツの名門老舗のヴーリッツァー社や高級機種で躍進している新興のシュヴェンク&セゲルケ社などをはじめとして各社がボックスウッド材やモパネ材などグラナディラ材以外のクラリネットを販売しています。そしてNHK交響楽団の首席クラリネット奏者の松本健司氏をはじめとして日本のプロ奏者の複数の方がボックスウッドの楽器も演奏するようになってきました。
写真4はボックスウッド(現代)の楽器、写真5はグラナディラ(現代)の楽器です。両社とも同じドイツのメーカーのヴーリッツァー社のものでドイツ管の管体構造のクラリネットですが、キーメカニズムはエーラー式というドイツやオーストリアで用いられているものではなくてフランスで開発された現在一般的に普及しているベーム式のメカニズムを採用した楽器です(リフォームドベームと呼ばれています)。ボックスウッドのほうが上位機種なのでキーが少し追加されていますが基本的には同じキーメカニズムです。

4.ボックスウッドのクラリネットの特長
ボックスウッドの楽器が復活した理由が絶滅を危惧されているグラナディラの代替というだけであったらプロ奏者の方々が使用することはないでしょう。私もお気に入りのグラナディラの楽器を持っているので買い替える必要はありません。ボックスウッドの楽器の魅力はグラナディラの楽器では味わえない、暖かくて明るくソフトな音色、物理的な軽さと柔らかい吹き心地だと思います。それはまさに古典派からロマン派中期までの音楽にふさわしく、作曲された当時の音色に近い音ではないかと思うのです。
私事になりますが、どのような経緯でボックスウッドの楽器の魅力に気が付いてそれを手に入れることになったのかを書いてみたいと思います。私は以前より、モーツァルトの五重奏曲と協奏曲のオリジナル楽譜に書いてあったと言われる普通のクラリネットでは出せない低音域を、それが出せるいわゆるバセットクラリネットで吹いてみたいと思っていました。しかし現代のバセットクラリネットはこの二曲を演奏するだけしか用途がないのにもかかわらずとても高価なために買う気にはなりませんでした(A管として使用することは可能ですが)。そんなとき偶然、モーツァルトの五重奏曲を初演したと思われる楽器を復元した古典バセットクラリネット(写真2)をリーズナブルな価格で譲ってもらえる話が転がり込んできました。コロナ禍で外出も困難な時期、在宅勤務で家にこもっていてSNSを見る時間が大幅に増え、偶然そこで古典クラリネットの名手満江菜穂子さんと知り合ったからでした。即決で入手しました。現代の楽器に比べてかなり演奏至難ではありましたが初演者のアントン・シュタートラーが演奏したものとほぼ同じと思われる楽器(ただし現代に製造した複製品)でモーツァルトの五重奏曲をオリジナルのまま演奏できるようになりたいという気持ちと、オーケストラ活動休止と在宅勤務で通勤不要となった期間をうまく活用して毎晩練習し、そのなんとも言えない暖かくちょっととぼけた感じの音色に魅了されました。そして、新響の室内楽コンサートでモーツァルトの五重奏曲を演奏することができました。そんなとき、ボックスウッド製の現代の楽器が販売されているのを知りYouTubeで演奏動画も見たことで、古典楽器と音色が似ていてモダン楽器の機動性を備えたその楽器を入手してオーケストラで吹いてみたいと思ったわけです。2022年の初夏に入手に成功し、その秋にベートーヴェンのトリオ「街の歌」で本番デビュー、そして4月の前々回のコンサートにおいてドヴォルザークの交響曲第7番でオーケストラ本番デビューというわけでした。練習では共演者や指導者の方から暖かくてよい音がすると言われてとても嬉しかったです。一方でこの楽器の音色は、暗くて重たい雰囲気の曲や楽器の機能の限界を追及するような曲には向かないような気がします。例えばチャイコフスキーやショスタコーヴィチ、そしてマーラー、マメールロワ以外のラヴェルなどには向かないと思います。ということで今回(10月)はグラナディラの楽器を使用します。
音色の違いは、百聞は一見に如かずならぬ百言は一聴に如かず、その音色が聴ける動画をいくつか紹介します。最初の動画(演奏動画1)は、4月(前々回)のコンサートの曲目、ドヴォルザークの交響曲第7番の第二楽章冒頭のクラリネットのソロです。モダンボックスウッド⇒グラナディラ⇒古典ボックスウッドの順で吹いています。古典ボックスウッドはピッチがやや低め(A=430Hz)です。次(演奏動画2)は、前期ロマン派のブルグミュラー(ピアノ練習曲で有名なブルグミュラーの弟)のクラリネット曲の冒頭を比較演奏した動画です。この二つの動画でこれらの楽器の音色の違いをお分かりいただけるでしょうか。ただし演奏しているのが私なので違いは分かってもその素晴らしさは伝わらないかもしれません。そこで三つ目の動画(演奏動画3)はボックスウッドの楽器の魅力を最大限聴かせてくれる名人の演奏。比較動画ではありませんがボックスウッドの楽器の魅力がお分かりいただけると思います。
5.ボックスウッドのクラリネットを扱う苦労
最後にボックスウッドの楽器の難点をあげておきます。それはまさに20世紀以降、材質がグラナディラに取って代った理由といえるでしょう。吸湿・乾燥による体積変化がグラナディラより非常に大きいのです。クラリネットは最上部のバレル(写真2,3,4,5参照)、楽器の上半分の上管、下半分の下管そして最下部のベルの4個に分解できるようになっていて、演奏が終わったら分解してケースに納めます。それらを組み立てるには写真6のように凸部(左)を凹部(右)に差し込みます。凸部の外径より凹部の内径がわずかに大きめになっていて遊びがあり、凸部にはコルクが巻いてあるのでその膨らみによってきっちりと一体化するようになっています。コルクは弾力があるのである程度の力を加えれば回すことができますし、ピッチを調整するために少しだけ抜いた状態を保持もできます。ところがしばらく演奏しているとその部分がカチカチに固まってびくともしなくなってしまうことが頻繁におきました。息に含まれる水分を木材が吸収して膨張したため凸部と凹部の木部同士がきっちりとはまりこんでしまったというわけです。かなりきつくて演奏後にもう分解できないのではないかという恐怖を何度も味わいました。一度はどうにもならなくなって練習中の長い休憩時間に近くの雑貨屋でサンドペーパーを購入して凸部外径を削りました。それもあって最近は落ち着いた感じですがまだ油断は禁物のようです。
もうひとつ、吸湿による膨張と乾燥による収縮のために悲劇がおきました。昨年秋に室内楽コンサートの本番を終えたあとのことです。演奏終了後すぐに水分をとってケースに収納すればよかったのですが、スタンドに立てたままにしてちょっと目を離したらなんと楽器本体の一部に亀裂が走ってしまいました。大ショックでした。演奏時の息の水分を吸収して膨張した楽器本体は内側もまた外側もゆっくりと湿気を含んで膨張し管体内外の歪みが生じてもその応力に何とか耐えていたようなのですが、乾燥した室内で特に空調の風が楽器に当たったことで表面(特に外部の表面)が急激に乾燥して収縮し、まだ湿気を保っている部分との歪みが大きくなりそれに耐えられなくなったのだろうとのことでした。その部屋は空調が入ってるかどうかもわからないほどで風があたっているという認識は全くなかったのですがその説明が一番納得できます。たしかにカラッと晴れて10月末だというのにかなり暑い日でした。楽器の割れというのは結構あるトラブルで、演奏に全く支障がないレベルまで修理ができたとはいえやはりショックです。これからもこのリスクはグラナディラの楽器よりかなり高いとのことでひやひやものです。
最後に、これは苦労ではないのですがボックスウッドは使用して水分に接するとだんだん色が濃くなってくるようです。楽器の最上部のバレルと呼んでいる樽状の部品はピッチ(音の基準高さ)に応じて使い分けるものでこの楽器には長さが少し異なる三つが付属していました。いつも一番長いものを使ってきたところ段々内部の色が濃くなってきました。写真7は一度も使用していないもの(上)といつも使用しているもの(下)のバレルの内部の写真です。使用しているものの色が濃くなっているのがわかるでしょう。古典のボックスウッドの楽器は大体こんな感じの落ち着いた“あめ色”をしています。これは内部なので1年でこんな色になりましたが本体外部は直接水分に触れたりしないので変色するにしてもだいぶ時間がかかりそうです。白に近い黄色の本体に金メッキのキーも派手な感じで良いですが“あめ色”の本体も渋くていい感じです。楽器全体がいつかはこのような色になってくるのでしょうか?さて?何年かかるのか。それまで自分が元気にこの楽器を吹けていられれば良いのですが。
※1:ボックスウッドは日本産の柘植とは微妙な違いがあるようです。“柘植は、ツゲ科ツゲ属の常緑低木で、日本原産の植物です。一方、ボックスウッドは、ツゲ科ツゲ属の常緑低木で、主に欧州原産の植物です。両者は、葉幅や葉の形、葉色などが異なりますが、見分けることは難しいとされています(Wikipediaより引用)”。
※2:バセットクラリネットは普通のクラリネットの最低音(五線の下加線3本目の下のミ)よりも下のドまたシまでが出せる特殊な楽器です。モーツァルトの友人でクラリネットの名手アントン・シュタートラーの発案で当時の楽器職人テオドール・ロッツが製作したと伝えられています。モーツァルトのクラリネット五重奏曲と協奏曲のクラリネットパートそして歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」のなかの長大なアリアのオブリガートクラリネットパートはその楽器のために書かれ、普通のクラリネットでは出せない低い音が使われていたと推定されています。そのオリジナル楽譜やその楽器は現存せず当時の記事や楽器の絵が残されているだけです。それらの資料から推定されたオリジナルの音を出せるように現代のクラリネットを少し長く伸ばして低音が出るようにした楽器が多くのクラリネットメーカーからバセットクラリネットと称して製品化されています。
※3:リングキーは指で塞ぐ孔の周りにある可動式のリングで、孔を指で塞ぐとそこにあるリングキーも一緒に押されて、それと連動したキーにより別の孔も塞ぐことができるもので写真1,2,3の楽器にはまだありません。
第263回演奏会のご案内
今度の新響はショスタコーヴィチ祭り
ショスタコーヴィチは20世紀の社会主義体制の中を生き抜いた大作曲家です。1906年サンクト・ペテルブルクに生まれ、1917年のロシア革命を経験。スターリンに寵愛され社会情勢に敏感に反応しつつ、独自の作品を発表しました。スターリン死後は共産党員となり、1975年に病気で亡くなるまで作曲活動を続けました。暗く心にしみる中にも爆発力と推進力がある作品が多く、現在も根強いファンが多くいます。今回のコンサートでは、ショスタコーヴィチの初期、中期、後期の作品から1曲ずつ選びました。
バレエ音楽『黄金時代』(1930年)
初期の作品は前衛的な音楽が特徴で、西欧の革新的な技法や軽音楽の影響を受けていました。オペラおよびバレエ音楽は初期に書かれたものが多く、『黄金時代』もその一つです。
ある資本主義国で開催されている工業博覧会「黄金時代」に、ソ連のサッカーチームが招待され地元の人々と交流するお話。西側の人々を表すのにフォックストロットやタンゴといった当時西側で流行していた音楽を用い、ソ連市民は行進曲や歌謡的な音楽を用いて描き分けています。プロパガンダ的な要素が強いですが、ショスタコーヴィチのユーモアが効いています。今回は序曲、アダージョ、ポルカ、踊りの4曲からなる組曲を演奏します。
交響曲第9番(1945年)
スターリン独裁体制において「社会主義的リアリズム」が提唱され、中期の作品はこれに基づいた作品が目立ちます。第二次世界大戦中に書かれた戦争3部作の最後の作品ですが、7番や8番とは違い、短く室内楽的な作品です。このため、勝利を祝うベートーヴェンのような「第九」を期待していた当局から批判されることになりました。
交響曲第12番「1917年」(1961年)
1953年にスターリンが死去し、ソ連は「雪解け」の時代が始まります。激しい弾圧は終わり、限定的ながら自由も得られました。ショスタコーヴィチは8年ぶりに交響曲の作曲に取り掛かり、交響曲第4番などの初演もようやく実現しました。
交響曲第12番は「1917年」と標題がついています。1917年とはレーニンによる10月革命のことで、ソヴィエト政権は翌年3月に第一次世界大戦から離脱しました。元々レーニンを題材にした交響曲を構想していたのですが第二次世界大戦の勃発により計画がなくなり、20数年を経てソ連共産党大会で発表するために作曲されました。「体制に迎合して書かれた作品」として低く評価されることもありますが、そこはショスタコーヴィチ、しっかり聴きごたえのある作品です。
政治や戦争と結び付けて捉えられてしまうショスタコーヴィチですが、このような言葉を残しています。「芸術の中心にあるのはいつまでも人間であり、人間の精神的世界であり、人間の理念、理想、志向である。」
どうぞお楽しみに!(H.O.)
『タプカーラ』再考のとき
『シンフォニア・タプカーラ』を新響が演奏するのは、1979年改訂版の初演を翌1980年4月の第87回演奏会で行って以来、今回で17回目という。40年ほどの間にこれだけの頻度で演奏しているオーケストラは無く、初演に至る由来からみても自他ともに認める新響の十八番(おはこ)と言って良いのであろう。実際作曲者の伊福部氏が初演当初から練習に立ち合っている事もあり、その意図を最も体現した演奏を実現している筈である。あっても不思議はない・・・・あって欲しい(苦笑)。
だが、そうした恵まれた特殊な環境下で演奏している作品だからこその、敢えて言えば悪弊も頭を擡げないとも限らない。入団40年を超えた私自身も、初演を除くとほぼ全ての演奏を経験する僥倖を得てはいる。だが新響のこの曲に対する向き合い方の特殊性が、ともすれば古色蒼然とした後ろ向きのものになってはいまいか?という不安を覚えてもいる事をまずは白状しておこう。演奏の都度「本当にこのような音・このような演奏で良いのか?」との疑問をかねがね抱いて来た。自分でもなかなか整理がつかなかったその不安の由来を、今回初めて1番フルートを吹く機会に・・・・意外かもしれないがこれまでずっとピッコロを吹いており、フルートは初めてなのである・・・・改めて考えてみた。
◆新響入団のころ
1982年9月5日は新響のオーディションを受け、晴れて入団を果たした記念すべき日だ。25歳になる直前。今も鮮明な記憶がある。オーディションの事はまた別の機会に詳述する事を考えているので深くは触れないが、現在と違ってそれは練習の休憩時間に行われていた。つまり練習の合間に審査をする首席奏者以外の団員は全て部屋から出され、且つそれまでのセッティングのまま、自分のパートの席にお行儀よく座っているとは決して言えない各首席と指揮台との間に立たされ、ひと夏かけて練習したモーツァルトのニ長調の協奏曲を吹いた。現在のオーディションと違い、演奏を終えても拍手がある訳でもなし、終えていいものかも良く分からない(苦笑)。良い印象はないとあって、いくつかの曲折や軋轢もあったが、とにかく「サブトップ」という資格で入団を許された。本来はトップの席が空くのでその後任を採る事を目的としたオーディションだったから(事前にそう聞かされてもいた)つまりは補欠合格だった訳で、実はこれが後々まで境遇に影響するに至るのだが、とにかく入れば何とかなろうとの一心で対応。浅慮だったのである。
合格者は次の休憩時間を利用して団員の前で自己紹介の挨拶しなければならない。不合格者は自己紹介の必要もないので帰ってしまうから、まぁ勝ち残りという訳で、オーディション後の練習を聴く事になった。実はこの時初めて新響の音を耳にしたのである。伊福部氏の『日本狂詩曲』で作曲者も来ている。指揮は当然ながら芥川氏。ヴィオラのソロに始まる最初の楽章『夜想曲』は無難に過ぎた。次の第2楽章『祭り』に移る。クラリネットの軽快な走句の後に初めて強奏のテュッティとなった。
「!!!」 驚いた。
「なんでこんなに音が汚いんだ!!」
◆表現意慾と演奏技術
演奏者とは、常にその持てる技術の壁と向き合い、自分の表現を実現したいという欲求との間に折り合いをつける事を余儀なくされる立場にある。重要な事はこの折り合いをどのようにつけるかである。持てる「技術」と譜面から読取った音楽をこのように表現したいという「意慾」との関係性(バランス)を分類すれば、次の3点に絞られる。
①意慾>技術
②意慾<技術
③意慾=技術
単純な図式である。③が理想との予感は誰しもが抱くであろう。だが特にアマチュアの場合には①か②の状況にある。そして練習を通じて③に少しでも近づける努力を怠らない事がオーケストラの活動姿勢や運営を決定するのである。これは当然個人の次元でも同様で、そうした個人の考え方や努力の方向が、その集積たるオーケストラの演奏を性格づける図式となろう。
私は学生時代を通じ、②を徹底的に指導された。すなわち「自分の技術の内のりで表現をせよ」という事で、この徹底によって所謂『カラヤンコンクール』優勝(1978年)の形で実証されていた。欧米の音楽大学の現役学生(日本ではこうした学生は「アマチュア」とは見做されないが、彼の地では演奏でメシを食っていない学生は全てアマチュア扱い・・・・少なくともプロではない・・・・なのである)によって編成された複数のオーケストラを凌いでの優勝とあって、②の関係性を疑いの余地なきものと心得ていた。
個々の奏者のレヴェルでは敵いようがない。だが、例えばバトントスの技を磨く事で4人のリレー競技ならメダルも取れると同様のあり方が、オーケストラにも、否オーケストラだからこそ通用する事をその時知ったのだった。
例えばff(フォルテシモ)の強奏部分があるとすれば、それを演奏する各員は自分の持てる音量の幅の中で対応する。大きな音だからと言って音質が変わったり、況してや音が割れたりする事は許されない。それは既にその者の技術の範囲を超えている事(すなわち①意慾>技術)を意味する。これが自分にとっての「常識」だった。この日新響の音を聴くまでは・・・・。
新響のサウンドを汚いと感じたのは、このオーケストラが極限まで(そう、極限まで)①を突き詰める団体だったからで、瞬時にそれを感じ取る事は出来た。というのも先述のコンクール以後、その学生オケでも「表現意慾と演奏技術」のバランスを如何にするか?を巡っての議論が起こり、それは当然に運営や指導陣の人選までに影響を及ぼして、半年間に及ぶ事実上の活動停止状態をもたらした事を経験していたからだった。その時は「情熱か技術か」というスローガン?だったが、これは言葉こそ異なるが前述した①か②かいずれを優先するかを選択する議論にほかならない。我々は当然のように②をあくまで推し進め、最終的に①を信条とする連中が別のオケを作って袂を分けたが、当然我々からみて彼らは「異端」の存在だった。故に新響のオーディションを通ってからそうした異端の真っただ中に飛び込んでしまった事に肌身で勘づいたのだ。何を迂闊と言ってこれほどの迂闊もあるまい。芥川氏は「ボテボテのピッチャーゴロでも、一塁にヘッドスライディングする高校野球こそがアマチュアのあるべき姿」と広言し、新響にもそれを求めていると後で知った。せめてオーディションを受ける前に一度くらいその演奏を聴いておけよ・・・・その時になって自分を責めたが、後の祭り。
とはいえせっかくオーディションに通ったので「異世界」に加わった。大丈夫きっと何とかなる、とけなげにも信じていたのだ。翌年には1番フルートの席にも就いた(一応サブトップなので)。そこで自分の技術の範囲を守ってソロを吹くと「お前の演奏はおとなし過ぎる」という。はっきり「つまらない」とまでいう奴がいる。腹立たしさからどういう演奏なら良い演奏なのかを訊けば、気合が足りない、もっと気合を入れろという。ああ気合ね、案の定・・・・でも高校時代、全国大会の常連だった吹奏楽部で、上級生に散々気合を入れられて来たわが身にとっては、今でも最も嫌いな言葉だ。そこで「どうやったら演奏に気合が入るのでしょう?」と、その中身をもう少し具体的にご教授願えば、要は「音が割れてもいいから音量を上げ、ピッチも上ずるくらいに上げる」。そうした演奏の事らしい。冗談じゃない!
その瞬間オーディション時の事を思い起こした。そもそも補欠合格になった理由が「音が小さい」だったのだ。この話をしても今では団内の誰も信じてくれないが(笑)、これは正真正銘の事実。「音」といっているものの中味が、彼我で違い過ぎており、話が通じなかったのだと悟った(これも気づくのが遅い)。譬えて言えば、向こうは明日の仕事の事も終電の時刻も関係なく、潰れるまで呑んだその量を自分の酒量と言っているのだ。酒に関しては身に覚えはいくらでもある事ながら、こと演奏に於いてそのようなものを自分の「酒量」とは断じて受け容れられない。ギャップは海より深く山より高かった。
そしてひと度そんなギャップを悟ると、こんな音につきあう事をしなければならないくらいなら辞めようかと真剣に考え、別のオーケストラ結成にも参画した(今だから言うと、その団体とはいまも高レヴェルに活動を続ける『ザ・シンフォニカ』である)。
それでも辞めなかったのは、ある時から「自分の技術の範囲内での表現」と言いはしても、ではその自分の現在の「技術」とは一体どれほどのものなのか?と考え始めたからだった。技術の拡充を図る方法の具体性に疑問を持ったのだ。音量もその範疇にある。
大した技術もないその内のりで、ちまちまと表現して矮小な満足を得ているだけではこれ以上に進歩はない。むしろ異端の環境に身を置いた事を奇貨として、自分の技術の幅を拡げる場と捉えて対応する事を考えるべきでは?それでようやく毎週練習場に足を運ぶ自分に折り合いをつけた。
そうこうするうちに決定的な一事があった。『未完成』の練習の折の事だから1985年の入団3年目。1番フルートの席にいた。第1楽章の息の長いソロを吹くと、指揮の山田一雄氏が棒を止め一喝。「そこはもっと、切ったら血の出るような音で吹いてよ!」。「注意」ではない。はっきり叱られたのだ。いま新響を振るマエストロは誰しも団員を練習の場で叱る事は皆無だし、当の山田氏ものべつ幕なし怒っていた訳でもない。そしてこちらとしても相応に「気合」を入れて演奏していただけにこれは結構ショックではあった。「切ったら血の出るような音を出せ」って、つまり「お前の音には血が通ってない」っていう意味じゃないか。音に血なんか通うわけねぇだろ!!バカヤロー。呑んで荒れた。
更に2年後、『ダフニスとクロエ』のソロでは「エチュード(練習曲)みたいに吹いている」と、これまた有難くも手痛いご指摘を賜った。まったくなぁ。いずれにせよこうした事態を経験してこちらも意地になった事だけは確かである。本番までには血の通った音が出、「練習曲」に終わらぬ演奏が出来た事は、自分の名誉のため、敢えて付記しておく(因みに氏とはその後新響以外でも接点が出来、『アルルの女』のソロを吹いた折には当初から賛辞も得て、その後の共演を期待出来る段階に入ったが、直後に亡くなった)。
辞めずに済んだもうひとつの理由は、新響にも「意慾>技術」のあり方を見直そうとの動きが出てきた事がある。これは新響だけではなくアマチュアオーケストラ全体の気運でもあったと考えている。芥川氏の晩年には新響は技術的に(この技術とは合奏に於けるそれの事)行き詰まり、その打開策を模索していた。そこに高レヴェルの技術を持つ若い世代を迎え、彼らの技術相応の表現を具現化すべき変革は焦眉の急となっていたのである。当方の「信仰」に基づくノウハウの提案も漸く迎えられる土壌が出来たと言える。それまではいくら提議してもその都度無視され続けていたのだった。当時は既に首席奏者になっていたので、インスペクターや演奏委員長としての立場を通じても、その方向性を明確に打ち出す事が出来るようになっていた。
芥川氏の歿後数年にして、ハバロフスクからヴィクトール・ティーツ氏を招いた時に、その音に対する要求を目の当たりにして気づいたが、芥川氏は旧ソ連(ロシアも未だに伝統を引き継いでいようが)のオーケストラのサウンドを新響に求めていたように思う。それは金管楽器に最大限の音量を要求し、それをベースとして、弦楽器を始めとするその他のセクションにも対応し得る音量を求めるスタイル。これは体格も奏法も異なる日本人にはそもそも無理なものだった。音が荒れる訳である。
という次第で、その後の変革は必然的に急速に進んだと考えている。意慾と技術のバランスは抵抗なく「意慾<技術」に転換していった。もちろんこれは大局的な流れであり、細部を見れば今もいくらでも問題を見出せよう。だがこれまで述べたような流れを知る身としては、感慨を禁じ得ぬものではある。こうした自分の内側と、取り巻く環境の変化によって、辛うじて新響での命脈を保てたのだと今にして思う。
◆新響と『タプカーラ』の現状
長々と個人的な新響との距離感と、表現意欲と技術とのバランスの推移について書いたのは、こうした流れの中で頻繁に演奏され続けてきた『シンフォニア・タプカーラ』の現在について言及したかった為だ。正直に告白すると、私はこの曲の演奏に臨む都度、過去の亡霊を見る思いがする。どうした事かこの曲に代表される伊福部作品そして他ならぬ芥川氏の作品に限って、表現意欲が各員の持てる技術を超えてしまって、それを無意識に「是」として憚らない状況が繰返されて来ている。『シンフォニア・タプカーラ』という曲名を目にしたとたん「思考停止」のトランス状態になっているのでは?と考えざるを得ない演奏箇所がやたらとある。簡単に言えば相変わらず音が汚いのである。アンサンブルの観点からも、音程を確認するべき部分からも、音量のバランスから言っても時間をかけてじっくり取組む必要を感じるが、いつもそうはならずに終わる。
象徴的な話がある。芥川氏が亡くなった直後に行われた1989年5月の追悼演奏会での事だ。新響は『エローラ交響曲』を演奏したが、指揮をした外山雄三氏がリハーサルの冒頭に「新響さんで芥川先生の曲を演奏するのは、ベルリンフィルでブラームスをやるようなやりにくさがあるんです」と語ったのを記憶している。冗談半分の言ではあったが、意外な本音がそこには含まれていたように感じる。これは新響が伊福部作品、とりわけ『タプカーラ』を演奏する場合の、指揮者全般の心根にも通じるのでは?との想像をどうしてもしてしまう。
「新響だから『タプカーラ』は知り尽くしている筈。自分が殊更に何かを付け加える必要はない。それより他の曲の練習に時間をかけたい」
「変な汚い音がするけど、伊福部先生直々の指示に基づく、深い意味のある音なのだろう」
などと、明言はもちろんしないが、こうした考えが指揮者の裡に起こっても不思議はないような気がする。如何せん、かつては作曲者が必ず練習に立ち会っていたという、他に例を見ない特殊な団体なのだ(但し、伊福部氏ご本人は新響がどんな演奏をしようが「大変結構です」「お好きなようになさってください」しか言わない人だった)。という訳で指揮者は良く言って「新響にお任せ」、はっきり言うと腰が引けている。つっこみ不足な指揮者の姿勢は当然トレーナーの指導にも反映するから、やはり掘下げ不充分を来たしかねない。
そして対する新響も殆ど根拠のない「本家意識」を漠然と抱き、先祖返りのようなサウンド・・・・それを芥川氏以来の伝統とでも錯覚していようか?・・・・での演奏を繰り返す。という次第で、指揮者・オケ双方が真摯に作品の詳細を見直す事無くここまで来てしまった感がある。
恐らくは40数年間に17回、すなわち平均すれば2年に1回という演奏頻度も、作品との対峙に於いてマイナスに働いている要素となっているのではあるまいか?10年間は同じ曲を演奏しないという新響の選曲ルールは、作品に対する良い意味でのリセット感覚をもたらしているように思うが、伊福部(そして芥川)作品については当然の如くこのルールの適用外なのだ。時間をかけ、距離を置いてこの作品を見直す、という機会に明らかに欠けている。これは作品にとっても、新響にとっても不幸な事では?というのが偽らざる(あくまで個人的な)感想である。
使用している譜面にも大きな問題が内在している。現在団が保管し実際の演奏に使用しているパート譜は、1980年の改訂版初演に際し、作曲者の手書き総譜(スコア)から当時の団員個々が筆写した譜面である。初演に向けての全員参加・手作りの美談とすべきなのだろうが、写譜は相当に慣れた者が行っても誤りを生じるリスクは避けられないものだ。現に演奏の現場でこれまで数々の誤りが発見され、その都度部分的な訂正がなされてきた(が、全てを訂正しきれていない)。
更に現在流布している作曲家協議会編のスコアは、初演時の元となったスコアとは異なっている。指揮者の手元に置けるスコアは現在これしかない。その為現在指揮者のスコアと我々の手元にあるパート譜には無数といえる異同が存在し、本来であれば混乱を来してもおかしくないレヴェルと言える。「同床異夢」と言ってよいこの状態が表面化しないのも、この曲を巡るオケと指揮者の特殊な関係性に由来するように感じる。
団所有のパート譜には、改訂直後の初演に向けた練習の場で伊福部・芥川師弟の間のやり取りの結果決定した「改変」・・・・2回ある1拍ずつのゲネラルパウゼの一方を1拍増やした・・・・の跡が刻まれているが、現在のスコアはこの改変後の結果を記すのみなので、パート譜はその経過を刻む文献としての歴史的価値をもつ。とはいえ指揮者との齟齬(そご)必定の状況の譜面を使用し続ける事にはいい加減見直しが図られなければならない性格のものと考えるべきで、 実際個々のパート毎の対応が図られつつあるのが現状である。
60余年に亘って先人たちが営々と培ってきたものは貴重であり、最大限尊重されるべきで、それを否定するつもりは毛頭ない。
が、そうした歴史を踏まえた上で、こと『シンフォニア・タプカーラ』の現状については、新響との関係性に於いて、実は緊密な関係あるが故に顕在・潜在いずれにも様々な問題を抱える作品となっている事に、最近になって改めて気づかされた。
以上に述べた事は当然ながら演奏する側のあり方に属する問題である。聴く人が新響の『タプカーラ』に求めるべきものは当然ながら多様。「芥川也寸志と新交響楽団」時代の『タプカーラ』こそを至上至高の演奏として、「現在の新響」にそれを求めて会場に足を運ぶ人が今も一定数はいるに違いない。が、我々がオーケストラとしてあるべき方向性を追求してゆくと、そこで求められるものとの距離は隔絶する一方になる事を避けられまい。そしてその隔絶を恐れて根拠の薄い「伝統」に従う姿勢にも限界が来ている。
身近過ぎるほど身近にあることで、この作品との接し方に、我々は今後悩み続ける事になるだろうとの予感がある。芥川氏の謦咳に接した団員は現在では20人ほどか?当然今後は年々少なくなっていく。そうした流れの中で何を継承し、何を変えて或いは捨て去らなければならないか?についての結論を迫られている事に真摯に悩み、取組む時なのだ。
今回新響とのしがらみ?の無い、まさに次世代の中田延亮氏を迎えての『タプカーラ』の演奏が、その真摯な取り組みへの嚆矢(こうし)となる事を切に願う。
ファリャ:バレエ音楽「三角帽子」全曲
新響ではこれまで数多くの「バレエ音楽」を演奏してきた。以下にその一部を挙げた(数字は初演年):
・ストラヴィンスキー/「火の鳥」 (1910)
・ストラヴィンスキー/「ペトルーシュカ」 (1911)
・デュカス/「ペリ」 (1912)
・ラヴェル/「ダフニスとクロエ」 (1912)
・ドビュッシー/「遊戯」 (1913)
・ストラヴィンスキー/「春の祭典」 (1913)
・ファリャ/「三角帽子」 (1919)
・プーランク/「牝鹿」 (1924)
これらは新響が過去に演奏したバレエ音楽の半数近くを占めるのだが、かなり短い期間で一挙に生を受けていることに気付くはずだ。そう、これらの作品はすべて一人のロシア人プロデューサー、セルゲイ・ディアギレフ (1872-1929) との関係のなかで生まれたものである。
美術雑誌の主宰を足がかりに、大々的な展覧会の成功などでロシア芸術界における地位を高めていたディアギレフは、進出先のパリでも展覧会や演奏会を企画し、度重なる成功を収めていた。そんな彼がバレエ界に革新をもたらたすことになったのは、実は最大のパトロンであった大公ウラジーミル・アレクサンドロヴィチの死が契機であった。1909年にオペラを中心に予定していた演奏会を縮小せざるをえなくなった結果として、ヴァーツラフ・ニジンスキーやアンナ・パヴロワらを中心メンバーとするバレエ公演が実現し、これが実質的に「バレエ・リュス」(ロシア・バレエ団)の旗揚げであるとみなされる。バレエが芸術ジャンルとしては凋落しつつあったパリでは、総合芸術としての新境地を目指した彼の試みは大きな衝撃をもって迎え入れられた。
もっとも、彼は元々はバレエにそこまでの興味を示していなかったようであるが、これを機に意欲を高め、いよいよ新進気鋭の作曲家への新作委嘱に取りかかっていく。これによる一つの(そしておそらくは最大の)成果として、ほとんど無名に近かったストラヴィンスキーが、いわゆる三大バレエを通じて一挙スターダムにのし上がったのは周知のことである。しかし、委嘱先は必ずしもロシア人にとどまらず、先に挙げたようなフランス人作曲家たち、そしてレスピーギやファリャといった変わり種にも及んだ。ともかく、ディアギレフ、そしてバレエ・リュスが、ロマン派の完全な終焉によって混乱していた20世紀初頭のクラシック音楽界において果たした役割は底知れない。
ディアギレフがマヌエル・デ・ファリャ (1876-1946) への委嘱に至った詳らかな経緯は定かではないが、おそらくスペイン風味の作品を求めることでそれまでとは毛色を異にしようとしたのだろう。ファリャはもともと、パントマイム作品としてこの「三角帽子」を独自に準備していた(当初は「代官と粉屋の女房」という実に安直なタイトルであった)。そこへディアギレフからの依頼が来たものだから、都合は良かった。1917年にはいったんパントマイムとして20名足らずの小オーケストラによって初演されたが(指揮をつとめたのは奇しくもトゥリーナであった)、バレエとしての上演にあたって2管編成に拡張、音楽そのものも結局かなり書き換えられた。1919年に行われたバレエ版の初演時には、やはりスペイン人である、かのパブロ・ピカソが美術を担当したことは特筆に値するであろう。
バレエ音楽は当然ながら踊るために書かれているから、根底には愉しさが横たわっているものだが、そうしたなかでもこの作品は本当に天真爛漫で、底抜けの愉しさは群を抜いている。断じて難しいことを考えず、まずは目まぐるしく移りゆく音楽の流れに身をゆだねていただくのがよい。しかし、それは決してこの作品が芸術的に軽んじられてよいことを意味しない。細かい場面設定一つひとつが、音楽と密接に結びついて、鮮やかに表現されている。絶対音楽的な目線でも、一度聴いたらたちまち耳に残りそうな麗しい旋律群、クセになるリズムの扱い(特に随所で現れるヘミオラの効果は見事である)、独特の和声観などは、いずれも他国発のクラシック音楽には見受けられないものである。J.S.バッハは「フランス組曲」や「イギリス組曲」といった舞曲集を残したが、この作品はさながら「スペイン組曲」であると言えようか。
簡単に筋書きだけ述べておく。舞台はアンダルシア。主要な登場人物は代官(コレヒドール)、粉屋、そしてその女房のわずかに3人である。タイトルの「三角帽子」というのは、この代官が被っているものであり、社会的地位や権威を象徴するという。語感からはパーティーグッズのような様相が想像されてしまうが、実際には横からではなく上から見て三角形であるということだ。
この作品に登場する代官は、芸術作品におけるプロトタイプ的な権力者像としてご多聞に漏れず、やはりろくでもない好色男だ。粉屋の美人の女房に夢中になり、誘惑すべく昼下がりの製粉所に現れる。しかし、気の強い女房は「ファンダンゴ」を踊って誘惑しかえすばかりか、ブドウを手に代官をもてあそぶ。そこへ粉屋も現れ、代官を棒で懲らしめる。代官はその場を逃げ出し、夫婦はふたたびファンダンゴを踊る(ここまで第1部)。
その晩、近所の人々が華麗に「セギディーリャ」を踊っている。粉屋は人々に勇ましく「ファルーカ」を踊ってみせる。音楽がいささか不気味な雰囲気に転じると(ここで現れる有名な「パロディー」については、あえて伏せておこう)、なんと粉屋が無実の罪で警察に連行されてしまう。代官の罠にはまったのである。クラリネットが模倣する鳩時計が夜の9時を告げると、ふたたび代官が現れて「ミニュエ」を踊り出す。突如として音楽が騒々しくなり、代官がうっかり水路に転落するさまが表現されると、それを助けた女房との押し問答に入る。しまいには銃による脅し合いにまで発展し、女房が逃げだした隙に代官は家に忍び込んで、濡れた服を脱ぎ捨てる。
そのころ、這々の体で逃げ出してきた粉屋は、脱ぎ捨てられた代官の服を見て仰天するが、すぐさま復讐の策に思い至る。彼は代官の服に着替えてふたたび出て行ったのだ(ここまで第2部)。やむなく粉屋の服に着替えた代官は、逃げた粉屋を捜す警察らに袋叩きにされ、平和を取り戻した夫婦は近所の人々と陽気に「ホタ(終幕の踊り)」を踊り明かすのであった。
実はファリャは芥川先生のお気に入りの作曲家の一人であったらしい。1988年には新響でも、自身の提案によって驚異のオール・ファリャプログラムを実現させている(第119回演奏会。奇しくもこれが氏にとって最後の定期登場となった)。トリには「三角帽子」の第2組曲。練習ではどれだけキリが悪くても、残り時間が迫ると無理やり「終幕の踊り」に移り、実に楽しげに振っていたと伝え聞く。
氏の生前を知る団員もしだいに減りつつあるが、その精神は脈々と受け継がれている。言わずもがな「タプカーラ」ともども、氏の想いをも乗せた演奏会となることをどうかご期待いただきたい。
初演:
パントマイム版:1917年4月7日、エスラバ劇場(マドリード)にて
ホアキン・トゥリーナ指揮
現行版:1919年7月22日、アルハンブラ劇場(ロンドン)にて
エルネスト・アンセルメ指揮
楽器編成:
ピッコロ (フルート持ち替え)、フルート2 (1番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ (オーボエ持ち替え)、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、カスタネット、小太鼓、大太鼓、トライアングル、シンバル、タムタム、木琴、グロッケンシュピール、テューブラーベル、ピアノ、チェレスタ、ハープ、弦五部、メゾ・ソプラノ独唱
参考文献:
『ファリャ バレエ音楽《三角帽子》全曲』 全音楽譜出版社 2021年
濱田滋郎 『スペイン音楽のたのしみ — 気質、風土、歴史が織りなす多彩な世界への"誘い"』 音楽之友社 2013年
興津憲作『ファリャ — 生涯と作品』 音楽之友社 1987年
R.Buckle(鈴木晶 訳)『ディアギレフ — ロシア・バレエ団とその時代』 リブロポート 1984年
伊福部昭:シンフォニア・タプカーラ 改訂版
昭和15年(1940)に開催されるはずだった「東京オリンピック」は中止となった。それでも国威発揚を狙った「紀元二千六百年奉祝行事」は各地で行われている。あまり知られていないが「聖火リレー」もあった。『北海道樺太年鑑昭和16年版』1)の「明治神宮奉祝文聖火継走行事」の記事によれば、道内各方面から集まった「聖火」は7月7日夜に札幌神社(現北海道神宮)に到着、道内273市町村長の奉祝文が神社外苑綜合運動場にて北海道庁長官に渡され、続いて大イベント「聖舞頌楽祭」が行われた。記事には「伊福部昭氏の揮指(ママ)下に、札幌小樽全楽団の団員六百人が越天楽の奏楽あり、此れに勇崎愛子氏等の古典的な舞踊を配し、世紀の大聖行事は午後九時三十分終了」とある。
伊福部昭は26歳、当時すでに作曲家として知られ、当時の『音楽年鑑』2)にも「作曲家連盟員。札幌農大出身。チェレプニン賞一等入賞」と紹介されている。この日に演奏された「交響舞曲 越天楽」も自作だ。この受賞が作曲者として認められる契機となったが、北海道帝国大学農学部林学実科を卒業後、林務官として働き始めた弱冠21歳であった。当時の国家公務員(主に高等官以上)を収録した昭和13年(1938)の『職員録』3)には「北海道庁厚岸(あっけし)森林事務所農林技手 月63」とある。月給63円は現在の貨幣価値でざっと計算すれば約19万円。作曲は独学で、審査員名にモーリス・ラヴェルの名を発見し、見てもらいたい一心で送ったという。作品を東京で取りまとめた音楽関係者は、はるか道東の若い林務官による作品の破格さに当惑した。外してしまおうとの意見もあったが、送ってみればまさかの第1位。これがデビュー作「日本狂詩曲」である。
「聖舞頌楽祭」の年に林務官を辞しているが、音楽で食べていくのは厳しく、引き続き北大農学部の林学教室嘱託4)として勤めるかたわらの作曲活動であった。ちなみにこのイベントで舞踊を担当した勇崎愛子(本名アイ)とは翌年に結婚するが、伊福部の作品に「シンフォニア・タプカーラ」を含めて舞踊にかかわるものが多いのは彼女の影響が大きいようである。今から43年前の昭和55年(1980)4月6日、本日演奏する「シンフォニア・タプカーラ」改訂版初演時の当団のプログラム冊子5)に、当時65歳の作曲家自身が次のような言葉を寄せている。
作者は、アイヌ語でシャアンルルーと呼ぶ高原の一寒村に少年期を過しました。そこには、未だ多くのアイヌの人達が住んでいて、古い行事や古謡が伝承されていました。
タプカーラとは、彼等の言葉で『立って踊る』と云うような意をもち、興がのると、喜びは勿論、悲しい時でも、その心情の赴くまま、即興の詩を歌い延々と踊るのでした。
それは、今なお、感動を押え得ぬ思い出なのです。
その彼等への共感と、ノスタルヂアがこの作品の動機となっています。(以下略)
少年期を過ごした「シャアンルルー」を知るために、手元の『地名アイヌ語小辞典』6)に見出し語「an-rur」を見つけた。「あンルル」(ひらがなはアクセントを示す)は「反対側の海にのぞむ地方;山向うの海辺の地。――太平洋岸のアイヌは日本海岸を、日本海岸のアイヌは太平洋岸を、それぞれ「あンルル」と呼ぶ」とあった。「シャアンルルー」の「シ」は「①真の、本当の ②大きな」という意味をもつ。an-rurの項目に戻れば、「トカチの古名を「し・アンルル」si-anrur(ずうっと山向うの海辺の地)というが、それはイシカリ地方のアイヌがそう呼んだのだという」。十勝の音更(おとふけ)村(当時は河西支庁管内)で少年時代を過ごした作曲者だから、これに相違ない。
伊福部家は因幡国の一ノ宮である宇倍神社(現鳥取市国府町)の神官として古代から続く家である。その「66世」にあたる利三(としぞう)と母キワの三男として大正3年(1914)5月に生まれたのが昭だ。父の利三は慶応3年(1867)生まれで、明治23年(1890)に神奈川県警察の巡査となった。その後は日清、日露の両戦争に出征、戦後は同39年に北海道警察部へ移り、函館水上警察署長、倶知安(くっちゃん)警察署長などを歴任して大正3年(1914)3月に釧路警察署長に就任した。昭が生まれた時に利三は46歳で、同11年3月に54歳で帯広署長を最後に退職7)、翌年に音更村長となった。当時の市町村長は官選なので内務省人事の一環である。この時に昭は9歳。
明治政府は北辺の守りを堅固にするために北海道の殖民と開拓事業に力を入れていたが、先住民のアイヌにとっては大きな災難であった。土地を奪われて困窮するアイヌが増え、明治32年(1899)に「旧土人保護法」が施行される。土地を取り上げておきながら「保護」するのはアメリカの先住民に対する処遇と同様だが、狩猟採集の伝統的な生活から引き離しての「営農指導」に政府は熱心であった。9歳で釧路から帯広に近い音更に移ってきた少年は、自らの生活と文化を否定されながらも懸命に日々の暮らしを送るアイヌたちの歌や踊りを目の当たりにした。その肉声や旋法、リズムなどに大きな影響を受けたことは想像に難くない。
第1楽章 Lento molto-Allegro
ゆったりと時間が流れる広大なシャアンルルーのレント・モルト。やがて踊りを感じさせるアレグロが近づいてくる。タプカーラとはアイヌ語で「立って踊る」の意だが、3拍子の3拍目、4拍子の4拍目にアクセントがつく。「即興の詩」の字余り・字足らずが独特な興を添える。
第2楽章 Adagio
ハープの下降音型は夕暮れか。ゆったり流れる笛の調べ。音更村の大地に満ちていた空気を、コールアングレと名のつく西洋楽器が奏でる。
第3楽章 Vivace
始まりは「緊急地震速報」の元となったE-H-F-B-F-Gis-Bという不協和音(作曲者の甥・伊福部達東大名誉教授-音響学が採用)。短調でありながら、深刻かつどこか脳天気な雰囲気をも併せ持ちつつ、たたみかけるように突き進んでフィナーレ。
伊福部昭は平成18年(2006)にこの世を去るが、病床でも箏演奏家の野坂恵子に献呈する予定の二十五絃箏曲『ラプソディア・シャアンルルー』を構想し、書き始める直前であったという8)。失われてしまったアイヌたちの「ずうっと山向うの地」への想いは最後まで消えなかったようだ。(文中敬称略)
初演:
原典版:1955(昭和30)年1月26日 米国インディアナポリスにてフェビアン・セヴィツキー指揮 インディアナポリス交響楽団、翌31年3月16日に上田仁指揮東京交響楽団で国内初演
改訂版:1980(昭和55)年4月6日 東京文化会館大ホールにて芥川也寸志指揮 新交響楽団第87回演奏会-日本の交響作品展4
楽器編成:
ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トムトム3、小太鼓、キューバン・ティンバレス、ギロ、ハープ、弦五部
出典:
1) 『北海道樺太年鑑』昭和16年版 小樽新聞社編 昭和15年 p. 33
2 )『音楽年鑑』昭和16年度 大日本音楽協会編纂 共益商社書店 昭和16年 p. 119
3 )『職員録』昭和13年7月1日現在 内閣印刷局編 同 昭和13年 p. 796
4 )『現代出版文化人総覧』昭和18年度版 協同出版者編 協同出版社 昭和18年発行 p. 342
5 )「新交響楽団第87回演奏会-日本の交響作品展4 伊福部昭」プログラム 1980年4月6日
6 )『地名アイヌ語小辞典』 知里真志保 北海道出版企画センター 1956年
7 )『北海道人名辞書』再版 北海民論社 大正12年発行 p. 567
8 )ウィキペディア「伊福部昭」(出典『音楽現代』2006年4月 p. 95)
この他に伊福部昭公式ホームページ(暫定版)http://www.akira-ifukube.jp/を参照
トゥリーナ:幻想的舞曲集
1.スペインと音楽
スペインの音楽と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるだろうか。大半の人は、クラシック音楽ではなく、フラメンコを思い浮かべるのではなかろうか。確かにスペインには、ドイツやイタリアに比べ、バロックやオペラのような典型的なクラシック音楽は少ないかもしれない。しかし、ここには他国にはない混沌とした歴史があり、その地理的な事情も合わさって、数え切れないほどの民族音楽が存在する。フラメンコはその一つに過ぎず、中にはバグパイプを使う地域もあるくらいである。
スペインは地理的には、ユーラシア大陸の西端に突き出たイベリア半島に位置し、北にはピレネー山脈が、南にはジブラルタル海峡がある。南北からの文化の流入によって独自の文化が形成されつつ、大西洋からは対外的に文化を輸出することが可能だったと考えられる。
また歴史的には、イベリア族やケルト族の流入によりその土地の歴史が始まったと言える。バグパイプを使う地域があるのは、このケルト族の影響である。その後、ローマ帝国や西ゴート王国による支配だけでなく、イスラム勢力であるウマイヤ朝による征服もあった。多くの植民地を持つ大国を経験したかと思えば、アルマダの海戦をはじめとする数々の対外戦争による国力の衰退、そしてウエストファリア条約でのオランダ独立などによる国際的な地位の低下も経験した。このような、イベリア半島で多くの民族・宗教が入り乱れた歴史と、スペイン帝国の栄枯盛衰の歴史は、スペインの民族音楽と世界のラテン音楽を作るのに貢献してきた。と同時に、その経緯があったからこそ、たとえスペインがドイツやオーストリアのようなクラシック音楽大国でなくとも、民族音楽が国民楽派として変容した時、それはとてつもない勢いを持つことになり、聞き手もそのエネルギーを感じることを禁じ得ないと言える。
2.トゥリーナについて
19世紀のスペインでは、王位継承をきっかけとした3回に及ぶカルリスタ戦争を始め、無数の暴動が発生した。他のヨーロッパ諸国が栄えつつある間に、不安定な状態が続いたわけである。それに伴い、芸術の発展も遅れをとっていた。
そんな中、1882年にトゥリーナは生まれた。場所はセビーリャという、アンダルシアの中心都市である。彼はマドリードで学ぶ時期もあったが、1905年には学習の場を国外に移した。スコラ・カントルムという音楽学校があるパリの街である。そこで彼は作曲やピアノを学びつつ、デュカスやドビュッシーなどのフランス人作曲家とも出会っていった。しかし、1907年10月の演奏会において、彼は人生を変える出会いをする。イサーク・アルベニスという作曲家との出会いである。トゥリーナとアルベニスは、ファリャを含めて3人で話す機会があったようだが、ここで注目すべきは、3人全員がスペイン人であったという事実である。アルベニスが語るヨーロッパの音楽観に感化されたトゥリーナは、「ヨーロッパを見据えたスペイン音楽」を書いていこうと意を決するのである。そして彼はパリにいるうちから、スペインを題材にした作品を発表していった。1913年にスコラ・カントルムを卒業すると、第一次世界大戦もきっかけとなって、彼は翌年スペインに帰国した。それから数年経った1919年に書かれた曲が、今回演奏する「幻想的舞曲集」である。彼のスペイン音楽への決意を反映するかのように、スペインの民族音楽をふんだんに活かした作品となっている。
その後トゥリーナは、スペイン内戦により音楽活動を縮小したり、独裁政権の下で活動をしたりしたこともあった。しかし彼は確かに、セビーリャ人としてスペイン独自の音楽を大切にし、その発展に貢献したのである。
3.Danzas fantásticas 幻想的舞曲集Op.22
この曲は、まずピアノ曲として、しばらくのちに管弦楽曲として書かれた。各楽章のスコアには、とある小説から取られた文言が題辞として書かれている。ただしそれらの文言は、楽章の元のイメージになっているだけで、小説と曲に内容面での関連はないようである。むしろ、各楽章で全く異なる雰囲気を醸し出すそれぞれの民族音楽の方が、より重要だと思われる。
第1楽章 Exaltación 高揚
曲は静かに始まるが、注目すべきは途中から現れる3/8拍子である。これはピレネー山脈の南側に広がるアラゴン地方のホタという民族舞踊であり、この曲ではチェロとティンパニによってレとラが交互に鳴らされる中、木管楽器により旋律が奏でられる 。(譜例1)

譜例1
譜例の1小節目や5小節目では、「レーシーラー」と降りずに、「レーシドシラー」となっているが、これは歌唱でいうところのメリスマ(日本の「こぶし」に似た唱法)のような手法が現れているように思われる。単調な流れにつむじ風のような動きを付けることで味が出ており、スペインの民族舞踊によく見られるものである。
ホタでは、特徴的な衣装を着た男女二人が一組になり、両手に持ったパリーリョス(スペイン民族舞踊で用いるカスタネットのこと)で軽い音を小気味よく立てながら、かかとやつま先で軽やかなステップを踏む(図)。地面から飛び跳ねつつ回る動きにも上品さが見られる踊りであり、楽しそうだ。
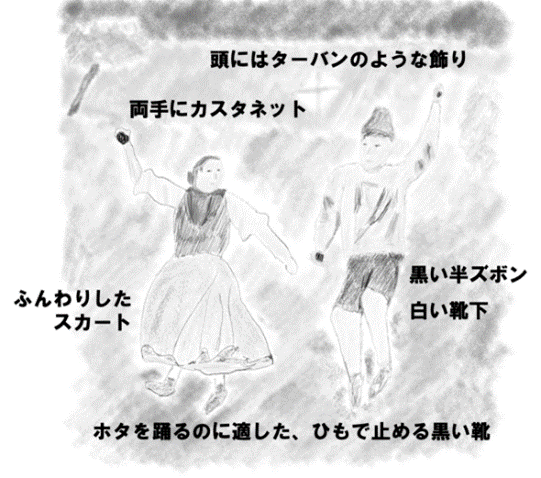
図: ホタの踊り
参加する楽器が増えていくと気分が高ぶるが、数小節かけてcediendo(徐々に速度が緩くなる)すると、次に木管楽器やホルン、ヴァイオリン、ヴィオラにより、横向きの流れを持った旋律が出てくる。(譜例2)

譜例2
楽章の後半に現れる同じリズムも、徐々に速度が緩んだのちに出てくる。その時はffで歌い上げられるためか、満を持して登場するように聞こえ、一気に視界が開ける。ニ長調の持つ、喜びを伴った明るい響きが溢れ出てくる。私はこの瞬間に、クラシック音楽とアラゴンのホタが融合するのを見る。
第2楽章 Ensueño 夢
特徴的な5/8拍子のリズムを持つ、ソルツィーコというバスク地方の踊りが展開される。
第3楽章 Orgía 狂宴/饗宴
迫力ある2拍子で前に進むフレーズが強いインパクトを持つ。一方で、落ち着きつつも楽しげな雰囲気が垣間見えるフレーズも聴き逃したくはない。そして全体を通して、ピアノ版より幾分か勇ましさが強調されているように聞こえる。文献により、ファルーカやカンテ・ホンド、パソ・ドブレなどの民族音楽の影響が様々に言及されているが、ここからも分かるように、それほどにスペインの民族音楽は多様性に富み、複雑だというわけである。なお、「狂宴/饗宴」という題とは裏腹に、トゥリーナによると本楽章は、「セビーリャのどこかの小さい家にあるごく普通の庭」での踊りのようである。
さて、ここまで読まれた方は既にお気づきかもしれないが、この曲は民族音楽を存分に使っているとはいえ、スペインの音楽のほんの一部に過ぎない。この曲を聞いて、束の間のスペイン旅行を味わっていただきたいと思うと同時に、スペインに存在する数限りない民族音楽に興味を抱くきっかけとしていただければ、この上ない幸せである。
初演:1920年2月13日 Bartolomé Pérez Casas 指揮 Orquesta Filarmónica de Madrid (Teatro Price in Madrid)
楽器編成:フルート3 (3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、鐘、シンバル、太鼓、グロッケンシュピール、トライアングル、ハープ、弦五部
参考文献:
Downs, L., Spanish dances and the piano music of Albéniz, Granados, Falla, Turina, and Mompou. The University of Oklahoma. 2010.
Draayer, S. R., Art song composers of Spain: an encyclopedia. Scarecrow Press. 2009.
Marco, T., Spanish music in the twentieth century. Harvard University Press. 1993.
上原由記音/濱田滋郎『粋と情熱 スペイン・ピアノ作品への招待』ショパン 2004年
ギルバート・チェイス(館野清恵訳)『スペイン音楽史』全音楽譜出版社 1974年
濱田滋郎『スペイン音楽のたのしみ 音楽選書』音楽之友社 1982年
読売日本交響楽団ホームページ 交響詩 <幻想舞曲集>プログラムノート
“https://yomikyo.or.jp/pdf/book/orchestra-201609-01.pdf”
(最終閲覧日:2023年5月23日)
オレゴンシンフォニーホームページ プログラムノート
“https://www.orsymphony.org/concerts-tickets/program-notes/1819/pablo-villegas/#Turnina”(最終閲覧日:2023年5月23日)
Turina, Joaquín. Danzas fantásticas. Jordi Masó. Naxos: 8.557150 (CD), tracks1-3. Recorded 2003. Liner notes for Danzas fantásticas, 2-4.
Turina, Joaquín. Danzas fantásticas. BBC Philharmonic. Chandos: 10753 (CD), tracks1-3. Recorded 2011. Liner notes for Danzas fantásticas, 6-7.
指揮者 中田延亮氏に聞く
今回の演奏会で初めて中田延亮氏をお迎えするにあたり、インタビューを行いました。音楽との出会い、演奏会へ向けた期待、指揮者としてのポリシーなど、興味深いお話をたくさん伺えましたので、どうぞご一読ください。
人生の方向を変えた「エグモント」の衝撃
■まず、音楽やオーケストラとの出会いからお話を始めさせていただきましょう。
子供の頃、ピアノを習っていた時期もあったのですが、あまり好きになれずに、やめてしまいました。音楽との本格的な出会いということになると、京都の中高一貫校に入学してオーケストラ部に入ったことがスタートになります。最初、楽器はチェロをやりたかったのですが、新入生の枠がすでに埋まっているという理由で断られ、連れて行かれたのがコントラバスの部屋。それが、その後ずっと自分の相棒となる楽器との出会いでした。
それから数か月後、地道な個人練習やパート練習を経て合奏に参加することができたのですが、初めてオーケストラの中で音を出した時のことは忘れられません。練習していた曲は、ベートーヴェンの「エグモント」序曲。冒頭、全奏でドーンという音が鳴るのですが、その音が出た瞬間、「俺たち、なんかすごいことをやってる」みたいな感動に震えました。まさに、その後の一生を変えてしまうような衝撃的な経験で、それから完全に音楽とオーケストラにハマってしまったわけです。
親が医師だったこともあり、色々と悩んだ結果、筑波大学の医学専門学群に入学しましたが、音楽家になるという道を諦めていたわけではありません。大学のオーケストラで活動していく中で、たまに同年代の音大生たちに出会うことがありましたが、音楽のことだけ考えて、それに打ち込める環境にいる人たちが羨ましくてしかたがない。音楽をちゃんと勉強したいという気持ちがどうにも抑えられなくなり、親を拝み倒して、筑波大学に籍を置いたまま桐朋学園のソリスト・ディプロマコースに通うことになりました。
■コントラバス奏者から指揮者へ向かわれた理由、ヨーロッパで活動され始めた経緯などをお聞かせください。
自分は音楽を演奏することが大好きで、コントラバスはその重要な手段であるものの、楽器そのものが好きでたまらないという感じではありませんでした。また、ある時スコアを見ながら思ったのは、「自分はこの曲がこんなに好きなのに、コントラバスのパート、いうなればスコアの1段分しか演奏できないのか」ということ。曲の全体に関わるには、オーケストラを指揮するしかないと思い至り、コントラバスの演奏と指揮活動を並行していく形になったのです。
奏者としては、新日本フィルハーモニーに首席として入団することができましたが、海外で勉強して帰国した同僚たちと接するうちに、今度はヨーロッパで音楽を一から勉強し直したいという気持ちが沸々と湧いてきました。またこれが抑えられなくなり、オーケストラに1年間の休みをもらってウィーンに行くのですが、いざ行ってみると、プレイヤーとしても指揮者としても、勉強すべきことが多すぎる。「こっちに腰を落ち着けてじっくり勉強しないとダメだ」と痛感し、新日本フィルを辞めて、滞在許可証と生活費を得るために定職を探すことにしました。
そんな時に、運よくバレンシアに新設される州立歌劇場のオーディションにコントラバス奏者として合格し、それからスペインに活動の拠点を置くことになったのです。
スペインの作曲家たちと伊福部 昭の底流に共通する「何か」を見つけたい
■今回の初共演を我々もとても楽しみにしていますが、 演奏会に向けて、どのような思いや期待をお持ちですか。
プログラムについては、自分の考えとオーケストラ側の希望を擦り合わせながら最終的にこの3曲に決まりました。スペインの二人の作曲家も伊福部先生も、ヨーロッパのクラシック音楽の中心や本流といえる場所から少し距離を置いた所にいたわけですが、中心とのつながりを持ちながら、自分の音を紡ぎ、オーケストレーションを磨いていったように思います。もちろん、 曲想やリズムの感じ方など、まったく違う部分が多いのですが、一緒に演奏することで、作曲家としての底流にある共通点や親和性のようなものを見つけていけるのではないか、と期待しています。
次に新交響楽団というオーケストラについては、長い年月しっかりとした活動を続けられていることが素晴らしいと感じています。世の中の状況は常に変わりますし、それはメンバーである皆さん一人ひとりにもいえることでしょう。たくさんの人が集まって初めて活動できるオーケストラが安定的な活動を続けるのは大変なことですし、長い時間を積み重ねて自分たちの歴史を創られてきたことはリスペクトに値します。特に邦人作品の演奏活動に関しては、伊福部先生をはじめとした多くの作曲家の作品が世の中に認知され、愛好されていくプロセスに大きな貢献をしてきたのではないか、という印象を持っています。
今回の「シンフォニア・タプカーラ」についても、この曲を最も多く演奏しているのは新響だと聞いています。きっと、曲に対するたくさんの思い出があり、イメージが醸成されているでしょう。ある部分では私の考えに近いものがあると思いますが、ある部分ではまったく違うかもしれません。それをリハーサルという過程で融和させていって、我々なりの答えを出していきたいですね。そういう過程を踏めることが、とても楽しみです。
■スペインの二人の作曲家について、またスペインの風土や国民性などについて、少しご紹介いただけますか。
まず、ファリャはスペイン全土で高く評価されている国民的作曲家といっていいでしょう。一方、トゥリーナは、彼の作品が持っている音楽的な重要さに比べて、ややマイナーな作曲家として位置づけられているように感じます。しかし、この二人はとても仲がよく、強い絆で結ばれていたようです。1900年代初めのスペインのオーケストラ音楽を共に築き上げていった戦友といっていいかもしれません。これは勝手な想像ですが、もしこの演奏会をファリャが空の上から眺めていたとしたら、自分の曲とトゥリーナの曲が異国の地で一緒に演奏されることを、とても喜んでいるのではないでしょうか。
スペインには15年間住んでいて、いまだに「行く」というより「帰る」という感じがする国です。風土に関していえば、とにかく天気がいい。私も仕事のことなどで悩んでいた時期がありましたが、部屋の中で鬱々としていても、外に出てカフェのテラスでコーヒーなんか飲んだりすると、もう5分後には、「まあ、いいか。色々と不安もあるけど、空は青いし、いま自分が生きていることにイエスと言おう」みたいな気分になるんです。
私がバレンシアに住み始めた時期は、リーマンショックの影響でスペインも不景気のどん底に陥っていました。しかし、そんな時でも街ゆく人々はにこやかで、街には笑顔が溢れていました。悲しいことや苦しいことはあるかもしれないけど、どういう環境であれ、自分がいま生きていることを積極的に肯定して、幸せに生きる。そういう心の持ちようをスペインで学んだように思います。住んで本当によかったと思っていますし、またいつか「帰りたい」と願っています。
音楽と社会のより良いつながり方を求めて
■いま指揮者として大切にされていることや、これからの活動についてのお考えなどをお聞かせください。
いまの自分として、指揮者という仕事の面白さや醍醐味を一言で表すとしたら、「コミュニケーション」という言葉に集約されるかもしれません。何かの曲を勉強していて、その素晴らしさに心打たれることはしばしばですが、実際に音にすることで、素晴らしさをオーケストラとも、お客様とも分かち合うことができます。そうやって、曲とオーケストラと聴衆をつなぐ、人とつながることに指揮者という仕事の本質を感じています。
それから、オーケストラとの距離感という面では、自分とオーケストラを含めて「我々」という意識を常に持っています。一人ひとりのプレイヤーは、ピアノの1つの鍵盤ではありません。それぞれに人生があって、一人の人間としてオーケストラという集団に身を置いています。演奏会をやるということは、指揮者とオーケストラが互いにリスクを取り合って前に進む冒険のようなものでしょう。開演時間が来て一緒にステージに上がれば、もう一蓮托生です。途中で多少の怪我があったとしても、みんなで一緒にゴールして、満ち足りた気持ちで聴衆の拍手に答礼したい。そういう指揮者でありたいですね。
最後に今後のことについての思いを少しお話ししましょう。我々はコロナ禍の中で音楽活動が「不要不急」という言葉で括られるという切ない思いをしました。その経験を経て、これからの社会に対して音楽がどのようにあるべきか、どうすればより良いつながり方ができるのか、そこで自分には何ができるのか、それを考え続けています。そのために何か新しい活動や、指揮者としての新しい在り方が必要になった時、それに積極的に向かって行ける勇気を持ちたいと思っています。
取材・原稿制作:田川 接也(ファゴット)
第262回演奏会のご案内
今注目の指揮者 中田 延亮
中田は1975年京都に生まれ、筑波大学医学専門学群(他大学の医学部にあたる)に進みました。在学中に音楽を志し、桐朋学園を経て新日本フィルハーモニー交響楽団の首席コントラバス奏者として演奏する傍ら、指揮の研鑽を積むという異色の経歴です。2006年からバレンシア歌劇場管弦楽団に在籍、その後もスペインを拠点に指揮者として活動していました。
日本人作曲家の作品に取組んでいきたいという中田との初共演には、新響が大切な作品として度々演奏している伊福部昭の「シンフォニア・タプカーラ」と、スペインの作曲家ファリャの代表作「三角帽子」を選びました。
日本の民族主義的作曲家 伊福部 昭
伊福部昭は北海道釧路に生まれ、小学生のときに父親が村長になった音更村(現在の十勝地方音更町)に移り住み、アイヌに接しました。タプカーラとはアイヌ語で「立って踊る」といった意味で、喜びの時も悲しい時も、その心情の赴くまま即興の詩を歌い延々と踊るアイヌの人々への共感と思い出が「シンフォニア・タプカーラ」の動機となっています。
北海道帝国大学で林学を学び、卒業後も林務官として勤務する傍ら作曲を続け、ほぼ独学で作曲家となりました。その後は管弦楽作品の他に「ゴジラ」などの映画音楽を残し、また教育者として多くの作曲家を育てました。当団創立指揮者の芥川也寸志も弟子の一人で、新響は伊福部作品を幾度となく取り上げ、その際の作曲家立ち合いのリハーサルは当時の団員の良い思い出となっています。
スペインの民族主義的作曲家 ファリャとトゥリーナ
バレエ「三角帽子」「恋は魔術師」などで知られるファリャはスペインの作曲家。アンダルシア地方のフラメンコに大いに影響を受け、マドリードで活動をした後にパリに7年間ほど滞在しデュカやラヴェルと交流を持ちました。ちょうど同じ頃にマドリードからパリに留学していたのが6歳違いのトゥリーナでした。2人は親友で、ともにスペイン民族的な音楽にフランス印象派が混在した作品を残しました。
「三角帽子」は、美人の粉屋の女房を気に入った代官が、手を出そうと言い寄るが、かわされて逃げていくというお話。ここでいう三角帽子はパーティで使うようなとんがり帽でなく、大きなツバに3つ角がある帽子で代官の権威の象徴なのです。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
ドビュッシー:交響詩「海」
印象派音楽
ドビュシーは印象派音楽の代表的作曲家とされている。そもそも印象派音楽とは何だろうか。その時代背景から見ていこう。
印象派の中心となったのは19世紀後半から20世紀初頭のフランスである。バロック期から19世紀中ごろまで音楽の主流はドイツであり、フランス・パリにおいても活躍するのはドイツ出身の作曲家ばかりであった。サン=サーンス、フランクらフランスで音楽を学んだ作曲家はそんな状況から「フランスにもドイツに負けない正統的な器楽文化を」という目的で国民音楽協会を設立する。国民音楽協会はソナタ形式や交響曲や弦楽四重奏曲といったドイツ風の堅牢な形式を導入しようとした。事実近代フランスの交響曲や室内楽の傑作はこの協会設立後の産物である。しかしサン=サーンスらの次の世代、ドビュシーやラヴェルのころになると、協会の方針を拒否し、フランス独自のアイデンティティを確立しようと、フランス的な「軽さ」を導入しようという動きが広がる。
さらにこの時代のフランス芸術は航海技術の向上により流入するようになった異国文化へ強い関心を抱いていた(エキゾチシズム)。絵画の印象派が日本の浮世絵に影響されたことは有名である。音楽においてもその傾向は見られ、この時期には異国の名を冠した曲が多数作られている。エキゾチックな要素が西洋の伝統的な語法を拡張、あるいは解体する方向へと作用していくのである。
こうして生まれた新たな音楽の作風を当時の批評家たちは絵画の印象派になぞらえて「印象派音楽」と呼ぶに至った。
印象派音楽と捉えられるドビュッシーの『春』を酷評したサン=サーンスは、古典的な音楽を取り戻そうとしつつもこう述べている。「近代の和声が基づいている調性は死の苦しみにある。それはもっぱら長調と短調の2種類だけであることのせいだ。古代の旋法が登場するであろう。そしてそれに続いて無限の多様性をもった東洋の旋法が音楽に入り込むであろう。(中略)そこから新しい芸術が生まれるであろう」。異文化の流入により新たな音楽の潮流が生まれる時代にサン=サーンスも葛藤しつつもそれを受け入れ、自身の曲に取り入れる姿勢を見せている(『動物の謝肉祭』の「水族館」、「幻想曲」)。
ドビュッシー自身も1889年のパリ万博でジャワや中国の音楽を聴き、強い影響を受けた。また「海」の初版スコアの表紙に葛飾北斎の『富嶽三十六景』のひとつ『神奈川沖浪裏』を採用している。
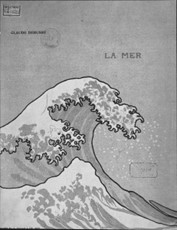
「『海』初版スコアの表紙」
印象派音楽とドビュッシー
しかしドビュシー自身は印象派であることを否定している。ドビュッシーの作風が世に知れ渡っていた1908年に出版者ジャック・デュランに宛てた手紙で自らの作品を「馬鹿どもが『印象主義』と称するもの」とした上で、次のように書いている。「この印象主義という用語は、とりわけ芸術における最も素晴らしい神秘的な創造主であるターナーにそれをまとわらせて憚らない美術批評家たちによって、可能な限り悪用されてきた用語です!」
「印象」という言葉はモネの『印象・日の出』という絵画に由来しており、この絵が風刺新聞に皮肉交じりに取り上げられた際に「印象派」という語で評された。この語には新たな芸術趣向を揶揄する意味合いが込められており、ドビュッシーもそれを快くは思わなかったのであろう。
ドビュッシーの音楽
ドビュッシーは印象派(impressionnisme)よりも象徴派(symbolisme)からの影響を受けているとされている。象徴主義芸術は人間の内的な形なき思想や観念を、神話や文学のモチーフを用いて表現する手法を用いている。象徴派の詩人たちと交流が多かったドビュッシーは、楽曲の題材として象徴派作家の詩に取り上げられるものをいくつか採用している(『月の光』『牧神の午後への前奏曲』)。
ドビュッシーは作曲法としては印象派音楽と共通するものを用いてはいるが、作曲の題材としては風景や日常生活などを題材とした印象派とは異なる趣向を持っていた。
サン=サーンスらの古典派志向の活動に反して、新たな趣向を持つ楽曲を発表していったドビュッシー。その様式を分類に当てはめて理解するため、当時の批評家たちは印象派という語を用いた。このカテゴライズが現代まで残り、ドビュッシーは印象派音楽の代表として認知されている。音楽史における時代転換の一役者として、ドビュッシーは時代の代表たりうるだろうが、印象派という分類に収まるかは疑問の残るところである。
ドビュッシーは後年こう語っている。「音楽はその本質からして厳格な伝統形式の中で流れることはできない。(中略)音楽は、色彩と時間にリズムを与えたもの」。この観念は『海』で実体化されている。
『海』ができるまで
『海』は1905年に初演された。1903年に指揮者メサジェに宛てた手紙には「私は次のような題を持つ3つの交響的素描を作曲しています。1:サンギネール諸島付近の美しい海、2:波の戯れ、3:風が海を躍らせる、総題は『海』です。おそらくあなたは、私が船乗りとしての素晴らしいキャリアを約束されていたこと、そして生活上の様々な偶然が私の進路を変えさせたにすぎないことをご存じないでしょう。それでも、私は彼女(=海)に対する情熱を持ちつづけてきました。」と記している。ドビュッシーは海兵隊員であった父親に船乗りになることを期待されていた。さらにこう続けている。「あなたは前述の作品に関連して、大西洋は必ずしもブルゴーニュの丘に打ち寄せはしないと私におっしゃるでしょう!…そして、それはまさに(画家の)アトリエで書かれた風景画に似たようなものだと!でも私には無数の思い出があります。私の考えでは、そちらの方が現実よりましです。」
フランス東部の内陸に位置するブルゴーニュにいてもドビュッシーの海への思いは強かったようだ。
『海』の解説
『海』には循環形式という方式が用いられている。循環形式は複数の楽章にわたって共通の主題や動機が用いられ、それが相互に関係しながら展開する曲の形を示す。循環形式に大きく寄与しているのが以下の2つの楽想である。一つ目は第1楽章冒頭のチェロの16分音符+付点8分音符の2度の動きである(A)。この動きは第1・3楽章の終結部で上下反転させた形でも現れる。二つ目は循環主題であり、Aに続けてコールアングレとトランペットによって提示される(B)。これらの主題は特に第1楽章と第3楽章で印象的に表れ、変容されていく。

「楽想A」

「楽想B」
これらの主題を軸として、しかし決められた図式に乗って変化していくのではなく、気付かないようなふとした音の動きがより大きな動きを誘い出して、次々に広がっていく。これが既存の形式ではない形を生んでいくのである。
第1楽章 De l'aube à midi sur la mer海の夜明けから真昼まで
(旧題:サンギネール諸島[注:コルシカ島西海岸]付近の美しい海)
コントラバスとティンパニのH音の背景にハープの5度音F♯と6度音G♯の響きからチェロによるAの音型が導き出され、この上へ向かう動きが続くヴィオラの上行音列の推進力となる。Aの逆付点のリズムとこの上行音列から様々な要素が紡ぎだされ、幾重にも重ねられて動きが加速しながら伝播していく。続けて、これらの音列とは相容れないBの循環主題が奏でられ、音楽は広がりをみせていく。
楽章の中ほどでAの楽想がチェロの4声の楽形へと発展し、後半部はこの波のしぶきを思わせる動きが主題となって進行していく。
終結部ではホルンによるBの3連のリズムに由来する調和を象徴するようなコラール風の主題が登場する。この主題は第3楽章でも用いられる。
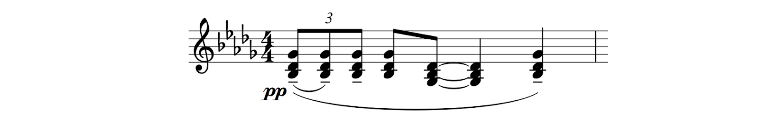
「コラール風の主題」
第2楽章 Jeux de vagues波の戯れ
この楽章は副題のとおり、戯れのように様々な主題が生まれては消え、消えては生まれる絶え間ない生成で成り立っている。それらの主題は複雑に組み合わさっているものの同一の原型を志向してはおらず、いかなる図式化も拒否する。この予見不可能な動きによって、この楽章は「絶えず一新される形式」と評される。
第3楽章 Dialogue du vent et de la mer 風と海との対話(旧題:風が海を躍らせる)

「低弦による動機」
冒頭は一陣の風を思わせる低弦による動機が提示されたのち、コールアングレとクラリネットによってAが、続けてトランペットによってBが奏でられる。しばらくすると第1楽章の終結部でのコラールが遠くに聞こえる。そしてAとBの楽想による再び凄まじい「対話」が行われたのち金管によるコラールを合図に、
すべての要素と縮小された循環主題が歌い上げられる。楽曲はfffのD♭の和音によって締めくくられる。
終わりに
海は絶え間なく変化し続け、同じ姿を見せることはない。その様子を表現したこの曲も同様である。オーケストラもリハーサルから何が変わるのか内心はらはらしながら演奏することとなるだろう。本日演奏される一度限りの『海』をお楽しみいただければ幸いである。
初演:1905年10月15日 カミーユ・ジュヴィヤール指揮 コンセール・ラムルー管弦楽団
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、コルネット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、トライアングル、シンバル、タムタム、ジュドタンブル(鍵盤付き鉄琴。本日はグロッケンシュピールおよびチェレスタにより演奏)、ハープ2、弦五部
参考文献:
菅原明朗 ポケットスコア『ドビュッシー・[海]』全音楽譜出版社 2008年
松橋麻利『作曲家・人と作品-ドビュッシー』音楽之友社 2007年
ステファン・ヤロチニスキ(平島正郎訳)『ドビュッシィ―印象主義と象徴主義―』音楽之友社 1986年
フランソワ・ルシュール(笠羽映子訳)『伝記 クロード・ドビュッシー』音楽之友社 2003年
フランソワ・ルシュール編(笠羽映子訳)『ドビュッシー書簡集1884-1918』音楽之友社 1999年
岡田暁生『西洋音楽史』中公新書 2005年
ミヒャエル・シュテーゲマン(西原稔訳)『大作曲家 サン=サーンス』 音楽之友社 1999年
ドビュッシー:交響組曲「春」
ドビュッシーと音楽の出会い
1862年、イル・ド・フランスにあるパリ西郊約20kmの町サン・ジェルマン・アン・レにてアシル=クロード・ドビュッシーは生まれた。ドビュッシーが8歳の頃、普仏戦争が起こった関係で、伯母と共に南フランスのカンヌへ疎開することになった。ここで、イタリア人ヴァイオリニストにピアノを教わることになる。ドビュッシーが音楽と出会った瞬間だ。圧倒的に蒼い空と果てしなく広がる海が見えるこの土地での体験が、音楽家ドビュッシーの感性を刺激した。
作曲家までの道のり
1871年、普仏戦争の講和に反対したパリ市民の反乱が本格化し、世界初の労働者政権であるパリ・コミューンが誕生した。この反政府軍に参加していたドビュッシーの父親だが、政府軍によってわずか2ヶ月で鎮圧され、牢獄につながれる身となってしまう。そこで出会ったのが、シャルル・ド・シヴリという音楽家だ。この父の出会いをきっかけにドビュッシーは、シヴリの母であり、ショパンの弟子でもあるモテ夫人にピアノを習うことになる。モテ夫人はドビュッシーの才能を見抜き、熱心に優しく質の高いレッスンを授けた。そして約1年の指導の末、ドビュッシーは競争率約5倍の難関を突破し、国立パリ高等音楽院に入学する。
当初はピアニストを目指し、学内コンクールでも年々上位の賞を獲得していき、順調にピアニストへの階段を上っているように見えた。しかし、気乗りしない試験曲を弾くことから、3回目のコンクール以降は賞が取れないこともあり、徐々にピアノへの熱は冷めていく。一方で、同時期に参加していたソルフェージュのコンクールでは、1回目の参加から頭角を現し、3回目で第1等賞を獲得した。そして、めでたく4年でソルフェージュのクラスを終えた後、和声のクラスに学んだ。この場でドビュッシーは自己を確立させていった。和声の規則を教われば教わるほど、それに納得できない自身の感性に目覚めていったのだ。この頃からドビュッシーは歌曲を作り始め、自ら歌い、友人たちに披露していたという。そうする間に、自らの発露の場は作曲だとの意を強くしていった。
20歳になると、フランスの若き芸術家たちの登竜門とも言われる「ローマ大賞」の予選を受ける。1回目の参加は予選落ちしてしまったが、翌年の2回目は第2等賞、そして翌々年の3回目でローマ大賞を受賞した。しかし、ドビュッシーにとっては、自分の信じる音楽と伝統的な様式との折り合いをつけることを学んだ成果ともなった。ローマ大賞を獲得したドビュッシーは、ローマのヴィラ・メディチへの留学権を得て、作曲活動に励むことになる。音楽家ドビュッシーの真の個性が表れるのはここからだった。
交響組曲「春」
この曲はドビュッシーがローマ大賞を獲得し、ローマへ留学していた時に作曲された。ボッティチェリの名画「プリマヴェラ(春)」と、絵画部門でローマ賞を受賞したマルセン・バッシェの同名の留学作品からインスピレーションを得て、「苦しげに誕生し、しだに花咲き、歓喜に達する自然の姿を描こうとした」といわれている。
当時ローマへの留学権を得たドビュッシーだったが、ローマでの生活は彼の性格には合わず、わずか2年でパリへ戻ることとなる。それゆえ、ドビュッシーの留学作品のうち、真にローマ作品といえるのはこの曲のみである。そして、作曲家として一本立ちしたドビュッシーの現存する最初の大規模な作品というべきものでもあろう。
元は管弦楽と2台のピアノに合唱を含んだ編成であったが、この版は製本所の火災で焼失してしまった。そのため、作曲から25年後にドビュッシーの指示を得たアンリ・ビュセールが、合唱部分を管弦楽に含めた新たなオーケストレーションに編曲し完成させた。本日の演奏はこの版によるものである。
第1楽章 Très modéré
この楽章は3つの部分に分けて考えられる。冒頭、嬰ヘ長調の主題がフルートとピアノのユニゾンで静かに始まり、短調に変化してヴァイオリンに受け継がれ、クレッシェンドと共に高揚し、展開されていく。続いて二つ目の主題が弦楽器により奏でられ、第2部へと移る。そして第2部の後半では、ヴィオラのソロを挟んで動きは活気を帯びていき、急速な下降半音階と共に静けさが戻り、再提示部となる第3部へ移る。一つ目の主題が転調を伴い何度も繰り返されて最高潮に達すると、全音音階がゆったりと引継ぎ、低音部によって再び二つ目の主題が歌われ、第1楽章は静かに終わる。
第2楽章 Modéré
概ね第1楽章の主題の変形から成立しており、前後2部に分けられる。まず、第1楽章冒頭の音群を変形した旋律が木管楽器によって奏でられる。その後、テンポがしだいに速くなり、ホルンとチェロに第1楽章の主題の変形が現れ、後半部が始まる。そして、スケルツァンドの主題では今まで現れなかった律動的な旋律が登場する。曲の終盤では、金管楽器が後半部冒頭の主題を高らかに鳴らし、その主題動機を圧縮した伴奏形を他の全楽器で奏して、曲は最高潮に達する。
初演:1913年4月18日 ルネ・バトン指揮 国民音楽協会(パリ)
楽器編成:フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2(2番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、シンバル、トライアングル、小太鼓、ハープ、ピアノ2、弦五部
参考文献:
音楽之友社編『最新名曲解説全集 補巻第1巻 交響曲 管弦楽曲 協奏曲』音楽之友社 1982年
NHK交響楽団編『N響名曲事典 第4巻』平凡社 1958年
松橋麻利『作曲家・人と作品-ドビュッシー』音楽之友社 2007年
ドヴォルザーク:交響曲第7番 ニ短調
ドヴォルザークの交響曲
アントニーン・レオポルト・ドヴォルザーク(Antonín Leopold Dvořák 1841-1904)は生涯に9曲の交響曲を書いている。
この有名な作曲家の姓は、日本語ではドヴォルザーク、ドボルザーク、ドボルジャーク等と表記が一定していないが、最近ではドボジャークと書かれることも多い。これはドヴォルザークの母語であるチェコ語の「ř」の音を日本語の音に正確に移すことが困難なことによる。(rの上のvはハーチェクという記号で一部の子音や母音について様々な音をあらわす。WBCチェコチームのユニフォームの胸元に「ČESKO」と記されていたのを見た人も多いと思うが、「C」の上についているのも同じ。)
「ř」の発音は、スラヴ語学の泰斗千野栄一の名著「チェコ語の入門」の説明によると、「Řはチェコ語の特徴的な音で、巻き舌のル(r)の音を調音点を狭めるようにし、なるべく前のほうで発音するときでます。」とのことなので、是非お試しあれ。(主に子音を出すときに呼気を妨げる位置:筆者注)ただし、チェコでも子供にとってはこの発音は難しいらしく、できない場合は学校で特別に居残り練習をさせられるとのことなので、日本語話者の我々が出来なくても全く気にすることはない。筆者の耳には、「ドヴォジャーク」がチェコ語ネイティブの発音に比較的近いように聞こえるが(これだとDとvの間に母音oが入っているように見えてしまうのが残念ではあるが)、所詮音韻体系の異なる別言語同士で正確に音を移すことはできないので、以下、ドヴォルザークで通すこととする。ちなみに、「á」でaの上についている記号はチャールカと呼ばれる記号で、母音の上について長母音「’」を表す。
1865年に書かれた第1番から、最後の交響曲第9番「新世界より」が作曲された1893年に至る28年間に、創作活動の節目に、9つの交響曲が書かれている。ベートーヴェン、ブルックナー、マーラー等と同じ9曲ではあるが、これら3人の作曲家の場合、1番、3番等の番号の若い作品も世界中のオーケストラの通常のレパートリーになっており、どの作品も比較的偏りなく取り上げられているが、ドヴォルザークの場合はやや事情が異なっている。もっぱら演奏されるのは最後の2曲の9番「新世界より」、8番で、あとはたまに本日のように7番が取り上げられるだけで、5番、6番が演奏される場合は小さな事件になり、1番から4番の生演奏に接したことがある人はチェコ・フィルハーモニー管弦楽団の楽団員以外にはほとんどいないのではないかといった状況になっている。
8番、9番の演奏頻度が高いのは、この2曲はドヴォルザークのみならず古今東西のあらゆる交響曲のなかでも傑出した作品なのでもっともな面はあるが、本日の7番をはじめ、ブラームスの交響曲第2番を彷彿とさせるニ長調交響曲第6番や、「ワーグナー」という名で呼ばれることもある変ホ長調交響曲第3番など、もっと頻繁に演奏されてよいのではないかと思う。
古楽演奏者でモダンオーケストラの指揮者でもあったニコラウス・アーノンクールによれば、入念な準備と十分なリハーサルが必要な割にはうまくいかないため指揮者が避ける交響曲がいくつかあって、ベートーヴェンの第4番、シューベルトの第4番等と並んでドヴォルザーク7番もそのような曲とみなされているとのことである。
なお、交響曲第7番はかつて第2番と呼ばれていたことがあり、新世界交響曲も古いLPレコードのジャケット等に交響曲第5番と記されているものがあるが、これは作曲者の生前に出版された交響曲が現在の5番から9番までの5曲のみで、しかも出版社が必ずしも作曲順ではない番号を割り振ったことによる。新旧番号の対比は次の通り。旧番号→現行番号:1→6 ニ長調 作品60(B.112)、2→7 ニ短調 作品70(B.141)、3→5 へ長調 作品76(B.54)、4→8 ト長調 作品88(B.163)、5→9 ホ短調 作品95(B.178)「新世界より」。
1893年の新世界交響曲を最後に交響曲は手がけておらず、晩年はオペラの作曲に注力したドヴォルザークであるが、1896年から1897年にかけて管弦楽作品では5曲の交響詩を作曲した。そのうち4曲は民族的バラードに基づく一連の作品で、1曲はグスタフ・マーラーの指揮で初演された、リヒャルト・シュトラウスを想起させる「英雄」をタイトルに含む作品である。これらの作品もドヴォルザーク晩年の円熟した管弦楽の書法に裏打ちされたいずれ劣らぬ素晴らしい作品であるが、やはり日本では演奏される機会が少ないのは大変残念である。是非とも一聴をお勧めする。なお、新交響楽団では第247回演奏会(2019年10月13日 指揮/寺岡清高)にて全5曲を取り上げている。
交響曲第7番 ニ短調
交響曲第7番には少し先輩のヨハネス・ブラームス(1833-1897)の影響、特にドヴォルザークが作曲の直前に初演に立ち会ったその第3交響曲(ヘ長調 作品90)からの影響が強くみられることは夙(つと)に指摘されているが、この両者の関係は、第7番作曲の10年ほど前にさかのぼることができる。ドヴォルザークは1874年からウィーンの文部省の奨学金に応募、数年にわたり給付を受けているが、その選考に際してはブラームスが強く後押しをしていたことが知られている。また応募に際し提出された「モラヴィア二重唱曲集 作品20 B.50」に深く感銘を受けたブラームスはこれをドイツの有名な音楽出版社であるジムロック社に紹介し、それ以降ドヴォルザークの作品は同社から出版されることになる。
引き続き「スラヴ舞曲集第1集 作品46 B.78」「ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品53 B.108」「交響曲第6番ニ長調 作品60 B.112」等の名作が次々に出版されていった。これはそれまでチェコの中では知られていたものの、まだ無名であったドヴォルザークが国際的に知られることのきっかけとなった。このようにブラームスの知己を得たドヴォルザークの作品は、ヨーゼフ・ヨアヒム、ハンス・リヒターなど、ブラームスとの関係が深い著名演奏家たちの取り上げるところとなり、次第にヨーロッパ大陸を超えてイギリスでも知られるようになっていった。
ドヴォルザークは1883年に、ロンドン・フィルハーモニック協会(現ロイヤル・フィルハーモニック協会)の招待を受け、翌1984年に初めてロンドンを訪れ、自作の指揮を行ったが、これが大変な評判を呼び、その結果、ドヴォルザークはフィルハーモニック協会の名誉会員に推薦され、新たな交響曲の作曲依頼を受けることとなった。前述したように同じころブラームスの交響曲第3番を聞いて創作意欲がたかまっていたドヴォルザークは、1884年12月13日から翌年3月17日のわずか3か月の間にこの交響曲第7番を仕上げ、すぐに再度ロンドンを訪れ1885年4月22日に聖ジェイムズホールで自身の指揮で初演を行った。この演奏会は大成功で、初演から間もなくハンス・リヒター、ハンス・フォン・ビューロー、アルトゥール・ニキシュといったドイツ系の指揮者たちがこの曲を演奏したが、これは交響曲作曲家ドヴォルザークの名声を広めることとなった。イギリスでは「ボヘミアのブラームス」とまで呼ばれるようになるが、ドヴォルザークはこの後も2回訪英しており、1891年にはケンブリッジ大学より名誉博士号を授与されている。
ちなみに第8番のト長調交響曲が、最近では少なくなったものの「イギリス」というニックネームで呼ばれることがあるが、これは、本来のドヴォルザーク作品の出版社であるジムロック社が作品に十分な対価を払おうとしなかったことから、例外的にイギリスの出版社であるノヴェロ社から楽譜が出版されたことによるもので、「イギリス」の名を冠するならば、上記の作曲経緯などに照らせば、第7番こそその名に相応しいといえるのではないか。
なお、作品番号と並んで記されている「B.141」は、チェコの作曲家・音楽学者ヤルミル・ブルクハウザー(1921-1997)が作成したドヴォルザークの年代順の作品目録による番号で(モーツァルト作品のケッヘル番号(KV)、シューベルト作品のドイッチュ番号(D)に相当)、作品番号のないものも多く、作品番号自体必ずしも作曲年代順とはなっていないドヴォルザーク作品の整理に大いに役立つものとなっている(最後の作品である歌劇「アルミーダ」はB.206)。
第1楽章 Allegro maestoso ニ短調 8分の6拍子 ソナタ形式
ティンパニのトレモロに乗って、低弦により緊張感を孕んだ陰鬱なニ短調の第一主題が提示される。交響曲第7番は直前に作曲された、プラハの国民劇場再開の式典のために書かれた、チェコの宗教改革者で民族的英雄でもあるヤン・フスを称える「劇的序曲『フス教徒』」(作品67 B.132)とも深く関係しているが、第一主題の提示に続き9度の跳躍を伴う劇的な「フス教徒」の主題に基づく動機が現れる。第二主題は対照的に穏やかな変ロ長調で示されるが、これも「フス教徒」で使われている中世チェコの聖歌に基づくもの。展開部は徹底して提示部の素材が繰り返し使われ、短縮された再現部を経てコーダに至る。
第2楽章 Poco adagio ヘ長調 4分の4拍子 三部形式
激しく反抗的な第1楽章とは対照的な、ブラームスの交響曲第3番の緩徐楽章を思わせるクラリネットの穏やかなヘ長調のテーマはどこか諦めに似た感じを持っている。中間部はホルンの美しい独奏により始まりヘ短調の全楽器による強奏に達するが、続く木管楽器と少人数の弦楽器によるアンサンブルは室内楽を思わせる美しい箇所。現在演奏されるものは、初稿より4分の1ほど短縮されている。
第3楽章 Scherzo: Vivace – Poco meno mosso ニ短調 4分の6拍子 三部形式
スケルツォのタイトルが付されているが、主部は4分の6拍子の対位旋律と2分の3拍子のアクセントをもつメロディーが交錯するチェコの民族舞曲「フリアント」。ドヴォルザークは前の交響曲第6番の第3楽章にもフリアントを用いているが、7番のほうがより一層洗練されていて、ドヴォルザークの全交響曲のなかでも屈指の楽章の1つ。中間部はテンポをやや落としてト長調の主題がカノンのように楽器を変えて重ねられていく。フリアントの再現は、第1楽章のように短縮されて代わりに長めのコーダが付されている。
第4楽章 Finale: Allegro ニ短調 2分の2拍子 ソナタ形式
クラリネット、ホルン、チェロによるオクターブの跳躍と増二度音程を含む解決しない不穏な動きに続きヴァイオリン、クラリネットによるコラール風の重苦しい第一主題が提示されるが、これらはいずれもやはり「フス教徒」に関連している。第二主題は重厚陰鬱な第一主題とは対照的に、イ長調のどこか懐かしさを感じさせるチェコ民謡風の旋律がチェロによって提示される。この楽章にもやや長めのコーダが付いているが、コーダの最初に、弦楽器がユニゾンの低音で付点のついた音形を奏するのに対して、全木管楽器が喧しく増二度を含む音程の分散和音を上行―下行する箇所は、オーケストラのスコアが目に浮かぶようで印象的。最後はMolto maestoso(きわめて荘厳に)となり第一主題の前半部が変形されて最後6小節で長調に転じ、全楽器によるニ長調の和音の強奏で終わる。
初演:1885年4月22日 作曲者自身の指揮によるロンドン・フィルハーモニック協会の演奏会(於ロンドン 聖ジェイムズホール)
楽器編成:フルート2 (2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、弦五部
参考文献:
Honolka Kurt, Dvořák Haus Publishing, 2005
内藤久子『ドヴォルジャーク』音楽之友社 2004年
Bärenreiter 版スコア(Jonathan Del Mar校訂TP507)Jan Smacznyによる序文
「This music gets under my skin」 Nicolaus Hartnoncourt in conversation with Monika Mertl on Dvořák and the nature of Czech music (ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団とのCDライナーノーツ Teldec 39884-21278-2)
千野栄一/ズデンカ『チェコ語の入門』白水社 1971年
因縁の3曲
新響との共演は、コロナ問題で中止になったコンサートもあったので、今回が2013年以来9回目。ドヴォルザークとドビュッシー2曲というプログラムは、いずれも私にとって思い出深い曲である。
チェコ人の指揮者ズデニェック・コシュラー(Zdeněk Košler)氏は、私が東京藝術大学在学中の1960年代後半に客員教授として特別講義や学生オーケストラのリハーサルをされたが、1972年スイス・ローザンヌで開かれた国際ユースオーケストラ・フェスティヴァルに東京ユースオーケストラと共に参加すると、コシュラー氏も客演指揮者として携わっていらして再会した。フェスティヴァル終了後、私は予定通りウィーン高等音楽院で、ハンス・スワロフスキー教授のクラスを聴講した。ウィーンでは当時共産圏であったチェコスロヴァキア入国ヴィザを簡単に取得できたので、ウィーンから僅か56㎞東に位置するブラティスラヴァのスロヴァキア国民劇場音楽監督とプラハのチェコ・フィルハーモニー常任指揮者を兼務されていた氏の許に足繁く通い、リハーサルやコンサートを見学したり、美味しいチェコ料理とピルゼンビールをご馳走になりながら楽譜上の問題点から音楽家・指揮者としての生き方まで、様々なアドヴァイスを戴いた。プラハでは、モーツァルトが1787年10月29日に<ドン・ジョヴァンニ>を初演指揮したスタヴォフスケー劇場で<ドン・ジョヴァンニ>を聴き、カミュと並び高校時代から愛読していたカフカの仕事場をプラハ城から下る「黄金の小路」で覗いた他、コシュラー氏はヴルタヴァ(モルダウ)川に繋留されている船を改造したボテル(botel)に泊まる事を薦めて予約の労を取り、休日にはドライヴに誘ってボヘミアの森と草原を案内して下さったから、音楽に昇華・結晶される前のチェコスロヴァキア風物・文化に触れる事が出来た。私が影響を受けたもう一人の師、セルジュ・チェリビダッケ氏に初対面したのもブラティスラヴァであった。
1970年代末から、私自身もスロヴァキア・フィルハーモニー、ブラティスラヴァ放送管弦楽団等を何度かコンサートで振ると、出演料は国外持ち出しが禁止されているチェコ・コルナで支払われた。プラハの空港には、外国人がチェコ通貨で口座を開ける銀行があったものの、入金して1年経つと国に没収されてしまう。3回目の客演から、半額は西ドイツマルク払いになったが、残りのコルナを使い切るのに苦労するという共産圏ならではの奇妙な体験をした。演奏会翌日、ドヴォルザーク・スメタナ・ヤナーチェク等の大型スコアの他、ボヘミアン・ガラスや絹のテーブル・クロス等を買い漁り、重くなった旅行鞄をパリの家に持ち帰った。ちなみに、今回使うドヴォルザークのスコアは、当時のギャラの一部である。
数式と睨めっこをしていた大学時代、新橋と有楽町の間の高速道路下でコリドー街と呼ばれていた一角に、輸入レコードの専門店があった。或る日、まだ日本でプレスされていなかった<春>の英デッカ盤を見つけて、全く知らない曲だったからワクワクしながら鎌倉の家へ急いで帰って聴き入った記憶がある。ブダペストで出版されたこの曲のスコアも、プラハの楽譜屋で買ったものだ。
<海>のスコアを入手したのは中学2年の頃。当時、日本で出版されていたスコアはベートーヴェン等ほんの一握りで、ドビュッシーやラヴェルはポケット版でも高価な輸入版しか無かった。第1曲の中程で、岩に打ち上げる波が煌めきながら弾けるかのようにチェロパートが分かれて弾く場面はどの様に記譜されているのか知りたくて、なけなしの貯めた小遣いを叩(はた)いてフランス・デュラン版のスコアを初めて買った。¥1250と書かれたヤマハの正札が今でも付いている。最初のページには、フランス国立オーケストラと来日演奏したシャルル・ミュンシュのサインもある。数学の問題集に疲れると自転車で突っ走り、稲村ヶ崎の岩場に座って江の島とバックに聳える富士山を見ながら読み耽ったので、現在の版よりも上品だった淡いブルーの表紙はすっかり変色して茶色になってしまった。
波間の富士と言えば北斎の「神奈川沖浪裏」。この版画はドビュッシーに<海>のインスピレーションを与え、1905年に出版された初版スコアの表紙に、その一部が使われた。ブーローニュの森近くにあるドビュッシーの家で、若いストラヴィンスキーと一緒のところをサティが撮った写真では、後ろの壁に、この版画が懸かっている。
<海>を演奏する度に思い起こすのは『金槐和歌集』に収められた実朝の一首である。
大海(おほうみ)の 磯もとどろに 寄する波
破(わ)れて砕けて 裂けて散るかも
バソンの軽重を問う
維持会会員の皆さま。いつもお世話になっております。
私はドイツ式ファゴット歴45年で、新響では33年間もお世話になっております。
7年ほど前から日本においてバソンと呼ばれているフランス式バスーンを勉強する機会に恵まれました。世界中でほとんどのシェアを占めているドイツ式(またの名をヘッケル式)のファゴットと絶滅危惧種とまで言われている少数派のフランス式(またの名をビュッフェ式)のバソン。バソンの会の一員であり新交響楽団で(おそらく)バソン吹き第1号の私がバソンの名を世に広めるべく書き綴っていきたいと思います。
私のバソンとの出会いは、ファゴットを始めて間もない高校生のころ、中学生でありながらプロのオーボエ吹きを目指していた弟の勉強用にとサン・サーンスのソナタ集のレコードが我が家にはありました。その中のバソン吹きの大家モーリス・アラール氏の演奏を聴いた私は「なんじゃこりゃ!」と叫んでしまいました。まるでテナーサックスのように聴こえるファゴットとは異なるバソンの音色に驚いたのです。それから何十年も経った還暦も近づいていたある日、大学で一緒にファゴットを吹いていた後輩が今ではバソンを吹いていることを知りました。私は何かに導かれるようにCDを買いあさり、その音色に魅せられ、彼と連絡を取り、楽器店を紹介してもらい、家族の許しを得てバソンを購入しました。まるで苦いふき味噌が大人になってから美味しく感じられるように、若さゆえテナーサックスに聴こえていたバソンの音が、還暦近くまで齢を重ねたことで得も言われぬ心地よいものに変わったのでした(最近買い求めたふき味噌が美味でした)。
まずは簡単にファゴット(バソン)の歴史について書きたいと思います。なお、ファゴットというのはドイツ語(またはイタリア語など)の呼び方で、バソンはフランス語です。楽器の名前は国によって呼び方が異なりますが、日本ではドイツ式をファゴット、フランス式をバソンと呼ぶことが多いです。今から何百年も前、モーツアルトやベートーベンの時代、18世紀から19世紀はじめころのファゴットはキーの数が2~5個くらいのバロックファゴットから発展したものでした。この時代にはまだドイツ式もフランス式も存在しませんでした。
19世紀は木管楽器の世界においてさまざまな発明がなされ、大きく発展した時代ですが、バロックファゴットからの発展の流れは緩やかなものでした。19世紀の中頃、ヨーロッパ全土でほぼ完成したフランス式バソンが演奏されていました。
一方、ドイツ式ファゴットは1923年のファゴット奏者アレメンレーダーの論文から始まります。革新的な改良の末、ファゴットの普及が始まったのは、それまで独自のファゴットを使用していたウィーン・フィルがドイツ式に変えた1870年ごろです。その後ドイツはもちろん、アメリカやヨーロッパ各国にドイツ式は広まっていきました。フランス以外で最後までバソンで頑張っていたイギリスも、1930年代にトスカニーニ率いるニューヨーク・フィルの演奏旅行が大きな契機となりドイツ式旋風が巻き起こりました。フランスでも1960年にカラヤンが音楽監督に就任したパリ管弦楽団でファゴットに乗り換えるなどしています。
さて、Wikipediaによる数年前までのバソンの記述には誤りが非常に多く、それが世の中に広まってしまってしまい、惨憺たる状況にあるといえます。今(2023年3月)では訂正が入っており、間違いは大幅に減っているようですが、すでにあの有名なコミック『のだめカンタービレ』にも悪い影響を与えてしまっているようです。微力ながら世にはびこるバソンへの誤解を払拭していきたいと思います。
1.フランス式のバソンは音が小さいから4本で吹いている?
Wikipediaから引用してみましょう。
「バソンは音量があまり大きくないことから、ベルリオーズのように1パートに2本重ねて4管として使われることが多い。」
恐らく音が小さいと言っているのはドイツ式ファゴットと比べてとのことだと思うのですが、ベルリオーズが『幻想交響曲』を作曲したのは1830年です。これに対してバソンの製作会社ビュッフェの工房設立は1825年(バソンを作り始めた年は不明)、ヘッケルが工房を設立したのは1831年です。ドイツ式ファゴットが完成するのは1870年ごろと言われているので、当時のファゴットの音量が小さかったことを言うことはできても、バソンの音が小さいとは言えないはずです。
ベルリオーズ先生に直接聞いて確かめてみましょう。
「ファゴットは通常2つのパートで書かれるが、大きなオーケストラは常に4つのファゴットを備えているため、不自由なく4つのパートで書くことができます。さらに良いのは最低音声部を倍管にして低音を増強する3つのパートにすることもできます」
(ベルリオーズ著 "A Treatise on Modern instrumentation and Orchestration" 110ページより)
楽器の音の大きさ云々とは仰っていませんねえ。また楽器・古楽研究家の佐伯茂樹著『ピリオド楽器から迫る オーケストラ読本』(39ページ)にはこのように書かれています。
「シャブリエの狂詩曲《スペイン》はベルリオーズの《幻想交響曲》と同じように、2管編成で書かれているにもかかわらず、ファゴット(バソン)だけ4本使われている。おそらく、これは8フィートのベースラインを重視したルイ王朝時代から続く伝統なのだろう」
たしかにバソンはファゴットより音量が小さめですが、2本を4本にしてもたった3dBしか大きくなりません(筆者の仕事は騒音などの音関連の技術職です)。Wikipediaの記述を修正願いたいものです。
2.バソンの音色はホルンに似ている?
これもWikipediaの記述から起こる誤解です。モーリス・アラール大先生のバソンの演奏を聴いてホルンに似ていると思う人なんていないんじゃないでしょうか。Wikipediaでは「音色がホルンに近く」と書いてありますが、別の箇所には「指揮者のジョン・フォウルズは、ヘッケル式ファゴットはホルンとの音の同質性が高すぎると考え、ヘッケル式が優勢であることを1934年に嘆いた」と書いています。(英語版は後者のみ記載あり)ドイツ式のほうがホルンに音色が似ているそうです。こちらも修正を希望します。
3.「キーが多く完成度の高いファゴット」
バソンの知名度を飛躍的に高めてくれた「のだめ」ですが、同時にたくさんのニセ情報もばら撒いてしまったようです。本当かどうか数えてみました。
キーにはトリルキーや速いパッセージのための替え指キーなどもありますので、押えることのできるすべてのキーを数えてみましょう。
バソン:22キー(ビュッフェBC5613R)
ファゴット:23キー(ヘッケル41i)
う~む、ファゴットの方が確かに多いですが、あえて言うほどの違いは無いと思うのですが。写真はファゴットとバソン(の下部、右手の親指で押える個所です。ぱっと見、バソンの方が広々としているので、これが「キーが少ない」という話になってしまったと考えます。この部分のファゴットはキーが多いというよりタンポが多いですね。

楽器の下部:左が現代ファゴット、右が現代バソ
4.バソンはバロック時代からほとんど変わってない?
歴史のところで述べたように、バロック時代のファゴットはキーが2〜5個くらいです。
フランス式バソンが完成した頃にはキーの数が15個ほどになっています。
バロックファゴットとバソンがほとんど変わっていないのかどうか比較をして調べてみましょう。写真をご覧ください。ね、ぜんぜん違うでしょう。緩やかに発達してきたといってもバロックファゴットとバソンはこんなに異なる楽器なのです。

モーツアルトの時代の7キーの楽器 バロックファゴット
・材質は楓
・最低音のB♭キーは通常は「開」
・キーの数は2~5個

現代のバソン
・材質はローズウッド
・最低音のB♭キーは通常は「閉」
・キーの数は20個以上
5.バソンを使っているのはフランスの一部のオケだけ?
バソン奏者がいるオケは、フランス以外にもあります。ベルギーや日本です。忘れていけないのは日本。静岡のプロのオーケストラには何と三人もの日本人バソン奏者がいるのです(「のだめ」連載時にこのオケは設立されていない)。なお私はバソン用のリードをイギリスのバソン奏者から購入しています。ということはイギリスでリードを作って売っているんだからオーケストラのバソン奏者も少数ですがいるのかも知れません。
6.バソンはフランスの伝統楽器?
「のだめ」ではマルレ・オーケストラのファゴット募集オーディションにポール君がバソンを引っ提げてやってきました。オーディションではファゴット募集にもかかわらずバソンで受けたポール君、指揮者の千秋先輩ら審査員の聴いた演奏は素晴らしいものでしたが、他の審査員からファゴットで募集したのでとバソンでの採用に難色を示されてしまいます。それに対して審査員のコンマスは「フランスの伝統楽器なんだから、守れるのなら守ったほうがいいんじゃないのか!?」とポール君の採用に前向きです。バソンはフランスの伝統楽器なのでしょうか。
時は19世紀中期、まだドイツ式ファゴットが発明されたばかりの頃、フランス式バソンはヨーロッパ中で演奏されていました。フランス式と呼んではいますが現在主要メーカーがフランスにあるので便宜上フランス式と呼んでいるのであって、かつては敵国イギリスのBoosey & Hawkes社もバソンを作っていたほど広まっていたのです。フランスの伝統楽器だったらイギリス人は死んでも使わなかったに違いありません。
ところで、現フランス国立フィルの首席バソン奏者であるフィリップ・アノン 氏はこのように言っています。
「私は1977年にファゴットを始めたのですが、フランスのファゴット・コミュニティでは、(バソンからファゴットへ)変更した人たちに対して憎しみがありました。彼らは裏切り者とみなされたのです。忘れてはならないのは、1945年からわずか30年後、反ドイツの怨念が、特に戦争で苦しんだ教授たちの間でまだ強く残っていたことです」
フランス人にとってバソンが伝統楽器なのかはわかりませんが、守りたいと思う気持ちは間違いではないのかもしれません。
7.ファゴットとバソンが並んで演奏するなんて考えられない?
「のだめ」で、アルマオケの首席ファゴットはドイツ式を吹いています。ポール君はオーディションに合格してもファゴットに乗り換える気は無いので、バソンとの混成パートになってしまいます。実際キーシステムが違うため運指は微妙に異なり、乗り換えは簡単ではありません(最近バソンを吹き始めた筆者の感想です、逆もまた然りと考えます)。
コンマスはポール君の採用に前向きなのでこのように言いました。
コンマス:「ファゴットの中にバソンが一人いてもいいんじゃないか?」「できなくはないだろ」(汗
千秋先輩:「できなくはないでしょうね」(汗
二人が汗をかきながら「ファゴットとバソンが一緒に出来ると言ってはみたものの本当に出来るのだろうか」と苦悩の声が聞こえてきそうですが、心配はいらないようです。
1960年ごろ書かれたイギリスのファゴット奏者アンソニー・ベインズ博士は『木管楽器とその歴史』でこのように述べています。
「これら2種類のバスーンはいずれも完璧なものではなく、お互いに音色も同質ではないにもかかわらず、共用するとかなりうまくいくのは奇妙なことである。イギリスのオーケストラではしばしば共用されているのを見受けるが、一般に最良の効果が得られるには(もちろん奏者にもよるが)ビュッフェを上声部に使い、ヘッケルに下を吹かせると、よりよいといわれている」
バソンとファゴットの混成は現代のオーケストラでもベルギーやフランスで見ることができます。
8.バソンは本当に絶滅危惧種なのでしょうか。衰退の一途をたどるのでしょうか。
誤解を解くなんて偉そうなことを言ってまいりましたが、バソンが衰退の一途をたどってきたことに間違いはありません。アメリカでは1953年、モーリス・アラール氏のおじであるレイモンド・アラール氏がボストン交響楽団を引退しました。スペインでは1980年ごろまでにはフランス式をドイツ式に持ち替えています。ブラジルでも1987年にはノエル・ドゥヴォらのバソンセクションが引退や乗り換えによってバソン戦線を突破されてしまいました。前出のベインズ博士は両楽器を演奏した経験からこうも言っています。
「2種類の楽器を比較してみると、運指法からはどちらが決定的にまさっているということはいえない。ヘッケルの長所は音域の最高部から最低部まで〈ピアノ〉から〈フォルテ〉まで、音色がオーケストラ内で一様に〈効果的〉であることで、この楽器では音を強いたり、鼻音のようにしたり、ぼてぼてさせたりすることなしに、明瞭で効果的なものにするためのリードを手元に揃えておくことは比較的容易である。フランス式の楽器で、これに相応する結果を間違いなく得ることは決して不可能ではないが、はるかに困難である。この型の楽器はリードのちょっとしたむら気にも敏感で、完全条件を備えていないリードだと直ちに露見してしまうような弱点が各音域にいくつかある。これがヘッケル式が自国以外でも成功を収めた本当の理由で、つまりオーケストラ奏者にとって生活が楽になるというわけである。」(『木管楽器とその歴史』所収)
私がファゴットとバソンの両方を吹いてみてわかること。ファゴットは博士が言っているようにすべての音域で音程と音色が安定していて、低音が気持ちよく鳴り(ブリブリ吹けます)、中音域は憂いを奏で、高音域では透明感があり、どの音域でも他の楽器とよく合う音色です。一方バソンは、(私がへたくそなのかもしれませんが)いくつかの音が安定しません。(音程と音色)そして低音域は鳴りづらくて苦手です。でも高音域は倍音が豊富で吹いていて気持ちいい!ファゴットとバソン、優劣はつけられません。私はどちらの楽器もそれぞれの個性があって大好きです。
9.バソンの未来
バソンは無くなってしまうのでしょうか。ファゴットがドイツ式だけになってしまったらオーケストラの世界はどうなるのでしょう。ヘッケル式を演奏するアメリカの演奏家は、世界中のオーケストラの地域差がなくなってしまったことを嘆いています。またジュリアード音楽院の元学長は同様の見解を示し、音の均一性は良い目標ではない、国籍やオーケストラによって異なるサウンドが欲しいと述べています。
そうです、絶望するには早すぎます。日本にはプロのバソン吹きは私の知る限り少なくとも5人はいます。アマチュアも数十人もいます。海外でも2つの著名なオーケストラのプロのファゴット奏者が、ファゴットのみのアンサンブルにバソンを再び取り入れることに強く関心を寄せているそうです。一人目は、ニューヨーク・フィルハーモニックのキム・ラスコウスキーです。ニューヨーク・フィルの同僚にバソンを披露した後、彼女はこう言ったそうです、「ファゴットセクションは、チューニングが合っていれば、私が吹いても構わないと思っていますよ」と。またニューヨーク・フィルに加え、ケルン・フィルハーモニー管弦楽団も2016年にバソンを2本、ファゴットセクション用にドイツキーシステムにカスタマイズしたものを発注したそうです。
伝統的な製法でバソンを作ってきたビュッフェ社も、最近ではクロワッサンキーやU字管など新しい技術でバソンを吹きやすく改良しています。またセルマー社から独立した技術者デュカス氏はヘッケル式の運指で演奏できるバソンを製作しています。前述のケルン・フィルはこの楽器を購入したようです。これによってファゴット吹きは以前に比べてバソンに転向しやすいかもしれません。かつてバソンしかなかった1900年ごろ、アメリカではドイツ式ファゴットが入ってきたときファゴットに慣れないバソン吹きのために、バソンの運指に似せたファゴットが作られたこともあるそうです。近い将来、多くののファゴット吹きがバソンの音色に魅せられてバソンに転向することがあるかもしれません。それが筆者の願いです。
第261回演奏会のご案内
パリを拠点に世界的に活躍し、その理知的なタクトから豊かな色彩溢れる指揮者、矢崎彦太郎と共演するようになり今年で10年なります。今までフランスの管弦楽作品を中心にプログラミングしてきましたが、今回はいよいよドビュッシーの代表作である「海」を取り上げます。
ドビュッシーの2つの交響的な絵画
フランス印象派を代表する作曲家であるドビュッシー(1862-1918)が、交響詩「海」を作曲したのは1905年。オペラ「ペレアスとメリザンド」が成功し、作曲家としての地位が確立された時期でもあります。「海上の夜明けから真昼まで」「波の戯れ」「風と海との対話」という3つの楽章からなり、海の情景が時間経過とともに描かれます。初版のスコアの表紙には、葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」が使われました。
交響組曲「春」はドビュッシーがローマ大賞を獲得してローマに留学していた1887年に作曲されました。ボッティチェッリの名画「プリマヴェーラ(春)」から着想を得て作曲したと言われており、春の息吹や喜びが描かれています。残念ながら火災により楽譜が焼失したのですが、合唱とピアノの版は残っており、ドビュッシーの指示でビュッセルにより新たにオーケストレーションされました。
ドヴォルザークの正統派シンフォニー
もう1曲は、矢崎からのリクエストでドヴォルザークのシンフォニーを演奏します。
チェコ国民楽派を代表する作曲家であるドヴォルザーク(1841-1904)は、国際的名声を得て1884年にロンドン・フィルハーモニック協会の名誉会員に選ばれました。その際の依頼によって生まれたのが交響曲第7番です。完成したのは作曲家が43歳の時で、ドビュッシーが「海」を作曲したのも同じ43歳。ともに円熟期の代表作です。
ドヴォルザークといえば「新世界」交響曲があまりにも有名ですが、この第7番は絶対音楽的な性格が強く、形式的にも古典的な構成で、9つの交響曲の中でもっともドイツロマン派的な作品です。ブラームスの交響曲第3番の影響が強いといわれていますが、ドヴォルザーク独特の素朴で温かな響きを持ち民族的な要素も散りばめられている魅力的な曲です。
どうぞお楽しみに!
第260回演奏会ローテーション
| 二つの祈り | 別宮第3番 | ウォルトン第1番 | |
| フルート1st | 林 | 松下 | 吉田(新井) |
| 2nd | 兼子 | 黒住 | 岡田 |
| 3/Picc | 藤井 | - | - |
| オーボエ1st | 山口 | 堀内 | 周藤 |
| 2nd | 堀内 | 岩城(+コールアングレ) | 山口 |
| コールアングレ | 岩城 | - | - |
| クラリネット1st | 大藪 | 末村 | 境澤 |
| 2nd | 進藤 | 石綿 | 中條 |
| バスクラリネット | 品田 | - | - |
| ファゴット1st | 松原 | 田川 | 藤原 |
| 2nd | 田川 | 松原 | 浦 |
| コントラファゴットト | 浦 | - | - |
| ホルン1st | 山路 | 名倉 | 大内(高野*) |
| 2nd | 大原 | 大原 | 大原 |
| 3rd | 大内 | 山路 | 名倉 |
| 4th | 高野* | 高野* | 山路 |
| トランペット1st | 瀧野 | 倉田 | 小出(瀧野) |
| 2nd | 北村 | 中川 | 青木 |
| 3rd | 中川 | - | 竹本 |
| トロンボーン1st | 武田(香) | 武田(香) | 武田(浩) |
| 2nd | 志村 | 志村 | エキストラ |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | エキストラ | 4th | - | エキストラ | - |
| テューバ | 土田 | - | 坂巻 |
| ピアノ・チェレスタ | 藤井 | 藤井 | - |
| ハープ | 見尾田* | 見尾田* | - |
| ティンパニ | 桑形 | 嘉瀬 | 桑形/嘉瀬 |
| パーカッション | 小太鼓・トライアングル/今尾 中太鼓・タムタム/嘉瀬 シンバル/鈴木* 大太鼓/足立 |
小太鼓・トライアングル/今尾 大太鼓・トムトム/足立 シンバル・タンバリン/鈴木* |
シンバル・小太鼓/今尾 タムタム/鈴木* |
| 1stヴァイオリン | 内田智(堀内) | 内田智(堀内) | 堀内(内田智) |
| 2ndヴァイオリン | 今村(小松) | 今村(小松) | 小松(今村) |
| ヴィオラ | 星野(村原) | 星野(村原) | 村原(田川) |
| チェロ | 柳部(安田) | 柳部(安田) | 柳部(安藤) |
| コントラバス | 宮田(植木) | 宮田(植木) | 宮田(植木) |
*はエキストラ
弦()はトップサイド、管()はアシスタント
『青春の作曲家たち』のころ =「二つの祈り」の記憶と現在=
◆異色の作品=1983年の新交響楽団=
別宮という姓は伊予国(現愛媛県)を本貫とするようだ。「べっく」と読む訳だが、宮の字を「く」と読む例を寡聞にして他に知らない(「ぐ」の例はあるが)。この姓を初めて目にしたのは大学生の時で、アンドレ・プレヴィン編『素顔のオーケストラ』という本によってだった。訳者は別宮貞徳(べっくさだのり)。その後同人が書いた、世の中にある翻訳の出鱈目ぶりを痛烈に斬りまくった本を何冊も読んだ。翻訳界の大御所として君臨する人らの「名訳」にさえ容赦なく批判を浴びせる姿勢は、まさに快刀乱麻。痛快といえる読後感を得た記憶がある。
その後に別宮貞雄なる作曲家によるフルートソナタの譜面を手に入れ、特に公に演奏する当てもないまま、個人的に練習を重ねて今に至る。2楽章構成の短い曲で実質はソナチネと言うべき作品である。パリ留学中に作曲家の脳裡に突如飛来した旋律。その瞬間にこれはフルートの音楽と認識された…との自身のコメントが譜面巻末に載っていた。もっとも曲の短さと難易度とは無関係で、以来大いに手を焼き続けている。今回、この作曲家の第3交響曲を演奏するに当たり、同様の技術的難所や陥穽が諸所に散りばめられている事を思い知り、もう少し真面目にソナタに取組んで「免疫力」をつけておくべきだった、と反省している。この作曲家と上記の翻訳家が兄弟である事を知ったのはつい最近である。まぁ滅多にない姓だから、いずれそんな処であろうとは想像していたが。
さて、新響が別宮貞雄氏の作品を初めて取り上げたのは1983年4月の第99回演奏会に於いての事である。1976年に日本の交響作品展によってサントリー音楽賞を受賞して以来、翌1977年を除く毎年4月のシーズンはこの企画による演奏会が芥川也寸志氏の指揮により行われていた。1983年は7回目に当たり『青春の作曲家たち』と銘打って5人の作曲家らの、初期作品をプログラムに載せた。演奏順に並べると
・小倉朗:交響組曲 イ短調(1941)
・松平頼則:南部子守唄を主題とするピアノと オルケストルの為の変奏曲(1939)
・戸田邦雄:交響幻想曲「伝説」(1943)
・渡辺浦人:交響組曲「野人」(1941)
・別宮貞雄:管弦楽のための「二つの祈り」
である。
芥川氏はこのプラグラムの劈頭に「青春讃」として次の一文を寄せている。
単に青春とは言えば,それはおそらく,心の問題であろう。50才の青春,60才の青春もないとはいえない。
しかし,作曲家にとっての青春の---と言えば,それは丁度,人生における青春時代と同じく,再びかえることのない,貴重な,若き日々における創作生活を指すことになろう。 その時代の作品は,それから後の作曲家本人を,逆に創っていくことになる。
小倉 朗 25才
松平頼則 32才
渡辺浦人 32才
戸田邦雄 26才
別宮貞雄 34才
日本の音楽史を刻み込む,それぞれ貴重な作品群である。
この企画により『管弦楽のための二つの祈り』を新響は初体験したのである。
その時のプログラム(パンフレット)を探し出したが、20ページに及ぶ大仰なもので、コロナ禍によってカネ詰まりの苦しい状況下にある現在からみると、途方もない贅沢に映る。が、その贅沢は体裁だけではなく、各曲について作曲者自身に解説させている内容によって徹底している。すなわち当時いまだ現役であった各作曲者の謦咳に触れる機会を新響は享受していた事を意味する。事実彼らは新響の練習過程にも幾度となく、入れ替わり立ち替わりに立ち会い、自作品に関する貴重な助言や示唆を団員に与えていたのである。これ以上の贅沢があろうか?
またプログラムには作品ごとに作曲家自身の「解説」が掲載されている。本人が自作について語る内容が盛り込まれている点を考えても、この冊子は今や非常に貴重な文献となったが、現時点でも内容は公開されてはいない。そこで今回別宮貞雄氏の文章のみだが、ここに転載する事とした。当人も書いているが『~二つの祈り』がこの企画の俎上に上った経緯について、芥川氏の勘違い?を疑っている。そしてそれに半ば便乗する形で、自らの「青春」と結び付け、総括した一文は、作品の解説とは異なった趣を持つに至っているように思えるのである。
以下に全文を引用する。
~わが音楽的青春始末~
敗戦の翌年春,前年に行われなかった毎日コンクールがかわりにひらかれて,私の「管弦楽のための二章」が演奏され、入賞した。私が書いたはじめての作品,24才の時のものである。芥川さんは,これと「二つの祈り」とを混同されていて,実はこちらの方を上演したかったようなのだが,かんちがいをいいことに,それは勘弁していただいた。とても恥ずかしくて,今更皆様にきいていただく気にはなれない,何せ生まれてはじめてまとめた曲なのだから。
私は音楽の道に入ったのがとてもおそかった。こどもの頃からレコードで名曲をきくことだけはしていたが,妹のみようみまねでピアノにさわったのが,中学も卒業する頃だし,旧制高校時代には趣味としては深入りするようになっていたが,池内友次郎先生の門をたたいたのは大学に入ってからである。物理学者になろうと志をかためたのと,並行してというのは変かもしれないが,たしかトーマス・マンの芸術論の影響で,あやふやな芸術とのつきあいにあきたらなくなったのである。
デュボアの教科書で和声の初歩からはじめたのだが,もう昭和19年,戦いもたけなわで,なんとか和声法と対位法の初歩を型どおりおえる位で,敗戦。大学には研究生活の環境などとても整わないままに,好きな音楽に没頭した。それでも三月には大学は無事卒業した。そんな中で,先生にすすめられてとりくんだのが,件の作品である。生意気にも先生の指導に背をむけて幼稚な自己流に固執した記憶はある。大したものが出来るわけはないのだが,ただリディア調の旋律が少しばかりチャーミングであったからか,まさか入賞などまじめに考えてもいなかったのに,第2 位ということになった。これが私の人生の方向転換のきっかけである。受賞のことよりも,はじめて聞いた自分のオーケストラ作品の美しさ(別に大したことではなく,しかるべく書いてあれば,オーケストラというものはいい音を出すものである。)から受けた感銘,それが病みつきになったのだろう。
翌昭和22年秋にも,コンクールに応募した。「管弦楽のための古典組曲」というもので,バッハの古典組曲と,ラヴェルの「クープランの墓」が着想のもとであった。音はとてもラヴェル風とまではゆかなかったが,いくらかフランス趣味であった。これでも第2位ということになった。そしてそのあとで小倉朗さんにされた批評が私を大きく変えたのである。彼にモダニズムの浅薄さと,ドイツ古典の偉大さについて,説教された。だがはじめは,私にとってこれはマイナスであった。あらためてベートーヴェンを勉強したりしたのだが,かえって曲が書けなくなった。その頃の作品で今のこっているのは歌曲だけである。
大学の理学部をでてから,文学部美学科にいたのだが,そこも卒業となり,いよいよ自分の一生をどうするか,決心する必要があった。
何とか作曲家になりたいと思った。それで昭和26年8月渡仏,パリ国立音楽院のフューグ科と作曲科に入った。そこいらの話は書けばきりがないが,要するに職人的技術を身につけた。それからミヨーから自由の尊さを学んだ。メシアンにも影響を受けた。3年いて、最後にまとめた作品は管弦楽のための「序奏とアレグロ」である。
帰ってから室内楽作品発表会をしたりしていたが,翌々昭和31年,当時毎回日本人の作品を上演していた東京交響楽団の定期演奏会のために、書き下ろしたのが、この「二つの祈り」である。つまり私にとって4曲目の管弦楽作品になる。34才の時のもので,果たして青春の香が残っているかどうか,心もとないが私はひとより10年も後れて音楽の勉強を始めたのだから,そのことを考えれば,青春の作品といってもおかしくはないだろう。少くとも修業時代をしめくくる作品といえよう。5月10日斎藤秀雄先生の指揮で初演された。第1楽章は前奏曲,第2楽章はファンファーレ付のフーガとも考えられる。終わりのストレッタに重なる金管楽器の旋律はグレゴリオ聖歌のクレドによるものである。
34歳時点での作品である事そのものは、本人が言うほど「青春」からかけ離れたものとは言えない。前記の「青春讃」に芥川氏は作曲当時の彼らの年齢を明記している訳だが、5人の作曲者のうち別宮氏を含む3人が30代を迎えてからの「初期作品」なのだ。違いがあるとすれば『管弦楽のための二つの祈り』は初演された昭和31(1956)年度の尾高賞を受賞している…すなわち他と比べ、当人にとって4作目とはいえ、極めて完成度の高い作品であったという点にあろう。
◆難物だった「フランスもの」と克服
僕は前年1982年9月に新響入団。この第99回演奏会で初めて1番フルートを吹く機会を得たので(但し『~二つの祈り』には出ていない。残念)、この演奏会については今もかなり鮮明な記憶がある。最も驚いたのは最後に演奏された別宮氏の作品だけが、他の4曲とは全く異なる響きを持っていた事だ。簡単に言えばフランス的な響き。上記の解説中の言葉を借りれば「フランス趣味」ということになろうか?否、フランスで正統な教育を受け、研鑽を積んだ末に結実した作品なのだから、最早「趣味」はあり得ない。はっきりとした作曲者の志向が感じられ、オーケストレーションを含めて、一線を画していた。これをひとたび耳にしてしまうと、他の作品はどこか木に竹を接いだような、生硬さがどうしても気になった。これには理由もあった。ひとつは作品が成立した時代の違い、もうひとつは僕個人の音楽体験の薄さとでもいうものである。
別宮氏の作品以外はすべて1940年前後のものであり、戦時下の日本社会に於ける音楽の位置づけを、反映したものとならざるを得なかった側面がある…とひとくくりに論じる事には慎重でありたい。が、そうした状況を度外視しても、例えば外交官としての海外勤務の中で、ハイデルベルグ大学で和声学・音楽学を聴講する機会を得た戸田邦雄氏以外は、みな日本国内で作曲を勉強せざるを得なかった人々である点で一致している。大雑把な括りをすれば明治以来、西洋音楽(とはいえドイツ音楽偏重である)を受容し、自身のものとすべく格闘した世代の作曲家群ともいえようか?或いは殊更に「日本的な」情緒を前面に押し出し、技法的に東西音楽の融合を図ろうとする試みも多々行われていた。そうした背景に基づいて創出された作品の数々から「こなれ切れないもの」を感じてしまいがちなのも無理はないのかもしれない。
その一方で、こうした作品に対する僕自身の音楽経験も全く不足していたとしか言いようがない。そもそも日本人の手になる管弦楽作品というものに接する機会そのものが極めて限られており、況してや1940年代以前のそれを生の音で聴く事については絶望的な状況だった(だからこそそうした作品を積極的に取り上げて紹介した「芥川也寸志と新交響楽団」はサントリー音楽賞受賞に値する活動と評価されたのだ)。大学入学後に初めてオーケストラというものに接してからせいぜい5年という段階で、身の周りに溢れる古今の名作を吸収することに手一杯の状況。音楽全般に対する知識はもちろんのこと、作品に対する関心も、足もとの日本のものにまでは到底及ぶべくもなかった。はっきり言えばとるに足らぬものとの認識が常にあったので、我が国の先人らによる作品の価値が解るようになるまでには、その後新響での演奏体験を重ねることが不可欠であった。が、それでも相応の時間を必要とした事を白状しておこう。
『管弦楽のための二つの祈り』は1956年に世に出ており、他の作品とは15年程度の開きがある。この15年間に日本社会が激変した事は周知の通りで、その様な状況下でこの作曲家は渡仏し、かの地で斯界の権威といえる大家らの下で修業を積んでいる。こんな機会を得られた人は他にはいない。それによって別宮氏に潜在していた「フランス趣味」が大きく発展・顕在化し、作品として確立したと考える必要があろう。それ故にこの作品は、従来の日本人の作品群から隔絶した響きと作風を示す異色の存在となった。当然の帰結と言えよう。
そしてそのような異色性こそが、ヨーロッパの音楽一辺倒で経験を積む事に一心不乱だった僕個人の「未熟な」耳にとっても、他に比して非常に親近感があったのだと思わざるを得ない。簡単に言えば解りやすかったのだ。
しかしながら…ここからがむしろ重要な点であろうが、5曲の中では別宮氏の『~二つの祈り』の演奏が、新響にとって最も困難だった。この時の録音は後にフォンテックよりCD化され、市販されている。それを聴くと判るのだが、演奏会を締めくくる最後の曲ながら、演奏の粗さがはっきり聴きとれるのである。「どうしたことか?」と思う訳だが、1980年代当時のアマチュアオーケストラは、概して「フランスもの」の演奏が下手だった。これもまた維新以来のドイツ偏重の音楽教育がもたらした明らかな弊害のひとつと今なら断言出来そうなところだ。つまりフランス音楽に対する経験知識の不足(はっきり「欠乏」というべきかもしれない)は明らかであったし、ドビュッシーやラヴェルの管弦楽作品に代表されるようなある種「曖昧模糊」とした音のイメージから、何となく芯のないもやもやとした発音を各楽器がしてしまい、総体として何ら輪郭のはっきりしない音の塊を仕上げてそれでよしとする結果に明け暮れていたように思う。
そもそも絶え間なくフランスの作曲家の作品をプログラムに取り上げ、地道に研鑽を積むという姿勢では無かった。独墺の「名曲」を常にメインに据えて、やや食傷すると口直し程度にフランスの作品をやるという頻度。これではうまくいく筈もなく、当事者たちも本番を終えると「やっぱりフランスものはさまにならなかった」「むずかしい」という反省になり、独墺の作品に回帰してしまうのだ。だからそのさまにならないフランス音楽の難しさというものをどう克服したら良いのかの?解が得られぬ状況が長く続く事になったのだ。私見だが新響でもその状態のまま20世紀が終ってしまった感がある。
つまり1983年当時の新響にとって『管弦楽のための二つの祈り』は芥川氏の情熱をもってしても、はっきり手に余る難物だったという事だ。演奏は他の曲のそれと同様に「直線的」に終始し、且つ輪郭を欠く曖昧模糊とした部分を含むという状況。となれば、もたらされた意に添わぬ結果は残念ながら当然の帰結で、本来違和感も意外性も無かったのである。
爾来40年になろうとしている。別宮氏のこの作品の演奏も今回で3回目となる。新響の取り組み方も全く変わり、しっかり結果を出せるようになった。
個人的なイメージでは2003年1月の第180回演奏会ではっきり潮目が変わったように感じている。このシーズンでは『牧神の午後への前奏曲』『牝鹿』『幻想交響曲』というフランス音楽の代表作を俎上に乗せるに当たり、指揮者の小松一彦氏がこれらの作品の演奏にふさわしい具体的奏法を細かく伝え、厳格に守るようオーケストラに求めたのだ。僕はこの当時演奏委員長の立場で、小松氏を新響に迎えるまでの様々な打合せの場に同席していたので、氏が上記の作品を選ぶ上でどのような考えを抱き、新響にアプローチしようと目論んでいるかを、かなり具体的に把握出来ていた。期待もした。そして指揮台に立つや、練習の現場で氏が絶えず求めたのは「明確な音」に徹して弾くことだった。「曖昧模糊」のイメージ先行とは真逆の形である。この厳然とした指導によって、確かに正しい結果をこのオーケストラから引き出したのだった。それ以後、パリを活動の本拠に据えた矢崎彦太郎氏を迎えて、その指導を受けるようにもなり、新響の「フランスもの」も少しずつ、でも着々とこなれたものになってきたように思う。これがこの20年ほどの間の事で、裏を返せば40年のうち前半20年は苦闘と模索の連続だったのである。
1983年4月の演奏会を思い起こしてまず感じるのは「若さ」だ。取り上げた作品もすべて作曲家の若書き。演奏する団員の平均年齢も30代前半と低かった(現在の平均年齢は知りたくもない)ので、それを反映した結果として演奏自体にも若さがあった。この若さには未熟・無謀・直情・無分別…などの否定的な側面も確かにある。
だが、いまになって当時の音を聴くと、その後の成熟に向かう過程で喪ってしまったかも知れないものにも気づく。なんと、それはまさにわが人生の軌跡にほかならないではないか(一向に成熟には向かわず、喪う一方ではあるが)との念を禁じ得ず。
ウォルトン:交響曲第1番
交響曲第1番に至るまで
1902年、ウィリアム・ウォルトンは音楽教師の父と歌手の母の息子としてイングランド北西部のオールダムで生まれた。少年期にピアノとヴァイオリンを学んだが習得には至らず、歌の素質があったことから、父親の指導する教会の合唱団に参加、その後、オックスフォードのクライストチャーチ大聖堂聖歌隊学校に10歳で入学、ここで音楽の才能を発揮。入学後に作曲も始め、無伴奏の合唱曲、独唱曲、オルガン曲など残している。
この才能あふれる少年は学生監の目に留まり、彼の取り計らいにより16歳でオックスフォード大学クライストチャーチ校へ進学。大学ではストラヴィンスキー、ドビュッシー、シベリウス、ルーセルなどの作品研究にのめりこんだようだが(正式な音楽教育ではない)、音楽以外の科目を落とし、学位を得ないまま中退することになってしまう。
1920年の大学中退後、オックスフォードの仲間だったサシャベレル・シットウェルとその兄オズバート・シットウェルは、ウォルトンをシットウェル家に招き入れるだけでなく、作曲に専念できるように経済的にも支援を行った。シットウェル家で出会った様々な人物との交流の影響もあり、1922年の「ファサード」(シットウェルの妹、イーディスの詩による朗唱と器楽による演奏。とても面白い!)、「弦楽四重奏曲」(ザルツブルクの音楽祭でアルバン・ベルクに賞賛される。本人はのちに破棄しているが。)に繋がっていく。
そしていよいよ1929年、有名な「ヴィオラ協奏曲」を発表。聴衆に熱狂的に受け入れられ大成功、その2年後に発表されたカンタータ「ベルシャザールの饗宴」が、ヴィオラ協奏曲に勝るとも劣らずまたまた大成功。次は交響曲!ウォルトンは交響曲作曲の動機を得ることになった。
インマ・フォン・ドルンベルク男爵夫人
「交響曲第1番」はインマ・フォン・ドルンベルク男爵夫人に捧げられている。
1929年、ウォルトンはドイツの若い未亡人であるドルンベルク夫人と出会い、恋に落ち、1931年の初めまでスイスのアスコナで生活を共にしていた。
ちょうど「ヴィオラ協奏曲」や「ベルシャザールの饗宴」の成功の時期と重なっていて、ドルンベルク夫人との充実した日々が創作意欲に大きく影響したということか。
「交響曲第1番」の作曲を開始した1932年3月、この時ウォルトンはイギリスのシットウェル家に滞在していたのだが、スイスのドルンベルク夫人の病気によって作曲を中断。5月にスイスに戻りそこで作曲を継続するものの、ハミルトン・ハーティ卿(このころ深く関わりのあった指揮者)と合意していた初演の時期を延期することになってしまう。
第1楽章と第2楽章は1933年の早い段階で完成させたが、第3楽章以降が遅れており、再び初演は延期。第3楽章の作業はその年の夏の間にも続けられ、1933年9月には第4楽章の冒頭やコーダのスケッチをするところまでは進んだものの、主要部分をどうするかで行き詰まり、第4楽章の作曲は中断。1934年3月に予定されていた初演は再び延期となる。
異例の「部分的」初演→全曲初演
ハーティ卿が首席指揮者を務めるロンドン交響楽団は、1934年の秋に「12月3日に先に出来上がった3つの楽章だけ初演する」と発表。ハーティ卿、先に出来上がっているものだけでも世に出して励ましとしたかったか、度重なる延期に業を煮やしたか。
第4楽章の中断は半年以上にも及んだが、これにはドルンベルク夫人との関係が悪化したことが影響しているという人もいれば、もともとウォルトンは作曲に時間をかけるという人もいる。確かに多作ではないし、「ベルシャザールの饗宴」では、あるフレーズに7か月もかけている。真実やいかに。
結局のところ、ウォルトンの日記でも読まない限り本当のところは分からないのだが、ドルンベルク夫人との関係は1934年に終わっていること、その年12月の部分的初演の前には別の女性、アリス・ウィンボーンとの新たな出会いがあったことから、第4楽章の作曲が中断している時期に、私生活がいろいろと「込み入っていた」ことだけは確かなようだ。
さて、ハーティ卿指揮による部分的初演が成功に終わったのちに、ウォルトンは第4楽章の作曲を再開。最終的に1935年8月30日に「交響曲第1番」は完成した。待望の全曲初演は再びハーティ卿指揮のもと、BBC交響楽団によって行われ、大衆と批評家の両方から大変な熱意をもって受け入れられた。
個人的にウダウダと
第2楽章にあまり目にすることがない「con malizia(悪意をもって)」という指示。「ははぁーん、これは何かあったな」と込み入ったドラマを期待して調べものに勤しんだ。
どうやらその期待は外れていなかったようなのだが、そうだったとしても、ウォルトン個人の経験を単純に交響曲に当てはめていったということではない。1930年代当時の不安定で不穏な世の中の影響だって無視はできないだろう。あくまでインスピレーションを得たであろう体験の1つとして、頭の片隅にチョコンと置いて聴いていただければと思う。
いずれにせよ、第3楽章の深い憂うつ(con malinconia)を経て、第4楽章の輝かしい冒頭→エネルギッシュなフーガ→壮大な終結に向かう様子は、長いトンネルを経て目に飛び込んでくる景色がハッピーであることを連想させる。
今回、コロナ禍により大規模編成の曲からウォルトンの「交響曲第1番」に変更となった。演奏会自体が中止になったり、曲目変更を余儀なくされたり、何かと制限がある日々が続いたが、大所帯の新響を活かした超がつくような大規模編成の曲にも、今後だれに遠慮することもなくチャレンジできる……長いトンネルの向こうにそんな世の中が待っているんじゃないかと、第4楽章の練習録音を聴きながら期待する筆者であった。
第1楽章 Allegro assai(きわめて速く)
第2楽章 Presto con malizia(急速に 悪意をもって)
第3楽章 Andante con malinconia(歩くような速さで 憂うつに)
第4楽章 Maestoso(荘厳に)
初演:
(第1楽章~第3楽章)1934年12月3日
指揮:ハミルトン・ハーティ卿 ロンドン交響楽団(クイーンズホール,ロンドン)
(全曲)1935年11月6日 BBCシンフォニーコンサート
指揮:ハミルトン・ハーティ卿 BBC交響楽団(クイーンズホール,ロンドン)
楽器編成:フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ(第4楽章のみ奏者2名)、シンバル、小太鼓、タムタム、弦五部
参考文献:
David Lloyd-Jones, William Walton Symphony No.1 Study Score, Oxford, 2002
金澤正剛『ヨーロッパ音楽の歴史』音楽の友社 2020年
マイケル・トレンド(木邨和彦訳)『イギリス音楽の復興 音の詩人たち、エルガーからブリテンへ』旺史社 2003年
柴田南雄/遠山一行 総監修『ニューグローヴ世界音楽大事典 第3巻』 p.43-46, Hugh Ottaway:奥田恵二訳 ウォルトン,ウィリアム(・ターナー) 講談社 1994年
TheFamousPeople.com(William Walton Biography)
https://www.thefamouspeople.com/profiles/william-walton-472.php (参照:2022年11月3日)
The Guardian(Symphony guide: William Walton's First)
https://www.theguardian.com/music/tomserviceblog/2014/apr/01/symphony-guide-william-walton-first (参照:2022年11月3日)
別宮貞雄《音楽は心の問題》 ~生誕100年に寄せて~
別宮貞雄(1922~2012)は、東京大学理学部物理学科(相対性理論)および同大学文学部美学科を卒業、在学中に毎日音楽コンクールに入賞し、パリ国立高等音楽院に留学した英才である。フランスではミヨーやメシアンのもとで作曲技法を学び、音楽観や世界観の上で大きな影響を受けつつ端正な古典的音楽形式を範とする美学観のもと、前衛的な語法による音楽創作から距離を置きながら、直截(ちょくせつ)で明快かつ豊かな旋律と抒情性に富む独自の作風を確立していった。その眼差しは終生ほとんどぶれていない。
代表作は繊細で美しい歌曲「さくら横ちょう」、優れた劇場感覚に満ちた狂言をもとにしたオペラ、合唱曲、管弦楽、室内楽、東宝特撮ホラー映画「マタンゴ」に代表される映画音楽など作品は多岐にわたる。基本的にはダイアトニックと三和音、多彩なリズムの変化により、情景や揺れ動く心を捉えていくという風情があり、近年では多くの作品が演奏会やメディアにて紹介されている。
「現代音楽のわかりにくさは人間の予知能力を無視したことによる由縁で、わからなくても慣れればわかるようになる、ということではなく、本当にいいものはすぐにわかる」という観点から、先入観のない鋭い批判精神を常に持ち続けていた。創作活動に加えて、大学での教育、評論や作曲家団体役員など多方面での活躍に反映されている。
根底には、自然科学的秩序としてのコスモロジーの中、音楽は観念を表現できないものだから、直観こそが重要で、作曲当時の自分を表現、すなわち「音楽は心の問題」という信念が見えてくる。
別宮貞雄の作曲家としての本格的な出発点は、ベートーヴェンの音楽への傾倒から、大学入学後に音楽の師を求め、ドイツ音楽理論家として名高い諸井三郎に習おうとしたところから始まる。学校の先輩で理系でもある箕作(みつくり)秋吉(しゅうきち)に相談したところ、池内友次郎を推薦され、和声法と対位法を習うことになった。池内はパリ国立高等音楽院に学び、フランス近代音楽の先駆者として後世多くの優秀な門下を輩出した名伯楽であり、師匠の選択は、作曲家としての人生に大きな影響を及ぼしたといえる。実は箕作秋吉と諸井三郎は犬猿の仲だったことを後に知った、と別宮貞雄は述べている。
管弦楽のための二つの祈り
フランス留学で身に付けた近代的作曲技術の集約として、並々ならぬ意気込みで作曲した初期創作活動の到達点ともいえる作品である。純音楽的には「前奏曲、ファンファーレとフーガ」という構成で「当時の世界というものに向かい合った心の状態を表現したもの」と別宮貞雄は後に述べている。
第1楽章 Douloureux「悲しみを持って」
相互に関連性を持つ主題が交互に登場する変奏曲ともいえる。短三度を伴う主題と半音階的進行を伴う対位。八分の七拍子、八分の五拍子と進行して情感に溢れ、心が動いていく。
第2楽章 Vaillant「雄々しく」
ファンファーレに続いて増四度による緊張に満ちた主題が登場しフーガで展開していく。強靭ともいえる主題と構成でクライマックスを構築するストレッタでは、トランペットに定旋律(Cantus Firmus)としてグレゴリオ聖歌「クレド」の主題が登場する。クレド(Credo)は「信条」「約束」、キリスト教で「信仰宣言」。明確な三和音で力強く終止する。
初演:1956年5月10日東京交響楽団第78回定期演奏会
指揮:斎藤秀雄 東京交響楽団(日比谷公会堂)
受賞:1956年 毎日音楽賞(第8回)、尾高賞(第5回)
楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、小太鼓、中太鼓、大太鼓、シンバル、タムタム、トライアングル、チェレスタ、ピアノ、ハープ、弦五部
第3交響曲「春」
新潟県妙高高原の赤倉にて春スキーを楽しんでいるときに着想を得たという。前衛への反証として西洋近代の伝統的形式にこだわった第1交響曲、その反動として無調的な傾向のヴァイオリン協奏曲、さらに反動で辛辣な第2交響曲、そのまた反動で、自分が書きたいものを素直に書こうとした第3交響曲「春」、「春」とくれば「夏」として、大戦と終戦という深刻な第4交響曲「夏」、家族の不幸(奥様の逝去)による悲しみのチェロ協奏曲、そして最も古典的で「運命」の動機という第5交響曲「人間」と続いている。
第1楽章 「春の訪れ」(あっという間に春はやってくる)
春の息吹を告げる導入、ファンファーレの高まりから第1主題に入る。長い主題の後に対照的な第2主題が提示される。後半はソナタ形式の展開部と再現部が融合されたようなもので、終結はファンファーレが想起されてくる。冒頭のホルンから始まる春の目覚めと厚みを増す感情の高揚、4本のトロンボーンの硬質な響きと金管の重奏が、自然の威容と厳しさを表現しているのだろうか。
第2楽章 「花咲き、蝶は舞い・・・・・・」(そして鳥がさえずる。深い山の中の自然の美しさ)
自然の息遣いに満ちた風情がある。鳥のさえずりにはさまれた蝶の舞いが優雅。
第3楽章 「人は踊る」(人々は浮かれだす)
短い序奏で始まる舞曲。単に浮かれているだけではなく、ディズニーランドのパレードとかミッキーマウス・マーチのように、人々が踊りながら行進していくような躍動感がある。2つの主題によるソナタ形式で、展開部では第3の主題も出てくる。
初演:
(第1楽章のみ)「祝典序曲」としてNHK委嘱初演
1981年10月31日 音楽コンクール50周年記念演奏会
指揮:森正 NHK交響楽団(NHKホール)
(放送初演)1984年4月5日 NHK-FM
指揮:荒谷俊治 東京フィルハーモニー交響楽団
(初演)1987年3月19日 現代の音楽展’87
指揮:山田一雄 東京フィルハーモニー交響楽団(新宿文化センター)
楽器編成:フルート2、オーボエ2(2番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン4、ティンパニ、小太鼓、大太鼓、シンバル、タンバリン、トムトム3、トライアングル、チェレスタ、ハープ、弦五部
作品への想い
新交響楽団は、過去に2回、別宮貞雄の「管弦楽のための二つの祈り」を取り上げてきた。
第99回演奏会
「日本の交響作品展7 青春の作曲家たち」
1983年4月3日(日) 東京文化会館(指揮:芥川也寸志)
第233回演奏会
「新交響楽団創立60周年1956-2016」
2016年4月10日(日) 東京芸術劇場(指揮:飯守泰次郎)
長年にわたり日本の近現代作品に触れていると、個々の作曲家の持つ機能的・論理的な表現手段としての作品への関心とともに創造の感性が磨かれていき、練習を重ねていく毎に高まる緊迫感とテンションが研ぎ澄まされていく。音楽創造体験の厳しさと面白さがそこにある。
別宮貞雄の作品も、堅固な構成とともに感覚的で豊かな情感と美しさ、その中に厳しさと緊張感があり、技術を尽くして音楽を鍛えて磨いていく創作過程と作曲家の感性・感情を創造しながら、心の琴線に触れつつ、いつも新たな気持ちで演奏会を迎えている。
別宮貞雄氏とは、新交響楽団をはじめ多くの演奏会にてそのお姿をお見かけし、筆者にも自然体そのもので接していただいた。
筆者は今回で「管弦楽のための二つの祈り」の演奏が3回目となる。最初は20代半ば、2回目は50代半ば、そして還暦を過ぎた今回と、年を経ての演奏体験を通して、年齢を重ねるたびに別宮貞雄の音楽すなわち心の表現への理解が異なっていることに気づかされた。さらに深い理解のもと臨んでいきたい。
参考文献:
『NEW COMPOSER 2003 vol.4』(日本現代音楽協会 会報)
『NEW COMPOSER 2005 vol.6』(日本現代音楽協会 会報)
新交響楽団第233回演奏会<古典的な構築形式と豊かな感情表現の融合>(新交響楽団 筆者記載)
http://www.shinkyo.com/concert/p233-1.html
別宮貞雄作品集/第3交響曲「春」第4交響曲「夏1945年」-現代日本の作曲家シリーズ3/FOCD2510 (株)フォンテック
1996-2000年の演奏会
第171回演奏会
2000年10月7日(土)東京芸術劇場大ホール
曲目 ウェーバー/「オベロン」序曲
メンデルスゾーン/交響曲第4番「イタリア」
ドヴォルザーク/交響曲第7番
ドヴォルザーク/スラブ舞曲第1番(アンコール)
指揮 原田幸一郎
<東京の夏>音楽祭「映画と音楽」
2000年7月30日(日)紀尾井ホール
曲目 サン=サーンス/「ギース公の暗殺」(映像付)
武満 徹/3つの映画音楽
コープランド/映画のための音楽
サティ/「幕間」(映像付)
指揮 小松一彦
主催 アリオン音楽財団/朝日新聞社
第170回演奏会
2000年7月15日(土)東京文化会館大ホール
曲目 ラヴェル/高雅で感傷的なワルツ
小倉 朗/管弦楽のための舞踏組曲
ストラヴィンスキー/バレエ音楽「火の鳥」(全曲版)
指揮 飯守泰次郎
第169回演奏会
2000年4月30日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 ショスタコーヴィチ/交響詩「10月革命」
同/交響曲第7番「レニングラード」
指揮 小泉和裕
第168回演奏会
2000年1月29日(土)東京芸術劇場大ホール
曲目 シューマン/交響曲第3番「ライン」
ヴィラ=ロボス/ブラジル風バッハ第7番
諸井三郎/交響曲第3番
指揮 飯守泰次郎
合唱団鯨演奏会
1999年11月28日(日)東京国際フォーラム
曲目 芥川也寸志/交響管絃楽のための音楽
芥川也寸志/21世紀賛歌「人間はまだ若い」
ベートーヴェン/交響曲第9番「合唱付き」
指揮 黒岩英臣
第167回演奏会
1999年10月11日(月祝)東京芸術劇場大ホール
曲目 グリンカ/歌劇「ルスランとリュドミラ」より序曲
カリンニコフ/交響曲第1番
チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」
指揮 ヴィクトル・ティーツ
第166回演奏会<芥川也寸志没後10年>
1999年7月11日(日)サントリーホール
曲目 芥川也寸志/交響三章(トリニタ・シンフォニカ)
同/交響管絃楽のための音楽
同/絃楽のための三楽章(トリプティーク)
同/交響曲第1番
同/エローラ交響曲
(アンコール:「赤穂浪士」)
指揮 飯守泰次郎
松伏町芥川也寸志没後10年演奏会
1999年7月17日(土)田園ホール・エローラ(埼玉県松伏町)
曲目 芥川也寸志/「えり子とともに」
同/「煙突の見える場所」
同/「猫と庄造と二人のおんな」
同/「赤穂浪士」
同/「八甲田山」
同/トリプティーク
同/エローラ交響曲
指揮 飯守泰次郎
奏楽堂芥川也寸志没後10年演奏会
1999年7月18日(日)旧東京音楽学校奏楽堂(上野公園)
曲目 (7/17のエローラ交響曲に替わり第一交響曲)
指揮 飯守泰次郎
新交響楽団九州演奏会
5月2日(日)福岡アクロスシンフォニーホール(福岡市民オーケストラと合同演奏会)
曲目 ベルリオーズ/幻想交響曲(福岡市民オーケストラ)
伊福部 昭/シンフォニア・タプカーラ(新交響楽団)
チャイコフスキー/祝典序曲「1812年」(合同演奏)
芥川也寸志/交響管絃楽のための音楽より第2楽章(アンコール)
指揮 井崎正浩
5月3日(祝)熊本県立劇場
曲目 チャイコフスキー/祝典序曲「1812年」
プロコフィエフ/舞踏音楽「ロメオとジュリエット」より
伊福部 昭/シンフォニア・タプカーラ
芥川也寸志/トリプティークより第2楽章(アンコール)
同/交響管絃楽のための音楽より第2楽章(アンコール)
指揮 井崎正浩
5月4日(休)九州厚生年金会館(小倉)
曲目、指揮は5月3日と同じ
第165回演奏会
1999年4月17日(土)東京芸術劇場
曲目 チャイコフスキー/祝典序曲「1812年」
伊福部 昭/シンフォニア・タプカーラ
プロコフィエフ/舞踏音楽「ロメオとジュリエット」より
指揮 井崎正浩
第164回演奏会
1999年1月16日(土)東京芸術劇場
曲目 ブラームス/交響曲第3番ヘ長調
深井史郎/パロディ的な4楽章
サン=サーンス/交響曲第3番ハ短調「オルガン付」
指揮 飯守泰次郎
オルガン 松居直美
第163回演奏会
1998年10月4日(日)東京芸術劇場
曲目 リスト/レ・プレリュード
シューベルト/交響曲第8番ロ短調「未完成」
R.シュトラウス/ツァラトゥストラはかく語りき
J.シュトラウス/歌劇「こうもり」序曲(アンコール)
指揮 大町陽一郎
第162回演奏会
1998年7月12日(日)東京芸術劇場
曲目 ワーグナー/「ニーベルングの指環」ハイライト
虹の掛け橋とワルハラ城への神々の入場...「ラインの黄金」より
ワルキューレの騎行...「ワルキューレ」より
ヴォータンの告別と魔の炎の音楽...「ワルキューレ」よリ
森のささやき...「ジークフリート」より
夜明けとジークフリートのラインの旅...「神々の黄昏」より
ジークフリートの死と葬送行進曲...「神々の黄昏」より
ブリュンヒルデの自己犠牲...「神々の黄昏」より
指揮 飯守泰次郎
独唱 ソプラノ 小濱妙美 バリトン 多田羅迪夫
第161回演奏会
1998年4月18日(土)東京芸術劇場
曲目 メシアン/交響的瞑想「忘れられた捧げ物」
マーラー/交響曲第6番「悲劇的」
指揮 小泉和裕
第160回演奏会
1998年1月17日(土)東京芸術劇場大ホール
曲目 深井史郎/舞踊曲「創造」
ブリテン/シンフォニア・ダ・レクイエム
シベリウス/交響曲第2番
指揮 渡邉康雄
第159回演奏会
1997年10月10日(金・祝)東京芸術劇場
曲目 ドビュッシー/交響組曲「春」
スクリャービン/法悦の詩(交響曲第4番)
ブラームス/交響曲第4番
指揮 飯守泰次郎
第158回演奏会
1997年7月6日(日)東京芸術劇場
曲目 ストラヴィンスキー/春の祭典
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番
指揮 井崎正浩
第157回演奏会
1997年4月5日(土)東京芸術劇場
曲目 武満 徹/鳥は星形の庭に降りる
ブルックナー/交響曲第7番
指揮 飯守泰次郎
第156回演奏会
1997年1月25日(土)東京芸術劇場
曲目 連作交響詩「わが祖国」全曲
指揮 小林研一郎
第155回演奏会/創立40周年記念シリーズ4
1996年10月10日(木・祝)オーチャードホール
曲目 ベートーヴェン/序曲「レオノーレ」第3番
交響曲第6番「田園」
交響曲第5番「運命」
指揮 原田幸一郎
第153・154回演奏会/創立40周年記念シリーズ3
日本の交響作品展 '96
1996年7月6日(土)東京芸術劇場
曲目 尾高尚忠/みだれ(1938、47改作)
早坂文雄/ピアノ協奏曲第1番(1948)
橋本国彦/交響曲ニ調(1940)
指揮 本名徹二
ピアノ独奏 野平一郎
1996年7月7日(日)サントリーホール
曲目 平尾貴四男/俚謡による変奏曲(1938)
松平頼則/パストラル(1935)
深井史郎/ジャワの唄声(1942)
諸井三郎/交響曲第3番(1944)
指揮 本名徹二
第152回演奏会/創立40周年記念シリーズ2
1996年4月14日(日)東京芸術劇場
曲目 ハチャトゥリアン/バレエ音楽「ガイーヌ」より
ショスタコーヴィッチ/交響曲第9番
プロコフィエフ/交響曲第5番
指揮 小泉和裕
第151回演奏会/創立40周年記念シリーズ1
1996年1月20日(土)東京芸術劇場
曲目 ワーグナー/歌劇[タンホイザー]より序曲とヴェーヌスベルクの音楽<パリ版>
ワーグナー/楽劇[ワルキューレ]より第1幕全曲(演奏会形式)
指揮 飯守泰次郎
独唱 ジークリンデ 渡辺美佐子
ジークムント 若本明志
フンディング 高橋啓三
※チラシなどは準備中です。
2001-2006年の演奏会
第195回演奏会<創立50周年シリーズ・4>
2006年11月12日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 ワーグナー/楽劇「トリスタンとイゾルデ」抜粋
(演奏会形式)
指揮 飯守泰次郎
独唱 トリスタン:成田勝美(T)、イゾルデ:緑川まり(S)、マルケ王:長谷川顯(B)、ブランゲーネ:小山由美(MS)、クルヴェナール:成田博之(Br)
合唱 栗友会・樹の会
第194回演奏会<創立50周年シリーズ・3>
2006年7月22日(土)サントリーホール
曲目 芥川也寸志/交響管絃楽のための音楽
伊福部昭/管絃楽のための日本組曲
黛敏郎/涅槃交響曲
指揮 小松一彦
(指揮は岩城宏之氏を予定しておりましたが、6月13日に逝去されたため変更になりました。)
男性合唱 栗友会
第193回演奏会<創立50周年シリーズ・2>
2006年4月16日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 伊福部 昭/管絃楽のための日本組曲より「七夕」(追悼演奏)
猿谷紀郎/Swells of Athena 揺光の嵩まり
ショスタコーヴィチ(バルシャイ編)/室内交響曲 Op.110a
R.シュトラウス/アルプス交響曲
指揮 高関 健
第192回演奏会<創立50周年シリーズ・1>
2006年1月22日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 三善 晃/交響三章
ショスタコーヴィチ/交響曲第8番
アンコール:ショスタコーヴィチ編/タヒチ・トロット(二人でお茶を)
指揮 小松一彦
第191回演奏会
2005年10月16日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 シベリウス/交響詩「ポヒョラの娘」
シベリウス/ヴァイオリン協奏曲
ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」
指揮 渡邉康雄
ヴァイオリン独奏 アナスタシア・チェボタリョーワ
第190回演奏会
2005年7月17日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 矢代秋雄/交響曲
ラヴェル/バレエ音楽「ダフニスとクロエ」(全曲版)
指揮 飯守泰次郎
合唱 栗友会
第189回演奏会
2005年4月17日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 ベートーヴェン/序曲「エグモント」
シューマン/交響曲第4番
ブラームス/交響曲第2番
指揮 飯守泰次郎
第188回演奏会2005年1月16日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 ローマ三部作
レスピーギ/交響詩「ローマの祭」
同/交響詩「ローマの噴水」
同/交響詩「ローマの松」
指揮 小松一彦
龍ケ崎第九演奏会(龍ケ崎市文化振興事業団 市制50周年記念事業)
2004年12月12日(日)龍ケ崎市文化会館
曲目 ベートーヴェン/交響曲第9番「合唱付き」
指揮 大町陽一郎
独唱 ソプラノ三縄みどり、アルト加納悦子、テナー井ノ上了史、バス黒田博
合唱 龍ケ崎第九市民合唱団
第187回演奏会
2004年10月17日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 オール・チャイコフスキー・プログラム
歌劇「エフゲニー・オネーギン」 よりポロネーズ
組曲「くるみ割り人形」
幻想序曲「ロメオとジュリエット」
交響曲第4番
指揮 ヴィクトル・ティーツ
大久保混声合唱団 第31回定期演奏会
2004年8月1日(日)新宿文化センター大ホール
曲目 ブラームス/Nanie~哀悼歌~
高田三郎/わたしの願い
指揮 辻 志朗
第186回演奏会
2004年7月4日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第3番
シベリウス/交響詩「タピオラ」
シベリウス/交響曲第7番
指揮 渡邉康雄
ピアノ独奏 ウラジミール・オフチニコフ
郡山特別演奏会(郡山文化協会 市制80周年記念事業)
2004年6月5日(土)郡山市民文化センター大ホール
曲目 ベートーヴェン/交響曲第5番「運命」
湯浅譲二/交響組曲「奥の細道」
R.シュトラウス/歌劇「ばらの騎士」組曲
指揮 本名徹次
主催 郡山文化協会
第185回演奏会
2004年4月17日(土)東京芸術劇場大ホール
曲目 R.シュトラウス/歌劇「ばらの騎士」組曲
石井眞木/交響詩「幻影と死」(遺作・完全版初演)
ベートーヴェン/交響曲第5番(クライヴ・ブラウンによる新校訂版)
指揮 高関 健
第184回演奏会
2004年1月18日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 安部幸明/交響曲第1番
ラヴェル/ラ・ヴァルス
フランク/交響曲ニ短調
指揮 小松一彦
第183回演奏会
2003年10月11日(土)東京芸術劇場大ホール
曲目 プロコフィエフ/組曲「キージェ中尉」
ラフマニノフ/パガニーニの主題による狂詩曲*
アンコール:ラフマニノフ/前奏曲Op.24-4ニ長調(ピアノ)
ベートーヴェン/交響曲第7番
指揮 小泉和裕
ピアノ独奏 ウラジミール・オフチニコフ*
第182回演奏会
2003年7月20日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 湯浅譲二/交響組曲「奥の細道」
R.シュトラウス/4つの最後の歌
シューマン/交響曲第2番
指揮 飯守泰次郎
ソプラノ 緑川まり
第181回演奏会
2003年4月27日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 石井眞木/秋のヴァリアンテ(追悼演奏)
バルトーク/中国の不思議な役人
ピーター・バルトークによるオリジナルスコア復元版(合唱付き)全曲
ヴァイル/交響曲第2番
バーンスタイン/管弦楽のためのディヴェルティメント
指揮 高関 健
合唱 東京アカデミッシュカペレ
第180回演奏会
2003年1月26日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 ドビュッシー/牧神の午後への前奏曲
プーランク/バレエ組曲「牝鹿」
ベルリオーズ/幻想交響曲(独奏コルネット付き初演版/べーレンライター社原典版)
ベルリオーズ/ラコッツイ行進曲(アンコール)
指揮 小松一彦
第179回演奏会
2002年10月14日(月・祝)東京芸術劇場大ホール
曲目 シベリウス/フィンランディア
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番
シベリウス/交響曲第1番
シベリウス/カレリア組曲よりマーチ(アンコール)
指揮 渡邉康雄
ピアノ独奏 アンドレイ・ピサレフ
北欧音楽祭すわ2002 新交響楽団演奏会
2002年11月3日(日)下諏訪総合文化センター やまびこホール
曲目 シベリウス/フィンランディア
スウェーデン民謡/二人だけの牧場に
ノルウェー民謡/セーテルの娘の日曜日
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番
シベリウス/交響曲第1番
ピアノ独奏 ウラジミール・オプチニコフ
合唱 北欧音楽祭すわ合唱団
指揮 渡邉康雄
主催 北欧音楽祭すわ2002実行委員会
新交響楽団 長野演奏会
2002年11月4日(月・休)長野県県民文化会館大ホール
曲目 藤森 章(編)/オープニングファンファーレシベリウスプロローグ*
シベリウス/交響曲第1番
チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番
グレインジャー/チャイコフスキーの花のワルツにもとづくパラフレーズ
(ピアノ独奏:アンコール)
シベリウス/フィンランディア(管打楽器*)
同/カレリア組曲よりマーチ(アンコール:管打楽器合同演奏)
ピアノ独奏 ウラジミール・オプチニコフ
共演 長野県高校選抜吹奏楽団*
指揮 渡邉康雄
第178回演奏会
2002年7月13日(土)東京芸術劇場大ホール
曲目 ワーグナー/ファウスト序曲
ブルックナー/交響曲第8番(ノヴァーク原典版)
指揮 飯守泰次郎
伊福部 昭米寿記念演奏会
2002年5月19日(日)紀尾井ホール
曲目 伊福部昭/土俗的三連画(1937年)
伊福部先生の米寿を祝う「四つの舞」(2002年)
1.扇の舞 石井眞木
2.魂殖ゆの舞 眞鍋理一郎*
3.皐月の舞 三木 稔***
4.悠久の舞 今井重幸**
伊福部昭/ギリヤーク族の古き吟誦歌(1946年)
[オーケストラ編曲1984年:芥川也寸志・松村禎三・黛敏郎・池野成]
伊福部昭/シンフォニア・タプカーラ(1954年)(1979年改訂版)
伊福部昭/SF交響ファンタジー第1番より抜粋
指揮 石井眞木,真鍋理一郎*,今井重幸**,榊原 徹***
ソプラノ 宇佐美瑠璃
2002年4月20日(土)東京文化会館大ホール
曲目 J.S.バッハ-菅原明朗/パッサカリア
J.S.バッハ-シェーンベルク/前奏曲とフーガ
マーラー/交響曲第1番「巨人」
指揮 小泉和裕
第176回演奏会
2002年1月13日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 ブリテン/青少年のための管弦楽入門
ーパーセルの主題による変奏曲とフーガ
ヤナーチェク/狂詩曲「タラス・ブーリバ」
メンデルスゾーン/交響曲第3番「スコットランド」
指揮 ジェームス・ロックハート
第175回演奏会
2001年10月13日(土)東京芸術劇場大ホール
曲目 ダンディ/「魔の森」
メンデルスゾーン/「真夏の夜の夢」より
ブラームス/交響曲第1番
指揮 飯守泰次郎
第174回演奏会
2001年7月28日(土)東京文化会館大ホール
曲目 ラフマニノフ/歌劇「アレコ」より
間奏曲・女性の踊り・男性の踊り
同/ピアノ協奏曲第2番
同/交響曲第3番
同/ヴォカリース(アンコール)
指揮 ヴィクトル・ティーツ(ハバロフスク極東交響楽団芸術監督)
ピアノ タチヤナ・ザゴロフスカヤ(サンクトペテルスブルグ音楽院助教授)
第173回演奏会<山田一雄没後10年>
2001年4月28日(土)東京芸術劇場大ホール
曲目 山田和男/おほむたから(大みたから)
マーラー/交響曲第5番
指揮 飯守泰次郎
第172回演奏会
2001年1月27日(土)東京芸術劇場大ホール
曲目 ウォルトン/序曲「ポーツマス・ポイント」
ブリテン/四つの海の間奏曲
ホルスト/組曲「惑星」
ウォルトン/「スピットファイヤー」よりプレリュード(アンコール)
指揮 ジェームス・ロックハート
会津第九の会 第8回公演
2000年12月24日(日)會津風雅堂(福島県会津若松市)
曲目 ウォルトン/序曲「ポーツマス・ポイント」
ベートーヴェン/交響曲第9番「合唱付き」
指揮 ジェームス・ロックハート
独唱 左近史江、吉田和子、佐藤淳一、石原貴之
合唱 会津第九の会
※チラシなどは準備中です。
1976~1985年の自主演奏会の記録
<1985年>
第109回演奏会(11月3日)東京文化会館
ベルリオーズ/序曲「ローマの謝肉祭」
ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第5番
チャイコフスキー/交響曲第4番
指揮:芥川也寸志 ピアノ:須田真美子
第108回演奏会(7月20日)新宿文化センター
<マーラーシリーズ7>
シューベルト/交響曲第8番
マーラー/交響曲「大地の歌」
指揮:山田一雄
第107回演奏会(4月7日)東京文化会館
<日本の交響作品展9「小山清茂」>
小山清茂/管弦楽のための「信濃囃子」
同/弦楽のための「アイヌの唄」
同/管弦楽のための「鄙歌」第1番
同/管弦楽のための「うぶすな」
同/交響組曲「能面」
指揮:芥川也寸志
第106回演奏会(1月27日)新宿文化センター
近衛秀麿/越天楽
ブラームス/交響曲第3番
ホルスト/組曲「惑星」
指揮:山岡重信
<1984年>
第105回演奏会(9月26日)昭和女子大学人見記念講堂
<マーラーシリーズ6>
マーラー/交響曲第3番
指揮:山田一雄 独唱:伊原直子 合唱:晋友会、藤沢ジュニアコーラス
第104回演奏会(6月24日)新宿文化センター
ベートーヴェン/交響曲第3番
ワーグナー/楽劇「神々の黄昏」より
指揮:山田一雄
第103回演奏会(4月1日)東京文化会館
<日本の交響作品展8「東北の作曲家たち」>
伊東俊幸/オーケストラのためのコンポジション
佐藤喜美/エメラルドの幻影
林芳輝/筝と管弦楽のためのラプソディ
安達弘潮/遠き神々の物語
片岡良和/抜頭によるコンポジション
指揮:芥川也寸志 箏:松坂尚子 語り:熊倉一雄
第102回演奏会(1月29日)新宿文化センター
モーツァルト/交響曲第40番
伊福部/ラウダ・コンチェルタータ
ショスタコービッチ/交響曲第5番
指揮:芥川也寸志 マリンバ:安倍圭子
<1983年>
第101回演奏会(11月1日)東京文化会館
<マーラーシリーズ5>
柴田南雄/北園克衛の「三つの詩」
マーラー/交響曲第2番「復活」
指揮:山田一雄 独唱:大島洋子、木村宏子 合唱:新星日響合唱団
第100回演奏会(6月26日)新宿文化センター
芥川也寸志/交響管絃楽のための音楽
ベートーヴェン/交響曲第9番
指揮:芥川也寸志 独唱:S常森寿子、A伊原直子、T林 誠、B栗林義信
合唱:湘南市民コール、松原混声合唱団
第99回演奏会(4月3日)東京文化会館
<日本の交響作品展7「青春の作曲家たち」>
小倉朗/交響曲イ短調
松平頼則/南部子守歌を主題とするピアノとオルケストルの為の変奏曲
戸田邦雄/交響幻想曲「伝説」
渡辺浦人/交響組曲「野人」
別宮貞雄/管弦楽のための「二つの祈り」
指揮:芥川也寸志 ピアノ:土屋律子
第98回演奏会(1月23日)簡易保険ホール
<マーラーシリーズ4>
モーツァルト/交響曲第35番
マーラー/交響曲第9番
指揮:山田一雄
<1982年>
第97回演奏会(9月15日)東京文化会館
ショスタコービッチ/祝典序曲
伊福部/日本狂詩曲
チャイコフスキー交響曲第5番
指揮:芥川也寸志
第96回演奏会(7月3日)簡易保険ホール
ベートーヴェン/交響曲第6番「田園」
バルトーク/管弦楽のための協奏曲
指揮:山岡重信
第95回演奏会(4月2日)東京文化会館
<日本の交響作品展6「清瀬保二」>
佐藤敏直/哀歌
清瀬保二/郷土舞踊
同/エレジー亡き母に捧ぐ
同/古代に寄す
同/ピアノ協奏曲
同/日本祭礼舞曲
指揮:芥川也寸志 ピアノ:林 光
<1981年>
第94回演奏会(11月29日)東京文化会館
バッハ-菅原明朗編曲/パッサカリア
ショスタコーヴィチ/交響曲第11番「1905年」
指揮:芥川也寸志
第93回演奏会(9月19日)新宿文化センター
<マーラーシリーズ3>
マーラー/交響曲第7番
指揮:山田一雄
第92回演奏会(7月29日)東京文化会館
芥川也寸志/コンチェルト・オスティナート
ブルックナー/交響曲第7番
指揮:山岡重信 チェロ:安田謙一郎
第91回演奏会(4月5日)東京文化会館
<日本の交響作品展5「菅原明朗」>
菅原明朗/交響写景「明石海峡」
同/チマローザの断章による合奏協奏曲
同/アコーディオンのための協奏交響楽
同/交響的幻影イタリア
同/ファンタジア
指揮:芥川也寸志 アコーディオン:御喜美江
<1980年>
第90回演奏会(11月20日)日比谷公会堂
<マーラーシリーズ2>
モーツァルト/コンチェルト・ロンド二長調
マーラー/交響曲第6番
指揮:山田一雄 ピアノ:渡辺 達
第89回演奏会(9月6日)東京文化会館
ストラビンスキー/バレエ音楽「春の祭典」
ブラームス/交響曲第1番
指揮:山岡重信
第88回演奏会(6月15日)東京文化会館
プロコフィエフ/「ロミオとジュリエット」より
ベートーヴェン/交響曲第7番
指揮:河地良智
第87回演奏会(4月6日)東京文化会館
<日本の交響作品展4「伊福部昭」>
伊福部昭/ラウダ・コンチェルタータ
同/ヴァイオリン協奏曲第2番
同/タプカーラ交響曲
指揮:芥川也寸志 マリンバ:安倍圭子 ヴァイオリン:小林武史
<1979年>
第86回演奏会(12月1日)東京文化会館
<マーラーの夕べ>
マーラー/「花の章」
マーラー/交響曲第5番
指揮:山田一雄
第85回演奏会(8月4日)東京文化会館
芥川也寸志 /交響三章
チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」
指揮:芥川也寸志
第84回演奏会(6月2日)日比谷公会堂
ヒンデミット/ウェーバーの主題のよる交響的変容
シューベルト/交響曲第9番「グレート」
指揮:河地良智
第83回演奏会(4月6日)東京文化会館
<日本の交響作品展3「早坂文雄」>
早坂文雄/映画音楽「羅生門」より
同/古代の舞曲
同/左方の舞と右方の舞
同/管弦楽のための変容
指揮:芥川也寸志
<1978年>
第82回演奏会(12月1日)日比谷公会堂
<リヒャルト・シュトラウスの夕べ>
R.シュトラウス/ティルオイレンシュピーゲルの愉快な悪戯
R.シュトラウス/楽劇「サロメ」より7つのベールの踊り
R.シュトラウス/交響詩「英雄の生涯」
指揮:河地良智
第81回演奏会(8月4日)郵便貯金ホール
<サマーコンサート>
ドボルザーク/交響曲第9番「新世界より」
ロッシーニ/「どろぼうかささぎ」序曲
レオンカバルロ/「道化師」間奏曲
ヴェルディ/「椿姫」前奏曲
ヴェルディ/「運命の力」序曲
指揮:尾高忠明
第80回演奏会(4月26日)日比谷公会堂
<小倉朗交響作品展第2夜>
小倉朗/オーケストラのための舞踊組曲
同/ヴァイオリン協奏曲
同/弦楽合奏のためのコンポジション
同/オーケストラのためのコンポジション
指揮:芥川也寸志 ヴァイオリン独奏:都河和彦
第79回演奏会(4月1日)東京文化会館
<小倉朗交響作品展第1夜>
小倉朗/交響組曲イ短調
同/日本民謡による5楽章
同/オーケストラのためのブルレスク
同/交響曲ト調
指揮:芥川也寸志
<1977年>
第78回演奏会(10月3日)神奈川県民ホール・(11月6日)渋谷公会堂
ベートーヴェン/交響曲第5番「運命」
ベートーヴェン/交響曲第3番「英雄」
指揮:河地良智
第77回演奏会(8月4日)東京文化会館・(8月8日)大阪フェスティバルホール
<鳥井賞受賞記念コンサート>
清瀬保二/日本祭礼舞曲
箕作秋吉/小交響曲ニ長調
尾高忠尚/日本組曲
早坂文雄/古代の舞曲
伊福部昭/交響譚詩
指揮:芥川也寸志
第76回演奏会(4月4日)東京文化会館
ショスタコービッチ/交響曲第7番「レニングラード」
指揮:芥川也寸志
第75回演奏会(2月1日)虎ノ門ホール
プーランク/牡鹿
バルトーク/弦楽のためのディベルティメント
ブラームス/交響曲第2番
指揮:堤俊作
<1976年>
第74回演奏会(10月11日)東京文化会館
<日本の交響作品展昭和8年~18年(第2夜)>
清瀬保二/日本祭礼舞曲
安倍幸明/小組曲
高田三郎/山形民謡によるバラード
諸井三郎/小交響曲変ロ調
伊福部昭/交響譚詩
指揮:芥川也寸志
第73回演奏会(9月3日)東京文化会館
<日本の交響作品展昭和8年~18年(第1夜)>
平尾貴四男/古代讃歌
箕作秋吉/小交響曲ニ長調
大木正夫/五つのお伽噺
尾高忠尚/日本組曲
早坂文雄/古代の舞曲
指揮:芥川也寸志
第31回定期演奏会(3月29日)郵便貯金ホール
シャブリエ/スペイン狂詩曲
プロコフィエフ/キージェ中尉
シベリウス/交響曲第2番
指揮:芥川也寸志
1986~1995年の自主演奏会の記録
<1995年>
第150回演奏会(10月15日)東京芸術劇場
ブラームス/悲劇的序曲
ヒンデミッ/ウェーバーの主題による交響的変容
ベートーヴェン/交響曲第3番「英雄」
指揮:原田幸一郎
第149回演奏会(7月30日)サントリーホール
ワーグナー/歌劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」第一幕への前奏曲
ブルックナー/交響曲第8番
指揮:飯守泰次郎
第148回演奏会<映画誕生100年記念演奏会>(7月16日)東京芸術劇場
サン=サーンス/「ギース公の暗殺」
アイスラー/「雨」についての14の描写
サティ/幕間
深井史郎/「空想部落」
武満 徹/弦楽器のための「ホゼイトレス」
芥川也寸志/「煙突の見える場所」「猫と庄造と二人の女」「八甲田山」「日蓮」
指揮:小松一彦 司会:秋山邦晴
第147回演奏会(4月30日)東京芸術劇場
モーツァルト/交響曲第31番
マーラー/交響曲第7番
指揮:小泉和裕
第146回演奏会(1月16日)東京芸術劇場
ベートーヴェン/交響曲第2番
ドビュッシー/交響詩「海」
ファリャ/バレエ「三角帽子」全曲
指揮:フランシス・トラヴィス メゾソプラノ独唱:福田玲子
<1994年>
第145回演奏会(10月10日)東京芸術劇場
ウェーバー/歌劇「魔弾の射手」序曲
ベートーヴェン/交響曲第4番
伊福部昭/シンフォニア・タプカラ
指揮:原田幸一郎
第144回演奏会(7月23日)東京文化会館
伊福部昭/日本組曲
マーラー/交響曲第2番「復活」
指揮:小林研一郎
独唱:大倉由紀枝(ソプラノ)伊原直子(アルト) 合唱:武蔵野合唱団
第143回演奏会(4月23日)東京芸術劇場
ロッシーニ/歌劇「どろぼうかささぎ」序曲
伊福部昭/交響譚詩
ブラームス/交響曲第2番
指揮:原田幸一郎
第142回演奏会(1月29日)東京芸術劇場
モーツァルト/交響曲第33番
伊福部昭/日本狂詩曲
ショスタコーヴィチ/交響曲第10番
指揮:小泉和裕
<1993年>
第141回演奏会<ベルリン芸術週間参加記念演奏会>(10月10日)東京芸術劇場
藤田正典/オーケストラのための「輪廻」(委嘱作品)
伊福部昭/オーケストラとマリムバの為のラウダ・コンチェルタータ
チャイコフスキー/交響曲第5番
指揮:石井眞木
第140回演奏会(7月10日)東京芸術劇場
ドボルザーク/交響曲第8番
ラヴェル/マ・メール・ロア
ラヴェル/ラ・バルス
指揮:原田幸一郎
第139回演奏会(4月24日)東京文化会館
ワーグナー/楽劇「ローエングリン」第一幕への前奏曲
ワーグナー/歌劇「タンホイザー」序曲
ブルックナー/交響曲第4番
指揮:飯守泰次郎
第138回演奏会(1月3日)東京文化会館
チャイコフスキー/「ロミオとジュリエット」序曲
芥川也寸志/交響三章
リムスキー・コルサコフ/シェイラザード
指揮:フランシス・トラヴィス
<1992年>
第137回演奏会(10月4日)東京芸術劇場
ウェーバー/「オイリアンテ」序曲
バルトーク/管弦楽のための協奏曲
ブラームス/ピアノ協奏曲第1番
指揮:原田幸一郎 ピアノ独奏:野島 稔
第136回演奏会<山田一雄追悼演奏会>(7月19日)サントリーホール
山田和男/大管弦楽の為の交響的「木曽」
マーラー/交響曲第5番
指揮:小泉和裕
第135回演奏会<現代の交響作品展'92>(4月11日)東京文化会館
夏田昌和/モルフォジュネシス-オーボエとオーケストラのための(公募作品)
一柳 慧/ピアノ協奏曲第一番「空間の記憶」
石井眞木/交響三連作「浮遊する風」
指揮:石井眞木 夏田昌和
独奏:柴山 洋(オーボエ) 一柳 慧(ピアノ) 山口恭範(打楽器)
第134回演奏会(1月19日)新宿文化センター
ベートーヴェン/「献堂式」序曲
ベルク/「ヴォツェック」より
シューベルト/交響曲第9番「グレート」
指揮:フランシス・トラヴィス ソプラノ独唱:橋爪ゆか
<1991年>
第133回演奏会(11月4日)川口リリアホール
ヴェルディ/「運命の力」序曲
R.シュトラウス/「薔薇の騎士」序曲
ベートーヴェン/交響曲第7番
指揮:原田幸一郎
第132回演奏会(7月21日)東京文化会館
フランク/交響曲ニ短調
ラヴェル/道化師の朝の歌
ビゼー/アルルの女
指揮:山田一雄
第131回演奏会(4月21日)東京芸術劇場
ワーグナー/「トリスタンとイゾルデ」より前奏曲と愛の死
R.シュトラウス/交響詩「ドン・ファン」
スクリャービン/交響曲第2番
指揮:フランシス・トラヴィス
第130回演奏会<現代の交響作品展'91>(1月19日)東京芸術劇場
松村禎三/管弦楽のための前奏曲
石井眞木/笛とオーケストラのための協奏曲「解脱」
伊福部昭/交響頌偈「釈迦」
指揮:石井眞木 横笛独奏:赤尾三千子 合唱:合唱団OMP
<1990年>
第129回演奏会(11月4日)サントリーホール
ベートーヴェン/コリオラン序曲
シベリウス/ヴァイオリン協奏曲
チャイコフスキー/マンフレッド交響曲
指揮:原田幸一郎 ヴァイオリン独奏:漆原朝子
第128回演奏会(7月22日)東京文化会館
ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」
ドビュッシー/小組曲
レスピーギ/ローマの松
指揮:山田一雄
第127回演奏会(4月1日)東京文化会館
ショスタコーヴィチ/交響曲第1番
ブラームス/交響曲第1番
指揮:高関 健
第126回演奏会(1月20日)新宿文化センター
芥川也寸志/交響管絃楽のための前奏曲(初演)
芥川也寸志/ポイパの川のポイパの木
芥川也寸志/交響曲第1番
指揮:山田一雄 語り:岸田今日子
<1989年>
第125回演奏会(10月21日)新宿文化センター
ベートーヴェン/交響曲第8番
R.シュトラウス/交響詩「死と変容」
ドヴォルザーク/チェロ協奏曲
指揮:原田幸一郎 チェロ独奏:毛利伯郎
第124回演奏会(7月23日)サントリーホール
シューマン/交響曲第4番
細川俊夫/ヒロシマレクイエム(委嘱初演)
指揮:今村 能 混声合唱:合唱団OMP 児童合唱:東京少年少女合唱隊
第123回演奏会(4月1日)東京文化会館
ストラヴィンスキー/ペトルーシュカ
チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」
指揮:本名徹二
第122回演奏会(1月22日)サントリーホール
デュカス/魔法使いの弟子
レスピーギ/「リュートのための古代舞曲とアリア」第3番
ベルリオーズ/幻想交響曲
指揮:山田一雄
<1988年>
第121回演奏会(10月16日)昭和女子大学人見記念講堂
バルトーク/舞踊組曲
R.シュトラウス/オーボエ協奏曲
ブラームス/交響曲第4番
指揮:森山 崇 オーボエ独奏:柴山 洋
第120回演奏会(7月31日)サントリーホール
マーラー/交響曲第9番より第4楽章
マーラー/さすらう若人の歌
マーラー/交響曲第1番
指揮:山田一雄 独唱:伊原直子
第119回演奏会(4月3日)東京文化会館
ファリャ/「はかなき人生」より
ファリャ/スペインの庭の夜
ファリャ/「三角帽子」第2組曲
指揮:芥川也寸志 独唱:春日成子
第118回演奏会(1月17日)新宿文化センター
ムソルグスキー/はげ山の一夜
ラヴェル/スペイン狂想曲
マーラー/交響曲第4番
指揮:山田一雄 独唱:大沼美恵子
<1987年>
第117回演奏会(9月26日)新宿文化センター
ハイドン/交響曲第88番「V字」
ドビュッシー/交響詩「海」
ルトスワフスキー/管弦楽のための協奏曲
指揮:今村 能
第116回演奏会(6月21日)サントリーホール
マーラー/交響曲第10番よりアダージョ
ムソルグスキー=ラヴェル/展覧会の絵
ラヴェル/「ダフニスとクロエ」第2組曲
指揮:山田一雄
第115回演奏会(4月5日)東京文化会館
李煥之/春節組曲より
呉祖強/二泉映月
チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲
朱践耳/納西一奇
指揮:芥川也寸志 ヴァイオリン独奏:左軍
第114回演奏会(1月25日)サントリーホール
平尾貴四男/古代賛歌
早坂文雄/左方の舞と右方の舞
小倉 朗/オーケストラのための舞踏組曲
伊福部 昭/タプカーラ交響曲
指揮:芥川也寸志
<1986年~新響30周年企画シリーズ~>
第113回演奏会(11月30日)東京文化会館
芥川也寸志/アレグロ・アスティナート
芥川也寸志/絃楽のための三楽章
芥川也寸志/交響管絃楽のための音楽
芥川也寸志/エローラ交響曲
芥川也寸志/交響曲第1番
指揮:芥川也寸志
第112回演奏会(9月23日)新宿文化センター
山田耕筰/音「曼羅陀の華」
ストラヴィンスキー/バレエ組曲「火の鳥」(1919年版)
ベートーヴェン/交響曲第5番「運命」
指揮:山田一雄
第111回演奏会(7月20日)新宿文化センター
モーツァルト/交響曲第39番
ショスタコーヴィチ/交響曲第4番(日本初演)
指揮:芥川也寸志
第110回演奏会(4月6日)東京文化会館
マーラー/交響曲第8番「一千人の交響曲」
指揮:山田一雄
独唱:豊田喜代美、大倉由紀枝、岩崎由紀子、辻 宥子、春日成子、林 誠、勝部 太、岡村喬夫
合唱:新響30周年祝祭合唱団、武蔵野合唱団、荒川少年少女合唱隊、台東区立金竜小学校音楽部、藤沢ジュニアコーラス、多摩ファミリーシンガーズ
第260回演奏会のご案内
今回の演奏会では指揮に湯浅卓雄氏を迎え、イギリスの国民的作曲家ウォルトンの交響曲と、今年で生誕100年となる別宮貞雄作品を演奏します。
長年イギリスに居を構え、国際的に活躍してきた湯浅氏にとって、ウォルトンの交響曲第1番は特に大切にしているレパートリーの一つです。また、ナクソスの「日本作曲家選輯」シリーズで多くの邦人作品の録音をしていますが、別宮貞雄の交響曲第1番、第2番も発表しており、造詣の深いアプローチが期待できます。
とにかくカッコいいウォルトンの交響曲第1番
ウィリアム・ウォルトンは1902年ランカシャー州オールダム生まれ。父親は教会合唱団の指揮者で10歳からオックスフォード聖歌隊学校で学び、その後オックスフォード大学に進むも中退し、ロンドンでほぼ独学で作曲活動を始めました。
交響曲第1番は作曲の途中に映画音楽を手掛けるなどしたため3年かけて完成しました。ウォルトンは、ローレンス・オリヴィエ監督の『ヘンリィ五世』など多くの映画音楽を書いており、しばしば演奏される『スピットファイヤー』も同名の映画の音楽を再編したものです。
ウォルトンの交響曲第1番は、近代的な作風ながら端正で活力に満ち華やか。現代の映画音楽にも通じる聴きやすい曲ですので、初めて聴く方にも楽しんでいただけるでしょう。
美しく心に響く別宮貞雄の音楽
別宮貞雄は1922年東京生まれ。東京大学理学部物理学科と同大学文学部美学科を卒業後、渡仏しパリ音楽院でミヨー、メシアンに作曲を学びます。「音楽本来の使命は、普通の人々の感情に幅広く訴えるところにある」と主張し、前衛音楽に向かわず、調性のある古典的なスタイルに繊細な抒情性を盛り込んだ独自の作風を確立しました。
『管弦楽のための二つの祈り』は帰国後に修行時代の集大成として作曲され、毎日音楽賞と尾高賞を受賞した別宮の出世作。「悲しみを持って」「雄々しく」と名付けられた2つの楽章からなり、しっかりした構造の中に人間の感情が表されています。
『第3交響曲』は1984年別宮61歳の時に完成。「春」という副題があり、春の訪れと山の自然と喜びに満ちた人々が表現されています。瑞々しく陽気さに溢れたこの曲は、聴くと楽しい気分になることでしょう。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
第259回演奏会ローテーション
| ジプシー男爵 | シューベルト第3番 | シュミット第1番 | |
| フルート1st | 黒住 | 吉田 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 林 | 兼子 |
| Picc | 岡田 | - | 岡田 |
| オーボエ1st | 岩城 | 周藤 | 山口 |
| 2nd | 平戸 | 平戸 | 堀内(+コールアングレ) |
| クラリネット1st | 中條 | 境澤 | 品田 |
| 2nd | 末村 | 大藪 | 進藤 |
| ファゴット1st | 浦 | 藤原 | 松原 |
| 2nd | 藤原 | 浦 | 田川 |
| 3rdファゴット | - | - | 浦(+コントラファゴット) |
| ホルン1st | 大内 | 大内 | 山口 |
| 2nd | 山路 | 市川 | 山路 |
| 3rd | 大原 | - | 名倉 |
| 4th | 市川 | - | 大原 |
| トランペット1st | 北村 | 瀧野 | 小出(北村) |
| 2nd | 竹本 | 中川 | 青木 |
| 3rd | - | - | 瀧野 |
| トロンボーン1st | 武田(香) | - | 武田(浩) |
| 2nd | 志村 | - | 志村 |
| 3rd | 岡田 | - | 岡田 |
| テューバ | - | - | 坂巻 |
| ティンパニ | 桑形 | 今尾 | 今尾 |
| パーカッション | 小太鼓/嘉瀬 大太鼓/足立 シンバル他今尾 |
- | - |
| 1stヴァイオリン | 内田智(今村) | 内田智(今村) | 堀内(今村) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(滑川友) | 小松(滑川友) | 小松(滑川友) |
| ヴィオラ | 星野(田川) | 星野(田川) | 星野(田川) |
| チェロ | 柳部(安田) | 柳部(安田) | 柳部(安藤) |
| コントラバス | 宮田(亘理) | 宮田(亘理) | 宮田(亘理) |
*はエキストラ
弦()はトップサイド、管()はアシスタント
フランツ・シュミット:交響曲第1番
■フランツ・シュミットは晦渋(かいじゅう)か?
フランツ・シュミットはオーストリア=ハンガリー帝国プレスブルク(現スロヴァキアの首都ブラチスラヴァ)出身、ウィーンで活躍した作曲家でウィーン国立歌劇場の首席チェロ奏者でもあった。またオルガンやピアノの演奏も得意とした。シュミットと時代が近い主なドイツ・オーストリアの作曲家の生存期間を線表にしたのが下図である。代表作品などもごく一部だが記載した(“〇番”は交響曲の番号)。シュミットはマーラーやR.シュトラウスの後輩世代にあたり、プフィッツナーやレーガーといった、生前は脚光を浴びていたが現在では忘れられた感がある二人の作曲家とほぼ同世代である。シュミットの曲も彼ら二人と同じで派手な要素が少ないので、一般の聴衆にはあまり受けないと思われている。この同世代の二人と合わせて“三大晦渋作曲家”とでも呼びたくなる。一方で同世代のシェーンベルクらのように調性を放棄するような破壊的革新は行っていないので新しもの好きの受けも良くはない、ということでどっちつかずの評価を受けてきたようだ。
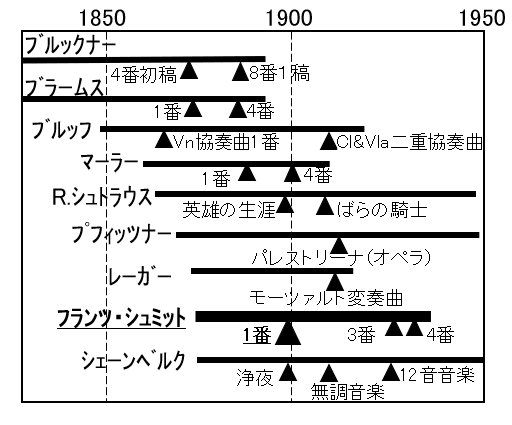
■シュミットは初めて聴いてもわかりやすい
新交響楽団が最初に定期演奏会でシュミットの曲を取り上げたとき、その直前に商店街主催の手づくり音楽祭への出演を依頼された。定期演奏会のプログラムはあいにくシュミットの中でも一番晦渋と言われる交響曲第4番。音楽祭のために別の曲を取り上げる余裕はなくこの曲を演奏することになったのだが、多くのお客さんが退屈してしまうのではないかと危惧した。ところが、その時の指揮者で本日と同じ寺岡先生が演奏に先立ち、シュミット愛に溢れる熱いプレトークで作曲のいきさつや聴きどころを語ったためか、演奏中見渡した限り寝ている方は見当たらず、終演後は“シュミットって素晴らしい曲ですね”と複数のお客様から声をかけていただいた。そんなわけで事前に聴きどころを知っておけば実はとても楽しめる作曲家なのである。
■聴きどころ
交響曲第1番はシュミットが25歳の時に完成した意欲作で、ウィーン楽友協会の作曲賞において審査員全会一致の一等賞を受けている。華々しく始まり堂々と終わるこの曲は交響曲の王道ともいえるもので個人的印象だがシューベルトの交響曲「グレート」を聴くような思いがする。ドイツやオーストリアのクラシック音楽の伝統を取り込んでおり、これはどこかで聴いたことがあるな、というのがたくさん頭に浮かんでくる。しかしそのままの引用はなくシュミット独特の苦みばしった個性的な和声がつけられているためかシュミット独特の響きがするのである。
1楽章はニュルンベルクのマイスタージンガー前奏曲を彷彿とさせるカッコよい序奏で始まる。弦・木管楽器の付点リズムはバロック音楽のフランス風序曲のそれのようでバッハの管弦楽組曲第3番の華麗さも思わせる。その後のトランペットの歌うようなソロはブルックナーの交響曲第3番冒頭やマーラーを連想させる。
2楽章の最初にクラリネットのソロで始まるハンガリー風の哀愁に満ちた旋律はシュミットの特長のひとつである。その後牧歌的なホルンに導かれて木管が奏でる幸せな部分では田園交響曲の第2楽章の小鳥の囀り(さえずり)やワーグナーのジークフリート第2幕の“森のささやき”を思い出す。この楽想は最後に金管のコラールとして再現し宗教的な幸福感に満たされる。
3楽章は都会に出てちょっとあか抜けたブルックナーのようなスケルツォ。中間部はシュミットの真骨頂、世紀末ウィーンの気だるい甘さと破滅の予感。ラヴェルのラ・ヴァルスの世界と同じ匂いがする。
4楽章はバロック音楽の壮大なリバイバル。オルガン曲や合奏協奏曲などを思わせる。対位法を駆使したバロック舞曲もしくはオルガン曲風の部分が少々長いが、だからこそそのあとの壮大な金管によるコラール到来が圧倒的である。これはブルックナーの第5交響曲第4楽章のようでもあるが、コラールの頂点で昇天したように終わるのはブルックナー。一方シュミットは“人間界”に戻ってきて明るく終結する。
初演:1902年1月25日 作曲者指揮 ウィーン演奏協会管弦楽団(ウィーン) (ウィーン交響楽団の前身)
楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2(2番はコーラングレ持ち替え)、クラリネット2、ファゴット3(3番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、弦五部
参考文献:
IMSLP Symphony No.1 (Schmidt, Franz)
https://imslp.org/wiki/Symphony_No.1_(Schmidt%2C_Franz)
参照日:2022年8月21日
Wikipedia 1. Sinfonie (Schmidt)
https://de.wikipedia.org/wiki/1._Sinfonie_(Schmidt)
参照日:2022年8月21日
シューベルト:交響曲第3番
■31年の生涯
1797年ウィーン郊外で生まれたフランツ・シューベルトは、音楽の教師であった父からの手ほどきもあり早熟な音楽の才能を発揮した。
短時間に熱中して次々に素晴らしい作品を完成させる一方、内気で引っ込み思案な性格故に、自分の作品を積極的に売り込むことをしなかったのだが、彼の才能に惚れ込んだ友人たちが彼を守り助けた。
ゲーテ、ミュラーなどたくさんの詩人や友人たちの詩にも作曲し、数多くのリートを披露した。シューベルトが敬愛したベートーヴェンは、病で死に瀕している時に彼のリートの数々を知り、その才能に驚き、なぜ彼をもっと早く知らなかったのかと嘆いた。シューベルト自身も病に冒され、ベートーヴェンの死後1年半あまりで31歳の生涯を終える。
■交響曲第3番 /1815年18歳
この曲はシューベルトの交響曲の中で最も短く、軽快に簡潔にまとめられている。モーツァルトやハイドンの影響も感じられるが、彼の得意とするリートの特徴もうかがえる。同じ年に書かれた『野ばら』や『魔王』といった名曲とともに個性が開花されていったのではないか。
滅多に書き直しをしない彼は、この作品の手稿譜にも訂正や試行錯誤の跡を残していないと言われている。後期の『未完成』や『グレート』といった重厚感ある交響曲と比べると、この第3番はリートを書く延長のようにスラスラっと仕上げたような印象を受ける。
第1楽章: Adagio maestoso - Allegro con brio ニ長調 4/4拍子 序奏付きソナタ形式
荘厳な雰囲気だが真冬の厳格さではない序奏。クラリネットの雪解けのようなメロディが始まる。オーボエがイ長調へ転調をして、共通する付点のリズムを軽やかに歌い上げる。
第2楽章: Allegretto ト長調 2/4拍子 三部形式
洗練されているが気負わない、生き生きとした旋律をヴァイオリンが歌い出し、その後をフルートが引き継ぐ。中間部のクラリネットののどかな旋律は、ずっと続いて欲しい平和な日常を歌いあげているようだ。
第3楽章: Menuetto: Trio - Vivace ニ長調 3/4拍子 三部形式
3拍子の軽やかなテンポ感の楽章。中間部トリオでは、それまでの雰囲気から一転して、オーボエとファゴットによるゆるやかな舞踏が始まる。
第4楽章: Presto vivace ニ長調 6/8拍子 ソナタ形式
タランテラの陽気な踊りのようなリズムを持つ。アウフタクトの軽快なフレーズが繰り返され、若きシューベルトの躍動感あふれる楽章となっている。
初演:1881年2月19日 オーガスト・マンス指揮 「水晶宮コンサート」(ロンドン)
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦五部
参考文献:
レシーニョ・エドゥアルド、プリンチペ・クィリーノ、プレフーモ・ダニーロ『大作曲家の世界 2ウィーン古典派の楽聖』音楽之友社 1990年
ひのまどか『音楽家の伝記 シューベルト』ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 2020年
ヨハン・シュトラウス2世: 喜歌劇「ジプシー男爵」序曲
ヨハン・シュトラウス2世(1825-1899)は74年の生涯で500曲を超える作品を書きました。そのうち16曲のオペレッタ(喜歌劇)を作曲しており、「ジプシー男爵」は10曲目にあたるオペレッタ作品です。シュトラウス60歳の誕生日の前日に初演されました。シュトラウスが作曲したオペレッタといえば「こうもり」が有名ですが、それに次ぐオペレッタの代表作が「ジプシー男爵」です。
1883年の春、オペレッタ「愉快な戦争」の初演を指揮するためブダペストに滞在していたシュトラウスはハンガリー人の作家ヨーカイ・モールと知り合います。彼の小説「シャッフィ(ザッフィ)」が気に入ったシュトラウスは同じくハンガリー人のジャーナリスト、イグナーツ・シュニッツァーがこの小説を基に書き上げたオペレッタ台本に作曲をすることとなり、およそ2年の歳月を費やして異国情緒あふれるこの魅惑的なオペレッタを創作しました。
物語は18世紀初頭のハンガリーが舞台。かつてはこの地方を治めていたトルコの総督の娘でしたが現在はロマ族(ジプシー)として暮らすザッフィと、亡命を余儀なくされた豪族の息子バリンカイ(自称「ジプシー男爵」)の恋愛と宝さがしをめぐる楽しいストーリーがエキゾチックな音楽とともに目まぐるしく展開します。
この序曲には劇中で使われているさまざまなメロディが登場します。大きく分けて6つの場面で構成されます。
(1) Allegro moderato
序曲の冒頭は弦楽器による力強いメロディ【譜例1】で始まります。この旋律は第1幕第12場「ロマ族の合唱」《ジングラー、ジングラー》に基づきます。
ツィンバロン(ハンガリーの民族楽器)を思わせる弦楽器による音型を経て、クラリネットの独奏によりエキゾチックな旋律【譜例2】が現れます。
(2)Andantino
弦楽器により冒頭のメロディが再現された後、フルートのカデンツァを経てオーボエによるのどかな独奏【譜例3】に受け継がれて舞台は穏やかな雰囲気に包まれます。このオーボエの旋律は第1幕第13場でザッフィがバリンカイに歌う《この土地こそ、あなたの故郷》に基づきます。
(3)Allegretto moderato
オーボエによるのびやかで美しいメロディはポルカ風の楽しげな旋律【譜例4】へ受け継がれます。この生き生きとしたメロディは第2幕第1場でザッフィ、ツィプラ、バリンカイが財宝を探すときに歌う三重唱《だから、すべての石を叩きましょう》に基づきます。
(4)Tempo di Valse
明るいポルカ風のメロディは調性の変化とともに次第に盛り上がり、ここでシュトラウスの真骨頂ともいえる優美なワルツ【譜例5・6】が登場します。このワルツは第2幕第3場でアルゼーナが歌う《喜びに満ちた都市ウィーン》に基づきますが、「宝のワルツ(または宝石のワルツ)」(Schatz-Walzer)としてもよく知られており、単独でも演奏される大変美しい曲です。
(5)Allegro moderato
優美なワルツの世界から一転、荒々しいロマ族の舞曲【譜例7】が現れます。この舞曲は第1幕第12場でロマ族の人々が登場する場面で演奏されます。
(6)Andantino
この舟唄【譜例8】は第1幕の冒頭で歌われる船頭たちの合唱《本当の船頭とは言えませんよ》の旋律に基づきます。
舟唄の後に「宝のワルツ」【譜例6】が再び現れ、序曲の締めくくりは前述のチャールダーシュ(緩やかなラッスlassuと急速なフリッスfrissの2部で構成されるハンガリーの民族舞曲)で一気に盛り上がり、華やかなフィナーレを迎えます。
(譜例準備中)
初演:1885年10月24日 作曲者指揮 アン・デア・ウィーン劇場(ウィーン)
楽器編成:フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、大太鼓、シンバル、小太鼓、グロッケンシュピール、シュポーレン(拍車)、ハープ、弦五部
参考文献:
宮沢縦一・福原信夫・高崎保男『オペラ全集-音楽現代名曲解説シリーズ1』芸術現代社 1992 年
永竹由幸『オペレッタ名曲百科』音楽之友社 1999年
伊藤剛(解説)「ジプシー男爵」序曲(スコア) 日本楽譜出版社 2022年
コントラ・ファゴット演奏記
■オーケストラにおけるコントラ・ファゴット
コントラ・ファゴット特集の第2部では、コントラ・ファゴットを効果的に使用したオーケストラの名曲を、実際にこれらの曲を演奏した際の筆者の個人的な感想などを織り交ぜながらご紹介します。
コントラ・ファゴットはいわゆる「特殊楽器」であり、基本的には大規模な編成の楽曲にしか出番がありません。しかし新響は大編成曲に取り組むことが多いうえ、素晴らしい団楽器を所有していますので、コントラ・ファゴットがコンサートに登場する頻度は他のアマオケに比べてもかなり高いと思います。
では、どういった楽曲に、どのような役目で登場するのか?まずは、コントラ・ファゴットの楽器としての特徴をご紹介しますと、最低音域の約1オクターブは凄い音がします。音量や音程というより「バリバリ」「ビリビリ」「ゴオオ」といった重低音です(余談ですが、この音域を吹きながらテレビなどのブラウン管モニターを見ると、画面が波打って見えます。まさに自分の体全体が振動している感覚で、一度体験すると病みつきです)。プリミティブでエッジが立っており、存在感はあるのですが、チューバのようなオケ全体を抱擁する厚みのある音質ではありません。また音域によって鳴り方の差がかなり激しく、低音域以外は音量がガクッと減り、響きが少なく細い音になってしまいます。しかも音程も全体的にそれほど良くありません(というか低すぎてよく判らない)。
こうした特徴から、コントラ・ファゴットがオーケストラの中で担う役割は
①見た目要員(デカくて目立つので座ってるだけで大編成っぽさを醸し出す)
②ベースライン(でもメインじゃなくてサポート)
③たまーにソロ
となります。全体の9割以上は「②ベースライン」のお仕事であり、コントラ・ファゴット単体として目立つような場面は稀です。このため、コントラ・ファゴットは音質や音程にさほど気を遣わず、とりあえず出番が来たらバリバリ物音をさせておけばよいという甘い認識が流布しがちです(本人は自己満足に浸っているがブリブリ五月蠅いだけのコントラ・ファゴット奏者のことを、界隈では自戒を込めて「工事用ドリル」と呼びます)。しかし実際には、オーケストレーションを俯瞰して自分の役割を考え、よく計算して吹くことで、オケ全体のサウンドにうまく効果をつけたり、リズムやテンポのエッジ・芯となることが可能です。筆者としては、ファゴットに比べてコントラ・ファゴットが面白いのは、こうした客観的な「調整作業」が楽しめるあたりだと思っています。
また「③たまーにソロ」については、曲の絶対数は少ないのですが、コントラ・ファゴットにソロ、またはパートソリを書いてくれる作曲家としては
・マーラー
・ラヴェル
・ストラヴィンスキー
・ショスタコーヴィチ
などが代表格です。これらの作曲家の曲に加えて、デュカスの『魔法使いの弟子』が吹ければ、コントラ・ファゴット吹きとしてのソロ・レパートリーはほぼコンプリートです。音質が非常に特徴的な楽器であるため、ソロも音色を活かした、キャラクターの立った内容のものが多く、比較的悩まずに楽しく吹くことができます。では、コントラ・ファゴットが活躍する名曲をいくつかご紹介しましょう(新響の演奏会で筆者が近年実際に吹いた楽曲に絞っていますので偏りあり)。
■コントラ・ファゴットの名曲たち
①ラヴェル:管弦楽組曲『マ・メール・ロワ』より「美女と野獣の対話」 →第227回演奏会(2014年10月、指揮:矢崎彦太郎先生)

エロール・ル・カインによる「美女と野獣」
コントラ・ファゴットをソロ楽器として扱った曲の代表格。クラリネットが囚われの美女役(何故かクラリネットは「美女」の役を当てられることが多いですが、この時の「美女」はクラリネット首席のS田氏でした)、コントラ・ファゴットが彼女に求婚する野獣役となり、両者の対話が展開されます。最終的に美女が求婚を受け入れると、野獣にかけられていた呪いは解け、人間の姿に戻った野獣と美女はめでたく結ばれる…というストーリーが、ラヴェル一流のオーケストレーションで見事に表現されています。5分足らずの小曲ですが完全にコントラ・ファゴットだけで1つのキャラクターを演じ切れるので自由度が高く、没入して吹ける素晴らしいソロです。
このソロを吹くにあたり、当然悩んだのは「『野獣』とは何ぞや?」ということ。ラヴェルのメロディからは粗野で凶暴なモンスターという印象は受けず、立ち振る舞いは優雅で品性が感じられるけれど見た目だけ(呪いのせいで)グロテスク、というイメージでした。「美女と野獣」の原作(もとはフランスの異類婚姻譚です)を調べたり、映画や絵本などを見比べたりと色々研究した結果、筆者の場合は、エロール・ル・カインというシンガポールの絵本作家が描いた野獣をイメージモデルとして音色やフレーズ作りを行いました(しかしプロの演奏を聴いても実に様々な野獣が居り、野獣界は相当広いようです)。
また、このソロはとにかく音域が広く、最低音域のEから、上はその2.5オクターブ上のB♭まで出てきます。超低音の、いかにも「野獣」といったグロテスクな音色と、意外と線が細くて優雅な高音域の音色の振れ幅の広さ、いびつなアンバランスさがうまく出れば最高なのですが、実際には音を出すのも一苦労でした(超高音域は普段使わないので指使いを知らず、インターネットで運指を調べたところ「good luck!」と書いてあり目を疑いました)。
②ラヴェル:管弦楽のための舞踏詩『ラ・ヴァルス』 →第227回演奏会(2014年10月、指揮:矢崎彦太郎先生)
ラヴェルの代表作の1つであり、この曲の優雅さ・狂気・崩壊の予感が綯い交ぜになったグロテスクな雰囲気づくりに、コントラ・ファゴットのゴリッとした低音が一役買っています。また、意外と知られていないのですが、早い半音階で乱高下するコントラ・ファゴットのソロがあります。この部分は、半音階の下降音型が高音の木管楽器を何種類かリレーしながら降りてきて、コントラ・ファゴットで折り返してファゴット(アンカー)に引き継ぐという瞬間芸的な見せ場になっています。大方の作曲家は、コントラ・ファゴットについてそれほど器用な楽器ではないと思っている節がある中、こんな技巧派のリレー選手にまで抜擢してくれるところに、ラヴェルのコントラ・ファゴット偏愛を感じます(ちなみにこれがブルックナーだと、木管楽器のリレーはだいたいフルート→オーボエ→クラリネット までで、並ファゴットすら仲間に入れてもらえません)。指揮の矢崎先生からは、この部分について「ちょっとコントラ・ファゴットの音程がはっきりしないな。もう少し半音階だって判るように吹いてくれない?」と血も涙もないリクエストが結構しつこくありました。先述のとおりコントラ・ファゴットの低音域というのはもはや骨伝動に近く、吹いている本人も実はイマイチ音程が判りません(結局それほど器用な楽器ではないのです)。とはいえ指揮者から敢えてリクエストがあったからには開き直るわけにもいかず、なんとか半音階だと判ってもらえるように練習したのですが…合奏中にしっかり吹けたぞ!と思って矢崎先生のお顔を見ても「ふふ~ん?」みたいな半笑いでいらっしゃり、会心の「OK!」という表情はして頂けないままに終わってしまいました。めちゃくちゃ悔しいので『ラ・ヴァルス』はもう一度吹きたい曲の1つです。
③マーラー:交響曲第2番『復活』第4楽章 →233回演奏会(2016年4月、指揮:飯守泰次郎先生)
冒頭のアルト独唱に続き、金管楽器のコラールが奏でられます。このコラールの最後、ドミナントからトニカへ終止する和音にほんの少しだけコントラ・ファゴットが重ねられています。音にしてたった3つ分の出番なのですが、これが世界の深度を劇的に変える素晴らしい働きをするのです。コントラ・ファゴットの最低音が加わることで、それまで名もなき木造の教会で賛美歌を歌っていたのが、一気にサン・ピエトロ大聖堂の石造りのドームになります(イメージ)。低音フェチとしては垂涎の出番なのですが、張り切る気持ちを抑えつつ、荘厳に、穏やかに、深い音で、しかし存在感ばっちりに吹かねばなりません。マーラーはコントラ・ファゴットを重用してくれる作曲家の1人ですが、筆者としては、この場面での使われ方が費用対効果ナンバーワンだと思います。

『復活』第4楽章の金管コラール。和音が終止する最後の3音だけ、コントラ・ファゴットが重なる
④マーラー:交響曲『大地の歌』第6楽章 →217回演奏会(2012年4月、指揮:飯守泰次郎先生)
第6楽章の冒頭から、低音楽器のCのロングトーンが「ズゥーン…」と繰り返し鳴り響き、ここにオーボエなどのメロディが乗っかってきます。この低いCは、低弦(ピッチカート)+コントラ・ファゴット+ハープ+ホルン2,4+銅鑼 で奏しますが、音が減衰していく楽器が多いため、コントラ・ファゴットが持続音の低い響きの要となります。また短いですが諦観あふれる静かで素敵なソロもあります。
この時の指揮者は飯守先生。第6楽章に出てくる弦楽器の特殊なリズムのことを「ここは不整脈です!」と繰り返し仰っていたのが印象的でした。それまでは、コントラ・ファゴットの低いCのロングトーンはお寺の鐘(梵鐘)のイメージかな?と思って吹いていたのですが、飯守先生のお話を聞いてからは「なるほど、あちらが不整脈なら、この繰り返されるCも心身の不調の表出=頭痛だな」と勝手に納得。当時筆者は入団2年目のペラペラ新人で、飯守先生が恐ろしくてたまらず(音程や発音に異常に厳しいのです)、周りのベテラン団員も気合十分で鬼気迫っていたため、非常に張りつめた精神状態で吹いていました。緊張のあまり本当に頭痛がしてくるほどで、真に迫った表現ができていたかもしれません(笑)今でもこの楽章の冒頭を聴くと、あの時の空気感が蘇って不整脈を起こしそうになります。
⑤ブラームス:交響曲第3番 →222回演奏会(2013年7月、指揮:山下一史先生)
コントラ・ファゴットの使い方が上手い作曲家として、忘れてはならないのがブラームスです。ブラームスは、管楽器セクションにおける最低音パートとしてチューバよりもコントラ・ファゴットを頻用しています(チューバは当時発表されたばかりの新しい楽器でした)。ソロではないのにコントラ・ファゴット単体の音色もしっかり聞こえるし、オーケストレーションにおいてもキーとなる、非常に重要でやりがいのある役割を担わせてくれます。このためコントラ・ファゴット奏者は例外なくブラームスが好きです(断言)が、だからこそ良い音色、音程、音量とニュアンスで最高のアンサンブルを追求したくなってしまい、ものすごく悩みます。筆者はブラームスのコントラ・ファゴットが一番難しいと思っています。

第1楽章の展開部。主題がミステリアスに暗示される場面で、コントラ・ファゴットの超低音が轟く。
四角く囲ったC♭はコントラ・ファゴットがコントラバスより1オクターブ低い音域で吹いている(この超低いC♭は、通常の4弦コントラバスでは音域外)
交響曲第3番もコントラ・ファゴットが有効に使われています。特に第1楽章の真ん中あたり、展開部が始まるところはコントラ・ファゴットの低い響きが炸裂しており、一発で「ここから展開部だな」と判るような暗い緊張感を効果的に演出しています。恐らくですが、このコントラ・ファゴットの役目を例えばチューバで代わりに吹いたとしても、音質が柔らかすぎてコントラ・ファゴットほどのおどろおどろしさは出ないでしょう(自画自賛)。ブラームスに、ソナタ形式の構成の要として活用してもらえるのは至上の喜びであります。
⑥プーランク(フランセ編):『ぞうのババール』 →223回演奏会(2013年10月、指揮:矢崎彦太郎先生)
コントラ・ファゴットに限らず、特殊楽器を扱う上で「持ち替え」は重要なスキルの1つです。ただでさえ緊張する本番中に、落とす・リードを割る・間違える(特にクラリネットは見た目がそっくりなB♭管とA管を頻繁に持ち替えるため「勘(管)違い」の危険性が高い)といった様々な事故リスクを回避しながら、心身を瞬時に切り替えねばなりません(楽器によって息の圧力、アンブシュア、指使い、譜面の読み方、演ずべきキャラクターなどが全然違います)。作曲家の中にはこの辺りをあまり考慮してくれない人も居て、物理的に楽器の持ち替えが間に合わない場合もありますが、そんな時は適当に前後の楽譜の一部を端折ってしまいます(俗に「捨てる」と言います)。
プーランクの『ぞうのババール』は同名の絵本をもとにしたナレーション付きの音楽劇で、2ndファゴット奏者がコントラ・ファゴットを持ち替えて演奏します。ファゴット族の活躍する場面が非常に多い曲で(音色が象っぽいからでしょうか)、主人公の象が体操をするシーンはコントラ・ファゴットの長い単独ソロ、その次の象たちがドライブするシーンではファゴット2本による別のソロ…という調子に、前後どちらも絶対捨てられない場面でのノータイム持ち替えが頻発(ほぼ象しか出てこない話なので、ファゴットが象役なら当然かもしれません)。各シーンの音楽の間をナレーションがつなぐ構成だったので、短いナレーションの間にコントラ・ファゴットからファゴットに大急ぎで持ち替えて、またナレーションの間にこんどはコントラ・ファゴットに持ち替えて…という感じで、しまいには自分が今吹いてるのはファゴットなのかコントラ・ファゴットなのか判然としなくなってきてしまい、頭と口が大混乱状態でした。筆者の中ではこの曲がダントツで持ち替え難易度ナンバーワンです。この時はフリーアナウンサーの中井美穂さんをナレーターとして招聘しており、中井さんの素敵なお話が聞けるのを心待ちにしていたのですが、実際はそれどころではなく「何でも良いからなるべくゆっくり話してくれ…!」とひたすら願いながら持ち替えしまくっていたためお話を楽しむ余裕はありませんでした。
こんな調子で、コントラ・ファゴットを編成に含む楽曲の生演奏をホールで聴かれる際には、持ち替えに着目されると、冷静を装いつつ必死で心身を切り替えている奏者の様子が観察できてなかなか面白いと思います。マーラーの交響曲などがおすすめです(たった一発の三和音のためにコントラ・ファゴットを3rdファゴットに持ち替えさせるなど、ギリギリの瞬間芸が多い)。
いかがでしたでしょうか。「もともとそれほどコントラ・ファゴットに興味ないし…」という読者の皆様の声が聞こえるようですが、今回、維持会費で修理をさせて頂いたご報告としてニュースに寄稿の機会を頂けることとなったため、つい欲張って特集を組んでしまいました。今回の演奏会でも、シュミットの交響曲第1番にコントラ・ファゴットが登場します。シュミットのオルガンのようなサウンドを支える最低音として、随所で良い仕事をしています。オーバーホールでますますパワーアップした新響のコントラ・ファゴットに、是非注目(耳)してお聴き頂ければ幸いです。
コントラ・ファゴット、令和の大修理
■コントラ・ファゴットという楽器
少々大袈裟なタイトルをつけましたが、本年7月、維持会費で団所有のコントラ・ファゴットのオーバーホールを行いました。
コントラ・ファゴットは、木管の最低音部を受け持つファゴットのさらに1オクターブ下の音を演奏する超大型木管楽器です。ちなみに、この呼び方はドイツ語でありまして、英語ではダブル・バスーン、もしくはコントラ・バスーンといいます。最低音のB♭は5弦コントラバスの最低音Cより低く、88鍵のピアノの最低音であるAから半音しか違わないという低さ。そのため管長が約6mと非常に長く、管が4回も折り返されています。もはや楽器というより大型工作機械にしか見えないかもしれませんし、乱暴に言えば、まあ音もそんな感じでしょうか。

団所有のコントラ・ファゴット(右端)と団員の普通のファゴット。2本写っているのはたまたまで、特に意味はありません。
1600年代中頃に開発された楽器で、ヘンデルやハイドンが祝典音楽や宗教曲に使用し始め、交響曲ではベートーヴェンが第5番で初めて使用したことが有名です。「第九」でも使われますが、この頃はまだコンラバスの補強という役割。後年、フランス近代の作曲家やマーラーなどによりオーケストラの中で目立つソロが与えられるようになります。尚、どのような曲で、どのように活躍するのかは、第2部に委ねることとしましょう。
■新響の楽器はどんなもの?
さて、新響のコントラ・ファゴットですが、これはとても古い楽器で、今回のオーバーホールで解体されたところ、製造番号が455であることが判明。修理をお願いしたマイスターの調べでは、1933(昭和8)年の製造と想定されるそうです。年齢にすれば満89歳。黒柳徹子さん、草笛光子さんと同い年になります。
1933年といえば、この楽器の生まれ故郷であるドイツでは、アドルフ・ヒトラーが首相に就任。日本は中国大陸への進出により国際連盟を脱退し、世界から孤立し始めます。その後の大戦へ向けて、世の中が不穏な空気を醸し始めた時代といえるでしょう。

分解されて初めて判明した製造番号。最近の楽器は分解しなくても確認できる金属部分に刻印されています。
そのような時代にファゴットの最もメジャーな製造者であるヘッケル社*の工房で生まれたこの楽器は、海を渡って日本へやって来て日本放送協会(NHK)の所有となります。NHK交響楽団で使用された後、ポストを新しい楽器に取って代わられたのでしょうか、使われなくなったものをN響のファゴット奏者として活躍された山畑 馨先生から有償にて譲り受けたと聞いています。いつごろ新響の所有になったのかについても、古老といわれるOBの方にヒアリングを試みましたが、判明しませんでした。ただ、私が入団した1982年には、既に「かなり古い楽器」として新響に存在しており、ヘッケル製と聞いて「すげーな」と驚いた記憶があります。
<注釈>
*1813年に創業されたファゴットの世界的メーカー。ドイツ中西部、ライン川に面したヴィースバーデンに拠点を構える。極めて高い品質を誇り、一昔前プロの世界では「ヘッケルにあらずばファゴットにあらず」とまでいわれたほど。基本的に受注生産で「何年待ち」といわれているが、中古品の出物もあり、ひょんなことで待たずに手に入れてしまうケースも多いと聞く。アマチュア奏者の中でも、運と経済力に恵まれた人が所有することがある。
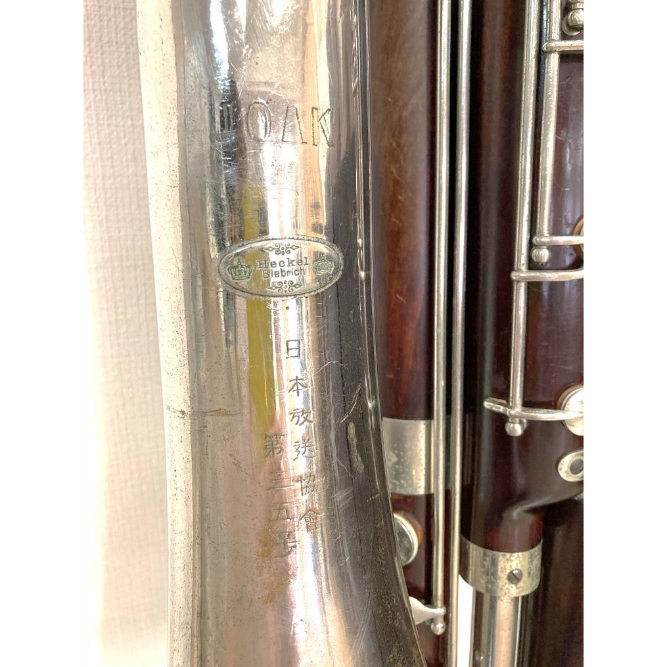
新響のコントラ・ファゴットのベルの部分。ヘッケル社の刻印(楕円形のプレート)の下に、「日本放送協會 第三十五号」と手彫りされている 。
■今回のオーバーホールとこの楽器のこれから
当団のコントラ・ファゴットは、私が関わった範囲では、約30年前と約15年前にも維持会費でオーバーホールを行わせていただきました。30年前には石森楽器で超ベテランの職人さんに徹底的にやってもらい、15年前は野中貿易の工房で少々軽めのオーバーホールを実施。今回は横浜に工房を構えるファゴット専門のマイスターに依頼し、すべて分解してタンポ(トーンホールをふさぐフタのようなもの)やキーのフェルトなどを全数交換して、全体の調整をやってもらいました。このマイスターはプロ奏者からの信頼も厚く、工房では、第一線で活躍されている有名人の楽器が何本も分解されて置かれているのを目にすることができます。海外のメジャーオケからも修理依頼が来る、とても腕の良い人ですので、これでしばらくは良い状態で鳴ってくれるのではないかと期待しています。
昭和初期にドイツで産声を上げ、日本に渡ってN響で活躍した後に、昭和・平成・令和とアマオケで第二の人生を送っているこのコントラ・ファゴット。「ちゃんとメンテナンスをやっていけば、あと100年は使えますよ」とのお墨付きをマイスターから頂戴しました。ちなみに、ヘッケル社のコントラ・ファゴットをいま新品で購入するとしたら、多分1000万円を超えるでしょうし、発注から納品までどれだけの年月がかかるのか分かりません。そういう意味でも、アマオケとしては極めて貴重な楽器を保有していることになります。いまもとても良い音色で鳴ってくれているこの楽器を、これからも大事に使い続けていきたいものです。
このように、維持会費は団所有の楽器の購入や修理、メンテナンスなどに有効に活用させていただいています。今後とも変わらないご支援、何卒宜しくお願い申し上げます。
第259回演奏会のご案内
再評価が進むフランツ・シュミット
フランツ・シュミットという作曲家をご存知でしょうか。最近日本でも少しずつ聴く機会が増えてきたようです。新響では2015年に交響曲第4番、2018年に「ノートルダム」の音楽、2021年に交響曲第3番をウィーン在住の指揮者寺岡清高と演奏してきました。今回はフランツ・シュミットをメインに、ウィーンの大作曲家シューベルトとヨハン・シュトラウスの作品をプログラミングしました。
フランツ・シュミットはウィーン音楽院で作曲を学び、ウィーン宮廷歌劇場ではマーラーの指揮の下チェロ奏者を務めました。同じ年に生まれた新ウィーン楽派のシェーンベルクが12音技法をあみだしたのと対照的に、伝統的なロマン派を貫きました。今回演奏する交響曲第1番は、重厚な響きと歌心溢れるシュミットらしさを堪能できる曲です。
天才シューベルトの若きシンフォニー
シューベルトは、ウィーンにとって特別な作曲家です。この街で活躍した大作曲家は多いですが、その中でもシューベルトはウィーン生まれのウィーン育ち、それまで貴族のための音楽だったものが、市民が担い芸術性を高めるのに大いに貢献しました。ベートーヴェンを崇拝しつつもモーツァルトの音楽を好み、師匠のサリエリからモーツァルトの真似だと非難されたようです。「歌曲王」として『魔王』や『野ばら』といった多くの名曲をのこしていますが、交響曲は『未完成』『ザ・グレート』が演奏されるくらいです。しかし、あとの6曲も魅力的な作品ばかり。特に今回演奏する第3番は、18歳の作ながらシューベルトらしさが表れた楽しく美しい曲です。
ヨハン・シュトラウス2世の人気オペレッタ
そしてウィーンと言えばシュトラウス・ファミリー。父ヨハン・シュトラウス1世は自身の楽団を持ち「ワルツ王」として人気を博していました。音楽家を目指す長男のヨハン・シュトラウス2世を、父はあの手この手で阻止しましたが、母の後押しで何とか2世はデビューし、その後父と母は離婚、父亡き後は2世の方が「ワルツ王」と呼ばれるようになりました。『美しく青きドナウ』、『ウィーンの森の物語』、『皇帝円舞曲』といった超有名なウィンナーワルツは2世の作品です。オペレッタにも進出し、特に『こうもり』『ジプシー男爵』は成功を収め、今日でも上演機会が多い2演目です。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
坂入健司郎先生インタビュー
今回、初めて指揮をお願いする坂入健司郎先生にZoomでインタビューをしました。運営委員長の大原久子とプログラム担当メンバー3名、安藤彰朗、兼子尚美、林真央で、指揮者になるきっかけ、演奏曲目への思い、ご趣味の話など、多岐にわたってお話を伺いました。思わず身を乗り出したり、笑いに包まれたりと和やかなインタビューとなりました。
■どうして指揮者になりたいと思われたのですか?
坂入:幼稚園生の時からなりたいと思っていました。両親は特にクラシックが好きというわけではなかったのですが、クラシックのCDが発売されるCMを見て、あれが欲しいと買ってもらい、熱心に聴きました。ちょうどその頃、お誕生日に、両親や親戚の人からCDを頂いたのですが、それが「新世界より」でした。最初は、同じ曲がかぶったことにがっかりしたのですが、聴き比べて面白いと思ったのです。
― 坂入先生は楽器も演奏なさいますが、自分で音を出したいというよりも、オケ全体を引っ張りたいと思われたのでしょうか。
坂入:最初に聴くことから入ったので、楽器を練習するのがとてもつらかったんですね(笑)。いい演奏が頭で鳴っていると、なんでこんなにできないのか、と自分自身に幻滅をするよりも、こういうバランスで、こういう構成でと、準備したうえでオケの指揮をする方が性に合っていると思ったんですね。今も、スコアを読みながらピアノは弾きますし、またチェロもオーケストラで弾くのは好きなのですが、会話を楽しむために練習をしている感じです。出したい音を目指して個人練習をしているとベルリン・フィルやウィーン・フィルの音に比べると切なくなる。でも指揮に関しては、そういうオケを聴いても、さらにこう工夫できるのでは?と想像がかき立てられるので、性に合っていると思います。
― 今でもチェロを弾かれていますか?
坂入:はい、今は指揮が多くなってしまいましたが、弾くこともあります。
■オケの演奏経験があることは指揮に生きますか?
坂入:とても大切なポイントですね。指揮者は1人で100人に対するので、結構怖い仕事だと言われます。しかし、自身がチェロを弾いた体験で、指揮者側がオケを信頼することが、本当に大切だということを実感しました。オケで弾いていると、指揮者があきらめた瞬間ってわかりますよね。このオケだとこのくらいかなと。そういうことは一切したくないと、指揮を始めてからずっと変わらず思っています。リミットを設定しない、このメンバーだからこそ、もっと上を行けるという姿勢を崩さず貫きたいというのはオケの中にいて気づいたことです。
― プレーヤー目線ですね。素晴らしいと感じます。先生のような指揮者とご一緒できて嬉しいです。先日の初回練習では、指揮がエネルギッシュで、演奏していても気持ち良かったです。
坂入:以前に比べると、指揮の動きはコンパクトになりました。きちんと準備しているオケであればあるほど、指揮者はそれほど動かなくてよいのですね。だからこそ、欲しい時にはしっかりと引っ張るようにもなりました。
■会社での仕事と大学時代の研究は?
坂入:ぴあ株式会社では、WEBマーケティングを行いました。購入者、メールマガジンの登録者にメールを送ることや、システム系だったり、効果測定だったり、チケットを買った人が次に何を買うかという効果分析もしていました。慶應義塾大学の経済学部では、文化経済学という分野が専門で、マクロ経済の応用を学びました。論文を書くため、ラフォルジュルネや金沢の21世紀美術館の収支を見て研究をしたこともありました。
― 音楽、指揮につながるものばかりですね。
坂入:はい、その頃もずっと指揮者になりたかったので。ぴあ株式会社で、WEBマーケティングの後は、チケット営業をしたのですが、あえてクラシックでないものを扱いました。ライブハウスとか韓流とか。ファン層がどうしてそのライブに行くのかを勉強できましたね。
― それでは、クラシックの文化事業として一般化されるとよいアイデアなどはお持ちでしょうか。
坂入:そうですねえ。日本では、コロナのころは国から助成金・補助を求めて動きましたが、民間から支援をもらうのか国から支援してもらうのか不明瞭なところがあります。ヨーロッパなどでは、国とか州単位で予算が出て、オケや歌劇場の運営が成り立っていますが、アメリカではほとんど民間企業の寄付で成り立っています日本でも、民間からの支援をどうもらうかということも考えないといけないと思います。クラウドファンディングなども盛んになっていますが、社会全体がクラシックを盛り上げていこうという空気を醸成することが大切ですよね。クラシック界は価値の見せ方が上手でないと感じます。2000人のホールで100人の生の演奏が聴けることはすごいこと、贅沢なことなんです。一般的にその価値を知ってほしいと思って、今頑張っています。たとえば、クラシック以外でいうなら、先日東京ドームで行われたボクシング大会では、5万人近いチケット収入、PPV(中継の有料配信)の収入がほとんどでスポンサー収入は10%に満たなかったそうですよ。そういうビジネスモデルもできています。クラシックでも、そうやって価値を知ってもらうように頑張りたいと思います。
― 先生なら実現できそうですね。新交響楽団でも、若い人にクラシックに目を向けてほしいと考えています。
坂入:子供のためのコンサートに関しては、思うところがあります。自分にとって、ゲームは難しかったんですが、攻略本などを読んで、ちょっと背伸びするのがはまるきっかけだったんですね。だから、いつもどこかで聴いている有名な曲ばかりを演奏する子供のためのコンサートではなく、最初からストラビンスキーなどを演奏して知らない世界に子供たちに体験してもらうことが大切だと思います。たとえ、音に違和感を覚えることがあっても、そういう刺激を与えることで、ひとりでにクラシックの世界にはまっていく子供が増えるのではないかと思うんです。
■作曲家の意図と個性の表出は?
― クラシック音楽で、作曲家の意図を取り入れるこ
とが重要だと思うのですが、個性をどのくらい出してよいと思われますか。
坂入:譜面の要素を引き出すのは指揮者の基本姿勢ですが、そのうえで、ブラームスのように任せる範囲が狭い作曲家もいれば、自由度の高い作曲家もいます。譜面だけの情報だけではなく、書簡なども読み解いて、どういう演奏が望まれていたのかを知る必要もありますね。
■初回練習が終わって新交響楽団の印象は?
坂入:とてもいい感触でした。新響って、とても小さい時から聴いていて、もう20年近く聞いています。飯守泰次郎先生のマーラー「交響曲第1番」松山冴花さんのベートーヴェン「Vn協奏曲」の演奏会の時には、打ち上げにも行きました。Vnは素晴らしかったですね。天真爛漫で、音のパレットが多い演奏でした。
― そうなのですね。ほかにどの演奏会が印象に残っていますか。
坂入:高関健先生のマーラー「交響曲第7番」や、飯守先生のスメタナ「わが祖国」、ブルックナー「交響曲第6番」、芥川也寸志さんの「交響三章」、小松一彦先生の貴志康一作品も素晴らしかった。飯守先生の「ペレアスとメリザンド」、シェーンベルクは強烈でした。また、「エローラ交響曲」は大好き交響曲なので、いつかやりたいと思っています。
― ぜひ新響と一緒に。今回も、「わが祖国」にご来場いただいた際のチケット購入メールから、指揮依頼のご連絡を差し上げました(笑)。本当に数多くの演奏会にいらしてくださっていたのですね。私たちにとっては、初めての先生で緊張しました。
坂入:私も緊張しました。ずっと聴いてきたオケなのでプロオケを振るよりも緊張しました。
― (一同驚き)
― イメージされていたオケと同じでしたか。
坂入:イメージと違っていました。高関先生、矢崎先生、飯守先生といった指揮者と共演する伝統のあるオケなので、オケの中で演奏を固めてくるかと思ったのですが、特に、バーバー、パリのアメリカ人は、オケの自由度が高いと感じました。準備はしっかりとされている、しかしコミュニケーションを取りながら変化し、しかも浸透が速いので、この後がとても楽しみになりました。「新世界より」は、逆に基本に忠実でありたいと思っているので、奇抜な解釈はしないようにしています。この曲は、何十回も演奏している方もいらっしゃるでしょうし、いろいろな引き出しのある方もいると感じました。
― 曲について初めての合奏での発見はありましたか?
坂入:ガーシュウィンは、今回、初稿で行いますが、亡くなった後の改訂版、さらに、新校訂版というのが出ています。いつものCDで聴く演奏とは異なり、シンプルです。よりパリを意識しており、ラヴェルに弟子入りしたかったガーシュウィンの思いが伝わる演奏になる予感がしました。タクシーホーンは、初演では音が違うことがわかっていて、これも反映し、初演時の感動を伝えたいと思っています。アメリカ音楽のスタンダードとして伝えるのではなく、パリの人にも「天才・ガーシュウィン」が伝わるようなものにしたいと思います。
■初めて指揮をする今回の3曲への思いは?
― 今回は「新世界より」をメインに持ってきましたが、初めて指揮をされると伺いました。子供の時に聴き比べて、指揮者になりたいと思われたという曲ですが、大切に取っておかれたのでしょうか。
坂入:チェコの音楽と日本人には親和性があると言われますが、私は、日本のメロディとチェコのものは違うと思います。日本人が歌うと演歌になってしまう、それは残念なことで、この曲を演奏するのを躊躇していました。練習の時にも話した内容ですが、今回、チェコの香りが伝わるものにしたいと思っています。30年近く温めた曲を、20年聴いてきた新響と演奏できる、特別な演奏会です。
― バーバーは、先生からの強いご要望でしたが、思いをお聞かせください。
坂入:この曲はリハーサルで演奏をした方はお気づきのように、凄まじい曲です。バーバーは、マーラー、ブロッホに続く、ユダヤの音楽家だといえます。今回取り上げる「管弦楽のためのエッセイ第2番」は、最初のピアニシモのところから、革新的ですね。フルート、チューバとバスドラムと、最高音と最低音が鳴ります。最後の祈りの音楽といい、名曲中の名曲だと思います。ぜひ紹介したくて選びました。
今回は、単なるアメリカプログラムではなく、ヨーロッパの歴史を俯瞰できるようにしたかったのです。新響にとっても難しいと思うのですが、今回は3曲とも言語が違います。旧約聖書のヘブライ語、フランス語とアメリカ英語のミックス、そしてチェコ語。
― この曲は抒情性がキーワードだと思ったのですが、ユダヤの音楽だと言われるとピンときました。魂が入っている曲だと感じます。
坂入:ヨーロッパから亡命したユダヤ人指揮者、ブルーノ・ワルターが第2次世界大戦中に初演を指揮しています。ナチスによるホロコーストを皆が知っていた時なんですね。最後のクライマックスは命を落とした魂も加わって、復活を祈るような音楽です。
― この曲は、今回初めて知りました。練習の最初、技術的な難しさに気を取られていましたが、慣れてくるとその精神性を感じるようになりました。ティンパニの音を戦争になぞらえる人もいると聞きます。
坂入:打楽器ソロは戦いを表す。それが終わって静かになり、祈りが始まるんですね。
―「パリのアメリカ人」はいかがですか。
坂入:ジャジーなのりと、ラヴェルのような繊細さをハイブリッドにしたいと思っています。
■多趣味……その先にやはり指揮が?
― 話は変わりますが、ファスティング中だとか。
坂入:そうなんです。今日は1食も食べていないんですよ。びっくりするほど、空腹感がありません。今は、2泊3日で草津のホテルで温泉とサウナを楽しみながらファスティング中です。身体が絶好調になりますよ。サウナと温泉が大好きで、これは、もう趣味といっていいレベルですね。週に1回は入らないと、体調が悪くなりますね(笑)。名古屋ならここ、大阪ならここと行く場所を決めています。とにかく汗を出して水風呂に入ると疲れが吹き飛びます。ほかに、釣り、料理、お酒も好きですね。釣りは湖。ルアー釣りが好きですね。料理は、指揮と似ていると思います。さじ加減の仕方が、本当に似ている。レシピ通り(譜面通り)にしても、演奏者や指揮者によって、味が変わる。さっきの個性の話に通じますね。
― 指揮者のシノーポリさんも同じようなことをおっしゃっていましたね。
坂入:そうそう。
― 運動はなさるんですか?
坂入:運動は好きで、陸上部でした。中学では吹奏楽部でしたが、弦楽班を作るという学校の意向で、チェロを貸与されて演奏していました。活動は週に3回の練習だったので、空き日を使って陸上部を兼部しました。キャプテンを務めいたんですよ(笑)。最初、短距離で、部員が少ないので、長距離も出ていました。最後は、駅伝のほうが成績を伸ばせましたね。また、コロナで何もできなかったときに、市民プールに毎日行っていたら、泳げるようになりました。
― 立派なアスリートですね。こういうことも、指揮者につながりますね。
坂入:クロールをしていると肩こりが治ります!指揮をしていると肩が凝るので、その解消に良いですね。指揮者は、首、腰がやられがちなので、運動も大切ですね。
― 100歳までご活躍出来るほど、指揮者生命は長くていらっしゃいそうですね。先生のすべての活動が、指揮につながっているようです。
■今後の展望は?
坂入:直近の目標としては、2024年にブルックナーの全曲を演奏したいですね。プロアマ問わず。もう一つは海外ですね。先日海外の指揮コンクールに参加し、審査員だった山田和樹さんや樫本大進さんから沢山のアドバイスもいただき、活動の場をヨーロッパにも広げるべきだと確信しました。今後の展望が、この1か月で広がった気がします。
― どのような指揮者を目指されますか?指揮者の方って本当にいろいろなタイプの方がいらっしゃるのですが、例えば、80歳になった時にどんな指揮者になっていたいか、など。
坂入:最近、もう若手ではなくなったと感じます。大学オケを指導するようになったのですが、学生は一回り下なんですね。若いつもりでも、言葉の使い方や距離の取り方が全然違うんですね。だから、80歳になってもどんな世代ともコミュニケーションが取れる、信頼関係の築ける指揮者になりたいと思います。棒に対する情報は変わらないのですが、言葉のコミュニケーションは常にアップデートしたいと思います。80歳になっても、この指揮者若いな、と思われるような。でも指揮者はそれまでの経験が生きるものなので、さすが80歳とも思われる指揮者でありたいですね。
― 坂入先生ならきっとそうなりそうですね。長生きして見届けなくては。楽しみです。
ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」
■ドヴォルザークの生い立ち
1841年、チェコのプラハから北に30kmほど離れた小さな村にてアントニン・ドヴォルザークは生まれた。幼いころから音楽に慣れ親しんだドヴォルザークは、音楽教育を受け才能を開花させていった。18歳で音楽学校を卒業し、経済的な苦労を抱えながらも音楽家として活動しながら作曲を続けていき、30代半ば頃から作品が世間に認められ始めると国際的な名声を手にするようになっていった。
■チェコ国民学楽派
チェコはヨーロッパの中心に位置し、常に周辺国の政治的・文化的影響を受け続けてきた。そのような歴史を経て、18世紀末から19世紀前半にかけてチェコの人々の間では文化的アイデンティティを確立しようという動きが活発になっていった。その中でも口頭伝承されてきたチェコ民族音楽を楽曲に取り入れた作曲家を「チェコ国民楽派」と呼ぶ。ドヴォルザークの他にベドルジハ・スメタナ(1824~1884)が代表として挙げられる。
■新世界アメリカ
1892年、51歳のドヴォルザークはアメリカの音楽院に院長として招聘され、プラハから12日間の長旅を経てニューヨークに降り立った。友人に宛てた手紙の中でニューヨークの第一印象を「ほとんどロンドンのような巨大な町であり、生活は朝から晩まで、通りもまた非常に様々な様相を見せながら、実に生き生きとしていて活気に満ちている」と綴っている。
新天地での生活は、音楽院での責務に加えて異国の著名な作曲家として人々に注目されて忙しく、また街を行き交う交通の騒がしさによって落ち着いて作曲することもままならない日々であった。
交響曲第9番はアメリカ在住中の1893年1月から5月にかけて作曲された。日々の喧騒から離れることを強く望んだドヴォルザークは、作曲後の6月に故郷ボヘミアからの入植者が集まるアイオワ州のスピルヴィルという町を訪れる。アメリカ奥地の美しい静かな自然や同国人に囲まれて、ドヴォルザークは非常に安らかな休暇を過ごした。滞在の様子を同行人はこう記している。
「ドヴォルザークはきわめて率直で自然を大いに愛しむ方です。スピルヴィルを訪問している間も、小さな森(果樹園)を通り、川の土手に沿って歩く朝の散歩を日課とし、鳥のさえずりをなによりも楽しんでいる様子でした。」
「新世界より」という副題がつけられた交響曲には、アメリカ文化の刺激を受けつつも故郷チェコへの郷愁が強く映し出されている。
■第1楽章
静かな弦の旋律から始まり、突然ffの荒々しい弦、ティンパニ、管楽器の呼応が切り込む。異国への船旅、汽車の轟音そして音楽はニューヨークの喧騒へと向かっていく。テンポがAllegroになるとホルンによって第1主題(譜例1)が鳴り響く。鏡像型のリズムはチェコの民族舞踊を想起させる。フルートとオーボエによる中間主題(譜例2)はアメリカの黒人霊歌「静かにゆれよ、楽しい馬車」との関連が唱えられることもあるが、第1主題と同様のチェコの民族音楽的特徴を兼ね備える音型となっている。
■第2楽章
冒頭、叙情的な旋律(譜例3)がコールアングレによって奏でられる。「遠き山に日は落ちて」としても知られるこの旋律はボヘミアへの郷愁を思わせる。アメリカ民謡からの引用だとも唱えられるが作曲者は「私は最後のシンフォニーのためにアメリカでモティーフを集めた。その中にはインディアンの歌も含まれている。だが真実は伝えられていない。…これらのモティーフは私個人のものであり、若干のものを私はすでに携えている。それはチェコの音楽である…」と語っているように、アメリカの要素がそのまま引用されている訳ではなく、ドヴォルザーク個人の感性を経て曲に表されている。
憂愁を帯びた瞑想的な曲調がしばらく続いた後、踊りのようなメロディーによって少しの盛り上がりを見せ、再び冒頭の主題が奏でられる。そしてコントラバスの和音によって楽章は静かに幕を閉じる。
■第3楽章
穏やかな第2楽章から対照的に、ボヘミアの農民の踊りを思わせる軽快な旋律から始まる。主題はフルートとオーボエで呈示され、クラリネットが追随する。そして牧歌的な旋律のトリオへと展開していく。これらの主題における旋律の呼応や3連符の音型といった特徴にチェコ民族音楽を見出すことができる。
■第4楽章
有名な半音階の序奏から始まる。鉄道好きとして知られるドヴォルザークが汽車の車輪の動き出す様を表現したと言われている。回転数が上がったところで、ホルンとトランペットの異国趣味的な響きの第1主題(譜例4)が力強く響く。その後、全楽章を通じて唯一のシンバルの一打を経てクラリネットによって第2主題(譜例5)が奏でられる。こちらは第1主題とは対照的に故郷ボヘミアへの憧れを、透き通るような自然の流れと美しさを陶酔させる。
第4楽章は前3楽章の主題が随所に姿を見せる交響曲の統括的な楽章となっている。最後はオーケストラ全体による和音が鳴った後、弦楽器は短く切り、管楽器だけが音を伸ばしてディミヌエンドしていき、哀愁を帯びながら楽曲は閉じていく。
(譜例準備中)
■おわりに
247回2019/10/13 ドヴォルザーク/連作交響詩
252回2021/1/17 スメタナ/連作交響詩「わが祖国」
253回2021/4/18 ドヴォルザーク/序曲三部作『自然と人生と愛』
258回2022/7/18 ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」
近年、新響はチェコ民族音楽を楽曲に取り入れたチェコ国民楽派の作曲家を多く取り上げてきた。これまで培ってきた民族音楽への理解と新進気鋭の若手マエストロによる「新世界より」にご期待いただきたい。
初演:1893年12月16日 アントン・ザイドル指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック カーネギーホールにて
楽器編成:フルート 2(2番ピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トライアングル、シンバル、弦五部
参考文献:
内藤久子『作曲家◎人と作品シリーズ:ドヴォルジャーク』音楽之友社 2004年
内藤久子『チェコ音楽の歴史:民族の音の表徴 』音楽之友社 2002年
ガーシュウィン:パリのアメリカ人
■大西洋を渡って見えた世界
ジョージ・ガーシュウィン(1898-1937)の故郷アメリカは1920年代に経済・技術・文化などさまざまな面で急成長したが、少なくとも文化・芸術面において当時世界で最も華々しい街がパリであったことは想像に難くない。この時期にパリに住んでいた著名人としては、ラヴェル、コクトー、モネ、ココ・シャネルに加えて、諸外国からもプロコフィエフ、ストラヴィンスキー、コール・ポーター、ディアギレフ、ピカソ、藤田嗣治、ヘミングウェイ、ジェイムズ・ジョイス、ル・コルビュジエなど様々な分野のカリスマが集結していた。
アメリカにおけるアフリカ系などの移民に対する人種差別はパリでは影を潜め、性的マイノリティを公言する者に対しても遥かに寛容であった。シャネルが短くしたスカートから露になったくるぶしが人々を驚かせるなど、進取の気性に富むこの街に好奇心旺盛なガーシュウィンが惹かれたのも当然といえる。1923年と26年に短期で滞在し、28年にはパリを含め3ヶ月以上ヨーロッパに滞在し、その間に「パリのアメリカ人」の大半を作曲した。
新大陸-旧大陸、ジャズ(ポップス)-クラシック、ユダヤ-クリスチャン、といった様々な境界のはざまにいたガーシュウィン。ガーシュウィンと同じくユダヤ系であったポストモダニズムの哲学者、ジャック・デリダ風に言えば、そういった二項対立を「脱構築」し、純粋なクラシックの教育を受けていなかったからと異端扱いするのではなく、多様であるが故に唯一無二であったガーシュウィンを一人の煌めく個性として受容する心持ちはダイバーシティが推進される現代にも通じるのではなかろうか。
■作品構成
パリの喧騒を表した序盤、郷愁漂うトランペットのブルースに始まる緩やかな中盤、チャールストンに始まる軽やかな終盤からなる三部形式と大まかに捉えることもできるが、初演時に作曲者自ら交響詩との副題を付けたとおり、自由な形式となっている。何より、パリ滞在時に見た情景や感情を天性のメロディセンスで彩った作品と言える。同行していた兄・アイラの日記を参考に、もしジョージも日記を付けていたら、という空想を通じて当時の雰囲気を少しでも再現したい。
■1928年3月31日(パリ)
雨模様。ホテルにて朝食をとる。ここではスモークサーモンが大人気らしく、皆こればかり食べている。日中はホテルにて今取り掛かっている交響詩を書き進める。パリジャンの気取った歩き方に着想を得たテーマ(譜例)を随所に使うつもりだが、我ながら気に入っている。16分音符のスタッカートのモチーフで人々がガヤガヤと喋る様子も散りばめたい。
この国のシトロエンだかルノーだかのクラクションは、アヒルの鳴き声のようで実に愛嬌がある。これはぜひ曲に取り入れたいので早急に調達せねばならない*1。聞き慣れたフォードのクラクションはホエザルの雄叫びさながら、荒々しい轟音*2で毎度たまげるのでご勘弁願いたい。
夕方5時にアイラと合流し、コンサートに足を運びフランク、オネゲル、バッハ、私の「ラプソディ・イン・ブルー」などを聞いてきた。ラプソディの出来栄えはご愛嬌であったが、アンコールで私も呼ばれたので舞台に上ってピアノを披露し、観客はご満悦だった様子である。
ラヴェル、プロコフィエフ、ブーランジェ…会うべき人が本当に多い。せっかくテニス発祥の地*3にいることなので全仏オープンも見ていきたいが、今取り掛かっている作品も終わらせないといけないし…あぁ忙しい。
脚注)
*1:曲中では習慣的にA,B,C,Dの音が使われるが、アルファベットは音名ではなく通し番号に過ぎず、実際は全く異なる音程を想定していたとの見解がある。
*2:youtube動画「1923 Model T Ford Aaoogha horn」など。
*3ガーシュウィンは1936年に米ハリウッドへ移住し、同時期にナチスによる迫害を逃れて近所に越してきた前衛作曲家シェーンベルク(1874-1951)と毎週のようにテニスをする仲となる。還暦過ぎのシニアを相手にして勝負になっていたのだろうか。
初演:1928年12月13日 ウォルター・ダムロッシュ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック カーネギーホールにて
楽器編成:フルート3(3番ピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、サクソフォン3(アルト、テナー、バリトン)、ティンパニ、グロッケンシュピール、木琴、小太鼓、トムトム、大太鼓、トライアングル、シンバル、ウッドブロック、タクシーのクラクション、チェレスタ、弦五部
参考文献:
Ira & Leonore Gershwin Trusts 2012 Excerpts from Ira Gershwin’s 1928 Diary. Words Without Music: The Ira Gershwin Newsletter
McAuliffe, M. 2016 When Paris Sizzled. Lanham: Rowman & Littlefield.
バーバー:管弦楽のためのエッセイ 第2番
「アメリカ」が、今日の演奏会の曲目をつなぐ縦糸となる。アメリカと一口に言っても、それぞれの持つイメージは様々だろう。ニューヨークの喧騒、あか抜けた街並み、広大な景色、牧歌的な風景。本日の演奏会でも、様々な曲想でこの国の多様な姿が表現されるだろう。
1曲目のバーバーは、激しさを内包しつつ古き良き時代のアメリカが伝わってくるような作品である。
■心に染みるバーバーの旋律
J.Fケネディ大統領の葬儀、9.11同時多発テロ犠牲者の慰霊式典、日本では、昭和天皇崩御追悼演奏会、映画では、「プラトーン」「エレファントマン」などでも、その切なく美しい旋律が人々の心に響いた。「弦楽のためのアダージョ」である。
この愁いに満ちた旋律を紡ぎだしたサミュエル・バーバーは、1910年にペンシルベニアで、医師である父とピアニストの母の間に生まれた。
6歳から音楽を学び、7歳のときに作曲を始めた彼は10歳で最初のオペレッタを作曲。14歳でフィラデルフィアのカーティス音楽院の最優秀クラスに入学した。そこでは作曲・ピアノ・声楽についても腕を磨き、指揮はフリッツ・ライナーに師事。絵に描いたような神童だ。
1935年にローマのアメリカン・アカデミーに留学し、翌年、弦楽四重奏曲第1番ロ短調(作品11)を作曲する。その直後、創設間もないNBC交響楽団との共演のためトスカニーニに新曲を委嘱され、その緩徐楽章を弦楽オーケストラ用に編曲した。「弦楽のためのアダージョ」の誕生だ。1938年に初演されて以来、その評価は今も続いている。
彼の作風は、伝統的であり豊かな旋律に特徴がある。それは、同時代にパリへ留学したアメリカの作曲家たちの革新性とは一線を画すものであった。
■伝統的な抒情性に加わる新しい試み
3曲ある「管弦楽のためのエッセイ」は、40年にもわたって作曲された。いずれも文学にも造詣の深かった彼が提示した「文学形式の音楽」とも言える。
今回演奏する第2番は、ブルーノ・ワルターがニューヨーク・フィルハーモニック創立100周年を記念して委嘱し、1942年に作曲された。特に第2番は、「単楽章による交響曲」と評されるほど濃密な内容を持つ。また抒情的な旋律、荘厳な音色、伝統的な和声といったそれまでの特徴に加え、五音音階(ペンタトニック)による主題の構成や、第4音・第5音の強調という、彼にとっては新しい試みを加えている。初演直後、有力紙の批評家は、「『管弦楽のためのエッセイ第2番』がこの作曲家の作品の中で最高のものだ、コープランドなどの曲が刺激になったのだろう」と述べている。
演奏をしていると、この新しさが作品に緊張感と同時に奥深い陰影を与えていると感じる。時に激しい展開は第二次大戦中の世相が影響しているのかもしれない。
■10分に凝縮された濃密さ、緊密性
この曲の醍醐味は、何といっても主題の展開の妙と複数の主題の緊密な絡み方、旋律の美しさにある。
フルートソロで始まる、五音音階に基づく第1主題は深い淵のようなテューバと大太鼓を背景にしつつ、バスクラリネットに受け継がれ、展開しながら木管楽器に引き継がれる。ティンパニがリズミカルなモチーフを加え、第2主題が展開される。クラリネットとファゴットが冒頭の主題を基に、3連符のリズムで軽快なフガートを奏で、緊張感の高まりとともに第2主題が響きを重ねる。讃美歌のような第3主題は、弦楽器によって静かに開始される。その後トランペットとホルンが第1主題を朗々と吹き、祈りのような第3主題は最後に勝利の宣言のような壮大さで締めくくられる。本日、あっという間に通り過ぎる旋律をお聞き逃しなく。
■後半生の苦悩とその後
1958年には歌劇「ヴァネッサ」によりピュリツァー賞音楽部門賞を得るなどして、順風満帆にみえたバーバーの人生だが、1960年代には「新ロマン主義」に分類された彼の音楽的アイデンティティと、成功の基盤であった感情表現豊かな「調性的」音楽は時代遅れとみなされるようになった。後半生の作品は批評家からは軽視され、彼は深刻なうつ状態に陥ってしまう。
1981年ニューヨークの自宅で失意のうちに死去。だがその後しばらくして、それまで軽視されていた作品群も再評価され改めて演奏されるようになった。20世紀の音楽をめぐる流行や思潮に翻弄され続けたとも言えるだろう。現在、サミュエル・バーバーはアメリカでもっとも愛されている作曲家の一人となっている。
初演:1942年4月16日 ブルーノ・ワルター指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック カーネギーホールにて
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓(響き線なし)、シンバル、タムタム、弦五部
参考文献・資料:
アラン・ブラックウッド著/別宮貞徳 監訳『世界音楽文化図鑑』東洋書林 2001年
堀内久美雄編『新訂 標準音楽辞典』音楽之友社 1966年
「WALTER SIMMONS」(参照:2022年5月21日)https://waltersimmons.com/writings/704
「Wise Music Classical」(参照:2022年5月21日)
https://www.wisemusicclassical.com/composer/72/Samuel-Barber/
『新世界より』随想
◆初めての交響曲
満13歳の誕生日に、叔母から『新世界より』のLP版レコードを贈られた。
いまやレコードやLP版とは何か?の説明さえ必要なご時世とも考えるが、煩雑なので割愛。今のCDの先祖と考えてもらうほかはない。レコードを聴くために、その2年ほど前、親にせがんで小型のステレオを買ってもらい、序曲や組曲や器楽の小品のレコードを集めて聴いていた末の事だ。1970年代初頭とあって世の中は高度成長期真っ只中。3C(車とクーラーとカラーTV)を備える事が中流家庭の目標となり、僕の周囲でもそれを達成した家庭が日増しに・・・・誇張ではない・・・・多くなっていった。だが末端公務員の父親のもたらす収入で暮らす我が家には3Cはひとつとして無く、住まいは6畳と4畳半二間の借家。そこにポータブルとはいえステレオが入り込んだ事は画期だったと言える。「ひとり息子の懇願とはいえ、ずい分無理をしてくれたのだな」。いま心底そう思って亡き両親の事を偲ぶ。
現在では想像も難しいが、自宅で好きな時に音楽を聴くという環境を整える事自体が困難な時代だった。再生装置も音源たるレコードも極めて高価で、特にクラシック音楽愛好家はコンサートに通うか(これも相応にカネはかかるが、労音のような団体が安価な会費で演奏会を提供してもいた)、街の「名曲喫茶」で割高なコーヒーと引換えに終日リクエスト曲がかかるまで粘り続けるかしかない・・・・というような状況にあったのだ。流石に僕個人は名曲喫茶とは既に無縁の世代だが、学生時代を過ごした高田馬場駅間近にさえそうした店は確かに残っていた。
そうした環境下で『新世界より』は、初めて意志に任せて適宜聴く事が出来る唯一の「交響曲」として、生活の中に位置づけられる存在となった。朝起きると通学前に全楽章聴き、帰宅するとまた頭から終わりまで聴く。そこには必ず
・恭しくレコードを取り出して回転するテーブルにセットし、静かに針を置く。
・聴き終わると針を上げてレコードをとり上げて盤面にブラシをかけ、疵がつかぬよう細心の注意を以てジャケットにしまう。
という神聖な儀式が毎回伴った。いまこうして思い出して書いてみても本当に煩わしく且つ仰々しいと感じる。が、ひとたび疵がついたり埃が侵入したりすれば消えぬ雑音の原因となってしまうほどの繊細な音源だったから、当然の行為としてこれらを受け容れていた。更に、僕の場合は、この曲しか大掛かりな曲の音源が無いのだから、それは大事に扱ったのだった。
◆フルートと「新世界」
「新世界」に浸る日常を送る一方で、わが人生に重大な転機が近づきつつあった。
2年ほど前から既に樹脂製の横笛を吹いていて、授業で用いていたリコーダーと比べても圧倒的に演奏の自由度が高い事を知り、本格的にフルートを始めようと考えていたのだ。なけなしの小遣いを貯め続けて、この時期ようやくフルートを買うに何とか手が届く処まで来ていた。既に教則本の類は何種類も読破(?)して運指はほぼ覚え、脳内で楽器を操作する毎日(勉強手につかず)。あとは実物の楽器に触れればたちまちにメロディが吹ける・・・・という事はこの歳になるまでついぞ訪れぬ事になるのだが・・・・との期待に浮かれていた。
そして・・・・23,000円(大金である)をはたいて最廉価モデルながら念願の実物を手に入れる。いま思えばこれがその後の長い人生を狂わす(苦笑)契機となった訳だが、「新世界」からここに至る2ケ月弱の時間が、わがささやかな音楽生活の原点となった事は確かである。『新世界より』とフルートとの個人的な関わりは、思いのほか深いものであったと今更ながら実感している。
楽器を入手する前はこの交響曲に出て来るフルートの音にひたすら神経を集中させる日々を送っていた・・・・第1楽章の中間部に、ホルンに続いて殊更に高音のフルートソロが聞こえる。「そうか、フルートを吹くという事はこうした音さえ出さねばならないのか!」とその音群の運指を調べると難しい指の動き。実際フルートは高音域の運指が他の音域に比較して極度に難しいのだが、またぞろそれを駆使して脳内で「演奏」を繰り返す。
この困難なソロが、2番奏者のピッコロ持ち替えによって演奏する指定になっている事実を、高校生時代にミニチェアスコアを入手して初めて知った。ピッコロなら何の事もない指遣い(あくまで指遣いは)。「なぁんだ」だが、この件は今も悩む「フルートの高音域運指に関する諸問題」の入り口となった。
今回の演奏会では若い指揮者を迎えるに当たってローテーションの若返りを図った関係で、老兵(僕の事。念のため)が2番フルートに回り、このソロを吹いている。実は全楽章を通じてピッコロはこの4小節のソロ部分でしか使用されない。10秒に満たないソロの為に特殊楽器を持って練習にも、もちろん本番にも臨まなければならないのだ。こうした場合の最大の懸念は、楽器を忘れる事(笑)。そしてウォームアップも無しにフルートから楽器を持ち替えるや、いきなりピッコロにとって出しにくくて割れやすい音からソロを吹かねばならない点にある。「なんでこんな楽器の遣い方をするかなぁ」と詮無い事ながらドボルザークの楽器用法には疑問を感じないでもない(同じようなピッコロの遣い方が第8番にもあるので)。そこにかつてこのソロをフルートで修練を積んだ事を無駄にするのも惜しい、との心根も頭をもたげ、「持ち替えをせずにフルートで吹いてしまおうか」という誘惑に駆られがちの日々を送る事になる。
「今日は楽器を忘れたと言って、フルートでの演奏を既成事実化しようか」
「どうせフルートで吹いても指揮者は気づくまい」
「周囲は、その音さえ出てれば良い程度の関心しか持ち合わせていまい」
などなど、次々と湧いては消える黒い情念と逡巡との間に揺れ動く。でも気が弱いから、結局毎回ピッコロに持ち替えている自分に気づく、と白状しておこう。
それでも自分には、ソロが終われば再びフルートに持ち替えて最後まで演奏すべき音がある。全曲を通じて第2楽章に8小節(うち1小節は八分音符1個のみ)の音しかないテューバ奏者や、第3楽章が唯一の出番のトライアングル奏者のように、作曲者の楽器用法に不条理・理不尽をより強く訴えかけるべき奏者らが沈黙している中で、結構なご身分の立場で何を言えようか!また自分にとって音楽生活の契機に位置づけられる作品だ。恨みなど到底覚えるべきものではない。
叔母は当年86歳で健在。コロナ禍中とあって近くに住みながらもここ数年は顔を合わせる事も叶わずに来ている。そろそろ顔を見せに行くか、とこの文章を書いて、いま改めて思う。
◆「まどいせん」とは何か?
『新世界より』第2楽章のテーマとなる旋律には歌詞が付され歌になっているのはご存知の通り。そもそもはドボルザークの弟子に当たるフィッシャー(William Arms Fisher/1861–1948)が"Goin' Home"と題して付けた歌詞を嚆矢とするようだ。我が邦ではなんとあの宮澤賢治が『種山が原(たねやまがはら)』とした歌詞を付したのが最初。1924(大正13)年の事というのは今回調べてみて知った。因みに『家路』の題名は同様に作詞を行った野上彰(のがみ・あきら/1909-1967)によるが、恐らくこの歌詞は殆ど知られていないのではないかと個人的には考える。現在最も知られ歌われているのは「遠き山に~」で始まる堀内敬三(ほりうち・ けいぞう/1897-1983)の、題名もそのままの『遠き山に日は落ちて』であろう。うろ覚えの人もおいでだろうから1番の詞を以下に示す。
遠き山に 日は落ちて
星は空を ちりばめぬ
きょうのわざを なし終えて
心軽(かろ)く 安らえば
風は涼し この夕べ
いざや 楽しき まどいせん
改めて素晴らしい詞だなぁと思う(「星は~ちりばめぬ」は文法的におかしいのでは?との疑念はあるが)。
さて、この歌詞については今でも忘れられない事がある。小学6年生の季節も今時分、林間学校の準備を進めていた。林間学校と言えばキャンプファイヤ、とくればそこで歌われる歌集・・・・という事で、今後も長く使用に耐えるものをとの意図からであろう、立派な歌集が出来た。当然この歌が収められていた。が、中身をみてびっくり。この歌詞最後の「まどいせん」が「まどいません」となっている!・・・・印刷業者がこれは「惑いません」の誤りだろうと気を利かせ「ま」の字を挿入したのだろうが立派な誤植。こういう人間味のある誤植は、変換ミスばかりが横行しがちな今や絶滅したが、厳格であるべき教師らの校正の網の目をくぐって生き残ってしまったのだった。流石にこのまま放置という訳にもいかず(そもそも字余りで歌えない)、我々は「ま」の字を抹消した。四半世紀も前の小学生が行った墨塗り教科書を実習する羽目となった訳だ。
だが自分自身もこの印刷業者を嗤えない。「まどいせん」の意味も考えずにただ歌っていたのだから。やがて疑義も芽生えたが、「窓にどんな線が入っているのだろう?」程度の疑問が湧いたに過ぎない。長ずるに従い次第に多少の知恵もついて前後の文脈も考えられるようになった。挙句「これは『まどい船』という舟なのだ。夜舟に乗り、涼風に当たって楽しもうという事に違いない。何せ『いざや』というくらいだ。気合が入っている」・・・・との結論に至ったのが、前述の「まどいません」事件直前。当時は納涼船なるものの存在は知らなかった。また「まどい」の語を辞書で調べても「惑い」しか出て来ないので、「まどい船」とは漠然と夕涼み用に造られた舟を指す、辞書にも載らぬ未知の言葉なのだという解釈をせざるを得なかった。やはり賢い子供ではなかったなぁ(そして変わらぬままこんにちに至る)、とつくづく思うのである。
その後古文というものを学ぶに及んで「~せん」⇒「~せむ」の語尾が意志を表している事を理解した。だが「まどい」の何たるかが解らなければ「まどい船」の段階からの進展はない。流石に古語辞典を引いてみた。正しくは旧仮名の「まどゐ(まとゐ)」で円居・団居の漢字を当てる。「人々が輪になって座ること。車座。団欒(だんらん)。」と大抵の辞書にあり、揃って『源氏物語』の「若菜・下」の用例を引いている。千年を超える歴史を持つ由緒ある言葉!「さあ、楽しい集まり(或いは団欒)を持とう」の意である。舟とは何のゆかりもなかった(苦笑・・・・当たり前)。
堀内敬三は僕の出身高校の校歌も作詞していて、相応の親しみは持っていたつもりだったが、既存の旋律に歌詞を当てはめるという困難克服のため、こうした古語をも駆使してひとつの詩的世界を完結し得る力に、改めて畏敬の念を抱いた。またこの歌詞に限らず文語の意味は旧仮名遣いで表記しなければ意味も曖昧になると知った。本来「まどゐせむ」である。
今回改めて気づいた事がある。この一節「いざや・楽しき・まどいせん」を歌った時「楽しき」ではなく「楽し」としていたのではないか?である。この「楽しき」部分の旋律の音は分割されていない。またこの歌詞は冒頭からずっと六音-五音の謂わば六五調の旋律線をなぞるが、最後の一節だけが七五調になっている。文意からも文法的にも「まどゐ」に係る連体形であるべきだが、歌唱の際にここだけリズムが崩れるのは避けがたく、意味を犠牲にしても「楽し」の終止形にしていたように思う。終止形にしてしまうと、「いざや~せん」という呼応関係が成り立たなくなるという難もあるが、どうせ続く「まどいせん」の意味がほぼ不明だから、文意など考えずに歌っていたというのが真相ではなかろうか?もっともこれは僕が通った埼玉県下の小学校ならではの慣習だった可能性も否めない・・・・と思って家人に訊いてみた。彼女も「楽し」の記憶があるといって、小学校教師だった両親の遺品の中から、昭和40年代の教育現場で使われていたとおぼしき歌集を探し出してきた。この歌のページをみると旋律線に合わせて「楽し」になっている!・・・・子供の頃の記憶の強靭さを思うべきか?或いはこの頃から文語の歌詞が軽視が始まり、歌い継がれてきたかつての唱歌が教科書から今もどんどん消えている流れに通じているのか?大人になって知る歌詞の文意のしみじみとした味わいを思うと、ひたすら残念の感去らず。
新響のおカネの話などなど(後編)
(編集人より)
前号に引き続き小出さんの、運営委員長時代のエピソードの数々を収めた後編をお送り致します。知られざる新響の「裏面史」ともいえる内容です。前編についてはhttp://www.shinkyo.com/concert/i257-1.html
からお読み戴けます。
■第三章「帰国後の新響」
5年の時間が経過、芥川さんも亡くなり、新しい=若い魅力的な団員も増え(自分が年取った)雰囲気が随分変わり、でも再び新響で音楽できる喜びにあふれ、ちゃんと楽器がそろってチューニングがある!うれしさありましたね。
再入団当時(1996年)、創立40周年で、邦人作品2夜連続の演目!おお、これぞ新響だ!その演奏会で一応エキストラでの出演依頼をいただいていたのですが、「どうせ再入団するのだから(勝手に決めるな)さっさとオーディションを受けろ」、となりまして。メンバーはそれなりに変わっていましたが、オーディションで審査する人(首席奏者群)はほとんど変わっていなくて、皆怖い顔していた=なまじその人たちを知っていたので何を言うかよくわかり、余計足が震えて、おまけにその日、オーディションの前に邦人作品のパート練習があって、それ終わってすぐ、「ではMozartの第5番をよろしく!」。いろいろご意見はあったようでしたが、でもまあ何とか再入団できて今日に至っております。「おかえりなさい」といってくださったPercussionのN氏(元団員)に感謝です。再入団してほどなくして財務を拝命しまして、その後2001年度~2002年度にかけて、時代の変遷とともに新響もいろいろと変わり、ちょうど節目だったのでしょうか、自身が運営委員長に就任し、新しい指揮者や懐かしい指揮者との出会いもあり、充実した委員長時代(話せば一か月ぐらいかかるよね、当時演奏委員長を務めていた松下さん!)を過ごすことができました。
いくつかのエピソードをご紹介致したく。
1. 故小松一彦先生:先生ご自身、「僕の毒気に充てられないように」なんておっしゃるぐらい個性強烈でした。小松先生の若かりし頃の指揮を2度拝聴していたことも何とも言えないご縁を感じました。エピソードとしては、
①三連発大好き:ローマ三連発企画(レスピーギのローマシリーズ)、オケコン三連発(オーケストラ・コンチェルト、いちばん有名なのはバルトークですが、それを除いた三曲)、等。
②こういう企画書がFaxで会社に届く、しかも数十ページ。
③当時の携帯電話は電波が悪く通じない圏外も多かったのに、圏外表示になっている私の携帯に小松先生だけ着信がある(通称亜空間通信)。電話口では「指揮者の小松です」と、アダージェットで低音の神の声が:暗闇でしか聞こえぬ声がある…。
2. 高関先生との再共演:バルトークの『中国の不思議な役人』全曲でしょうか。この曲はとにかく演奏が難しく、でもやりがいが大変あった曲を先生のタクトで演奏できたのは大変幸せでした。その後も幾度となく共演できたのはとてもいい経験になりました。
3. 最後に登場するは、最近の国際情勢もあるので少々出すのに気が引けるのですが、その某国のピアニストVO氏を招聘、チャイコフスキーのピアノ協奏曲を演奏した時のこと。VO氏招聘を指揮者の紹介で話が進み、VO氏も一度練習に来られ、そのすごさに団員一同感動。これはすごい演奏会になるぞ!と思っていたら、「前日にイタリアでコンサートがあり、その日の朝に東京に着ければ演奏会に出演できる。何とかできないか。」なんて話が舞い込みまして、指揮者は怒り心頭。運営サイドは、チラシは印刷しちゃっているし今更演目変えられないし、ソリスト変更といってもそう話は簡単ではないという感じで、某国サイドとの交渉、国内仲介者の某大学事務局と無駄になった費用負担の交渉等取り進め、指揮者のご尽力もあり、最終的に同じ某国のAP氏が来てくださることに。AP氏、めっちゃくちゃかっこよくてイケメン、お嬢様もいらしてとにかくかわいい~なんて話もあり、当時の新響女性団員も写真撮ったりと、大騒ぎ。肝心の演奏も、きらびやかかつ華麗で、万雷の拍手で演奏会は大成功。打ち上げで盛り上がり、当方は委員長の責務として、当時の団長とともにAP氏をホテルに送り届けましたが、そこにはイケメン日本人男子が数名待っていた。AP 氏はQueenのVocal故フレディ・マーキュリーと同じ(個人的見解)で、自由な愛の表現者であったことが判明。私自身の実体験(ちょっとした身体的接触)として鮮烈に記憶に残っております。
ちなみに同行していた団長は、そばで傍観しギャハハと笑ってスルー、私は痕跡を消しつつ自宅に帰りWifeに話したら大爆笑され。どうも打ち上げの場でもその傾向はあったらしいと、ほかの男性団員からは後日聞いております。新響はユニークな人々の集団ではありますが、この経験は二度とごめんこうむります。委員長時代は2年間でしたが、この通り濃密な、多様性に富んだ経験ができました。
18歳以降、オケとともに人生があり、その大半を新響とともに過ごし、オケと新響なくして自身の音楽人生はないです。これだけ多様な音楽に出会い、指揮者や指導者に出会い、肝を冷やした演奏から喜びいっぱいの演奏、たくさん経験できました。
この後どれだけ新響で続けられるかわかりませんが、そろそろおカネから解放されて、純粋に音楽を楽しみたいですが、悲しい財務の性、おカネのことはこれからもかかわっていくのだろうな、と思います。
最後まで駄文をお読みいただき、感謝です。維持会員の皆様、今後とも新響をよろしくお願いいたします。
第258回演奏会のご案内
新しい時代の指揮者 坂入健司郎
坂入は1988年生の34歳。幼稚園の頃からクラシック音楽にのめり込み、小学1年生の誕生日に『新世界より』のCDを複数種プレゼントされて指揮者の仕事に興味を持ったという。多くの指揮者と交流を持ちつつも音大には進まず慶應義塾大学からサラリーマンに。自分のオケを持ち働きながら指揮活動を続け昨年プロとして歩み始めた今大注目の指揮者です。
アメリカからチェコを想う『新世界より』
プラハ音楽院教授として地位も名声も手に入れたドヴォルザークは、51歳の時ニューヨークのナショナル音楽院の院長に招聘されアメリカに渡りました。受け持った学生の中には黒人もいて黒人音楽に触れ、元々鉄道ファンなのに加え船にも興味を持ち毎日のように波止場や鉄道の駅を訪れ、そして祖国を思いホームシックになりました。そんなアメリカ滞在中に作曲されたのが彼の最後の交響曲『新世界より』です。アメリカ的な要素がチェコの音楽と融合したドヴォルザークの最高傑作の1つですが、汽車や汽船も登場します。
ドヴォルザークがアメリカに滞在したのは3年間と短かったのですが、アメリカのクラシック音楽が独自性を持って発展するきっかけとなりました。
パリに行ったアメリカ人作曲家 ガーシュウィン
ガーシュウィンが音楽を学び始めたのは12歳と遅かったのですが、若くしてポピュラーソングの作曲家となり、多くのミュージカル・ナンバーを世に出すヒットメーカーでした。クラシック音楽に取り組んで管弦楽作品も残しており、『パリのアメリカ人』はニューヨーク・フィルの委嘱で書かれた交響詩です。同名の映画やミュージカルがあり最近も上演されていますが、実は音楽が先で後から物語がつけられたのです。20代の時に訪れたパリの街の様子が描かれ、当時の最先端のフランス音楽の要素を取り入れたシンフォニック・ジャズとなっており、パリを走る車のクラクションも登場します。
パリでラヴェルに弟子入りを志願しますが、「一流のガーシュウィンなのだから二流のラヴェルになる必要はない」と断られたのだそうです。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
リヒャルト・シュトラウス:交響詩「死と変容」
シュトラウスと交響詩
「死と変容」は交響詩という音楽形式で書かれている。交響詩とは、ロマン派時代にリストが提唱した詩的なニュアンスを含む標題のある管弦楽曲である。
ロマン派以前のベートーヴェン、ハイドンらの古典派の音楽を学んだシュトラウスが交響詩の作曲を始める動機となったのは、オーケストラの指揮を始めた20歳頃に出会ったワーグナーの革新的な音楽であった。表題を基にした濃密なストーリー展開や、交響曲に比べ短く聴きやすいことから忽ち人気を博すこととなった。
シュトラウスは1888年の「ドン・ファン」を皮切りに1898年の「英雄の生涯」までの10年間で7つの交響詩を作曲している。
「死と変容」は、彼が25歳の時に作曲した3作目の交響詩で、自身が指揮するオーケストラのヴァイオリン奏者であったアレクサンダー・リッターの作詩を題材にしている。
ストーリーは大略次のようなものである。死の床にある病人が迫りくる死との戦いの中で、幸せな若き日を回想し生への強い執着を見せるが、ついには力尽き、追い求めた理想は実現することはなかった。しかし、死して魂となった今、まさに自分の理想とする世界を見つけ、天に召されるというものである。
死との闘争、甘美な過去の回想、そして魂が天に召される神々しい情景が独特のリズムと色彩豊かな音色で展開する。若き天才作曲家の創造した約25分間のドラマティックな音絵巻を堪能していただきたい。
楽曲について
序奏部はハ短調のLargoで第2ヴァイオリンとヴィオラの不規則なリズムで静かに始まる(譜例①)。死の床にいる病人の不安定で弱い脈拍のようだ。時折来るフルートの装飾音は痛みのようにも聞こえる。
ハープの分散和音に乗って、フルートとクラリネットが幸せな思い出を回想しているかのような甘美な旋律(譜例②)を奏でると、オーボエも新たな回想の旋律を続ける(譜例③)。夢の中で人生の幸せな出来事を思い出して微笑んでいるかのようだ。
穏やかな回想シーンから一転、ティンパニの一撃を合図に死との闘争が始まる。低弦と低音木管による重厚な上昇音階のフレーズは、病人を執拗に鞭打つようで痛々しい。
死との闘いの中で生への執着は強くなり、死に対する宣戦布告のような勇ましいテーマが全奏される(譜例④)。
死との闘いが激しさを増し、青春時代の回想と絡み合いながら生への執着が頂点に達すると、雄叫びのようなテーマ(譜例⑤)が奏される。
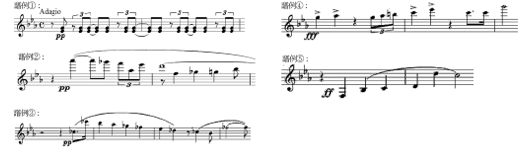
再び静寂が戻ると、速度を落とした回想シーンとなる。弦パートの三連符にフルート、ソロヴァイオリンが(譜例③)の旋律を重ね、 (譜例②)も交えながら幸せな場面が続き、次第に曲調は力強く情熱的に展開していく。
突然トロンボーンとティンパニが死との闘争の狼煙を上げると、若き日の回想、死との闘争が激しく絡み合いながら、生への執着が高まるが、次第にテンポが緩み再び現実引き戻される。
その後、短い冒頭の序奏部に続き、再びティンパニの強打で最後の戦いが始まるが、病人に抗う力はほとんど残っておらず、間もなくドラ(タムタム)の重い一撃により最期の時が訪れる。
長く苦しい死との闘いが終わり、魂が肉体から解放されると、天上からは一筋の光が現れる。ハ長調の清らかな明るい変容のテーマ(譜例⑤)が幾重にも奏されながら、光は大きく輝きを増していき、ついには全奏で頂点に達したのち、この上なく美しく幸福に満ちた響きの中、静かに終わる。
1900年頃のドイツの平均寿命は50歳に届かない中、シュトラウスは2度の大戦をくぐり抜け、病弱であったとは到底思えぬ85歳という長寿を全うしている。
筆者の推測ではあるが、この曲は生きる希望を見出し、自らを奮い立たせるために作曲したのではないだろうか。生きることは素晴らしい、そして死は決して恐ろしいことではないから安心しなさいとこの曲を通して言ってくれているような気がするのである。
初演:1890年6月21日 作曲者自身の指揮 アイゼナハ市立劇場
楽器編成:フルート3、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、タムタム、ハープ2、弦五部
参考文献:
『作曲家別 名曲解説ライブラリー9/R.シュトラウス』音楽之友社 1993年
江藤光紀『(総譜解説)死と変容』日本楽譜出版社 2019年
ブラームス:交響曲第4番ホ短調
誕生からシューマン夫妻との出会い
ブラームスは1833年5月7日にハンブルクで生まれた。父はコントラバス奏者で、幼いブラームスの音楽的才能を見抜き、まず自らヴァイオリン、チェロを教え、次いでハンブルクの有名ピアノ教師につけた。この教師がさらにその師匠につかせ、と彼の才能を見抜いた人々によって、彼の音楽教育環境はどんどんアップグレードされていった。ピアノと同時に作曲も始めている。10代前半からピアニストとして演奏会を開き、また家計を助けるためにハンブルクの酒場でもピアノを弾いていたという。20歳の時にシューマン夫妻と出会い、その後押しにより音楽界にデビューを果たし、初期には歌曲、室内楽曲を中心に創作活動を進めていった。
交響曲第4番作曲まで
交響曲第1番の作曲に20年以上かかった、というのは有名である。ブラームスは決して筆は遅くない。ブラームスの、崇拝するベートーヴェンに引けを取らない作品を、という強烈な思いが、20年超もかかった原因だと言われている。交響曲第1番が1876年に完成すると、ベートーヴェンの呪縛から解放されたかのように、一気に管弦楽作品の傑作群が生まれる。4曲の交響曲の他、管弦楽の代表作のほとんどがここからの10年間に作曲されている。その最後を飾るのが1885年に完成した交響曲第4番である。
作品と構成
全体的に古風な雰囲気の感じられる曲だ。随所にブラームスらしい、情感あふれる表現が見られるものの、基調には荘厳で背筋の伸びたような立派さがある。
第1楽章 Allegro non troppo 快速で、だがやりすぎず。ホ短調、2/2拍子。
いきなりヴァイオリンのオクターブの第1主題の旋律が半拍先行して始まり伴奏が後を追う。哀愁をおびた、いかにもブラームスらしい旋律である。主題は変形されながら進み、ホルンとチェロのユニゾンによる朗々たる第2主題が現れる。
古典的なソナタ形式は提示部を繰り返すのが通例で、ブラームスも第1~3番の交響曲には第1楽章の提示部に繰り返し記号がある(実際の演奏では繰り返さない場合も多いが)。これに対して第4番は繰り返しがない。だが、展開部の始まりの8小節間は曲の冒頭と全く同じなので、提示部が繰り返されたのかと一瞬思ってしまうが、9小節目になると実は展開部に入っていたということがわかる仕掛けになっている。
展開部の最後は一瞬小休止の気配を見せた後、忍び込むように再現部に入る。最終部のコーダに入ると第1主題が冒頭とは対照的にきっぱりとアクセント付きのffで奏され、そののち劇的に楽章を終える。
第2楽章 Andante moderato 歩く速度よりやや速めで。ホ長調、6/8拍子。
冒頭にホ音で始まりホ音で終わるフリギア旋法の旋律がホルンと木管のユニゾンで提示される。調性としてはハ長調だ。と、これを受け継いで、最後の伸ばしの音のホ音を主音とするホ長調で同じ旋律が奏される。ホ音が伸ばされている間にハ長調の「ミ」からホ長調の「ド」に変わってしまうという、しりとりのようなトリックだ。この後は終始ホ長調でこの旋律が展開しながら曲が進んでいく。
第3楽章 Allegro giocoso 快速で、おどけて。ハ長調、2/4拍子。
最初の18小節で3つの主題が次々と明るく元気よく提示される。ただし提示はあっという間に終わるので、要注意だ。以後はこれらが自由に展開されていく。この楽章しか出番のないトライアングルが大活躍するのも要注目。
第4楽章 Allegro energico e passionate 快速で力感をもって、情熱的に。ホ短調 – ホ長調 – ホ短調、3/4拍子 – 3/2拍子 – 3/4拍子。
この曲の中でも最も古風で荘厳な楽章で、シャコンヌ風の変奏曲の形式をとっている。この楽章でトロンボーンが加わる。最初の8小節で主題が提示され、その後きっちり8小節単位で30の変奏が展開される。まずは理屈抜きで、変奏曲の名手ブラームスが繰り広げる、それぞれ全くキャラクターの違う、それでいて有機的に推移する変奏を堪能していただきたい。
筆者なりに大きな区切りをつけると、第12変奏までが第1部、第13~15変奏が第2部で、この間はホ長調である。また第12~15変奏の間は3/2拍子で、1小節の長さがそれまでの倍になっている。第16~30変奏が第3部で、3/4拍子に戻る。第3部冒頭で主題の旋律が再現されるが、和音の進行や弦の動きが主題とはやや異なる。第30変奏の最後に4小節おまけがついたのちに終結部に入り、冒頭の主題が3度目の登場となる。この後は強奏が続き、力強く荘厳に曲を締めくくる。
初演:1885年10月25日 作曲者自身の指揮 マイニンゲン
楽器編成:ピッコロ(2番フルート持ち替え)、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、トライアングル、弦五部
参考文献:
さいとうみのる『世界の音楽家たち 第Ⅱ期 新古典派の完成者 ブラームス』汐文社 2006年
ひのまどか『ブラームス「人はみな草のごとく」』リブリオ出版 1985年
吉田秀和『ブラームスの音楽と生涯』音楽之友社 2000年
諸井誠『ブラームスの協奏曲と交響曲 作曲家・諸井誠の分析的研究』音楽之友社 2014年
ウェーバー:歌劇「魔弾の射手」序曲
カール・マリア・フォン・ウェーバーは1786年、現在の北ドイツ、シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州の東側に位置するオイティンという街に生まれた。19世紀ごろから始まる初期ロマン派時代に活躍したドイツの作曲家である。交響曲等、幾つかの純器楽の作品を残しているものの、とりわけオペラの分野でもっともその名が知られている。今回は、その中でも最も代表的な「魔弾の射手」の序曲を取り上げる。
オペラの巨匠、その意外な生い立ち
幼少期のウェーバーはモーツァルトのような先天的な音楽の才能を示すことがなく、音楽そのものにもほとんど興味がなかった。それでも、舞台監督で音楽愛好家でもあった父親の影響で、幼少期から舞台と音楽との関連性を養っていた。彼の名作のほとんどがオペラ作品なのは、これが理由と言える。
10歳前後からは本格的に音楽の教育を受け始める。父によって叩き込まれた表面的な教え方に終止符をうち、作曲法、指揮法等を理論的に学び始めた。それから「交響曲の父」とよばれたフランツ・ハイドンの弟であるミヒャエル・ハイドンをはじめ、ドイツやオーストリアに点在した当時の著名な作曲家から英才的音楽教育を受け、少しずつ音楽家としての素質を作り上げて行った。
「魔弾の射手」の誕生、ドイツロマン派オペラに与えた多大な影響
ウェーバーは彼の作品を披露するため、父のアントンと旅をしている最中に、父より耐え難い窮迫にさらされていた。旅芸人の一座に囲まれながら、街から街へと振り回されては、彼の才能は父によってありとあらゆる手段で公に晒され、それから得た僅かなお金を見せ、「才能のあるものはたったこれっぽっちの収入で生きて行かなければならない」という言葉に翻弄され続けてきたという。そういった苦悩に晒され続けているうちに、ウェーバーの中に劇的な感情が生まれた。その募り募った感情が音楽という形で爆発する。それは古典派とロマン派の境目にある1821年に「魔弾の射手」として結実し、当時のオペラ界に大きな衝撃を与えた。ウェーバーはこの後に「オイリアンテ」「オベロン」というオペラを作曲しているが、まさにこの「魔弾の射手」がドイツロマン派のオペラの発祥となり、後のリヒャルト・ワーグナーに多大な影響を与えることとなる。1820年以前のオペラは主にイタリア語が主流であり、ドイツ語のオペラはモーツァルトが3作書いただけである。 曲調も古典的で単調、オペラの内容もコミカルなものが多かったが、ウェーバーの心の奥底にあった闇と苦しみが、思わぬ形で西洋音楽史に偉大な痕跡を残すこととなり、ウェーバーは一躍ドイツオペラの巨匠として、一気に名誉を得た。
古典派音楽からロマン派音楽への変化
前述の通り、曲は古典派の作品から進化を遂げたばかりで、曲も、オーケストレーション、強弱、音域においてかなり幅が広がり、表現力や感情がより一層増したものとなっている。序曲においても同じである。とくに注目すべき点は、音楽史の中でmp,mfという強弱記号が頻繁に使われるようになったことで、全体的な強弱の域が広がったという点である。古典派以前の作曲家はpp,p,f,ffという四つの記号しか使わず(例外は少なからず有る)、それぞれの強弱がどれくらいの音量なのかは曖昧で、それほど大事ではなかった。しかしロマン派時代に入り強弱のレベルがppp,pp,p,mp,mf,f,ff,fffの8段階に広がり、両端のpppとfffを除いても強弱の幅は古典派に比べて膨れ上がっているのが分かる。
古典派時代 : pp<p<f<ff
ロマン派時代: pp<p<mp<mf<f<ff
これもロマン派時代の曲の特徴である表現性、感情性の重視傾向の要素の一つと言える。今回はそんな表現力、感情力に溢れた演奏を是非身に感じて楽しんで頂きたい。
初演:1821年6月18日 作曲者自身の指揮 ベルリン王立劇場(現コンツェルトハウス)
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、弦五部
参考文献:
J. Palgrave Simpson, The Musical Times and Singing Class Circular Vol.12, No.267, Musical Times Publications Ltd. 1865
Catherine Jones, Translation and Literature Vol.20, No.1, Readings in Romantic Translation, Edinburgh University Press 2011
Joseph Kerman, Gary Tomlinson, Listen 5th edition, Bedford/St.Martin's 2004
第257回演奏会ローテーション
| 魔弾の射手 | 死と変容 | ブラームス第4番 | |
| フルート1st | 岡田 | 吉田 | 松下(新井) |
| 2nd | 藤井 | 林 | 兼子 |
| 3rd | - | 黒住 | - |
| オーボエ1st | 岩城 | 堀内 | 平戸 |
| 2nd | 堀内 | 山口 | 山口 |
| コールアングレ | - | 岩城 | - |
| クラリネット1st | 進藤 | 末村 | 品田 |
| 2nd | 末村 | 石綿 | 大藪 |
| バスクラリネット | - | 品田 | - |
| ファゴット1st | 田川 | 松原 | 藤原 |
| 2nd | 松原 | 浦 | 田川 |
| コントラファゴット | - | 藤原 | 浦 |
| ホルン1st | 大内 | 名倉(大内) | 山口 |
| 2nd | 山路 | 大原 | 大原 |
| 3rd | 名倉 | 山路 | 大内 |
| 4th | 市川 | 市川 | 山路 |
| トランペット1st | 瀧野 | 倉田 | 小出 |
| 2nd | 中川 | 北村 | 青木 |
| 3rd | - | 中川 | - |
| トロンボーン1st | 武田(浩) | 武田(浩) | 鈴木* |
| 2nd | 志村 | 鈴木* | 志村 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | - | 坂巻 | - |
| ティンパニ | 今尾 | 今尾 | 桑形 |
| パーカッション | - | Tamtam桑形 | Triangle今尾 |
| 1stヴァイオリン | 堀内(山口) | 堀内(山口) | 堀内(山口) |
| 2ndヴァイオリン | 今村(朝倉) | 今村(朝倉) | 今村(朝倉) |
| ヴィオラ | 田川(星野) | 田川(星野) | 星野(田川) |
| チェロ | 柳部(安田) | 柳部(安田) | 柳部(安藤) |
| コントラバス | 宮田(加賀) | 宮田(加賀) | 宮田(加賀) |
*はエキストラ
弦()はトップサイド、管()はアシスタント
飯守泰次郎氏に聞く(第159回演奏会プログラムより)
以下にご紹介するのは、前回飯守泰次郎氏の指揮によりブラームスの交響曲第4番を演奏した1997年10月の第159回演奏会のプログラム掲載のインタビュー記事の抜粋です。
---先生とのこれまでの4回のコンサートでは、ブルックナーとワーグナーがほとんどだったので、今回は、初めてとりあげる作曲家ばかりです。まずブラームスについてうかがいたいのですが。
飯守 カール・ベームによれば「ブラームスには3つの顔がある」。まさにその通りで、実に的を射ています。ブラームスは北ドイツの、ハンブルクよりさらに円舎の出身で、彼の音楽にはこの地方特有の暗さと重さがあります。パリやウィーンなど、気候の比較的おだやかな都会の音楽とは本質的に違うのです。暗い冬が長く続く地方では、ずっと家の中に閉じこもって暮らすことになりますから、だんだん気分が内向きになってくるでしょう。ブラームスの音楽にはそんな内向性があります。
その後ブラームスは、ヴァイオリニストのヨアヒムとの出会いを経てウィーンに至り、ウィーンの洗練と伝統的な様式感を身につけます。しかも、古典的なフォルムを重視してベートーヴェンを研究し、古典派をきわめて正統的に継承します。古典的な形式を重んじたのは、ブラームスが内気できちょうめんな面があったことも関係していると私は思います。ブラームスはベートーヴェンを正しく継承したからこそ、あの第1番の交響曲を書くまでに長い時間を必要としたのでしょう。
---40歳を過ぎてようやく世に出したのですね。
飯守 そうです。さて、3つめのブラームスの顔は、パーティ嫌いで内気だった一方で、酒場に通いつめ、そこのドイツ女性と踊ることを好んだという意外な一面です。以前オランダ航空の機内で見たテレビ映画で、老齢のブラームスが酒場のでっぷりと太った若いとはいえない女性の踊りを見て思わず席を立ち、彼女の豊満な胸に顔を埋めて踊り出し、彼の信奉者たちが困惑して視線を床に落とすという印象的な場面がありました。この、隠しきれない男性としての欲求は、実は各交響曲にもちらりと顔を出しているのです。なにか、根源的なものですね。これもブラームスの特徴です。
---日本でよく学校の音楽室にある肖像画のいかついイメージだけがブラームスではないのですね。
飯守 そうですね。彼には「ハンガリアン舞曲集」という作品がありますが、ハンガリー的な、民族的な気風に溢れたものにも強い憧れがあった。巨漢ブラームスが、「よっこいしょ」と老体にムチ打って踊ったり体操したりするようなリズムが、交響曲第2番などにもありますね。こうした部分は野暮だけれども良さがあって、これがなかったらブラームスの魅力は半減していたろうし、この点が古典的といってもハイドン、ベートーヴェンやシューベルトとはどこか違う理由でしょう。彼の作品には必ずと言ってよいほど、この種の民族音楽的な気風が隠れていて、それが魅力になっています。
もうひとつ、彼を特徴づけるものに、非常に成熟したロマンティシズムがあります。ブラームスのロマンティシズムは、個人を超えた次元に発展していると思います。彼にはシューマン夫妻との出会いがありましたが、ロベルト・シューマンの死後、残ったクララ・シューマンヘのブラームスの思慕は遂げられず、その愛は彼の心の奥底に深く埋めこまれてしまうことになります。それでも彼は、クララという人格から非常に多くのものを得たのでしょう。それでいて、作曲家として評価を得た後も村の小娘にぞっこんになってしまうような一面もあったそうです。
---そういうところは、前回ブルックナーについてうかがったお話と似ていますね。
飯守 その通り。さらに、ブラームスの音楽の特徴として私自身が付け加えるならば、ドイツ語でBogenという言葉があります。これは、大きな弧を描くような息の長さという意味ですね。
それと、高度に完成された作曲技法。ブルックナーがブラームスに会った際、プルックナーはすでに4つの交響曲を書いていながら見せる勇気がなくて見せられなかったという話もあります。
---前回のブルックナーについてのお話では、当時の音楽における表現の拡大傾向についてもお話が出ましたが、ブラームスはどうだったのでしょうか。
飯守 表現主義的な傾向はワーグナーから生まれたものですが、これはフランス音楽界にも強い影響を与え、初期のドビュッシーにも影響がみられます。一方、同時代のブラームスは、ワーグナー的な劇性には拒絶反応を示した、と言われており、たしかにブラームスは厳しい古典的な様式感を身につけていました。しかし、それにもかかわらず、彼独特の内面的表現力の強さと楽器法の新しさは、やはり表現主義につながっていく部分であると私は考えています。
また、ブラームス自身意識していなかっただろうけれど、彼の表現は時によると印象派を思わせる響きさえあると思います。
---それでは、今回の新響とのコンサートに向けてどんなことをお考えですか。
飯守 まず、ブラームスのBogen、息の長い音楽を表現していきたい。それから私は、ブラームスという人の「円熟」にとても魅力を感じます。彼は内気な人で、貧乏で狭い家に暮らした幼少の頃のことなどもあまり語りたがらなかった。ベートーヴェンやマーラー、リヒャルト・シユトラウスなどの饒舌さとは異なる内面の持ち主で、その内面から巨大なシンフォニーを作り上げた彼の円熟と個性を表現したい。
そして、先ほど触れた印象派的な響き。この4番ではたとえば第1楽章の木管と弦との会話のような所がそうですね。このどこか漂うような、転調がどこに向かっているのかわからず、調性がつかめないような部分は印象派に通じるところです。ヘミオレ[注:ギリシャ語の1 1/2に由来する語で、たとえば3拍子での2小節を2拍子の3小節のように分ける音型のこと]が多用されているのもブラームスの特徴で、その感覚もとても大切にしたい。
新響のおカネの話などなど(前編)
維持会員の皆様、いつも新交響楽団の活動をサポートいただき、誠にありがとうございます。まずは自己紹介を。
小出高明と申します。東京生まれの博多育ち、現在は横浜市在住。当団には、1980年5月に入団し、1991年10月に一旦退団(海外転勤でマレーシアへ)しまして、帰国後1996年5月から今日に至るまで当団にてViolinを弾いております。仕事は某エネルギー関連会社に大学卒業後入社、何の因果か、会社では経理部門に配属になり、その後は海外事業関連の仕事をしており、経理とは離れております。入社当時は今のようなシステムはほとんどなく、すべて電卓(上司はそろばん)で、経理上のいろいろな計算を行い、原価計算、減価償却費計算、財務諸表などを作成していたので、新響でも財務を拝命しまして、長年マネージャーを務めておりましたが、昨年度で一担当に退き後進に道を譲りました。
今回は、維持会の皆様に「新響のカネ」について寄稿するよう、維持会ニュース編集人より要請があり、誠に乱筆ながら、ペンをとりたいと思います。お金の話として私が語れるのは、維持会員の皆様よりいただいている貴重な会費の使途ではなく、通常会計での話です。それだけではあまりにも味気ないので、第一章「新響の財政」、第二章「マレーシアでのオケ事情=ただし1990年代前半」、第三章「帰国後の新響」と3部構成で臨みます。
■第一章「新響の財政」
「金は天下の回り物」。現代社会において、お金の形態は劇的に変化=キャッシュレス化、電子マネー、バーコード、仮想通貨など、さまざまな形態がありますが、お金が回れば経済回る!それはオケの活動をはじめとする芸術活動も同じですね。
オケで必要とするお金は、アマチュアオケの場合、純粋にオケの活動に関係する経費のみで、団員にオケから給与を支給する必要はありません。逆に新響では、団員が一定の活動経費(団運営の一般経費と演奏会にかかる経費負担)を団に上納(ノルマ)、それに外部チケットの売り上げで資金調達し、運営しております。コロナ下で入場者数に一定の制限を設けており、その分売り上げは制約を受けるので、ただでさえ赤字体質なところ、台所はさらに火の車であります。
経費は、演奏会場利用料、指揮者・ソリスト(めったにないですが)の出演料から、楽器運搬や練習関連経費、楽譜経費、などです。大体どのプログラムでも同じようなレベル感ですが、数年前に取り上げた『トリスタンとイゾルデ』のような企画もの(超有名な指揮者・ソリスト等出演者(ギャラがめっちゃ高い)、合唱、特殊楽器必要、作曲家への委嘱など、でも来ない限り、発生経費のそれほど変化はありません(2割程度)。
出ていく方の話はこれくらいで、収入について。上記の通りチケット売り上げがほとんどです。ほかの収入は、各演奏会プログラムへの広告掲載収入(最近は掲載していない)や、数年に1度「お座敷」といって依頼演奏会(不定期)に招待される時にいただく出演料が主なものです。また、ごくまれに外部からいただく助成金がありますが、これは審査が厳しい=企画性があるか、日本の文化・芸術の発展に寄与するものか、国際交流に多大な貢献をしている、など、なかなか厳しいハードルがあります。
申請先によりガイドラインが異なるので、申請先が増えるだけ手間が増える=助成金担当者はたくさんの書類を作成し、財務はその予算立案で参画。また、企画が承認されて助成金決定されると、報告書提出、場合によっては監査があり、厳しいチェックがあります。特に国の機関からいただける場合はしっかりとした監査があり、3~4名で乗り込んできて、伝票帳票類をひっくり返し検算、ほぼ半日仕事になるので、会社休暇取って対応したりしました。バブル期など以前は今に比べればゆるくて、報告書だけ出してはいそれでおしまい、なんて感じでしたが、今は、きちんと助成金の対象経費が支払われているか、非対象経費は含まれていないか、対象経費でも当該年度以外のものは入っていないか、領収書が正しいものか、などなど厳しいものです。このように、財務管理は様々な業務が絡んでおりますが、お金の管理をしっかりしないと演奏会を安心して実施できないです。
一般企業同様、新響も経費削減実施し演奏会を乗り切っておりますが、お客様に大勢ご来場いただくことでチケットがたくさん売れるのが一番効果的です。そのためには、皆様の心に残る、よい演奏をお届けすることが最善の策だと、日頃考えております。単純に有名な演目を取り上げること、超企画物を演奏すること、新響の伝統的ファンの方々にとって芥川先生の作品をはじめとする様々な日本人作曲家の演目を取り上げること、とお客様の興味は千差万別。それぞれのベクトルは異なるので、お客様皆様にとって共通して魅力的な企画というのはなかなか難しいですが、年に4回ある演奏会を活用してそういうことを実現していくと、財政も少しは好転するのではないか、と思います。
私の某国友人に新響の件を話したところ、「ありえない、自分でお金負担して演奏するなんてLogicalではない。しかもいろいろボランティアで仕事もして、何の得にもならない。報酬得て演奏するのが普通だろう!」なんてご意見もありまして、たぶん世界的に見てこのようなアマチュアオケが星の数ほど存在する国は日本ぐらいなのでは?と思ってしまいます。他の国々のアマチュアオケ事情は、自身の経験以外は知らないのですが。そういうわけで、わたくしの心のふるさとマレーシアでのオケ体験を次章で紹介します。
■第二章「「マレーシアでのオケ事情=ただし1990年代前半」=
社命でマレーシア国はKuala Lumpur(KL:マレーシア、省略形が多い)に1991年10月~1996年3月まで、家族帯同で駐在。マレーシアといえば、Twin Tower、ビーチリゾートのペナン島、ボルネオ島側だとコタキナバル、原油タンカーにとって重要なマラッカ海峡(お客さん連れて30回ぐらい行きました)、あたりが有名でしょうか。最近ではGACKTがKL居住していることで注目されていましたね。ほかにも2名程マレーシアに駐在した団員がおりますのも、何かの縁。
常夏の国ですが、中東のようなとんでもない気温(53度=華氏ではない、の経験あり)にはならず23度~35度(雨期)あたりで推移し、7~8月は日本より過ごしやすく、よく母親が避暑にきていました=Dry Seasonで、それほど暑くないのですよ。King of FruitのDurianがおいしく(賛否あり、私はフリーク)、ほかのフルーツ:マンゴー、マンゴスティン、パパイヤ、スターフルーツ、バカでかい八朔みたいなの、また現地料理:マレー料理(サテ、ナシゴレン等)、中華系の料理(マレーシアで独自の発展)、インド料理等々、それぞれ基本Spicyで、もともとSpicy Foodは大好きだったのでドはまり。1歳未満で連れて行った娘も、帰国した時には、Spicy大好きになっていました。日本の辛口カレーに「なんだこれ?」みたいな顔していましたね。一時日本ではやったバクテー(中国語:肉骨茶)も美味です=日本に紹介されていたのとは異なるものでしたが、Healthyで、夜飲んだ後に、深夜皆で現地のGROに連れて行ってもらっていました。さてGROとは何でしょう?ご想像にお任せいたします。
駐在して2か月ぐらいたった時、日本人(駐在員のご家族、ホルン奏者)から連絡があり、「KLでオケがあるけど手伝ってくれないか」、とのこと。なんと、元新響団員が指揮者をしていると。なんという偶然。この方はもともと商社マンで東南アジアを中心に仕事していたけど退職し自身でビジネスを立ち上げてマレーシアで仕事している傍ら、同国のアマオケで指揮を執ることになったようです(詳細は存じ上げないですが)。
オケの名前はKL Symphony Orchestra(KLSO)。最初の練習が強烈な体験でした。自身のオケ経験で、チューニングなしで練習が始まったのは初めて。楽器が揃っていないのはある意味仕方ないけど、音合わせないのか!私は、現地の方のコンマスと二頭体制で一応コンマスを拝命したのですが、指揮者(O氏)に、小出「チューニングは?」、O氏「今までやったことない」。その時のコンマスPY氏「なにそれ?」、小出「Aの音のピッチ合わせるのがオケの始まりだけど。チューナーは?」、PY氏「なにそれ?」てなやり取りが5分ほどあり、私が持っていたチューナーでチューニングのやり方を指導=浸透するのに時間を要しましたね。多民族国家マレーシアらしく、マレー人、中国系マレーシア人、インド系マレーシア人、日本人、ユーラシアンといわれるポルトガルの末裔の方々、そして老若男女(多分小学生もいた)で構成されていて、KLSOのメンバーはおそらく60名程度、ほかの足りない楽器やメンバーは、マレーシア国内のペナン島のオケ、フィリピンやシンガポールからのプロの助っ人で何とか。
では実力はどうかというと、鍛えがいのあるレベルでした。日本でいうと、普通の中学や高校のオケのレベルぐらいかと。皆さん、個人個人はそれなりに弾けるのですが、オケは別物なので、そこからいろいろ、僭越ながら教えていきました。弦楽器のセクション練習を受け持ったりして、指導すると音が変わるので、かなり面白かったですし、英語の練習にもなって、有意義でしたね。半年後に演奏会でしたが、最初のころはほとんど音楽にならなかったけど、指揮者が、”Mistake never mind! Please play!”と勇気づけ?だんだん音が出始め、そこに助っ人が加わり皆も弾けるようになってきて面白かったです。面白いといえば、だれも自分のミスを認めない!何か指摘すると、「私じゃない、こいつが悪い」と平気で他人のせいにする。いやいや、「あんたしか演奏していない場所だよ」、「いや、こいつが邪魔したから演奏できなかった。」とか、演奏直前まで、譜面製本していない人とか(ホチキスで左上端を止めたまま練習に参加)=譜めくりできないじゃん!、譜面を1ページずつクリアフォルダのあるファイルに入れている人=何も書けない・・・・等々、面白かったです。
「音楽に国境はないなあ」、どこかの誰かに聞かせたいような感想を持ちました。その後、コンマスを一度引き受け(気が進まなかった、現地の方の邪魔はしたくなかった)、『運命』、『白鳥の湖』などを演奏する機会に恵まれました。KLのオケは、そのあと活動を休止したのですが、そういえば一度もFeeを払った記憶がないので、KL市がお金を出していたのか、誰かがボランティア?で負担していたのか、謎であります。
そのほか、KL City Orchestra(KL市のオケだったかと:プロ)とか、Malaysia National Symphony Orchestra (MNSO:マレーシア国立交響楽団=完全にプロ)に参加。同国では国営石油会社Petronasが運営するMalaysia Philharmonic Orchestraが有名ですが、当時は存在してなくて、私は国立オケにエキストラでそれなりの回数出演=先方からの要請、会社に許可もらって出演しました(なんと、ギャラが出て。困ったぐらいの金額。ボランティアですから、とお断りしても決まりだから、とお役所のご回答。ありがたく頂戴し、一緒に働く現地社員との昼食会で使ったりしていました)。さすがにプロだけあってKLSOみたいなことはありませんでしたが、それでも主要楽器には助っ人参上。日本にあるようなホールもそれなりにありましたが、客席数が少ないので、World Trade Center(パシフィコ横浜を小さくしたようなもの)の大きなイベントルームで行われ、国立オケお披露目だったため、国のVIPが招待されており、その方々は最前列のソファー席に、場内アナウンスに先導されてご入場。これ、オケがスタンバイした後でしたね。それで、TV中継も入りまして、そしたら演奏中にTVカメラマンが演奏中に中継ルームと無線で話し始めて、指揮者が驚いて振り返っていましたね。お客様の反応はというと、演奏中は静かに聞いておられましたが、演奏終わって拍手が来て数秒で終わるのが面白かったです。この時の指揮者は前出のO氏だったのですが、曲がおわってカーテンコールみたいにするときに、拍手→静寂を繰り返していました。こうやって文化が根付くんだなと・・・・。
こういう幾多の経験をマレーシアでできたのはとても幸せでしたし、駐在3年目にマレーシアに大学オケで後輩だったM氏が駐在できて、国立オケで一緒に演奏したりする奇遇もあったり、人の縁って面白いですよね。
現地のクラシック奏者とも仲良くなり、当時のマハティール首相夫人の前で室内楽オケ(20名ぐらい)で演奏できたのも思い出だし、日本人学校にそのメンバーで出向いて演奏会もしましたし、個人的に日本人会でも何度か演奏をしましたね。
駐在期間中に、Violinの裏板が2度ほどはがれて(首が接しているところが)、日本に持ち帰ってもらって新響団員の陳さんのところで修理していただきました=それほど当時のエアコン事情はよくなかったです。高温多湿=鉛筆で紙に字が書けないぐらい湿気がある時もあり、しかも、結構停電があった=やたらと雷が落ちる(日本のすごい雷なんてかわいいもの)ので多かった=駐在後半、停電は改良されましたが、エアコンがそのたびに止まる。
楽器以外では、会社で個室が与えられ(多分、今の会社の常務の部屋より大きい)、秘書もいて、Driverもついて、という具合に、会社人生で最高の時期をマレーシアで過ごしたこともあり、とても幸せな駐在生活でしたが、なんといっても現地の方々がとても素晴らしく、そのおかげでよい仕事をすることができたことが大きいです。
医療は少々怖かった。日本の某医大卒業のお医者様が2名いたので何とかなりましたが、普通医者は患者に「いらっしゃいませ」って言わないよなあ、バリウム検査の時に、胃を膨らます錠剤飲んで20分も放置されないよなあ、血をとる時に新しい注射針を使うけど、それに息吹きかけ(フーフー)しないよなあ~、等々。
そのような、楽しい4年5か月が残念ながら終わり日本に帰国しましたが、新響に再入団して新たなオケ人生が始まりました。
後編:第三章「帰国後の新響」は次号に掲載します。お楽しみに!
第257回演奏会のご案内
今回のコンサートでは、指揮に飯守泰次郎氏を迎えドイツ・ロマン派の作品を演奏します。バイロイト音楽祭の助手を務めるなど長年ドイツを中心に欧州で活動しドイツ文化に造詣が深い飯守氏のタクトで、その魅力をお楽しみください。
ブラームス最後のシンフォニー
ブラームス(1833-1897)は、バッハ、ベートーヴェンと並びドイツ作曲家三大Bに数えられています。4つの交響曲のそれぞれに個性があります。第1番はベートーヴェンを意識し約20年かけ完成された荘厳で堂々としたもの。第2番はドイツの田園風景を思わせ明るく開放的。第3番は恋する気持ちが表れ甘美で哀愁的。そして最後に書かれた第4番は、それらすべての要素を併せ持つ最もブラームスらしい交響曲かもしれません。ブラームス自身も「自作で一番好きな曲」としていました。
1885年にブラームス自身の指揮でマイニンゲン宮廷管弦楽団で初演されましたが、同団の補助指揮者をしていた若き日のリヒャルト・シュトラウスがトライアングルを担当しました。
リヒャルト・シュトラウス=ドイツ・ロマン派最後の巨匠
R.シュトラウス(1864-1949)は、25歳からの10年間で「交響詩」と呼ばれる標題のついた作品を集中して作曲しました。『死と変容』もその一つです。若い頃は病弱でたびたび死の危機に直面することがあり、その時の心境を音にしたものです。
変容Verklärungは、キリストが光り輝く姿になった時にも使われる言葉で、日本では成仏の方がピンとくるかもしれません。作曲から60年後、シュトラウスが死の間際に昏睡状態から目覚めて「死と変容と同じだった」と言ったということです。
ドイツ国民オペラの始まり=「魔弾の射手」
ウェーバー(1786-1826)が歌劇「魔弾の射手」を作曲したのは1821年、19世紀初頭のドイツではイタリアオペラが主流でした。モーツァルト「魔笛」やベートーヴェン「フィデリオ」といったドイツ語のオペラはありましたが、外国の話が題材で、ドイツ民話に基づいたこのオペラは大成功を収めました。
物語はボヘミアの森。結婚がかかった射撃大会で悪魔に魂を売って入手した魔弾を使うことに。7発中6発は必ず命中するが1発は悪魔の望む場所に当たるという魔弾。悪魔は最後の1発を婚約者に当たるようささやくが結果はいかに!
どうぞお楽しみに!(H.O.)
ビゼー:「アルルの女」第1組曲・第2組曲より
パリから高速鉄道で南に約4時間。乾いた大地に照り付ける強烈な日差し、突如現れる巨大な円形闘技場。アルルに到着した者は異国に迷い込んだような錯覚に陥ります。ゴッホゆかりの地として有名ですが、私も古代ローマ時代から時が止まったかようなこの街に魅了され、度々訪れることとなった旅人のひとりです。本日お聴きいただくのは、そんな魅惑の街アルルの女への恋心から自らの命を落とす男の話です。
~あらすじ~
南仏カストゥレの農家の長男フレデリは、アルルで出会った美しい女のことが忘れられないが、馬の番人の情婦であると聞き、幼馴染ヴィヴェットとの結婚を決意。しかし婚約の日、馬の番人がアルルの女をさらう計画を耳にし、翌朝、窓から飛び降り命を絶つ。
組曲の成り立ちと構成
1872年、パリ。ヴォードヴィル座の芸術監督に就任したレオン・カルヴァロ(1825-97)は、作家アルフォンス・ドーデ(1840-97)の短編集『風車小屋だより』から『アルルの女』を戯曲として上演することを計画し、付随音楽をジョルジュ・ビゼー(1838-75) に依頼。完成した小編成の全27曲は、親しみやすい前奏曲と間奏曲、そして台詞にぴったりのBGMから成り、当時まだ誕生していないはずの映画音楽を思わせます。劇の上演は失敗に終わったものの、フル・オーケストラ用に編曲した組曲(第1組曲)が好評を博し、ビゼー没後には親友エルネスト・ギロー(1837-92)の編曲により別の組曲(第2組曲)が誕生。本日は、それぞれ4曲から成るふたつの組曲から6曲を演奏します。
1. Prélude(第1組曲第1曲)
劇音楽全体の前奏曲。南仏プロヴァンス民謡「王の行進」から始まり、中間部でサクソフォンが無垢な弟の動機を奏でる。
2. Pastorale(第2組曲第1曲)
第2幕第1場の間奏曲と合唱を基に編曲された。南仏の田園風景が目に浮かぶ。
3. Intermezzo(第2組曲第2曲)
第2幕第2場の間奏曲に基づく。第2場ではフレデリがヴィヴェットの愛を受け入れるまでが描かれる。
4. Menuetto(第2組曲第3曲)
原曲には存在せず、オペラ『美しきパースの娘』から転用された。フルート独奏曲として有名。
5. Adagietto(第1組曲第3曲)
第3幕第1場。農家に仕える羊飼いのバルタザールと、ヴィヴェットの祖母ルノーが再会し、若き日の恋の思い出を語り合い抱擁する。
6. Farandole(第2組曲第4曲)
第3幕第1場の終盤。婚約の日、翌朝の悲劇を暗示するかのように、聖エロアの日を祝うファランドール(南仏プロヴァンス地方の踊り)を夢中で踊るフレデリ。プロヴァンス太鼓のリズムに乗り、民謡「馬のダンス」と「王の行進」が交互に奏でられ、最後には一体となる。
なお、この作品にはアルルの女は一度も登場しませんが、作曲家が同時期に息を吹き込んでいたもう一人の宿命の女、カルメンとして後にその姿を現したように思えてなりません。ビゼーはオペラ『カルメン』初演の約3ヵ月後、36歳の若さで亡くなりました。
南仏への憧れ
この作品の創造の源となったのは南仏への憧れではないでしょうか。南仏はドーデの生まれ故郷であり、ビゼーにとってはローマ留学時代の思い出の旅先でした。遠く懐かしい場所だからこそ、より鮮明に描くことができたのかもしれません。異国を旅することが叶わない昨今ですが、近い将来、彼の地を再訪することを夢見て演奏したいと思います。
初演 :第1組曲1872年11月10日、第2組曲1880年3月21日 ジュール・パドゥルー指揮 コンセール・ポピュレール
楽器編成:フルート2(ピッコロ持ち替え)、オーボエ2(コールアングレ持ち替え)、クラリネット2、アルト・サクソフォン、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、コルネット2、トロンボーン3、ティンパニ、プロヴァンス太鼓、シンバル、大太鼓、小太鼓、ハープ、弦5部
参考文献:
ドーデ―(桜田佐訳)『風車小屋だより』岩波文庫1932年
ドーデ―(桜田佐訳)『アルルの女』岩波文庫1941年
遠山菜穂美『アルルの女』組曲 第1番・第2番
(スコア解説)全音楽譜出版社2017年
ミシェル・カルドース著、平島正郎、井上さつき訳
『ビゼー:「カルメン」とその時代∼』音楽之友社1989年
プーランク:組曲「牝鹿」
本日のプログラムの中で、いわゆる王道の名曲にはさまれたこの作品。今回の演奏会で取り組むことになるまで、私は恥ずかしながら作曲家プーランクのことさえまともに知りませんでした。しかし先日ちょうど初合わせを終え、既に軽妙洒脱な本作品に愛着がわいています。あまり馴染みのない方も、拙文が演奏会をお楽しみいただく一助となれば幸いです。
フランシス・プーランク
1899年、南仏・アヴェロン地方出身の敬虔なカトリック信者である父親と生粋のパリジェンヌの母親のもと、パリ都心部、8区のマドレーヌ地区に生まれました。裕福な家庭で幼少期から母親にピアノの手ほどきを受け、モーツァルトやドビュッシーを崇拝していました。プーランクは母親譲りのちゃきちゃきとした楽しい音楽と、父親譲りの真撃な宗教的な音楽を絶妙に操り続けた作曲家で、ウィットに富んだ軽妙な場面転換が特徴的です。和声的にはサン=サーンスやビゼーと比較してかなり凝ったエスプリの効いたもので、不協和音も不協和音に聞こえません。
演奏会用組曲「牝鹿」
本作品は彼が初めて手がけたオーケストラ作品であり、後にプーランクの名声をより確固たるものにした作品と位置づけられています。
1923年、ロシアで精力的に活動していたバレエ団「バレエ・リュス」の敏腕プロデューサー、セルゲイ・ディアギレフの依頼で作曲されました。結婚式を目前に控えた青年と妖精との、叙情的で幻想的なロマンティック・バレエ《ラ・シルフィード La Sylphide》の現代版、というのが依頼内容であったそうですが、本作品《牝鹿》の舞台は青いソファが1つ置かれただけの白く塗られた部屋、時期は暑い夏の午後。3人の若い男が16人の可愛い女の子達と無邪気に戯れているという他、明確なあらすじはありません。
チャイコフスキーの『眠りの森の美女』のヴァリアシオン、ストラヴィンスキーの『プルチネルラ』や『マヴラ』の影響を受けたとされる一方、1920年代初頭のサロンにおける「優雅な宴」を再現したともされます。快活なメロディ、哀愁を帯びたロマンティックな旋律を凝った和声で軽妙にはぐらかす、という場面が幾度となくでてきます。
本日演奏する組曲版は円熟期に入った1939年、プーランク自身がバレエ曲のうち数曲を抜粋し、演奏会用組曲として編曲したものです。私個人としては、あらすじがはっきりしない、また、視覚的なバレエの振り付けからも解放されているという点で、弾き手、聴き手それぞれの感性を自由に発揮して演奏を楽しんでよいのではないか、と解釈しています。
第1曲 Rondeau, Largo-Allegro
短い序奏に続き、華やかで軽快なメロディがトランペット、ホルン、弦楽器へと受け継がれます。神秘的な和音で短調の部分をはさみながらも上手にはぐらかされ、あっという間に明るい曲調に戻り締め括られます。
第2曲Adagietto
オーボエの憂愁をたたえたメロディに始まり、弦に受け継がれ、優しく歌われます。若者の悩みを象徴するかのような音楽は、部分的に吹奏楽のような響きに身を任せつつ、最後は静かにひっそりと終わります。
第3曲 Rag Mazurka, Moderato-Allegro molto
名目通り、快活な踊りの曲調ではじまり、メンバー各々が騒がしく個性を主張しますが、時に涙をみせているか
のような情景が目に浮かびます。
第4曲 Andantino
これまでとはうってかわった清楚な装いで、女子会が開催されている様子。人数が増え、騒いでいるところに男性らしいフレーズが入れ替わり立ち替わり顔を出します。
第5曲 Finale, Prest
ここまでの総括となる色彩感のある音楽に加え、再び出てくるジャズ風のサウンド、快活なフィナーレをお楽しみ下さい。
初演:1924年1月6日、モナコ公国モンテカルロにて、ディアギレフ・バレエ団による(パリ初演は同年5月)
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット3(3rdファゴットはコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、グロッケンシュピール、小太鼓(響き線あり)、小型小太鼓(響き線なし)、中太鼓(響き線なし)、合わせシンバル、吊りシンバル、大太鼓、トライアングル、タンブリン、ハープ、チェレスタ、弦5部
参考文献:
『標準音楽辞典』堀内久美雄 編 音楽之友社 2008年
『ラルース世界音楽事典』福武書店 1989年
『プーランクは語る 音楽家と詩人たち』
フランシス・プーランク、ステファヌ・オーデル編
(千葉文夫訳)筑摩書房 1994年
2020年9月 矢崎先生インタビュー(プーランク解説動画)
プーランク:組曲「牝鹿」
本日のプログラムの中で、いわゆる王道の名曲にはさまれたこの作品。今回の演奏会で取り組むことになるまで、私は恥ずかしながら作曲家プーランクのことさえまともに知りませんでした。しかし先日ちょうど初合わせを終え、既に軽妙洒脱な本作品に愛着がわいています。あまり馴染みのない方も、拙文が演奏会をお楽しみいただく一助となれば幸いです。
フランシス・プーランク
1899年、南仏・アヴェロン地方出身の敬虔なカトリック信者である父親と生粋のパリジェンヌの母親のもと、パリ都心部、8区のマドレーヌ地区に生まれました。裕福な家庭で幼少期から母親にピアノの手ほどきを受け、モーツァルトやドビュッシーを崇拝していました。プーランクは母親譲りのちゃきちゃきとした楽しい音楽と、父親譲りの真撃な宗教的な音楽を絶妙に操り続けた作曲家で、ウィットに富んだ軽妙な場面転換が特徴的です。和声的にはサン=サーンスやビゼーと比較してかなり凝ったエスプリの効いたもので、不協和音も不協和音に聞こえません。
演奏会用組曲「牝鹿」
本作品は彼が初めて手がけたオーケストラ作品であり、後にプーランクの名声をより確固たるものにした作品と位置づけられています。
1923年、ロシアで精力的に活動していたバレエ団「バレエ・リュス」の敏腕プロデューサー、セルゲイ・ディアギレフの依頼で作曲されました。結婚式を目前に控えた青年と妖精との、叙情的で幻想的なロマンティック・バレエ《ラ・シルフィード La Sylphide》の現代版、というのが依頼内容であったそうですが、本作品《牝鹿》の舞台は青いソファが1つ置かれただけの白く塗られた部屋、時期は暑い夏の午後。3人の若い男が16人の可愛い女の子達と無邪気に戯れているという他、明確なあらすじはありません。
チャイコフスキーの『眠りの森の美女』のヴァリアシオン、ストラヴィンスキーの『プルチネルラ』や『マヴラ』の影響を受けたとされる一方、1920年代初頭のサロンにおける「優雅な宴」を再現したともされます。快活なメロディ、哀愁を帯びたロマンティックな旋律を凝った和声で軽妙にはぐらかす、という場面が幾度となくでてきます。
本日演奏する組曲版は円熟期に入った1939年、プーランク自身がバレエ曲のうち数曲を抜粋し、演奏会用組曲として編曲したものです。私個人としては、あらすじがはっきりしない、また、視覚的なバレエの振り付けからも解放されているという点で、弾き手、聴き手それぞれの感性を自由に発揮して演奏を楽しんでよいのではないか、と解釈しています。
第1曲 Rondeau, Largo-Allegro
短い序奏に続き、華やかで軽快なメロディがトランペット、ホルン、弦楽器へと受け継がれます。神秘的な和音で短調の部分をはさみながらも上手にはぐらかされ、あっという間に明るい曲調に戻り締め括られます。
第2曲Adagietto
オーボエの憂愁をたたえたメロディに始まり、弦に受け継がれ、優しく歌われます。若者の悩みを象徴するかのような音楽は、部分的に吹奏楽のような響きに身を任せつつ、最後は静かにひっそりと終わります。
第3曲 Rag Mazurka, Moderato-Allegro molto
名目通り、快活な踊りの曲調ではじまり、メンバー各々が騒がしく個性を主張しますが、時に涙をみせているか
のような情景が目に浮かびます。
第4曲 Andantino
これまでとはうってかわった清楚な装いで、女子会が開催されている様子。人数が増え、騒いでいるところに男性らしいフレーズが入れ替わり立ち替わり顔を出します。
第5曲 Finale, Prest
ここまでの総括となる色彩感のある音楽に加え、再び出てくるジャズ風のサウンド、快活なフィナーレをお楽しみ下さい。
初演:1924年1月6日、モナコ公国モンテカルロにて、ディアギレフ・バレエ団による(パリ初演は同年5月)
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット3(3rdファゴットはコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、グロッケンシュピール、小太鼓(響き線あり)、小型小太鼓(響き線なし)、中太鼓(響き線なし)、合わせシンバル、吊りシンバル、大太鼓、トライアングル、タンブリン、ハープ、チェレスタ、弦5部
参考文献:
『標準音楽辞典』堀内久美雄 編 音楽之友社 2008年
『ラルース世界音楽事典』福武書店 1989年
『プーランクは語る 音楽家と詩人たち』
フランシス・プーランク、ステファヌ・オーデル編
(千葉文夫訳)筑摩書房 1994年
2020年9月 矢崎先生インタビュー(プーランク解説動画)
メンデルスゾーン:交響曲第3番イ短調 「スコットランド」1842年 ロンドン稿
メンデルスゾーンの交響曲
フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ(1809-1847)はドイツ初期ロマン派の代表格で、彼は音楽の発想が音楽以外のものと結びついていることが多い。本日演奏する交響曲第3番「スコットランド」もその代表曲の1つである。1829年に両親へ宛てた手紙の中で、スコットランドの歴史や風景から作曲のアイデアを得たと書いている。これに「音画的手法と異国情趣」の2つを加えたことで、特に高い人気を集めたものが交響曲第3番「スコットランド」と第4番「イタリア」である。
交響曲第3番「スコットランド」
着想を得たのは、エディンバラの観光中であった。彼は思いついたメロディーをその場で書き記したと見られている。交響曲第3番は1842年1月20日に完成した。1843年には彼自身が再校を行い、数か所の訂正と変更がなされている。通常1843年版が演奏されるが、本日演奏するのは1842年ロンドン稿である。相違点を1つ挙げると、ロンドン稿第4楽章の再現部へ向けた19小節の準備部分が、1843年版では8小節に短縮されている。使用楽器もロンドン稿では弦楽器群であるが、1843年版では木管楽器群である。本日の演奏では上記のような違いをぜひ楽しんでもらいたい。
作品構成
この曲の最大の特徴は「4つの楽章すべてを途切れなく続けること」である。彼が作品全体のまとまりを重視したためだ。
第1楽章Andante con moto-Allegro un poco agitato イ短調 3/4拍子-6/8拍子
冒頭はヴィオラが中心で、フルート以外の木管楽器とホルンが重なったあと、2小節間のヴァイオリンのユニゾンでシンコペーションを作りながら進んでいく。冒頭のモティーフの変形が変ロ長調、ffで現れ、静まりながら主部へつながる。523小節目で冒頭のAndanteが再現され、次楽章へ切れ目なくつながっていく。
第2楽章 Vivace non troppo ヘ長調 2/4拍子
弦の序奏を受け、フルート+オーボエ、ファゴット、ホルンの順でモティ―フが出る。主題は9小節目アウフタクトからクラリネットが受け持つ。(譜例1)
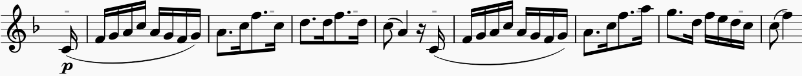
譜例1
72小節目アウフタクトからは弦による第2主題。この楽章は2つの主題が交互に現れることにより形成されている。最後はattaccaでそのまま第3楽章へつながる。
第3楽章 Adagio イ長調 2/4拍子
ニ短調の和音で始まり、第1ヴァイオリンの旋律、第2ヴァイオリンとヴィオラのピッツィカートに加えて低弦と管で穏やかな流れが作られ、10小節目から主題が出てくる。
対して34小節目アウフタクトから管楽器の第2主題が現れ、主旋律はホルンである。第2楽章同様attaccaで、第4楽章へつながる。
第4楽章Allegro vivacissimo-Andante maestoso assai イ短調 2/2拍子-イ長調 6/8拍子
3小節目アウフタクトからヴァイオリンによる主題が現れ、102小節目アウフタクトからオーボエソロのホ短調の第2主題が始まる。
418小節目で雰囲気が変わり、第1楽章同様ヴィオラが主体となる。楽章終盤へ向けその他の楽器も加わり、ffの全合奏で華やかに曲が終わる。
初演:1842年3月3日 作曲者自身の指揮によりライプツィヒ・ゲヴァントハウスにて。(初演稿)
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、ティンパニ、弦5部
参考文献:
星野宏美『メンデルスゾーンのスコットランド交響曲』
音楽之友社 2003年
ハンス・クリストフ・ヴォルプス(尾山真弓訳)
『大作曲家 メンデルスゾーン』音楽之友社 1999年
池辺晋一郎『メンデルスゾーンの音符たち 池辺晋一郎の「新メンデルスゾーン考」』音楽之友社 2018年
Claudio Abbado 1985 “SYMPHONIEN NOS.3&4” London symphony orchestra UNIVERSAL MUSIC
「遅れて来た神童」の悲劇=メンデルスゾーン評価の変転を巡って=
◆ゲーテとメンデルスゾーン
いま小林秀雄はどの程度読まれているのだろうか?ふとした折りに気づきしばし考え込んだ。
自分の学生時代は(40年以上前)、彼の文章は漱石と並んで入試問題に引用される双璧だったから、読まずに済ませる事が出来ない存在だった。漱石と違ってまだ存命だったし、肉声にも新たな文章にも接する機会がいくらでもあった。旧制高校の教養主義によって人格形成された最後の世代が社会の上層部にいた時代で、読書の位置づけも今より遥かに重かったから、「知らない」「読んでいない」と口に出来ない雰囲気は、文理系を問わず学生間に共有されていたように思う。
彼の数ある著作の中で、音楽愛好家のみならず広く読まれていたのが『モオツァルト』だった。大した分量ではないが、内容は晦渋で難解である。いま読み返してもそう感じるが、流石に当時に比べると文章の背景となる基本的な情報や知識も積みあがってはいるので理解すると同時に疑問や反論も湧くようになったが、20歳やそこらの経験では当時は全体をとにかく読んではみたという印象しかない。そしてその挙句は「哀しみは疾走する。涙は追いつけない」などという片言隻語を覚えるのみで、すべてを理解したような振りをしていたに過ぎない(少なくとも「読んでいない」と言わなくて済む)。今もこの語句だけは記憶にある、という人は多かろう。
さて、その『モオツァルト』は、エッケルマンの『ゲーテとの対話』中にある、この大知識人のモーツァルト観から始まっている。ゲーテはこの作曲家の作品を独自の視点から愛好しているが、ベートーヴェンの作品に対しては冷淡だったという。次いである時メンデルスゾーンがゲーテにハ短調交響曲(『運命』である)をピアノで弾いて聞かせるくだりがある。やや長いが関係する全文を敢えて引く。
メンデルスゾオンが、ゲエテにベエトオヴェンのハ短調シンフォニイをピアノで弾いてきかせた時、ゲエテは、部屋の暗い片隅に、雷神ユピテルのやうに坐つて、メンデルスゾオンが、ベエトオヴェンの話をするのを、いかにも不快さうに聞いてゐたさうであるが、やがて第一楽章が鳴りだすと、異常な昂奮がゲエテを捉へた。「人を驚かすだけだ、感動させるといふものぢやない、実に大げさだ」と言ひ、しばらくぶつぶつ口の中でつぶやいてゐたが、すつかり黙り込んでしまつた。長いことたつて、「たいへんなものだ。気違ひじみてゐる。まるで家が壊れさうだ。皆がいつしよにやつたら、いつたいどんなことになるだらう」。食卓につき、話が他の事になつても、彼は何やら口の中でぶつぶつつぶやいてゐた、といふ。
『モオツァルト』の中で、作曲家フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ”Felix Mendelssohn Bartholdy “(1809~1847)が登場するのはここだけで、彼は端役に過ぎないし、何かの伏線となる存在でもない。だから大抵の人はこの一節は忘れてしまう。自分もそうだった。せいぜいが「そうか、ゲーテとメンデルスゾーンは同時代人だったのか-」程度の関心でこの部分を読み飛ばしていた。小林秀雄もゲーテの事は『ファウスト』第2部を苦吟中だった彼の年齢を80歳と明記しているものの、メンデルスゾーンについては何ら情報を呈示していない。高名な上にも高名な賢人に対して(臆することなく)ベートーヴェンを語り、その作品を敢えて披露して不興を買うメンデルスゾーン・・・・小林秀雄の筆致から、何となく既に作曲家として一家を成した壮年(と言っても彼は38歳で早世しているが)になってからの対話、と思い込んでいたのだ。
ところが最近になって『メンデルスゾーン家の人々=三代のユダヤ人』(ハーバート・クッファーバーグ著・横溝 亮一訳 東京創元社1985年刊)を読み、この時のメンデルスゾーンの年齢を知って意外の感を得る。何と20歳である。祖父と孫の年齢差。この事実を知ってから『モオツァルト』の上記の挿話に対する個人的なイメージにも大きな変化が起きた事を、この本が購入以来30年以上我が家の書庫に死蔵されたままだった事実と共に白状しよう。同書によれば両者はこれが初対面ではない。最初に会ったのはメンデルスゾーンが12歳になったばかりの1821年11月の事で、フェリックス少年に作曲を教授していたツェルターの人脈によった。この時この少年は16日ほどもゲーテの許に滞在し(ゲーテが離さなかったのである)、毎日2時間はこの老人の求めに応じてピアノ(主にバッハや自作の曲)を弾いて聴かせた。その後も何度か対面の機会があったようだが、1830年5月、ロンドンでのデビューとなったイギリス旅行・・・・この折に『スコットランド』は着想されている・・・・から帰国した3か月後にゲーテの許を訪ねる。ゲーテの死の2年前でこれが最後の対面となった。既に作曲家としての名声を得ていたメンデルスゾーンはこの時、彼自身の作品の演奏を望むゲーテの意向とは別に、ベートーヴェンの作品を数多く弾いたという。つまり『モオツァルト』にある上記の逸話はこの時の事という訳である。ベートーヴェンは3年前に死んでいる。何故老人の機嫌を損ねる・・・・少なくとも困惑させるような行動に敢えて出たのだろうか?という疑問は当然湧くが、それ以前にゲーテともあろう大物が、初演(1808年)から既に20年以上を経過したこの時まで、『運命』という大作品を耳にした事が無かった?個人的にはこの疑問の方が大きい。よほど敬遠していたのだろうか?
◆神童と早熟
さて、ここでモーツァルトとメンデルスゾーンの対比を考えてみるのも一興だろう。ふたりとも早熟の天才だった。モーツァルトの神童ぶりについては虚々実々の逸話を通じてあまねく知られている。が、その逸話は当時ヨーロッパ各地にいて、彼同様にその特技を売り込むべく旅をして回っていた多くの「神童たち」との差別化を図る為に生み出されたものもまた多いのである。少年モーツァルトは、そうしたライヴァルたちと、時に公開の場で持てる才能を競わされている。モーツァルトの今に至る名声の一部はいくつもの競争を勝ち抜いたその結果もたらされたと言っても過言ではない。
だが・・・・メンデルスゾーンの早熟な天才ぶりには、大げさな虚飾はまずないと言って良い。というよりそうしたものを必要とする環境が無かった。父親はベルリンで銀行(『メンデルスゾーン銀行』・1939年まで存続した)を経営する実業家。裕福な家庭で教育は全て家庭教師によって行われる。語学・古典文学・絵画・ピアノと並行して8歳より作曲を前述のツェルターから学ぶ。そして家庭内でしばしばコンサートを開き、時には楽師を雇ってオーケストラを編成して自らの指揮で自作品を披露する機会もあった。これは同時にサロンであり、わざわざ旅をせずとも著名な知識人や芸術家が向こうから来ては、少年にあらゆる知的刺戟を与えてくれた。これが10代前半の話である。16歳で『弦楽八重奏変ホ長調』を作っているし、17歳では有名な『真夏の夜の夢』序曲を完成している。これらの作品の完成度とその創作年齢はモーツァルトに充分比肩しよう(個人的には超えていると確信している)。そして彼の音楽経歴の中でも、音楽史上でも大きな業績となる『マタイ受難曲』の蘇演。初演以来100余年。作曲家の歿後全く忘れ去られていたJ.S.バッハ畢竟の名大作を、音に蘇らせた仕事。これを20歳の時に成し遂げているのである(前述ゲーテとの最後の対面はこの直後だ)。その後活動拠点をそのバッハゆかりのライプツィヒに移して、26歳でゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者となり、楽員の待遇改善と増員にも奔走して一流のオーケストラに育て上げた。指揮台にも立てばピアノの独奏も手掛け、例えばシューベルトの『グレイト』を初演するなど広範なレパートリーを築き上げた。早熟というに余りあろう。だがこの早熟さが彼の作品の性格を決定し、将来の悲劇にも通じてゆくのである。
◆姓と信仰の変転
メンデルスゾーンの祖父はモーゼス”Moses” (1729~1786)という。デッサウに生まれたユダヤ人で、そのゲットー内に疎外されたまま終わる人生に見切りをつけて1743年14歳でベルリンに出る。そこで絹織物商の仕事の傍ら勉学に励み、著作を世に問うた事を契機にして哲学者としての名声を得、更には啓蒙家としてユダヤ人の解放運動にも奔走するに至る。こうしてモーゼスはドイツ人社会に認知された存在となったのである。あらゆる活動に於いて名を知られ始めたものの、モーゼスはユダヤ人の慣習としてそもそも姓を持っておらず、モーゼスの名に出身地のデッサウをつけて名乗っていた(国も時代も異なるが「レオナルド・ダ・ヴィンチ」のようなものだ)。必要に迫られた彼は、そこで父親の名メンデルに因んでその息子の意をドイツ語に直しそれを姓とする。「メンデルスゾーン”Mendelssohn”」という風変わりな姓はこうして生まれた。その後ドイツ社会に同化した彼だが56歳で世を去るまで、終生ユダヤ教徒という立場を捨てる事はなかった。
その次男アブラハム”Abraham”(1776~1835)は前述の通り、はじめハンブルクで兄と共に銀行を開設。作曲家フェリックスもこの自由都市で生まれている。後に家族ともどもベルリンに移住し銀行経営を続けるが、富の蓄積と共に更にドイツ人社会との融和が必然となり、且つそれが社会動向としてもモーゼスの時代と比較してより進んだ。その結果として、義兄(妻の兄=これも改宗者)の強引ともとれる説得によりアブラハムはキリスト教への改宗を決意するに至る。そしてルター派へ改宗するのと同時に、義兄の姓をも受け容れて「バルトルディ"Bartholdy"」に改姓した。
これらが完結した後に生まれた作曲家メンデルスゾーンは「ユダヤ人だがキリスト教徒で、姓はバルトルディ」という事になる。因みにこの父親は息子が名声を得ると「かつて私は父の子として知られていた。だが、今では息子の父親として知られている。」との言葉を残す。つまり「著名な哲学者の子にして、有名な作曲家の親という間の存在」と自虐とも言える自己評価を自認していた訳だ。傑出した才能の人ではなかった。
さて息子フェリックスはこの自らの改姓について珍しく父親に反発する。祖父モーゼスへの敬慕が大きな理由としてあった。祖父が創始し、且つそのあらゆる著述活動によって社会的にも充分に認知されていたメンデルスゾーンの姓を消滅させたくないとの思いである。そして最終的には両方を我が姓とするべく、父親をも説得するに至るのである。すなわち「メンデルスゾーン バルトルディ」という並列の二重姓でこれが正式。アブラハムの子孫がこの二重姓を名乗る。その中にはこのふたつをハイフンでつないである一族もあるようだが、この作曲家の正式名は単なる並列で表記する。
ドイツ人としての姓を設け、ユダヤ教をも捨てて同化を図る。三代50年にも亘るこの努力は、だが作曲家の死後半ば水泡に帰した。
◆作品の受難
メンデルスゾーンの作品は主に英国で受け入れられ、彼の死後もその名声をしばらくの間保っていた。だが作品に対する評価は徐々に変わる。反ユダヤ主義が台頭し「ユダヤ人作曲家メンデルスゾーン」としての立ち位置に追いやられる。また作品そのものに於いても、既にベートーヴェンに始まった「思想(言葉)」や「理念」に基づく作品こそが正統との思潮が急速に高まり、それは着実にヴァーグナーに受け継がれてゆく。だが「神童」メンデルスゾーンには後継者はいない。そもそも彼の作品群は、その思潮に立ち向かえるほどの力を持ってはいなかったのである。才能の赴くままに曲を書く。それだけだった。神童は神童のまま完成したが、受け容れる社会はモーツァルトが生きた時代とは大きく変わっていたのだ。遅れて来た神童の悲劇である。
そうした状況の中でヴァーグナーが書いた『音楽に於けるユダヤ性』なる論文が世に出る。
メンデルスゾーンの4歳下で、生前交流のあったヴァーグナーはその中で、ユダヤ人芸術家としてメンデルスゾーンの才能を唯一の例外と認めながらも、決定的な鉄槌を下すのである。
彼は、ユダヤ人も特別な才能がじゅうぶんあること、独自の立派で多様な文化を持つこと、高く、鋭敏な自尊心を持つことなどを示してくれた。…しかし、彼はこうした優れたものを自ら用いもせず、我々が芸術に期待する心の奥底に触れるような力を、ただの一度も我々に与えはしなかったのである…
その後の歴史を俯瞰できる立場のクッファーバーグは前述の『メンデルスゾーン家の人々』の中でその末路を以下のように総括する。
実際、ヴァーグナー支持派の興隆は、19世紀末におけるメンデルスゾーンの人気衰退の大きな要因のひとつであった。メンデルスゾーンの音楽は、清澄さ、形式性、清楚さといった古典的な感覚において…擁護派からも非難する側からも…ヴァーグナーの重量感たっぷりで長大な音楽劇のアンチテーゼとして評価されていた。
ヴァーグナーと支持者たちはこうした作品をもって「未来の音楽」を創造していると信じていたのである。ドイツではヴァーグナーがメンデルスゾーン攻撃の急先鋒であり、結局それはナチ時代を通じてメンデルスゾーンの音楽が全く消滅してしまう事態へとつながっていった。
ニーチェはメンデルスゾーンの音楽を、ベートーヴェンとヴァーグナーの作品群に挟まれた「愛すべき間奏」と評している。思想とドラマにむせ返るほどに満たされたふたりの大家の作品群に挟まれた「息抜き」とも言える位置づけだ。こうした軽視は、20世紀に入り反ユダヤ主義がドイツ社会を席捲すると決定的になった。
ナチス政権時代、ユダヤ人作曲家の手になるという理由だけで作品の演奏は禁じられたし、特に1936年以降はドイツに於いては標準的な音楽の教科書からメンデルスゾーンの名は抹消され、楽譜は禁書扱いとなった。同じ年、ライプツィヒのゲヴァントハウス前に建てられていた彼の銅像は破壊されている(再建は2008年)。フェリックスの子孫の中には収容所送りになった者も出た。
こうした呪縛が解け始めたのは戦後1960年代に入ってから。未だに作品の全集編纂は完結していない。メンデルスゾーンの作品復権の歴史はまだまだ浅いと言わざるを得ないのである。
ゲーテはかつて7歳当時のモーツァルトを実見し演奏を聴いている。12歳のメンデルスゾーンとの初対面の折り、老ゲーテは目の前でピアノの腕前を見せる少年に、ちょうど30年前に死んだかつての神童の再来を見た。その才能と音楽はモーツァルトの天衣無縫を髣髴させ、且つそれを容易に超えるものとさえ感じられた事を述懐している。それはベートーヴェン以降の「思想」「理念」先行のものとは一線を画していた。
この大賢人は、メンデルスゾーンのピアノで再現されたベートーヴェンの音楽に嫌悪を覚えながらも、音楽藝術が今後進まざるを得ず、最早とどめることも不可能となった奔流の行く末をはっきりと予見した。そしてそのような音楽をもう自分の耳が受け容れ切れぬ事を改めて知り、諦念に駆られていたかもしれない。
それあってこそメンデルスゾーンが自身の作品を目前で弾く時のみ、最晩年のゲーテは心の平安を得ていたように僕は想像するのである。
今回のコンサートに使用する楽譜のこと
COVID19のために中止となってしまった第249回演奏会用の維持会ニュースの原稿を2/3ほど流用して、追加・改訂した記事となります。
今回のコンサートで使用する版、つまりどのような楽譜を使用するかにまつわる話をします。
1.コンサートに使用する楽譜の調達
ライブラリアンという仕事は、オーケストラで使用する楽譜に関わる仕事をする係です。プロのオーケストラの場合、奏者がライブラリアンを兼ねることは稀でそれを専門とする方がいます。プロオケのライブラリアンはそれだけ大変な仕事なのです。一方、アマチュアのライブラリアンの仕事は(少なくとも新響では)、使用する楽譜の調達、配布、回収、保管だけですので同じ職名で呼ばれるのはプロのライブラリアンに申し訳なく思っています。
さて楽譜の調達手順ですが、コンサートのプログラムが決まったらその曲の楽器ごとの譜面(パート譜)を探します。新響が所有しているかを確認し、所有していなければ購入かレンタルとなりますが、そのほかに著作権の切れた作曲家の楽譜が無料でダウンロードできるIMSLPという巨大なデータサイトもあります。そこの譜面を使用することは法的に問題ありませんので有力な選択肢のひとつです。
楽譜の調達で厄介なのが版の問題です。数十年前までは版の問題といえばブルックナーの交響曲くらいで、楽譜のいろいろな版の存在をあまり気にしませんでした。指揮者が自分の責任で譜面に手を入れることもしばしば行われてきました。しかし、次第に、作曲家の書いた楽譜に忠実に演奏することが正しいことであり、楽譜をいじるなんてもってのほか、とされるようになってきました。それと並行して作曲家の自筆譜の研究が進み、たとえばベートーヴェンの交響曲のようにいろいろな校訂者がベートーヴェンの自筆譜や筆写譜や多数の文献をあたって、これこそが作曲家のオリジナルだと主張し〇×校訂版と銘打って出版するようになりました。今ではベートーヴェンに限らず、古典派からロマン派の作曲家、さらには近代の作曲家の作品まで、いろいろな版が原典版として出てきているというわけです。したがって、楽譜の調達前に指揮者の意向を聞いて指定された楽譜を調達します。
2.「アルルの女」組曲の仏独の出版社の違い
今回取り上げる「アルルの女」組曲は、小編成のオーケストラ用にビゼーが作曲した劇音楽を元に、第一組曲はビゼーが、第二組曲はビゼーの親友のギローが二管編成+αに編曲したものです。この組曲は複数の会社から楽譜が出版されていますが出版社によって楽器の指定に違いがあります。図1の左側は1873年Paris: Choudens社(以下C社) のもの、図1の右側は1904年Leipzig: Breitkopf und Härtel社(以下B社)のものです(いずれもIMSLPより)。木管楽器はフランス語とドイツ語の違いや並び順の違いはありますが同じです。問題はホルンとトランペットです。C社は2 Cors en Mi♭と2 Cors en UTとあります。これはEs管のホルン2本とC管のホルン2本ということ、一方、B社のほうはHörner in FがI~IVあり、これはF管のホルン4本でということです。どちらの譜面で演奏しても音は同じですが指定された楽器の調性指定が異なっているわけです。現代のホルン(ダブルホルンと言われている一番よく使われているもの)はF管とB♭管が一本の楽器で切り替えられるようになっており、さらにレバーの操作でバルブを切り替えて半音階を滑らかに演奏できるようになっていますからEs管やC管の指定で書かれた楽譜も無理なく演奏できます。しかし、ビゼーが生きていたころはまだそのようなバルブホルンが十分には普及しておらず、転調した場合に必要な多くの音を無理なく出すために複数の異なる調性の楽器を用意して演奏したのでC社の楽譜はこのような楽器指定になっているということと考えられます。ならば現代ではC社のような楽譜の存在は無意味かというとそうでもなく、ホルンやクラリネットなどの移調楽器には楽器の調性ごとに特有の音色や調性感がある(と信じられている)のでそれにどこまでこだわるかということになります。使っている楽器はF管とB♭管どちらかなんだから楽譜がF管(またはB♭管)で書かれてた方がいいに決まってるじゃないかと思うのですがそう単純には割り切れない(奏者もいる)のが奥深いところです。

図1 アルルの女第1組曲冒頭の楽器指定の比較(左が仏C社、右が独B社旧版)
右のHörner in F IとIIに書いてある音符は参考のために書いてあるだけでIとIIの奏者は演奏しない。
次にホルンの下の段をご覧ください。C社は2 Trompettes en UT と 2 Pistons en SI♭,一方B社はTrompeten in Bとなっています。詳しいことは省略しますがPistonとは要するにコルネットのことです。コルネットはトランペットと音域は同じで形が似てはいますが異なる楽器で、トランペットよりもややまろやかな音が出ます。いずれにしろこれらはどちらが正しいのか?間違っていのか?というわけではないようです。
最後にもう一つ、実はB社の楽譜には楽器指定の致命的な誤りが一つあります。アルルの女ではプロヴァンス太鼓というベルトや紐で肩から下げて叩く太鼓が使用されるのですがフランス語ではこれをTambourinと書きます。でもこの綴りはドイツ語ではタンバリンのことなのです。B社は楽器指定がドイツ語で書いてあり、この太鼓のパートにもドイツ語でTambourinと書いてあるのでそのままとればタンバリンのことになってしまうというわけです。実際にタンバリンで演奏してしまっている例もあります。なお、最近出版された新しいB社の楽譜は2本のトランペットと2本のコルネットになっていてプロヴァンス太鼓もきちんとそのように指定されているとのことです。
今回のコンサートではB社の旧版のパート譜を使用しますが、もちろんプロヴァンス太鼓で演奏しますのでご注目ください。また違いがはっきりとはわからないかもしれませんが4本のトランペットのうちの2本はコルネットで演奏する予定ですのでこちらの方もお楽しみに。
3.メンデルスゾーン交響曲第3番の版の話
今回演奏する交響曲第3番には近年出版されたベーレンライター版というのがあります。矢崎先生はその版を指定されました。さっそくスコアとパート譜を購入です。新響は過去の演奏で使用したBreitkopf版を所有しているのですが両者は異なるとのことなので購入しました。届いてびっくり、スコアが分厚く、まるでマーラーの交響曲かと思うような重量です。なんと1楽章が二回印刷されています。次に2,3楽章、そしてそのあとに4楽章も二回印刷されている。なんだこれ、ひどい乱丁!? と思い前書きを読んでみると、二つの版が一冊にとじ込まれているのだと書かれています。つまり、今回取り上げる1842年版という通常演奏されない版の1楽章、次に一般的な版の1楽章、そのあとの2,3楽章はわずかな違いしかないので異なる個所だけ五線譜が二段になって印刷されています。そして4楽章はまず、一般的な版、そして最後に1842年版。というわけで6楽章分印刷されてるのでやけに分厚いということでした。1楽章の最後の方と、4楽章の最初の方はびっくりするくらい普通の版と異なっているので楽しみにしていてください。(ちなみにこの新校訂版、明らかな音の間違いが何箇所か新たに作り込まれていました。やれやれ。)唯一世の中に出回っているこの新しい版の演奏を聴いて面白いことがあったのでそれを紹介してこの記事を終わります。
まずは、こちらのリンクからYouTubeにあがっている1842年版の8分30秒あたりからを聴いてみてください。聴き始めて10秒間くらい激しい音楽が続き、そのあと急に静かになったところで唐突におっさんが “ワァオッ!” て叫んだみたいに私には聴こえたのです。 電車の中で、イヤホンで聴いていたために楽器音に聴こえなかったのかもしれませんがこれはファゴットのソロなのです。メンデルスゾーンの最終稿自筆譜(つまり一般的な版の元となる自筆譜)(図2)では、このファゴットのソロが斜線で消されています。しかし1842年版ではこの部分が残っているのです。この演奏ではテンポが速くてあわただしすぎるのですが、今回はそんな慌てたテンポでは演奏しないので普通は聴けないファゴットの瞬間芸的なソロがおっさんの叫び声ではなく音楽的に聴こえると思いますのでお楽しみに。

図2 自筆譜の該当箇所
第256回演奏会のご案内
メンデルスゾーンの傑作「スコットランド」
ドイツロマン派の作曲家メンデルスゾーンは、とても裕福で教育熱心な家に生まれ、音楽だけでなく絵画や文学、外国語にも堪能な神童でした。
交響曲を5曲残していますが、第3番が最後に作曲された交響曲です。メンデルスゾーンはイギリスを何度訪問しており、スコットランドに旅行した際に訪れたエディンバラのホリールード宮殿に着想を得て作曲されました。筆の速かったメンデルスゾーンが12年もかけた自信作で、美しい旋律と豊かな抒情性に溢れ、スコットランドの自然が目に浮かぶようです。一般的に演奏されるのは1843年改訂版ですが、今回は1842年ロンドン稿を使用して演奏します。
メンデルスゾーンは脳出血により38歳の若さでこの世を去りました。一時はワーグナーが批判しナチス体制から演奏禁止とされましたが、近年再評価・研究され大作曲家として認知されています。
ビゼー、不朽の名作「アルルの女」
パリに生まれ声楽家の父とピアニストの母を持つビゼーは、9歳でパリ音楽院に入学する神童で、優れたピアニストでしたが、オペラ作曲家を目指しました。36歳の時に作曲した歌劇「カルメン」の初演が不評に終わり、3か月後失意のうちに敗血症により亡くなりました。
「アルルの女」の物語は、南フランスの町アルルの闘牛場で見かけた女性に一目惚れした青年が、婚約者との結婚を決意するも、自分の婚礼の日にアルルの女が別の男と駆け落ちすると聞いて嫉妬から自殺するという悲劇。しかしその音楽は楽しく躍動的なものが多く、広く親しまれています。
劇付随音楽の原曲は極めて小編成(木管各1~2本、金管はホルンのみ)ですが、第1組曲はビゼー自身が4曲を選んで通常の編成に書き直したもの。第2組曲は死後に友人のギローが完成させたもので、有名なメヌエットは実はビゼーの歌劇「美しきパースの娘」からの転用です。今回は2つの組曲から6曲を選び物語の順に演奏します。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
ブルックナー:交響曲第3番ニ短調
< 伝統と革新 >
ヨーゼフ・アントン・ブルックナー(1824~1896)の生涯は「孤独」であり、作品は「孤高」の存在である。
オーストリアのリンツ郊外の小村「アンスフェルデン」で生まれたブルックナーは、後世「リンツ」「ウィーン」という大都市の生活でも簡素な生活習慣をほとんど変えず方言丸出しで田舎育ちを隠すことはなかった。素朴で傷つきやすく頑固な性格、風格とは無縁の風貌と服装、特異な振舞いと奇癖、そしてなによりも人格の基礎となった敬虔なカトリック教徒としての矜持は終生変わることはなかった。これは自然や美しいものへの愛情と結びつき、芸術的な霊感として作品に反映されている。
作品では宗教的な楽想と田舎の舞曲レントラー風で楽しくのどかな楽想との対比、生活では質素で信仰に満ちた生活とシュトラウスのワルツを愛し踊り好きなこと、そして女性たちへの独特な尊敬の念が同居している。
自らの葛藤とともに「オルガニスト」「音楽理論教師」「作曲家」が交錯した生涯は、多くの矛盾と対立を生みだしてきた。
■交響曲第3番の独自性
第一級の和声法と対位法の理論家でもあったブルックナーの作曲様式は、前例のない独特な造形感覚に満ちている。「ソナタ形式」を文法としての頑固なまでの運用、楽想の並行的または突然の移行、「漸層法」とでも言うべき主題や断片の積み重ねによる頂点の構築、主題群の中での独自の和声や対位法(転回・反行)、同一楽器群(弦・木管・金管)の独立した扱い、「ブルックナー開始」「ブルックナー・リズム」(2+3ないしは3+2)「ブルックナー・ゼクエンツ」(音形の反復)、「ブルックナー・ユニゾン」、そして「ブルックナー休止」。
交響曲第3番は、ベートーヴェンの交響曲第9番からの影響を含ませながら、伝統的な形式の中にブルックナー独自の作曲様式を全て駆使し、独自性を確個たるものにした革新的な作品といえる。
「ワーグナー交響曲」とも呼ばれるが、リヒャルト・ワーグナー(1813~1883)への献呈(1874年5月9日)によるもので作曲者自ら自筆譜に記入している。献呈譜の表紙にはワーグナーの名前が大きく豪華に記載されている。
■受難・試練
交響曲第3番の辿った運命は、ブルックナーの生涯で最大の試練をもたらした。作曲者自身の改訂による「稿」と第三者の解釈や評価に影響を受ける「版」について、特に異稿が一番多い作品でもある。「稿」として3つとアダージョ(第2番)があり、「版」としては各々の自筆原稿と若干異なる印刷譜が2つある。
1872年「第1稿」、1876年緩徐楽章の異稿「アダージョ第2番」、1877年「第2稿」(大幅な改定)、3度にわたるウィーンフィルからの「演奏拒否」、そして同年12月16日「第2稿」初演の失敗は「受難」の頂点となった。
1878年「第2稿」出版後、1889年に「第3稿」が完成し、翌1890年に出版されて、同年12月21日の初演は12回も呼び出されるほどの成功を収めた。13年前の屈辱は完全に晴らされたのである。「第3稿」は芸術家として最高の栄誉に恵まれてきた晩年の改訂で、作風も洗練され冗長さも改善されている。
各稿及びアダージョ(第2番)は、音楽学者レオポルト・ノヴァークの校訂により刊行されており、本日はノヴァーク校訂第3稿(1889年)を使用する。
第1楽章 どちらかといえばゆっくりと 神秘的に
ニ短調、2/2拍子。ソナタ形式。冒頭のトランペットによる開始旋律は空虚で独特な空間を持ち象徴的で作品全体を支配していく。呈示部だけでも全く曲想の異なる第1主題、第2主題、第3主題とあり、主題・形式毎に頂点の構築を伴うため長大である。(第1稿では746小節、第3稿でも651小節の長さ)
第2楽章 アダージョ 動いて ほぼアンダンテで
変ホ長調、4/4拍子。三部形式。アダージョはブルックナーの交響曲の核心をなすといっても過言ではない。情熱と法悦に満ち、冒頭主題から中間部第1主題と第2主題に進むにつれて広がりと神秘性を深め、独特な輝きと共に頂点に進む。「第2稿」でワーグナー諸作品からの引用など削除され大幅に変更された。
第3楽章 かなり急速に ―トリオ
ニ短調、3/4拍子。三部形式。根源的な力に満ちたリズムは明確で構成も簡潔、ブルックナーのスケルツォは理解しやすい。楽想が執拗に反復される。金管の下降進行にはワーグナー的な力を感じる。トリオは他の交響曲同様レントラー風の舞曲で素朴、故郷の香りが漂う。
第4楽章 アレグロ
ニ短調、2/2拍子。ソナタ形式。第1主題はまるで「ワルキューレ」第3幕の怒れるヴォータンを思わせる。全く異なる曲想の第2主題(2重主題)と第3主題から展開部と再現部に続き、第1楽章を含めた各主題の回帰・結合から、圧倒的で壮大な頂点を築いて全曲を終える。
ブルックナーは終生ワーグナーを敬愛していたが、自らの音楽理論と作曲様式は、ワーグナーとは異なる独自の発展を遂げてきた。
交響曲第3番は、時間芸術としての音楽の本質のうえでもまさに「孤高」の存在といえる。
初演:第2稿 1877年12月16日 作曲者自身の指揮 ウィーン・フィルハーモニー
第3稿 1890年12月30日 ハンス・リヒター指揮 ウィーン・フィルハーモニー
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、ティンパニ、弦五部
参考文献:
土田英三郎『ブルックナー ―カラー版作曲家の生涯―』 新潮社 1988年
レオポルト・ノヴァーク(樋口隆一訳)『ブルックナー研究』音楽之友社 2018年
新交響楽団「第209回演奏会プログラム」「第220回演奏会プログラム」「第226回演奏会プログラム」「第243回演奏会プログラム」土田恭四郎
(新響HP「いままでの演奏会」に各回の演奏会詳細あり)
http://www.shinkyo.com/02past/
ワーグナー:歌劇「タンホイザー」序曲
愛欲の世界はお好き?
今回のプログラムの中で圧倒的に有名なこの曲は、ワーグナーがドレスデン宮廷歌劇場の指揮者であった1845年に書いたオペラ「タンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦」の序曲で、本日演奏するのは、初演後から1851年にかけて改訂されたドレスデン版である。序曲というだけあって、この序曲はオペラに登場するさまざまな音楽を「いいとこ取り」して聴ける曲である。
物語の主人公は、中世の騎士タンホイザー。恋人のエリザベートがいながら、官能の愛を望むようになり愛欲の女神ヴェーヌスが住むヴェーヌスベルクに赴き、肉欲の世界に溺れていた。
ある時、故郷を懐かしく感じたタンホイザーは、強い決意を持ち、ヴェーヌスから離れ、故郷に戻ってくる。
帰郷した当日はちょうど歌合戦が行われていた。歌のお題はなんと「愛について」。他の騎士は「愛は神聖なもの」というような女性に対して奉仕的な愛を歌う。恋人のエリザベートとの再会を果たし、強い(?)決意を持つタンホイザーも当然……。
本心には勝てないと言うことだろうか。
「愛欲こそ最高だぜ!」
この発言は観衆から強い反感を買う。そしてついには強い決意を持って離れたはずのヴェーヌスを讃える歌「ヴェーヌス讃歌」を歌いだす。
人間という生き物は、なかなか変わることができないということかもしれない。
自らの過ちに気づくが時すでに遅し。故郷から追放され、ローマへ巡礼に行き教皇の許しが得られれば帰郷が許されるとされ、タンホイザーは巡礼の旅に出る。
序曲はこの巡礼に向かう人々の大合唱のフレーズから幕を開ける。その後、「懺悔の歌」が奏でられ、次々と色々な楽器に受け継がれていく。
懺悔の歌
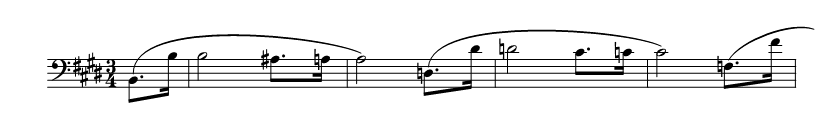
このメロディーが落ち着くと、突然まったく毛色の違った旋律が顔をだす。いわゆるヴェーヌスの誘惑の曲である。
ヴェーヌス讃歌

この誘惑のテーマは曲中に何度も顔を出し、タンホイザーの揺れる心を表現しているように感じられる。
話を戻そう。巡礼に向かったタンホイザーだったが、ローマ教皇の赦しを得ることが出来ず、自暴自棄になる。友人に止められながらも、再びヴェーヌスベルクに帰ろうとする。
その頃、故郷では、戻ってきた巡礼団の中にタンホイザーがいないことに気付いた恋人のエリザベートが、自らの命と引き換えにタンホイザーの赦しを得ようと決意した。その後、ぼろぼろの風体で故郷に現れたタンホイザー は、エリザベートの葬列を目撃。我に帰りその亡骸に寄り添うように息を引き取る。
あらすじを聞くと、正直に言ってしまえばふざけた話である。タンホイザーはとても身勝手で自己中心的な人間で、現代でいう「ダメ男」という言葉がしっくりくる。そして、恋人のエリザベートは、典型的な「ダメ男を好きになってしまう」女性である。現代もワーグナーの時代も、人間の根本は変わらないのかもしれない。
私が、皆様に聴いて感じていただきたいのは、懺悔の歌とヴェーヌスベルクのテーマの雰囲気の違いである。
懺悔の歌は、何か美しく天に昇るようなイメージで、どこか悲しくもあるフレーズであるのに対し、ヴェーヌスベルクのテーマは、より直接的で刺激的なフレーズのように感じる。
2つのフレーズを比べて、皆さんはどちらがお好みだろうか。恋愛などさまざまな自由が与えられた現代社会においては、刺激的な愛を求めがちであるように感じられ、ずっと恋愛をしていたいというような、いわば恋愛中毒といったような人間も多くいる。反対に、神聖な愛とは、現代におけるどのような愛なのか。
さまざまな経験を重ねているであろう団員のさまざまな経験から奏でられる愛の形を是非感じていただければと思う。
初演:1845年10月19日 作曲者自身の指揮、ドレスデン宮廷歌劇場にて
楽器編成: ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン 4、トランペッ ト3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、トライアングル、タンブリン、弦五部
参考文献:
吉田真『作曲家・人と作品 ワーグナー』音楽之友社 2005年
CD「歌劇タンホイザー全曲パリ版」解説書(ゲオルク・ショルティ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、解説 渡辺護)ポリドール1970年
ワーグナー:歌劇「リエンツィ」序曲
リヒャルト・ワーグナーは1813年5月22日にザクセン王国(現ドイツ)のライプツィヒで生まれました。両親は音楽家ではありませんが、父親が演劇好きだったためかオペラ歌手や役者になった兄・姉もいました。
ワーグナーは数々のオペラ作品を生み出しましたが、作曲だけでなく、台本からすべて創作したのが特徴です。パリに滞在していた時、イギリスの作家エドワード・ブルワー=リットンの小説「コーラ・ディ・リエンツォ」を読んで「リエンツィ」のオペラ創作を思い立ちました。「リエンツィ」は彼のオペラでは3作目にあたり、初演時のワーグナーは29歳。「トリスタンとイゾルデ」や「ジークフリート」などの名作を生み出す前の若いころの作品です。「リエンツィ」は全5幕にわたる長大なオペラで約6時間かかります。第5幕のラストでは宮殿が燃えて崩れ落ちるなど演出面でも大規模でした。「リエンツィ」の初演が大成功したことで世間に知られるようになり、初演の翌年にはドレスデンの宮廷指揮者に就任しました。ワーグナーのオペラ1作目「妖精」は生前には上演されず、2作目「恋愛禁制」は初演で失敗し、なかなか結果を残せなかった彼にとって「リエンツィ」は出世作に位置付けられます。
■「リエンツィ」あらすじ
<第1幕>舞台は14世紀のローマ。貴族たちの横暴によりローマは乱れていました。民衆から信頼のあったリエンツィはローマのために護民官になります。護民官とは民衆の生命、財産を守るために設けられた官職のことです。貴族の息子アドリアーノはリエンツィの妹イレーネを愛していたので、リエンツィ側につきました。
<第2幕>貴族たちはリエンツィの暗殺を計画しますがうまくいかず、逆に捕らえられてしまいました。捕まった貴族の中にはアドリアーノの父親もいたため、アドリアーノはイレーネと一緒に貴族たちを釈放するようリエンツィに頼みました。彼は悩みましたが、貴族たちを釈放してしまいます。
<第3幕>釈放された貴族たちが反乱を起こしたので、リエンツィは戦い、そして勝利しました。しかしその戦いの中でアドリアーノの父親が殺されてしまい、リエンツィ側だったアドリアーノは苦しみます。
<第4幕>貴族たちを釈放したことによる反乱で多くの犠牲者が出たことから、民衆はリエンツィに反感を抱き始めました。父親を殺されたアドリアーノは民衆に呼びかけて、リエンツィに復讐しようと企みます。この時イレーネはリエンツィとともに生きることを決意しました。
<第5幕>宮殿で神に祈りを捧げるリエンツィのもとにイレーネがやってきて、リエンツィとともに生きる決意を伝えます。そこへ民衆が押しかけ、宮殿に火を放ちました。イレーネを助けようとアドリアーノが駆けつけた時、リエンツィ、イレーネ、アドリアーノの3人は焼け落ちる宮殿の下敷きになってしまいました。
■「リエンツィ」序曲
「リエンツィ」序曲にはオペラの中で使われている旋律やテーマが所々に登場します。
・曲の開始、区切りに用いられるトランペットは民衆に呼びかける合図。

・第5幕でリエンツィが神に祈りを捧げる場面で歌われる旋律。

・戦いのシーンでリエンツィが呼びかける聖霊の騎士の主題。

・第2幕でリエンツィを讃える行進曲。

初演:1842年10月20日 カール・ライシガー指揮
ドレスデン宮廷歌劇場にて
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、セルパン(本日はコントラファゴットで演奏)、ホルン4、トランペット 4、トロンボーン3、オフィクレイド(本日はテューバで演奏)、ティンパニ、大太鼓、シンバル トライアングル、小太鼓、リュールトロンメル(中太鼓)、弦五部
参考文献:
吉田真 『作曲家・人と作品シリーズ ワーグナー』音楽之友社 2004年
淺香淳編 『最新名曲解説全集第19巻歌劇Ⅱ』 音楽之友社 1980年
江藤光紀解説・ポケットスコア『歌劇<リエンツィ>序曲』日本楽譜出版社 2016年
新任首席奏者に聞く-その3
◆はじめに
こんにちは。コントラバス首席の宮田と申します。シリーズ3回目となる「新任首席に聞く」の掉尾を飾っていただけないか、と『維持会ニュース』編集人の松下さんから依頼され、やや緊張しながら引き受けました。これまでのお二人(Fg藤原さん、Fl吉田さん)のような面白い文章にはならないかと思いますがお許しください。
◆まずは自己紹介をします。
・東京都在住、27歳女性、1Kの部屋で一人暮らし(ペットはサボテン)
・育ちは千葉県北西部。中高は都内の某女子校、大学(+院)は都内の某国立大学。
・実家は松戸市なので頻繁に帰省します。
・仕事はバイオ系研究開発職。新卒入社して4年目になります。そろそろ新規テーマ提案を、と圧をかけられ悩んでいます。
・新響に入団したのは2018年8月、首席を拝命したのは2019年12月です。
・好きな作曲家はマーラー、チャイコフスキーなど。わりとなんでも好きになります。マーラーの交響曲は5,7,9しか演奏したことがありませんがいつか全部やりたいです。
・音楽以外の趣味は読書(小説)、パンダ。好きな作家は小川洋子。国内のパンダは最近生まれた2頭以外は見分けられます。
◆コントラバスという楽器について
あまり脚光を浴びる機会も多くないので、この場を借りて少し楽器の紹介をさせてください。
コントラバスはオーケストラの弦楽器の中で一番多様性に富む楽器だと思います。楽器の個体差も大きいし、活躍するジャンルも幅広いです。オーケストラにおいては、曲の土台、骨格となるような音を出していることが多いです。
楽器の個体差について少し詳しくお話しすると、そもそも4弦(上からG/D/A/E)と5弦(G/D/A/E/HもしくはC)の楽器の両方ともが一般的に使われています(ソロチューニングは2度高くなります。4弦楽器でEより低い音を出したい時のためにE線を伸ばすことを可能にするCマシーンというものもあります)。実は弦の数だけではなく、楽器の大きさ自体も異なります。国内においては一般的に5弦の楽器がいわゆる「フルサイズ」で、4弦の楽器はほとんどが「4分の3サイズ」という若干小さ目サイズです。楽器の重さも違っていて、4弦楽器と5弦楽器の持ち運びやすさは全く異なります。また、容積の違いから、生まれる響きも異なってきます。新響で所有している楽器はほとんどが5弦で、重厚な響きを作り出すのに一役買っています。今回の演奏会に参加するメンバーも6人全員が5弦を弾いておりますので注目してみてください。また、楽器の裏が平らになっているものと丸みを帯びているもの、なで肩の曲率、楽器の厚み、装飾など、よく見るといろいろと個体によって異なる特徴があって面白いです。
弓の持ち方の種類も「ジャーマン」と「フレンチ」があり、ざっくり言うと、下から持つのがジャーマン、上から持つのがフレンチです。国内では圧倒的にジャーマンの方が多いですが、最近フレンチの人が増えているような気がします。やや気取った感じがして、敬遠した目で見てしまいますが(笑)。ジャーマンの中でも鉛筆を持つように弓をしっかりとホールドする「チェコ式」と、親指を離して持つ「ウィーン式」の持ち方があり、こちらはウィーンの方が少ない気がします。私は大学の時に師事した先生の先生がルートヴィヒ・シュトライヒャー(ウィーンの超有名なコントラバス奏者・指導者でその名を冠した教本が広く流通している)だったため、ウィーン式の持ち方をしています。
~よくある質問~
① 楽器の重量は何kgくらいですか?
→個体差はありますが約10kgです。
②ウッドベースですか?
→ジャズに使えばウッドベースということになります。
③運搬はどうしているんですか?
→新響では団器を毎回の練習にトラックで持ってきてくれます。大変ありがたいです。団の楽器を所有していて毎回持ってきてくれるアマチュアのオケはなかなかありません。新響以外のオケの練習に行くときは、個人所有の楽器に専用の車輪をつけて転がしていきますが、特に夏場などはそれなりの重労働です。
~コントラバスのここがすごい~
改めて、という感じかもしれませんが、奏者目線からコントラバスの魅力をご紹介したいと思います。まずは振動です。楽器体験で小学生に楽器を触ってもらいながら弾いたりすると、かならず「ぶるぶるする!」と驚かれます。出てくる音も「振動」という感じがします。とにかく楽器全体(と一緒に体も)が鳴っている感覚、それが私の思うコントラバスを弾くことの最大の魅力です。それから、ピチカートの音の豊かさ。弦分奏などでバイオリンの人が「ピチカートの響きが薄い」と言われることがよくありますが、コントラバスはよく響くピチカートを出すことが比較的容易にできます。また、一般的に思われているよりも非常に多彩な音を出すことができます。Black Bass Quintetというコントラバスアンサンブルの団体があり、彼らの演奏を聴くとコントラバスのイメージがガラッと変わるかもしれません。(動画:https://www.youtube.com/watch?v=ZQZ4JvCoSlE)
でもやはりオーケストラにおけるコントラバスの魅力は、音楽の土台を作っていることだと思います。和音でいえば一番重要なのは一番下の音です。コントラバスが動かないと曲が動かない、コントラバスの音程が悪いと全部悪く聞こえてしまう、目立たないながらも責任は重大です。その裏返しで、私たちが上手にお膳立てをすればオケは意のまま、というような側面もあります。その楽しさと難しさを感じながら日々練習を重ねています。
◆なぜコントラバスを?
中高の部活動として始めました。はじめは手芸部に入るつもりだったのですが、新入生歓迎演奏会で管弦楽部の演奏を聴いて、超かっこいい!と思い入部しました。もともとピアノを習っていたり、小学校でブラスバンドに所属していたり(打楽器でした)しましたが、もっと楽しそうなものを見つけてしまった気持ちでした。はじめはバイオリンやフルートなどの花形楽器を希望しましたが、経験者が多くて遠慮していたところをコントラバスの先輩に拾ってもらいました。当時の身長は140cmに満たないくらいだったので、よくもその選択をしたなあと今になって思います(今は160cmあります)。
中高の部活動は、楽器の数や講堂の広さといった問題から独自の形態に進化を遂げており、独特な楽器の配置(なぜかコントラバスの前にクラリネットがいる)、交響曲1曲暗譜など、今思うと不思議なところでした。指揮者も学生で、外部のコーチには年に数回見ていただくだけです。でも、自分たちで音楽を作り上げる楽しさを存分に味わうことができました。また、現在プロのコントラバス奏者として活動されている永田由貴さん(前述のBlack Bass Quintetのメンバーでもあります)がこの部活の卒業生で(当時は芸大生)、コーチとして教えに来ていただいていました。永田さんのレッスンはとにかく楽しくて、いつもにこにこしていらっしゃって、コントラバスって楽しいよね!と全身で語っているような、そんな雰囲気をよく覚えています。とにかく楽しい部活でした。
大学のオーケストラに入ったのが私にとって一つの転機でした。中高の部活もそれなりに一生懸命打ち込んでいたのですが、やはり大学生の音楽はレベルが違いました。そもそもそのオーケストラに入りたくて受験勉強を頑張った面もあるので、どのくらいのレベルであるかは知っていたのですが、やはり入ってみると部員の熱量が中高の比ではありませんでした。触発されるように私も猛然と楽器を練習しはじめて、ようやく「コントラバスが弾けます」的なレベルになりました。第100回定期演奏会でマーラーの交響曲第5番を演奏したときはパートリーダーとして悪戦苦闘しながらもやり遂げたという感覚がありました。自分の地元(松戸市・森のホール21)での演奏会企画も得難い経験でした。
去りがたい気持ちを残しつつ大学オケを去った後はいくつかのオケに気の赴くままに参加していましたが、縁あって何度かエキストラとして新響の演奏会に参加させていただき、演奏のエネルギー、プログラムの多彩さ、団員の良い意味でのまじめさ、楽器を運搬してくれるありがたさなど総合的に魅力を感じて入団しました。今は新響をメインとして活動しつつ、余力があるときは他のオーケストラにも参加しています。
◆先生について
中高ではほとんどきちんとした指導者につかずに先輩から教わり、ときどきコーチに教えていただく方式でしたが、大学のオケでは先生を紹介してもらえたので、個人レッスンに通い始めました。東大オケでは長年にわたりお世話になっていた檜山薫先生という方がいらっしゃるのですが(コントラバスの基礎練習本としてどこの楽器屋さんにも並んでいる『HIYAMA NOTE』の著者でいらっしゃいます)、私が入団した時すでに檜山先生はお亡くなりで、田中洪至先生を紹介してもらいました。田中先生は東フィルの首席を務められた後ウィーンで活躍された方で、前述のとおりルートヴィヒ・シュトライヒャーに師事していたので、私はシュトライヒャーの孫弟子ということになります。田中先生には楽器の持ち方から教えなおしていただき、基礎的なことをしっかりと習いました。次第にソロの曲にも挑戦するようになりましたが、コントラバスのソロの曲というのは基本的にハイポジションを駆使したものが多くなります。要求されるテクニックや身体能力がオケとはかなり異なっており、私には結構きついなあと思っていました。社会人になったのを機に、レッスンにはいかなくなってしまいましたが、ときどきソロの譜面を引っ張り出して弾いてみるのは楽しいです。
新響では、読響で長く首席をされており現在は東京音大で教えていらっしゃる星秀樹先生にお世話になっています。演奏会ごとに2回実施するパート練習の片方を見ていただくのが通例ですが、なんとこの前は「今日時間あるから行きますよ」と、もう片方のパート練習の日にも突然いらっしゃって指導していただきました。そこまで気にかけていただいているとは正直思っていなかったので、驚くと同時に嬉しくもあり、期待に応えなければと思いました。
◆健康って大事だな
いきなり話が変わって恐縮です。最近つくづく思うのが健康って大事だなということです。ひとつにはコロナのこと、もうひとつには五十肩をはじめとする個人的な健康事由です。
コロナの感染が拡大し、多くのオーケストラが少なからぬ影響を受けている中、新響も活動停止を余儀なくされた期間があり、現在も練習時間を短縮しながら活動しています。密を避けるために大編成の曲はできず、プログラムにも影響が出ています。休団を続けているメンバーもいます。早く安心して自由な活動が再開できるようになってほしいものです。
コロナとは無関係に、今年3月に右肩に五十肩(またの名を四十肩、正式には肩関節周囲炎)を発症しました。27歳ですので冗談じゃないと思って肩専門医のいる病院でMRIの画像まで撮ってもらったのですが、水が溜まっている、つまり炎症、つまり本当に五十肩ですとのことでした。発症期間は楽器を弾く動作がとても辛くて、4月の演奏会には参加できないし、その後も一生楽器を弾けないのではないかと思って絶望しました。診断を受けてから、演奏会に参加できなくなった場合のことを考えて、首席の皆さんやパートの皆さんに相談したのですが、温かいお言葉をいただいたり、おすすめの医院を教えていただいたり、理学療法士の団員からリハビリ方法を教えてもらうなど、本当に助けられました。幸いにも数週間で自然治癒し、4月の演奏会にも参加できました。今に至るまで再発はなく、楽器を弾くことができています。今回の五十肩を通じて痛感したのは、いつどんな理由で突然楽器が弾けなくなるかもわからないなということと、新響には頼れる団員がたくさんいるということ(と、五十肩経験者は意外といるのだなということ)でした。楽器が弾ける体であるうちはその幸せを行使すること、長く楽器が弾けるように健康に気を配ること。若いくせにと笑われるかもしれませんが、健康って大事です。これからも体を大切にしていきたいと思います。
◆ダイバーシティ&インクルージョン
また話が変わって恐縮です。最近よく聞く言葉でダイバーシティ&インクルージョンというのがあります。多様性を認め合い受け入れること、といったような意味合いで、会社でもこの理念のもと「女性管理職を3割に」とか言われたりします。
世の中の流れに従うように、女性のコントラバス奏者も増えてきています。私自身27年しか生きていないので伝聞によるところが多いですが、昔は女性奏者はかなり少なかったそうです。現在でも国内外で著名な演奏家は全員男性ですが、近年はプロ・アマともに女性演奏家が増えてきています。またしてもコントラバスアンサンブルの紹介になりますが、女性コントラバス奏者のカルテットla la la camarade というのがあります。らららクラシックのコントラバス特集に出演した4人の女性奏者(永田さんを含む)が番組をきっかけに結成した団体で、女性は体格的に不利であることを忘れさせてくれる素晴らしいカルテットです。
私は自分が首席に選ばれた意味がよくわかっていないのですが(聞くのは何となく怖いし)、ひとつにはこういったダイバーシティの流れがあるのかな、と自分なりに解釈しています。先にこのシリーズに寄稿された新任首席の藤原さん、吉田さんも若手女性ですし、多様な立場の意見を取り入れようという流れが背景にあるのかもしれません。考えすぎかもしれませんが……。高齢化が進んでいると言われがち(?)な新響ですが、ここ数年で若い団員も増えてきています。ベテランも若手も男性も女性も、枠にとらわれることなく互いに認め合って音楽を楽しめるのも新響の良さだと思います。
◆最後に
コントラバスという楽器について、私の人となり、新響の魅力について、少しでも伝わりましたでしょうか。維持会員の皆様におかれましては今後とも私たちのことを見守り、ご支援いただけましたら幸いです。不安なことが多い世の中ですが、音楽で心の安らぐ時間を届けられるよう日々精進して参りたいと思います。
第255回演奏会のご案内
遅咲きの大作曲家ブルックナー
ブルックナーはオーストリアの大作曲家、今年が没後125年にあたります。リンツ近郊の村に生まれ、聖フローリアン修道院で聖歌隊として学び、同修道院の教師、オルガニストを経て、リンツ大聖堂のオルガニストとなります。その後本格的に作曲を行い、ウィーンに出たのが44歳でした。
ブルックナーは通し番号のないものを含め11の交響曲を書いていますが、それらはいずれも宗教的でオルガンの響きと自然の森を想わせ、独自の世界があります。
ワーグナーに献呈した交響曲
今回演奏する交響曲第3番には「ワーグナー」というニックネームが付いています。ブルックナーはリンツ時代にワーグナー作品を研究してから熱烈なワーグナー信者で、第3交響曲の初稿を持ってバイロイトのワーグナー宅を訪ね献呈を受けてもらったのです。しかしウィーン・フィルに演奏不可能と判断され演奏が見送られ、第2稿の初演も失敗に終わったのでした。
ブルックナーの交響曲は、複数の稿(本人による書き換え)や版(編集や校訂)が存在することが特徴で、自身のより良くしようという音楽的欲求が反映されているのでしょう。今回演奏する第3稿は初稿から16年後に改訂されたもので、作曲家としての地位が確立し第8交響曲を作曲している時期です。初稿から大きく変更されワーグナーの影響は減りましたが、洗練されてわかりやすい曲となっています。
パリのワーグナー
ワーグナーはドイツの大作曲家、ブルックナーより11歳年上です。ベートーヴェンからのロマン派音楽の流れを交響曲という形で受け継いだブルックナーとは対照的に、ロマンティック・オペラに発展させたのがワーグナーです。20代後半で3年間パリに滞在していた時に「リエンツィ」を作曲しましたが、パリでの上演がかなわずドレスデンで初演しました。その後作曲した「タンホイザー」は、パリ公演の際にバレエの挿入を求められ改訂したにもかかわらず3日で中止となったのでした。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
ブラームス:交響曲第2番
ブラームスの交響曲第2番は、オーストリアの南、ケルンテン地方のヴェルター湖畔にある、避暑地ペルチャッハにて作曲された。自然豊かなペルチャッハで手掛けられたこの作品は、美しさやあたたかさが感じられる柔和な曲で、ブラームスの「田園交響曲」とも呼ばれている。交響曲第2番は短期間で作り上げられ、交響曲第1番を20年以上かけて書いた翌年に発表された。
ブラームスの4つの交響曲のうち、第2番以外の3つは低音域の管楽器としてコントラファゴットが編成に入っている。第2番のみ、コントラファゴットは使用されずテューバが登場し、低音の補強による豊かなサウンドやトロンボーンとのコラールによるハーモニーを楽しむことができるオーケストレーションとなっている。本日は、コントラファゴットとテューバが両方使用されている「大学祝典序曲」、コントラファゴットのみが使用されている「ハイドンの主題による変奏曲」、テューバのみが使用されている「交響曲第2番」のプログラムだ。 低音の響きにも耳を傾けながら、演奏会を楽しんで頂きたい。
第1楽章 アレグロ・ノン・トロッポ ニ長調 3/4拍子
冒頭に低弦が演奏する基本動機が曲を通して登場する。この低弦の動機と共に、ホルンや木管によりゆったりとした美しい第1主題が奏でられる。その後出てくる、ヴィオラとチェロによる第2主題は豊麗な音が響き、魅力的なものとなっている。
第2楽章 アダージョ・ノン・トロッポ ロ長調 4/4拍子
長調ではあるが、どことなく寂しげな第1主題により始まる。この主題は4拍目から出発し、音楽の重みが弱拍である4拍目と次の小節の2拍目にあるのが特徴だ。明るい交響曲第2番の中で、重い一面を見せる。
第3楽章 アレグレット・グラツィオーソ ト長調 3/4拍子
オーボエの愛らしい主題から始まるこの楽章は、演奏時間が短い中でテンポやリズムが何度も変化し、ブラームスならではの工夫がなされている。
第4楽章 アレグロ・コン・スピリート ニ長調 2/2拍子
弦楽器が静かに基本動機を用いた第1主題を掲示し、管を加えて明るい旋律が続いた後、休符を挟んで突然大きな音量でエネルギーが放たれる。強烈な音型や、木管の柔らかい旋律を経て、ヴァイオリンとヴィオラによる第2主題が現れる。その後、トランクイロ(静かに)で弦と木管が三連符で応答する。結尾は金管楽器が加わり、歓喜のたかまりを感じながら華やかにしめくくられる。
初演:1877年12月30日 ハンス・リヒター指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、弦五部
参考文献:
ウォルター・フリッシュ(天崎浩二訳)『ブラームス 4つの交響曲』 音楽之友社 1999年
吉田秀和『ブラームスの音楽と生涯』 音楽之友社 2000年
西原稔『作曲家◎人と作品シリーズ ブラームス』 音楽之友社 2006年
淺香淳『作曲家別 名曲解説ライブラリー7 ブラームス』 音楽之友社 1993年
ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲
1872年の秋にウィーン楽友協会の芸術監督に就任したブラームスは、その職務により多忙な日々を送る一方で、夏にはウィーンを離れて創作に没頭した。1873年にはミュンヘンの近くにあるシュタルンベルク湖のほとりのトゥッツィングを訪れ避暑生活を送っているが、「ハイドンの主題による変奏曲」は、この美しい景色に囲まれた町で作曲された。
この変奏曲の主題は、当時ハイドンが作曲したとされていた、管楽器のためのディヴェルティメント「野外のパルティータ」(Hob.II:41-46)の第6曲第2楽章から取られた。ブラームスは、ハイドンの研究家である友人を通してこの曲を知るが、後の研究から、この「野外のパルティータ」は現在ではハイドンの真作ではないと考えられている。
主題 アンダンテ 変ロ長調 2/4拍子
最初にオーボエとファゴットにより主題が提示される(譜例)。低弦楽器がピッツィカートを奏でる中、オーボエが中心となり音楽が進行する。
譜例(準備中)
第1変奏 ポコ・ピウ・アニマート 変ロ長調 2/4拍子
弦楽器がゆったりと流れるように歌う。8分音符と3連符、上行する旋律と下行する旋律が組み合わさり、奥行きのある響きを作り出す。
第2変奏 ピウ・ヴィヴァーチェ 変ロ短調 2/4拍子
主題冒頭の付点リズムを利用した変奏。強弱の変化に富んだ躍動的な旋律が印象的である。
第3変奏 コン・モート 変ロ長調 2/4拍子
オーボエとファゴットが8分音符を主体とした牧歌的な旋律を歌う。この旋律は、弦楽器へと引き継がれていく。
第4変奏 アンダンテ・コン・モート 変ロ短調 3/8拍子
オーボエとホルンがゆったりと奏でる旋律がヴィオラの細かい動きと組み合わさって、憂いを帯びた雰囲気を作り出す。弦楽器と管楽器が入れ替わりながら音楽が進んでいく。
第5変奏 ヴィヴァーチェ 変ロ長調 6/8拍子
一変して活動的な変奏となる。3拍ずつのまとまった旋律がスタッカートで演奏されるが、休符やスフォルツァンドにより拍子感が乱れる。
第6変奏 ヴィヴァーチェ 変ロ長調 2/4拍子
活動的な変奏が続く。弦楽器のピッツィカートにのせて、ホルンとファゴットが美しい和音を軽快に奏でる。後半は弦楽器も加わり、変奏曲はクライマックスを迎える。
第7変奏 グラツィオーソ 変ロ長調 6/8拍子
始めにフルートとヴィオラが優しく穏やかに奏でる。シチリアーノ(舞曲の一種)による変奏である。
第8変奏 プレスト・ノン・トロッポ 変ロ短調 3/4拍子
暗く密やかな変奏。弦楽器と管楽器が交替しながら8分音符で不気味に動き回る。
終曲 アンダンテ 変ロ長調 2/2拍子
最初にバスにより提示されたフレーズが、16回繰り返され、変奏されていく。終曲自体が小さな変奏曲となっている。最後に再び現れた主題は、壮大なコーダへと続き、この変奏曲は華やかに締めくくられる。
初演:1873年11月2日 ウィーン楽友協会ホール
ブラームス指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット2、ティンパニ、トライアングル、弦五部
参考文献:
菅野浩和、門馬直美『作曲家別名曲解説ライブラリー7 ブラームス』 音楽之友社 1993年
西原稔『作曲家◎人と作品シリーズ ブラームス』 音楽之友社 2006年
今村央子『ブラームス ハイドンの主題による変奏曲・大学祝典序曲・悲劇的序曲』ミニチュアスコア解説 音楽之友社 2016年
ブラームス:大学祝典序曲
■ブラームスの生きた時代
ブラームスが活躍したのは日本の明治時代。木戸孝允(1833-1877)、坂本龍馬(1836-1867)、大隈重信(1838-1922)、渋沢栄一(1840-1931)、伊藤博文(1841-1909)等が同世代です。明治維新で改革が進み、鉄道や洋装・洋食など多くの文化が普及し、教育制度も整えられました。
本日2曲目に演奏する「ハイドンの主題による変奏曲」をブラームスが作曲した1873年には、岩倉使節団がドイツ帝国首相ビスマルクに謁見しています。当時のドイツは、戦前の日本の模範として大きな影響を及ぼしています。
| 年 | ブラームスの略歴 | 日本の出来事 |
| 1833 | 5月7日ハンブルク(ドイツ)で誕生 | 天保3年(江戸時代)徳川家斉将軍在任 |
| 1873 | ハイドンの主題による変奏曲作曲 | 明治6年 徴兵令発布 |
| 1876 | 交響曲第1番 作曲 | 明治9年 日朝修好条規(江華条約)締結 |
| 1877 | 交響曲第2番 作曲 | 明治10年 西南戦争 |
| 1880 | 大学祝典序曲 作曲 | 明治13年 「君が代」初演 |
| 1883 | 交響曲第3番 作曲 | 明治16年陸軍大学校開設 |
| 1885 | 交響曲第4番 作曲 | 明治18年 内閣制度発足 |
| 1897 | 4月3日 ウィーン(オーストリア)で逝去 | 明治30年 貨幣法制定 |
■「大学祝典序曲」作曲の経緯
ブラームスは1876年にケンブリッジ大学から名誉音楽博士号贈呈の通知を受けますが、イギリスでの贈呈式に出るための「船嫌い、英語苦手」と辞退します(筆者はこのエピソードを知ってブラームスに親近感を覚えました)。しかし、3年後の1879年、ドイツのブレスラウ大学(現ポーランドのヴロツワフ大学)からの名誉博士号授与には快く応じました。その返礼として作曲された作品が「大学祝典序曲」です。授与の翌年1880年5月に着手し、同9月には完成と短期間に書き上げられました。ブラームス独自の主題を軸に、ドイツの学生歌が4曲巧みに引用されています。
主題
学生たちが遠くで行進するような主題(譜例1)から始まります。
この主題は冒頭ではハ短調でひそやかに奏でられますが、場面が変わるとハ長調で力強く奏でられたり、柔らかく滑らかに奏でられたり、その後も学生歌を繋ぐ役割として様々な形で登場するため、ご注目ください。
学生歌1
最初に登場する歌は「我らは立派な学び舎を建てた"Wir hatten gebauet ein stattliches Haus"」
トランペットを中心に輝かしく高らかに響きます(譜例2)。ホルン・トロンボーン・テューバも加わり金管楽器が主体の場面です。原曲の旋律はミクロネシア(旧ドイツ領)の国歌にもなっています。
学生歌2
次に登場する歌は「祖国の父"Landesvater"」
第2ヴァイオリンが流れるような旋律を奏でます(譜例3)。第1ヴァイオリンの対旋律、チェロの分散和音、コントラバスの旋律的なベースの動きなど、弦楽器が主体です。その後、フルート&オーボエ→クラリネット&ファゴットへと受け継がれ木管楽器の音色の違いも楽しめます。
曲の後半にも、再び第2ヴァイオリンを中心に登場します。ご注目ください。
学生歌3
3番目に登場する歌は「あそこの山から来るのは何?"Was kommt dort von der Höh’ "」
ファゴットが個性的で軽快な旋律で駆け抜け(譜例4)、次第に大勢で盛り上がる場面になります。終盤では管楽器が旋律、弦楽器が裏打ちとなり力強く再登場し、フィナーレへと突入します。
学生歌4
フィナーレに登場する歌が「大いに楽しもう"Gaudeamus igitur"」
管楽器が堂々と歌ったあと(譜例5)弦楽器も続き、全ての打楽器が鳴り響く中、壮大なハ長調の和音で締めくくられます。
原題のラテン語で動画サイトを検索すると、欧州を中心に現在でも愛されていることが分かります。カタカナで「ガウデアムス」でも視聴できますので原曲も終演後にお楽しみください。
余談ですが、筆者が「大学祝典序曲」と出会ったのは高校1年生の5月。管弦楽部に入部し最初に配られた楽譜でした。筆者は高校からホルンを始めたため、この曲はホルンで初めて演奏した記念すべき曲でもあり、また演奏できることを大変嬉しく思っています。大学への憧れがあった当時の気持ちを思い出しながら演奏します。
初演:1881年1月4日 ブラームス指揮
ブレスラウ管弦楽協会第6回予約演奏会
ブレスラウのコンツェルトハウスにて
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、トライアングル、弦五部
参考文献:
西原稔『作曲家◎人と作品シリーズ ブラームス』 音楽之友社 2006年
池辺晋一郎『ブラームスの音符たち 池辺晋一郎の「新ブラームス考」』 音楽之友社 2005年
今村央子『ブラームス ハイドンの主題による変奏曲・大学祝典序曲・悲劇的序曲』ミニチュアスコア解説 音楽之友社 2016年
新響・昔話3=傘寿を過ぎたOBの独り言=
編集人注)
新響OB戸田昌廣氏による『新響・昔話』第3回(最終回)です。
【ソ連への親善演奏旅行】
まずは、この訪ソを主宰した「日ソ青年友情委員会」から、参加する新響団員に宛てた宣言文を抜粋してみます。
"新響のソヴィエト親善演奏旅行は、日ソ青年間の文化、芸術、スポーツなどあらゆる分野における交流を目的としている日ソ青年友情委員会と、全ソ青年団体委員会との文化交流協定にもとずいて実現されるものです。
両委員会は異なる社会体制のもとにあっても国民が相互に生活を知り、文化を知り、芸術を知り、スポーツを知り、また政治や経済を理解しあってこそ世界平和に寄与できるものとして、交流活動を盛んに行っておりますが、新響の訪ソも日ソ両国青年間の相互理解を深める上で、たいへんよい機会であると思います"
この時、日ソ青年友情委員会の委員長は芥川氏であり、同委員会は労音側とは不仲にあった政党、労働団体に支援された組織でした。
したがって労音は中国を、芥川氏はソ連を向いての労音独立騒動であり、その帰結として新響の訪ソがあった、と言えるかと思います。
その後中国では文化大革命が始まって国内はグチャグチャになり、一方ソ連は1917年のソヴィエト10月革命50周年を迎えて力を付け、他国との交流を広げておりました。
私達新響は、横浜港から2泊3日の船旅でナホトカへ、そこから夜行列車で1晩かけてハバロフスク、そして6発プロペラエンジンの巨大な旅客機で8時間飛んでやっとモスクワへ着くという旅程でありました。
その後まもなく(多分翌年)シベリア上空の開放が実現して、日ソ共同運航便が週1便飛ぶようになったという時代でした。
訪れた所はハバロフスク・イルクーツク・モスクワ・レニングラード(現在のサンクト・ペテルブルグ)で、各地毎に両国の国歌演奏で始まる親善演奏会を5公演行いました。
当時日本では、鉄のカーテンの向こう側のソ連の実情や市民生活等々が知られていなかった為か、帰国してから演奏旅行の件ではなくあの国の日常は如何に?との質問がマスコミから受けた主たるものでした。
それから2年後(1969年)九州の新聞社から"九州・沖縄芸術祭"というのを立ち上げる計画だが「芥川也寸志と新交響楽団」と言う題目で協力をいただけないか、と言う話がありました。九州各県とまだ米国統治領だった沖縄を加えた地方を一周するという演奏旅行の話でした。
沖縄の日本への返還は1972年でしたので、各自旅券を持って車が右側通行の那覇へ飛び、その後鹿児島へ戻って九州各県を周りました。
当時日本各地には現在のようにプロ・アマ含めてオケは殆どなく、有名人の芥川氏が指揮をし訪ソの実績のある新響ならば、とのことで声がかかったのだと思います。
大げさに言えば、ソ連にしろ沖縄にしろ、国の策に先駆けた民間交流で一役買っていたと言えるのではないでしょうか。
(おわりに)
私が新響の運営に携わっていたのは、この後3年程でした。在団20年、退団してからもう40年の余が過ぎているわけですから、団から見れば昔々の過去の人間です。
新響が縁で築いた我が家庭も、今では子・孫と大人数の家族となり、皆が皆何らかの形で音楽と関わりのある日々を送っております。
あちこちに遠く離れて暮らしておりますが、音楽が共通の言葉(話題)となって家族間の繋がりに大変役に立っている今日この頃です。
新響で培った音楽との生活が今になっても続いていて、80余年の人生を楽しんでおります、新交響楽団ありがとう。
新任首席奏者に聞く-その2
(メールでの首席事務連絡時の雑談)
・吉田 「外呑みができなくなって、1日3時間ぐらい笛吹いているのではないですか?」
・松下さん「笛の練習時間はいざ知らず、呑む事で浪費していたお金が貯まって困惑しています。近々ゴッホかルノワールの絵の1枚くらい買おうかと考えております(笑)」
・吉田 「そのうち笛が3本ぐらい増えているでしょうね(笑)」
・松下さん「そんなことより、維持会ニュースの新シリーズ『新任首席奏者に聞く』の第2弾として原稿執筆をお願い致したく」
・吉田 「馬刺しのご褒美がないとモチベーションが上がりません」
・松下さん「何頭分でもご馳走しますから…」
…というわけで、コロナ明けの馬刺し(+酒)を励みに、思いつくがままに筆を進めてみる。
◆年齢・性別と表現に関するちょっとした考察
それは
男性の中の女性の
あるいは
女性の中の少年の
あるいは
少年の中の老人の
喜びか?
小沢健二『薫る(労働と学業)』より
<表現と年齢について~年をとると若返る?>
長年フルートパートの首席奏者をお務めの松下さんに対して、生意気にも普段から上記のようにずけずけものを言ってしまっているが、私より20歳以上年上の大先輩である。博識で笛の音も神々しく、「このお方は仙人なのでは」と思ってしまうが、気力は明らかに自分より若い。新響ではこのような年齢不詳の方々に囲まれて、「年をとるって何だろう」と考えることがある。
指揮者の先生方は特に年齢を超越している。ある分奏の際、トレーナーのF先生に「飯守先生はいつももっとゆっくりですか?」と尋ねられ、団員から「ここはもう少し速いです」と答えたところ、F先生は「うーむ、若返っちゃったかな…」と呟かれた。飯守先生に限らず、特に本番中は、私には指揮者の先生方が、少年が嬉々として遊んでいるように見える瞬間がある。作曲家もしかり。ライネッケのフルート協奏曲の瑞々しさ!とても84歳で書いたとは思えない。
私自身は30代後半になるが、上手に歳を取れなくて困っている。もちろん外見や体力の話ではない。このぐらいの歳になれば、ものわかりがよくなり、欲も少なくなり、自己主張も消えるものかと思っていたが、その気配がない。でもそれはきっと私だけではなく、他の団員だって楽器を手に遊んでいる大きな子供のようなものである。
日本では「誰々何歳がどうした」というニュースを聞かない日はなく、何かにつけ年齢を意識せざるを得ないため、無難に年相応の仮面を被って生きることになる。ところが、表現者になったとたん、その仮面が剥がれるようだ。技術や体力は衰えるが、音の艶やテンポ等は、実際の歳とは必ずしも比例しないように感じる。自分の倍以上の歳の団員に遠慮を忘れるのも、一緒に演奏していると年齢の差を感じないからかもしれない。
新響に入りたての20代前半の頃は、大の大人が、子供が遊ぶように一生懸命演奏活動に取り組むのを不思議に思っていたが、今は自分が若い方々にそのように思われているのだろうか。
<表現と性別について ~男の中の女?~>
・Sさん「そのお弁当おいしそう。どこで買ったの?」
・Oさん「でしょ?東武に新しいお店ができて…」
・Aさん「Yさんのお子さん見た?大きくなって。よその子の成長って早いよね」
・Kさん「そういえばこの前職場で…あ!出番だ!行かなきゃ」
・みんな「頑張って!」
これはコロナ前の本番当日の楽屋風景である。管楽器の女性楽屋はいつも賑やかで、その話題は食べ物、家族、仕事、政治、もちろん音楽と幅広く、天使が通る隙間なんて全くないほど切れ目なく続く。楽屋での会話が演奏会の楽しみのひとつなので、感染予防のため私語を控えなければならない今はとても寂しい。楽屋からフルート教職員組合(フルートの先輩方3名は現役または元教職員なので、こう呼ばれている)のおしゃべりが聞こえなくなる日が来るなんて…。一方、用があって男性楽屋にお邪魔したときには、おにぎりの咀嚼音が聞き取れるほどの静かさに驚いた。
楽屋の風景は男女でこんなにも違うわけだが、演奏となると、性別が入れ替わるように感じることがある。フルートはその音の特徴から女役を担うことが多いのだが、いつだったか、松下さんの美しいフルートソロを聴いて、とある団員が「美しい娘を思い浮かべて後ろを向いたら、でかい松下が吹いてて調子狂うんだよな…」と呟いていた。女性的なものを表現するのは女性の方が適しているというわけではない、ということを実感した瞬間だった。
数年前に彩の国さいたま芸術劇場で、テロ・サーリネン振付によるダンス『MORPHED』(エサ=ペッカ・サロネンの音楽と、マリメッコのデザイナーによる衣装も素晴らしかった!)を観た。ダンサー8人はすべて男性だったが、男性の強さだけではなく弱さや繊細さが表現され、とても新鮮で納得でき、改めて男らしさ女らしさって何だろうと考えてしまった。
翻訳家の松岡和子さんは、従来のシェイクスピア作品の翻訳の女言葉に違和感を持ち、新訳に取り組まれていると聞いた。演奏者が翻訳家の役目を担うクラシック音楽においては、曲に対する解釈が演奏の度にアップデートされるとも言えるだろうから、何が正解かわからずとも、固定観念を持たずに柔軟でいたい。
オーケストラは不思議だ。あらゆる立場や属性が取り払われるだけでなく、ベテラン男性団員の中に秘められた美少女、入団したばかりの若い団員が既に持ってしまった枯れた味わいがまぜこぜになって、とにかく今一緒に演奏している。ただ「音楽が好きだ」という理由だけで集まった多種多様な団員がこれまで奏でた音を記憶する新響という生き物は、今後さらに年をとっていくわけだが、成熟しつつ常に若返りたいし、時代とともにどんどん姿を変えていきたい。首席としてというより、一団員としてそんな風に思っている。
(後日のメール)
・吉田 「ゴッホかルノワールは無事購入できましたか?」
・松下さん「いずれを落札すべきかに未だ思い悩んでいますが、それより先に読譜のための眼鏡を新調しないとまずいことに気が付きました!ガイドとして出てくる他パートの音符と、自分が吹くべき音群との見分けがつかず、混乱を来たしています」
・吉田 「そういえば、維持会ニュースの原稿に御大を登場させてしまいましたが…」
・松下さん「私の事は如何様にもいじって戴いて構いません。原稿を読んでみて、そうだ仙人になってカスミを食べて命永らえられれば、老後資金の心配もする必要も無くなり、理想というべき状態じゃないか!と気づかされた次第です(笑)」
◆音楽的自叙伝
自分のことより普段の新響の様子をお伝えできればと思い書いてきたが、このような機会もなかなかないので、ファゴットの桃ちゃんに倣って、自分と音楽との関わりについても書いてみようと思う。
<音楽との出会い>
武満徹にとってのリュシエンヌ・ボワイエ『聞かせてよ愛の言葉を (Parlez-moi d'amour) 』のような、音楽との衝撃の出会いエピソードがあればよいのだが、残念ながら特にない。
元ピアノ教師の母は、音大生の頃、同級生が楽器を持って構内を歩く姿(特にマリンバ奏者がマレットの束を持ち歩く姿)に憧れていた。また、ピアノは孤独なので子供には合奏できる楽器をやらせたかったらしい。そこでまず兄にバイオリンを習わせてみた。兄はつらそうに毎日同じ曲を練習していた。「そんなに嫌ならバイオリンやめなさい!」「やめない!(泣)」を繰り返しながら思いのほか続いてしまったので、私はバイオリンを免除され(あんなに難しそうな楽器できる気がしない)バレエ教室に通うことに。家で聴く母とその生徒のピアノ、兄のバイオリン、そしてバレエ教室で流れるクラシック音楽が、私の音楽の原点なのだと思う。
<フルートとの出会い>
小学校3年生の頃、バレエ教室のガラスのドアに激突して膝の靭帯を切断する大けがをして踊れなくなった。ちょうどその頃、近所に新しくフルートの教室ができたので母に「やってみる?」と言われ、何も考えずにコクンと頷いた。その楽器がトランペットでもコクンと頷いていたと思う。大人になってから自分で楽器を選んでいたとしたら、私はどちらかといえば地味で暗い性格なので、華やかなイメージを持たれがちなフルートは選ばなかっただろう。今でも楽器を聞かれる度に俯いて「フ…フ…フルート…」とどもってしまう。もし今楽器を始めるなら、一人でも楽しめるギターがいい。ただ、フルートの他の楽器と比べて持ち運びしやすいところは気に入っている。ピッコロも持たなければならないときは「やれやれ荷物になるな」と思うが、バスクラリネットやコントラファゴットの横では口が裂けても言えない。
<オーケストラとの出会い>
中学生の頃、佐治薫子音楽監督率いる千葉県少年少女オーケストラが設立され、母に「受けてみる?」と言われてまたコクンと頷いたものの、1度目は不合格、2度目の受験で入団することができた。大勢で演奏するのは初めてで戸惑ったが、入団間もなく芥川也寸志『交響管絃楽のための音楽』を演奏して、「なんだかわからないけどオーケストラって楽しい」と思った(在籍中はこの曲を千葉県各地で数えきれないほど演奏した)。その時の私にとって、芥川もベートーヴェンも「昔の作曲家」だったので、後に芥川先生を直接知る方々と一緒に演奏することになるとは思ってもみなかった。
同オーケストラでは錚々たる顔ぶれの指揮者やソリストと共演する機会に恵まれたが、西洋音楽だけではなく、冨田勲『新日本紀行』、宮川泰『宇宙戦艦ヤマト』等の邦人作品を作曲家自身の指揮で演奏できたことも、今思えば大変かけがえのない経験だった。新響でも引き続き同時代の日本の作曲家とも一緒に活動できたらと思っている。
県立千葉高校のオーケストラ部にも所属していたが、新響にはOB・OGが複数おり、先輩後輩とまた一緒に演奏できるはとても嬉しい。因みに、一つ上の代のコンミスが作曲家の小出稚子さん。芥川作曲賞をはじめ受賞歴も華々しいが、オランダ留学後、インドネシアでガムランを学び、独自の方法で楽しい音を生み出し続けている先輩に興味津々で、いつか演奏できないかな…と勝手に夢見ている。
<新響との出会い>
子どものころのオーケストラ活動は環境に恵まれ充実していたものの、他の世界も見てみたいと思い、大学ではワンダーフォーゲル部に入り山に登ったりしていた。ところがある時ひょんなところで「お前、シンキョ―入れよ」と言われ、「シンキョ―?」と思いながらネット検索して、「この団なら武満徹が演奏できるかも」と思い(学生時代はフランス語を専攻していたが、美術系のゼミに所属し、武満徹について卒論を執筆した)、とりあえずオーディションを受けたところ、ここでも1度目は不合格、2度目の受験で拾ってもらった。入団して10年以上経つが、未だに武満徹は演奏したことがない。
<先生のこと>
小学4年生から高校生頃までは、近所のヤマハ音楽教室で、音大を卒業したばかりの篠崎美千代先生に習っていた。先生は教則本と並行して、私の飽きっぽい性格に合わせてどんどん色んな曲をやらせてくれた。毎回のレッスンが楽しみで、これまで続けてこられたのは先生のおかげだと思う。
大学生の頃には、ムラマツ・レッスンセンターで鬼才・木ノ脇道元先生に1年程教えていただいた。先生は無類の映画好きで、私も学生時代はろくに大学に行かず映画ばかり観ていたので、映画の話ばかりしていたような気がするが、孤高のイメージのある先生に「一人でやるのは良くないよ」と言われたのを何となく覚えていて、懲りずにまたオーケストラに入ろうと思ったのかもしれない。因みに、先生の所属するアンサンブル・ノマドには「今度は何をやるのかな」といつもわくわくさせられている。
社会人1年目で早くもドロップ・アウトして、「留学でもするか」と思い付き、フランスはニースの夏季講習でヴァンサン・リュカとクロード・ルフェーブルの指導を1週間ずつ受けた。結局「留学以前の問題だな」と気づいてすぐに帰国するのだが、他の楽器のレッスンを聴くのも面白かったし、音楽以外にも、南仏の強烈な日差しのなかバカンス気分で遊び歩いたり、様々な国から集まった受講生たちと夜な夜な喋ったりするのも楽しかった。「同期がキャリアを積んでいるときにこんなことしてていいのかな」という後ろめたさを抱えながらふらふらしていた、あの宙に浮いていたような1カ月が懐かしい。
2年程前からは、武満徹の初演を数多く手がけた小泉浩先生にご指導いただいている。今練習している曲をみていただけたらぐらいに思っていたところ、楽器の鳴らし方からやり直すことになった。先日もマルセル・モイーズ『24の旋律的小練習曲と変奏(初級)』を取り出して、「あなたはこの教則本もやるといいんだけどなあ。初級と書いてあるけど、とんでもない。こんなに難しいものはないんだよ。やるかい?」と言われた。「はい」と言うしかない。まだまだ道のりは長そうだ。
<楽器のこと>
楽器にこだわりはなく、篠崎先生に薦められたムラマツのADというモデルを長年愛用していたが、その後同じくムラマツのSRを経て、今は小泉先生に選んでいただいた1974年製のパウエル(所謂オールド・パウエル)を使用している。ヘインズ党の小泉先生がパウエルを推すのはかなり珍しいらしい。管が薄く、キーも軽量で、見た目にも優美な楽器でうっとりする。これまでの楽器と比べて音の鳴るポイントが狭く、音程もとりづらく、大きな音が出づらく、当初は大変苦労したが、今はそれも含めて楽しんでいる。
<好きなフルーティスト>
立派な演奏よりも自然な演奏に憧れる。小泉浩先生の深い音色、木ノ脇道元先生の原始的な音、セバスチャン・ジャコーのリラックスした音、アンナ・ベッソンの心躍るトラヴェルソ、たまたま動画サイトで見つけたマウロ・スカッピーニの歌心溢れるサン=サーンス『ロマンス』、BODY&SOULでのライブを聴いて間もなくの訃報が信じられなかったジャズフルートの巨人ジェレミー・スタイグ、ジャック・ズーン、マチュー・デュフォー、有田正広、もちろんランパル…。今後びっくりするようなフルーティストに出会えることを期待している。
<好きな音楽>
今取り組んでいる曲に一番の愛情を注いでいるつもりだが、これまで新響で演奏したなかでお気に入りは、ラヴェル『古風なメヌエット』、ウェーベルン『6つの小品』。宝物のような小品に出会うことができるのも、新響ならではだと思う。このところ演奏機会の多い土の匂いのする東欧の曲も好き。ロマン派には苦手意識があったが、つい先日ラジオから唐突にマーラーの『大地の歌』が流れてきてなぜか感動してしまった。苦手な曲もいつコロっと好きになるかわからない。具体的な物語のある曲は、未だにどうしても恥ずかしくて入り込めず上手に吹けない。
普段は時代やジャンルを問わず何でも聴く。すごいと思うのは大貫妙子、小沢健二、ボブ・ディラン。最近はBUCK-TICKにはまり、藤井風にびっくりした。よく聴くラジオは細野晴臣「Daisy Holiday!」、「Barakan Beat」、「空気階段の踊り場」(お笑いだが選曲も楽しみ)、「France Musique」。土曜の朝寝の後、大貫妙子『SUNSHOWER』を聴きながら洗濯物を干している時間が幸せ。
<音楽以外で好きなもの>
運動不足解消を兼ね、10年程前からバレエのレッスンを再開した。今習っているのはクラシックだが、観るのはモダンやコンテンポラリーも好きで、印象に残っているのはデヴィッド・ビントレー『ペンギン・カフェ』、ローザス『Hoppla!』、フィリップ・ドゥクフレ『PANORAMA』。映画も大好きで、好きな俳優はイザベル・ユペール、アデル・エネル、フローレンス・ピュー。最近印象に残った映画はコゴナダ監督『コロンバス』、ダミアン・マニヴェル監督『イサドラの子どもたち』。因みに、この原稿の締切日はデイヴィッド・バーン×スパイク・リー『アメリカン・ユートピア』の公開日!
◆維持会の皆様へ
私はかつて、人前で決まった時間にかしこまって演奏するのが何だか気恥ずかしくて、誰に聴かせるでもなく演奏している方が、もっと言えばむしろ演奏しない方が、純粋な音楽になるのでは、と思うこともありました。しかしながら、今回のコロナ禍においても無観客はどうしても考えられませんでした。当たり前ですが、聴いてくださる方々がいなければ、新響は存在しないも同然です。その場でお客様と素晴らしい音楽を分かち合うのが最大の喜びだと再認識しました。制限つきの練習をせざるを得ずもどかしくもありますが、皆様の応援が大変励みになっています。いつもご支援いただきありがとうございます。私たちの演奏が少しでも気晴らしになっていましたら、それ以上の幸せはありません。
第253回ローテーション
| 自然の中で | 謝肉祭 | オセロ | シュミット交響曲 | |
| フルート1st | 岡田 | 吉田 | 吉田 | 松下 |
| 2nd | 藤井 | 岡田 | 岡田 | 兼子 |
| Picc | - | 藤井 | - | - |
| オーボエ1st | 大山 | 大山 | 岩城 | 平戸 |
| 2nd | 岩城 | 岩城 | 大山 | 山口 |
| クラリネット1st | 末村 | 末村 | 大藪 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 進藤 | 石綿 | 進藤 |
| ファゴット1st | 藤原 | 藤原 | 藤原 | 浦 |
| 2nd | 田川 | 田川 | 田川 | 松原 |
| ホルン1st | 名倉 | 名倉 | 名倉 | 山口 |
| 2nd | 市川 | 市川 | 市川 | 山路 |
| 3rd | 大原 | 大原 | 大原 | 大内 |
| 4th | 山路 | 山路 | 山路 | 大原 |
| トランペット1st | 北村 | 北村 | 北村 | 倉田 |
| 2nd | 瀧野 | 瀧野 | 瀧野 | 中川 |
| トロンボーン1st | * | * | * | 志村 |
| 2nd | 志村 | 志村 | 志村 | * |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 坂巻 | 坂巻 | 坂巻 | - |
| ティンパニ | 桑形 | 桑形 | 桑形 | 今尾 |
| パーカッション | Cymbals足立 Triangle鈴木* |
Cymbals足立 Triangle鈴木* Tamb今尾 |
Cymbals足立 Triangle鈴木* |
- |
| ハープ | - | 見尾田* | 見尾田* | - |
| 1stヴァイオリン | 内田智(今村) | 内田智(今村) | 内田智(今村) | 内田智(今村) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(平田) | 小松(平田) | 小松(平田) | 小松(平田) |
| ヴィオラ | 村原(田川) | 村原(田川) | 村原(田川) | 村原(田川) |
| チェロ | 柳部(河野) | 柳部(河野) | 柳部(河野) | 柳部(安藤) |
| コントラバス | 宮田(萩原) | 宮田(萩原) | 宮田(萩原) | 宮田(萩原) |
*はエキストラ
弦()はトップサイド、管()はアシスタント
第254回ローテーション
| 大学祝典 | ハイドン変奏曲 | 交響曲第2番 | |
| フルート1st | 兼子 | 吉田 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 林 | 黒住 |
| Picc | 藤井 | 岡田 | - |
| オーボエ1st | 平戸 | 平戸 | 堀内 |
| 2nd | 岩城 | 岩城 | 岩城 |
| クラリネット1st | 大藪 | 品田 | 進藤 |
| 2nd | 品田 | 石綿 | 末村 |
| ファゴット1st | 田川 | 田川 | 松原 |
| 2nd | 浦 | 浦 | 藤原 |
| コントラファゴット | 藤原 | 藤原 | - |
| ホルン1st | 山路 | 山口 | 名倉 |
| 2nd | 市川 | 山路 | 大原 |
| 3rd | 大原 | 大内 | 山口 |
| 4th | 大内 | 市川 | 大内 |
| トランペット1st | 瀧野 | 倉田 | 倉田 |
| 2nd | 中川 | 北村 | 中川 |
| 3rd | 北村 | - | - |
| トロンボーン1st | 志村 | - | 武田香 |
| 2nd | 武田香 | - | 志村 |
| 3rd | 岡田 | - | 岡田 |
| テューバ | 土田 | - | 坂巻 |
| ティンパニ | 今尾 | 足立 | 桑形 |
| パーカッション | BassDrum足立 Cymbals桑形 Triangle鈴木* |
Triangle今尾 | - |
| 1stヴァイオリン | 内田智(小松) | 内田智(小松) | 内田智(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 中島(今村) | 中島(今村) | 中島(今村) |
| ヴィオラ | 村原(田川) | 村原(田川) | 村原(田川) |
| チェロ | 柳部(安田) | 柳部(安田) | 柳部(安藤) |
| コントラバス | 宮田(山田) | 宮田(山田) | 宮田(山田) |
*はエキストラ
弦()はトップサイド、管()はアシスタント
第254回演奏会のご案内
ブラームスは好きですか?
今回の演奏会はオール・ブラームス。ブラームスはドイツの大作曲家で北ドイツのハンブルクで生まれ、ウィーンで生涯を終えた。ハンブルクの冬は寒く長く曇りが多く、人々は勤勉で真面目。そのような土地柄を反映してか、ブラームスの音楽は深くそして心にしみる。
映画にもなった「ブラームスはお好き」というサガンの小説があるが、最近では「ブラームスが好きですか」という韓流ドラマがあり、これは親友であるシューマンの妻クララを慕っていたブラームスにかけた物語らしい。生涯独身のブラームスだが、恋多き人生でもあった。
自分に厳しく完璧主義で納得のいかない作品は残さなかった。幼少期よりピアニストとして活動していたブラームスにはピアノ曲や室内楽曲は比較的数が多いが、管弦楽作品は少なく、4つの交響曲といくつかの協奏曲と管弦楽曲のみで、どの曲もオーケストラの主要レパートリーとなっており、ブラームスが大好きな演奏家は多いだろう。
ブラームスの田園交響曲
交響曲第2番は、ベートーヴェンを意識して20年費やした交響曲第1番が完成した後、ふっきれたように4か月で書き上げられた。南オーストリアのヴェルター湖畔にあるペルチャッハという避暑地で作曲され、重厚で劇的な第1番とは対照的にのびやかで明るく、ブラームスの田園交響曲とも呼ばれる。自然を愛するブラームスは美しい風景を気に入り、翌夏には同所でヴァイオリン協奏曲も書いている。
これらの名曲を生み出し名声が高まったブラームスに、ドイツ(現ポーランド)のブレスラウ大学から名誉博士号が贈られた。その返礼として作曲されたのが「大学祝典序曲」で、儀式の音楽ではなく4つの学生歌が引用された楽しい演奏会用序曲。ラジオの大学受験講座のテーマ曲に使用されていたので聴いたことのある方も多いだろう。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
シュミット:交響曲第3番 イ長調
『交響曲第3番』は、オーストリアで活躍した作曲家、フランツ・シュミットによって書かれた曲です。シュミット(1874 ‐1939)は、オーストリア=ハンガリー帝国プレスブルク(現スロヴァキアの首都ブラチスラヴァ)出身の作曲家で、4つの交響曲やオペラ等を書いています。この時代、新ウィーン楽派のスタイルが流行していました。しかし、彼はシューベルト、ブラームス、ブルックナー等の後期ロマン派の要素を多く取り入れ、伝統を引き継いでいます。
『交響曲第3番』は、彼がオーストリア代表として、第一次世界大戦終結から10年後の1928年に開催された「国際シューベルト作曲コンクール1928」に応募するために作曲した曲です。彼は、スウェーデンのクルト・アッテルベリ(1887‐1974)の『交響曲第6番』に次いで2位になっています。この曲は、コンクール用に作曲されたため、巨大編成の曲が多いシュミットには珍しいシューベルト時代の小さい編成で書かれています。
古典的な4楽章で構成されています。
・第1楽章Allegro molto moderato
・第2楽章Adagio
・第3楽章Scherzo. Allegro vivace—Trio. Molto più tranquillo
・第4楽章Lento—Allegro vivace
この曲は、長調で書かれているのにもかかわらず、短調に多くの時間を費やしています。加え
て、穏やかな曲調の中でも、終わりの見えない転調が生み出す不安感は、シューベルトの転調技法の斬新さを取り入れていると考えられます。転調技法は、第1・2楽章で多く用いられています。
第1楽章は、フルートの主題から始まり、その主題が次の調や楽器に巧みに繋がっていきます。小さい編成で書かれていますが、彼のオルガニストとしての腕前を活かした、オルガンを思わせる響きが特徴です。
第2楽章では、それがさらに顕著になっており、彼独特のハーモニーの美しさが感じられます。
第3楽章のスケルツォでは、第2楽章の主題が変形して登場しています。強弱や曲風の変化も激しく、シュミットの遊び心が詰まっています。
第4楽章は一変し序曲から始まります。ハーモニーが折り重なっていく美しさが際立っています。その後は、6/8拍子のAllegro vivaceに展開していきます。様々なメロディが掛け合いをしているところが魅力です。
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、弦五部
初演:1928年12月2日(ウィーン楽友協会)ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、フランツ・シャルク指揮
参考文献:(いずれも最終閲覧日:2021年3月18日)
Clements, Andrew. "Schmidt: Symphony No 3; Chaconne." The Guardian, 15 July 2010, www.theguardian.com/music/2010/jul/15/schmidt-symphony-3-chaconne.
Franz Schmidt: Symphony No. 3 in A major for orchestra. Universal Edition, www.universaledition.com/franz-schmidt-647/works/3-symphonie-544.
大阪交響楽団「2013年度 定期演奏会 曲目解説」2013年2月28日http://sym.jp/publics/index/104/detail=1/c_id=231/page231=2
指揮者:寺岡清高コメント
第二次大戦後、戦時中ナチスに協力したと誤解されたこと(今日では名誉は回復されています)、そして何より行き着く所まで行ってしまった感のある複雑な和声と、演奏自体が非常に難しいせいで、シュミットを実演で聴く機会はまだまだ多くありません。しかしその音楽は、ウィーンゆかりの作曲家達、例えばシューベルトの歌心、ブラームスの作曲書法、師であるブルックナーのオルガンサウンドと宗教的敬虔さに満ちています。そこに加えて、ウィーン宮廷歌劇場芸術監督マーラーの下で積んだチェロ奏者としての劇場体験と、マーラーの作品を含む同時代作品の演奏経験まで兼ね備えたシュミットの音楽は、正にウィーンロマン派音楽の最終形態とも呼べるもので、一度はまるとなかなか抜け出せない中毒性を持っています。今回採り上げる交響曲第3番は、シューベルト時代の小さい編成で書かれていますが、しっかり「シュミットのオルガンの音」がします。私のライフワーク作曲家の一人でもあるシュミットの魅力をまだご存知でない方、この機会に是非シュミットサウンドを全身に思う存分浴びて下さい
ドヴォルザーク:序曲三部作『自然と人生と愛』
ドヴォルザークといえば交響曲第9番「新世界より」や弦楽四重奏曲「アメリカ」等が有名だが、彼が愛してやまなかったのは、故郷チェコの風景、そして民族であった。
ドヴォルザークはプラハから少し離れた村で肉屋兼宿屋(食堂)の長男として生まれた。父も叔父も楽器を演奏し彼も幼い頃からヴァイオリンやヴィオラを始め、優れた才能を示した。そのまま肉屋を継ぐところを、ドイツ語(当時チェコはオーストリア=ハンガリー帝国の一部だったため商売をするにもドイツ語を話せることが必要だったが彼はチェコ語しかできなかった)と音楽を教えてくれた先生の強い勧めでプラハのオルガン学校に進学し、苦労の末音楽家の道に進むことができた。「モラヴィア二重唱曲」や、幼い我が子を続いて亡くした頃に作曲した「スターバト・マーテル(悲しみの聖母)」などで有名になり、次々に曲を発表して名声を確立していく。ブラームスに認められてウィーンに住むようにも言われたが、彼はチェコを離れようとはしなかった。
妻の姉が嫁いだカウニツ伯爵の別荘がプラハから60キロ離れたヴィソカー村にあったが、彼は1885年に伯爵の持っていた近くの小さな家を買い取り、夏の家に改装した。
ルサルカ荘と名付けられたこの家をドヴォルザークはこよなく愛し、半年以上を過ごすこともあったそうだ。周囲には美しい自然とのどかな田園風景が広がり、2階の書斎の窓からも素晴らしい眺めを楽しむことができた。森や池もある周囲を散策するのが彼の何よりの楽しみだった。
ニューヨークの音楽院長にと招聘されアメリカに旅立つ直前の1891年の3月から1892年の1月までに「自然と人生と愛」は作曲されている。当初は序曲3部作の1つのまとまった作品として扱われたが、翌年出版されたときには独立した3つの序曲とされた。どの曲にも冒頭の「自然」のテーマが共通して登場し、チェコの民族音楽を思わせるメロディが出てきて、ドヴォルザークの故国の自然への愛と、民族の自立への思いが込められているようだ。
『自然の中で』ヘ長調〖自然〗
最初にファゴットにより「自然のテーマ」が奏でられてどんどん広がっていき、豊かな自然の広がる美しい風景を表現している。ヴィソカーでドヴォルザークが早朝飼っていた鳩に餌をやってから村を通り抜け、森の中を散歩する様子が目に浮かぶようだ。
「謝肉祭」イ長調〖人生〗
イースター前の肉食を控える期間の前に行うのが謝肉祭であり、チェコでも仮装パレード等各地で楽しいお祭りがある。肉断ちする前に盛大に肉をさばいて食べる、というのが起源なので、肉屋のマイスターの資格を持つ唯一の作曲家であるドヴォルザークにとっては、とりわけ印象深いお祭りだったに違いない。
この曲はお祭りや村人の踊りを表すように華やかに始まる。のどかで田園風な中間部では「自然のテーマ」もゆったりと現れ、また最後はにぎやかに盛り上がって終わる。この曲は3曲中で最も頻繁に演奏されている。
「オセロ」嬰ヘ短調〖愛〗
この曲はシェイクスピアの「オセロ」のストーリーに基づいて作曲されている。
静かに始まり、第1主題はオセロを表し第2主題はデズデモーナを表している。ドヴォルザークはスコアに手書きで場面を書き込んでいた。曲の後半から「オセロの心の中に嫉妬と復讐の念が育ち始める」「オセロの怒りは頂点に達して彼女を殺す」。その少しあとで第2主題がフルートで演奏されるが、ここには「彼女は再び、そして最後に潔白を訴える」。「彼女は安らかに死ぬ」「取り返しのつかなくなったオセロは自分のしたことを後悔し始める。嫉妬の苦しみは薄らいでいく」そして木管の静かなアンサンブルで「彼は祈る」。「彼女に最後のキスをする」静かにティンパニがトレモロを始めるところで「自分のおぞましい行為を思い返す」。「自殺を決断する」「自殺する」。それぞれの場面を想像しながらお聞きください。
楽器編成:ピッコロ(謝肉祭のみ)、フルート2(オセロで一人はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット(自然の中でのみ)、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ハープ(自然の中で以外)、ティンパニ、シンバル、トライアングル(オセロ以外)、タンブリン(謝肉祭のみ)、大太鼓(オセロのみ)、弦五部
初演:1892年4月28日 (プラハ 芸術家の家にて)作曲者自身の指揮
参考文献:
REPERTOIREEXPLORER In der Natur
op.91 Othello op.93 Musikproduktion Hoflich 2008年(ポケットスコア)
New York Philharmonic Leon Levy Digital Archives (HP)
渡 鏡子 『スメタナ ドヴォルジャーク』 音楽之友社 1980年
黒沼ユリ子 『ドボルジャーク―その人と音楽・祖国』富山房インターナショナル 2018年
新響・昔話2=傘寿を過ぎたOBの独り言=
編集人注
新響OB戸田昌廣氏による『新響・昔話』第2回です。今回のテーマに関しては以下に、より詳しい状況が著者本人によって語られています。またそれに触発された拙稿も合わせてご参照ください。
第232回演奏会プログラム「座談会新響のルーツを探る」
第233回演奏会維持会ニュース「小説『仮装集団』と新交響楽団」
【労音からの独立とは】
ソ連がスターリンの死後(1953年)、1917年のソヴィエト革命以来の政治路線を修正した事により、毛沢東の共産中国といざこざが始まり共産主義の世界がぎくしゃくしてきました。
この揉め事が日本にも伝播して、国内の革新政党間の関係がおかしくなり、当時青年層に盛んだった文化活動等の活動方針にも対立が生まれ、純粋・単純な音楽活動と思って参加し享受していた労音の内実が露わになって来て、そうだったのか・・・と、世間に大ショックを与えたのが私達の労音からの独立騒動だったのです(1966年)。
当時私達は"東京労音新交響楽団"と称して団員の技術レベルによって第1・第2・第3の三つのオケと吹奏楽団の四つのグループがあり、総勢250名位の団員と4名の指揮者により各団が独自に活動しておりました。
活動は別々でも東京労音の組織内グループですので、運営ルール・楽譜・備品・大型楽器等は共通で4グループと労音事務局とで運営委員会を以って安定した運営が出来ていたと思います。
ところが、各団が順調に活動していた1965年、労音より4団体へ組織改革の提案があり、それからの約1年の間、楽器を持ってオケで音楽に親しんでいる団員にとってはピンとこない労音からの問題提起に付き合うことになったわけです。各団の運営委員は労音と議論する中で、その改革内容が音楽以外のところにある・・・ということが分かってきたのですが、多くの団員にとってはそんなことはどうでも良くて各団とも通常の活動をしていました。
結論から言えば、このオケの創始者であり指導者である芥川也寸志氏の政治姿勢が労音側と異なってきて邪魔になり、それなりのすじから排除するようにとの指示があったのでは、と理解するに至りました。この間芥川氏自身からもこれはごくごく政治的な問題だから論点を間違わないようにと言われておりました。
1966年3月にこの問題にケリを付けるかたちで、第1・第2のオケと吹奏楽団は労音から離れ、第3オケはまだメンバーも少なく力量も弱いので労音の中でやって行く、と各団の総意にて独自の道を歩む事になり今日に至っております。この時、第1オケ(今の新響)からは2名が労音の主張に賛同して去りました。
新任首席奏者に聞く-その1
<はじめに>
・『維持会ニュース』編集人の松下氏(フルートパート首席)より、「維持会ニュース紙面にて『新任首席奏者に聞く』という連載を新たに開始するので一発目を書くように」との下知を受けました。新響の並み居る奇人変人の中にあっては刺激の少ない話題しか持ち合わせておらず恐縮なのですが、松下氏の御下知には逆らえません。こんな人間が吹いてるんだな、と少しでも親近感を持って頂ければ幸いです。
<基礎情報>
・藤原桃(ふじわら・もも)と申します。
・35歳、家族は夫(大学オケの同期、ファゴット吹き)と娘(4歳)。
・千葉県生まれ、茨城県育ち、千葉県在住。関東平野を出たことがありません。
・職業は市役所職員。大学では民俗だの文化財だのを勉強していたので、入庁当初は文化財担当配属でしたが、その後異動を重ねて現在は国民健康保険課*1所属。
・新響には2010年7月に入団し、11年目。2020年シーズンよりファゴットパート首席を拝命しています。
<使用楽器>
・モーレンハウエル(プロフェッショナルモデル5ピース)昨年末に買ったばかりで、実は今回の演奏会がデビュー戦です。
・ファゴットは本体が4つのピース(部品)から成っており、吹くときにはそれらを組み立ててあの長い筒のような形状にするわけですが、この楽器は普通より1つ多い5ピースから成っています(分解できる部分が1か所多い)。それによって普通の楽器よりも小さいケースに収納できるのがポイントです。新響の練習へ参加するのに往復2時間近く楽器を持ち運ぶので、ケースが小さいことは意外と重要です。
・「貴婦人」とも形容される、優しくてふくよかな音色が最大の魅力。まだまだ買ったばかりで吹き込みが足りないので、コロナ禍を逆手にとってじっくり育てていこうと考えています。
<練習環境>
・自宅に電話ボックスくらいの防音ブース(ヤマハ・アビテックス)を入れています。中で迂闊に方向転換できないくらい狭く、夏場は30分でサウナと化します。子供が産まれたら自宅にいつでも吹ける環境が無い限り練習できないと思い、娘の出産前に導入したものですが、この決断は正しかったと思っています。
・毎日夜9時くらいには娘とともに寝てしまうので、翌朝4時頃起きて30分~1時間程度防音室の中で練習しています(不真面目なので毎日は吹きません。1週間のうち4日くらい)。
・なお仕事、家事、育児に加え楽器までやっていて凄いね!とお褒め頂くことがありますが、新響の託児制度や家族の多大なる理解協力など、様々な助けを得てなんとか(適当に)こなしている状況です。新響団員にはさらに何足もの草鞋を完璧に履きこなしている超人が山ほど居り、尊敬するばかりです。
<新響以外の活動>
・茨城の知人に誘われた木管五重奏団で、10年くらい活動を続けています。水戸芸術館のオーディションに受かったので、来年あたり水戸芸術館でコンサートを行う予定です。
<趣味嗜好(好きなもの)>
1)曲、作曲家
・どんな人のどんな曲でも吹き始めるとだいたい好きになりますが、特に素晴らしい職人技だと思うのはラヴェルのオーケストレーション。人類を超越していると思うのはメンデルスゾーンとシューベルト(自然、宇宙のなせる業としか思えない)。
・例外として、シューマンのオーケストラ曲はまだ良さを理解できる境地に至っていません(ピアノ曲は好き)。
2)ファゴット奏者
・読響首席の井上俊次氏。何を吹いても独特の、人間味に溢れた演奏になるすごい人。大きなソロはもちろん、ちょっとしたフレーズであっても、井上さんはどう吹くだろう…とワクワクさせてくれる(そして120%井上さんらしい演奏を聞かせてくれる)、ファゴットって本当に味のある楽器だなと思わせてくれる素晴らしい奏者です。ああいう奏者になりたいと思っています。
3)ファゴット以外の楽器
・クラリネット(特にシャリュモー音域*2は最高)、ホルン。
・クラリネットはオケでもアンサンブルでも常に寄り添いたい、最愛の相手。クラリネットを引き立てるためにファゴットを吹いていると言っても過言ではありません。
・ホルンはフルオケの中で勇猛なソロも吹けるのに、木管五重奏のメンバーにもなれる。おいしすぎます。次の人生ではホルンを吹きたいと思っています。
・なお弦楽器は弦楽四重奏曲が山ほどあって羨ましいが自分で弾きたいとは思いません。無理。
・ファゴット以外に演奏できるのはピアノ、サックス(後述)。
4)その他
・クラシック以外で好きなのはビートルズ、井上陽水。
・ビールはサッポロ。
5)楽器以外の趣味
・大相撲鑑賞。長らく嘉風関のファンでしたが、引退しちゃったので現在は宝富士推し。
・アニメ鑑賞も好きで、広く浅く色々見ます。最近良作だと思ったのは「映像研には手を出すな!」 *3
<音楽との接点(1)ピアノ>
・小学1年生から高校3年生までピアノを習っていました。先生に言われるがまま常套コース*4をすすみ、全音出版社の青いピアノ譜ばかり弾かされて辟易していましたが、大学入学後は呪縛から解放されて楽しく弾けるように。基本的な読譜力とか調性感、和音を掴む感覚なんかはピアノのお蔭で多少身についたかなと思います。今は娘に邪魔されながら、モンポウの「歌と踊り」 *5を少しずつ練習中。
<音楽との接点(2)バリトンサックス>
・中学入学と同時に吹奏楽部に入部(運動音痴なのでそれ以外の選択肢はなかった)。顧問の先生の「あなたは肺活量が多いから」の言葉に騙されて吹くことになったのがバリトンサックスでした。
・一般的には、サックス族の中では花形とはいえないバリトンサックスですが、実は一度経験すると虜になってしまう最強の楽器です。発音も運指もさほど難しくないうえ、音量が出る、音程が良い、音の立ち上がりも良い。中学吹奏楽部くらいのレベルだと完全に低音セクションを牛耳ることができます。わたしも13歳にして低音の魅力に開眼し、3年間けっこう頑張って吹きました。ちなみに新響のファゴットパートは、4人中3人がサックス経験者です。
・一方で、高校入試の前くらいにテレビCMか何かで偶然ファゴットの音色を知り、なんとなく興味をもちます。
<音楽との接点(3)ファゴット(吹奏楽部)>
・高校入学と同時に引き続き吹奏楽部に入部。気になっていたファゴットが、ちょうど先輩が引退してしまい空きがあるということで、すんなりファゴット担当に決まります。先輩・同期ゼロなので教本を見ながら独学(ファゴットあるある) *6。
・ファゴットはバリトンサックスに比べると音程が悪く、小さい音しか出ず、運指も複雑怪奇(高音域は自分で運指を創作するように、と先輩のメモがあり目を疑う)。楽器の性能としてサックスに激しく劣るという印象を受け、開始早々ファゴットを選択したことを若干後悔します。さらに吹奏楽界におけるファゴットの扱い(マーチの楽譜はほぼ100%「option」。ファゴット譜が存在しない曲も結構ある)も徐々に分かってきて、他の部員が合奏しているのを尻目に狭い準備室で1人「ワイセンボーン」 *7を練習しながらファゴットを選択したことを若干後悔する日々が続きます(実際にはファゴットが大活躍する吹奏楽曲もたくさんあります)。
・しかし高校1年の夏のコンクールでドビュッシーの『海』吹奏楽編曲版を吹くことになり、認識が変わります。吹奏楽曲の譜面とは桁違いの難易度にひっくり返りそうになりますが、合奏してみると、なんとファゴットを活躍させてくれることか。当時オーケストラ曲はほとんど聞いたことがありませんでしたが、ファゴットを続けるならオーケストラに入るしかないと確信します。この頃から『N響アワー』なんかも少しずつ見るようになります(折しも首席ファゴット奏者として水谷上総氏が就任したばかりで、その活躍ぶりに夢中でした)。
<音楽との接点(4)ファゴット(管弦楽団)>
・大学1年生で迷わず管弦楽団に入団。管楽器の1年生はオケの乗り番を与えてもらえず、半年くらいは「必修アンサンブル」をひたすらやらされるのですが、そこでまずは木管アンサンブルの楽しさにハマります。セクションで所有しているアンサンブル譜の蔵書を手当たり次第に吹き、自主コンサートなども企画開催しました*8 。今でも木管アンサンブルは大好きで、自分にとってオケとアンサンブルは音楽活動の両輪です。
・オケ曲の乗り番をもらえるようになってみると、こちらも予想通り大変楽しく、オケ漬けの学生生活に。団でけっこう良いコントラファゴットを所有しており、(積極的に吹く人が居なかったので)ほぼ独占状態でたくさん吹けたのも低音好きの自分にとっては幸せな状況でした *9。
<新響に入ったきっかけ>
・大学オケの木管セクションには代々語り継がれている神話があり、それは「オーボエの大先輩に『シンキョー』という日本で一番上手いアマオケに所属する『神』が居るらしい」というものでした。「新響」という名前はその文脈の中で初めて知りましたが、自分には縁のない天界の話だと思って聞き流していました。
・一方、大学オケには「木管アンサンブルツアー」という年中行事もありました。端的に言えば世代間交流のためのお楽しみ会で、木管セクション+ホルンパートの現役団員から卒業された大先輩方までが(時には家族連れで)那須だの河口湖だのに楽器を持って大集合し、日中はアンサンブルまたは観光、夜は宴会を楽しむという2泊3日の小合宿です。初対面の先輩と一緒に吹いてもらったり、最終日にはその場にいる全員でモーツァルトの『グランパルティータ』を吹いたり、宴会では昔の定期演奏会の話や先輩の武勇伝を聞いたりと大変楽しい会で、わたしも毎年ツアーの開催を心待ちにしていました。
・ある年、アンサンブルツアーの宴会で楽しく飲んでいると、夜中の0時近くになって「オーボエの神が降臨されたから挨拶に来い」と先輩から呼び出しを受けます。そこで初めてお会いしたのが、大学オケの大先輩で新響オーボエ首席の堀内さんでした。これは「神」のオーボエを間近で体感できる千載一遇のチャンス!翌朝、わたしは無謀にも『ルネ王の暖炉』 *10の譜面を握りしめて堀内さんを突撃し、一緒に吹いてほしいと請願しました。これがきっかけで堀内さんに名前を覚えてもらったようですが、肝心のアンサンブルは「神」の音色に聞き惚れていて大したパフォーマンスはできなかったと記憶しています。
・この時は「貴重な体験ができて寿命が延びたわい」くらいに思っていたのですが、意外にも翌年のアンサンブルツアーに「神」堀内さんはまた降臨されました。宴席で、自分が4月からは千葉で市役所勤めすること(当時大学院の修士2年だった)、オケを続けたいがどこに入ろうか悩んでいることなどを話すと、神というよりは菩薩のように穏やかな堀内さんの目の奥が一瞬キラリと光ったようでした。
・ツアー終了後ほどなくして、堀内さんから新響入団のお誘いのメールを頂戴します。お誘い頂いた事自体は夢か現かと思うほど嬉しかったのですが、一方で、これまで競争とは無縁のユルい環境でしか音楽をやってこなかったため、そんなにレベルの高い団でやっていけるのか(やっていくのが楽しいのか)、そもそも入団に際してオーディションを受けねばならないのが嫌すぎて実際はかなり迷いました。しかし現人神からの天啓に背くという選択肢をとる勇気もなく、とりあえず大人しく練習見学に行き、オーディションを受けることに。オーディションは全然うまく吹けた気がしませんでしたが、何の手違いか入団させて頂いてしまいました。熱烈な憧れをもって入団してくる団員も居る中恐縮ですが、わたしの場合は堀内さんにお誘い頂かなければまず新響に入っていなかったと思います。堀内さんとアンサンブルツアーには足を向けて寝られません。
<新響入団後~現在>
・入団後最初のシーズン(第210回)はマーラーの交響曲第7番がメインでした。マーラー初体験だったうえ7番というのは特に変わった曲で、もはや全てが意味不明でしたが、高関先生の指揮で無我夢中のうちに本番を終えた直後「ああ、こんな体験をしてしまったらもうやめられないな」と思った記憶があります。
・とはいえ入団後2年くらいは正直レベルについていけず、tuttiで失敗しては落ち込んでいたのですが、ファゴットパートのメンバーが常に励まして(練習後に必ず飲みに連れて行って)くれたおかげで何とかドロップアウトせずに踏ん張れたようです。オケ中での立ち振る舞いが判ってきて、練習の度に心臓バクバク状態にならなくなってきたのはようやく入団3年目くらいから。前首席の田川さんが、未熟者のわたしにもチャレンジングな乗り番をたくさん充ててくれたお蔭で、経験を積むことができたと思っています。
・田川さんは、30年以上ファゴットパートの首席を務められた大ベテラン。演奏面ではもちろん、パートの皆にも常に細やかに気をまわして下さる(パートで飲みに行くと注文は全部田川さんがしてくれる)頼りがいのある最高の首席だったのですが、数年前から世代交代のご意向を少しずつ伺うようになり、今まで散々お世話になった手前断れないので致し方なく引き継がせて頂いて現在に至ります。
<首席の仕事と自分のパートについて>
・首席は各パートの管理、技術力維持向上に責任をもつ立場です。パートの管理というのが意外と面倒で、毎回の演奏会における楽譜の管理*11、出欠状況の把握と代奏の手配、パート飲み会の設定など、途切れなく仕事があります。さらにここ1年は新型コロナウイルスの影響により、前例のない案件について緊急に判断せねばならない場面が多く、責任の重さを改めて感じているところです。
・技術面では、演奏会のローテーション(誰がどの曲のどのポジションを吹くか)を決めること、会議に出席して練習計画・内容などを審議すること、入団オーディションの審査をすること、などが仕事です。会議は月1回ペースで実施され、首席のメーリングリストでは毎日メールが山ほどやりとりされています。
・演奏会のローテーションは、アマオケにおいては紛争要因になることも少なくない*12のですが、新響は首席が勝手に決めてくれるのでその点が大変良いと入団当初から思っていました。今はその重責が自分にのしかかっているわけですが、あの人がこのパートを吹いたらどんな感じだろう、と色々シミュレーションしてはワクワクするのはなかなか楽しいものです。プロオケだと首席はパートで最も上手い人であり、1stの席にしか座らないと思いますが、少なくとも新響のファゴットパートの場合はわたしが最も上手い人ではありません。もちろん常に技術力向上を目指してはいますが、現在のファゴットパートは名手揃いで、全員1st、2nd、コントラファゴット、何でも吹ける頼もしいメンバー。首席云々はあまり考えずほぼ均等にローテーションをまわすことができる、大変ありがたい状況です。
・メンバーの質には恵まれているものの、現在のファゴットパートは定員6名のところ在籍4名。わたし以外の3名は全員アラカン(アラウンド還暦)のおじさまです。若手新人を迎え入れて、育成・世代交代の準備をすることは急務と考えています。ファゴットという楽器は演奏人口が他の管楽器に比して多くないため、アマオケ界においては売り手市場。新響のように拘束が多く、練習は厳しく、団費も安くないオケに敢えて身を投じなくても、好きな時だけ楽しく吹ける場所がたくさんあり、特にわたし以下の世代ではそういった関わり方を好む人の方が多いのかなという気はしています。それでも新響の演奏に感動して、活動内容に魅力を感じ、積極的に関わっていきたいと思ってくれる人を探して、ぜひ仲間になってほしいと思っています。
<新響の魅力とは>
・新響の魅力は「濃ゆさ」だと思っています。入団後びっくりしたのが、音符のあるところは常にフルスロットルな音がすること。連譜は全て全力、フレーズもお尻まで全部歌い込む。はみ出ちゃいそうだから最後はちょっとすぼめとこう、とか、ここは目立たないからちょっと楽に吹こう、とかいう選択肢がない。結果的に他とズレたり飛び出ることもあるし、よりスマートで整った演奏を目指すならもう少し大人の引き際もあるだろうと思うのですが、音楽的に表現したいことは常に全力でやることによって、新響ならではの密度あるサウンドが出来あがっているのかなと感じます。
・団員そのものが人間的に濃ゆいのも新響の面白いところです。たとえば2010年の211回演奏会では、権代敦彦氏の『ジャペータ』という曲を演奏しました。「ジャペータ」とは、パーリ語で「荼毘(だび)」の語源となった言葉らしいのですが、果たして本当にそうなのか?という論争が団内で巻き起こりました。わたしはたまたま学生時代にサンスクリット語(古代インド語。パーリ語に近い)を履修しており、これはいよいよ自分の出番が来たか…と勿体つけて辞書をひっぱり出してきたところ、その一瞬の間に「東大のインド文学教授の兄に聞いてみた」だとか「外語大のパーリ語専門の同僚に確認したが」なんて報告が次々と上がってきており仰天した覚えがあります。辞書を元の棚にそっとしまいつつ、パーリ語の話題でこれだけ盛り上がって追求できる新響団員の知識、人脈、マニアックな探求心に心底感嘆したものです。
・とはいえわたしの在籍するこの10年の間にも、ザ・新響といった濃ゆさの塊みたいな団員が何人か辞め、全体に高齢化も進み、やりたい事同士がぶつかり合うような勢いが少し弱まってきたようにも感じます。魅力をそのままに、うまく世代交代していけるか。長い歴史を持つ新響ですが、世間の変化のスピードがどんどん速くなる中、ある意味今が過渡期なのかなと感じています。わたしも凡人なりに、常に全力で音楽を楽しみつつ、この60年以上続く素敵な団を盛り上げていければと思っています。維持会の皆さま、どうか今後とも変わらぬご支援の程をよろしくお願いいたします。
*1 市役所内の異動したくない課トップ3の1つ(激務+制度が複雑なため)。わたしは財務担当なので、日々保険税収入と保険医療費支出の不均衡に頭を悩ませています。
*2 最低音域。これぞ木が鳴っているという感じの、ちょっと鼻詰まり気味で太い音がする。
*3 2020年1~3月NHK総合で放送。アニメ制作に青春をかける高校生たちの話。
*4 「バイエル」→「ブルグミュラー」→「ツェルニー」を主軸に「ハノン」「ソナチネアルバム」「ショパンのワルツ集」「バッハのインベンション」等々の教本を併行して進めていくコース。「ツェルニー」の教本は「30番」を終えると「40番」、それを終えると「50番」とだんだん1冊あたりの曲数が増えていき、心が折れそうになる。
:*5 50年以上かけて書き溜められた小品群。モンポウ自身が80歳超えてから弾いた自演録音が最高によい。ちなみに、新響をよく振ってくださる指揮者の湯浅先生の口癖も「音楽は『歌と踊り』です」。
*6 以来ずっと独学で、実はファゴットをきちんと習ったことが一度もありません。未だに間違えている指使いなどが発覚し、新響の他のメンバーに教えてもらうことも。子育てが一段落したらいつかレッスンにつきたいと思っています。
*7 ファゴット奏者が必ず使用する教則本。1巻、2巻とあり、2巻の曲は芸大の入試でも吹かされます。
*8 ダンツィの木管五重奏曲(有名なのは「B-Dur」「g-moll」の2曲だが、実は全部で9曲ある)全曲公開録音演奏会などというマニアックなのもやりましたが、お客さんは4人しか入りませんでした。
*9 団のコントラファゴットを勝手に持ち出しては、方々のオケでエキストラを請け負って荒稼ぎしていました(もちろん団規違反にあたる)。
*10 ミヨー作の木管五重奏曲。7曲からなる組曲で、1曲目冒頭のオーボエのメロディが、暖かいようなアンニュイなような独特の魅力がある。このメロディを素敵に吹けるオーボエ吹きはうまいというのが持論です。
*11 シーズン前に配り、シーズン後に回収するだけなのですが、これがなかなか揃わなくてライブラリアンに怒られます。何故譜面というのは散逸しやすいのか。
*12 吹きたい曲(パート)が重複した場合、技術力の劣る先輩が年功序列を持ち出してきた場合、大きなソロがある場合などに揉めることが多く、吹く前から精神力が擦り減ります。
第253回演奏会のご案内
自然を愛した作曲家ドヴォルザーク
今回のコンサートでは、チェコの大作曲家ドヴォルザークの演奏会用序曲を取り上げます。元々序曲とは劇音楽のオープニングに演奏され、劇全体のあらすじや雰囲気が伝わるように作られたものですが、それが劇用でなくそれ自体で完結するものが演奏会用序曲で、多くは物語性や詩的情緒があります。
国際的に評価されるようになったドヴォルザークは、念願だった田舎の別荘をプラハ近郊のヴィソカーに持ち、自然に親しみ村の人々と交流をしました。そこで作曲されたのが序曲三部作『自然と人生と愛』です。本来3曲連続で演奏することを意図して書かれましたが、「謝肉祭」は比較的演奏されることが多いものの、まとめて演奏される機会はあまりありません。
人生にあたるのが活気あふれる人々の生活が表現された序曲「謝肉祭」、愛にあたるのが感情の紆余曲折が表現された序曲「オセロ」で、どちらにも序曲「自然の中で」のテーマが用いられています。この作品が後の一連の交響詩(新響は2019年10月に演奏)の作曲につながっていきました。
後期ロマン派最後のシンフォニスト、フランツ・シュミット
ドヴォルザークの時代、チェコはオーストリア=ハンガリー帝国の支配下にありました。その首都ウィーンでは、新ウィーン楽派と呼ばれる調性のない前衛的なスタイルが台頭する一方、シェーンベルクと同じ歳のフランツ・シュミットは、後期ロマン派のスタイルを守った作曲家でした。
シュミットは、マーラーが音楽監督をしていた時のウィーン宮廷歌劇場のチェロ奏者、ピアノの名手でもあり、ウィーン音楽アカデミーの院長まで務めました。作曲家としては4つの交響曲やオペラなどを残し、それらはブルックナーやブラームスといった偉大な先人の伝統を引き継ぎつつ、モダンで独創的な作風となっています。
ウィーンゆかりの作曲家であるシューベルト没後100年の作曲コンクールに応募するために書かれたのが交響曲第3番です。巨大編成で厚い響きの作品が多いシュミットですが、この曲はシューベルトを意識してか、編成が小さく穏やかで、オルガン的な響きのする美しい曲です。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
スメタナ:連作交響曲「わが祖国」
■チェコという国
「中欧」とよばれる地域のど真ん中に位置するのがチェコ共和国である。南のオーストリアから時計回りで、ドイツ、ポーランド、スロバキアの4国に囲まれ、スロバキアのすぐ南はハンガリーである。首都プラハは、ベルリンとウィーンのほぼ中点でもある。こうやって見ると、周囲の国々はそれぞれ独自の音楽文化に溢れており、チェコの音楽はその点からも極めて興味深い。日本やイギリスなどの島国とは異なる政治・宗教・文化の歴史がある。プラハを中心としたボヘミア、ブルノを中心としたモラヴィア、さらにポーランド国境近くのシレジアの3つの地方がチェコ共和国を形成している。筆者がこの国を初めて知ったのは、チェコスロバキア時代の1964年、東京オリンピックの女子体操で3個の金メダルを獲ったチャスラフスカからであろうか。1993年にチェコとスロバキアに分離した。チェコは、ビールの国民一人当たり消費量が、ダントツで25年連続世界一でもある。プラハの市街や自然はこの上なく美しく、中欧の真珠とも言われている。
長い歴史の中で、チェコがある地域は多くの大国に支配されてきた。15世紀にはヤン・フスが教会改革を実施、教会の世俗権力を否定し、ドイツ人を追放したため、フスとプラハ市はカトリック教会から破門された。さらにコンスタンツ公会議でフスが「異端」とみなされ火あぶりにされると、ボヘミアでは大規模な反乱が起きた(フス戦争)。 その後、ハンガリー王国、ポーランド王国の支配を受け、16世紀前半にはハプスブルク家の支配を受けることになった。チェコ人は政治、宗教面で抑圧されたため、1618年のボヘミアの反乱をきっかけに三十年戦争が勃発した。ボヘミアのプロテスタント貴族は解体され、農民は農奴となり、完全な属領に転落した。これらが、本日のプログラムの背景にある。
■スメタナ
スメタナ(Bedřich Smetana、1824年3月2日-1884年5月12日)はフランクやヨハン・シュトラウス2世とほぼ同年代で、10歳前後の先輩には、メンデルスゾーン、シューマン、リスト、ヴァーグナー、ヴェルディがいる。同じチェコのドヴォルザークは後輩であり、スメタナから直接指導を受けていた。音楽的には、何とも贅沢で華々しい時代であったであろう。ヴァイオリンの神童、ピアニストとして才能を発揮し、6歳の時には既にピアノ公演も経験した。チェコは当時オーストリア帝国の支配下、1848 年に起きたプラハ革命運動に参加し民族主義的な楽曲を書いたが、政治情勢に失望した。スウェーデンのヨーテボリに移り、音楽教師、聖歌隊指揮者として著名になった。この頃から規模の大きいオーケストラ音楽の作曲を開始している。同時に、異国での滞在により民族的な自覚が高まった。実はチェコ語が堪能になったのは成人してから。当時スメタナの生まれ育ったボヘミア北部では、ハプスブルク家の制度により公用語はドイツ語だった。チェコ語を習得すると決めてからは毎日勉強を怠らなかったという。祖国で音楽家として進むことを決意してプラハに戻り、チェコオペラという新たなジャンルの最も優れた作曲家となった。1866年に、スメタナ初のオペラ作品「ボヘミアのブランデンブルク人」と「売られた花嫁」が、プラハの仮劇場で初演され大きな人気を得る。同年には、同劇場の指揮者に就任した。「わが祖国」は大きな反響を呼び、スメタナは「チェコ音楽の祖」と呼ばれるようになり、現在に至っている。しかし耳の病に冒されていたスメタナは、初演をもはや聴くことは出来なかった。スメタナは、「わが祖国」をプラハの街に捧げている。
■連作交響詩「わが祖国」 Má Vlast (My homeland)
祖国であるチェコの歴史、伝説、風景を描写した作品である。6曲から成る連作交響詩は、2曲ずつ組で仕上げられ、奇数番目の曲(ヴィシェフラド、シャールカ、ターボル)は、歴史的あるいは回顧的な動機を用い、偶数番目の曲(ヴルタヴァ、ボヘミアの森と草原から、ブラニーク)は生きた現在の鼓動あるいは未来をあらわそうと意図されている。これによって、人民と国土が離れがたく結ばれていることを示したのであるが、今までにこのようなやり方で自分の祖国を音楽的に描いた者がなかったことを彼は意識していた。そしてこのようなとらえ方が、当時のチェコの社会の代表的な人々の考え方とは相いれないが人民には受け入れられるものだと考えていたので、そのために彼はこの作品の題名を単に祖国としないで、わが祖国=自分のとらえ方による祖国、としたのだと説く者もある。そしてスメタナが尊敬していたシューマンのやり方をまねて、この作品の曲頭にあらわれる旋律線に、自分の名-姓の頭文字であるB-S(Es)、つまり変ロ-変ホを入れているのも面白い。
1946年以来行われている「プラハの春」音楽祭は、毎年5月12日にスメタナの命日を記念して、「わが祖国」全曲の演奏で幕を開け3週間程開催される。1990年のクーベリック/チェコ・フィルなどは、他の如何なる世界のメジャーオーケストラも寄せ付けないほど激しく、美しく、魂の演奏となっている。本日の飯守/新響も少しでも近づける演奏をしたい。2020年は、COVID-19感染防止のため、「プラハの春」音楽祭は中止となった。わが祖国への想いのエネルギーが蓄積し、つぎに開催されるときが楽しみである。
1.ヴィシェフラド(高い城) Vyšehrad 変ホ長調 1874年11月18日作曲
ヴィシェフラド(古城の名前、地名)には、ヴルタヴァ河畔にそそり立つ岩上の城砦があり、チェコの王たちの居城だった。伝説の女帝リブシェが城を構えていたと言われ、神話の中の予言が表現されている。吟遊詩人ルミールがハープをかき鳴らし玉座の前で英雄の武勲や愛の歌を歌うさまを思い浮かべる。これはヴィシェフラドの動機であり,「わが祖国」全体を通じての重要な動機である。
栄光と名誉、戦闘が語られ、さらに没落と廃墟が描かれる。戦いの中にそびえ立つ塔は崩れ落ち、玉座は滅ぼされ、城は灰じんに帰する。その廃墟から昔の歌のこだまが響いてきて、全体は悲歌の調子の中に消えていく。
なお、ヴィシェフラドにはスメタナ、ドヴォルジャークなどの墓がある。
2.ヴルタヴァ(モルダウ) Vltava (The Moldau) ホ短調 1874年12月8日作曲
ヴルタヴァは、南ボヘミアから流れ出て北に向かって国を通り抜けエルベ川と合流する川で、ボヘミアのすべての水脈がこれに注ぎ込む。冷たい水源(フルート)と暖かい水源(クラリネット)から流れ出し、岩を洗う清く澄んだ渓流が水しぶきをあげ(ヴァイオリンのピツィカート)、その後せせらぎながら一つの流れに合する。林や草原を抜け、村人たちの楽しい祭りの場を過ぎていく。夜になると月光に照らされ水の精たちが踊る。岩に狭められ、谷を通って聖ヨハネの早瀬に突進する。それからプラハに向かって広々とした流れとなり荘厳に進む。ヴィシェフラドの岩を洗う。そしてざわめきながら永遠の流れは、見渡しがたい彼方に流れ去る。
スコアには作曲家の書き込みがある。ヴルタヴァの第一の源、第二の源、森の狩、農民の婚礼、月光・水の精の輪舞、聖ヨハネの急流、いっそう幅広くヴルタヴァは流れる、ヴィシェフラドの動機。これらを思い浮かべながら聴くと、その情景がはっきりと見えてくる。世界中で広く愛されているこの曲のスコアの終りには、痛々しくも「全くの聾になって」と書き添えられていた。なお、旧来「モルダウ」として親しまれた曲名だがこれはドイツ語であり、現在は学校の教科書でも「ヴルタヴァ」である。
3.シャールカ Šárka イ短調 1875年2月20日作曲
シャールカはプラハの北方にある谷の名で、ここに伝わる少女シャールカの物語、伝説の女王リブシェの時代のアマゾーネの幻想的な物語である。弓を引くのに邪魔な乳房を切り取ったということから、ア(無し)+マゾン(乳房)と名付けられた種族の伝説アマゾンはチェコにも存在する。恋人に裏切られた少女シャールカが、怒りに燃えて全男性に復讐を誓う。遠方からツティラートとその戦士たちが、思い上がった女たちを懲らしめるためにやってくるのが聞こえる。シャールカは計略を考え、わざと木に縛り付けられて苦しんでいるように見せかける。美しい少女の姿を見たツティラートは恋に落ち、彼女を解き放つ。彼女は用意しておいた酒で宴の席を設け、民族色豊かな舞曲が次第に盛り上がりドンチャン騒ぎ、ツティラートと戦士を眠らせてしまう。シャールカの吹くホルンの音を合図に、女軍は復讐の機が来たのを知る。荒々しく襲いかかる女たちの手にかかって眠っていた戦士たちは倒れ、最後にシャールカの剣でツティラートも死ぬ。シャールカの動機は、復讐心に燃える女性らしいものをよく表し、ツティラートとその戦士たちの行進曲と巧みな対照をなしている。愛の場面、酒宴の描写、酔った人たちが眠りに落ちて、2番ファゴットが低いハ音でいびきを聞かせるところへ、少女の復讐のホルンが鳴り響くと次第に狂乱的になり,クライマックスを築く。アマゾン軍が勝利を収め、最後に低音楽器でツティラートの動機の変形が浮かび上がる。
4.ボヘミアの森と草原から Z českých luhů a hájů (From Bohemia's woods and fields) ト短調 1875年10月18日作曲
田園的な音画である。この曲では古典主義に戻り、弦楽器と木管楽器で深いものを表現している。ボヘミアの国中が、森も草原も村も、伝説やおとぎ話をもった山も、偉大な過去と、それから未来を歌う。曲の注釈によると、ボヘミアの景色を眺めたときに呼び起こされるすべての感情が音で表わされている。森や草原のあらゆる側から、あるときは楽しく、あるときは深いメランコリーをこめて歌が聞こえてくる。人目につかない森の陰(ホルン独奏)、エルベの谷にある草原も、みんな歌われている。
美しい夏の日を思わせるこの曲は、力強いト短調の和音で始まる。甘美なクラリネットの旋律は朗らかな長調に変わる。弦楽器で奏される五声のフガートは、夏の午後、頭上に太陽をいただく田園の喜びである。2小節ずつ挿入され、その後に全貌をあらわすポルカの動機は、収穫の祭あるいは農民の祭をあらわす。激しいプレストに高まって終わるこのチェコ民族の賛歌は、スメタナの曲の中でも、最も牧歌的な音楽である。
5.ターボル Tábor ニ短調 1878年12月13日作曲
フス戦争の戦士を讃える曲である。ターボルは南ボヘミアにある町で、フス教徒の運動の拠点になった地名として有名である。フス教徒の中でも過激派のヤン・ジーシカを中心とする一派がこの町に立てこもり、ターボル派と呼ばれて激しい抗争を続けたため、チェコ人にとっては、常に革命を思い起こさせる地である。この曲のモットーとなっているフス派の有名な讃美歌《なんじら神の戦士》に基づく「タ、タ、ター、ター」は、ティンパニと低弦のざわめきの上にホルンが信号風に表れ、弦の総奏を中心とした旋律(譜例2)などに変化しながら、曲全体を通してしつこく数多く意義深く使われている。
そこには、確固たる意志、勝利への戦い、不撓不屈の魂が歌われている。フス派の讃美歌が動機的に分解して使われ、完全な形ではレント・マエストーゾになったところで光輝と栄光をもって現れる。金管が旋律と和声を運んでいき、まるで堅い花崗岩の上で刀が振り上げられたように響く。その他の点では、この曲は細部にわたる標題はなく、全体としてフス戦争とフス教徒の不屈の精神とを讃えている。
6.ブラニーク Blaník ニ短調 1879年3月9日作曲
前曲ターボルから続けて演奏され、ついに勝利の動機が決定的に奏される圧倒的な感覚がある。ブラニークは中部ボヘミアと南ボヘミアの境にある山で、深い森に覆われている。15世紀の終り頃から、この山には国が最大の困難に直面したときに救いに現れるはずの騎士たちが眠っているとの伝説があり、1848年の革命の前、民族運動の盛り上がった時代には重要な意義をもって広まっていった。スメタナは、若いころこの地方に住んでいたことがある。ブラニークの騎士たちの指導者は聖ヴァーツラフなのであるが、スメタナは、聖ヴァーツラフの讃美歌の代わりにフス派の讃美歌を取り入れ、この伝説を本質的に変えてしまった。ターボルと同じく、《なんじら神の戦士》が曲の構成の基礎におかれている。この讃美歌の旋律を基礎として、チェコ民族の覚醒と幸福、繁栄へと進んでいく。行進曲形式による自由の思想の勝利を高らかに歌うこの曲の終りに、ヴィシェフラドの動機が織り込まれている。こうして伝説と歴史とのつながりが象徴化され、全6曲をまとめ上げて力強く終わる。
先に述べた「プラハの春」音楽祭の最後に演奏されるのは、同じニ短調のベートーヴェン第九である。聴覚が失われる中で、かえって作曲への情熱が高まるという状況はベートーヴェンに通ずるものがある。
新響は、24年ぶりに全曲を演奏する。前回は、1997年小林研一郎氏指揮、本日の演奏者の約半数が経験者で、他半数の団員は新響では初めてとなる。新たにわが祖国、わが日本を想い演奏したい。
初演 :全6曲の初演:1882年11月5日 アドルフ・チェヒ指揮
曲毎では、1.1875年3月14日、2.1875年4 月4日、3.1877年3月17日、4.1876年12月10日、5.および6.1880年1月4日
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トライアングル、大太鼓、シンバル、ハープ2、弦五部
参考文献:
渡 鏡子『スメタナ/ドヴォルジャーク』音楽之友社 1970 年
金子建志『スメタナ 連作交響詩《我が祖国》の楽曲解説』
(千葉フィルハーモニー管弦楽団HPより)
https://www.chibaphil.jp/archive/program-document/mavlast-commentary
スコア Bedřich Smetana “Má Vlast” Edition Supraphon 1987
新交響楽団第156回演奏会プログラム 1997年1月25日
新響・昔話1=傘寿を過ぎたOBの独り言=
編集人注
今号より、1966年に新響が労音からの独立した当時から団の運営に携わって来られたOBの戸田昌廣の執筆による「新響・昔話」を連載致します。どうぞご期待ください。
【日本のうたごえ祭典】
今から60年程前、1960年頃のはなしです。その頃東京では’60年安保闘争(日米安保条約改定反対)のデモが盛んで、連日国会周辺ではデモ隊で賑わっておりました。私は国鉄(現・JR)に勤めていて20代の前半でしたので、労働組合の青年部員として恰好のデモ要員でした。
10日に1回位デモへの順番が回ってきたと思いますが、勤めが終わってから大きな労組の旗を以って日比谷の野外音楽堂での集会に参加し、その後国会周辺へのデモ行進で盛り上がって新橋・銀座とどなりながら(シュプレヒコール)歩き、数寄屋橋で流れ解散、と言うことをやっておりました。
そんな世相の’60年の1月に私は新響に入団しました。その何年か前から労音(勤労者の音楽鑑賞組織)の会員になっていて、月1回の例会(音楽会)に行きクラシック音楽に親しんでおりました。
東京労音には会員による自主サークルとしてオーケストラがある事は知っていましたが、職場にジャズ・バンドがありそれに熱を入れて腕を磨いていたわけです。
オケに入ったものの、楽器はトロンボーンなのでまるっきり出番が無く、ダラダラとしていたように思います。
ところがその年の12月に新響が千駄ヶ谷の東京都体育館(現・東京体育館)で行われた「日本のうたごえ祭典」への出演に加わってビックリ仰天!それからオケに嵌まることになってしまったのです。うたごえ運動についてはよく知らなかったのですが、その以前より若者を中心に全国的に活動していて、私の職場にも時々アコーディオンを持った運動員が来て、少人数のグループでロシア民謡等を唄っているのを横目でみていたような気がします。
都体育館で行われた「日本のうたごえ祭典」はうたごえ運動の全国大会で、日本各地区から選ばれた代表グループが一堂に集まって交流する・・・・という音楽会で、最後に新響の出番となりアンコールでうたごえ運動のテーマソング「祖国の山河」**①を作曲者自身の指揮による大合唱で終わるというプログラムでした。
とにかく会場に居る全員が出演者で、観客や聴衆は誰もいないわけですから全員合唱はすごい音の洪水で、今になってもあの時のショックは忘れられません。指揮者はオケに背を向け会場全体を相手にし、大して大きくなかった新響はセンプレ・フォルテッシモで悲鳴をあげながら終わる、という行事でした。
記録によると、この「祭典」への出演は’59年~’64年迄あったとありますが、’65年から労音との組織問題が起こり“うたごえ運動”との縁は途切れてしまったわけです。
**①(備考)
合唱曲「祖国の山河」は、1953年の第1回
“日本のうたごえ祭典”のために創られた平和組曲「日本のうたごえ」の終曲で、作詞:紺谷 邦子 作曲:芥川 也寸志 です。
(追記)
この次は、中・ソ間のケンカが巡り巡って私たちの趣味の世界にまで押し寄せて来て面食らった、労音問題に触れてみたいと思います。
「東欧」から来たあの男
「東欧」という言い方はやめてくれ、と彼は私に言った。「チェコは中央ヨーロッパの国だ」
私は1990年代前半に2年間、パリのとある研究所で仕事をしていた。着任後間もない時期、右も左もわからない私の世話をしてくれたのが、同じ研究室にいたチェコ人の男である。名をPといった。**①
研究室は、チェコ人のPの他に、ルクセンブルク人、ドイツ人、ロシア国籍のタタール人、ルーマニア人、日本国籍なのだがフランスで生まれ育ったため日本語がおぼつかない日本人、そして何人かのフランス人で構成されていた。研究室のボスはトランシルヴァニア地方(ルーマニアとハンガリーの国境地帯)出身のユダヤ人女性。国籍が6回も変わったと言っていた。ヨーロッパの現代史に翻弄された人と言っても過言ではない。冷戦下のハンガリーからフランスに亡命してきた彼女には、映画が何本も作れるようなストーリーがあるのだが、またの機会に譲る。彼女は昨年惜しくも92歳で他界した。「野獣」とさえ呼ばれた気性の激しい人、と皆は言うが、私にはとても優しくしてくれた。
研究室のメンバーは皆フランス語を話すのだが、当時の私は話せない(今もそうだが)。私に対してはとりあえず英語で話してくれるのだが、彼ら同士で話し始めるとフランス語になってしまうので、私には理解できない。「聞かれたくないことは、その人が理解できない言葉で話すんだよ」ということを知ったのはずいぶん後のことである。私は時として差別の対象となりうるマイノリティだったのだ。
マイノリティはもちろん私だけではなかった。当時は、多様であることが重要な人権問題として今のように認識されていたわけではない。しかし該当する人々はその当時からもちろん普通にいた。研究室メンバーの中にもレズビアンの女性が1人とゲイの男性が1人いた。心優しい彼らは、異文化の地から来た私のつらい気持ちを親身になって理解しようとしてくれた。私が20年以上経った今でも「友」と感じることができるのはこの二人と、そしてPの三人だった。
Pを含む多くの研究室メンバーは、この二人について時々心ない陰口を叩いたりもしていた。その一方で、みんなで連れ立って食堂で昼食をとり、そのあとは近所のカフェに行くのが毎日の習慣でもあった。研究室で飲んで語り合ったり誰かの家でパーティをやったり、仲良くしているのだが、同時に、「その場にいないと何を言われているかわからない。でもそんなの当たり前」であった。個人主義(良い意味で、である。念のため)の心の強さを感じる。**②
ヨーロッパの人はプライバシーに踏み込んだり踏み込まれたりするのを嫌がる、とよく言われる。しかし私の印象ではちょっと違う感じがする。私の周囲にいた人たちは、平気でお互いに踏み込みあっていた。ただ日本と異なるように思えるのは、「ここまではいいけどここから先はだめ」をはっきり(微笑みながら、である)表現しているのでわかりやすい、というところだろうか。
さて、本稿の主題のPである。今でも二年ごとに小さな研究集会で彼と会っているので、三人のうちで私にとって最も近い存在は彼だと言えるだろう。
彼は6カ国語を話す。チェコ語、スロヴァキア語(彼はスロヴァキア出身である)、ロシア語(当然。チェコスロヴァキアは共産圏だった)、ドイツ語(徹底的なトレーニングを受けたと彼は言っていた)、英語(話せるのは当たり前らしい)、そしてフランス語である。ロシア人に向かって、ロシア語の単語(「カニエシュナ」と私には聞こえた)の使い方について彼が説教していたのには笑ったが、言語能力だけではなく知識と教養、そしてもちろん研究の能力も彼は飛び抜けて高かった。★①
しかし90年代前半の、ベルリンの壁崩壊から3年ぐらいしか経っていない当時、彼は、西ヨーロッパ人から見れば「旧東側(の遅れた地域)から来た者」であった。つまり彼にとっては「東欧」という語はとりもなおさず「旧東側」という「差別」を意味していたのである。彼もまたマイノリティだった。
壁崩壊前、チェコスロヴァキア(チェコとスロヴァキアはひとつの国だった)の極めて優秀な研究者だった彼は、当時としてはおそらく例外的に西側スイスへの留学を許された。初めて鉄道で西側への国境を越えた時に驚愕したと彼は私に言った。
「乗ってる人たちが笑ってるんだよ」
列車の中で人が笑って話をしている。これはそれまでの生活で彼が目にしたことがない光景だったそうである。
「俺はそのとき、自分が汚いものに思えて、車内のトイレに行って体を洗ったんだ」
私はそれを聞いて涙が溢れてきたのを覚えている。周りでその話を聞いていた西ヨーロッパ人の同僚たちは「そんなわけねーだろ」と半ば嘲笑するような表情を浮かべていたが、私は彼の話を信じた。彼が私を「親友」と他人に紹介するようになったのは(そのたびに何となく照れ臭いのだが)その時以来かもしれない。
彼は、極めて優秀な人にありがちな、ちょっと尖ったところのある性格でもあったが、私は全く気にしなかった。使う言語が私にとって不自由な外国語だったせいもあっただろう。ニュアンスまでを簡単に感じたり伝えたりすることができないのは気楽なものである。でも伝えたい気持ちがなぜか伝わることもある。不思議なものだ。
彼はおよそあらゆる種類の文化に造詣が深かった。10代前半のころ、プラハの建築の歴史についての小論文コンクールで賞を取ったことがあるらしい。彼と街を歩くと面白い。「プラハの古い建築物には増築に増築を重ねているものが結構あるんだ。そうするとひとつの建築物にいくつものスタイルが共存するようになるんだ。面白いだろう?例えばこの建物はこっち側はゴシック様式だがこっち側はルネサンス様式だ。それはどういうわけかというと~」のように、さながら『ブラタモリ』である。
彼がパリからプラハの研究所に戻り、私も日本に帰国したあと、日本-チェコの短期研究者交換プログラムを獲得して彼が来日したことがある(私もプラハを訪ねた)。彼を東大寺の大仏殿に連れて行った時のことが忘れられない。大仏殿の建物の中に入った瞬間、彼は凍りついたように立ちつくし、そのまま5分間ほども微動だにせず、圧倒されたように高い天井に見入っていた。
「この建築物がここで作られたその時代、俺たちが作っていたのは石の小屋に毛が生えたようなものだったんだぜ」**③
もちろんヨーロッパでも、立派な石造建築物が作られていたのだが、率直に感動している彼の、初めて目にするものに対するこの敬意に、私は心を打たれた。
東京の私たちの研究所の近くの住宅街の、何の変哲もない街並みに彼は「なんでこんな素晴らしいところを教えてくれなかったんだ」と感動していたのも印象深かった。彼は私などの全く気付かないところに美を見出すようだった。
余談だが、彼が私の家に来た時に、トイレから文字通り飛び出してきたことがあった。「この電子トイレは一体何だ?????」ウォシュレットのことである。私「電気で動くんだよ」、彼「違う。電気じゃない。電子トイレだ」。今となっては懐かしいエピソードである。
ところで、チェコはピルスナービールの本場である。当然、彼は日本のビールに興味津々であった。あれこれ飲み比べたあとの彼の結論は、七福神のマークを指差して「これがダントツ」であった。彼の舌には、他との差が歴然だったそうだ。
彼は優れた歌い手でもあった。彼はもちろん私がオーケストラでオーボエを吹くことを知っていたのだが、来日した時に彼が「これがチェコの音楽だ」と言ってわざわざ持ってきてくれたのは、スメタナでもドヴォルザークでもなく、ヤナーチェクのグラゴールミサのCDだった。難解ともいえるとっつきにくい曲で、私は最初、このCDを聴き通すことができなかったほどである。
彼に、ドヴォルザークについてどう思うか聞いてみた。「優れた芸術家だ」という答えであった。
ではスメタナは?と聞いてみた。「ボヘミアのフォークソングだよ」というのが彼の答えであった。モーツァルトを「BGMだ」と言い切ってしまう彼らしい、なんとなく皮肉を含んだ答えだな、とも思ったが、フォークソングとは民謡のことで、言われてみれば国民楽派というのはそこに根ざしたものだな、そこに目を向けないと本質を見失ってしまうのかも、と20年近く前の会話を今あらためてかみしめている。
彼はその後、所属する研究所の所長になったはずなのだが、その後どうしているかと尋ねたところ、「面倒だから所長は辞めて研究室のボスに戻った」とのこと。所長になったら忙しくて研究ができなくなったらしい。彼にはそれが我慢できなかったのだろう。
ごく最近、彼が交通事故にあったという知らせを受けた。命に別状はないということでほっとしながらもやはり心配で、「返信いらない。とにかく良くなることを願っている」というメールを出したところ、「自転車で時速40キロで走っていたら避けきれずトラックとぶつかった。でも肩を脱臼しただけだから、入院して手術するけど大丈夫」という返事。私は冗談交じりに「どうせ3日後には研究室にもどってるんだろ?」と返信した。3日後メールが来た。「研究室にいる」。頑丈なものである。**④
【脚注】
**①チェコ人でPといったらPavelだろうと思ったそこのあなた、違います。ふふ。
**②パリの人はよそよそしい、ということになっているが私は今ひとつ納得できない。少なくとも「見ず知らずの赤の他人」に対しては東京よりずっと親切だと感じる。あえて言えば、誰もが心のどこかで、自分は何らかの意味でマイノリティであるという意識を持っているようにも思う。まあそんな綺麗事で済まされるわけでもないのだが。
**③大仏殿は、西暦700年代に創建されたが、当初の建物は焼け落ちてしまったそうである。しかしその後何回か再建され、現在建っている大仏殿は創建から1000年近く後に建てられたものである。ただ、創建時は現在よりさらに大きかったとのこと。
**④日本の私たちの研究室に来ていた学生さんがある朝、「遅れてすみません。自転車で軽トラとぶつかって、僕は全然大丈夫だったんですけどトラックがへこんじゃって」と言いながら来たことがあった。頑丈な人は一定の頻度で世界中にいるらしい。
★①(編集人=ロシア語単位修得者=注)
“конечно”・・・通常は「カニェーシュナ」の表記か?「もちろん」「確かに」といった意味。
“Вы любите музыку?“”конечно”(音楽はお好きですか?/もちろん)の例文が岩波書店版露和辞典のこの語の項にある。
第252回演奏会のご案内
チェコの国民的作曲家スメタナ
今回のコンサートでは、チェコ国民音楽の祖として知られるスメタナの代表作、連作交響詩『わが祖国』を演奏します。中欧に位置するチェコの首都プラハは、歴史的な建物が残る美しい街並みで、多くのホールを有する音楽の都でもあります。毎年「プラハの春音楽祭」が開催され、オープニングはスメタナの命日である5月12日に『わが祖国』全曲が演奏されます。この音楽祭が始まったのは1946年、ドイツから解放され明るい希望に満ちた春を迎えた時です。長年自由と独立を求めてきたチェコの人々にとって『わが祖国』は大切な曲なのでしょう。
スメタナ(1824-1884)は幼少期よりピアノとヴァイオリンに親しみ、その後プラハで学びピアニストとして活動を始めます。チェコは当時オーストリア帝国の支配下にありましたが、1848年に起きたプラハ革命運動に参加し、愛国的な作品を書きました。ピアニストとして高く評価されず政治情勢にも失望し、スウェーデンのヨーテボリに移りピアニスト、指揮者として成功しますが、異国での滞在により民族的な自覚が高まったスメタナは、祖国で音楽家として進むことを決意してプラハに戻り、その後、チェコ国民オペラを上演する仮劇場(国立劇場完成までの仮劇場)の首席指揮者に就任、チェコの農村風景を描いた『売られた花嫁』など8つのオペラを作曲しました。
チェコの伝説、歴史、自然をテーマにした『わが祖国』
「ヴェシェフラド」は高い城という意味ですが、プラハの丘の城跡でチェコ人にとって歴史的シンボルです。かつて伝説の女帝リブシェが城を構えていたと言われ、神話の中の予言が表現されています。「ヴルタヴァ」はモルダウとして有名な曲です。ヴァルタヴァ川はチェコ最長の川で、プラハ市街地を流れます。「シャールカ」はリブシェ亡き後に起こったとされる乙女戦争の伝説の物語。「ボヘミアの森と草原から」はチェコの田舎の美しい風景と人々の暮らしが表現されています。「ターボル」と「ブラニーク」は15世紀に起きたフス戦争(チェコの宗教改革派とカトリックとの戦争)の戦士を讃える曲です。
スメタナは晩年聴力を失い、『わが祖国』は失望と苦悩の中で作曲されました。チェコ音楽確立を目指し、単に民謡の引用でなく近代西洋音楽の手法で自国の文学や歴史を表現するという信念があったのでしょう。その音楽は今も私たちの心に響きます。どうぞお楽しみに!(H.O.)
新響の新型コロナウィルス感染症対策について
新型コロナウィルス感染症の流行に伴い、世の中全体が大きな影響を受けはじめて半年余りが経ちました。厳しい状況や立場に置かれている皆様には、この場をお借りしてお見舞い申し上げます。
新響は3月の連休の翌週より活動の自粛に入りました。予定していた2回の演奏会と、多くの練習の機会が失われました。新響の50年以上の歴史の中で、かつてこれほどのダメージを受けたことはないと思われます。それは私たちだけのことではなく、世界のいたるところで同じ様な前代未聞、史上初が起きているわけではありますが、新響にとっても大変な痛手です。
その後、感染症の状況、社会の状況は刻々と変化し、様々な活動が試行錯誤をしながら再開したり、形を変えての活動を試みています。新響も対策を講じたうえで、10/18の演奏会に向けて活動を再開しました。本稿ではここに至る経緯と「対策」の部分について、あくまで私からの目線でということにはなりますが、お話させていただこうと思います。
まず私事について少々ご紹介いたします。私の本業は医師で、病院に勤務し主に入院患者さんの治療に当たっています。現在、医療職でコロナのことと無関係でいられる人はほぼいないと思われます。私の職場では直接コロナ患者さんの治療を行っているわけではありませんが、それでもこの数か月の間に様々な状況に直面してきました。流行の波は今後も大小様々な形で訪れる可能性があると思われますが、病院は感染症の発生リスクが高い場所であると同時に、クラスターが発生すると甚大な被害が生じることが自明です。これに備え、現在私は新響を一時休団し、入院患者さんやスタッフを守るための対策に日々取り組んでおります。
こうした対策を行い始めた流行初期の今年2月頃、世間では主にダイアモンドプリンセス号のことが話題になっていた当時、今後は市中感染が発生し、世の中全体が影響を受けるようになることは時間の問題と思われていました。その頃私が見ていた資料の一つに、約100年前のスペイン風邪のものがありました。当時の人類にとっての「新型」インフルエンザによるパンデミック(世界的大流行)だったわけですが、現在の新型コロナウィルス感染症の流行と類似している点が多々ありました。その資料の中で見たグラフで、流行に伴う死者数が1年強の間に3回にわたって上下する、つまり1年強の間に3回の流行の波があったことが記録されたものに目が留まりました。それを見て、今度の新型コロナウィルスも似たような経過をたどるであろうことを私なりに直感しました。新しい未知の病気ですから、実際のところ今後どうなっていくのかは誰にもわからないことですが、長期的な問題になるであろうという予想は、現在現実世界において裏打ちされつつあるように思います。
感染が拡大傾向を示す度に、世の中では「不要不急の外出の自粛」や「三密を避ける」といった呼びかけがなされました。この「不要不急」という言葉は、言わんとすることはわかるものの定義は曖昧で、私はあまり好きではありませんが、言わんとすることを汲み取ると、趣味の範疇である新響の活動は残念ながらこの「不要不急」に含まれるのだろうと思います。また、オーケストラ活動は「三密」そのものです。中止となった新響の活動をいつどのように再開すればよいのかは、とても難しい問題でした。これについて相談するための団内の会議が、6~7月にかけてオンラインで行われました。
仮に新響が活動を再開することになっても、私個人は前述のような状況の中で近々の活動への参加は難しいと考えておりました。事情は違っても同様な立場の方がある程度いらっしゃるのではと想像しておりましたが、実際に会議の場でもそのような意見がいくつか披露されたほか、活動再開に対して慎重な意見がありました。一方、当時は緊急事態宣言が解除されて間もなくで、感染拡大の状況もやや落ち着いていたこともあり、この機会に活動を再開しないと今後再開できるタイミングを失い、新響自体の存続にかかわるといった切実な意見も多く出されました。正解の無い難問に対して皆で一様に頭を悩ませましたが、結果的に感染対策を講じたうえで活動を再開するという結論になりました。
新型コロナウィルス感染症は人類にとって文字通り新規で未知の感染症であり、適切な感染対策が何なのかについて、まだはっきりわからないところが多々あります。オーケストラ活動を安全に行うための対策がどうあるべきなのか、新響が検討を重ねていた当時も国内外のいくつか機関による実験や検証が行われていました。参考になる有意義な情報が示されはしましたが、当然のことながらこれをやれば大丈夫といったシンプルな結論が出るわけでなく、新響がどうすればいいのかという具体的な方法が示されているわけでもありませんでした。
また、私から見てそうした情報は主に飛沫感染を避けるための距離をどうすべきか、飛沫はどのように広がるのか、といった内容が中心で、日頃の練習時に問題になる接触感染対策についての情報に関しては不足が感じられました。特に管楽器は息を管に吹き込んで演奏するので、それは飛沫を楽器に吹き込みながら演奏していることにほかなりません。もし奏者がウィルスをもっているとしたら、その人の楽器そのもの、および楽器から排出される呼気由来の結露水(と書くと難しいですが、いわゆる「唾」)は感染源になりえます。例えば、それらに触れた手で奏者がドアノブを触り、そのドアノブを他人が触れば、接触感染が成立してしまう可能性があります。このような細かいことにまで配慮した感染対策がなければ、オーケストラ活動を安全に再開することは難しいだろうと私は感じておりました。
世の中に定まったガイドラインが無いなか新響が活動を再開するのであれば、自分たちのガイドラインを自ら用意するしかありません。それは普段の新響の活動を良く知り、且つ医療関係者である私がお役に立てることであろうと考え、団内向けに「練習における新型コロナウィルス感染症対策 (案)」なる資料を作成しました。医療機関において、既にあるガイドラインを実害が生じないようアレンジして、その現場の状況やスタッフに合った内容に工夫するのは医師の仕事です。私にとって資料作成はそんな仕事の応用でした。飛沫感染についての奏者同士の距離の問題に加え、接触感染対策として物品や手をアルコール消毒するタイミングなどについてを詳細に指定する内容になりました。
私がこの資料を作成し団内に公表したのは、厳密には新響が活動再開を決める少し前でした。資料に記載した対策を厳密に行うことは、平時であれば一般の方には受け入れがたいであろうレベルの面倒くささであり、賛否ありうると想像していました。しかし私としては、単に感染対策していますというポーズであったり、世間で行われている対策をただなぞるような内容の対策ではなく、ある程度以上の根拠をもって実効性のあることをしなければ、「感染対策」をしたとは言えないと考えていました。新響に所属する一医療人として、新響の皆さんには自身と近親者の安全を守るために、こうした責任を果たしたうえで胸を張って趣味活動を行ってほしいという気持ちがありました。ですので、団員の皆さんには再開の決断をする前にこの資料見てほしかったのです。
幸い団内からは資料に対して好意的な評価を多くいただきました。こんな面倒くさいことをしてまで演奏したくない(!) といった本音的な意見は表向きは出ず(笑)、活動の再開と演奏会の開催が決まりました。その後、私の作成した資料も参考にされたうえで、団内の感染予防小委員会での検討を経て、新響の感染予防対策が完成しました。
困難な状況でも工夫と努力で活動を続けるようなことは、通常は後に振り返って武勇伝や美談となることが少なくないように思います。しかし今般の相手は感染症であり、場合によっては重症化したり死に至ったり、幸い救命されても後遺症が残ることがあるといった可能性があり、徒にリスクを冒すことは許されない部分があります。今回作成した対策は、ここまで徹底できればおおむね大丈夫であろうというレベルにはなっていると思いますが、こうしたことに絶対は有りませんので、しばらくうまくいったからといっても慢心することなく注意していくことが必要です。安心して演奏に集中できる環境が作っていければと思います。
以上、維持会の皆様にお読みいただく文章としては少々ふさわしくない内容になってしまったかもしれませんが、新響が活動を再開するに至る経緯と「対策」の成り立ちについて、私なりにお話させていただきました。状況や考えの一端が伝われば幸いです。
本来、いわゆる「不要不急」の中にこそ、生きていくうえで大切なものがたくさん含まれているように思います。私にとって新響はその一つですが、前述のような職場の事情や医師としての社会的立場を考えると、いまは普段通りに参加することが難しいです。通すべき筋を通し、身近な人や世間に迷惑をかけずに活動へ参加するにはどうしたらよいか? この正解の無い難問とは、今しばらく向かい合わざるを得なさそうです。せめて今後世情があまり混乱せず、ようやく再開できた新響の練習や演奏会が無事に継続できますことを祈るばかりです。
今後演奏会場ではお客様にもご協力いただかねばならない感染症対策上の決まりがいくつかあり、お手数やご負担をおかけすることになると思われます。どうか事情をお汲み取りいただき、安全な演奏会開催に御協力賜れれば幸いです。どうかお気をつけてお越しいただき、万感のこもった演奏をお楽しみください。
2020年9月発行(第251回演奏会)維持会ニュースより
シベリウス:交響曲第1番ホ短調
■作曲と普遍的原理の追究
自粛期間中、娘がゲームばかりしているものだから「プレイばかりでなく、ゲームを創る側の人になるのはどうかな」と言ったら、「それならお母さんも、演奏ばかりしていないで曲を作ったら」と返され、何も言えなくなった…。
名作曲家の作品への追究は、科学者の法則への追究と似ている。数学者のシルベスターは、「音楽は感覚の数学、数学は理性の音楽」と言った。名作曲家の音楽は、作品それぞれが個性的であるにも拘らず、その作曲家に共通する普遍的な原理が刻印のように存在する。シベリウスの作品もまさにそれで、初めて耳にする曲でも「あぁシベリウスの音楽だ!」とわかる。
■シベリウスの交響曲
シベリウスはフィンランドの民族と自然を代表する国民楽派として知られる一方、交響曲作家として絶対音楽の洗練と抽象化を追究した。交響曲作家は表現の多様性を求めて後期になるほど重厚長大にする例も多いが、シベリウスの場合は逆で、1 - 2番約40分、3 - 5番約30分、6 - 7番約20分と、後期になるほど曲がコンパクトになり、エッセンスが凝縮されて行く。交響曲には分類されないが、1892年に書かれた管弦楽のための交響詩「クレルヴォ」が合唱付き約80分、1925年に完成した交響詩「タピオラ」が20分弱だったことを併せると、この傾向は顕著と言える。
曲の洗練と抽象化を突き詰めるとどうなるか。シベリウスは1920年半ば頃から交響曲第8番の執筆を開始し、1933年に第1楽章はほぼ完成し清書も行われたそうだが、第1楽章だけでかなり大規模になったようで、結局彼は全てを破棄してしまった。この失われた第8番に対する考察は諸説あるが、「シベリウスの厳しい自己批判」(神部智『作曲家・人と作品シリーズ シベリウス』)というのが一番近いのではないかと思える。
■交響曲第1番
交響曲第1番は1899年、33歳の時の作品である。「シベリウスの交響曲は第4番以降で独自の書法を確立した」(濱田滋郎『シベリウス 交響曲第1番』)と評されているが、第1番においても既に、清冽な響き、素朴で懐かしい音律(教会旋法の使用)、悠大な和声感、独特のリズムと音響(例えば半音階的無窮動)が、シベリウス以外の何物でもないと感じさせる。
第1楽章 ホ短調 Andante, ma non troppo(2/2拍子)– Allegro energico(6/4拍子)
ティンパニのトレモロに伴われクラリネットが静かに序奏を奏で、その後ヴァイオリンの3度の清冽な響きとともに力強く熱い主部が開始する。ト長調とホ短調両者の色彩を併せ持つダイナミックな旋律が印象的である。ソナタ形式。
第2楽章 変ホ長調 Andante (ma non troppo lento)(2/2拍子)
緩徐楽章。ハープの変ホ音に導かれ、弱音器をつけたヴァイオリンとチェロが変ホ長調なのかハ短調なのか判然としない切ない旋律を奏でる。途中、シベリウス得意の4分の6拍子や、疾風怒濤の無窮動パッセージと組み合わされる。
第3楽章 ハ長調 Scherzo: Allegro(3/4拍子)
低弦のピッツィカートによる和音の連打に乗って、ティンパニ、ヴァイオリンがスケルツォの動機を奏で、管楽器へと引き継がれる。導音のない教会旋法的旋律で、素朴な力強い舞曲が繰り広げられる。ひとときの安らぎのような優美な中間部を持つ、三部形式。
第4楽章 ホ短調 Finale: Andante(2/2拍子)– Allegro molto(2/4拍子)
「幻想曲のように」という指示のある自由な形式の終楽章。まず第1楽章冒頭序奏の旋律が、今度はテンション高めに奏でられる。その後短い動機から成る慌ただしい部分を経て、悠大な旋律が最初はハ長調でヴァイオリンのG線で奏でられる。この旋律は終盤、より広大に悠久にロ長調で奏でられ大団円となる。最後は厳しいホ短調に戻り曲を閉じる。
■新響の原点回帰
さて未曾有のパンデミックの中、新響においても、音楽活動を再開すべきか、その場合どのように、と、何度も真剣な議論が行われた。オーケストラの醍醐味の一つに、19世紀末から20世紀にかけての大規模で複雑な曲を華やかに演奏する、というものがある。今回の新響も、予定ではストラヴィンスキー「春の祭典」を取り上げる筈だった。だが、この状況では大規模編成ものは難しい。一つの解は「古典への回帰」であろう。しかし今回湯浅先生率いる新響はシベリウスを選んだ。これは「内面への回帰」と言えると思う。1907年にシベリウスはマーラーと対面したそうだが、マーラーが「交響曲は一つの世界のようなものである。そこには全てが含まれていなくてはならない」と言ったのに対し、シベリウスは「交響曲においては全ての動機を内的に連関させるスタイルの厳格さ、深遠な論理が重要である」と述べたそうだ(神部智『作曲家・人と作品シリーズ シベリウス』)。
初演:1899年4月26日 作曲者自身の指揮 ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団によりヘルシンキにて
楽器編成:フルート(ピッコロ持ち替え)2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、トライアングル、ハープ、弦五部
参考文献:
「シルベスターの数学と音楽で多忙な日々」
https://www.irishtimes.com/news/science/james-joseph-sylvester-s-busy-life-of-maths-and-music-1.2329647
神部智『作曲家・人と作品シリーズ シベリウス』音楽之友社 2017年
濱田滋郎『シベリウス 交響曲第1番』(スコア解説)日本楽譜出版社2016年
第251回演奏会(2020.10.18)パンフレット掲載
芥川也寸志:交響三章(トリニタ・シンフォニカ)
作曲家芥川也寸志が新交響楽団の前身の労音アンサンブルを初めて指揮したのは1955年11月9日であり、翌年3月1日の規約の成立をもって新交響楽団が創立された。「交響三章」はその8年前の1948年8月30日に完成したが、このとき、芥川は最下位で入学した東京音楽学校(現東京藝術大学音楽学部)を前年に首席で卒業後、研究科に在学中で、弱冠23歳だった。最初の管弦楽作品である「交響管絃楽のための前奏曲」に続く2番目の管弦楽作品となる。翌年以降放送とステージで初演されて好評を得、芥川の事実上の出世作となったが、後にゼネラル(現富士通ゼネラル)のテレビ受像機のコマーシャルに第3楽章が使われ、1980年代には一躍人気曲となった。本作品の2年後に作曲された「交響管絃楽のための音楽」、5年後の「絃楽のための三楽章(トリプティーク)」とは音楽上の特徴が共通する点も多く、初期の代表作となっている。
曲は3つの楽章から構成される。
第1楽章 カプリッチョ(Capriccio)Allegro
ファゴットの伴奏音型に誘われてクラリネットが諧謔的な第1主題を奏する。伴奏音型はこの楽章の最後まで続き、躍動感を維持している。第1主題は伴奏形を変えながら木管楽器、弦楽器に移動していき、下降音型とシンコペーションを持つ第2主題が登場する。ピアノソロによる第1主題の再現の後、第1主題、第2主題の変化形が現れるが、ここで2/4拍子と3/8拍子からなるリズム音型が現れて気分が変わり、チェロとファゴットに第3主題が登場する。以上の各主題が変形を繰り返し、徐々に静かになっていき、あっけなく終わる。この楽章には芥川の音楽の特徴である、躍動的なリズム、軽快な旋律、執拗な反復(オスティナート)が現れており、プロコフィエフやショスタコーヴィチの雰囲気も感じられる。また、この楽章の変拍子のリズム音型は「春の祭典」のリズムを彷彿とさせるが、芥川は幼少の頃からストラヴィンスキーの「火の鳥」や「ペトルーシュカ」のレコードを聞きながら遊んだそうで、著作『音楽を愛する人に』で「春の祭典」を紹介していることからも、影響を受けた可能性がある。
第2楽章 ニンネレッラ(子守唄 Ninnerella)Andante
ファゴットのソロで牧歌風の第1主題が奏され、作曲中の1948年7月に生まれた長女に対する愛情と喜びが感じられる。この旋律はクラリネット、フルート、弦に移っていく。中間部はオーボエで哀愁を帯びた第2主題の旋律が奏でられるが、「たっぷり歌って、素直にもの悲しげに」との指示がある。この旋律は徐々に盛り上がり、フルオーケストラによる慟哭となる。これが収まるとトランペットが第1主題を再び奏で、楽器を変えながら最後は祈るように終わる。師の伊福部昭譲りの魂を揺さぶるような美しい旋律は芥川作品の最大の魅力だが、この第2主題には深い悲しみも感じられ、戦死した次兄多加志への鎮魂の思いが投影されているとも考えられる。
第3楽章 終曲(Finale)Allegro Vivace
フルオーケストラによる2小節の導入部に続き、元気の良い第1主題が提示され、いろいろな楽器に現れた後、5/8拍子のリズム動機を挟んで第1主題に類似した第2主題がクラリネットに現れる。フルート、弦に移った後、再度第1主題が現れ、オーケストラ全体に広がって盛り上り、静かになると、第1ヴァイオリンにプロコフィエフを思わせる軽快な第3主題が現れてオーケストラ全体に広がって盛り上がると第1主題が重なり、そのまま力強く終わる。
この楽章もひたすら前に進む躍動感に満ちてパワーがあり、芥川の音楽の魅力を良く表している。
ここからは恐れ多いので芥川先生とさせていただく。
新交響楽団は本年創立以来64年となったが、芥川先生は1989年に逝去されたので今年で31年経ち、新響史のほぼ半分が芥川先生との接点がない状態になっている。この結果、先生の指揮、指導に接したことのある団員は28人ほどを残すのみになっている。芥川先生は遠慮されたのか、自身の作品を新響ではあまり振られなかった。特に「交響三章」は取り上げる機会もあまり多くなかったが、第3楽章を実に楽しそうに振られていたことが印象的である。芥川先生の練習はテレビの「音楽の広場」などで見られた、優しい語り口とは全く違って、大変厳しく、弦楽器奏者に一人ずつ弾かせることなどもしょっちゅうあったが、団員は先生の情熱を感じ、必死でついて行った。
芥川先生は新響の練習や合宿、著作などで、アマチュアについて「音楽はみんなのもの」、「アマチュアは愛が語源であり、アマチュアこそ音楽の本道」、「アマチュアを『素晴らしきもの』の代名詞にしたい」、「アマチュアらしい素晴らしい響きにするためには、各団員が自身に挑戦する精神で必死に練習する必要がある」などの内容を、いろいろな表現で情熱的に述べられていた。大変説得力があり、さすがは文豪芥川龍之介の息子だと感じ入ることが多かったが、文豪の三男と紹介されることは嫌がっていたと聞く。
このような芥川先生の理想、精神は現在の新響にも脈々と引き継がれており、邦人作品の中でも芥川先生およびその師の伊福部先生の作品に対する新響団員の愛着は並々ならぬものがある。今後も長く共感と愛情をもって演奏していきたいものである。
初演:放送初演…1949年9月16日 NHKラジオ放送、作曲者自身の指揮 東京フィルハーモニー交響楽団
ステージ初演 … 1950年10月26日 日比谷公会堂、尾高尚忠指揮 日本交響楽団(現NHK交響楽団)
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン2、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、ピアノ、弦五部
参考文献:
毛利蔵人『交響三章』(スコア解説)全音楽譜出版社 1992年
芥川也寸志『音楽を愛する人に 私の名曲案内』筑摩書房 1990年
新交響楽団『第126回演奏会プログラム』 1990年
第251回演奏会(2020.10.18)パンフレット掲載
新型コロナウイルス感染拡大の予防に関する取組みとお願い
新交響楽団では政府及び地方自治体の方針を踏まえ、東京芸術劇場のガイドラインに沿って最大限の感染予防と拡大防止のための対策を実施した上で第251回演奏会を開催します。ご来場を予定されているお客様には以下のお願いがございます。ご協力お願いいたします。
【ご来場前のお願い】
・以下に該当する方はご来場をお控えください。
①平熱と比べて高い発熱(平熱より1℃以上もしくは37.5℃以上)がある方、体調がすぐれない方。
②新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある方。
③過去2週間以内に入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある方。
※①~③の理由によるご来場キャンセルの場合はチケットの払い戻しをいたしますので、shinkyo@music.nifty.jpまでご連絡ください。
・「花束受付」を設置しないため、出演者への贈り物はお控えください。
・クロークサービスの営業を停止しております。ご来場の際、大きなお荷物はお持ち込みいただかないようお願いいたします。
【入館時のお願い】
・マスクの常時着用にご協力お願いいたします。マスク着用されていない方はご入館いただけません。
・入退場時、休憩時等の社会的距離の確保にご協力ください。
・コンサートホール入り口にサーモグラフィを設置します。計測の結果、37.5℃以上の発熱があった方はご入場をお断りさせていただきます。あらかじめご了承ください。そのほか、ホールスタッフの判断により、特定の症状が見受けられる方のご入場はお断りさせていただきます。
・咳エチケットやこまめな手洗い、手指消毒にご協力下さい。受付の近くに消毒液をご用意しております。
・給水機は使用停止およびドリンクコーナーは閉鎖していますので、飲み物の必要な方は、蓋つきの飲料を持参いただくか館内の自販機をご利用ください。
【退館時のお願い】
・終演後は、アナウンスに従って退出していただけますようご協力お願いいたします。
・退館時は密集しないよう、社会的距離を考慮し、適度な距離を保ってご退場ください。
・出演者の出待ちはお控えください。
上記以外にも東京芸術劇場の方針https://www.geigeki.jp/info/covid19_notice/を遵守していただけますよう、ご協力お願いいたします。
※来館者や出演者、スタッフが感染症を発症した際は、保健所と適切に連携して対応するとともに、必要に応じ、ウェブサイトなどで情報提供を行います。
シベリウス:「カレリア」組曲
ジャン・シベリウス (1865−1957) はフィンランドの小都市ハーメンリンナで、スウェーデン語を母語とする家庭に生まれた。英才教育とは無縁ながら、シベリウスは子どもの頃から自発的にピアノやヴァイオリンに興味を示し、15歳の頃には偉大なヴァイオリニストになることを夢見ていた。また独学で作曲理論を身につけることにも熱心だった。
親族に強力に説得されてヘルシンキ大学の法学部に籍を置くが、二足のわらじでヘルシンキ音楽院にも通い音楽の勉強に没頭する。その頃、友人であるアルマス・ヤーネフェルトの妹で、後に伴侶となるアイノ・ヤーネフェルトに出会う。フィンランド語を話す名門ヤーネフェルト家との交流は、シベリウスのフィンランド文化への芸術的な関心を引き起こすようになった。
その後ベルリンやウィーンにも留学して多くのアカデミックな経験を積むが、ウィーンではウィーン・フィルのヴァイオリンのオーディションを受けて失敗し心の傷も負っている。しかし作曲活動が衰えることはなかった。
シベリウスが生まれる半世紀以上前、フィンランドは600年続いたスウェーデンの支配から帝政ロシアへの割譲により、フィンランド人が自国のアイデンティティを求める気運が高まっていた。
特に、医師や教育者であったエリアス・リョンロートが編纂した民族叙事詩『カレワラ』は、カレリア地方に伝わるフィンランド独特の伝説や歌謡を収集して壮大な物語にまとめたもので、フィンランド人の民族アイデンティティの象徴として、帝政ロシアからの独立を導く原動力になった。
シベリウスも『カレワラ』から多くのインスピレーションを受けて愛国的な作品を作曲し、フィンランド国民の支持と尊敬を集めた。
シベリウスはスランプや借金、過度の飲酒癖に悩まされていたが、1897年からは政府の年金支給を受けて作曲に専念することができるようになった。1904年には妻の意向もあり、ヘルシンキの都会生活を離れ郊外のトゥースラ湖畔に転居し、以後の50年はそこで過ごしている。交響曲を始めとして海外での自作の演奏会を開き、大成功を収めた。
主な創作活動は60代までだが、和暦に換算すると、慶応から明治、大正、昭和の戦後の時代までの91歳という長寿を全うした。
■「カレリア」組曲について
カレリア地方はフィンランド南東部とロシア北西部に広がる森と湖の地である。叙事詩『カレワラ』にインスピレーションを受けていたシベリウスは、フィンランド人の魂のよりどころであるカレリア地方にアイノと新婚旅行に行くことにした。
翌1893年、ヘルシンキ大学のカレリア南部のヴィープリ(現ロシア領ヴィボルグ)出身の学生有志から依頼を受けて、愛国的な歴史舞台劇「カレリア」の劇付随音楽を作曲する。その中から3曲を選んでコンサート用に改編したのが「カレリア」組曲である。同じく愛国的情熱に溢れる「フィンランディア」と並び、最もポピュラーな作品の1つとなっている。
間奏曲 Intermezzo
弦楽器群の幾何学模様のようなパート譜を見ると驚くが、霧の中から目覚めるように響く金管楽器の旋律が魅力的な曲。
バラード Ballade
劇では吟遊詩人が歌う場面。原曲ではバリトン独唱だったがコールアングレのソロで演奏される。
行進曲風に Alla marcia
明るく親しみやすい行進曲で、コマーシャルなどでも使われているポピュラーな曲。
初演:劇の上演…1893年、組曲の初演…1894年 ヘルシンキにて
楽器編成:フルート2、ピッコロ1、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、 大太鼓、トライアングル、タンブリン、弦五部
参考文献:
神部智『作曲家・人と作品シリーズ シベリウス』音楽之友社 2017年
第251回演奏会(2020.10.18)パンフレット掲載
新響の活動再開に向けて
●活動中止までの1か月
2月24日、新響は室内楽演奏会、お客様にマスク着用をお願いした以外は予定通り開催した。同じ日にはミラノのスカラ座が閉鎖したというニュースが出た。イタリアは大変なんだと思った。少し前には都内の区が関係するアマチュアオケのいくつかが演奏会中止を発表した。自治体は慎重になるよねと思った。翌25日政府よりイベント開催の必要性を検討せよとの要請が出た。その週末の新響は分奏で少人数の集会ということで実施したが、翌週の合奏の中止を決めた。
3月11日、合同委員会(新響は月1回会議を行っている)。「この1~2週間が瀬戸際」という政府見解を受け、3月14,15日の合奏は中止、演奏会開催の可能性を残し、開催あるいは中止の条件について協議した。予定通り維持会ニュースは発送し、翌週21,22日の合奏はアルコール消毒にマスク着用、私語禁止など三密を避けて行った。3週間ぶりの練習で私たちは音楽の楽しさを再認識することが出来たが、この矢崎先生とのリハーサルが最後の活動となった。
3月24日、東京オリンピック延期が発表され、ホールから演奏会開催可否の検討を要請される。東京都の施設としての立場があるのであろう。委員会を待たずに団長、演奏委員長と3者で相談しホールには開催中止連絡する。対面最後の合同委員会を27日に行い、中止を承認、それに伴う業務の確認をする。延期や無観客演奏については行わないことを決め、月1回は合同委員会を開催することを確認して、新響はいつまで続くかわからない活動休止に入った。本番予定の2週間前であった。
●ZOOMで委員会開催
リモートワークが推奨される中、活動休止中の合同委員会もオンラインで行うこととなった。中にはガラケー・オンリーの団員もいるので、そういう人も参加できるよう準備しつつ、いろいろシステムを試し手軽で経験者も多いZOOMを使うことにした(ズーム飲み会で有名、画面が分割されて全員の顔が写る)。長年、実際に顔を合わせて委員会を行うことを大切にしてきたが、おそらくコロナ後もオンラインでの会議を行うことになるだろう。
4月の委員会では早くも7月演奏会の中止を決定した。その頃プロオーケストラは6月7月での公演再開を模索中であったが、アマチュアの場合はある程度の練習期間が必要で、6月に仮に再開できる世の中になっていたとしても十分な練習はできない。合唱を伴うのもリスクが高い要因の一つである。こうして記念すべき第250回演奏会は欠番となった。
その後は活動再開への準備をしつつ、休止期間に何ができるか、自宅に立派な練習室がある団員ばかりではないので事務所を開放するなど、団員のモチベーションを維持するためにはどうしたらよいかを考える。コロナを機に基本練習や具体的な目標を持って個人練習に励む団員も多かったと思う。
●はたして演奏できるのか
5月に入ると、ベルリンの研究グループが、「新型コロナウイルス(COVID-19)パンデミック期間中のオーケストラ演奏業務に対する共同声明」を発表した。それまではYouTubeで、ファスナー付きマスクを着用してベルにカバーを付けた演奏映像がアップされるなど、管楽器演奏では口周囲および楽器開口部からの飛沫を止めることが必要と考えられてきた。今回の発表では、症状のある者は待機、重症リスクのある基礎疾患を持つ者は免除、会場に入った直後と業務終了後には石鹸で手洗いか消毒を行い、ホール以外ではマスク着用、管楽器の唾・結露(管内に溜まる水分)を使い捨てティッシュで受けて床を掃除するという条件はあるが、管楽器は2m、それ以外の楽器では1.5m距離をとれば演奏可能としている。
6月には東京都交響楽団が東京文化会館のステージを使用して試演と飛沫計測を行い、それに基づいた指針を発表した。飛沫計測とは楽器演奏により発生する飛沫を可視化装置(光を当てて散乱した光を撮影する)にて測定する。結果は管楽器演奏時の飛沫は口元や楽器の近くのみで、会話よりも飛沫を放出はしないことがわかり、通常のように並んでもよいという見解が出された。
その後も、多くの演奏団体や楽器メーカーで可視化装置を用いた検証がされている。
なお、ベルリンの研究の筆頭研究者はシャリテ大学公衆衛生学教授のDr.Willichで、私が毎年参加しているワールド・ドクターズ・オーケストラの指揮者である。また、都響の試演に立ち会った医師の多くが私の古くからの友人である。オーケストラに関わる医者の世界はとても狭い。
6月5日にはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団が本拠地の楽友協会で観客数を100人に限定して3か月ぶりの演奏会を開催した。日本でも6月21日に東京フィルハーモニー管弦楽団がオーチャードホールで定期演奏会を開催、指揮者を日本人に変更し、休憩なしのプログラム、管楽器にはアクリル板が設置された。
私は6月26日の東京交響楽団のサントリーホールでの公演を聴いた。飯守先生でメンデルスゾーン交響曲第3番他。弦楽器と指揮者はマスク着用。魂の込められた演奏、静寂がいつもよりシーンとしていた。久々に何人かの新響のメンバーにも会い、新響も良い形で活動が再開できるよう頑張ろうと思った。
●活動再開に向けて2回のアンケート
<1回目>
緊急事態宣言が解除され、新響も10月演奏会を行うかどうかの検討に入ることになった。10月の演奏会を開催するとすれば、少なくとも7月初めにはある程度のことが決まっていないと間に合わない。6月20日にできるだけ多くの団員が参加しての意見交換会を兼ねた合同委員会を計画していたが、より有意義にするためアンケート調査を行った。提出方法を複数用意し約100人いる団員のうち74の回答を得た。コメント欄を設け、文章で考えていることを書いてもらうことにした。省略しながらもまとめた文書はA4版にして10ページを超え、団員のいろいろなアイディアと様々な思いを知ることができた。結果は、
・新響としてどうすべきと思うか:予定通りのプログラムで開催20%、曲目変更して開催47%、中止すべき26%。
・開催する場合個人として出演するか:参加したい59%、条件によっては参加したい20%、条件によっては参加しない8%、出演しない11%。
その他に練習参加時の不安について、活動休止期間にすべきこと、アフターコロナでの活動について意見を募った。
数字だけ見れば、演奏会やろう!出るよ!という団員が約2/3いることがわかったが、否定的な団員の意見も尊重しなければならない。意見交換会ではまず中止すべきという人に発言をしてもらった。概ね所属企業の方針や家族の事情などの理由が多かったが、どんなに感染予防をしてもリスクはゼロにならないから中止すべきという意見もあった。
そうこうしているうちに、やろうよ!とは言いにくい雰囲気になる。個人的な理由を聞いていてはきりがなく、出演できない団員に寄り添いつつ新響として前に進みたい。不参加の場合でも演奏会参加費を徴収しない(通常、新響では自己都合で休団する場合も演奏会参加費が満額かかる)、曲目は変更、当然適切な感染予防対策を行うことを条件として、再度アンケート調査を実施することとなった。
<2回目>
7月4日の委員会に向けての2回目のアンケートは、より数字で表現できるように5段階から選択する手法でおこなった。84の回答があり、
・新響としてどうすべきと思うか:開催すべき26%、どちらかといえば開催が良い33%、どちらかといえば中止が良い29%、中止すべき6%、どちらとも言えない6%
・開催する場合個人として参加するか:参加予定70%、参加しない(コロナの影響)16%、参加しない(コロナ以外の理由)5%。
パート別の参加予定者数もカウントした。
約6割が開催寄りの回答をしており、数字で言えばGOではある。しかし問題はある。3割の団員が不参加となると、新響の主な収入源である演奏会参加費や団員のチケット販売がその分減少する。感染の心配をする者もいる。出来る限りの経費削減をし、状況が変われば潔く中止することを約束。参加を希望する団員が全員演奏できて、新響らしくて、演奏者も指揮者もお客様も楽しめるようなプログラムにしたいと考えた。この時期にアマチュアオケの活動を再開する意義を確認し、ウィズ・コロナの活動へと舵を切った。
●お金と練習会場の問題
このシーズンの練習開始日は当初8月1日で、その後はオリンピック等のため8月22日が2回目の練習となる予定であった。開催決定から1か月では間に合わないので8/22開始とし、それに合わせて準備をしていく。ほぼ予定通りに練習を進められることはラッキーだったと思う。
不参加団員分の演奏会参加費とチケット売上げ分など100~150万円の収入減が見込まれる。少しでも経費を削減するために、まず考えたことはネット印刷を利用して印刷物を安くあげることと、有料チラシ配布をやめチケット販売を自前でやること。これで35万円ほどの節減。いつもお世話になっている業者の皆様には本当に申し訳ない。曲目変更に伴い、特殊楽器と楽譜の費用で30万円ほどの削減。助成金は曲目変更でもいただけることになった。どうしても足りない分が維持会費を使わせていただく予定である。
都内の練習会場は6月以降徐々に使用できるようになってきた。コロナ以前から予約していた練習会場のうち、2か所は特に制限がなく、体温測定や手洗い消毒、密にならないといった一般的な注意のみで使用可能でありがたいが、新響がよく利用している江東区の施設は、使用定員が大きく制限され、300m2超の広い会場でも合奏が出来ない。かといって今から合奏可能な会場を見つけることは難しく、合奏予定を弦分奏と管打分奏に変更が必要となった。
練習会場のコロナ対応は様々で、9月でもまだ管楽器演奏禁止の区もあり、活動開始のめどが立っていない団体もある。
●なぜシベリウスか
元々のプログラムは「別宮貞雄/交響曲第1番、ストラヴィンスキー/春の祭典」であった。ご存知のように「春の祭典」は5管編成、ホルン8本という巨大編成。フルでそろえば練習会場やホールのステージはぎゅうぎゅう詰めだ。そうでなくても不参加者が多くてエキストラだらけになるので、やるなら編成の小さな曲にせざるを得ない。演奏会開催決定前から指揮の湯浅先生には状況報告とプログラム変更についてのご相談をしていた。
湯浅先生もコロナの影響で仕事はすべてキャンセル。コロナ以降で最初の指揮の仕事が新響の演奏会となる。11月にイギリスでシベリウスの交響曲第1番を演奏することになっているそうで(結局イギリスに行くのは難しくキャンセル)、是非やりましょうというお話だった。湯浅先生との前回の演奏会はシベリウスの交響曲第2番だったのでその続きということもある。新響らしさということで芥川作品を取り上げることにも賛成いただいた。
小さい編成といってもいろいろな解釈がある。新響はどうしても編成の大きい曲を演奏することが多く、一般的なアマチュアオーケストラと比べて、モーツァルトといった古典派の曲に憧れがある。なので、これを機会に小編成で是非!!という声が多かった。しかし、Vn,Vaの出演者が少なく低弦や管打楽器の多くは参加すること、練習がコロナの影響で予定通りに行くとは限らないこと、奏者間の距離が通常より大きくアンサンブルがいつもと勝手が違うことを考えると、私としては、普通に2~3管編成の曲でハードルの高くない曲でと思っていた。湯浅先生から小編成のモーツァルトやハイドン、ベートーヴェン偶数番は「危険極まりない」と言っていただけ、先生と「難しい曲」のイメージがいっしょでよかった。アマチュアオケ的に「簡単な曲」というと語弊があるが、やり慣れた分かりやすい曲も候補にしていたが、むしろ皆が知り過ぎていて完成度を求められるからと、シベリウスで行こうということになった。北欧のオーケストラは10型(1stヴァイオリンの人数が10人という意味)程度の小さめの編成でシベリウスを演奏するとのこと。シベリウスの自然を感じる音楽は胸にしみ、最後の高揚感はコロナの時代の私たちに希望を与えてくれるのではないかと思う。
こうして曲目が決まったのが7月18日、練習開始まで1か月であった。
●新響の感染予防~ウィズ・コロナでの活動
維持会ニュース編集長の松下さんがDr.小出に原稿依頼をしたと聞き、どうも彼が新響の感染予防対策を考えたと思われているのかと思った。確かに彼は新響メーリングリストに感染症対策案を投稿したが、実際の「新響感染予防対策」はホールや練習会場等のガイドラインを加味し私の方で考えて案を作り、実際に練習を取り仕切るインペク陣などの意見も尊重して作ったものである。私が小出さんの投稿をスルーしたのは、ちょうどアンケート集計や候補曲の調整をしていて忙しかったのもあるが、新型コロナについての情報は刻々と変化し、直近の状況に合わせて作成したかったのと、できるだけ具体的にどうするかを示すべきと思ったからだ。歯科医師でも感染予防や公衆衛生的な考え方の教育は受けており、日々患者さんの口に手を突っ込みつつ、自院のスタッフをいかに守り安心して仕事ができるかを常に考えている。
人との間の距離や手洗い・消毒、換気などは一般的なので、新響独自なことを紹介する。一つは管楽器のフェイスシールド着用である。フェイスシールドで吹けるかどうか、まず自分で試してみた。楽器に当たって吹けないという意見を複数もらったが、私は管楽器演奏時の楽器の向きについては専門家である。まっすぐという人でも少し下を向き、顔に対して楽器がほぼ直角の人は顔自体が下を向く傾向がある。だから口元が隠れないということはないし、シートを額から離し角度調整することで影響は少なくなる。人と合わせるのはどうか、ちょうど9月の室内楽演奏会で予定していたロッシーニ管楽四重奏は各発音様式(フルート、シングルリード、ダブルリード、金管)がそろっており、フェイスシールド着用で演奏してみた。聴こえ方は少々変わるが、許容範囲内であることを確認。いろいろなタイプのフェイスシールドを紹介し、どうしてもフェイスシールドが無理と言う人のために、演奏用マスクを考案して作り方を紹介した(現在管楽器演奏用マスクがいくつか市販されているが、サージカルマスクを用いた私考案の物の方が有効ではないかと想像している)。
管楽器は何もせずに演奏することが一般的であるが、それは「プロ奏者が演奏会本番にホール舞台面で演奏する」時のことを考えての検証結果であり、アマチュア奏者が広くない会場で長いリハーサルでも大丈夫というわけではないだろう。つい話してしまうし咳やくしゃみは生理現象である。顔を触らないという効果も期待できる。
もう一つは出席簿に記入する代わりに、毎回の練習で1人1枚の出席票を提出してもらう。出席票には入室時間と体温と緊急時連絡先を記入し体調についての問診にチェックをする。出席状況と並びと距離の記録のために写真を撮る。新響は練習の出席率が高いことが魅力の一つであるが、少しでも体調が悪ければ欠席を推奨し急な欠席もしかたないと考えることとした。
可能な限り接触感染を防ぐために他人の楽器や物には触れないための具体的な対策を考えた。譜面台は各自が持参し、本来皆で行う運搬作業も大型楽器は使う本人が運ぶこととした。管楽器の唾・結露については、新響としてペットシート(吸収して床を汚さない)を大量購入し練習時に運び、使用後は各自が袋に入れて持ち帰る。消毒用アルコールは効果の高い医療用と同レベルの物を用意し触れずに噴霧し手指の消毒ができるようにした。
そして練習後の宴会の禁止。これは皆まじめに守っている、無事演奏会を行うことの方が大事だからだ。アンケートでは宴会が出来ないようなら演奏会を開催しない方がよいという意見も出ており、私も宴会までが練習と思って今まで音楽活動をしてきたが、宴会しなくても練習は十分に楽しく充実感があることが再認識できた。
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
演奏会本番は、東京芸術劇場のガイドラインにそって、できるだけの感染予防対策をして開催する予定です。座席は市松模様(左右と前後が空席)になるように用意しています。今まで定員の50%以内しか収容できなかったのが、政府の方針が緩和され、9月19日にはクラシックコンサートは100%入れることが可能になります。しかし準備もあるため、今回の演奏会は市松模様のままで実施する予定です。維持会席も左右と前後が空席となり、楽々ゆったり聴けるまたとない機会となっていますので、どうぞ楽しみにしてください。
2020年9月発行(第251回演奏会)維持会ニュースより
第251回演奏会のご案内
アマチュアとは音楽を愛すること
新型コロナウイルス感染症のため、多くのコンサートが中止になりましたが、制約を受けながらも少しずつホールでの演奏会が再開されています。しかし音楽を楽しみでやっているアマチュアに許されるのだろうかとも悩みましたが、新響はできるだけのことをして前に進もうとなりました。約半年ぶりの活動再開には、新響らしくて、私たちも聴いてくださる皆様も音楽の喜びを共有できるプログラムにしたいと考えました。
フィンランド~日本から一番近いヨーロッパ
北欧の国フィンランドは、ヨーロッパの中で日本からの距離が最も近く国民性も似ています。シャイで時間に正確、木の家に住み靴を脱ぐ。言葉の音が近く、森林面積が多く自然を信仰している。日本人がフィンランドの国民的作曲家シベリウスの音楽に共感するのは、そのような背景があるのかもしれません。
カレリアとは、現在のフィンランドの南東部からロシアの北西部にかけて広がる森林と湖沼の多い地方で、フィンランドの歴史と伝承文化の宝庫でもあります。愛妻家で知られるシベリウスが新婚旅行に行ったのもカレリアで、その翌年カレリア地方の歴史劇の挿入音楽を依頼されました。そのうちの3曲が組曲として現在コンサートでよく演奏されています。
すでに交響詩で名声を得ていたシベリウスは、その後交響曲作曲家としての道を進みます。ベルリオーズの「幻想交響曲」に感銘し標題のある交響曲を計画しましたが、結局は純粋な交響曲第1番が完成しました。チャイコフスキーやブルックナーの影響を受けながらも、フィンランドの風土が根底にある自然を感じる曲です。
芥川也寸志、若き日の名曲
新交響楽団の創立指揮者にして音楽監督であった芥川也寸志は、文豪芥川龍之介の息子として生まれ、作曲家として魅力的な作品を残す一方、指揮者や音楽番組の司会者などさまざまな音楽活動を通して音楽を広め、日本の戦後の文化の発展に大きく貢献しました。今回演奏する「交響三章」は、東京音楽学校在学中の作品で、躍動するリズムと叙情的なメロディーの生き生きとした曲です。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
第249回演奏会のご案内
矢崎彦太郎=新交響楽団8度目の共演
パリを拠点に世界的に活躍し、その理知的なタクトから豊かな色彩溢れる指揮者、矢崎彦太郎との共演は8回目となります。フランスの管弦楽作品を中心にプログラミングしてきましたが、今回はドビュッシーの代表作「海」を取り上げます。
ドビュッシーの2つの交響的な絵画
フランス印象派の作曲家であるドビュッシー(1862-1918)が、交響詩「海」を作曲したのは1905年。オペラ「ペレアスとメリザンド」が成功し、作曲家としての地位が確立された時期でもあります。「海上の夜明けから真昼まで」「波の戯れ」「風と海との対話」という3つの楽章からなり、海の情景が時間経過とともに描かれます。初版のスコアの表紙には、葛飾北斎の「富嶽三十六景」が使われました。
交響組曲「春」はドビュッシーがローマ大賞を獲得してローマに留学していた1887年に作曲されました。ボッティチェッリの名画「プリマヴェーラ(春)」から着想を得て作曲したと言われており、春の息吹や喜びが描かれています。残念ながら火災により楽譜が焼失したのですが、合唱とピアノの版は残っており、ドビュッシーの指示でビュッセルにより新たにオーケストレーションされました。
メンデルスゾーンの傑作「スコットランド」
ドイツロマン派の作曲家であるメンデルスゾーン(1809-1847)、ドイツのとても裕福で教育熱心な家に生まれ、音楽だけでなく絵画や文学、外国語にも堪能な神童でした。特に三大ヴァイオリン協奏曲の一つであるヴァイオリン協奏曲ホ短調や、結婚行進曲で知られる「真夏の夜の夢」は有名です。指揮者としてもライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団で多くの作曲家の作品を初演し、バッハの「マタイ受難曲」を蘇演するなど音楽界で大きな影響力を持っていました。
交響曲を5曲残していますが、出版順に番号が付けられ第4番と第5番はメンデルスゾーンの死後に出版されているため、第3番「スコットランド」が最後に作曲された交響曲です。メンデルスゾーンはイギリスを10回訪問し計20か月も滞在しましたが、スコットランドに旅行した際に訪れたエディンバラのホリールード宮殿に着想を得て作曲されました。1829年に着手して全曲が完成したのが1842年。筆の速かったメンデルスゾーンが時間をかけた自信作で、美しい旋律と豊かな抒情性に溢れるこの曲はスコットランドの自然が浮かぶような魅力的な曲です。一般的に演奏されるのは1843年改訂版ですが、今回は1842年ロンドン稿を使用して演奏します。
メンデルスゾーンは脳出血により38歳の若さでこの世を去りました。一時はワーグナーが批判しナチス体制から演奏禁止とされましたが、近年再評価・研究され大作曲家として認知されています。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
248回ローテーション
| 魔笛 | ロンドン | 悲愴 | |
| フルート1st | 松下 | 松下 | 吉田 |
| 2nd | 兼子 | 新井 | 藤井 |
| 3rd(Picc) | - | - | 兼子 |
| オーボエ1st | 大山 | 平戸 | 堀内 |
| 2nd | 岩城 | 岩城 | 山口 |
| クラリネット1st | 中條 | 末村 | 品田 |
| 2nd | 進藤 | 石綿 | 大藪 |
| Bassクラリネット | - | - | 進藤 |
| ファゴット1st | 浦 | 浦 | 田川 |
| 2nd | 荒川 | 荒川 | 松原 |
| ホルン1st | 山路 | 大内 | 名倉(大内) |
| 2nd | 大内 | 市川 | 山路 |
| 3rd | - | - | 大原 |
| 4th | - | - | 市川 |
| トランペット1st | 倉田 | 野崎 | 小出(北村) |
| 2nd | 北村 | 青木 | 中川(倉田) |
| トロンボーン1st | 日比野 | - | 日比野 |
| 2nd | 志村 | - | 志村 |
| 3rd | 石黒* | - | 石黒* |
| テューバ | - | - | 土田 |
| ティンパニ | 今尾 | 今尾 | 桑形 |
| パーカッション | - | - | BassDrum簑輪* Cymbals,TamTam今尾 |
| 1stヴァイオリン | 堀内(内田智) | 堀内(内田智) | 内田智(堀内) |
| 2ndヴァイオリン | 中島(滑川友) | 中島(滑川友) | 中島(滑川友) |
| ヴィオラ | 村原(柳澤) | 村原(柳澤) | 柳澤(村原) |
| チェロ | 柳部(安田俊) | 柳部(安田俊) | 柳部(安藤) |
| コントラバス | 中野(宮田) | 中野(宮田) | 宮田(中野) |
*はエキストラ
弦()はトップサイド、管()はアシスタント
チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」
この曲の創作は1892年~93年にかけての冬のヨーロッパ旅行中に始まったとされる。もともと1889年(交響曲第5番初演の翌年)には新しい交響曲への意欲を見せていたチャイコフスキーは、コンスタンティン・ロマーノフ公(詩人としても名を残したチャイコフスキーの支援者であった)への手紙でも、「私は自身の全創作の完結といえる壮大な交響曲を書きたくてたまらない。(中略)これを果たすまではなんとしても死にたくありません。」と熱烈な創作意欲を燃やしていた。しかしながら、その後書かれた交響曲「人生」は、作曲者自身が気に入らずオーケストレーションの途中で放棄してしまう。けれどもこの曲のスケッチにおいて、「幻滅。第4楽章は消え去るように終わる。やはり簡潔に。」とあり、既に終楽章を緩徐楽章で終えるアイデアは念頭にあったようだ。
そして、前述のヨーロッパ旅行中に別の交響曲のアイデアが浮かんだ。手紙の裏やホテルの領収書にスケッチがなぐり書きされていたというから、そのアイデアのひらめきが突然だったのであろう。1893年2月3日にモスクワ近郊のクリンの自宅に帰ったチャイコフスキーは翌日からわずか1ヶ月と3週間ほどの間に全草稿を書き上げる。甥のダヴィドフに2月初旬に宛てた手紙に「フランスから帰って4日もたたないうちに第1楽章は出来上がってしまったし、残りも頭の中では出来上がっている。(中略)私は自分がまだまだ働けることを知ってとても嬉しい。このうれしさはきっと君には想像もできないほどだ。」とあり、意欲にあふれている。
多忙を極める中、彼がオーケストレーションを終え完成の日付を入れたのは1893年8月19日であった。
彼はアイデアが浮かぶのを待って仕事をするのではなく、自分をプロの職人と考え、たゆまず仕事をした。
その試行錯誤のほどが自筆譜からも窺える。
チャイコフスキーの死と、標題「悲愴」
1893年10月16日に行われた、成功とは言えなかった初演のわずか9日後、チャイコフスキーは急死する。異色の緩徐楽章での、死に絶えるように終わる「悲愴」というタイトルのこの作品が彼の絶筆となったことから、この曲を遺言のように考えたり、死因に関しても同性愛の発覚を恐れた自殺ではないかと人々を騒がせてきたのだが、はっきりとしたことは分かっていない。コレラ説もあるが、不自然な点が多くあり定かではない。それでもチャイコフスキーが自らの死期が近いことを感じながら、最後の交響曲として書き上げたことは確かであろう。
悲愴という標題についてだが、当初チャイコフスキーはただ「標題的」とだけ名付けるつもりであったし、作品としても内的標題があったが、標題音楽とは異なる手法が用いられていた。初演の後には、リムスキー=コルサコフが何らかの標題があるのか尋ねたが、「もちろんあるが明らかにしたくない」と答えたという。
ところが、前述したように初演は反響が良くなく、チャイコフスキーは大変困惑した。翌朝弟のモデストに副題に関して意見を求め、弟ははじめ「悲劇的」と提案したがチャイコフスキーは受け入れず、しばらくしてふと浮かんだ「悲愴」は作者に気に入られ、この名が冠されたといわれる。
この曲の各楽章は「嘆息の動機」(繋留音を含めた2度下降音程を特徴とする音型)と呼ばれる、バロック時代の修辞法による動機から導かれる。標題「悲愴」の性格にふさわしいものであろう。
作品構成
全体の構成
この曲の特色はやはりまず楽章構成だろう。第2楽章に前例のない5/4拍子のワルツ、第3楽章にタランテラとマーチの様式のスケルツォが置かれ、フィナーレには一般的なAllegroに代わりAdagio(Andanteだとする説もあるが)が位置している。一見反規則的な形式であるが、古いソナタ形式の本質的な性格は守られており、チャイコフスキーの創意工夫と緻密さの2面が窺える。
また、各楽章は近親調(第1、4楽章h-moll、第2楽章は平行のD-dur、第3楽章はその下属調G-dur)で書かれたが、フィナーレのコーダにおいて初めてh-mollの主和音が現れる。作品を通した調構成に、コーダにおいて最終的に主調を確立するという一貫的な発展をさせる意志が感じられる。
第1楽章 Adagio-Allegro non troppo ロ短調、4/4拍子、ソナタ形式
序奏ではコントラバスの5度音程の上にファゴットの独奏が現れる(譜例1)。この基本動機は3回繰り返されるたび、属和音の嘆息で終わりながら上がっていく。
これを支えるコントラバスの半音階的な下降には、苦難の歩みを表すバロック時代の修辞音型「Passus duriusculus(辛苦の歩み)」が用いられる。嘆息の動機とともにすでに標題の性格が提示される。第1主題はテンポが上がったAllegro non troppoから、まずヴィオラで嘆息の基本動機が現れ発展していく。そして金管楽器群の挿入により始まる主題の行進曲的な変奏は、短3度ずつの転調を繰り返しながらニ長調へ落ち着き、ロマンティックな第2主題へと導かれる。
展開部は突如激烈に始まり、ロシア正教のパニヒダから「主よ、眠りし汝の僕しもべの霊に安らぎを与えよ」の引用である金管のコラールを経て、嘆息の動機が再び現れ激しいクライマックスを形成した後、静か
に祈るように終わる。
第2楽章 Allegro con grazia ニ長調、5/4拍子、三部形式
交響曲の歴史上前例のない5拍子のワルツだが、スラブ民族の音楽では珍しいことではなく、チャイコフスキーは同年に書いたピアノ曲(作品72)にも用いている。
ワルツ主題が2・3拍に分割されるのに対し、伴奏がしばしば3・2拍に分割されることで、旋律と伴奏の間にリズム的対位法が生み出されている。また、中間部は嘆息に基づいていることがわかる(譜例2)。
第3楽章 Allegro molto vivace ト長調、4/4(12/8)拍子
この楽章はタランテラの様式のスケルツォと行進曲からなる。初めはタランテラの旋律に対し行進曲のリズムが伴奏の役割を果たしているが、この伴奏は次第にスケルツォの対旋律として成長し、徐々に行進曲として移行してゆく。そして後半再現されるト長調の行進曲はスケルツォの影響を受けずほとんど自立した姿になる。
しかし、軽やかだったオーケストレーションには、この行進曲の発展により、重苦しく激しく、追い立てられるような切迫感が生み出される。この楽章でのみ用いられるシンバルと大太鼓もその変化を効果的に演出する。また、行進曲を導く金管楽器のファンファーレは、ベートーヴェンの運命の動機を想起させる。最後には、タランテラも再び現れる派手に高潮した行進曲となり、低音域に押し潰されるように荒々しく終わる。
第4楽章 Adagio lamentoso ロ短調、3/4拍子、三部形式
交響曲としては異例の遅い終楽章で、作曲者自身がレクイエムの気分に満ちていると指摘した、この曲の性格をはっきり打ち出す楽章である。そして さらなる特色は、第1主題の旋律を第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンに分散させている点である。 (譜例3)
チャイコフスキーの時代、2つのヴァイオリンセクションは向かい合って座っていたこともあり、旋律は引き裂かれるように第1、第2ヴァイオリン間を揺れ動く。余談だが、実はこの試みは、ドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」の第4楽章にも見られる。どちらが先に考えたのかと思うが、両作品とも1893年の作曲でその結論は分からない。クライマックスでは、繰り返されてきた第1主題は次第に嘆息の動機へ収束してゆき、金管のコラールがこの動機を反芻しながらコーダへと導く。そしてここまで回避されてきたロ短調の主和音が確立され、消えるように曲が終わる。
初演:
1893年10月16日、作曲者自身の指揮でサンクト=ペテルブルクにて。
楽器編成:
フルート3(第3奏者ピッコロ持ち替え)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、大太鼓、タムタム、弦五部
参考文献:
マイケル・ポラード(五味悦子訳)『伝記 世界の作曲家7 チャイコフスキー』偕成社 1998年
寺西春雄『チャイコフスキー』音楽之友社 1984年
ゲ・ア・プリベーギナ(不破湘太訳)『楽聖・チャイコフスキー』新英社 1989年
池辺晋一郎『チャイコフスキーの音符たち 池辺晋一郎の「新チャイコフスキー考」』音楽之友社 2014年
千葉潤(解説)『チャイコフスキー 交響曲第6番《悲愴》ロ短調 作品74』音楽之友社 2004年
園部四郎(解説)『チャイコフスキー交響曲第6番〔悲愴〕』全音楽譜出版社
溝部国光(解説)『チャイコフスキー交響曲第6番《悲愴》』日本楽譜出版社
ハイドン:交響曲第104番ニ長調「ロンドン」
1. ハイドンとその時代
フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(Franz Joseph Haydn)は、1732年オーストリアのウィーンから東に約43kmのローラウ(Rohrau)という村で生まれました。時はバロック音楽時代の末期。そして没年は1809年、古典派音楽から初期ロマン派音楽へ移行する直前。ハイドンが生きた時代は、西洋音楽史の転換期にあたります。1740年、8歳の頃にハイドンは音楽的才能を認められて、生まれ故郷からウィーンに移り住み、聖シュテファン寺院聖歌隊のメンバーになりました。聖歌隊で約9年間活動し、声変わりで退団した後、ヴァイオリンやオルガンを演奏したり、歌手として歌ったりして生計をたてていたようです。またこの頃に作曲の勉強を本格的に始め、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハから大きな影響を受けました。
1757年に25歳でボヘミアのモルツィン伯爵の宮廷楽長の職に就いたハイドンは、交響曲第1番を作曲しました。(モーツァルトはその7年後、1764年、8歳で交響曲第1番を作曲しています。)1761年、ハンガリーの大貴族エステルハージ家の副楽長に就任、1766年には宮廷楽長に昇任し、1790年エステルハージ家ニコラウス侯爵が亡くなるまで、宮廷楽長として恵まれた生活を送りました。ハイドンの音楽生活は教会音楽に始まり、その人生の大半の時間を王侯貴族お抱えの音楽家として過ごしたのです。
1791年~92年、および1794年~95年、ロンドンの興行師兼音楽家ザロモンの招きにより、ハイドンはイギリスを訪問して大成功を収めます。エステルハージ家の宮廷楽団は20名程度でしたが、ロンドンでは大ホールの公開演奏会で40名を超える楽員を使って演奏することが出来ました。興行師ザロモンは市民のために公開演奏会を企画して切符を売って営利を得、ハイドンはその演奏会での演奏を前提にした交響曲を作曲して多額の報酬を得たのです。当時、ヨーロッパの他国に先んじて市民階級が台頭していたイギリスでは、音楽は特権階級の独占から市民へ解放されており、「宮仕えの音楽家」であったハイドンは近代市民社会の「自立した音楽家」として大成功を納めた最初の作曲家とも言えます。
本日演奏する交響曲第104番は2回目のロンドン訪問の最後の年となる1795年、63歳の時に作曲されました。同じ年、ベートーヴェンはピアノ協奏曲第1番、第2番を作曲しています。また本日演奏するモーツァルトの歌劇「魔笛」はその3年前1791年に生まれていました。ロンドンでの演奏会のためにハイドンが作曲した一連の交響曲12曲(第92~104番)は「ザロモン交響曲」または「ロンドン交響曲」とも呼ばれ、後年「驚愕」「奇蹟」「軍隊」「時計」「太鼓連打」という愛称で呼ばれるようになった名曲が含まれています。わかりやすいメロディを作品の随所に入れることによって、ハイドンは演奏会に集まった市民たちから熱烈に歓迎されたのです。
この時期ロンドンでは楽団の規模がどんどん大きくなり、ヘンデルの「メサイア」を500名以上の楽団と合唱団が演奏したという記録が残っています。ハイドンもそのような大編成の演奏を聴いて影響を受け、ウィーンに戻ってからオラトリオ「天地創造」(1796~98年)、オラトリオ「四季」(1798~1801年)を作曲することになります。そして1809年、ナポレオン侵攻下のウィーンで、77年間の生涯を閉じました。
ハイドンの生涯は、作曲家や演奏家を支えてきた主体が、教会であった時代、王侯貴族であった時代、そして市民階級が聴衆の中心になった時代にまたがっています。交響曲第104番が作曲された時代は、産業革命の進展と経済活動の発展、それにともなう市民階級の台頭と王侯貴族勢力の衰退、フランス革命に始まる市民革命による社会構造の大きな変革期にあたるのです。
2. 作品の構成
交響曲第104番はハイドンが作曲した最後の交響曲です。19世紀になってから「ロンドン」と呼ばれるようになりました。
第1楽章 Adagio-Allegro
ニ短調 4分の4拍子-ニ長調 2分の2拍子、序奏付きのソナタ形式。
オーケストラのすべての楽器がフォルティッシモ(ff)でニ短調の序奏を始めます(譜例1)。その後、ファゴットと弦楽器が冒頭と同じ音型(譜例1)をピアノ(p)で演奏する中、第1ヴァイオリンがフォルツァンド(fz)で割り込んできます(譜例2)。
ハイドンがロンドンに滞在していた1790年代は、自動車も蒸気機関車も発明される前です。ガス灯も普及する以前ですから、夜の照明はロウソクやランプの灯りの時代です。日常生活には、雷の音か、馬の嘶いななきや、馬車の車輪が軋む音以外、大きな音がするものはありませんでした。ですから聴衆は、40名以上の楽員がフォルティッシモ(ff)で演奏する雷鳴のような「大音響」には度肝を抜かれたに違いありません。ある意味では現代のヘヴィ・メタルのロック・コンサートで爆音を体感するのと同じような感覚を味わったのです。曲の冒頭でオーケストラの大音響と緊張感のある密やかな音を対比させることによって、演奏会に集まった聴衆を一気に魅了しようとしたハイドンの意図を感じます。
序奏の後、提示部は弦楽器によるニ長調の第1主題で始まります(譜例3)。
第2主題はイ長調で木管楽器と弦楽器で提示されます(譜例4)。
第2楽章 Andante
ト長調、4分の2拍子、変奏曲形式。
弦楽器によるト長調の主題で始まります(譜例5)。その後、第1変奏、第2変奏、第3変奏、コーダと進みます。
第3楽章 Menuet:Allegro-Trio
ニ長調-変ロ長調、4分の3拍子、複合三部形式。
Menuet部分はA(譜例6)-B(譜例7)-Aの三部形式です。
Trioは変ロ長調で、オーボエやファゴットがヴァイオリンとともに主題を演奏します(譜例8)。
第4楽章 Finale:Spiritoso
ニ長調、2分の2拍子、ソナタ形式。
ホルンとチェロが低音のdの音を2小節演奏してから(譜例9)、民謡風の主題(譜例10)がすぐ始まります。
3. ハイドンの作品における強弱記号と「くさび形」記号
交響曲第104番の楽譜には、強弱記号が5種類しかありません。ピアニッシモ(pp)、ピアノ(p)、フォルテ(f)、フォルティッシモ(ff)、フォルツァンド(fz、その音を強く)です。ではハイドンの時代はこの5種類の強弱だけで演奏していたのでしょうか。近年の古楽研究の成果によりかつての演奏技法が少しずつ解明されてきて、演奏家は作曲家の指定には従うものの、かなり自由に強弱をつけて演奏していたことがわかってきました。ハイドンは演奏家の自由を尊重して、あえて最低限の強弱記号しか指定しなかったのです。
楽譜に書かれていることだけを忠実に演奏するという観点からはハイドンの作品はつまらない曲だとされていた時期がありましたが、実は和声の進行や音楽の方向性を正しく解釈した上で、作品に内在する音楽を自由に表現できるのがハイドンの作品なのです。そして、そのような演奏によってこそハイドンの音楽の素晴らしさが花咲き、作曲技巧の面白さや諧かいぎゃく謔が表出してくるのです。こんなところにハイドンを聴く面白さがあるのではないでしょうか。
ハイドンの作品を演奏する上で、もうひとつ重要なポイントがあります。それは「くさび形」記号 ▼または▲)です(譜例3、4、5、6、7、10)。この記号は現代ではスタッカーティシモ(staccatissimo)と呼ばれて「スタッカート(staccato)よりも鋭く音を切って演奏する」記号として使われていますが、バロック時代から古典派の時代には「その音符をはっきり弾いてほしい」という意味で用いられていました。くさび形記号は単純に「短く・鋭く」という意味ではなく、「それぞれの音を大切に、意味を持たせるように演奏する」という作曲家の意図が込められています。従って、強く演奏したり、鋭く切って演奏したり、逆に音を長く保って演奏したりすることもあり、千変万化のくさび形記号なのです。この小さな印の中には、「音符に何らかの意味を持たせて」、「この音に注意して」という意図が明白に込められているので、音楽を瑞々しく、生き生きと表現する大きな手がかりになるのです。
初演:
1795年5月4日、ロンドン キングズ劇場での慈善コンサート。4月13日との説もある。
楽器編成:
フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦五部
参考文献:
岡田暁生『西洋音楽史』中央公論社 2005年
片山杜秀『ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる』文藝春秋社 2018年
木村靖二、岸本美緒、小松久男『詳説世界史研究』山川出版社 2017年
レオポルド・モーツァルト(塚原哲夫訳)『バイオリン奏法』全音楽譜出版社 1974年
モーツァルト:歌劇「魔笛」序曲
今回初めにお送りするのは、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-91)が最後の年に作曲した歌劇「魔笛」より、序曲である。この高潔さと卑俗さのまじりあった奇妙な作品は、実は都市伝説で何かと騒がれる秘密結社「フリーメイソン」と強い関係がある。ここでは、フリーメイソンや時代背景との関係を紐解きながら「魔笛」を解説していく。本日の演奏とともに美しい旋律の中に隠された秘密についても楽しんでいただきたい。
「モーツァルトと18世紀オペラ」
18世紀ヨーロッパは啓蒙主義の時代。従来の権威や伝統が批判され、「理性」を基にした新しい秩序を打ち立てることが主張された。音楽史では「古典派」と呼ばれる時代とほぼ重なる。この社会の変動はオペラに対しても影響を与え、劇の展開が錯綜した従来の在り方に批判が起き、ピエトロ・メタスタージオ(1698-1782)がイタリア語オペラの台本の改革を行った。メタスタージオは劇の進行に一貫性を持たせるために、喜劇的な内容をオペラから除外した。この台本によるオペラはオペラ・セリアと呼ばれる。一方で喜劇的な内容のオペラはインテルメッゾやオペラ・ブッファで扱われるようになった。
18世紀後半に入ると、モーツァルトが台本改革の発展を受け、オペラ・セリアの新たな世界を築き上げた。また、1781年にウィーンに定住したモーツァルトは、ドイツ語オペラのジングシュピール(魔笛はこの分野に入る)やオペラ・ブッファに取り組み、当時の3つのオペラのジャンルで名を残したのである。
「フリーメイソンと魔笛」
18世紀ヨーロッパでは、啓蒙主義の拡大とともにフリーメイソンの活動が活発化していた。フリーメイソンとは、啓蒙思想における「自由」、「平等」、「友愛」の精神を基に活動していた18世紀に生まれた秘密結社で、当時のウィーンの文化人の多くがフリーメイソンの会員だったといわれている。モーツァルトは1784年にフリーメイソン分団に入会し、「フリーメイソンのための葬送音楽」や歌劇をはじめとした作品を提供している。
同様にフリーメイソン会員だった、ウィーンの中規模市民向け劇場の座長、エマヌエル・シカネーダー(1751-1812)の依頼でモーツァルトは、1791年に「魔笛」の作曲を始めた。シカネーダー台本による「魔笛」は、パントマイムする動物たち、おどけた鳥人間、空中船に乗る童子などが登場する民衆劇の寓話的な世界に啓蒙主義やフリーメイソン的な儀式なども組み込まれており、実に雑多な要素を包含している。次の章では魔笛のあらすじについて解説する。
「魔笛のあらすじ」
第1幕は、大蛇に襲われた王子タミーノが3人の女に救われるところから始まる。3人の女が仕える<夜の女王>はザラストロにさらわれた女王の娘パミーナを助けるようタミーノに依頼する。パミーナの肖像画を見たタミーノは彼女に一目惚れし、喜んで依頼を受ける。そして魔法の笛を持って、鳥刺し男パパゲーノとともにザラストロの神殿へと向かった。3人の子供に導かれて神殿の門までたどり着いたタミーノは、神官との問答をするうちにザラストロが悪人かどうかわからなくなる。一方、パミーナはザラストロの部下モノスタトスに追い詰められていたが、タミーノとはぐれたパパゲーノに助け出される。その後、再び捕らえられた先で、パミーナとタミーノは出会い、互いに惹かれ合う。
第2幕では、ザラストロの命により、本当の愛を見つけるために試練を与えられることになる。タミーノとパパゲーノは数々の試練を乗り越えていくが、試練のために口をきいてくれないタミーノに愛が失われたと感じたパミーナは、絶望して自殺しようとしてしまう。しかし、3人の子供が現れて救われ、パミーナはタミーノの愛を知る。互いの愛を知ったタミーノとパミーナは2人でさらなる試練に立ち向かい、打ち勝つ。一方パパゲーノも夢がやっと叶う。理想の女性パパゲーナと結ばれ、たくさんの子供たちが生まれる。みんなの幸せが面白くない夜の女王はザラストロを襲うが、あえなく失敗し滅ぼされてしまう。ザラストロの世界の勝利で歓喜のうちに幕となる。
以上が魔笛のあらすじである。この物語とフリーメイソンの関係についても様々な指摘がなされている。その中でも、夜の女王、ザラストロ、王子タミーノに関するものが有名である。夜の女王はフリーメイソンを厳しく取り締まったハプスブルク家の女帝マリア・テレジア、ザラストロはフリーメイソンのメンバーをモデルにしていると考えられている。また、第2幕でタミーノが受けた試練は、フリーメイソンの入会儀礼がモデルになっているといわれている。
「序曲 ~秘められた“3”~」
今回の演奏会では、魔笛の中でも序曲のみを演奏する。この序曲はしばしば単独で演奏されるほど有
名である。さて、フリーメイソンと魔笛が強い関係を持っていることは前述したが、序曲にも様々な形でそれを暗示するものが潜んでいる。フリーメイソンの理念は、「自由」、「平等」、「友愛」の3つであることに加え、位階が3つ、入信式で戸を3回たたくなど、3という数字と特別な関係を持っている。ここで魔笛の序曲も見てみると、まず主調が変ホ長調というフラット記号(♭)が3つの調であり、序曲冒頭のAdagio部分で和音が3回鳴り響く(譜例1)。また、序曲の中間部でも、短・長・長で成る3つの同一和音の組み合わせが、全管楽器によって3回繰り返される(譜例2)。
いずれの場合も、魔笛にとって重要な楽器であるフルート、オーボエの音が、この3回の和音の間で3度ずつ上昇していく。このように序曲は3と関係があり、実は序曲に限らず、オペラ全体が3と関係するように様々な工夫がなされている。是非、譜面に散りばめられたこの“3”という数字について注目しながら演奏を楽しんでいただきたい。
初演:
1791年9月30日、ウィーン近郊(現市内)のアウフ・デア・ヴィーデン劇場にて。
楽器編成:
フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、弦五部
参考文献:
長野順子『魔笛 <夜の女王>の謎』ありな書房 2007年
アッティラ・チャンパイ、ディートマル・ホラント編『モーツァルト 魔笛』音楽之友社 1987年
坂口昌明『≪魔笛≫の神話学 われらの隣人、モーツァルト』ぷねうま舎 2013年
西村理/渡辺崇聖/沼口隆/広瀬大介/宮西桐子/向井大策『CD付き もう一度学びたいオペラ』西村理監修,西東社 2008年
ハイドンへのある視点
◆車大工の家
ひとつのエピソードから始めよう。若き日の福澤諭吉(1835~1901)が、江戸幕府の使節の一員として初めてアメリカに渡った折りの事である。彼はかの地で、生まれて初めて馬車というものを目の当たりにして当惑する。後にその時の事を語っている。
所が此方は一切万事不慣れで、例えば馬車を見ても始めてだから実に驚いた。其処に車があって馬が付て居れば乗物だと云うことは分りそうなものだが、一見したばかりでは一寸と考が付かぬ。所で戸を開けて這入ると馬が駈出す。成程是れは馬の挽く車だと始めて発明するような訳け。(『福翁自伝』)
広汎な蘭書を精読する事を通じ、西洋の文物に対する理解は当時の日本人の中でも群を抜いて高かった彼(事実、米国内の生産現場を視察するごとに、その背景にある理論や原理を説明抜きで理解できていた)にして、馬車に対する想像力はかくの如くに働かなかったのである。無理もない。江戸幕府は軍事的理由から、大河への架橋や大型船の建造を禁止するのと同列に、馬車の製造も禁じている(貴人でさえ移動には輿か駕籠を用いた)。それ故に車輪による乗物自体が王朝時代の牛車以降日本には殆ど存在せず、僅かに祭りの山車か運搬に用いる粗末な大八車・・・・程度のもの、しかもそれを馬で曳かせるという発想自体が生まれなかった。これは今考えるとひどく奇妙な事にも思えるが、既に開国期を迎えた日本にあって、殊更に開明的であった福澤先生の脳内さえ支配していたほどだから、一般の日本人にとっての「車」とは到底人が乗って馬が曳くものとの認識には至らなかったであろう。
さて、ハイドン(Franz Joseph Haydn1732~1809)の事である。彼には幼少年期の記録が殆ど無い。この事は後世に大作曲家として記憶されている人々と一線を画している。モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart 1756~1792)のように眉毛が唾で濡れ放題となる事請け合いの神童神話(?)に取り囲まれている訳でも無い。かといって、酔った父親の怒声が突如深夜に湧きおこり、子供の悲鳴共々ピアノの音がいつまでも鳴りやまない・・・・「これって虐待では?」。今ならさしずめ近隣から児童相談所へ通報があって不思議のない逸話があるでもない(誰の事か判りますね)。功成り名を遂げた晩年に至っても当のハイドンが殆ど語らなかった為、どんな子供だったか判らないのである。
その中ではっきりしているのは彼が「村の車大工」の息子として生まれている事実だけだ。
この幼少年期の記録の乏しさと「車大工」の語が合併すると、我々日本人はとかく「貧困」の存在を連想しがちで、挙句にハイドンに対しては、
寒村の一画で、大八車などの修繕で辛うじて生計を立てていた貧しい職人の家から、突如として偉大な才能が現れた・・・・
というようなストーリーを勝手に描いてしまう。少なくとも個人的にはつい最近までそうした想像を当たり前のようにしていた。それは前述の通り日本人にとっての、自動車の出現以前の「車」とその製造に従事する人に対する伝統的なイメージの貧弱さに起因するのだろう。
だがヨーロッパ社会は全く異なっている。古代ローマには馬によって牽かれる戦車があったし、様々な形態の馬車はハイドンの出生以前から広く普及し、ヒトとモノを輸送する手段となって久しい。当然その交通を前提としたインフラとして、舗装された道路が四通八達している。「神童」モーツァルトがヨーロッパ中を巡ったのも、ゲーテがアルプスを越えてイタリアに至ったのも、すべては馬車による旅だった。つまりヨーロッパは既に「車社会」だったという訳。とすれば車産業に関わる業種の規模も裾野の広さも相応のものであった筈で、こうした背景を前提として、改めてハイドンの出自を考えてみると(特に日本人にとって)かなり違ったものになってくるのではあるまいか?そこに「貧困」や「零細」が入り込む可能性は限りなく低い。
ハイドンの生家は今も遺る(記念館になっている)。地域を治める領主の宮廷で使われる馬車の新調や保守・修繕なども請け負っていたというから、御用達の車大工だった訳で、それにふさわしい規模の工房と人数を擁していた筈である。家屋は後世の補修はあるにせよ、日本人の抱く車大工のイメージとは隔絶した構えであり、生まれた部屋と称する一画も、ベートーヴェンハウスの屋根裏部屋とは広さも採光も違う。且つハイドンは12人兄弟といい(何人成人したかは不明)、5歳下のミヒャエル(Johann Michael Haydn, 1737~1806)も作曲家となっている(ウェーバーはその弟子)。確かに血縁者に音楽家は認められないが、兄弟そろって6歳になるとウィーンに出て聖歌隊に入る事で音楽家としての人生をスタートしているのだから、それ以前から並み以上の豊かさの中で当然ながら音楽は身近にあった筈である。才能の片鱗も垣間見せていたろう。だがそれを殊更に外部に喧伝する必要がなかったほどに物心両面にわたってのゆとりがあった、と考える方が自然に思える。ハイドンの作品を通じて流れる「落ち着き」「穏やかさ」というものの源流をそこに感じてしまうのは、聊かうがちすぎだとしても。
◆交響曲(シンフォニー)の成立~ハイドンまで
今でも小中学校の音楽室にあった作曲家の肖像画を時折想い出す。まずバッハとヘンデル(このふたりは共に1685年生まれ)そして次がハイドンだった。明治以来(ちょうど『明治100年』と言われた時代)の洋楽導入がドイツ音楽一辺倒だった思潮を反映し、幼い純真な少年(筆者の事。念の為)にも音楽と言えばドイツ、ドイツ音楽と言えば交響曲!という先入観をいやが上にもすりこませるに充分な装置だった。とはいえ、大バッハが交響曲を遺した訳でも無い。が隣のハイドンに至っては100曲以上も交響曲を書いている。この量的なギャップというものが当時でさえ不可解と感じられた。
調べるとバッハの厖大な作品目録の中で、『シンフォニア』と題された管弦楽作品が1曲だけある(BWV1046a 注1)。これは何らかの祝祭の機会に書かれたものと言われているが、確かにその冒頭からあふれ出る華美・盛大な気分はそうした推定を容易にさせるものを持って いる。バロック時代には『シンフォニア』とは祝典のための音楽だった。
一方でオペラの序曲として演奏される『オペラ・シンフォニア』というものがあった。スカルラッティ(Alessandro Scarlatti 1660~1725)はナポリにおいて、急-緩-急の3部構成的な序曲を既に1680年代から作品に用いていた。これが短期間のうちにオペラから独立し、ひとつの器楽作品のジャンルへと変貌してゆく。「交響曲(シンフォニー)」へ脱皮の第一歩である。これがドイツではなくイタリアで創始された点はもっと重要視されても良い。
ハイドンが生まれた時、大バッハは既に47歳。とすればふたりの作曲家の肖像の間には、本来もう一世代然るべき作曲家のそれが加えられるべきなのだ。事実この間「忘れられた」作曲家たちによる絶えまない交響曲創造への堆積がある。
例えばバッハの息子たち・・・・次男であるC.P.E.バッハ(Carl Philipp Emanuel Bach 1714~1788)は3楽章形式のシンフォニアとそこにメヌエットを加えた4楽章構成の交響曲を合せて20曲以上書いた。ロンドンで評価を得た末子のJ.C.バッハ(Johann Christian Bach 1735~1782)もシンフォニアを約60曲残している。モーツァルトは8歳の折にロンドンで彼に会い、その影響から3楽章構成の最初の交響曲(注2)を書くに至る。
秀逸なオーケストラを擁したマンハイムを拠点としたシュターミッツ(Carl Philipp Stamitz 1745~1801)の手になる作品(シンフォニアだけで51曲ある)も忘れるべきではない。ここでは詳細を述べる紙数は無いが、彼らによってソナタ形式をはじめとした独立した性格を有する4楽章形式の交響曲はひとつの定型を得るに至る。
同世代若しくは半世代前の数多あまたの作曲家たちによって、急速に形成されつつあった交響曲の土壌。その上にハイドンという種子が落ち、この分野における収穫の時期を迎えた。我々がこんにち耳に出来るのは、その限られた上にも限られた上澄みの一掬に過ぎない。
◆宮仕えの日々と多作
ハイドンは1761年29歳の折から約30年間ハンガリーのエステルハージ(Eszterházy)侯爵家に仕えた。彼の100曲以上(その全容は掴み切れない)交響曲の大部分はこの間に、自ら楽長を務める宮廷楽団の為に、更には特定の演奏機会の為に作曲されている。それは定められた日常業務であり、大バッハが教会の楽長の職務としてその儀式典礼の為に絶えず新作を創造していた姿と変わらない。ハイドンはそうした作曲家の最後の世代だったと言える。
例えばある朝、いつものように控えの間にいる作曲家は、主人から今日は交響曲を5曲作曲せよ(!) と命令される。一晩で城を築けと臣下に無理難題を平気で命じる織田信長のような君主だが、こうした場合の事を彼は後年述懐している。
私は座席にすわり、その時の気分が悲しいか、愉しいか、厳粛かふざけっぽいかにしたがって、楽想を作り始める。ひとつのアイディアが私をとらえたならすぐ、私は全心の努力をもって、芸術の法則にしたがって、楽曲を完成させることにつとめる。
1日に5曲の交響曲を作るなど荒唐無稽の事にしか思われなかったが、ある時を境に考えを変えた。彼の交響曲群の中に特殊な楽器編成の作品が混じっている事に気づいてからだ。例えば交響曲第12番・31番・39番そして第72番の4曲はいずれもホルンが4本用いられており、当時としては異例と言える。作曲家は「いまそこにある」合奏体の編成での演奏を前提に作品を仕上げる事が常態であって、ありもしない楽器を編成に加えて曲を作る事はしない。即座に演奏できない作品は無意味だった。
とすれば上記の4つの交響曲は、通常2人だったホルン奏者に対し、何らかの事情で2人が加わって4人のホルン奏者が揃うという特殊な事情の現出によって「その為に」ハイドンに作品を書くよう指示が下ったとの想像されてくる。
記録によるとエステルハージ家の宮廷楽団にホルン奏者が4人揃った時期は1763年8月~12月と1765年5月~翌66年2月の2度、最長でも13か月間に過ぎない。4つの交響曲はその短時日の期間に、他の作品を多作するのに並行して書かれたと想像するほかはない(交響曲の番号がまちまちなのは、作曲順に番号が付けられている訳では無い為である)。更にこれ以外にも4本のホルンを使っている作品が書かれている事実を知れば、「1日に5曲の交響曲」は流石にオーバーだとしても、ハイドンが目まぐるしく変化する状況の中で、新たな作品の創造を求められていた事だけは、この一例を見ても間違いない処だ。
そして主人にしてみれば、こうした無理難題への解決能力のある音楽家を手元に置いている事はひとつのステータスとなる(他人の能力を量る上での尺度は、いつの時代も質よりまず量だ)。その「業務命令」の内容とハイドンの対応を考えれば、多作は当然の帰結であった。その量以上に重要なのは、仕事の繰返しの中で絶えず創意を重ね、交響曲の洗練されたスタイルを確立した事である。
ハイドンといえど初期の作品にはシンフォニアの残照とでもいうべき3楽章構成の作品がいくつもあるが、それも一定の様式に固着せず、様々なスタイルが試みられている。その様な試行錯誤の繰返しの結果として4楽章 に構成が固まり、且つこの4つの楽章にそれぞれ異なった性格を初めて与えるに至る・・・・従来の交響曲で はシンフォニアの時代同様、楽章ごとの個性は重視されてはいなかった・・・・ハイドン以後の交響曲では余りに当然の要素になってしまったが故に、なかなか彼の創意に気づかずにいるが、これは重要な進化だった。
現代の我々がこの作曲家の交響曲群を見渡した時、例えばベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770~1827)に於ける『英雄』のように、ある作品を境にした特筆すべき飛躍を見出すのは難しい。だがともすると見落としてしまいがちな何らかの特徴が、独創が、工夫が各曲に必ずある。多作の中で培われる進歩とは本来そうしたものだ。むしろ多作を強いられる条件を、ハイドンは奇貨として活用していたと考えるほかはない。
◆転身と成功
1790年にハイドンはそれまでの宮廷音楽家の地位を離れウィーンに移る。間をおかずロンドンのオーケストラを主宰するヴァイオリン奏者ザロモン(Johann Peter Salomon 1742~1815)によって渡英の機会を得。それ以前から既に一部の作品群は出版され、名声は高まりつつあったのだ。
大作曲家の輩出という点ではやや見劣り感のあるイギリスだが18世紀末のこの時期、市民層の形成により、音楽作品は宮廷の奥で一部の人々が享受するものでは既になくなっていた。首都ロンドンは大規模かつ高質なオーケストラを擁した、新作音楽の一大消費地とでも評すべき都市に変貌を遂げている。限られた人々を対象に作品を書き続けていたハイドンにとって、かの地のオーケストラを前提に、不特定多数の聴衆の為に意識して作品を発表する「興行」は、自由人としての恩恵を物心両面で充分にもたらした。つまり彼は市民社会での作曲家への転身にこの時成功したのである。その失敗によって貧困の中で死んだモーツァルトの轍を踏まない幸運を彼は得たという事だ。
この充実の中で合計12曲の交響曲が新作された。現在交響曲第93番から第104番に数えられる作品群である。掉尾を飾る『ロンドン』はその2度目の渡英の折に作曲されている。既に60歳を過ぎていた作曲者。随所に見られる闊達な表現と構成の緻密さに、この都市に活躍の場を得た彼の得意をみる。
言うなればハイドンの交響曲は程よく抑制のきいた「良き趣味」が、人々の支持を得ていた時代の最後の産物なのかも知れない。決して派手さはない。だが彼以前そして彼以後の音楽史全般を頭に入れ、あらゆる音楽作品をひとわたり聴いた上で、改めてハイドンの作品群に目を転じると、改めてその存在の大きさに思い至る・・・・という立ち位置にあるように思える。
彼の完成させた交響曲というジャンルはベートーヴェンに引継がれると、人間感情のより強い発露の手段へと変質を余儀なくされる。『ロンドン』が初演された1795年の時点で、このあまりに人間的な後継者はまだ交響曲を書いていない(ハイドンの影響を強く受けたという第1交響曲が初演されたのは1800年)が、『第九』の初演は、『ロンドン』から30年足らずである。ハイドンが宮廷楽長として30年以上に亘って営々脈々と築き上げた交響曲のスタイルは、その後の同じ程度の時間の推移の間に劇的と言って良い大変容を遂げた訳である。社会構造の変化が、人々の音楽を含むあらゆる慾求を激変させ、それが交響曲の変貌に深く反映している事には論を俟たない。そしてその後の音楽も創作され続けられた・・・・だが、人々の刺激への慾求にはやがて限界が来る。その追求に倦み、疲弊してしまうのだ。これは生身の心身を持つ存在の宿命と言えよう。誰しもここから逃れきれない。
いたずらに奇矯に奔る事も特異な趣味を押し付ける事もなく、内心の辛苦を無理に隠す作り笑いも過剰な謙遜もない。それでいてユーモアもあるし、微笑ましい程度の悪戯っ気も備えている・・・・ハイドンの作品に触れると、どういう性格の人を終生の友人とすべきか?の回答も自ずと明らかになってくるように最近とみに感じている。
注1)有名な3声のインヴェンションは、2声のそれと区別して「シンフォニア」と呼ばれるが、ここでは管弦楽の為の作品に限定している。またこの作品は有名な『ブランデンブルグ協奏曲』第1番に転用(作品番号も同一)されているので、それを聴けば『シンフォニア』の性格を類推する事ができる。
注2)「交響曲」と「シンフォニア」とを区分する定義は非常に曖昧なまま放置されているのが実情のようだ。日本ではハイドン以降の作品に対しては、初期段階の作品で3楽章形式を採っていても「交響曲」としている。本稿でも仕方なくこの実情を前提に論を進める。解りにくい部分があるとすればそれは筆者の思考の整理に帰するものである。
主な参考文献
『福翁自伝』福澤諭吉 岩波文庫
『名曲解説全集』交響曲1 音楽之友社
『音楽史の点と線』岩井宏之 音楽之友社
『バッハの息子たち』久保田慶一 音楽之友社
『西洋音楽史』下 D.J.グラウト 音楽之友社
『音楽大事典』平凡社
『ウィーン音楽文化史』渡辺 護 音楽之友社
*以上の稿は2011年7月第214回演奏会の交響曲第101番『時計』に関する曲目解説原稿をベースとして、大幅に加筆・修正を施し、再構成したものです。
新響のチケットシステムについて
維持会の皆様、いつもありがとうございます。
2018年10月本番の第243回演奏会から新響ホルンパートの一員になりましたYと申します。第244回からチケット係を、前回第247回からは広報も担当しています。
松下編集長から「『新響維持会ニュース』の執筆陣の若返りも図りたい」とご指名頂きました。若いかどうか微妙な年代ですが、新響では確かに若いほうで、平成元年生まれです。もっと若い20代の団員も活躍しているので、次々とバトンタッチできれば良いなと思っております。そして20年後くらいに令和生まれの団員が入ってくることを、だいぶ気が早いですが今から心待ちにしています。
今回の執筆依頼を機に今までの『維持会ニュース』を読み返してみました。1996年1月の第151回演奏会以降は新響ホームページの過去の演奏会ページに「維持会ニュースより」として掲載されています。
知識も経験も豊富な先輩方による個性的でディープな内容ばかりですが、チケットについては私が確認できた範囲では誰も書いていないようです。歴代チケット係の苦労話など、本当は私が一番聞きたいのですが・・・・。
私が現状を書きますので、5年後10年後50年後100年後!?のチケット係が、昔はこんなことやっていたのかと面白がって読んでくれていたら嬉しいです。詳しい技術は分かりませんが、10年も経てば、もしかしたら紙のチケットはほぼ廃止され、今のスマートフォンよりさらに進化したデバイスで入場するようになって、チケット係は入場システム管理係のようなものになるかもしれませんね。実際に今でも、紙のチケット代わりにスマートフォンで表示したコードを読み取るような演奏会もあります。紙のチケットが完全になくなるのは寂しいですが、このようなシステムが導入される日も近いかもしれません。
◆皆様のお手元にチケットが届くまで
果たして維持会の皆様にも興味をお持ち頂ける内容なのか不安ですが書いてみます。
①本番4ヶ月前
新響がお世話になっている音楽事務所であるコンサートイマジンさん(以下イマジンさん)に演奏会情報を伝えチケットを発注します。東京芸術劇場だと1,999席分です。
完成したチケットはイマジンさん扱い分(電話窓口、劇場窓口、インターネット窓口=チケットぴあさん)と、新響扱い分に分けて頂きます。
②本番約3ヶ月前(1つ前の演奏会の本番前後)
イマジンさんから新響扱い分のチケットを受けとります。内容を確認したあと、席種ごとに仕分けします。
ちなみに新響扱い分のチケットの額面上の総額は約400万円!チケットを受け取った直後に家の引っ越しがあった時は、チケットの束を無くさないか心配でしたが貴重品扱いで大切に運び、10月の超大型台風の時は例え窓ガラスが割れたとしても楽器と楽譜とチケットだけは守れるように防水して安全な場所に置きました。
③初回練習日~当日リハーサル前まで
団員用チケットを配布します。この方法は後ほどご説明します。
④本番1~2週間前
維持会の皆様からのお申込を元に維持会席数を確定し、チケットを係に渡します。
⑥演奏会当日
維持会窓口に座席表をご用意し、先着順で座席をお選び頂き、チケットをお渡しします。入り口でもぎって、いよいよ開演です。
◆チケット管理システムについて
私がチケット係になって、ちょっとした改革を始めました。
まず改革その1、チケット管理システムの刷新です。私の前の担当者まではExcelマクロを駆使した何だかすごいシステムを使っていたのですが、座席番号(席番)で検索ができないという弱点がありました。おそらくマクロのための理由があったのでしょうが、階数・何列目・何番が全て別の列になっていました。全席リスト化はされているのですが、タブの切り替えとスクロールがとても多い状態で、該当の席を探すのが手間でした。
仕組みがよく分からない部分もあったので過去のシステムは使わずに、新しく自分で分かるようなシステムを作り始めました。システムといってもプログラム言語やExcelマクロは使わず、簡単なExcel関数と手入力が元になっています。
まず、検索がしやすいように、1つの席番は1つのセルにすることにしました。例えば2階A列3番という席だったら、過去のシステムは[2]というセルと[A]というセルと[3]というセルに分かれていたのですが、私は1つのセルに[2A3]と短縮した席番を入力しています。1つのセルに入った文字列はCtrl+Fで簡単に検索できます。
Excelで2行1セットの四角を作り、上の行は席番・下の行は団員名を入れる欄としました。その四角を座席数に合わせて配置し、座席表にしました。団員から申し込みがあると、内容に沿って座席表の空欄に名前を入力する作業をします。名前を入力したら上の行の席番をコピーし、別のシートに貼り付け、団員に渡す封筒用のラベルを作っています。その封筒のラベルを元にチケットの束から該当のチケットを探し出し、封筒に入れて毎週の練習で団員に配布しています。
◆団員チケットについて
第244回までは団員からのチケットの申し込み方法はメールか練習日に置く所定用紙のみでしたが、第245回からは申し込みフォームを導入しました。改革その2です。団員のみに公開しているURLにアクセスすると希望する席種・枚数・要望などの入力ができるようになっています。
メールよりも必要事項が分かりやすく団員からも好評で、私も入力形式が決まっているので確認しやすいです。
第246回からはホールの全エリアを細かくブロック分けし、ブロックごとの残席数を団員に伝えています。チケット管理システムの座席表の空席に色付けしたものも申し込みフォームに載せ、細かい希望にも応えられるようにしています。これが改革その3です。Excel関数を使ってブロックごとの残席数をカウントし、空席に自動で色をつけていますが、最初は知らない関数ばかりでした。こういう機能ないかなと調べているうちにExcelに少し詳しくなりました。マクロを使わないと以前のシステムほど自動化はできませんが、少しずつ使いやすいシステムに改革しています。
将来的には、映画館の座席予約のように、団員が空席をリアルタイムに確認しながら希望の座席を押さえていくようにしたいと思っております。そのようなシステムを作れそうな団員に相談しているところです。
◆広報について
広報としては第247回から公式Instagramを開設しました。
2019年8月1日に開設して第247回本番当日10月13日までの2ヵ月半でフォロワー数が120名を超えました。12月10日時点でのフォロワー数は150名です。
Facebook・Twitterもそれぞれ担当の団員が更新しています。良かったらご覧下さい。
・公式Instagram https://www.instagram.com/shinkyo_pr/
・公式Facebook https://www.facebook.com/shinkyo.tokyo/
・公式Twitter https://twitter.com/shinkyo_tokyo
コンサートスクウェア・ぶらあぼなど各種演奏会情報掲示板での宣伝もしています。
他のアマオケだと「チラシ挟み」と呼ばれる、演奏会のチラシを他の団体の演奏会のパンフレットに依頼して挟む宣伝活動がありますが、新響ではその活動は全てコンサートイマジンさんに委託しています。
◆新響入団1年半を経て
2018年の7月の練習から新響に参加して1年半が経過しました。
約100名の団員の名前はチケットをご用意する内に大体覚えました。全団員との接点が増えたのがチケット係を担当して良かったことの1つです。
入団する前まで高校と大学のOBオーケストラという狭い範囲での活動が中心だった私にとって、新響の本番は初体験の連続です。初めてのブルックナー作品&ワグナーチューバパ―ト担当(第243回)、初めてのバンダパート演奏(第244回『トリスタンとイゾルデ』第2幕冒頭)、初めての芥川先生作品&バルトーク作品(第245回)、初めてのバーンスタン作品(第246回)などです。指揮者の先生方も全員初めての共演でした。毎回指揮者もコンセプトも変わりますが、全てが特別な演奏会として強く印象に残っています。
新響の団員募集ページには「常に新しい視点をもって活動をしていくために、新しい力を必要としています」と書いてあります。私には何もできないと思っていましたが、チケット係に関してはご紹介しましたように「新しい視点」で少しずつ工夫をしています。
技術面では他のベテランメンバーに比べると経験も技術もまだまだ足りないのですが、バンダで出番が一瞬だけの曲も含めると、第243回から第247回まで5回連続で全曲に乗せて頂きました。席数が限られている管楽器では珍しいことです。1月の第248回は前半2曲ともホルンが2管なので、ハイドンが初めての降り番ですが、『魔笛』序曲では新響に入団してから初めて1stの席に座ります。
今後も運営面でも技術面でも技術を磨いてさらなる高みを目指していきたいと思っております。よろしくお願いします。
第248回演奏会のご案内
今回は名曲コンサート
指揮に飯守泰次郎氏を迎え、クラシック音楽の王道ともいうべき大作曲家の名曲を演奏します。モーツァルト、ハイドン、チャイコフスキーという作曲家の名前は皆さんご存知と思います。その代表曲をプログラミングしました。
ウィーン古典派~モーツァルト、ハイドン
コンサートの前半は、ウィーン古典派の名曲を2曲。古典派とは、18世紀から19世紀初頭の音楽で、最大の特徴は“ソナタ形式”というスタイルです。通奏低音がなくなったことでメロディがわかりやすく軽快になり、楽器も発達し現在の管弦楽に近い形となってきました。それまでは教会や王侯貴族のためにあった音楽が市民が楽しむための音楽へと変わってきたのです。200年以上たっても新鮮で、現在も親しまれています。
モーツァルトは “神童”として幼くして作曲を始めており、35歳で亡くなるも、交響曲や室内楽曲など数多くの作品を残しました。「魔笛」は亡くなる2か月前に完成した最後のオペラで、大ヒットしました。当時はイタリア語のオペラが一般的でしたが、この台本はドイツ語で書かれており、ドイツオペラの祖となっています。王子が王女を救うために魔法の笛の力を使い試練を乗り越えるという、大蛇や夜の女王などが登場する楽しくメルヘンなお話です。
ハイドンはモーツァルトより24歳年上で77歳まで長生きし、モーツァルトと同様に数多くの作品を残しました。“交響曲の父”と呼ばれていますが、100を超えるハイドンの交響曲のうち、4種の木管とホルン、トランペット、ティンパニがそろっているのは第99番以降のみであり、今回演奏する第104番は最後の交響曲でハイドンの集大成ともいうべき作品で、とても活き活きとした躍動的な曲です。ロンドンを訪問した時に作曲・初演されて大成功を収めており、のちに「ロンドン」という愛称がつけられました。
古典派からロマン派へ~チャイコフスキー
演奏会の後半は、ロシアの大作曲家チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」です。
古典派音楽はベートーヴェンの後、ロマン派へと発展していきます。古典派の形式を受け継ぎながらも、多彩な転調や感情表現、テーマ性を持つようになり、オーケストラの規模が拡大、世界に広がって各地で民族音楽と結びついた国民楽派が生まれました。その代表的な作曲家がチャイコフスキーです。
交響曲第6番の初演の9日後に亡くなり遺作となりましたが、急死(コレラという説が有力)だったため死を覚悟して作曲されたわけではないでしょうが、心臓の鼓動が消えるように終わります。「悲愴」という副題はチャイコフスキー自身が付けたものですが、ロシア語を日本語に直訳すると熱情的という意味になるそうで、自身は最高傑作と考えていました。
特に日本人にはチャイコフスキーを好きな人が多いと言われています。メロディが親しみやすくどこか懐かしい感じがするのは、隣の国だからかもしれません。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
ドヴォルザーク:連作交響詩「水の精」、「真昼の魔女」、「金の紡ぎ車」、「野鳩」、「英雄の歌」
はじめに
今回お送りするのは、ドヴォルザークが晩年の連続した期間に作曲した5つの交響詩である。交響詩においては交響曲に比べるとはっきりとした、言わば元ネタとなるようなストーリーなどが存在する場合がある(後述「ドヴォルザークと交響詩」参照)。今回演奏する5曲のうちはじめの4曲--『水の精』『真昼の魔女』『金の紡ぎ車』『野鳩』はそれぞれが一篇の詩に依っている。今回、演奏会の全曲の解説を書かせていただけるという僥倖に恵まれたので、気になる項目だけ拾い読みしても読みやすい構成とした。順番にこだわらず、お好きなところから読んでいただきたい。
ドヴォルザークの生涯
ドヴォルザークは1841年、チェコのプラハから30kmほど離れた小さな村に生まれた。幼い頃から音楽に囲まれて育ち、16歳になってプラハのオルガン学校でオルガンの演奏、音楽理論や作曲を学んだ後に音楽家として本格的な活動を始めた。30代半ばごろから頭角を現し、40~50代にかけては音楽家としての最盛期を迎え、国際的にも大作曲家の一人として認められるようになった。そうしたなかで1892年にプラハ音楽院で教鞭をとりはじめると、今度は「新世界」アメリカのナショナル音楽院から招聘の手紙が彼の元へ舞い込む。ボヘミアに強い愛着を持っていたドヴォルザークが異国からの誘いに応じたのは、かなりの蒸気機関車好きだったと言われる彼のアメリカ大陸横断鉄道への興味があったためかもしれない。アメリカに渡ってからのドヴォルザークは、当地の黒人や先住民の音楽に近づいた。今日では考えられないほど強い人種差別的偏見が広く浸透していた当時においてその試みが困難なものであったことは容易に想像されるが、最終的に広く受け入れられるようになったことは交響曲第9番『新世界より』の成功をみれば明らかである。アメリカの黒人霊歌から大いに着想を得たこの交響曲は、アメリカの人々に熱狂的な喝采をもって受け入れられた。そんな中でも、次第にドヴォルザークはアメリカでの生活を苦に感じるようになっていった。幼い頃からボヘミアの音楽の中で過ごし、育ってきた音楽家である。当然といえば当然ではあるが、この頃の作品からはアメリカの文化を取り込もうという姿勢よりもボヘミアへの強い郷愁が感じられる。
帰国した1895年からの約10年間で、ドヴォルザークは今回取り上げる5つの交響詩以外にも4つのオペラを含む多くの作品を書き上げているが、その中には民族的な要素が多く見られる。特にチェコ周辺の国々に広く伝わる水の精の民話を元にしたオペラ『ルサルカ』は、ドヴォルザークが作曲中に滞在したチェコのヴィソカーの森にある神秘的な湖の風景から得られたインスピレーションによって生み出された傑作である。時の皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の喝采をも得たこの作品は、今なおチェコ・オペラのなかで最も人気の高い作品の一つである。世に送り出した作品が次々と成功を収める中で新たな題材の選択に困難を強いられたドヴォルザークは、それからしばらく作曲から遠ざかる。1年2ヶ月ものブランクを経て書き上げた最後のオペラ『アルミダ』が1904年3月に初演されるも、大きな支持は得られないままその年の5月に62年の生涯を閉じることとなった。
ドヴォルザークと交響詩
ドヴォルザークが初めて交響詩の形式による作曲に手を染めたのは、1891年、『自然と人生と愛』であったと言えるだろう。3曲の演奏会用序曲『自然のなかで』『謝肉祭』『オセロ』からなり、それぞれ独立しているが共通した「自然」というテーマが統一性をもたせている作品である。演奏会用序曲というのは、演奏会で単体で演奏されるように書かれた曲のうち、オペラの序曲がストーリーを彷彿とさせるのと同様にテーマやストーリー、すなわり標題をもたせて作られた曲のことである。交響詩はこの演奏会用序曲と同じ「標題音楽」に分類することができる。音楽は絶対音楽と標題音楽とに大別されるが、 前者は「人の持つ人性の内的な営みを,一般的情調として,これを象徴的に記述しようとした音楽」すなわち抽象的に世界を描いたものであるのに対し、後者は「ある特定の感情を具体的に表出しよう」とし、「ある特定の人物の性格・言動・経験などや,事物の景観や事件をも音化しようとするもの」(いずれも石桁真礼生『新版 楽式論』より)と説明される。
『自然と人生と愛』を書いた時点ではドヴォルザークは絶対音楽に近い立場をとり、標題を楽想に優先させることをためらっていたらしい。しかしこれ以前の作品にも具体的な描写や明確な感情が現れている(交響曲第8番など)ことからすると、彼がその後改めて「交響詩」というジャンルに取り組んだことは自然に思われる。
『自然と人生と愛』から5年後、アメリカから帰国したドヴォルザークはかつて『幽霊の花嫁』の題材を得たエルベン(後述)の民族詩集『花束』に再び題材を求め、4つの交響詩を次々と生み出していく。これらの作品には題材としたエルベンの詩に対する執着とも言えるこだわりが感じられる。大まかなストーリーだけでなく一つ一つのセリフ、言葉に至るまでを忠実に表現しているのである。残念ながらチェコ語の素養がない私にはわからないが、曲の旋律にのせて詩を歌うことが可能な部分も曲中にあるという。生前から親交を深めた同郷の音楽家ヤナーチェクはこうした手法を称賛し、これを手本とした話し言葉の抑揚に基づく「発話旋律」をひとつの作曲手法として昇華させている。
4曲のうち『金の紡ぎ車』だけは早くからカンタータ(交声曲)としての作曲を考えていたものの、渡米によって中断したのち帰国後にようやくとりかかったらしい。驚くべきはその作曲ペースで、『水の精』『真昼の魔女』『金の紡ぎ車』は1896年の1月に半月ほどの短期間で次々とスケッチを書き上げ、4月までに相次いで完成させている。その年の10月には『野鳩』の作曲にも取り掛かり、翌11月には完成させた。こうしたことからもチェコの民話に基づいたこれらの曲に対するドヴォルザークの情熱が感じられる。ちなみに、連続して作られた初めの3曲に関しては、ドヴォルザークは3曲をひとまとまりに考えていたようである。
それから約一年後、再びペンをとったドヴォルザークは新たな交響詩の作曲に取り掛かる。最後の管弦楽曲にもなったこの『英雄の歌』はそれまでの4曲とは大きく異なり、エルベンの詩に着想を得たものではない。しかしながらボヘミアの民俗的なテーマが織りなすこの曲は、しばしば作曲したドヴォルザーク自身の人生に対照されたり、あるいは直前に帰らぬ人となった親友ブラームスの死に影響されたとも言われる。
ドヴォルザークは旧来の絶対音楽の形式をなるべく引き継ぎながら標題音楽に取り組んだが、具体的な表現に取り組んだことを考えると、同じく比較的具体性の高いテーマを持ったバレエ音楽を書く気を起こさなかったことが不思議にも思えてくる。『白鳥の湖』『くるみ割り人形』などのバレエ音楽の傑作を残したチャイコフスキーとの親交があり、しかもチャイコフスキーが『白鳥の湖』を書いた年に彼と会っているのだから、存在を知らなかったわけではないだろう。『白鳥の湖』ではドヴォルザークの興味をバレエに向けるに足りなかったのであろうか…
エルベン
エルベンはドヴォルザークがちょうど生まれた頃に活躍していたチェコの詩人、歴史家で民話の収集・研究家である。1811年、プラハ北東のミレティーンに生まれ、プラハで哲学・法学を修めたのち、1837年から裁判所の書記官として働き始める。その後プラハ市の初代の古文書保存官となり、一般には知られていない貴重な文献に触れながら、チェコ国内を旅行して各地の民話・民謡を積極的に収集した。1870年に亡くなるまでチェコ語にまつわる多種多様な資料の発掘に取り組み、その葬儀は壮大な国民的行事であったという。民話の収集においては、仕事中の年老いた人々が口ずさむ歌に耳を傾け、羊飼いたちの話を聞き、多数の材料を集めた。その活動から、エルベンは「チェコのグリム」と呼ばれることもある。今回の『水の精』など4曲の元となった『花束』は1858年に発表された、民話・民謡のテーマを歌い込んだ詩集である。これは「バラッド(語られる詩)」と呼ばれる物語詩で、テーマとしては暗く陰鬱で、悲劇的なものが多い。エルベンは民話・民謡をそのまま詩としてまとめるのではなく、自ら手を加えて緊張感あふれる詩篇に仕上げている。『花束』はチェコにおいては学校で取り上げられるほどポピュラーな作品であり(その割に日本語の文献は非常に限られていて執筆者泣かせであった)、ドヴォルザークやヤナーチェクと言った音楽家に限らず多くの詩人たちの作品や映画など、後世に多大な影響を与えている。
ドヴォルザークとブラームス
ブラームスはドヴォルザークより8つ年上の、「ドイツ3大B」の一人にも数えられるドイツの大作曲家である。二人の出会い--というよりはブラームスによるドヴォルザークの発見というべきかもしれないが--は1874年、ドヴォルザークが作曲家として世に広く知られるよりも前のことであった。そのころ、ドヴォルザークはヴィオラ奏者として働いていた楽団をやめ、収入の低い教会のオルガニストになる代わりに作曲の時間を多く確保して沢山の曲を書いていた。それでも新婚で生活に困窮していたドヴォルザークは、友人の勧めでオーストリア文化省の奨学金に応募する。この奨学金の審査員を務めていたのが、ブラームスだったのだ。ブラームスはドヴォルザークの稀代の才能を見抜き、奨学金選考会でドヴォルザークの後押しをしたようである。ドヴォルザークはそれから何年か続けて奨学金を得るのだが、4年目の1877年に、ブラームスへ手紙を送っている。その内容は、選考会での後押しの礼を述べるとともに、ブラームスの支援を求めるものであった。当初からドヴォルザークの曲に興味を示していたブラームスはこの願いを快く聞き入れ、自分の作品の出版元であるベルリンのジムロック社の社長に紹介したのだった。このブラームスの取次によってドヴォルザークの曲がヨーロッパ各国で人気となり、その地位と名声を高め安定した収入をもたらしたことを考えれば、ブラームスはドヴォルザークの大恩人ということになるだろう。それからも二人の交流は生涯にわたって続いた。二人が顔を合わせた回数は決して多くはなかったが、互いに率直に意見を述べあい、称賛し合うよき友人だったらしい。ブラームスはドヴォルザークについてこんな言葉を残している。「あの男は、我々の仲間の誰よりも発想が豊かである。彼の捨てた素材をかき集めるだけで、主題をつなげていくことができる。」ドヴォルザークがアメリカへ渡っていた時期にもやり取りを欠かさず、音楽面でもサポートしていたブラームスだが、1897年に帰らぬ人となってしまう。その直後に書かれたことから、5曲目の交響詩『英雄の歌』はブラームスの死に影響されてその生涯を音楽に描き出したのではないかとも言われるが、真偽は定かではない。
ここからはそれぞれの曲についてもう少し詳細な解説を加えていく。末尾のエルベンの詩と合わせて鑑賞の一助としていただければ幸いである。
『水の精』
日本語では「水の精」と訳されるヴォドニーク(vodník)だが、これは一般に妖精と聞いてイメージされるような美しい人型をした精ではない。むしろ現地の人からすると我々の河童に対するイメージが割と近いらしい。ロシアや東欧諸国をはじめとするスラブ語族の人々の間で古代より親交されてきた低位の水神、あるいは水の精で、魚の世界を支配している。ロシアではヴォジャノーイの名前で知られており、体は鱗で覆われ、指の間には膜があり、目は火のように赤いというからなんとも恐ろしい河童である。「精」と聞くとなんとなく美しいものをイメージしがちだが、「精」(「精霊」ではない)のもつ本来の語義からすれば河童だって水の精なのである。特にこの作品における水の精は恐るべき水の世界の支配者として描かれているから、そこを履き違えては冒頭から登場する水の精のテーマの印象が違ってくるだろう。同時に流れてくる2ndバイオリンの16分音符が、なんとも言えない不安と恐怖に満ちた雰囲気を醸し出す。
ホルンのFisに導かれるようにして場面が変わると、そこには湖に惹かれていってしまう娘と母の姿が。正気ではないのであろう、心ここに在らずといった感じの娘のテーマと、恐れや悲しみといった感情のなかに懇願する様子が垣間見える母のテーマはそれぞれの登場人物の感情を驚くほど明らかに表現している。その後これらのテーマを中心として曲は詩と同様に劇的に展開していく。
初演:1896年11月14日 ヘンリー・J・ウッド指揮
編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、イングリッシュホルン、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、チューバ2、ティンパニ、グロッケンシュピール、トライアングル、シンバル、大太鼓、タムタム、弦5部
『真昼の魔女』
この曲はドヴォルザークの交響詩の中で最も簡潔で--きっと元のエルベンの詩が短いためである--、非常にわかりやすくどこかディズニーのアニメーション音楽のような雰囲気をもっている。曲にそのまま映像をつけるだけで立派なアニメーションになりそうだ。はじめのテーマで聴く者を物語の世界に引き込み、一人一人の登場人物に与えられた明確なモティーフとともに劇的にストーリーが展開されていくあたりはいかにもアニメーション的である。母の気を引こうと駄々をこねる子供、それを慈愛に満ちた声でなだめる母、そして突如現れた魔女といった一つ一つの場面がはっきりと繰り広げられていく。また、冒頭の穏やかなお昼頃の雰囲気や家族の待つはずの自宅へうきうきとした足取りで戻ってくる父親など、詩では直接語られない部分もありありと描写することで、より一層音楽を聴く者を物語に没入させる力を強めている。
初演:1896年11月21日 ヘンリー・J・ウッド指揮
編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、ベル、トライアングル、シンバル、大太鼓、弦5部
『金の紡ぎ車』
この曲はもっとも長いストーリーを背景に持ち、それ故に冗長だと酷評されることもあるが、それでもドヴォルザークの交響詩らしい、詩の描写に忠実な表現が見られる作品である。おとぎ話にありがちなストーリーの繰り返し(場面4など)がみられるエルベンの詩にドヴォルザークはこだわり、一つ一つの場面を音で表現しきっている。文字で描かれた詩の情景を見事に音楽化したドヴォルザークの手法は称賛に値するだろう。ヴァイオリンソロで紡がれる繊細なドルニチカ(主人公である娘)の姿や、4分の3拍子で小気味好く回る紡ぎ車など随所にドヴォルザークらしさが現れている曲である。
初演:1896年10月26日 ハンス・リヒター指揮
編成:フルート2(1番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、イングリッシュホルン、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、トライアングル、シンバル、大太鼓、ハープ、弦5部
『野鳩』
この曲もエルベンの詩を元に書かれたものの、前の3曲がひとまとまりとしてドヴォルザークに意識されていたのに対して、少し後から単独で書かれたものである。それでも、前の3曲を書いていた頃から構想は練っていたようだから、やはりエルベンの詩集を元に短期間に集中して書かれた交響詩としてまとめて扱っても問題ないだろう。これまでの3曲とは異なり「呪い」がはっきりとしたテーマに据えられているのが特徴的だ。冒頭から葬送行進曲のリズムを表すホルンとティンパニに導かれて、フルートとヴァイオリンによる未亡人のテーマが歌われる。これが曲全体の核となっていく。エルベンの詩の冒頭では、未亡人の涙が実は偽りの涙であり、彼女が夫を毒殺したのだという事実が知らされていないが、ドヴォルザークは葬送行進曲の中に「運命の動機」と名付けた主題でそれを暗示している。この罪の意識は何度か繰り返され、未亡人の苦しみを克明に描写している。
初演:1898年3月20日 レオシュ・ヤナーチェク指揮
編成:フルート2(1番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、イングリッシュホルン、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、トライアングル、シンバル、大太鼓、タンブリン、ハープ、弦5部
『英雄の歌』
この曲は、エルベンの詩ではなく作曲者自身が描いた詩的なテーマを音楽として紡いでいるという点において他の4曲とは大きく異なる。すでにいくつかの項し触れたが、その自伝的な内容や作曲時期から、この曲はドヴォルザーク自身の生涯を描いているとも、親友ブラームスの生涯を描いているとも言われるが、どちらの説も決め手に欠けるようだ。いずれにせよ重要なのは一人の英雄の生涯を見事に描いた作品であるという点だ。構想の段階では『英雄の生涯』、ついで『英雄礼讃』と題され、ドヴォルザークの弟子ノヴァークが『英雄の歌』を推すまで『勝利の歌』とされたこともある。序奏に続く主要な3つのセクションからなる、交響曲を思わせる4部構成となっている。序奏では自信に満ちた若き英雄の姿が表現され、続く第1部では打撃を受けた英雄の悲嘆の歌と失望を、第2部では慰めと自信の回復を、第3部では英雄の反撃と勝利の歌を描写している。
初演:1898年12月4日 グスタフ・マーラー指揮
編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、トライアングル、シンバル、大太鼓、弦5部
参考文献
石桁真礼生 『新版 楽式論』 音楽之友社 1998年
ギー・エリスマン (福元啓二郎) 『不滅の大作曲家 ドヴォルジャーク』 音楽之友社 1975年
属啓成 『ドヴォルザーク 音楽写真文庫Ⅷ』 音楽之友社 1963年
クルト・ホノルカ (岡本和子) 『<大作曲家> ドヴォルザーク』 音楽之友社 1994年
内藤久子 『作曲家 人と作品 ドヴォルジャーク』 音楽之友社 2004年
Stephen Scott Johnson, NARRATIVE AND FORM IN DVORAK'S SYMPHONIC POEMS BASED ON THE FOLK POETRY OF KAREL JAROMIR ERBEN , 1997
「新版 ロシアを知る事典」
世界文学事典 集英社 編者 『世界文学事典』編集委員会 2002年
増補改訂 新潮世界文学辞典 編集 新潮社辞典編集部 1990年
「金色の髪のお姫様 チェコの昔話集」 カレル・ヤロミール・エルベン文、アルトゥシ・シャイネル絵、木村有子 訳 岩波書店 2012年
カレル・ヤロミール・エルベン編 出久根育 絵 阿部賢一 訳 「命の水 チェコの民話集」 西村書店 2017年
文章、挿絵 Lucie Lemová(ルツィエ・ロモヴァー) 翻訳 Mgr. Jan Budka 「貴重なチェコの童話」 PRAH 2008年
第247回演奏会に向けて
10月のコンサートはドヴォルザークの交響詩5曲という驚きのプログラム。チェコだってこんなプログラムはなかなかやらないでしょう。めったに演奏されない曲を一気に聴ける千載一遇のチャンスです。とはいえ知名度の低い曲、興味を持てないとなかなか足が向かないかもしれません。この記事は、これらの曲について好き勝手に書き散らかして少しでも興味を持っていただこうという趣旨です。ですからドヴォルザークに関する知識が豊富な方は笑いながら読み飛ばしてください。
1.ドヴォルザークの知られざる作品たち
ドヴォルザークの曲でよく知っている曲は?と問われれば、多くの方は、スラブ舞曲、『新世界より』、チェロ協奏曲、弦楽四重奏曲『アメリカ』、『ユーモレスク』と答えるのではないでしょうか。そのほか交響曲第8番、7番、6番やいくつかの円熟してからの室内楽曲や序曲くらいは知られていますが、若い頃の曲はあまり聴かれません。ドヴォルザークがブラームスに出会ってスラブ舞曲の作曲を勧められる以前はワーグナーの影響を露骨に受けていて、交響曲第1番、2番などはいずれもブルックナーかと思うような1時間ほどの物々しい曲を書いていたのです。また、交響曲第3番、4番、5番は、演奏時間は並みですがローエングリンやタンホイザーにそっくりなフレーズが顔を出したりして思わずニヤリとしてしまいます。第4番の二楽章冒頭を聴くと、一瞬タンホイザー序曲が始まったのかとびっくりします。そう、実は彼はブルックナーに負けないくらいのワグネリアンだったのです。とはいえ、それらは十分に聴き応えがある佳曲です。ぜひ聴いてみてください。
URL1.交響曲第4番第二楽章https://youtu.be/DaXP_-gnV8I?t=767
さて、ドヴォルザークのオペラとなると知っている方はもっと減るでしょう。私は10年以上前になりますが、ドヴォルザークのオペラ『ルサルカ』の中のアリアが収録されたCDでそれを知り、その美しさに感激しました。
URL2.「ルサルカ」より月に寄せる歌https://www.youtube.com/watch?v=YSLMRtUi_dI
この『ルサルカ』、1900年の作曲で『新世界より』やチェロ協奏曲の後の曲、つまり最晩年の作ということになります。アメリカから祖国チェコに戻ったドヴォルザークの作品について何も知らなったことに気が付いて調べたところ、交響詩を5曲、オペラを4曲も作曲していたのです。あの『新世界より』とチェロ協奏曲の後に作曲したのなら聴き応えがある完成度の高い曲に違いない、と期待に胸を膨らませて早速CDを購入し、まず一曲目の『ヴォドニク(水の精)』を聴きました。いきなり親しみやすいメロディーで木管が大活躍、さすがドヴォルザーク、あまり知られていないのはどうしてだろう、といぶかりながら聴き進めるうちに、まるで森で迷ったように堂々巡りをしている気分に。ここはさっき聴いたメロディーだけど?まだやっているの?みたいな感じでなかなか終わらないのです。“高い完成度・巨匠の円熟”?そんなものは無関係といった印象です。2曲目の『真昼の魔女』。これもすぐに鼻歌で歌えるメロディーで始まり、ご機嫌。途中怖い雰囲気になり、ここで魔女が出てきたのかな、なんて楽しく聴くうちにこの曲はちょうどよい長さで終了しました。でもこれも“大作曲家晩年の円熟の境地”とは遠い印象を受けました。3曲目『金の紡ぎ車』。またもや口ずさめるメロディーが次から次へと出てくるのですが、なんだかとりとめがない。それに、無意味な繰り返しがあるように感じる。なが~い。どうしたドヴォルザーク(笑)!4曲目『野鳩』、これはそれなりに有名な曲だけあって聴きごたえ抜群。同じことを繰り返しすぎのようなところもあるけれど、それも効果的。終結部はリヒャルト・シュトラウスの『四つの最後の歌』の終曲みたいな寂寥感が素晴らしいと感じました。そして、最後の『英雄の歌』。タイトルに英雄とあるだけあってカッコよく勇ましい部分もあるけれど、前半は悲劇の英雄といった趣の哀愁漂うメロディーが次から次へと出てくる。ドヴォルザークだなあ~という印象でした。これら5曲を聴いての感想は、クラシック音楽史上の最高峰ともいえる名曲『新世界より』やチェロ協奏曲を書いた後の大作曲家晩年の作として完成度や円熟といったものを期待すると裏切られるけれど、気になって仕方がない愛すべき曲たちといった印象でした。ちなみに、ドヴォルザークの主要な曲の作曲年を同時代の主要作曲家と並べて書くと以下のようになります。ドヴォルザークやチャイコフスキーが、マーラーやリヒャルト・シュトラウスの作品とほぼ同時期に作曲されていたことはちょっと驚きです。また、1888年は『ドン・ファン』、マーラー1番、チャイコフスキーの5番、1893年は新世界と悲愴が作曲されたクラシック音楽にとってとんでもない“特異年”だったことに気が付きます。さて、今回取り上げる5曲の交響詩は、マーラーの交響曲第2番『復活』とリヒャルト・シュトラウス『英雄の生涯』に挟まれた年に作曲されています。牧歌的なこれらの曲が新しい音楽の幕を開ける刺激的な曲とほぼ同じ時期に作曲されたということは少々不思議な気持ちになります。
ドヴォルザークとその周辺の名曲年表
:下線はドヴォルザークの曲 【 】内は重要な出来事
1873 交響曲第3番
1874 交響曲第4番、ワーグナー「神々の黄昏」、ブルックナー交響曲第4番第一稿
1876 ピアノ協奏曲、ブラームス交響曲第1番
1877 【ブラームスの目にとまる】
1878 【ブラームス宅を訪問】 スラブ舞曲第一集
1880 交響曲第6番、ヴァイオリン協奏曲
1882 ワーグナー「パルシファル」
1884 交響曲第7番
1885 ブラームス交響曲第4番
1887 ピアノ五重奏曲第2番
1888 R・シュトラウス 「ドン・ファン」、マーラー交響曲第1番、チャイコフスキー交響曲第5番
1889 交響曲第8番
1890 ブルックナー交響曲第8番第二稿
1891 序曲「謝肉祭」、ピアノ三重奏曲「ドゥムキー」
1892 【アメリカに渡る】
1893 交響曲第9番「新世界より」、弦楽四重奏曲「アメリカ」、チャイコフスキー交響曲第6番「悲愴」
1894 マーラー交響曲第2番、ブラームスクラリネットソナタ
1895 チェロ協奏曲、【チェコに帰国】
1896 交響詩「ヴォドニク(水の精)」「真昼の魔女」「金の紡ぎ車」「野鳩」、【ブラームス体調不良】
1897 交響詩「英雄の歌」、【ブラームス死去】
1898 リヒャルト・シュトラウス 「英雄の生涯」
1900 歌劇「ルサルカ」、マーラー交響曲第4番
1904 【ドヴォルザーク死去】
1905 リヒャルト・シュトラウス 「サロメ」
2.ブラームスとドヴォルザーク
ドヴォルザークは1877年にブラームスに認められて多くの支援を受けます。ドヴォルザークが作曲家として食べていけるようになったのもブラームスのおかげといってよいでしょう。大当たりしたスラブ舞曲の作曲を勧めたのもブラームスです。そして、その後ドヴォルザークの作品からワーグナー臭さが急に抜けます。交響曲第6番はブラームスの第2番との共通性が指摘されていますし、交響曲第7番もブラームスの第3番と共通するものがあるといわれています。ブラームス的な堅固で無駄のない構成の絶対音楽を書くようになります。そんなドヴォルザークがアメリカから帰国後なぜ交響詩のような標題音楽に転向し、よく言えば牧歌的で郷愁を誘う、わるく言えばぴりっとしない曲を連作することになったのか。私はこう考えたのです(注意:以下は単なる妄想であって確たる証拠はありません。)。すなわち、「交響曲第6番からチェロ協奏曲までの絶対音楽の傑作群はブラームスが添削したに違いない! 少なくともかなりのアドバイスは受けたのだろう」 と。ドヴォルザークはワグネリアンだったのだけれど、ブラームスに引き立てられて出世しました。“良い人”ドヴォルザークはそんな恩人に逆らうことはできないし、ブラームスの作品も素晴らしいし尊敬している。自分には絶対音楽における構成力が不足しているからアドバイスをもらうに越したことはない、と考えたのは自然ではないでしょうか。そこで、作品を書いてはブラームスに送って添削してもらっていたのではないか!と考えたわけです。そんなわけでブラームスに出会ってからは得意の魅惑的なメロディーを効率よく使用しつつ、ブラームス的な無駄のない堅固な構成の作品が発表できたのではないかと。その状況証拠としてブラームスの有名な発言があります。「彼(ドヴォルザーク)の屑籠をあされば、交響曲が一曲書けるだろう」。つまり、没にした(=屑籠に捨てた)ドヴォルザークのメロディーをブラームスは知っていたということになりませんか(こじつけ(笑))?
ところが、ドヴォルザークがチェロ協奏曲を書いてアメリカから祖国チェコに帰ったあと、ブラームスは体調を崩します。ちょうどそのころ作曲したのが今回演奏する最初の四つの交響詩なのです。ブラームスはもう添削してくれない。完全に独力で作曲することになったドヴォルザークは若いころからのワグネリアンの本領を隠さず発揮、まるでワーグナーの示導動機のような手法を使いながらもあふれ出るメロディーを詰め込んで、チェコの民話に基づく標題音楽(交響詩)を作曲したのでした。もはや交響曲のような堅固な構成などは考えもしなかったのではないでしょうか。ついにドヴォルザークは、ブラームスの呪縛と絶対音楽の呪縛から解き放たれ、再び自分の言葉だけで“饒舌”に語るようになったのです。
3.五つの交響詩から受ける印象
最後に、今回演奏する5曲の交響詩から受ける印象を書いてこの与太話を終わろうと思います。最初の4曲「ヴォドニク(水の精)」「真昼の魔女」「金の紡ぎ車」「野鳩」はチェコの民話を集めた詩集にある “コワーい”お話に沿って作曲されています。それぞれのストーリーはプログラムの解説に譲りますが、日本の昔ばなしでもグリム童話でもオリジナルはとても怖くて残酷ですね。それらと同じような感じです。妖怪や魔法使いも出てきます。まさにチェコ版の「日本昔ばなし」や「水木しげるの妖怪譚」といった趣です。音楽はそのお話をかなり忠実に追っていくのですが、おどろおどろしいメロディーは少なくて、前述のように鼻歌で歌いたくなるような親しみやすいものがたくさんです。この辺りが、怖いけれど愛すべき、水木しげるの妖怪を私に連想させてしまう理由かもしれません。また、「金の紡ぎ車」など繰り返しが多いということを書きましたが、お話のほうで同じようなことを3回繰り返すことになっている箇所ではそれを忠実になぞって同じ楽節を3回繰り返したりしているのです。律儀ですね。これがもしバレエ音楽だったら舞台上で3回繰り返すわけですからおそらく違和感はないのです。ですからできるだけストーリーに沿って場面を頭の中に描きながらお聴きになることをお勧めします。ここに簡単なストーリーが載っているサイトのURLをあげておきます。
URL 3 交響詩の解説とストーリー(大阪交響楽団HP)http://sym.jp/publics/index/269/detail=1/c_id=661/page661=2
最後の5曲目「英雄の歌」。この曲に具体的なストーリーはありません。ドヴォルザークは、自己の芸術の遍歴を表現しているというようなことを書き残してはいるのですが、実はブラームスのことを表しているのだという解釈もあるようです。また彼は、曲のタイトルであるチェコ語を他の言語に正しく訳すことは困難だ とも言っています。ちなみにこの曲のチェコ語タイトル“PÍSEŇ BOHATÝRSKÁ” をインターネットで訳すと “リッチソング、金持ちの歌、裕福の歌” なんて訳されてしまいます。ところで「英雄の・・・」といえばリヒャルト・シュトラウスの「英雄の生涯」が思い浮かびます。シュトラウスの曲は、成功した超エリート英雄の自慢話、一方ドヴォルザークのほうは、憂いに満ちた祖国の英雄物語といった印象です。欧州の中央で歴史に翻弄されてきたチェコに対する祖国愛というものを強く感じます。まるで、祖国フィンランドをたたえるシベリウスのフィンランディアに相当するような気もします。でもそこは優しいドヴォルザーク、それほどは勇ましくありませんが。この曲はドヴォルザークの最後の器楽曲で、そして一度聴いたら忘れられないメロディーが溢れた傑作といえましょう。これまであまり演奏されることがなかったのが不思議なくらいの名曲だと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。それでは10月13日演奏会場でお待ちしております。
第247回ローテーション
| 水の精 | 真昼の魔女 | 金の紡ぎ車 | 野鳩 | 英雄の歌 | |
| フルート1st | 岡田 | 吉田 | 吉田 | 松下 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 岡田 | 新井 | 吉田 | 岡田 |
| ピッコロ | 藤井 | 藤井 | - | - | - |
| オーボエ1st | 堀内 | 堀内 | 平戸 | 山口 | 岩城 |
| 2nd | 大山 | 大山 | 山口 | 岩城 | 平戸 |
| コールアングレ. | 平戸 | - | 堀内 | 堀内 | - |
| クラリネット1st | 進藤 | 末村 | 末村 | 品田 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 大藪 | 大藪 | 石綿 | 進藤 |
| バスクラリネット | 中條 | 中條 | - | 中條 | - |
| ファゴット1st | 浦 | 浦 | 松原 | 藤原 | 藤原 |
| 2nd | 松原 | 松原 | 浦 | 田川 | 田川 |
| コントラファゴット | - | - | 田川 | - | - |
| ホルン1st | 山口 | 山口 | 山口 | 大内 | 大内 |
| 2nd | 大原 | 大原 | 大原 | 山路 | 山路 |
| 3rd | 名倉 | 名倉 | 名倉 | 大原 | 大原 |
| 4th | 山路 | 山路 | 山路 | 市川 | 市川 |
| トランペット1st | 倉田 | 倉田 | 野崎 | 小出 | 小出 |
| 2nd | 北村 | 北村 | 中川 | 中川 | 野崎 |
| バンダ | - | - | - | 1野崎、2倉田、3北村 | - |
| トロンボーン1st | 日比野 | 日比野 | 日比野 | 日比野 | 日比野 |
| 2nd | 武田香 | 武田香 | 武田香 | 志村 | 志村 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 岡田 | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 | 土田 | 土田 |
| テューバ2nd | 賛助 | - | - | - | - |
| ティンパニ | 桑形 | 桑形 | 桑形 | 桑形 | 桑形 |
| シンバル | 鈴木* | 鈴木* | 鈴木* | 今尾 | 今尾 |
| 大太鼓 | 山本 | 山本 | 山本 | 鈴木* | 鈴木* |
| トライアングル | 今尾 | 今尾 | 今尾 | 山本 | 山本 |
| 他打楽器 | ドラ,鐘/山田* | 鐘/山田* | - | タンバリン/賛助 | - |
| ハープ | - | - | 見尾田* | 見尾田* | - |
| 1stヴァイオリン | 内田智(堀内) | 内田智(堀内) | 内田智(堀内) | 堀内(内田智) | 堀内(内田智) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(今村) | 小松(今村) | 小松(今村) | 小松(今村) | 小松(今村) |
| ヴィオラ | 村原(田川) | 村原(田川) | 村原(田川) | 村原(田川) | 村原(田川) |
| チェロ | 柳部(安藤) | 柳部(安藤) | 柳部(安藤) | 柳部(安田浩) | 柳部(安田浩) |
| コントラバス | 宮田(中野) | 宮田(中野) | 宮田(中野) | 中野(宮田) | 中野(宮田) |
*は賛助
弦()はトップサイド
第246回ローテーション
| ベルリオーズ | プロコフィエフ | バーンスタイン | |
| フルート1st | 吉田 | 松下 | 岡田 |
| 2nd | 新井 | 兼子 | 兼子 |
| 3rd | 兼子(Picc) | 岡田(Picc) | 松下(Picc) |
| オーボエ1st | 平戸 | 堀内 | 堀内 |
| 2nd | 岩城(C.I.) | 平戸 | 平戸 |
| C.I. | - | 山口 | 山口 |
| クラリネット1st | 品田 | 高梨 | 高梨 |
| 2nd | 末村 | 大藪 | 石綿 |
| Esクラリネット | - | - | 大藪 | BassCl | - | 進藤 | 進藤 |
| ファゴット1st | 藤原 | 田川 | 浦 |
| 2nd | 松原 | 浦 | 松原 |
| 3rd | 浦 | 藤原(Contra) | 田川(Contra) |
| ホルン1st | 名倉 | 山口 | 大内 |
| 2nd | 大原 | 名倉 | 山路 |
| 3rd | 大内 | 大原 | 山口 |
| 4th | 山路 | 市川 | 市川 |
| 5th | - | 山路 | - |
| 4th | - | 大内 | - |
| トランペット1st | 小出 | 小出 | 倉田 |
| 2nd | 中川 | 中川 | 北村 |
| コルネット1st | 野崎 | 野崎 | 青木(Tp.3rd) |
| コルネット2nd | 青木 | - | - |
| トロンボーン1st | 武田浩 | 武田浩 | 志村 |
| 2nd | 山崎* | 志村 | 山崎* |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ1st | 桑形 | 桑形 | 山本 |
| ティンパニ2nd | 山本 | - | - |
| パーカッション | シンバル/鈴木* 大太鼓/古関和* トライアングル1/皆月* トライアングル2/古関香* タンブリン1/今尾 タンブリン2/蓑輪* |
小太鼓1、グロッケンシュピール/今尾 小太鼓2/m皆月* シンバル/古関(和) 大太鼓・トライアングル/山本 木琴・タンブリン/鈴木* |
ラージカウベル、ウッドブロック、ギロ、マラカス/山本 ボンゴ、タムタム、タンブリン、小太鼓、テナードラム/古関(和)* 木琴、グロッケンシュピール、トライアングル、フィンガーシンバル、鐘/鈴木* ビブラフォーン、ティンバレス、シンバル、コンガ、大太鼓、小太鼓/皆月* |
| 鍵盤 | - | Pf藤井泉 celesta藤井泉 |
Pf藤井泉 celesta藤井泉 |
| ハープ | |||
| 1stヴァイオリン | 内田智(堀内) | 堀内(内田智) | 堀内(内田智) |
| 2ndヴァイオリン | 中島(朝倉) | 中島(滑川友) | 中島(滑川友) |
| ヴィオラ | 柳澤(安宅) | 柳澤(安宅) | 柳澤(安宅) |
| チェロ | 柳部(安藤) | 柳部(日高) | 柳部(日高) |
| コントラバス | 中野(宮田) | 中野(宮田) | 中野(宮田) |
*はエキストラ
弦()はトップサイド
第247回演奏会のご案内
ドヴォルザークの連作交響詩
今回の演奏会ではドヴォルザーク晩年に作曲された交響詩5曲を一挙に演奏します。
すでに国際的に認められプラハ音楽院教授をしていたドヴォルザークは、ニューヨークのナショナル音楽院に招聘され、4年間の渡米中に交響曲第9番「新世界より」や弦楽四重奏曲「アメリカ」といった名曲を書きましたが、ホームシックにより任期を中断してプラハに戻りました。故郷への想いを強くして取組んだのがこれらの交響詩でした。尊敬していた同じチェコの作曲家であるスメタナが、チェコの自然と歴史を音楽にした連作交響詩「わが祖国」にも影響されたでしょう。ドヴォルザークがこれらの交響詩を作曲したのは、帰国した翌年の55歳。奇しくもスメタナが「わが祖国」を書き終えたのも55歳の時でした。
チェコの民話による交響詩
最初の4曲は、チェコの作家・民俗学者エルベンの詩集「花束」を題材にしています。チェコの民話に基づくもので、エルベンは「チェコのグリム」とも言われています。
簡単にお話を説明しましょう。
水の精 娘が水の精と結婚し水の世界に住んでいたが、実家に帰ってなかなか戻らないので、水の精は怒って自分たちの子供を殺す。
真昼の魔女 母親が「悪いことをすると魔女が来る」と子供を叱るので、悪口を言われた魔女が復讐のために子供を殺す。
金の紡ぎ車 王に見染められた美しい娘を、継母が実娘を嫁がせようと殺すが、魔法使いが生き返らせる。金の紡ぎ車がその件を王に話して、継母と実娘は死刑になる。
野鳩 夫を殺して若い男と再婚した妻が亡夫の墓を参ると、傍らの樫の木で亡夫の生れ変わりの鳩が鳴き、良心の呵責で妻は自殺する。
題名を見るとメルヘンチックですが、実は物騒な話です。しかしチェコ民族の教訓や人生観が表れているのかもしれません。曲は活き活きとしており、魅力的なメロディで語られます。
余談ですが、ドヴォルザークは大の鉄道マニアとして知られていますが、鳩の飼育も趣味にしていたということです。
英雄の物語の交響詩
「英雄の歌」は若き日の英雄が意志と自信を持ち、困難に会い悲観と失望、それに打ち勝って最後は勝利を収めるというストーリーです。英雄はドヴォルザーク自身とも言われており、R.シュトラウスの「英雄の生涯」を思わせますが、「英雄の歌」の方が1年早く作曲されました。
初演はマーラーが指揮し、ブラームスの追悼演奏会としてブラームス交響曲第2番とともに演奏されました。ブラームスはドヴォルザークの才能を見出して世に出るきっかけを作り、渡米中の楽譜の校訂を引き受けるほど親しくしていました。マーラーは曲を気に入り、その後もドヴォルザークの良き友人であり支援者であったということです。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
二足の草鞋
今シーズンから参加しております、クラリネットパートの中條と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
実は私、新響への入団は今回が初めてではなく、いわゆる「出戻り」と言われる団員です。新響との出会いは、今から20余年前になります。訳あって大学のオーケストラには入らず、友人から「日本で一番上手な(アマチュア)オケ」と紹介されたこのオケの門を初めて叩いたのが、当時大学2年生だった1996年10月のこと。オーケストラのお作法を全く知らない素人なのに、よくも入団を許してくれたものだと、懐の広さに今でも感謝しています。
以来、2010年4月に仕事の都合で退団するまで、無我夢中で参加してきました。その間、良い思い出も大失敗も多数ありました。新響は、他のアマチュア団体と比較しても演奏会の年間回数が多く、練習への出席も厳しいため、まさに全力で最後尾を走っているつもりでやっておりました。今でも過去演奏会の録音を時々聴いては、当時の懐かしい気持ちに浸っています。
退団後は、海外に渡航する機会があり、現地のオーケストラに参加したり、帰国後は子育てなど家庭の事情があって新響には戻らず、都内の様々な音楽団体にお邪魔して武者修行をしたり、クラリネット以外の楽器に手を出してみたり…と、自分なりに見聞を広げながら第二の音楽ライフを楽しんできました。新響以外に、創意工夫しながら独自に楽しんでいるアマチュア団体は数多く、音楽の楽しみ方は本当に様々であり、むしろ違いがあるから面白いのだと思って、充実した日々を過ごしていました。
そんな私がなぜ新響に出戻ったかといいますと、これもひとえにタイミングでしょうか…。この春、下の子供が中学生になり、子育てがひと段落したことから、妻(新響ヴァイオリン奏者)が「そろそろ戻ってきたら?また一緒に演奏しようよ」と背中を押してくれたことがきっかけで、新響のオーディションを再度受けることを決めました。これは相当の「覚悟」が必要なことでして、知っている顔ばかり並ぶ前での演奏はかなりの緊張を強いることです(まさに「苦行」以外の何物でもありません。)。何とか再入団することができ、5月から練習に参加できることになりました。
私が退団してからの新響の様子はおよそ知っていましたが、久々に復帰して実際に演奏に参加してみると、なるほど、新響というのはこういう団体だったんだなぁと、入団当初に受けたインパクトがよみがえってきます。と同時に、時代の流れといいますか世代交代等により、新響は間違いなく進化していると感じる部分もあります。自分はその進化に寄与できるのか、はたまた団員の平均年齢上昇要因にしかならないのか。それは今後の自分次第ということになります。初心に帰って精進したいと思っています。
さて、先ほど「クラリネット以外の楽器」云々と書きましたが、今から1年半ほど前からサクソフォーン(サックス)という楽器をクラリネットと並行して演奏しています。
きっかけは、クラリネット歴30年を迎え、この機会に何か新しい楽器を始めて、自分の芸の幅を広げようと思ったことです。どこか楽団に入ったとか、誰かに一緒にやろうと誘われたとかではなく、ただの思い付きです。過度な負担にならないよう、クラリネットと演奏方法があまり違わないものをということで、サックスに白羽の矢が立ちました。プロの奏者でも「両刀遣い」の方はおられますし、実際、周囲にクラリネットとサックスを両立させている人がいたのも心強かったです。
クラリネット(黒色)とサックス(金色)は、見た目こそずいぶん違いますが、木管楽器というカテゴリーでは共通していますし、発音原理が「シングルリード(1枚の葦の発音体を振動させて音を出す)」という点ではほぼ同じです。つまり、「音を出す」というハードルは最初からクリアされています。実際、初めてサックスを手にして吹いてみた際、ごくふつうに音は出ました。「おぉ、これはいけるぞ!」とにわかに思いました。
しかし、「音」と「音色」は似て非なるものです。巷に「桃栗三年柿八年、サックス三日で鳴り響く」という風刺のきいた言葉があるのですが、これは半分当たりで半分外れです。あのサックスらしいメタリックな音色を出せるようになるのは、けっこう難しい…。私が新響で初めてサックスを披露した際、「(せっかく新世界の作品を取り上げているのに)何だか旧大陸のような音色がする」とか「木製のサックスから出てくるような音」といった微妙なコメントをいただきました。
また、練習を重ねるにつれ、運指(指遣い)やビブラート、楽器構造などの「概ね似ているけど、実は全然違う」という部分がだんだん鮮明に見えてきました。私が思うクラリネットとサックスの最大の違いは、クラリネットはすべての音域で弱い音を出すのが得意なのに対し、サックスは特に低音域で弱い音を出すのがものすごく難しいところです。また、サックスは比較的運指が楽(合理的)だと言われていますが、一部でクラリネット以上に困難を極めるところもあります。
社会人が楽器の練習に時間を費やせるのは週末が多いと思いますので、複数の楽器をやっていると時間の使い方が難しいのではと思われるかもしれません。特に、楽器の習得には「スタートダッシュ」が必要になりますので、最初は楽器に慣れるためにも、ある程度時間をかけることが必要になります。そのため、私の場合は、最初の半年間は土日にそれぞれ3~4時間ほどサックスを練習していました。それ以降は、練習時間が落ち着いてきて、クラリネットもサックスもそれぞれ1時間程度、決まったメニューをこなしながら、うまく両立しているつもりです。
クラリネットには大小さまざまなサイズの楽器があり、それを曲によって使い分けますが、サックスも同様に、通常使われる4つのサイズの楽器があります。私はそのうちの「アルト」から始め、のちに「テナー」も吹くようになりました。サイズが少し違うだけで、出てくる音色はがらりと変わり、一般的にはアルトは女性的、テナーは男性的と言われます。実際に両方吹き比べると、その違いをあらためて実感しますし、それぞれの良さ・持ち味をも実感するようになりました。私は勝手ながら、サックス奏者は「ソプラノ」「バリトン」を含む4つの楽器を一通り演奏できるようになることで、奏者として成熟していくのではないかと確信しています。いやはや、目指すべき道はまだまだ遠く険しいです。
さて、そんな私が今回の演奏会でサックスパートを担当します。
サックスは近現代になってから登場した楽器のため、吹奏楽やジャズでは大活躍しますが、オーケストラに登場する機会はそれほど多くありません。ですが、珠玉のような作品がいくつか存在します。例えばラヴェルの『ボレロ』には素敵なソロ(独奏)がありますし、ビゼーの『アルルの女』のソロを聴いてサックスを始めたという方を何人か知っています。以前、ベルクのヴァイオリン協奏曲を演奏した際には、サックスがごく弱い音で演奏しながらも、オケ全体の音色感を作っていく様子をステージ上で味わい、「サックスはいつも朗々と演奏する楽器」という自身のサックス観が覆りました。
サックスが使われている曲は、どれもその特徴が最大限生かされるように工夫されており、「とりあえずサックスでも使っておくか」という作曲家は皆無だと思います。そのため、演奏する者としては気が引き締まる思いがします(ちなみに、これがクラリネットですと、首をかしげたくなるオーケストレーションにときどき出会うことがあります。)。今回取り上げるプロコフィエフとバーンスタインでも、随所にサックスらしいソロが登場しますが、あらかじめ弁解しておきますと、圧倒的に難しく上級者向けなのが前者、技術的には難しいけれどノリノリで楽しめるのが後者です。
プロコフィエフの『ロメオとジュリエット』はテナーサックスで演奏します。全曲を通じて数小節しか吹くところがなく、おまけにほぼすべてソロです(ものすごく緊張します。)。私は今のところ、個人練習の大半の時間をこのプロコフィエフに費やしていますが、まだまだ自分にゴーサインが出せていません。演奏会当日にピントが合うよう、これからも粘り強く練習していくつもりです。ちなみに、前回(1999年)新響がこの曲を取り上げた際には、私はバスクラリネットを担当しており、まさにテナーサックスの隣で演奏していました。当時、エキストラでご出演の音大生が「とても難しいんです」とおっしゃっていた気持ちが、今になってようやく分かりました。
続いて、バーンスタインの『シンフォニックダンス』はアルトサックスで演奏します。こちらはソロが適度にありつつも、他の楽器と一緒に(ユニゾンで)演奏する箇所も多く、オケとの一体感を感じられます。音量のバランスもそこまで神経質にならずに済むため、オケの中でサックスを初めて吹く曲としては理想的だと思っています。“新世界”の作品にふさわしい、輝かしい音色を目指します。
新響では、邦人作品を含め特色のある演目をお客様にお届けできるよう、各団員が様々なアイディアを持ち寄り、選曲会議の場で議論を重ねています。音楽を本業としていない私たちですが、ご自宅がLPレコードやCDだらけで、YouTubeでも見つからない秘蔵音源を持っている団員もいます。また、複数種類の楽器を自由に演奏できる団員も多数おり、自分が楽しいと思えることは何でもやるという、まさにアマチュアの本懐ともいうべき活動をしている集団だと思っています。
今回の「『ロメオとジュリエット』しばり」の演奏会のように、これからもストーリー性のあるプログラムをお届けできるよう、そして、サックスのように普段はオケに登場しないような楽器であっても(エキストラではなく)団員が対応できるよう、私も一団員として楽しみながら「音楽道」に邁進してまいりたいと思います。
バーンスタイン:「ウェストサイドストーリー」よりシンフォニックダンス
本日の「ロメオとジュリエット」の物語は、互いに争うグループに属する男女が恋をし、グループ間の憎悪のためこの恋は実らない、というプロットはそのままに、ミュージカルとして現代に蘇る。
1949年1月6日に新進気鋭の振付師で演出家のジェローム・ロビンスがレナード・バーンスタインに「ロメオとジュリエット」のミュージカル化の思い付きについて電話をしたのが、すべての始まりだった。さらに脚本家のアーサー・ロレンツを巻き込んで完成したのが、ミュージカル「ウェストサイドストーリー」であり、半世紀以上経った今なお、最も人気のあるミュージカルの一つとなっている。
30歳台になったばかりの3人により1949年から検討されたミュージカルの内容は、「ロメオとジュリエット」を現代のニューヨークに蘇らせることで、カトリックとユダヤ教の宗教対立をテーマにした「イーストサイドストーリー」などいろいろな構想が生まれたが、当時ウェストサイドで社会問題になっていたプエルトリコ移民と貧しい白人の不良グループ間の抗争をベースにすることに落ち着いた。
バーンスタインは、ミュージカル「キャンディード」の作曲も並行していたので、当初筆はなかなか進まなかった。その後、スティーヴン・ソンドハイムという才能溢れる作詞家を得て、青少年の非行、人種差別、貧富の差などの社会問題に対するメッセージが感じられるような歌詞や台詞が多く散りばめられたミュージカルが完成し、1957年8月19日にワシントンで世界初演された。そして同年9月26日にはニューヨークのウィンターガーデン劇場(後に「キャッツ」専用劇場になったことで有名)でブロードウェイ初演となった。
原作で重要な役割を果たす仮死の薬は現実的ではないため、後半の展開は原作とはかなり異なったも
のとなったが、ドラッグストアが舞台上の重要な要素の一つになっているのは作者たちの一流のユーモアかもしれない。
映画化はロバート・ワイズ(後に「サウンドオブミュージック」の監督も務めた)とジェローム・ロビンスの両監督のメガフォンで1960年8月に撮影が始まり、1961年10月にニューヨークで公開されたが、アカデミー賞に11部門でノミネートされ、10部門で受賞するという輝かしい成果をあげた。ちなみに舞台となったウェストサイド地域は映画撮影の頃に行われた再開発により現在はリンカーンセンターなどに変貌しており、特にニューヨークフィルの本拠地であるエイヴリーフィッシャーホールが建つ前の場所は映画撮影の中心地であった。
原作、ミュージカル、映画で登場人物の比較対応をすると次ページの表のようになる。
なお、映画ではトニー役のリチャード・ベイマーとナタリー・ウッドはそれぞれ歌うつもりで録音も行われたが、それぞれジム・ブライアントとマーニ・ニクソンの吹き替えに変えられた。ナタリー・ウッドは試写会で激怒し、マーニ・ニクソンは相応の報酬を要求したがいずれも抗議は受け入れられず、マーニ・ニクソンにはバーンスタインが個人的にボーナスを渡したという。ナタリー・ウッドはかなり良く歌っているが、マーニ・ニクソンと比べればその差は明らかで、吹替えの判断は正しかったと言わざるを得ない。このマーニ・ニクソンは「王様と私」でデボラ・カーの、「マイフェアレディ」でオードリー・ヘップバーンの吹き替えを行なって、最強
のゴーストシンガーと言われる人だが、「サウンドオブミュージック」で尼僧の1人として出演するまではクレジットされることもなかった。
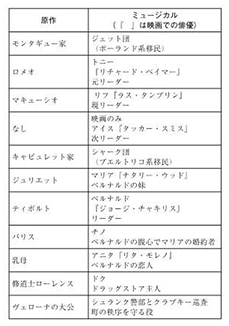
シンフォニック・ダンス
バーンスタインが、映画用のオーケストレーションで力を発揮したシド・ラミンとアーウィン・コスタルの協力を得て、ミュージカルの中の主要なダンスナンバーを取り出して、大編成のオーケストラのための組曲として編んだもので、1960年に完成した。9つの部分が切れ目なく演奏されるが、編曲チームの感触を優先して曲の順を決めたため、ミュージカルや映画の中での曲順に沿っているわけではないが、結果として音楽上の効果を最大限高めることに成功している。
1. プロローグ(Prologue)
ミュージカルや映画の導入部とほぼ同じで、不安を感じる増4度(全3音)の音の跳躍(譜例1 映画の序曲では口笛も)に続き、フィンガースナップの音がする中でアルトサクソフォーンがスイング調の旋律(譜例2 ジャズのフィーリングでとの指示がある)を奏で、いかにもニューヨークの不良少年らしい雰囲気を出している。同じシマ(縄張り)を争うポーランド系のジェット団とプエルトリコ系のシャーク団が登場し、疾走し(低弦のジャズっぽいピチカートが印象的)、喧嘩を始め、警官の笛で制止されるまでが描かれるが、映画ではミュージカルよりかなり長くなっており、意表をつく振り付けは素晴らしい。映画で特に有名なのはジョージ・チャキリスが足を高く上げる場面だが、筆者の見た限りでは、ミュージカルでの高さにははるかに及ばない。
フィンガースナップはこの後も色々な場面で使われるが、かなり個人差があって苦手な人には大変難
しい。この点、ブロードウェイの公演でのフィンガースナップは音量やクリアさが半端ではなく、本場のパワーのすごさを感じた。
また、増4度の音程は「ウェストサイドストーリー」のあらゆる場面で使われ、この作品を特徴付けているので、どのように使われているかを探しながら聴くことをおすすめしたい。
2. どこかに(Somewhere)
決闘でリフを殺してしまったトニーがマリアとど こかへ行って幸せに暮らしたいという気持ちを表した美しい旋律(譜例3)で、オリジナルのミュージカルでは少女の声(新演出では少年のボーイソプラノ)で「どこかに安らぎの地がある」と歌われる。この美しい旋律はまずヴィオラ・ソロに現れ、ホルン、ヴァイオリンに引き継がれる。
映画では、トニーがベルナルドを殺したことを聞いたマリアが自分の部屋で祈っているとき、トニーが忍んで来て2人でこの曲が歌われる。
3. スケルツォ(Scherzo)
ミュージカルでは「どこかに」の前に、流れるような旋律が小さな編成で演奏され、「ウェストサイドストーリー」の意図するメッセージを発信する重要な部分となっている。この部分では、ジェット団とシャーク団が仲良く踊るという現実から逃避した夢をトニーとマリアが見るのだが、決闘の前の場面で現実性に欠けるため、映画ではカットされている。
4. マンボ(Mambo)
ここから3曲はアメリカに来てまだひと月のマリアとリフに誘われて来たトニーが出会うことになる体育館でのダンスパーティの音楽で、マンボはその頂点に位置し、たくさんの打楽器(特にラテン系のもの)が演奏に参加する。トランペットなどの金管が派手なフレーズを景気良く奏でると、オーケストラメンバー全員が「Mambo!」とシャウトすることになっているが、シャウトをしない演奏や録音もある。新響のシャウトのパワーはいかに。
このマンボの音楽は、プエルトリコのラテン音楽と、トランペットなどでシェイク、フラッター、グリッサンドなどの特殊奏法を使ったニューヨークのジャズとが融合した、楽しくパワフルなもので、バーンスタインならではの音楽になっている。ミュージカルでも映画でも素晴らしい踊りが披露されるが、映画では、この曲でトニーが体育館に到着し、アニタ(リタ・モレノ)と宙返りを披露するリフ(ラス・タンブリン)の派手な踊りが印象的だった。
5. チャチャ(Cha-Cha)
トニーがマリアと出会って意識し、チャチャチャのリズムに簡単なステップで踊り、一目惚れした心境を表している。バスクラリネットの洒落た前奏に続いて弦楽器のピチカートとフルートにより演奏される(譜例4)が、この旋律は出会いの後にトニーが歌う「マリア」と同じである。映画ではトニーとマリア以外はソフトフォーカスとなり、互いの存在に気づいて惹かれる様子を映画ならではの手法で表現している。なお、このシンフォニックダンス中にはフィンガースナップはないが、ミュージカルと映画では踊りながらのフィンガースナップがある。
6. 出会いの場面(Meeting Scene)
トニーとマリアが幻想的な雰囲気で初めて言葉を交わす(初めて会ったとか手が冷たいなどたわいのないもの)短い場面で、4本のヴァイオリン・ソロによる気持ちの高揚が感じられる旋律(譜例5)が聞こえるが、このようなロマンチックな旋律の中にも増4度音程が含まれて将来の悲劇を予感させる。
7. クール〜フーガ(Cool〜Fugue)
シャーク団との決闘の前にジェット団のメンバーはドクの店に集まるが、皆興奮気味。リーダーのリフは冷静になれと諭し、踊ることで興奮を鎮めさせる。
この曲でも増4度の音程を持つ主題(譜例6)が不安を醸し出し、徐々に盛り上がって踊りも激しくなり、落ち着きを取り戻して静かに終わる。スイングせよ(swing)との指示があり、アルトサクソフォーン、ヴィブラフォン、トランペット、ドラムスなどが活躍してジャズの雰囲気にあふれており、シンフォニックダンスの中でも最も素晴らしい曲ではないだろうか。
この曲に付けられた振り付けも綿密に計算されたもので、意外性があり、変化に富み、今見ても全く古さを感じさせない素晴らしいものである。しかし、この場面と次の乱闘の場面のダンスの練習はミュージカル、映画とも過酷を極めた。決して妥協を許さないジェローム・ロビンスは、誰かが怪我をしたり動けなくなったりするまで、ハードな練習を続けさせた。
映画では、決闘後のシーンとなっており、決闘でリフとベルナルドが殺されるという予想もしなかった結果に動揺するジェット団メンバーが、ガレージの中で自動車のライトを点け、踊ってクールダウンする。リフが亡くなっているので、ミュージカルでは存在しないナンバー2のアイスのリードで踊りが始まるが、アイスを演じたタッカー・スミス(リフの歌の吹き替えもやっている)の存在感はリフ以上で、そのカッコ良さに強く惹かれる。クールを決闘の後に持って来たのはきわめて自然でリアリティの向上に効果を上げており、クールのダンスは映画でも最大も見どころではないだろうか。
8. 乱闘(Rumble)
ジェット団とシャーク団は決闘によりシマの決着を図ろうとするが、その激しい乱闘を激しい音楽で描く。リーダー同士の話し合いで素手での対決のはずだったのがいつの間にかナイフを持つ者も現れ、仲裁のために来たトニーの目の前でリフがベルナルドに刺されてしまう。リフのナイフはトニーに託され、トニーはリフが殺されたことで逆上し、ベルナルドを刺してしまう。この曲に付けられた振り付けは各人の動きがカウントで決められた計算尽くされたものだったが、あまりの激しい動きから怪我人が絶えず、練習や公演では代役が何人も用意されたという。
乱闘の最後には、バーンスタインのアイデアで、ミュージカルにはないフルートソロによる静かなカデンツァが追加され、最後のフィナーレに続く。
9. フィナーレ(Finale)
ベルナルドを心ならずも殺してしまったトニーは、マリアとの再会を果たすが、その瞬間、チノの撃った銃弾に倒れる。フィナーレはマリアの腕の中で息を引き取る時に流れる音楽で、マリアが歌う「恋する私(I have a Love)」の旋律(譜例7)が流れ、「どこかに」の断片も現れ、静かに終わる。この時ジェット団とシャーク団が協力してトニーの遺体を運ぶ。映画でのこのシーンは秀逸で、涙なしでは見られない。
原作では手違いが重なってロメオもジュリエットも死を選んでしまうが、ウェストサイドストーリーではマリアはこれからも力強く生きていくことが予感される。
ウェストサイドストーリーにはシンフォニックダンスに含まれる曲以外に、体育館のシーンでの「ブルース」、シャーク団メンバーにより踊られる「アメリカ」という優れたダンスナンバーがあるが、これらは映画版で楽しむことができる。
その映画版ではマリア役のナタリー・ウッドとトニー役のリチャード・ベイマーは撮影当時23歳で、原作の16歳のロメオと14歳のジュリエットの設定とはかなり差があるが、その分大人の恋になっているし、曲順の変更によりミュージカルでの不自然さがなくなってリアリティが増し、登場人物に共感できる感動的なものに仕上がっている。
「ウェストサイドストーリー」において、主要な役にはオペラ並みの歌唱能力を要求する一方で、オペラではないことをバーンスタイン自身も認めている。バーンスタインは、筋と関係なく声をひけらかすオペラの悪弊を嫌い、もしオペラならばトニーが撃たれた後にマリアが歌うであろうアリアをいろいろ作曲してみたものの、どうしても本物にならず、ほとんどを台詞のみにせざるを得なかったことを語っている。要はリアリティの追求の違いで本質的な違いはないということらしい。
それにもかかわらず、一般にミュージカルがオペラと比べて低く見られがちなのは、ミュージカルファンの筆者としては大変残念に思っており、「ウェストサイドストーリー」は、「レ・ミゼラブル」、「オペラ座の怪人」と並ぶ芸術性の高い三大傑作ミュージカルであると確信している。
バーンスタインのミュージカル音楽の高い芸術性の一例として、ダンスナンバーではないためシンフォニックダンスには含まれていないが、決闘直前のクインテット(トゥナイト)を挙げたい。この曲では、ジェット団、シャーク団、トニー、マリア、アニタがそれぞれの今宵(トゥナイト)の心情を歌って対位法的に絡み合うというミュージカルではかつてなかった高みに達している。個人的見解だが、「レ・ミゼラブル」の第1幕最後にジャンバルジャン、ジャベール、マリウス、コゼット、エポニーヌ、テナルディエ夫妻でそれぞれの心情が歌われる名曲「One Day More」は、作曲家のクロード=ミシェル・シェーンベルクがバーンスタインのクインテットにヒントを得て比肩できるようなものを目指したものと考えている。
新響では2010年1月24日の第208回演奏会でシンフォニックダンスを取り上げている。新響のプログラムビルディングには10年以内の再演は原則ないという10年ルールがあるが、今回はロメオとジュリエット特集の上で欠かすことのできない曲であることと、ほとんど10年に近いということで取り上げられた。
「ウェストサイドストーリー」が提起した人種差別や格差、貧困の問題は半世紀たった今でも存在し、リアリティの高いこのミュージカルの先見性や問題提起、斬新な音楽や振り付けにはまったく古さを感じさせない。特にバーンスタインの音楽は20世紀の音楽中の大傑作であることは疑いなく、この曲はもはや現代の古典になっていることを確信できる。個人的には映画「ウェストサイドストーリー」はミュージカル映画だけでなく、すべての映画の中で映画館、テレビ放送、ビデオテープ、LD、DVD、BDと媒体が変わりながらも最も多く見た映画であり、文句なしのマイベストワンとなっており、ミュージカルの舞台とともに今後も見続けていきたいと思っている。
譜例準備中
初演:1961年2月13日 ニューヨーク・カーネギーホール ルーカス・フォス指揮ニューヨーク・フィルハーモニック
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、Esクラリネット、クラリネット2、バスクラリネット、アルトサクソフォーン、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3(1番はD管持ち替え)、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、ボンゴ、タンブリン、ティンバレス、トムトム、小太鼓2(うち1台は小型)、コンガ、中太鼓、大太鼓、4つの音に調整された太鼓、ドラムセット(シンバル、小太鼓、トムトム、大太鼓)、トライアングル、吊りシンバル、合わせシンバル、フィンガーシンバル、カウベル3(うち1つは大型)、タムタム、ヴィブラフォン、グロッケンシュピール、鐘、ウッドブロック、ギロ、マラカス大小、木琴、警官の笛、ハープ、ピアノ、チェレスタ、弦五部
参考文献:[Bernstein Orchestral Anthology Volume 1](シド・ラミンによる解説)Boosey & Hawkes Music Publishers Limited. 1998バーンスタイン指揮、イスラエル・フィル演奏のウェストサイドストーリー CD解説 グラモフォン F60G 50122/3
プロコフィエフ:バレエ組曲「ロメオとジュリエット」より
今からさかのぼること20年前の1999年4月17日、新響は今日と同じくプロコフィエフの「ロメオとジュリエット」をこの東京芸術劇場大ホールで演奏している。当時大学生だった私は3階席の奥の方でこの演奏を聴いていた。その時の新響のロメオとジュリエットの演奏を聴き涙が止まらなくなり、演奏後もしばらく席を立てなかった。こんな経験は初めてだった。新響に入団したいと思った理由の1つになった。
ロシアの作曲家プロコフィエフは、シェークスピアの有名な悲劇「ロメオとジュリエット」を題材に、全52曲からなるバレエ音楽を作曲した。本日は、作曲者自身が演奏会用に抜粋した組曲の第1番から1曲と第2番から5曲を演奏する。
1. モンタギュー家とキャピュレット家(第2組曲第1曲)
冒頭の耳をつんざくような金管楽器の不協和音は、「ヴェローナの平和を乱す者は死刑に処する」と宣告するヴェローナ大公エスカラスの主題である。
その後、キャピュレット家で行われる仮面舞踏会での騎士と貴婦人たちが踊る威圧的な音楽が始まる。中間部には、望まない結婚の婚約者パリスとジュリエットが踊る、冷ややかではあるが美しい音楽が挟まれる。
2. 少女ジュリエット(第2組曲第2曲)
14歳の少女ジュリエットの茶目っ気、可憐さ、そして恋への憧れと不安を表現している曲である。まだロメオを知らない無垢で明るいジュリエットが前半で表現されている。
後半は、オーケストラとしては珍しくテナーサクソフォーンを起用している。その独特で少し陰のある音色は、恋への憧れ、不安といったジュリエットの内心を描写し、さらにはその後の展開も予感させる。
3. 修道士ローレンス(第2組曲第3曲)
両家の仲直りのためにと、ロメオとジュリエットの結婚を執り行うローレンスの穏やかで慈愛に満ちた音楽である。素朴なファゴットのソロの後、チェロの美しい高音の旋律が続く。またファゴットのソロに戻り、静かに終わる。
4. ティボルトの死(第1組曲第7曲)
両家の争いを表すような不穏な音楽が弦楽器によって始まる。キャピュレット家のティボルトが、ロメオの親友マキューシオを挑発する。ところどころで顔を出す飛び跳ねるような旋律は明るく快活なマキューシオを表しているが、次第に挑発に乗ってしまい不穏な音楽にのみこまれていく。加勢したいと思いながらもジュリエットのことを考え手を出さずに見守るロメオの目前で、ティボルトはマキューシオを殺してしまう。
一瞬の間の後、親友を殺されたロメオは我を失って激昂し、ティボルトと闘う。お互いが激しく立ち回り剣を交錯させる決闘の様子を弦楽器が見事に描き出す。激しい戦いの末、ロメオはティボルトを倒す。決闘のシーンの後に挟まれる15回もの無機質な音の連打は、ティボルトが絶命していくまでのカウントダウンである。そして、ホルンやトランペットが最強奏でティボルトの葬送行進曲をうたい上げ、曲を締めくくる。
5. 別れの前のロメオとジュリエット(第2組曲第5曲)
追放前のひとときを過ごしたロメオとジュリエットは、2人のまどろみの時間から、別れの時を迎える。フルートによる「花嫁の含羞」を経て、ホルンやクラリネットによって、ロメオの決然とした態度が示される。さらに、オーケストラ全体が一丸となってロメオの「出発の決意」を雄々しく演奏する。ひとしきり盛り上がりをみせたあと、音楽は鳴りをひそめる。フルートとクラリネットによる静かな伴奏とともに、寂しく不安げな主題がオーボエや低弦でひっそりと提示される。これから起こる悲しい出来事の予兆であるかのような不安な雰囲気で終わりを迎える。
6. ジュリエットの墓の前のロメオ(第2組曲第7曲)
徹頭徹尾、直情的に悲壮感が伝わってくる音楽である。仮死状態のジュリエットを見つけたロメオの悲痛な嘆きを、弦楽器や金管楽器が異常な熱量で表現する。なりふり構わず声を上げて号泣しているかのようなこの曲想は、鋭く心に突き刺さる。悲嘆に暮れた失意のロメオが毒薬を飲み自らの命を絶って音楽はいったん落ち着き、その後のジュリエットの死を静かに暗示して曲は終結する。
“要するに代償を求めず、ただひたすら音楽を愛し、それに没入していく心、それがアマチュアの中身であり、魂でもあろう。”
(第113回演奏会「新響と30年 芥川也寸志」(1986年11月)プログラムより)
新響草創の頃から関わった芥川也寸志の言葉である。新響のプログラムには団員勤務先のページがある。仕事をしているにもかかわらず、時間その他諸々をなんとかやりくりして音楽活動にのめりこむ、アマチュアの矜持の証である。
同じ記事の別の箇所では、アマチュアの訳語である「愛」を辞書で調べた結果が列挙されている。その中で「大切にして手離さない」というものがある。まさに、新響団員にとって音楽とは「大切にして手離さない」ものであろう。一方、「ロメオとジュリエット」では、究極的な犠牲を払ってでもお互いを「大切にして手離さない」姿勢を貫く。昔のことでもあり記憶が美化されていることは承知の上だが、20年前の私を捉えたのは、音楽の中の2人の、そして舞台上で演奏していた新響の「大切にして手離さない」心意気だったのではないかと考えている。
本日も20年前と同様、お客様と感情を共有し、願わくば過去の私のような体験をしていただけるよう、新響は音楽に没入する。その様を、どうかあたたかくご覧いただきたい。
初演:1938年12月30日(バレエ)チェコスロヴァキア国立ブルノ劇場※これに先立ち、第1組曲は1936年モスクワ、第2組曲は1937年レニングラードにて初演された。
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、テナーサクソフォーン、トランペット2、コルネット、ホルン4、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、小太鼓2、木琴、グロッケンシュピール、タンブリン、トライアングル、ハープ、ピアノ、チェレスタ、弦五部
参考文献:新交響楽団第113回演奏会「新響と30年 芥川也寸志」(1986年11月)プログラム
ベルリオーズ:劇的交響曲「ロメオとジュリエット」より
今回の演奏会で扱う曲の共通点は、すべてウィリアム・シェイクスピアの「ロメオとジュリエット」を原作としていることである。各曲目解説の前に、まずこのシェイクスピアの「ロメオとジュリエット」について簡単に触れておきたい。
イングランドの劇作家であるウィリアム・シェイクスピアによって1595年前後に初演された「ロメオとジュリエット」。まずはこの作品のあらすじを簡単に振り返ってみる。
舞台は、14世紀のイタリア、ヴェローナ。当時のヴェローナは、神聖ローマ帝国とローマ教皇の対立の影響を受け、支配層が皇帝派と教皇派に別れていた。物語の中心となる両家、モンタギュー家とキャピュレット家もこの対立ゆえに、抗争を繰り返していた。
モンタギュー家の1人息子であるロメオは年上の女性ロザラインへ恋心を抱き、その叶わぬ恋に日々悩んでいた。そのような最中友人に誘われ、キャピュレット家のパーティーに忍び込み、そこでキャピュレット家の1人娘のジュリエットと運命的な出会いを果たす。2人は互いに惹かれ合い、たちまち恋に落ちた。夜更けにキャピュレット家の庭に忍び込んだロメオは、バルコニー越しにジュリエットと互いの愛を確かめ合い、翌日再び会うことを誓う。翌日修道士ローレンスのもと、2人は密かに結婚の誓いを交わした。この2人の愛が両家の対立に終止符をうつことをローレンスは心から願っていたのである。
しかしその直後、広場で友人達が争っている最中、親友のマキューシオがキャピュレット夫人の甥ティボルトに殺されてしまう。親友を殺された怒りからロメオは、ティボルトと決闘を行い、殺してしまう。このことにより、ヴェローナの大公はロメオに街からの追放を命じる。従兄弟を殺された悲しみやロメオと離れ離れになってしまう辛さに苦しんでいるジュリエットに、キャピュレットは親戚のパリスと結婚することを命じ、ジュリエットをさらに追い詰めることとなる。
ジュリエットは藁わらにも縋すがる思いで修道士ローレンスに助けを求める。ローレンスは彼女とロメオを添わせるために、ジュリエットに仮死薬を使った計画を立てる。しかし、この計画を手紙でロメオに伝えようとするものの、手紙がロメオの元に届く前に、ロメオは自身の下僕からジュリエットが自殺したと聞いてしまう。ロメオはすぐさまジュリエットのもとに向かい、仮死薬で眠っている彼女が本当に死んでしまったと思い込み、その後を追おうとその場で毒薬を飲んで息をひきとる。その後仮死状態から目を覚ましたジュリエットは目の前で亡くなっているロメオを見て、あとを追うように短剣で自ら命を絶つ。
最愛の娘と息子が純粋な愛を求めたものの、両家の対立がゆえに、2人の尊い命を失うこととなった事実は、両家を和解の道へと導いていく。
現代における「ロメオとジュリエット」は、純粋な恋愛、恋愛悲劇等、ともすればロメオとジュリエットの哀れな叶わぬ恋物語という部分が強調されがちではあるが、物語の最後に大公が述べたことも忘れてはいけない。「両家の対立という無意味な人間の憎しみが、互いに愛し合い、互いに滅ぼし合うという罰を受ける結果をもたらした」からである。
この物語がこれほどまでに印象深い悲劇となったのは、その宿命性や運命性を受け手に強く感じさせたからであろう。特段個性的に描かれてはいない2人の若者が、本人たちの力の及ばない運命の狂いに巻き込まれ、自ら命を絶ってしまう。単なる悲劇ではなく、この宿命性と2人の抒情的な恋愛の雰囲気は、死という悲しみと一方で美しいともとれる死の結末により物語を私達の中に色濃く印象付けるのではないだろうか。シェイクスピアは、この運命や宿命といった要素を作品の中に数多くちりばめており、さらにそこに劇的要素を加えることで、その悲劇性をより強めているのである。こうしたさまざまな要素により、「ロメオとジュリエット」は初演から今日まで変わらず多くの人の心に響く作品となったのだろう。
ベルリオーズと「ロメオとジュリエット」
「ロメオとジュリエット」といえば、プロコフィエフやチャイコフスキーの作品を先に思い浮かべる人が多いのではないだろうか。私自身も今回この曲目解説のために調べてみるまで、ベルリオーズの「ロメオとジュリエット」がこれほどまでに印象深い壮大な作品であるということは知らなかった。
フランスに生まれ、パリ音楽院にてオペラと作曲を学んだベルリオーズ。彼の最初の交響曲は「幻想交響曲」である。ベートーヴェンから影響を受けて、個人の情熱や苦難を取り入れた自叙伝的作品とされる。次いで2番目に作曲された交響曲は「イタリアのハロルド」。この作品も彼個人がイタリアの旅行の中で得たものの回想が表現されている。そして3番目に作曲された交響曲が「ロメオとジュリエット」である。それまでの個人の感情や経験に基づく交響曲とは趣向を変えて、シェイクスピアの作品に秘められた想いを自身の音楽で表現することを試みた。
ベルリオーズがこのシェイクスピアの劇的な作品に感銘を受けたのは、作品自体の力の他に、後に彼の妻となるハリエット・スミスソンの影響がある。彼女の演じる多くのシェイクスピア作品に刺激を受けて、ベルリオーズは演劇音楽の創作を本格化しようと心に決め、詩人であるエミール・デシャンとともに1827年から1830年にかけて多くの作品を創り出すこととなる。この間に作曲された「レリオ、あるいは生への復帰」「クレオパトラの死」などに含まれるさまざまなパッセージは、「幻想交響曲」や「ロメオとジュリエット」の中にも共通した要素を見ることができる。
ベルリオーズの「ロメオとジュリエット」の作品化を決定づけたのは、ベッリーニの「カプレーティとモンテッキ(イタリア語表記の両家名)」である。この作品に非常に感銘を受けたベルリオーズは、財政難に苦しみながらもパガニーニから多額の寄付を受けたことで、この壮大な作品「ロメオとジュリエット」を仕上げることができた。
ベルリオーズのこだわり
ベルリオーズは、ベートーヴェンの第九交響曲にならって、この作品を合唱付きの交響曲にした。二重の合唱部分は、モンタギュー家とキャピュレット家両家の対立を表し、物語の中で重要な人物となる修道士ローレンスやマキューシオなどを独唱としている。また、この交響曲で特徴的なのは充実した管弦楽の響きで、これを合唱と合わせることで、ロメオとジュリエットの繊細な愛を表現しようとした。
さてこの交響曲の中には、あの有名なバルコニーのシーンがロメオとジュリエットの愛のデュエットとしては作られていない。ここにも実はベルリオーズのこだわりが隠されている。この作品はオペラではなく、あくまで交響曲として作ったものであり、2人の若者の純粋な愛は、歌がなくとも管弦楽の響きが既に表現している、むしろ歌を抜きにした音楽だけでしかこの愛を表現することはできないと考えたがゆえに、作品の半分以上が管弦楽のみで構成されているのではないだろうか。
さらにベルリオーズのこだわりが見て取れるのは、その作品の終わり方にある。ロメオとジュリエットの死で作品を終えるのではなく、修道士ローレンスによる語りにしているのである。両家が対立し続けるところを、ローレンスが仲裁に入る形で合唱を書き、思いやりと和解の誓いを両家へと導く場面を創った。これもシェイクスピアの作品から読み取れるメッセージを忠実に再現しようとしたからなのではないか。
このほかにも、舞台における合唱の位置、両家の立ち位置、合唱の入退場のタイミング、ソリストが着る衣装の色、ホルンやシンバルに見て取れる細かな楽器の指示など細部にいたるまでこだわりをもち、ベルリオーズがこの作品に対していかに情熱を注ぎこんでいたかが伝わってくる。
今回私達が演奏するのは、この偉大な作品のうち、管弦楽のみで演奏される一部分である。しかしベルリオーズがこの作品にどれほどの想いをかけたのか、全体を通して表現しようとしたことは何か、楽譜上の音符1つ1つからそうした想いをくみ取り、私達の演奏にベルリオーズの想いをのせて皆様にお届けできれば幸いである。

初演:1839年、パリのコンセルバトワールにて、ベルリオーズ自身の指揮による。
楽器編成(全曲の場合):ピッコロ、フルート2、オーボエ2(1人はコールアングレ持ち替え)、クラリネット2、ファゴット4、ホルン4、トランペット2、コルネット2、トロンボーン3、オフィクレイド(またはテューバ)、ティンパニ2対、大太鼓、シンバル、アンティーク・シンバル、トライアングル2、タンブリン2、ハープ2、弦五部(第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン各15以上、ヴィオラ10以上、チェロ14以上、コントラバス9以上)、アルト独唱、バス独唱、合唱84人以上
参考文献:
Hector Berlioz[Roméo et Juliette, Symphonie dramatique. Op.17 Hol. 73]edit. D. Kern Holoman, Bärenreiter. 2018
中野好夫『ロミオとジュリエット』新潮社 2017年
W.デームリング(池上純一訳)『ベルリオーズとその時代』西村書店 1993年
フランコ・ゼフィレッリ監督・脚本[Romeo and Juliet]1968年
第246回演奏会のご案内
3つのロメオとジュリエット
シェイクスピアの戯曲「ロメオとジュリエット」は、古くからオペラやバレエなどに形を変え、現代でも映画やミュージカルとして上演されています。今回の演奏会では、それらの中から3人の作曲家による音楽を演奏します。
シェイクスピアは400年ほど前のロンドンで活躍した劇作家、劇場に所属し俳優として活動していましたが、脚本も手掛け、その後劇団の共同所有者として経営にも関わっていました。イタリアで生まれたルネサンス文化がイングランドにも伝わり、プロの劇団が多く誕生して演劇が盛んにおこなわれるようになった時期です。「ロメオとジュリエット」は1595年頃に初演された恋愛悲劇で、対立する2つのグループの若い男女が恋に落ち悲しい結末へ至るというドラマは、時代や国を超えて普遍性があり、今でも人気のある物語です。
ベルリオーズのロメオとジュリエット
フランスの作曲家ベルリオーズは、「幻想交響曲」に代表される巧みでドラマティックな作風で知られ、管弦楽法の父とも称されています。ロメオとジュリエットを題材にして作曲された劇的交響曲は、3人の独唱と合唱が付いた1時間半を超える大作で、そのため現在でも上演機会の少ない作品ですが、ベルリオーズらしい美しい旋律の斬新な音楽となっています。全体の半分くらいは管弦楽のみの曲からなり、抜粋での演奏でもロメオとジュリエットの世界を楽しんでいただけます。
プロコフィエフのロメオとジュリエット
ロシアの作曲家プロコフィエフは、レニングラードのキーロフ劇場(現マリインスキー劇場)からの依頼でロメオとジュリエットのバレエ音楽を作曲しました。途中キーロフが手を引き、代わりに契約したモスクワのボリショイ劇場も踊るのは不可能とし、作曲から3年後にようやくチェコのブルノで初演されました。それまでの間に作曲家自身によりコンサート用組曲に編み直され、先に音楽だけが初演されたのでした。
この作品は当時としては画期的で、それまでの古典的バレエは踊りを中心としたシーンが重視されていましたが、それらが排除され演劇的なバレエとなり、音楽も踊りの伴奏というより物語が表現されています。
そしてバーンスタイン
バーンスタインはアメリカ人で20世紀後半に世界的に活躍した指揮者で大スターでした。作曲家としても一流で3つの交響曲やミュージカルなど舞台音楽を残しています。振付師で演出家のジェローム・ロビンズから「ロメオとジュリエット」のブロードウェイ版をやろうと提案され、ニューヨークのスラム街での不良たちの抗争を題材として作られたのがミュージカル「ウェストサイド・ストーリー」です。ロメオとジュリエットがトニーとマリアに、敵対するモンタギュー家とキャピュレット家はポーランド系アメリカ人とプエルトリコ系アメリカ人の2つの不良グループに置き換わります。映画にもなり現在でも上演される人気の演目です。
今回演奏する「シンフォニックダンス」は作曲者自身がミュージカル中の主要曲を集めて大編成のオーケストラ用に編曲したものです。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
シベリウス:交響曲第2番ニ長調
【作曲家シベリウス】
シベリウスを論じようとするとき、ともすると安易に「フィンランドの」という形容詞をつけてしまいがちである。確かに代表作は交響詩「フィンランディア」であるし、フィンランド人のアイデンティティーを支える民族的叙事詩「カレワラ」に題材をとった多くの曲と合わせてロシアの圧政に対抗するフィンランド人に勇気を与えたことは間違いない。しかしシベリウスは、フィンランドという枠を超えて、音楽史上の大作曲家たちと肩を並べる作品群を残した、ということを忘れてはならない。特に彼の7曲ある番号付きの交響曲(番号の無いクレルヴォ交響曲はあえてはずす)は「フィンランドの」という形容詞をつける必要のない、音楽そのものとしての傑作群である。純粋に音楽的な観点からは「フィンランディア」よりもむしろ7曲の交響曲の方を代表作というべきだろう。
シベリウスは14歳から始めたヴァイオリン(その前にはピアノを習っている)と独学の作曲に非凡な才能を示し、音楽家をまっとうな職業とは認めない親族、特に母方の祖母らの反対を押し切る形で、一度入学したヘルシンキ大学理学部から創設間もないヘルシンキ音楽院に移籍している。(途中一度法学部を経ているが、形だけ。)シベリウスの才能は、入学当初からたちまち音楽院内の注目を集めるところとなるほどのものだったが、極度のあがり症のため、ヴァイオリンでは演奏会で実力を発揮できず、次第に作曲に力を入れていくこととなる。実は後にウィーンに留学した際に、そのあがり症のためもあり、ウィーンフィルのヴァイオリンのオーディションに落ち、それを機に完全に作曲に専念する決心をしたようだ。
シベリウスは上述した「フィンランディア」や「カレワラ」関連の作品で、若くしてフィンランドでも注目される作曲家と認められており、作品も高い評価を受け、聴衆にも受け入れられていた。だが、家庭的には、激しい浪費癖、度を越した社交好き、過度の飲酒などの問題を抱えており、成功した作曲家としてそれなりの収入と周囲の援助もあったが、常に多額の借金を抱え、家計は火の車だったようだ。「芸のためなら女房も泣かす」を地で行っていたと言える。
交響曲の作曲は比較的遅い時期に始まっており、第1交響曲の初演は1899年である。本日演奏する交
響曲第2番は、シベリウスの7曲の交響曲の中でも最も有名で演奏される機会も多い。比較的内省的な他6曲と比べて全体に親しみやすく、フィナーレでは豪華な大団円を迎え、カタルシスが味わえる、というところもその一因だろう。だが実は他の交響曲同様、2番にも様々な斬新な試みがちりばめられている。指揮の湯浅先生によれば「ドイツ流の伝統的な音楽理論ではアナリーゼ(楽曲解析)不能」なのだそうだ。と言っても曲を楽しむのにアナリーゼは不要だ。肩ひじ張らず自然に聴けば、特に違和感なくすんなり耳に心地よく入ってくる。
【作曲の経緯】
この曲が作曲されたのは、1901年のイタリア滞在がきっかけとなっている。このイタリア行きを勧めたのは、シベリウスの崇拝者にして理解者、後には親友となるパトロン、カルペラン男爵という人物である。パトロンと言っても自身が資産家なのではなく、シベリウスのために金策に走り回ったというのが実態である。2人の交流はカルペランが「フィンランディア」の命名を提案したことがきっかけで始まった。1901年の2月から北イタリア、ジェノヴァの東25㎞ほどのリヴィエラ海岸沿いにある、ラパッロという小村で家族での滞在が始まった。カルペランの狙いは当たり、フィンランドとは全く異なる冬でも温暖な地で、次々と新たな曲の着想を得、着々とスケッチがたまっていった。途中家族を放置して単身ローマに逃げるという事件はあったものの、ローマでは、イタリアで書き溜められたスケッチがまとめられ、交響曲第2番として、全曲のおおよその形が出来上がった。その後家族と合流、5月に帰国してからはフィンランドでこの交響曲の仕上げに没頭
し、1902年1月に完成、3月にヘルシンキで自身の指揮で初演され、空前の大成功を収めることとなる。
時に寒々しいフィンランドの光景を連想させるような曲想が登場するこの曲が、温暖なリヴィエラ海岸で着想されたというのは、やや意外な感じがする。
【曲の構成】
・第1楽章
やや速く
曲は4分の6拍子。大きな2拍子ともとれる。まずは弦楽器のニ長調のミミ・ミミミ・ファファファ・ ソソソ(以後移動ド表記とする)というひそやかな動きで始まる。この2度進行は、第1楽章を通して現れるモチーフで、この後も何度かキメの箇所で現れる。続いて木管で提示される第1主題が前述の音符3つ単位の2度進行、ミ-レ-ド、ミ-レ-ドで始まる。少し進行すると弦楽器のピチカートで少し気分が変わり、木管主導の第2主題を導き出す。第2主題は長い伸ばしの音の後で音の動きの3回繰り返し、というパターンで始まる。第2主題部分は比較的緊張感が高く、何度か高まりと弛緩を繰り返す。ここで注意すべきは、この間フルートが何度か4分音符3つの合いの手を入れるのだが、2つ目の音は、2本が全音でぶつかっており、初めて聞くと音を間違ったかのような印象を受けるが、これで楽譜通り。提示部の最後、緊張感が徐々に冷めていく中で、冒頭のモチーフが何度か現われ、すっかり収まったところで、オーボエただ1本の第2主題で展開部が始まる。展開部では、提示部で登場したモチーフが第1、第2主題の間の経過部で現れた動きも含めて、文字通り展開されもつれあい、どんどん緊張感が高まっていく。ついには短調に変形された第1主題が第2主
題を導き、最高潮に達したところで弦楽器群の壮麗なサウンドが楽しめる。と、ここで、主導権は金管群に移る。交響曲の一番の盛り上がり部分を金管のみにここまで委ねる、というオーケストレーション非常に珍しい。盛り上がり感を残したまま、曲は再現部に入り、最後は冒頭のモチーフが繰り返されながら徐々に静まっていく。
・第2楽章
歩く速度で、ただしテンポを揺らして - 歩く速度で、音を保って
ティンパニのトレモロで曲は始まり、低弦のピチカートがしばらく続く。するとそれに乗ってファゴット2本のオクターブで第1主題が奏される。しばらくすると、オーボエとクラリネットが副主題を奏する。これらの主題は緊張感とともに高揚感を高まらせながら盛り上がり、最後は金管主導の頂点に達する。ホルンがとどめを刺して金管の盛り上がりが完全に収まると、静寂の中から弦楽器のひそやかな第2主題が始まる。徐々に木管が絡みながら弦主導で粘り強く盛り上がっていき、ある程度の盛り上がりを見せたところで、いったん収まる。ここから印象的なトランペットのソロが始まり、楽器間の呼応が繰り返され、徐々にフィンランディア前半と似た雰囲気の重苦しく劇的な盛り上がりを見せていく。最後は金管主導となり最高潮に達したところで興奮は一気に収まるが、再度一瞬金管が短く小さい叫びをあげる。この後、低弦がピチカートを始めると、ここからはだいぶ平穏な雰囲気となるが、そのまま再び弦楽器を中心に木管が彩を添えながら徐々に壮麗に盛り上がっていき、金管も加わった小さい頂点ののち徐々に落ち着いていく。この後は、木管と弦の断片的な短いフレーズの応酬があり、最後に、もう一度金管も含めた一瞬の盛り上がりを見せて静かに収束する。
・第3楽章
非常に活発に - ゆっくりと滑らかに - 次の楽章に続けて演奏する
まずは疾風のような非常に速いスケルツォが始まる。これが終わると、今度は一転してオーボエのソ
ロから始まる非常にゆったりしたトリオとなる。一度全オケで盛り上がったのち静まると、突然金管が冒頭のフレーズで乱入してくる。ここから再び非常に速いスケルツォで、ほとんど冒頭のリピートと言って良い。そしてすぐまたゆったりしたトリオに戻る。これまた1回目のリピートだが、次第に第4楽章のテーマの断片が現われ、ついには完全に第4楽章への推移となっていく。そして第4楽章冒頭の豪華・壮麗な第1主題へと盛り上げていく。盛り上がり切ったところが第4楽章の冒頭である。
・第4楽章
フィナーレ、ほど良く速く - 遅すぎず速すぎず- 非常に幅広く
2分の3拍子で、第1主題、2分音符単位のニ長調の「ド-レ-ミ、シ-ド-レ」というモチーフが弦楽によって華麗に提示されて第4楽章は始まる。しかしいくつかの展開の後、盛り上がりが一段落すると、曲は地下潜航とでも言うべき曲想に入り込んでしまう。この部分は弦楽器のうねるような短調の音階的動きが延々繰り返され、その上で木管が入れ替わりながら物悲しい旋律を奏でる。この繰り返しは最終的に長調に転調することで一気に空気を変え、金管が荘厳なモチーフを提示する。いったん落ち着くと、フルートに第4楽章冒頭のモチーフが静かに現れ、木管、低弦と受け渡され、さあ、このまま曲の最後に向かって徐々に盛り上がっていくのか、と思いきや、一転雲行きが怪しくなり、緊迫感が増したのち、予想に反して第4楽章の冒頭の再現に向かって盛り上がっていく。再現された第4楽章冒頭はいっそう豪華さを増している。しかしこれも長くは続かない。再び地下潜航となる。今回は繰り返しがより執拗だ。短調のうねる音階は木管にも展開され、これでもかと繰り返される。途中先ほどと違うパターンで一瞬長調に転調する気配を見せるが、それもすぐに元通り。おまけに、先ほど長調に転調したのと全く同じパターンが現われたところでも転調しない。短調のまま同じことが繰り返される。さらに同じパターンがもう一度現れて、「今度こそ転調か」と期待してもやはり転調しない。最後の最後についに転調を果たし、再び金管のファンファーレ風モチーフとなる。最後、
第4楽章冒頭のテーマが現われ、ついに最終的な大団円に向かっていく。最後はトランペットとトロンボーンが高らかにコラールを強奏して曲は終わる。
初演:1902年3月8日、作曲者自身の指揮によりヘルシンキにて。
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ1、ティンパニ、弦五部
参考文献:
ひのまどか『シベリウス―アイノラ荘の音楽大使』(作曲家の物語シリーズ)リブリオ出版 1994年
ハンヌ=イラリ・ランピラ(舘野泉監修、稲垣美晴訳)『シベリウスの生涯』筑摩書房 1986年
音楽之友社編 作曲家別名曲解説ライブラリー18 北欧の巨匠 グリーグ/ニールセン/シベリウス 音楽之友社 1994年
神部智『シベリウス』(作曲家・人と作品シリーズ)音楽之友社 2017年
第245回演奏会ローテーション
| 芥川 | バルトーク | シベリウス | |
| フルート1st | 松下(Picc) | 吉田(Picc) | 松下 |
| 2nd | 藤井(Picc) | 岡田(Picc) | 兼子 |
| 3rd/td> | 岡田(Picc) | - | - |
| 4th | 新井(Picc) | - | - |
| オーボエ1st | 岩城 | 堀内 | 山口 |
| 2nd | 堀内 | 平戸(CI) | 岩城 |
| C.I. | 平戸 | - | - |
| クラリネット1st | 末村 | 進藤 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 高梨(BassCl) | 大藪 |
| BassCl | 高梨 | - | - |
| ファゴット1st | 浦 | 藤原 | 田川 |
| 2nd | 藤原 | 浦(Contra) | 松原 |
| ホルン1st | 大内 | 大内 | 山口 |
| 2nd | 名倉 | 山路 | 大原 |
| 3rd | 山路 | 大原 | 名倉 |
| 4th | 市川 | 市川 | 山路 |
| トランペット1st | 倉田 | 北村 | 小出 |
| 2nd | 北村 | 中川 | 青木 |
| 3rd | 中川 | - | 野崎 |
| トロンボーン1st | 武田浩 | 武田浩 | 日比野 |
| 2nd | 志村 | 岡田 | 志村 |
| 3rd | 岡田 | - | 岡田 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 古関 | 古関 | 桑形 |
| パーカッション | 2:1/鈴木* 2/山本 3/今尾 4/桑形 |
シンバル、トライアングル、タムタム/今尾 大太鼓、グロッケンシピール/山本 小太鼓、テナードラム/桑形 |
- |
| 鍵盤 | - | Pf1藤井 Pf2,celesta井上* |
- |
| ハープ | 見尾田* | 見尾田* | - |
| 1stヴァイオリン | 堀内(内田智) | 堀内(内田智) | 内田智(堀内) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(滑川友) | 小松(滑川友) | 小松(中島) |
| ヴィオラ | 柳澤(安宅) | 柳澤(安宅) | 柳澤(安宅) |
| チェロ | 柳部(安藤) | 柳部(安藤) | 柳部(安藤) |
| コントラバス | 中野(宮田) | 中野(宮田) | 中野(宮田) |
*はエキストラ
弦()はトップサイド
バルトーク:舞踏組曲
ハンガリーはヨーロッパの中でも東に位置し、西欧とは全く異なる民族的・文化的背景を持つ。しかしオスマン帝国やハプスブルグ家の支配下に置かれた期間が長く、その影響を否応なく受けてきた。音楽面では、貴族階級を相手に楽器を演奏するロマ楽団が著しく発達した。ロマはもともとハンガリーにいた民族ではなく北インドからヨーロッパへと広がっていった移動型民族だが、ハンガリーに多く定着した。その結果、ハンガリーの伝統的な民俗音楽とは異なるロマの大衆娯楽的音楽がハンガリーを代表する音楽であるという認識が西欧まで広まっていった。そうした中で埋もれていた農民の民俗音楽に光を当てたのがバルトークである。ただ、彼が行ったのは単なる自民族礼賛ではなかった。
バルトークはきわめて野生の感覚を持った人だった。聴力や嗅覚は周囲の人が信じられないほどに優れていたし、何よりも自然を愛していた。誰も気に留めないような木を長々と見つめたり、牛の糞を杖でつつきまわしたりすることはしばしばだったという。その一方で、非常に頭脳明晰で現代的な思考も持ち合わせていた。キリスト教信者である妹に無神論を説く手紙は、無慈悲なまでに鮮やかな弁証法を駆使している。27歳の時のこの手紙に見られる批判的で自由な精神が、西欧音楽の枠に囚われなかった彼の根底にあるのだろう。そんな彼が民俗音楽に何を見出したのかをこの場を借りてお伝えすることで、本日の演奏をより楽しんでいただければ幸いである。
<バルトークの生い立ち>
1881年にハンガリーの農村(現在のルーマニア領)で、農業学校校長の父と教師の母の間に生まれた。10歳で作曲家兼ピアニストとして人前に立ち、18歳でブダペスト音楽院に入学。ドイツ音楽を基礎とした教育を受け、初期の作品にはリヒャルト・シュトラウスやワーグナーの影響が色濃く見られる。
このころの彼は愛国主義的な一面を持ち、母への手紙にそれが読み取れる。「僕自身は、全人生のあらゆる点において、常に、断固として、ある一つの目的のために尽くすつもりです―ハンガリーのため、祖国ハンガリーのために。(略)会話では、ハンガリー語を使ってください!!」第一次世界大戦前後における複雑な政治的状況の中で愛国精神を抱くのは当然と言えば当然だったのだろう。この気持ちも手伝って、次第にハンガリーの農民の歌に惹かれていく。
<民俗音楽収集家としてのバルトーク>
バルトークは熱心な民俗音楽収集家だった。ハンガリーとその周辺の国々の農村を訪ね、古くから伝わる歌を12年間で9,000以上も集めた。移動手段や録音機材が今ほど発達していなかったことを考えると、異様なまでの執着だ。大変な思いをして集めた旋律を、持ち前の聴力と集中力と思考力で正確に記譜・分類していった功績はそれだけでも特筆に値する。作曲家でもあるバルトークは、ときには民謡の旋律をそのまま用い、またときには母国語のようにあやつって民謡風の旋律を生み出した。舞踏組曲は後者である。
<民俗音楽に見出したもの>
何が彼を民俗音楽に向かわせたのか。愛国精神も一つの理由だろう。しかし、それ以上の価値をバルトークはそこに見出していた。音楽史的には19世紀以前のロマン主義への反動の時代であり、印象主義や無調音楽がもてはやされ始めていた。バルトークもこの影響をもろに受けている。そうした中で出会った民俗音楽を、彼は旧来の音楽からの突破口と捉えた。変化に富んだ自由なリズム、それまでの長短調組織から解放してくれるような旋法に「古代世界の持つ理想的な単純性」を見出し、完璧さの真の模範であるとまで言っている。さらにベートーヴェンやバッハの旋律にも古い民謡の影響が見られることを指摘し、これを裏付けている。
バルトークは戦時下の状況が許す限りにおいて周辺の国々へも足を延ばして民俗音楽を収集した。そして、地理的にはごく限られた東ヨーロッパの地域における音楽の豊かな多様性に驚く。それらを詳細に分析した結果、この豊かさは移民や植民地化に伴う多民族間の絶え間ない交流がもたらした果実である、という結論に至る。ここにおいて彼は既に愛国主義者ではなく、民族の垣根を超える普遍的な眼を持っていたといえよう。本日演奏する舞踏組曲はまさに、諸民族の共存をテーマとして作曲された曲である。
舞踏組曲は、1923年にブダペスト市成立(ブダとペストの合併)50周年を記念する式典のために作曲された委嘱作品である。異なる国々の民俗音楽風に作曲した5つの楽章と、それらを織り交ぜたフィナーレから成る。全ての楽章はアタッカで切れ目なく演奏され、ⅠとⅡの間、ⅡとⅢの間、ⅣとⅤの間には小さなリトルネロ(間奏)が置かれる。
Ⅰ Moderato
テナードラムとピアノのグリッサンドに導かれ、ファゴットの提示する朴ぼく訥とつとした主題で始まる。弦楽器とピアノが不協和音で不規則なリズムの合いの手を入れながら、管楽器によるメロディが奏されていく。コル・レーニョ(弦楽器の弓の木の部分を弦に当てて音を出す奏法)やポルタメントは、何か原始的な楽器を思わせる。曲は緩急を繰り返しながら次第に激しさを増し、クライマックスに達した後、最初のモチーフがppで再起する。そして哀愁を帯びたハンガリー風のリトルネロで静かに終わる。
Ⅱ Allegro molto
土の香りがしそうな強烈な短3度の音型の繰り返しが印象的。連続するシンコペーションはエネルギーに満ちている。ぐるぐる回るような踊りだろうか。3/4拍子や5/8拍子、7/8拍子で書かれた不規則なリズムでも、踊りのステップは勢いを失わない。Ⅰと同様にハープによって導かれたリトルネロは、弦楽器のフラジオレットとともに儚げに消えていく。
Ⅲ Allegro vivace
5音音階による快活な旋律はいかにもハンガリーらしい。この楽章ではハンガリー的な要素とルーマニア的な要素が交代で現れる。いずれのテーマも明るくカラッとしていて躍動感がある。ハープやピアノをふんだんに用いた華やかなオーケストレーションもお楽しみいただきたい。
Ⅳ Molto tranquillo
幻想的で浮遊感を感じさせる和声、切れ切れに現れるメランコリックな木管楽器の旋律が美しい。この旋律はアラブの都市の音楽のイミテーションであり、独特な節回しは捉えどころがなく不思議な感じがする。ヴァイオリンとチェレスタによる短いリトルネロも捉えどころがないままに消えてゆく。
Ⅴ Comodo
暗く引きずるような保続音の上で、ヴィオラとクラリネットに始まる原始的なリズムが繰り返される。チェロ、ヴァイオリン、フルートと重なっていき、執拗な下降音型が抑圧された印象を与える。突然の強奏も一定のテンポを保ったままで緊張感に満ち、またすぐに抑圧される。そして不吉な予感を孕んだままFinaleへとつながる。
Finale(Allegro)
これまでの楽章の断片がパッチワークのように組み合わされて登場する。トロンボーンに始まるⅡの再現は丁々発止として気が抜けない。立て続けにⅠ、Ⅲ、Ⅴの旋律が顔を出す。短いリトルネロの後、ヴィオラのソロが素朴なメロディを歌い、その一人の踊りは次第に大勢の踊りになっていく。最後は華々しく盛り上がって幕切れとなる。
初演:1923年11月19日、エルンスト・フォン・ドホナーニの指揮によりブダペストにて。
楽器編成:フルート2(両奏者ピッコロ持ち替え)、オーボエ2(2番はコーラングレ持ち替え)、クラリネット2(2番はバスクラリネット持ち替え)、ファゴット2(2番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット2、トロンボーン2、テューバ1、ティンパニ、トライアングル、グロッケンシュピール、テナードラム、小太鼓、大太鼓、シンバル、タムタム、チェレスタ、ハープ、ピアノ(4手)、弦五部
参考文献:
伊東信宏『バルトーク 民謡を「発見」した辺境の作曲家』中公新書 1997年
ベーラ・バルトーク(岩城肇訳)『バルトーク音楽論集』御茶の水書房 1988年
横井雅子『ハンガリー音楽の魅力 リスト・バルトーク・コダーイ』ユーラシア選書 2006年
アガサ・ファセット(野水瑞穂訳)『バルトーク晩年の悲劇』みすず書房 1973年
セルジュ・モルー(柴田南雄訳)『バルトーク 生涯・作品』ダヴィッド社 1957年
芥川也寸志:オーケストラのためのラプソディー
●芥川先生の遺されたもの
私は今から36年前に生まれ、12年前に新響へ入団した。これは「情熱と愛情を持って新響を30余年導いて下さった芥川先生」に接することを不幸にして得ず、「テレビの中の芥川先生」を生で見ることもほぼ叶わなかった、いわばポスト芥川世代であることを意味する。
「アーさん」については、先ず、「棒が決して得意ではなく、だいぶん苦労した」という昔話をよく聞いた。これについては後年、芥川先生が「岩城に棒さばきを褒められた」と嬉しそうに話されていたと聞く。今回調べたところ、それは新響113回演奏会(創立30周年記念、オール芥川也寸志プログラム)当日のことであった。岩城宏之氏の芥川先生追悼記事によると、文化会館の練習室で東京都交響楽団を指揮してのリハーサルを終え、「大ホールで芥川さんが指揮をしている」と聞いて舞台袖で《交響管弦楽のための音楽》の指揮を見、「その見事なタクト捌きに僕は驚嘆して、褒めちぎった」そうである。
その他、OB、OG、年の離れた友人たちからは、「練習では厳しく、時には一人ずつ弾かされた」、「練習の時間配分が悪く、1回も音を出さずに終わる団員もいた」等の苦情めいたものから、「一緒にレストランに行ったものの、何を頼めば良いか心配していたら、皆の気持ちを汲み取って(安価な)カレーライス!と真っ先に叫んで下さったので、安心して好きなものを注文できた」「自慢の愛車シトロエンでのドライブに交代で連れて行ってもらった」「アベックが多数いちゃついていることで有名な某所を愛車のヘッドライトで照らす悪戯を披露された」等の心温まるものまで、数々の伝説を伺ってきているが、直接存じ上げないこともあり、以下の拙稿においては、「ハイカラで気品があったイケメンの音楽家」で、「音楽の勉強のために冷戦時代のソ連へほぼ無一文で密入国し、ショスタコーヴィチ、ハチャトゥリアン、カバレフスキー等の錚々たる音楽家に認められた熱いハートの大作曲家」で、「悲しい叫び声にも似た響きをあげていた当団体を、30歳から晩年まで日本全国どこからでも練習に駆けつけ、無給で育て続けて下さった偉大な指導者」、としてのみ扱わざるを得ない。昔話をご期待頂いた方々にはお詫び申し上げる。
先生がご尽力くださった30余年と、その後の30年を経て、新響も代替わりが進み、先生にご指導頂いた経験のある団員はおよそ4分の1にまで減った。昭和から平成を経て「令和」へ至るとともに、黒電話はショルダーフォンを経てスマホへと進化し、神器とまで言われた白黒テレビはカラー化を経て一部では顧みられない無用の長物へと変わり、「モーレツ社員」が賛美された日本社会で「働き方改革」が叫ばれるに至る等、取り巻く環境は大きく変化した。こんな中、新響が唯一変わっていないのは、音楽を熱烈に愛する団員が幸運にも集まり続けている、ということだろう。

入団当時に私が心を打たれたのは、芥川先生の遺されたアマチュアリズムに関する言葉であった。世代を超えて受け継いでいきたい、新響のアイデンティティである。
――Webster大辞典によると、“Amateur”の第一義には“Love”とある。(略)代償を求めず、ただひたすら音楽を愛し、それに没入していく心、それがアマチュアの中身であり、魂でもあろう。(略)ただひたすらに愛することの出来る人たち、それが素晴らしくないはずがない。(略)これからも新交響楽団は、今と同じように美しく、愛に満ちあふれた素晴らしい存在であってほしい。――(第113回演奏会パンフレットより)
短かい杖 芥川也寸志
現代の音楽は、今や大きな過渡期に入っている。一つの音楽の歴史は終り、一つの新しい歴史の出発を求めて、われわれはいま、模索の時代に生きている。
現代音楽の一種の混乱は、栄光ある過去何世紀にもわたるヨーロッパ音楽の、大きな流れの中心的存在であった調性の崩壊にもとづいていることは明らかだ。バロック以前の作曲家たちにとっては、いかに調性をわがものとし、自由に扱うかが、それ以後の作曲家たち、ことにドイツ古典派の作曲家たちにとっては、確立された調性の機能をどう拡大させるかが、ロマン派の作曲家たちにとっては、調性の束縛のなかでどのように自由たりうるか、いかに支配しうるかが、それぞれ課題であった。そしてドビッシーは、技法的に調性と対決し、それを崩壊に導く手がかりをつくり、シェーンベルクは十二音技法をもって、さらに徹底した挑戦を行なった。
このように、ヨーロッパ音楽は調性を中心にして動いてきたのであり、歴代の作曲家たちは、調性を杖にして道を歩いてきた格好だともいえる。そして現代では、このような古典的な意味での調性は、すでに崩壊してしまっている。それでは過去何世紀にもわたる、大きな音楽の流れの中心であった、調性にかわるべきものは何か。現代における調性とは何か。
この問いに対する現代作曲家の答えは、それぞれまちまちであろう。少し大げさにいえば、”オーケストラのためのラプソディー”は、私なりの、一つの、パロディー風なそれへの答えである。ふるさとの歌――オスティナート――そして短い杖をふりまわす――。
明るく、少しおかしく、楽しげに響くことを期待している。(初演プログラムより)

●作風の変遷とオスティナートについて
芥川氏の作風は、以下の3期に分けることができる。
第1期(〜32歳頃):律動的なメロディの執拗な反復(オスティナート)と、甘く叙情的なメロディを融合させた作曲スタイルを確立。前者は伊福部昭、後者は橋本國彦に強い影響を受けたとされる。二人は芥川氏の師であった。
第2期(〜42歳頃):新しい音楽手法の模索。巨大な岩塊をくり抜いて造られたインド・エローラ石窟の体験から強い刺激を受け、何もないところから音を積み上げていく従来型の作曲法ではなく、全ての音が鳴っているところから音を削っていく「マイナス音楽」の探求を思い立つ。また、世界的な前衛音楽志向や、これを取り入れた友人の黛敏郎にも影響を受けた可能性があり、当時の流行であった無調・微分音・クラスター(群音)手法の採用も見られる。
第3期(〜晩年):第1期へ回帰して「オスティナート」にこだわり、限られた動機を執拗に反復する単一楽章形式の楽曲を多く残した。第2期で獲得した前衛的な手法の採用が見られるものもある。本日演奏する「ラプソディー」はこの時期(46歳)に書かれた作品である。
オスティナートへのこだわりについて、以下のような言葉が残っている。
――食事の前に心臓音をとっておいてテープで回してわりと大きく増幅して、食事のあと聴いてごらんなさい。一分以内に完全に同じ心臓になりますよ。(略)それをスライダクターで回転を速め、少しずつスピードを上げていって、ある速さに達したらテープを止めておいて、心臓音を聴いてごらんなさい。(略)止まりはしないけれども、猛烈なショックを受けることは確かだ。音楽というのは、そういうところにつながってないとウソだと思うんだな。(略)だから、本来の古い音楽の形では、オスティナートというのは音楽そのものだったと思うんですよね。(略)緻密な精神的な知能的な喜びじゃなくて、肉体的な喜びとして働きかける。おそらくいまの作曲家は大部分、それは音楽の堕落だというだろうけれども、僕はそこをむしろ高めるというか、音楽の高まりだと思うんだ。――(出版刊行委員会編『芥川也寸志 その芸術と行動』東京新聞出版局 1990年より)
●作曲ノートの解説のようなもの
クラシック音楽として最も知られる「ラプソディー」は恐らく「ラプソディー・イン・ブルー(ガーシュイン、1924年)」であろう。市井においては「ボヘミアン・ラプソディ(クイーン、1975年)」であろうか。一般に「即興的なキャラクターを持った、非定形で、民族的あるいは叙事的な楽曲」だと解されており、本曲の冒頭はその特徴をよく表している。
曲はホルンの咆哮で始まるが、すぐにtuttiの打撃的な強奏で中断される。ヴァイオリン・ヴィオラが提示する躍動的な1つ目の動機が発展した後、再びホルンが咆哮し静寂が訪れる。ついで「馬子唄のように」と指定された、五音音階からなる民俗音楽的で叙情的な2つ目の動機がヴィオラにより提示される。やがてこの動機は、即興的なキャラクターを持つ「ほぼカデンツァのように」と指定されたヴァイオリン・ヴィオラによる強奏で中断される。
ところで、この2つ目の動機を構成する五音音階(Ges/H/C/Des/E)は、日本の伝統的な五音音階(四七或いは二六抜き音階)とは構成音がやや異なっており、むしろDesを除いては六音の琉球音階((A)/H/Des/(D)/E/Ges)と一致する。本曲が完成した1971年9月は沖縄返還協定調印後3ヶ月足らずの時期である。芥川氏の何がしかの想いをそれとなく反映させた、と見るのは飛躍しすぎだろうか。
話を戻そう。曲はやがて、金管群とハープによる呪文のような3つ目の動機を経て、躍動的なテーマを執拗に反復するアレグロ・オスティナートに突入していく。このテーマは、芥川氏が大変気に入っていたもので、後々サインにも添えられる程であった。

曲全体を通して調性感は希薄であるが、調性の持つ力学のようなものを薄く残している。調性を確定するにはカデンツ進行が必要であるが、この曲では、その進行の途中で当該調性とは異なる音、具体的には半音ずらされた音が多用されている。これは、調性を確定できるか曖昧な楽句、即ち調性という杖として体を支えるには短すぎる楽句が多用されている(=ふりまわされている)、と見ることができる。作曲ノートを乱暴に意訳し、まとめとする。「この曲は、西洋音楽の中心であった調性に変わるべきものは何か?現代における調性とは何か?という問いへの1つの答えとして、民族音楽的なもの、律動的メロディの執拗な反復、そして薄い調性感を利用して書いたものである。」
初演:文化庁が委嘱し、1971年 9月12日に完成。同年10月4日、文化庁芸術祭「管弦楽の夕べ」にてNHK交響楽団(森正指揮)が初演。尚、この演奏会では、本曲の他にモーツァルトのハ短調ミサが演奏された。
楽器編成:フルート4(各奏者ピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ1、クラリネット2、バスクラリネット1、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ1、ティンパニ1、パーカッション4(第1奏者:カバサ、ギロ、シンバル、グロッケンシュピール/第2奏者:ギロ、カバサ、マラカス、グロッケンシュピール/第3奏者:ギロ、カバサ、グロッケンシュピール、ムチ、大太鼓、ボンゴ、マラカス/第4奏者:カバサ、ギロ、小太鼓、テナードラム、タムタム)、弦五部
参考文献:
出版刊行委員会編『芥川也寸志 その芸術と行動』東京新聞出版局1990年
芥川眞澄監修 新・3人の会著『日本の音楽を知るシリーズ 芥川也寸志 昭和を生き抜いた大作曲家』(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス発行
NAXOS 芥川也寸志:オーケストラのためのラプソディ/エローラ交響曲/交響三章(ニュージーランド響/湯浅卓雄指揮)CDのリーフレット
新交響楽団創立10周年記念特別演奏会BEETHOVEN CYCLES(1966年9月、10月、11月、12月)プログラム
新交響楽団創立20周年記念第73、74回演奏会 日本の交響作品展 昭和8年〜18年(1976年9月、10月)プログラム
新交響楽団第100回演奏会(1983年6月)プログラム
新交響楽団第113回演奏会「新響と30年 芥川也寸志」(1986年11月)プログラム
昭和46年度文化庁芸術祭「管弦楽の夕べ」(1971年10月4日)森正指揮、NHK交響楽団 演奏会プログラム
NHK交響楽団HPより1971〜1980年演奏会記録https://www.nhkso.or.jp/data/document/library/archive/kiroku1971_1980.pdf
ご協力:芥川眞澄様、株式会社スリーシエルズ 西耕一様、株式会社木之下晃アーカイブス 木之下貴子様、新交響楽団OB、OGの皆様
変転と継承と =新交響楽団の「昭和」と「平成」
◆終焉に向かう昭和の光景と「空気」
新帝即位も間近となり、巷間「平成最後の~」のキャッチフレーズが当たり前に流布しているのを目の当たりにすると、昭和の終焉を知る身には隔世の感としか言いようのない感慨が浮かぶ。新響に於いても今回の第245回演奏会が「平成最後の演奏会」であり、その2日後には新たな時代に入る事が確定している。
では「昭和最後の演奏会」は?・・・・と改めて調べてみると昭和63(1988)年10月16日の第121回演奏会(指揮:森山 崇/於:昭和女子大学人見記念講堂)がこれに当たっていた。当時を知る古参の団員でも、この演奏会が昭和最後だったと認識・記憶する人はまずいないのではなかろうか?無理もない。それは僅か3か月足らずの後に訪れた昭和天皇崩御によって「結果的に」掉尾のものとなったのであって、演奏会時点で最後になるとは考えられなかったからである。
この「考えられなかった」・・・・という言葉の中身は微妙で、少なくとも「予期できなかった」の意味ではない。「考えてはいけない」若しくは「考える事が憚られる」という含意だった。そこには天皇の死という、大部分の日本人が経験していない重大事が絡むものだったからである。
この「考えてはいけない」「考える事が憚られる」という空気は、昭和天皇のご病状が悪化した1988年9月以降特に顕著になった。季節は秋である。国内各地の歌舞音曲を伴う祭礼は自粛されたし、学校の運動会や体育祭も無期延期や中止が相次いだ。もちろんこれらは決して強制されたものではない。「どう対処すべきか?」を真摯に考える事なく、半ば反射的に自粛で対応する姿勢に巻き込まれる・・・・国全体が思考停止していたとしか思えない。
この年日産から発売された『セフィーロ』という車のCMについては今もはっきりと記憶がある。助手席から井上陽水が「みなさんお元気ですか?」と語りかける企画だったが、ある時からこの語りかけ部分が無音になった。口パクでは何の意味も無い訳で、このCM自体が他に差替えられてお蔵入りになった。この奇妙さ。「お元気でない人」に対する今でという忖度という事になろうか?天皇のご病状はニュースの冒頭で必ず報じられ、一向に快方に向かわぬ情報が重なるほどに世情を暗くしていったし、それが更なる自粛を生み出す事につながった。
年末が近づくと「年賀状はどうするべきか?」という議論まで起きた。虚礼廃止の風潮が高まる以前の事で、企業間では盆暮の贈答も年賀状のやり取りも盛んにおこなわれていた時代である。取引先との忘年会は相次いで中止。年初の賀詞交歓会はどうなるのか?全く見当がつかない状態だった。そして年賀状に至っては個人的なやり取りにまで波及しそうになった。流石に「毎年誰に対しておめでとうと言っていたのか」という声が上がり、まぁ平常通りに落ち着いたように記憶する。私個人はちょうど喪中(6月に母親を喪っていた)に当たっていたのでこの年賀状騒動とは無縁でいられた。不幸中の幸い?というべきか。
天皇の死によって元号も初めて変わる、所謂「一世一元」の制度は実は歴史も浅い(明治期に制定)。明治・大正期のように世の中が緩やかに流れていた時代はまだしも、果たして現在の社会に適合するものなのか?社会や市民生活に対する有形無形の重大な影響を及ぼす事は、こうした事例を思い出すだけでも疑問として起こりそうなものだ。が、今回の生前退位の議論の中で、昭和末年当時の社会の混乱(その殆どはこれまで述べたように世間全般の「空気」から起こった)についての記憶に基づく声は挙がらなかった。何故だろう?という疑問が今も残る。その記憶に照らしてみれば、「平成最後の〇〇」の濫発にはいささか食傷しつつも、新時代を迎える現在の社会の空気が明るい事は、個人的に救われた気持ちになるというものだ。
◆新響にとっての内憂と外患
天皇陛下のご不例(この語をこの時初めて生きた言葉として用いた)。これ自体が日本国民にとっての内憂だったが、まさにこの時期新響の場合更なる内憂を抱えていた。それは芥川氏の病状が判らなかった事である。この年1988年の4月24日、芥川氏がその保存運動の先頭に立っていた東京藝術大学奏楽堂の移転記念演奏会にて新響を指揮したのを最後に、氏は療養に入り入院(肺がんと診断され手術を受けていた事は死後に知った)。その後の詳細情報は新響にも一切入らなくなった。翌1989年4月の演奏会は芥川氏の指揮と決定していたので、その具体的な企画や曲目を決定すべき時期に差しかかっていたが、何ら決められる事が無い。そもそも出演の可否さえ判らないのである。指揮者がどの練習に参加できるかさえ不明である限り、全体の練習計画も立てられない。だが出演の可否が判らないからといって代わりの指揮者を探し始める決断もできないのである。
現在の新響ならこのように既に出演が予定されている指揮者の健康状態に不安が生じた場合、次の候補を探し出す決定をする事は合同委員会の協議によって可能だ。だがこの当時は違う。芥川氏は新響の音楽監督であって、団内の音楽的決定の全てに氏の承認がいる。その当の本人との音信が不通なのだから我々には対処の術が無かった。そしていつしかこの件は天皇のご病状と同様に「考える事が憚られる」領域に入りつつあったのだった。
そんな状況下に運営委員会を開いても早急に決めて行動しなければならない事に対して為せる事が何もない。途方に暮れて終了後街に出ると、天皇ご不例の最中とあって、街も暗く沈んでいる。さらにこちらは肉親を喪って間がなく、家に帰っても誰もいない状態とあって、昭和63年の秋口以降、全てが息をひそめていた印象しかない。昭和最後の年はかくして暮れていった。
明けて昭和64年1月7日土曜日。年初早々から仕事はトラブルを抱え、この日は休日出勤が予定されていた。気が進まぬまま起き、テレビを点けるといつもと様子が違う。瞬時に「これは天皇崩御だな」と直感した。来るべきものが来た感覚。まずは身支度をダークスーツと暗色のネクタイに変更した。予め社内には「重大事態発生時」の身なりにつき指示の文書が回っていた。おそらく日本のどの企業もそうしたお触れが出ていた筈で、重大事態が何を指すかについても、皆が暗黙の理解をしていたのである。
それはそれとしてもうひとつの懸案事項が急遽持ち上がった。この晩の新響の練習を予定通り挙行するかどうか?である。年明け最初の、そして本番2週間前の練習である。そうでなくとも年末年始の休みを挟むと、それまでの蓄積が目減りしてしまう事が往々にしてあるとあって、是が非でも音を出したい処。インスペクターとして実質的にこのシーズンから練習計画を取り仕切っていたこちらはもう仕事どころではない。メールも携帯電話も普及していなかった時代である。関係者間で連絡を取り合うのも難儀が予想されたが、偶々週末だった事もあってみな自宅に待機していた。そして協議の末に昼までには「予定通り決行」の方針が定まった。
そぞろな気分のうちにとにかく予定の打合せをこなし、会社を出られたのが15:00過ぎ。この時点で既に次の元号「平成」は発表されていたが、私はまだそれを知らずにいた。冷たい雨の降る都心に出るにも電車はガラガラ。所々に半旗や喪章をつけた国旗を目にする。定刻にはメンバーが練習会場である水道橋の『神田パンセ(旧労音会館。今はもうない)』に集まった。が、当然ながら年始の挨拶もなく、何か時節を誤ってひどく場違いな処で、見当はずれの事をやっている・・・・という感覚から抜け出せなかった。寡黙なまま盛り上がりに欠けた練習が終わると、皆そそくさと家路についた。日頃の練習のように終了後に呑みに行く事もせず。そもそも酒を呑もうとしても流石に開いている店が殆ど無かったし、あっても開店休業の状態だったのだ。帰宅後に視るテレビもどこも同じような画面しかない。かつて学生時代にNHK交響楽団の関係者から、天皇崩御の際に備えた厳粛な音楽の演奏を、既に録画済みであるとの事を耳にした事があった。その種の映像も当然何度も目にしたが、事前に収録されたものであるという先入観が邪魔をして、何か空疎な気分が伴っていた。
この日はレンタルビデオショップだけが盛況だったと後に知ったが、不謹慎ながら得心も行った。昭和という時代の終焉がこのような形になる事は想像していなかった・・・・もっともどのような形も想定できなかった訳だが。
平成最初(第122回=これも結果的にそうなった)の演奏会は2週間後の1月22日にサントリーホールに於いて行われた。指揮は山田一雄氏でメインのプログラムは『幻想交響曲』。この曲は新響にとって鬼門のようで、何度演奏してもどこかしらに瑕を残して今に至っている。そしてこの時の演奏は年初からの練習も進捗しなかった事もあってか特に不首尾に終わった感がある。個人的な失敗も絡んでいた。
私はその当時、新響に於けるインスペクターとして練習に関わる実務を引き受けると共に、『東京マーラー・ユーゲント・オーケストラ(TMJ)』という団体の結成に深く関わり、代表(という名の雑用係)を務めていた。指揮者に同じ山田一雄氏を仰ぎ、新響の練習と並行してマーラーの第三交響曲を練習中だった。雑用係だから練習の都度に山田氏とは事前連絡をとり、その日の会場や練習内容について話し合っていた。
これも年が明けてからの練習の事と記憶するから、本番1週間前の時期という事になろうか?日曜日だった。新響の練習を午後に控えたその朝にも山田氏とは連絡を取っていた。その打合せに沿って会場最寄りの駅改札口で氏を出迎える。歩き始めた処で、
「先生、今朝お伝えした通り、今日は『幻想』からお願いします」 と伝えるとやや間があって、
「・・・・ああ~~」
叫びと共に人混みの流れの中ながら頭を抱えて立ちつくしてしまった(このあたりの情景はヤマカズさんの往年を知る人には容易に思い浮かぶだろう)。何とTMJの練習と勘違いしてマーラーのスコアを持って来てしまっていたのだった。仕方なく私のスコアを提供してひとまず練習の形は間に合わせたが、所詮他人のスコアである。練習は低調に終わってしまった。新響にはこの内情は伏せていたが、これは偏に私の責任である。本番の直前になってさえこんな混乱を来しているようでは結果も知れていよう。
当時の新響の演奏は出来不出来の波が大きかった。だが自分の不手際を敢えて度外視したとしても、団全体の気分は未だ昭和の終焉を引きずっていて、平成の新時代への切替えに至っておらず、更には音楽監督たる芥川氏の長期の不在と不明の病状という要素が加わり、少なからぬ影響を演奏に与えていた事は間違いない。
◆芥川氏の死=新響の昭和と平成と=
それから10日と経たぬ1月31日。この日一日の出来事は、30年を経た今も時間単位で記憶を呼び戻す自信がある。
午前中家人から電話が会社に入った。病院からの帰途で、子供が出来て9月下旬が予定日という。この時を含め3人の子を持った訳だが、自分の子が生まれる?現実味皆無の感覚だった。が、とにかく人の親となるからには待ったなしで決めなければならない事(まだ所帯も定めていなかった。)も沢山湧き出してくる。とにかく晩に待合わせて相談という運びになった。
その夕刻17:00過ぎ。外出先に連絡が入り、芥川氏の訃報を知る。病状を知る事も無かった分、突然の死去とのイメージが強く、ショックも大きかった。朝家を出る時には予想もしなかった、新響と私生活上の問題が同日同時に降りかかってきた。言うなれば「公私」の狭間の中でどう対処するか?の回答が容易に出ないが、とにかく帰宅するほかない。飛び乗ったタクシー内のラジオからは芥川氏死去のニュースが流れていた。
繰返しになるが現在とは違い、通信手段と言えば携帯電話やメールではなく固定電話が当たり前。即座に仲間内で情報が共有できるという時代ではない。確実に電話のそばにいられる団員を基点にして連絡を集約する方法で情報をその都度確認する事に決まる。その結果として新響の運営メンバーの大半は芥川邸に向かう段取りを取られていた。
が、こちらは流石に今日ばかりは自分の生活を優先せざるを得ない・・・・という結論に達し、行きつけの店で家人と落ち合ったが。だが個人的な話を進める間にも、何度か新響のメンバーと連絡をとっていて、その都度店を出入りする必要がある。様子を見ていたなじみの店主(女性)より理由を訊かれたので、芥川氏が亡くなった事、その関連の連絡で落ち着けないでいる事を伝える。
「芥川也寸志さんて草笛光子のご主人だった人よね」 「えっ!?」
意表を衝かれた。自分が世事に疎いだけかもしれないが、それにしても我々にとっての彼は、まずは芥川「先生」であり、新響の音楽的決断の全権を握る「音楽監督」の位置づけで、ある種雲の上の人だった。が、世間の人にとっては、作曲家として知られると同時に、テレビでもよく顔を見かけるある種の「タレント」であった。女優との結婚歴が無かったとしても、芥川氏を見る目には全く異なる角度があったのだった。
因みにその草笛光子氏は現在85歳を超えて未だ女優としての生命を保っている。昨2018年初頭から1か月間『日本経済新聞』の『私の履歴書』にこの女優の自伝が掲載されていたので、芥川氏との2年ほどの結婚生活にどの程度踏み込んでくるのかを、個人的な興味もあって毎日読み進んだ。が、結婚生活はすれ違いの連続との話があるばかりで詳細には殆ど触れられておらず、肩透かしの感が残った(これは余談)。
平成元年の1月は終わった。
この月は日本にとっても新響にとっても自分個人にとっても、殊更に寒く暗く、そして長かったという印象が去らない。そこには死の影が貼りつき、その影響は長く尾を引いた。それでも人は日常を喜怒哀楽のうちに暮らし、絶え間なく人生を送っていかなければならない事を痛感していた。先年に母親を亡くして初めて気づいたのは、親が死んでいくら悲しかろうが、生きているこちらは時が来れば確実に腹が減る、という哀しい現実だったので、尚更にそう感じていたのかもしれない。
そしてはからずも個人的に生と死の交錯を経験する日となった平成元年の1月末日を以って新響の「昭和」も終わり、同時に「芥川也寸志と新交響楽団」の時代も幕を閉じた。
これはすなわち芥川氏の謦咳に直に接し、新響のメンバーひとりひとりが、その音楽に対する姿勢や精神を学び得た時代が終わりを遂げ、今後は彼の遺志と精神とを継承しつつ、我々ひとりひとりが芥川氏の唱えた「アマチュアである事」の自覚に基づいて、そのあるべき姿を模索する時代が到来した事を意味した。言うなれば新響に残された氏の遺産を、時代ごとの状況と考え合わせて、「変えるべきもの」と「不変であるべきもの」とに取捨して継承するという宿題を突き付けられた訳だ。そしてここに新響に於ける「昭和」と「平成」との明確な時代区分があると考えざるを得ない。
芥川氏の不在によって全てが停滞していた同年4月1日の第123回演奏会は、2月に入って決定した本名徹二氏の指揮によって、2ヶ月弱の練習期間で危機を乗り切った。この演奏会のひとまずの成功によって、ようやく新響の平成時代は始まったと感じている。
ずいぶんと昔の事になった・・・・。
作曲家「芥川也寸志」とアマチュア音楽家「芥川也寸志」
芥川先生ご存命の頃、団員同士の会話では、芥川先生を親しみと敬意をもって“アー様”呼んでいた。
アー様と新響のお付き合いは、1955年から1989年まで34年の長きに亘った。ところが、1986年の第113回演奏会以前、新響はアー様の作品を4曲しか演奏させてもらえなかった。『絃楽のためのトリプティーク』『交響管絃楽のための音楽』『交響三章』「コンチェルト・オスティナート」の4曲だけである。1976年に始まった『日本の交響作品展』であっても、一切取り上げることはなく、10年目の第113回演奏会『日本の交響作品展10:新響と30年--芥川也寸志』に至って、新響はやっと4曲以外の作品を演奏する機会を得た。これ以降、新響は映画音楽を含め数多くの芥川作品を取り上げてきた。アー様ご存命の頃、作曲者と共に演奏したこれらの作品は、今日では新響のレパートリーになったと言える。しかしながら、演奏させてもらえなかった作品もあり、今回取り上げる『オーケストラのためのラプソディ』もしかりである。アー様が新響に許さなかった理由は「新響じゃ無理だから」・・・・・。
アー様没後の再演の方が、私にとって、より大きな感動を体験できた演奏が多い。特に、『日本の交響作品展10』で共演できた「交響曲第1番」は、僭越ながら、作曲者自らの指揮ではさしたる感銘を受けなかったのに対し、没後、第126回山田一雄、第166回飯守泰次郎、第232回湯浅卓雄といった指揮者との再演では、演奏しながら毎回「鳥肌」ものだったのだ。アー様は「はにかみや」な面もあって、自分の作品を指揮する時もそんな一面が出て、指揮が控えめだったかもしれない。日本の楽壇を代表する名指揮者とアー様の指揮者としての力量の差だったのかもしれない。作曲者としてのある種の先入観から、作品を客観的に捉えられなかったのかもしれない。いずれにせよ、没後の再演は、私にとってかけがえのない貴重な演奏体験になっている。
ショスタコービッチ作品などでアー様の指揮ぶりは、自作の指揮とは全く違うのであった。「はにかみ」は一切なく、全身からオーラを放出して作品の深層部を引き出しているように感じた。若き日の単独渡露体験、ロシア作曲者との交流、客観的なスコアリーディングなどが織り交ざった結果であろうか。もう一つ忘れてならないのは、アマチュアの純粋さであろう。アー様の寄稿にこのような一節がある。
“Webster大辞典によると、“Amateur”の第一義には“Love”とある。まさに愛してやまぬ、これこそアマチュアの心であろう。
・・・途中略・・・
私はいつも、アマチュアを「素晴らしきもの」の代名詞にしたい位に思っている。ただひたすらに愛することの出来る人たち、それが素晴しくないはずがない。私がいつも、新交響楽団の肩書に、小さくアマチュア・オーケストラといれるように頼んでいるのは、それを忘れないようにするために、そして、大勢の方々にそれを分かって頂きたいためにである。”
http://www.shinkyo.com/04history/をご覧いただきたい。
アー様は、指揮者として新響の一員であり、いや、アー様ご自身は新響を一心同体だと思っていたのであり、高い理念の基で「アマチュア指揮者」を体現していたのだと確信している。
第245回演奏会のご案内
芥川也寸志没後30年
新響の音楽監督であった芥川也寸志が亡くなって今年で30年になります。芥川也寸志は1925年に文豪芥川龍之介の息子として生まれ、東京音楽学校(現東京藝術大学)作曲科に進み作曲家として魅力的な作品を残す一方、指揮者や音楽番組の司会者などさまざまな音楽活動を通して音楽を広め、日本の戦後の文化の発展に大きく貢献しました。今回の演奏会では芥川作品の中から、後期の代表作の一つである「オーケストラのためのラプソディ」を演奏します。
芥川の初期の作品には「管絃楽のための音楽」「交響三章」といった洗練された旋律と軽快なリズムの曲があり、その後「エローラ交響曲」のような前衛的な作風を経て、1971年に作曲されたのが「オーケストラのためのラプソディ」です。ラプソディとは自由な形式で民族的・叙事的な内容を表現した曲のことです。ほら貝のようなホルンの咆哮、日本の横笛を思わせるフルート、伝統的な5音階による旋律が散りばめられ、短いパターンを何度も繰り返すオスティナートで躍動的に終わります。芥川作品の中でも特に日本的な作品かもしれません。
バルトーク 舞踏組曲
いっしょに演奏する曲には、民族的な作曲家であるバルトークとシベリウスの作品を選びました。
バルトークはハンガリーの作曲家で、「中国の不思議な役人」「管弦楽のための協奏曲」など国際的に活躍しましたが、民族音楽の研究家でもあり、ハンガリー国内の民謡収集だけでなくルーマニアやスロヴァキアなども調査し、彼の作品にも反映されました。
「舞踏組曲」はブタペスト市50周年記念音楽祭のために1923年に作曲され、ハンガリー風の旋律以外にルーマニア風、アラブ風などの旋律による5つの舞曲と終曲からなります。ハンガリーと周辺国との連帯という意味を込めて作曲したということです。
シベリウス 交響曲第2番
シベリウスはフィンランドの国民的作曲家です。シベリウスの作品の中でもっとも人気があるのが今回演奏する交響曲第2番といってもよいでしょう。当時のフィンランドはロシアの統治下にあり、貧困に苦しみロシア化政策により自律性も危ぶまれる状態の中で、愛国独立運動が盛り上がっていました。シベリウスは第2番を作曲した1901年に、助言と資金援助を得てイタリアの地中海に臨む暖かなラッパロという都市に旅行し、途中ローマにも滞在してオペラや教会音楽を見聞きしたことが、この曲に大きな影響を与えています。
ドラマチィックでカンタービレながらフィンランド語的な響きで、そして最後には勇壮なメロディが繰り返されて高揚していきます。その光はきっと当時のフィンランドの人々の愛国心に届いたことでしょう。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
リヒャルト・ワーグナー:トリスタンとイゾルデ
1.「トリスタンとイゾルデ」を楽しむには
2018年5月の日曜日、SNSやテレビなどのニュースに“ワグネリアン”の文字が踊った。“ワグネリアン”という競走馬が日本ダービーで優勝したのである。これで日本中にワグネリアンということばが広まったのだが本来の意味を知っている人はどのくらいいただろうか。ご存じのようにワグネリアンとはワーグナー音楽愛好家のことであり、そこには“ワーグナーの熱狂的な愛好家でちょっと危ないかいもしれないやつ”というニュアンスもこめられている(かもしれない)。馬主にもワーグナーの熱狂的な愛好家がいたのだろう。ところで、ワグネリアンという言葉はあるがベートーヴェニアンとかブラームシアンとかいうのは聞いたことがない。バッハ、ショパンにもない。ほかにはモーツァルティアンくらいだろうか。(なお、ブルヲタというブルックナー愛好家を自虐的なニュアンスで呼ぶ言葉はある。)いずれにしろワーグナーの音楽に魅せられると万国共通、熱狂してしまう傾向にあるようだ。そして冗談でなく真の意味で危ない人も歴史上にいた。
話を戻そう。ワグネリアンの中で、おそらく一番人気なのが本日演奏するトリスタンとイゾルデではないだろうか。その魅力とはなんだろう? 一人のワグネリアンの見解として述べさせていただくと、エロティシズムが音楽によって表現されつくされていてその凝縮度が彼の作品の中でも抜きんでているからだと思う。全曲約4時間のうちの大部分が、主人公であるトリスタンとイゾルデの心理的駆け引きと性愛の場面に費やされ、音楽は二人の心理状態や行為をこれでもかと言わんばかりに深く、そして執拗に表現する。焦燥、期待、興奮、絶頂、気怠さ、恍惚、裏切り、絶望などを音楽でよくもこれだけ精緻に深く表現できるものだと思う。まさに奇跡的な音楽だと言わざるを得ない。全てが聴き所と言ってよいほど充実していて、一度嵌ると抜け出せない魅力にあふれているのである。
しかし一方で「いつ終わるとも知れぬ音楽を聴かされ、一眠りして目が覚めたがまだ同じ歌手が同じように歌っていた。」などと揶揄されることもある。その理由は、とにかくなかなか話が進まないからなのである。本日演奏される、このオペラの中核となる第二幕、約70分間に何が起こるかと言えば、不倫の逢引きを女性主人公が待ち焦がれる場面(第1場)、ようやく会えてからの愛の場面(第2場)、二人が愛の絶頂を迎えるところで寝取られた王様とその家来たちが踏み込んで、王様が延々と嘆いたあと男性主人公がやけになって王の家来に刺される(第3場)。以上で終わりなのである。波乱万丈、紆余曲折のストーリーはない。何が面白いかと言えば、前述のように男女の愛にまつわる登場人物たちの心理描写につきる。ではその面白さを味わうにはどうすればよいだろう。それは以下の二つではないだろうか。
1)主人公への感情移入
まずは登場人物、特に二人の主役トリスタンとイゾルデの置かれている境遇や心境に、できる限り想像をめぐらせて理解・共感して感情移入することである。そのためにはこのオペラの背景をできるだけ細かく知っておくことが必要である。オペラの背景いわゆる前史の説明はワーグナーの台本によくある特徴(悪い癖?)で、登場人物の歌の中に「あのときああした。あそこでこうした。」と、延々と回顧談が出てくる。これは字幕をご覧になっていればある程度はわかるのだが、初めて見る方には情報量が多すぎて、また暗示的にでてくるので把握しきれないおそれがある。そのため、この物語の背景、登場人物の境遇、粗筋などを事前によく理解しておくとよい。
2)主要な示導動機(ライトモティーフ)の理解
「トリスタンとイゾルデ」は他のワーグナーの作品と同じように、特定の物、人物、感情などの概念を表す短い旋律を多数組み合わせて作られている。この旋律を示導動機と呼んでいる。普通の歌劇にあるような、わかりやすいメロディーで一つの歌が構成されるいわゆる「アリア」というものはない。示導動機は、歌やオーケストラに変幻自在に現れて劇の進行や登場人物の心理状態を表現する。難しそうに思えるかもしれないが、主要な示導動機(旋律)を覚えてしまえばとても理解しやすいともいえる。ちなみに、この手法を最初にわかりやすく取り入れて名曲「幻想交響曲」を作ったのがベルリオーズである。
それでは、以上二つに関して順に説明していこう。
2.主人公たちへ感情移入するための準備
1)「トリスタンとイゾルデ」の背景
厳格なキリスト教が社会の規範であり、君主と家臣の上下関係、女性の純潔、騎士道精神が絶対であった中世ヨーロッパ。モロルトという名の勇者の活躍によりアイルランドは圧倒的な力で周辺諸国を傘下に収めていた。マルケ王が治めるコーンウォールも例外なく屈辱的な境遇にあった。マルケ王は領民からの信望は厚いものの戦は得意ではなかったのだ。しかしあまりに非道な支配に耐えかね、ついにアイルランドに戦いを挑む。傍目からは勝ち目がない戦いのように見えたが、実はコーンウォールにはトリスタンという、カレオール出身のまだ若く無名だが非凡な勇者がいたのである。彼は敵国の勇者モロルトを巧みに挑発し、孤島での両者一騎打ちの決闘に持ち込む。トリスタンのことをただの若造と侮ったモロルトは、不覚にもトリスタンの剣の一撃を頭に受けて命を落とす。将軍のモロルトを失ったアイルランド軍は敗走し、それ以来弱体化してしまう。
さて、勝利したトリスタンがその後どうなったかだが、さすがモロルト、戦いの際に猛毒を塗った剣でトリスタンに傷を負わせていたのである。治療の甲斐なくトリスタンは瀕死の状態になってしまう。そこで、医術が抜きんでていることで知られていたアイルランドならば解毒できる人物がいるかもしれないと考え、トリスタンは藁をもつかむ思いで身分を隠して一人小舟に身を横たえ、アイルランドに向けて流れる潮にまかせて船を出す。運よくアイルランドの岸辺にたどり着き、運ばれたところが高度な医術を身につけていることで名高いアイルランドの王女イゾルデのもとであった。
イゾルデはトリスタンを見て、その高貴で美しい姿に惹かれつつ親身に治療を施す。話せるくらいに回復したのでイゾルデが名前を尋ねるとトリスタンは「タントリス」と答える。ちょうどそのころ、討たれたモロルトの首がコーンウォールからアイルランドに送り返されてイゾルデのもとに届く。実は、モロルトはイゾルデの従兄であり婚約者でもあったのだ(しかしその婚約は多分に政略的なものであったのかもしれない。少なくともイゾルデの言葉にモロルトへの心よりの愛を感じさせるようなものはみあたらない)。モロルトの頭蓋骨に剣の破片を見つけたイゾルデはひらめくものがあり、若者(自称タントリス)の持っていた欠けた剣にその破片を合わせてみる。なんとぴったりだ。目の前に横たわる美しい若者が祖国アイルランドの敗戦のきっかけを作った敵の勇者だったのだ。イゾルデはモロルトの復讐を果たそうと病床のトリスタンに剣を振り下ろそうとする。しかしトリスタンは全く動揺することなく、美しい瞳でイゾルデを見据えるだけであった。そのときイゾルデにどのような心境の変化があったのか。その場で剣を取り落し、その後もトリスタンの治療に精を出すことになる。無事回復したトリスタンはこの恩は一生忘れないと言い残して去る。
トリスタンはコーンウォールに帰国し、親友のメロートとともに、マルケ王に再婚を迫る。マルケ王は若くして妻を亡くし子供がいなかった。そして主従逆転したアイルランドとの関係を維持するためにもアイルランドの王女イゾルデを娶るべきであるとマルケ王に強く勧める。マルケ王は非常に謙虚な性格で、いまさら年老いた自分にそのつもりはないと固辞するのだが優しく優柔不断な性格とコーンウォールのためを考え、ついにその勧めを受け入れる。そして、イゾルデを迎えに行くためにトリスタンは再びアイルランドへ向かい、アイルランド国王と話をつけ、めでたくイゾルデをコーンウォールに戻る船に乗せることに成功する。この船の上の情景からオペラが始まる。
2)主要登場人物の紹介とその心理状態
主人公への感情移入の助けとするために、次は登場人物それぞれに焦点をあてて説明してみる。
■トリスタン
トリスタンはフランスのブルターニュ地方のカレオール出身で、今はコーンウォール一番の勇者であり、マルケ王が最も信頼する家臣である。父はトリスタンが生まれる前に戦死し、母もトリスタンを生んだ後すぐに亡くなってしまっているので両親のことは記憶にない。死への憧れが強く、オペラの前史で少なくとも1回もしくは2回、オペラの中でも3回は“未必の故意”で死のうとして3回目でついに死んでしまう。前史での2回とは、最初にモロルトを挑発して決闘に持ち込んだという無謀な行動。次に、イゾルデのもとで治療を受けているときに素性がばれ、イゾルデに剣を振り下ろされそうになったとき何の抵抗もせずにイゾルデの目を見据えた、という行為である。この瞬間トリスタンはイゾルデのことをどう思ったのか?そして治療してもらい無事に帰してもらうことになった時、イゾルデに対して単に感謝の念だけではなかったことは明らかだろう。しかし、船上で図らずも媚薬を飲んでしまうまではそのそぶりを見せるどころか、イゾルデをマルケ王の後妻にする計画まで率先して奨めてしまう。この行為を理解するのに、中世の厳しい身分制度やコーンウォールとアイルランドの関係を慮ったものであると解釈するのが無難ではあるのだろうがもっと深い解釈もできるような気がする。とにかくトリスタンは勇士ではあるがいろいろ鬱屈したものを多く抱えた面倒くさいやつなのである。
■イゾルデ
トリスタンにモロルトが打ち取られるまではたいへんに羽振りが良かったアイルランド国の王女であるからプライドがとても高かったはずである。また、アイルランドは薬草の調合技術が進んでおり、イゾルデはその秘術を身につけている。敗戦によりプライドはずたずたにされてしまったのだろうけれど、自分のもとに担ぎ込まれた素性のよくわからない若者を親身に治療するのだから、とても高貴な精神と優しさを持ったお姫様に違いない。目の前の若者が婚約者モロルトのかたきであることが判明したのちもなお、なぜその“かたき”を取らずに治療を続けたのか?理屈では割り切れない感情が沸き起こったとしか思えない。トリスタンの美しさや憂いをたたえた眼差しにやられてしまったのか?いずれはトリスタンと結ばれると思い込んでしまったのではないかと考えられる。ところが、マルケ王に嫁がねばならないということになり、しかもよりによってあのトリスタンが、まるで貢物を運ぶかのように自分を迎えにきたことで逆上し、愛しさ転じて憎さ百倍、元敵国の爺さん(と言っても多分50歳未満)の妻になるくらいならトリスタンを殺して自分も死んでやると思っている。
■マルケ王
コーンウォール国の王でトリスタンの伯父にあたる。とにかく「人格者」である。最初の妻には先立たれ、その後は独身であった。ということからそれなりの年齢であることが推察される。トリスタンに全幅の信頼を寄せており、最初は乗り気でなかったイゾルデとの結婚もトリスタンの強い勧めで承諾した。にもかかわらずトリスタンに裏切られることになる。最後には全てを許して二人を結婚させようとするのだが…。登場すると嘆いてばかりである。
■ブランゲーネ
イゾルデの従者であり、ずっとイゾルデの身の世話をしている。第一幕では死の薬を用意するようにイゾルデに言われるが、動揺のあまり媚薬を用意してしまう。第二幕のトリスタンとイゾルデの逢引きの場面では見張り(全曲中で特に美しい歌を二回歌う)をしているのだが役に立たず、二人が絶頂を迎えるその瞬間にマルケ王たちに踏み込まれてしまう。第三幕直前にマルケ王に全てを打ち明けて許してもらうのだが、時すでに遅し…。など、やることが全て裏目に出てしまう。後悔はいかばかりだったであろうか。ブランゲーネは筋書上も音楽上も非常に重要な役割を担っている。なにしろ第一幕でイゾルデの指示のとおりに死の薬を渡してしまったらそもそもオペラが成り立たないわけであるし。
■クルヴェナール
トリスタンの忠実な家臣。少々お調子者でもあり、トリスタンの苦悩などは表面上しか理解できていないようであるがトリスタンに最後まで仕え、トリスタンを裏切ってマルケ王に密告したメロートを討つ。しかし、最後には問答無用でマルケ王にまで“お命頂戴”などといってしまうものだから王の部下に討たれてしまい、トリスタンの亡骸の近くで息を引き取り、涙を誘う。本当に“いいやつ”なのである。
■メロート
このオペラで唯一の悪役。トリスタンの元親友だがトリスタンとイゾルデの仲をマルケ王に密告、逢引きの場面に踏み込んでトリスタンを刺す。トリスタンがアイルランドとの戦いで活躍するまではトリスタンと同格か格上だったのかもしれない。それまでは親友としてふるまっていたのだがトリスタンが破格の出世をしたとたんに足を引っ張る。悪役ではあるものの世間によくいそうな普通の“ちっちゃい”やつである。
■羊飼いと舵取り
動きのほとんどないこのオペラにおける数少ないスペクタクルな場面展開を作る二つの役。第3幕でトリスタンとクルヴェナールに船が来たことを知らせる羊飼いと「マルケ王の一行が攻めてきた。もうだめだ。」と伝える舵取り。出番は一瞬だが場面を切りかえるために欠かせない役である。
3. 主な示導動機(ライトモティーフ)の説明
このオペラを楽しむもう一つの条件、示導動機を紹介しよう。実はたくさんあるのだが厳選して7つだけ紹介する。第一は「憧れの動機」(譜例1)である。本日最初に演奏される前奏曲の冒頭において、この動機の前半部分をチェロ、後半部分を木管(オーボエ、クラリネット、オーボエ)によってほぼ譜例通りに、ただし音が上昇しながら3回演奏される。
チェロの奏する前半はトリスタンまたは“憧憬”を表し、木管が奏する後半をイゾルデまたは“欲望”を表すとも言われている。このライトモティーフは半音階で上昇して下降、きれいな協和音に解決するかと思いきや次の音がかぶさってさらに上昇してそのサイクルを繰り返していくというもので、トリスタンとイゾルデがお互いを求めあう憧憬(欲望)がいつまでたっても満たされずに高まっていく様子に通じると思われる。その後すぐ、さらに際限ない胸の高まりを感じさせる「愛のまなざしの動機」(譜例2)がチェロで奏され、さらに続いて「愛の魔酒の動機」(譜例3)が現れる。このとき同時に、和声のためのただの背景のようで聞き逃しかねないがとても意味ありげで不穏な「死の動機その2」(譜例4)が低音楽器により奏されている。この二つは同時に奏されることが多い。
トリスタンとイゾルデはお互いの憧憬と欲望が我慢の限界にきて、ついに二人で魔酒を飲み干す。死の薬のはずだったのだがそれが実は愛の薬(媚薬)であり、二人を踏みとどまらせていた社会通念や道徳といったタガが外れて突っ走り、そして破局に向かうというこのオペラの本質を表しているといってもよいだろう。なお「死の動機その1」もあるのだが、特に目立ってわかりやすく出てくるのは本日演奏しない第一幕なのでここでは省略する。
もちろん二幕にも出ては来るのだが。残りの厳選ライトモティーフ3点、まずは「光(昼)の動機」(譜例5)。これは少し説明が必要である。
トリスタンとイゾルデは媚薬を飲んでからはもうあっちの世界に行ってしまっており、昼、つまり社会や人間関係に縛られる世界を忌み嫌っているわけである。あまりに卑近なたとえで恐縮だが、夜に書いた手紙や作文、特にラブレターを「昼に見るなんて恥ずかしくて無理!」ということの極端なものと考えてもよいかもしれない。そのためこのライトモティーフは「傲慢な(insolent)昼の動機」または少々意味不明だが「憧れの痛みの動機」などとも呼ばれている。第2幕はこのライトモティーフで開始され、数えきれないほど何度もいろいろなところで繰り返される。6個目は「至福の動機」(譜例6)または「まどろみの動機」とも呼ばれる、まったりとした幸福感に包まれたもので、愛の場面で絶頂を迎えたあと、その熱を冷ますような感じで出てくることが多い。確かに“絶頂の後の至福”そんな感じである。
次はいよいよ「愛の死の動機」(譜例7)である。これは終曲「イゾルデの愛の死」で冒頭から繰り返し演奏される忘れられない旋律であり、第二幕ではトリスタンとイゾルデの愛の場面でひたすら盛り上がり「死んでしまったほうがいいのだろうか」と歌う場面で初めて登場し、最後の絶頂まで繰り返し登場して高揚して行く。
以上7つの示導動機を紹介したが、研究者によればこのほかにもたくさん、50個近くの示導動機があるそうである。ただしワーグナーは示導動機の記録を残しておらず、研究者によって分類や名称はかなり異なっている。名称の違いにはさほどこだわる必要はなく、示導動機がいろいろな場面でテンポやリズムや調性を変えて出てくるのと台本(字幕)に出てくる言葉とだぶらせて聴ければ十分楽しめるはずである。
ここまでがトリスタンとイゾルデを楽しむための予備知識なのだが本日は大変残念ながら1幕は前奏曲だけ、3幕は第3場からの演奏なのでもうすこし細かい筋書を予習しておいたほうがよいだろう。次の章ではそれを紹介する。
4. 物語の進行(やや詳しい粗筋)
1)第一幕
前奏曲にはこの楽劇の魅力が凝縮されている。トリスタンとイゾルデの飽くことなき憧憬と張りつめた心理状態が表現される。冒頭に流れるのは「憧れの動機」(譜例1)、くりかえされるのは「愛のまなざしの動機」(譜例2)と「愛の魔酒の動機」(譜例3)でそれと同時に低音でうごめくのは「死の動機その2」(譜例4)である。
【第一場】本日演奏されません。
船の上、イゾルデはマルケ王に嫁ぐためコーンウォールへ向かっている。その船を操るのは、あのトリスタンである。同じ船に乗りながらトリスタンはイゾルデに会おうともしない。トリスタンに惹かれ、命を救ったにもかかわらず、なぜマルケ王の后とならねばならないのか、なぜトリスタンに無視されるのか、イゾルデは激しく苛立つ。
【第二場】本日演奏されません。
窓の向こうにトリスタンと従者クルヴェナールの姿が見える。イゾルデはその姿を見つけてトリスタンへの恨み言をつぶやき、トリスタンを連れて来るようにと侍女ブランゲーネに命令する。ブランゲーネはそれをトリスタンに伝えにくるが、トリスタンはあいまいな返事で逃げようとする。一方、トリスタンの従者クルヴェナールは「アイルランドのモロルトとトリスタンが小島で決闘し、トリスタンが見事に勝ってモロルトの首をアイルランドに送りつけた」とうたう。根はいいやつなのだがずいぶん無神経だ。
【第三場】本日演奏されません。
クルヴェナールに笑いものにされたイゾルデは、激怒する。そしてブランゲーネに向けて、トリスタンとの因縁を解き明かす。前史で述べた内容である。あのときに剣を振り下ろしていればこんなことにはならなかったのに、とイゾルデは後悔する。
ブランゲーネは、夫になるマルケ王は素晴らしい方、イゾルデ様を一目見て夢中にならない男などいるはずがない。それにイゾルデの母が持たせてくれた媚薬を使えば大丈夫とうたう。イゾルデの苛立ちはそういうことではないのだが、ブランゲーネも無神経なタイプだ。そこでイゾルデは、媚薬ではなく死の薬を指し示す。うろたえるブランゲーネ。
【第四場】本日演奏されません。
クルヴェナールが到着の準備を急がせるためにイゾルデの部屋に入ってくる。イゾルデはクルヴェナールに、トリスタンに赦しを求めに来るようにと伝える。クルヴェナールが退場するとイゾルデはブランゲーネに死の薬を用意するよう命じる。動揺するブランゲーネ。そこへトリスタンが登場する。
【第五場】本日演奏されません。
二人の沈黙の後、トリスタンとイゾルデの間でかなり回りくどいやり取りが続く。イゾルデの本心はトリスタンの口から愛しているという言葉を聞きたいのだろうが、ストレートにそれを口にせず、自分の婚約者のかたきであるのがわかっていながら救ってやったことを言ってなじる。トリスタンは、ならばここで仇を討てばよいと言って剣を渡す。しかしイゾルデは和解の償いの盃を二人で飲み干そうと盃を差し出す。お互いはすでにどうしようもないほど惹かれ合っているが意地の張り合いである。盃に入っているのは死の薬であると察しているトリスタンは進んで盃をあおる。イゾルデはトリスタンから飲みかけの盃を奪い取って競うように飲み干す。しかし実は、ブランゲーネが恐ろしさのあまり死の薬ではなく媚薬を入れてしまってだ。これによりそれまで必死だった意地の張り合いも、気にしていた世間の目も身分の違いも吹っ飛んで本能の赴くままの男女になって熱烈な抱擁を交わす。その直後に船が港に到着し、マルケ王の家臣たちの歓声にさえぎられる。ブランゲーネはイゾルデを正装に変え、クルヴェナールはトリスタンを讃えるために部屋に飛び込んでくる。別働隊のラッパ隊がファンファーレを吹き、唐突に第一幕が終わる。
2)第二幕 本日すべて演奏されます。
【第一場】
第二幕の前奏曲はいきなり「昼の動機」(譜例5)の強奏で始まる。イゾルデの居室の前庭、イゾルデがトリスタンのお忍びの来訪を待ちわびるそわそわした音楽と、マルケ王一行の夜の狩における角笛のこだまが聴こえてくる。扉には目立つように松明が掲げられている。舞台上にはイゾルデとブランゲーネ。イゾルデは「恋は盲目」状態に陥っている。松明を消すのがトリスタンへの合図となっており、イゾルデは早く松明を消すようにブランゲーネに迫る。しかしブランゲーネは、今日の狩は仕組まれたものであり、二人の逢引きを取り押さえるための陰謀だと警告する。消せだの消さないだのの一悶着の後、最終的にイゾルデが松明を手にして、その火を消す。この辺りからトリスタンが登場して二人の抱擁に至る第二場冒頭までの音楽の盛り上がり方はものすごい。
【第二場】
ここからがいよいよ愛の場面。トリスタンが庭に飛び込んできて二人の固い抱擁と燃え盛る情熱が激しい音楽で表現される。待ち焦がれていたことが実現したが未だに信じられない様子が良く出ている対話が続き、さらに逢引きを邪魔していた昼の光に対する憎しみを歌う。これがかなり長いし、言っていることもとても理屈っぽい。さすがドイツ人ワーグナー、散々焦らしてくれる。
ようやく音楽が静かになって、えもいわれぬ甘く気だるい雰囲気がかもし出されてくるといよいよ史上最長で最甘の愛の二重唱が始まる。昼に決別し夜への賛歌となり、音楽による性愛描写が続く。ここまでエロティックに愛の場面を表現した音楽は他にないだろう。しばらくすると見張り台のブランゲーネが警告の声を発する。ここがまた大変に美しい。この最中、二人は一声もうたわないのだがいったい何をしているのだろう?想像にお任せする。この陶酔的な音楽の後は一時的に緊張が緩んで気だるい雰囲気となる。ここで「至福(まどろみ)の動機」(譜例6)が何回か聴こえてくる。トリスタンは「このまま死なせてくれ」などと言う。その後しばらく“賢者タイム”なのか哲学的なやり取りが続く。トリスタンはやはり「死」を考えている。イゾルデは、あなたが死んだら愛も終わってしまうのでは?と問い掛ける。それに対しては「それならば、ともに死のうではないか。…中略…、ただ愛に生きるために!」ここではじめて「愛の死の動機」(譜例7)が現れる。再び性愛の音楽が盛り上がる。死んでもいいかと思わせるぐらいの盛り上がりである。イゾルデはこの死の宣誓に「身も心もあずけて」同調する。そこでまたブランゲーネのあの美しい警告の歌が響く(さすがワーグナーうまいです)。夜は白々と明けてきている。今度はイゾルデが「私を死なせて」と呟く。これ以上ないくらいの絶頂を迎えるかという瞬間に破局を迎える。「愛の夜」は突然終焉のときを迎える。
【第三場】
「逃げなさい、トリスタン!」慌てて飛び込んできたクルヴェナール。だが既に遅し、マルケ王とメロートたちがその場に踏み込んでくる。侍女が心配したとおり夜の狩は罠だったのだ。マルケ王は信頼していたトリスタンが自分を裏切ったことを延々と嘆く。しかしトリスタンは一切弁解をしない。「昼」の世界にいる者には「夜」の世界のことなど理解できるわけがないということであろうか。トリスタンはイゾルデの方を向くと「これからトリスタンが行く先へついてくるか? そこは陽の光の射さぬ国…」と歌う。トリスタンは第一幕でイゾルデの盃を受けたときから死を覚悟していたと考えられるがここでも暗示的に死への願望が現れていると言えるだろう。イゾルデはこの申し出を受ける。するとメロートが剣を抜いて挑発してくる。トリスタンも剣を抜いて応戦するかと思ったその瞬間、トリスタンはわざと自分の剣を落とし、メロートの刃に飛び込んでいく。一同がトリスタンの行為に呆然としているうちに第二幕が終わる。
第二幕終結後第三幕開始までのできごととして、トリスタンはクルヴェナールによって故郷のカレオールに連れ帰られる。トリスタンは深手を負っており、ほとんど回復の見込みがないような状況である。イゾルデはその後を追うことができず、事情は明らかではないがコーンウォールにとどまる。
3)第三幕
【第一場】本日は演奏されません。
場面はトリスタンの故郷カレオール。トリスタンは、瀕死の重傷を負って昏睡状態に陥っている。ようやく目覚めたトリスタンにクルヴェナールが、故郷カレオールに来た経緯を話す。トリスタンはイゾルデに会いたいという強い欲求を狂ったように延々とうたう。クルヴェナールは、イゾルデに来てもらえるようコーンウォールへ使者を送っており、今到着を待っているところだと話す。トリスタンはいまだ来ないイゾルデの船を待ち焦がれ、これまでの出来事を回想し、狂乱し失神する。
しばらくして意識を取り戻したトリスタンは、再び、船に乗ったイゾルデの幻影を見る。そこへ船がこちらに向かっているという合図が鳴り響く。その知らせに、トリスタンは飛び上がらんばかりの勢いで喜ぶ。
【第二場】本日は演奏されません。
トリスタンは、当然じっとしていられない。寝台から立ち上がり、包帯をむしりとる。おびただしく血がしたたりおちる。自分で傷口を広げるなど狂っているとしか言いようのない行動だ。そしてついにトリスタンの耳にイゾルデの声が届く。イゾルデの姿を認め、身体をあずけて崩れ落ちるトリスタン。再会した二人は媚薬を飲んだ直後のように見つめあう。しかしトリスタンは「イゾルデ!」と一声発して息絶える。イゾルデは亡骸をかき抱いて嘆き悲しむ。
【第三場】本日はここから演奏されます。
羊飼いがもう一隻船が着いたことをクルヴェナールに告げる。マルケ王とメロート、ブランゲーネがやってくる。クルヴェナールは剣を片手に戦い始めるが多勢に無勢だ。主人のかたきであるメロートだけは何とか倒して復讐を果たすが、調子に乗ってマルケ王に向かって戦いを挑もうとするのでマルケ王の家臣に討ちとられてしまう。マルケ王がこの戦いのありさまを見て嘆き、ブランゲーネは必死でイゾルデに呼びかける。媚薬の秘密をマルケ王に打ち明けたところマルケ王はすべてを許してイゾルデをトリスタンと結婚させようと急いで船を出したのだ。しかし、そんな周囲のもろもろの出来事からはイゾルデはもはや超越している。いよいよクライマックスの「イゾルデの愛の死」となる。
「やさしく、おだやかな彼の微笑み、その目を柔和に開く、そのさまをごらんになれますか、みなさん? しだいに輝きをまして彼がきらめくさま、星の光にとりまかれて昇って行くさまを? ごらんになれますか?」文章だけでは気がふれてしまったようにしか思えないが、ここまで通して音楽を聞いてくると本当に「やさしく、おだやかな彼の微笑み」が見え、イゾルデが確実に昇天していく様子が聴こえてくる。ここがワーグナーの音楽魔術の最たるものだと思う。「この高まる大波の中、鳴りわたる響きの中、世界の呼吸の吹きわたる宇宙の中に── 溺れ── 沈み─われを忘れる─このうえない悦び!」と「愛の死」を歌い、イゾルデはトリスタンのなきがらの上に斃れる。
初演:1865年6月10日 ハンス・フォン・ビューロー指揮 ミュンヘン宮廷劇場
楽器編成:フルート3(3番奏者ピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ1、クラリネット2、バスクラリネット1、ファゴット3、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ1、ティンパニ、シンバル、トライアングル、ハープ、弦五部
その他別働隊として
第一幕:舞台上にトランペット3、トロンボーン3(本日は演奏されません)
第二幕:舞台裏にホルン6
第三幕:舞台上にコールアングレ、ホルツトランペット(本日は演奏されません)
参考文献:
1. 城後麻美著『トリスタンとイゾルデ論』http://pippo.sakura.ne.jp/page/tristanundisolde0.htm
2. 高辻知義著『ワーグナー』岩波文庫 1986年3. ベディエ編 佐藤輝夫訳『トリスタン・イズ-物語』岩波文庫 1953年
4. スタンダードオペラ鑑賞ブック[4]ドイツオペラ(下) 音楽之友社 1999年
5. 品田博之 新交響楽団第195回演奏会プログラム解説 2006年
6. John Weinstock and Matthew Heisterman制作“Tristan and Isolde”https://www.laits.utexas.edu/tristan/index.html
新響のチラシを作っています
◆ヤマカズさんの揮毫による『大地の歌』
2019年に還暦を迎える私が新響に入団したのは1983年の8月。23歳のことである。この1月に244回を数える演奏会も当時まだ101回。山田一雄先生のマーラーの第2番『復活』と柴田南雄「北園克衛による3つの詩」というプログラムであった。まさに全身これ音楽といったヤマカズさんの鬼気迫る棒との出会いは鮮烈で、これまで新響で演奏会を100と数十回を馬齢とともに重ねてはいるが、初めてのあの演奏会は今も記憶が鮮明だ。
チラシのデザインを担当した最初は入団の翌年であるが、本欄への寄稿にあたって久しぶりに古いチラシのファイルを探してみたら、私の第1作は1984年7月、そのヤマカズさんでシューベルトの未完成とマーラー『大地の歌』を演奏した第108回演奏会のようだ。今ひとつ確信が持てないのは、それ以前の演奏会のチラシが見当たらないからで、その理由が自分の担当でなかったためか、それとも単に保存しなかったか今となっては不明である。
白地に『大地の歌』と墨痕鮮やかに入った縦書きのタイトルは、実はヤマカズさんご自身の筆によるものだ。どこにもクレジットが入っていないのは、ご本人から「くれぐれも書・山田一雄などとは記さないこと」と釘を刺されていたからである。わざわざその部分に傍線か傍点が振られた手紙を担当者に見せてもらった。その躍動感溢れる書は、私など素人からすればひと目見て立派な書家の作品であったが、ヤマカズさん一流の韜晦であろう。バラしてしまったが、とっくに時効だからお許しいただけるだろう。
◆出版社で学んだアナログの版下製作
当時、私は小さな音楽出版社に在籍していた。その頃、御茶ノ水駅近くの神田駿河台にあった『パイパーズ』という管楽器専門出版社で、若造社員である私は書籍の荷造りから伝票起こし、問屋さんへの納品から返品整理に加え、小さな記事の取材から執筆など、よろず承っていた。その中で版下(はんした)製作の仕事も引き受けている。
版下という言葉は印刷業界でも今の若い人は知らないかもしれないが、印刷物の版を作る、いわゆる原版だ。文字を打ち込んだ写植の印画紙を台紙に貼り込んだもので、写真やイラストなどの扱い、色の指定(モノクロの場合はグレーの度合)などの加工指示を書き込んだトレーシングペーパーをこれに重ねて印刷会社に持ち込む。
そう、写植という言葉も今では説明が必要だろう。これは「写真植字」の略で、原稿の文字列に赤ペンで書体と大きさ(級数)を指定したものを業者がその通りに打ち込み、印画紙に焼き付ける。原稿も当時は手書きである。これを当時は駿河台下の猿楽町の写植屋さんに持ち込み、印画紙に焼き付けてもらった。大小さまざまな出版社が集中する神田には家族経営などの小さな写植屋さんも多く、他にも書籍の箱を足踏みの機械でパタパタ作っていた箱屋さんのこともふと思い出した。あそこの親爺さんはまだ健在だろうか。
写植屋さんでもらってきた「焼きたて」の印画紙を台紙に貼り付けるのだが、その際ペーパーセメントという専用の糊を使う。有機溶剤なので有毒で刺激臭があり、緑色の缶には換気に留意せよという注意書きに「長く吸うと、たとえば気が狂うなど……」と、それこそ刺激的な注意書きがあったのを覚えている。
版下に線を引くのはロットリングという製図用のペンで、太さによって0.1ミリ、0.25ミリなど何種類か常備していた。このペンは少し放置しておくと乾燥で目詰まりを起こし、インクが出てくるまでお湯に浸けては振るなど苦労したこともある。またこのロットリングを定規にぴったり付けすぎると定規の下にインクが流れて汚れるし、線の引き始めは太くなりやすいので、運ぶ手のスピードの制御などコツが必要だった。
この版下仕事は同社でバイトしていた大学3年生頃から始めているので、実は大学の定期演奏会のチラシが私にとっては「作品1」である。1984年の段階で、会社でどこまで担当していたかは覚えていないが、月刊誌『パイパーズ』の本文の他に、広告代理店が入っていない楽器店の広告版下なども多く手がけたもので、場合によっては店に成り代わってキャッチコピーを考えたり、店側が持ち込んだ原稿を見栄え良くするため書き直すこともあった。
ちなみに入社して最初に行くことになった取材は埼玉県の陸上自衛隊朝霞駐屯地。ここで起床や食事、消灯の際に鳴らすラッパ隊の皆さんから話を聞く仕事だった。カメラマンとともに緊張して訪問したが、隊長さんは非常に協力的でほっとしたものである。昔むかし自衛隊がまだ出来たての頃、食事ラッパに乗せて歌われた「〽ヤンキーのおかずはキャベツにコロッケ、自衛隊のおかずはキャベツだけー」という替え歌を教えてもらったのが頭に今も焼き付いている。日米の食事の質にかなりの落差があった頃の話だ。
◆芥川也寸志=新響の頃のチラシ
新響でチラシを任された経緯については忘れてしまったが、版下製作の経験者だったので必然的だったのかもしれない。それ以前は新響でもプロのデザイナーに依頼していたようで、入団した頃の『復活』のチラシもそうだった。最初の頃は私の担当も毎回ではなく、たとえばショスタコーヴィチの交響曲第4番を日本初演(「アマチュア初演」ではない)した1986年7月の第111回のチラシはデザイナーによるものであった。指揮は芥川也寸志さんで、当時3日間の合宿にもたしか全日程参加され、この曲にかける熱意はひときわ大きかったのを覚えている。
私が毎回担当するようになったのは第115回(1987年4月)からで、この回は『中国作品展』と銘打ち、李煥之、呉祖強、朱践耳という中国の作曲家の作品とチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲というプログラムであった。ソリストには上海音楽院の学生、左軍さんをお招きしている。
私の担当するチラシとしては初めて2色(墨+茶色)を使い、日本画家であった私の祖父・木村華邦が描いた『中国風景』をまん中にあしらった。ラーメン丼などによくある柄で縁取るというベタなデザインなので今見ると赤面してしまうが、思えば当時のカラー印刷は高嶺の花であった。新響から予算を制限されてやむなく、というよりは小出版社に勤めていた私の過剰なコスト意識だったのかもしれないが。
第119回(1988年4月)はオール・ファリャ・プログラム。チラシではメインの『三角帽子』にちなんで、全体が黒地のまん中の真っ赤な正方形の中に、私が描いた三角帽子のイラストをあしらった。インターネットのない頃だから、図書館かどこかへ行ってその筋の本を探し、三角帽子がどんなものであるか描き写したものである。本番の演奏で芥川さんは実に楽しそうに振っておられたのが記憶に残っているが、それが新響では最後の演奏会になってしまった。翌年1月に逝去されている。その4月(第123回)は追悼演奏として芥川さんの『交響管絃楽のための音楽』の第2楽章だけを指揮者なしで演奏したが、それからちょうど30年後にあたる2019年4月(第245回)には、<没後30年>として芥川さんの『オーケストラのためのラプソディ』を演奏する。もうそんなに経ったかと思うと感慨深い。
没後1周年にあたる第126回はヤマカズさんの指揮で『追悼・芥川也寸志』と題する演奏会だった。芥川作品のみの演奏会で、チラシには音楽家を撮る大家として知られた木之下晃さんの写真を大きくあしらい、芥川さんが生前折に触れて強調された「音楽はみんなのもの」という言葉を最上部に掲げた。昔のチラシを改めて1枚1枚見てしまうと、それぞれの演奏会にまつわる思い出が尽きないのだが、本稿の趣旨から外れてしまうのでこのあたりで切り上げよう。
◆色を決める難しさ
私は1991年に9年ほど勤めていたパイパーズを辞め、フリーライター兼編集者として独立した。最初はライターの仕事など来るはずもなく、多かったのが書籍編集の請け負いである。たとえば『地球の歩き方』(ダイヤモンドビッグ社)のフランス編を全部レイアウトしたり、当時の運輸省労働組合の機関誌の割り付けなども行った。その傍ら、いろいろな出版社に「地図に関するこんな文章を書いているので、よろしければ使ってください」といった内容のダイレクトメールを送りつけ、幸運にもいくつかの会社から仕事をもらった。
子供の頃から熱を上げていた地図の楽しさを世に紹介したいという思いから、できればそちらの方面の仕事をしたかったのである。最初に拾ってもらったのは小学館の『サライ』という雑誌(現在は「気になるバス停」を連載中)、その後は幸いにして地元のけやき出版から『地図の遊び方』という単行本を上梓する機会があり、それ以降は幸運にも仕事は途切れていない。
版下製作上の苦労といえば、まず色である。新響のチラシでは2色(墨+特色など)から3色の時代が長いが、当時はアナログなので、色の見本帳を参照しながら指定を行った。ときに色校正の刷り上がりがイメージ通りでなく、その段階での変更はリスクを伴ったが、思い切って変更して成功することもあった。しかし必ずしもうまくいくとも限らない。
その後はセットインク(藍・赤・黄・墨のカラー印刷用)の4色をそれぞれパーセントで指定する方式に変えたのだが、10パーセント刻みで掲載された色見本帳を購入、それを睨みながら悩む場面も多かった。難しいのはたとえばオレンジ色で、バランスが少し崩れると赤系または茶系のどちらかに転んでしまったりするので厄介である。紙との相性もあり、色校正で鮮やかに見えても本番の紙だと沈んでしまったりもするから、完全に満足できた回はそれほど多くない。
◆アナログからデジタルへ-イラストレーターの導入
これが大きく変わったのが、デジタル化である。プロの世界では「イラストレーター」というパソコンの画面上でデザインするソフトを使うのが当たり前になった頃も相変わらず印画紙を貼り付ける方式を続けていた私であるが、徐々に版下用品が店頭から姿を消し始め、入手が難しくなってきたこともあり、デジタルに弱い私もさすがにそちらへ乗り換えることに決めた。アナログの版下をいつもの印刷会社に持ち込んだ際に、「今ではこういう版下を見たことのない若い社員もいます」と言われたほど、私は前時代的だったのである。
最初にそのイラストレーター(略してイラレ)で作ったのは、第222回演奏会(山下一史指揮・シュトラウス『ツァラトゥストラはかく語りき』他)であるが、イラレの入門書などを購入して傍らに置きつつ、えらく長い時間をかけて四苦八苦して作った覚えがある。まずは初心者でもできる「長方形ツール」に色を付ける方法だけを使い、テキストデータで作った曲目やチケット関係の細々した内容をイラストレーターの画面上の版下に流し込むのだが、そもそもA4のワク(トンボなど)を作ることからして難問だった。書体も従来気に入っていたものが選択肢になく別に選び直したが、太さやバランス、詰め打ちの方法も最初は勝手が違いすぎて戸惑うばかりであった。
文字の詰め打ちというのは、同じサイズの文字であっても漢字と平仮名、アルファベットでそれぞれ構造が違うので(たとえば「み」と「く」、WとIの横幅は大きく異なる)、同じように字を配置すると見栄えが悪い。このため写植の時代では写植屋さんに「字間2歯ツメ」とか「ツメウチ」「ツメツメ」などと指定し、彼らのセンスに任せていた。それでも、大きなタイトル文字などでバランスが気に入らなければ、カッターで字と字の間に切り込みを入れ、ピンセットで印画紙の表面だけを剥がし、要らない余白を削除して詰め、ペーパーセメントで貼り直すという面倒な作業もあった。それがイラストレーターなら画面上で簡単に詰め打ちできる。最大のメリットは色のパレットから直接ピンポイントで選ぶことができ、何度もやり直しが利く点である。実験的な色使いも簡単にディスプレイで確認できるので、かつてのように4色の組み合わせを思い描いてドキドキしながら色校正を待つこともない。
◆外国語表記の難しさ
曲目や日時などには英文表記を併記しているが、これにも難問がある。以前なら各国語のアクセントや発音記号の扱いは写植屋さんでうまく対応できないこともあり、パンフレットなどから切り取って貼り付けるなどという非常手段もやった。特に出現頻度の低いチェコ語(ドヴォルザークDvořákのRの上の∨印など)やポーランド語(たとえばルトスワフスキLutosławski)などはアクセント記号等の扱いが悩ましい。しかしそれも昨今ではインターネットで検索すれば珍しいアクセントもコピペで対応できるので本当に助かる。直近では2019年4月の第245回のチラシ。バルトーク(BARTÓK Béla)ではÓというアクセント付きの文字を用いるが、小文字はいくらでも出てくるのに、大文字はなかなか見つからない(新響では英文表記の人物の姓は大文字のみとしている)。それでもハンガリーの音楽関係サイトでなんとか発見したので対応することができた。
ここ10年ほどは、掲載内容について新響団員のメーリングリストでチェックしてもらっているので安心感があるが、特に外国語表記については団内に英語、ドイツ語、フランス語の専門家がいらっしゃるので助言を仰ぐことができてありがたい。私たちは音楽という共通項で繋がってはいるが、それぞれ平日に従事している職業はさまざまなので、こういう時にその多様性が発揮されるのだと感じる。
◆失敗談、そしてこれから
最後に失敗談を。1990年7月の第128回演奏会は東京文化会館で『新世界』と『ローマの松』というプログラムだったが、なんと開演時間を忘れてしまったのである。刷り上がってきた時には青ざめた。「14時開演」というゴム印を急遽作ってコンサートサービス(今もチラシの配布ではお世話になっている)にお送りしたものである。それからもう一つは何回か忘れたが、フランクの交響曲。「ニ短調」のところを「ニ長調」とやってしまった。そんな曲があったんですねと誰かに皮肉を言われたが、こういう大きなタイトルなどは意外に「魔物」がひそんでいて要注意なのである。印刷会社に救われたこともある。団員のメーリングリストでのチェックも通り抜け、私も読んだつもりでスルーしていたのがある年の7月の演奏会。ところが英文表記だけAprilになっていたのを印刷会社の担当者が発見してくれた。
30年以上もやっていると、時には以前とそっくりな色使いやデザインになることもあり、どうしてもマンネリは否めない。そろそろ次世代のチラシを担う新響の若手が現れるのを期待しているので、もし団から「選手交代」が指示されればすぐ替わるつもりである。そうでなければもうしばらくは担当することになりそうだが、毎回いろいろな点で反省しつつ、終着点のない「良いチラシ」を目指し、自分なりに試行錯誤を繰り返していくことにしよう。
ワーグナーの楽しみ方
今回のコンサートでワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』を取り上げるのでそれに関しての記事を書くようにとの依頼がありました。前回のプログラム解説も執筆し、今回のプログラムも書く羽目になり、なぜ維持会の原稿まで書かねばならないのか「もういい加減にしてくれ」と、言いたいのをぐっとこらえ、今回の企画の首謀者なので致し方ないと引き受けたわけです。実はワーグナーについて気の利いたことを書くことは非常に難しいのです。ワーグナーを好きな人はもう徹底的に好きなので知識は膨大で理解は深い。中途半端なことを書いても馬鹿にされるのがおち。一方で、一通り聴いていて知っているけれど嫌いという方も結構います。今回のコンサートに、ワーグナーを絶対聴きたくない大嫌いな方はそもそも来られないので対象外にするとして、そのほかの、なんとなく嫌いとか食わず嫌いの方も含む、ワーグナー初心者の方むけに書いてみました。
1.ワーグナーの世界の入口
まずは何の予備知識もなく、『ワルキューレの騎行』、『タンホイザー』序曲、『ニュールンベルクのマイスタージンガー』前奏曲を聴いてみましょう。前々回の維持会ニュースで好評(?)だったYouTubeのリンクをQRコード(HPではURL)で貼りますのでスマホで聴いてみてください。まずは『ワルキューレの騎行』、次に『タンホイザー』序曲、そして最後は『ニュールンベルクのマイスタージンガー』前奏曲です。いずれの曲も冒頭1分くらいをまず聴いてみましょう。いきなり引き込まれるものがあればワーグナー好きの素質ありです。
『ワルキューレの騎行』は、『地獄の黙示録』というベトナム戦争を題材にした映画の、戦闘ヘリによる爆撃シーンに使用されて一躍有名になった大変に勇壮な曲ですが、そもそもは戦死した英雄たちを、神々の住むワルハラ城に連れて行く役目の“戦乙女ワルキューレ”たち8人が、空を飛ぶ馬にまたがり集合する場面の音楽です。ですから戦争という点で共通する要素はあるわけです。中盤から歌も入り、テンションMAXでぶっ飛んでいますね。だいたい“戦乙女”という発想が常識はずれです。もともとは伝説として語り継がれてきた女性の英雄たちを指すわけですが“艦これ”をはじめとしてあり得ないものが美少女に結びついてゲームやアニメになったりしている今の時代のほうが受け入れやすいかもしれません。この手のゲームの発想は、さかのぼればワーグナーに行きつくともいえるかもしれません。ためしにワーグナーのオペラの登場人物、ブリュンヒルデ、ジークフリート、アルベリッヒなどをネットで検索してみてください。ゲームや同じようなにおいのするアニメ関係が多量に出てきます。きっとそれらの原作者・制作者はワーグナー好きなのです。
さて、次の『タンホイザー』序曲は打って変わって、宗教的な祈りの音楽で始まります。このオペラで根幹をなす『巡礼の合唱』の旋律で、オペラの中では「恩寵による救済」を表す主題です。そして1分11秒くらいから始まるチェロ、その後ヴァイオリンで奏される半音階進行のおもわず懺悔したくなるような旋律が「悔悟」の主題、その後トロンボーンで再び朗々と巡礼の合唱の主題が奏されます。なにか偉大で神聖なものを仰ぎ見るような気持になりませんでしょうか。ワーグナーの生涯を聞く限り、お世辞にも彼が宗教的で敬虔な人間だったとは思えないのですが、宗教的なものを音楽で表現する能力は並外れたものがあります。
次は『ニュールンベルクのマイスタージンガー』に行きましょう。ひたすら健康的で祝典的な音楽で、これはこれで根拠はないけれど気持ちが大きくなってきませんでしょうか。ワーグナーの音楽はよく麻薬のようであると言われることがあります。聴く者の精神に直接作用して、自分(聴衆)があたかも偉大で神聖な存在になったかのような錯覚を起こさせるという意味です。ワーグナーの麻薬は、依存性はあるものの健康は損ないませんのでご安心ください。ただし政治家を志す方は気を付けてください。とんでもない先例がありますので。
これらの三曲の冒頭を聴いて心動かされるものがあったら、できるだけよい音で聴ける環境で通して最後まで聴いてみましょう。はい、これであなたはもうワグネリアンです。
ワルキューレの騎行
https://www.youtube.com/watch?v=pMTR3ypErYw&start_radio=1&list=RDpMTR3ypErYw
タンホイザー序曲
https://www.youtube.com/watch?v=AP6tTV-7mbg&index=2&list=RDpMTR3ypErYw
ニュールンベルクのマイスタージンガー前奏曲
https://www.youtube.com/watch?v=5JUqTtzovbw
2.トリスタンとイゾルデのこと
さて、今回のコンサートで演奏する『トリスタンとイゾルデ』を楽しむための予習に移りましょう。数多あるオペラで男女の恋愛沙汰が出てこないものはほとんどありません。しかし、延々4時間ものあいだ男女の主人公二名の性愛だけを純化して取り上げたオペラというのはこれだけかもしれません。中世ヨーロッパでまとめられた恋愛物語である『トリスタンとイズー物語』を題材とし、それをワーグナーは大幅に改編、登場人物3人(トリスタンとイゾルデそしてマルケ王)の心理描写に絞って前代未聞のオペラに仕立て上げました。簡単に粗筋を述べましょう。オペラの前史、つまり背景はそれなりに複雑です。
【背景】
時代は中世。マルケ王が治めるコーンウォールはアイルランドの属国的な立場であったが、最近は反発し敵対していた。コーンウォールの騎士トリスタンとアイルランドの騎士モロルトが決闘してトリスタンがモロルトを討ち取り、その結果コーンウォールが勝利する。しかしモロルトの剣に塗られていた毒が傷口から入り、トリスタンは重篤な状態となる。そこで彼は、特別な医術でその解毒ができる敵国アイルランドの王女イゾルデのもとに、名を偽って治療のために訪れる。イゾルデは婚約者モロルトを討った騎士であることを見破り、仇を取るため瀕死のトリスタンに剣を振り下ろそうとするが、一目みて抑えがたいほど なにか“感じる”ものがあり、治療して本国に帰してしまう。
一方、若くして妻を亡くして独り身だったコーンウォールのマルケ王は本心では望んではいないものの家臣たちの強い勧めにより、后として王女イゾルデを迎えることになる。コーンウォールとアイルランドの政略結婚の意味合いが強い。不本意にも、元敵国の王に嫁ぐためトリスタンの操る船に乗せられたイゾルデはコーンウォールに向かっている。
このような状況の中でオペラが始まります。
オペラを楽しむためには登場人物に感情移入することが必須ですので、ここでイゾルデとトリスタンの心境を想像してみましょう。現代ではちょっとどうかと思いますが、中世だからこそのものだと考えて想像力を巡らせてください。
【イゾルデ】
属国だったコーンウォールに敗れ、婚約者を殺され、しかもその国の王と政略結婚させられようとしている。プライドはズタズタ。「なぜ、あの時トリスタンを殺さなかったのかしら。でも、トリスタンのことを思うとうずく(抱かれたい?!えっ?)。なぜ元敵国の王に嫁がねばならないの?おまけに迎えに来たのはあのトリスタン。あいつを殺して自分も死んでやる!」
【トリスタン】
悲劇的な出生(父親は戦死、出生後すぐに母親も死んだ)から、自己を犠牲にする性格。身分を重んじ主君に忠誠を尽くす。「治療してもらう時、身分を悟られたと感じたのだがなぜイゾルデは救ってくれたのだろうか?そのときの眼差しの優しさと高貴さが忘れられない。ダメだダメだ、身分が違いすぎる。そんなことを考えるだけでも許されないことだ。主君マルケ王の后に迎えるのだ。それでいいのだ。」
もうひとつ、ワーグナーのオペラを楽しむのに大事なのは“ライトモティーフ”をある程度知っておくことです。“ライトモティーフ”とはオペラに出てくる感情や概念やいろいろなモノ(たとえば剣、黄金、媚薬など)に特定のメロディーを当てはめたもので、そのメロディーをうまく組み合わせて各種の場面の状況を音楽で表現してゆく手法です。代表的なものをいくつかご紹介しておきましょう。いつもの通り、下記QRコード(HPではURL=準備中)をスマホで読めばYouTubeにあがっているライトモティーフを聴くことができます。トリスタンとイゾルデには50近くのライトモティーフがあるといわれていますが本日演奏される 第一幕前奏曲 第二幕、第三幕第三場を楽しむためには最低7個くらいを覚えていればとりあえずよいかと思います。なお、ライトモティーフの記録をワーグナーが残しているわけではなく後世の研究者が分析した結果なので、研究者によって同じ旋律に違った名称をつけています。
【主な示導動機(ライトモティーフ)の説明】
第一は「憧れの動機」(譜例1)です。前奏曲の冒頭において、この動機の前半部分をチェロ、後半部分を木管(オーボエ、クラリネット、オーボエ)によって3回演奏されます。

譜例1 憧れの動機
https://youtu.be/FcQeTCsQ5w4?list=PL78TsyiiZjhGGJhndz_P-8EbshbYcFDxB
チェロの奏する前半をトリスタンまたは“憧憬”を表し、木管が奏する後半をイゾルデ または “欲望”を表すとも言われています。このライトモティーフは半音階で上昇して下降、きれいな協和音に解決するかと思いきや次の音がかぶさってさらに上昇してそのサイクルを繰り返していくというもので、トリスタンとイゾルデがお互いを求めあう憧憬(欲望)がいつまでたっても満たされずに高まっていく様子に通じると思われます。
第二は、「愛のまなざしの動機」(譜例2)、さらに続いて「愛の魔酒の動機」(譜例3)。これと同時に、とても意味ありげで不穏な「死の動機その2」(譜例4)も低音楽器により奏されています。この二つは同時に奏されることが多いです。なお「死の動機その1」もあるのですが、特に目立ってわかりやすく出てくるのは本日演奏しない第一幕なのでここでは省略します。もちろん二幕にも出ては来るのですが。

譜例2 愛のまなざしの動機
https://youtu.be/NE2gTGG6k_Y?list=PL78TsyiiZjhGGJhndz_P-8EbshbYcFDxB

譜例3 愛の魔酒の動機
https://youtu.be/bzQkCRTW_b4?list=PL78TsyiiZjhGGJhndz_P-8EbshbYcFDxB
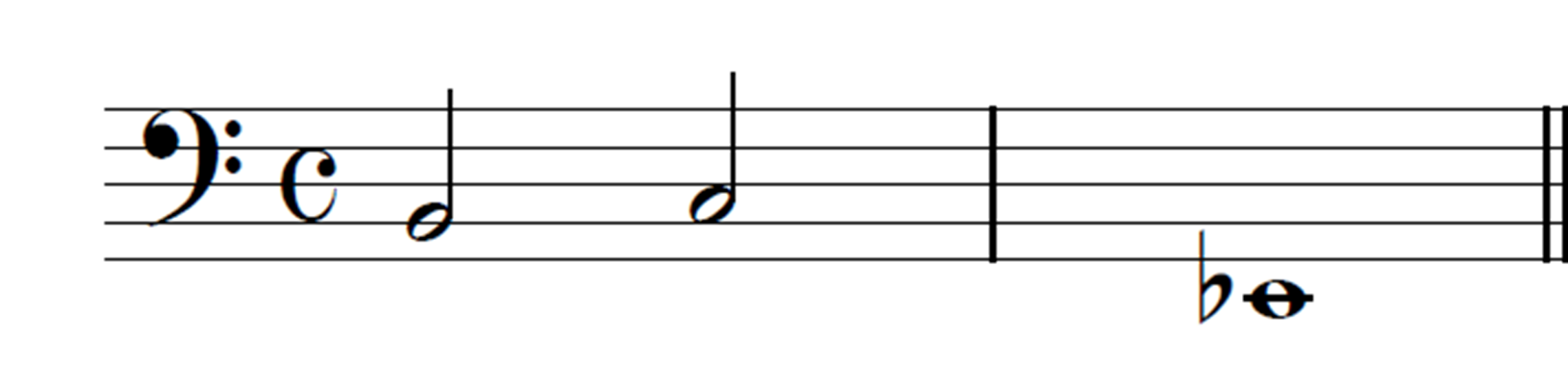
譜例4 死の動機その2
残りの厳選ライトモティーフ3点、まずは「光(昼)の動機」(譜例5)。これは少し説明が必要です。

譜例5 昼(光)の動機
https://youtu.be/UeE7kjSsSkI?list=PL78TsyiiZjhGGJhndz_P-8EbshbYcFDxB
トリスタンとイゾルデは媚薬を飲んでからはもうあっちの世界に行ってしまっており、昼、つまり社会や人間関係に縛られる世界を忌み嫌っています。そのためこのライトモティーフは「傲慢な(insolent)昼の動機」などとも呼ばれています。第2幕はこのライトモティーフで開始され、数えきれないほど何度もいろいろなところで繰り返されます。
6個目は「至福の動機」(譜例6)または「まどろみの動機」とも呼ばれる、まったりとした幸福感に包まれたもので、愛の場面で絶頂を迎えたあと、その熱を冷ますような感じで出てくることが多いです。確かに“絶頂の後の至福”そんな感じです。
![]()
譜例6 至福(まどろみ)の動機
https://youtu.be/T455gOFjYJE?list=PL78TsyiiZjhGGJhndz_P-8EbshbYcFDxB
最後は「愛の死の動機」(譜例7)です。これは終曲「イゾルデの愛の死」で冒頭から繰り返し演奏される忘れられない旋律であり、第二幕ではトリスタンとイゾルデの愛の場面でひたすら盛り上がり「死んでしまったほうがいいのだろうか」と歌う場面で初めて登場し、最後の絶頂まで繰り返し登場して高揚して行きます。

譜例7 愛の死の動機
https://youtu.be/QCSrw2tP77I?list=PL78TsyiiZjhGGJhndz_P-8EbshbYcFDxB
以上7個のメロディーを頭に叩き込んでおいていただければ十分に楽しめるはずです。
現在、世界最高のワーグナー指揮者(の一人)である飯守泰次郎と日本が誇る世界水準のソリストたちがお送りするワーグナーの最高傑作『トリスタンとイゾルデ』を存分にお楽しみ下さい。
第244回演奏会のご案内
2018年まで新国立劇場芸術監督を務め、世界トップレベルのワーグナー公演の数々を自らの指揮で成し遂げた飯守泰次郎によるワーグナーです。新交響楽団は1993年から共演を重ねており、これまでも「ワルキューレ」第一幕、「ニーベルングの指輪」抜粋、2006年に「トリスタンとイゾルデ」抜粋を取り上げました。それらの公演は新響演奏史に残る名演として語り継がれています。このたびソリストをお呼びして久しぶりに本格的にワーグナーを取り上げるにあたり、新国立劇場では取り上げなかった「トリスタンとイゾルデ」を飯守氏が選ばれたことには大きな意味があるに違いありません。そしてイゾルデには、二期会の公演で同役を歌い絶賛を浴び、新国立劇場のワーグナー公演でも存在感を見せつけた池田香織をはじめ、現在日本で望みうる最高のソリストをお迎えいたします。
「トリスタンとイゾルデ」
ワーグナーと聞いてどのような曲を思い浮かべられるでしょうか。映画「地獄の黙示録」で使用された勇ましい「ワルキューレの騎行」、お馴染みの「結婚行進曲」や吹奏楽経験者なら知っている「エルザの聖堂への入場」で知られる「ローエングリン」、そして式典などでよく演奏される堂々とした「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲など、耳にする機会が多いと思います。今回取り上げる「トリスタンとイゾルデ」はその一部が「前奏曲と愛の死」としてオーケストラだけでも取り上げられます。中世の説話「トリスタン物語」をもとにしながらワーグナーが大胆に脚色して自ら台本を作成し、それに音楽をつけました。オペラで演じられる部分のストーリーは非常に単純で、男女の主人公トリスタンとイゾルデの愛を極限まで凝縮したものとなっています。台本はワーグナーにありがちな“哲学的な”非常に理屈っぽいものなのですが、そこにつけられた音楽はたいへんに官能的な魅力にあふれており、聴く者を陶酔の境地に誘います。ワーグナーは無調音楽を志向したわけではないのに、官能性や劇的効果を極限まで追求した結果、調性音楽の枠を踏み越えたかのような革新的なものとなっています。今回は主人公二人の愛の場面をたっぷり味わっていただけるよう第二幕はカットなし、演奏会形式ではありますがすべての役に個別のソリストを配してお届けします。
飯守泰次郎のワーグナー
飯守氏はいまさら言うまでもなく、ワーグナー指揮の第一人者として国内外に名を馳せています。その演奏は、骨太の分厚い響きで重要な示導動機をたっぷりと鳴らす、あまり聴くことができなくなった伝統的なワーグナー演奏を思わせます。音の出だしやリズムを指揮棒で強制的に合わせることを嫌い、音楽の必然のタイミングを奏者が感じとって自ずと合わせてくることを求め、また和声の美しさを非常に厳しく追及されます。アマチュアの新交響楽団に対しても容赦ありません。そのような厳しいリハーサルを経ることで、ワーグナーの最高傑作ともいわれる「トリスタンとイゾルデ」の陶酔の境地を出現させたいと考えています。どうかご期待ください。(H.S.)
ブルックナー/交響曲第7番 <名声への道のり>
■ワーグナーとの出会いと別れ:「パルジファル」の夏
1882年7月、ヨーゼフ・アントン・ブルックナー (1824-1896)は、バイロイトに滞在していた。リヒャ ルト・ワーグナー(1813-1883)にとって6年ぶりの新作「パルジファル」の初演(1882年7月26日)が、ヘルマン・レーヴィ(1839-1900)の指揮で祝祭劇場にて行われたのである。
この時のワーグナーとの会見がブルックナーにとって最後となった。ワーグナーはブルックナーの手を取りながら、いつもの通り彼の全作品の演奏を 約束した。感激のあまりブルックナーは跪いて、ワーグナーの手に接吻しながら言った。「おお先生、あなたを崇拝します!」ワーグナーの「まあ落ち着いて、ブルックナー、おやすみ」という言葉が最後となった。
このエピソードが書かれたブルックナーの書簡によれば、「パルジファル」を観ながら、あんまりうるさく手を叩いたので、後ろに座っていた先生(ワーグナー)が脅かすような仕草をされた、どうかこのことは誰にも話さぬよう、あの世へ持っていく何よりも大切な思い出なのです、と続いている。
ブルックナーは「パルジファル」第1幕終了後、祝祭劇場の前でスリの被害にあい、所持金全部を盗られている。
ブルックナーにとって、ワーグナーは「大家の中の大家」、憧れの巨匠であった。1865年5月18日ミュンヘンでハンス・フォン・ビューロー(1830-1894)指揮「トリスタンとイゾルデ」初演の際に初めて会見、ワーグナーへの敬愛は神格化ともいえるほど深まっていく。ワーグナーの総合芸術作品に関しては終生まったく無関心であったが、「トリスタンとイゾルデ」で得た和声と作曲技法は、大きな収穫となった。 1873年9月初め、ブルックナーは祝祭劇場建設中のバイロイトを訪問、ワーグナーはこの突然の訪問者から交響曲第3番の献呈申し出を受諾する(翌 1874年5月9日付で献呈)。自分以外の作曲家にあまり興味を示さないワーグナーだが、ブルックナーは例外であった。1875年11月に「タンホイザー」上演のためワーグナーがウィーンを訪れた際も、交響曲の演奏を約束し、他の指揮者に演奏を勧めるなどかと持ち上げている。
バイロイトはブルックナーにとって聖地となった。1876年8月には完成したばかりの祝祭劇場で「ニーベルンゲンの指輪」全曲初演を聴き、ワーグナー没後もバイロイト詣でを続けている。 1883年1月22日に交響曲第7番第2楽章アダージョのスケッチを終えたが、既にワーグナーの命はもう長くないのではないかと思いつつ、嬰ハ短調のアダージョが心に浮かび作曲の筆を進めていたという。3週間後の2月13日、ワーグナーは静養先のヴェネツィアにて69歳で死去、翌日ウィーン音楽院でブルックナーは訃報に接し、手放しで泣いた。その頃、アダージョのオーケストレーションをほぼ終え、ハ長調のクライマックス(練習記号「W」)まで筆を進めていたので、ワーグナーテューバとテューバによる35小節の コラール(練習記号「X」)を、故人となった熱愛する不滅の巨匠の思い出のために、として書き加えた。
この葬送の音楽は、1896年10月15日カール教会でのブルックナーの葬儀の際、フェルディナント・レーヴェの編曲によりウィーン・フィル指揮者ハンス・リヒター(1843-1916)の指揮で宮廷歌劇場の金管奏者により奏せられている。
最初のバイロイト訪問後、ブルックナーはウィーン・アカデミー・ワーグナー協会に入会、ワーグナー没後の翌年1884年1月23日に、同協会の名誉会員に指名されている。こうして当時の所謂「ワーグナー派」と「ブラームス派」の党派抗争で渦中の人となり、ブルックナーは多くの支持者を得ると同時に多くの敵をも持つことになった。
ワーグナー批判の急先鋒はウィーン大学哲学部音楽史・音楽美学講座教授で評論家のエドゥアルト・ハンスリック(1825-1904)である。彼は美学の領域で急進的な立場をとり、著書『音楽美論』は形式美学と絶対音楽論のバイブルとなった。ハンスリック派の代表はヨハネス・ブラームス(1833-1897) だが、もともとはワーグナーとハンスリックの芸術論争に端を発している。
ワーグナー派とブラームス派の感情的な論戦は、雑誌や新聞の批評合戦であり、実生活上では同じ町に住む同業者、ブラームスとブルックナーはウィーン楽友協会の仲間、ハンスリックとブルックナーは ウィーン大学の同僚でもある。
■交響曲の世界
ブルックナーは、1855年7月から6年間にわたり、ウィーン音楽院教授で音楽理論の大家ジーモン・ゼヒター(1788-1867)から厳格な指導を受け、伝統的な音楽理論(和声学、対位法、カノンとフーガ)を完全にマスターした。ゼヒターとの通信教育のやりとり、各課程の修了証明書、ゼヒター著『作曲法 の基礎』にある多数の書き込みが基礎的な勉学を証 明している。その間、1856年4月25日リンツ大聖堂オルガニストに就任、宗教音楽界の最重要ポストの一員としてリンツの名士となる。
1861年3月26日をもってゼヒターからの勉学を終了後、今度はリンツ州立劇場首席指揮者オットー・キツラー(1843-1915)に師事する。ドレスデン出身のキツラーは、ブルックナーより10歳若く、チェリストとして各地で豊富な経験を積み、実践的かつ進歩的な音楽家であった。すでに第1級の和声理論家となったブルックナーは、キツラーから古典派、ロマン派、後期ロマン派の和声法と管弦楽法を教わり、ワーグナーの作品から斬新で大胆な和声法と管弦楽法を知ることになる。
また教科書として、19世紀ドイツ楽式論を代表するA.B.マルクス著『作曲論』、E.F.リヒター著『音楽形式』、J.Ch.ローベ著『作曲の手引』が主に用いられ、楽式論の基本原理として、終生ブルックナーの作曲手順の規範となった。具体的には、交響曲におけるソナタ形式の枠組みを独自な原理のもとに固持し、楽節の基本単位が8小節、あるいは偶数小節であることを頑なに守り、交響曲の自筆総譜の下に、楽節構造を示す数字を記入するようになっていった。勉学の成果は、練習課題帳と管弦楽曲、具体的には、弦楽四重奏曲、行進曲、管弦楽曲、序曲、交響曲の他、多数の未出版の歌曲や舞曲が残されている。
1863年7月、2年のカリキュラムを19か月で修了し、ほどなくしてキツラーはリンツを去り、後任としてウィーン宮廷歌劇場のヴァイオリン奏者イグナーツ・ドルン(1836-1872)が赴任する。ドルンは、ベルリオーズ、ワーグナー、加えてリストの音楽の信奉者であり、ブルックナーは当時の前衛的な作品として標題音楽や交響詩の世界を知ることになる。その後、ドルンはブルノに異動するが、酒におぼれ、 最後には錯乱して1872年に精神病院にて急死する。
ブルックナーは、ゼヒターとの理論学習を盤石な土台として、キツラーから自由作曲法の基礎を学び なおし独自の確個とした楽式を構築していった。
■交響曲の傑作
交響曲第7番は、「対位法の傑作」交響曲第5番、規模や内容の充実度において交響曲と比肩する弦楽五重奏曲、簡明で抒情性と明快さを持った交響曲第 6番と続く傑作のひとつであり、人気の高い作品である。ブルックナーは60歳にして交響曲の作曲家としての名声を確立し、生前第2楽章のみの演奏を含め31回演奏されている。
それまでのブルックナーは、どちらかというと、宮廷礼拝堂で上演のため宮内省から委託された「ミサ曲ヘ短調」の1872年6月16日初演の成功により、教会音楽の作曲家として認められるようにはなっていたがまだ無名で、作曲家としては理解されず冷遇されていた存在であった。
長大な音楽、「杓子定規」的なソナタ形式、提示部の3つの主題、ゼクエンツ(反復進行)を活用した和声進行、独特なユニゾン、音楽がどこへ行くのかわからない即興性、自由でファンタスティックな旋律は、ブルックナー独自の造形感覚である。個性は残しつつ、初期の交響曲にみられるような独創的で桁外れ、頑固なまでの厳格さと強引さ、唐突な場面転換の音楽は身を潜め、作曲技法も洗練されて聴きやすく自然な音楽の流れがこの曲で確立されている。同時期の作品で、ウィーンでの幾多の苦難を耐え忍ぶことができたことを神に感謝するために作曲した教会音楽の大作「テ・デウム」と関連があり、主題として最終楽句「non confundar in aeternum(わが望みはとこしえに空しからまじ)」を用いていることでも知られている。
交響曲第6番完成の2週間後にあたる1881年9月23日に第1楽章から作曲を開始、1882年10月16日に第3 楽章が先に完成した。同年12月29日第1楽章、第2楽章は1883年4日21日、そして第4楽章は何度かの点検を経て1883年9月5日に聖フローリアン修道院にて完成した。
全曲の完成に先立って、ウィーンでまずはピアノ連弾にて私的な場ではあるが紹介されている。1883年2月に第1楽章と第3楽章、全曲が完成した後に1884年2月27日のワーグナー協会の催しで、ブルックナーの名誉会員推挙を受けてとの名目でベーゼンドルファー・ホールにてまずは全曲初演が行われた。
この作品初演を成功裏に導いたのはウィーン音楽院の教え子たちで、特に「ブルックナー3使徒」と呼ばれた音楽家である。ピアニストのヨーゼフ・シャルク(1857-1911)、その弟で指揮者のフランツ・シャルク(1863-1931)、指揮者のフェルディナント・レーヴェ(1865-1925)は、その生涯をブルックナーの交響曲普及のために捧げ、大きな役割を果たしている。
ピアノ連弾での初演者であるヨーゼフ・シャルクは、1883年末にピアノ連弾スコアを携えてライプツィヒを訪れ、演奏の可能性を探っていた。結局、ウィーン音楽院の同窓生で当時ライプツィヒ市立劇場の指揮者だったアルトゥール・ニキシュ(1855-1922)に打診、連弾を通して若き指揮者はオーケストラ初演を約束する。ニキシュは、ブルックナーと手紙や電報で何度も連絡を取り、批評家たちを招いてピアノによるレクチャーを行うなど周到に準備、オーケストラともリハーサルを5回実施、最後の2回にはブルックナーも同席し、その場でも指揮者の立場から部分的な手直しを提案している。このような万全の態勢で1884年12月30日、ゲヴァントハウス管弦楽団により行われた歴史的な初演は喝采に包まれた。
1885年3月10日のミュンヘン宮廷楽長ヘルマン・レーヴィ指揮によるミュンヘン初演は、ライプツィヒを凌ぐ大成功となり、作品の評価は決定的なものとなった。その後、カールスルーエ、ケルン、ハンブルクでも演奏、オーストリア国内では、グラーツにてブルックナーの弟子カール・ムック(1859-1940)によって初演されたが、ムックは14回もリハを重ねている。オーストリアでの初演の意向に関しては、グラーツよりウィーン・フィルの方が先だったが、 ウィーンではハンスリック派が優勢であり、ドイツでの成功に水を差すことを恐れたブルックナーは断ってしまう。結局1886年3月21日、ハンス・リヒター指揮ウィーン・フィルによりウィーンで初演され、熱狂的な反響を呼んでいる。その年のうちにニューヨー ク、シカゴ、ボストン、アムステルダムでも演奏され、 ブルックナーの名声は、ゆるぎないものとなった。
ヘルマン・レーヴィの尽力により、この曲はバイエルン王ルートヴィヒ2世(1845-1886)に献呈されている。1886年3月、革装献呈スコアは宮廷書記官によってホーエンシュヴァンガウ滞在中の国王に届けられた。しかし国王はその3か月後、廃位宣告を受けて幽閉され、シュタルンベルク湖にて変死している。
第1楽章 アレグロ・モデラート
ホ長調、2/2拍子。ソナタ形式。3つの主題と各々の転回形が巧みに絡み合い、淀みのない音の奔流が魅力となっている。ホルンとチェロを主体とする冒頭の第1主題(譜例1)は、あらゆる交響曲の中でも 美しいものの一つといえよう。ホ長調の自然倍音による2オクターブにわたる分散和音の上昇と冒頭ら22小節という長さは、無限の広がりと可能性を示している。ハンス・リヒターがブルックナーに尋ねたところ、イグナーツ・ドルンが夢に現れ口笛でこの主題を吹き、成功を掴むだろうと言った、そこですぐに起きてロウソクに火を灯し、急いで書き留めた、とのこと。ワーグナーが「ニーベルングの指輪」 序夜「ラインの黄金」の作曲に際して、夢遊病状態での体験から原始の響きとして変ホ長調主三和音のホルンによる自然倍音の上昇音型「生成の動機」を創作したという話を彷彿とさせる。どちらも夢の中でというのが象徴的である。ここではホ長調に半音階上がることで、愛と幸福に満ちた情景に包まれ、ホ長調-ハ長調-ロ長調-ホ長調-嬰へ長調-ロ長調と続く和声進行により醸し出されるロマン性は、ブルックナーの内面からあるがままに噴出された感情を表現しているのだろうか。
続いて抒情的な第2主題(譜例2)、軽妙な第3主題 (譜例3)が各々ロ短調で提示されていくが、目まぐるしい転調を伴う和声進行と展開を伴って次第に興奮を高めてクライマックスを形成していくプロセスが続く。
展開部では、まず第1主題が転回形で用いられ、 続いてチェロによる第2主題の転回形が深い抒情性を醸し出し、ところどころに第3主題も登場していく。後半はハ短調にてまずは第1主題の転回形が強奏され、続いてニ短調で第1主題がダイナミックに進み、ホ長調で再現部に入る。再現部は、提示部とは異なるプロセスでいくつものクライマックスを築いていき、やがてバスのホ音によるオルゲルプンクト(持続低音)の上に第1主 題後半のモティーフが「非常に厳かに」形成されていく。ここで初めて登場するティンパニが効果的に使用されている。
コーダは第1主題による勝利の音楽として輝かしく展開し、最高潮のうちに閉じられる。
第2楽章 アダージョ、極めて厳かに、そして非常にゆっくりと
嬰ハ短調、4/4拍子。第1主題と第2主題によるA1-B1-A2-B2-A3の5部形式。前作の交響曲第6番の柔和で気品のある美しい音楽に満ちたアダージョより更に深みを増し、ブルックナーの心象を表現しているような厳粛且つ荘厳な音楽。第1主題の前半 (譜例4)はワーグナーテューバを主体とするコラール。ワーグナーテューバは、ホルンと同様に移調楽器のため実音で記載されず、この交響曲の調性では シャープの数が多い。嬰ハ短調は、ワーグナーの「指輪」にある「黄昏の動機」の調性であり、ワーグナーへの想いであろうか。後半は「テ・デウム」の最終 楽句(前述)が引用されている。
第2主題(譜例5)は、モデラートとなり嬰へ長調 3/4拍子にて弦楽器で呈示、ベートーヴェンの交響曲第9番第3楽章を彷彿とさせる音楽。第1主題によるA2への帰還は、その後転調を伴い高調し、ハ長調から発展してト長調にて金管の輝かしい響きにより最初の頂点に進む。次のB2では、第2主題がB1よりも現実性を帯びて変イ長調にて再現、この楽章のクライマックスとなるA3を導いていく。A3は第 1主題が弦楽器の装飾を伴いつつ厳かに再現、「テ・デウム」最終楽句のコラール楽句を用い音階的上昇音形でA2よりも壮大に発展していく。このような和声的な音階は、ブルックナーの特徴ともいえる方法であり、特別な強い訴えを持って密度の濃い感情を噴出させながらハ長調の頂点に到達する。この時に、ノヴァーク版ではティンパニ、トライアングル、シンバルが加えられている。収束とともに奇跡とも思える変二長調へ移行、その後、前述したワーグナーテューバとテューバによる葬送の音楽が嬰ハ短調で厳粛に登場する。最後は魂の安らぎを願うような、諦念の境地を暗示するような嬰ハ長調の静かな響きで締めくくられる。
第3楽章 スケルツォ:非常に速く トリオ:幾分遅く
イ短調、3/4拍子。三部形式。弦楽器の初動とトランペットによる主題(譜例6)で構成されている。交響曲第6番のスケルツォとは異なり、前楽章の緊張を解放するような野性的で快活な雰囲気。それでいて硬直せずに転調を繰り返し、4小節単位にて進展する。最初の終止はハ短調、その後の中間部はブルックナーの特徴として、初動と主題の転回形が用 いられ、主調のドミナントとなって再現部に入り、イ短調で終結する。
トリオは、ヘ長調で田園的な主題(譜例7)が穏やかに転調と転回を繰り返しながら進み、平易に終わってスケルツォに帰還する。
第4楽章 フィナーレ 動きをもって、しかし速くなく
ホ長調、2/2拍子。自由なソナタ形式。当初この楽章は周囲から理解不能ということで批判の的となった。ソナタ形式の再現部において、提示部の3 つの主題による構成要素を再現部では全て逆転させて再現するという、古典的なソナタ形式の規範からみれば理解不能で混乱を招く構成となっている。 個々の構成要素を対比させ、小節数やディナーミク (強弱法)も調節することで、伝統的な構成要素を熟知しているがゆえの自由な形式の中で、即興演奏のごとく各主題を動的に処理している自己完結型の楽章といえる。
第1主題(譜例8)は、第1楽章第1主題を用いて快 活に進み、第2主題(譜例9)は一転して変イ長調のコラール風、そして第3主題(譜例10)はイ短調で第1主題を発展させた激烈な旋律にて、各々転調を多く含みながら提示部を構築している。展開部は、第1主題と第2主題の転回形が縦横無尽に転調しながら進み、再現部では第3主題がロ短調で回帰、第2 主題、第1主題とますます幅広く、より大きな輝きをもってオルガンの即興演奏のように展開していく(ブルックナーにとってオルガン演奏は徹頭徹尾、即興演奏の芸術であった)。そして強烈なカデンツから、第1楽章冒頭主題が回帰し、巨大なコーダとなって歓喜のうちに終わりを告げる。
■交響曲
ワーグナーは、亡くなる前に、妻コジマとの会話の中で、ベートーヴェンの交響曲と他の器楽作品との本質的な違いについて思いを巡らし、ソナタや弦楽四重奏曲ではベートーヴェンが音楽を奏でている が、交響曲では世界全体が彼を通じて音楽を奏でている、と語ったとされている。
18世紀までの音楽美学では、交響曲は副次的な重 要性しか持たない曲種だったが、19世紀に入る前後の短期間で最高の曲種と位置づけられるようになった。ベートーヴェンの登場により、交響曲は、共同 体の理念の最高の音楽表現と位置づけられるようになる。芸術擁護や演奏の場の時代的な変化もあるが、大規模な楽器編成による対照的な音色の統合、音響的多様性と長大化、高い作曲技術の要求により、作曲家と聴衆の双方に多くの負担を求めるようになってきた。
楽式論の成文化が始まり、多くの人々が音楽の形式をめぐって論戦を行った。そして作曲家はベートーヴェンの残した交響曲の巨大な影と格闘することになる。 芸術とりわけ音楽が、政治的社会的変革の媒体として働き得るという信念に基づき、ワーグナーは、 交響曲の領域におけるベートーヴェンの至高性を認識したうえで、ベートーヴェン自身が交響曲第9番によって交響曲の終焉を告知したものと断言し、さらに偉大な全包括的な芸術作品、ワーグナー曰く「総合芸術作品」の究極的な実現を公言する。このような姿勢は、伝統主義者の激しい反応を呼び起こし、「ワーグナー派」と「ブラームス派」の党派抗争へとつながっていった。
19世紀は個性の時代であり、ブラームスもブルックナーも同時代に生きた作曲家として、自らの道を切り開き、独自の世界を築いていったのである。
■ハース版とノヴァーク版
作品の発展過程のうえで、作曲家自身によってなされた変更は重要なものである。「スケッチ」「草稿」から始まり「原稿」に署名と日付が入ると「第1稿」という流れがある。ここに「改作」「改定」が入り、「第2稿」「改定版」となってまたいくつかの状況が生まれてくる。更に「初版」の印刷が入り、そのための「初版稿」とか、各々の過程で更に変更や追加が加えられていく可能性もある。
ブルックナーの場合、ややこしいのは、自らの意思による「改良」に加えて、周囲からの助言に伴う「改良」があり、特に「ブルックナー3使徒」による短縮やおびただしい改定が、師からの承諾の有無にかかわらず「改定版」として存在することで、現代の目からは「改竄」と表現すべき状況にもなっている。 交響曲第7番には、「初版」(1885)、国際ブルックナー協会による「原典版」として「ハース版」(第 1次全集版1944)と「ノヴァーク版」(第2次全集版1954)が出版されており、残された自筆譜や資料の解釈により、いくつかの相違が散見されている。2 つの「原典版」の違いに関しては、ブルックナーの最終判断と最終意図に関することであり、その判断には困難が伴うが、大きな相違として知られているのは第2楽章の打楽器の有無があげられる。
■3つの領域-矛盾からの告解と感謝
ブルックナーの生涯には、「オルガニスト」、「音楽理論教師」、「作曲家」という各々異なる領域が存在し、それぞれに彼は業績を残している。
「オルガニスト」としては、聖フローリアン修道院オルガニスト、リンツ大聖堂オルガニスト、ウィーン宮廷礼拝堂オルガニストを歴任、1869年4月~5 月にナンシー・パリ旅行、1871年7月~8月のロンドン旅行にオルガニストとして派遣され、空前の成功を収め国際的に名を高めている。
「音楽理論教師」としては、寒村ヴィントハークでの国民学校助教師、聖フローリアン修道院付属学校助教師から始まり、ウィーン音楽院和声法対位法オルガン演奏講師、ウィーン大学哲学部和声法対位法講師に上り詰める。そしてブルックナーが長年主張してきた音楽と学問との深い絆をウィーン大学が認め、1891年11月7日ウィーン大学哲学部名誉博士 という栄誉ある称号が与えられた。
「作曲家」としては、周知のとおり厳しい論争にさらされながらも、ウィーン古典様式とシューベルトのロマンティシズムを手中にしながら、3曲のミサ曲を経て教会音楽「テ・デウム」で、また交響曲では第7番で国際的な地位を確立する。そして1886 年7月9日フランツ・ヨーゼフ騎士十字勲章を授与され、皇帝から経済的援助も得られるようになった。
この3つの領域が交錯したブルックナーの生涯に は多くの矛盾と対立があり、ブルックナー自身の風変わりな服装や奇癖と共に、混乱が生じていた。
ブルックナーは、全生涯にわたり熱烈かつ真剣なカトリック教徒であり続け、毎日の祈祷記録と共に、その信心深さは全ての音楽に潜在している。教会音楽のみならず、交響作品には、荘厳で祈りに満ちた本質が表れている。
「神との対話」のための教会音楽と、「人間との対話」のための交響曲が、ブルックナーの特異な個性の中ではあくまでもひとつのものであり、交響曲第7番は、「テ・デウム」と共に、ブルックナーの告解と感謝、そして対話が融合したものとして、私たちに心情を直接語りかけているのである。
(譜例準備中)
初演:
1884年12月30日 アルトゥール・ニキシュ指揮 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
楽器編成:
フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、ワーグナーテューバ4、テューバ、ティンパニ、トライアングル、シンバル、弦五部
参考文献:
土田英三郎『ブルックナー ―カラー版作曲家の生涯―』新潮社 1988年
『作曲家別名曲解説ライブラリー⑤ ブルックナー』音楽之友社 2006年
田代櫂『アントン・ブルックナー 魂の山嶺』春秋社 2005年
マーク・エヴァン・ボンズ(近藤譲・井上登喜子訳)『「聴くこと」 の革命 ベートーヴェンの時代の耳は「交響曲」をどう聴いたか』 アルテスパブリッシング 2015年
マーク・エヴァン・ボンズ(土田英三郎訳)『ソナタ形式の修辞学 古典派の音楽形式論』音楽之友社 2018年
レオポルト・ノヴァーク(樋口隆一訳)『ブルックナー研究』音楽之友社 2018年
新交響楽団第209回演奏会プログラム『ブルックナー:交響曲第9番<永遠のゲネラル・パウゼ>』2010年
新交響楽団第220回演奏会プログラム『ブルックナー:交響曲第5番<真のブルックナー:厳格な技法とファンタジーの融合>』 2013年
新交響楽団第226回演奏会プログラム『ブルックナー:交響曲第6番<ブロック様式からロマン派様式への転換>』2014年
(新交響楽団ホームページから「過去の演奏会」より第209回、第220回、第226回の各演奏会詳細) http://www.shinkyo.com
ワーグナー/歌劇「ローエングリン」より 第1幕への前奏曲、第3幕への前奏曲
この歌劇が完成した1848年はワーグナーの生涯に おける重大な転機の始まりにあたります。この年の 2月にフランス・パリで起こった2月革命はドイツに も広がりました。ワーグナーもこの運動に加担したため、政府から追われ海外へ亡命することとなるのです。亡命生活は長期にわたりますが、その最初の 9年間を過ごしたスイスで彼は総合芸術論を展開し、 従来の歌劇を否定しました。これが以降の楽劇へと 展開されていくことになります。 「ローエングリン」は亡命前にドレスデンで完成したのですが、この亡命により初演は友人の作曲家 フランツ・リストの助力を得て実現することとなり ます。しかしその初演に亡命中のワーグナーは立ち合うことができませんでした。彼が自作の演奏を聴く(見る)ことができたのは初演から10年以上も過 ぎた1861年3月12日だったのです。
■歌劇「ローエングリン」のストーリー
舞台:ブラバント公国(現在のベルギーとオランダの一部)
主な登場人物:ローエングリン(白鳥騎士)、エル ザ(ブラバント公国先公の娘)、テルラムント(ブラバントの伯爵)、オルトルート(テルラムントの妻で妖女)、ハインリッヒ王(ブラバントに遠征に来たドイツ国王)、ゴットフリート(エルザの弟)
第1幕
ドイツの藩国ブラバントに激励、募兵に来たドイツ・ハインリッヒ王に、土地の伯爵テルラムントが「先公の遺児エルザが王位継承権のある弟のゴットフリートを殺害した」と訴えます。審判のため呼び出されたエルザは「白鳥の騎士が自分を救いに来てくれる」と述べ、彼女の祈りに応えるように白鳥に引かれた小舟で美しい騎士(ローエングリン)が登場。騎士はエルザに対して「テルラムントと戦い勝てばエルザを妻にすること、そして自分の素性は一切尋ねないこと」を問いかけます。エルザがこれを受け入れたので、騎士はテルラムントと戦い勝ちます。しかしテルラムントの命は助けておきました。
第2幕
テルラムントと妻オルトルートが夜の城庭で話しています。オルトルートは妖女(魔法使い)で、実はエルザの弟ゴットフリートを魔法で白鳥に変えていたのでした。オルトルートはテルラムントに騎士の身体の一部を切り落とすか、もしくはエルザに尋ねてはならない素性を問わせれば騎士を倒すことができると吹き込みます。さらにその場に現れたエルザにも騎士に対する疑念を植え付けるのです。やがて夜が明け人々が婚礼のために登場すると、テルラムントは素性不明の騎士との戦いは無効だと訴えますが、騎士は相手にせずエルザとの婚礼会場に向かいます。
第3幕
華々しい前奏曲の後有名な婚礼の歌(結婚行進曲)。2人きりになった騎士とエルザ。しかしエルザはオルトルートに植え付けられた疑念に耐えきれず、ついに不問の誓いを破り騎士に素性を尋ねてしまいます。そこへテルラムントが乱入し騎士に切りかかりますが、エルザの差し出した剣により騎士はテルラムントを倒します。しかしすでに問いが発せられてしまったため、騎士は2人の幸せは終わったことを告げ、人々の前で自分が聖杯守護王パルジファルの息子・聖杯騎士ローエングリンであることを打ち明け、自分の秘密が破られた今モンサルヴァートの聖杯城へ帰らねばならぬことを告げるのでした。そして騎士を迎えに天空から白鳩が、水上に小舟を曳く白鳥が現れます。オルトルートは自分の計略が成功したと歓喜の声を上げますが、ローエングリンが祈りをささげると白鳥は一度水中にもぐ り美しい少年の姿となります。この少年こそがエルザの弟ゴットフリート。術を破られたオルトルートは地に倒れます。ローエングリンは白鳩に引かれた小舟で去り、残されたエルザは悲しみのあまりゴットフリートの腕の中で息絶えるのでした。
■音楽
歌劇「ローエングリン」は、「さまよえるオランダ人(以下オランダ人)」「タンホイザー」から続くワーグナーのロマン歌劇の最後の、そして次の楽劇への転機にあたる作品です。従来の形式は残しながらも新しい要素が織り込まれた歌劇だと言えます。「タンホイザー」では残されていた独唱歌の番号形式は使われておらず、内容・構成的にも音楽と劇の融合が見られます。管弦楽についても「オランダ人」「タンホイザー」の2管編成から3管編成となり、同一楽器による和声の多彩化が図られました。新しい時代を予感させるこの歌劇は、前作「タンホイザー」とともにワーグナー作品の中でも広く親しまれる作品となっています。
第1幕への前奏曲
Langsam(ゆったりと)の指示で始まるこの曲は聖杯をテーマとしています(聖杯=十字架で処刑されたキリストの血を受けたと伝えられる器)。木管と8パートに分かれたヴァイオリンが天上の和音 で呼応した後、ヴァイオリンによって聖杯の動機が奏されます(譜例1)。この動機は歌劇中でもローエングリンの登場や名乗りの場面で奏されます。ヴァイオリンのイ長調から木管のホ長調、中音楽器のイ長調を経てクレシェンドで高揚し、金管コラールで曲の頂点を迎えます。
華やか且つ神々しい響きが収まるとヴァイオリン が美しくも気高い旋律を奏し音楽が静まり冒頭の和音、動機で静かに曲が終わります。天上の聖杯の輝きが人間の住む下界へ降り再び天上に戻っていく光景を表している、ワーグナー作品の中でも最も美しい音楽の1つではないでしょうか。
実は聖杯自体はこの歌劇には登場せず、ワーグナーの最終楽劇「パルジファル」でその輝きとともに舞台に現れるのです。
第3幕への前奏曲
Sehr lebhaft(とても快活に、生き生きとして)。 第1幕の前奏曲とは対照的に明るく始まるこの曲は、第3幕の婚礼への華やかな気分が感じられる音楽です。爆発的に歓喜を表す音楽のあと3連符のリズムに乗って中音楽器群が歓呼の音楽(譜例2)を堂々と奏します。中間部では愛らしく結婚式に華を添え るような音楽が木管、ヴァイオリンに奏でられ、その後再び歓喜の音楽となります。テューバ、コントラバスも加わって重厚な響きとなり、最後はト長調の和音で曲が終わります。歌劇ではこの前奏曲の最後の和音が徐々に静まり、有名な婚礼の合唱=結婚行進曲へと続くのです。
ロマン歌劇の前2作「オランダ人」「タンホイザー」は女性が自分の命と引き換えに愛する主人公を救おうとする「救済」の内容ですが、この「ローエングリン」は逆に男性が女性を救いに来るも叶わず去っていくという内容です。表面的には女性(エルザ)がその愛ゆえに不問の誓いを破らずにいられなかったという悲劇ですが、実は男性(ローエングリン)もエルザとの愛に救いを求めるものの自身の神性ゆえ秘密保持を貫かねばならなかった(救済が叶わなかった)という悲劇も描かれていると言えるでしょう。このような悲劇作品ではありますが、その音楽には美しく幸福感に満ちたものが多数あり、例えば結婚行進曲が悲劇的内容にもかかわらず現在の結婚式でも演奏されるのは、その音楽ゆえではないでしょうか。
ワーグナーはオペラを極めましたが、実はベートーヴェンを崇拝し交響曲的な世界観をオペラに取り込んだとも言えます。その功績は後に続く作曲家たちにも影響を与えました。特に交響曲分野ではブルックナーがワーグナーを尊敬しており、交響曲第 7番第2楽章には、偉大なる先輩作曲家への想いが込められています。詳しくはブルックナー交響曲第7 番曲目解説を参照下さい。
今回は前奏曲2曲からワーグナー歌劇の世界を覗いて頂きましたが、新響が次回に取り上げる「トリスタンとイゾルデ」は第2幕全曲を中心にオペラを より深く知って頂ける演奏会となります。ご期待下さい。
(譜例準備中)
初演:(歌劇全曲) 1850年8月28日ワイマールにて フランツ・リスト指揮
楽器編成:(前奏曲) フルート3、オーボエ3(1幕は1本がコールアングレ)、クラリネット3(1幕は1本がバスクラリネット)、ファゴット3、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、 シンバル、トライアングル(3幕のみ)、タンブリン(3幕のみ)、 弦五部
参考文献:
高木卓(解説)『ワーグナー ローエングリン第一幕・第三幕への前奏曲』(ポケットスコア)全音楽譜出版社 2007年
バリー・ミリントン(三宅幸夫監訳、和泉香訳)『ワーグナー バイロイトの魔術師』悠書館 2013年
ヴァルター・ハンゼン(小林俊明訳)『図説ワーグナーの生涯』アルファベータブックス 2012年
マルティン・ゲック(岩井智子、岩井方男、北川千香子訳)『ワーグナー(上)』岩波書店 2013年
『ワーグナー歌劇“ローエングリン”全曲』(LPレコード 解説・渡辺譲)東芝EMI 1982年
ワーグナーテューバのこと
●ワーグナーテューバとは
ワーグナーが楽劇『ニーベルングの指環』を作曲するにあたり、金管楽器の音色のヴァリエーションを増やすために考案した楽器です。ワーグナーは金管楽器を4つの群として考え、ホルン群を8本に増強し、トランペット群にはバストランペットを、トロンボーン群にはコントラバストロンボーンを加え、テューバ群として通常のテューバにホルン奏者が演奏するテューバを加えました。実際に調達にあたったのはワーグナーの助手をしていたハンス・リヒターで、元は名ホルン奏者、『指環』のバイロイトでの初演では指揮を担当しました。
ホルン奏者が演奏する必要があったため、マウスピースがホルンと同様に小さいことと、ホルンと同様に左手でバルブ操作ができることが、単なる小型のテューバではない特徴となっています。
ワーグナーはワーグナーテューバを『指環』でしか用いませんでした。金管楽器群の響きに奥行きを持たせるだけではなく、テューバ群のみを室内楽的に使用したりもしました。ワーグナーの熱狂的信者であったブルックナーは1876年の「指環」初演時に立ち会っています。今回演奏する交響曲第7番は、ブルックナーがワーグナーテューバを初めて使用した曲で、第2楽章のテューバ群の荘厳な響きで始まるコーダはワーグナーの死を悼んで付け足されました。その後の8番、9番でもワーグナーテューバを登場させ『指環』と同じような使い方をしました。
●新響のワーグナーテューバ
当団のワーグナーテューバは、ドイツのアレキサンダー社製B管シングル2本、F管シングル2本の王道ともいうべき4本セット。新響40周年で飯守先生とワーグナーの楽劇『ワルキューレ』第1幕全曲を演奏するのに向けて、1995年に維持会費で購入させていただきました。ユーロが発足する前で円が強く、ドイツの楽器店を通して購入しましたが、現在日本で注文して購入する場合の約半額で入手できました。(注:『ワルキューレ』は『ニーベルングの指環』全4曲のうちの1つ。)
それまではワーグナーテューバが必要な時は、都内の楽器店から借りており、金額もさることながら毎週の受取や返却がとても手間でした。その後約20年間に、ワーグナー『ニーベルングの指環』抜粋、ブルックナー交響曲7,8,9番、火の鳥全曲版、春の祭典、中国の不思議な役人、アルプス交響曲で使用させていただきました。毎回の練習で自前の楽器で演奏できるのは本当にありがたいことです。
また購入当時はワーグナーテューバを所有している人はほとんどなく、多くのアマチュアオーケストラでブルックナーなどを演奏するときに苦慮していたため、他のオーケストラに貸出しをしていました。十分に元が取れ良い状態で残したいので、現在は基本的に貸出していません。最近では中国製の安価な楽器も流通しており、アマチュア奏者が自前で購入する人も多いようです。
●ワーグナーテューバと似ている楽器たち
もう30年以上も前の話、私が大学の管弦楽団でホルンのパートリーダーをしていた時、コンサートのメインはブルックナー交響曲第4番に内定していました。それがいつの間にか第7番に変わり、しかもワーグナーテューバをユーフォニアムで演奏するという!私の「ロマンティック」を演奏する機会が飛んでしまったのは残念だが、執行部の決定だからしかたない。でもユーフォニアムはないだろうと思ったわけです。ユーフォニアムの方が入手しやすいし、ワーグナーはテューバ群として想定しているのだから本来ユーフォニアムの方が適切だと言う。ちなみにその時の指揮者(=当時新響にもたびたび登場していた山岡重信先生)の息子さんはユーフォニアムのプロ奏者なので、その辺の思い入れかもしれません。こうしてワーグナーテューバの譜面はトロンボーン・テューバパートに取られてしまいました。どっちにしても自分はホルンを吹いていただろうけど、上手な後輩が多数いてパートの活躍の場が減ることは、とても悔しかったのでした。
その6年後に同大学がブルックナー交響曲第8番を演奏した時は、東京藝術大学所有の大正時代のワーグナーテューバのセットをお借りしました。この楽器はニッカン(日本管楽器=現在はヤマハに吸収合併)が1923年に製造したもので、東京音楽学校の『ワルキューレ』日本初演に向けて用意されたとのこと。ウィーンの楽器の完全なコピーで、当時日管には東京帝大工学部卒の天才的な設計士がいたのだそうです。
東京音楽学校ではブルックナー交響曲第7番の実質的な日本初演を1933年に行っています。実質的な、というのは、1918年に久留米の捕虜収容所でドイツ兵によってブルックナー第7番が演奏されたという記録があるのだそうで、楽器がそろっていなかっただろうと想像しますが、その初演から今年はちょうど100年となります。
実は「ワーグナーテューバ」というパートはありません。スコア・パート譜には、TenorTubaとBassTubaと表記されています。音の高い2パートがTenor in B、低い2パートがBass in F。通常のテューバは、区別するためにKontrabassTubaとなっている曲もあります。
TenorTubaと書かれていても、ワーグナーテューバを使わない曲もあります。作曲された背景等により違い、慣習で決まっています。R.シュトラウスの『ドン・キホーテ』『英雄の生涯』のTenorTubaは、日本ではユーフォニアムが多いですが、ドイツ・オーストリアではドイツ式バリトンが使われます。ホルスト『惑星』のTenorTubaはイギリスの曲ですしユーフォニアムです。マーラーの交響曲第7番にはTenorHornというパートがありますが、これはまた別の楽器でホルン奏者ではなくトロンボーン奏者が担当します。細目の管でワーグナーテューバとよく似ていますが、左右逆でマウスピースがトロンボーン用です。
●演奏時の問題点
ワーグナーテューバの音程が悪いのは、ホルンは右手をベルに入れており音程調整ができるが、それができないからだ・・と言われることがあります。私も昔ホルンを吹くとき楽器自体の音程の癖の克服のために右手を駆使していましたが、今は楽器が良くなり右手で意図的に音程を調整することはあまりありません。それでもワーグナーテューバを吹くのが難しいのは、ホルンと息の抵抗感が違うことと楽器の構え方にあるでしょう。
私の場合はワーグナーテューバを腿に置いて普通に構えると、眉間くらいにマウスピースが来て、マウスパイプはほぼ水平になります。普段から楽器を立てて吹くユーフォニアムやテューバは、マウスパイプが顔に対してほぼ垂直になってもマウスピースが大きいため可能なのだと思います。それに対しマウスピースの小さいホルンは、人によって顔に対するマウスパイプの角度がだいぶ違い、歯並びや顎の位置、筋肉のバランスや求める音色によっても変わってきます。体格が大きくほぼ水平で吹いている人は、何の問題もなく吹けると思うのですが、普段マウスパイプを下向きで吹いている私が同じ楽器を吹こうとすると、ホルンを吹く時よりも顔が上向きになり下顎を余計に前に出すことになるのです。
ワーグナーテューバを吹いて不調になるという人は多いですが原因はその辺だと思います。ですので、普段ホルンを吹いているときと同じアンブシュアで吹けるよう、試行錯誤中であります。現在は四苦八苦しながら取り組んでいますが、本番では心のこもったハーモニーが奏でられるようにしたいと思います。
ブルックナーと数にまつわる話
◆清張のブルックナー観=数える話=
予想もしない処で知人にばったり出遭う・・・・かつて松本清張の推理小説『数の風景』を読み進むうち、突然ブルックナーに関する記述に出くわした時に、これと同じ感慨を抱いた事があった。既に四半世紀も前の事ながら、その時の驚きと唐突感は今もよく覚えている。この小説自体はあまり出来の良い中身ではないが作中、目に入る事物の数・・・・例えば行く道端の電柱の数や階段の段数、駐車場の車の数など)を数えないでいられない「ニュメロマニア(計算狂)」と思しき女が出て来る。これは神経症の一種らしいが、この女の性向が後の展開の軸になって関わってゆくとあって、まぁそれはそれで興味も湧く。ただそのニュメロマニアの同類としてブルックナーの名が突如現れるのには驚いた。作家はここでH.シェンツェラー(Hans Hubert Schonzeler)著の『ブルックナー・生涯/作品/伝説(山田祥一訳)』にある記述の概要と、未完に終わった交響曲のスケッチを転載する。8小節単位で作曲家自身が書き込んだ数字(1~8までの繰返し)があり、それがこの作曲家の数に対する強迫神経症の証拠であるという。単にフレーズを示しているとしか思えぬが。
音楽作品と数字という点では大バッハが有名で、各作品の数値的な美学はもとより、A=1、B=2という具合にアルファベットをそれぞれ数に当てはめ、作品から読み取れる数を具体的な文字に変換して、そこに現れる言葉によって作品に隠されたメッセージを見出すというこじつけまがいの「研究」さえ古くから行われている。清張は当然にこの例にも触れているが、大バッハの例に比較するとブルックナーはこの内容に於いて見劣りも甚だしい。僕は厖大な『昭和史発掘』を含め清張の主だった作品は大抵読んでいるが、作中に譜面を伴ったものはこれしか知らない。しかも別にストーリーの展開とは殆ど無関係なのに、これほどにこだわる理由もよく解らない。
新響が初めて飯守泰次郎氏を招き、ブルックナーの交響曲第4番『ロマンティック』を演奏したのが1993年4月(第139回演奏会)。それまでブルックナーの交響曲は1975年に同じ第4番を、1981年に第7番を演奏しただけだった(指揮は共に山岡重信氏)ので、ブルックナーの人となりと作品をテーマとして、この作曲家に関する著作があり、東京藝術大学で教鞭をとられていた土田英三郎氏を招き、練習の初期段階でレクチャーをお願いした事があった。『ロマンティック』に関する詳細な分析に基づく講義の余談として、ブルックナーが果たして計算狂であったか否か?に触れられた。氏は「松本清張の小説にそんな話もありますが・・・・」と今考えれば『数の風景』を例示しておいでだった訳だが、しかしご自身の考えとしては明確に否定されていた。ただ小説を執筆途上だったと思われるある時、作家本人から電話があって、この説に関して相当に食い下がられたという事実を苦笑交じりに語られていた。これが妙に記憶に残っている。作家松本清張の執着心と取材力を思うべきだろう。
だが自分の乏しい読書体験から照らしても、博覧強記にしてあらゆるテーマを網羅して作品を世に送り出した作家も、こと音楽の分野に関してはあまり見るべきものが無いように感じる。有名な『砂の器』も現代音楽の作曲家を主人公としながら、内容は難解・冗漫になって効果は上がらない。むしろ先日亡くなった橋本忍の脚本による映画(1974年・監督は野村芳太郎)で改めてテーマが絞られ、扱われる音楽を含めて解りやすくなって、ようやく日の目をみた感がある。音楽を題材にした作品で個人的な好みは、『魔笛』の台本作者にして興行師のシカネーダーをテーマとした『モーツァルトの伯楽』(『草の径』所収)くらい。計算狂のテーマなら黒川博行の『カウント・プラン』の方がよほど面白い(完全な脱線)。
シェンツェラーが、ブルックナーの自筆譜の各小節に悉く数字が書き入れてある事を根拠に、作曲家がニュメロマニアであったと断定し、松本清張がその説を無批判に受容れ、『数の風景』中に譜例まで引用しているのは、ちょっとお粗末に過ぎるように感じる。小節ごとに数字を書き込む事などは普通に行われているからだ。例えばショスタコーヴィチの作品のように同じ音型が数十小節も続くような場合、作曲者自身でさえ回数を数える便宜として繰返しの小節数を書き込む事はある。そうした譜面は珍しくないし、そうした回数が無ければ奏者が適宜書き込んでいる。
そもそも音楽作品の創造やそれを演奏する事は、数字や「数える」行為と決して無縁ではあり得ない。例えば我々は作品を演奏するに当たって、速度(テンポ)の決定要因である拍を数え(その拍を更にいくつにも細分化して数えさえする)、その集積の単位となる小節数を数える。これは音を出していない休みの間も継続するし、むしろその間の方が数える事の重要度は高まる。またこれとは別に、音の高さを振動数という数値で認識し、異なる複数の音の振動数比が単純であるほど、そこに純粋なハーモニーが現出する事を意識している(この関係を最初に見出したのは数学者のピタゴラス)。もしオーケストラで活動していながら、数値や数える行為に全く無関心の人がいるとしたら極めて不可思議な存在だし、現実問題として自力で演奏する事は不可能だろう。むしろこちらの方が立派な「病気」に思える。
因みに今回この稿を起こすに当たり、ネット上で『数の風景』とブルックナー関連の記述を検索してみたが、僕のような屈折した(笑)見解は全く見当たらなかった。それどころか殆ど反応らしい反応が無い。驚くほどである。これは詰まる処『数の風景』の読者にはブルックナーという作曲家は遠い存在であり、またブルックナー(に限らず音楽全般の)愛好者は、あまり松本清張を読まない・・・・という状況を意味するのかもしれない。この作品を通じた両者の接点は感じられず。
芸術家という人種はどこか世間の常識良識とはかけ離れた側面を持っているし、また社会もそうした性格を密かに期待していたりする。そして当人もそうした社会の空気を逆手にとって、徒に奇矯であろうと目論んだりするから始末に悪い場合がある。そうした中にあって、ブルックナーという作曲家の人となりはやや特殊と言えるかもしれない。伝記作家にとっても、あの長大で晦渋な作品に比して、創作者の平穏に過ぎた生涯を見渡して、何かしらの接点を見出さずには済まされない。シェンツェラーの説は、ブルックナーの起伏に乏しい生涯(他の作曲家らとの比較の問題だが)に対し、「ニュメロマニア」という特異な兆候を微かに見出し、それとばかりに小躍りして針小棒大に喧伝しているとの印象を拭えない。
だが清張作品を信奉する一方で作曲家と無縁の衆生は、読み進んでも一向に屍体が登場しないこの推理小説によって「ブルックナーなる作曲家はニュメロマニアである」と刷込まれ、信じ続けるのであろう。何かぞっとせぬ光景ではある。
◆忸怩たる記憶=数えられなかった話=
わが国のアマチュアオーケストラがブルックナーの交響曲をようやく採り上げるようになったのは、1970年代も半ばにさしかかった頃だろう。前記の通り新響が『ロマンティック』を演奏したのが1975年。この辺りが本格的にブルックナーに取組み始めた嚆矢ともいうべき時期だったように認識している。以前にも『維持会ニュース』に書いた事があるので重複は極力避けるが、僕が早稲田大学交響楽団(ワセオケ)に入団した翌年の1978年1月初頭に、交響曲第7番をこの学生オーケストラは演奏している(指揮は新響と同じく山岡重信氏)。
続く7月には在京学生の選抜オーケストラであるジュネス・ミュジカル・シンフォニーオーケストラがNHKホールで第9番を演奏。このオーケストラ自体が、通常の学生オケでは演奏が困難な作品を大学の枠を超えた選抜メンバーで実現させる事を目的としていた。その団体にしてブルックナーであり且つ第9番ある。位置づけは自ずから判ろうというものだ。この時オーディションに通って、2番フルート奏者として参加出来た。個人的に初めてブルックナーを演奏した訳だが、恐らくアマチュアオケがこの未完の交響曲を採り上げたのはこれが最初で、いきなり第9番からブルックナーに入ったという自分の経験は、その後の人生に何らかの影を落として今に至っている、と言えるかもしれない。
なおこの時の指揮も山岡氏。こうして当時を振り返ってみると、氏がアマチュアへのブルックナー浸透に果たした役割は大きかったのだと改めて認識する。この後、どこのオーケストラでも大抵『ロマンティック』か第7番しかとりあげない時代が長く続いた。この2曲が他に比べて「解り易い」ものであり、技術的にも何とかなる(と思い込める)ものだったから・・・・と言えようか?
この直後の9月、ワセオケは総勢150名ほどでその山岡氏と渡独。ベルリンで開催された第5回国際青少年オーケストラ・コンクール(いわゆるカラヤン・コンクール)に『春の祭典』をメインプログラムに引提げて参加し、優勝を果たした。すると当のカラヤンが優勝のご褒美として我々を指導してくれる事になった。慶事である。だがその際にカラヤンが『春の祭典』を再びとりあげるのはコンクール優勝へのあらぬ誤解の原因となりかねないとの懸念が双方から持ち上がり、急遽別の曲をという運びに。そこで俎上に乗ったのが年初に演奏したブルックナーの第7番だった。長い曲なので第1楽章のみ。それで充分だった。
確かにこの交響曲を演奏した直後からはコンクールを目指して丸々半年に亘って『春の祭典』ばかりを練習していたのだから、それがダメとなれば直近で演奏した(つまり最も練習に時間をかけた)曲はワセオケにとってブルックナーという事になる。僕は『春の祭典』こそローテーション入り(ピッコロ)していたが、まだ1年生だった年初のブルックナーとは無縁。演奏経験のある上級生はひしめいているとあって、「これでカラヤンとは縁が切れたな」と、楽器は早々に仕舞い込むとやや自棄気味に羽をのばし、西ベルリン(まだ壁があった時代である)の巷を飛びまわった。
だが、宿舎に帰ると筆頭トレーナーのT氏よりお呼びがかかる。このT氏とは、今年2018年7月下旬に『週刊文春』誌上で、2年ほど前に起こしたワセオケの現役学生に対するパワーハラスメント問題を録音音声付きで暴かれた、後の「永久名誉顧問」・・・・記事が出た直後に辞任した。「永久」の称号はどうなるのか?・・・・である。だが当時は間違いなくコンクール優勝の真の立役者にして功労者だった(故に例の記事によって「晩節を汚してしまったな」との個人的な思いはある)。
さて、T氏のもとに出頭すると「ブルックナーの1番フルートは君が吹きなさい」とのご下命。「大」の字が付くかどうかは分からないが明らかな抜擢だ。有難くお受けし自室に戻ったは良いが、練習しようにもそもそも譜面も無いのである。気まぐれに楽譜屋に立ち寄ってパート譜を衝動買いする、という事の出来るようなシロモノではない。もちろんこれはオーケストラ全体もそうで、こんな事態を想定して日本からブルックナーの譜面を携えて来ている筈もない。
だが翌日には1番フルートの譜面が手渡された。今でも忘れる事のない深いブルーの表紙のパート譜。めくってみると最初のページの角に"Berliner Philharmoniker"というスタンプが捺してある。何と!ベルリンフィルハーモニー管弦楽団所蔵の譜面だった。通常は門外不出の扱いの筈だが、まぁあの「帝王」カラヤンがひとたび「やる」と口にしたのだ。山だって簡単に動こうというもので、譜面の都合くらい何でもあるまい。
当たり前だが1番フルートのパート譜はこの1冊しかない。すなわちオーレル・ニコレやカールハインツ・ツェラーやジェームズ・ゴールウェイなど歴代の名首席奏者らが使用した譜面そのものが、いま自分の手元に回ってきた訳である。社会経験も音楽経験も乏しくボンヤリしていた(これは今も変わらず)20歳当時とは言え、流石にこれは大変な事を引き受けてしまった、という悔悟の念がひしひしと湧いてきた。
初練習はさる教会で行われた。茫然自失の体で臨んだ為この教会の佇まいさえよく覚えていないのだが、練習に先立って例のT氏から、「この教会を使える事になったのも、国際交流基金の助成対象に今回のワセオケがなっていて、そのお墨付きがあっての事だからな。有難く思え」という趣旨の訓示があった。何の事かよく判らなかった。
だが、この日の練習後誰からともなく「あの教会は有名な『イエスキリスト教会』ではなかったか?」と囁かれ始めた。フィルハーモニーザール完成以前、ベルリンフィルと名指揮者らによる往年の数々の名盤の録音が行われた教会である。現在のように簡単に情報が入手できる時代ではなし、個人的にはこの日の記憶だけがひどく曖昧なのでその真偽は判らないが、恐らく本当だろう。
唯一よく覚えているのは、そうした贅沢ずくめの環境下での練習に於いて、「案の上」自分の出来が非常に悪かった事だ。いかんせん・・・・並み居るメンバーの中で自分だけが演奏経験が乏しい上に、山岡氏(そもそもワセオケOBにして、この時音楽監督だった)の振りがよく分からないとあって、出るべき処で出られず、余計な処で飛び出す事に終始した。挙句に周囲の上級生(ほぼ唯一の2年生たる自分以外みんな上級生だが)らから、「この曲知らないのか?」と異口同音に訊かれる始末。要するにもっと勉強して来い!という事だが異国の地とあって勉強の手立ても無いのだよ、まったく。
何が問題だったか?は自分でもよく解っていた。このブルックナーの作品の小節を「数えられなかった」のだ。第1楽章は終始2/2拍子、すなわち二分音符を1拍として1小節2拍。それが443小節あるので指揮者は886拍!!を振る・・・・というほど単純ではない。テンポが一定の行進曲とは違うのである。ブルックナー特有の第1楽章のテンポは2拍子としては遅すぎ、4拍子に分けて振るには速すぎる上に、絶えず変化を求められるので、指揮者は自分のテンポを奏者により正確に伝える為にも2拍と4拍の部分を振り分ける。
この振分けは指揮者によって異なり、それが独自の解釈を構成する重大要素でもあるので、マエストロを迎えての初回練習では誰であっても「ここは2つ(拍)で振る」とか「ここからは4つで何小節目から2つ」というような説明が必ずあり、楽員側はそれを自らの譜面に書き込む厳粛な儀式が執り行われる事になる。そして既に前年の後半、6か月以上にも亘る練習を経て、本番での演奏経験のある諸先輩方は、山岡氏のそうした振り分けがしみついており、何の違和感もなく棒に反応する。その中にあって新参者の僕だけがその洗礼を受けておらず、且つベルリンフィルからの借り物の譜面は殆どまっさら。今考えると不思議に思うほど何の書込みも無かった。だがこの楽章の前半にあるフルートのソロ部分には、運指に関する記号が書き入れてあったから、明らかに演奏の現場で使われた譜面なのだ。
このように何の手助けも無い状態となれば、トラブル発生は必至だった。長い休みの小節を数える間に、山岡氏の棒の動きを凝視すればするほど、それが2拍なのか4拍なのかが曖昧に見えはじめ、曲がどこまで進んでいるかが判らなくなって自分の出番を誤る事を繰返したという次第。当時の経験不足を度外視しても、これはやはり当然の帰結だったと思う。
消沈して宿舎に帰ると、次の練習に捲土重来を心密かに誓い、パート譜に愧じぬ演奏を期して独り「数える」練習に励んだ。ところがカラヤンを指揮台に迎える件は、その後数日にして水泡に帰した。彼がザルツブルグ辺りで練習の折に指揮台から落ち、腰を痛めてしまったからである。彼はワセオケを指導するという約束自体は翌1979年10月に日本で果たされたが、曲も異なればワセオケの技倆も変わってしまっていた。ブルックナーの第7交響曲をカラヤンの指揮で演奏する機会は永久に失せてしまった訳だ。負け惜しみ半分交じりの気分で「残念」と思った記憶が去らない。
爾来ちょうど40年の時が過ぎた。いままたこの交響曲を演奏できるのは奇縁とも云うべきだろうが、過去の経験から照らして、毎回の練習に振り向けるエネルギーの半分は小節数を「数える事」に費やされるだろうと予感している。もちろんこれが基本動作とは理解しているが、いくつになっても同じ事を繰返しやっているなぁ。
そして・・・・今になっても時に数え間違える。「命長ければ恥多し」という兼好法師の言葉がどこからか聞こえてくるような心地もする。
わが身に苦笑禁じ得ず。
第243回ローテーション
| 第1幕への前奏曲 | 第3幕への前奏曲 | 交響曲第7番 | |
| フルート1st | 岡田 | 吉田 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 岡田 | 兼子 |
| 3rd(Picc) | 藤井 | 藤井 | - |
| オーボエ1st | 平戸 | 平戸 | 山口 |
| 2nd | 山口 | 山口 | 岩城 |
| C.I. | 岩城 | 岩城 | - |
| クラリネット1st | 末村 | 中島 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 大藪 | 進藤 |
| Bass・3rd | 品田 | 末村 | - |
| ファゴット1st | 浦 | 浦 | 藤原 |
| 2nd | 松原 | 松原 | 田川 |
| 3rd | 田川 | 藤原 | - |
| ホルン1st | 大内 | 大原 | 山口(阿部*) |
| 2nd | 宮坂 | 宮坂 | 大内 |
| 3rd | 山路 | 山路 | 名倉 |
| 4th | 市川 | 市川 | 宮坂 |
| ワーグナーテューバ1st | - | - | 大原 |
| 2nd | - | - | 山路 |
| 3rd | - | - | 入山* |
| 4th | - | - | 市川 |
| トランペット1st | 北村 | 倉田 | 小出(中川) |
| 2nd | 倉田 | 北村 | 野崎 |
| 3rd | 中川 | 山之内 | 青木 |
| トロンボーン1st | 日比野 | 日比野 | 日比野 |
| 2nd | 志村 | 志村 | 志村 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 古関 | 今尾 | 桑形 |
| パーカッション | シンバル今尾 |
シンバル/古関 トライアングル/山本 タンバリン/桑形 |
シンバル/今尾 トライアングル/山本 |
| 1stヴァイオリン | 堀内(中島) | 堀内(中島) | 堀内(中島) |
| 2ndヴァイオリン | 内田智(小松) | 内田智(小松) | 小松(内田智) |
| ヴィオラ | 村原(柳澤) | 村原(柳澤) | 柳澤(村原) |
| チェロ | 柳部(安藤) | 柳部(安藤) | 柳部(安田俊) |
| コントラバス | 中野(郷野) | 中野(郷野) | 中野(郷野) |
*はエキストラ
管()はアシスタント、弦()はトップサイド
第243回演奏会のご案内
偉大なワグネリアン~ブルックナー
新交響楽団と飯守泰次郎氏との初共演は1993年。ちょうど日本に拠点を移した頃ですが、それまではドイツを中心に歌劇場で活躍し、ワーグナー芸術の総本山であるバイロイト音楽祭の助手を長年務めました。2014年から新国立劇場のオペラ芸術監督を務め、在任中に「ローエングリン」「ニーベルングの指環」などワーグナーの7つの作品を自ら指揮しました。
ワーグナー信奉者はワグネリアンと呼ばれ著名人のワグネリアンが多く存在しますが、作曲家でワグネリアンと言えばブルックナーが筆頭かもしれません。ワーグナーは歌劇・楽劇を多く残し交響曲は1曲のみ。政治力を持ち自信家で女性関係も激しかったのに対し、ブルックナーは交響曲と宗教曲が中心で、敬虔なクリスチャンで独身。正反対なのに、ブルックナーはワーグナーの音楽を愛していました。
ワーグナー最後のロマンティック・オペラ
「ローエングリン」はワーグナーの作品の中で最も人気のある曲の一つで、世継ぎである弟殺しの疑いをかけられたエルザを、白鳥の騎士が名前と素性を訊ねないことを条件に助けますが、結婚式後にエルザはその禁断の質問をしてしまい、騎士は去っていくという物語です。この作品の後、ワーグナーは「楽劇」という音楽と演劇が融合した概念を提唱しました。
今回はその中の特に有名な2曲を演奏します。第1幕への前奏曲は、透明感のある柔らかな曲。第3幕への前奏曲は、勇壮で華やかな曲。歌劇ではこの後に有名な結婚行進曲が合唱を伴って演奏されます。最後には登場人物のほとんどが死んでしまう悲劇ですが、音楽は美しく心にしみます。
ブルックナーの出世作~交響曲第7番
ブルックナーは劇場建設中のバイロイトに出向いてワーグナーを訪問し、交響曲第2番と第3番の総譜を見せ、興味を持ってもらえた第3番をワーグナーに献呈しました。ブルックナー自身が指揮した初演は失敗に終わり、その後の交響曲も初演後ほとんど再演されなかったのですが、第7番は大成功を収めヨーロッパ各地やニューヨークでも演奏され、ブルックナーの名声は広まりました。
第2楽章の執筆中にワーグナーが危篤となり、ワーグナーの葬送行進曲として書かれましたが、死の知らせを受けテューバ群の荘厳な響きで始まるコーダを付け足しました。この曲でブルックナーは初めてワーグナー・テューバを使用しました。ワーグナーが「ニーベルングの指環」のために開発し、テューバを中心とした新たな音色を持つ楽器群をホルン奏者が担当できるようにした物で、「指環」での使い方を踏襲し4本のワーグナー・テューバと通常のテューバで和音を奏でます。ブルックナー自身の葬儀の際も、このアダージョが金管アンサンブルに編曲され演奏されました。
どうぞお楽しみに! (H.O.)
チャイコフスキー: 交響曲第4番ヘ短調
チャイコフスキーは7つの交響曲(番号が付けられている6曲とマンフレッド交響曲)を作曲しているが、人気が高く、演奏頻度が高いのは後期の第4番、第5番、第6番「悲愴」の3曲である。
初期の第1番「冬の日の幻想」、第2番「小ロシア」、第3番「ポーランド」は、ロシア国民楽派の作品に近く、民族的な素材がふんだんに取込まれていることはその副題からも想像ができ、素朴で、比較的単純な仕上がりとなっている。これに対し第4番は、標題音楽的な印象を感じさせながらも高度な形式を取っており、交響曲作曲家としての評価を決定付けた大作である。
冒頭より強烈な序奏に始まり、いきなりこの曲の奥深い世界へ引き込まれてしまう。この序奏は「運命の動機」であり、楽章途中に「運命から逃れることはできない!」と言わんばかりに何度も登場する。この序奏によってはじまる第1楽章は烈しく、重苦しく、深い悲しみに満ち、それでいて力強い生命力が感じられる。第2楽章は寂しく、儚い。第3楽章は一転して軽快で、陽気である。そして第4楽章には猛烈な勢いがあり、勝利を勝ち得るかのような展開を見せる。しかし突如、運命の動機が再現されるが、すぐに運命を克服して盛大なラストを迎える。
曲の中には、烈しい感情的要素がふんだんに詰め込まれており、作曲者が異常な心理状態であったことが想像できる。ロシアの厳しく広大な自然環境をも彷彿とさせるが、この曲が書き上げられたのはヴェネツィアである。重厚なこの曲と、明るくて大らかなイタリアの水の都のイメージがどうしても一致しない。やはり彼の心理状態によるものが大きく影響しているのだろう。
当時のチャイコフスキーには、不幸と幸福の相反する2つの劇的な出来事が発生していた。不幸な出来事は、結婚と破局。交際3 ヶ月でスピード結婚したものの、翌月には破局を迎え、入水自殺を試みている。一命を取りとめたことは、我々にとっても本当に幸いであった。
幸福な出来事は、裕福なフォン・メック夫人からの高額な経済援助を得られたことである。生活のための教職から解き放たれ、作曲活動に専念できるようになったのは、この時期からである。ちなみにメック夫人とは、14年間も手紙を取り交わして心を通わせているが、1度も会う事はなかったようである。
そして手紙の中からは、本曲に対する作曲者の見解を見ることができる。私の拙い文章よりも、作曲者本人のことばを引用した方が曲の本質をご理解いただけるであろう。日本楽譜出版社のミニチュアスコアの解説にわかり易く書かれているので、翻訳部分に『 』を付けて引用させていただく。
第1楽章 Andante sostenuto(3/4拍子)-Moderato con anima(9/8拍子) ヘ短調、ソナタ形式
『序奏は全曲の本質である』『運命、絶大なる力、それは幸福を築こうとする意欲の全てを消失させるものである。圧倒的で、克服不可能な力であり、それにはただ服従するよりほかに仕方がなく、そして空しく悲嘆に暮れるばかりである』
『運命の力に対してだんだんと絶望的となり、夢のなか、忘却の彼方に逃避しようとする』
第2楽章 Andantino in modo di canzona(2/4拍子) 変ロ短調、3部形式
『夕闇の迫る頃、人が仕事に疲れて家のなかに一人で座っているときの憂鬱な心地。読もうとしていた本もいつしか手許から滑り落ち、数限りない回想がいろいろな形で甦ってくる』
第3楽章 Scherzo. Pizzicato ostinato-Allegro(2/4拍子)ヘ長調、複合3部形式
『これといって明確な感情はない。それは気紛れと陽気な戯れの連続で、全楽章を通じて弦のピツィカートがそれを表現する。相互になんの関連性もない空間的な映像が、ちょうど半ば眠っている人間の頭脳から出てくるように、種々の色合いで表われる。すなわち、酔った農夫、街の騒音、遠のく軍隊行進曲など』
第4楽章 Finale. Allegro con fuoco(4/4拍子) ヘ長調、(自由な)ロンド形式
『他の人々の幸福を喜ぶべし、しかして汝は生くることを得』
引用は、以上。
■譜例紹介
私はチェロ弾きであるので、チェロおよび低音楽器を中心に譜例を抽出した。
※譜例準備中
譜例1(第1楽章 序奏):
ホルンとファゴットにより始まる序奏は、すぐに金管全体へ、そしてオーケストラ全体へ拡大する。
序奏以降、第1楽章で7回、第4楽章終盤に再び登場する「運命の動機」である。
ファゴット譜より
譜例2(第1楽章 第1主題):
ヴァイオリンとチェロにより奏でられるが、譜面を見ないと何拍子かわかりにくい。不安定な心情を表しているものと思われる。
チェロ譜より
譜例3(第2楽章):
オーボエにより始められ、チェロに引き継がれる。その後は楽器を替えて楽章中にたびたび登場する。
チェロ譜より
譜例4(第3楽章):
弦楽器全員でのピツィカートにより演奏される。コントラバスは楽器が大きく弦が太いので、大変そうである。
コントラバス譜より
譜例5(第4楽章):
弦と木管全員が同じ動きで、大迫力の演奏をする。一糸乱れぬ演奏ができるかどうか。
チェロ譜とコントラバス譜より
■ 新交響楽団とロシア音楽、チャイコフスキーの人気度について
新交響楽団の誕生と発展に大きく関わった芥川也寸志氏は、ロシア音楽へ深く傾倒していた。新響62年の歴史の中で、前半30年は、芥川氏の影響が絶大であり、定期公演に於いても比較的ロシア音楽が多く取り上げられている。
1967年には、無謀にも(?)冷戦真っ只中にあったソヴィエト社会主義共和国連邦への演奏旅行を行ない、モスクワほかのご当地にて、チャイコフスキーの交響曲第5番を演奏している。
私の新響との出会いも、ロシア音楽であった。1983年の芥川指揮によるショスタコーヴィチ第5番を聴衆として聴いているが、この時の火の出るような熱い演奏は今でも記憶に残っており、その後の入団のきっかけとなった。
その後の新響は多くの指揮者の指導を受け、優秀な若手が加わり、レパートリーを広げ、大きく成長している。反面、昔の本能的で若々しい演奏に比べ、今は少し洗練された大人(?)の演奏へと変わりつつあると感じるが、ロシア音楽に対する芥川魂は、今の新響にも残っていると思う。
さて、ここでチャイコフスキーの人気度をご紹介したい。
「音楽の友」4月号に読者アンケートによる人気ランキング(各項目上位20位)の記事があったので引用する。
好きな作曲家では、2位。
好きな交響曲では、第5番が3位、第6番が7位、第4番は少し下がるが16位。
好きな協奏曲では、ピアノ協奏曲が2位、ヴァイオリン協奏曲が3位。
他にも管弦楽曲では4曲がランク・インしている。
以上のデータからも、人気の高さが窺える。
では新響での演奏頻度はどうか? 後半31年目にあたる1987年1月/第114回以降の定期公演での交響曲の演奏履歴を調べると次の通りである(カッコ内は指揮者/演奏年月)。
第4番:第187回(ヴィクトル・ティーツ/ 2004年10月)
第5番:第141回(石井眞木/ 1993年10月)、第214回(井㟢正浩/ 2011年7月)
第6番:第123回(本名徹二/ 1989年4月)、第167回(ヴィクトル・ティーツ/ 1999年4月)
マンフレッド:第129回(原田幸一郎/ 1990年11月)
なお第1~3番は62年間で1度も演奏されておらず、意外であった。
もっと演奏されても良いのでは? という気もするが、新響には10年ルールというものがあり、定期公演では同じ曲目を10年間は演奏しないという原則があるので、致し方ないだろう。
平均すると、5年に1度しか演奏されない計算となるので、本日の貴重な演奏機会を充分楽しむようにしたい。
ご参考までに、新響の作曲家別交響曲演奏回数ランキング(31年目以降)は次の通りである。
1位:マーラー[18回]※大地の歌を含む
2位:ベートーヴェン[11回]※依頼公演での「第九」演奏会を除く
3位:ブラームス[10回]
4位:ショスタコーヴィチ[8回]
5位:チャイコフスキー[7回]
※マンフレッドおよび、本日公演含む
最後に、日本オーケストラ連盟ニュースの特集に、「2016年度 定期演奏会演奏回数ランキング(正会員25楽団、交響曲以外含む)」が特集されているが、作曲家別でチャイコフスキーは4位である。新響の演奏頻度=5位は、世間的にも順当であろう。
初演: 1878年2月10日、ニコライ・ルビンシテイン指揮、ロシア交響楽協会モスクワ支部演奏会
楽器編成: フルート2、ピッコロ1、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボー
ン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、トライアングル、弦五部
参考文献
溝部国光(解説)『チャイコフスキー 交響曲第4番 ヘ短調』(ポケットスコア)日本楽譜出版社 2004年
『音楽の友』2018年4月号 音楽之友社 2018年
日本オーケストラ連盟ニュース『36 ORCHESTRAS Vol. 98』日本オーケストラ連盟 2018年
チャイコフスキー: ヴァイオリン協奏曲ニ長調
■チャイコフスキーの生涯
チャイコフスキーは作曲家としては意外な経歴を持っているかもしれない。役人から転身、ペテルブルク音楽院卒業から突然の死までの短い作曲家人生のなかで、彼は交響曲、協奏曲、室内楽、バレエに歌劇…あらゆるジャンルで名曲を残した。
有名曲の多さでは古今の作曲家の中でも指折りの大作曲家であり、クラシック音楽に馴染みのない者
でも耳にしたことのあるメロディが多いだろう。
チャイコフスキーの生み出すあのロマンチックで甘美な旋律は、人々の感情を揺さぶり訴えかけてくるが、それゆえお涙頂戴で面白くないというクラシック愛好者も多い。
しかし、チャイコフスキーの人生を知ると、小心者で不器用な人間チャイコフスキーが、正直に人間臭さを見せながらも、英知により作り上げた傑作たちの姿が見えてくる。
■音楽家への転身まで
幼い頃より音楽に触れるが、当時のロシアは音楽家への理解が少ない時代。6歳の頃には数カ国語をマスターするなど聡明であったチャイコフスキーは10歳で法律学校へ入学し、官僚への道を歩む。しかし音楽への興味は深く、当時グリンカのオペラ「イヴァン・スサーニン」の上演を聴いて感銘を受け、友人への手紙で「やがて私は音楽家になるような気がする」と告げていたという。卒業後、役人の仕事に就くも馴染めず鬱々としていたとき、新しく創設された音楽院のことを知り、たまらず門を叩いたのであった。政治や宗教への見識も広く知識人でもあった彼が、音楽院で学び、ロシア5人組などさまざまな人間との交友を得ていった。卒業後はモスクワ音楽院に教師として就任、その年に交響曲第1番「冬の日の幻想」を完成させるなど、本格的に音楽家としての歩みを始めた。
■激動の狭間で
今宵の演目でもある名曲、交響曲第4番やヴァイオリン協奏曲は、チャイコフスキーにとって激動の時期に生まれた。この頃、2人の女性との出会いがある。
1人目は、彼の作曲家人生を語る上で外せない人物。チャイコフスキーの楽曲に感銘を受け、支援を申し出た未亡人、メック夫人である。1876年、彼が36歳の時であった。
また、翌年にはつかの間の妻となったアントニナという女性と結婚。しかし、結婚生活は彼にとって全然合わないものであり、チャイコフスキーは絶望の淵、ついにはモスクワ川に投身自殺を思い立つまでだった。
メック夫人からの援助によって経済的余裕ができた彼は教授としての仕事も辞め、結婚生活から逃れるべく旅に出る。チャイコフスキーは作曲に専念し、旅の最中に受けた刺激を最高の音楽に昇華させた。オペラ「エフゲニー・オネーギン」、交響曲第4番を完成させ、そしてすぐ続けて生み出したのが、ヴァイオリン協奏曲である。
こうしてチャイコフスキーの活動は一気に飛躍していった。華々しい作曲家人生のように見えるが、チャイコフスキー自身は実に繊細で、孤独を愛していた。同性愛者であったらしいという話も最近ではよく知られている。晩年、メック夫人から援助の打ち切り通告があったが、彼女とは14年間に渡り手紙だけのプラトニック・ラブを貫いたともいわれ、生涯会うことはなかった。メック夫人との手紙は700通以上にわたり、チャイコフスキーを知る上で重要な資料ともなっている。
1893年53歳で交響曲第6番「悲愴」を書き上げた後も彼はなお作曲への意欲をみせていたが、不慮の死により生涯に幕を閉じた。
■ヴァイオリン協奏曲
数あるヴァイオリン協奏曲の中でも、チャイコフスキーらしいその堂々たる風格と哀愁に満ちた抒情的な旋律が存分に溢れるこの作品は、あらゆるヴァイオリニストが名演を残してきた。ヴァイオリン弾きとして、演奏の喜びが溢れんばかりにこみ上げてくる名曲であるが、最初の評価はそうでもなかったようである。
チャイコフスキーが結婚生活から逃れ、ジュネーヴ湖畔のクラランにいたとき、作曲上の弟子であり、親しいヴァイオリニストでもあるコーテクがラロのスペイン協奏曲の楽譜を持ってくる。チャイコフスキーはこの曲に感銘を受け、創作中のピアノソナタを中断してヴァイオリン協奏曲を書き始めたという。そして着想からわずか11日でスケッチを終え、コーテクの意見を聞きながら作曲を進め、1ヶ月たらずで総譜を仕上げた。
当時、ヴァイオリンの第一人者とされていたレオポルト・アウアーのもとに初演を依頼すべくこの曲を持っていくが、演奏不能と切り捨てられてしまう。そこへアドルフ・ブロツキーというヴァイオリニストが手を差し伸べることになる。彼による初演もかなりの酷評で、チャイコフスキーはかなりショックを受けるが、ブロツキーは当初よりこの曲の真価を見出しており、以降もこの曲を何度も取り上げて演奏した。後にアウアーも演奏するようになったという。こうして今でも愛されるヴァイオリン協奏曲としての名声を確立していくこととなった。
※譜例準備中
第1楽章 Allegro moderato – Moderato assai ニ長調
第1ヴァイオリンによる穏やかな序奏で始まり、tuttiがこたえる(譜例1)。
音楽がじわじわと動き出し、弦と木管が対話をしながら高揚し、再びオーケストラが静まったところに独奏のメロディが奏でられる(譜例2)。
この冒頭のカデンツァ風の5小節は、ヴァイオリンの高低音域が惜しみなく使われ、これから始まる華やかな協奏曲に期待を抱かせる。情感溢れる主題やカデンツァが盛り込まれた第1楽章では、ヴァイオリンのさまざまな表情が存分に堪能できることだろう。
第2楽章 Canzonetta. Andante ト短調
ふつふつと感情が見え隠れするような、もの哀しく、哀愁にみちた主題(譜例3)と、対してあたたかみをもった、明るく、感情の起伏が豊かな主題(譜例4)。交互に現れるこの2つの主題を、ヴァイオリンが豊かに歌いあげる。
クラリネットが再び2楽章冒頭の旋律を示した後、切れ目なくフィナーレへと続いていく。
第3楽章 Finale. Allegro vivacissimo ニ長調
民族舞踊の躍動感や華やかなテクニックを楽しめる最終楽章。突如始まるオーケストラが躍動を示すと、ヴァイオリンは堂々たるソロで応えた後、飛び跳ね踊るようなトレパーク風のリズムで駆け出してゆく(譜例5 第1主題)。
やがて、これもまたロシアの舞曲風であるが、ゆったりとした第2主題が現れる(譜例6)。作曲の動機となったラロのスペイン協奏曲からの影響も大きく、民族的な表現や演奏効果に重きをおいて作曲をしたようである。
2つの主題は絡み合いながら進展し、最後は第1主題をもとにエネルギッシュな盛り上がりを見せ、華やかに終わる。
初演: 1881年11月22日、ハンス・リヒター指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団、アドルフ・ブロツキー独奏
楽器編成: フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦五部
参考文献
伊藤恵子『作曲家◎人と作品シリーズチャイコフスキー』音楽之友社 2005年
『作曲家別名曲解説ライブラリー チャイコフスキー』音楽之友社 1993年
園部四郎『チャイコフスキー 生涯と作品』音楽之友社 1960年
グラズノフ:演奏会用ワルツ第1番
第242回演奏会の幕開けを飾るのは、グラズノフの小品である。軽やかで優美なこの佳曲は、チャイコフスキーの名曲をお届けする前にふさわしい前菜となるだろう。
■グラズノフの半生
グラズノフは1865年にサンクトペテルブルクで生まれた。父は出版業を営み、母はピアニストであった。彼は10歳からピアノを学び、11歳で作曲を始める。優れた聴覚と記憶力に恵まれた、才気あふれる少年であった。
1879年にバラキレフと出会い、作曲を師事。バラキレフは「ロシア五人組」の指導者的役割を果たした人物で、グラズノフの早熟な才能を見抜き、彼をリムスキー=コルサコフに紹介した。
グラズノフは2年間、リムスキー=コルサコフから和声と作曲の技法を教わり、弦楽四重奏曲と交響曲をそれぞれ1曲ずつ完成させる。交響曲第1番を作曲したのは弱冠16歳のとき。バラキレフが指揮を務めた初演は大成功を収めた。
若くして注目の的となったグラズノフは、豪商のベリャーエフというパトロンを得る。ベリャーエフはグラズノフの熱烈なファンとなり、彼の作品を優先的に演奏させるために交響曲演奏会を発足させたり、彼の作品を出版するためにライプツィヒにベリャーエフ出版社を設立したりした。この出版社を通して彼の作品は西欧でも知られるようになる。
1890年代には、交響曲第3番から第5番の3曲、弦楽四重奏曲を2曲、そしてバレエ「四季」「ライモンダ」を作曲する。創作意欲が盛んなこの時期に、本日演奏する「演奏会用ワルツ第1番」も書かれた。作曲されたのは1893年、彼が28歳の時であり、この曲は母エレーヌ・グラズノフに捧げられている。
その後、グラズノフは1899年にサンクトペテルブルク音楽院の教授となり、さらに1905年には院長を務めた。
彼は、殊にバレエ音楽について、ロシアで最も優れた作曲家としてチャイコフスキーに次ぐ地位を確立している。
■演奏会用ワルツ第1番について ※譜例準備中
グラズノフはワルツの名手である。彼の3つのバレエ曲「ライモンダ」「四季」「愛のはかり事」には多くの優美なワルツがある。
「演奏会用ワルツ第1番」はあくまでも踊りのためではないワルツとして作曲された。(注)翌年には、第2番も作曲されている。ゆったりと美しい旋律が曲を導いていくのが特長だろう。
この曲は複合三部形式で、序奏とコーダが付いている。主部のテーマはヴィオラとクラリネットの優しい音色で提示される。
ひとしきり歌いあげたところで、続けて木管楽器主体の悲哀を帯びた旋律が引き継ぐ。しっとりとした一抹の不安の告白からぬけだし、冒頭のテーマに戻ってくる。
フルートが誘う中間部では、主部とは対照的な形のテーマが提示される。大きな3拍子でゆっくりと下降した後、気持ちがこみ上げるように駆け上がる。
このテーマの盛り上がりがはじけると、寂寥(せきりょう)感漂うクラリネットのデュオがはじまる。そして、ヴァイオリンやフルートがそれを受け継ぎ、また明るい中間部のテーマへ回帰。
再度主部のテーマに戻り、中間部のテーマの変形やヴァイオリンの軽快なモチーフが相まってコーダに突入。コーダは活気にあふれ大団円を迎える。
「演奏会用ワルツ第1番」は、チャイコフスキーからロシアバレエ音楽の系譜を受け継いだグラズノフが残した佳曲のうちの1つである。色彩溢れる夢うつつの世界を、堪能していただければ幸いである。
(注)この曲は「演奏会用」ワルツであるが、後世バレエ作品に引用されている。1956年に振付師のフレデリック・アシュトンがグラズノフの作品を組み合わせて「誕生日の贈り物(Birthday Offering)」という一幕もののバレエ作品を作ったが、その際に、この曲が採用されている。バレエに馴染み深い方はどこかで聞いたことがあるかもしれない。
初演: 1893年12月、サンクトペテルブルク、リムスキー=コルサコフ指揮
楽器編成: ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット3、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、シンバル、大太鼓、小太鼓、トライアングル、グロッケンシュピール、ハープ、弦五部
参考文献
ジェームズ・バクスト(森田稔訳)『ロシア・ソヴィエト音楽史』音楽之友社 1971年
柴田南雄/遠山一行総監修『ニューグローヴ世界音楽大事典』講談社 1994年
音楽之友社編『名曲ガイド・シリーズ③管弦楽曲①』音楽之友社 1984年
「楽曲視聴 NHK交響楽団」
https://www.nhkso.or.jp/library/sampleclip/music_box.php?id=93&iframe=true&width=840
(2018年6月1日アクセス)
『部屋と食パンと編集長』
編集長は今晩の夜ごはんをコンビニで買った。
この時期、手に取るのはいつも食パンだ。たまにシシャモを買うこともある。コンビニの店員さん達にはもう顔を覚えられて、「いつもありがとうございます」と釣り銭を渡された。
つい1時間前までは会社員として、ミスを起こさないよう細心の注意を払い、鬼の形相で業務を実施していた。泥臭く電卓を叩き、数字を合わせる。
華麗なる退社後、編集長は電車でスマートフォンを取り出し、受信メールをチェックする。
職場ではスマートフォンを見られないので、この瞬間はちょっとドキドキする。
とはいえ仕事後なので自分のキャパシティの残りは限られている。
(『行列が出来る編集長』だな。行列が出来るのは私の脳内にだけど。)と、くだらない言葉を閃いたがそれを打ち消し、今晩のプログラム編集の実施事項を確認する。
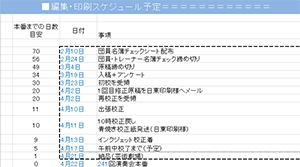
食パンを携えて自宅に帰る。
食卓の椅子に座ってしまうともう立ち上がれないことは実証済なので、部屋の電気と、パソコンに電源を直ぐに入れる。「…ヴーム…」と重厚な雰囲気を発しながらパソコンが起動した。
「中途半端な演奏会プログラムは作らない。それが新響プログラム編集の流儀だ。」と直接聞いたことはないが、自分が一般の客として新響の定期演奏会で手にした演奏会プログラムは衝撃の充実度であった。 その後新響に入団し、自分がプログラム編集を担当し4年になる。編集長を担当するのは編集チームの中で持ち回りだ。
パソコンが起動した瞬間、腕…ではなく胃袋が鳴った。
プログラムの曲目解説執筆者の方から、お伺い事項に対してのお返事メールが来ていた。
部屋には誰もいないのに、編集長は「ありがとうございます!」と独り言を言い、頭を下げた。
プログラム編集の実施内容は、演奏会本番までにプログラムが完成するようにスケジュールを決めるところから始まる。日数を逆算し、受領原稿の締め切り日や外部の印刷会社に原稿を提出する期日などを決定する。間に合うか、間に合わないか、ギリギリになると自分の首が絞まるので、穏やかな自分らしさを保てるように自問しながら決める。
そして今回のページレイアウト案を考え、表紙に曲名を入力する。ここまでは序奏である。
最初の盛り上がりが、曲目解説執筆者を募るところである。
曲目解説執筆者は、自ら曲目を書いても良いと立候補して下さる方もいらっしゃるが、プログラム編集委員から、曲目解説を書いて頂きたい方にお願いする場合もある。もし、書いてくれる方がいなかったら、プログラム委員が自ら書かなくてはならない。
いたいけなプログラム編集委員のメンバーが3人くらいで壁ドンしそうな勢いで、「曲目解説を書いてもらえませんか」とお願いする様子は、もう新響の風物詩と言っても良い。
とはいえプログラム編集委員も人の子なので、声を掛ける人にも仕事や家族がいることを忘れていないし、有り体に言えば(執筆をお願いされたら迷惑かな~、すごい嫌われたらどうしよう。)と震えながら、ありったけの勇気を出して声をかけている。
快く曲目解説の執筆を引き受けて下さる方は、本当に救いの神様のような存在である。
プログラム編集委員にとっての神様的存在の方は他にもいらっしゃる。
団内のプロの著作業の方には毎回校閲をして頂いてとても助かっている。
また、ドイツ語のプロの専門家の方にはアドバイスを頂くことや詩の対訳をお願いすることもある。フランス語に造形が深い方からはフランス語の綴りのアクサンテギュの記号等もご確認頂くこともあり、新響は無比の人材がいらっしゃる。
曲目解説執筆者が決定したら、原稿提出期限や執筆留意事項などを、執筆者を含め広くプログラム作成関係者に電子メールで送付するほか、外部の印刷会社には当団の編集スケジュールを送付する。
また、プログラムに掲載する『団員名簿作成チェックシート』を直近の内容に修正し、シーズンの最初の全体練習でパートごとに配布。団員全員にお名前や所属している勤務地や学校名、運営委員の該当有無、正団員該当、賛助等をチェックして頂く。2週間後、回収したチェックシートをもとに、掲載用団員名簿に最新内容を反映させる。
真夜中の編集長は食パンをトーストせずに貪り、パソコンデスクの前の椅子に座り、曲目解説の執筆者から提出して頂いた原稿を確認し、レイアウト用フォーマットに落とし込む。
執筆者から原稿を受領した瞬間はとても嬉しい。自分が最初の読者になれるのは編集長ならではのやりがいである。
原稿内容の数字を半角や全角に統一し、誤字脱字、改行の位置、楽器編成、参考文献の初版、著者等をインターネットで調べる。細々とした決まり事も委員内で共有されているので、それらを一つずつ確認していく。
校閲をして頂いている方や点字プログラム担当委員に原稿内容を送付し、言い回しやプログラム内の整合性などもアドバイスを頂く。
そして校閲して頂いた意見を原稿執筆者に確認して頂いて、編集を進めていく。編集長自ら原稿の写真を集めることもある。
前述した掲載団員名簿を常に最新状態にするよう、新入団員や退団者の情報を団内人事担当に確認したり、新たに団内の運営に携わることになった方の情報をキャッチする。
編集長は出来れば6時間は眠りたいので、関係者から受領した質問について返信の電子メールを作成し、内容に失礼の無いように見返した後で夜12時までに送信し、パソコンの電源を落とした。
編集チームに入った時は編集のイロハのイも知らなかったが、優しいプログラムマネージャーに逐一編集技術を教えて頂きながら編集経験を積むことが出来た。
また凄腕編集技術をお持ちの先輩がいらっしゃり、指揮者の先生のエッセイを頂く際に、先輩に手書き原稿をWordに文字起こしして頂いた時に、先生に確認された内容が素晴らしかったので、先生から「新響には出版社の方がいるのですか?」と聞かれたことがあった。
指揮者の先生のエッセイがある場合の編集の流れは、シーズンの初めに運営委員長経由で先生に執筆をご依頼し、先生の手書き原稿をFAXで受領後に、Wordで原稿を入力し(以下「原稿おこし」と呼ぶ)、その原稿を先生にご確認頂く。
団内でも内容を確認しつつ、並行し先生から修正箇所を手書き原稿で頂いたものをWordファイルに修正、再度先生に見て頂く。タイミングによっては先生練習の際に楽屋にお持ちし原稿をご確認頂くこともある。
先生から、原稿に載せる写真を手交でお借りした時、ふんわりとパフュームが漂ってきてドキンとした。
原稿の了を頂いたら、曲目解説原稿と同様の編集作業に進む。
一連の原稿確認が終了したら、プログラムのレイアウト案を外部の印刷会社に電子メールで送付する。数日後、印刷会社から初校が届くので、内容を確認し、再修正の期日とともに関係者に連絡する。新響の内部ウェブサイトにも掲載し、プログラム委員以外の団員にも確認頂く。先生のエッセイがある場合も、ここで先生に初校を見て頂く。
各方面から連絡を頂いた内容を、編集長が初校に赤ペンで手書き記入しPDF化して関係者に送付。期日になったら、印刷会社に送付する。そして数日後に再校を受領、内容確認の上関係者に連絡し、OKになったら最終の原稿を印刷会社に提出。翌日最終稿を受領する。
演奏会の10日前位に、印刷会社にお邪魔して出張校正を行う。関係者で原稿の最終チェックを行うものである。平日の夜に仕事帰りの社会人が集う。集中して原稿内容の確認を出張校正参加者全員で行い、この場でも修正点が挙がる。
編集チームのきっちりとしているメンバーはいつも相互で助け合っている。
出張校正で出た修正点を、赤ペンで手書き記入しPDF化して関係者に送付する。
翌日、印刷会社から郵送で最終原稿を受領、修正点が反映されているか確認し、問題なければ校了となり印刷会社に必要部数を印刷依頼する。
演奏会当日、出来上がったプログラムを手に取った時には嬉しい。
駆け出しの頃の編集長は、関係者とのやり取りや調整で失敗して、「おい編集長なんてことだ!」的なお怒りのメールを真夜中に受信し、スマートフォンが手動で振動し、身体が文字通り飛び上がったことがある。
駅構内で1時間立ち尽しながら返信をしたこともあるし、翌日の仕事の昼休みには先輩方とのランチを抜け出して、外の店で返信をしたこともあった。
積み重ねた合計が身長分ほどの涙の食パンを食べたら、歴代の凄腕編集長に近づけるのだろうか。
「金では買えない経験だ。」と呟き、今日も編集長はよく練られた食パンを平らげた。
音が出る!画が動く! クラリネット紹介
楽器紹介シリーズ 今回はクラリネットです。
オーケストラの管楽器の中でもかなりポピュラーな楽器で吹いたことのある方も多いと思います。
ここでは、クラリネットに関するとりとめのない話のあとに、オーケストラ曲の中でクラリネットが目立つ箇所をスマートフォンですぐに試聴できるようにYouTubeのリンクをQRコードにして列挙しますのでスマートフォンのカメラで写してリンク先に飛んで映像と音をお楽しみください。
(ホームページではURLをクリックしてください。)
話題1.いろいろなクラリネット
音域が広いのがクラリネットの特徴の一つで、普通のソプラノクラリネットで4オクターブ弱の音域があります。また、短いものから長いものまで多くの種類があり、通常ルート(楽器屋さん)で入手可能なものだけでも小さい順にソプラニーノクラリネットとしてAs管、Es管、D管の三種類、ソプラノクラリネットとしてC管、B管、A管の三種類、分類総称なしでG管、バセットホルン(F管)、アルトクラリネットEs管、バスクラリネットB管、コントラアルトクラリネットはEs管、コントラバスクラリネットはB管があります。そのうちオーケストラで頻繁に使用されるものにアンダーラインを引きました。
一方、斜体で示したものはオーケストラではまず使用されないものです。これらのうちいくつかを並べて撮影したのが右の写真です。左からソプラニーノEs管、ソプラノB管、ソプラノA管、バセットホルン(F管)、バスクラリネット(B管)です。クラリネットはマウスピースにリードを取り付けてそれを振動させて音を出します。楽器の大きさに応じてリードの大きさも違います。

話題2.絶対音感はクラリネット奏者にとっては邪魔?!
先ほどB管、A管、Es管などと書いていたのはどういう意味かというと、楽譜のドにあたる音を吹いたとき(指使いの表にある“ド”の音の運指で吹いたとき)に実際に出る音名を表しています。シのフラット(ドイツ音名でB(ベー))が出る楽器がB管、ラ(ドイツ音名でA(アー))が出る楽器がA管というわけです。同じ指使いでも楽器によって違う音が出る、これがすなわち移調楽器です。指使いを一種類だけ覚えればこれだけの種類の楽器が吹けてしまうのでとても便利です。
さて、オーケストラの曲ではこれらの楽器の持ち替えを頻繁にやらねばなりません。たとえば次に挙げた譜面はブラームスの交響曲第3番1楽章の冒頭です。最初in BとあるのはB管で吹けということです。つまり最初の音は、譜面上はレですが実際はドの音を出すことになるわけです。これだけでも絶対音感のある人は気持ち悪いそうですが、さらに4段目の真ん中にmutano in Aとあります。これは、ここでA管に持ち替えろという指示です。持ち替えた直後の最初の音は譜面上ソなのでB管のままで吹くとファになりますがA管に持ち替えているのでその半音下のミを出すことが要求されていることになります。書いてある音符と違う音がでる。それも頻繁に変わってしまう。オーケストラのクラリネット奏者はこれに耐えなければなりません。絶対音感がある人は音符を見てその絶対的な音の高さが頭に浮かびますが、この能力を持っていても封印しないと気持ち悪くてやっていられません(たぶん)。実際、しっかりした絶対音感があって中学の吹奏楽部でクラリネットを始めた人が、大学でオーケストラに入りB管だけでなくA管も吹けと言われて耐えられなくて辞めたり、A管を拒否してすべての譜面をB管一本で吹きこなしたりした人がいました。楽器の持ち替えは作曲家が楽譜に指示しています。だいたいはA管とB管の持ち替えなのでシャープ系の曲はA管、フラット系の曲はB管というように調子記号(五線譜の一番左についているシャープ♯やフラット♭)が少なくなるようになっていますが、マーラーの交響曲などではたまに逆に調子記号が増えたり、あり得ない短時間で持ち替えたりしなくてはならないような、いじめのような楽譜もあります。ステージ上でクラリネット奏者があわてて楽器を持ち替えていたらそういうことだと思ってください。

“音が出る!画が動く!”その1:クラリネットとオーボエを聴き分けよう
こんなことを書くと「両者の違いが判らないことなんかないだろう」と思う方がほとんどかもしれませんが、以前こんなことがありました。あるロシアの作曲家の60分近くかかる交響曲でクラリネットが嫋々と長大なソロを吹く曲を新響で演奏したときのこと、コンサート終了後あるお客様がご自分のブログでその曲に対する薀蓄もとりまぜながら、読み応えのある文章で演奏の感想を述べられていました。そこに“オーボエのソロが云々”という記述があったのですが、どう考えても前後の文脈からそれはクラリネットのソロのことなのです。それを見たとき結構ガッカリしたものです。
でも、「そんなものかな?木管楽器に詳しくない方には結局、“本体が黒くて金具がごちゃごちゃついている縦に吹く楽器”くらいの認識なのかもしれない。」と納得したものです。そんなわけで、“音が出る!画が動く!”の第一弾は、木管楽器の聴き比べです。以下に挙げるのは、フルート→オーボエ→クラリネットとソロがリレーされる、木管楽器の聴き比べにはうってつけの曲、レスピーギのローマの噴水の第一曲です。本年1月の第240回のコンサートでも取り上げたので覚えておいでの方も多いと思います。下のQRコードを読み込むとこの動画の開始後4分3秒が頭出しされます。さっそくフルートのソロの始まりです。そのあとオーボエそしてクラリネットです。音色の違いをお楽しみ下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=vkp_GpVUvvY&feature=youtu.be#t=4m03s
“音が出る!画が動く!”その2:クラリネットが活躍する曲
ここからは、独断と偏見で選ぶクラリネット名ソロ集です。紙面も限られているので曲の解説は省略し、その雰囲気を一言であらわしてみました。おおよそ年代順に並んでいます。お聴きになられれば、さまざまなキャラクターを吹き分けられる、表現の幅がとても広い楽器だということがお分かりになっていただけるのではないでしょうか。
(1)素朴・純粋:モーツァルト/交響曲第39番第三楽章の中間部
なんとシンプルなメロディーでしょう。
https://www.youtube.com/watch?v=QsSulfTeGrM#t=2m5s
(2)平和・自然:ベートーヴェン/交響曲第6番「田園」第二楽章の中間部
吹いていて気持ちいいです。
https://www.youtube.com/watch?v=7_t9m2YZa0s#t=5m39s
(3)典雅・跳躍:ベートーヴェン/交響曲第8番第三楽章の中間部
ピアニッシモの高いF(ファ)で終わるのが難しい!
https://www.youtube.com/watch?v=Cg-pJBieZzk#t=0m18s
(4)阿鼻叫喚:ベルリオーズ/幻想交響曲第五楽章
ソプラノクラリネットC管のソロの後、Es管のソロが続きます。
https://www.youtube.com/watch?v=iKOCo9JgrT8#t=1m29s
(5)安寧・平穏:ブラームス/交響曲第3番第二楽章
二番クラリネットと二本のファゴットに伴奏されてのソロ。
https://www.youtube.com/watch?v=vCnSjMrEGCE
(6)躍動・舞踏:リムスキー=コルサコフ/スペイン奇想曲
吹奏楽でもよく演奏されます。
https://www.youtube.com/watch?v=vLOVVzmEnto#t=0m45s
(7)甘美・陶酔:ラフマニノフ/交響曲第2番第三楽章冒頭から
極甘ロマンティック!
https://www.youtube.com/watch?v=Qf1ZChhsl3E
(8)民謡・哀愁:コダーイ/ガランタ舞曲
長大なソロが二か所あります。ほとんどクラリネット協奏曲。
https://www.youtube.com/watch?v=iPJZNrNtHpM#t=1m9s
https://www.youtube.com/watch?v=iPJZNrNtHpM#t=14m16s
(9)即興・粋:ガーシュイン/ラプソディーインブルー冒頭から
特殊奏法(グリッサンド)のソロです。
https://www.youtube.com/watch?v=ss2GFGMu198
(10)扇情・淫靡:バルトーク/バレエ音楽 中国の不思議な役人
この曲の抜粋を、中学や高校の強い吹奏楽団がときどき演奏しますが、このバレエの場面はR18(?)指定です。
https://www.youtube.com/watch?v=PpYMNBGWjaM#t=3m22s
(11)抑圧・憂鬱:ショスタコーヴィチ/交響曲第10番第一楽章
20世紀最高の交響曲の一つ。
https://www.youtube.com/watch?v=XKXQzs6Y5BY#t=3m36s
第242回ローテーション
| 演奏会用ワルツ | Vn協奏曲 | 交響曲第4番 | |
| フルート1st | 兼子 | 吉田 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 新井 | 岡田 |
| 3rd(Picc) | 岡田 | - | 兼子 |
| オーボエ1st | 岩城 | 山口 | 平戸 |
| 2nd | - | 岩城 | 宮内 |
| C.I. | 堀内 | - | - |
| クラリネット1st | 末村 | 品田 | 中島 |
| 2nd | 大藪 | 進藤 | 大藪 |
| 3rd | 石綿 | - | - |
| ファゴット1st | 藤原 | 藤原 | 田川 |
| 2nd | 田川 | 浦 | 浦 |
| ホルン1st | 大原 | 山口 | 大内(宮坂) |
| 2nd | 宮坂 | 宮坂 | 市川 |
| 3rd | 山口 | 大原 | 山口 |
| 4th | 市川 | 市川 | 大原 |
| トランペット1st | 北村 | 野崎 | 小出(北村) |
| 2nd | 中川 | 青木 | 倉田(中川) |
| トロンボーン1st | 武田香 | - | 武田香 |
| 2nd | 志村 | - | 志村 |
| 3rd | 岡田 | - | 岡田 |
| テューバ | - | - | 土田 |
| ティンパニ | 古関 | 古関 | 桑形 |
| パーカッション | シンバル付大太鼓/桑形 小太鼓/今尾 グロッケンシュピール/簑輪* トライアングル/古関香* |
- | 大太鼓/簑輪* シンバル/今尾 トライアングル/古関 |
| ハープ | 見尾田* | - | - |
| 1stヴァイオリン | 堀内(内田智) | 堀内(内田智) | 堀内(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 中島(田川) | 中島(田川) | 中島(庄司) |
| ヴィオラ | 村原(柳澤) | 村原(柳澤) | 柳澤(村原) |
| チェロ | 柳部(安藤) | 柳部(安藤) | 柳部(安田俊) |
| コントラバス | 中野(郷野) | 中野(郷野) | 中野(郷野) |
*はエキストラ
管()はアシスタント、弦()はトップサイド
第242回演奏会のご案内
偉大なメロディメーカー チャイコフスキー
チャイコフスキーはクラシック音楽の中でも、最も愛されている作曲家の一人といってもよいでしょう。メロディーは甘美で叙情的、オーケストレーションは壮大で華やか。クラシック音楽にあまり詳しくない方でも、聴いたことのあるチャイコフスキーの曲は多いはずです。今回は、チャイコフスキーの3大交響曲の一つ交響曲第4番と、4大ヴァイオリン協奏曲の一つと称される彼の協奏曲を取り上げます。
チャイコフスキーにとっての「1877年」
チャイコフスキーは1840年生まれのロシアの作曲家です。法律を学び法務省に勤めていましたが、22歳のときペテルブルク音楽院が創立したのを機に作曲の勉強に専念します。53歳でコレラにより急死するまでの約30年の作曲家人生の中でも、交響曲第4番を作曲した1877年前後は名曲ぞろいです。同じ年にバレエ「白鳥の湖」、オペラ「エフゲニー・オネーギン」が完成し、翌年にはヴァイオリン協奏曲を作曲しました。
この年にチャイコフスキーの身に何があったかというと、まず一つはメック夫人という富豪から多額の資金援助を受けるようになり、教職を辞め作曲に専念できるようになったこと。メック夫人とは一度も会うことはなかったが、亡くなる数年前まで資金援助と書簡での交流は続き、交響曲第4番は彼女に捧げられています。それから、ヴァイオリン奏者のコーテクという青年と出会ったこと。チャイコフスキーは同性愛者でコーテクは愛人であったと言われていますが、彼のヴァイオリン協奏曲の作曲にはコーテクが関わっていました。そして電撃結婚。元教え子アントニーナにラブレターをもらい、宿命と感じたチャイコフスキーは翌月には婚約、挙式をしましたが、同居生活に耐えられず自殺を図った末に結婚は破綻しました。
人の心に語りかけるチャイコフスキーの音楽
交響曲第4番は、「宿命」の動機といわれる印象的なファンファーレで始まり、人生の幸福と苦悩、楽しさと辛さ、懐かしさと諦めが散りばめられた「言葉のないオペラ」のようです。チャイコフスキー自身の経験が、作品を飛躍させたのでしょう。
指揮の山下一史氏は円熟期にさしかかり、我々団員もそれぞれの人生をいろいろな想いで過ごしてきて、今の新響だからこそ表現できるチャイコフスキーの第4番を、大切に演奏したいと考えています。
ヴァイオリン協奏曲は、結婚の失敗から心を病みスイスのレマン湖畔を訪れていたときに書かれた作品。当時のペテルブルグ音楽院教授のヴァイオリンの名手に「演奏不能」と拒否されたことで、技巧的な面がクローズアップされがちですが、美しく躍動的で、洗練された中にもロシアの民族的な顔をのぞかせ、オケとの対話も魅力的な名曲です。
今回ソリストはニューヨーク在住の松山冴花氏。新響はブラームス、ベートーヴェンの協奏曲を共に演奏してきましたが、さらに深みのある演奏を期待しています。
民族的な作風でチャイコフスキーの後継者ともいわれたグラズノフの美しい小品とともにお楽しみください。 (H.O.)
第242回演奏会のご案内
偉大なメロディメーカー チャイコフスキー
チャイコフスキーはクラシック音楽の中でも、最も愛されている作曲家の一人といってもよいでしょう。メロディーは甘美で叙情的、オーケストレーションは壮大で華やか。クラシック音楽にあまり詳しくない方でも、聴いたことのあるチャイコフスキーの曲は多いはずです。今回は、チャイコフスキーの3大交響曲の一つ交響曲第4番と、4大ヴァイオリン協奏曲の一つと称される彼の協奏曲を取り上げます。
チャイコフスキーにとっての「1877年」
チャイコフスキーは1840年生まれのロシアの作曲家です。法律を学び法務省に勤めていましたが、22歳のときペテルブルク音楽院が創立したのを機に作曲の勉強に専念します。53歳でコレラにより急死するまでの約30年の作曲家人生の中でも、交響曲第4番を作曲した1877年前後は名曲ぞろいです。同じ年にバレエ「白鳥の湖」、オペラ「エフゲニー・オネーギン」が完成し、翌年にはヴァイオリン協奏曲を作曲しました。
この年にチャイコフスキーの身に何があったかというと、まず一つはメック夫人という富豪から多額の資金援助を受けるようになり、教職を辞め作曲に専念できるようになったこと。メック夫人とは一度も会うことはなかったが、亡くなる数年前まで資金援助と書簡での交流は続き、交響曲第4番は彼女に捧げられています。それから、ヴァイオリン奏者のコーテクという青年と出会ったこと。チャイコフスキーは同性愛者でコーテクは愛人であったと言われていますが、彼のヴァイオリン協奏曲の作曲にはコーテクが関わっていました。そして電撃結婚。元教え子アントニーナにラブレターをもらい、宿命と感じたチャイコフスキーは翌月には婚約、挙式をしましたが、同居生活に耐えられず自殺を図った末に結婚は破綻しました。
人の心に語りかけるチャイコフスキーの音楽
交響曲第4番は、「宿命」の動機といわれる印象的なファンファーレで始まり、人生の幸福と苦悩、楽しさと辛さ、懐かしさと諦めが散りばめられた「言葉のないオペラ」のようです。チャイコフスキー自身の経験が、作品を飛躍させたのでしょう。
指揮の山下一史氏は円熟期にさしかかり、我々団員もそれぞれの人生をいろいろな想いで過ごしてきて、今の新響だからこそ表現できるチャイコフスキーの第4番を、大切に演奏したいと考えています。
ヴァイオリン協奏曲は、結婚の失敗から心を病みスイスのレマン湖畔を訪れていたときに書かれた作品。当時のペテルブルグ音楽院教授のヴァイオリンの名手に「演奏不能」と拒否されたことで、技巧的な面がクローズアップされがちですが、美しく躍動的で、洗練された中にもロシアの民族的な顔をのぞかせ、オケとの対話も魅力的な名曲です。
今回ソリストはニューヨーク在住の松山冴花氏。新響はブラームス、ベートーヴェンの協奏曲を共に演奏してきましたが、さらに深みのある演奏を期待しています。
民族的な作風でチャイコフスキーの後継者ともいわれたグラズノフの美しい小品とともにお楽しみください。 (H.O.)
シューベルト:交響曲第8番「ザ・グレート」〈偉大なるアマチュア〉
新交響楽団創立指揮者の故芥川也寸志は、生涯にわたり「アマチュアであることへの誇りとこだわり」を発信されていた。代償を求めず、ただひたすら音楽を愛し没入していく心の大切さが新交響楽団の活動の原点となっている。
ウィーンの申し子ともいえる作曲家フランツ・ペーター・シューベルト(1797年1月31日~ 1828年11月19日)は、「アマチュア」だった。仕事として常に誰かに仕えて作曲したというよりは、友人への感謝とか、そして自分のために、交響曲、室内楽曲、ピアノ曲、歌曲、オペラ、劇付随音楽、教会音楽、合唱曲といった幅広いジャンルで、1,000曲以上もの曲を創り続けていた。
シューベルト本人の言葉、すなわち日記や詩、また音楽家、画家、俳優、詩人といった数多くの親密な友人たち(圧倒的に男性が多い)の証言が逸話となり、豊かな内面世界を持ち精神的にも成熟した若者としての人柄が見えてくる。
特定の家も持たず、家族も持たず、友人たちの家を転々とする放浪生活の中で、周囲のお喋りや騒音に惑わされることなく、いつも紙と詩のテキストにかがみこみ(強度な近眼であった)、ひたすら五線紙に向かって一気にペンを走らせていた。
心象風景に映る孤独と死、沈黙と絶叫という緊張関係の中で、抒情的な側面から深淵な精神に満ちたものまで、多面的なシューベルトの音楽は愛され続け、私たちを魅了している。誰もが子供の時から折にふれて耳にしてきた音楽で、おそらく気が付かないだけでもシューベルトの作品がたくさんあるに違いない。
シューベルトが生きた時代は、伝統的に貴族が握っていた権力と影響力が市民階級・中産階級に緩やかに移行されてきた時代と重なる。
フランス革命の洗礼を直接受けず、君主制を残したカトリックの多民族国家オーストリア帝国の首都ウィーンでは、ヨーロッパの「芸術の都」として18世紀後半から20世紀前半までの約200年間、数多くの作曲家が活躍していた。
生まれも育ちもウィーンで著名な作曲家では、シューベルト以外でヨハン・シュトラウスとアルバン・ベルクくらいだろうか。ウィーン古典派の時代、オペラのグルック、交響曲のハイドン、幅広いジャンルで駆け抜けたモーツァルト、革命の旗手ベートーヴェン、そしてシューベルトの登場は「芸術の都」の黄金時代を反映している。音楽史的には「古典派」から「ロマン派」への移行期と説明されている時代、シューベルトが生活していた社会は、徐々に科学的世界観が否応なく広がっていく中で、従来の音楽と哲学に対する姿勢が変化し、芸術の本質に関する高い美的価値が社会に広がりを見せていく時期であった。社会体制の変化に伴い芸術に対する庇護や演奏の場が変化していく環境の中で、人々が音楽を聴くという行為そのものの変化が、シューベルトの作品の多様性につながっている。
■交響曲ハ長調D.944 「ザ・グレート」
規模や内容の充実度のうえで比類なき大作。堂々とした響き、流麗な旋律、威厳と人間的な温かさを兼ね備えた特有のロマンティシズム、雄大な構想と魔術的な筆致は、即興的で自由自在である。表題の「ザ・グレート」は、交響曲第6番D.589ハ長調と区別するため、単に「大きい方」という程度の意味合いで後世名付けられたが、まさしく「偉大(ザ・グレート)」と呼ぶにふさわしい。
4楽章の構成そのものはオーソドックスであり、編成も古典的である。ベートーヴェンの後期交響作品には限定的に使用されていたトロンボーンが加わることで、オーケストレーションに厚みが加わり、ホルンとトロンボーンの効果的な使用が色彩感と響きの多様性を生み出している。オーボエが常に重要な場面でリードを務め、ベートーヴェンの交響曲第7番を彷彿とさせる。
第1楽章 アンダンテ(ハ長調、4/4拍子)~アレグロ・マ・ノン・トロッポ(ハ長調、2/2拍子)
長い導入部を持つ長大なソナタ形式。ホルンのみで始まる冒頭の旋律は、ロマン的で且つ堂々としており確信に満ちている。古典的旋律の定型8小節に収まっているが、2+1+2+1+2という構造で個性的。これは形を変えながらも交響曲全体を支配している。すぐに各木管楽器の1番が主旋律、2番が対旋律、弦楽器がさらに別な対旋律で支える、という複雑な構造となり、その後の弦楽器のみの柔和で優美な部分は、ヴィオラとチェロが各々二部に分かれて主旋律と対旋律が絶妙に重なっていく。このような多種の要素による重層構造がとても精緻である。
溌剌とした第1主題はテンポが速くなり2/2拍子で付点リズムによる弦楽器で登場、木管楽器による3連音符が続いて発展していく。第2主題はオーボエとファゴットによるメランコリックな旋律で始まるのだが、古典的なルールでは5度上のト長調で登場するところ、3度上の変ホ短調で示されるところが面白い。この主題が展開し、流麗なロマンティシズム溢れるところでのトロンボーンの登場は、英雄的な雰囲気を醸し出している。その後も調性の変化を伴って展開部と再現部へと進み、最後は序奏の旋律が回帰、力強くこの楽章を閉じる。
第2楽章 アンダンテ・コン・モート(イ短調、2/4拍子)
A1-B1-A2-B2-A1という大規模な三部形式。展開部を欠くソナタ形式で動きをもって歩くように進行し、夢幻的な美しさを持っている。低弦による導入的な刻みののち、A1部としてオーボエが奏でる哀愁を帯びた美しく気品のある第1主題がこの曲の白眉といえる。この旋律は3+2+2+2という構造で、クラリネットが重なる次の旋律は3+2+2という構造になっているのが面白い。続いてイ長調の柔らかい旋律が展開していく。B1部にあたる第2主題は、ヘ長調で幸福感を表すようにチェロやコントラバスを伴い第2ヴァイオリンで登場。この後の展開で第2主題が1小節ごとにトロンボーンから木管と続いて演奏されていく響きが天国的でとても美しい。そして第1主題がA2部として戻ってくるのだが、経過部としてホルンと弦楽器の12小節に及ぶ掛け合いが秀逸。A2部の第1主題がさらに立体的・色彩的に発展して叫びのような頂点を築き、落ち着きを取り戻したかのようにチェロが第1主題を反行形のような優美で魅力的な旋律を奏で、B2部として第2主題がイ長調で登場。その後に第1主題による比較的短いコーダが続き、静かに美しい楽章を閉じる。
第3楽章 スケルツォ/アレグロ・ヴィヴァーチェ(ハ長調、3/4拍子)
スケルツォとトリオのそれぞれにABA形式を有する大掛かりな複合3部形式。スケルツォの主部だけでソナタ形式の構想をしており、民衆の踊りのような素朴だが陽気で力強い舞曲。そしてト長調とハ長調による流麗な旋律を対照させ、時には組み合わせて発展していく。
トリオはイ長調、スケルツォの主部と対照的にレントラーを思わせるワルツで、優美かつ雄大な旋律である。
第4楽章 フィナーレ/アレグロ・ヴィヴァーチェ(ハ長調、2/4拍子)
第1楽章よりも長大なソナタ形式。力強く躍動感のある情熱的な音楽。快活な第1主題、そしてト長調による抒情的な第2主題が木管楽器で提示、この二つの主題は共に果てしなく歓喜と陶酔を伴って最後まで流れていく。劇的な展開の後に展開部へ進むコデッタ(小結尾)、ハ長調のドミナント(属音)G音が鼓動のように続く中、徐々に和声が変化して展開部が変ホ長調で登場する。この後、クラリネットによる第1主題や第2主題と異なる旋律は、ベートーヴェン交響曲第9番「歓喜の主題」が引用されている。この旋律の前半は、すでに第2主題の後半で奏でられる下降音型の変形ともいえる。
再現部は第1主題がハ短調と変ホ長調の間を彷徨し、第2主題はハ長調で登場、さらに大きな輝きを持って発展を続けていく。コーダは今までの主題が組み合わされ、短調の大胆な和声を織り込みながら圧倒的なクライマックスを構築、明瞭かつ確信に満ちた堂々たる勝利となり、全曲を閉じる。
■「ザ・グレート」の変遷
シューベルト没後10年、1838年1月にロベルト・シューマンが、シューベルトの遺品の中から発見し、ライプツィヒでメンデルスゾーンが初演して蘇ったという話、シューベルトからウィーン楽友協会に献呈されたが、無視されて公表に至らなかった、というエピソード、いずれも感動を伴って劇的に誇張されてきたのではないだろうか。
シューマンの「再発見」とメンデルスゾーンによる「初演」は、歴史的に意義のあったこと。ウィーン楽友協会ではパート譜を作成しており、公の演奏会として聴衆には披露されていないが「プローベ(試演)」にシューベルトが立ち会った可能性も否めない。後年のウィーン・フィルでも「新作試演会」がよく行われたことを鑑みれば興味深い。
シューベルトは生前、交響曲の番号を付けていなかった。楽譜が残っているもので断片とかスケッチも含め交響曲は14曲とされている。交響曲の並びに関する検討や、スケッチからの後世の補作による交響曲への番号付けのこともあり、後期の交響曲に於いて、番号が時代とともに変遷してきた経緯がある。
かつて「ザ・グレート」は、「第7番」「第9番」と番号が変わってきた。シューベルト没後150年の1978年、国際シューベルト協会による作品目録改訂版に基づくベーレンライター社の新全集版として2002年「ザ・グレート」が「第8番」として出版されて以降、「第8番」の表記で落ち着いてきている。
根拠としては、作曲された順番に交響曲の番号を付与する前提で、自筆譜のままでも演奏できるという意味で完成されているもの、逆に言えば自筆譜のみでは演奏不能な交響曲(後世の作曲家・指揮者等により補作された作品も含む)を番外としたこと、交響曲ロ短調D.759(いわゆる「未完成交響曲」1865年5月1日グラーツ近郊にて再発見)は、1・2楽章のみだが、知名度と完成度から交響曲とみなして「第7番」とする、等が挙げられている。
尚、1825年にシューベルトがザルツブルグ旅行中に作曲し、旅行した土地の名前を付した「グムンデン・ガスタイン交響曲D.849」に関しての行方は、はっきりとした結論はでていないが、「ザ・グレート」の前段階にあたる作品として同一曲とみなす傾向がある。
新交響楽団では第84回演奏会(1979年6月2日)と第134回演奏会(1992年1月19日)にて「ザ・グレート」を演奏、この時は「交響曲第9番」の表記であった。本日は3回目の演奏となる。
■千万人と雖(いえど)も我往かん
筆者が初めて「ザ・グレート」を知ったのは、中学2年生の時で、1971年12月13日(月)東京文化会館でオットマール・スウィトナー指揮によるNHK交響楽団の演奏だった。三兄に連れられて行ったが、とても興奮したことを覚えている。
それまで、シューベルトといえば、「未完成」交響曲とか、母と自宅の白黒テレビでたまたま観た映画「未完成交響楽」(注1)、ディズニーの映画「ファンタジア」の「アヴェ・マリア」程度にしか知らなかった。
5日後に事件と遭遇し母の死と直面、筆者も入院生活を余儀なくされたが、三兄がFM放送からカセットテープにダビングしてくれたこの時の演奏を聴き続けていた。
父が生前「座右の銘」としていた「孟子」の一説「自反而縮 雖千萬人 吾往矣(自ら反かえりみて縮なおくんば、千万人と雖も、吾往かん。)」(注2)という言葉と重なってくる。
「ザ・グレート」は、若者が、「人生」という旅の中で様々な経験を積みながらも確信をもって勝利に到達する喜び、苦悩や苦難に立ち向かい常に前向きに生きていく強い歩みの大切さを示唆している。
注1:
1933年オーストリア映画。ストーリーはシューベルトとエステルハージ伯爵家令嬢カロリーネとの悲恋。「わが恋の終わらざる如く この曲も終わらざるべし、名曲『未完成交響曲』はなぜ未完成なのか?」
注2:
意味:「自分の心を振り返り、やましいところがなく正しいと確認すれば、たとえ相手が千万人であっても恐れずに敢然と進んでいこう」
初演: 1839年3月21日、フェリックス・メンデルスゾーン指揮 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
楽器編成: フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、弦五部
参考文献
チャールズ・オズボーン(岡美知子訳)『シューベルトとウィーン』音楽之友社 1995年
喜多尾道冬『シューベルト』朝日新聞社 1997年
マーク・エヴァン・ボンズ(近藤譲・井上登喜子訳)『「聴くこと」の革命 ベートーヴェンの時代の耳は「交響曲」をどう聴いたか』アルテスパブリッシング 2015年
コルンゴルト:劇的序曲
■不遇の天才
モーツァルトの再来と謳われた後期ロマン派最後の天才は、しかし時代の波に翻弄され、失意のうちに没した。その人生を、『劇的序曲』を作曲した14歳までに重点を置き紹介したい。
1897年5月29日、エーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルトはオーストリア=ハンガリー帝国のブリエン(現在のチェコ南東の都市ブルノ)で生まれ、4歳の時にウィーンに移り住んだ。帝国主義の終盤、社会情勢の混乱の中、植民地から吸い上げた富を利用して、当時のウィーンの人々は享楽的・退廃的な文化生活を愉しんだ。芸術、音楽、学問など諸分野は著しい高まりをみせ、世紀末ウィーンと称される。
エーリヒの父、ユリウス・コルンゴルトが息子の音楽に与えた影響は計り知れない。当時有力な批評家であり前衛音楽・無調音楽などを嫌悪していたユリウスは、幼少から才能を発揮したエーリヒをそれらから徹底的に遠ざけ、慎重に育成した。エーリヒが11歳の時に作曲したバレエ音楽「雪だるま」は、師であるツェムリンスキーがオーケストレーションを担当し、1910年に初演された。楽しげなワルツの情景描写力、流暢で官能的なメロディラインは子供のそれではなく、人々はエーリヒを神童と評した。
その一方で、あまりに子供離れした音楽により、本当はユリウスやツェムリンスキーが作曲したのではないかというゴーストライター疑惑、さらにはヴォルフガングというミドルネーム自体出来すぎでエーリヒが成長してから後付けされたのではないかという難癖まで、エーリヒは苛烈な批判や中傷にさらされた。
これはエーリヒの才能に対する単なる嫉妬だけではなく、舌鋒鋭い批評家であった父への恨みも含まれていたのだろう。息子の才能を誰よりも大切にしていた父の負の影響は、皮肉なことにその後のエーリヒの人生に常に付きまとうことになる。
14歳の夏休みの間、エーリヒはピアノ付きの部屋に閉じこもり、「劇的序曲」の作曲に着手した。名指揮者ニキシュの依頼によりエーリヒにとって初の管弦楽曲として作曲されたこの曲は、バイタリティーに溢れ力強く、爛熟して艶やかである。12月4日にニキシュの指揮により初演され、成功を収めた。
代表作の一つであるオペラ「死の都」の初演は、1920年、エーリヒが23歳の時であった。大喝采で迎えられ、後期ロマン派の作曲家として確固たる名声を手にしたエーリヒであったが、この頃からユリウスとの亀裂が顕在化する。息子の成功に伴い、ユリウスの批評の関心は「対象の音楽家がエーリヒをどのように扱っているか」だけになっており、当時の音楽家たちはユリウスの批評を恐れてエーリヒの作品を度々演奏するようになった。エーリヒは自分の作品が無理解のまま演奏される屈辱と、自分の一番の支持者であったはずの敬愛する父との間で苦悩する。父との対立はエーリヒの結婚に際して深刻化し、両者の仲は一層冷え込んでゆく。結局のところ、子離れできない父は天才を自分の手の届く範囲から放したくなかったのである。
1926年に初演された自信作のオペラ「ヘリアーネの奇蹟」の大失敗により挫折を味わったエーリヒは、その後娯楽音楽や劇場音楽に転向する。ナチス・ドイツの台頭により、ユダヤ系であったエーリヒは1934年アメリカに渡り、映画音楽の製作に注力する。1936年には「風雲児アドヴァース」、1938年には「ロビン・フッドの冒険」でアカデミー賞を受賞し、後世の映画音楽に絶大な影響を与えた。かの有名な「スター・ウォーズ」のテーマ音楽も、エーリヒが作曲を担当した映画「Kings Row」の音楽を聴けば明らかなように、エーリヒ抜きにして生まれ得なかった。
第二次世界大戦後、エーリヒはウィーンに戻り、再び純音楽に復帰しようとするも、2度目の挫折を味わうことになる。第二次世界大戦のイデオロギー対立は音楽の世界も無縁ではなく、伝統的な和声を超えた全く新しい前衛的な音楽がもてはやされ、ロマンチックなエーリヒの音楽は完全に時代遅れだと唾棄された。失意のうちにアメリカに戻り、2曲目の交響曲を作曲中だった1957年、脳出血で死去。ウィーンの表舞台に返り咲くことはなかった。
後年のエーリヒは好んで次のようなジョークをよく言ったそうだ。「私は作曲家になりたかったわけじゃない。父を喜ばせたかっただけ」
モーツァルトと同じく早熟な天才であり、過干渉・過保護な父の期待に応えるべく作曲を行ったエーリヒは、己の内なる音楽を熟成させ、生涯を通じてそれを表現した。その魅力は、時代ごとの価値観に迎合することなく、ジャンルを超えて自らの音楽を追求した点にあるのではないか。
■「劇的序曲」について
題名の「劇的」は、「ドラマチックな」序曲というより「劇場の」序曲を意味するが、後に劇場音楽に転向するエーリヒを図らずも暗示するものとなっている。
全体はソナタ形式であり、弦楽器の神秘的な序奏部から現れた主題(譜例1)が全曲を貫いて、調性や趣を変えながら随所で繰り返される。

3連符の高まりを受けて、主題の変形であるロ長調の提示部が管弦合わせて華々しく鳴り響く。決然たるメロディの中に妖しげな半音階が混在し、独特な曲調を呈する。
続く弦楽器のワルツは、他の作曲家の影響を受けつつも14歳のエーリヒ独自の爛熟を見てとれる。優雅なハープの手法は師ツェムリンスキー譲りのものであり、リヒャルト・シュトラウスの「ばらの騎士」を思わせるフレーズ(譜例2)が登場する。

Più mosso(より速く)の変拍子に始まる快活な中間部の後、主題の音の高低が逆転したようなクラリネットのソロ(譜例3)が奏でられる。その印象的な旋律に導かれ、短い混沌を経て、倍速の序奏部及び提示部が再現される。

終盤は主題の変形を様々な楽器が受け継ぎ、きらびやかな終幕を迎える。
初演:1911年12月14日、アルトゥール・ニキシュ指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
楽器編成: フルート2、ピッコロ、オーボエ2、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、トライアングル、木琴、ハープ、弦五部
参考文献
早崎隆志『コルンゴルトとその時代:“現代"に翻弄された天才作曲家』みすず書房 1998年
柴田南雄・遠山一行総監修『ニューグローヴ世界音楽大辞典』講談社 1994年
Jessica Duchen, Erich Wolfgang Korngold, Phaidon Press1996
参考Web
『Erich Wolfgang Korngold Society』http://www.korngold-society.org
怒濤のエキストラ体験記=後編=
(編集人記)
昨年10月29日の依頼演奏会の際、欠員が生じた2番フルートパートのエキストラとして、維持会員の細越敦子さんにご参加戴きました。
前号(練習開始までの経緯)に続き、練習日記と本番を記録した体験記後編をお送り致します。前編はこちら
◆9月3日(日)18:15~21:15 寺本先生・合奏
初参加となったこの日は、依頼演奏会の為の2度目の合奏とのことだったが、驚くべき事に弦楽器群のアンサンブルが、普通のアマチュアオーケストラなら本番直前にやっとたどりつけるレヴェルの完成度だった。自分が関わった数々の団体なら当たり前の練習・・・・縦の線が合っていない関連パートを取り出して合わせるだとか、音程が合っていないパートの該当部分の音を逐一確かめるだとかといった内容ではない。従ってそれに類する指示もほとんどされない。
管楽器の技量もさることながら、何が新響を新響たらしめ圧倒的に他のアマオケの追随を許さないかといえば弦楽器の一体感なのだと改めて感心した。ホールで聴くだけでは到底想像もできなかった衝撃である。
普段からパートそれぞれでひとつの楽器のように合わせるコツをつかんでいるせいだろうが、どんな練習をどのぐらい続けるとこれほどまでにも弦楽器の音が揃うのだろう?
そもそも技術が高い人が集まっている事もあるのだろうが、ひとつの楽器のように機能させるという目標・価値観を共有している事が他の音楽団体と決定的に違うのではないだろうか?価値観の共有なんて簡単に書いているが、本当はそれこそが難しいはず。技術が高い人なら逆に、無意識に歌いたいと思い、つい音量が大きくなったり音が際立ってしまったりすることもあるはず。そんな人が数人でもいればすぐにパートとしてでこぼこしてしまう。正直に言えばうまいプロオケでもそうした凸凹が目立たないように、弦楽器の後ろの方が「エア弾き」だったりする。ひとりひとりはアマチュアより断然上手いはずなのに、パートの一体化を優先して後ろの奏者は弾いていない・・・・サラリーマン的などと揶揄されてしまう理由はそういう所であるに違いない。結果が全てであるから。
でも新響は弦楽器の後方も全員同じ価値観できっちり合わせようとしている。その目的意識の共有こそが素晴らしいし、音楽に真摯な姿勢に感じ、とてもすがすがしい。
長らく新響をホールで聴いて来て、僭越ながら弦楽器の響きが変わったと感じたターニングポイントをいくつか思いだす。
弦楽器は門外漢ながら「パートがひとつの楽器のよう」と感じた演奏会では、まず思いだせるのは2003年7月20日第182回演奏会、飯守泰次郎氏によるシューマンの交響曲第2番。
「あ、オケの響きが変わった」。そうはっきりわかった。それが何によるのかその時はまだ分からなかったが、それまでは弦楽器が微妙に演奏のベクトルを合わせづらそうにしている時もままあったのに、その演奏会では向きが同じ方向なのがはっきり私にも「見えた」気がした。
2004年1月18日第184回演奏会、故小松一彦氏によるフランクの交響曲ニ短調も忘れられない。フランク独特の転調の妙を指揮者とオーケストラが価値観を共有していた。指揮者の意図にオケが共感できることが、オケの響きを変えるのだ、変わったのだ、とこの時理解できた。
そして2017年4月23日第237回演奏会の寺岡清高氏によるツェムリンスキーの交響詩『人魚姫』は完全に弦楽器セクションが一体化しており、練習するとここまでできるのか!と鳥肌が立つ感覚を今も思いだせる。
そのように価値観を共有しているせいか、驚くことにボウイングや弓の使い方など技術的な注意や指導もほとんどされない。
「今のその音(音型)はちょっと軽い跳ねた感じがある。若干キャラクターが違う。もう少し静かで重々しい荘厳な音が欲しい。同じ音型のほかのパートも同様に」。
・・・・と、こんな抽象的な指示で当該パートはその箇所を直す上に、言われていない問題点をもその場その場で修正している。同じ音型がある管楽器パートも反応している。すごい。
音程感覚や音楽の価値観を共有していると、ものすごく細かい部分の音の「形」や「スピード」などによってこそ、初めて可能となる表現ニュアンスの変更を当然のように求められるのか・・・・衝撃だった。ソロの部分でならまだわかるけれど、オーケストラの弦楽器のような集団に対してそうした指示がなされ、それにすぐ全体として反応できるなんて。しかも2回目の合奏で!う~むむむむ。
そんな衝撃を受けつつも、周囲との調和を乱さない音を出そうと(つまりびびって)こそこそと吹いていたら練習終了後、大明神(『新響維持会ニュース』編集人にしてフルート首席のM氏の事)から「もっとはっきり吹け、そしてもっと小さくしろ」とのお達し。はっきり、でも小さく・・・・それって矛盾では?そうおっしゃる大明神はp吹いていても音量ありますよ・・・・音圧があるだけでなく・・・・でも、かすれるようなpppももちろん吹けるので言い返せない。
更には「小さい音を出す事と聞こえない事とは違う」「ボソボソと貧乏臭い音で吹くな」「いかにも『わたし自信がありません』という姿勢だ。背筋を伸ばせ!顔を上げろ!」と天の声が矢継ぎ早に飛んで来た。とほほな気分はこの後も当分続くのであった。
◆9月17日(日)15:00~17:30 大貫先生・初合奏
台風接近による豪雨の中、某合宿所にて大貫先生の初めての合奏に参加。先生は「こういう大きな規模のオーケストラの指揮は今日が初めてです。」と謙遜されていたが、とても勉強になる合奏だった。曲ごとに背景と曲想を説明しながらこうして欲しいと細かい指示がなされた。例えば『怒りの日』のトランペットは、死者を墓場から甦らせ、全ての人間を審判する場面を表している」とのこと。また「Salva me」と出て来たところで「これは”save me”、助けて、です。あれ?死者を哀悼していたはずなのに、自分が『助けて』? 怒りの日におののいて『自分だけは助けて』と言っている訳ですね。」等々。人柄と深い造詣と分かり易い指揮ですぐにオケの信頼を得ていた印象。
オーケストラだけの曲と歌が入る曲と決定的に違うのは、音符に言葉が割り振られる事だ。
例えば先般『新響維持会ニュース』No.151にオーボエ首席の堀内さんが書かれていた空耳?の話のように、心を込めて「ロマン派のフライ盛り」を演奏しても、音そのものは意味を持たないので指揮者に心を読まれない限り「そこはフライ盛りではなく『暗い森だよ』」と突っ込まれる事は無い。
でもある音型に歌詞が「Libera me(=Leave me)」と割り振られれば、その音形には(音やリズムが多少変わっても)「私を解き放ってください」という意味を持ち、同じ音型の楽器の音符も同じ意味を持ち、何度も繰返される。歌詞を頭の中で浮かべながら演奏すると音は違うだろうか?しかし楽器の音は言葉そのものを発音できないし、結局は合唱が歌っている音に形やスピード合わせることに注力する。
ここは自分もオペラを演奏する上でいつも迷う部分である。場面やあらすじや歌詞はある程度知っている必要はあると思うが、歌とは違って歌詞を深く掘り下げて学べば楽器の演奏もうまく行くとも言えない。歌に似せること、アンサンブルすること。つまりクラリネットとのユニゾンでクラリネットの音を真似てひとつの楽器の音を目指すというイメージはあるにせよ、発音と音色の自在さという技術の問題に帰結してしまう。そうでなければ歌曲は歌手が楽器を演奏した方が名演になってしまうし、宗教曲はその宗教を信仰している宗教家が最高の演奏家になってしまう。そもそも作曲家が最高の演奏家でそれ以外の名演はなくなってしまう。クラシックが全世界で親しまれているのは宗教・人種を越えた普遍性があり思想や宗教を越えた部分で共感できる真理・法則があるからではないだろうか。
2ndクラリネットと同じ音のユニゾンの音程が合わないところがあり、音色と発音の問題だと自覚する。クラリネットのような音を目指してみよう。アタックとスピード、口の中の響かせ方でもっと芯のある音を、という処だろうか。
◆10月15日(日)17:30~21:00大貫先生・合奏
前回の課題を含め色々細かく練習したつもりだったが、3曲目”Offertorio”のフルート3本でのppp部分が音程崩壊していたと他パートから指摘があったとの旨、大明神からお叱り。同じ音型で3回、2ndフルートを挟んで1stフルートとピッコロはほぼユニゾン。その間に私が音を入れ和音を作る。両側にそれぞれ音程を合わせよう、小さい音で何とかしようとしすぎていて逆にうまく行っていない気がする。むしろ2ndが大き目に出すべきか。
◆10月22日(日)10:00~16:00大貫先生・合奏
午前中はオケだけの練習で音程の確認が主体だった。”Offertorio”の冒頭チェロが受け持つ低音から高音域に至る朗々とした旋律の細かい音程調整にかなり時間をかけた(この部分については練習前にも自主的に集合してパート練習も行っていた。こうした地道な努力の姿を、本番までの間随所で見た)。
2ndクラリネットとのユニゾンは合って来ているのだが、まだ不安がある。お互い相手に合わせようと探しに行って、すれ違ってしまうという状態に陥っている感じがする。
午後はソリスト、合唱団とで歌合わせ。
歌の曲はどんなソリストとご一緒できるか、いつもどきどきする。4人とも素晴らしい声だが、特に私は今回2ndフルートでメゾソプラノと重なる部分が多いので、素晴らしい声との共演は本当に幸せな瞬間だった。
前回指摘を受けた”Offertorio”のフルート3本の箇所は注意したのでうまく行ったと思う。大明神は何やらpppの高音C(ハ音)の音程の運指を色々と試しておいでだ。フルートはキーが少ない構造上、他の木管楽器ほどには替え指は無いはずなのだが・・・・自身で開発しているのか。一体いくつ替え指を持っているのだろう?
指揮者から何度か「短三度の音程は広く、長三度は狭くします。短三度、短三度…どこまで広げるんだ、となるのですが(笑)。」との指示。歌のソリストは旋律的音程の人が多いけれど、そういう風に捉えているのだな、と勉強になった。完全音程を広く!は、師匠の宮本明恭先生からもいつもレッスンで口酸っぱく言われているのだが。
◆10月28日(土)16:00~20:00 大貫先生G.P
G.P.は「ゲネラル・プローベ」。すなわち演奏者全員が一堂に会した通し総練習である。
クラリネットとのユニゾンも解が見えた感あり。でもエキストラとして他のパートから厳しく見られているのだからもっと小さい音で上手く霞め、と言われて更に全体に小さくしようとしてみる。なんだかオケのピッチもすごく上がってしまっていて、合わせるのが辛い。
そう思っていたら指揮者から第5曲”Agnus Dai”はソロもソプラノよりメゾソプラノの方が大きい方が良いので、フルートも2ndが大きい方が良いと言われて気持ち良く大きく吹いていたのだが、「指揮者はああ言ったがちゃんと芯のある音ならppで充分聴こえるはず。」と大明神から怒られてしまった。だって霞めとおっしゃったのに・・・・霞みながら芯がある音って???
大明神はまだ替え指を探っていてイライラのご様子。1st奏者の苛立ちを上手く受止るのも2nd奏者の重要な役割と分かってはいるのだが、そこまでの余裕はこちらにもない。
◆10月29日(日)ステリハ~本番
この日も台風直撃で大荒れだった。
昨夜は練習後、大雨をついてフルートパート3名で呑みにいき頭が痛い。大した量では無かった筈だが。共に早稲田大学交響楽団出身のM氏とI嬢(ふたりは親子ほどの年齢差がある)の酒量は尋常ではない。品書きの端から銘柄順に二合単位で日本酒を注文しては次々に呑んでいくのだから、付合っていたら命がいくつあっても足りないと悟った。
G.P.時に注意された点について酔った勢いでM大明神に反論メールを出したら早朝から大量のお叱りメールが。第5曲の”Agnus Dai”の3本のソロは指揮者が指示したように2ndが大きい方がいいと私も思うと書いただけなのに・・・・。
なかなかに心も足も重い本番だ。でも行かないと。会場に着いても大明神とは更にメールのやり取りが続く。動揺して吹けなくなってしまうので無視しようと決意。しかし他のパートからの反対論?を押し切って自分をエキストラとして推薦してくれた大明神に見捨てられたら孤立無援だよなぁ。追い詰められているなぁ。
でも考えてみれば追い詰められた孤独な本番なんて、今までも何度もあった。
ドヴォルザークの交響曲第8番も第4楽章のソロがとてつもないテンポになり辛かった(たいてい練習よりオケがつっぱしってしまう)。ベートーヴェン交響曲第4番の冒頭ppのB(変ロの音)だってむちゃくちゃ緊張した。『魔笛』のソロでは2時間散々吹いて来て疲れ切った所で吹かなければならず、コケたらオペラ台無しなのに精神力を試される極端に遅いテンポで、しかも全く同じフレーズを炎と水の魔法の2回。3回目の公演では疲れ果てて泣きそうだった。
いいや。練習どおり自分がやるべき事を精一杯真摯にやれば。そう思うと妙に頭が冷めてくる。追い詰められた本番時に自分を支えてくれるのは、ここまでは練習したという確信と、もっと苦しい時もあったから今回もまぁ何とかなるさと言う謎の自信(=開き直り)をもたらせてくれる綱渡りの経験量らしい。
ステリハではまず”Offertorio”冒頭のチェロの旋律を取り出して最終確認。男性合唱が少しばらばらしていたが「母音を大きくして」とベル・カント的な指示がされ全体が落ち着きまとまって行く。大明神も替え指は決定したらしくpppの高音Cが安定して冴えわたっている。
私は大貫先生を信じて息のスピード上げて音量もだしてしまう。本番で指揮者を信じるって普通だもの。
ああ、この楽器はこの規模のホールでこのぐらい息のスピードを上げて吹くと反応がいい楽器なのね。オケのピッチも練習より低めでピッチを上げなくて楽に演奏できる。周りは針のむしろどころか、クラリネットが後ろから1stも2ndもぐいぐい合わせてくれるのが分かる。大明神も”Agnus Dai”で音量落として下さったので楽に吹ける。少しご納得いただけたのか、ステリハが終わると声をかけられ、「ブレスをとる前でテンポが速くなる。次にブレスが長くてフレーズが切れてしまうところが1箇所、そして完全五度が狭い。それだけ注意して」と温和なアドヴァイス。死ぬ気で直訴して良かった(・・・・と思っていたら終演後この件に関し、「あれは時間切れで仕方なしに2番吹きのレヴェルに合わせて妥協の産物として言ってみただけ」と冷水を浴びせられ、一瞬殺意が芽生えた)。
楽屋で本番前の休憩時間ぎりぎりまでブレスの位置を変えたり、完全五度を広げたりと何度も確認。ステージ袖では本番中の冷静を期して、脳内で曲の難所を反芻した。
そして本番。冒頭の合唱から実に感動的だった。本当に名曲である。音楽のスケール感、合唱部分もソリスト部分も全て鳴った時の響き、複数の声部の使い方、オーケストレーションの上手さ。本当に良く書けている。散々練習した末の本番中、しみじみ名曲と味わえる曲を演奏するのは本当に幸せである。
そんなこんなでエキストラとしての疾風怒濤・波乱万丈の新響本番は無事終了した。
吹っ切れて演奏できたこともあり、自分なりに得る所が多かった。散々叱られつつも大明神に音程もダイナミクスもpppのかすれるところまでついて行ってきっちり合わせられたのは自信になった。大明神がアタックや音の末尾、細かい音色の変化やニュアンスなど、本当に隅々まで気を配っているのが隣の席に座ってとても良くわかった。見習わなければと改めて思う。
1stフルートが旋律で音程の幅を広げていても2ndはハーモニーを作る時は1stと破綻ができない範囲で支える他パート(例えばホルン)に寄り添って合わせる。ピッコロが低めに取ったらそっちにも合わせる。がっちり一体化している2ndヴァイオリンとも要所々々で同じような顔(音)をしながら協働する。
一瞬一瞬どこに合わせるべきか判断しながら隅々まで気を配りつつ、1stフルートにはどこまでも寄り添い演奏する緊張感。これこそが2ndフルートの醍醐味なのだと改めて認識させられた。普通のアマオケでは木管の各1st同士が合わせるぐらいが精一杯で、2nd同士で音を合わせてオケの中核として支えるところまでなかなか積み上がらない。そもそも色々な所で合っていないせいだろうが、2nd同士の音が聴こえない。各所で適切に音程が合っているからこそ、2nd同士のわずかな音程の違いさえ音がざらざらした感触として分かり、即座に直せた時はまるでジグソーパズルのピースがぴったりまったような充実と痛快さ!本当に貴重な経験だった。1stを吹く時とは違う高揚感と達成感と喜びは言葉ではいい尽くせない。この貴重な経験は必ず今後の演奏活動の支えとなってくれるだろう。
調性崩壊に向かう時代にあって、なお古典的とも言える技法で、でもスケール感の大きい歌曲を書き続けたヴェルディ。その強い信念と歌しかしらないイタリア人の頑迷とも言える価値観に改めて深い感銘を受ける。
貴重なエキストラの機会を下さった大明神ことM氏と、常に温かい目で見守って戴いた新響の皆様に心から感謝申し上げます。
長々お読み戴き有難うございました。
フランツ・シュミット:歌劇「ノートルダム」より間奏曲と謝肉祭の音楽
■間奏曲はお好きですか?
歌劇の幕と幕の間、または幕中での小休止に演奏される楽曲である間奏曲には名曲が多い。ビゼーの「カルメン」、マスカーニの「カヴァレリア・ルスティカーナ」、レオンカヴァルロの「道化師」などがすぐに思い浮かぶが、歌劇中で使用されるテーマを用いたり、次の幕で行われる内容を連想させるようなものが多く、長い歌劇中の息抜きや気分転換を図ったり、次の幕への期待を高める効果がある。美しいメロディー(時には歌劇とは無関係なものも使用されることがある)を持つものが多く、歌劇中で聴いても、独立した管弦楽曲として聴いても心地良い。
1969年に発売され、現在も売れ続けているカラヤン指揮のベルリン・フィルによるオペラ間奏曲集は、発売当時クラシック音楽としてはベストセラーになり、私もレコード(CDではない)を購入し繰り返し聴いた。このアルバムに含まれた曲はほとんど知っている曲だったが、1曲だけ全く知らなかったのに特に印象的な曲があった。それが本日のプログラムの最初に演奏する「ノートルダム」の間奏曲だったのだが、実演に接することもなく長い月日が流れ、本日シュミットに造詣の深い(2015年の第231回演奏会でシュミットの交響曲第4番を演奏)寺岡清高氏の指揮で演奏する幸運に恵まれたことになる。
■シュミットの音楽
歌劇「ノートルダム」の作曲者であるフランツ・シュミット(1874-1939)は、プレスブルグに生まれた。当時はオーストリア=ハンガリー帝国で、現在はスロヴァキアの首都ブラティスラヴァ。ちなみにラフマニノフ(1873-1943)、シェーンベルク(1874-1951)、ラヴェル(1875-1937)と同世代である。しかし、これらの人々と比べるとあまりにも知名度が低く、影が薄い。
シュミット一家は1888年にウィーンに移住し、すでにピアノに非凡な才能を発揮していたフランツはブルックナーなどの著名な指導者に作曲、ピアノ、チェロを学び、1896年に卒業後、ウィーン宮廷歌劇場(現ウィーン国立歌劇場)のチェリストに指名されるとともに、1914年からはウィーン音楽アカデミーのピアノ教授(1927年から31年は校長)をつとめた。
作曲を始めたのは比較的遅く、初期の作品を自ら破棄しているために若い頃の作品はほとんど残っていないが、当時ウィーンで流行していた12音技法などには目もくれず、ハーモニーに斬新な面はあるにせよ、古典を踏まえ、師のブルックナーやリスト、マーラー、レーガーなどの影響を感じさせる管弦楽の濃厚な響きを持つスタイルを貫いた。また、旋律は生地のスロヴァキアやハンガリーの影響を思わせるものが多い。
■マーラーとの確執
ウィーン宮廷歌劇場およびウィーン・フィルにシュミットが加わった翌年、マーラーが芸術監督になった。ハプスブルグ家の支配が続き、世紀末の爛熟した文化に酔うウィーンの誇り高い伝統を破壊しようとする気性の激しいマーラーに、シュミットは当初は新風を吹き込むものと歓迎したが、その後宮廷歌劇場に渦巻く陰謀に巻き込まれることになる。シュミットの交響曲第1番が成功し、名誉あるベートーヴェン賞を受賞した1902年に、新聞がシュミットの作品をマーラーの作品と比較したことがマーラーを激怒させ、シュミットを敵視するようになったことが発端だが、マーラーの義理の兄弟に当たる宮廷歌劇場のコンサートマスターのアーノルド・ロゼーが楽団員をシュミットに敵対させるように仕向けた黒幕だと言われている。それまでチェロのソロを務めていたシュミットに、ウィーン外のポストを勧誘して宮廷歌劇場から追放しようとするような陰謀が続き、シュミットも反マーラーを公言するようになり、二人のぎくしゃくした関係はマーラーが芸術監督を辞任する1907年まで続く。解雇されそうになった時には、シュミットは自らチェロの末席に座ることによって解雇を免れ、1911年に辞任するまで宮廷歌劇場及びウィーン・フィルの団員であり続けた。
このような二人の対立は歌劇「ノートルダム」の運命にも影響を及ぼすこととなる。
■歌劇「ノートルダム」
歌劇「ノートルダム」は、パリの観光地の中でも人気の高い、世界遺産ノートルダム大聖堂を舞台として書かれたヴィクトル・ユゴーの長編小説「ノートルダム・ド・パリ」に基づく歌劇で、シュミットと本職が化学者のレオポルト・ウィルクとの共作で台本が作られた。1904年から歌劇が作曲され、1906年に完成された。しかしその演奏は前述したように対立関係にあったマーラーや他の指揮者に拒否され、初演はマーラーが亡くなった後の1914年まで行われなかった。この初演の年、ヨーロッパの各国は第一次世界大戦に巻き込まれていくが、1918年の敗戦を機にオーストリア=ハンガリー帝国は崩壊することになる。
原作の「ノートルダム・ド・パリ」はロマ(ジプシー)の美しい娘エスメラルダを巡る3人の男(つまり四角関係)の宿命を描く悲劇で、次のようなあらすじとなっている。
エスメラルダを見初めたノートルダム寺院の司教補佐フロロは、背骨は曲がって容貌は醜いが清い心を持つ鐘楼守カジモドに命じて彼女を誘拐しようとする。この時彼女を助けた王室射手隊隊長のフェビスにエスメラルダは一目ぼれしてしまうので、フロロは嫉妬からフェビスを襲ったばかりか、エスメラルダには濡れ衣の罪で死刑にすると脅したものの拒否される。エスメラルダは死刑にされそうになるが、鐘楼で見ていたカジモドが彼女を救い、ノートルダム大聖堂の中に避難させた。軍隊が動員されてノートルダムが陥落すると、エスメラルダは絞首刑に処せられる。この様子を塔の上から見ていたフロロはカジモドにより突き落とされ、カジモドは姿を消す。後に刑場の墓穴ではお守り袋を首にかけた骸骨を抱きしめる背骨の曲がったもう一つの骸骨が見つかった。
これに対し、歌劇では、ノートルダムはパリと特定されておらず、小説では端役の元詩人グランゴワールがエスメラルダの夫としてエスメラルダを巡る第4の男に設定され、司教補佐は名前が明らかにされていない。また、小説のエピローグの部分はなく、カジモドが司教補佐を突き落す場面で終わっている。
小説の「ノートルダム・ド・パリ」は「ノートルダムのせむし男」の題名で多数映画化された他、ミュージカル、バレエなどにも翻案されているが、原作と同じ筋立てになっているものはほとんどない。これはフランス文学者の鹿島茂明治大学教授によれば、「大まかなストーリー」と「キャラの普遍性」が先行する「神話性」を有するユゴー作品の特徴だそうである。実際、ディズニーの映画「ノートルダムの鐘」に至ってはハッピーエンドになってしまっていたり、同じユゴーの手になる「レ・ミゼラブル」も様々に翻案されて映画化、ミュージカル化などがなされていることで納得がいく。
■間奏曲と謝肉祭の音楽
間奏曲と謝肉祭の音楽は、通常の場合と大いに異なり、歌劇「ノートルダム」が影も形もない時点で、まず「管弦楽伴奏付きのピアノのための幻想曲」と して構想され、次に2曲からなる「未完のロマンティックオペラの間奏曲」として完成され、1903年にウィーン・フィルにより初演され拍手喝采を浴び、それ以来ドイツ、オーストリアでは人気曲となっている。
その後、この作品を発展させる形で歌劇全体が作曲されたが、本日演奏するのはオリジナルな形で、間奏曲の前後に似た雰囲気の謝肉祭の音楽が置かれた3部構成になっている。歌劇として完成された時には曲の順番が変えられており、3番目の部分が最初に登場する。
最初の部分は、歌劇では本来の間奏曲の直前の第1幕第2場の大詰めで演奏される、民衆を表す合唱を伴う謝肉祭の音楽となっている。弦楽器のトレモロで始まり、ファンファーレ的な全合奏に続き、たくさんの人が集っているような華やいだ軽快な2拍子の音楽(譜例1)が続く。

2番目の部分は有名な間奏曲となるが、歌劇では第1幕第2場と第3場の間の間奏曲になる。まずヴァイオリンが変ロ長調の2音からなる序奏主題を奏した後、変ニ長調になりハープを伴って弦楽器がハンガリーのチャールダーシュ風の叙情的な主題(譜例2)を少しずつ変化させながら奏でる。師のブルックナーを連想させる重厚な響きが印象的で、全合奏に発展した後に曲は徐々に静まって終わる。なお、この間奏曲のテーマは第1幕第1場や第2幕第3場などいろいろな場面で使用されている。

3番目の部分は、歌劇では前奏曲に続く幕開けの音楽として使用されている。本日の演奏では2番目の部分に続く経過部として急に弦楽器の動きが激しくなり、4小節のトリルに続いて最初の部分と同じような気分の軽快な3拍子のテーマ(譜例3)を持つ謝肉祭の音楽が奏でられる。

私はノートルダム大聖堂を数回訪れている。外観、内部とも素晴らしいが、そのうち1回は行列に並び、長い階段を息を切らして最上階まで登り、有名な鐘も見た。「ノートルダム・ド・パリ」のカジモドはこういう風景を見たのかと感動し、「ノートルダム」の間奏曲が頭に浮かんだことは懐かしい思い出になっている。ドイツ・オーストリアでは非常にポピュラーなのに日本では滅多に演奏されない「ノートルダム」の間奏曲、およびシュミットの作品がもっと日本で演奏されることを願いたい。
なお、シュミットに関しては新響第231回演奏会時のプログラムの交響曲第4番の解説が大変参考になるので、ホームページから参照していただければ幸いである。
初演: 間奏曲と謝肉祭の音楽 1903年12月6日、 ウィーン楽友協会大ホール エルンスト・フォン・シューア指揮 ウィーン・フィル
日本初演: 1956年7月27日、日比谷公会堂 指揮 エドゥアルト・シュトラウス2世
歌劇全曲: 1914年4月1日 ウィーン宮廷歌劇場 指揮 フランツ・シャルク
楽器編成: フルート2、ピッコロ、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、ティンパニ、シンバル、タムタム、ハープ、弦五部
参考文献
Stanley Sadie(edit), The new Grove Dictionary of Music and Musicians vol.16 Mcmillan Publishers Limited 1995
ヴィクトル・ユゴー(辻昶、松下和則訳)『ノートル=ダム・ド・パリ』(上)(下) 岩波文庫 2016年
鹿島茂『100分de名著 ノートル=ダム ・ド・パリ』テキスト NHK出版 2018年
歌劇「ノートルダム」CD解説書 Capriccio C5181 2013
フランツ・シュミットとウィーンフィルそしてマーラー
新交響楽団がフランツ・シュミットを取り上げるのは今回が2回目です。最初にとりあげたのは2015年10月12日で、彼の最高傑作のひとつである交響曲第4番を演奏しました。その時のプログラム解説で、フランツ・シュミットは「宮廷歌劇場管弦楽団のチェロ奏者として採用され、ほどなくウィーン・フィルハーモニー管弦楽団にも加入した。マーラーにその能力を買われて首席奏者の座についたこともある(シュミットが1896年から1911年に宮廷歌劇場のチェリストだった時期は、ちょうど、マーラーが実権を握っていた1897年から1907年と重なる。絶対者として君臨するマーラーに対しては反感をもち、マーラー嫌いを公言していたようである)。」とあります。この時代を感じさせる興味深いものを入手したので皆様にもご覧いただきたいと思い、ここでそのコピーを掲載します。ほぼ毎回、新交響楽団を聴きに来て下さる友人に今回のコンサートを案内したら貸してもらったものです。
まずは、1899年12月3日のウィーンフィルのコンサートのプログラムです。指揮はグスタフ・マーラーで曲目は、ブラームス交響曲第3番、ドボルザーク交響詩『野鳩』、ベートーヴェン『献堂式』序曲 です。そして写真三枚目のメンバー表のチェロの欄をご覧ください。下から三番目にSchmidt Franzの名前が見つかります。どういう順番に並んでいるのか、首席奏者のマークなどもないので席次はわかりません。
次は時代が下って、1924年2月10日のウィーンフィルのコンサートのプログラムです。これは全曲フランツ・シュミットです。一曲目は本日取り上げる歌劇「ノートルダム」より間奏曲と謝肉祭の音楽 です。二曲目はオルガン曲で 幻想曲とフーガニ長調 (世界初演)、三曲目が交響曲第2番、ドイツ語ですが曲目解説の最初のページも掲載しておきます。
このように当時のウィーンではフランツ・シュミットの音楽がかなり取り上げられていたようです。以前、「マーラーの後はフランツ・シュミットが見直される」といわれたこともありました。マーラーは超メジャーな作曲家としていまやベートーヴェンをしのぐほどの演奏機会がありますが、一方でまだまだ演奏機会の少ないシュミットのことを、この記事を見てすこしだけでも身近に感じられるようになっていただけたら幸いです。

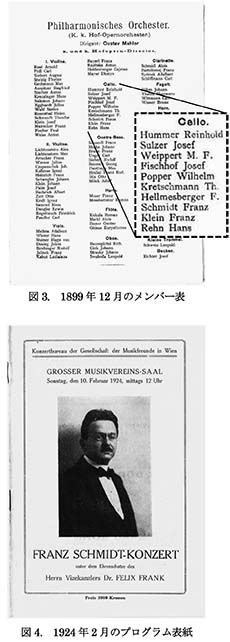

第241回ローテーション
| ノートルダム | 劇的序曲 | グレート | ||||
| Fl | 1 | 吉田 | 1 | 吉田 | 1 | 松下 |
| 2 | 兼子 | 2 | 新井 | 2 | 岡田 | |
| Picc. | 石川 | Picc. | 藤井 | ― | ― | |
| Ob | 1 | 岩城 | 1 | 山口 | 1 | 堀内 |
| 2 | 山口 | 2 | 宮内 | 2 | 平戸 | |
| ― | ― | ― | ― | 1アシ | 宮内 | |
| Cl | 1 | 中島 | 1 | 末村 | 1 | 品田 |
| 2 | 大藪 | 2 | 石綿 | 2 | 大藪 | |
| ― | ― | BassCla. | 岩村 | ― | ― | |
| Fg | 1 | 田川 | 1 | 田川 | 1 | 浦 |
| 2 | 笹岡 | 2 | 笹岡 | 2 | 藤原 | |
| Contra | 浦 | Contra | 藤原 | ― | ― | |
| Hr | 1 | 大原 | 1 | 大内 | 1 | 山口 |
| 2 | 市川 | 2 | 市川 | 2 | 菊地 | |
| 3 | 大内 | 3 | 大原 | 1アシ | 大内 | |
| 4 | 宮坂 | 4 | 宮坂 | ― | ― | |
| Tp | 1 | 小出 | 1 | 倉田 | 1 | 野崎 |
| 2 | 北村 | 2 | 北村 | 2 | 青木 | |
| 3 | 中川 | 3 | 中川 | ― | ― | |
| Tb | 1 | 武田香 | 1 | 武田香 | 1 | 日比野 |
| 2 | 志村 | 2 | 志村 | 2 | 志村 | |
| 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | |
| Tu | ― | ― | ― | 土田 | ― | ― |
| Timp | ― | 古関 | ― | 古関 | ― | 桑形 |
| Perc | シンバル | 今尾 | シロフォン | 今尾 | ― | ― |
| タムタム | 桑形 | トライアングル | 今尾 | ― | ― | |
| ― | ― | シンバル | 桑形 | ― | ― | |
| 鍵盤 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Harp | 1 | 見尾田(*) | 1 | 見尾田(*) | ― | ― |
| 2 | 小野(*) | ― | ― | ― | ― | |
| Vn | 1 | 堀内(伊藤真) | 1 | 堀内(伊藤真) | ― | 堀内(中島) |
| 2 | 内田智(小松) | 2 | 内田智(小松) | ― | 小松(内田智) | |
| Va | ― | 村原(柳澤) | ― | 村原(柳澤) | ― | 柳澤(村原) |
| Vc | ― | 柳部(安田俊) | ― | 柳部(安田俊) | ― | 柳部(安田俊) |
| Cb | ― | 中野(郷野) | ― | 中野(郷野) | ― | 中野(郷野) |
第241回演奏会のご案内
ウィーンにこだわる指揮者 寺岡清高
寺岡氏は早稲田大学文学部を卒業後、桐朋学園大学を経てウィーン国立音楽大学指揮科で学びました。今もウィーンに在住し、ヨーロッパ各地のオーケストラに客演するほか、2004年大阪交響楽団正指揮者に就任し現在は同楽団常任指揮者を務めるなど、国内でも活躍しています。
19世紀末から20世紀初頭のウィーンでは各分野の芸術が花開き、世紀末ウィーンと呼ばれます。音楽の世界では、ロマン派の素晴らしい作品も生まれましたが、シェーンベルクをはじめとする無調の新ウィーン楽派の陰に隠れた感があります。今回の演奏会では、そういった作曲家の中からフランツ・シュミットとコルンゴルトの作品を取り上げます。
シュミットは1874年生まれ、マーラー率いるウィーン宮廷歌劇場でチェロ奏者を務めており、作曲家としての出発は遅いですが、伝統的ながら斬新で歌に溢れた作品を遺しています。
歌劇「ノートルダム」は、文豪ヴィクトル・ユゴーの傑作「ノートルダム・ド・パリ」を基にしています。ノートルダム大聖堂を舞台とした醜い鐘つき男とジプシーの美しい踊り子の悲しい恋の物語です。Norte-Dameとはフランス語で我らが貴婦人という意味で聖母マリアを指し、ゴシック様式の美しい聖堂はパリを象徴する建物の一つです。
シュミットの代表作であるこのオペラは、中でも間奏曲が有名で、カラヤンが好んで演奏した美しい曲です。
コルンゴルトは1897年生まれ、幼くして作曲の才能をみせた神童で、ウォルフガングという名前からもモーツァルトの再来と呼ばれるほどでした。今回演奏する「劇的序曲」は14歳の時に大指揮者ニキシュの委嘱により作曲されました。
早くから一線で活躍し世界的なオペラ作曲家として認められました。その後映画音楽にも活躍の場を広げ「ロビンフッドの冒険」でアカデミー音楽賞を受賞、「スターウォーズ」の音楽で知られるジョン・ウィリアムズらに影響を与えました。
原題のSchauspiel-Ouvertüreは劇への序曲といった意味ですが、オペラや映画音楽で活躍したコルンゴルトらしくドラマティックな作品となっています。
シューベルトの最後の交響曲
さて後半は、同じくウィーンで活躍した作曲家シューベルトの大曲、交響曲第8番を演奏します。シューベルトは1797年生まれ、歌曲王として知られ「野ばら」「魔王」など多くの名曲を残しています。交響曲では「未完成」が有名ですが、「グレート」も同様に人気でよく演奏される曲です。
交響曲第6番が同じくハ長調のため、区別するために「大きい方のハ長調」という意味で「ザ・グレート」とされていますが、雄大でロマンティックな楽想は、まさに偉大と呼ぶに相応しい作品です。作曲家自身この曲をとても気に入って「歌曲をやめてオペラと交響曲だけにする」と言ったと伝えられています。しかし程なくして31歳の若さで病死、初演されたのは10年後でした。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
怒濤のエキストラ体験記=前編=
(編集人記)
去る10月29日の依頼演奏会の際、欠員が生じた2番フルートパートに対し、維持会員の細越さんにエキストラを依頼しお引受け戴きました。これまで新響の団員が退団後に維持会に入会する事こそあれ、維持会会員が新響の演奏に参加されたケースは皆無だったと思われますので、体験手記の執筆を依頼し、ご快諾戴きました。
今号(練習開始まで)・次号(練習日記と本番)の2回に分け掲載致します。
◆引き受けてしまった!
そのメールは、2017年8月25日に日付が変わったばかりの深夜家でゴロゴロしていた私のスマホを僅かに震わせた。
また通販サイトからの広告かな、とノロノロメーラーを開くと、タイトルに「エキストラ」の文字。しかも送信元は維持会編集人M氏で、「新響の依頼演奏会で2ndフルートをお願い出来ないか」とある。読み進めるうち携帯がにわかに自前振動しはじめる…。
あらゆる管楽器のうち演奏者人口の多さはフルートとクラリネットが双璧だろう。クラリネットの演奏者人口が多いのは、中・高の吹奏楽で木管の主要楽器だから。通常のパート数が多く、しかもソプラノからコントラバスまで広い音域の一族郎党楽器が完備している。これが大量採用に直結している。だが、フルートは中・高の吹奏楽ですら定員枠が狭く席がない。それでも演奏者人口が多いのは、年齢を問わず個人で始める人がいて、ひとりでもそれなりに楽しめる人気楽器だからである。
オーケストラにおいてはフルートの狭き門は吹奏楽の比ではない。正団員はもちろん、エキストラで呼ばれるというチャンスそのものがほとんど無いのに、よりにもよって新響のフルートパートにエキストラ?しかも普段よりお世話になっている大明神(M氏の事。この瞬間に神棚に祭り上げられた)からの「依頼」という名の、事実上のご下命である。当然全ての予定をキャンセルして全身全霊でお引き受けせねば!ぼんやりしていてはいけない。は、早くっ!ソファーからいきなり立ち上がり直立不動でお引き受けするメールを・・・ててててて手が、ゆゆゆ指がっ・・・・・落ち着け自分。
そんなこんなでお引き受けすることになった大役だが案の上、ウマい話にはウラがあった。
後日M氏から招かれた酒席で、練習から本番に至るまでの詳細を聴く。と何と『維持会ニュース』に体験手記原稿を書くというおまけがもれなくついているという。・・・・・あのぅわたくし、名前しか有名じゃない私立大学純理系バケガク科卒ですけど?M氏のような高尚な文章なんて書けません・・・・・エキストラの感想を4,000字で『いいから』?・・・・・何て簡単に言うことだろう。
「…マジですか?」「もちろん。こんなことで僕が冗談言ったことありますか?」「…ないですね…。」「維持会員でエキストラに出る人なんて新響維持会始まって以来初めてなんだから頑張ってください。」「…はい…。」「笛もですよ。フルート3本で目立つ所がある。貴方は日頃何でもないところをポロっとミスする癖があるけど、新響でポロは許されないからね」「・・・・・・」。
夏だというのに、M氏の背後に厳冬荒波日本海が忽然と現れ、なぜか石川さゆりの『津軽海峡冬景色』が聴こえてくる・・・・・いやヴェルディ『レクイエム』だけミケランジェロの『最後の審判』の幻覚と、グレゴリオ聖歌『怒りの日』の幻聴であるべきか・・・・・。
そういえば以前、M氏にF.クーラウの『序奏とロンド』のアドヴァイスを戴いた時、「そこはまだpでしょう?すぐ我慢できなくて日本海の荒波に向かってがなっているような音になっちゃうんだから。もっとため息みたいな虚無感とか悲劇性とかの表現は無いのかね?骨の髄から演歌の人だよねー。」と言われたっけ・・・・とほほ。
こんな厳しい感じの掛け合い漫才が本番まで続くことになろうとはこの時はまだ知る由もない。
◆こんな事になったそもそものはじまり
何故こんな絶大な上下関係があるか含めM氏との関係を語らねばならなるまい…と言っても全く皆さんの想定内であろう。想定外の事があるとすれば、同じ会社だと言うことか(部署は違い、会社では偉い大先輩であるが)。
知り合う以前から社内(因みに社員数35,000人ほどの規模)にフルートが上手い人がいるらしい、という噂は聴いていた。その後会社に音楽団体ができ、産休明けすぐにリクルーターM氏から直接社内メールが来て、その団体に「参加しませんか」とお誘いをもらったのである。
後日M氏の提案により『ブランデンブルグ協奏曲第4番』をご一緒することになり(むろん私が2ndフルート)、ソロヴァイオリンを弾くことになったM氏の大学の先輩U氏の紹介がてら演奏会に誘われ、新響と出会うこととなった。
それは忘れもしない2001年10月13日第175回演奏会。人生を変えたブラームスの交響曲第1番(指揮は飯守泰次郎氏)。
オーケストラが最大の緊張時、音を出す前のわずかな瞬間キキキ…と軋(きし)む奇跡を初めて経験した。そして満を持して冒頭の爆発的和音。まるで音に切り付けられたと感じて思わず息をのんだ。
今年初めの『牧神の午後への前奏曲』のソロのように、今や時に穏やかで微妙な陰影や色彩感のある音色を自在に操るM氏であるが、当時は刃物のような圧倒的な音圧と響きを誇っていた。しかもオーケストラと一体になるべきところは完全に溶け込み、出るべきところで飛び出す絵本のように笛だけが浮き立って来るのである。
こんな笛の音を出す人が、本当にいるのだと衝撃だった。
かつての東欧圏のオーケストラの笛の音のような圧倒的な笛の音は、今考えれば幼少の頃、NHKの音響技師を務めていた父親の縁もあって、テレビからいつも流れていたN響で聴いた宮本明恭先生を髣髴とさせた(・・・・・亡くなったかのような言いようだがご健在で齢80歳過ぎてますますお元気です)。
演奏が終了しても脱力感からなかなか立ち上がれない。でも隣に座っていたU氏はあまり意に介さぬご様子だったのが妙に印象に残る。
ロビーでM氏の顔を見て「凄かったです」と伏し目がちに感想を述べ、そうであろうとドヤ顔をされてしまった時点で、その後今に至る絶対的な上下関係は決定した。それまで自分が出していた笛の音は全く間違いだったという完全な敗北感。自分の矮小な価値観や僅かな自信は一瞬にして崩壊した。生ぬるくて楽しい笛人生との決別だった。
そこからは笛を吹く事は難行苦行と化した。だってあんな音出ないよ。何度泣いたことであろう。本当に苦しい日々を重ねた挙句池袋で宮本先生のレッスンを受けられる事を知り、M氏に相談したところ「音づくりから教えてもらうつもりで是非受けてみたらどうか」、と勧められたのである。
その時初めて知ったのだが、プラハ音楽院で勉強された宮本先生こそそうした伝統的な音の、日本人には稀有の体現者であり、M氏も学生時代から私淑されていて、同じ東ドイツ製の名器を手に入れたりして奏法を研究されていたらしい。入門後のレッスン内容を私からじっくり聴き出した上で、M氏自身も先生の門を敲いた。
宮本先生に師事してからというもの、敗北感・挫折感は輪をかけたものとなっている。60分のレッスンの大半をロングトーンと音作りに費やす事も珍しくない。「もっと勢いのある音を!」と常に言われる。そうした笛の音の価値観と奏法が確かにかつての東欧圏には歴然と存在していて、それを手に入れられるか否かは絶対的な違いなのだろう。
宮本先生との間には更なる壮絶な絶対的師弟関係が存在している。語るも涙の現在進行形でまだ文章にできそうもない。
◆イタリア音楽の本質を形作るもの
今回エキストラの話をいただけたのは私がイタリア人指揮者セルジオ・ソッシ氏(故人)のオペラ団体でモーツァルトのオペラを何度も経験し、歌と一緒に演奏するのに慣れていた事が大きいだろうと勝手に思い込んでいる。一度M氏経由で新響フルートパートのO女史にエキストラに来ていただいた。
しかしヴェルディはオペラの規模(登場人物、合唱編成、オケ編成)が大きいので演奏する機会が無かった。しかも名曲レクイエムである。期待はいやが上にも膨らむ。
ところでイタリア人作曲家と言われて、他にどんな名前が出てくるだろうか。
先にフルートは人気楽器と記載した通り、エチュードも多く協奏曲・ソナタ・室内楽など曲に困ることは無いが、イタリア人作曲家となると筆頭はヴィヴァルディぐらいで、あとはペルゴレージ、ボッケリーニ、ドニゼッティ・・・・・フランス人作曲家やドイツ人作曲家に比べれは作曲家の人数も曲そのものもかなりと言っていいほどで、知られていないし、探すのが難しい。
オーケストラの曲になると更に少ない。交響曲は恐らくほとんど無いのでは?有名なのは次回新響演奏会のレスピーギのローマ三部作だろう。しかしこの曲も交響曲の形式とは言えず、非常にオペラ的である。
イタリアと言えば音楽含めた芸術の都であり、今の楽譜の速度記号・強弱記号や発想記号はイタリア語であり、モーツァルトのオペラだってほとんどイタリア語なほど。音楽大国なのでは?長らく不思議に感じていた。
その謎はパウル・ベッカーの『西洋音楽史』を読んで氷解した(といってもこの本はM氏から頂いたものである)。
この本の前提は「音楽史上の音楽の違いは単なるメタモルフォーゼ(変化)でしかなく、優劣の差はないし、進化している訳でもない」なのだが、第十七章にこんな文が出てくる。
「--(略)--特にモーツァルトの歌劇はイタリアではかつて何の反響も呼び起こしたことがなかった。イタリア人は常に歌い手である。歌うことしか知らない。--(略)--彼ら(十九世紀初めの三十年あまりに現れたロッシーニ、ベッリーニ、ドニゼッティ)は声楽の上に、器楽と、その演奏上の名人芸とから得た影響を取り入れたに過ぎないのである。かくして歌劇における歌手の主権は十九世紀半ばにイタリアに新しい大家が現れるまで揺るがなかった。その大家とはジョゼッペ・ヴェルディである。彼は三人の先駆者達の音楽を帰納して、その声楽上のベル・カント(肉声の美しさだけを生かそうとする表現法)の観念を越えて、新の人間的ないわば個性的な表現を与えたのである」。
つまりドイツ語圏で発達した交響曲を作曲したか否かで作曲家の経歴を考えることこそ無意識交響曲偏重によるもので、イタリアの作曲家が交響曲を作らないのは歌い手である国民性ゆえ自然な事であり、そこには優劣も進化の有無も無いのである。モーツァルトのオペラでさえ彼にとっての歌ではなく器楽的らしい。歌が入る曲でないとイタリア人作曲家の音楽に出会う機会が極端に少ないのは当たりだった訳である。
極端な論に感じるかも知れないが、前出のソッシ氏も「イタリアではモーツァルトのオペラはあまり演奏されない。だって歌う曲は山ほどあるから。」とおっしゃっていたので大筋で正しいのだと思う。
ちなみにソッシ氏がよくソリストに注意していたのは「1小節の中で重要な音はルバートさせる。ただし1つの音が長くなったら他の音は短くし、1小節の長さは変えない。音楽は休符も含め譜面に指示されたテンポで流れ続けなければならない。ルバートしようとしてどの音も長くしてはいけない。それではカンツォーネだ。」とのこと。指揮も無理が無くスムーズだった。「オーソーレミヨー」の揺れ揺れテンポのイメージが強いイタリア歌曲だがそれはカンツォーネだけで、オペラでは譜面に厳密が価値観らしい。そういえばアバドもトスカニーニも譜面に厳密な気がする。
レスピーギ:交響詩「ローマの噴水」
イタリアの作曲家レスピーギの代表作といえば、ローマの風物や行事を題材にした3つの交響詩「ローマの噴水」(1916)、「ローマの松」(1924)、「ローマの祭り」(1928)があげられる。「ローマの噴水」は、一般的に「ローマ三部作」と呼ばれるこれらの3つの交響詩シリーズの第1作目にあたる。
レスピーギは1913年にローマのサンタ・チェチーリア音楽院の作曲科教授となり、ローマに移住した。ローマの風物はレスピーギの心を強くとらえ、1916年にまず「ローマの噴水」を書きはじめ、同年秋に完成した。スコア冒頭の作曲家自身による序文には次のような説明がある。
ローマの4つの噴水で、その特徴が周囲の風物と最もよく調和している時刻、あるいは眺める人にとってその美しさが、最も印象深く出る時刻に注目して受けた感情と幻想に、表現を与えようとした。
ローマを歩くと噴水や給水場の多さに驚くが、その起源をたどると古代ローマ帝国までさかのぼる。「すべての道はローマに通ず」ということわざは有名だが、ローマ人の真の偉大さはインフラの整備にあった。それは街道をはじめ、上下水道、城壁、各種の公共建築(広場、劇場、円形闘技場、競技場、公共浴場)など、多岐にわたっている。
レスピーギのローマ三部作は、かつてのローマ帝国の輝かしい栄光を音楽で綴ったようにも思える。「ローマの噴水」では水道の終着点である噴水を、「ローマの祭り」では巨大な円形競技場や広場を、そして「ローマの松」では街道の女王と呼ばれたアッピア街道を取り上げている。その根幹をなしているのは392年にローマ帝国の正式な国教となったキリスト教で、三部作の随所に聖歌や鐘の音を聴くことができる。
「ローマの噴水」では作曲者の序文にあるように、数あるローマの噴水の中から4つを選び、夜明けから夕暮れまでの情景を音楽で描写している。そしてこの4つの情景は途切れることなく、続けて演奏される。
ちなみに第1曲の舞台となったジュリア谷を出発点として、第4曲のメディチ荘の噴水まで、ローマの旧市街を時計回りに歩いて巡ることができる。実際に歩いてみると作曲者の選んだ情景と時刻とが、まことに絶妙な組み合わせであることに驚かされる。これからレスピーギが選んだ4つの噴水を巡ってみよう。
なお各楽章には作曲家自身による詳細な序文が記されているので、それぞれの解説の冒頭に記しておく。
第1曲「夜明けのジュリア谷の噴水」
交響詩の第1曲はジュリア谷の噴水から霊感を受けたもので、牛の群れが過ぎ去り、ローマの夜明けにたちこめた霧の中に消えてゆくという、牧歌的な情景を描いている。
ボルゲーゼ公園の中にあるボルゲーゼ荘(現在のボルゲーゼ美術館)からパリオリの丘の間に位置するジュリア谷の噴水と夜明けの光景が表現されているが、具体的にどこの噴水かは特定されていない。まずここからローマの一日が始まる。
第2曲「朝のトリトンの噴水」
全管弦楽のトリルの上でホルンが突然フォルティッシモで鳴り響くと、第2曲の「トリトンの噴水」が始まる。その響きは喜びにあふれた叫び声のようであり、ナイヤード(水の精)とトリトン(半人半魚の海の神)が群れをなして走りより、互いに追いかけあい、水しぶきの中で放縦な踊りを踊ろうとする。
古代ローマの水道から引いた給水場や泉水をはじめ、広場や教会、建造物を含めた都市全体を劇的に変えたのは、17世紀のバロック美術の巨匠ベルニーニである。古代遺跡が残るひなびた古都ローマは、彼の手によって絢爛豪華な装飾にあふれる美の都に変貌していった。
ローマ旧市街のバルベリーニ広場にあるトリトンの噴水は、このベルニーニの作品で1643年に完成した。ギリシャ神話のポセイドンの息子であるトリトンが、4頭のイルカに支えられた大きな貝の上に乗り、空に向かって高々とほら貝を吹いている。
第3曲「昼のトレヴィの噴水」
次に管弦楽の波動の上に厳粛な旋律が現れる。これは「昼のトレヴィの噴水」である。主題は木管楽器から金管楽器へと移り、勝利に満ちてくる。ファンファーレが鳴り響く。光り輝く水面の上に、ポセイドンの馬車が海馬に引かれて、人魚とトリトンの行列を従えて通り過ぎる。この行列は、弱音器をつけたトランペットが遠くからふたたび響く間に遠ざかってゆく。
一般的にトレヴィの泉と呼ばれているこの噴水は、バルベリーニ広場からトリトン通りを経てパンテオンに向かう旧市街の中心にある。途中石畳の細い路地を抜けると、突如として視界が開け、壮大な噴水が現れる。
ヴィルゴ水道から水を引いて造られた泉水が起源で、ローマ教皇クレメンス12世により建築家ニコラ・サルヴィの設計で改造され、1762年に完成した。噴水はポーリ宮殿の壁と一体となったデザインで、中央に海馬とトリトンを従えたポセイドンが立ち、両脇に女神たちを従えている。
第4曲「黄昏のメディチ荘の噴水」
第4曲の「メディチ荘の噴水」は、もの悲しい主題で始まる。この主題は、静かな水音の上で響くかのようである。夕暮れの郷愁のひとときである。大気は晩鐘の響き、鳥のさえずり、木々のざわめきなどに満ちている。その後、すべてが夜のしじまに静かに消えてゆく。
トレヴィの噴水からスペイン広場を目指す。映画「ローマの休日」でオードリー・ヘプバーン扮するアン王女がジェラートを食べたスペイン階段の上には、二つの鐘楼を持つフランス・ゴシック様式の教会が建っており、今でもフランス人神父によるフランス語のミサが行われている。メディチ荘はその隣に位置する。高台にあるメディチ荘からはローマ市街が一望できる。また、庭園は出発地点のボルゲーゼ公園と隣接しているので、ちょうど一周したことになる。
メディチ荘は現在フランスの国有資産となっていて、在ローマ・フランス・アカデミーが1803年から使用している。それ以来、ローマ賞受賞者がここに留学し、音楽の分野では大賞を受賞したドビュッシーが1885年から1887年にかけて住んでいた。建物の表記もフランス語で書かれており、このエリア全体がローマの中のフランスといった雰囲気を醸し出している。この第4曲もレスピーギ自身が影響を受けたドビュッシーの印象主義の影響を色濃く感じる。
夜明け、朝、昼と噴水とともに過ぎて行ったローマの一日も黄昏時をむかえ、もうすぐ終わろうとしている。遠くで教会の鐘が鳴り、小鳥の歌や葉擦れの音とともに曲は静かに消えていく。
初 演:1917年3月11日、ローマ アウグステオ楽堂 アントニオ・グァルニエリ指揮による
楽器編成: フルート2、ピッコロ、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トライアングル、シンバル、鉄琴、鐘、ハープ2、チェレスタ、ピアノ、オルガン(任意)、弦五部
参考文献
『ニューグローヴ世界音楽大事典』講談社 全21巻+別巻2巻 1993 ~ 95年
『最新名曲解説全集6 管弦楽曲III』音楽之友社 1980年
『ミニチュア・スコア レスピーギ 交響詩 ローマの噴水』音楽之友社 1992年
塩野七生『ローマ人の物語(10)すべての道はローマに通ず』新潮社 2001年
藤原武『ローマの道遍歴と散策─道・水道・橋─』筑摩書房 1988年
フランク:交響曲ニ短調
本作品は、フランスの交響曲を代表する名作とされるが、正直あまり取っつきやすい曲ではない。四角四面で重苦しく、妙にねばっこい。批評家の小林秀雄は初めてこの曲を聴いたとき、気持ち悪くなって1楽章と2楽章の間で吐いたという。それでもこの、ほとんど体臭のようなフランクの音楽の匂いには、他のどの作曲家にもない独特の魅力がある。それは彼の人間性と生き方から醸造されたものだ。フランクは孜々たる瞑想の人だった。楽壇だの楽派だのまったく関係なく、ただ神に対する自分の言葉として、一生かけて音楽を練り上げていったのである。
■フランクの生涯
セザール・オーギュスト・フランクは、1822年に当時オランダ領だったベルギーの古都リエージュで産まれた。母親はドイツ人で、祖先もゲルマン系。「フランス音楽の父」と言われるフランクだが、正式にフランスに帰化し「フランス人」となったのはようやく50歳になってからのことだ。父親は銀行員だったが、幼いフランクと弟にピアノとヴァイオリンを仕込み、すでにフランクが12歳のときには「神童」として各地で演奏させ金儲けをしていた。さらにフランクが14歳になると、より高度な教育を受けさせようと一家をあげてパリへ移り、フランクはパリ音楽院に入学する。ここで5年ほどピアノやオルガン、作曲を学び、在学中にはフーガ、ピアノ、オルガンで賞をとるなど(オルガンは興が乗ったフランク少年が即興パートを長大に弾きすぎて二位にされたとか)才能を見せるものの、「ピアノの軽業師」への復帰を急ぐ父に半ば引きずられ途中で自主退学、その演奏活動も強引な父のやり方が災いして次第に行き詰まっていった。
結局パリでピアノ教師およびオルガン伴奏者として生計を立てはじめたフランク。1848年にはピアノの教え子で女優のデムソーと結婚、これに大反対だった父と決定的に袂を分かち、実家を飛び出してしまう。勘当された若夫婦の生活は(よくあるパターンだが)決して楽なものではなく、フランクは家庭を支えるために日々働き暮らした。生徒たちにピアノやオルガンや作曲を教え、礼拝日には教会のオルガン廟にうずもれて演奏に没入し、そうした中でも毎日早朝に1~2時間は「思索の時」をとってコツコツと作曲する。この生活スタイルは彼が死ぬまで碌々と続いた。
そんなフランクの周りには、作曲の教えを受けるために、また彼の誠実で情に篤い人柄に惹かれ、多くの弟子が集まるようになっていた。彼らは師を「Père Franck(フランク親父)」と呼び慕い、フランクの音楽を世間に紹介しようと奔走する。こうした弟子たち《フランキスト》の中には、ヴァンサン・ダンディ、エルネスト・ショーソンなど、後にフランスを代表する作曲家となる若者が数多くいた。
オルガンの確かな腕前、それに弟子たちの担ぎ上げもあってじわじわと知名度が上がっていたフランクは、1872年にパリ音楽院のオルガン教授に任命される。しかしオルガン弾きでありながら自己流で作曲し、そのくせ生徒にも人気があるフランクを快く思っていなかった他の教授陣は、フランクを冷遇し、作品を正当に評価しようとしなかった。
1889年に初演された「弦楽四重奏曲」が初めて聴衆から喝采され、ようやく彼の音楽が受け入れられ始めた矢先、フランクは乗合馬車で事故にあう。これがもとでその後こじらせた風邪から腹膜炎にかかり、翌1890年には亡くなってしまう。皮肉なことに、フランクの作品は彼の死後になって急に評価されはじめ、特に本日演奏する交響曲と、ヴァイオリンソナタ、弦楽四重奏曲、ピアノ協奏曲である「交響変奏曲」など、彼が50歳を過ぎてから書いていった晩年の作品群が、現在でもひろく知られる代表作となっている。これらの作品は、狙ったかのように1ジャンル1曲ずつしかない。フランクにとっては、それで十分だったのだろう。彼が弟子たちに、口癖のように教えていたのは「少しを、きわめてよく書くように」だったという。この教えに、フランクと彼の音楽の真髄が表れている。
■交響曲について
曲が完成したのはフランクが66歳のときで、最晩年の作品の1つである。初演時の評判は芳しくなく、荒涼として陰気だとか、雅趣も魅力も愛嬌もないとか、辛辣な批判の声が浴びせられた。たとえばグノーは「ドグマの域にまで高められた不能性の断言」(自分が無能なことを教義さながらに述べたような曲だ)と酷評した。それでも当のフランク自身はそういった外からの不評を気にすることなく、初演の出来栄えを心配する家族に対して「ああ、私の思った通りに響いたよ」と満足げに答えたという。
3楽章構成。ポイントは「循環形式」を採用していることであり、以下の譜例に示す3つの主題が全楽章にわたって何度も登場する。

主題A

主題B

主題C
第1楽章は、主題Aと主題Bが繰り返し、しかも次々と転調しながら展開される(演奏する側としては、ほんの1小節だけ目を離した隙に、1つだった譜面上のフラットが6つに増えていたりするので油断ならない)。がっちりと重厚に組み上げられた大聖堂のような印象は、同じく敬虔なカトリック教徒でオルガン奏者だったブルックナーの作品に通ずるものがある。
第2楽章は、コールアングレのソロで奏でられる主題Cから始まり、次いで主題Bの要素を含むヴァイオリンのメロディが登場。

第2楽章Vn 主題

スケルツォ

スケルツォのトリオ
第3楽章で曲はニ短調からニ長調になり、ベートーヴェンよろしく苦悩は歓喜になる。唐突に爆発して始まり、すぐに新しい主題「歓喜の動機」が登場する。

歓喜の動機

第3楽章第二主題
初 演:1889年2月17日、ジュール・ガルサン指揮 パリ音楽院管弦楽団
楽器編成: フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、コルネット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、ハープ、弦五部
参考文献 フランソワ・ポルシル(安川智子訳)『ベル・エポックの音楽家たち セザール・フランクから映画の音楽まで』水声社 2016年
今谷和徳/井上さつき『フランス音楽史』春秋社 2010年
ノルベール・デュフルク(遠山一行/平島正郎/戸口幸策訳)『フランス音楽史』白水社 1972年
エマニュエル・ビュアンゾ(田辺保訳)『不滅の大作曲家 フランク』音楽之友社 1971年
ヴァンサン・ダンディ(佐藤浩訳)『セザール・フランク(音楽文庫69)』音楽之友社 1953年
吉田秀和『主題と変奏(中公文庫)』中央公論新社 1977年
河上徹太郎『河上徹太郎全集』第一巻および第四巻 勁草書房 1969年
『最新名曲解説全集 第2巻 交響曲Ⅱ』音楽之友社 1979年
『(ミニチュアスコア)フランク 交響曲ニ短調』全音楽譜出版社 2009年
レスピーギ:交響詩「ローマの祭り」
■第1曲 「Circenses(チルチェンセス)」
猛獣どもは二日も前から食物を与えられなかったばかりか、凶暴性と飢えをいやが上にもつのらせようとする配慮から、目の前に血のしたたる肉の塊を見せびらかされていた。(中略)ネロは、クニクルム(地下道)への扉を開けと合図をした。それを見ると観衆はたちまちしずまった。獅子を入れてある場所の格子戸がきしむ音がきこえた。獅子は一頭また一頭と、大きな頭にたてがみをひるがえした淡黄色の巨体を砂場へ運んだ。そのうち、ある一頭が子供を両手にだいているひとりのキリスト教徒のそばへ寄っていった。
子供は身をふるわせて泣き叫びながら必死に父親の首にすがりついた。父親はせめて一瞬間でも命をのばしてやろうと思ったのか、子供を首から引き離して、わきにひざまずいている者たちの手に渡そうとした。ところがその叫びとその動作が、獅子をいら立たせた。突然、短い、するどい唸り声をあげたかと思うと、獅子は前足の一撃で子供を押しつぶし、父親の頭を口にくわえてまたたく間に噛みくだいてしまった。(シェンキェーヴィチ(木村彰一訳)『クオ・ワディス』岩波文庫 1995年より)
本日の最後を飾る「ローマの祭り」は、いきなり切って落とすように、古代ローマの血なまぐさい公開処刑の場面からはじまります。「チルチェンセス」は「サーカス」と同義のイタリア語で、ここでは皇帝ネロ(紀元37年~ 67年)が民衆の歓心を買うために開催した、キリスト教徒虐殺の見世物のことをいいます。数々の文学書や歴史書、映画、芝居で取り上げられている、この、世にも残虐な場面を、レスピーギはわずか4分ほどの楽曲の中で見事に描き切っています。
コロッセウムの内外で荒々しく吹き鳴らされるファンファーレ(ステージ上4人、ステージ外9人のトラッペット奏者にご注目ください)、ライオンの檻の扉がきしむ音、次第に高く裏返っていくキリスト教徒たちの聖歌の歌声、観客の熱狂。古代の情景が、音楽の力だけで生々しくよみがえります。
■時間を旅する「ローマの祭り」の構成
「ローマの祭り」は、古代から中世、近世、そして現代へと、時間を旅して4つの祭りを見物する、壮麗な歴史探訪アトラクションです。伝統的な4楽章から成る交響曲の形を受け継ぐ面もあり、それぞれに独立した主題を持つ楽曲が、急─緩─緩─急の順で配置されています。
4つの楽曲は一続きに演奏されます。そのつなぎめも見事なのですが、反面、曲の切れ間が少しわかりにくいとも言えます。また、第1曲があまりにも衝撃的で、音量も強烈なので、その後に続く音楽は幾分地味な感じがするかもしれません。
ここで眠くなってしまわないように、第2曲以降の魅力を、レスピーギ自身が書いた解説を手掛かりにして語ってまいりましょう。
■第2曲「Giubileo(五十年祭)」
巡礼者達が祈りながら、街道沿いにゆっくりやってくる。ついに、モンテ・マリオの頂上から、渇望する目と切望する魂にとって永遠の都が現れる。「ローマだ!ローマだ!」。歓喜の讃歌が突然起こり、教会はそれに答えて鐘を鳴り響かせる。
「五十年祭」は西暦1300年に始まった、ローマ・カトリック聖堂の扉が50年に一度開かれて特別な赦しが与えられる「聖年」の行事です。当初は50年に一度、その後は25年に一度となり、加えて、「特別聖年」が開催されます。最近では2015年の12月から約1年間、特別聖年により「聖年の扉」が開かれ、世界中からの巡礼者がこの扉をくぐるために長い列に並びました。
第2曲で描かれる中世の巡礼たちも、遠方からローマを目指してはるばると歩いてきたのでしょう。疲れきった歩みの足取りを伴奏にして、木管楽器が渋い音色で、古い聖歌の旋律を奏でます。
■モンテ・マリオの頂上でオルガンが鳴る
長い歩みの後に、巡礼たちはついに、ローマで一番高いモンテ・マリオの丘にたどり着きます。巡礼たちが都を一望して「ローマだ!ローマだ」と歓喜する瞬間の音楽が感動的です。伴奏はつんのめるようなシンコペーションになり、譜例2の聖歌が輝かしい長調の旋律に変容して、オルガンとトロンボーン他によって高らかに奏されます。
「ローマの祭り」でオルガンが鳴るのはほんの数か所ですが、いずれも、「ここぞ!」というクライマックスで効果的に登場します。第1曲ではキリスト教徒の最期の歌声がかき消える瞬間、第2曲でも、この「ローマだ!ローマだ!」の場面で、フットベダルで鳴らす低音を含む重厚な和音が鳴り渡ります。演奏会場と一体のパイプオルガンがうなる重低音を、たっぷりとお楽しみください。
■第3曲「L'Ottobrata(十月祭)」
ローマの諸城(カステッリ・ロマーニ)での十月祭は、葡萄で覆われ、狩りのひびき、鐘の音、愛の歌にあふれている。その内に、柔らかい夕暮れの中にロマンティックなセレナードが起ってくる。
カステッリ・ロマーニはローマから25kmほど隔たった美しい丘陵地帯にある14の町の総称で、貴族たちが城を建てた別荘地です。葡萄の名産地でもあり、神聖ローマ帝国のカール5世(1500 ~ 1558年)が、この地でワイン造りを命じました。
「十月祭」は秋の葡萄の収穫祭です。現代も、毎年10月第1週に開催される「マリーノの葡萄祭り」では、ルネサンス期の装束でパレードが行われ、「町の噴水からワインがあふれ出す」という夢のようなイベントが開催されます。
第3曲の魅力は、いかにもイタリアらしい、伸びやかで情感あふれる旋律の美しさです。鈴をつけて走る馬の軽快なリズムに乗って演奏されるヴァイオリンの旋律は、上機嫌の伊達男がとびっきり明るいテノールで歌いながら、田園風景の中を颯爽と駆ける様子をイメージさせます。
後半でソロ・ヴァイオリンとチェロが奏でる甘美なセレナードも、この曲の聴きどころです。この歌を誘い出すために、マンドリンが特別出演して、優しい愛の調べを奏でます。マンドリンの音量に寄り添う弱音のオーケストラのアンサンブルを、耳を澄ませてお聴きください。
■第4曲「La Befana(主顕祭)」
ナヴォナ広場での主顕祭の前夜。特徴あるトランペットのリズムが狂乱の喧騒を支配している。騒音はふくれあがり、次から次へと、田舎風の動機、サルタレロのカデンツァ、小屋の手回しオルガンの節、物売りの呼び声、酩酊した人の耳障りな歌声、「ローマ人のお通り!」のストルネッロ(イタリア語の都々逸のようなもの)などが流れてくる。
クラリネットの頓狂な祭囃子で始まる最後の祭りは、現代の楽しいクリスマス市です。噴水の側にメリーゴーランドが設置され、屋台で色とりどりのお菓子が売られ、バルーン売りや即興マジシャン、大道芸人が秘術を尽くすナヴォナ広場のクリスマス市は、現在も12月1日から主顕祭の1月6日まで毎日、朝から深夜まで開催されます。
■10人の打楽器による祭囃子
第4曲には数多くの魅惑的な旋律がめまぐるしく現れ、惜しげもなく消えていきます。クラリネットが吹くサルタレロのカデンツァは、「sguaiato(下品に)」と書き込まれ、既に酒気帯びです。少し後に、トロンボーンが似たような旋律を吹こうとしますが、こちらは完全に酩酊していて、断片を繰り返すのみであえなく沈没します。
いよいよ夜も更けた大詰めでは、大編成のオーケストラがfffのユニゾンで開放的な旋律を奏し、これを10人の打楽器奏者が一斉に楽器を鳴らして伴奏します。まさに「どんちゃん騒ぎ」で、この「どんちゃん」のクレッシェンドが、祭りを最高潮に導きます。
■初演はトスカニーニ&ニューヨーク・フィル
「ローマの祭り」は1929年、ニューヨークでアルトゥーロ・トスカニーニの指揮により初演され、大成功をおさめました。3部作の中で〈祭り〉だけが、イタリアではなく米国で初演されたわけです。レスピーギより12歳年上で、「劇場の魔術師」として既に世界的な名声を得ていた同郷の先輩が積極的に取り上げたことで、この曲の知名度は高まり、全世界で不動の人気を獲得しました。一方でレスピーギは、本当はこの曲を自分の指揮で初演したかったらしい、とも伝えられています。
その思いを込めてというべきか、レスピーギはスコアに、クレッシェンドや強弱、ニュアンス、テンポについて、実に細やかな指示を書き込んでいます。どんちゃん騒ぎの舞台裏には綿密な設計図があるわけです。一部には「演奏不能!」と抗議したくなる、無謀な速さの指示もみられます。
マエストロ矢崎は平然と、「本番は(練習よりも)もっとテンポを上げます!」とおっしゃっています。どこまで盛り上がるのか、新響はどこまでついていけるのか? 聴衆のみなさまも、ぜひともご一緒に盛り上がって、祭りを成功に導いてください。
初 演: 1929年2月21日、ニューヨーク・カーネギーホール アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック交響楽団
楽器編成: フルート3(ピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、小クラリネット、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット4、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、タンブリン、ラチェット(ガラガラ)、鈴、小太鼓、中太鼓、トライアングル、シンバル、大太鼓、シンバル付き大太鼓、タムタム、グロッケンシュピール、鐘、木琴、タヴォレッタ(板)2、ハープ、ピアノ(4手連弾)、オルガン、場外のブッキーナ(トランペット)3、マンドリン、弦五部
参考文献
門馬直美『最新名曲解説全集 管弦楽Ⅲ』音楽之友社 1980年
山田治生『トスカニーニ 大指揮者の生涯とその時代』アルファべータブックス 2009年
シェンキェーヴィチ(木村彰一訳)『クオ・ワディス』岩波文庫 1995年
第240回ローテーション
| フランク | ローマの噴水 | ローマの祭り | ||||
| Fl | 1 | 松下 | 1 | 吉田 | 1 | 岡田 |
| 2 | 兼子 | 2 | 石川 | 2 | 新井 | |
| ― | ― | Picc. | 兼子 | 3/Picc. | 松下 | |
| Ob | 1 | 堀内 | 1 | 宮内 | 1 | 平戸 |
| 2 | 山口 | 2 | 平戸 | 2 | 宮内 | |
| E.H. | 岩城 | E.H. | 岩城 | E.H. | 岩城 | |
| Cl | 1 | 中島 | 1 | 品田 | 1 | 高梨 |
| 2 | 石綿 | 2 | 進藤 | 2 | 大藪 | |
| BassCla. | 岩村 | BassCla. | 高梨 | BassCla. | 品田 | |
| ― | ― | ― | ― | EsCla. | 末村 | |
| Fg | 1 | 藤原 | 1 | 田川 | 1 | 田川 |
| 2 | 浦 | 2 | 笹岡 | 2 | 笹岡 | |
| ― | ― | ― | ― | Contra | 浦 | |
| Hr | 1 | 山口 | 1 | 菊地 | 1 | 大内 |
| 2 | 宮坂 | 2 | 宮坂 | 2 | 大原 | |
| 3 | 大原 | 3 | 山口 | 3 | 菊地 | |
| 4 | 市川 | 4 | 大原 | 4 | 市川 | |
| Tp | 1 | 倉田 | 1 | 北村 | 1 | 小出 |
| 2 | 青木 | 2 | 中川 | 2 | 青木 | |
| Cor.1 | 野崎 | 3 | 倉田 | 3 | 野崎 | |
| Cor.2 | 中川 | ― | ― | 4 | 中川 | |
| ― | ― | ― | ― | Banda1 | 北村 | |
| ― | ― | ― | ― | Banda2 | 倉田 | |
| ― | ― | ― | ― | Banda3 | (*) | |
| ― | ― | ― | ― | Banda4 | (*) | |
| ― | ― | ― | ― | Banda5 | (*) | |
| ― | ― | ― | ― | Banda6 | (*) | |
| ― | ― | ― | ― | Banda7 | (*) | |
| ― | ― | ― | ― | Banda8 | (*) | |
| ― | ― | ― | ― | Banda9 | (*) | |
| Tb | 1 | 武田浩 | 1 | 日比野 | 1 | 日比野 |
| 2 | 志村 | 2 | 武田香 | 2 | 武田香 | |
| 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | |
| Tu | ― | 土田 | ― | 土田 | ― | 土田 |
| Timp | ― | 桑形 | ― | 古関 | ― | 古関 |
| Perc | ― | ― | トライアングル | 今尾 | 大太鼓・鈴・鐘・シンバル付き大太鼓 | 今尾 |
| ― | ― | シンバル+鐘 | 桑形 | タムタム・ラチェット・トライアングル |
桑形 | |
| ― | ― | グロッケン1 | (*) | 小太鼓 | (*) | |
| ― | ― | グロッケン2 | (*) | タンブリン | (*) | |
| ― | ― | ― | ― | 中太鼓 | (*) | |
| ― | ― | ― | ― | シンバル | (*) | |
| ― | ― | ― | ― | 木琴 | (*) | |
| ― | ― | ― | ― | グロッケンシュピール | (*) | |
| ― | ― | ― | ― | タヴォレッテ(板) | (*) | |
| 鍵盤 | ― | ― | ピアノ | 井上(*) | ピアノ1 | 藤井 |
| ― | ― | チェレスタ | 藤井 | ピアノ2 | 井上(*) | |
| ― | ― | オルガン | 石丸(*) | オルガン | 石丸(*) | |
| Harp | ― | 篠崎史(*) | 1 | 篠崎史(*) | ― | ― |
| ― | ― | 2 | 篠崎和(*) | ― | ― | |
| Vn | 1 | 堀内(内田智) | 1 | 堀内(中島) | ― | 堀内(中島) |
| 2 | 小松(伊藤真) | 2 | 小松(滑川) | ― | 小松(滑川) | |
| Va | ― | 柳澤(村原) | ― | 村原(小畑) | ― | 村原(小畑) |
| Vc | ― | 柳部(安藤) | ― | 柳部(安田俊) | ― | 柳部(安田俊) |
| Cb | ― | 中野(郷野) | ― | 中野(郷野) | ― | 中野(郷野) |
第240回演奏会のご案内
矢崎彦太郎=新交響楽団6回目の共演
パリを拠点に活躍し、そのタクトから色彩豊かな音が溢れる矢崎彦太郎を指揮に迎え、フランスの代表的作曲家フランクの交響曲と、同じラテンのイタリアの代表的作曲家レスピーギの「ローマ三部作」のうち2曲を演奏します。
近代フランス音楽の父-フランク
フランスの交響曲といえば、ベルリオーズの「幻想交響曲」が有名ですが、それと並んで代表する作品はフランクの交響曲ニ短調でしょう。
フランクは、1822年にネーデルラント連合王国(のちにベルギー)のリエージュで生まれました。父親は息子をリストのようなピアニストにしたかったため、ヴァイオリンを弾く弟とともに1835年に一家でパリに移住し、その後帰化してパリ音楽院に学びます。今では作曲家として知られるリストですが、当時は女性ファンがコンサートで失神するようなアイドル的存在でした。富と名誉を夢見た父親は、息子らの出演する商業的な演奏会を行いましたが、フランクは結婚を機に父親から逃れ、教会オルガニストとして堅実な道を歩みました。
オルガニストとして、また作曲家としても名声を得るようになり、1872年にパリ音楽院教授の候補となりますが、帰化したはずが21歳までの期限付きだったため、実はベルギー国籍であったことが判明。再度帰化申請をして、フランス人としてパリ音楽院に任用されました。弟子にはダンディやショーソンなどがおり、人間性や芸術性から大変慕われていました。
交響曲ニ短調は、晩年の1888年に作曲されました。フランクはバッハやワーグナーを研究し、また敬虔なカトリック教徒でしたので、精神的な内面を深く表現した作品となっています。オルガン的な重厚な響きを持つこの曲は、ともすると「フランス的ではない」と評されることもありますが、人生のほとんどをパリで過ごしたフランクの作品にはそのエスプリが宿っていると言えるでしょう。
イタリアのオーケストラの魔術師-レスピーギ
「近代イタリアの交響曲」といっても、あまり思い浮かばないのではないでしょうか。ヴェルディやプッチーニなどに代表されるオペラが隆盛をきわめていた当時のイタリアに現れた管弦楽曲作曲家がレスピーギでした。
レスピーギは、1879年にボローニャで生まれました。ロシア帝国劇場管弦楽団の首席ヴィオラ奏者としてサンクトペテルブルクに赴任した際に、リムスキー=コルサコフの指導を受けています。1913年にサンタ・チェチーリア音楽院作曲科の教授としてローマに移住し、亡くなるまで過ごしました。
ローマ三部作は「交響詩」と名付けられてはいますが、それぞれ古典的な交響曲にみられるような4楽章構成となっており、「ローマの噴水」はローマにある有名な噴水を4つ、「ローマの祭り」はローマで行われる4つの祭りを題材として、非常に華やかなオーケストレーションで描かれています。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
ホルスト:組曲「惑星」
イギリスの作曲家グスターヴ・ホルストの代表作。
イギリス音楽ではあるが、その枠を超えて広く親しまれている作品である。それは親しみやすい旋律と大編成オーケストラによる変化に富んだ曲想、そしてタイトルのユニークさによるものであろう。『惑星』という曲名に超自然的なイメージを膨らませる人もいるのではないだろうか。
初演時には広く聴衆に受け入れられたこの曲も、同時代の革新的な作品(例えばドビュッシー『海』やストラヴィンスキー『春の祭典』など)と比較され芸術的価値が低いと見なされたためか、しばらくはイギリス音楽の一代表作と認識されていたにすぎなかった。今日の高い知名度は1961年頃にヘルベルト・フォン・カラヤンが演奏会で取り上げレコーディングも行ったことがきっかけだと言われている。
■ホルストについて
ホルスト(Gustav Theodore von Holst 1874年9月21日生-1934年5月25日没)は、イングランドのグロスターシャー州チェルトナム(イギリスの保養地として知られている。)で生まれ、ロンドン王立音楽院で学んだ。オーケストラのトロンボーン奏者だったこともある。学生時代に同郷の作曲家ヴォーン・ウィリアムズと親交を深め、それは生涯を通じて続いた。1905年から亡くなるまでロンドン近郊にあるセントポール女学校の音楽教師を務めるなどの教育活動に時間を割いていたので、作曲はもっぱら週末であったようだ。愛娘イモージェン・ホルスト(1907-1984 作曲家、指揮者、音楽評論家)によると「日曜日にピクニックに行く感覚でサンドイッチを持って一緒に出かけ、学校の音楽室で作曲を行っていた」そうだ。
またホルストは好奇心の旺盛な人間だったようで、民謡に興味を持ち、これが彼の作品に影響を与えていることは否めない。また言葉と音楽の一体化(中世の詩などを用いた合唱曲)にも取り組み、インド哲学やサンスクリット(梵語)にも興味を持った。これが占星術、天文学へもつながっているのだろう。社会主義にも関心を持ち、ハマースミス社会主義聖歌隊の指揮者になったことが伴侶イザベル・ハリソンとの出会いのきっかけとなったそうだ。これらの好奇心からいろいろと吸収したものが『惑星』にも凝縮されているような気がする。
■ホルストの作品と惑星の作曲
ホルストの作品は旋律の美しさが特徴だと思う。
ここに力強さ、色彩感などが加わり音楽の魅力を高めている。そしてどのような編成(大オーケストラ、合唱曲など)でも音楽が非常に明確である。
『惑星』にもこの魅力は詰まっているが、他の作品からよりはっきりとホルストの魅力は感じられる。『吹奏楽のための第1組曲・第2組曲』『セントポール組曲』は今や演奏会の主要なレパートリーとなっているし、他にも『サマセット狂詩曲』『ムーアサイド組曲』『ハマースミス』『ブルック・グリーン組曲』(弦楽合奏のとても美しい曲)などの魅力的な作品がある。ちょっとユニークなところでは日本のダンサーから委嘱された『日本組曲』という作品。海外から見た日本をイメージした感じ(和楽器などを用いているわけではないが)で五木の子守唄などを取り入れた魅力的な作品だ(作品番号32、惑星と同時期の作曲)。作品数は他の作曲家に比べて決して多くないかもしれないが、『惑星』以外の作品にもホルストの素敵な世界が広がっており、この機会に耳を傾けて頂くのも良いかもしれない。
さて本日演奏する組曲『惑星』であるが、ホルストが作曲に取りかかる前の1913年頃に興味を持った占星術がきっかけになっている。19世紀の占星術家アラン・レオの影響を強く受けたそうだ。レオの占星術マニュアル「統合の技法」にある各惑星のタイトルがホルストのそれと共通している。このタイトルはローマ神話の神とも共通する部分はあるが天王星と海王星は内容に相違がある(天王星=ウラノス=天空神≠魔術師、海王星=ネプチューン=海神≠神秘)。
しかしホルスト自身は初演時に「この作品は表題音楽ではなく、神話の神とも関係ない。手引きとしては各曲のサブタイトルが広義に解釈されれば充分」と言っている。占星術との関係とこの発言の意図するところはどういうことだろうか。おそらくインスピレーションはもらったが、そこから曲に対するイメージをぐっと広げていったということではないだろうか。「戦い~」「平和~」「快楽~」などに対して…。「木星が快楽、喜びを表すだけではなく人間の祝祭にもつながり、土星は老いてしかし高みに到達すること」などホルストが意図した奥深い表現が込められているような気がする。
…とまあ作曲の背景にはいろいろとあるようだが、お客様には大編成オーケストラによる音の饗宴を聴いたままにお楽しみ頂ければ良いのではないかと思う。例えば火星からはスペースファンタジー映画音楽的なイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれないし…。
■組曲『惑星』について
1914年5月から作曲に着手、1917年頃に完成。最初は2台のピアノのために作曲された。その後オーケストレーションがなされていくが、ホルストによる指示にもとづき弟子たちにより筆記完成されている曲が多い。これはホルストが17歳で右手を神経炎に冒され筆記も困難を極めた為、回りの人に代筆をしてもらったようだ。ちなみにスウェーデン人の父親からピアノを学んでいたが、ピアニストへの道もこのために断念している。
『惑星』は4管編成の大オーケストラの作品となっており、バスフルート、バスオーボエ、テナーテューバといった特殊管楽器、チェレスタ、ハープ2本、オルガン、さらに海王星では女性合唱も加わる。なお、作曲者はスコアにバスフルートと表記しているが、実際にはアルトフルートを指している。
地球を除く7つの惑星がタイトルとなっている。ほぼ太陽に近い順になっているが火星と水星が入れ替わっているのは、西洋占星術における黄道12宮と守護惑星の関係に基づく(筆頭の牡羊座の守護惑星が火星、以下、牡牛座=金星、双子座=水星など)とも、音楽構成上の理由(始まりが急緩~)とも、あるいは戦争(第1次世界大戦)がホルストにインパクトを与えたため、とも推測されているようだ。
1. 火星~戦争をもたらす者~
Mars, the Bringer of War
「ダダダ・ダン・ダン・ダダ・ダン」という5拍子のリズムが曲を支配する。冒頭は木製マレットのティンパニ、ハープ2台、コルレーニョ(弓の木の部分で弦をたたく)奏法の弦楽器群でこのリズムが始まるが、クライマックスでは全オーケストラにより圧倒的なリズムが奏される。このリズムにのって管楽器が不気味な旋律を奏でる。リズムが変わりテナーテューバによる軍神ラッパ風旋律(トランペットが受け応える)が印象的。第1次世界大戦開戦を暗示させる音楽とも言える。
2. 金星~平和をもたらす者~
Venus, the Bringer of Peace
曲は一転、動から静へ別世界となる。編成も小さくホルン以外の金管楽器は沈黙する。冒頭はホルンの旋律と木管楽器の和音により美しい世界が創出され、ヴァイオリン・ソロが愛の女神を象徴するかのような旋律を奏でる。組曲の中で最も美しい作品である。小編成ながらもチェレスタとハープ2本が有効に使われ、音のイメージの広がりが感じられる。
3. 水星~翼をもった使者~
Mercury, the Winged Messenger
スケルツォ風の作品。8分の6拍子の中に各楽器が交互にパッセージを奏しつなげていく。翼の生えた天使が縦横無尽に飛び跳ねる姿を彷彿とさせる軽快な曲。(占星術では「神の翼あるメッセンジャー」と位置付けられ火星と金星の間を繋ぐ役割だそうだ。)ここでもチェレスタが効果的に使用されている。オーケストラの腕の見せ所とも言える作品(言い換えれば難曲?)である。組曲中最後に作曲された。
4. 木星~快楽をもたらす者~
Jupiter, the Bringer of Jollity
組曲の中で一番有名な作品。序奏と3つの舞曲・旋律で構成されるが、ホルンが各旋律で中心となっている。弦楽器の細かい音にのったシンコペーションの序奏に続き躍動感あふれる旋律がリズム隊に乗って奏され、3拍子となり1拍目の和音にのって快楽的な音楽、そしてAndante maestosoの壮麗な旋律へと続く。再現部でこれらが繰り返されて高揚のうちに曲が終わる。中間部Andante maestosoの旋律はホルスト自身により「I Vow to Thee, MyCountory(私は祖国に誓う)」という歌曲としても編曲されており、故ダイアナ元皇太子妃の葬儀でも歌われた。また日本の歌手・平原綾香が「Jupiter」としてリリース、大ヒットとなった。
5. 土星~老いをもたらす者~
Saturn, the Bringer of Old Age
組曲の中で最も演奏時間が長い作品(約10分)。タイトルと冒頭の印象から地味なイメージだが、ダイナミックスや曲想の変化がとても大きく、木星とともに組曲の中核を成す作品といえる。冒頭はフルートとハープのシンコペーション和音にのりコントラバスが老境を感じさせる旋律を奏する。低弦のピッツィカートにのった金管楽器のコラールがゆっくりとしかし力強い歩みを感じさせる。最後は老いて高みに到達するような恍惚感に溢れる美しいエンディング。何かをやり遂げた境地だろうか。この惑星に突入して燃え尽きたカッシーニのように…。ホルストが組曲中で最も愛着を持った作品とも言われている。
6. 天王星~魔術師~ Uranus, the Magician
個性的な作品が並ぶ組曲『惑星』の中でも強烈な個性を持つのがこの天王星ではないだろうか。冒頭ソ(G)、ミ♭(Es=S)、ラ(A)、シ(H)の4つの音がトロンボーン群に呈示され、さらにティンパニに含まれるファ(F=V)を加えて、ホルストの名前(Gustav-- Holst)を表すという説もあるようです。ホルストのホロスコープ(占星術の星図)が天王星を暗示しているとも。ファゴットに始まる怪しいリズムが盛り上がり、ホルン、木管楽器、弦楽器が諧謔的な旋律を恥ずかしげもなく強奏、そして冒頭トロンボーンの4音による速いリズムがヴィオラ、木管楽器、ハープなどに出てマーチが奏されるが、オルガンのグリッサンドという珍しい終止を迎え、金管楽器の和音のあと静かに曲が終わる。フランス作曲家デュカスの『魔法使いの弟子』とともに魔術を描いた代表作である。
7. 海王星~神秘なる者~ Neptune, the Mystic
この組曲が作られた時に太陽系で最も遠い惑星であった海王星。神秘性をたたえ曲も和声構成を含め幻想的イメージである。フルートを中心とした木管楽器群が神秘の世界へ導く。金管楽器のコラールにのったチェレスタ、ハープ、高弦のアルペジオが印象的。そしてチェロから木管楽器に引き継がれるパッセージに導かれるように舞台外の女性合唱が加わる。クラリネットからヴァイオリンへ旋律が引き継がれ、女性合唱のヴォカリーズ(歌詞のない歌唱法)の中、神秘性を湛えたまま静かに曲は終わる。
『惑星』が作曲された後の1930年に太陽系9番目の惑星・冥王星が発見された。ホルスト自身も晩年に冥王星の作曲に取り掛かったようだが病のために実現しなかったそうだ。その後イギリス作曲家コリン・マシューズが『冥王星、再生する者』を作曲、冥王星付の惑星が普及していくこととなる。新響も前回『惑星』を演奏した第172回演奏会(2001年1月)でこの冥王星付の演奏を検討した(実際は冥王星抜きのホルストのオリジナルで演奏)。そして、その後2006年の国際天文学連合総会で冥王星が準惑星に降格?されてしまったので、今ではホルストの作品が実際の惑星と一致することとなった。時代の変化を感じさせる。余談だが新響の前回本番当日が大雪で交通もズタズタだったにも関わらず、900人以上のお客様にご来場頂いたのは感謝感激であった。今回も(前半の邦人作品ともども)大勢のお客様に音楽をお楽しみ頂ければこの上ない喜びである。
初 演:
1918年9月29日、エイドリアン・ボールト指揮
ニュー・クイーンズ・ホール管弦楽団(試演・全曲)
1919年2月27日、エイドリアン・ボールト指揮
ニュー・クイーンズ・ホール管弦楽団(金星、海王星を除く5曲のみ)
1919年12月22日、グスターヴ・ホルスト指揮(金星、水星、木星の3曲のみ)
1920年11月15日、アルバート・コーツ指揮 ロンドン交響楽団(全曲)
楽器編成: フルート4(3番はピッコロ、4番はピッコロとバスフルート持ち替え)、オーボエ3(3番はバスオーボエ持ち替え)、コールアングレ、クラリネット3、バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン6、トランペット4、トロンボーン3、テナーテューバ、バステューバ、ティンパニ(奏者2人)、小太鼓、大太鼓、シンバル、トライアングル、タンブリン、タムタム、鐘(テューブラーベル)、木琴、グロッケンシュピール、チェレスタ、ハープ2、オルガン、女性合唱(6声部で2群に分かれる。舞台裏)、弦五部
参考文献
マイケル・トレンド(木邨和彦訳)『イギリス音楽の復興 音の詩人たち、エルガーからブリテンへ』旺史社 2003年
山尾敦史『ビートルズに負けない近代・現代英国音楽入門』音楽之友社 1998年
ニコラス・キャンピオン(鏡リュウジ監訳 宇佐和通・水野友美子訳)『世界史と西洋占星術』柏書房 2012年
鏡リュウジ『占星術の文化誌』原書房 2017年
『(ミニチュアスコア)OGT232 ホルスト組曲「惑星」』音楽之友社 2000年
『最新名曲解説全集 第6巻 管弦楽曲Ⅲ』音楽之友社 1980年
『クラシック名曲ガイド② 管弦楽曲』音楽之友社 1994年
岸辺成雄編『音楽大事典 5 へ~ワ』平凡社 1983年
黛 敏郎:曼荼羅交響曲
■合理的非合理と非合理的合理
先年亡くなった作曲家冨田勲に『祭りの笛』という小品がある、と聞いても知る人は少なかろう。これは『新日本紀行』の音楽の一部で、誰もが知るオープニング・テーマの直後に間奏的に配されている。
日本の祭囃子を描写しているが、肝腎の笛の旋律は複数のピッコロに委ねられる。そして演奏に際して作曲者は敢えて楽器のピッチ(基準となる音高)をずらすように指示している。微妙にずれたピッチの笛がいちどきに鳴る時、それは未熟な演奏や稚拙な構造の笛からもたらされる結果ではない「明らかな意図」による日本的な響きをもたらす。惹き起される郷愁…そこに作曲者の意図がある。
或いは鄙(ひな)びた山寺の堂内に老若男女が集まり、念仏を唱えるとする。声の高さや強さや抑揚はまちまちだが、それが幾層にも重なる事でもたらされるのは、決して不快な音の混沌ではなく、ある種の荘厳にほかならない。
こうした一見無秩序ともとれる音の集積を、日本人は日常の生活の中で違和感なく受け容れ続けてきた。そこにひとつの響和を見出しているのである。
これとは逆に西洋ではギリシア以来、如何にして純粋な調和=ハーモニーを得るかに腐心し続けた。個々の音の関係を「協和」と「不協和」に峻別し、キリスト教の調和的な世界観と相俟って、ひたすら協和した音に神の救済や恩寵を求める音楽が生み出される。やがて調性が確立されると、転調の妙を巧みに組み合わせて作品を複雑化・長大化させ、曲折の果てに協和したハーモニーで完結の充足をもたらす音楽の伽藍を築き上げてきた。その整然とした姿と比較すると日本の混沌の中の美意識は、ともすれば未開・不完全と映るかもしれない。だがこれは質ではなくあくまで拠って立つ精神的基盤の差異にほかならない。
だが西洋音楽の均整の基盤だったハーモニーの体系は、その余りの自己肥大によって20世紀に入って完全に崩壊し、存立の危機に立たされる。代わって創始された無調や十二音の技法は、それまでの調性音楽が持っていた音の色彩と比較すると、余りに生硬で無機的なものにならざるを得なかった。それは長い協和の伝統とはかけ離れており、受け手である聴衆はもとより、送り手である作曲家も暗中模索を余儀なくされていたと言える。そうした模索の一端として、電子音楽や偶然音楽などと並んで東洋の音楽やその音律にも目が向けられるようになっていた。
黛敏郎がパリに留学した1951年当時のヨーロッパの作曲界はそのような状況にあった。早熟な22歳の作曲家は、西洋音楽がその進化の果てに自縄自縛の状況に陥っているのを目の当たりにする。そこで彼は最新の音楽思潮や電子音楽そしてミュージック・コンクレート(具体音楽)など彼の地ならではのものを吸収すると「もはや学ぶ事無し」と1年ばかりで帰国しているが、それは当然の結果と言えた。
ミュージック・コンクレートは、それまでの音楽を構成してきた伝統的な楽音の枠を脱し、むしろそれ以外の自然音や生活音・騒音をも素材化し、録音技術を駆使して「作品」に仕上げる。究極の調和を突き詰めた果てに、最も根本に据えて磨き続けられた楽音からさえ離れてゆく…こうした新たな潮流に肌身で接した彼は言う。
「ヨーロッパの前衛音楽は、合理的、論理的思考を極限まで推し進めることによって必然的に、(合理的非合理)ないし(論理的非論理)ともいえるような次元 に到達しようとしている」
この言葉は否定的なニュアンスで捉えられるべきではない。帰国後の若き作曲家はこうした合理的非合理の産物というべき技法による作品を自身で多数書き、また最新の作品の紹介もしているのである。
そしてある時期から日本の梵鐘の音に関心を向ける。1955年には創設されたばかりの「NHK電子音楽スタジオ」にこもり、ひたすらこれを科学的に分析し、成分音を拾い出す試みに日々を費やすようになる。
黛敏郎が梵鐘の音響分析に傾倒していった背景にミュージック・コンクレートと電子音楽の基盤があった事は言うまでもない。楽音以外の素材への関心はこれらの技法によって自ずと刺戟された。彼がヨーロッパの地で体感した、合理の末に西洋音楽が行き着いた非合理。帰国後、その延長線上で日本固有の音の素材を収集するうち、冒頭に示した祭りの笛の音律や衆生の念仏に秘められた、西洋的な価値観からすればおよそ無秩序な音の集積によってもたらされる独特の響和に改めて彼は気づき、そこに日本的な美意識に根ざした混沌的調和とも云うべき解を見出したのである。更にはその調和の根源に、仏教的な世界観を見通すに至る。黛敏郎の知性と感受性を以って初めて可能となった飛躍。梵鐘はその象徴だった。
■涅槃から曼荼羅へ=非合理的合理による解=
彼はこの梵鐘の分析を「カンパノロジー(*注1)」と名付け、最終的には複雑極まりない構成音を、西洋音楽の基盤である12の音のいずれかの枠に割り付けていった。1959年に発表された『涅槃交響曲』(*注2)はその分析と再構成の作業の所産にほかならない。
この作品では冒頭から西洋の音の文脈の中で再構築された「梵鐘」がオーケストラによって響く。男性コーラスによる「読経」部分では、ユニゾンから開始した詠唱がやがて12の声部に分かたれ、半音程で全ての声がぶつかりながら音楽が進んで最高潮を迎える。両肘をピアノの鍵盤に押し付けて1オクターブ内の全ての音を同時に出すのと同じで、当然濁った灰色の響きになる筈だが、それが読経の声塊として迫ると、不協和の音の集積からある種荘厳で不可思議な響和がもたらされるのである。こうして黛敏郎はヨーロッパの音楽が必然的に陥っていた「合理的非合理」を、仏教的(そして日本的)な「非合理的合理」の音響世界の中で初めて打開し得た。『涅槃交響曲』の真価のひとつは蓋けだしここに求められるべきだろう。
2年を経て『曼荼羅交響曲』に至る。この間に作曲者の「カンパノロジー」は完成を見ている。それまでに彼は、日本各地にある歴史的な名鐘の音の分析を終えていた。ある基音を定めて他の成分の音を出現頻度(鐘の不規則な響きによって、各音の強弱や有無が生じるという事なのだろう)順に並べる。するとその上には半音差で二種類の「陽旋法」が見出せるという。彼はこのような音律を無意識的に鐘の組成として落とし込んだ先人らの智慧と美意識に感じ入り、これらの音を素材(音列)として活用して、新たな交響曲の骨格とした。
表題の「曼荼羅」とはサンスクリット語の"mandala"を音写したもので、本来は「本質・中心・精髄などを持つもの」の意。仏教では「仏の悟りとその世界」を意味する。インドに於いては、修法に及んで邪物の侵入を防ぐために地面に引いた円を指したと言われるが、中国に渡るとそれは仏教世界の宇宙を、図絵として示したものをいうようになった。
日本へは平安時代の初期に弘法大師がもたらしている。ここで生半可な解説をする事は敢えて避けよう。数ある曼荼羅の代表として金剛界・胎蔵界の両曼荼羅があり、寺院にあっては聖なる空間を構成する法具と位置付けられる。その上で前者が「智」を、後者が「情」を表すという対称を成しているとの理解があれば充分である。黛敏郎は音楽に於いてその対称を現出させる事を企図する。
第一部の『金剛界曼荼羅』は素材の音列の個々の音がより際立つように書かれ、その目的からテンポも柔軟なものになっている。打楽器を含め金属的な響きも多く全体としては鋭さの際立つ部分に満ちている。
続く『胎蔵界曼荼羅』の第二部は冒頭から「梵鐘」の名残りを見出せはするので『涅槃交響曲』の系譜を引く事は、第一部に比較して理解はしやすい。とはいえこれとて極めて抽象的で、結局のところ聴く者は直面する響きを受け容れ、享受する以外になす術はない。ふたつの楽章はそれぞれ独自の個性を持つが、いずれも末尾は同じ音に集束してゆく。
「曼荼羅」の表題に惑わされがちだが、作品として仏教に関わるメッセージや具体的なドラマが表現されているわけではない(これは例の読経を含んだ『涅槃交響曲』でさえ同様である)。この新たな交響曲では「梵鐘」を更に抽象化し、両界曼荼羅によって示されている仏教的宇宙を、言葉や声さえ排除して「音のみによって表現する(初演時の作曲者の言葉)」姿勢に徹している。これはもはや外からは窺うかがいようのない黛敏郎の内なる世界であって、他者たる聴衆は、仏教に関するいかなる知識を足がかりにして作品を理解しようとしても結局は徒労に終わる。唯一彼はオーケストラの対称的な配置という目に見える形で、曼荼羅を示してはいるが、この配置とても響きの交叉という効果を目論んでの措置だ。こうした空間を活用した実験的手法は1960年代当時の音楽状況を反映している。
成立の過程を概観すると、この交響曲は拠って立つ日本的美意識の根源と作曲家の思想的基盤に於いて、キリスト教と表裏一体となった西洋音楽の対極にある存在とも言える。だが素材は12の音に限られており、20世紀ヨーロッパ音楽の延長線上にある。
黛敏郎が最も影響を受けたストラヴィンスキイやメシアンなどの作風に拠っている部分もあるため、ともすれば仏教的思惟からの影響を見出せず、表題から受けるイメージとのギャップに困惑する人があっても不思議ではない。
その困惑を解消するためには、西洋音楽が行き着いた合理的非合理を体験した作曲家が、日本人が日常的に受け入れている独自の「ハーモニー」に非合理的合理を見出す⇒底流にある仏教の影響も踏まえ、その象徴として梵鐘の音を追求の究明に向かう⇒『涅槃交響曲』の作曲によって両者の融合を図り、独自の解を得る⇒そこから更に自身の思惟を純化発展させて、ようやく『曼荼羅交響曲』の帰結に至る…という10年にも亘る長い道のりを考える必要がある。迂遠な話だがそうした文脈の中で捉えてこそ、この作品の価値や位置づけを我々は初めて理解できるのではないだろうか。
(注1) カンパノロジーとは黛敏郎の造語。鐘を製造する際の合金の割合や鋳造の方法を研究する学問の名称を意味する。そこで得られた音響(カンパノロジー・イフェクト)に基づく作品群の表題にもこの名称が冠されている。
(注2)『 涅槃交響曲』に関連する文は、以下の拙稿をベースにしている。作品理解の一助とされたい。
初演:1960年3月26日、岩城宏之指揮 NHK交響楽団 日比谷公会堂「第4回 3人の会」
楽器編成: ピッコロ、フルート、オーボエ、コールアングレ、クラリネット、Esクラリネット、バスクラリネット、ファゴット、コントラファゴット、ホルン2、トランペット2、トロンボーン2、テューバ、ティンパニ、木琴、グロッケンシュピール、鈴、ヴィブラフォーン、ムチ、シンバル、吊りシンバル(大・小)、中国シンバル、タムタム(大・小)、ゴング、キン、鐘(テューブラーベル)、大太鼓、チェレスタ、ハープ、ピアノ、弦五部
参考文献
黛敏郎『曼荼羅(mandala)』3人の会プログラム 1960年3月10日
團伊玖磨/芥川也寸志/黛敏郎『現代音楽に関する3人の意見』中央公論社 1956年
秋山邦晴『現代音楽をどう聴くか』晶文社 1973年
東川清一『音楽理論入門』ちくま学芸文庫 2017年
早坂 文雄:左方の舞と右方の舞
■北の天才作曲家
早坂文雄は1914年に仙台で生まれ、1918年に札幌に移り住んだ。北海中学校(現在の私立北海高等学校)に進み、音楽に興味を持ち独自にピアノや作曲を始めた。音楽部はあったがハーモニカ合奏で、人手不足の穴埋めに駆り出されたが、上達著しく全国ハーモニカ独奏選手権大会で2等になったほどであった。
もとは裕福な家であったが、16歳の時に父親が家出し翌年には母親が病死、高等学校への進学をあきらめクリーニング店に就職した。ご用聞き先の家にピアノがあると上がり込んで弾かせてもらうので首になり、印刷所に勤めては音楽活動に力を入れすぎて解雇された。
同じ歳の伊福部昭と知り合ったのは1932年、18歳の時。ともに「新音楽連盟」を結成し“国際現代音楽祭”を開催して、早坂がピアノ、伊福部がヴァイオリンを担当。ストラヴィンスキーやサティなどの室内楽を演奏した。
当時の札幌は人口17万人ほどの地方都市であったが、名ヴァイオリン奏者のハイフェッツなど多くの海外の一流音楽家が訪れており、洋楽への関心は高かったであろう。ネヴォという名曲喫茶があり、早坂と伊福部は毎週土曜夜に足を運んだ。10時を過ぎて彼らだけになると主人が目当ての現代音楽をかけてくれる。当時の日本のレコード会社は海外の新譜をそのまま全部プレスしており、毎月買込んでいる新譜を聴かせてもらっていたのである。
住込みの教会オルガニストをしており、神父になることも考えていたが、日本放送協会懸賞作曲賞で『二つの讃歌への前奏曲』が2位となり、作曲家になる決心をする。
そして1938年に『古代の舞曲』がワインガルトナー賞を受賞し、披露演奏会のために上京した際、東宝入社を強く勧められた。東宝の社長は植村泰二で、北大卒業生であり札幌音楽普及会を創設するなど札幌の音楽界に力を尽くしてきた人物。悩んだが、半年後に上京した。
その後、年に3~4本のペースで映画の作曲を行い、特に「羅生門」「七人の侍」など黒澤明監督作品を手がけており、毎日映画コンクール発足から4年連続で音楽賞を受賞するなど、顕著な功績をあげている。映画の仕事を単なる生活の糧としてではなく、「音が映画の上においてもっと大きな地位を占めるべきだ」と考え、いろいろ試み真剣に作曲をしていた。純音楽では“新作曲派協会”を組織し、常に新しい可能性を探って作品を生み出していた。
24歳で肺結核の診断を受け、その後幾度かの入院療養をしつつも精力的に作曲を行っていたが、1955年、41歳の若さでこの世を去った。もう少しでも長く生きることができれば、どのような音楽が生まれていただろうか。
■雅楽について
『左方の舞と右方の舞』の左方、右方は雅楽の言葉である。
雅楽とは、もともと古代中国の儒教の礼楽思想、つまり正しい行いと正しい音楽が相応するという考え方に基づく音楽を指し、儀式のための音楽であった。日本は古くからアジア大陸と交流があり、6世紀に朝鮮半島から、7世紀には中国から音楽が伝わり、その後も様々な芸能が渡来した。9世紀、平安時代になるとそれらが整理体系化され、中国系を「唐楽」、朝鮮半島系を「高麗楽」と呼ぶようなった。平安京の構造がそうであったように、当時は対称性、対照性が重んじられており、楽器や人の位置なども左右対称であった。唐楽が左方に、高麗楽は右方に配され、交互に演じられる。また、それまでに多種多様な楽器が伝来したが、それも淘汰された。
野外で奏され舞をともなう舞楽は、絃楽器は用いられず管楽器と打楽器のみの編成で、唐楽と高麗楽では用いる楽器が一部異なる。左舞はメロディに合わせて振付けられているのに対し、右舞はリズムに合わせて振付けられているといった違いもある。
雅楽は、あまり変化することなく伝承され古典的なレパートリーが中心であるが、近年は国立劇場が作曲家に新作雅楽を委嘱しており、最初の試みは黛敏郎「昭和天平楽」(1970年)で、その後多くの作曲家が手がけている。中でも武満徹「秋庭歌」(1973年)は評価が高く、その後追加作曲され「秋庭歌一具」として頻繁に演奏されている。
■日本的なもの
早坂が、雅楽をテーマにした、あるいは雅楽の雰囲気を持つ作品を多く残したのは、飛鳥、奈良、平安朝への憧れがまずある。もう一つは作曲家チェレプニンの影響もあるのではないか。『古代の舞曲』に着手した後ではあるが、チェレプニンの指導を受け、より「日本的なもの」とは何かを意識するようになっていく。
彼にとって「日本的なもの」の表現は、単に民族的な素材を用いるということではなく、民族の本質が現れ、かつ時代的に発展性を有するものでなければならなかった。その後は「汎東洋主義(パンエイシャニズム)」を提唱している。西洋音楽に抵抗するところに東洋音楽の新しい様式が生まれる。例えば、東洋の感性に従った無限形式、欧州のような合理的なリズムではない割切れない刻み方、東洋的な感性の無調音楽で新しい音楽を生み出そうと考えた。
日本的・東洋的な美学を生かす作風は、多くの作曲家が影響を受け、特に早坂の映画音楽の助手をつとめ、その仕事を通じてオーケストレーションを学んだ武満徹は『弦楽のためのレクイエム』を早坂に捧げている。
『左方の舞と右方の舞』は、雅楽的な響きではあるが、具体的な雅楽の素材は使わずに、雅楽から喚起されて作曲したオリジナルである。早坂の代表作の一つである。1941年8月19日に完成、植村泰二に献呈された。
典雅な、優美な、清澄な、高貴な、おおらかな、透徹した、そうして簡潔にして抑制した日本美の核心的情操を表現したいと思ったのだ。われわれが日本の伝統を憶憬することは、それは宮廷のみやびを慕い、宮廷のみやびを習うことに尽きるのではあるまいか。これは悠遠のむかしから今日に至るまで、日本の伝統感覚として、われわれの心底に湧き出て、一貫して流れた国民的感覚なのである。
(再演時のプログラムの作曲者のノートより)
左方の主題と右方の主題が交互に出現し、左方→右方→推移部→左方→右方→推移部→展開→コーダといった構成となっている。
まず木管楽器の重音による笙を想わせる響きで左方の舞が開始される。笙は左方のみで用いられる慣例がある。この響きと同時に、打楽器が左方の鞨鼓の奏法であるトレモロを鳴らす。この序奏からAndanteへと入り息の長い旋律を奏していく。ここでは五音音階が用いられており、この旋律は2回繰り返される。そしてオーケストラが重層的になって左方の主題がffで示される。
次にModeratoの右方の部分へと入る。一定したリズムパターンが示された後、木管楽器群のユニゾンで右方の主題が現れる。このメロディが数回繰り返されて、厚みを増して広がっていき、やがて静まると推移部を経て、笙の響きで再び冒頭のLento nobileとAndanteの左方の部分が復活し、短縮された形で奏される。次の右方の主題は従前と異なるリズムパターンを伴って現れ、弦楽器で1回だけ奏される。再び推移部では左方の要素である打楽器のトレモロで始まり、右方の主題のリズムによる半音階下降で終わる。そして突然に全合奏の強奏となり、力強い新しい主題が弦楽器で奏され、これに左方の主題が挟まれて、始めの部分では見られなかったような濃密なテクスチュアで新しい展開を見せる。クライマックスを形成し、やがて打楽器のリズムと弦楽器の重音によるコーダへと導かれていく。静的に不動に持続され、消えるように終わっていく。
初演:1942年3月3日、マンフレート・グルリット指揮、東京交響楽団、日比谷公会堂
楽器編成: ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン2、テューバ、ティンパニ、ウッドブロック、トライアングル、小太鼓、カスタネット、シンバル、大太鼓、タムタム、チェレスタ、ハープ、弦五部
参考文献
秋山邦晴(編集・構成)『新交響楽団第83回演奏会〈日本の交響作品展3「早坂文雄」〉』パンフレット 1979年
木部与巴仁『伊福部昭の音楽史』春秋社 2014年
佐野仁美『武満徹と戦前の「民族派」作曲家たち-清瀬保二、早坂文雄と「日本的なもの」の認識について』神大学表現文化研究会 2011年
寺内直子『雅楽を聴く―響きの庭への誘い』岩波書店 2011年
組曲『惑星』にかかわる3つの話題
◆惑星と遊星
夜空に煌めく星々の中で、またたくこともなく明るい光を放ちながら独自の動きをする5つの星(水金火木土星)に、人々は古代から注目していた。例えばその星々の動きによって将来の吉凶を占う「学問」を生み出している。ギリシャ人はこの5星を「プラネーテース(πλανήτης)」と呼んだ。そもそもは「放浪者」を表す語だという。1年をかけて天空を規則正しくひと巡りする恒星の間をうろうろしている放浪者の意だ。
言い得て妙とすべきだろう。ラテン語のplaneta、英語のplanetはいずれも放浪者を語源とするという訳だ。
さて、この星の放浪者の訳語としてわが国では「惑星」の語が定着している。ホルストの作品名も『組曲「惑星」』で、これは当然のように受け容れられている。では「遊星」という語を見聞きした事はないだろうか?実はこれは惑星と同じものを指すもうひとつの訳語なのである。
明治の開化期に西洋の天文学が日本に入ってきた際、"planet"の語を東京帝国大学では「惑星」、京都帝大では「遊星」と訳し、それぞれの学派が代々研究の場で使用して現代に至る・・・・・というような話を読んだ事があって長い間信じ込んでいた。だが今回改めて調べてみるとこれは俗説で。既に江戸時代の蘭学者が、遅くとも19世紀の初頭までに「惑星」「遊星(游星)」の語を用いて天文書を訳出しているようだ(前者の方が後者に比して初出が100年ほど早い)。考えてみれば天文学は暦法と表裏一体の関係だから、改暦が何度も行われていた江戸時代には医学と並び、蘭学の柱のひとつだった。とすれば専門書の翻訳の過程でオランダ語"planeet"に行き当たらない訳がない。そこでそもそもの由来である放浪者の意を汲み、「惑」「游」などの漢字を当てて訳語を作っていた事になる。蘭学者や長崎の通詞らが行い続けた、語の原義に遡って適切な「漢語」を造語するという努力の蓄積が無ければ、後の日本の近代化のあり方も随分と違う形になっていたろうと考えざるを得ない。実際その時期に日本で造られた医学用語、例えば「血管」「細胞」「神経」・・・・・・などの和製漢語は、近代以後そのまま中国語の語彙に入って今に至るのである。因みにplanetは中国語では「行星」という。日本からの逆輸入の所産ではない。高度な天文観測が行われていた古代中国由来の語なのか?その歴史は今後調べてみたい。
◆冥王星の処遇
『惑星』をよく知らない人がこの曲に接して最初に持つ疑問のひとつに、組曲に入っていない星の件がある。ひとつは「地球」。これが入らないのは地球上に住む人類の目から捉えた惑星のみを対象としているという事で、太陽を巡る星々を俯瞰的に眺めた「科学(自然科学)」ではなく、例えばホルストが当初着目した「占星術」のような、謂わば人文科学的な視点から捉えた「惑星」に限定されているのだ。もうひとつが「冥王星」。こちらは発見されたのが1930年と新しく、ホルストが作品を仕上げた1916年時点には「存在」していない星だったので、当然対象となり得なかった。ホルストは終曲『海王星』の末尾を女声合唱によるフェードアウトで太陽系の果てを示し、その先の無限の宇宙を暗示するように曲を完結させている。
ところが冥王星が発見された事によって俄かに落ち着かない人々が出てきた。例の「科学的見地」によって、『惑星』は未完成の作品とする声が上がったのだ。そこで『冥王星』を新たに加えて完結させたいという野心を抱く作曲家が幾人も世に現れ、「完成」を試みた(ホルスト自身は冥王星発見直後の1934年に死去)。最も有名なのはホルストと同国の作曲家コリン・マシューズ(Colin Matthews 1946~)の手になる『冥王星Pluto, the renewer=再生者の意)』だろう。plutoは冥府王すなわち死後の世界の王の意で(プルトニウムの語源でもある)「再生者」というのはどうなの?と個人的には思わざるを得ないが、2000年に完成されたこの曲はある時期結構演奏されていた。とはいえ前述のとおり本来『海王星』で静寂のうちに終わる曲なのだ。そのあとに堂々たる1曲が出てくるのは甚だ都合が宜しくない、という訳でマシューズは例のフェードアウト部分をカットしてそのまま『冥王星』に続くように改変している。流石にこの荒業に首を傾げる指揮者もいて、一旦オリジナルに従って曲を終え、改めて『冥王星』に入るという措置を採る人もあった。題して『組曲惑星(冥王星付き)』の出来上がり。イギリスでは人気が上がり、結構な頻度で演奏されたというから、日本人とは少し感覚が異なるように感じる。
だが・・・・・周知のとおり2006年になってご本尊の冥王星が惑星の座から転落し「準惑星」となってしまった。そもそも軌道が海王星の内側に入っていたり、当初考えられて大きさを遥かに下回り、地球の月ほどの大きさしかない事が分ったりと以前から怪しい存在ではあった。その後、より大きな天体が太陽系内で発見されたりしていよいよ危うくなっていた処で、決定打となったのは「太陽を巡る軌道付近に衛星以外の星が無い」との基準(定義)。これを冥王星は満たせなかったため格下げ処置を喰らってしまったのである。
今年になってNASAが惑星の新たな定義を提唱。それによれば冥王星はもちろん月もまた惑星なのだそうだ(何じゃそりゃ?)。だが冥王星が惑星に復帰できる可能性は極めて低いだろう。「発見」から80年余。紆余曲折の末に、ホルストの時代の常識からはずいぶんと遠い処まで来てしまった感がある。
時代のあだ花として「蛇足」を音にしたとしか言えなくなってしまった『冥王星』が、今後どのような運命を辿るか?を注視する事は、ホルストの『惑星』を語るうえで不可欠な材料となりそうな雲行きである。
◆ドアと合唱の問題
前述の『海王星』末尾で、ステージ裏から突如聞こえる女声合唱(4部)は神秘的で効果も抜群。その終わりに向かってのフェードアウトを、ステージにつながるドアを次第に閉めてゆく事で実現させるよう、ホルストはスコアに詳細な指示を書いている。作曲家は思いつきで熟慮の上で音符や指示を書けばそれで作業は終わり。あとは演奏者(指揮者)におまかせとなる訳だが、『海王星』の実際の演奏現場では解決・対処すべき問題がふたつ生じる(演奏の出来の問題は別枠で)。
ひとつは合唱の指揮の問題である。
指揮者が見えない場所で演奏する事になるので、ステージ上のオーケストラと如何に出を合わせるか?現在では指揮者の正面に小型カメラを置き、ステージ裏のモニターに指揮者を映して、それに合わせる事が出来るようになった。ちょっと想像しにくいかも知れないが、こうした方法をとった場合でも、合唱メンバーはそのモニターを直接見て演奏をする訳ではない。副指揮者を置き、その人がモニターから出のタイミングを測りながら合唱を指揮するのである。ステージとの間の距離によりあるため、表の指揮者のタイミングで出てもオーケストラとの音の間に遅れが生じてしまう。それを防ぐ為の措置で、副指揮者の存在は不可欠且つ重要なのである。故にモニター設備の無かった時代はどのように対処していたのか?その労苦は想像に余りある。閉まりゆくドアの隙間から懸命に指揮者の棒を目視で追いつつ、合唱に合図をしていたのだろう。そして終盤は、ドアの隙間も極めて僅かとなれば、逆にステージ上の指揮者が消えゆく音に合わせて棒を振っていた・・・・・としか考えられない。
もうひとつは如何にしてフェードアウトを美しく円滑に進め、曲を終息させるか?という問題。
確かにドアを徐々に閉めてゆくことで一定の効果は得られよう。だがステージの裏側はホール毎に広さも構造も千差万別だし、そもそもそこで音を出して客席に届かせる機能を備えてはいない(当たり前)。ステージと楽屋を隔てるドアもまちまちだ。残念ながらドアの開閉ひとつで素晴らしいフェードアウトが実現されるという事は「全く」期待出来ないのである。
とすれば当然対策が求められる。指揮者の考え方にもよろうが大別すれば2通りだ。すなわちドアを徐々に閉め(この「奏者」の役割も重要だ)、合唱者各々が譜面の指示通り声量を絞ってゆくのに並行して、
① 合唱の人数を徐々に減らす。
② 合唱の演奏位置を徐々にステージから遠ざける。
である。①は当然声量が落ちてゆくのでフェードアウトは容易になるが、声の「厚み」が喪われてしまうという弊害が生じる。声の幅を確保するためには「最後の一兵(と言っても最低4名は残るが)」となるまで人数を絞るという訳にはいかず、そこには限界がある。
そこでもうひとつの策として②が出てくる。演奏位置を遠ざけると言っても、合唱の一団が何らかの乗り物で移動するのではない。銘々が「自分の脚」を使って移動してゆくのである。つまり歌いながら楽屋奥に歩くという方法。こうした場合最も注意すべきは客席に足音が聞こえてしまう事なので、メンバーはみな靴を脱ぐ。東京芸術劇場のステージ裏は無駄と思えるほどに広い。遠ざかってゆくための余地は充分なのだが、そこを裸足の女性ら(今回は約30名)がコーラスを繰り返しながら奥へ向かって歩き去ってゆく場面を想像すれば、この曲に対する興味のあり方もまた変わるのではあるまいか?
『惑星』の神秘的な終息は、文字通りの舞台裏でかくも涙ぐましい措置によって初めて成り立っているのである。この部分をカットするのも、終えてから更に『冥王星』を演奏するのも、余りに無粋と思えてしまう。如何なものだろうか?
オーボエ吹きの四方山話
<はじめに>
維持会のみなさま、オーボエの堀内です。いつも温かいご支援をありがとうございます。今回は維持会ニュースのご担当でもあり、オーケストラの中ではオーボエとは一蓮托生でありますフルートの松下さんより、何かオーボエにまつわることほか何でも良いので執筆を、とのご依頼(ご下命?)を頂戴しまして、不慣れなことこの上ないのですが、しばしお付き合いいただけましたら幸いです。
◆オーボエとは
みなさまは「オーボエ」と言いますと、まず思い浮かべるのは、コンサートで演奏が始まる前の音合わせ(チューニング)という方が多いかと思います。あるいはオーケストラの中では旋律を受け持つことが多い、はたまた、某国営放送のテレビなどで時折アップになりますとフルートやクラリネットが涼しげに演奏している横でオーボエだけが顔を真っ赤にして必死にくらいついていたり、何となく楽器の先端を見ては小首を傾げて気難しい顔をしているなぁ、といった印象をお持ちの方もいらっしゃるかも知れません。その全てがその通りでして、オーボエはホルンとともに世界で一番難しい楽器としてギネスブックに認定されているほど(どういう基準で選ばれたのかは謎なのですが・・・)、本当に難しく、しかも手間のかかる楽器なのです。
オーボエの魅力は何といってもあの音色です。印象的なフレーズを受け持つことも多いのですが、意外にも演奏で一般的に使われる音域は2オクターブ半程度でして、他の木管楽器(フルートが約3オクターブ、クラリネットは4オクターブ弱、ファゴットは約3オクターブ半)と比べても音域は限られています。また、楽器のメカニック(指を押さえる仕組み)も非常に複雑で運指もあまり合理的とは言えないうえに、とにかく狂いやすく(1つのネジが16分の1回転でもするともう音が出なくなり、そういうネジがざっと数えても20個以上ついています)、しかも吹くには楽器の先端にリードという2枚の葦を重ねたパーツをつけ、そこから息を吹き込んで演奏しないといけません。息を入れるところ(リード)の内径は細いところで3ミリ弱しかなく、極細のストローに常に息を吹き込んでいるのを想像するとお分かりいただけると思いますが、吹いているときは血圧も間違えなく上がっています。高血圧だと命がけです。したがいまして、フルートやクラリネットがたやすく演奏してしまうような指回りの速い曲は得意ではありませんし、口にも相当な負荷がかかり続けています。また、クラリネットのような小さな音を出すことも得意ではありません。どうしてこういう楽器を選んでしまったんだろう、と思うことが今でも年に4回くらいあります(演奏会の度⁉)。
◆標準的なオーボエ人とは?
こんな楽器を(不幸にも)選んでしまったオーボエ人にはどんな人が多いのか。良い音楽をやるためには一緒にやるメンバーの人間性を理解しておくことが非常に大切でして、これはオーボエに限ったことではないのですが、標準的なオーボエ人は、比較的真面目で常識的な人が多いです(自分で言うな‼と野次が聞こえてきそうですが・・・・・)。あと、こういう楽器を扱うには繊細、かつ神経質にならざるをえず(時々情緒不安定)、また、苦しいことにも耐えて喜びに変えられるような我慢強さや意志の強さも必要ですし、凝り性で頑固、他にも自己顕示欲が異様に強い人が稀に混じっているのも特徴でしょうか。指揮への憧れも強く、アマチュアで指揮をするオーボエ吹きにも割とよく遭遇します(かく言う私も学生指揮者をやっていました。今思うと恐ろしい話です)。プロの方でも、オーボエを吹きながら、或いはオーボエは潔くやめてしまい、指揮者に転身する人も少なからずいます。
◆オーボエ奏者の悩み
これは本当に沢山あるのですが、何かひとつと言われれば迷わず「リード」と答えます。オーボエを演奏する際に口で咥える部分でして、今では楽器屋さんで色々な種類のリードが売られていますが、それでも良いものは限られますし、全国のアマチュアオーボエ奏者(推定3,000人・・・・・本当か?)で奪い合いになります。そういった中、今日はマエストロとの合奏なのにリードがない、といった日には、練習場への足取りは確実に重くなります。ということで、やむなく自分で作ることになるわけです。
◆オーボエのリードができるまで
オーボエのリードは、実際に口にくわえる葦の部分とそれを巻きつけるチューブとに分かれます。
工程ですが、直径が1センチ程の葦をまずは3つに割り、長さを揃えた後にカンナのような機械で0.6ミリ弱まで薄くします(この工程も個人的には興味があるのですが、機械を揃えるのに数十万円かかり、また技術を習得する時間や作業時間も相応に必要なため、私はこの工程まで終わった材料を購入して、その先を自分でやっています)。
この段階ではかまぼこのような形をしていますが、次にこれをヘルトナーゲルという機械にかけて舟のような形にしていきます。実はこの形状も100種類以上ありまして、その中から自分の好みの型を見つけていくのが骨の折れる作業なのですが、知らないオーボエ吹き同士でも、何番の型を使っているの?・・・・・といった会話で盛り上がれるのもオーボエならではです。
ここまできますと、次はいよいよ材料をチューブに巻きつけます。材料の両端を少し削り水に浸したものを少しずつ糸でチューブに巻いていくのですが、ここが最も神経を使うところでして、材料にごく僅かにヒビが入ったり、目に見えないくらいの隙間ができたり、少しでも傾いたりするともう使えません。特にヒビが入ると微かに「ピキッ」という、いやーな音が聞こえて手にもその感触が伝わり、何とも言い難い絶望感に襲われます。一方、ここが上手くいくと、まだ先があることをすっかり忘れて相当テンションがあがってきます。意外と単純です。
いよいよ次は削りです。削りも完全に手作業でやる方もいるのですが、それでは時間もかかるし量も確保できないので、ここではメイキングマシンという機械を使います。これは型をなぞってカンナがけをするもので、理屈上はこの機械にかけるとードができあがります。ということで、この機械もそこそこ良い値段で売られています。私はドイツ製のものを使っていますが機械のつくりは意外にも大雑把、ただ、やることはとにかく繊細で、削る厚さも根元が0.5ミリ強、先端や両端に向けて少しずつ薄くなっていき、先端の両端は0.1ミリを僅かに下回る程度に仕上げていくので、途中で欠けたり、あるいは、あともう少しのところでヒビが入って廃棄になることもあります。ですので、私はほんの少し厚めに削って最後は手作業で仕上げていきます。メイドインジャパンの精巧な機械を誰か開発してほしいものです。
さて、ここまできてようやく楽器にリードをつけて音色や反応を確かめるのですが、相手は自然のもので繊維の太さや密度も1本1本違うため、10本同じように作っても吹き心地は1本1本違い、演奏会の本番で使える物はその中で1〜2本程度だったりします(最悪全滅の時も)。しかも寿命は長くても数カ月、ものによっては1回で見切ってしまうこともあるので、暇さえあればリードをいじっている感じです。こういう状況が恒常的に続くので、楽器を準備して直ぐに練習に取りかかれる楽器は本当に羨ましく思います。
それならリードが完成すれば一安心か、というと残念ながらそうでもなく、実は気温や湿度の変化にも影響を受けます。日本にはご承知の通り四季があり、特に冬場は乾燥します。リードは水分を含んでいないと音が出ないので、1月の演奏会はとても神経質になります。水入れを携帯してリードを抜いて水を含ませながら演奏することもよくあります。ただ休みが少ないとそうもできないので、霧吹きを舞台に持ち込んでシュッと吹きかければ良いのでは、と思いつき、我ながら流石‼と甚だしい勘違いをしたまま今年1月の演奏会(火の鳥)で実行に移したのですが、吹きかけた瞬間、霧はリードではなく自分の顔に吹きかかり、何をやっているんだろうと虚しさに襲われながら、その後必死に気をとり直して吹き続ける、という苦い思い出がまた一つ増えました。今は、オペラ歌手が良くやっているペットボトルにストローを挿してそれを飲めば良い(リードを湿らすのではなく自分の渇きを潤せば良い)のでは、というのが自分なりの答えでして、今度の冬にはそれを実行してみようと思います。
さて、そうなると梅雨は最高ですね、と言われそうですが、残念ながら梅雨は梅雨で色々と問題が出てきます。というのも湿度が高いと今度はリードが重くなってコントロールが利かなくなるのです。実際には少し薄めにしておくことで凌ぐのですが、そうやってリードを準備しても、たまたま練習の日が快晴だったりするともうお手上げで、オーボエを始めたての人が出すようなビャービャーな音になってしまうので、色々な状況を想定してリードを用意しておくことになります。ついでに、夏場ですと学生時代は志賀高原など高地でよく合宿をしたものですが、都内で吹く場合と高地ではまた状況が違って、高地で良かったリードが都内に戻るとビャービャーで全く使い物にならない、といったことは良くあります。
こういうことを初めから知っていたら、やっていなかったのかなぁと思うこともありますが、でも、そんなことを含めても意外と楽しいもので、一人リードと向かい合っている時間もニンマリしながら幸せを感じていたりします。ここまでくると、もう立派なオーボエ中毒奏者の出来上がりです。
◆好きな作曲家
話題はガラッと変わりまして、好きな作曲家をどうしても一人と言われたら、これはもうブラームスですね。交響曲は4曲とも大好きですし、ヴァイオリン協奏曲の第2楽章の冒頭には、ヴァイオリニストも思わず嫉妬してしまうオーボエの美しい旋律が出てきます。理屈抜きで感覚的に身を委ねられる、あの雰囲気は本当に最高です。
あとはモーツァルトも好きですね。交響曲、オペラは言うに及ばず、個人的にはフルートとハープの協奏曲やクラリネット協奏曲や五重奏曲の緩徐楽章がたまらなく好きです。もれなく泣けます。
◆身構えてしまう作曲家
好きな方には本当に申し訳ないのですが、(この際どさくさ紛れに)私が身構えてしまう作曲家にも触れておきますと、それはワーグナーとリヒャルト・シュトラウスです。スコア(総譜)を見ますと、野心剥き出しでオーケストラの楽器を駒のように扱い、上から目線でやってみろ!と半端ない威圧感で言われている気がして、演奏するときも聴くときも相当身構えてしまいます。やればやったで音楽のうねり巻き込まれて、最後はもの凄く充実感が得られるのですが、そこまでいくのが大変で、毎回、本番でもリハーサルでもエネルギーを吸い取られる感じがします。ただシュトラウスも晩年に作曲されたオーボエ協奏曲はしなやかで色の変化が本当に美しく、戦争(第二次世界大戦)の影響があったとすれば手放しには喜べないですが、純粋に大好きな曲の中の1つです。
◆新響での失敗談?
私は1995年に新響に入団して早いもので20年強が過ぎました。入団以来、諸先輩は変わらず大活躍していますし、年齢は平等に1つずつ増えていくので、未だに若造気分が抜けませんが、気づけば「本当に」若い人も増えてきて、私も歳をとったんだなぁ、と当たり前のことを今更ながら感じる毎日です。他愛のない話続きで恐縮ですが、他人の不幸は蜜の味?なんだそうで、私の失敗談をいくつかご紹介します。
・飯守泰次郎先生のリハーサルにて
飯守先生のリハーサルは緊張の連続で、毎回、容赦ない指示が次から次へと浴びせられます。常に音楽に献身的で、多くの調性からのインスピレーションや、「音程は宇宙からいただくもの」、といった名言も私たちの心に深く刻まれることとなりました。
『トリスタンとイゾルデ』のリハーサルだったと思いますが、飯守先生いわく「そこの木管楽器が大きい、どうしてそういう音を出すのですか、信じられません・・・(以下続く(結構長いんです))、もう1回!」(演奏する)、「オーボエ、もっと小さく!」 (演奏する)、「まだ大きい」 ・・・と何度か繰り返す中、こちらも必死に音を絞っていくわけですが、ついには音がかすれて出なくなってしまい「しまった」と思った瞬間、飯守先生は「それです‼素晴らしい‼みなさんやればできるんです‼」と満面の笑み。きっと飯守先生の心の中では、素晴らしいオーボエの音が響いていたに違いありません。どんな音がしていたのか、是非とも聴いてみたいものです。
・小松一彦先生のリハーサルにて
小松先生も非常に独特な世界観をお持ちで、強烈な個性と毒が非常に魅力的なマエストロでありました。リハーサルでも独特な言い回しで音楽を作り上げていくプロセスがとても充実していて、もっと新響を振っていただきたかったと思う指揮者です。
そんな小松先生との、ドヴォルザークの交響曲第8番第2楽章のリハーサルでのことです。小松先生いわく、この楽章のイメージを一言で言うと「ロマン派のフライ盛り(ゆっくり粘っこく言うのが小松先生スタイル)。そういうつもりでオーボエもソロを吹いてください。」と。私は正直???マークが頭を支配していたのですが、何とか応えようと必死で、ロマン派に衣をつけて揚げるとこってりしたこんな感じかな、と想像力をこれ以上ないくらいに膨らませて演奏。それを聴いた小松先生も頷いて先に進まれたので、まぁ、そういうことだったのかと自分を納得させ、忘れないように私のパート譜にもその旨、書き込んでその日は帰宅したのですが、後日、ヴァイオリンをやっている妻がその書き込みを見つけて大爆笑しているではないですか。妻いわく、小松先生が言ったのは「ロマン派の暗い森」。私は間違えなく「フライ盛り」と聞いて、自分なりにイメージを膨らませて演奏して小松先生も頷いたのに、その想いをどうしてくれる‼、とその時は正直思いましたが、今にして思うと「暗い森」が正しかったのかなぁ、という気がしています。
・演奏会当日、楽器がない‼
2011年7月の演奏会はすみだトリフォニーホールでの演奏会で、その日はハイドンの交響曲第101番の時計が出番でした。当日、2歳目前の娘を抱っこヒモで抱え、着替えやオムツ、ごはんやおもちゃなどをコロコロ鞄に詰めて引きながら、リュックにオーボエやリード、譜面など一式を入れて、錦糸町駅からホールに向かっている筈でした。しかし、ホールの前に来た時に楽器一式が入ったリュックがないことに気づき、妻が持っているかと尋ねたものの持っていない、と。これは大変‼と子供と荷物は託して錦糸町駅に戻り捜索願。駅員さんも「出てこないかも知れませんね、まぁ今日は無理でしょう」と何とも冷たい反応。今日は演奏会なのに。その後しばらくして千葉駅にリュックの忘れ物があるらしいとの情報に、すがる思いでたまたま来た特急電車に飛び乗り千葉駅では猛ダッシュ。駅員室に着くと、そこには私のリュックがあるではないですか。急いで受け取り反対の電車に飛び乗り、何とかホールの舞台袖にたどり着いたのが、時計のリハーサルがちょうど始まり第1楽章の序奏がホールに鳴り響いているところでした。嬉しいやら気まずいやら恥ずかしいやら、複雑な思いでリハーサルに合流して何とか演奏会本番も自分の楽器とリードで務めることができました。その日の本番のことはあまり思い出せないのですが、その前の出来事は今でも鮮明に残っています。娘を忘れなくて良かったね、と多くの方から慰めてもらい、もうやるまいと固く決意をしたのですが・・・・・。
・あれ、また楽器がない?
これは今年の2月のことですが、『こうもり』序曲と『人魚姫』の初回のリハーサルに行く途中、電車の乗り換えで娘に気を取られて、またまた楽器を電車に忘れてしまいました。前回はオーボエだけでしたが、今回はオーボエとコールアングレ(イングリッシュホルン)が入ったケースでしたので、前回以上に気づいた瞬間には頭が真っ白になりました。こちらもすぐに捜索願を出し、奇跡的に先の駅で見つけてもらい、2本とも無事戻ってきました。めでたし、めでたし。3度目がないよう、気をつけます。反省。
◆オーボエ族の仲間
オーボエ族としてオーケストラで使われるのは、オーボエと、ドヴォルザークの交響曲第9番の第2楽章『家路』で出てくるコールアングレ(イングリッシュホルン)が一般的ですが、この他に、今度の演奏会で取りあげますホルストの『惑星』では、バスオーボエという珍しい楽器が登場します。長さはちょうどオーボエの2倍くらい、ふくよか、かつ独特な音色で、曲中でも非常に効果的に使われています。是非、当日は耳を澄ましてお聴きいただけましたら幸いです。
<終わりに>
拙い文章に最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。
オーボエは本当に手間のかかる楽器で悩みも尽きないのですが、それでもこの楽器が好きですし、週末の度に無意識のうちに身体が新響の練習にむかうのも、オーケストラが、そして一緒に演奏する仲間が好きだからだと思います。更に、演奏会では維持会のみなさまをはじめとするお客さまとも同じ空間で音楽を共有できるわけでして、これは何よりの喜びです。いつまでできるか分かりませんが、これからも仲間とともに大好きな音楽を1つ1つ大切に紡いでいきたいと思います。今後とも末長く、お付き合いいただけましたら幸いです。引き続き、宜しくお願いいたします。
第239回ローテーション
| 左方の舞と右方の舞 | 曼荼羅交響曲 | 惑星 | ||||
| Fl | 1 | 吉田 | 1 | 吉田 | 1 | 松下 |
| 2 | 石川 | Picc. | 松下 | 2 | 石川 | |
| Picc. | 岡田 | ― | ― | 3/Picc.1 | 岡田 | |
| ― | ― | ― | ― | 4/Picc.2 | 藤井 | |
| ― | ― | ― | ― | AltoFl/1'' | 新井 | |
| Ob | 1 | 宮内 | 1 | 岩城 | 1 | 堀内 |
| 2 | 岩城 | E.H. | 山口 | 2 | 平戸 | |
| E.H. | 堀内 | ― | ― | 3 | 岩城 | |
| ― | ― | ― | ― | BassOb. | 【賛助】 | |
| ― | ― | ― | ― | E.H. | 山口 | |
| Cl | 1 | 高梨 | 1 | 高梨 | 1 | 品田 |
| 2 | 石綿 | EsCla. | 末村 | 2 | 中島 | |
| BassCla. | 岩村 | BassCla. | 岩村 | 3 | 進藤 | |
| ― | ― | ― | ― | BassCla. | 岩村 | |
| Fg | 1 | 田川 | 1 | 浦 | 1 | 浦 |
| 2 | 笹岡 | Contra | 田川 | 2 | 藤原 | |
| ― | ― | ― | ― | 3 | 笹岡 | |
| ― | ― | ― | ― | Contra | 田川 | |
| Hr | 1 | 大原 | 1 | 大内 | 1 | 山口 |
| 2 | 市川 | 2 | 菊地 | 2 | 菊地 | |
| 3 | 松尾 | ― | ― | 3 | 大原 | |
| 4 | 宮坂 | ― | ― | 4 | 大内 | |
| ― | ― | ― | ― | 5 | 松尾 | |
| ― | ― | ― | ― | 6 | 市川 | |
| ― | ― | ― | ― | 1assi | 宮坂 | |
| Tp | 1 | 倉田 | 1 | 倉田 | 1 | 小出 |
| 2 | 中川 | 2 | 中川 | 2 | 青木 | |
| ― | ― | ― | ― | 3 | 北村 | |
| ― | ― | ― | ― | 4 | 野崎 | |
| Tb | 1 | 日比野 | 1 | 日比野 | 1 | 武田香 |
| 2 | 志村 | 2 | 岡田 | 2 | 志村 | |
| ― | ― | ― | ― | 3 | 岡田 | |
| ― | ― | ― | ― | Tenor Tuba | 武田浩 | |
| Tu | ― | 土田 | ― | 土田 | 土田 | |
| Timp | ― | 桑形 | ― | 古関 | 1 | 古関 |
| ― | ― | ― | ― | 2 | 桑形 | |
| Perc | シンバル | 鈴木(*) | ヴィブラフォン | 鈴木(*) | シンバル・鐘 | 鈴木(*) |
| 小太鼓 | 今尾 | 小物各種 | 梶尾(*) | 大太鼓・トライアングル | 梶尾(*) | |
| ウッドブロック・トライアングル | 梶尾(*) | 小物各種 | 笠原(*) | 小太鼓・木琴・鉄琴 | 今尾 | |
| 大太鼓 | 古関(*) | 鐘ほか | 桑形 | タムタム・タンブリン | 笠原(*) | |
| カスタネット | 古関 | ― | ― | ― | ― | |
| タムタム | 笠原(*) | ― | ― | ― | ― | |
| Harp | ― | 見尾田(*) | ― | 見尾田(*) | 1 | 見尾田(*) |
| ― | ― | ― | ― | 2 | 小野(*) | |
| Vn | 1 | 堀内(滑川) | 1 | 堀内・小松 | 1 | 堀内(小松) |
| 2 | 中島(朝倉) | 2 | 中島・内田智 | 2 | 内田智(中島) | |
| Va | 村原(槇) | 村原・槇 | 槇(小畑) | |||
| Vc | 柳部(大庭) | 柳部・安田俊 | 柳部(安田俊) | |||
| Cb | 中野(郷野) | 中野・植木 | 中野(郷野) | |||
第239回演奏会のご案内
イギリスの名曲と邦人作品
指揮者の湯浅卓雄氏は、イギリスを中心に国際的に活躍しており、CDレーベルのナクソスとは専属契約を結び、中でも「日本作曲家選輯」で多くの録音を残しています。今回の演奏会では、イギリスの作曲家ホルストの代表作である組曲「惑星」と、日本人作曲家の作品を2曲演奏します。
惑星=宇宙のシンフォニー
「惑星」が作曲されたのは1914~16年。バスオーボエやテナーテューバなどの特殊楽器を含む大編成管弦楽にオルガンと女声合唱が加わり、色彩的で迫力のある作品となっています。ホルストは占星術から構想しており、地球を除いた太陽系のそれぞれの惑星にキャラクターが記された曲が割り当てられています。メロディはとても親しみやすく、特に木星の主題の一つはホルスト自身により改作されイギリスの愛国歌「我は汝に誓うわが祖国よ」となっており、日本でも平原綾香が「Jupiter」として歌い、大ヒットさせています。
左方の舞と右方の舞
早坂文雄は1914年生まれ札幌育ち、ほぼ独学でピアノを習得、同じ歳の伊福部昭と出会い、来札したロシア人作曲家チェレプニンに師事し作曲を続けました。23歳の時にワインガルトナー賞受賞がきっかけで東宝に入社し映画音楽を手がけ、特に「羅生門」「七人の侍」など多くの黒澤作品で音楽を書いています。同時に交響作品にも取り組み、今回演奏する「左方の舞と右方の舞」は1941年に書かれた早坂の代表作です。日本的・東洋的な美学を生かす作風は後の世代の作曲家に大きな影響を与えました。その一人が黛 敏郎でした。
雅楽において、左方は中国・インドを、右方は朝鮮半島を源流とする舞を指します。2つに分けるのは陰陽、つまり宇宙のすべての事物は陰と陽に分けられるという思想からきています。また、雅楽で用いられる管楽器は、笙が天、龍笛は空、篳篥は地を現わし、それぞれが重なり一つの宇宙となるのです。
曼荼羅交響曲
黛 敏郎は1929年生まれ、東京音楽学校(現東京藝術大学)を卒業してパリ音楽院に留学するも「もう学ぶことはない」と1年で帰国。電子機器を用いるなど前衛的な音楽を生み出す一方、1958年には梵鐘の音響を分析し管弦楽で再現した涅槃交響曲を作曲し、その後は日本的な作品を数多く残しました。また、数多くの映画音楽を書き、「題名のない音楽会」では司会を32年続けるなど、戦後のクラシック音楽界のスターでした。
涅槃交響曲の2年後に、同じく仏教思想を音楽にしたのが「曼荼羅交響曲」です。曼荼羅とは、密教の儀式に用いる仏の描かれた図のことで、思想の宇宙観を示すものです。
宇宙に思いを巡らすコンサート
科学が進み、宇宙が解明されつつある現代に比べ、昔の天文学は生活や政治、宗教に密着しており、人々は宇宙をより身近に感じていたのかもしれません。音楽の宇宙の中に身を置いてみませんか? どうぞお楽しみに!(H.O.)
ニールセン:交響曲第4 番「不滅」
カール・ニールセン(1865-1931)はデンマークに生まれ、デンマークで学び、デンマークを拠点に活動した、まさに同国及び北欧を代表する作曲家である。大きな戦乱に伴うデンマークの激動の時代において優れた作品を遺し、不滅の精神性を体現したとも言える人物であった。
1 時代背景
ニールセンが活躍したのは主に19世紀末から20世紀初頭にかけてであるが、これは北欧において、ちょうど他の大作曲家も登場していた時期にあたる。その先駆者とも言うべき人物は、ノルウェーを代表する作曲家グリーグ(1843-1907)であり、1868年にかの有名なピアノ協奏曲を作曲するなど、ニールセンよりも一足先に北欧音楽界での足跡を残している。また、フィンランドの巨匠、シベリウス(1865-1957)は、実はニールセンと同じ年の生まれである。ニールセンが交響曲第4番を完成させた1916年時点においては、フィンランディア(1899年)、交響曲第2番(1901年)、ヴァイオリン協奏曲(1903年)等、既に代表作を世に送り出していた。
また、ニールセンは6曲の交響曲作品を残しているが、交響曲の主流であったドイツ・オーストリアに目を向けると、1896年にブルックナーが交響曲第9番を、1909年にはマーラーが交響曲第9番を、それぞれ作曲している。両者とも、これら最後の交響曲の作曲後まもなく死去していることから、ドイツ系交響曲の歴史は終焉を迎えつつある時代であったといえる。一方で、シェーンベルクが確立した十二音技法による無調音楽への関心が高まりつつある時期でもあった。
2 作曲家としての軌跡
ニールセンは、1865年6月5日に、デンマークのノーレ・リュンデルセにて生誕した。童話作家として名高いアンデルセンの出身地である小都市オーデンセに近い農村地帯であり、四季の変化や起伏豊かな丘陵景観等といった幼少期の自然体験が、ニールセンの独自性ある作風に大きな影響を与えたと言われている。
ペンキ職人であった父は、12人の子沢山の家庭であったが故に生活は困窮していたが、音楽の嗜みがあり、村の楽隊でヴァイオリンとコルネットを演奏していた。ニールセン自身も、6歳のときに父からヴァイオリンを学び、父と同じ楽隊で演奏するようになっていった。貧しい家庭事情もあり本格的な音楽のレッスンを受けてはいなかったものの、即興的に演奏したり自分でメロディを作り出したりするなど、作曲家としての才能の片鱗を見せていたようである。
ニールセンが本格的に音楽の勉強を始めたのは、1884年、19歳のときに首都コペンハーゲンの王立大学院ヴァイオリン科に入学してからであった。デンマークの作曲家、指揮者として絶大な勢力を持っていたゲーゼにその才を見出され、ヴァイオリン奏法のみならず作曲法、音楽理論について学ぶ機会を得たと言われている。1888年に卒業するまでの間、初期の作品群は、ニールセンにとって身近な楽器であったヴァイオリンを用いた、弦楽器の小曲が主なものとなった。
音楽院を卒業後、ニールセンは1889年に王立劇場に第2ヴァイオリン奏者として入団した。1905年に退団するまでの間、演奏活動を通してオーケストラの各楽器の機能について精通していく中で、作曲家としては次第に交響曲やオペラにも取り組むようになった。交響曲第1番(1892年)、オペラ「サウルとダヴィデ」(1901年)、交響曲第2番「4つの気質」(1902年)、オペラ「仮装舞踏会」(1906年)等を次々と完成させ、ニールセンはデンマーク国内における自身の地位と名声を着々と固めていった。
その功績が認められ、1908年には自身がかつて奏者として所属していた王立劇場の楽長に就任した。これは、ニールセンがデンマーク楽壇の第一人者として認められていたことを意味するものである。国内においては、その作品が高く評価されていただけでなく、カリスマ的な人格もあってか、後世の音楽家に大きな影響を与えることとなった。一例を挙げると、ニールセンは前述のシェーンベルクが確立した無調音楽に対し否定的な見解を持っていたことから、デンマークの王立大学院においてシェーンベルクは長い間タブー視されることとなった。他方、後述する特異性のある作風が、デンマーク国外ではなかなか受け入れられなかった面もあると言われている。
3 激動の時代において
1914年に勃発した第一次世界大戦は、ヨーロッパを混沌に陥れた。中立政策をとっていたデンマークも例外ではなく、強大な隣国ドイツに翻弄される小国ならではの悲哀といえる困難期を迎えることとなった。周辺海域において戦争が展開される中、国土を海で囲まれ海運に頼らざるを得ないデンマークでは、次第に食料等の生活物資や工業の原材料、石炭等が欠乏するようになった。産業の停滞、それに伴う失業、インフレ等が引き起こされ、国民生活は厳しいものとなっていった。
本日演奏する交響曲第4番は、ニールセンがこの1914年に作曲を開始し、大戦の最中であった1916年に完成させたものである。本作品には、“Det Uudslukkelige”(英訳は“The Inexstinguishable”)とデンマーク語のサブタイトルが付けられた。日本では一般に、本日のプログラムにも記載があるとおり「不滅」と訳されるが、拡大する戦争への不安、戦争に伴う経済状況の悪化といった、苦難の時代に直面したデンマーク国民の心情やニールセンの意志に鑑み、「滅ぼし得ざるもの」と訳すのが妥当であるとする説もある。
ニールセン自身は、総譜の前書きにおいて、「この題名によって、音楽だけが完全に伝えることができるひとつの言葉、生への根源的な意志、を示そうとした。」「音楽は生命で、そしてそれに似て『不滅』である。この交響曲は、偉大な芸術のみならず、人間の魂までもが『不滅』であることを強調すべく意図されたものである。」等と述べている。自身の音楽への気概、戦争の嫌悪、生への希求等といった思いが読み取れる記述であるといえる。
一方で、ニールセンはこのサブタイトルについて、「これは標題ではなく、ただ音楽に近づくための提言に過ぎない。」とも付け加えていることから、「不滅」とは、曲全体を貫く精神的なシンボルとして捉えるべきものと解釈されている。
4 不滅
ニールセンの作品の特徴としては、非伝統的な調性の導入、主題を何層にも多声に展開させていく作曲方法及びそこから生み出される緊張感、リズムや強弱の急激な変化等が挙げられる。これらは、当時のデンマーク国内では耳慣れない斬新性をもつものであり、デンマークにおけるロマン主義音楽からの脱皮を決定的なものにしたと言われている。
交響曲第4番についてであるが、まず本作品は一般に、伝統的な交響曲のように「何調」と記されることがない。これは、調の選択において、基本調とそれに対応する調との対比といった構成がとられていない、非伝統的な調性が導入されていることに起因する。
また、本作品は単楽章制をとっているが、その中でも4つの楽章要素から構成されている。実質的には古典的な4楽章制の交響曲に近いものとなっているが、これらの楽章要素がブリッジ風の楽句によって全く切れ目がなくつなげられることで、自然に次の要素へと順次移行するように作られている。
第1部では、冒頭で躍動感に満ちた激しい主題が示されるが、この主題はその後も形を変えて何度か登場する。これに対し、穏やかで優美な旋律が2本のクラリネットにより奏でられるが、後に第4部でも再現され、全曲が大きな一つの楽章になるよう統一する役割を果たす。
ヴァイオリンのブリッジを経た後に、田園舞曲風の気楽な雰囲気が漂う旋律が木管楽器により自然と奏でられるのは、第2部である。これと対照的に、ヴァイオリンが突如として、緊迫感と悲劇感のこもった旋律を奏で始めるのが、第3部となる。
第4部は、躍動感あふれるメロディで始まる。途中から登場する1人を加えた2人のティンパニ奏者による強烈な連打が印象的であるが、これが戦争に関連させたものであることを、ニールセン自身も認めている。クライマックスにおいては、金管楽器を中心に第1部の第2主題が力強く奏でられ、「不滅」をうたい上げるかのごとく、充実した響きの中に全曲を閉じる。
初 演: 1916年2月1日、コペンハーゲンにて自身の指揮によって行われた。
楽器編成: フルート3(うち1本はピッコロ持ち替え)、オーボエ3、クラリネット3、ファゴット3、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ2、弦五部
参考文献:『作曲家別名曲解説ライブラリー 北欧の巨匠 グリーグ/ニールセン/シベリウス』音楽之友社 1994年
『クラシック名曲ガイド①交響曲』音楽之友社 1994年
大束省三著『北欧音楽入門』音楽之友社 2000年
村井誠人著『デンマークを知るための68章』明石書店 2009年
ニコリーネ・マリーイ・ヘルムス著 村井誠人・大溪太郎訳『デンマーク国民をつくった歴史教科書』彩流社 2013年
チャイコフスキー: 幻想序曲「ロメオとジュリエット」
シェイクスピアを初めて読んだのは、19歳の夏のこと。冷房がよく効いた大学の図書館で、森永のビターチョコレートをぼりぼりと食べながら読んだのが、シェイクスピアとの出逢いであった。(記憶が鮮明なのは、チョコレートで本を汚してしまい、その罪を司書さんに告白したからである。ちょっぴり、叱られた。)
聴衆の皆様には、楽曲の音楽的理解だけでなく、とある19歳の日本人青年がそうであったように、シェイクスピアが紡いだ言葉の世界を堪能して頂きたく、譜例と共に、そのあらすじをご紹介したいと思う。
「ロメオとジュリエット」のあらすじ
舞台は、イタリア、花の都ヴェローナ。モンタギュー家の一人息子ロメオは、愛するロザラインへの恋が叶わず、思い詰めている。そんな彼を哀れみ、ロメオの友人であるベンヴォーリオは、他の美しい人を見ることを勧め、キャピュレット家の仮面舞踏会にロメオを誘う。 それが、天運の始まりであった。キャピュレット家に到着し、ロメオはひとりの佳人に出逢う。名は、ジュリエット。ロメオは、ジュリエットを一目見た時には、もう、昔のロメオではなかった。
“ ああ、あの人の美しさで、松明はさらに明るく燃えている!
ほかの女に立ち交じっているその姿は、純白の鳩がカラスの群れに舞い降りたよう。”
ロザラインへの恋が、本当の恋ではなかったように、ジュリエットの美しさに心奪われたロメオは、舞踏会が終わったのを見計らって、彼女に近づき、その前に跪くと、愛の言葉を囁き、唇をそっとジュリエットの頬に置いたのであった。 しかし、彼らの恋には残酷な運命が待ち構えていた。彼らの生家であるモンタギュー家とキャピュレット家はヴェローナを二分する宿敵であったのである。
“ 私のただひとつの恋が、ただひとつの憎しみから生まれるなんて。
この世に産声を上げたときから、この恋は許されるものではなかったのね。”
ロメオは、嘆いた。その運命を呪った。そして、決心をした。生家が宿敵同士であろうと、私の心は、ジュリエットに捧げるのだ。敵の家だとて、構うものか。ロメオは、キャピュレット家の高い石垣をひらりと越えて、庭の茂みを進むと、二階の窓から柔らかい光が漏れているのを見つけた。それは、バルコニーに佇む、ジュリエットその人であった。
“ おお、ロメオ、ロメオ、どうしてあなたはロメオなの?
憎い敵はあなたの名前だけ。名前になんの意味があるというの?
ロメオ、どうか、その名前だけを捨てて。
その名の代わりに、わたしのすべてを受け取って。”
チャイコフスキーの曲は、ここからはじまる。ああ、憎い。バルコニーのシーンを書かないなんて。しかし、名曲であるのは、変わらない。ここからは、譜例も共に紹介したい。
バルコニー越しに、愛を誓い合ったロメオとジュリエット。ロメオはすぐさま修道僧ロレンスの元に足を運ぶと、結婚をさせてほしいと嘆願する。
修道僧ロレンスは、ロザラインを愛していたロメオの恋の心変わりに驚きながらも、長らく続いた両家の確執が、彼らの結婚によって愛に変わるかもしれないと考え、結婚することを認め、人知れず、式を挙げたのであった。 式を挙げ、ふたりの愛は深くなったが、両家の確執も、また深かった。ロメオは式が行われたその日の内に、両家の争いに巻き込まれてしまう。
争いは激しさを増し、(管楽器による強い打音は剣が交わる音を表している。)とうとうロメオはジュリエットのいとこであるティボルトを殺害してしまい、ヴェローナを追放されることとなる。
そんな悲劇が起きれども、ロメオとジュリエットの愛は変わらない。追放される前夜に、ふたりは忍び逢い、お互いの愛を確かめながら、その不運を嘆くのであった。
“ 夜よ、どうか明けないでおくれ。
朝になれば、私は行かねばならない。
ああ、光が。あれは、太陽がもたらす妬み深い光だ。
立ち去って生きるべきか、留まって死ぬべきか。”
“ いいえ、違う。あの明るさは太陽のものではないわ、絶対に。
だからそばにいて。”
“ 君がそう言うならば、喜んで死のう。死よ、来るがいい!”
“ でも、駄目、ああ行って、もう明るくなってしまう。朝が来てしまった。”
“明るくなればなるほど、僕らの心は暗くなる。”
愛し合いながらも、引き裂かれてしまったふたり。修道僧ロレンスは、そんなふたりのために一計を案じる。それは、42時間だけ仮死状態となる薬をジュリエットに飲ませて、葬儀を行った後に仮死状態から蘇生をして、ロメオのもとに出奔させるという計画であった。
不安を感じながらも、仮死薬を飲み、その鼓動が止まったジュリエット。その死を知り、キャピュレット家の人々は、悲嘆に暮れ、早すぎる死を運んだ死神への怒りを口々に叫んだ。ただひとり、その真意を知っている、ロレンスを除いては。
静かな夜。厳粛な葬儀が行われ、ジュリエットは美しい花に囲まれた墓に横たわっている。そこに1人の男が訪れた。ロメオである。ロメオは驚き、嘆き、嗚咽し、絶望した。なぜか。ロメオは、ロレンスの計画を知らなかったのである。不幸にも計画を知らせる届けが、行き違って届かなかったのである。もう、愛するジュリエットは、この世にいない。ジュリエットが本当に死んでしまったと思い込んだロメオは、この世にいる理由はないと、毒薬が入った杯を飲み干し、その命に自ら終止符を打つ。(各主題が交錯し、音楽は激しくなり、叫びとも言えるような鋭い一音が、ロメオの死を表している。)
“ああ、恋人よ、私の妻よ。
息の根を吸い取った死神も、君の美しさには勝てないのだ。
どうして、君はまだ美しいんだ?
姿形をもたぬ死神は君に恋をし、君を愛人として、永遠に闇の中に囲い込もうとしているのか?
そうはさせるものか。わたしが、いつまでも君のそばにいよう。
薬屋よ、お前を信用していいな。愛するジュリエットのために。
ああ、こうして口づけをしながら、私は死ぬ。”
時は、残酷なり。ジュリエットは、起きた。ロメオが死んだあとに。愛とは、死か。それとも、死とは、愛なのか。ロメオと同じく、愛する人を失ったジュリエットは、静かに短剣を胸に突き立てるのであった。(ティンパニの一音が、ジュリエットの死を表している。)
“ 愛する人の手に握られた、この杯。この毒が、愛する人の死を招いたのだわ。
ああ、意地悪、すっかり飲み干して、一滴も残してくれなかったのね。
その唇にキスを。まだすこし、付いているかもしれない。
あれは人の声? 急がないといけない!
ああ、嬉しい、ロメオの短剣がここに。
あなたの鞘は、わたしの胸。
ここで錆びついて、わたしを死なせて”
曲は落ち着き、心臓の鼓動のようなティンパニの打音から、葬送行進曲が始まる。弦楽器による第二主題が憂いを帯びながら響き渡り、管楽器がコラールのような天上の音楽を演奏して、曲は終りを迎える。
以上が、あらすじと、簡単な譜例を用いた楽曲解説である。ここで、ひとつ疑問がある。ジュリエットが死に、葬送行進曲が流れ、天国の調べのような美しい曲想が流れる。天に召されたふたりは、結ばれたのだろうか。それとも……
音楽は、言葉がないのが幸せである。その結末は聴衆の皆様のご想像に任せたい。
初 演: 1870年3月4日、ニコライ・ルービンシュテイン
指揮ロシア音楽協会モスクワ支部第8回交響楽演奏会にて(ただし初稿版)
楽器編成: ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、大太鼓、ハープ、弦五部
参考文献: シェイクスピア(松岡和子訳)『ロミオとジュリエット』ちくま文庫 1996年
川端康成『川端康成全集第19巻』新潮社 1999年
松岡和子『深読みシェイクスピア』新潮社 2011年
リスト:交響詩「レ・プレリュード」
「─われわれの人生とは、その厳粛な第1音が死によって奏でられる未知の歌への前奏曲にほかならないのではないか?」
フランツ・リストは19世紀最高のピアニストとして名高い。人間離れした大きな手をもち、ダイナミックな演奏と巧みな技術で聴衆の心をつかむ彼の演奏会にはいつもあふれるほど人が押し寄せ、アイドル的な存在だった。その一方で、リストは作曲家としても大きな功績を残している。
『レ・プレリュード』は、リストが作曲した13曲の交響詩のなかで最も演奏される機会の多いものである。『レ・プレリュード』は日本では『前奏曲』と訳されることが多いが、フランス語の原題は『LesPréludes』であり、複数形(単数ならLe Prélude)。この理由は、冒頭に掲げた標題の一部のように、リストは「人生=死後に対する前奏曲」と捉え、数多の人生をあらわしているからである。
「交響詩」という形式は音楽史上リストが初めて提唱したものである。それまでの「交響曲」に対し、管弦楽曲にそれに対応する詩を結びつけ、詩の形式と音楽の形式を融合させることで、作曲家の想念が聴き手により正確に伝わるようになるとリストは考えた。リストが創始した交響詩は、その後もリヒャルト・シュトラウスをはじめとする多くの作曲家によってさまざまな作品が花開くジャンルとなった。
作曲の経緯はすこし複雑である。もともとは交響詩としてではなく、フランスの詩人ジョゼフ・オートランの詩に基づく男声合唱曲『四大元素』の序曲として作曲された。『四大元素』は「北風」、「大地」、「波」、「星々」の四部からなる合唱曲で、すでに『レ・プレリュード』に用いられる様々なモチーフを含み、それらには歌詞がついていた。たとえば、『レ・プレリュード』の冒頭に登場し、最も重要な主題は『四大元素』の「星々」にもみられ“hommesépars sur ce globe qui roule(この回転する地球上に散らばっている人間たち)”という歌詞が対応している。
ところが、リストは何らかの理由でこの序曲を『レ・プレリュード』という独立した交響詩として発表した。標題もオートランの詩からではなく、アルフォンス・ド・ラマルティーヌというオートランの師にあたる別の詩人の同名の詩『Les Préludes』から着想を得て、自身で新しく書き直したと言われている。
『レ・プレリュード』はリスト自身の記した標題に基づき、「緩・急・緩・急」と続く4部からなる。以下のそれぞれの部の冒頭に、標題の対応する部分を示す。
第1部 人生のはじまり─愛
「─われわれの人生とは、その厳粛な第1音が死によって奏でられる未知の歌への前奏曲にほかならないのではないか? 愛はあらゆる存在の夜明けの光である」
弦楽器の疑問符のようなピチカートに続き、最も重要な主題(譜例1)が弦楽器のユニゾンで示される。この主題は全曲を通してさまざまなかたちに変奏されていく。初めは生まれたてのように少し不安げに聞こえるが、だんだんと跳躍の幅を広げて緊張を増していき、頂点で12/8拍子に移行して低音楽器群の朗々とした歌へと引き継がれる。
そののち、冒頭の主題が穏やかなかたちに変形されてチェロ、ホルンに現れ(譜例2)、人生のはじまりの暖かい時期を示すようである。続いてヴィオラとホルンが奏でる愛のテーマもやはり冒頭の主題の変形である。これは『四大元素』の「大地」でも歌われる。
第2部 嵐
「─しかしどんな運命においても、嵐によって、幸せな幻影はそのひと吹きで吹き飛ばされ、祭壇は雷でこわされてしまう」
チェロによって弱音で冒頭の主題が奏でられるが、ここでは嵐を予感させる仄暗い色である。弦楽器のトレモロや半音階での昇降、減七の和音が嵐への緊張感を高める。
嵐がはじまるとトロンボーンが大きな風圧をもって冒頭の主題を鳴らし、たたきつける雨粒や雷のような鋭い音型も各楽器に現れる。そして、ホルン、トランペットがファンファーレのような音型を奏し、嵐の激しさは頂点に達する。
第3部 田園
「─嵐によって深く傷つけられた魂は、田園の静かな生活の中で過ぎ去った嵐の記憶を慰めようとする」
嵐が収まり、穏やかにオーボエとヴァイオリンがテーマを再現する。そして6/8拍子となりホルンから木管楽器群へと素朴な旋律があらわれ、愛のテーマも再び登場してともにうたい、のどかな田園風の音楽となる。
第4部 戦い
「─しかし人は自然の懐に抱かれる静けさにいつまでも浸っていることに耐えられず、“トランペットの警笛”が鳴れば危険な戦いの地へと赴き、自己の意識と力を取り戻す」
第3部の田園風の穏やかな気分は徐々に高揚していき、まさにトランペットによるファンファーレが現れるのをきっかけに音楽は前進する勢いをもって、2/2拍子の行進曲へ移行する。テーマがいずれも行進曲風のリズムに変形されて登場し、第1部の12/8拍子が再現されてクライマックスを迎える。
リストは、1855年に発表した「ベルリオーズと彼のハロルド交響曲」という論文の中で次のように述べている。「芸術における形式とは精神的内容の器、想念をおおうもの、魂にとっての肉体なのだから、形式はきわめて繊細に、内容とぴったり合っていなければならない」 交響詩『レ・プレリュード』はこのようなリストの理想をまさに具現化したもので、標題と密接に結びついた見事な変奏は、次々とあざやかな景色を描くのにとどまらず、リストの精神的な理想をも反映した壮大な作品である。
初 演:1854年2月23日、ワイマール、リスト指揮
楽器編成: フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、小太鼓、大太鼓、シンバル、ハープ、弦五部
参考文献:渡邊學而『リストからの招待状 大作曲家の知られざる横顔Ⅱ』
丸善ライブラリー 1992年
福田弥『作曲家 人と作品 リスト』音楽之友社 2005年
Rena Charnin Mueller, EMB Study Scores Les Préludes,Editio Musica Budapest 1996
ファゴットあるいはバスーン ~その秘密と魅力~
■ファゴット奏者の小さな悩み
ファゴットを演奏している者の悩みの一つ、それは楽器の知名度が世間的に低いということです。オーケストラの演奏に接する機会の多い維持会員の皆さんは、もちろんご存知の楽器だと思いますが、クラシック音楽に馴染みの少ない方々には、悲しいながら、21世紀の今日においても浸透しているとはいえない状況です。例えば、楽器を持って近所のクリーニング屋に寄ったとします。「あら、それ楽器? 何をやってらっしゃるの?」と、店のおばさん。「秘密です」とか気取るのもいかがなものなので、一応楽器名を言って説明を試みますが、だいたいは首を傾げられて終わりです。同じ管楽器でも、フルートやトランペットという名前を出せば、おばさんの反応や目の輝きは全く異なるでしょう。ですので、私は一般の皆さんには、楽器をやっていることをなるべくアピールしないようにしています。説明が面倒くさいからです。
というマイナー感溢れる話で始まりましたが、日本社会で有名か無名かは本質的にはどうでもよいことであり、ファゴットがオーケストラや室内楽にはなくてはならない楽器であることは間違いのないことです。あ、言い忘れましたが、ファゴットというのはドイツ語とイタリア語で、英語ではバスーン、フランス語ではバソンです。語源はいずれも「束ねられた2本の木」とのことですが、形状が酷似している兵器「バズーカ砲」も同じ言葉に起源を持つことが容易に想像できますね。
■オケの中で与えられる多彩な役割
外見の特徴は、何といっても長いことです。木管の他の楽器と比べて、圧倒的に長いですが、あれでも楽器の最下部において管がUターンしており、2本に折り畳まれている状態。もし真っ直ぐな1本の管だったら、とても普通の人が演奏できる代物ではありません。あとは、トーンホール(音を変えるための穴)を塞ぐためにキーがたくさん付いていることでしょうか。とにかく管体が長いので、遠隔地のトーンホールを塞ぐための仕掛けが大がかりになります。キーの数も多く、運指は極めて複雑。左手の親指では、何と10個のキーを操作します。などと言うと、他の楽器の方から「信じられなーい」と驚いてもらえることもありますが、要は慣れです。一度に出せる音は所詮一つですから、たいして自慢できることではありません。
それから、発音源にも少し触れておきましょう。ファゴットは、オーボエと同じように2枚の葦材を合わせたリードが発音源となります。2枚でできているので、ダブルリードです。「二枚舌」とも言われることもありますが、多分オーボエの人の方が嘘が上手いと思います。
外見や仕様はさておき、音楽的な特徴は、かなりの低音からある程度の高音まで、非常に広い音域の音を出せることがまず挙げられるでしょう。概ね3オクターブ半近くはいけます。また、ユーモラスな感じから、深遠な表現、心情を吐露するような泣きの表情まで、多彩な音色が出せることも特徴。音域や音色の幅が広いことは楽器の表現能力上、大きなメリットであり、オーケストラではかなり多岐にわたる役割を与えられます。チェロやコントラバスと一緒に低音域でオケを支えることもありますし、トロンボーンやチューバの咆哮に加担することもしばしば。木管のアンサンブルの土台となることもあれば、肉声的な音色を活かして中高音域で存分に歌うソロもあります。
■最も「人使いの荒い」作曲家は誰?
ストラヴィンスキーやラヴェル、リムスキー=コルサコフ、ファリァ、ショスタコーヴィチなどの近代作曲家たちは、楽器の特性を活かした「どソロ」*を書いてくれていて、それはそれで大変ありがたいのですが、ファゴットを演奏していて最も面白いと思えるのは、やはりモーツァルトとベートーヴェンでしょう。「どソロ」は少ないですが、全音符を吹いているだけで心から感動できるような役割を与えられています。いま流行りの言葉でいえば、使い方が「神」なのです。ファゴット吹きは、ウィーンの方に足を向けて寝ることはできません。
ちなみに、ファゴットに関して最も「人使いの荒い」作曲家は誰だと思われますか。私はチャイコフスキーだと思っています。今回演奏する幻想序曲「ロメオとジュリエット」でも、後半から終結部の最後の音まで、1番ファゴットには殆ど休みがありません。金管と一緒の強奏が終われば、今度はチェロと一緒に嘆き、その次は長い木管のコラール。正直、しんどいです。ただ、チャイコフスキーは、何かの嫌がらせで人使いが荒いのではなく、ファゴットという楽器がすごく好きなのでしょう。彼の交響曲には本当に魅力的なソロがたくさんあります。ありがたいです。「しんどい」とか愚痴を言っていると、バチが当たりますね。
■初心者でも「ひと山あてられる」かも
ところで、なぜ私は、わざわざオーケストラで最も知名度の低い楽器を選んだのでしょうか。行きがかり上、その辺のいきさつにも少し触れておきます。
私がちゃんと楽器を始めたのはけっこう遅く、高校に入学してからです。中学の途中から突然クラシック音楽が好きになり、高校に入ったら吹奏楽をやってみたいと漠然と思っていました。ただ、入部する場合、当然「初心者」ですので、中学から吹奏楽をやってきた人たちについて行けるのか、不安もありました。それでも、「まあいいか」と楽観的な思いで吹奏楽部の門を叩いたところ、初心者の私に申し付けられた楽器は、アルト・サックスでした。フルート、クラリネット、ホルン、トランペット、トロンボーンなどは既に「経験者」で埋まっており、サックスだけ希望者がいなかったのです。
そんなわけでサックスと出会い、高校3年間は吹奏楽でサックスを一生懸命吹きました。しかし、クラシック好きの少年としては、「いつかはオーケストラ」なわけです。私も「大学に入ったら絶対にオーケストラをやるんだ」と決心し、オケがなさそうな大学は志望の対象から除外。まあ、大学はどこかに入るとして、問題は楽器です。サックスではオケに入れません。まれにソロ楽器として使われますが、基本は「なし」です。そこで思い当たったのが、ファゴットでした。音域が近いのと、楽器を斜めに持つという構え方が似ていることに加え、高校からやっている人は殆どいないので(当時の九州では、そうでした)、大学からまた初心者で始めても「ひと山あてられるのではないか?」と思ったわけです。
第一志望の大学は力及ばず不合格となりましたが、当時の国立大学は一期校・二期校があり、なんとか二期校の方に滑り込むことができ、晴れて大学生です。その大学のオケには高校の先輩がいたので、入学式前にオケに入部すると同時に、泥酔も経験(今日ではかなり問題となるので、ここだけの話です)。新入部員第一号だったこともあり、全ての楽器を選ぶことができた中で、私は迷わずファゴットを指名しました。元々そのつもりだったので、「迷わず」は誇張ですが、いずれにしても、そこからファゴット吹きとしての人生がスタートしたわけです。
■温厚でバランス感覚に富む人たち
それから今日まで、長い月日が流れました。自分の感覚としては本当にこの前のことのようですが、実際にはかなりの時間です。大学卒業後、新響に入団してから、もうすぐ35年が経とうとしているのですから。
私のファゴット吹きとしての人生も、そう長い時間は残っていないと思いますが、この楽器を選択したことに全く悔いはありません。本当によかったと思っています。音色も大好きですし、オケや室内楽で担う役割も気に入っています。それから、もう一つ挙げるとしたら、仲間でしょうか。高音木管の人たちから見れば多少「ぬるい」のかもしれませんが、ファゴットを演奏する人は、基本的に温厚でバランス感覚に優れた人が多いように思います。私が長い間、新響で演奏を続けてこられたのも、現在のメンバーはもちろん、退団された方も含め、パートの皆さんのおかげであるといえます。社交辞令ではなく、本当に感謝しています。
なんだか「手前味噌」のような流れでコーダに突入してしまいましたが、ファゴット、あるいはバスーンという楽器のこと、以前より興味を持って見ていただけるようになりましたでしょうか。今回のコンサートで演奏する、リスト、チャイコフスキー、ニールセンの3曲。ファゴットだけが目立つ派手なソロはありませんが、曲それぞれに、場面に応じて重要な役割が与えられています。木管のアンサンブルを支えていたり、低弦と一緒に動いていたり、金管一味に加担していたり、多彩な役どころが用意されています。7月15日は、木管楽器2列目のステージに向かって右側、斜め上に突き出た茶色くて長い楽器に是非ご注目ください。
さて、付け足しのようになって申し訳ありませんが、最後にまたファゴット奏者の小さな悩みを紹介して終わらせていただこうと思います。それは、楽器がかなり多くのパーツに分かれ、水がたまる箇所の拭き取りなども行わなくてはならないため、片付けに非常に時間がかかること。練習場から最後に出るのは、だいたい我々です。でも、わざとゆっくりやっているわけではありません。あれでも十分急いでいるのです。そんな我々を温かい目で見守ってくれている(相手にしていないという話もあります)オケの皆さん、ありがとうございます。
*注釈)ファゴットの目立つソロがある近代作品
ストラヴィンスキー:春の祭典、火の鳥
ラヴェル:ボレロ、道化師の朝の歌
リムスキー=コルサコフ:シェエラザード
ファリァ:三角帽子(全曲版)
ショスタコーヴィチ:交響曲第4番、第7番〜10番
世界一幸福な国デンマーク
維持会員の皆様こんにちは!運営委員長の大原です。いつも演奏会チラシの裏面に簡単な紹介を書いています。今回のチラシでは「不滅」について書かせていただきましたが、それでも短い文章ではお伝えできないこともありますので、この維持会ニュースでもうちょっと膨らませてご紹介します。
■山下先生とニールセン
指揮の山下先生と初共演をした10年前、まず演奏したのは「英雄の生涯」でした。実は当初ブラームス4番に決まりかけていたのですが、初めてお会いしていろいろお話をする中で、ライフワークはR.シュトラウスであり、なかでもこの曲への思い入れの強さを感じたのです。
この時の話の中で出てきたもう一つの名前がデンマークの作曲家ニールセンでした。2回目の共演でニールセンをやろうとなりましたが、山下先生からニールセンをやるのであれば、まずもっともニールセンらしい第2番「四つの気質」からがよいのではとなり、今回満を持して代表曲である第4番「不滅」を取り上げます。
山下先生のキャリアは1986年「ニコライ・マルコ指揮者コンクール」での優勝から始まりました。ニコライ・マルコはウクライナに生まれ、レニングレードで活躍した後、西側に移住、コペンハーゲンにも暮らしデンマーク放送交響楽団(=デンマーク国立交響楽団)の創立と発展に関わりました。第二次世界大戦勃発後は渡米し指揮法の教師となり、「指揮者と指揮棒」という著書が現在アメリカで利用されている指揮法の手引書の元になっています。そのマルコを称えて1965年から3年に1度デンマークで開催される由緒あるコンクールです。現在は、優勝賞金の他に北欧25ものオーケストラとの共演、デンマーク国立交響楽団首席指揮者の育成指導を受けられる、サポートがつく、ウィーンフィル、ベルリンフィルなど超名門オケの指揮者候補を探すコンペで見てもらえるといった特典がついており、若い才能を育てるという意味合いの強いコンクールのようです。
山下先生も優勝後北欧各地のオケを指揮し、それがきっかけで1993~98年にヘルシンボリ交響楽団の首席客演指揮者を務め、1998、99年にはマルメ交響楽団の定期公演に出演しました。ヘルシンボリではニールセンの6つの交響曲を毎年1曲ずつ全曲演奏したということです。マルメはスウェーデン第3の都市で最南端のスコーネ県の中心、ヘルシンボリも同じ県でマルメから60kmほどにあります。
マルメとヘルシンボリは私にはちょっとだけ馴染みのある地名でした。同期の友人がマルメの大学に留学していたからです。北欧は高福祉で知られていますが、予防歯科の最先端でありスウェーデンに留学する日本人の歯科医師は少なくありません。よほど良い所だったらしく、日本であまり知られてない頃からIKEAのファンであり、今でも時々ザリガニパーティ(スウェーデンの夏の風物詩)をしているようです。IKEAは言わずと知れた世界的家具店ですが、その本社機能があるのがヘルシンボリです。
スコーネ地方は1658年までデンマーク領であり、地理的にも近いためデンマークとのつながりが強く、方言も言語学的にはデンマーク語に近いのだそうです。ヘルシンボリは対岸のヘルシンゲルと4kmしか離れておらずフェリーで20分。EU加盟までは、税金の高いデンマークから酒やたばこが安く買えるヘルシンボリに買い物にくる人も多かったとのこと。2000年にはコペンハーゲンとマルメを結ぶ橋が開通し(東京アクアラインのように人工島と海中トンネルがある)、30分で行けるようになり、マルメとヘルシンボリはコペンハーゲン都市圏に含められているようです。蛇足ですが、デンマークから歯の治療にスウェーデンに行く人もいるようです。
■ニールセンとシベリウス
ニールセンが北欧の作曲家というとフィンランドのシベリウスみたいな感じの曲なのかな、と想像する方もあるかと思いますが、だいぶ雰囲気が違います。
以前、新響で渡邉康雄先生に振っていただいた時期があり、シベリウスの作品を数多く演奏する機会がありました。フィンランド人の母を持ち日本でのシベリウス演奏の一人者であった指揮者渡邉暁雄氏のご子息であります。シベリウス作品との組み合わせとして、同じ北欧のノルウェーの作曲家グリーグの作品はどうでしょうかという問いに、北欧だからといっしょにしてはいけないと言われたそうです。
最近フルートを吹くデンマーク人の友人に今度ニールセンの不滅を演奏するのだという話をつたない英語でしたところ、私もこの前シベリウスを演奏したわと答えました。もしかしたら北欧の人自体はこだわりがないのかもしれません。
じゃあノルウェーとフィンランドは仲が悪いのかとも思いましたが、ノルウェーは今年のフィンランド独立100周年のお祝いに国境のハルティ山の頂上をプレゼントしようとしたのですから、仲良しなのでしょう。結局は憲法で国土の一部を渡すのを禁じられているため断念したようです。
ニールセンとシベリウスは同じ1865年の生まれで、同じ北欧に生まれ国を代表する大作曲家となった二人ですが、ほぼ同じ数の交響曲を残し最後の交響曲も同じ1924年に作曲されています。また、若い頃はヴァイオリニストであり優れたヴァイオリン協奏曲を書いている点も共通です。
ニールセンは1931年に65歳で亡くなり、シベリウスは91歳まで生きましたが、作曲は1930年に数曲書いたのを最後にほとんど作曲していません。その理由はわかりませんが、ニールセンという存在を失ったことも関係しているような気がします。
ニールセンの死後22年経った1953年にコペンハーゲンでニールセン・フェスティバルが催された時、シベリウスは「偉大なるデンマークの民カール・ニールセンは、その作品には音楽のあらゆる形式が含まれているが、生まれながらの交響曲作曲家だった。最初から明確にもっていた志を遂げるため、その偉大なる知性をもって天賦の才能を磨いた。その力強い個性によってひとつの流派を打ち立て、多くの国の作曲家たちに影響を与えた。頭脳と精神について言うならば、カール・ニールセンは、いずれも最高級のものを持ちあわせていた」というメッセージを寄せています。シベリウスは本当にニールセンを認めていたのでしょう。
■デンマーク人はなぜ幸福か
さてデンマークといえば何を思い浮かべますか?高福祉、王室、レゴ、北欧デザイン家具、アンデルセン、チボリ公園・・・。
何と言ってもデンマークは世界一幸福な国なのだそうです。もっとも「幸福度」には様々な調査機関、指標による報告があり、いろいろな結果があるようです。国連の支援を受けコロンビア大学が行った調査では、富裕度、健康度、人生の選択における自由度、汚職などが考慮され、2013年発表の第1回の調査でデンマークは1位でした(次の2015年発表では3位)。ちなみに日本は43位→46位。他にもいくつかの調査でデンマークが1位になっています。
これは物質的な豊かさではなく「国民が幸せと感じるか」。デンマークでは教育や医療の保障が充実し、貧富の差が少ないということがあるでしょう。それだけでなく国民性として、そもそもあまり期待をしない、他人と比べない、平等を好む、贅沢を望まない。だから少しのことでも幸せを感じることができるということのようです。毎日の暮らしを楽しむことが重要で、家具などのデザインが心地よいのかもしれません。
■そして「不滅」
ニールセン交響曲第4番の副題の「不滅」ですが、デンマーク語のDet Uudslukkeligeのニュアンスは、消し去り難いもの、滅ぼすことのできないものといった方が近いそうです。
作曲されたのは1914~16年、第一次世界大戦が始まった頃です。内村鑑三の「デンマルク国の話」という1910年の講話をまとめた著書があります。北欧の小さな国であるデンマークは、日本の面積は10分の1、人口は20分の1でしかないのに、貿易高は日本の2分の1で国民1人あたりの富は独英米より多い豊かな国である。50年前に敗戦し国土を失ったが、樹木を植え天然資源と土地を有効活用し、貴い精神で新たな良い国を得たのだという話です。非戦論者の内村はデンマークを模範にすべきと考えたわけです。
開戦直後にデンマークは中立を宣言しましたが、ドイツの要求を受け入れざるを得ず、沿岸領域を占領されて貿易ができず、物資が不足し失業率が上昇しました。そのような困難があっても人間の魂は滅ぼすことができないという意志が込められているのでしょう。
幸せとは何か、考え直してみたくなりました。
第238回ローテーション
| レ・プレリュード | ロメオとジュリエット | ニールセン4番 | ||||
| Fl | 1 | 岡田 | 1 | 吉田 | 1 | 松下 |
| 2 | 吉田 | 2 | 新井 | 2 | 石川 | |
| 3 | 兼子 | Picc. | 岡田 | 3/Picc | 兼子 | |
| Ob | 1 | 堀内 | 1 | 宮内 | 1 | 平戸 |
| 2 | 宮内 | 2 | 堀内 | 2 | 岩城 | |
| ― | ― | E.H. | 山口 | 3 | 山口 | |
| Cl | 1 | 高梨 | 1 | 中島 | 1 | 品田 |
| 2 | 石綿 | 2 | 進藤 | 2 | 大藪 | |
| ― | ― | ― | ― | 3 | 末村 | |
| Fg | 1 | 田川 | 1 | 田川 | 1 | 浦 |
| 2 | 笹岡 | 2 | 浦 | 2 | 田川 | |
| ― | ― | ― | ― | 3/Contra | 笹岡 | |
| Hr | 1 | 山口 | 1 | 大内 | 1 | 菊地 |
| 2 | 宮坂 | 2 | 市川 | 2 | 大内 | |
| 3 | 松尾 | 3 | 宮坂 | 3 | 山口 | |
| 4 | 市川 | 4 | 松尾 | 4 | 大原 | |
| Tp | 1 | 野崎 | 1 | 野崎 | 1 | 小出 |
| 2 | 青木 | 2 | 青木 | 2 | 北村 | |
| ― | ― | ― | ― | 3 | 中川 | |
| Tb | 1 | 武田香 | 1 | 武田香 | 1 | 武田浩 |
| 2 | 志村 | 2 | 志村 | 2 | 日比野 | |
| 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | |
| Tu | |
土田 | |
土田 | 土田 | |
| Timp | |
古関 | 今尾 | 1 | 桑形 | |
| ― | ― | ― | ― | 2 | 古関 | |
| Perc | 小太鼓 | 古関 | シンバル | 古関 | ― | ― |
| シンバル | 桑形 | 大太鼓 | エキストラ(*) | ― | ― | |
| 大太鼓 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| Harp | ― | 見尾田(*) | ― | 見尾田(*) | ― | ― |
| Vn | 1 | 堀内(伊藤真) | 1 | 堀内(伊藤真) | 1 | 堀内(中島) |
| 2 | 内田智(小松) | 2 | 内田智(小松) | 2 | 小松(内田智) | |
| Va | 槇(小畑) | 槇(小畑) | 柳澤(村原) | |||
| Vc | 柳部(安田俊) | 柳部(安田俊) | 柳部(安田俊) | |||
| Cb | 中野(植木) | 中野(植木) | 中野(植木) | |||
第238回演奏会のご案内
山下一史、9回目の登場
新交響楽団が初めて山下一史氏を指揮に迎えてから10年が経ちました。積極的に日本の現代作品に取組み、2016年からは千葉交響楽団の音楽監督を意欲的に務めるなど、音楽が社会や地域といかに関わるか意識した活動をしているように感じます。一言でいうと情熱の指揮者。この10年間に新響とほぼ毎年共演していますが、山下氏が新響にいつも求めるのは「プラスサムシングのある演奏をしよう」。単に楽譜の音を並べるのではなく、聴く人の心に届く演奏をしなければならないと私たちは気づかされます。
今回のプログラムには、そんな山下氏にぴったりなロマンティックな管弦楽作品2つと、デンマークの作曲家ニールセンの交響曲第4番を選びました。
山下一史とニールセン
山下氏のプロとしてのキャリアは、1986年ニコライ・マルコ国際指揮者コンクールでの優勝から始まりました。ニコライ・マルコはデンマーク放送交響楽団の創設に功績のあった指揮者で、優勝者は北欧各地でのコンサートを指揮します。山下氏はその中でヘルシンボリ交響楽団を振ったのがきっかけで、同楽団とニールセンの交響曲6曲全てを演奏しました。ヘルシンボリはスウェーデンですがデンマークにとても近い都市です。北欧でニールセンの交響曲を指揮した日本人はそうはいないでしょう。
ニールセンはデンマークの国民的英雄ですが、フィンランドのシベリウスと同じ1865年の生まれです。同じ北欧に生まれ国を代表する大作曲家となった二人ですが、ともに交響曲作曲家として認められ、ほぼ同じ数の交響曲を残し最後の交響曲も同じ年に作曲されています。また、若い頃はヴァイオリニストであり優れたヴァイオリン協奏曲を書いている点も共通です。
シベリウスが森や厳しい自然を思わせる作風なのに対し、ニールセンの音楽は表情豊かで革新的。デンマークの平原や国民性がそうさせているのかもしれません。
交響曲第4番「不滅」
今回演奏する交響曲第4番は、ニールセンの作品の中で最も有名です。日本では「不滅」という副題で親しまれていますが、デンマーク語のDet Uudslukkeligeのニュアンスは少々違うようで「滅ぼし得ざるもの」「消し難きもの」といった表記も増えています。作曲されたのは1914~16年、第一次世界大戦が始まった頃です。北欧の盟主であったデンマークは、幾度かの戦争を経て誇り高い小国主義の国でしたが、中立を貫くことができず生活物資の欠乏やインフレといった困難な時代を迎えていました。そのような逆境においても人間の魂は滅ぼすことはできないのだという意志が暗示されています。
豊かな躍動感の中に民族的で田園風景を思わせる美しい部分もあり、最後は堂々と締め括られます。きっとデンマーク人に大きな勇気と希望を与えたのでしょう。2組のティンパニが大活躍をするので視覚的にも楽しめる、ライブで聴いていただきたい曲です。
ツェムリンスキー:交響詩「人魚姫」
人々はアレクサンダー・ツェムリンスキー(1871-1942)の名前を聞いて、何を思い浮かべるだろうか。シェーンベルクに似ている、あ るいは難解でつかみどころがないという印象を持つだろうか。その中でも比較的わかりやすいものを…というわけではないが、本日演奏するツェムリンスキーの交響詩『人魚姫』“DieSeejungfrau”は、名の通りハンス・クリスチャン・アンデルセン(1805-1875)の童話『人魚姫』(Den lille Havfrue, 1837)をもとにしている。
この交響詩『人魚姫』は、ツェムリンスキーの没後に楽譜が長らく失われた状態であったが、1980年にウィーンで第1楽章が、第2楽章と第3楽章がワシントンで発見され、初演から実に80年後の1984年に、音楽学者のペーター・ギュルケの指揮により蘇演される。
第1楽章 「 海底/人間界の人魚姫、嵐、王子の救出」
“Sehr mäßig bewegt”
冒頭においては、コントラバス、ファゴット、テューバなどによって低く静かに奏されるイ短調の主音 A の保続音をベースに、これも低音部で、コントラバス、ハープの低音部、チェロによって、はじめは A-E の 5 度、それから A-Gの 7度まで上行するが、決してオクターブ上に届くことのない音階の繰り返し、それにジグザグに動きながら下降してくる、オーボエ、クラリネット、ハープによる音型がまざって、主要主題の背景を構成している。(譜例)。こうした音型と楽器の組み合わせは、海底での仄暗(ほのぐらい)水の動きを仔細に描いているかのようである。
第2楽章 「人魚姫の憧れ、海の魔女のもとで」
"Sehr bewegt, rauschend"
冒頭のシンバルのロールに続いて、管楽器の細かいトリルと弦楽器のトレモロの連なりによって巨大な音の奔流となり、その後、人魚の王子への憧れが叙情的で遊び心たっぷりに描かれる。
第3楽章 「人魚姫の最期」
“Sehr gedehnt, mit schmerzvollem Ausdruck”
人魚姫の苦悩と死、そして救いが描かれる。曲全体を支配するイ短調は、彼が手本として考えていたブラームスやロベルト・フックスの作品では憂鬱や孤独といった意味を与えられていることが多い。しかしその結末においては、突然の増4度転調によって、それまでの基盤となっていた陰鬱なイ短調の世界を脱し、音楽は最も遠い変ホ長調の世界へと飛翔していく。これはツェムリンスキーの、それまで自分の関わっていた内的・外的な世界を捨て、全く新しい可能性に向かって踏み出していく姿勢を感じさせなくもない。
ツェムリンスキーは、裕福なユダヤ人一家の息子としてウィーンに生まれた。幼少期から音楽の才能を現し、13歳の若さでウィーン楽友協会音楽院に入学後、ピアノをブラームスの友人であるアントン・ドール、音楽理論をフランツ・クレンとロベルト・フックスの下で学んだ。また作曲をフックスの兄であるヨハン・ネポムク・フックスから本格的に学んでいる。弟子にはシェーンベルク、アルマ・シントラーがいた。
アルマとは師弟関係を超えた恋仲でもあったとされるが、のちにアルマはグスタフ・マーラーのもとへと去る。ツェムリンスキーが『人魚姫』の作曲にとりかかったのはマーラーの結婚式の翌年1902年である。
初演は、ツェムリンスキーの弟子であり義弟でもあったアルノルト・シェーンベルク(1874-1951)が、交響詩『ペレアスとメリザンド』を初演したのと同じ演奏会でおこなわれた。このとき、『ペレアスとメリザンド』は多くの批評家から厳しく批判されたものの、逆にいえばその個性が注目を集め、いわばスキャンダル的な印象を残した作品となった。一方『人魚姫』は、演奏会では一応肯定的に受け止められたものの、批評家の関心を強く引くことはなく、ツェムリンスキーは深く失望したという。多くの批評では、ツェムリンスキーの作曲の技術については高く評価しつつも、作品の内容や表現の個性については批判するかもしくは冷淡にあしらう態度が見られたとされ、この時にはすでに「伝統に根ざしたツェムリンスキーの折衷主義」と、「革命的天才シェーンベルク」という対比が形成されていたのである。
作曲の動機は定かではない。その直前のシェーンベルクへの手紙で、ツェムリンスキーは「交響曲『死について(„Vom Tode“)』の準備」に触れている。のちにマーラーの妻となる弟子のアルマに密かに想いを寄せていたツェムリンスキーが、成就しえない片想いの気持ちを『人魚姫』に託したという推測は、あまりにも短絡的かもしれない。しかし、単に標題音楽、描写音楽を作曲することが彼の目的ではなく、アンデルセンの題材を借りて、人生の悲劇や死を抽象化して作品に残したかったのではないかと思う。
曲中においては人魚姫の心理の様々な葛藤が象徴的に描かれており、世俗の粗暴な現実や、無味乾燥なアカデミズムの入り込む余地のない繊細な美が支配している。また無垢な純粋さとエロティックな激情の対比といった緊張が根底に内在しており、書法でいえばクリムトの絵画のように輪郭や背景が浸透して装飾的効果を発揮しているところが、ツェムリンスキーのテクスチュアの特色といえよう。
ブラームスやマーラーに認められて世紀末ウィーンの楽壇に期待の新星としてデビューしたツェムリンスキーは、彼自身は創作面ではモダニズムの推進者の位置に立つことなく、伝統と前衛の狭間に立って伝統を活性化し、前衛の開拓地に潤いを与える役割を担った。
その立ち位置のためか、ツェムリンスキーは生前も死後もしばしば「折衷主義者」の非難を浴びてきたが、保守と革新の対立の激しかった当時とすれば、特殊で困難な道を歩むことを選んだといえる。より先鋭的な響きを求めて調性から離れて行くべきか、音響の表現性の拡大、色彩性の濃淡の変化、情感・気分の陰影の豊かな表現が実現される方向を目指すべきか。結果的に彼は学んできた伝統的書法による後者の道を選んだ。生後100年余りを経て漸く再評価されてきたツェムリンスキーの、伝統と革新の共存が織りなす格別に美しい音楽をお楽しみいただければと思う。
初 演: 1905年1月25日 作曲者自身の指揮によりウィーンにて ウィーン演奏会協会管弦楽団
楽器編成: フルート4(ピッコロ2持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、Esクラリネット、バスクラリネット、ファゴット3、ホルン6、トランペット3、トロンボーン4、テューバ、ティンパニ、低音の鐘(テューブラーベル)、トライアングル、シンバル、グロッケンシュピール、ハープ2、弦五部
参考文献
石田一志『ツェムリンスキーを巡る環』音楽之友社 1992年
渡辺 護『ウィーン音楽文化史』音楽之友社 1989年
Die Seejungfrau: Fantasie in drei Sätzen /Critical Study
Score, Universal Edition AG, Wien, 1984
Otto Kolleritsch (Hg.): Alexander Zemlinsky. Tradition im
Umkreis der Wiener Schule, Universal Edition AG, 1976
ベートーヴェン:交響曲第8番 ヘ長調
「この曲が聴衆に受け入れられないのは、この曲があまりに優れているからだ」
これは初演時にベートーヴェンの口から漏れ出た言葉であるとされている。このエピソードが“通ごころ”をくすぐり、ベートーヴェン・ファンの間で交響曲第8番は非常に人気の高い曲となっている。ベートーヴェンの言葉からもわかるように、初演の客受けはイマイチであったようである。ベートーヴェンの全交響曲のなかで最も演奏時間が短く、編成も小さく、また『運命』や『第九』のようにドラマチックな展開がないことから、より大きくより派手な曲に期待が向いていた当時、ベートーヴェンが予想していたような反応は得られなかった。加えて、同時期に発表された交響曲第7番(音大を舞台としたテレビドラマのテーマ曲としても使われ、一躍大人気曲となった、あの曲である)があまりにも熱狂的に聴衆に迎え入れられてしまったことから、第7番の陰に隠れてしまったのである。 しかし、この曲はベートーヴェン本人が最も愛した曲であり、発表当時から“隠れた名曲”としての圧倒的な存在感を放ち続けている。本日はそんなちょっぴりマイナーなこの名曲についてお話ししたいと思う。
交響曲第8番は今から200年と少し前の1812年の夏、ボヘミアの温泉療養地にて書かれた、ベートーヴェン41才のころの作品である。ベートーヴェンはすでに芸術家としての名声をほしいままにし、「貴族なんかに我々の芸術が分かってたまるものですか」という発言に表れているように、自己意識が高く仕事に誇りを持っていた。
プライベートでは、アントーニエという既婚女性と熱烈な恋愛関係にあり、公私ともに順調な状況でこの曲の構想は練られた。このころアントーニエに宛てて3通の熱烈なラブレターをしたためていた(宛名の記載はないが、後世の研究で彼女宛とする説が有力)。ベートーヴェンの死後に机の引き出しから発見された手紙には「不滅の恋人よ」「目が覚めた時からあなたのことで頭がいっぱいだ」「あなたと完全に一緒か、あるいは完全にそうでないか、そのどちらかでしか生きられない」など、なかなか強烈な内容が見られ、アントーニエに対して並外れた愛情を抱いていたことは明らかである。
しかし、この交響曲の完成を待たずに二人は破局してしまう。その原因はアントーニエ夫妻の間に子供ができたこと、アントーニエ以外の女性とベートーヴェンの間に子供ができたことなど様々な説があるが、真偽のほどはさておき、何はともあれ二人は二度と会うことはなかった。しかし、ラブレターを何十年も大切に保管していたことや、破局後もこの“不滅の恋人”を意識した曲を作っていたことから、ベートーヴェンにとって生涯忘れることのできない女性だったのは確かであろう。
以上述べたように、この曲はベートーヴェンが人生最大の恋愛をしながら書いた作品である。全編明るく、そしてテンポの良い雰囲気が保たれており、生命の喜び、そして幸せな家庭へのあこがれを感じさせる。しかし、最後どことなく感情的になってやけっぱちに終わらせているようにも聞こえてしまうのは、先入観からだろうか。
第1楽章 アレグロ・ヴィヴァーチェ・エ・コン・ブリオ
冒頭からいきなり主題が提示される、潔い出だしである。古典を意識したあっさりした曲調であるが、転調とテンポ変化をしながら分断されるメロディや、いたるところにちりばめられたスフォルツァンドが意外性をもたらし、古典とは一線を画していることをこれでもかとアピールしている。またベートーヴェンらしい苦悶や緊張感もしっかりと盛り込まれており、「このぼくがもし古典を書いたとしたらこんな感じ?」と言わんばかりである。最後は出だしの勢いからは想像できないほどあっさりと、こっそり終わる。
第2楽章 アレグレット・スケルツァンド
歯切れよく跳ねる木管楽器の和音に始まり、ヴァイオリンとチェロ・コントラバスが対話を繰り広げる。男女のゆかいな会話を思わせ、時折、笑い声のような強奏がはさまれる。この楽章を通して続く木管楽器の和音は、時計のような規則的に動く機械を連想させ、かわいらしく楽しい雰囲気を演出している。実際、この曲が書かれた当時はメトロノームが発明された時期と重なり、メトロノームに着想を得たともいわれている。
第3楽章 テンポ・ディ・メヌエット
メヌエット形式を明らかに意識した楽章であるが、ベートーヴェンは「メヌエット」ではなく「メヌエットのテンポで」という指示しか記さなかった。転調しながら展開する美しいメロディを盛り込むことで、「ロマンチックなメロディを入れてしまったからメヌエットにならなかった」という皮肉にも感じられる。
ちなみに、中間部にホルンが担当する牧歌的なメロディは、ポストホルンに着想を得たものである。このポストホルンとは、郵便馬車が町へ到着した際に吹き鳴らす合図であり、連絡手段が手紙しかなかった当時、ポストホルンはいわば恋人からの着信音であった。ベートーヴェンにとってポストホルンは特別な存在であり、この曲のほかにも“不滅の恋人”を意識した作品にたびたび登場する。
第4楽章 アレグロ・ヴィヴァーチェ
激しいリズムと大幅な強弱変化、大胆な転調がこれでもかと盛り込まれた挑戦的な楽章である。嵐のように目まぐるしく情景が変わり、エネルギッシュに突き進んでいるかと思いきや突然分断されるなど、この楽章でもユーモアが冴えわたっている。そしてわざとらしく長々と盛り上げられ、クライマックスを迎える。
この作品はベートーヴェンの交響曲の中で唯一、誰にも献呈されることはなかった。それは幸せな思い出やアントーニエへの思いがつまった、ベートーヴェンの私的な宝物だったからかもしれない。
初 演: 1814年2月27日、作曲者自身の指揮によりウィーンにて
楽器編成: フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦五部
参考文献:青木やよひ『ベートーヴェン〈不滅の恋人〉の謎を解く』講談社現代新書 2001年
ルイス・ロックウッド(土田英三郎・藤本一子監訳 沼口隆・堀朋平訳)『 ベートーヴェン 音楽と生涯』春秋社 2010年
平野昭『ベートーヴェン Ludwig van Beethoven』音楽之友社 2012年
カール・ダールハウス(杉橋陽一訳)『ベートーヴェンとその時代』西村書店 1997年
金聖響・玉木正之『ベートーヴェンの交響曲』講談社現代新書 2007年
『最新名曲解説全集 第1巻』音楽之友社 1982年
J.シュトラウス2世:喜歌劇「こうもり」序曲
「ワルツの父」と呼ばれたヨハン・シュトラウス1世の息子ヨハン・シュトラウス2世は、「ワルツ王」の名で親しまれるが、ワルツの他にオペレッタやポルカも多数手がけている。オペレッタだけでも16作品も残しているが、中でも『こうもり』は「オペレッタの最高傑作」と言われている。 オペレッタは、オッフェンバックの『天国と地獄』を代表とする歌劇の形式で、19世紀中頃のパリで発祥し、のちにウィーンに伝わった。コメディの要素が強く、「喜歌劇」「軽歌劇」「小歌劇」等と訳される。軽妙な筋書と歌による、庶民の娯楽的作品で、オペラに比べると軽視される傾向があり、一流の歌劇場では上演されないことも多い。格式を重んじるウィーン国立歌劇場でも、かつてはオペレッタを上演しなかったのだが、(ヨハン・シュトラウス2世作曲のオペレッタ「騎士パズマン」を「オペラ」という名目で初演するという前例はあった)、『こうもり』だけは別格扱いであった。 現在でも『こうもり』はウィーン国立歌劇場の大晦日の定番として上演されている。
喜歌劇「こうもり」のあらすじ
『こうもり』という題名の由来だが、動物のこうもりとはさほど関係がなく、後述のとおり、ファルケ博士の仮装の姿を指している。このオペレッタはいわゆる「ドッキリカメラ」のような内容で、ターゲットは、新興成金の銀行家アイゼンシュタイン氏。実は、それ以外の出演者は全員仕掛け人なのだ。このドッキリの発案者はファルケ博士。彼のこの言葉からオペレッタは幕を開ける。
「今夜はこうもりの復讐をお見せしましょう。」
第1幕 アイゼンシュタイン家の居間
時は1874年の大晦日、舞台はオーストリアの温泉地イシュル。以前に、ある仮装舞踏会にアイゼンシュタインとその友人ファルケ博士は連れ立って出かけたが、その帰りに、アイゼンシュタインは泥酔したファルケ博士を「こうもり姿」の仮装のまま道ばたに置き去りにした。その姿を子供たちが見て、「こうもり博士」というあだ名をつけられてしまった。その恨みをいつか
は晴らしてやりたいと、ファルケ博士はずっと考えていたのだ。
大晦日のこの日、アイゼンシュタインは公務員を侮辱した罪で、短期間だが刑務所に入ることが決まっていたのだが、ファルケ博士は、楽しいパーティがあるから刑務所に入る前にこっそり行こうと誘う。もちろん博士の復讐はもう始まっている。喜んだアイゼンシュタインがパーティに出かけた後、家に残されたアイゼンシュタインの妻ロザリンデのところに、元恋人のアルフレートがやって来る。アルフレートはまるで本当の夫のように振る舞う。2人が恋を楽しもうとしていると、ちょうどそこに刑務所長フランクがアイゼンシュタインを迎えに来た。アルフレートは今さら夫でないとは言えずに刑務所に連行されてしまう。
第2幕 オルロフスキー公爵の別荘
その晩、ロシアの大貴族オルロフスキー公爵のパーティにアイゼンシュタインが来てみると、そこではみんなが新しい恋に夢中。なぜか自分の家の女中アデーレに似た女性を見かけ、おかしいとは思いつつもそのことは置いておくが、この女性はアデーレ本人。そして仮面を付けた美しいハンガリーの貴婦人を見つけ、夢中になって口説こうとする。実はこの貴婦人の正体は彼の妻ロザリンデ。すべてはファルケ博士の仕組んだワナだったのだ。ロザリンデは情けない夫に口説かれるふりをしながら、証拠をつかもうとアイゼンシュタインの懐中時計を奪う。
第3幕 刑務所長の部屋
元日の早朝。酔いも残るアイゼンシュタインが急いで刑務所に出頭してみると、すでにアイゼンシュタインは逮捕されたとのこと。真相を確かめるためアイゼンシュタインは弁護士に変装して様子を伺っていると、そこにロザリンデがやって来て、アルフレートを牢から出してほしいとアイゼンシュタイン扮する弁護士に相談を始める。怒ったアイゼンシュタインは正体を明かし、妻を責め立てる。しかしロザリンデの手には動かぬ証拠が。昨夜奪った彼の懐中時計である。何が何だかわからず頭を抱えるアイゼンシュタイン。そこへファルケ博士がパーティの参加者とともに現れて種明かし。
「これが私の仕組んだこうもりの復讐だ。」とファルケ博士。そしてロザリンデの「全てはシャンパンの泡のせいね。」という言葉で幕は閉じる。
序曲について
序曲とは歌劇の始めに演奏される部分で、本編の中身の予告という役割もあり、劇中のハイライトとして、各場面のメロディが多数使われる。
冒頭の飛び跳ねるようなフレーズ(譜例1)が、これから始まる笑いの復讐劇を予感させる。オーボエのやわらかなメロディがそれに続く(譜例2)。このメロディは第3幕の終盤の三重唱で、アイゼンシュタインが歌うものと同じなのだが、劇中ではアルフレートとロザリンデの前でアイゼンシュタインが弁護士の変装を解き、2人に対し「そうだ、お前たちに欺かれた男だ!」と叫ぶ場面なので、序曲のオーボエの雰囲気とはだいぶ異なる。しばらくすると鐘が6つ鳴る(譜例3)が、これは第2幕のフィナーレで時計が6時を知らせる部分と同じである。
第2幕終盤の舞踏会の有名なワルツ(譜例4)、ロザンリンデが第1幕の三重唱で歌う「私ひとりで8日間あなたなしに暮らさねばならないのね」という哀歌(譜例5)など劇中の旋律が次々に現われる。最後は今までに出てきたメロディが再現され、華やかで浮き浮きとした雰囲気の中で曲は閉じられる。賑やかかつ美しい曲で、管弦楽曲として独立して演奏されることも多い
曲である。
初 演: 1874年4月5日、作曲者自身の指揮によりウィーン、アン・デア・ウィーン劇場にて
楽器編成: フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、シンバル付き大太鼓、小太鼓、鐘、トライアングル、弦五部
参考文献
Stanly Sadie(中矢一義、土田英三郎 訳)『新グローヴオペラ辞典』白水社 2006年
喜歌劇≪こうもり≫ 3幕のオペレッタ
演奏:バイエルン国立歌劇場合唱団、バイエルン国立管弦楽団
指揮:カルロス・クライバー
録音:1975年10月 ミュンヘン(CD解説)
新響生活50年をふりかえって =出逢った人々のことなど=
*50年前入団、そして昨年退団
1966年(昭和41年)11月に入団しました。当時団員だったクラリネットの大前研一氏から「来年ソ連に演奏旅行があるのだけど入らない?」と話が有り、オーボエ名人でトップだった井上卓也氏のオーディションを受けました。「もっと練習してください」と言われて入りました。東京文化会館地下のAリハーサル室の練習に初めて参加してびっくりしました。欠席者が多い、開始時間が守られてない、芥川先生の指揮が分からない。呆然として、「演奏旅行から帰ったらすぐやめよう」と思いました。でも、飲み友達ができてしまったので居座ってしまいました。あれから50年経った昨年の11月、後期高齢者になったので退団しました。
*芥川也寸志氏
私たちの仲間内では愛情をこめて「アーさん」でした。アーさんは新響を立ち上げて、育ててくれた恩人です。1925年から1989年まで、昭和を目いっぱい生きました。享年63歳でした。
私たちにとっても偉い人でしたが、放送局などの業界ではとんでもなく偉い人で、テレビの収録などで放送局に行くと、ほとんど神様で、局の広いスタジオがピリピリしてました。作曲家、タレント、として有名でしたが、音楽著作権協会の立ち上げなど、社会的に立派なこともされました。練習に行くと目の前5メートルの処にその神様が指揮棒を持って立ってるのですよ。凄いでしょう。
数回目の練習中、神様が話の成り行きで私の事を「社長」と呼んだので、その後50年間、新響の中での私の名前は「社長」になりました。このことで一番面白かったのは、混み合う帝国ホテルのロビーで、遅れてきた友人が遠くから大声で「社長!」と叫んだのです。ロビーに居た紳士淑女たちは尊敬の目で一斉に私を見ました。似た話ですが、ビオラのトップの柳澤君は「組長」と呼ばれてました。ビオラ仲間での帰りに電車の中で、女性団員が「組長、席が空きました」と言って座らせたら、徐々に周りからお客さんが居なくなったという話を聞きました。組長だったらベンツだと思うのだが。何かの帰りで全員黒服だったのです。
鹿島の合宿で食後の昼休みにアーさんを交えて10人位で雑談しているときに、つぶやくように「幸せって平凡な中にあるのかな」言われてびっくりしたことがあります。有名人で超幸せなアーさんと思っていましたからとても印象に残っているのです。多分ご長男がお生まれになったことが思いの中にあったかなと思いました。
「もう一度、ブラームスの1番をやりたかった」というのが最後の言葉だったと聞きました。アーさんは名誉職も含めて多くのお仕事をされてましたから、数えきれない肩書をお持ちでした。ご病気ということでそれらの肩書を次々と減らしてゆくことになりましたが、そういうなかで、「新交響楽団音楽監督」の肩書は最後まで残してくれました。
*戸田昌廣氏
新響は私が入団する10年前に労音の下部団体「東京労音新交響楽団」として生まれました。クラシック音楽が広く聴かれ始めた頃でいろんな音楽鑑賞団体が生まれました。しばらくは良かったのですが、徐々に問題が増えて行き、10年後の1966年3月に独立しました。この10年間、団長だった戸田さんは大変苦労されました。労音は新響を放したくなかったですから、その矢面に立って多量の会議、交渉で仕事も手につかない状態でした。今の新響の幸せは、あの独立時の苦労と、独立後の運営の苦労と、芸術家のアーさんの対応、その他書ききれないほどの苦労のおかげです。
1980年に退団されたのですが、その後もOB会長としてお世話になってます。近年はトロンボーンをチェロに替えてご活躍です。あれこれと、しかも長期にわたって新響はお世話にはなったのですが、戸田さんは新響に文句は言えません。だって、どうやったのかわかりませんが、コンサートミストレスを嫁さんにしちゃったのですから。
*都河和彦氏
私が入団した翌年に都河和彦氏が入団しました。当時のアマチュア界はもちろん、プロの演奏家の間でも名の知れた人だったので、「新響なんかに入ってくれるかな?」と噂になってた名人です。演奏面で力を尽くしてくれました。アーさんのわからない棒を心で受け止め、コンサートマスター(コンマス)の位置から発信することで、全体のアンサンブルが落ち着いてゆきました。まもなくアーさんの棒も見やすくなってゆきました。都河さんがいることで特に弦楽器が質量ともに充実しました。外に対しては新響の顔でしたから、協奏曲の独奏者にお願いした、特に弦楽器のソリストの方々とのお話もスムースで、周りに居た団員も楽しませてもらいました。オーケストラ曲にはたくさんコンマスのソロもあるのですが、中でも毛利伯郎先生をお招きして演奏したドヴォルザークのチェロ協奏曲第3楽章。チェロ独奏とコンマス独奏の丁々発止の演奏は一生忘れられません。毛利先生が目の前の都河コンマスを睨みながら楽しそうに協奏してた姿は素晴らしい画像として脳裏に焼き付いてます。
尊敬する都河さんですが、本来この人は、大酒のみで、ヘビースモーカーで、とんでもない人なのです。先日紀尾井ホールで会いました。奥様がおっしゃるには、「このほど数週間酒もたばこもやめたら初めて血液が全部正常になりました」と嬉しそうにいうのです。夫思いの奥様に守られて、従順で、健康で、まともになってる都河はつまらん!入団当時は、こんなに凄くて変な奴がこの世に実在してるのか、と思ったものでした。10年前まで、同じ人種の今は亡き渡辺 達(pf)と3人で飲んでました。
都河さんはAPA(日本アマチュア演奏家協会)の機関誌に何十年も前から随筆を書いてます。面白くて、それだけでAPAに入っている意味があります。最新の3月号では弓の悩みを書いてます。ヴァイオリンは200年前の名器ですが、弓は長年使ってたヴィヨームをやめて2万円のカーボン弓を愛用してる、と書かれてました。数百万円の弓から2万円の弓へ。やっぱり無茶苦茶な都河さんです。彼もまもなく後期高齢者です。
*100人の団員、2000人のお客様
私は新響の演奏は日本一だと勝手に思ってますが、もうひとつ日本一があります。それは宴会芸です。歌舞伎、寸劇、落語、瞬間芸など、笑い転げます。100人の団員がいろんなことをやって、運営上の仕事も担って新響が続いてます。そのうえ会社勤めもしてるんですよ。素晴らしい人たち、というよりは本当に面白い奴らなんです。僕の自慢の後輩さん達です。
もっと大事なのはお客様です。私は一人のお客様でもちゃんと演奏できると思ってる者ですが、終わった後の拍手は大事です。私は拍手には敏感です。団員はいつも反応を気にしています。皆さんは社会人ですから褒めてくれます。でもそれを聞く方は敏感で、言葉の裏なんかも考えます。アンケートも含めて褒められることが多いですが、ほんの少し、トウガラシも欲しいです。ほんの少しですよ。じつは一番敏感なのは「批判」ですので。
新響はいろんな人の参加と支えで60年続いてきました。これからもずうっと続きます。退団した今、私は2000人の一ひとりになりました。支える側になりました。どうぞよろしくお願いいたします。私もいっぱい拍手します。そして七味唐辛子も少々。
鑑賞に役立つ? トランペットのウンチク
トランペットの小出 一樹と申します。維持会の皆様にはいつも大変お世話になっております。感謝申し上げます。
各楽器の奏者のリレーエッセイ(?)が進み、トランペットの順番がやってきたとのことで、今回の執筆のご指名を受けました。どんなことを書くのがふさわしいのか難しいところですが、いつも熱心に聴きに来て下さる皆様が、演奏を聴くときの隠し味になるような楽器にまつわるウンチクをご案内できればなどと考えてみました。といっても、いわゆる普通の「楽器紹介」のようなものは世間に詳しいものが色々あると思いますので、そういった一般的な紹介とは少し違った、私なりの視点で何かご紹介できないかと思いつつ書き進めてみました。その結果、書いているうちにどうしても私好みのマニアックなラッパ談議に話が傾きがちになってしまったところがあります。その辺をあらかじめお許し願いつつ、読み進めていただければ幸いです。
トランペットという楽器は、その音や形を多くの皆様がご存知なのではないかと思います。演奏会会場や写真・イラストで見て、それとわかる方が少なくないのではと思います。まずは見た目のことからお話していきます。
*見た目の色と音のとの関係
殆どのトランペットは、銀色だったり金色だったりと、金属的な光沢のある見た目をしています。トランペット自体は真鍮(銅と亜鉛の合金)で出来ていますが、真鍮のままだとすぐに腐食して光沢が曇ってしまったり、楽器を持つときにいちいち錆が手についてしまい汚れたりカブれたり大変なことになるので、大抵何らかの塗装がしてあります。
塗装は銀メッキ、ラッカー(樹脂による塗装)仕上げ、金メッキの3種類がほとんどを占め、数的にこの順番で流通しています。銀メッキはクリアで軟らかい音色、ラッカーはパワフルでつややか、金メッキは華やかで音が割れにくいなど、それぞれの特徴があります。非常に大雑把に言って、クラシックでは銀メッキや金メッキが使われることが多く、ジャズやポップスなどではラッカーが多い傾向があります。それぞれ必要とされているサウンドを追求していった結果、そういう傾向になっているのだと思います。新響のトランペットセクションで使用されている楽器も、一番多いのは銀メッキの楽器、次に金、ラッカーといった感じです。
トランペットの構造は比較的単純で、ホルンやチューバといったほかの金管楽器に比べると、曲がっている管の本数なども少なく、直線的でシンプルに見えると思います。また、演奏の中での役割も、曲が盛り上がって音の大きくなったところで目立ったことをして見栄を切るといった大味な役割が特徴的(!)なので、なんとなく楽器自体もあまり難しい部分はないのでは?と思われる節があるかもしれません。しかし、トランペットにも繊細な要素があります。次に楽器の作りと音への影響についてのお話をしたいと思います。
*細工で音が変わる
例えば、楽器を横から見たときに特徴的なこの支柱、写真1では2本立っていますが、機種により1本だったり、無いものもあります。見た目的にいかにも楽器の強度を保つための、補強のための支柱に見えますが、実は強度的にはこの支柱は無くても大丈夫で、これは音色や吹奏感(吹いた感じ)を整えるための調節を行う目的でここにあります。

似たような目的の支柱はほかにもいくつかあり、中にはネジを差し込まないのに支柱の中にネジ溝が彫られている(写真2)といった、見た目では意味が分からない加工が施されているものもあります。これは楽器の開発段階で、無数の形や大きさの部品をあちこちつけたり外したりしながら、意図したサウンドが出せる楽器にするために行われた試行錯誤の結果なのです。
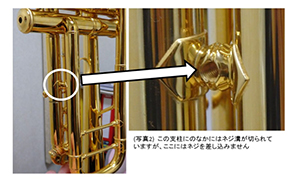
こうした部品の場所が数mmでも違ったり、数gでも重さが変わったりすると、音にダイレクトに影響します。例えば、洗濯バサミを楽器のどこかに適当につけただけで音や吹奏感が変わってしまい、全く別の楽器の様になってしまうことがあります。そうした繊細さを利用した、楽器をチューニングするための部品も色々販売されています。
しかし、買った楽器自体に自分で何か細工をして音を改善するのは実際には難しいことが多い様に思います。練習を重ねて音を良くするより、道具をなんとかして良くなるならその方が楽なわけで、何かがうまくいかないときに楽器をいじくりたくなるのは人情ですが、残念ながらあまり良い方向の変化に結びつかないことが多い様に思います。私も一部の楽器でネジやバネを形や材質の違うものに変えていますが、それですごく吹きやすくなったかどうか、あるいは音がよくなったかどうか、変えた当初は少し何かが変わったように思えても、しばらく使っていると変える以前の状況もだんだん忘れてきたりして、残念ながら効果はあまり定かではありません。そこで悩める演奏者が次に工夫を考えるのがマウスピースです。次にマウスピースのウンチクについて、お話したいと思います。
*マウスピースのウンチク
マウスピースとは口に当てる部分の長さ約8.8cmの部品です(写真3)。

人の唇の形や歯並びは千差万別ですし、また演奏で奏でたい音も人それぞれであるばかりか、曲や状況でも変わってきます。マウスピースはそんな様々なニーズに対応するべく、色々なサイズのものが用意されており、状況に合ったものを選べるようになっています。
楽器を作っているメーカーはだいたいマウスピースも製造・販売しています。日本のヤマハは約40種類、アメリカのバックというメーカーは約100種類のラインナップです。その他、アメリカやヨーロッパにもこうしたメーカーがいくつかあるほか、マウスピースを専門に製造しているメーカーもあり、それぞれが数10種類の製品を備えているので、理論的には数100種類の中から選べることになります。それぞれのメーカーのカタログには、要所となる部分のサイズや、大まかな用途が解説されているので、今自分が必要としている物のだいたいの当たりを付けることができます。現在使用しているマウスピースのサイズとの違いや、解説部分に書いてある用途などを参考にして選ぶのです。例えばあるメーカーのオーケストラでの使用を想定したマウスピースの解説部分には、「落ち着きのある重厚な音を好むオーケストラ奏者向き」とか「パワフルなダークサウンド。本格的なシンフォニーオーケストラ奏者向けの代表品」といった、演奏者の心をくすぐる文章が踊っています。
多くの奏者は、初心者の段階でたまたまそこにあった、あるいはしかるべき先輩や先生に勧められたマウスピースを使い楽器を始めると思われますが、前述の通り何か演奏に行き詰った時、マウスピースを工夫することで解決を図ろうとすることがあります。つまり、マウスピースをもっと良い、自分のニーズに合うものに変えればいいんじゃないか?と思うわけです。
しかし、数多くの既製品があってもそのすべてを取り揃えている店はありませんので、試しに手に取ってみることのできる種類は限られます。入手可能な中で色々試してみた結果、これとこれの中間のサイズがあるといいのになどといった微妙なニーズが発生することもあります。また、楽器店や専門の工房の中にはマウスピースのカスタマイズを受け付けているところもあります。知り合いから「あそこの工房に頼んで中を少し削ってもらったら吹きやすくなった」などといった話を聞いてしまうと、演奏に悩みがあるときほどそういう話には惹かれてしまいます。そこで既製品で満足がいかない場合、自分用にマウスピースをチューニングしたら良くなるのではなどと考えてしまうことがあります。チューニングについての詳細は本当にマニアックになってしまうのでご紹介を避けますが、こうしたチューニングは諸刃の剣で、うまくいくととても良い結果が得られる一方、うまくいかないときは結局どのマウスピースを使ってもうまくいかないという、脱出困難な深みにはまっていってしまうことがあり、注意が必要です。こうした工夫の変遷を経た結果、結局元のマウスピースに戻したなどという話はよく聞きます。ですから私自身は、問題に対して道具を工夫してみる努力は行ってみるべきだと思いますが、それだけで何かを解決しようというような過度な期待や追及は禁物であろうと思っています。
実際、私もこうした「マウスピースの旅」(!)に出て色々翻弄されたことがありましたが、幸い人づてに信頼できる工房にめぐり逢ってチューニングを受け、さらにそのマウスピースや楽器に対する考え方を指南してもらうことができました。その結果、いまでは「これでうまくいかなかったら道具のせいでなく自分のせい」と思えるもので演奏ができるようになりました。
以上、楽器のウンチクをご案内すると言いながら、実は私の体験談みたいな話になってしまいましたが、私なりの(だいぶ偏った)視点で、トランペットについてのご紹介をさせて頂きました。トランペットに関わりの無い方にはどうでもよいようなお話も多々してしまいましたが、他の楽器の奏者と同じく、トランペットの面々も色々とこだわりを持って楽器に取り組んでいるというイメージが少しでも伝わり、演奏をお聴きになるときのほんのちょっとした隠し味になっていただけましたら幸いです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
第237回ローテーション
| こうもり序曲 | ベートーヴェン8番 | 人魚姫 | ||||
| Fl | 1 | 兼子 | 1 | 吉田 | 1 | 松下 |
| 2/Picc. | 岡田 | 2 | 新井 | 2 | 兼子 | |
| ― | ― | ― | ー | 3/Picc.1 | 岡田 | |
| ― | ― | ― | ー | 4/Picc.2 | 藤井 | |
| Ob | 1 | 堀内 | 1 | 山口 | 1 | 岩城 |
| 2 | 山口 | 2 | 宮内 | 2 | 平戸 | |
| ― | ― | ― | ― | E.H. | 堀内 | |
| Cl | 1 | 高梨 | 1 | 品田 | 1 | 中島 |
| 2 | 石綿 | 2 | 進藤 | 2 | 大藪 | |
| ― | ― | ― | ― | Es Cl. | 末村 | |
| ― | ― | ― | ― | Bass Cl. | 岩村 | |
| Fg | 1 | 浦 | 1 | 浦 | 1 | 田川 |
| 2 | 笹岡 | 2 | 田川 | 2 | 笹岡 | |
| ― | ― | ― | ― | 3 | 浦 | |
| Hr | 1 | 大原 | 1 | 山口 | 1 | 大内 |
| 2 | 市川 | 2 | 菊地 | 2 | 市川 | |
| 3 | 宮坂 | ― | ― | 3 | 大原 | |
| 4 | 松尾 | ― | ― | 4 | 菊地 | |
| ― | ― | ― | ― | 5 | 山口 | |
| ― | ― | ― | ― | 6 | 松尾 | |
| ― | ― | ― | ― | 1assi | 宮坂 | |
| Tp | 1 | 北村 | 1 | 野崎 | 1 | 小出 |
| 2 | 中川 | 2 | 中川 | 2 | 野崎 | |
| ― | ― | ― | ― | 3 | 北村 | |
| ― | ― | ― | ― | 1assi | 中川 | |
| Tb | 1 | 志村 | ― | ― | 1 | 武田浩 |
| 2 | 武田浩 | ― | ― | 2 | 中島(*) | |
| 3 | 岡田 | ― | ― | 3 | 志村 | |
| ― | ― | ― | ― | 4 | 岡田 | |
| Tu | ― | ― | ― | ― | 土田 | |
| Timp | ― | 桑形 | 古関 | 皆月 | ||
| Perc | シンバル付 大太鼓・鐘 |
古関 | ― | ― | シンバル グロッ ケンシュピール |
今尾 |
| トライアングル | 桑形 | ― | ― | トライアングル・鐘 | 古関 | |
| Harp | ― | ― | ― | ― | 1 | 見尾田(*) |
| ― | ― | ― | ― | 2 | 井田(*) | |
| Vn | 1 | 堀内(小松) | 1 | 堀内(小松) | 1 | 堀内(内田) |
| 2 | 中島(伊藤真) | 2 | 中島(伊藤真) | 2 | 中島(田川) | |
| Va | 柳澤(槇) | 柳澤(槇) | 村原(小畑) | |||
| Vc | 柳部(安藤) | 柳部(安藤) | 柳部(安田俊) | |||
| Cb | 中野(渡辺) | 中野(渡辺) | 中野(渡辺) | |||
第237回演奏会のご案内
音楽の都 ウィーン
今回は第231回演奏会に引き続き、ウィーン在住の寺岡清高氏を指揮に迎え、ウィーンにちなんだ3曲を演奏します。
前半は、「ワルツ王」ヨハン・シュトラウス2世の人気オペレッタ「こうもり」の序曲と、ベートーヴェンの交響曲第8番です。交響曲第8番は第7番と同時に初演された曲で、人気の第7番の陰に隠れた印象ですが、古典的ながらも創意工夫に溢れ、躍動感のある名曲です。
世紀末ウィーンの作曲家 ツェムリンスキー
寺岡氏は19世紀末から20世紀初頭のウィーンの作品をライフワークとしており、後半はその中からツェムリンスキーの交響詩「人魚姫」を取上げます。
ツェムリンスキーという名前に馴染みがない方も多いと思いますが、芸術の花開いた世紀末ウィーンの音楽シーンで重要な役割をした作曲家です。
ウィーンで生まれたツェムリンスキーは13歳でウィーン楽友協会音楽院(現在のウィーン国立音楽大学)に入学し、優秀な成績でピアノ科を卒業した後も作曲を学び、ブラームスに見出されます。その後はワーグナーやマーラーの影響を受け、ロマンティックな作品を残しています。指揮者としても有能で、ウィーン・フォルクスオーパーの初代監督を務めました。
現代音楽の祖として有名なシェーンベルクの作曲の師であり、義理の兄でもあります。また、アルマ・シントラー(後のマーラー夫人)も彼の弟子にあたります。
人魚姫の物語
「人魚姫」は皆さんご存知のアンデルセンの童話。海の底に暮らす人魚姫は、難波した船から瀕死の王子を救い出し、恋をする。魔女に薬をもらい、声と引換えに人間の脚を手に入れるが、もし王子が他の娘と結婚すれば海の泡と消えてしまう。めでたく王子と御殿で暮らせるようになったものの、声を失った人魚姫は王子を救ったことを話すことができず、王子は浜辺で介抱した娘を命の恩人と勘違いし、結婚することに。人魚姫の姉が魔女にもらった短剣で王子を刺せば人魚に戻れると告げられるが、人魚姫は海に身を投げ泡となり天国に昇るという、悲しく切ないお話です。
アルマに恋をしたツェムリンスキーでしたが、結局アルマはマーラーと結婚し、失恋してしまいます。ちょうどその時期に作曲されたのが「人魚姫」でした。人魚姫の物語の光景や心情が音楽でドラマティックに表現されています。
シェーンベルクの交響詩「ペレアスとメリザンド」と同時に初演されたのですが、「ペレアス」の評判が良くてツェムリンスキーは落胆したのか、その後演奏されることはありませんでした。ツェムリンスキーが1938年に米国へ亡命したこともあって楽譜は散逸していましたが、1980年代にようやく蘇演され、再評価されています。「ペレアス」よりもわかりやすく、映画音楽のように楽しめる作品となっています。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
セコバイ弾きの哀愁、そして矜持
1番は、やはり格好が良い。ある都知事は公約に掲げる、「都民ファースト」と。惜しくも大統領の椅子に手が届かなった女性候補者はかつてこう呼ばれていた、ファーストレディと。各航空会社は利用者に高級感を演出する、ファーストクラスで。ある野球チームの監督はかつてインタビューにこう答えた、「そのチームはイチバンです。」と。
一方で、これが2番となると、何となく脱力感が出てくる。「都民セカンド」、第三者の厳しい目にも到底耐えられそうにない。セカンドレディ、どことなく愛人感が漂う。セカンドクラス、おそらくトップリーダー的な人には利用されない。「そのチームはニバンです。」そういえば、昨シーズン最大11.5ゲーム差をひっくり返された球団があった。
その他、二軍、二の次、二の舞、二番煎じ、二の足を踏む、二番じゃダメなんですか等、2番にはどうにもネガティブな言葉、表現が多い気もする。
ところが、殊にオーケストラにおいては、1番のみならず2番までもが、いや2番こそが、輝くことも時折ある。そう、2番だって決して捨てたものではない。そんな2番手奏者(と書くと実力的に劣るにように思われるが、そんなことは決してない、たぶん…)を務めることが多い、バイオリン弾きの私であるが、その魅力等について、以下に独断と偏見と浅い知識に基づいた薀蓄を披露してみたいと思う。
1:セカンドバイオリンについて
オーケストラ愛好家にとっては常識の範疇であるかもしれないが、大抵のクラシック楽曲において、バイオリン奏者は第一バイオリン(ファーストバイオリン、通称ストバイ)と第二バイオリン(セカンドバイオリン、通称セコバイ)に分かれて弾くこととなる。ファーストという名のとおり、オーケストラの顔たるコンサートマスター率いる花形楽器であるストバイに対し、セコバイはその次の二番目に偉い、なんてわけはない。むしろ、あまり日のあたることのない、中々地味な役割を与えられることが多い。
そもそも、セコバイとは何なのか、語弊を恐れずに言うのであれば、バイオリンでありながらバイオリンと認識されにくい楽器である。大抵のバイオリニストは幼少の頃、バイオリン協奏曲の優美な旋律を奏でる高名なソリストを目にして、いつかは自分もこうありたいと夢見るものである。少し大きくなると現実を悟りソリストは無理とわかりつつも、オーケストラという集団に新たな可能性を見出し、壮大な交響曲のメロディを華々しく演奏するバイオリニストの姿を想像するのが、世の常であると思う。ただ、そのメロディ等を演奏できるのはバイオリンといってもストバイの方であり、その陰に隠れるセコバイにまで考えが及ぶことはない。すなわち、ソリストやストバイに憧れてバイオリンに興味をもつ人はいても、派手な出番のないセコバイをやりたくてバイオリンを始める人は、ほぼいないといえる。
幸いにというか、この新交響楽団のバイオリンパートはストバイとセコバイのメンバーが固定されているわけではないため、演奏会ごとにいずれのパートも経験することができる。とはいえ、セコバイに割り当てられたメンバーが毎回ふて腐れてモチベーションも上がらない中で演奏しているのかといえば、決してそんなことはない。実は、セコバイにはセコバイならではのやりがい、楽しさが存在するのである。
2:セコバイあるある
セコバイ弾きがオーケストラにおいて、普段どんなことをしているのか。以下、あるあるネタ形式でざっと挙げてみたい。
(1)とりあえず「刻み」
これはざっくりと言うと、オーケストラにいる他の楽器の伴奏のことである。管楽器やストバイ、チェロ等、様々な楽器が華々しいソロを弾く裏で、セコバイは細かいリズムをひたすら実直に「刻む」ことをやっていることが多い。
一言に「刻み」といっても、中々奥が深い。曲の背景的な役割からメロディの合いの手まで、幅広いバリエーションがある。また、ただ正確にリズムを刻むだけであれば、それは機械にもできるのであるが、オーケストラは自由自在に動き回る、まさに生き物。そして「刻み」は、その生き物の鼓動とでも言えようか。オーケストラの流れ、息遣いに合わせ、正確かつ活力溢れる鼓動を打ち込んでいく役目がセコバイにはある。そのためには、自身の音のクオリティはもちろんのこと、メロディ楽器のちょっとした歌い回し等も含め、オーケストラ全体の状況を瞬時に把握し頭に入れた上で、その場その状況に合わせた「刻み」を展開していくこととなる。
他にも色々とやるべきことは多いものの、この「刻み」こそが、セコバイに与えられた最も重要な役割であるといっても過言ではない。傍目には単調な「作業」に見えてしまうのかもしれないが(たしかに、何の考えもなしに弾くとそうなってしまうのであるが)、さにあらず、オーケストラの重厚な響きを支えるという大きな醍醐味があり、かつ高度な技術な要求される「音楽的な営み」なのである…と信じ、セコバイ弾きは今日も人知れず「刻み」に熱意を傾けている。
(2)気が付くとみんな演奏している
では、「刻み」のない箇所で、セコバイは何をしているのか。答えはいたってシンプルであり、大半は休符、お休みである。休みの間といえども侮るべからず、小節数をしっかりと数え次の出番に備えておくのも演奏の一部である、と太鼓を嗜む家人が言っていた、そういえば。
とはいえ、他の楽器が力強く演奏する中、セコバイだけが長いお休み中というケースはままある。決して落ちた(どこを弾いているか見失った)わけではなく、作曲家の指示に従った結果であるのだが、どういった佇まいでじっと座っていればいいか、毎回軽く頭を悩ませるところである。ちょっとした顔芸でも試してみようかと思いつつも、小心者が災いし、結局は神妙(そうな)面持ちで出番をひたすら待っている次第である。
(3)おいしいところは滅多に回ってこない
こんなわけで、セコバイに単独の「おいしい」メロディを割り振ってもらうことは、まずもってない。自宅での個人練習は先述の「刻み」を延々と繰り返すばかりであり、家人は何の曲を練習しているのかさっぱりわからず、何が楽しくて練習しているのか理解に苦しんでいることであろう。
セコバイと同じような役割を担う楽器で、ビオラというちょっと大きめなバイオリン的な楽器もあるのだが、こちらの方が俄然メロディの出番は多い…と思う。なぜなら、ビオラにはビオラしか出せない音色、音域があり、オーケストラの中で映えるのであるが、セコバイに出せる音色、音域は悲しいかな、通常ストバイに割り振られるのである。
(4)団体芸ならできる
もちろん、メロディ的な旋律をもらえないこともない。大概は、他の楽器とのユニゾン(同一のメロディ)であるが。
特に、ストバイの旋律のオクターブ下を弾くのが、よくあるパターンである。この場合、客席で聞いたときの印象はどうしてもストバイにもっていかれるのであるが、良いこともある。というのも、バイオリンで高音を繊細、優美にかつ正確に奏でるのは、見た目以上の指南の業。1オクターブ下げた方が、弾くのが俄然楽なのである。カラオケに例えてみるとわかりやすい。サビの部分の高音は音程がとりづらく声もか細くなってしまいがちであるが、1オクターブ下げて歌うこと楽に歌えることもある。これを作曲家の指示によりできてしまうのが、セコバイのお得なところである。
なお、単独のメロディを弾くことを全く放棄したわけではなく、ときたまおいしい旋律が割り当てられることもある。それはそれで、後述の問題が発生するわけであるが。
(5)そしてメロディは急に振られる
先ほど、セコバイには「合いの手」的な役割があると書いたところであるが、これがとにかく曲者である。例えば、ここは伴奏だなと思って演奏している箇所で、突如としてメロディや重要なつなぎ(「合いの手」)が割り振られる。または、思いがけないところで指揮者と目が合ってしまい、さぁお前らここからだ的な合図を送られる。
こういった状況において、まず初回練習等では、とりあえずビビる。事前にちゃんと研究しておけば良いのにという話はさておき、ここで行くのか、的な驚きと不安。そして、案の定情けない音しか出てこない。また、二回目以降に同じ箇所を弾く時は、今度は意識して妙に張り切る。すると力んで余分な力が入り、やっぱり悲惨な音しか出てこない。
加えて厄介なことに、こういったセコバイの出番は1~2小節等のみの非常に短いフレーズで、すぐさま伴奏に戻ることも往々にしてある。何しろ、「合いの手」であるので。失態を取り返す暇もなく、悶々とした気持ちを抱えながら、オーケストラは無情にも先へ進んでいくのである。
この伴奏とメロディの気持ち的な切り替えが、セコバイの最も難しいところであると感じている。学芸会で、名脇役の気持ちで演技に入り込んでいた子供が、いつの間にか主役がいなくなり急に自分にスポットライトを当てられても、途方に暮れるばかりであろう。すなわち、その場その場で様々な役割を演じ分ける必要があるのだが、そういった瞬発力や器用さが一向に身についていかないのが、悩みの種である。実生活にも通ずるところがあるのかもしれない。
3:セコバイ弾きとして
ここまで思いつくがまま、セコバイの魅力等について書かせて頂いた。良い部分のみならず、色々とネガティブな面も書いてしまったところもあるが、無論、基本的にはセコバイ弾きとして、オーケストラでの演奏を楽しませてもらっている。セコバイならではの楽しみ、スリル、色々な発見、そしてやりがいを満喫しつつ、次回演奏会に向けて地道に楽器を奏で続ける日々である。
次回演奏会では、時折絶妙な存在感を醸し出す、セコバイのいぶし銀的な魅力に気づいて頂ければ、セコバイ弾き冥利に尽きるというものである。そううまくはいかなったかとしても、本原稿の内容を頭の片隅に入れて頂き、セコバイ勢の奮闘に温かい目を向けて頂ければ幸いである。
ストラヴィンスキー:バレエ音楽「火の鳥」
「火の鳥」と言えば、手塚治虫の長編漫画を思い出す方も多いのではないかと思う。手塚治虫のライフワークであり、古代から未来に亘る時空を超えた永遠生命体として火の鳥が描かれる。残念ながら、この漫画と本日演奏するバレエ音楽の元になるロシア民話とは直接の関係はない。しかし、手塚治虫によれば、バレエ「火の鳥」を観て、火の鳥を演じたバレリーナの魅力に心を奪われたのが漫画「火の鳥」を描くきっかけだったそうである。
そのバレエ「火の鳥」はセルゲイ・ディアギレフが1909年に創設したロシアバレエ団(バレエ・リュス)の初のオリジナル作品であった。なお、バレエ・リュスは外国公演の際の名前で、ロシア国内ではバレエ・リュスとして公演を行ったことはない。ディアギレフは、1910年のパリ公演にロシアに関係したオリジナル演目を計画し、ロシアの民話「イワン・ツァレヴィチ(イワン王子)」と「火の鳥と灰色の狼」を基に、振付けのフォーキンと共に台本を書いた。作曲については、当初リャードフに依頼しようとしたが、遅筆でパリ公演には間に合わないと判断したディアギレフは、「花火」の音楽で注目されていたとはいえ、無名に近かったストラヴィンスキーに依頼することとし、彼は見事にディアギレフの期待に応えたのであった。
フォーキンは優れた踊り手でもあったが、近代バレエの方向性を決定した振付師である。フォーキンはそれまでの古典的バレエが、筋とは関係なく、突然パ・ド・ドゥ(主役の男女2人による踊り)が始まったりするのを嫌い、バレエの振付けに関する提言を公表している。その中で、舞踊は登場人物の精神や心の表現でなければならないこと、音楽と舞踊は調和すべきこと、シーンの中断はあってはならないこと、音楽と踊り手の動きがそれぞれ意味を持っていなければならないことなどをのべている。「火の鳥」では情景を彷彿させる音楽が書かれ、その音楽に合った振付がなされた。練習にピアニストとして毎回立ち会ったストラヴィンスキーはリズムに興奮してくると、壊れそうなほどの大音響でピアノを叩き、これに後押しされたフォーキンは独創に満ちた踊りを完成させたと言われている。
1910年のパリ・オペラ座での初演はバレエ団メンバーの猛練習もあって大成功だった。火の鳥はフォーキン自身が踊り、バレエ・リュスとストラヴィンスキーの名はバレエ界に轟くことになり、その後ロシアを題材とする三部作「火の鳥」「ペトルーシュカ」「春の祭典」が生まれ、ストラヴィンスキーの曲によるユニークなオリジナル作品はバレエ・リュスの中心的作品になっていく。
「火の鳥」の音楽には、本日演奏するオリジナル版(1910年版)の他に、その組曲版(1911年版)、2管編成に編成を小型化して演奏機会の増加を図った組曲版(1919年版)、1919年版にさらに手を加えた組曲版(1945年版)の計4つの版がある。これはストラヴィンスキーの経済状態が良くなかったため、異なる版を作ることにより収入増を狙ったものと考えられている。
さてあらすじである。
「火の鳥」のスコアには各所にいわゆるト書きが書かれて音楽が表している状況を説明しており、フォーキンの振付けはそれをわかりやすく表現している。
以下、導入部と第1幕、短い第2幕で構成され、切れ目なく続くこのバレエの舞台の様子と音楽を実況中継風に説明することを試みたい。
導入部
始まりました。大太鼓のトレモロに乗って、チェロとコントラバスが上下にうねる旋律をゆっくりと奏しております。これは不死身の魔王カスチェイの支配する魔界の闇を表しているようです。
第1幕
(1)カスチェイの魔法の庭園
弱音器を付けたホルンや弓を駒に近づけて弾くポンティチェロ奏法は不気味な雰囲気を作り出しています。
ここで、幕が上がりました。魔王カスチェイが住む魔法の庭園が月明かりに照らされて見えます。庭園の中央には黄金の実をつけた林檎の樹があるようです。この黄金の林檎は幸福の象徴であると聞いております。
(2)イワンに追われた火の鳥の登場
あっ、何かが舞台上空を横切ったようです。木管やヴァイオリンに鳥の羽音を模した音楽が聞こえます。真っ赤な衣装をつけた女性ダンサーが飛び跳ねて魔法の庭園に現れました。どうやら、これが火の鳥のようです。もう一人、若い男性が弓を持って魔法の庭園に現れました。王子イワン・ツァレヴィチでしょうか。火の鳥を追っていたようです。オーボエのソロによるロシア民謡風の旋律が聞こえます。
(3)火の鳥の踊り
6/8拍子になりました。クラリネットとフルートやハープ、ヴァイオリンなどにせわしないモティーフが聞こえ、鳥の羽音を模したもののようです。3本のハープのグリッサンドも聞こえます。火の鳥は高い跳躍で魔法の庭をあちこち飛び回っております。イワン王子は何をしているのでしょうか? いました。どうやら木陰に身をひそめて、火の鳥が飛び回っている様をじっとうかがっているようです。やっ、イワン王子は、木陰から飛び出して火の鳥につかみかかりました。
(4)イワンによる火の鳥の捕獲
音楽が激しくなりました。火の鳥はもがき、逃げようと必死ですが、疲れ果てて捕まってしまいました。ヴィオラのソロが聞こえ、火の鳥は何かを訴えているようです。
(5)火の鳥の懇願
火の鳥の悲しみを表すような悲しげなテーマがオーボエとヴィオラ・ソロで奏されています。トランペット・ソロの音で火の鳥は 、自分の体から美しい1枚の羽根を抜き取ると、それをイワン王子に渡しました。「もし、あなたが危険にさらされた時には、この羽根があなたを助けてくれるでしょう」と言っているようです。男性は、女性のお願いには弱い。羽根をもらうと火の鳥の踊りを思わせるような速いテンポとなりました。火の鳥は飛び立って行ったようです。ホルンにイワン王子のテーマが聞こえますが、火の鳥を逃がしてやって満足した気持ちが感じられます。
(6)魔法にかけられた13人の王女たちの登場
森の向こうに城門が見えて参りました。イワン王子は好奇心にかられて思わず足を止めています。そのとき、城門が開き、ヴァイオリン・ソロが奏でる優美な旋律に合わせて中から白い衣装をまとった12人の乙女たち、そして少し衣装が違う一人の乙女が現れました。これはツァレーヴナ王女、他の乙女も皆王女であると聞いております。
(7)金の林檎と戯れる王女たち
弦楽器のトレモロが聞こえます。2/4拍子の軽快な舞曲に乗って、乙女たちは、林檎の樹の周りにやって来ると、黄金の林檎を手にして楽しそうに踊り始めました。林檎のキャッチボールもしています。イワン王子はどうした? あ、いました。物陰で乙女たちを見ています。
(8)イワンの突然の出現
イワン王子はひときわ美しいツァレーヴナ王女に興味を持ったようで、ホルンによるテーマとともに乙女たちの前に姿を現し、挨拶をしました。王女たちはびっくりした様子です。
(9)王女たちのロンド
王女たちは、イケメン王子に好感を持ったようです。ピッコロに先導され、ハープのアルペジオに乗って、オーボエが4/4拍子の美しい旋律を歌い、王女たちは踊り始めました。この踊りはロシアの古い民族舞踊のホロヴォードで、第2主題がヴァイオリンとチェロで歌われています。
ツァレーヴナ王女はここがカスチェイの城であること、王女たちはカスチェイの魔法によって閉じ込められていることを話した模様です。
(10)夜明け
時間が経つのは早い。東の空が白み始め、城からはトランペットの音が聞こえました。13人の王女は再び城に幽閉されるようです。ツァレーヴナ王女とイワン王子は最後の接吻を交わし、王女たちは城の方へ戻って行きました。音楽は悲しそうです。
(11)イワンのカスチェイ城内への侵入
急に音楽のテンポが上がり、王女たちを助けようと決意したイワン王子がシンバルなどの打楽器の音とともに城門を開けました。
(12)魔法のカリヨン、カスチェイの怪物番兵の登場、イワンの捕獲
おお、何ということだ! 門からは異様な格好の兵士がたくさん飛び出して来ました。どうやらカスチェイの部下の怪物番兵のようであります。打楽器、ハープ、チェレスタが騒々しい雰囲気を出しています。イワン王子は抵抗していますが、捕らえられて縛られてしまったようです。
(13)不死身の魔王カスチェイの登場
低音管楽器が鳴っています。何か恐ろしいものが登場しそうだ。あっ、出て来ました。骸骨のような実に醜悪な容貌です。これは魔王カスチェイのようです。
(14)カスチェイとイワンの対話
イワン王子がカスチェイの前に引き出されました。カスチェイが厳しく尋問しております。イワン王子は堂々たる態度で一歩も引かないばかりか、カスチェイに唾を吐いたようです。この間、オーケストラは目まぐるしく動いております。
(15)王女たちのとりなし
先ほどの王女たちが出て来ました。ヴァイオリン・ソロが聞こえ、どうやらカスチェイにイワン王子を許してもらうよう、懇願している様子です。カスチェイは聞く耳を持たないようで、わっはっはっはと笑ったのちに何か呪文を唱えようとしているようです。危うし、イワンは岩にされてしまうのか?
イワン王子は羽を取り出してかざしています。これこそ火の鳥がくれたもの。アラジンの魔法のランプのように火の鳥は現れるのか?
(16)火の鳥の出現
弦のハーモニックス奏法のヒューという音と木管楽器の早い動きが聞こえます。来た、来ました。約束違わず火の鳥が飛んで来ました。悪者に対して何やら魔法をかけたようです。
(17)火の鳥の魔法にかかったカスチェイの部下たちの踊り
オーケストラ全体が目まぐるしく変化しています。カスチェイとその部下はキリキリ舞の状態で踊らされてヘトヘトになっています。
(18)カスチェイの部下全員の凶悪な踊り
オーケストラ全体で和音を一発強烈に響かせると、ファゴットとホルンがシンコペーションで荒々しい旋律を奏でています。カスチェイの部下たちは、この音楽に乗って再び激しく踊り始めました。火の鳥はと見ると全員を操るような面白い動きをしていますが、そのうち疲れ果てた部下たちはバタバタ倒れていきました。
(19)火の鳥の子守唄
これは絶好のチャンスだ。火の鳥はヴィオラの先導の後ファゴットで美しい子守唄を歌い、カスチェイと部下たちを眠らせてしまいました。火の鳥はイワン王子を林檎の樹の所に招いてカスチェイの弱点を教えているようです。果たして不死身のカスチェイにアキレス腱はあるのか?
(20)カスチェイの目覚め
大変、コントラファゴットが鳴っています。身の危険を感じたカスチェイが目を覚ましたようです。イワン王子はと見れば、林檎の樹の根元にあった大きな卵を抱えています。どうするイワン?
(21)カスチェイの死
カスチェイが襲いかかってきましたが、イワン王子は卵を地面に叩きつけて割ってしまいました。大太鼓、タムタム、管楽器と低音弦がグロテスクに鳴り響き、カスチェイは死んだ模様です。会場内では拍手が起きています。
(22)深い闇
会場が暗くなり、あたりは深い闇に包まれました。そのまま第2幕に突入です。
第2幕
(23)カスチェイの宮殿とその魔力の消滅、石にされた騎士たちの復活、全員の歓喜
弦の明るい響の上にホルンが平和な気分のロシア民謡風の旋律を奏でています。この旋律はヴァイオリンや他の楽器に引き継がれ、盛り上がります。カスチェイの宮殿は消滅し、13人の王女は自由の身になり、石にされていた12人の騎士たちも元の姿に戻ったようです。騎士たちと12人の王女、イワン王子とツァレーヴナ王女は結婚することになり、舞台上の全員が喜びをかみしめています。
ここで幕が降りてまいりましたので、以上で実況中継を終わります。
新響の創立指揮者で音楽監督であった故芥川也寸志からストラヴィンスキー三部作上演が提案され、初めて「火の鳥」(1919年版)を演奏したのは43年前の1973年であった。次に「ペトルーシュカ」を取り上げ、さらに1975年6月1日には「春の祭典」を加えて念願の三部作一挙上演という画期的な演奏会を実現できたことが、新響にとってその後の邦人作品や現代作品を演奏する上で極めて重要な一歩であったことを再確認して本稿を終えたい。
初演:1910年6月25日 パリ・オペラ座 バレエ・リュス公演 指揮:ガブリエル・ピエルネ
火の鳥:タマラ・カルサヴィナ イワン王子:ミハイル・フォーキン
楽器編成:ピッコロ2(2番はフルート持ち替え)、フルート3、オーボエ3、コールアングレ、クラリネット2、小クラリネット、バスクラリネット、ファゴット3(3番はコントラファゴット持ち替え)、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トライアングル、タンブリン、シンバル(奏者2人)、大太鼓、タムタム、グロッケンシュピール、木琴、チェレスタ、ピアノ、ハープ3、バンダ(トランペット3、テナー・ワーグナーテューバ2、バス・ワーグナーテューバ2、テューブラーベル)、弦五部
参考文献
『バレエ・リュス その魅力のすべて』芳賀直子 国書刊行会2009年
『ディアギレフ・バレエ年代記1909-1929』 グリゴリエフ(薄井憲二・森瑠依子訳) 平凡社2014年
『ダンスの20世紀』市川雅 新書館1995年
マリインスキー劇場公演ビデオ フォーキン振付け版
ドビュッシー:バレエ音楽「遊戯」
スペイン国王、アルフォンソ13世が尋ねられた。「ディアギレフ君、君は指揮者ではないし、ダンサーでもない。ピアニストという訳でもない。一体全体、君は何をしておるのかね?」機知に富んだ会話と人心掌握の術に長けた希有の興行師は、満面に笑みを浮べて答えた。「陛下、畏れ多くも陛下と同じでございます。あくせく働くことはおろか、これといったことは一切何も致しません。ですが、私は、なくてはならない人間なのです。」
ディアギレフは、1872年、ウラル山脈近くにあるペルミで貴族の家庭に生まれた。典型的なディレッタントで、リムスキー=コルサコフに作曲を習ったり、文芸・美術雑誌<ミール・イスクストヴァ>を創刊して評論を書き、展覧会をオルガナイズしていた。
ロシアとフランスは、啓蒙君主であった女帝エカテリーナ2世(在位1762-96)以来、文化的に接近していたが、ビスマルク率いるプロイセンに対抗する為、1894年の露仏同盟締結に及んで、政治・経済の結び付きも強められた。時代の流れを鋭く嗅ぎ分けて、ディアギレフは1906年にパリで「ロシア美術展」を開催する。1907年にはパリ・オペラ座でリムスキー=コルサコフ、グラズノフ、ラフマニノフ等が自作自演する「ロシア音楽会」を企画し、翌08年はシャリアピンにタイトル・ロールを歌わせて<ボリス・ゴドノフ>を上演。以上の周到な準備を重ねて、いよいよ09年、パリ・シャトレ座にバレエが登場し、パリっ子達の度肝を抜いた。
バレエの原型はルネッサンス期に北イタリアで生まれ、1533年カテリーナ・デ・メディチとアンリ2世の婚礼の際、フランス宮廷に持ち込まれた。太陽王ルイ14世の厚い庇護もあり、18世紀末に「ロマンティック・バレエ」として完成されたが、19世紀後半になると低俗化して凋落の一途を辿る。一方、ロシアでは17世紀にロマノフ王朝に取り入れられた後、西欧化政策の一環として発展を続け、19世紀中頃にはタリオーニ、プティパ等優れた踊り手、振付師をフランスから招聘し高水準の技巧と、チャイコフスキーの3大バレエに代表される強い創作エネルギーを保持していた。つまり、20世紀初頭の時点では、本家フランスと分家ロシアの勢力関係は完全に逆転していて、ディアギレフは、この状況を巧みに利用したのだった。
バレエを総合芸術と捉え、演出・振付・舞踊・音楽・舞台装飾・衣装デザイン全てが、必然性を持って有機的に調和しなければならないと考えたディアギレフは、常に斬新な舞台を求めて各分野から新進芸術家を掘り起こし、「天才を見つける天才」と呼ばれた。しかし、高い芸術的水準を狙う余り、不世出のプロデューサーの力を持ってしても経営は常に苦しく「借金の天才」とも言われていた。
ドビュッシーの生涯は、1880年代後半から1914年の第1次大戦開戦までと言われるベル・エポック(Belle Époque:美しき時代)と概ね重なっている。当時パリは、世界の首都になったかの如く空前の繁栄を見せていたが、その要因の一つに、国家的プロジェクトとして1855年から1900年まで、ほぼ11年間隔で5回開かれたパリ万国博覧会が挙げられる。「産業と芸術の万博」と名付けられたパリ万博は、第3回の1878年にコンサート会場としてトロカデロ宮が新築され、フランス革命100周年を記念して開かれた1889年の第4回はエッフェル塔が誕生し、ガムランやヴェトナムの舞踊は若いドビュッシーを驚嘆させた。川上音二郎・貞奴が出演した1900年の第5回には、ギマールの設計によるアール・ヌーヴォー様式で飾られた地下鉄が開通した。
生活水準の向上は余暇の大衆化を生む。自動車・鉄道等交通手段の発達と相俟って身近になったヴァカンス旅行はルイ・ヴィトンのトランクやシャネルの活動的モードを出現させ、タイヤ製造会社のミシュランによる<ミシュラン・ガイド>も刊行された。ノルマンディーの海岸リゾートに於ける海水浴やテニスの流行とともに高まるスポーツへの関心は、クーベルタンが提唱して1896年にアテネで産声をあげた近代オリンピックに結実する。プルーストが著した<失われた時を求めて>には、この時代の雰囲気が克明に描かれている。
ドビュッシー最後のオーケストラ作品となった<遊戯>は、1912年にバレエ・リハーサル用のピアノ・スコアが約3ヶ月で書き上げられ、翌13年にオーケストレーションが完成された。ディアギレフが<遊戯>を委嘱したのは、ニジンスキーが<牧神の午後への前奏曲>に振付けて踊り、スキャンダルを引き起こした直後であった。<牧神>をバレエに使う事自体、余り乗り気でなかったのに渋々承諾したドビュッシーは、このスキャンダルが踊りの仕草に向けられたものだったので、騒ぎから慎重に距離を置いていた。ところが、1913年5月15日に、ニジンスキー、カルサヴィナ、ショラーの踊り、バクストの装置・衣装、モントゥーの指揮による<遊戯>の初演がシャンゼリゼ劇場で行われると、今度はスキャンダルすら起こらない。この公演には<火の鳥>、<シェヘラザード>の再演もプログラムに組まれていたが、当時の聴衆にとって<遊戯>は捉え所のない退屈な音楽に思われて冷たく迎えられ、散々の 酷評を受けたのだ。しかも、2週間後の5月29日、同じシャンゼリゼ劇場で<春の祭典>初演という暴動寸前の歴史的大スキャンダルが勃発すると、<遊戯>は、その存在すらも一般音楽ファンからは忘れられた。
19世紀末芸術家の中で20世紀芸術へ移行する原動力となった芸術家として、ドビュッシー、セザンヌ、マラルメの3人を挙げているブーレーズは、全体で110小節、時間にして10分の小品とも言える<牧神の午後への前奏曲>を20世紀音楽への「偉大な前奏曲」と述べている。彼や現代ドイツ音楽の代表的な作曲・理論家のシュトックハウゼン等が、第2次大戦後になって<遊戯>の特徴である「絶え間ないテンポの移行と瞬時に輝きを変えていく音色によって構築された、時間のねじれと流動を続ける形式」を再発見・再評価して、「楽譜の限界を超えるフレクシブルな音楽」は20世紀前半に書かれた最も重要な先駆者的作品であると名誉挽回された。
<遊戯(Jeux)>といっても子供のお遊戯ではなく、Jeux de l’amour(愛の戯れ)とJeux de sport(スポーツのプレイ)を掛けたものと考えられる。Jeux(jeuの複数形)には、ゲーム、競技場、賭事、演技・演奏、駆引き、機能等広い意味があり、「遊戯」という日本語訳から一般的に受けるイメージが原題に適っているとは思えない。私が学生の頃、この曲のレコードは日本でほとんど出ていなかったので、タイトルだけ見て子供の為の曲だと思っていた。ドビュッシーは、次に<おもちゃ箱(La Boîte à joujoux)>という未完の曲を書いているから、子供の為の2曲セットだと早合点したのだ。
夜間照明に照らされた黄昏時のテニスコートでボールが見失われ、青年が捜しに行く。二人の若い女性が現れ、一人ずつ踊っていると、男が戻ってきて片方の女と踊り抱擁する。もう一人の女は嫉妬にかられ皮肉っぽくからかうので、男は踊りの相手を変え、さらに後には三人で踊り始める。幻想の世界へと誘(いざな)われ、恍惚のうちに常軌を逸したクライマックスに達すると、どこからかボールが飛んで来て三人は驚き、公園の闇の中へ消え去る。
「青年」は、テニスウェアを纏った「牧神」だったのかも知れない。
初演:1913年5月15日 パリ・シャンゼリゼ劇場にて ピエール・モントゥー指揮
楽器編成:ピッコロ2、フルート2、オーボエ3、コールアングレ、クラリネット3、バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン4、トランペット4、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トライアングル、タンブリン、シンバル、木琴、チェレスタ、ハープ2、弦五部
ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲
◆笛とエロス
例えばこんな歌がある。
笛竹の声の限りをつくしても
なほ憂き伏しや夜々に残らむ
藤原良経(『六百番歌合』 12世紀末)
「寄笛恋」の題に基づいて詠まれた一首。笛に寄する恋とはまずは笛の「音」に伝える恋情である。言葉を得る以前、声の良否が恋の武器であった頃の遠い記憶が、言葉にならぬ言葉を伝える術として人に蘇ったものだろうか? 事実、恋と笛の音とを結びつける話は数多あり、それぞれに味わい深い。
『枕草子』には特に笛に関する章段があって、 「後朝(きぬぎぬ)の別れの後、男が忘れていった見事な笛を枕辺に見つけるのも風情がある」などと書いてある。前晩の記憶…人を待つ夜の静けさ。やがて近づいた笛の音と共に忍んで来た男の姿や声音。その衣服の色あいと焚きこめられた香り。交わされた言の葉の数々。こうしたものが遺された笛によって改めて呼び起こされ、恋の余情を醸し出す。
その笛を紙に包み手紙のように仕立てて男の元に届けさせる。当然そこには笛に託した恋の歌が添えられる事になる。これが「寄笛恋」で、もちろん男も歌を返し、互いの心のうちを交し合う。ここではもはや音を離れ、笛という「物」に心情が託されている。とすれば男が故意に、だがさりげなく笛を置いてきたという想像にさえ行き着く。王朝文化の一端が偲ばれようというものだ。女性の部屋に招かれた僥倖(ぎょうこう)にすっかり舞上がり、いたずらに酒杯を重ねた挙げ句、終電に飛び乗ったところで、うっかりフルートを忘れてきた事に気づくようでは駄目なのである(苦笑)。
『徒然草』に「女の足駄で作った笛の音には、妻を恋う秋の鹿が必ず寄ってくる」とある(第九段)。この場合は確かに笛の「音」と恋の話だ。挿話的に出ているに過ぎない記述だが、女の霊力(妹(いも)の力というべきか?)と笛にまつわるそこはかとないエロティシズムを感じさせ、僕は格別の印象を持っている。
そしてギリシャ神話に登場するパン(Pan)の吹く笛も恋情を伝える役割をしている。半獣半人の姿の彼は、牧人と家畜の神でありながら山野に美少年や妖精(ニンフ)を追いかける好色性を併せ持ち、この呼びかけの道具として葦笛を使う。この笛をシュリンクス(注1)(syrinx)というが、これはかつて彼の追跡を逃れようとして葦に変容した同名のニンフであったという伝説がある。また、この神は午睡を好む。その娯たのしみを妨げられるとその怒りは、譬(たと)えようもない恐怖となって人々に襲いかかった。英語のpanicの語源はここにあるという。
◆詩と音楽と
ステファヌ・マラルメ(1842-1898)は中級官吏の子として生まれ、英語教師を生活の糧としつつ詩作を続けた。上の神話を踏まえた『半獣神(牧神)の午後』を1876年に出版する(注2)。34歳のことである。容易に公表の場を得られぬまま10年の曲折を経ていた。この詩の主題はふたりのニンフとの、言わば恋の駆引きをめぐる半獣神の情慾と妄想にほかならない。
ドビュッシーもまた苦学力行の人だった。音楽とはおよそ無縁の貧しい境遇に生まれ、10歳で音楽院に入学した後も絶えず学資の獲得には悩まされた。そうした彼にとってローマ大賞受賞(22歳)による2年間のイタリア給費留学は、幸運以外のなにものでもなかった筈だが、元来伝統的な音楽の語法に飽き足らぬ身には、何ら実り無きものに終わった。そして1887年に失意のうちにパリに戻ると、それまでの「音楽」との訣別を確信し、数年の模索の時代を過ごす事になる。ピエール・ブーレーズが「意志による独学主義」と評した彼のこの姿勢。その模索の中でマラルメに代表される象徴派詩人達との親交を得る事になる。彼は音楽家としては唯一、「火曜会」と称された彼らのサロンへの出入りを許されるが、この出遭いこそが音楽に新しい窓をあける契機となったのだ。彼は『半獣神の午後』に触発された音楽を、前奏曲・間奏曲・敷衍曲(パラフレーズ)の三部作として計画し、結局1893年に『前奏曲』のみ完成させた。この曲は110小節で構成されているが、これはマラルメの詩の110行と一致している。詩の全体を1曲に昇華させたという意図の反映だろうか。
牧神のまどろみの中に物語は始まる。彼の奏でる葦笛の空ろな音が、けだるい午後の水辺を渡ってゆく。その音の行く末の汀(みぎわ)に眠るふたりのニンフ。牧神は様々な想念と情念を秘めてふたりに挑みかかる。幕を開ける両者の駆引。遁走と追跡。そして遂に牧神は彼女らを掌中に収めようとする…が、ここぞという処で、抱擁からすり抜けられて果たせない。この間の激しい情念と動きは牧神の笛に仮託されるのみ。ふたりとの対話もないまま、ひたすら彼の陶然とした独白のうちに展開する無言劇…遂には魂の甲斐無き昂揚も果て(注3)、周囲には懶(ものう)げな午後の静けさが戻ってくる。
僅か10分足らずの間に繰り広げられる音の情景は、詩の内容への具体的な対応を意図していないにも関わらず、聴く者の裡(うち)に確かな心象をもたらす。それは「印象」などという曖昧なものとは明確な一線を画す、言わば音楽に結晶した言葉の姿とさえ思えてくる。ここに我々は「音楽的な詩」と「詩的な音楽」との境界を超えた、まばゆいばかりの融合の奇跡を見るべきだろうか?
そしてこの奇跡は短く儚(はかな)い。儚いが故にそれは一層聴く者の心をとらえ、消えゆく音に対し愛惜に似た感情を呼び起す。この感情は譬(たと)えてみれば、半ばにして覚めた美(うま)し夢に対する追憶にも似ていよう。夢…そうだ。確かに夢なのだ。そこに気づく時、この音楽に喚起された我々の心象は、牧神のそれと既に渾然となっている。
笛の音が戻ってくる。空ろな笛の音に寄せた牧神の現うつつ無き恋情は、我々の心に生じた幽かな昂(たかぶ)りを誘って、再び彼の午睡の夢の中にまぎれてゆくのである。
注1):フランス語では「シランクス」。ドビュッシーは晩年、この題名で無伴奏フルートのための作品を作曲している(1913年)。
注2):マラルメにはこの作品に先立つ半獣神をテーマとした詩作の一群がある。『半獣神の午後』はその集大成とも言えるが発表の場を得られず、友人らの協力を得て、親交のあったマネの挿絵を施した豪華版としての出版となった。
注3):象徴的な表現の原作や音楽に対し初演から約20年を経た1912年5月、バレエ・リュスの公演で、牧神を演じるニジンスキーが、ニンフから得たヴェールを用いて、自じ瀆とく行為を想像させる極めて「具体的な」振り付けによって、この部分を再現している。当然スキャンダルを引起してドビュッシーの不興も買ったが(マラルメは既に他界している)観衆はやがて肯定的な評価に転じた。
初演:1894年12月22日パリにてギュスタブ・ドレ指揮
楽器編成:フルート3、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、アンティク・シンバル、ハープ2、弦五部
参考文献 『音楽のためにドビュッシー評論集』杉本秀太郎訳 白水社1993年
『ドビュッシー音楽評論集』平島正郎訳 岩波文庫1996年
『マラルメ詩集』渡邊守章訳注・解題 岩波文庫2014年
『六百番歌合』新日本古典文学体系 岩波書店1998年
第236回ローテーション
| 牧神の午後への前奏曲 | 遊戯 | 火の鳥 | ||||
| Fl | 1 | 松下 | 1 | 岡田 | 1 | 吉田 |
| 2 | 吉田 | 2 | 松下 | 2 | 兼子 | |
| 3 | 新井 | Picc.1 | 吉田 | 3/Picc.1 | 岡田 | |
| ― | ― | Picc.2 | 兼子 | 4 | 新井 | |
| ― | ― | ― | ― | Picc.2 | 松下 | |
| Ob | 1 | 平戸 | 1 | 宮内 | 1 | 堀内 |
| 2 | 山口 | 2 | 平戸 | 2 | 山口 | |
| C.I. | 岩城 | 3 | 山口 | 3 | 宮内 | |
| ― | ― | C.I. | 岩城 | C.I. | 岩城 | |
| Cl | 1 | 中島 | 1 | 品田 | 1 | 高梨 |
| 2 | 石綿 | 2 | 大藪 | 2 | 末村 | |
| ― | ― | 3 | 中島 | Es(D) | 進藤 | |
| ― | ― | Bass | 岩村 | Bass | 岩村 | |
| Fg | 1 | 浦 | 1 | 浦 | 1 | 田川 |
| 2 | 笹岡 | 2 | 笹岡 | 2 | 浦 | |
| ― | ― | 3 | 田川 | 3/Contra.2 | 笹岡 | |
| ― | ― | Contra | 星(*) | Contra.1 | 星(*) | |
| Hr | 1 | 箭田 | 1 | 大内 | 1 | 箭田 |
| 2 | 松尾 | 2 | 市川 | 2 | 大内 | |
| 3 | 大原 | 3 | 菊地 | 3 | 大原 | |
| 4 | 市川 | 4 | 松尾 | 4 | 宮田 | |
| ― | ― | ― | ― | W.T1菊地 | W.T2松尾 | |
| ― | ― | ― | ― | W.T3鵜飼(*) | W.T4市川 | |
| Tp | ― | ― | 1 | 小出 | 1 | 野崎 |
| ― | ― | 2 | 中川 | 2 | 倉田 | |
| ― | ― | 3 | 北村 | 3 | 中川 | |
| ― | ― | 4 | 倉田 | Banda1 | 北村 | |
| ― | ― | ― | ― | Banda2 | 小出 | |
| ― | ― | ― | ― | Banda3 | 高沢(*) | |
| Tb | ― | ― | 1 | 志村 | 1 | 武田香 |
| ― | ― | 2 | 武田浩 | 2 | 志村 | |
| ― | ― | 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | |
| Tu | ― | ― | 土田 | 土田 | ||
| Timp | ― | ― | 桑形 | 古関 | ||
| Perc | クロタル | 古関 | トライアングル・木琴 | 皆月 | 大太鼓・グロッケン | 今尾 |
| クロタル | 今尾 | シンバル | 古関 | トライアングル | 村川(*) | |
| タンブリン | 今尾 | 吊シンバル | 桑形 | |||
| ― | ― | ― | ― | シンバル(合せ・吊り) 鐘(Banda) | 鈴木(*) | |
| ― | ― | ― | ― | タンブリン・タムタム・木琴 | 皆月 | |
| 鍵盤 | ― | ― | Celesta | 藤井 | Piano | 井上(*) |
| ― | ― | ― | ― | Celesta | 藤井 | |
| Harp | 1 | 篠﨑史(*) | 1 | 篠﨑史(*) | 1 | 篠﨑史(*) |
| 2 | 篠﨑和(*) | 2 | 篠﨑和(*) | 2 | 篠﨑和(*) | |
| ― | ― | ― | ― | 3 | 稲川(*) | |
| Vn | 1 | 堀内(伊藤真) | 1 | 堀内(伊藤真) | 1 | 堀内(佐藤) |
| 2 | 小松(田川) | 2 | 小松(田川) | 2 | 小松(大島) | |
| Va | 槇(大森) | 槇(大森) | 柳澤(槇) | |||
| Vc | 柳部(安田俊) | 柳部(安田俊) | 柳部(安田俊) | |||
| Cb | 中野(渡辺) | 中野(渡辺) | 中野(渡辺) | |||
第236回演奏会のご案内
矢崎彦太郎=新交響楽団5回の共演
パリを拠点に活躍し、ますます理知的な音楽作りに磨きがかかる矢崎彦太郎を指揮に迎え、フランス印象派の大作曲家ドビュッシーの作品と、パリと関わりの深いストラヴィンスキーの作品を演奏します。
今回取り上げるのは、ドビュッシーの最初の傑作といえる「牧神の午後への前奏曲」と、最後の管弦楽作品となった「遊戯」、そしてストラヴィンスキーの出世作「火の鳥」です。この3曲はいずれも20世紀初頭のパリで、バレエ・リュス(ロシアバレエ団)によりバレエ作品として初演されています。
ストラヴィンスキーとモダンバレエ
バレエ・リュスは、ロシア人のディアギレフによって1909年に結成され、パリを中心に欧州各地で公演を行いました。ディアギレフは元々「芸術世界」という雑誌を刊行し、サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場管理部官員をしていました。自身は作曲も振付もしませんでしたが、プロデューサーとしてモダンバレエを開花させ、作曲家に委嘱して多くの名曲が生まれました。
「火の鳥」とは輝く黄金の羽根を持ち魔力で主人公を助ける架空の鳥です。ロシア民話を題材とした作品を1910年の新作として当初別の作曲家に依頼するも間に合わず、若手作曲家だったストラヴィンスキーに依頼して半年で仕上がりました。
初演時は本物の馬が2頭登場し火の鳥役のダンサーがワイヤーで宙吊りになるなど大仕掛けで、公演は大成功しました。コンサートで多く演奏される組曲版は2管編成で20分程ですが、今回演奏する全曲版は初演時と同じもので、4管編成にハープ3台、バンダが付いている大編成で50分の大作です。
その後ディアギレフから「ペトルーシュカ」「春の祭典」が委嘱され、ストラヴィンスキーは大作曲家への道を進みます。
ドビュッシーのバレエ音楽
「牧神の午後」は1912年に新作バレエとして上演されましたが、管弦楽曲としてはマラルメの同名の詩のために着手され1894年に完成しました。ブーレーズが「現代音楽はこの曲とともに目覚めたと言ってよい」と評するように、10分ほどの小曲ですが内容の凝縮した作品です。「牧神」は山野と牧畜をつかさどる半獣神で、葦笛を奏でニンフ(妖精)と戯れます。牧神を象徴するフルートの調べが全体を包みます。
「遊戯」というと何のことかわかりにくいですが、原題のJeuxを英語にするとPlay。テニスに興じながら恋の駆け引きをする3人の男女をテーマにしています。ドビュッシーは最初この依頼に乗り気でなかったのですが、台本・振付を担当した第一舞踊手であるニジンスキーの強い要望により倍の報酬で引受け、1913年に新作として上演されました。
テニスラケットをかかえパントマイムのような動作の踊りは評判が芳しくなかったのですが、音楽自体は観衆に好評でした。2週間後に初演された「春の祭典」の騒動の陰に隠れてしまいましたが、自由で流動的な作風は再評価されています。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
ブラームス:交響曲第1番ハ短調
伝わらなかった愛のメッセージ
この曲についての音楽的な解説は、数多ある名解説に譲り、ここではブラームスとクララ・シューマンとの関係に焦点を当てた解説を試みたい。
ブラームスといえば、その恩師ロベルト・シューマンの妻クララとの特別な人間関係が思い起こされる。興味本位には謂わば“禁断の恋”とも伝えられる一方、ふたりは終生プラトニックな愛を貫いたとも言われている。
そのふたりの間では1854年(ブラームス20歳、クララ34歳)からクララが亡くなる1896年まで多くの手紙が交わされた。ところが、それらの往復書簡は1887年にクララの意志により、特に濃密な関係を築いたと推測される年代のものの大半が破棄されてしまった。ふたりの愛がどのようなものであったのかを知るための最も重要な手がかりが隠されてしまったのだ。それでも、クララの長女マリエの機転によって破棄を免れた手紙やクララ自身が残した日記から、後世の研究者たちはふたりの愛のかたちについてさまざまに推測を試みてきた。しかし、結局確かなことはわからないままだ。だが、仮にそうした詮索がなにか確かな答えを得たとしても、ブラームスの遺した偉大な業績とその芸術的価値をなんら左右するものではない。
残された書簡などから読み取れることは、どのような愛の形であったとしても、ふたりは終生互いの尊敬の念に支えられた、このうえない親密な友情と、清透な恋愛感情との綯ない交ぜになった崇高で高貴な愛を貫こうとし、そうした愛の交歓はブラームスの創作活動にとってかけがえのない精神的支えであったということである。少なくとも私にはそのように思える。
実際の音楽活動において、ふたりはそれぞれの活動についてさまざまに情報をやり取りしていたし、演奏会があれば互いに聴きに出かけることもしていた。また、作曲が完成すると、ブラームスはクララに楽譜を送って講評を求め、あるいは、居所が近ければ必ずクララにピアノで聴かせてもいた。クララはブラームスの音楽的才能を高く評価していたので、彼の才能が存分に生かされていれば大いに賞賛し、彼女の期待を裏切るような場合には仮借なき辛辣な批評を述べることもあった。完成したばかりの未出版の作品であれば、ブラームスはクララの意見を取り入れて書き直すことも厭わなかったようである。
こうしたことからも察せられるように、ブラームスは誰よりもクララからの好評価を望んでいたのであり、それはすなわち、ブラームスにとってのクララとの愛の交歓は、彼がその全情熱をかたむけて作り出す作品をも支配するほどのものであったということである。
つまりは、ブラームスの作品そのものにこそ、ふたりの愛の結果が移し込まれているのだ。
そうしたことが窺える、ふたりの書簡とクララの日記の一部を紹介したい。
「…私の作品について、長いお手紙をください。汚い音調のところ、退屈なところ、偏へん頗ばな芸術性、感情の冷たさ等について、どうぞたくさん叱ってください。」(1860年9月/ブラームスからクララへ)i
「あなたはまたも芸術の深淵への道を見いだしたのね。…合唱の加わるところの和声は硬いと思います。…ホ長調のコラールは素晴らしく(中略)私を喜ばせましたが、終わりに近いテノールのホの音は重すぎます。なぜ嬰ヘの音を使わなかったのですか。…」(1860年9月/クララからブラームスへ)i
「『セレナーデ』は驚くばかりの詩想に満ち(中略)私は完全に音楽に引き入れられ、感動のあまりヨハネスの腕に身を投げ入れたい気がした。聴衆の冷たい態度は、心臓から血が溢れるように私の胸を痛めた。彼のために、彼の阻そ碍がいをのぞく力が私にあったら…」(1860年11月/ヨアヒムによるブラームスの諸作品を聴いた際のクララの日記)i
さて、この交響曲第1番は1876年11月に初演された。遡ること8年前の1868年9月12日、ブラームスはクララの誕生日を祝って一通の書簡を彼女に送った。そこには本文もブラームスの署名もなく、“ヨハネスからクララへ”と題して9小節のメロディが歌詞を伴って記されていた。

このメロディこそ、この交響曲第1番の終楽章に現れる、アルペンホルンを想起させるあのメロディだった。歌詞の内容は「山の高みから、谷の深みから、きみに幾千回もの挨拶を送る!」というものである。その後8年を経て、ブラームスはこの交響曲第1番を完成させ、前述のとおり、その終楽章にこのメロディを引用した。着想から20年余を経て紆余曲折の後に漸く完成させたこの、音楽史的にも圧倒的な価値を持つ交響曲に、ブラームスは至極個人的なメッセージを密かに込めたのだった。しかし、当事者以外は知ることのなかったはずのこの事実は、後世の研究によって多くの音楽愛好家の知るところとなった。
このような、この上なくロマンティックに仕組まれた愛のメッセージが、果たしてクララに伝わったのかどうか、以前から私は疑問に感じていた。以下に、私なりに検証してみたい。
この交響曲の完成の14年前の1862年6月、ブラームスはこの曲の初期稿の第1楽章(序奏を欠いている)をクララにピアノで弾いて聴かせたが、彼女はそのときの感想をヨーゼフ・ヨアヒム(ヴァイオリニスト・指揮者・作曲家、ブラームスの盟友)へ手紙で書き送り、絶賛している。ところがその14年後の1876年、この交響曲の初演の1か月前の10月にブラームスは再度自らピアノを弾いてその全曲をクララに聴かせたのだが、彼女はその日の日記にかなり否定的な感想を書いている。
それは、こののちの初演後の批評家たちの反応も「この新作の交響曲は一度聴いてみて、多くの曖昧なところを残している。…」ii、「…真ん中の2つの楽章には問題ありだ。…どちらかといえばセレナーデか組曲向き…」iiiなど、あまり芳しくないものが多かったが、クララも同様に感じたのか、「私は悲しみ、打ちのめされたことを隠すことができません。…まさしくヘ短調の五重奏曲、六重奏曲、ピアノ四重奏曲と同等のものに思えるからです。旋律の活気が欠けているように思われ…」iiと書いているのだ。
クララのこの感想に私は違和感を覚える。不可思議でもある。なぜ悲しんだり打ちのめされたりしたのであろうか。たしかに、ブラームスはこの曲の初演後すぐに改訂を加えたと伝えられる。特に、2楽章についてはかなり手を入れたとも言われている。であるとすれば、クララがブラームスのピアノ演奏で聴いたのは、私たちが現在聴いているものとは同じではない箇所があったと推測できるが、そうした、私たちには今や耳にすることのできない部分をクララは特に気に入らないと感じたのかもしれない。また、オーケストラそのものではなくピアノ演奏で聴いたため、オーケストラとしてのダイナミズムやニュアンスが伝わらなかったためだったのだろうか。
このような仮説を立て、私自身を多少なりとも納得させることができても、それでも尚かつ私が腑に落ちないのは、彼女はアルペンホルンのメロディが引用されていることには全く気づいていなかったと思われるからである。もし気づいていれば、少なくともなんらかの喜ばしさを示したはずである。しかし、この日記にはそのような記述は全くない。後世の研究者たちも戸惑いがあるのか、この日記の内容についてなにか論評した形跡が見当たらないのだ。
そもそも誕生日を祝う件の書簡が送られた2年ほど前から、ふたりの間にはあるわだかまりが生じており、1868年のクララの誕生日当時にはまだそのことを解消できずにいた。そのため、クララは多分この書簡を複雑な思いで一度は読んだが、すぐどこかにしまい込んでしまい、そのメロディを記憶として留めることはなかったと思われる。そのため、その後8年を経て完成されたこの交響曲に、そのメロディが用いられていることに彼女は気づかなかったのではないだろうか。クララの日記はまた、彼女が気づかないことに、ブラームスは一言も触れることはなかったことも示唆している。
伝えられるべきことが伝わらなかったのだ。長年の逡巡ののちに完成させた初めての交響曲のフィナーレに、感動とともに受け止めてもらえるはずの愛のメッセージを託したのに、嗚呼、なんということか。ブラームスは大いに落胆したに違いない。
私のこのような推測が正しければ、ほんの少しの気持ちのすれ違いが遠因で、ブラームスの個人的な愛のメッセージが企てどおりに伝わらなかったわけだが、しかし、そのことによってこの終楽章の音楽的価値が左右されるわけでは全くない。この点は強調しておきたい。また、私たちがそのメロディに隠された個人的ないきさつなど知らなくても、この交響曲の芸術的な価値が減ずることでもないのだ。
それでもしかし、私はなにか残念な思いに囚われる。
私は更に、クララがこの秘められたメッセージに終生気づかずにいたのかどうか、ということも知りたいと思い、さまざまな資料をあたってみたが、どこにもクララが気づいた形跡や、ブラームスが打ち明けた痕跡も見つけることはできなかった。
この上なくロマンティックに仕組まれた愛のメッセージは最後まで伝わることなく、1886年5月20日、クララは76歳でその生涯を終えた。クララの最期をブラームスは看取ることができず、やっとの思いで埋葬の場に駆けつけたと伝えられる。翌年の4月3日、ブラームスもクララのあとを追うようにその64年の人生の幕を閉じた。19世紀ドイツ・ロマン主義の終焉でもあった。
第1楽章
Un poco sostenuto-Allegro-Meno Allegro
序奏部とコーダを両端に置いたソナタ形式、動機労作。
第2楽章
Andante sostenuto
リート形式 (A-B-A’)。
第3楽章
Un poco Allegretto e grazioso
コーダ付きのリート形式 (A-B-A’-Coda)。
第4楽章
Adagio-Più Andante
-Allegro non troppo, ma con brio-Più Allegro
序奏部-変則ソナタ形式(呈示部-展開的再現部)
-コーダ。
初演: 1876年11月4日、オットー・デッソフ指揮による、カールスルーエのバーデン大公宮廷管弦楽団 第1回予約演奏会にて。
楽器編成: フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、弦五部
参考文献
[ⅰ]ベルトルト・リッツマン(原田光子訳) 『クララ・シューマン/ヨハネス・ブラームス「友情の書簡」』みすず書房 2013年
[ⅱ]西村稔『作曲家・人と作品シリーズ ブラームス』音楽之友社 2006年
[ⅲ]ウォルター・フリッシュ(天崎浩二 訳)『ブラームス 4つの交響曲』音楽之友社 1999年
伊福部 昭:シンフォニア・タプカーラ
今から36年前、新響が本日の「改訂版」を初演したプログラム冊子に、当時65歳であった作曲家自身が次のような言葉を寄せている。
作者は、アイヌ語でシャアンルルーと呼ぶ高原の一寒村に少年期を過しました。そこには、未だ多くのアイヌの人達が住んでいて、古い行事や古謡が傳〔伝〕承されていました。
タプカーラとは、彼等の言葉で『立って踊る』と云うような意をもち、興がのると、喜びは勿論、悲しい時でも、その心情の赴くまま、即興の詩を歌い延々と踊るのでした。
それは、今なお、感動を押え得ぬ思い出なのです。
その彼等への共感と、ノスタルヂアがこの作品の動機となっています。(以下略)
この一文はその後に頒布されたCDの解説や書籍など各所に引用されているので、どこかで目にした方が多いかもしれないが、作者が少年期を過ごした「シャアンルルー」という地名らしきものが何を意味するか気になっていた。ネットを探せば「十勝平野」だとか「大海原」という解釈が見られるものの、どうも釈然としないので、手元の『地名アイヌ語小辞典』を参照してみた。
「シャアンルルー」はないが、アンルルーan-rurなら載っている。「反対側の海にのぞむ地方;山向こうの海辺の地。──太平洋岸のアイヌは日本海岸を、日本海岸のアイヌは太平洋岸を(略)」と、方向性をもつ地名的な概念であることが示されており、続いて十勝の古名としての「si-anrur」も掲載されていた。「①真の、本当の ②大きな」という意味をもつsiを冠したことで「ずうっと山向こうの海辺の地」と強調されている。もとは石狩アイヌが十勝を指した呼び名という。これに相違ない。
余談だがこのsiには「糞」という意味もあるそうで、ずいぶん以前に新響プログラムの編集者として伊福部邸でインタビューをお願いした際、「シシャモと言ったら『馬鹿な(糞)日本人』の意味になってしまうので、あの魚はススヤムと発音しなければ」というお話をうかがった。林務官として道東のある僻遠の村に赴いた際、お役人様に生の鮭を食わせては失礼と、わざわざ鮭の缶詰をご馳走になったという笑い話も印象に残っている。
伊福部昭は大正3年(1914)に北海道釧路町(現釧路市)で父伊福部利三・母キワの三男として生まれた。伊福部家は因幡国一宮たる宇倍神社(現鳥取市国府町宮下)の神官を代々つとめた家で、昭が67世(代目)というから、古代からの話である。伊福部氏は鑪(たたら)製鉄の特殊技術を持った一族であった。
父の利三は官吏で、大正12年(1923)には十勝・音更村の官選村長となった。当時の明治政府は先住民族アイヌに対して日本型の営農指導などを通じた同化政策を進めており、明治32年(1899)施行の旧土人保護法成立でその態勢は確固たるものとなっていく。伝統的な生活から無理に引き離され、深刻な差別も生まれていくのだが、同39年にはこの音更にもアイヌ子弟の教育を目的とした庁立音更尋常小学校が置かれている。9歳で釧路の町からここに移った伊福部昭がアイヌの歌や踊りを目の当たりにし、その肉声や音調、リズムの感覚などに大きな影響を受けたことは想像に難くない。
その後は札幌第二中学校(現札幌西高)を経て北海道帝国大学農学部林学実科に入学、卒業後は帝室林野管理局の林務官として厚岸森林事務所に奉職した。独学で作曲を始めていた伊福部が本格的にデビューしたのがチェレプニン賞(モーリス・ラヴェルも審査員であった)で第1位入賞した「日本狂詩曲」であるが、国内の作品を東京でまとめて送る手続の中で、当時第一線の楽壇の面々から「あまりに西洋音楽の作法から外れ、日本の恥」として応募から外されそうになったエピソードは、その作風の強い独自性を物語る。
さて、根室本線の旧狩勝トンネルを抜けた東側は、広大な十勝平野を俯瞰する絶景として「日本三大車窓」にも数えられていた。その風景はまさに石狩アイヌが見たシャアンルルーであろう。原生林で覆われていた大地は碁盤目に道路が走り、今では見渡す限りの畑に変貌したが、その昔─100年近く前に存在した音楽と即興の詩と踊りとは、どんなものであっただろうか。
第1楽章 Lento molto-Allegro
ゆったりと時間が流れる広大なシャアンルルーのレント・モルト。やがて踊りを感じさせるアレグロが近づいてくる。即興の詩の字余り・字足らずが独特な興を添えながら。中間部では何の詩かわからないが、朗々と奏でられる。
第2楽章 Adagio
ハープの下降音型は夕暮れか。ゆったり流れる笛の調べ。夜はまだ長い。
第3楽章 Vivace
始まりは「緊急地震速報」の元となったE-HF-B-F-Gis-Bという不協和音(作曲家の甥・伊福部達東大名誉教授-音響学が採用)。短調でありながら、深刻かつどこか脳天気な雰囲気をも併せ持ちつつ、たたみかけるように突き進んでフィナーレ。
以上、筆者の勝手なイメージに基づく記述であるが、最後に作曲家が自著『音楽入門』で記した「現代生活と音楽」と題する一文の冒頭を掲げておこう。
私たちはかっては、農耕には農耕の歌を、漁(すなど)りには漁りの歌を、馬を追うには馬子唄を、また少年時代にはさまざまな遊びに伴った童べ唄を、冠婚葬祭や年中行事にはそれに伴った多くの唄や音楽を持っていたのでありますが、近代の機械文明は、この私たちから、そのようなもののすべてを取り上げてしまったのであります。
初演:原典版:昭和30年(1955)1月26日、米国インディアナポリスにてフェビアン・セヴィツキー指揮 インディアナポリス交響楽団、翌31年3月16日に上田仁指揮東京交響楽団で国内初演
改訂版初演:昭和55年(1980)4月6日、東京文化会館大ホールにて芥川也寸志指揮、新交響楽団(第87回演奏会-日本の交響作品展4)
楽器編成: フルート2、ピッコロ、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トムトム、小太鼓、ティンバレス、ギロ、ハープ、弦五部
参考文献
知里真志保『地名アイヌ語小辞典』北海道出版企画センター 1956年
伊福部昭『音楽入門』(1985年改訂版)
現代文化振興會 1985年
新交響楽団第87回演奏会プログラム 1980年4月6日
伊福部昭公式ホームページ(暫定版)http://www.akira-ifukube.jp/
吉松 隆:鳥のシンフォニア“若き鳥たちに”
吉松隆は、今を生き今を知る作曲家である。
吉松は1953年に渋谷で生まれた。音楽への「スイッチ」が入ったのは中学3年生の時だ。フルートを趣味にする父は、音楽の授業で交響曲のレコードを聴いた話を聞き、息子が音楽に興味を持ったことに喜んだ。レコードをプレゼントしてもらい、父が所蔵するスコアを見ながら「運命」を聴いた吉松少年は、作曲家になる決心をした。オーケストラがあるという理由で慶應義塾高等学校に進みファゴットを吹いた。作曲の勉強は、伊福部昭の『管絃楽法』を手始めに独学で行った。曾祖父が小児科医であったことから医学部への進学を考えていたが、作曲の勉強に忙しく推薦で工学部に進学する。シンセサイザーに興味を持ち、コンピューターを触りたいという理由であった。目的を達して大学を中退し作曲に専念する。
吉松にとってのヒーローは、松村禎三そしてシベリウスである。
とにかく交響曲を書きたかった。松村作品のエネルギーに圧倒された。コンクールへの応募を機に松村に弟子入りし、伊福部の孫弟子にあたる。当時の作曲の世界はいわゆる現代音楽(=前衛的で無調)でないと認められない風潮であったが、メロディがあって調性のある作品で挑み続けた。「魂の師匠」であるシベリウスには、二十世紀に生き、ヨーロッパ楽壇の中心から離れた自分と共振するものを感じたという。吉松作品の透明感のある響きや自然のモチーフは、シベリウスへの想いがベースとなっているのであろう。
吉松には「鳥」をテーマとした作品が多い。
出世作である「朱鷺によせる哀歌」(1980、弦楽オーケストラ作品)に始まり、サックスの名手・須川展也のために書かれた「サイバーバード協奏曲」(1991)や、代表的な管弦楽作品である「鳥たちの時代」(1986)などの鳥シリーズが主軸となっている。その理由として
1. 人間より遥かに昔から「歌」を操っている音楽家としての大先輩である。
2. 翼を持って大地のしがらみから飛翔する「自由」な存在である。
3. 空の彼方の異界と交感する「魂」の隠喩(メタファー)である。
の3つのポイントがあるという。
鳥たちの歌は「ぴ」あるいは「ぴぴぴ」「ちちちち」というような断片的なパッセージの組み合わせでできている。(譜例1)これらを組み合わせてメロディ細胞のような「音形(モチーフ)」を作る。これが「素材」(鳥の旋律細胞)となる。(譜例2)さらに、その素材を構成する音は、無調や十二音のシステムではなくハッキリ調性感を伴う「旋法(モード)」を使う。いわば、現代音楽で使っていた「音列主義(セリエリズム)」や「クラスター」の発想を、「調性」の中で使ってみたら?という発想だ。そうすると、はっきり調性感のあるサウンドの中で現代音楽風の自由な手法が展開できる。(譜例3)(『作曲は鳥のごとく』~鳥の作曲法より)
今回演奏する「鳥のシンフォニア」は5楽章からなる20分弱の小交響曲である。当初は交響曲第6番にするつもりもあったが、委嘱作品であり、また少々短いことからこの曲名となったという。仙台ジュニアオーケストラの第20回記念演奏会のために書かれ、2009年に初演された。
第1楽章 Prelude:Moderato
前奏曲。各楽器群が鳥たちの歌を受け継いでいき、それらは重なって自由に羽ばたいていく。鳥たちの歌の楽譜には「自由に」と記され、「拍節にとらわれず鳥がさえずるように自由に(アドリブを交えて)奏すること」と指示されている。
第2楽章 Toccata:Allegro animato-meno mosso
技巧的なパッセージの繰返しと和声進行的な部分からなるトッカータ。バッハのトッカータとフーガと同じニ短調で書かれている。疾走する4拍子はドラマチックで、若い鳥たちが希望に向かってるかのよう。
第3楽章 Dark Steps:Allegro
スイングとブルーノート・スケールで書かれたジャズ風の楽章。Darkとは、ミ♭、ソ♭、シ♭が入ることで、テンションがかかり暗い響きになること。時折出現するアドリブ風・ソロにも、鳥の音形が使われている。
第4楽章 Nocturne:Andante amabile-Allegro
夜想曲。ゆったりとロマンティックに歌われる。夜の森の中で、鳥たちが羽を休め語り合う情景が浮かぶ。
第5楽章 Anthem:Moderato
仙台ジュニアオーケストラ創立20周年を祝う讃歌(アンセム)。3連符に乗って高らかにメロディが鳴り響き、勇壮にティンパニが躍動し、最後はハ長調で開放的に終わる。
~鳥のシンフォニアによせて~ 吉松隆
私がクラシック音楽に目覚めたのは、中学から高校にあがる頃でした。そして、高校のオーケストラでファゴットを吹き、あらゆるジャンルの色々な音楽を聴きあさりながら、オーケストラの作曲家になる夢に燃えていました。ですから、今回、仙台ジュニアオーケストラのために書いた「鳥のシンフォニア~若き鳥たちに」は、そんな十代の頃の私が「こんな曲があったら…」と思っていた「見果てぬ夢」を反映しています。
それは…「カッコよくてスピード感があってオーケストラがバンバン鳴って、でもメロディを静かに歌う部分もあって、現代風だけど分かりやすく、楽譜はきっちり書かれているけど自由に演奏できる部分もあって、あんまり難しくなく、でもやさしすぎない曲」。
作曲家にそんな注文を出したら、「ありえない!」と叫んで、たぶん卒倒することでしょう。でも…今回、敢えて(無謀にも)そんな夢に挑戦してみました。(もしかしたら大失敗かもしれませんが…)タイトルの「シンフォニア」は、「若い交響曲」というような意味で名付けました。5つの短い楽章からなり、これから音楽の広大な森を自由にはばたく「若い鳥たち」によせる5つの賛歌です。
自分の街にオーケストラがあって、そこで新しい音楽が生まれ、そこから新しい音楽家が巣立つ。そういう「森」を育て、「鳥」を大きく羽ばたかせることこそ、何にも代えがたい「音楽の力」です。この曲が、そのささやかな「夢の証し」になればと願ってやみません。
(初演時のプログラムノートより)
初演: 2009年11月1日
仙台市青年文化センターコンサートホール
山下 一史指揮 仙台ジュニアオーケストラ
楽器編成: ピッコロ1、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、打楽器4(ティンパニ、バードコール、トライアングル、ウインドチャイム、ウィンドベル、カウベル、タンブリン、ウッドブロック、シンバル〔合わせ、吊り、ハイハット〕、小太鼓、トムトム、大太鼓、タムタム、木琴、グロッケンシュピール)、ピアノ、弦五部
参考文献
吉松隆『作曲は鳥のごとく』春秋社 2013年
吉松隆『調性で読み解くクラシック』ヤマハミュージックメディア 2014年
作曲家 吉松隆氏にきく
―本日は「日本酒の飲めるお店」というリクエストをいただきました。日本酒はお好きなんですか。
吉松 三十半ばくらいから飲むのは、ほとんど日本酒ですね。日本酒に合う食事が身体に合うようで、歳を取ってさっぱり系になってきました。
―音楽家は食にこだわる方が多いと思うのですが、料理はされるのですか。
吉松 昔ちょっとこりましたけど、今はやってないですね。何年か前まで一人暮らししていた頃は、出汁に凝ってみるとか、安いサバ買ってきて煮込むとか、蕎麦打ってみるとか、そういうあんまり役に立ちそうにないものにハマったこともありましたけど。
音楽家は、車の運転とか釣りとかをする人も多い。音楽のこと考えないで、1 時間も 2 時間も無心でやっていられるものがないと、どこかで行き詰って難しいからかも知れないですね。
―先生もそうですか?
吉松 僕は昔からパソコンやイラストをやっていたので、音楽を忘れるのは得意ですね。
―ご自分の本やCDジャケットのイラストが素晴らしいですね。
吉松 時間や音楽を忘れて描いていたということはあるかもしれません。最近は流石にあまりそういうことはないですが、パソコンおたく第一世代ですので。
―パソコンはかなりお詳しいのですね。
吉松 詳しいというか、商売道具ですね。コンピューターがあまり一般的でなかった頃から、未来の音楽はコンピューターでやるものだと思っていました。それで慶応義塾大学の工学部に進学しました。でも、当時は工学部でも巨大なタンスみたいな物しかなく、モニターもキーボードもなく紙テープの穴で答えが出てくるのです。
―新響では日本人の作品を積極的に取り上げており、過去に何度か先生の作品が候補になったことがあるのですが、今回ようやく演奏することが出来ます。
吉松 「鳥のシンフォニア」は、ジュニア・オーケストラの子供たちのために書いたもので、初演以来演奏される機会があまりなかったので、どこかで出来ないかなとちょうど思っていた時だったんですよ。
ただ、アマチュアオケも随分上手くなってきているので、あまり易しいのを書くと飽きられてしまうし、だからといって、グチャグチャ難しいのを書くわけにもいかないし、バランスが難しかったかな。
―この曲は先生の管弦楽作品の中でも、編成や時間的にアマチュア・オーケストラが取り上げやすいです。今回を機会に、流行らせたいと思います。
吉松 ただ、委嘱作品って、他のオケがなかなか手を出さないですよね。誰かがお金と手間をかけて委嘱して出来たものを、良い曲だからといって横取りしては失礼だと思うんでしょうか。コンチェルトでも、他の演奏家がどんどん演奏するかと思うと、そうでもないんですよ。多分 20~30 年経てば違うんでしょうけど、委嘱者が初演して一年でも経ったら全然演奏してくれてもいいのに。
―我々が演奏しても良かったのでしょうか。
吉松 もちろん全然問題ありません。こちらとしては、もっと演奏してくれた方が有難いです。コンチェルトなどは特定のソリストと綿密に作ってしまうので、他の人だと音楽的に根本が違ってしまう場合があるんですけど、最近ではサクソフォーンとかトロンボーンとか、新しい世代の人たちが、違った感性で演奏してくれるのは嬉しいですよ。
―高校時代にオーケストラでファゴットを吹いていらしたのですよね。
吉松 ファゴットに欠員がいるからと押し付けられたのです。今は吹いてないです、楽器は結局買わなかったので持っていないですし。
その時のトラウマのせいかファゴットには高音書けないですねぇ。書いていてヘ音記号から上に行くと、もう本能的に・・・。コンチェルトにはすごく高い音を書いたけど、オーケストラには書けないですね。
―作曲をしてオーケストラの仲間に楽譜をあげていたということですが。
吉松 木管五重奏、ヴァイオリンソナタ、無伴奏チェロソナタ、フルート2本のソナタなど膨大にあったのですけど、楽譜は手書きのモノをあげちゃったので全然残ってない。あの頃はコピーがなかったし、昔のコピーは青焼きで時間経つと消えてしまうんですよ。
―どこかに残っていたり、覚えていて書き直すことはできないのですか。
吉松 覚えてないですね。昔のスケッチが段ボールに何十箱とあったのだけど、引っ越した時に捨ててしまいましたし。ピアノ曲の楽譜はかなり残っていて最近 15,6 歳くらいの時に書いたピアノ曲集(優しき玩具)を録音してもらったんですけど、今と作風が全然変わっていなかった。音の選び方とか、趣味がね。
―先生のヒーローは、松村禎三先生だったのですね。
吉松 現代音楽界では武満徹さんと松村禎三さんですね。武満徹さんは、楽譜やレコードも割と手に入ったし、文章も書いておられたから情報があったし、音響のタイプが自分と似ていた。でも松村さんはちょっとタイプが違うナゾの人で。交響曲など一体どうやって作っているのか直に会って聞きたいというのが大きかった。
―それで松村先生に師事したのですね。
吉松 やはりあの時代に交響曲を書いているということが大きかったですね。黛敏郎さんとか矢代秋雄さん三善晃さんなどはアカデミックなイメージがありすぎて。僕の中ではずっと独学でやるというつもりだったから。やはり武満さん、伊福部さん、松村さんは、独学組のヒーローだったですね。それで、松村さんの交響曲、オーケストレイションのセンスが非常に気になって、武満さんよりは松村さんに付いたということなんです。
―可愛がられたのではないですか。
吉松 いや、たぶん一番可愛くない弟子だったでしょうね。何かを教わるという気はなかったので、曲が出来たら楽譜を持って行って見せて、「ちょっと息が短い」とか、「このタイトルは何?」とかたまに言われるくらいで、あとは音楽や作曲について青臭い議論をふっかけていただけだったような気がします。
その代わり、僕がロックに凝っているのを聞きつけて、「一回ロックについて教えに来い」と言われて。レポート用紙何十枚かの資料を作って、それこそプレスリーから、当時クイーンとかプログレが出たギリギリの70年代初めくらいまでの主だった曲のサンプルのカセットテープも作って聞かせて。そしたら、プログレとかクイーンは「小賢しくてつまらん」と。何が気に入ったんですかと聞いたら、ジョン・レノンの「マザー」っていう曲があるでしょ、ずっと“マザー”って叫んでいるだけなんだけど、あれが一番良かったって言われて。だから、感覚が全く違うな、と。
―交響曲が書きたくて松村先生の門を叩いたということですが、交響曲にこだわっていらっしゃるというのはどうしてですか。
吉松 そもそも中学3年の時に「運命」を聞いてそのスコアを見たその夜に「作曲家になりたい!」と思ったわけで、交響曲は人生の大目標だったんです。ところがなぜか、その頃(1960~70年代)は、現代音楽の全盛期で交響曲を書くというのは古臭いと馬鹿にされていた時代で。でも、ああいう音楽を作るためにクラシックの作曲家を目指したというのが大きかった。
―独学でやっていくつもりだったということですが。
吉松 昔は独学にすごくこだわっていました。独学でなければ作曲家ではない、と信じていたほどです。ただ、ある程度歳を取ってきて、若い人にアドバイスをと言われると、それはやっぱり教わった方がいいですよと言ってしまうんですけど。
松村先生に付いた時も、これとこれは勉強しなさいと言われると逃げてましたね。和声法と対位法の先生を紹介されたのだけど、すぐ逃げ出しちゃったしね。僕としては、機能和声法みたいなあんな変なもの耳に仕込まれたらダメになると思ったんですよ。そう言うと「変な考え方するね」って驚かれるんだけど。コンセルバトワールの流麗とした和声進行法とか、ジュリアードで教えているジャズのコード進行とか、あれはあれで美しいんだけど、やはり自分が持っているものと相反する美学でしょ。
―時間をかけて自分で発見した方が身に付くのですね。
吉松 それもあります。中学の時にギターを始めて、ヴィブラートを発見したんですよ。勝手にいじっていて、こうすると音がきれいになると自分で気づいた。それで翌日学校でギターやっている友人に、「お前知ってるか?こうやると音がきれいになる」と言ったら、「それはヴィブラートっていうんだ」「そんなことは初歩の初歩で知ってる」と言われておしまい。あの発見した時の喜び無しに教わってしまうなんてそんなつまらないことはない、と。少なくとも僕は、ヴィブラートとドミナント、トニカは自分で発見したと思っているんですよ。
人によっては、お薦めコースを教わって最短距離で行く方がいいという人がいるでしょう。でも、旅だって目的地に着くことだけが目的なわけではなくて、行く途上で思いもかけないものに出会ったり迷ったりすることの方が旅の醍醐味だと思うんですよ。
昔は、酒を飲んでラベルに何県何市って書いてあるとそこに行こうと、翌日旅に出ることが多かったですよ。でも、そこに行かないで、途中に良い所があればそこで電車降りて別のところに行ってしまう。なるべく回り道をした方が楽しいという感じでした。
―現代音楽撲滅運動を提唱されていますが。
吉松 僕が始めた70年代の頃の現代音楽っていうのは、大本営発表みたいなものだから。武満さんというのは国際派の神様で、日本だと三善さんや松村さん。そのまわりに賞や批評から音楽コンクールまで「現代音楽以外は認めない」人たちがいて、それに盾突くと、国内でも国外でもクラシックの作曲なんかできないという状況だった。それに反抗していた訳ですよ。
―ということは、現代音楽が嫌いということではないのですね。
吉松 あの頃は自分が日本で一番現代音楽オタクだったと思います。一番現代音楽を聴いていて、レコードやテープ、CDをたぶん日本で一番持っていたんじゃないかと。だからこそ、ああいう方向に全員が向いて行ってしまうということが気に食わなかった。
今は、撲滅と言うと、本当に撲滅されてしまうような気がしてまずいですが、当時は言ってみれば、戦争の無っ只中に軍隊に入った新人の兵隊が、突然「戦争反対!」って言い出した、みたいなものですね。現代作曲家としてデビューして音楽誌に文章を書かせて貰ったんですけど、一行目に「現代音楽は嫌いです」って書いたら、総スカンを食いましたね。こんなことを書いてこの業界で生きていけるのかって言う。でも、この業界で生きていく気はさらさらないという前提で始めた訳で。
―いわゆる前衛音楽ですね。
吉松 当時は前衛も意味があったんです。それ以前の伝統的な形の音楽では、日本人の出る幕がないわけですよ。新しい世代、新しい文化圏から世界的に何かを発信するためには、いったん古いモノを全部否定してみせないとならない。だから、前衛、プログレッシブ・ロックのプログレッシブ(進歩的)のように新しい響きで自分たちの存在理由をアピールする重要な意味があった。でも、アピールしたとたんに権威主義的になってしまった。新しいものを切り拓くというポジションと、日本人にも関われる、世界的にどこまで自由にできるかという意味では、非常に理想郷だったのです、あの時代は。
現に武満さんや黛さんなど30歳にもならないような若者が数多く出てきた。東京オリンピックで黛さんが入場曲のカンパノロジーを作曲した時はまだ30代。今だと東京オリンピックで30代の作曲家の曲を使うって考えられないでしょう。それが出来た時代だから。
―松村先生のお弟子さんですから、伊福部先生の孫弟子に当たりますね。
吉松 でも全然音が違うでしょう。
―音や響きは違いますが、例えば先生の交響曲第2番「地球にて」の最後の方など、伊福部作品みたいと感じます。
吉松 あの頃、冨田勲さんの「新日本紀行」みたいな日本的なものを気に入っていたんですけど、冨田さんは平尾喜四男さんについていてフランス系なんです。だから同じ香りがするのかも知れません。
実際、伊福部さん松村さんの神様はラヴェルなんです。音からは想像できないんだけど、スコアを見ると、ラヴェルネタが実に多くて、それに気付いたときは、結構ショックでした。ただ、ラヴェルはチリチリと細かい音型で水晶時計のような繊細な響きを作るんですけど、伊福部さん松村さんが書くとドロドロドロっとアジア的な音がする。響きに対する根本的な何かが違うような気がする。
だからオーケストラでも、例えばロシアでは伊福部さん芥川さんの曲は良いと言われるけど、武満さんの曲はわからない。逆に、フランスのオケは武満さんのサウンドはラヴェルやメシアンに近いからわかるんだけど、たぶん伊福部さんはわからないだろうね。
日本人だったら、ああゴジラの…と知っているから、その美学というか描く方向がわかっているけど、それを知らない人が伊福部さんの曲を聴いたら、ただシンプルに書いていると思われるんじゃないかと。スコアを見るとものすごくみっちりと書いてあるのに、音だけ聴くとただ何か一本線で書いてあるような感じに聞こえる。
―伊福部先生の「管絃楽法」で勉強されたのですよね。
吉松 伊福部さんの若い頃は、ゴジラの作曲家と言われるのを嫌がってたそうですけど、ある時から積極的に受け入れるようになった。それこそ僕が現代音楽撲滅と言っていた頃は、伊福部さんの音楽は完全無視されていたんですよ。だけどやっぱり伊福部さんの音楽って、演奏会をやったりCD出すと売れるものだから、ファンは途切れずにいたんだろうな。 そんな中で「管絃楽法」という本だけは聖書みたいな存在だったわけです。
―伊福部先生の管絃楽法の絃の字は・・・
吉松 あれは雅楽の絃の字なんですよ。僕は高校の時に、読んだあの本の影響でコンクールで最初に出した時に表紙で落とされた。普通、ドイツ語とかフランス語で書くのに、日本語で「管絃楽のための」と書いちゃったものだから。
―今だったらそっちの方が恰好いいのにと思いますね。
吉松 僕もそう思いますよ。
―先生の作品の曲名は特徴的なものが多いのですが、どのようにして決まるのですか。
吉松 16~7 歳の頃から「タイトルノート」というのを作っていたんです。科学用語や鳥の名前、星の名前など音楽的なイメージを刺激する言葉をとにかく収集していました。それをシャッフルして組合せ、タイトルを作っていました。どれとどれを使おうかというのは思い付きですね。イメージがわかるようなわからないような、そんなポジションが、曲を作っていて一番面白いと思うのです。
「朱鷺に寄せる哀歌」や「オリオンマシーン」は、いつか使おうと思って取っておきました。さらに、そうやって生まれた曲が孤立しないように、必ず「これは鳥のシリーズのここだ」とか「動物のシリーズのここだ」という風に、全ての作品がはまるように考えていたんです。今でもそのノートはあります。
―「星」と「鳥」と「動物」ですね。
吉松 最初が星で、そこからだんだん下がっていって、星~天使~鳥~動物~人間~大地、というグレードで順番に作っていったのです。鳥のシリーズを始めたときにデビューして、その頃たくさん書いたので「鳥」関係の曲が多くなってしまいましたが。確かに一番イメージが作りやすいですね。
―鳥というのは、ご自分のことを重ね合わせているのですか。
吉松 いろいろあります。日本人は白い鳥を見ると魂みたいなイメージがあるでしょう。だから最初に「朱鷺に寄せる哀歌」を書いた時は淡く儚い透明な鳥のイメージでした。でも「デジタルバード」という室内楽曲を書いた時は、バッグス・バニーというアニメに、砂漠を高速で走るニワトリがいて、あの動きが面白くてプレストで鳥の曲を書けないかと思ったのです。
でも、おかげでその後、白いきれいな鳥という発想と、漫画みたいなポップな鳥という発想を合体させるのに相当苦労しました。アレグロとレントの両方を技術的に鳥で表現できるようになったのが「鳥たちの時代」という曲で、そこから様々な早さと性格の楽章を全部合体出来るようになったら、シンフォニーにしようと思っていました。
まさに、卵がヒナになり、翼を広げるまでの自分自身が成長する過程ですね。
―鳥もいろいろな種類がありますよね。ダチョウから、ハチドリまで…。
吉松 そうですね。最初の交響曲の「カムイチカプ」というのは、シマフクロウという大きな鳥のことなんです。一方「チカプ」という曲は小さな鳥が群れているイメージで、当然ながら鳴き方や飛び方から翼の動かし方まで持っているテンポが違うんですよ。鳥を核にしてプレストからレントまでの振幅が表現できるというのは、面白いと思います。
「朱鷺に寄せる哀歌」が最初に再演されたのはメキシコだったんですよ。で、朱鷺はどういうものかと聞かれ、大きな鳥で・・と答えたら、ああ、コンドルねと言われて。彼らにとっては死にかけた人の上をコンドルが飛んでいるっていうイメージなんです。音のセンスは国によっても文化によっても全然違う。
日本でも、新潟には昔は朱鷺がたくさんいて、田んぼにいると追い払う「鳥追い唄」があるぐらいだった。でも朱鷺に寄せる哀歌を書いた時には、絶滅しそうでかわいそう、という感覚。これも時代かなあと。
―若い頃に書かれた作品に、思い入れはおありですか?
吉松 若い頃の曲を聴くと、むかし書いたラブレターを人前で読まれてしまうみたいな、そういう感じがあります。「朱鷺に寄せる哀歌」なんかは、なんだかピュアすぎて聴いていてどこか恥ずかしいです。
―とても良い曲だと思うのですが。
吉松 むかし書いた曲は、今だったらこうするのに、と書き直したくなる気持ちと、よくこんなのを書いたよな、と呆れる気持ちと両方あります。でも、そのときの若い自分は一生懸命やってたんだから、後になって手を加えてしまうのは悪いなという気がします。
―ブルックナーのように何度も改訂している人もいますね。
吉松 気持ちは分かるんですけど、それを始めると収拾つかなくなってしまう。一旦作品が世に出たら聴き手の気持ちも加わりますし。シベリウスのヴァイオリン協奏曲や交響曲第5番で、本人が世に出すなと言っていた原典版が最近聴けるようになったけど、面白い部分もあるし、これは書き直したかったんだろうなっていう部分もある。でも、聴き手としては複雑ですね。
僕も書き直すことはありますよ。でも、CDになって出版もされてしまったら、いくら作曲者でも勝手に書き直せないじゃないですか。あ、でも「鳥のシンフォニア」はまだCDになってないから書き直せるかな。
―先生の作品にはジャズ、ロック、アニメなどが出ていますね。
吉松 最近「ファイナルファンタジー」の音楽を書かれた植松伸夫さんとお話ししたときに、僕は最初に惹かれた曲がベートーヴェンの「運命」で、これがきっかけでクラシックの作曲家になろうと決めたという話をしたんです。で、その後に惹かれた曲はと聞かれ、ビル・エバンスのピアノの音が良くてと答えたら、じゃあジャズをやられたんですかと言う。いや、学生の頃はプログレッシブ・ロックをやっていてと答えたら、ずいぶん雑食ですねと言われてしまいました。でも僕の中では、それが同じ線の中にあったんですよね。
―多くの管弦楽作品を藤岡幸夫さんが振っていて、信頼関係がおありと思いますが、いろいろな指揮者に振ってもらいたいというお考えはありますか。
吉松 それはあります。出来れば生きているうちに。楽譜だけじゃ伝わらないことって多いですから。僕が指揮者にいつも言うのは「楽譜通りにきれいにやるな」ということなんです。そう言うと、誤解されそうですが、要するに、楽譜に書いてある音を均質に間違いなく弾くだけなら機械でも出来る。盛り上がるところとか、ロックンロールみたいなところとか、楽譜には書きようがないものを表現するのが人間でしょう。楽譜に書いてあることしか演奏しない、というんじゃ音楽にならない。そこでまず喧嘩するんです。
例えばクラシックのオケはAllegroを、「安全に走れる最大限のスピード」と捉えている。でも僕は、安全でなく空中分解ギリギリでも良いから、アクセルを踏み込んで欲しいと思うんです。きれいで安全なそんな演奏を聴きたい訳じゃない。そう言うと、アインザッツが合っていないような演奏を録音したり人に聴かせられないと言われるんですけど、作曲家の最終権限でやってもらっちゃうんです。おかげで凄く険悪な状況になったこと一度や二度じゃありません。
でも僕が死んだ後、またゼロから丁寧に弾かれちゃうんだろうな、とは思いますね。1 回それで喧嘩して、あいつはそういう演奏を前提にして書いているんだなというのがわかって初めて伝わるわけでしょう。
―藤岡さんはわかっておられるのですね。
吉松 彼は僕がどこで怒るか知っているから。例えば、AllegroMoltoって書いてあるのに、安全運転のスピードで演奏したり、ホルンやトランペットで音が出にくい高い音をピッコロトランペットとかを隠し持ってきれいに吹いちゃうと、怒るんです。出せない音を必死になって顔真っ赤にして吹くのが欲しくてわざわざ高い音を書いているのに。きれいに吹いちゃったら全然ぶち壊しだろう、と。まあ、困った作曲家だな、とは思ってるんでしょうけど。だから、そういうポイントで怒るのを知っていると、そういうもんだというのが伝わる。伝わってないと、楽譜に書いてあることを全てきれいに演奏するだけの中身の無い音楽になっちゃうでしょう。
―なるほどそれで金管楽器はきついのですね。
吉松 僕の作品は金管がきついので、イギリスでCD録音したときは「ヨシマツシフト」とか言って倍管使っていたんですよね。ホルン6 パートなら 12 本、トランペット 3 パートなら 6本。ティンパニも2人いました。
特にホルンには評判悪くて、「ヨシマツさん、管楽器は息をしないと吹けないんです。知ってますか?」とか「こんな高い音ホントは出せないんです、やめてください」とか、いつも言われてました。でも金管は、当たり前に吹ける音域を当たり前に使うと緊張感がなさ過ぎてダメなんです。それで演奏者にはきついんですけど、ちょっと高めの音でピークを作ってもらう。ところがある時、「あれ、随分上手く吹けてるな」と思ったら、ピッコロトランペット隠し持ってる。
サキソフォンやフルートなど管楽器の曲を書くと、初演の時は必ずと言っていいほど「これは絶対吹けない」とお墨付きもらうんですが、15年くらいたつと普通にコンクールなどで学生が吹くようになる。だから「吹けない」って言われても、気にしちゃダメですね。チャイコフスキーだってラフマニノフだって、当時は人間が弾けるとは思われなかったのに、今は普通に学生が弾くでしょ。
左手のピアニストになられた舘野泉さんにも、最初は凄く難しい曲を書いてしまったんです。でも、「これは弾けない」と言われて「じゃあ書き直しましょうか」と言ったら「いいです」。それで百回くらい弾いていたら弾けるようになって「いやあ、良いリハビリになった」と言われました。人間の能力に限界はないんですね。
―アインザッツを合わせないような指揮がよいのでしょうか。
吉松 そういうわけではないんですけど、どこまで内容に迫っているかですよね。プロだと3日間とか1週間とかで本番やるけれども、アマチュアだと半年とか1年とかずっと同じ曲を延々と練習して、もう見ないで弾けるくらいだけど、じゃあちゃんと弾けているかというとそういうわけではない。でも、完璧に弾けて音が合っているというだけではない音楽が存在する。ショスタコーヴィチやブルックナーなんかは特にそう感じますね。
だから、僕が「練習見てください」と言われた時に一番言うのは、「楽譜通り弾くな」ということなんです。「選りに選って作曲家がそんなこと言うなんて」と驚かれますが、必ず言いますね。「なんで楽譜通り弾いてるんですか」って。
―とても共感できます。
吉松 問題は、それをどう取るかですよ。でたらめ弾いていいよって言うことじゃない。要するに楽譜に固執するあまり、ここで何をやりたいのかっていう音楽の本体が飛んでしまっている場合が多いわけです。
例えばドレミファソラシドっていうフレーズが楽譜に書いてあったとしても、ドのベロシティ(強弱を表す数値)が 1.0 だとしたら、レは 0.9、ミは 4.3 というように楽譜に書けない暗黙のイントネーションが楽派や作曲家によってあるんです。それを「楽譜にそう書いてある(そうとしか書いていない)から」という理由で均一に演奏してしまったら、スウィングもグルーヴも何にもなくなっちゃう。
そういうことは、どう説明しても分からないというレベルのこともあるけれど、意外と作曲家のひとことで「あ、そうか」と分かることもあるんです。だから作曲家の言葉は聞いた方がいい。言うことを聞くかどうかは別としてね。
―私たちは現役の作曲家の作品を演奏したいのです。
吉松 ええ、なるべく生きてる間にやったほうがいいですよ。例えば武満さんのスコアでは、3連符と5連と7連のパッセージが同時に出て来たりするんです。それをリハーサルで、3連の2拍目と5連の3拍目ではどっちが先に出るべきか、なんて計算してずーっと何時間も練習してたら、武満さんが現れて「ああ、こんなの合わなくていいんですよ」と一言言っておしまいになったんですって。要するにあれは「縦の線に合わせない」という前提で書いてあるわけで、ぴったり 1/5、1/7 のところに音を出して欲しいということではない。でも、そんなこと楽譜からだけでは分からないですよ。どんな綿密に書かれた楽譜も、音楽をすべて伝えることは出来ませんから。
―楽譜は世界共通の記号になっていますけど、時代によっても想いも違うでしょうし。作曲家によっても違うでしょうね。
吉松 例えば、文字で「われわれはうちゅうじんだ」って書いてあったら、僕らは「我々は宇宙人だ」って自然にアクセントを普通に付けて読むでしょ。だけど日本語を全然知らない人が読むと「ワレワレハウチュウジンダ」になる。書かれた文字(音符)はちゃんと再現しているけど、意味(音楽)は伝えていない。音楽も言語もどこにアクセントがついて、どこにイントネーションが付くっていうのは暗黙のうちにあるわけです。バッハにはバッハの、武満さんには武満さんのがあるわけ。だからその作曲家のイントネーションとか、それこそボキャブラリーとか、身に纏っているモノを聞き取り理解して欲しいですよね。それによって世界が全然変わることもあると思うしね。
―先生に練習に来ていただける日を楽しみにしています。
吉松 「楽譜通り弾くな」って最初に言おうかな。
2016年8月21日
聴き手・構成:大原久子(ホルン)
トロンボーンのお話
維持会員の皆様、トロンボーンパートの武田浩司と申します。いつも新響の活動にご協力いただき、ありがとうございます。235回演奏会では吉松、伊福部、ブラームスとタイプの異なる3人の作曲家の作品を取り上げます。ここではブラームス作品でのトロンボーンの出番について、少々マニアックな内容を書かせていただきます。
トロンボーンには大きくアルト、テナー、バスの3種類があります(昔はソプラノもあったそうですが、現代ではほとんど使われることはありません)。トロンボーンは3本で演奏することが非常に多く、新響を含め現代のオーケストラではテナー2本とバス1本で演奏することがほとんどです。テナーには1つの補助バルブがついていて、B♭とFを切り替えられるように、またバスには2つの補助バルブがついていて、B♭/F/G♭/D(あるいはB♭/F/G/E♭)を切り替えられるようになっています。「バス」トロンボーンと呼びますが、実は基本となる管の長さは「テナー」と同じです。 1ポジション(スライドを最も縮めた状態)ではアルト、テナー、およびその補助バルブに切り替えた状態ではそれぞれ以下の音が出せ、スライドをそこから伸ばすことで約4度音を下げることができます。この音(スライドを動かさなくても出せる音)は自然倍音列と呼ばれます(譜例ではペダルトーン:第1倍音は除いています)。
![]()
アルトとテナーにある音部記号は見慣れない方もいるかもしれませんが、それぞれアルト記号、テナー記号(あるいは両者まとめてハ音記号)と呼ばれており、前者はヴィオラとアルトトロンボーン、後者はチェロ、ファゴット、テナートロンボーンによく使われている記号です。記号の中心が「ド」の音になります。
現在では上記のように1あるいは2個の補助バルブを必要に応じて切り替えながら、ある程度近くて吹きやすいスライド位置で演奏しています。しかし、ブラームスがこの曲を作曲した頃には補助バルブは一部のバルブトロンボーンを除きあまり一般的ではなく、アルト/テナー/バスのトロンボーンはそれぞれE♭/B♭/Fの長さで、単純にスライドを伸び縮みさせて音を変えていました。
トロンボーンはホルン、トランペットと異なり、スライドを伸び縮みさせることで当初から半音が演奏できました。ベートーヴェンが交響曲第5番で初めてオーケストラ作品に採用するまでは、合唱の補強として教会で演奏していました。しかしトロンボーンは当時一般的にオーケストラに使われている楽器ではありませんので、使われる場面も限定的でした。ベートーヴェンの交響曲第5番でも、最後の音符は全員で全音符をフェルマータで伸ばしていますが、トロンボーンだけが四分音符で終わってしまい、全員が気持ちよさそうにフェルマータで伸ばしている間楽器を構えたままにするか悩ましいところです。今回の演奏会で取り上げるヨハネス・ブラームス(1833-1897)は、ベートーヴェンよりはやや後の年代ですが、同時代の作曲家と比べて古典的な作風と言われており、トロンボーンの出番は同様にごく一部に限られます。交響曲第1番では第1~3楽章は全て休み(Tacet)で、第4楽章で初めて登場します。第4楽章ではとても有名な、1番奏者泣かせの(=音が少し高い)コラールがあります。そこでは以下のような譜面を演奏しています(譜例は音楽之友社 ミニチュアスコア[1]に基づく)。

トロンボーンの音符の下に書き加えた数字はスライドのポジション番号で、1が最もスライドを縮めた状態、そこから番号が増えるごとに半音ずつ下がり(=スライドが伸び)、6では上の譜例で書いた自然倍音列から完全4度下がります。アルトとバスのパートには2つ番号を書いていますが、上の段が補助バルブなしの楽器で演奏した場合、下の段が現代のテナー/テナー/バスの3本で演奏した場合の番号で、F○やD○と記載したところは、それぞれFおよびDの補助バルブに切り替えた状態となります(特にバスの下段はこれに限らず、いくつかの組み合わせがあります)。現代と昔の楽器でポジションが顕著に違うのがバストロンボーンで、最後の3音だけ見ると現代では3→6→4と少し動かせば済むのですが、補助バルブ無しのF管では6→1→6と大きく動かさなければいけませんでした。F管バストロンボーンでは、6ポジションまでスライドを伸ばそうと思うと一般的な手の長さではぎりぎり足りず、スライドの持ち手の部分にハンドルを付けて長く伸ばせるようにします。

引用元http://www.wikiwand.com/en/Types_of_trombone
6ポジションまで伸ばしたF管バストロンボーンは人の背丈以上の長さになりますので、それをハンドルを駆使して6→1→6と操作している様子は視覚的効果も大きいと思います。現在のバストロンボーンがB♭になっているのも、ハンドルを使わないと全ての音を出すことができず、B♭であればちょうど右腕を一番伸ばした状態で演奏が可能といわれています[2]。私は10年以上前に浜松にあるヤマハの工場見学に行った際に、このF管バストロンボーンを触らせていただく機会があり、友人と一緒にE♭アルト、B♭テナー、Fバス(補助バルブ無し)でこのコラールを吹いてみましたが、この移動の箇所で思わず笑いが起きていました。
ブラームスの交響曲第1番は、他のブラームスの交響曲と比べても特にトロンボーンの音符の数が少ない曲です。アルトトロンボーンの音の数を数えてみましたが、80個でした。おそらくブラームスに乗っているメンバーの中で最少と思います。コラールのところは有名ですが、ぜひ他の出番も探しながらお楽しみ下さい。
[1]音楽之友社 ブラームス 交響曲第1番ハ短調作品68
[2]佐伯茂樹、『金管楽器の歴史を知ろう』(2005)
打楽器パートより維持会員の皆様へ
維持会の皆様、こんにちは。打楽器パートの桑形 和宏(くわがた かずひろ)です。
留年が決まった大学4年生の1982年冬に入団、芥川先生指揮の第99回定期演奏会『青春の作曲家たち』でデビュー後、あっという間に30年以上が経過してしまいました。今では、練習のない土曜日に他のことをやっていると、「本当に今日は練習がないのか」と不安になってしまうほど、新響が完全に生活の一部と化しています。
さてこのたび、当「維持会ニュース」に拙文を掲載してもらえることになりました。「維持会と打楽器」を軸に、我がパートのメンバー紹介や自らの自慢話、そしてオーケストラに多大な影響力を発揮する「ティンパニ」について書いてみることにしました。しばらくお付き合いくだされば幸いです。
1)維持会と打楽器
演奏会当日にお配りしているプログラムの最後のほうに、「新交響楽団維持会のご案内」というページがあり、そこには、「……。集まった会費は、ティンパニ……テューブラーベル等の楽器購入や」と記載されています。
そうなんです。維持会費で買っていただいた楽器なくしては、わが打楽器パートの、さらに言えば新響の演奏は立ち行きません。まず始めに、この場をお借りいたしまして、深く御礼申し上げます。
しかしながら、いただいた維持会費でどんな打楽器を購入したのか、申し訳ないことに、これまで細かくご報告できる機会がほとんどありませんでした。今回お伝えできる機会をいただけ、少しだけ胸のつかえがおりた思いです。
と申しましても、大小含め相当数の楽器をお世話いただいており、全部を書ききることはできません。そこで今回は、ステージ上でひときわ目立つ5種類について、どんな楽器なのか、そしてそれはいつどんな場面で登場するのかを写真入りで紹介いたします。
2)楽器紹介その1
まず、5種類のうちの2種類を紹介いたします。
1:テューブラーベル
 のど自慢で有名なアレ。音程のある金属の棒が計18本ぶら下がっており、主に木槌で叩きます。木槌は、最寄りのホームセンターで購入することがほとんどです。とても重い楽器で、持ち上げるには最低でも4人は必要です。
のど自慢で有名なアレ。音程のある金属の棒が計18本ぶら下がっており、主に木槌で叩きます。木槌は、最寄りのホームセンターで購入することがほとんどです。とても重い楽器で、持ち上げるには最低でも4人は必要です。
これまで、矢代秋雄先生、石井眞木先生などの邦人曲で大活躍したのをはじめ、『タラス・ブーリバ』や『展覧会の絵』などにも登場しました。今後は、2017年4月に演奏予定の『こうもり』序曲で、1本だけですが使用します。
今年7月の演奏会では、三善晃先生の『管弦楽のための協奏曲』に1回だけ登場しました。また、ベルリオーズ『幻想交響曲』の第5楽章に出てくるカリヨン(教会の鐘)の代用楽器として、練習時には重要な役割を果たしてくれました。
2:アンティークシンバル
 別名クロタル。音程がある金属製の円盤が並んだ、優しい音のする楽器。使用頻度はそう多くはないのですが、ラヴェルやプーランクといったフランス音楽、邦人作品などで使用してきました。
別名クロタル。音程がある金属製の円盤が並んだ、優しい音のする楽器。使用頻度はそう多くはないのですが、ラヴェルやプーランクといったフランス音楽、邦人作品などで使用してきました。
単音で使用する際には、円盤を取り外し、手に持って演奏することも多いです。来年1月の『牧神の午後~』では、手に持って演奏し、この世のものとは思われない美しい音を響かせる予定です。
アマチュアオーケストラでこの楽器を所有している団体は、そう多くはないと思います。さらに新響では、2セット(2オクターブ)所持しており、この上ない贅沢を享受しています。
3)楽器所有の2つのメリット
本稿でご紹介しているような、考え方によってはある意味「特殊な」打楽器を団で所有、すなわち維持会費で購入させていただいたことにより、大きなメリットがうまれています。
1:財政上のメリット
先ほど「特殊な」と申し上げましたが、邦人作品を含めた近現代の作品を演奏する機会が多い新響では、結構使用頻度が高く、「やや特殊な」くらいの感じでしょうか。
未所有の楽器が必要な場合、どこかから調達する必要があります。他団体のご好意に甘えて使っていない楽器を借りたり、団員が私物を持ち込んだりして対応していますが、それにも限界があります。さすがに、私物のテューブラーベルを持っている団員はいません。その際にはリース屋さんから借りることになりますが、結構お金がかかるもので、毎回の練習に借りていたら大変なことになってしまいます。
下世話な話で恐縮ですが、2シーズン使えば、購入代金はほとんど元が取れてしまうといっても過言ではありません。それ以降はもちろん費用がかからないわけで、財政面で非常に助かる結果になっています。
2:練習上のメリット
本番で使用する楽器で毎回練習できるという、理想的なリハーサルが可能になりました。楽器の特性、演奏上の立ち位置、音量に対する力加減などを、計12~13回の練習の都度確認しながら演奏会当日を迎えることができています。演奏する側としては何よりもありがたく、とても助かっています。贅沢な練習環境に身を置けることに、改めて感謝申し上げなければなりません。
前回の『幻想交響曲』では、ステージリハーサルを含めて3回の練習にカリヨン(鐘)をリースしました。自分の適応力の低さを棚に上げて申し上げますと、少ない練習回数でタイミングや音量、叩く場所による音質の違いなどの楽器の特性を把握するのに、非常に苦労しました。しかし、「運営委員会」に「カリヨンを買ってくれ」と訴えても、相当高価なため、まず許可は下りなかったでしょう。
4)楽器紹介その2
ここでも2種類紹介します。最後のひとつ「ティンパニ」につきましては、私の思い入れも含めて、最終章で詳しく紹介させてください。
3:シロフォン
 いわゆる「木琴」です。使用頻度は高く、今年7月の三善先生の作品で大活躍、今回の『鳥のシンフォニア』でも重要なパートを受け持っています。
いわゆる「木琴」です。使用頻度は高く、今年7月の三善先生の作品で大活躍、今回の『鳥のシンフォニア』でも重要なパートを受け持っています。
西洋音楽での出番も多く、ショスタコーヴィチをはじめとする多くの作曲家にとって、欠かせない楽器になっています。来年1月定期の『火の鳥』全曲版には、オブリガート風の難しいパッセージが出てきます。団員の名人芸にご期待ください。
ところで、シロフォンに限ったことではありませんが、大型打楽器には悩みがあるのです。それは、楽器の支えの部分や車輪に相当ガタがきているという悩みです。新響には専用の練習場というものがありませんので、毎回「楽器運び」が発生します。その際の「転がして運ぶ」ことの繰り返しがその原因です。
楽器運びを手伝ってくれる団員も状況を承知しており、とても丁寧に運んでくれるので大変助かっています。と言っても、現状はだましだまし使っているのが正直なところです。
4:ヴィブラフォーン
 クラシック、というよりもジャズを思い浮かべる方が多いかもしれません。
クラシック、というよりもジャズを思い浮かべる方が多いかもしれません。
外見はシロフォンに似ていますが、全く異なる楽器です。まず、鍵盤が金属であること、そして電源を使用して鍵盤の下でファンを回すことにより持続音がビブラート(振動)すること、さらにはペダル操作によって音の長さが調節できること、です。
前回の三善先生の作品をはじめとする邦人作品で時折使用されます。また、『ウェストサイドストーリー』後半部分に登場する難しいパッセージは有名です。
ただ、音量に乏しいことが欠点といえば欠点で、オーケストラが大音響で鳴っている部分には、ほとんど使われることはないようです。
なお、この楽器を初めて使用した純音楽作品は、アルバン・ベルクのオペラ『ルル』であると言われています。私は、上下2巻のスコア(総譜)を持っていますが、結構出番があるので驚いた記憶があります。
5)打楽器のパート事情
現在の在籍団員数は4人、若者から壮年までの幅広い年齢層、旅行業や作家などといった多種多様な職業構成、そしてどんなに忙しくても打楽器から足を洗えないメンバーが揃った、極めて魅力的な集団です。私以外の3人はとても器用で、どんな種類の打楽器でも、そつなく演奏することができます。私は、特別支援学校で進路指導を担当しており、あまり学校にはおらず、多くの時間を生徒の進路先訪問に費やす毎日を送っています。
しかし、メンバー数は全盛期の8人から半減してしまいました。8人が在籍している際には、出番を確保するのに苦労していましたが、今ではエキストラ(プログラムには「賛助」と記載)に頼っているのが現状です。理想の団員数は、5~6人といったところでしょうか。
幸い、今回の演奏会では1曲の必要人数が最大で4人のためにエキストラをお願いする必要はないのですが、最近では例外的なことです。
エキストラは、4~5人の決まった方々に助けてもらっています。交通費や練習後の飲み会等で確実に足が出ているにもかかわらず、皆さん笑顔で、そして完璧に練習して参加してくれます。エキストラの方々の演奏に、大きな刺激を受けることも多いです。特にお願いする機会が多いS氏は、18歳のころから一緒にティンパニを教わった兄弟弟子で、約30年ぶりに旧交を温めることができました。
現在の最大の悩みというか課題は、新響に打ち込んでくれる新入団員を迎えることです。
なかなか入団希望者が来てくれない打楽器パート、一部の団員からは、「パートに威圧感がある」「雰囲気が近寄りがたい」などと指摘されていますが、それは大きな誤解です。腕自慢の方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、練習を見学に来てみてください。
6)ティンパニ
最後はいよいよティンパニです。オーケストラ曲には必ずと言ってよいほど使用されており、新響の演奏会ではいつも最後列中央に鎮座しています。来年1月に取り上げる『牧神の午後~』のように、ティンパニが使われていない曲もありますが、少数派と申し上げてよいでしょう。
ティンパニには明確な音程があり、作曲者の指示に従って調律します。曲の間で音高を変えることもしばしばです。また、楽器の大きさによって、使用可能な音域が異なります。
以下、私の独自の考えを表明してしまう個所が時々登場するかもしれませんが、どうかお許しください。
1:新響には6台のティンパニが
入団してからしばらくの間は、団の所有する楽器は4台でした。23,26,29,32(単位はインチ、概ね打面の直径)の、大きさが異なる4台です。
その後、無理をお願いして26,29を各1台ずつ買って戴き、現在の6台所有に至っています。なぜ同じ大きさが2台ずつあるのか疑問に思われるかもしれませんが、このことによって、できない曲が大幅に減ると同時に、演奏の幅が限りなく広がりました。事例は限りなくあるのですが、いくつか具体的に述べてみます。
(1)ショスタコーヴィチの交響曲第10番の終結部には難易度Аクラスのティンパニのソロがありますが、これは以前のような大きさの異なる4台では演奏できません。なぜなら、32インチの楽器では要求されている「シ」の音が音域外のため出せないからです。また、「レ」もしくは「ミ♭」を、23インチで出さなければなりません。楽器が小さいうえに23インチの最低音に近いためヘッド(皮)がゆるんでおり、張りのある音が出にくいのです。この2つの問題は、右から26,26,29,29というように並べると容易に解決でき、安心して気持ちよく演奏に臨むことができました。
(2)今年4月に演奏したマーラーの『復活』。作曲者は7台でできるように書いていますが、新響の場合は所有楽器の音域の関係上、実際には9台必要となります。しかし、1台だけ借りて楽器を掛け持ちするなどの工夫をし、支障なく練習を進めることができました。本番は舞台裏用にもう1台借りましたが、もし4台しかなかったら、練習のたびに最低3台は借りねばならず、運搬と財政面での負担が大きくなったことでしょう。
(3)三善先生の『管弦楽のための協奏曲』は4台で演奏できるように書かれていますが、音替えが目まぐるしく、本番に向けて危険を感じていました。そこで「ファ♯」に調律した5台目の楽器を用意したところ、はるかに容易に演奏できるようになりました。このようなことは、6台に増えた当初から頻繁に行なっています。ぎりぎりの音替えや難しい手順を 要求される場合、別に1台用意することで非常に安心して演奏でき、とても助かっています。贅沢な話ですね。
(4)7月に演奏した『幻想交響曲』の4,5楽章は、2名のティンパニ奏者を要求しています、これは管楽器の1,2番とは少々異なり、単に音が違うだけで2名は全く対等の扱いです。6台楽器があるおかげで、(26,29)を2セット用意でき、練習初日から本番と同じ条件で取組むことができました。
(5)『ジュピター』や『運命』、そして今回演奏するブラームスの1番など、「ドとソ」を指定している名曲は数多くあります。これまで(26,29)または(29,32)のセットで演奏せざるを得ませんでしたが、曲によっては(29,29)と同じ大きさの楽器で演奏したほうがより良いと考えられる場合があります。現在の新響では、それが可能なのです。
2:ティンパニとの長い付き合い
中学生の頃、私が入団する以前に新響でホルンを吹いていたN氏(歳は離れていますが従兄弟です)からもらった『第九』のレコードを聴いたのが、ティンパニとの出会いです。曲の美しさもさることながら、「なんとすばらしい音がする楽器なんだ」と心底感動したことが思い出されます。
大学入学後、前述のS氏と一緒にМ先生に師事し、一から教わりました。習いたての頃は、「大きい音も大事だが、美しく小さい音を自在にコントロールしたい」と思い、練習に励んでいました。今でも、大きい音よりは小さい音のほうに自信があります。
転機が訪れたのは、縁あってある演奏会に出演できることになった大学3年生の時(おおげさですいません)。そのとき首席フルートを吹いていたのが、本維持会ニュース編集長の松下さんです。30年以上も前で記憶が定かではありませんが、確か最初の練習の時、指揮者から「全体的にティンパニが小さすぎる」と指摘され(松下さん、覚えてますか?)、大ショックを受けました。それからは「美しく気持ちのこもった大きな音」を目指して練習に打ち込むようになり、現在に至っています。
ちょうど耳の高さに打面があるトランペットとトロンボーン、テューバのメンバーには、相当ご迷惑?をかけていることと思います。
ところで、今までで一番大きな音を出そうと思ったのは、ブルックナー8番の4楽章の最初。逆にできるだけ小さな音を出そうと思ったのは、『トリスタンとイゾルデ』です。どちらも、指揮は飯守先生でした。
3:ティンパニのバチ
 一概には言えませんが、原則として、柄の先にフェルトを丸く巻いたものをバチとして使用します。今回演奏する『タプカーラ交響曲』には、ワイヤーブラシで叩いたり、少し痛いですが手で直接叩いたりする奏法が登場しますが、これは特殊な例だと思います。他に、例えば『幻想交響曲』4楽章後半部分のように、作曲者の指定で、フェルトが巻かれていないネギ坊主のような形をした木のバチで叩くこともあります。
一概には言えませんが、原則として、柄の先にフェルトを丸く巻いたものをバチとして使用します。今回演奏する『タプカーラ交響曲』には、ワイヤーブラシで叩いたり、少し痛いですが手で直接叩いたりする奏法が登場しますが、これは特殊な例だと思います。他に、例えば『幻想交響曲』4楽章後半部分のように、作曲者の指定で、フェルトが巻かれていないネギ坊主のような形をした木のバチで叩くこともあります。
私は約30組のバチを所有しており、その日の気分に左右されながらも、その場にあった音を想像しながらいろいろなバチを使い分けています。頭の大きさやバチの重さで、また叩き方で、硬い音、柔らかい音、重めの音、軽めの音を出していきます。本番ではいつも10組ほどステージ上に持ち込んでいますが、実際に使うのはそのうちの半分ほどです。
ここでは、柄の材質によってバチを3つのカテゴリーに分けて紹介します。愛用のバチの一部を、写真左より「竹バチ」「木のバチ」「アルミシャフト」の順番に並べてみました。違いがお分かりいただければ幸いです。
(1)竹バチ:柄の部分が竹、または合竹でできており、ややしなるのが特徴。重さは1組で約50g。私の持っている竹バチのほとんどは、長年打楽器トレーナーとしてお世話になったS先生の手作りです。
(2)木のバチ:柄の部分が木でできており、見た目ではしなりはありません。1組で約90g。ティンパニを習い始めのころから使っているものばかりで、刻印が手垢ですり減って、見えなくなっています。
(3)アルミシャフト:愛称は「金属バット」。1組で約180gもある、格段に重いバチ。「ここぞ」というときに使用します。
最近、古関君がこのバチを多用するようになり、うれしい限りです。現在、ブラームス1番の冒頭でこのバチを使うかどうか悩み中です。
余談ですが、できるだけ長く打楽器を続けられるよう、また、重量のあるアルミシャフトのバチを自在に操れるよう、スポーツクラブでの筋トレを欠かさないようにしています。いちばんきついのは、鏡の前に立って行う、9㎏のダンベルをバチに見立ててのシャドートレーニングです。先日指を痛めてしまいましたが、もう大丈夫。原稿書き終わったら行ってきます。
4:ブラームスの第1番
何十年もオーケストラをやっていると、昔やった曲を再度演奏する機会がどうしても多くなってきます。今回のブラームスの1番もそのうちの1曲です。同じ曲を演奏する際には、昔のことを忘れ、改めて1から譜面を見直すようにしています。
今回特に強く意識したいことは、音色と音質です。この曲でブラームスは、ティンパニの音符を、「・」のスタッカートが付いている音、楔形のスタッカートが付いている音、そして何もついていない音の3種類に書き分けています。
その違いが少しでもオーケストラ全体に寄与できるように頑張ります。
もうひとつ、お恥ずかしいことに、今回あることに気付きました。この曲のティンパニには「ff」が非常に少なく、1楽章に3か所(繰り返し部分は除く)、4楽章に2か所の計5か所しかないのです。最後は非常に盛り上がって曲が終わりますが、この部分も「ff」ではなくただの「f」のままなのです。前回の演奏では、オーケストラの盛り上がりの流れに乗って強打してしまいました。
ないと困るけれど大きすぎるのはよろしくないと考えたのか、興奮したティンパニ奏者の強打を防ぐ意味でそうしたのか、真意はよくわかりません。本稿〆切後の10月1日にトレーナーの石内先生のパート練習があるので、忘れずに訊いてみることにします。
以上、長々とおつきあいくださり、どうもありがとうございました。
今後も、維持会の皆様を頼ってしまうことが多いかと思います。その節は、くれぐれもよろしくお願い申し上げます。
第235回ローテーション
| 鳥のシンフォニア | シンフォニア・タプカーラ | ブラームス1番 | ||||
| Fl | 1 | 兼子 | 1 | 吉田 | 1 | 松下 |
| 2 | 吉田 | 2 | 新井 | 2 | 岡田 | |
| Picc. | 藤井 | Picc | 兼子 | ― | ― | |
| ― | ― | Picc | 藤井 | ― | ― | |
| Ob | 1 | 宮内 | 1 | 山口 | 1 | 堀内 |
| 2 | 山口 | 2 | 桜井 | 2 | 平戸 | |
| ― | ― | C.I. | 岩城 | ― | ― | |
| Cl | 1 | 高梨 | 1/Es | 末村 | 1 | 中島 |
| 2 | 大藪 | 2 | 石綿 | 2 | 進藤 | |
| ― | ― | Bass | 品田 | ― | ― | |
| Fg | 1 | 浦 | 1 | 田川 | 1 | 藤原 |
| 2 | 笹岡 | 2 | 笹岡 | 2 | 田川 | |
| ― | ― | Contra | 浦 | Contra | 浦 | |
| Hr | 1 | 大内 | 1 | 山口 | 1 | 箭田 |
| 2 | 宮田 | 2 | 大原 | 2 | 大原 | |
| 3 | 菊地 | 3 | 菊地 | 3 | 大内 | |
| 4 | 市川 | 4 | 宮田 | 4 | 市川 | |
| Tp | 1 | 小出 | 1 | 倉田 | 1 | 野崎 |
| 2 | 北村 | 2 | 北村 | 2 | 中川 | |
| 3 | 青木 | 3 | 青木 | ― | ― | |
| ― | ― | 1assi | 小出 | ― | ― | |
| Tb | 1 | 武田浩 | 1 | 武田香 | 1 | 武田浩 |
| 2 | 武田香 | 2 | 志村 | 2 | 志村 | |
| 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | |
| ― | ― | assi | 武田浩 | ― | ― | |
| Tu | 土田 | 土田 | ― | ― | ||
| Timp | 桑形・今尾・ 古関・皆月の 4人で 左記パートを 配分 |
古関 | 桑形 | |||
| Perc | bird calls | snare drum | 皆月 | ― | ― | |
| triangle | timbales | 皆月 | ― | ― | ||
| brass wind chimes | guiro | 皆月 | ― | ― | ||
| wind bells | tomtoms | 今尾 | ― | ― | ||
| cowbells | ― | ― | ― | ― | ||
| tambourine | ― | ― | ― | ― | ||
| wood blocks | ― | ― | ― | ― | sus. cymbals | ― | ― | ― | ― | cymbals | ― | ― | ― | ― | snare drum | ― | ― | ― | ― | tomtoms | ― | ― | ― | ― | bass drum | ― | ― | ― | ― | TamTam | ― | ― | ― | ― | xylophone | ― | ― | ― | ― | glocken-spiel | ― | ― | ― | ― |
| 鍵盤 | Piano | 藤井 | ― | ― | ― | ― |
| Harp | ― | ― | 見尾田(*) | ― | ― | |
| Vn | 1 | 堀内(田川) | 1 | 堀内(田川) | 1 | 堀内(佐藤) |
| 2 | 小松(伊藤真) | 2 | 小松(伊藤真) | 2 | 小松(内田智) | |
| Va | 村原(柳澤) | 柳澤(村原) | 槇(伴) | |||
| Vc | 柳部(大庭) | 柳部(大庭) | 柳部(安田俊) | |||
| Cb | 中野(上山) | 中野(上山) | 上山(中野) | |||
(*)はエキストラ
第235回演奏会のご案内
創立60周年シリーズ第4弾
記念シリーズの最後として、新響が大切な作品として度々演奏している伊福部昭の「シンフォニア・タプカーラ」と、同時代を生きる作曲家、吉松隆の小交響曲を取り上げます。そして後半はクラシック音楽の王道レパートリーであるブラームスの交響曲第1番を演奏します。
ゴジラの作曲家 伊福部 昭
伊福部昭は北海道に生まれ、中学時代に後に音楽評論家となる三浦淳史と出会って音楽に興味を持ち独学で作曲を始めます。北海道帝国大学で林学を学び北大オケではコンサートマスターをつとめました。卒業後も林務官の仕事の傍ら作曲を続けコンクール第1位入賞を機にチェレプニンに短期間指導を受けますが、ほぼ独学で作曲家となりました。その後は民族色の強い個性的な多くの作品を残し、「ゴジラ」などの映画音楽や大学で教え多くの作曲家を育てるなど2006年に91歳で亡くなるまで活躍し、今年は没後10年にあたります。
今回演奏する「シンフォニア・タプカーラ」改訂版は、新響が1980年に開催した伊福部昭の個展で初演され、新響では16回目の演奏となります。タプカーラとはアイヌ語で「自発的に踊る」という意味で、心を揺さぶるメロディと熱狂的なリズムのオスティナートで表現されるこの曲を、新響はこれからも演奏し続けていきたいと考えています。
鳥の作曲家 吉松 隆
吉松隆は東京に生まれ、中学時代にアマチュアフルート奏者の父親に<運命・未完成>のレコードを買ってもらい渡されたスコアを見て衝撃を受けて作曲家を志します。オーケストラがあるという理由で慶應義塾高校を選び、大学は工学部に進むも作曲に専念するため中退します。憧れの松村禎三に師事(つまり伊福部昭の孫弟子にあたる)しましたが独学であることにこだわり、いわゆる現代音楽が無調で前衛的なことが当たり前の時代に、調性とメロディのある音楽で挑み続けました。現在までに交響曲6曲を含む多くの作品を生み出し、大河ドラマ「平清盛」など放送や映画でも活躍しています。
吉松の作品の多くは「鳥」をテーマにしています。鳥は美しく歌い自由に空を飛ぶ。鳥は吉松自身であり聴く者の魂なのかもしれません。今回演奏する「鳥のシンフォニア」は、2009年に仙台ジュニアオーケストラの委嘱で作曲され、山下一史の指揮で初演されました。鳥の歌やジャズが出現する5楽章からなる楽しい曲です。
ベートーヴェンの後継者 ブラームス
ブラームスはベートーヴェンの9つの交響曲を意識して慎重になり、最初の交響曲は構想から21年もの歳月をかけて完成されました。当時は交響詩や標題交響曲など新しいジャンルが台頭していましたが、この第1番はベートーヴェンからのスタイルを踏襲しつつも、オリジナリティに満ちています。初演は聴衆の期待に応えて成功し、「ベートーヴェンの第10交響曲」とも呼ばれました。最後は第九の歓喜の歌に呼応するかのように歌いあげ感動的なクライマックスとなります。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
別宮貞雄:管弦楽のための二つの祈り
別宮貞雄(1922~2012年)は、前衛的な語法による音楽創作が主流の時代に、端正な古典主義的美学感を確立、調性と旋法に依拠した明快な旋律と抒情性を重んじる創作姿勢を貫いた作曲家で音楽言論人であった。日本の作曲家による音楽団体「日本現代音楽協会」では、書記長(現事務局長職)と委員長(現会長職)として活躍、また桐朋学園大学教授、中央大学文学部教授を歴任した。
学生時代から音楽を嗜みつつ物理学や美学を専攻する英才であり、感覚だけではない論理性と楽理を背景に、古典の持つ明快な構築性と、歌や旋律の持つ豊かな抒情性を融合した作風を確立するに至った。基本的にはディアトニック(Diatonic)で3度音程を基軸にする和音が好んで使用されている。
物理学と音楽
物理学という自然科学畑から出発したからこそ、理屈により全てを概念的観念的に数え上げてそれを音楽にする、というのではなく、音楽は心の問題であり、人間の認知能力の範囲で現在の自分を表現したものとする信念が感じられる。
東京に生まれ、幼少より物理学を志望、旧制第一高等学校から東京帝国大学(現東京大学)理学部物理学科で理論物理学を専攻し1946年卒業した。当時の物理学科では、学部3年卒業は試験官の前で卒業研究の口頭発表だったが、テーマは「相対性理論」とのこと。
1947年に文学部哲学科(のちに美学科が設立)に再入学、エルンスト・クルトのベートーヴェン研究「ロマンティッシュ・ハーモニー」を研究し、1950年「ベートーヴェン様式による浪漫的なるもの」という論文をだしている。
音楽への興味は高等学校在籍時から趣味として嗜みが深まり、大学に入るころ、トーマス・マンの「トニオ・クレーゲル」(Tonio Kröger)から芸術における手仕事の重要性を知り、まずは音楽理論をしっかりと学ぶべく池内友次郎に師事、和声法と対位法を学ぶ。大学在学中から作品を発表し続け、「毎日音楽コンクール作曲部門」にて1946年より3年連続入賞している。
東京大学文学部美学科卒業後、1951年にパリ国立高等音楽院でフェーグ科(フーガ、追走曲科)と作曲科に入学、ここでの3年にわたる留学で、ダリウス・ミヨーとオリヴィエ・メシアンに学び、職人的技術としての作曲技法の習熟と、音楽観や歴史観で大きな影響を受けた。ミヨーの作曲科には外国人枠で空席が一つしかなく、シュトックハウゼンと争ってその席を勝ち取ったという逸話がある。
作品は多岐にわたり、歌曲、ピアノ曲、室内楽、オペラ、演劇の付随音楽、交響曲5曲を含む管弦楽、映画音楽や演劇付随音楽などを残している。筆者は昨年集中的に実演に接する機会があった。「二つのロンデル」(1951年)として書かれた「雨と風」「さくら横ちょう」。ことに「さくら横ちょう」は、中田喜直も同時に付曲しており、各々ポピュラーな歌として日本的な心象を鮮やかに表現している。「ピアノのためのソナチネ」(1965年)もピアノの特性を発揮した秀逸な小品で、狂言に題材をとった「三人の女達の物語」(1964年)にはすぐれた劇場感覚が感じられる。東宝特撮ホラー映画「マタンゴ」(1963年)の音楽を手掛けていたことも注目したい。
洋楽と邦楽
能・狂言の世界に関心を示し始めた西洋音楽の作曲家として、別宮貞雄は、高度に完成された芸に対する畏敬の念を持っているからこそ、単純にこれを洋楽と結び付けることはしなかった。そもそも洋楽と邦楽とは本質的に離れたもので、具体的には西洋近代音楽はポリフォニーとしての構築性を獲得するため、邦楽の持つ微妙な音程と音色の操作という要素を犠牲にしてきた。
このため両者を無理に融合させようとすることは困難で、筋の立った仕方で結びつけ、かつ構造性を追求するのであれば、他の一面をあきらめるのが根本的態度、と強調しているところは興味深い。
カトリックと音楽
東京大学文学部に再入学後に受洗している。パスカルの「瞑想録」(Pensées)で、神の存在もまたその不存在も証明できない、しかしそのどちらかを仮定してそれに賭けて生きる方がいいのではないかという文書に出会ったことがきっかけであった。世界は数理的な秩序に支配されていると信じられている傾向があるが、そのことが解明されてわかること自体が人間にとっては一番不思議であり、一方で自己の存在と自由意思を持った我を信じていることは錯覚ではなく矛盾がある。このことを納得するためには、自分にとっては神の存在を認めることが一番よいと判断した。と明確に論じている。物理学と哲学、そして音楽創作を極めていく上での意思と理性が投影されている。
そして「二つの祈り」
新交響楽団は、第99回演奏会『日本の交響作品展7 青春の作曲家たち』で芥川也寸志の指揮により演奏した。演奏会に配布したプログラムには作曲者たちからの曲目解説が記載されているが、別宮貞雄は、「わが青春的音楽始末」として次のように述べている。
“つまり私にとって4曲目の管弦楽作品となる。34才の時のもので、果たして青春の香が残っているかどうか、心もとないが、私は人より10年も遅れて音楽の勉強を始めたのだから、そのことを考えれば、青春の作品といってもおかしくはないだろう。少なくとも修業時代をしめくくる作品といえよう。”
フランス留学で身に付けた「技術」の集大成として、並々ならぬ意気込みで世に問うた初期創作活動の到達点ともいえる作品である。当時の世界というものに向かい合った心の状態を表現し、伝統音楽的な「前奏曲」と「フーガ」という形式を踏襲しつつも、単純な踏襲ではなく、文学的な追求や感傷に煩わされることなく、純粋な音楽に浸って人間的な感情を受け、そして心の奥底を表現しているような情感に満ちている。
第1楽章 Douloureux
「悲しみを持って」と名付けられた前奏曲。相互的に関連性を持つ主題が交互に登場し、変奏曲ともいえる。短三度を伴う主題と半音階的進行を伴う対位。表情的でリリシズムに溢れた音楽が進行し、八分の七拍子、さらに八分の五拍子と盛り上がりを見せながら、「深い悲しみ」が押し寄せる波の如くに心の底まで音楽が染み渡っていく。
第2楽章 Vaillant
「雄々しく」。ファンファーレ付のフーガ。堂々たる金管楽器によるファンファーレに続き、「悪魔の音程」(Tritonus)といわれる増四度による緊張に満ちた主題が登場しフーガで展開していく。ファンファーレの主題も交錯しつつ、クライマックスを構築するストレッタでは、主題の対位としてトランペットに定旋律(Cantus Firmus)でグレゴリオ聖歌「クレド」主題が登場する。クレド(Credo)は、キリスト教の主要な教義を列挙した祈りとしてミサの中で重要な「信仰宣言」であり、この定旋律(Cantus Firmus)は信念の祈りとしてコラールに発展し、明確な三和音で力強く終止する。
自然体の音楽
別宮貞雄は、先入観のない鋭い批判精神を常に持ち続けており、歯に衣を着せぬ論評は、時に重みを持って受け止められ、議論や批判の精神に開かれているべき音楽界への祈念であったに違いない。新交響楽団で「二つの祈り」を演奏して以来、よく演奏会にお見えになったが、常に飄々した雰囲気で自然体を崩さなかった。もし、本日の演奏会にもいらしていたら、60年を迎えた新交響楽団をどのように論評されるのだろうか。今を生きている新交響楽団の心からの音楽として、溢れ出る感情を持って演奏に臨みたい。
初演:1956年5月10日 東京交響楽団第78回定期演奏会 日比谷公会堂
東京交響楽団 指揮/斎藤 秀雄
受賞:1956年 毎日音楽賞(第8回)尾高賞(第5回)
楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、小太鼓、中太鼓、大太鼓、シンバル、タムタム、トライアングル、チェレスタ、ピアノ、ハープ、弦五部
参考文献
『日本現代音楽 別宮貞雄 管弦楽のための二つの祈り』音楽之友社
『最新名曲解説全集 第7巻 管弦楽曲Ⅵ』音楽之友社
『NEW COMPOSER 2003 vol.4』日本現代音楽協会 会報
『日本の交響作品展7 青春の作曲家たち』新交響楽団第99回演奏会パンフレット 新交響楽団
三善晃氏との絆
JLC5005番号の古いレコードがある。
と言っても、レコード棚の中段に鎮座しているフェリックス・ヴァインガルトナー指揮、ロイヤル・フィルハーモニーによるベートーヴェンの交響曲第5番ほど古くはない。この78回転SP4枚組で総重量2kgといった代物は、蓄音機時代の遺物的存在だ。JLC5005はモノラルだが、33.1/3.回転のLPで、かつて東芝レコードの特徴だった赤い透明なプラスティック盤。棚に納まって55年は経っている。私と一緒に、鎌倉からヴィーン、ローザンヌ、ロンドン、パリと引っ越した仲だ。このレコードこそ、私が初めて耳にした三善晃氏の音楽である。ジャケット裏に載っている三善氏の顔写真も高校生のように初々しい。東大仏文科在学中に留学したパリ国立音楽院で着手され、帰朝直後の1958年に初演されたピアノ・ソナタを山岡優子氏が演奏している。2年後に作曲された〈交響三章〉と共に、初期の代表作品となった。
憑かれたようなテーマが単刀直入に語り始める第1楽章、ゆっくりなテンポが醸し出す香かぐわしいフィールドを流麗な旋律が淀みなくたゆたい逍遥する第2楽章アンダンテ、凛々しく決然としたロンドの第3楽章と各楽章は鮮やかなコントラストを見せながら、それぞれの主題が関連性を内に秘めて、有機的なまとまりのある構成だ。中学生だった私は、第2楽章が特に印象深く、日本人もこのようにスマートな音楽を書けるのかと驚き、感動を覚えた。
東京藝術大学では、作曲科のレッスンだけでなく、作曲科以外の学生を対象とした和声学のクラスも持っていらした。私は他のクラスに入れられたが、ヴァイオリン専攻だった家内は教えて戴いたし、その頃鷺ノ宮近辺に住んでいた彼女は、阿佐ヶ谷駅へ向うバスの中から、買物籠片手に歩いていらした三善先生を、時々見かけたらしい。
1980年代に毎秋、日本音楽コンクールの作曲部門と器楽部門のお手伝いを10年近く続け、本選に残った応募者の作品やコンチェルト伴奏の指揮を執った。私は審査には加わらなかったが、翌年からドイツのオーケストラの監督に就任するのでシーズン始めの9月・10月は日本に戻れない旨をお話しすると、審査会議室に呼ばれて、審査委員長だった三善氏から、長年の協力に対して委員特別賞を戴いた。
三善氏が久しぶりにパリにいらしたのは、その数年後だったと思う。スケジュールが空いていらした一日、ドライヴにお誘いして、御希望されたミリー=ラ=フォレ(Milly-la-Forêt)を訪れた。パリから南へ約60km、フォンテンブロー手前のミリーは人口5,000人ほどの小さな村。ジャン・コクトーが1947年から16年間過ごした終焉の地だ。現在コクトー記念館となっている彼の館は、当時まだ公開されていなかった。しかし、村外れにある12世紀に建てられた素朴な石積みのサン=ブレーズ=デ=サンプル礼拝堂は健在で、この礼拝堂が1959年に修復された際、コクトーは線描デッサンによる壁画を描き、ステンドグラスもデザインした。祭壇画は天使に見守られた荊冠のキリストだが、ミリーはフランスに於ける薬草栽培発祥地の一つで、昔は礼拝堂も病院の一角を占めていたから、側面には伸びやかに育ち花開く薬草が描かれている。その薬草を見上げる愛嬌たっぷりの猫の下にコクトーのサインが認められ、自筆で.Je.reste.avec.vous(私はあなたがたと一緒に居ます)と刻まれた石は、詩人が眠る墓碑である。三善氏はコクトーのファンだったらしく、初めて墓参出来たのを喜んでいらした。外に出て、庭に吊るされた幾つかの小さな鐘を交互に叩いて一つ一つの音に寸評を下したり、1479年に樫と栗の木を組んで建てられた市場の建物が残る中央広場近くのレストランで、シェフが薦める鰻の稚魚入りオムレツに舌鼓を打ったのは、楽しい思い出だ。
敬愛する作家の辻邦生氏と三善氏の対談を読み返す。昨年10月、軽井沢に遺された辻氏の山荘を訪ねた折に出会った貴重な資料だ。すれ違ってはいるものの、お2人共1950年代後半にパリ留学をされている。「ヨーロッパに於ける日本人創作家のあり方」「美と倫理の問題」「個と共同体の関連」「ナイーヴな情熱と情念的直観」などを縦横かつ精緻に語られる大先輩の発言には共感する点も多く、大いに啓発されて、「文化の上澄みだけをすくい取って日本に持ち帰っても何にもならない。文化とは結果ではなく、そこに到る全ての経験なのだから」と述べられた森有正氏の名言が脳裡に再び蘇る。
時間・色彩・言語
5月連休の穏やかな某日、とても小さな自宅の庭に、次女が生まれた時に植えた金木犀の枝が電線に届くほど大きく生い茂ってきたので、ミステリアスな樹の中に自ら鋏を持って潜り込み、剪定作業に没頭した。静寂な時間の経過とともに、枝を切り落としていくにつれて差し込む木洩れ日の色彩が変化していくたびに、大好きなヨハン・セバスチャン・バッハの平均律クラヴィーア曲集やカンタータ、ブルックナーの合唱曲や弦楽五重奏、中世から現代までの合唱作品など、精緻で美しい響きが心の中で響いてくる。
その日の午後、家族と一緒に小石川後楽園を散歩した時も同様な感覚に浸った。幾何学的な西洋庭園ではなく、移動しながら景色の変化を伴う回遊式庭園の中、自在な景色から音楽が「音色」として心の中に入り込む。西洋的な色彩の強い音楽景観を考えると、イメージは異なるのかもしれないが、武満徹『グリーン』『ガーデン・レイン』を景色として鑑賞した気分であった。「音色」とは、音楽の要素のひとつであり、「音」と「色」の融合と見れば、心に響く「色彩」そのものであろう。音楽の発展は「言葉」と「言語」によって生み出された記号:記譜法の確立によるもので、楽譜は作曲者と演奏者を結ぶ最小限の絆でしかなく、そこから生み出される音楽の音色は、時間の流れにより常に変化していくもの、と考えていた。
最近、「音色」や「言葉」に関して、いろいろと考えを巡らすことが多い。例えば、テューバの持つ演奏表現の概念としての“B to C“、2009年7月「新交響楽団第206回演奏会」のプログラム冊子で、「ベートーヴェン交響曲第3番「英雄」<音楽史上の革命性>」と題する解説には未だに思い入れがある。(以下引用)
“B to C”から“B to B”へ
バッハは「バッハ」(小川)ではなくて、「メーア」(大海)という名であるべきであった、という言葉は、バッハの音楽の果てしない広大さと深さをたとえたものとして、ベートーヴェンの有名なしゃれといわれている。(中略) 長年テューバを演奏している筆者にとって、テューバはベートーヴェンの死後に開発された新しい楽器とはいえ、バッハ(Bach)から現代(Contemporary)へというテューバの持つレパートリーの広さと演奏表現の可能性としての概念を認識しているが、時代を超越した精神世界の奥深くへいざなう音楽の流れとして、バッハ(Bachからベートーヴェン(Beethoven)という大きな概念を感じている。(後略)
http://www.shinkyo.com/concert/p206-3.html
人間は「言葉」を持つことで「知識」を蓄え、自己の存在と生き方を考えるようになった。精神世界への探求のひとつとして「芸術」が存在しているのであれば、“B to C“は、バッハ(Bach)から現代(Contemporary)から拡大し、“B to B”も含むBC”西暦紀元前(Before Christ)から現代(Contemporary)へという概念と考え直している。18世紀まで西洋音楽はどちらかというと声楽がメインであり、音楽は始めに言葉ありき、とすれば、いつの時代でも言葉は常に音楽と関連しているので、古典から現代までの音楽を解釈するためには、言葉による音楽語法の違いや共通点を常に意識することが重要である。すなわち「言語」というパラダイムの中で音楽をより深く見ていると、創造や解釈にいろいろな違いがあること、答えは一つではなく、創造の選択肢を増やしていくことが、音楽を嗜むことの醍醐味と言える。
「平穏」「歓喜」「情念」「快楽」「法悦」「祈り」「強靭」「死」「鎮魂」「悶絶」「暴力」「狂気」「抑圧」「抵抗」「闘争」「復讐」「殺戮」「差別」「凄惨」「絶望」「慟哭」「憤怒」など、通常コミュニケーションの手段としてストレートに使用することも経験することも憚られるような「文言」、演奏者は、解釈の一つとして、個人的な妄想としてではなく、音楽作品を通して、このようなイメージを聴き手の心に印象づけることが重要で面白い。バレエは踊りで。演劇は演技で。全て同じことといえよう。
新響は、クラシック音楽というジャンルの中で、世間一般に「有名」と言われる作品に限らず、我々が持つ演奏可能な技術の範囲内で、様々な音楽の創造にチャレンジしてきている。個々の作品には、古典と現代、国の違いを問わず、各々の言葉によるパラダイムのもと、アカデミックで論理的な構築と凝縮度の高い洗練された作風があり、音楽空間でのテンションの適切な変化のもと、作品の持つ鋭さ・厳しさ・優しさをライブで体験することは、楽しみの一つといえるだろう。
コンテンポラリーな作品は、当初まったく訳が分からず、変拍子や不協和な響きとか音程の動きが読みとれずに疑心暗鬼となってくが、練習を重ねていくうちに、諸和音の進行や旋律から、統一原理のようなものとして主題やメロディが次第に見えてきて、曲の全体の構造と秩序感が見えてくると、機能的で論理的な作品への関心と創造の感性が磨かれる。練習をすればするほど、緊迫感と共に演奏のテンションが高まり研ぎ澄まされ、立体的で拡がりのある時間と空間、不均衡や伸縮、異なる方向性を持つ多層的な展開の中で、混在しあって自由自在に展開していく音楽創造の面白さに気が付くことがある。新響が、従来の「邦人作品」をも含め、例えば、別宮貞雄『管弦楽のための<二つの祈り>』 三善晃『管弦楽のための協奏曲』といった近現代の日本人の作品を積極的に取り入れているのは、従来の音楽創造の幅をさらに広げるものを直接体感できることの面白さに気が付いてきたことの表れといえよう。
音楽の全体像を掴むためには、演奏に必要な時間を費やさなければならないが、視覚に訴える美術・絵画は一瞬の時間で全体像を把握することができる。時間芸術と呼ばれる音楽は、過ぎ去る時間に音を絡ませて聴き手の心象に主題・旋律・響きを明晰に刻印し、記憶の襞に印象を摺り込ませていくことであり、音楽空間と音楽風景の中には、時間の変化と共に近景と遠景が入混じり、そして奥行きのある立体的な空間が大切といえる。歴史・国・ジャンルを問わず「名曲」といわれる音楽には、このような要素が明確に存在しているに違いない。
指揮者の矢崎彦太郎先生は、以前、練習で下記のようなお話をされた。
・譜面は音楽ではない、楽譜上に書かれた音符や記号を響きとして解き放つ行為が演奏で、そこから建てられるもの、すなわち音楽は毎回違うものである。それが嫌だったら音楽をやらない方がよい。
・リハーサルは何のためにあるのか。本番でどういうことが起きてもいいようにシミュレートするためで「ここはこう決まったから」と事前に決められた手順通りに行うというものではない。音楽は毎回違うのだから、決して人のせいにしない。言い訳もしてはいけない。その時に周りの景色を見て聴いて、何が起きてどうなっているのかが大事で、それが面白いからオーケストラをやる。それがしんどいと思うのであれば、一人で楽器を弾いていればよい。演奏とはそれだけの覚悟が必要である。
・みんな聴いている。演奏者だけとか指揮者だけがその時の成り行きで演奏を変えなければならないのではなく、全員が一つの立場であり、作曲家の作品の前では、指揮者も演奏家も我々は全く同じ立場。「アマチュアだからいいだろう」ということは一切なく、だれが演奏しようが同じレベルを望まなければ、作曲家に対して失礼だし、お客様に対してもの失礼だし、何よりも自分自身に対して失礼なのだ。
世に名曲と言われるクラシックの音楽といえども、感動することもあれば、まったく理解できずに関心を失うこともある。有名無名にかかわらず、音楽の素晴らしさや価値に気付かされることの一例として、新響が常に意識してなければならない矜持が、明確に存在している。
「時間」というカンヴァスに音という絵具で描かれた楽譜を「言語」というパラダイムで読み解き、緊迫感とテンションを持って演奏することで「色彩」として解き放つこと。現在の新響の演奏プログラムにはそのことが反映され、常に新響は新たな出会いを求めて挑戦し、未来を創っていることを確信している。
追伸:
10年前の「創立50周年シリーズ・1」第192回演奏会(2006年1月22日)、三善晃先生の「交響三章」を小松一彦先生の指揮で演奏した。プログラム掲載のため2005年11月7日小松先生同席にて三善晃先生とのインタビューは未だに忘れることができない。題して「日本人としてのロマン主義の探求」。お二人とも既に故人となられた。今でも原稿を読むと胸が熱くなる。
http://www.shinkyo.com/concerts/p192-1.html
ベルリオーズ:幻想交響曲
村上 「ベルリオーズってむずかしくないですか?僕なんか聴いてると、ときどきわけがわかんないんですが」
小澤 「むずかしいっていうか、音楽がクレイジーだよね。わけのわからないところがある。だから、東洋人がやるには向いているかもしれない。こっちのやりたいことがやれるし。昔ローマで『ベンヴェヌート・チェッリーニ』っていうベルリオーズのオペラをやったんですよ。そのときなんか、もう何だって好きにやり放題できて、お客さんもそれで喜んでくれて」
ご存知、小説家の村上春樹氏と指揮者の小澤征爾氏の対談の一節である。そう、本日演奏する「幻想交響曲」は、ベルリオーズの代表作にして、訳が分からない曲の「分かりやすい」例ではないだろうか。
1827年、パリ。当時20代前半で未だ無名のベルリオーズは、イギリスから来たシェイクスピア劇団の「ハムレット」を観劇して感激。主演女優、ハリエット・スミスソンに一方的に恋をする。何通も恋文を送るが、返事は来ない。そこで「ロメオとジュリエット」のリハーサルを覗きに行くと、丁度、ジュリエットを演じる彼女がロメオに抱きかかえられる場面。気が動転した彼は、突然叫び声をあげて逃げ出す。怖れを感じた彼女は、彼からの手紙を受け取らないよう、小間使いに命じたのであった。
「幻想交響曲」が作曲されたのは、失恋の傷も癒えぬ1830年、ベートーヴェンの死から3年後のこと。当時はベートーヴェンの音楽でさえ、斬新過ぎて受け容れられなかった時代。そのベートーヴェンを崇拝していたベルリオーズは、自らの失恋体験をもとに全く新しい交響曲を創り上げた。作曲者自身、次のようにこの曲を解説している。
交響曲のプログラム
病的な感受性と激しい想像力に富んだ若い音楽家が、恋に絶望し、発作的にアヘンによる服毒自殺を図る。麻薬は致死量に達せず、彼は重苦しい眠りの中で奇怪な幻想を見る。夢の中で、感覚、感情、記憶が、彼の病んだ脳に音楽的な映像となって現れる。愛する人が一つの旋律となり、固定観念のように現れ、付きまとう。
第1楽章 夢─情熱
彼はまず、漠とした不安や情熱、理由のない喜びや憂鬱を思い起こす。次いで、彼女によって点火された、燃えるような恋心、ほとんど狂気に近い苦悩、再び取り戻した優しさ、宗教的な慰めを思い起こす。
第2楽章 舞踏会
舞踏会の華やかなざわめきのなかで、彼は愛する女性の姿を再び見る。
第3楽章 野の情景
夏のある夕暮れに、彼は二人の牧童が吹く牧笛を聴く。静かな自然のたたずまい。そよ風に樹々がささやき、未来への明るい希望が膨らむ。しかし、再び彼女の姿が浮かび、彼は不吉な予感におののく。もし、彼女に捨てられたら…。再び牧笛が聞こえてくるが、もう一人の牧童はそれに応えない。日没、遠雷、孤独、そして静寂…。
第4楽章 断頭台への行進
嫉妬に狂った彼は、愛する女性を殺し、死刑を宣告されて断頭台に連れて行かれる夢を見る。その行列の行進曲は、時に陰鬱で荒々しく、時に輝かしく荘重に響く。固定観念が一瞬現れるが、それはあたかも最後の愛の追憶の如く、ギロチンの一撃によって断ち切られる。
第5楽章 魔女の夜宴の夢
彼は夢で魔女の宴のなかに居り、彼を弔うために集まって来た妖怪たちに囲まれている。奇怪な音、うめき声、けたたましい笑い声。その時、固定観念が現れるが、それはかつての気品を失い、野卑でグロテスクな舞曲となっている。彼女が、魔女となって現れたのだ。歓迎の叫び、弔鐘、『怒りの日』の下賤なパロディー、魔女のロンドが続き、最後は、『怒りの日』とロンドとが同時に奏されて熱狂する。
さて、二人の運命や如何に。ハリエットは「幻想交響曲」の初演を聴くことはなかったものの、その後の再演を偶然聴きに訪れ、自分が主題と知って動揺。これを機にベルリオーズとの交際が始まり、やがて結婚、長男ルイが誕生する。しかし、幸せは長くは続かない。「出逢った頃の妻は、食べたくなるほど可愛かった。あれから40年!あん時、食べておけば良かった(綾小路きみまろ)」どころか4年で亀裂が入り、程なく別居。彼女は脳卒中に倒れ、死別する。ベルリオーズは別の女性と再婚するが、再婚相手や長男ルイにも先立たれ、晩年は孤独だったという。
彼は生活のため、音楽評論の仕事をたくさん引き受けた。いずれも、きみまろ顔負けの、皮肉や毒舌に満ちた文章である。例えば、アマチュア音楽家については、こんなことを書き残している。
「私は、アマチュアを全くもって信用していなかった。アマチュアのオーケストラは最悪に違いなかったし、実際そうだった」(小話集『音楽のグロテスク』より)
うぅん、何とまあ、身も蓋も無い!
さて、本日の演奏である。天国のベルリオーズに一矢報いるべく、我ら東洋人、小澤征爾氏の言葉を頼りに、矢崎氏のタクトの下「好きにやり放題」やって、お客様に喜んでいただきたい。
初 演:1830年12月5日、パリ音楽院のホールにて
楽器編成: フルート(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、バンダオーボエ、クラリネット2、Esクラリネット、ファゴット4、ホルン4、トランペット2、ピストン付コルネット2、トロンボーン3、オフィクレイド(テューバ)2、ティンパニ(奏者4人)、シンバル、大太鼓、小太鼓、鐘、ハープ2、弦五部
主要参考文献
『ベルリオーズ回想録』ベルリオーズ(丹治 恆次郎訳) 白水社1981年
『音楽のグロテスク』ベルリオーズ(森 佳子訳) 青弓社2007年
『小澤征爾さんと、音楽について話をする』 小澤征爾/村上春樹 新潮社2011年
『失敗は、顔だけで十分です。』綾小路きみまろ PHP研究所2006年
ポール・デュカス:バレエ音楽「ラ・ペリ」
『魔法使いの弟子』で有名なポール・デュカス(1865-1935)による『ラ・ペリ』は、ペルシャ神話のペリ(仙女)とイスカンデル(アレキサンダー大王)が、不死の花をめぐって繰り広げる「一幕の舞踊詩」であり、決して叶うことのない〈不死への希求〉と〈女性への恋〉が主題となっている。
デュカスが70年の生涯で残したのは、わずか10数曲。45歳のときに作曲した『ラ・ペリ』は、事実上最後の大作である。音楽批評家としても筆をふるったデュカスは、厳しい自己批判精神の持ち主であり、晩年には70曲余りの未完成曲と未発表曲を破棄している。そんな完璧主義者が、『ラ・ペリ』の作曲に向かうだけでなく、曲を完成させ、公演まで実現させた傍らには、あるバレリーナの存在があった。
ナターシャ・トゥルハノヴァとの約束
「最近作った曲を聴いてくれないか。賭けに負け
て、書くと約束してしまったんだよ。きみに駄作と
言われれば、この譜面も捨ててしまうがね」
1910 ~ 1911年冬のある日、デュカスは音楽批評家のピエール・ラロを訪ねてそう言った。そして聴かせたのが『ラ・ペリ』であり、「約束」の相手というのが、バレリーナのナターシャ・トゥルハノヴァであった。
トゥルハノヴァは1885年キエフ生まれ。モスクワのコンセルヴァトワールの朗読のクラスで3年間首席となるも、喉の病気によりバレエの道へ進む。1907年にパリへ渡り、1911年からはバレエ・リュス(ロシア・バレエ団)の公演に出演する傍ら、独自のバレエ・コンサートを開催しており、デュカスはその初期から協力していた。
美貌と教養を兼ね備えたトゥルハノヴァをデュカスは「大天使」と呼び、彼女のために『ラ・ペリ』を作曲した。その証拠に、楽譜出版社への譲渡契約書には、トゥルハノヴァに5年間の独占権を与える旨が明記されている。デュカスにとって『ラ・ペリ』はトゥルハノヴァと切り離せない曲であった。それゆえ、初演までは困難な道をたどることになる。
実現しなかったバレエ・リュス公演
1909年の旗揚げからパリで一大旋風を巻き起こしていたバレエ・リュス。その興行師セルジュ・ディアギレフと新進のダンサーであったワツラフ・ニジンスキーは、1911年3月に『ラ・ペリ』を聴いて気に入り、同年6月のパリ公演のプログラムに加えることに決めた。
しかし、この計画は契約の段階から難航する。ディアギレフは『ラ・ペリ』を世界中で公演する権利を求め、振付のミハイル・フォーキンはトゥルハノヴァに主役は務まらないと主張したのだ。デュカスがこれを受け入れるはずがない。両者間で条件提示が果てしなく続いた。
結局、レオン・バクストよる衣装デザインの他には何も決まっていない状態で、オーケストラ・リハーサル初日を迎えた。既に本番5日前。舞台袖で待ちくたびれたトゥルハノヴァを見て、デュカスはバレエ・リュス公演での『ラ・ペリ』の初演を撤回する。
トゥルハノヴァ主宰バレエ・コンサートの成功
バレエ・リュスでの不遇から数ヵ月後、デュカスの後押しもあり、トゥルハノヴァは同時代のフランス音楽による自身主演のバレエ・コンサートを企画する。曲目は、ヴァンサン・ダンディ『イスタール』、フローラン・シュミット『サロメの悲劇』、デュカス『ラ・ペリ』、モーリス・ラヴェル『アデライド、または花言葉』(『高雅で感傷的なワルツ』の管弦楽版)。これらを作曲家自身が指揮し、衣装と舞台装置は曲ごとに異なるフランスの美術家が担うという、これまでにない独自の試みである。
年明けから綿密な準備が行われた。演出はジャック・ルーシェ、振付はイヴァン・クリュスティーヌ、衣装と舞台装置はルネ・ピオ、イスカンデル役はアルフレッド・ベケフィ。デュカスの詩と一体となった総合芸術を目指したトゥルハノヴァは、彼らと頻繁に連絡を取り合った。本番3週間前には稽古が開始され、オーケストラ・リハーサルの回数は17回に及んだ。
1912年4月22日、満席のシャトレ座で初演を迎え、2回から4回に増やされた公演の後には連日拍手が鳴りやまず、新聞・雑誌でも絶賛された。4つの演目の前には各作曲家がこの公演のために作曲したファンファーレが演奏されたが、デュカスの輝かしいファンファーレは、今日では本編よりも耳にする機会が多い。
もし『ラ・ペリ』がバレエ・リュスのレパートリーとなっていれば、ファンファーレだけではなく本編も有名になっていたかもしれないが、世俗的な成功を嫌ったデュカスは、そんなことは考えもしないだろう。むしろ、ディアギレフが革新性を求めたのに対し、フランスの伝統を受け継いだ公演を実現させたことに、満足していたのではないだろうか。本日は、バレエ・リュスの輝かしい歴史の陰に隠れながらも、デュカスとトゥルハノヴァが確かに栄光に輝いた、1912年4月22日シャトレ座の夜に思いをはせて演奏したい。
あらすじ:
イスカンデルは、不死の花を求めてイランの地をさまよい歩いている。ついに地の果てにたどり着き、仙女が不死の花を持って眠っているのを見つける。イスカンデルはそっとその花をとるが、仙女は目を覚ましてしまう。イスカンデルは美しい仙女に恋をする。仙女は花を取り戻すために、踊りながら次第にイスカンデルに近づく。顔と顔が触れるほどに近づくと、イスカンデルは惜しむことなく花を返す。仙女は光の中に消える。イスカンデルは闇に包まれ、自分の最期の時が近づいたのを知る。
初 演: 1912年4月22日、パリ、シャトレ座、デュカス指揮、ラムルー管弦楽団
楽器編成: ピッコロ、フルート2、オ-ボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット3、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、トライアングル、タンブリン、小太鼓、木琴、チェレスタ、ハープ2、弦五部
主要参考文献
『最新名曲解説全集 第5巻 管弦楽曲Ⅱ』 音楽之友社 1980年
『ディアギレフ ロシア・バレエ団とその時代(上)』 リチャード・バックル(鈴木 晶訳)リブロポート社 1983年
Simon-Pierre Perret/Marie-Laure Ragot, Paul Dukas ,Fayard, 2007
Helen Julia Minors, La Péri, poème dansé (1911-12):
A Problematic Creative-Collaborative Journey, DanceResearch, Volume 27 Issue 2, Edinburgh University Press, 2009
http://dx.doi.org/10.3366/E0264287509000309
第234回ローテーション
| ラ・ペリ | オケコン | 幻想 | ||||
| Fl | 1 | 吉田 | 1 | 岡田 | 1 | 松下 |
| 2 | 新井 | 2 | 兼子 | 2/Picc. | 吉田 | |
| 3/Picc. | 兼子 | 3 | 松下 | ― | ― | |
| Ob | 1 | 宮内 | 1 | 山口 | 1 | 堀内 |
| 2 | 山口 | 2 | 平戸 | 2 | 平戸 | |
| C.I. | 岩城 | 3/C.I. | 岩城 | C.I. | 岩城 | |
| ― | ― | ― | ― | banda | 宮内 | |
| Cl | 1 | 高梨 | 1/Es | 中島 | 1 | 品田 |
| 2 | 大藪 | 2 | 進藤 | 2 | 末村 | |
| Bass | 岩村 | 3 | 石綿 | Es | 中島 | |
| Fg | 1 | 田川 | 1 | 藤原 | 1 | 浦 |
| 2 | 藤原 | 2 | 田川 | 2 | 笹岡 | |
| 3 | 浦 | 3 | 笹岡 | 3 | 藤原 | |
| ― | ― | ― | ― | 4 | 田川 | |
| Hr | 1 | 山口 | 1 | 箭田 | 1 | 大内 |
| 2 | 箭田 | 2 | 大内 | 2 | 市川 | |
| 3 | 大原 | 3 | 宮田 | 3 | 菊地 | |
| 4 | 宮田 | 4 | 菊地 | 4 | 大原 | |
| ― | ― | 5 | 山口 | ― | ― | |
| ― | ― | 6 | 市川 | ― | ― | |
| Tp | 1 | 小出 | 1 | 小出 | Cor.1 | 野崎 |
| 2 | 北村 | 2 | 中川 | Cor.2 | 中川 | |
| 3 | 青木 | 3 | 野崎 | Tp.1 | 北村 | |
| ― | ― | 4 | 青木 | Tp.2 | 青木 | |
| Tb | 1 | 志村 | 1 | 武田浩 | 1 | 武田香 |
| 2 | 武田浩 | 2 | 武田香 | 2 | 志村 | |
| 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | |
| Tu | 土田 | 土田 | 1 | 土田 | ||
| ― | ― | ― | ― | 2 | 井戸(*) | |
| Timp | 桑形 | 桑形 | 1 | 皆月 | ||
| ― | ― | ― | ― | 2 | 古関 | |
| Perc | シンバル | 桜井 | Ⅰ | (*) | シンバル | 桜井 |
| トライアングル | 鈴木(*) | Ⅱ | 鈴木(*) | 大太鼓1 | 今尾 | |
| 大太鼓 | 古関 | Ⅲ | 今尾 | 大太鼓2 | 鈴木(*) | |
| 小太鼓 | 今尾 | Ⅳ | 古関 | 小太鼓 | 鈴木(*) | |
| タンブリン | (*) | Xylo/Vib/Glsp | 皆月 | 鐘 | 桑形 | |
| 木琴 | 皆月 | ― | ― | 3mov Tim3 | 今尾 | |
| ― | ― | ― | ― | 3mov Tim4 | 桑形 | |
| 鍵盤 | Celesta | 藤井 | Piano | 藤井 | ― | ― |
| ― | ― | Celesta | 井上(*) | ― | ― | |
| Harp | 1 | 篠崎(*) | 篠崎(*) | 1 | 篠崎(*) | |
| 2 | 稲川(*) | ― | ― | 2 | 稲川(*) | |
| Vn | 1 | 堀内(大隈) | 1 | 堀内(大隈) | 1 | 堀内(伊藤真) |
| 2 | 小松(田川) | 2 | 小松(田川) | 2 | 小松(大島) | |
| Va | 村原(柳澤) | 村原(柳澤) | 槇(柳澤) | |||
| Vc | 柳部(安田俊) | 柳部(安田俊) | 柳部(安藤) | |||
| Cb | 中野(上山) | 中野(上山) | 中野(上山) | |||
(*)はエキストラ
飯守先生インタビュー番外編
飯守泰次郎先生とは1993年の初共演以来今回で25回目の定期演奏会となります。インタビュー本編は当日お配りするプログラムでお読みいただきますが、維持会ニュース用に楽しいお話をしていただきました!
~どの国の料理が一番お好きですか?
飯守 何と言ってもイタリア料理です。もちろんフランス料理もすごいんですけど、あまりに良くできていて、手が入っていて完璧過ぎる。イタリアの方が、素材が自然で。日本もそうでしょう、素材の自然さがすごくある。そうすると、イタリア料理がやはり自分には一番合っているような気がするなあ。
~ワインはお好きですか?
飯守 やっぱり好きですよ。ドイツの中だったら当然ビールで、特に暑いときには何と言っても冷たいビールをグーッとね。だけど、やっぱり落ち着いて良い料理の時にはワインですね。料理によって、日本料理の時には日本酒を飲みます。でも僕は、そんなにこれでなくてはいけないとか、そんな難しいことは言わない。お腹が空いていたら何でもいいんです。音楽やっているとね、どこの国の音楽かというのと直結しているのが食べ物とお酒ですね。あと言葉もですけれど。
~料理はなさるんですか?
飯守 僕は料理は全然ダメ。それこそ、すき焼きとか余りものとか・・・。たまに、家ですき焼きを作ります。ドイツに居た頃にすき焼きをやると、肉を薄く切るじゃない?あれがドイツのお肉屋さんはいい気がしないのね。良い肉ほど厚いというのがあちらの考え方で、薄く切るのは彼らにとっては冒涜みたい。肉屋さんに頭下げて、すき焼きをやっていました。
~スキーは今も滑られますか?
飯守 今時間がなくなって。数年前に脱臼骨折やってからも、それからまた返り咲きして。スキーを始めたのは学生時代で、その後20年ぶりに再開したのだけれど、自転車と同じで体が覚えていて滑れたのです。
~ヨーロッパでも滑っていらしたんですか?
飯守 滑りました。スイスが一番いいですね。雪の質が良いし、スキー場の規模が違う。普通ここがスキー場ですって柵や紐があるのに、それがない。だから、大体の地形でわかる。注意しないと、気が付いたら人の庭に出たり、崖にも注意とか立ち入り禁止とか、書いてないんだ。
~他にスポーツは何かされますか?
飯守 あとは健康のために泳ぐ。スポーツジムに行っていますが、今は時間みつけるのが大変。あとは、もうただ歩く。30分しか時間ないっていう時は歩く。1時間とか。1万歩ってなかなか歩けないんだよ。で、やっぱり6,000歩くらい。
~本番を振ると体重減るのですか?
飯守 ああ、減る!減りますよ。1kgは絶対減る。曲にもよって、ワーグナーだったら2kg。一種の脱水状態だ。そのあとガブガブ飲む。
~猫を抱いた写真を拝見しましたが?
飯守 ずっと居たんですけどね、今は居ない。黒猫で尻尾が長いというのが好きでね。もちろん、トラ猫でも三毛猫でもいいんですよ。僕が小学生の頃は家に12匹いました。というのは、6匹居たうちの1匹が黒猫で、それが6匹子供を産んで倍になって。海外でもずっとじゃないけれど飼っていました。やっぱり猫って居ないとさびしいです。
~やはり猫派ですか?
飯守 絶対猫ですね。ただ、昔子供の頃に2匹家に犬が居たことがあります。最初の犬はまだ満州にいた頃、いきなり居なくなって、どうも中国人に盗まれたらしい。もう一匹は中学校時代、車に轢かれてしまって。
~猫のどういったところがお好きなんでしょうか?
飯守 自由なところでしょうか。生まれ変わったら何になるかと言われたら、僕はやっぱり猫かなと。寝たいときに寝て、食べたいときに食べて、かわいがって欲しい時にかわいがられて、十分になったらスッと居なくなるという。犬はそうはいかないでしょう。忠誠を尽くさないといけないから。もう一つまったく違うんだけど、渡り鳥になりたい。行きたいところに行ける。旅が何千キロと出来るというのは、すばらしい。コースは決まっているんでしょうけどね。しかし、渡り鳥の身の危険というのはすごいらしいから。猫だって野良猫は大変ですよね。野良猫の一生は厳しいと思うので、飼い猫の方がいいですね。勝手なもんでしょう?
~学生時代に副科でホルンを吹いていたのですよね。
飯守 僕はホルンの音がものすごく好きでね。やっぱりオーケストラの音を変えるのはオーボエとホルンだと思うんですが、ホルンが一番影響力が強いと思う。学校で指揮の勉強をしていると、指揮のトレーニングはもちろん、オーケストラの中に入って指揮者と向かって自分が演奏することがどんなに大事か。それで、何か楽器をやるように齋藤先生に言われていたんです。そうすると、学校のオケで不足している楽器が一番良い訳ですよ。ちょっと下手でもすぐ入れる。その時に足りなかったのは、コントラバス、ファゴット、ホルン。どれにするかと言われたら、コントラバスは大き過ぎる、ファゴットは重い、それでホルンなら一番軽いなと思って。
~どのような楽器を使っていたのですか?
飯守 アメリカの、メーカーは忘れてしまいました。それで、エロイカの2番ホルンを吹いてね。あの3楽章の・・・。本番は何とかなったけれど、それはそれは大変だった。楽器を潰してしまったことがあって。当時柔らかいケースが流行っていたんですよ。危険なんですけど。楽器を持ってラッシュアワーの電車に乗ったときに、ドアが開いて人がなだれ込んできて、楽器が飛ばされた。それで探していたら、誰かが下を見ていているわけ。その人が潰しちゃったというか、ラッパが曲がっちゃった。それで、直したけれど一度歪んじゃったものは元には戻らない。
~弦楽器はやられなかったんですか?
飯守 ヴァイオリンをやっていたんだけど、あまり長くはやらなかった。というのは、うちは家族が皆音楽をやっていて、兄がヴァイオリン、姉がピアノ、もう一人の姉がフルート。始めたんだけど、まだ子供だったでしょ?1/8のヴァイオリンを弾くと、ものすごく安っぽい音がする。あのヴァイオリンの音じゃない。兄貴は1/2だと立派な音で、ビブラートをかける。僕はちょっと間違えれば音程が気になる。そして兄貴のヴァイオリンにやきもちを焼いて、だったら自分はピアノをやるんだと。ピアノは音程が決まっているから。ピアノに変わって良かった面もあるけれど、やっぱり一緒にヴァイオリンもやっておけば、もっと良かったなあと。留学した時にもう一回ヴァイオリンをやったんだけど、二十歳過ぎてヴァイオリンというと、ちょっと遅いね。
~絶対音感はピアノでついたのですか?
飯守 それは関係あるんですかね。確かにピアノを3歳か4歳の頃、立って弾いていたんだけど、そうやっているうちに、見えないけれど黒鍵と白鍵の違いが分かって、それで家族が、この子は絶対音感があると。だから訓練されたわけではないけど、遊んでいて黒い鍵盤、白い鍵盤という感覚で身についたようです。
音楽は強要されたことがないから。桐朋学園の音楽教室に入ると、それは競争は激しいし。僕はその競争が嫌いで遊びたくて。そういう意味では、高校も普通の学校に行って普通の社会人になりたいと思っていて、音楽家はどこか欠けていると(笑)。だけど結局、どこの高校も受験地獄で大変で、これはやっぱりちょっと適わないなと。で、先生にも音楽をやりなさいと言われて。だから優柔不断で、やはり音楽しかなかった。
~音楽の道に進むと決意されたのはその頃ですか?
飯守 やっぱりそうですね。大好きだからずっとやっていたかったけど、本職には絶対なりたくなかった(笑)。一応ピアノ科に入って、そうしたら齋藤先生に、君は絶対音感がある、初見が上手いと。あの先生は指揮者をハントしていた訳です。指揮者とピアニストがやっぱり一番良いコンビネーションだと思います。
レパートリーが多いということは、凄く魅力だった。ピアノだったらピアノの曲、アンサンブル。指揮であればそれこそもう、交響曲から序曲から、宗教曲、ミサ曲、コンチェルト…なんでもある。指揮者になる人っていうのは色んな動機があるけれど、僕は指揮台に立ちたいっていうよりも、音楽とかレパートリーが好きだった。
~自分で音を出せないもどかしさはありますか?
飯守 それね!それはもどかしい。それが一番、それが今も付きまとっている。自分で音を出すのだったら自業自得ですよねぇ。
2016年2月21日
まとめ:大原久子(ホルン)
第234回演奏会のご案内
創立60周年シリーズ第3弾
新交響楽団は、創立以来アマチュアオーケストラとしての可能性を追求し活動をしてきました。2013年からはパリを拠点に活躍する矢崎彦太郎を指揮に迎え、フランス音楽にも積極的に取り組んでおります。矢崎との4回目の共演となる今回は、フランス交響曲の金字塔ともいえるベルリオーズの幻想交響曲に挑みます。
近代管弦楽法の父ベルリオーズ
幻想交響曲が作曲されたのは1830年、ベートーヴェンの第九交響曲とほぼ同時期、ブラームスはまだ生まれてもいない時です。交響曲が絶対音楽であった時代に各楽章に標題がついた物語になっていること、それまで使われたことのないコール・アングレやE♭クラリネットなどの特殊楽器を含み、ハープ2台、ティンパニ奏者2人(一部は4人)という大編成で、当時は極めて斬新な作品だったのです。ドイツやロシアの大作曲家たちにも多大な影響を与えました。200年近く前の最先端の曲ですが、ドラマチックでわかりやすく、あまりクラシックに馴染みのない方でも楽しめる曲です。
ベルリオーズは開業医の息子で医学部に進学しましたが、解剖学で挫折して音楽の道へ進みます。23歳の時にシェイクスピア劇団の主演女優に片思いし、その体験を基に書かれたのが幻想交響曲です。作曲者自身の解説を要約すると「病的な感受性と激しい想像力を持った若い芸術家が、恋の悩みから絶望して阿片自殺を図るが、服用量が少なすぎて死に至らず、奇妙な一連の幻想を見る」とあり、失恋して恋人を殺し死刑になり自分の葬式に悪魔や魔女が踊る、でもそれは夢の中というお話なのですが、その後ピアニストと恋をし婚約したのに別の男と結婚されて、相手を殺して自分も自殺しようと企てますが未遂に終わります。この感受性と情熱が名曲を生んだのでしょう。
日本の正統派作曲家 三善 晃
三善は高校生の頃に作曲を志し、東京大学仏文科在学中にフランスに渡りパリ音楽院で作曲を学びました。その後は数々の賞を受賞し積極的な創作活動を行う一方、桐朋学園では長く学長を務めるなど教育者としても活躍しました。多くの合唱曲を残し管弦楽作品が吹奏楽に編曲されるなど、作品は広い分野で親しまれています。
今回演奏する「管弦楽のための協奏曲」の総譜には、自身の言葉で「この作品までは、内的な秩序に手がかりを得ていた音の追及を、はじめて、外的存在としての音と内的秩序の接点に求めてみたものです。」とあり、シェーンベルクの影響をうかがわせる意欲作です。
10年前の新響創立50周年で指揮の故小松一彦氏と「交響三章」を演奏しましたが、次は「管弦楽のための協奏曲」をという約束をようやく果たせます。精緻で端正な三善作品は、ある意味難解な現代音楽かもしれませんが、カッコよくて美しい、曲の持つエネルギーを楽しんでいただければと思います。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
小説『仮装集団』と新交響楽団=虚構と現実のはざま=
仮装集団と聞くと、昨今は11月あたりの渋谷の鬱陶しい雑踏風景を思い浮かべる向きも多かろうと想像するが、これは先年亡くなった山崎豊子氏の小説の題名である。この作家といえば『白い巨塔』をはじめ『大地の子』『不毛地帯』『二つの祖国』『沈まぬ太陽』などドラマや映画になった作品がまず出てこよう。或いは大阪の船場の商家を舞台とした『暖簾』『ぼんち』『女系家族』などの初期作品を愛好する人も多い。だが『仮装集団』の名を挙げる人はなかなか無い。この小説は作家が社会派小説を手がけるステップとなった重要な作品ながら、知名度も低く例外的に映像化もされていない。それは音楽を隠れ蓑にした、特異な実在組織をテーマとした異色の作品となっているからであろう。
主人公は流郷正之(りゅうごう・まさゆき)という35歳の男。大阪の勤労者音楽同盟(勤音)で演奏会企画を担当している。この勤音が発足したのが昭和20年の終戦から6年目、小説の舞台はその7年後に設定されているから昭和33(1958)年頃で、現実の世界では新響が「東京労音新交響楽団」して発足した直後の時期という事になる。著者はこの小説はフィクションであり、作中の「勤音」は実在する労音(勤労者音楽協議会)とは無関係であることを強調してはいる。が、作品に描かれるこの組織の描写を見れば、労音をモデルとしている事は衆目の一致する処だ。つまりこの小説は新響創立当時の出身母体たる労音内部の政治的状況の変容を描いているという点で、極めて興味深い作品なのである。
僕自身はこの小説を30年以上前、新響入団直後に読んだ。出版社にいる大学時代の友人に、新響に入った事と、この団体が過去に労音との関わりがあった事を話すと「ああ山崎豊子の『仮想集団』だね」といきなり切り出されたのだった。彼は在学中に僕の影響を受け(これは極めて珍しいが事実である)、音楽愛好家となった博覧強記の畏友だが、思わぬ所から労音に関連する文学作品の情報を得た事になる。やはり持つべき友は選ばねばいけない。
小説は、流郷が企画した『蝶々夫人』のステージ場面から始まる。クラシック音楽とは本来縁遠い勤労者をも対象とするだけに歌舞伎の要素を演出に採り入れる。鑑賞する側の理解と共感を得て、アンケート調査の結果も良好。勤音への入会者は一気に増大して成功裡に終わったかに見える。
だか、こうした企画とその演奏会の真の成否の評価は後日開催される「運営委員会」による批評会に委ねられるのである。この運営委員会を構成するのは各企業や業界の労働組合の代表者。するとそこで展開される「批評」というものもひと味違ってくるのである。
例えばこんな発言がされる。
「今度のオペラは、アメリカやヨーロッパで上演された「蝶々夫人」の流れを汲む単なる恋愛形式のもので終わっている。我々の意図する「蝶々夫人」はそんなものではない。例えば第一幕でピンカートンが蝶々さんと結婚するその日、「未来の妻はアメリカ女性」と唄うところがあるが、あれなど、日本女性に対する人格無視も甚だしく、明らかにアメリカ帝国主義者の被圧迫民族に対する優越的な態度というべきでこういった彼らの思い上がった優越意識は、日本人に影響のある水域で水爆実験をする時の行動、つまりわれわれをモルモット視している意識に共通するものがある!」
最初にこの部分を読んだとき、苦笑失笑あい混じった笑いを禁じ得なかった。いくら何でもこれはこの団体の特異さを示す為に、作家が敢えてした誇張だろうと考えてようやく納得した覚えがある。そしてそのまま長く忘れていた。
さて、前回の第232回演奏会のプログラムに掲載された座談会『新響のルーツを探る』は、新響の発足当初から労音から独立する前後の状況に関する当事者の貴重な証言を収めており、個人的には極めて興味深かった。『仮想集団』に描かれた内容は決して虚構ではなかったのだという驚きと感慨を抱くに充分だったのだ。今回本稿を起こすに当たり小説を再読中、前述の発言箇所から座談会の一節が思い起こされた。労音からの独立=新響創立~独立当時、長く運営委員長を務められた戸田昌廣氏の次の談話である。
私は労音の会員になっていたけれど、組織の中にいても分からなかった。最初に違和感を抱いたのは、ベートーヴェンの第9を東京労音合唱団と一緒に演奏した時かな。その時にまったくピントはずれなことを言ってきたのです。たとえば「芥川也寸志は自分のテンポで振っているけど、こちらは労働者のアマチュアだからテンポなどは話し合って決めてもらいたい」とか。オーケストラではそんな事は考えられないよね。
音楽作品のテンポを話し合って決める?荒唐無稽な話である。だがこの荒唐無稽な事実を知り、初めて例の作中発言に作家の誇張でも戯画化でもないリアリティが感じられた。『仮装集団』を読み進むと、戸田氏の語られたこの事実が更に深い意味を持っていた事は後述する。
いずれにせよ共通するのは音楽の、そして芸術精神の不在だ。演奏の良し悪しなど関係ない。あるのは特定の政治思想教化の手段として、作品が有益か否かの価値判断だけだ。
だがそうした中で、学生時代以来の音楽愛好の延長線で勤音に入った流郷正之は、自分のヴィジョンに基づいて企画した演奏会の成功のほかに関心を向けない。彼はひとりこうした議論を冷めた目で見やりつつ、次なる企画への野心を育てる。そしてショスタコーヴィチの『森の歌』を取上げてその実施に向けて動き出す。
米国を帝国主義と非難する団体なのだから、ソ連建国の讃歌たる『森の歌』の上演は結構ずくめにも思われるが、決してそうではない。勤音では例の運営委員会の承認を要するのだが、
「今度の『森の歌』を決める時、運営委員会で、『森の歌』は、ショスタコビッチがプロコフィエフやハチャトリアンなどと一緒にソ同盟共産党中央委員会から、資本主義文化の影響を受けて音楽の社会的使命を忘却したと批判される前の作品か、以後の作品であるかを問題にし、ショスタコビッチが中央委員会の批判を受け入れた後の作品だというので、取り上げることになったそうじゃあないですか」
と、勤音会員の会話によってこの選曲の内部事情が説明されている。しかもこの曲はスターリン死後批判が起こると、彼への礼讃部分の歌詞が変更されたシロモノだ。思想が絡むとこうした音楽不在の論議が必ずつきまとう。
わが新交響楽団の選曲は合同委員会で検討されるが、例えば昨年春に演奏した橋本國彦氏の交響曲第2番を決める議論の過程で、「橋本國彦の交響曲第1番は皇紀2600年を奉祝する目的で作曲された作品であり、天皇制を無批判的に肯定し、ひいては軍国主義讚美につながるものである。新響として取り上げるべきではない。橋本が戦後公職を追われ、戦争協力を自己批判した後に書かれた第2番こそが不偏不党・平和主義?を標榜する新響の演奏対象にふさわしい」との意見が大真面目に呈示されたとすれば失笑を買うだけだろう。幸いこうした意見は無く(あたりまえ)、第1番も新響は20年前の創立40周年の折りに演奏している(曲折はあったが)。自由な選曲・・・・この当たり前の事が出来ない窮屈さは、現在では想像しがたい。
勤音会員を合唱団に動員した日本語訳による『森の歌』の上演(因みに実在の大坂労音は1954年8月に労音会員の合唱団によって上演している)は大きな反響を呼び、会員数は更に増大。流郷の組織に於ける評価も高まり、やがて企画責任者の地位を得る。だがこの上演を分水嶺として次第に彼を取巻く内外の状況に変化が進行してゆく。
外部の変化は、こうした盛り上がりをみせる勤音の活動に危惧を覚えた財界の動きである。娯楽に乏しい戦後の時期、社員の余暇管理目的で各企業が設置援助している社員の合唱サークルが、この『森の歌』に参加して「ソ連建国万歳、レーニン万歳」を歌い上げる事を放置していられる訳がない。作中では日東レーヨン社長門林雷太(もんばやし・らいた)が、大阪の財界に提唱して労音に対抗する組織結成を図る。当時繊維は花形産業だ。その業界大手の社長ともなれば財界への影響力も大きかろう。
実在の団体として「音楽文化協会(音協)=1963年4月設立=」がこれに該当するが、設立はこの小説の舞台よりもう少し後だ。だが作中では豊富な資金力にあかせて一流演奏家を招聘し、硬軟合わせたプログラムを低廉な会費で提供。短期間のうちに勤音と熾烈な競争を繰広げる存在に成長するのである。これは目に見える敵だ。流郷は対抗すべく、勤音内部の様々な抵抗や制約を受けながらも、ヒロインを勤音会員から公募するアイディアを打ち立てて、「創作ミュージカル」の実行に奔走する。
勤音内部にも変化が兆し始めていた。全国組織結成を期に政治色が急速に濃厚となる。勤音の顧問となった文化人を参院選に推そうとする処から始まって、「人民党」の支配が強まり尖鋭化してゆくのである。そしてこの党の路線を反映する形でソ連から中共(中華人民共和国)への傾斜が明白になってゆく。
流郷が提案した勤音の創作ミュージカルを決定する委員会でも党の息のかかった幹部から、
「勤音のミュージカルは、会員の主体性を生かすところに最も大きな意味がある、その意味で現代の中国が一つの歌舞劇を作るのに、一人の作家、一人の作曲家に任せきりではなく、大衆討議にかけて、大衆が納得するまで何度も修正しながら完全して行くという創造方法を、われわれも学ぶべきだと思う」
との発言が出る。前述の「『第九』のテンポは話合いによって決めてもらいたい」という労音合唱団員の声と軌を一にしている。またシナリオ作家の人選では「~のような修正主義者では会員は承知しない」という声が上がる。
だが流郷は演奏会にかける企画として目ぼしいもののない中国歌舞団や、人民党の影響下にある日本の民俗芸能集団の公演案を歯牙にもかけない(実際これは失敗する)。結果、組織内の中ソ対立の図式の中では「親ソ」とみなされてしまうのである。更に彼はソ連の著名なヴァイオリニストを招聘して苦心の末コンサートを挙行する。これが彼にとって致命傷となった。
この様な組織内部の路線の変化については、当時の新響の立ち位置を含めた労音の実態として、前述の戸田氏が座談会冒頭で簡潔・的確な説明をされている。
当時のソ連(ソヴィエト社会主義共和国連邦)はスターリンからフルシチョフの時代になり、スターリン批判を行って平和共存へと路線変更をしたんです。それが原因で平和共存路線を受け入れられない中国とソ連が喧嘩をはじめました。当時の中国はソ連のことを「修正主義」と呼び、ソ連は中国共産党のことを「教条主義」と呼んで、互いに非難し合っていました。一方日本の共産党は中国寄りで、社会党はソ連寄りでした。・・・・(中略)・・・・労音の中では共産党が勢力を握っていたので、新響はまさに共産党の文化サークルだったのです。
このように現実の労音は日本共産党の支配が強まり、親中共への転換が進行しつつあった。小説の中で描かれる、勤音から人民党に資金が密かに流され、組織が急速に党に侵食されてゆく不気味な動きは、中ソの国家間対立に端を発する代理戦争が、末端の組織にまで浸透していた顕れという事になる。
こうした末に行われた勤音の運営委員選挙では親中共派が多数派となって実権を握り、流郷が手がけていたソ連関連のプログラムは全て中止となるに至る。
勤音の人民党による支配が明確となった情報を得て、音連の後援者たる関西の財界関係者が会合をもつ。その席上、膨大な信徒を擁す、さる宗教団体も更なる信徒獲得の為に音楽鑑賞団体を設立する計画が話題に出る。それを聞いて門林は言う。
「なるほど、そうすると、音連も勤音も、新しく出来る宗教音楽協会も、みんな音楽以外の目的のために音楽鑑賞団体をつくって人集めをしているわけで、これからは三つ巴の乱戦というわけやな」
この第三の団体は現実には創価学会が母体となった「民主音楽協会(民音)=1963年10月設立=」なのだが、考えるべきは「音楽以外の目的のために」みなが団体を拵えているという門林の本音であろう。その目的は三者三様だが、音楽はその目的に至る手段に過ぎない事が、ここで明白になる。
音楽を愛好する。それだけが流郷の原動力だった。が、この組織内でそれを純粋に保つ事は最早出来ない。全てが政治的に色分けされてしまい、否応なくその奔流の中に身を投じざるを得なくなる。これは労音に於ける芥川氏の場合も同様だったと言えまいか。戸田氏のお話、
芥川先生が共産党ではない方向へと動き出しはじめたのです。上野の東京文化会館に練習場が移ってからすぐの頃、芥川先生は長期間アメリカへミュージカルの勉強をしに行き、「南太平洋」や「回転木馬」などの楽譜を持ち帰って来ました。帰国後に労音の事務局へ行ったら「なんだ、アメリカかぶれして」と、とても批判的な言葉を聞き、えっ、と驚きました。労音の中ではだんだんと芥川也寸志が邪魔になってきて、何とか彼を労音から追い出す手はないかと思い始めたようでした。
芥川氏の姿は流郷と重なる。芥川氏が変わったのではない。労音が変わったのだ。組織の目的が変わり、その手段としての音楽が、変質を求められたからに他ならない。「共産党の文化サークル」たる存在だった新響にも決断の時が来る。
労音をとるか、独立して自力でやっていくか。その結果、自分から飛び出すのはやめよう、ぎりぎりまで待とうということになりました。結果的に1966年3月に追い出されるという形で独立したのです。
流郷も突然左遷され、事実上勤音を追われる。委員会への出席状況の悪さ、東京への頻繁な未承認出張と経費の多さ、勤音主催の創作ミュージカルの公募ヒロインに手を付けた事(おいおい)、そしてライヴァルたる流郷を音連へスカウトしたい門林社長との面談(密談だが漏れていた。門林が故意にリークしたとの憶測も可能だろう)・・・・現在でも仕事は出来るが協調性のない一匹狼的なサラリーマンがはまりがちな陥穽だが、こうした理由は日頃大仰な理論を振りかざす集団からすれば取るに足らぬ矮小なものばかり。が、殊更に政治的信条を持たぬ流郷に対してはこれで充分だった。余りに呆気ない突然の解任である。
山崎豊子氏は『白い巨塔』を書くための取材に取りかかるまで、大学の医学部が6年制である事さえ知らなかったという、まことしやかな逸話をどこかで聞いた事がある。文字通り一からの緻密な取材によって巨大な作品に仕上げて行く作家だが、その人にして、『仮装集団』は書きにくい小説だった事を「あとがき」で述懐している。労音側も音協サイドも、ある時期から取材に応じなくなった為であるという。それは音楽鑑賞団体を装いながらも、真の目的を他に秘めた組織の性格が、作家の旺盛な取材力により白日の下に暴かれる事への警戒の顕れに感じられる。
山崎氏の取材資料の中には新響の労音離脱の記事も含まれていた。小説執筆の時期とは合致しないが、執筆の途上、芥川氏にも取材の手が伸び、作中の流郷の姿に反映されているのではないか?この想像に無理はないだろう。
この小説から改めて痛感するのは、音楽という芸術が持つ「危うさ」である。個々の音は本来何ものをも表現し得ず、且つそれ自体には何の意味もない。それを編み上げてひとつの作品に仕上げ、意味あるものとする。我々はそれを聴いて創作者の意図に従って理解する。だが理解の対象となるその意図は他の媒体に比べ遥かに伝達の力は脆弱と言わざるを得ない。それは操る人々の思惑が介在する余地となり、様々な「仮装」の道具として利用されてしまう宿命を負っている。
『仮装集団』が書かれたのが1965年。新響労音離脱の前年である。新響の独立は、労音という組織の政治色を社会に認知させるひとつの象徴となったが、労音以外の団体設立がそれ以前である事を思えば、既にこの組織の過度な政治色は鮮明となっており、利害に障る組織に危機感が醸成させていた。新響の独立はその流れの行き着いた最後ともいうべき時期に当たる。まさにぎりぎりだが、英断・勇断だったと言える。
それから半世紀の間にソ連は崩壊し、中国は資本主義経済を部分的に導入して米国並みの格差社会に変貌している。この政治情勢の変化によって労音もあり方の変更を迫られ、それに伴って他団体の様相も変容した。
だが今もどこかで音楽が仮装の手段として利用され続けている事だけは間違いない。そして「オーケストラ」という形をもつ集団さえ、いつの間にか音楽を仮装手段としないとも限らない事を、我々は常に銘記すべきなのだろうと思う。
創立60周年特別インタビュー飯守泰次郎氏にきく
飯守先生は1993年4月の初共演から数えて23年の長きにわたり、新響をご指導くださいました。今回の演奏会は2年ぶりの共演となります。2014年からは新国立劇場のオペラ芸術監督に就任されご多忙を極める中、これまでの新響との思い出や今回の演目について、また指揮者とオーケストラの関係など、大いに語っていただきました。
■これまでの23年を振り返って
~飯守先生とのおつきあいは長く自主演奏会では24回、そのほかにも芥川先生没後10年の時には埼玉県松まつぶしまち伏町の田園ホール・エローラや上野の奏楽堂など、芥川先生ゆかりのホールで、振っていただきました。
飯守 芥川作品のCD録音もありましたね。
新響とのプログラムはやはりドイツ・ロマン派が多いですが、時々ドビュッシーやサン=サーンスなどのフランス物や、スクリャービンも取り上げました。ヴィラ=ロボスの「ブラジル風バッハ第7番」は素晴らしかったですね。
~その時、その時代を反映したプログラムになっていると思います。先生との最初の演奏会は1993年、曲目は「ローエングリン」第一幕への前奏曲、「タンホイザー」序曲、ブルックナーの交響曲第4番でしたね。
飯守 驚きましたよ。こんなに優秀なアマチュア・オーケストラが世の中に存在するのかと。それまで私はアマチュアを指揮したことはあまり無かったのです。大学のオケを振ったことはあったのですが。しかも新響はその後もさらに立派に発展していきました。
~当時は海外にいらっしゃったのですよね。
飯守 まだオランダにいて、日本と行ったり来たりしていました。国内の仕事の日程調整がどうにも難しくなり、帰国したのが1997年です。
~あらためて振り返ると新響の節目、例えば創立40周年や50周年など我々の記憶に残る演奏会には必ず先生がいらして、気がついたら今年で創立60周年。特にワーグナーとブルックナーは何度も取り上げていますが。
飯守 ワーグナーとブルックナー、そしてブラームスが多いですね。ワーグナーから始めたのは、1972年に二期会で私が「ワルキューレ」の日本人初演を指揮し、高い評価をいただいたのがきっかけかもしれません。それまで私はずっとヨーロッパに行ったきりで、日本ではあまり知られていなかったのです。「ワルキューレ」以降、日本でワーグナーを依頼されるようになりました。
だから新響との初共演も、そのご縁だと思います。でもオペラの経験のない新響がワーグナーをいきなり始めるのは難しいから、同じ後期ロマン派で響きが共通しているブルックナーも取り上げましょうとか、そんな話の流れになったのだと思います。ブルックナーならまず4番から、ということでしょうか。意外にもその次にいきなり8番に挑戦しましたね(笑)。それ以来、新響には非常に良い印象があります。
~今までを振り返ってみて、先生が特に思い出に残る演奏会はありますか。
飯守 やはり、オール芥川プログラム(第166回演奏会「芥川也寸志没後10年」)ですね。特にサントリーホールでのアンコールで「赤穂浪士」を演奏し始めた時、もうそこに明らかに芥川先生がいらっしゃるという気配に圧倒されました。これ以上私が棒を振る必要はない、でも曲の途中でいなくなるわけにもいかず指揮台でほとんど指揮をしないで、新響の演奏に聴き入っていたことが思い出されます。それから「ワルキューレ」第1幕全曲(第151回演奏会・創立40周年記念シリーズ1)や、「トリスタンとイゾルデ」(第195回演奏会・創立50周年シリーズ・4)ですね。ともに忘れ得ない名演でした。
~ワーグナーの思い出として最初に浮かぶのは、とにかく音程が大変だったことです。
飯守 私も「トリスタンとイゾルデ」の時は、ゲネプロまで頭を抱えたことは覚えています。でも本番は非常に良かった。なぜ本番まで集中できなかったのか、それが今もまったく分からないのです(笑)。とにかく本番が素晴らしい演奏でした。奇跡が起きたのですね。
■別宮貞雄の思い出
~今日の初練習での別宮貞雄「管弦楽のための二つの祈り」第2楽章冒頭で、先生が一言おっしゃっただけで今までとはまったく違う音がしたので驚きました。別宮先生にお目にかかったことはありますか。
飯守 別宮先生はよく存じ上げています。あの方はとても感覚的で情感が豊かで、年を重ねてさらに自然体になられたように思います。この「二つの祈り」は、若い頃の作品だからかもしれませんが、一生懸命作ったという感じがしますね。
~「二つの祈り」を芥川先生の指揮で演奏した時、別宮先生はしょっちゅう練習に来てくださいました。あと新響の演奏会もよく聴きに来てくださった。大柄でしたが、あまり自分からお話しされるような方ではなかったですね。
飯守 「二つの祈り」は別宮先生の作品の中では構成を重視した曲だと思います。第1楽章は彼らしい情感が溢れていますが、第2楽章は努力して書いた印象を受けますね。「二つの祈り」は、別宮先生のやや理屈っぽい一面かもしれません。後期になるとロマンティックな作風に変わっていきます。もうひとつ特に別宮先生らしいところといえば、作品の中に必ず三和音が存在することでしょうか。
演奏する側が、どれだけ別宮作品らしい感覚的な面を表現できるかが課題だと思います。
~単なる堅い曲にならないようにしないといけませんね。アクセントなどもそこに書いてあるから強く演奏するのではなく、感覚で必要性を感じなければと今日の練習で思いました。
飯守 まさにその通りです。
■マーラーの音楽の内容と心の奥底に迫る
~先生とマーラーの交響作品を取り上げるのは、5番、大地の歌、1番に続いて4回目です。マーラーを演奏する上で、どのようなアプローチをしていけばよいでしょうか。
飯守 やはりマーラーという人間のパーソナルな特徴を掴むことが不可欠です。
ワーグナーやブルックナーなどを演奏する時は、彼らの残した曲を立派に作り上げたいと考えますが、マーラーの場合は、作品の背後にある心理学的な内容を表現したいと思っています。そうでないとマーラーらしくならず、ただ難しいだけの曲で終ってしまいます。その意味ではワーグナーの方が、楽譜をすべて忠実に指定どおり演奏すれば、作曲家の意図した表現が実現できるように書かれています。それが、ワーグナーの書き方の素晴らしいところなのです。
~演奏すること自体がとても難しいですけどね。
飯守 もちろんワーグナーもマーラーも、極めて高い演奏技術が求められるのは当然のことです。特にマーラーはウィーンで、いつも楽員や劇場と衝突していて、この先は私の勝手な想像ですが、彼の作品の中にはオーケストラの特定の楽員を思い浮かべて、その奏者が吹けそうにない難しいパッセージを書いた部分があるのでは、と思えて仕方がない部分があるのです(笑)。トロンボーンやホルン、トランペットなど、奏者にとっては大変な技術的要求がありますね。
話を戻すと、ワーグナーは音楽が人間の心に与える影響を知り尽くしていました。調性と和音(ハーモニー)、上行や下行や跳躍といった音型、オーケストレーションなど、ドイツ音楽の法則を見事に駆使して、聴く人の心を操作するのです。たとえば「ワルキューレの騎行」を聴けば天馬に乗って空を飛び回っているような気分になるし、「ジークフリートの葬送行進曲」なら誰が聴いても葬送の情景が目に浮かぶわけです。
~かたやマーラーの場合は、楽譜どおりに演奏できたとしてもだめだということですね。
飯守 そうなのです。大変優れた指揮者でもあった彼は、楽譜にこと細かに指示を書いていますが、それをきちんとやるだけでは足りないのです。昨今、どこのオーケストラも競うようにマーラーを取り上げますし、見事な演奏はたくさんあります。マーラーのスコアを正確に演奏すればサウンドだけは立派に鳴るのです。しかしそれでは、彼の音楽の内容や心の奥底を表現するには至らないのです。
同じ後期ロマン派の作曲家であるブルックナーも、立派な演奏はたくさんあります。しかし、教会のオルガニストを長く務め、信仰が極めて厚かったブルックナーの音楽の本質的な部分である宗教性の表現が、欠落していることが多いと思います。たとえばブルックナーにはアーメン終止(注)がよく出てくるのも、教会(カテドラル)の巨大な空間を思わせるのも、彼の音楽の宗教性であって、その理解なしにスコア通りサウンドだけ鳴らしてもブルックナーにはなりません。
話がそれますが、交響曲の歴史がハイドン、モーツァルトから始まった頃は、古典的な精神に基づく純粋音楽、つまり音楽それのみで成り立つ純粋で抽象的な音楽でした。そこに、やがてはワーグナーに至る劇的な要素を持ち込んだのは、やはりベートーヴェンです。あくまで私個人の考えですが、極端にいえばベートーヴェンが音楽に最初の「毒」を持ち込んだのです。交響曲第3番「英雄(エロイカ)」冒頭の2発の和音が、私には「ハイドン!」「モーツァルト!」と聴こえることがあります。この2つの和音は、それまでの交響曲の概念をすべて覆した、ベートーヴェンによる歴史な変革だと思うのです。
交響曲の世界から逸脱して劇音楽の方に進んだ後期ロマン派の頂点がワーグナーです。対照的に、同じ後期ロマン派で、響きにおいてはワーグナーと大変共通性のあるブルックナーは、古典派からシューベルトを経由した純粋音楽の最後の作曲家だと思います。
マーラーはブルックナーの弟子で、師と同様に交響曲を書き続けましたが、表現は極めて劇的で、音楽の内容も徹頭徹尾、心理学的な方向を追求し、人間の病的な心理の奥まで到達しています。指揮者で精神科医でもあったシノーポリが指摘していることですが、そもそもマーラーの音楽の形式と内容に大きな矛盾があるのです。あまりに心理学的で緻密な内容を交響曲の形式に無理して詰め込んだので、「もはやマーラーにおけるソナタ形式は残骸に過ぎない」というシノーポリの指摘は非常に的を射ています。また、アドルノは「ソナタなどの音楽形式は本来は内容を増幅し助けるものだが、マーラーの場合は、形式と内容の矛盾のために、しばしば爆発的な破綻を来たす」といいます。マーラーの音楽によく出てくる、唐突と思われるくらいの急激な変化は、まさに西洋音楽の伝統的な形式が破綻して起きた爆発であり、そこにマーラーの難しさがあるのです。
~マーラーは表現しにくいということですか。
飯守 そうですね。若い頃「子供の不思議な角笛」などのオーケストラ歌曲を多く書いていて、本質的には歌曲の作曲家でありながら、どうしても交響曲を作曲すべきだと考えたことは、彼の大きな矛盾です。
非常に大切なことは、マーラーは数多くの重大な矛盾を抱えた作曲家であるということです。彼は、ボヘミア生まれのユダヤ人で、ドイツ語を話す、ここにすでに矛盾があります。そしてウィーン宮廷歌劇場(現在のウィーン国立歌劇場)の総監督のポストを手に入れるために、ユダヤ人でありながらキリスト教に改宗しました。さらに、非凡な指揮者としてのキャリアと作曲家としての創作の間で苦しみました。時代に先駆けて音楽の歴史を変えてやろうという強い意志やポストへの野心の一方で、子供のように純粋で過敏ともいえる感性を持ち続けました。散歩を好みいつも自然を渇望しながら、キャリアのために大都会ウィーンに身を置かなければなりませんでした。彼の生涯は矛盾に満ちているのです。
~そういったマーラーの矛盾を演奏に出していくということが重要ですね。
飯守 そう、極めてデリケートで繊細な精神的内容を持った彼の音楽には、小手先ではとても到達できないのです。マーラーの作品世界に身を投じる勇気が求められ、極端にいえば「共に病む」ような覚悟が必要になるのです(笑)。もしマーラーその人が実際にここにいたら、皆逃げ出してしまうのではないかと思いますね。絶対に友人にはなりたくないような彼の人柄を理解して演奏しなければなりません。
交響曲第1番のような初期においては、まだマーラーも少なからず健康でありたいと願っていたと思います。しかし第1番から、精神的で芸術的にも高度な内容と、一方で極めて世俗的な人間の素の部分が共存していて、これも彼の矛盾のひとつですね。途中でチンドン屋みたいな音楽が出てくるでしょう。
~確かに、マーラーの作品にはよく入ってますよね、チンドン屋みたいな音楽が。子供の頃に聴いたのでしょうか。
飯守 近くの兵営の軍楽隊の音を聴いて育ったようですね。幼児体験は、彼の生涯に渡って強烈な影響を残していると思います。行進曲が出てくるといっても、マーラーの作品の中ではほとんどが葬送行進曲です。
~今回の第2番の第1楽章にも行進がありますね。
飯守 そう、あれも死を象徴する調性ともいえるハ短調(c-moll)です。病的なほど繊細といえばシューマンも同じですが、シューマンは常に救われたいという思いを抱えて苦しんだのに対し、マーラーは、もはや救われたいとも思わなかったのです。
~「大地の歌」を先生に振っていただいた時に、最終楽章で「これは不整脈です」とおっしゃったところがあって、とても印象に残っています。それ以来、普通に脈打っている人が考える音楽ではないと思います。
飯守 彼の作品の背景には、妻のアルマとの関係がうまくいっていなかったことによる苦悩も、やはりあるでしょう。彼女は日記に、夫が仕事から帰ってくる足音が聞こえるだけでぞっとする、と書いています。アルマ・マーラーは美しく、誰からもちやほやされて、作曲の才能にも恵まれていましたが、マーラーとは性格が合わなかったのです。もちろんマーラーと彼女が結婚したことは素晴らしいし、双方にとってよいことだったとは思いますが、男性が放っておけない女性だったので、マーラーの死後、次から次へと恋人や夫ができましたね(笑)。
~マーラーと結婚している時でさえ建築家のヴァルター・グロピウスと三角関係に陥って、彼はおかしくなってしまいましたよね。
飯守 アルマの浮気が発覚してマーラーは気が転倒し、すべての練習をキャンセルして精神科医のフロイトのところへ行って、夫婦の危機を訴えたようですね。フロイトに「いったい誰が苦しいのか考えたことがあるのか。奥さんの方が辛いことが、あなたには分からないのか」と図星をさされてしまったのです。
~そのせいで交響曲第10番が完成しなかった。音楽界には大きな損失ですね。
飯守 あのアダージョに続く楽章が完成していれば、と考えると、たしかに惜しいですね。
今回演奏する交響曲第2番「復活」は、そこまで精神的な苦悩を深める前のマーラーの哲学が非常に力強く前面に打ち出されています。人間がこの世の中で何のために生きるか、という問題が、彼の作品の中でもこの曲で一番肯定的に前面に打ち出されているのです。冒頭はきわめて悲劇的に始まりますが、非常に肯定的に終曲を閉じます。
あるときマーラーと友人が気楽な食事中に「死」が話題になり、友人が「そのときは自分は存在していない」と言った途端、マーラーはコップをテーブルに叩き付け「何と軽はずみなことを言うのだ、私たちは蘇り、死は克服されるのだ」と激高したそうです。マーラーが一番こだわっていたのが「死」であり、死がすべてを征服するかのように言われるがそうではなく死こそ征服されるのだ、という考えに彼は集中していたのです。
■指揮者とオーケストラの関係
~今日の初練習であらためて感じられたことはありますか。
飯守 総じてオーケストラ全体が立派になっていると思います。それがとても嬉しかった。ただ、リハーサルで出す最初の音、最初のフレーズに、奏者の具体的な表現に現れてくるべきイメージと意思が足りません。音を出してからではなく、出す前に、その音に対する意思とイメージが存在するべきなのです。
~今日は2年ぶりの初回練習ということで、全員がとても緊張していたと思います。
飯守 でも新響は、やはり組織が非常にしっかりしていて、それが皆さんの「音楽が好き」という心に支えられているところが素晴らしいと思いますね。
~最初に先生がいらした時と比べると、団員の半分以上は変わっていると思います。ただし昔からの団員もそれなりに残っていますので、年齢層が広くバランスよく揃っていると思います。
飯守 若い人と、新響の歴史を経験してきた人が一緒というのは、とても良いことですよ。
皆さんは、バレンボイム指揮のブルックナー交響曲の全ツィクルス曲演奏会は聴かれましたか。
~ベルリン国立歌劇場管弦楽団(シュターツカペレ)の日本公演ですよね。
飯守 私は全曲聴きたくても日程が合わず、第8番の1回しか行けませんでしたが、大変素晴らしかったですね。バレンボイムとシュターツカペレ・ベルリンは、1992年から23年間、一緒に仕事をしています。指揮者とオーケストラとの間で長年かけて培われた確固たる信頼関係から生まれる阿吽の呼吸とでもいうか、失われつつあるヨーロッパの伝統が、バレンボイムとシュターツカペレ・ベルリンにはまだ残っているのです。彼らの演奏するブルックナーからは、まるで魔法のような音、はっとさせられるような音、ふだん聴けないような音が聴こえてくるのです。これこそがブルックナーの響きであり、長い年月をかけて熟成させた信頼関係から生まれた、オーケストラとして最高の響きというべきでしょう。
~バレンボイムとシュターツカペレの信頼関係ですが、長い間には当然メンバーも変わっているでしょうし、もちろん古株の方も残っている。やはり自分たちのオケはこうなんだという姿勢が大事ですよね。
飯守 オーケストラは生身の人間の集まりですから、物事がすいすいと、うまく進むわけがありません。長年同じオーケストラにいれば不満も出てくるし、摩擦も起きます。バレンボイムとシュターツカペレの演奏は完壁でしたが、それでも思うようにいかない事は多々あるはずです。それを乗り越えて、あの境地に到達したのです。
プロのオーケストラや劇場の事務局には、指揮者とオーケストラの間に入って調整する、いわゆるインテンダントがいます。指揮者対オーケストラという対立構図を作るのではなく、オケ全体のメリットを考え、調整する視点が不可欠なのです。新響では奏者である皆さんが運営もしているのは大変だと思いますが、問題解決にあたってはとても厳しい一面と、けっこう気楽にやっていく一面、この二つの兼ね合いが大切だと思います。
~最後に、これからの新響に向けてのメッセージをお願いいたします。
飯守 新響は、アマチュア・オーケストラの中でも特別に長い素晴らしい歴史をすでに持っています。特に、山田一雄先生とマーラーの全交響曲を演奏したことは、皆さんの誇りだと思います。これほどの活動をこれからも維持するだけでも大変なことだと思いますが、創立60周年という大きな節目に、邦人作品である別宮作品とマーラー、しかも「復活」という巨大な作品を選んだことは、新響がその名の通りこれからも「新しい響き」を求めてさらに発展していきたい、という決意の表れであると感じられます。
「復活」は、マーラーの中でも最大級の作品で、2人のソリスト、巨大編成のオーケストラ、大人数の合唱団が、総力を結集しなければなりません。60周年にふさわしい演奏ができるよう、私も皆さんと力を合わせたいと思い ます。
~先生と新響も強固な信頼関係を築けたら、と思います。今日はありがとうございました。
注)アーメン終止IVの和音(ファ・ラ・ド)などからIの和音(ド・ミ・ソ)に移行して終止するもの。賛美歌の最後の「アーメン」がこの和音で歌われることが多いことから、この名がある。飯守先生による補足:もう一つ「ドレスデン・アーメン」と呼ばれる、少し長めで、上行形で終わるものがいくつかある。特にマーラーの「復活」では、この「ドレスデン・アーメン」の音型が多く現れる。
2016年2月21日
聴き手:土田恭四郎(テューバ)
まとめ・編集:藤井泉(ピアノ)
マーラー:交響曲第2番 ハ短調「復活」
グスタフ・マーラー (1860-1911) は、現代のわれわれにとって、10ないし11曲の壮大な交響曲と重要な歌曲集の作曲家である。だが、同時代の多くの人たちにとってマーラーは、作曲家というよりもむしろ、1897年から1907年の10年のあいだヨーロッパ音楽界の頂点に位置するウィーン宮廷歌劇場(現在のウィーン国立歌劇場)に君臨した指揮者・音楽監督であったといえるだろう。しかし、交響曲第2番の作曲とかかわっていた1888年から1894年、つまり彼が28歳から34歳の時期には、さまざまな歌劇場で指揮者として頭角を表しつつあったものの、マーラーはまだそのような輝かしい地位からは遠く離れたところにあった。
18歳になる年にウィーン音楽院(ピアノ、ついで作曲)を卒業したのち、マーラーは、ライバッハ(現在はスロヴェニアの首都リュブリャーナ)、オルミュッツ(現在、スロヴァキアのオルモウツ)、カッセル(ヘッセン大公国の首都の一つだったが、プロイセン王国に併合)、プラハ、ライプツィヒ、ブダペスト、ハンブルク等、さまざまな都市の劇場の楽長を短期間のうちに歴任してゆく。ちなみに、交響曲第2番の作曲とかかわっているのは、ライプツィヒからハンブルク時代にいたるかなり充実した時期にあたる。上昇志向のきわめて強いマーラーにとって、こういったポストの遍歴は、音楽家としてより優れた活動の場を求める過程であった。しかしそれとともに、ハプスブルク帝国内およびドイツ(成立後間もないドイツ帝国)で、このような多言語・多民族・多文化的空間のなかに身を置いて経験を積み重ねていったことは、マーラーの音楽そのものとも深く結びついているように思われる。
このことにさらに深くかかわっているのは、マーラーの出自である。マーラーは、1860年、チェコの東方の地域モラヴィアに近いボヘミアの小村カリシュト(現在、チェコ共和国のカリシチェ)で、ユダヤ人の両親のもとに生まれているが、まさにこの年にハプスブルク帝国でのユダヤ人の居住地の移動が認められた機会を利用して、家族はボヘミアとの境界に近いモラヴィアの商業都市イーグラウ(現在、チェコのイフラヴァ)にすぐさま居を移す。マーラーの音楽のなかにさまざまなかたちで現れる少年時代の自然の思い出は、このイーグラウと結びついて いる。
この時代にはハプスブルク帝国内の諸地域で、それぞれの民族と言語に基づいたナショナリズムが盛り上がりを見せる一方、マーラーが少年時代を過ごしたイーグラウのようなモラヴィアの重要な都市では、ハプスブルク帝国の中心に座すオーストリア王国──民族的にはドイツ人であり、そしてドイツ語が話されるオーストリア王国──、とりわけその首都ウィーンに対する強い憧れがあった。モラヴィアの言語はボヘミアと同じくチェコ語であるが、イーグラウではドイツ人(民族的な意味での)が多く移り住み、いわば支配者の言語としてのドイツ語が広く話されていた。酒造業を主な生業としていたマーラーの父親は、商業的な意味でもドイツ語を用い、またドイツ語圏文化の教養を身につけることにも腐心していたようだ。マーラーはそのような家族の教育のもと、イーグラウのドイツ人ギムナジウムで学んでいる。
ユダヤ人がヨーロッパのキリスト教社会の中でそれなりの社会的地位を獲得してゆくためには、伝統的なユダヤの生活習慣をある程度脱して、ヨーロッパ社会に「同化」してゆくことが不可欠だった。マーラーの両親はすでにそういった同化ユダヤ人として生活していたことになる。しかし、それと同時に、マーラーの家族は、カリシュトやイーグラウでのユダヤ人コミュニティとのつながりを保ち続けていた。マーラー自身も、イーグラウのシナゴーグ(ユダヤ教会)に通い、13歳のときにはバル・ミツヴァ(ユダヤ教の成人の祝い、キリスト教でいえば堅信礼にあたるか)を受けている。そしてまた同時に、15歳からの3年間を音楽の勉強のために過ごしたウィーンをはじめとして、ハプスブルク帝国内でのカトリック的環境において、あるいはライプツィヒやハンブルクなど、プロテスタンティズムが支配的な地域において、異なる性格のキリスト教文化をごく自然なものとして身につけている。反ユダヤ主義が強烈に作用していた、カトリックの街ウィーンで、1897年にユダヤ人のマーラーがウィーン宮廷歌劇場の音楽監督のポストに就任するための一種の下工作として、マーラーは彼の支持者たちの説得によってユダヤ教からカトリックに改宗している(そうだとしても、ユダヤ人がウィーン文化のトップの座につくということは、同時代のウィーンの人々にとってはほとんどありえないことだった)。最終楽章に「復活」という主題を掲げた交響曲第2番はそれより以前に作曲されたものだが、だからこそいっそう、この交響曲には、マーラーの音楽に広く見られるさまざまな文化的混淆状態(ドイツ・ロマン主義の異なる要素、自然や軍楽隊の音など少年時代の記憶、さまざまな文化に根ざす民謡など)とともに、ある種の不思議な宗教的混淆状態が存在しているといえるかもしれない。
さしあたり素朴な疑問として感じられるのは、伝統的なユダヤ教の文化的伝統からはほとんど離れていたとはいえ、ユダヤ教のうちにあったマーラーが、なぜ「復活」というテーマを取り上げているのかということである。そしてまた、作曲にかかわっていた時点では、カトリックの牙城ともいえるウィーンと直接の関係はないとはいえ、マーラーがハプスブルク帝国内のカトリック的伝統と馴染んでいた文化的環境を考えるとき、ルター派のコラールを思わせる音楽をこの交響曲のなかで(第4、5楽章)用いていることは、本来ならばそれほど自明のことではない。こういったことも念頭に置きつつ、それぞれの楽章についてふれてゆきたい。
第1楽章
この楽章は、もともと「葬礼」という標題をもつ交響詩として1888年に完成していた(ライプツィヒ時代)。こういった経緯のため、実際にマーラーが交響曲第2番に集中していたのは1893年と1894年(ハンブルク時代)の夏の休暇の時期であったにもかかわらず、この交響曲の成立時期はしばしば1887年から1894年の7年間にわたるかのように見られることがある。後に述べるように、「復活」という主題がこの交響曲に組み込まれたのは、作曲の最後の段階になってからなので、交響詩「葬礼」の作曲時点ではまだ、マーラーが取り憑かれていた「死」への想念に対する回答としての「復活」が想定されていたわけではない。第5楽章の完成後に、初演は不成功に終わったこの交響詩は、交響曲第2番の第1楽章として書き直されることになる。
ちなみに、マーラーは1891年にこの「葬礼」を、彼が敬愛する指揮者ハンス・フォン・ビューローの前でピアノによって演奏したが、そのときには指揮者としてのマーラーを高く評価していたこの偉大な指揮者にこの音楽を理解してもらえず、きわめて辛辣な言葉を聞かされることになったために、マーラーはひどく落胆したようだ。
第2楽章
第2楽章と第3楽章は(あるいは第4楽章も加えて)、後年、マーラー自身の言葉によって「間奏曲」の性格をもつものと位置づけられている。第2楽章は、ゆったりとくつろいだレントラー(3拍子の民謡的な舞曲)の性格をもつ曲想によって始まり、マーラーはこの楽章を「もはや失われてしまった無邪気さへの哀愁に満ちた追憶」と説明している。A1-B1-A2-B2-A3-コーダという単純な形式による。
第3楽章
もう一つの「間奏曲」である第3楽章は、まったく異なる性格をもっている。マーラーはドイツ・ロマン主義の二人の作家、アルニムとブレンターノによる詩集『少年の魔法の角笛』に惹かれ、この民謡的な詩集から20曲以上の歌曲、あるいは交響曲の楽章を作曲している。マーラーの第2番から第4番までの交響曲は、詩集『少年の魔法の角笛』と密接に結びついているが、この第3楽章は、詩集の第1巻に含まれる「魚に説教するパドヴァの聖アントニウス」と題される詩に作曲された歌曲(これはマーラーの歌曲集『少年の魔法の角笛』のうちに含まれる)の音楽をスケルツォの主部としてそのまま用いている。マーラーはこの曲の楽想が、子ども時代のボヘミアの音楽の記憶と結びついていると語っている。この詩集には、さまざまな性格の民謡が含まれているが、聖人がいわば「馬の耳に念仏」のように魚に説教する様子を諷刺的に描いたこの詩は、マーラーの音楽にしばしば現れる諧謔的なアイロニーに合致するものであり、マーラーはこの音楽にかなり満足していたようだ。
第4楽章
スケルツォの第3楽章が不気味に終わった後、アルトのソロにより「原光」と題された楽章が始まる。この曲は、マーラーのすべての交響曲のなかでも初めて声楽が用いられた楽章であり、またこの交響曲第2番全体のなかでも「復活」が歌われる最終楽章へと音楽が橋渡しされてゆく転換点となっている。「原光」と題されたテクストは、詩集『少年の魔法の角笛』第2巻からとられたものだが、マーラーはこのテクスト(部分的に変更が加えられている)に対して、いくつかの詩行ごとにかなり性格の異なる音楽を与えている。
「ああ、小さな赤いバラ」という最初の印象的な言葉に続き、金管楽器によるコラール風の音楽が現れる。深い瞑想と宗教性をもつ音楽がさらに続いたのち、「私が広い道を歩いていたら」という詩行から突然、素朴な民謡風の音楽に転じる。天使は「私」にこちらにきてはいけないというのだが、その「私」はまだ子どもであるようにも感じられる。「私」は神さまのもとに行くことを望んでいるのだけれど、天使が指示しているように、まだその時ではないのかもしれない。しかし、「私」は天国での生活を幸せに満ちたものとして思い描いている。このように無垢な子どもが天国の至福のなかで歌う様子は、同様に『少年の不思議な角笛』の詩を取り入れている交響曲第3番や第4番、またゲーテの『ファウスト 第二部』をテクストとする交響曲第8番にも見られるように、マーラーの音楽のなかでも特徴的な要素である。しかし、この民謡風の曲調は、神のもとにいたることを切望する言葉とともに、次第に崇高なものへの憧れに満ちた、その意味できわめてロマン主義的な音楽へと移り変わってゆく。
ところで、この詩にはなぜ「原光 (Urlicht)」という標題がつけられているのだろうか。ドイツ語に特有のこのur-という言葉は、ある事物(この場合は「光Licht」)の根源的、原初的な状態を示すものである。「原光」というタイトルは哲学的な意味合いさえ感じさせるが、これはマーラーによって付けられたものではなく、もとの詩集でもこの標題が与えられている。直接的にはもちろん最後の二つの詩行のなかにあらわれる、神の「光」を指しているだろう。しかし、それとともに、道行く「私」が出会った野に咲く小さな赤いバラの花を目にして、すべての光の源であるようなイメージがその小さなバラに重ね合わされているのだろう。この楽章の冒頭の「ああ、小さな赤いバラ」という言葉は、そのようなイメージとして音楽のなかに浮かび上がる。
第5楽章
マーラーはこの第5楽章をどのようなものとするか、最初なかなか構想が固まらなかったようだ。一転してイメージが収斂していったのは、1894年に亡くなったハンス・フォン・ビューローの葬儀がハンブルクの聖ミヒャエリス教会で行われた際に、18世紀ドイツの詩人クロップシュトックによる「復活」がコラールで歌われたことに強い感銘を受けたからだと、マーラー自身が後年書簡のなかで述べている。しかし、このよく知られたエピソードによってのみ、この楽章の性格を考えないほうがよいかもしれない。クロップシュトックの5つの連からなる詩のうち、葬儀で用いられたのは最初の3つの連であり、マーラーが交響曲第2番第5楽章に用いたのはさらにそのうちのはじめの2つだけである。「ああ信じるのだ、わが心よ」から始まるテクストは、マーラー自身が書いたものであり、第5楽章の作曲中に送られた書簡をみても(「第5楽章は壮大で、合唱によって終わりますが、その歌詞は小生の作です」)、むしろマーラー自身のテクストにこそ、彼の思想が集約されているといえるだろう。
キリスト教において「復活」という場合、なによりもイエス・キリストの復活が連想される。しかし、このクロップシュトックの詩のなかで深い信仰心と感情によってうたわれているのは、死者が復活し、神の国に入ることへの希望と喜びである。このことは最後の審判の日に起こることとされる。だからこそ、約35分かかる第5楽章のなかでおよそ20分もたって、ようやくクロップシュトックの「復活する、そう、おまえは復活するのだ」という言葉が合唱によって静かにあらわれるまでに、黙示録的文書のなかで描かれるような地上の災厄や、輝かしい神の栄光、悪との抗争が音楽によって展開されてゆくことになるのだ。舞台裏でホルンによって演奏される厳かな音(ユダヤ教の祭儀で用いられていた角笛の一種、ショファーをおそらく念頭においたものだろう)や華やかなトランペットは、この最後の日に天が開け、神が現れるときを表すものである。
そのとき地上の死者たちも甦る。合唱によって静かにクロップシュトックの詩が歌われるとき、それがプロテスタントのコラール風であることは、ルター派の敬虔主義につながるクロップシュトックのテクストであること、プロテスタントのハンス・フォン・ビューローの葬儀で、実際に少年合唱によるコラールとして歌われていたこと(それがどの作曲者の曲によるかはわかっていない)を考えるならば、自然なこととして受けとめることもできるだろう。しかし、マーラー自身のテクストになってからは、音楽はこの世の苦悩と至高の存在への憧れに満ちたものへと性格をかえてゆく。神へと向かう熱い思いが壮麗に鳴り響くときには、その音楽はむしろカトリック的な伝統を思い起こさせるものである。
とはいえ、キリスト教における最後の審判だとすれば、そこには必ず再臨のキリストの姿があるはずなのだが、マーラーが第5楽章のために用いたテクストにはそれについての言及は一切ない。クロップシュトックの詩は、キリスト教における死者の復活の信仰に基づいたものだとはいえ、もともとそこにはこの世の最後の日の恐ろしいイメージが描かれることはなく、この日はむしろ復活とともに神の国に迎え入れられる「感謝の日、喜びの涙の日」(第3連)と呼ばれている。クロップシュトックの「復活」の言葉が現れるまでのあいだの20分間、マーラーがことさらにあの壮大な世界審判の日の情景を付け加えているのである。ある研究者は、マーラーが描き出している終末論的情景は、むしろ「ダニエル書」(「多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。/ある者は永遠の生命に入り/ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。」(12:2))に見られるような、ユダヤ教本来の伝統に連なるものであると指摘している。
マーラーがこの第5楽章の最後に、神のもとへと向かうことを高らかに歌いあげるとき、この「神」とは何なのだろうか。青年時代のある書簡の中で、マーラーは「至福の命の灼熱と、身を焼き尽くす死への憧れ」が交互に入れ替わるような内面を吐露しながら、彼にとってのあらゆる神聖なものとして「芸術、愛、宗教」をあげている。マーラーにとって宗教が特別に重要な意味をもつものであったことはまちがいない。しかし、それは一般的な意味での信仰心であったり、キリスト教社会の中で密かにユダヤ教的要素を保持しようとしていたというよりも、むしろドイツ・ロマン主義の連関の中で形成されてきたような、より理念化された至高の存在に向かうものであるようにも思われる。マーラー自身が書いた第5楽章のためのテクストのうちに、「神」という言葉は、実は最後に一回現れるだけである。黙示録的な情景とクロップシュトックの信仰心に満ちた復活の希望がおもに示される前半に対して、マーラー自身のテクストに音楽が移行してからは、「復活」という主題は、もともとの宗教的なコンテクストから離れて、次第に死の想念と絶えず格闘していたマーラー自身の生の苦悩とそれに対する勝利へと意味合いを移していく。そのようにして──交響曲第8番「千人の交響曲」の最後に『ファウスト 第二部』の「神秘の合唱」が歌われたあと、同じく変ホ長調でパイプオル
ガンを伴う壮大なコードが鳴り渡るのと同じように──神のもとへの救済の音楽が鳴り響くのである。
初演: 1、2、3楽章のみ、1895年3月4日、ベルリン。この演奏会全体の指揮はリヒャルト・シュトラウスだが、交響曲第2番についてはおそらくマーラー自身。全曲の初演は1895年12月13日、ベルリン、指揮はグスタフ・マーラー。
楽器編成: フルート4(すべてピッコロ持ち替え)、オーボエ4(3, 4番はコールアングレ持ち替え)、Esクラリネット2(2番は4番クラリネット持ち替え)、クラリネット3(3番はバスクラリネット持ち替え)、ファゴット4(3,4番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン10(舞台上に6、舞台外に4)、トランペット10(舞台上に6、舞台外に4)、トロンボーン4、テューバ、ティンパニ(奏者2人各3台、後から第3奏者が加わる)大太鼓、シンバル、タムタム(高音と 低音各1)、トライアングル、小太鼓(複数)、グロッケンシュピール、鐘(低く、一定の音律を持たない鋼鉄の棒)、ルーテ(むち) 舞台外にティンパニ1台、大太鼓、シンバル、トライアングル ハープ2、オルガン、弦五部、ソプラノ独唱、アルト独唱、混声合唱
主要参考文献
Stuart Feder, Gustav Mahler: A Life in Crisis, Yale University Press, 2004.
Michael Haber, Das Jüdische bei Gustav Mahler, Peter Lang, 2009.
Vladimír Karbusický, Gustav Mahler,s Musical Jewishness, in: Jeremy Barham (ed.), Perspectives on Gustav Mahler, Ashgate, 2005.
Wolfgang Schreiber, Mahler. rororo, 1971.
Sponheuer/Steinbeck (Hrsg.), Mahler Handbuch, Metzler, 2010.
Renate Ulm (Hrsg.), Gustav Mahlers Symphonien, Bärenreiter, 5. Auflage 2010.
『マーラー書簡集』ヘルタ・ブラウコップフ編(須永恒雄訳) 法政大学出版局 2008年
『グスタフ・マーラー』クルシェネク/レートリヒみすず書房 1981年
『グスタフ・マーラー 失われた無限を求めて』アンリ=ルイ・ド・ラ・グランジュ(船山隆・井上さつき訳) 草思社 1993年
『マーラー 輝かしい日々と断ち切られた未来』前島良雄 アルファベータ 2011年
三善晃:管弦楽のための協奏曲
当団では2006年に創立50周年シリーズの幕開けとして、三善晃の「交響三章」を取り上げた。10年後の今年、創立60周年シリーズでこの曲を取り上げることで、当時の指揮者である故小松一彦氏との、「次は管弦楽のための協奏曲を」という約束をようやく果たすことが出来る。
三善晃は1933年東京生まれ。東京大学文学部仏文科に在学中の1953年に『クラリネット、ファゴット、ピアノのためのソナタ』が日本音楽コンクール作曲部門第1位となる。1955年から1957年にかけてパリ国立音楽院に留学、アンリ・シャランのクラスに学ぶ一方で、レイモン・ガロワ=モンブランに個人的に学ぶ。放送詩劇『オンディーヌ』(1959)で芸術祭賞とイタリア賞を受賞。1960年東大卒業。『ピアノと管弦楽のための協奏的交響曲』(1954)、『ピアノ協奏曲』(1962)、『管弦楽のための協奏曲』(1964)で、第3回、第11回、第13回尾高賞受賞。桐朋学園大学学長、日本現代音楽協会委員長、日本音楽コンクール委員長、東京文化会館館長等を歴任。1999年芸術院会員、2001年文化功労者となる。『遠方より無へ』(1979)など著述も多数ある。
実に多才で、『対話十二章 現代の芸術視座を求めて─三善晃対談集』(1989・音楽之友社)では、作家、建築家、詩人、能楽師、彫刻家、演出家、装幀家、画家、陶芸家、美術史家と対談しており、氏の博識には驚嘆せざるを得ない。
また、相撲好きなのは有名で、ある日、学生だった池辺晋一郎氏を芸大から車で送っていた時のこと。車の中では相撲の中継が流れていて、当時の横綱が負けてしまった時、池辺氏が「弱い横綱ですね」と言ったところ、それから一切口を開かず、そのまま新宿辺りで池辺氏を車から降ろしてしまった…というエピソードもある。
三善は合唱曲も多数作曲しているが、そのことが管弦楽曲の作曲に少なからず影響しているようだ。
日本語と変則的リズム
民族音楽あるいは近代音楽には、「5拍子」や「7拍子」などの変則的なリズムが時々見られるが、多くの場合、2または4拍子と3拍子の混合(複合)。つまり「2+3」なら「5拍子」、「4+3」なら「7拍子」になる。例えば民族舞踊のダンスの中で「手を2回叩いて(2拍子)、ぐるっと回る(3拍子)」というようなアクションを考えた時、これは「1・2」+「1・2・3」の「5拍子」がきわめて自然であることが分かる。
これに対し、三善が楽曲の中で使っている変則的なリズムについてはこの例とは多少異なるようだ。前述の演奏会のためのインタビューで、「合唱曲はもともと言葉の音楽で、日本語の音楽です。それは器楽曲を書く時も同じなのです。まったく変わらないですね。つまり器楽曲で日本語を書いている、という事がいえると思います」と語っている。作品の中に変則的なリズムが多くなっているのは、「言葉の音楽」で作曲されているためと言えるだろう。
その言葉の音楽で作曲され、変則的リズムを多用した曲に、1992年全日本吹奏楽コンクールの課題曲Cとして作曲された、吹奏楽のための「クロス・バイ・マーチ」がある。
マーチと銘打っているだけあって、2拍子で演奏出来るように構成されてはいるが、ガイドとして括弧書きで書いてあるように、実際は変則的リズムの連発である。速いテンポでめまぐるしく変化するリズム、しかも音域も広い上に細かい動きが多く、吹奏楽コンクールの課題曲としては最も難易度の高い楽曲だろう。この難曲を当時の高校生が見事に演奏しているが、日本の吹奏楽のレベルの高さを感じさせられる。
ちなみにこの「管弦楽のための協奏曲」も吹奏楽版にアレンジされており、同じく高校生による名演が残されている。
管弦楽のための協奏曲
一般的に協奏曲とは、独奏楽器(楽器群)と管弦楽による独奏協奏曲を指すことが常識となっているが、「管弦楽のための協奏曲」における「協奏曲」についてはバロック時代の合奏協奏曲などのコンチェルト様式を指している。この名称は、新古典主義のヒンデミットによって創り出された。
この楽曲について三善は、「私は、異なった持続を同時に組み合わせることを試みようとした。この不自由さは、おそらく作曲者の外側に、初めから存在しているものであったろう。そのことが前作(『ソプラノとオーケストラのための「決闘」』1964)のように内側から発想をとらえるのではなく、外から発想にかようものをリアライズしてみたい気持ちにかなっていた。それで、協奏という名も、この、組み合わせの試み、という意味でつけた。」と著書で回想している。
総譜の解説にも「この作品までは、内的な秩序に手がかりを得ていた音の追求を、はじめて、外的存在としての音と内的秩序の接点に求めてみたものです。」とあり、シェーンベルクの影響をうかがわせる意欲作となっている。
第1楽章 確保と二つの展開
木管・金管・弦それぞれの、三つの主題による二つの発展
動機の提示が3/8+4/8の速いテンポで行われる。楽曲が始まってすぐの音楽的緊張感によって、三善ワールドに引き込まれる。とにかくめまぐるしい変化がこの楽章の魅力。
第二楽章 複合三部
弦合奏のなかに他楽器の演奏を配した三部形式
第1楽章から一転して、叙情的な雰囲気の中にどことなく不気味な曲想が展開される。
第三楽章 変奏と復帰
一つの楽想を、各楽器群それぞれが独自にかたちを変えて初めから協奏する、その変容が各個別に一、二楽章の復帰を行う
第1楽章同様激しい音楽が復帰する。主題や和音が復帰、拡大される。ホルンの雄叫びをバックに一気呵成に楽曲が閉じられる。
初 演:1964年10月22日
オリンピック東京大会芸術展示(NHK 主催)
演奏/ NHK交響楽団
指揮/外山雄三
受 賞:昭和39年度芸術祭賞、尾高賞(第13回)
楽器編成: フルート3、オーボエ3(3番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット3(3番はEsクラリネット持ち替え)、ファゴット3、ホルン6、トランペット4、トロンボーン3、テューバ1、ティンパニ、テューブラーベル、銅鑼(ゴング)、タムタム2、トムトム4、ボンゴ、吊シンバル、合わせシンバル、小太鼓、大太鼓、木魚1対、木琴、ヴィブラフォン、グロッケンシュピール、ピアノ、チェレスタ、ハープ、弦五部
参考文献
『遠方より無へ』三善晃 白水社2002年
『対話十二章 現代の芸術視座を求めて』三善晃 音楽之友社1989年
『日本大百科全書(ニッポニカ) 』小学館1984年
新響創立50周年シリーズを機に行われたインタビュー
http://www.shinkyo.com/concerts/p192-1.html
第233回ローテーション
| 二つの祈り | 復活 | ||||
| Fl | 1 | 吉 田 | 1/Picc.3 | 松 下 | |
| 2 | 藤 井 | 2/Picc.4 | 新 井 | ||
| 3/Picc. | 岡 田 | 3/Picc.1 | 兼 子 | ||
| ― | ― | 4/Picc.2 | 岡 田 | ||
| Ob | 1 | 山 口 | 1 | 堀 内 | |
| 2 | 宮 内 | 2 | 平 戸 | ||
| C.I. | 桜 井 | 3/C.I.1 | 岩 城 | ||
| ― | ― | 4/C.I.2 | 宮 内 | ||
| Cl | 1 | 末 村 | 1 | 品 田 | |
| 2 | 石 綿 | 2 | 進 藤 | ||
| Bass | 岩 村 | 3 | 中 島 | ||
| ― | ― | Bass | 岩 村 | ||
| ― | ― | 4/Es.2 | 大 藪 | ||
| ― | ― | Es.1 | 高 梨 | ||
| Fg | 1 | 藤 原 | 1 | 田 川 | |
| 2 | 野 田 | 2 | 浦 | ||
| Contra | 笹 岡 | 3 | 笹 岡 | ||
| ― | ― | 4/Contra | 藤 原 | ||
| Hr | 1 | 大 内 | 1 | 箭 田 | |
| 2 | 宮 田 | 2 | 山 口 | ||
| 3 | 菊 地 | 3 | 大 原 | ||
| 4 | 市 川 | 4 | 市 川 | ||
| ― | ― | 5 | 菊 地 | ||
| ― | ― | 6 | 宮 田 | ||
| ― | ― | Banda | 7 大内 | 8 鵜飼(*) | |
| ― | ― | 9 河野(*) | 10 菅野(*) | ||
| Tp | 1 | 倉 田 | 1 | 野 崎 | |
| 2 | 北 村 | 2 | 青 木 | ||
| 3 | 中 川 | 3 | 小 出 | ||
| ― | ― | 4 | 中 川 | ||
| ― | ― | 5 | 北 村 | ||
| ― | ― | 6 | 一 井(*) | ||
| ― | ― | Banda | 1 倉田 | 2 石黒(*) | |
| ― | ― | 3 高沢(*) | 4 川合(*) | ||
| Tb | 1 | 武田浩 | 1 | 武田香 | |
| 2 | 武田香 | 2 | 志 村 | ||
| 3 | 岡 田 | 3 | 武田浩 | ||
| ― | ― | 4 | 岡 田 | ||
| Tu | 土 田 | 土 田 | |||
| Timp | 皆 月 | 1 桑形 | 2 古関 | ||
| Perc | シンバル | 古 関 | 合わせSym.・小太鼓(一部) | 桜 井 | |
| 中太鼓・大太鼓・タムタム | 桑 形 | 大太鼓・ルーテ・舞台裏Cym付BD | 今 尾 | ||
| 小太鼓・トライアングル | 今 尾 | 小タムタム・Tri.・小太鼓(一部)・ Timp.3番、舞台裏Timp. |
皆 月 | ||
| ― | ― | 大タムタム・舞台裏Tri. | 中川(*) | ||
| ― | ― | 吊りSym.・グロッケン・鐘・小太鼓(一部) | 梶尾(*) | ||
| 鍵盤 | Cele./Piano | 藤 井 | Organ | 石丸(*) | |
| Harp | 見尾田(*) | 1 見尾田(*) | 2 堀乃北(*) | ||
| Vn | 1 | 堀内(小松) | 1 | 堀内(小松) | |
| 2 | 大隈(大島) | 2 | 大隈(田川) | ||
| Va | 槇(村原) | 柳澤(村原) | |||
| Vc | 柳部(大庭) | 柳部(安田) | |||
| Cb | 中野(渡辺) | 中野(渡辺) | |||
(*)はエキストラ
第233回演奏会のご案内
創立60周年シリーズ第2弾
新交響楽団は、創立以来アマチュアオーケストラとしての可能性を追求し活動をしてきました。1979~90年には山田一雄指揮によるマーラー交響曲チクルスに挑んでいます。今でこそアマチュアオーケストラがマーラー作品を演奏することは当り前になっていますが、当時としてはかなり挑戦的なことでした。その経験が現在の新響の血肉となっています。今回は1993年から共演を重ねている飯守泰次郎を指揮に迎え、第2番「復活」を演奏します。
また、新響は創立20周年「日本の交響作品展」でサントリー音楽賞を受賞し、その後も日本人作曲家の作品に取組んできました。ベートーヴェンやモーツァルトと同じように邦人作品を取上げ、共感をもって演奏していきたいと考えています。
マーラー「復活」への想い
交響曲第1番「巨人」は大編成ながら管弦楽のみの作品ですが、この第2番は混声合唱と2人の独唱、パイプオルガンが加わり金管が増員され、さらに感動的な作品となっています。「巨人」の主人公が死に、最後に復活を遂げるドラマで、復活があるからこそ死は生の消滅ではなく、この世の人生の労苦は十分に意味深いというマーラーの死生観が込められています。
作曲当時マーラーはハンブルグ市立歌劇場の正指揮者でしたが、ハンブルク楽友協会の指揮をしていたハンス・フォン・ビューローに認められ後継者となりました。そのビューローの葬儀の印象がこの第2番に盛込まれています。合唱付きの終楽章がベートーヴェンの真似と受取られるのを心配していたマーラーは、葬儀で歌われたクロプシュトック(ドイツの詩人)の「復活」という賛歌に感銘を受け、この詩を使用しました。
マーラーの交響曲の魅力は、美しく時に叙情的な旋律と、スケールが大きく複雑な構造ですが、ともすればそれが苦手とされてしまうかもしれません。しかし第2番は比較的明解で、マーラーを聴きなれない方にも楽しんでいただけると思います。
別宮貞雄「管弦楽のための二つの祈り」
別宮貞雄(1922-2012)は東京大学理学部物理学科と文学部美学科の両方を卒業した秀才。在学中に作曲の勉強を始め毎日音楽コンクールに入賞、東大卒業後にパリ音楽院に留学、ミヨーやメシアンに師事しています。別宮賞を制定し自ら作品の評価を行うなど、長く日本の作曲界の中心的存在でした。5曲の交響曲をはじめ、調性のあるメロディックな作品を残しています。
今回演奏する「二つの祈り」は、留学後に東京交響楽団の委嘱で作曲された修行時代の集大成的な作品です。新交響楽団第99回演奏会「青春の作曲家たち」(1983)にて、当時日本の第一線で活躍する作曲家の若き日の作品を集めて演奏をした際に、この「二つの祈り」を取上げました。
「悲しみをもって」「雄々しく」と名付けられた2つの楽章からなる作品で、荘厳な前奏曲で始まりグレゴリア聖歌の現れるフーガが力強く演奏されます。
今回演奏する2曲は、ともに作曲家34歳の時に書かれた作品。作曲家の瑞々しい感性をお楽しみください。(H.O.)
座談会 新響のルーツを探る
新交響楽団は2016年に創立60周年を迎えました。今回は新響OBとベテラン団員を囲んで、人間でいえば還暦を迎えた今だから話せることや、音楽監督・芥川也寸志の思い出など、大いに語っていただきました。
出席者 戸田昌廣(トロンボーンOB)、都河和彦(ヴァイオリンOB)、秋山初瀬(ヴァイオリン)、新山克三(チェロ)、桜井哲雄(オーボエ、写真撮影)、大原久子(運営委員長、ホルン)、土田恭四郎(団長、テューバ)
■今だから語る東京労音からの独立事件
─ 新響の歴史について順を追って伺いたいと思います。まずは60年代の東京労音からの独立について
お聞かせください。1956年に芥川也寸志が東京労音新交響楽団を設立し、1966年に東京労音から独立、
現在の新交響楽団となったわけですが。
戸田 この事件が新響の将来を決定づけ、今日までその精神が続いていると思います。ご存じのとおり創立当時の新響は東京労音(以下労音)に所属していました。まず時代背景から申し上げますと、当時のソ連(ソヴィエト社会主義共和国連邦)はスターリンからフルシチョフの時代になり、スターリン批判を行って平和共存へと路線変更をしたんです。それが原因で平和共存路線を受け入れられない中国とソ連が喧嘩をはじめました。当時の中国はソ連のことを「修正主義」と呼び、ソ連は中国共産党のことを「教条主義」と呼んで、互いに非難し合っていました。一方日本の共産党は中国寄りで、社会党はソ連寄りでした。労音は会員制を基本に運営される音楽鑑賞団体で、その代表的な音楽活動はうたごえ運動でした。労音の中では共産党が勢力を握っていたので、新響はまさに共産党の文化サークルだったのです。でも当時の我々はそういった事情をよく理解していませんでした。私も新響に入る前に労音の会員になっていたんですよ。だってたった1000円でいろいろな演奏家の演奏が聴けたのですから。その後、芥川先生が共産党ではない方向へと動き出しはじめたのです。上野の東京文化会館に練習場が移ってからすぐの頃、芥川先生は長期間アメリカへミュージカルの勉強をしに行き、「南太平洋」や「回転木馬」などの楽譜を持ち帰って来ました。帰国後に労音の事務局へ行ったら「なんだ、アメリカかぶれして」と、とても批判的な言葉を聞き、えっ、と驚きました。労音の中ではだんだんと芥川也寸志が邪魔になってきて、何とか彼を労音から追い出す手はないかと思い始めたようでした。当時芥川先生は「労音との対立は団員の問題ではない、政治的な問題だ」としきりに言っていました。でも私たちには政治の問題と言われてもよく分からなかった。まだ若造だったし、勉強してもさっぱり理解出来なかった。
大原 大学には必ずそういう組織がありましたよね。
新山 だから今の日本共産党とは全然違う、まったく別物。議会政治とか認めないんだからね。
戸田 私は労音の会員になっていたけれど、組織の中にいても分からなかった。最初に違和感を抱いたのは、ベートーヴェンの第9を東京労音合唱団と一緒に演奏した時かな。その時にまったくピントはずれなことを言ってきたのです。たとえば「芥川也寸志は自分のテンポで振っているけど、こちらは労働者のアマチュアだからテンポなどは話し合って決めてもらいたい」とか。オーケストラではそんなことは考えられないよね。
新山 話し合って決めることではないよね。
戸田 ああ、これはかなりおかしい、不思議だなと。
新山 それから少人数でアンサンブルを組んで、工場にオルグに行けって言われてね。工場に行って労働者の前でロシア民謡などを演奏したりして。
戸田 要するに文化工作隊なんですよね。共産党の宣伝をするために中国でもやっているでしょう。60年安保闘争の前後はそういう時代だったところに新響がいて、芥川也寸志という邪魔者が出てきて、どうしたら潰せるかということになってしまった。それでいろいろ考えた結果、団員は芥川先生についていくということではなくて、労音のやっていることは、ちょっと変だよね、肌に合わないねと。
新山 もう嫌になっちゃった。労音の上層部からの圧力が。工場行けとか、中国の曲をやれとか。
戸田 そこで僕たちは労音相手に2回、3回と大規模な対話集会をやったんです。当時団員は250人いました。第1オーケストラ、第2オーケストラ、第3オーケストラと吹奏楽、4つの団体に分かれていて250人。
大原 どうやって団員が集まっていったのでしょ うか。
新山 やっぱり労音オーケストラということが大きかったね。
戸田 労音を通して募集したのに加えて、朝日新聞に募集広告3行記事でポンと出したの。そうしたら労音を知らない人も、上野の東京文化会館に集まってきたわけ。
新山 芥川さんも最初の頃は「誰でもいいから皆で集まって一緒にやりましょう」と言っていたよね。
戸田 ここが芥川先生の凄いところなのですが、始まって4、5年くらいは皆で一緒にやっていたんです。例えば昨日フルートを始めた人も、ずっとやってる人も同じところでやるわけですよ。そうすると上手な人が嫌になって辞めてしまい、オケがまったく上達しなくなっちゃった。そこで芥川先生はダーウィンの進化論を持ち出して、当時の労音の役員を説得しはじめたのです。今では入団オーディションなんて当たり前でしょう。当時は団員を上下に分けるなんてとんでもない事だったのです。今の新響は分奏やパート練習をしていますよね。これだって考えられないことでした。
─ 分かれて練習するのもだめだったのですか。
戸田 オーケストラというのは全員でやるからオーケストラだって。信じられないでしょう。そういう時代だったんですよ。
大原 でもだんだんと欲が出てきたんですね。
新山 そう、上達してくるにつれて欲が出てきた。
大原 団員を4つに分けたのは芥川さんでしょうか。
戸田 そうです。最初は2つに分かれていました。そうしたら各々の実力に合うところが出来て、さらに増えて3つのオーケストラになりました。
大原 分けたら逆に団員が増えていったのですね。
戸田 もちろん。あっという間に増えちゃった。アメーバが増えるように(笑)。そして皆が労音とは合わないね、と思い始めてきました。芥川先生の言ったことはこういうことだったのか、と徐々に分かるようになってきたのです。じゃあ我々はどうするか。労音をとるか、独立して自力でやっていくか。その結果、自分から飛び出すのはやめよう、ぎりぎりまで待とうということになりました。結果的に1966年3月に追い出されるという形で独立したのです。
─ 新響としてはどのようにして意思決定したのでしょうか。
新山 それこそ今でもやっている総会で決めたんだよ。
戸田 総会の日は第3オーケストラの練習として東京文化会館をとってあったところへ全員集合しました。臨時総会をやるからと言って集まってもらったのです。夜の6時か6時半頃に行ったら、マスコミがいてね。マスコミが大勢押しかけて来たんですよ。「すごい、何だこれは」と驚きました。来なかったのは毎日新聞社くらいでしたか。そこで大きな事件として扱われた結果、労音というのはこういう団体だったのかと世間にばれてしまったのです。それから徐々に労音の会員数が減っていき、経団連と商工会議所が作った東京音協(東京音楽文化協会)などの新たな団体が出来たりしました。
─ でも、そのままなんとなく労音についていったら、お金は出してくれるし、楽ではあったと思うんですよ。
新山 確かに今から思えば楽だったよね。
戸田 組織としてはよく出来ていたと思いますよ。
─ それでも、どうしても独立したかったのですよね。
戸田 それはね、やっぱりみんな音楽好きだったということかな。独立した当時はお金も何もない。まずはティンパニからだと、芥川先生が20万円をぽんとポケットマネーから出してくれました。だって楽譜から楽器から、何から何まで全部労音の物だったから。でも何だかんだ言っても4つの団体がぎりぎりの状態とはいえ活動していったのだから、その時の選択は正しかった、間違ってはいなかったと思います。
■ソ連演奏旅行 ~鉄のカーテンの向こう側へ~
─ 独立した翌年の1967年にソ連へ演奏旅行に行かれたんですよね。
戸田 芥川先生と新響が労音から独立したことによって、うたごえ運動や共産党などからは完全に縁が切れたんですよ。ちょうどその頃、日本はソ連と文化交流を始めていました。まだモスクワへの直行便がない時代です。そして芥川先生が日ソ青年友情委員会の日本側の会長をやっていた縁で、ソ連へ行けることになったのです。
秋山 全ソ青年団体委員会からの招待ということだったので、ソ連に着いてからの諸費用はすべてソ連側が負担してくれました。その上にお小遣いとして1人につき40ルーブルほど頂けたんです。ナホトカ往復の船代のみ団員の個人負担でした。
戸田 負担額は6万円くらいでしたか。
新山 当時の初任給が3万円から4万円の時代だから高いよね。
秋山 まず船でナホトカに着いて、すぐにシベリア鉄道でハバロフスクへ行きました。ハバロフスクで演奏して、イルクーツクでも演奏して。バイカル湖観光の後、イルクーツクから飛行機でモスクワへ移動したのです。当時はプロペラ機だったんですよ。モスクワで何回か演奏した後、レニングラード(現サンクトペテルブルク)へ行ってそこでも演奏しました。レニングラードではレニングラード・フィル(現サンクトペテルブルク・フィルハーモニー交響楽団)を聴くことが出来たんです。
戸田 私が凄いと思うのは、演奏旅行の1967年はソヴィエト連邦革命50周年の年でブレジネフが書記長、それこそソ連が一番勢いのあった時期に行ったということです。レニングラードに着いた日の午前中は記者会見で、夜は市内観光の予定でした。記者会見の新響サイドは芥川先生、副団長の仙名さん(副指揮者兼ファゴットOB)と私の3人でしたが、会見が終了した後に「今日はレニングラード・フィルのシーズン初日だ」と耳にしたんです。「指揮者は誰」という話になって、ムラヴィンスキーの指揮でショスタコーヴィチの交響曲第5番と第6番をやると。「先生、夜の観光はなしにしましょうよ」と盛んに言ったら、ソ連側が調べてくれたのです。でもあいにく満席でした。そうしたら凄いよ、特別に舞台の両サイドに椅子を並べて席を作ってくれたんです。60名のメンバー全員がそこで聴くことができました。ソヴィエト共産党の力には驚きましたね。とにかく大名旅行でした。
秋山 渡航の前に、芥川さんが団員の勤め先宛てに「訪ソ参加要請書」を出してくれましたよね。
土田 当時の会社だとOKを出さないところもありそうですね。
戸田 旧富士銀行の行員が2人いたけれど、1人は行けなかった。
桜井 あと新響も事務的で、パート内の定員を超えると行けなかったりした。都河さんは行けなかったよね。
戸田 パスポートとかビザの作成とか凄く大変なのよ。今よりもずっと大変だった。
─ ソ連が鉄のカーテンと言われていた頃ですよね。
桜井 説明会の時に石川嘉一さん(チェロOB)が 「ソ連に行ったら2度とアメリカに入国できないって聞いたんですけど、本当ですか」と真剣に質問していたよね。
戸田 渡航履歴があるだけでアカのレッテルを貼られた。
新山 その頃中国に1回行ったことがあるけど、パスポートに中国のスタンプが押してあるだけでアメリカへは行けなかったね。パスポートを取り直さないとダメだった。
■画期的だった日本の交響作品展
─ 70年代以降の話に移ろうと思います。1975年にストラヴィンスキー三部作の一挙上演、翌年1976年
が創立20周年で、その後10年に及ぶ日本の交響作品展がスタートします。
戸田 当時の新響幹事は指揮者、代表、運営委員長、技術委員長と事務局長の5人でした。私が代表、太田さん(チェロOB)が事務局長で、都河さんが技術委員長でコンサートマスター、運営委員長が故橋谷さん(コントラバスOB)だったところへ、芥川先生が「来年の20周年の時には日本の作品やろうよ」と言ってきた。私たち幹事は「よし、それでいきましょう」と盛り上がったのですが、団員にポロっと話したら猛反対にあっちゃった。そんな訳の分からない代物は嫌だ、やりたくないってね。そんなものを演奏するためにこのオケに入ったんじゃない、ブラームスやベートーヴェンがやりたいんだ、とか。会場も上野の文化会館を2回分しか取ってなかった。でも理事会では「やっぱりやろう、団員を口説こう」と。それで作戦を組んで、オルグをしたんです。
─ またオルグですね(笑)。
戸田 楽器別にやったら偏ってしまうので、居住地別にやりました。電車の路線ごとに集まったけれど、なかなか上手くいかなくてね。でもこの流れが変わったこととして印象深いのは、鹿島の合宿でのミーティングの時にアメリカ大使館勤務のマーサ・デヴィット(チェロOB)が言った言葉です。「私は世界中あちこちへ行くけれども、日本にいる時は日本の曲をやりたい。ベートーヴェンやブラームスはどこへ行っても演奏できるけれども、日本の作品を日本で演奏できたら最高です」と発言したの。そうしたら皆が「それ、いいね」と気持ちが傾いていったんですね。こうして日本の交響作品展が実現し、その後10年間シリーズ化しました。当時はプロオケでも邦人作品をほとんど演奏しませんでした。
土田 電車の吊り広告でこの時の新響のポスターを見たことは、今でも覚えています。まだ学生時代の頃でしたが。
大原 「日本人は日本人の作曲家に冷たくはないか」というようなキャッチフレーズでしたよね。
─ プロオケでさえ取り上げなかった邦人作品ですから、もちろん参考音源などはなかったわけですよね。どうやって曲を作り上げていったのでしょうか。
戸田 それは芥川先生が全部やってくれたんだよ。こっちは全然分からないんだから(笑)。
新山 例えば松村禎三の「前奏曲」とか、まったく分からないわけよ。チェロのパート譜しか見てないわけだから、他パートが何をやっているのかさっぱり分からないんだよね。それでも芥川先生と一生懸命、時間をかけて練習を重ねていったら、松村禎三さんが演奏会本番に来て、「私はこういう曲を作ろうと思っていた」と言ってくれたんだよね。
─ まさに作曲家が思っていた通りの演奏だったということですね。当時はどんな練習をしていたのでしょうか。今はまず曲を最初から最後まで通すところから始めますが。
新山 当時は通らないわけよ。まず通らない。
戸田 だから指揮者に言われたとおりにやるしか ない。
─ 日本の交響作品展が評価されて、1977年に鳥井音楽賞(現サントリー音楽賞)を受賞したわけですが。
都河 鳥井音楽賞候補として決選に新響が残った時、芥川先生は審査委員でした。だから「私は当事者ですから席を外します」と言われて、投票には加わらなかったんだよね。
桜井 席を外すことによって、逆にプレッシャーをかけたのかもよ(笑)
─ 芥川先生ご自身は自分の曲をあまり演奏しませんでしたよね。
都河 個展は1986年の創立30周年の時が初めてです。この「芥川也寸志交響作品展」が交響作品展シ
リーズの最後でした。
土田 そうですね、あれが交響作品展の10回目です。10年目では是非とも先生の個展やりましょうという
ことになったのですが、先生はずっと固辞されていました。でも創立30周年だし、シリーズ最後だからということで、渋々引き受けてくれたんです。
戸田 そう、我々と「絃楽のための三楽章」をやった時も渋々だったよ。自分の作品を新響の演奏会でやるのを遠慮していたのかな。あと師匠の伊福部さんをはじめ、他の作曲家の方が優先だと思っていたのかも。
秋山 自分の作品をやりたいがために新響を振っている、と思われるのが嫌だったのかもしれませんね。
戸田 芥川さんの美学だよね。
大原 30周年の時は誰が説得したんですか。
土田 その時の委員会のメンバーだね。理事長が松木さん(ヴァイオリンOB)、運営委員長が藤井章太郎さん(フルート)、技術委員長でコンサートマスターが故白木さん、インスペクターが柳澤さん(ヴィオラ)。
大原 その当時は都河さんもコンサートマスターでしたよね。
都河 そうでしたが、私自身が説得に行った記憶はないなぁ。
■交響曲第1番、そしてこれから
─ 今回は交響曲第1番を取り上げているのですが、ちょっとショスタコーヴィチやプロコフィエフに似
たところがでてきますよね。
都河 とにかく先生はソ連の作曲家が好きでし たね。
戸田 新響を作る前の1954年に、まだ国交のないソ連に単身ウィーン経由で密入国したくらいだから。
新山 その時にショスタコーヴィチにも会っているんだよ。
戸田 一緒に撮った写真があるよね。
大原 演奏していると「本当にショスタコが大好きなんだろうなぁ」と思います。
土田 ショスタコ、プロコ、そして時々伊福部ね。
新山 この曲の第1楽章を弾いていると涙が出そうになる、本当に悲しくなるんです。青山斎場での先
生のお葬式で第1楽章が流れてたんだよね。
土田 流れてましたね。しかも新響の演奏だった。
新山 そう、新響の演奏。
土田 というか当時は音源がそれしかなかったから。
─ 最後に、現在の新響に対して思うところがあれば伺いたいのですが。
戸田 まぁよくやるよね、という感じかな。それに尽きるよ。昔から「新響の常識は、世の中の非常識」と言われていたけれど、今でもそういうところはありますね。
都河 でも最近の新響はすごく上手いんだけど、なんかパワーがないというか、爆発力がないというか。
新山 芥川さんはよく「新響は下手なプロのようにはならないでくれ」と言っていたね。技術ばかり求めて、熱のない演奏はしちゃいけないよって。
都河 今はちょっとそういう感じがするよね。
大原 音程とか、フレーズの縦の線を合わせるのは手段であって目的ではない、と私はいつも言っていますし、もっと浸透させたいと思っています。でもその両立がなかなか難しくて。新響は真面目な団体なので、音程や縦の線を合わせることも目的の1つなんですよ。
新山 70年代の新響はとにかく下手くそだったけれども、熱のある演奏をやってたよ。あと新響は音がうるさいってよく言われていた。
土田 音がうるさいというのは、雑音が大きいという事でもあった。新響はガチャガチャ弾く、とプロの先生方からよく指摘されていたよね。
戸田 私は娘や孫たちが海外にいるから向こうで演奏会を聴く事が多いのですが、ヨーロッパやアメリ
カのオケは決してうるさくないんです。日本の国民性かもしれませんが、プロオケを含めた日本のオケは、弦楽器の弓に圧力がかかりすぎて大きい音じゃなくてうるさい音になっちゃう。音が「大きい」と「うるさい、でかい」とでは大違いで、日本人の解釈が間違っているのではないかと思うことがあります。あと、一昨年クロアチアへ孫が参加したジュニア・チェロ・コンクールを聴きに行ったのですが、その時は中国の小学生が1位になりました。その子は10回やったら10回とも同じように弾けるなと思った。新響も何度やっても同じような演奏をする、というのでは面白くないと思うよ。
大原 それは飯守先生や矢崎先生、湯浅先生をはじめ、どの指揮者にも言われます。本番は違うのだか
らねって。確かに少し前までの新響は、練習で体に染みこませたものを本番で披露するというのが、長
年のスタイルだったと思います。でも今はそうではなくて、本番は瞬間芸術なのだからその場その時の空気でやろうよ、というのが最近の主流になってきています。最近おつき合いさせていただいている指揮者はそういう考え方の方々が多いですね。
戸田 それは良いことだね。「おっ、そうくるか、じゃあこっちはこうやってやろう」って指揮者とやりあっていくのが良い演奏だよね。そうやっていくうちに音も変わっていくと思います。
─ 今日は遅くまでありがとうございました。
土田 労音時代やソ連演奏旅行の話はもう10回以上戸田さんから伺っていますが、毎回新しいお話が出
てきて面白いよね。それだけ奥が深くて、何度聞いても飽きない。いろいろあったんだなと思うと、とても感慨深いです。
都河 新響60周年って言うけど、大したことではないよ。もっと古いオケは他にもたくさんあるんだから。
─ 新響もまだまだこれから、ということですね。この言葉を噛み締めながら歩んでいきたいと思います。
2015年11月7日
司会・進行:村原大介(ヴィオラ)
聴き手:朝倉 優(ヴァイオリン)、伊藤真理子(ヴァイオリン)
写真撮影:桜井哲雄(オーボエ)
編集・構成:藤井 泉(ピアノ)
エルガー:交響曲第2番 変ホ長調
音楽愛好家にとってロンドンの夏の風物詩と言えば伝統的な音楽行事であるPromsが思い浮かぶでしょう。Promsはクラシック音楽を普段聴きに来ない人でも、チケットが安くて、より親しみやすい雰囲気であれば魅力を感じてくれるのではないかと、ロバート・ニューマンが1895年に企画した音楽祭が現在に引継がれているものです。
Promsの醍醐味はイギリス内外から集まる実力派音楽家達の演奏に夏の短い間に集中して触れられ、それもチケットが買い求めやすい価格であることです。そして、Promsで最も有名なのが最終日の“Last Night of the Proms”です。お祭り騒ぎの終焉にふさわしいプログラム構成(簡単に言うとイギリス人受けする曲が中心)で会場は興奮状態に包まれます。ドレスコードも男性がタキシードと女性がイヴニングドレスと華やかな会場となりますが、演奏会自体はとてもフランクで、オーケストラと一緒に歌ったり、会場で国旗を振り回したり、紙飛行機や風船を飛ばしたり、クラッカーを鳴らしたりと何でもありです。そして、このLast Night of the Promsに必ず演奏される曲がエルガーの「威風堂々第1番」です。この曲は初演の時に3回もアンコール演奏をしたほどイギリス国民の心を魅了している曲で、「第二の国歌」と言われているほどです。国王エドワード7世からも賞賛され、国王は中間部の旋律に歌詞をつけたらどうかとアドヴァイスを与えられたことから、この曲に「Land of Hope and Glory(希望と栄光の国)」の歌詞がつけられLast night of the Promsでも大合唱されます。現在ではProms in the Park と言ってハイドパークやイギリス各地の公園でProms最終日に野外コンサートを行ない、中継を使って本拠地ロイヤル・ アルバートホールと同時刻にこの曲を大合唱しています。
このようにイギリス国民に愛されているエルガーは、1857年に日本でお馴染みウスターソースの発祥地であるウスターで生まれています。父親が楽器店を経営しつつ教会のオルガニストでもあり、その影響もあってエルガーは小さいころから音楽に目覚め幼少の頃から作曲も手掛けています。しかし、経済的な事情で音楽専門教育を受ける機会に恵まれず、父親の楽器店で経理を手伝いながら独学で音楽を勉強していました。若い頃に仲間とオーケストラを設立し、そこではファゴットを吹いていましたが、やがてヴァイオリン修行をしにロンドンへ行き、その後、ウスターへ戻りヴァイオリン・ピアノ教師として収入を得るようになりました。
1986年、エルガー29歳の時にその後の人生に深く関わる人に出会います。エルガーのピアノ教室にキャロライン・アリス・ロバーツが入門してきたのです。この女性こそエルガーの才能を最後まで信じ献身的に支え続ける妻となった人でした。1888年に二人は婚約し、その記念としてエルガーは「愛の挨拶」を作曲しアリスに捧げています。この「愛の挨拶」は今日も名曲として知られていますが、この曲で大金は手に入らなかったようです。というのも、この楽譜は買取りだったので、エルガーは出版元のショット社から5ポンドの報酬を受けたのみで大儲けしたのはショット社であったとのことです。
エルガーの野望は一流の作曲家として世に知られることでしたが、なかなか作品が売れず苦しい生活が続いていました。ようやくエルガーが作曲家として知られるようになったのは実に42歳の時、1899年に作曲した「エニグマ変奏曲」の大成功によります。その後1901年に作曲した「威風堂々第1番」が前述の通りイギリス人の心を捉え、気付くと世界的な有名作曲家となっており、1904年には王室からナイト爵位を授かるまでになりました。そして1908年に「交響曲第1番」を発表すると、この曲は瞬く間に世界へ知られるようになりイギリスを代表する交響曲となりました。
この「交響曲第1番」よりも前に着手されていた交響曲があり、それはスーダンで戦死した名将ゴードン将軍の英雄伝を基にした「ゴードン交響曲」です。この曲は結局陽の目を見ることはなかったのですが、エルガーはこの曲を流用して「交響曲第2番」を「交響曲第1番」の3年後に書き上げました。
元々はゴードン将軍へ捧げる曲だったはずの「交響曲第2番」は一転して敬愛していた英国王エドワード7世に捧げられています。英雄交響曲でお馴染みのベートーヴェン交響曲第3番も元々はナポレオンに捧げようとしましたが、ナポレオンが皇帝に即位すると撤回しています。また二つの曲とも変ホ長調であること、第2楽章が葬送行進曲であることなど構成が似ていることから、この「交響曲第2番」はエルガーの「英雄交響曲」とも呼ばれています。
この曲は完成前に国王が崩御されたため、国王の追悼に捧げられることになりました。国王は音楽の偉大なパトロンでありエルガーの才能を愛しており、エルガーをバッキンガム宮殿の晩餐会にも招いていました。この曲は国王の追悼に捧げられてはいますが、曲自体は追悼のための挽歌ではなく、エドワード7世の平和で繁栄した栄光の時代の叙事詩、回顧といった性格の曲となっています。一方で、この曲はエルガー自身の生涯を表している曲でもあります。それはエルガーが友人に宛てた手紙にこのように書いてあることで分かります。“私は協奏曲、交響曲第2番、そしてオデ(合唱曲「ミュージック・メイカーズ」の歌詞に採られた、アーサー・オショーネシーの詩「Ode」を指す)に自分の魂を書き出した。そして知っているよね、この三つの作品に自分自身を表したことを”
1911年5月24日に行われた「交響曲第2番」の初演は残念ながら失敗に終わっています。演奏が終わった瞬間、観客は呆気にとられたかのように静かで拍手もほとんど起こらなかったそうです。これに対してエルガーは「一体どうしたのだ。皆詰め物をした豚の置物みたいだ。」と感想を述べています。しかしながら、初演から9年後の1920年にエイドリアン・ボールドの指揮によって行われた演奏は大成功を収め、この作品の真の価値が認められました。
今日でもこの「交響曲第2番」はエルガーの最高傑作の一つとして重要なレパートリーに定着しています。
1920年のエイドリアン・ボールド指揮によって演奏された「交響曲第2番」は妻アリスにとってこの世で聴いた最後のコンサートとなってしまいます。数年前から体調が思わしくなかったアリスは、このコンサートの数週間後にエルガーの腕に抱かれて静かに息を引き取りました。アリスを失ったエルガーは創作意欲に陰りが見え始め、その後は特に目立った作品は残していません。1932年にBBCはエルガーに「交響曲第3番」の作曲を委嘱しますが、体調が思わしくなく筆は進みませんでした。そして1933年に体調が更に悪化し入院しますが、その時に大腸癌が既に手遅れの状態であることが判明します。「交響曲第3番」は未完のまま1934年2月23日、エルガーは76歳の生涯を閉じました。
本日演奏する「交響曲第2番」の自筆スコアには謎かけ好きなエルガーが三つの書き込みをしています。一つはスコアの冒頭に書き込んである英国ロマン派の詩人パーシー・ビッシュ・シェリー(1792-1822)の詩の一節です。
Rarely, rarely comest thou, Spirit of Delight!
(めったに、めったに汝は来ない、歓びの精霊よ!)
この書き込みの意味については今日なお論議が続いているのですが、この詩の最後の詩句を調べたところ、厚い友情で結ばれていた亡き国王への想いが表れているのではないかと思われてならない詩句でした。
Spirit, I love thee-Thou art love and life! O come! Make once more my heart thy home!
(精霊よ、汝を愛している! 汝は愛であり、生命だ!戻って来て、もう一度この胸に宿っておくれ!)
二つ目の書き込みはスコアの最後にあるVenice/Tintagelです。いずれも作曲当時エルガー夫妻が訪れた地名で、この曲を作曲する上で何らかの影響を受けた場所と考えられます。ヴェニス(ヴェネツィア)は、同地のサン・マルコ大聖堂の礼拝堂が第二楽章を作曲する際のイメージとしてあったと言われています。またティンタジェルはイギリス最西部コーンウォール地方の街ですが、エルガーが敬愛していた女性、アリス・ステュワート・ワートリー(エルガーはウィンドフラワーと呼んでおり、妻アリスも公認していた女性)が保養していた地です。そのアリスにエルガー夫妻は会いに行っており、エルガーが「この曲はあなたの交響曲なのです。」と手紙にも書くほどアリスの影響を受けたことをスコアに書き残したのではないかと思われます。
そして三つ目はHans himself!の書き込みです。これはエルガーのよき友であり交響曲第1番の初演を手掛けてくれた指揮者ハンス・リヒター(1843-1916)のことです。この曲の初演もリヒターに指揮して貰いたくて書込みをしたのだと思われます。
楽曲は4楽章形式で第1楽章はアレグロ・ヴィヴァーチェ・エ・ノビルメンテ。「ノビルメンテ」はエルガーが好んで使った発想標語ですが、上品に、気高くと言う意味です。「威風堂々第1番」のトリオ同様、高貴な気品に溢れエルガーの作風を感じられるものになっています。第2楽章はラルゲット、「交響曲第1番」と異なり緩徐楽章となっています(交響曲第1番は第3楽章が緩徐楽章)。葬送行進曲のリズムを持つこの楽章は、エドワード7世が崩御した後に作曲されたとも言われていますが、否定的な意見が多いです。第3楽章はロンド─プレスト。曲の途中に第1楽章のチェロ主題が帰ってくる面白い構成になっています。第4楽章はモデラート・エ・マエストーソ。エルガーらしい荘厳な主題で始まりますが、終わりはエレジー風のコーダで第1楽章の冒頭の主題と第4楽章の冒頭の主題とが回想されると曲は次第に弱まり静寂な終わりを迎えます。
初演:1911年5月24日 ロンドン音楽祭にて
エルガー自身の指揮、クィーンズホール管弦楽団により演奏
楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、Esクラリネット、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、タンブリン、ハープ2、弦五部
参考文献
『エドワード・エルガー 希望と栄光の国』 水越健一著(武田書店)
『最新名曲解説全集2交響曲II』(音楽之友社)
芥川也寸志:交響曲第1番
芥川也寸志(1925~1989年)は、桁外れな行動力と企画力を持った「作曲家」「社会運動家」であり、その生涯を音楽活動に挺身した。作曲活動だけにとどまらず、まさに獅子奮迅の多面的活躍で、日本 の音楽文化向上に多大な貢献を残した「音楽家」であった。
作曲家としてあらゆる分野での音楽の創作活動はもちろんのこと、特に後半生での顕著な活動として「音楽は人間が生きていくうえで、なくてはならないもの。音楽はみんなのもの。」という信念のもとに、音楽の啓蒙と音楽家の権利を守るための活動、平和のための社会運動にも奔走し、多くの作品や著作と共に業績を残している。團伊玖磨の弔辞「黛敏郎の言葉を借りれば、芥川也寸志の最後は壮烈な文化への戦死であった、ということです。」(1989年2月27日青山斎場葬儀)と言わしめた。
桁外れな行動の一つとして、1954年に当時国交のなかったソヴィエトへ、常識では帰国が保証されない状況の中での潜入(密入国)を敢行、ショスタコーヴィチやカヴァレフスキーと親交を結び、ソヴィエトでの作品出版による印税を手にして帰国、という冒険譚が有名である。
芥川也寸志の全貌に触れるには、紙面が限られているので「交響曲第1番」作曲までの前半生に集中して筆を進めていきたい。
生涯の前半
芥川也寸志は、文豪芥川龍之介の三男として東京府北豊島郡滝野川町大字田端(現北区田端一丁目)に生まれた。東京高等師範学校附属中学校(現筑波大学附属高等学校)4年の時に音楽の道へ進むことを決意、1941年から橋本國彦に作曲、井口基成にピアノを「バイエル」から手ほどきを受けている。1943年東京音楽学校(現東京藝術大学音楽学部)本科作曲部入学、橋本國彦に近代和声学と管弦楽法、下總皖一と細川碧に対位法、永井進にピアノを学ぶ。翌1944年に学徒動員で陸軍戸山学校軍楽隊に入隊し、テナー・サキソフォンを担当する。この時に「第三種兵器」として与えられた楽器には “Made in USA”の刻印があったという。軍楽隊では実技の傍ら連歌隊や行進曲の作・編曲にもたずさわり、その作業から管楽器に関する知識を得た。
1945年東京音楽学校に復学後、講師として着任した伊福部昭の講義に感銘を受け、以後生涯の師弟関係を結んでいる。1947年に本科卒業作品として「交響管絃楽のための前奏曲」、1948年に自己のキャラクターを明確に打ち出した「交響三章」を発表、そして事実上の出世作ともいえる「交響管絃楽のための音楽」を1950年に発表し、NHK放送開始25周年記念管弦楽懸賞の特賞に入選、名声を確立した。(その賞金で家を買ったという話は生前よく伺った。)
1953年、当時のスター作曲家のグループとして「三人の会」を團伊玖磨、黛敏郎と共に結成。センセーショナルな出来事として日本の作曲界に多大な影響を与えた同年、弦楽に対しても並々ならぬ手腕を発揮した「絃楽のための三楽章―トリプティーク」を発表し、以上の三作で作曲家としての不動の地位を築き上げる。
このようにして芥川也寸志は、日本が太平洋戦争に敗れて低迷していた戦後という時代の楽壇に、彗星の如く颯爽と登場したのである。
橋本國彦が、戦後の自由な環境の中で創作の腕を揮った1947年発表の「交響曲第2番」(新交響楽団第229回演奏会[2015年4月19日 湯浅卓雄指揮]で演奏)でみられる開放的で抒情性がありながら、どこか内向性と懐古的表現に充ちた音楽とは根底が異なり、新しい時代の中で躍動感と推進力に満ちた作品を次々と発表。まさに時代の寵児として活躍の第一歩を踏み出したと言える。
明快な音楽
芥川也寸志の音楽はとにかく解り易い。フランス・アカデミズム風音楽から、深く心酔していた伊福部昭の土俗的で強靭なオスティナート(執拗な反復)を多用した音楽、橋本國彦に通ずる都会的モダニズムといったスタイリッシュな音楽、ロマン的でセンチメンタルな節回しで甘くカンタービレな志向、そしてソヴィエト流社会主義リアリズムに傾倒し、ショスタコーヴィチやプロコフィエフといったロシア国民楽派の流れを汲むソヴィエト現代音楽をそれぞれ範として、見事に共存相乗させている。
明快でダイナミック、そして甘美なリリシズム、ストレートで魅力的な旋律、独特な躍動するリズム、生き生きとした生命力あふれるリズム構成、多面的な表現力は、芥川也寸志の作品の魅力といえる。そして「交響曲第1番」にはその魅力が満載である。
交響曲第1番
1954年「三人の会」第一回発表会にて「シンフォニア」として発表、その後、前述のソヴィエト渡航を経て1楽章と2楽章の間にスケルツォ楽章を加えて4楽章形式として改作した。
重苦しく暗い抒情を持ち、またこの作品以前に試みられた書法が集大成され、交響曲を作曲するにあたり並々ならぬ意気込みが窺えるスケールの大きな重量感ある大作である。
ショスタコーヴィチやプロコフィエフへの共感を強く滲ませ、ところどころに伊福部昭が出現、という印象があるが、ショスタコーヴィチのような冷徹で強靭な曲想を分かり易く解釈し、厳しさと謙虚さを同居させ、現実認識への鋭い批評精神と使命感を、全曲にわたって循環主題の如く登場する「リズム動機」(譜例1~4)として自己を表現しているものと思われる。そして躍動感と推進力は、根底として「リズムは生命に対応するものであり、あらゆる音楽の出発点であると同時にあらゆる音楽を支配している、リズムは音楽を生み、リズムを喪失した音楽は死ぬ」という信念の表現ともいえるだろう。
尚、改作初演された1955年12月8日の直前、11月9日に当時の「労音アンサンブル」が初めて指揮者に芥川也寸志を迎え、翌年1956年3月1日、新交響楽団が正式に発足(規約発効)、芥川也寸志は音楽監督・常任指揮者に就任している。
第1楽章 アンダンテ 4/4拍子
ソナタ形式。四六の短三和音のクロマティックな下降に支えられて深刻な旋律が上行する。この旋律は、前述の「リズム動機」と共に曲の進行につれて形を変えて登場することで交響曲の有機的な統一と一貫性を導いており、また和音の平行進行、クロマティックな下降、上声部と下声部の反進行は、交響曲の構造を支配している。その後発展して短三和音の響きの中で「リズム動機」が明確に登場。「リズム主題」から導かれた弦楽器のシンコペーションに乗って木管楽器により出現する第2主題ともいえる旋律は、抒情的な美しさに満ちている。そしてショスタコーヴィチのような厳しさをもって弦楽器に冒頭のモチーフと似た旋律が登場。伊福部昭のような壮大で重厚な響きを経て、他の様々なモチーフと組み合わされて再現部に進み「リズム動機」を回顧して静かに終わる。
第2楽章 アレグロ 2/4拍子
軽快なスケルツォ。弦楽器で提示される主題が木管楽器、さらに金管楽器に渡されて、というように小気味よく進行。「リズム動機」を思わせる主題が、弦楽器のユニゾンから、木管楽器、金管楽器と加わって、各楽器群が各々鳴りやすい音域の中で自然に最強音に達するよう周到な配慮が施されて圧倒的なユニゾンで終わる。
第3楽章 「Chorale」アダージョ 2/4拍子
長短三和音の組み合わせによるコラールは、パッサカリアのごとく反復されるごとに重層的に塗り重ねながら発展していく。対位法的な中間部ののちに「リズム動機」が復元され、コラールが再現されていく。
第4楽章 アレグロ・モルト 4/4拍子
短三和音が主体となって律動的で時には諧謔味も効かせて快活に進行。プロコフィエフのバレエ音楽に登場するような転調を続ける速いリズムパターンがオスティナート的に展開、長三和音と短三和音のクロマティックな下降の対比が鮮やか。突然fffで1楽章冒頭のメロディーに似た旋律が、映画のワンシーンのごとく登場、増三和音が響き渡る中で金管楽器により朗々と鳴らされ、強奏の後に「リズム動機」が回顧されてくる。そして冒頭のリズムパターンが再現されて、不屈な魂を表現するかの如く、増幅された圧倒的なエネルギーと共に一気呵成に駆け抜ける。
音楽に対する限りない憧れと情熱
音楽だけにとどまらない多面的な行動力は、新交響楽団の創立以来、音楽監督としての生涯にわたる活動にも生かされている。緊張に満ちた練習と妥協を許さない厳しい要求、「アマチュア」という言葉を音楽的能力の不足の言い訳には決してさせないという厳しい姿勢、技術の巧拙とは無関係に、愛する音楽を損得抜きで徹底的に高めなければならない、という決然とした理念がそこにはある。音楽への憧れと情熱を具現化し、「音楽」を社会の中に育て広げていくのには何が必要かを問い続けた表れの一つとして、アマチュアのオーケストラや合唱団への地道な指導と指揮活動があった。
三代続く江戸っ子としての矜持とも思える感激屋的な気質と実行力は、自己の主張は曲げず、しかし相手の言うこともよく聴くという生来の長所として時々「照れ屋さん」となって垣間見え、新交響楽団の企画と運営、演奏面での向上に大きな足跡を残している。新交響楽団の中だけでも残された数多くのメッセージ、思い出や証言等をまとめると、きっと「芥川也寸志大全集」として何十冊もの分量となるにちがいない。
新交響楽団は、「交響曲第1番」を1986年に創立30周年記念「日本の交響作品展10」(113回演奏会)で作曲者本人の指揮で初めて演奏、その後も没後1年として1990年に故山田一雄(第126回演奏会)、トレーナーの森山崇(松伏町)、没後10年の1999年に飯守泰次郎(第166回演奏会)で演奏してきている。
本日はおよそ20年ぶりの再演となるが、新交響楽団創立60年を迎えた最初の演奏会の初めに「交響曲第1番」を湯浅卓雄の指導により演奏することは、単なる「再演」ではない。すでに没後27周年を迎え、この作曲家の謦咳に接したことのない団員も多くを占めるに至った今、「指揮者」「指導者」「社会運動家」「文化人」「タレント」ではなく「音楽家」としての芥川也寸志の作品に真摯に対峙することによって、新交響楽団の新たな音楽創造の第1歩としての「演奏」が実現するものと確信している。(文中敬称略)
初演:1954年1月26日「三人の会」第1回演奏会
日比谷公会堂 東京交響楽団
指揮/芥川也寸志
改作初演:1955年12月8日東京交響楽団第74回定期演奏会
日比谷公会堂 東京交響楽団
指揮/上田 仁
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン6、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、小太鼓、タムタム、木琴、ハープ、弦五部
参考文献
『芥川也寸志 その芸術と行動』 出版刊行委員会編(東京新聞出版局)
『芥川也寸志 交響曲第1番』(全音楽譜出版社)
『芥川也寸志 没後10年』 新交響楽団第166回演奏会パンフレット(新交響楽団)
「芥川也寸志と新交響楽団」の晩年
当初こそ恐る恐る自分の体験を書いていたが今や何の遠慮も臆面もなく私的な回想を書くようになってしまった。今回もお許し戴きたい。
私は新交響楽団が設立された翌年の生まれで、つまりはこのオーケストラとほぼ同年齢であるという事に、迂闊にも最近になるまで気づかなかった。考えるだに恐ろしいが、新響は来年2016年に創立60周年を迎える。この記念すべき年の演奏会企画は何年も以前から団内で取り沙汰されていたにもかかわらず、「60周年」の時期を、自分の人生の行く末と重ね合わせて考えた事が全く無かったのだから、締まらない話である。まぁそれは仕方がない。
◆1987年2月の会合
新響に入団したのが1982年。25歳目前の時期で、新響は設立以来四半世紀を経ていた事になる。むろんこのオーケストラは常に芥川氏と共にあった。もはや歴史というより神話の時代に入りかけているソ連への演奏旅行や、ストラヴィンスキーの三大バレエ音楽一挙上演。そして創立20周年の折(1976年)には芥川氏の企画力と指導力により、『日本の交響作品展』を挙行し、「芥川也寸志と新交響楽団」として翌1977年にサントリー音楽賞を受賞。どれひとつとってもアマチュアオーケストラとしては未曾有の快挙であり金字塔だった。
指揮者とオーケストラとは程度の差こそあれ絶えず緊張関係が介在するものだ。だが前述のような歴史を築き上げる中で、芥川氏と新響は長く蜜月時代を送ってこられたのではないかと想像できる。思うにサントリー音楽賞受賞という大きな成果を得てからの数年間が、彼と新響の歴史の中でも充実し活気に溢れた活動を展開した時代だったのではなかろうか。
だが私が飛び込んだ1982年時点では、団内にはやや異質な空気の萌芽が既にあり、それは時を経るにつれ濃厚になっていったように思える。本来蜜月とは長くは続かないからこそ蜜月なのだ(この齢になれば断言できる)。
この時期になると、芥川氏という親の庇護の下に未だありながら、無体に背伸びしたがる思春期を、新響というオーケストラは迎えていた。強いて言えば、指揮者としての芥川氏の「音楽(性)」に飽き足らないものを感じ始めたという事もあろう。また団員の世代交替(後でも述べる)に伴い、新響を支えてきた組織の制度疲労に起因する矛盾や問題も表面化しつつあった。ひとたびそうした時期に入ってしまえば、元の「子ども」の時代に戻る事はあり得ない。芥川氏も練習を通じてそれを敏感に感じ取り、常に何らかの苛立ちが介在していた印象が強い。
例えば氏が音楽監督である事を前提にしたオーケストラの諸制度は、活動の実状から次第に乖離したものになっていたと感じる。管楽器奏者各員の出番(ローテーション)は、各パートの首席奏者が独自に決め、音楽監督が最終的に承認するという形に(少なくともタテマエは)なっていた。だがそれは団の草創期のように芥川氏が毎回の練習に指揮者として指導し、全団員にくまなく目が行き届いて個々の技量を正確に把握出来てこそ初めて成り立つ。130名以上の団員を抱え、且つ氏が指揮をしないシーズンにまで適用できる制度ではなかろう。そして実際、各パート間の情報共有もなく、より有効なパート間の人員配置(残念ながら長く同じオーケストラで演奏活動をしていても、奏者間の相性の良し悪しと言うものは存在するものなのだ)への配慮も行われず、その為初回練習で隣に座った他パートの人と「おや、貴方が今回はこの曲に乗っておいでですか」と挨拶を交わすのが常態で、今考えると笑い話のような光景だ。現在このローテーションのすり合わせは、演奏委員会の重要な職務のひとつとなって久しいから、まさに隔世の感が深い。
更に団員誰の目にもはっきり目に見える不合理として、芥川氏が「君臨」する練習の場にその理由があった。当時も今も練習への出席率や5分前にはチューニング開始といった基本部分は全く変わっておらず、こうした決まり後とが新響を支える根幹である事に変わりはない。だが当時は氏が指揮台に立つや、あとはどのような時間配分や曲順になるかはこの指揮者の胸先三寸で、管楽器奏者はいつ来るか判らぬ自分の出番に備えてひたすら外で待機し、結果として最後の10分しか出番が無いという事もままあったのだ。
さすがにこうした練習方法については抜本的な見直しが必要だとの認識が団内に醸成されつつあった。また新響がオーケストラとしての合奏の技術に行き詰まっているのではないかとの認識も急速に浸透しつつあった。「アマチュア」の勢いを失わず、且つ合奏の技術を高めてゆくのは、現在の新響でもはっきり難しい。況して芥川氏は「勢い」を最優先に考えており、これを矯めてまでして合わせる事を、少なくとも積極的には新響に求めていなかった(はっきり言えば否定していた)。
コンサートマスターにして技術委員長だった白木善尚氏(昨年12月他界。享年58)が主体となり、インスペクターの役職を設けて練習計画の策定や時間配分を芥川氏と事前に確認する道筋をつけると並行して、合奏体としての技術を高める為の方法論が運営委員会の場でさえ議論されるようになった。
平素より勢いや元気を優先する新響の演奏に対し(主に酒席で)不平を抱いていた私は、考えるところを10ページほどの資料にまとめて合同委員会の席上で呈示した。それが白木氏や初代インスペクターとなったヴィオラ首席の柳澤氏の目に留まり、インスペクターグループの一員に組入れられる事になった。これが1987年の半ばである。
さて、当時の新響規約を目に出来ないのでやや記憶は曖昧だが、現在の団長の職名は「理事長」と云い、その下に技術委員会や各運営業務を統括し代表する5名の「理事」がいて、「理事会」を構成する。このメンバーが新響側を代表して、音楽監督である芥川氏と意思決定に携わるという制度だった。今回当時の日記を読み返して改めて判ったが、インスペクター制度が始動して間もない時期から、このグループからも理事を出す話が持ち上がり、年末の総会で私が承認された。と言っても、ボンヤリ総会の会場に入ったら開会直前に柳澤氏に手招きされ、「お前やってくれ」と闇雲に言われて気づいた時には承認されていたという経緯。だがとにもかくにも入団5年、満30歳にして新交響楽団の理事になった。今こう書いてみても何か立派そうだ。確かに当時は一介の運営委員に過ぎなかったのだから一種の大抜擢で、我ながら大した出世である(笑)。そして何をやれば良いのかの説明も受けず(説明しない方も問題だが)に引受けたのだから、偏に愚かというべきであろう。
その最初の理事会に出席すべく芥川邸に赴いた日の事である。1988年2月7日日曜日の晩。新響に飽き足らない私は東京マーラーユーゲントオーケストラ(TMJ)という団体の代表となり、3週間足らずに迫ったサントリーホールでの演奏会の練習とかけもちだった。ソ連という国家もベルリンの壁も磐石と思われた冷戦時代末期(文中の「左傾化」の語も今では想像さえ難しいだろう)、日本はバブル景気で騒々しい時代だ。
私の日記の当日の条に以下の記述がある。やや長いが引用する。
(前略)・・・・私はと云えば調子の悪い分奏で練習を終えると皆と別れ、成城に向かった。新響の理事会の為、芥川氏邸に集まる予定であったのだ。メンバーは土田・R.K.・白木・北村・S.K.(注:原文はいずれも実名。現在も新響に在籍若しくは故人のみ原文のままとした)そして私の6名である。私は今回新たに理事会の構成メンバーに加えられたインスペクターの代表としての出席である。
この晩、来年7月のコンサートに際して細川俊夫氏に委嘱作品を依頼するか否かが焦点となった。「広島」をテーマにした人声や録音をも使用したものとする計画について、作曲者自身の言により確認しているが、何せテーマがテーマである。私個人の気分としては、日本の社会状況を考える限り、余り乗り気にはなれないのだ。過度に左傾化した現状を考えると、実にこのテーマはとらえ難いものとなってくる。妙に政治臭が漂い、後に新響の歴史を振り返った時、何やら実にエゲツナイ行動をとったと評価されはしまいかと不安になってくるのである。これは漠然とした不安以外の何ものでもないが、私は一種の胸さわぎを覚える。
芥川氏もこの点に触れ、団員のコンセンサスがとれることが最重要の由語ったが、同時に何故細川の作品を新響がやらねばならないのかが全く不可解、との旨も明言した。正直な処不快感を拭い得ぬという様子であった。私は我が意を得た(部分的に!!)。確かに細川氏の作品を今とりあげなければならぬ必要は何もないのである。
会合は10時すぎまで続いた。・・・(以下略)
芥川氏は翌年1月末に亡くなっているから、この会合は氏の最晩年の時期だった事に思い当たる。更に云えば僅か2ヶ月後の4月24日、芥川氏が保存運動の先頭に立った上野の奏楽堂での演奏会が、新響との最後のコンサートとなった訳だから、この晩に彼が示した新響の活動への不満は、結果として「遺言」とも言える性格のものになった。そして「広島をテーマにした」作品は『ヒロシマ・レクイエム』と題されて翌年7月に委嘱初演されている。だが、それは最終的に第5部にまで膨らんだこの作品の冒頭のふたつ楽章に限られてしまい、初演の記録にも新響の名は残っていない。芥川氏の懸念はある意味で的中していたとも言える。
◆永続すべき組織と個人の宿命と
ここまでの拙文を読まれた方は、殊更に芥川氏と新響の運営陣が対立する図式を思い浮かべるかもしれない。こうした誤解の発生を最も私は恐れる。
この晩芥川邸を訪れた6名は、実は私に限らずみな30歳そこそこの世代だった。つまり新響と変わらない「年齢」で、もちろんこのオーケストラの誕生前後の事をなにひとつ体験していない。だがこの世代はそれぞれが学生時代に所属したオーケストラを通じ、新響とは別の「アマチュアオーケストラ」のあり方を体現して来ていた。そうした目に映る新響の実状には、これは敢えてネガティヴな言い方をすれば、疑問やある意味の悪弊を感じる部分があった。また当然ながら新響という団体の活動を今後このようにしていきたいという意慾が根底にあった。そうした将来的な活動の可能性のひとつとしてこの日、委嘱作品の話が俎上に上った訳で、これは我々にとってはあくまで一例に過ぎない。
芥川氏が毎回企画して1976年から続いていた『日本の交響作品展』は既に創立30周年に当たる1986年に終了していた。新響と言えば邦人作品とのイメージを流布させたこの輝かしい企画も、年を経るにつれそれにふさわしい「作品」や作曲家の候補が先細りとなり、集客や団員の士気を保つ事が困難になっていった。そして団員側からの逆提案で氏の作品展とする事でその掉尾を飾る事になったのである。彼は「自分の作品を新響で演奏したいが為にこの企画を始めた訳ではない」と当初は難色を示したと聞いた。だが作品展の行き詰まりは誰の目にも明らかとなっていたのだ。
翌1987年には『中国作品展』を芥川氏の提案で行っている。今とは比較にならぬほど中国は「遠い国」で、そこから作曲家や演奏家を招聘するには彼の政治力・影響力が必須だった。これは当初から単発ものであったので、1988年以降の企画に頭を悩ました結果として団員サイドから出てきたのが細川俊夫氏への作品委嘱というアイディアだった。この案は『日本の交響作品展』企画が進行していた時期には到底想定され得ないものだったと想像する。その是非については、この音楽監督の入院による沈黙とその末の逝去によって、永遠に答えを得られなかった。つまり見切り発車の形で翌年実行された事になる。
組織にとっては、ある時点の条件化では必然だったり最善だったりした事も、時間の経過と周囲の条件の変化によって、やがて弊害が生じて必ず見直しを迫られる時期が来る。創立から一世代30年の時を経て、新響という組織も確かにひとつの転機を迎えつつあった。芥川氏の晩年がちょうどそれに重なりってしまった事は、組織と個人の「寿命」の差異の象徴にも思え、創立から30年間の「芥川也寸志と新交響楽団」の時代に彼が成し遂げたまばゆいばかりの活躍の軌跡を思い起こすとき、尚更の感慨を禁じ得ない。
30年近い時間が流れ、あの場にいた我々も当時の芥川氏の年齢に近づいた。「還暦」を迎える新響に対し、有限な存在が新響という組織に改めて、何を遺すべきかが問われているとも言える。当時の彼が我々の世代に対して抱き続けた「伝える姿勢」こそに、いま想いを致すべきなのだろうと思うのだ。
知られざる名曲 エルガーの交響曲第2番
維持会員の皆様、いつも応援頂きありがとうございます。第232回演奏会で取り上げるエルガーの交響曲第2番について書かせて頂きます。
さて、普段クラシック音楽に親しんでいらっしゃる方でもエルガーの交響曲をご存知の方は少ないのではないでしょうか。私も今回演奏会の候補となるまで演奏したことも、聴いたこともなく、また正直なところ興味の対象外でした。私が知っているエルガーの曲といえば『威風堂々』、『愛の挨拶』、そして新響でも取り上げた『エニグマ変奏曲』の他にはチェロ協奏曲位でしょうか。オーケストラのレパートリーとして広く親しまれているのは『威風堂々』の第1番、そしてやや通好みかもしれませんがエルガーの出世作である『エニグマ変奏曲』も取り上げられる機会が多い曲です。またチェロ協奏曲も今日では名曲として知られていますが、この曲の知名度は悲劇の天才チェリスト、ジャクリーヌ・デュ・プレの影響によるところが大きいでしょう。特にエルガーやイギリス音楽のファンでもない私が今回この文章を書いているのは全く未知だったエルガーの交響曲第2番を演奏する機会を得たことに大いなる喜びを感じているからです。ですから専門的なことではなく、一ホルン奏者の個人的かつ主観的なこの曲への思いを書かせて頂きます。
といいつつもまず若干解説的なことを書かせて頂くと、エルガーは42歳の時に作曲した『エニグマ変奏曲』により作曲家としての名声を確保します。そして『威風堂々』第1番の大成功、交響曲第1番、ヴァイオリン協奏曲と初演時から好評で迎えられます。しかし、ヴァイオリン協奏曲の翌年に作曲されたこの交響曲第2番の初演は不評で成功とは言えませんでした。ちなみにチェロ協奏曲の初演も失敗で、真価を認められるまで時間を要しています。
さて、交響曲第2番の初演が不評だったことの個人的な推察です。交響曲の第1番も第2番も演奏時間60分近い大曲です。第1番はフランクの交響曲のような循環形式にて作曲されていて、冒頭に提示されるテーマが繰り返し演奏されます。またこのテーマが明らかにテーマと分かる聴き取りやすい旋律であり、初めて聴いた人も繰り返されるテーマに親しみを感じられたことが初演から好評だった一因とも考えられます。それに対して第2番は華やかな曲想で快活な部分も多いのですが、音が多く、動きが細かい、悪く言えば騒がしい印象を与える可能性もあり、もう少し整理して聴きやすくしたらと思わないでもない一面があります。多分、初演が失敗だった要因としてエルガーが書いた情報量が多すぎて聴衆の多くが戸惑ったのではないでしょうか。また静かに消えるように終わる最後が肩透かしだったとも言われています。今日でも第1番の支持者は第2番を好まず、第2番の支持者は第1番を好まないという傾向があるようです。
この文章を書いているのは約3か月の練習期間の半ばですが、私は毎週、この曲の練習をすることをとても楽しんでいます。とんでもなく難しい箇所や金管奏者として耐久力を要求されることはあるのですが、それでも音を出すことが気持ち良いのです。それは大学のオーケストラに入り、いつか演奏してみたいと思う曲が沢山あって、あこがれの曲を演奏できる新鮮な喜びを感じていた若かりし頃に近い感覚かもしれません。
少し話がそれますが演奏者というのはどの楽器であっても基本はその楽器の音が最も美しく心地良く響く、いわゆる良い音を目指し日々研鑚を積んでいます。ですが音楽表現というものは心地良い音だけでは成り立ちません。時には演奏者が不快に感じる音も要求されますし、その曲が生まれた文化背景によっては奏者が好むスタイルとは異なる音質や表現が求められることもあります。我々日本人の演奏者はもちろん一人一人の趣味嗜好は異なるものの、ベートーベンやブラームスなどドイツ音楽が好きで、目標はベルリンフィルと思っている人が比較的多いと思います。
新響は最近でこそフランス音楽を得意とする矢崎氏の薫陶を受け、フランス物を少しはそれらしく演奏することも出来るようになってきましたが、やはり、フランス音楽やロシア音楽のスタイルが身に付いている訳ではなく、「ドイツ音楽ではないのだから」という注意を受けながらのリハーサルを経てなんとか演奏会を迎えています。
今でこそ世界中のオーケストラが国際化して国毎の特徴が薄れつつありますが、少し前であればフランスのオーケストラ、ロシアのオーケストラなどとても個性ある音色を持っていて真似しようと思っても出来るものではありません。もちろんフランス的なとかロシア的なというものが音色の猿真似ではなく、可能な範囲での音質の調整、発音やアクセント、アーティキュレーションなどの工夫し、その曲にふさわしい音楽表現を実現していくものなのですが、不慣れな曲への戸惑いや違和感を覚えながら、ということが無くもありません。
誤解なきように付け加えるなら新響はどんな曲であってもその曲の本質を捉えた演奏をしようと真摯に取り組んでいます。そして毎回の演奏会で反省を踏まえながらも少なからず達成感を得ることが出来きています。アマチュアとしての限界はあるものの、真面目に取り組んだことは結果に反映されることを知っていて常にベストを目指すというのが新響の良いところと自負しています。
さて、ではエルガー的なイギリス的な音とはと考えてみると、例えばイギリスのオーケストラでもオーボエとかクラリネットとか楽器によってはとても特徴的な音色を出しているものもあります。ですがイギリスのオーケストラの音は音色的な特徴というよりも総じて自然体で無理が無く柔らかく豊な響きを持っていることにあるように思います。エルガーのスコアには、あまり馴染みのないnobilmente(上品な、気品のある)という指示がありますが、正に上品で気品のある音こそイギリス的な音の特徴です。そして、そのような音は先に書いた各演奏者がその楽器にとっての理想とする良い音を出そうとすることに通じるのです。それゆえ難しい箇所はあっても音を出すことにストレスがなく、演奏していて音を出すことが心地よいと感じられるのだと思います。
話が脱線してしまいましたが、ホルン奏者の視点でのエルガーの交響曲第2番の魅力を書きたいと思います。
まずこの曲は変ホ長調で書かれています。変ホ長調は調性の性格的には「壮大で英雄的」と言われています。変ホ長調で書かれた名曲としてはベートーベンの第3交響曲『英雄』を始め、シューマンの第3交響曲『ライン』、R.シュトラウスの『英雄の生涯』とホルンが活躍する「壮大で英雄的」な曲が並びます。またホルン協奏曲には変ホ長調で書かれたものが多く、ホルンと最も相性の良い調性であり、ホルンが朗々と鳴り響きく調性なのです。そしてこの曲もその例に違わず全楽章に渡り、ホルンが大活躍します。またホルンに限らず金管楽器の出番が多く、また金管楽器に細かい動きまでも要求していることに特徴があります。それは金管バンドの活動が盛んな金管大国イギリスならではと言えます。この曲は「エルガーの英雄交響曲」と呼ばれることがあります。それは元々、チャールズ・ジョージ・ゴードン将軍という英雄と称える曲を書こうという動機があったこと、ベートーベンの『英雄』交響曲と同様に第2楽章が葬送行進曲風であることなどからですが、曲の完成時にはゴードン将軍を称えるという動機は薄れていたようです。また葬送行進曲は国王エドワード7世の崩御に対して書かれたとされることがあるようですが、実際は親友のアルフレッド・ロードウォルドへの追悼だったというのが真実のようです。また故エドワード7世に献呈されたこの曲は大英帝国の黄昏と形容されることもあり、華やかでもあり、気品と優雅さを備えながら、懐かしさや慈愛に満ちており、20世紀の初頭に作られたロマン派の音楽の集大成でもあります。総合的にはエルガー独自の音楽でありながら、部分的にはワーグナーやブルックナー、あるいはシベリウスなどを連想する箇所もあります。
また多彩なオーケストレーションによるダイナミックなオーケストラサウンドはハリウッドの映画音楽の先駆け的でもあります。実は私が最初にこの曲のCDを聴いた時にイメージしたのは『スターウォーズ』です。
第1楽章冒頭からの華やかな音楽は勝利の凱旋を想起させ、私的には『スターウォーズ』第一作エピソード4の最後、ルーク達がメダルを授与される式典が頭に浮かびました。憂いを帯びたチェロによる第二主題の後の展開部は静かな部分が多いのですが、陰影や色彩の変化に富み、ここも無重力の宇宙空間の漂いを感じます。壮大な一楽章の最後はホルンにさえ、2オクターヴの半音階の上昇音型を演奏させ華やか終わります。
葬送行進曲と言われる第2楽章は確かに葬送的な音楽ではありますが、荘厳さの中にも激しい感情の起伏も感じられ、深く感動的な音楽はブルックナーのアダージョに通じるものがあります。第2楽章は本当に感動的で個人的にはこの交響曲の一番の聴き所だと思っています。
続く第3楽章は軽快なスケルッツォですが、演奏する上ではとても難しい楽章です。8分の3拍子のプレストの楽章でありながら16分音符の音型をホルンやトロンボーンが演奏することを要求しています。第3楽章は内容的には軽めだと思いますが、変化に富み、楽しめる音楽だと思います。
第4楽章はチェロと低音管楽器によって静かなテーマで始まりますが、紳士的であり懐かしさや郷愁を感じます。この楽章全体に過去の栄光を懐古するといった趣があり、それが黄昏と呼ばれる所以でしょう。この楽章の第二主題ではエルガーが自筆のスコアに親友である大指揮者ハンス・リヒターに対し、「これは君自身だよ」と書き込んでいますが、この朗々かつ堂々としたテーマはとても印象的です。展開部では非常に難しい音型が続き、演奏者にとっては難所が続きます。終盤では様々な主題が交錯し大きな盛り上がりをみせるものの、最後は第1楽章の主題を回想しつつ静かに消えるように終わります。この終わりこそがこの曲の魅力であり、寂しさや懐かしさを感じつつなんとも心地よい余韻を残してくれるのです。
さてここまで書いてきたようにこの曲の魅力は素晴らしい旋律、テーマに満ちていること、ダイナミックなオーケストラサウンドを堪能できることです。全楽章にこれでもかと溢れる旋律はどれもが魅力的で、素直に音楽って良いなと感じられます。ですが下手な演奏をしてしまうと整理がつかずにただ騒がしい音楽になってしまう可能性もあり、またアンサンブルの乱れが曲を台無しにしてしまうことも有り得ます。指揮者の湯浅氏はこの曲は20世紀の交響曲の最高傑作のひとつとの思い入れを持っており、演奏会に向けてこの曲の魅力が最大限に伝えられるように団員一同準備しておりますので、どうぞ湯浅卓雄/新交響楽団によるエルガーの交響曲第2番にご期待ください。
第232回ローテーション
| 芥川1番 | エルガー2番 | |
| フルート1st | 岡田 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 吉田 |
| picc | 藤井 | 兼子(+3rdFi) |
| オーボエ1st | 山口 | 堀内 |
| 2nd | 桜井 | 山口 |
| C.I. | 岩城 | 岩城 |
| クラリネット1st | 品田 | 高梨 |
| 2nd | 石綿 | 大藪 |
| Es.Cl | - | 末村 |
| Bass.Cl | 進藤 | 岩村 |
| ファゴット1st | 浦 | 藤原 |
| 2nd | 田川 | 笹岡 |
| C.Fg | 笹岡 | 田川 |
| ホルン1st | 大内 | 箭田 |
| 2nd | 市川 | 大内 |
| 3rd | 大原 | 山口 |
| 4th | 宮田 | 大原 | 5th | 菊地 | - | 6th | 山口 | - |
| トランペット1st | 北村 | 小出 |
| 2nd | 倉田 | 野崎 |
| 3rd | 中川 | 倉田 |
| トロンボーン1st | 志村 | 武田浩 |
| 2nd | 武田香 | 武田香 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 古関 | 桑形 |
| パーカッション | シンバル/桜井 大太鼓/桑形 小太鼓/今尾 シロホン・タムタム/皆月 |
シンバル/古関 大太鼓/今尾 小太鼓/今尾 タンバリン/桜井 |
| ハープ | 見尾田(*) | 見尾田(*),堀之北(*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(大隈) | 堀内(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(田川) | 小松(田川) |
| ヴィオラ | 槇(村原) | 柳澤(村原) |
| チェロ | 柳部(安藤) | 柳部(安田俊) |
| コントラバス | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) |
(*)はエキストラ
第232回演奏会のご案内
2016年は新交響楽団創立60周年
人間でいえば還暦、アマチュアオーケストラとしての可能性を模索し活動をまいりましたが、今一度振り返り新しい出発とすべく、創立60周年シリーズとして新響らしい企画で取り組んでいきます。
新響の前身となる東京労音アンサンブルが、当時すでに作曲家として世に知られていた芥川也寸志を招聘し、1956年に発足しました。芥川は、演奏のみならず運営にも深く関わり1989年に亡くなるまで新響を愛してくださいました。
芥川の大作「交響曲第1番」
今回の演奏会では創立60周年シリーズの第一弾として、芥川の交響曲第1番を、多くの日本人作品の録音で知られる湯浅卓雄の指揮で演奏します。
黛敏郎、團伊久磨とともに活動をしていた「三人の会」の第1回演奏会のために作曲されました。3楽章形式でしたが、その後ソヴィエトへ渡航しショスタコーヴィチやハチャトリアンなどの名だたる作曲家たちと交流して帰国後、第2楽章が加えられ4楽章からなる「交響曲第1番」として初演されたのが、ちょうど60年前のことです。第1番とつけられましたが、番号付きの交響曲はその後書かれませんでした。
芥川作品の特徴は、明るく快活で、わかりやすい和音と親しみやすいメロディです。この曲は少々重厚な曲想ではありますが、30歳の若いエネルギーに満ち、ソヴィエト音楽への憧憬が垣間見える愛すべき作品となっています。「交響管弦楽のための音楽」や「トリプティーク」がコンサートの演目として頻繁に演奏されるのに比べ出現機会が少ないのが残念ですが、芥川の代表作として未来に繋いでいきたいと考えています。
エルガーの「英雄交響曲」
そしてもう一曲は、湯浅が今も居を構え拠点にして活動してきたイギリスの、国民的作曲家エルガーの交響曲第2番です。エルガーは「威風堂々」や「愛の挨拶」などで有名です。
若きエルガーはドイツ・ライプツィヒへの留学を希望するも経済的に叶わず、イギリスで活動をする中で名声を得ました。出世作であるエニグマ変奏曲がドイツで演奏された際には、面前でR.シュトラウスに賞賛されたということです。
交響曲第2番は、当初イギリスの軍人ゴードン将軍の英雄伝を聞き着手された後、国王エドワード7世に献呈するために作られました。勇壮で変ホ長調であること、ナポレオンに献呈されたこと(後に撤回)など、ベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」と類似しています。
作曲中に国王が崩御し表向きは追悼曲となりましたが、エルガーの自伝的な想いが込められています。この曲が出来たのはエルガー53歳の時でしたが、次の交響曲が未完に終わり、この第2番が最後の交響曲となりました。複雑でドラマティックなこの曲は、どことなくR.シュトラウスの「英雄の生涯」を思わせます。作品の中でエルガーがそれまでの人生を振り返ったように、新響もこれまでの60年を振り返り、新たな出発となるような演奏をしたいと考えています。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
フランツ・シュミット:交響曲第4番ハ長調
19世紀から20世紀への転換期におけるウィーン、このハプスブルク帝国の首都は、グスタフ・クリムトの華麗な絵画をはじめとして、いかにも装飾的な様式の造形芸術で知られている。しかし、パリがフランス革命を経て、19世紀の首都たる世界都市への変貌を遂げていったのに対して、ウィーンは内政的には豊かであっても、いまだに宮廷文化を模範にせざるを得ないような、時代遅れのバロック都市のままだった。19世紀後半に進行した、時代錯誤的な帝政の支配体制とブルジョワ中心の市民社会的秩序との乖離は旧来の文化価値の形骸化をもたらしていた。このように残骸と化した文化価値の空白である「価値真空」(ブロッホ『ホフマンスタールとその時代』)を覆い隠す装飾として、かの有名なリングシュトラーセ(環状道路)が作られたのもこの時代である。
芸術のための芸術、装飾のための装飾を過剰なまでに追求したこの19世紀末ウィーンにおいて、新たな道を切り拓こうとしていった芸術家のひとりがシェーンベルクである。彼の唱導した十二音音楽は弟子のヴェーベルンやベルクに受け継がれ、この時代における最大の音楽潮流となった。しかしこの時代のすべての作曲家が十二音技法を採用していたわけではない。そうした、あくまで調性を捨てることのなかった「保守的」な作曲家の一人に、シェーンベルクと同年生まれのフランツ・シュミットがいる。
彼の同時代的意義についての考察は後ほど述べることとする。
フランツ・シュミット(1874-1939)は当時オーストリアであったプレスブルク(現スロヴァキアの首都ブラティスラヴァ)に生まれる。幼少の頃より傑出した天賦の楽才をみせ、音楽アカデミーを卒業後は宮廷歌劇場管弦楽団のチェロ奏者として採用され、ほどなくウィーン・フィルハーモニー管弦楽団にも加入した。マーラーにその能力を買われて首席奏者の座についたこともある(シュミットが1896年から1911年に宮廷歌劇場のチェリストだった時期は、ちょうど、マーラーが実権を握っていた1897年から1907年と重なる。絶対者として君臨するマーラーに対しては反感をもち、マーラー嫌いを公言していたようである)。またピアニストとしても一流であり、音楽理論にも秀でていた上、高等音楽学校の学長まで務めている。
寡作であったフランツ・シュミットの作品は4曲の交響曲、室内楽曲、オルガン曲、そして最高傑作とされるオラトリオ『七つの封印の書』といったアカデミックな傾向のものが多い。そのためオペラ作曲家として成功をおさめたツェムリンスキーやシュレーカーのように大衆的人気を得ることはなかった。また最後まで調性を放棄しなかったがゆえに、メシアン、ブーレーズら戦後現代音楽の旗手たちに注目されることもなかった。そして「ブラームスとブルックナーの遺産の番人」などといった皮相な評価を与えられ、第二次大戦後オーストリア国内を除いてほとんど忘れられた存在であった。
また同時期にウィーンで活動していたにもかかわらず、フランツ・シュミットとシェーンベルク楽派の音楽家たちの間には、個人的な交際はほとんどなかったようである。しかしお互いの存在と能力は充分に認め合っており、音楽活動には深い関心を寄せていた。
そうしたフランツ・シュミットが、なぜ十二音音楽の方向へ進まなかったのか。それは、われこそはウィーンにおける保守本流の作曲家であるという強い自意識のなせる業ではないかと考えられる。しかし決して時代錯誤的な懐古趣味でウィーンの伝統的な音楽様式を復古させようとしたのではなく、伝統の蓄積に敬意を払いつつ、その上に新たなる様式を創造することに心を砕いた。そしてそのためには「現代的」でないという批判など恐れるに足らないと考え、あえて十二音音楽という時流に逆らったのである。この姿勢は特に作曲家が力を入れたであろう4つの交響曲の分野に顕著である。
交響曲のうち第3番から第4番にかけてオルガンの響きや教会音楽を離れ、濃厚で芳醇な末期ロマン派色に染まってゆく。明朗で健全な曲想から、病んだ世界への変転(メタモルフォーゼ)。最初の妻カロリーネは精神に変調をきたし精神病院に収容され、1932年には娘エンマが、出産の直後に死去する。そういった経験は、32年から33年にかけて作曲された交響曲第4番に暗い影を落としている。
この第4交響曲は構成自体が非常にユニークである。単一楽章で書かれている上に、曲中のすべての主題が冒頭のトランペット・ソロの主題(※譜例)に由来するという手法で有機的統一が図られている。曲の中間には四楽章制の交響曲におけるアダージョ楽章やスケルツォ楽章に相当する部分が存在するが、同時に曲全体が一つの大きなソナタ形式となっている。この構成について作曲者はこう語っている。「ソナタ形式における展開部は、ソナタ楽章の内部における実験のための空間であり、作曲者の仕事場である…交響曲を展開部で始めることですら可能である。それは必然的に単一楽章を生みださずにはおかない。」
冒頭のトランペットにより静かに奏でられる主題は、調性と無調の間をたゆたいながら我々の心に言い知れぬ不安感を呼び起こす。この第1主題は作曲家が黄泉の世界にいる娘に発した呼びかけ(モールス信号)である。すると第2主題で娘の幻影が立ち現れる。「死」の想念は、第2主題にあたるパッショナート(情熱的に)と指示された箇所にも現れる。そしてこのパッショナート主題を再び奏でる独奏チェロによって、葬送行進曲を間に挟んだアダージョ部分が導入される。
アダージョ部分に続くスケルツォは、またもや「死」を連想させるタランテラのリズムが支配している。様々なモチーフはさながら行き交う人の動きのようでもあり、それをシニカルに見つめる作曲者自身の視点も感じられる。こうしたモチーフの動きが目一杯詰め込まれ、ついにホルンの咆哮により示されるスケルツォの終結部分は、作曲者自身が語るように、「破滅」なのである。
そうした個々の部分にとどまらず、この交響曲自体が深い憂いと悲しみを湛えているのは言うまでもない。冒頭のトランペットの旋律は、作曲者自身の言によれば「人を永劫へと導く最後の音楽」であり、それゆえに、どれだけクライマックスを構築しても、それが栄華の表現にはならず、諦観の裏返しになったり、この世を儚む慟哭になったりする。聴き手はロマンティックな音楽に身を任せようとした途端に裏切られる。豊かな情感を保ちながらも、やがて、ある焦燥を感じさせながら、疾駆していく何物かを聴衆に残す。ツェムリンスキーを思わせるような、ロマンティックではあるが、調性に挑戦するかの如く危うげな雰囲気を伴って、新たな時代に挑んでいく姿勢を見ることができる。オーストリアがファシズムに呑み込まれていく、困難で不安な将来を予感させる時代を象徴している、これが彼にとっての《不安の時代》の和音とでも言うべきものだろう。
フランツ・シュミットがオーストリア共和国の消滅とともに世を去ったというのは、実に象徴的な出来事である。7年の後に再びオーストリアという国が地上に姿を現したとき、ヨーロッパの音楽界は一層急速にボーダーレス化が進み、もはや各国特有の音楽的伝統はさほど意味を持たなくなった。ウィーンの伝統に深く根ざしたフランツ・シュミットの音楽は、それゆえに他国に伝播せず、戦後の作曲家たちにも注目されなかった。
私がウィーンに留学し、世紀末ウィーンの文化に係る文献を探っていた時も、この作曲家の名前はシェーンベルクなどの大きな存在の陰に埋もれ、目にすることは稀であった。しかし戦後現代音楽に大きな影響を与えた両大戦間のウィーンにおける様々な音楽活動を顧みるとき、作品それ自体の価値は勿論、「場所の価値」としてもフランツ・シュミットの名は欠かすことができない。本日は今一度彼の音楽に耳を傾け、その歴史的意義に思いを馳せながら、「保守」と「革新」との相剋が生んだ豊かな音楽と向き合っていただきたいと思う。
初演:1934年1月10日、オスヴァルト・カバスタ(被献呈者)指揮、ウィーン交響楽団
楽器編成:フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、Esクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、バステューバ、ティンパニ、大太鼓、
小太鼓、シンバル、タムタム、ハープ2、弦五部
参考文献:『ウィーン音楽文化史 下巻』渡辺護著(音楽之友社)
“Das Ende der Symphonie in Österreich undDeutschland zwischen 1900 -1945”Carmen Ottner, Musikverlag Doblinger, Wien, 2014
“Die österreichische Symphonie im 20. Jahrhundert”Hartmut Krones, Böhlau Verlag, Wien, 2005
ベートーヴェン:交響曲第1番ハ長調
「宣戦布告」
初演された際に、同時に初演されたピアノ協奏曲第1番と七重奏曲作品20と比べてとりわけ聴衆の大
きな注目を集めたのが交響曲第1番であった。この作品の持つ響きは、現代の私たちにとっては古典的
で常識に従ったものと感じられるが、当時の聴衆や音楽関係者にとっては非常に斬新なものであった。そのため、注目を集めると同時に人々を当惑させた。
いきなり属七和音で始まる開始部は、当時の伝統的な流派を打ち破るものであり、「宣戦布告」とみなされ、奇妙だと人々には評された。
今では曲中よく使われる属七和音は当時の感覚ではひどい不協和音とされていたのだ。当時の批評の
中には「ベートーヴェンのような天才的な芸術家にはそのような自由な発想は許されてあるべきであるが、大きな演奏会で演奏されるべきものではない」「管楽器があまりにも多く用いられていて、この作品はシンフォニー(管弦楽作品)というよりはハルモニー(管楽器アンサンブル)のように聞こえる」などとするものもあった。
しかし後になると、この音楽が困惑や奇妙さを人々に与えつつも、当時の人々が慣れ親しんできた音楽に新たな衝撃を与え、「このような音楽表現は新たな芸術性があり、創意の豊かさに溢れ、和声の響きに革新を見出している」と評価されるようになっていくのである。
「苦悩」
この曲を書いたとされる1799年より少し前、ベートーヴェンはすでに耳が聞こえにくくなったと感じ始めていたが、後に難聴で音が聞こえなくなった彼が愛したのはメトロノームだった。振動という形で音を感じ取っていた彼は指揮をする場面もあったのだが、打楽器の起こす振動が他の楽器の振動を掻き消してしまうため、テンポを取ることが出来なく困っていた。そんな時、1816年にヨハン・メルツェル(1772-1838)によってメトロノームが発明されたのである。この年以降の楽曲には全てメトロノームの速さが指定されており、この速さはベートーヴェンがメトロノームからとった適切とされる速さであるが、実際には演奏不可能とされる速さのものもある。
第1楽章 Adagio molto-Allegro con brio
ハ長調 4/4拍子-2/2拍子
「アダージョの序奏+ソナタ形式による主部」という構成である。前述のように、序奏は非常に個性的な和音で始まっている。この曲はハ長調の作品なのだが、最初にヘ長調の属七和音という意外性のある響きで始まっている。最初の交響曲の最初から「新しさ」を感じさせるのはベートーヴェンらしい。
その後、ゆっくりと調性を探るような感じですすみ、次第にハ長調に入っていく。主部は活気のあるものとなっている。この主題はモーツァルトの「ジュピター」交響曲の第1楽章の主題と似ていると言われているが、「ジュピター」の威厳のある落ち着きに比べると、よりリズミカルで可愛らしい感じだ。第2主題は第1主題に基づく小結尾があり、呈示部は終わる。
展開部は、第1主題の素材に基づいて劇的に盛り上がり、再現部は全楽器で力強く始まる。呈示部の自由な再示の後、コーダがついて第1楽章が結ばれる。
第2楽章 Andante cantabile con moto
ヘ長調 3/8拍子
この楽章もソナタ形式で作られている。まず、第2ヴァイオリンによるおだやかな第1主題で始まり、その後この主題を模倣するように進んでいく。この主題はモーツァルトの交響曲第40番の第2楽章の冒頭と似ていると言われている。第2主題は途中に休符を挟みながら上下する独特な流動感を持っていたり、途中からティンパニが聞えて来るのも印象的だ。
展開部はそれほど長くなく、第2主題の展開で始まる。ここでもティンパニが効果的に使われている。しばらくして第2ヴァイオリンに第1主題が表れ再現部になる。
第3楽章 Menuetto:Allegro molto e vivace
ハ長調 3/4拍子
楽譜にはメヌエットと書いてあるのだが、ベートーヴェンが得意とするスケルツォに近い躍動的な雰囲気を持っていて革新的であり、後の交響曲に影響を与える要素となった。強弱の対比、レガートとスタッカートの対比などを効果的に使い、変化に富んでいる。最初の主題は、クレッシェンドしながら音階を上って行くような強さを感じさせるもので、この音楽的な進行は、第4楽章とも関連している。
トリオは主部と同じ調性で書かれている。木管とホルンが同音を反復するような牧歌的な雰囲気で始まり、その後主部が再現して終わる。
第4楽章 Adagio-Allegro molto e vivace
ヘ長調 2/4拍子
第1楽章同様「アダージョの序奏+ソナタ形式による主部」という構成で作られている。ベートーヴェンの他の交響曲で第4楽章に序奏がついているのはこの曲と第3番「英雄」だけだ。序奏は、ユニゾンの強い響きで始まり、その後繰り返し1つずつ登るような音階が続く。この辺を聞くと、ベートーヴェンの「ユーモア好き」がよくわかる。
この音階が完結し、テンポがアレグロになったところで爽やかに主部に流れ込んで行く。第2主題も明るく楽しげなものだ。展開部は、この2つの主題を使って時々短調に転調をしながら進んでいく。呈示部よりも少し短縮された再現部の後、再び第1主題を示し、活気のあるコーダで全曲が結ばれていく形になっている。
初演:1800年4月2日 ウィーン・ブルク劇場にて、ベートーヴェン自身の指揮により演奏
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦五部
ニコライ:歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
ペイジ夫人:女房は陽気で、身持ちがいい。
MISTRESS PAGE:Wives may be merry and yet honest too.
のっけから問題発言と現代では受け取られてしまいかねないが、この歌劇の原作となったウィリアム・シェークスピアの戯曲「ウィンザーの陽気な女房たち」の台詞でタイトルにある「陽気」を表した言葉である。発するのは、太っちょの騎士フォルスタッフ(ファルスタッフ)からうぬぼれもはなはだしく惚れられていると大いなる勘違いをされたペイジ夫人(ライヒ夫人)で、当時の中産階級の典型として描かれている。中産階級とは言え、この台詞はこの戯曲では数少ない韻文で書かれており、ペイジ夫人の社会的身分が決して低くないことを示している。
韻文とは、日本語で言えば七五調などのように一定の決まりを持って発音される文章で、英語の詩は基本的に必ず韻文で書かれなければいけない。上手に朗読すれば、まるで音楽のように心地よく響く。
さて話を音楽に戻そう。
本日、ウィーンにちなんだ演奏会の幕開けに演奏されるのは、ドイツ生まれでウィーンで活躍したオットー・ニコライの唯一と言っていい人気作品、歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」の序曲である。カール・オットー・エーレンフリート・ニコライは1810年6月9日にプロイセン王国のケーニヒスベルクに生まれた。ケーニヒスベルクは現在ロシアに属し、カリーニングラードと呼ばれている北海沿岸の都市である。ケーニヒスベルクと言えば、一筆書き問題で有名なあの都市である。
―えっ、知らないって。曲とは関係ないので興味のある向きは帰ってから調べてみてほしい。
音楽家であった父の下で幼少から天与の才を見せたが、父親の愛情を感じられず、出奔。ベルリンで教会音楽を学ぶ。メンデルスゾーンがバッハのマタイ受難曲を復活演奏したジングアカデミーで、1831年3月にイエスのパートを歌った。
1833年には交響曲第1番を初演するなど、成功を収めた後、1840年代にウィーンへ活動の場を移し、ケルントナートーア劇場の楽長に就任する。1842年には現在のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の前身となるフィルハーモニー・アカデミーの最初の演奏会を開いている。その後、メンデルスゾーンの退任により空席となったベルリンの宮廷礼拝堂の楽長に推挙されるなど活躍したが、「ウィンザーの陽気な女房たち」の初演から2月後にこの世を去った。奇しくも宮廷礼拝堂の楽長に就任する予定の2日前、プロイセン王立芸術アカデミー会員に選ばれたその日であった。
シェークスピアの戯曲「ウィンザーの陽気な女房たち」は、かの偉大な劇作家の作品としては評価が低いが、この戯曲を題材にしているものは多く、有名なヴェルディの「ファルスタッフ」をはじめとして、サリエリも同じタイトルのオペラ・ブッファ(18世紀に生まれた喜劇的なオペラ)を、イギリスのヴォーン・ウィリアムズは歌劇「恋するサー・ジョン」を作曲している。ニコライとヴェルディについては面白い逸話があり、ニコライ作曲の歌劇Ilproscritto(追放されし者)は最初ヴェルディに依頼が来たが、断られてニコライに、反対に「ナブッコ」はニコライが断ったためにヴェルディに持ち込まれた。
「ウィンザーの陽気な女房たち」は、アリアや合唱曲の間を台詞でつなぐジングシュピール(ドイツ語による歌芝居や大衆演劇の一形式)として作られている。序曲は主に第3幕の素材で構成され、冒頭の静謐な音楽はウィンザーの森への場面転換で歌われる第12番「月の出」の合唱、主要部にはいると第13番の「三重唱」(フルート夫人、ライヒ夫人とファルスタッフ)や第14番の「妖精のバレエ」、ハンガリー風の音楽は第16番の「全員の踊りと合唱」からと様々な魅力的な旋律が次々に演奏され、いかにもウィーンの喜歌劇を思わせる上品で流麗な音楽が紡がれる。
初演:序曲と歌劇の抜粋は1847年4月1日ウィーンにて。全曲は1849年3月9日ベルリンの王立歌劇場(現在の国立歌劇場)にて。
楽器編成:フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、シンバル付き大太鼓、弦五部
なかなか聞けないコントラバスの話
維持会員の皆様、いつも応援していただきありがとうございます。この維持会ニュースでは、各楽器にまつわる話がご好評をいただいているらしく、私もご指名を受けました。とは言え、ネットで何でもかんでも情報が簡単に入手できる現在、調べてもなかなか出てこないようなお話を含めて、できるだけ平易な言葉でご紹介させていただきます。
コントラバスは、ご存じのようにオーケストラの演奏会では、舞台の上手、右奥に配置されていることが多いです。弦楽器5部の再低音部を受け持ちます。楽器の名前を知らない人からは「でっかいヴァイオリン」、ケースに入れて担いで街を歩いていると「でっかいギター」とか言われてがっかりしたりもします。確かに、ヴァイオリン一家のおじいさんみたいな感じはするのですが、実はヴァイオリンとは先祖を異にし、ヴィオラ・ダ・ガンバの最低音域楽器であるヴィオローネから進化しています。コントラバスの形や大きさは、実はきちんとした標準みたいなものはなく様々なのですが、ヴァイオリンからチェロまでの弦楽器と明らかに違うのは、「なで肩」の形状をしていること。これが一見してわかる決定的な差です。当然、家族で一番大きいのですが、弓は一番短くて太いです。弓も、ドイツ式とフランス式があって違う持ち方をします。ヴァイオリンからチェロまでは、4本の弦で5度調弦ですが、コントラバスは4度調弦、しかも弦は4本だったり低い弦を加えて5本(さらに5本目はドだったりシだったり)だったりします。ソロの演奏ではスコルダトゥーラがあり、長2度高く(上からラ-ミ-シ-ファ#)するのが普通ですが、ウィーン式調弦(4度と5度の混合)、5度調弦にしたりなど、考えただけで完全に頭が狂いそう。でも私はソロ演奏をしないので大丈夫。
さて、新響のコントラバス団員は現在9人います。数年前、13人まで達し全員がステージに乗ったことも1度だけありましたが、現在は丁度いい感じです。特徴的なのは年齢構成。20代2人(最近入団)、40代4人、60代3人で、30代と50代がいない。何と歪な構成なのでしょう。でもみんな仲がいいです(と思っています)。だいたいコントラバス弾きというのは、協調性が高く温和な人柄が多く、そうでない人もいっぱいいますが何となく馬が合うので、初対面の人でも100人中99人とは最初から楽しく飲む自信があります、他の人とは付き合いの悪いこの私が、です。
そういうコントラバス弾きは何故、その楽器を始めたのか?楽器が大きいだけに、だいたい早くても中学か高校からです。吹奏楽やオーケストラの部活で弾く人がいなく、楽器が余っていた。他の楽器を希望したがくじ引きで負けてしまった。音大に行くならヴァイオリンやチェロは遅すぎて無理なのでコントラバスでもやれと言われた。体が大きいから、または手が大きいからやらされた。これも100人中99人ぐらいが大体こんな理由です。
私も45年ぐらいこの楽器を弾いていますが、皆さん何故こんなに長く続けられるのでしょうか?まずは、楽器を始めてすぐに嫌にならなかったことですね、始まりがなければ何もない。他の楽器に比べて音符の数が少なく、少し練習すればそれなりに恰好がついて、他の楽器の美しいメロディーと合奏ができる。私は高校生のときに既に、一生コントラバスを弾き続けると公言していました。これは当時の感覚で言っていただけと思うのですが、それ以降もコントラバスの魅力を発見し続けられた結果、弾き続けているのだと思います。何が、そんなに楽しいの?! ぶん、ぶー、ボン。メロディーは滅多に出てこない。休みを数えるのが大変。小さな楽器では簡単に弾けるパッセージなのに動きが大きくて至難の業。音程!音程!と叱られる。コントラバスの楽しさを感じなければ続けることはできない。楽しいと思えなければ早くやめて他の楽器に変わった方が良いのです。
どんなところが楽しいのか。
一言でいうのは難しいですが、オーケストラ全体の土台となる音程、リズム、躍動感、雰囲気を決めてしまう可能性を持っていることでしょうか。伴奏も楽しいです。最近の7月の演奏会を例にとると、『ダフニスとクロエ』の無言劇にあるフルートの大ソロの伴奏をコントラバスがピチカートで受け持ちますが、実は完全にソロに付けているところもあるし、ちょっと伴奏がリードぎみだったり、誘ったりしているところもあります。ただ、ソロ奏者や指揮者にはそれを余り気づかせないで、絶妙な駆け引きで結果としてソロがうまくいったときの感動をひっそり共有して噛みしめています。
マーラー第4番第3楽章の天上の音楽を奏でるメロディーも、その雰囲気はコントラバスのピチカートが実は決めてしまっている。そうそう、マーラー第5番第4楽章のヴァイオリンのアウフタクトに続くドのピチカート、この1発でマーラーの人生観すべてを表現できるのではないかと思うぐらい、4分音符1個の重みを感じて弾きます。ブラームス第3番第3楽章のチェロのアウフタクトに続くファのピチカートだって、この1発だけでお客様の1人でも魂がゆさぶられたら嬉しいと思いながら弾きます。
今度の10月の演奏会では、ベートーヴェン第1番を取り上げました。ベートーヴェン交響曲のパート譜は、コントラバスのエチュードとも言われることがあります。オーケストラのオーディションのオーケストラスタディでもよく使われるようです。難しいのですが、溌剌として優雅な傑作の第1番は、最初に8分音符のキザミが出てきた時点でもう楽しくてしようがない曲です。
伴奏が楽しいことばかり書いてきましたが、時々はメロディーを弾く練習をします。やはり伴奏はソロのためにあるので、ソロがどう演奏されるべきなのか勉強しておく必要があるからです。親戚の結婚式でソロを弾いたことがありますが、決してコントラバスのソロを人前で弾くべきではないと、つくづく反省しました。すべては伴奏のためで、私は十分です。
あとは、最近やっとわかってきたことですが、音程や音を出すタイミングなど、どうしても他人のせいにしがちなのですが、自分が悪い、或いは悪い原因が自分にあると思うこと、が重要かと考えるようになりました。そう思うことが進歩するための唯一の原因だからです。その原因がなければ、進歩はありません。私の演奏寿命はあと10年足らずかも知れませんが、最後まで進歩できるようコントラバスを弾き続けたいと思います。
さて、新響は、打楽器などと共に大型楽器を所有しており、団のコントラバス(5弦6台、4弦3台)を使用することができます。新響が、毎週の練習でコントラバスのフルメンバーに近い状態で練習できるのは、実はここに理由があります。みんな家では自分の楽器で練習するのですが、毎週楽器を車に乗せたり、担いだりして、渋滞道路や満員電車の環境で都内の練習場に通うのは現実には無理です。多くのアマチュアオーケストラで、本番直前にならないとコントラバスが揃わない理由だと思います。良い音楽を絶えずいつまでも追及したい方、入団ご希望される方、お待ちしております。
ベートーヴェンの交響曲第1番
◆ついに来た曲
1978年1月5日は、個人的には記念すべき日で、この晩に行われた所属する学生オケのコンサートで『魔笛』序曲の2番フルートを吹いた事から、(因果と云うべき)わがオーケストラ人生は始まった。爾来かれこれ40年近い歳月が流れ、新響で過ごした時間さえ、この9月でまる33年を数えるに至った。入団の翌年7月に第100回定期があったから、これだけで130回もの演奏会のステージに座っていた勘定になる。その他に不定期の演奏会もあれば、他のオーケストラの演奏会にも頻繁に出ていたから(自分で設立した団体もあった)、それやこれやを合わせれば200回以上の正式なコンサートを体験している筈で、我ながら感心もする。
だが、古今東西の作品を演奏し続けていながら、基本中の基本とも言うべきベートーヴェンの、しかも交響曲で未体験のものがあった。それが今回演奏する第1番である。
この作品は他の交響曲に比較して特に演奏に支障が伴う訳ではないし、もちろん見劣りするものでもない。ただ「どうせベートーヴェンをやるなら他の(有名な)交響曲を」という慾に目が眩んだオーケストラは、なかなか積極的に取組もうと考えない傾向は確かにある。また新響のような大規模な団体は、こうした小編成を前提とした作品をなかなか取上げ難いとう事情もあるのかもしれない。この曲以前のモーツァルトやハイドンの交響曲をなかなか取上げられない理由と軌を同じくする。
とは言えベートーヴェンのこの作品は通常の2管編成の規模で書かれているのだから、やろうと思えば出来ておかしくない。他の交響曲についてはいずれも2回以上、他ならぬ新響で演奏した経験を持つ身にとっては、詰まる処、積極的に「やろうとしない」見えざる意志が働いて、僕からこの曲を遠ざけていた・・・・とでも考えざるを得なかったのである。
「やっと来たなぁ(生きてて良かった!)」はやや大袈裟としても、この交響曲を演奏する機会が無いまま、「半人前」の無為な時間を過ごして引退する事になるのでは、との不安が無いでも無かったので、これでようやくそうしたもやもやの感情を払拭し、わが(繰返すが、因果と云うべき)オーケストラ人生にひとつの区切りをつけられようと考えている。
◆洞穴から覗く獅子の爪
ベートーヴェンは曲の出だしにこだわり抜いた作曲家で、その特徴はこの最初の交響曲にも遺憾なく発揮されている。
「起立⇒礼⇒着席」をピアノの和音と共に行った子供時代を思い起こして戴ければ良いかも知れない。この場合の「起立」と「着席」で鳴るのは主和音(ドミソ)で、同じものである。ここに「礼」に当たる属和音(ソシレ)が入る事で、ひとつの時間的経過による緊張と指向性が生じる。西洋の音楽はこのように、「始まった処に変化を経て戻る」という基本を備えていて、上記の3つの和音進行は、喩えて言うなら極めて原始的な生物・・・・口と肛門を両端とした、単純な管・・・・に等しいが、ひとつの「音楽」である。原初的だが、それ故に本質的な構造という事になる。
彼以前の交響曲はこうした本質を忠実になぞり、序奏部で主和音がまず提示され(つまり「起立」の部分)、その時点で調性が明らかにされる。つまりこれから演奏される音楽が何調なのかはこの瞬間に判る構造になっており、そこから出発して以後如何に紆余曲折があっても、最後はまたそこに確実に戻る(「着席」である)。これによって聴く側は落ち着くべき場を得て、深い安堵と調和を感得する事につながる。
ところがベートーヴェンは、この根本を崩しかねない事を仕かける。冒頭いきなり属和音が鳴る。上記の例で言えば「起立」抜きの「礼⇒着席」のみの和音進行で、これが調性を変えつつ3度繰返される。そして決定打となるべきその3度目の「着席」は、この曲全体を本来支配するハ長調の和音ではない。
これが如何に当時の聴き手の耳を翻弄し、混乱させたか?は、こうした仕かけに慣れ切ってしまった現代の我々には想像すべくもない。が、逆にその後200年間に生み出された作品を概観出来る立場として、この作品がもたらした後世への影響というものを知る事が出来るとも言えよう。
元来へそ曲がりな僕は、この冒頭を初めて聴いた時、200年前の人々と同じ?驚きと感動を得た・・・・と言いたいが、まず感じたのはある種の「わざとらしさ」だった事を白状しよう。凝り過ぎ、奇の衒い過ぎの感を容易には拭えなかったのだ。そしてその感覚からの脱却には、この作曲家の他の作品を相当数繰返し聴き込む事が不可欠だった。
朝比奈隆氏はこの交響曲を喩えて「獅子の爪」という言い方をしている。洞穴から獅子が爪の部分だけを出している。すると僅かばかり見える爪から、獅子全体の大きさや獰猛さを推し量り、他の動物はその洞穴には近づかなくなるという話だった。つまりこの最初の交響曲は、ベートーヴェンの全9曲の作品群を想像させるに充分な「爪」の風格を既にして備えている、という事である(『朝比奈隆 ベートーヴェンの交響曲を語る(朝比奈隆+東条碩夫著 音楽之友社刊)』所収)。それは既にこの冒頭の部分に顕れている。こうした開始部分の調性の混沌は『第九』でも形を変えて再現されているくらいだから、そこから遡って初期の作品に「予感」や「萌芽」を見出すのはある意味容易である。既に結末を知っている小説を読み返し、その伏線を書き出しから探し当てるのに似ていよう。
この交響曲の初演時点(1800年)で、作曲者は30歳になっていた。流石にこれは「遅咲き」だが、これはベートーヴェンとオーケストラの縁・・・・というよりオーケストラを私的に抱えていた宮廷との「距離」を反映している事がひとつの理由だろう。やむを得ない。
例えば35歳で死んだモーツァルトなら同年齢で第39番まで完成。有名な最後の三つの交響曲の一画は既に創作されていた事になる。ハイドンは長命(77歳で歿)だったが、100曲を超える交響曲のうち30曲ほどは完成させていたようだ。
「市民」ベートーヴェンにとって、これらの先人たちとは既に交響曲の価値や位置づけそのものが変わっていたとは言えるので、単純な比較に余り意味はなかろう。だがベートーヴェンに続くシューベルトはこの年齢で、長大な『グレート』を含む8曲全ての交響曲を既に書き終えていた。享年31。彼にとっては「最晩年」に当たる時期だった。
ここで改めて思うのは人の生の長さ(短さ)と対応する生の密度との事だ。
モーツァルトやシューベルトがせめてベートーヴェンほどの寿命を得ていれば、とは虚しいながらもつい我々が陥りがちな夢想であろう。だがそれは彼らの生涯を概観出来る立場にして初めて可能となる、生者の驕りかもしれないと最近考えるようになった。彼らの作品群は彼らの生の丈に合った形で完成し、完結している。最早付け足すものはないという事だ。
いま逆の事をよく想う。
ベートーヴェンが彼らほどの時間しか与えられておらず、この最初の交響曲しか遺していなかったとしたら・・・・斬新さとある種の奇矯さを兼ね備えた新しい交響曲という評価は得られたかもしれないが、当然「獅子の爪」とは認識されないまま終わったに違いない。何せその後に生み出される交響曲が無ければ、当然「獅子」たり得ず、従って他を脅かす「爪」ともなれる訳が無い。ここに後世の我々が特定の作曲家(に限らないが)の「初期作品」とか「習作」とかと称されるものに対峙する際の難しさが潜んでいるように感じる。
そうしたものに向き合う時、我々は得てして、作品の背後に、本来姿の見えない筈の「獅子」の姿を想起している。「それで良い」という考え方を否定はしないし、予め大団円を知った上で、改めて冒頭から小説を読み返して理解を深める事も、確かな楽しみ方のひとつである。だがそのような属性を払って単独の作品として向き合い、純粋に味わう姿勢というものを忘れるべきではないとの念が、最近自分の中では強まっている。頑迷・・・・「齢をとったという事だろうなぁ」と感じるのはこうした折である(苦笑)。
初めてこの曲を演奏する定期終了直後に迎える誕生日で、自分がこの作曲家の享年を超える事に、最近になって気がついた。
昔のクラオタ、久しぶりにお宝発見!
いきなり私事で恐縮ですが、クラシック音楽を熱心に聴き始めてからすでに40年以上が経過してしまいました。どんなきっかけで夢中になったのかはっきりと覚えていないのですが、中学生のころには『FM fan』という雑誌を必ず購入して熱心にFM放送でクラシック音楽を聴いていたものです。この雑誌には二週間分のFM放送の番組表が載っており、放送する曲名、演奏者と演奏時間が詳細に記載されていました。発売日に必ず購入し、番組表の中から面白そうな曲を見つけては赤線を引いていきます。交響曲、交響詩、協奏曲、室内楽曲などで聴いたことのない曲があれば必ずチェックをつけ、FM放送をオープンリールテープまたはカセットテープに録音するわけです。聴きはじめた頃はほとんど知らない曲ばかりですから番組表は真っ赤になりました。しかし録音テープは決して安くはなかったので中学生の小遣いで買える分量は高が知れており、とても全部録音できるわけがありません。そこでクラシック音楽に関する雑誌の記事や本を読んで自分が面白いと思う曲を厳選して録音したものでした。そうやって少しずついろんな曲を知っていったのです。
最初の頃はとにかく毎回が超名曲の発見ばかりで、楽しくて夢のようでした。ブラームスの交響曲第3番をはじめて聴いて、とても美しいけれど恥ずかしいメロディーの第三楽章に感動し、カッコよく始まる第四楽章ではどうして最後しょぼくれて終わってしまうのか納得がいかなかったこと(まだ若かったのです)や、マーラーの交響曲第1番を始めて聴いて、これぞ求めていた作曲家だ、とばかりに舞い上がる思いだったことなどが鮮明に記憶に残っています。そこらをちょっと掘れば必ずお宝を掘り当てるみたいな感じでした。とは言っても最初に聴いてすぐに感動するということは少なくて、なんだか凄そうなところがあるぞ と感じて何度も繰り返して聴いているうちに、完全に嵌まってしまうということが多かったものです。
しかし、いつの頃からか掘っても掘ってもお宝になかなか巡りあわなくなっていきました。最初に聴いたときになんだか凄そうだと感じる箇所が全くないし、我慢して何度繰り返して聴いてもさっぱり感動しない曲が増えていったのです。
そのあたりからは徐々に指揮者や演奏家の違いのほうに興味が移って行き、聴く曲のレパートリーを広げることはあまりしなくなりました。オーケストラに所属して演奏していても聴いてつまらない曲は、演奏してもいくつかの例外を除いてはやはりつまらないと感じました。忘れられた名曲などと称される曲を取り上げたことも多数ありましたが、まあ悪くないかもねと思う程度のものがほとんどだったものです。もう、新しい曲を見つけて心ときめくことなどはないのだろうなと半ばあきらめの境地(大げさですが)で長年過ごしていたのです。
今回のコンサートを寺岡清高氏に指揮していただくということが決まったとき、どんなプログラムを新響案として候補にあげようか考えました。新響ではすべての団員が平等にプログラム案を提案することができるのです。寺岡氏の過去のコンサートを調べてみたらフランツ・シュミットという作曲家を多く取り上げられていることが分かりました。フランツ・シュミットという作曲家の存在はかろうじて知っており、音源もひとつだけDAT(デジタルオーディオテープ)に録音したものを持っていましたが、1回しか聴くことができないうちに再生装置が壊れてしまい、そのままお蔵入りになっていたのでした。今回“ひょっとしたら”と気を取り直してYouTubeで聴いてみたところ、“なんだかこれは凄そうだ”という、中高生の頃に超名曲たちを生まれて初めて聴いたときのような感覚が走ったのです。そこで音源を購入して何回か聞いてみたところ、この曲は久しぶりにめぐり合えた真のお宝(超名曲)であると感じるに至りました。その曲こそが今回取り上げるフランツ・シュミットの交響曲第4番なのです。久しぶりにめぐり合えたお宝です(あの時DATが壊れてよかった!)。
シェーンベルク、ベルク、ウェーベルンなどの新ウィーン楽派の無調音楽や、ドビュッシーのバレエ音楽“遊戯”、ストラヴィンスキーの“春の祭典”などの革新的な音楽が発表された20年も後の1930年代の曲なのですが非常にロマンティックであり、シューベルト、ブラームス、ブルックナーそしてマーラーの流れが行き着いた終着点のような音楽です。そして、ただの懐古趣味の音楽では全くなくて、非常に複雑な転調とシュミット節とでもいうような強い個性が感じられる音楽でもあります。うれしいことに決して不快な和音は出てきません。旋律は深い憂いをもっており心がしめつけられるような美しさがあります。特に第二楽章は、いつまでもこの中に浸っていたいと思わせる音楽です。第一次世界大戦を経験し、さらにナチスの台頭で風前の灯となって滅びゆく古きよきウィーンを偲ぶような気にさせます。そんなわけで久しぶりにお宝にめぐり合って舞い上がってしまいました。
そんなわけで手当たり次第にフランツ・シュミットの他の曲を調べてみました。交響曲は四曲、オペラ、オラトリオ、ピアノソロと管弦楽のための“ベートーヴェンの主題による変奏曲”、騎兵の歌によるオーケストラのための変奏曲、三曲のピアノ五重奏曲、二曲の弦楽四重奏曲など、それほど曲数は多くないですが聴き応えのある曲が揃っていました。特にオペラ“ノートルダム”は間奏曲だけが非常に有名ですが、充実した音楽で構成されたオペラです。交響曲は第2番と第3番が第4番と比較しても遜色のない名曲といって良いでしょう。オラトリオ『七つの封印の書』はまだ断片的にしか聴いていませんがとんでもなく凄そうです。
また、ピアノ五重奏曲のうちの二曲がピアノ、ヴァイオリン、クラリネット、ヴィオラ、チェロという非常に珍しい編成で、しかもかなりの力作でした。クラリネットが入っているので楽譜も入手しました。
さて維持会員の皆さま、新交響楽団の第231回演奏会のプログラムを見て、なんだか知らない曲がメインだから今回はパスしようか、秋の観光シーズンで連休だし・・・・などと考えている方いらっしゃいませんか!それは大変もったいないですよ。フランツ・シュミットの交響曲第4番はマーラー級の名曲です。マーラーなら他のオケでもどこかですぐにやるでしょうがフランツ・シュミットはそうそう演奏されません。それも、フランツ・シュミットの活躍したウィーン在住で、フランツ・シュミットを重点的に取り上げている寺岡氏の指揮で聴けるのですからこのチャンスを逃す手はありません。ぜひ聴きにいらしてください。なお、事前にYouTubeなどで数回聴いておくとフランツ・シュミット流の複雑な転調に耳が慣れて生の演奏をより一層堪能できると思います。
蛇足ですが、前述のクラリネット入りのピアノ五重奏曲変ロ長調の第二楽章と第三楽章を新交響楽団室内楽演奏会(9月27日17時開演 地下鉄有楽町線護国寺駅徒歩5分の同仁教会 入場無料)にて演奏いたします。この曲は交響曲第4番とほぼ同時期の1933年につくられた曲で、全体を覆う雰囲気は共通する部分があります。この曲は交響曲第4番よりも聴く機会がかなり少ないと思いますのでこちらもどうかお聴き逃しなく。
小松 一彦氏を偲ぶ
時間が経過してしまったが、今年3月30日、指揮者の小松一彦氏が亡くなった。享年65。新響とは15年にも及ぶ長い交流があったが、第207回定期(2009年10月12日:東京芸術劇場大ホール)以後、一切の音信が途絶えていた。小松氏はこの演奏会の直後に倒れ、入院生活を送っているとの情報こそ漏れ伝わって来たが、詳しい病状も復帰の時期も、全く不明なまま時間のみ経過する状況が続いていた。亡くなってから多少なりとも判った話では、再び指揮台に復帰の目処がつくまで一時は回復されていたとの事。早すぎる享年と併せて、殊更にその死が惜しまれる。
個人的にこの訃報に接したのは、亡くなった当日土曜日の夜、新響の練習終了後で、非常に早い情報だった。翌日師事している元NHK交響楽団首席フルート奏者のM先生に、レッスンを終えて開口一番「小松先生が亡くなられました」と伝えると、氏よりひと回りも年齢が上で、N響時代以来の交流もあって、入院以後はその消息を日頃気にかけていたM先生も流石に絶句し、「小松さんはいくつでしたか?残念です。明日あたり死亡記事が出るでしょうね」と言葉少なに語っていたのが記憶に残る。実際に各紙に訃報が載ったのは死去して3日後の4月2日(火)だった。
小松氏と新響との邂逅は1994年の『芥川也寸志メモリアル・コンサートII. 映画音楽の夕べ(2月13日:田園ホール・エローラ)』まで遡る。これは芥川氏が生前、その監修に当たった埼玉県松伏町のホール落成を記念する行事の一環で、そこでは芥川氏が手がけた数々の映画音楽を、その映像を実写しながら実演奏で紹介するという企画で、評論家の秋山邦晴氏の解説を伴った画期的なものだった。
映画音楽でしかも映像との連動となれば、当然ながら秒刻みの時間に制約される。そもそもこうした音楽は作曲される時点で、シーン毎の所要時間を詳しく計り、寸分違わずその時間内に収まるよう作られている。演奏する側は常とは違う「時間」をいやでも意識せざるを得ず、ともすると時間内に演奏する事にのみ関心が向かいがちになる。
文章にしてしまうとその難しさは伝わり難いが、音楽の本質が時間の芸術である事を思い出すべきだろう。各音の「長短」によってリズムが生まれ、そのリズムも作品の開始と終止の間にしか存在し得ない。そしてそのリズムの間に於ける演奏者による「意図的な長短」は、音楽の「表現」と表裏一体である。凡百な演奏は、この時間の制約を忘れ、寸足らずのまま、或いは逆に間延びしたままの音の集積に、せっかくの作品をおとしめてしまう。もちろんこれは映画音楽にとどまるものではない。
初対面の小松一彦氏がこの時新響に見せた指揮の手腕とは、時間に縛られていながら、その制約をオーケストラ奏者に意識させる事なく、且つ音楽としての表現をなし得た事だった。これは放送の現場での仕事によって培われたものだったのだと感じている。
個人的にはこの時演奏した『煙突の見える場所(五所平之助監督・1953年)』の芥川氏の音楽に対し「ここはプロコフィエフ風にやってください」とコメントした事が記憶から去らない。東京の下町(千住にあった「お化け煙突」周辺の)風景と、この音楽との違和感はさて置くとしても、印象にだけは確実に残る(その後何度もこの映画を通してみてしまった)。「(同じ芥川氏の)『交響管絃楽のための音楽』と同じです」とはこの時共に仕事をした編曲者の毛利蔵人氏の言葉。芥川氏は丸3日の徹夜仕事でこの映画音楽を仕上げたというから(秋山氏のその折の解説)、自らの出世作となった音楽と多少似ていたとしても、それは責められまい。秋山氏も既に亡く、毛利氏も40代で鬼籍に入った。
いずれにせよ以後こうした企画は氏の独壇場と位置づけられ、続く1995年7月の第148回定期『映画生誕100年記念演奏会』や2000年7月の『東京の夏』音楽祭での指揮につながってゆく。これらの演奏会では芥川氏の作品にとどまらず、サン=サーンス(映画音楽を書いているのだ)やアイスラー、エリック・サティなどの手がけた映画音楽を、その映像共々披露する事になる。
こうした形で優れた手腕を発揮して新響に新風を吹き込むべき存在であった氏だが、映像を離れ、真に「音楽」のみで我々と向き合う機会は2003年1月の第180回定期まで待たねばならなかった。これは受入れるべき新響の側に理由があったのだ。
最近出版された『ドラッガーとオーケストラの組織論(山岸淳子著PHP新書)』を興味深く読んだ。そこには
「指揮者の仕事はオーケストラと練習の場で対峙する時にこそ存在する。故に聴衆を前にした時点で見えるものは、その仕事の結果でしかない」
という趣旨の事が出てくる。つまり聴衆の立場でいる限り、オーケストラを動かしている現場としての練習の実態を知る事は残念ながら殆ど不可能と言って良いという事で、その通りだなぁと思う。実際その練習の現場に於いて、指揮者という存在は、オーケストラに対し様々な言辞・行動を通じて、自身の目標とする演奏を創り上げてゆこうとする。対するオーケストラの楽員ひとりひとりは、自己の音楽的欲求や見識や、そして取りも直さずその持てる技量とのバランスの中で、指揮者の意図を実現すべく腐心する。
またオーケストラという組織としての目標や「文化」というものも厳然と存在し、それらがまた楽員の価値観形成にも少なからず影響している。もちろんそうしたものを形作り、担っているのは個々の楽員であり、つまり組織と個人が互いに影響し合っているという事だ(新響も50年以上の歴史の中で、当然そうしたものを形成して来ている)。
指揮者はそうした個々人の集団の中に単身飛び込んできて、唯一「自らは音を出さない」存在として、限られた練習時間の中で成果を示さなければならない。そこに求められる方法や能力とはどのようなものか?・・・・ここにマネージメント論や組織に於けるリーダーシップ論などと共通するものをドラッガーは見出している訳だが、興味を感じる方は一読されたい。指揮者という仕事が具体的にどういうものかのイメージは掴める筈である。
極めて単純に言えば、小松一彦氏が初めて関わった当時の新響では、小松氏の練習スタイルはなかなかに受入れられ難いものだったのだ。例えば氏はオーケストラに対して、あるべき音を追求する際、細かく奏法まで指示した。
また、ある一定の音型パターンが繰返される場合に「自然に」生じてしまう「弛緩」を断じて許さなかった。例えばショスタコーヴィチの交響曲を演奏すると、何十小節も同じリズムが続く事が多々ある。こうした時、日本人なら真面目に取組むだろうと思いきや、十小節も続かぬうちにだれ、テンポも乱れてくるのである。「そんなにしつこくしなくても」とか「皆でほどほどの処に落としどころを見つけよう」という「空気」が支配するのだろう。だが小松氏はこれを絶対に許さなかった。「ぬるい!」「ダレる!」と一喝し、何度もやり直しを求めた。
「当たり前じゃないか」と今なら団内の誰しもが思うところだが、これはともすると作品を耳で聴いた印象そのままに、音にしてしまいがちなアマチュアのオーケストラにとって弊害の最たるもので、特にアマチュアとしてのプライドを抱く当時の新響の楽員にとっては、ひとつのショックとして受取られた。また映画音楽のようなきっちり時間内に収めるべく表現する才能は、時に「想定外」の指揮ぶりによって本番に於けるアマチュアの力を引出すタイプの指揮者のスタイルとは対極にあり、音楽的に「冷たい」「つまらない」と捉えられる事があった。
1980年代末から10年以上に亘ってインスペクターや演奏委員長を務めた体験から言えば、新響は発足以来の「文化」を背景に後者のタイプの指揮者に、よりシンパシーを感じており、また指揮者の側にも芥川氏の理念を体現する組織への「理解(配慮)」を基盤に、接しているケースが多かった。つまり新響をなかなか「指導」の対象とせず、練習の必然の結果としての本番を迎えるスタンスから遠かった。故にその演奏は100点もあれば50点もあるというように成否の落差が激しかったのである(それは結局2002年の「オーケストラ・ニッポニカ」の設立まで程度の差こそあれ、傾向として途切れなかった)。個人的な感想を敢えて言えば、小松氏の出現までの新響はアマチュアの屈折したプライドと、それを助長する一部の評価に甘んじ、音楽そのもの・作品そのもの、そして真に指揮者が導こうとするその方法にも、真摯に向き合っていなかったのである(もちろんこうした全てが、現時点で解消されているほどに、新響は進歩していないが)。
こうした弊害の最たるものがフランス音楽へのアプローチだった。当時のアマチュアオーケストラはどこも「聴いた印象」をそのまま音にしていた。これは意外に今でも続けられている事かも知れない。何となく曖昧な発音、明確さを欠く音質で演奏し、常に違和感を拭えぬまま失敗する・・・新響も思い出したようにフランス音楽をプログラムに採り上げ、何かしっくり来ないものを抱えながら本番を迎えては、案の上うまく行かず、その後の反省会では「やはりフランス音楽は難しい」と結論付ける事を繰返していたのだ。
またフランス音楽に限らず、自らの言葉で巧みにイメージを語り、それに合わせた音をオーケストラから引出すタイプの指揮者も世には多い。そうした指揮者に対峙すると、良い効果をもたらす場合がある反面、楽員個々の「言葉に対する感受性」や「イメージを音にする技量」によって、結果にバラツキが出やすいという弊害がある。アマチュアオーケストラの場合、特に弊害が目立つ。これも当時の新響とて例外ではなかった。
このような点が新響団内でも価値観の変遷と相俟ってあるべき姿の論争や確執の原因となっていったのである。これが2000年前後の新響の姿だった。
「オーケストラ・ニッポニカ」の設立によって団内の確執がようやく終息し、晴れて小松氏を定期演奏会(第180回)の指揮者として翌年初頭に迎える事が決定した2002年7月、氏とプログラムに関する打合せに出席した。すると開口一番、「フランスものを採り上げよう」と発言された。しかもドビュッシー・プーランク・ベルリオーズという王道とも言うべき布陣である。ドビュッシー(牧神の午後への前奏曲)は30年ぶり、プーランク(牝鹿)は初めて、そしてベルリオーズ(幻想交響曲)は山田一雄氏と演奏(1989年1月)して、不出来だった因縁の曲だ。だがそれを敢えて採り上げ演奏する事で、「新響も新たな時代に入ったのだ」とのメッセージを発信したいとの願いが、我々にもあり小松氏もまたそれを汲み取ってくれていた。ここに氏の新交響楽団への想いを深く感じ取るべきだろう。
同年(2002年)秋から始まった練習を通じ、新響は初めてフランス音楽への接し方、特にその音とそれを引出すための奏法というものに出遭ったと言える。それはフランスの作曲家らの作品に取り組む際には不可欠と言えるものである。新響は氏の指導を受けることで、初めて本格的にフランス音楽の演奏を実現出来た、と評価しても決して過言ではなく、特に『牧神の午後への前奏曲』『牝鹿』は、今録音を聴いても、それまでの新響には無かった音が現出している事に驚く(『幻想交響曲』は、この曲に対する新響サイドの「トラウマ」から逃れきれていないのが残念だが)。『牧神~』に於ける自分のフルートソロの出来はさておき「これで新響もひとつの壁を乗り越えたのだな」という実感と安堵感が沸々と終演後に湧き上がって来た事を、この演奏会を期に、長年務めた演奏委員長を退任した時の心境と共に思い出す。
その後の共演では、新響が苦手としていた作品や、やろうとして出来なかった「邦人作品」を多く採り上げた。前者の中ではラヴェルの『ラ・ヴァルス』とフランクの交響曲を挙げるべきだろう。前述のフランス作品と併せて、これらを「聴かせられるもの」のレヴェルにまで引上げて戴いた。
また芥川氏の歿後20年となる演奏会で、芥川氏の作品と共に、新響が芥川氏の指揮で日本初演したショスタコーヴィッチの交響曲第4番を再演している事も忘れるべきではない。小松氏は新響に常に配慮し、歴史の節目となる時に、重要な作品を数多く自ら採り上げて指揮している。
後者も重要である。安倍幸明の交響曲第1番・黛敏郎の『涅槃交響曲』『BUGAKU(舞楽)』そして貴志康一の『日本スケッチ』である。これらの曲はかつての新響ではまぎれもない日本人の手になる作品でありながら「邦人作品」の範疇に入らないため、演奏される望みを絶たれていた。
『涅槃交響曲』の演奏を実現するまで15年以上の時間が必要だった。初演指揮者だった岩城宏之氏を迎え、まで2ヵ月を切り、いよいよ練習開始という段階になって岩城氏の訃報が入る(2006年5月)。ここで小松一彦氏に指揮を引受けて戴けなかったら、この曲の演奏は更に延びていた。いや演奏はもう実現しないものとなっていたかも知れない。
演奏会当日、ステージリハーサルが終了した処で氏がこちらに近づき、「『論文』読ませていただいた。これまでの『涅槃~』の解説の中で一番良いものだね」と話しかけてきた。当方の書いた曲目解説を、事前に通読していてくれた訳で、極めて多忙な中で、作品への思い入れだけでようやくまとめた駄文に対する、この上ない「望外の評価」と感謝するほかない。
貴志康一の作品を世に紹介する事は、指揮者としてのライフワークとかねて語っていた氏が、結果的に新響との最後の共演となった演奏会で採り上げた事を、遺された我々はどう考えるべきだろうか?
自らの死に対する予感があったのか?これから新響と長く付き合っていく上で、置くべき最初の「布石」としての選曲だったのか?或いは新響が今後「自国」の作曲家を改めて策定していくための指針とすべきなのか?・・・考えていけば切りはない。だが我々は考えなければならない。
小松一彦氏のような才能と手腕と、そして理解を以ってアマチュアオーケストラと接し、その集団の能力を進展させて行ける指導者にして指揮者は、そう容易には今後現れないだろうとの予感がある。「偉大な」指揮者にはアマチュアと深く接するだけの時間的余裕を今や望めない。才能ありながら雌伏の期間を過ごす若手の指揮者は、やがて世に出る機会を掴めばアマチュアからは離れていくかもしれないとの懸念が常に付きまとう。小松氏の死をきっかけに、新響が必要とする指揮者の何たるかを改めて考え、将来を見通す必要があるように感じてやまない。
夜半、小松氏の振ったフランクの交響曲(第184回定期:2004年1月)を聴く。10年という時間を経て、この曲の演奏を巡る氏の言動や想いに関する記憶が改めてよみがえり、しばし泪やまず。
(2013年12月25日記)
新交響楽団在団44年の思い出-5
編集人より
コンサートマスターを長年に亘って務められた都河和彦氏による回想録を、前年より掲載しております。今回は新響創立40周年からの10年間のうち、2001年までの前半5年間の部分をご紹介致します。
◆創立40周年(1996年)からの10年間
1996年1月、飯守先生指揮でワーグナーの楽劇「ワルキューレ」第1幕全曲を演奏会形式で演奏しました。音楽が素晴らしくて先生の熱の入れようは尋常ではなく、歌手も素晴らしく、今でも記憶に残るコンサートです。練習の休憩時、先生に「都河さん、木管と金管の音程、どうしたらいいんだろう?」と話しかけられて返事に窮しました。「ヨーロッパの人達は幼い時から教会で合唱しているから和音感覚が出来あがっているが、日本には教会に行く習慣がないので日本人は和音感覚が欠如している」とおっしゃっていました。今思えばこの時が、飯守先生の新響に対する音程・和音への要求が厳しくなった始まりでした。それ以来、先生が新響の練習に見える度に「一に音程、二に音程、三・四がなくて五に音程」の厳しい指導が始まることになります。
6月、新潟県小出町文化会館こけら落とし演奏会に招かれ、大町陽一郎先生指揮・魚沼第9合唱団との第九公演がありました。前夜宿泊した旅館にはホルンの大原久子さんの新潟の御実家から銘酒「八海山」がドーンと差し入れられ、多くの団員がへべれけになっていました。また本番当日の舞台練習で事件が起きました。もうリハは終わりと思った4人のソリストが楽屋に帰ったのですが、それに気付いた大町先生が激怒、「ソリストを呼んで来い!」と怒鳴りました。あわてて戻ってきたソリスト達に対する「君達、歌いたくないんだったら歌わなくてもいいんだよ!」という大町先生の叱責に全員が凍りつきました。しばらくしてソリスト全員が声を揃えて「申し訳ありませんでした!」と謝ったので先生も機嫌を直し、公演は大盛況で終わりました。
7月は6日、7日連続(芸術劇場とサントリー・ホール)で本名徹二先生に「日本の交響作品展」を振って頂きました。早坂文雄のピアノ協奏曲は当初高橋アキさん独奏の予定でしたが都合が悪くなり(8/17に逝去された御主人秋山邦晴氏の看病だったと思います)、高橋さんが著名な作曲家でピアニストでもあった野平一郎氏を紹介して下さいました。
10月は原田先生指揮でベートーヴェンのレオノーレ序曲3番、交響曲第6番、第5番という超ド名曲プロを初めてのオーチャード・ホールを使って開きましたが、新響が自由席券を出し過ぎ、7月に2日にわたって7曲の邦人作品を振って下さった本名先生を含む200名くらいのお客様が入場できなかった、という珍事がおきました。新響定期はそれ以来、全席指定になったと記憶しています。
この頃日本の石油業界は斜陽になり会社の早期退職の勧奨に乗ってこの年の暮、28年間勤務したモービル石油を53歳で退職しました。あまり愛社精神が無かった私は「これでもう嫌な上司にこき使われなくて済む」「これからはヴァイオリンの練習をし直し」とルンルンの気分だったのですが、すぐに家人が持ってきた英語翻訳の仕事に忙殺され、ヴァイオリンの技量が戻ることはありませんでした。
97年1月のコンサートはコバケン氏がスメタナの連作交響詩「わが祖国」全6曲を振ってくださいました。ファースト・ヴァイオリンに難しいパッセージがあり、コバケン氏は「この個所は暗譜するように」と指示されたのですが、50台半ばで記憶力が衰えつつあった私はついに最後まで暗譜できませんでした。
98年1月、名指揮者渡邉暁雄氏の長男で超長身の渡邉康雄先生が新響に初登場、お得意のシベリウスの交響曲第2番をメインに振ってくださいました。先生にはその後数回振って頂きましたが、くらしき作陽大学の関係でオフチニコフ氏やピサレフ氏、チェボタリョーワ女史といった世界的なピアニストやヴァイオリニストをソリストに連れてきてくださいました。
7月は飯守先生指揮によるワーグナーの楽劇「ニュルンベルグの指輪ハイライト」コンサートがありました。4日間・16時間にわたる楽劇から先生が約3時間分の7曲を選定して下さったのですが、先生がいささかハイになって当時のインスペクター、日高容(いるる)氏が先生の面倒見に苦労されていた記憶があります。先生が練習の帰りに上着を電車に忘れたので某団員に回収に行ってもらった、演奏会当日先生が舞台用の靴を忘れたのでデパートに買いに走った、本番で曲順が分からなくなった先生がセコバイ・トップだった日高氏に「次は何?」と聞き、日高氏は「森のささやき」と答えた等々・・。またこのコンサートのための5月の鹿島合宿で現コンミス堀内真実さんがオーディションを受け、入団してくれました。プログラムの一つに「ワルキューレの騎行」がありメチャ難しかったので私はいかに誤魔化すかに腐心していたのですが、堀内さんの隣で弾いていた伊藤さんから「彼女は完璧に弾いている」と聞き、次のコンミスは彼女だと確信しました。
10月には、2年前の96年6月に小出町文化会館こけら落としの第九公演でご一緒した大町陽一郎先生が新響定期に初登場され、シューベルトの「未完成」やR・シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語りき」等を振ってくださいました。未完成冒頭の弦の16分音符は普通弓先でデターシェで弾きますが、先生は弓中で跳ばすよう指示されてびっくりしました。「ツァラ」では私が難しいソロを担当しましたが初練習の後、大町先生にちょっぴり褒めて頂きました。その当時「開演5分遅れ」は音楽界の常識でしたが本番後の打ち上げの席で先生が「このオケは練習が時間通りに始まる感心なオケだと思っていたのに、本番は5分遅れとはどういうことだ!」とおっしゃったので団員一同唖然としました。大町先生とは2004年龍ケ崎市での「第九」公演でもご一緒しました。
99年5月、ゴールデンウィークを利用して4日間の九州演奏旅行があり、福岡と熊本で演奏しました。九州出身の指揮者井崎正弘氏が同行してくださり、当時の運営委員長福島氏の尽力で地元の福岡市民オケとの合同演奏が実現しました(チャイコフスキーの祝典序曲「1812年」)。コンサート後のパーティーで新響対福響の演芸合戦があったのですが、永年合宿の演芸会で鍛えている金管グループの活躍で新響側の圧勝でした。
7月11日の「芥川也寸志没後10年」コンサートでは予定されていたコバケンが「作曲のため多忙」という理由で指揮を断ってきたため、飯守先生がヨーロッパでの仕事をキャンセルして振って下さり(交響三章、エローラ交響曲、交響曲第1番等)、新響の窮地を救ってくださいました。
7月17日はエローラ・ホール、18日は芥川先生が保存に尽力された上野公園内の奏楽堂でも先生没後10年の演奏会があり、やはり飯守先生が数曲の映画音楽、エローラ交響曲、交響曲第1番等を振ってくださいました。
10月、みちのく銀行の招聘でロシアのオケを引き連れて東北地方で時々演奏会を開いていたロシア人指揮者、ヴィクトル・ティーツ先生を新響にお招きし振っていただきました(ヴィオラの奥平一氏が先生の評判を聞きつけ、東北地方でのコンサートを聴きに行って話が決まった、と記憶しています)。プログラムはグリンカ、カリンニコフ、チャイコフスキーとオール・ロシアものでした。小柄な方で指揮は軍隊式、テンポとリズムに大変厳しい方でした。その後、2001年と2004年と2度お呼びし、ラフマニノフとチャイコフスキーを振っていただきました。リハーサルはロシア語だったので、さすがに通訳がつきました。私と同じヘビー・スモーカーだったので携帯灰皿を沢山プレゼントしたら大喜びなさっていました。
2000年7月30日、紀尾井ホールにおける(東京の夏)音楽祭「映画と音楽」で、又々小松先生と映画音楽のコンサートを開きました。前年入団してすぐコンマスになった慶應ワグネル・オケ出身の田澤昇君が確かサン・サーンスの「ギーズ公の暗殺」で素晴らしいソロを披露しました。残念ながら彼はほんの数年で退団してしまいました。
8月13日、打楽器パートの上原誠氏が沖縄でシュノーケルの事故で水死、という痛ましい出来事が起きました。まだ40台半ばだったでしょうか。彼は数多くの打楽器、邦人作品、そしてヤマカズ先生の業績に詳しく、自宅は音楽資料の山という音楽学者のような団員で、奇しくもヤマカズ先生と同じ命日でした。
12月24日、会津にバス旅行して「会津第九の会」とベートーヴェンの第九を共演したのですが、指揮は芸大でトラビス先生の後任になったイギリス人のロックハート先生が引き受けて下さいました。先生は翌01年1月の新響定期に初登場、ウォルトン、ブリテン、ホルストのイギリス物を振ってくださり、翌年1月にも「スコットランド」等を指揮して下さいました。リハーサルは当然英語で、「イン・リハーサル・テンポ」、「イン・コンサート・テンポ」の2語が印象に残っています。
01年5月、飯守先生が飯守+新響にとって初めてのマーラー(交響曲第5番)を振ってくださいました。先生との練習が始まった頃、成城学園前で「弦楽器トリオ」を経営している新響団員陳さんの店へ飯守先生の紹介ということで若い女性ヴァイオリニストが来店したので、陳さんは「飯守先生のマーラーの指揮はこんな振り方で分かりにくい」と身振り手振りで真似したら、次回の練習から俄然分かり易い指揮に変わった、という伝説があります。そう、彼女はしばらくして先生が結婚なさった3人目の奥様、高橋比佐子さんだったのです。お二人の結婚披露パーティーは表参道近くのイタリアン・レストランを借り切って行われ私も出席しましたが、先生が常任指揮者を務めていた東京シティ・フィルの団員やソプラノの緑川まりさん等多くの音楽関係者が見えていました。
10月の定期も飯守先生がブラームス交響曲第1番等を振って下さり、2楽章のヴァイオリン・ソロは私が担当しました。翌月の『音楽現代』にこのコンサ-トの批評が載り、某評論家が「絶美のヴァイオリン・ソロ」と褒めて下さいましたが、「絶美」という表現を目にしたのはこの時が最初で最後です。(2012年11月30日記)
(次号に続く)
第231回ローテーション
| ニコライ | ベートーヴェン | シュミット | |
| フルート1st | 岡田 | 松下 | 吉田 |
| 2nd | 吉田(+picc) | 新井 | 藤井(+picc) |
| オーボエ1st | 堀内 | 堀内 | 岩城 |
| 2nd | 桜井 | 平戸(*) | 平戸(*) |
| C.I. | - | - | 堀内 |
| クラリネット1st | 高梨 | 高梨 | 品田 |
| 2nd | 進藤 | 末村 | 末村 |
| Es.Cl | - | 進藤 | |
| ファゴット1st | 藤原 | 浦 | 田川 |
| 2nd | 田川 | 笹岡 | 藤原 |
| C.Fg | - | - | 浦 |
| ホルン1st | 大原 | 大内 | 箭田 |
| 2nd | 市川 | 宮田 | 大原 |
| 3rd | 箭田 | - | 大内 |
| 4th | 宮田 | - | 市川 |
| トランペット1st | 北村 | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 青木 | 青木 | 倉田 |
| 3rd | - | - | 小出 |
| トロンボーン1st | 志村 | - | 武田浩 |
| 2nd | 武田浩 | - | 志村 |
| 3rd | 岡田 | - | 岡田 |
| テューバ | - | - | 土田 |
| ティンパニ | 皆月 | 古関 | 桑形 |
| パーカッション | シンバル付大太鼓/今尾 | - | シンバル・小太鼓/今尾 大太鼓/皆月 タムタム/古関 |
| ハープ | - | - | 見尾田(*),堀之北(*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(小松) | 堀内(小松) | 堀内(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(伊藤真) | 大隈(伊藤真) | 大隈(佐藤) |
| ヴィオラ | 柳澤(槇) | 柳澤(槇) | 村原(柳澤) |
| チェロ | 柳部(大庭) | 柳部(大庭) | 柳部(安田) |
| コントラバス | 中野(上山) | 中野(上山) | 中野(郷野) |
(*)はエキストラ
第231回演奏会のご案内
ウィーンにこだわる指揮者 寺岡清高
今回の演奏会では、指揮に寺岡清高を初めて迎えます。早稲田大学文学部を卒業後、桐朋学園大学を経て1992年よりウィーン国立音楽大学指揮科で学びました。早稲田大学交響楽団ではコントラバスを演奏していましたが、指揮者への想いを断ちがたく専門家への道を目指しました。今はウィーンに在住し、ヨーロッパ各地のオーケストラに客演するほか、2004年からは大阪交響楽団の正指揮者に就任し現在は同楽団常任指揮者を務めるなど、国内でも活躍しています。
その音楽への情熱と真摯なアプローチから紡ぎ出される音楽は、説得力を持って心に響きます。
世紀末ウィーンといわれる19世紀末から20世紀初頭に作られた音楽、特にマーラーや新ウィーン楽派の陰に隠れたシュミットやハンス・ロット、ツェムリンスキーなどの曲を積極的に取り上げるなど、ウィーンにこだわった活動をしています。その寺岡との初めてのコンサートに、ウィーンにちなんだ3曲を選びました。
ウィーンゆかりの名曲を2曲
ニコライは、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の創設者としても知られています。「ウィンザーの陽気な女房たち」はシェイクスピアの書いた喜劇。主人公である大食漢の老騎士ファルスタッフは、同じくシェイクスピアの「ヘンリー4世」の登場人物で、エリザベス女王が気に入り「彼の恋物語を見たい」と書かせたのがこの戯曲と言われています。勘違いして2人の裕福なご婦人に言い寄るも、逆に懲らしめられてしまいます。この喜歌劇はウィーンフォルクスオーパーの十八番でもあり、美しい旋律の軽快で明るい序曲は、演奏会にもよく登場します。
音楽の都ウィーンと言えば、やはりベートーヴェン。9つの交響曲を書いていますが、記念すべき第1番は29歳の時、七重奏曲やピアノソナタ「月光」などと同じ時期で、すでに人気作曲家となったベートーヴェンが満を持して書いた作品。同じウィーンのハイドンやモーツァルトといった古典派の技法を取り入れつつ、独自の意欲的な試みもみられ、若々しく生き生きとした交響曲です。
後期ロマン派最後のシンフォニスト
そしてフランツ・シュミット。シェーンベルクと同じ1879年の生まれで、シェーンベルクが12音技法の道に行ったのとは対照的にいかにもロマン派的な交響曲を4つ残しており、古風な面と斬新な響きを併せ持っています。シュミットはウィーン音楽院にて作曲とチェロを学び、ウィーン宮廷歌劇場のチェロ奏者を務めていました。
今回演奏する第4番は、シュミットの一人娘が亡くなり追悼のために書かれた作品です。哀愁のある旋律が魂を揺さぶり、リズムが胸を打ちます。
作品は素晴らしいのにあまり演奏されない作曲家ですが、再評価され少しずつ演奏機会が増えてきました。きっといつかブレイクする時が来ると思います。是非聴いてみてください。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
マーラー、ラヴェルそしてプルースト
マーラー(1860-1911)はパリと相性が悪かった。1900年、ヴィーン・フィルハーモニー初の外国旅行に同行して、第5回パリ万国博覧会コンサートの指揮を執ったが、事前の宣伝は殆ど行われず、数少ないポスターには、故意か偶然か、マーラーの名前が“Malheur”と印刷されていた(フランス語で“malheur”は不幸の意味)。シャトレ座で6月18日に開かれた第1回コンサートのプログラムには“Mahler”と正しく表記されていたが、企画全体が杜撰で、ヴィーンへ帰る旅費すら危ぶまれる始末。マーラーは金策に走り、ロチルドゥ(Rothschild)(注1)伯爵に泣きついて必要な財源をやっと確保したらしい。当然の帰結として、モーツァルトの交響曲第40番、ベートーヴェンの交響曲第5番等を組んだ演奏会の聴衆は少ない。会場をトロカデロ宮に移してベルリオーズの〈幻想〉をメインに据えた第2回、ベートーヴェンの〈英雄〉、シューベルトの〈未完成〉等を演奏した第3回と徐々に客の入りが増え、オーケストラは無事ヴィーンに戻れた。心労が嵩じたマーラーはオーストリア南部山岳地帯のケルンテン州へ逃げ帰り、第4交響曲の仕上げに取りかかる。今日から見れば思いも及ばない難行苦行の珍道中になったとはいえ、個人的にはパリのオーストリア大使館で、強力な政治家として名を馳せていたジョルジュ・クレマンソー(注2) の弟に、ヴィーンから嫁いだソフィーとベルタの姉妹を紹介される運にめぐりあった。ベルタは解剖学者のツッケルカンドル夫人としてヴィーンの芸術サロンを主宰し、このサロンでマーラーは19歳若いアルマ・マリア・シンドラー(1879-1964)と出会って1902年に結婚した。次にパリを訪れた1910年はコロンヌ管弦楽団と交響曲第2番のフランス初演に臨んだものの、第2楽章の途中でドビュッシー、デュカ、ピエルネといったパリ楽壇の重鎮が退席するという屈辱を味わった。翌1911年、ニューヨークで連鎖球菌に感染して、4月にヨーロッパへ戻る。パリで血清療法を試みるが不首尾に終わり、ヴィーンの病院に移送されて6日後の5月18日に帰らぬ人となった。
ラヴェル(1875-1937)もヴィーンでは疎外感に苛まれた。〈ダフニスとクロエ〉の素晴らしい演奏に接したヴェーベルンは、指揮者のアンセルメに「木管楽器を何故4本も使うのだろうか。ベートーヴェンは2本ずつで充分力強い音を出せたのに」と冷たく嫌みを言った。ウインナ・ワルツへのオマージュとして書かれた〈ラ・ヴァルス〉は管弦楽版に先立ち1920年10月23日にヴィーン・コンツェルトハウス小ホールで、ラヴェル自身とカゼッラ(注3)による2台ピアノ版が初演された。この時ラヴェルは、未亡人になっていたアルマ・マーラーの許に滞在したが、彼女はラヴェルのことを「ナルシストで、背は低いが均整がとれている軟弱な美男子」と評した。1937年にラヴェルが亡くなった時には「ドビュッシーやストラヴィンスキーの方が個性が強く独創的だが、ラヴェルはポピュラーな巨匠となった。2つの太陽の間にある月のように」と述懐している。17年間で点数が多少上がったというべきであろう。
マーラーはラヴェルより15歳年上であるが、ともに19世紀末の風潮の中を生きた。ヴィーン分離派(Sezession)やアール・ヌーヴォー真っ盛りのベル・エポック時代である。政治的には普仏戦争(1870-71)と第一次世界大戦(1914-18)の間で大きな争いは無かったが、フランスだけではなくヨーロッパの世論を二分したドレフュス事件(1894-1906)(注4) 等、爛熟した文化と不安定な世相は表裏一体であった。その雰囲気はマルセル・プルースト(1871-1922)が著した〈失われた時を求めて〉に克明に描かれている。文学だけでなく美術・音楽にも造詣が深かったプルーストは、作中に小説家のベルゴット、画家のエルスティール、作曲家のヴァントゥイユを登場させて芸術論を展開する。「もし言語の発明、言葉の形成、観念の分析がなかったら、音楽だけが魂のコミュニケーションを可能にする唯一の例となったに違いない(第5篇〈囚われの女〉)」と宣言した彼の著作でマーラーについて言及している箇所はないが、プルーストに昔の記憶を蘇えらせたマドレーヌの香りは、マーラーの軍楽隊と民謡の響きに相当し、子供時代を回顧する心情はラヴェルに〈マ・メール・ロワ〉や〈子供と魔法〉を書かせた。美しい表現の狭間に、ノスタルジックで淡い終末観が漂っている。それは彼等3人の作品が持つ自伝的傾向と時間意識という共通項に根ざしているからではないだろうか。尚、第7篇〈見出された時〉には、ラヴェルが「パレストリーナ(注5) のように美しいが、理解するのが難しい曲」と実名で紹介されている。
ヴィーンは1972年にヨーロッパへ渡った私が最初に住んだ町だ。路面電車が走る傍らの広大な工事現場から砂埃が舞い、戦争で多くの成年男性が失われたので太ったオバさん達ばかり目立って20年はタイムスリップした上に、ヴィーン訛りドイツ語の悠長なリズムは時計の針もゆっくり進むように感じられて、正に“gemütlich”(注6) という言葉でしか形容できない博物館的な佇まい。美術史美術館で初めてフェルメールと出会って感激し、高等音楽院の学生は、かつてマーラーが監督だった国立歌劇場の立見席に1シリング(約13円)で入れたので毎日通った。さすがに〈パルジファル〉の後では膝が笑って階段を下りるのに苦労したが。シェーンベルクやベルク、ヴェーベルンがとてもロマンティックに響くのを聴いて、〈トリスタンとイゾルデ〉との結びつきを実感したのもヴィーンだった。今回のプログラムは、ヨーロッパに於ける私の原点と35年以上住んでいるパリを総括している。芸術作品こそ「失われた時」を見出す唯一の手段なのだから。
注1:ロスチャイルド家。ヨーロッパのユダヤ系財閥、貴族。「ロスチャイルド」は英語読み。フランス語読みは「ロチルドゥ」、ドイツ語読みは「ロートシルト」。
注2:ジョルジュ・クレマンソー(1841-1929)後のフランス首相。第一次世界大戦終了時にヴェルサイユ条約に調印した。
注3:アルフレード・カゼッラ(1883-1947)イタリアの作曲家・ピアニスト・音楽教師。
注4:1894年にフランスで起きた、当時フランス陸軍参謀本部勤務の大尉であったユダヤ人のアルフレド・ドレフュスがスパイ容疑で逮捕された冤罪事件。
注5:ジョヴァンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナ(1525年?-1594)イタリア・ルネサンス後期の音楽家で、カトリックの宗教曲を多く残し「教会音楽の父」ともいわれる。
注6:ドイツ語。心地よい、心にかなったという意味。
第230回ローテーション
| 古風なメヌエット | ダフニスとクロエ | マーラー4番 | |
| フルート1st | 吉田 | 松下 | 岡田 |
| 2nd | 新井 | 吉田 | 新井 |
| 3rd | 岡田(picc) | 兼子(picc) | 松下(+picc1) |
| 4th | - | 岡田澪(Alt)(*) | 兼子(+picc2) |
| オーボエ1st | 岩城 | 堀内 | 堀内 |
| 2nd | 桜井 | 平戸(*) | 平戸(*) |
| 3rd. | 桜井(C.I.) | 岩城(C.I.) | 岩城(+C.I.) |
| クラリネット1st | 末村 | 中島 | 品田 |
| 2nd | 大藪 | 末村 | 進藤(+EsCl) |
| 3rd | - | 高梨(EsCl.) | 石綿 |
| BassCl | 岩村 | 岩村 | 岩村 |
| ファゴット1st | 浦 | 浦 | 田川 |
| 2nd | 田川 | 野田 | 藤原 |
| 3rd | - | 田川 | 野田(+C.Fg) |
| C.Fg | 藤原 | 藤原 | - |
| ホルン1st | 大内 | 大原 | 箭田 |
| 2nd | 大原 | 市川 | 大原 |
| 3rd | 箭田 | 大内 | 大内 |
| 4th | 宮田 | 宮田 | 市川 |
| トランペット1st | 倉田 | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 北村 | 青木 | 青木 |
| 3rd | 中川 | 北村 | 中川 |
| 4th | - | 中川 | - |
| トロンボーン1st | 武田浩 | 武田香 | - |
| 2nd | 志村 | 武田浩 | - |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | - |
| テューバ | 土田 | 土田 | - |
| ティンパニ | 桑形 | 桑形 | 皆月 |
| パーカッション | - | シンバル/古関 大太鼓/桜井 小太鼓(小)/今尾 グロッケン/皆月 |
シンバル・タムタム/桑形 大太鼓/桜井 トライアングル/今尾 鈴・グロッケン/古関 |
| 鍵盤 | - | チェレスタ/井上(*) | - |
| ハープ | 篠﨑(*) | 篠﨑(*)、稲川(*) | 篠﨑(*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(佐藤) | 堀内(佐藤) | 堀内(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(田川) | 小松(田川) | 小松(田川) |
| ヴィオラ | 村原(柳澤) | 村原(柳澤) | 柳澤(村原) |
| チェロ | 柳部(安田) | 柳部(安田) | 柳部(安藤) |
| コントラバス | 渡邊(中野) | 渡邊(中野) | 中野(渡邊) |
(*)はエキストラ
マーラー:交響曲第4番ト長調
マーラーは1887年、27歳の時にアルニムとブレンターノによる詩歌集『少年の魔法の角笛』と出会っており、これを題材として多数の歌曲を生み出している。多くは後に同名の歌曲集となり、一部は第二、第三、第四交響曲に用いられている。そのため、これら3つの交響曲を角笛交響曲と呼ぶこともある。
第四交響曲の第4楽章は1892年に作曲されたフモレスケと題された『少年の魔法の角笛』からの最初の歌曲集の中の「天上の生活」が用いられている。マーラーは当初は第三交響曲の第7楽章として「天上の生活」を用いる構想を持っていたが、最終的には肥大化した第三交響曲には含めず、新たに「天上の生活」を核とする第四交響曲を作曲することとなった。
マーラーは第四交響曲の完成時、親しい友人のナターリエ・バウアー=レヒナーに「第四交響曲は前の三つの交響曲と密接に関係しており、それらはこの第四交響曲によってはじめて終結するのだ。それらは内容においても、構造においても、四つでひとつに完結した四部作である。」と語っている。また第三交響曲の作曲中には「僕が第二交響曲で提起し、答えようとした人間への究極の問い、すなわち、我々は何のために存在するのか、我々はこの世の生を終えてもなお存在するのか、という問いは、ここではもう僕にとってどうでもいいことなんだ。全てが生き、生きなければならず、ずっと生きてゆくことになる世界で、それがどういう意味があるというのだろう?このような交響曲において、神の無限の創造性に思いを凝らしている精神が、亡きものになるなどといったことがあってよいだろうか?いや、人間は確信をもってよいのだ。全ては永遠に、不滅のものとして保護されている、と。キリストも、『わたしの父の家には、多くの住処がある』、といっているとおりだ。それに、そこには人間の苦悩や悲しみが入り込む場所はない。それは崇高な明るさに支配された、永遠に光り輝く昼だ。もちろんそれは、神々にとってそうなのであって、人間にとっては恐ろしく途方もないもの、全く捕えようのないものなのだ。」と語っており、マーラーが第一交響曲を含め四部作としているのはマーラーの世界観の発展を表しているからと考えられる。すなわち現実世界の人間が理想を求めて闘う第一交響曲から始まり、人間の生と死の意味を考える第二を経て第三、第四では自然や愛、天上の世界を表現するに至っている。第四交響曲は「天上の生活」を核にしていることもあり、全体にメルヘン的な要素が強く表れている交響曲である。
第三交響曲との関連
第三交響曲の第5楽章には『少年の魔法の角笛』の「三人の天使は歌う」が使われている。詩の内容はイエスを裏切ったペトロの懺悔に対し、イエスが「お前が十戒を破ったというなら、跪いて神に祈りなさい、いつも、ひたすら神を愛しなさい、そうすればお前も天国の喜びを得よう!」と答え、三人の天使が「ペトロの罪は晴れました!」と歌うものである。これは「天上の生活」の中で天国の喜びを得たペトロに繋がるもので、第三と第四交響曲の密接な関係を示している。
楽器編成について
第四交響曲はトロンボーン、テューバが含まれておらず、マーラーの交響曲としては小編成なものになっている。マーラーは第3楽章のクライマックスでトロンボーンを使うことも考えたが、その箇所の為だけに編成を拡大することはしなかったそうである。なおトロンボーン、テューバがないという以外では三管編成を超えており、一般的なオーケストラの編成と比較するならば小編成とはいえない。
「この世の生活」
マーラーの歌曲集『少年の魔法の角笛』には「この世の生活」が含まれている。元々、最初に作曲された5つのフモレスケでは「この世の生活」と「天上の生活」が対になっていた。後に「天上の生活」は歌曲集からは削除されることになるが、この二曲は内容的に対比される関係にある。「この世の生活」ではお腹を空かせた子供が食べ物を求めているのだが、母親が麦を刈り、粉を挽き、ようやくパンが焼き上がった時には餓死していたという残酷な現実世界を表している。それに対し、「天上の生活」では食べ物や音楽に溢れ、喜びに満ちた世界が描写されている。
「天上の生活」
マーラーは第二交響曲を作曲中の1893年に「僕の《天上の生活》では、構想はまったくふさわしいかたちで実現され、何から何まで幸運にも構想どおりだったように思える。」と語っており、この曲への自負と愛着が感じられる。「天上の生活」の詩の内容(「天上の生活」対訳参照)を見ると意味深長であり、辛辣な表現や皮肉やパロディとも感じられる。詩の中に登場するヨハネは洗礼者ヨハネのことであり、ヘロデはイエスの殺害を目的に「ベツレヘムの嬰児大虐殺」を行った悪名高きユダヤの王のことである。となると子羊は暗にイエスを指していることになる。また牛をシンボルにしている聖ルカが牛を殺すというのも皮肉である。しかし、一方で聖マルタが料理することや、チェチーリアが音楽を奏でることに違和感はない。また殉教したとされる伝説のウルズラと1万1千人の処女も天国では楽しく過ごしていると考えられるだろう。
つまりここに描かれている世界が光に溢れた影のない楽天的な天上界であるなら、地上での善も悪も意味をなさない世界とも考えられる。詩の内容そのものの解釈は限定されるものではないが、マーラー自身はこの詩について「そこには、深い神秘と結びついた何という悪戯っぽさが隠されていることか!すべてが逆さになり、因果律などは一切通用しない!それはまるで、突然、あの反対を向いている月の裏側をみたようなものだ」と語っている。
第一楽章 中庸の速さで、速すぎずに。ト長調 4分の4拍子 ソナタ形式
初演時に聴衆は単純なテーマに驚いたが、展開部ではついていけなくなったとのことである。マーラー自身は次のように説明している。「それが最初に現われるときには、花についた朝露のしずくが、太陽の光が差し込む前にそうであるように、ごく目立たない。でも陽光が野原に当たりはじめると、その光線は真珠のような露ひとつひとつによって幾千という光と色に分解し、そこから光の洪水のような反映が僕らを照らすのだ。」また次のようにも語っている。「僕は第一楽章で、こんなに子供のように単純で、まったく自身を自覚していないようなテーマの楽器付けのために、これまでにない苦労を味わったんだよ。最もポリフォニー的な楽句でさえ、こんなに苦労したことはなかった。奇妙にも、僕はずっと前から、音楽をポリフォニーとして以外考えられなかったから、その複雑で錯綜した進行にすっかり慣れているのさ。しかしこの場合には、多分、僕に、訓練を受けた学生ならば誰でも簡単に使えるような対位法、つまり純粋書法の能力がいまだに欠けているのがいけないのだろう。」あくまでもソナタ形式に忠実でありながら、極めてマーラー的で複雑なポリフォニーが展開される。マーラー自身は次のような言葉も残している。「第一楽章は、三つまでも勘定できない、といった調子ではじまるんだけれど、すぐに九九ができるようになり、最後には何百万といった目がまわるような数字を計算してしまうのだ。」
第二楽章 落ち着いたテンポで、慌ただしくなく。スケルツォハ短調 8分の3拍子 三部形式
マーラーはこのスケルツォについて「その性格の点で、第二交響曲のスケルツォを思い起こさせ、また新しいものを古い形式を使って表現した唯一の楽章である。」と語っている。この楽章の特徴として、コンサートマスターはフィーデル風にと指定された一全音高く調弦されたヴァイオリンに持ち替えた独奏を行う。マーラーはこのヴァイオリンを「友人ハインが演奏する」と書いており、「死の舞踏」を意識したグロテスクなものとなっているが、中間部では穏やかで夢想的なメルヘンも展開される。
第三楽章 静かに、少しゆるやかに。ト長調 4分の4拍子 変奏曲形式
非常に美しい緩徐楽章であるが、変奏曲形式であり、変奏によりテンポも大きく異なる。マーラーはこの楽章を「聖ウルズラの笑い」と名付け「この曲をみると、子供時代に見た、深い悲しみをいだきながら涙を浮かべるようにして笑っていた母親の顔が思い浮かぶ」と語ったそうである。また「この曲全体では、神々しく晴朗な旋律と深く悲しい旋律とがあらわれるが、きみたちはそれらを聴くと、ただ笑ったり泣いたりすることしかできないだろう。」と説明している。
第四楽章 非常に心地よく。ト長調 4分の4拍子
ソプラノ独唱により、『少年の魔法の角笛』からの「天上の生活」が歌われる。先に説明した通り、マーラーは先にこの歌曲を作曲しているが、第四交響曲に用いるにあたり、他の楽章の編成に合わせてオーケストレーションを拡大している。スコアには独唱について「子供らしい明るい表情で、まったくパロディなしで」という注釈が書かれている。
完成:1900年8月5日
初演:1901年11月25日、作曲者自身の指揮によりミュンヘンにて
楽器編成:フルート4(3、4番はピッコロ持ち替え)、オーボエ3(3番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット3(2番はEsクラリネット持ち替え、3番はバスクラリネット持ち替え)、ファゴット3(3番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット3、ティンパニ、大太鼓、トライアングル、鈴、グロッケンシュピール、シンバル、タムタム、ハープ、弦五部(コントラバスは第5弦を持つもの)
参考文献:
『グスタフ・マーラーの思い出』ナターリエ・バウアー=レヒナー著、高野茂訳(音楽の友社)
『マーラー』(新潮文庫―カラー版作曲家の生涯)船山隆(新潮社)
天上の生活(『少年の魔法の角笛』より)
私たちは天国の喜びをいろいろ楽しんでいます。
だから現世のことは遠ざけるようにしています。
この世の騒ぎなど
天国では何も聞こえません!
すべてがやさしくゆったりと暮らしています。
私たちは天使のように暮らしていますが
そうでいながらとても楽しいのです。
私たちは踊ったり飛びあがったり
跳ね回ったり歌ったりします
天国の聖ペトロがこちらを見ています。
ヨハネが子羊を放すと
屠殺者ヘロデがそれに目をつけます。
私たちは辛抱強い
汚れのない、辛抱強い
かわいい子羊を死へと導きます。
聖ルカが牡牛を屠ります
なんの心配も気づかいもなく。
ワインにお金などかかりません
天国の酒場では。
天使たちがパンを焼いてくれます。
あらゆる種類のおいしい野菜が
天国の庭で育ちます
おいしいアスパラガスにインゲン豆
それに欲しいと思うものはなんでも。
私たちは鉢にいっぱいにいれてもらえます!
おいしいリンゴ、おいしい梨、おいしいブドウ、
園丁たちはなんでも取らせてくれます。
ノロジカやウサギがほしければ
みんなが通っている道を
それらが走っていきます。
斎日がきたとしても
魚たちがすぐにみんな喜んでこちらに泳いできます!
そこにさっそく聖ペトロがやってきて
網と餌をつかって
天国の池の中へと引き入れます。
聖マルタがきっと料理をしてくれるでしょう。
地上の音楽など
私たちの音楽とは比べものになりません。
一万一千人の乙女たちが
思い切って踊り始めます。
聖ウルズラもそれを見て笑っています。
地上の音楽など
私たちの音楽とは比べものになりません。
チェチーリアとその身内のものたちが
すばらしい宮廷音楽家となって演奏します。
天使のような歌声が
感覚を喜ばせてくれ
すべてが喜びで目覚めます。
ラヴェル:「ダフニスとクロエ」第2組曲
◆ラヴェルとストラヴィンスキイ
ニコライ・ディアギレフ率いるロシア・バレエ団(バレエ・リュス)がパリに於いて上演(*1)した演目を俯瞰すると、1910年からの4年間が奇蹟とも言うべき時期だった事に気づかされる。以下の初演記録を参照されたい。
・1910年6月25日:『火の鳥』
・1911年6月13日:『ペトルーシュカ』
・1912年6月8日:『ダフニスとクロエ』
・1913年5月29日:『春の祭典』
20世紀の代表的なバレエ音楽として、現代の我々が真っ先に頭に浮べ得るこれらの傑作が、この短い時間の中で毎年創作され世に出ている。舞台美術や衣裳・振付けと云ったそれぞれ全く独立した分野の総合芸術であるバレエ。個々の準備や稽古に費やされるべき時間を考えれば、初期段階で完成が求められる音楽の創作に充てられる時間は限られている。1年という時間の緊密さ(短さ)は想像に難くない。
ラヴェルとストラヴィンスキイはこの4年間でひとつの時代を築き上げた。結果だけ見るとストラヴィンスキイが時期的にも量的にも先行しているように思える。彼は『春の祭典』の初演(これがどのような阿鼻叫喚のスキャンダルをもたらしたかは有名だ)時点で30歳。88年に及ぶ長い生涯の中で、確かにここでひとつのピークを迎えており、ラヴェルに比してより華々しくも見える。
だがこの輝かしい歴史の契機については、少し詳しく経緯を辿ってみる必要がある。
1909年のはじめ、ディアギレフは明くる年の公演に向け、ラヴェルに1冊のバレエ台本を手渡した。バレエ団の主宰者はこの作曲家の才能に着目し、音楽を依頼したのだった。しかしながら『ダフニスとクロエ』と題されたこの台本の熟読を重ねるにつれ、ラヴェルは失望を深める事になる。
主人公たる男女二人は共に美貌と健康な肉体を誇り、しかも実は高貴な生まれ。それぞれ故あって捨てられるが曲折の後に真実が判明して結ばれ、ハッピーエンドに至る。当然登場する恋の妨げとなるライヴァル(ドルコーン)も根は善人で、さしたる邪魔にもならぬ都合の良さ。海賊の登場する冒険譚はありきたりと言えばそれまでの内容だが、それに加えて書き込まれた、振付けの都合を優先した詳細な指示は、彼の意慾を減退させた。
ラヴェルはこうした陳腐さや小細工に拘泥せず、ギリシャ時代に書かれた原作(*2)の背景にある健全な古代の精神をこそ、「音楽による大フレスコ画(ラヴェル自身の言葉)」として表現しようとの構想を温めていた。そのため合唱を含む大規模な編成を企図したが、費やされるカネも時間も厖大とあってディアギレフと衝突。最終的に主宰者の納得を得るに至ったが、その交渉によって時間切れとなり、やむなくディアギレフが代打として起用したのが、前年彼に認められたばかりのストラヴィンスキイだった。この若き気鋭の才能はいずれ世に知られたには違いない。だがディアギレフの委嘱をこの時受けた事で、後に「三大バレエ」となる作品群の創造に、一気呵成の勢いを獲得したのである。
その間ラヴェルは3年をかけて周到な準備をした。掉尾の「全員の踊り」だけで丸1年を費やしたというが、その規模と完成度と内容の緻密さ、そして前述したバレエ公演の準備期間を考えれば信じ難い早書きと言える。それを実現した背景には、先行したストラヴィンスキイの仕事から受けた刺戟があったに違いない。若きふたり(ラヴェルも30代前半)を競わせ、毎年の公演を成功させたディアギレフの手腕は、この一事を取上げても傑出していると思わざるを得ない。それはもちろん音楽の分野に限らないのである。名伯楽と言うべきであろう(*3)。
◆「第2組曲」の事
この組曲は「夜明け」から「パントマイム」を経て「全員の踊り」で終結する。「夜明け」は文字通りの夜明けの描写であり、「全員の踊り」は登場人物総出の舞踏の場面であるから解り易い。ただ「パントマイム」はやや説明が必要だろう。これは海賊の横暴(第2部)によって引き裂かれたダフニスとクロエが「夜明け」の場面で再会。それに続いて始まるダフニスによる求愛の舞踏で、フルートのソロに乗って演じられる。そして応じるクロエ共々両者の言葉を交わさない無言劇(個人的な感覚だが、僕はこのソロを吹くたびに静謐な能の舞台を想起してしまう)が繰広げられる。そしてその後に行き交い始める音の応酬を経て、急速に速まるテンポと音域の昂りの果てに、稲妻のようなピッコロからアルトフルートまでの4オクターブにも及ぶ下降線を以って懶い低音に落ち着くが、そこにひとつの官能の成就が象徴されている。長年様々な作品を演奏していると、陰に陽にそれとわかる描写や表象に行き当たる事があるが、これは極めて急速な変化のうちに完結しており男性的だ(笑)。ラヴェルの志向した健全にして率直な古代の人間像はこうした箇所にも顕れている……というべきだろう……か。
「全員の踊り」は5拍子を基本にしている。これは古代=非近代の舞踏リズムで、ここに於いてラヴェルの意図は一層明らかにされている。前述のストラヴィンスキイの作品を含め、非西欧・非近代的な世界観に対する確実な志向が見出されよう。前述の4年間に作られたバレエ音楽は、それぞれ民話の世界のロシアや古代ギリシャを舞台にしており、最後は原始のロシア社会に行き着いている。ディアギレフがパリ市民の嗜好を敏感に感じ取り、興行を企画していたのであろうと想像する。
だが『ダフニスとクロエ』に向かう時、そんな事はどうでも良い。純粋に音楽へ耳を向ければ自ずと様々な場面は思い浮かべられよう。それで充分というものだ。
バレエやオペラの為に書かれた長大な作品の中から、人気のある場面や独立した名曲を抜粋し、組曲として演奏される例は多い。作曲家自身が改作する事も、他の人がそれを構成する事もある。だが『ダフニスとクロエ』の場合は、演奏時間50分を超える全曲のうち「夜明け」から終結までが、手を加えられる事無くそのまま演奏されているに過ぎない。これを「組曲」と名づける事には違和感がある。
しかもこれを「第2組曲」と呼ぶ。当コンサートでもそれを踏襲しているが、対応すべき第1組曲(*4)の存在はほぼ忘れ去られているのだから、「第2」の名を冠する事も殆ど無意味というものだ。初演から100年を経て、これほど知られた作品でありながら、首を傾げたくなる妙な慣習が放置されているのもこの曲の特徴……ではある。100年間世界中で数え切れぬほど繰返し演奏されて、その現場では必ずや指摘されているはずの山なす間違い箇所が、一向に改訂されない譜面ともども、いい加減見直したらどうだとこの曲を演奏する度に考えてしまう。
実はそういう曲なのである。
*1:バレエ・リュスの公演は1909年に始まり、ディアギレフの歿年である1929年まで毎年5月~6月の期間に行われている。
*2:『ダフニスとクロエ』の原作は、紀元2~3世紀の頃にロンゴスによって書かれたギリシャの恋愛物語。
*3:ディアギレフはこのふたりの他にもバレエ音楽を多数委嘱している。例えばドビュッシーは『遊戯』を書き上演されているが、僅か半月後に初演された『春の祭典』の陰に隠れ、忘れ去られている。
*4:第1組曲は、第1部「夜想曲」「間奏曲」から第2部「戦いの踊り」までが、切れ目無く演奏される形をとるが、現在この部分だけの演奏を聴く機会はほとんど無い。
全曲初演:1912年6月8日 ピエール・モントゥ指揮、パリ シャトレ座 ロシア・バレエ団
楽器編成:フルート2、ピッコロ、アルト・フルート、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、Esクラリネット、バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン4、トランペット4、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、中太鼓、小太鼓、タンブリン、トライアングル、カスタネット、ジュ・ド・タンブル(鍵盤グロッケンシュピール)、チェレスタ、ハープ2、弦五部
参考文献:
『ダフニスとクロエー』ロンゴス著、松平千秋訳(岩波文庫)
『音楽大事典』ラヴェルの項(平凡社)
『ベレエ・リュス その魅力のすべて』芳賀直子著(国書刊行会)
ラヴェル:古風なメヌエット
1ラヴェル ~生涯について~
モーリス・ラヴェルは、1875年に、フランスの南西部はバスク地方、スペイン国境近くにある小村シブールにて、スイス系の父とスペイン・バスク地方出身の母との間に誕生した。もっとも、生誕後すぐにラヴェル一家はパリに移住したため、ラヴェル自身は生粋のフランス育ち、パリジャンであったといえよう。
幼い頃から音楽教育を施されたラヴェルは、1889年にパリ国立音楽院のピアノ科に入学した。音楽院でピアノや和声学について学ぶ中で、ラヴェルはピアニストとしてではなく、作曲家としての道を徐々に歩み始めることとなった。
ラヴェルは作曲活動の初期にピアノ作品を多く残しており、本日演奏するこの作品も、そのうちの一つとなる。1895年、まだ20歳の学生であったラヴェルは、当初はピアノ曲として本作品を世に送り出した。なお、これはラヴェルにとって、生涯で最初の出版作品でもあった。
本作品以降も、ラヴェルは次々と話題作を世に送り出し、その名は広く知られるようになった。特に1920年代には、自作の指揮者、ピアノ奏者として世界各地への演奏旅行を行う等、音楽活動を幅広く精力的にこなした。一方で、1900年代前半における作曲コンクール「ローマ賞」への5度にわたる落選、1914年に勃発した第一次世界大戦におけるフランス軍への入隊及び戦場への従軍、1917年の最愛の母の死、戦争及び母の死による精神的ダメージに起因する作曲活動の不調等、ラヴェルは決して順風満帆とはいかない紆余曲折のある人生を送っていたともいえる。
また、周期的な不眠症にも悩まされていたラヴェルであったが、1930年代中頃からのいわゆる最晩年は、脳疾患とみられる症状により、譜面はおろか文字すら書くことが困難になっていたと言われている。頭の中にあふれ出る音楽のアイデアをこの世に書きとめておくことができないまま、1937年には病状が急激に悪化し、開頭手術を受けた直後に62歳でこの世を去った。
2古風なメヌエット
さて、作品「古風なメヌエット」であるが、「後向きの小品」と作曲家自身の言葉にもあるように、古典的かつ厳格な形式、3/4拍子の舞曲である「メヌエット」として書かれたものである。一方、「古風な(antique)」と名付けられたところに、その内容は単なる「古典的な(classique)」音楽ではないとする、作曲家の自己主張も垣間見える作品となっている。
形式は、18世紀後半の古典派時代に定着した、メヌエット(A)―トリオ(B)―メヌエット(A)の伝統的な構成となっている。また、主調の短調(A)を同主長調(B)と対比させ、急激なアクセント付け(A)と穏やかな抒情性(B)といった対照的な雰囲気を交替させる曲想ともなっている。
こういった厳格な古典の形式を踏襲しつつも、古典派時代にはない斬新さ、新鮮さが感じられるのは、その内容に創意工夫が散りばめられているためである。その一例を挙げよう。下記の譜例は、トリオ(B)の冒頭部分である。8小節区切りのフレーズであるが、2小節目が変形され2、3拍目が引き伸ばされたようなフレーズになっている。このことにより、旋律構造と小節線が1拍ずれて聞こえるようになる等、古典派時代の作品にはない柔軟なリズムが際立つ旋律となっている。
3ラヴェル ~編曲について~
モーリス・ラヴェルは、俗に「管弦楽の魔術師」、「スイスの時計職人」と評されるほど、管弦楽法に秀でた技能を有していた。そして、作曲もさることながら、自身の作品を改作、編曲することも特に好んでいた。
「亡き王女のためのパヴァーヌ」、「マ・メール・ロワ」、「高雅で感傷的なワルツ」等、ラヴェルは自身のピアノ作品を多数オーケストラに編曲している。元来は学生時代に作曲されたピアノ曲であった本作品(下記譜例参照)も、1929年、ラヴェル54歳の円熟味の増した晩年に、余暇で訪れた故郷バスク地方にて、オーケストラ曲に編曲された。
ラヴェルによる自作の編曲の特色として、まず原曲が編曲に適していたことが挙げられる。ラヴェルはピアノ作品を作曲する際、その音色を念頭に置いた「ピアノのための音楽」にとどまらず、旋律線と構造を重視した「音楽作品」として捉えていたと言われている。そのため、編曲により原曲の魅力を損なうことなく、音色を変化させ新たな芸術作品として世に送り出すことに成功していた。
また、ラヴェル自身が指揮者として活動していたことも、編曲された作品の完成度に大きく寄与している。作曲活動の傍ら、指揮者としてヨーロッパからアメリカ・カナダ等、各地で演奏旅行を行ったラヴェルは、演奏者への質問等の実践的な経験も活かし、そのオーケストラ技法を洗練させていったと考えられる。
本日は、ラヴェルの生涯に思いを馳せつつ、その生涯をかけて培われた職人芸の集大成ともいえる、この魅力あふれる小作品を、お楽しみ頂ければ幸いである。
初演:原曲版:1898年4月18日パリにてリカルド・ビニェスによる
オーケストラ編曲版:1930年1月11日パリにて自身の指揮による
楽器編成:フルート2、ピッコロ、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、ハープ、弦五部
参考文献
『古風なメヌエット(スコア)』(日本楽譜出版社)
『作曲家別 名曲解説 ライブラリー⑪ ラヴェル』(音楽之友社)
『近代・現代フランス音楽入門』磯田健一郎著(音楽之友社)
『ラヴェル 生涯と作品』アービー・オレンシュタイン著、井上さつき訳(音楽之友社)
『ラヴェル その素顔と音楽論』マニュエル・ロザンタール著、伊藤制子訳(春秋社)
運営の話から なぜか歯の話
維持会マネージャーの松下さんより「最近の運営改革について」というお題でニュース執筆を依頼され、私は6月は忙しいので勘弁してほしいとお断りしたはずだったのに、だいぶ経って再度依頼され諦めていただけなかったようでした。別な内容でもよいかと何度も申しましたが、結局運営の話から始めたいと思います。
新響の問題点としては、財政と人材確保。20年前は約130名の団員がおり、その分の団費収入で余裕のある活動ができたのが、ここ10年は100~110名程で、この春には一時100名を切ってしまったのです。当然その分団費・演奏会費やチケット収入も減少するわけで、演奏会参加費値上げや維持会費の蓄えを使い、何とか新響らしい活動を続けさせていただいています。
団員数が低迷している原因としては、新響の敷居の高さにあるのでしょう。オーディションがある、年に4回演奏会がある、お金がかかる。一度入団してもらえれば、新響の良さを実感してもらえると思うのですが難しいものです。まずは、多くの見学者に来てもらって良さを伝えオーディションを受けていただく率を上げることを目標に取組んでいます。演奏も団体としてもコミュニケーションが大切ということです。
もうひとつ考えたのが「団友制度」でした。団員ではないけど演奏会参加費を払い新響の演奏会に出演できるというものです。年4回の演奏会に出るのは辛いとか、試しに新響で演奏してみたい、この曲を演奏したいといった方に出演してもらえれば、それが正式入団につながる可能性もあるし、財政的にも助かる。また、高齢団員が長く新響を続けるための受け皿にもなるのではないかと考えました。
しかしながら、問題はどのような方に団友になっていただくかです。公募はもちろん団員の紹介だとしても、どのくらいの技術レベルなのか、合奏能力があるのかわかりません。であれば、結局オーディションを受けていただく必要はあるし、入団と団友参加で差をつけるのは運用上難しいということで、まずは現首席が信頼できる新響OBを対象に団友制度を始めてみようということになりました。現実的には、財政的に助かる団友を迎えるか、将来の入団を望める若い人に賛助出演を依頼するか(謝礼をお支払いしています)なかなか難しいところです。
このやり方では団友制度は高齢団員対策にはなりにくく、その代わりに「65歳以上降り番制度」を始めることになりました。自己都合で休団する(演奏会出演を休む)場合は、演奏会参加費を全額出すことになっているのですが、65歳以上であれば参加費を払わないで休団することができるというものです。
年に4回出演する体力的金銭的な負担を軽減できるというのが目的です。私も含め新響のフル活動についていけなくなったらキッパリ引退して潔く席を空ける覚悟の団員は多いと思いますので、この制度がどのくらい効果があるかわかりませんが、良い形で活きればよいと考えています。
ひと昔前は、60歳を超えてアマチュアオーケストラを続ける人はまれで、特に管楽器は40歳を超えたら引退を考える風潮でした。今は新響に限らず、60歳を超えても続ける人が増えているように思います。最近、65歳以上の高齢者の身体機能や健康レベルは10~20年前より5~10歳は若返っている(日本老年学会報告)というニュースが話題になりましたが、特に管楽器の場合は歯のトラブルで吹けなくなるという人が減っているように思います。実際8020(80歳で20本以上の歯がある)を達成している人は20年前は1割ほどでしたが、最近の調査では40%以上ということでした。歯のケアに気をつけている管楽器奏者が増えているということかもしれません。
管楽器を吹くのに歯は欠かせないものです。歯が無いと吹けないだけではなく、歯の形や歯並びが楽器演奏に大きく関係しています。特にマウスピースの小さい金管楽器(トランペット、ホルン)での影響は大きいです。
今シーズンの矢崎先生の初回練習日のこと、当団首席トランペットの野崎さんが前歯の差し歯が駄目になって今回の演奏会は降りて休団すると言っているという話を聞き、私は降板しないよう説得を試みました。聞くと、上顎側切歯(真ん中から2番目)の差し歯が外れてグラグラし、今は接着剤で固定しているが口唇が痛くて吹けないし、抜歯が必要と言われており治療して慣れるのに数カ月はかかるから、ということでした。
1本抜歯した場合、一般的な治療は両隣りの歯を削ってブリッジにするかインプラントということになります。ブリッジの場合、両隣りを含め3本違う歯の形になってしまい、それで吹けなくなる金管奏者も多いと聞きます。かといってインプラントにすればよいわけではなく、インプラントの手術をして歯が入るまでに半年かかるし、歯の形の調整も難しい、失敗率もそれなりにあります。少し前に某プロオケ首席ホルン奏者が前歯をインプラントにし、それが原因で引退したと聞いたことがあります。
一般的な治療とは、どの歯科医師にも出来て時間がかからず結果にあまり差がないもの、特に保険治療は最低限の治療ということになると思います。普通の歯科医院で、抜歯してブリッジかインプラントという提案は至極まともではあります。最近ではMI(侵襲を最小にする)という考え方に基づいた治療をする人も増えてはいますが、治療に個人の技術の差が出やすいし、予防・メンテナンスが重要で、自費診療になるので残念ながら一般的ではありません。
なるべく歯の形を変えず、歯の寿命が短くならず、トランペット演奏を中断しない方法を考え、人工歯を作って両隣りの歯に接着することを提案しました。最小の侵襲です。接着剤で付けるだけなのでブリッジよりも壊れやすいかもしれませんが、その時はまた付ければよいのです。
歯の形については、私は多くの管楽器奏者の歯の治療をするうちにそれなりのノウハウを持っています。アンブシュアや音色、吹き心地を見ながら、人工歯の長さ・下の歯とのバランス・形などを調整していきます。野崎さんの場合どのように調整をしたかというと、
・表面は、まずは抜く前の差し歯と同じくらいで作ってみましたが、本来はもっと内側だったというので変えたところ、その方が吹きやすいとのこと。
・調整の途中「低音がうまく出ない」という状況になった。歯が短かったために口唇を横に引き気味のアンブシュアとなったためで、長くすることで解決。
・抜歯直後だったので内側の形をわざと薄く作ったところ、息の入り具合に違和感があるとのことで、普通の形にしました。内側の形も重要なのです。
・歯の角の形で音色を重くしたり明るくしたり変化させることが出来るので、最後の仕上げに野崎さんに希望を聞いたところ「可能な限り重く」とのこと。そのようにさせていただきました。
こうして歯の形が決まり、表に接着剤が出ないよう最小面積で接着をしました。小一時間の処置の結果、野崎さんは歯のために一度も練習を欠席することなく、無事今回のマーラー4番に出演となりました。
歯の話を書いていて思い出したのが、今は亡き千葉馨先生のお宅にあった歯科用エンジンです。地方大学の歯学部の学生だった私は、当時ちょっとホルンが上手かったので、知人に「一度ちゃんと見てもらった方がよい」と言われ、憧れの奏者のレッスンを受けられるのならと紹介をお願いしました。千葉先生のことは皆さんご存知と思いますが、N響首席を長年務めた名ホルン奏者です。
レッスン初日に先生の前で一通り吹いた後で、「僕の持っている学生よりも良いね。で、どうしたいの?」と聞かれ、返事に困りました。大学では「君たちを歯科医師にするのに国は1人当たり数千万円かけるのだから、ちゃんと卒業して歯科医師になり社会に貢献せよ」という教育を受けていましたから、ホルンが上手くなりたい以上の意味はありませんでした。
私が歯学部の学生だと知ると、棚にある歯科用エンジンを指し「僕はホルンを吹くために前歯を削って隙間を開けたかったのだけど、どの歯医者もやってくれなくてね。しかたがないから、道具を買って自分で削ったのだよ。」教科書でしか見たことのない、古いタイプの治療器具でした。
その頃千葉先生は55歳。当時N響の定年が55歳で、十分にホルンの演奏が出来る千葉先生の引退を反対する運動が起きていたように記憶しています。晩年は総入れ歯だったそうですが、病気で倒れられるまで魅力的なホルンを吹いておられました。
とてもチャーミングな方で、裏ワザなども教わりつつ楽しいレッスンに数回通わせていただきましたが、大学が忙しくなり、卒業して医局に残ってからはホルンどころではなくなり、それっきりとなってしまいました。今思えば、私が楽器演奏と歯の関連を意識したのは、それが最初だったのかもしれません。
フルートの知られざる憂鬱
常にオーケストラの中央にあり、煌めく楽器を駆使して珠を転がすような音色(たぶん)を聞かせる楽器。華やか以外の形容が難しい印象のフルートの世界にも、人知れぬ憂鬱の種が潜んでいる。楽器の宿命的な特性と、それによって培われる奏者の人格との関係について、同情を買う目的でやや詳しく説明してみたい。
◆息を吹き込む話
『ハムレット』にこういう一節がある。
嘘をつくくらいやさしいよ。こうして指と親指で孔(あな)を押さえるだろう、そして息を吹きもむんだ、そうすれば、美しい音色がでる。(第3幕第2場)
嘘をつく難度は人それぞれだが、その他はその通り。孔を塞いで息を歌口から入れる。これはリコーダーの話だが、フルートを演奏するのも行為としてはこれで全てであって、これ以上でも以下でもない。孔を塞ぐのはもちろんだが、歌口から息を入れるって・・・・・そんな事は管楽器(木管楽器)なら当たり前だろう!と感じる向きもおいでだろう。でも実は違う。
オーケストラに居並ぶ楽器群は、みな独自の発音源を有している。弦楽器ならその名の通り弦だし、金管楽器なら親からもらった自らの唇、そして木管楽器のうちフルート以外は「リード」という振動体を有している。つまりこれが発音源となって楽器の管体に音を与える。このリードは演奏者の身体に直接接触しているので、演奏する者は確実にその振動を体感出来る。
フルートはというと、こうした発音体は備わっていない。あるのは歌口という径10mmをやや超える程度の穴だけである。そしてこの穴の一方に下唇を乗せ、穴の反対側の壁に向けて息を吹き込む事で、音を得ている。実のところ長年フルートを吹いていても、無限に繰返されるこの行為の、一体何によって音がもたらされているのかを理解、どころか実感さえ出来ない人は多いのではないか?と薄々予感している。かくいう僕もそのひとりである。
音が出るからには振動するなにものかが必ずやある筈である。が、それが何かが解らない。例えば管内の空気が振動しているのであろうと想像はできる。だがその振動がどのような過程を経て起こるのか?はよく解らない。フルートのような楽器を指して「無簧(むこう)楽器」などという分類がある。この簧とは振動体すなわちリードの事を通常指す。
そして理屈はわからないがうつろな穴に向けて今日も息を吹き込んでは、出る音に一喜一憂する。こうした行為を長年繰返すうちに、フルート奏者は自ずと人生や世の中のありように懐疑的とならざるを得ず、虚無的な人生観に到達しがちである。貴方の周辺に見え隠れするフルート吹きもきっとこんな人間である(はずである)。
確固たる発音体を有する他の管楽器群は、管の一端にあるその音源を息によって発音させれば、管本体の機能によって変化増幅されて、他の一端からその結果としての音が発せられる。この増幅の最後のひと頑張りをもたらそうと、金管木管の違いを問わずその音の出口を拡げて指向性や拡散効果を期するような構造になっている。この先端部分を通常「ベル」という。楽器によってはこのベル部分の形状に工夫を凝らし、音色や発音に変化を加えようと意図されているものもあるが、それとてその部分から音が出る事が前提となっている。先人の工夫は実りその効果は絶大である。
ところが明確な発音体を持たぬフルートの場合、このベルに該当する部分は「足部管」と名づけられているに過ぎない。何故ならフルートに於いてはこの管の末端部からは殆ど音が出ていないからである。音は例の歌口の処から理由もわからずに出ているだけだ。
マーラーの作品ではオーボエやクラリネットは構えた楽器を上に向け、ベル部分から発せられる音の指向性を活かし、これらの楽器の音をより強調する手法が時折現れる(ホルンなどは奏者を後ろ向きにして演奏させる事までやる)。ベルを持たないフルートには何らなす術もなく、勢いよくベルアップする周囲の楽器に対し「何も臆面も無くそこまでやらなくとも・・・・・」とは思いつつも、永劫回帰仲間入りできないわが身に、一抹の寂しさを感じているものなのである。そしてやおら背筋を伸ばし、胸を張って「こちらとしても精一杯音を出しております」という姿勢(もちろん何の効果も無い)を大仰に示してお茶を濁しているのが実状で、フルート吹きがマーラー嫌いになるとすれば、果たしてこんな処に遠因があるかも知れない。
そもそも懐疑的な性格は、周囲からの孤立感が深まるに従い、このようにして更に被害者意識を増幅させるに至る・・・・・フルート奏者の人格は形成されてゆくのである。
◆孔をふさぐ話=運指=
フルートの音域は3オクターヴを超えるから、単純に考えれば約40種類ほどの音が出せる事になる。これらを出すためには胴体にあいた孔を開閉して調整する。この開閉は10本の指でそれぞれの孔を担当させる訳だ。標準的な楽器の孔の数は12個。これを10指で賄わなくてはならない上に、右手の親指は楽器を支えるためだけに存在していて他に何もしていない(笑)ので、その他の9本の指で全ての孔の開閉が可能なようにキイのシステムが考案されている。因みに右手親指の役割はオーボエもクラリネットも同じで、楽器の保持に専念。例外はファゴットで、この指に10個以上のキイの操作を課しているのである。どうしてこういう事になってしまったのかは知らないが、「生まれ変わってもファゴットだけはやれないだろうな」と、個人的には諦念に近い感慨を常に抱いている。
驚くべき事にフルートの基本的な指遣い(運指という)は14種類しかない。つまり隣り合った指を順番に離していく事によってほぼ得られるこの14の運指を覚えさえすれば、明日からといわず老若男女を問わず3オクターブを超える音をフルートで出せるようになるという誠に喜ばしい現実が待っている。リードの心配をしないで済むという特長と考え合わせると、フルートという楽器は金管楽器にむしろ近い。
フルートは強く吹くと(音量を上げると)音程が上ずり、弱く吹くと下がるという宿命的な特性がある。これにはまず歌口に吹き込む息の角度を変え、本来吹き込む息の「半分」を目安にしている管の中に入る息の量で調整するという事で対処する事になる。すなわち音量を上げるに従って管の中に入る息の量を増やし、音程を下げる(上げる場合にはこの逆)。この微妙なさじ加減を誤って不用意な音を出すと、飯守先生あたりからすかさず「音程!」と呪詛のお言葉を頂戴する事になるので、それはそれは神経を使うのである。
ただこうした息の加減で音程を作る場合、弱く吹いて音程を上げなければならない(或いは強く吹いて音程を下げなければならない)場合に様々な制約が生じる事がある。こうした場合の対応策として変則的な運指、いわゆる「替え指」が必要となってくる。
或いは全てのキイを押さえる運指と、それらを全て離す運指の音の組合せのトリルは、正規の運指では物理的にも音楽的にも不可能なので、そこには「トリル運指」という特殊な替え指が存在する。これは他の木管楽器でも事情は一緒。
フルート奏者とはこうした事を蔑ろに出来ぬ人種で、そうした替え指の集大成として「運指事典」というものが出版されている。他の木管楽器でこうしたものが出版されているとの話は聞いた事が無い(あるかも知れないが)。フルートの替え指ほど単純でない事が理由かもしれないとは思う。いずれにせよそこには音程調整やトリル運指の他に様々な重音(すなわち3~4個の音からなる和音)を出す運指など、あらゆるものが網羅されていて、オーケストラの作品でも出くわす機会の多い特殊なトリルなどは、この事典なしには対応し得ず、これはこれで役に立っている。
だが実際の演奏の現場では、この事典にある運指だけでも足りない。自分の奏法・・・・・というより癖や、使っている楽器の特性に合わせ、自分なりの替え指を日頃から準備し、適切に使うという事がどうしても必要になる。身につけるべき運指の数は無限にあり、比べて人生は余りに短い、のだ(苦笑)。
そもそも替え指によってもたらされる音の殆どは、単独では凡そ音楽として使いものにはならない。他の一連の正しい音との間に挟んでこそそれは生きる。冒頭のハムレットの言葉と符合しないでもないが、すなわち替え指とはある種の「嘘」であって、他の真実と綯い交ぜにしてこそ初めてその一連のストーリーをより本当らしく見せる機能を持つ。最も一般的に使用されている教則本である『アルテ』は、その最終の第3巻の殆どを替え指のための練習曲に充てているが、これなどさしづめ「上手に嘘をつく」ための練習に他ならない(幸いな事に、大抵のフルート奏者はこの最終巻に行き着く前にどこかで挫折する)。「嘘も方便」を地でゆく話であって、不条理といえば不条理極まりない。
そしてそうした不条理を忘却するために、特定の替え指を知らないが為に正攻法で挑んでは練習で苦労したり本番で失敗したりする他のフルート奏者の姿を目にしては、「馬鹿正直は時に罪悪だよなぁ」などと言って内心ほくそ笑みつつ僅かばかり溜飲を下げているのが、フルート奏者の偽らざる姿なのである。
◆楽器の話=材質=
フルート以外の奏者は、隣で演奏する同パートの人の持つ楽器が、自分の楽器とは異なる材質で出来ているかもしれないなどという事を、恐らく生涯夢想だにしないだろう。余りに当たり前の事だからで、それは平穏な人生を意味している。
だがフルートは全く別世界だ。今シーズン演奏するマーラーの交響曲に出ているフルート奏者4名の楽器は木管あり14金あり銀製ありと全くバラバラだが、こうした事は特に統一する意思を明確に出さない限り奏者各人の自由に委ねられるし、それが普通という感覚がこの世界にはある。考えてみれば不思議な事だ。
パリ管弦楽団の往年の首席フルート奏者であるミッシェル・デボスト氏はこんな事を書いている。
「黒魔術が流行している」と物理学者や音響学者はいって、周囲の音響条件すなわち空気、および管の形状とサイズしか重要でないと反論するだろう。管の材質だって無視される。
でもわれわれフルーティストは、フルートに使われるさまざまな材質のあいだにはひとつの世界があって、これはたんに値段の問題ではないということをよく知っている。(『フルート奏法の秘訣』)
材質によって音色が変わる・・・・・という科学的な根拠は無いとされている。が、これはどうであろう。例えばフルート以外の木管楽器で金属製の楽器がまがいなりにも存在するのはクラリネットだけである。これさえ滅多に目にしたり音を耳にしたりする機会は無い。オーボエやファゴットの金属化はとうの昔に断念されていよう(そもそもそういう発想がない)。そうした楽器に「金属化」が進まないのは、逆説的だが金属管にする事によって本来の音色が変わってしまう事を恐れている事が理由ではなかろうか?だとすれば、材質と音色には一定の関係がやはり認識されている事になる。
フルートの場合、管の材質には様々な金属が試されてきたが、近年は洋銀・銀・金・黒檀(要するに木管だが、この分野にもかつては様々な素材が試された)あたりに落ち着いた感がある。だが特に金と銀については細分化が急速に進行して「収拾がつかない」状態に陥っていると見るべきだろう。
例えば銀。これは元々規格が決まっていて純度は925/1000すなわち92.5%が基本だった(残り7.5%は銅)。僅かにドイツの古い楽器に一部900/1000の純度のものがあった程度。だが今や純度は950/1000や953/1000や958/1000果ては997/1000というものまで現れた。なぜ953とか958のような中途半端な純度のものがあるかというと、これは冶金技術の未熟だった時代(19世紀後半)に造られたフランスの名器の材料を分析した結果としてはじき出された純度という触込み。この時代の名器には人気があって、今でも現役として使用されているので、それを発展させたモデルというものが商品として価値を認められているという現実がある。
だが、そうしたこだわりを具現化したものを含め、商品の選択肢としては非常に拡大されたものの、何がどう違うのか?はこの問題によほど強い関心を持つ人以外には恐らく永遠に解らないだろう。
更にここに管厚というもうひとつの要素が加わる。この銀の場合、管体の厚さは0.33mmから0.46mm程度まで5段階ほど規格がある。これと上記の材質と組合せると、これはもう混乱以外の結果を予想できない(こうして極めて単純化して状況を説明しているだけで頭が痛くなる)。もちろんこうした選択肢は金製の楽器にもあって、当然お値段にもはね返ってくる。
それでも・・・・・そうした混乱の極みともいうべき選択肢から、各人は自分が今後つき合っていくにふさわしい伴侶を選んでいる。フルートを吹く人々というのは、よほど根気が良いのかこだわりが強いのか、或いは真逆で全く何も考えてないのかものごとに無頓着なのか、思い切りが良いのか付和雷同しているだけなのかよく解らない部分がある(恐らくは自分でも解っていない)。
大抵の場合、息を吹き込んで鳴るまでの抵抗感や持った時の感触で最終決定している。もちろん世の中には「音色」を評価基準にしていると高言する人は絶えないが、楽器本来の音色が「試奏」程度の短い時間で出せるという錯覚を起こしているという共通点がある。
仲間の誰かが新しい楽器を入手したとき、或いは初対面の同好者に使用している楽器を確認するとき、それがどんなものなのか?を理解するのに、フルート以外の管楽器であればどこのメーカーのどういうモデルかを聞けば大体はそれで済む。ところがフルートの場合全く事情が異なるのだ。しっかりした楽器を造っていながら全然聞いた事のない個人的な工房というものが常に生まれている一方で、規模も販売網も確立している専門メーカーが世に出しているモデルの数は数知れず、その型番を聞いたところで実際には何も判らない。故にメーカーを聞き出すのと並行して、先記の材質(それが翡翠や象牙やヒトの大腿骨でないとどうして言えよう)から管厚や歌口の形状やメカニズムの仕様など逐一を聞き出し、ようやくにそれがどういうものであるかを頭の中で思い描ける状態になる。極めて厄介な話だが、フルートを吹く人々というものはこうしたネタを絶えず探し回っている厄介な存在だから、何ら苦ともしないのである。
一定以上の規模がある楽器店のフルートの売り場は、貴金属店のそれと同じ雰囲気を持っているし、各楽器に付いている値札の数値も概ね100万円単位(!)で同じようなものだ。僕は現在、昨夏ネットオークションで落札した銀製(925/1000)の楽器を使っていて、富裕層で構成される新響のパートメンバー各位の、目も眩まんばかりの錚々たる楽器に比べて、桁違いに安いところに落ち着いている(苦笑)が、ここに行き着くまでの紆余曲折やいま家に転がっている楽器の数々については、周囲の人々の広く知るところとなって久しい。先述のデボスト氏も言う。
いずれにせよフルートというのは、あけすけにいえば、ひじょうに金のかかる配管工事以外の何ものでもない。
確かに「配管工事」に金をかけ過ぎた自覚がある。フルート以外の楽器であれば、今ごろ郊外にこぢんまりとしたマンションの1室くらい手に入れていたかもしれず、老後の様相もまた違うものになっていた可能性は否めない。
フルートという楽器とつき合ってゆくに伴う憂鬱は絶えないのである。
第230回演奏会のご案内
■矢崎彦太郎=新交響楽団3回目の共演
パリを拠点に世界中で活躍する矢崎彦太郎氏を指揮に迎え、マーラーのソプラノ独唱を伴った交響曲第4番と、ラヴェルの管弦楽作品2曲を演奏します。氏の柔かいタクトからは色彩豊かな音が溢れ、異国の風を感じるような魅力があります。ソプラノには、演奏活動のほかにベネズエラ大使夫人としてエル・システマ活動も行うコロンえりか氏を迎えます。
■マーラー交響曲第4番~天上の音楽
マーラーはウィーンで活躍した作曲家で、主に交響曲と歌曲を作曲しました。番号の付いていない「大地の歌」を含めて10曲の交響曲を残しましたが(第10番は未完)、そのうち5曲に声楽が使われています。他の純器楽の交響曲にも自作の歌曲と関連を持たせるなど、歌にこだわった作曲家でした。
当時マーラーは指揮者として高名で、夏休みに集中して作曲活動を行っていました。1897年ウィーン宮廷歌劇場監督に、1898年にはウィーンフィルの定期演奏会指揮者に就任しました。交響曲第4番を作曲したのは丁度この頃でした。
ユダヤ人であったマーラーは、歌劇場監督になるためカトリックに改宗しました。復活信仰を持っており、「子供の不思議な角笛」(ドイツの民衆歌謡の詩集)から「天上の生活」を題材にしています。トロンボーンなしの小ぶりな編成でモーツアルトのような面もあり、時には激しく、また牧歌的に、最後は美しいソプラノで天国が歌われます。
■ラヴェル~管弦楽の魔術師
前半は、フランスの代表的な作曲家で管弦楽の魔術師とも呼ばれるラヴェルの管弦楽作品を2曲演奏します。
「ダフニスとクロエ」は、当時パリで成功を収めていたロシア・バレエ団の主宰者であるディアギレフから1909年に依頼を受けて作曲されました。この頃ラヴェルは、サン=サーンスが設立した国民音楽協会を脱退し、独立音楽協会を創設し現代的な新しい音楽を目指していました。
お話は古代ギリシャ、山羊に育てられたダフニスと羊に育てられたクロエがそれぞれ山羊飼い・羊飼いに拾われて、成長して恋に落ち、実は高貴な生まれで最後はめでたく結ばれるという恋物語です。ディアギレフは合唱まで付いてバレエ的でないと気に入らず、今ではコンサートで演奏される機会の方が多いですが、ラヴェルの最高傑作と言っても過言ではないでしょう。全曲だと1時間近くかかりますが、ラヴェルはこれから2つの組曲を作りました。特に第2組曲は演奏機会も多く吹奏楽でも有名な人気のある曲です。
「古風なメヌエット」は、ラヴェルが20歳の時にピアノ曲として作られましたが、管弦楽に自ら編曲したのはその34年後で、ラヴェルの最後の管弦楽作品となりました。古典派の様式であっても、とても斬新で洒落た曲です。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
第229回ローテーション
| 祝典序曲 | 橋本2番 | ショスタコーヴィチ10番 | |
| フルート1st | 牧 | 岡田 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 藤井 | 吉田(+picc) |
| 3rd | 藤井(picc) | 牧(+picc) | 兼子(picc) |
| オーボエ1st | 山口 | 堀内 | 亀井 |
| 2nd | 桜井 | 山口 | 山口 |
| 3rd. | 堀内 | 岩城(C.I.) | 岩城(+C.I.) |
| クラリネット1st | 末村 | 高梨 | 品田 |
| 2nd | 大藪 | 大藪 | 中島 |
| 3rd | 石綿 | 岩村(BassCl.) | 進藤(+EsCl.) |
| ファゴット1st | 野田 | 浦 | 藤原 |
| 2nd | 浦 | 野田 | 田川 |
| 3rd | 田川(C.Fg) | 田川(C.Fg) | 浦(+C.Fg) |
| ホルン1st | 大原 | 大内(assi箭田) | 箭田 |
| 2nd | 宮田(*) | 市川 | 大内 |
| 3rd | 箭田 | 大原 | 大原 |
| 4th | 市川 | 宮田(*) | 市川 |
| トランペット1st | 北村 | 小出 | 野崎(assi小出) |
| 2nd | 倉田 | 北村 | 北村 |
| 3rd | 野崎 | 倉田 | 倉田 |
| トロンボーン1st | 武田香 | 志村 | 武田浩 |
| 2nd | 志村 | 武田浩 | 武田香 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 古関 | 古関 | 桑形 |
| パーカッション | シンバル/桑形 トライアングル/今尾 大太鼓/桜井 小太鼓/皆月 |
シンバル/鈴木(*) トライアングル・大太鼓/桜井 小太鼓/皆月 チューブラベル/今尾 |
シンバル/古関 タンバリン・銅鑼/桜井 大太鼓・シロホン・トライアングル/皆月 小太鼓/今尾 |
| 鍵盤 | - | - | - |
| ハープ | - | 見尾田(*) | - |
| 1stヴァイオリン | 堀内(佐藤) | 堀内(佐藤) | 堀内(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(田川) | 大隈(田川) | 大隈(田川) |
| ヴィオラ | 柳澤(村原) | 柳澤(村原) | 村原(柳澤) |
| チェロ | 柳部(大庭) | 柳部(大庭) | 柳部(安田) |
| コントラバス | 渡邊(中野) | 渡邊(中野) | 中野(渡邊) |
(*)はエキストラ
ショスタコーヴィチ:交響曲第10番ホ短調
ショスタコーヴィチ作品との出会いとその交響曲
10代半ばにショスタコーヴィチに凝り始めた私は、当初交響曲の第5番と第10番ばかり聴いていた。なぜならば、この2曲しか国内版のスコア(総譜)が出ておらず、輸入版スコアは高くて買えなかったからだ。今回の練習時にも当時購入した定価700円のスコア(消費税は未導入、ちなみに5番は500円)を持参している。
それが今では、各15曲の交響曲と弦楽四重奏曲全部、6曲の協奏曲全部、そして何曲かの管弦楽曲が国内版で容易に入手できる。大作曲家として認知されている証拠だろう。
主に聴いていたレコード(CDはまだない)は、コンドラシン、ムラヴィンスキー、スヴェトラーノフといった、ソ連の指揮者とオーケストラによる演奏である。いずれもが正座しながら鑑賞しなければならないような、ある種独特の緊迫感と緊張感を感じることができる。
さて、今回のプログラム執筆にあたり、「ショスタコーヴィチ交響曲一覧表」を作成してみた。
「ショスタコーヴィチが好きなのは打楽器をやっているからですか」とよく尋ねられるが、実はあまり関係ない。「感動的な共感できる旋律」と「時にはブルックナーを思わせる息の長い音楽」が主な理由である。本日演奏する10番も、その例外ではない。
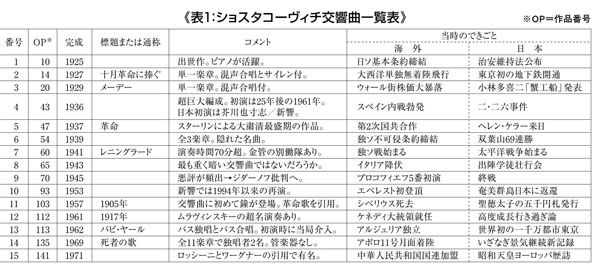
作品に対する評価
さて、ショスタコーヴィチは、ソ連国民として生涯を送ったこと、その表現の極端な幅広さ(二面性?)、そして20世紀最大の作曲家のひとりであるという宿命からか、いくつかの作品が様々な側面からの評価を受けている。真贋論争で物議を醸した『ショスタコーヴィチの証言』出版の影響も大きいだろう。
ソ連の歴史や共産主義を題材にした作品には、「体制に迎合」とのレッテルを貼られているものもある。また、第10交響曲を含めた一部の曲では、背景にある作曲者の真意を追究するべく、数々の推理や謎解きが行われている。しかしながら、これら話題に上る各作品は、例外なく名曲である(と思う)。
交響曲第10番について
作曲者自身によれば、この曲は「1953年の夏から秋にかけて」作曲されている。カラヤンが唯一録音したショスタコーヴィチ作品としても知られる。同年12月の初演に対する反響は大きかったようだ。翌年には3日間にわたる「公開討論会」が開催されたことからも、そのインパクトの強さがうかがわれる。
まずは、以下にこの曲の特徴をざっとあげてみたい。
(1)ソ連を代表する作曲家が、激しい批判を受けた後、8年ぶりに作曲した交響曲
(2)スターリンの死後(同年3月5日)に作曲が開始されたらしい
(3)内容が暗く、極めて内省的かつ抒情的である
(4)過去の大家がなしえなかった10番目の交響曲
(5)標題のない絶対音楽
以上のような特徴からか、この曲に隠されている「何か」について、多くの見解が出ている。作曲後60年以上、そして作曲者の死後40年を経て、なかば定説化している感もある。例えば「スターリンの死と関係がある」「第3楽章のホルンは某女性のイニシャル」など。その他、ここには書ききれないので、関心のある方は、各解説書をご覧になったりサイトを検索したりしていただきたい。「なるほどな」と思えるものも多い。
作品の背景を知ることは重要である。しかし、結果的に「隠された何か」が潜んでいるとしても、出発点は「心に湧き出た音楽」であったと私は考えたい。作曲者自身も、前記公開討論会において「人間の感情と情熱を描きたかったのだ」と述べているのだから。
しかし、この言葉は漠然としているような気もする。「感情と情熱」を描いていない音楽は果たして存在するのだろうか。よくわからなくなってきたので、各楽章の解説に移る。
第1楽章《抒情的なモメントの方が多い》
モデラート。ソナタ形式。全792小節の、間違いなく20分以上はかかる長大な楽章。静かな抒情的な部分→やや盛り上がったのち再度静まる→大いに盛り上がる→静かに回想して終わるという、ショスタコーヴィチの交響曲に時折見られる手法である。
最近、この楽章には「espr.」(表情豊かに)の書き込みが非常に多いことに気が付いた。伸ばしているだけの音に書かれている場合もあれば、打楽器以外の全パートに書かれている個所もある。第1、第3楽章においては、表情を表す用語が重要な意味を持っている。
曲は、静かな低弦のメロディーから始まる(譜例1)。このフレーズは重要で、高い音、低い音、強い音、弱い音、時には2倍の長さになっていたるところに登場する。
うごめくような静かな弦楽合奏は68小節も続き、69小節目になってようやく管楽器(クラリネット)が登場、「semplice」(素朴に 単純に)と指示された第1主題を提示する。ピッコロのデュエットを中心とする終結部は、透明感で溢れかえっている。

第2楽章《短すぎたようだ》
アレグロ。ものすごい勢いの楽章。高速テンポを維持したまま、4~5分であっという間に終わってしまう。最後の1音は、全曲中の最大音量であるsffff。この楽章は、「いちとー、にーとー」と数えていると、絶対に出遅れてしまう。
第3楽章《だいたい成功していると思う》
3部形式。第2楽章の後なので緩徐楽章の印象を受けるが、実はアレグレットである。途中、11小節だけラルゴの部分がある。
陰気なワルツ風のメロディーで開始されるが、伴奏を含めて「dolce」(優しく柔らかく)の指示がある。前述の「女性」のテーマは、ほぼ同じ形で、ホルンのみに計12回登場。後半に何回か出てくる弱音のタムタム(ドラ)は、不気味な暗さの表出に一役かっている。
なおこの楽章より、ショスタコーヴィチのイニシャルとされるD-Es(S)-C-Hの音型(譜例2。ドイツ語読みで表記するとDmitrii SCHostakowitch)が、わかりやすい形で頻出するようになる。

第4楽章《序奏部はいくらか長いが、これは構成上楽章全体の均衡を保たせていると思う》
アンダンテ→アレグロ。ソナタ形式。第1楽章と同じく、低弦の内省的なメロディーで始まる。初めて聴く方は、「また暗いぞ」「いつまでこれが続くんだ」と感じられるかもしれない。やがてオーボエ、次いでファゴットが、「dolce」と指示された哀愁きわまる旋律を奏する。その後、ファンファーレ風のクラリネットを合図にアレグロの主部に突入、これまでとはうって変わり、軽やかかつ華やかに展開しながら、豪華絢爛な結末を迎える。
なお、第2楽章を除いて、木管楽器による長いソロが随所に現れる。聴きどころのひとつであろう。
湯浅先生による練習は原稿を書いている時点ではまだ行われていないが、先生がどのようなアプローチをされるのか、今から期待と緊張でワクワクしている。貴重なショスタコーヴィチ体験ができる機会を持てることに感謝したい。
初演:文献によって異なっているが1953年12月17日ムラヴィンスキー/レニングラード・フィルが多数派
楽器編成:ピッコロ、フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ3(3番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット3(3番はEsクラリネット持ち替え)、ファゴット3(3番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、トライアングル、タンブリン、タムタム(ドラ)、木琴、弦五部
参考文献:
『作曲家別名曲解説ライブラリー(15)ショスタコーヴィチ』(音楽之友社)
『Zen‐on score ショスタコービッチ交響曲第十番ホ短調
作品93』解説園部四郎(全音楽譜出版社)
『名曲解説全集交響曲Ⅲ』(音楽之友社)
『世界史年表・地図』亀井高孝・三上次男・林健太郎・堀米庸三編(吉川弘文館)
『日本史年表・地図』児玉孝多編(吉川弘文館)
橋本國彦:交響曲第2番
<モダニストとアカデミスト=その生涯の潔さ>
『芥川也寸志 その芸術と行動』(東京新聞出版局)「Ⅱ芥川也寸志、芥川也寸志を語る―未公開対談―」の中に、芥川也寸志が東京高等師範学校附属中学校(現筑波大学附属高等学校)から東京音楽学校(現東京藝術大学音楽学部)へ入る時のエピソードを話している。
”中学校の三年生のときにお袋に連れられて新宿の「高野」の二階のレストランで、その先生(筆者注:高等師範附属小学校の主事先生)に初めて会いました。「音楽をやりたいけれども、よろしくお願いします」と。そのときに、さらに連れていかれたのは橋本国彦さん。橋本さんに「ピアノを弾けるか?」ときかれ、「いや、何もできません。ヴァイオリンは自己流で少し弾くだけです」「それはいかん。ピアノを習え。こわい先生じゃないとだめだ」ということになった。そして井口基成先生を教えてくれたんです。井口先生にバイエルから教わったんです。井口基成にバイエルを教わった人は、まずいないだろうと思うんですね(笑い)。”
芥川也寸志は、1941年から橋本國彦と井口基成に師事して1943年東京音楽学校本科作曲部入学、橋本國彦から近代和声学と管弦楽法を学んでいる。翌1944年に学徒動員で陸軍戸山学校軍楽隊入隊後の話として、「行進曲陸軍」を陸軍が公募して陸軍軍楽隊の中で選抜投票するということがあり、作曲者名非公開でいろいろな曲を聴かされたが、非常にいい曲があり、実は橋本國彦さんのだなと聴いてすぐわかった、というのも興味深い。
橋本國彦(1904~1949年)は当時、唯一の官立であった東京音楽学校主任教授として厳格なアカデミズムの立場を代表する教育者、作曲家、演奏家、指揮者であった。
生涯と音楽
橋本國彦は、関東大震災後の大正と昭和の変わり目から1945年の終戦まで、クラシック音楽の作曲家として常に日本楽壇の中枢で活躍し、急速に勃興していく「昭和モダニズム」を尖鋭的に表現していった。1920年代後半に集中的に生み出された歌曲、「班猫」「お菓子と娘」「舞」といった記念碑的作品で評価を確立している。
作曲を志して1923年東京音楽学校にヴァイオリン専攻で入学、信時潔に作曲を師事しピアノや指揮も習得した。東京音楽学校からの盟友といえる声楽家の四家文子によると、橋本國彦(作曲)の曲ができると、ピアノも達者な橋本や井口基成(ピアノ)がピアノを弾き、徳山たまき(王偏に蓮)(バリトン)と四家文子(アルト)が歌った、とのこと。夢を持ち切磋琢磨していったに違いない。
時代にも環境にも非常に敏感で、大衆音楽にも精力的に深く係わり、モダニズムとアカデミズムの両軸に乗って活動の場を広げていった。東京音楽学校で教鞭を執った1929年から1946年までは、学校を代表する「顔」の一人として、その役割を忠実に果たしていく。1934年から2年半、文部省給費学生として欧米に遊学して見聞を広め、高名な作曲家たちとの交流から最先端の音楽を吸収していくが、帰国後は「時局の要請」という、どちらかというと政治的な側面での活動に捉えられていく。いわゆる器用貧乏なところが災いしたのか、戦後は東京音楽学校退職後に立ち直る間もなく44歳の若さで胃癌のためこの世を去った。
橋本國彦の作曲者としての役割は、薫陶を受けた矢代秋雄、黛敏郎、そして芥川也寸志に引き継がれ、この若き門下生たちが戦後の洋楽界をリードして大きな役割を果たしている。
『橋本國彦歌曲集』(全音楽譜出版社)に四家文子による「天才橋本國彦を偲んで」に作品の特徴が列挙されているので紹介したい。
「1-もともと彼がバイオリン科にいたので、メロディーが流麗で美しいこと。2-同じ理由で、バイオリンやフルートの助奏を伴ったものが多く、アンサンブルの調和美に富んでいる。3-フランス風の和声に立脚しているので、ドイツ風の歌に比べて、繊細な美しさがみなぎっている。4-近代音楽のドビュッシーやラベルの傾向を逸早くとり入れて、当時耳なれなかった朗読調を日本歌曲に活かした。5-注目すべき点は、頭の緻密な彼らしく、テンポ、強弱、表現法等に、非常に細かく指示が与えられていること。時には、その通りに歌い表わすには、名人芸を必要とする程に、要求に妥協がないこと。」
交響曲第2番
1946年に井口基成と共に東京音楽学校を退職した橋本國彦は、新憲法制定を祝う祝賀会のために「新憲法普及会」からの委嘱で作曲・初演した。自筆譜の記載によれば、鎌倉市極楽寺の自宅にて、第1楽章「1947年3月4日~3月26日脱稿(Beethovenの命日)」、第2楽章「1947年4月16日完成」という短期間で創作されているが、以前から持っていた構想をまとめた可能性が高い。戦時下という状況下で見事な構想力と作曲の技巧がいかんなく発揮された皇紀2600年奉祝曲「交響曲ニ調」(第1番)と異なり、交響曲第2番は、開放的で徹底した抒情性、ブラームスの交響曲を彷彿とさせる音色、「祝典」とは無関係なまでの内向性と懐古的表現に充ち、何事にも束縛されることなく創作の腕を揮った曲といえる。1948年「ルンバ・ラプソディ」を作曲した黛敏郎に生粋のモダニストとして先鋭的な様式を教えた人物の作品とは思えず、ベートーヴェン交響曲第6番「田園」と同じ「へ長調」という調性が興味深い。
作曲者自身の指揮による初演後、永年忘れられてきたこの曲が再び発掘され、東京藝術大学での録音に至った経緯については、楽譜作成工房「ひなあられ」のHPを参照されたい。
http://www.medias.ne.jp/~pas/hashimoto.html
http://www.medias.ne.jp/~pas/hashimoto-sym2.html
第1楽章 アレグロ・モデラート
へ長調、3/4拍子。厳格なソナタ形式。第1ヴァイオリンがドルチェ・エ・カンタービレにて柔和で憧憬に満ちた第1主題を演奏(譜例1)。力強い推移部(譜例2)を経て、フルートにイ短調で第2主題が登場(譜例3)。対位法的な展開の後、メノ・モッソでホルンが優美に演奏するコデッタ(小結尾)主題がとても優しい(譜例4)。その後冒頭に戻った後、コデッタ主題から発展して展開部に入る。アレグロ・アッサイでコデッタ主題の展開形によるカノンは躍動感あふれ都会的でスタイリッシュ。再現部は冒頭と同じ主題から始まり、全ての主題を回顧して華々しく終わる。第1主題に基づく要素が他の主題にも用いられて展開されているところが面白い。

第2楽章「Finale」
へ長調、4/4拍子。主題と6つの変奏、そして独立したスケルツァンドとマエストーソ。交響曲第1番第3楽章「主題と変奏曲とフーガ」の持つ力強さや重厚さとは異なり、開放的で明快な曲。
主題:アラ・マルチア、4/4拍子、爽やかで気品があるマーチ(譜例5)。
第1変奏:アレグロ・アッサイ、木管楽器が中心。
第2変奏:アレグロ・ブリランテ、無窮動的な16分音符が続き、華やかな雰囲気。
第3変奏:ドルチェ・エ・カルマート、3/4拍子、第1楽章の第1主題と同じリズムで懐古的。
第4変奏:アレグロ・マ・ノン・トロッポ、4/4拍子、ヘ短調。音形が特徴的。
第5変奏:アレグロ・ルスティコ、へ長調、ファゴットから始まる主題変奏が温かい。
第6変奏:アレグロ・リゾルート、(Finale)と記載あり。4分音符で勇壮な金管楽器群、16分音符の木管楽器群、3連音符の弦楽器群、異なるリズムと音色の描き方が特徴。場面展開的な移行部を経て、スケルツァンドに入る。
スケルツァンド:6/8拍子、変ロ長調。第1楽章の移行主題や第2主題の要素が組み合わされており、スケルツァンド主題(譜例6)は、第2楽章最後に登場する「平和の鐘の主題」(譜例7)の予告となる。
マエストーソ:4/4拍子、第2楽章冒頭の回帰で本来のフィナーレ。今までの主題が次々と登場。ゲネラルパウゼの後に「平和の鐘の主題」がテューブラーベルで演奏され、第1楽章第1主題が重なって有機的な統一と一貫性を見せながら、ロマンティックな交響曲を壮麗に結ぶ。

潔さ
橋本國彦は、柔軟な発想に富む多面的な作曲家であり、常にその時代の国家体制の要求に応えていく一方で、時代精神を反映した文化・芸術の大衆化という条件を克服しながら、多種多様な作品を残していった。
政治的に凝り固まった人物ではなく、紙一重の過敏さを持つ繊細な心は「春風秋霜」(春風の爽やかさで人に接し、己に対しては秋霜の厳しさで律する)にて、「潔さ」に通じるものである。「潔い」とは己の行動に責任を持つことであり、自信を持っていることでもある。
新響は1996年に創立40周年記念「日本の交響作品展」のメインプログラムの一つとして橋本國彦の皇紀2600年奉祝曲「交響曲ニ調」(第1番)を据えた。本日、「ソ連」という社会主義的ナショナリズムによる抑制下で、ショスタコーヴィチの強靭な自己の精神が漲る作品とともに、潔く本来の自己を表現した「交響曲第2番」を、湯浅卓雄先生の指導により再演することは、新響にとって日本人自らが自国の作品を検証していくうえで意義のあることといえよう。
本日の演奏に際して、楽譜作成工房「ひなあられ」岡崎隆氏にあらためて感謝の意を表したい。
初演:1947年5月3日 新憲法施行記念祝賀会(主催:憲法普及会)帝国劇場
橋本國彦指揮 東宝交響楽団(現東京交響楽団)
CD初録音:「日本作曲家選輯 東京藝術大学編」2011年2月20日~21日 東京藝術大学奏楽堂
湯浅卓雄指揮 藝大フィルハーモニア Naxos 8.572869J
楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、小太鼓、トライアングル、テューブラーベル、ハープ、弦五部
参考文献:
『芥川也寸志 その芸術と行動』出版刊行委員会編(東京新聞出版局)
『日本作曲家選輯 東京藝術大学編 橋本國彦』CD解説(Naxos 8.572869J)
『橋本國彦歌曲集』(全音楽譜出版社)
ショスタコーヴィチ:祝典序曲
本日演奏する「祝典序曲」と「交響曲第10番」は共通点があります。それはいずれの曲もスターリンの死後(1953年)に発表されているということです(祝典序曲は1954年、交響曲第10番は1953年)。独裁者スターリンは政治・経済・文化へ大きな影響と恐怖を与え、ショスタコーヴィチも例外でなく彼の作曲家人生は大きくスターリンに左右されました。それ故スターリンの死後に作曲された曲には、スターリンに対する思いが込められているようです。まずはショスタコーヴィチの生涯からみて行きましょう。
ドミトリィ・ドミトリエヴィチ・ショスタコーヴィチは1906年9月12日にペテルブルクに生まれました。父親のドミトリィ・ボレスラヴォヴィチ・ショスタコーヴィチと同じ名前なのは、洗礼式の日に司祭が父親の名前をとってドミトリィにすべきと押し切ったためだそうです。ショスタコーヴィチは天才児で、絶対音感があり、一度演奏した曲はすぐに暗譜で繰り返し演奏できる驚異的な記憶力がありました。ペトログラード(ペテルブルクが改称)音楽院に13歳で入学しますが、入学試験の準備期間中にショスタコーヴィチの母ソフィアはペトログラード音楽院院長であったグラズノフにショスタコーヴィチの作品を聴いてもらい、グラズノフから「音楽院の
中で、かつて、あなたの息子さんほど才能のある子供がいたことは記憶にありません。」とお墨付きを貰っての入学でした。18歳の卒業時には交響曲第1番を発表して一躍注目を浴び作曲家としての地位を得ました。
若いころのショスタコーヴィチはたいそう辛辣で気が強かったそうです。その性格と残忍性を嫌う性格から、スターリンを特に忌み嫌っていたみたいです。ショスタコーヴィチのスターリンへの憎悪は次のように記載されています。「一般的にいって、粗雑さと残虐は、わたしがなによりも憎んでいる性質である。〈中略〉そのかずある例のひとつはスターリンである。」(「ショスタコーヴィチの生涯」より)
そのスターリンが1936年1月にショスタコーヴィチのオペラ「マクベス夫人」の上演中に退席してしまう事件が発生します。要は曲がよく分からなかったみたいです。そして、その二日後に発行されたプラウダに「音楽の代わりの支離滅裂―ConfusionInstead of Music」と題する論文が発表され、これに端を発してショスタコーヴィチに対する批判が始まります。所謂プラウダ批判です。「人民の敵」とのレッテルが貼られたショスタコーヴィチは汚名返上のために有名な交響曲第5番を作曲します。実は同時期に交響曲第4番が作曲されていたのですが、この曲を発表して更に立場が危うくなることを恐れショスタコーヴィチは抽斗ひきだしの中に楽譜を隠しました。交響曲第4番が日の目を見たのは完成後25年経った1961年です。交響曲第5番は当局に好まれる曲に仕上げていますが、シニカルなショスタコーヴィチは終楽章に強制された歓喜、果てしない悲劇を込めて作曲したそうです。
その後もスターリンによるイデオロギー統制が続く中でショスタコーヴィチは作曲活動を続けますが、ショスタコーヴィチが交響曲第9番を作曲するにあたり、当局からファンファーレ、賛歌が必要だと言われ、ベートーヴェンをイメージした荘厳な第9交響曲を書くことが要求されました。それは4管編成のオーケストラと合唱と独唱によるスターリンへの賛歌を書くことでした。ショスタコーヴィチ自身も当初は当局に賛歌を書いていると公表していましたが、完成した交響曲第9番は合唱もなければ独唱もなく賛歌もない室内楽的な交響曲でした。
これにスターリンはひどく腹を立て、中央委員会書記であったアンドレイ・ジダーノフの文化政策におけるイデオロギー統制「ジダーノフ批判」の対象となってしまいました。ショスタコーヴィチはモスクワ音楽院を解雇され、作品の演奏も禁じられることになり、家族の生活のためにはイデオロギー的に更正したことを証明する作品を書くことが必要となり、1949年にオラトリオ「森の歌」を書き上げました。この曲はスターリンの大植林計画に捧げる曲として作曲されましたが、要は露骨なスターリン賛歌です。スターリン万歳!と終始唄われるこの曲は大成功を収めますが、初演後ショスタコーヴィチはホテルで号泣し、気を落ち着けるためにウォッカを何杯もあおったが酔えなかったそうです。
ショスタコーヴィチは生涯に交響曲を15曲作曲し、バレエ音楽、オペラ、管弦楽曲、室内楽曲、そして彼の生活を支えた映画音楽などを多数作曲し1975年8月9日に息を引き取りました。遺作(作品番号147)となったヴィオラ・ソナタのヴィオラを弾いたドルジーニンは、初演後に聴衆の鳴り止まない喝采を残らず作曲者に注ぐため楽譜を頭上高く掲げたそうです。
祝典序曲は第37回ロシア革命記念日の祝典のためにソヴィエト共産党中央委員会からの委嘱によって1954年に作曲された説と、1947年8月に十月革命30周年を記念して作曲した説がありますが、ここでは1954年に作曲され発表された曲として紹介します。
前述の通り、第37回ロシア革命記念日の祝典のためとも1952年のドン=ヴォルガ運河の開通に捧げられたとも言われている祝典序曲は、1954年11月6日にモスクワのボリショイ劇場に於いて初演されました。演奏会当日のわずか数日前になってショスタコーヴィチは大至急で序曲を書き上げて欲しいと指揮者に打診され3日で作曲したと言われています。確かに天才ですので3日で書き上げることも可能だと思います。
とはいえ何か題材がありそうなので、調べてみると過去に作曲した作品が引用されているのが分かりました。まず、冒頭のファンファーレ。これは娘ガリーナの9歳の誕生日のために1944年頃に作曲された7つのピアノ小品曲「子供のノート」の第7曲の「誕生日」の冒頭から引用されています。そしてプレストに入りクラリネットが奏でる第一主題が、前述のオラトリオ「森の歌」の第5曲「スターリングラード市民は前進する」で用いられた旋律です。特に5曲目は「スターリングラード市民は前進する」のその題名通り、スターリンにちなむこの地名が何度も歌われています。1953年にスターリンが死ぬと、次のソ連書記長フルシチョフのスターリン独裁体制批判に伴い1962年に歌詞を大幅に変更し、地名をヴォルゴグラード(市名は1961年に改称)、題名を「コムソモール(共産党の青年団)は前進する」に変更しています。そして終盤には「ジャズ組曲第2番」の第3曲が顔を出し、最後に冒頭と同じく「誕生日」のファンファーレが奏でられると、曲はコーダへ続き華々しく曲を閉じます。
第一主題はホルンとチェロの第二主題が始まると段々と第二主題の伴奏側に回り始め、曲の後半に向かって断片的になり、第二主題が主役にとって代わります。そして最後は「誕生日」のファンファーレを再度引用し、そのファンファーレもわざわざバンダ(オーケストラ本体とは別に、多くは舞台裏、観客席等の離れた位置で演奏する別働隊のこと)まで付けて壮麗に演奏します。これはまさに忌み嫌っていたスターリン(=第一主題)の忌まわしい思い出を抹消し、芸術緩和・復興の「誕生」を祝った曲ではないかと思うのです。そしてショスタコーヴィチのシニカルさもまさに表れている曲ではないかと思うのですが、考えすぎでしょうか?
初演:1954年11月6日ボリショイ劇場にて
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ3、クラリネット3、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、トライアングル、弦五部、バンダ(トランペット3、ホルン4、トロンボーン3)
参考文献
『ショスタコーヴィチの証言』ソロモン・ヴォルコフ著水野忠夫訳(中央公論新社)
『ショスタコーヴィチ』千葉潤著(音楽之友社)
『ショスタコーヴィチ 祝典序曲』大輪公壱著(全音楽譜出版社)
ショスタコーヴィチとウィーン
この原稿の依頼から〆切までの1ヶ月弱の間に、1週間のウィーン滞在が決まっており、平和なオフが、ネタ探しの修行と化した。ショスタコーヴィチとウィーンは極めて縁遠い存在だと思っていたのだが、調べるうちに、交響曲第10番作曲時期、両者の間に一定の関係があったということが分かった。尚、氏の一生については第229回演奏会プログラムと重複すると思うのでここでは取り上げない。
■ショスタコーヴィチとウィーンの関わり
交響曲第10番作曲直前期の、氏とウィーンの関わりについて調査した。
・1946年半ば 来訪計画
ハチャトゥリアン・オイストラフ・オボーリンと西ヨーロッパを周遊中、来訪を計画するも果たせず。
・1947年6月初旬 来訪計画
ショスタコーヴィチへの敬意を表して開催されるコンサートに出演するべく来訪を予定するも果たせず。
・1952年12月 初めてのウィーン来訪
世界平和会議第3回(1950年11月ワルシャワで開催された第1回では、核兵器不使用を訴えるストックホルム・アピールに署名している)に派遣され、憧れの地ウィーンを初めて訪れた。
尚この会議には19人の音楽家が参加している。
ウィーン市の音楽学校の会議室で、ショスタコーヴィチとオーストリアの作曲家(アルフレッド・ウール/マーセル・ルービン/ハンス・アイスラーら)が初めて出会った。ショスタコーヴィチは『ピアノのためのプレリュードとフーガ』(3曲)を演奏。
・1953年3月5日 スターリン・プロコフィエフが逝去
・1953年6月 2回目のウィーン来訪
文化代表団の一員として、オーストリア=ソヴィエト協会一般会議に派遣された。オーストリアの作曲家達(ヨーゼフ・マルクス/フランツ・サルムホーファーら)と滞在。映画音楽の役割・ソヴィエトの作曲家の立ち位置について意見交換。
予定のない夜には、演奏会を聴きにアン・デア・ウィーン劇場、コンチェルトハウス等に赴いた。当時、アン・デア・ウィーン劇場は、戦争により建物が破壊されたウィーン歌劇場の代わりとして機能しており、氏が聴いたのはこのウィーン歌劇場(ウィーン・フィルの母体)の演奏であると思われる。また、ベルク・オネゲル・ストラヴィンスキーの作品を聴いたという記録も残っている。
会議に派遣された同僚達が驚いたことに、プラーター公園で彼は、猛スピードのジェットコースターに乗りたいと言い出し、「このスリルがたまらないね。すごく楽しかったよ。僕がオペラ『鼻』の作曲家だなんてとても思えないだろう!」という感想を残した。あわせて地獄列車(幽霊列車?※英訳時点での誤訳の可能性あり)にも搭乗、「安っぽい子供だましだ」と評した。
・1953年6月末 交響曲第10番第1楽章を書き進めている(カラ・カーエフへの手紙)
◇ショスタコ―ヴィチがウィーンで聴いたコンサート
1953年6月の滞在期間とウィーンでの公演記録を照らし合わせ、知り得た情報を元に調査したところ、少なくとも以下のコンサートは聴いたと思われる。
◎第5回国際音楽祭開催祝典演奏会
1953年6月6日(土)19:30開演 コンチェルトハウス大ホールにて
オーケストラ:ウィーン交響楽団
ヴァイオリン独奏:アーサー・グリュミオー
指揮者:パウル・ザッハー
挨拶:マンフレッド・マウトナー・マルクホフ/フランツ・ヨーナス/エルンスト・コルプ
演目:アルテュール・オネゲル:オーケストラのためのモノパルティータ (1951)
アルバン・ベルク:ヴァイオリン協奏曲『ある天使の思い出に』(1935)
イゴール・ストラヴィンスキー:三楽章の交響曲 (1942-1945)
※パウル・ザッハー(1906~1999)は、スイスの指揮者・作曲家。作曲家(ストラヴィンスキー・バルトーク・オネゲル・ヒンデミット・武満徹ら)へ、多数の作品委嘱を行い、近代音楽作曲家のパトロン的な役回りも果たした。
■ウィーンの歴史
ケルト人の集落ウィンドボナが起源とされる。1世紀末にローマ帝国により征服され、北方の宿営地として重要な役割を果たしたが、帝国没落に伴い4世紀末までには破棄され、以降400年間の相次ぐ多民族の侵入により荒廃。
ドイツ語圏辺境のこの地がドイツ語圏随一の大都市へと成長した背景には、宮廷所在地としての地位を得たことが大きいが、これはオーストリアを治めていたバーベンベルク家が1155年に遷都したことに始まる。その後、1278年からハプスブルク家の支配下となると、1918年に至るまで、ごく短い途絶を除き、権力の中枢であり続けた。
新興国であったハプスブルク家は、16世紀に入ると婚姻政策の偶発的な成功が相次ぎ、ボヘミア・ハンガリーを初めとする多くの王国を獲得。1683年のオスマン帝国撃退により異民族侵入の危機が払拭されると、17世紀末には王宮ホーフブルク・離宮シェーンブルン宮殿等が造営されて華やかなバロック文化が栄え、後の「音楽の都」の礎となった。他方、カトリック教会による「対抗宗教改革」の重要拠点ともなり、イエズス会が検閲等により教育・文化面において決定的な影響力を及ぼしたことで、他の欧州都市が中世都市から近代都市へ成長する中、後れを取ることとなる。
18世紀半ばになり、自国の後進性を認識したマリア・テレジア、その子である王権神授説を否定したヨーゼフ2世により近代化が始まると、イエズス会の影響力は排除され、教育機関の刷新が行われて義務教育制度ができ、総合病院が開設され、プラーター公園が一般市民に開放されるなど都市環境が改善されていった。
19世紀半ばに産業革命を迎えて急激に人口が増加、1910年には203万を数える大都市となる。フランツ・ヨーゼフ1世は自ら立案して大規模な都市改造を行い、市壁を取り壊して五角形状の道路(リンク)を整備し路面電車を導入、歴史的建造物やモニュメントを街路に面して配した。現在の旧市街の外観はこの改造による。
1918年に第一次世界大戦に敗れると帝国は崩壊し各地方が次々と独立、ウィーンは経済的困窮に追い込まれる。新しい共和国の首都になると社会主義系市政が発足、農村部保守層との政治的確執は、国政全体の不安定へとつながった。この時代をウィーンで過ごしたヒトラーは、やがて母国オーストリアをドイツに併合、ウィーンも一都市に甘んじることとなる。
1945年の第二次世界大戦後、ウィーンは米英仏ソ四ヶ国の共同占領下に置かれ、中心部は国際警察により管理された。映画『第三の男』はこの時代を良く伝える。1945年11月、オーストリア戦後初の選挙が行われ保守党・社会党の連立政権が誕生、以降1987年に至るまでこの連立体制は続いた。
1955年にオーストリアは主権国家として独立を回復。旧ハプスブルク帝国継承国家の大半が共産圏に組み込まれる中、オーストリアは経済的には西側との関係を保ったまま永世中立国として歩むことになった。これには、戦後間もなくのソ連軍占領下での異常な治安の悪さによる共産党の不人気、アメリカからの多額の経済援助が関係していると思われる。
1973年から一連の国連施設が建設され、ニューヨーク、ジュネーヴに次ぐ第3の国連都市となり、国際原子力機関IAEA、国連工業開発機関UNIDO等の所在地となっている。
■プラーター公園
何世紀にも渡り皇室専用の狩猟場であったが、1766年、ヨーゼフ2世が市民に一般開放。すぐに多くの飲食店、カフェ、ケーキショップがテントを広げ、最初のメリーゴーラウンドが設置された。当初は庶民の行楽地であったが、数十年のうちに上流社会の人々の憩いの場として発展。1895年には、運河の流れる水の都ヴェネツィアを模倣し本物のゴンドラを浮かべた遊園施設「ウィーンのヴェネツィア」がオープン。シュトラウス父子・ランナー等の指揮の元、オペレッタが上演された。第二次世界大戦では戦場となり、大いに被害を受けたが、急ピッチで復旧が進められた。
現在、公園の一角にはプラーター遊園地と呼ばれる一角があり、「プラーター」と言うとこの地を指すことが多い。園内への入場料はかからず、アトラクションに乗る毎の清算となる(2€~10€程度)。250に及ぶアトラクションの中には、世界一の高さ(117 m)の回転型ブランコ”Prater Turm”、上下反転して高速回転するコーヒーカップ”Extasy”等、物理的な意味で容赦ないものも少なくない。
◇プラーターとウィーン
ショスタコーヴィチ来訪当時にあったと思われアトラクションを少なくとも3つ発見し、うち2つは恐らく氏が搭乗したものであると思われたので乗ってみた。
①観覧車(ショスタコーヴィチが乗った記録はない)
1896年、英国人技師ウォルター・B・バセットにより建設された。バセットはヨーロッパに4基の観覧車を建設しているが、これは3基目でかつ唯一現存するものである。「第三の男」・「リビング・デイライツ」等、多くの映画に登場することで有名で、プラーター公園の象徴的な存在。建設当時は20人乗りのゴンドラ30台が回っていたが、現在は設備への負担を減らすために15台となっており、ゴンドラ個体識別用の番号は偶数番のみが存在する。第二次世界大戦終戦間近の空爆により全台が全焼したが、窮乏に苦しんだ時代にあっては記録的な早さで復旧され、1947年5月には早くも再開。1920年~1981年に至るまで、現役世界最大の観覧車であった。
※第三の男(The Third Man)
監督 キャロル・リード
脚本 グレアム・グリーン
音楽 マリア・カラス
出演 ジョゼフ・コットン / オーソン・ウェルズ / アリダ・ヴァリ他
公開 1949年(英国)/ 1953年(日本)
第二次世界大戦で破壊され荒廃したウィーンを舞台とした英国映画で、愛と友情と正義の物語。ウィーンでの撮影は1948年10月~12月に行われており、シュテファン寺院・ホテルザッハー・再開間もないプラーター遊園地等、当時の貴重な映像が多数含まれる。また、作品の重要なキーとなる犯罪は、シナリオ執筆にあたって脚本家が実際に見聞したものでもあり、当時の悲惨さを良く伝える。アントン・カラスが作曲・演奏するチターも、この映画が名作となった一つの所以であろう。ストーリーはここでは紹介しない。是非ご覧下さい。
②木製ジェットコースター“Hochschaubahn”
1950年に建設された450mを約3分15秒で走行する木製ジェットコースターで、当時の姿を今なお伝える。オーストリア最高峰グロースグロックナー周辺を再現したとされる人工景色の中を、8人乗り(2列4行)の列車2台が連結された最大16人収容の車体(シートベルトなし)で周る。最高高さ15m、最高速度55km/h。所有者によれば、1953年当時唯一のジェットコースターであった筈とのこと。ギシギシという大きな音を立てて急傾斜の坂道を15m程度の高さまで登り、徐々に加速しながら下る様は、木製であること・シートベルトをしていないことも相まって、妙なスリルがあった。3回のアップダウンを繰り返した後、油断している最中に横から水が吹きかけられるといった趣向もあり、殊の外、楽しんだ。
③幽霊列車“Geisterbahn”
プラーター最大(600㎡)かつ最長(215m)のお化け屋敷(ヨーロッパで最大、最長、走行位置の高さが地面から最高とも)で、1948年に設立された。2人乗りのカートに乗って周る。暗い世界の中、モンスター・魔女・吸血鬼などの身の毛もよだつような空想世界のオブジェが一体ずつ突然出現・消失したり、落ちゆく橋と共に突然落下していったりといった、ビックリ屋敷的な要素を併せ持つ。人の目の順応を妨げるため、出現はぼんやりとした光によって行われ、各オブジェ間の距離が十分にあけられているため、結果的に走行路が長くなったと考えられる。戦争体験のあるショスタコーヴィチには子供だましとしか思えなかったとのことだが、十分驚かされ続けた。
◇モーツァルトとプラーター公園
1762年にマリア・テレジアの御前でピアノを演奏した6歳の神童モーツァルト。(床で転び、手を取ってくれた7歳のマリー・アントワネットに「大きくなったら僕のお嫁さんにしてあげる。」と言ったとされる。)10歳の時に一般公開されたプラーター公園には、1781年ウィーンに移住して以降、友達と連れ立ってよく行っていたらしく、1785年にはお下劣歌詞をつけた不朽の迷作(名作)、四重唱カノン『プラーター公園に行こう(K.558)』が完成している。歌詞はご自分でお確かめ下さい・・・。
ショスタコーヴィチにおけるファゴット奏者の歓びと苦悩
ファゴットパートの藤原と申します。入団してもうすぐ5年、古参の多い当団ではまだまだぺーぺーの三下ですが、何の因果か今回ショスタコーヴィチ10番の1stを吹くことになってしまい、身に余る重責に日々もがき苦しんでおります。この悶絶(もんぜつ)躃地(へきち)するわたしの様子を見た維持会ニュース編集人(フルート首席の松下氏)から「『ショスタコーヴィチにおけるファゴット奏者の歓びと苦悩』をテーマに寄稿してもらいたい」と依頼を受け(つくづく容赦の無い編集人です)、苦しみに拍車がかかったわけですが、良い機会でもあるので自分なりに考えたことを書き出してみます。多分に主観的かつ不真面目なたわ言ですがお付き合いください。
■ファゴットとその奏者の特徴
ファゴット及びファゴット奏者について、茂木大輔氏は著書『オーケストラ楽器別人間学』の中でこのように書いています。
「…きわめて広い音域を持っており、その音色も変化に富む。このことは当然、奏者の性格に大きな幅をもたせ、多様な側面を持った厚みのある人間像をつくりだす。
もの悲しく、か細い高音はペーソスを、柔らかく深い中音は暖かみを、しわがれた低音は老成した内省的な性格を、それぞれ奏者にもたらし、かん高く苦しげな最高音域の存在は、いざとなったらなりふり構わぬ姿勢を奏者にそなえさせる。
しかし、これらすべての音域に共通するものは、きわめて特徴あるアタックによってもたらされる、とぼけた、ひょうきんな印象である…」
茂木大輔氏はご存知のとおりN響の首席オーボエ奏者であってファゴット奏者ではないのですが、それにしては(失礼ながら)割合的を射た分析です。オーケストラの中で演奏するにあたり、広い音域と多様な音色を持っているということは、様々な役割を受け持たせてもらいうるということであり、これはファゴットの大きな魅力、奥深さの1つです。しかしながら、あの「ぽー」という独特の、脱力系の発音の印象が強すぎるために、ファゴットという楽器は(他にも特筆すべき多彩な側面がありながら)一般的な印象としては「おとぼけキャラ」という結論に尽きてしまう悲しい性のようです。「良い人」は得てして本命の恋人にはなれないように、器用で害のないファゴットは下支えやクッション材、潤滑油として諸々便利に使われても、ど直球のソロを充ててもらえることはなかなかありません。また他の楽器に比べるとあまり大きい音が出ない、音の通りが悪いという性能的弱点もあり、これも作曲家たちをしてファゴットをソロから遠ざけしむる要因の1つです。
■オーケストラにおけるファゴットの役割
結果的に、オーケストラ曲においてファゴットが通常受け持つ仕事は
① 低音(ベースライン)
② 中継ぎ(メロディとも伴奏ともつかないアンコの部分とか、メロディ楽器のハモリなど)
③ たまにソロ
の主に3種類となり、①と②が圧倒的に多いということになります。
もちろんソロ以外の仕事にやりがいが無いかと言われるとそんなことはなく、特に①についてはファゴットの場合、木管セクションにおけるベースという意味合いで非常に重要です。木管楽器の中で演奏上目立つのはオーボエやフルートの1stですが、彼らは2ndファゴットの根音から幾重にも積み重なったサウンドのてっぺんで危ういバランスを取り続ける儚い存在なのです(編集人の松下氏も、フルートなどセクション内のしわ寄せ担当なのだと常々ぼやいておられます)。大学の管弦楽サークル等では、譜づらが簡単だからといってこの重要な2ndファゴットに初心者を充ててしまい、木管セクション崩壊の危機に見舞われるケースがままあります。
また②の中継ぎですが、これは低音が得意というほどでもないし、かといってソロをガツガツ吹きにいく闘志もないファゴット吹きの活路であります。一般的にオーケストラのファゴット(特に1st)はこの「中継ぎ」職にあたる役割ばかりやらされるので、必然的に小器用さ、奥ゆかしさ、メロディ楽器をたてる能力がどんどん磨かれていくことになり、奏者には慈愛の心と自己抑制力が育まれます。ちなみにわたしはこの「中継ぎ」ポジションが最も好きで、クラリネットの3度下でハモっているときが、練習後のビールの次に幸せな瞬間です。要約すれば、①や②の仕事に歓びを感じられないファゴット吹きはオーケストラに向いてないということです。
■オーケストラにおけるファゴットのソロ
次に③ソロについてですが、冒頭でも分析したとおり、ファゴットという楽器は一般的な印象として「おとぼけ」という何を持っても払拭しがたいイメージが他の特色を凌駕しております。ごくたまにソロという僥倖が与えられた場合も、本流のかっこいいメロディではなくて、ボケキャラ、お笑い担当等、いわゆる三枚目の役割であることが多いように思われます(ファリャ『三角帽子』の悪代官役などが典型)。こういった濃いキャラクターの役が割り当てられやすいというのはある意味「おいしい」立場と言えるかもしれません。奏者としても具体的なイメージを持って表現しやすく、かつ主役でない気楽さもあり、割合楽しく吹くことができます。
ではファゴットは絶対音楽においてはソロが全然無いのかと言われれば、実はそんなこともありません。例えばベートーヴェンは何故かファゴットを重用してくれる代表的な作曲家の1人で、薄暗い迷路を彷徨(さまよ)うような独特の長いソロ(交響曲第5番3楽章)や、歓喜のテーマの裏で奏される奇跡的に美しいオブリガート(交響曲第9番4楽章)など、様々な表情をもった魅力的な見せ場を惜しみなくファゴットに与えてくれます(あまりに垂涎の出番ばかりなので、厚遇されることに慣れていない身としては、こんなにおいしいソロがファゴットで本当に良いのかしらと疑心暗鬼になるほどです)。ただしベートーヴェンの場合、いずれのソロにおいてもその性質として「純朴さ」が根底にある印象です。ファゴット本来の音色で、気張らず、朴訥と自然体で吹くのが最も素敵に響くフレーズばかりであると個人的には思います。こういったところ、やはりベートーヴェンは最もファゴットをよく理解してくれている作曲家の1人といえましょう(ファゴット奏者は概ねベートーヴェン贔屓であります)。
また、今回の演奏会で採り上げる橋本國彦の交響曲第2番2楽章にも、ファゴットの大きなソロがあります。これは我がパートのエース、浦氏が担当しますが、まさしく「古きよき美しき日本」といった、穏やかでもの淋しい素敵なメロディです。こういった日本むかしばなし系のフレーズも、ファゴットの飾らない中音域が自然と情緒をかもし出すらしく、ソロとして吹かせてもらえる場合が意外とあります。
■ショスタコーヴィチにおけるファゴット
ではいよいよショスタコーヴィチにおけるファゴットについてですが、不甲斐ないわたしを叱咤するためにトレーナーの寺本先生が合奏中に仰った言葉を借りれば「ショスタコのファゴットは千両役者。おいしいところは全てファゴットが持っていく」とのこと。千両役者とは大層な称号を頂いたものですが、実際のところあながちお世辞とも言えません。ショスタコーヴィチはオーケストレーションの中で、ソロの管楽器に長いモノローグ(独白)を任せることが多いのですが、そういうのがいかにも上手そうなオーボエとかクラリネットだけでなく何故かファゴットまで語り手に選抜してくる、むしろ最も強調したい本音の部分に敢えてファゴットを充ててくるという傾向があります。
さらに困ったことには、それぞれのソロに求められているのが(というかショスタコーヴィチの曲そのものが往々にしてそうとも言えますが)極限状態に近い苦悩、恐れ、痛みなどの先鋭的な表現であり、ファゴットらしい穏やかさ、純朴さ、おとぼけといった性格とはほぼ正反対であるということです。ただでさえ慣れない大量のソロ、しかもどうやら普通に吹いたのでは到底歯が立たず、生ぬるいファゴットらしさから1本ぷっつん切れなきゃならないらしい、ということでショスタコーヴィチにおけるファゴット奏者は苦悩することになるのであります。
なぜショスタコーヴィチは、ファゴットにとって不向き・不慣れと思われる大立ち回りばかりを敢えてファゴットに与えるのでしょうか。ショスタコーヴィチとファゴットに特化した研究というのは(一応探しましたが)見当たらず、かといって今から彼に電話して聞くわけにもいかないので、これは各奏者が自分で考えねばならない問題です。初合奏から2ヶ月弱の間四苦八苦して吹いてみて、わたしとしては、これはショスタコーヴィチが「意外性の魅力」を狙った結果であるという結論に至りました。普段クラスの中で物静かな子がたまに発言すると学級長以上の重みがあるように、いつもおちゃらけているあの男子が急に真面目に迫ってくるとドキッとするように、常時と全く異なる一面を見せられたとき、人はその意外性に魅力を感じるものです。シリアスでドラマチックなソロが得意で、しょっちゅう受け持っているような楽器が吹くよりは、ファゴットがいつもの穏やかな表情をかなぐり捨てて死ぬ気の形相で吹く方が、普段とのギャップも相まって訴求力の高い、濃密なソロになると彼は考えたのではないでしょうか。ショスタコーヴィチにとっては、雄弁な人の小慣れた物言いより、素朴で普段は声の小さい人が珍しく感情をむき出しにして訴える言葉のほうが、彼の本心を乗せやすかったのかもしれません。彼がそこまで考えたうえで敢えてファゴットを選んでくれているとすれば、わたしが今ソロを前にして不器用にのたうちまわっている苦悩自体も表現の肥やしになるわけです。
それから、実はショスタコーヴィチがファゴットのためのソロ曲(およびファゴットを含む編成のアンサンブル曲)を1曲も残していない、という事実もポイントの1つです。つまりファゴット奏者が彼の曲を吹きたいのであれば1人のままではだめで、オーケストラとかオペラに乗るしか無いということです。どうやらこの作曲家はファゴットのそのものが好きなわけではなく、大編成の中のソロ楽器としてファゴットを使うことが特に好きだったようです。ファゴット奏者にとっては、こうしてショスタコーヴィチの書いた旋律を演奏できること自体が意外と貴重な機会であり、これらのソロが、直接的にショスタコーヴィチの音楽を表現できる唯一のチャンスです。とにかく自分の好きなように彼の鈍色のメロディを吹ける、というのはそれだけで奏者として嬉しいことでもあります。
以上好き放題書き連ねて参りましたが、結論としては当然「ショスタコーヴィチのファゴットはつらいけどオイシイ」ということに尽きるわけです。「千両役者」とヨイショされたところで三枚目が急にスターになれるわけではないですが、せっかく引っ張り上げられた檜舞台の真ん中です。普段のファゴットとはぎょっとするほど違うソロで大向うの皆様を小唸りでもさせられれば、ショスタコーヴィチを吹くファゴット奏者としてはこの上ない歓びであります。
第229回演奏会のご案内
■時代に翻弄された2人の作曲家
今回の演奏会では、戦時中に活躍した作曲家橋本國彦と、同じ頃ソヴィエトの国民的作曲家であったショスタコーヴィチの作品を演奏します。東京音楽学校の作曲科教授として時局に応じた音楽を作曲せざるを得なかった橋本と、スターリンの元で体制が求める音楽を書くことを求められたショスタコーヴィチ。2人の天才音楽家は、国は異なれども同じような境遇だったかもしれません。その2人が束縛から解放され、自らを取戻して書いた曲をプログラミングしました。
1996年の新交響楽団創立40周年記念「日本の交響作品展」のメインプログラムに据えたのが橋本の交響曲第1番でした。「皇紀2600年」(昭和15年)記念のための曲で戦時色の濃いものでしたが、魅力的で心に残る傑作でしたので、いつか第2番も取り上げたいという思いがありました。
■橋本國彦 交響曲第2番~平和への願い
橋本國彦(1904-49)は、東京音楽学校(現在の東京藝術大学)に当時作曲科がなくヴァイオリン専攻で入学、1937-39年に欧米に留学し特にウィーンで作曲を学びました。帰国後は母校の作曲科教授となり、諸団体の要請に応じて「時局音楽」を数多く作曲しました。橋本自身は政治色の強い人ではありませんでしたが、官学の作曲科主任教授としての役割をはたす必要がありました。終戦後に戦争協力の責任を取り辞職、間もなく胃癌のために世を去ります。
交響曲第2番は、新憲法制定を祝う祝賀会のために委嘱され1947年に作曲・初演されましたが、構想は戦時中からあったようです。歌曲を得意とした橋本らしく美しい旋律に溢れた叙情的な曲で、自筆譜には副題に「平和の鐘」と書かれた跡があり、最後に鐘が希望に満ちて鳴り響きます。
■ショスタコーヴィチ 交響曲第10番~自由への突破口
ショスタコーヴィチ(1906-75)は元々前衛的な曲を書いていましたが、粛清を恐れて交響曲第4番を封印し第5番からは社会主義リアリズムに転ずるも、第9番が短く軽妙だったためスターリンに激怒され、プロパガンダ的な作品を作り当局にある意味「迎合」していました。
交響曲第10番は、1953年にスターリンが死んだ直後に発表され、第9番の作曲から8年も経過していました。15曲ある彼の交響曲の中で最も美しい曲と言われており、人間的な感情と情熱を描きたかったと作曲者自身が述べていますが、自分のイニシャル(DSCH)音型や「スターリンの肖像」など、いろいろな意味が込められているようです。
祝典序曲は、交響曲第10番の作られた翌年の革命記念日のために委嘱されました。明るく快活な元気の出る曲で、最後は金管楽器のバンダが加わり華やかに幕を閉じます。記念というよりは、むしろ「スターリンからの解放」を喜んでいたのかもしれません。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
サン=サーンス:交響曲第3番ハ短調「オルガン付き」
生い立ち
サン=サーンスは1835年、パリに生まれた。生後2か月で、内務省の役人を勤める父を亡くし、母と叔母に育てられた。ピアニストであった叔母シャルロットより3歳になる前からピアノの手ほどきを受け、みるみる音楽的な才能を開花させた。わずか3歳と5か月で作曲の真似事をするようになり、5歳になるころには小さめのソナタを見事に弾きこなしたという。そして7歳の頃には聴衆を魅了するほどの腕前となる。世間は彼を「モーツァルトに匹敵する神童」と呼んだ。
サン=サーンスの才能は音楽に限ったものではなかったそうだ。
3歳のころにはすでに読み書きができ、代数の問題を解いた。7歳になるころにはラテン語・ギリシア語を読みこなしていたという。その後サン=サーンスは、音楽家として名をはせたその裏で多くの才能を発揮した。戯曲や詩、小説を書き、天文学、自然科学、考古学、哲学、民俗学など幅広い分野の著書をいくつも発表している。
話を元に戻そう。
音楽家としてのサン=サーンスは1848年、13歳の時にパリのコンセルヴァトワールに学んだ。ここで、オルガンと出会う。
3年後の1851年にはオルガンコンクールで1等賞を受賞する。惜しくもローマ賞は逃すものの、当時活躍していたオルガニストが絶賛するほどの腕前だったという。そしてこの頃、ピアニストとしても頭角を現し、演奏旅行を頻繁に行なっていた。
パリのコンセルヴァトワールを卒業したあとも、サン=サーンスは音楽家として、また作曲家として活動を続けた。引き続きピアニスト・オルガニストとして大活躍し、ベルリオーズには「彼は何もかも心得ている。足りないものは未知なる経験だけだ」と言わしめ、リストからは「世界で一番偉大なオルガニスト」と賞賛された。演奏によって生活費を稼ぎながら、その蓄えで作曲に没頭していくことになる。
その後1871年、普仏戦争敗北後、パリ・コンセルヴァトワールのロマン・ビュシーヌ教授が、フランス国内の作曲家を奨励するための協会結成に向け広く呼びかける。これに呼応しサン=サーンスは、セザール・フランクとともに「国民音楽協会」を立ち上げ、その創立者として活躍した。当時、ドイツ古典派の名曲や軽いオペレッタが主流であったフランス音楽界に一石を投じ、フランス近代の器楽曲の名曲を生み出す基礎づくりに奔走した。
人生の転機
幼きサン=サーンスにピアノを教え、事細かに世話を焼いてきたシャルロットが亡くなったのは、国民音楽協会を立ち上げた翌年、彼が37歳の年だ。ほかの女性と接触することを拒むほど、母性的に支配していた叔母。その叔母が亡くなって、初めて息子と二人きりになれた母親は、ここぞとばかりに彼を溺愛し束縛したという。いわゆる彼の半生は、叔母と母によるマザーコンプレックスの人生だったと言われている。
ちなみにモーツァルトはファザーコンプレックス、メンデルスゾーンはシスターコンプレックスと言われ、天才と呼ばれた人生の裏側には、人知れず大きな壁があったことが伺える。
やがてサン=サーンスは、母親の息詰まる愛情には耐えられなくなる。1875年、40歳の彼は、突如19歳のマリ=ロール・トリュフォという女性と電撃結婚した。当然そのことに、世間はあっと驚いた。この当時にして、21もの歳の差婚である。
やがて夫婦には、アンドレとフランソワという、二人のかわいい息子が生まれた。幸せに暮らすサン=サーンス一家。見るからに、いよいよ母親の束縛からも解放されたかのような新婚生活だった。
しかしここで、サン=サーンスに悲劇が襲う。1878年、彼が43歳の年に、二人の息子たちを事故と病気で次々と失ってしまうのだ。つかみかけた人並みの幸せが無残にも崩れ、サン=サーンスはとことん失意に明け暮れた。
3年後、サン=サーンスは思いつきのように夫婦で夏の温泉地に出かける。しかしある朝、彼は妻を置き去りにして、突然ホテルから姿を消してしまう。後の手紙によると彼は、かつて溺愛してくれた母のもとへと帰ったという。子供という、鎹かすがいが外れた夫婦の愛情をつなぎとめるものは、もはや何もなかった。そんな彼を慰めるものは、かつての母性的な支配だったのだ。しかし、7年後にその母親も亡くなる。サン=サーンスは、いよいよ悲しみに明け暮れたという。
そんな中でも作曲活動は精力的にこなした。これらの功績が名声を高め、1892年、57歳の時にケンブリッジ大学から音楽博士の称号を贈られ、1913年、78歳にはフランスの最高の勲章である、大十字章グラン・クロワを贈呈された。
1921年12月16日、86歳のサン=サーンスは、取材のために訪れたアルジェリアで肺炎に倒れ、帰らぬ人となった。葬儀は、彼の多大なる功績をたたえて、フランス音楽家の中で唯一となる国葬で執り行われたという。
交響曲第3番
本日お送りする交響曲第3番は、1885年、妻と離別し母親のもとに身を置いた激動の時代に書き始められた作品である。混乱の人生にありながら、新しい何かを創造しようとどれほど曲づくりに執着したかは、内容の凄さからうかがい知れる。
丁度この年の夏、ロンドンのロイヤルフィルハーモニー協会が、次シーズン用に新しい曲に取り組みたいと、ドリーブ、マスネ、サン=サーンスに作曲を依頼した。その依頼を受けて書かれたものだ。提示された報酬は30ポンド。その年の冬から翌1886年の4月末にかけて作曲された。
初演は、完成から半月後の5月19日。ロンドンフィルハーモニーの演奏で行われ、まずまずの成功を見た。大成功を収めたのは、翌年1月の故郷パリでの初演だ。雑誌「ル・メネストレル」はこの演奏会について「ブラヴォが終わらないのではないかと思われるほど聴衆が熱狂した」と記している。この曲の成功によりサン=サーンスは「フランスのベートーヴェン」と称えられることとなった。
さて、普通の交響曲は4楽章で構成される。しかしこの交響曲第3番は、2楽章構成と珍しい形を持つ。従って本日も楽章間の休みは中間に一回だけである。ただし、音楽的には一つの楽章が前半と後半の2部に分かれており、1曲で合計4部構成になっている組み立てが交響曲の体を成す。
第1楽章の第1部は、アダージョの序奏とアレグロ・モデラートの主部で構成されている。この第1部に、のちの各部、各楽章の主題のほとんどが現れる。第2部はポーコ・アダージョ。オルガンの音色に導かれて美しいメロディが奏でられる。
第2楽章の第1部はスケルツォに相当する部分。劇的な性格を持つ主題がアレグロ・モデラートで刻み付けられる。そして第2部は有名なオルガンの強奏で幕を開け、主題をはなやかに昇華させていく。ピアノのアルペジオも鳥肌もので、かつて弾きこなしてきた鍵盤の競演は、まるで彼の人生を見るかのようだ。ラストの興奮極まったフェルマータの和音は、もう筆舌に尽くしがたい。
サン=サーンスは、番号のない2曲も含めて、合計5曲の交響曲を作曲した。そのうち4曲がごく若い時期に書かれたもので、本日演奏する第3交響曲だけが51歳という円熟を迎えたときの作品である。
彼自身、この作品に「私のすべてをつぎ込んだ」と話しているほどの入れ込みようだった。なるほどその後の人生で、もう交響曲を書くことはなかった。
チャイコフスキー:バレエ音楽「白鳥の湖」より
沿革
1875年、チャイコフスキーはモスクワのボリショイ劇場から新作バレエの音楽を依頼され、「白鳥の湖」を書き上げる。1877年の初演はオーケストラの練習が2回しかなかったことによる準備不足もあって失敗に終わったが、やがて一定の評価を得て1883年まで3回の振付改訂を伴って41回再演された。その後、1881年から実施された劇場改革の一環で、モスクワのバレエ団への経費が壊滅的に削減され、老朽化した衣装・舞台設備を新調することができなくなり打ち切られた。尚、当時の文化の中心であったサンクトペテルブルクでこの作品を改訂して上演する計画はチャイコフスキーの生前からあったが、1893年の彼の急逝により果たされなかった。
この作品に新たな息吹が与えられたのはチャイコフスキーの没直後、「眠れる森の美女」(1890年)、「くるみ割り人形」(1892年)で彼と組んで成功を収めていたマリインスキー劇場の振付家プティパが追悼演目として上演するよう提案したことに始まる。振付家イワノフの協力を得、チャイコフスキーの弟モデストが台本の一部を改訂、指揮者ドリゴが配曲変更・作曲者晩年のピアノ曲を編曲して追加するなどし、先ず第2幕のみを1894年に追悼上演、翌1895年全幕蘇演。ここに初めて真価が認められ、永遠の命が与えられた。今日に至るまで絶え間なく各国の舞台で上演されているが、その大半の基礎となっているのはこのプティパ=イワノフ版である(その他、原典譜を用いた版もある)。1900年には、全曲版から抜粋した演奏会用組曲も出版され、1901年に初演された。
あらすじ(1896年ユルゲンソーン刊スコアによる。※概ね蘇演版に沿うと思われる)
中世ドイツ、城の世継ぎジークフリート王子の成年式。村娘たちがワルツを踊る中、母である王妃に翌日の舞踏会で花嫁を選ぶよう命じられた王子は承諾し、皆はお祝いの踊りを繰り広げる。自由な独身時代への別れに気の乗らない王子は、夕空を飛ぶ白鳥の群を見て、親友達と気晴らしの狩に出かける。
深い森の湖畔に辿り着いた王子は、白鳥を見つけ、射ようとする。途端に白鳥は王冠を付けた娘の姿に変わり、「悪魔ロットバルトの魔法をかけられた王女オデットである自分は、仕える娘共々昼間は白鳥の姿にされている。誰とも愛の誓いを交わしたことのない若者が生涯愛し続けてくれるまでこの魔法は永遠に続き、誓いが破られれば白鳥達は永遠に人間の姿に戻れなくなってしまう。悪魔の破滅は、オデットへの愛のために誰かが自分を犠牲にするときだけやってくる。」と告げる。悪魔が現れ、二人の会話を聞いて姿を消す。二人はめくるめく一夜を過ごし、王子はオデットに告白して翌日の舞踏会に招くが、その時間にはオデットは白鳥の姿でおらねばならず、窓の外を飛ぶことしかできないと告げる。
翌日の舞踏会。各国から招かれた花嫁候補が踊っても意に介さない王子の前に、貴族に扮した悪魔がオデットに良く似せた娘オディールを従えて登場。騙された王子は、窓辺で必死に訴えるオデットに気づかず、オディールと永遠の愛を誓ってしまう。途端に悪魔はその正体を現して嘲笑、取り乱した王子は、人間の姿に戻ることがかなわなくなり絶望して入水しようと決意したオデットを追って森の湖畔へ向かい、許しを乞うて許される。すべての運命を受け入れたオデットと王子は相次いで命を絶ち、二人の愛によって悪魔も滅びる。オデットと王子は昇天し、天界で結ばれる。
楽曲解説
本日は、8曲を抜粋してお届けする。
導入曲
もの悲しいオーボエによる「白鳥の主題①」(譜例1)が特に印象的。バレエにライトモチーフが用いられた初めての場面と言われる。並々ならぬ関心を抱いていたワーグナーの影響であろう。そもそもこの主題は、ワーグナーのオペラ「ローエングリン」(1850年)で、白鳥の曳く小舟に乗って登場した騎士が「私の素性を問うてはならぬ」と歌う「禁断の動機」(譜例2)を、題材としている。白鳥に関わるバレエを書くにあたって、ワーグナー作品の中で最も好んだとされる「ローエングリン」を思い浮かべたのは必然だったのであろう。
第1曲 情景
王子の成年式にふさわしい分厚い全管弦楽による力強い旋律が奏され、バレエの幕開けとなる。中間部では村娘と若者達の朴訥としたミュゼット風田舎踊りがオーボエに現れ、再現部では賑やかな宴が始まる。
第2曲 ワルツ
弦楽器によるピッツィカートによる前奏に次いで、王子の求めで村娘達がワルツを踊り始める。次々と奏される豊饒な旋律に、感嘆させられる。中間部の優美なトリオを挟み、冒頭を再現して結ぶ。
第10曲 情景
悪魔が支配する湖の情景を現す、第2幕の導入曲である。「白鳥の湖」の旋律の中で、最も有名であろう「白鳥の主題②」(譜例3)がオーボエに現れる。この主題は、前述「禁断の動機」のもう1パターンの変形である。即ちチャイコフスキーは「ローエングリン」に着想を得て、2つの主題を創ったことになる。この主題はやがて増殖され、悪魔を暗示する3連符が現れる(譜例4)。
第13曲E パ・ダクシオンより
恋に落ちた王子はオデットに愛を告げ、二人は愛の踊りを踊る。木管とハープが二人を神秘的な世界に導いた後、ヴァイオリン独奏が甘美な旋律(譜例5)を歌い、続いて小刻みな木管の中で奔放な動きを繰り広げる。やがて主題はチェロ独奏に移り、ヴァイオリン独奏によるオブリガートとの絶妙なアンサンブルが、二人の熱烈な愛を象徴する。本日は、第5部(通称E)より、組曲版第4曲にも抜粋された部分を演奏する。この曲は、チャイコフスキーの初期のオペラ「ウンディーナ」(1869年)の「愛の二重唱」の流用でもある。
第20曲 ハンガリーの踊り(チャルダーシュ)
王妃主催の舞踏会では各国の舞踏団が踊る。ハンガリーの特色ある民族舞曲であるこの曲は、「チャルダーシュ」の形式に則り、テンポの遅い官能的な前半部分「ラッシャン」と、熱狂的で速い後半部分「フリシュカ」からなる。「酒場」を意味するハンガリー語「チャールダ」に由来するこの踊りは、19世紀には禁止令が出るほどヨーロッパ全土で大流行していた。
第21曲 スペインの踊り
スペインの舞踏団が踊る、カスタネットの響きが印象的な民族舞曲。「ボレロのテンポで」と指定がある。「ボレロ」は18世紀後半にスペインで始まった3拍子の踊り。
第29曲 情景・終曲
悲愴かつ雄大な旋律の中、心ならずも裏切ってしまった王子がオデットを追って湖岸に登場、ハープによるアルペジオで静まって、終曲への導入となる。チャイコフスキー第一作目のオペラ「地方長官」(1866年)の「愛の二重唱」が流用されている。「白鳥の主題②」がオーボエに現れ、「悪の半音階」の後、悲愴感に満ちて再び奏される。王子は王女に許しを乞うて許され、二人は悲しい運命を受け入れる。「悪の半音階」・「白鳥の動機②」・3連符による「悪魔の動機」が同時に奏され(譜例6)、二人は相次いで自害。金管により「白鳥の主題②」が熱情的に響き、死をも恐れぬ二人の愛が悪魔を滅ぼしたことを示す。弦楽器のトレモロとハープの幻想的な旋律の中で、昇天した二人は結ばれ、終幕となる。
調性配置
チャイコフスキーは、この作品を完成する頃には、交響曲3曲・弦楽四重奏曲3曲・ピアノ協奏曲第1番等を完成させており、作曲家としての円熟期にさしかかろうとしていた。その一端が、遠隔調と近親調の関係性をキャラクター間の関係に当てはめた調性配置の妙から見て取れる。この曲の登場人物と調性を結びつけた(Roland John Wileyの分析に依る)上で、五度圏に当てはめたものが、図1である。先ず、白鳥達(h-Moll)と王子(D-Dur)はセットになって同じ位置におり、その対極、即ち最も遠隔な調に、王子の不幸(As-Dur)と悪魔(f-Moll)がある。また、オデットの結婚の予感(Ges-Dur)の対極には悪魔(C-Dur)がいる。一方、オデット(E-Dur)、彼女の結婚の予感(fis-Moll)、白鳥達(h-Moll, A-Dur)、王子(D-Dur)は極めて近い位置におり、チャイコフスキーが調性関係を、音楽的表現の方法として意識的に用いていたことが見て取れる。尚、この方法は、作曲にあたり参考にしたとされる、彼が好んでいたバレエ「ジゼル」(1841年)において既に用いられていたもので、チャイコフスキーがこの分野の伝統に則って作曲を行ったということが分かる。
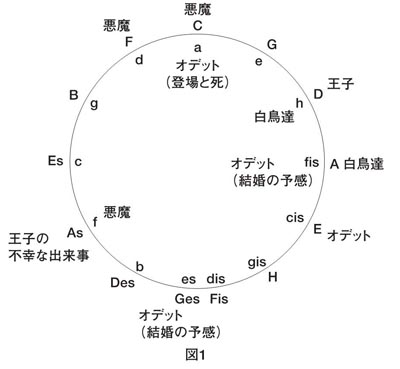
全曲版初演:1877年2月20日、ライジンガー振付、リャーボフ指揮、ボリショイ劇場による。主役オデット=オディールはカルパコワ。
組曲版初演:1901年9月1日、ウッド指揮、ロンドン・クイーンズ・オーケストラにより、ロンドン・クイーンズ・ホールにて。
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、コルネット2、トランペット2、
トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、タンブリン、シンバル、カスタネット、タムタム、トライアングル、グロッケンシュピール、ハープ、弦五部
参考文献
『ミニチュアスコア チャイコフスキー バレエ組曲 白鳥の湖 作品20』(音楽之友社)
『TCHAIKOVSKY,S BALLETS』Roland John Wiley著(CLARENDON PRESS・OXFORD)
『チャイコフスキーの音符たち 池辺晋一郎の「新チャイコフスキー考」』池辺晋一郎著(音楽之友社)
『作曲家別名曲解説ライブラリー チャイコフスキー』(音楽之友社)
『作曲家 人と作品シリーズ チャイコフスキー』伊藤恵子著(音楽之友社)
『永遠の「白鳥の湖」チャイコフスキーとバレエ音楽』森田稔著(新書館)
ベルリオーズ:序曲「ローマの謝肉祭」
早速ですが、問題です。「ローマの謝肉祭」というオペラは存在するでしょうか?正解は×です。残念ながらそういったオペラは存在せず、本日演奏する序曲「ローマの謝肉祭」は、イタリア、ルネッサンス期の彫刻家の波乱に富んだ自叙伝をもとにした歌劇「ベンヴェヌート・チェッリーニ」というベルリオーズ自身が書いたオペラが元になっています。このオペラは約4年の作曲期間を経て1838年にアブネックの指揮によりパリのオペラ座で初演されますが、「場内一致のエネルギーでもって無茶苦茶に野次り倒された」とベルリオーズ自身の回想録にもあるくらい、散々の評価だったようです。しかしながらリベンジとばかりに、5年後の1843年、ベルリオーズ39歳の時にこのオペラの2つのモチーフをもとに改めて作曲されたのが、この序曲「ローマの謝肉祭」です。
この序曲はとても華やかな序奏に始まり、それに続くところが大まかに前半のゆったりした部分と後半の非常に速い部分とに分かれます。
前半のゆったりした部分は、主人公チェッリーニとテレーザによる愛の二重唱がモチーフとなっており、この旋律がまずはコールアングレによって奏でられ、のちに弦楽器などに発展していきます。ところで、なぜこの旋律がコールアングレで始まるのか。
これは、私にとっては積年のささやかな疑問!? であったわけですが、今回曲目解説の大役を仰せつかったのを機に、ベルリオーズ自身が書いた「管弦楽法」を調べてみたところ、次のようなことが書かれていました。
~特に速い楽節ではオーボエにも増して貧弱な効果しか得られない。オーボエに比べて鋭さがなく、くぐもった重たい音は、オーボエのような陽気な田舎風の旋律にはそぐわない。鋭い苦しみの表現はおおよそその範疇を超えており、苦悩の嘆きなどは表現できない。…哀愁が漂う、夢想的で気高い、やや霞のかかった、あたかも遠くで演奏されているかのような音である。過去の想い出や感傷の表現において、また作曲家が隠された繊細な記憶に触れたいと思う時に、これにまさる楽器はない。~
表現できないなどと、ここまではっきり言われると若干の腹立たしさもなくはないのですが、ベルリオーズに歯向かったところで勝ち目はありませんので、ここは大人しく引き下がり、むしろこうした素敵な旋律を吹けることに喜びを感じながら演奏する次第であります。
一方、後半の非常に速い部分はイタリアの軽快な郷土舞踊「サルタレッロ」をもとにしたもので、目まぐるしく旋律が展開して、皆様にはとてもワクワクしていただけるのではないかと思います。ちなみに、メンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」の第4楽章もこの「サルタレッロ」が関係しています。どちらも心拍数“180”は決して下らない!? 演奏する者にとっては一瞬たりとも気の抜けないスリリングな曲であります。
実はこの部分にはエピソードがあります。この「サルタレッロ」は、歌劇「ベンヴェヌート・チェッリーニ」初演に際して、同様のモチーフの箇所で作曲家ベルリオーズが指揮者アブネックに対して何度も「もっと速く!! 勢いをつけて!!」と注文をつけたものの、うまく演奏できなかった部分だったということ。一方、この序曲の初演の指揮者であったベルリオーズは、初演当日にたまたま国民衛兵の式典に管楽器奏者が借りだされていたために、管楽器なしでのリハーサルの後に本番を迎えなければならなかったこと。そんな中、全く知らないこの序曲を公衆の前で演奏することになりすっかり困惑していた管楽器奏者たちに対して、ベルリオーズは次のような言葉をかけています。
「恐れることはありません。楽譜のとおりなのです。みなさんはそれぞれに才能をお持ちの方たちばかりです。できるだけ指揮棒をよく見てください。休止に気をつけて。そうすればうまくやれます」
結果は大成功。ただ1つのミスもなく、聴衆からはアンコールのリクエスト。しかも、アンコールは更に良い演奏。当日のリハーサルの経緯も知り、違った結果を心待ちに聴いていたアブネックは、きっと落胆したに違いありません。
また、肝心の謝肉祭(カーニバル)ですが、復活祭に向けて約40日間の断食に入る前のお祭りでありまして、元々は宗教的な意味合いに由来していたものの、ベルリオーズの回想録での描写を見ても、すでに当時においても堅苦しさとは無縁の民衆のお祭りだったようです。
転じて、本日の打上げでは、美味しいお肉とお酒で、みんなで演奏会の成功を喜び合い、さながら「池袋の謝肉祭」ということで盛り上がりたいと思います!!
(その後の断食は?…えっ!?)
余談ですが、ベルリオーズの「管弦楽法」では、オーケストラという章があり、時間と資金と労力が得られれば、巨大オーケストラの編成はかくあるべきだと、真面目に書かれています。
ヴァイオリン120人、ヴィオラ40人、チェロ45人、コントラバス37人、木管楽器62人、金管楽器47人、打楽器55人、ハープ30人、ピアノ30人、オルガン1人で計467人
(実際には木管、金管、打楽器は楽器ごとに更に細かい指定があります)
やはり天才が考えることは、凡人の理解を遥かに超えています。果たして後の作曲家たちの参考になったのでしょうか。もっともこんな編成の曲を作られたところで、なかなか演奏できませんが。
作曲:1843年
初演:1844年 パリにて
出版:1844年
楽器編成:フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2(2番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット2、
ファゴット2、ホルン4、トランペット2、コルネット2、トロンボーン3、ティンパニ、トライアングル、タンブリン、シンバル、弦五部
参考文献
『管弦楽法』エクトール・ベルリオーズ、リヒャルト・シュトラウス著、小鍛冶邦隆監修、広瀬大介訳(音楽之友社)
『作曲家別名曲解説ライブラリー19ベルリオーズ』(音楽之友社)
『不滅の大作曲家 ベルリオーズ』シュザンヌ・ドゥマルケ著、清水正和・中堀浩和共訳(音楽之友社)
『大作曲家とその時代シリーズ ベルリオーズとその時代』ウォルフガング・デームリング著、池上純一訳(西村書店)
『ベルリオーズ回想録』ベルリオーズ著、丹治恆次郎訳(白水社)
「オケ中ピアノ」あれこれ
秋も深まったとある昼下がり。第228回演奏会の演目であるサン=サーンスの交響曲第3番「オルガン付き」のパート譜を手に、「ついにこの曲を弾ける時が来た」と感慨深く眺めているとこへ1本のEメールが届いた。それは維持会マネージャー氏からの「維持会ニュース」への執筆依頼であった。
かく言う私はプログラム編集人の端くれでもあるのだが、新響が取り上げる曲の中には初演を含め、曲目解説を執筆するにあたっての資料が極端に乏しい曲も少なくなく、執筆者選びに奔走することが往々にしてある。そういった際、まさに藁にもすがる思いで博識のマネージャー氏に執筆依頼をするのが常となっている。そして面倒な依頼にもかかわらず嫌な顔ひとつせず、いつも素晴らしい名文を書き上げてくれるのだ。そんな彼の依頼を断ることなど出来ようか。ということで、今回は私にとって一番身近な、だが一般的にはあまり知られていない「オーケストラの中のピアノ」について書いてみようと思う。
ピアノを称して「楽器の王様」というらしい。確かにベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」冒頭のように、オーケストラをバックにして繰り広げる壮大かつ絢爛豪華なピアノの響きは、その軍艦のようなたたずまいとあわせて、まさに「王者」と呼ぶにふさわしい。だがオーケストラの中のピアノ、つまりオーケストラ作品の1パートとしてのピアノ、略して「オケ中ピアノ」となるとその様相はかなり違ってくる。
そもそも「オケ中ピアノ」が入るオーケストラ曲はいつ頃から登場したのか。その前にピアノとオーケストラの成り立ちについて簡単にふれておきたい。
言うまでもないことだがベートーヴェンやブラームスといった、いわゆる古典派からロマン派にかけての有名なオーケストラ作品では「オケ中ピアノ」は登場しない。そして興味深いことに、ちょうどその時期はピアノという楽器そのものの発展期とぴたりと重なっている。
ピアノの歴史は比較的浅く、フランス革命(1789年)以降にようやく大量生産されはじめ、19世紀の産業革命を経てようやく工業化の波に乗り飛躍的に発展していった。特に産業革命による良質の鉄の製造技術の発展は、鋼鉄製のピアノ弦とそれを支える鋳鉄製のフレームを実現し、ピアノはより現在に近い形に近づいてく。そして楽器の発展に触発されるように偉大な作曲家たちによる優れたピアノ曲が次々と生み出され、19世紀のピアノはあらゆる面で急速に発展していった。ベートーヴェンからシューマン、ショパン、そしてリストからラフマニノフまでを含めて、現在ピアノ・リサイタルで取り上げられる作品の大多数は、この時代に集中していると言っても過言ではない。
その表現力は、それ自体が一つのオーケストラとしての無限の可能性を秘めており、古典派からロマン派にかけての大作曲家の創作意欲を大いに駆り立てた。こうしてピアノはピアノ製作者、作曲家、そしてヴィルトゥオーソ・ピアニストの三者一体となった「ピアノ芸術」として、孤高の道を歩むことになる。
一方のオーケストラであるが、古典派期に交響曲や協奏曲、歌劇といった分野を中心に飛躍的に発展するとともに、演奏の場が宮廷からコンサートホールへと移行していく過程で、その規模は拡大の一途をたどる。しかしその間クラリネットなどの歴史の浅い楽器や、トロンボーンなどを加えながらも、オーケストラの基本的な編成は既に古典派期にはほぼ出来上がっていた。古典派後期からロマン派以降は、主に管楽器や打楽器等の種類が多様化し、楽器編成がより拡大する傾向にあった。例えばピッコロやコールアングレ、バスクラリネット、コントラファゴットなどの標準的な楽器の同族楽器や、タムタムやグロッケンシュピールなどの多様な打楽器群の参入である。またベルリオーズ「幻想交響曲」(1830)のように、オーケストラ作品にハープが効果的に使用されるようになったのもこの時期だ。だが鍵盤楽器は、協奏曲に代表される独奏的な扱いを除いて、まだオーケストラには登場しない。
ここで本題の「オケ中ピアノ」の初登場を検証したい。今まで私が新響で弾いた作品を、作曲年順に15番目まで列記してみる。
1,サン=サーンス:交響曲第3番ハ短調「オルガン付き」(1886)
2.ドビュッシー:交響組曲「春」(1887)
3.マーラー:交響曲第8番「千人の交響曲」(1906)
4.サン=サーンス:「ギース公の暗殺」(1908)
5.ストラヴィンスキー:バレエ音楽「火の鳥」(1910)
6.ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1911)
7.プロコフィエフ:スキタイ組曲(1915)
8.ファリャ:恋は魔術師(1915)
9.レスピーギ:交響詩「ローマの噴水」(1916)
10.ファリャ:「三角帽子」第2組曲(1919)
11.バルトーク:舞踊組曲(1923)
12.レスピーギ:交響詩「ローマの松」(1924)
13.ショスタコーヴィチ:交響曲第1番(1925)
14.コダーイ:組曲「ハーリ・ヤーノシュ」( 1927)
15.レスピーギ:交響詩「ローマの祭」(1928)
こうして並べてみると壮観で、感慨深いものがある。それぞれの曲について、新響との思い出を交えながら述べてみたい。
まず今回取り上げるサン=サーンスの交響曲第3番が、記念すべき「オケ中ピアノ」の第1号となっている。しかもこの曲のピアノ・パートの後半は1台4手の連弾となり、作曲者の並々ならぬ意欲を感じる。そして次に登場するドビュッシー交響組曲「春」(1887)にもピアノ連弾が登場する。新響では1997年の第159回演奏会(飯守泰次郎指揮)にて、アンリ・ビュッセルによる編曲版(1912)を取り上げたのだが、この編曲版には全編にわたって1台4手の連弾が入っている。そのほか1台4手の連弾は、14番目のバルトーク「舞踊組曲」(1923)、そして15番目のレスピーギの交響詩「ローマの祭」(1928)にも登場する。
3番目のマーラー「千人の交響曲」は、1986年の新響創立30周年の一環として、山田一雄先生の指揮にて東京文化会館で演奏された。しかしその名の如く巨大編成のため、天下の東京文化会館をもってもフルコンサートピアノがステージに乗りきらなかった。何とか大屋根と側板部分は乗ったものの、ピアノ奏者は下手のカーテンの奥で弾かざるを得なかったという悲しい歴史は、団内でもあまり知られていない。また80分をゆうに超える大曲にもかかわらず、ピアノの出番は第2部の中間部にほんの少しあるだけで、弾く前にも、そして弾き終わった後にも膨大な待ち時間が発生する。そのため本番時のモチベーションの維持と、寒さ対策は必須と言えよう。
そして5・6番目には満を持したかのように「火の鳥」「ペトルーシュカ」と、ストラヴィンスキーの3大バレエの2作品が立て続けに登場する。新響では「火の鳥」は1910年版(全曲版)と1945年版(組曲版)、「ペトルーシュカ」は1911年版と1949年版の両方を取り上げ、その何れも経験できたのは身に余る光栄といえよう。ピアニスト目線で新旧の版の違いを比べると、後の改訂版の方がピアノの出番が多く、難易度もぐんと上がっていることが分る。例えば「火の鳥」1945年版の「魔王カスチェイの凶悪な踊り」を経験してしまうと、1910年版の「凶悪な踊り」はまるで気の抜けたコーラのようで、「こっそり1945年版で弾いてしまおうか」と思ったほどだ。しかし当然ながらこっそりと、指揮の飯守先生にも気づかれずに弾く場面ではないので、欲求不満はつのる一方であった。
話はそれるが、「はるさいの枕詞はと人問はば、言はずとも知れ変拍子なり ─詠み人しらず─」と古来歌にも詠まれた(注1)ストラヴィンスキー「春の祭典」(1913)には、「オケ中ピアノ」は登場しない。ただでさえ予測不能の変拍子の連続で、オーケストラが「阿鼻叫喚の地獄絵図」と化す中、オケ慣れしないピアニストがさらなる無間地獄へと突き落す可能性を危惧して排除されたのであろうか。同じことがバルトークの代表作「管弦楽のための協奏曲」(1943)にも当てはまる。「管弦楽のための」と謳っておきながらピアノが入っていないなんて、かえすがえす残念だ。しかもハープは2台も入っているのに、である。一方、ルトスワスキーの「管弦楽のための協奏曲」(1954)にはピアノが登場し、作曲家の勇気に拍手を送りたくなる。
さて本題に戻して、7番目にはプロコフィエフ「スキタイ組曲」(1915)とファリャ「恋は魔術師」(1915)が入ってくる。「スキタイ組曲」はストラヴィンスキーの「魔王カスチェイの凶悪な踊り」をさらに輪をかけて狂暴にしたような曲で、体育会系「オケ中ピアノ」の筆頭といえる。冒頭から延々と続く最強音でのグリッサンドでは、軍手が欲しいほどだ。ここを抜けると低音の補強に入るのだが、引き続き懸命にグリッサンドをしているお隣のハープ奏者を見るにつけ、「まだピアノでよかった」と胸をなでおろすのであった。
なお、このグリッサンドと低音楽器の補強という役回りは、スキタイ以降の「オケ中ピアノ」の定番パターンの1つとなる。さすがの「王者」も、「オケ中」の下手の奥という不利な立地では、上段から押し寄せる打楽器群と金管楽器群の咆哮による総攻撃は勝てず、客席まで音が届かないことがほとんどである。まさに「労多くして功少なし」を地で行くような役回りだが、少しでもずれると聴こえてしまうというやっかいな代物でもある。
またこの圧倒的に不利な戦いに果敢に挑んだ強者が、前任の新響ピアノ奏者でソリストとしても活躍した故・渡辺達さんだ。しかしながら彼を以てしても多勢に無勢、激闘の末にはグリッサンドの跡が血で染まった鍵盤が残されたという事実は、今や伝説として語り継がれている。
ファリャ「恋は魔術師」(1915)は、10番目の「三角帽子」(1919)とあわせて、芥川先生の新響・定期演奏会(注2)における最後の指揮であった。「三角帽子」の終曲には定番のグリッサンドの連続が出てくるのだが、幸か不幸かこの終曲の後半は芥川先生の大のお気に入りでもあった。そのため練習の最後5分間は、たとえどんなに他の部分が仕上がっていなくても、あたかも何かの儀式のように取り上げるのが常であった。それはリハーサル番号7番からで、先生が「猫の喧嘩」と名付けられた弦楽器の16分音符のユニゾンから、終わりまでである。どのパートも練習の最後に演奏するには体力的に厳しい箇所なのだが、対する芥川先生の満面の笑顔は今でも心に残っている。
9番目にはレスピーギの交響詩「ローマの噴水」(1916)が登場し、その後「ローマの松」(1924)、「ローマの祭」(1928)とつづく。このローマ三部作を通して、レスピーギは「オケ中ピアノ」の扱いがとても上手いなとつくづく思う。たとえば「昼のトレヴィの泉」や「ボルゲーゼ庭園の松」のように木管楽器と重なって煌びやかなパッセージを弾いたり、「アッピア街道の松」のように低音楽器と重なって重厚なサウンドを作り出したり、「ジャニコロの丘の松」のように単独の幻想的なソロがあったりと、じつに多彩にピアノを活用している。このピアノ・パートを弾く時はいつも、オーケストラの一員として音楽を表現する喜びに満たされる。あまりにも感動した私は、その後本当にローマへ行き、噴水をめぐり、ジャニコロの丘へ登り、そしてアッピア街道を歩いてしまった。
13番目にはショスタコーヴィチの交響曲第1番(1925)が颯爽と登場する。「オケ中ピアノ」のもう一つの定番である「オクターブの単旋律による単独のソロ」は、この曲が初めての試みかもしれない。特に第2楽章の中間部から再現部にかけての半音階と、再現部に入ってすぐの単旋律のソロに至るまでの緊張感は尋常ではない。その後の4番(チェレスタのみ)、5番(1937)、そして7番「レニングラード」(1941)と、ショスタコ交響作品を弾く時は、自分の寿命が少しずつ削られていくような強いストレスと、緊張を強いられる。そこには音楽の喜びや楽しさがみじんも感じられない厳しさがあり、単に「レニングラード」という地名を聞いただけで、条件反射的に冷や汗が出てくるほどだ。
最後になるが、邦人作品で「オケ中ピアノ」が登場したのはいつであろうか。引き続き16番目から20番目を見てみよう。
16.アイスラー:「雨」についての14の描写(1929)
17.バルトーク:中国の不思議な役人(1931)
18.深井史郎:パロディ的な4楽章(1933)
19,プロコフィエフ:組曲「キージェ中尉」(1934)
20.伊福部昭:日本狂詩曲(1935)
あくまでも自分が在団中に新響で取り上げた作品での順番ではあるが、巨匠・伊福部先生を押さえて、深井史郎の「パロディ的な4楽章」(1933)が邦人第1号となった。しかもこの作品は「ペトルーシュカ」と並んで、もっとも難しい「オケ中ピアノ」の1つと言えよう。しかしながら両作品とも、試作段階において「ピアノが主体的な役割を演じるオーケストラ作品」として着想されたことを考えると納得がいく。新響では1999年の第164回演奏会(飯守泰次郎指揮)で取り上げた。しかも驚くことにこの時のプログラムは、ブラームス:交響曲第3番、深井史郎:パロディ的な4楽章、サン=サーンス:交響曲第3番「オルガン付き」と、「オケ中ピアノ」にとって記念すべき演奏会であった。今になって気がついても遅きに失する.のだが、当時はよりによって「オケ中ピアノ」の大曲が1つの演奏会に2つも重なってしまったため、複雑な心境であった。結局、サン=サーンス「オルガン付き」は前述の渡辺達さんにお願いし、私は深井作品に専念することとなった。
その8年後の2007年、オーケストラ・ニッポニカで「パロディ的な4楽章」を取り上げた際には渡辺達さんが弾かれ、また時が流れて8年後の2015年、とうとう私にサン=サーンス「オルガン付き」を弾く機会が回ってきた。そして今回の「オルガン付き」をもって、晴れて「オケ中ピアノ」の主要作品はほとんど弾いたこととなり、感無量となった運びである。また記念すべきこのタイミングに維持会ニュースに執筆出来きたことは、望外の喜びでもある。
参考文献:『チャイコフスキー・コンクール : ピアニストが聴く現代』中村紘子著(中央公論社)
注釈:
注1:出典「演奏する側から見た『春の祭典』」松下俊行
http://www.shinkyo.com/concerts/i158-1.html
注2:第119回演奏会(ファリャ作品展)1998年4月3日
ヴィオラ弾きによるヴィオラのご紹介
維持会員の皆様、こんにちは。当団にてヴィオラを弾いております、村原大介と申します。この度、維持会ニュースに寄稿をというお話をいただき、軽い気持ちでお引き受けしたものの、どんなことが書かれているのか参考にと過去のニュースの投稿を見てみましたら、皆さん素晴らしい文章をお書きになっていて、えらいことを引き受けてしまったなと困惑している次第です。とはいえ、新響の団員の生の声をお届けできる貴重な機会ということで、拙い文章ではありますが、どうぞお付き合いの程お願い申し上げます。
■まずは自己紹介
私は、新響に2013年の1月に入団しました。まだ入団して2年ほどの新参者でありますが、私の父が新響のヴィオラ奏者であった関係で、親子二代でおよそ50年にわたり、新響のある生活を送っております。父は私が生まれる前から新響の団員であり、物心ついた頃から、毎週土曜日の夕方からは家には居ないことが当たり前でした。練習後の宴会で意気投合した10人くらいの団員の方と一緒に帰宅し、我が家で二次会が開かれたこともありました。また、合宿があった時には、母と子供は千葉の大原にあった祖父母の家に置いていき、一人で当時の合宿所があった茨城の鹿島まで車を走らせて合宿に参加し、合宿の後は祖父母の家までまた迎えに来るという、今考えても「良くやるなあ」と思わされる生活をしていました。そんな父の影響で、小さいころから新響の演奏会を聴きに行っていました。在りし日の伊福部昭氏とタクシーに同乗させていただいたこともありました。そして、いつの間にか自分もヴィオラを弾くようになっていました。
■ヴィオラという楽器について
さて、このヴィオラという楽器、ヴァイオリンやチェロのように子供用の楽器がある訳ではありません。世界的なヴィオラ奏者といえども、「3歳からヴィオラを始める」なんてプロフィールは見たことがありませんし、ヴァイオリン弾きには、「神童」と呼ばれる人がいますが、ヴィオラの「神童」なんて聞いたこともありません。音楽にさほど興味のない方は、ヴィオラという楽器の存在すら知らないということも少なくありません。また、ソロ楽器としてヴィオラを演奏する例は、アマチュアではほぼ聞きません。専ら、オーケストラや弦楽アンサンブルで、内声部を慎ましく弾いている楽器です。居ても居なくても分からないなどという意地悪を言われることもあります。しかし、ヴァイオリンにはない渋い響きや、大作曲家(個人的にはブラームスが一番です)の絶妙なヴィオラの使い方にはまると、その魅力から抜け出せなくなるのです…。
■ヴィオラ弾きについて
よく考えてみると、こんなにも地味な楽器を、どのようなきっかけで始めるのでしょうか。少なくとも、カッコいいから始めたという人は皆無でしょう…。私が出会ってきたヴィオラ奏者は、大きく分けて3つのパターンに分けられました。
一つ目は、幼少からヴァイオリンを習い、大きくなってヴィオラに転向するというパターン。基本的な奏法が既に身についていますから、遅れて始めてもモノになるのが早く、オーケストラのヴィオラパートとしては即戦力として期待できる存在です。転機は様々でしょうが、ヴァイオリンと比較してマイナーであるため天下を取りやすいと考える野心家もいるかも知れませんし、ヴィオラの渋い響きに魅了されて自分でも弾きたいと思って転向する例もあるでしょう。さらには、ヴァイオリンに挫折して転向を余儀なくされるという例もあるかも知れません。
かく言う私はこの「ヴァイオリン挫折組」に当たります。ヴァイオリンのレッスンに通っていた教室の弦楽合奏団で、私は同年代の仲間達が当たり前のように進んでいた最上級クラスの合奏団に入れる基準(モーツァルトの協奏曲を弾けなくてはなりませんでした)を満たしていませんでした。見るに見兼ねたある先生から、ヴィオラを弾くのであれば、その合奏団に入れてもらえるという話が出ました。ヴァイオリンが思うように弾けずに悩んでいた(今となっては大した悩みではないのかも知れませんが、両親や師匠の手前、当時は割と深刻な問題であったと記憶しています…)
私は、父のヴィオラが家にあるという理由だけでその話を受けることになりました。初めてヴィオラを持ち、弦楽アンサンブルの中で曲を弾いたときの感想は、「ヴァイオリンと比べて高い音や細かい音を弾かされない。しかもあまり目立たない。これは助かった!」というものでありました。当時の私には、数年の後にマーラーやリヒャルト・シュトラウスといった作曲家によって、そんな怠惰な思想が粉々に打ち砕かれるという運命を知る由もなかったのです…。とはいえ、合奏団にヴィオラ奏者がほとんど居なかったことも手伝い、様々な弦楽アンサンブルやクァルテットの曲を演奏する機会に恵まれました。ヴァイオリン奏者のままでは団のお荷物だったであろう私にとって、ヴィオラという楽器はまさに救世主のような存在だったのでした。
話が脱線してしまいました。二つ目は、学校の部活やサークルで初めてオケや弦楽アンサンブルをやろうとして、ヴィオラを始めるというパターンです。ヴァイオリンは腕利きの集まりで、楽器未経験の人にはややハードルが高いのですが、ヴィオラはどこも人数不足で、比較的難易度も高くはないことから、初心者の方が始めるにはちょうどよい楽器なのです。こうしてヴィオラを始めた人は、性格的にもおっとりとした癒し系の人が多く、ヴィオラパートの雰囲気づくりには、不可欠な存在です。
三つ目は、吹奏楽経験者が大学でオケに入ろうとするも、オーディションの壁にぶつかり、止む無くヴィオラに転向するというパターンです。オーケストラと吹奏楽では、管楽器の人数構成が全く違います。私の母校のオーケストラは、所謂名門と呼ばれる大学オケではありませんでした。それでも、演奏会の出番に偏りが生じないように管打楽器の定員は決まっており、定員を超えた応募のあるパートはオーディションが行われていました。不運にもオーディションに通らなかった人のうち、それでもオーケストラがやりたいという人の駆け込み寺的存在なのが、ヴィオラパートなのです。オーディションで蹴落とされたことに対する怨念によるものなのか、楽器初心者でありながらメキメキと頭角を現す人が多く、管楽器奏者時代に培われた、言わば「俺様力」を遺憾なく発揮し、パートを引っ張る存在になってくれます。しかし、中にはその過程で、発展途上な音を出してしまう自分が許せず、残念ながら楽器を辞めてしまうという例もあります。
これまでの例は、あくまでも私の体験でありますが、新響入団までに関わってきたいくつかのオーケストラでは、ほぼこの3パターンの人達の集まりだったといえます(一部主観があるかも知れませんが…)。
■おわりに
書き記してみると、始めるきっかけがこれほど多様な楽器というのは、珍しいのではないかと思います。しかし、私が今まで関わったどこのオケであっても、ヴィオラパートは穏やかな人が多く、雰囲気も和やかというのは共通です。他の楽器から転向した人達も、いつしかヴィオラの雰囲気に馴染んでいくようです。当団のヴィオラパートも、皆穏やかで(新響で唯一?)和やかな雰囲気の中で練習しております。ただ、ヴィオラパートのもう一つの宿命として、演奏者の絶対数の少なさのため、人数不足に陥りやすいということがあります。当団も例に漏れず、現在団員を大募集中です。維持会員の皆様におかれましても、オーケストラを探しているヴィオラ奏者がいましたら、ぜひご紹介いただければ大変幸いです。
今後とも、よりよい音楽を皆様にお届けできるよう、精進していきたいと思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
第228回ローテーション
| 第九 | ローマの謝肉祭 | 白鳥の湖 | サン=サーンス3番 | |
| フルート1st | 松下 | 吉田 | 兼子 | 松下 |
| 2nd | 牧 | 牧(+Picc) | 新井 | 岡田 |
| 3rd | 岡田(Picc.) | - | 藤井(Picc.) | 吉田(+Picc.) |
| オーボエ1st | 堀内 | 岩城 | 亀井 | 堀内 |
| 2nd | 岩城 | 桜井 | 山口 | 岩城 |
| コールアングレ | - | 堀内 | - | 山口 |
| クラリネット1st | 品田 | 品田 | 進藤 | 品田 |
| 2nd | 中島 | 石綿 | 末村 | 大藪 |
| バスクラリネット | - | - | - | 岩村 |
| ファゴット1st | 田川 | 藤原 | 田川 | 浦 |
| 2nd | 藤原 | 田川 | 浦 | 藤原 |
| コントラファゴット | 浦 | - | - | 田川 |
| ホルン1st | 箭田 | 大内 | 箭田 | 森 |
| 2nd | 山口 | 市川 | 森 | 大原 |
| 3rd | 鵜飼 | 大原 | 大内 | 鵜飼 |
| 4th | 大原 | 鵜飼 | 大原 | 市川 |
| トランペット1st | 野崎 | 北村 | 倉田 | 野崎 |
| 2nd | 小出 | 倉田 | 北村 | 小出 |
| 3rd | - | - | - | 倉田 |
| コルネット1st | - | 小出 | 小出 | - |
| コルネット2nd | - | 中川 | 中川 | - |
| トロンボーン1st | 武田 | 町谷 | 志村 | 武田 |
| 2nd | 志村 | 志村 | 武田 | 町谷 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | - | - | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 桑形 | 皆月 | 古関 | 桑形 |
| パーカッション | 大太鼓/古関 トライアングル/今尾 小太鼓/今尾 シンバル/中川 |
トライアングル/古関 シンバル/桜井 タンブリン/今尾 |
大太鼓・カスタネット/今尾 トライアングル・タムタム/桜井 シンバル/中川 小太鼓・タンブリン/皆月 |
シンバル/中川 大太鼓・トライアングル/今尾 |
| ピアノ | - | - | - | 藤井、井上* |
| ハープ | - | - | 山崎* | - |
| 1stヴァイオリン | 堀内(滑川) | 堀内(大隈) | 堀内(大隈) | 堀内(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(田川) | 小松(大島) | 小松(大島) | 小松(佐藤) |
| ヴィオラ | 柳澤(村原) | 村原(柳澤) | 村原(柳澤) | 柳澤(村原) |
| チェロ | 光野(柳部) | 光野(柳部) | 光野(柳部) | 柳部(光野) |
| コントラバス | 中野(植木) | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) |
(*)はエキストラ
第228回演奏会のご案内
今回は、ますます円熟味が増し説得力のあるタクトを振る山下一史を指揮に迎え、ロマンティックな名曲を演奏します。
■永遠の名作「白鳥の湖」
ロシアの大作曲家チャイコフスキーの作品の中でも、最も有名で愛好されているのがバレエ音楽「白鳥の湖」と言っても過言ではないでしょう。ドイツの童話を元に作られましたが、「ローエングリン」と同様に白鳥の化身が登場するなどワーグナーの影響を受けていると言われています。
お話は、ジークフリート王子が白鳥の住む湖で美しいオデット姫に会う。姫は悪魔に白鳥の姿に変えられ夜だけ人間の姿に戻るが、呪いを解くにはまだ女性を愛したことのない男性に愛を誓ってもらう必要がある。王子の婚約者を選ぶ舞踏会にオデット姫を招待するが、だまされて悪魔の娘オディール(黒鳥)を選んでしまう。悪魔を討つも呪いは解けず2人は命を絶つ―という悲劇です。現世で結ばれハッピーエンドという演出もあります。
今日ではバレエの代名詞のような存在となっている「白鳥の湖」ですが、初演は失敗で何回か上演されても評判にならず、お蔵入りになってしまいます。初演から16年後にチャイコフスキーが亡くなってマリンスキー劇場が追悼公演として上演し大成功を収め、世界中で歓迎される人気作品となりました。
作曲者自身が選んで演奏会用組曲を作りましたが、今回は組曲以外の魅力的な曲も加えてたっぷりと演奏します。
■サン=サーンス~オルガンとシンフォニーの融合
白鳥の登場する音楽で同じくらい有名なのは、サン=サーンスの「白鳥」でしょう。サン=サーンスはフランスの大作曲家ですが、「白鳥」の登場する「動物の謝肉祭」と同じ年に作曲された交響曲第3番は、彼のもっとも代表的な作品です。
当時フランスでは、舞台音楽は人気があっても交響曲など純器楽曲は重要視されていませんでした。そんな中、サン=サーンスは番号なしの物も含め5曲の交響曲を書き、古典主義的な作品を残しました。国民音楽協会を設立し、同時代のフランスの作品を演奏する活動をしていましたが、2歳でピアノを弾き3歳で作曲をした神童であったサン=サーンスは、モーツァルトやベートーヴェンに親しみ、シューマンやワーグナーを紹介するドイツびいきでもありました。
18歳で教会のオルガン奏者の職を得て、その後はパリの最高峰の教会オルガニストとして長年勤めていました。集大成ともいえる交響曲第3番では大胆にオルガンが使われています。ドイツロマン派のようなカチッとした重厚さの中に、新しい試みやフランス的エスプリも感じられる魅力的な作品です。東京芸術劇場のパイプオルガンの響きとともにお楽しみください。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
わがアマオケ放浪の記
当団でファゴットを吹いている野田と申します。当団には4回入団(非公認最多入団記録です)しています、と言っても意味が分からないと思いますが、転勤の多い会社で働いているので、転勤の度に退団し本社へ戻って来ては再入団する、の繰り返しで都合4回入団したと言うことです。新交響楽団は入団時にオーディションがあるのですが、かつて在籍していた者に既得権はなく、他の入団希望者と同様にオーディションを受けることになります。従って4回入団した自分は5回のオーディション(2回目の入団の時に再オーディションとなった為です)を受けています。
「マーラー8番を演奏するので新響に入らないか?なかなか2回は演奏できないぞ。」と大学の先輩から声を掛けられたのが当団に入団するきっかけでした。マーラー交響曲8番を2回って何?と思われるかもしれませんが、そうなんです。大学在学中に出身校が創立100周年を迎え、それを記念して大学のオーケストラと合唱団で故岩城宏之の指揮でマーラー交響曲第8番を演奏したのですが、新交響楽団でも故山田一雄とのマーラーシリーズが佳境を迎えていてマーラー交響曲第8番を演奏することになっており、新交響楽団に入団してこの演奏会に乗れば2回演奏できる訳だったのです。ご存知の通り「千人の交響曲」と言われるくらい大掛かりな曲ですので、滅多に演奏する機会はありません。「これは良い機会だ!」と思ったのは言うまでもありません。
当時は大学オーケストラの先輩も多く所属していたので馴染みやすいかなとも思い、当団への入団を決意すると、早速オーディション対策としてファゴットの巨匠である霧生吉秀先生のレッスンを受けに行きオーディション課題曲のレッスンを受けました。オーディション会場は新宿文化センターのリハーサル室。各パートのトップの方に囲まれた中でオーディション。何とか合格して、斯くして1986年に新交響楽団へ第1回目の入団を果たしました。そしてマーラー交響曲8番の演奏も無事に果たしたのです。
年4回行われる演奏会と年に数回行われた合宿に明け暮れ楽しく過ごした新響生活ですが、初めての転勤辞令でお別れとなってしまいました。行先は仙台。東京文化会館でのブラームス交響曲第1番の演奏を最後に退団し仙台へ異動。この時は未だ独身でしたので、ちょくちょく東京へ戻ってきては新響の練習を覗いて、エキストラとして参加したこともありした。仙台では地元のアマチュアオーケストラである仙台ニューフィルハーモニーへ入団し音楽活動を続けていました。4年間の仙台での任期を終え東京へ戻り、新響へ復帰すべく2度目のオーディションを受け、上記の通り再オーディションの結果2回目の入団を果たしました。
飯守泰次郎氏との『ワルキューレ』第1幕全曲、ブルックナー交響曲第8番、故小松一彦との映画誕生100年記念演奏会、と思い出に残る演奏会を経験した後、新交響楽団創立40周年記念シリーズで本日演奏するプロコフィエフ交響曲第5番をメインとする演奏会に向けた練習中に転勤辞令がでました。行先は福岡です。プロコフィエフは他の団員に代わって貰い、後ろ髪を引かれる思いで福岡へ行きました。福岡でもさっそく地元のアマチュアオーケストラである福岡市民オーケストラに入団して、ラプソディー・イン・ブルー、ベートーベン交響曲第7番やオペラ『蝶々夫人』等を演奏しました。そんな中、当時の新響ホルン吹きで福岡出身の方から新響と福岡市民オーケストラのジョイントコンサートを福岡で行ないたいとの申し出があり、早速福岡市民オーケストラの幹部にそれを伝え協議を開始。当初は演奏レベルが違いすぎるからジョイントコンサートは無理だ、と反対意見もありましたが、最終的にはオーケストラのステップアップには良い経験だ、との理由でジョイントコンサートを受けることを決定し、指揮者も福岡出身の井崎正浩氏に決め準備を進めていました。ところが、ジョイントコンサートの直前にロンドンへの転勤辞令を受取り、ジョイントコンサートに出演することなくロンドンへ旅立ちました。ジョイントコンサート後にロンドンへ福岡市民オーケストラのメンバーからメールがたくさん届きましたが、演奏の内容よりも演奏会後の宴会芸で新響に負けたことを悔しがるメールが殆どで大笑いしました。
イギリスはアマチュアオーケストラがとても多い国です。ロンドンにも多数ありますが、練習日がどのオーケストラも平日なので、会社が終わって家に戻り車で練習に行ける範囲にあるオーケストラを探し、最終的にBromley Symphony Orchestraへ入団しました。入団に際してオーディションはないのですが、イギリスでは国立音楽学校が認定する「グレード」があり、オーケストラの団員募集には「グレード8以上の人求む」とあります。さすがに今更グレードを取る訳にもいかないので、電話でオーケストラ経験を延々と述べ、練習で一緒に吹いてOKかどうか判断してくれと懇願したら、それでは次回の練習に来て下さいと言われ、申し出を断られずにほっとするようなドキドキするような不思議な気持ちで電話を切り、初の練習に臨みました。Bromley Symphony Orchestraは1年に4回演奏会を行ない10月から6月までを活動シーズンとしていましたので、新響より演奏会当たりの練習回数が少なく、その中で曲目を仕上げていくので彼らの腕はなかなかのものでした。初参加は確かバルトークの『管弦楽のための協奏曲』の練習だったと思いますが、大学の時に吹いたことがある曲でしたので何とかこなして入団と相成りました。
Bromley Symphony Orchestraはイギリス人作曲家の曲を多く取り上げて演奏しましたので、日本ではなかなか演奏する機会の無い曲に触れることができ本当にいい経験でした。また、エルガー交響曲第1番を演奏した時などはオーケストラがあまりにもしっくり演奏するので思わず鳥肌が立ってしまい、以来この曲が大好きな曲の一つになっています。依頼演奏会で演奏したティペットのオラトリオ『われらが時代の子(A Child of Our Time)』はセカンド・ファゴットの担当でしたが、セカンドにソロがある曲があり、オーケストラのメンバーから温かい(?)目線を浴びたのもいい経験でした。
当然のことながらオーケストラの練習指導は英語です。どこの国でも同じですが、指揮者が合奏を途中で止めてやおらオーケストラに指示を出します。この英語は何とか分かるのですが、たまにジョークを交えるので、そうなるとお手上げです。周りの楽団員が笑って聞いている時も、はてなマークを顔面一杯にしつつ、次の合奏がどこから始まるのかだけを聞き逃さないように耳を集中していたものです。ファゴットの仲間が「合奏がどこから始まるかよく分かるね。隣のイタリア人は落ちてばかりだけどね。」と感心してくれたこともあり、その時は努力が報われた感じでした。楽しかったロンドン生活も4年間の勤務を終え東京へ戻り、新響へ復帰すべく4度目のオーディションを受け、3回目の入団を果たしました。
3回目の入団時は子供が小中学生で何かと手が掛かる頃でした。小学校の親の会に出席したり、学校を清掃したり、子供のピアノ発表会に出演したりなどで催し物が増え、毎週土曜日に新響に出ることが段々と難しくなり、残念ながら1年足らずで退団を決意しました。それからほどなくして大阪へ転勤辞令が出て、家族で大阪へ引っ越すことになりました。大阪では住まいを神戸にしたので、当地では神戸市民交響楽団に入団。関西には新響の姉妹オーケストラ(?)である芦屋交響楽団があるのですが、諸事情により神戸市民交響楽団を選ぶことになりました。
大阪から本社への転勤辞令が出たのは大阪へ転勤して1年後。家族は神戸での生活が落ち着き始めたばかりでしたので、やむを得ず一人で東京へ逆単身。この時に新響へ復帰出来るチャンスもあったのですが、さすがに週末は神戸の家族に会いに行くため断念しました。そうこうしている内に家族を東京へ引き纏めることになったのですが、ほぼ同時期にロンドンへ転勤辞令。なかなか落ち着かせて貰えません。2回目のロンドン駐在ではオーケストラ活動をしなかったのですが、その代わりにオーケストラやオペラの演奏会には数多く行きました。ロンドンの著名オーケストラの演奏会は£10~£35程度(今の為替ですと約1,800円~約6,300円)で聴けますので、回数を気にせずに行くことが出来ます。お勧めはバービカンホールをホームとするロンドン交響楽団。個人の力量も高く、また素晴らしいアンサンブルを披露してくれるオーケストラです。その他、ご存知の通りロンドンフィルハーモニー、フィルハーモニア、BBC交響楽団と素晴らしいオーケストラ揃いですので飽きることなく駐在期間を過ごしました。
2年のロンドン駐在を終え日本に戻ってきたのが昨年の6月。帰国した翌週に梅雨が明け、一気に猛暑が日本列島を襲い、ロンドンの穏やかな気温ですっかり毛穴が閉じていた自分にはとてもきつい夏の始まりでした。そんな中、新響の仲間から練習を聴きに来ないか?と言われ、池袋の芸術劇場リハーサル室へ見学に行きました。前回退団してから10年が経っていましたが、久々に新響のメンバーに会って、何とも言えない懐かしさがこみ上げて来たのと、パワーアップした新響を聴いて再入団したいなと思うようになり、新響のエキストラもしながら5回目のオーディションを受け4度目の入団を果たし、今に至っています。今回の演奏会は因縁なのでしょうか、プロコフィエフ交響曲5番を吹かせて頂いております。
これから数年後に転勤辞令を貰うかもしれません。多分あるでしょう。その時は今まで通り退団して、東京に戻ってきたら再入団したいものだと思う今日この頃です。
余談ですが、当団の練習で使う団員出欠表は入団順に名前が連なっていますので、いつになっても自分の名前はファゴットの一番下です。
新交響楽団第227回演奏会(2014.10.26)維持会ニュース
ル・ベルヴェデールの響き
「パリから少なくとも30kmくらい離れた辺りに小さな家を探して戴けませんか?」音楽学者ジャン・マルノールの娘ジュヌヴィエーヴに宛てた1通の手紙からドラマは始まった。パリ北西郊外のルヴァロワや凱旋門近くのアパルトマンを点々としていたラヴェルは、叔父の遺産を相続して、パリの喧騒から逃れ孤独になれる近郊で、しかも望む時には友人達を呼び寄せられる範囲内に住みたいと思ったのだ。いささか身勝手なこの希望は、誰でも心の内に秘めている想いだろう。親しい友情の中にも、いくばくかの煩わしさが含まれているのは事実だ。
孤高の人かと思えば友人達と冗談を飛ばし合うのが好きな淋しがり屋、心根は優しく思いやりがあるのに表面的にはクール、脆弱な身体だが強情で決闘も辞さない熱血漢、プライドが高く楽観的でいて執念深くいつまでも思い悩み、几帳面で神経質ながら日常的な事にはルーズで無秩序といった矛盾や葛藤を抱える心情は珍らしくないかも知れないが、ラヴェルの場合は相反の振幅が大きかった。それは5回もローマ大賞に落選し、不正ではないかと疑問視された判定を繞ってパリ音楽院長が辞任に追い込まれたスキャンダルと、後年その反動かと言われたレジョン・ドヌール叙勲を彼が拒絶したスキャンダル、いわゆる二つのラヴェル事件にも現われている。
家探しを依頼した頃、彼は心身ともに疲労とストレスの極限に達していた。一つは1917年1月に最愛の母が他界した事。もう一つは1914年8月に勃発した第一次大戦である。20歳の時にヘルニアと虚弱体質で兵役免除されていたにもかかわらず、愛国心と機械好きの性格から空軍を志願したが、結局陸軍で軍用トラック運転手の任務に就いた。近代科学戦の嚆矢となった第一次大戦は、かつて人類が体験したことのない苛酷な戦いで、ラヴェルもヴェルダンの近くに於て、何度か命を落としそうになった。
連合国の反対を押し切って参戦し、独領だった青島(チンタオ)を攻略した程度の日本からは想像出来ないが、国中を戦場と化し、社会・思想・文化の変革とその痛みをヨーロッパ諸国にもたらした第1次大戦の痕跡は現在も顕著で、国連やユーロの萌芽となったのだ。大戦直前の1913年に〈春の祭典〉をシャンゼリゼ劇場で初演して怒号と罵声に包まれたストラヴィンスキーは、1918年11月11日午前11時に調印された休戦協定を祝って、同日朝に〈11楽器のためのラグタイム〉を書き上げた。終戦に伴う「祭りの日の朝」の様な楽天的気分は、戦前の印象主義・原始主義・神秘主義・表現主義を消滅させ、率直な作風や明快な協和音と節度のある形式美に衆人の目を向けさせた。この1918年にドビュッシーが56歳の生涯を閉じ、新古典主義への出発点となった〈兵士の物語〉がローザンヌで初演された事実は、新しい時代の到来を象徴している。アメリカから戻ったプロコフィエフがパリに住み、交響曲2番・3番や〈道化師〉の初演をパリで行なったのもこの頃だ。
ジュヌヴィエーヴが見つけたのは1907年に建てられた粗末な家。しかしラヴェルは、見晴らし台という意味の屋号〈ル・ベルヴェデール(Le Belvédère)〉にふさわしいバルコニーからの美しい眺めに魅せられた。イル・ドゥ・フランスの柔らかな日差しの下、地平線まで続くランブイエの森が濃緑に輝きながら広々と開けた空に接している風景は、どの部屋からも見渡せられる。彼は1921年4月16日に登記し、5月から住み始めて、1927年まで趣味に合わせて内装を徐々に整えていった。
場所はイヴリーヌ県のモンフォール=ラモリ(Montfort-l’Amaury)。パリの南西、ブーローニュの森からヴェルサイユを経由して45kmの地点。麦畑と牧草地に囲まれた185mの丘にある小さな村で、当時の人口は1500人足らず、現在でも3500人がひっそりと暮らしている。
ラヴェル自ら描いた幾何学模様の壁紙は黒、白と灰色を基調とし、161cmの小柄な体型に合わせた狭い廊下のつき当りに音楽室がある。母親の肖像画が見下ろすエラール社のグランドピアノは1909年製。タッチが軽く、クリスタルのように透明でやや硬質な響きは、音の立ち上がりが速いクリアな輪郭だ。食堂の家具の上には、ぜんまい仕掛けでさえずる小鳥や日本の版画、象牙の小箱等所狭しと並べられて〈子供と魔法〉の舞台さながら。サロンの棚は忍者屋敷のようなどんでん返しの戸になっていて、裏に隠し部屋がある。3匹のシャム猫と過ごした家の雰囲気はモンフォールへ移る前に書かれた〈マ・メール・ロワ〉の童話世界を髣髴とさせるし、椅子の背にラヴェルが描いたフルートを吹くギリシア風の少女からは〈ダフニスとクロエ〉のフルート・ソロが聞こえる。
1932年パリでタクシーに乗ったラヴェルは衝突事故に巻き込まれ、翌年後遺症とも思われる運動失調症と失語症に悩まされ始めた。1937年12月、パリのクリニック・ボワローに入院して萎縮した脳の手術を受ける。手術そのものは成功したと伝わるが、9日後の12月28日朝、62年間刻み続けたリズムに終止符が打たれた。
終の栖は、後年ラヴェル記念館となって公開され現在に至る。その管理人を1954年から70年まで務めたのは、家政婦としてプルーストの最期を看取ったセレスト・アルバレであった。1997年には修繕費用捻出のためのチャリティ・コンサートをラヴェル協会から要請されて足繁く通った。ラヴェルが息を引き取ったクリニックがあったボワロー通りは、私のアパルトマンから歩いて2分の距離。モンフォールから我が家に戻る時は、ラヴェル最後の道行きをいつも想い浮かべないではいられなかった。
プロコフィエフ:交響曲第5番変ロ長調
新天地を求めて
その作曲家にとって、作品番号100となる交響曲は非常に重要な意味を持っていた。時は第二次世界大戦末期。彼の祖国は、ナチス・ドイツを相手に熾烈な戦闘を続けている。「誰もが祖国のために全力を尽くして戦っている時、自分も何か偉大な仕事に取り組まなければならないと感じた」と本人が回想しているように、祖国愛に駆り立てられ、意欲的に作曲に取り組んだ。もちろん、100という節目となる数字も、その意気込みを後押ししたことは想像に難くない。
作曲家の名前は、セルゲイ・セルゲーヴィチ・プロコフィエフ。その代表作の一つである交響曲第5番について詳しく述べる前に、それまでの彼の足跡をたどってみたい。
彼は1891年4月、旧ロシア帝国のウクライナ(現在は独立国)南部に生を享けた。幼少よりピアノに親しみ、作曲では驚くべき神童ぶりを発揮。13歳でペテルブルク音楽院に入学する。卒業後は、気鋭の作曲家・ピアニストとして頭角を現していくが、ロシア革命前後から、彼を取り巻く環境に変化が生じる。
旅行で訪れたヨーロッパでは、ロシア・バレエ団を率いるセルゲイ・ディアギレフに出会い、才能を認められ、作曲を依頼された。西欧でも自分の力が認められるという手応えを掴んだのである。そして、1917年にロシア革命が勃発。政治混乱の中では思うような作曲活動ができないと考えたプロコフィエフは、アメリカに渡ることを決意する。当時ヨーロッパは、まだ第一次世界大戦の戦火の中にあり、安全に活動ができるアメリカが彼の新しい天地となったのである。「当時のロシアでは音楽など無用のものだったが、アメリカに行けば学ぶことも多いだろうし、同時に人々が私の音楽に興味を持つだろうと信じていた」と彼は語る。
こうして、翌1918年5月、アメリカへ向けて出発。当初その渡航は亡命というような大袈裟なものではなく、本人は2~3ヶ月で帰国するつもりだったというが、実際に祖国への本格的な帰還を果たすのは、17年後のこととなる。
ニューヨークからパリへ
プロコフィエフは、ニューヨークを拠点に音楽活動を行い、その間、ピアノ協奏曲第3番や歌劇「三つのオレンジへの恋」といった名曲を生み出しているが、アメリカ国内での評価は必ずしも芳しいものではなかったようだ。そして1922年、本格的な活動の拠点をヨーロッパに求めることを決断する。それまでも度々仕事でパリやロンドンを訪れており、作品も高く評価されていたので、それは自然な成り行きだったのだろう。1922年3月から約1年半を南ドイツのエッタールという風光明媚な山村で過ごし、1923年10月、いよいよパリに拠点を移すことになる。
その頃のパリは、まさに芸術の最高峰が集う、世界における文化の中心地。ここでプロコフィエフは、以前から親交のあったディアギレフのロシア・バレエ団との仕事に力を入れる。当時のロシア・バレエ団は、作曲にストラヴィンスキーやラヴェル、美術には画家のピカソやマティス、ルオー、衣装デザイナーのココ・シャネル、台本はジャン・コクトーが受け持つという、驚くべき“オールスター軍団”。プロコフィエフは、そこで「鋼鉄の歩み」や「放蕩息子」といったバレエ音楽を作曲し、絶対君主であったディアギレフから“私の二番目の息子”と可愛がられた。ちなみに、一番目の息子はストラヴィンスキーである。
ラヴェルとプロコフィエフ
このように、パリでの音楽活動は、非常に刺激に満ちて充実したものであったが、ここで本日の演奏会の前半を飾る作曲家、ラヴェルとの接点に少し触れてみたい。
二人の出会いは、プロコフィエフがパリに活動拠点を移す前の1920年。パリで催されたある音楽会で、彼は小柄なロマンスグレーの紳士を紹介された。すでにフランス楽壇の重鎮であったモーリス・ラヴェルである。出会いを光栄に思ったプロコフィエフは、最大の尊敬を込めてラヴェルの手を握ろうとしたが、ラヴェルは驚いて手を引っ込めてしまう。そのシャイな作曲家は、過剰に敬われることが大嫌いだったのである。
その後二人が特別な親交を結んだという記録はないが、後年プロコフィエフは、ラヴェルの訃報に接し、彼に対する思いを綴っている。「いま電報がラヴェルの死の悲しい知らせを運んできた。世界は時代の最も偉大な作曲家の一人を失った」とその手記は始まり、「戦争直後のフランスの若い音楽家たち…オネゲル、ミヨー、プーランク、そして他の数人…が『ラヴェルの音楽はもう時代遅れで、新しい作曲家と新しい音楽言語が舞台に現れた』と宣言したことがあった。年月が過ぎ、新しい作曲家たちはフランス楽壇でそれぞれにポジションを得たが、ラヴェルはいまだに重要なフランス人作曲家の一人であり、今の時代で最も優れた音楽家の一人であり続けている」と結んでいる。
ラヴェルは、「作曲家は創作に際して個人と国民意識、つまり民族性の両方を意識する必要がある」という考え方を持っており、この点は音楽に民族性を強く打ち出したプロコフィエフとの大きな共通点であろう。
ふたたび祖国へ
1920年代後半になると、プロコフィエフはソビエト連邦と名前を変えた祖国を度々訪れ、作品も高い評価を得るようになっていた。その手応えもあり、これまでに培った作曲技術や音楽経験、最先端芸術のエッセンスを祖国の人々のために生かす時が来たのではないか、と考えるようになった。
その思いを後押ししたのがセルゲイ・ラフマニノフの言葉だったといわれる。たまたま大西洋横断航路で同じ船に乗り合わせたラフマニノフは、彼にしみじみと語ったという。「私は再び祖国の地を踏むことはないだろう。私や私の音楽は、ソビエトでは誰も必要としまい。いま帰ったところで『何者か?』と問われるだけだ。もう、若者に道をあける番だ。私は、あの世で若い頃の過ちを後悔することになるだろう」。祖国から求められている時に、そして祖国に貢献できるうちに帰国すべきではないか、とプロコフィエフは強く思うようになったのである。
こうして、パリとモスクワを行き来する生活に終止符を打ち、1935年、44歳になったプロコフィエフは、家族を連れてモスクワへ正式に活動の拠点を移した。
祖国への帰還後も彼は意欲的な作曲活動を続け、1936年には、最高傑作ともいえるバレエ音楽「ロミオとジュリエット」や、数ある作品の中で最もよく知られている「ピーターと狼」を完成。1939年には、カンタータ「アレクサンドル・ネフスキー」を世に送り出すなど、作曲家としての充実期を迎えた。
自由で幸福な人間への讃歌
そのような時期の集大成ともいえる曲が、交響曲第5番である。彼の意気込みは冒頭に記した通りであるが、この曲の特徴は、高度な作曲技法を駆使し、溢れんばかりの多彩なモチーフが縦横無尽に展開されることと同時に、曲に祖国の人々への思いが込められていることだろう。このナショナリズムは、当時のソビエト政府から強要されたものではなく、彼の心の中から自然に湧き出てきたものだった。彼自身も手記の中で次のように述べている。
「私の第5交響曲は、自由で幸せな人間、その大きな力、その純粋で高貴な魂への讃歌の意味を持っている。だが、私は意識してこのテーマを選んだとは言えない。それは私の中に生まれ、表現されることを強く要求していたのである。音楽は私の中で熟し、ついには魂を溢れさせるものとなった」。この曲を聴いて、どこかメカニカルな印象を持たれる方は多いかもしれないが、盛り込まれているのは至ってヒューマンなテーマなのである。
彼は永遠に勝利したのか
交響曲第5番は1944年に、わずか2ヶ月間で作曲され、翌1945年1月13日にモスクワ音楽院の大ホールにおいて、本人の指揮によって初演された。その演奏会は、20発の祝砲が鳴り渡った直後に開始され、ソ連全域にラジオ中継されるという、国民的記念行事の感を呈するものだった。
後に世界で最も優れたピアニストの一人となるスヴャトスラフ・リヒテルは、この演奏会に立ち会った印象を回想している。「この交響曲の中で、彼は自分の才能のすべてを出していた。それと同時に、そこには時間と歴史、戦争、愛国主義、それらすべての勝利とプロコフィエフ自身の勝利があった。彼は以前から常に勝利していたが、ここにおいて芸術家として永遠に勝利したのだ」。勝利という言葉を繰り返す手放しの称賛であるが、その言葉からは29歳のリヒテルの感動と興奮が伝わってくる。
このように、第5交響曲は大きな拍手をもって世に迎えられたが、初演直後の1月末に彼は階段から転落して後頭部を強打。意識不明のまま病院に搬送されるという不幸に見舞われている。退院後は以前と同じように作曲活動を続けるが、次第に病気がちになり、1949年の夏以降は、1日30分しか作曲活動が許可されないような病状に陥ってしまう。しかし、限られた時間の中でも作曲をやめることはなく、1953年3月に61歳で没する直前まで、その意欲は衰えなかったという。
リヒテルが称えたように、彼は永遠に勝利したのだろうか。それは、彼が生み出した数多くの作品が、いま世界中のオーケストラやソリスト、バレエ団、歌劇場などの重要なレパートリーを占めていることから客観的に肯定できるだろう。しかし、彼は自分自身の勝利は望んでいなかったのかもしれない。最後にもう一度、彼の手記を引用して終わりたい。
「作曲家は詩人や彫刻家、画家とまったく同じように、人間、人類に仕える義務がある。人間の生活を美しくし、そして守らねばならない。それには、まず作曲家自身がよき市民でなければならない。そうすれば、自ずとその芸術は人々の生活を称え、人々を輝かしい未来に導くだろう。それが芸術の不変の掟だと私は思う」。
■第1楽章
アンダンテ、ソナタ形式。フルートとファゴットが奏でる緩やかな旋律(譜例1)で曲は始まる。この第1主題はヴァイオリンに歌い継がれ、オーケストラ全体を支配する。低音部の新たな楽想を交えて曲は展開し、フルートとオーボエによる、やや速度を上げた第2主題が始まる。その後、展開部では多数の楽想が対位法的に巧みに組み合わされる。そして、金管楽器を主体に第1主題が壮大に回想され、重々しく終わる。
■第2楽章
アレグロ・マルカートのスケルツォ的楽章。ヴァイオリンの刻みに乗ってクラリネットが軽妙な主題(譜例2)を演奏する。中間部では、ヴィオラとクラリネットが期待感に満ちた旋律を奏で、それに他の木管楽器が加わって、展開しながら盛り上がりを見せる。その後、トランペットがスタッカートを引きずるように演奏する主題の変奏を経て、曲はテンションを上げ、断ち切られるように終わる。
■第3楽章
透明な美しさをたたえたアダージョ。弦の分散和音進行を背景に、クラリネット、フルートとファゴット、ヴァイオリンと、叙情的な旋律が受け継がれていく。特にヴァイオリンの高音部などは、『ロミオとジュリエット』によく似た清澄さを醸し出している。途中、葬送行進曲を思わせる部分や、凶暴さをも感じさせる強奏部を経て、冒頭の主題が戻り、静かに閉じる。
■第4楽章
アレグロ・ジョコーソ。フルートとファゴットによる楽句で導入部が始まり、チェロが第1楽章の第1主題を朗々と回想した後、クラリネットが浮き立つようなメロディ(譜例3)を歌う主部に移る。中間部では、低音弦楽器がコラール風の荘重な主題(譜例4)を奏で始め、それがフーガのように金管楽器などに展開される。その後、長大なコーダとなり、緊張感をもって盛り上がりを見せた後、突然弦楽器がソロの集団となる。そして、最後の小節で全奏となって、華々しく曲を閉じる。
初演:1945年1月13日 モスクワ音楽院大ホールにて、作曲者自身の指揮による
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、小クラリネット、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トライアングル、シンバル、タンブリン、ウッドブロック、小太鼓、大太鼓、タムタム、ピアノ、ハープ、弦五部
参考文献
『プロコフィエフ自伝/随想集』(音楽之友社)
『プロコフィエフその作品と生涯』サフキーナ著(新読書社)
『プロコフィエフ音楽はだれのために?』ひのまどか著(リブリオ出版)
『作曲家別名曲解説ライブラリープロコフィエフ』(音楽之友社)
ラヴェル:管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」
本日会場にいらっしゃる方のほとんどが「なんとなく」このワルツの一部分は耳にしたことがあるのではないだろうか。私のウィンナ・ワルツのイメージは、豪華で煌びやかなドレスを身にまとったセレブリティな貴族女性と、黒いタキシード(中はフリフリレースの白シャツ)で決めた紳士的な男性がパーティーで優雅に踊る姿。「ベルサイユの薔薇」そして「オルフェウスの窓」の社交界。しかしこの「ラ・ヴァルス」を初めて聴いたときの複雑な感情は忘れられない。
「ラ・ヴァルス」とウィンナ・ワルツ
英語で「ザ・ワルツ」。このネーミングセンス。管弦楽版の初演は1920年12月だが、これがもし100年前だったら、ウィンナ・ワルツの創始者である2人(ワルツの父、ヨハン・シュトラウス1世とダンス音楽団の団長ヨーゼフ・ランナー)のワルツ合戦に、フランスから「俺の作品こそが正真正銘のワルツだ!」とケンカを売っているようなタイトルと受け取られたかもしれない。
このシュトラウス1世の息子、ワルツの王、ヨハン・シュトラウス2世は父の後を継ぎウィンナ・ワルツの様式を完成させ、黄金時代を築いた。しかしその後は徐々に下火となっていき、ウィンナ・ワルツに象徴される宮廷舞曲や王侯貴族や富裕層を中心とした舞踏会そのものが社会の変革に合わせて徐々に表舞台から退いていかざるを得なくなった。
R.シュトラウスの「ばらの騎士」、プロコフィエフの「シンデレラ」や「戦争と平和」など、20世紀になってから書かれた名作におけるワルツは、いずれも作品の時代設定に合わせて過去に遡るための「音によるタイム・マシーン」になっており、「ラ・ヴァルス」もそうした中の1つである。
「ラ・ヴァルス」(1920年)の構想は「スペイン狂詩曲」(1908年)以前にさかのぼる。ラヴェルは1906年以来ずっと「ウィーン」という題名の交響作品のアイディアをあたためていた。しかしハプスブルク家の皇位継承者である皇太子暗殺がきっかけで第一次世界大戦が勃発し、終戦によってハプスブルグ王朝が終焉を迎えることとなる。そのため、当時曲が予定通りに完成していたとしても、「ウィーン」という標題で発表することははばかられたであろう。
ディアギレフによる依頼
まだ大戦中の1917年に、ロシア・バレエ団の主宰者ディアギレフ(「ダフニスとクロエ」も彼の委嘱)がラヴェルにバレエ曲の作曲を持ちかけた。そこに交響詩「ウィーン」の素材がどの程度使われたかは不明だが、同年1月に母を亡くしていたラヴェルは作曲が手につかず、結局新しいバレエ曲は1919-1920年に書き上げられた。しかし「天才を発見する天才」と称されていたディアギレフは、既に作曲家に対して絶対的な判定者として振る舞うようになっていた。ラヴェル自身の演奏によるこの曲の2台ピアノ版を聴いたディアギレフが「舞踏に向いていない」という理由で受理しなかったために、両者の仲は決裂したと言われている(真相は不明。だがラヴェルは後に自伝で「絶対に舞踊曲のつもりだった」と反論している)。
ディアギレフの言い分はある意味でもっともであるし、何よりも2台ピアノの演奏からこの音楽の本当の姿を想像することは難しかったであろう。後の「ボレロ」(1928年)でも明らかなように、ラヴェルには1つのプロットに徹底して拘る異様なほどの職人気質が潜んでいる。もしディアギレフが、ラヴェル一流の色彩溢れる管弦楽法で書かれた「ラ・ヴァルス」のオーケストラ版の演奏を最初に聴いていれば、この曲がどんな作曲家のそれよりも絢爛豪華に、ひたすら1曲の『ワルツ』をイルミネイトしていることが分かったのではないだろうか。稀代の興行師ディアギレフには「バレエに不向きな曲」という感想を持たれてしまったこの曲のバレエとしての初演は、1929年にイダ・ルビンシュタイン夫人の舞踊団によって行われている。彼女こそは「ボレロ」の委嘱・初演者に他ならない。
曲について
第一次世界大戦(1914-1918年)の終戦後に初演されたこの曲のスコアの冒頭には、
「渦を巻いている雲の切れ間から、ワルツを踊っている多くのカップルが見え隠れする。だんだん雲が晴れてゆき、Aのところでくるくると旋回しながら踊っている大勢の人で賑わう巨大なホールが見えてくる。舞台は次第に明るくなり、Bのフォルティッシモでシャンデリアの光が燐然と響きわたる。1855年頃の王宮である。」
とあり、A・Bも小節番号と同様にスコア上に書かれている(譜例1、2)。
ラヴェルは「私はこの作品を、ウィンナ・ワルツの一種の神格化として構想した。私の心の中でこの神格化は、幻想的で宿命的な旋回の印象と結びついている」と述べている。序盤こそ煌く舞踏会のワルツの体でありながら、徐々に様子がおかしくなり、最終的には完全に崩壊するこの曲は、ウィンナ・ワルツの優雅さよりも、破壊へと突き進む痛ましさが全体の印象として際立っている。そこには、第一次世界大戦と最愛の母の死による精神的打撃の深さを認めることもできるであろう。さらに言えば、この破壊にとり憑かれたような音楽からは、意識の深部に抑圧された自己破壊、自己否定の欲望というものを感じとることもできるのではないだろうか。音楽評論家である塚田れい子によれば、
「古き良き時代の陽気なウィンナ・ワルツは、もはやここにはない。甘やかなワルツはすでにノスタルジアの世界に閉じ込められていて、混沌の中からやっと姿を現したワルツは高揚のなかでカタストロフを迎え、宿命的に歪められたその姿はもう戻ることはない。」
とある。ワルツを踊ること、それは幸福であろうし、享楽である。しかしこのワルツは、もっと言えばこの曲の中で踊っている人々は、自ら踊っているのか、それとも踊らなければならないような状況なのか。揺れては立て直し、何度崩壊しそうになってもワルツを踊る人々。不安気であり、少し異常である。それはラヴェルの感じていた精神的な不安や恐怖、そして異常である。それは「ボレロ」「古風なメヌエット」等の作品でも垣間見える。ラヴェルの最も黒く、それ故に人々を惹きつける部分であろう。
「ラ・ヴァルス」は、一貫して3/4拍子で書かれているが、拍節感(メトリーク)の変化やヘミオラ(注1、譜例3、4)を効果的に組み合わせることによって、生半可な変拍子の曲よりも、よっぽどリズム的な変化に富んでいる。
曲は「序奏付きのワルツ」という定型で書かれている。まず序奏部には、遠景から聞こえてくるような神秘的なコントラバスの霧の中から、後で用いられる動機の幾つか(譜例5、6)が断片的にちりばめられている。
弱音器付のヴィオラによって第1ワルツ(譜例7)に入ってからは、第2ワルツ(譜例8)→第3ワルツ(譜例9)というように型どおりに進んでいくが、弦のポルタメントがいかにも爛熟した宮廷文化末期といった感じの甘美な歌を奏でるあたりがラヴェルらしいところだろう。
ラヴェルは戦争によって失われた古き良き時代に思いを寄せながら、ウィンナ・ワルツへの陶酔と共に、そこに渦巻く虚無感や絶望感を表現しようとしたのかもしれない。2台のハープを駆使したシャンデリア風の輝きや、打楽器の豪胆な一撃(実際に踊られるワルツでは、ここまで刺激的な炸裂は考えられないであろう)、何かに憑かれたような音の渦巻きは強烈な印象を残す。破壊へ向かって突き進み、最後はワルツの崩壊を暗示するような圧倒的なクライマックスで結ばれる。
[注記]
注1:リズム用語。本来2分割されるべきものを3分割すること。主に3拍子の曲で、2小節をまとめてそれを3つの拍にわけ、大きな3拍子のようにすること。
管弦楽版初演:1920年12月12日、カミーユ・シュヴィヤール指揮、ラムルー管弦楽団による
楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、タンブリン、トライアングル、シンバル、カスタネット、クロタル(アンティク・シンバル)、タムタム、グロッケンシュピール、ハープ2、弦五部
参考文献
『ポケットスコアラ・ヴァルス』(日本楽譜出版社)
『演奏法の基礎レッスンに役立つ楽譜の読み方』大村哲哉著(春秋社)
『ポケット音楽辞典』(音楽之友社)
[CD]「Ravel」ボストン交響楽団、ベルナルト・ハイティンク指揮(岡本稔)
[CD]「RAVEL:TZIGANE・SHEHERAZADE」ロンドン交響楽団、クラウディオ・アバド指揮(塚田れい子)
「ラヴェル(1875~1937)管弦楽のための舞踏詩〈ラ・ヴァルス〉」金子建志(千葉フィルハーモニー管弦楽団
演奏会用プログラムノートより)「ラヴェルラ・ヴァルス:ワルツと、ワルツを踊るもの」
Bokuno Ongaku
http://bokunoongaku.minibird.jp/?p=549/
ラヴェル:組曲「マ・メール・ロワ」
マ・メール・ロワは、5曲からなる組曲で、17-18世紀の作家の童話を下敷きに子供向けの4手のピアノ連弾組曲として作曲された。最初の2曲、「眠りの森の美女」「おやゆび小僧」はシャルル・ぺロー(1628-1703)の童話集『マ・メール・ロワ(マザー・グース)』から、「パゴダの女王レドロネット」はドーノワ夫人(1650?-1705)の『緑のヘビ』から、「美女と野獣」はボーモン夫人(1711-1780)の童話集『子供の雑誌』から採られた。最後の「妖精の園」はラヴェルの創作である。
このピアノ連弾組曲は、子供が演奏し親しみやすいように、形式を単純にしつつも表現を洗練させた作品となっており、ラヴェルが懇意にしていたゴデブスキー家の2人の子供、ジャンとミミーに献呈された。その約30年後にミミーは以下のように書いている。
「女王レドロネットや美女と野獣、そして私のために創作してくれたかわいそうなねずみの冒険といった、わくわくするような物語をラヴェルは私を膝の上に乗せてよく聞かせてくれました。そんな彼のことを私は大好きでした。彼は私と兄のジャンのためにマ・メール・ロワを作曲してくれましたが、私も兄もそのありがたみがわかる年齢でもなく、むしろこれを演奏するのは大変だなと思っていました。ラヴェルはこの曲の初演を私たちに望んでピアノのレッスンをしてくれましたが、私は聴衆の面前で演奏することを考えるだけで体がこわばってしまいました。」
結局、初演はパリ国立高等音楽院の学生であった11歳のジャンヌ・ルルーと14歳のジュヌヴィエーヴ・デュロニーに委ねられた(なお、ジャンヌ・ルルーはパリ国立高等音楽院の教授となった)。
本日演奏するのは、このピアノ連弾組曲が作者自身によって管弦楽化されたものである。管弦楽化にあたって音の増強がほとんどなく、原曲に大変忠実な編曲となっている。ピアノ連弾組曲との聞き比べも興味深い(ピアノ連弾組曲には、アルゲリッチとプレトニョフによる演奏がある)。
そもそも作曲は、その音楽にもっとも適した楽器のために行われるものであり、作者自身によって編曲が行われることは珍しい。編曲は、人気のある旋律を別の楽器によって演奏するために、作曲者以外によって行われるのが一般的である。ところがラヴェルの作品には「古風なメヌエット」、「亡き王女のためのパヴァーヌ」、そして「道化師の朝の歌」など、ピアノ曲を管弦楽曲に自身の手で編曲したものが少なくない。
編曲によって原曲から大きく変化するものは音色である。音楽の本質が音色と響きに緊密に結びついている場合、編曲は難しく、原曲の良さが失われかねない。一方で、音色と響きが副次的な役割を果たし、音楽が旋律線と構造によって保たれている場合には、編曲による影響は少ない。ラヴェルの音楽は後者の性質を持っていると考えられる。
なお「前奏曲」、「紡ぎ車の踊りと情景(Dance durouet e scéne)」、「間奏曲」を加えたバレエ版も作者によって編曲されている。
■眠りの森の美女のパヴァーヌ
(Pavane de la Belle au Bois dormant)
イ短調、遅く、4/4拍子
わずか20小節の小曲。全音階を基調とした美しいメロディをフルートが奏でる(譜例1)。
■おやゆび小僧
(Petit Poucet)
ハ短調、ごく中庸な速度で
きこりの7人の子供たちが、森に捨てられ途方にくれる様子が描かれている。頻繁に変化する拍子が子供たちが道に迷った様子を描く(譜例2)。ピアノ連弾組曲版に対してヴァイオリンとフルート、ピッコロによる鳥のさえずりが追加された(譜例3)。
■パゴダの女王レドロネット
(Laideronnette, Impératrice des Pagodes)
嬰ヘ長調、行進曲の速さで、2/4拍子
パゴダとは一般的に仏塔という意味であるが、ここでは17-18世紀にドイツのマイセン窯などで作られた中国の神の坐像をモチーフにした磁器製の首振り人形を意味する。ピッコロによるにぎやかな旋律(譜例4)からはじまり、人形たちが歌い、楽器を演奏し始める様子が、東洋的な5音音階やチェレスタやグロッケンシュピール、タムタムなどで表現されたエキゾチックな楽器を用いて描かれている。
■美女と野獣の対話
(Les Entretiens de la Belle et de la Bête)
へ長調、中庸なワルツの速度で、3/4拍子
意地悪な仙女によって野獣の姿に変えられた王子が心豊かな美女と出会い、元の姿に戻る様子が描かれている。クラリネットによる美女の主題(譜例5)がはじまり、やがてコントラファゴットによる野獣の主題(譜例6)が登場する。その後、美女の主題と野獣の主題が協奏される。この曲はサティの「ジムノペディ」へのオマージュだといわれている。
■妖精の園
(Le Jardin féerique)
ハ長調、ゆっくりと重々しく、3/4拍子
弦楽器によるゆるやかな3拍子の美しい旋律からはじまり(譜例7)、それに続くチェレスタとソロ・ヴァイオリン、ソロ・ヴィオラによる旋律(譜例8)がたぐい稀な美しさを湛えている。そして終曲らしく華麗なフィナーレへと向かう。
作曲:ピアノ連弾組曲(1908-1910)、管弦楽編曲(1911)、バレエ版(1911-1912)
ピアノ連弾組曲初演:1910年 パリのカヴォー・ホールに於ける独立音楽協会第1回演奏会にて、ジャンヌ・ルルーとジュヌヴィエーヴ・デュロニーの演奏による
管弦楽編曲版初演:不明
バレエ版初演:1912年 パリのテアトル・デ・ザールにて、ガブリエル・グロヴルの指揮による
楽器編成:フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット2(2番
はコントラファゴット持ち替え)、ホルン2、ティンパニ、大太鼓、シンバル、タムタム、トライアングル、木琴、ジュ・ド・タンブル(グロッケンシュピール)、チェレスタ、ハープ、弦五部
参考文献
『Ravel』Roger Nichols著(Yale University Press)
『モリス・ラヴェル その生涯と作品』シュトゥッケンシュミット著、岩淵達治訳(音楽之友社)
『1001 Classical Recordings You Must Hear before You Die』Matthew Rye著(Cassell Illustrated)
『作曲家別名曲解説ライブラリー ラヴェル』音楽之友社編(音楽之友社)
『ミニチュアスコア マ・メール・ロア』(音楽之友社)
『美女と野獣』ボーモン夫人著、鈴木豊訳(角川文庫)
『完訳 ペロー童話集』ペロー著、新倉朗子訳(岩波文庫)
ラヴェル:道化師の朝の歌
「鏡」とは
この作品は1904年から1905年にかけて作曲されたピアノのための組曲「鏡」の第4曲目にあたる。「鏡」は「夜蛾」「悲しげな鳥たち」「海原の小舟」「道化師の朝の歌」「鐘の谷」という極めて審美的で絵画的な、そして謎めいたタイトルの5つの小品から成り立つ。
そもそも「鏡」というタイトル自体が想像力をかきたてる。個人的ではあるが「5つの映像(イマージュ)を映し出す鏡」とも「客観的な現実の反映」とも受け取れる。またラヴェルは作品をまず鍵盤楽器で発表し、のちに改作することを好んだ。実際に彼の作品のほぼ半数は何らかの方法で作り変えられている。この「鏡」も、「海原の小舟」と「道化師の朝の歌」の2曲がラヴェル自身によって管弦楽化された。
ラヴェルとスペイン
5曲のうち「道化師の朝の歌」のみタイトルが“Alborada del gracioso”とスペイン語表記になっている(他4曲はフランス語)。特に日本では「道化師」と訳される“gracioso”の翻訳に関しては各国共通の悩みの種のようで、英訳では“Jester”や“clown”、または“comedian”など様々である。これに対してマルグリット・ロン(注1)は著作『ラヴェル-回想のピアノ-』の中で次のように述べている。
「“gracioso”という用語は、フランス語にはこれに相当する言葉がなく、“bouffon”というのは大分意味がずれている。グラシオーソには民衆の思想を表す民族性がある。これらはスペインの黄金世紀の演劇の喜劇役者であり、コントラストの効果をあげるためのもので、一種の反ヒーローである。だが作家次第で、心理的に実に多様な現れ方をしている。」
同じくアルフレッド・コルトー(注2)も著作『フランス・ピアノ音楽2』の中で、「“gracioso”にはこれに置き換え得るフランス語が見当たらない」と指摘している。題名に関してラヴェルは多くを語っていないが、スペイン語で記すことが作曲家自身、一番ぴったりとする感覚であったのだろうか。ここではまずラヴェルの生い立ちについて簡単にふれておきたい。ラヴェルの死の翌年に出版された『自伝素描』(注3)の中で、作曲家自身は次のように語っている。
「1875年3月7日、サン=ジャン=ド=リューズに隣り合わせたバス=ピレネの町シブールで、私は生まれた。父は、レマン湖のスイス側の岸にあるヴェルソワの出で、土木技師だった。母は、バスク地方の古い家柄に属していた。3か月のとき、シブールを離れてパリに行き、以後ずっとそこに住んだ。」
また、スペインの作曲家マヌエル・デ・ファリャは、ラヴェルの管弦楽組曲「スペイン狂詩曲」を聴いた際に次のように述べている(注4)。
「私は狂詩曲のスペイン的な性格に驚かされた。しかしラヴェル自身が認めるように、彼は国境近くの生まれで、わがスペインとは隣人関係しかもっていないことを知っているというのに、私はこの音楽家の鋭敏で正統的なスペイン的特質をどうしたら説明できるのだろうか。だが、私はすぐにこの疑問を解決した。ラヴェルのスペインは母を通して理想的に感じ取られたスペインなのである。私は彼女がすばらしいスペイン語で語る洗練された会話にうっとりしながら、マドリッドで過ごした彼女の若き日の思い出話を聞いたものだった。」
ラヴェルの生まれたシブールは、フランス南西部のスペインに近いバスク地方に位置する。そしてそのバスクの古い家柄に属するシブール生まれの母親を持ったことにより、作品の題材が、例えば歌劇「スペインの時」や「スペイン狂詩曲」のようにスペインそのものであったり、作風にスペイン的抒情性が見受けられるのは極めて自然なことのように思える。
楽曲について
ここでは原曲のピアノ版と比較しながら記したい。まず冒頭部分であるが、ピアノ版では「乾いた響きで、アルペジオは詰めて短く」と指定されている。またラヴェルの全ピアノ作品を作曲者自身から直接助言を受けたヴラード・ペルルミュテールによる校訂版では「ギターのつまびき音のように」と補足されている。まさにギター音楽を連想させる冒頭部分だが、オーケストラ版ではハープと中間部の主役を担うファゴット、そして弦楽器のピッツィカートに分割して奏され、よりコミカルな雰囲気を醸し出している。この序奏に導かれて主要主題がオーボエからコールアングレ、クラリネットと受け渡される(譜例1)。
序奏から引用された3連符を伴った旋律はスペイン風にも聴こえる。オーケストラ全体で奏した後、リズム部分にカスタネットが登場する。この瞬間、たとえここまで何の予備知識が無く聴いたとしても、スペインが舞台であることを確信するだろう。そこにはスペインの太陽に照らされた乾いた空気や、街のざわめきが感じられる。そして時折、仮面をつけた道化師の姿が見え隠れする。あくまで私見ではあるが、道化師は「鏡」に映った自分自身の姿とも受けとれる。
中間部はラヴェルが「より遅く、表情をよくつけて語るように」と指示した右手による息の長い単旋律から始まる(譜例2)。
オーケストラ版では第1ファゴットにゆだねられ、より表情に富んだ語りとなっている。あたかも歌劇(オペラ)の叙唱(レチタティーヴォ)のような道化師の語りは、朝の歌(オーバード)とも恋の嘆きとも受け取れる。これに呼応するようにスペイン風リズムの協和音の響きが交錯し、重なり合いながら中間部のクライマックスを形成する。
再現部では今までの憂愁などなかったかのように場面転換される。ここでは主要主題(譜例1)は後回しにされ、急速な連打音やダブル・グリッサンドなどの繊細かつ高度なピアノ技巧が展開される。オーケストラ版ではこのダブル・グリッサンド部分の最後に、ピアノ版には存在しない木管楽器のフラッター奏法による新たな4小節が追加されている。最後に主要主題が部分的に想起され、華やかな幕切れとなる。
[注記]
注1:1874-1966年。20世紀前半のフランスを代表するピアニスト・ピアノ教育者。
注2:1877-1962年。20世紀前半のフランスを代表するピアニスト、指揮者、教育者、著述家。
注3:1938年に出版された「ルヴュ・ミュジカル」誌のモーリス・ラヴェル特別記念号に掲載された。内容は1928年にロラン=マニュエル(フランスの作曲家・音楽学者・音楽評論家)が聞き取りしたものにもとづく。
注4:出典『On Music and Musicians』マヌエル・デ・ファリャ著(Marion Boyars, 1979)
ピアノ初演:1906年1月6日 パリのサル・エラールに於ける国民音楽協会演奏会にて、リカルド・ピニェスによる
管弦楽編曲版初演:1919年5月17日 パリにて、ルネ・バトン指揮、パドルー管弦楽団による
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、タンブリン、シンバル、トライアングル、クロタル(アンティク・シンバル)、カスタネット、木琴、ハープ2、弦五部
参考文献
『ラヴェル-回想のピアノ-』マルグリット・ロン著、ピエール・ロモニエ編 北原道彦・藤村久美子共訳(音楽之友社)
『フランス・ピアノ音楽2』アルフレッド・コルトー著、安川定男・安川加寿子共訳(音楽之友社)
『作曲家別名曲解説ライブラリー11 ラヴェル』音楽之友社編(音楽之友社)
『ラヴェル-生涯と作品-』アービー・オレンシュタイン著、井上さつき訳(音楽之友社)
『ラヴェル』ウラディミール・ジャンケレヴィッチ著、福田達夫訳(白水社)
『ラヴェルピアノ曲集、鏡』モーリス・ラヴェル作曲、ヴラード・ペルルミュテール校訂・監修、岡崎順子注釈・訳(音楽之友社)
「フランス音楽の彩と翳Vol.6 スペイン!!」矢崎彦太郎
http://www.ses-amis.net/cms/ombres-et-lumieres/25/
明晰なるもの
明晰ならざるものフランス語ならず(ce qui n'est pas clair n'est pas français)。18世紀フランスの文学者リヴァロルのこの言葉は、「明晰でないもの、それは英語、ギリシャ語、ラテン語である」と続く*。
フランス語の文法は極めて厳格である。時制は神経症的と思えるほど複雑であり、学習者は日本語で培われた時間感覚の大雑把さを呪う羽目になる†。フランス語の正書法は極めて厳密であり、書き取りのテストでは、意味はわからなくても文字にはできるというほど綴りと発音が一致している。しかし母音の種類が極端に多いため、学習者は日本語で培われた音韻認識の枠組の大雑把さを呪う羽目に(以下略)。
このようにフランス語が明晰・厳密だというのは大体真実だが、あくまで「大体」である。規則の通りに話したり書いたりしたつもりでいると、ほぼ毎回間違いを指摘される。納得できず理由を聞くと、答えはいつも「例外だから」。フランス語には山ほども例外があって、それをいちいち覚えなければならないのである。はぁそうですか。なるほど明晰にして厳密な言語である。それに比べるとドイツ語 -大学時代私は落第点を取り続けていたので、どういう言葉か本当は知らない-の方がよっぽど規則的に思える。そういえばリヴァロルはドイツ語に言及していない。
*原典の文脈では、言語の明晰さというより語順の明確さに関する記述のようである。
http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~rhotta/course/2009a/hellog/2012-04-09-1.html
http://pourlhistoire.com/docu/discours.pdf(p17、4段落目)
†母語を呪うことは慎むべきである。
フランスとドイツ。それぞれの音楽について、皆さんはすでにある程度の印象をお持ちと思う。どちらがより「明晰さ・厳密さ」を、どちらがより「雰囲気」を重視しているようにお感じだろうか。ドイツ音楽が「明晰さ・厳密さ」、フランス音楽が「雰囲気」ではないだろうか。
論理的な建築物としての音楽を営々と発展させ開花させたバッハ、ベートーヴェン、ブラームス。モチーフに意味を持たせ一分の隙もなく組み合わせることで全てを構成したワーグナー。それに対していかにもふわっとした、まさに印象派の絵画のようなドビュッシー、華やかなラヴェルやシャブリエ。そして重厚な音楽に背を向けてしまったようなサティ、プーランク等々。
ずいぶん前のことになるが、私もそういう印象を持ちながらフランスに赴任した。
しかし現地で私が経験した音楽は、そのようなものではなかった。
滞在数ヶ月が経ち仕事や生活にも慣れ、多少の余裕ができてオーボエの先生を探しまわっていたある時、幸運な偶然に助けられて、パリの数ある音楽院のひとつで教鞭をとっていたJ.G.先生に出会うことができた。私はそれから約1年間、週末にレッスンを受けることになったのである。
最初のレッスンは忘れ難い衝撃となった。よく知られたFerlingの『48の練習曲集』を持っていったのだが、ではまずその「第1番」を吹いてみなさいということになった。
当時日本ではドイツ流の吹き方に人気があった。ヴィンフリート・リーバーマン、ローター・コッホ、ギュンター・パッシン、マンフレート・クレメントといった世にも美しい音色を奏でる人たちに多くのアマチュア奏者は憧れた。私もその「音色を真似ようと」心がけていた。
そのことを披露するかのように「第1番」を吹き終えてJ.G.先生の方を見ると、顔色がさえない。困っているように見える。
「君はそういうふうにこの曲を吹きたいのですか?」
「はい」
「私は思うのですが、たとえばドイツの奏者の多くは、楽器としてのオーボエの長所をとてもよく引き出して美しい音色を作ります。でも、オーボエを音楽の道具として考えたとき、彼らのやり方が唯一でしょうか?(本当はもうちょっと手厳しい言い方だった)」
J.G.先生に私は、音楽がお留守になっている、と言われたのである。
-----------------------------------------------------------
これに10年ほど先立つ20代の頃、私は国内のある夏季音楽アカデミーに参加する機会に恵まれ、ドイツのオーボエ界の重鎮であり今もお元気で活躍されているH.W.先生のレッスンを受けたことがあった。私にとってのH.W.先生のレッスンの印象は、一言で言えば「心」であった。歌って示しては下さるが、言語に還元するアプローチはなさらなかった。J.S.バッハのオーボエソナタ(BWV1030)の第2楽章のレッスンはとりわけ印象に残っている。H.W.先生は
「これはピエタ(イエスのなきがらを抱く聖母マリア)なのです」
とおっしゃっただけで、「あとはあなたが音楽を作るのです」とばかりに、私たちが吹くのをただ聞いていらした。
私の「音楽を作ること」のイメージはそういうものだった。そのために美しい音色が必須と思っていたのが、いつの間にか本末転倒になっていたのだろうか。
パリでのレッスンはH.W.先生のレッスンとは異なっていた。先ほどのやり取りののちもう一度吹いた「第1番」の冒頭、私はそれでも音色に魅力を持たせようと思ってビブラートをかけて始めた。すると
「冒頭のフレーズを全体の構成の中にきちんと位置づけていますか?ここをそのように始めてしまうとあとで必ず困ります。可能な限り静かに。もちろんビブラートなしで始めてください」
しばらくするとcresc.が見えるので、そろそろいいだろうと思って「歌おう」とすると
「まだだめです。この曲の最初の山はまだ5小節も先でしょう?やりすぎては台無しになります」
その5小節後「ここだ」と思って頑張ると
「それでは足りません!もっと輝かしく、ビブラートを効果的に使って!勝手に遅らせない!正しい時間に100%の音を出して!」
・・・・以下省略するが、ここで私が要求されたのは、あいまいさのない、「明晰な」演奏であった。
J.G.先生がお手本としてこの曲を吹いて下さったことがあった。その演奏は、まるで言葉のようだった。華麗な音色で魅了するのではなく、「音楽を表現するためにオーボエを使っている」演奏であった。
練習曲であっても曲に対する敬意を忘れない、正面から向き合ってメッセージを理解する、などの、今から思えば基本的なことがらを思い知らされた。この「第1番」は、その後2ヶ月以上も合格点がもらえず、結局「練習曲はもういいですから別の曲にしましょう」という先生のお言葉により、Ferling48は「第1番」敗退、2番以降は不戦敗の練習曲集となった。
ある身近な先生の教えに私はもっと早く気づくべきだった。新響を長くご指導下さった柴山 洋先生である。先生は若い頃の私に言って下さった。
「岩城君、君は今、肉体派のオーボエ吹きだ。肉体派は魅力的な演奏をすることができるけれど、あるとき急にその力を失う日が来る。私も何人か見てきた。君はその前に、頭脳派に転向できれば、きっと長く吹き続けることができると思うよ。」
柴山先生はJ.G.先生と同じことを私におっしゃっていたのではないか。当時の私はその意味を理解していただろうか。
先生はフランス語に堪能でいらした。「明晰ならざるものフランス語ならず」という言葉を私に教えて下さったのは他ならぬ柴山先生だった。ヴェルレーヌの詩Art poétiqueの一節をもじった、ご自身の現代音楽の演奏を集めたお手製のCD*1を下さったり、ご自身でパリの古楽器店にお出かけになり100年も前のこわれたオーボエを購入され、ご自分の手で修理されお仕事に使われるなど、楽しいエピソードをたくさんお持ちの先生であった。先生は突然他界された。お礼を申し上げることもできなかった。悔しくてならない。
*1ジャケット表面には
De la musique contemporaine avant toute chose,
Et pour cela préfère le HAUTBOISと、
ジャケットの背には
Du hautbois avant toute chose!
と記されている。
今回の演奏会で私たちはフランス音楽のプログラムに取り組んでいる。ラヴェルを「スイスの時計職人」と呼んだのは誰であったか。スコアは精密で、すべての楽器が正しく部品として機能したときに初めて本来の響きがする音楽に違いない。「明晰な演奏」をお届けできるだろうか。少しでも近づくことができればと願っている。
=後日談=
フランスのメジャーオケの首席奏者になられたJ.G.先生が先頃来日された。私は先生の公開レッスンを聴講したのちあいさつに行き、
“Vous vous souvenez de moi?”(私を覚えておいでですか?)
と切り出してみた。
先生は、相手の発音が悪くてよく聞き取れないときの典型的なフランス人の表情 -日本人の習慣では「いやな顔」に分類されるので慣れるまではつらい- を示されたあと
“Non.”(いいえ。)
と答えられた。
そのあと少しお話をしたが、やはり思い出せないご様子だった。
どうやらそんなものらしい。
第227回ローテーション
| 道化師の朝の歌 | マメールロワ | ラ・ヴァルス | プロコフィエフ | |
| フルート1st | 吉田 | 岡田(+Picc.) | 兼子 | 松下 |
| 2nd | 牧 | 吉田(+Picc) | 新井 | 岡田 |
| 3rd | 藤井(+Picc.) | - | 牧(+Picc.) | 藤井(Picc.) |
| オーボエ1st | 岩城 | 宮内 | 山口 | 堀内 |
| 2nd | 桜井 | 堀内(+C.I.) | 宮内 | 山口 |
| コールアングレ | 堀内 | 堀内 | 岩城 | 岩城 |
| クラリネット1st | 末村 | 品田 | 中島 | 高梨 |
| 2nd | 進藤 | 石綿 | 大藪 | 進藤 |
| エスクラリネット | - | - | - | 品田 |
| バスクラリネット | - | - | 岩村 | 岩村 |
| ファゴット1st | 浦 | 浦 | 浦 | 田川 |
| 2nd | 野田 | 藤原(+C.Fg) | 野田 | 野田 |
| コントラファゴット | 藤原 | - | 藤原 | 藤原 |
| ホルン1st | 大原 | 大内 | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 大内 | 市川 | 大原 | 市川 |
| 3rd | 山口 | - | 大内 | 森 |
| 4th | 鵜飼 | - | 森 | 鵜飼 |
| トランペット1st | 小出 | - | 倉田 | 野崎 |
| 2nd | 北村 | - | 北村 | 小出 |
| 3rd | - | - | 中川 | 中川 |
| トロンボーン1st | 町谷 | - | 町谷 | 武田 |
| 2nd | 志村 | - | 志村 | 町谷 |
| 3rd | 岡田 | - | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 土田 | - | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 皆月 | 皆月 | 皆月 | 桑形 |
| パーカッション | 大太鼓/中川 クロタル・タンブリン/桑形 トライアングル/桜井 小太鼓/今尾 カスタネット・木琴/鈴木* |
木琴・トライアングル/今尾 シンバル/桜井 大太鼓・小太鼓・タムタム/中川 グロッケンシュピール1/古関 グロッケンシュピール2/鈴木* |
大太鼓/中川 タンブリン・クロタル/桑形 トライアングル/桜井 小太鼓/今尾 シンバル/古関 カスタネット・グロッケン・タムタム/鈴木* |
トライアングル・タンブリン/鈴木* 合わせシンバル/桜井 吊シンバル/皆月 大太鼓/古関 ウッドブロック・タムタム/中川 小太鼓/今尾 |
| 鍵盤 | - | 藤井(Cele.) | - | 藤井(Piano) |
| ハープ1st | 篠崎* | 篠崎* | 篠崎* | 篠崎* |
| ハープ2nd | 篠崎* | - | 篠崎* | 篠崎* |
| 1stヴァイオリン | 堀内(大隈) | 堀内(大隈) | 堀内(大隈) | 堀内(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(田川) | 小松(田川) | 小松(田川) | 小松(大島) |
| ヴィオラ | 柳澤(村原) | 柳澤(村原) | 柳澤(村原) | 村原(柳澤) |
| チェロ | 柳部(光野) | 柳部(光野) | 柳部(光野) | 光野(柳部) |
| コントラバス | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) |
(*)はエキストラ
第227回演奏会のご案内
パリを拠点に国際的に活躍する矢崎彦太郎を指揮に迎え、フランス印象派を代表する作曲家ラヴェルと、フランスに縁の深いロシアの作曲家プロコフィエフの作品を演奏します。
■ラヴェル=管弦楽の魔術師
ラヴェルは華麗で精密なオーケストレーションで知られていますが、中には自身のピアノ曲を管弦楽曲に仕上げたものが多くあります。
「道化師の朝の歌」は、5曲からなるピアノのための組曲「鏡」の中の一つをラヴェル自身が管弦楽に編曲しており、スペイン風の軽快で色彩豊かな曲です。「鏡」とは情景や心情を映し出すという意味と思われますが、文字通り道化師の朝帰りの情景か道化師に見立てた伊達男か、あるいはラヴェル自身の心の幻影なのでしょうか。
「マ・メール・ロワ」は、英語でマザーグース(ガチョウおばさん)という意味で、欧米に古くから伝わる童謡を指し、「眠りの森の美女」「親指小僧」「美女と野獣」といったおとぎ話が登場します。小編成のオーケストラでやさしく子供に語るような、鳥が鳴いたり東洋風な響きも伴う幻想的な曲です。
「ラ・ヴァルス」は、ウィンナワルツへの礼賛として着想され、オーストリア宮廷を舞台としたバレエ音楽として書かれたのですが、依頼主のディアギレフから「傑作ではあるがバレエには向かない」と受取りを拒否されました。優雅なようでいて、同時に華やかさと不気味さが同居する迫力のある曲です。
■プロコフィエフ=ソ連時代の国民的作曲家
ラヴェルがパリで活躍していた第一次世界大戦の頃、プロコフィエフもパリに10年ほど住んでいました。
プロコフィエフは、サンクトペテルブルク音楽院で作曲とピアノを学んだ後、ロシア革命で国を離れ日本経由でアメリカに向かいます。その後ディアギレフの依頼でバレエ音楽を書くなどフランスを拠点に活動をしていましたが、ディアギレフの急死により祖国への帰国を考えるようになりました。
「ピーターと狼」で知られるプロコフィエフの交響曲は第7番までありますが、今回演奏する第5番がもっとも有名で、作曲家自身も作品番号100となるこの曲に意欲的に取組みました。作曲は第二次世界大戦中、初演時は演奏開始時に祝砲が鳴りソ連全土に中継放送されるなど、国民的な行事となりました。
プロコフィエフの作風は、初期は奇抜で斬新でしたが、その後は叙情的でわかりやすい方向へ変わっていきます。この第5番はその中間的な性格で、「わたしの第5交響曲は自由で幸せな人間、その強大な力、その純粋で高貴な魂への讃美歌の意味を持っている。」という言葉を残しています。スターリン体制から身を守るために必要だったのか、心から祖国のために取組んだのか。どちらも見え隠れするところが、この曲の魅力となっているのかもしれません。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
第226回ローテーション
| ワルキューレの騎行 | 夜明けとラインへの旅 | ブルックナー第6番 | |
| フルート1st | 吉田 | 岡田 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 牧 | 兼子 |
| 3rd | (picc1)牧 | 新井 | - |
| Picc | (picc2)岡田 | 吉田 | - |
| オーボエ1st | 山口 | 亀井 | 宮内 |
| 2nd | 亀井 | 山口 | 堀内 |
| 3rd | 宮内 | 宮内 | - |
| C.A. | 岩城 | 岩城 | - |
| クラリネット1st | 末村 | 進藤 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 高梨 | 中島 |
| 3rd | 高梨 | 末村 | - |
| B.Cl. | 岩村 | 岩村 | - |
| ファゴット1st | 浦 | 浦 | 田川 |
| 2nd | 野田 | 野田 | 藤原 |
| 3rd | 田川 | 藤原 | - |
| ホルン1st | 森 | 森 | 箭田(森) |
| 2nd | 市川 | 市川 | 大内 |
| 3rd | 鵜飼 | 鵜飼 | 山口 |
| 4th | 山口 | 山口 | 大原 |
| 5th | 大原 | 大原 | - |
| 6th | 箭田 | 箭田 | - |
| 7th | 大内 | 大内 | - |
| 8th | 高野* | 高野* | - |
| トランペット1st | 小出 | 北村 | 野崎(北村) |
| 2nd | 中川 | 中川 | 小出 |
| 3rd | 青木 | 青木 | 青木(中川) |
| バストランペット | 武田 | 武田 | - |
| トロンボーン1st | 志村 | 志村 | 町谷(志村) |
| 2nd | 町谷 | 町谷 | 武田 |
| 3rd | 井上* | 井上* | 岡田 | 4th | 岡田 | 岡田 | - |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ1st | 古関 | 古関 | 桑形 |
| 2nd | 中川 | 中川 | - |
| パーカッション | シンバル/桜井 トライアングル/今尾 中太鼓/桑形 |
グロッケン/今尾 トライアングル/今尾 シンバル/桜井 |
- |
| ハープ | 見尾田他計6名* | 見尾田他計6名* | - |
| 1stヴァイオリン | 堀内(小松) | 堀内(小松) | 堀内(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(笠川) | 大隈(笠川) | 大隈(佐藤) |
| ヴィオラ | 村原(柳澤) | 村原(柳澤) | 柳澤(村原) |
| チェロ | 柳部(光野) | 柳部(光野) | 光野(柳部) |
| コントラバス | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) |
*はエキストラ
管楽器()はアシスタント、弦楽器()はトップサイド
音楽に於ける「意味」
■「ヒロシマ」を巡って
佐村河内守(さむらごうちまもる)という作曲家の名と、交響曲第1番『HIROSHIMA』という作品名を目にしたのがいつの事だったか、正確には覚えていないがそれが新聞のCD広告だった事は確かである。10万枚単位で売れているという。アマチュアであろうともオーケストラと名がつくものに籍を置いて長年活動していれば、交響曲を書けるような作曲家なら、大抵その名は耳に入る筈だが、この人の名はそれまで全く知らなかった(「『サムラカワチノカミ』って時代がかり過ぎだが、それで名は何と言うのだろう?」と疑問を抱いたほどである。同じように考えた人が多くいた事は後に知った)。そこには「全聾」とか「現代のベートーベン」の惹句もちりばめられてもいたが、なぜこの21世紀の現代に交響曲であり主題がヒロシマなのか?に最初の違和感があった。
交響曲というジャンルは既に19世紀末にピークを超え、100年以上かけてゆっくりと坂を下りつつある。それは従来交響曲という形式が表現するに適した浪漫主義の衰退と軌を一にする。20世紀に入ってからの交響曲は、主として(あくまでも主として、だが)前世紀の嗜好が辛うじて通用するような、国家の英雄主義的なストーリーや特定の指導者の賛美(または表裏一体の隠れた呪詛)の為の道具に堕した・・・・と個人的には考えている。そして「芸術」としての交響曲は最盛期の俤とは別の、小規模な作品形態へと変貌を遂げている。このジャンルの作品は残念ながらブルックナーとマーラーが残した巨大な作品群を最後に「絶滅」し、その後に生き残ったものは小さきが故に辛うじて生き残ったという感が個人的にはぬぐえずにいる。それは19世紀から20世紀へという時代そして社会の変転が、交響曲を必要としなくなったという事である。交響曲の存続には、それまでの社会が経験し得なかった特殊なテーマが必要になった。その確かな一端に「ヒロシマ」がある。
だが、かの地の惨禍をテーマとした重要な作品は(それは決して音楽のジャンルにとどまらないが)、既に出尽くしている感を拭えない。大木正夫の交響曲第5番『広島(1953年)』や他ならぬ芥川也寸志の『ヒロシマのオルフェ(1960年)』、有名なペンデレツキの『広島の犠牲者に捧げる哀歌(1960年)など、明確なテーマとして取り上げているものはもちろん、その惨禍に対する作品への反映までを考えれば、真に枚挙に遑もない状況だろう。だが時間の経過と共に、あからさまに正面からこのテーマに取組むという思潮は退いていったように思える。ひとつにはこれが奇妙に政治化されて行った事と無縁ではない。
今でも忘れられない事がある。1980年、学生だった僕はNHKホールで毎年7月に行われていた『青少年音楽祭』の開催に関わる仕事をしていた(もちろん演奏にも参加)。この年の指揮者は井上道義氏。彼を囲んで数人の事務方と選曲の打合せを進める中で、これまで無かった20世紀の作品を演奏してみたいという機運が高まり、井上氏から前述のペンデレツキの『広島の犠牲者に捧げる哀歌』を是非とも取り上げようという意見が出て話がまとまる。ところがこの演奏会を録画・放映するNHKサイドにこの選曲案が伝わるとストップがかかった。考え直して欲しいというのである「ヒロシマ」が政治的なテーマとなってしまい、趣旨や質とは全く無関係に、この都市の題のついた作品を、不偏不党を標榜する公共放送の8月(放映は毎年この時期だった)の電波には乗せられないのだといった趣旨の説明を、担当の洋楽部の偉い人から聞かされる。そして仕方なく武満徹氏の「政治的に」無色透明な作品『グリーン』を代わりに選ぶ仕儀となった。周知の事かも知れないが、この作品は1960年代に日本で初演されるに際し、作曲家の配慮により「ヒロシマ」の名を冠した曲名に改められている。その善意は全く裏目に出てしまった事になる。責められるべきは誰であろう。
新響が細川俊夫氏に委嘱した作品に『ヒロシマ・レクイエム』がある。もちろん新響が広島をテーマにした作品をと依頼した訳ではない。指揮者の今村能氏を通じて話が進むうちに、細川氏からこれをテーマとしたいと伝えてきたのだ。この件が新響の運営委員会に出されると「なぜいま『ヒロシマ』なのだろう?」という議論が起きたのを記憶している。またその際も「政治的な」手垢がつかないか?との懸念の声も上がったと記憶する。だが細川氏自身が広島出身だと判るとそこで議論そのものは解消した。これが1988年(完成・初演は翌1989年7月)の事で、既に四半世紀も前の事になる。
こうした個人的な「ヒロシマ」と音楽作品を巡る様々な体験を踏まえると、佐村河内氏の作品の出現と、世の中の反響には、20世紀の亡霊の印象が拭えなかった。
その彼をNHKスペシャルが特集(『魂の旋律 音を失った作曲家』2013年3月31日放映)するというので、日頃殆ど見ないテレビの前に陣取った。「全聾」の彼がどのようにして作曲をするのか?この一点に個人的な関心は絞られていた。が、番組はひどい出来だった。簡単に言えば、絶え間ない頭痛と耳鳴りの病苦に苦しむ姿、作品を捧げるべく震災の被災地を訪れて、苦吟する姿、そして彼の「作品」に感動して涙する善男善女の姿・・・・が交互に映し出されるばかり。作曲という行為とつながるものは何も無い。
極めつけは苦悶の末に頭の中で完成させたレクイエム(ピアノソナタ)を、記譜する作業の現場に「神聖な行為だから」とカメラを入れさせなかった事。そして一晩経つと浄書された譜面が出来上がっている・・・・「鶴の恩返し」じゃあるまいし・・・・「これは胡散臭い。胡散臭すぎる」と番組終了直後から家人をはじめとした周囲に吹聴し、例外なく閉口された(苦笑)。
今年に入って事実が全て判明するとNHKはこの番組の制作過程を検証し、反省・お詫びを表明した。要は「取材や制作の過程で、本人が作曲していないことに気づくことができませんでした」という訳だが、編集した結果の映像しか目に出来ない立場であってもはっきり「これはおかしい」と感じるレヴェルで、恐らくは制作する側にもそうした違和感を覚える人がいただろう。組織というものに身を置いていれば誰しも経験があろうが、そうして上がる疑問を遮り「それでもやれ」とゴーサインを出した立場の者が必ず存在する。気づかなかったのではなく、気づいた声を無視した、これが実態だろう。真に反省すべきはこの立場の者だが、恐らく永遠にそれが誰かは判らない。
そしてもし本当に気づかなかったとすれば、それは作曲という行為、特に交響曲のような大がかりなものに対するそれへの致命的な理解不足と言える。『現代のベートーベン』の姿に迫ろうとするなら、真に全聾の偉大な先達が、200年以上前にどれほど作曲過程でメモやスケッチを残しているかを調べ(調べようと思えばたやすい事だ)、そうした行為が長大な作品の創作に不可欠である事が理解できたはずだ。また管弦楽用の作品を書けば、そこにはどの楽器にどの音を割り当てるか、楽器同士の組み合わせをどうするかという「オーケストレーション」の作業を避けては通れない。この時作曲家は実演奏の場に立ち会って、その音色を確認する必要がある。ベートーヴェンの時代に比して編成が遥かに大規模になっている現代に於いて、「作曲家」はどう対処したのか?
そもそも交響曲の創造には、よほどの構成力と作曲技法が求められ、頭の中だけで作り出せるものでは決して無い。短い歌謡曲の旋律だけを作曲するのとは違うのである。こうした行為には絶えず断片的ながらも譜面が介在する筈だが、そうしたものは一切当人からは示されず(それもそのはず、佐村河内氏は譜面を書けなかったのだ)、番組では単に外部の専門家に作品の分析を語らせる事でお茶を濁した。事実の発覚以後、この専門家らに対する批判も取りざたされたが、彼らは単に完成した作品を分析しただけで、誰が作曲したかの追求に責任はない。事実を知れば知るほど、杜撰極まりない制作姿勢だった事が判る図式である。
■交響曲に於ける「意味」とは
2001年9月15日付発行の雑誌『タイム』には、佐村河内氏のインタビュー記事が載っている。
氏の経歴と、聴覚に障碍を持ちながらも作曲したゲーム音楽の作品によって、その地歩を固めた半生が紹介された後、次の文章がある。
His condition has brought him a certain celebrity, which he fears may detract from an honest critique of his work. He understands the inspirational appeal of the story of a digital-age Beethoven, a deaf composer who overcomes the loss of the sense most vital to his work. "I used to be able to hide it, to do my work without people noticing it," he says.
"彼の状態(聴覚障害が襲った事)は、確固たる名声(彼はその名声が、自分の作品への偽らざる批判から遠ざけてしまうかもしれない事を怖れている)をもたらしたのである。彼は、デジタル時代のベートーヴェン(下線筆者)・・・・作品への生命線となる感覚(聴覚)の喪失を克服した作曲家・・・・の物語の神秘的な魅力を理解している。「私はみなが、自分が全聾である事に気づかずに自分の仕事を行うため、それをかつては隠しおおせていた」と彼は言う。"
この一文が佐村河内守氏を『現代のベートーベン』とした「出典」である。日本語としてこなれない拙約で、且つ多少文章のニュアンスが異なるかも知れないが、この記者は単に「聴覚に障碍がある作曲家」という共通の観点によってのみ、この偉大な作曲家を引き合いに出したに過ぎない印象がある。『タイム』の編集サイドが想定する一般的な読者層のクラシック音楽に対する認識が垣間見える。そして佐村河内氏は、自分の障碍が作品の評価そのものに影響する事を恐れ、この事実を隠していた時期があった事を告白している("used to be able to hide"は、今では隠せなくなってしまったというニュアンスだろう)。
だが"a digital-age Beethoven"はひとり歩きし、『現代のベートーベン』として、作品の「質」をも表す記号として喧伝されてゆく。初めてこの惹句を新聞広告で目にした時「得体の知れないシンフォニー1曲書いた程度で大げさな!」と感じ、何かこちらが気恥ずかしくなったのを思い出す。『タイム』で絶賛という事も書いてあったように思う。もちろん原典に当たるもの好きなどいる筈もないという計算済みだ。
そして先述のNHKスペシャルの反響もあって、善男善女は『HIROSHIMA』に感動して、そこに「描写」された惨禍と人々の苦悩と祈りを見出すと同時に、聴覚障害を乗り越えてその作品を書いた、被爆二世の作曲者の生き様に感銘した。昨年2013年の後半にはひとつの現象とさえなていた感がある。
はっきり言って彼の交響曲は、100年以上前の作品群を換骨奪胎したスタイルでしかなく、そうした要素が上手くまとめられてはいるが、独創は何もないという類のものだ。だが作品の「質」に対する批判はそうした人々の感動に水をさすものとして、ほぼ封印された。この時点で佐村河内氏の作品は、通常の芸術とは別種のものとなっていた訳で、これは10年以上前の彼の言葉を信じるなら、「障碍故に作品に対する評価を歪めたくない」という、彼自身が恐れていた事態そのものである。が、彼はそうした嫌らしい風潮に自ら歯止めをかける事を既にしなくなっていた。この間の彼の人間としての変質を思うべきだろう。
2014年が明けて、「代筆者」の告白によって全てが明るみに出た。個人的には「やっぱりな」と思っただけだが、案の定というかこれに対し騙されたと怒る人が沢山出た。感動を返せとさえ言う。そして彼の作品を収めたCDは店頭から消えた。怒っている人は一体何に対して怒っているのだろう?というのが率直な疑問だった。問題だと佐村河内氏を糾弾する人もいた。
もし彼と彼の「作品」を問題視するなら、そもそもの出発点として偽作の交響曲に「意味」や「ストーリー」を過剰に見出そうとした事そのものに原因があるとしか思えない。その過剰な行為の結果ゆえに、それが虚構と知った時に怒りが湧いたという図式である。そしてそうした虚構を増幅し、補強し続けた「作曲家」を取巻く周囲の関係者の行為も、行過ぎた?商業主義も糾弾されて然るべきだろう。
更にこの虚構は、交響曲第1番が成立当初は『現代典礼』と自ら名づけた「指示書」による作品で、「ヒロシマ」とは全く無関係であった事が判明して、致命的な崩壊に行き着いた。簡単に言えばこれらの事件は音楽以外のところで全て起こった事で、言うなれば作品の属性に過ぎぬ事だ。あらゆる虚構もストーリーも、彼の「作品そのもの(本質)」とは無縁だった。そして佐村河内氏自身が、この音楽と無縁だったのだから、その徹底振りには、最早嗤(わら)うほかすべがない。
その一方で、
「一体、音楽とは何が具体的に表現でき、また我々はそれにどう向き合って享受すべきなのか?」
という事こそが、改めて深く考えられるべき問題として突きつけられたようにも思えてくる。
我々は自分を取巻く周囲のモノに対し、常に「意味」を求めている。自分に対してそれが存在している意味を考え想像し、その用途や形状や色合いなどの属性を含め、名を知り或いは名づけ、それで意味づけを行ったつもりになって、初めて心を落ち着ける。
「音楽」に対しても同様に接しようとする。そもそも言葉を介している音楽(歌)には、対処のしようがある。そもそもそのように作られているのだから。だが交響曲に代表されるような大掛かりで抽象的な音楽に対峙する場合、作曲者自身がよほどの意図を持って書いた作品意外、意味づけは本来殆ど不可能ある。
19世紀の交響曲は浪漫主義の思潮の中で、時空を超えて人々が共有可能のテーマを想定し得た。だが、20世紀以降それが不可能となって久しい。交響曲の褪色はある意味必然で、またそれ故に純音楽としての成り立ちも可能となるのである。かくして交響曲は確かに難解な音楽となった。そうした中で人々が敢えて交響曲に対峙しようとする時、作品への理解は、そこに附帯するストーリーをまとわせ、どれだけ意味づけが出来るかにかかっている・・・・というのはひとつの考え方ではある。大量消費の要素をそこに絡めようとすれば、この考え方はたちまち必須の条件となろう。
その一方で、音楽に対するときぐらい「意味づけ」から解放され、可能な限り音を音そのものとして捉えたいという欲求もあり得る。音楽に求める癒しの形のひとつとして、あらゆる具体的な意味から離れ、交響曲が創出するひとつの簡潔・整然とした秩序ある世界を経験するあり方である。
音楽への「理解」についてその正否を論じても仕方がないが、前者の理解方法が如何に恣意的で移ろいやすく、また音楽とはかけ離れた事情に影響され易いかは、今回の事件で判明した筈・・・・である。
今回取上げるブルックナーの交響曲は、特定のモチーフも無いために意味づけが殆ど不可能な上に、作曲者も生涯エピソードに乏しい朴訥そのものの田舎人。それだけに接し方も難しい部分があろう(個人的にはこうした素朴さこそが救いに思えるが)。
だが満艦飾に盛り付けたストーリーが嘘と判った時に、怒りの念を起こす事だけは避けられよう。「意味」に満ち溢れたワーグナーの音楽と対極にあると捉えて聴く事も、また一興とすべきかと思う。
ニーベルングの指環に関する雑文三題
226回演奏会でワーグナーの「ニーベルングの指環」からコンサート用抜粋曲を演奏するということでプログラム解説の執筆を引き受けることになりました。そこで、「ニーベルングの指環」についてあらためていろいろ調べ物をしました。維持会ニュースではプログラム解説に書ききれなかった雑多な内容をいくつかご紹介します。
■雑文1 ニーベルングの指環の予習
プログラム解説には、演奏する二曲を少しでも思い入れを持って聴いていただけるように、粗筋や聴きどころなどを書きました。しかし開演前の短い時間で読んでいただける分量や内容となるとどうしても限界があります。一方、この維持会ニュースはコンサートのだいぶ前に皆様のお手元に届きますので興味があれば予習に時間を割いていただけると思います。そこで、読みやすくて面白いネット上の記事を以下にご紹介します。いずれも個人の愛好家が自分の言葉で解説しているものです。
○ニーベルングの指環の全貌をひと通り知りたい方
(1)1998年4月25日『新響ニュース』より
「ニーベルングの指環」早わかり
http://www.shinkyo.com/concerts/i162-1.html
(2)1998年6月『新響維持会ニュース』より
時代性を超越した創作神話『ニーベルングの指環』
http://www.shinkyo.com/concerts/i162-2.html
(3)『るりこんのオペラハウス』の中の ワーグナー「ニーベルングの指環」のページ
(3)-1全体粗筋
http://www.d3.dion.ne.jp/~rulicon/ring.htm
(3)-2ラインの黄金:
http://www.d3.dion.ne.jp/~rulicon/rheingold.htm
(3)-3ワルキューレ:
http://www.d3.dion.ne.jp/~rulicon/walkure.htm
(3)-4ジークフリート:
http://www.d3.dion.ne.jp/~rulicon/giegfried.htm
(3)-5神々の黄昏:
http://www.d3.dion.ne.jp/~rulicon/gotterdammerung.htm
人物が一覧表になっていて、それぞれに一言コメントあり。全体の簡単な粗筋と4つのオペラごとの少し詳しい粗筋があって読みやすいです。
(4)オペラに使用されているライトモティーフの譜例と音源を網羅したページ(ただし英語)
http://www.pjb.com.au/mus/wagner/#d44
ちょっとわかりにくいですが、すべてのライトモティーフの音が出ます。
○ニーベルングの指環の元となるゲルマン叙事詩や北欧神話などとの関連性を知りたい方
(5)『無限空間』の中の「ニーベルングの指輪:神話・叙事詩から見た人物解説」
http://www.moonover.jp/2goukan/helden/wagner.htm
(6)「ドイツ叙事詩 ニーベルンゲンの歌」について
http://www.moonover.jp/2goukan/niberunku/index.htm
ゲルマン叙事詩や北欧神話の愛好家のページですが、素人の域を超えた情報量。ただし、著者はワーグナーのオペラにそれほど思い入れはないようです。
(7)ニーベルングの指環の場面を多量の絵で表現
武神妖虎氏制作 『ニーベルングの指環』
http://manji.gozaru.jp/
絵の枚数も膨大で台本もすべて和訳してあり(こういうのをバンド・デシネというらしい)、すごい力作です。ただし絵のタッチは好き嫌いが分かれるところかもしれませんし、少々露骨な描写もあるので作者がR15指定にしています。
■雑文2 ニーベルングの指環とコミック/ゲーム
今回解説を書くにあたってネタさがしのために『ニーベルングの指環』の主要登場人物をGoogleで検索してみました。その結果、ヒット数は以下のとおりでした(検索日5月10日)。ブリュンヒルデ約494万件、ジークフリート約24万件、ウォータン8390件、アルベリッヒ23300件 とブリュンヒルデが圧勝でした。 ちなみにワーグナーは約36万件でした。何でブリュンヒルデがこんなにヒットするの?というわけでその中身を少し紹介します。
“ブリュンヒルデ”でたくさん引っかかったのが「極黒のブリュンヒルデ」。なんじゃこりゃ?ということで調べてみたら、少年ジャンプに連載中の漫画でアニメ化もされているとのこと。粗筋を見る限り登場する魔女集団をヴァルキュリア(ワルキューレ)と呼ぶことぐらいが共通点のようで、なんでブリュンヒルデなのか? 作者がワーグナー好きなのかもしれません。
その次に出てくるのが「聖ブリュンヒルデ学園少女騎士団と純白のパン●ィ」(伏せ字は筆者)。これはいわゆるエロゲーといわれるジャンルのゲームのようです(勘弁してくれ~)。ゲームといえば「ファイナルファンタジー」や「パズドラ」のキャラクターにもブリュンヒルデがいるそうです。
ジークフリートのヒット数は桁違いに減りますが、やはり最初に出てくるのはゲーム系。「蒼覇王・カイゼルジークフリート」「蒼剣の覇王・ジークフリート」なんていうのが出てきます。また、青森のお菓子屋さん「ジークフリート」(銘菓「青い森」が有名だそうです)は青森では結構有名なお店のようです。ネットではほとんど出てきませんでしたが、白鳥の湖の王子様の名前もジークフリートでしたね。
さて、ウォータンで検索すると最初に出てきたのがこれ! 川崎市の水道キャラクター ウォータン だそうです(脱力~)。Water(ウォーター)→ウォータン だそうですから全く関係ないですね。
アルベリッヒのヒット数も多くてびっくりしたのですが、これもアニメ系で「聖闘士星矢」というちょっと古い漫画(アニメも)に出ていたのでした。この漫画にはジークフリート、ハーゲンやミーメまでいます。設定を見ると明らかに北欧神話に影響を受けた漫画でした。
ブリュンヒルデに戻りますが、あの「崖の上のポニョ」のポニョの本名がブリュンヒルデだというのはご存知でしょうか。しかも、ポニョが人間に変身して大波に乗って地上にやってくる場面の音楽がポニョの主題を用いていながら「ワルキューレの騎行」にそっくりな音楽になっているのです。
以上、どうでも良いお話でした。
最後に、「ニーベルングの指環」と名づけた漫画が五つあるので紹介します。私が全部を読んだのは(1)だけですがこれはなかなかの優れもので、粗筋の把握だけでなくストーリーを忠実に再現し、しかも飽きさせません。作者はワーグナーの台本をかなり読みこんでいるように思います。ただ、この本の前書きに、ワーグナーとクナッパーツブッシュといえば必ず出てくるあの有名音楽評論家の独断と偏見に満ちた“名(迷)解説”がついているのでご注意ください。書店に在庫はないでしょうから興味があるかたはネットでどうぞ。
(1)あずみ椋:「ニーベルングの指環」
お薦め。ただし絵は完全に少女漫画で、アルベリッヒやミーメの顔も整っていて違和感はある。
(2)里中満智子:「ニーベルングの指環」
1よりはアルベリッヒやミーメはそれらしい顔に見える。
(3)池田利代子:「ニーベルングの指環」
途中からストーリーが違ってくいとのことです。未読。
(4)松本零士:「ニーベルングの指環」
これは全く異なるストーリーのようです。未読。
(5)佐木飛朗斗:「妖変ニーベルングの指環」
連載が途中で打ちきられています。未読。
■雑文3 「演出に蹂躙(?)される音楽」
ワーグナーはオペラの作曲だけではなく作詞もト書きもすべて自分で制作しています。したがって『ニーベルングの指環』の各場面の状況はもちろんのこと、要所では登場人物の動きに至るまで事細かにスコアに記されています。上演にあたって音楽と詩はスコアに忠実に再現されている(というか、忠実に再現しようと努力されている)わけですが、一方で設定やト書きには全く忠実でない上演が近年非常に多くなっています。
第二次世界大戦でドイツ敗戦後に再開したバイロイト音楽祭では、ワーグナーの孫のヴィーラント・ワーグナーが舞台装置のほとんどない暗い空間に色のついた照明だけという演出を行いました。これは歴史的な名演出として語り伝えられています。具体的な舞台装置や小道具は一歩間違えると音楽のすばらしさをぶち壊す危険があるのですが、この演出は多彩な照明を駆使した抽象的なもののため、観客が音楽から喚起された感動を阻害されずに増幅させる効果があったというようなことがいわれています。考えてもみてください、勇壮な『ワルキューレの騎行』の音楽の中、模型の馬に乗った体格の良い中年の女性歌手8人が舞台の横から“のそのそ”と出てくる情景を! 何らかの方法で誤魔化す、言い換えれば様式化とか抽象化は大なり小なり必要になるのは自明です。ヴィーラントの演出はこれを徹底的に推し進めたものなのだという理解を私はしています。
この後しばらくはこのような方向の上演が主流になったとのことですが1976年にバイロイト音楽祭でフランスの演出家パトリス・シェローにより、舞台装置や設定を読み替えた革新的な上演がなされました。ライン川の場面では巨大なダムが現れ、ラインの乙女は娼婦のような衣装。神々の長ウォータンはフロックコートを着ている。19世紀の西欧社会を舞台に、権力階級、資本家と労働者階級の対立というようなテーマを盛り込んでいます。登場人物の動作や出てくる小物はワーグナーの指定に沿ったものも多いのですがそれらを具体化し明晰な明るい舞台にしたのです。これは登場人物への感情移入がしやすくなり、音楽のすばらしさだけでなく具体的な人間ドラマを感じられるという効果があったように思います。
これをきっかけにしてなのか、いろいろな設定の読み替え上演がなされてきました。ドイツの演出家ゲッツ・フリードリッヒは舞台設定をSF的な未来世界にして舞台に巨大なタイムトンネルを設置しました。ちなみに全曲通しの日本初演はこの演出での上演でした。核戦争後の世界を設定したものもありました(ハリー・クプファー)。このあたりまでは、舞台背景や装置が重厚で深刻な雰囲気をかもし出す方向は維持されており、ワーグナーのト書きとは全く異なるものの、音楽の雰囲気を壊すどころか新たな刺激を受けて感動が深まることが多かったように思います。
しかし、舞台設定読み替えの傾向は最近ますます先鋭化し、最近では音楽の壮麗・雄大な雰囲気にあえて水を差すことで何か新しいものを提供しようという方向になっているように思えます。たとえば、ブリュンヒルデの愛馬グラーネがおもちゃの馬だったり、ジークフリートが熊のぬいぐるみを持って出てきたり、神々族のいる世界(ワルハラ城)が米国の砂漠のモーテルだったりとかです。『ニーベルングの指環』以外でも『ローエングリン』ではねずみのぬいぐるみを着た兵隊が多数出てきたり、『さまよえるオランダ人』に出てくる船が手漕ぎボートのようなしょぼい船で、舞台が扇風機の工場だったりと枚挙に暇がありません。さらには、すばらしい音楽が流れているときに舞台上で大きなピストルの発砲音を出したり、設定にないダンサーが四六時中舞台でどたばたと痙攣したり、音楽以外のノイズをあえて出すような演出も見受けられます。こうなると目をつぶっても耳が邪魔されるわけで困ったものです。ワーグナーの壮麗・雄大で官能的な音楽魅了され、そこからワーグナーのオペラを見聞きしてきた私にとっては演出家が音楽を蹂躙しているとしか思えないのですがこれもワーグナーのオペラに新たな価値を見出すための挑戦なのでしょう。諦めとともに生暖かく見守っていきたいと思います。
ここからは全くの私見なのですが、ワーグナーの音楽はモーツァルトや晩年のリヒャルト・シュトラウスのように楽しくもあり悲しくもある とか ふざけているようで実はさびしい とかいう多面性を持ったものではないように思っています。『ワルキューレの騎行』は誰が聞いても勇壮で猛々しいし、ジークフリートとブリュンヒルデの愛の場面の音楽にパロディーやお笑いは感じられない。したがって茶化されてしまうと、そこで鳴っている音楽は救いようのない茶番になってしまうような脆さがあるように思います。一部の“天才”演出家はそれを知ったうえであえてその雰囲気とは相容れない視覚効果を提供しているのでしょう。ただ、音楽を邪魔する雑音だけは舞台で出さないでほしいと思います。演出がいやになったらアイマスクをすれば音楽に集中できますが、雑音は遮断できないから(笑)。“天才”演出家の皆さんへの音楽愛好家からのささやかな御願いでした。
ブルックナー:交響曲第6番
〈ブロック様式からロマン派様式への転換〉
聖者か、それとも俗物か?
19世紀ドイツ・ロマン派を代表する作曲家の一人、ヨーゼフ・アントン・ブルックナー(1824年~1896年)は、音楽史上でも実生活でも孤高な存在であった。
ヴェルナー・ヴォルフ(1883~1961)による評伝「ブルックナー―聖なる野人―」(音楽之友社)の「まえがき」に興味深い記述がある。ベルリン生まれでヨーロッパ各地にて指揮者として活躍、その後アメリカで音楽教育に携わり終生ブルックナーの音楽に帰依してきた彼の母親は、当時の音楽社交界の花形で、家には著名な作曲家や演奏家が始終出入りしていたという。

“わたしはまだ存命中のブルックナーに会う機会に恵まれた。1890年代のはじめだったと思うが、ある日、両親からわたしたち子供はこういわれた。「有名な作曲家のブルックナーさんがお見えになるから、ちゃんとお行儀よくするのですよ。」 そういわれてもとくにどうということはなかった。家にはそれまで(人名の記載省略)、錚々たる大音楽家が訪ねてきていたからである。ひとりひとりの個性は違っていても、これらの音楽家には、風格というものが備わっていた。
そしてある日、ついに彼があらわれた。(中略) だが実際に彼に会ってみて意外の観に打たれた。事実、これが作曲家!?と思わずにはいられなかった。(中略) この男はこれまでのどの音楽家ともちがった身なりをしていたので、わたしたちは唖然としてたちすくんでしまった。彼の着ている短めの黒い上着、だぶだぶのズボンは、スイスの田舎で見かけた農夫を思い出させた。
彼の口数は少なかったが、妹が部屋に入ってくると、妹の前に膝をついて、生粋の上オーストリア訛で「どやねん!いとはん!」といった。妹はびっくりして泣き出した。面倒なことになったが、それだけにとどまらなかった。昼食のとき、この風変わりな客は魚料理を手でつまみ、魚の骨を二つにへし折った。それで、両親がわたしたちになぜお行儀よくしなさいといったのか、初めて納得がいったのだった。
だが、この御老体の音楽を耳にするとすぐ、その風変わりな服装や奇癖は、みな気にならなくなった。(以下略)“
ブルックナーは子供たちにとって道化師であり、ずんぐりした姿と身なりは滑稽なものに映っていたのだろう。風変わりな服装は、オルガンを弾くのにも好都合であった。特に目立つのは、赤や青の水玉や市松模様、あるいは赤い色のバカでかいハンカチで、これは風呂敷としても使用しており、彼独特の合理性から生まれたものであった。
ブルックナーは、1880年8月13日から9月11日まで、夏季休暇を利用してヨーロッパの最高峰モンブランを観るという個人的な欲求のためスイス方面に旅行している。しかしながら彼の日記には旅の印象や感動の体験といったものの記載はなく、出会った若い娘の名前が驚くほどたくさん記載してあった。
また、踊りが好きなブルックナーは、シュトラウスのワルツをこよなく愛し、季節のカレンダーのメモ欄に、一緒に踊った女性の名前が克明に記入されていた。(どのような姿でどう踊ったのだろうか。)
終生変わらぬ若い女性に対する憧れは尊敬の念のみで結びついており、常に結婚を意識したもので、それ以外の目的で親しくなることは神の禁令にそむく忌まわしいことであった。
音楽以外では無関心であったブルックナーだったが、このような結婚願望をはじめとする強いこだわりは、風変わりな服装と相まって、ブルックナーの特異な素朴さから生み出された個性であり、人間ブルックナーと、創造者ブルックナーとの間の大きな相違から発生する矛盾と混乱が、彼の人生と創造全体の隅々にまで及んでいる。
ワーグナーとの交流
憧れの巨匠ワーグナーと初めて会ったのは1865年5月18日ミュンヘンでのことである。ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」初演を聴くために居たのだが、指揮者のハンス・フォン・ビューローとの出会いから実現した。交響曲第1番を見せるよう求められても、ひたすら恐縮していたブルックナーにはその勇気がなく、献呈の機会を逃してしまった。この時にワーグナーからもらった1枚の肖像写真は、終生自宅の祭壇にうやうやしく祭られていた。
1873年5月初め、それまでに自作の交響曲第2番と第3番のスコアを観てくれるよう懇願していたが、なかなか返事がなく、ブルックナーはワーグナーの承諾も無くバイロイトを訪問した。ワーグナーはバイロイトの祝祭劇場等の建設で忙殺されており、ブルックナーの申し出を一旦は断ったが、結局は交響曲第3番の献呈を受けている。
ヴィーンのアカデミー・ワーグナー協会に入会したブルックナーに対するワーグナーの評価は高く、バイロイトでもヴィーンでもブルックナーに会うたびに、「君の交響曲と全ての作品を私自身が演奏しますよ。」と言っていた。息子のジークフリートによれば、この約束は社交辞令にすぎなかったようだが、ブルックナーにとっては最大の励ましだったであろう。
ブルックナーは、ワーグナーの音楽にどのような関心を抱いていたのだろうか? 「タンホイザー」の第3幕、失意のタンホイザーが愛欲の女神ヴェーヌスのもとへ帰ろうとする場面で「おやおや、あの男はまたあの女のとこへ行きよる」と言った。また「ヴァルキューレ」の終幕では、「なぜあの女(ブリュンヒルデ)を焼き殺すのか?」と隣の弟子に尋ねたという。
さまざまな証言からは、あくまでもオーケストレーションや主題処理のテクニック、半音階的和声など音楽的側面のみが関心の対象であり、文学的・視覚的側面には無関心だったといえる。ワーグナーの音楽が持つ常軌を逸したような巨大さは、彼にとって永遠なるものであった。

交響曲第6番
規模や内容の充実度において交響曲と比肩する傑作「弦楽五重奏曲」を書いた後、作曲に取りかかっている。後期の創作活動への道を探る過渡的な作品と位置づけられており、ブルックナー自ら「対位法の傑作」とみなした交響曲第5番とは対照的に簡明で判り易く、ロマン的な瞑想性の上にあるのびやかな抒情性と明快さが特長である。この曲は、楽器群の音色によるタテのブロックを主張しつつ、楽想のかたまりが突然移動し、楽想が並列的に扱われるといった単純なヨコのブロック移行という所謂ブルックナー独特のブロック様式から、各ブロックが主題の変化とともに多くの経過句が入って自然に流れていくことで、聴きやすく洗練されたロマン様式への転換を示唆している。
1879年9月24日に第1楽章を書き始め、前述のスイス方面への旅行から戻ってきた直後の1880年9月27日にこの楽章を完成した。第2楽章は1880年11日22日完了、第3楽章は1880年12月17日から翌年1月17日まで、そして第4楽章は1881年6月28日スケッチを完了、1881年9月3日に完成している。この曲は「親切な家主」として感謝されていたアントン・フォン・エルツェルト=ネーヴィンとその妻アミーに献呈されている。
1883年2月11日初演当日、興奮したブルックナーは、弟子と共に朝の9時には左右不揃いの靴(片方は先のとがったエナメル靴)をはいて会場に姿を現した。近くのレストランでブルックナーからいくつかの命令を与えられた弟子の一番大切な任務は、師の宿敵である批評家ハンスリックを見張ることであった。この時は第2楽章と第3楽章のみしか演奏されず、ハンスリックからは冷遇され、その後この作品は注目を集めることがなかった。そのため複雑な改訂稿をもっていない。
第1楽章 マエストーソ
ニ長調、2/2拍子。ソナタ形式。ヴァイオリンが個性的で輪郭の鋭いリズムを刻む中(譜例1)、低弦による第1主題が「堂々と」(マエストーソ)登場(譜例2)。付点リズムの展開が続いて主題の全てが全奏で反復されて厳粛な中で緊張が高まる。
柔和で女性的な第2主題(譜例3)はヴァイオリンで、対比リズムとしての低弦による3連音符と共に登場する。抒情的で9度の飛躍が陶酔的。対位法的にこの主題が確保され、短い経過句で発展して力強い第3主題が登場(譜例4)。美しい移行句が続き、展開部に入る。主要主題は転回形で現れ、上行運動によって力が増幅、そして変ホ長調で第1主題が展開部のクライマックスとして出現、真のクライマックスである壮大な再現部の始まりが、イ長調で堂々たる威厳をもって登場する。このような重なりはブルックナーの優れた移行句といえる。
各主題が再提示される再現部を経て、最大のパッセージの一つとして幅広く長大なコーダに入る。鼓動のように刻まれるバスのリズムの上にコラールが鳴り響き、畏敬に充ちた転調と3連音符がまるで天上から光が降り注ぐ如く煌めきと荘重さが増しておおらかに展開。最高潮のうちに閉じられる。


第2楽章アダージョ、極めて荘重に
へ長調、4/4拍子。ソナタ形式。この交響曲の白眉。柔和で気品のある美しい音楽に満たされている。ヴァイオリンによる第1主題(譜例5)。そしてオーボエが嘆きのフレーズを添える(譜例6)。半音下降の音形は「嘆息」であり、バッハのロ短調ミサにもあるラメント・モティーフ(嘆きのモティーフ)のような、大いなる嘆きを表現している。そして全体に登場する全音階的下降音形は、宗教的で厳かな雰囲気を醸し出している。
第2主題は、幸福感を表す明るいホ長調でヴァイオリンとチェロにより対位法的に示される(譜例7)。さらに古典的な第3主題が葬送行進曲のように登場(譜例8)。ハ短調と変イ長調が混合し、変イ長調への無限の悲しみを秘めた転向を伴うこの主題は印象に残る。展開部は木管の全音階的下降音形(冒頭の低弦による音形)、ホルンとオーボエを経て、へ短調への復帰で始まる再現部は呈示部よりさらに立体的・色彩的に発展していく。コーダは単純且つ素朴だが、第1ヴァイオリンによるヘ長調の下降音階とチェロの上昇音階が魅力。卓越した効果をあげる無比な技術は、作曲家としての偉大さを示している。

第3楽章 スケルツォ:速くなく
トリオ:ゆっくりと
イ短調、3/4拍子。三部形式。ブルックナーの他の交響曲に登場するスケルツォとは異なり、幻想的で緊張感の中にも落ち着いた色彩がある。この楽章のみ〈ゲネラル・パウゼ〉が要所にあるのが面白い。低弦が属音のホ音を歯切れよくきざみ、三つの異なるメロディーが一体となって登場している(譜例9)。中心部には魅惑的なメロディーを経て第1部はイ長調で終結。トリオはハ長調でゆるやかに始まる。冒頭は弦のピチカートにより、変イ長調の属7和音第1転回のような響だが、ホルンが力強くハ長調で登場し、さらに木管が交響曲第5番の第1楽章第1主題のようなテーマで変イ長調を主張するかのように入ってくる(譜例10)。とても秀逸な調性の変化であり、最後は何事もなかったかのようにハ長調で終わる。第3部は第1部がそのまま再現してこの楽章を閉じる。

第4楽章 終曲 運動的に、速すぎずに
イ短調、2/2拍子。ソナタ形式。快活で情熱的な音楽。序奏が先行してイ短調で始まる(譜例11)。落ち着きがなく、ホルンとトランペットがイ長調で第1主題の前触れの如く割り込んできて、ホルンによる第1主題(譜例12)が呈示される。まるでアイドルグループが歌うポップスのような快活で明るい音楽。活力と躍動感に満ちた弦、ファンファーレ風な金管、なめらかな音形の木管が融合され、存分にブルックナーの公私にわたる高揚が反映されているようだ。オルガンの名手として即興演奏を楽しんでいる姿かもしれない。英雄的なファンファーレの後、第2主題はハ長調でヴァイオリンにより対位法的に登場する(譜例13)。〈常にきわだたせて〉と書いてある2つの決定的なメロディーとヴィオラの対比も美しい。要所に「トリスタンとイゾルデ」から「愛の死」の動機がそっと見えるのは偶然だろうか。第3主題は管楽器によるおおらかなもの(譜例14)と木管の歯切れのよい軽やかなもの(譜例15)からなる。展開部と再現部は、以上のテーマがブロックの如く、より大きな輝きを持って発展して明瞭かつ劇的に変化し、第1楽章の主題が回帰して重ねられ、巨大なコーダとなって終わりを告げる。

ブルックナーの花園
ワーグナーの「楽劇」には、古代ギリシャ悲劇のように、人間の持つ感情が深い洞察力と想像力で表現されており、ストーリーの展開に伴って、登場人物の性格や感情や欲望、お話の過去・現在・未来(予言)の全てを、音楽がドラマとして雄弁に語っている。ブルックナーの音楽には、ベートーヴェン、ワーグナー、ブラームスのような、人間的なドラマ性とか文学的側面を彷彿とさせるような感情が感じられない。実生活での体験や感情がどのような形で作品の内容に影響を与えているのだろうか。
ヴィーン大学の和声法・対位法の無給講師として採用されたブルックナーは1876年4月24日にヴィーン大学で就任講演を行った。(因みに交響曲第6番作曲中の1880年11月28日に有給化が承認されている。)原稿によれば、和声法と対位法について充分な知識を持つことが、創作にとってばかりではなく、音楽作品の正当な評価と判断にとって、いかに必要かを力説し、音楽がその構成要素の最小限にいたる
まで固有の法則をもつ有機体であるという思想が、格調のある名文によって明瞭に読み取れる。対位法と和声法のあらゆる技術を駆使し、独自なオーケストレーションと並はずれて強い調性感覚でこの思想を実現したものが、ブルックナーの交響作品といえよう。
ブルックナーの音楽的な妄想の中には、「ロマン的瞑想」と名付けられた「花園」があるに違いない。そこには、燦々と輝く天上の光を浴びて、ブルックナーのハンカチの如く、カラフルでポップな色とりどりの花が一面に咲き乱れており、ブルックナーが独特な風貌で歩いている。刻々と変わる調性と音響を表現するように、スキップしたり、立ち止まったりしながら、子供や女性に捧げるための花を摘み、静かに瞑想している姿が見えるようである。
注)新交響楽団第209回演奏会プログラム「ブルックナー:交響曲第9番〈永遠のゲネラル・パウゼ〉」及び第220回演奏会プログラム「ブルックナー:交響曲第5番〈真のブルックナー:厳格な技法とファンタジーの融合〉」も併せて参照していただきたい。
(新響ホームページから「過去の演奏会」を選択し第209回演奏会及び第220回演奏会の詳細にあり)
http://www.shinkyo.com/concert/p209-3.html
http://www.shinkyo.com/concert/p220-2.html
初演:1883年2月11日ヴィーン楽友協会ホール、ヴィルヘルム・ヤーン指揮ヴィーン・フィルハーモニー(第2楽章、第3楽章のみ初演)
1899年2月26日ヴィーン楽友協会ホール、グスタフ・マーラー指揮ヴィーン・フィルハーモニー(大幅なカットとオーケストレーションの変更あり)1901年3月14日シュトゥットガルト宮廷劇場、カール・ポーリヒ指揮 シュトゥットガルト宮廷楽団(全曲)
日本初演:1955年3月15日日比谷公会堂、ニクラウス・エッシュバッハー指揮 NHK交響楽団
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ1、ティンパニ、弦五部
参考文献
『ブルックナー ―カラー版作曲家の生涯―』土田英三郎(新潮社)
『ブルックナー ―聖なる野人―』ヴェルナーヴォルフ、喜多尾道冬・仲間雄三訳(音楽之友社)
『作曲家別名曲解説ライブラリー⑤ ブルックナー』音楽之友社編(同社)
『アントン・ブルックナー 魂の山嶺』田代櫂(春秋社)
ワーグナー:序夜と三日間のための舞台祝典劇『ニーベルングの指環』より
第一夜楽劇「ワルキューレ」より ワルキューレの騎行
第三夜楽劇「神々の黄昏」より 夜明けとジークフリートのラインへの旅
全曲上演には四夜を必要とし、延べ上演時間15時間にも達するオペラ『ニーベルングの指環』から有名なオーケストラ曲を2曲お送りします。
『ニーベルングの指環』は、古代から中世にかけてドイツから北欧を経て発展した「ニーベルンゲン伝説」を元にしてワーグナーが創作したオリジナルストーリーによる壮大なオペラです。序夜「ラインの黄金」、第一夜「ワルキューレ」、第二夜「ジークフリート」、第三夜「神々の黄昏」の4つのオペラにより構成されています。
本日演奏される2曲は、オーケストラの壮麗な響きを楽しめる有名曲で、演奏時間も長くありませんから単なる格好いいオーケストラ曲としても十分楽しめます。しかし、オペラの筋書きを知り、この曲の場面や登場人物を知れば楽しみは何倍にもなるでしょう。
1.『ニーベルングの指環』のあらすじ
◆序夜「ラインの黄金」と第一夜「ワルキューレ」の前史:神話の時代、世界は神々の長ウォータンが治めている。神々とはいえ妙に人間臭くて、ワルハラ城の建築資金支払いのためにニーベルング族をだましてその財宝を略奪したりする結構ずるいやつらでもある(なお、この財宝はニーベルング族のアルベリッヒがライン川から盗んだ黄金で、それから作った黄金の指環は世界征服の力があるといわれている)。とにかく、そのようなことをしなくてはならないほど神々族の権威には翳かげりがさしてきているのだ。ウォータンはこの難局を打開すべく、神々の掟に縛られずに自由な意志と愛によって行動する人間を利用して再び神々の栄光を取り戻そうと画策する。
◆第一夜「ワルキューレ」から第二夜「ジークフリート」まで:上記計画に基づいてウォータンが人間の女に産ませた兄妹(ジークムントとジークリンデ)の近親相姦によりウォータンの孫にあたる英雄ジークフリートが産まれる。紆余曲折の末、ウォータンが知の女神エルダに生ませた9人の娘の長女ブリュンヒルデとジークフリートが二人の意志によって深く結ばれる(叔母と甥の結婚! これでは省略しすぎですが後ほどもう少し詳しく解説します)。
◆第三夜「神々の黄昏」:その後ブリュンヒルデとジークフリートの2人は神々族を呪うニーベルング族の末裔ハーゲンが仕掛けた陰謀に嵌ってお互いを裏切り、ジークフリートはハーゲンに殺される。最後にすべてを悟ったブリュンヒルデは、ウォータンの遠大な計画の失敗と神々族の終焉を毅然とそして神々しく宣言してジークフリートの遺骸を焼く炎の中に身を投じる。この炎が神々族の住む天上のワルハラ城にも至り、すべてを焼き尽くして災いの元であった黄金の指環は元のライン川に戻る。そして世界は浄化され救済される(自由な意志と愛によって行動する人間たちの時代がやってくる。と解釈されることが多い)。
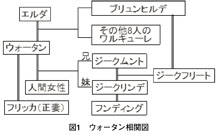
2.圧倒的な音楽の力
『ニーベルングの指環』は突っ込みどころ満載のストーリーです。神話を元にしたファンタジーのようでありながら、生々しくも不道徳な愛がたくさんあり、裏読みすればきりがなさそうな寓意や首尾一貫しない性格の登場人物など一筋縄ではいかないのです。男性主役のジークフリートは双子の兄妹の不倫の子供で女性主役ブリュンヒルデとジークフリートは叔母と甥の関係でありながら結ばれる。もう一人の主役であるウォータンはニーベルング族をだまして財宝を略奪したり、あちこちに子供を作って回ったりです。ウォータンとブリュンヒルデのやり取りも単なる父娘の愛以外の何かを感じてしまいます。とてもではないが不道徳でついていけないと感じる方も多いでしょう(実は魅力的なオペラのほとんどは不道徳なストーリーなのですが:薔薇の騎士、ドン・ジョヴァンニ、フィガロの結婚、椿姫等々。堅物のベートーヴェンは、ドン・ジョヴァンニのカタログの歌を聴き、モーツァルトはなぜこんな不謹慎な歌を作ったのか理解できないと言ったとか)。
ワーグナーはこのオペラで何を言いたかったのかについては多数の研究があります。旧態依然としたがんじがらめの社会体制や権力闘争を繰り返す勢力が滅び、愛と自由が勝利するというのが最大公約数の解釈のようです。これを拡大して舞台設定を近代以降の社会体制に、登場人物を実在の人物になぞらえるような穿った解釈もなされてきました。たとえば資本主義化する19世紀西欧社会の寓話という解釈(バーナード・ショーの解説)などがあります。これらがワーグナーのト書きとは異なる革新的な演出の生まれる素地になったのでしょう。これが高じて最近では演出家が自由奔放に設定の読み替えをしています。その一方で音楽の力は厳然としており不変で圧倒的です。たとえどんな演出がなされようが目を瞑って音楽に耳を傾ければ本来の筋書きが必然のように思えてくる、現代の道徳や常識からは大きく逸脱した登場人物にも感情移入してしまう、という危険な音楽なのです。「ワーグナーの音楽は麻薬のようである」と言われますが、まさにそのとおりだと思います。今日は麻薬のエッセンスを短い時間ですがお楽しみいただきます。
3.「ワルキューレの騎行」
1)この曲に至るまでの物語
ワルキューレの騎行が演奏されるのは第一夜「ワルキューレ」第三幕の冒頭です。その前の第一幕と第二幕のあらすじ(双子の不倫とその顛末)を紹介しておきましょう。
「ウォータンと人間との間の双子の兄妹の妹ジークリンデは少女のうちに略奪され、フンディングの妻として売られて奴隷のような生活を強いられていた。あるとき離れ離れになっていた双子の兄ジークムントと出合い、愛し合い、逃亡する。ウォータンは本心ではこうなることを望んでいたにもかかわらず、逃亡する彼らを神々の定めた結婚の掟のもとに罰せざるをえなくなってしまう。その兄妹を守ってはならないとウォータンから指示されたブリュンヒルデだがその兄妹の愛に心打たれ、ウォータンの命にそむいてフンディングから彼らを守ろうとする。しかしジークムントはウォータンに剣を砕かれてフンディングに刺されてしまう。ブリュンヒルデはジークリンデだけをなんとか連れて逃げる。自分の命にそむいたことで怒り心頭のウォータンがそのあとを追う」ここで第二幕終了。
2)「ワルキューレの騎行」の場面とその音楽
「ワルキューレの騎行」の場面でワーグナーの書いたト書きはおおむね以下のようなものです。
「岩山の頂上付近。舞台右方はモミの木の森。左方には岩山の頂上があってそのなかは広間ほどの広さがある洞穴である。舞台後方は岩場で、その奥は視界が開けて急な絶壁である。ちぎれ雲が嵐によって激しく通り過ぎていく。はじめに四人のワルキューレが岩山におり、ついで四人のワルキューレが岩山に向かってくる。いずれも鎧兜で装備し、馬に乗って稲妻が光る空を飛んでやってくる。」
ワルキューレとはウォータンが知の女神に産ませた9人の女神たちで長女がブリュンヒルデです。彼女らは戦死した人間の英雄たちを神々族の戦士とするために神々のいるワルハラ城に連れてくる役目を担っています。この音楽は彼女らが戦死した英雄を馬に乗せて集結する場面で、本来は8人の女性歌手の歌が入りますが今回の演奏は歌が巧妙にカットされてオーケストラだけでその雰囲気を味わえるようになっています。概ね二つまたは三つの示導動機(人物・物・概念などをそれぞれ固有の旋律で表したもの)からなっており、同じ示導動機が同じ楽器群で執拗に繰り返されます。ワルキューレの動機はトロンボーンやトランペット(譜例1)、騎行の動機は主にホルン(譜例2)、馬のいななき・嵐や風の音を表す効果音はひたすら木管と弦楽器が担当します。強靭なワルキューレが8人も集まって力いっぱい歌うシーンなのでどのパートもエネルギー最大で、常に力漲る演奏が要求されます。

オペラではそのまま切れ目なく、双子の妹を連れてブリュンヒルデが合流する場面になります。実はジークリンデはすでに兄の子を孕んでおり、それがジークフリートなのです。「もう逃げるのは疲れたから殺してくれ」というジークリンデにブリュンヒルデが語る「あなたのおなかの中には聖なる命が宿っている」というとき、勇壮でしかも悲劇的なジークフリートの動機が高らかに演奏されます。そこから幕切れまではウォータンとブリュンヒルデの対話のみで音楽は大変に盛り上がり、感動の終結を迎えます。といっても本日は演奏されません。まだ聴いたことのない方は「ワルキューレの騎行」の後の音楽を幕切れまでぜひ別の機会に聴いてみてください。

4.「夜明けとジークフリートのラインへの旅」
1)この曲に至るまでの物語
本日演奏する二曲目は、4つのオペラの最後「神々の黄昏」の初めのほうの場面の音楽です。結ばれたブリュンヒルデとジークフリートが夜明けを迎え、そしてジークフリートがライン地方に冒険に行く様子を描いています。
少し時間を巻き戻して、まずブリュンヒルデとジークフリートが結ばれた経緯を簡単に説明しましょう。第三夜「神々の黄昏」の前史にあたる第二夜「ジークフリート」の最終場面です。
年月が経って勇敢な英雄に育ったジークフリートが、ウォータンの怒りにより長い眠りにつかされていたブリュンヒルデを目覚めさせます。眠りの間は歳を取っていないことになっているので両者の歳の差は気にしなくて良いのでしょう。目覚めたブリュンヒルデは以下のように歌います。
「私は、あなたが母の胎内にいるときにあなたの命を助け、生まれる前にあなたを盾でかくまったのです。そんなに昔からあなたを愛していたのです。ジークフリート!」
ジークフリートは一瞬、目の前の女性が母なのかと勘違いします(母と息子!?)。こんなことを言われたら普通はたじろいでしまうでしょうが、ジークフリートにとっては母でも叔母でも問題なし。一方、ブリュンヒルデはウォータンから下された罰により神性を奪われて初めて人間の男性に抱かれるわけで、それを嘆いたりしますがすぐに受け入れてめでたく合体。オペラ史上最も壮大で天真爛漫な愛の音楽が延々と続きます。これで「ジークフリート」は幕となります。

2)「夜明けとジークフリートのラインへの旅」の場面とその音楽
第三夜「神々の黄昏」では、未来を予言する女神たちの不吉な夜の場面で始まりますが、その後次第に夜が明けていきジークフリートとブリュンヒルデの住む岩山に切り替わります。本日の演奏はこの場面の音楽から始まります。なんとも壮大な夜明け、それに続いて朝から凄い「愛の二重唱」です。今日の演奏は歌の部分を大幅にカットしていますが雰囲気は十分に伝わると思います。特に高貴な優しさと愛の高揚を感じさせる「ブリュンヒルデの動機」(譜例3)と元気の良い英雄の動機(譜例4)が印象的です。

ジークフリートの角笛をあらわすホルンのソロのあとはジークフリートが岩山を下りて川を下って行く様子を壮麗にかつエネルギッシュに描写する部分になります。このあたりの音楽は、主なものだけでも「炎」「ライン川」→「ラインの乙女の歌」→「黄金(のファンファーレ)」→「指環」→「(神々の)黄昏」→「ハーゲン」と多数の示導動機が次から次へと出現し、まるで早送りの映像を見るようです。この部分は、炎で囲まれたブリュンヒルデの岩山を降りてライン川に至ると、黄金を盗まれたことを嘆くラインの乙女の歌が聞こえてくる、最後はジークフリートを陰謀に陥れるハーゲンのいる館に到着する、ということをあらわしていると考えてよいでしょう。
オペラ上演ではこのあと切れ目なくハーゲンの住む館でのやり取りが始まるので、コンサートでは曲をどうやって終わらせるのかが悩みの種なのですが、本日は館に到着する直前から第一幕のエンディングに飛んで演奏を終わります。このエンディングは、ジークフリートがハーゲンの陰謀にはまって記憶を喪失し、別の男に変装してブリュンヒルデを誘拐しに来る場面を締めくくる音楽です。記憶を消されて変装したジークフリートと、見知らぬ男に襲われたと思っているブリュンヒルデ、二人の行く末を暗示するような切迫した音楽で幕を閉じます。
このあとの第二幕と第三幕では、陰謀、裏切り、復讐、殺人そして最後にすべてを悟ったブリュンヒルデの自己犠牲(自死)による神々の終焉と世界の救済という壮大なエンディングを迎えるのです。

「ワルキューレ」初演:1870年6月26日、バイエルン宮廷歌劇場、フランツ・ヴェルナー指揮
「ワルキューレの騎行」の部分の編成:ピッコロ2、フルート2、オーボエ3、コールアングレ、クラリネット3、バスクラリネット、ファゴット3、ホルン8、トランペット3、バス・トランペット、トロンボーン4、コントラバス・チューバ、ティンパニ2組、トライアングル、シンバル、中太鼓、ハープ6、弦五部
「神々の黄昏」初演:
1876年8月17日、バイロイト祝祭劇場にて開催された第1回バイロイト音楽祭において、『ニーベルングの指環』四部作として初演。ハンス・リヒター指揮
「夜明けとジークフリートのラインへの旅」の部分の編成:ピッコロ、フルート3、オーボエ3、コールアングレ、クラリネット3、バスクラリネット、ファゴット3、ホルン8、トランペット3、バストランペット、トロンボーン4、コントラバス・テューバ、ティンパニ2組、トライアングル、シンバル、グロッケンシュピール、ハープ6、弦五部
参考文献
『ジークフリート伝説ワーグナー『指環』の源流』石川栄作(講談社)
『ニーベルンゲンの指環ワルキューレ』R・ワーグナー、高橋康也・高橋迪訳、アーサー・ラッカム絵(新書館)
『ニーベルンゲンの指環ジークフリート』R・ワーグナー、高橋康也・高橋迪訳、アーサー・ラッカム絵(新書館)
『ニーベルンゲンの指環神々の黄昏』R・ワーグナー、高橋康也・高橋迪訳、アーサー・ラッカム絵(新書館)
『バイロイトの魔術師ワーグナー』バリー・ミリントン、三宅幸夫監訳、和泉香訳(悠書館)
『完全なるワーグナー主義者』バーナード・ショー、高橋宣也訳(新書館)
第226回演奏会のご案内
今回の演奏会は今秋に新国立劇場芸術監督に就任、ますます活躍の幅が広がる飯守泰次郎を指揮に迎えます。新交響楽団と飯守とのつきあいは、1993年4月の第139回演奏会から始まりました。バイロイト音楽祭の音楽助手として長年ワーグナーの音楽と関わってきた飯守との初共演は、ワーグナー楽劇「ローエングリン」第一幕への前奏曲と歌劇「タンホイザー」序曲、そしてブルックナー交響曲第4番でした。以降、新響は飯守の音楽と人間性に魅了され数多くの演奏を積み重ね、それぞれの演奏会が新響にとって大切な宝物となりました。24回目となる今回は、初共演と同じくワーグナーとブルッナーの音楽を取上げます。
ワーグナーは19世紀ドイツの作曲家で、楽劇と呼ばれる大規模で音楽を重要視したオペラを多く残しました。それらは多くの歌手と大きな仕掛けと時間が必要なため、聴く方も大変ですが、前奏曲などの管弦楽のみの部分を取り出してコンサート用に演奏されることも多く、ワーグナーの音楽を気軽に楽しんでいただけると思います。
今回は「ニーベルングの指環」という4部作、合計すると16時間もかかる長大なオペラから2曲を選んで演奏します。「指環」は世界征服も可能な力を持つ魔法の指輪をめぐる物語で、ジークフリートは主人公で英雄、ワルキューレは神々の長の9人の娘たちで女騎士、そのうちの1人ブリュンヒルデがジークフリートの恋人です。「ワルキューレの騎行」は、天馬に乗ったワルキューレたちが空を飛んでいる場面の勇壮な曲で、「地獄の黙示録」など数多くの映画やТVに用いられ、ワーグナーで一番有名な曲といっても過言ではないでしょう。「夜明けとジークフリートのラインの旅」は、ブリュンヒルデと過ごした主人公が永遠の愛を誓い、新たな活躍を求めてライン川に旅立っていく場面の輝かしい曲です。
ブルックナーは19世紀ウィーンの作曲家で、宗教的で荘厳な交響曲を残しました。ブルックナーはワーグナーを崇拝しており、第1回バイロイト音楽祭での「ニーベルングの指環」の初演も聞いています。作曲にも大きな影響を受けており、特に交響曲第3番はワーグナーに献呈しています。また、ワーグナーの死に際し嘆き悲しみ、ワーグナー・チューバ4本による葬送音楽を書いています。
今回演奏する交響曲第6番の作曲中に、ブルックナーはスイス旅行に出かけて大自然を満喫しており、その影響かこの第6番はのびのびとした親しみやすさがあり、ブルックナーの田園交響曲とも言われています。もちろんブルックナーらしいリズムや響きを持っていますが、他のブルックナーの交響曲と比べて、長さもほどほどでメロディが多く映画音楽のようで聴きやすいのに、演奏機会が少ないのはとても不思議です。ぜひこの機会にお聴きください。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
サン=サーンス:ヴァイオリン協奏曲第3番
指揮とともに静かに始まる弦楽器のトレモロに導かれて、独奏ヴァイオリンのG線の音色が深々と鳴り響く。その情熱的な音色に、一瞬にしてサン=サーンスの世界に惹き込まれてしまった。
私はこのサン=サーンスの「ヴァイオリン協奏曲第3番」が大好きである。
■サン=サーンスとヴァイオリン協奏曲
シャルル・カミーユ・サン=サーンス(1835-1921)は1835年10月9日に官史の家庭に生まれ、幼い頃から音楽的な才能を発揮した。2歳半より叔母から音楽の手ほどきを受け、3歳で最初の曲を作曲、7歳の時にピアノ演奏で聴衆を魅了し、モーツァルトと並ぶ神童とまで評価された。そして13歳でパリ音楽院に入学し作曲とオルガンを学び、15歳で「交響曲イ長調」を作曲した。やがて作曲家兼オルガニストとして活躍し、「世界で最も偉大なオルガニスト」と賞賛された。
彼は86年という長い生涯の中で様々な曲を作曲するが、その中でヴァイオリン曲は3つのヴァイオリン協奏曲、「序奏とロンド・カプリチオーソ」「ハバネラ」が有名である。今回の「ヴァイオリン協奏曲第3番」は1880年、サン=サーンスが45歳の時の作品で、当代きっての名ヴァイオリニストで初演者でもあるパブロ・デ・サラサーテに献呈された。ドラマティックな構成、情熱的でダイナミックなテーマや、流れるように美しいテーマが聴き手の心に強い印象を残すことから、彼のヴァイオリン協奏曲の中でも最も多く演奏されている。
■第1楽章(アレグロ・ノン・トロッポ、ロ短調)
ソナタ形式で書かれている。曲の冒頭、弦楽器のトレモロに乗って独奏ヴァイオリンのG線を中心とした低音で、力強く情熱的な第1主題(譜例1)が始まる。上昇旋律やアクセントのある和音、下降旋律を経て第2主題へと移行する。
ゆったりとした第2主題は優しさに満ち溢れ、第1主題とは対照をなす(譜例2)。
その後、展開部では第1主題・第2主題が転調して表れる。転調後の第1主題は、提示部とは異なり、16分音符が連なる音階が展開され、より高揚感が増す。一方第2主題は、提示部と同様にゆったりとしたのびやかな旋律になっている。
そして第1楽章は終盤へ向かう。独奏ヴァイオリンにより第1主題が再現され、トリルによってさらなる展開を期待させる。さらに3連符に続く16分音符の音階が細かくなり、緊迫感をもって第1楽章の終結を迎える。
■第2楽章(アンダンティーノ・クアジ・アレグレット、変ロ長調)
第2楽章は、第1楽章の情熱とは対照的に、ゆっくりとしたテンポで始まる。舟歌(バルカロール)の流れるような美しい旋律は聴く者を夢の世界へと誘うようだ。この穏やかな主題の中で、上昇と下降を繰り返すアルペジオが曲調に変化をつける。第2楽章中盤では、流れるような旋律(譜例3)が奏でられ、このテーマは第3楽章の序奏(譜例4)の伏線となっている。
そして第2楽章の白眉ともいうべき終盤を迎える。独奏ヴァイオリンの高音のフラジオレット(譜例5)とクラリネットのユニゾンのアルペジオが、静謐で天国的な雰囲気を醸し出す。なおこのヴァイオリンのフラジオレットは音程と表現の両立が難しく、ソリストの腕の見せどころでもある。
■第3楽章(モルト・モデラート・エ・マエストーソーアレグロ・ノン・トロッポ、ロ長調)
第3楽章は、独奏ヴァイオリンがカデンツァを力強く演奏し、それにオーケストラが雄々しく応えるという劇的な序奏から始まる。この緊迫したかけ合いは第3楽章の特徴の1つといえる。
その後、オーケストラの跳躍音と共に独奏ヴァイオリンの華々しい第1主題(譜例6)が表れる。この第1主題は、高音の符点リズムや3連符が特徴的で、急速な下降旋律や16分音符のスタッカートなどの技巧的な面も伴う。
第2主題は対照的に明快で楽しい旋律となっている(譜例7)。はじめに独奏ヴァイオリンが伸びやかな主題を奏で、途中からオーケストラを伴って繰り返し演奏される。そして讃美歌風のコラールが始まる(譜例8)。これまでとは雰囲気が一変し、全体的に高音を中心とした流れるような弓使いで奏でられる。しばらくすると軽やかな3連符が表れ、少しずつオーケストラと共にクレッシェンドしていき、オクターヴの3連符の直後、冒頭の序奏が再現される。
序奏の後は再び第1主題が華々しく表れるが、途中からオーケストラによる穏やかな旋律に変化し、そのまま転調した第2主題へと移行する。この第2主題は、はじめとは異なり深い音色でゆったりと始まる。3連符が表れると徐々にクレッシェンドし、オクターヴの旋律でオーケストラも主張し始め、次第に音の厚みが増して盛り上がりを見せる。
再びコラールの美しい主題が登場する。音量はフォルテから始まり、すぐにピアノに落ちてまたフォルテに戻る。このコラールの小さな変化は、曲が終盤に向かっていることを暗示しているようだ。それから8分音符の音階が長く続き、軽やかな3連符のアルペジオがいよいよ第3楽章の終盤を知らせる。
終盤になると、オーケストラも壮大になり3度目の第2主題が転調して表れ、テンポが上がると共に曲の盛り上がりが最高潮に達し、そのまま畳み掛けるように華麗な終結を迎える。
初演:1881年1月2日、パリにて、パブロ・デ・サラサーテの独奏による
楽器編成:フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペッ
ト2、トロンボーン3、ティンパニ、弦五部
参考文献
『サン=サーンス』ミヒャエル・シュテーゲマン著、西原稔訳(音楽之友社)
[CD]「デュメイサン=サーンスヴァイオリン協奏曲第3番他」松沢憲解説(EMI CLASSICS)
[CD]「サン=サーンスヴァイオリン協奏曲第3番他」福田弥解説(EMI CLASSICS)
(譜例準備中)
リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェヘラザード」
■海と音楽
ニコライ・アンドレーヴィチ・リムスキー=コルサコフは1844年、貴族の家庭に生まれた。家族が音楽好きであり、ピアノの教育を受けるなど音楽的に恵まれた環境で育ったが、同時に一族には海軍の軍人が多く22歳上の兄も海軍軍人であり、兄が寄港先の国々から送ってくる手紙を通して彼は海に興味を持ち、自身も船乗りになりたいと思っていた。
12歳でサンクト・ペテルブルクの海軍兵学校に入学した。趣味としてオペラや音楽会に通ううちグリンカのオペラに出会い、熱中する。自己流で作曲した作品が彼のピアノ教師の目にとまり、作曲の才を認められて音楽活動サークル「力強い仲間」の中心人物だったバラキレフを紹介された。17歳の時である。「力強い仲間」での理論的拠りどころはベルリオーズ著の「管弦楽法」だった。バラキレフは民族主義的というよりはむしろ当時イタリア一辺倒だったロシア音楽界に、ベルリオーズ、シューマン、リストなどのロマン派の風を吹き込もうとしていたらしい。バラキレフに勧められ、リムスキー=コルサコフはベルリオーズのこの本と、グリンカのスコアの実例だけを頼りにいきなり交響曲の作曲を始めた。
18歳で兵学校を卒業すると士官候補生として艦隊勤務を命じられる。海上勤務は3年半に及び、ヨーロッパ諸国から、南北戦争中のアメリカ、南米など世界各地を回った。この間ロンドン、ニューヨークをはじめ、行く先々でオペラや演奏会を聴いたようだ。
陸上勤務に復帰すると同時に「力強い仲間」にも復帰し、ここから本格的な音楽活動が始まる。完成した交響曲などで作曲家として世に知られることになり、28歳で音楽院教授に迎えられた。後に「和声学教程」や「管弦楽法原理」などの著作で知られる大家も、最初は作曲の実技能力のみで、理論はからっきしであったらしい。海軍は程なく退職したが、海軍軍楽隊監督官は長らく勤めており、作曲のため全ての管楽器を買い揃えて自分で吹いて研究したという。
■シェヘラザード
交響組曲「シェヘラザード」は1888年に作曲された。1887年に亡くなったボロディンの未完のオペラ「イーゴリ公」の完成作業を行ったことで、その東方的、遊牧民的な背景から千夜一夜物語へとつながっていったという見方もある。
曲はグリンカとベルリオーズから出発したリムスキー=コルサコフの管弦楽技法が一つの頂点に達したものと言える。固定楽想を使っているという点で、幻想交響曲との類似も指摘される。
■千一夜物語
千一夜(千夜一夜)物語は、ご存知「船乗りシンドバッド」「アラジンと魔法のランプ」「アリババと百人の盗賊」などを含む多数の物語から成り立つ物語集である。多数の話の全体を包括する「メタ物語」として、シャーリアール王とシェヘラザードの物語が登場する。あらすじは以下の通り。
シャーリアール王は妻の不貞を知ったことから全ての女性を信じられなくなり、若い女性と一夜を過ごしてはその日のうちに殺す、ということを繰り返すようになった。見かねた臣下の娘、シェヘラザードが王を改心させることを志願する。シェヘラザードは毎夜魅力的な話を王に語る。話の面白さに引き付けられた王は、次の話が聞きたくなり、今夜もまた明夜もシェヘラザードを殺すことができない。千一夜目についに王は自らの過ちに気づき、改心してシェヘラザードを正妻にすることを誓う。
■曲の構成
曲は4楽章からなる。それぞれに作曲者自身による千夜一夜物語的な題名がついているが、必ずしもアラビアンナイトから選んだ4つの話のストーリーを音楽で表現しているわけではない。第2曲、第3曲は対応する話がどれであるかもはっきりしていない。むしろ、シェヘラザードの語る物語の世界、物語に没入し、また我に返るシャーリアール王の心の揺れ動き、それにより王の心をひきつけ殺されまいとするシェヘラザードの駆け引き、などが絡み合って織りなす中世アラビアの王宮の夜の世界が音楽によって表されているかのようである。全曲にわたってシェヘラザードを表すヴァイオリンのソロが繰り返し現れ、その部分はヴァイオリン協奏曲のような趣である。したがってこの曲の場合、演奏会や録音でもソロヴァイオリンを弾くコンサートマスターの名前は特にクレジットされるのが通例である。
第1曲 海とシンドバッドの船
曲の冒頭はいきなりシャーリアール王の主題が提示されて始まる。暴君的な荒々しさの中にも威厳の感じられる主題である。全曲にわたってベルリオーズ流の固定楽想として現れるこの主題をまずは覚えておいていただきたい。続いておずおずとした、そして清楚な木管の和音の後、ひそやかなハープの導入とともにシェヘラザードの主題が独奏ヴァイオリンによって奏される。王との初めての夜、はじめは緊張感に満ちているが、次第に肝が据わっていき、本来の妖艶さを現していくシェヘラザードを思わせるようなソロだ。
ヴァイオリンのソロが終わると切れ目なく海の描写になる。もうシェヘラザードの語る物語は始まっているのだ。この海の描写の旋律は王の主題そのものであり、もう王は自分がシンドバッドになった気分である。大きくうねる海の描写は作曲者自身の艦隊経験に基づいているのか。うねりが少し収まるとホルンが王の主題の断片を静かに奏し、それに木管楽器のソロが入れ替わりシンドバッドのテーマで答えるというやり取りが何回か続く。その後ヴァイオリンソロが現れる一瞬は、王の心が物語の世界から現実に戻り、目の前にいる生身のシェヘラザードに気づく。それもすぐに王のテーマを用いた海の描写に戻る。王のテーマは様々に変形され、海のうねりもどんどん大きくなり、王の心も揺れ動く。再びうねりは収まり、日の光もさす。海が収まってもテーマは相変わらず冒頭の王のテーマの変形だ。これがチェロや木管のソロに現れる。また一瞬シェヘラザードの姿が見えるが、三たび海は大きくうねり始め、猛々しい姿を見せる。しかしそれもしばらくして収まっていく。海の姿と一緒に王の心も静まっていき、王は完全にシェヘラザードの語りの世界に取り込まれていく。最後にヴァイオリン群で静かに王のテーマが奏される。ということは、王とシェヘラザードが一体となったことを表すのか。
第2曲 カランダール王子の物語
2曲目はいきなりシェヘラザードのヴァイオリンソロで始まる。既に何夜も殺されずに生き延びてきている自信からか、もはや緊張感は消えている。むしろぐいぐい積極的で、妖艶さもかなりのものだ。物語もすんなり始まる。
カランダール王子は今でいうちょっと「KY」というか、ズレた感じの人間だ。その滑稽なところがまずファゴットの思い切り自由なソロで表される。これがオーボエのソロに受け継がれると伴奏がちらほら付き始め、ヴァイオリン群、続いて木管群がメロディーを奏するころになると人数も増えて、少しずつ世間と調子がそろい始め、歩調も軽やかになる。が、チェロとオーボエのソロに受けつがれると、また何やら物思いにふけっているような哀愁ただよう調子になってしまう。
すると突然トロンボーンが鳴り響き、謎の人物の登場となる。最初は一人のような気もするが、途中から明らかに人数が増える。騎馬の集団だろうか。カランダール王子もさすがにちょっとあわてた風だが、集団は構わず進んでいく。曲は最初のトロンボーンの主題が変形されて進行する。歩調は時に激しく、時に軽やかに、歩調も合ったり乱れたりである。ひとしきり集団に翻弄された後、カランダール王子の旋律がファゴットによりカデンツァ風に奏される。すると王子も次第に集団に飲み込まれて、オーケストラ全体が一体となってカランダール王子のテーマが盛り上がっていく。「KY」からの脱皮成功か、と思われるが、やはり王子は王子、テーマは次第に哀愁を帯びた調子に戻ってしまう。曲の最後の盛り上がりは、ああ、やっぱり駄目だったか、というような嘆きにも聴こえる。
第3曲 若い王子と王女
第3曲にはヴァイオリンソロによるシェヘラザードの導入はない。いきなり物語が始まる。弦楽器の美しい旋律はすっかりリラックスしたもので、もう殺される心配はないから前置きもいらないという感じだ。曲はたおやかにたたずむ若い王子と王女を表しているような弦楽器群の美しい旋律が続き、木管のオブリガートが彩りを添える。しばらくすると、舞曲風の曲調になる。王子と王女が踊っているのだろう。途中からはどんどん弦楽器がゴージャスに盛り上げていく。
美しい物語からふと目が覚めると眼前には生身のシェヘラザードが現れる(ヴァイオリンソロの登場)。王子と王女を表す弦楽器群の豪華な合奏にシェヘラザードのヴァイオリンソロが絡み、さらに木管が彩を添え、夢の世界と現実のシェヘラザードの姿が交錯する。一度大きく盛り上がった曲は次第に静かに収まり、最後はかわいらしく終わる。
第4曲 バグダッドの祭り、海、青銅の騎士のある岩にての難破、終曲。
一転、曲は緊迫して始まる。王の機嫌は悪い。第3曲のリラックスした雰囲気がうそのようだ。シェヘラザードも必死に恐怖に耐えて気丈に物語を始めようとしている。だが王の怒りは収まらない。2度目のヴァイオリンソロでは、シェヘラザードはいっそう身を固くして、声も絞り出しているようだ。だがともかく話を始めることはできた。バグダッドの祭りだ。にぎやかな話にようやく王も引き込まれ始めたようだ。
曲はバグダッドの雑踏を表しているのだろう。突然横から金管も乱入してくる。弟子のストラヴィンスキーが「ペトルーシュカ」でこの場面を参考にしたのではないかと思わせるような祭りのシーンである。王のテーマ、シェヘラザードのテーマ、第1曲から第3曲までに現れたテーマなどが次々に現れては消え、入り乱れ、また時に一体化し、祭りは延々と続き、盛り上がりを見せていく。シェヘラザードも一気呵成に語り続けているのだろう。王の気分も高揚してくる。しかし祭りの盛り上がりが最高潮に達すると、突然トロンボーンによって話は海の場面に転換されてしまう。極限まで盛り上がった気分の王には、脈絡なく変わった場面も気にならない。海は大荒れである。巨大なうねりが海面を押し上げ、押し下げ、船は木の葉のように翻弄される。ここで荒れ狂ううねりを表す金管の旋律はやはり王のテーマである。木管と弦は吹き荒れる風である。そしてついに船は難破する。と同時に王の心も崩壊する。砕け散った船の残骸は海面に点々としているが、海は一気に穏やかになる。美しい海の風景とともに王の心も別人のように晴れ渡る。女性に対する不信もすっかり払拭された。
するともはや物語の世界からは完全に覚醒した王の眼前にはシェヘラザードの姿がある。これまでのソロよりも音域を低く留め、抑えた感じになっているところに、シェヘラザードの安堵感が感じられる。王はシェヘラザードを自分の正式な妻とすることを決心し、曲は静かに終わる。
初演:1888年10月22日 サンクト・ペテルブルクにて、作曲者自身の指揮による
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2(2番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット2、ファゴット2、ホ
ルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、吊りシンバル、大太鼓、小太鼓、タンブリン、トライアングル、タムタム、ハープ、弦五部
参考文献
『ボロディン/リムスキー=コルサコフ』
(大作曲家・人と作品)井上和男著(音楽之友社、1968年)
『リムスキー=コルサコフ、交響組曲「シェエラザード」』
(最新名曲解説全集5、管弦楽曲Ⅱ)pp. 329-333、門馬直美著(音楽之友社、1982年)
ハチャトゥリアン:バレエ音楽「ガイーヌ」より
だだだだだだだだだだだだだだだ、だららっらっら、だららっらっら、だららっらっら、だららっらっら
運動会を思い出してくれたことでしょう。え、これでは分からない?いや、演奏を聞けば、きっと思い出すはず。分からない人は、よほど足が遅くて運動会をサボっていたか、お母さんのお弁当が美味しすぎて徒競走に出ることを忘れていたかのどちらかでしょう。今日は、思い出に浸る、そのような一日になることを願っております。
■音楽に囲まれた生活
アラム・ハチャトゥリアン、彼は故郷を愛し、そこにある音楽を生涯愛し続けた。1903年にグルジアの首都である「歌う町」トビリシに生まれた彼は、幼年時代を音楽の鳴り響くこの町で過ごすことになる。「歌う町」と呼ばれる町、これはハチャトゥリアン自身も認めることであり、
「私はいつも、この町を驚くほど響きに富んだ町と呼んでいる。(中略)音があちこちに響き渡り、町は音楽で溢れていた。タールやケマンチャ、ズルナーやドゥドゥークの楽音、1声からなるアルメニアの歌や多声的なグルジアの民謡、邸お抱えの民俗楽士のアンサンブルや柿売りの呼び声―—−そういったものが幼いころの私を取りまいた音の響きだった……」
と語っている。このように、民謡や民族音楽というハチャトゥリアンの音楽における重要な要素は幼年時代における音楽的土壌がもたらしたものであると考えられる。
■ガイーヌについて
彼は、ガイーヌを作曲する以前に、アルメニアの村における生活を題材としたバレエ「幸福」を作曲している。ガイーヌは、このバレエ曲を元に作られた音楽であり、バレエ「幸福」にまったく新しい第3幕、第2幕のかなりの部分、第1幕、第4幕の若干の小曲を書き足してガイーヌを完成させた。彼はバレエ「幸福」を作曲するにおいて、
「1939年の春・夏をアルメニアで過ごし、これから作るバレエ『幸福』の素材を集めた。ここではまた、ふるさとの民族音楽の、アルメニアの民間伝承のメロディーを真剣に学び始めた」
「あまりにも舞曲的な音楽だったので、バレエを〈シンフォニー化〉することを私の課題にした」
「私は民衆によって生み出された歌が、舞曲ふうのメロディーが、有機的にバレエの中へ入り込むように、また、これらがバレエ全体の音楽から分離できないようにしたかった」
と述べているように、民族音楽や民謡などの民族的モチーフをバレエ音楽に組み込むこと、バレエ音楽を〈シンフォニー化〉することを、自身の作曲の目標とした。また、ハチャトゥリアンは、ガイーヌというバレエ音楽には、舞踏性、ときには悲劇性にまで達するドラマティズム、それに叙情性、という3つの基本的要素がそのスコアの中に含まれていると示している。今回演奏する曲を聴いて頂いたとき、それぞれこの3つの要素が十分に含まれていると感じて頂けることであろう。
■剣の舞について
これほどまでに有名な曲でありながら、バレエ曲の1曲であると、これほどまでに知られていない曲はないであろう。また、この名曲がたったの一晩で書かれたことを知る人も少ないのではないだろうか。彼の言葉と手記から、その作曲の過程を見てゆこう。
「初演の前日になって、どうしてももう1曲新しい舞曲が必要だということになった。午後3時からとりかかったのだが、真夜中を過ぎても手がかりがつかめない。時間だけがむなしく過ぎていく。私はさまざまなリズムを指で机をたたいて試してみた。何か新しいリズム、剣をもって舞うにふさわしい激しいリズムが必要だった。…明け方近く、ついに新しいリズムが見つかった。それが『剣の舞』だ」
「1942年11月、劇場の依頼で、もうスコアが完成した後だったが、私は『クルド人の舞』(後になって『剣の舞』と呼ばれるようになったものと同じを書き足した。午後の3時に書き始めて、夜中の2時まで、ぶっ通しに働いた。翌朝、オーケストラにアレンジして、リハーサルを行った。(中略)私は思い出す。『剣の舞』のスコアの中で、3拍子の鋭いシンコペーションのリズムの箇所の上に「ちくしょう、バレエのいいようにしてくれ!」と書かざるを得なかったことを。もうひとつ思い出すのは、最初、私は踊りの最後の部分は、長くて徐々のディミヌエンド(次第に弱く)で終わりたかったのだが、アニーシモワとバレリーナたちは、私を説得して、逆に、徐々のクレッシェンド(次第に強く)で踊りの終わりとしたことだ」
こうして、名曲『剣の舞』はたった一晩で作曲されたのである。
今回の演奏に用いるスコア上には、上述のハチャトゥリアンの言葉で語られる「徐々のクレッシェンド」が書かれていないために、この言葉を残した当時の演奏とは少し異なったものにはなるかもしれない。初演が終わった後も曲の推敲を重ねていた事が窺える。彼は、音楽のジャンルとしてのバレエ音楽の特殊性を深く思量していた為に、バレエという踊りの芸術と、バレエ音楽という音の芸術の仲介者として、多くの葛藤と喜びを作曲の中に感じていたことであろう。
■バレエ音楽とは
最後に、ハチャトゥリアンにとって、バレエとは何なのか、彼の言葉をもって曲目解説を終わりたい。
「最良のバレエは、偉大な芸術である。その中には、人間の生活のすべての多様性、人間の豊かな精神体験のすべてを表現することができる」
「バレエは、オペラと同じく、諸芸術の総合の最高の表現だ、と私は考えている。音楽、舞踊、パントマイム、劇の動作、演劇・舞台の本源、装飾絵画、建築術、そしてときには、教会の合唱や詩の言葉も……何と手段が豊かなことか! 現実描写の可能性、偉大な思想的・芸術的概念の具体化の可能性、強い性格、情熱、感情の高揚などを明らかにする可能性、これらが何とかぎりなく秘められていることか! 視聴者に美的感化を及ぼす可能性が何と多様なことか!」
バレエ、音楽、そして諸芸術、その美しさと、表現の多様性に取り憑かれた作曲家アラム・ハチャトゥリアン。今日は、その作曲家の芸術的精神、民族的なものに対する愛慕と称美、そのようなことが少しでも感じられるような演奏をしたいと、思うわけです。では、後ほど舞台で。
初演:1942年12月9日ペルミ市 キーロフ記念レニングラード・オペラ・バレエ劇場にて、P.E.フェリットの指揮による(演出:N.A.アニーシモワ)
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、アルトサクソフォーン、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、吊りシンバル、大太鼓、小太鼓、タンブリン、テューブラーベル、タムタム、グロッケンシュピール、テューバフォン(管状の鍵盤をもつ鉄琴)、木琴、ウッドブロック、ハープ、ピアノ、チェレスタ、弦五部
参考文献
『ハチャトゥリヤン その生涯と芸術』ヴィクトル・ユゼフォーヴィチ著、寺原伸夫・阿蘇淳・小林久枝訳(音楽之友社)
『剣の舞 ハチャトゥリヤン-師の追憶と足跡』
寺原伸夫著(東京音楽社)
アラビアンナイトのこと
リムスキイ=コルサコフの傑作、交響組曲『シェヘラザート』を新響が採り上げるとなれば、この組曲のベースとなっている『アラビアンナイト(千一夜物語)』の事を看過する訳にはいかない。だがこれについて何を語ればよいのか?というより、先に白状しておくと、実を言えばこの本を読み通した事が無いのだから、それについて原稿を書こうという試み自体が既に愚かしくもあり、無謀でもあり既にして正気の沙汰ではない。が、せめてこの物語の性格くらいはここで解説しておかないと、読者である会員の方々が次なる演奏会へ足を運ぶ意慾も変わってこようと思われるので、無理を承知の使命感に基づいて、本稿を進める事にしたい。
◆恐ろしく読みにくい書物
僕は文学部の学生としての大学生活4年間の殆どを、オーケストラの部室か大学の図書館で過ごし、教室に顔を出した日数は明確に数えられるような生活を送っていた。もちろん成績は最悪で、オマル・ハイヤーム(12世紀のペルシャの詩人・哲学者)をテーマとして書いたおおよそ150枚の卒論は指導教官から酷評されたが、それでも4年で「出所」し、まがいなりにも就職できたのだから、思えば良い時代だったと言える。そうした中でまぁまぁ読書の習慣だけは何とか身につけたので、それを親に支払ってもらった授業料に辛うじて見合う唯一のものと考える事にしている。
世の読書家と言われる人々に比すれば誠にささやかなものだが、硬軟取り混ぜた読書体験を経て、世の中には「読みにくい本」というものが存在する事も身を以って知った。
分量のある本の頭の方しか読まないのを喩えて「聖書のマタイ読み」の言葉がある。聖書など本来どの福音書から読んでも良い筈だが、書物というものはすべからく表紙から入るものであるとの生真面目に考える人ほど、最初のマタイ伝から読んで挫折してしまう。
『源氏物語』54帖もご承知の通りひどく長くて、これは途中から読むという手立てが無いではないが、まぁ普通は頭から読む。するとやはり途中で挫折する人が古来絶えないと見えて、この場合は典雅に「『源氏』の須磨帰り」などと言う。つまり『桐壺』から読み始めて12番目の『須磨』の辺りで本をなげうつの意で、まぁ光源氏も須磨に都落ちするのを見届けたのでこの辺で・・・との心理が読者に働いてもおかしくは無い。だがまがいなりにも『須磨』まで行き着ければ大したもので、大抵の人は、あの忌まわしき(?)古文の授業で『桐壺』の冒頭を読まされただけで充分にウンザリしているのではないだろうか?・・・・と別に上から目線で読書を論じているつもりは毛頭無く、僕自身も「マタイ読み」「須磨帰り」に甘んじている本は沢山あって、今となってはその累々たる挫折の数々を、改めて踏破して行くのが老後の楽しみという半ば自棄半ば開き直りの心境に陥っている。
『アラビアンナイト』はそうした踏破対象のひとつである。この書名を聞くと『アリババと40人の盗賊』『アラジンと魔法のランプ』などをまず思い浮かべる人も多かろうが、これらはまぁ子供にも読ませられる部類の内容で、且つストー^リーも単純にされて、より親しまれているに過ぎない。ついでに言えばこれらの話は後世の補作の過程で紛れ込んだものとも言われている。
この本の冒頭はご存知の方も多かろう。ペルシャのとある王(シャリーアル)が、自分の妃と黒人奴隷との不貞を目の当たりにした事に起因して極度の女性不信に陥り、奴隷はもちろん妃も殺した後は、未だ手付かずの娘に夜伽させ、一夜明けると殺してしまうようになる。これを毎夜続けて遂には国中に処女がいなくなる(殺されるくらいならどんな醜男やろくでなしとでも早々に結婚して、捨てるべきものは捨ててしまおうと考える生娘も大勢いた筈だ・・・・と僕は考えてしまうのである)。そこで王は大臣に娘のシャーラザット(シェヘラザート)を差し出せと命じる。彼女は一計を按じ、妹と共に王の寝所に入ると千と一夜に亘り、払暁まで王に様々な物語を聞かせ続けて、命を永らえる手立てとする。これが膨大な物語の端緒・・・・であるからして、そもそも徹頭徹尾「大人の」世界の物語である。だから「読みにくい」と言っても、シャーラザッドが夜毎、王の寝所で聞かせる物語の内容が難解な訳では無い。
ではこの本が読みにくい理由は何か?と言えば、ひとつの話が次の話へとどんどん枝分かれしてゆき、脈絡無く玉石混淆とも言える様々な話が無限に拡大して、なかなか収まらないという点にある。シャーラザッドがある晩から語り始めた話を例にして説明しよう。
長く子に恵まれなかった、さる支那の王に男の子が生まれた。当然当代一流の学者がついて教育に当たる。この王子が10歳になった時、その聡明さを扶育官から聞いた王は、テストをしようと考える。ところが教育していた賢者が王子に対し、占いを立てると7日の間無言を通さないと、身の破滅が降りかかると出る。そこで王子にくれぐれも無言を徹底するよう言い置き、自らも姿をくらましてしまう。
その結果、王子は父の質問に何も答えない。父王は失望し怒る。そしてその夜、父の愛妾がこの王子を籠絡しようと迫る(相手は10歳だが、まぁ早熟な時代の話と理解しよう)。相変わらず王子は無言で、勿論拒絶する。女の方は収穫なしの上に、自分の言動が王の耳に入る事を怖れ、先手を打って王子に乱暴されたと讒言(ざんげん)する(ひどい女である)。父親たる王は相変わらず弁明さえせぬ王子を憎み、死刑にしようとする。
・・・・ここまででも実際は充分に長い話だが、問題はこの後からである。王子の処刑を命じられた大臣らが、言辞を尽くして王に翻意を促す。と、それを覆そうとする愛妾。この両者の間で「男と女とはそもそもどちらが不実であるか?」という論争になるが、この論争というのが、具体的にとんでもない男女を主人公とした「物語」で、王に対してこれを語って聞かせ、説得を試みる事になる。つまりシャーラザッドが王に語っている物語の中で、また物語が延々と語られるという劇中劇のような構造に事態は発展するのである。
そして更に重要な事実を申し添えれば・・・・ここに登場する大臣は7人もいる。そして7人の大臣が女の例をそれぞれ挙げると、愛妾の方は単身、その全てに対して男のデタラメさ加減を盛込んだ物語で応じる図式で、単純に考えても、ここに双方合わせて14の「話」が並ぶという訳である。それらがどんな話なのか各々一例ずつ挙げよう。
まずは大臣のひとりが語ったストーリー。
ある王の太刀持ちと懇ろな仲になっていたある人妻が、太刀持ちの小姓(きっとむくつけき太刀持ちの寵童だったのだろう)に目をつけ、自宅に招いて男女の仲になった。するとそこに件の太刀持ちが訪ねてきた。人妻はすかさず小姓を地下室に隠す。その上で太刀持ちを中に入れ、小姓との間で繰広げていた事の続きをしようとする。
するとそこに亭主が帰って来てドアを叩く。女は慌てず、太刀持ちに対して自分を大声でののしりながら家を出るように言い、男はその通りにして家を出て行く。入れ替わりに亭主が入ってきて、何があったのかを当然訊く。女は平然と「不始末をしでかした男が助けを求めて家に飛び込んできたのでかくまった。いま出て行った男はその主人で、『使用人を出せ!』とうるさくつきまとわれたが知らぬ存ぜぬで通し、男は悪態をついて出て行った」と言い、青い顔をして地下室で震えていた小姓を出して、帰らせた。
「アラーのお恵があるでしょう」と平然という妻に対し、何も知らぬ亭主(こうした悪知恵の働く多情な女の亭主は、大抵うすぼんやりしたおめでたい男だ)は「これは本当に良いことをした」と喜ぶ女というものはこれほどに平然とウソをつけるものなのだ(だから王も妾のいう事を鵜呑みにしてはいけない)と訴えた訳だ。
愛妾の方も負けてはいない。
武芸に秀でたある美しい王女に、美男の王子が恋慕した。が、王女の方は軟弱な男は大嫌い。それでも何とか自分と槍試合をして自分が負ければ受け容れようと言うところまで話は漕ぎ着いた。果たして試合をすると王子が負ける。願いは叶わなかった。
王子はこの王女の事が忘れられず、ひと財産全てを宝石に替え、且つ老人の姿に身をやつして王女の館に向かい、庭に控える。王女と取巻きの小姓らがやってくる。小姓のひとりが老人に呼びかけられ、彼と接吻する事(それだけ)と引換えに一番大きな宝石をもらう。翌日も別の小姓が同じ条件で宝石をもらう。それを見ていた王女は、宝石が手に入るなら、うす汚い老人だが接吻くらいいいだろうと、翌日老人のところに出向き、一番良い宝石を求める。宝石を手渡すと・・・・その「老人」は正体を現して王女に飛びかかり、本懐を遂げてしまう。結局このふたりは結婚するに至る。
男など誰しも、このようにあくどい事を平然とするものでございます(10歳の王子も同じでした)と、まぁこう言いたい訳でしょう。
話の出来は玉石混淆ながらこうしたものが7対の14話ずっと続く事になる(因みにここに挙げたふたつは良質な方である。もっとエロティックな話も多々あるのだが、それは『新響維持会ニュース』読者の良識と、編集人の掲げる崇高且つ高邁な方針とは相容れないとの判断から割愛。興味のある人は原作を当たって戴きたい)。そうした14の話と逐一付きあい、しかもその一話一話を真剣に読めば読むほど、いつしかこれはそもそも支那を舞台にして、年端もいかぬ王子の生死がかかっていたはずだ・・・・という肝腎の部分を忘れてしまうのである。『アラビアンナイト』の読みにくさの理由のひとつがここにあると僕は思う。これで多少はご理解戴けただろうか?
◆そして物語はまだまだ続く
結局7人の大臣が展開した弁論とも言える物語と、愛妾による反論によって7日が経過した。そこで王子が初めて口を開いてこれまでの事情と真実を語る。王は怒りの矛先を当然ながら讒言した愛妾に向け変え、処刑しようとする(どこまで行っても短慮な王様だと思うが)。王子はそれを諫め、「様々な考えや思惑が人々にはあるもので、全てはアラーの神のご意志に委ねましょう」などと今ならまだ小学生の癖に小賢しい事を言ってのけるのである(なんで支那の国の話なのにアラーなんだ?という突っ込みはさて置いて)。
周囲はもちろん王も、王子の利発さに感心し讃える。すると彼は「いえいえ。世の中にはもっと賢い人が沢山おります」と言って、その賢い人々の物語をその場で話し出すのである。これがまた長い上にいくつも続く・・・・結局当然だがこの王子が父王の跡を継いでめでたしとなる訳だが、この結末に至るまでに読者は20編に近い枝葉の物語を読まされる事になる。
このひとまとまりの長い長い話は、シャーラザットにして語るのに第576夜から第606夜(バートン版での数え方。各編纂によって大きな異同がある)まで費やしている。という事は、約1ヶ月に亘って夜毎この物語が続いていたという事である。語る方は文字通りの命がけだが、それを聞くシャリーアル王もいささかウンザリしていたのではないだろうか?しかもまだ千一夜ある全体の半分しか進んではいない・・・・。
実際シャリーアル王はシャーラザッドの物語に「じっと」「おとなしく」耳を傾けていた訳ではなく、千一夜の間に彼女に王子を3人生ませている。一夜の相手をその都度殺していた王が、子供まで拵えたのだから、その時点で王は考えを変えており、彼女の命は保障されていた事になるが、そういう矛盾を衝くのは野暮である。この王には同じように女性不信状態にある弟の王がおり、これがシャーラザッドの妹(ずっと姉共々シャリーアル王の寝所に控えていた)を娶って、全てが大団円となる。これが発端に比べて知る人が極端に少ない『アラビアンナイト』の結末である。
ここまでお読みになった方々は「読みにくいと言いながら、それでもお前は結末まで知っているではないか、通読こそしていなくとも、せいぜい第600夜近辺までしっかり読んでいるのではないか」と考えられるかもしれないが、これは「拾い読み」の結果で、実際には第24夜から第34夜まで続く『せむし男及び仕立て屋とキリスト教徒の仲買人と御用係とユダヤ人の医者との物語』という、表題を目にするだに込み入り具合が予測出来る物語で、早々に僕は挫折している。この全編を読破する事は近い将来ライフワークとなろう。齢を重ねる毎に「ライフワーク」が増えて行くのが最近の悩みであるが・・・・。
現代の我々にとって『アラビアンナイト』の世界は、古い時代の説話や神話に共通する「ストーリーの迷宮」とも言うべき性格を持っている。が、これを迷宮と感じ、また書物としての読みにくさを感じてしまうのは、近代以降、論理の一貫性や矛盾の無さと言った整然と体系化された価値観を我々が絶対視している事に起因するのかもしれない。そしてそれがあくまで相対的なものに過ぎず、この世界がそれだけで構成されている訳では決してないのだという示唆を、改めて与えられているようにも思えてくる。
この感覚は19世紀のヨーロッパ人も共有していただろう。そもそも『アラビアンナイト』は18世紀のパリで編纂・出版されたのが最初であり、イスラム圏に厳然と校訂・編纂された「原典」があってそれを翻訳したというものでは無い(そこに「増補」の物語が入り込む余地もあった)。そして編纂作業を経るうちに育まれ、芸術全般が触発されていったエキゾチズムの延長線上に、リムスキイ=コルサコフの交響組曲『シェヘラザート』が生み出されたと考えても良い。
この曲の美しく整然とした佇まいの全容を思い浮かべつつ、『アラビアンナイト』の混沌とした世界に浸るというのも、また一興と言えるかもしれない。
新交響楽団在団44年の思い出-6
編集人より
コンサートマスターを長年に亘って務められた都河和彦氏による回想録を、前年より掲載しております。今回は新響創立50周年を迎えた2006年から退団された2012年までを最終回としてご掲載致しました。
◆創立40周年(1996年)からの10年間-②
03年4月27日のコンサートは高関先生がバルトークの『中国の不思議な役人(全曲版)』を振ってくださいました。初練習の2月8日(土)は午後に娘の結婚式に出席した後、練習に駆け付けたのですが、この曲は私が新響で弾いた数々の曲の中で最も難しかった曲の一つ、との印象があります。このコンサート前の4月8日に新響を何度か振ってくださり、ベルリン演奏旅行にも連れて行ってくださった石井眞木先生が67歳の若さで逝去されるという悲しいできごとがありました。先生の遺灰は遺言により中国の砂漠に撒かれた、と聞きました。
7月のコンサートは飯守先生が湯浅譲二先生作曲の交響組曲『奥の細道』と、ソプラノ独唱に緑川まりさんを迎えたR・シュトラウスの『4つの最後の歌』等を振ってくださいました。シュトラウスの第3曲『眠りにつくときに』で私がヴァイオリン・ソロを担当して緑川さんの伴奏をしたのはなつかしい思い出です。
10月の定期は小泉和裕先生指揮でオフチニコフ氏がラフマニノフの『パガニーニの主題による狂詩曲』を弾きましたが、どうも両者の息があまり合わなかった、という記憶があります。
私は03年11月末に還暦を迎え、技術の低下、眩暈(めまい)、左肩痛や右腕の痺れ等に悩まされるようなってコンマスを降りて退団しようと考え、04年1月のコンサートで小松一彦先生に安部幸明の交響曲第1番を振っていただき短いソロを担当したのが新響定期演奏会でのコンマスとしての最後の舞台になりました。「退団」の方は「ヴァイオリンのメンバーが足りないから辞めないでくれ」と頼まれ、しばらくヴァイオリンの1団員として残ることになりました。
04年4月の石井眞木没後1周年コンサートでは高関先生がR・シュトラウスの『ばらの騎士』組曲、石井眞木先生の『幻影と死』、ベートーヴェン『運命』を振ってくださったのですが、石井作品が静かに始まった途端、「ガラガラ・ドッシャーン」という楽譜にはない大音響が会場に響き、演奏は中断しました。ビブラフォンの足のネジが緩んでいて山台から転がり落ちたということでしたが、多くの団員が「眞木先生の亡霊が出た!」と感じていたようです。
6月に郡山での特別演奏会がありました。地元のテレビ局が郡山出身の著名な音楽家、作曲の湯浅譲二先生と指揮の本名徹次氏に関連した演奏会を企画、本名氏指揮で新響が少し前の定期で取り上げた『ばらの騎士』、『奥の細道』、『運命』のプロで演奏しました。4月の定期で『ばらの騎士』のヴァイオリン・ソロを弾いたコンミスの堀内真実さんが旅行に参加できなかったので私がソロを弾き、『運命』は岸野ゆかりさんがコンミスを務めました。本名氏は薄皮饅頭で有名な柏屋の御曹司だったので本番の日の朝、会場に饅頭の差し入れがあったと記憶しています。
8月の大久保混声合唱団の伴奏もコンマスが出演できなかったので私がコンマスを務めました。暑い盛りのコンサートで眩暈がひどく、コンサート後すぐに近くの耳鼻科病院に駆け込んでまずい飲み薬を処方してもらいました。12月の大町先生指揮・龍ケ崎第九市民合唱団との『第九』公演では左肩痛で満足に弾けませんでした。この痛みはなかなか消えずもう退団と考えたのですが、ヴァイオリン・メンバー不足ということでまたも退団できませんでした。左肩痛については、翌年4月に新響チェロ団員白土菜穂さんの整形外科医の御主人に治療を受け大分和らぎました。
05年の4回の定期はヴィオラが足りないということで(痛い左肩をかばいながら)ヴィオラを弾きました。1月の小松先生指揮でのレスピーギの「ローマ三部作」の大音響、7月の飯守先生指揮ラヴェルの『ダフニスとクロエ』全曲の難しさが思い出に残っています。
10月は渡邉先生がアナスタシア・チェボタリョーワ女史(1994チャイコフスキー・コンクール最高位)を招いて芸術劇場でシベリウスのヴァイオリン協奏曲とドヴォルザークの『新世界』等を振って下さいました。アンコールでドヴォルザークの『スラブ舞曲』を演奏中、かなり大きな地震が起き聴衆は一瞬どよめき団員はふらつきながら弾いていましたが、渡邉先生は夢中になってタクトを振り続けていました。打ち上げで私が先生に「地震に気付かれましたか?」と尋ねたら「え、何のこと?」との答えでやはり、と思いました。
◆創立50周年(2006年)から現在(2012年)までの6年間
2006年2月、芥川先生の師匠で、新響が数多くの作品を何回も演奏した伊福部先生が91歳で逝去されました。新響は先生の個展を1980年に開いて以来、古稀(70歳)記念(’84)、喜寿(77歳)記念(’91)、傘寿(80歳)記念(’94)、米寿(88歳)記念(2002)とお祝いのコンサートを重ねてきました。ちなみに03年の文化功労者受賞お祝いコンサートは長田雅人指揮・ニッポニカが、卆寿(90歳、04年)お祝いコンサートは本名徹二指揮・日本フィルが開きました。03年の受賞お祝いパーティーでは「昔、出征する兵士を鼓舞する曲を書けとお上に言われて書いたことがある。今回文化庁から電話というので『イラクに派遣される自衛隊員を鼓舞する曲を書けというのだな、困ったな』と考えながら電話に出たら『文化功労
章を受けて頂けないでしょうか?』ということで驚いた」とユーモアたっぷりにスピーチなさっていました。先生の死はまさに「巨星落つ」の感があり、お葬式で香典返しとして頂いた5匹のゴジラの砂糖果子と、先生の筆跡で「伊福部昭作・日本狂詩曲」と書かれた花瓶は我が家の家宝になっています。
50周年記念の1月のコンサートは小松先生がショスタコーヴィッチの大曲、交響曲第8番を振って下さり、4月は高関先生がR・シュトラウスの大曲『アルプス交響曲』を振ってくださいました(私は06年4月から09年1月まで又、ヴァイオリンに戻りました)。
7月のサントリー・ホールでのコンサートでは指揮界の大御所、岩城宏之氏が黛敏郎作曲の『涅槃交響曲』を振って下さる予定でしたが6月に他界(74歳)、昔岩城氏にお世話になった小松一彦先生が1月定期に続き、急遽振ってくださいました。
11月は飯守先生指揮で緑川まりさんたち素晴らしい5人の歌手陣と男声合唱でワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』抜粋をコンサート形式で演奏、曲の難しさに音をあげましたが、またまた素晴らしいワーグナーの世界にどっぷりと浸かることができました。
07年7月には山下一史先生が初登場、お得意のブラームスやR・シュトラウスの交響詩『英雄の生涯』等を振ってくださいました。『英雄~』のヴァイオリン・ソロはコンミスの前田知加子さんが担当して名演を披露しました。山下先生とはそれ以来5回共演、2013年7月にも予定されています。彼が1986年に急病のカラヤンの代わりにジーンズ姿で急遽ベルリン・フィルで第九を振った話は有名です。昨年(2011年)3月の大震災直後の日経新聞の手記には、「仙台フィル本番前のリハーサルの休憩時間に大揺れがきた、ホテル20数階の自室まで階段を登った、翌朝ホテルには食べ物がなく外の屋台で何とか食べることができた、知り合いのタクシー運転手が福島空港まで送ってくれて帰京できた」等の苦労話を書かれていました。また、私は「Daily Yomiuri」という英字紙を愛読しているのですが昨年暮、山下先生の大きな写真が出ている記事が目にとまり読み始めたらびっくりしました。「広島の原爆資料館にはすっぽり抜け落ちた若い女性の髪が展示されているが、この髪の主は指揮者・山下一史氏の母親、博子さんのものである」とあったのです。山下先生の母上は18歳の時爆心地近くで被爆、数日後に髪がすっぽり抜け落ちたそうです。記事は山下先生がベルリンで勉強していた高関先生に合流、一緒にベルリン・フィルのリハーサルを盗み聴き?していたことにも触れていました。
08年4月の定期は飯守先生がシェーンベルグの交響詩『ペリアスとメリザンド』を振って下さり、練習では濃密なシェーンベルグの世界にどっぷりと浸ることができたのですが本番数日前、米イェール大学に出張中だった家人から電話がかかり、「食中毒にかかって入院している。体力が落ちているので迎えに来てほしい」とのことで急遽渡米、折角積み重ねた練習をフイにし、新響にも迷惑をかけてしまいました。
10月の定期は小松先生がエルガーの『エニグマ変奏曲』やドヴォルザークの交響曲第8番等を振ってくださり、9月の合宿は(鹿島が使えなくなったので?)千葉県蓮沼の「小川荘」という民宿を初めて使用しました。オケが練習できるホールはありましたが、駅から遠い、施設が汚い等々、余り良い印象はありませんでした。このコンサートではエニグマが難しかったこと、ドヴォルザーク第8番第4楽章冒頭の野崎・青木のトランペット・コンビによる完璧で見事な演奏が印象に残っています。
09年1月のこれまた小松先生指揮の『芥川也寸志没後20年』のコンサートでは芥川先生の下で20年間コンマスを務めた私に花を持たせようということだったのでしょう、第1曲目の『トリプティ-ク』のコンマスとソロを務めるよう演奏委員会から要請がありました。演奏技術の低下や左肩痛、右腕の痺れ等から固辞したのですが、四方八方からの圧力に屈して引き受けたら、やはり本番のソロはいささか悲惨な結果になりました。これで今度こそ退団、と思ったらヴィオラ首席だった柳澤秀悟氏から「人数が足りなくなったからヴィオラに戻ってくれ」と頼まれ、今回の退団まで3年間ヴィオラ・セクションでお世話になりました。
9月に小松先生とショスタコーヴィッチの交響曲第5番等を携えて小出・新潟演奏旅行に行き、10月の定期も小松先生が振ってくださったのですが、その後先生が急病で入院され現在まで容態が分からず、何とも心配なことです(編集人注:小松先生は2013年3月に死去)。
10年1月は曽我大介氏が初登場してバースタインの『キャンディード』序曲等を振って下さり、翌11年1月はエネスコ、今年10月はガーシュウィンとコープランドなど、今迄新響が殆ど取り上げなかった作曲家の作品を振って下さいました。今後もこれら新分野でのおつきあいが続きそうです。
10月の定期は山下先生が新進気鋭の作曲家、権代敦彦氏の『ジャペータ-葬送の音楽I』を取り上げ、9月の蓮沼での合宿には権代氏も来て下さいました。ハープの篠崎さんが何度か権代さんに作品を委嘱していて舞台に登場する時の衣装の強烈さが印象にあったのですが、合宿参加のため東京駅に現れた時もズボンは真っ赤でした。10年ほど前から新響の弦楽器トレーナーをしてくださっているN響ヴァイオリン奏者の齋藤真知亜氏はここ数年、年に一度「Biologue」と銘打ったリサイタルを開いているのですが、今年6月の目黒教会でのコンサートでは権代氏に「キリストがゴルゴダの丘を十字架を背負いながら登って磔にされる」ことを主題にしたヴァイオリン独奏曲の作曲を依頼、初演しました(お二人ともクリスチャン、ということを初めて知りました)。又ハープの篠崎さんは今年10月オペラシティーで開いた『ハープの個展シリ-ズ40周年記念』コンサートでは今をときめく作曲家、権代敦彦・西村朗・野平一郎諸氏に新作を依頼、作曲者がオケを指揮する、と超意欲的なコンサートを開いたのですが、権代氏は真っ赤なジャケットを着て自作を指揮、ご満悦でした。
11年7月に飯守先生の推薦で登場したアメリカ在住の女性ヴァイオリニスト松山冴花さんのブラームスのコンチェルトは圧巻で、銘器ヴィヨームと名弓トゥルテの相性は抜群でした。団員の総意で今年7月にも彼女をお招きしてサン・サーンスのカデンツァを使ったベートーヴェンのコンチェルトを弾いていただいたのは私の最後の新響定期として良い思い出になりました。
私はここ数年聴力が低下して、広い会場で練習する新響ではトレーナーや指揮者の注意や要求が聞こえづらくなったので(小規模な室内オケの活動では問題ないのですが)、大編成オケでの活動はもう無理、と判断して今年7月の定期演奏会で44年間の新響ライフに終止符を打つことにしました。振り返ってみると、これまで69年間の人生のほぼ3分の2を新響で過ごし、数々の思い出・感動を頂いたことにいくら感謝してもしきれません。多くの団員・指揮者・トレーナー・作曲家・独奏者と知遇を得ることができ、また69年も生きていれば当然ですが、多くの方々との悲しい別れもありました。
日本には数多くのアマチュア・オケがありますが、新響は演奏面・運営面でも常にそのトップを走り続けてきたと思います。これからもずっと、日本アマオケ界の雄としてはばたき続けて欲しいと願っています。(2012年11月30日記)
*2012年末から1年半6回に亘って連載致しました都河和彦氏の回想録は今回で終了です。44年間、新響と共に歩んで来られた軌跡は、新響としても将来に伝えられるべき財産です。執筆戴いた都河氏には改めて感謝致します。有難うございました。
今後この全文は新響のホームページで読む事が可能です。
「これまでの演奏会」http://www.shinkyo.com/02past/ から
「第220回演奏会」以降の「詳細はこちら」に入り、維持会ニュースの欄をご覧ください。
第225回演奏会のご案内
曽我大介〜新交響楽団4回目の登場
今回の演奏会は、ドラマチックな演奏が魅力的な曽我大介を指揮に迎え、2つの物語の音楽をお届けします。「剣の舞」で有名な「ガイーヌ」と、フィギュアスケートでもたびたび使用されてお馴染みの「シェヘラザード」です。
ガイーヌ〜ソ連コルホーズのお話
1942年に初演されたバレエ「ガイーヌ」は、ソヴィエト時代の作曲家ハチャトリアンの代表作です。ガイーヌはアルメニアのコルホーズ(集団農場)で働く愛国心の強い女性。夫が密入国者の手伝いをしていることを知り、危険を冒して告発し、その時夫を捕まえ自分を助けてくれた警察隊長とめでたく結婚するというお話です。(改訂版では若者の恋の話に変わっています。)全曲で100分ほどかかる作品ですが、今回はその中から剣の舞、レズギンカなど5曲を演奏します。アルメニアの民族色に富み、躍動的で迫力のある音楽をお楽しみください。
シェヘラザード〜アラビアンナイト
1888年に作曲された交響組曲「シェヘラザード」は、ロシア5人組の一人で色彩的な管弦楽法で知られるリムスキー=コルサコフの代表作です。シェヘラザードはアラビアンナイト(千夜一夜物語:10〜16世紀にアラビア語でまとめられた民話集)の語り手として登場する女性。ペルシャの王が妻の不貞を発見した怒りから、処女と結婚しては一夜限りで翌朝殺してしまうことを繰り返した後、大臣の娘シェヘラザードと結婚をした。王は夜に彼女がする不思議な話が面白く、朝になっても次の話を聞きたくて彼女を殺すことが出来なかった。これが千夜続き、その間に3人の子が生まれ王は改心したというもので、話には、アラジンと魔法のランプやアリババと40人の盗賊など、有名なお話が含まれています。
この曲は4つの楽章からなり、それぞれに表題は明記されていませんが、シンドバットの冒険など4つの物語を表しています。各楽章で語り手であるシェヘラザードの主題が高音域の美しいヴァイオリンソロで演奏されます。
大谷康子~華麗なるコンサートミストレス
シェヘラザードではコンサートマスター(第一ヴァイオリンのトップとしてオーケストラの演奏をまとめる役割で、ヴァイオリンソロを受持つ)として大谷康子を迎えます。大谷は81〜94年東京シティフィルハーモニー管弦楽団、95年から現在まで東京交響楽団のコンサートマスターを務める日本を代表するヴァイオリン奏者で、他にもソロやボランティア活動など、各方面で活躍し華のある演奏で聴く者を魅了します。
今回はサン=サーンスのヴァイオリン協奏曲第3番でもソロを演奏します。美しくロマンティックで力強さもあるこの曲はピッタリでしょう。当団との初共演にご期待ください!
どうぞお楽しみに!(H.O.)
第224回ローテーション
| 黛 | 芥川 | 松村 | 伊福部 | |
| フルート1st | 吉田 | 岡田(+Picc.) | 松下 | 松下 |
| 2nd | 藤井 | 藤井 | 兼子(+Picc.) | 新井 |
| 3rd | 岡田(Picc.) | 吉田(+Picc.,Alto) | - | 兼子(Picc.) |
| オーボエ1st | 堀内 | 堀内 | 堀内 | 宮内 |
| 2nd | 宮内 | 桜井 | - | 桜井 |
| コールアングレ | 岩城 | 岩城 | 岩城 | 岩城 |
| クラリネット1st | 末村 | 品田 | 進藤 | 高梨 |
| 2nd | 大藪 | 中島 | 中島 | 大薮 |
| バスクラリネット | 岩村 | 岩村 | - | 石綿 |
| ファゴット1st | 齊藤 | 田川 | 浦 | 浦 |
| 2nd | 田川 | 齊藤 | - | 野田 |
| コントラファゴット | 野田 | 野田 | 齊藤 | 田川 |
| ホルン1st | 大内 | 鵜飼 | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 山口 | 市川 | 大内 | 森 |
| 3rd | 箭田 | 森 | - | 鵜飼 |
| 4th | 大原 | 山口 | - | 市川 |
| 5th | - | 大内 | - | - |
| 6th | - | 大原 | - | - |
| トランペット1st | 倉田 | 北村 | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 倉田 | 北村 | 野崎 | 小出 |
| 3rd | 中川 | 中川 | - | 中川 |
| トロンボーン1st | 武田 | 武田 | 武田 | 志村 |
| 2nd | 志村 | 志村 | 岡田 | 小倉 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | - | 岡田 |
| テューバ | 土田 | 土田 | - | 土田 |
| ティンパニ | 中川 | 桑形 | 桑形 | 古関 |
| パーカッション | 大太鼓/古関 マラカス・グロッケンシュピール・タムタム/皆月 小太鼓+拍子木/浦辺 シンバル/桜井 中太鼓/今尾 |
ボンゴ/今尾 コンガ/中川 タムラム/鈴木* シンバル・鈴/桜井 マリンバ/浦辺 ウッドブロック/皆月 |
タムタム・大太鼓・シンバル/桑形 テューブラベル・ヴィブラフォーン/皆月 マリンバ・木琴・シンバル/古関 |
トムトム/今尾 大太鼓・ティンパレス/皆月 |
| ピアノ | 藤井 | 藤井(+Cele.) | - | - |
| ハープ | - | 見尾田* | - | 見尾田* |
| 1stヴァイオリン | 堀内(小松) | 堀内(小松) | 堀内(佐藤) | 堀内(佐藤) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(田川) | 大隈(田川) | 大隈(田川) | 大隈(田川) |
| ヴィオラ | 村原(柳澤) | 村原(柳澤) | 柳澤(村原) | 柳澤(村原) |
| チェロ | 柳部容(光野) | 柳部容(光野) | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) |
(*)はエキストラ
伊福部昭: オーケストラとマリムバの為のラウダ・コンチェルタータ
マリンバと簀の子(すのこ)、という組み合わせでピンと来る人は、小さい頃からマリンバのレッスンを受けていた人に違いない。私もその1人で、今から40数年前に小学4年生でマリンバを始めた時は、身長不足を補うために簀の子を置いていた。この楽器は左右に長いので、高音域から低音域に移る際には歩いて(時には跳んで)移動する。簀の子は、誰が考えたか知らないが、子供が演奏にあたって打面を適当な高さに保つために導入されたようだ。私より小さい低学年の子は、さらに高い簀の子の上でレッスンを受けていた。
マリンバはアフリカ起源の楽器とされている。音の高さの順に並べた木片の下に瓢箪(ひょうたん)をぶら下げた形が原形というが、現代マリンバの直接の祖先は19世紀に中南米で用いられていたもので、グアテマラでは2月20日を「マリンバの日」と決めているそうだ。いずれにせよ「西洋音楽」が行われていたヨーロッパに入ってくるのはだいぶ後になってからで、当然ながらいわゆるクラシックの作曲家たちは、この楽器を滅多なことでは用いていない。シロフォン(木琴)をよく用いたショスタコーヴィチやストラヴィ
ンスキーも、オーケストラ曲にマリンバのパートは書かなかった。
それでもヴァイオリンやピアノその他の楽器のために書かれた作品をマリンバで演奏することは、日本でも戦前から行われている。私もレッスンではしばしばクライスラーやサラサーテなど、主にヴァイオリンの楽譜が課題として与えられたが、これはおそらく日本の代表的木琴奏者であった平岡養一(1907~1981)らの先駆者がもたらしたスタイルだろう。
本日演奏される「ラウダ」も、最初は平岡の「演奏生活50周年記念演奏会」のために木琴協奏曲として1976年に完成したものだ。しかし結局演奏はされず、その後1オクターブ低い音域をもつコンサートマリンバ用に書き換えられ、1979年9月12日に新星日本交響楽団(現東京フィルハーモニー交響楽団)の創立10周年記念演奏会で初演された。初演の独奏者が安倍圭子さんである(指揮:山田一雄)。
私がマリンバを習っていた頃には、もちろん現代の作曲家によるソロ曲もあったのだろうが、当時は曲の存在も知らず、相変わらずヴァイオリンピースを練習する日々であった。しかしいつも頭のどこかで「ホンモノではない」という引け目を感じていたのも確かである。大学のオーケストラの合宿では「借り物」であることを開き直り、合宿所の下駄を音階順に並べてビゼーの「ファランドール」を宴会芸に出したりもしたけれど。
そんな与太話は措くとして、私の積年の「もやもや」を払拭してくれたのが、この「ラウダ」であった。新響に入った翌年、1984年1月の第102回演奏会で安倍圭子さんの演奏を目の当たりにして、まさにこの音楽こそがマリンバのための音楽であり、他のどの楽器にも代替し得ないものと確信することができたのである。
ラウダ・コンチェルタータという題名は、作曲者の言葉を借りれば「司伴楽風な頌歌というほどの意」という。手元の『イタリア語小辞典』(大学書林)でLaudaを引いてみると「古代イタリアのBallataという抒情詩体に基づく、宗教的、抒情的、そして劇的対話形式による詩体;賛歌」とあった。どうもピンと来ないが、雰囲気はわかる。司伴楽は今風に言えば協奏曲。戦前はコンチェルトの訳語のひとつとして用いられたようだ。
ついでながらBallataといえば、伊福部さんの代表作のひとつである「交響譚詩」のイタリア語表記がBallata Sinfonicaである。この作品は、戦時中に夜光塗料の研究開発中に放射線被曝で病死した研究者の次兄・伊福部勲への追悼曲だ。放射能汚染が生んだ怪獣「ゴジラ」(映画では伊福部昭が音楽を担当)との因縁を覚えるが、ここでは措く。
遅ればせながら作曲者の経歴をざっと記しておこう。伊福部昭は1914年に北海道の釧路で生まれ、後に十勝の音更(おとふけ)に移る。この地で子供時代をアイヌの人々と過ごし、彼らの音楽や踊りに日常的に接していたことが、作品の基層に大きな影響を与えたという。その後は北海道帝国大学農学部林学実科に入学、卒業後は道東・厚岸(あっけし)の森林事務所に勤めるかたわら、旧制中学の頃から独学で始めた作曲活動を続けていた。そこで作曲したのが「日本狂詩曲」で、これがチェレプニン賞を受けたことにより作曲家としての地位を確立する。後の活躍については、もう私が駄文を追加することもないが、本日演奏する他の3曲の作者である芥川也寸志、黛敏郎、松村禎三の3人は、ともに伊福部の門下生だ。
さて、「ラウダ」について、作曲者はこう説明している。
「ゆるやかな頌歌風な楽案は主としてオーケストラが受け持ち、マリムバは、その本来の姿である打楽器的な、時に、野蛮にも近い取扱がなされています。この互いに異なる二つの要素を組み合わせること、言わば、祈りと晩性との共存を通じて、始原的な人間性の喚起を試みたものです」
曲は単一楽章の形式で、冒頭はAdagio religioso(敬虔なアダージョ)、ヴァイオリンとヴィオラによってG-F-D-E♭という音型が呈示され、すぐチェロとコントラバス、それに大太鼓の4分音符の連なりが、無限の奥行きを感じさせる。その後で入ってくるソロ・マリンバは、pesante e poco barbaroとあるように「少々粗野に」3連符を始める。特に最初の一撃のフェルマータの音は、誰もが息を呑むだろう。そして延々と「舞踊」が続き、やがてオーケストラが入って来てもこの3連符はなかなか停まらない。
楽器はヤマハのいわゆる「安倍圭子モデル」で、標準的なマリンバより低音部が追加されており、ふつう下に向いている共鳴管は、まっすぐ伸ばすと床につかえてしまうのでコントラファゴットのように折り曲げられて上を向く。このあたりの低音をフォルテで演奏すると、何次にもわたる倍音群が渦を巻くように響き、聴いている人を「ガムラン」にも似た一種独特の音響の海に誘い込んでいく。新響は1993年のベルリン芸術週間でこの曲を演奏し、帰国後にも取り上げた。その演奏会プログラムで私が安倍圭子さんにインタビューしたものを以下に再録してみよう。
大変な曲です。従来のマリンバの曲にはない、プリミティヴなエネルギーを徹底して追求した、とてもユニークな作品だと思います。「リズム楽器としてのマリンバ」を前面に出している。オーケストラの方も、伴奏というより共演しながら両者がこの曲の持つ「生命のうた」をうたいあげていく。そこに私はいつも大きな喜びを感じています。
この曲は手が速く動くとか、そんな上っ面で弾いているだけではだめです。魂を込めて、一つ一つの音を充実させなければいけない。そしてこのスケールの大きな曲の本当に息の長いフレーズが持続できるだけのエネルギーが必要です。
初演から14年が経ちましたが、自分の中でつねに育ってきている「ラウダ」を意識します。だから以前に新響さんと演奏した時とは変わっていると思いますよ。これだけ骨の太い、肉厚な音楽をマリンバでどこまで追求できるか、ということをスコアを見て考えながら、いつも新しい試みをしています。先日のベルリンの演奏ともまた違った演奏になると思います。
その演奏会からちょうど20年が経過した。よく新響の練習にお見えになった伊福部さんも鬼籍に入られたが、安倍さんの中で「つねに育ってきているラウダ」は、現在ではどんな音楽に変貌しているだろうか。マリンバという楽器の可能性を、ある意味で究極以上に広げたこの作品が今日どのように響くのか、簀の子で育った私も楽しみにしている。
初演:1979年9月12日 東京文化会館にて
山田一雄指揮 マリンバ独奏:安倍圭子
新星日本交響楽団
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コ
ントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トムトム3、大太鼓、キューバンティンバレス、ハープ、弦五部
松村禎三:ゲッセマネの夜に
接吻と裏切り
ユダがイエスを裏切る。この事は誰もが良く知るところだが、その行為の実体を知る人はそれに比較して意外に少ないのではないだろうか。それは何か。イエスを「売る」報酬として銀貨30枚を受取った事か。或いは彼の裡にそもそも裏切ろうという意志が芽生えた事か。
ジョット(Giotto di Bondone1267?~1337 イタリア)の絵はその裏切り行為の瞬間を凍結している。捕縛に来た祭司長をはじめとした敵対者に対し、彼らと結んだユダが、接吻によって相手がイエスである事を示す。所謂『ユダの接吻』の場面(注1)である。それはゲッセマネに於けるイエスにとって最後の夜に起き、翌日彼は十字架に架けられる。
実はユダに限らず、弟子たちは様々な形でこの夜イエスを裏切っている。ある弟子の一群はイエスから自分が祈っている間は眠るなと命じられるが、眠ってしまう。ペテロは「自分は決してイエスを『知らない』とは言わない」と師の予見を否定するが、結局夜が明けるまでに師の言葉どおりの行為を、自ら気づかぬままにする事になる。師から「~するな」と言われた事を犯し、片や「自分は~しない」と明言していながらそれを破る。この世の中に存在する裏切りとは人の心の弱さを反映して、大抵そのような形をとるものだ。
だがユダの「裏切り」はこれと全く異なる。彼は群集の中でイエスを指差し、声高にその存在を知らせはしなかった。ただ師に対し弟子がとるべき礼節と愛情を示す、日常的な所作を行っただけである。ここにあるのは人の弱さとは異質の、より深い意図と強い意志であると捉えざるを得まい。そしてその行為のさりげなさ故に、裏切りの罪はより深まる。
イエスはこうした数々の裏切りを弟子たちに明言し、自身に訪れる運命を見据えていた。そしてこのゲッセマネの一夜、全てその通りとなった。この地の名は、彼の生地であるベツレヘムや終焉の地たるゴルゴダなどに比較して知名度は低い。だがジョットのこの絵と共に、もはやそれが記憶から去る事はないだろう。
「ゲッセマネの夜に」の作曲を進める間、松村禎三は絶えずこの絵と向き合っていた。彼が特に注目していたのはイエスのユダを見つめる目だ。接吻による裏切り…それを予期していたはずのイエスも、さすがに怒りのまなざしを向けているようにも見える。或いは悲しみに充ちた予見に対する寸分違わぬ回答として、諦念を以ってこの弟子を見つめているのかもしれない。そしてそのいずれの場合も、師への裏切りという大きな罪に対する許しを与えようとする意志を、その視線から読み取る事ができよう。取り巻く群衆の描写を背景としたふたりの間に、神学的解釈とはまったく別の様々なドラマをこの絵から見出すのはそれほど難しい事ではない。
だが作曲家の視点はより遠く深く透徹している。作品を書き上げた後の言葉。
…イエスのまなざしはユダを突き刺し、通りこして永遠のかなたに人間の悲しい営みを見とおしているように思える。この透徹さにあやかりたいという思いがこの曲を書くためのエネルギーの基盤となった。
作曲家はこの絵のイエスのまなざしを見つめ続けた。そして見つめ続ける作曲者自身のその目は、通常の音楽家が持つものと異なる。その由来と性格とを知る事は、我々がこの作品と対峙する際にきわめて重要に思える。
凝視の確立
松村禎三(1929~2007)は生地京都にある旧制第三高等学校卒業後の1950(昭和25)年、東京音楽学校作曲科の受験に失敗している。学科試験後の検査で、両肺結核の診断を受けた為である。その後、都下北多摩郡清瀬村(現在の東京都清瀬市内)の療養施設に入る。いつまで続くかも知れぬ療養生活と繰返し受けねばならなかった手術の苦痛、日常にはびこる周囲の死との対峙…そうした環境下、所内で盛んに行われていた句作に親しむ様になる。作曲の師である池内友次郎(高濱虚子の次男)の勧めでもあったが、こうした療養所内の文学創作活動は、現在では想像も出来ぬほどに盛んで、外部の俳人や文学者らとの接点も確固たるものがあった。
例えば彼の療養所と同じ地域にはハンセン病患者の収容施設、国立療養所多磨全生園がある。社会から完全に隔絶されたこの園内ではより本格的に小説が書かれ、「文壇」を形成する作家群の中には『いのちの初夜』で知られる北條民雄(1914~1937)がいた。彼は文通によって若き日の川端康成(1899~1972)に師事し、それが一連の作品が世に出る契機となっている。松村禎三の入所時期は北條の死後10年以上を経ていたが、長期の療養生活を送る環境の中で、文芸の占める地位に変りは無かったろう。「療養俳句」という語さえあった時代である。
「松村旱夫(ひでりお:これはベートーヴェンの歌劇「フィデリオ」にちなむ)」の俳号で句作を重ねてゆく中で、秋元不死男(1901~1977)に師事。いち早く頭角を現し、師の主宰する『氷海』のほか『天狼』『環礁』など、当時の俳壇を代表する各誌への投稿で、しばしば巻頭を争うようになる注2。そして北條民雄に於ける川端のような存在である秋元を介して世に問うた一連の作品は、1953(昭和28)年、24歳の折に第1回氷海賞を受賞する。その時期の受賞作や代表的な句。
・オリオン落ちて寒き日本中明ける
・照るも翳るも村の藤棚一斉に
繰返し手術を受けて生死の境界に足を踏み入れる事もあったこの年の俳句に対し、ともすれば我々は死の影や生への希求を読取ろうと努めるが、多くの場合それは徒労に終わる。松村の凝縮された俳句表現には、極めて僅かな心象が時にほのめかされるに過ぎないからである。
いかなる作品であっても創作する側は眼に映る対象を、ぎりぎりの言葉に削り込む作業に没頭し、鑑賞する側はその過程とその間の作者に訪れた裡なる風景を、結果として示された言葉から読み取る他にすべは無い。一切の説明的な表現が省かれた個々の作品を解読するためには、鑑賞する側が同レヴェルの感度を要する。これは他の文学ジャンルとは異種の、対象への「凝視」を求められる世界である。作る側と受け手がその凝視の姿勢と対象とを共有する事が、鑑賞に於いて不可欠な条件となっている。松村禎三は外界から閉ざされた長い療養生活の中で、句作を通じてこの透徹した凝視の姿勢と能力を得たのである。
結核が治癒し、療養所生活から解放されて以前の生活に戻ると、作曲活動を再開注3し、俳句と訣別する。結局彼の句作期間は1953年をピークとする前後5年でしかないが、この長くも短くもある時間に句作を通じて培われた「目」は、その後音楽を創作して行く中でも、彼の芸術を形成する強固な根幹となっていた。
その作曲姿勢~音楽と俳句~
作曲の世界に復帰した松村禎三には確固たるひとつの視点があった。それは「現代ヨーロッパ音楽」に対する閉塞感についてである。ひとつの文明も人間の一生のように、ピークを迎えやがて衰退する。かの地の音楽について言えば300年も前にそのピークを過ぎ、20世紀半ばの現在は完全に行き詰まっており、実験という名で発表される作品群は、混迷を糊塗しているだけに堕しているという考えである。この打破の道筋の中で「日本」「民族」「汎東洋」を基盤とした作風と理論とを確立していた伊福部昭(1914~2006)との接点が生まれる。伊福部の下にはそのような閉塞感とその打破の気概を共有する、若き作曲家らが集まっていたのである注4。その環境下で弟子たちは研鑽を積み、やがてそれぞれ独自の方法で自らの課題を克服して行ったが、松村禎三が作曲という行為に対し行き着いた姿勢は、他の弟子たちとは終生異なっていたと言える。
それは対象への凝視・冗長の排除・本質の摘出というべきもので、彼は常に事象を見つめ続けていた。その対象は絵画や写真のように形あるものには無論限らず、無形の思想や理念に於いても同じだ。そうした創作の契機となった対象へのあくなき観察と、結果としての音楽への細心の反映は彼の作品の明確な特徴となっている。説明的なものは一切無い。彼の音楽に対峙する我々が、作曲者と同様に、最小限度に与えられた対象を、作曲者と同じ次元で凝視し、それによって両者を我々ひとりひとりの感性の奥底で関連付ける。そのような音楽の受止め方は、まさに凝縮された言葉から、対峙する者が個々に無限の宇宙を描くほかない俳句の世界と表裏を共にするものだ。
ここにかつて一度は離れていた句作と、その後の作曲活動との間を結ぶ本質的な融合があった。それはやがては彼自身に再認識され、年齢を重ねるに従い、更に強まっていった。
俳句は物事を凝視するところから生まれ、音楽は情動の流れに沿うものであり、併存しないように思われたのです。齢を重ね、今の私にはいささかの矛盾もなくなりました。
これは彼が60歳を前にしての言葉だが、70歳を超えた晩年には「俳句への回帰」とも言うべきこの傾向がはっきり顕れ、「ゲッセマネの夜に」作曲の前後には、特定の俳句をテーマとした作品がいくつも書かれている。
「ゲッセマネの夜に」も題材が絵画であるという違いこそあれ、根底にある姿勢は同じである。作曲者はジョットの『ユダの接吻』の介在以外の情報を我々に遺してはいない。現れる旋律のひとつひとつが何を表現し、意図しているかも示していない。具体的メッセージを示す固定された動機がある訳でもない。
どこか虚無的で空疎な旋律から始まる音楽は、切り裂く悲鳴のような高音域の饒舌を経て、やがて暗く重々しい響きと荒々しい旋律の繰返しに変る。向き合う我々は、そこから「裏切り」という言葉に附帯する虚無や苦悩や非難、贖罪やイエスの許しといった、ある種具体的なストーリーやメッセージを汲み取ろうとしがちである。何らかの「意味」を見出せないものを容易に受入れられないからだ。作曲者も当然それを想定している。
だが真に落ち着くべき最終地点は、作曲者と同様にユダに向けられたイエスのまなざしを凝視し、そこから彼によって紡ぎ出されたひとつの音楽と虚心に向き合い、我々ひとりひとりが音楽から受取れるある種の感情を素直に享受する…困難は伴うものの、真に許されているのはこれだけという気がする。この作品に対峙する誰しもが感じるであろう峻厳さは、対象への凝視によって松村禎三が晩年に行き着いた境地の表象と言うべきだろう。
この稿を擱筆した今、これまで遠かった俳句の世界に対する想いが去らない。松村禎三の音楽とその創作の元となった対象への凝視とによって、逆に俳句の本質への道すじを我がものにできまいかとの考えにずっととり憑かれている。
注1 この『ユダの接吻』の記述はマタイ・ルカ・マルコ・ヨハネの4福音書のうち、マタイ・マルコの2書にしかない。ルカによる福音書ではユダは接吻するために近づくが、イエスに退けられている。またヨハネによる福音書には接吻そのものの記述が無い。
注2 この時期10代ながら既に秀句を次々投稿していた寺山修二(1935~1983)と知り合い、その後終生交流を続ける事になる。
注3 療養所生活を送る間、彼は作曲活動と全く絶縁していた訳ではない。「弦楽四重奏による交響的断章」「序奏と協奏的アレグロ」などの作品を書いている。
注4 例えば門下のひとりである黛敏郎は、東京音楽学校作曲科卒業後パリ音楽院に留学するも、「もはや学ぶ事なし」と1年で帰国している。
初演:2002年9月8日
石川県立音楽堂コンサートホールにて
岩城宏之指揮 オーケストラ・アンサンブル金沢
トロンボーンを加えた最終稿初演:
2005年6月10日 東京文化会館大ホールにて
小松一彦指揮 東京フィルハーモニー交響楽団
楽器編成:フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット、コントラファゴット、ホルン2、トランペット2、トロンボーン2、ティンパニ、大太鼓、タムタム、シンバル(大・中)、ヴィブラフォン、木琴、マリンバ、テューブラベル、弦五部
参考文献
『新約聖書』新共同訳(日本聖書協会)
『旱夫抄 松村禎三句集』松村禎三著(深夜叢書社)
『松村禎三 作曲家の言葉』アプサラス編(春秋社)
『火花―北条民雄の生涯』高山文彦著(飛鳥新社)
『松村禎三 年譜』アプサラス第2回演奏会プログラム 西耕一編
CD『松村禎三:交響曲第1番、第2番/ゲッセマネの夜に』解説 西耕一著(NAXOS)
芥川也寸志:エローラ交響曲
〈エローラ音楽試論〉
デッカイナア! とまずはじめに思いました。とにかく、とてつもなく大きくて、どれくらいといったらいいのか、全く見当がつきかねる。まるで、無限のひろがり。
得体の知れぬ巨大な怪物にでもめぐり会ったような不気味さと、その前に立った自分がどんどん小さくなってゆくような不思議な気持を味わいながら、これはいったいどうしたことだ? と自問せずにはいられなくなりました。
インドのエローラ石窟院を訪れたときのことです。正確にいえば、エローラ石窟院の第16窟、シヴァ神に捧げられたカイラーサナータ寺院に足を踏み入れたときのことです。
このヒンドゥー教の寺院は、他の石窟と並んで巨大な岩山に彫られているものですが、その特徴の一つは、殆んど周囲が絶壁でかこまれていることです。つまり石窟という言葉はやや不適当なわけで、ヒンドゥー教徒たちは、恐らく大変な労力を費して、丁度、地下室を作るような格構に、岳陵を上の方から(建物の部分だけを残して)彫り下げていったわけです。そして更に、建物のために残された岩塊を彫り込み、その中の礼拝堂を作り、多くの僧房をくりぬき、壁面には数しれぬレリーフを彫って、地下の大寺院を刻み出したのです。(ですからこの場合、建物という言葉も不適当なのです。)
つまり、普通の建築物が土台から積み重ね、組み合せて作られるのに対して、これは全然アベコベの構成です。けずって作られた空間です。必要なものを加えてゆくことによって作られるのではなく、不必要なものをのぞいてゆくやり方です。建物の周囲の絶壁との間のひろがりは、莫大な労力によって彫りとられたものなのです。
このアベコベシステムが、まず私をびっくりさせたらしい。(もっとも、この寺院のうす暗い一番奥の室に入って、これが御神体です、とインド人に説明され、ふたかかえもあろうと思われる石の塊に、顔をくっつけるようにして眺めていたとき、また何やらいわれ、やがてその意味が男根であることがわかったときは、正に腰の抜ける寸前でありました。)
ピラミッドを見たときも、ヴァチカンやヴェルサイユを見たときも、やはりデッカイナアと思いましたが、エローラはまたこれとは違うデッカイナアでありました。 ピラミッドの場合は、いわば積み重ねてある一塊の石と、自分の肉体との比較の上に立っ
た大きさであり、たとえどんなに大きく感じたとしても、その極限までの大きさしか感じない。
ところがエローラは、一体相手がどこまで続いているのか見わけることも出来ない。そこに作られている空間は大地に続き、空にひろがり、宇宙につながっている、といった無限のひろがりを持っているように思えたのです。それは私にとって、正にショ
ッキングな出来事でありました。
それ以来、これは一体どうしたわけだ?という自問を今も尚繰返し続けているのですが、少くとも、今迄の積み重ねて作る空間、建築的な空間、音を横に加え、縦に加えて作る時間的空間の裏側に、けずりとって作る空間があるということ、それを音楽の上でも追求することが出来るということがわかってきました。
今迄の加算の概念の上に立つ音楽に対して、これは滅算による音楽といえるかもしれませんし、プラス空間に対してマイナス空間という言葉も使えるかもしれません。今迄の西洋音楽史の裏側にある、全く異質な空間構成法です。
エローラで体験したもう一つの痛切なものは、表現の生々しさ、ということです。まるで本能的衝動が爆発して出来上っているような感じに打たれたのです。ここで筆さばきのうまい人ならば、例の御神体を引合いに出して、鮮かに展開を試みることも出来るのでしょうが、私にはとても出来そうにない。(その時聞いた説明によれば、この寺院における礼拝の儀式は、信者たちが牛の乳を御神体にそそぎかけることによって始まるということです。)
ここでも、一体どうして? が始まるわけですが、これは極く簡単に現代の音楽が、抽象に抽象を重ねてきたことによると、いってしまってはいけないでしょうか。
ほぼ18世紀の終り頃から、純音楽にあっては、楽譜に忠実に再現して演奏されることが、全く当り前の要求になったときから、即興性は殆んど失われてしまったといっていい。すべて合理的に計算され、設計され、しかも周到な準備を経て鑑賞者に提供される。
作る方も“抽象”は金科玉条であり、生活における現実的な経験からはだんだん遠ざかってしまった。
エローラの壁に刻みこまれたレリーフから発散した圧倒的な迫力や逞しさは、私にとってはまったく新しい驚異だったのです。
この時から原始芸術が私をとらえてしまいました。自然民族の音楽における様々な形式の中に、実に多くの新しい音構成への可能性が暗示されているように思えたからです。
ことに、その即興的性格、終った瞬間に開始の状態に戻っているあの独特な構成、現実生活に直接結びついた生々しさ、男性と女性の差異が直接音楽に現われ、多くのものがこの二つの性格に分けられていること、その日常的性格、それとは全く対立するアニミズムやトーテミズムの中における非日常的性格、更にそれらが同時に重なり合っている同時性と対立性、などに強く興味をかきたてられたのです。
今日ではわずかに、アフリカを母胎とするジャズ音楽のインプロヴィゼイションが“本能への同帰”を叫んでいるようにしか見えませんが、現代の音楽にとっても、これは大きな課題であるといっていいでしょう。
現代の音楽は一つの危機にさらされている――と思います。それは、何世紀にもわたって音楽家の言葉として――というよりも文字として使われてきた、平均律音組織の崩壊です。現に、具体音楽や電子音楽の登場によって、それは現実的なものとなりました。
最も原始的な形式より、中世を経て今日に至る西洋音楽の歴史は、明らかに音組織によってはっきりと区切ることが出来ます。更にその組織の基礎となる音程の体系は、4度、3度、2度、という縮小する形となって現われます。
最も普遍的に、近代音楽の創造者と見られるドビッシィの書いた長2度体系の音楽は、第2次大戦後、全く普遍化した12音音楽によって、更に短2度に縮小されました。今迄使われてきた演奏形態では、これ以上縮小された体系の音楽は演奏不可能です。短2度、即ち半音は、12平均律での最も小さな音程単位だからです。
これ以上進むためには、どうしても今迄の音組織や、大部分の演奏家や楽器を捨てざるを得ません。先駆者ハバが試みたように、半音よりも小さな音程の書ける特種な記譜法による、特種な訓練を経た、特種な演奏家による微分音音楽に行くか、具体音楽
や電子音楽を始めた勇敢な作曲家達がやったように、今迄の楽器や、五線紙や、演奏家を全部捨ててしまうしかありません。つまり、壁に行きあたっている――危機といってもいいでしょう。
この危機から――敢てそういわせて頂けば――脱却するためには……というよりも、たとえそれを危機と感じようが感じまいが、重要なことは縮小型の考え方をやめてしまうということです。私が勝手ないい方をした縮小型――これは丁度、ヨーロッパの画家たちが、ガクプチを作ることによってタブローの中に構図を設定してゆく、あの求心的な構成法にあてはまります。また建築家たちが、壁を作ることによって、空間を構成してゆく方法にもあてはまります。画家の使う構図という言葉を、作曲家が使う音楽形式という意味におきかえてもいいのなら、まず楽章の数をきめ、各楽章の形式をきめ、ソナタ形式ならば2ツの主題をきめ、更にモティーフをきめてゆく方法、その考え方に他なりません。
まず、一番大きなワクを設定し、だんだんとその中に小さなワクを作ってゆくような、合理主義的な思考を超えることです。
ここに新しい音構成への足がかりがあります。東洋の空間、原始芸術の形式は、この意味でいろいろな暗示を私に投げかけてくれるのです。
しかし、これは勿論生やさしい仕事ではありません。何年手さぐりしてみても、私には到底無駄なことかもしれません。いわばこの交響曲は、その手さぐりのはじまりです。外見的には、殆ど今迄の形式を破ることが出来なかったようです。ただ、エローラで受けたあの感銘は、もう忘れられそうにありません。それが私にとって、怪物に似た恐ろしい未知の世界へ挑戦する意欲をかきたててくれるのです。(ここで、音楽にあってはバルトークをはじめとして、メシアン、ジョリヴェ、ケージなどの仕事、最近の建築に現われている新しい様式、アンフォルメル一派の絵画などについてふれたいのですが、長くなる上にいずれ機会があったら、まとめた文章にしてみたいと思っていますのではぶきます。)
この交響曲は、忘れ難い想い出を私自身記念するために、エローラ(ELLORA)と名づけました。
楽器編成はスタンダードな3管。8名の打楽器が加わり、絃楽器群は12のパートに別れます。
全20楽章。これらは2ツの性格に分けられています。レント、アダジォの楽章と、アレグロの楽章です。
各楽章の演奏順序は指揮者に一任され、ある楽章を割愛することも、重複することも全く自由です。(ただし、第17楽章から第18楽章へ、第19楽章から第20楽章へは常に続けて演奏される。)
今仮に、レント楽章をf○ アレグロ楽章をM● と
すると、初演は次の配列で行われます。
ffffMfffMMffMMMfMMMf
○○○○●○○○●●○○●●●○●●●○
(初演時プログラムより抜粋)
初 演:1958年4月2日 新宿コマ劇場にて
作曲者指揮、NHK交響楽団
楽器編成:ピッコロ、フルート2、アルトフルート、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン6、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、ボンゴ、コンガ、マリンバ、ウッドブロック、鈴、タムタム、ピアノ、チェレスタ、ハープ、弦五部
カイラーサナータ(エローラ第16窟)
空間。それは当たり前のものであるが、ここでは違う。百年もかけてコツコツ掘り出した空間なのである。しかし、その空間は、思ったより明るかった。まず目に飛び込んできたのは、あらゆる壁面を飾る彫刻である。神々と動物たち。それがポリフォニックに押し寄せてきた。
カイラーサナータは、基本的には、崖を大きくコの字形に削り取り、そのコの字に囲まれている中に数階建ての寺院が建つ、という構造をしている。そして寺院を囲むコの字の壁面にも複雑に回廊が掘られ、あらゆる壁面には、大小さまざまな彫刻が施されている。しかし、それらは造られた物ではなく、百年もかけて掘り出された物なのである。
(中略)表の一角には、何やら戦争の物語か、大勢の人間のダイナミックな群像が彫られている。回廊の上の方には、岩から滲み出す水を上手に導いて、空中風呂のようなプールも作られていた。
寺院の一番奥に立って、背後を囲む高い崖を見上げると、芥川先生が強調されていたプラスとマイナスの逆転が実感できる。まったく大変なことを考え、しかもそれを百年もかけてコツコツとよく掘ったものだ。壁面と寺院の間を、緑鮮やかなオウムが飛び交っている。
(写真準備中)
エローラ石窟群の第16窟カイラーサナータ寺院を俯瞰する。100年の歳月をかけて岩山から削り出した「マイナス建築」。1983年に世界遺産に登録された。上の写真は削り出してできた寺院周囲の断崖。
(写真準備中)
カイラーサナータを仰ぎ見る。石柱には自然石のままの模様
(写真準備中)
戦争の物語だろうか。大勢の人物によるダイナミックな群像で埋め尽くされた壁面(上)
と、寺院を下で支えるゾウの彫刻群。これらもすべて岩山から削り出されたものだ。
*元団員の田中司さんが1990年8月にインドを訪れた後に執筆した『家族でインドの旅』から一部を抜粋した。
黛敏郎:ルンバ・ラプソディ
〈アプレゲールの反逆児:フランス近代音楽とジャズの融合〉
黛敏郎(1929~1997)が亡くなって16年。新響では、近年故・小松一彦の指揮で彼の代表作である「涅槃交響曲」や「BUGAKU」を演奏したこともあり、馴染みのある作曲家だが、若い方と話す機会が多くなった昨今、「黛敏郎」の話題に及んでも、案外知っている人が少なく、年月の流れを痛感している。
黛敏郎という人物
「黛敏郎」というキーワードから思うがまま列挙してみよう。まず企画・監修・司会を自ら行った歴史的長寿テレビ番組「題名のない音楽会」。東京藝術大学講師。「作曲家協議会」「日本著作権協会」会長。東京音楽学校旧奏楽堂の保存運動などの公的活動。憲法記念日でのニュースで登場するナショナリズム溢れる論客。「自由国民会議」代表世話人。「日本を守る国民会議」運営委員長。「三人の会」。そして三島由紀夫との交流。
生涯の後半はどちらかというと政治的な側面で語られることが多かったが、多方面に活躍していた黛敏郎の本質は作曲家であったといえる。
作品と来歴
黛敏郎の作品には、一貫してモダンなムードの中に、作曲者独特の逞しく力強い音楽が流れている。「涅槃交響曲」「曼荼羅交響曲」をはじめとする多数の管弦楽作品、歌曲、オペラ「金閣寺」「古事記」、バレエ「BUGAKU」「ザ・カブキ」「M」、そして190本以上にわたる映画音楽、例えば「カルメン故郷に帰る」「赤線地帯」「東京オリンピック」「黒部の太陽」、日本人として初めてハリウッドに招かれた作品「天地創造」もある。また日本テレビのスポーツ番組のテーマ曲として「スポーツ行進曲」は、作曲者や曲名を知らなくても、誰もが耳にしたことがあるに違いない。
彼はアプレゲール(戦後派)として第二次世界大戦後の日本音楽界に颯爽と登場。パリ国立音楽院に1951(昭和26)年留学して1年で帰国後、〈アヴァンギャルド〉〈モダニスト〉として電子音楽をはじめ最先端の前衛音楽様式へのアプローチを重ね、梵鐘や読経といった日本の伝統的音文化に係わる要素と、音列技法としての前衛という手法を融合した作品を生み出し、日本文化や思想にも深く探求していった。彼の言動は常にマスコミを刺激し続け、シリアスな音楽もポピュラーな音楽も分け隔てなく係わっていった姿勢は、作曲家のあり方のひとつといえよう。
センセーショナルな出来事として特筆すべきは、團伊玖磨、芥川也寸志と共に、従来の作曲家グループとは大いに性格を異にする「三人の会」を1953(昭和28)年に結成したことである。会は当時のスター作曲家のグループとして日本の作曲界に多大な影響を与えた。
「ルンバ・ラプソディ」の時代
戦前日本の都市部の盛り場や劇場では、米国風のジャズとかハワイアンが幅を利かせ、日本がアジアへ進出していくとアジアの民族音楽が国内に流入してきた。米国との開戦により米国音楽は禁止されたが、アジアや中南米の音楽はそうでもなく、黛敏郎は多感な十代の少年期、異国趣味の中で東洋や中南米の音楽に影響を受けていた。
終戦の年1945(昭和20)年春に東京音楽学校作曲科に入学した時、芥川也寸志は2年上級、そのさらに1年上には團伊玖磨がいた。音楽学校では、当時生粋のモダニストであった橋本國彦に師事、ストラヴィンスキーをはじめとする先鋭的な様式から戦意高揚音楽に代表される大衆的音楽の世界に触れていく。終戦後に橋本國彦が辞職した後、新任の池内友次郎と伊福部昭に師事、池内友次郎からパリ音楽院流の作曲法(和声学、対位法)、伊福部昭から管弦楽法を学び、結果としてラヴェルを理想とするフランス・アカデミズム風音楽、民族的でダイナミック、オスティナートを多用したオーケストレーションが彼の音楽的関心として作品に深く刻まれている。
敗戦でジャズの演奏禁止が解けたこの時代、黛敏郎はアルバイトでジャズ・ピアノを弾き始める。約2年間進駐軍クラブ等で演奏し、「ブルーコーツオーケストラ」の前身であるジャズバンドにも在籍、実地でジャズを学び大いに惹かれていく。ジャズは彼の異国趣味をますます駆り立て、アプレゲールの新時代を謳歌していった。
学生時代のエピソードのひとつが、『芥川也寸志その芸術と行動』(東京新聞出版局)の黛敏郎著『「三人の会」は不滅である』の中で紹介されている。本科2年生(17才)の時に書いた「ヴァイオリン・ソナタ」を、学内の大スターで1級上の江藤俊哉、園田高弘両氏が学内演奏会で取り上げてくれることになったが、上級生より、2年生の分際でこのような前例もなく、要するに生意気だとクレームがあった。その時に敢然と支持し、前例があろうとなかろうと演奏に値する作品をやるのは当然だと頑張り、実現にこぎつけてくれたのが、最上級生であった芥川也寸志であった。芥川也寸志の、過去の因習にとらわれず良いと思ったことは進んでやっていく実行力もさることながら、東京音楽学校はじまって以来の天才と注目された黛敏郎の実力が垣間見える。
ストラヴィンスキーとの交わり
ストラヴィンスキーは、黛敏郎が愛した作曲家のひとりであり、ストラヴィンスキーが1958(昭和33)年4月に来日してNHK交響楽団を振る、というニュースに、黛敏郎はすぐにNHK交響楽団のエキストラを志願、「鶯の歌」「ペトルーシュカ」「花火」でチェレスタにて出演、ストラヴィンスキーが最初にNHK交響楽団の練習場に現れた時の感激的一瞬を「『音楽之友』1959年7月号」にて回想している。
「ルンバ・ラプソディ」という作品
新響は、2012年10月にガーシュウィンがルンバのリズムをオーケストラに取り入れた「キューバ序曲」を演奏した。「ルンバ・ラプソディ」は、明瞭で陽気な「キューバ序曲」とは趣を異にしており、粗削りだがスタイリッシュさと独特なモダニズムを感じる(本稿執筆に際して、あらためて「ルンバ」をwebで検索すると、最近人気の自走式掃除機が最初にずらりと出てくるのが気になっている)。
1948(昭和23)年4月9日に完成、師の伊福部昭に楽譜を渡して初演の斡旋を依頼した。伊福部はいろいろと動いたが、色良い返事が得られず、そのうち黛自身がこの曲の材料を「シンフォニック・ムード」の第2部で活用、という経緯もあり、結果的に「ルンバ・ラプソディ」はお蔵入りという状況となり、そのまま伊福部のところに預けられていた。伊福部昭は楽譜の返却を何度も黛敏郎に申し出たそうだが、黛敏郎としては師匠の手元に残してもらいたいという希望から結局受け取らず、そのまま作曲者が逝ってしまった。最近まで発行されてきた黛敏郎に関する本や資料のディスコグラフィーにもこの曲の掲載がなかったほどで、幻の曲であった。
半音ずつ下がって始まる基本動機が現れ、派生する特徴的な動機群は「シンフォニック・ムード」とも共有しており、「シンフォニック・ムード」は、ラテン音楽と東洋的でガムラン音楽のような色彩が特徴的だが、「ルンバ・ラプソディ」は、それ以上に原色的で、ストラヴィンスキーの、特に「ペトルーシュカ」をモデルとしていることが伺える。
序奏(Adagio)は霧の中から徐々にルンバのリズムが聴こえてくる、という、まるでラヴェルの「ラ・ヴァルス」のような展開が印象的。序奏の後、ルンバのリズムで軽快且つお洒落に音楽が進み(Doppio movimento→Poco mosso)、突然、弦楽器とピアノ、続いて金管楽器の荒々しく力強いファンファーレ風の動機が出現(Piu agitato)、ビッグバンドのホーンセクションが生み出す力強さ(音圧)への憧憬を思わせる。その後、一瞬まるで「春の祭典」のような音が聞こえてきて、中間部(Tempo di Fox trott Medium)でスタイリッシュなダンス音楽が登場する(ワルツの様式であるFox trottは、キツネとは全然関係ない)。その後に、ピッコロとクラリネットによるカデンツァ風音楽を経て(Tempo Rubato)、ルンバに戻り(Tempo di Rumba)、次第に高揚して(Piu mosso)、まるで「火の鳥」の「魔王カッチャイの踊り」のような半音上昇進行形を経て8ビートで叩きつけるような爆発的な頂点を迎え、最後(Sostenuto)は静かに、そしておしゃれに終結していく。唐突な場面転換などに早熟さが感じられるが、19歳の学生が作曲した作品であることを思えば、若さに満ち溢れた爽やかなドライブ感が面白い。近代フランス的な新古典主義風のスタイル、洒脱なテクスチュアにジャズのイディオムを柔軟に取りこんで、「戦後」という時代に〈アプレゲールの反逆児〉として颯爽と登場した新鮮な息吹が感じられる。
「ルンバ・ラプソディ」演奏に際して
時間芸術といわれる音楽は譜面のことではない。音楽を演奏するということは、確立された約束事(記譜法)に従って記載された譜面を元に、一瞬で消え去る音を奏者の技術と感性を頼りに生み出される瞬間の創作を集積したものである。作曲者が創造した音楽を知るには、作曲者が残した譜面を絆としてその想いをくみ取ることが重要であり、特に演奏に接する機会は貴重な体験となる。
「ルンバ・ラプソディ」を初演された湯浅卓雄先生の指導により、黛敏郎の黎明期の輝きを体験できることは、新響にとって望外の喜びといえよう。
この度の演奏に際しては、西耕一氏、東京藝術大学演奏藝術センターにお世話になった。あらためて感謝の意を表したい。
世界初演:CD録音『日本作曲家選輯 黛敏郎』
2004年8月25日~27日マイケル・フォーラー・センター(ニュージーランド・ウェリントン市)にて
湯浅卓雄指揮 ニュージーランド交響楽団
日本初演:2009年6月20日 東京藝術大学奏楽堂
湯浅卓雄指揮
東京藝術大学音楽学部学生オーケストラ
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、小太鼓(Tamburo)、小太鼓(Petite caisse)、タムタム、マラカス、拍子木、グロッケンシュピール、ピアノ、弦五部
参考文献
『芥川也寸志 その芸術と行動』出版刊行委員会編(東京新聞出版局)
『黛敏郎の世界』西耕一、市川文武共編 京都仏教音楽祭2010実行委員会企画(株式会社ヤマト文庫)
第224回演奏会のご案内
■伊福部昭生誕100年
2014年は日本を代表する作曲家である伊福部昭が生まれて100年目にあたります。魅力的な作品の数々は民族的でありながらグローバル、また「ゴジラ」など多くの映画音楽でも活躍をしました。新交響楽団は今までも伊福部作品を大切に取り上げてきましたが、今回の演奏会では、彼の門下生である黛敏郎、芥川也寸志、松村禎三の作品とともに演奏します。
指揮には湯浅卓雄を迎えます。湯浅は高校卒業後にアメリカ留学を経てウィーン国立音楽大学で指揮を学び、イギリスを中心に国際的に活躍し、現在は東京藝術大学演奏藝術センターの教授を務めています。世界最大のクラシック音楽レーベルとなったナクソスで多くの録音を残していますが、特に「日本作曲家選輯」シリーズにおいて日本人作品を紹介し、曲に新たな生命を吹込み鮮やかに聴かせてくれます。
■偉大な作曲家と弟子たち
伊福部は1914年(大正3年)釧路生まれ。中学2年の時に独学で作曲を始めますが、北海道帝国大学(現在の北海道大学)農学部に進み卒業後は道庁の林務官となりますが作曲を続け、チェレプニン賞(フランスで開催された日本人作品のコンクール)で1位となります。第二次大戦後、知人から映画音楽の誘いがあり日光に転居、東京音楽学校(現在の東京藝術大学)の作曲科講師となりました。その最初の教え子に黛、芥川がいました。この2人はその後作曲以外にも多方面で活躍したのは万人の知るところです。
松村禎三は旧制第三高等学校(現在の京都大学)を卒業後に東京藝術大学を目指しますが、試験時の身体検査で結核に冒されていることがわかり長期の療養を余儀なくされます。その快復期に書いた作品が毎日音楽コンクール第1位となり、その時に声をかけられた伊福部に師事をするようになりました。
伊福部は、その後東京音楽大学で作曲科教授、学長を務めるなど、多くの弟子たちを輩出しました。
■ベルリンの感動をふたたび
新響は1993年にベルリン芸術週間に招聘されましたが、その時演奏したのが伊福部「ラウダ・コンチェルタータ」でした。協奏曲風の頌歌(神をたたえる歌)という意味で、自然と人間が対話し昂揚していきます。独奏マリンバには、ベルリン公演と同じ安倍圭子を迎えます。安倍は世界的に活躍するマリンバ奏者で、76歳にして現役の演奏家として日本のマリンバ界をリードしています。「ラウダ」は元々木琴協奏曲として書かれたが演奏されず、安倍のマリンバを想定して書き直されました。安倍により初演され十八番となっています。
芥川「エローラ交響曲」もまた新響にとって大切な曲の一つです。インドのエローラ石窟寺院に衝撃を受けて書かれたこの曲は、神秘的で躍動感のある名曲です。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
新交響楽団在団44年の思い出-4
編集人より
コンサートマスターを長年に亘って務められた都河和彦氏による回想録を、前々号より、掲載しております。以下に新響創立30周年からの10年間のうち、1989年1月の芥川氏死去後の部分をご紹介致します。
◆創立30周年(1986年)からの10年間-2
(1990年=芥川先生歿の翌年)4月には高関健先生が初登場、ショタコーヴィッチの交響曲第1番とブラームスの交響曲第1番を降ってくださり、コンミスは高関先生と桐朋音大時代の顔なじみで後にプロのヴィオリストに転向した長谷川弥生さん(音楽評論家長谷川武久さんのお嬢さんで、チェリスト長谷川陽子さんのお姉様)が務めました。ブラームスの最初のリハーサルで、第4楽章中盤のpoco fの指示がある弦のユニゾンの個所で高関先生が「弦の皆さん、ここは力一杯思い切り弾いて下さい。でないと一生後悔しますよ」とおっしゃったのを今でも覚えています。高関先生とは現在まで20年を超えるお付き合いになり、色々お話しましたが「桐朋時代、堀米ゆず子さんとカルテットを組んでいた」とか、「ベルリン・フィルでヴィオラのエキストラで弾いていたら、借り物の弓を折ってしまった」等のエピソードが印象的でした。
10月は原田先生が教え子の漆原朝子さんを招いてシベリウスのヴァイオリン協奏曲を振って下さいました。漆原さんはその年、私が勤務していた会社の「モービル音楽賞」を受賞、授賞式では原田先生共々彼女を祝福しました。2011年10月、小淵沢での『リゾナーレ音楽祭』で彼女と久しぶりに再会、この21年前の思い出話をすることができました。
‘91年1月には伊福部門下で芥川先生の弟弟子の作曲家石井眞木氏が新響の指揮台に初登場して松村禎三、自作、伊福部作品を指揮して下さいました。石井先生にはそのあと数回振っていただき、’93年には新響をベルリンへの演奏旅行に連れて行って下さいました。このコンサート以前の新響の演奏会場は東京文化会館、サントリー・ホール、新宿文化センター等でしたが、このコンサートで初めて前年10月にオープンした池袋の東京芸術劇場を使い、以降この会場を最優先で使うことになります。
新響には団内結婚のカップルが大勢いらっしゃいますが、この頃私共夫婦はヴィオラ団員の内田吉彦さんから「結婚するので仲人をして欲しい」と頼まれました。お相手は慶応ワグネル・オケ出身でヴァイオリンの明美子(はるこ)さんで新響ではなく弦楽合奏団の「アンサンブル・フラン」の団員だったので、「彼女が新響に入ってくれるのなら引き受ける」と条件を付けました(職権乱用ですね)。式は3月に一ツ橋の如水会館で行われ、披露宴で新郎新婦と私共仲人はカルテットを演奏しました。明美子さんは約束通り翌年新響に入団、まもなくコンミスに就任しました。
又この頃、新響のパート首席決定に関する「民主化」がありました(何年のことか記憶がなく、記録も見当たらないのですが)。私の東大オケ後輩で長田浩一君というオーボエの名手が入団してきて、ほどなくオーボエ・パートの首席になったのですが(1988-1996在団)、来年度の各パートの首席を決める「技術委員会」で「パート首席を技術委員会が“お手盛り”で決めるのはおかしい、団員の投票制にすべきだ」と発言したのです。私が入団する前はどなたがコンマスやパート首席を決めていたのか知りませんが、各首席による「技術委員会」が組織されてからは技術委員会でパート首席決めるのが慣例になっていました(例えば、「オレのパートに○○が入団したが、オレより上手いからトップを譲りたい」とか「××パートは現トップが一番だからこのままで行こう」とか、いわゆる密室で決めていました)。長田氏のこの発言に各トップは虚をつかれましたが、ごもっともと皆が納得し、各パート・メンバーによるパート首席投票(コンマスは全団員による投票)のシステムが出来あがり現在まで継続しています。プロ・オケはコンマスやパート首席を決めるには定められたルールによるオーディションを行っているようですが、新響以外のアマ・オケはどのように決めているのでしょうか?
‘91年4月、新響にとっては初の外国人指揮者となるアメリカ生まれ、スイス国籍のフランシス・トラビス先生が初登場しました。新響団長の土田恭四郎氏のお兄様が芸大教授で、芸大指揮科教授として赴任してきたトラビス先生を新響に紹介して下さった、と記憶しています。R・シュトラウスの『ドン・ファン』と、私にとって初めての作曲家スクリャービンの交響曲第2番等を振ってくださったのですが、すべての弦パートの譜面に自分でボーイングをつけてくださっていたのには驚きました。英語でリハーサル、というのも新響メンバーにとって初体験だったはずですが、トラビス先生がゆっくり、ハッキリしゃべってくださったので大部分の団員はついていけました。当時チェロ・パートのジョン・ブロウカリング氏がNHKTVで英会話の講座を持っていてトラビス先生と新響を番組で取り上げ、私の『ドン・ファン』のソロがTVに流れました。先生とは何度か食事をしましたが健啖家で、あの指揮のエネルギーはここから生まれるのだ、と痛感しました。
7月の定期はヤマカズ先生がフランクの交響曲等を振ってくださいましたが暑い盛りで、高齢で体力が落ちた先生がリハに通われるのは大変で、コンサート直後の8月13日に79歳で逝去されました。翌’92年7月のヤマカズ先生の追悼演奏会はヤマカズ、カラヤンのもとで勉強した小泉和裕先生が振ってくださいました。小泉先生はその後新響を10年間、7回振って下さることになります。
‘92年1月、トラビス先生にベルクの『ヴォツェック』より三つの断章と、シューベルトの交響曲第9番『グレート』等を振っていただきましたが、ヴォツェックのソプラノは芸大大学院生だった橋爪ゆかさんが見事に歌いました(20年後の2012年9月、飯守泰次郎指揮・読響が二期会創立60周年記念公演でワーグナーの『パルジファル』を4夜公演したのですが、橋爪さんが『クンドリ』役として2夜登場、素晴らしい歌声を響かせていてうれしく思いました)。この打ち上げパーティーで私が「トラビス先生のシューベルト第4楽章のテンポが速すぎて私は右肩を痛めた。医者に行くので治療代を払ってほしい」とスピーチしたら「その請求書は天国のシューベルトに廻しておくよ」とユーモアたっぷりに切り返されてしまいました。
4月11日のコンサートでは石井眞木先生の発案で新響が新作を公募、応募作品の中から石井先生が芸大生夏田昌和氏の『モルフォジェネシスーオーボエとオーケストラのための』を選び、夏田氏自身の指揮で初演しました(オーボエ独奏は柴山洋氏)。
このコンサートの約2週間後の4月24日に私は20歳の長女を事故で亡くしたのですが、数日後の自宅での通夜・告別式にはトラビス先生初め、多くの新響団員が弔問に来て下さいました。
10月には原田先生が、やはり私が10年前NYで知遇を得た野島稔氏をソリストに、ブラームスのピアノ協奏曲第1番を振って下さいました。見事な演奏でしたが打ち上げの席で原田先生が「実は数日前、野島氏から『(この曲はすごく手を広げないと弾けない曲で)猛練習していたら手を痛めてしまって弾けない』という電話があった。こんな難曲の代役はおいそれとは見つからないので何とか頼む、と拝みこんだら痛み止めの注射を何本も打って今日演奏してくれた」と明かされたので、ゾーッとし、それから野島氏に深く感謝しました。
11月にはトラビス先生指揮で東京駅丸の内口構内での「エキコン」に出演、ベートーヴェンの『第九』第4楽章等を演奏しました。
‘93年1月にはトラビス先生が『シェラザード』を振って下さり私がソロを弾いたのですが、重要なハープは私の幼馴染で今や日本ハープ界の大御所、篠崎史子さんが客演してくださいました。このコンサートの模様をクラリネット団員の進藤秋子さんの友人のセミプロカメラマンが撮影してビデオを私に下さったので、トラビス先生を我が家にお招きして鑑賞会を開きました。
4月の演奏会には、飯守泰次郎先生が得意のワーグナーとブルックナー(交響曲第4番)で新響に初登場、あっという間に多くの団員が先生の音楽の虜になりました。今年で19年目のお付き合いになり、2013年4月にも25回目の共演が予定されています。
9月、石井眞木先生の引率で『ベルリン芸術週間』に参加、ベルリン・フィルの本拠地「カラヤン・サーカス」で伊福部先生のマリンバ・コンチェルト(独奏は安倍圭子先生)、石井先生の『交響三連作 浮遊する風』」等の邦人作品を演奏しました。この演奏会にはダルムシュタット在住で当地の歌劇場で活躍していた石井先生旧知の岩本忠生(チェロ)・瀬尾麗(ヴィオラ)ご夫妻がエキストラとして参加して下さいました。ご夫妻とは今でも交流があり、毎年帰国の折には我が家で室内楽を御一緒しています。又、新響のチェロ団員石川嘉一さんの友人でベルリン・フィルのチェロ首席だったオトマール・ボルヴィツキーさんには車で町を案内してもらうなど大変お世話になりました。この演奏旅行には80年に退団した家人もエキストラとして参加したのですが、石井先生が選んだハープ奏者早川りさこさんは、東大オケ指揮者として私共がお世話になり仲人もしてくださった早川正昭先生のお嬢さんということを旅行中に知り、びっくりしました(彼女は2001年、N響に入団しました)。
’94年1月、新響事務所を矢来町から十条労音に移転」と創立50周年年表にあります。新響の事務所は、’69年に神田から新宿区須賀町、’76年大久保駅前、’84年矢来町と引っ越しを重ねてきました。これらは事務所兼楽器置き場として使い、練習は主に東京文化会館の地下リハーサレル室を使っていましたが、十条労音には音楽ホール、楽器倉庫、幾つかの小部屋とレストランがあって、ホールがやや狭く音響が悪いものの使い勝手が良く、道路拡張で立ちのきが決まった今年(2012年)7月まで20年近く使用してきました。新響は練習時、2,3人の保母さんに頼んで団員のお子さん達の保育をお願いし、若いお母さん達が練習に打ち込める制度がありますが、十条労音の小部屋を使えるようになったのでこの保育制度が導入できたと記憶しています。7月から事務所が護国寺に移転しましたが、今後保育制度がどうなるか心配です。
‘94年は伊福部イヤーでした。先生の傘寿(80歳)を記念して4回の演奏会でそれぞれ伊福部作品を取り上げました(日本狂詩曲、交響譚詩、日本組曲、シンフォニア・タプカーラ)。
2月、エローラ・ホールで(埼玉県)松伏町依頼の『芥川也寸志映画音楽特集』のコンサートがありました。構成・司会は新響が音楽資料等でそれまでお世話になってきた音楽評論家の秋山邦晴先生、指揮は新響初登場の小松一彦先生でした。小松先生は十条労音での初練習で「出してしまった音は消しゴムで消せないんだからね!」などとキビシイことをおっしゃっていました。コンサートでは『五瓣の椿』『八甲田山』などの映画のシーンを舞台後方のスクリーンに投影しながら芥川先生の代表的な映画音楽10曲を演奏しました。
同年5月、東京都からの依頼で三宅島への3泊4日の演奏旅行がありました(私は仕事が忙しくて参加できませんでした)。指揮のトラビス先生は空路でしたが、海路だった団員は悪天候で船が揺れて大変だったそうです(三宅島の火山が大爆発し、全島民が避難したのは6年後の2000年8,9月でした)。
‘95年1月16日の定期でトラビス先生がベートーヴェン2番やファリャ『三角帽子』等を振ってくださった翌日早朝、阪神・淡路大震災が起きました。新響の演奏会が17日だったら開催できなかったことでしょう。当時、ヴァイオリン団員がとても多く、ファースト・ヴァイオリンは10プルト(20人)だったこと、コンサート後、芸大退任が近かった先生が団員10人ほどを巣鴨の芸大官舎に招き、奥様が手料理を御馳走して下さった思い出があります(そして3/20にオウム真理教による地下鉄サリン事件が起きました)。
同年7月16日、前年の秋山・小松コンビで『映画生誕100年記念』と銘打った定期が芸術劇場で開かれ、サン・サーンス、エリック・サティ、武満徹、芥川也寸志等の映画音楽を演奏しました。武満作品(『弦楽のためのホゼイトレス』)に対する小松先生の的確な指示が印象的でした。秋山先生は翌96年に亡くなられましたが、小松先生とのお付き合いはその後2009年まで続くことになります。
2週間後の7月30日には飯守先生がブルックナーの交響曲第8番をサントリー・ホールで振ってくださいましたが、第2楽章スケルツォで事故が起きかけました。ダ・カーポしてまだ楽章が終わっていないのに先生の棒は明らかに「終わり」を告げていたのです。私は心臓が止まる思いでしたが、思い切って次を出たらすぐに何人かが追従、先生もすぐに棒を振りだして何とか無事に終わりました。
これら2週間しか空いていない2回の定期演奏会の背景は、芸術劇場とサントリー・ホール両方とも取れてしまい、どちらかキャンセルするとホール側の心証を悪くするだろうから両方使ってしまえ、ということだったようです。 (2012年11月30日記)
(次号に続く)
ショーソン:交響曲
<はじめに>
本日お越しのお客様の中にはショーソンのファンの方が何人いらっしゃるのでしょうか。エルネスト・ショーソンの名前は、母国フランスでも、日本と同じくらいの控えめな印象しかないそうで、近代フランス音楽が確立し始めたころの巨匠たち、フランク、サン=サーンス、ドビュッシー、フォーレ、ラヴェル等に比べ地味な響きでしかないようです。
しかしショーソンの音楽は、特にドビュッシーとフランクをつなぐ重要な役割をつとめました。音楽の勉強を遅く始めたにもかかわらず、努力によりこれを補い、今やドビュッシーやラヴェルによって頂点に達した印象主義音楽の先駆者と評されています。
ショーソンは歌曲を中心に39の作品を残しています。彼はフランクに師事したフランキストであり、ワーグナーに心酔したワグネリアンでもありました。本日取り上げますショーソンの唯一の交響曲は、ワーグナー旋風の吹き荒れる中、その影響を受けつつも、ワーグナーのような劇音楽的ではなく、旋律の美しい繊細で叙情的な音楽を聴かせてくれます。
<ショーソンの生涯>
ショーソンは1855年1月20日パリで生まれました。父親は公共土木事業請負の職を持ち、母親は、天賦の繊細さと芸術的天分を持ったひとでした。
パリの第10区には、今でもピエール・ショーソンという名の通りが実在しています。ピエールはエルネスト・ショーソンの伯父さんであり、その小路に影響のある地主でした。通りは全長100mほど、道幅7m足らずの小さいもので、写真で見るとお世辞にもお洒落なパリの小道ではないのですが、ショーソンが生まれたころの一家の様子を想像させてくれます。
ショーソンの両親は2人の子どもを亡くしています。1人はショーソンの生まれる4年前に同じエルネストと名付けた子どもを、もう1人は、ショーソンが10歳のとき、法学部の学生で22歳になろうという長兄を死の手によって奪われました。深い悲しみにあった両親は、ショーソンの体が弱かったこともあってか、彼を1人の家庭教師に委ねました。幼少期の彼は、この家庭教師から、古典文学・美術への愛好心や音楽に関する非常に鋭い知覚と美への嗜好を育まれました。
ド・レイサック夫人が家庭教師から紹介されたのは、ショーソンが15歳のときでした。少年ショーソンは、芸術家や知識人の集まる夫人のサロンで、経験に富んだ年長者との接触により、思想を取り入れ、感性を研ぎ澄ませていきました。夫人はよくショーソンを理解し、彼の心の中にしまいこんでいた芸術性をうまく引き出す役割を生涯担っていたのです。当時、ショーソン少年は文学、美術、音楽のいずれに自分を捧げてよいのか悩んでいました。文学では、密かに書き留めた『内面の日記』や『ジャック』と題する物語、また彼のオペラ『アルチェス』の台本がショーソンの文学的才能の証拠として残されています。また絵画も彼の心をとらえ、父親が許したデッサンの勉強もあってか、旅行の際にも画帳を常に携行していたそうです。
しかし、あらゆる芸術の中で最も勝ち得たのはやはり音楽でした。ピアノを習いたいと息子が願ったとき、ものになるのかと半信半疑だった両親に、ピアノ教師は「偉大な音楽家になれるであろうし、楽器を始めるのに少しも遅すぎはしない」と言い切りました。ピアノの上達は速かったようで、このような芸術的に豊かな環境の中で、彼は自分の天職を音楽家と決めたのでした。
ショーソンがこの決心を父に告げたとき、実は驚くほどの反発にあってしまいます。父親は彼に大学に入って法律の勉強をすることを強く望んでいたのでした。ショーソンは両親を苦しませまいと自分の欲望を抑え、法学部への勉強を始めました。音楽の勉強をしたい気持ちとの板ばさみになりながらも、大学資格試験に合格し、本格的に法律の勉強を始めることとなります。そして、大学の博士課程を経て弁護士の資格を得ることが出来たのです。
「弁護士」という成功に満足した父親は、これからは自由に音楽を勉強することを許しました。こうしてショーソンは24歳のときにパリ音楽院の門をくぐり、マスネーの管弦楽法の教室に、ついでフランクの教室にも入り込みました。26歳の期末試験に提出された作品に対し、マスネーは「並外れた素質、ローマ大賞(フランス国家による留学制度、若手芸術家の登竜門)のコンクールに参加できよう!」と批評しています。しかし、同じ年にコンクールの予選に落選してしまいます。
ショーソンはパリ音楽院を出てからも、フランクによる作曲の指導を受けていましたが、28歳での結婚を機にやめています。結婚と音楽の両立にしばらく悩んだ末に独立を決心したのがその理由でしたが、フランクとの深い交友関係は生涯続くことになります。
結婚は結果として成功だったようで、妻の明るい性格はショーソンを生来の悲観主義から逸らせてくれました。31歳で国民音楽協会の書記に就任し、私財の一部を恵まれない音楽家に施すなど、忙しい中にも着実に作品を残し、聴衆や批評家からも好意をもって迎えられています。そして、本日演奏される「交響曲(1889-1890)」や、ドビュッシーによって絶賛された「ヴァイオリンと管弦楽のための《詩曲》(1896)」などの名曲が生まれることとなるのです。私が個人的にお気に入りの曲は「ピアノ、ヴァイオリンのためのコンセール(協奏曲)(1889-1891)」で、2曲目のシシリエンヌはNHKラジオ番組のテーマ曲だったと記憶しています。
1899年4月、44歳のショーソンは「四重奏曲」の第2楽章を完成させました。直ちに第3楽章の作曲にとりかかったのですが、完成させることはかないませんでした。なぜでしょうか。木立が点在するセーヌ河畔で、毎日徒歩や自転車に乗って散策しては作曲を進めていた彼は、6月のある日、夫人と子どもたちを迎えに、自転車で近くの駅へ行くことにしました。長女が先に門を出て、しばらく進んで振り返ると、どういうわけか父親の姿が見えません。引き返した長女が見たのは、正門の柱の根元にこめかみを砕かれて倒れていた音楽家の姿でした。過労によるものなのか、暑さでふらついた結末なのか、誰にもわかりませんでした。弔電で山積みとなった彼の仕事机には、数小節だけ書かれた第2交響曲が残されていたそうです。
普段のショーソンは、家庭にあっても社会にあっても陽気で明るい性格でした。それにもかかわらず、彼の作品は喜びに支配されることはありません。幼年時代の2人の兄の死が、暗い影を落としていたのでしょうか。彼は、「死が恐ろしいのではなく、(中略)なすべく神に命ぜられた仕事を果たすことなく死ぬのが恐ろしいのです」「たとえ1頁であっても、人の心にしみ透るものを書かずには倒れたくない」と、彼は友人にあてた手紙で告白しています。「心にしみ透る作品を書く」。ショーソンが絶えず念頭においていたこの言葉を私たちも心にとどめ、今日の演奏を聴いて、1人でも心に染みとおった方がいてくださるならば、ショーソンにとってもこの上ない喜びとなることでしょう。
<交響曲変ロ長調 Op.20について>
1889年から1890年にかけて作曲された交響曲変ロ長調は、ショーソンの十指に満たない器楽曲の一つです。その頃のフランス音楽では、サン=サーンスの「交響曲第3番ハ短調(オルガン付き)」やフランクの「交響曲ニ短調」などが生まれていて、オーケストラ界にとっては上昇気流の真っ只中でした。そんな中に作曲されたショーソンの交響曲は、彼に対する評価を確実なものにしました。事実、これまで彼の曲に冷淡であった何人かの批評家が、この交響曲に多くの才能が認められることを告白しています。
<第1楽章>
導入部 ラン(緩やかに、遅く)
長くゆったりとした導入部は、クラリネットとヴィオラ・チェロ・バスのユニゾンで静かに始まります(譜例1)。
つづいてトランペットが哀愁感たっぷりに(譜例2)を吹きます。
主部 アレグロ・ヴィーヴォ(速く、生き生きと)
ホルンとファゴットが主題を軽快に演奏します。その後、いくつかの主題がさまざまな楽器で演奏され、主題の結合を経て、最後は2分の2拍子のプレストで主題の強奏のうちに楽章を終わります。
<第2楽章>
トレ・ラン(きわめて緩やかに)
ショーソンらしい叙情性にあふれた楽章です。彼はこの楽章のためにずいぶんと時間を割いたようで、自筆譜には数多くの切り貼りや修正の後が残されているそうです。冒頭のヴァイオリンとヴィオラ(ファゴット、クラリネット)の掛け合いが非常に美しくも悲しく、ここだけでご飯が三杯食べられそうです。エンディングも感動的。
<第3楽章>
アニメ(快活に)
胸騒ぎのような弦楽器の分散和音にのった、トランペットと木管の痛切な叫びで始まります。その後、活気を帯びた曲想が続きますが、突然我に返ったように美しい金管楽器によるコラールが始まり、ついで第1楽章の(譜例2)がよみがえります。最後に(譜例1)を思い出しながら、ゆっくりと静かに曲を閉じます。
初演:1891年4月18日、パリのサル・エラールにて、作曲家自身の指揮による
楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット3、ホルン4、トランペット4、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、ハープ2、弦五部
参考文献
『不滅の大作曲家 ショーソン』ジャン・ガロワ(西村六郎訳)(音楽之友社)
『音楽テーマ事典1』(音楽之友社)
プーランク(フランセ編曲):「ぞうのババール」
子どもたちが大好きな絵本、『ぞうのババール』。絵本が生まれたフランスでは、ババールの生誕80周年を記念する展覧会が、昨年9月までパリ装飾芸術美術館のおもちゃギャラリーで開催されていました。本日演奏するプーランクの『ぞうのババール』についても、子供向けのコンサートでお馴染みの演目であるようです。ババールの絵本と音楽が子どもたちに愛されるのは、何も不思議なことではありません。どちらも子どもたちに導かれて生まれたからです。
<絵本について>
森で生まれた象のババールが、母親を撃ち殺した狩人から逃げるうちに街にたどり着き、人間の暮らしを身に付けて森に戻ると王様に選ばれ、そして結婚する…。このちょっと変わった絵本の作者ジャン・ド・ブリュノフは、プーランクと同様、1899年にパリの裕福な家庭に生まれました。画家を志してアカデミー・ド・ラ・グランド・ショミエールで美術を学び、親友の妹でピアニストのセシルと結婚、やがて男の子のロランとマテューが生まれます。
1930年の夏の夜、セシルは子どもたちに小象の物語を作って聞かせました。その話が気に入った子どもたちは、大喜びで父親のジャンに伝え、ジャンはそれを絵本にします。あくまで家族のための絵本のつもりでしたが、出版の仕事をしていた兄と義兄に勧められ、1931年にファッション雑誌で有名なジャルダン・デ・モード社から出版。当時の絵本としては珍しい大型本が好評で、発売されるや否や飛ぶように売れたそうです。
その後、ジャンは続編を出しますが、結核のため1937年に37歳の若さで亡くなり、続きは息子のロランに引き継がれます。ババールシリーズは、これまでに27か国語に翻訳され、167か国で1,300万部を販売。今や世界中の子どもたちに愛されています。
<音楽について>
プーランクが『ぞうのババール』の作曲を始めたのは、絵本の誕生から約10年後のことです。第2次世界大戦に動員されていたプーランクは、休戦中の1940年の夏を、リムーザン地方のブリーヴ・ラ・ガイヤルドにある友人宅で、いとこやその家族と過ごしました。ある日プーランクがピアノを弾いていると、その音楽に退屈した4歳の女の子が、絵本『ぞうのババール』をピアノの譜面台に置いたため、プーランクはその子を喜ばせようと『ぞうのババール』の作曲を始めます。
曲が完成したのは、それから5年後の1945年。プーランクが再びブリーヴに赴いたときに、少女へと成長した女の子に「それで、ババールは?」と聞かれたことがきっかけとなったそうです。このようにして生まれた語りとピアノのための『ぞうのババール』は、ブリーヴで時を共に過ごした子どもたちや友人たちに捧げられています。本日私たちが演奏するオーケストラ版は、プーランクから推薦を受けたジャン・フランセ(1912年~1997年)により、1962年に編曲されました。
<絵本の読者としてのプーランク>
朗読を伴う曲と言えばプロコフィエフの『ピーターと狼』が有名ですが、プーランクの『ぞうのババール』には原作の絵本が存在するという点で大きく異なります。プーランクの『ぞうのババール』の特筆すべき点は、話の一部が省略されてはいるものの、絵にも物語にもかなり忠実であるという点です。
プーランクは、「私の記憶はすべて視覚的記憶です」と言っており、絵画に並々ならぬ情熱を抱いていました。好きな同時代の画家を6人挙げるように言われれば、すかさず「マティス、ピカソ、ブラック、ボナール、デュフィ、パウル・クレー」と答えたそうです。1956年には、その名も『画家の仕事』という歌曲集を作っています。
また、20世紀の偉大な文学者が集ったことで知られるアドリエンヌ・モニエの書店の常連であったことからもわかるように、プーランクは若い頃から文学、とりわけ詩に夢中でした。詩をもとに作曲された魅力的な歌曲の数々が、詩への愛を物語っています。
絵や言葉に対して研ぎ澄まされた感性を持っていたプーランクは、良き絵本の読者であったに違いありません。だからこそ、絵本『ぞうのババール』を忠実に音楽に再現することができたのでしょう。
<ババールの目は子どもの目>
私はこの曲を演奏することになって初めて絵本『ぞうのババール』を読みましたが、やはり文明礼賛とも読める内容にはかなりの抵抗がありました。ジャン・ド・ブリュノフの生きた時代は、フランスが帝国主義のもとに植民地政策を推し進めていた時代です。さらに、絵本が出版された1931年には、植民地帝国のプロパガンダの到達点となる国際植民地博覧会がパリのヴァンセンヌの森で開催され、800万人の観客を動員しました。植民地との関係が特別なことではなかった当時のフランスでは、『ぞうのババール』の物語も違和感なく受け入れられていたと考えられます。
以上のような時代背景を知った上でもこの絵本を純粋に楽しむことができないのは、私が物事を批判的に見てしまう大人だからです。本稿の冒頭に掲載した絵本の表紙写真をご覧ください。ババールの目は点が2つだけ。これは、批判的なものの見方をさせないためだそうです。もしかしたらプーランクは、戦争中の不安な心を、ババールの純粋な眼差しに癒されていたのかもしれません。本日は客席の大人の皆様も、ほんのひとときだけ子どもに戻って、ババールたちと一緒に冒険の旅をお楽しみください。
初演:1946年6月14日ラジオ放送にて、ピエール・ベルナックの朗読と作曲家自身のピアノによる楽器編成:フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オ-ボエ2(2番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット2(2番はバスクラリネット持ち替え)、ファゴット2(2番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン2、トランペット2、トロンボーン、テューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、吊りシンバル、小太鼓2(tambourおよびcaisse claire)、タンブリン、トライアングル、ムチ(fouet)、タムタム、ホイッスル、手回しクラクション(klaxon a` manivelle)、起動ク
ランク(manivelle)、ハープ、弦五部
参考文献
『フランシス・プーランク』アンリ・エル(村田健司訳)(春秋社)
『フランスの子ども絵本史』石澤小枝子、高岡厚子、竹田順子、中川亜沙美(大阪大学出版会)
『植民地共和国フランス』N. バンセル、P. ブランシャール、F. ヴェルジェス(平野千果子、菊池恵介訳)(岩波書店)
Centre national de documentation pédagogique
http://www.cndp.fr/crdp-reims/poletheatre/service_educatif/babar.pdf
プーランク:「モデルは動物たち」組曲
<はじめに>
本日の演奏会ではプーランクの作品を2曲取り上げますが、3年前に他のオーケストラでここ芸術劇場にて矢崎彦太郎先生の指揮で「牝鹿」を演奏して以来、プーランクに魅了されてしまった私にとってはこの上ない幸せなプログラムとなりました。パリジャンならではの天真爛漫さや精妙洒脱なユーモアセンス、遊び心に溢れたこの作品、日本では一般的に「模範的な動物たち」などと呼ばれていますが、今回新響は「モデルは動物たち」として紹介することになりました。
“Les Animaux mod`eles”という題を提案したのはプーランクの友で、レジスタンスの闘士である詩人のポール・エリュアール(1895年-1952年)ですが、矢崎先生がこの曲をめぐる2人の往復書簡をお読みになり、曲の雰囲気や背景などを踏まえタイトルを付けられました。エリュアールの詩をテキストにした作品には他に合唱曲「人間の顔」や「雪の夜」などがあります。
<作品の概要>
プーランクはパリオペラ座からの依頼で、17世紀の詩人、ラ・フォンテーヌ(1621年-1695年)の寓話(動物などを擬人化した教訓的なたとえ話、イソップ物語など)から選択した6編に「夜明け」と「昼食」を加えバレエ音楽を作曲、後にその中の「熊と二人の仲間」、「セミと蟻」を省いて組曲として再編しました。フランス的な叡知の詰まった傑作であるこの寓話をプーランクもエリュアールも大変気に入っていました。1940年7月に題材が決定、1941年完成、1942年8月にパリオペラ座で初演されました。時は第二次世界大戦の真っ只中、時代の趨勢を意識して作曲され、ドイツ軍に対する批判やフランスの未来に対する希望が寓意的に且つ分かり易い明快な音楽で表現されています。演奏会は大成功を収め、オネゲルが「プーランクの才能が完全に開花した。シャブリエ、ストラヴィンスキー、サティの影響は消化され、プーランク本来の長所の中に溶け込んだ。」と大絶賛しました。国家委嘱作品になることを望まれていたものの友人のレーモンド・リノシェ追悼のために捧げられました。
<簡単なあらすじ>
1.夜明け…7月、ブルゴーニュ地方の夜明け。ある1日が始まります。
2.恋するライオン…ライオンが美女に恋をします。恋をしたライオンは…。
3.中年男と2人の愛人…金持ちの中年男を2人の女が奪い合い挙げ句の果てには…。
4.死神と樵(きこり)…人生に疲れ果てた樵は死神を呼びますが…。
5.2羽の雄鶏…仲の良い2羽の雄鶏のもとに雌鶏が舞い込んできますが…。
6.昼食…仕事を終えた人々が戻り昼食を始めます。
<フランシス・プーランクについて>…今年は没後50年
19世紀末ベル・エポックの開幕。この頃のパリはアメリカ、ロシア、日本など世界各地から多彩な文化が集まる国際都市でした。第5回パリ万博前年の1899年1月7日にプーランクは敬虔なカトリック教徒であるパリの製薬会社経営の父とピアニストの母のもとに生まれます。14歳の時にストラヴィンスキー作曲「春の祭典」の初演(当時一大センセーションを巻き起こした)を聴き、衝撃を受け音楽家を目指します。15歳になるとスペイン生まれのピアニスト、ビニェスに師事し、その後1917年サティ作曲の「パラード」(台本:コクトー、舞台:ピカソ、当時あまりにも斬新で大騒動となる)に遭遇、これにも大きな衝撃を受けます。また、コクトーのサロンに出入りし始めた当時18歳の彼は本格的に作曲を学びたいと考えましたが、父の反対を受け、パリ音楽院には入学せず3年の兵役後にケクランから作曲を学びます。1920年にはフランス6人組(オーリック、オネゲル、デュレ、プーランク、タイユフェール、ミヨー。音楽スタイルは違っていた)としてデビュ
ー、1924年、モンテカルロ(モナコ)での「牝鹿」公演の大成功で彼の名声は広まりました。
第二次世界大戦中フランスは、ドイツ占領下と同時にヴィシー政権の施政下にありました。ボルドー地方に徴兵されていたプーランクは1940年9月、敗戦の混乱が収まったのを機にパリへ戻り、1944年のパリ解放までパリで作曲活動を続けました。エリュアールやアポリネールの詩を読むと当時のフランスの苦しい状況を理解することができますが、「そうであっても、これ以上に典型的にフランスであった時代は他にはない、いかなる犠牲を払っても祖国フランスの運命に希望を見出そう」とプーランクも言っているように、誇りを失わず希望を持って歩んでいた人も多く存在しました。そんな時代にこの「モデルは動物たち」は創作されました。
晩年は1960年北米に演奏旅行し大成功を収めましたがその後、1963年1月30日、コクトーの「地獄の機械」に基づく4番目のオペラに取り組んでいる途中、突然の心臓発作で死去、2月2日、サン・シュルピス寺院にて葬儀が執り行われました。満64歳、独身主義者でしたが子供の純真さを愛する生粋のパリジャンでした。彼はあるインタビューで「もし、無人島に流されるとしたら、持っていきたい詩はラ・フォンテーヌ、ボードレール、アポリネール、エリュアール、ロンサール、音楽ならばモーツァルト、シューベルト、ショパン、ドビュッシー、ストラヴィンスキー」と答えています。
初演:1942年8月8日 パリ・オペラ座にて、ロジェ・デゾルミエールの指揮による
(振り付け・台本:セルジュ・リファール、舞台装置・衣装:モーリス・ブリアンション)
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、小クラリネット、バスクラリネット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トライアングル、シンバル、吊りシンバル、大太鼓、中太鼓、小太鼓、タンブリン、クロタル、タムタム、グロッケンシュピール、木琴、ハープ2、ピアノ、チェレスタ、弦五部
参考文献
『ニューグローヴ世界音楽大事典』スタンリー・セイディ編(講談社)
『音楽大事典』(平凡社)
研究論文:プーランクのバレエ組曲「模範的動物」の考察、お茶の水音楽論集第3巻P28(2001・4)田崎直美(お茶の水女子大学)
スコア(MAX ESCHIG版)
『フランス詩人によるパリ小事典』賀陽亜希子(白凰社)
『ドレ画 ラ・フォンテーヌの寓話』ラ・フォンテーヌ(窪田般彌訳)(現代教養文庫)
『プーランクは語る 音楽家と詩人たち』フランシス・プーランク、ステファヌ・オーデル編(千葉文夫訳)(筑摩書房)
レコード芸術1999年4月号Vol.583(音楽之友社)
第223回ローテーション
| モデルは動物たち | 象のババール | ショーソン | |
| フルート1st | 兼子 | 岡田 | 松下 |
| 2nd | 吉田 | 吉田(+Picc.) | 新井 |
| 3rd | - | - | 藤井 |
| Picc | 藤井 | - | - |
| オーボエ1st | 山口 | 岩城 | 亀井 |
| 2nd | 岩城 | 堀内(+C.A.) | 桜井 |
| C.A. | 堀内 | - | 宮内 |
| クラリネット1st | 品田 | 進藤 | 末村 |
| 2nd | 進藤 | 品田(+B.Cl) | 大薮 |
| Es.Cl. | 大薮 | - | - |
| B.Cl. | 石綿 | - | 石綿 |
| ファゴット1st | 田川 | 田川 | 浦 |
| 2nd | 浦 | 斉藤(+C.Fg) | 斉藤 |
| 3rd | 斉藤 | - | 田川 |
| C.Fg | (*) | - | - |
| ホルン1st | 山口 | 森 | 箭田 |
| 2nd | 森 | 山口 | 市川 |
| 3rd | 大原 | - | 大内 |
| 4th | 市川 | - | 大原 |
| トランペット1st | 北村 | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 倉田 | 青木 | 倉田 |
| 3rd | 青木 | - | 小出 |
| 4th | - | - | 青木 |
| トロンボーン1st | 武田 | 武田 | 町谷 |
| 2nd | 小倉 | - | 志村 |
| 3rd | 岡田 | - | 岡田 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 皆月 | 古関 | 桑形 |
| パーカッション | シンバル/今尾 吊りシンバル,タムタム/桑形 トライアングル,グロッケンシュピール/古関 鉄琴,Tambu/浦辺 中・小太鼓,Tamba/中川 |
シンバル,グロッケンシュピール/中川 Tamb./今尾 吊りシンバル,タムタム/その他全部 |
- |
| ピアノ | 藤井 | - | - |
| チェレスタ | (*) | - | - |
| ハープ1 | (*) | (*) | (*) |
| ハープ2 | (*) | - | (*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(小松) | 堀内(小松) | 堀内(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(佐藤真) | 大隈(佐藤真) | 大隈(佐藤真) |
| ヴィオラ | 村原大(柳澤) | 村原大(柳澤) | 柳澤(村原大) |
| チェロ | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) | 柳部容(光野) |
| コントラバス | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) |
(*)はエキストラ
第223回演奏会のご案内
■フランス物の名手、矢崎彦太郎
矢崎は1947年生まれ、上智大学数学科に学んだ後に東京藝術大学の指揮科を卒業、ヨーロッパに渡り研鑽を積み、1979年からパリに拠点を移し世界各地で活動をしています。
日本においては2002年から東京シティフィルの首席客演指揮者を務め、長年にわたる日仏音楽交流への貢献に対しフランス政府より芸術文化勲章を授与されています。柔らかな指揮から色彩的な音楽が奏でられます。
■今年はプーランク没後50年
プーランクは1899年パリ生まれ、父は敬謙なカトリック教徒の家系、母は生粋のパリジェンヌであり、軽妙で洒落た音楽と厳かな宗教音楽の双方を併せもつ作風で知られています。今回の演奏会では動物の登場する明るく楽しい2曲を演奏します。ともに、徴兵されたプーランクが休戦により戦地から戻った1940年に着手されています。当時フランスはドイツ軍の占領下にありました。
「モデルは動物たち」は、日本では一般的に「典型的動物」「模範的動物」と呼ばれている曲です。直訳で何のことだかわかりにくく、堅苦しい語感からかあまり日本では演奏される機会がありませんので、新響は「モデルは動物たち」として紹介することにしました。17世紀のフランスの詩人、ラ・フォンテーヌがイソップ物語を元に書いた寓話から6つの話を選んで作ったバレエで、後に組曲に再編したものです。寓話とは動物などを擬人化した教訓的なたとえ話で、この曲にはライオンや雄鶏が登場しますが、動物をモデルにして人間の出来事を物語にしただけでなく、フランスをそれらの動物に見立て、フランスが希望を持てるようにという意図が隠されています。
「ぞうのババール」は、1931年に発表され人気を博した絵本で、プーランクは親戚の子供たちが夢中になっているのを見て、ピアノと語りのための音楽を作曲しました。ババールは洋服を着て2本足で歩く擬人化された象で、猟師に母を殺されジャングルから逃げてパリへ行き、老婦人と友達になって平和に暮らすが、故郷を思い出し森に帰って象の国の王様になります。古き良き時代のフランスを懐かしむかのような物語を、プーランクは愛情に満ちた音楽で魅力的に表現しています。今回は、のちにフランセが編曲した管弦楽版を語りに中井美穂を迎え演奏します。
■ショーソン-フランス・ロマン派の傑作
ショーソンは1855年パリ生まれ。父親の意向で法学を勉強し弁護士に任命されますが、その後パリ音楽院でマスネやフランクに学びます。毎年バイロイトに出向くワグネリアンでもありました。ショーソン唯一の交響曲は、フランクのそれと同じ形式で、明るくフランス的エスプリを感じる曲です。44歳で別荘の門柱に自転車で激突して亡くなり、残した作品が少ないのは残念です。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
R.シュトラウス: 交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」
R.シュトラウスは、1864年にミュンヘンで生まれた。父は、管弦楽団の第1ホルン奏者。その影響から、幼いころよりピアノやヴァイオリンに親しんだ。やがて作曲を夢中に勉強するようになる。彼は生涯において、主にオペラ・歌曲・管弦楽曲を多く作曲した。このうち、管弦楽曲の多くは20~30代に集中している。そして、それらのほとんどが「交響詩」という形をとった。
交響詩はR.シュトラウスが活躍するひとむかし前に、フランツ・リストらが作り上げた世界だ。その頂点を、R.シュトラウスが築き上げたといっても過言ではない。それら交響詩の中にあって、本日演奏する「ツァラトゥストラはかく語りき」は、彼の交響詩の集大成ともいえるべき作品の一つだろう。これら交響詩を糧に、着実に実力を蓄えたR.シュトラウスは、次なるジャンルの「オペラ」へと羽ばたいていくことになる。
■作曲されたその背景
「ツァラトゥストラはかく語りき」が作曲されたのは1896年。同じ時代を生きた作曲家をみると、ワーグナー、ブルックナー、マーラーなどと、有名どころが活躍していた時代だ。そのような中、R.シュトラウスは作曲当時32歳。生まれ故郷のミュンヘンにいた。
若きR.シュトラウスは、この頃ミュンヘン宮廷歌劇場の指揮者として活躍する傍らで数々の交響詩を作曲し、その名声を高めていた。かの「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」や「ドン・キホーテ」、そして「ツァラトゥストラはかく語りき」などの交響詩は、このミュンヘンの地において作曲された。
その「ツァラトゥストラはかく語りき」が作曲された直後、R.シュトラウスは同歌劇場の音楽総監督に就任した。だが、これまで世に出た交響詩は、当時としては余りにも斬新だった。これが、古き良きものを大切にしてきた宮廷歌劇場との間に対立を生む。お互いになんとか関係の修復を試みるも、その溝は結局埋まらない。やがて、R.シュトラウスはミュンヘンの歌劇場を去ることになる。
この「ツァラトゥストラはかく語りき」は、1896年の2月に着手し、8月に書き上げられた。総譜とパート譜は、直ちにミュンヘンのヨーゼフ・アイプルから出版された。出版社への売値は3200マルク。当時の相場としてはまだ安い。
同年暮れの11月27日、ドイツのフランクフルト・アム・マインにて、本人の指揮により初演された。その3日後の11月30日にはベルリンでニキシュの指揮により、またその翌日12月1日にはケルンで演奏された。
■ツァラトゥストラとは何か
さて、この曲はスタンリー・キューブリック監督の映画「2001年宇宙の旅」で冒頭が印象的に使われた。その関係からか、一般的には序奏の部分があまりにも有名。しかしそれ以外の部分は、それほど知られていない。R.シュトラウスの作品は、冒頭が派手で、最後に穏やかとなる形がよくある。これはその典型だ。
作曲の詳細を少し書こう。
ミュンヘン大学の哲学科で学んだR.シュトラウスは、1880年代にニーチェが書いた「ツァラトゥスト
ラはかく語りき」もじっくり読み上げた。そっくりタイトルにしたこの曲は、著書の影響を存分に受けていることは明らかだ。
さて、ニーチェの書いた「ツァラトゥストラはかく語りき」とは何だろうか。
ツァラトゥストラは、紀元前6世紀ごろのペルシャのゾロアスター教、その教祖と言われる伝説的人物だ。ドイツ語でゾロアスターのことを、ツァラトゥストラという。
この哲学書の内容をざっくり言えば、ツァラトゥストラが山にこもり、思案したのちに悟りを開いて、各地で予言した思想が本に書かれている。徳や戦争、科学、有限と無限の生、そういった事をいろいろ語るあらすじだ。これらの説話を通して、当時の理性的な人々に対し、「古代の永遠なる自然に根源的な救済」(ディオニソス的なもの)を示した内容となっている。
つまり、永遠回帰の思想を描いたあらすじだ。それらを曲として描いたと、当然世間は思った。ところがここで、R.シュトラウス本人は違った見解を示す。「ニーチェの書いた著書の内容を曲にしたのではなく、これを書いた超人的なニーチェの思想を、曲に表現したものだ」と。
■R.シュトラウスの込めた想い
R.シュトラウスは、何を書いたのか。情報を集め、違う角度から考えてみた。ドイツの、R.シュトラウス研究の第一人者、シュテファン・コーラ氏の研究成果には、別の哲学的なとらえ方が見られる。
R.シュトラウスは、正真正銘のニーチェ主義者だった。ニーチェはR.シュトラウスのちょうど20歳年上。考え方も生き方も、ちょうど同時代に活躍した著名人だ。ニーチェ読者としてのR.シュトラウスは、今の平和な時代の人間とは少し違い、当時の時代を生きる人として、書に特別な理解があったようだ。R.シュトラウスは、自らの手控えとしてその哲学箴言書に、ニーチェの「アンチ・クリスト」の序章から、こんな言葉を書きつけていたとされている。
「政治や民族統一の夢や、あわれむべき議論を下方に見下ろすためには、山上に住む訓練をしておかねばならない」と。
「ツァラトゥストラはかく語りき」の作曲は、彼が32歳の時。それから、一連の交響詩が完成し、世に評価されるころ、R.シュトラウスは作曲の活動拠点を、山へ移す。
その後の作曲のほとんどを、海抜1800メートルの高地、シルス・マリア(スイス)で取り組むようになったのだ。
R.シュトラウスは、政治や戦争、民族運動を「下方の出来事」として遠巻きに見ていたい人間だったようだ。山にこもり悟りを開き、下方の人々にそれを説いたツァラトゥストラ。それに対しR.シュトラウスも、山で作曲し世に(下方に)問うた両者は、単なる偶然の一致として片づけられない何かがある。
ツァラトゥストラとR.シュトラウス。私にはこの二人が重なって見えて仕方がない。そうしたときのツァラトゥストラとは、ニーチェその人だ。時に、思想の表現について、検閲が厳しさを増していた時代。R.シュトラウスは楽曲を通し、哲学的な何かを世に残したかったのではないか。
もう少し書こう。
コーラ氏の研究成果では、後世ナチス政権下の世相にあって、R.シュトラウスは内なる抵抗者であったことを暗に示唆している。反ナチス、つまり和平を重んじる考え方だった。
作曲されたタイミング、彼の行動、抑圧された時代背景などから、この曲に込めた思いを考えるときに、R.シュトラウスは当時の独裁・争いを暗に批判し、人が人として自然に生きることへの素晴らしさを、哲学的に描きたかったのではないか。オブラートに包まれた中の、真の意味。しかし分かる人には、分かるような何かを曲に託した。私個人としては、そんな気がしてならない。
■曲の内容について
序奏
冒頭、トランペットが吹くテーマは、「自然のテーマ」と呼ばれている。このテーマは、これ以降の曲中にたびたび登場する。全体を統括する、冒頭の主題となっている。『ド・ソ・ド』と、ミを加えず上昇し、続いて長和音、短和音へと移動する様は、自然の神秘と解決されない謎を示している。
後の世の人々について
低弦の上に「あこがれのテーマ」と呼ばれる主題がファゴットなどで出てくる。その後出てくるホルンのテーマは、グレゴリオ聖歌の「クレド(われ唯一の神を信ず)」に由来している。この辺は弦楽器のパートが対位法的な厚みを増して書かれていて、聴きごたえがある。
歓喜と情熱について
まさしく熱い情熱を感じるモチーフ。表情豊かに印象深い主題が奏でられ、これが立体的に展開してゆく。クライマックス付近で、トロンボーンがこの流れに反して「嫌悪のテーマ」を吹く。
埋葬の歌
やがて静まり返り、オーボエが「埋葬の歌」を粛々と奏でる。上向したがる「あこがれのテーマ」と下向きの音が動き絡み合いながら、静かに静かに沈み込んでいく。
科学について
コントラバスとチェロが静かにゆっくり動く。科学的な「フーガ」が用いられているが、時に様々な三連符が奏でられ、科学で解明されない神秘性を醸す。しばらくするとこれにフルートが加わり、幸福感のある明るい流れになる。その後「自然のテーマ」「嫌悪のテーマ」などが木管楽器で複雑に絡み合い、美しく盛り上がる。
病より癒えゆくもの
トロンボーンで前出のフーガが提示される。このテーマは「自然のテーマ」の変形で、非常に立体的に展開する。大きく盛り上がった後ひと区切りがつくが、その後静かな再現部に入る。しばらくするとトランペットの信号音が発せられ、これらが「嫌悪のテーマ」と絡み合いながら、色彩を増してゆく。
舞踏の歌
雰囲気が変わり、非常に華やかな三拍子。このワルツこそ、R.シュトラウスの真骨頂ではなかろうか。ソロ・ヴァイオリンによるウィーンの舞踏風旋律。それが全体の踊りに波及していく。やがてホルンが「夜の歌」を奏でる。これらさまざまな主題が融合していきながら、華やかさをどんどん増し、クライマックスへ向かう。
夜のさすさい人の歌
その盛り上がりの頂点から崩壊が始まり、鐘がならされる。鐘は全部で12回鳴るが、これは深夜を告げている。背景は半音下降で進行し、ワーグナーの「神々の黄昏」を暗示している。アンチ・ワーグナーだったR.シュトラウスだが、作曲当時はワーグナーを信奉していたことに由来しているかもしれない。
やがて自然と人間の対立と共生が永遠に続くかのごとく、楽曲は遠のくように終わってゆく。その穏やかさが、まるで冒頭の序奏につながるような様は、永遠回帰を想像させる。
初 演:1896年11月27日フランクフルト・アム・マインにて、作曲者自身の指揮による
楽器編成:ピッコロ、フルート3(3番は第2ピッコロ持ち替え)、オーボエ3、コールアングレ、小クラリネット、クラリネット3、バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン6、トランペット4、トロンボーン3、テューバ2、ティンパニ、大太鼓、シンバル、トライアングル、グロッケンシュピール、鐘、ハープ2、オルガン、弦五部
参考文献
『R.シュトラウス(作曲家別名曲解説ライブラリー9)』(音楽之友社)
『リヒャルト・シュトラウスの実像』日本リヒャルト・シュトラウス協会編(音楽の友社)
『ニーチェ ツァラトゥストラ』西研(NHK出版)
『ツァラトゥストラはこう語った(MINIATURE SCORES)』(音楽の友社)
CD『交響詩ツァラトゥストラはかく語りき・作品30』(解説)長谷川勝英(DECCA)
ブラームス:交響曲第3番
いつだったか、友人に好きな曲を聞かれて「ブラ4(ブラームス/交響曲第4番)と、ブラ3(ブラームス/交響曲第3番)の3楽章」と答えたら、「根暗だね(笑)」と言われたことがありますが、誰に何と言われようと私はブラームスの交響曲が大好きです。キャッチーなメロディではないので初めて聴いた時は正直捉えどころがなくてよく分からないような印象でしたが、何度か聴いていると不思議と音楽が心の奥深くまで入り込んでくるのです。そんな不思議なブラームスの魅力を、ブラームスファンのみならず、あまりブラームスの音楽に馴染みがない方々にも、本日の演奏を通して感じて頂けたら幸いです。
****************
今から180年前の1833年、ブラームスはドイツのハンブルクで生まれました。大変貧しい家庭でしたが、音楽家だった父はブラームスに6歳頃からヴァイオリンなどを教え始め、7歳からはピアノを習わせます。家にはピアノが無かったにも関わらず、教師の助けもあり10歳の時には父の主催する演奏会でベートーヴェン『ピアノ五重奏曲』と、モーツァルト『ピアノ四重奏曲』を演奏して天才の片鱗を表し、15歳の時にはピアノの独奏会を開いたというのですから驚きです。作曲と音楽理論については、12歳頃から本格的に学び始めます。ただ家庭は相変わらず貧しかったため、家計を助けるために酒場やダンスホールでピアノ演奏のアルバイトをしていたそうです。
さて、本日の演目である交響曲第3番が作曲されたのは今から130年前の1883年、ブラームス50歳の時です。この交響曲が完成する約半年前、音楽界には衝撃が走りました。巨匠・ワーグナーがこの世を去ったのです。当時のヨーロッパ音楽界では、「ワーグナー派」対「ブラームス派」の対立抗争が巻き起こっていました。1868年にワーグナー作曲『ニュルンベルクのマイスタージンガー』と、ブラームス作曲『ドイツ・レクイエム』が初演され、大成功をおさめた頃から本格化したこの対立は、ブラームスの意思とは関係なく過熱していきました。常に新しい音楽表現を追い求めたワーグナーと、古典的な形式を守りつつ試行錯誤の末に独自の音楽を確立させたブラームス。ワーグナーの死がこの交響曲第3番の作曲に影響を与えたのかどうかはっきりとは分かりませんが、抗争が少し沈静化したことでブラームスは落ち着いて作曲に取り組むことができたのではないでしょうか。
構想から約20年もかけて完成された交響曲第1番、その翌年にわずか数か月で完成された交響曲第2番、そしてその6年後、50歳の時に作曲されたこの交響曲第3番。当時ブラームスが何を考えながら作曲したのか、この曲で何を表現したかったのか、思いを巡らしながら聴いてみるとより一層深くブラームスの音楽を味わうことができるでしょう。
【第1楽章】
管楽器の『ファ・ラ♭・ファ』という音型でこの交響曲は幕を開けます。1音目の『ファ』で「お、始まったぞ!」と聴衆をわくわくさせておいて、2音目の『ラ♭』の和音で「ん?何が起こったんだ?」
と不安な気持ちにさせ、3音目の『ファ』でまた「ああ良かった」と落ち着かせる(譜例上段)。そして続けてヴァイオリンの『ファ・ラ・ファ』という対称的な音型が登場します(譜例下段)。この音型は手を変え品を変え全曲を通して出てきますので、ぜひ注意深く聴いてみてください。ちなみにこの3音をラテン文字で表すと『F・A♭・F』となり、それはドイツ語で『frei aber froh(自由に、しかも喜ばしく)』をもじったものだと言われています。
【第2楽章】
美しく穏やかな木管楽器のメロディが印象的な第2楽章。冒頭、クラリネットの美しいメロディに低弦楽器が静かに相槌を打ちます。その対話は次第に他の楽器も取り込み、大きなうねりとなりますが、すぐにまた落ち着きを取り戻します。再びクラリネットとファゴット、続いてオーボエとホルンのメロディに弦楽器が相槌を打ち、どこか遠い昔に思いを馳せているような雰囲気に…。楽章を通して管楽器と弦楽器の対話から美しい音楽のうねりが生まれますが、そのうねりはあくまでも平和的で、悲観的ではありませんが楽観的でもなく、全てを悟った上で訪れた心の穏やかさが表れているように感じられます。
【第3楽章】
チェロの美しくも切ないメロディで始まる第3楽章。このメロディはその後ヴァイオリン、フルート、オーボエ、ホルンによっても奏でられますが、どの楽器にバトンタッチをされてもそれぞれの楽器の良さが存分に味わえる大変魅力的な旋律です。個人的には、この美しいメロディの裏で三連符を弾いている時がこの交響曲を演奏している中で一番幸せです。メロディの裏では常に三連符が流れていますが、実はこの三連符は分業制で、1つの楽器がずっと奏でているわけではありません。異なるパートが代わる代わる三連符を受け渡して一つの流れとなっているのですが、それが心の奥深くを揺さぶるような独特のうねりを出しています。自分が演奏していてそのうねりの一部に上手く入り込めた時は、本当に幸せな気持ちになります。
【第4楽章】
第3楽章の最後の空気感をそのまま受け継いだような弦楽器とファゴットのメロディで始まる第4楽章。CDだといつも冒頭の音が小さくて聴こえず、ボリュームを上げてしまいますが、それをすぐ後悔することに。トロンボーンの美しい響きが急に大きくなり、イヤホンから大音量が漏れ出します。トロンボーンに導かれた強く弾むようなリズムは徐々にエネルギーを集めて高まり、木管楽器の下降音階で頂点に達します。そして、今まで眉間に皺を寄せていたのが嘘のようなチェロとホルンの伸びやかなメロディが出てきます。ここから、メロディの裏で常に動いている細かい三連符にぜひ注目してみてください。ここでも第3楽章と同じく分業制で、色々な楽器が代わる代わる三連符を奏でることで、メロディに独特の彩りを添えています。また、中盤の管楽器がパイプオルガンのように鳴り響く場面でも、弦楽器が今度は力強く三連符を鳴らして音楽を推し進めていきます。落ち着きを取り戻した終盤、ヴィオラの切ないメロディに導かれて管楽器が厳かに奏でる旋律は、まるで遠い昔に思いを馳せているようで、どこか哀愁が漂いながらもいつの間にかどこからか光が差してきて明るい響きに変わり、最後はその光の中で静かに幕を下ろします。
初演:1883年12月2日ウィーンの楽友協会ホールにて、ハンス・リヒター指揮による
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、弦五部
参考文献
『ブラームス』三宅幸夫(新潮社)
『ロマン派の交響曲―「未完成」から「悲愴」まで』金聖響・玉木正之(講談社)
『ブラームス交響曲第3番へ長調作品90 ミニチュアスコア』西原稔(音楽之友社)
新交響楽団在団44年の思い出-③
編集人より
コンサートマスターを長年に亘って務められた都河和彦氏による回想録を、前々号より、掲載しております。以下に新響創立30周年からの10年間のうち芥川氏の死去前後までの、前半部分をご紹介致します。
◆創立30周年(1986年)からの10年間-1
1986年4月にはヤマカズ先生指揮でマーラーの交響曲第8番『千人の交響曲』を演奏、7月には芥川先生指揮でショスタコーヴィッチの交響曲第4番の日本初演、そして11月には全団員の念願だった『芥川也寸志個展』が開かれました。マーラーでは本番前日のゲネプロ会場に困っていたら、開館間近だったサントリー・ホールが音響テストを兼ねてホールを提供してくれました。本番では東京文化会館の舞台を大幅に広げ、8人の独唱者、3つの合唱団が参加して文字通り千人で演奏、新響史上最大規模のコンサートだったと思います。
芥川個展について先生は長らく固辞しておられたのですが、多くの団員の懇請でようやく実現しました。芥川先生は常々「新響コンサートのプログラムは将来、新響の歴史を示す貴重な資料になるものだから心をこめて編集しなさい」とおっしゃっていましたが、落合宏氏、樋口のぞみさんが中心になって編集し、先生の数多くの写真・資料や寄せ書き等で分厚く、表紙に『新響と30年 Yasushi Akutagawa 1986』と先生の自筆署名があるこのコンサートのプログラムは新響史上最も豪華なものでした。
87年4月、芥川先生が親交のあった中国人作曲家の3作品と上海音楽院生の左軍(さぐん)氏独奏のチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲による「中国作品展」が開催されました。呉祖強(ごそきょう)作曲のゆったりとした「二泉映月」は、私共日本人にとっては歌い方がよく分からなかったので、当時読売日本交響楽団のコンマスだった中国人ヴァイオリニスト潘寅林(ばん・いんりん)氏をお招きしてポルタメントのかけ方等について指導を受けました。また左軍氏の楽器はあまり良くなかったので本番では当時理事長だった松木英作氏が自分の名器「ヴィヨーム」を貸し、左軍氏は見事な演奏を披露しました。演奏会終了後のパーティーで何人かの団員による「松木さんは左軍さんにヴィヨームをあげるべきだ」とのシュプレヒコールが起きたので、松木氏は真っ青になっていました。この時の超美人の中国人通訳だった湯(たん)さんの紹介で、無量塔蔵六氏のもとでヴァイオリン造りを学んでいた中国人・陳宇さんが翌年新響に入団しました。私は彼の日本での保証人になりましたが、数年前日本に帰化しました。彼は成城学園前で「弦楽器トリオ」(私が名付け親です)を経営、多くの新響団員の楽器のメンテナンスを引き受け、度々工房で開く室内楽パーティーでは水餃子をはじめ、様々な中華料理を御馳走してくれています。
88年7月のヤマカズ先生のマーラー・シリーズ最終回(11回目、メインは交響曲第1番)では冒頭の曲目を変更してマーラーの交響曲第9番4楽章を演奏しました。前年脳溢血で倒れ、11カ月間昏睡したまま88年4月に逝去したコンバス奏者、橋谷幸男氏を追悼するためでした。彼は私より5歳年下で早大在学中の1969年末に新響に入団、すぐに運営委員長として敏腕を振るい、ヤマカズ先生を説き伏せてマーラー・シリーズを実行、多くの団員から慕われていました。私が勤務していたモービル石油と同じ系列のキグナス石油勤務ということもあって親しく付き合い、新響外で『アンサンブル・フェルマータ』という室内オケを立ち上げ10年ほど一緒に活動しました。追悼演奏のマーラー第9番終楽章「アダージオ」の終盤部はpppやppppと最弱音になります。橋谷氏の死の哀しみのためか、ヤマカズ先生の棒が厳しすぎたのか、この個所で私の弓が震え出し何人かのヴァイオリン・メンバーに伝染させてしまいました。弦楽器は弱音で弾く時、右腕が緊張すると弓が勝手に?震えてしまうことがあります。大昔、フルトヴェングラーがベルリン・フィルに最弱音を要求したら弦の首席奏者達は怖くて音が出せず、弦楽器パートの後方から細々とした音が聴こえてフルベンは満足した、という話を聞いたことがあります。又、最近読響のコンマスを引退された藤原浜雄氏は昔「弓が震え出したら、楽器を上に挙げれば良い」とおっしゃったそうですが、残念ながら当時私はその秘策を知りませんでした。
89年1月31日、新響を33年間育て、私が21年間お世話になった芥川先生が63歳の若さで逝去されるという悲しい出来事がありました。青山葬儀場での盛大な葬儀には師匠の伊福部先生を初め、土井たか子社会党委員長も参列されていました(芥川先生は政治的には左派で私が新響に入団した1968年には美濃部革新派都知事を応援しており、4月の知事就任1周年記念集会で新響は芥川先生作曲の革新都政応援歌?を演奏しました。團伊玖磨、黛敏郎と53年に結成した『3人の会』で黛氏は右派だったのは興味深いことです)。弔辞では黛氏が「芥川さん、あなたは日本音楽著作権協会理事長などの激務を重ね死に急いだ、壮烈な文化への戦死だった」と述べられたと記憶しています。
先生が4月に振る予定だったストラヴィンスキーの『ペトルーシュカ』とチャイコフスキーの『悲愴』は、ヤマカズ先生紹介の若手指揮者、本名徹二氏が振ってくださいました(本名氏にはその後、40周年(1996)の2日連続の邦人作品演奏会と郡山演奏会(2004)でお世話になることになります)。『悲愴』終了後、私が「天国におられる芥川先生へ捧げます」と短いスピーチをして、先生の『交響管絃楽の為の音楽』第2楽章を追悼演奏として、指揮者無しで演奏した思い出があります。
5月にはサントリー財団主催の芥川也寸志追悼コンサートがサントリー・ホールで開かれ、新響が芥川先生の遺作を含む数曲を外山雄三氏の指揮で演奏しました。コンサート後のパーティーで私が外山先生に「新響は20年近く前に先生にチャイコフスキーの4番を振っていただきましたが、もうアマ・オケは振りたくない、とおっしゃっていました」と話したら、「ボク、そんな失礼なことを言いましたか?」と、とぼけて?いらっしゃいました。
芥川先生逝去の半年後、埼玉県松伏町に先生が建設に関与した『田園ホール・エローラ』が完成、90年1月新響は森山崇氏指揮で芥川作品ばかりのコンサートをこのホールで開きました。また同年4月にサントリー音楽財団が「芥川作曲賞」を創設しました。
89年7月の定期では、指揮者今村能氏の提案で今村氏と親しい新進気鋭の作曲家細川俊夫氏に『ヒロシマ・レクイエム』の作曲を委嘱、サントリー・ホールで初演しました(今村氏は87年にもルストワフスキ『管弦楽のための協奏曲』等を振っていただいたのですが、私は仕事が多忙で休団していました)。『ヒロシマ~』は8人の独唱、2つの合唱団、そして日本語の語り二人と英語の語り一人が入る大規模な曲で、英語の語りは当時新響チェロ団員だったアメリカ人のジョン・ブロウカリング氏が担当しました。作曲者の細川氏はクフモ音楽祭と重なり初演の会場に見えませんでしたが、5月の鹿嶋合宿に現代音楽専門のコンバス奏者、溝入敬三さんと来て下さり、現代音楽についてレクチャーしてくださいました。「皆さんは例えばドとレの間にはドのシャープかレのフラットしかない、と思っているでしょう。でも理論上もっと多くの音が無数に詰まっているんです。それらの音を使ってあげないと可哀そうじゃないですか」とのコメントには全団員唖然としました。
10月、私が80~82年のNY滞在中に知遇を得、88年から日本で指揮活動を始めた原田幸一郎先生が新響の指揮台に登場、やはりNYで知り合ったチェリスト毛利伯朗氏(現読響首席)がドヴォルザークのコンチェルト(ドボコン)を弾いてくださいました。毛利氏はドボコンの最初の練習には我々が合宿中だった鹿島ハイツに夜間タクシーで駆けつけ、すぐ私達の酒盛りに加わりました。翌朝の初練習でチューニングの時「ワー、指先までアルコールが残っている!」と叫んだのですがソロを弾き始めた途端、すべての団員が彼の素晴らしい音色、表現力、技術にあっという間に引き込まれてしまいました。本番も見事な演奏で、第3楽章終盤での毛利氏とコンマスだった私との丁々発止の掛け合いは未だ脳裏に残っています。
90年1月20日、『追悼・芥川也寸志』の定期コンサートが新宿文化センターで開かれ、芥川作品3曲をヤマカズ先生が振ってくださり、『ポイパの川とポイパの木』の語りを岸田今日子さんがしてくださいました。1月27日は松伏町の依頼、翌28日は台東区の依頼で芥川作品を演奏し、27日は森山崇氏指揮(於エローラ・ホール)、28日はヤマカズ先生指揮(於奏楽堂)でした。(2012年11月30日記)
親父の「ツァラ」
「恭四郎、カラヤンという指揮者とベルリンフィルの演奏会が近々あるのだが、一緒に行かないか?」 突然父から言われ、面食らった。1979年秋のこと、私は4年目の気ままな大学生活を満喫していた時である。なんでも外国人の接待でベルリンフィルの来日公演チケットを押さえたが席が余っているのでどう?とのこと。普段の父とは様子が違っていて、こちらの様子を伺いながらの申し入れに対し、即座に反応したのはいうまでもない。30代で香港の領事をしていた父によれば、「海外ではこのような演奏会に招待という接待がある。お前はただ演奏会にくればいいから。」という話だった。たぶん兄達は家にいなかったのと、どうも事前に断られた様子もあり、声をかけてくれたのだろう。父からまともに演奏会の誘いがあったのは初めてのことだった。
この年のカラヤンとベルリンフィルとの来日公演は、すごいプログラムであった。10月16日から26日まで、東京の普門館にて、マーラー交響曲第6番『悲劇的』、シューベルト交響曲第8番『未完成』とチャイコフスキー交響曲第5番、ドヴォルザーク交響曲第8番とムソルグスキー(ラヴェル編)組曲『展覧会の絵』、ベートーヴェン交響曲第9番『合唱』、ハイドンのオラトリオ『天地創造』、ヴェルディ『レクイエム』、モーツァルト『レクイエム』とブルックナー『テ・デウム』、というラインナップ。最初の10月16日が、モーツァルト交響曲第39番とR・シュトラウス『ツァラトゥストラはかく語りき』であった(その後の演奏会に連日一番安い席を求めて通い詰め、ベルリンフィルに酔いしれた思い出がある)。
当時の父は、横須賀にあるB大校長という要職にあり、普段は母上と横須賀に近い官舎で生活していたので、たまたま家に帰って来た時のことであろう。その後チケットが郵送され、席で会おうとのこと。上着を着てネクタイを締めて会場に行ったら既に父と母上が到着しており、その後外国人の夫婦がやってきて型どおりの挨拶を済ませ、演奏が始まるのを緊張して待った。あのバカでかい普門館で座席が前の方の上手側であったためか、電子オルガンのスピーカーが目の前にあり、その存在感のあるスピーカーから出てくるバカでかい冒頭の電気的な重低音、レコードで何度も演奏を聴いた綺羅星のごとくのトッププレーヤー達のソロが印象に残っている。電子オルガンは「パナトーン」(パナソニック製)だった。
K察官僚として数々の修羅場を乗り越えてきた父は、若い時からとにかく剣道一筋、武道と海軍(主計中尉として軍艦「武蔵」乗艦)、そして国家公務員としての矜持は強靭なものであった。一族の長としてどこに行っても常に中心に居て、その風貌から「威厳」があり、よくいえば「謹厳実直」、悪く言えば「単純」というか、よく母が生前「単細胞」といって笑っていたのを覚えている。クラシック音楽とは全く無縁と言ってもよく、普段は話題にもあがらなかった。ときたま朗らかに、「お前達は俺のことクラシックを知らないと思っているだろう、俺はベートーヴェンの『月光』ソナタを知っているし弾けるぞ!」と自慢げに語っていた(家族の誰も父のピアノを聴いたことが無い)。
私が高校生のとき、出張でヨーロッパの駐在官の激励巡視があった。玄関にて家族全員で見送りの時、「この出張のために眼鏡とコートを新調したぞ!スーツケースも新しいのを購入したぞ!飛行機はファーストクラスだぞ!どうだ!いいだろう!」と、満面に笑みをたたえて自慢げに言うところが憎めない父であった(因みに最近までこのコートとスーツケースは私が所有し愛用していた)。
出張の自慢話のひとつとして、ボンのベートーヴェン・ハウスに寄った時、「現地のスタッフに、私はベートーヴェンの『月光』ソナタを知っておる、それに1楽章は弾くこともできる、と言ったら、皆驚いていた!受付にいた地元のおばあさんはとても感心していたぞ!どうだ!すごいだろう!」とよく話していた。ある時、その自慢話をしていた父の隣で、父方の祖母(女高師(注1)から東京音楽学校分校でピアノを習得)が、ぼそっと「あの程度の曲は誰でも弾ける。」と独り言を言っていたのが強烈な印象として残っている。
父にとって『ツァラトゥストラはかく語りき』という曲は、冒頭のところのみがこの曲そのものだと思っていたようで、「せっかち」な性分から、座禅とかならともかく、じっとしていることができず、とにかく剣道で鍛えた精神力で「我慢」するという感じであった。1975年NHKホールでのベーム=ウィーン・フィルによるブラームス交響曲第1番を、たまたまテレビ中継で観ていて「ベームとかいう人の指揮は凄い!まさに剣道と同じ間合いに通ずる!剣聖!10段の構えだ!」と、何事も剣道が中心の世界であった。
自他共に認める超人であった父だが、1997年膵臓癌に侵されていることが判明、手術したが結局癌を除去することができず、退院の時に医師から「あと半年」、と母上に告げられ、本人に知らせることなく家族は覚悟を決めていた。みるみると痩せていく父であったが、母上の懸命な支えにより体力も気力も回復していったのは奇跡であった。
1998年の秋、両親が住んでいた家に家族でご機嫌伺いのため行った時、何気なく新響の話とか演奏会のことなどについて話をしたところ、是非演奏会に行きたい、とのこと。大町先生による『ツァラトゥストラはかく語りき』の演奏会(注2)であった。「この曲なら知っている。」とのこと。その演奏会には母上と共に来場、終演後にロビーで会った時、「楽しかった!おまえもなかなかやるな!」と、満面の笑みで一言。父にとって最初で最後の新響の演奏会となった。翌年1999年1月に体調を崩して入院、道場に立ちたいという強い意志を見せながら、7月4日早朝に家族全員で看取られてその波乱に満ちた77年の生涯を閉じた。
思えば、父にとって『ツァラトゥストラはかく語りき』は特別な何か共感するようなものであったのではないだろうか。父の存在と生涯がこの曲に被っているように思えてならない。冒頭の「きわめて幅広く」曙が到来する単純だがハ長調という絶対的な主題は、父の姿そのものである。「大いなる憧憬」や「歓喜と情熱について」は表情豊かで人間性溢れる父の憧れと悩みの表現であり、「埋葬の歌」は戦争経験や修羅場に直面した時の深い感情、思索と沈静の姿と重なる。「科学について」は、厳格な対位法から派生した科学的な形式としてのフーガとして、幼少のときからの厳しい教育と躾による自覚を伴った哲学の勉強と官僚となっての姿、別の見方をすれば剣道を通しての厳格な姿勢が出ており、「嫌悪の主題」は、曲がった事が嫌いな性格からくる雄叫び、もっとストレートに言えば凶悪犯罪に立ち向かう父の慟哭とつながる。「病より癒えゆくもの」は、建前(フーガ)と本音(嫌悪)が、官僚としての生涯を通して常に対峙していたことを示しており、「舞踊の歌」は周囲に見せていた陽気な姿といえる。そして「夜のさすらい人の歌」は、晩年の姿で、死を前に深い思想に包まれるかの如く、ゆっくりと静かに過去を回想してさまよう姿であり、解決されない知性と感性の相剋の謎を残して、私にその問題を残して旅立っていく父の姿であろうか。
「真の紳士にして、真の武人であれ」をモットーにB大では常に学生を鼓舞し、魅力ある人物としてその生涯で多くの人から慕われていた父は、峻厳と寛容を持った意思の人であり、情の人として多くのエピソードを残していった。「ツァラトゥストラはかく語りき」は私にとって父への憧憬である。この曲を通して親父としての父と対峙することで、父への想いをかみしめていきたい。
注1)
女高師⇒東京女子高等師範学校(現在のお茶の水女子大学)
注2)
第163回演奏会
1998年10月4日(日)東京芸術劇場
曲目 リスト/レ・プレリュード
シューベルト/交響曲第8番ロ短調『未完成』
R.シュトラウス/『ツァラトゥストラはかく語りき』
J.シュトラウス/歌劇『こうもり』序曲(アンコール)
指揮 大町陽一郎
第222回ローテーション
| ブラームス | シュトラウス | |
| フルート1st | 松下 | 吉田 |
| 2nd | 岡田 | 新井 |
| 3rd | - | 藤井(+Picc) |
| Picc | - | 兼子 |
| オーボエ1st | 堀内 | 山口 |
| 2nd | 宮内 | 岩城 |
| 3rd | - | 桜井 |
| C.I. | - | 亀井 |
| クラリネット1st | 品田 | 高梨 |
| 2nd | 進藤 | 石綿 |
| Es Cl | - | 末村 |
| Bass Cl | - | 大藪 |
| ファゴット1st | 田川 | 齊藤 |
| 2nd | 浦 | 田川 |
| 3rd | (*) | |
| Cfg | 齊藤 | 浦 |
| ホルン1st | 箭田 | 森 |
| 2nd | 山口 | 鵜飼 |
| 3rd | 大内 | 大原 |
| 4th | 市川 | 山口 |
| 5th | - | 大内 |
| 6th | - | 市川 |
| トランペット1st | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 中川 | 青木 |
| 3rd | - | 倉田 |
| 4th | - | 北村 |
| トロンボーン1st | 町谷 | 武田 |
| 2nd | 志村 | 町谷 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | - | 土田 |
| 2nd | - | (*) |
| ティンパニ | 今尾 | 古関 |
| パーカッション | - | トライアングル/今尾 大太鼓、グロッケン/皆月 シンバル、鐘/中川 |
| オルガン | - | (*) |
| ハープ | - | (*) |
| 2nd | - | (*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(真)(大隈) | 堀内(真)(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(笠川) | 小松(田川) |
| ヴィオラ | 田代(柳澤) | 柳澤(田代) |
| チェロ | 柳部容(光野) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 中野(渡辺) | 中野(渡辺) |
第222回演奏会のご案内
今回の演奏会は19世紀末期のドイツロマン派の作品をプログラミングしました。今回の2曲は共に映画の名作で使われていることでも有名です。イングリッド・バーグマン主演の「さよならをもう一度」(1961年)ではブラームスの交響曲第3番第3楽章の甘美なメロディがアレンジされて全編で流れ、SF映画「2001年宇宙の旅」(1968年)では「ツァラトゥストラはかく語りき」の冒頭がメインタイトルで鳴り響きます。
ブラームス:交響曲第3番
ブラームス50歳の時に3番目の交響曲は書かれました。第2交響曲の作曲から6年が経ち、この間イタリアやハンガリーなどを旅行した経験からか、無骨で素朴な第1番・第2番に比べ、より流暢で洗練されています。
また、ベートーヴェンの第3交響曲になぞらえて「ブラームスの英雄交響曲」と呼ばれることもあり、確かに1楽章や4楽章で勇壮な個所はありますが、ロマンティックで哀愁を感じる名曲です。
R.シュトラウス:「ツァラトゥストラはかく語りき」
この巨匠に対して「ブラームスが創造したものは無能力のメランコリーである」と批判をした哲学者がいました。ニーチェです。ブラームスと同時代に活躍したニーチェは、若い頃から音楽に関心を持ち作曲もしていました。当時ワーグナー派とブラームス派が激しく対立していましたが、彼はワーグナーに心酔していました(後に決裂)。
そのニーチェの主著である「ツァラトゥストラはかく語りき」を題材に交響詩を書いたのがR.シュトラウスです。彼はミュンヘン大学の哲学科で学び、32歳の時に同著に触発されて作曲しました。「ツァラトゥストラ」は、紀元前6世紀頃のゾロアスター教の教祖のことで、ニーチェが自分の思想を語らせています。簡単に言うと、神ではなく今を生きる自分自身を大切にするということかもしれません。哲学というと難しいですが、R.シュトラウスの巧妙なオーケストレーションで楽しい曲となっています。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」
■『田園交響楽』のこと
「あなたがたの見ていらっしゃる世界は、本当にあんなに美しいのですか?」彼女はやがて言った。
「あんなにって言うのは?」
「あの『小川のほとりの景色』のように」
(アンドレ・ジッド『田園交響楽』/神西清訳)
盲目の少女と牧師との対話である。十代の半ばまで光と言葉(彼女を育てたのは唖者の老婆だった)に閉ざされ、人間としての生活から隔離されていた少女は、老婆の死を契機に牧師に拾われ、初めて教育の機会を得た。言葉とその表す意味を学ばせ、更に牧師はオーケストラにある各楽器の音の組合せを様々聴かせる事で、色の名とその色彩とを理解させようと腐心する。聴覚という唯一の窓を通じて、少女の外界への認識は一挙に飛躍してゆく。
そしてこの日「田園」と出逢う。
少女の脳のう裡りに汚れなき世界の像が閃ひらめく瞬間。ヘレン・ケラーの自伝映画『奇跡の人』の井戸水のシーンを髣髴ほうふつさせる。この短編小説前半のヤマ場のひとつだ。だがこれを境に彼女と牧師の関係は確実に変質し、悲劇…少女はやがて手術を受けて光を得るが、結局死を選ぶ事になる。見える者の不幸を知った故に…の伏線ともなってゆく。
初めてこの小説を読んだ後の一時期、僕は盲目の少女に「田園」を聴かせた牧師の(そしてジッドの)意図を考え続け、この曲を繰返し聴き込んだ事があった。想えばそれはもう数十年も前になる。
周知の通り、この交響曲には楽章ごとに作曲者自身による標題がつけられている。だがこの事を以って、音楽が何かを描写していると考えるのは適当ではない。ベートーヴェンは作品のスケッチの片隅に、
「どんな場面を思い浮かべるかは、聴くものの自由に任せる。・・・あらゆる光景は器楽曲であまり忠実に再現しようとすると失われてしまう。・・・音の絵というより感覚というにふさわしい。」
と書いている。つまりまず具体性を期していないという事だ。
それだけではない。科学技術の恩恵に満ちた現代に生きる者の「特権」として、我々はいまこの作品に関するあらゆる情報を得られる。例えば作曲者が散策した川辺の情景も、当時のウィーン郊外の田園風景も、求めれば時空を超えてたちどころに知ることが可能となって久しい。そしてこうした情報をより多く得れば作品への理解もそれだけ進展するようにややもすると勘違いしがちである。現代人が陥りやすい誤謬の最たるものだ。
その勘違いはひとまず措おくとしても、このようにある特定の場所や光景に「田園」を限定してしまうとすれば、それは作曲者の意図とは別物になってしまう。誰もが日常意識せぬまま心に宿している各々の自然(そしてそこに生きる人々の営み)に対する「感覚」を、この音楽により触発させる事にこそ真の意図があると、上に挙げた作曲者の言葉から、我々は気づかなければならない。故にそこには統一された具象的なものは何ら必要とされないのだ。
この世の光を未だ見ぬ少女にさえ美しき「風景」を想起させ得る音楽。これはひとつの奇蹟の姿である。ここに於いてジッドの『田園交響楽』は、作曲者の意図を究極の姿で示しているのだと思い至る。真に偉大な音楽が聴く人の心に及ぼす力の大きさと剄つよさ、そして少女の裡うちに音楽が鳴った一瞬に現れたであろう情景…それは最早色彩を超えた光そのものとでも言うべき神々しき世界だったかもしれない…とを想いつつ改めてこの緩徐楽章に聴き入ると、静かに迫りくる感動を禁じ得ない。
■「田園」の背後にあるもの
「田園」がベートーヴェンの心の中で急速に形成されつつあった1807年後半から翌年にかけての時間は、彼の全人生を見渡すと、俄かにある種の平穏と言うべきものが訪れた区切り時期にあった。但しこの平穏は幸福を意味してはいない。第4交響曲やヴァイオリン協奏曲に現れる穏やかな作風の源泉となった、さる伯爵未亡人との恋愛は4年という時間を経て完全な破局を迎えていた。宿痾しゅくあとなった耳疾は様々な治療を試みるも奏効せず、この時点で悪化こそ止まったものの決して好転はしてはいない。また10年余りを費やした「運命」はようやく完成に漕ぎ着けている。長期に亘る様々な案件が失望と達成感とを伴ってそれぞれの結論を得つつあったその時期、37歳の作曲者には一時的にせよ精神に空隙くうげきが生じ、行く末に対する諦念とも言える感情が心に忍び寄ったのではないだろうか。そこまでの彼の交響曲を聴きこんだ上で「田園」に対峙する時、そうした背景を想像させるものがこの作品には潜んでいると僕には感じられてならない。直前に完成され、同時に初演された前述の「運命」との対照を思えば尚更のことだ。
この交響曲には、それと判る明確なモデルがある。これも異例と言えよう。それは四半世紀も前の1785年にクネヒト(Justin Heinrich Knecht/1752―1817)が出版した“Le portrait musical de lanature ou grande symphonie(『自然の音楽的肖像あるいは大交響曲』とでも訳すべきか?)”なる作品である。5楽章の構成で総譜の表紙には楽章毎にそれぞれに標題が示されている。それは標題というには余りに冗長に過ぎ且つ説明的で、例えばヴィヴァルディの「四季」各曲に付されたソネット(14行詩)を思い出させるが、その中には、「太陽の光がふりそそぐ」「鳥がさえずる」「小川は谷間を流れ」「雷鳴」「嵐」「嵐の静まった後の感謝」などという、「田園」の楽章ごとの標題と符合する語句が見出されるのである。近年「世界初」として、このクネヒトの作品が音となって世に出た。一聴して、それが時代のスタイルを基盤とした拙い描写以上の音楽ではない事が判る。僕が常に座右に置いて、事あるごとに引いている「音楽大事典(平凡社)」でも、南ドイツに生まれた、モーツァルトより4歳年長のこのオルガニストにして作曲家・音楽理論家に関する記述は20行ほどしかない。しかもその1/3はベートーヴェンの「田園」との関連性に関するものとあって、この先駆者の詳細は殆ど何も知る事が出来ない。つまり全く忘れられた作曲家となっている訳である。さもあろう。だが同時代人たるベートーヴェンはこの作品の存在を、いつの時期かは不明だが知る機会があった(例えば同じ出版社から彼も自作を世に送り出している)。それは彼の心のどこかにしまい込まれ、通常ならそのまま終わる筈だった。
「田園」にはそれまでの交響曲全般を特徴づける躍動や激した部分は殆ど無い。また彼のいくつもの作品に見られるような闘争や葛藤や大団円としての勝利・歓喜といったドラマトゥルギー(ドラマ的な筋立て)とも無縁だ。代わりにあるものは、一貫して流れる穏やかさやのびやかさであり、淡々とした静けさを基調としつつも、聴く者に対して確実に迫って来る抑制された情動である。
この作品のスケッチは「英雄」を手がけていた頃既に見えているという。だが、それが全体像を結んで産み出されるには、それまでの半生を謂わば「駆け抜けて」きた作曲者にとっても、従来とは違った心の静謐せいひつが必要だったに違いない。失意と希望との狭間に人生を歩む中で、程度の差こそあれ誰しもが経験する精神の真空状態。それがこの時期不意に、束の間訪れた。諦念と安息が表裏一体になった感情とも言える。そうした感情が彼をして自然への「精神的な回帰」を促し、自然の描写をテーマとしていたクネヒトの作品の標題形式や楽章構成に改めて目が向けられ、創作の契機となったのではあるまいか。この作品が極めて短期間の内に書かれた事実にも注目すべきだろう。こうした例はほかになかなか無い。
1804年に完成した「英雄」以降の10年間に産み出された作品群を、ロマン・ロランは「傑作の森」と賞しているが、「田園」はその中にあっても極めて独創的なものに感じられる。それは作曲者の常とは異なる心象の反映にほかならない。
だがこうした安寧あんねいの状態は長く続かない。ベートーヴェンにはこの後約20年の時間が残されていたが、この交響曲を生み出す背景となった束の間の心の静謐が再び巡ってくることは遂になかったのである。
初 演:1808年12月22日 ウィーンのアン・デア・ウィーン劇場にて、作曲者自身の指揮による
楽器編成:フルート2、ピッコロ、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット、トロンボーン2、ティンパニ、弦五部
参考文献
『田園交響楽』アンドレ・ジッド(神西清訳)(新潮文庫)
『ベートーヴェンの生涯』ロマン・ロラン(片山敏彦訳)(岩波文庫)
『新編ベートーヴェンの手紙』全2冊(小松雄一郎訳)(岩波文庫)
『孤独の対話―ベートーヴェンの会話帖―』山根銀二(岩波新書)
『音楽大事典』岸辺成雄編(平凡社)
R.シュトラウス:「ばらの騎士」組曲
リヒャルト・シュトラウスのオーケストラ作品といえば、本日の演奏会で最初に取り上げる「ドン・ファン」をはじめとして、「死と変容」、「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」、「ツァラトゥストラはかく語りき」、「ドン・キホーテ」、「英雄の生涯」といった交響詩の傑作をすぐに思い浮かべることができる。しかし、歌劇「ばらの騎士」を管弦楽用に編曲してできあがったこの組曲については、彼の他の管弦楽作品とはかなり事情が異なる。シュトラウスの作曲活動は、おもに歌曲、管弦楽作品、オペラの3つの領域に集中しているが、上にあげたような交響詩が20代半ばから30代半ばにかけてのかなり若い時期(1888―1898年)に書かれた作品であるのに対して、「サロメ」(1905年)によって本格的に始まったシュトラウスのオペラ創作は40代以降の仕事に属する(ちなみに歌曲は生涯を通じて作曲され続けていた)。歌劇「ばらの騎士」は1910年(作曲者46歳)に完成され、1911年にドレスデン宮廷歌劇場で初演されているが、この作品はシュトラウスのオペラとしては初めて大成功を収めるものとなった。のみならず、その後に作曲された数多くのオペラを含めても、「ばらの騎士」はシュトラウスのオペラのなかで一般にもっとも有名な作品と言えるだろう。このオペラがこれほどまでに親しまれている理由は、一つには、ウィーンの代表的詩人ホフマンスタールによる緻密で繊細な言葉、見ていて楽しくわかりやすい喜劇としての物語構成にあるだろう。そして、もう一つは何といっても、全曲のあちこちで聴くことのできる魅惑的な旋律に求められるのではないだろうか。このオペラからは、その後、抜粋によるさまざまな管弦楽編曲版が生まれているが、そのこともこのオペラの音楽の素晴らしさを裏書きしていると言えるだろう。

マックス・リーバーマンが描いたR.シュトラウス(1918年)
今日演奏される「組曲」は、そのようなオペラの名旋律を抜粋した編曲のなかでももっとも有名なものだが、成立の由来はあまりはっきりしていない。この「組曲」は一般に、ニューヨーク・フィルハーモニックの指揮者であったアルトゥール・ロジンスキーの編曲によるものとされることが多い。しかし、作曲者自身が編曲に関わったのかどうかも含め、さまざまな情報が錯綜している。オペラそのもののスコアの版権は1943年にロンドンのBoosey &Hawkesに移っており、1944年頃に編曲されたこの「組曲」の楽譜も1945年にこの出版社から発行されているが、スコアにもこの「新しい編曲」が誰の手によるものかまったく記載されていない。
歌劇「ばらの騎士」
それはともかくとして、この作品の内容そのものに話を進めたい。そのためにはまず、オペラの物語について紹介する必要がある。というのも、この「組曲」は多くの部分でオペラの物語の展開に沿って構成されているからだ。
第一幕。幕が開くとそこは元帥夫人の寝室で、ベッドに横たわる元帥夫人を前にして主人公のオクタヴィアンが愛の言葉を交わしている。オクタヴィアンは17歳の若き貴族(オペラでは女性が演じる)であり、年上の女性の愛人として密会の時を過ごしているというわけだ。そこに元帥夫人のいとこであるオックス男爵がやってくるので、オクタヴィアンは急いで隠れ、田舎娘の女中に変装する。オックス男爵の用件は、近く自分が結婚するので、貴族の作法にのっとって、銀のバラを結納として花嫁に手渡す代理人を紹介してほしいということだった。オックス男爵はそれを依頼しつつも、奥女中「マリアンデル」に変装したオクタヴィアンにしきりと色目を使う。彼の結婚も、莫大な富によって下級の貴族に列せられた商人ファーニナルの財産や、宮殿のそばにある邸宅が目当てなのだ。元帥夫人はこの「代理人」としてためらいつつもオクタヴィアン(ロフラーノ伯爵)を推薦する。
第二幕は、ファーニナル家での晴れやかな祝祭的情景で始まる。花嫁となるゾフィーたちが胸をときめかせながら待ちうけるなか、オクタヴィアンが「ばらの騎士」として邸宅の扉からさっそうと登場する。そして貴族の作法通り、銀のバラをゾフィーに手渡す。若い二人は顔を合わせた瞬間から強く惹かれあい、親しく言葉を交わすのだが、そこに花婿となるオックス男爵が現れる。しかし、そのあまりに下品で粗野なふるまいにゾフィーは強い嫌悪をあらわにし、オクタヴィアンも怒りを隠せない。オックス男爵が席を外したすきに、ゾフィーはオクタヴィアンに自分を救ってくれるよう懇願し、互いの気持ちを確認した二人は口づけを交わして愛の歌を歌う(その間も酔ったオックス男爵はファーニナル家の女中を追い回して手がつけられない)。その場をオックス男爵の付き人に押さえられたオクタヴィアンは、オックス男爵に対してゾフィーに結婚の意思はないことを伝えるが男爵はまったく相手にしない。しかし、オクタヴィアンは剣を抜いて男爵に切りつけ、負傷した男爵は血を見て大騒ぎをする。オクタヴィアンはその場を退去せざるを得ない。男爵は手当てを受けるが、そこに秘密の手紙が届けられる。それは元帥夫人のところで会った「マリアンデル」からの逢引の申し出で、男爵はそれを見てほくそ笑む。
第三幕は、とある料亭の特別室(部屋の奥にはベッドも用意されている)が舞台となる。オックス男爵はそこで町娘の身なりをしたオクタヴィアンと密会を行うことになっている。男爵は元帥夫人の奥女中マリアンデルだと思い込み、言い寄って思いを遂げようとするが、実はオクタヴィアンの計略によって、男爵をやりこめるためのさまざまな手筈がそこでは整えられていた。「マリアンデル」を口説こうとする男爵の前に、結婚相手を名乗る女や「パパ、パパ!」と言いたてる4人の子どもたちまで出現し、料亭の亭主は「重婚」だと騒ぎだすのである。そこに風俗の乱れを取り締まる警察まで現れたため、オックス男爵は、同席している「マリアンデル」は自分の婚約者のゾフィーだと偽って切り抜けようとする。しかし、そこにファーニナルやゾフィーまで現れ、集まった野次馬たちは男爵とファーニナル家の「醜聞スキャンダル」と騒ぎ立てる。この混乱の場に元帥夫人が現れ(それはオクタヴィアンの想定外)、警察に対しては「これはみんな茶番劇でそれだけのこと」と言って事態を収拾し、オックス男爵をたしなめて立ち去らせる。元帥夫人とオクタヴィアンの様子を見ていたゾフィーは二人の関係を悟り、自分はオクタヴィアンにとって「虚しい空気」のような存在でしかなかったのだとショックを受ける。元帥夫人はオクタヴィアンをゾフィーへと向かわせるとともに、ゾフィーも気遣う。元帥夫人は静かに身を引き、若い二人は互いの愛情を確認し合って結ばれることになるのだった。
このオペラの舞台は「マリア・テレジア治世の最初の10年」の時代、つまり1740年から50年頃のウィーンで、このオペラが作曲された時よりも約150年前という時代設定になっている。しかし、エロティックな情事が題材となり、風俗警察まで登場して、ヒステリックに道徳的「醜聞スキャンダル」を叫びたてる声が描かれるあたりは、むしろ「世紀末ウィーン」として知られる、このオペラと同時代のウィーンの文化的・社会的状況を強く連想させる。おそらく同時代の観客もこのオペラを、完全に自分自身の時代の状況に重ね合わせて受け止めたであろう。オペラのなかで使われているワルツも、少なくとも19世紀中葉以降の時代をいやがおうでも連想させる(設定された時代だと、J. S. バッハの最晩年期、ハイドンの少年期にあたる)。
ちなみに、R. シュトラウスは「ウィーン世紀末」の文化的革新運動のなかでは、例えばグスタフ・マーラーや画家グスタフ・クリムトとともに、比較的穏健な旧世代に属している。共同作業によってテクストを書いた作家ホフマンスタールは、実は、シェーンベルク、建築家アドルフ・ロース、批評家カール・クラウスといった急進的思想をもつウィーンの芸術家たちとまったく同世代なのだが、彼の作家としてのメンタリティはむしろ年上の世代と一致する部分を多くもっていた。ホフマンスタール/シュトラウスの「ばらの騎士」は、モーツァルトの「フィガロの結婚」とストーリー的にもある程度似たところをもつとはいえ、「フィガロの結婚」の作者であるボーマルシェがフランスの貴族社会を痛烈に諷刺する意図をもっていたのに対して、「ばらの騎士」ではウィーンの上流社会における保守的な価値観がすみすみまでゆきわたっている。このオペラが作曲された1909年から1910年は、まさに急進的な芸術家たちが過激な一歩を踏み出した時代にあたるが、シュトラウスとホフマンスタールは、そういった時代の流れとは一線を画したところで素晴らしい成果を生み出していたことになる。
「組曲」の構成
さて、オペラの説明がいくぶん長くなってしまったが、肝心の「組曲」の構成をこのオペラの筋を念頭に置きながら見ていきたい。この作品は「組曲」と名づけられているが、実際には独立した小曲によって成り立っているのではなく、オペラのなかのいくつかの部分が切れ目なくつながっているので、いわばオペラの名場面メドレー集と思っていただいたほうがよいかもしれない。
「組曲」の冒頭は、オペラの冒頭の音楽をそのまま用いている。ホルンの力強い上行音形に対してヴァイオリンが優雅に包み込むが、これはそれぞれ若いオクタヴィアンと元帥夫人を表している。幕が開いたとき寝室でこの二人が優しい愛の言葉で戯れていることを考えると、この冒頭の音楽はかなりエロティックな情景として聞くこともできるだろう。音楽はそのまま第二幕冒頭のばらの騎士を待ち受けるファーニナル家の華やかな場面へと続いていく。ゾフィーの不安と期待が頂点に達したまさにその瞬間、白と銀の華やかな衣装に包まれたオクタヴィアンが輝く銀のバラを手にして登場する(シンバルとともに華やかな転調)。オクタヴィアンはばらの騎士の口上を述べて銀のバラをゾフィーに手渡し(オーボエのソロ、輝くようなフルートとチェレスタ)、ゾフィーも儀礼に従ってそれにこたえるが、ためらいがちに言葉を交わすうち、二人の心のうちには抑えようのないときめきと幸せな感情が湧き起ってくる。
ここで突然けたたましい音楽となり、男爵の付き人のイタリア人二人が、この若い二人を取り押さえる場面が挿入される(叫ぶような木管)。そして低弦とトロンボーンなどの鋭い音形とともに、オックス男爵がいかめしく二人の前に立つ。ここで音楽は突然、ヴァイオリンが旋律を奏でるきわめて優美なワルツにかわるのだが、実はこの魅惑的なワルツもオックス男爵のテーマなのである。オペラのなかでは、オクタヴィアンに切りつけられて動転しながらも、医者の介護を受けワインを供された男爵が、次第に上機嫌になり女たらしの妄想にふけっているところに、「マリアンデル」からの手紙を受け取り、浮かれた気持ちでさらに妄想を膨らませる場面にあたる。このオペラのなかでオックス男爵は、低俗で野卑、田舎者まるだしでケチ、好色で若い女の子のことしか頭にないが、さえない見かけの中年男(第三幕でのドタバタでは、かつらをはずして禿げ頭をさらす)として描かれている。しかし男爵は、喜劇的人物としてなぜか憎むことのできない愛嬌を感じさせるとともに、あくまでも貴族としての優雅さを備えた人物として想定されている。オックス男爵のワルツはそのような優雅さを感じさせるとともに、一般にウィーン的特質としてとらえられているような「心地よさ・お気楽さ」を体現するものでもある。
この後、第二幕冒頭でのばらの騎士を待ち受ける音楽を部分的にはさみつつ、第三幕終盤、「茶番」が収束したのちに歌われる美しい三重唱(元帥夫人、オクタヴィアン、ゾフィー)の音楽へと移ってゆく。元帥夫人は、オクタヴィアンを彼の愛する別の女性にゆだねるときがこのように早く来るとはととまどい、ゾフィーは伯爵夫人に対する心の葛藤を抱いている。そして、オクタヴィアンはゾフィーへの後ろめたさを意識している。しかし、次第に若い二人の想いは「あなたを愛している!」という言葉に収束してゆき、音楽もここで壮大なクライマックスを迎える。元帥夫人は二人を残してそっと退場し、オクタヴィアンとゾフィーは優しい二重唱を歌う(ヴァイオリンとクラリネット)。
オペラではこの清純で静かな二重唱が二人の幸せを予感させながら全曲を結んでいるのだが、「組曲」にはこのあと、スネアドラムの導入に続いて、華々しい終曲が用意されている。この音楽は、第三幕で「マリアンデル」との逢引どころか、ファーニナル家の娘との結婚も破談に終わり、さんざんな目にあったオックス男爵が「帰るぞ!」という声とともにいかがわしい料亭をあとにする場面にあたる。ここにはそれまでオペラの各所に現れていた、好色なオックス男爵のいくつかのお気楽な鼻歌が、いわばパロディー的に戯画化され、乱暴な(それでも優雅な)旋律となって組み込まれている。オペラではこの楽しいワルツに重ねられて、4人の「隠し子」の「パパ、パパ!」という叫び声や、勘定を要求するさまざまな人々の声が入り乱れ、騒然とした雰囲気となっている。オペラの筋書きを知っていれば、おそらく小太りのオックス男爵が腹を立てて足をふみならしながら退場する喜劇的情景を想像できるだろうが、そもそもこの部分は「組曲」でたどるストーリーの流れからはずれている箇所でもあり、「組曲」の最後を華やかに飾る元気で壮麗なワルツとして、単純に楽しむことができるだろう。
初 演:1944年10月5日ニューヨークにて、アルトゥール・ロジンスキー指揮ニューヨーク・フィルによる
楽器編成:ピッコロ、フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ3(3番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット2、小クラリネット(クラリネット持ち替え)、バスクラリネット、ファゴット3(3番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、グロッケンシュピール、トライアングル、タンバリン、小太鼓、大太鼓、大ラチェット、シンバル、チェレスタ、ハープ2、弦五部
参考文献
Hugo von Hofmannsthal, Gesammelte Werke. Dramen V:Operndichtungen. Frankfurt. a. M.: Fischer, 1979.
Richard Strauss, Der Rosenkavalier in Full Score. New York:Dover, 1987.
Günter Brosche, Richard Strauss. Werk und Leben. Wien:Edition Steinbauer, 2008.
Phillip Huscher, Richard Strauss. Suite from Der Rosenkavalier,Op. 59 (Program Notes, Chicago Symphony Orchestra)
http://cso.org/uploadedFiles/1_Tickets_and_Events/Program_Notes/052710_ProgramNotes_Strauss_Rosenkavalier.pdf
Wikipedia:"Der Rosenkavalier"
http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Rosenkavalier
http://en.wikipedia.org/wiki/Der_Rosenkavalier
R.シュトラウス:ドン・ファン
本日は新交響楽団の演奏会に足をお運びくださり、ありがとうございます。これから曲目解説を始めます。クラシック音楽に詳しい方にとってはもう知っている事かもしれません。では、はじめましょう。
■リヒャルト・シュトラウスはこんなひと
その1 幼年時代から青年時代
リヒャルト・シュトラウスは1864年6月11日にミュンヘンで生まれました。父はミュンヘン宮廷歌劇場管弦楽団首席ホルン奏者にして王立音楽院の教授であったフランツ・ヨーゼフ・シュトラウス、母はミュンヘンの有名なビール醸造業者プショル家の娘ヨゼフィーネ。リヒャルトは、生活に何の不自由のない豊かな家庭に生まれたのでした。子供時代の彼は、活発で利発、持ち前の集中力で勉強したことはすぐに覚えてしまい、また、それが楽しいのでますます勉強に励む、といった素晴らしく優秀な生徒だったそうです。それは音楽の学習にも言える事でした。リヒャルトは父の仕事の同僚たちからあらゆる音楽の教育を受けました。父はベートーヴェンやモーツァルトといった古典音楽の信奉者で、当時世間で大人気であったリストやワーグナーの音楽を徹底的に嫌っていました。その影響で、幼いリヒャルトもワーグナーに対して嫌悪感を抱いておりました。
こうして、ギムナジウムを卒業し大学に入学するころには、作品番号のついていない作品を数多く作曲しており、リヒャルトの音楽の才能、知識は誰から見ても音楽学校に行く必要がないくらいに優秀なものでありました。そこで、彼はミュンヘン大学の哲学科を進学先に選んだのでした。

1886年頃のR.シュトラウス
その2 交響詩の時代
1882年秋、ミュンヘン大学に進学したリヒャルトですが、結局卒業できませんでした。音楽家としての仕事が忙しくなってしまったようです。ここで、リヒャルトはハンス・フォン・ビューローに出会います。ビューローはマイニンゲン宮廷管弦楽団の指揮者で、リヒャルトの作品を高く評価していました。自分の楽団の演奏旅行の演目にまだ19歳のリヒャルトの作品「管楽セレナード」を加えていたぐらいです。ビューローは、指揮棒をあまり握ったことのないリヒャルトをマイニンゲン宮廷管弦楽団の副指揮者に推薦したのでした。ビューローの様々な取り計らいにより、1885年21歳のとき、リヒャルトはマイニンゲン宮廷管弦楽団の副指揮者の地位に着きます。
ビューローの下で指揮者修行を進めたリヒャルトですが、ここで、マイニンゲン宮廷管弦楽団の第1ヴァイオリン奏者アレクサンダー・リッターと出会います。リッターの粘り強い解説によって、リヒャルトのワーグナーやリストに対する偏見はなくなりました。
リヒャルトは交響詩の作曲を始めました。その後、ミュンヘン、ワイマール、ベルリン等さまざまな土地の管弦楽団の指揮者を務めながら、「ドン・ファン」「ツァラトゥストラはかく語りき」「家庭交響曲」等の10作品を書き上げていきます(「ツァラトゥストラはかく語りき」は次回新響で取り上げます。乞うご期待)。ところで、リヒャルトの作品は物語や神話から題材をとっているものが多く、お話に付随したおまけみたいな音楽なのでは、なんて思われそうですね。これに対してリヒャルトは次のように語っています。
物語から着想を得ているけれども、そこから自己の内で論理的な展開をしていかなかったらただの文学の伴奏音楽になってしまいます。
その3 愛しのパウリーネ
1887年、リヒャルトは友人から「弟子をひとり引き受けてくれないか」と頼まれます。その弟子とは、才能あふれる女性歌手パウリーネ・デ・アーナ。リヒャルトは彼女をオペラの歌手として起用できるまでに育て上げ、最初のオペラ「グントラム」に彼女を起用します。この作品は歌手にとって歌うのが大変な曲だそうですが、パウリーネは文句のつけようがないほど見事に歌いました。そのため、リヒャルトはリハーサルの時に上手なパウリーネを放っておいて、他の歌手に多く注意を与えていたそうです。放っておかれたパウリーネは「なぜ私に注意してくださらないの?」と言ってリヒャルトに譜面を投げつけたとか。二人はこの年の9月に結婚することになります。リヒャルトは30歳、パウリーネは33歳、姉さん女房ですね。リヒャルトはパウリーネのことをとても愛し、「四つの歌曲」等彼女のために多くの歌曲を作っています。

左からリヒャルト、妻パウリーネ、息子フランツ
その4 オペラの時代
交響詩や歌曲等を作曲していたリヒャルトは、友人のアレクサンダー・リッターに薦められ、当時社会の中で騒がれていた事件を元にしたオペラの作曲に取りかかります。そして出来上がったのが先述の「グントラム」でした。しかし、この作品は、たいした評判にもならず、結果は失敗に終わりました。この失敗でリヒャルトはオペラに対する創作意欲を失っていましたが、ついで作曲した「火の試練」が少々の成功を収め、気を良くしたリヒャルトは「サロメ」を発表します。この作品は大成功し、また、多くの批判も受けました。聖書を題材にしている物語であるにもかかわらず、あまりにも露骨なエロティシズムに満ちていたからです。しかし、リヒャルトは臆することなくオペラの製作に突き進んでいきます。ここで、リヒャルトはフーゴー・フォン・ホフマンスタールという詩人に出会います。ホフマンスタールの戯曲「エレクトラ」を見たリヒャルトは、この作品をオペラに仕立てようと考えたのでした。「サロメ」の成功の後、リヒャルトはホフマンスタールとの交流を開始します。二人の間では頻繁に手紙が交わされており、現在本となって出版されています。二人の作り出したオペラは「エレクトラ」「ばらの騎士」「ナクソス島のアリアドネ」「影のない女」「エジプトのヘレナ」「アラベラ」の6作品です。すべての作品は大成功を収めました。しかし、二人の間の友情、協力は1929年にホフマンスタールの突然の死によって終わりを告げたのでした。ただ、この後もリヒャルトはオペラを作り続け、最後の作品は「カプリッチョ」となりました。
その5 ナチス・ドイツ政権下
1933年にアドルフ・ヒトラー率いるナチスがドイツの政権を握ると、世界的作曲家にして指揮者のリヒャルトはドイツの国威を世界に示す道具として利用されることとなります。この年、彼は帝国音楽局総裁の地位につきました。しかし、1935年にはこの地位を下りることになります。オペラ「無口な女」の台本がオーストリア在住のユダヤ人シュテファン・ツヴァイクによるものであったからです。このことについて、リヒャルトは次のように述べています。
私にとっては二種類の人間しか存在しません。才能のある人とない人です。
ユダヤ人迫害はドイツにとって不名誉な恥であり、頭の悪い証拠である。才能のない怠惰で凡庸な人間がより高い精神性、より大きな才能の持ち主と戦うために思いついた最低の手段である。
その6 最期
1949年9月8日にリヒャルトは85歳の生涯を閉じました。遺言により葬儀では「ばらの騎士」の終幕の三重唱が歌われました。人生の後半において戦争に巻き込まれて大変なこともありましたが、豊かな家庭に生まれ、才能に恵まれ、常に挑戦的で革新的であり、あらゆる名誉を手にした天才作曲家でした。
■作品20「ドン・ファン」について
「ドン・ファン」はリヒャルトが25歳のときに初演された作品です。本当はこの曲の前に「マクベス」を完成させていたのですが、ビューローに手直しすることを忠告されました。そのためこの作品が最初の交響詩となったのです。
ドン・ファンというお話は、もともとスペインの伝説であったものをスペインの聖職者が宗教劇として仕立てたのがはじまりです。その後はさまざまな戯曲、オペラ、詩などの題材に使われています。特に有名なのは、モリエールの戯曲、バイロンの詩、モーツァルトのオペラ「ドン・ジョバンニ」あたりでしょうか。最近ですと1995年の映画「ドン・ファン」(フランシス・F・コッポラ製作、ジョニー・デップ主演)です。あらすじは次のとおり。
ドン・ファンという女好きな貴族がいました。彼は「おお、素敵な女性だ」と思ったら、即座に「結婚しよう」と口説き落としてしまいます。身分の違う人だろうと、聖職者の尼さんであろうと、お構いなしです。しかも満足したらすぐ飽きて次の女に手を出すものですから、泣いた女、恨んでいる男は数知れず。全く、神をも畏れぬ所業です。父親が怒って「このままなら親子の縁を切るぞ」と言っても聞く耳を持ちません。ある日、過去に自分が殺した男の石像に向かって話しかけたところ、なんと、その石像が動いたのです。実は、この石像は死神だったのでした。ドン・ファンは、その石像を晩餐会に招きます。石像は招待されたとおりに晩餐会に現れ、ドン・ファンを地獄へ連れて行ってしまいましたとさ。
もともと世の人々に教訓をもたらすための宗教劇だったのですが、後世は宗教訓話から離れて、理想の女性を追い求める男のロマンへと変わってきたようです。リヒャルトがこの曲を作るにあたって基にしたニコラウス・レーナウの詩はまさに、理想の女性を求める熱き男の血潮を歌ったものでした。リヒャルトはこの詩を曲の冒頭に掲げています。
出でよ、そして絶えず新たな勝利を求めよ
青春の燃える鼓動が躍動する限り!
おそらく、リヒャルトは「理想の女性」を求め続けるドン・ファンの姿に、理想の芸術を求め続ける自分の姿を投影したのではないでしょうか。とにかく、自分をネタに作曲することが多い人でした(交響詩「家庭交響曲」や歌劇「インテルメッツォ」が極端な例)。
この曲、演奏するのが「超」大変です。分散和音、半音階、跳躍音程、転調、と演奏者にとって嫌なものの連続で、息つく暇がありません。練習中はリヒャルトが憎らしくなります。にもかかわらず、アマチュア・オーケストラは結構この曲をとりあげています。やっぱり、かっこいいですもんね。今回、聞きに来てくださっているお客様の中にも演奏した人が多数いらっしゃるのではないでしょうか。リヒャルト・シュトラウスはまさに「アマチュア・オーケストラの熱き血潮をたぎらす」作曲家ですね。新響も熱き血潮で演奏しますのでご期待ください。最後までお読みくださってありがとうございました。では、舞台でお会いしましょう!
初 演:1889年ワイマールにて、作曲者自身の指揮による
楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、トライアングル、グロッケンシュピール、ハープ、弦五部
参考文献
DVD『ドン・ファン』
(制作:フランシス・フォード・コッポラ1995年アメリカ映画)
(Shochiku Home Video)
『ドン・ジュアン』モリエール(鈴木力衛訳)(岩波書店)
『R.シュトラウス(作曲家別名曲解説ライブラリー9)』(音楽之友社)
『大作曲家R,シュトラウス』ヴァルター・デビッシュ(村井翔訳)(音楽之友社)
『リヒャルト・シュトラウスの「実像」―書簡、証言でつづる作曲家の素顔』
日本リヒャルト・シュトラウス協会編(音楽之友社)
維持会会員の方からの投稿です
今年4月で新響さんを聴かせていただいて丸42年になるS.K.です。維持会ニュースNo.132(2012年12月20日発行)掲載の、都河和彦氏による『新交響楽団在団44年の思い出-①(以下思い出-①)』ならびに松下俊行氏による『ブルックナーの交響曲第5番』を拝読していくつか想う所がありましたので、維持会ニュース編集人・松下氏のご許可を得て投稿させていただくことにしました。
1:まず、都河和彦氏に厚く御礼申し上げます。永年にわたりコンサート・マスターを務められ、多くの団員の方々をリードされ、数々の名演を聴かせてくださったことに心から感謝しています。
私が初めて新響さんを聴かせていただいた1971年4月の時点で都河氏はすでに“新響の顔”でいらしたと私は記憶しています。コンマスを退任されてからは永年にわたって向かい合って演奏されてきた“盟友”の柳澤秀悟氏の後方でVa.を弾いていらっしゃいましたが、都河氏がステージ上においでになるだけで新響さんの演奏、音楽創りを安心して楽しむことができたのは私だけではなかったはずです。
都河氏に関する思い出として、あえて「聴けなかった」演奏を挙げさせていただきます。それは、1978年4月26日の第80回演奏会「小倉朗交響作品展」第2夜での小倉朗氏のVn.協奏曲の独奏です。同年4月1日の第79回演奏会「小倉朗交響作品展」第1夜は聴かせていただけたのですが、第2夜当日は(私の記憶に間違いがなければ、JRに分割される前の)日本国有鉄道のストライキがあって聴きに行くことはできても帰宅できなくなる危険性が高かったため、行くのを断念してしまいました。絶対に聴いておくべき演奏会だった、と今でも悔やんでいます。なお、これからは同じ維持会員として新響の演奏を一緒に楽しんでいけたらいいな、と勝手に考えているところです。
2:都河氏の『思い出-①』により、私が新響さんを聴かせていただくようになる前の新響さんの活動その他がよくわかりました。中でも、
・1965年には年17回以上!のコンサートをこなされたこと、
・現在アマ・オケのラスベート交響楽団さんの指揮者などとして活動されている秋山俊樹氏がかつて新響さんのコンマスを務めていらしたこと、
・芥川也寸志先生のダンディーぶりや“独裁”ぶり、
はとても興味深く拝読しました。私が新響さんを初めて聴かせていただく直前の1970年11月に外山雄三氏を客演指揮者に迎えられた際に打ち上げの席で「もうアマチュアは振りたくない」という意味のことをポロっとおっしゃった、というエピソードは客席にいるだけの立場では知りえないことなので、記していただいたことに感謝いたします。新響さんがマーラー(交響曲第1番)に挑戦された演奏会や若き日の小林研一郎氏が新響さんを指揮された演奏会は、私も客席で聴かせていただいたので今でも覚えています。
3:私が42年にわたってオーケストラ演奏会を聴き続けるキッカケとなった演奏会のひとつは、1975年6月1日に渋谷公会堂で開かれた芥川也寸志先生指揮の新響さん演奏によるストラヴィンスキー三部作の演奏会でした。因みに、もうひとつは1977年12月22日に東京文化会館大ホールで開かれた渡邉暁雄氏指揮による東京都交響楽団第102回定演(マーラー交響曲第6番他)です。三部作の演奏会で『ペトルーシュカ』のピアノ・ソロを担当された渡辺達氏が2012年4月にお亡くなりになっていたことを都河氏の『思い出-①』によって知りました。アマ・オケのレヴェルが向上した現在でも、『ペトルーシュカ』は容易には演奏することのできない“難曲中の難曲”だと私は考えています。三部作演奏会の前年1974年にも新響さんは『ペトルーシュカ』を演奏されていますが、その時もピアノ・ソロは渡辺氏でした。両方とも聴かせていただいた私は、「あの2回の『ペトルーシュカ』演奏は、芥川先生と渡辺氏がいらっしゃらなかったらできなかったのではないか」と今でも思っています。この紙面をお借りして渡辺氏のご冥福をこころよりお祈り申し上げます。
4:都河氏の『思い出-①』の終わりの部分と松下氏の文章の前半『アマチュアオーケストラに於けるブルックナー』部分とに、山岡重信氏指揮による3つのブルックナー交響曲演奏について触れられた記述があります。その3つとも会場で聴かせていただいたこともあって、私には強い思い出があります。
1975年10月の新響さんによる第4番は確か日比谷公会堂での演奏でしたが、大きな空間いっぱいに響きわたる大音響が耳に快かったのを覚えています。新響さんにとって初のブルックナー交響曲演奏で、当時のホルン・セクションは現在と全員異なっていますが第3楽章での一体感のある演奏は見事でした。
1978年1月の早稲田大学交響楽団さんによる第7番の演奏には母高の吹奏楽部の同期生が乗っていたこともあり、ひと際印象に残っています。私は小学校・中学校のオーケストラも含めて100団体を超える学生オーケストラの演奏会を250回程聴かせていただきましたが、モーツァルトの『魔笛』序曲、ラヴェルの『ダフニスとクロエ』第2組曲、ブルックナーの交響曲第7番が演奏されたその定演はその250回程のコンサートの中でも間違いなくNo.1の演奏会だったと今でも思っています。
1978年7月のジュネス・ミュジカル・シンフォニー・オーケストラによる第9番は、東大、早稲田、慶應、上智、明治・・・・各大学オケから選抜された方々による演奏だっただけにその技術レヴェルは極めて高いものでした。ただ、演奏の一体感という点では、新響さんによる第4番や早稲田大学交響楽団さんの第7番のほうが優れていたと思います。
5:新響さんによるブルックナー交響曲第5番の演奏は今回が初めて、というのは意外でした。約150回も演奏会を聴かせていただいたのに私はしっかり記憶していなかった、ということになります。
私が初めてブルックナー第5番の演奏を聴いたのは確か1980年頃で白柳昇氏指揮による明治大学交響楽団さんの定演でした。パワーあふれる演奏だった記憶があります。現在の明治大学交響楽団さんでブルックナーのそれも第5番というのはピンときませんが、当時の大学オケはどちらのオケもいろいろな曲目にチャレンジされていました。とはいえブルックナー第5番は演奏機会の少ない曲でした。松下氏のご説明で、“アマ・オケがブルックナー交響曲を選曲することの難しさ”や“第5番の特徴”がよくわかりました。
かつて朝比奈隆氏が東京の5つのプロ・オケとブルックナーの交響曲第4・5・7・8・9番を1曲ずつ演奏されたことがあります。会場は東京カテドラル聖マリア大聖堂でした。天井の驚くほど高い、残響時間(私の実測で)7秒間という特殊な会場での演奏会で、私は東京都交響楽団さんによる第5番のみを聴きました。通常のコンサート・ホールでは体験することのできない演奏でした。
今回の新響さんは、音響の良さに定評があるとはいえ1803席あるにしてはコンパクトなすみだトリフォニー大ホールでの演奏ですから、大聖堂での演奏とはかなり異なる演奏になるはずです。それでも、ブルックナー愛好家でいらして「第5番が一番好き」とおっしゃっているという高関健氏の指揮ですばらしい演奏・音楽創りをしてくださるものと確信しています。とても楽しみです。
新交響楽団在団44年の思い出-②
編集人より
前号よりコンサートマスターを長年に亘って務められた都河和彦氏による回想録を掲載しております。以下に第2回目をご紹介致します。
◆創立20周年(1976年)からの10年間
新響創立20周年の76年には芥川先生の発案で10人の日本人作曲家の33-43年代の作品を集めた『日本の交響作品展』を9月、10月の2夜にわたって開き、日本音楽界への貢献が評価されて翌77年、『芥川也寸志と新交響楽団』が第8回鳥井音楽賞(現サントリー音楽賞)を受賞しました(芥川先生はこの賞の選考委員でしたが当事者なので、決選投票の際は席を外されたそうです)。私は授賞式直前に日帰りスキーに行って左肩を負傷、式で弾く予定だった芥川先生の『トリプティーク』のソロをやはりコンマスだった秋山氏に代わってもらい、芥川先生に小言を言われたのはほろ苦い思い出です。当時私が勤務していたモービル石油も「モービル音楽賞」を設けており、事務を担当していた広報部の社員によると、新響が受賞候補になったが決選投票で敗れたそうです。
この邦人作品展では平尾貴四男(1907~53)の『古代讃歌』を取り上げたのですが、芥川先生が打ち合わせのために妙子未亡人を訪ねたら、秦の始皇帝の頃の興味深い書体の書が目にとまり、「その書体で『新響』と書いてほしい」と頼んで書いていただいたのが現在も使われている「新響ロゴ・マーク」ということです。
その後も日本人作曲家のシリーズは続き、78年4月のコンサートはNHKのテレビドラマ『事件記者』のテーマ音楽で有名だった小倉朗先生の個展を2夜にわたって開き計8曲を演奏、私は先生のヴァイオリン・コンチェルトのソロを弾かせて頂きました。このコンサートの練習時、家人が海外出張で私が6歳と2歳の娘達の面倒を見ざるを得ず新響の練習を1回休んだら、次の練習で家人が芥川先生に呼び出されて「都河君は新響にとって必要な人だから、練習を休ませないでくれ」と叱られ、謝ったそうです。このコンサートの後、芥川先生初め10名ほどの団員が小倉先生に招待され、新宿「つな八」の2階座敷で天麩羅を御馳走になったのはなつかしい思い出です。小倉先生は文章も素晴らしく絵もお上手で、このコンサートのプログラムの表紙は先生自身が描かれた「自画像」でした。鎌倉の喫茶店での絵の個展には2度伺いました。伊福部昭先生は中国の書物、コーヒー、煙草に詳しく、また特徴ある書は見事でした。芥川先生も何冊か本を出版されているだけあって文章が素晴らしく、何度か頂いた年賀状には可愛い女の子の絵が描かれていました。後述するヤマカズ(山田一雄)先生の力強い書も見事なものでした。神は人によっては二物も三物も与えるのですね。
78年8月のサマー・コンサートは尾高忠明氏がドヴォルザークの『新世界』等を振ってくださいましたが、尾高先生の新響登場はこれまでこの1回のみでした。
同年12月のコンサートは『リヒャルト・シュトラウス特集』で河地良智先生に交響詩『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』、楽劇『サロメ』より7つのベールの踊り、交響詩『英雄の生涯』を振っていただき、『ティル~』のソロは田中久生氏が、『英雄の生涯』のソロは私が担当しました。河地先生には77年から80年まで4年連続で振っていただいています。
79年12月には当時の運営委員長橋谷幸男氏の尽力でヤマカズ先生(山田一雄氏)をお招きしてマーラーの交響曲第5番を演奏、その後88年まで11回続いたマーラー・シリーズの幕開けとなりました。初回の練習では全団員が曲の難しさと先生の分かりにくい棒に悪戦苦闘、阿鼻叫喚の感がありました。
80年1月芥川先生と黒柳徹子さんが司会をするNHKTV『音楽の広場』に新響が出演、私がヴィヴァルディの「秋」のソロを弾きました。モービル石油広報部の社員が私のTV出演を知りNHKに掛け合ってスタジオ・リハーサルの写真を撮って社内広報誌に記事を掲載、また英訳された記事がニューヨーク(NY)のモービル本社の広報誌にも転載されたので、8月にNY本社転勤になったとき「お、あのヴァイオリニストが来た!」と言われてしまいました。
同年4月、新響は芥川先生の恩師で、同年紫綬褒章を受章した伊福部昭先生(当時66歳)の個展を開きました。伊福部先生は何度かリハーサルに見えましたが、山高帽・黒マント・黒装束・蝶ネクタイにステッキ、という「怪傑ゾロ」ばりのダンディーなお姿で、芥川先生の「ここはどう処理しましょうか?」の質問には「お好きなように」と答えられ、我ら団員にも敬語を使われてびっくりしました。プログラムはマリンバ・コンチェルト『オーケストラとマリムバのためのラウダ・コンチェルタータ』(ソロ・安倍圭子)、ヴァイオリン協奏曲第2番(ソロ・小林武史)、そして『シンフォニア・タプカーラ』(改訂版初演)でした。マリンバ・コンチェルト第3楽章の終結部は同じ音型が数十小節続くのですが、本番で芥川先生が1小節早く振り終わってしまい、ソリストと数名の団員が楽譜通り終わるという事故が起き、先生が安倍氏に「ゴメーン!」と謝った表情を未だに覚えています。小林武史先生とはこの時の共演が御縁で今でも親交があります。『シンフォニア・タプカーラ』は伊福部先生からスコアをお借りして団員が手分けして写譜し、パート譜を作りました。芥川先生は「写譜とういう作業はどんなに注意したつもりでも必ず間違いがあるもの、何回も何回も見直しなさい」とおっしゃっていましたがご指摘通り、練習が始まると数々の写譜ミスが見つかりました。新響はこの曲をその後様々な指揮者と何度も再演、すっかり十八番になりました。
私は同年8月からニューヨーク(NY)のモービル本社に2年間単身赴任し、新響は休団しました。アメリカではジョン・レノンが凶弾に倒れ(12/8/80)、レーガン大統領の暗殺未遂事件(3/30/81)が起き、そしてアメリカに亡命していたムスチフラフ・ロストロポ-ヴィッチがワシントン・ナショナル交響楽団を指揮してNYタイムズの毒舌批評家ハロルド・ショーンバーグに「Apparently, Mr. Rostropovichi doesn’t know how to conduct.」などと酷評されていた時代です。仕事の傍ら頻繁にコンサートに通い、NYのアマ・オケでの演奏やアメリカ人との室内楽を楽しみました。マンハッタンの教会でのコンサートでは私がバッハのコンチェルトを弾き、団のマネージャーから「涙が出た」とのお褒めの手紙を頂きました。セントラル・パークで野外コンサートをやることになり、「本番にはプロのコンマスが来るが、練習ではお前がコンマスをやれ」と言われ引き受けたのですが、本番に現れたユダヤ人ヴァイオリニストの上手さにびっくり、「アンタ、何者?」と聞いたら「ロシア国立オケのメンバーでアメリカに演奏旅行で来たんだが亡命して、今はフリーのミュージシャンだ」という答に又々驚きました。
タングルウッド音楽祭には2度行き、バーンスタインや小澤征爾の指揮振りを見、そして80年のエリザベート王妃国際コンクールで優勝した堀米ゆず子さんのシベリウスのヴァイオリン協奏曲を聴きました。終演後、堀米さんに会いに行ったら小柄な方で「この体格で何であんな立派な音を出せるのか!」と驚いた記憶があります。また当時、堀米さんと同年の加藤知子さんがジュリアードに留学しており、82年のチャイコフスキー・コンクールで2位に入賞しました。
NYシティ・オペラでコンバスを弾いていた三浦尚之氏が毎年『ミュージック・フロム・ジャパン』と銘打ったコンサートをカーネギー・ホールで開いていて日本人演奏家を招き、日本人作曲家の作品をアメリカに紹介していました。旧知の黒沼ユリ子さんが広瀬量平氏のヴァイオリン協奏曲を弾き、渡米直前に新響が伴奏したマリンバの安倍圭子さんと再会したのもなつかしい思い出です(安倍先生とは帰国後の84年1月、芥川先生の指揮で伊福部先生のマリンバ協奏曲を再共演したのですが、終演後のパーティーで「カーネギー出演のため渡米したらビザに不備があって拘留され、本番に間に合わないのではと心配したら紫色の冷や汗が出、白い下着が紫色に染まった」という不思議な思い出話をしてくださいました)。又、当時NYで大活躍していた東京カルテットの原田幸一郎、チェロの毛利伯郎、ピアノの野島稔等の諸氏と知遇を得ましたが、後年これらお三方と新響で共演することになるとは当時は夢にも思いませんでした。82年暮の帰国直前、アメリカ人のボスから「社内でコンサートをやれ」との業務命令を受け、オフィスにはピアノがなかったので「弦楽四重奏にしてくれ」と言ったら「セキュリティーの関係で部外者は入れられない」とのことでやむなく、バッハ、ヘンデル、ベートーヴェン等のソナタを文字通り独奏しました。帰国して翌年新響に復団、まもなくコンマスにも復帰しました。
83年4月、長野県飯田市へ貸し切りバスで1泊の演奏旅行がありました。62年入団の新響チェロの名物古参団員石川嘉一さんの慶応大学時代の友人が飯田市で大きな書店を営んでおり「芥川+新響」を招待して下さった、と記憶しています。この旅行に運転手つきの車で同行したフランス人がいました。私が在米中に入団したヴィオラのルネ・アムラムさんで、当時スポーツ用品メーカー「スポールディング」の日本支社長でした。「社長」といえば、新響のオーボエ・パートには66年入団で、豪徳寺で電器店を経営していたので「社長」というニックネームで呼ばれる桜井哲雄さんという名物古参団員がいるのですが(芥川先生が名付け親とか)、アムラムさんが入団した時、さる団員が桜井さんに「社長、大変だ、大変だ、本物の社長が入ってきたよ!」とご注進に及んだそうです。
アムラムさんはその後の合宿にも運転手付きの車で参加、合宿所近くのホテルに宿泊していました。彼はアメリカの名ヴィオリストのミルトン・トーマスが使っていた名器ガリアノが売りに出た、というニュースを聞いてすぐNYに飛び、超有名弦楽器店「ジャック・フランセ」で入手したそうです(店にピンカス・ズッカーマンが来ていてアムラムさんが買ったヴィオラを試奏してくれたとか)。アムラムさんは当時の新日フィルのコンマスのルイ・グレーラーさん達とカルテットを楽しんでおり、また自宅で新響のヴィオラ分奏や室内楽パーティーをする時、近くの鮨屋「すし勘」から職人を呼んで鮨を握らせ、家が近かった私も何度か御相伴に預かりました。
84年11月、伊福部先生の古希(70歳)を祝うコンサートが芥川先生を初めとする弟子達によって東京文化会館で開かれ新響が『シンフォニア・タプカーラ』『日本の太鼓』等を演奏、弟子達がハッピ姿で太鼓を叩き、舞台にはゴジラの縫いぐるみも登場した楽しいコンサートでした。
85年11月に「芥川先生の還暦をお祝いする会」が六本木の国際文化会館で開かれ、先生は団員のファッション・デザイナー秋山さんが赤革を使って手作りしたチャンチャンコを着てご満悦でした。ヤマカズ先生も駆けつけ、『トリプティ-ク』を指揮してくださった、と記憶しています。
小松先生を偲んで
2013年3月30日指揮者の小松一彦先生が亡くなりました。1994年の初共演から病気で倒れられる数ヶ月前まで、新交響楽団の数多くの演奏会を振っていただき、常に情熱を持って厳しく温かく指導してくださいました。50周年記念、200回記念、芥川没後20年演奏会など、どの演奏会も我々の心に残る大切な思い出となっています。小松先生は新響を愛してくださり我々もまた小松先生を信頼し、これからも多くの作品を共に演奏することを楽しみにしておりましたが、残念ながらかなわなくなりました。心よりご冥福をお祈りいたします。
新交響楽団との共演記録
(いずれも指揮:小松一彦)
芥川也寸志メモリアル・コンサートII. 映画音楽の夕べ
1994年2月13日(日)田園ホール・エローラ(埼玉県松伏町)
曲目 芥川也寸志/「えり子とともに」「煙突の見える場所」「挽歌」
「 猫と庄造と二人のおんな」「危険な英雄」「道産子」「破戒」
「 五瓣の椿」「日蓮」「 八甲田山」
新交響楽団第148回演奏会<映画誕生100年記念演奏会>
1995年7月16日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 サン=サーンス/「ギース公の暗殺」
アイスラー/「雨」についての14の描写
サティ/幕間
深井史郎/「空想部落」
武満 徹/弦楽器のための「ホゼイトレス」
芥川也寸志/「煙突の見える場所」「猫と庄造と二人の女」
「八甲田山」「日蓮」
<東京の夏>音楽祭「映画と音楽」
2000年7月30日(日)紀尾井ホール
曲目 サン=サーンス/「ギース公の暗殺」(映像付)
武満 徹/3つの映画音楽
コープランド/映画のための音楽
サティ/「幕間」(映像付)
新交響楽団第180回演奏会
2003年1月26日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 ドビュッシー/牧神の午後への前奏曲
プーランク/バレエ組曲「牝鹿」
ベルリオーズ/幻想交響曲
新交響楽団第184回演奏会
2004年1月18日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 安部幸明/交響曲第1番
ラヴェル/ラ・ヴァルス
フランク/交響曲ニ短調
新交響楽団第188回演奏会
2005年1月16日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 ローマ三部作
レスピーギ/交響詩「ローマの祭」
同/交響詩「ローマの噴水」
同/交響詩「ローマの松」
新交響楽団第192回演奏会<創立50周年シリーズ・1>
2006年1月22日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 三善 晃/交響三章
ショスタコーヴィチ/交響曲第8番
新交響楽団第194回演奏会<創立50周年シリーズ・3>
2006年7月22日(土)サントリーホール
曲目 芥川也寸志/交響管絃楽のための音楽
伊福部昭/管絃楽のための日本組曲
黛敏郎/涅槃交響曲
新交響楽団第197回演奏会
2007年4月30日(月・休)東京芸術劇場大ホール
曲目 ルーセル/交響曲第3番
ラフマニノフ/交響曲第2番
新交響楽団第200回演奏会
2008年1月27日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 芥川也寸志/交響三章
黛敏郎/バレエ音楽「舞楽」
ストラヴィンスキー/バレエ音楽「春の祭典」
新交響楽団第203回演奏会
2008年10月13日(月祝)東京芸術劇場大ホール
曲目 ディーリアス/ブリッグの定期市
エルガー/エニグマ変奏曲
ドヴォルザーク/交響曲第8番
第204回演奏会<芥川也寸志没後20年>
2009年1月25日(日)東京芸術劇場大ホール
曲目 芥川也寸志/絃楽のための三楽章〜トリプティーク
芥川也寸志/チェロとオーケストラのためのコンチェルト・オスティナート
ショスタコーヴィチ/交響曲第4番
チェロ独奏 向山佳絵子
新交響楽団2009年新潟公演
2009年9月22日(火休)魚沼市小出郷文化会館大ホール
2009年9月23日(水祝)りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館コンサートホール
曲目 芥川也寸志/交響管絃楽のための音楽
黛 敏郎/バレエ音楽「BUGAKU(舞楽)」
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番
新交響楽団第207回演奏会
2009年10月12日(月・祝)東京芸術劇場大ホール
曲目 ヒンデミット/ウェーバーの主題による交響的変容
貴志康一/交響組曲「日本スケッチ」<貴志康一生誕100年>
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番
インタビュー
・小松先生インタビュー:第180回演奏会パンフレット
・プロの技術、アマチュアの心:第188回演奏会パンフレット
・三善 晃「交響三章」―日本人としてのロマン主義の探求:第192回演奏会パンフレット
・小松先生からのメッセージ:第197回演奏会維持会ニュース
小松先生からの寄稿文
・マエストロ小松からのメッセージ:第184回演奏会パンフレット(準備中)
・三善 晃とショスタコーヴィチの世界徒然:第192回演奏会パンフレット(準備中)
・マエストロ岩城宏之へのエレジー:第194回演奏会パンフレット
・二つの名交響曲徒然:第197回演奏会パンフレット
・熱いハートとクールな頭脳で―― 新響万歳!:第200回演奏会パンフレット
・上品なイギリス音楽と人間愛に満ちたドヴォルザーク:第203回パンフレット
・小松先生からのメッセージ(芥川也寸志没後20年):第204回演奏会パンフレット
・貴志康一:交響組曲「日本スケッチ」(曲目解説):第207回演奏会パンフレット
第221回ローテーション
| ドンファン | ばらの騎士 | 田園 | |
| フルート1st | 兼子 | 岡田 | 松下 |
| 2nd | 吉田 | 新井 | 兼子 |
| 3rd | 岡田(+picc) | 丸尾(+picc) | - |
| Picc | - | - | 吉田(+1stAssi) |
| オーボエ1st | 亀井(淳) | 宮内 | 堀内 |
| 2nd | 桜井 | 岩城 | 岩城 |
| 3rd | - | 山口(+C.A.) | - |
| C.A. | 山口 | - | - |
| クラリネット1st | 品田 | 末村 | 品田 |
| 2nd | 進藤 | 大薮 | 高梨 |
| 1st&2nd (Assi.) | 大薮 | - | - |
| 3rd | - | 高梨(Es.Cl.) | - |
| B.Cl. | - | 石綿 | - |
| ファゴット1st | 浦 | 浦 | 田川 |
| 2nd | 斉藤 | 斉藤 | 斉藤 |
| 3rd | - | 田川(+C.Fg.) | - |
| C.Fg | 田川 | - | - |
| ホルン1st | 鵜飼 | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 市川 | 森 | 兪 |
| 3rd | 大原 | 大内 | - |
| 4th | 森 | 大原 | - |
| 1st (Assi.) | 大内 | 箭田 | - |
| トランペット1st | 小出 | 野崎 | 野崎 |
| 2nd | 中川 | 倉田 | 青木 |
| 3rd | 青木 | 北村 | - |
| トロンボーン1st | 武田 | 武田 | 町谷 |
| 2nd | 町谷 | 小倉 | 志村 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | - |
| テューバ | 土田 | 土田 | - |
| ティンパニ | 桑形 | 古関 | 皆月 |
| パーカッション | トライアングル/今尾 鉄琴/古関 シンバル/中川 |
小太鼓/今尾 大太鼓,/桜井 シンバル/中川 グロッケンシュピール,ラチェット/(*) タンバリン/桑形 トライアングル/皆月 |
- |
| チェレスタ | - | 藤井 | - |
| ハープ1 | (*) | - | |
| ハープ2 | - | (*) | - |
| 1stヴァイオリン | 堀内(大隈) | 堀内(大隈) | 堀内(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(佐藤真) | 小松(佐藤真) | 小松(佐藤真) |
| ヴィオラ | 柳澤(田代) | 柳澤(田代) | 柳澤(田代) |
| チェロ | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) | 柳部容(光野) |
| コントラバス | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) |
(*)はエキストラ
第221回演奏会のご案内
今回の演奏会の指揮は、2012年に文化功労賞に選ばれ、2014年に新国立劇場芸術監督就任予定の飯守泰次郎。ますます音楽へのこだわりが深くなり聴く者に感銘を与えます。曲は飯守の得意とするドイツ音楽から「ドン・ファン」「ばらの騎士」「田園」と楽しいプログラムを選びました。
「ドン・ファン」はR.シュトラウス(1864-1949)が最初に発表した交響詩で、華やかなオーケストレーションで成功を収めました。ドン・ファンとは、スペインにいたとされる伝説的人物で"千人斬り"の好色漢。文学作品やオペラ、映画などの題材になっています。モーツアルトの「ドン・ジョバンニ」(イタリア語)は夜這した先で父親を殺してしまい、その霊によって地獄に堕ちますが、こちらの「ドン・ファン」は最高の愛を追い求める理想主義者として描かれています。
「英雄の生涯」を最後に一連の交響詩を作曲した後は、オペラを多く書いています。「ばらの騎士」はその中でも人気があり現在も世界中の歌劇場で頻繁に上演されています。ばらの騎士とは婚約の印に銀の薔薇を届ける使者のことですが、舞台となるウィーンの貴族社会でこのような習慣は実際にはなかったようです。侯爵夫人と不倫していた若い貴族が、夫人の従兄の男爵に見つかりそうになって女装したら口説かれて、男爵の使者として銀の薔薇を渡した娘と恋仲になって結婚する〜という喜劇です。今回演奏するのは演奏会用に編曲された組曲で、わかりやすく楽しめます。
「田園」はベートーヴェン(1770-1827)の言わずと知れた代表作です。9つの交響曲のうち、作曲家自身がタイトルをつけたのはこの曲だけで、5楽章からなり各楽章に標題がついているという点でも独特な作品です。のどかで美しい風景が広がりますが、当時としてはかなり前衛的だったでしょう。第5番「運命」と同時期に作曲され同じ演奏会で初演されましたが、この2曲は正反対で、第5番が激しい内面を現す絶対音楽であるのに対し、第6番は外に目を向け明るい標題音楽となっています。ウィーン郊外のハイリゲンシュタットに住み自然を愛したベートーヴェンの癒しのひとときかもしれません。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
ブルックナー:交響曲第5番
<真のブルックナー:厳格な技法とファンタジーの融合>
後期ロマン派最大の作曲家の一人、ヨーゼフ・アントン・ブルックナー(1824年~1896年)は、1868年44歳でヴィーン音楽院教授の和声法・対位法・オルガン演奏の教授に任命され、リンツからヴィーンに移住した。音楽院以外の仕事も多く、当時の一般市民からすればかなり豊かな生活水準ではあったが、創作の時間がないという不安から、執拗なまでに助成金の援助や要職への任命の懇願を文部省に行っている。当時のヴィーンでは作曲家として無名であり、音楽院では必ずしも優遇されていたわけでもなかった。深い謙虚さというよりは大仰なへりくだった部分と誇り高い自尊心が共存していた独特なキャラクター、音楽的教養に欠けるといった誤解もあり、受難の日々が続いた。独特な造形感覚が作品の全体像の把握を困難にして、長大な音楽そのものが当時のヴィーン楽壇で理解を超えるようになってきたといえよう。
本格的に交響曲の分野に進出してきたブルックナーは、ヴィーンに来た翌年1869年に交響曲第0番(第2稿:晩年に整理した際に自ら0と記載)を書きあげ、1871年から1876年まで交響曲第2番から第5番までの初稿を書きあげていく。現在知られているブルックナーの交響曲で改訂を伴う前の第1稿を毎年作曲したこの6年間は、創作活動のひとつの頂点といえよう。当時のヴィーン・フィルでは、これはという新作の試奏会(Novitätenkonzert:シューベルト交響曲第8番「グレート」が試奏された記録がある)があり、ブルックナーの交響曲では第0番の第1楽章や第2番、第3番、第4番と試演や初演で取り上げられていったが、演奏不可能としてたびたび拒否され、その後のブルックナー自身による度重なる改訂や弟子たちによる改竄が、複雑な版の発生という問題に繋がっていく。
交響曲第5番は、ヴィーン大学への度重なる求職活動と重なり、対位法の大家としてその能力を存分に証明した作品といえる。交響曲第4番の初稿完成3カ月後の1875年2月14日に作曲が開始され1876年5月16日に完了した。その後、バイロイトでのヴァグナー『指輪』4部作の初演におもむき、ヴィーン・フィルの演奏拒否に伴う交響曲第3番の最初の改訂や交響曲第1番の校閲が行われた。1877年5月16日から見直しを開始、1877年12月16日ヴィーン・フィルによる交響曲第3番(第2稿)の初演失敗という運命の時を経て、翌年1878年1月4日(アダージョの最終日付)で改訂が終了し、唯一の決定稿の完成をみている。
この時の改訂で重要なことは、交響曲史上初めてバス・テューバが加筆され、ハーモニーの重厚感の拡大に成功していることである。このことは1875年ヴィーン・フィルにベルリンから16歳のテューバ奏者が招聘されたことに関連している。交響曲第4番第1稿まではバス・トロンボーンが金管セクションを支えていたが、1880年交響曲第4番の改訂(第2稿)にバス・テューバを追加、以降の作品でも積極的に多用している。
1878年11月4日、筆写譜の最後に日付と署名を入れ、文部大臣カール・リッター・フォン・シュトレマイヤーに同日付で献呈された。その後は校閲や改訂という記録が無く、機会を逸したのか、作品の斬新さと巨大さゆえに拒絶されてしまう不安を抱いていたのか、ブルックナーの交響曲ではめずらしく「稿」として単一のもので、次作の交響曲第6番と並んで複雑な改訂稿をもっていない。
ヴィーンフィルでは、全曲であれ一部であれ、作曲者の生前に演奏したという記録が無い、すなわち生前にブルックナー自らオーケストラでは一度も聴くことのなかった唯一の交響曲である。
「交響曲第5番」
初期交響作品群で顕著に見られるブルックナーの「やりたい放題」とも思える当初の意図が、そのまま反映され原型をとどめている。すなわち初稿にこめられた「本来のブルックナーの音楽」が決定稿として残っている作品である。
ブルックナーは古典的なソナタ形式を交響曲に忠実に取り入れた。特に第1楽章と第4楽章に於いて伝統的な形式よりさらに拡大し、従来の2つの主題に加えて呈示部の小結尾を拡大して第3主題まで発展させている。この3つの主題は互いに対比し、各々異なる動機でできている複合体として機能している。
ある分析によれば、冒頭の音から全曲の主題が作られているという見方もあるくらい、ほぼ全ての主題と動機を同じ5つの音(わずかな相違も含めて)から形成した。また第2楽章と第3楽章が同じ伴奏形、第1楽章と第4楽章も同じ序奏で開始、という対称性による楽章の統合が堅固となっている。ベートーヴェンの「第九」を思わせる精密な設計によるゴシック様式の大伽藍のような構築、随所に現れるコラール風の楽想、比類のない対位法の技法を駆使しての巨大さは、当時の交響作品の全てを凌ぐものである。ブルックナーは「幻想的」と呼び、対位法上の傑作と位置付けた。
生真面目に主題を発展させて加工していく頑固なまでの厳格さと、音楽がどこに向かっていくのかわからない、即興演奏もかくやと思える自由でファンタジーな面が同居している。唐突にでてくる音楽は、よく見ると冒頭の主題に関連できるような構成になっており、対位法という技法のひとつの側面、技法を用いて音楽を突き詰めて、音楽の展開も「杓子定規」に書いている。
交響曲第0番から第6番までの初稿の傾向として、オーケストレーションは、理論的にこうあるべきだ、というところは崩さずに、そのまま管弦楽法のパレットに強引に当てはめてしまうところが散見される。クライマックスの構築についても、後期の交響曲にみられるように、緩除楽章の最後の方で音楽が高まっていき頂点で爆発する、という自然な流れが確定されておらず効果的ではない。
改訂も含め後期の作品になると洗練され、聴きやすくはなっているが、「本来のブルックナーの音楽」は、どこに音楽が行くのか判らない、というところに真骨頂がある。当時としては驚くほど尖鋭的で斬新な音楽がそこにあった。
このような結果により、巨大さと演奏時間の長さが生じている。演奏者や聴き手の負担を考えているところが見当たらない。宗教的なコラール風の旋律(聖)と、レントラー風のダンスのリズム(俗)を同じ曲に入れて平然としているのは、ブルックナーの特異な素朴さと自然さであろう。
第1楽章 序奏部:アダージョ― アレグロ
ベートーヴェン「第九」第3楽章のアダージョと同じで自由にして壮麗なる変ロ長調、2/2拍子、序奏付きのソナタ形式。序奏はモーツァルトのレクイエムの冒頭部分、ニ短調を変ロ長調に置き換えて拡大したような音楽。曲全体の原旋律である低弦のピッツィカート(譜例1)と弦の対位法的な旋律(譜例2)が印象的。突如ユニゾンで上昇動機(譜例3)が登場して金管のコラールが出現(譜例4)。同じプロセスが続いて収まったところで、高弦のトレモロの中をヴィオラとチェロによる特徴的なリズムと音程の第1主題(譜例5)が出現。この主題は魅惑的な転調を見せて全管弦楽に進行、落ち着いた後にヘ短調で始まる第2主題(譜例6)が弦5部のピッツィカートにより厳かに登場。続いて第1ヴァイオリンが呼応する。第3主題(譜例7)は変ニ長調で管楽器の伸びやか旋律を中心に進んでゆき、次第に曲想が盛り上がり変ロ長調の頂点に達して急速に静まる。
展開部はホルンとフルートの対話に始まり、まもなく導入部が回帰、第1主題が入ってきて発展し、第2主題の要素も弱い音で重なる。金管のコラールが鳴り響き導入部の最後と同じ構成となる。展開部は拡大された導入部としての意味もあり注目したい。再現部は各主題が全体的に著しく短縮されており、ブルックナーでは初めてのこと。コーダは導入部の低弦のモティーフが繰り返されて第1主題の前半が執拗に反復され、第1主題の反行形もみられて高揚していき最高潮のうちに閉じられる。
第2楽章 アダージョ、非常にゆっくりと
ニ短調 2/2拍子。A-B-A-B-A-Codaのロンド形式。最初に書かれた楽章で、初期のブルックナーの交響曲やミサ曲の「原型」が残っており、特に後半は荘重で厳粛な、歌詞のないミサ曲のようである。主部は弦5部の三連音のピチカートに乗ってオーボエによる物寂しい第1主題(譜例8)。極めて繊細に工夫された音楽で、この主題は全体を支配している。第2主題はハ長調で弦楽合奏による深い趣をたたえたコラール風の美しい旋律(譜例9)で「非常に力強く、はっきりと」提示され、交響曲第7番第1楽章を思わせながら頂点を築くと第1主題が回帰する。弦の6連符の動きの上に管楽器が主要主題を展開し、強弱の急激な交換が行われる。第2主題の回帰は低弦に八分音符の動きが入り発展的に進行、木管とホルンにより主要主題が奏でられる。フルートによる第2主題の反行形に始まる長いソロが印象的。第1主題の最後の登場にはヴァイオリンの6連符の動きの上に、徐々にトランペットやトロンボーンも加わって高潮していき、第1主題の後半に基づく7度や9度の跳躍が厳粛な雰囲気を醸し出していく。後半の3本のトロンボーンによるコラールは、第7交響曲第2楽章や第4交響曲終楽章の最終稿を彷彿させる。コーダはあっさりと終わるため解決されない印象がある。
第3楽章 スケルツォ:モルト・ヴィヴァーチェ、急速に、トリオ:同じテンポで
ニ短調、3/4拍子。複合三部形式。スケルツォ主部だけでソナタ形式をとり、アダージョ楽章冒頭のピチカート音形が速度を速めて登場して第1主題が呈示(譜例10)。第2主題はヘ長調で「テンポをかなり落として」レントラー風(譜例11)。ブルックナーの出身地であるオーバーエステライヒ(上オーストリア)のレントラーで、ウェーバーの歌劇「魔弾の射手」に登場する農民の踊りのように素朴で力強い。次第に高揚し小結尾となり、展開部へ続く。展開部では前半が第1主題、後半は第2主題。その後再現部は呈示部と同様に進むが、最後の14小節はコーダとなりニ長調の輝かしい和音で閉じられる。
中間部は変ロ長調、2/4拍子、3部形式。ホルンに導かれて木管が愛らしい旋律を奏でる(譜例12)。この対をなす動きは第1楽章冒頭のフレーズから由来している。呈示部に続き展開部、再現部と続いて軽やかに終始、そして主部の再現と進む。
第4楽章 終曲 アダージョ― アレグロ・モデラート
変ロ長調、2/2拍子。序奏付きのソナタ形式に2つのフーガが組み込まれ、ソナタ形式と対位法が融合、壮大・堅労且つ重厚でモニュメンタルなフィナーレ。序奏は第1楽章の序奏の再現で始まり、第1楽章第1主題、第2楽章第1主題が回想される。ベートーヴェン「第九」フィナーレに通じるもの。呈示部として第1主題(譜例13)が決然と低弦に登場、最初のフーガが開始される。第2主題(譜例14)は変ニ長調で第2ヴァイオリンに登場し、これはスケルツォ楽章第2主題に基づいている。ファンタジーな中間動機(譜例15)がホ長調で入り、第2主題がト長調で再開、と続いて第1主題の冒頭の音型に基づく第3主題(譜例16)が力強く奏される。呈示部の終わりと思われるところに突然金管が荘重なコラール(譜例17)を奏する。
展開部では、このコラール主題に基づくフーガで始まり、後半は第1主題が加わって自然な高揚感と共に壮大で複雑な二重フーガに発展していくところが秀逸。再現部は、第1主題の再現にコラール主題が合わさって短く、第2主題は比較的型どおりで、第3主題の再現は第1楽章第1主題が繰り返し用いられ、大規模なものとなっている。コーダではフィナーレの第1主題の動機にはじまり、ブルックナー自ら「Choral」と名付けた壮大なる頂点に達して、圧倒的なまでの勝利となって全曲が終わる。
「ハース原典版」
交響曲第5番は1896年4月にヴィーンのドブリンガー社から出版された。この「初版」は弟子のフランツ・シャルクによる改訂版であり、第4楽章を中心に大幅なカットや編成の拡大、オーケストレーションの変更がなされ、テンポの変化に関する表示も数多く付加されている。1898年のフランツ・シャルクによる初演も同様の内容で演奏されたと思われ(ブルックナーは病気のため初演には立ち会っていない)、改訂の度合いが極端で「改竄版」と現在は評されている。1929年ヴィーンに国際ブルックナー協会が設立、1930年からの第1次批判全集(ハース版)による原典版が1935年に出版されるまでは、ほとんど唯一のスコアとして演奏されていた。
尚、1951年より第2次批判全集(ノヴァーク版)が出版されている。交響曲第5番に限っていえば、ノヴァーク版とハース版とには根本的な差異はない。
「真のブルックナー」
ブルックナーは存命中から作品が全て否定されてきたわけではない。理解者が潜在的にいたが、弟子たちが先走った変なことをして本当の理解の妨げとなったということがいえよう。改訂後の方が作品の質が向上したのかどうかが問題で、少なくとも第1稿は作曲者の理想であることは間違いがない。
カトリックへの深い信仰が思考の基盤となっているブルックナーの作品には、教会の伽藍を空から見ると十字架になっているように、地上の人間では測りがたい秩序が存在する。ソナタ形式の枠組みの中で対位法という技法を用いて、教会の規定を厳守するがごとく取り組み、また心の核にある敬虔の念から出たファンタジーを併せて表現した。
このような人智を超えた啓示と共に、自らの霊感の命ずるまま自然に書きあげた結果がこのような曲になった。ここには、音楽の本質は決して言葉だけでは表現できないという事実がある。
「真のブルックナー」に向き合うのには、作曲者の意図をありのまま全て受け止める覚悟が必要である。「本来のブルックナーの音楽」は、鷹揚で悠然且つドラマチックといった改訂時からの思い入れを取り除き、複雑なスコアの全体を見渡して隅々に目を配り、一定のリズムとテンポを維持しながらも刻々と変わる調性と音響バランスをコントロール、そして音楽は自然に息づいていなければならない。
フィナーレの最後、全楽器によるユニゾンとそれに続くゲネラル・パウゼには、ブルックナーの「完全なる勝利」が響で表現されている。交響曲第5番作曲後、規模や内容の充実度において交響曲と比肩する弦楽五重奏曲の創作、1884年交響曲第7番の圧倒的な成功と1886年「テ・デウム」初演に始まる晩年の名声と名誉への喝采と称賛が、この「勝利へのゲネラル・パウゼ」を証明している。
本稿執筆に際して、東京藝術大学音楽学部楽理科教授土田英三郎氏からご助言いただいた。感謝の意を表したい。
ブルックナー 1880年頃の写真
注)ブルックナーの生涯、個性、音楽の考察に関しては、新交響楽団第209回演奏会プログラムで筆者が記載した「ブルックナー:交響曲第9番<永遠のゲネラル・パウゼ>」を併せて参照していただきたい。(新響ホームページから「過去の演奏会」を選択し第209回演奏会の詳細にあり)http://www.shinkyo.com/concert/p209-3.html
初 演:
1878年4月20日ヴィーンにて ヨーゼフ・シャルク、フランツ・ツォトマンによる2台ピアノ編曲版(ヨーゼフ・シャルクによる2台ピアノ用編曲)
1894年4月8日グラーツ市立歌劇場にて フランツ・シャルク(ヨーゼフ・シャルクの弟)指揮 初版(改訂版)
1935年10月20日ミュンヘンにて ジークムント・フォン・ハウゼッカー指揮 原典版(ハース)
日本初演:
1962年4月18日大阪フェスティバルホールにてオイゲン・ヨッフム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
楽器編成:
フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、弦五部
参考文献
『作曲家別名曲解説ライブラリー⑤ ブルックナー』 (音楽之友社)
『ブルックナー ―カラー版作曲家の生涯―』 土田英三郎(新潮社)
『アントン・ブルックナー 魂の山嶺』 田代櫂(春秋社)
ベルク:3つの管弦楽曲
1. はじめに
「ベルク! シェーンベルクの一派で“ゲンダイオンガク”でしょ。なんだかよくわかんないよ。」という先入観をお持ちの方はいらっしゃいませんか。確かに初めて聴いてすぐに耳に馴染むような音楽でないかもしれません。でもベルクの曲はとてもロマンティックな、感情に訴えかける音楽であるとして愛好されていることも事実なのです。無調や12音技法を用いていながら、というよりも無調音楽だからこそ表現できる感情があることをベルクが最初に実証したように思えてなりません。それは、オペラ「ヴォツェック」「ルル」、そしてヴァイオリン協奏曲などのベルクの代表作の幅広い人気が物語っているとも言えるでしょう。そんな魅力を感じる人がたくさんいる作曲家なのに食わず嫌いでいるのはもったいない。このコンサートをきっかけにベルクでも聴いてみようじゃないかと思われる方が増えることを期待しています。
本日取り上げる「3つの管弦楽曲op.6」は前記3曲とは異なって、ストーリーや悲劇的背景がない絶対音楽ですが、過激な感情爆発と異常な沈潜が頻繁に交代し、所々で軍楽隊や酒場の踊りのような俗っぽい音楽が顔を出すところなどはマーラーを髣髴とさせるとても人間くさい音楽です。
図1:アルバン・ベルク(1909年 24歳)
2. ベルクの生涯について
ベルクは1885年ヴィーンで書籍・絵画・礼拝用品を扱う裕福な商人の家に生まれました。家庭内は絵画、文学、音楽等の芸術に親しむ環境で、14歳ころから独学で歌曲を作曲するようになります。ところが15歳で父を亡くして経済的に苦しくなり、また生涯ベルクを苦しませることになる喘息も発症してしまいます。悪いことは続きます。17歳のときにはベルク家に仕えていた女中に子供を産ませてしまうのです。しかも、学校の卒業試験で落第し、その果てに自殺未遂を起こしてしまいます。自業自得の面もありますが、とにかく激動の思春期だったわけです。
なんとか翌年に卒業し、また彼女はその子(図2)を連れてベルク家を去りました。ベルク唯一の子供であるその娘はベルクの埋葬の際に一度ベルク家に姿を現しただけだったとのことです。
アルビーネ・ショイフル
1902年に17歳だったベルクとベルク家の女中マリー・ショイフルとの間に生まれた。
転機は18歳のときに訪れます。弟子を募集していたシェーンベルクに、書き溜めていた歌曲を兄が送ったことがきっかけでシェーンベルクの弟子になるのです。“超俺様”的な師匠であったシェーンベルクにこき使われもしたようですがウェーベルンと並ぶ優秀さで勉強を終え、その後も師の右腕として無調音楽や12音音楽などの新しい音楽の普及に努めます。また、ベルクはマーラーに心酔しており、交響曲第4番のヴィーン初演の際には熱狂した仲間とともに楽屋に押しかけてマーラーから指揮棒を奪い取った(?)との逸話が残されています(図3)。
図3:ベルクが生涯宝物として大切にしていた指揮棒、
1902年に楽屋でマーラーから奪い取ったもの。
21歳でのちに妻となるヘレーネと出会い、ベルクは生涯(少なくとも表向きは)愛妻家として通します。余談ですが彼女は実はオーストリア皇帝の落とし子だったといわれています。
1914年29歳のとき、ビュヒナーの劇「ヴォイツェック」(章末の注参照)を観劇し、この戯曲でオペラを作曲することを決心します。その頃は、本日演奏する「3つの管弦楽曲op.6」をちょうど作曲していた頃でした。その後第一次世界大戦が勃発し兵役につきますが病弱なためすぐに事務職に回されます。この軍隊生活での人を人とも思わない理不尽な、ベルクにとっては耐え難かった経験がオペラ「ヴォツェック」の曲想に大きな影響を与えたといわれています。
戦後は、これまた名曲である「叙情組曲」を作曲します。無調および12音技法で書かれた非常に緻密な音楽なのですが妙に熱いものを感じさせる曲です。実はこの曲、人妻のハンナ・フックス・ロべッティン(図4)への熱烈なラブレターでもあったのです。ただ、この不倫の恋は生前には発覚せず妻のヘレーネとの関係に問題は生じませんでした。
図4:ハンナ・フックス・ロベッティン
ベルクの叙情組曲を贈った恋人で、マーラーの妻アルマの3人目の夫ヴェルフェルの姉である。
アルマはベルクとハンナ・フックスの不倫の恋を知っていた。
1926年、数々の困難を乗り越えて「ヴォツェック」が上演されると大評判となり、一躍大作曲家としての名声を得ます。とはいってもその後も寡作であり、まとまった曲としては歌曲「ワイン」、ヴァイオリン協奏曲そしてオペラ「ルル」(未完)しか作曲していません。1935年に虫刺されが原因で敗血症にかかり亡くなってしまいます。アルマ・マーラーとその2番目の夫グロピウスとの間の娘の夭折を悼んで書いたヴァイオリン協奏曲が最後の完成した作品となります。
ベルクは、写真からもうかがい知れるように上品で聡明、とても心やさしく魅惑的な人だったとのことです。その音楽は大編成で過激な音響が多用されてはいますが、その中に人間の弱さを実感できた人にしか表現できない深い感情がこめられているように思います。
(注)「ヴォイツェック」は、実際に起こった殺人事件をもとに19世紀の劇作家ビュヒナーが書いた未完の戯曲・下級軍人ヴォイツェックが、貧困と虐待により精神を病み、浮気をした情婦のマリーを刺殺し自分も溺死するという筋書きである。ベルクはこの戯曲に綿密に構成された無調音楽を付けることで、虐げられる者の抑圧された心情や、虐げる側の無邪気な残酷さを生々しく表現したオペラを作曲した。ここぞというところには超ロマンティックな調性音楽を配置して絶大な効果を生んでいる。なお、オペラでは主人公の名前が「ヴォツェック」に変更されている。
3. 3つの管弦楽曲 op.6 について
1914年に作曲され、第1曲と第3曲はその年の9月8日にシェーンベルクに献呈されました。第2曲は遅れて翌年の8月にシェーンベルクに届けられています。師シェーンベルクの「管弦楽のための5つの小品op.16」を意識していることは明らかですが印象はだいぶ違います。シェーンベルクのほうは無調の技法確立を目的とし、官能性を故意に排除したような印象がありますが、ベルクのほうはとても官能的です。そういう意味ではマーラーの影響をより強く感じます。特に第3曲は後半のクライマックスでハンマーの打撃により打ちのめされてしまうとこ
ろや、悲壮な軍隊行進曲が出てくるあたりなど、ベルクが心酔していたマーラーの第6交響曲の終楽章や歌曲「レヴェルゲ(邦題:死んだ鼓手)」のオマージュであると言えます。また、ちょうど「ヴォツェック」を構想したときの作品であり両者には多くの類似箇所があります。
初演は作曲されてからだいぶ経過してから行われています。その理由は、「きわめて演奏が難しいこの曲を二回程度しか練習できない通常のコンサートで取り上げることを了解しなかったためである」とベルクが書いています。また、ベルクの弟子がスコアを見て「シェーンベルクの5つの管弦楽曲とマーラーの第9交響曲を一緒に演奏したように聴こえるでしょう」と言ったそうです。確かに複雑で演奏上大変難しい曲なのですが、我々は音源を練習前にいつでも聴くことができ、本日までに高関先生そしてトレーナーの先生方のご指導で14回も練習してきましたのできっとあの世のベルクも了解してくれることでしょう。
第1曲:前奏曲
最初は打楽器や低音楽器がモゴモゴと蠢いていますが、その中からファゴットのエロティックな長音のソロが浮き立ってきます。調性のない単純なフレーズでもなぜか歌心があるのがベルクの特徴です。続く艶かしいトロンボーンの超ハイトーンの異様な美しさも堪能ください。その後はベルクの真骨頂とも言うべきロマンティックな無調の旋律がオーケストラの各楽器群により繰り返されます。最後は再び打楽器等の蠢きで曲を閉じます。
第2曲:ワルツ
ロマンティックな無調旋律による二分の二拍子の部分の後、高音の下降音形に導かれてヴァイオリンのソロにより酔っ払ったような卑俗なワルツが一瞬現れます。その後の物思いにふけるようなチェロやヴァイオリンのソロ、怪獣の叫びのようなフラッター奏法のトランペットなどで徐々に混乱状態(演奏自体は混乱しない予定)になった後、再びワルツが垣間見えます。ラヴェルの「ラ・ヴァルス」のような雰囲気のところもあります。しかしワルツは長続きせず、木管のハイトーンによる静寂のうちに曲を閉じます。
第3曲:行進曲
不気味な行進曲で始まります。マーラーの歌曲「死んだ鼓手」のパロディーでしょうか。一度盛り上がった後、危ない人の独り言のような小クラリネットのソロが続きます。その後は次第に激しさを増して冷酷な行進曲に突入。さらに狂気の度合いが増していき、音が分厚く重ねられて阿鼻叫喚の世界になったクライマックスでハンマーの三連発が打ち込まれます。再びゾンビのように立ち上がりますがさらに一発のハンマーとティンパニの連打がこれを叩きのめします。一瞬の沈黙の後の首を絞められた悲鳴のような高音や、その後のクラリネットとファゴットにより刻まれる上昇音型は何を意味するのでしょうか(「ヴォツェック」の印象的な場面に類似の音楽が使用されています)。最後に三み度たび立ち上がりますがハンマーの一撃により止めを刺されて終わります。
初 演:第1曲と第2曲のみ1923年6月5日、ベルリンにて
アントン・ウェーベルンの指揮。全曲は1930年4月14日、オルテンブルクにてヨハネス・シューラーの指揮。
楽器編成:
フルート4(ピッコロ持ち替え4)、オーボエ4(4番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット4(3番は小クラリネット持ち替え)、バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン6、トランペット4、トロンボーン4、テューバ、ティンパニ2(奏者3人)、小太鼓、中太鼓、大太鼓、シンバル付大太鼓、グロッケンシュピール、吊りシンバル、合わせシンバル、小タムタム、大タムタム、トライアングル、ハンマー、シロフォン、チェレスタ、ハープ2、弦五部
参考文献
『アルバン・ベルク生涯と作品』 フォルカー・シェルリース(岩下眞好/宮川尚理訳)(泰流社)
『新ウィーン学派の人々 同時代者が語るシェーンベルク、ヴェーベルン、ベルク』
ジョーン・アレン・スミス(山本直広訳)(音楽之友社)
『アルバン・ベルク 伝統と革新の嵐を生きた作曲家』 ヴィリー・ライヒ(武田明倫訳)(音楽之友社)
『20世紀を語る音楽』 アレックス・ロス(柿沼敏江訳)(みすず書房)
ブルックナーの交響曲第5番
私事から話を始める事をお許し願いたい。私は1982年9月に新響のオーディションを受け入団を果たした。という訳で今年在団30年を迎えた事になる。青雲の志を抱いて社会に出帆し、「世のアマチュアオーケストラの隆盛をこの手で実現せん」と勇んでこの集団に参加した24歳の青年も、いたずらに馬齢を重ね、今や自分の年金支給開始年齢を気にするテイタラクとなっている。
世の中もこの30年の間にベルリンの壁は取払われ、ソ連は崩壊し、白人以外の米大統領が現れて、日本の総理大臣は18人(!)替わった。そうした時代の激流の渦中・・・つまり明日何が起こっても不思議は無い!という時代に身を置きながらも、新響がブルックナーのこの交響曲を取上げる日が自分の在団中にやってこようとは、流石に予測出来なかった。今やわが身の不明を恥じる日々を送っている。
◆アマチュアオーケストラに於けるブルックナー
概してブルックナーの交響曲はアマチュアオーケストラの演奏会プログラムとしては取上げにくい。理由はいくつかあるが「難度」と「長さ」と「編成」は必ずついて回る問題に違いない。簡単に言えば、長いのでメインに据えなければならないにもかかわらず、管打楽器の演奏に要する人数が少なく、その癖演奏が難しいという事である。
これも私事になってしまうが、私が早稲田大学交響楽団に入団したのが1977年4月。その時既にこの団体では2ヵ月後の演奏会に向けてマーラーの第4交響曲を練習していた。翌年の1月には山岡重信氏の指揮でブルックナーの交響曲第7番を演奏している。その年の9月には『カラヤンコンクール』での優勝を果たしているのだから、一定以上の技術的基盤は築きつつあった時代だ。これが学生オケの中では早期の例で、この頃から遅まきながら徐々にブルックナーが取り上げられるようになったと記憶している。
また同じ1978年の7月には在京の学生オケ選抜メンバーによる「ジュネス・ミュジカル・シンフォニー・オーケストラ」によって、山岡氏の指揮で第9番が演奏されている(『青少年音楽祭』於・NHKホール。この演奏会の詳細については、第209回定期の維持会ニュースに、同じ参加メンバーだったテューバの土田恭四郎氏が『ブルックナー三昧だったあの頃』で記述している)。私もオーディションに通り、この集団の技術レヴェルについて体感している。本来このオーケストラは選抜メンバーであるだけに、所属する自団体独自では演奏が困難なプログラムを演奏する事をひとつの目的としていた。そこでブルックナーの最後の交響曲が対象となった事実は、今から35年近く前のアマチュアオーケストラに於ける技術面から見たこの作曲家の位置づけを想像させるに充分であろう。
「長さ」は「編成」の要素と相俟ってプログラム構成上の時間配分と「出番」の問題として顕れる。概して70分を超える作品をプログラムのメインに据えると、まず3曲構成にする事は困難になる。2曲構成・・・しかも他の1曲はごく短いものを据えざるを得ないという著しくバランスを欠いた形になってしまうケースが殆どで、これでもメインの曲の編成さえ大きければ、ひとまず軋轢は回避できる。ブルックナーと同じような長さを持つにもかかわらず、マーラーの交響曲が取り上げられる頻度が比較にならぬほど高いのは、こちらは管・打楽器が大編成であるため、メンバーの出番が確保されるからである。アマチュアオーケストラに於けるプログラムビルディングにはこうした内部事情ゆえの偏りが生じる事を完全には避けきれない。それは新響のように年4回もの演奏会を持ち得る団体であっても例外ではないという事だ。こうして改めて考えてみるとブルックナー愛好者(私もその端くれ)にとってはなかなか厳しい世界である事を考えさせられる。
◆第5交響曲=ブルックナー「らしさ」の追求=
そうした中でもとりわけこの第5交響曲は更にプログラムに載る事が少ないのは、長さや編成や技術的な問題に加え、「扱いにくさ」にあるように思える。必ず問題になるのが終楽章であろう。一般にこの作曲家の交響曲の終楽章は、その長大・雄渾な第1楽章から続く他の2つの楽章と比較して、明らかに尻すぼみになっているものが多い。形式も定まらず総花的な展開の果てに短い終結部がついて「唐突」とさえ感じられる終止。ひとまず盛り上がってはいるものの、終楽章のみを見てもやや首をかしげざるを得ず、況して作品全体からみると著しくバランスを欠く。最も演奏されているであろう第7・第8交響曲然りで、演奏する側はこのアンバランスを前提として(それしか選択肢は無い訳だが)演奏に必要となる様々な力の配分を組み立てる事になる。「何だか釈然としないが、ブルックナーとはそんなものだ」という認識が何となく醸成されて、今もあるがままが受け容れられた演奏が繰り返されている。
そのような認識や尺度を基盤として第5番に向かうと、その長大にして緻密に書かれたフィナーレを前にして戸惑いを禁じ得ないだろう。ひと言で表せば「わかりにくい音楽」という事だ。初めにそれまでの楽章の全てが回想される。これを以ってベートーヴェンの『第九』と比較する向きもあるし、その後三重フーガが出てくるとなれば、況してこの偉大な先達が示した交響曲の到達点をなぞっているようにも見える。
だがブルックナーの書いたこの終楽章は、『第九』のような整然さを備えておらず、ある部分で野卑であり、他の部分ではより神聖で厳粛である。謂わば「聖なるぼくとつ朴訥」としか表現し得ないものがそこに展開されているように思えてくる。少なくとも作曲家が書いた通りの音を出し、テンポに従っていくとそうなる・・・ように感じる。「聖なる朴訥」とは、微妙な言い方になるが「健常者には決して備わる事の無い聖性」のようなものだと個人的には考える。そしてそれがブルックナー「らしさ」の非常に重要な要素になっているという事も。絶筆となった第9番の終楽章(それは草稿のみが存在する)も、こうした荘厳な建造物を思わせる構成と性格を持っていた。つまり作曲家にとって、究極的に実現されるべき終楽章の原形が、第5交響曲に既に予感され、現実の形となっていたと考えるべきなのではあるまいか?
だが残念ながらこうしたものに直面し、理解し、現実の音によって表現しようとすると、どうしても我々の常識に基づいて何かを仕掛けてしまいがちである。すなわちテンポや強弱など、譜面に書かれたものを「不自然」と捉えて敢えて無視し、「常識的な」音楽に作り変えてしまう。「ブルックナーとはそんなものだ」という訳である。世の中に広く流布している「名演」と言われるものにもこうしたものが多くある。これは極めて残念な事とせざるを得ない。
今回新響は第5番を初めて演奏するに当たって、指揮者である高関 健氏のこの曲に対する・・・とりわけ終楽章に対する・・・意向を正しく反映するべく、真摯に取り組んでいる。それはあるがままの音によってブルックナーらしさを追求するという行為にほかならない。技術的な課題の克服をしつつ(アマチュアオーケストラがこの作曲家の作品を手がけて40年近い時間が経過しても、容易に解決しない)、こうした追求に努める事は、かつてなかなか顧みられなかった部分であるだけに大きな価値がある。アマチュアに限定せずともブルックナー演奏史にとって、ひとつの事件として語られるコンサートにしたい。
学生オーケストラによるブルックナー演奏の草分け時代を知る「老兵(私の事。念のため)」の願いは、まさにこれに尽きるのである。
新交響楽団在団44年の思い出-①
新響維持会員の皆様こんにちは。新響創立(1956年)12年目の1968年に入団、44年間在籍して35年間コンサート・マスター(コンマス)を務め、ここ数年はヴィオラを弾き、今年7月に退団した都河(つがわ)和彦です。このたび皆様の維持会に入会させて頂き、これからは新響を応援する側に回りたいと思っていますのでよろしくお願いします。このたび『新響維持会ニュース』編集人の松下俊行氏から「いくら長くても良いから維持会ニュース用に在団時代の思い出を書け」との命を受けたので僭越ですが、入団前の新響の歴史にも触れ在団期間中の思い出を年代順に述べさせて下さい(新響創立50周年記念演奏会[2006年]のプログラムに掲載された過去50年分の演奏記録と今年10月の定期演奏会プログラムの「最近の演奏会記録 2006年~2012年」を参照しながら思い出を綴りました。オーケストラの活動には演奏と運営の両面がありますが、私は新響ではずっと演奏サイドでのみ活動してきたので、以下でたまに触れた運営に関する記述には少々不正確な記述があるかも知れません。正確な「新響56年史??」を書くためには、各時代に演奏・運営面で活躍した数多くの団員の証言が必要と思います)。
◆新響創立(1956年)からの10年間
上記創立50周年年表によると、1955年2月労音アンサンブル結成、同年9月芥川也寸志氏を指揮者に迎え翌56年8月、正式団名を「東京労音新交響楽団」に決定、とあります。
ここでウィキペデイアによる芥川先生の略歴に触れておくと、1925年7月12日に文豪芥川龍之介の三男として生まれ(父は27年に自殺)、43年東京音楽学校予科作曲部に入学、44年学徒動員で陸軍戸山学校軍楽隊に入隊。戦後45年に東京音楽学校に復学した時、作曲科講師の伊福部昭と出会い決定的な音楽的影響を受けます。50年に『交響管絃楽のための音楽』がNHK放送25周年記念懸賞で特別賞を受賞して一躍有名になり(25歳)、54年にはまだ国交がなかったソ連に自作を携えて単身密入国、ソ連政府から歓迎を受け、ショスタコーヴィッチ、ハチャトリアン、カバレフスキーの知遇を得たそうです(29歳)。アマチュア演奏家達の熱意に打たれて新響を創立した56年は31歳の若さだったということになります。翌57年はヨーロッパ旅行の帰途インドに立ち寄ってエロ-ラ石窟院の巨大な岩を削って造られた空間に衝撃を受け、この時の感動から『エローラ交響曲』を作曲、伊福部昭と同様に若き芥川に大きな音楽的影響を与えた作曲家、早坂文雄に捧げたそうです。
上記年表によると、新響は57年に第1回、58年に第2回の定期演奏会を日本青年館で開き、59年に会津労音例会、60年は上田・熊谷労音例会、61年は秩父・熱海労音例会に出演、62年には4月の東京労音で4回、5月の栃木労音で2回のコンサートを開いています。63年は東京労音、水戸労音等でベートーヴェンの『運命』を中心に計7回の演奏会をこなした後、12月には東京労音例会で第九を5回公演しています。
64年4月は北海道各地の労音で連続5日の演奏会、5月に定期、8月にサマー・コンサート、そして10月東京労音八王子例会、となかなか忙しい年だったようです。
65年はもっとすごくて、2月の定期のあと3月と4月に4回の東京労音例会、4月下旬からは四国各地の労音で7回の演奏会、7月に浜松労音で2回の演奏会、8月サマー・コンサート、9月日立労音、12月定期等々、今では考えられない過密なスケジュールをこなしています。メンバーは現在と同じで殆どサラリーマンだった筈、どのようにしてこの過酷なスケジュールに対処できたのでしょうか?
◆創立10周年(1966年)からの10年間
「66年2月に東京労音から独立」と50周年年表にはあります。私が大学4年生だった66年の『週刊朝日』に、「新響が労音からケンカ別れした」という趣旨のトップ記事が掲載され、冒頭の「この事件の主人公は白いシトロエンに乗って颯爽と登場する。」という名文?と芥川先生の写真は今でも記憶にあります。「労音の新響に対する運営や選曲への干渉が煩わしくなって独立することにした」というのが記事の趣旨だった、と記憶しています。
労音から離脱したこの年は創立10周年に当たり、4月の定期演奏会の後、9月・10月・11月・12月の4回の演奏会でベートーヴェンの交響曲全9曲を演奏する「ベートーヴェン・チクルス」を敢行しています。
1967年9-10月に新響は日ソ文化交流協定に基づいて訪ソ親善演奏旅行を行っています。4月に14回定期、8月に訪ソ記念特別演奏会を開いた後、9月22日~10月9日にモスクワ等4都市で5公演を行いました。東大オケ5年生だった私は(留年しました)この直前に新響のオーディションを受けて合格したのですが、「ソビエト旅行のメンバーはもう確定している」とのことで参加できませんでした。
67年12月の第15回定期演奏会も私は多忙で出演できず、東大と東大オーケストラを卒業後モービル石油(株)に入社した1968年4月の定期が新響初舞台でした。新響の練習に参加してみて、芥川先生(当時42歳)の力強い指揮ぶりに圧倒され、また並はずれた行動力や企画力、先見性に感銘を受けました。常にパリッとした濃紺のジャケット、折り目のついたグレーのズボン、糊のきいた青いワイシャツ、赤と紺のストライプのネクタイ、ピカピカに磨かれた革靴というダンディーぶりにも感服しました。殆どの練習には外車を運転して来られ練習後、原宿の中華料理店「南国酒家」で夜食をよく御一緒した記憶があります。
このコンサートでは東京交響楽団(東響)の若きコンサート・マスターだった徳永二男氏がメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を独奏、メインはベルリオーズの幻想交響曲でした。(翌69年11月東大オケ同期でチェロを弾いていた明子と結婚したのですが、彼女にとってもこのコンサートが新響初舞台でした。東大オケで『幻想』を演奏したばかりで新響はチェロ奏者が足りなかったので、オーディションを受けずに「もぐり入団」出来たそうです。)新響の当時のコンマスは東工大出身の河野土洋氏で、私はこのコンサートではファースト・ヴァイオリンの第3プルト外で弾いたのですが、このコンサート後私もコンマスに任命されました。
当時、芥川先生は東京交響楽団(東響)の財政再建のため同団の理事を務められており、東響に維持会員制度を導入、後日新響でも採用したと記憶しています。その関係で同年8月、東響・新響の合同演奏会が秋山和慶・芥川也寸志両氏の指揮で開かれました。弦の奇数プルトは東響、偶数プルトは新響ということで、コンマスは徳永氏、私は第2プルト内で弾きました。東響との合同演奏会は前年の67年10月、4年後の72年8月にも行われました。
68年10月の定期には芥川先生が当時指揮界の巨匠だった近衛秀麿先生にお願いして、モーツァルトの『ジュピター』等を振っていただきました(創立12年目の新響にとって初めての客演指揮者だったそうです)。近衛先生の指揮は分かりにくく、皆で「先生の肘の動きに合わせよう」などと打ち合わせた記憶があります。
芥川先生は前年67年にアマチュア合唱団「鯨」を立ち上げており、68年12月ベートーヴェンの『第九』で2回共演しました。私にとって『第九』はあこがれの曲でしたがそれまで弾く機会がなく、これが私の「第九初体験」でした。「鯨」との年末共演は翌69年はヘンデルの『メサイア』でしたが、70年からは連続5年間、いずれも『第九』の2回公演を実施しました。
69年8月から芥川先生の仕事の都合で練習日が土曜から木曜に変わりました。72年4月から又土曜に戻りましたが、この間会社に楽器を持参せねばならず、練習に間に合う様に会社を抜け出すのも大変でした。先生も忙しくて練習に遅刻したり、練習が予定通り進まなくて一音も出すことなくスゴスゴと帰る団員もいた、と記憶しています。
69年10月末から10日間、九州沖縄芸術祭参加の演奏旅行があったのですが、コンマスの河野氏は参加できず、私も仕事の都合と自分の結婚式の準備で参加できなかったので、上智大学出身の秋山俊樹氏が急遽入団、コンマスを務めてくれました。
70-72年頃、組織改革がありました。芥川先生は「音楽はみんなのもの」が口癖でテレビでは柔和な笑顔を振りまいていましたが、我々新響団員に対しては「作曲家と指揮者は神様と思え」も口癖で、我々の拙い演奏には苦虫を噛み潰したような厳しい表情で叱咤激励していました。この頃数多く入団してきた民主的運営の学生オケ出身者が新響の「芥川独裁」「芥川・アンド・ヒズ・オーケストラ」といった雰囲気に反発、団内に不協和音が流れ始めたので数グループに分かれて話し合いが持たれました。結果として芥川先生のそれまでの功績に対し、今迄の「常任指揮者」に加え「音楽監督」にもなっていただいて権限をより強化し、団員は先生に忠誠を誓うという形で落ち着いた、と記憶しています。またそれ以前の運営体制は常任指揮者・委員長、副委員長2名、事務局長、数人の各委員という構成でしたが、72年頃には音楽監督兼常任指揮者、理事長、運営委員長、技術委員長(私)、事務局長から成る「理事会」が団運営の道筋をつけていくようになりました(その後、いくたびの変遷を経て、現在の団長、運営委員長、演奏委員長、インスペクター、各委員の体制に落ち着きました。新響には創立以来「規約」が存在し、組織等についての規約変更は、各年末の総会で諮られ多数決で決定されてきました。
70年に芥川先生は3度目の結婚をされ、成城学園前に豪邸を新築なさいました。打ち合わせのため理事会メンバーで何度かこのお宅にお邪魔しましたが、忙しい先生に1時間ほど待たされるのが常でした。
70年11月は外山雄三氏を客演に迎え、チャイコフスキーの交響曲第4番等を振っていただきました。藝大卒業後N響に入団、ウィーンに留学という輝かしい経歴で、ずっとプロ・オケばかり振ってきた厳しい練達の棒についてゆくのが大変で、打ち上げの席では「もうアマチュアは振りたくない」という意味のことをポロッとおっしゃいました。
71年8月のサマー・コンサートでの芥川先生指揮・リムスキー=コルサコフの交響組曲『シェラザード』では私がヴァイオリン・ソロを担当しました。このコンサートでは「服装自由」だったので私は黄色と青のアロハシャツを着て弾いたのですが、隣席のサブ・コンマス秋山氏はデザイナーの奥様初瀬さんがデザインした「白装束のアラビアの王様」の衣装で登場して聴衆に大受けし、私のソロはすっかり霞んでしまいました。
71年10月の定期で新響は初めてマーラーを取り上げました。交響曲第1番です。9月末の鎌倉合宿で芥川先生が、「新響はついにマーラーを演奏できるまでになった!」と感慨深くおっしゃったのを未だに覚えています。
芥川先生は若手有望指揮者と見込んだコバケン(小林研一郎氏)にも新響の指揮を何度か委ねました(71,72年)。73年暮の『第九』は芥川先生が振る予定だったのですが直前に風邪で倒れ、急遽コバケンが暗譜で振ってくださいました。このコバケンが74年の第1回ブタペスト指揮者コンクールに出場することになり、新響が課題曲の練習台になったのですがその甲斐あって?彼が優勝したのはなつかしい思い出です。
73年8月のサマー・コンサートの『ピーターと狼』では芥川先生が浪花千栄子さんにお願いして名調子の語りを披露して頂きました。
74年8月のサマー・コンサートではチャイコフスキーの『白鳥の湖』抜粋を演奏しましたが、黒柳徹子さんが素晴らしい語りをしてくださったこと、そして『ナポリの踊り』でトランペット(Tp)の野崎一弘氏がこれまた素晴らしいソロを聴かせたことは未だ記憶に残っています。野崎氏の父上は昔N響のTp奏者で、彼はその後も数々の名演を新響演奏会で披露、私と同年代ですが現在もTpの首席を務めています。
当時、芥川先生は尊敬してやまないストラヴィンスキーの3部作(火の鳥・ペトルーシュカ・春の祭典)の一挙上演が夢で、73年『火の鳥』 74年『ペトルーシュカ』、75年3部作全曲と3年がかりの周到な準備で上演を成功させました。74年、75年と『ペトルーシュカ』のピアノ・ソロを2回名演し、ここ数年私の飲み仲間だった渡辺達氏が今年4月、62歳で急逝したのは悲しい出来事でした。
75年10月の定期は早稲田大学オケ出身で読売日本交響楽団(読響)ヴィオラ奏者を経て指揮者に転向した山岡重信先生を初めて迎え、ブルックナーの交響曲第4番等を振っていただきました(山岡先生は、私は渡米中で出演できませんでしたが、80年と81年にも振ってくださいました)。このコンサート直前の合宿では、合唱団「鯨」の紹介で鹿島神宮にある雇用促進事業団運営の「鹿島ハイツ」を初めて使いました。それ以前は軽井沢、岩井等の宿泊施設でしたが、「鹿島ハイツ」は都心からは少々遠いものの、音楽ホールがあって他の設備(大浴場・テニスコート・宴会場等々)も充実した理想的な合宿所で、その後2007年まで毎年のように年2回、2泊3日の合宿を行いました。合宿2日目夜の宴会では新入団員が何らかの芸を披露するのが慣例となり、楽器以外でも芸達者の団員が多いことに驚きました。何組かの団員家族が車で子供連れて来ており、幼かった我が家の長女と次女も何度か参加して芥川先生に可愛がっていただきました。
第220回ローテーション
| ベルク | ブルックナー | |
| フルート1st | 岡田(+Picc) | 松下 |
| 2nd | 丸尾(+Picc) | 兼子 |
| 1st (assi.) | - | 岡田 |
| 2nd (assi.) | - | 藤井 |
| 3rd | 兼子(+Picc) | - |
| 4th | 藤井(+Picc) | - |
| オーボエ1st | 岩城 | 堀内 |
| 2nd | 山口(奏) | 宮内 |
| 1st (assi.) | - | 亀井(優) |
| 2nd (assi.) | - | 桜井 |
| 3rd | 宮内 | - |
| 4th | 亀井(淳)(+C.I.) | - |
| クラリネット1st | 末村 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 末村 |
| 1st (assi.) | - | (*) |
| 2nd (assi.) | - | 石綿 |
| 3rd | 品田(+es) | - |
| 4th | (*) | - |
| Bass&es | (*) | - | ファゴット1st | 斉藤 | 田川 |
| 2nd | 進藤 | 浦 |
| 1st (assi.) | - | 斉藤 |
| 2nd (assi.) | - | 進藤 |
| 3rd | 田川 | |
| Cfg | 浦 | |
| ホルン1st | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 森 | 大内 |
| 3rd | 鵜飼 | 大原 |
| 4th | 市川 | 兪 |
| Assi | - | 山口、森 |
| 5th | 大原 | - |
| 6th | 大内 | - |
| トランペット1st | 倉田 | 野崎 |
| 2nd | 北村 | 小出 |
| 3rd | 小出 | 中川 |
| Assi | - | 北村、倉田 |
| 4th | 中川 | - |
| トロンボーン1st | 町谷 | 武田 |
| 2nd | 武田 | 志村 |
| 3rd | 小倉 | 岡田 |
| Assi | - | 町谷 |
| 4th | 岡田 | - |
| テューバ | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 皆月 | 桑形 |
| Assi | - | 中川 |
| 2nd | (*) | - |
| 3rd | 桑形 | - |
| パーカッション | 小太鼓,中太鼓,シンバル付き大太鼓/今尾 吊りシンバル/桜井 グロッケンシュピール、大太鼓/古関 合わせシンバル、小タムタム/桑形 大タムタム、ハンマー/中川 トライアングル、シンバル付き大太鼓/(*) シロフォン/(*) |
- |
| ハープ | (*) | - |
| 2nd | (*) | - |
| 1stヴァイオリン | 堀内(真)(小松) | 堀内(真)(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(笠川) | 大隈(田川) |
| ヴィオラ | 柳澤(石坂) | 田代(柳澤) |
| チェロ | 光野(柳部容) | 柳部容(光野) |
| コントラバス | 中野(植木) | 中野(植木) |
第220回演奏会のご案内
ブルックナーの「神聖なる」交響曲
ブルックナーはウィーンで活躍した後期ロマン派の作曲家です。1824年生まれでスメタナと同じ歳、ブラームスがちょっと年下で同じ年代です。00番(習作)、0番を含め11曲の交響曲を残しました。比較的演奏頻度が高いのが4、7、8、9番ですので、今回演奏する第5番はあまり馴染みのない方も多いかもしれませんが、むしろ第5番が一番好きというブルックナー愛好者が多いようです。
では、第5番がどこが違うのかというと、まず冒頭、4、7、8、9番は、「ブルックナー開始」と呼ばれる弦楽器の霧のようなトレモロが用いられますが、第5番は低弦のピチカートに乗って高弦のゆったりした音の「対話」から始まります。ブルックナー自身が「対位法的」交響曲と呼んでおり、特に第4楽章はベートーヴェンの第九の影響を受け、二重フーガ現れるなどしっかりとした構成のフーガとなっています。
ブルックナーは他人の意見に左右され改訂を繰り返したことが知られていますが、この曲は完成後初演されたのが16年後で、初演に病床で立ち会えず一度も聴いていないため改訂を行っておらず、よりブルックナーらしさが残っているのかもしれません。また、この曲が作られたのが職を失い収入が激減し精神的にも苦しい時期で、作曲で困難を乗り越えようとするブルックナーの意思を感じる部分も多いです。
そういった理由からか、私はこの曲を聴くとヨーロッパの壮大な大伽藍がイメージされます。ウィーンでいえばシュテファン寺院でしょうか。きっぱりと荘厳で神々しい、個人的な感想ですがブルックナーの交響曲11曲のなかで一番「カッコいい」のではないかと思います。
指揮者高関健はブルックナー愛好者であり。やはり第5番が一番お好きということでした。この第5番は構成が2管編成で小さい割に演奏時間が長大なためか、アマチュアでは演奏機会が少ないのですが、今回は木管楽器を倍管にして取り組み、大編成の壮大な響きをお楽しみいただけると思います。
ベルク唯一の管弦楽作品「3つの管弦楽曲」
ベルクは1885年生まれ、シェーンベルクの弟子で新ウィーン楽派の作曲家です。歌劇「ヴォツェック」「ルル」など歌のある作品が多く、この「3つの管弦楽曲」にも歌が感じられます。無調音楽ではありますが和声的な面もあり、マーラーの影響も受け非常にドラマチックで、ブルックナーの第5番以上にカッコいいかもしれません。巨大な編成と複雑な譜割りのためか、これまたあまり演奏機会のない曲ですが、いつかやってみたかった憧れの曲に挑戦します。難しい現代音楽という先入観を持たずに聴いていただきたい名曲です。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
コープランド:交響曲第3番
私はアーロン・コープランドの音楽が好きで、学生の頃から愛聴していたし、交響曲第3番もその中の1曲として、なんとなく聞いていた。
そういう意味では今回は個人的に念願かなって、コープランドの本格的作品の実演奏体験となるわけだが、私が個人的にコープランドの作品が好きなのは、やはり自分が打楽器奏者であって、打楽器の使い方が非常に効果的だということも大きな要因としてあるだろう。
新交響楽団の演奏会にいらしていただいているお客様は、非常にマニアックな楽曲にも精通された方から、普段あまりクラシック音楽を聴く習慣をお持ちでない方まで、非常に幅広くいらっしゃるので、果たしてアーロン・コープランドという作曲家に関してどの程度の予備知識をお持ちか見当がつかない。作品どころか、名前も聞いたことのないという方も少なからずいらっしゃるのではないか、と思われる。
コープランドは1990年まで生きていた人なので、同時代の作曲家と言ってよいと思う。

アーロン・コープランドは1900年、ニューヨークのブルックリンにユダヤ系ロシア移民の息子として生まれた。16歳のときにルービン・ゴールドマークに作曲を師事する。このルービン・ゴールドマークという人は、やや名前が知られているオーストリアの作曲家カール・ゴルトマルクの甥であると同時に、ニューヨークのナショナル音楽院に赴任してきて、あの超有名曲『新世界より』を残したアントニン・ドヴォルジャークの教えを受けている。
ジョージ・ガーシュウィンもルービン・ゴールドマークに師事していた時期があるので、そういう意味では2人とも、ゴールドマークを通じて、ドヴォルジャークの孫弟子ということになる。
1917年から21年までゴールドマークの教えを受けたあと、コープランドはパリに渡り、ナディア・ブーランジェ女史の弟子となった。
この時期のパリというのは、言うまでもなく、1913年にストラヴィンスキーの『春の祭典』が初演され、ラヴェルの代表作品が次々に世に出、ミヨーやプーランクといった「フランス6人組」が新風を巻き起こしている時期でもあった。音楽の分野だけでなく美術、舞台芸術、文学、あらゆる表現芸術が「沸騰していた街」であったと言っても良いだろう。
ブーランジェは有能な師であったばかりでなく、いつも授業が終わればフランス風サロンを開き、青年コープランドをストラヴィンスキーに引き合わせたりしている。コープランドは「時代のアイドル」ストラヴィンスキーと握手できたことに大変感激したようだ。
ブーランジェはもう一人重要な人物の家にコープランドを連れて行って引き合わせている。ロシアからパリに亡命してきていた指揮者セルゲイ・クーセヴィツキーである。
この初めての出会いの時には、このロシア人亡命指揮者が、この後のアメリカの音楽界にどれほど重要な役割を果たすのかは、双方とも知るよしもないのだが。
この時代のパリという街では、ロシア・バレエ団によって、『シェエラザード(1910年)』、『火の鳥(1910年)』、『ペトルーシュカ(1911年)』、『ダフニスとクロエ(1912年)』、『春の祭典(1913年)』、『三角帽子(1919年)』といったバレエの新作が続々と上演され、そしてコープランド自身、滞在中の1923年にはロシア・バレエ団とストラヴィンスキーによる『結婚』の初演に立ち会っている。
ブーランジェの教室もそういう当時のパリの熱狂とは無縁であるはずもなく、ブーランジェはコープランドにバレエ音楽の作曲を薦める。
ブーランジェは「アメリカ音楽は今やまさに離陸寸前」だと見ていたようなのだが、ではいったい「アメリカ音楽」とはいったいどういうものなのか?-という問題に明確な答えを示せる者は、アメリカにもヨーロッパにも誰もいなかった。
パリに渡って図らずも自分探しの結果、やはり「アメリカ音楽」を書かねばならない、という結論にぶち当たるところは、ガーシュウィンにも通じるのだが、祖国を離れてはじめて自分のアイデンティティがわかるというのは、この時代や、ガーシュウィン、コープランドの2人に限ったことではなく、現代でも誰でも同じことなのだろう。
1924年にコープランドがパリ留学を終え、「アメリカ音楽」を書こうと意気に燃えて帰国したニューヨークは、数ヶ月前にガーシュウィンの『ラプソディ・イン・ブルー』が初演されて、空前の熱狂となっていたのも不思議な巡り合わせだ。
「アメリカの音楽」を書くべきという問題は、ずっと前にコープランドの師のゴールドマークのさらに師である、ドヴォルジャーク大先生がアメリカの黒人音楽や、アメリカの民謡をもっと研究しなさいよ、と言っていたわけなのだが、自分の国の文化の価値にはなかなか気付けないところは、当時のアメリカだけでなく、我が国も含めいつの時代でも同じ問題なのだろう。新交響楽団とご縁の深かった伊福部昭先生が「作品は民族の特殊性を通過して初めてインターナショナルになり得る」と繰り返し述べられていたことや、リヒャルト・シュトラウスにあこがれて、そっくりな曲を書いていたバルトークがコダーイに誘われてハンガリーの民謡採集の旅に出て、あのバルトーク独自の作風の境地に至る経緯にも通じるものがある。
出世作となった『エル・サロン・メヒコ(1936年)』、それに続く『ビリー・ザ・キッド(1938年)』、『ロデオ(1942年)』、『アパラチアの春(1944年)』などのバレエ音楽がアーロン・コープランドの代表作となっていく。
パリで直面した「バレエ音楽」、アメリカ的な音楽とは?-という問いが、これらの代表作群に繋がっていることは否定できない。
そして、パリでの出会いと言えば、その後、ボストン交響楽団の指揮者となっていたセルゲイ・クーセヴィツキーの存在も大きい。コープランドを始めとするアメリカ現代音楽の擁護者としても大きな功績を残すのだが、1942年にクーセヴィツキー財団を設立し、多くの作曲家に新作を委嘱する。
新交響楽団が第208回演奏会で曽我大介氏と取り上げたバルトークの『管弦楽のための協奏曲』もクーセヴィツキー財団の委嘱作品だが、このコープランドの交響曲第3番もクーセヴィツキー財団からの委嘱で書かれた作品で、セルゲイ・クーセヴィツキー、ボストン交響楽団によって初演されている。
コープランド、バーンスタイン、クーセヴィツキーの写真(タングルウッドにて、1941年)
完成したのは1946年だが、委嘱を受けたのは大戦下の1944年であり、委嘱の際に作品の趣旨や傾向に注文があったわけではないのだけれども、時節柄、戦時下のアメリカの国威発揚音楽になっているのは否定できない。
直接的に民謡が引用されたりしているわけではないけれども、前記の代表作のバレエ音楽群でコープランドが身につけたアメリカ的要素が随所に発揮され、第4楽章の冒頭部分に有名な『市民のためのファンファーレ』をほとんどそのまま組み入れてしまっていることもあるなど、「アメリカ的」な交響曲と呼ばざるを得ない。そもそも1943年に書かれた『市民のためのファンファーレ』そのものが、戦時体制下の国威発揚が産み出した作品なのである。
限られた素材を4楽章形式の「本格的」交響曲に仕立てあげるのに、若干無理をして引き伸ばしている感があるのは確かで、冗長に感じられる部分もあるかもしれないが、「アメリカの交響曲」に挑戦し苦闘する作曲家の意気込みを買っていただきたい。
コープランドの音楽に今日始めて触れられて、興味を持たれた方は、ぜひとも文中に触れたバレエ音楽の諸作品も聞いてみていただきたいのである。
結局、アメリカ的な音楽って何?という問いに結論めいたものを出すとすれば、コープランド的な要素こそが「アメリカ音楽」を感じさせる部分はあるのではないかと思われる。レナード・バーンスタインやジョン・ウィリアムスなどに引き継がれた、いかにもアメリカ風な響きというのはコープランドによって編み出されたものなのかもしれない。
第1楽章 Molto moderato
木管楽器による素朴な主題に始まり、オーケストラ全体によって繰り返され、その後まもなく『市民のためのファンファーレ』に通じるような金管楽器のファンファーレによってクライマックスとなる。冒頭の木管楽器の主題が戻って来て静かになっていく。
第2楽章 Allegro molto
スケルツォ的な位置づけの楽章で、激しく駆け回る早い部分とトリオ的に挟まれるゆっくりした部分からなる。
第3楽章 Andantino quasi allegretto
緩徐楽章だが、中間部に舞曲的な部分を挟み、また瞑想的な雰囲気に戻っていき、そのまま切れ目なく第4楽章に繋がる。
第4楽章 Molto deliberato (Fanfare) - Allegro risoluto
第3楽章の静けさの中から『市民のためのファンファーレ』をフルートが静かに奏し始め、単独作品でもある『市民のためのファンファーレ』をほぼそのまま導入部に用いたソナタ形式のフィナーレとなっている。
勇壮な金管楽器のファンファーレ、忙しく駆け回り跳躍する弦楽器や木管楽器(超絶的に難しい!)、印象的に使われる多くの打楽器群などをお楽しみいただければと思う。
初 演: 1948年10月18日、ボストン
セルゲイ・クーセヴィツキー指揮、ボストン交響楽団
楽器編成:フルート3(3番は2番ピッコロ持ち替え)、ピッコロ、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、小クラリネット、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット4、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、中太鼓、シンバル、ウッドブロック、タムタム、ラチェット(がらがら)、むち、シロフォン、グロッケンシュピール、鐘、クラベス、アンヴィル(金床)、ハープ2、チェレスタ、ピアノ、弦五部
ガーシュウィン:ラプソディ・イン・ブルー
■はじめに
芸術の秋、クラシックのコンサートを聴きに本日この会場へ足をお運びいただいた方々へ謹んで申し上げる。残念ながら、本日お聴きいただくこの『ラプソディ・イン・ブルー』は、いわゆる
それなのに、今でも繰り返し演奏され、世界中の人々に楽しまれている。むしろそのような曲だからこそ、他のオーケストラ作品には無い魅力を持っている。バーンスタインも、前述のようなコメントを残しているにも関わらず、弾き振りで見事な演奏を残している。これも、この曲に魅力を感じていればこそであろう。

■ガーシュウィンの生い立ち
ジョージ・ガーシュウィン(1898-1937)は、ユダヤ系ロシア移民の息子として生まれた。ガーシュウィンという姓は、父親のモーリスがアメリカに移民した際に、もともとの“ゲルショヴィッツ”をアメリカ風に変えたものであった。子どもの頃は、喧嘩に明け暮れる不良少年であった。しかし、ガーシュウィンが14歳の時、兄アイラのために親が中古のピアノを買ったことから、彼の音楽人生が始まる。世界に名だたる作曲家と比べ、かなり遅いスタートであった。
音楽と本気で向かい合うようになり、彼の中に眠っていた才能は一気に開花した。15歳の時には職業ピアニストとして仕事をするようになる。さらに、自ら作曲をしたいという意欲が高まり、作曲家としての活動も開始。21歳の時には『スワニー』を発表してヒットさせるなど、ポピュラーソング・ブロードウェイミュージカル作曲家としての成功と、元来の社交的な性格も手伝って、一躍スターダムにのし上がった
■ラプソディ・イン・ブルーの誕生
1924年1月3日、兄アイラと共にビリヤードに興じていたガーシュウィンは、驚愕の事実を新聞記事で知る。その内容は「2月12日、ポール・ホワイトマン楽団が、『近代音楽の実験』と題して演奏会を開催。アメリカ音楽とは何かを問いかけるその演奏会では、ガーシュウィン氏による新作のジャズ・ピアノ協奏曲を発表」というものだった。ガーシュウィンは知らなかった。
ポール・ホワイトマンは、自らの楽団を率いて興行を行っていた人物で、以前よりガーシュウィンと付き合いがあった。その中で彼の才能を見出していたのである。
慌ててホワイトマンに確認すると、「いちいち君に相談していたら、同じような企画をたてているライバルに出し抜かれるから」との返事。しかし、大々的に宣伝されたことで、彼は否応無しに曲を書かざるを得なくなった。
それまでガーシュウィンは管弦楽曲を書いた経験が無かった。当時ホワイトマン楽団のアレンジャーであり、組曲『グランドキャニオン』を後年作曲して有名となるファーディ・グローフェがジャズ・オーケストラへの編曲を手伝い、わずか3週間で曲は完成した。ただし、ガーシュウィン自身が弾くピアノ・パートは譜面が出来上がらず、本番当日アドリブで弾くことになった。また、有名な冒頭のクラリネットのソロも、練習の合間に楽団のクラリネット奏者がふざけて演奏したものを採用した。
この演奏会は全部で24曲の演奏が予定され、『ラプソディ・イン・ブルー』は最後から2曲目であった。長時間にわたる演奏に、もはや聴くことすら苦痛になってきた聴衆は、その奇抜な冒頭に度肝を抜かれ、やがて熱狂に変わった。心配された独奏ピアノは、ガーシュウィンの圧倒的な即興演奏により喝采を浴びた。
かくして、「近代音楽の実験」におけるこの曲の初演は大成功に終わる。稀代の名ヴァイオリニストであるヤッシャ・ハイフェッツや、ロシアから亡命してきたセルゲイ・ラフマニノフなどクラシック界の著名人が審査員として招かれ、この曲は大いに賞賛された。他のどこの国のものでもない「アメリカの音楽」としての『ラプソディ・イン・ブルー』誕生の瞬間であった。
■ガーシュウィンの「アメリカ音楽」
「人種のるつぼ」と化した20世紀初頭のアメリカでは、音楽も多様であった。ヨーロッパからのクラシック音楽の流れだけでなく、黒人の間で広まっていた「ラグタイム」「ブルース」など、当時彼の身の周りにあった音楽を、新進気鋭の流行作曲家ガーシュウィンはどんどん吸収し、作曲に活かした。
ここで注目すべきは、この曲の下地になっているのは、「都会的で落ち着いた店で流れるお洒落なジャズ」ではないということである。巷には「ジャズとクラシックの融合」というこの曲の教科書的な紹介文を安易に理解し、ブランド物のスーツでパリッと決めたような上品で洗練された演奏がまかり通っている。そのような『ラプソディ・イン・ブルー』の演奏は、 ―良し悪しはともかく― ガーシュウィンの意図したものとは異なるのである。
この曲が作られた1920年代のアメリカは、様々な人種、民族、神聖なものと世俗的なもの、成功者と落ちぶれた者などが混沌として存在していた。猥雑な中にもパワーあふれる時代であった。けたたましいほど強く刻まれるリズムが特徴的な「ラグタイム」の持つ力強さや「ブルース」の持つ寂寥感は、そんな時代の反映であろう。
当初ガーシュウィンは、曲名を『アメリカン・ラプソディ』と考えていた。そんな彼が「アメリカ音楽」としてこの曲で表現したかったものは、20世紀初頭のアメリカの猥雑な雰囲気、怒号や嬌声、それらが混然一体となった社会そのものだったのではないだろうか。
■さいごに
ユダヤ人であるガーシュウィンは、アメリカン・ドリームの裏にある人種や民族の違いについて、より一層強く感じていたであろう。だからこそ、黒人発祥の音楽を取り上げ、当時の音楽界の重鎮達に認めさせたかったのかも知れない。
しかし、そうでありながらも、この曲に悲壮感は無い。むしろ明るく、時に軽快で時に穏やかな、幸せに満ちた音楽である。
ここに、彼からの「色々辛いこともあるけど、腐らないで前向きに頑張ろうじゃないか。な?」といったような、気さくなエールがあるような気がしてならない。肩肘張らずに、ひとつこいつの軽口に付き合ってやろう。そんな気持ちで聴いていただければ幸いである。
初 演:1924年2月12日、ニューヨーク
楽器編成:
(初演時)独奏ピアノ、木管楽器3(サクソフォーン、クラリネット、オーボエ、ファゴットを持ち替え)、ホルン2、トランペット2、トロンボーン2、テューバ、打楽器、チェレスタ、ピアノ(独奏とは別)、ヴァイオリン8、バンジョー
※ジャズ・オーケストラのために作曲されており、現在のオーケストラ編成とは異なる
(現在の編成)
独奏ピアノ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、サクソフォーン3(アルト2、テナー)、ホルン3、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、グロッケンシュピール、タムタム、小太鼓、シンバル、トライアングル、弦五部、バンジョー
※グローフェがガーシュイウィンの死後、現在のオーケストラ編成に合うように編曲し直したもの。本日はバンジョーを除きこの編成で演奏
参考文献
『ラプソディ・イン・ブルー ガーシュインとジャズ精神の行方』末延芳晴著(平凡社)
ガーシュウィン:キューバ序曲
■ガーシュウィンにとってキューバとは?
皆さんはキューバという国にどのような印象をお持ちですか? バリバリの社会主義国家、カストロ、チェ・ゲバラ、野球、カリブ海。私が思い浮かべられるのはそんな程度ですが、ガーシュウィンにとってキューバとはどんな国だったのでしょうか。
アメリカが禁酒法時代の1932年2月、ガーシュウィンはキューバで休暇を過ごしました。1930年代、首都ハバナから北西140キロにあるリゾート地バラデロにはアメリカ人富裕層の別荘が多く建てられました。1962年10月のキューバ危機以降、アメリカとキューバには国交がありませんが、現在もメキシコやカナダを経由してキューバへ行きバカンスを過ごすアメリカ人は多いようです。
『キューバ序曲』の4年前、1928年に発表された『パリのアメリカ人』も、ガーシュウィンの代表作の一つです。『パリのアメリカ人』では、アメリカの旋律を用いて、パリの情景や、パリを訪れたアメリカ人(ガーシュウィン)の心情が描写されていますが、対して『キューバ序曲』では、キューバの旋律とリズムを用いており、キューバそのものを描写したような雰囲気に仕上がっています。どちらも名曲ですが、『パリのアメリカ人』では、アメリカとフランスとの違いをまざまざと見せつけられて戸惑うガーシュウィンが、『キューバ序曲』では、キューバ滞在を思いっきり楽しんでいるガーシュウィンが目に浮かびます。
■ルンバ
ガーシュウィンはキューバでボンゴやクラベスなどの打楽器類を入手して持ち帰り、それらの打楽器類とキューバのリズムを用いてこの『キューバ序曲』を作曲しました。当初は『ルンバ』という曲名で発表し、のちに『キューバ序曲』に改題しました。

キューバ序曲の自筆譜(表紙)
『ルンバ』と言っても最近人気の自走式掃除機のことではありません。もっともあの掃除機の名前はルーム(Room)と音楽のルンバ(Rumba)を組み合わせた造語だそうで、全く関係無いわけではありません。ガーシュウィンは『キューバ序曲』でルンバのリズムをオーケストラに奏でさせることに成功しました。ガーシュウィンが用いたルンバは、奴隷としてアフリカからキューバへ連れてこられた人達の間で発生した音楽で、一方、現在の社交ダンスでのルンバは、そのキューバ発祥のルンバが他国の文化と混ざり合って洗練され発展した音楽であり、両者は雰囲気が少し異なります。
■管弦楽の可能性を広げた『キューバ序曲』
この『キューバ序曲』をあまりご存知でない方は、曲が始まってすぐ、びっくりするかもしれません。「今日は新響の演奏会だよね? 私、間違って違う団体の演奏会の会場に来てしまったのかしら」。いえいえ、ご安心ください。今日は新響の演奏会ですよ。たまにはこんな曲も演奏するのです。およそ“クラシック音楽”とは言い難いような雰囲気の曲ですが、これでもれっきとした管弦楽曲なのです。使用している特殊楽器といえば、打楽器のボンゴ、クラベス、マラカス、ゴード(ギロという解釈もありますが本日はシェケレという楽器を使用します)だけで、それ以外はベートーヴェンやマーラーの曲で使用するのと同じ楽器です。
ガーシュウィンは500曲もの歌曲(歌曲というよりも歌謡曲という表現のほうが適しているかもしれません)を書き残しています。管弦楽曲はわずか7曲です。“ポピュラー音楽とクラシック音楽の両方のジャンルで活躍した”とよく評されますが、そもそもポピュラー音楽とクラシック音楽の境界線がどこにあるのかについては、人によって解釈がまちまちです。『キューバ序曲』も、楽器編成で分類すれば管弦楽曲に分類されますが、使用しているリズムは明らかにポピュラー音楽のものです。どちらのジャンルか判断しにくいですが、明らかに管弦楽曲であることは確かです。普段、ベートーヴェンやマーラーといった“管弦楽曲のスタンダード”を楽しむ我々に、ガーシュウィンは「たまにはこんな曲もいいんじゃない?」という素敵な提案をしてくれました。ガーシュウィンの功績は、そこにあるのではないでしょうか。
曲は3つの部分とコーダから成り、軽快なリズムで始まり、続いて、夜の静けさのような美しい中間部、そして再び軽快なリズム、最後に、全曲を通して活躍するキューバの打楽器類が一層盛り上げて、華やかに終わります。
キューバ序曲で使用する特殊楽器。手前から時計回りにボンゴ、マラカス、クラベス、シェケレ
初 演:1932年8月、ニューヨーク、ルイゾーン・スタジアム
楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シロフォン、グロッケンシュピール、小太鼓、大太鼓、シンバル、クラベス、ゴード(シェケレ)、マラカス、ボンゴ、弦五部
参考文献
『大作曲家 ガーシュイン』ハンスペーター・クレルマン著 渋谷和邦訳(音楽之友社)
『ラプソディ・イン・ブルー』に臨んで
維持会員の皆様、日頃ご支援賜りありがとうございます。クラリネットパートの高梨と申します。団員歴は2000年の7月演奏会のシーズンより所属し、途中1年程ブランクありの12年目です。新響としてはまだまだ若い方というのが恐ろしい。他のアマチュアオーケストラですと下手すれば長老です。
そんな私、今回の演奏会で配られるプログラムの曲目解説も執筆しております。それを知ってなお、『維持会ニュース』担当者は私に「『維持会ニュース』にも何か書きなさい。さもないと(以下略)」と言ってきましたので、書かせていただきます。ちなみに、『維持会ニュース』担当者は、フルート首席の松下さんと言います。皆様が演奏会にいらっしゃる時に、維持会受付に必ずいる背の高い男性です。フルートよりも、同じような色をした別の鋭利な鉄製の何かを持っていそうな雰囲気のあの方です。月夜の晩ばかりではありません。頼まれたら書かないわけにはいかない理由、お分かりいただけますでしょうか(笑)
クラリネット奏者にとって『ラプソディ・イン・ブルー』を吹けるのは、千載一遇のまたとない嬉しい機会だと言っても過言ではありません。
まずは、とにもかくにも冒頭のおいしいソロ!しかも、この『ラプソディ・イン・ブルー』という曲のこのソロは、他の管弦楽曲のものと違い、ある程度の即興性が許容されております。つまり、譜面どおりに吹く必要が無いのです。これほど嬉しいことはありません。いつも譜面どおりに吹けずに指揮者に怒られているわけですから。逆に言うと、そこに奏者のセンスが問われるので、ある意味恐ろしい課題を与えられているのですが。
さらに、有名な割に演奏する機会にめったに巡り合うことができません。それは、ドイツ、フランス、ロシア、イギリスで生まれた、いわゆる王道のクラシック作品ではないから、と考えられます。確かに、マーラーやブルックナーの交響曲のような長大な作品と比べ、気軽に聴くことができる内容です。演奏会で取り上げようとしても、他の曲とのバランスとか、そもそも内容がシンフォニック・オーケストラの演奏会に相応しくない等といった理由で候補に挙がらないのでしょう。
以上のような理由で、この曲を吹くことができるのは、クラ吹きにとってまたとない、ありがたいことなのです。
しかしながら、不肖私、この『ラプソディ・イン・ブルー』を最初に聴いた時の感想は、「なんだこの退屈な曲!」というものでございました。音楽史で説明されているような「ジャズとクラシックの融合」ではなく、「ジャズにもクラシックにもなりきれない」ように聴こえました。当時中学2,3年生だった私が聴いたのが、名盤の誉れ高いバーンスタイン/コロンビア交響楽団のCDです。バーンスタイン自身の弾き振りによる、非常に洗練された爽やかな演奏です。
先日、「初演時のラプソディ・イン・ブルーの再現演奏」を聴きました。そこにあったのは、たたみかけるような強奏、暑苦しいまでの甘いメロディーでした。特に冒頭のクラリネットのソロは、ある程度譜面通りではあるもののチンドン屋をもっと崩したような演奏で、度肝を抜かれました。バーンスタインの演奏を都会の整然としたオフィス、初演時のそれは田舎の寄り合いの宴会だと言えば、雰囲気はお分かりでしょうか。とにかく人間臭い、ともすれば下品スレスレの音楽でした。
我々が現在聴くこの曲の演奏は、後年『グランド・キャニオン』を作曲するファーデ・グローフェがガーシュウィンの死後、シンフォニック・オーケストラ用に編曲したものです。新響が今回の演奏会で演奏するのはこの版です。しかし、ガーシュウィンが初演当時書いたのは、ジャズ・オーケストラのためのもので、編成に歴然とした違いがあるのです。グローフェの編曲の腕は大したもので、原曲の粗野で猥雑な雰囲気は綺麗に覆い隠され、後に「シンフォニック・ジャズ」と言われるに相応しいクラシックコンサートピースになっています。
『ラプソディ・イン・ブルー~ガーシュインとジャズ精神の行方~』という本で、長年アメリカ文化を研究していた末延芳春さんという方が、ガーシュウィンはこの曲で、自分の身の回りにあった黒人音楽、ユダヤ系である自分のルーツのユダヤ音楽を盛り込んでいた、と書いています。そうすることで、彼自身の考える「アメリカ」のアイデンティティーを表現したかったに違いない、と考えるのは行き過ぎでしょうか。
黒人音楽、ユダヤ音楽と書きましたが、具体的には、黒人音楽とは「ラグタイム」「ブルース」、ユダヤ音楽とは「クレツマー」のことを指します。このうち、クレツマーは馴染みが無いと思います。私も知りませんでしたが聴いてみてびっくりしました。基本的な編成にクラリネットが入っていて音楽リードするのですが、これがモーツァルトやブラームス等をして数々の傑作を生みださせたあのクラリネットなのか!と思うくらい個性的、いやもっと言ってしまえば滅茶苦茶な奏法なのです。例えて言うなら、弦楽器や打楽器の伴奏の前で家畜が終始いなないている、そんな感じです。
初演の再現演奏、クレツマーと考え合わせると、もうこれは真面目に吹いている場合じゃないぞと思うようになりました。飲んで酔っ払ったオッサンがご機嫌に一節唸る、そんな感じが合うのではないかと。
初演時、練習の合間に楽団のクラリネット奏者が、下から上へ駆け上がる音階をしゃっくり上げるようにつなげて(グリッサンドと言います)吹いてふざけていたところ、それを聴いたガーシュウィンが気に入って採用になり、この曲のクラリネットの譜面にはグリッサンドと書かれるようになったというエピソードがあります。ジャズの即興演奏にも通じますが、要するに「面白ければ、何でもあり」という精神ですね。
バーンスタインの演奏に退屈してしまった自分は、つまるところこういった面白い要素の臭いをかぎ取りながら、それでも突っ込んだ表現をせず、常識的な演奏にまとめたそのスタイルに違和感を覚えたのだと思います。そして、ある意味非常識な演奏に触れ、そう!こっちだよこっち!という芽が開花してしまったようです。
今回の演奏会では、私はそんな姿勢でこの曲に取り組もうと思っております。「ジャズとクラシックの融合」といった仰々しい肩書は脇に置き、ふざけたソロでこの曲を開始してみて、皆さんのご機嫌を伺おうと思います。クラシック作品の鑑賞ではなく、お笑い芸人のネタ見せが始まった、そんな感じでお聴きいただければ幸いです。それがお気に召さない方は、最初の1分程度我慢していただければ、独奏ピアノとして今回お迎えした小原孝さんの素晴らしい演奏をご堪能いただけますのでご安心を。
第219回ローテーション
| キューバ序曲 | ラプソディ・イン・ブルー | 交響曲第三番 | |
| フルート1st | 岡田 | 吉田 | 松下 |
| 2nd | 藤井 | 新井 | 吉田 |
| 3rd | 丸尾(+picc) | - | 兼子(+picc) |
| Picc | - | - | 岡田 |
| オーボエ1st | 岩城 | 山口 | 亀井(淳) |
| 2nd | 山口 | 堀内 | 亀井(優) |
| C.A. | 桜井 | - | 宮内 |
| クラリネット1st | 高梨 | 高梨 | 末村 |
| 2nd | 石綿 | 石綿 | 進藤(秋) |
| Es.Cl. | - | - | 品田 |
| B.Cl. | 大藪 | 大藪 | 大藪 |
| Alto Sax | - | 進藤(秋) | - |
| Alto Sax2 | - | (*) | - |
| Tenor Sax | - | (*) | - |
| ファゴット1st | 齊藤 | 齊藤 | 浦 |
| 2nd | 田川 | 進藤(牧) | 田川 |
| C.Fg | 浦 | - | 進藤(牧) |
| ホルン1st | 森 | 山口 | 箭田(Assi森) |
| 2nd | 兪 | 市川 | 大原 |
| 3rd | 山口 | 森 | 鵜飼 |
| 4th | 市川 | - | 兪 |
| トランペット1st | 小出 | 倉田 | 野崎(Assi倉田) |
| 2nd | 中川 | 北村 | 北村 |
| 3rd | 青木 | 中川 | 小出 |
| 4th | - | - | 青木 |
| トロンボーン1st | 志村 | 志村 | 武田(Assi志村) |
| 2nd | 小倉 | 小倉 | 町谷 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 浦辺 | 中川 | 古関 |
| パーカッション | ボンゴ/今尾 クラベス/古関 シェケレ/皆月 マラカス/中川 シンバル/桜井 小太鼓,大太鼓(一部) ウッドブロック/桑形 木琴,グロッケンシュピール 大太鼓/(*) |
タムタム,シンバル/田中 小太鼓,トライアングル/皆月 大太鼓/今尾 シンバル,グロッケンシュピール/古関 |
シンバル/桜井 中太鼓,ガラガラ/中川 タムタム,ムチ/田中 木琴,テューブラーベル/皆月 小太鼓,グロッケンシュピール トライアングル,クラベス/今尾 大太鼓,ウッドブロック アンヴィル/桑形 |
| ピアノ | - | - | 藤井 |
| チェレスタ | - | - | (*) |
| ハープ1 | - | - | (*) |
| ハープ2 | - | - | (*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(大隈) | 堀内(大隈) | 堀内(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(佐藤真) | 小松(佐藤真) | 小松(田川暁) |
| ヴィオラ | 石坂(柳澤) | 石坂(柳澤) | 柳澤(田代) |
| チェロ | 柳部容(光野) | 柳部容(光野) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 植木(中野) | 植木(中野) | 中野(植木) |
(*)はエキストラ
第219回演奏会のご案内
アメリカ音楽を作り上げた作曲家
ガーシュウィンとコープランドの2人は、ともに「アメリカ音楽を作り上げた作曲家」と称されています。黒人文化に由来する音楽のジャズやヨーロッパの伝統的な民謡が元となったカントリーミュージックなど、アメリカ独特の音楽を取り入れたのが、クラシック分野における「アメリカ音楽」でしょう。
ガーシュウィンは1898年、コープランドは1900年、ともにユダヤ系ロシア移民の息子として生まれ、ピアノを本格的に始めたのも同じ14歳でした。
ジャズとクラシックのクロスオーバー
ガーシュウィンは15歳で楽譜店のデモ演奏をするピアニストになり、ミュージカル作曲家となります。1924年にジャズバンドを率いるホワイトマンにピアノ・コンチェルトを依頼され「アメリカ音楽とは何か?」と題された実験コンサートで大成功を収めました。これが有名な「ラプソディ・イン・ブルー」です。組曲「グランドキャニオン」で知られる当時ホワイトマン楽団専属アレンジャーだったグローフェによって編曲されました。その後独学でオーケストレーションを学びます。38歳の若さで亡くなったので、管弦楽曲は少ないですが、多くのミュージカルと歌曲を残しました。
ブルーは「憂鬱な」といった意味ですが、ジャズのルーツであるブルースの語源なので、「ジャズ的狂詩曲」というところでしょうか。クラリネットのグリッサンドで始まるワクワク楽しい曲で、多くのCMや「のだめカンタービレ」のエンディングに使われ一度は耳にしているはずです。ピアノ独奏には「ねこふんじゃった」のアレンジ演奏で知られ、NHK教育テレビへの出演など多方面で活躍している小原孝を迎えます。
古き良きアメリカを感じる交響曲
コープランドは15歳で作曲家を志し、21歳でフランスに留学しました。パリではジャズの要素を取り入れて作曲していましたが、1924年の帰国後はアメリカ民謡を研究してアメリカ的な音楽を模索し、「アパラチアの春」、「ビリーザキッド」といった明るく親しみやすい曲を書きました。1946年に作曲された交響曲第3番は、それらの集大成ともいえるでしょう。その後は前衛音楽への道に進み90歳まで長生きをしましたが、これが最後の交響曲となりました。
抽象的な交響曲として書かれていますが、「市民のためのファンファーレ」が登場したり、ジャズや民謡が顔を出す愛国心溢れる曲です。ドラマ「大草原の小さな家」の情景が浮かんで来るのは、私だけではないかもしれません。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
マーラー:交響曲第1番
■マーラーのこと
グスタフ・マーラーは、1860年7月7日、ボヘミアのカリシュトという小さな村(プラハとウィーンの中間でプラハ寄り。現チェコのカリシュチェ)で、ユダヤ人商人の家に、12人兄弟(14-15人いたらしいが幼少で死亡)の2番目として生まれた。2歳の頃にはすでに数百の民謡を覚えていたなど非凡な音楽的才能を示すとともに幼少期から音楽教育を受けた。民謡を多く聴いた環境は、本日の交響曲第1番だけでなく、マーラーの全曲にわたり大きな影響を及ぼしている。
1883年ドイツのカッセル王立歌劇場指揮者となって名声を高め始めた翌年、第1番の作曲に着手、1888年に完成した直後の28歳でブダペスト王立歌劇場監督、翌年自らの指揮で初演を行う。この年には両親の死など不幸にも遭う。また、ウェーバーの孫の夫人マリオン・ウェーバーと恋仲となるが、その後人間関係、自身の健康状態にも問題を抱えていく。まさにこれから踏み出すマーラーの輝かしい光と影の生涯を暗示する。青春の情熱、恋と哀愁、ブルーノ・ワルターは、ゲーテの“若きウェルテルの悩み”になぞらえて、第1番をマーラーの“ウェルテル”とも言ったようだ。本日のお客様も、現在或いは過去の自分の青春と照らし合わせて、曲をお感じにな
るのも良いであろう。
36歳の時、ウィーン進出のためかカトリックへの改宗。41歳、美貌で多くの男性芸術家をとりこにしたアルマと結婚(19の「歳の差婚」)。後述する秀逸の交響曲群を残して、「私の時代が来る」と将来を自ら予見するが、フロイトの精神分析を受けた後、1911年50歳で世を去る。

ハンブルク第2稿初演の頃のマーラー、32歳
■マーラーの交響曲と第1番の位置づけ
第1番は、全交響曲の中で比較すると、型破りな中にも明快で特異な存在とも言える。だからなのか、マーラー指揮者と言われるようなマエストロの中には、第1番だけはあまり演奏しないという方も何人かいらっしゃるようだ。しかし、「青春の交響曲」とは言え、完成度は高く(実は初めての交響曲でなく、第1番以前に4曲ほど書いていたらしい)、古典的な伝統を守ろうとしながらも、先鋭的・個性的な要素が多く取り入れられた。
マーラーの交響曲を5つのグループに分けてみよう。
①第1番:同時期の「さすらう若人の歌」と密接に関係
②第2番、第3番、第4番:「少年の魔法の角笛」と関連する3部作、声楽付き
③第5番、第6番、第7番:「リュッケルトの詩による5つの歌曲」「亡き子をしのぶ歌」と結びつき、リュッケルト交響曲とも呼ばれる。声楽なし
④第8番、大地の歌:カンタータ風の第8番、リートを同化させた大地の歌
⑤第9番、第10番(未完):死を意識した最晩年の器楽曲
ここで、器楽のみと声楽付きが交互になっていることは、非常に興味深く、マーラーのオーケストレーションの巧みさと声楽・歌曲を愛することによる周期的な考えの変遷にも見える。
今年の4月に新響が演奏した「大地の歌」は、こうやって見ると第1番とは対極的な交響曲なのかも知れない。4月から未ださめやらぬ飯守マーラー・ワールドの中で、他方の極を体験した直後、この青春の交響曲を演奏できることはこの上ない贅沢である。
■「巨人」はマーラー自身が削除、最初は5楽章の交響詩
標題が「巨人」となっているが、正式にはマーラー自身によって削除されている。ただ、一般にはこの標題でニックネーム的に呼ばれる。「巨人」は、ドイツの作家ジャン・パウルの長編小説の題名に由来する。主人公の青年が様々な経験を経て人格が形成され、最後は王座につくというようなストーリーであるが、天才主義とか巨人主義に反対する思想が織り込まれている。決して巨人主義礼賛ではなく、人生に目覚めた20代の青年の抒情味あふれた感情を持ち、血気盛んに人生に突入する姿を表したものか。しかしマーラーにとっては標題として十分ではなく、聴衆の誤解も招くと考えた。
また、最初は4楽章の交響曲でなく、5楽章の交響詩だった。1893年のハンブルクでの上演時につぎの標題を付けている。
第1部 青春の日々により ― 花、実、いばら
1. 終わりなき春
2. 春の章
3. 順風に帆を上げて
第2部 人生喜劇
4. 座礁(カロ風の葬送行進曲)
5. 地獄から天国へ ― 深く傷ついた心の突然の爆発
これらの標題は、「巨人」を含めて、1896年、ベルリンでの演奏時にすべて破棄された。
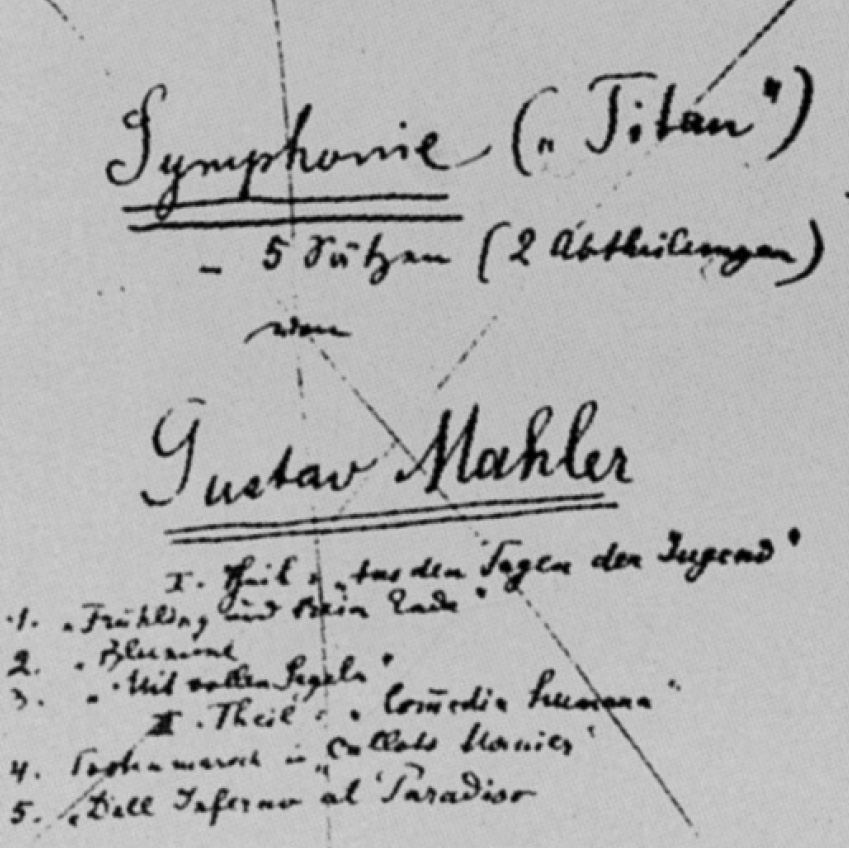
自筆譜の表紙。標題「巨人」をマーラー自身が削除。
■スコアの版数
初 稿:1889年ブダペストで初演。5楽章版。現存しない。
第2稿:第2、第3、第5楽章改訂。1893年ハンブルクで初演。
第3稿:花の章を除く4楽章版。1896年ベルリンで初演、'99年刊行。
決定稿:第3稿ベース、1906年。
全集版:第3稿ベース、1967年、エルヴィン・ラッツ校訂。
新校訂版:全集版の改訂、1992年、カール・ハインツ・フュッスル監修。
第3稿以降が4楽章の交響曲だが、指揮者マーラーの常で、演奏するたびに曲の随所を部分的に変え続けた書き込みが多く存在し、改訂されていった。「新校訂版」で、マーラーの指示が不完全である個所や、明らかな印刷ミス、もしくは自筆譜との矛盾など細部を整理されたが、大きな波紋を呼んだ点もある。従来コントラバスのソロであった第3楽章冒頭の主題は「ソロとは1人でなく、グループのこと」という注記が付された。つまり、コントラバス・パート全員でということ。新校訂版が世に出て20年、様々な議論もあったかも知れないが、未だにコント
ラバス・パートによる演奏例は少ないようだ。

第1楽章 ニ長調 4/4拍子
緩やかに重々しく、自然の音のように
静かに6オクターブ(7つ周波数)の「ラ」のフラジオレット(弦楽器の倍音技法で透明感がある)が重なった持続音で始まる。まるで、霧のかかった深い森にさまよい込んだよう(チューニングと同じ「ラ」だが、現実から一瞬で幻想の世界へ)。その後、「ラ」から「ミ」へ4度下降の非常に特徴的な動機の提示。そして、この4度下降は郭公
かっこうの鳴き声を模したものである。郭公は普通3度下降で鳴くように言われたり歌われたりするのだが、ボヘミアの郭公は4度であったのだろうか。実はこの4度動機は、第1楽章のみならず全曲の主要な動機や主題を生成していく。さらに、本日の前半の曲目であるベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲ニ長調でも大変重要な4度の動きと一貫性があり、演奏会全体として意義深いプログラムとなっている。遠くからファンファーレや、ホルンの牧歌的な響きが聞こえる。低弦の半音階的に上行する動機から、4度動機が繰り返された後、チェロの第1主題。
第1主題も4度動機で開始、「さすらう若者の歌」の第2曲「朝の野原を歩けば」に基づく。思わず歌いたくなるような若々しく弾む旋律。第2主題はイ長調で木管が奏し、第1主題の対位旋律に対応する。展開部に入ると序奏の雰囲気に戻り次第に沈み込むようになるが、ホルンの斉奏をきっかけに、第1主題と第2主題。やがて半音階的に上昇する動機が不安を高めるように繰り返されフィナーレを予告、トランペットのファンファーレが鳴りクライマックスをむかえる。
再現部では、各主題が短く省略された形で急速に展開されコーダ的に進む。ティンパニの4度動機の連打と共に突然終結する。
第2楽章 イ長調 3/4拍子
力強く動いて、けれどもあまり速くならぬよう
4度の「ラ-ミ」を基本とした低音弦による力強いオスティナートから始まるレントラー風舞曲。歌曲集「若き日の歌」の〈ハンスとグレーテ〉(草原の5月の踊り)が使われている。しばらくして、木管楽器のベル・アップ奏法で主題が客席へ強くアピールされる。トリオでは、テンポを少し落とし、憧れに満ちた甘美な旋律がヴァイオリンと木管楽器で交互に奏され、ホルンに続いて最初の舞曲が再現、最強奏で終わる。

初演後の雑誌に載った風刺マンガ。
第3楽章 ニ短調 4/4拍子
儀式のような荘重さと威厳を以って、決してひきずらないように
ティンパニの4度下降の刻みに続いて、弱音器付き独奏コントラバスが哀愁を帯びた旋律を奏し、その後カノン風に展開していく。カロ風の葬送行進曲と言われるが、モーリッツ・フォン・シュヴィントのエッチング「狩人の葬列」に影響されたとされている。旋律は、ボヘミア民謡を思わせる「マルチン君(兄さん)」(フランス民謡では「フレール・ジャック」、英語では「アーユースリーピング」、日本では「グーチョキパーでなにつくろう」で超有名)を
短調にした、極めてグロテスクかつパロディックな楽章の冒頭である。初演時は、不評極まりなかったらしい。突然、辻音楽師の奏でるおどけた旋律がオーボエ等に登場したり、軍隊のリズムが遠くから聞こえてきたり。
ハープとチェロのアルペジオをきっかけに中間部は「さすらう若人の歌」の第4曲「彼女の青い目が」が転用されており、弱音器付きヴァイオリンが4度上昇から優しく歌う。私はどうしても「赤とんぼ」(山田耕筰)を思い出してしまう。日本の懐かしい故郷の風景は、ボヘミアのそれと似ているのであろうか?
再現部へと続き、やがて低音楽器群と若干の打楽器だけが残って静かに消え入るように終わり、アタッカで次楽章に続く。
第4楽章 ヘ短調 2/2拍子
嵐のように激しく揺れ動いて
静寂を破るシンバル、ティンパニの乱打、激しくうねる弦楽器群に乗って、木管を中心とした管楽器群がエネルギッシュにテーマを奏す。嵐が止み静けさが訪れると長調に転じ、第1ヴァイオリンによる夢想的な美しい主題。金管楽器によるファンファーレ風の動機(楽章の後半に繰り返し登場し、クライマックスへ導入される)。やがて夢の世界へ、第1楽章冒頭に出てきた森の風景に戻り、かっこうの鳴き声、遠くのアルペンホルンなど回想。そして、クライマックスではミリタリー・マーチの曲調に乗って、第1楽章ののどかな主題が勝利のコラールに変
わり、オーケストラの最強奏となる(スコアでは、この箇所はホルン奏者全員7名に立奏の指示がある。アバドがベルリン・フィルに就任することが決まった直後のリハーサルで、「立つんですか?マーラーの時代ならともかく。」とのエピソードも話題になったが、やはり視覚的効果を含めてこの曲のハイライトであろう)。テンポは上がり、熱狂が頂点を極めて全曲が終わる。合唱を伴うニ長調のベートーヴェン第九のエンディングが最高なら、器楽のみによるニ長調交響曲のエンディングとしては、これが最高にかっこいい。
初 演:1889年11月20日、ブダペスト、マーラー自身の指揮(5楽章版)
楽器編成:フルート4(3、4番はピッコロ持ち替え)、オーボエ4(3番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット3(3番は小クラリネットおよびバスクラリネット持ち替え)、小クラリネット2、ファゴット3(3番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン7、トランペット5、トロンボーン4、テューバ、ティンパニ(2人)、大太鼓、シンバル付大太鼓、シンバル(合わせ・吊り)、トライアングル、タムタム、ハープ、弦五部
参考文献
『作曲家別名曲解説ライブラリー・マーラー』より
マーラーの交響曲 門馬直美著(音楽之友社)
『グスタフ・マーラー ―現代音楽への道―』柴田南雄著(岩波新書)
『マーラー 私の時代が来た』桜井健二著(二見書房)
『マーラーの交響曲』金子健志著(音楽之友社)
『小澤征爾さんと、音楽について話をする』小澤征爾、村上春樹著(新潮社)
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲
■絶望から飛躍へ
「想像を絶する」ということばを我々は安易に口にするが、ベートーヴェンが自身の耳に異常を感じ、快復の見込みがないと知った時の絶望ほど、想像を絶するものはないのではないだろうか。
1802年、ベートーヴェンは31歳になっていた。ボンからウィーンにやってきて十年の歳月がたち、もはや音楽界・社交界で知らないものはいない。数々の演奏会の成功、相次ぐ楽譜の出版依頼、音楽好きな貴族たちとの交遊。そんな自分がまさか難聴になるなんて。「もっと大きな声で話してくれ」、「(他の人に聴こえる)笛の音が聴こえない」など言えるわけがない。音楽家としてこれほどの屈辱、責苦があろうか!

若き日のベートーヴェン
人一倍自尊心が強く繊細な心の持ち主であるベートーヴェンは、10月、ついに自ら人生を絶とうと遺書を書く。「ハイリゲンシュタットの遺書」である。
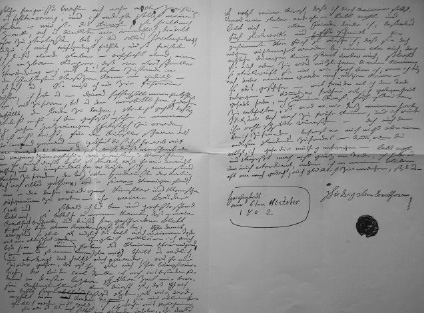
ベートーヴェン自筆の遺書
この特殊な文書に定型があるとするならば、ベートーヴェンがしたためた遺書はどうみても長大だ(しかもあろうことか四日後に追伸まで書いている)。辛く苦しい状況を切々と嘆き、医者の無能さを罵り、周囲の人間にいかに誤解を受けているかを訴える。そして極めつけは、「こんな出来事に絶望し、もう一歩で命を絶つところであった― 芸術、これのみが私を思いとどまらせたのだ。ああ、課せられた使命、そのすべてを終えてからでなければ私は死ねそうにない。」
もはや「遺書」とは言えまい(事実、発見されたのはベートーヴェンの死後)。判読しづらい筆跡で綿々と綴られた「手紙」は、絶望の先にあるものが「生への決別」ではなく、「生への執念」を示している。快癒という希望の断念。そうした絶望の極限状態がもたらしたものは、類まれな才能と己の使命感を強く自覚することであった。
聴覚のハンディは外との関わりを狭めてしまったが、内なる創作世界は限りなく広がっていった。死の淵から戻ってきた彼は、意欲的に新境地を切り開いていく。このあとの10年ほどをロマン・ロランは「傑作の森」と呼んだが、まさしくベートーヴェンのひとつの頂点である。交響曲第3番『英雄』、ピアノ・ソナタ第23番『熱情』をはじめとする超名曲の数々は枚挙にいとまがない。ことに1806年は交響曲第4番、ピアノ協奏曲第4番、弦楽四重奏曲第7番~第9番(ラズモフスキー第1番~第3番)、そしてヴァイオリン協奏曲を世に送り出した。
■協奏曲を超えた協奏曲
さて、このヴァイオリン協奏曲、アン・デア・ウィーン劇場コンサートマスターのクレメントが初演し演奏会としては成功したが、「脈略がなく支離滅裂」「品のない個所が何度も反復」「関連なく積み重ねられた大量の楽想」などと新聞で評された。酷い言われようである。事実それ以来めったに再演されることがなかったという(ちなみに後年名手ヨーゼフ・ヨアヒムが演奏し再び注目されるようになった)。
しかし、あながち批評が的外れではないことも確かである。互いに関連はあるものの、いくつもの楽想の存在、繰り返し出てくる音型。それまでの協奏曲にはない交響曲のような形態で、独奏ヴァイオリンさえも管弦楽とともに扱われている。名人芸を披露することだけではなく、ひとつのパートとして、作品の構造や内面に深く関与することが求められている。交響曲と協奏曲を結びつけた、全く新しい協奏曲といえよう。
むろん当時の人々には、協奏曲は華やかなヴィルトゥオーゾを単純に楽しむもの、ということが共通認識としてあったはずで、とするとこれは「何か違うぞ」と感じたことだろう。
独奏者にとっては、個人の演奏技術はもちろんのこと、全体を把握し深く理解することが演奏上最も重要であり不可欠である。技術と意識の両輪が揃わねばならず、覚悟のいる曲であることは間違いない。
<聴きどころ>
演奏時間が45分前後の大曲である。第1楽章ですでに20分以上を要するが、ソナタ形式であり、第2楽章は変奏曲、第3楽章はロンドと、古典的な形式を踏襲している。覚悟のいる大曲だからと言って、聴くほうは構える必要はまったくなく、むしろ全体的には、素直な明るさに満ちている。
第1楽章はティンパニがD(レ)を四分音符で5回連打して始まる(譜例1)。なんて斬新な始まり方だろう!これが全体を通して最も重要な要素である。形を変えていろいろな楽器に何度も出てくるから、それを発見するだけでも面白い。
まず伸びやかで美しいニ長調の第一主題をオーボエが提示する(譜例2)。すると、早くも先ほどの譜例1の変形が、第1ヴァイオリンから始まって弦楽器に次々現れる。続いて木管楽器に上昇音階の楽想(譜例3)が出てくると、空気が暖まり静まると見せかけ、突然、これまでと対照的な性格の音楽が変ロ長調で鳴り響く(譜例4)。この意外性!200年前の聴衆の大半はここで置いていかれたかもしれない。
しかし、すぐに第二主題の明るい旋律がやさしくふりそそぐ(譜例5)。安心していると急に短調の響きになり、ヴィオラとチェロの三連符がはじまると音楽が動き出す。新しい形だ。実は後で独奏と弦楽器とで同様の関係が出てくるのだ。ここはその予告編。
やがて第一・第二主題に親近感のある堂々たる楽想(譜例6)が第1ヴァイオリンに現れ低弦部がこれに応える。ここでは第2ヴァイオリンとヴィオラに注目。16分音符をせっせと刻む伴奏だが、これが音楽に推進力を与え生き生きとさせる重要な働きを担う。これぞベートーヴェンだ。こうしてようやく前奏が終わる。

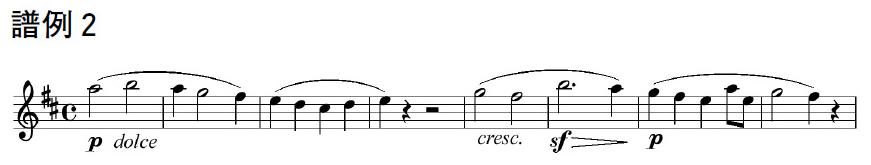

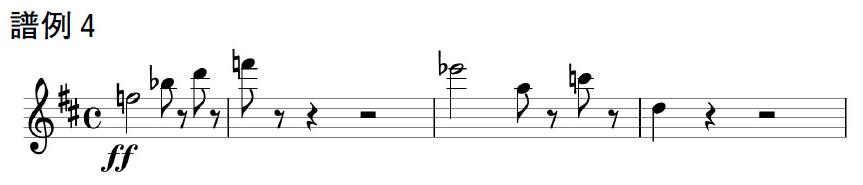


いよいよお待ちかねヴァイオリン・ソロの登場である。カデンツァ的な導入部分を経て、ヴァイオリンならではの高音域で主題がお披露目される。やがてオーケストラに第二主題が繰り返し現れ、ソロはそれの変奏で美しく絡む。提示部の終わりが近づくと譜例1のリズムが効果的に繰り返し用いられ、ソロの聴かせどころを導き出して前半を締めくくる。
前奏さながらの立派な間奏をはさみ、再びソロが入ると、今度はたちまち風向きが変わり哀愁を帯びてくる。物悲しげな表情のヴァイオリンに、ファゴットがねだるような問いかけ、譜例1の音型で弦楽器群がうなずくかのようなやりとり。どの楽器も最大限にその特徴が生かされていて素晴らしい。そして静かにたゆたうソロ、背後では譜例1のリズムがオスティナートの如く静かに続く。トランペットとティンパニがそれを引き継ぐと、夜明けの近いこと
を予感させる。
再現部では久しぶりにオーケストラに第一主題がffで帰ってきた。燦々と輝く太陽に喜びを爆発させる。しばらくはニ長調主体で進んでいく。やがてソロが弾き切ると、突然変ロ長調に変わって驚くが、すぐにカデンツァが導入される。
ところで、ベートーヴェンはカデンツァを書いていない(但し自身で編曲したピアノ協奏曲にはカデンツァがある)。現在ではクライスラーや前述のヨアヒムによるものが一般的だが、アウアー、フレッシュ、サン=サーンス、イザイ、ブゾーニ、シュニトケ等多数存在する。ピアノ用をヴァイオリンに編曲したり、まったくのオリジナルを演奏することもある。ソリストの腕の最大の見せ場であると同時に、どのカデンツァを弾くのか興味は尽きない。
カデンツァが終わると、ソロが昔を懐かしむように第二主題を奏するが、それも束の間、晴れやかに終わる。
第2楽章は不思議な曲だ。目立った転調もなく、テーマを繰り返しているのに、飽きないどころか一回ごとに思いが募る。
弦楽器による主題は目を閉じて祈りを捧げるかのよう(譜例7)。

第1変奏ではホルンとクラリネット、第2変奏ではファゴットが旋律を受けもつ。管弦楽による間奏が終わると、慈しむようなヴァイオリン・ソロが始まる。伴奏は最小限の和音、ピチカート。ソロの楽譜には全曲でこの箇所にだけcantabile(カンタービレ)とある。簡素な音符は研ぎ澄まされたようでいて、冷たさなどどこにもない。深い愛情があふれていて胸が熱くなる。終わりが近づいて初めて転調すると、夢から引き戻され第3楽章へ突入する。
一転して快活で楽しい雰囲気に。小気味良いこの主題は狩猟音楽からきているという(譜例8)。

しばらく続くソロとオーケストラとの掛け合いがわくわくさせる。すると急展開。何やらメランコリックなメロディーが。想定外の流れに完全に引き込まれてしまう。ソロはすぐにオブリガートになってしまい主役はファゴットに。独特の音色が悔しいけれどぴったりである。
ロンドの主題が戻り再現部。カデンツァはコンパクトながらヴァイオリンの多彩な表現力を存分に発揮する。長いトリルがカデンツァの終わりを告げると、低弦が冒頭主題の短縮形で切り込んでくる。調性をどんどん変えながら進みコーダへ。最後は駆け抜けるように爽快に幕を閉じる。
■終わりに
遺書を書いた8日後に、ベートーヴェンは二つの変奏曲を出版するため、ブライトコプフ・ウント・ヘルテル社宛てに文書を添えている。そこでは、「まったく新しい様式でそれぞれ完全に異なる手法で書いた」ということを、ことさらに強調していたという。その一方で、後日バッハの作品集を送付された礼とともに「大切に研究していくつもりです。」と述べ、続きがあればまた送ってほしいと熱心に依頼している。
目新しさをのみを追い求めるだけではなく、地道な努力の積み重ねの上にある「新しさ」だからこそ、200年後の現在でも「新しさ」が色褪せないのではないだろうか。
初 演:1806年12月23日 フランツ・クレメント独奏、アン・デア・ウィーン劇場
楽器編成:独奏ヴァイオリン、フルート、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦五部
参考文献
『ベートーヴェンの生涯』青木やよひ著(平凡社)
Hedwig M. von Asow, Ludwig van Beethoven
Heiligenstädter Testament Faksimile, Verlag Doblinger, 1957(今井顕訳)
『鳴り響く思想 現代のベートーヴェン像』
大宮眞琴、谷村晃、前田昭雄 監修(東京書籍)より、
「第8章 ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲をめぐって」
ヘルムート・マーリンク著、横原千史訳
『ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲』[総譜](日本楽譜出版)
第218回ローテーション
| ベートーヴェン | マーラー | |
| フルート1st | 丸尾 | 兼子 |
| 2nd | - | 新井 |
| 3rd | - | 松下(+Picc) |
| 4th | - | 藤井(+Picc) |
| オーボエ1st | 宮内 | 亀井(淳) |
| 2nd | 亀井(優) | 山口(奏) |
| 3rd | - | 岩城(+C.A.) |
| 4th | - | 桜井 |
| クラリネット1st | 品田 | 高梨 |
| 2nd | 石綿 | 大藪 |
| 3rd | - | 末村(A&C&es) |
| 4th | - | 進藤(es) |
| Bass&es | - | 品田 | ファゴット1st | 田川 | 長谷川 |
| 2nd | 斉藤 | 進藤 |
| 3rd | - | 浦(+CFg) |
| ホルン1st | 鵜飼 | 箭田 |
| 2nd | 兪 | 山口 |
| 3rd | - | 大原 |
| 4th | - | 市川 |
| 5th | - | 森 |
| 6th | - | 鵜飼 |
| 7th | - | 兪 |
| トランペット1st | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 中川 | 青木 |
| 3rd | - | 倉田 |
| 4th | - | 北村 |
| 5th | - | 中川 |
| トロンボーン1st | - | 武田 |
| 2nd | - | 志村 |
| 3rd | - | (*) |
| 4th | - | 小倉 |
| テューバ | - | 土田 |
| ティンパニ | 皆月 | 桑形 |
| ティンパニ | - | 浦辺 |
| パーカッション | - | 大太鼓&大太鼓付シンバル/今尾 シンバル/桜井 タムタム/田中 トライアングル&吊りシンバル/古関 |
| ハープ | - | (*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(真)(小松) | 堀内(真)(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(福永) | 大隈(佐藤(真)) |
| ヴィオラ | 柳澤(田代) | 柳澤(石坂) |
| チェロ | 柳部(容)(光野) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 中野(加賀) | 中野(加賀) |
隔たりを越える覚悟
―― ベートーヴェンとマーラーにおける回想と考察 ――
■ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲の思い出
ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲と聞いて真っ先に思い浮かべる人がいる。
ゾンヤ・シュタルケ。旧東ドイツ・ハレのマルティン・ルター大学に在籍、学生オーケストラで演奏していた頃、演奏会にてこの曲のソリストを務められた。旧西ドイツのハノーファーに生まれ、クリスティアン・テツラフに師事。2002年バッハ国際コンクール入賞後、現在はマーラー室内管弦楽団、ルツェルン祝祭管弦楽団などで活動している。
生まれ育った場所が違うことが原因ではないと思うが、いずれにせよ、当時ゾンヤと楽員の間には、何か心の隔たりがあったと思う。第2楽章、大きく息を吸い込みテンポルバートをかけるゾンヤ。その気迫に圧倒される団員もいれば、呼吸音にクスクスと笑う団員もいた。それでもゾンヤは躊躇しない。自分には「これが自分の音楽だ」と彼女が訴えかけているように感じた。
そんな時、私は指揮者のニコラウスの口癖を思い出していた‐”man muss immer ein Risiko auf sich nehmen!”(常にリスクに対する覚悟を持て!)。彼はファビオ・ルイージの弟子で隣町ライプツィヒのメンデルスゾーン音楽院から来ていた。今はチューリンゲンの歌劇場で指揮をしている。「感情的すぎる」「彼の演説は聴く気にならない」楽員たちの間では色々言われていた。でも、私はニコラウスの音楽も、ゾンヤの音楽も好きだった。だから自分にこう言い聞かせた。「ゾンヤが示した覚悟には、私たちも同じく覚悟を持って応えなければならない」と。
■マーラー:初めての交響曲
指揮者としてのマーラーとオーケストラとの間にも、このような心の隔たりがあったのは有名な話である。すなわち、過酷な指導で自身の芸術を追求するマーラーに戸惑う楽員という構図である。
交響曲第一番の作曲時期、マーラーはアルトゥール・ニキシュの元でライプツィヒ市立歌劇場の第2指揮者を務めていた。作曲と指揮活動、言わば作品の創造とそれを具現化する場所。その両立に苦心しつつもマーラーは交響曲第一番の作曲に没頭する。そのことで、彼は指揮者としての職務をおろそかにし、楽員や音楽監督との衝突を招く事になる。マーラーの熱心な指導、オーケストラへの愛情とある意味矛盾していたことが、余計に大きな反発を引き起こしたのかもしれない。
1888年3月、2部構成の交響詩という形でこの曲は完成に至る。その後、マーラーはライプツィヒを離れ、ハンガリー国立歌劇場にて自身初の音楽監督に就任する。初演は1889年11月、マーラー指揮の下、同歌劇場管弦楽団(ブタペスト・フィルハーモニー管弦楽団)により行われた。それまでの間、マーラーの元に次々と家族の悲しい知らせが届く。父ベルンハルトが1889年2月、妹レオポルディーネが同年9月、そして、母マリーが10月に他界したのである。凄まじいプレッシャーのなかでの初めての交響曲作曲は、大きな決意に満ちたものであったに違いない。それを裏付けるように、彼は完成後も、『巨人』という副題を始め、細かい編曲から楽章構成、楽器編成に至るまで、幾度も改訂を重ねた。結局、現在の全4楽章構成の上演は1896年ベルリンにて、ライプツィヒでの完成から実に7年後のことである。
マーラーの決意とチャレンジ精神は、交響曲第一番の斬新さに表れているように思う。そして、その斬新さ故に、この曲が評価されるには初演後も長い歳月が必要であった。その運命を象徴するかのようなその斬新なコンセプトについて次に述べたい。
■音と言語のグローバル化
交響曲第一番の冒頭、マーラーは”Wie ein Naturlaut”(自然の音のように)と記している。今回はこの”Naturlaut”という言葉に着目したい。この単語はNatur(自然)とLaut(音)からなる複合名詞である。
「音」という単語について、ドイツ語ではTonとLautの二つの単語がある。違いとしては、Tonは人の声や楽器の音等、特定の箇所から入ってきている響きを持った音を指すが、Lautの場合、雑踏等、周りから溢れてくる様々な音を指す。英語でいう”too”と組み合わせて、”zu laut”と形容詞にすれば「うるさい」という意味になる。私の経験上「自然の音」というと”Naturlaut”より”Naturton”を連想する。それでもあえてLautを使ったのは、この周りから溢れ出てくるニュアンスがほしかったのではないだろうか。いわば、自然の音ではなく、音が溢れる自然そのものをオーケストラの楽器で表現することで、新しい表現・芸術のジャンルとしたかったのかもしれない。例えば、第一楽章の導入部は朝の目覚めを表しているが、エドヴァルド.グリーグの組曲「ペールギュント」の”Morgenstimmung”と比較すると、ある意味アプローチの仕方が真逆と言える。
従来の枠に囚われない豊かな発想力は言語の分野でも発揮された。彼がハンガリー国立歌劇場にて試みた、現地言語(ハンガリー語)でのドイツ・オペラ上演である。これは、地元の人々のオペラに対する関心を呼び起こし、歌劇場の収益も上がった。こうして、マーラーの指揮活動は、プロレタリアートの娯楽としての歌劇場の興業に大いに貢献したのだった。なお、彼は早くも2年半で、今度はハンガリーを去り、ハンブルク市立歌劇場へと活動拠点を移すが、主な原因は、ハンガリーでの反マーラー派の総監督就任であったと言われる。当地での功績としても、音楽史の観点からしても、マーラーのハンガリーでの活動は大きな意義のあるものだった。
マーラーがハンブルク市立歌劇場への招聘を受け入れた条件の一つが、作曲のための十分な余暇だった。演奏者・歌手の人材にも恵まれ、マーラーは充実した音楽作りに励む。結果として、モーツァルトのドン・ジョヴァンニはブラームスに、ワーグナーのジークフリートはハンス・フォン・ビューローに絶賛され、これがマーラーの立場を音楽界の高みへと押し上げていくのである。
音においても言語においても、自身の作品においても他者の作品においても、マーラーは既成概念の枠に囚われず、その枠組みを広げることに全力を尽くした。そこには、ユダヤ人という人種の面でも、個人の性格の面でも、既存の文化・習慣への反感が少なからずあったであろう。しかし、最も根幹には、周囲への感情よりは、自身への想いがあったのではないかと思う。つまり「既成の枠を越えなければならない」という決然とした使命感である。
斬新な試みで歌劇場の発展に貢献したマーラーは楽員たちに覚悟を持って迎えられたという。マーラーだけでなく、楽員たちもまた「隔たりを越える」ために大きな覚悟と勇気が必要だった。双方の覚悟があって初めて実現したマーラーの音楽活動であったとも言えるのではないだろうか。
■あとがき
”Rak! du hast wirklich gute Arbeit gehabt!”(ラク!お前本当に良い仕事したな!)
終演後、興奮気味のニコラウスにこう言われた時、初めて味わう喜びがあった。自分も覚悟を決めて良かったと。それから7年の歳月が流れた。思い出の欠片は残りつつも、その喜びを忘れかけている、無意味に生きる自分がいたように思う。そんなある日、ハレの大学オーケストラが来日公演をすることになり、昔の仲間から誘いを頂いた。第218回演奏会の翌々日24日、場所は宮城県仙台市。東日本大震災の犠牲者追悼に、ヘンデルの生まれ故郷ハレにちなんでメサイアを演奏する。
震災と福島第一原発事故から約一年半。欧州に限らず外国では、原発事故について日本人以上に深刻に捉えている部分もある。このような状況下で来日公演に踏み切るには相当な覚悟が必要だったに違いない。昨年から来日予定がずれ込んできたことがそれを物語っている。参加しようと残った楽員も一握りだった。
それでも、「相手が示した覚悟には、同じく覚悟を持って応えなければならない」。
その決意を胸に仙台へ赴く。

マルティン・ルター大学アカデミーオーケストラ演奏会
ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲他
指揮: ニコラウス・ミュラー
独奏: ゾンヤ・シュタルケ(ヴァイオリン)
(現マーラー室内管弦楽団、ルツェルン祝祭管弦楽団)
ザクセン・アンハルト州、ハレ市内、同大学記念講堂Löwengebäude(獅子の館)にて
○参考文献
「反ユダヤ主義 ‐世紀末ウィーンの政治と文化‐」村山雅人著/講談社(1995年)
「マーラー 私の時代が来た」桜井健二著/二見書房(1987年)
「マーラー その交響的宇宙」岩下眞好著/福井鉄也/音楽之友社(1995年)
タムタムスタンド
第217回演奏会のマーラー「大地の歌」(指揮飯守泰次郎先生)でタムタムを担当した田中 司です。今回、維持会の会計でタムタムスタンドを購入致しましたので、維持会ニュースにお礼を兼ねて「タムタムスタンド」に関しての一文を書くことに致しました。
「タムタムスタンド」の前に、まず「タムタム」という楽器について簡単に説明致します。今回使用したのは、中国製、直径38インチ(95cm)の物ですが、青銅製の丸い巨大な盆状で、縁にあいている2つ穴に紐を通し、専用のスタンドに吊るし、重くて柔らかい大きな頭のバチ(マレット)でたたきます。底力のある余韻の長い、低いお寺の鐘のような音がします。名称は、オーケストラの中では「タムタム」、楽譜にもそう書かれているのですが、「ゴング」または「ドラ」の方が一般的です。東方起源のこの打楽器は、今ではオーケストラになくてはならない仲間ですが、ヨーロッパでのオーケストラへの登場は、フランスの作曲家フランソワ・ジョセフ・ゴセック(1734年〜1829年)による「ミラボーの葬送用音楽」(1791年)からです。
それでは、いよいよ「タムタムスタンド」ですが、今まで使っていたのは、芥川先生の時代に購入したものです。勿論その時にタムタムも一緒に購入しました。それは、今回使用した物より一回り小さいのですが、その後新響では、タムタムを使う曲を数多く演奏するようになり、サイズの大きな物も購入し、曲によって使い分けています。今回は、大きなサイズの方を使いました。どちらのタムタムも楽器自体に問題はないのですが、古いスタンドは、多少支障をきたしています。まず、サイズの大きい方に対してはスタンドが小さい。それから、スタンドは脚と枠で出来ているのですが、そのジョイントのネジが壊れてしまってグラグラしている。の二点です。そこで今回、維持会にお願いしてスタンドを新調し、実に気持ち良くたたく事が出来ました。感謝しております。
そこで「スタンド談義」です。どんな発音体でも、多くの場合、スタンドは、主役の本体と同じ位重要でおまけに大げさです。一番良い例が鐘楼です。鐘という発音体のスタンドは鐘楼という立派な建物なのです。オーケストラのティンパニもバロック時代に今のスタイルが確立されたと思われますが、その後楽器としては大変な進化を遂げました。しかし、その進化はもっぱらスタンドの部分です。発音体である釜と皮の部分は昔のままです。それに比べるとタムタムのスタンドはあまり進化していないようですが、新しいスタンドを使ってみての感想は「たたきやすい」です。原因は、「固定度」が高くなっているからだと思います。「大地の歌」では、タムタムが43発出てきますが、その中でフォルテは2発だけで、残りは全てピアノからピアニシッシモです。フォルテよりもこの小さな音に「固定度」が極めて重要だったのです。
この状況は、鋸で木を切る場合と似ています。フォルテに相当する丸太や薪を切る時には、良く切れる鋸さえあれば、適当に足で押さえてゴリゴリ切れます。しかし小さな木を切る場合にはそうは行きません。しっかりした「スタンド」が必要になります。「万力」で小さな木を固定して良く切れる鋸で切らないとうまく切れません。
「大地の歌」では、タムタムを静止させて、同じコンディションでたたくと良い音が出るという事を改めて発見しました。蛇足となりますが、そのたたき方にも「鐘楼」が良いヒントとなりました。マレットをしっかり握り、その握った手と下腕を鐘楼の鐘を打つ丸太、上腕を丸太を吊るす綱と思って、たたくというより振ってぶつけるのです。うまく行くと、マーラーがこの曲に望んだと思われる、深山幽谷から湧き出た様な、東洋的な響きがオーケストラを包むのです。43発の内、フォルテを除く41発はそういう音を狙ってたたきました。新しいスタンドのおかげで、修行僧の様な気持ちで、「大地の歌」のタムタムに集中する事ができました。
『巨人』とは?
…さて、ちょっと困ったことになっている。あろうことか、この維持会ニュースの原稿を用意することとなってしまった。7月の演奏会で取り上げるマーラーをネタに、何でもお好きなようにとの依頼(指令)であったが、どうしたものか。自由に書くと言っても、何しろ音楽史・音楽理論の方面にかけては新響随一の不良団員(ヘタレ)である自覚がある、この私。中々筆が進みそうにない。
マーラーといえば、前回演奏会の『大地の歌』に引き続き、2回連続で取り上げることとなる。演奏するのは、交響曲第1番。通称は、『巨人』。いわゆる、名曲である。そこで、『巨人』ネタで何か書けないものかと考えてみた。まず思い浮かんだのが、私のこよなく愛する某在京プロ野球球団。明日の試合の予告先発は…って、そっちじゃない。そう、肝心のマーラーの『巨人』のことについて、実はほとんどわかっていなかったことに、今更ながら気付いてしまった。
とはいえ、これもいい機会だと、不良団員なりに心を入れ替え勉強してみることとした。以下、リサーチした内容を基に、細かい点で誤りもあろうかとは思うが、「巨人」について考えてみようと思う。
■1:『巨人』というタイトル
そもそも、このマーラーの交響曲第1番は、なぜ『巨人』と呼ばれているのだろうか。マーラーがJR水道橋駅徒歩5分の某野球場で、私のようにビール片手にメガホン振り回し、絶叫、時に熱狂していたわけでないことだけは、確かであるが。
このタイトルの由来は、実は小説の題名である。ドイツ・ロマン派の作家ジャン・パウルが、1800年から1803年にかけて執筆した長編教養小説『巨人』を、マーラーは青年時代から愛読していたとされている。そこで、本作品を作曲するにあたり、『巨人』というタイトル及び各楽章の標題(詳細は後述)を、小説の内容にあやかって名付けたというわけである。なお、余談であるが、本作品はドイツ語だと、”Titan”。英語でも、同様。ちょっと期待していたが、残念ながらGiantではないらしい。
もっとも、この『巨人』というタイトル、実は後にマーラー本人の手で削除されてしまっている。意外ではあるが、一般に広く呼ばれている『巨人』とは、あくまで本作品の通称にすぎないのである。 マーラーにとって曲のタイトルと各楽章の標題は、本作品を一般の人々に理解しやすくするための「道しるべ」的な位置づけに留まるものであった。すなわち、これらの趣旨は、本作品に文学的な意味をもたせることではなく、楽章相互間、楽章と全体との関係を理解してもらうための、手がかりを与えることにすぎなかったのである。タイトル等が独り歩きしてしまうことで、かえって聴衆の誤解を引き起こし、本作品を正当に理解する妨げになることを後に懸念し、マーラーはタイトル等を全て除去してしまったというわけである。
とはいえ、元の小説の内容がほとんど忘れ去れている現代にまで、「巨人」の通称は広く語り継がれている。文学的な意図こそなかったことがはっきりしているものの、小説「巨人」と本作品とは、本当に全く関わりがないものであったのだろうか。
小説『巨人』の内容は、天才的で奔放な主人公が恋愛その他の人生経験を積みながら、円満な性格になっていくまでの経緯を描いたものであったらしい。私なりに勝手に解釈するに、現代でいうところの、青春小説のようなテイストであったのだろう。そして、「青春」こそが、本作品に関わるキーワードであるように思えるのである。
本作品の作曲当時、マーラーはまだ20代後半の(おそらくは)血気盛んかつ悩み多き若者であった。20代といえば、俗な言い方をすれば、社会の荒波に否が応でももまれ始める、誰もが体験する大変かつ多感な時期。若者マーラーとしても、自分の今後の生き方に悩みつつも、周囲をとりまく環境や世界に全力でぶつかっていく、そんな情熱に満ち溢れていたのではないだろうか。また、情熱的な青年の悩みといえば、やはり恋愛沙汰(恋愛、そして失恋…)に他ならない。実際、マーラーが友人にあてた手紙には、本作品が恋愛事件を直接の動機として作曲されたものである旨、記されている。
こういった、いわば「若さ故」の感情を原動力として、マーラーは本作品を作曲するに至ったのではないかと、私は考える。こういった作曲の背景に関わる部分において、小説『巨人』の内容と本作品とは、リンクしてくるところがあるように思えるのである。
■2:マーラーという巨人
ここまで、まずは本作品の『巨人』たる由来を見てきたところであるが、そういえばマーラーは、クラシック音楽界の「巨人」と、よく称されている。写真を見る限り、メガネをかけた神経質そうなおじさんくらいの印象しか私にはなかった、このマーラーという大作曲家。一体どのような経歴の人物であったのか、次に検討してみたい。
1860年にボヘミアのカリシュテという村の、比較的裕福な家庭にて生誕したマーラーは、幼少の頃から非凡な音楽の才能を示していたらしい。現代でいうところの、音楽の英才教育的なものも、どうやら受けていたようである。その甲斐と本人の才能もあって、1875年(15歳)にはウィーンに上京し、学友協会付属の音楽院に入学。ピアノ、作曲、指揮等を学び、3年間で優秀な成績を修めて修了した。18歳で大学院修了とは、現代の感覚ではちょっと信じがたいところである。
その後の音楽家としての活動については、指揮と作曲が2つの大きな柱となっている。有名な話であるかもしれないが、マーラーは作曲家としてのみならず、当時は指揮者として各地で名を馳せる存在であった。音楽院卒業後の1880年に、歌劇場の指揮者の地位に就いたのを皮切りに、ヨーロッパ各地のオーケストラを指揮し、着実に名声を上げていった。1897年にはウィーンの宮廷歌劇場の指揮者に就任し、以降ニューヨークのメトロポリタン歌劇場に移るまでの10年間、ウィーンのオペラに黄金時代をもたらしたとされている。
このような指揮者としての華々しい経歴を重ねていった一方で、マーラーは作曲家としても精力的に腕をふるっていた。一般的に、マーラーはベートーヴェンの系譜に連なる最後の交響曲作曲家であると言われている。最初の交響曲である『巨人』を作曲した1888年から1911年に死去するまでの約25年間で、9曲(『大地の歌』も含めると10曲)のいずれも傑作揃いの交響曲を残している。(まさに、1番から9番まで隙なしの、自慢の超強力打線!)なお、交響曲とともに多くの優れた歌曲も残しているが、オペラの指揮者として定評があったにも関わらず、自らのオペラ作品は不思議なことにひとつも作曲していない。
シーズン中は指揮者としての仕事に忙殺される中、マーラーはいわば「夏休み作曲家」として活動せざるをえなかった。そんな中で、いずれも超大作である交響曲等を生み出していったことを考えると、超人的な能力の持ち主であったといえよう。しかも、決して「やっつけ仕事」的な作品はひとつもなく、脱稿後も改訂補筆を繰り返す等、いずれの作品も細部のオーケストレーションにまでこだわりぬいて作曲されている。さらに、指揮者の経験からなのか、他の作曲家に比べ譜面上の演奏に関する指示が数多く、やたらと細かいことも、大きな特徴である。(私のような不真面目な演奏者であっても、必然的にドイツ語の勉強をせざるを得なくなるのである。)
自分の交響曲を指揮することも多く、1889年の『巨人』のブダペストでの初演の際も自らタクトをふるっている。もっとも、観客の評判はあまり芳しいものではなく、敵意ある批評や嘲笑的な批判にもぶつかったようである。
■3:『巨人』の特徴 初演当時こそ大衆に歓迎されなかった本作品であるが、現在では19世紀末の交響曲の傑作と評されている。国内のオーケストラで演奏される機会も、比較的多い。(個人的な話になるが、私が初めてマーラーの作品を演奏したのも、本作品であった。)この名曲『巨人』が、いったいどのような構成になっているのか、簡単に見ていきたいと思う。
本作品は、作曲された当時は下記の2部構成5楽章からなる「交響詩」であった。また前述のとおり、当初は各楽章に標題がふられていたが、後に全て取り除かれている。
●第1部 青春の日々から。若さ、結実、苦悩のことなど。
・第1楽章 果てしなき春。序奏は明け方のはじまりのころの自然のめざめを描く。
・第2楽章 花の章
・第3楽章 帆に風をはらんで
●第2部 人間の喜劇
・第4楽章 座礁。カロの書式による葬送行進曲。
・第5楽章 地獄から天国へ。
このうち、元来の第2楽章『花の章』は、1896年のベルリンでの演奏会にあたり削除され、本作品は現在のかたちである4楽章からなる「第1交響曲」となった。日の目を見ることがなかった『花の章』であるが、譜面が第2次世界大戦後に発見され、近年では独立して演奏されることもある。この楽章のカット理由については、正確な理由は未だ明らかになっていない。少なくともこの改訂により、本作品の演奏時間は約50分間と、マーラーの交響曲にしては比較的短いものとなっている。
また、本作品はほぼ同時期に作曲された歌曲『さすらう若人の歌』と、不即不離の関係にあるとされている。というのも、一部の旋律が何とそっくりそのまま用いられているのである。具体的には、『巨人』の1楽章第1主題と『さすらう若人の歌』の第2曲『朝に野辺を行けば』、『巨人』の第3楽章中間部と『さすらう若人の歌』の第4曲中の『菩提樹』の旋律である。マーラーの歌曲と交響曲との関係について、素材や様式的類似性の共有が認められるものは多いが、『巨人』と『さすらう若人の歌』ほどわかりやすい例は、他にはない。
この歌曲は、恋人を他の男に奪われてしまった若者の悲運を歌ったものであり、内容的に『巨人』作曲の背景ともつながりがあるように見える。前述のとおり、当時まだ20代の若者であったマーラー。自分の生き方に迷っていた『さすらう若人』でありつつも、音楽界の『巨人』への道を着々と歩み始めていたのではないだろうか。
■4:新響の「巨人戦」
以上、何とも雑駁な文章になってしまったが、私なりにマーラーについて調べてみた結果である。調査していく中で、本作品に対するイメージが、私の中でも少しずつ具体化されてきた。まだまだ若輩者で、ひたすら「さすらい続ける若人」な私ではあるが、次の演奏会では少しは良い感じのパフォーマンスができそうである。この根拠のない自信を確信に変えて「情熱的」な演奏をすべく、(なるべく)ナイター観戦の時間を少しばかり削り、日々の個人練習に費やしていきたいと思う。
最後に、演奏会の宣伝を。次回演奏会では、ソリストに松山冴花先生をお迎えし、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲と、この『巨人』を、飯守泰次郎先生の指揮で取り上げさせて頂くこととなっている。7月22日(日)のデーゲーム(14時開演の昼公演)、会場は東京ド…ではなく、オペラシティコンサートホールでの、新響・「巨人戦」。ぜひご来場の上、我々の熱演をお楽しみ頂き、(終演後には)熱い拍手と声援を頂ければ幸いである。
○ 参考文献
「作曲家別名曲解説ライブラリー① マーラー」(音楽之友社)
「大作曲家マーラー」ヴォルフガング・シュライバー著・岩下眞好訳(音楽之友社)
第218回演奏会のご案内
「巨人」―マーラーの青春の交響曲
ウィーン音楽院を優秀な成績で卒業したマーラーは、20歳で指揮者としてのキャリアをスタートするとその後は引く手あまたで、各地を渡り歩いていました。交響曲第1番が作曲されたのは、歌劇場のソプラノ歌手に失恋したり、未完のオペラの補筆を依頼したウェーバーの孫の夫人との不倫騒動があった頃で、若き日のマーラーの苦悩や希望が現れています。
元々この交響曲第1番は5曲からなる交響詩として作曲され、その時の標題が「巨人」でした。これはドイツの作家ジャン・パウルの長編小説の題名に由来し、主人公の青年がさまざまな経験を経て人格が形成され最後は王座につくというストーリーです。この交響詩の各曲には次のような副題がついていました。第1部<青春の日々より> 1:終わりなき春、2:花の章、3:順風に帆を上げて、第2部<人生喜劇> 4:座礁(カロ風の葬送行進曲)、5:地獄から天国へ。自身が4楽章の交響曲に改編した際に「花の章」を削除、標題や副題も破棄されましたが、今でもニックネームとして残っています。
ウィーン音楽院の学友でライバルであったハンス・ロットがなくなったのもこの頃でした。ブルックナーの弟子であった彼は、自作の交響曲をブラームスに酷評され精神に変調を来たしてしまいました。ロットのこの曲はマーラーの音楽に影響を与えており、特に交響曲第1番のスケルツォはよく似ています。
初演後に描かれた風刺画には、マーラーの吹く巨大な金管楽器から様々な動物が飛び出しており、センセーショナルであったことが覗えます。葬送行進曲の旋律を独奏コントラバスが弾いたり、最後はホルン7本が立って演奏するなど、現代でも十分に斬新な曲です。
ヴァイオリン協奏曲の王様
ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲は、ブラームス、メンデルスゾーンの作品とともに「三大ヴァイオリン協奏曲」と称され、傑作の森とも呼ばれるベートーヴェン中期を代表する作品の1つです。同じ頃に作曲された交響曲第4番やピアノ協奏曲第4番と同様に明快で叙情的な曲です。曲の素晴らしさからヴァイオリン協奏曲の王様とも評されています。
ソリストには、ニューヨークを本拠地とし、日本でも数々のオーケストラと共演している松山冴花を迎えます。昨年新響&飯守泰次郎とブラームスの協奏曲を共演し、瑞々しく感情豊かな演奏を聴かせ、その音楽性に団員も魅了されました。
この演奏会でまた魅力的な演奏をしてくれることを期待しています。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
マーラー:大地の歌
「大地の歌」は、マーラーの創作の過程のなかでは、1906年の夏に作曲された交響曲第8番「千人の交響曲」と1909年から1910年にかけて作曲された交響曲第9番のあいだに生み出された作品である。
独唱つきの6つの楽章からなるこの「大地の歌」が作曲されたのは、マーラーにとって大きな転機の時期だった。マーラーがこの作品の作曲に取り組む前年、1907年の夏に彼は娘を病気で失い、また1897年以来10年間音楽監督を務めたウィーン宮廷歌劇場を事実上辞職させられている。すぐにニューヨークのメトロポリタン歌劇場での仕事が決まったために、マーラーは1907年の冬以降、妻とともにアメリカで過ごすことになる。マーラーが「大地の歌」の作曲に取り組んだのは、1908年の夏、休暇のためにヨーロッパに戻り、アルプスの自然に囲まれたトープラッハ(現イタリア・ドッビアーコ)で家族とともに過ごしていたときだった。
「大地の歌」で用いられている詩のテクストは、1907年に出版されたハンス・ベートゲ編訳による『中国の笛』からとられている。マーラーが「大地の歌」のためにこの詩集から選び出した詩は、李白、孟浩然、王維などの詩の翻訳なのだが、それらは原作の中国語から直接訳したものではなく、他の詩人によるドイツ語の翻訳詩(さらにそれもフランス語の翻訳詩に由来する)を参考として作られたものだった。そのため、場合によってはもとの詩を特定することが難しくなるほど原作から離れている。マーラーはそういった経緯については何も知ることなく、単純にベートゲによる翻案(Nachdichtung)のうちに描き出されたオリエンタルな世界観に惹きつけられたのだろう。
「大地の歌」は、テノールとアルト(あるいはバリトン)が6つの楽章を交互に歌うという連作歌曲の形式を持つと同時に、その副題に示されているように「一つの交響曲」でもある。連作歌曲としての性格は、なによりも「大地の歌」という作品全体の標題に収束していくようなそれぞれの詩のテクストの内容によって作り上げられているのに対して、交響曲としての特質は基本的に、管弦楽によって演奏される音楽の形式的な側面により深くかかわっている。しかし、この二つの側面は別々の特質として存在するというよりも、むしろ互いに補完し合っているように思われる。
「大地の歌」は、詩のテクストに寄り添って作曲された比較的自由な形式をもつ作品とみなされることも多いが、作曲家・音楽評論家の諸井誠は、「大地の歌」を交響曲としてとらえる立場からこの曲の構造分析を行っている。そのような視点で見るとき、ソナタ形式で書かれた第1楽章、緩徐楽章の第2楽章(諸井によればこの楽章もソナタ形式)、そして第3楽章から第5楽章までを一つのまとまりとみなすスケルツォ風の部分、そして最後にシリアスで充実した内容を持つ最終楽章という、伝統的な4楽章構成の交響曲の姿が浮かび上がってくる。
諸井誠はおもに音楽そのものの分析に焦点を当てているが、こういったとらえ方は詩のテクストのうえでも非常に説得力がある。この作品全体を貫いているのは、悠久の大自然のなかで「この世」(これは「大地」と訳されているErdeと同じ)の人間の生がいかにはかなく虚しいものであるかという感情である。
第1楽章では、厳格な形式を伴いつつこの中心主題がいわば正面に据えられて歌われる。緩徐楽章としての第2楽章では、秋の寂しく枯れ果てた情景と重ね合わされた「孤独」な情感が歌われ、抒情的な性格がひときわ強い。それに対して、第3部としての第3楽章から第5楽章では、それまでの厭世的で悲観的な性格とは打って変わって、この世の楽しさ美しさ力強さが歌われている。しかし、そのような明るさは見かけのものでしかない。これらの楽章のテクストは他の楽章と比較するとき、情景描写的・物語的であり、深い情感に踏み込むことはない。そして、全曲の半分の長さを占める最終楽章では、その冒頭から「この世」の見かけの楽しさが根底から
否定される。この楽章のテクストは、さびしい夕暮れの山の情景を描く前半の部分(孟浩然の詩による)と、友との別れを描く後半の部分(王維の詩による)からなるが、全体として「この世」に疲れ「別れ」を告げる情感が漂っている。
このように見るとき、交響曲としての楽章構成をほぼとりながら、それに対応する詩のテクストが配置されることによって、この作品全体の思想が織り込まれているのを見て取ることもできるだろう。
以下、そういった構成をある程度念頭に置きながら、それぞれの楽章の詩と音楽について簡単にふれたい。
第1楽章 この世の哀れについての酒の歌
李白「悲歌行」(悲しき歌)による。酒宴の席で酒を飲む前にうたわれる詩でありながら、そこで詠じられているのは「この世(Erde)」のつらさや虚しさである。琴を鳴らし酒を飲むという、この世の楽しみについても確かにふれられているのだが、それはこの世の虚しさを覆い隠すためのものでしかない。むしろ、「天」や「地(Erde)」の大自然は悠久の流れの中にあるのに対して、人間の存在はごくはかないものでしかないことを詠い手は強く感じて
いる。
そして詩の終盤、突然のように、月明かりに照らされた墓場にうずくまる怪しい猿の姿が描き出される。「猿だ! 聞いてくれ、あのかん高く耳をつんざく啼き声が/生の甘い香りのなかへと響き渡るのを。」この戦慄を覚えさせる情景と不気味な鳴き声は、まさに生の虚無の深淵のイメージに重ね合わされているといえるだろう。音楽もこの箇所が一つの頂点をなしている。
第2楽章 秋に一人寂しきもの
銭起「效古秋夜長」(古(いにしへ)の〈秋夜長〉に效う(ならう))による。ただし、ベートゲの詩は原詩からかなり離れているところが多い。晩秋の寂寥とした情景が細やかにそして美しく描き出されている。しかし、ここではそのような枯れ果てた情景そのものよりも、むしろそれと重ね合わされた「孤独」な情感が詩の中心にある。そういったなかでも、「親しき憩いの場よ、お前のところに行こう」という箇所、あるいは「愛の太陽よ、おまえはもう二度と輝こうとしないのか、/私の苦い涙をやさしく乾かしてくれるために」という箇所では、マーラーらしい諦念を含んだ憧れの音楽が聞かれる。ここにはマーラーの想いがとりわけ凝縮されているのかもしれない。
ちなみに標題に関して、日本語に訳してしまうと分からなくなるのだが、ベートゲの詩では「一人寂しきもの」は女性(die Einsame)であるのに対して、マーラーのテクストではわざわざそれが男性(der Einsame)に書き換えられている。おそらくマーラーは自分自身を重ね合わせているのだろう。
第3楽章 青春について
第3楽章から第5楽章までの三つの楽章に使われている詩と音楽は、ある共通した性格を帯びている。これらはいずれもこの世の楽しみを謳歌するような内容をもち、その他の楽章にみられるような虚しさや寂しさの感情はまったく現れない。そのため、抒情性ではなく、情景の描写や物語的な性格がきわだっている。それもあってか、これらの楽章ではいわゆる「中国的」な旋律がひときわ目立つ。
第3楽章は、李白の「宴陶家亭子」(陶家(とうけ)の亭子(ていし)に宴す)による。ベートゲの詩では「陶器の園亭」。ここで描かれている「園亭」は「陶器でできている」とされているのだが、これは単に「陶家」の園亭のことであり、ベートゲが参照したドイツ語の訳詞が完全に勘違いしていたために生じた誤解だった。
それはともかくとして、この詩では、池の中に建てられた園亭で友人たちが酒を酌み交わしながら楽しく談笑し、詩作に興じているさまが描かれている。その様子が池の水面に上下さかさまに映っているのも趣がある。マーラーはそういった情景に対して、「青春について」という標題を新たに与えている。
第4楽章 美について
李白「採U曲」(Uを採るの曲)による。ベートゲの詩では「岸辺で」。川のほとりで乙女たちが蓮の花を摘んで楽しんでいる。輝く陽の光のなか、ときおり風が彼女たちの衣の裾をなびかせる様子もなまめかしい。そこに突然、馬に乗った若者たちが現れて駆け抜けてゆき、あたりの草や花は踏みしだかれる。馬上の若者たちが去った後、再び乙女たちの情景となるが、そのうちの最も美しい一人が憧れを秘めて男の子を見送る、といった話の流れだ。
この情景の内容に応じて、音楽もABAという形式をとっている。乙女たちの細やかな様子は、例えば木管やホルンなどのトリルにも表現されている。それに対して中間部では、とりわけ金管や打楽器によって描かれる、馬に乗って駆け抜ける男たちの荒々しい若々しさが特徴的だ。ベートゲの詩では、この部分は各6行の4連の詩のうちの第3連目にあたるが、マーラーはここにかなりの加筆を行って二つの連とし、全部で11行に増やしている。もちろん音楽的にもこの部分は大きな盛り上がりを見せる。このあと再び乙女の情景となり静かに終わる。
第5楽章 春に酔えるもの
李白「春日酔起言志」(春の日に酔いより起きて志を言う)による。酔ってこの世の憂さから一切解き放たれたかのように歌う。八分音符で刻まれる音形は、この男のふらついた足取りだろうか。はじめのうちは春に歌う小鳥の声に耳を澄ませているが、そのうちそのような趣さえどうでもよくなり、投げやりな楽天的明るさで終わる。
第6楽章 告別
孟浩然「宿業師山房待丁大不至」(業師(ごうし)の山房(さんぼう)に宿(やど)し、丁大(ていだい)を待てども至らず=業僧の山寺に泊まって丁家の長兄を待っていたが来なかった)と王維「送別」による。それに対応するベートゲの二つの詩「友を待って」と「友の別れ」を用いて一つの楽章としているのだが、実はこの二つの詩は、ベートゲの詩集では見開き2ページのうちに隣り合って収められており、マーラーはまったくその詩集のレイ
アウトのまま、これら二つの詩をつなげて使っていることになる。ただし、ベートゲの詩では王維に基づく「友の別れ」は一人称で語られているのに対して、マーラーのテクストでは三人称の語りに変えられている。
前の楽章とは完全に対極をなす深い虚無的な情感によって始まる。詩の第2連が終わったところで、三連符+二連符の伴奏音形にともなわれてオーボエのソロが始まる。ここからは「憩いと眠り」への静かな憧れに満ちた美しい音楽がしばらく続くが、寂寥としたフルートのソロとともに歌われる第4連では「最後の別れを告げる」予感が支配している。続く第5連と第6連では、音楽は前に流れ、いかにもマーラー的な強い憧れに満ちた音楽となる。
そのあと、この楽章の冒頭が今度はコールアングレとともに再現され、比較的長い器楽だけの部分が続くが、この箇所は二つめの詩(「彼は馬から降りて、男に」から始まる)へと接続していくための橋渡しとなる。後半の王維の詩は物語的な性格をもっており、アルトによる歌も語り的である。「この世では、私に幸せは恵まれなかった!」というところでは、オーボエのグリッサンドによる深い嘆息も聞かれる。
しかし、詩の最後の部分で、そういった静かで寂しげな語りは一転する。三連符の伴奏音形にともなわれたヴァイオリン、フルート、アルトによる美しい音楽が現れ、静かな高まりを見せていくが、この箇所ではベートゲの詩をマーラーが大きく書き換えている。とりわけ、最後の一連はほぼマーラーの創作といってもよい(ベートゲの詩では「大地はいずこも同じもの/そして白い雲が永遠に、永遠にある…」の二行だけ)。「いとしいこの大地は」という歌詞とともに歌われるこの最後の一連の音楽は、全曲のなかでもひときわ美しい。ちなみに、オーケスト
ラが次第にe(「ミ」)の音へと収束していくことによって、この最後の情感が導き出される。ここでは、人間の生の営みとは無関係に永遠に続いていく「大地」への憧れが「永遠に(ewig)」という言葉とともに歌われている。しかし、それと同時にマーラーは、ここで「大地」に対比される人間という存在のはかなさを静かな諦念をともなって受け入れているのだろう。
このように「大地の歌(Das Lied von der Erde)」という作品全体を見渡したあとで、この曲の標題でいわれているErdeとは何かということをもう一度考えてみたい。最初にもふれたように、「この世」のはかなさ・虚しさ・つらさ・寂しさに対する感情がこの作品全体の底に流れている。その意味では、「この世についての歌」といったほうがふさわしいのかもしれない。
ただし、ここでの「この世」とはキリスト教的な価値観での「あの世」(=神の国)に対比されるもの(「現世」)ではなく、その対極には悠久の大自然が想定されている。しかし、この悠久の大自然も、第6楽章の最後で歌われているように、まさに「大地」なのである。つまり、同じErdeという言葉によって「この世」と「大地」という両極的なものが意味されていることになる。とはいえ、全曲の最後で、永遠の「大地」のなかでの「憩いと眠り」(それはもちろん死に通じる)に想いを馳せるとき、「この世」の悲しみや苦しみへの嘆きはいわば乗り越えられている。そのように考えるとき、「大地の歌」という従来から用いられている日本語の標題も、やはりこれはこれでもっともなものであるとあらためて感じた。
初 演:1911年11月20日、ミュンヒェン、ブルーノ・ヴァルター指揮
楽器編成:ピッコロ、フルート3(3番ピッコロ持ち替え)、オーボエ3(3番コールアングレ持ち替え)、クラリネット3、小クラリネット、バスクラリネット、ファゴット3(3番コントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、グロッケンシュピール、トライアングル、シンバル、タムタム、タンバリン、大太鼓、ハープ2、チェレスタ、マンドリン、弦五部
参考文献
『グスタフ・マーラー 全作品解説辞典』長木誠司著(立風書房)
『交響曲の聴きどころ』諸井誠著(音楽之友社)
『グスタフ・マーラー』柴田南雄著(岩波新書)
『マーラー 愛と苦悩の回想』アルマ・マーラー著、石井宏訳(音楽之友社)
Hans Bethge, Die chinesische Flöte. Leipzig: Inselverlag, 1922(1907)
Das Lied von der Erde:The Literary Changes
(The Mahler Archives)
http://www.mahlerarchives.net/DLvDE/DLvDE.htm
イベール:祝典序曲<伝統的洗練と古典性>
淡い雲海の中を抜けると、まるで3Dのように突然雄大な大地が目の前に広がり、そして歓喜に沸く大勢の人々が上空を穏やかに飛ぶ飛行機に搭乗している私たちに手を振って迎えてくれる。まるで映画のごとき情景が飛び込んでくるような、それでいて厳粛な雰囲気に満ちた曲は、ジャック・イベール(1890-1962)にとって意味のある作品と言えよう。
■イベールという人物
鋭く豊かな才気に満ち、緻密なデッサンと生命感にあふれる現代的な感覚で詩情と機知に富んだ作品を創作したイベールは、フランス近代楽派の重鎮としてラヴェル亡き後のフランス楽壇にて重要な役割を果たしている。フランスを代表する要職や仕事を要請されながら、燦々と降り注ぐような洗練と個性は時に炸裂し、数多くの作品を幅広い分野に書き残している。
パリで生まれ、コンセルヴァトワール(国立音楽院)に入学。1919年に「ローマ大賞」を受賞して翌年から3年間ローマに留学、その時に書いた曲が、新響の第202回演奏会で取り上げた代表作の交響組曲「寄港地」であり、その作品は彼の名を一躍全ヨーロッパに広めていった。1925年、管弦楽法についての総合的な教本を書くという重要な仕事を任せられているが、それはローマ留学によって身に付けた技法の確かさの証明であり、1937年から、かつての留学先として滞在したローマのフランス・アカデミーであるヴィラ・メディチ(Vila Medici)の館長という要職に就いている。その時にフランス政府より、1940年に紀元2600年を迎える日本のために祝典序曲の作曲を依頼されたのである。
■紀元二千六百年奉祝楽曲発表演奏会
1940年(昭和15年)、当時の大日本帝国は、幕末以降皇紀として数えられていた紀元2600年として国民意識高揚を狙い、音楽界でも様々な参画があったが、中でも政府と音楽界を挙げての奉祝行事として奉祝楽曲発表演奏会が1939年より企画された。盟邦諸国に奉祝楽曲の献納を依頼、ドイツのR.シュトラウス、イタリアのピツェッティ、ハンガリーのヴェレッシュ、イギリスのブリテン、フランスのイベールによる作品が送られた。演奏会に際して企画・楽譜出版・連絡のため委員会が組織され、さらに当時の主たる演奏団体が合同し、大編成による管弦楽団が
結成されて、結局はブリテンを除く4曲が1940年12月に延べで6回の演奏会(東京と大阪)にて披露されたのである。
■「祝典序曲」解説
自信に満ちた稀にみる精巧なオーケストレーションは、活気と色彩があり、交差しながら追いかけていくような楽器間のバランスによって更に際立っている。具体的には、フランスの伝統的洗練と古典性をもって声部間の交差を多用し緊密さを獲得して、楽器群同士の重複を避けながら、響きの明るさを生み出す澄んだ音を選びとっている。
アレグロ・モデラート、4分の4拍子にて短い序奏から祭典の期待が高まり、喜びが高らかに告げられる。続いて8分の6拍子にて低弦から歓喜に満ち溌溂とした第1主題が提示され、次第にフーガのように高まりをみせていく。
クラリネットにより何かを暗示させる旋律を経て、4分の3拍子にて、まるで大都会の夜景の如く、煌びやかな全管楽器によるコラールが、第2主題としてハープとトランペットの主導によりfffでジャズ風に鳴り響き、弦楽器も加えて頂点を極めていく。そして静まっていくと、トロンボーンとテューバによる荘厳な雰囲気が準備されて、バスク
ラリネットとアルトサクソフォーンが4分の4拍子にて奏する厳かで且つ抒情的なテーマが第3主題として登場する。
宗教的な聖なる高まりを感じさせるがごとく、まるで天から燦々と降り注ぐ眩い光の中を上昇していくように、楽器を替えてその霊的な興奮を高めていき、8分の6拍子にて第1主題の動機とリズムが更に加えられ、fffにて第1主題と第3主題が一緒になって登場、更に4の3拍子で第2主題も現れて各主題が交錯、8分の6拍子から歓喜の情が一つにまとまって高らかに第3主題が歌いあげられ、炸裂した祝福と共に賛歌が響き渡っていく。
とにかく大成功を収めた日本の初演時における評価として、音楽評論の草分けとして著名な太田黒元雄の「祝典序曲」に対する批評は注目に値する。
荘重な「祝典序曲」奏祝演奏会
歌舞伎座における紀元二千六百年奉祝楽曲発表演奏会の曲目を飾った四つの曲のなかではフランスのイベールの「祝典序曲」が最も引き締まった印象を与えた。殊に旋律的な穏やかな部分には荘重な美しさがある。以下略。
■「祝典序曲」の真意
「祝典序曲」が、当時の日本の国策として紀元2600年を祝う演奏会のために、フランス楽壇を代表して作曲・演奏されたことは歴史的事実ではあるが、作品自体は日本的なものとは無縁であることは紛れもない。
この作品が創作された時代は、ドイツを中心として国際緊張が高まり、作曲された前年1939年にドイツ軍がポーランドに侵攻、第2次世界大戦に突入した政情不安のときである。
1940年6月にドイツ軍がパリへ入城し、フランスが対独降伏をした時代、イベールはフランスに帰国する際に自筆譜が紛失、再度楽譜を書きなおして手を加えている。ドイツ軍のパリ占領に伴いフランス初演はすぐには実現せず、1942年1月18日にパリ音楽院管弦楽団/シャルル・ミュンシュ指揮にて行われた(このコンサートは大成功を収め、当時南仏アンティーブに避難していたイベールに精神上の慰めを与えた)。
1944年8月20日にパリが解放され、8月26日にシャルル・ドゴールがシャンゼリゼを行進、ドイツ軍残党による銃声の中、ノートルダム教会でミサを挙げて全世界にパリが解放されたことを告げた。解放後のパリ音楽院演奏協会のコンサートは、シャルル・ミュンシュ指揮のもと、同年10月22日にこの「祝典序曲」と、オネゲルの「解放の歌」(初演)が演奏されている。
因みに同時代の日本で「交響譚詩」を1943年春に脱稿した伊福部昭は、アレキサンドル・ニコライエヴィチ・チェレプニンによる日本人を対象とした作曲賞「チェレプニン賞」を1935年に受賞したが、「チェレプニン賞」の審査員としてイベールは係わっていた。伊福部の作品に紛れもない民族の生活に根差した日本の国民音楽を見出したチェレプニンは1936年に横浜にて作曲法や管弦楽法を伊福部昭に対して示唆に富んだ個人授業をしている。
イベールの「祝典序曲」は、伊福部作品に共通する国民音楽と同様なもの、言い換えれば創作活動の根本理念として国民音楽的な精神が内在しており、それは「紀元二千六百年奉祝」という日本の国策とは全く関係なく、当時の国際情勢の中でのフランスの解放を示唆しているのではないだろうか。
初 演:1940年12月7日 山田耕筰指揮
紀元二千六百年奉祝交響楽団
楽器編成:フルート3(3番ピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、アルトサクソフォーン、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット4、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、タムタム(低音)、グロッケンシュピール、ハープ2、弦五部
参考文献
『受容史ではない 近現代日本の音楽史
一九〇〇~一九六〇年代へ』
(現代日本の作曲家, 別冊3)小宮多美江著(音楽の世界社)
伊福部昭:交響譚詩
伊福部昭はこの曲の表題を「交響譚詩―亡兄に捧ぐ―」とした。兄の勲氏は北海道帝国大学時代にリサイタルを開いた程のギターの名手であったが、1942年に蛍光塗料研究中の放射線障害により30歳の若さでこの世を去った。その次の年、太平洋戦争の戦況が悪くなり始めた1943年に、日本音響株式会社(日本ビクター)主催の「ビクター管絃楽コンテスト」に応募すべくこの曲は作られた。審査の結果第1位となり、その年の9月にSPレコード化、そのレコードが翌年の文部大臣賞を受けた。
この曲は二つの譚詩(バラード)から出来ている。第1譚詩は元気に遊び回った子供時代の思い出をイ短調で音楽にしている。速度記号の中に“capriccioso”とあるが、これは「奇想的な」という意味である。後述するチェレプニン(ロシアの作曲家、ピアニスト)が7年前の1836年に「写譜して勉強しなさい」と伊福部に渡した最初のスコアが、リムスキー=コルサコフの「スペイン奇想曲」であった。それに学んだというよりは、チェレプニンが伊福部音楽の中に奇想曲的なものを感じたのだろうか、興味はつきない。
第2譚詩はハ短調で別れの悲しみを歌う。曲の最後の11小節はコールアングレのソロで、ト短調の別れの歌とそれに続く長い祈りのイ音で、聴く者を静寂の中に導く。「第2次大戦中、蛍光物質の研究に斃れた(たおれた)兄のために起稿し、昭和18年春に脱稿したものです。戦争が烈しくなり、大きな編成を採ることが困難な時代だったので、2管持ち替えの小さなものとしました」と、スコアのあとがきに伊福部は書いている。
その8年前の1935年、伊福部はボストン交響楽団のレコード演奏を聴いて指揮者のセヴィツキーに手紙を出した。そのセヴィツキーから返事が来て「作品を見たいのでなにか送れ」という。伊福部は作曲中のヴァイオリン協奏曲を3楽章の管弦楽曲に直して送ったところ絶賛された。この曲を「チェレプニン賞作曲コンクール」に出すことにしたのだが、条件が「演奏時間10分以内」であった。そこで第1楽章をカットして第2、第3楽章の2曲を「日本狂詩曲」として応募したところ、見事「一等賞賞金参百円」であった。この時カットされた第1楽章の「じょんがら舞曲」が8年後、「交響譚詩」の第2譚詩に一部使われることになる。この当時は兄の勲氏もまだ元気で、よく写譜を手伝ってもらっていた。そういう懐かしい感謝の思い出もこの曲にはこもっている。
伊福部は音楽学校には行っていない。札幌二中からヴァイオリンを始めた。後に北海道帝国大学農学部林学実科に入る。今の北海道大学であるが、入学するとすぐに学内の「文武会管弦学部」でコンサートマスターを任される。作曲も中学から始めているが先生についたことはない。唯一習ったのは前述のチェレプニンからのみである。チェレプニンがコンクールの翌年の1936年に来日して横浜にいた時で、伊福部は就職1年目だった。「是非とも出て来い」と言われて、厚岸(あっけし)から上京し、宿代まで出してもらって作曲法と管弦楽法を1ヶ月間習っただけなのだが、そのチェレプニンが伊福部に音楽家になるように勧めた。酒が強かったことも気に入られた理由だったようである。後に東京音楽大学の学長まで務めた。
伊福部は子供の頃からアイヌの音楽に深く触れていた。父親が十勝の音更(おとふけ)村長でアイヌ集落も管轄していた上、大層尊敬され好かれてもいたので、「和人」には見せないコタンの行事も見せてもらっていた。何かにつけて集まると歌と踊りになるのだが、詩も含めた全てが即興的だった。これは勉強以上のことだったと思われる。全ての音楽の原点は民族の生活から生まれた民族音楽なのだが、記譜法が発明されてユニバーサルになった分失ったものも多い。伊福部はそういう時代の中でアイヌ音楽に接していたのである。
さて私事で恐縮だが30年程前、私は新響が先生からお借りしていたスコアを返すべく尾山台の伊福部邸をお尋ねしたことがある。玄関に入るなり奥様に三つ指をついて迎えられて大慌てのところへ、先生も出てこられて「上がっていけ」と仰る。もちろん固辞した。だいたい大作曲家とセカンド・オーボエ奏者とで何を話すというのだ! だが結局私は先生の書斎に上がり込んでしまった。
部屋いっぱいの民族楽器に囲まれての1時間、先生の旺盛な好奇心に乗せられて私もずいぶんと話をした。居心地の良い部屋と、それにも増して先生の大きさと暖かさに、今でも思い出してはジーンとこみ上げるものがある。話も終わってご夫妻に丁重にお礼を申し上げて、いい気持ちで下り坂を多摩川に向かって歩いた。しばらく歩いてふと振り返ると驚愕。奥様がこちらを向いて道路に立っておられるではないか。慌てて三拝九拝、曲がり角までの道のりのなんと長かったことか。もう一度最敬礼をして伊福部邸を辞した。
その出来事の少し前の1980年の春、新響は芥川也寸志の指揮で伊福部の「タプカーラ交響曲」を練習していた。第1楽章の練習番号の22まで来た時、芥川先生が隣で座って聞いていた伊福部先生に「この全員休みの8分休符は2つにした方が良いと思いますが」と言うのである。驚いた。そんな事を言われたら普通は怒って席を蹴って帰ると思うのだが、伊福部先生は顔色ひとつ変えず「お好きなようにしてください」と答えられた。この優しい言葉の後ろには、揺るがない自信みたいなものが感じられる。「そんなことで伊福部音楽は変わらないよ」と言っているようだ。新響所有の譜面は当時のままで、全てこの箇所に鉛筆で8分休符が書き加えられている。そんな歴史のあるちょっと見にくい手書きのこの譜面を長く使い続けて欲しいと思う(現在の巷の新版はきちんと8分の2拍子になっている)。
2002年5月19日、新響主催で「伊福部昭米寿記念演奏会」を紀尾井ホールで開いた。先生の弟子達、というよりは音楽界の重鎮達が大勢集まって祝賀会も大変な盛り上がりであった。故芥川也寸志夫人の芥川眞澄さんが挨拶に立たれ次のようなエピソードを紹介された。
主人は、昭和21年に音楽学校で先生にお目にかかって、その日の内に日光にある先生のお宅まで押しかけて三日三晩居候して、それから弟子にさせて頂いたという話はもう有名にございますけど、その後もついに尾山台にある先生のお宅の近くに家族ごと引っ越してしまって家族ぐるみで奥様にも先生にも大変お世話になりましたことを何度も繰り返し申しておりました。
この時写真と録音の係だった私が、何かのことで先生に近づいた折「耳が遠いので皆の話がほとんど分からないのですよ」とそっと告げられた。ええっ、なのにあの笑顔で祝賀会を2時間も過ごされているなんて。ひょっとして尾山台での私の話も我慢して聞いてくれたのだろうか。この時の録音を文章化したのだが、渡し損なってしまった。そのうちあの世で謝ろうと思う。
1989年2月の寒い日、芥川先生のお葬式の帰りに成城の道路を歩きながら作曲について聞いた。先生は「新しいものを作るのは大変でね、どうしても何かに似てくるんですよ」と真顔で仰っていた。どのように返事をしたらよいのか分からず恐縮してしまったのだが、その伊福部昭先生も2006年2月8日に目黒の病院で亡くなられた。91歳であった。「弟子達よりも長生きして申し訳ない」と何回も話されていたが。
初演は1943年11月20日、山田和男指揮、東京交響楽団、日比谷公会堂で行われた。録音の初演は同年9月4日に同じ演奏者で既に行われている。
初 演:1943年11月20日 山田和男指揮東京交響楽団
楽器編成:フルート2(2番ピッコロ持ち替え)、オーボエ2(2番コールアングレ持ち替え)、クラリネット2(2番バスクラリネット持ち替え)、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、ハープ、弦五部
参考文献
『伊福部昭・音楽家の誕生』木部与巴仁著(新潮社)
『芥川也寸志・その芸術と行動』出版刊行委員会編(東京新聞出版局)
『私のなかの歴史北の譜』北海道新聞夕刊1985年3月28日から4月8日まで掲載
(伊福部昭公式ホームページより)
『伊福部昭交響譚詩』ポケットスコアOGT-302(音楽之友社)
喜びをもとめて
維持会の皆さま、いつもご支援どうもありがとうございます。
月日は本当に信じられないスピードで駆け抜け、私、、今年で新響に入団して10年目となりました。心臓がクチから飛び出しそうなくらいに緊張したオーディションのこと、その100倍?!憂鬱だった合宿での新人宴会芸(第二次オーディション?)のことは未だ懐かしむことができませんが、憧れだったオケに入団してからの10年を振り返り、10年前の私とリンクするような?本を読みましたのでご紹介したいと思います。
◎『オケ老人!』(小学館文庫/荒木源著)
新響内でも出回って?いるそうで、既に読まれている人も多いと思いますが、あらすじは・・・。
30代の主人公がたまたま立ち寄った市民オケの演奏会に感動し、入団希望の連絡をしたところオーディションもなく入団OK!これはラッキーと10年以上もケースの中で眠っていたヴァイオリンを取り出し練習に駆けつけてみると、そこは、あの感動したオケとは別世界?の世界最高齢のアマオケ。その街には紛らわしい名前の「エリートオケ」と「老人(ばかりの)オケ」があり、どこでどう勘違いしたのか老人ばかりのガタガタの楽団に入団してしまったのです。もちろん、そこでは主人公が最年少で期待の星?であった訳なのですが、本当に入団したかったのは「エリートオケ」の方。その後「エリートオケ」のオーディションに辛うじて合格し、2つのオケを行き来することになり、アレやコレやいろんなことがあり、最後は、めでたしめでたし・・・と、かなり端折りましたが、楽しさテンコ盛りのお話です。
「エリートオケ」に入団して必死に追いつこうと努力している主人公は、まさに私?!
ちょっと違うのは、今まで雲の上だった人達が一緒にいることにドキドキし、練習中に飛び出したり、ヘンな音を出しませんようにとビクビクしながら「頑張ってついて行きますので宜しくお願いします」と小さな声(初々しかった?)での挨拶(お願い?)に「ついて来るんじゃなくて一緒に弾こうよ」と優しく嬉しい言葉をかけてもらえて、温かく受け入れてもらえた(と思っております!)こと。
この言葉は今でも私の「やる気」の素!「音楽っていいな!!」と思える瞬間をたくさん運んできてくれて、それからの10年、新響は私の生活の一部となりました。それまでとは確実に心の意識が変わったと思います。
ちなみに、、『オケ老人!』の書評を書いている藤谷治さんの『船に乗れ!』(ポプラ社)も私を睡眠不足にしてくれました。藤谷さんといえば、盗まれた「あのチェロ」がどうなったのか、ずーっと気になっていたのですが・・・『船上でチェロを弾く』(マガジンハウス)の中で、その顛末が詳細に述べられているらしいです。そうとは知らず乗り遅れてしまった私、、さっそく読んでみようと思います。
今回ご指導下さる飯守先生は、技術だけで解決しない音程は友情や愛情であり、誰が合っている・間違っているではなく思いやりなのです。思いやりの精神で響きを作るのです。とおっしゃっています。
シゴトが忙しくて自分の時間をつくれない日々もツライけれど、ひとりっきりで楽器と向き合う練習は、もっと(精神的に)キツく、「あぁ~~できないよ~つらいよ~」という日がくるのですが、泣きながらでも、もがいていると「あっ!わかってきた」という日がやってきて、この喜びを感じたくて弾いているようなもの?!
これからも喜びを求めて、思いやりの精神を忘れずに、あきらめずに、いい音楽を目指していこう。
雛祭りの日、私に(が?)ソックリな伯母が77歳になりました。何事にも一生懸命でアクティブなその伯母を見ていると、私も30年?は楽しいことがいっぱいありそうです。
【おまけ】
演奏会を聴きにいらしたお客さまの書いて下さったアンケートの内容はすべて、団員向けに作成される『新響ニュース』に掲載され、団員全員の手に渡るのですが、新響での私、そのお客さまのナマの声をタイプするシゴトもしております。活動するのは年4回と裏方の地味~なシゴトですが、誰よりも早くアンケートを読める役得感や、私だけ?が見ることのできる紙面の風景のことなど、つぶやかせていただきます。
演奏会で回収されるアンケートは毎回100~130枚ですが、邦人作品、ストラヴィンスキー、ショスタコーヴィチなどインパクト大!(ストレスいっぱい?)の演目の時ほど反響(枚数)が多く、最高記録は155枚!213回の飯守泰次郎先生(指揮)・松山冴花さん(Vn独奏)をお迎えした時でした。
タイプするにあたっての一番の苦労は、躍動感溢れる?個性豊かな文字たちの解読です。この作業さえクリアできれば99%は終わったようなもの?!初シゴトの時は37枚でしたが解読できたのは、たったの10枚。あとの残りは何が書いてあるのかサッパリわからず、練習場で皆に聞きまくりましたっけ。それから大先輩方のお知恵を盗むこと9年、今では文字を見ただけで誰が書いたものかわかるほどに(ホントです!)どんな文字でも翻訳?できるようになりました・・と思います。でも・・判読可能な文字!大歓迎デス。
文字だけでなく絵も書いてある、黒ペンではなくカラーペンなど多色使いのアンケートも増えています。初めて住所・氏名・メールアドレスの印鑑が押されているものを見た時はビックリ仰天でした。(いつも持ち歩いているのでしょうか??確かに、間違いなく次回のご案内を郵送させていただきます。)こういったものはニュースに掲載することができないため、私一人で楽しませてもらうのですが(団員の皆さまゴメンなさい。。)、小学生の子供たちの鉛筆で書いてくれた全部ひらがな!の感想や絵などは本当に微笑ましく、「そのトランペットのピストンは多すぎるでしょう」とか「バヨリン(←と書いてあるのです)の弦は4本だよ」とか「○○パートのオジさん(あっ、スミマセン。。)、そんなにカッコよかったっけ?」とかツッコミを入れたりしながら元気をもらっています。ちなみに、高校生になると、キラキラペン率9割!句読点の代わりに絵文字が書かれていることが多く、「へぇ~~コレって、こういう時に使うのねぇ・・・」と感心しながら、これまた勉強させてもらってます。
もう時効?!だと思うので告白してしまうと、最近の若い人は(小学生までも!)、どんな時も、場面に関係なく「ヤバイ」と言うようなのです。美味しくても「ヤバイ」、感動しても「ヤバイ」・・私、あまり若くないので理解に苦しみますが・・そうとは知らなかった2年前、「私は学校で○○を吹いているのですが、『未完成』の○○のソロが超~~ヤバかった!!!」というアンケートに言葉を失いました。「えっ?!私は、あの素晴らしいソロにうっとりしたけど・・でも、、もし、そんなにヤバかった?のだとしたら、他人に言われるまでもなく、本人が一番そう感じているわけだし・・」その時は、どうしてもタイプすることができずに胸の中にしまい込んでしまったのですが、それは私の大きな勘違いで「超~~素晴らしかった!!!」という意味だったのですね。あぁ~まだまだ修行が足りないかも。今更ですが○○さんには、こっそりお詫びしなくては。
今までに対面したアンケート数、約4000枚!
タイプしようか困ってしまうようなイジワル?な内容に心が痛むこともあるにはあるのですが・・・。
使われている文字の多くがデジタルに置き換えられて、表情をなくしてしまった今、文章として書かれている内容とともに、筆圧・文字の大きさ・乱れ具合などによって書いている人の感情を察することのできる手書き文字を、たくさん(過ぎる?)見ることのできる喜びも感じています。
ところで、もし「超感情移入型」のマーラーさんが会場にいらしてアンケートを書いて下さったとしたら・・・きっと私の手には負えないなぁ。。
今回も皆さまからのナマの声!心をこめてタイプさせていただきます。
「紀元2600年」祝典再考=イベール『祝典序曲』によせる雑感=
イベールの『祝典序曲』は日本の「紀元2600年」の祝典に寄せられた作品で、同時に贈られた他国の数曲と共に、二千六百年奉祝交響楽団によって昭和15年(1940年)に初演されている。
現代に生きる日本人は、ともするとこの時代に対して「暗黒」「統制」「支配」・・・ネガティヴなイメージ以外のものが抱けず、故にこの祝典の性格も同じようなものとして漠然と捉えるばかりで、今もって関連する一連の作品群と真摯に向合う気力に欠けているように思える。
『祝典序曲』を演奏する機会を得たいま、改めて作品に横溢する「自由な」精神から、祝典の性格や当時の日本社会の実態の見直しを試みる事は、決して無駄ではなかろう。それは我々の視点を改める事に通じるからである。
■干支の話
ベートーヴェンの没年である西暦1827年は、日本では文政10年に当たる。その盛夏の事である。『南総里見八犬伝』を執筆途上だった曲亭(瀧澤)馬琴はある日、最後まで残っていた1本の歯を失った。明和4年(1767年)生まれの彼はこの時61歳(数え年)。既に10年近く前から入れ歯の世話になっていたが、流石に全ての歯を失くした事は一大事だった。日記に彼は書く。
予(われ)、今茲(ここ)に六十一歳にして歯牙皆脱了。故(もと)に復(かえ)るの義か。自笑に堪(た)えたり。(『馬琴日記』文政十年六月三日の条)
ここにあるのは、生まれ変わるべき「還暦」の年に歯を全て失い、本当に生まれたての赤ん坊のようになってしまったわが身を哄笑する老人の姿である。以後、入れ歯との苦闘が前にも増して日記に頻繁に現れるようになる。
だが彼には数年後に始まる眼疾(白内障と言われる)によって、遂には失明に至る運命が待ち受けていた。28年に亘って書き継がれた『八犬伝』の晦渋極まりない文章のうち、その最後の5年分ほどについては、光に閉ざされた苛立ちと絶望に隣り合わせた記憶を頼りの口述によっていた。全ての歯を失ったこの日は、その長い苦難の初段階に過ぎなかったのだ。
改めて断るほどの事でもないのかもしれないが、還暦とは自分の生まれ年の干支に「還る」年の事を指す。
「干支」と書いて「えと」と読み(因みにこれは訓読み。音読みなら「カンシ」)、毎年末年始には新たな年の干支が話題にもなるが、この場合十干(じっかん)十二支(じゅうにし)=十の幹と十二の枝=のうち十二支のみが取り上げられることがほとんどである。本来は甲子(きのえね)や丙午(ひのえうま)の様に十干の部分(甲乙丙丁・・)との60通りの組合せで年(及び日)を表す。十干は万物を形成する元素とも言える五行(ぎょう)(木(き)火(ひ)土金(つちかね)水(みず))を兄(え)と弟(おと)に各々分化したものである。即ち「木の兄(きのえ)=甲」「木の弟(きのと)=乙」の様になる。これを順番に十二支(子丑寅卯・・)と並べる事によって出来る60通りの組合せを指して干支という。つまり干支を「えと」と読むのは十干を構成する「兄弟」の古訓に由来するという事になる。
馬琴に話を戻せば、生年の明和4年は「丁(ひのと)亥(い)」の年だった。61年目に当たる件の文政10年に再びこの干支が巡って来て、飛んだ「再生」の年となった。
干支の発祥は勿論古代中国だが歴史は古く、殷虚から出土される甲骨文に既に現れていると言われるがこれは当然というべきで、司馬遷が『史記』を著すに当たって歩猟したであろう、今は失われた様々な文献には、悉くこの干支が明示されていたからこそ、彼は最古の王朝(夏王朝)に出現した歴代の王に関わる詳細な年代までを特定出来ている。『史記』の完成によって、中国に於ける国家としての歴史とその記述のスタイルは確立したと言って良い。そして歴史を記述するという行為とその編纂のスタイルは、干支による年代の表示と共に文明をもつ社会の証として、周辺の地域にも伝播していく。
詳しい説明は省かざるを得ないが、時代を経るうちに、干支に対して「辛酉為革命、甲子為革令」・・・即ち辛酉(かのととり)の年に王朝が変わり、甲子の年には法律が変わるとの考えが現れるようになる。また、この辛酉から次の辛酉までの60年間を1元とし、21元=1260年(これを1蔀(ぼう)とよぶ)毎に世界的な大変革が起きるという思想=讖緯(しんい)説にも発展した。それは遅くとも6世紀には日本にも伝来していた。こうして特に辛酉と甲子の2つの干支は重要視されるに至り、日本では7世紀以降この2つの干支の年には必ず改元(年号を改める)が行なわれている。
甲子は60通りの干支の筆頭だが、辛酉は58番目。するとこの年に改元された元号は僅か4年で甲子の年を迎えて再び改元される事になる。こうした慣習は西暦661年(斉明天皇7年・辛酉)から1864年(元治元年・甲子)まで1200年に亘って連綿と続いていた。それほどにこの思想が浸透していたという証左というべきだろう。
■神武天皇即位の年代確定
『史記』の完成から800年近くを経て、日本もようやく国家としての体裁を整えるべく、歴史の記述に取組む事となった。『日本書紀』の編纂(7世紀後半~8世紀)がそれである。これは中国の史書に倣った日本初の修史事業というべきものであり、「歴史」ゆえの合理性がそこには当然求められることになった。この合理性とはとりも直さず膨大な伝承を、かの国の史書と共通する時間の座標軸にはめ込んでゆき、整理する作業をともなう。勿論それまでにも干支による記録は各氏族間に点在していたには違いが、全てを天皇家の国家統一に関する伝承を中心に据えた形での時間の再構築が必要となったのである。その原点が神武天皇の即位の年代決定であった。
この困難な作業に従事した人々は、西暦601年(推古天皇9年)が辛酉の年であった事に着目し、重視した。この年には聖徳太子によって斑鳩(いかるが)に都が移されている。因みに12年(甲子)には十七条憲法が定められる。これも上記の「甲子為革令」の確証となったであろう。仏教伝来直後の当時は革新の時代でもあった。
この推古天皇9年を起点として上記の1蔀=1260年を遡った辛酉の年を神武天皇の即位の年と定めたと考えられている。これによって神武紀元の元年が西暦紀元前660年となる訳である。但し、この1260年間に即位した天皇の数は既知のものとなっており、増やす事も出来ないから一代当たりの在位期間が引き伸ばされ、それに伴って恐ろしく長寿の天皇を数多く産み出す結果となった(例えば神武の崩御は127歳。これを初めとして以後崩年がいずれも100歳を超える天皇が続く)。が、その様な不自然さはむしろ初期の天皇を超人化させる一助にさえなった。
現代の我々には荒唐無稽と見えるこうした事象や、考古学的には裏づけのしようのない年代の確定は、讖緯思想に基づいた彼らなりの必然性のある作業の結果だったのである。
■紀元2600年の日本
さて、昭和15年がその神武天皇即位から2600年目に当たる事に着目した日本政府は、この記念事業企画を昭和10年から行なっていた。紀元2600年という区切りそのものには積極的な意味はないし、この年は甲子でも辛酉とも関係はない。だがこの区切りの良い年に、海外に「神国日本」肇国の悠遠をアピールし、国内にあっては他国に勝る歴史ある日本文化の優越を知らしめて国威と民心の発揚を図る必要が、為政者の側にあった。
そして同年11月10日には内閣主催の奉祝会開催を中心として、各地で様々な行事・・・勤労奉仕や観艦式・記念碑の建造などを含む・・・が行われる。万国博覧会の開催やオリンピック(夏季のみならず冬季のそれも)誘致も計画された。
その一環として海外にも奉祝の為の楽曲を委嘱しようとの計画が立案される。「恩賜財団紀元二千六百年奉祝会」と「内閣二千六百年記念祝典事務局」とがこの計画を実際に推進してゆき、次の5曲が日本政府に対して贈られる結果となった。このうち今我々に余りなじみの無いピエッティはイタリア、ヴェレシュはハンガリーの作曲家である。
・イベール:『祝典序曲』
・ピエッティ:『交響曲イ長調』
・R.シュトラウス:『日本建国2600年祝典曲』
・ヴェレシュ:『交響曲』
・ブリテン:『シンフォニア・ダ・レクイエム』
その他3人の「著名な」人々のうち、R.シュトラウスはまだしも、イギリスやフランスのような国々からも作品が寄せられている事と、この祝典の背景となる「戦時の日本」のイメージが容易に重ならないかも知れない。
だが実際にイベールの『祝典序曲』は1940年6月に日本に到着しており、同年12月に歌舞伎座に於いて山田耕筰の指揮により初演されている(ブリテン以外の作品も、指揮者こそそれぞれ異なるが同日に演奏)。その山田耕筰もこの時、歌劇『黒船(夜明け)』を奉祝曲として書いている。同じ目的で創作された中で有名なのは信時潔の交声曲『海道東征』だろうか。菅原明朗は『紀元二六○○年の譜 交声曲-時宗-』を残す。その他歌謡や舞踏の為の作品を含め、数多の楽曲がこの年の為に作られているのである。
『祝典序曲』を耳にする人は、そうした日本国内の様々な思惑や意図とは無縁の、「自由」な感情の発露を感じ取る筈だ。大規模なオーケストレーションと華やかな響き、そしてジャズのフレーズまで登場する音楽的なスケールの大きさ・・・このような音楽が、昭和15年の日本で響いたという事実には、ある種の意外感や違和感が伴う。少なくとも個人的にはそうだった。
そして海外から寄せられたこれらの曲と比較すると、日本人の手になる様々な作品(それは決して音楽に限らない)に対し、いささか狭量な印象が拭えないのは残念というほかはないが、我々が現在抱いている「軍国主義」や「暗黒時代」のイメージにはきっちりはまるように思える。となればその象徴とも謂うべきものが「紀元2600年」祝典であり、これを契機にこの国は更なる暗黒に突き進んでゆく・・・これが戦後日本の一貫した歴史観のように思える。
確かに当時の日本という国家が陥りつつあった国際的な孤立とそれに伴う独善は進行していたし、また祝典と同時期には天皇制の真の「歴史」に関する書籍の発禁措置もとられている。
■祝典の本質
だが最も肝腎な事は、この紀元2600年=昭和15年の時点の日本は、大多数の日本人にとっていまだ「暗黒」の時代ではなかったという点だ。
近年(2010年)に出版された『紀元二千六百年=消費と観光のナショナリズム=』(ケネス・ルオフ著/木村剛久訳 朝日選書872)は、ともすれば「戦後史観」によって、紀元2600年祝典を含めたこの時代に対して現代の日本人が犯しがちな断定や評価に関し、意外とも思える事実をいくつも挙げて反証している。
著者(1966年生まれ)はポートランド州立大学教授で英語圏に於ける天皇制研究の第一人者の評価があるアメリカ人。彼はこの祝典が、民間のあらゆる企業のビジネスチャンスを引出し、特に出版や百貨店や観光(この年だけで1800万人もの人が訪れた国内の皇室ゆかりの地や神社ばかりではなく、当時の日本の植民地へのツアーまで企画され、万単位の民間人が海外各地に出たという)などの興隆を引き出した事実を、史料の裏付けを以って記述する。その上で言う。
率直にいって、多くの日本人がアジア・太平洋戦争中もいつも通り暮らしていたという見方、あるいはナチ政権が非道な犯罪に手を染めていた時もドイツ人が国内旅行を楽しんでいたという見方は、日本人やドイツ人がこの暗い時期にずっと苦しんでいたというとらえ方に比べて、不愉快かもしれないし、そんな事があってもいいのかと思えるかもしれない。同じように、アジア・太平洋戦争が消費主義を抑えるのではなく、それを加速し、消費主義がナショナリズム感情をあおり、ナショナリズム感情が日本人にいっそうの消費を促すといったフィードバック関係が生じていたという事実も、当惑をもたらすかもしれない。だからといって、「戦時の暗い谷間」において、日本では消費主義は押さえつけられ、人々は観光旅行を計画するどころではなく、ぎりぎりの生活を強いられていたという神話を受け入れれば、それで満足できるというものではないのである。
勿論これはひとつの見方であって、拘泥する必要はない。だがその主張は傾聴には値しよう。
この論の前提は、日本人の圧倒的大多数が、「戦中」というと、戦局が本当に悪化した昭和17年(1942年)後半以降の、真に暗黒だった時代のイメージを全体に敷衍させてしまい、消費活動も普通に行えて自由だった、直前までの時代をも暗闇に覆ったままでおり、その視点からのみ紀元2600年式典も捉えている、という事にある。
戦後生まれの外国人に改めて指摘されてみれば確かに思い当たるところが無いでもない。現代の日本人たる我々はこの祝典の実態を殆ど知らず、せいぜい初代の天皇即位を国家の成り立ちとしてそれを祝う事を利用した、為政者による恣意的な「今ある体制とその行為に対する無条件の肯定と賛美」の押しつけ・・・程度に捉えてそれで済ませている。つまりショスタコーヴィチがいう、スターリンによる「強制された歓喜」や21世紀のこんにちに至るも「泣き女」や「喜び組」が演出する独裁者の為の祭典と同一視しているという事である。それ故に祝典に寄せられた多くの音楽作品に対しても、創作者の意向も全く無視された体制側の強制の反映として拒絶するか、或いはショスタコーヴィチの作品のように、その背後にあるものを読み取ろうと試み、徒労を繰返しているかだ。そして祝典から5年後に訪れた帝国の滅亡も相俟って戦後は急速に忘れ去られ、音楽作品に関しては滅多に演奏される事もない事が拍車をかける。
白状すれば筆者も長くそうしたイメージにとらわれ、この祝典に向けられた前述のブリテンの作品や深井史郎の『創造』を新響が取り上げた15年ほど前の演奏会の際(第160回定期1998年1月)、このニュース上にそうした見解を前提とした原稿を書いた事があった(『祝祭と鎮魂と--紀元2600年を巡る二つの作品--』この文中の干支や紀元についての説明は、その際の原稿を一部流用している)。
だが、その祝典が民間の自主的な消費行動を刺激し、況してや海外を含めた旅行熱を現出させた、謂わば絶大な「経済効果」をもたらした一大イヴェントであったとなれば、その位置づけは大きく異なって来よう。そもそも自由な海外渡航(移住も!)を国民に認めている国が、独裁的な体制を維持できるだろうか?我々はこの時代の実態を知ろうとも努めず、考えようともしていない。
こうした当時の体制と社会の「明るさ」とを背景にすると、イベールの『祝典序曲』の持つ自由闊達さが初めてよく理解できるものとなるように思う。そして当時の日本人もまたこれを違和感なく受容できるほどに、個人も社会もまだまだ自由であった事を思うべきだろう。これは日本人の手による同時期の作品だけを耳にし、あの時代に対する固定化したイメージを払拭しない限り、まず読み取る事ができない性格のものである。
是非この作品を真摯に聴いてみて戴きたい。残念ながら前述の通り、実演は滅多に耳に出来ないのだから。
但し、この後の日本が辿った道を我々はさすがに熟知している。本当の暗黒があり、神国日本の滅亡があった。国家としての独善と孤立は滅亡を見るまで自ら止む事は無かったのである。そこには個々の人間の一生と同じく、国家なり社会なりの、人間が形成する限り逃れよう・逆らいようのない盛衰の周期があるように思えてくる。
明治維新から神国日本の崩壊に至るまでの時間は77年。更にその再生から今年2012年まで67年が経過している。馬琴は齢(満)60にして「歯無し」となった。いまこの年齢で全ての歯を失くす人は殆どいないだろう。人の寿命も延びている。だがその人の世の変転や、大は国家から小は数人の組織の消長・栄枯盛衰を見渡してみると、60年で一巡する干支と、その循環の中に再生を求める人間の思考と営みは、個人と集団とを問わず、実は変わっていないのではないかと思えてくる。今年で創立56年を迎えたわがオーケストラとて例外ではないと、自省すべきなのかも知れない。
「紀元2600年」は残念ながら再生とは逆に、帝国の「終わりの始まり」直前の、最後の光芒だったように思える。終末が本当に訪れるその瞬間まで、人はすがるべき何かを求めて、事さらに明るくあろうとするものなのか?・・・『祝典序曲』が現代の我々に訴えかけるものを改めて噛みしめたい。
第217回演奏会のご案内
西洋のなかの東洋
ドイツで長年活動し現在は日本を代表するマエストロとして幅広い活躍をしている飯守泰次郎を指揮に迎え、東洋が見え隠れするクラシック曲をプログラミングしました。
9番目の交響曲~生は暗く死もまた暗い
後期ロマン派の作曲家マーラーは、歌劇は残しませんでしたが、多くの歌曲を作り歌劇的な交響曲を書きました。「大地の歌」は歌を愛したマーラーが最後に書いた独唱を伴う交響作品で、研ぎ澄まされた美しい曲です。交響曲として位置付けられていますが連作歌曲としての性格を強く持っています。本来交響曲第9番となる曲でしたが、ベートーヴェンやブルックナーが第9交響曲を書いてこの世を去っていることを意識したマーラーは、番号を与えずに単に「大地の歌」としました。
この曲の歌詞は、ドイツの詩人ベートゲが李白らの唐詩を自由に翻訳編集した詩集「中国の笛」をマーラー自身が適宜改変したもので、実際の唐詩と一致してはいませんが、共鳴して音楽の拠りどころとしています。マーラーがボヘミアに生まれたユダヤ人であること、この「中国の笛」に出会った1907年に長女を亡くし自らは心疾患の宣告を受け、ウィーン宮廷歌劇場を辞任し渡米するという転機を迎えていたことが、東洋的な無常感や自然への礼賛に共感させたのでしょう。最後は「永遠に、永遠に」と現世に別れを告げます。
交響譚詩~踊りと詩の音楽
伊福部昭は映画「ゴジラ」の音楽でも知られる作曲家です。新響ではその作品を度々取り上げ大切に演奏をしてきました。1942年に伊福部の次兄が急逝しその追悼曲として作曲されたのが交響譚詩です。譚詩はバラードの日本語訳で、音楽と舞踏が分離せず渾然一体となった状態をさしています。力強く躍動感のある第一譚詩と寂しげな第二譚詩からなるこの曲は2管の小さめの編成で書かれ、ビクター主催の懸賞で第1位となりすぐにレコード化されたこともあり、もっとも頻繁に演奏される代表曲となりました。
北海道帝国大学で林学を学び森林事務所に勤務していた伊福部が世に出たのは、チェレプニン賞(日本人を対象としたコンクールでパリで審査された)で「日本狂詩曲」が第1位入賞したことがきっかけでした。応募に合わせるためカットされた幻の日本狂詩曲第1楽章「じょんがら舞曲」が、第二譚詩に組み込まれています。ロシアの作曲家チェレプニンは「ナショナルであることこそがインターナショナルである」と指導し、伊福部の民族的な作風の原点となりました。
イベールが日本のために作曲した名曲
イベールは「寄港地」で知られるフランスの作曲家で、チェレプニン大賞の審査員の一人でもありました。日本政府は1940年の「紀元二千六百年祭」のための祝典音楽を同盟国に依頼し、フランス政府はイベールに作曲を要請しました。神武天皇が即位してから2600年目にあたるとして、大日本帝国の国威発揚のため様々な記念行事が行われ、この年の12月に8回にわたって開催された奉祝演奏会でもっとも評判の良かったのがこの祝典序曲でした。輝かしく壮大でエスプリもあるこの曲は、戦争色とは関係なくお楽しみいただけるでしょう。
どうぞお楽しみに!(H.O.)
第217回ローテーション
| 交響譚詩 | 祝典序曲 | 大地の歌 | |
| フルート1st | 藤井 | 岡田 | 松下 |
| 2nd | 丸尾(+picc) | 吉田 | 新井 |
| 3rd | - | 兼子(+picc) | 吉田(+picc) |
| Picc | - | - | 兼子 |
| オーボエ1st | 宮内 | 亀井(淳) | 堀内 |
| 2nd | 堀内(+C.A.) | 亀井(優) | 岩城 |
| 3rd | - | - | 山口(+C.A.) |
| C.A. | - | 桜井 | - |
| クラリネット1st | 末村 | 末村 | 品田 |
| 2nd | 石綿(+B.Cl.) | 大藪 | 進藤 |
| 3rd | - | - | 石綿 |
| Es.Cl. | - | - | 大藪 |
| B.Cl. | - | 高梨 | 高梨 |
| Alto Sax | - | 進藤 | - |
| ファゴット1st | 浦 | 斎藤 | 田川 |
| 2nd | 田川 | 浦 | 長谷川 |
| 3rd | - | - | 斎藤(+C.Fg) |
| C.Fg | - | 長谷川 | - |
| ホルン1st | 大原 | 森 | 箭田 |
| 2nd | 市川 | 兪 | 兪 |
| 3rd | 鵜飼 | 大原 | 山口 |
| 4th | 山口 | 市川 | 鵜飼 |
| トランペット1st | 北村 | 小出(Assi.野崎) | 野崎 |
| 2nd | 中川 | 北村 | 小出 |
| 3rd | - | 倉田 | 倉田 |
| 4th | - | 中川 | - |
| トロンボーン1st | 志村 | 武田 | 武田 |
| 2nd | 小倉 | 志村 | 志村 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 桑形 | 古関 | 皆月 |
| パーカッション | - | 小太鼓/今尾 大太鼓・タムタム/浦辺 シンバル/桜井 グロッケンシュピール/皆月 |
大太鼓/桑形 シンバル/中川 トライアングル・タンブリン/今尾 グロッケンシュピール/古関 タムタム/田中 |
| マンドリン | - | - | (*) |
| チェレスタ | - | - | 藤井 |
| ハープ1 | (*) | (*) | (*) |
| ハープ2 | - | (*) | (*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(小松) | 堀内(小松) | 堀内(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(田川) | 大隈(田川) | 大隈(滑川) |
| ヴィオラ | 柳沢(田口) | 柳沢(田口) | 柳沢(石坂) |
| チェロ | 柳部容(光野) | 柳部容(光野) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 中野(加賀) | 中野(加賀) | 中野(加賀) |
(*)はエキストラ
西暦2001年の新交響楽団 =マーラーの第5交響曲を巡るある回想=
10年ぶりにマーラーの第5交響曲を取上げるに当たり、前回演奏した当時の新響を振返ってみたいと思う。
■選曲の「10年ルール」
演奏会が活動に於ける大きな節目である限り、どこのオーケストラでも「何をやるか?」は運営の要諦のひとつであると言って過言ではない。これを巡って団体内の意見が四分五裂して、ひとたびこじれればそれは組織の存立そのものさえ揺るがしかねない問題に発展しがちである。各奏者は自分ひとりでは解消しきれない、音楽に対する様々な欲求や見識を抱えて、オーケストラの門を敲く。そしてその一員となれば、当然そうした欲求の充足の具体的な方策を、日常の活動に従いつつ模索する事になるのである。「何故そんな事を・・・」と思われるかもしれないが、そもそもこうした欲求無しに、演奏をするという事はあり得ないのだ。
新響ではそうした不毛且つ根源的な問題を解消するひとつの方策として10年間は同じ曲を定期演奏会にかけないという所謂「10年ルール」を設け、依頼した指揮者との選曲交渉の場でも、厳格に適用されるルールとして定着している(何度も新響と共演した経験のある方々には、周知戴いているほど)。
例えば前回の定期で取上げたチャイコフスキーの交響曲第5番は30年間で3回しか公式の演奏会にかかっていない。この有名な交響曲をこの頻度でしか演奏していないアマチュアオーケストラというのは、演奏会の回数にもよるだろうが極めて珍しいのではないか?と感じている。新響の場合演奏会は年4回。1回に必ず3曲は難しいから平均して2.5曲(実情はもう少し多いと思うが)として1年に10曲、それを10年で100曲・・・つまりチャイコフスキーのような知られた作品でも、全く知られていない「隠れた名曲」であっても同等に扱われ、他の99曲を演奏した上でないと再演はされていないという事である。こうして考えると改めてこの「10年ルール」が新響の演奏活動に対してもたらしている「曲目の多彩さ」ともいう影響の大きさを痛感せざるを得ない。そしてこれだけ厳密にこのルールを運用して、同じ曲の演奏頻度を極力避けるようにしてさえ、まだまだ演奏した事が一度も無い、数々の優れた作品があるという現実・・・「日暮れて道遠し」の感は常につきまとっている。
但し、このルールは伊福部氏の作品、そして芥川氏の歿後は彼の作品に対してはやや緩やかな適用にはなっている。新響が特別なつながりのあるこれら2人の作品・・・例えば『タプカーラ交響曲』や『絃楽のための三章』など・・・を、ともすると頻繁に演奏しているイメージがあるのも無理からぬ事なのである。
■2001年の団内模様(ふたつの委員会)
という訳で今回の定期でマーラーの第5交響曲を取上げるのは、そのルールに厳格な運用の結果にほかならない。前回が2001年4月の第173回定期だったのでまさに10年という時が経過するのを待ち「満を持して」この大作に取組むという事になるが、これだけの時間が経過する間には、新響という組織もずい分と変化しているものだと改めて痛感する・・・というよりも、ちょうどこの10年前が、新響の大きなターンニングポイントだったと個人的には考えざるを得ない。
当時と比較してこの団体の活動を司る諸々の運営体系を実際に運用し、団体の運営を進めてゆく個々の人々の考え方がこの2001年という年を契機として大きく変転したという事である。
新響には活動を推進してゆく為の組織として「運営委員会」と「演奏委員会」というふたつの委員会があり、それぞれの役割分担を果たす事でこれが両輪となり、活動方針や具体的な方策が、両者によって構成される「合同委員会」によって決定されてゆく(重要事項については総会による承認によって決定)。かつて芥川氏が存命の時代は、「音楽監督」の役職があり、演奏委員会(当時は「技術委員会」名称)のメンバー選出に当たっての人事権を持っていたが、氏の歿後は常に空席であり、その空席を補うべくこうした機構が徐々に整備されて来ていた。簡単に言えば合同委員会の決定権限が強化されたという事である。また演奏委員会は演奏会に於ける団員個々の人事権に限って、握るに至っている。これが芥川氏歿後10年を経るうちに、音楽監督の空席を前提として、新響が行なった組織改革の中身である。この事は後に説明する事に深く絡んでくるのでご記憶されたい。
この両委員会の構成メンバーの選出方法は全く異なっている。
演奏委員会を構成するのは各パートの首席奏者に限定される。高度な演奏技量が選出の尺度となる各首席奏者は1年毎に見直され、全団員による投票から始まる一連の厳重な手続きを経て最終的に総会の信任で決まる。委員長はこのメンバーの中から演奏委員会でまず人選される事から始まり、合同委員会の推薦⇒総会の信任の手続きで最終的に決まる。この手続きはかなり煩雑であり、投票から総会まで2ヵ月近い時間もかかり、制度を管理・運営するための膨大な人の手間もかかる。が、個々の団員にとって演奏会のローテーションを管理するという謂わば音楽監督の「人事権」を代行する人々を選ぶからには、各人の「納得」を得る上でもこうした制度を長い時間をかけても、敢えて創始してきた歴史がある。このプロセスを経て首席奏者になる人の数は、当然ながら限られている。
これに対し運営委員会のメンバーの人選は、まず運営委員長を全団員の投票によって選出する事から始まる。選挙期間が設定され告示⇒政見発表⇒投票・・・という流れで委員長が決まり、そこから委員長の意向によって各運営マネージャーが「組閣」されてゆく(総会で信任)。
これと並行してこのオーケストラの運営に積極的に関わっていこうとする者や委員長の指名によって「運営委員」が決まる。この運営委員には特別に信任手続きを必要としない。すなわち運営委員会のメンバーは自分の「意思」さえあれば、よほどの欠格条件が無い限り、確実に委員会入りして、その運営に対して深く関わっていく事が可能なのである。
こうした両委員会の成立ちの違いは、それぞれが果たすべき「機能」の違いに由来するものであるが、その違いが両委員会の性格の差異も決定づけていた。それは例えば構成メンバーの「流動性」に起因するものであったかも知れない。
演奏委員会のメンバーすなわち各首席奏者の顔ぶれは、若い人材を入れるべく毎年改選を行ってもそうそう変わるものではない(例えば筆者は現時点で、23年間フルートの首席奏者を務めている)。また自パートの人事に対する責任感は、他方で内向きの関心に傾きがちで、本来負っている運営の片翼への責任に対する無自覚さを生み、団全体の運営に対する無関心へ向かっていた事は、当時の状況を振り返ってみるとその一員として、やはり認めざるを得ない。
それは具体的には「合同委員会」への不参加という形ではっきり表れていた。これは裏を返せば合同委員会の「運営委員会化」という事を意味する。この風潮は新響と深く関わった最後の「部外者」である石井眞木氏との関係が切れた1994年以降強くなったように思われる。
■事後承認とルール無視の風潮
それ以降2001年当時に至るまで、この運営委員会の主流は、『日本の交響作品展’76』のサントリー音楽賞受賞によって新交響楽団を世に知らしめるにあたり多大な貢献をした人々とその賛同者たちだったと言ってよい。彼らは芥川氏の謦咳にも深く触れ、その歿後は生前の言動を伝えるとともに、その路線の「一部」に過ぎなかった「邦人作品」を更に深耕させていく事で、新響というオーケストラの独自性を確立してゆく方法であるという考えだった。そこでは「演奏会企画」が重視され、選曲するとはすなわち「企画を決めること」であり、その「企画」とは「どのようなテーマを持って、選曲の候補曲中に『邦人作品』を盛込むか?」を考える事に変貌しつつあった。そしてこうした「企画」重視は次第に選曲の「10年ルール」を浸蝕するにまで至ったのである。
この人々の企画立案の能力と、その実現に向けての行動力には瞠目すべきものがあった。それあってこそ自他共に新響の一時代を築いたと認められていたと言える。例えば1999年10月の第167回定期では、当時ハバロフスクの極東交響楽団芸術監督だったヴィクトール・ティーツ氏を招いているが、この実現のために彼らは文字通り東奔西走しており、それを団員も周知していた。或いは「邦人作品」企画に対する注力もそうである。費やされる時間も労力も到底他の団員の及ぶところではないレヴェルのものであったと断言できる。
こうした状況が何をもたらしたかと言えば「運営(企画)の専業化」に他ならない。彼らは自負と自信を以って、新響の方向性を決め、推し進める。一方で他の団員は、彼らの行動力を目の当たりにして、「彼らに任せておかざるを得ない⇒任せておけば良い」という依存的な体質に変容した。
これが更に進み、「行動を起こした者の考えには従うべきである」という風潮が蔓延し始め、団内でも公言されるに至る。「何故ならその行動は、純粋な情熱によるものだからだ(その情熱こそが、新響をアマチュアたらしめる根本である)」が理由として付け加えられた。そしてこれがさらに進行すると、こうして予め組立てられた「企画」に対し、合同委員会で異議をさしはさむ事が事実上出来なくなっていったのである。つまり莫大な予算が動くかも知れない非常に重要な案件であったとしても、誰かがその行動力によって独断専行してしまった事は、合同委員会でも「追認」するだけになってしまった。追認と言っても前述の通り、演奏委員会のメンバーは殆ど欠席で、一方の運営委員会の主流は彼らだった訳だから、こうなると殆どこのメンバーによる「壟断」と言って過言でない状態に陥っていたという事である。
これは新響の規約が緩やかな規定にとどまり、団員個々の「良識」によって運用されるように作られている事に一因があったと考える。そのような性格の規約でなければアマチュアオーケストラは早晩立ち行かなくなるからである。だが、反面その条文の行間や間隙を突けば無限の拡大解釈も可能である事を意味する。この時点で規約はそうした危機を迎えていた。
この体制は1996年7月に行なわれた2夜連続の演奏会(第152・153回定期)『日本の交響作品展’96』によって確立したと言えるかもしれない。彼らの主導によって新響創立40周年企画として行なわれたこの演奏会の掉尾を飾る作品として、諸井三郎の「交響曲第3番」が演奏されたが、その僅か3年半後の2000年1月(第168回定期)にも再演されるに至る。選曲に於ける「10年ルール」はあっけなく、いとも簡単に破られたのである。この選曲については遅くとも1999年前半には結論が出ていた筈であるが、新響内での評価も共有されていないこの作品の演奏に関して、空前絶後とも言えるルール逸脱がどのような過程を経て行なわれたのか?については、今もよく判らない。つまり極めて密室性の強い、横紙破り的な決定がなされたとの懸念を禁じ得ないのである。「壟断」の典型的な一例に敢えて挙げたい。
実を言えば2001年のマーラーも「10年ルール」を逸脱している。前回の演奏は1992年7月(第136回定期:指揮は小泉和裕氏)だが、この2001年は、新響と「マーラーシリーズ」を完結させた指揮者 山田一雄氏の歿後10年目に当たっていた。そして同時にこの指揮者の「埋もれた」作品である『おほむたから』の再演が試みられた。つまり『山田一雄歿後10年』という企画のもとに、選曲のルールは譲歩を余儀なくされる結果となった訳だが、この程度は仕方ないと受け止められていた。何と言ってもこの指揮者は新響にとって大恩ある人だった。そして『おほむたから』・・・これは本来『おほみたから(「おおみたから」とよむ)』と題されたものであるが・・・は、昭和20年(1945年)の年頭に演奏されたまま、50年ぶりの蘇演という事もあり、遺族より自筆スコアを借り受けてそこから改めてスコアとパート譜を起こすという「新響らしい」手作り作業(但し、流石に作業はPC入力に置き換わっており、全員が手書きで譜面を起こすという「美談」は過去のものとなっていた)も伴った。
だがこのマーラーの交響曲第5番が、10年を待たずして再演が決定された経緯についても、やはり不透明さは拭えないのである。
■技術的衰退
こうした状況の中、新響全体の技術レヴェルは明らかに後退していたと断言できる。演奏委員会の団内に於ける影響力は相対的に低下し、技術向上のための積極的な選曲案を呈示する代わりに、降りてきた演奏会企画(すなわち選曲)に沿ってその実行に当たっての技術的具体案を練るだけの存在になっていたためである。また企画によって俎上に上る頻度が格段に増えた「邦人作品」は、団員の演奏意慾を確実に下げていた。
そもそも新響創立40周年企画の一環として、この『日本の交響作品展’96』が決定するまでの経緯に於いても、「邦人作品」に対する新響内の位置づけを含め、議論が絶えなかった。それは新響の根強い成功体験となった1976年の同企画立案に際して芥川氏が提唱した新響にとっての「邦人作品」の定義である、
① 旋律が明確である。
② 調性がある。
③ 戦前・戦中時代の作品である
が、その後20年近い時間を経過する中で、その位置づけに変化を来たしているのではないか?との疑問に根ざしていた。日本の音楽界の実情も社会情勢も激変し、日本人の音楽作品の質も内容もおのずから変わって行く中で「 」付きの「邦人作品」にのみこだわる意味を見出しかねていたといえる。すなわち大半の団員は「邦人作品」への対応に倦み始めていたのである。これは今思い返しても危険極まりない兆候だった。新響に加わろうとする演奏者の殆どは、このオーケストラの技術的な力に自分を寄与させたいと考える。これは今も変わっていない。決して「邦人作品」を否定するものではないが、それが個々人の入団の「目的」とはなり難い。という訳で、企画を推進した彼らの真意は違うところにあったのかもしれないが、結果として個々の団員にとって・・・特に演奏委員会のメンバーにとって・・・「技術的向上の否定」と捉えられる結果を生んだ事は否定出来ない。事実2000年10月の演奏会(第171回定期)に於いて明らかな破綻となって顕れる。
筆者はこの直後に演奏委員長となった。2001年の年明け以降、演奏委員会の活性化に努めるべく腐心する。同時にこれまで傍観気味に過ごしていた、合同委員会での劣勢だった意見に、委員会としてバックアップした。それは「選曲に対する団員としての(そして新響の技術的向上を実現する見地から演奏委員会としての)意見を一層強く提示すること」にほかならなかった。これから半年ほどの間は、合同委員会は選曲を巡る論争の場となった。両者の主張や議論の推移について、それ以前もそれ以後も見られぬほどの綿密な議事録が毎回作成され、団内への公表前には両者のチェックが必ず入った。この一事を見ても、委員会の雰囲気が量り知られようというものである。半年ほどは一進一退の状況が続いた。ギリギリまで決着がつかず、最後は運営・演奏両委員長間での妥協策が図られた事もある。こうした状況の中で4月のマーラーの第5交響曲は演奏されていた。
■政策論争と転機
2001年8月初旬の合同委員会で、運営委員会サイド(つまり彼ら)から突然新響の体制改革案が提示された。この日筆者は委員会を欠席する事になっており、それを見計らった電撃策だった(と今でも思っている。それまでは必ず委員長間で事前に委員会に諮る内容について連絡を取り合っていたからだ)。それは、
①音楽監督を復活する(具体的な指揮者名あり)。
②音楽監督に対応する組織として、両委員会は統合する。
という事を主意としていた。その会合の出席者から晴天の霹靂というべき情報を受けて仰天すると同時に、その意味するところを考えた。
①については具体的候補者はあるものの、打診がどの程度進んでいるのかは明らかでない。実現の可能性も判らなかった。つまり将来的な①を実現する為に、すぐにでも②の体制改革をして行こうとするプラン・・・すなわち両委員会を統合する事に主眼があり、それは取りも直さず演奏委員会を無力化する意図と読めた(今でもそうだったと信じている)。またこれを実現するためには流石に「運用」で凌ぐ訳にもいかず、大幅な「規約改正」が必要とされた。
これが公表されると、これまで「邦人作品」路線を疑問視し、両委員会の確執を感じとっていた団員間にも考えを鮮明に表明する風潮が醸成されていった。そうした団員と筆者を含む演奏委員会のメンバーとの会合も頻繁に行われるようになる。事は選曲に端を発したこのオーケストラの「今後」の体制にまで深くかかわるものである。こうした時には様々な思惑から議論が交わされる。だがそこで最も主流になったものは、新響の「演奏主体・技術の向上」に対する危機感を抱く人々であったと言って良い。そして遂にはその流れの中から次期運営委員長擁立へと移っていく、というよりそうしない限り新響の本来の持ち味である「技術力」の保持は、難しいとまで我々は思いつめていたのである。新響団員である限り誰しも、「邦人作品」と向き合う事を否定しない。ただその偏重によって「技術力」が軽視される結果を招いている現状は望ましくない。技術力があればどのような企画も実現でき、且つ新たな人材も集まる。故に将来に向って団員のモチヴェーションを高揚させるべく、選曲の枠も更に拡大すべきである。という考え方である。
この年11月末の運営委員長選挙は、両派からそれぞれの候補者が擁立され、「政策論争」が起こった。これは例年予定調和的に信任投票で収束する委員長選挙とは全く趣を異にするもので、それ以前に例はなく、その後の10年間にも無い出来事だった。それぞれが政見を述べ、団員からの質問も相次いだ。開票結果も緊迫感の中で公表され、まさに「僅差」で我々の候補者が勝った。その後の新響の方向が明確になった瞬間だったと言える。「新政権」が運営の布陣をすると並行して「選曲ワーキンググループ」を立ち上げられたのはこれまでの流れを一望すれば当然だった。そして翌2002年、彼らは新響を去り、オーケストラ・ニッポニカを設立するに至る。選挙の際は僅差だったが、結局大多数の者が新響に残った。これが「邦人作品」に対する団員の考え方の表れと考えるべきであろう。
とはいえ、この後しばらくの間は、新響の「企画力」が衰えるのではないか?との懸念が団内に絶えなかったのも事実である。「選曲イコール企画」という呪縛が如何に強かったかの証左だった。だがここ10年の間に、技術的な理由や「邦人作品」定義の範疇外を理由に、それ以前には取上げられなかったあらゆる日本人作曲家の作品…例えば黛敏郎・武満徹・三善晃・矢代秋雄・湯浅譲二・権代敦彦等・・・の演奏を通じ、それが杞憂であった事を知っている。技術力を向上させて新たな人材を確保しつつ、広いレパートリーを聴衆に呈示する事が、聴衆・奏者双方の利益に資するという確信を得て今日を迎えている。
選曲の持つ重要性はこれまでに見たとおりだ。「ルール」に縛られる必要はないが、団員個々の演奏に対する向上心への希求を無視しては、この組織は成立たないとの認識は、この10年間で団内に深く浸透したと確言できよう。
新響の秘密〜運営委員長就任6年目にあたって〜
維持会員の皆様には、いつも新響をご贔屓にしていただきありがとうございます。本日は運営委員長の業務内容や新響の運営についてのお話をさせていただきたいと思います。
私が新響に入団してから早いものでもうすぐ19年、私のホルン人生の半分を新響で過ごしている計算です。東京で入るオーケストラを探したとき、コネがないと難しかったり、ホルンは一杯だからとあまり良い顔をされない所が多い中、新響は常時全パート募集(現在一部パートはクローズしています)で、見学の対応も丁寧で練習後飲みに誘ってくれたので、新響に入ることにしました。
実は学生の頃、参加していた室内オーケストラで、新響の名物運営委員長だった橋谷さん(故人)にエキストラで出演いただいたことがあり、楽器ができて運営もできる人はなかなかいないので、卒業後は是非東京に来て新響に入らないかと誘われたことがありました。結局卒業後しばらくは大学の医局で修行していましたが、その室内オーケストラでは立ち上げから関わってマネージャーという名前で会計と楽譜以外のほぼすべての業務を自分一人でやっていました。1人でやった方が手間暇がかからないというだけでマネジメント能力があったわけではありませんが、オケ運営のノウハウを手探りで身につけていました。
運営委員長就任は2006年11月で現在6年目です。私の入団から運営委員長になるまでの14年間に9人運営委員長が入れ替わり、平均任期は1.56年。毎年改選があり通常2年務めて交替するのが新響のやり方と思っていましたので、長くやってることがいいかどうかはわかりませんが、おかげさまで現在新響は平和だということかと思います。
<運営委員長のお仕事>
オーケストラの運営というと、本番や練習会場の予約、宣伝活動やチケット販売、プログラム作製、楽譜や楽器の手配、演奏会の受付といった実務を思い浮かべると思います。もちろんそのような実務を取り仕切るのが運営委員長ではありますが、「新響が良い演奏活動をするためにどう運営して行くか」を考え実施するのが運営委員長の責務と考えています。ですので、具体的に運営委員長はこれをするという業務はなく、実際に前任者から何も引き継ぎはなかったし、その時々の運営委員長の考え方や状況で組織は変化します。
プログラムに掲載する団員名簿をご覧になると運営委員の印が半分以上についていてマネージャーが10人以上いるのがわかると思います。運営業務はもっと少ない人数で管理し決定した方が効率的かもしれません。しかし企業ではなく団員に上下関係はありませんので、業務を細かく分けて多くの団員が運営業務を行い、実務をする者が自分の判断で出来るような形を取っています。私は各セクションの業務をできるだけ把握するようにし、うまく回らない箇所を自分でカバーしてしまうので、結果自分の首をしめることもありますが。
新響には「運営委員会」ともう一つ「演奏委員会」というものがあります。演奏委員会はパート首席からなる組織で、ローテーション(誰がどの曲の何番を受持つか)やオーディション、練習内容について決定します。演奏委員会がクローズドであるのに対し、運営委員会・合同委員会は団員であれば誰でも参加し意見を述べることが出来ます。どういう指揮者や曲目になるかはアマチュアオケマンにとって最重要ポイントですが、それを首席奏者会ではなく、運営が先導して全団員が参加できる合同委員会で決めるというのが新響のこだわりです。
<すべては良い演奏のために>
やはり、新響は一番に「良い演奏」を目指さないといけない、それは過去も未来もきっと同じです。では、新響にとって良い演奏とはどんな演奏でしょうか?単に小ぎれいでそろっているだけの演奏をして「お上手ね」なんて言われても少しも嬉しくはありません。もちろん、いわゆる技術的に高いものを目指すことは当然ですが、言葉に表すのは難しいけど、気持ちのある演奏、「ああ面白いかった」と言われるような演奏をしたいと私は思います。そのために何が必要なのでしょうか。
新響のよいところの一つは、団員の皆が新響に一所懸命関わっているところだと思います。前プロ1曲決めるにも戦いで、皆が新響の一員であることを楽しんでいたのではなかったかと思います。だから想いもあったし演奏にエネルギーが生まれた。今はどうでしょう、パワーが減って来てはいないでしょうか。ですから、運営委員長としてまずやらなければいけないと思うことは、団員全員の新響に対する興味やモチベーションをもっと上げることであり、それが「良い演奏」につながるとのだと思います。
もう一つ新響のよいところとして、幅広い年齢層の団員が集まっている点だと思います。これについては高齢化だと憂いている人もいるかもしれませんが、私は誇りに思います。新響で演奏するという点では、団歴の長い人もそうでない人も平等です。新陳代謝は必要だけど、無理に世代交替をしようとすることはない。新響には守らなければいけないことがあり、その上で変わっていかなければならないのです。だから、団歴の長い人にも運営でもっと活躍してもらいたいし、若い人には新響がどのようになりたってきているのかを知ってもらいたい。そのための場を作り将来に伝えていくことが、委員会に今まで多く出席して運営を見て来た私の義務ではないかと考えています。
以上は、5年前に運営委員長に立候補したときの演説の一部です。当時、団員の平均年齢は上がっているのに無理に運営を若い世代に託そうとして上手く行かず、演奏技術自体は良くはなっているのになんか求心力がなく、演奏会にお客さんもあまり入らないという状況でした。このままいくと新響がつぶれるんじゃないかという危機感がありました。
まず運営組織をフラットにし、適材適所を考え多くの団員が活躍できる場を作りました。それから団員が演奏する曲に対して興味と愛着を持てるように、例えばプログラム作成に誰もが参加できるようにし、記事は出来次第ネットで閲覧できるようにしました。それとお客さんをたくさん入れることを考えました。これが一番力を入れた点かもしれません。演奏会は、どんなに上手い演奏したとしても、お客さんが少なければ良い演奏会とは言えません。満席だと演奏する方も充実感があるしお客様にも新響って人気があるのねと思ってもらえます。細かいところでは、見学に来てくださる入団希望者の方に明るく挨拶しましょう〜というところから、新響のイメージアップをはかるようにしました。それとチラシの裏面の文章は、別に運営委員長の仕事ではありませんが、私が毎回書いています。以前は新響を語るような内容が多かったのですが、そうではなくお客さんに演奏会に行ってみたいな〜と思ってもらえるよう、企画意図と曲の魅力が伝わるようにしています。
<皆がいるからこそ新響>
新響には定年はありませんし、何年かごとの再オーディションもありません。つまり、入ってしまえば(団費演奏会参加費を払って練習に出てさえいれば)ずっと団員でいることが出来ます。オケのレベルを上げるために定年や再オーディションが必要なのではと言われたことがあります。実は私も入団したての頃、なんでやらないのかと思っていましたが、それは新響らしい演奏をするためにやらないのだと理解するようになりました。技術だけ優れている人をその時々で集めても良い演奏にはならないし、上手い人もそうでない仲間も、皆がいるから新響なのです。
新響のローテーションには、本番の出来だけでなく練習時の演奏も評価され反映されますので、ある意味数年ごとにオーディションを受けるよりシビアかもしれません。それよりも大切なのは、団員が新響に愛着を持てるかどうかだと思います。新響には60歳を超えた団員が多数いますが、今でも進歩して素晴らしい演奏をする団員もあり、若い団員の励みや目標になっています。そして将来新響のレベルについて行けなくなったら自分から身を引く覚悟でいるのは私だけではないでしょう。
それはそれとして、新しい団員を獲得し演奏での活躍の場を作ることも積極的にしています。それは新響が将来も新響であってほしいというのが団員の願いだからです。
<全団員が納得して活動をすること>
団員向けに新響ニュースが作成され練習時に配布されます。1964年に第1号が出されて以来、現在1255号まで発行され、練習日程や団員の情報、各委員会の議事録などが掲載されます。ほぼ毎週の時代もありましたが、今はメーリングリストでも連絡ができるため、月に1〜2回の発行となっています。合同委員会の議事録は詳細に書かれ、指揮者や曲目の決定過程などを知ることが出来ます。その議事録も書記が作成し出席者が確認して修正し、団員に伝えたいことを盛り込みます。とても手間がかかっているますが、全団員が納得して同じ方向を向いて活動をするためには必要なことなのです。
また、ローテーションを決めるのも手間がかかっています。各首席が自分のパートの案を提出し、演奏委員会で2〜3時間かけて協議します。単に上手い順に割り当てるのではなく、各団員の適性やモチヴェーション、将来性などを考え、演奏自体および新響の活動が良い結果になるよう考えます。そのパート首席も投票を参考に決めるのですが、その手順も長年の協議を経て今に至ります。全団員が決定に関与して手順を踏んで決めるというのも、全団員が納得して演奏をするために必要なことなのです。
<曲目はどのようにして決まるか>
例えば団員にどんな曲を演奏したいかアンケートをとって上位の曲を中心にプログラミングするというアマチュアオーケストラは多いのではないかと思いますが、新響はそれはしません。個人の演奏したいしたくない、好き嫌いという気持ちでは議論にならないからです。新響にとって演奏する意義があるかどうかを考えます。
昔から「10年ルール」という不文律があって、一度演奏会で取り上げたら10年間は演奏しないことになっています。レパートリーが偏らないためですが、この曲には当分会えない(もしかしてこれで最後)気持ちで、大切に演奏することができるのではないかと思います。
新響の場合は、まず指揮者が決まってから曲を考えるのですが、指揮者の意向をかなり尊重します。曲を決めるために指揮者を囲んで食事会をすることもあります。もちろんまず新響としてこれをやりたいという意思表示をしますが、曲や組み合わせにはこだわりを強く持つ指揮者もあり、協議に長い期間かかることもあります。指揮者に面白いと思って振っていただいた方が、結果的に良い演奏になるし、また新響と共演したいと思ってもらえるのではないかと考えています。
規模の大きいアマチュアオーケストラでは、どうしても大編成の曲ばかりになってしまいがちです。新響の場合、管打楽器は3管編成の倍の人数を定員としており、優秀な人があれば定員オーバーでも入団いただくので、毎回全員出演できるプログラムを組むのは難しいです。できるだけ全員が活躍できるようにしたいが、たまには編成の小さい古典派のような曲もやることもオケにとっては必要です。基本的には定員分の席の数を揃えるのが原則だが、そのプログラムが新響にとって意義があれば出演できない団員があっても納得してもらう。しかし、前後の演奏会でバランスをとるようにしています。
難易度や経費なども考慮しますが、余程でない限りこれらでは制約しないので、結果的に手間もお金もかかる企画になり、新響らしい(無茶な?)プログラムになることが多いです。その時には維持会費を使わせていただいており、維持会があるからこそ実現できるプログラムも少なくありません。特に来年は、経費のかかる企画が並びますので、どうか楽しみにしていてください!!
<運営上の悩み事>
その他にも、団員三大義務(=練習参加、団費演奏会参加費納入、集客:練習出席率と滞納金とチケット販売枚数は集計され団内に公表されます)、託児の会など新響の運営で紹介することはたくさんありますが、きりがありませんので、最後に「新響総括図」を掲載したいと思います。これは大昔からあるもので、年に1度の総会で配布される総会資料の最後のページに必ず載せているものです。新響の運営の基本的な考え方は、これに集約されていると言ってもよいです。
しかし、すべてがうまく行っている訳ではありませんし、いつも問題点はあります。新響が通常演奏会場にしている池袋の芸術劇場が改修工事で6回使えず、特に今度の演奏会は、元々15日の日曜にミューザ川崎で行う予定でしたが、震災の影響で使用できなくなり、何とかホールを確保しましたが、土曜夜というイレギュラーな演奏会となり、維持会員の皆様にはご迷惑をおかけします。また、20年間メインの練習会場として慣れ親しみ現在は楽器庫としても使用している労音十条会館が、来年道路拡張のために取壊される予定で、倉庫の移転と練習会場の確保が課題であります。
あとは合同委員会(平日の夜に行っています)の出席者が少ない。何か揉め事や刺激的な議題があると20人近く参加するのですが、任せておいてもそう変な事にはならないという安心感があるのか少なくて困っています。驚くような企画を提案するしかないでしょうか。AKB48のように年に1回じゃんけん大会でトップやパートを決めて演奏会をしよう・・・とか。
<アマチュアである誇り>
このような私たちの活動も、見方によっては音楽遊びを大真面目にやっているに過ぎず、単なる自己満足かもしれません。その活動に意味を持たせてくださるのが、聴いてくださるお客様であり、特に維持会の皆様には財政面だけでなく精神的な支えになっていただいており、感謝しています。
もう一つ私たちの活動を支えているのは、アマチュアとしての誇りなのではないかと思います。アマチュアとは音楽を愛すること。音楽はみんなのもの、音楽にはプロもアマチュアもない。でもアマチュアらしい新響にしか出来ない演奏をしよう〜という気持ちで取り組んでいます。
今回の演奏会ではロシア5人組の作品をプログラミングしましたが、彼らはアマチュア作曲家でした。5人組の指導者的な役割であったバラキレフは音楽の仕事をしていましたが(大学では数学専攻)、リムスキー=コルサコフは海軍軍人(のちにペテルブルグ音楽院の教授となる)、ボロディンは化学者(医学部教授)、ムソルグスキーは文官、キュイは陸軍軍人として余技の作曲活動を行っていました。当時ペテルブルグ音楽院が設立され西洋音楽を教え音楽を専門の職業とするための場であったのに対抗し、無料音楽学校を設立するなどロシア国民楽派といわれる活動を行いました。
もちろんアマチュアと言っても、ボロディンは作曲家として社会的責任を意識して活動をしていたということですし、私たちが新響で楽器を演奏するのとは次元が違うでしょう。以前新響でロシアから指揮者のティーツ先生をお呼びしたとき、あまりに厳しかったのですが、どうも日本で言うところのアマチュア演奏家という概念がないということがわかり、厳しいのも納得でした。しかしながら、同じ「非職業」で音楽に接し、自国の作品を取り上げようと取り組んでいる私たちにとって、非常に親近感がありますし、アマチュアの本分である「音楽を心から楽しむ」ことを実感できる演奏会にしたいと考えています。
3曲とも楽しくリラックスして聴けるプログラムです。ホールも木の温かい響きのする東京オペラシティですので、是非ご来場ください。
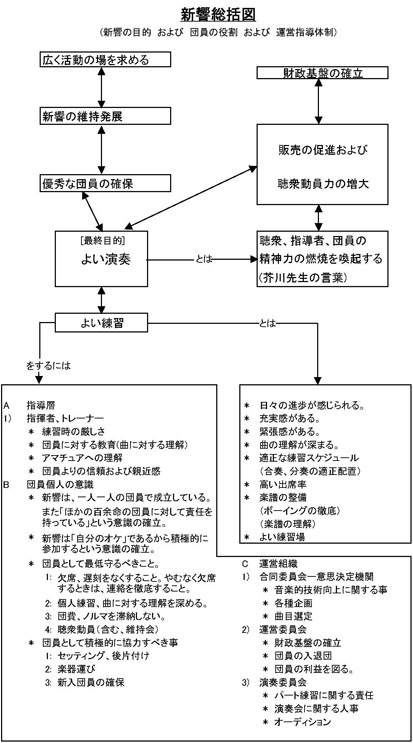
ムソルグスキー/ラヴェル:組曲「展覧会の絵」
●少年時代から展覧会の絵作曲まで
モデスト・ペトローヴィチ・ムソルグスキーは1839年にロシア、プスコフ県トロペツ郡カレヴォというロシア最西部の小村に生まれた。西へ100kmほどで現在のベラルーシとの国境である。ムソルグスキー家は由緒ある貴族の家系であり、小村と言ってもその領地は広大であった。母親も音楽に優れた人だったが、ピアノと音楽に対する息子の非凡な才能にいち早く気づき、7歳から音楽の専門家の家庭教師をつけた。当時のロシア貴族は、幼少時は家庭で教育されるのが常であり、音楽以外の学科もこの家庭教師が教えた。
カレヴォ時代は自家の農奴や近くのトロペツの町の人々とも接し、ロシアの民話、歌、故郷の歴史等に親しんだ。後の民族的、民衆的音楽への志向は、この時代の環境が少なからず影響していると思われる。
10歳になると、これまた当時のロシア貴族の子弟の常として、ペテルブルクの寄宿学校に入り、13歳で近衛士官養成学校に入学したが、並行して当時人気の音楽教師ゲルケからピアノと音楽の教育も受けた。この時期はピアニストとして成長著しく、学内やサロンでしばしば演奏していたようである。士官学校での成績も一貫して優秀で、17歳で当時の花形部隊に配属された。
軍勤務の中でも音楽活動は継続していた。その中で1857年にバラキレフと出会う。バラキレフはムソルグスキーの音楽の師であると同時に、経験不足を理由にしり込みする弟子たちに、積極的に作曲活動を進めるよう扇動する役も担っていた。
バラキレフの周りには、彼の強烈な指導力の下、音楽家を中心としたサークルが形成されていた。メンバーには音楽家だけでなく、音楽以外の芸術家、学者なども含まれていた。その中に以後ムソルグスキーと深く関わりを持つ人物がいた。考古学者、芸術史家、芸術評論家のスターソフである。彼は生涯にわたって多方面からムソルグスキーの音楽活動を支えた。このサークルの作曲家たちを「力強い一団(仲間)」と呼んだのもスターソフである。ロシア国内では5人組というより、こちらの呼称の方が一般的であるらしい。
「力強い一団」は1860年代の10年で大きく成長し、様々な紆余曲折はあったもののロシア音楽界での評価を高めていった。しかし個々の作曲家が力をつけ自立していった結果、バラキレフの指導力は低下し、サークルは徐々に解体し、ムソルグスキーはメンバーとも疎遠になっていった。
わずかな例外の一人がスターソフで、ムソルグスキーは頻々と彼の家を訪ねていた。スターソフ家では多くの人々と知り合ったが、その中の一人にハルトマン(ロシア語の発音ではガルトマン)という建築家がいた。ハルトマンは1834年ペテルブルクの生まれで、画家でもある。二人はたちまち親しくなり、そこから親交が始まった。しかし出会って3年後の1873年、ハルトマンは動脈瘤の破裂により急死してしまう。
翌年1874年の2月から3月にかけて、スターソフらにより、故ハルトマンの遺作展が開かれた。会場はハルトマンの母校であるペテルブルク美術アカデミーである。遺作展では水彩画、建築デザイン、舞台装置や衣装のデッサン等の他、工芸品なども展示された。その中には、お伽噺のバーバ・ヤガーの家の形の暖炉時計もあり、作品総数は400点にのぼった。
この遺作展を見たムソルグスキーは、これらの作品にちなんだピアノ組曲を書くことを思いついた。
ある種興奮状態にあった彼は、1874年6月にこの曲をわずか3週間で完成させた。筆の遅いムソルグスキーには異例の速さである。
●リムスキー=コルサコフによる改訂と出版
このピアノ組曲は彼の生前には演奏されることなく埋もれていた。長年のアルコール摂取過多が原因で1880年に42歳の若さでムソルグスキーが亡くなると、使命感に駆られたリムスキー=コルサコフが、未出版あるいは未完の楽譜の整理と校訂を行った。作業は2年間にわたり、その間、自分の作曲活動を縮小してまで精力的に行った。展覧会の絵も、改訂を経て1886年に出版された(通称リムスキー=コルサコフ版、以下RK版と略す)。
バラキレフのサークルでも年少で、年齢が近いことからこの二人は特に仲が良く、1872年から約1年間は、リムスキー=コルサコフの結婚まで、同居生活を送っていた。夜ごと音楽議論を戦わせていたようで、その点からも彼は自分がムソルグスキーの音楽の最大の理解者であると自負していたのではないだろうか。
この改訂作業は、今となっては作品本来の力強さや独創性を損なうものとして批判的に捉えられる傾向がある。だがリムスキー=コルサコフの目には作品の多くは未完成であると写り、これらを完成させる使命を自らに感じたのであり、また、この作業により多くの曲が出版され、世の知るところとなったゆえに、自筆譜までさかのぼって調べようという音楽家が現れたわけで、その意味で彼の貢献は多大であると言える。
●ラヴェルによるオーケストラ編曲版
ピアノ曲としての展覧会の絵は、楽譜出版後もほとんど演奏されることはなかった。この曲が一気に有名になるのは1922年にラヴェルによるオーケストラ編曲版が初演されてからである。ラヴェルに編曲を依頼したのは指揮者のクーセヴィツキーで、このオーケストラ編曲版の成功により逆にピアノの原曲が注目されるようになった。ただし使用された楽譜は、まずはRK版で、ムソルグスキーの自筆譜に基づくいわゆる原典版が演奏され始めるのはさらに後の事である。
ラヴェルがベースにしたのもRK版であり、その時点で原典版から和音、ダイナミクス等の若干の変更がある。有名な違いは、第4曲ビドロの冒頭で、原典版ではffで始まるのに対し、RK版ではppとなっている点と、もうひとつ、第6曲サミュエル・ゴールデンベルクとシュミュイレの最後が、原典版ではC-D♭-B♭-B♭であるのに対し、RK版ではC-D♭-C-B♭となっている点である。ラヴェル版もこの2点はRK版と同じである。加えてラヴェルは第6曲の後のプロムナードを割愛している。
●曲とハルトマンの絵の関係
展覧会の絵という曲は、ハルトマンの絵をそのまま音で描写した、というものではない。事実、曲から感じられる壮大さ、強烈さからすると、対応すると言われている実在の絵のサイズは驚くほど小さい。小さいものはハガキ大、大きくてもA2サイズ程度である。
絵を見る限り「展覧会の絵」の各曲がそれらを直接に音で表現したものとはとても思えない。象徴的なのは第6曲で、2人のユダヤ人の絵は、実は別々の2枚の小さな絵なのである。どちらが金持ちとも貧乏人ともわからないし、会話をしているわけでもない。ムソルグスキーはこの2人に性格をつけ、会話する絵を頭の中に作り上げ、それを曲にしたのである。
要するに、この曲は「音によるハルトマン回顧展」なのである。もちろん、実際の回顧展の出品作品からインスピレーションを受けたことは間違いないが、直接知るハルトマンの人となり、思想などからムソルグスキーが作り上げた架空のハルトマンの絵を、音で表現したものなのではないだろうか。
●曲の構成
Promenade プロムナード
まずは有名なトランペットソロで始まるプロムナードである。回顧展に足を踏み入れたムソルグスキーの、作品たちへの期待、故人を偲ぶ気持ち、などがないまぜになった心持ち、というところか。
I.Gnomus グノムス
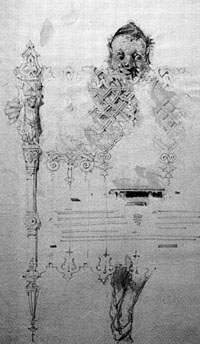
地の底に住むという、伝説の小人の妖怪である。悪賢くていたずら好きだが、ロシアの人々には愛されているという。速く細かい動き、静止、ゆっくりした動き、の繰り返しが、小さい妖怪の動作なのか。
Promenade プロムナード
一つ見て、次の絵に進むムソルグスキーの心持は、やや穏やかになったようである。
II. Vecchio Castello 古城
題名はイタリア語だが、一貫してロシア的な雰囲気のこの曲からすると、ムソルグスキーの思い描いたのはロシアの城かもしれない。薄暗い感じなのは天気が悪いせいか、夕暮れなのか。
Promenade プロムナード
暗い絵の後だが、なぜか元気が出てきた。振る手もちょっと大きい感じだ。
III.Tuileries チュイルリー
チュイルリーはルーブル美術館に隣接する公園。現存する。ピアノ版には遊びの後の子供たちの喧嘩という注釈がある。公園の絵は無いが、喧嘩する子供たちのデッサンはいくつかある。
IV.Bydlo ビドロ
ビドロとは牛の曳く荷車のことである。この曲の解釈は最も議論が多い。圧政に苦しむポーランドの人々を牛車に喩たとえた、という説もある。苦役にあえぐロシアの農奴かもしれない。ppで始まるラヴェル版、RK版だと目の前を通り過ぎる牛車の傍観者の視点、ffで始まる原典版は重い荷を引く当事者の視点、という解釈が一般的になっているようだ。
Promenade プロムナード
ちょっと心が冷えてしまったようだ。歩く速度も心なしか遅い。
V.Ballet des poussins dans leurs coques 殻をつけたひよこの踊り

ちょこまか動く、まだ殻をつけたままのひよこたち。絵はジュリアス・ゲルバーのバレエ「トリルビー」のための衣装デッサン。
VI.Samuel Goldenberg und Schmuyle サミュエル・ゴールデンベルクとシュミュイレ

金持ちと貧乏人という設定はスターソフが生前のムソルグスキーから聞いていたようで、出版譜の解説に書かれている。高圧的な金持ちと、卑屈でなにやら言い訳している貧乏人。
(Promenade)
ピアノ版にはあるこのプロムナードはラヴェル版では割愛されている。
VII.Limoges - Le marchè リモージュ:市場
リモージュはフランス中部やや西よりの陶器で有名な都市。数年前に筆者は訪れたことがある。早速市場に行ったが、今は屋根がついて薄暗い感じで、屋台や小さな店が並んでいた。曲の感じからして当時は青空市場だったに違いない。自筆譜には女が取っ組み合いをしている、と書かれた文字が線で消されているという。
VIII.Catacombae - Sepulchrum Romanum, Cum mortuis in lingua mortua
カタコンベ:ローマの墓地、死者たちと共に死せる言葉で

骸骨が壁一面に積み上げられた地下墓地である。この曲は2つに分かれている。前半は金管主体でカタコンベの雰囲気を表し、途中からヴァイオリンの高音のひそやかなトレモロが始まる。ここからが「使者たちと共に死せる言葉で」に相当する。闇になれた目に映る骸骨が燐光を放っている。
IX.La cabane sur des pattes de poule(Baba Yaga)
鶏の足の上に建つ小屋(バーバ・ヤガー)
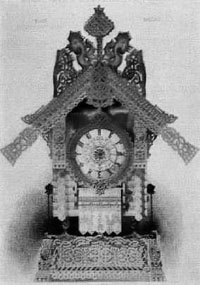
森にすむ骨と皮だけにやせこけた老婆の妖怪、バーバ・ヤガーの住む小屋である。臼に乗って移動し、その跡をほうきで消すという。曲の感じでは、かなり激しく動き回っているように思える。中間部では神秘的な森の様子も描かれている。
X.La grande porte de Kiev キエフの大きな門
キエフはモスクワ遷都以前のロシアの中心であり、その時代の栄光を象徴する壮麗な凱旋門があったが、老朽化していた。この門を再建するための建築コンペがあり、ハルトマンもこれに応募した。結局門は再建されなかったが、ムソルグスキーはそのハルトマン設計の門をこの曲で音として構築し、曲の最後に据えることにより、ハルトマンの業績と人物を讃えた。途中挿入されるロシア聖歌は故人を悼むためとも考えられる。ハルトマンと共にロシアの栄光も讃えるような、壮大なフィナーレは、大伽藍が目の前に現れたかのようである。

ピアノ版初演:不明
ラヴェル編曲版初演:1922年10月19日、セルゲイ・クーセヴィツキー指揮、パリオペラ座にて
楽器編成:フルート3(うちピッコロ持替)、オーボエ3(うちコールアングレ持替)クラリネット2、バスクラリネット、アルトサックス、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、グロッケンシュピール、鐘、木琴、トライアングル、ガラガラ、ムチ、小太鼓、大太鼓、シンバル、タムタム、ハープ2、チェレスタ、弦五部
参考文献
『ボロディン、ムソルグスキー、リムスキー=コルサコフ―嵐の時代をのりこえた「力強い仲間」(作曲家の物語シリーズ)』ひのまどか(リブリオ出版)
『追跡ムソルグスキー「展覧会の絵」』團伊玖磨、NHK取材班(NHK出版)
『ムソルグスキーその作品と生涯』アビゾワ(伊集院俊隆訳)(新読書社)
『ムソルグスキー、「展覧会の絵」の真実』一柳富美子(東洋書店)
ボロディン:交響曲第2番
【序奏】
ボロディンという作曲家は、クラシックを好きな人にとってもさほど馴染みはないのではないかと思うが、私個人にとっては、誕生日(11月12日)が同じということから始まって、色々と身近に感じて来た作曲家の一人である。私が初めて経験したオーケストラの演奏は、中学校のオーケストラ部だったが、その時の曲目の中に、彼の交響詩「中央アジアの草原にて」があった。ちょうど授業で国民楽派とかロシア五人組などを習った頃でもあり、それまで知っていたクラシックの名曲とは雰囲気が大きくかけ離れていて深い印象を持った。またその頃、NHKの深夜ラジオ番組のテーマ音楽に有名なノクターン(弦楽四重奏曲第2番第3楽章)が使われており、父がかけっぱなしにしていたラジオから流れて来る甘美なメロディーと癖のある和音進行によく耳を傾けたものだった。その後数え切れないほど彼の曲を演奏したが、彼の生涯を思い起こす度に、よくこれだけの宝を残してくれたと、心から尊敬せずにはいられない。
【主題提示部】
1833年、サンクトペテルブルグでアレクサンドル・ポルフィリエヴィチ・ボロディンは大貴族の私生児として生まれた。当時の習慣に従い、父のもとで働く農奴の嫡出子として届け出がなされ、母親や実父、義父に大切にされて育ち、化学と音楽の両方の才能を存分に伸ばし、17歳でペテルブルク医科大学に入学した。ヨーロッパ留学から帰った1862年から1887年までの25年間、この大学で化学者、医者として勤務した。彼の留学先はドイツのハイデルベルク大学で、ここではブンセン、キルヒホッフ、ヘルムホルツといったそうそうたる学者たちに学び、また同期の留学生にはメンデレエフが在籍しており、ボロディンが化学の分野でも世界第一線で活躍した人物であることが分かる。化学者としての業績で代表的なものは、ボロディン反応(ハンスディッカー反応)の発見である。この反応はハロゲン化アルキルの合成法であると同時に、ラジカル反応の例として現代の有機化学の教科書にも出てくる。また、求核付加反応の一つであるアルドール反応を発見した。

ボロディンは、この留学中に優れたピアニストであるエカテリーナ・プロトポポーヴァと出会い、彼女を通じてシューマン、リスト、ワーグナーの音楽を知る。そして彼女は生涯の伴侶となった。

ロシアに戻って間もなくバラキレフと出会い、彼のグループ『力強い仲間』(日本ではロシア五人組と呼ばれている)に加わる。バラキレフの影響と指導の下、彼は交響曲第1番を書き始め、約5年をかけて完成した。1869年から交響曲第2番を書き始めるのであるが、この年彼はオペラの作曲に意欲を持ち、「イーゴリ公」に取りかかり始める。「イーゴリ公」はこの後度々作曲を中断し、結局20年近くかけて半分しか完成しなかったが、文字通り彼のライフワークとなる。中断中に「イーゴリ公」のための音楽の多くが交響曲第2番に転用され、「イーゴリ公」に盛られている東洋的な情緒、勇壮で英雄的な楽想は交響曲第2番にも同様に流れている。
1872年、ボロディンはロシア初の女子のための医学課程開設の責任者となり、1875年には化学科の主任教授となる。プライベートでも妻の転地療養に付き添い、また養女を迎えるなど一段と多忙になり落ち着く暇もなかった。その忙しい仕事の合間を縫って、1曲1曲を極めて長い期間をかけて作曲し続けた彼は自分のことを日曜日の作曲家と語っていたが、実際には夏休みの作曲家と呼ぶのがふさわしいくらいだった。そんな彼を励まし続けたバラキレフグループの仲間たちの存在や、当時の音楽界の巨匠リストがボロディンの音楽を絶賛し自ら指揮をして演奏したことが、かろうじて彼を音楽の世界に繋ぎ止めていた。毎週末の夜はリムスキー=コルサコフと楽器の研究を続け、楽器の知識や管弦楽法を身に着けていった。そんな時、たまたま足に火傷を負いひと月大学を休む羽目になったため、交響曲第2番を無事に完成することが出来た。
1887年の2月、大学主催の舞踏会の席で彼は突然倒れ、そのまま息を引き取った。心臓発作であった。医者である彼は死期を悟り、それを誰にも語らず秘かに身辺の整理をしていたという。
【展開部】
ボロディンはいわゆるアマチュアだったわけだが、思わぬところでそれを認識させられたことがあった。学生時代作曲の師匠からドミナントをひと通り教わり、次に各種サブドミナントを習い始めると、準固有和音やらドッペルドミナントなど様々な表情を持った綺羅星のごとき和音を沢山知ることが出来た。そして、喜び勇んでそれらを駆使したソプラノ課題などを作って持っていき、師匠からお叱りを受けるということが度々あった。師匠…つまり作曲のプロ…の言葉を要約すると以下のようになる。
和声進行の基本はトニックとドミナント。極時々、ちょっとした色の変化を付けるためにサブドミナントを混ぜる。サブドミナントを多様するのはいかにもアマチュア。それらは砂糖を入れ過ぎた珈琲のようなもの。甘ったるくてすぐに飽きが来る。
ところでそのサブドミナントが連なる和声進行は、まさにボロディンの「ノクターン」や「中央アジアの草原にて」の中で、彼の個性と言っていいほど、度々使われているのである。しかもそれは何と甘く心をくすぐり、うっとりとさせる響きであろうか!なるほど確かに彼はアマチュアだが、間違いなく極上のアマチュアだった。もちろんボロディンはアマチュアという立場に甘んじることなく一人の音楽家として世界に討って出たのだと思うが、もしかしてプロとしての縛りとか、常套手段からは比較的自由であったため、このような個性的な音楽が書けたのかもしれない。
【再現部】
1869年、交響曲第2番は第1番が初演された直後に着手するが、いつものごとく時間を要し、最終的に完成したのは1876年だった。初演は成功とは言えなかったが、リムスキー=コルサコフやリストが行ったその後の演奏は成功し、ボロディンの名声は国際的に広まりつつあった。なおこの曲の出版の準備段階でボロディンが亡くなったため、リムスキー=コルサコフがグラズノフの協力を得て校訂したが、出版の際に校訂者として彼らの名前が入り、ボロディンの楽譜に手を加えたかのような誤解を与えてしまっている。実際にはメトロノーム記号を加えたり、テンポの指定をしたのみでリズム、旋律、和声にはいっさい手を加えていない。
第1楽章は、叙事詩的な雰囲気に石のような強さと簡潔さが加えられている。第2楽章スケルツォでは、巧みな管弦楽法とシンコペーションが見事な成果を上げる一方、トリオは東洋風のもの憂い静けさを醸し出す。第3楽章の緩徐楽章は、自由なロンド形式で詩情豊かなムードに包まれ、そして直接祝祭的な第4楽章フィナーレへとつなげられている。全体を通じて東洋風の素朴で勇壮な主題が、前述の彼独特の和声法である多様なサブドミナントや柔らかいドミナント(Ⅲの和音など)で味付けされ、変拍子の使用によってロシア的な抑揚も付け加えられている。まさに「ロシアの誇り」とでも呼びたいところだ。時間をかけた分この曲への愛情は強く、やりたいことを全部詰め込んだ印象を受ける。自信作だったことだろう。
【コーダ】
ボロディンは妻への手紙の中で、自分のことを「同時に、音楽家であり、公務員であり、化学者、管理者、芸術家、官吏、慈善家、他人の子供の父親、医者、そして病人…であることの難しさ。ついには最後に上げたものとして終わる」と語っている。音楽家としてだけではなく化学者としても超一流で、しかも温厚で優しい人柄から色々厄介なことを自ら引き受け、多忙を極めた生活の中に一生懸命時間を作って作曲を続けたボロディン。しかもそれらはごく少ない曲数であるが当時も多くの名声を集め、そして後世にも残って皆から愛され、こうして演奏され続けている。同じアマチュアとして音楽に取り組んでいる我々にとって、大いなる目標であり、また駄目な自分を叱咤激励する存在であり、文字通り「アマチュアの鑑」である。

初演:1877年3月10日、エドゥアルド・ナープラヴニーク指揮、サンクト・ペテルブルクにて
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トライアングル、タンブリン、シンバル、大太鼓、ハープ、弦五部
参考文献
『ボロディン、ムソルグスキー、リムスキー=コルサコフ~嵐の時代をのりこえた「力強い仲間」』
ひのまどか著(ニューグローブ音楽事典)
リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲
この曲、曲目解説などという面倒なものを読む必要のない底抜けに楽しくわかりやすい曲です。何の予備知識もなしで楽しめますので難しいことを考えずに楽しんでください。難しい顔して粗探ししながら聴いてはダメですよ(笑)。解説終わり
というわけにもいかないので、“ロシア五人組”やリムスキー=コルサコフ、そしてスペイン奇想曲について簡単にご紹介します。
1.“ロシア五人組”のこと
本日はいわゆる“ロシア五人組”の中で名曲を残した三人の作曲家の代表的なオーケストラ曲を揃えました。皆様は残りの二人の名前を思い出せますか?“研究家やロシア音楽愛好家以外にはあまりなじみのない二人”ですが、せっかくですからその二人のことにも触れてみます。
ロシア的な西欧音楽を書いて最初に成功した作曲家はグリンカ(1804-1857)だと言われています。その業績を発展させてロシアならではの音楽を創造し普及させようとしたのがロシア五人組です。グリンカの音楽は、ロシア国外での高評価にもかかわらずロシア国内ではあまり取り上げられなかったようです。そんな現状を変えようとグリンカの弟子バラキレフは、キュイ、ムソルグスキーさらにリムスキー=コルサコフ、ボロディンを仲間に迎え、お互い切磋琢磨してグリンカの精神を受け継いだ多くのロシア的な曲を産み出したのでした。そう、残りの二人はバラキレフとキュイという作曲家です。
バラキレフ(1837-1910)は才能豊かだが独善的な人だったようです。アカデミックな作曲技法を身に着けていたのですが、そのようなものはロシア音楽の本来の力を損なうとでも思っていたようで五人組の後輩たちにはそれらを習得させませんでした。あげく音楽界と衝突して失踪してしまいます。数年後に復帰しますが五人組を組織した頃の勢いは戻らないまま生涯を閉じました。
一方、キュイ(1835-1918)は辛らつな批評家でもありました。ラフマニノフが第1交響曲初演時に悪意ある批評を受けてノイローゼになったというのは有名な話ですがその批評を書いたのがキュイなのです。たくさんのオペラを作曲したのですが忘れられ、一部のピアノ曲だけが演奏されています。
2.リムスキー=コルサコフのこと
リムスキー=コルサコフは、バラキレフやムソルグスキーとは対照的で人格者として多くの人から尊敬された生涯を送りました。13歳でロシア海軍兵学校に入学、卒業後海軍に入隊し18歳で遠洋航海にも出ています。一方で音楽的才能にも恵まれ、趣味で作曲していました。18歳でバラキレフに出会ってその強烈な個性にひかれてそのグループに参加します。そこでいきなり交響曲の作曲を勧められ四苦八苦しながら完成させています。ただ、若き天才作曲家だったのではなく、バラキレフの無謀な要求に逆らえずなんとか仕上げた素人仕事だったのだと本人が後に述懐しています。
彼はバラキレフたちのもとで体系的な作曲技法を身につけないまま作曲を続けます。徐々に才能を開花させ、交響曲第2番「アンタール」や歌劇「プスコフの娘」などを作曲し評判となります。するとどういうことかペテルブルク音楽院から教授として招かれてしまうのです。いざ教授になってみたら自分が体系だった作曲技法の知識を持っていないことに気づき、愕然としたとのことです。そこで猛勉強をして和声学や対位法などを身に付けたのでした。教授就任時まだ27歳で海軍に所属したままだったというのですからペテルブルク音楽院もずいぶんと思い切ったことをしたものです。
リムスキー=コルサコフはムソルグスキーやボロディンの未完成に近い曲の補作を精力的に行ったことでも有名です。「はげ山の一夜」、「ボリスゴドゥノフ」、「ホヴァンシチーナ」「イーゴリ公」などの名曲は彼が補筆完成させなければ埋もれたままだったかもしれません。
さて、彼の晩年は20世紀初頭ロシア革命前夜の不穏な時代でした。ペテルブルク音楽院も無期限ストライキのような状況になり、彼は教授として学生たちの説得に当たりますが学生たちの妥当な要求には理解を示したために逆に音楽院を追われてしまいます。ところが、多くの理解者の働きかけにより反動的な音楽院院長が解雇され彼は復職を果たすのです。このことからも彼が多くの人から尊敬されるリベラルな考えの持ち主であったことが推察できます。
3.スペイン奇想曲のこと
「ECOS DE ESPANA(スペインからの響)」
5つの部分が切れ目なく演奏されます。一度聴いたら忘れられないエキゾチックな旋律そしてヴァイオリン、クラリネット、フルート、ホルン、ハープなどの派手なソロと華麗なオーケストレーションが魅力です。実はこの旋律たちはリムスキー=コルサコフのオリジナルではなく、JOSE INZENGAというスペインの作曲家がまとめたスペイン民謡集「ECOS DE ESPANA(スペインからの響)」に掲載されているものなのです。この民謡集の譜例を使って各曲を簡単に紹介しましょう。

ECOS DE ESPANA(スペインからの響)の表紙
1)アルボラーダ【Alborada】

アルボラーダの直訳は「夜明け」で、たとえばラヴェルの「道化師の朝の歌(Alborada del gracioso)」では「朝帰りの歌」を意味します。ただ、ここは底抜けに明るい少々おバカな曲で、そういった意味はないようです。
2)変奏曲【Danza prima】
一転して優雅な主題をホルンが奏で、いろいろな楽器の組み合わせで変奏していきます。

3)アルボラーダ【Alborada】
1曲目と同じ主題が半音上の変ロ長調で再現されます。オーケストレーションも1曲目より派手になっています。
4)シェーナとジプシーの歌【Canto gitano】

金管のファンファーレで始まり、各楽器のソロが聴きものです。情熱を内に秘めたしかし躍動的な旋律が魅力です。
5)アストゥリア地方のファンダンゴ【Fandango Asturiano】

開放的でさらに躍動的な「これぞスペイン!」とでもいいたくなるような旋律がカスタネットのリズムを伴ってどんどん盛り上がっていきます。最後はアルボラーダが高速で再現し限界まで加速して終わります。
初演:1887年10月31日、ペテルブルクにおいて作曲者自身の指揮、マリインスキー劇場管弦楽団
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2(うちコールアングレ持替)、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、小太鼓、大太鼓、トライアングル、シンバル、タンブリン、カスタネット、ハープ、弦五部
参考文献
JOSE INZENGA『ECOS DE ESPANA』
Biblioteca Digital Hispánica
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital
『ボロディン/リムスキー=コルサコフ』井上和男(音楽之友社)
『ロシア音楽史』フランシス・マース(森田稔・梅津典雄・中田朱美[訳])(春秋社)
第216回演奏会のご案内
ロシア5人組
19世紀中頃から、自国の民謡や民族音楽の語法や形式を取り入れた国民楽派と呼ばれる作曲家が活躍しました。ロシアにおいては、歌劇『ルスランとリュドミュラ』で知られる作曲家グリンカがイタリアで音楽を学んだ後、ロシア的な作品を書き『ロシア音楽の父』と呼ばれました。そのグリンカの愛弟子のバラキレフを中心としたグループが『ロシア5人組』です。
その頃設立されたペテルブルク音楽院が西欧音楽の伝統を教え、音楽を専門の職業とするための場であったのに対し、国民楽派の5人組はバラキレフ以外は他に本職を持つ非職業作曲家であり、無料音楽学校を開設するライバル関係にありました。今回の演奏会は、5人組のうちリムスキー=コルサコフ、ボロディン、ムソルグスキーの代表作をプログラミングしました。
非職業作曲家たち
リムスキー=コルサコフは海軍の軍人でした。12歳で海軍士官学校に入学し、在学中の17歳で5人組に参加しました。海軍士官として世界各国を訪れており、異国情緒ある曲多く書いています。『スペイン奇想曲』はその一つで、スペイン民謡を主題に多くの独奏楽器が活躍する華やかな楽しい作品に仕上げています。才能を認められ27歳でペテルブルク音楽院の教授に招聘され、多数の弟子を育てた管弦楽法の大家として名を残しています。
ボロディンは医科大学の教授でした。アルデヒドの研究で高名な化学者で、『日曜音楽家』だったため遺した作品数は多くありませんが、5人組では唯一交響曲で成功した作曲家でした。交響曲第2番は作曲家が『勇士』と名付けており、ロシアの広大な風景と人々の生活が豊かな響きで表されています。
「展覧会の絵」への思い
ムソルグスキーは軍人でしたが、その後文官となり、残念ながら晩年はアルコール依存症になり職を追われました。親交のあった建築家でデザイナーのハルトマンが急死し、その遺作展に着想を得たのが組曲『展覧会の絵』です。ハルトマンの絵を表わす10曲の合間に、絵の間をムソルグスキーが歩く様子を表わす「プロムナード」(フランス語で散歩という意味)が6回挿入されています。終曲の有名な「キエフの大門」は実在の建物ではなく、当時建築予定だった凱旋門のデザインコンペに出品されたもので、「卵の殻をつけた雛の踊り」はバレエの舞台衣装のデザイン画でした。人付き合いの苦手だったムソルグスキーにとって、仲の良い友人のハルトマンの死は大きなショックだったでしょう。この曲には亡き親友への想いが込められています。
原曲はピアノ独奏曲ですが、生前には演奏も出版もされませんでした。リムスキー=コルサコフが遺稿を整理して出版され、世の中に出ます。ピアノ曲としてはかなり難曲ですが、多くの作曲家が管弦楽への編曲を行いました。中でも最も演奏されているのが、オーケストラの魔術師といわれるラヴェルによる編曲の版です。色彩豊かな壮大な曲となっています。
どうぞお楽しみに!
第216回ローテーション
| スペイン奇想曲 | ボロディン2番 | 展覧会の絵 | |
| フルート1st | 松下 | 岡田 | 吉田 |
| 2nd | 新井 | 松下 | 藤井(+picc) |
| 3rd | - | 兼子(+picc) | 兼子(+Picc) |
| Picc | 丸尾 | - | - |
| オーボエ1st | 山口 | 亀井(淳) | 堀内 |
| 2nd | 桜井(+C.A.) | 亀井(優)(+C.A.) | 宮内 |
| 3rd | - | - | 岩城(+C.A.) |
| クラリネット1st | 品田 | 品田 | 高梨 |
| 2nd | 石綿 | 進藤 | 末村 |
| B.Cl. | - | - | 大薮 |
| Alto Sax | - | - | 進藤 |
| ファゴット1st | 長谷川 | 田川 | 浦 |
| 2nd | 浦 | 齊藤 | 長谷川 |
| C.Fg | - | - | 田川 |
| ホルン1st | 森 | 箭田 | 山口 |
| 2nd | 山口 | 市川 | 兪 |
| 3rd | 大原 | 森 | 箭田 |
| 4th | 市川 | 大原 | 鵜飼 |
| トランペット1st | 倉田 | 小出 | 野崎(Assi.北村) |
| 2nd | 北村 | 中川 | 青木 |
| 3rd | - | - | 手塚 |
| トロンボーン1st | 武田 | 武田 | 志村 |
| 2nd | 志村 | 志村 | 小倉 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 桑形 | 桑形 | 古関 |
| パーカッション | 大太鼓/中川 シンバル/古関 小太鼓/今尾 タンバリン+カスタネット/皆月 トライアングル/浦辺 |
大太鼓/中川 シンバル/古関 タンバリン/皆月 トライアングル/今尾 |
大太鼓/中川 シンバル/桜井 小太鼓+鞭/皆月 トライアングル/浦辺 グロッケンシュピール+木琴/今尾 チューブラーベル/桑形 タムタム+ラチェット/田中 |
| チェレスタ | - | - | 藤井 |
| ハープ1 | (*) | (*) | (*) |
| ハープ2 | - | - | (*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(長沼) | 堀内(長沼) | 前田(佐藤真) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(田川) | 小松(田川) | 小松(田川) |
| ヴィオラ | 常住(石坂) | 常住(石坂) | 常住(田口) |
| チェロ | 光野(柳部) | 光野(柳部) | 柳部(光野) |
| コントラバス | 中野(植木) | 中野(植木) | 中野(植木) |
(*)はエキストラ
マーラー:交響曲第5番
■作曲経緯
本作品の作曲は1901年に始まり、夏には最初の二つの楽章が完成していた。この1901年という年はマーラーにとって意義深い年であり、2月にはウィーンで「嘆きの歌」、11月には「交響曲第4番」が初演されるなど音楽面での成功がある一方、同11月には宮廷画家のヤーコプ・エミール・シントラーの娘アルマに初めて出逢い、二人は急接近し、翌1902年3月には結婚、長女マリア・アンナをもうける。マーラーの生涯で、最も幸福な時代(束の間であったが)は「交響曲第5番」とともに始まったのである。
ウィーンフィルの指揮者でもあった多忙なマーラーは、夏の休暇はオーストリア南部ヴェルト湖畔のマイエルニヒにある別荘で過ごし、作曲に専念することにしていた。

マイエルニヒの別荘
アルマとの新婚生活にあった1902年夏もこの自然豊かな別荘に滞在し、「交響曲第5番」をほぼ完成させている。(ただしその後幾度も改訂があった)。
当初は4楽章構成を考えていたマーラーだったが、結局は5楽章構成となった。この変更にはアルマの存在が、少なからず影響したようである。すなわち、第4楽章〈アダージェット〉である。トーマス・マンの小説を元にした、ルキノ・ヴィスコンティ監督映画「ヴェニスに死す」で用いられ、特に有名な楽章となった〈アダージェット〉は、アルマに贈ったものだと言われている。マーラーと親交のあったオランダの指揮者、ウィレム・メンゲルベルク が所有していたスコアには、マーラー直筆の修正の他に、第4楽章〈アダージェット〉の部分にメンゲルベルクによる以下のような証言が書き込まれているからである。
「注、このアダージェットは、グスタフ・マーラーの、アルマに宛てた愛の証であった! 手紙の代わりに、彼はこの手稿を彼女に送ったのである、それ以外には何のことばも書き添えずに。彼女はそれを理解して、彼にこう書き送った。あなたが現れる運命であった!!!、と(ふたりが、私にこのことを語ってくれたのだ!)W.M.」

クリムトが撮影したアルマ
社交界の華として知られていたアルマが、夫マーラーの創作や指揮活動に対して行った貢献は大きかった。義父のカール・モルは画家であり、ウィーン分離派と呼ばれる、グスタフ・クリムトを中心とする革新派の芸術家集団に属しており、自然彼女の周囲には始終画家や音楽家といった芸術家たちが出入りするような環境があった。そのような中で、彼女自身も作曲に興味を示し、ツェムリンスキー(オーストリアの作曲家・指揮者、シェーンベルクの師)に個人的についている。
師に尊敬以上の感情を抱いていたアルマであったが、ちょうどその頃にマーラーが彼女の前に現れたのである。アルマはそれまでの芸術的な環境を、そのままマーラーとの生活に持ち込んだ。そもそもふたりが出逢ったのも、解剖学者ツッカーカンドルが主催したパーティに、モルが分離派の芸術家として招かれ、それにアルマがついていったのが機縁であった。
アルマとの結婚以後、マーラーは、クリムトや美術家アルフレート・ロラーといった分離派のメンバーと深い交流を持つようになる。ベートーヴェンを中心とした総合芸術をテーマとする1902年の分離派展で、マーラーが自らウィーン歌劇場の演奏家を連れて、ベートーヴェン「交響曲第9番」の編曲版でオープニングを飾ったのはこうした事情から自ずと生じた出来事であった。分離派の芸術家に漂う、新しい造形表現、世紀末の官能・退廃的雰囲気はマーラーにも少なからず影響を及ぼしたであろう。

クリムト「ベートーヴェンフリーズ(一部)」
■曲について
全体は5楽章からなる。3部に分けられており、第I部:第1,2楽章、第II部:第3楽章、第III部:第4,5楽章とされている。葬送行進曲に始まり、歓喜の叫びに終わるという、形式としては伝統的な交響曲図式を意識して書かれており、各モチーフ・素材は、生まれ故郷ボヘミアの民謡に由来するなど、なにか「どこかで聞いたような」旋律が用いられている。
第1楽章:葬送行進曲
冒頭のトランペットの葬送の主題による葬送行進曲
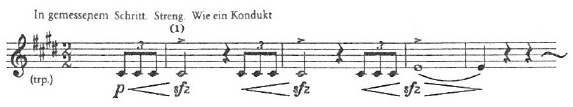
とその後に続く、緩慢で沈痛な表情のトリオ部

この二つの変奏と、それらの合間に二つの中間部が挿入されている。
一つは「激情的に、荒れ狂って」と指示された突発的で攻撃的な旋律と、もう一つは弦楽のみによる哀愁を帯びた一つ目の中間部の変奏である。
最後は行進曲主題に回帰するが、半音階的下降によって弱められ、埋葬後の静寂をあらわすような、力無い主題が断片的に続くなか、低弦のピッツィカートで止めが刺される。
第2楽章:嵐のように荒々しく動きをもって。最大の激烈さ。
第1楽章の素材が随所に使われ、関連付けられている。短い序奏につづいてヴァイオリンが激しい動きで第1主題

を奏する。曲はうねるように進み、テンポを落とすとチェロが第2主題

を大きく歌う。これは第1楽章の中間部変奏に基づいている。
展開部以降、第1主題、第2主題が交互にあらわれる。楽章の終わり近く、金管の輝かしいコラールが現れるが、
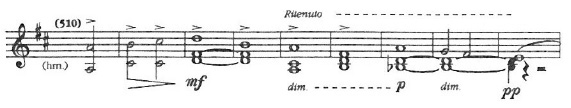
この明るさの暗示は再度阻止され、冒頭部の威嚇的な動機の回帰によって否定される。最後は煙たなびく戦場のような雰囲気で終わる。
第3楽章:スケルツォ
マーラーが初めて〈スケルツォ〉と明記した長大な楽章である。オブリガート・ホルンがソロ的に扱われているのが特徴である
第1,2楽章からは一転して楽しげで、4本のホルンによる特徴的な「信号音」から第1主題

をオブリガート・ホルン、木管がそれぞれ紡いでいく。「信号音」は節目節目で繰り返しでてくる。
第1主題が変奏されながらひとしきり発展した後、レントラー風(ドイツ民族舞踊)の旋律を持つ第2主題

がヴァイオリンで提示される。これは長く続かず、すぐに第1主題が回帰する。まもなく、展開的な楽想になり「より遅く、落ち着いて」と記された長い第3主題部

へ入ってゆく。この主題は変奏されながら進行し、最後は弦楽器による玄妙なピッツィカートで扱われる。第1主題の再現後、第2主題、第3主題も混ざり合わさって劇的に展開し、第2主題が穏やかに残り、提示部と同様に第3主題による静止部分がきて、最後は再びピッツィカート。 コーダは大太鼓のリズムにのり、壮大なクライマックスのうちにスケルツォは閉じられる。
第4楽章:アダージェット
ハープと弦楽器のみで演奏される、静謐感に満ちた楽章。冒頭は「リュッケルトによる歌曲」の「私はこの世に忘れられ」と通底する雰囲気をもっている。中間部ではやや表情が明るくなり、その後、ハープは沈黙、弦楽器のみでいつ果てるともない美しい調べを奏でる。終楽章との間に切れ目はない。
第5楽章:ロンド-フィナーレ
第4楽章の余韻が残る中、ホルン、ファゴット、クラリネットが牧歌的に掛け合う。このファゴットの音型

は、歌曲「少年の魔法の角笛」から「高い知性への賛美」からの引用である(この歌曲はウグイスとカッコウの歌比べをロバ(愚か者の象徴)が審判し、ロバはカッコウの陳腐な“コラール”に軍配を上げる、というものである。この滑稽な内容が、「闘争、葛藤を経ての勝利」の図式や終楽章で現れるコラールをパロディ化しているという解釈もある)
短い序奏が終わると、ホルンによるなだらかな下降音型が特徴の第1主題、

低弦によるせわしない第2主題

が呈示され、これらに対位旋律が組み合わされて次第に華々しくフーガ的に展開する。再び第1主題が戻り、提示部が変奏的に反復される。第2主題も現れ、すぐ後に第4楽章の中間主題がコデッタとして現れるが、軽快に舞うような曲調となっている。
壮大なコーダでは、第2楽章で幻のように現れて消えた金管のコラールが、今度は確信的に再現され、最後は速度を上げて華々しく終わる。
参考文献
『グスタフ・マーラー全作品解説事典」長木誠司(立風書房)
『マーラー事典』(立風書房)
WIKIPEDIA 「交響曲第5番(マーラー)」
初 演:1904年10月18日 マーラー指揮
ギュルツェニヒ管弦楽団 ケルンにて
楽器編成:フルート4(第3、第4奏者はピッコロ持ち替え)、オーボエ3(第3奏者はコールアングレ持ち替え)、クラリネット3(第3奏者はバスクラリネット持ち替え)、ファゴット3(第3奏者はコントラファゴット持ち替え)、ホルン6、トランペット4、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、グロッケンシュピール、シンバル、大太鼓、小太鼓、タムタム、トライアングル、ホルツクラッパー、ハープ、弦5部
シェーンベルク:5つの管弦楽曲作品16 (1949年改訂版)
■表現主義としての無調音楽
シェーンベルクは、長調・短調といった調性を決定的に解体した作曲家として知られている。5つの管弦楽曲作品16が作曲された1909年(またその前年の1908年)は、シェーンベルクが爛熟した後期ロマン主義的様式から、「不協和音の解放」による「無調性」へと最初の一歩を踏み出す決定的な転換点となる年だった。ちなみにシェーンベルクはいわゆる「十二音技法」の創始者としても知られているが、この1908/1909年に始まった「無調音楽」には、十二音技法の音楽(1923年に始まる)に見られるような体系性や構築的理論はまったくない。無調音楽 を支えているのは、彼が「内的強制」と呼ぶような、芸術家の内奥から生じる表現意欲だけである
シェーンベルクは1911年に出版した著書『和声学』のなかで、次のように述べている。「芸術家の創造は衝動的なものである。意識はそれに対してほとんど影響を与えない。芸術家は、自分が何をするか指図されているかのような感覚をもつのである。」あるいは、彼が1911年に友人の画家カンディンスキーに宛てた手紙では次のように書かれている。「伝統的な効果を目指す作品構成はすべて、意識の行為から完全に解き放たれていません。しかし芸術はまさに無意識に属するものです。ここでは自己を表現することが求められます。自己を直接的に表現するのです!」自己を直接的に表現しようとするとき、伝統的な表現形式は足枷となる。そのため、多くの場合、 伝統的表現形式は破壊され、荒々しく粗暴とも見える表現、あるいは伝統的感覚を逆なでするような表現がとられることになる。シェーンベルクにとって「調性」とはそのような足枷の一つであり、彼の目指す表現のために「不協和音の解放」が行われなければならなかった。
こういった芸術の方向性は、この時代のカンディンスキーの創作もそのようにとらえられているように、一般的に「表現主義」という芸術様式として理解されている。表現主義においては、十二音技法に見られるきわめて理知的な構成原理にもとづいた表現とは対照的に、人間の生身の衝動、直接的感情、無意識がいわば剥き出しのまま表現される(ちなみに、この表現主義の時代にシェーンベルクは数多くの絵画を描いているが、それも直接的な自己表現の要求から生じたものと考えられる)。その意味で表現主義は、ロマン主義が一つの極点まで達したものといえるかもしれない。ただし、その「表現」がもたらそうとするものは、ロマン主義の「美」の対極にある。

シェーンベルク「自画像」(1910年頃)
シェーンベルクの表現主義時代の作品のうち、とくに重要なものとしては、「シュテファン・ゲオルゲの“架空庭園の書”による十五の詩」作品15、モノドラマ「期待」作品17、そして「ピエロ・リュネール」作品21をあげることができるだろう。「5つの管弦楽曲」は、ゲオルゲ歌曲集(作品15)で踏み出した無調性の試みを、最初に管弦楽によって推し進めた重要な作品である。
■「世紀末ウィーン」のなかでの無調音楽
機能和声にもとづく調性の解体は、音楽史における必然的な過程として語られる。しかし、シェーンベルクにとってこのことは、「世紀末ウィーン」という、彼が生きていた特定の時代環境のなかで生じた現象でもあった。一般に「世紀末ウィーン」という言葉は、ウィーンで伝統的・歴史主義的芸術に対する反抗が生まれた1890年頃から、第一次世界大戦が始まる1914年までの時代、あるいはその時代のウィーンの文化現象・社会現象を指す。この時代の革新主義者たちのうち、一方では「接吻」などで知られる画家クリムトや有名な分離派館を設計したオル ブリヒ、あるいはグスタフ・マーラーなど、伝統的な美術・建築・音楽から革新的な一歩を踏み出しながらも、きらびやかな装飾性や官能性によって、保守的なウィーンの貴族や大市民層からもある程度の成功をおさめていた。しかし他方で、批評家カール・クラウス、建築家アドルフ・ロースを筆頭とする過激な革新主義者たちは、ウィーン特有の装飾性を容赦なく攻撃していた。シェーンベルク(そしてまた弟子のベルク、ウェーベルン)は、完全にこのクラウス=ロースの陣営に属している。彼らにとって「装飾」とは、真の姿を隠蔽するものに他ならな い。シェーンベルクは著書『和声学』の序文のなかで、ウィーンに特有の「快適さ」を求める性向、不快さを避けるために「うわべ」で生きる人々に激しい批判を向けているが、それは「装飾」をはぎ取り、真の姿を剥き出しにすることと重なり合う。シェーンベルクにとって、無調性への道は装飾批判と同じ方向にある。(ただし、シェーンベルクはマーラーに対してつねに変わらぬ敬意を抱いていた。)彼の無調音楽が聴衆の不快をかき立てるとすれば、それは単に和声という純粋に音楽上の理由によるだけではなく、人間の内面が剥き出しに表現されていることによって生じる不安のためでもあるだろう。ウィーンの表現主義には、ドイツの他の都市で展開した表現主義とは異なり、ほとんど神経症的ともいえる極度の内面的緊張がみられるが、シェーンベルクの無調音楽にもそういった特質を明確に見て取ることができる。
■「5つの管弦楽曲」の標題性?
今述べたことは、例えば、物語的な状況設定をもつモノドラマ「期待」(一人の女が暗い森の中をさまよい、おそらくは自分が殺した恋人の死体に行き当たる)などにはもっともよく当てはまる。しかし、「3つのピアノ曲」作品11(1909年)、この「5つの管弦楽曲」作品16(1909年)、あるいは「6つのピアノ曲」作品19(1911年)といった抽象的形式をもつ作品についても、無意識の領域における自己の直接的表現という点では基本的に同じことがいえるだろう。
このことは「5つの管弦楽曲」につけられた各曲の標題からも見て取ることができるかもしれない。この作品に標題をつけることは、もともとシェーンベルクの意図していたことではなく、単に出版社の要請によるものだった。シェーンベルクは日記のなかでこの作品の標題の問題に言及しつつ、次のように書いている。「音楽が素晴らしいのは、すべてを言うことができ、知っている者はすべてを理解できるということにある。だからといって、自分自身にさえ告白しない秘密を外に漏らしたことにはならない。しかし、標題はそれを漏らしてしまう。」それでも、この作品に標題をつけることに同意したのは、「それらがきわめて曖昧であり、曲によっては技術的なことをいっているだけなので、秘密を漏らすことにはならない」からとされる。1912年にこの作品が最初にペータース社から出版された際には、標題は表示されていなかったようだが、その後、Ⅰ.「予感」、Ⅱ.「過ぎ去ったもの」、Ⅲ.「和声の 色調」、Ⅳ.「急転」、Ⅴ.「オブリガートの叙唱レチタティーヴォ」、という標題が各曲に掲げられることになる。今回演奏される1949年版では、3曲目の標題が「ある湖の夏の朝(色彩Farben)」と大きく変更されているが、これについては後でふれたい。
これらの標題は、確かにシェーンベルクが言うように曖昧なものであり、特定の具体的状況を表すものではない。しかし、全体として見たとき、その構成は一つの物語的展開を指し示しているようにも思われる。つまり、不安に駆られた「予感」に始まり、「過ぎ去ったもの」の抒情的ともいえる回想、そして1949年版の標題では例外的にある特定の状況を示す「ある湖の夏の朝」(これも一つの回想とみることができるだろう)。第4曲では「急転」によって物語は大きな転換を迎える。これは「予感」の成就でもある。ちなみに、「急転(Peripetie)」とはもともとアリストテレスが『詩学』のなかで用いた概念で、ギリシア悲劇において主人公がある事実を認識することにより、悲劇的運命へと向かう転換点を意味する(オイディプスが、父親を殺し母親と結婚していたことを悟る瞬間がその典型的な例である)。第5曲目の標題に対して、そのような物語の内容に関わる解釈を求めることは無理だが、しかし「叙唱レチタティーヴォ」という語りの様態に関わるものではある。
第3曲は、シェーンベルクが『和声学』のなかで言及している「音色旋律」を実際に試みた作品として、音楽史のなかで重要な位置を占めているが、ここでは「ある湖の夏の朝」という1949年版での標題についてふれたい。「和声の色調(Akkordfärbungen)」という最初の標題(あるいは1922年版の標題「色彩(Farben)」)は、日記のなかでシェーンベルク自身が述べているように「技術的」なものにしか関わらないが、「ある湖の夏の朝」は場合によっては作曲者のきわめて個人的な体験を漏らすものであるかもしれない。少しばかり伝記的なことがらに入り込ん でゆこう。シェーンベルクの絵画の創作に大きな影響を与え、彼に絵の指導も行っていた年若い芸術家リヒャルト・ゲルストルが、シェーンベルクの妻マティルデと関係をもっていたことが1908年に露呈、マティルデはウェーベルンの仲介もあってシェーンベルクのもとに戻るが、ゲルストルはその年のうちに自殺する。予感していた事実にシェーンベルク自身遭遇した場所が、彼が身内や親しい友人と夏の休暇を過ごしていたトラウン湖(オーストリア)のほとりにある町だった。pppの和音が2拍ごとに楽器編成が交代するかたちで演奏されるとともに、次第 に楽器編成や和音が移り変わってゆくことによって音の色彩の繊細な変化を表現するこの曲は、確かに湖の静かな水面の波紋のように聞こえる。そして、ときおり魚の飛び跳ねる音も描かれる(クラリネットなどの素早い上昇音形)。何人かのシェーンベルク研究者は、この「ある湖」はトラウン湖だろうと推測している。
第3曲「ある湖の夏の朝(色彩)」と第4曲「急転」は、音楽の構成上、明確なコントラストをなしており、そこにはある劇的な展開が感じとられる。しかし、このことから、シェーンベルクに深い衝撃を与えた事件を、その翌年に作曲された「5つの管弦楽曲」のうちに単純に読み取ろうとするならば、それは下世話なゴシップ的関心でしかないかもしれない。しかし、この衝撃的な事件の精神的余波をも含んだシェーンベルクの内面が描かれているということは間違いないだろう。
最後に、今回演奏する1949年版について。1912年のオリジナル版では、管楽器がかなり大きな編成でコントラバスクラリネットなどの特殊楽器も用いられていた。1949年版は基本的に2管編成となり、演奏会のプログラムにのせやすい編成にまとめられている。
参考文献
Eberhard Freitag, Schönberg. rororo, 1973.
Gerold W. Gruber(Hrsg.), Arnold Schönberg.
Interpretationen seiner Werke. Laaber-Verlag, 2002.
Matthias Henke, Arnold Schönberg. dtv, 2001.
Hartmut Krones, Arnold Schönberg. Werk und Leben. Steinbauer, 2005.
Willi Reich, Arnold Schönberg oder der konservative Revolutionär. Fritz Molden, 1968.
Arnold Schönberg, Harmonielehre. Universal Edition, 2005(1911)
初 演:1912年9月3日(オーケストラによる全曲演奏として)
サー・ヘンリー・ウッドの指揮ロンドンのクイーンズ・ホールにて
楽器編成:ピッコロ2(第2奏者はフルート3持ち替え)、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、小クラリネット、 クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シロフォン、タムタム、シンバル、大太鼓、トライアングル、ハープ、チェレスタ、弦5部
マーラーで登場する「ホルツクラッパー」は団員の自作です
マーラーの交響曲は打楽器が盛り沢山なものが多く、その中にしばしば「木」が登場する。厳密に言えば「ルーテ」か「ホルツクラッパー」の2種類であるが、どちらもムチと訳されてしまうので混乱しているようだ。このうち交響曲第2番「復活」などに出てくるルーテは、実際にはふつう中華鍋などを洗う細い竹棒を束ねた「ササラ」を使うことが多く、交響曲第2番「復活」などでは、これで大太鼓のリム(縁)を叩く。この種のササラは打楽器専門店で「楽器」として買えば高いけれど、ホームセンターで買えば1ケタ安かったりする。これも打楽器の値段の不思議なところだ。
それはともかく、もう一つのムチである「ホルツクラッパー」はたいてい2枚の細長い板の片方を蝶番(ちょうつがい)で繋ぎ、双方の板を持ってパチンとお見舞いするのが常だ。油断すると時に指を挟んでしまうことがあり、もし万が一演奏会でパチンと音がしなかった時は、奏者はきっと必死で痛みをこらえている。
有名なところではムソルグスキー(ラヴェル編)の『展覧会の絵』や、ブリテンの『青少年のための管弦楽入門』などがお馴染みであるが、気持ちよく寝ているお客さんを起こすには効果てきめんの一撃だ。そのパシッと鳴らす緊張した効果をうまく使った作品に、新響の元音楽監督・芥川也寸志さんによる『赤穂浪士』のテーマ曲がある。
この曲以外では「一発モノ」が多いのであるが、マーラーの交響曲5番の3楽章に出てくるのは音形がタタタンタン×4小節、それが2か所という異例な多さ。一般にはこれも2枚板のムチを使うことが多い。ついでながら「ホルツクラッパー」とはホルツつまり木材をクラッペンする-カチッ、ピシッとかパタンといった音を立てるモノ、というドイツ語である。
さて、今回初めての高関先生との合奏ではとりあえず団が所有している2枚板の「ムチ」で演奏した。休憩時間にホルツクラッパーはムチで良いかどうかお訊ねしたところ、それでもよいがあまりムチのような(明るすぎる)音ではなく、少し低い音が望ましいとのこと。新響打楽器のメンバーで話し合ったところ、田中司さんが「作ってみよう」となった。
1週間後に出来上がったのは長方形の断面の筒を専用の板で叩く構造。2枚の板という「常識」は雲散霧消している。傍目では心太(ところてん)を押し出す筒に見えるが、構造的にはオルガンの木のパイプの応用だという。実はこのオルガンのパイプを、田中さんはこれまで何本作ったかわからない。本職は小学校の理科教諭であったが、実はオルガン製作者としても有名なのだ。放課後の模型工作クラブの小学生たちにポルタティーフ・オルガン(文字通り持ち運べる小型オルガン)作りを指導して始まったもので、最近まで「アントレ」という古楽器専門誌に「ポジティーフ・オルガンを作ろう」というオルガン作り講座を延々と連載していた。
音を響かせるためのパイプだから叩けばいい音がするに違いない。叩ける場所は贅沢にも4面あり、その1面をナラ、その他はパイン(松)として、どこを叩くかは自由。叩くバチの方はナラ製である。どこをどう叩くかで音色が選べるところがミソだ。早速9月25日の練習で高関先生に披露したところ、「気に入った」とのこと。どの音が良いかはホールへ行ってから決めよう、ということになった。トリフォニーホールでどんな音が響くだろうか。お楽しみに。
思えば田中さんはこれまで、新響で必要とされる「特殊楽器」をいくつも作った実績がある。最初はガーシュウィン『パリのアメリカ人』に出てくるクラクション。4つの音の高さが要求されるもので、ふつうはラッパにゴム球を付けた手動式であるが、あえて自動車用バッテリーを動力とした本格的なものを作っている。これが1960年代末頃。この「パリアメ・クラクション」は、結局いくつものプロ・オーケストラを渡り歩くほど好評だったという。

ホルツクラッパーの写真
ビゼー『アルルの女』のファランドールで使うバスクの太鼓はオイル缶を向かい合わせに繋いで胴とし、これに本皮を張った。最近ではリヒャルト・シュトラウスの『アルプス交響曲』では風音を出すウィンドマシン。ゴワゴワした触感の帆布(はんぷ)が擦れる音を利用したものである。他にも、たとえばテューブラーベルの長いものを吊すスタンドとか、打楽器のスタンド入れの箱(キャスター付き)も、楽器屋で見かけないものはすべて田中さんの手作りだ。最近になって定年退職されたので、これを機に自宅アトリエに何でも工作できる装備一式を揃えた。今後は何が登場してもおかしくない状況だが、現在のところは孫に贈るための小さな椅子にとりかかっている。
〈マーラーとシェーンベルク: 新時代への扉を開いた 巧みな音楽表現と挑戦〉
新響と高関先生とのマーラー交響曲への取り組みも4回目を迎え、いよいよ交響曲第5番の登場となります。そこで今回のプログラムについて先生にインタビューを行い、ざっくばらんなお話を伺ってきました。
構成:土田恭四郎(テューバ)
― シェーンベルクは久しぶりですか?
高関:実はこの曲はこれまで1回しか振ったことがないのです。
― 意外です!もう何百回も振っていらっしゃるのかと。今回の編成でやったのが一回?
高関:そう、1回のみです。そもそも日本では演奏されてないですね。ヨーロッパでは歴史的に大事な曲としてよく聴かれます。
― このバージョンを選ばれたのは?
高関:楽譜が手に入りやすいからです。演奏用のパート譜は今もうほとんどこの版しか手に入らないのかな。この作品は出版について言えば、ウニベルザール社(※1)と契約できなかったのです。現在はペータース(※2)から出ていますが、ペータースの社長の名前で、ヒンリクセン(※3)というレーベルで、いわば自費出版の形ですね。
― 当時は生活も苦しく、演奏されるたびに、当時の音楽界から攻撃されながらも、新しいものをやっていこうという挑戦を感じます。
高関:だいたい彼の作品番号10番台はめんどくさい曲が多くて、20番台に入ってくると、作品として安定してくる。今回の作品16というのは、まさにその過渡期の曲ですよね。作曲家自身が作品に相当愛着を持っていたようで、改訂を重ねています。オーケストラだけでも4つの演奏版があり、但しウェーベルンの作品6のように、異なる音響に変更されるということはあまり無い。その意味では完成度は最初から高かったのでしょうね。今回の1949年版は演奏効果が上がるバージョンだと思います。
― 確かに、最初に作曲された大編成の版を聴いても違和感がありません。
高関:他にも室内オーケストラ版が出版されていて、2台ピアノの8手版っていうのもある。この8手版の原稿はシェーンベルクセンターのホームページ(※4)で見ることができます。室内オーケストラ版もまた演奏する価値があると思います。
― 5曲ともそれぞれ個性がありますが、12音ではないですね。
高関:まだ12音技法は確立されていません。先ほど申し上げたように過渡期にあたり、「グレの歌」(※5)を作曲中です。「グレの歌」と同様に、この曲も楽章ごとにどんどん作風が変わっていきました。機能和声の終わりから無調になっていきます。作曲技法も複雑を極め、1曲目は完全に複リズムですよね。4拍子と3拍子が同居している。錯綜そのものがテーマでしょうね。2曲目も異なる音価が同居しています。3曲目はいわゆる色彩だけを追求するような実験、そして4曲目以降は完全に無調で書法がほぼ12音技法になっている。移り変わる時期の作品だと思います。家庭的にも奥さんの駆け落ち事件が勃発したり大変な時期ですね。特に5曲目が、その後の「月に憑かれたピエロ」や、12音になってからの「管弦楽のための変奏曲」(※6)、「セレナーデ」(※7)などに似ている感じはあります。
― シェーンベルクは絵画の方でも素養があり、自画像なども有名です。マーラーのことも描いています。仲良しだったのですね。
高関:ええ、仲良しです。マーラーの葬送の絵を描いていますよね。
― マーラーの手紙に関して多くの本が出版されていますが、シェーンベルクとも手紙のやりとりが多く、シェーンベルクとアレクサンダー・ツェムリンスキーがウィーンで「創造的音楽家協会」を立ち上げ、マーラーが名誉会長になっていますね。当時の音楽界からコテンパンにやられた時にマーラーが弁護して、ということが奥さんのアルマ・マーラーの手紙に書いてありました。
高関:アルマ・マーラーの言っていることはほとんど嘘で脚色です(笑)残念ながら。
― シェーンベルクの演奏会では、聴衆が騒ぎだして、そうするとマーラーが立って諌めたとか。そのようなことが2回あったと書いてありました。

高関:マーラーは席を立たなかったという話です。最後まで残っていた何人かのひとりだった。彼らの音楽はとても理解できないが、自分が応援しないと、彼らの居場所がなくなってしまう、そういうスタンスだったみたいですね。マーラーが亡くなってから「私的演奏協会」をシェーンベルクが主宰した。相当の回数の音楽会をやって、ウェーベルンとベルクを含めた自分たちの曲と併せて、当時の先進的な作品を色々紹介しています。客が居ようと居まいと関係なく実施した。マーラー交響曲第7番のカゼルラ(※8)編曲ピアノ4手版を、カゼルラとツェムリンスキーが弾いた、そういう演奏会だった。ピアノ連弾で1時間20分…(笑)。因みに交響曲第6番はツェムリンスキー編曲の連弾版がありますね。
― ところで、マーラーは交響曲第5番作曲のころから、多忙にもかかわらず色々な国を回って演奏会もやる、作品の校訂はする、とそのパワーには驚きます。
高関:すごいバイタリティですよ。1907年を例にとりましょう。10年にわたって務めてきたウィーン王立歌劇場音楽監督をこの年いっぱいで辞任します。最後の公演が10月15日の「フィデリオ」です。そして翌1908年1月1日には、すでに契約が整っていたニューヨークのメトロポリタン歌劇場で「トリスタンとイゾルデ」を振ってデビューしています。この間を縫ってマーラーは、なんと北欧に演奏旅行をしています。サンクト・ペテルスブルクでは10月26日にベートーヴェンの第7交響曲を含むプログラム、11月9日に第5交響曲の最後の自作自演を行い、その間の11月1日にはヘルシンキに客演して、ベートーヴェンとヴァーグナーのプログラムを振っています。そして翌2日に、滞在先のホテルに訪ねてきたシベリウスと会っています。街を歩きながら互いに交響曲談義をしたそうですが、物別れに終わったというお話ですね。シベリウスは第3交響曲を初演したばかり、一方のマーラーは第 8交響曲を完成していたのですから、意見が合わなかったのも当然と言えるでしょう。この間、契約の問題などいろいろ雑事に追われながらも、サンクト・ペテルスブルクとヘルシンキまで旅行しているのです。マーラーはウィーンをクビになって、失意のうちにアメリカに行ったというのは全くの嘘です。実際はすごい希望を持ってアメリカに旅立ったのですね。
― マーラーはチャイコフスキーの前で「エフゲニー・オネーギン」を指揮して絶賛された、という話を聞いたことがあります。
高関:そうですね、当時を代表する大指揮者だったから、ものすごく色々な人との交流があったようです。
― マーラーは交響曲第5番を書いて、その10年後に亡くなっていますね。え?そんなに短い生涯?という感じがします。
高関:1901年から翌年夏にかけて第5番を書いているわけですが、この頃がマーラーの人生の絶頂期ですね。王立歌劇場での仕事も好調で、11月にアルマ・シントラーと出会い、翌3月には結婚しています。こうした経緯が第5番にすべて反映されている。本当に不思議な曲ですね。第1楽章では葬送行進曲を書いているわけでしょう。もう俺は死ぬか、というような。第2楽章でこれからどうやって生きていこう、と悩み抜いているところに、突然彼女が現れ第3楽章で有頂天になって、第4楽章で「大好き!」って告白して、第5楽章で結婚できました、と報告している(笑)。第5楽章のスコアを見て驚くのは、一回も短調にならない!
― 一瞬たりともですか!色々な作曲家のD-durの良いとこ取り、という感じがします。
高関:いわゆる借用和音はありますが、楽想が短調になることはないのですよ。もう本当に、徹底的にD-Durです。
― 実際にマーラーが、この曲は君のために書いたとアルマに言っているのでしょうか?
高関:言っていますね。楽譜の最初のところに「アルマに捧ぐ」と献呈文が書いてある。それは結婚してからだから、後から書いているのですけど。
― スコアをおこす仕事をアルマ本人が手伝っていたそうですね。
高関:第5番についてはアルマが写譜したスコアが残っています。それが出版のときの版下になった。なんとアルマは紫色のインクで書いています。わたしは女よっていう感じで(笑)このアルマの写譜も自筆原稿とは違うのですよ。自筆原稿はモーガン・ライブラリー(※9)で公開されています。ニューヨークにある大コレクションですけど、沢山の作曲家の自筆原稿を持っています。ぜひホームページを見ていただくと良いと思います。
― アルマはウィーン社交界でとてもモテたそうですね。
高関:アルマは、実の母親が早く亡くなって父親が再婚している。家庭環境としてはちょっと複雑だったようです。大変に早熟で15~16歳で既に大人の社会に頻繁に出入りしていたようですね。マーラーとは19歳離れていて1902年に結婚した時は22歳。その前にグスタフ・クリムトとアレクサンダー・ツェムリンスキーと結構良い仲だった。マーラーと会ったときは、ツェムリンスキーの弟子として紹介されているはずです。写真を見て判る通り、ものすごく立派な体格の人ですね。並んで立つマーラーのほうが小さいですから。そして美貌にも恵まれ本当にきれいな人だったらしいですよ。クリムトが書いた「Der Kuss(接吻)」という有名な絵がありますよね。相手はアルマだっていう話があります。
― マーラーを選んだのは権力があったから?あと才能を感じたのでしょうか?
高関:権力は十分ありましたね。しかし何と言ってもアルマはマーラーの才能に惹かれたのでしょう。ただ相性はそんなに良くなかったようです。マーラーが多忙を極めていて、あまりアルマのことを省みなかったのです。マーラーは仕事が好きで演奏活動の他に、空き時間に作曲に没頭してしまう。アルマは欲求不満がだんだん溜まっていた。そこに、自分より若いグロピウス(※10)さんが現れて、という話。それが1910年の最後の夏です。マーラーは第10交響曲の作曲を中断してアルマのところへ飛んで行き、3人で話し合って、グロピウスは一度身を引いた。しかしマーラーは大きな衝撃を受け、8月下旬に夫婦でオランダにいたフロイトを訪ね、精神分析も受けていますね。この件で数週間を費やし、9月12日には第8交響曲の初演が予定され、その準備に掛かってしまったので、第10番のオーケストレーションができ上がらなかったのです。
― アルマ・マーラーは交響曲第10番の作曲を止めちゃった!
高関:完全に止めたのですよ(笑)。マーラーのプランでは夏休みの間に全曲がParticell (=下書き)の形で完成するはずだった。それが不倫騒ぎで中断してしまい、それなら来年の夏に持ち越し、と決めて11月からニューヨーク・フィルの仕事に専念したつもりが、翌年の2月演奏旅行中に病気になって、そのまま回復できずにヨーロッパに戻り、5月に亡くなったというわけです。
― そのようなアルマとの関係がグジャグジャになる前の、もうとにかく大好き!というのが、この交響曲第5番ですね。
高関:1楽章cis-mollから5楽章D-durへという…あまりにも出来すぎた話です。
― 今回使用する版の経緯について伺います。どのようなバージョンがあるのでしょうか。
高関:先ほど触れたように、まず自筆原稿はニューヨークのモーガン・ライブラリーにあり、ホームページで公開されているので、私たちも閲覧できます。それから、先ほど申し上げて初版の版下になったアルマによる写譜、これにはマーラー自身の訂正加筆を含めたくさんの書き込みが含まれます。次にシェーンベルクの蔵書の中に、なぜ彼の手許に行ったのかが不明ですが、マーラーの訂正書きの入った第2版の出版前のゲラ(1904年)があります。今演奏されている基本の楽譜のさらに前の状態です。古いパート譜の原型は1919年のペータース版で、いわゆるゲーラー版というものです。交響曲第5番の価値を見出したライプツィヒのゲーラー(※11)という指揮者が、きちんと演奏したいからもっと整備された楽譜がほしいとマーラーに言って、マーラーがそれを認めて楽譜を作り直させた。ゲーラーは第8交響曲のミュンヘンでの初演の際に、ライプツィヒから派遣された合唱団の下 振りをしましたが、その時にマーラーと交流を持ったようです。出版のペータース社がライプツィヒにあったので、出版社とも話がまとまった。ゲーラー版により、それまで不備だった楽譜の状態が統一され、基本となる楽譜が出来上がった。現在手に入る全音の小型スコアもドーヴァー(※12)もカルマス(※13)も、すべてゲーラー版のコピーです。その後、1964年にエルヴィン・ラッツの校訂による最初の全集版が出ました。この版が最近まで演奏に使われてきました。しかしパート譜はまだ手書きで、スコアとの不一致も多く見られました。その後に細かい訂正を加えた1989年版が出ましたが、2002年にさらに多くの資料を評価したうえで、全く新しく編集されたクビークによる新全集版が出版されました。今回の演奏に使いますが、コンピュータ製版により、スコアとパート譜との不一致も解消されています。
― 10年前に新響が使用した譜面から1000箇所以上も変わっていると、練習のときにおっしゃっていましたね。

高関先生のマーラーのスコア。版ごとの訂正個所が、色とりどりのペンでびっしりと書き込まれている
高関:クビークによる新全集版の底本となったのは、作曲者がニューヨークに滞在中の1910年から11年にかけて、将来の演奏を見据えて行った改訂を新たに書き込んだパート譜のセットです。実はマーラー自身が最終の改訂を書き込んだスコアは行方不明になっているのですが、幸いにもパート譜には改訂が良い状態で書き込みが行われていました。これまで不明瞭だった強弱をはじめとして、松葉の位置がずれているとか、忘れているとか、音が違っているところもかなりあります。今回の演奏では、新全集版に更に私が書き込みを行いましたが、フレージングと表現の整合性を得る目的に限られます。
全集版の編集における大原則ですが、基本は作曲家が書いた楽譜を最も尊重します。しかしマーラーが残した資料は、スケッチや下書きから、演奏に使ったスコアやオーケストラのパート譜など、多岐にわたります。こうした資料を詳しく調べながら、自筆原稿での間違いや書き損じなどを訂正し、編集者が付け加えたり変更したりする場合は、例えばカッコを付ける、破線にするなど、それがはっきりと読者にわかるように楽譜に表現することだと思います。疑問点については議論を尽くし、違う意見が考えられる際は、違う可能性を併記することもありますね。たとえば高関音楽学者が(笑)、これは違っているだろ?といって自分だけの判断で勝手に書きこんでしまうと、その時点で楽譜としての価値、整合性が失われてしまうのです。だから新全集版としては、あらゆる資料をあたって、マーラーがここまで変えた、という段階までで止まっている。そこから先は演奏するほうの判断で変える事は構わないよ、と書いてあるのです。
― それが、校訂報告ですね。
高関:はい。例えば自筆原稿はこういう状態だった、ゲラ刷りはこうである、ゲラを書くための写譜の人が書いた楽譜の状態はこう、といくつもの段階が校訂報告に書いてあるのです。それでマーラーの場合、特に面倒なのは、初演の時のパート譜がここにある、再演された時のパート譜が別にここにある、その次に新しく演奏するために作ったパート譜だけど演奏しなかった、というのもある(笑)
― 基本的に一番新しいのが、一番マーラーの意志を反映している、ということでしょうか?
高関:その通りだと思います。1989年版までは最も大事な実際の演奏に使われたパート譜までは参照されていなかったのです。例えば第3楽章のオブリガート・ホルンが前に出てくる話についても、新全集版では校訂報告のなかで、どの演奏会で舞台のどこで吹いたのかを検証した記事があります。
マーラーの発想は他のホルン奏者とはっきり分離して立体的に聴こえること、つまりオペラ的な遠近感の獲得にあります。マーラーと交流の深かった指揮者メンゲルベルクが使ったスコアが残っています。マーラーは第5番を1906年3月にコンセルトヘボウで振っていますが、メンゲルベルクは事前の練習を買って出て、マーラーの練習にも出席、作曲者の指示を細かくメモしています。このスコアにはマーラー本人も赤いインクで多数書き込んでいます。その中に「(第3楽章の)ホルン・ソロはいつもはっきりと、そのためにソリストのようにコンサートマスターの前に位置すること。」と書き込まれています(編者注:今回の演奏会ではこれを踏まえ、第3楽章のオブリガート・ホルンは指揮者横の位置で演奏します!お楽しみに)。
― パート譜にはもしかしたら奏者が書き込みをしたかも。
高関:ええ、奏者はマーラーが言ったことを書きこんでいます。あるパートには奏者のサインまで入っている(笑)。
― まさにその場で、そのパートでは駄目だからこうしろとか、やったのかもしれませんね。
高関:そういうようなところはありまして、例えばもともとホルンに書いた動きをファゴットに移したりしています。理由はホルンで吹いたら重すぎる、音量が大きくなってしまうから…。

― バランスに関して、あと管楽器のベルアップ、ものすごくしつこいですね。
高関:ええ、ものすごくうるさいです!どこからベルアップするかにもこだわっている。しかし指示通り楽器を上げることに意味があるのです。例えば指示が頭からではなく、2拍目からになっていたりします。クレッシェンドをする段階でベルを上げていくのです。そこまで判ってマーラーは指定しています。決して効率的ではないけど、彼はその響き方が好きだったのですね。
― 視覚的効果とあわせてダイレクトに聞こえてほしいということでしょうか。
高関:そうです。直接音がほしい、という意味ですね。それから面白いのは第5楽章最後のティンパニのパー ト。4個全部使うじゃないですか、♪レー・ド・シ・ラ・レードーシーラー…というのは、

ウィーンではティンパニは基本的に1人で3個しか使えず、瞬時に音程を変えることができないという認識でした。現在でもウィーン・フィルはペダルでなく、レバーを手回しでチューニングしていますが、当時すでに同じシステムだった。したがって、当初マーラーのアイデアには無かったのです。自筆原稿をみると♪レ・ラ・レ・ラしかないのです。初版の楽譜も同様です。ところが1880年代にドレスデンでペダル・システムの楽器が開発されて、例えば「サロメ」では4個のティンパニを、音程を変えながら豪快に鳴らしているわけですね。マーラーは1904年にライプツィヒのゲヴァントハウスに客演していますが(第3交響曲)、そのころペダル・ティンパニの存在を知ったらしいのです。どうやらティンパニ奏者が、それは叩けますよ、とマーラーにアピールしたのね。それでドとシが追加され た、ということのようです。
― 最初のトランペットのソロについてマーラーによる有名な但し書きがありますね。
高関:トランペット・ソロについて、3連符は詰めてアッチェレランドしているような、軍隊のファンファーレのように吹くように、という但し書きを自筆原稿ではトランペット・パートの上に書きました。しかし後になって自分で削って消しているのです。初版にも但し書きはありません。当時楽譜に但し書きをすることはあんまり良いことじゃないという、品格の問題があって。しかしどうしても必要で、ゲーラー版ではスコアの欄外に復活しています。ところで、このファンファーレはメンデルスゾーンの結婚行進曲からの引用ですね。同時にローエングリンのイメージもある。マーラーの音楽は本当にそういう引用が多いから、原曲が判ってくると、そこにウラの意味を読み取ることができます。
いずれにせよ、どこまでがマーラーの意志かというのを判定することはすごく難しい。昨年新響で第7番を演奏した際、編集者のクビークさんとかなり突っ込んだ意見の交換をすることができました。
― これからも研究が進みますね。
高関:先ほども申しあげましたが、第5番ではマーラーがニューヨーク滞在中(1910~11年)に最終の改訂を書き込んだスコアが行方不明なのですよ。しかし、すでに燃えてしまったとか無くなったとかではなく、おそらくどこかにはあるだろうと。まだ出てくる可能性はある。最近も第9番の最終楽章の下書きがアルマと交流のあったピアニストの遺品の中から発見されました。マーラーの作品研究はこれからも進んでいくと思います。
― 今回のプログラム、シェーンベルクもマーラーもすごく立体的な音楽と感じています。マーラーとシェーンベルクは後期ロマン派として20世紀にまたがっていますが、マーラーはロマン派の最後のスタイル、いわゆる19世紀末の音楽でその先には行かなかった。シェーンベルクはそれをあえて破壊したことで、現代音楽への出発点の位置を確立したと思います。
高関:そうですね!交響曲第5番は、マーラーがポリフォニーに目覚めた作品です。それまでの歌曲との関連から抜け出て、いわゆる主題労作だけで曲を書いた、ベートーヴェンのように書こうとした最初の作品です。歴史的にはマーラーのちょっと後にシェーンベルク、最近話題になっているハンス・ロット(※14)、それからシマノフスキ(※15)が居て、という時代です。ツェムリンスキーも近くに居て、みんなで切磋琢磨してやっていたわけです。その中から、シェーンベルクだけが抜きん出てきたのです。発想の勝ちなのです。それを見て追随したのが、やはり一緒に居たウェーベルンとベルクだった。そして彼らの作品も残った。実はシマノフスキにも相当面白い作品があります。当時ウィーンではオリエンタリズムが流行して、マーラーが唐詩をテキストに「大地の歌」、ツェムリンスキーが同様にインドの詩作をテキストに「抒情交響曲」(※16)、シマノフスキがイスラムに没頭して「交響曲第3番“夜の歌”」を書いています。しかしシェーンベルクはそこには目もくれず、ひたすら形式の追及に向かった。そこの差ですね。当時異国情緒の作品はたくさんあるわけですが、今では廃れて演奏されないですね。
― 高関さんにはマーラーの交響曲を、第9番、第6番、第7番と指揮していただいて、いよいよ第5番に来た!という思いです。新響としては、第5番の演奏は今回4回目となりますが、とても難しい曲と感じています。
高関:指揮者にとっても難しい曲です。俗な言い方をすれば、発想だけが盛り上がって、前のめりな演奏になることが良くあります。複雑な作品なので時間をかけて練習しないとできないところがありますね。新響の皆さんとの十分な練習の成果が、本番で発揮されると良いですね(笑)!
1)Universal Edition
2)Peters Edition
3)Henri Hinrichsen(1868-1942)
4)http://www.schoenberg.at/index.php?lang=en
5)Gurre-Lieder(1900-11)
6)管弦楽のための変奏曲― Variationen für Orchester(1926-28)op.31
7)Serenade(1920-23)op.24
8)Alfredo Casella(1883-1947)
9)The Morgan Library & Museum www.themorgan.org/
10)Walter Adolph Georg Gropius(1883-1969)「バウハウス」創立で著名なドイツの建築家。1910年にアルマと不 倫関係にあったとされる。
11)Georg Göhler
12)Dover Publications
13)Edwin F. Kalmus & Co., Inc.
14)Hans Rott(1858-1884)
15)Karol Maciej Szymanowski(1882-1937)
16)Lyrische Symphonie(1922)op.18
第215回ローテーション
| シェーンベルク | マーラー | |
| フルート1st | 兼子 | 松下 |
| 2nd | 丸尾 | 吉田 |
| 3rd | 藤井(+Picc) | 兼子(+Picc) |
| 4th | - | 岡田(+Picc) |
| Picc | 岡田 | - |
| オーボエ1st | 亀井(淳) | 堀内 |
| 2nd | 亀井(優) | 山口 |
| 3rd | - | 岩城(+C.A.) |
| C.A. | 桜井 | - |
| クラリネット1st | 末村 | 高梨 |
| 2nd | 品田 | 末村 |
| 3rd | - | 進藤 |
| EsCl | 大薮 | - |
| BsCl | 石綿 | 石綿 | ファゴット1st | 浦 | 田川 |
| 2nd | 田川 | 浦 |
| 3rd | - | 斎藤(+CFg) |
| コントラファゴット | 斎藤 | - |
| ホルン1st | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 市川 | 兪 |
| 3rd | 大原 | 鵜飼 |
| 4th | 兪 | 森 |
| 5th | - | 園原 |
| 6th | - | 大原 |
| トランペット1st | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 倉田 | 青木 |
| 3rd | 中川 | 北村 |
| 4th | - | 中川 |
| トロンボーン1st | 武田 | 武田 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 足立 | 土田 |
| ティンパニ | 古関 | 桑形 |
| パーカッション | シロホン+シンバル(弓)/今尾 タムタム+トライアングル/中川 大太鼓/浦辺 シンバル/古関 |
グロッケンシュピール/浦辺 トライアングル/皆月 小太鼓+ホルツクラッパー/中川 大太鼓/今尾 シンバル/古関 タムタム/田中 シンバル付き大太鼓/古関 |
| チェレスタ | 藤井 | - |
| ハープ1st | (*) | (*) |
| 2nd | - | (*) |
| 1stヴァイオリン | 前田(大隈) | 堀内(真)(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(佐藤(真)) | 小松(笠川) |
| ヴィオラ | 常住(田口) | 常住(田口) |
| チェロ | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 中野(植木) | 中野(植木) |
第215回演奏会のご案内
2010~2011年は「マーラー・イヤー」
今年はウィーンで活躍した大作曲家マーラー(1860-1911)の没後100年、昨年は生誕150年にあたります。マーラーの作品が演奏される頻度が増えたり、関連する映画や書籍が発表されるなど、国内外で盛り上がっています。新響は1979年から10年にわたってマーラー交響曲全曲シリーズに取り組み、最近では高関と第9番、第6番、第7番と演奏してきました。マーラー・イヤーの締めくくりとなる今回の演奏会では、最も人気の高い第5番を演奏します。
アルマへのラブレター
交響曲第5番が作曲された1902年、マーラーはウィーン宮廷歌劇場監督として地位も名誉も得て、私生活でもアルマと結婚し長女が誕生します。まさに人生の絶頂期に作られたこの曲は、それまでの第2番~第4番が声楽入りの作品なのに対し、純器楽によるより新しい表現へと発展させた、彼の成熟期の代表作となりました。5楽章からなる大作ですが、中でも弦楽器とハープだけで演奏される第4楽章アダージェット(小さなアダージョの意)は世界でもっとも甘美なアダージョの一つで、マーラーが19歳年下のアルマへの愛情を表現した曲と言われています。実際にアルマは交響曲第5番のスケッチからフルスコアを作成する仕事を手伝っていました。
大ヒットしたCD『アダージョ・カラヤン』や映画『ヴェニスに死す』で有名ですが、日本では伊丹十三監督の『タンポポ』で使われていて聴き覚えのある方も多いでしょう。
ロマン主義から無調音楽へ
マーラーが活躍していた頃のウィーンはいわゆる世紀末ウィーンと呼ばれ、文化が熟し芸術の各分野で新たな飛躍を遂げました。アルマは才能と美貌に恵まれ、画家クリムトなどの芸術家を魅了したウィーン社交界の花でした。そのアルマと結婚してマーラーの交友関係も変わり、新しい芸術を目指す分離派と交流を持つようになります。音楽家ではアルマの作曲の師であるツェムリンスキーとその弟子のシェーンベルクがマーラーの家に出入りして音楽談義をするようになりました。
シェーンベルクは、初期はマーラーと同様に後期ロマン派の作風でしたが、新しい方法論を模索し無調音楽へ、そしてさらに無調を理論化した十二音音楽を確立します。当時そのような前衛音楽は聴衆に受け入れられませんでしたが、マーラーは支援し擁護し続けました。「シェーンベルクの音楽はわからない。でも彼は若い、おそらく彼が正しいのだろう。」
シェーンベルクが無調へと向かった最初の管弦楽作品が「5つの管弦楽曲」です。20世紀以降の現代音楽の先駆的存在で、のちの作曲家に大きな影響を与えました。現代音楽というと難解で堅苦しいイメージがありますが、この作品はメロディがわかりやすく響きの新鮮な聴きやすい曲です。
どうぞお楽しみに!
四半世紀ぶりのハイドン
今回ハイドンの交響曲第101番『時計』を取上げるが、新響がハイドンの作品を演奏したのは1987年9月の第117回定期(指揮:今村 能)の交響曲第88番『V字』以来、実に24年ぶりという事になる。私事ながら言えば、入団から来年で30年にならんとする新響人生の中で、ハイドンを公式に演奏する機会を初めて得た記念すべき年に今年2011年はなった訳で、慶賀の至りというべきであろう。
そこで改めて調べてみると、驚いた事にこの団体はその55年を誇る歴史の中でも、
・1965年4月 交響曲第94番『驚愕』
・1970年4月 交響曲第101番『時計』
・1987年9月 交響曲第88番『V字』
・2011年7月 交響曲第101番『時計』
と今回を含めて4回(3曲)しか取上げていないと知った。この中で1965年の『驚愕』は新響が未だ労音からの独立以前、各地で行われていた「例会」に於ける演奏であるため複数回の演奏を行なってはいる。が、逆に定期演奏会のプログラムという範疇からは厳密に言えば外れてしまう性格のものだ。つまり新響は「生まれてこの方、ハイドンを1度も演奏した事が無い団員がいてもおかしくない団体」との定義が成立してしまう。アマチュア・オーケストラの盟主(?)を自負する(??)団体として、「これってどうなのよ?」との疑問も出てこよう。
ハイドンがなかなか俎上にあがらない理由には以下のようなものが考えられる。
①編成上の問題(管楽器)
ハイドンは交響曲という形式を完成させ、ベートーヴェンによるこの形式の爆発的な発展のまさに基礎を拵えたが、その完成の過程ではオーケストラそのものが発展途上にあった。またこの作曲家は30年にも及ぶ宮廷での楽長生活の中で、その特定のオーケストラの為に作曲せざるを得なかった。その為その後の交響曲に見られるような編成の完備した「五体満足な」作品が非常に少ない(これはモーツァルトの交響曲にも言える事である)。
こうした作品を取上げると、まず管楽器奏者の出番が制限されてしまう。どこのアマチュアオーケストラにとっても出番がない奏者を如何に生じさせないようにするか?が運営の要諦であって、もし不揃いの編成の交響曲をプログラムにもってくれば、その埋め合わせには大曲を並行して用意しなければならなくなる。プログラムのバランスからみると、これは決して容易な事ではないのである。
結局どうしてもハイドンを取上げる際には、管楽器の編成が整った作品に限定されがちになる。新響が3曲しか演奏していないのもそのあたりに理由があると言える。
②編成上の問題(絃楽器)
管楽器に限らず、編成上の問題は絃楽器にもある。この場合は「規模」の話になる。即ち何人の絃楽器奏者で演奏するか?という、これまた切実な話である。
ハイドンの時代のオーケストラは近代のそれとは異なり、絃楽器奏者の人数も非常に少ない小規模なものだった。これがオーケストラの発達に伴って楽器の性能も上がり、且つ人数の規模も急速に大きくなっていった(そして作品もそうした傾向に拍車をかけるように、大規模なものが創造されてゆく)。
現在の我々はその終着点の規模の団体になっている訳だが、ハイドンの交響曲を演奏するに際し、彼の時代の演奏スタイルを知っているだけに、この我々が持てる規模をフルに活用する事が必ずしも妥当ではないのではないかという疑問に常につきまとわれている。
そこで「小編成」のオーケストラ構想が出る事になるが、これは「常に出番がある」事を前提としている絃楽器奏者にとっては、権利の侵害につながりかねず、必ず抵抗運動が沸き起こる。大抵はここでこの構想は立ち消えになり、一歩踏込んだ次の段階に議論が進まない恨みが無いとは言えない。
また「小編成で演奏する事が本当に良い結果をもたらすのか?」という疑問も一方にはあるため、問題はなかなか一筋縄で解けない状態になっている面もある。
かくしてこの①と②を総合すれば、新響というオーケストラは「どんな大編成を必要とする作品でも演奏できる規模を持ってしまったが故に、小編成の問題を含む作品に対する対応力に欠ける」という一種のパラドクスに陥っているという事が判ってくる。この団体のプログラムにハイドンやモーツァルトの作品が極端に少ないのは、こうした理由が潜んでいるのである。
③演奏の難しさ
岩城宏之氏が『楽譜の風景(岩波新書)』の中でハイドンの交響曲について以下のように言及されている事に、注意を払ってみるべきだろう。
ハイドンはあらゆる作曲家の中で最も難しいと言われていたのを実感として味わい、手も足も出ぬ敗北感に打ちひしがれた。
百以上書かれたハイドンの交響曲は、気軽に聴いていれば、どれも単純明快で、テンポの変化もないし、始まればそのまま、一気呵成に終わってしまうように思える。
しかしちょっと調べると、フレーズの入り組み方など、モーツァルトやベートーベンよりはるかに複雑だし、第一、アンサンブルの難しさは、後のロマン派の作曲家たちの作品の比ではない。
ベートーヴェン以後の交響曲の隆盛を知り、その恩恵を充分に蒙っている現代の我々は、ハイドンの交響曲をともすれば未だ完成されていないスタイルの「習作」のように捉えがちな気がしている。
それは速い楽章のメリハリの無さと見えたり、緩徐楽章の冗漫さと感じられたり、或いはオーケストレーションの未分化(木管楽器のパートは2本揃っていても殆どがユニゾンである)などという形で耳目に障る事がある。これらは作曲者の生きた時代背景を反映している。
我々は概ね、この印象を拭いきれない時点で、ハイドンの交響曲をプログラム検討の俎上から下ろしてしまっている。実に残念且つ愚かしい事だと考えざるを得ない。
現実にはそうした点を克服し、一個の確立してスタイルを表出した演奏を作り上げる過程で詳細に作品の構造を見てゆくと、岩城氏のいう「複雑さ」に気づき、「難しさ」に行き当たるのである。ここで初めてハイドンの交響曲の演奏に対するやりがいが理解されうる状態になる。
思い切った私見を披露すれば、ハイドンの作品は、バロック時代までの「良き趣味」の残滓を最も好ましく昇華して交響曲という形態として次世代への確固とした橋梁として完成させているのではないか?と考えている。
新響は今回の定期を機会に、ハイドンの作品そのものの評価や演奏にとどまらず、彼の交響曲の演奏を軸に、これまで演奏できなかった様々な理由・事情の解決を含め、洗い直しを図る契機とする事が好ましいように思う。
「これまでそうだったから」という理由だけで、こうした優れた作品をやらない法は無い。
チャイコフスキー:交響曲第5番
■音楽家チャイコフスキーの誕生
神が与えた才能を…開花させる為に
(妹宛1863年4月15日)
チャイコフスキーの音楽からは何を感じるだろう。あの甘い旋律からくるロマンティックな感触であろうか。彼の作品には常に歌があり、時として感情過多とも思える表現で我々に訴えかけてくる。それゆえに彼の音楽を敬遠する向きもあろう。しかしクラシック音楽に馴染みのない者でも「白鳥の湖」の情景(オーボエの旋律)や、「くるみ割り人形」のいくつかの舞曲などはどこかで耳にしたことがあるほど、彼の音楽の美しさ、親しみやすさは広く親しまれている。本日演奏する交響曲第5番は、そんな要素が凝縮された作品だと言える。
実はこの作曲者の経歴はちょっと変わっている。少年時代から音楽との接点はあったものの両親は彼を音楽家にすることは考えていなかったようで、法律学校で学び法務官となるという道を辿るのである。しかしRMO(帝室ロシア音楽協会)と出会い22歳でこの音楽院の学生となった彼は、やがて役所を辞め正真正銘の音楽家として歩きはじめる。RMO卒業後、そのモスクワ支部に教授として迎えられ、そこの責任者ニコライ・ルビンシテインとRMO創設者でその兄アントン・ルビンシテイン兄弟の手厚い比護を受け、教鞭を取りながら創作活動を行うのである。
■繊細なる大作曲家
ひとりと感じるのは何という喜び!
(A.メルクリング宛1885年9月20日)
1866年には交響曲第1番「冬の日の幻想」や初のオペラ「地方長官」を完成させるが、世間に認められるのは1871年に作曲した弦楽四重奏曲第1番(第2楽章が有名な「アンダンテ・カンタービレ」)であろう。さらに1875年にピアノ協奏曲第1番を完成、ようやく名声を高めた。そして彼のオペラ代表作「エフゲニー・オネーギン」、交響曲第4番、ヴァイオリン協奏曲など、今日の代表作群に名を連ねる作品を生み出していったのである。
こうして大作曲家として着実に歩む彼であったが、その性格は実は繊細で、孤独を愛し、時には男色に走るなど、その社会的高名からは想像しがたい側面があった。主に3人の女性と関わりをもった女性関係からもそれが感じられる。その一方で生涯最も心を許し、14年間の付き合い、700通以上の手紙、そして金銭的援助も受けたナジェージダ・フォン・メック夫人とは、生涯一度も会うことはなかったのである。何と控えめであろうか。また指揮者としても自分に自信が持てず、交響曲第5番も含めて自分の指揮に対する劣等感から、作品自体否定的に感じることもあったようだ。
そんな彼は西欧の音楽家たちと対等に付き合った最初のロシア音楽家とも言える。ドヴォルザーク、ブラームス、20歳年下のマーラーなどとの交流は彼の音楽に少なからず影響を与えたであろう(因みに新響が今年演奏する(した)作品の中では、ドヴォルザーク交響曲第7番が本日の交響曲第5番と同時代の作品で、しかも両作曲者は各々その総譜を相手に送っている。またマーラーの交響曲第5番は、ライプツィッヒで対面した後1907年にサンクトペテルブルクでロシア初演されている)。
■交響曲第5番完成まで
1888年5月に西欧演奏旅行から帰還したチャイコフスキーは新たな交響曲を手掛ける。その年の夏までの完成を目指して取組んだこの作品のスケッチには「運命の前での完全な服従」「不満、疑い、不平、非難」「信仰の抱擁に身を委ねる…」「『慰め』『ひとすじの光明』『いや、希望はない』」といった言葉が残されており、新たな作品を暗示している。8月に交響曲第5番を完成し、彼が西欧に旅行した際ドイツ・ハンブルグへ招聘してくれたアヴェラルマン(ハンブルグ・フィルハーモニー協会理事長)へ献呈された(冒頭の作曲者の写真は、このアヴェラルマンが撮影させたものである)。
しかしチャイコフスキーはこの交響曲に対して、しばらくは否定的なイメージを持っており、メック夫人への手紙でも「失敗作」と書いている。その原因の一端に彼の指揮に対する自信のなさがあったようだ。何回かこの曲を指揮したが一度としてオーケストラに的確な指示が出来ず落ち込み「この作品を火に投げ込むつもりだった」ところまで憎んでしまったようだ。しかし後の1892年、大指揮者ニキシュの名演もあって評価を変えたようである(火に投じられていたら、本日演奏出来なかった! 良かった)。
■交響曲第5番について
この作品にはロシア音楽の特徴である「歌」、ほとんど全ての旋律、音形が器楽によって奏される「歌」で構成されている。またベートーヴェンの交響曲のテーマ性やベルリオーズの「イデー・フィクス(固定楽想)」も取り入れられており、ロシア・ロマン派作品の美しさと西欧的交響曲の構成力を伴ったバランスの取れた交響曲と言える。彼の後期交響曲中、第4番や第6番に比べて感情表現が抑えられているとも言われるが、それでも随所に運命との格闘、憧れと絶望、凱歌といった人間の感情表現が感じられる。
第1楽章
弦楽器を伴ったクラリネットの暗い旋律で始まる。この旋律は全曲を通じての基本動機(運命の動機)となる。まるで錘おもりをつけてロシアの大地を歩むがごとく。スケッチにある「運命への服従」であろうか。やがて弦楽器のリズムにのって木管楽器が動きのある旋律を奏する。この楽章の第1主題ともいうべき旋律はやがて弦楽器に移りさらなる高揚を経てひとつのクライマックスを迎える。溜息のようなフレーズと対話が弦、木管楽器、ホルンに奏されるが弦楽器のピッチカートをきっかけに暗さが消え、第2主題がヴァイオリンに歌われる。単純な音形ながらリズムの躍動とオーケストレーションの変化が心に訴える高揚感を伴い第2のクライマックスを迎える。この辺りの展開はチャイコフスキーならではであろう。曲は展開部に入り第1主題、第2主題の変形を繰り返し、再現部に入る。コーダで盛り上がりを見せたあと、第1主題を繰り返しながら再び冒頭の雰囲気へと戻り低弦の暗く深い響きで終わる。
第2楽章
冒頭、低弦の和音で始まる。前楽章の最後を彷彿とさせるが、和音進行が違った展開を予感させる。高弦も加わり夜明けのような高揚を迎えたあと、ホルンにより第1主題が奏される。チャイコフスキーの音楽の中でもっとも穏やかながら美しい旋律であろう。クラリネットのオブリガートを伴った後曲想に動きが出て、弦楽器のリズムにのってオーボエとホルンが愛らしいカノン風旋律で対話をする。さらにチェロにより第1主題が歌われ高揚して短い終止を経たあと、カノン風旋律が高弦により歌われる。この美しく希望的な音楽はこの楽章のひとつの感動的クライマックスを築く。全曲中でも最も陶酔的な場面であろう。曲想は短調に変わりクラリネットの美しくも切ない旋律が木管楽器、弦楽器と歌われ不安感を掻き立てられた後、頂点で基本動機が金管楽器により力強く奏される。ここでは救世主のような感じだ。穏やかな雰囲気の中、弦楽器のピッチカートを伴いヴァイオリンが第1主題を歌い、木管楽器、弦楽器のカノン風旋律と歌われた後、突然基本動機がオーケストラの全奏で叩き付けるように表れる。今度は希望を打ち砕くかのように…。嵐が過ぎ去った後の空虚の中でカノン風旋律が歌われながら、この楽章は静かに終わる。
第3楽章
スケルツォの代わりにワルツが置かれている。チャイコフスキーのワルツはバレエ音楽などで華やかなものが多いが、こちらはやや控えめながら愛らしい。ワルツの旋律がヴァイオリンに歌われ、木管楽器に移る。オーケストレーションの変化で色を変えながら続いた後、木管楽器にとぼけたような音型が出てひとつの区切りとなる。第2主題は弦、木管楽器が奏する細かい音型で、いわばここでスケルツォ的楽想となる。期待感と不安感を伴って盛り上がりを見せ、ワルツに戻り、基本動機が木管楽器により控えめに奏された後、全奏の和音で楽章を終わる。
第4楽章
冒頭で基本動機がホ長調で表れる。まず弦楽器、そして管楽器によって堂々と歌われる旋律は運命に打ち勝った勝利感に満ち溢れている。一度曲が収まった直後にティンパニのクレッシェンドに導かれて強烈なリズムを伴う舞曲風第1主題が表れる。オーボエと低弦の対話や弦楽器ののびやかな旋律を経て、木管楽器に第2主題が表れる。この旋律は弦楽器に移ってさらに高揚するが、この間低音楽器群にリズムが持続され曲の推進力となっている。やがて金管楽器により基本動機が力強く奏され一端は収まるが、すぐに激しいリズムで第1主題群が登場する。激しさ、性急さを伴ってクライマックスを迎え、ホ長調の属和音上で一度終わる。コーダはまず基本動機がマエストーソで奏され壮大な頂点を迎えた後に第1主題群が奏され音楽は高揚、さらに第1楽章第1主題が金管楽器に奏されてエンディングとなる。この交響曲に関心を示したブラームスが唯一認めていなかったこの楽章だが、続けて演奏されると人間の勝利への願望、喜びを表し絶大な効果が感じられる。またこれだけ色彩的、音響的な盛り上がりを見せるこの作品がほぼ通常の2管編成、打楽器もティンパニのみ、というのは驚きである。
■新響とチャイコフスキー
新響はロシア音楽を度々取り上げるが、チャイコフスキーは2004年10月のオール・チャイコフスキー・プロ(交響曲第4番、くるみ割り人形組曲などを演奏)以来プログラム上では取り上げていない(アンコールでは今年1月くるみ割り人形より「パ・ド・ドゥ」を演奏)。今回久しぶりに彼の交響曲を演奏するが、団員の中にはその喜びを噛み締めている者が少なからずいるのではないだろうか…と練習中に感じた。それが音となってお客様に少しでもお届け出来れば幸いである。
初 演:1888年11月5日 サンクトペテルブルク・フィルハーモニー協会演奏会にて作曲者自身の指揮による
楽器編成:フルート3(第3奏者はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ1、ティンパニ、弦5部
参考文献
『チャイコフスキー 交響曲第5番』 ミニチュアスコア(OGT2121) 音楽之友社
『チャイコフスキー』 作曲家人と作品シリーズ伊藤恵子 音楽之友社
『名曲解説全集第2巻』 音楽之友社
ハイドン:交響曲第101番「時計」
■交響曲(シンフォニー)の成立~ハイドンまでの道
バッハ(Johann Sebastian Bach 1685~1750)の厖大な作品目録の中で、『シンフォニア』と題された管弦楽作品が1曲だけある(BWV1046a 注1)。これは何らかの祝祭の機会に書かれたものと言われて いるが、確かにその冒頭からあふれ出る華美・盛大な気分はそうした推定を容易にさせるものを持って いる。バロック時代において『シンフォニア』とはそうした祝典のための音楽だった。
一方でオペラの序曲として演奏される『オペラ・シンフォニア』というものがあった。スカルラッティ(Alessandro Scarlatti 1660~1725)はナポリにおいて、急-緩-急の3部構成的な序曲を既に1680年代から作品に用いていた。これが短期間のうちにオペラから独立し、ひとつの器楽作品のジャンルへと変貌してゆく。「交響曲(シンフォニー)」へ脱皮の第一歩である。
西洋音楽の基礎を確立したバッハの作品には交響曲はない。が、音楽史上で彼に連なるハイドン(Franz Joseph Haydn 1732~1809)には100曲以上の交響曲作品があり、「交響曲の父」と呼ばれる。ハイドンの生年時バッハは47歳。故にこの間に「忘れられた」作曲家たちによる絶えまない交響曲創造への堆積があったと考えるべきであり、事実それはあった。
例えばバッハの息子たち…次男であるC.P.E.バッハ(Carl Philipp Emanuel Bach 1714~1788)は3 楽章形式のシンフォニアとそこにメヌエットを加えた4楽章構成の交響曲を合せて20曲以上書いた。ロ ンドンで評価を得た末子のJ.C.バッハ(Johann Christian Bach 1735~1782)もシンフォニアを約60曲残している。モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart 1756~1792)は8歳の折にロンドンで彼に会い、その影響から3楽章構成の最初の交響曲(注2)を書くに至る。
秀逸なオーケストラを擁したマンハイムを拠点としたシュターミッツ(Carl Philipp Stamitz 1745~1801)の手になる作品(シンフォニアだけで51曲ある)も忘れるべきではない。ここでは詳細を述べる紙数は無いが、彼らによってソナタ形式をはじめとした独立した性格を有する4楽章形式の交響曲はひとつの定型を得るに至る。
同世代若しくは半世代前の数多あまたの作曲家たちによって、急速に形成されつつあった交響曲の土壌。その上にハイドンという種子が落ち、この分野における収穫の時期を迎えた。我々がこんにち目にしているのはあくまでその結果である。
■宮仕えの日々と多作
ハイドンは1761年29歳の折から約30年間に亘り、ハンガリーのエステルハージ(Eszterházy)侯爵家 に仕えた。彼の100曲以上(その全容は掴み切れない)交響曲の殆どはこの間に、自ら楽長を務める宮 廷楽団の為に、更には特定の演奏機会の為に作曲されている。それは定められた日常業務であり、大バッハが教会の楽長の職務としてその儀式典礼の為に絶えず新作を創造していた姿と変わらない。ハイドンはそうした作曲家の最後の世代だった。
例えばある朝、いつものように控えの間にいる作曲家は、主人から今日は交響曲を5曲作曲せよ(!) と命令される。一晩で城を築けという信長のような君主だが、こうした場合の事を彼は述懐している。
私は座席にすわり、その時の気分が悲しいか、愉しいか、厳粛かふざけっぽいかにしたがって、楽想を作り始める。ひとつのアイディアが私をとらえたならすぐ、私は全心の努力をもって、芸術の法則にしたがって、楽曲を完成させることにつとめる。(注3)
主人にしてみれば、こうした無理難題への解決能力のある音楽家を手元に置いている事はひとつのス テータスとなる(他人の能力を量る上での尺度は、いつの時代も質よりまず量だ)。その「業務命令」の内容とハイドンの対応を考えれば、多作は当然の帰結である。そしてその量以上に重要なのは、仕事の繰返しの中で絶えず創意を重ね、交響曲の洗練されたスタイルを確立した事である。
初期の作品にはシンフォニアの残照とでもいうべき3楽章構成の作品がいくつもあるが、それも一定 の様式に固着せず、様々なスタイルが試みられている。その様な試行錯誤の繰返しの結果として4楽章 に構成が固まり、且つこの4つの楽章にそれぞれ異なった性格を初めて与えるに至る…従来の交響曲で はシンフォニアの時代同様、楽章ごとの個性は重視されてはいなかった…ハイドン以後の交響曲では余 りに当然の要素になってしまったが故に、なかなか彼の創意に気づかずにいるが、これは重要な進化だ った。
現代の我々がこの作曲家の交響曲を見渡した時、ある作品を境にした特筆すべき飛躍を見出すのは難しい。だが我々が得てして見落としてしまいがちな何らかの特徴が、独創が、工夫が各曲に必ずある。多作の中で培われる進歩とは本来そうしたものだ。むしろ多作を強いられる条件を、ハイドンは我がものとして活用していたと考えるべきなのだろう。
■転身者としての成功
1790年にハイドンはそれまでの宮廷音楽家の地位を離れウィーンに移る。間をおかずロンドンのオー ケストラを主宰するヴァイオリン奏者ザロモン(Johann Peter Salomon 1742~1815)によって渡英の機会を得る。それ以前から既に一部の作品群は出版され、名声は高まりつつあったのだ。
大作曲家の輩出という点ではやや見劣り感のあるイギリスだが18世紀末のこの時期、市民層の形成により、音楽作品は宮廷の奥で一部の人々が享受するものでは既になくなっていた。首都ロンドンは大規模かつ高質なオーケストラを擁した、新作音楽の一大消費地とでも評すべき都市に変貌を遂げている。限られた人々を対象に作品を書き続けていたハイドンにとって、かの地のオーケストラを前提に、不特 定多数の聴衆の為に意識して作品を発表する「興行」は、自由人としての恩恵を物心両面で充分にもたらした。つまりハイドンは市民社会での作曲家への転身にこの時成功したのである。その失敗によって貧困の中で死んだモーツァルトの轍を踏まない幸運を彼は得たという事だ。
この充実の中で合計12曲の交響曲が新作された。現在交響曲第93番から第104番に数えられる作品群である。『時計』(注4)はその2度目の渡英の折に作曲されているが、12曲中でも最も充実した内容を誇る。この時既に60歳を過ぎていた作曲者。その闊達な表現と構成の緻密さに彼の得意をみる思いがする。
この作品の楽章ごとの細かい解説は敢えて避けよう。28分ほどの間に繰広げられる洗練された技法と その均整美、そして4楽章それぞれの性格の差異と、それを超えた全体の調和に対し、虚心に耳を傾けて戴きたい。
思えばハイドンの交響曲は程よく抑制のきいた「良き趣味」が、人々の支持を得ていた最後の時代の産物というべきかも知れない。彼の完成させた交響曲というジャンルはベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770~1827)に引継がれると、人間感情のより強い発露の手段へと変質を余儀なくされる。『時計』が初演された1794年の時点で、このあまりに人間的な後継者はまだ1曲も交響曲を書いていないが『第九』の初演は、それからきっかり30年後である事にもっと注意が払われても良い。社会構造の変化が、人々の音楽に対する欲求を激変させ、交響曲の変貌に深く反映しているように思えてくる。
■雑感二題
その1) 『時計』というと、この緩徐楽章がテーマ音楽だった『百万人の英語』というラジオ番組を想い出す(前回定期の『大学祝典序曲』と併せてひとつの時代風景だ...と言っても判る人にしか判らない話)。「鯨が魚でないのは馬が魚でないのと同じである(A whale is no more a fish than a horse is.)」 などという不可思議な例文を無邪気に暗記していたあの頃…。それから30年の時間が過ぎたが、この構 文の出番は一度もなく、外国語はどれも身につかなかった。
その2) 新響がハイドンの交響曲を取上げるのは1987年9月の第117回定期の第88番(V字)以来、実に四半世紀ぶり。調べてみるとその前は1970年の『時計』と1965年の第94番『驚愕』のみ。つまり新響55年の歴史の中でこの作曲家の交響曲は今回を含めて4回(3曲)しか演奏されていない。新響演奏のハイドンを今日ここで体験できた事は、聴き手・演奏者の如何を問わず、子々孫々にまで自慢すべき事であるに違いない。
注1)有名な3声のインヴェンションは、2声のそれと区別して「シンフォニア」と呼ばれるが、ここでは管弦楽の為の作品に限定している。またこの作品は有名な『ブランデンブルグ協奏曲』第1番に転用(作品番号も同一)されているので、それを聴けば『シンフォニア』の性格を類推する事ができる。
注2)「交響曲」と「シンフォニア」とを区分する定義は非常に曖昧なまま放置されているのが実情のようだ。日本ではハイドン以降の作品に対しては、初期段階の作品で3楽章形式を採っていても「交響曲」としている。本稿でも仕方なくこの実情を前提に論を進めている。解りにくい部分があるとすればそれは筆者の思考の整理に帰するものである。
注3)この君臣間のやり取りに関しては『ウィーン音楽文化史(渡辺護著)』による孫引き。但し、出典が明示されていないためどこから引用されたものなのかは現時点では判らない。
注4)『時計』は作曲者自身による命名ではないが、初演後間もない1798年時点でこの交響曲の愛称として用いられていた事が判っている。こうした事象もまた市民層への音楽の浸透を表すものと捉えられよう。
初 演:1794年3月3日 ロンドンにて作曲者自身の指揮による
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、トランペット2、ホルン2、ティンパニ、弦5部
主な参考文献
『名曲解説全集』交響曲1 音楽之友社
『音楽史の点と線』岩井宏之 音楽之友社
『バッハの息子たち』久保田慶一 音楽之友社
『西洋音楽史』下 D.J.グラウト 音楽之友社
『音楽大事典』平凡社
『ウィーン音楽文化史』上 渡辺 護 音楽之友社
プロコフィエフ:スキタイ組曲(アラとロリー)
スキタイ組曲を知っている人が、この曲を知らない人に紹介する時、決まって第2楽章を口ずさむ。スキタイ組曲の持つ粗野な部分が非常に印象的なのであろう。
クラシック音楽と言えば、音量を増幅する機械を使用せずに、奏者一人一人の演奏が直接聴衆の耳に 届けられる。大きなホールで2000人を相手に、一人の奏者しか音を出していないという状況も、クラシ ック音楽ならではである。逆に、100人近くの奏者が舞台に集まり、皆それぞれ全力で弾き、吹き、叩 く時の迫力は、これもまたクラシック音楽の醍醐味である。数名の演奏をマイクで拾い、それを100名 分の音量でスピーカーから流すのとは違う。
単に音量ツマミをひねった結果の「うるさい」音と、舞台上で奏者があえて「うるさい」音楽を表現するのは別物であり、後者には音量だけではなく、そこにいる奏者が何かを伝えようとする気合いのようなものが加味されるのである。このスキタイ組曲は、まさにその典型であると言えよう。この曲が始まる直前、おびただしい数の管楽器・打楽器が入場してくる。各奏者が舞台上の所定の位置につき演奏開始を待っている時、舞台上の雰囲気はまさに「戦闘配置につく」といった様相を呈し、これからの大戦(おおいくさ)に向けての気合い十分である姿が見てとれるはずである。
個人的な話で恐縮だが、私はこの曲ばかり聴いていた時期があった。学校の友人がチャゲアスやサザ ン、X(エックス)やプリプリ等に夢中になっている横で、毎日のようにスキタイ組曲を聴く中学3年生。当時の私は、とにかく騒々しい曲が好きで、後述する「春の祭典」や「中国の不思議な役人」等と並んで、毎日のヘビーローテーションに組み込まれていた。
楽器吹きは、曲が好きになると、演奏したくなる。14、5歳の私が憧れたこれらの曲を、当時所属して いた吹奏楽部で演奏するのは夢のまた夢であり、オーケストラスコアを購入して、もし演奏できるとしたら自分が吹くであろうパートの譜面を1人で吹いたりするくらいしかできなかった。傍から見れば、相当奇特な中学3年生であったに違いない。
ところが、現在私が所属しているこの新交響楽団という所は、私のような奇特な者、むしろその上を 行く人間が集まっている。上記の「春の祭典」や「中国の不思議な役人」等を次々と取り上げ、練習 後の飲み会では、私の知らないような作品について延々と蘊蓄を傾けるような濃厚な世界が繰り広げら れる。
今回、このスキタイ組曲を演奏会で取り上げることが決定し、やりたい事がある。中学3年生の自分 に会いに行き、「大丈夫! 将来、君はこの曲を吹けるから!」と声をかけたい。どんなにか喜ぶだろ うか。
今の自分の中には、当時の自分がかすかに残っている。練習の度に、当時の自分が大変喜んでいるのを感じる。新響は、そんな私を凌駕するほどの情熱を、この曲に、自分の楽器に、オーケストラそのも のに傾けてやまない者の集まりだと言っても過言ではない。そのような者が大量に舞台にひしめき合い 演奏するその心意気、迫力を是非受け取っていただきたい。
プロコフィエフは、「ピーターと狼」「ロメオとジュリエット」等で有名な、ロシアの作曲家である。美しいメロディ・ラインや、魅力的な転調が印象的である。このスキタイ組曲は、彼が20代中盤に差し掛かった頃の作品である。
当初は、スキタイ人を題材とした「アラとロリー」というバレエ音楽として構想されたが、興行主であ るバレエ団のディアギレフにより、「これでは春の祭典の二番煎じである」としてこの話は断られてし まう。そこで演奏会用の作品として組み直し、管弦楽組曲「スキタイ組曲」として1916年に発表した。 ある程度物語性を残しているので、「アラとロリー」という題名が付されることが多い。
■アラとロリーのあらすじ
あらすじを簡単にご説明する。古代のイラン系遊牧騎馬民族「スキタイ」の信仰の対象である「太陽 神ヴェレス」。その娘が森の神「アラ」である。その反対勢力が、暗黒魔人「チュジボーグ」。チュジ ボーグはアラを誘拐するが、スキタイ人の勇者ロリーがヴェレスの助けを借りアラを救う、というのが 内容である。
さらに、この曲の物語性への理解を深めるため、楽章ごとに解説を加える。
第1楽章「ヴェレスとアラへの讃仰」
野蛮で色彩的な音楽は、スキタイ人の太陽信仰を表している。兇暴な部分は太陽神ヴェレスを、柔和 な部分はその娘アラを表している。
第2楽章「邪神チュジボーグと魔界の悪鬼の踊り」
スキタイ人がアラに生贄を捧げていると、7匹の魔物に取り囲まれた邪神チュジボーグが野卑な踊り を舞い始める。
第3楽章「夜」
邪神チュジボーグは夜陰に乗じてアラを襲う。月の女神たちがアラを慰める。
第4楽章「ロリーの栄えある門出と太陽の行進」
勇者ロリーがアラを救いに現れる。太陽神ヴェレスがロリーに肩入れして、チュジボーグを打ち負かす。勇者と太陽神が勝ち、日の出を表す音楽によって組曲が終わりとなる。
冒頭の例に加え、吹奏楽コンクールでよく取り上げられる楽章は第2楽章であり、その短くまとまっ た演奏効果抜群の内容は、非常に記憶に残る。しかし、プロコフィエフは自伝の中で、「第1、第2楽 章はすぐにできたが、第3、第4楽章は作曲に時間がかかった。それだけに、第3、第4楽章の内容に は自信を持っている。」と語っている。是非、第3楽章冒頭の静謐な雰囲気、第4楽章最後の太陽神の イメージの圧倒的な表現も楽しんでいただきたい。
初 演:1916年1月29日 ペトログラード(現サンクトペテルブルク)にて、作曲者自身の指揮による
楽器編成:ピッコロ1、フルート3(アルトフルート1持ち替え)、オーボエ3、コールアングレ、クラリネット3(第3奏者は小クラリネット持ち替え)、バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット1、ホルン8、トラ ンペット5(第3奏者はソプラニーノ・トランペット持ち替え、第4奏者はアルト・トランペット、第5奏者は省略可)、トロンボーン3、バストロンボーン1、テューバ1、ティンパニ、シンバル2、大太鼓、トライアングル、タムタム、タンブリン、小太鼓、グロッケンシュピール、シロフォン、チェレスタ、ハープ2、ピアノ、弦五部
参考文献
『プロコフィエフ 自伝/随想集』 セルゲイ・プロコフィエフ 田代薫訳 音楽之友社
第214回演奏会のご案内
情熱と理性の指揮者 井崎正浩
井崎正浩は、1995年にブダペスト国際指揮者コンクールで優勝し国内外で活躍しています。特にハンガリーにおいては国内の主要なオーケストラのほとんどに客演しており、2007年にはソルノク市(ハンガリーの東方、ブダペストより100km)音楽総監督に就任しました。ソルノク市に所属する交響楽団、合唱団、舞踊団、劇場などの音楽文化団体の活動や施設運用を総括するポストで、井﨑がハンガリーでいかに活躍し期待されているかがうかがえます。
チャイコフスキーの運命交響曲
チャイコフスキーはロシアの大作曲家です。「白鳥の湖」や「くるみ割り人形」といったバレエ音楽や「悲愴」などの交響曲が有名ですが、なかでも交響曲第5番はもっとも演奏される機会の多い人気のある曲です。暗く深刻な序奏で始まり、甘美なメロディあり、優雅なワルツあり、そして最後には勇壮な行進曲で盛り上がって終わるという、とてもドラマチックなところが好まれるのでしょう。
この曲はチャイコフスキー48歳の時の作品で「運命の動機」が曲全体に登場します。まじめに生きてきたチャイコフスキーが年齢を感じ始め、人生を振り返って書いた切ない曲なのかもしれません。
天才プロコフィエフの若き日の作品
チャイコフスキーはペテルブルク音楽院で学びましたが(創設時に2年生に編入)、その50年後輩にあたるのがプロコフィエフです。卒業試験で既に出版されている自作のピアノ協奏曲第1番を演奏して賞を取り、その褒美としてロンドンに外遊しロシアバレエ団を率いるディアギレフに会いバレエ音楽を依頼され、作曲したのが「アラとロリー」でした。ストラヴィンスキーの「春の祭典」と似ているとして上演されませんでしたが、大編成管弦楽用に改編したのが「スキタイ組曲」です。
スキタイとは紀元前7~4世紀にアジア北西部を中心に活動していた遊牧騎馬民族で、ロシア民族の源流の一つと考えられています。「アラとロリー」は太陽神に反抗する暗黒の魔神が太陽神の娘アラを奪おうとするが、恋人のロリーが救い出し太陽神が魔神を打ち負かして日の出がくるというスキタイ人の太陽信仰に基づいた物語です。
初演時にはグラズノフが途中で退席するなど、聴衆には衝撃的な演奏でしたが、現在では吹奏楽でもよく演奏される人気の曲となっています。
交響曲の父 ハイドン
ハイドンは104曲(+数曲)と非常に多くの交響曲を作曲しました。古めかしいイメージがあるかもしれませんが、実に多様な曲を残し、楽しく優美で、ときにはユーモア満点の名曲ぞろいです。今回演奏する「時計」という呼称はハイドンがつけたのではなく、第2楽章が時計の振子を思わせることから19世紀につけられました。ラジオ「百万人の英語」のオープニングにも使われたので耳に馴染んだ
方も多いでしょう。
多彩なプログラムをどうぞお楽しみください。(H.O.)
第214回ローテーション
| プロコフィエフ | ハイドン | チャイコフスキー | |
| フルート1st | 吉田 | 松下 | 岡田(充) |
| 2nd | 藤井 | 兼子 | 新井 |
| 3rd | 兼子(+Alt) | - | 藤井(+Picc) |
| Picc | 岡田(澪) | - | - |
| オーボエ1st | 亀井(淳) | 堀内 | 横田 |
| 2nd | 亀井(優) | 岩城 | 山口 |
| 3rd | 桜井 | - | - |
| C.A. | 岩城 | - | - |
| クラリネット1st | 高梨 | 末村 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 石綿 | 進藤 |
| 3rd | 末村(+es Cl.) | - | - |
| B.Cl. | 大薮 | - | - |
| ファゴット1st | 田川 | 田川 | 浦 |
| 2nd | 齊藤 | 齊藤 | 長谷川 |
| 3rd | 浦 | - | - |
| C.Fg | 長谷川 | - | - |
| ホルン1st | 園原 | 鵜飼 | 箭田 |
| 2nd | 市川 | 市川 | 兪 |
| 3rd | 鵜飼 | - | 山口 |
| 4th | 兪 | - | 大原 |
| 5th | 大原 | - | - |
| 6th | 山口 | - | - |
| 7th | 箭田 | - | - |
| 8th | (*) | - | - |
| トランペット1st | 倉田 | 野崎 | 小出 |
| 2nd | 野崎 | 青木 | 中川 |
| 3rd | 北村 | - | - |
| 4th | 青木 | - | - |
| 5th | 中川 | - | - |
| トロンボーン1st | 武田 | - | 志村 |
| 2nd | 小倉 | - | 小倉 |
| 3rd | 志村 | - | 岡田 |
| 4th | 岡田 | - | - |
| テューバ | 土田 | - | 土田 |
| ティンパニ | 桑形 | 皆月 | 桑形 |
| トライアングル | 田中 | - | - |
| 大太鼓 | 今尾 | - | - |
| 小太鼓 | 中川 | - | - |
| シンバル1 | 桜井 | - | - |
| シンバル2 | 皆月 | - | - |
| タンブリン | 古関 | - | - |
| シロホン | 浦辺 | - | - |
| グロッケン | (*) | - | - |
| ドラ | (*) | - | - |
| ピアノ | 藤井 | - | - |
| チェレスタ | (*) | - | - |
| ハープ1 | (*) | - | - |
| ハープ2 | (*) | - | - |
| 1stヴァイオリン | 堀内(小松) | 堀内(小松) | 前田(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(福永) | 大隈(福永) | 大隈(福永) |
| ヴィオラ | 田口(佐々木) | 田口(佐々木) | 田口(佐々木) |
| チェロ | 光野(柳部) | 光野(柳部) | 柳部(光野) |
| コントラバス | 中野(加賀) | 中野(加賀) | 中野(加賀) |
(*)はエキストラ
ドヴォルザーク:交響曲第7番

交響曲第7番を作曲する前年のドヴォルザーク
【ドヴォルザークとスメタナ】
今やチェコを代表する作曲家と言えば、スメタナとドヴォルザークが真っ先に思い浮かべられるが、その二人の関係は必ずしも良好とは言えなかった。
ドヴォルザークよりも17歳年上のスメタナは、チェコ国民楽派の創始者として国内外に幅広く名が知られ、斬新かつ急進的なチェコ音楽の先鋒者としての評価を得ていた。 これに対してドヴォルザークは「チェコ的なもの」にとことん拘り、スラブ舞曲や民謡に素材を得た交響曲の作曲など、いわば保守的な作品を作り続けた。その結果、チェコ国内において、ドヴォルザークは「ただの平凡な作曲家」として軽視されたが、9曲の交響曲の他に10曲以上のオペラを作曲するなど精力的な創作活動を行い、次第に国際的名声を獲得するようになった。
この二人の対立関係は両者の死後まで続き、20世紀に入ってからも熱心なスメタナ推奨者であるネイ ェドリーがチェコの文化大臣となって、ますますドヴォルザークに対する評価が不当に虐げられることになる。
しかし、チェコ国内におけるこうした争いは、諸外国におけるドヴォルザークの音楽に対する評価には何ら影響を及ぼすことなく、むしろ自然と郷土への愛を歌う美しい作品として広く親しまれている。
特に、ドヴォルザークが好んで使う五音音階は、西洋音楽で使われる七音音階よりも東洋的で優しい 響きに聞こえ、交響曲第9番の第2楽章に「家路」という日本語のタイトルが付けられて親しまれているように、私たち日本人の生活にも彼の音楽はすっかりと根付いている。
【作曲の経緯】
1800年代の後半、イギリスではあまり知られていない作曲家、特に東欧やロシアの作曲家の作品を紹介する演奏会が頻繁に催されていた。ドヴォルザークの作品も民族色豊かな音楽として頻繁に取り上げられ、特に交響曲第6番はイギリスで大好評を博した。
1884年3月、ドヴォルザークはロンドン・フィルハーモニック協会の招きで初めてロンドンを訪問し、1万人を超える群集から熱狂的な大歓迎を受け、自ら指揮した演奏会も大成功を収めた。さらに翌年には同協会から新たな交響曲の作曲依頼を受け、1885年12月に作曲に着手。わずか4ヶ月足らずで交響曲第7番は完成した。
この時ドヴォルザークは43歳の円熟期。敬愛するブラームスの交響曲3番の初演に立ち会ったこと で、その影響を強く受け、また、メンデルスゾーンやモーツァルトなどの様々な作品からインスピレー ションを得て、自然を讃える壮大な交響曲ができあがった。
【曲の構成】
第1楽章 アレグロ・マエストーソ ニ短調 6/8拍子
冒頭、ホルンとティンパニの響きに導かれて、ヴィオラとチェロにより荘重なグレゴリア聖歌風の第1主題が提示される。これは神の導きにより、遠方より愛国者たちが祖国に帰ってくる場面だとされている。この後に1883年にドヴォルザークが作曲した劇的序曲「フス教徒」(注1)のモチーフが登場する。この旋律はチェコ人の熱い信仰心を表すものとして、スメタナの「わが祖国」などにも登場する。
重々しい中にも付点音符を伴う躍動的なリズムは、熱心な鉄道ファン(注2)だったドヴォルザークがレールの響きからヒントを得たと言われており、故郷を愛する人々の力強さと熱意を表している。

交響曲第7番の自筆スコア
(写真は指揮者のハンス・フォン・ビューロー)
第2主題は、フルートとクラリネットによって、平和と自然を愛するチェコの人々の穏やかな日常が描かれる。そして展開部は両者の掛け合いで音楽は進行する。後半、長いコーダ部分ではまたしても蒸気機関車を彷彿とさせる急き立てるようなリズムが登場し、激しく第1主題が再現された後にホルンによる主題の回想で静かに終わる。
(注1)フス教徒はカトリックの司祭である、ヤン・フスがチェコで始めた宗教改革に取り組んだ一派。チェコ語による典礼を推奨したが、後に異端派として処刑されたことから、フス派はボヘミア地方において、民族運動を象徴するものでもあった。
(注2)ドヴォルザークは大の鉄道ファンとして知られ、アメリカ滞在中はグランド・セントラル駅に日参し、熱心に蒸気機関車の行き先表示や番号をスケッチする姿が見られたという。作品の中にも鉄道にヒントを得たであろうリズムや加速感などが随所に感じられる。現在、プラハとウィーンを結ぶ特急「アントニン・ ドヴォルザーク号」が走っている。

EC76/77 アントニン・ドヴォルザーク号
第2楽章 ポコ・アダージョ ヘ長調 4/4拍子
ゆったりとしたクラリネットによる主題に伴って、オーボエ、ファゴットが内声的に穏やかなコラールを奏でる。その後、ヴァイオリンとチェロによる美しい民族的な主題が流れるが、これは交響曲第9番にも使われている「五音音階」で、私たち日本人にとってはどこか懐かしく、心地よい柔らかな響きを醸し出す。五音音階はロマン派にとって重要な音階であり、愛を象徴する場面ではショパンなども多用している。
ボヘミアの大自然のような牧歌的なホルンが奏でられると、次第に主題が変形されて現れては消え、 またしても交響曲第9番の第2楽章にも似たやさしい響きが聞こえてくる。
第3楽章 スケルツォ:ヴィヴァーチェ―ポコ・メノ・モッソ ニ短調 6/4拍子
ドヴォルザークは民族音楽の研究を通じて「スラブ舞曲」など沢山の舞曲を書いている。
この楽章は、チェコの代表的な民族舞曲フリアントのリズムをモチーフにしており、6/4拍子で書かれているものの、ヴァイオリン、ヴィオラの主題は3/2拍子のような音形を刻むという複雑な構造をとっている。一方では、ファゴットとチェロの隠し味のような対旋律が見え隠れし、躍動感とともに郷愁を表現することに見事に成功している。
中間部は少しテンポを落として自然倍音を活かした明るいカノンのような曲となった後、長いコーダ に入って楽章を終える。
第4楽章 フィナーレ:アレグロ ニ短調 2/2拍子
冒頭の劇的な音楽は、前述の序曲「フス教徒」から。最初と最後の楽章に民族運動を象徴する「フス 教徒」の主題を置くことにより、曲全体の愛国的な性格をより一層強調している。
弦楽器やクラリネットの駆け上るような音形は第2楽章で用いられた旋律を変形して用いている。第1主題はクラリネットとホルンによるうごめくような主題、チェロによって演奏される民謡風の幸福な第2主題はイ長調で、第1主題と好対照をなしている。
展開部ではこれらの主題に提示部の最後でヴァイオリンが演奏するメンデルスゾーンの交響曲第4番 「イタリア」に似たフレーズやモーツァルトの交響曲第41番「ジュピター」最終楽章も登場した後、第1主題の冒頭部分を力強く奏でて速度を上げると、ニ長調・Molto maestoso(非常に荘厳に)に転じて速度を緩め、変形された第1主題を壮大に演奏して、ニ長調で全曲を閉じる。
参考文献
『クラシック音楽史体系8 』(パンコンサーツ)
『名曲解説全集第1巻 交響曲上』(音楽之友社)
『交響曲読本』(音楽之友社)
『作曲家別名曲解説ライブラリー6 ドヴォルザーク』(音楽之友社)
初 演:1885年4月22日 ドヴォルザーク指揮、ロンドンフィルハーモニー交響楽団
楽器編成:フルート2(第3楽章でピッコロ持ち替え)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、弦五部
ブラームス:ヴァイオリン協奏曲
ブラームス(Brahms, Johannes:1833-1897)はその生涯に独奏楽器と管弦楽の為の協奏曲を4曲書いているが、作曲者45歳の年(1878)に書かれた作品番号77を持つニ長調のヴァイオリン協奏曲は、その内2番目にあたる、そしてヴァイオリンのみを独奏楽器とする唯一の協奏曲である(他の3曲は、ピアノ協奏曲第1番ニ短調作品15(1856-9)、ピアノ協奏曲第2番変ロ長調作品83(1881)、ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調作品102(1887))。
初演当初より、高名な批評家エドゥアルト=ハンスリック( 1 8 2 5 - 1 9 0 4 ) に「ベートーヴェン(1770-1828)とメンデルスゾーン(1809-1847)以来現れた最も重要なヴァイオリン協奏曲」と賞賛されたことから、ベートーヴェン(ニ長調 作品61、1806)とメンデルスゾーン(ホ短調 作品64、1844) の協奏曲と共に「三大ヴァイオリン協奏曲」と称せられることもある。因みに、同じく1878年に作曲されたチャイコフスキー(1840-1893)のヴァイオリン協奏曲(ニ長調 作品35)を加えて、四大ヴァイオリン協奏曲と称されることもあるが、チャイコフスキーは友人に宛てた手紙の中で、ブラームスの協奏曲について「回りくどくて退屈」等と酷評しており、一方チャイコフスキーの協奏曲は、ウィーンフィルハーモニーの演奏会に於ける初演を聴いた、ブラームスを支持するハンスリックにより、「悪臭がする」等とこれまた酷評されている。今日のわれわれから見れば、二人の天才的な作曲家が奇しくも同じ年に銘々が同じ調性の二曲の傑作コンチェルトを残してくれただけでも本当に有難い限りであるのだが。
18世紀を通じて近代的な奏法が確立されたヴァイオリンは、19世紀に入ると華やかな名人芸で魅了するヴィルトゥオーゾの時代を迎える。それらの演奏家の中には、その演奏が作曲家を刺激して優れた作品を生み出す契機となるような者もしばしば現れ、彼らは場合によっては作曲家に対し技術的な助言を与えることで、作品成立に深く係るようなこともあった。先行するベートーヴェンとメンデルスゾーンの協奏曲の成立に際しては、それぞれフランツ=クレメント(アン・デア・ウィーン劇場管弦楽団コンサートマスター)とフェルディナント=ダフィッド(ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団コンサートマスター)という名ヴァイオリニストの存在が大きな影響を与えたとされているが、ブラームスの協奏曲についても、2歳年長の大ヴァイオリニスト、ヨーゼフ=ヨアヒム(Joahim, Joseph 1831-1907)の存在無しには語ることが出来ない。
ヨアヒムとの出会いは、まだブラームスが無名時代の1853年に遡る。当時既にヴァイオリニストとして名声を確立していたヨアヒムは、彼の友人であるヴァイオリニスト、エドゥアルト=レメニーの伴奏者としてブラームスがピアノを演奏するのを聴くと直ちに興味を持ち、すぐに彼をロベルト=シューマン(1810-1856)に紹介した。その才能にいち早く目を留めたシューマンは、自ら主催する『音楽新報』誌に、「新しい道」と題する記事でブラームスを賞賛し、これがきっかけとなりブラームスは世に出ることとなった。(因みに、ブラームスがシューマンを訪問した時、シューマンはヨアヒムのためにヴァイオリン協奏曲を書いていた。残念ながらこの協奏曲は何故かヨアヒムの生前演奏されることがなかった。)従って、ヨアヒムはブラームスにとってはシューマンと並ぶ大恩人ともいうべきで、途中関係が疎遠になることもあったが、生涯を通じての芸術上の盟友でもあった。

ブラームスとヨアヒム
ブラームスがヴァイオリンのための協奏曲を作曲するきっかけとなったのは、ツィゴイネルワイゼンで有名なスペイン生まれの大ヴァイオリニスト、パブロ=サラサーテ(1844-1908)が、彼に献呈されたマックス=ブルッフ(1838-1920)のヴァイオリン協奏曲第2番(頻繁に演奏される第1番はヨアヒムに献呈されている)を演奏するのを聴いたことにあると言われているが、作曲に際してはヨアヒムの演奏を念頭に置き、自分の精通した楽器(ピアノ)ではないヴァイオリンという楽器の為の作曲であることもあり、一貫してヨアヒムに多くの助言を求めた。ヨアヒムは、上述のクレメントやダフィッド以上に曲の成立に深く係ることとなったが、1878年夏の作曲開始から1879年1月1日のライプツィヒに於ける初演を経て、1879年10月の楽譜出版に至るまでの一年以上に亘る両人の協働作業については、数多くのドキュメント・資料類が残っており、その過程をかなり詳しく追うことが出来る。それによると、ブラームスは必ずしも独奏ヴァイオリンの技術的な事柄ばかりではなく、音楽的により深い部分でもヨアヒムの助言を求めており(ヨアヒムは優れた作曲家でもあった)、それらは全てではないが、ブラームスの採用するところとなっており、この協奏曲は殆どブラームスとヨアヒムの共作といっても過言ではないと言われる程である。
楽曲は伝統的な古典的協奏曲の形式に従い三楽章からなるが、独奏ヴァイオリンがオーケストラをバックに華やかな技巧を示すロマン派のヴィルトゥオーゾ風の協奏曲とは異なり、独奏ヴァイオリンとオーケストラが対決・協調し合いながら両者が渾然一体となって、極めて交響的な響きを織り成している。ライプツィヒに於ける初演から一週間後のウィーン初演を指揮したヨーゼフ=ヘルメスベルガーは、この様な性格を評して「ヴァイオリンのための協奏曲ではなく、「反」ヴァイオリン協奏曲(nicht für,aber gegen Violin)」と呼び、20世紀前半に活躍した名ヴァイオリニスト、ブロニスラフ=フーベルマンも「ヴァイオリンがオーケストラに対抗する協奏曲-そして、最後はヴァイオリンが勝つ」と評した。
独奏ヴァイオリンには極めて独特な高度な技巧が要求されており(一例を挙げれば、9度や10度音程の重音の多用。左手がある程度大きくないと困難であるため、ヨアヒムは変更を求めたが、そのままとなった。)、ヨアヒムはそれを「実に普通とは違った難しさ」(wirklich ungewhonte Schwierichkeiten)と評している。初演時の批評においても、「ヨアヒム程の鍛えられた百戦錬磨の闘士を以ってしても、ソロパートの技術的な難しさ、扱い難さと格闘している様がはっきりと見て取れた」とまで言われた。曲はもちろん、ヨアヒムに献呈されている。
【第一楽章】アレグロ・ノン・トロッポ ニ長調 3/4拍子
全曲の半分以上の長さを占める堂々たるソナタ形式の楽章。作曲者とヨアヒムによる試演を聴いたク ララ=シューマンは当時の名指揮者ヘルマン=レヴィに宛てた手紙で、この楽章の雰囲気が前年作曲さ れた交響曲第2番と著しく類似していることを指摘している(同じ時代に、同じ調性、同じ拍子、同じ速度記号で書かれているので、ある意味尤もである)。牧歌的な第1主題により開始され第2主題を欠くオーケストラの提示部が次第に緊張感を高めて独奏ヴァイオリンの登場を準備する様は、それだけでも見事である。古典的協奏曲の形式に倣い、曲の終わりに独奏ヴァイオリンによるカデンツァが弾かれるが、ブラームス自身はカデンツァを残していない。作曲当時から多くのヴァイオリニストによりカデンツァが書かれているが、最も有名で演奏されることが多いのはやはり、ヨアヒムのものである。流石に曲の成立に深く係っているだけあって、時折他のヴァイオリニストによるカデンツァを聴くと違和感を覚える程、協奏曲本体と同化している(本日の演奏では誰のものが演奏されるかはお楽しみ)。変わったところでは、フェルッチョ=ブゾーニがオーケストラ伴奏つきのものを残しており、録音ではかつてギドン=クレメールがマックス=レーガーの無伴奏ヴァイオリンのための前奏曲をまるまる一曲(この楽章のカデンツァとして)弾いたものがある。
【第二楽章】アダージョ ヘ長調 2/4拍子
当初構想されたスケルツォと緩叙楽章を外して代わりに差し替えられた三部形式の中間楽章で、ブラ ームスはこれを「情けない」アダージョ(ein armes Adagio)と呼んだ。この表現には、構成的により大規模な作品を計画していたのを断念した無念さを見ることが出来るが、これはむしろ反語と受け止めた方が良かろう。開始早々暫くの間、オーボエが田園的な美しい旋律を嫋嫋(じょうじょう)と奏で続け、一段落し たところで漸く独奏ヴァイオリンが加わる。サラサーテはこの部分について、「ステージの上でヴァイオリンを持ったまま、オーボエだけが美しいメロディを奏でるのを聴いているのは嫌だ」と評している(彼は生涯で一度もこの協奏曲を演奏することはなかった)。確かに独奏ヴァイオリンにはそのままの形でこの美しいメロディが現れることはないが、広い音域を駆使して装飾的に絡み、嬰ヘ短調の中間部ではコロラトゥーラアリアの様に揺れ動く気分を切々と訴えかける独奏ヴァイオリンは、この楽器の魅力を十二分に伝えて余りある。ブラームスやサラサーテの言葉に騙されてはいけない。
【第三楽章】アレグロ・ジョコーソ、マ・ノン・トロッポ・ヴィヴァーチェ―ポコ・ピウ・プレスト ニ長調 2/4拍子
ロンド・ソナタ形式。冒頭のエネルギッシュな主題はハンガリー風であるが、最後のコーダではトルコ行進曲風に変形される。ハンガリー生まれのヨアヒムは、自身3曲のヴァイオリン協奏曲を作曲しているが、当時よく演奏された第2番の協奏曲(1853)はブラームスに献呈されており、その第三楽章は、「ハンガリー風フィナーレ」のタイトルを持っている。ブラームスはその協奏曲の献呈へのお返しとして、ヨアヒムに敬意を表し、自身の協奏曲のフィナーレにおいてもハンガリー風の主題を用いたのであろうか。
参考文献
Malcom MacDonald, Brahms(New York; Schirmer Books, 1990)
Clive Brown, Bärenreiter 原典版楽譜(BA 9049)の序文(Kassel, 2006)
Michael Struck, Henle 原典版楽譜(HN 9854)の序文(München, 2005)
初 演:1879年1月1日 作曲者自身の指揮、ヨアヒムの独奏ヴァイオリンによる。
於ライプツィッヒ ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のニューイヤーコンサートにて。
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、ティンパニ、弦五部、独奏ヴァイオリン
演奏時間:約38分
ブラームス:大学祝典序曲

若き日のブラームス
■作曲の経緯など
ヨハネス・ブラームスは1833年5月7日、ドイツのハンブルクで生まれました。そうなんです。昨日はブラームスの178回目の誕生日でした。同い年の作曲家には、ロシアのA.ボロディン(1833-1887)がおり、また発明家でノーベル賞の提唱者であるA.ノーベル(1833-1896)も同じ年にスウェーデンに生まれています。日本は江戸時代後期、「天保の大飢饉」が起こった年でした。
ブラームスが36歳のときの作品である《ドイツ・レクイエム》が大成功を収めてから、彼の作曲報酬は大きく上昇し、ウィーン楽友協会からも音楽監督就任要請があるなどブラームスの名声は各地で大きく高まっていました。そこへ満を持して交響曲第1番が発表されます。海を渡ったイギリスでもブラームスの作品と名声は広まっており、ケンブリッジ大学は1876年に、ブラームスに対して名誉博士号授与の申し出を行います。このとき仲介役を努めたイギリスの作曲家スタンフォードは、名誉博士号授与式の際に、完成されたばかりの交響曲第1番の、ブラームス自身の指揮によるイギリス初演を計画します。ところがブラームスは、船旅に気乗りしない、英語が苦手、儀礼的なことにたいして負担を感じるなどの理由から、この申し出を断ってしまいました。しかしその後、今度はロンドン王立フィルハーモニー協会が、授与式にブラームスが出席する必要を求めないということで、彼に金メダルを授与します。
この間にも交響曲第2番の大成功、ヴァイオリン協奏曲の発表など、次々と意欲的な作品を送り出し ているブラームスにたいして、1879年に、ドイツ(現ポーランド)のブレスラウ大学からも名誉博士号授与の申し出があります。これはブレスラウ管弦楽協会の指揮者であり、ブラームスを支持していたB.ショルツ(1835-1916)の推薦によるものでした。イギリスでの一件を気にしていたブラームスは、ショルツに手紙を書き、称号を受け取るためにはどうすれば良いか相談します。その答えが、何か曲でも書いてくれたらありがたいというだけで、船旅の必要もなく、特に面倒な条件もなかったため、これを受けることにしました。
現在のブレスラウ大学
はじめはブラームスも、歴史ある大学にふさわしい威厳のある曲、もしくは輝かしい曲を作ろうとしていたようですが、以前に彼がゲッティンゲン大学で哲学などを受講した際におぼえた学生歌を用いて、楽しい演奏会用序曲を作曲することにしました。したがってこの曲は、大学側から祝典的な行事などのために委嘱されて書かれた曲ではなく、ブラームス自身の感謝や喜びの気持ちを込めた曲なのです。このことからブラームスは《大学祝典序曲》というタイトルについて最後まで悩んでいました。
この少し前、敬愛するシューマン夫妻の息子で、ブラームスが名付け親となってかわいがっていたフ ェーリクスが病気で亡くなり、翌年にはブラームスの長年の友人である画家のフォイアーバッハが亡く なったことも知らされます。大きな名声の裏側で、大きな悲しみに包まれていたことが伺い知れます。
また、ボンでシューマンの記念碑の除幕式があり、シューマンの妻クララと出席しました。シューマン がライン川へ投身自殺を計り、精神病院へ収容された後に死を迎えた悲劇を改めて思い起こすとともに、シューマンによって世に羽ばたいた自分の存在を確認し、彼にたいする感謝の念を抱いたことでしょう。

ブラームスが敬愛していたロベルト&クララ・シューマン夫妻
このような心情も影響してか、ブラームスは《大学祝典序曲》の作曲中に《悲劇的序曲》の作曲を始 めます。彼自身によると「ちょっと違う曲も書いてみたくなったんだ」とのことですが、毒舌家で、皮肉やブラックユーモアの多かったブラームスですので、真意の程は分かりません。こうしてまったく性格の異なる2つの演奏会用序曲がほぼ同時期に書かれることとなり、演奏会でも2曲を同時に取り上げるプログラムが多かったようです。
ブラームスは1880年の5月頃から《大学祝典序曲》の作曲を始め、9月には《悲劇的序曲》とセットで4手ピアノ用の楽譜が完成しており、これらを9月13日のクララの誕生日にプレゼントして、2人で演奏しています。12月にはベルリンを訪れ、大学のオーケストラを指揮して試演会を開き、友人J.ヨアヒム(1831-1907)らにも聴いてもらいました。信頼する友人から多くの意見を求めたと思われます。初めて演奏会のプログラムとして登場するのは翌1881年1月4日で、このときも《悲劇的序曲》が一緒に取り上げられています。
■楽曲について
シンバル付き大太鼓を伴って、遠くから行進曲風の歯切れよい旋律が聴こえます。途中、弦とファゴ ット、ホルンにより賛美歌風の曲が挿入されますが、すぐに行進曲に戻り、今度はぐっと近付いてきます。やがて静かになると、穏やかなティンパニにのって、金管楽器によって明るくゆったりとした主題が奏されます。
これが《我らは立派な校舎を建てた》という学生歌で、イェーナ大学の学生組合が解散される時に、テュービンゲン地方の民謡に歌詞を付けて歌われてきたものと言われています。次第に楽器が増えて力 を増し、頂点を迎えます。経過句として再び行進曲が登場しますが、冒頭では短調だったものが、今度 は長調で現れます。すぐにヴァイオリンに柔らかい旋律が現れ、チェロの沸き上がるようなピチカートにのって第2ヴァイオリンとヴィオラによって、学生たちが宴会のときに歌う《祖国の父》を歌いだします。
木管楽器がこれを受け継ぎ、次に現れる主題を予告するように姿を変えてゆきます。この予告を受け てファゴットが軽快に《新入生の歌》を歌い始めます。
これは元々《狐の歌》と呼ばれていて、詩人L.ホルベルク(1684-1754)の書いた喜劇の中で農夫たちが歌う歌詞などをもとにして、民謡の旋律に歌詞を付けたものと言われています。大学での勉強を望む新入生が、希望を胸に馬で目的の大学に向かう様子を描いたものだそうです。しばらくこの主題を扱うと、冒頭に登場したいくつかの楽句を変形させて展開部を形成します。しかし冒頭の行進曲が現れて、すぐに再現部に入ります。ここでも《我らは立派な校舎を建てた》が管楽器で現れますが、呈示部のように柔らかいものではなく、弦楽器も伴って盛大に歓喜を謳歌しています。次いで《祖国の父》も姿を見せ、《新入生の歌》で盛り上げておき、《さあ愉快にやろうじゃないか》によって学生たちの感激と喜びを頂点に導きます。これは1700年代から愛唱されていた学生歌で、管楽器によって高らかに歌い上げられ、壮大に締めくくられます。
自由なソナタ形式を基本として、それぞれの学生歌を、変奏や独自の主題を用いて緻密につなぎ合わ せてゆく技法や、キャラクターに合わせた楽器の割り当てなど、ブラームスの優れた技法が存分に活用 された、創意溢れる傑作へと仕上がっています。また、ブラームスの管弦楽曲の中では珍しいほど打楽 器を多用していることにも注目です。
《大学祝典序曲》いかがでしたでしょうか。この後にも彼の傑作《ヴァイオリン協奏曲》や、彼が見いだしたチェコの天才作曲家、ドヴォルザークの交響曲が続きます。彼らが生きた時代に想いを馳せながら、ごゆっくりお過ごしください。
参考文献
『作曲家 人と作品シリーズ ブラームス』 西原稔著(音楽之友社)
『ブラームス 大学祝典序曲』ミニチュアスコアOGTー57 門馬直美解説(音楽之友社)
『作曲家別名曲解説ライブラリー ブラームス』 (音楽之友社)
初 演:1881年1月4日 ブラームス指揮
ブレスラウ管弦楽協会第六回予約演奏会
ブレスラウのコンツェルトハウスにて
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トラン ペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、トライアングル、弦五部
インスペクター体験記、そして震災・・
皆さん、インスペクターってご存知ですか?一般にはあまり馴染みのない言葉だと思いますが(アメリカの警察で警部のことを指したりするようです)、オーケストラでは練習の計画を立てたり進行を取り仕切ったりする役目を言います。
このインスペクター(以下インペク)を今年1月演奏会まで4年間務めさせて頂きました。振り返ってみると甚だ頼りないインペクだったと反省しきりです。それでも「この機会に是非体験談を」と新響で随一の存在感を示す維持会マネージャー氏から頼まれまして、まあ滅多にない機会だから、と引き受けた次第です。
ところが、いざ書こうと思ってもなかなか思いつきません。その時々はいろいろ考えながら取り組んでいた筈なのに、喉元過ぎれば何とかですっかり記憶から消えちゃっているのです。(単なる物忘れの進行かもしれませんが・・)
まあそれでも過去の資料などから記憶の糸をたどり(って言うと地道に取組んでいるように見えますが、実際は空っぽの頭をたたきながら唸りまくっていました。ああ見苦しい・・)何とかまとめてみました。ご一読頂ければ幸いです。
■成田空港から練習会場へ
5年前に新響は創立50周年を迎え、4回の演奏会で特別プログラムに取り組みました。自分がインペクに就任したのはその翌年4月の演奏会シーズンからです。「50周年が終わったから少しは軽めのプログラムになるかな」と考えていたら、とんでもない!前年に劣らない重量級のプロが並びました。そしてインペクとして活動を開始したのですが・・。
実はインペクに決まった直後(年末でした)に会社から転勤の内示が出まして、都内勤務(土日休み)から、成田空港勤務(土日・日月休みのシフト制)になってしまったのです。(会社が航空貨物関係なので、こんな場所にも職場があるのです。)さて困った!土曜出勤だと練習は遅刻か欠席。インペクどころか新響も続けられるだろうか、と頭を抱えつつ、年明けの正式な辞令を待って団内の関係者に相談しました。
「新響クビですかね~?」
「取り敢えず続けてみてよ。インペクも。
練習に間に合わない時はカバーするから」
という有難いお言葉(?)でクビにはならず、とにかくやってみることになりました。
でも初っ端のシーズンは流石に緊張しました。いくら仕事での遅刻は認めてもらっても、やはり「出来るだけ早く練習に入りたい」という思いはあり・・。土曜は残業がなければ16時までの勤務ですが、退社後は京成の成田空港第2ターミナル駅までダッシュ(実際は会社のバスで駅近くまで送迎ですが、バスの中を走っているような気持ちでした。)16時半くらい発のスカイライナーに飛び乗って日暮里経由で十条の練習場到着が18時くらい。17時45分の開始には間に合いませんが、何とか遅れを最小限にしようとしてました。(因みに当時の京成スカイライナーは今のシティライナーに相当するもので、空港から日暮里まで1時間くらいかかりました。今は30分弱ですね、今なら間に合ったかも・・でも高い!)
月4回の週末のうち土日休みと日月休みが半々なのと、十条以外の練習場だと18時以降開始のパターンがあり何とか間に合うこと、などで遅刻回数は当初心配した程は増えず「おまえは遅刻が多すぎるからクビ!」にはならずに済みました(ホッ・・・)。
こうしてインペク就任後2年間は成田から通い続けました。会社と新響という仕事と音楽の切り替えは移動の電車内だったのですが(今だから告白すると)譜面やスコアを読んだり演奏を聴いたりという模範生的なことは一切やらず、ただただ田園風景を眺めながら途中からウトウトしていただけでした。「ちゃんと勉強しろ!」とチェロのトップに怒られそうですが・・。でも印旛沼とか眺めながらマッタリしている時間はとてもとても貴重でした。(そういうことでトップの皆さんゴメンナサイm(_ _!)m)
3年目には再び都内勤務となり練習に100%出席出来る環境になりました。
■指揮者の先生方との思い出
インペクとしてお付き合いさせて頂いた指揮者の先生は、小松一彦先生、山下一史先生、高関健先生、飯守泰次郎先生、そして曽我大介先生の5人です。
このうち最も多かったのが小松先生の5回(他に演奏旅行で本番2回)でした。インペク最初のシーズンも小松先生でしたし、200回演奏会や芥川先生没後20年の記念演奏会、新潟演奏旅行といったイベント的なシーズンをご一緒させて頂きました。先生の指揮では、例えばショスタコでの厳格なテンポキープやドヴォルザーク、ラフマニノフで旋律を歌わせる時の表情は特に印象的でした。とてもフレンドリーな方で練習スケジュールの件などで良く携帯に電話を頂きました。「指揮者の小松です。」で始まり「安田さんとのホットラインでの連絡だけど・・」とこちらの気持ちを取り込みながら、いろいろな提案をして下さいました。「事務所は何とかするから」と言って半年先の予定を決めて下さったり・・。残念ながら体調を崩されて療養中とのことで、新響もここ1年半はご無沙汰しています。また元気なお姿を見せて頂きたいな、と思います。
次が山下一史先生の4回です。新響とも4年前が初共演でした。音楽への造詣の深さと的確なご指導が素晴らしく、年1回ペースでのお付き合いをして頂いています(今は常任の仙台フィルが大変なことになっていてご苦労されているようです)。
実は自分の失敗談ですが、確かイベールの『寄港地』の練習(第202回定期)の時でしたが、先生が練習終了時間を1時間勘違いされていたことがありました。おそらく自分の伝達ミスだと思うのですが・・。終了(20時45分)30分前になっても曲の半分にも達してません。「前半が難しいから時間をかけているのかな」と思って(思い込もうとして・・?)ましたが、先生が「ではここで休憩して・・」と言った時には鈍い自分も流石に(もしや!)と思い・・
「残り30分ですから休憩はちょっと・・」
「えー、9時45分までじゃなかったっけ」。
(ここからはパニックのためか自分の記憶が定かではないのですが)
「少し延長とか出来ないかな~?」
「出来ません!ダメです!」
この言下に切り捨てたことが後の飲み会で話題になり「指揮者にあれだけ言えるのはおまえしかいない」と褒められ叱られ・・。先生に申し訳ないやら、穴があったら入りたいやらで散々でした。(このシーズン後も先生は2回共演して下さり、来年1月もご一緒出来ることになっているので、取り敢えず水に流して下さったかな、とひとます安堵しております。)
高関先生とは3回ご一緒しました。全部メインがマーラーの交響曲でした。(第9番、第6番、第7番。因みに今年秋に第5番をご一緒します。)トレードマークの自転車出勤(?)は最近見かけられなくなりましたが、大指揮者でありながら、飄々と登場され団員の中にすぐに溶け込むさまは、さながら忍法「大衆隠れの術・・?」みたいな感じ。「先生、まだ来られてないのかな~」と周りの団員に聞くと「あそこに」。指さしたところにはすっかり団員と同化(?)した先生が談笑している、まさしく「健ちゃん」(失礼!)と言った感じでした。(因みに先生の練習はほとんど時間どおりに終わるのでインペクとしては有難かったです。)
曽我先生とは2回。2年前が新響初共演でした。独特のパフォーマンスも印象的でしたが、音程感覚や旋律の歌い方をとても大事にされていて、この両面からのアプローチが2回の演奏会でとても良い体験につながったと思います。初共演でのバーンスタイン『シンフォニック・ダンス』で練習スケジュールの確認メール中で「シャウト(叫ぶ)やフィンガースナップ(指パッチン)はどの程度やったら・・」と阿呆な問い合わせをしたら先生からは「とにかく思いっきりやって!指パッチンは練習が必要ですよ。」との返事。実際の練習でもシャウトのパート練習をやらされました・・^_^!!)
■飯守先生
そして今回共演する飯守先生とは2回ご一緒しました。実は最初に周りから「先生は良く練習会場や日時を間違えるから注意した方がいい。」とアドバイスを受けていました。本当かな、と思いつつも忙しい先生の貴重な練習がボツになったりするとインペクは磔にされるか滝野川に浮かぶかもしれない・・などと勝手に思い込み、それこそ必要以上に電話、ファックスで連絡を取り続けました。そのおかげ(?)か言われたような行き違いはなかったのですが、後で考えるとちょっと大袈裟に心配し過ぎたようです。(先生の名誉のために言いますと、実際はとても細かくスケジュールを確認されていたようです。)
ただ練習の時間配分は予定どおりにいかないことが多かったです。これは先生の所為というより新響側の問題が多いのですが・・。全ての作品と真摯に向き合いその世界に全精力を傾け入り込まれる先生にとって、我々の音程や出の間違いミスはまさしく「音楽を冒涜する悪行」。1小節間違えて飛び出したりすると「何でそんなことが出来るんですか!」と髪を振り乱し口からは泡を吹きながら(ちょっと大袈裟?)興奮して叱咤されます。うっかり間違っちゃった、という言い訳は全く通用しません。和声を宇宙的奇跡として捉えておられ、音程が悪いと「そんな音程は、その辺のコンビニでも売ってません!(コンビニ関係の方ゴメンナサイ!)」もし売ってるなら是非買いたい、と思うくらい打ちのめされます。でも先生の音楽とその姿勢には皆共感しているので、それこそバンジージャンプやジェットコースター程に底まで何回堕とされても、その都度這い上がり本番を迎えようとするのです。(ライオンの子供みたいでいじらしいかも・・)
今回のブラームスとドヴォルザークも先生が非常に情熱を傾け取組まれています。残念なことに震災の影響で先生との練習が1回中止となってしまったのですが、これから仕切りなおして5月の本番で素晴らしい音楽体験を披露出来たらいいな、と思っています。
■貴重な体験に感謝、そして震災
終わってみると4年間はあっと言う間でした。この原稿を書き始めた時は「何も覚えてないな~」という感じでしたが、書いているうちに段々思い出してきて・・。他にもトレーナー先生方とのやり取り、団内の多くの方のサポート、協力など、いろいろなことがありました。今にして思えば全てが自分には過ぎたる貴重な体験だったのかな、と感じられます。繰り返しになりますが、あまり頼りになるインペクではなかったですが、それでも多少なりとも新響のお役に立てたかな、それなら良かったけど・・などと思っています。そして自分にとって身に余る体験をさせて下さった団に感謝の気持ちで一杯です。
今シーズンからチェロの柳部容子さんが後任を務めてます。若さに溢れ何事にも積極的で周りへの気遣いもある彼女は、私が4年間かかって辿り着いたレベルを1ヶ月でクリアし、さらなるステップアップを遂げています。これからが本当に楽しみです。
そして・・・この原稿を書き始めた直後に3月11日、あの大震災の日を迎えました。東京の職場でいわゆる「帰宅難民」となり、その後の計画停電による交通機関マヒの影響も受けたのですが、東北地方を中心に被災された方々の苦労の比ではありません。被災者の方には心からお見舞い申し上げます。
新響の練習も2回休みとなりました。日常生活が混乱している中でのこの決断は正直とても有難かったです。でも2週間が過ぎて何となく不安定感が残る毎日。余震、計画停電、放射能ニュースの影響かな、とも思いましたが、3月26日に3週間ぶりに練習に出てみて感じました。「自分にはこの週1回の音楽体験が必要なんだ」と。
この原稿を書いている3月終わり時点で、いろいろ不安定要素はあるけど5月の本番は「是非成功させよう」というのが我々の気持ちです。スポーツ界、芸能界の方々もコメントされているように「みんなを元気付けることも大事」という気持ち、これを大切にしていきたいです。節電など苦労を分かち合うことはもちろんですし(3月26日の練習ではエアコンを止めました)諸援助など出来ることはやっていきたい、でも新響という場で音楽を発信していくことが我々にとって、そして聴きに来て下さるお客様にとって重要なことだと感じています。その気持ちを胸に抱き5月8日の東京文化会館大ホールのステージで聴衆の皆さん、そして団員みんなと素晴らしい音楽体験を共有出来る日をめざして頑張りたい思います。
音楽の帰るとき - 東北・関東大震災に寄せて -
3月11日、東北・関東で大地震が発生しました。広範囲での甚大な被害、原発や電力のこと、この原稿を書いているのは3月末ですが、まさに様相は「未曾有の国難」と形容せざるを得ないものになってきてしまいました。今回の地震で、音楽を生業とする人や音楽愛好家の多くが、音楽と人間との関係について改めて色々考えざるを得なかったのではないでしょうか。維持会ニュース編集人の松下さん(フルートパート首席)から原稿執筆依頼を受けた時には、入団してようやく1年というぺろぺろの新人として「新鮮な角度から新響を切り取った報告を書くように」とのお達しだったのですが、その後起こってしまったこの地震の存在を完全に無視することはやはり出来そうにありません。すでに多くの声明や意見が出されており、マスコミの怒涛の報道も相まっていささか世間全体が悲しみ疲れ、考え疲れた感もありますが、ご容赦ください。
今回の第213回演奏会での指揮者を務める飯守泰次郎先生は、ご自身のブログの中で今回の地震の話題に触れ、このように書かれています。
同じく指揮者で、新響とも度々共演している山下一史先生の文章も、3月22日の日本経済新聞文化欄に「音楽の出番を待つ」という題で掲載されました。山下先生はその時仙台フィルとのリハーサルの直前で、ステージ裏で地震に遭遇。雪の中なんとかホテルへ戻り、その後多くの人の助けを得てようやく東京に帰りつくまでの顛末が記事の中で詳細に報告されています。さらに仙台フィルの演奏会は6月まで中止になったことに続けて、山下先生は以下のようにつづられています。
お二人の記述からは、音楽が心を勇気づけるものとして、必ず人間から求められる存在であることに疑いを抱いていない一方で、音楽の必要性に対して「衣食住足りての」という認識も強く持っておられることが読み取れます。
音楽は常にこの2つの面を持つものであるという考え方は、恐らく多くの方が理解し賛同されるものと思います。山下先生の記事が載った翌日の日本経済新聞には、フランスの劇作家パニョルの記述として、人が笑うためには「永遠に生きていけるという保証が与えられねばならない」というものが紹介されていましたが、結局のところ、音楽を含む芸術や笑いなどには皆おなじことが言えます。マズローの欲求階層説やホイジンガのホモ・ルーデンス(遊戯人)を引けば、芸術や遊び、音楽を求める心は、「動物」としての生理的・安全にかかわる欲求がすべて満たされた上で初めて発生するものであって、それは最も「人間」的ともいえますが、良くも悪くもかなり限定された高度な欲求だということです。
とはいえ今回の震災のような状況でも発生しない限り、ことに我々音楽愛好家にとってそれを改めて意識するのは意外と難しいものです。どんなに善意に溢れて素晴らしい音楽を奏でたとしても、聴く側にそれを受け取る心身の余地が無いうちは、その音楽は必要とされるものではなく、演奏者側の自己満足になってしまう。地震に際して実に多くのチャリティーコンサートや音楽家の活動が行われていますが、中には「不謹慎」「いま本当に必要な物は何かを考えろ」といった批判をされてしまうものもあるのは、そんな音楽の一面によるものでしょう。もとより数年来の不況で、音楽が「生活か文化か!」といった極端な二元論でぶったぎられがちな社会情勢もあります(維持会の皆様という存在がある新響は本当に恵まれております)。しかしながら今回の震災でわたしが音楽に対して最も強く感じたのは、こうした社会的な音楽の立場や役回りよりさらに本質的・内面的なものです。すなわち、わたしという人間の心から音楽が離れる瞬間があったのか、という衝撃です。
この「有事」における音楽への批判の声を聞いて、音楽家や音楽愛好家は、音楽が否定され不必要とされる場合があるのだったと思い出さざるを得なかった。それで無力感を覚え、ショックを受けた面もあるでしょう。当事者だった場合はより深刻で、いつものように音楽が自分にしみ込まないので音楽に見放された気持ちになったり、もしくは自分がこんな状況なのに音楽なんて、と行き場のない怒りの矛先を音楽に向けてしまうこともあるかもしれない。ただそんな諸々の理屈や類推以上に、わたしは自分自身と音楽との関係が地震後の一定期間、大きく変化したことが大変な驚きでした。体も持ち物もたいした被害を受けず、知人もみな無事で済んだにも関わらず、わたしは震災から半月近くの間まったく楽器を吹かず、音楽を聴くこともありませんでした。常ならぬことの連続で精神がすり減り、音楽に対して細やかに寄り添うだけの余地がなかったのだと思います。できたことはまさに、おろおろ歩き、涙を流すことくらいのもの。正直に告白すると、地震当日の3月11日こそ「明日の新響の合奏は中止かな…いや這ってでも練習来いとか言いかねない団だし…」と実はそればかり考えていましたが、その後は音楽というものの存在自体を思い起こさない期間があり、そのことに後から気付いて愕然とする、という具合でした。逆にいえばそうした経験を経て、今回初めてわたしは「音楽の出番じゃない時がある」という事実をしんから理解した気もします。
それでも、音楽には必ず人間に必要とされる、という一面があることもやはり確かです。再び飯守先生の話題に戻りますが、先生は地震直後の3月13日に関西フィルとの特別演奏会を行っています。演奏会当日のプレトークで、以下のようなお話をされたとのこと(先生のブログより転載・抜粋)
山下先生の記事で登場した仙台フィルも、はやくも3月26日に復興コンサートを行い各ニュースに取り上げられました。ホールは使用できないので会場は市内の寺を間借りし、お客さんも100人ちょっとだったとのことですが、仙台にはすでに、おそらく山下先生の予想をも超える早さで、「音楽の出番」が訪れたのだということが判ります。
新響もちょうど同じ3月26日、地震後実に2週間ぶりで練習が再開されました(2週続けて練習が休みになるというのは新響ではまず無いことだそうです)。月並みな表現ですが、皆と「ご無事でしたか」と言い合える、一緒に合奏できるということに非常な幸せを感じました。自分のもとへ音楽が帰ってきてくれたことを知ったのもこの日です。こちらは逆に独りよがりな表現になってしまいますが、ドボルザーク7番を吹きながら、自分の身がフォルテシモの猛烈なtuttiの渦の中へ抵抗なく飲まれていく感触がした、その瞬間に確信した次第です。
卑近な例で恐縮ですが、わたしの妹は音楽の大学で歌をうたっており、文句の多い彼女の口癖は「歌なんてさ、腹がふくれるでなし、究極に非生産的でいったい何であたし歌うんだろうって思うわけよ」。とはいえその次に来るせりふは常に 「でもあたしには歌が必要だし、他に必要な人もいると思うからね」というものです。
我々はおおむねこの思考の流れでこの結論に行きつくが故に、音楽を愛し続けているのではないかと思います。地震によって音楽がひととき自分を離れ、また戻ってきたいま、この結論は自分の中でより揺るぎないものになっています。今回の演奏会で、聴いてくださる皆様との間に、音楽への新たな感慨を共有できれば大変嬉しいことです。そして被災地をはじめとする各所で、いまだ地震によって離れたままの音楽が、遠からぬうちにもとの人の心へ無事帰ることを願ってやみません。
第213回ローテーション
| 大学祝典序曲 | バイオリン協奏曲 | トボルザーク7番 | |
| フルート1st | 岡田(充) | 岡田(澪) | 松下 |
| 2nd | 新井 | 兼子 | 吉田 |
| Picc | 兼子 | - | - |
| オーボエ1st | 岩城 | 亀井(淳) | 堀内 |
| 2nd | 桜井 | 山口 | 横田 |
| クラリネット1st | 末村 | 品田 | 高梨 |
| 2nd | 品田 | 石綿 | 大薮 |
| ファゴット1st | 浦 | 田川 | 長谷川 |
| 2nd | 田川 | 浦 | 齊藤 |
| C.Fg | 齊藤 | - | - |
| ホルン1st | 大原 | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 市川 | 市川 | 山口 |
| 3rd | 園原 | 園原 | 鵜飼 |
| 4th | 兪 | 兪 | 大原 |
| トランペット1st | 小出 | 野崎 | 倉田 |
| 2nd | 中川 | 青木 | 北村 |
| 3rd | 青木 | - | - |
| トロンボーン1st | 武田 | - | 志村 |
| 2nd | 小倉 | - | 武田 |
| 3rd | 大内 | - | 岡田 | テューバ | 土田 | - | - |
| ティンパニ | 桑形 | 今尾 | 古関 |
| トライアングル | 今尾 | - | - |
| 大太鼓 | 中川 | - | - |
| シンバル | 中川 | - | - |
| 1stヴァイオリン | 前田(大隈) | 前田(大隈) | 堀内(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(笠川) | 小松(笠川) | 小松(田川) |
| ヴィオラ | 常住(佐々木) | 常住(佐々木) | 常住(佐々木) |
| チェロ | 柳部容(光野) | 柳部容(光野) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 中野(加賀) | 中野(加賀) | 中野(加賀) |
第213回演奏会のご案内
ドヴォルザーク=ボヘミアのブラームス
今回は指揮に飯守泰次郎を迎え、久々の東京文化会館での演奏会です。飯守は正統派ドイツ音楽の巨匠ですが、スラブ系の曲も得意としています。今回はその中でチェコの大作曲家ドヴォルザークの交響曲第7番を取り上げます。
ドヴォルザークといえば「新世界」交響曲があまりにも有名ですが、この第7番は絶対音楽的な性格が強く、形式的にも古典的な構成で、9つの交響曲の中でもっとも交響曲らしい作品です。ブラームスの交響曲第3番の影響が強いといわれていますが、ドヴォルザーク独特の素朴で温かな響きを持ち民族的な要素も散りばめられている魅力的な曲です。
ドヴォルザークとブラームスの友情
ドヴォルザークは肉屋の長男で家業を継ぐはずだったのですが、修業先の学校で音楽を学びプラハのオルガン学校に進みます。卒業後はヴィオラ奏者や教会オルガニストをしながら貧しいなかで作曲を続けていましたが、34歳から5年間オーストリア政府の奨学金を得ることができました。その審査員だったのがブラームスでした。ブラームスの推薦により出版社の契約作曲家になることができ、ドヴォルザークは世界的に認められるようになります。その後も二人の交流は生涯続きました。
ブラームスの円熟期の名曲
演奏会の前半では、ブラームスのもっとも脂ののった時代といわれる45歳前後に作られた2曲を取り上げます
大学祝典序曲は、ブレスラウ(現ポーランド・ヴロツワフ)大学から名誉博士号を贈られたお礼として書かれた曲です。その少し前にケンブリッジ大学から名誉博士号を贈りたいと通知があったときは、イギリスに出かけて儀式に参加することが条件だったので断ったのですが、こちらは面倒な条件がなく祝典曲を作曲してくれればありがたいということだったので称号を受けたのでした。4つの学生歌が引用された陽気でユーモラスな曲です。そのうちの1つ「新入生の歌」がファゴットのメロディで演奏されますが、この部分はラジオの大学受験講座のテーマ曲に使われたので特に有名です。
ブラームス唯一のヴァイオリン協奏曲は、ベートーヴェン、メンデルスゾーンの作品とともに「三大ヴァイオリン協奏曲」と称され、ブラームスらしい重厚な交響的な響きがする大作です。最初は4楽章で構想されていましたが、ブラームスの友人の名ヴァイオリニストのヨアヒムとのやりとりのなかで、伝統的な3楽章形式の曲は完成し、初演もヨアヒムが独奏をつとめて大成功を収めます。その後もヨアヒムやその弟子たちが何度も演奏し、この曲の存在感が高まりました。
ヴァイオリン独奏には、松山冴花を迎えます。世界から実力者の集まる仙台国際音楽コンクールで優勝し、ニューヨークを本拠地に演奏活動をしていますが、日本でも数々のオーケストラと共演をしています。
飯守の奏者に求める完成度は非常に高いものがありますが、それに応え作品への共感に満ちたものとなるよう、心をこめて演奏いたします。どうぞご期待ください。(H.O.)
<全身全霊・一音一音に魂を込めて> 辻志朗 高田三郎を語る
高田三郎作品のピアニストとして、節目のステージに高田三郎氏から幾度となく起用され、薫陶を受けられたピアニスト・合唱指導の辻志朗先生よりお話をうかがいました。土田:
辻志朗先生とは、大久保混声合唱団の定期演奏会(注1) に新響が出演した時にお世話になりました。志朗先生の父上で大久保混声合唱団を創立時から指導され、日本の合唱界に多大な貢献をされた辻正行先生が亡くなられた翌年の演奏会です。
辻:
「わたしの願い」は高田先生ご自身がピアノ伴奏をオーケストラに編曲された自筆譜での演奏で、とにかく真っ黒で何が書いているのかわからなくてね。パート譜とも違って大変でした。
土田:
新響は、自筆譜による曲の演奏は慣れているので大丈夫です(笑)。1976年に新響が創立20周年記念として「日本の交響作品展」を企画、高田先生の出世作「山形民謡によるバラード(1941年)」を演奏しましたが、管弦楽作品はその時以来の演奏となります。
辻:
私はあまり高田先生の管弦楽作品は聴いたことがないのです。高田三郎といえば合唱曲「水のいのち」というイメージではないですか。この曲は200版も出版されています。ちなみに晩年の先生の作品は不協和音で実験作品というか、「水のいのち」の好きな人は離れていくみたいな感じでしょうか。宗教三部作(注2)はとにかく重たいですよ。先生がすごく宗教というのを重く捉えていて、イスラエルの民がどれだけ大変な思いをしたのかということを、よくレッスンの度におっしゃって、イスラエルの民の大変さを和音で表わすかのようです。
先生の晩年は、とにかく難しい音で、難しい顔をして亡くなられた。お葬式の時、先生のお姿を幾度となく拝見しましたので。私はそのように思いました。奥様の留奈子さまに伺ったお話では、そのままキリストのように亡くなられたそうです。おれは死ぬぞーっと十字架にかかるようなポーズをとり、そのまま神のもとにいかれたのですから、けっして悲しいことではない、とおっしゃっておりました。
土田:
今回の2つの狂詩曲は木曾節と追分節をテーマとして、こぶしというか伊福部作品ほど原始的ではないのですが、エネルギッシュでわかりやすく、ノスタルジーと爽やかな抒情性を感じます。
辻:
高田先生がどのような音を書かれているのか、とても興味があります。新響のみなさんとご一緒した「わたしの願い」は、ピアノ伴奏とオケ版のイメージが全く違うのですよ。私はピアノ伴奏を弾いていたイメージでオケのスコアを見た時、どうしてここでこういう楽器がでてくるのだろうか、という感じさえ持っていました。先生は全く発想すら変えてあの曲を書いていたと思うくらい。びっくりしました。すごく新鮮な気持ちで指揮することができました。でも当時は、どちらの方が先生の想いだったのかな、と感じてはいましたね。
土田:
そうでしたか。新響にとって「わたしの願い」という合唱曲の傑作を、オケで演奏するのはとても貴重な経験でした。
辻:
華やかで明るくて、高田先生のオケはこういう響きがするのだと、とても面白く新鮮でしたね。先生の独特な和音が、私にはとても華やかに聞こえた。先生の曲は、物が迫ってくる、闇が迫ってくるような重さ、どんなに美しい曲でも、猛烈に詩の方に強いエネルギーがあって、詩をどう伝えるのか、という重さがあります。例えば「水のいのち」の詩を書かれた高野喜久雄さんと高田先生は、仏教徒とクリスチャンという違いはあるにせよ、お二人とも信仰という高みと深みの中に居られたがゆえ、常に人智を超えたものがそこにいて、というような重さがある。
いすれにせよ、私にとって高田先生はピアノ伴奏つきの合唱作品というイメージです。あの時の演奏はCDで発売されていて時々聴くのですが、すごく面白い。自分がピアノを弾いているのはあまり聞かないですけどね(笑)。よくあんなに録ったなあ、という感じ(笑)。
土田:高田先生との出会いは?
辻:
小学生の時から作曲家になりたくてずっと勉強していました。偉い先生に見てもらおうと思ったのでしょうね。中学生になって高田先生に指揮と作曲を習った父に連れられて先生のところへ伺いました。 のっけから怒鳴られまして、それでもなんとか1年くらいは通って、最終的には、おまえ向かないから、僕にはできることないから、と言われました。オーバーに言えば人生が変わった瞬間です。作曲家になろうと小学校からそれなりに和声学の勉強をして、疑いもせずに行こうと思っていた全てを否定したのが高田先生。それでピアノに転向して武蔵野音大に入り大学院を出てから先生と再会したのは、高田三郎作品演奏会で、先生が指揮をされて「確かなものを」混声三部合唱初演のときでした。当時は冒険でしたよね。20代でしたから。怒鳴られつつレッスンしていただいて。
土田:高田先生は志朗先生のことご存じでしたか?
辻:
ええ。お前か、みたいな(笑)。とにかくいろいろとやらせていただいて、高田先生の演奏会の合同曲というと私を使ってもらうようになりました。
土田:
私事で恐縮ですが、学生時代に四大学女声合唱団連盟の合同曲で高田先生が指揮された「わたしの願い」女声合唱版の練習を何回か現場で拝見したことがあります。驚きました。小柄な方でしたがとてもエネルギッシュ! 女子大生に向かって大声で、ばかものー!と怒鳴られる。でも合唱団は先生の指導に一生懸命ついていくのです。
辻:
とにかく全身全霊。声がでかくてね。もうすさまじい勢いでしたね。先生がこちらを見たときに、こっちが先生を見ていないと怒られるのですよ。でも指揮者をずっと見てるわけいかないでしょう。こっちはピアノ弾いているのに(笑)。 見そうな時はなんとなく視線がふっとくるのですね、その時に反応しないと怒られる。合唱団の中で自分を見ていない者を見つけると厳しく叱責されました。すごかったのは「水のいのち」の1曲目から2曲目の曲間で、準備のため動いた私に、まだ音楽は続いているのだ!ばかもの!と、びっくりしました。しかも本番中ですよ。小さい声でいえばいいものを、バカモノー!!とかなり強い口調で。前の方のお客様は聞こえたと思いますよ。終演後挨拶にいったら、お前は俺を恐れないのがいい!と褒めてくださった。恐れるやつだったら怒鳴らなかったのでしょうね。お前はでかいから立つな、主役は俺だ、とかね。
土田:とにかく厳しくて怖い先生だったのでしょうか?
辻:
とても愛情のある先生でした。ある演奏会の打ち上げで、先生は、どうだ!作曲やんなくてよかっただろう、と私におっしゃったのです。ようするに、だめだといったぐらいで作曲を辞めちまう程度の決意だったんだと、作曲家としては。どうしてもやりたければ、石にかじりついてでもその目標に向かっていくのが通常なのに、おまえは俺が一言いっただけで辞めちゃったじゃないか、お前の決意はそんなもんだった、そんな者に続くわけがない、と言われましたね。それはものすごくグサっときました。先生に習った時は中学生ですからね、当時は大作曲家に、お前は向かない、と言われれば、だめなのかな、と思いますよね(笑)。
本当に作曲家を目指すのであれば、それでも続けるやつが作曲家になっている、ということは、先生は私の音楽的能力も見たのだろうけど、性格とか人間として作曲家には向かないと見抜いたのであれば、猛烈な教育者ですね。時がたてばたつほど、先生への尊敬が湧きあがり、言い換えれば、恐怖感から畏敬の念に変って行きました。
土田:興味深いエピソードですね。先生のキャラクターとか如何でしたか?
辻:
ものすごく人間的な先生で楽しいお酒を飲まれる方でした。そして先生とはとてもいい関係を持つことができました。父も私も高田三郎そのものに近づこうとするのではなく、先生から和声や作曲を習っていたので、客観的に作品と向き合うことができ、作品として習ったとすれば、先生が指揮して私が伴奏ピアノを弾いた時に与えられるオーラですね。冗談みたいだけど、ピアニシモになると先生はしゃがむのですよ。ピアノより小さくなっちゃうので見えなくなってしまう(笑)。
とにかく先生はご自身の作品に確固たる信念をお持ちだから、人の演奏に対して厳しくなるのです。作曲家はこの演奏者がどういうふうにやってくれるのだろうか、自分の子供が社会にでていった、どういう風に染まっていくかが楽しみ、みたいな方が多いと思いますが、先生は、ここはこうだと、お決めになる。
土田:
ストラヴィンスキーは、自分の音楽を演奏するためピアニストや指揮者として活躍した、なぜなら作曲したとおりに聴いてもらうことができるからで、自分の作品を他人が指揮するのを聴くと怒りだした、というエピソードを聞いたことがあります。
辻:
高田先生が、とにかく自分の書いている音は一音たりとも無駄な音はない、全ての音に意味があって一音一音に魂を込めて書く、一音書く度に俺の髪は白くなっていく、ということをおっしゃっていた。だから俺は真っ白だ、じゃあもう書けませんね、とか思わず口にでかかった(笑)。70代の頃でしたね。70になって俺は初めて自分を許せるようになった、とおっしゃっていましたね。
土田:
高田先生の合唱作品は清廉潔白というか独自の境地にあり、孤高の作曲家というイメージがあります。でも志朗先生が冒頭おっしゃっていたように、重くて暗いところがあって、それはやはり言葉によるものでしょうか。
辻:
詩によってだと思います。高野喜久雄さんの「水のいのち」と吉野弘さんの「心の四季」は全然違うじゃないですか。思想的に。曲は似ているけど。そういうと怒られちゃうかな(笑)。似た雰囲気はありますけどね(笑)。
土田:それは作曲家の個性というものでしょうね。
辻:
高野喜久雄さんとのコラボが神に近くて、一番清廉潔白にみえるのかもしれない。それは詩がそうなのであって、高田先生がその詩から受けるインスピレーションでああいう音しか頭に浮かばなかったのではないだろうか。神を絶対に冒涜できない人ですから。だから神に近いそういう清らかな音を書いたのではないか。善と悪というのがものすごくはっきりとしていますね。悪に例えられるものは、ものすごい不協和音を使ったりしてね。
土田:
詩に対する思い入れがものすごく強くて、徹底的にそぎ落として推敲されたのですね。
辻:
先生は、いつも詩が書いてあるメモを持っていらした。ポケットから汚い紙を出して、もう何十回と読み直して、書いては消しを繰り返しながら曲を創っていかれる、という話は伺った。ものすごく考えて。とにかくまずは詩を読み込むところから入る。高野喜久雄さんの詩を読んでいくと、我々でさえ敬虔な気分になるのですから、お互い信仰に深く係わり理解し合ったもの同士がそれを読んだら、高田三郎はどんどん深み、というか、高みに入っていくのですね。そういう音に自然となっていったのでしょう。
先生は、これは何の音か、というような言い方をよくされる。例えば「水のいのち」四曲目で~充ち足りた死を~という詩の前にピアノで4度と1度、すなわち~アーメン~と弾くのですよ。全ての部分に意味があるのです。これってただのアーメンじゃないか、と思いながら当時はね、弾いていました。若かったから。
土田:当時は、そのようなことを先生にお話しすると大変なのですよね(笑)。
辻:
とても言えません。わざわざ怒られようと思いませんよ(笑)。当時は弾くしかなかった。高田先生が亡くなってからですね。私が先生の曲を振るようになったのは。振るようになると、そういうこだわりの意味が見えてくる。楽譜の見方が変わってくるのです。指揮者とピアノでは観ている場所が違う。だから詩と和音との関連というのを考えた時に、先生の音に対するこだわりをロジックとして感じました。詩からインスピレーションを受けている高田先生と高野喜久雄さんとのコラボでの独特なもの、という気がしている。「水のいのち」と「心の四季」を振る時は、私の中で何かが違っています。
高田先生の書いている作品はどことなく宗教の香りがしてくるのですけどね。神がかっているところにこだわっているのかもしれません。例えば「心の四季」で、~雪が全てを真白に包む 冬がそれだけ汚れやすくなっている~、pppで歌われる印象的な一節です。その言葉がものすごく潔癖なもの、潔白であればあるほど受けいれられやすい、そういう神がかっている言葉にこだわりを持って語らせるとかね。
土田:
高田先生の本を拝見すると「なぜ」という問いかけと、「死」に対する思い入れを感じます。子供のころからの胸いっぱいの様々な「なぜ」を唯一解決してくれたのが、ベートーヴェンの交響曲、すなわち音楽だった、という話に注目しました。
辻:
先生は、昔ご自分をよくベートーヴェンに例えていらした。俺の音楽は飯を食いながら聴ける音楽ではない、ベートーヴェンの音楽を聴きながら飯を喰えるか!モーツァルトではない、俺はベートーヴェンだ、と自分の作品への触れ方をおっしゃっていました。性格としてそういう音楽の創り方をしている、ということ。全てが主張です。ディベルティメントは書いていない。
土田:
前回(211回)の演奏会で権代敦彦さんの曲を演奏しましたが、クリスチャンである権代さんは学生の時に教会で高田先生の「典礼聖歌」をオルガンでよく伴奏しました、と伺いました。日本語による「典礼聖歌」を多数作曲されておりますが、日本の旋法を用いて書こう、という発想がすごいと思います。
辻:
先生が日本で一番大きく残された功績はそれだと思います。220曲もありますよ。しかも独特でどこから見ても高田三郎なのです。神の言葉として日本の文化の中にキリスト教の典礼を入れたということで、バチカンから叙勲され認められた(注3)。これはすごい。先生は国立音大で作曲科教授でありグレゴリオ聖歌の先生でした。イントネーションを重視したがために、曲のほとんどはアウフタクトから始まっている。グレゴリオ聖歌はそうだ、と先生はおっしゃっていました。アウフタクトこそ、最もイントネーションがクリアになる手法だと。
初めて高田作品に触れる方は、歌いにくい、言葉がつけにくい、と言いますが、ピアノはそうではなかったりします。とにかく合唱の言葉がたちやすい。それは確かですね。
土田:あらためて伺いますが、志朗先生が高田作品の演奏を通して学んだものは?
辻:
控えめの美徳。抑圧されたもの。ピアニストとして一番勉強したのはピアニッシモです。いかにクリアなピアニッシモを表現するのか、本当に鍛えられました。枯れた音、もっと弱く、とか。そもそも私が伴奏しているときの出番は、複数の合唱団による合同曲ですから合唱の人数も多くて(笑)。600人の合唱団に向かって、百人いようと千人いようとピアニッシモはピアニッシモだぞ、千人だから大きくていいということはない!とおっしゃる。その緊張感がすごかった。
オーケストラは楽器の集合体なので各自が事前にさらうことが前提ですが、合唱は全員同じことをやっているのでサボっていてもわかりません。でも、合唱は1人でも音楽を壊すことができる、怠け者が1人でもいれば合唱団は成り立たない、とおっしゃっていました。
さらう、ということは素晴らしいことなのです。
土田:高田先生の曲のピアノ伴奏は難しい?
辻:
そもそも、ピアノの書き方がとても難しい。ものすごく難しくて、中学生向けに書いているという作品でも弾きにくい。先生の合唱作品の伴奏をされているピアニストは皆さんそうおっしゃいます。
土田:志朗先生にとって高田作品への想いは?
辻:
私が高田先生の年に近づいていくにつれ、だんだん理解していくのかな。先生が振っていらしたころに私がもっと曲を理解していたら、もっといい演奏ができたなという思いはあります。例えば「水のいのち」は単なる水の歌だと思っている人が多い。生まれたものが天から地に落ちて、その魂がずーっと天に帰りたいと思いを持ちながら、最後に、~のぼれ のぼりゆけ~と、空への高まりとなって、最後の瞬間まで天を指し続けていく、という私たちの「いのち」の在り方を示しているのであり、だから、~何故 さかの ぼれないか~と、自分自身への詰問、という歌になるのです。
土田:単なる上流から下流への曲というのとは全然違いますね。所謂“Soul”「魂」ですね。
辻:
そうなのですよ。もっと宗教的な内容なのです。“The Soul of Water”です。そのような高田先生から習ったことを若い人に教えていきたい。どうしても自分の解釈がはいるから違うものになるかもしれませんが、やっぱり先生の精神、どのような想いで作ったのか、私にあれだけ語ったのを、伝えられればと思います。
典礼聖歌の練習で、先生は1時間あると50分しゃべっているのですよ。歌わせないで。イスラエルの民がどれだけ大変な思いをして、というような聖書の中の話を全部暗記していて語るのです。
土田:志朗先生は結局のところ高田作品がお好き?
辻:
好きなのかもしれない。でも自分からはやりません。やるとこだわりがでてくる。好きとか嫌いとかの次元ではないのです。とにかく私にとって高田三郎は一番影響を受けた作曲家でした。怒鳴られようと何しようと週に1回行ってレッスンを受けたのですから。和声学の勉強で、合っているのにも怒鳴られる。先生がご自分のを出されて、これとどっちがきれいだ、と聞かれる。それは先生の方がきれいです、としか言わざるを得ない。だったらどうしてそう書かないんだ!と怒られる(笑)。それで先生の和音が染み付いて行った可能性があります。すべて直球勝負。
土田:最後に高田先生のかわいいエピソードを。
辻:
お茶目でかわいい先生でした。自分で曲書いているのに、自分が間違えたときは、ごめんね、とかおっしゃって。憎めない人です。
先生は、本番前に必ずウィスキーのミニボトルをかっと飲んでいらした。気持ちを和らげるためだったのですね。大丈夫ですか?と伺うと、これを飲まないと上がるんだ、とのこと。先生が上がるなんて考えたこともない。ある曲の最後の音でガーッと決める時、俺に合図をくれ、ということもありました。指揮者に合図をしたのは初めてです。できないことはできない、という正直な方でした。
2010年10月28日
聞き手・構成:土田恭四郎(テューバ)
注1「大久保混声合唱団第31回定期演奏会」
2004年8月1日(日) 新宿文化センター
指揮:辻志朗
ブラームス:Nänie <哀悼の歌>
高田三郎:わたしの願い≪オーケストラ伴奏版≫ 他
注2 1979年「イザヤの預言」
1983年 預言書による「争いと平和」
1985年「ヨハネによる福音」
注3 1992年 ローマ法王ヨハネス・パウロⅡ世より“聖シルベストロ騎士団長勲章”授与
参考文献
「随筆集 くいなは飛ばずに」/高田三郎(音楽之友社)
「来し方 回想の記」/高田三郎(音楽之友社)
「ひたすらないのち」/高田三郎(カワイ出版)
「人物書誌大系31 高田三郎」/編者:国立音楽大学附属図書館
<辻 志朗プロフィール>
ピアノを故谷康子氏、故岡見淑子氏、前島あや子氏他に、音楽理論及びソルフェージュを故高田三郎氏、上明子氏、田中えりか氏他に師事。
武蔵野音楽大学音楽学部ピアノ科卒業、同大学院音楽研究科ピアノ修了。在学中、ピアノを渡辺規久雄氏、客員教授故ゲオルク・ヴァシャヘーリ氏、ゲルハルト・ベルゲ氏他に師事。伴奏法をヤン・ホラーク氏に師事。
修了後ウィーン国立音楽大学に聴講生として在籍し、指揮法&伴奏法、伴奏法、発声法を学ぶ。 現在、東京、神奈川、千葉、栃木、新潟、富山、鹿児島で20団体の合唱団の正指揮者として活動する他、全日本合唱コンクール、NHK学校音楽コンクール、全日本お母さんコーラス大会、各地の合唱祭、合唱講習会の講師を勤める。
ピアニストとしては、ピアノデュオ、声楽家とのアンサンブル、合唱作品の初演ピアニスト、レコーディング等の活動を行っている。
NHK交響楽団、東京交響楽団、東京フィルハーモニー管弦楽団、レニングラード国立歌劇場管弦楽団他、多くのオーケストラの公演に関与。
(社)日本演奏連盟会員 日本合唱指揮者協会会員、洗足学園音楽大学講師、NHK文化センター横浜みなとみらいランドマークタワー校「女声合唱講座」講師、高田三郎混声合唱作品全集「その心の響き」全4巻ピアニスト&指揮者。
07年公開 志の輔落語inパルコ「歓喜の歌」に於いて1ヶ月に渡る公演の合唱を担当。
08年4月発売 任天堂DS用ソフト“カンタン音学力”監修。
08年公開 シネカノン映画「歓喜の歌」に於いて合唱の指導を担当。
09年公開 東宝映画「零の焦点」に関与。
著書 「誰でもぜったい楽譜が読める!」音楽之友社 第14刷発売中
ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」
「ペトルーシュカ」はストラヴィンスキーの初期を代表する三部作の一つである。「火の鳥」(1910年)、「ペトルーシュカ」(1911年)、「春の祭典」(1913年)からなる三部作が、セルゲイ・ディアギレフ(1872~1929)の主宰するロシア・バレエ団のために作曲されたバレエ音楽の傑作であることは広く知られている。またそれぞれのスコアには副題として「M.フォーキンによって脚色された2つの情景からなるロシアのおとぎ話」、「I.ストラヴィンスキーとA.ベノワによる4つの情景からなる道化芝居」、「I.ストラヴィンスキーとL.レーリッヒによる2部からなるロシアの異教徒の情景」と記されており、3つの作品の性格を端的に表している。「火の鳥」は師であるリムスキー=コルサコフ譲りの豪華絢爛たる色彩豊かな響きが満喫できるロシアのおとぎ話であり、「ペトルーシュカ」はロシアの街をそのまま持ち込んだような生活の匂いのする民衆的なロシアが、そして「春の祭典」では有史以前の異教的なロシアが、あたかも過去に現実にあったように描かれている。ロシア・バレエ団の活動初期における天才興行師・ディアギレフは、当時芸術の国際的な中心地であったパリの観客がエキゾチックで刺激的な演目が好きなことを見抜き、観客の趣味に合致しそうなロシアのイメージを独自に作り出したのである。
ロシア・バレエ団による「火の鳥」はパリ・オペラ座での初演で大成功を収め、ストラヴィンスキーは一夜にしてロシアの若手作曲家の中でも最も才能豊かな人物として知られるようになった。そして次作品として「異教の生け贄(ルビ:いけにえ)の儀式を基にした交響的作品」という新たなアイデアを思いつき、ディアギレフの賛同も得ていた。しかしその夏の後半にローザンヌに滞在しているストラヴィンスキーを訪ねたディアギレフは、作曲家が「ピアノが主体的な役割を演じるオーケストラ作品」という全く違う分野に着手しているのを知って驚く。ストラヴィンスキーは現在の第2場にあたる部分をピアノで弾いて見せ、この作品の主役である「突然生命を与えられた人形」にペトルーシュカ(ピョートルの愛称)という名前までつけていた。しかしディアギレフはこの題材の絶大なる可能性を瞬時に見抜き、バレエ音楽として仕上げるよう懇願した。直ちに美術家であり舞台デザイナーでもあるベノワ(1870~1960)が共同制作者に選ばれ、4場からなる台本を作成した。そして翌年の1911年5月26日にスコアの最後の頁を完成させ、曲はそのベノワに献呈された。初演の指揮をしたのはピエール・モントゥで、次作品の「春の祭典」も初演することとなる。
初演は1911年6月13日にパリのシャトレ座で行われたが、「火の鳥」ほどの成功と評判はかち得なかった。しかしこの作品の音楽が前作よりはるかに独創的、前衛的であることは明らかである。また舞台においても、チャイコフスキーの三大バレエ(注1)に代表されるクラシック・バレエの定番であるソリストによる華麗なグラン・パ・ド・ドゥや、一糸乱れぬコール・ド・バレエ(群舞)、そしてソリストとコール・ド・バレエが一体となって最高の見せ場を作るグラン・パなどがどこにも見あたらない斬新なものであった。幕が開くなり19世紀前半のロシアの街から抜け出したような生活臭のする群衆が、無秩序にどんちゃん騒ぎを繰り広げている(ように見える)。街の娘の踊りは酔っぱらいのコサックダンスに中断され、そのコサックダンスも警官に中断される。しかし行商人、御者、ジプシー娘、手回しオルガン弾き、踊り子、民族衣装を着た娘たち、熊を連れた農夫、サモワールでお茶を給する屋台の主人といったロシアの庶民が好き勝手に動いているようで、ストラヴィンスキーの音楽も、初演を手がけたM.フォーキン(1880~1942)の振り付けもじつに緻密に計算され、絶大な効果を演出していた。こうした混沌のるつぼの中にペトルーシュカの悲劇が投げ込まれる、これがこのバレエの核心部分となっている。また初演時、当代きっての天才ダンサーであるV.ニジンスキー(1890~1950)によって演じられたペトルーシュカ役は、ダンサーの持つ美しさをすべて剥奪されることとなった。風にたなびく髪は帽子で隠され、鍛え上げて引き締まった肉体はだぶだぶのピエロ服に覆われ、端正な顔は白塗りにされた。繊細な表現を生み出す指先にまで分厚い手袋がはめられる。その上男性ダンサーの見せどころでもある高さのあるグラン・ジュテ(跳躍)や高速のピルエット(回転)も封印され、手足をバタバタとぎこちなく動かし、地面をはい回り、挙げ句の果てに虫けらのように殺され、最後は亡霊となって上半身を下向きにぶらんぶらんとぶら下がって幕となる。こんな不吉でグロテスクなものを見せられるとは世も末である、そう思った評論家や聴衆も多かったに違いない。また「空中で止まったように見える」と言われた高いジュテを誇るニジンスキー目当ての女性たちも、さぞがっかりしたであろう。だがこのような嫌悪に満ちた反応は興行師ディアギレフの狙い通りであった。センセーショナルで刺激的な公演は大きな反響を呼び、次第に聴衆の支持をかちえ、ストラヴィンスキーの作曲者としての地位も一層揺るぎないものとなった。なお今年は「ペトルーシュカ」が作曲・初演されてから、ちょうど100年を迎えることになる。
不思議なことだが、ストラヴィンスキーの三部作はバレエ公演としてクラシック・バレエほどは上演されず、もっぱらオーケストラ作品としてコンサート形式で演奏される方が多い。これはストラヴィンスキー自身が、次第にバレエの公演よりも演奏会形式を好むようになったことも大きい。1928年から作曲家自らが指揮台に立ってコンサート形式の演奏に取り組むようになると、オリジナルのバレエ・バージョンは演奏会用組曲に作成し直され、内容や編成が異なるいくつかの版が作られるようになった。また改訂版の作成は1945年にアメリカ国籍を取得してブージー&ホークス社と契約を結んだ以降に集中しているが、これは今までほとんど入手できなかった著作権料を獲得することにもあった。「ペトルーシュカ」においても1946年から1947年にかけて楽器編成のスリム化やリズム表記の整理などを含めた大幅な改訂が施された。本日の演奏はこの1947年版を使用する。
しかしながらペトルーシュカの作曲過程において、作曲家はサンクトペテルブルクに赴きディアギレフ、フォーキン、ブノワ、そしてニジンスキーらとバレエの進捗状況を綿密に打ち合わせていることから、音楽はバレエにおけるブノワの舞台とフォーキンの振り付けにぴったりと合致している。ここにバレエの筋を記したい。
第1場:謝肉祭の市場
舞台は1830年代の晴れた冬、マースレニツァ(ロシアの謝肉祭にあたる)のサンクトペテルブルクの海軍省広場。ロシア正教において復活大祭の前40日間の大斎(ルビ:おおものいみ)期間には、食の制限をはじめ生活の多岐にわたって厳格な規制があるが(注2)、マースレニツァはその大斎に入る直前の1週間をさす。多くの人々で賑わう広場の左手には客引きする女がいるバルコニー付きの建物があり、その下には大きなサモワールが置いてあるテーブルがある。中央に小さな見世物小屋があり、右手には菓子の屋台、のぞき紙芝居などがある。広場は着飾った娘や若者たち、御者、行商人、屋台の主人や客たちで賑わっている。冒頭でフルートが広場のざわめきを象徴する旋律を吹く。
これが弦楽器の小刻みな伴奏にのって繰り返されるうちに舞台の幕が開く。しばらくするとリムスキー=コルサコフの「100のロシア民謡集」に収められている「復活祭の歌」が全楽器で高らかに奏でられる。
歌詞の中では「ハリストス復活」と繰り返しでてくるが、この時はまだ大斎前で復活大祭までは6週間以上ある。バレエでは酔っぱらいたちがコサックダンスを踊るシーンになっている。だがすぐに変拍子の連続になり、2つの旋律が断片的に積み上げられ、酔っぱらいが警官に追い出されたり、祭りの興行師が群衆を楽しませたりする場面を繰り広げる。すると群衆の中から手回しオルガン弾きが一人の踊り子と共に登場する。今までの騒がしい音楽は後退し、2本のクラリネットにより手回しオルガンの素朴な旋律が奏でられる。
踊り子はトライアングルで拍子をとりながら陽気に踊り出す。ここでフルートとクラリネットで奏でられる旋律も、ロシア民謡の一節である。
さらに別の場所でオルゴール奏者と踊り子が登場し踊り始める。こちらはチェレスタを中心に演奏される。その後2組の踊り子たちが競い合って踊る場面となるが、突然手回しオルガンとオルゴールの音楽が中断し、元の喧噪に戻る。再び祭りの興行師が群衆の注意を惹きつけたり、酔っぱらいのコサックダンスが乱入したり、大道芸人がアクロバットを披露したりする場面となり、祭りは最高潮を迎える。すると突然音楽が中断し、小太鼓とティンパニの連打が鳴り響く。ここは二人の太鼓叩きが見世物小屋の前に現れ、群衆の中に割って入り喧噪を押さえこむ場面となっている。不気味なコントラファゴットとファゴットのモティーフが現れて、シャルラタンの登場を知らせる。シャルラタンとは客寄せの芸人を引き連れ、どこからともなく定住社会に潜入し、祝祭や大市などを格好の舞台として巧みな口上よろしく生半可な医術を営み、怪しげな薬を売りつけてはいずかたもなく去っていった近代前夜のヨーロッパの周縁者たちを指す。「魔法使い」や「人形使い」などと英訳、和訳されるが、パリ初演の配役表ではシャルラタンとなっていることから、現在日本でもバレエ公演の配役表ではシャルラタンと記されることが多い。この極めていかがわしい人物の登場により、バレエは現実から夢物語への境界を超えることとなる。群衆が固唾をのんで見守る静寂の広場で、シャルラタンはマントの下からおもむろに笛を取り出し、吹き始める。ここはフルートのソロによって奏される。群衆は夢心地になり、吸い寄せられるように見世物小屋の前に集まる。そして舞台の幕が静かに開き、3体の人形が現れる。右が道化人形のペトルーシュカ、中央がバレリーナ、左がムーア人となっていて、魔法使いが左から順に魔法をかける。突然生命を与えられた人形たちは、「ロシアの踊り」を踊り出す。
最初は足だけをバタバタとぎこちなく動かすだけの人形が、シャルラタンの合図でどんどん動きがエスカレートし、ついに見世物小屋を飛び出して広場の群衆の前で踊り出す。バレリーナとムーア人は上手に踊っているが、ペトルーシュカの動きはいまだにぎこちない。いったん音楽が静かになり、コールアングレとクラリネットのソロの掛け合いとなる中間部は、ペトルーシュカがバレリーナに恋心を抱き近づく場面である。しかしバレリーナの関心はムーア人にあるようで、怒ったペトルーシュカは棒を振り回し二人の間に分け入る。音楽は再び賑やかさを取り戻し、ドタバタ劇の末なんとか3人は仲良く踊るが、シャルラタンが魔法を止めたことにより広場にくずれ落ちる。すかさずティンパニと小太鼓の連打が鳴り渡り、幕が下ろされ場面が転換される。
第2場:ペトルーシュカの部屋
舞台は一転して暗くてみすぼらしいペトルーシュカの部屋になる。一面暗い色をした壁紙には星や三日月が描かれ、高いところにシャルラタンの肖像が飾られている。この第2場はストラヴィンスキーが作曲当初ピアノ協奏曲として着想した部分で、試作段階でディアギレフにピアノで弾いて見せた部分でもあることから、音楽はピアノ主体で進行する。またバレエの舞台においては、主役のペトルーシュカのほぼ一人舞台となっている。
幕が開くと部屋の扉が開いて、ペトルーシュカが蹴られてころがりこみ倒れ、扉が閉められる。2本のクラリネットによってペトルーシュカの主題から派生したモティーフが奏され、ファゴットも暗い影をそえる。
のろのろと身体をおこしたペトルーシュカは、やがて扉を激しく叩きながら部屋を回り、猛然と部屋から飛び出そうと試みる。ここで全楽器の強奏となり、ペトルーシュカの主題がトランペットに現れる。
ここは壁にかけられたシャルラタンの肖像画に向かって怒りをぶつける場面であるが、ふたたび倒れ込んでしまう。ここからペトルーシュカの独白になり、自分に人間の感情があることを恨み、寂しさや苦しみ、バレリーナへの恋心などのさまざまな葛藤を表現する。そこへ突然扉が開いてバレリーナが登場する。思わぬ出来事にペトルーシュカは狂喜するが、自分の気持ちを伝えようと焦る。飛び上がりながら近づいて行くがバレリーナは驚いて逃げ出し、無情にも目の前で扉が閉まる。ここで奏でられるクラリネットのソロは、ペトルーシュカの嘆きと絶望をあらわしている。扉に向かって激しく拳や頭を打ち付けるが、扉はびくとも動かない。ここはピアノとコールアングレの掛け合いとなっている。ついに部屋中をかけめぐり、全楽器の強奏となりトランペットにより再度ペトルーシュカの主題が吹かれる。シャルラタンの肖像画に怒りをぶつけ、再び外へ出ようと見せ物小屋の外に向かって叫ぶが、苦悶の末倒れ込んでしまう。すかさずティンパニと小太鼓の連打が鳴り響き、場面が転換される。
第3場:ムーア人の部屋
椰子の木や南国の花などの異国情緒あふれる壁紙に赤い床の豪華な部屋で、ムーア人は暇をもて余している。激しい序奏の後、クラリネットとバスクラリネットのユニゾンでムーア人の主題が吹かれる。
ムーア人はベッドに寝ころびながら椰子の実をボールのようにして遊んでいる。突然立ち上がり、三日月刀をひゅんひゅんと振り回し椰子の実を斬りつけるが、割れない。畏れをなしたムーア人は、椰子の実に向かってひれ伏し深々と頭を下げ礼拝する。そこへ小太鼓のリズムと共にバレリーナがおもちゃのラッパを吹きながら部屋に入ってくる。はじめは警戒していたムーア人だが、徐々に興味がわいてきて二人のデュエットによるワルツが始まる。
この部分はファゴットの分散和音にのり、フルートとトランペットの掛け合いによって演奏される。続いてハープと2本のフルートによるワルツに変わる。これらはヨーゼフ・ランナーのウィンナ・ワルツ「シェーンブルンの人々」からの旋律の引用である。ここはバレリーナだけの踊りで、ムーア人は座ってリズムをとり時々笑い声をあげて鑑賞している。おもむろにムーア人が立ち上がり、二人はすっかりロマンチックなムードになり一緒に楽しく踊る。だが突然二人はペトルーシュカの声を聞く。弦楽器の不安なトレモロにのって、トロンボーンがペトルーシュカの主題の変形を吹く。扉が開き嫉妬に駆られたペトルーシュカが乱入するが、圧倒的な力を誇るムーア人は猛烈に怒ってペトルーシュカを追い回す。曲調は一気に緊迫感を増し、ペトルーシュカの主題の断片が現れては消えていく。ムーア人は足をあげてペトルーシュカを踏みつけ、身体をつかんで部屋の外へ追い出す。ティンパニと小太鼓の連打が鳴り渡り、場面が転換される。
第4場:夕方の謝肉祭の市場とペトルーシュカの死
再び第一場と同じ日の、同じ市場に戻る。祭りは夕方になっても大きな盛り上がりを見せ、さまざまな人物がやってきては、色々な踊りを披露する。しばらくの間ペトルーシュカの物語は進行せず、オーケストラのほぼ全楽器による豪華絢爛な響きにのってロシア情緒あふれる多彩な踊りが次から次へと続く。まずオーボエによって「子守女の踊り」の主題が奏され、ロシアの民族衣装に身を包んだ美しい女性たちが現れる。
このメロディはホルンに移り、女性たちは扇子を持って優雅に踊り出す。さらにおどけた旋律が弦楽器にあらわれる。
若い男たちがコサックダンスを踊りながら乱入する場面で、ついには男女が一緒になり踊り出す。曲が4分の6拍子に転じると「熊を連れた農夫の踊り」に入る。クラリネットが農夫の牧人の笛を奏でる。
人々は驚いて道をあけるが、この合間をぬってテューバのソロがおどけたモティーフを奏する。これは農夫の連れた熊が後ろ足で立って進むありさまを描いたものである。この一行が去ると、二人のジプシー女を連れた行商人が登場する。弦楽器が行商人の主題をさっそうと奏し出す。
ついで行商人がアコーディオンを弾いてジプシー女が踊り出す場面となる。オーボエとコールアングレが快活なメロディを吹く。
タンバリンが打ち鳴らされるところは行商人が気前よく紙幣を巻く場面で、それを見た群衆が紙幣に群がって取り合いとなり騒然とする。行商人と二人のジプシー娘が去り、ピアノとハープの16分音符の連打がかすかに聞こえ、広場に小雪が舞い始めたことを示す。そして雪の中、馭者と馬丁たちによる勇壮な踊りが始まる。
先ほどの美しい子守女たちも加って全員の踊りとなり、全曲中最も華やかなクライマックスを迎える。いったん曲がおさまり、ピアノとハープの16分音符で仮面をつけた芸人たちの登場を知らせる。音楽は緊迫感を増し、悪魔の仮装をした男が高い跳躍をしながら踊る。そして仮面をつけた芸人たちと群衆が踊る真っただ中に、突然トランペットによる叫びがきこえ、見世物小屋の幕が揺れ出し、三日月刀を振りかざすムーア人に追われたペトルーシュカが飛び出してくる。そしてムーア人が逃げまどうペトルーシュカを刀で斬りつける。クラリネット2本の叫びの後、床に落とされたタンバリンの落下音により、ペトルーシュカが倒れたことをあらわす。驚いたムーア人とバレリーナは逃げ去る。雪の上に倒れた瀕死のペトルーシュカの痙攣はピッコロ、フルートが、そろそろと集まる群衆は弦楽器の弱音のトレモロによってあらわされる。ペトルーシュカが上体を起こし、雪の上の自分の血と傷の深さを見て絶望する様子はクラリネットからファゴット、そしてヴァイオリンのソロに引き継がれる。最期にピッコロのソロが吹かれ、ペトルーシュカはついに息絶える。
ファゴットの5度の跳躍がはじまり、警官がシャルラタンを引き連れ群衆をかき分けペトルーシュカの元へ行く様をあらわす。シャルラタンは尋問する警官に対して、ペトルーシュカをただの人形だと言い、魔法をかけ人形の姿に戻し、人々に亡骸を軽々と振って見せる。騒ぎは収まり、安堵した人々は家路につき始める。この部分はホルンの三連符によって奏され、曲も一瞬日がさしたように明るくなる。シャルラタンはマントの下に人形を隠すようにして引きずりながら見世物小屋の方へ向かう。それも束の間、弱音器をつけたトランペットによりペトルーシュカの主題の変形が鳴り響き、見世物小屋の屋根の上にペトルーシュカの亡霊が出現する。シャルラタンは恐怖のあまり怯え、亡骸を放り出してその場を立ち去る。一人残ったペトルーシュカの亡霊は大きく上半身をのばした後、急に下に向けて上半身をぶらんぶらんと揺らしている。ホルンの三連符に続いて弦楽器のピッツィカートで消えるように、謎を残したまま幕となる。
最後に新響のプロフィールに必ず記載されている「ストラヴィンスキー三部作一挙上演」についてふれたい。三部作一挙上演にあたってはまず1973年に「火の鳥」を取り上げ、翌年に「ペトルーシュカ」、そして1975年に「春の祭典」を加えて、念願だった一挙上演を3年がかりで演奏した(指揮:芥川也寸志)。その後1989年4月1日、第123回演奏会にて「ペトルーシュカ」を再演している(指揮:本名徹二)。この時は音楽監督の故芥川也寸志を失った直後の演奏会で、チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」と共に演奏された。なお過去の演奏会ではすべて1911年版を使用している。今回が新響にとっては初めての1947年版での演奏となる。
注1:「白鳥の湖」「眠れる森の美女」「くるみ割り人形」
注2:大斎期間は卵、乳製品、肉、魚、酒などを摂取できない(酒は日曜日と一部の土曜日のみ許される)。教会では結婚式は行われず、旅行や宴席などの享楽も出来る限り避けることが望ましいとされている。
参考文献
・『ニューグローヴ世界音楽大事典』
・作曲家別名曲解説ライブラリー『ストラヴィンスキー』(音楽之友社)
・グラウト/パリスカ共著『新西洋音楽史(下)』(音楽之友社)
・蔵持不三也著『シャルラタン 歴史と諧謔の仕掛人たち』(新評論)
・Hamm, Charles, “The Genesis of Petrushka”
・Sternfeld, F.W., “Some Russian Folk Songs in Stravinsky’s Petrouchka”
初演:1911年6月13日 パリ・シャトレ座
楽器編成:ピッコロ(3番フルート持ち替え)、フルート3、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット3、バスクラリネット(3番クラリネット持ち替え)、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トライアングル、シンバル、大太鼓、小太鼓、タンバリン、タムタム、シロフォン、チェレスタ、ハープ、ピアノ、弦5部
エネスコ:ルーマニア狂詩曲第1番・第2番
■エネスコの生涯
ジョルジュ・エネスコの名は、作曲家としてよりもヴァイオリンの名手としてよく知られているだろう。ヴァイオリンの教授として、メニューインなど多くの名手達を輩出したことでも有名である。
1881年8月7日(19日の説もあり)、ルーマニア北東部のドロホイ県(現ボトシャニ県)リヴェニ・ヴルナヴにて、父コスタケ、母マリアの第8子として誕生。12人生まれたうちジョルジュ・エネスコだけが、19世紀にルーマニアの村々を襲った疫病から生き延びたといわれている。
エネスコ一族は曾祖母、祖父、父母と、みな音楽的才能を持っており、中でも父は素晴らしいテノールの持ち主でヴァイオリンも弾いた。また、母は類まれなほどの澄んだ声を持ち、ギターの弾き語りをすることもしばしばだった。そんな音楽家の血筋の中、エネスコは3~4歳で異常なまでの才能を発揮し、7歳になった1888年には、ウィーン音楽院へ入学し、「ルーマニアの小さなモーツァルト」と呼ばれるようになっていた。メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲をわずか11歳で堂々と演奏し、「小さなヴァイオリニストとコンサートマスターとしての契約を結びたい」とシュヴェリン劇場専属オーケストラから提案があったことからも、ヴァイオリニストとしての成功を証明している。
その後1895年、精力的な父に付き添われたエネスコは、ウィーン・フィルのコンサートマスターであり作曲家でもあったヘルメスベルガーから、当時パリ音楽院の作曲科主任教授だったマスネに宛てられた推薦状を携え、パリ音楽院への入学を果たした。
エネスコはウィーンにいる頃から作曲を始めていた。最初は小品(全てヴァイオリンとピアノのためのもの)が中心だったが、やがて更に大きな作品の製作に取り組んでいき、1897年に完成した『ルーマニア詩曲』はコロンヌ指揮でパリにて初演され大成功を収めた。
パリ音楽院では、生涯の友となる学友、モーリス・ラヴェル、ロジェ・デュカス、フロラン・シュミット、などと知り合い、作曲家としての創作意欲も刺激されていた。もちろん世界で活躍する間も祖国とは絶えず繋がりを持っており、『ルーマニア詩曲』を作曲した後も1900年から1920年にかけてルーマニア楽派の作品を多く手掛け、ルーマニア人作曲家としての知名度を世界に知らしめた。
■二つの狂詩曲(ラプソディー)
ルーマニア狂詩曲は、エネスコ作品の中で最も広く知られている曲であろう。
これらは第1番(1901年)、第2番(1902年)と続けて作曲され、1903年2月23日、ルーマニア・ブカレストのアテネ音楽堂にてエネスコ自身の指揮で2曲同時に初演されている。
この時、最初に第2番、続けて第1番という順番で演奏したことから、この形式が演奏する時の定番となった。
まず演奏される第2番は、エネスコの故郷モルドヴァのバラードが主題に置かれ、農村的かつ内面的な傾向が伺える。弦のユニゾンによる開始はエネスコのお気に入りで、同様の手法が傑作・弦楽八重奏曲(1900年)、第一管弦楽組曲(1903年)でも使用されている。この弦のフリギア旋法の後、バラードが3回繰り返され、その後に活躍するのが、「田園の羊飼い達」の楽器である。バグパイプを思わせるオーボエとファゴット、パンの笛を模するフルート。その対話は幻想交響曲の第3楽章を想像させる。最後にすべてのオーケストラが静寂に包まれる中、クラリネットと弦の室内楽を伴奏にしたヴィオラのソロが、まるで馬車に乗った農民楽士が通過するかのように演奏する。その後オーケストラが馬車の捲き起こす風のように一瞬通りすぎ、第1番への予告となる。
そして始まる第1番。まるで即興のように聴こえる出だしの管楽器はハープのトレモロによって伴奏される。バラード風のルバートが多い旋律がクラリネットとオーボエによって演奏され、やがて多くの楽器が加わって厚みを増していく。続いて8分の6拍子の舞曲調となり、ジプシー風の旋律が奏でられる。その後東洋的楽想が続き、4分の2拍子になって徐々に活気を増していく。やがてこのあたりからルーマニア民族舞曲ホラの様式が組み込まれ、フルートから様々な木管楽器に受け継がれて華やかに進む。中にはアラビア風な曲調も挿入され、熱狂的な踊りとなっていく。クライマックスに達したところで音楽が突然やみ、尻切れトンボのようになると、ひなびた東洋風旋律が木管によってカノン風に歌われる。そして前の速いリズムに戻り結尾となる。
参考文献
『ジョルジェ・エネスク 写真でたどるその生涯と作品』/ヴィオレル・コズマ著/ペトレ・ストレイヤン監修(ショパン社)
『エネスコ回想録』ベルナール・ガヴォティ編著(白水社)
『最新名曲解説全集6 管弦楽曲Ⅲ』(音楽之友社)
『ミニチュアスコア』(日本楽譜出版社)
※曲目解説については、一部曽我大介先生にご助言いただきました。
初演:1903年2月23日
エネスコ指揮 アテネ音楽堂
楽器編成:ピッコロ(3番フルート持ち替え)、フルート3、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、コルネット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トライアングル、小太鼓、シンバル、ハープ2、弦5部
管弦楽の時代 / 2曲の狂詩曲
名曲『水のいのち』によって、合唱音楽の作曲家としての評価が定着している高田三郎 (1913~2000)だが、その作曲の原点が管弦楽曲であったことを知る人は少ない。音楽の志を抱き故郷・名古屋を後に上京した高田は、1935 (昭和10) 年、憧れの東京音楽学校(現・東京藝術大学) 作曲部に入学する。音楽学校での幾多の試行錯誤を経て、高田は「日本の旋律と関連のある作品を書いて行く」ことを作曲にあたる原則のひとつとして打ち立てた。「日本の旋律にしてもそのほんとうの精神を(そのムードではなく) 生かすことができるのは、われわれ以外になく、また、われわれの責任なのだから」
その後研究科 (現在の大学院) に進み、1941 (昭和16)年に卒業作品として『山形民謡によるファンタジーと二重フーゲ』を作曲する。奏楽堂において師フェルマー指揮する学生オーケストラによるリハーサルを聞き、「初めて自分自身に出会う事が出来た」と込み上げる涙を抑える事ができなかったという。この作品は後年『山形民謡によるバラード』と改題され、高田の管弦楽曲の代表作となった。
ところが、実は『山形民謡』と同じ年に作曲され、不遇な運命を辿った管弦楽曲があったのだ。それが『管弦楽のための組曲』である。
『管弦楽のための組曲』は4曲からなり、作曲当時は『幻想組曲』という題名が付けられていた(演奏時間約20分)。作曲から4年を経た1945年 (昭和20年)4月、この組曲はようやく初演の時を迎えようとしていた。ところが同13日、マンフレッド・グルリット指揮する中央交響楽団 (現・東京フィルハーモニー交響楽団) によるリハーサル終了直後、なんと練習場が空襲にあい、スコア・パート譜とも焼失してしまう。
本日演奏される2曲の『狂詩曲』は、この焼失した『管弦楽のための組曲』(1941)の第2~4曲から、作曲者が記憶をもとに再編したものである。それぞれ「木曾節」と「追分」をテーマとしており、2曲とも日本的な情緒と躍動感に溢れた、非常に親しみやすい内容を持っている(なお組曲第1曲のフーガは、前述『山形民謡によるファファンタジーと二重フーゲ』の後半部分に転用されている)。
2005年、高田氏ご遺族の依頼を受けNHKアーカイブスに問い合わせたところ、この2曲の狂詩曲を含む、全部で5曲の管弦楽曲の自筆スコア・パート譜が保管されている事が判明した(他の3曲は組曲『季節風』 (1942)、ヴァイオリンと管弦楽のための譚詩曲 (1944)、舞踏組曲『新しき土と人と』(原題『新しき泰』/1944))。
アーカイブスのご厚意を得て3年後、全5曲の浄書フルスコア、パート譜が完成した。これらの作品は初演後殆んど演奏されていないと思われ、2曲の狂詩曲も今回の上演が実に60有余年ぶりとなる。高田三郎の没後10年にあたり、今回の上演を作曲者はきっと雲上で喜んでくれている、と信じたい。
狂詩曲第1番 ~ 木曾節の主題による ~
(1945/演奏時間約6分)
日本放送協会委嘱作。作曲当時のタイトルは『長野』であった。1945 (昭和20)年10月18日、日比谷公会堂で行われた「第9回希望演奏会」で、作曲者指揮する松竹交響楽団により初演が行われた(その際、タイトルは『信濃路』と変更されている)。
序奏部分 (「木曾節」の主題が登場するまで) の日本的な抒情味の素晴らしさは、まさに絶品だ。こんな素晴らしい作品を、半世紀以上もの間埋もれさせておく日本の音楽界とは・・・ということまで改めて考えさせられてしまう佳曲である。
狂詩曲第2番 ~ 追分の主題による ~
(1946/演奏時間約10分)
1946 (昭和21)年作曲。翌年1月14日午前9時より、作曲者指揮する東京フィルハーモニー交響楽団により放送初演が行われた(NHK第一放送「日本の音楽」)。
オーケストレーションはたいそうシンプルかつ明解で、大胆な不協和音の強奏を取り入れた賑やかな盛り上がりが素晴らしい。中でもホルン・パートの主張の強さには注目させられる。実は高田氏は1941年 (昭和16年) の紀元2600年管弦楽団にホルン奏者として参加するなど、この楽器の名手でもあったのだ(ベートーヴェン『フィデリオ』序曲のソロを完璧に吹いた、というエピソードが伝えられている)。
最後に・・・高田三郎はその作曲人生を『管弦楽のための5つの民俗旋律』(2000)という大作で閉じたこ とを、ここに改めて記しておこう。
~執筆にあたり、高田三郎氏奥様の留奈子様より数多くの貴重な情報をいただきました。ここに厚く御礼申し上げます。~
岡崎隆(日本作曲家研究・コントラバス奏者)
※今回の演奏会では岡崎氏による浄譜を使用しました。
初演:第1番 1945年10月18日 日比谷公会堂
高田三郎指揮 松竹交響楽団
第2番 1947年1月14日 放送初演
高田三郎指揮 東京フィルハーモニー交響楽団
楽器編成:ピッコロ(2番フルート持ち替え)、フルート2、オーボエ2、Esクラリネット(1番クラリネット持ち替え)、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、トライアングル、タムタム、弦5部
超私的アマチュア考
ちょっと、まごついてしまった。オンガクなどという難しいことをやっているとは
思っていないので、「はあ」と答えたが、申しわけないような気がした。
私はギターを弾くだけで音楽家だとは思っていなかったからだ。
■ある雨の日に ~父とモーツァルト~
「今ラジオですっごくいい曲やってるんだ!ケッヘル600なんとか!ケッヘル!ほら早くつけて!」
ある雨の日のこと、父は家に着くなり慌てた様子でこう言った。言われた通りチャンネルを合わせると、それは何てことない、モーツァルトのクラリネット協奏曲だった。「こんなの誰でも知ってる曲よ」「ってゆーか私、この曲オケでやったんだけど。聴きに来たじゃん。覚えてないの?」妻と娘に畳み掛けられた父は、先ほどの興奮はどこへやら、一瞬にしてしゅんとしてしまった。
私の父のクラシック音楽の知識と言えば、Mahlerと書いてある楽譜を見て、「ん?マフラーか?ふーん、何だか相変わらず難しそうなことやってるな。俺にはさっぱりわからない!ハハハハハ!さて、『笑点』でも見るか。」という程であり、家で私が練習していても「今日もピーピーやるのか。頑張るなぁ!」と言うくらいであるし、たまに新響の演奏会に来てくれても、演奏を聴きに来ているというより、家では「フッ」とか「ハッ」という皮肉な笑いしかしない娘が、受付の仕事で「にこっ」と笑っているのを見て、「おい、まさか!あの娘が笑っている!ああ安心した!」と喜んでいるらしい。しかし、知識が無ければ音楽がわからないというほど可笑しな話は無いわけで、考えてみれば、仕事で疲れた耳にラジオの電波に乗って天上から降りてくるモーツァルトなんて、この上ない音楽体験であり、それを知覚できる父は、十何年も音楽をやっている私なんかよりも、ずっと音楽的な耳を持っているのかもしれない。そして少しでもこの曲を知ってしまい、どうしても演奏の上手下手を考えてしまう私は、もう父のような純粋な耳でモーツァルトのクラリネット協奏曲を聴くことはできないだろう。
■ニースにて ~私とフルート~
少し前まで、アマチュアということについてよく考えていた。子供の頃入っていたオーケストラの音楽監督には、「アマチュア用のベートーヴェンなんてないのよ!できるまで練習しなさい!」と言われた。「なるほど、そうか」と思った。個人的に習っていたフルートの先生には、「プロにもアマチュアの要素は必要だけどね」と言われた。「ふーん、そんなものか」と思った。ますますよくわからなくなって、プロだのアマだの考えるのは止めにした。
数年前、南仏ニースでの夏期音楽講習に参加したときのことだ。この講習は参加にあたって審査は無いが、参加者の殆どは音楽を専門的に勉強している学生だった。パリ管弦楽団ヴァンサン・リュカ氏のレッスンの際、学校名を聞かれたのでアマチュアである旨を伝えると、
《Ah, tu joue de la flûte pour le plaisir !》
(直訳で、「喜びのためにフルートを吹いているんだね」といったところ)
と言った。辞書によるとpour le plaisirは、「趣味で」という程度の意味で使われる成句のようだが、恥ずかしながらこの言い回しを知らなかった私は、直訳で受け取った。そして「なーんだ、喜びか。そういうことだったのか。プロだのアマだの考えて損しちゃった」と気が楽になった。そしてその後は練習も程々に、「ヴァンスにマティスの礼拝堂があるよ!」「カップ・マルタンにル・コルビュジエの休暇小屋があるんだって!一緒に行こう!」と周りの練習熱心な学生を連れ出して遊び歩いたが、最後には誰もついて来てくれなくなった。ピアノのSちゃんには、少し困った顔でこう言われた。「ごめん、やっぱり一緒に行けない。私、何しにニースに来たか考えてみたの…。」そして我に返った。あれ、そう言えば私、何しに来たんだっけ?もう少しちゃんと音楽を勉強してみたいと思って、会社を辞めてニースに来たのではなかったのか?フルート自体には元々それ程の情熱もなく、音楽が傍にあればそれで十分ということがわかると、帰国した数日後には、何事もなかったかのようにあっさりと会社員に戻っていた。
■エネスコはアマチュア作曲家?
フルートを吹く人のおそらく大半が持っている楽譜に、マルセル・モイーズ編纂の”Flute Music by French Composers”がある。これは、フランスの作曲家によるフルートとピアノのための作品が10曲収録された曲集で、その内の1曲がジョルジュ・エネスコ(Georges Enesco:1881~1955)の『カンタービレとプレスト』。幼い頃の私にとって、フルートの練習は親から与えられた日課に過ぎず、特に好きでも嫌いでもなかったが、このエネスコの曲は喜んで吹いたと記憶している。これまでエネスコといえばその曲だったので、今回新響で演奏することになって、同じ作曲家による『ルーマニア狂詩曲』を初めて聴いたときは、私の知っているエネスコとあまりに曲調が違うことに驚いた。あろうことか、私はこの作曲家がルーマニアで生まれたことも、ヴァイオリンの名手であったことも知らなかった。
作曲家とヴァイオリニストの二足の草鞋を履いていたエネスコだが、自らはあくまでも作曲家と考えていた。そのため、作曲するための時間も労力も奪うヴァイオリンを恨んだ。それでもヴァイオリニストとしても活動したのは、お嬢様向けの簡単な曲を書かざるを得ない友人の姿を見て、「自分の音楽を商業的な、官僚的なものにひきわたすこと」はどうしても避けたかったからだという。つまりエネスコにとってヴァイオリンは、作曲家としての自立を約束するための手段であった。誤解を恐れずに言えば、エネスコはヴァイオリニストとしてはプロであったのに対し、作曲家としては生涯アマチュアであった仮定することもできるのかもしれない。そんなエネスコの夢は、「ヴァイオリニストという経歴に終止符を打って、ルーマニアに引きこもって死ぬまで作曲をする」ことであった。しかし、二度の大戦、相次ぐ貨幣価値の変動、そして政治体制の突発的な変革などによって、故郷での隠遁生活の夢とは永遠の別れを告げる。それでも作曲への思いは晩年に至るまで変わらない。死が間近に迫っても思うのはただひとつ、作曲のことだった。
それは、人生の幕がおろされるその瞬間まで私の内奥でうち震えるものを音楽にすること、
そして、歳月がもたらした野生の実の酒を最後の一滴まで絞り出すこと。
私は命ある限り、歌をうたいつづけていたい。
私はいつも夢をみ、わけもわからず耳を傾け、作曲することで、煩わしい現実から逃避してきました。
人生は夢。夢は人生のすべて。
■「音楽はみんなのもの」
さて、困ったことになった。仮定であれ一度でもエネスコをアマチュアと呼んでしまった今、果たして私は芥川先生が言うところの音楽のアマチュア(音楽を愛する人)と呼ばれる資格を持っていると言えるだろうか。音楽を愛しているつもりであっても、20歳で前に所属していたオーケストラを卒団した時には「これで週末を自由に使える!」と心底解放された気持ちがしてしまったし、今でも時には「この日練習がなければ、あれもこれもできたのに!」と新響を恨みそうになることだってあるのだ。
私が子供の頃所属していたのは、間もなく結成15年目を迎える千葉県少年少女オーケストラ。その第一回定期演奏会の指揮者が故石丸寛先生だった。私は2期生だったので石丸先生から直接指導を受けたことはないが、先生が演奏会の録音CDに寄せて下さった次の文章を、音楽監督の佐治薫子先生が練習の合間に繰り返し読んで聞かせてくれた。
神という人もいれば、仏という人もあります。
小鳥のなんと美しく可愛いこと。
兎も、羊も、ライオンの仔でさえ、そして樹々の立つ雄大な緑の森も、
水の豊かに流れる川も、果てしなく蒼い空も、それらはすべて自然そのものです。
もう一度、ぼくは自分に問いかけます。
「このすばらしい自然、宇宙は、いったい誰がつくったのだ」。
ベートーヴェンが田園や小川のほとりを歩きまわって、
この、目に見えない素晴らしい力を追い求めたように、ぼくも自然を探し求めます。
君達は小鳥です、兎です、野辺の花です、大きな森です。
どうぞ自然に生きてください。
上手くやろうなどと考えずに、いつも自分の心と向きあって、
汚れのない音を出してください。(後略)
当時はこれを聞いても何とも思わなかったが、きっと意識せずとも「自然に生き」ることができていたのだろう。その頃はアマチュアを自称する必要もなかった。卒団してから早6年、俗世の荒波に揉まれて身についた無駄な知識や欲といった垢は、そう簡単に落とせるものではなく、今の私の出す音は「汚れのない音」には程遠い。
さてそろそろ、アマチュアオーケストラ歴50余年、いわばアマチュアであることにおいてはプロとでも言うべき新響で、新参者の私があれこれ言うのは終わりにしよう。冒頭の深沢七郎の言い方を借りれば、私はただフルートを吹いているだけだ。プロの演奏家は永遠に私とは別世界の存在であり、私のフルートはいつまでたっても素人じみている。それでも、父も私もエネスコも、みんな音楽に救われた点は同じであり、「音楽はみんなのもの」を掲げる新響は、アマチュアについて満足に説明もできない私なんかのことも、今のところは団員として受け入れてくれているようだ。ありがたや。
■おまけ
(東十条駅周辺の、とある小料理屋にて、馬刺しをつまみながら)
松下さん(フルートパートの首席):
「吉田さんは、フランス文学ばかりやっていてはいけませんよ。(『仮装集団』(新潮文庫)*を取り出して)山崎豊子!こういうのも読まないと。この人のすごいところは、ペラペラ(大切なことを言われていたのだろうが、既にこの時点で水ではない透明な液体を少なからず摂取していたため、残念ながら覚えていない)……というわけなんです。あ、すみません、ポテトサラダ下さい」
吉田:
「(グビグビ)へー。山崎豊子、読んだことないです。今、深沢七郎読んでます」
松下さん:
「深沢七郎。うーむ。いいじゃないですか。深沢七郎と言えば、ペラペラ(同上)……ですから、深沢七郎で維持会ニュースの原稿を書けばいいんですよ。そうしたら居酒屋の聖地、大塚に連れて行って差し上げましょう。そこでは様々な部位の馬刺しが食べられるのです(こういうことは鮮明に覚えている)。 そうそう、クリームチーズの酒盗和え、これがまた美味しいんですよ。すみません、これをひとつ…」
首席の命が絶対であるフルートパートにおいて、その命に背くことは次の演奏会の出番が無くなることに等しく、それは仕方がないとしても、さらにはフルートの飲み会に誘って貰えなくなるかも知れず、それは何としてでも回避しなければという切羽詰まった思いが(あるいは馬刺しへの執念が)この原稿を書かせたのであって、私の勝手なアマチュアに対する雑感を押し付けようなどという意図は、全くございません。
*編集人注)
●『仮装集団』山崎豊子著(1967年刊)
「大阪勤音(大阪労音を下敷きとした架空組織)」の企画者を主人公に、1960年当時の日本に於ける、大衆への「西洋音楽」の浸透運動の左傾化・政治化と、それに対抗する実業界などの動きを描いた長編小説。新響が労音から独立した創立当時(1956年)の、音楽が政治の道具とされていた時代の空気を余す事無く伝える証言として読む事も出来る。
音楽界の閉鎖性ゆえに、取材の苦労も未曾有のものだったと著者は「あとがき」で述懐している。またそうした体質に由来する理由からか、最新作を除いた山崎豊子の長編小説の中で、唯一未だに映像化されていない(したがって知名度が極端に低い)作品となっている。
第212回ローテーション
| 高田三郎 | エネスコ | ストラヴィンスキー | |
| フルート1st | 藤井(+Picc) | 吉田 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 岡田(澪) | 岡田(充) |
| 3rd | - | 丸尾(+Picc) | 岡田(澪)(+Picc) |
| オーボエ1st | 亀井(淳) | 横田 | 堀内 |
| 2nd | 桜井 | 亀井(淳) | 山口 |
| C.A. | - | 岩城 | 岩城 |
| クラリネット1st | 進藤(es.Cl.) | 末村 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 大薮 | 進藤 |
| B.Cl. | 高梨 | - | 高梨 | ファゴット1st | 田川 | 長谷川 | 浦 |
| 2nd | 齊藤 | 齊藤 | 田川 |
| C.Fg | - | - | 長谷川 |
| ホルン1st | 鵜飼 | 園原 | 箭田 |
| 2nd | 箭田 | 山口 | 大原 |
| 3rd | 園原 | 大原 | 山口 |
| 4th | 市川 | 鵜飼 | 市川 |
| トランペット1st | 北村 | 倉田 | 野崎 |
| 2nd | 青木 | 青木 | 小出 |
| 3rd | - | - | 中川 |
| Cornet | - | 小出 | - |
| Cornet | - | 中川 | - |
| トロンボーン1st | 武田 | 志村 | 武田 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 | 志村 |
| 3rd | 大内 | 大内 | 岡田 | テューバ | 足立 | 足立 | 土田 |
| ティンパニ | 古関 | 桑形 | 皆月 |
| トライアングル | 皆月 | 皆月 | 田中 |
| タムタム | 今尾 | - | 田中 |
| 大太鼓 | 中川 | - | 中川 |
| 小太鼓 | - | 今尾 | 今尾 |
| シンバル | - | 古関 | 桑形 |
| タンブリン | - | - | 桜井 |
| 木琴 | - | - | 古関 |
| ピアノ | - | - | 藤井 |
| チェレスタ | - | - | (*) |
| ハープ1st | - | (*) | (*) |
| 2nd | - | (*) | - |
| 1stヴァイオリン | 堀内(小松) | 堀内(小松) | 前田(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(滑川) | 大隈(滑川) | 大隈(日高) |
| ヴィオラ | 常住(内田) | 常住(内田) | 常住(内田) |
| チェロ | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) | 柳部容(光野) |
| コントラバス | 加賀(中野) | 加賀(中野) | 中野(加賀) |
新響「邦人作品」小史 ~日本人作曲家の作品を巡る流れ~
新響と邦人作品との関わりは長い歴史をもち、今シーズンも権代敦彦氏の作品を取上げる。ここに至るまでの様々な曲折について、以下に簡単に紹介して、現在の状況と今後を位置づけてみたい。
■創始と定義
1976年の創立30周年を記念して行なわれた「日本の交響作品展」で、芥川也寸志と新交響楽団はわが国の管弦楽黎明期(れいめいき)と言える作品の数々を取上げた。選定に臨んで新響が演奏すべき「邦人作品」として以下の3つの条件に適うものに限定している。
①旋律が明確である。
②調性がある。
③戦前・戦中の作品である。
これらの条件は戦後の音楽界に於ける作品傾向の混乱を考えれば、必要不可欠なものだった。いわゆる「現代音楽」の語に未だイメージされる、聴衆の感性とは隔絶した玉石混淆の「芸術作品」が横行していた状況下で、「邦人作品」の定義をまず明確に打出した事に芥川氏の炯眼(けいがん)を見る。誰でも思いつきそうな事ではあるが、実際には誰かが行なうまで気づかない典型というべきで事実、それまで誰もその仕事の重要さに気づかなかった。その結果、以下の作品群が2夜をかけて演奏されている。
*第1日
平尾貴四男/古代讃歌(1935)
箕作秋吉/小交響曲ニ長調(1937)
大木正夫/組曲「五つのお伽噺」(1933)
尾高尚忠/日本組曲(1937)
早坂文雄/古代の舞曲(1939)
*第2日
清瀬保二/日本祭礼舞曲(1940)
安部幸明/小組曲(1935)
高田三郎/山形民謡によるバラード(1941)
諸井三郎/小交響曲変ロ調(1943)
伊福部昭/交響譚詩(1943)
この功績に対し、翌年サントリー音楽賞(鳥井音楽賞)を受賞した事が、新響が社会的な認知を得、活動を拡大して行くための大きなステップとなった事は、改めて言及するまでもないだろう。だが「埋もれた作品」を音にする為に、様々な作品へのアプローチの過程で団員個々に対してもたらされた「財産」も、それに劣らぬものだった事に改めて注視すべきだ。例えば殆ど演奏された記録の無い作品には、スコア(総譜)はあってもパート譜が無い。そこで団員が分担してパート譜をスコアから筆写して作成するという作業が必要だった。現在ではスコアさえ入力すれば簡単に各パート用の譜面が作成出来るソフトウェアが容易に入手できるが、つい35年前当時は全て手作業に拠った。今更ながら隔世の感がある。
そうした中で最も特筆すべきは、当時健在(第2日目のプログラムでは、諸井三郎氏以外は全て存命)だった作曲者の殆どが、練習に立会って時に自作を指揮し、時に作品を加筆さえして、楽員との様々な共感の中で演奏を創り上げるという、望外の成果を得た事である。これこそ「作品への真摯な取組み=音楽への愛情=アマチュアの本質」という、芥川氏が提唱し、新響のバックボーンとして今もあり続ける精神の具現化へのひとつであった。
以後、「日本の交響作品展」は「邦人作品」の定義に則り選曲され、1986年の第10回(芥川也寸志作品展)まで毎年続いてゆく。私は1982年の入団なのでこの時代については「生き証人」としての資格と役割を自負もしているが(笑)、「邦人作品」に対し、団員間には実に様々な意見があった。決して全員が満腔(まんこう)の賛意を以って演奏をしていた訳ではない。「社会的な意義」を感じ、嬉々として演奏する者もいれば、「つまらない」と内心背を向けつつも、義務感に任せて練習に加わっている者もいた。加えて年4回の定期演奏会のうち、「邦人作品」の回のチケットの売れ行きが必ず思わしくないのを苦慮する声もあった(そうした人々の口から「邦人税」なる言葉を耳にした事がある)。
「それで良いのだ」と個人的には考える。120人もの人間が、それぞれ一家言を展開し得るほどの音楽的な欲求の満足を求めて、ひとつのオーケストラに集まっているのである。皆が同じ方向を向いて演奏に集中する姿は、理念としては正しく美しくもあるが、本来あるべき表現の「多様性」とは相容れない。我々は一糸乱れぬマスゲームへの参加を強要されているのではないのだ。出処進退の自由が個人に許されている集団の中で、個々様々な慾求とそれに対して眼前に与えられている作品(これは勿論「邦人作品」に限らない)との間に自分なりの妥協点を見出し、折合いをつけてゆく過程で起こる精神の動き・・・こそが、深い表現の源泉になるはずであり、事実そのような基盤によって「日本の交響作品展」は行なわれていった。結局これを根本で支えていたのは団員個々の「音楽への愛情」であったと断言できる。
だが、回を重ねるに従って「日本の交響作品展」もさすがに次第に当初の勢いを失ってきていた。それは「定義」の範疇内の、譜面を入手できる限りの一定レヴェル以上の作品を取上げ尽くしたとの感が蔓延していた事もあった。「マンネリ」の語は使いたくないが、どのような優れた企画であっても、10年という期間を開始当初の情熱とエネルギーを維持して毎回充実させる事は難しい。退き際が求められていたとも言える。そしてその掉尾(ちょうび)を飾る企画として、芥川氏の作品展を新響側から提示する事になった。「自分の作品を演奏会にかけたいがために、この作品展を始めた訳ではない」と固辞を重ねる音楽監督を新響が説得して、実現に至ったこの第10回目を以って、新響の「邦人作品」の演奏は、ひとつのピリオドを打った事になる。
現在でも新響と邦人作品を結びつけてイメージする人は多いが、現実的にはこの10年間の演奏会企画と活動が印象づけられているという事である。但し、それは1976年から1986年に至る期間の、日本のあらゆる「音楽状況」を踏まえて生み出された企画であったし、ここで言う「邦人作品」もまた、そうした時代背景を前提とした、極めて限定されたものだった事にもっと注意が払われて良い。そしてより重要なこととして、この間に日本のオーケストラ(プロもアマチュアも含め)のレヴェル向上と、「邦人作品」が演奏される機会の増加(これは確かに新響の功績である)など新響を取巻く環境も激変した事にも留意されるべきであろう。
■石井眞木氏の時代=同時代性=
1991年以降、新響は石井眞木氏の指揮により「現代の交響作品展'91」「現代の交響作品展'92」を行ない、日本人作曲家による作品(敢えて「邦人作品」と区別する)へのアプローチに新時代を迎える事になった。これはひと言で表せば「同時代の作曲家」の作品を対象にした事を特徴とする。
ここで新響は1976年当時の初心を思い出すべきであった。演奏の対象に如何に取り組むかに日々腐心する団員にとって、作品の創造者と時空を共有し、その謦咳に触れる事は常に無限の刺戟と意慾をもたらす。作品は確実に演奏者の血肉となり、そうした経過を辿った演奏こそが聴衆に真の感動を与える。石井氏は芥川也寸志と新響が、「邦人作品」の演奏を通じて体現していた(が、深く意識はしていなかったために、時間を追うごとに稀薄となっていった)「同時代性」というこの企画の本質を見抜き、それを新たな形で展開を試みたのだった。
実際この2度の作品展とその後のベルリン公演を通じ、松村禎三・一柳慧・藤田正典という戦後日本を代表する作曲家各氏との交流(特に一柳氏とは自作自演でピアノ協奏曲を共演)を通じ、作品の演奏に不可欠となる一層緊密なアプローチを体現したのだった。
更にこれを深耕させる手段として特筆すべきは、石井氏が提唱した作品公募というアイディアである。
―作曲家は常に自作が演奏される機会を求めている。新交響楽団の名に於いて公募し、『入選作はじっくり取り組んで演奏します』と言えば、応募作はたくさん集まる筈だ―
という自らの修行時代の体験に裏打ちされた理念に基づき、1991年の秋口に公表されると、年末までに果たして20曲ほどの作品が集まった。書法も分量も楽器編成(もちろん管弦楽曲である事が条件だったが)も様々だったが、高校生から70歳を過ぎまでと応募者の年齢もまちまちで、作曲をしている人の層の厚さに改めて驚いた。5曲ほどに絞り込んだ上で、新響の関係者数人が加わり、石井氏が各曲を論じていった。作曲家が作品のどのような尺度をもち、どこに着目して評価するのか?その「現場」に立ち会った訳で、これは今も非常に鮮烈な記憶として残っている。そして最終的に第一席として推したのが夏田昌和氏の『モルフォジェネシス~オーボエとオーケストラのための~』だった。この時夏田氏はまだ藝大大学院の学生。締切りぎりぎりに応募したため、学内の掲示板に貼られた公募書類をそのまま譲り受け、画鋲のあとも生々しい応募用紙を作品に添付して送ったと、その後述懐していたのを思い出す。
『モルフォジェネシス』は1992年の出光音楽賞を受賞し、夏田氏が作曲家としての地歩を固める契機のひとつとなった。この優れた作品はいずれ何らかのきっかけを得て世の中に出、結局は同じような評価を得たかも知れない。が、新響の公募が作品を世に送り出す先鞭をつけた意義は極めて大きかったと今も考える。
夏田氏は先達の例に漏れず、作曲者として自らの作品が音になって行く過程に立ち会い、それどころか本番に於いても自作の指揮を務める結果となった。こうした多くの事例を振返れば、新響が演奏すべき日本人作曲家の作品としての質と同時に、その「同時代性」を石井氏が如何に重視したか?が解ろうというものである。つけ加えれば、その演奏に際しては第一級の演奏家との共演も経験していた・・・恐らく継続すれば、新響の活動の柱として充実・発展は更に望めた筈である。
残念ながら当時の新響が石井眞木氏の真意やもたらされたもの(その作品を含めて)の真価を充分に理解していたとは必ずしも言えない。この貴重な関係はひとまず1993年10月の第141回定期<ベルリン芸術週間参加記念演奏会>で区切りをつけた。芥川氏歿後直ちに氏が孤立無援となった新響に手をさしのべた1989年からの足かけ5年間、新響が演奏した日本人の手になる作品は、それ以前と一線を画す、このようなものだった。
■曲折を経て=「伝統」の評価と継承=
1994年は芥川・石井両氏にとっての師である伊福部昭氏の生誕80年(傘寿)に当たった年である。新響の活動の軸として毎回の定期にこの作曲家の作品を1曲プログラムに入れていた。そしてこれを契機に日本人の作品選定が新響自身の手に委ねられると、2年後に迫った創立40周年記念行事を含めた5ヵ年の企画内容の案出と相俟って、かつての定義に寸分違わぬ「邦人作品」が復活する様子を見せる事になった。且つそれは、
①「5年で10曲」という演奏頻度のアップ
②「戦前・戦中の作品の絶対視」
との企画案となって表れた。
①についてはプログラムの構成に支障を来たす事と、団員の演奏意欲に関わるおそれがあった(芥川氏の時代でさえ「邦人税」の感覚があった事を思い出してほしい)。更には創立40周年の記念演奏会で演奏される邦人作品は、これと別枠であるという。これは流石に実現されなかった。
②はおのずから「存命作曲家の作品」の演奏を非常に困難にさせる条件だった。こちらの方がむしろ重大な変化だったが、当時は気づく者も無い状態だった。
そして1996年の創立40周年記念演奏会では、「日本の交響作品展’96」と銘打って、1976年のそれとほぼ同時代の作品が2日連続で演奏されている。
*第1日
尾高尚忠/みだれ(1938)
早坂文雄/ピアノ協奏曲(1948)
橋本国彦/交響曲ニ調(1940)
*第2日
平尾貴四男/俚謡による変奏曲(1938)
松平頼則/パストラル(1935)
深井史郎/ジャワの唄声(1942)
諸井三郎/交響曲第3番(1944)
50年余に及ぶ新響の長い歴史の中でも、この2回の演奏会の位置づけは難しい。
肯定的に見ればこれは「芥川也寸志と新交響楽団」の「伝統」を守り、その方向を更に深化させた演奏会である。新響は今後も「戦中・戦後の」「埋もれた」作品の初演・再演に努め、音楽文化の一翼を担ってゆこうとする、その使命感の表れという事になろう。
批判的な見地に拠れば、20年という時間の経過とその間の社会・音楽状況の変化を無視し、過去の「成功体験」に固執して、新たなもの・・・例えば「戦後の」「評価を得ている」作品・・・への拒絶と捉える事につながってゆく。
例えば石井眞木氏(そして芥川氏も!)の重要視した「同時代性」からこの演奏会を検証すると、作曲家中で存命だったのは松平頼則氏のみである。しかも同氏が自作の演奏を拒まれる(という事実があった)に至り、「作曲者との共感」を手にする事自体が不可能となり、あるべきアプローチは望むべくもなくなっていた。
また、既に評価の定まった作品も、新響ではなかなか演奏の機会が得られなかった。『涅槃交響曲』はこの時期以前から何度も俎上に上がりながらその都度否定されてきたし(2006年に演奏)、武満徹の作品を新響が「初めて」コンサートのプログラムとして取上げたのは1997年(創立後41年目)である。西洋の名作を毎回プログラムに乗せながら、自国の「名曲」を演奏しないという実情。こうした偏りを説明する明快な論拠を、当時の新響は持っていなかった(「プロオケが取上げるような自国の作品を新響はやるべきではない」とかつて聞かされた事があった。悪い冗談だろうが・・・)。
いずれにせよ、20年前と同工異曲の企画は、時間の経過と環境の変化の中で、団外からの評価とは別に、演奏者(団員)にとっての意味と意義を明らかに変質させていた事だけは否定のしようがない。春秋の筆法によれば、新響の「邦人作品」にこだわったこの2回の演奏会こそが、今後取り組んでゆくべき「日本人の作品」とはどうあるべきか?を考える契機となってその機運を盛り上げ、「邦人作品」の定義そのものの見直しに導いたと言えようか?
この見直しがひとつの「結論」を得るには、芥川氏時代の定義を尊重する人々によって「オーケストラ・ニッポニカ」が設立される2002年まで、実に6年以上の期間、議論が繰返された。今後新響が演奏すべき「邦人作品」の尺度については合致点を見出せなかった訳である。
以後の新響は時代・作風にこだわる事無く、且つ作曲者との「共感」を可能な限り重視しつつ、日本人の手に成るあらゆる作品を演奏の対象としている。故に今シーズンの権代敦彦氏の『ジャペータ‐葬送の音楽Ⅰ‐』と、次のシーズンで取上げる高田三郎氏(2000年死去)の1945年から翌年に書かれたふたつの『狂詩曲』との間に、何ら隔てるべきものはない。
こうした流れを改めて追ってみると、「永続的な活動」を目指す組織にとっての「伝統」とか「歴史の継承」とは何か?といった事を、今更ながら深く考えさせられるし、それらに対する評価の尺度を、組織として共有する事の難しさも痛感せざるを得ない。一時代の状況を背景に創始され評価された事柄や方針を、次世代に「そのまま」引継がせる事の是非は、あらゆる組織の中で、絶えず俎上に上がり議論されている筈である。激変を繰返す環境下での組織は、特定の人が唱える「大義」や「スローガン」だけでは存続し得ない。成員たる生身の人間個々の意慾をかきたてるべき条件を調え、且つ変わる事のない本質的な理念を見失わずに、新たな人材を絶えず取込んでいく事が不可欠である。つまるところは「ヒト」であって、個々の成員がいつの間にかその理念を自分のものとして受け容れていける環境(文化)の確立によってのみ、永続性が保てるのである。
芥川氏の歿年(1989年)以降に生まれた団員を迎える段階に既に新響は入っている。「アマチュア=音楽への愛」という一点に於いて、この組織に人は集まり、価値観を共有しているのだ。とすれば、氏が提唱したこの新響の本質と言うべき理念に基づき、特定の条件を付加する事なく、わが国の音楽作品を「純粋に」演奏対象として捉え、どれほど真摯に対峙出来るか?は、今後この組織の消長を量る重要な尺度のひとつになってゆくように思えてくる。
「賢者は歴史から学び、愚者は体験から学ぶ」という。「邦人作品」の変遷を振返り、その「歴史」から我々が改めて学ぶべきは、個人の限られた体験から離れ、取巻く環境の変化の渦中にあっても常に本質を忘れず、あるべき本来の姿を考え続ける事の大切さである。
第212回演奏会のご案内
高田三郎没後10年
高田三郎(1913〜2000)は多くの声楽作品を残したことで知られる作曲家です。名古屋に生まれ、東京音楽学校(現在の東京藝術大学)作曲部に学びました。この頃から日本語あるいは日本の旋律に関係した作品を書くことを心に決め、平尾貴四男、安部幸明らと「地人会」を結成します。
「音楽の伝統を尊重し、古典、浪漫、近代を通じて混沌たる現代へ流れる音楽の歴史から貴い糧を得よう。そしてそれによって培われた我々の音楽性を以て我々の心の歌を歌おう。」(「地人会はどう進んできたか」より)その言葉のように、西洋と日本の伝統文化を尊重した器楽作品を書きましたが、その後は合唱曲中心の活動に移り、なかでも『水のいのち』は多くの人に歌われ合唱のスタンダード曲となっています。またクリスチャンで、典礼聖歌(カトリック教会で使用される聖歌集)の作曲を手掛け
ました。
今回の演奏会では、数少ない管弦楽作品の中から2つの「狂詩曲」を演奏します。第1番は木曽節、第2番は追分節をテーマにしたもので、日本的な抒情味のある親しみやすい曲です。高田自身の指揮で初演されて以来演奏される機会がなく、今回約60年ぶりの蘇演となります。
ルーマニア狂詩曲
狂詩曲=ラプソディーとは叙事的で民族的な内容を持つ自由な形式の楽曲をいい、既成のメロディーが用いられたりメドレーのような構成になることが多いです。有名なものでは、ドボルザークのスラブ狂詩曲やリストのハンガリー狂詩曲などがあり、自国の民族音楽を元に作曲されています。今回は東欧の自然豊かな国ルーマニアの「狂詩曲」を演奏します。
ルーマニアの代表的な作曲家であるエネスコは、7歳でウィーン音楽院、13歳でパリ音楽院に入学した早熟の天才で、世界的なヴァイオリニストとしても活躍しました。「ルーマニア狂詩曲」はエネスコの曲の中で最もよく知られており、第1番はジプシー風の旋律からなる華やかな曲、第2番はバラード風の情緒溢れる曲です。
今回の指揮者である曽我大介はルーマニアと縁が深く、ルーマニア国立音楽大学を卒業後ルーマニアの多くのオーケストラと共演し、現在も関係を深めています。
バレエ音楽「ペトルーシュカ」
さて最後に演奏するのは、ストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」です。「火の鳥」「春の祭典」とともに、ストラヴィンスキーの三大バレエ音楽の一つとされます。他の2曲に比べ少々知名度が低いかもしれませんが、「のだめカンタービレ」で「きょうの料理」のテーマが混じってしまった曲と言えば、イメージできる方も多いのではないでしょうか。
ロシア版ピノキオのようなお話で、見世物小屋の人形ペトルーシュカが魔法で命を吹き込まれ、バレリーナの人形にかなわぬ恋をする物語です。今回は1911年の初演時よりオーケストレーションが整理され華やかになった1947年版で演奏します。
どうぞご期待下さい。(H.O.)
ブラームス:交響曲第4番 〈古典的様式にみえる近代性〉
ヨハネス・ブラームス(1833年ハンブルク生まれ、 1897年ヴィーンにて64歳で没)は、まぎれもなく19 世紀後半ドイツ・ロマン派音楽芸術における巨人で あり、その音楽は西洋音楽史上特異な位置を占めている。ブラームスと同時代に生きた指揮者ハンス・ フォン・ビューローが言いだしたドイツ「3大B」 (バッハ、ベートーヴェン、ブラームス)とよばれる概念の固定化に代表されているように、ブラームスの出現は、ドイツ音楽の系譜に繋がるベートーヴェン以降の最大の後継者という固定観念と繋がり、交響曲のジャンルにおいても、古典音楽を綿密に研 究した成果で得た技法と同時代の近代的な要素を取 り入れつつ、絶対音楽的立場から重厚で構成的な音楽の創造において、管弦楽に対する技巧の成熟と発展を示している。
・交響曲の特性
ベートーヴェンによって前人未到の領域まで完成された交響曲というジャンルにおいて、ブラームスは、交響曲第1番を1876年に発表されるまで着想から20年近くも練っている。ブラームスの交響曲は、長年培ってきた膨大な音楽の知識と技法的な体験による深みから生み出された作曲者の確固たる音楽的な理論性をもとに、独自の淀みのない緻密な構成による芸術作品といえよう。構成は古典的な4楽章性を崩しておらず、楽器編成も原則として当時としては規模の大きなものでなく2管編成の域をでていない。特色としては、中間楽章にスケルツォとかメヌエットを表示した楽章はないし、両端楽章に比べて編成を小さくして対比させている。全体として重厚かつ素朴で古典的な響きがするものの、特有の色彩による抒情性と柔軟性があり、ベートーヴェンの後継者というレッテルと巨大な壁を乗り越えた挑戦の結果といえる。
作曲時期によって第1番と第2番、第3番と第4番と大きくわけることができ、また互いに対照的な内容となっている。ブラームスは1862年よりヴィーンに定住、大作の「ドイツ・レクイエム」を1868年に発表して大成功、1872年にはヴィーン楽友協会の芸術監督に就任、ヴィーン音楽界の重鎮として名声を確立し数多くの名作を創作していくが、多忙の中、夏に涼しく静かな避暑地にて集中的に作曲を行うようになり、それは晩年まで続いた。このことは曲のアイデアを性格的に整理し、全く違った作品を同時に練り上げていくというユニークな創作の姿勢につながっていった。交響曲第4番は、交響曲第3番を書きあげた翌年の1884年から1885年にかけて書かれ、他の3曲とは異なる「憂愁」ともいえる孤立した性格を持っており、当時としては古典的な様式の中で作曲者の孤独と底に秘めた情熱が意思となって、孤高ともいえる個性が見事に表現されている。
・交響曲第4番について
ブラームスにとって最後の交響曲となったこの作品は、広く親しまれている屈指の名曲であり、オーケストラの演奏者にとってレパートリーとして重要 な作品といえよう。前項でも触れているように、作曲された当時の音楽的風潮からみてバロック的志向が強く保守的ではあるが、古い形式を用いることで「憂愁」とか「諦観」を表現、さらに緻密で複雑な効果と色彩によるロマン的な香りを作曲技法や語法の中に持ちこんで、ゆるぎのない強靭で成熟した音楽の魅力に満ちている。歌舞伎でいえば「見得」が随所にみられ、あえて申せば、江戸時代後期に歌舞伎を興隆に導いた七代目市川団十郎が、当時は限ら
れた階級の者にしか知られていなかった高尚な能の「安宅」を、大衆的な歌舞伎という演劇様式に取り入れて「勧進帳」を創作したことで新たな伝統を創造し、今では広く親しまれて人気のある演目となっていく過程と同じような感覚ではないかと思える。
1885年10月8日、限られた親しい友人たちを前に2台のピアノ編曲版で試演を行った時、第1楽章の演奏後、複雑な技法と古めかしい語法に対して戸惑いの雰囲気があり、賛否両論だったという。1885年10月25日ブラームス自身の指揮によるマイニンゲン公の宮廷劇場による初演では評判が良く、翌年までドイツやオランダの各地、ロンドンで演奏されたが、1886年1月17日ヴィーンフィルで楽友協会大ホールにてハンス・リヒター指揮によるヴィーン初演は大成功とはいえず、再演されたのは1897年3月7日に初演時と同じハンス・リヒターにて行われるまで時間が必要となった。病気で弱った身体にもかかわらず、大ホールの監督席に座っていたブラームスは熱烈な拍手で迎えられ、たちあがって返礼した。深く感動したブラームスは自分の名声が健在であることを実感したに違いない。以来、ヴィーンでは一般的に受け入れられることになった。尚、この演奏会はブラームスが自作を演奏会で聴く最後の機会となり、同年4月3日に息を引き取ることになる。
第1楽章:アレグロ・ノン・トロッポ ホ短調
2/2拍子 ソナタ形式
アウフタクトで哀愁を帯びた音楽がヴァイオリンによってはじまる。三度進行を主とした旋律で、三度の下降(シーソ♪)、その後は六度上昇(ミード♪、ひっくりかえせば三度の関係)の連続で休符をおいて、哀切な表現を湛えている。少しずつ緊張感を高めながらも、突然、木管にこれまでとは違う性格の三連音を含むリズムの旋律がロ短調で現れ、チェロとホルンに伸びやかで情緒的な美しい旋律が姿をみせる。対比してバスに三度のスタッカートによる下降音形が古めかしく面白い。その後、和解的でなめらかな旋律や和やかな音楽が出てきて、展開部・再現部と続き、最後は挑戦的で猛烈な嵐の如く突き進んでいく。古典的な編成で、これだけ密度のある重厚な響きが生み出されるオーケストレーションはすばらしい。
第2楽章:アンダンテ・モデラート ホ長調
6/8拍子 展開部のないソナタ形式
はじめのホルンと木管による旋律は、中世的で古めかしくまるでセピア色。短調かと思えるが、これはホ音を基音とする教会旋法のフリギア旋法であり、旋律の終わりでクラリネットに基音の長三度:嬰ト音がでてホ長調のしっとりとした明るい響きが構築され、フリギア旋法を活用した第1主題が綿々と続いていく。その後、ヴァイオリンに第1主題を思わせる美しい旋律が流れ、伴奏形に三連音による反抗的な音形が登場、次第に発展してスタッカートの強烈な音形として全体を支配していく。すぐに慰めるかのように、第2主題でチェロに表情豊かな旋律がロ長調で登場、他の弦楽器とファゴットが対位法的に絡み美しい。再現部はより劇的に進み、終結部ではホルンに最初の旋律が還ってきて、静かに消えるように終わる。
第3楽章:アレグロ・ジョコーソ ハ長調
2/4拍子 ソナタ形式
スケルツォに相当する楽章。面白いのは通常のスケルツォやメヌエットといった3拍子ではないこと。この楽章にトライアングルが加わり、その活躍は効果的。コントラファゴットもこの楽章から登場する。冒頭の第1主題は全合奏にて明るく強烈に且つ豪快にはじまり、形を変えて新しい動機を加えて
発展、第2主題がヴァイオリンでのびのびとト長調で登場、その後発展して展開部に突入、再現部では第1主題がppにて管楽器により主調ではなく変ニ長調にて登場。速度をゆるめて、ポコ・メノ・プレストとなり、ホルンとファゴットで柔和な第1主題に由来する旋律が続き、速度が戻ってクライマック
スまで押し進んで力強く終結する。
第4楽章:アレグロ・エネルジーコ・エ・パッショナート
ホ短調 3/4拍子
白眉ともいえる終楽章。8小節の主題を元にした 壮大な変奏曲であり、具体的には30の変奏と結尾部にて厳格且つ入念なパッサカリア(シャコンヌ)の形式を構築している。しかも全体をソナタ形式とも思える大きな有機体としてまとめており、これだけでも一つの作品として孤高の存在といえよう。パッサカリアやシャコンヌといえばバロック時代の様式であり、通常は主題を低声部で繰り返していくが、ブラームスはこの曲では主題を高声部に置き、それに和声と下行音形のバスを加えている。この楽章でトロンボーンが登場し、硬質で厳格な古典的ともいえる様式に貢献している。第2変奏でオーボエとクラリネットでmpによるレガート旋律が第2主題として印象的。中間部の第12変奏では2分の3拍子となってフルートが印象的なソロを聴かせ、第13変奏でホ長調に転じ、第14変奏と第15変奏でファゴット、ホルン、トロンボーン、後に木管も加わる深いコラール風の響きがすばらしく、またこのサラバンド風の歩みが懐かしさを醸し出している。その後は主題が再現されて発展し、ピュウ・アレグロとなって最後は力強く且つ激しく終了する。
・変奏曲の大家:ブラームス
ブラームスが持っていた芸術全般に対する洞察力、膨大な知識は圧倒的である。中世までさかのぼる音楽への知識と深い理解力を持ち、バッハを中心とした古楽の研究に没頭、厳格対位法の書法から、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンと進み、音楽理論と作曲技法を自己固有のものとして知識を拡大していった。多様性に富む膨大な楽譜のコレクションには同時代の作曲家はもちろん、いわゆる大作曲家たちの貴重な自筆譜や初版譜があり、記念碑的な全集版を手に入れるためにいかなる犠牲もあえて辞さなかった。そして、興味の対象には必ずしもならなかったとは思われるが、それらを心から楽しみ、学究的な慎重さで比較・研究している。
このように15世紀以来シューマンに至る大家の作品に惹かれ、その伝統の上でドイツ中世からバロックの音楽研究に由来する巧妙で多声的な処理による壮大な効果や荘重さ、旋律を自由に走らせる技巧を持ち、古い音楽を綿密に研究した成果の上に当時の近代性を持って管弦楽に対する技巧は十分に成熟されたものとなった。ブラームスの創作にはこれらの要素が密接に関係しており、その成果の一つとして、多くの試みをへて、1873年音楽史上不滅の作品「ハイドンの主題による変奏曲」が誕生したのである。変奏曲とフーガは、ブラームスにとってまさにぴったりの形式であり自由自在であった。主題と9つの変奏、さらに終曲はそれだけで19の変奏をなしており、低音で登場するテーマを用いて一連の変奏曲をなすパッサカリアとしてクライマックスを構成している。そして交響曲第4番の終楽章にも、このようなクライマックスを強調する手法として古い形式であるシャコンヌやパッサカリアを借りて、新しい内容を盛り込んだことが顕著な特徴である。
交響曲第4番の終楽章は、バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番」の終曲「シャコンヌ」、ベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」第4楽章をモデルにしていると思われるが、その主題(譜例1)に関して、特にバッハのカンタータ1 5 0 番 「 主よ 、 われ汝を求む ( N a c h d i r , H e r r , verlanget mich)」BWV150のシャコンヌによる終曲の合唱主題(譜例2)、及びバッハのロ短調ミサ第17曲「クルチフィクス(Crucifixus)」ホ短調の通奏低音にある、深い悲しみを簡潔に表わしている半音階的に下行する4度音程の伝統的な「ラメント・バス」(譜例3)が、多いに影響していると思われる。
・リベラリスト:ブラームス
若い時のブラームスは、金髪で青い目のなかなかの美男子だったというが、壮年時代からでっぷりと太り、その風貌は(資料を見ると40代後半に突然生やしたと思われる)立派な髭が目立つ堂々たる顔立ちにて、むっつりと無口で気難しく偏屈で頑固な親父という印象がある。(本人はこの顔立ちがお気に入りのようで、自身の髭写真がコーカサス系白色人種の実例図版として当時の教科書に載っていることを知人に話している。)若い時は頑固で反抗的だったそうだが、作品がしかるべき形で評価されるにつれて、人当たりもよく円熟し丸くなっていったようだ。回想録を読むと、友人たちとの会話で自分にかかわることを全てストレートに語りつくしており、相手によっては無愛想で皮肉屋で且つ慇懃なところは、品性が下劣ということではなく、学問を探求するインテリで、浮世の中でその場を取り繕ってなんとなく辻褄を合わせることができない正直な人だったと思われる。友人たちも当時のエリートとしての知識人が多く、パーティにて友人たちと談笑し、冗談を言い合ったりして当意即妙な会話は、他人が入ることのできない領域だった。
彼の言動から見えてくるのは、古典主義の遺産相続者として保守派のブラームス、革新を旗印にするヴァーグナー、という単純な図式とは異なるものといえる。当時のヴィーン楽壇における絶対音楽の純粋な形式美を理想とするブラームス派と、流行であった標題音楽や楽劇の思想を標榜するヴァーグナー派との抗争に巻き込まれていたとはいえ、性格が合わないという個人的な感情はさておいても、作品そのものを厳格に評価していることは、作曲の様式や技法という観点だけでなく、音楽に対する考え方、作曲への根拠や社会とのかかわりといった面で、20世紀音楽への橋渡しとして意味のあることを感じている。ヴァーグナーにしても、ブラームスにしても、音楽を創作する時の姿勢は異なるにせよ、究極的には同じものを追及しているのであり、表現の仕方が違っていたのであろう。
興味深いのは、ヴァーグナーの「ニュルンベルグのマイスタージンガー」と、ブラームスの「ドイツ・レクイエム」は1868年に初演されており、どちらも二人の名声を不滅のものにした作品で、かつ「ドイツ」という共通した土壌にある。二人とも1860年代は「ドイツらしさ」という言葉の意味に多大な関心を寄せており、ヴァーグナーは民族主義の観点からハンス・ザックスの言葉を象徴として「神聖なるドイツ芸術」を称え、宗教改革以来のプロテスタントのコラールを使用し且つ精緻な対位法にて音楽を構築。ブラームスは宗教改革でマルティン・ルターが訳したドイツ語聖書をドイツ語で書かれた最も重要な書物として、独自でテキストを慎重に選んで宗教性を外し、バロック的な対位法を用いて、確個たる驚異的なコラールとフーガを創造し、音楽家として現代を活きるドイツを表現した。「ニュルンベルグのマイスタージンガー」には反ユダヤ主義的な意図が解釈として見え隠れしており、後世政治的にも利用されているが、ブラームスの音楽にはそのような要素がなく、合理的な精神が見えてくる。
ブラームスは、宗教と政治の合理主義と共にリベラルな立場として社会と政治に関わり、当時の最先端の科学や技術に対して興味を持ち高く評価していた。音楽的には妥協を許さずに発展させる能力は近代的であり発明家ともいえる。ブラームスはリベラルな芸術家という側面があるがゆえ、その作品は、魅力と共に未来への音楽芸術に対する指針として永久に存在していくことであろう。
参考文献
『ヨハネス・ブラームスの思い出』ブラームス回想録集第1巻 ディートリヒ、ヘンシェル、クララ・シューマンの弟子たち著/ 天崎浩二編・訳/関根裕子訳(音楽之友社)
『ブラームスは語る』ブラームス回想録集第2巻 ホイベルガー、フェリンガー著/天崎浩二編・訳/関根 裕子訳(音楽之友社)
『ブラームスと私』ブラームス回想録集第3巻 シューマン、ヴィトマン、ゴルトマルク、スタンフォード、 スマイス、イェンナー著/天崎浩二編・訳/関根裕子訳 (音楽之友社)
初 演:1885年10月25日 ヨハネス・ブラームス指揮 マイニンゲン宮廷管弦楽団、マイニンゲン公宮廷劇場
楽器編成:ピッコロ(2番フルート持ち替え)、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、トライアングル、弦5部
あとがきに添えて: 〈テューバとブラームス その低音の魅力〉
古典的な音楽様式を貫いたブラームスの管弦楽の作品では、ある時期に、1835年にベルリンで生まれた新しい楽器テューバの使用が集中している。このことは1875年当時のヴィーンフィルハーモニーにベルリンからテューバ奏者(若干16歳!)が招聘され、F管のコンサートチューバが採用されていることに関連している。具体的には1877年に交響曲第2番、1880年「大学祝典序曲」「悲劇的序曲」で意識的に使用され、出番は少ないが古典的な形式感や伝統に則った音楽の中で、その独特の音色が生み出す深い響きにより、表現力に富んだこの楽器の魅力を充分に活かしており、所謂オーケストラのチューバをたっぷりと堪能できるのだ。因みに同時期ヴィーンに 定住していたブルックナーは、1875年からとりかか っていた交響曲第5番にバス・テューバとしてパートを追加、また1880年に交響曲第4番の改定の際にも追加して、それ以降の作品にテューバを積極的に多用している。
現代の楽器とは異なり小さくコンパクトな響きをしていた当時のテューバは、金管楽器が加速度的に進化していった過渡期という状況の中、ブラームスにとって特異な存在であった。テューバといえば低音パートを補足的に補強するというイメージがあり、ブラームスも1868年「ドイツ・レクイエム」はそのような使用が見受けられるし、1873年「ハイドンの主題による変奏曲」の草稿には、コントラファゴットがいない場合はテューバで代用との記載があり、出版に際しては削除されている。同時代の作曲家、たとえばヴァーグナー、チャイコフスキーではテューバが大いに活躍、後に続くマーラー、リヒアルト・シュトラウスといった後期ロマン派の作曲家も多用して確固たる地位をテューバが確立していく中、ブラームスは意識的にテューバという楽器を、脇役としてではなく無駄のない近代性を持って実験し、自身の持つ音楽様式と信念に基づき、学究的に選択していったに違いない。
ブラームスは、管楽器の最低音として長年コントラファゴットを多用し、時にはホルン、ファゴット、トロンボーンと共に独特なコラールにて古典的な響きと色彩に絶大なる効果を発揮している。奥行の深い響きを構築している要素として、最低音域のオーケストレーションに注目していただきたい。演奏者にとって難易度が高く、与えられた役割が重要なだけに脇役としてではない、実にやりがいのある存在といえよう。そして最低音域だけでなくオーケストラの全てのパートが脇役とならずに効果的に構築され、ここぞという要所にて真価を発揮しているのは、ブラームスの管弦楽の技巧の素晴らしさにあると思う。
本年(2010年)、交響曲第4番を作曲した当時のブラームスと同い年になった筆者にとって、ブラームスの作品には、強い想いと憧れが存在している。たとえテューバというパートがなくても、新交響楽団で最低音域を担当するテューバ奏者として、皆と音楽を共感しその響きの中に浸っている自分が存在している。ここでしか味わえない音楽体験!なんて素晴らしいことだろうか!
R.シュトラウス:交響詩「死と変容」
リヒャルト・シュトラウス3作目の交響詩「死と変容」は、1889年、彼が35歳の時に作曲された。死の床にある芸術家が、病魔と闘いながら自らの人生を回想し、やがて天に召されてゆくというストーリーを管弦楽作品にしたものである。「死と変容(Tod und Verklärung)」という表題は、「死と浄化」とも訳される。曲の結尾の雰囲気からは「浄化」と言うべき神々しさが感じ取られる。(注:この解説では、「死と変容」と表記させていただく)
ストーリーのおおよその内容は下記の通りである。
みすぼらしい小さな部屋の中で、ある芸術家が死との戦いに疲れ果て眠っている。
柱時計が不気味に時を刻み、彼は不規則な息を繰り返す。
子供のときの夢が、彼の顔に哀調を帯びた微笑みを浮かべさせる。
突如、死は襲いかかり、容赦なく彼を揺り起こし、再び恐ろしい戦いが始まる。
しかしこの戦いの勝利は決せられず、静寂が来る。
彼は過ぎ去った日々に思いを馳せる。
無邪気な幼い頃の日々。力の鍛錬に終始する少年時代。自己の理想を実現するための闘争。
心から憧れた全てのものを彼は死の床にもまた求め続ける。
再び死は彼に襲いかかり、最後の宣告を下し、死の鉄槌により肉体を引き裂く。
芸術家の魂は肉体を離れ、死の恐怖は安らぎへと変わる。
彼の求めた世界の浄化(変容)が、天空からの美しい余韻と響きと共に、
永遠の世界の中で完成される。
楽曲の聴きどころが聴き手により違うことは承知の上で敢えて申し上げる。「死と変容」の白眉は、この曲の最後の数分間、主人公である芸術家が天に召される情景であろう。「死と変容」のすべての部分はこのために存在すると言っても過言ではない。このラストシーンを、本日会場においで下さった皆様と一緒に是非味わいたい。
「死と変容」は、不規則なリズム(八分音符2つ+三連音符3つの組み合わせ、(譜例1)が醸し出す不安な雰囲気で開始する。このリズムは、弱音器を付けた弦楽器や、弱く叩かれるティンパニにより提示される。病床にある芸術家の不規則な呼吸、今にも止まりそうな弱々しい脈拍を模し、死を予感させる。このリズム、手を変え品を変え各所に現れては、自らの運命に抗おうとする主人公を現実へと引きずり戻す。最初は弱く奏されるが、曲が進むにつれてだんだん明確に、強く大きな音で提示されてゆく。迫りくる死の象徴である。
対して、ハープの伴奏にのってオーボエが演奏する、少年時代の懐かしく優しい思い出を表す旋律が提示される。(譜例2)
回想に浸り心穏やかになりかけた瞬間、突如ティンパニの強打に導かれて、死との壮絶な格闘が始まる。
地の底を這いずりまわる様な恐ろしい旋律(譜例3)が弦楽器と木管楽器の低音に現れる。最初は長いフレーズで、次第にフレーズが短くなってゆき、たたみ掛けていく。(譜例3) 繰り返しさらされる死の恐怖に、主人公が立ち向かう。「闘いのテーマ」とも言うべき音型が現れる。(譜例4)
病魔と闘い自らの運命に抗うような勇壮な雰囲気を持つこのテーマをもとに、全楽器入り乱れての強奏が続く。
その強奏が頂点に達すると、「芸術家の理想」の主題が提示される。(譜例5)
この主題は、低音から始まりオクターブの上昇を伴うという劇的な性格を持つ。各所でこのテーマが現れる。特に、曲の最後の芸術家が天に召される情景では繰り返し奏され、天上の高みに昇る様子を音型によっても表現している。
強奏が止み、フルートによって少年時代のテーマが奏された後、芸術家の回想は青年時代にも及ぶ。希望に満ちた堂々たる旋律がホルンと木管楽器によって奏され、次第に全体を巻き込み熱狂的な盛り上がりを見せていく。そのような盛り上がりの最中でも「闘いのテーマ」「死を予感させるリズム」が現れる。(譜例6)
ノスタルジックな回想の世界から死が目前に迫っているという現実へ容赦なく引き戻される心の痛みを演出するため、「死を予感させるリズム」をトロンボーンが演奏する場合は、「特に際立った印象を与えるため、観客にベルを向けて演奏すること」との指示が楽譜に書いてある。
死を予感させるリズム」による度重なる中断を受けながらも、芸術家の青年期の回想は激しく情熱的に展開し、再び「芸術家の理想」の主題が輝かしく登場する。彼の人生における全盛期が絢爛たる管弦楽で表現される。
しかし、また現実へ引き戻される。みすぼらしい部屋のベッドの上に横たわり、息も絶え絶えの情景が再び現れる。そして、再びテインパニの強打による死との闘いが始まる。もはやその闘いに勝つほどの体力・気力は残っておらず、やがて急速に音楽はその勢いを失ってゆく。上行型の半音階を弦楽器と木管楽器がだんだん小さく演奏することで、その様子を描いている(譜例7)。
そしてついに、彼は現世を離れる。いったん静寂が支配し、弱く叩かれるタムタム(ドラ)が非現実的な世界観を雰囲気作り、生の終わりを告げる。
人は死後どのようになるのかというのは永遠に正解が出ない問いである。リヒャルト・シュトラウスは、この曲の中でこの問いに敢えて答えている。「自分の理想が実現し、すべて満たされる」とでも言いたげなラストシーンをこの曲に用意した。「芸術家の理想」の主題が繰り返し奏され(譜例8)、輝かしく盛大なフィナーレを迎えるというものである。
曲目解説としては、それだけで十分であろう。しかし、前半に書いた「皆様と一緒に是非味わいたいラストシーン」を存分に味わうためには、もう1つ味付けをしたいと思う。
よく耳を澄ませていると、「芸術家の理想」主題の合間に、弦楽器によって少年時代の懐かしい思い出の主題が演奏されているのが分かるだろう。(譜例9)
この部分の響きが、筆舌に尽くしがたいほど美しい。「芸術家の理想」と「少年時代の懐かしく優しい思い出」により構成されているこの箇所は、あたかも「ああ、良かったな。いい人生だった。」と昔を回想しているようである。そのような往生を遂げられるこの芸術家は、実はこの上なく幸せなのではないだろうか。そんなことを考えながら聴くと、まるで良く出来た映画のラストシーンを見ているような、そんな気分にさせてくれるのである。
この幸福感に満ち満ちた響きの瞬間を、是非会場一体となって味わいたい。皆一緒に、リヒャルト・シュトラウスによる音の絵巻にしてやられてみませんか。
主要参考文献:
『交響詩<死と変容>(総譜)』リヒャルト・シュトラウス (オイレンブルク=全音楽譜出版社)
初演:1890年6月21日 リヒャルト・シュトラウス指揮 アイゼナハ市立劇場。
楽器編成:フルート3、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、タムタム、ハープ2、弦5部
※譜例準備中
権代敦彦:オーケストラのための ≪ジャペータ-葬送の音楽Ⅰ≫
ジャペータは、荼毘(だび)の原語であり、
身を焼き尽くすほどの梵火の意。
ガンジス河畔の町ベナレス。
この聖地で、ヒンズー教徒は人生の最期を迎え、
河辺の火葬場で荼毘に付され、
遺灰をガンジスに流されるのを、最大の喜びという。
魂は炎とともに天に昇り、灰となった肉体は、
この河を下り、やがて海に注ぎ、宇宙の一部となる。
ガンジスの川岸に座し、
このジャペータの炎に、
生と死、地と天、昨日と今日、
そして今日と明日、あらゆるものの繋がりを見る。
“ジャペータ”~葬送の音楽~は、
この炎に託した、死者の送りとその魂の浄化を願う音楽。
打ち続けられる1音(C#)から拡散、そして1音(C#)への収縮、
そんな行きつ戻りつを繰り返し、
あたかも、河が海に、地が天に、今日が明日に繋がるように、
生も死に、そして死がまた生に・・・・・
そんな繋がりの象徴、始まりも終わりもない音楽“ジャペータ”。
燃え尽きた後に、何も残らないように、
この曲の終わりにも、何も残らない。
ただ長い残響が消え去る頃、
その響きは、人の心に宿り、その中で生きはじめる。
「葬送の音楽」は、その時「(再)生への序曲」になる。
そんな願いも込められている。
初演:2007年11月30日 仙台市青年文化センター 山下一史指揮 仙台フィルハーモニー管弦楽団
楽器編成:ピッコロ(1番フルート持ち替え)、フルート2、アルトフルート(3番フルート持ち替え)オーボエ3、クラリネット3、コントラバスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット(3番ファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、ティンパニ、シンバル、マリンバ、チューブラベル、グロッケンシュピール、ゴング、木鐘、弦5部
<権代敦彦 プロフィール>
1965年、東京に生まれる。
桐朋学園大学で作曲を学んだのち、1990年から92年までDAAD奨学生としてフライブルク音楽大学に留学。1993年から94年まで、文化庁芸術家在外研修員としてパリに滞在し、95年までフランス国立音響音楽研究所(IRCAM)で、コンピュータ音楽を研究する。作曲を末吉保雄、クラウス・フーバー、サルヴァトーレ・シャリーノに、コンピュータ音楽をフィリップ・マヌリに、オルガンをジグモント・サットマリーに師事。
ローマのブッキ国際作曲コンクール第1位(1991)、ワルシャワのセロツキ記念国際作曲家コンペティション第2位(1992)、芥川作曲賞(1996)をはじめ、アムステルダムのガウデアムス国際音楽週間(1992)やISCM世界音楽の日々(2001)での入選、芸術選奨文部科学大臣新人賞(2002)など、国内外で数多くの賞を受賞。
カトリックの信仰に基づく儀式としての音楽空間を探究。近年は仏僧、聲明家とのコラボレーションを通じて、仏教音楽との交流から新たな領域を開拓している。また、ノイズ・ミュージックのMERZBOWをはじめ、ヴィデオ・アーティストの兼古昭彦、ダンサー・振付家の金森穣など、他分野における第一人者とのコラボレーションも多い。
コンサート・プロデューサーとしても意欲的な活動を行っている。1995年から5年間、渋谷ジァンジァンで、シリーズ「東京20世紀末音楽集団→2001」、1997年から99年まで神奈川県立音楽堂で、「権代敦彦シリーズ・21世紀への音楽」を企画制作。1995年および99年には、東京カテドラルで自らの個展をプロデュース。2004年には、サントリー音楽財団のコンサートシリーズ「トランス・ミュージック〜対話する作曲家」の特集作曲家として企画も手がけた。
オーケストラや合唱作品を集めたCD『薔薇色の肖像』(Fontec)が1999年に、ピアノ作品をまとめたCD『きらめく光のとき−祈り』(ALM RECORDS)が2004年にリリースされている。
2000年にはニュージーランドのウエリントン・ヴィクトリア大学、オークランド大学で講義を行う。また2003年、アーティスト・イン・レジデンスとしてノルウェーのベルゲンに滞在。ベルゲン大学グリークアカデミーで講義を行う。
2004-2005年、オーケストラ・アンサンブル金沢のコンポーザー・イン・レジデンス。カトリック教会オルガニスト。
現在、パリと東京を拠点に作曲活動を展開している。
第211回ローテーション
| 権代敦彦 | R.シュトラウス | ブラームス | |
| フルート1st | 兼子(+Picc) | 岡田(澪) | 松下 |
| 2nd | 吉田 | 藤井 | 丸尾(+Picc) |
| 3rd | 岡田(充)(+Alt) | 新井 | - |
| オーボエ1st | 堀内 | 堀内 | 亀井淳 |
| 2nd | 山口 | 山口 | 横田 |
| 3rd | 桜井 | - | - |
| C.A. | - | 桜井 | - |
| クラリネット1st | 末村 | 高梨 | 品田 |
| 2nd | 大藪 | 大藪 | 進藤 |
| 3rd | 品田 | - | - |
| B.Cl. | - | 石綿 | - |
| C.B.Cl. | 進藤 | - | - | ファゴット1st | 長谷川 | 浦 | 田川 |
| 2nd | 永井 | 永井 | 斎藤 |
| 3rd | 斎藤(+C.Fg.) | - | - |
| C.Fg | - | 長谷川 | 浦 |
| ホルン1st | 大原 | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 箭田 | 鵜飼 | 市川 |
| 3rd | 園原 | 園原 | 鵜飼 |
| 4th | 山口 | 市川 | 大原 |
| トランペット1st | 倉田 | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 北村 | 中川 | 青木 |
| 3rd | 中川 | 北村 | - |
| トロンボーン1st | 志村 | 武田 | 牧 |
| 2nd | 牧 | 小倉 | 志村 |
| 3rd | 大内 | 大内 | 岡田 | テューバ | - | 土田 | - |
| ティンパニ | - | 古関 | 今尾 |
| トライアングル | - | - | 皆月 |
| タムタム | - | 中川 | - |
| Perc. I | 浦辺 | - | - |
| Perc.II | 古関 | - | - |
| Perc.III | 皆月 | - | - |
| Perc.IV | 中川 | - | - |
| ハープ1st | - | (*) | - |
| 2nd | - | (*) | - |
| 1stヴァイオリン | 前田(大隈) | 前田(大隈) | 掘内(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(福永) | 小松(福永) | 小松(田川) |
| ヴィオラ | 常住(沼田) | 常住(沼田) | 常住(沼田) |
| チェロ | 光野(日高) | 光野(日高) | 柳部容(光野) |
| コントラバス | 中野(加賀) | 中野(加賀) | 加賀(中野) |
I:グロッケン、チューブラベル
II:グロッケン、木鐘、シンバル、マリンバ
III:グロッケン、チューブラベル
IV:ゴング、ティンパニ
(*)はエキストラ
第211回演奏会のご案内
ブラームスはお好き?
人それぞれかもしれませんが、オーケストラの演奏者にブラームス嫌いはいないのではないでしょうか。彼の作品は、我々にとって演奏することに喜びを感じる大切な宝物です。
ブラームスはドイツロマン派の作曲家で4つの交響曲を残していますが、第1番は19年かかって作曲され、続く3曲も非常に完成度の高いものとなっています。今回演奏するのは最後の交響曲である第4番。ブラームス53歳の時の作品です。すでに音楽界の重鎮となっていましたが、孤独で質素な生活を送り、シューマンの未亡人クララに想いを寄せながらも独身を通していました。そんな人生への切なさが感じられる傑作です。
ワーグナーやマーラーといった一歩先を行く作曲家と同時代でありながら、ブラームスは古典主義的な形式を尊重しました。特にこの第4番では古典的なソナタ形式をとり、フリギア調(古い時代の教会旋法の一つ)やシャコンヌ(バロック時代の3拍子舞曲の形式。短い主題に次々に変奏が展開される)を用いるなど、古めかしくも独創的です。内に秘めた感情が聴く者の心を揺さぶる、もっともブラームスらしい曲といえるでしょう。
この交響曲第4番は1885年、マイニンゲン宮廷管弦楽団でブラームス指揮により初演されましたが、このときトライアングルを担当したのがこの楽団の副指揮者をしていた21歳のリヒャルト・シュトラウスでした。
若き日のリヒャルト・シュトラウス
R.シュトラウスは20〜30代の時に「交響詩」と呼ばれる標題のついた作品を数多く作曲しました。今回演奏する『死と変容』もその一つです。
85歳で亡くなる直前まで指揮や作曲を続けていた長寿のシュトラウスでしたが、若い頃は病弱で、たびたび大病を患いました。死に直面したことのある自身の心境を曲にしたといわれています。床に伏した病人が、死の恐怖と戦いながら、幸福だった子供時代や理想に燃えた青年時代といった過去を回想し、闘病の末に天国へ行くという内容です。
R.シュトラウスの交響詩の中でも人気のあるる荘厳で美しい曲です。
権代敦彦〜現代の宗教音楽家
新響はこれまでに多くの日本人作曲家の作品を演奏してきましたが、今回は1965年生まれの権代敦彦の作品を取上げます。カトリック信仰に基づく宗教的な作品を数多く発表していますが、近年は仏教音楽との交流から新たな境地を開拓しています。今回演奏する『ジャペータ-葬送の音楽I』もそうした一つで、仙台フィルハーモニー管弦楽団の委嘱作品として、2007年に山下一史指揮により初演されました。「現代音楽の演奏は同時代人としての指揮者の使命である」と言う山下が期待する若手作曲家です。
ジャペータjhapetaとは、「火葬する」という意味の古いインドの言葉で、「荼毘」の元になっています。
どうぞご期待下さい。(H.O.)
マーラー:交響曲第7番
今年2010年はグスタフ・マーラーの生誕150年そして来年2011年が没後100年と2年連続のマーラー・イヤーを迎えメディアやコンサートにマーラーが取り上げられる機会が多い。しかしマーラー・イヤーでなくても現代のオーケストラレパートリーとしてマーラー作品が重要な位置を占めていることは言うまでも無い。マーラー・ブームと言われてからも久しいが、近年ではマーラー作品はプロのオーケストラだけでなくアマチュアにおいても日常的に取り上げられる定番となっている。しかしながら第7交響曲についてはマーラー・ブーム以後においても一般には分り難い曲とされ敬遠される傾向にあった。だが最近では演奏される機会も増え、この曲の持つ魅力が広く受け入れられてきている。
■マーラーの交響曲
「交響曲は一つの世界のようなものでなければならない。すべてを包摂するものでなければならない。」
これはマーラーがヘルシンキでシベリウスに会った時に様式と形式、モチーフの内的関連の重要性を主張したシベリウスへのマーラーの返答である。また次のナタリーエ・バウアー=レヒナーによる伝文の内容も良く知られるものである。
「私たちがその後、日曜日にマーラーといつもの道を歩いていてクロイツベルクの祭りに通りかかり、さらに腹立たしい乱痴気騒ぎに出くわしたときのことだった。そこではメリーゴーランドやブランコ、射的店、指人形劇、はては軍楽や男声合唱もが数え切れないほど軒を連ねて活動し、それがすべて同じ森の草地で他を顧慮することなく信じがたい音楽を奏でていた。そこでマーラーは次のように叫んだ。-『ねえ聞こえるかい?あれがポリフォニーというもので、僕はこういうところから学んだんだ。だって、こうしたざわめきも何千羽の鳥の声も、嵐がヒューヒューいうのも波がピチャピチャするのも火がパチパチ音を立てるのも、みな同じように多くの音があるということじゃないか。主題はまさにこのようにまったく違った方向から現れ、リズムも旋律も全く違っていなければならない。(そうでないものはみな単に声部が多いものというだけにすぎず、偽装されたホモフォニーだ。)ただ作曲家はそれらの音をともに調和して響き合う全体へと秩序づけ、一体化させるだけなんだ。』」
マーラーの交響曲の特徴は既成の様式や形式に収まるものではなく、様々な要素がポリフォニックに共存する多様性と発展性にあるといえる。マーラーにとってはシリアスな音楽も軍楽や俗謡も同じ次元・価値をもって世界を構成しており、そこに示される多面的で壮大なる世界がマーラーの音楽の魅力であることは間違いない。
■中期の器楽交響曲
1901年から1905年に作曲された5番、6番、7番の交響曲は声楽を伴わない純粋な器楽だけの交響曲としてグルーピングされる。この数年間はアルマ・シントラーとの出会いと結婚、そして子供の誕生、また指揮者としてもウィーン宮廷歌劇場の監督として最高の地位にありマーラーの生涯でも充実した幸福な時期にあたる。長女の死という悲しい出来事が訪れるのは1907年とまだ先のことである。これら中期の交響曲は標題を持たない絶対音楽であり、バッハ研究の成果としてきわめてポリフォニックな作曲様式が取り入れられた円熟したものとなっている。この後に声楽と器楽が完全に一体化する壮大な第8交響曲へと新たな世界を切り開いて行くことになるが、第7交響曲はマーラーの円熟期に書かれた器楽交響曲の集大成といえる。
■夜の歌
第7交響曲は一般的に「夜の歌」(Lied der Nacht)という副題を付けられることが多いが、マーラー自身はこの交響曲に副題は付けていない。「夜の歌」はマーラーが第2、第4楽章を夜曲(NACHTMUSIK)としていることに由来している。従って第2、第4楽章が「夜の歌」であるのは間違いないが、それをあたかも作品全体の標題として拡大解釈するのは間違いであろう。マーラー自身はこの作品の内的テーマについて何も語っていないということを重視すべきである。この曲についてマーラー自身の考えを知る手がかりとなるのはアルマ・マーラーの回想録にある次の一文である。
「1905年の夏、マーラーは一気に<<第7交響曲>>を書き上げた。彼の言うところの"青写真"は1904年の真夏にできたものだが。セレナーデの章を書いている時はアイヒェンドルフ的な幻想につきまとわれていたようだ---ささやく泉に、ドイツ・ロマンティシズムに。それはそれとして、この交響曲に一貫した表題はない。」
ここにあるように第2、第4楽章にあたる夜曲が第6交響曲とともに1904年の夏に作られており、特に第2楽章は第6との関連も見られる。他の楽章については着想に苦労したようだが翌年1905年の夏に一気に書き上げられている。つまりマーラーは第7交響曲を作曲する上で全体構想を最初から持っていたわけではない。「この交響曲に一貫した表題はない。」こそが真実なのである。
■第7交響曲の解釈をめぐって
スケルツォ楽章を中心とする5楽章構成で暗から明へという流れ、ロンド形式のフィナーレという点で第5交響曲との類似性がみられる。有名なアダージェットを含む第5番は楽章間の動機の関連性や一貫した流れが感じられ親しみやすいが、第7番については一貫性がなく雑多な印象を受けるため分かり難いと言われている。それでも第1楽章から第4楽章については夜のイメージとして捉えることも出来るため、一般的には「夜の歌」という副題を手がかりに解釈しようという傾向が多く見られる。その場合に突然世界の変わるハ長調のロンド・フィナーレをどう捉えるかが問題となり様々な解釈がされている。単純には夜に対する昼の音楽とするもの、あるいは夜のカーニバルであるとするもの、はたまた第4楽章の最後クラリネットに書かれたersterbend(死に絶えるように)という指示が死を暗示するものとし第5楽章は天上の祭典であるというものもある。またベートーヴェンの第5交響曲の終楽章に代表される栄光、勝利、歓喜を表すハ長調を用いての華やかな音楽が偽りの栄光、あるいは実現不可能な栄光を表現しているというシニカルな見方もある。「苦難を乗り越え栄光にいたる」という定型的な図式へのパロディ、音楽のための音楽、メタミュージックという指摘もある。しかしながら、学者、研究者、あるいは一音楽ファンの意見であろうとも全てを解明する定説とはなり得ない。先に述べたように第7交響曲についてマーラー自身が何の説明も行っていないという事実と、標題のない絶対音楽であるという点において全ては書かれた譜面の中にこそあり、何を感じ取るかは演奏者および聴き手一人一人に委ねられているからである。
アルマは晩年にラジオ番組の対談にて7番に限定した話ではないがマーラーの後期作品について次のように述べている。
「でも内容を理解する必要など本当はなくて、感じ取るだけで良いのです。それが分かればマーラーの作品はずっと身近なものになってきます。」
■調性について
一般に交響曲第7番ホ短調と表記されることが多いが、これは単に第1楽章の第1主題がホ短調であるということに過ぎない。スコアには調性も副題も記されておらず単に「交響曲第7番」と書かれている。といって無調音楽であるという意味ではなく5番と同様に発展的調性を取っているため作品全体を代表する調性は意味を持たないからである。
■テノールホルンについて
第1楽章で用いられているテノールホルンという楽器について正しく認識している人は金管奏者であっても少ない。誤解を生む要因として軍楽隊や金管バンドで使用される楽器は国や地域によって異なり、同じような楽器が異なる名称で呼ばれていたり、同じような名称が全く異なる楽器に付けられていたりすることによる。金管バンドの活動が盛んなイギリスでは他の多くの国ではアルトホルンと呼ばれるE♭管の楽器をテナーホーンと呼んでいる。マーラーが指定したテノールホルンとはドイツやチェコなどで使われている楽器で、音域的にはユーフォニアムやイギリス式バリトン、ドイツ式バリトンなどと同じB♭管の楽器である。これらの楽器の違いは主にヴァルブ構造と管の太さで、ユーフォニアムやイギリス式バリトンはピストンヴァルブを用い、ドイツ式のテノールホルンやバリトンはロータリーヴァルブを用いている。管の太さではイギリス式バリトンが最も細く、ユーフォニアムとテノールホルンは中程度、ドイツ式バリトンは最も太い。ホルンで有名なドイツの金管メーカーであるアレキサンダー社でもテノールホルンとバリトンを製造しており、カタログによればテノールホルンのボア(内径)が13.5mmでありバリトンは15.5mmとなっている。このテノールホルンのパートはオーケストラの実演ではトロンボーン奏者が担当することが多く、ユーフォニアムやバリトンで代用されることもあるが、マーラーは具体的な楽器を指定していることに留意すべきであろう。但し一般的なホルンやトランペットといった楽器も国や地域により使う楽器や音色が異なることを考えれば実際に使用する楽器そのものにあまり拘る必要はないのかもしれない。
■楽章構成について
これまで述べてきたように第7交響曲は全体を一貫した世界観で捉えるのでなく、個々の楽章をマーラー世界のオムニバス的なものとして捉えた方が違和感なく聴くことが出来る。同じナハト・ムジークである第2楽章と第4楽章でさえ、全く異質な音楽となっている。とはいえ第1楽章とフィナーレは主題の関連性、対比という点でも密接な関連があり、ソナタ形式である第1楽章とロンド形式のフィナーレは形式的にも構築性の高いものであり、これらの間に自由度の大きなロマン的な中間楽章が配置されている。また最初の3つの楽章は暗い楽想であり、和やかなセレナーデを経て明るいフィナーレに至るという点では交響曲としての構成も維持しているのである。
第1楽章 ゆっくりと~アレグロ(約20分)
序奏付きのソナタ形式である。ロ短調による暗く不気味なリズムの上にテノールホルンが序奏の主題を演奏する。テノールホルンはこの楽章しか用いられてないが、楽章全体に出現するその音は独特の効果をもたらしている。葬送行進曲ともとれるこの序奏部は第6交響曲の悲劇的な結末からの継続も暗示させる。長い序奏部を経てアッチェレランドしたのち、ホルンとチェロによりホ短調の第1主題が力強く提示される。第1主題はロ長調に転調し、再びホ短調に戻った後第2主題へと繋がる。第2主題はハ長調でヴァイオリンによる叙情的なもので印象的な部分であるが比較的短く、長大な展開部へと繋がる。展開部は各主題が様々に展開され調性と表情はめまぐるしく変化する。展開部の後半でトランペットによる弱音のファンファーレの後に展開される世界は実に印象的であり、マーラーらしい自然描写を感じさせる。特にハープのグリッサンドと共に現れる第2主題に長調に転じた第1主題が交錯する箇所は美しく神秘的であり、人智を超えた大自然の深遠さを想像させる感動的な音楽となっている。そのままクライマックスを形成した後で再び序奏が提示され再現部へと到る。コーダはホ長調に転じ華やかに終わる。
第2楽章 夜曲1(約16分)
一般にはハ長調とされることが多いが、長調と短調の交錯する不思議な世界が展開する。形式的には拡大された三部形式とも2つのトリオをもつ行進曲ともされているが、序奏+A+B+A+C+A+B+A+コーダの構成をとる。いわゆるセレナーデ的な音楽ではなくアルマの伝えるアイヒェンドルフ(注)的な幻想であり、マーラーの描く不思議な世界として自由な想像を呼び起こすものとなっている。曲は2本のホルンの掛け合いによる序奏に始まる。第6交響曲で多用された長調から短調に転じるモットー(動機)を経てゆったりとした行進曲風なAの主部に到る。主部も長調と短調を行き来して定まらない。Bの部分は変イ長調でチェロにより示される。Cの部分はヘ短調でオーボエが物悲しい旋律を歌う。なお序奏部は途中各部の接続的にも用いられ、カウベルが効果的に用いられている。またコーダも序奏をカデンツァ風に扱ったもので終止もあいまいなまま含みを持たせて終わる。
第3楽章 スケルツォ(約10分)
「影のように」と書かれており、幽霊の飛び交う奇怪でグロテスクな音楽であり、死者の踊るワルツ、死の舞踏を想起させる。主部はニ短調で中間部はニ長調で明るい兆しが見えるものの、すぐにもとの雰囲気に戻る。バルトークピチカートや多用されるグリッサンド、打楽器の効果的な使い方などマーラーの演出効果が際立つ、きわめて性格的な楽章となっている。
第4楽章 夜曲2(約12分)
愛情に満ちたアンダンテと指定されており、この楽章は窓辺で愛を奏でる本来のセレナーデであり、三部形式による。大音量を排した室内楽的な響きが用いられており穏やかで愛らしい楽章であり、この楽章にのみギターとマンドリンが加わることでセレナーデの雰囲気をよりいっそう演出している。主部はヘ長調で思わせぶりなヴァイオリンソロの短い序奏の後で素朴な主題がホルンにより提示される。中間部は変ロ長調となり朗らかな旋律をチェロとホルンが奏でる。この楽章で用いられているモチーフはそれぞれには単純なものであるが、それらが複雑に絡まることで味わい深い音楽となっている。
第5楽章 ロンド(終曲)(約17分)
ティンパニの強奏に導かれ金管による輝かしいハ長調の主題から開始される。このロンドの主部はエピソードを挟みながら、また形を変えながらも8回出現する。これまで標題は無くとも描写的であり陰影に富んだ音楽が展開されていたところに影の無い眩いばかりの世界に終始するフィナーレへの戸惑いが様々な解釈を生んでいる。しかしひねくれた解釈をするよりもバッハを手本とし対位法を極めてきたマーラーが自らの想像力と作曲技法を注ぎ込んだ純音楽であると捉えればこの楽章の真価が見えてくるのではないだろうか。アレグロ・オルディナレオという速度指定からもバロックを意識したものであることが伺え、弦楽器のソロの扱いなどを見てもバロック時代の合奏協奏曲を大編成のオーケストラに拡大しているようでもある。大音量に埋もれがちな細部にも耳をかたむければ実に複雑で精緻な音楽が展開されているのである。ロンドの主題はワーグナーのマイスタージンガーの引用も指摘されているが、第1楽章の主題の変形でもある。この楽章の終盤では第1楽章の主題がそのまま提示され、その主題が最後にはハ長調にて高らかに示され輝かしく曲を閉じる。このハ長調で示される主題は第1楽章との連続性を示しているだけでなく、次の第8交響曲の冒頭に歌われる「来れ、創造主なる聖霊よ」をも予感させるものとなっている。
注:アイヒェンドルフ(1788-1857)
ドイツの後期ロマン派の小説家、詩人
参考文献
『マーラー 未来の同時代者』クルト・ブラウコプフ(白水社)
『マーラー―音楽的観相学』アドルノ(法政大学出版局)
『マーラー』村井翔(音楽之友社)
『グスタフ・マーラー全作品解説事典』長木誠司(立風書房)
『グスタフ・マーラー 愛と苦悩の回想』
アルマ・マーラー 石井宏訳(中公文庫)
初 演:1908年9月19日(プラハにて作曲者自身の指揮による)
楽器編成:ピッコロ、フルート4(4番はピッコロ持ち替え)、オーボエ3、コールアングレ、クラリネット3、小クラ リネット、バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット、テノールホルン、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、タンブリン、シンバル、トライアングル、タムタム、グロッケンシュピール、ヘルデングロッケン(カウベル)、ティーフェス・グロッケンゲロイテ(低音の鐘)、マンドリン、ギター、ハープ2、 弦5部
ドビュッシー:「管弦楽のための映像」より〈イベリア〉
「プログラムなどはむろん何一つ要りません。会場の入り口でぬかりなく手渡される、紙きれ一枚の文学にしたがわなければならない音楽なんて、とことん下らないですからね。」
お気持ちはわかります。それでも、私たちの想像力をかきたてて止まない、「イベリア」の第2楽章「夜の香り」に思いを巡らせることは許して下さいますか?くれぐれも「説明なんかして音楽から神秘を追い出すことがないように」努めますので…。
■花の?女の?思い出の?
ゆふされば 今 花々は 梢こずえに搖ゆれて
香爐のやうに 花の香かが 風に薫くんじて、
音と 馨かをりと たそがれの空に 渦うづ巻まく。
憂鬱なワルツよ、ものうい眩暈くるめきよ。
「夜の香り」。一体どのような香りだろうか。曲の中に手がかりを求めても、音楽はその正体を明かされるのを拒むかのように次々と姿を変えてしまう。それならば曲の周辺を探すより他に方法はない。ドビュッシーが「イベリア」を作曲したのは1905年から1908年、新響でも最近演奏した『海』などの主要な管弦楽曲を書いた後の円熟期にあたるが、それらの作品の源泉となったのは青年時代に作られた85曲にのぼる歌曲に他ならない。ポール・デュカが「ドビュッシーが受けたいちばん強い影響は、文学者たちからのそれだ。音楽家からのではない」と言ったのも尤もで、文学や絵画などの前衛運動から取り残され、過去の繰り返しやワーグナーの模倣に止まっ ていた当時の音楽界に苛立った作曲家は、バンヴィル、ボードレール、ヴェルレーヌ、マラルメといった詩人達から霊感を得ていたようだ。中でも好きな詩人であったボードレールの作品からは、どことなく「夜の香り」を連想させる上記の詩を含む5篇を選び、歌曲集『ボードレールの5つの詩』を作曲している。
夜中に何よりも心魅せられるのは、わたしたち二人だけが知っているあの場所、森をよぎってわたしたちを招き寄せる、神秘に満ちた薔薇の茂み。夜中に咲き匂う薔薇の香りにもまして神々しいものが、この地上には何ひとつないのだから。わたしひとりだった頃には、この香りに酔い痴れるのを感じなかったのは、一体なぜなのかしら?
知的な面でドビュッシーに近かったのがボードレールだとすれば、生活の上で近くにいた作家は知る人ぞ知る「エロスの司祭」ピエール・ルイス。歌曲集『ビリティスの3つの歌』は、ルイスの散文詩集『ビリティスの歌』から3篇を選び作曲された。上に挙げた詩はそこに含まれないのでドビュッシーの目に触れたとは言い切れないが、どこか「夜の香り」を髣髴とさせないだろうか。詩集の後半には「咲き出す花々は、すべてわたしから生まれ出る花。息吹く風はわが吐息。過ぎゆく薫香かおりはわが欲望。」(「夜への讚歌」)と、女を花そのものとして官能的に歌った詩もある。ドビュッシー自身も女を花に例えて詩を書いているが、「彼女の若々しい花のような芳しさで私を包んでくれることを」(歌曲集『眠れぬ夜々』のために書かれたが「時代遅れ」という理由で生涯公表されなかった)のように、ルイスと比べると純粋だ。官能の世界とはあくまで距離を置いていた作曲家の作品の特徴に、官能性を挙げない訳にはいかないとは不思議な話だ。ルイスはこう言った。「完璧な純潔さっていうのは、とっても淫らなんだよ」。
「アンティーブの街角、そこにはたくさんのバラが咲き乱れていましたが、私の生涯を通じて、一度にあれだけたくさんのバラを見たことはけっしてありません―あの街道の香りはたしかに陶然とさせるものでした」
作曲家自身の発言にも触れておこう。ドビュッシーは「イベリア」を作曲していた頃、少年時代の最も鮮明な思い出を上のように回顧している。子供の頃について多くを語りたがらない作曲家が、花の香りについてはこんなにも鮮明な記憶を持っていたことには驚きを禁じえない。余談となるが当時のパリは、公共空間に溜まった汚物や糞便そして郊外の工場が発する悪臭で、匂いに関してはとても「花の都」ではなかったようだ。薔薇の花もドビュッシーの記憶の中でこそ強く匂いを放っていたのだろう。「イベリア」もまた現実のイベリアの描写ではない。1907年に民謡集を聴いてスペインの民族音楽に魅了されたという話はあるが、それ以前にもミュッセの処女詩集『スペインとイタリアの物語』に惹かれてスペインを題材にした曲を作っている。ミュッセの詩はスペインを訪れることなく書かれた。どこへ行っても「帰りたい病」に冒されるドビュッシーも、「イベリア」のためにわざわざスペインまで赴いたとは考え難い。「旅行を自分のために奮発してやる手段のない時には、想像力によってそれを補わなくてはならないのです」という作曲家の言葉の示すように、あくまで想像上のイベリアだと言えるだろう。
■イマージュとしての
「物質の根底には謎の植物が生育しており、物質の夜には黒い花が咲きみだれている。その花々はすでにビロードの感触と芳香の秘法をそなえているのだ。」
ここまでいくつか「夜の香り」を連想させる文章を挙げてきたが、それによって曲の象徴するものを特定したかったわけではない。音楽が直接の模倣ではなく、「自然のうちにある『目に見えない』ものの、感情を通じての転写」であると言ったのは作曲家自身である。その際ドビュッシーは「音楽は、自然と想像力との神秘的な照応をはたらかせてゆく」と考えていたが、これを既に詩において実行していたのがボードレールだ。吉田健一によるとボードレールは、「言葉を或る影像の生成に参加させ然も初に影像があって其処から発するその本来の性質に言 葉を還元することによって彼の詩を建設した」(「ボオドレエルの古典性」)。これは正にドビュッシーが「イベリア」を含む『映像』シリーズにおいて音楽で試みたことではないだろうか。私はここで哲学者ガストン・バシュラールの言う「物質的想像力」を想起する。つまり、「美からあらゆる接尾辞を引き剥がし、目の前に姿を現しているイマージュ(映像)の背後に、姿を隠しているイマージュを見いだす」想像力、言い換えれば、「現実のイマージュを形成 する能力ではなく、現実を超え、現実を歌うイマージュを形成する能力」だ。「夜の香り」が物質的想像力による夜の香りのイマージュであるならば、先に行ったような詮索は、それこそ「とことん下らない」。
■ただ音楽だけが
「ひとり音楽家だけが、夜と昼、天と地のすべての詩をそっくりとらえてその雰囲気を再構成し、その巨大な鼓動を脈打たせるという、特権をもっている。」
始めにドビュッシーの音楽の源泉として歌曲を採り上げたが、その泉が湧いたのはやはり器楽曲においてであると言えるだろう。「イベリア」に取り組んでいた頃には歌曲を作ることも少なくなっていた。音楽学者ステファン・ヤロチニスキによると、そもそも歌曲を作る上で大詩人達を選んだのも「それらの詩がすべて言い尽くそうとはせず、語のむかう先を音楽で彼の欲するように続けさせてくれたから」だという。歌を伴う曲を作るにしても「音楽は、 ことばが言いあらわす力を失うところから、はじまる」という考えを持っていたドビュッシーは、マラルメの詩に基づく最初の管弦楽曲『牧神の午後への前奏曲』を転換点に、以後は詩の昇華された形をひたすら音楽のなかに見出すようになったのである。
ここで改めて「夜の香り」という題について考えたい。「香り」には形がない。そして「夜」に於いてはその香りがどこから来たのかすら分からない。その神秘が詩以上に作曲家の想像力を掻き立てたのかもしれない。「夜の香り」という語の持つ神秘的な響きと同様に、ドビュッシーの「夜の香り」も決して一様には聞こえないだろう( 原語のLes parfums de la nuitは複数形である)。それはこの曲が「音楽」―他のどんな言語とも異なり、本来の性 質として多義性を持つ「音楽言語」で書かれた音楽―であるからに他ならない。そして音楽は何よりもまず「耳とよばれる器官のためにある」のだから、余計なおしゃべりはこの辺で終わりにしようか。
第1楽章 通りから道から
第2楽章 夜の香り
第3楽章 祭りの日の朝
※第2楽章と第3楽章は続けて演奏される(演奏時間:約20分)
参考文献
『伝記、クロード・ドビュッシー』 フランソワ・ルシュール 笠羽映子訳(音楽之友社)
『ドビュッシィ 印象主義と象徴主義』 ステファン・ヤロチニスキ 平島正郎訳(音楽之友社)
『水と夢 物質的想像力試論』 ガストン・バシュラール 及川馥訳(法政大学出版局)
『悪の華』 ボードレール 鈴木信太郎訳(岩波文庫)
『ビリティスの歌』 ピエール・ルイス 沓掛良彦訳(水声社)
『ロンドンの味 吉田健一未収録エッセイ』(講談社文芸文庫)
初 演:1910年2月20日ピエルネ指揮コロンヌ管弦楽団
楽器編成:ピッコロ、フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット3、ファゴ ット3、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、タンブリン、シンバル、カスタネット、シロフォン、鐘、チェレスタ、ハープ2、弦5部
マーラーの第7交響曲 本日の演奏について
生誕150 年を記念する今年、マーラーの作品を演奏する機会に恵まれ、指揮者として非常に光栄に思う。新交響楽団とは第9 番、第6 番に引き続き今回で3 曲目となるが、演奏が難しく、また楽譜について最も問題が多い第7 交響曲を取り上げる。曲の成立に加え、その後の作曲者による校訂および今回の演奏のための補筆について幾分かの解説を試みたい。
交響曲の作曲でマーラーは、これまで複数を同時進行することはなく、約2 年をかけて1 曲に集中して完成させていた。しかし第7 番は例外的に、第6 番を作曲中の1904 年に並行して作曲が始められ、第6 番の完成(8 月)と前後して、2 つの「夜の音楽」(Nachtmusiken)がすでに書き上げられている。翌1905 年8 月15 日に全曲が完成。2 曲の深い関連は、特殊な打楽器(カウベルと低い鐘の響き)の使用や、長和音と短和音を並置するモティーフからも明らかであろう。また、第6 番の最終楽章では当初、第7 番で使われるテノールホルンがオーケストレーションされていた。2 曲が共通の響きの中で作曲されていったことが想像できる。
第7 番では、テノールホルンの他にもマンドリンとギター、たくさんの打楽器が登場するが、他にもコントラバスに対し弦を引っ張り上げて指板に叩きつける指定をはじめ特殊奏法を多用、新しい響きを追求している。また表現上でも極端なテンポや強弱の変化、楽器間のアンバランスの指定を敢えて行うこともあり、このような書法は明らかに次の世代、つまりシェーンベルク(例えばセレナーデ作品24)を筆頭とする新ウィーン楽派に大きな影響を与えている。
同時にマーラーは、古い音楽への興味を以前から抱いており、第1 楽章のフランス序曲風の序奏(ロ短調!)や最終楽章での古典舞曲への接近は、明らかにバッハの管弦楽組曲を意識したものと考えられる。(最終楽章のテンポAllegro ordinario はヘンデルが好んで使ったもの。)しかし序奏部分のリズムの表現には苦心したようで、表記の錯誤が今もスコアに残る。バロック時代の記譜と演奏の実際について現在では研究も進んでいるが、マーラーが作曲当時すでに、この問題で頭を悩ましていたことは非常に興味深い。16 分音符や32 分音符だけでは、自身が持っていたイメージを表現しきれなかったようだ。こうした不統一は、第3 楽章スケルツォのレントラー(Ländler)舞曲における2 拍目の表記でも散見される。
完成から3 年後の1908 年、プラハではフランツ・ヨーゼフ一世の即位60 年を祝う博覧会が開かれていた。第7 交響曲は9 月19日、その会場内に建てられた演奏会館Koncertní Síň でチェコ・フィルと新ドイツ劇場のメンバーからなる祝祭管弦楽団により初演された。マーラーは9 月5 日にはプラハに到着し本番まで2 週間、分奏を含む24 回の集中した練習が行われた。その合間には、当然の如く寸暇を惜しんで改訂が繰り返された。クレンペラー、ヴァルター、プリングスハイムたちが手助けを申し出たものの、マーラーはそれを断り、パート譜をホテルに持ち帰ると、独りで改訂を続けた。14 日にヴィーンから到着した妻アルマは、書き込まれたばかりのパート譜で足の踏み場もないほど散乱した部屋の奥に作業を続ける憔悴しきったマーラーの姿を確認する。初演の結果は評価の分かれるものであった。第7 番はその後同年10 月にミュンヘン、翌1909 年10 月にはオランダで3 回、作曲者の指揮により演奏された。ヴィーン初演は同年11 月3 日、フェルディナンド・レーヴェの指揮により行われている。
出版についてはマーラー自身も相当腐心したが、1909 年にベルリンのボーテ&ボック(Bote & Bock 以下B&B)社からスコアとパート譜が出された。出版に関するマーラーと出版社とのやり取りの記録は、残念ながら第2 次世界大戦の戦火によりほとんど失われた模様である。B&B 社にとって、マーラー作品の出版は初めてで、作曲者に対する理解が十分行き届かず、度重なる改訂の要請に対応するのが難しかったようである。初版を出版の後、B&B 社は楽譜自体に改訂は行わず、「訂正と改訂リスト」を添付するに留めたが、この訂正表そのものが不十分で、「訂正表の訂正表」を出す事態となり、結果として校訂が非常に不徹底なままになってしまった。実際に第7 番では、同じ動きをする複数のパート間の不統一が、他の作品に比べ極めて多い。(作品が完成しているので、第9 番とは事情が異なる。)ある部分については、マーラーに独特の細かい音色の操作と判定できるが、譜割りがずれたり、パートが途中から脱落したり、音程が違うこともあり、そのままでは響きが明らかに濁る。強弱が全く記されていない部分も残る。
このような状態の改善を目的に国際マーラー協会が設立され、生誕100 周年にあたる1960 年、最も問題の多かった第7 番からエルヴィン・ラッツ(Erwin Ratz)の校訂により批判全集版の出版が開始した。これにより作品のあるべき姿が初めて提示され、現在のマーラー・ルネッサンスの契機となった。
その後は作品研究も格段に進み、演奏側からもラッツ校訂版に代わる新しい楽譜の登場が待望されていた。マーラー協会は要望にこたえ、ラインホルト・クビーク(Reinhold Kubik)博士を中心に新校訂版の編集に取り掛かり、最初に第5 番が2002 年に公刊された。これまでと一線を画した優れた出版で、出来る限り多くの資料を参照し、編集を最初からやり直している。またコンピュータ製版により、スコアとパート譜の錯誤もなく、大変読みやすくなった。新校訂版はすでに第2 番と第6番の編集が完成しており、間もなく出版される。第7 番についてもクビーク博士による校訂は終了しており2007 年3 月、マリス・ヤンソンス指揮バイエルン放送交響楽団により試演が行われた。現在は製版の段階に来ているとのことである。
群馬交響楽団と私が前回演奏に取り組んだのは、偶然にもヤンソンス氏による試演と同じ2007年3 月であった。ラッツ版の校訂に使われた資料のうち、自筆原稿(ファクシミリ)、初版および訂正表を書き込んだ初版を所持しているので、自分なりの検証を試みた。しかし、作曲者自身の訂正が書き込まれた版下、メンゲルベルク所有のスコア、コンセルトヘボウでの自作自演に使われたパート譜(メンゲルベルクが事前に入念に準備した)は参照できず、私の検証は当然かなりの憶測を含んだものになった。
前年(2006 年)に第2 番の新校訂版を試演した際に、国際マーラー協会と交流する機会を得たので、ラッツ版に残る錯誤または疑問点についてクビーク博士に照会を思い立ち、連絡を取ったところ、博士からはすぐに、自分の校訂の評価にも役立つと思うので疑問点をぜひ知らせてほしい、との返事を頂いた。時間も迫っていたが、私は疑問点をまとめて送ったところ、数日後に私のリストを丁寧に添削したお答えを頂いた。800 箇所を超える私の照会に対し、クビーク博士からはそのうち約350 箇所について、新校訂版ですでに訂正済み、あるいは今後も議論の対象になる、ということであった。私の間違った見解、特に軽率なパートの追加および音程の変更に対しては、版下など原資料の状態を示し、明快に否定された。その後新校訂版に含まれるはずの訂正表も送って頂いたので、もちろん本日の演奏にも反映させる。
新校訂版では、散見される表記の錯誤について、作曲者自身による改訂の最後の段階として、編集意見を付けた上で残される模様だ。演奏者は信頼できる楽譜を基に、各自が判断して演奏に取り組むことになる。クビーク博士とのやり取りを踏まえた上で、私は疑問点の整理と練習の効率化のために、自分なりの補筆が必要と考え今回も実行した。ただし、それは曲想に従って強弱やリズムの整合性を取り、不要な響きの削除などその純度を高める目的だけに留めたつもりである。たとえ分量が多くなったとしても、本日演奏を聴かれる皆さんにその変更が気付かれないとすれば、私の補筆は十分成功したものといえるだろう。
新交響楽団の点字プログラム
元団員の岡本 明と申します。維持会員の皆様には新響に対する絶大なご支援、心から感謝しております。
私は1966年の入団以来、40年以上の長きにわたって新響に在団させていただき、ビオラパートで、もっぱら雑音・非協和音の生成に貢献してまいりました。大学在学中、先輩の命令によって有無を言わせず入団させられてから、ついつい長居をしてしまいましたが、65歳前期高齢者という称号を国家からいただき、職場も定年退職という節目にあたり、前回の演奏会をもって退団させていただきました。思えば高校時代に初めてオーケストラに入り、最初の曲がシューベルトの『未完成』でした。そして尊敬する飯守先生のシューベルトとブルックナーの未完成交響曲2曲をもって新響生活を終えるというのは実にかっこいいものと思い、このチャンスしかない、というのが退団の理由です。
ビオラの片隅で弾いていた私の音は維持会員の皆様にはまったく聞こえていなかったと思いますが、それはビオラ弾きの最大のスキルである、皆から0.01秒遅れて音を出して決して飛び出さないようにすること、間違った音を出しても0.01秒以内に弾くのをやめて巧みにごまかすことに卓越していたからであります。このような私のいる新響を聴きに来て下さり、応援していただいている維持会員の皆様には心から感謝しております。退団にあたり改めて御礼申し上げます。
さて、音楽面ではまったく役立たずの私でしたが、新響の場を利用させていただいて世の中にアピールを試みていることが一つあります。それは演奏会での点字プログラムの配布です。そのきっかけは次のようなことでした。
「この間、お芝居を観に行ったら点字のプログラムがあったんです。簡単なものだったけど、おかげで筋が良くわかって楽しかったです。でも音楽会ではもらったことがないですね。」
数年前、ある全盲の女性と一緒に演奏会に行ったときに彼女が言った言葉です。「そういえば、どうして音楽会では点字プログラムを配らないんだろう。視覚障害のある人にとってはお芝居よりも音楽会の方が行く機会は多いのではないだろうか。」そう思って、プロのオーケストラの中のふたつほどに聞いてみたのですが、点字プログラムは配っていないという返事でした。そこで、じゃあ新響の演奏会で点字プログラムを配ってみようか、と考えたのです。
点字とは、ご存知の方も多いと思いますが、眼が見えない方のための、触って読める文字です。英語ではBraille(ブレイル)と言います。これは点字の発明者であるフランスのルイ・ブライユの名前にちなんだものです。発明者と言いましたが、実は最初に点字を考案したのは、やはりフランス人の軍人だったシャルル・バルビエという人です。真っ暗な中で軍事情報をやり取りするために、12の点を使ってアルファベットを現す暗号文字を考えたのです。戦争が一段落した後、バルビエはこれを盲の人の文字として使えないかと考えて盲学校に持ち込みました。そこの生徒だった12歳のルイ・ブライユはそれを見て、これだ!と思ったのでしょう、点字の研究に明け暮れ、やがて6点のアルファベット点字を作り出したということです。このとき彼はまだ15歳の少年でした。ブライユは20歳のときに『点を使ってことば、楽譜、簡単な歌を書く方法』と言う本を出しました。これが点字が公開された最初です。ブライユははじめは点字を音楽のために使おうと考えた、ということですから、点字と音楽は縁が深いのです。
なお、昔はフランス語のアルファベットにはWの文字がなかったのでこの最初の点字にはWがなかったそうです。歌が盛んなイタリア語もWがないようですから、必要なかったのですね。
6点点字はサイコロの6の目と同じく、縦に3つの点を横2列に並べた6点の組み合わせでカナ1文字を表します。日本では一般に使われている点字はすべてカナを基本としていて、漢字はありません(漢字点字もありますが、まだあまり普及していません)。すべてがカナで表されるので(カナというよりは,耳で聞く表音ベースと言う方が正しいかもしれません)、読み間違えのないように、文節ごとにスペースを入れる・改行後の新しい文の始まりはスペースを2つ入れる・などの決まりがあります。また、助詞の「は」「へ」はそれぞれ「わ」「え」で書く、「う」で伸ばす言葉は長音にするというルールもあります。たとえば「私は新交響楽団の演奏会へ行く」は「わたしわ しん こーきょー がくだんの えんそーかいえ いく」となります。これも耳で聞こえたのに近い表現をするためということです。さらにいくつかのルールがあり、なかなか奥が深いものです。
私はこの3月に定年になるまで、視覚障害・聴覚障害のある学生のための唯一の大学である国立大学法人筑波技術大学の教員をしておりまして、視覚障害や聴覚障害のある学生に教えておりました。重度の視覚障害のある学生に教えるためには点字の教科書を作らなければなりません。眼が見える私はまず普通の文字(インクで印刷するということから「墨字(すみじ)」といいます)で教科書を作ってからそれを点字に変える(点訳といいます)のですが、分からないことが多くて苦労していました。点字プログラム作成はその勉強にもなるし、視覚障害のある人にも喜んでもらえるなら、一石二鳥だというわけで始めたのです。新響も一所懸命練習をした成果をできるだけたくさんのお客様に聴いていただきたいのですが、長屋の大家の義太夫のように強制することもできず、お客様集めには毎回苦労しています。もし点字プログラムを作ることでお客様が一人でも増えるなら、一石三鳥にもなるわけです。さらには、もしこれが広まって、どの演奏会でも点字プログラムを配るのが当たり前、というようになるきっかけになれば、一石四鳥です。
恥ずかしながら私は正式に点訳の講習を受けたことがありません。しかしありがたいことに、点訳ソフトがあるのです。パソコンで作った漢字・かな混じりの文章をそのソフトに流し込んでやればあっという間に点字に変えてくれて、点字プリンタにかければ点字印刷ができあがります。じゃあ点字については何も知らなくても点訳ができるかというと、そうはいきません。点訳ソフトでできた点字文書にはいくつか誤りが発生します。人間でないと分からないこともあります(たとえば人の名前で、長田さんは「ながたさん」なのか「おさださん」なのかは機械には判断できません)。人手による校正が必要です。私は基本的に点訳ソフトに頼って、校正は見様見真似というか、分からないところは点字に詳しい人に聞きまくってやっている状態です。この校正は、点字のチェックだけでなく、もとの原稿の誤りを見つけるチェックにもなるので、プログラム作成担当者からは感謝されています。誤りではないけれど、日本語として少しおかしいような文章もこの段階で著者にアドバイスします。
以前はこのまま、「専門の点訳者が点訳したものではありませんので、誤り等があるかと思いますが、ご容赦ください。」という弁解をつけて、自分で数部プリントしていました。しかし受け取った点字使用の方から基本的な誤りをいくつか指摘され、やはりきちんと校正しなければならないと反省し、2年ほど前から専門の点訳者の方に最終チェックと修正をお願いすることにしました。幸いなことに、日本点字図書館のベテランの点訳者の方がボランティアで引き受けていただけることになりました。お願いすると毎回かなりの修正を入れて返してくださいます(ということは以前チェックなしで出していたものはとてもひどいものだったということであり、いまさらながらに申し訳なく、赤面しています)。さらに、ただチェック・修正するだけではなく、その理由もきちんと説明していただけるのです。また点訳者の心得も教えていただけます。おかげで私の点訳の腕も以前よりは少し上がってきていると自負しています。
点字プログラムの印刷は日本点字図書館にお願いしていますが、大変リーズナブルな価格で印刷していただき助かっています。
実はこの点字プログラム、困ったことがあります。それはとても分厚くなってしまうことです。点字は触って読むため一文字が墨字よりずっと大きく、そのため,墨字1ページは点字ではおおむね3,4ページになります。新響のプログラムはとくにページ数が多く、墨字で20ページにもなることがあります。それを全部点字化すると60ページ以上にもなってしまうのです。印刷のコストもかかりますし、持ち運びも大変です。読む方も大変です。両面印刷もできるのですが、それでも30枚以上になります。
私は、障害のある方も可能な限り、障害のない人と同じことができるようになるのが理想だと考えています。点字プログラムも墨字のものとまったく同じものを作りたいと思っています。また、視覚障害のある方がふらりと演奏会に来られてもいつでも点字プログラムが用意されているようにしたいと思っています。しかし実際には、どんなにがんばっても墨字のものとまったく同じ情報は提供できないのです。図や写真は点字にできませんので、説明文で代替しなければなりません。曲の解説にときどき譜例(楽譜)が出てきますが、これは楽譜専用の点字を使わないと表現できず、いまの点訳ソフトでは作れません。一般の点字使用者の方も読める方は多くないので、これは省略しています。団員名簿はページ数の関係から点字版では省略してしまっています。はたしてこれで良いのか?といつも迷いながら作業を進めています。いつでも点字プログラムを渡せるようにするというのも、実際には点字印刷にはコストもかかりますのでなかなか難しいのです。できるだけ余分な印刷をしないですむようにするには、何人の点字使用の方が見えるのかを事前に予測する必要があります。そのためには事前申し込みをいただくようにするのが一番簡単ですが、それでは一般の人と違うことを要求することになってしまいます。幸い、今のところ新響演奏会にお出でになる点字使用の方は、日本点字図書館や筑波大学付属視覚特別支援学校(以前の盲学校)で取りまとめていただいている方が多いので、大体の数を知ることができています。しかし本来は、ふらりと来られても点字プログラムがちゃんとあるようにしたいものと思っています。
ところで、最近改めて調べてみたところ、実はいくつかのプロのオーケストラでときどきは点字プログラムが用意されることが分かりました。日本には室内オーケストラを含めて32のプロオーケストラがあります。そのすべてに電話をして問い合わせてみたところ、少しでも点字プログラムを配布しているところが全体の4分の1の8団体ありました。東京の場合、現在11のプロオーケストラがありますが。そのうちの3団体で、全部の演奏会ではないけれど点字プログラムを配布しているということでした。5年・10年前から配布しているというところもありました。
内容は、墨字版とまったく同じではないけれど、曲目・解説・ソリストのプロフィールなどは載っているということです。東京のオーケストラ2団体は事前の申し込みなしでも当日受付に行けば受け取れるようにいつも5部用意し、毎回、2・3部が受け取られるそうです。定期会員からの要望が点字プログラム配布のきっかけとなったということでした。点訳・印刷は外部の団体に有料で依頼しています。
東京以外では5団体で点字プログラムを配布しています。事前に申し込めばカセットテープに入れた「音訳版」も提供しているところもあります。特徴的なのは、点訳から印刷までをボランティアに頼っているところが多い点です。献身的なボランティアがおられて、すべての点訳を引き受けてくれているそうです。ライトハウスなどの視覚障害関連の団体と連携しているところもあります。
しかしどこも「点字プログラム」が用意されていることをあまり大きく宣伝していないのです。これはなぜなのでしょうか?インターネットにも書いてないところがほとんどです。せっかく作っているのだからもっと周知してもらえればと思います。
一方、アマチュアオーケストラはどうでしょう。知り合いのいる約10団体に聞いてみたのですが、どこも点字プログラムは作っていません。日本にはそれこそ星の数ほどもアマチュアオーケストラがあるので、どこかはやってくれているとは思うのですが、本業の仕事の傍ら、墨字のプログラムを作るので精一杯で、点字まではとても手が回らないという状況だと思います(新響で岡本がやれたのは、大学教員っていうのはヒマだからか、といわれると困るのですが、決してヒマではありませんよ)。
ここでは音楽会のプログラムについて書きましたが、それに限らず、展覧会・博覧会などいろいろな場で点字の資料が用意されるようになって欲しいと思っています。
点字は重度の視覚障害のある人にとっての大切な文字で、音声からは得られない情報があります。もっともっと普及させる必要があると思います。しかし、先に書きましたように、作成の手間とお金が作成する際の障壁になっているのです。このようなところにこそ、文化庁・文部科学省などの助成が欲しいと思うのです。
新交響楽団の演奏会では最近は毎回10人から15人の方に点字プログラムを受け取っておられます。内容がよくわかって音楽がいっそう楽しめると言っていただいたり、わざわざお礼のお手紙を下さる方もあり、やりがいを感じています。 なお、新交響楽団では、視覚障害のある方と付き添いの方を年4回の定期演奏会にご招待しています。毎回そのご案内をインターネット上の毎日新聞のユニバーサロン(http://www.mainichi.co.jp /universalon/volunteer/message/)に載せていただいているので是非ご覧ください。
私は退団しましたが、幸いこれからもトランペットの小出氏が担当を引き継いでくれて、私が点訳をして、点字プログラムの配布を続けることになりました。
いささか長文になってしまって失礼いたしましたが、点字プログラムのことを維持会の皆様にも是非お伝えしておきたいと思い、書かせていただきました。もしお知り合いに点字使用の方が居られましたら、このことをお知らせいただければ幸いです。
マーラーとブルックナー ―― 心の拠り所としての神 ――
■異邦人としての意識
今から一世紀半前の1860年7月7日。グスタフ・マーラーはチェコのイフラヴァ(当時オーストリア領ボヘミヤ)近郊のカリシュト村にてユダヤ人ベルンハルト・マーラーとマリー・ヘルマンの第二子として生まれた。幼少の頃からピアノの才能を発揮し、10歳で演奏会を開く程の腕前であった。15歳でウィーン楽友協会音楽院(現ウィーン国立音楽大学)に入学する。18歳の若さで同音楽院にて作曲賞を受賞する等、若い頃から才能を発揮した。
しかしこのような活躍とは裏腹に、ボヘミヤ生まれの異邦人、更にはユダヤ人としての意識は強かった。当時の情勢としてカトリック圏のオーストリアはプロテスタント圏のドイツより更に保守的であり、反ユダヤの思想が渦巻いていた。音楽院を卒業後、指揮者としてのキャリアを積む過程でマーラーは自らの出生と対峙することとなる。ウィーン宮廷歌劇場の芸術監督候補となった1896年冬の日の事。仲介者の作曲家エデン・フォン・ミハロヴィッチに手紙を宛てている。そこで、彼はユダヤ人である事が就任の妨げになる事を恐れ、自分がカトリックに改宗していることを主張している(しかし、これは事実と反しており、実際改宗しているのは1897年2月である)。結果としては、このような働きかけが実を結び、彼は1897年ウィーン宮廷歌劇場の芸術監督となる。また1898年には、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の指揮者に就任する。
音楽だけでなく恋愛に関しても非常に努力家であった。音楽院を卒業し、作曲活動が本格化すると平行し、意中の女性のため曲を書いた。王立郵便局長の娘ヨゼフィーネ・ボイスル、カッセル歌劇場の歌手ヨハンナ・リヒター等が有名である。失恋続きであったが、1902年41歳の時、19歳年下のアルマ・シントラーと結婚する。同年に長女マリア・アンナ、1904年には次女アンナ・ユスティーナが誕生する。
■斬新な作風の交響曲
交響曲第七番『夜の歌』は、この時期から1905年にかけ作曲された。全五楽章編成、『夜の歌』という表題は、第二楽章、第四楽章にある『夜の音楽』というタイトルに由来する。初演は1908年プラハにて作曲者自身の指揮により行なわれたが評価は芳しくなかった。不評の理由はこの交響曲の展開の図式にあったと言われている。具体的には、第一楽章から第四楽章までが、落ち着いた夜の雰囲気を感じさせる曲想である一方、第五楽章で唐突に明瞭なファンファーレが鳴り響き、大音量のフィナーレが始まるといった内容である。周知の通り、従来の交響曲の多くは『苦悩⇒闘争⇒勝利』という図式が伝統的に使われてきた。第七交響曲の場合、言わばそれらからドラマチックな要素がそぎおとされ、単に『暗⇒明』という図式になっていると言える。この斬新な作風の交響曲が聴衆にとって難解であったことは日本においても同様である。日本初演は1937年に行なわれるが(東京音楽学校管弦楽部・プリングスハイム指揮)それ以来、1974年の次回演奏会(東京都交響楽団・渡邉暁雄指揮)まで演奏機会には恵まれなかった。哲学者・音楽評論家テオドール・アドルノ(1903-1969)はマーラー第七交響曲の第五楽章がそれまでの楽章に比べ『軽すぎる』と内容の薄さを批判している。
斬新な部分は交響曲全体の流れだけでなく、各楽器の音色・奏法にも見られる。まず、交響曲では使用される機会の少ない、テナーホルン、ギター、マンドリン等の特殊楽器が登場する。更に、右手を深く朝顔に差し込んだ独特のホルンの音色、後年のバルトークピチカートを思わせるチェロ・コントラバスの強烈なピチカート等の特殊な奏法がある。ピチカートの最後の一打では(第三楽章401小節目)、マーラーは譜面にフォルテfを五つ重ね『So stark anreißen, daß die Saiten an das Holz anschlagen(指板にぶつかる位に激しくピチカートする)』と表記している。
■ドイツ語の譜面表記から読み取れること
マーラーの先進的な姿勢は、言語学的な見地、つまりは、譜面に表記されたドイツ語からも読み取れる。マーラー自身がウィーン楽友協会音楽院にて薫陶を受け、妻アルマも敬愛していた作曲家にアントン・ブルックナー(1824-1896)がいる。マーラー第七交響曲と近い時期に作曲されたブルックナー第九交響曲のドイツ語と比較してみると興味深いことが分かる。なお、ブルックナー第九交響曲の作曲年は1896年(絶筆)、マーラー第七交響曲の作曲年の8年前にあたる。
『冒頭の』というドイツ語を取り上げてみよう。マーラー第七交響曲では名詞の語尾には何も付けず『am Anfang』と記している(第三楽章258小節目等)。それに比較し、ブルックナー第九交響曲では、中性名詞三格の語尾に『e』を付け『im Anfange』と記している(第三楽章77小節目)。中性名詞三格の語尾に『e』を付ける習慣は19世紀においても使われていた古風な言い回しとされている。1900年前後のこの時期においてどちらも同等な頻度で使われていたとすると、『am Anfang』は当時のニュアンスとして、比較的モダンな言い回しだったのではないだろうか。なお、現代ドイツ語の日常会話においては、まず殆どの場合『am Anfang』が使われる。ブルックナー・マーラー共にウィーンを中心に活動しており、地域での言い回しの違いの可能性は考えにくい。音楽以外、単語の選び方一つをとっても、マーラーが常に新しい方向を見据えていたことが伝わってくる。
■心の拠り所を探し求めて
第七交響曲初演の不評に悲嘆したマーラーであったが、1910年9月第八交響曲の初演が大成功を収めることとなる。その第一楽章のコラールにはカトリック古来の祈祷の言葉が用いられている。これは第七交響曲の初演失敗の反省からとも受け取れる。
第七交響曲初演前から第八交響曲初演の成功までのマーラーを取り巻く状況は非常に厳しいものだった。1907年、長女マリア・アンナが他界し、マーラー自身も心臓病の宣告を受ける。更に1910年、妻アルマの不貞が発覚し、精神的に窮地に追い込まれたマーラーは精神分析学者ジークムント・フロイト(1856-1939)の被験者となる。このような境遇があってか、第七交響曲の曲想には、方向性が定まらない一種の不安的さを見て取る事が出来る。感情の高まりに反して急激に掛かるデクレッシェンド・ピアノ、不規則なアクセント、定まらない調性(※)そして、既述の突然雰囲気を一新するフィナーレである。言わば、地に足の付かない宙に浮いた状態といったところだろうか。
※曲の終始に渡りハ長調とハ短調の間を行き来している第二楽章等
マーラーは異邦人というだけでなく、どこにも心の拠り所が持てなかったのかもしれない。その作曲活動は試行錯誤の繰り返しであった。脱ユダヤを目指しながらも、オーストリアの伝統文化と同化することもできず、新しい道を模索し続けた。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の指揮者を僅か3年で辞任したのも、楽団員との音楽的見解の衝突が原因の一つと言われている。『やがて私の時代が来る』という有名な台詞は、新境地を求める者として必然的に出た言葉だった。そう感じるのが自然ではないだろうか。
■あとがき
チェコは一度だけ赴いた記憶がある。学生時代、ナチス躍進期のドイツの研究のため1年程現地に留学していた。その頃、プラハに音楽留学中の桐朋音大の友人がおり、一度会い行った事がある。その時のエピソードを最後に紹介したいと思う。
気持ちいい晴れの日、一緒に町を回った。カレル橋、時計台、ヤン・フス像、ドボルザークホール、スメタナホール、そして、山の頂にそびえ立つプラハ城。プラハ城へ続く坂道の途中、ガラス工芸店でボヘミアングラスを買った。素朴な美しさのある透明感だった。チェコの美しい伝統文化と誇りを羨ましく思ったものだった。
晴れやかな青空、グラスの美しい透明感。しかし、それらと裏腹に、苦悩するマーラーの心は曇り切っていたのかもしれない。

プラハ旧市街広場にて。手前はヤン・フスの彫像、奥は聖ミクラーシュ教会
※ヤン・フス(1369-1414)
ボヘミヤ出身チェコ人の宗教思想家・宗教改革者。 免罪符に異を唱えカトリック教会と激しく対立。
1414年コンスタンツ公会議にて焚刑に処され、 故郷ボヘミヤに帰る事はなかった。
●参考文献
・『異邦人マーラー』 ヘンリー・A・リー著 渡辺裕訳 1987年 音楽之友社
・『グスタフ・マーラー -現代音楽への道-』 柴田南雄著 1995年 岩波書店
・『ブルックナー・マーラー事典』 根岸一美/渡辺裕監修 1998年 東京書籍
第210回ローテーション
| ドビュッシー | マーラー | |
| フルート1st | 吉田 | 松下 |
| 2nd | 丸尾 | 岡田充 |
| 3rd | 兼子(+Picc) | 藤井 |
| 4th | - | 新井(+Picc) |
| Picc | 岡田澪 | 兼子 |
| オーボエ1st | 亀井淳 | 堀内 |
| 2nd | 亀井優 | 山口 |
| 3rd | - | 横田 |
| C.A. | 桜井 | 岩城 |
| クラリネット1st | 末村 | 品田 |
| 2nd | 大藪 | 末村 |
| 3rd | 進藤 | 石綿 |
| EsCl | - | 進藤 |
| BsCl | - | 高梨 | ファゴット1st | 田川 | 長谷川 |
| 2nd | 斎藤 | 浦 |
| 3rd | 長谷川 | 斎藤 |
| コントラファゴット | 浦 | 田川 |
| ホルン1st | 大内 | 箭田 |
| 2nd | 市川 | 大原 |
| 3rd | 大原 | 山口 |
| 4th | 山口 | 園原 |
| トランペット1st | 倉田 | 野崎(アシ北村) |
| 2nd | 北村 | 小出 |
| 3rd | 中川 | 中川 |
| トロンボーン1st | 牧 | 志村 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 |
| 3rd | 大内 | 岡田 |
| テノールホルン | - | 牧 | テューバ | 足立 | 土田 |
| ティンパニ | 古関 | 桑形 |
| パーカッション | 小太鼓/今尾 鐘/中川 タンブリン/皆 カスタネット/今尾 木琴/浦辺 シンバル/桜井 |
大太鼓 ・ルーテ/古関 シンバル付き大太鼓/古関 小太鼓/浦辺 タンブリン/田中 シンバル(合わせ)/中川 シンバル(吊り)/桜井 トライアングル/今尾 グロッケンシュピール1/皆月 グロッケンシュピール2/古関 タムタム/中川 カウベル/田中・浦辺 低音の鐘/桜井・皆月 |
| チェレスタ | 藤井 | - |
| ハープ1st | (*) | (*) |
| 2nd | - | (*) |
| 1stヴァイオリン | 掘内(小松) | 前田(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(塩塚) | 大隈(田川) |
| ヴィオラ | 常住(田口) | 常住(田口) |
| チェロ | 柳部容(光野) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 中野(加賀) | 中野(加賀) |
第210回演奏会のご案内
「やがて私の時代が来る」
大作曲家として人気があるマーラーが生まれたのは1860年、今年は生誕150年にあたります。芸術の花開く世紀末ウィーンで、指揮者として名声を得ていましたが、作曲家としてはあまり受け入れられていませんでした。それから長い年月を経て自身の予言通り1970年代にマーラーブームが起こり、現在はクラシックコンサートの主要レパートリーとなっています。
マーラーイヤーである今回の演奏会では、マーラーをライフワークとする高関健を指揮に迎え2007年10月の第9番、2009年4月の第6番に続き、マーラーの交響曲を演奏します。
今回演奏する交響曲第7番は、1904~05年に作曲された5つの楽章からなる大曲で、テノールホルンやマンドリン、ギターといった通常オーケストラに登場しない楽器が使用され独特な雰囲気を出しています。同じ時期に作曲された第6番が劇的ながら伝統的な形式に従っているのに対し、第7番は多彩で前衛的です。ですので難解とされる向きもありますが、そこがまたこの曲の魅力なのでしょう。
マーラーとドビュッシー
同じ時代、フランスでは印象派の芸術が台頭していました。ドビュッシーは印象派音楽の代表的な作曲家です。今回演奏する「イベリア」は、印象派の作風を確立した円熟期の1905~08年に作曲され、1910年にはマーラー指揮によりアメリカで初演されました。マーラーはニューヨーク・フィルの演奏会でドビュッシーの曲を多く取り上げており、自分の同志と思っていたのかもしれません。
管弦楽のための映像は、「ジーグ」「イベリア」「春のロンド」の3曲からなり、それぞれイギリス、スペイン、フランスの民謡や舞曲が素材となった標題音楽ですが、客観的な描写ではなく心に映った印象を音楽にしています。必ずしも3曲まとめて演奏されるものではなく、特に「イベリア」1曲だけ演奏される機会が多いようです。スペイン情緒のなかにドビュッシーらしい響きがする楽しい曲です。
夜から朝へ
マーラー交響曲第7番に付けられる「夜の歌」という副題は、マーラー自身が第2楽章と第4楽章に「NachtMusik(夜曲)」と名付けていることに由来します。このため、曲全体を指すわけではありませんが、時には荘厳にそして愛らしくまた妖しく、夜の雰囲気を漂わせています。ところが第5楽章は一転して明るく活気に満ち、曲想が目まぐるしく変化します。朝が来てお祭り騒ぎが始まるのかのようです。
一方「イベリア」は、「街より道より」「夜の薫り」「祭りの日の朝」という3つの楽章からなります。マーラー交響曲第7番と同時期に作曲されたというだけでなく、夜~朝の情景の雰囲気を表現した音楽という共通項があり、その対比もお楽しみいただけると思います。
どうぞご期待下さい。(H.O.)
ブルックナー:交響曲第9番 〈永遠のゲネラルパウゼ〉
この世のものとは思えない彼岸の響きで満たされたこの作品は、ブルックナーの中でも別格の位置を占める未完の大作である。人智を超越した根源的な信仰告白と、カトリックによる信仰世界の官能性によって生み出された不思議な楽式構成による昇華された音楽空間は、奇跡としかいいようがない。
ヨーゼフ・アントン・ブルックナーは、1824年ベートーヴェンが交響曲第9番を作曲した年にオーストリア帝国の小村アンスフェルデンにて生まれ、1896年マーラーが交響曲第3番を作曲した年にヴィーンにて72歳で没した、まさしく19世紀ドイツ・ロマン派の時代を代表する作曲家の一人である。13歳のとき、リンツ郊外にあるザンクト・フローリアンの修道院で学び、17歳で補助教員を務めながら音楽理論の研鑽を積んで音楽家へとなっていった。32歳でリンツの大聖堂オルガニストの地位を得て44歳でヴィーン音楽院教授となり、当初はオルガニストとして成功を収める。作曲活動も宗教曲から交響曲の分野に進出したが、ヴィーンの楽壇にて作品が理解されずに認められない日々が続いたあと、交響曲第7番で交響曲の作曲家としての名声を60歳にてようやく確立、不動の評価を得るようになった。
■ブルックナーの個性
ブルックナーは、風刺画などでは背が低く描かれているが、ヴァーグナーやブラームスよりも背が高くて堂々とした体格をしていた。大食漢にて健康管理には無節操、健康上いろいろと問題を抱えていた。自然や美しいものを愛する気持ちが強く、生涯独身だったが美少女崇拝ともいえる晩年にいたるまで少女にその場で求婚してしまう結婚願望、当時の流行とは無縁で都会的な洗練さに欠けた無頓着な着こなし、生活の不安に対する強迫観念による猛烈な求職活動、病的なまでのさまざまな証明書の請願、謙虚さと卑屈とも思えるへりくだった態度は、周囲の失笑を買う世俗的一面といえよう。また、深刻な神経 衰弱に陥り、異常なまでの数字に対するこだわり、死体への異常な関心、敵意に満ちた批評に対する劣 等感から意気消沈して、音楽活動に疑念を抱いてしまうこともあった。このような世俗的な態度と素朴で閉鎖的な性格から、人生の神秘性と宗教性を見つめた作品が生み出されたことは、カトリック教徒としての矜持を終生持ち続け、敬虔なカトリック信仰が人格の基本にあったからといえよう。晩年の世俗的成功を見ると、彼はまさに19世紀的人間であり、神秘化とか偶像化とは無縁の、世俗から超越した隠遁者ではなかった。完全にマスターした音楽理論の知識と実践で独自の世界を構築したにすぎない。
■音楽的側面― 完全な音楽理論
ブルックナーが生涯を通して親しんだザンクト・フローリアンにある壮麗な修道院と付属教会には、中世からの知識の宝庫となる厖大な量の蔵書を誇る図書館と、ブルックナー・オルガンとよばれる大オルガンが有名である。このような環境から古典的な様式で創作された数多くの珠玉といえる宗教曲、並外れたオルガン即興演奏の能力が生み出された。
転機となったのは、30代で19世紀中葉を代表する音楽理論の大家ジーモン・ゼヒターの指導により伝 統的な音楽理論(和声法・対位法)を完全にマスターしたこと、また実践的且つ進歩的な音楽家でリンツ州立劇場の首席指揮者オットー・キツラーから、当時の進歩的な音楽の和声法と管弦楽法を学んだこ とであった。そしてリヒャルト・ヴァーグナーの斬新で大胆な音楽的側面を得ることになった。ゼヒターによる理論学習は彼の作品の磐石な土台となり、キツラーを通して知った自由な創作とヴァーグナーの音楽から、従来の伝統的な和声の禁則を犯すことに対する免罪符をブルックナーは得たのである。(ヴィーンのゼヒターに関する逸話として、シューベルトが死の15日前、対位法を学び直すべく彼のもとを訪れたのは有名な話。)
和声課題への解答(ブルックナーとゼヒターの筆跡)
■ヨハネス・ブラームスとの関係
ブルックナーが後半生を過ごすことになるヴィーンは、当時リベラルな空気と同時に伝統や権威を尊重する保守的な都市という側面を持ち、思想や音楽を通して論争が激しくなってきたときである。ヴィーン楽壇では、絶対音楽の純粋な形式美を理想とするブラームス派と、標題音楽や楽劇の思想を標榜するヴァーグナー派とで、互いに感情的な論戦を繰り返していた。ブルックナーはヴァーグナー派として抗争に巻き込まれていく。
ブルックナーとブラームスの影絵
ブルックナーとヴァーグナーの影絵
同時代ヴィーンに居たブラームスは、自立した作曲家としては完全な勝利者であり、ブルックナーにとっては脅威であった。古典的で絶対音楽的立場を敢然と守りぬいた重厚で構成的な音楽を創造し、当時の大きな風潮であったリストやヴァーグナーとは本質的に合わなかった。15世紀以来シューマンに至る大家の作品に惹かれ、その伝統の上でドイツ中世からバロックの音楽研究に由来する巧妙で他声的な 処理による壮大な効果や荘重さ、旋律を自由に走らせる技巧を持ち、ブルックナーと同様にバッハやベ ートーヴェンを敬愛していた。出身地(北ドイツとオーストリア)、宗教(プロテスタントとカトリック)、受けた音楽教育と生活環境の違いもさることながら、慇懃で無愛想でインテリ然としたブラームスと、素朴でお人好しで田舎者のようなブルックナーとでは、そもそも性格が合わなかったのであろう。
■交響作品の要素
ベートーヴェンのように一定の志向性があって求心的、というよりは並列的といえる。周囲の風景が時間とともに変化する、というよりは、人跡未踏の大地を歩いて突然景色が変化、例えば霧の中から突然巨大な山、深い森を抜けると開けた大地、または巨大な氷河で大きなクレバスに直面、という感覚である。またソナタ形式の枠組みにおいて、旋律の基本的造形を一定の単位で考えることで、彼の草稿にはいつしか譜面の下に古典的な旋律単位としての構造を示す数字を記載しているのがこだわりでもある。
因襲的な調性関係にこだわらず、ヴァーグナーの「トリスタン和音※」をそのまま使用している。動機が1つの声部ないしは複数の声部に続けて繰り返されて音高が変わって行くといった「ブルックナー・ゼクエンツ」を活用した転調法、大きな音程の上行や下行の飛躍を伴う旋律、オーケストラ全体による「ブルックナー・ユニゾン」、このような要素を通して楽想転換のため管弦楽全体を休止(ゲネラルパウゼ)させる「ブルックナー休止」が必要となった。また、リズムでは、主題その他の旋律的進行にて、鋭いリズム構成として三連音を使用した「ブルックナー・リズム」、付点リズムや複付点、三連音に二連音の重複など、いろいろな要素の重なりが見られる。
弦楽器群は管楽器群と対立してそれぞれ主役を担うが、「ブルックナー開始」といわれる冒頭の弦楽 器のトレモロで始まる手法が多い。金管楽器群では単に音量を増加させるのではなく主題を含めた旋律 を目立たせることも多いが、木管楽器群はヴァーグナーやブラームスとは異なり、金管楽器群の厚い編 成や強い響きに対してバランスを考慮しているとは思えないこともある。
名声を確立した第7交響曲からオーケストレーションが拡大されて三管編成となったが、ホルンも8本になり、且つ「テナー・テューバ」「バス・テューバ」として、ホルン奏者の持ちかえで「ヴァーグナーテューバ」が使用されている。第8交響曲を除いてハープ、コントラファゴットは使用されていないし、ピッコロ、バスクラリネットやコールアングレもみられない。打楽器も制限されている。ヴァーグナーのように色彩的ではなく、オルガンでいえば、ひとつの手鍵盤から他の手鍵盤に動いて新しい声部を加えていく方法、数多くのストップを選択することにより、ひとつの鍵盤を押すだけでも複数の音色とかオクターヴ上の音、あるいは5度の音を作ることが可能であり、そこから生み出される壮麗な音楽が基本となって「ブルックナー・ユニゾン」とか、コラールが荘厳に演奏される、深遠な「ブルックナー・トーン」が確立されている。
独特な音響は当時の人々を驚かせたに違いない。演奏家や聴衆にとって、断裂的な構成と原色的でアンバランスなオーケストレーション、そして異様な長大さは理解を超えたものであった。ヴィーンでブルックナーのよき理解者であったヨーハン・ヘルベック(シューベルトの「未完成交響曲」を発見し初演したヴィーン楽壇最有力者のひとり)の急逝も、作品の理解と普及の痛手となる。ヴァーグナー派であった弟子たちが、通俗性やドラマチックな展開を求めて短縮や改定を申し出たことによる作曲者自身の改訂に加え、時代の趣味に合わせて機会あるごとに弟子たちが、善意のために改竄を加えたことは、複雑な版の問題を生じている。皮肉にも、善意の改竄による普及がもたらしたことで、後世、ブルックナーの作品が注目されることになったが、背景には、愛好者が増えたことと音楽に理解を示す有能な指揮者が多くなってきたこと、ヴィーン音楽院の弟子たちから多くの有能な音楽家が輩出したことなどがある。
■交響曲第9番
第8番の第1稿完成後、1987年8月12日に作曲を開始した。しかし他の作品の改訂作業のため中断を 余儀なくされ、1891年にようやく集中するようになった。度重なる発病にもかかわらず、死の直前まで 衰えない創作力で終楽章を完成させるべく力を振り絞ったが、ほとんどコーダ直前まで多くの草稿を残しながらも未完に終わった。
書法的には、彼の交響作品の要素は共通として持っているが、第8交響曲での調性の扱いを大胆に発展させ、旋律も音程の飛躍が大胆になり、和声も漠然とした調性の中で動くという、新しい世界を示している。
第1楽章:二短調(荘厳に、神秘的に)
調性や構成でベートーヴェンの第9交響曲を連想させる楽章。ソナタ形式だが再現部の開始が曖昧で 自由且つ壮大な内容となっている。まず冒頭からこの世のものとは思えない響きが出現する。第1主題 群はホルンによる激情的な導入主題と、まるで全能の神を象徴しているような全楽器による強烈なユニ ゾンで演奏されるオクターヴ下行音型を経て、温かく穏やかなイ長調の第2主題群に入る。そして第3主題群として神秘的なニ短調の深遠な揺らぎを経過して、いままでの3つの主題群が有機的に組み合わ された展開部と再現部へ拡大、寂しげなコラール風音型を経て、強烈なコーダに突進していく。
第2楽章:スケルツォ 二短調(動きをもって、生き生きと)トリオ 嬰へ長調(急速に)
間にトリオをはさむ複合三部形式。冒頭に2小節の沈黙から第3小節目のアウフタクトで7度の変化 和音にて不安定な響きで始まる。和音が「トリスタン和音」の構成で変化しながら、常に嬰ハ音が二音 の導音として持続しているのが神秘的。一瞬の空白から冒頭音型が叩きつけるように登場する。その後、イ長調による優美で舞曲的な旋律を経て、また冒頭の強烈な主題がよみがえってくる。中間部のトリオは、ブルックナーにしては非常に早いテンポ。嬰へ長調(シャープが7つ)で快活なリズムにのって諧 謔的ともいえる音楽が繰り広げられ、途中で感傷的な旋律を経て快活なリズムに戻り、そしてスケルツ ォを反復する。尚、トリオに入るところで3小節ものゲネラルパウゼがあるのが面白い。決して音楽は休んではいない。
第3楽章:ホ長調(穏やかに、荘厳に)
実に崇高な音楽。ヴァーグナーテューバが登場して深く豊かな音楽を創造している。全体は5部のロ ンド形式と見えるがブルックナーが独自に到達したソナタ形式といえる。第1部は第1ヴァイオリンによる短9度の跳躍で始まり、まるでヴァーグナー「トリスタンとイゾルデ」冒頭のような半音階和声で大胆に進行。金管が咆哮し神秘的な音楽を経て、ブルックナーが「生への決別」と呼んだホルンとヴァーグナーテューバにて下行音型によるコラール風の動機が印象的に登場する。第2主題群として変イ長調の柔らかく内省的な音楽が美しい。第2部では今までの主題が浄化され、より緻密になっていく。第3部は、第2主題群が拡大されて密度も濃くなり、最大のクライマックスへと目指して劇的に進行。ここは実に壮麗な音楽で、ブルックナーの宗教曲の傑作「二短調ミサ」や「へ短調ミサ」の動機を思わせる音型が効果的に登場、クライマックスの頂点で嬰ハ短調の和声的短音階7音全てが鳴らされる不協和な響きで突然ゲネラルパウゼ。コーダは、第8交響曲のアダージョや第7交響曲冒頭の主題を回想し、愛と至福に満ちたホ長調の響きで静かに終結する。
■終楽章:フィナーレ
巨大な頂点と開放感、純粋で不思議な安らぎ、圧倒的で強烈な盛り上がりと勝利に満ちた力強さがあ るブルックナーの作品には、宗教曲が交響曲と深い関係を持っており、後期になるにつれて、カトリック的宗教性、大自然の息吹、ドイツ・オーストリアの土俗性、という三つの性格が複雑に絡み合い深化している。 土俗性という意味では、キリスト教とゲルマン性の二重構造が作品に潜んでおり、デモーニッシュともいえるゲルマン的な原初の記憶が潜んでいる。これは、ウェーバーやシューベルトにも共通した、神秘に満ちた森の中で生まれた民族の共有財産ともいうべきものが、無数に書き込まれているのではないだろうか。カトリックが信仰される前の古代の習俗がキリスト教に同化、吸収されて封じ込まれたが、消え去ることなくドイツ・オーストリアのゲルマン人の無意識の底に蓄積されたものがあり、ブルックナーも例外ではない。(日本人が古来の山岳信仰をたくみに仏教と同化させたように)音楽・宗教を通しての体験と学問を通して得た高い知識と経験による作品に対し、合理的な解釈をすることは可能だろうが、原初の記憶として合理的な説明などとは全く無縁のところに、ブルックナーの音楽の魅力があり、そこにあるのは鳴り響く音楽だけである。 ブルックナーは終楽章に相当な未練を残してこの世を去り、従来のどの作品よりも壮大なものになる はずだった終楽章は、偉大なる神への賛美として完成させなければならないものだった。現在まで残さ れた草稿を元に終楽章を復元・補完する試みがなされてはいるが、未完であるがゆえ、フィナーレは「永遠のゲネラルパウゼ」となってブルックナーの最後にして最大の作品となった。ブルックナーが生涯にわたり崇拝した神に献呈すべく、圧倒的な勝利の響きが信仰の勝利へと繋がり、時空を超えて私たちの心の中に鳴り響いている。
初 演:1903年2月21日フェルディナンド・レーヴェ指揮ヴィーン演奏連盟管弦楽団 ヴィーンのムジークフェライン大ホールにて(3楽章までのレーヴェによる改訂版)
1932年4月2日 ジークムント・フォン・ハウゼッカー指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー(オーレルによる批判全集版:原典版) 先に従来のレーヴェ改訂版を演奏、その後オリジナル稿として原典版を初演
日本初演:1936年2月15日クラウス・プリングスハイム指揮東京音楽学校第78回定期演奏会日比谷公会堂にて
楽器編成:フルート3、オーボエ3、クラリネット3、ファゴット3、ホルン8(ヴァーグナーテューバ4)、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、弦5部
※「トリスタン和音」
ヴァーグナー「トリスタンとイゾルデ」冒頭に登場する減五七和音の一種で、当時としては画期的。
交響曲第9番終楽章の草稿
シューベルト:交響曲第7番「未完成」
人間の創造力の深淵を知るという意味で、この曲は特別である。「神の啓示」を受けたという表現を単なるレトリックではなく、信じさせてしまう力を持つ。
これほどの曲を作るのに、どんな呻吟があったのか、特別な境遇が創作を後押ししたのか。「未完成」のままにした理由には作曲家の特別な思いがあったのか。後世に生きる私たちは、そうあるはずであると、シューベルトの周辺をさぐる。しかし、そこにあるのはむしろ、淡々とした日々の生活のような創作活動であった。
■はにかみやの神童
どこかで一度は目にしたことがある、彼の肖像画は、そのはにかんだほほえみの中にナイーブな内面をのぞかせている。ふくよかな顔、柔らかそうな巻き毛、結ばれた口元には芯の強さもうかがえる。
後世、「歌曲の王」と冠された、しかし生前は、ごく一部の人たちの中での名声にとどまったフランツ・ペーター・シューベルトは、父、テオドールと、母、エリザベートの第12子として1797年ウィーン郊外に生まれた。当時のウィーンは、イタリアオペラ、特にロッシーニの全盛期だった。シューベルト家のならいで、6歳で父の経営する学校に入学したフランツは、父にヴァイオリン、長兄イグナーツにピアノを習う。彼の音楽に対しての特別な才能を見抜いた父は、翌年には、教会オルガニストのホルファーにオルガン、声楽、和声法を習わせた。ホルファーをして「彼は私が何か教えようとしてもすでに知っていた」と言わしめた早熟の天才は、その後、11歳で、コンヴィクト※に入学を許可された。
ここで、宮廷楽長サリエーリの指導も受ける。その栄誉に心躍らせたのも束の間、イタリアの曲に重きを置き、ドイツの作曲家のことを評価していないサリエーリとの個人授業に、フランツは、だんだん苦痛を感じるようになる。彼は、ハイドンや、モーツアルト、ベートーヴェンに心酔していたのだ。
■才能と経済的困窮と
そのころから、時間を見ては作曲をしていた。残念ながら、それらの作品は残っていないが、13歳には、現存する最初の曲を書いている。コンヴィクトの学生オーケストラでは、第1ヴァイオリン首席奏者にも抜擢され、音楽的に、どんどん開花しようとしていた時期であった。しかし、ここでのフランツは、必ずしも幸せではなかった。家からの仕送りも少なく、「せめて、おやつに小さなパンか、りんごのひとかけを食べられたら、どんなにうれしいか。」と金の無心のための手紙を、兄に送ったほどである。
幼いころから息子の音楽的な才能を認めた父テオドールであったが、彼は息子に、自分の経営する学校で助教師として勤めることを希望し、作曲家となることをよしとしなかった。1789年のフランス革命以降、ウィーンも二度、革命フランス軍に占領され、社会不安やひどいインフレに悩まされていた。音楽家を支えていた裕福な貴族たちも、資産を失うものが多く、そんな社会情勢の中、作曲家を目指すよりは、当時社会的評価の高かった教師の道を考えるほうが、賢明な選択だったのだ。
父の経営する学校は貧しい家庭からは授業料をとらないことなどで評判を呼び、多くの生徒が集ったが、経営状況は厳しく、自分の息子たちが助教師として学校で教えることでその状況を軽減しようともしていた。
幼いころから神童ぶりを発揮していたフランツだったが、モーツアルトの父のように、それを熱心に世の中に知らしめようとする人や、メンデルスゾーン家のような経済力が彼のまわりにはなかった。
※コンヴィクト
帝室王立寄宿制学校。宮廷合唱隊(現在のウィーン少年合唱団)員はこの学校の給費生徒だった。教育程度は大変高く、有能な官吏や芸術家を輩出した。ウィーンで最も権威のある学校であった。
■あふれ出る音楽を譜面に
コンヴィクトを退学して、師範学校に入学した後、父の学校の助教師となったフランツだったが、子どもたち相手の授業に集中できず、思い立ったら授業中でも作曲をしている有様であった。
どんどんあふれ出てくる音楽を譜面に書き留め、しかし、その扱いには鷹揚であり、書いた曲をほしがるものがあれば気軽に与えたり、友人に貸した楽譜がそのままになっていたり、仲間から仲間へとまわって最後になくなったりしても気に留めなかった。
この間、「糸を紡ぐグレートヒェン」「野ばら」「魔王」といった歌曲や、「交響曲第2番」「交響曲第3番」を作曲する。歌曲を、敬愛していたゲーテに送るも、評価されず送り返されてしまうというつらい出来事はあったものの、その歌曲が世に出るようになり、「シューベルティアーデ」という彼の心酔者たちによるサロンができた。そういった内輪の人々の中で、自作を披露し、演奏するという生活が彼にとって、居心地のよい世界となった。
その後、多くの曲を怒涛のように作曲し、そして心酔していたベートーヴェンの今際の際に面会かない、しかし自身も、その1年後、31歳の若さでこの世を去ることになる。
シューベルティアーデ
■なぜ未完成?
今日演奏する交響曲は、完成されたスコアが第1、第2楽章しかないため「未完成交響曲」と呼ばれて いる。第3楽章以降は最初の9小節だけがオーケストレーションされ、残りはピアノ譜の下書きがあるのみ。この天から降ってきたような曲がなぜ完成されずに終わったのか、多くの人が様々な憶測をしている。
この曲は、25歳(1822年)のときに、オペラ「アルフォンソとエストレラ」を完成させた後、一気に書かれたもので、ほとんど直しの跡がないという。その作曲のスピードも驚くばかりなのだが、この曲がすでに頭の中に出来上がっていてそれを紙面に落としただけに思えるのも、まるで、神のほほえみのもと、インスピレーションを得たかのようだ。
作曲の翌年、1823年にシュタイエルマルクの音楽協会から名誉会員に推薦してもらったそのお礼にと、同協会の役員だったアンゼルム・ヒュッテンブレンナーに、この2楽章を送った。しかし、彼は後で残りの楽章が届くものと思い、協会に引き渡すことをせず、そのうちこの自筆譜の存在は忘れ去られてしまい、1865年5月にウィーンの指揮者ヨハン・ヘルベックが発見し、同年12月に初演するまでの43年間、世に知られずにいた。
なぜ未完成のままだったのか、については以下のような説がある。
・最初の2楽章までがあまりに美しく、まとまりがあったので、書きかけたスケルツォが先行楽章ほどの質の高さを持っていないことに気づき断念した。(ハンス・ガルの仮説)
・スケルツォのトリオ主題が、ベートーヴェンの交響曲第2番のそれに酷似していることに気づき、中断した。(マーティン・チューシッドの仮説)
・この曲に着手したころ悩まされ始めた難病を思い出させるので、この曲に嫌悪感を抱くようになった。(チャールズ・オズボーンの仮説)
・当時「H管」の金管が存在しなかったため、「ロ短調」の交響曲の完成が困難であることに気づき、作曲の継続を放棄した。(ブライアン・ニューボールドの仮説)
・当時、多くの曲を書き、未完成のままにしている作品も多いフランツにとって、この曲も多くのうちの一つ。そのうちに書こうと思っているうちにそのままになってしまった。
・第1、第2楽章ともに、3分の1拍子で、次の3楽章も同じ3分の1拍子に、困難を感じた。
・より高い収入につながりそうだったピアノ曲「さすらい人幻想曲」を書きあげるためにこの曲の完成を放棄した。
もちろん、今となっては、どれと判ずることはできないが、「未完成」であることで、より高い「完成」を見た稀有な作品の例だと思える。
■曲について
第1楽章:アレグロ・モデラート ロ短調 不安な心を表すかのような低弦の序奏の動機(H-Cis-D)で始まり、ヴァイオリンによるさざ波のような律動に乗ったオーボエとクラリネットの憂いに満ちた主要主題に発展する。第2主題は、ト長調でチェロが朗々と奏でる。当時珍しいロ短調でかかれたこの曲は、運命に抗しきれない人間の悲劇を描いているように感じる。
第2楽章:アンダンテ・コン・モト ホ長調
コントラバスのピチカート下降音階の導入後、ヴァイオリンに天上から降りてきたかのような旋律が奏でられる。ホ長調の明るさのなかに、苦痛、不安が顔をのぞかせる曲調である。転調の妙味、木管により奏でられる旋律の美しさに特徴がある。
■8番それとも7番?
さて、このロ短調の交響曲、私自身、高校生の時に演奏をしたのだが、その時は第8番であった。シューベルトの交響曲については、番号が変わっていて不思議に思う人も多い。その理由は、未完の作品が多いこと、作曲されたのは確実だが、現在行方知れずになっている作品があること、のちの指揮者が補作を行い、補作版にも番号が与えられて出版されていること、などにより整理が難しくなっているからだそうだ。
■ロ音を主音として
演奏する立場として、この緊密な構成、人々に愛され続けている旋律に身を置けることに幸せを感じる。また、ロ音を主音にして短調の曲を書いたシューベルトに、この世を超えた先を見ていたのか、死の世界を意識していたのか、神の申し子として作曲したのか、と思いを馳せる。
フランツ・シューベルトにとっては、普段通りの生活、作曲が、すでに天啓そのものであったのかも しれない。
参考文献
『作曲家別名曲解説ライブラリー シューベルト』音楽之友社
『作曲家◎人と作品シリーズ シューベルト』村田千尋著 音楽之友社
『シューベルト』バリー・カーソン・ターナー著橘高弓枝訳 偕成社
『シューベルトとウィーンの音楽家たち』青島広志著 学習研究社
シューベルト! http://schubertiade.info/(最新アクセス2010年3月8日)
初 演:1865年12月17日ヨハン・フォン・ヘルベック指揮 ウィーン楽友協会ホール
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、弦5部
ウェーバー:歌劇「オベロン」序曲
「魔弾の射手」や「舞踏への勧誘」で有名なカルル・マリア・フォン・ウェーバーは、1786年ドイツのオイティンに生まれた。
フォン(Von)が付いている家名からも分かるように、彼の家は貴族(男爵)であった。彼の父親は職業に永続性がなく、将校、役人、指揮者と職を変え、ウェーバーの生まれた翌年には劇団を結成する。そのため彼は幼い頃からドイツ、オーストリア全土を回ることとなる。
幼少より劇に親しんだウェーバーはオペラ作品へ飛躍する基礎を着実に培っていった。
特筆すべき事は、父方の従姉妹にあたる人がコンスタンツェ、つまりモーツァルト夫人であったのである。音楽家でもあった父親が、自分の子供を義従兄弟のモーツァルトのような音楽家に育てようと夢見た事は想像に難くない。(ウェーバーの生まれた年―1786年、モーツァルトは30歳で、「フィガロの結婚」を初演している。)
そのような環境のもとでウェーバーは9歳より正式な音楽教育を受け、18歳でブレスラウの歌劇場の 指揮者に就任する。その後プラハ歌劇場の芸術監督を務め、31歳でザクセン宮廷の楽長に任命され、ドレスデン歌劇場を本拠地とする事となる。
当時宮廷ではオペラというと、イタリアオペラが主流で、ドイツものは陰をひそめていた。そこでウェーバーはモーツァルトのドイツオペラ(「魔笛」が代表的)の手法を継承し、本格的なドイツオペラを書きあげた。それが彼の35歳の時に大成功をおさめた作品「魔弾の射手」である。
ウェーバーは若い時に2曲の交響曲を書いているが、もともと交響曲には固執しなかったようで、専らオペラの分野で活躍をしていた。
彼は、時代的に見ると古典派の時代に生きた作曲家だが、劇的・叙事的表現を画期的に進歩させ、ロマン派音楽の門を開き、又「交響詩」という新しいジャンルの方向へ導いていった作曲家であり「ロマン派の先駆け」に位置している。豊かなインスピレーションからくる〔大胆な和声法〕と斬新さを持ちながら〔気品あるメロディー〕を兼ね備えている。
それゆえウェーバーのメロディーは一度聴いたら人の心を離さない魅惑的なものが多い。
又、ウェーバーは当時まれにみるピアノの名手でもあり、オペラだけでなく優れたピアノ作品を数多く残していることも加えておかねばならない。
本日演奏する序曲「オベロン」は、ウェーバーが40歳の時の作品である。この時彼は結核を患っていて、この曲が絶筆の作品となる。
オペラ「オベロン」(または妖精の王の誓い)
「オベロン」は1826年、ロンドンのコヴェントガーデン歌劇場から依頼されたオペラで、台本はすべて英語によるものであった。ウェーバーは自らの死期を悟り、異例の速さで曲を書き上げた。そして病苦を押して渡英し、自身の手による指揮で大成功を収めた。
台本はシェークスピアの「真夏の夜の夢」と「テンペスト」をあしらったもので、この台本の基となったものは、ウィリアム・サザビーの翻訳したウィーラントの叙事詩「オベロン」である。そのため、おとぎ話のような雰囲気を出しつつ、さらに東洋のエキゾチックさを織り交ぜながら、幻想的な音楽に仕上げられている。
ウェーバーの指揮した初演は大絶賛を博したが、今日では台本が支離滅裂と評されていて、オペラとして上演されることはほとんどなく、序曲は管弦楽曲の傑作としてしばしば演奏されている。
この序曲は、オペラに登場する人物達の様々なテーマを盛り込んでいる。イメージし易くするため、あらすじを簡潔にまとめると、次のようになる。
紀元800年頃、妖精の国が舞台である。
妖精の王、オベロンは王妃ティタニアと「真実の愛」について夫婦喧嘩をしてしまう。そして「どのような困難にも負けずに愛し合う男女を見るまでは、仲直りをしない」と決めてしまう。オベロンはそのカップルに騎士ヒュオンとバクダッドの女王レツィアを選ぶ。二人はオベロンの魔法により相思相愛になり、様々な困難を乗り越えて最後に結ばれ、オベロンとティタニアもめでたく仲直りする。
Adagio sostenutoの序奏は20小節あまりの短さであるが、魔法の世界の不思議さ、妖精の情景を次のように表現している。すなわち、魔法の角笛(第一ホルン)で呼び掛ける妖精の王オベロン。妖精達が眠りから覚め(弱音器をつけたヴァイオリン)、ひそやかに答える。6小節目で、木管(フルート、クラリネットのppp)のスタッカートの音型が、風にふわりと舞う妖精達の群を思わせる。続いて行進曲風に奏され、やがて突如全ての楽器の強奏和音が鳴ったかと思うと瞬時に幻が消えたかのように沈黙があり主部へ。
主部はAllegro con brioニ長調。4/4ソナタ形式。
騎士ヒュオンの様子を表すような第一主題は、第一ヴァイオリンの16分音符のパッセージで勢い良く発展していく。急に魔法の角笛が鳴り妖精達が飛び交う。
続いてヒュオンのアリアのテーマがクラリネット独奏で現れる。
さらにレツィア「わが君、わがヒュオン」のテーマが歓呼するように奏される。
参考文献
『名曲事典』音楽之友社
『新音楽辞典』音楽之友社
『モーツァルトとコンスタンツェ』
フランシス・カー著 音楽之友社
『世界音楽名盤集7』コロムビア洋鑑賞協会(編)
初 演:1826年4月12日 作曲者指揮 ロンドン・コヴェント・ガーデン歌劇場
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、 ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、 弦5部
未完なるもの -シューベルトの交響曲の軌跡-
以下は前回『未完成』を取上げた第168回定期演奏会に向け、1998年9月発行の維持会ニュースに掲載された小文です。
『未完成』は作曲者の最後の作品--所謂(いわゆる)絶筆ではない。何らかの意図をもった中断と捉えなければならないが、それに至った事情は一切が不明である。その理由は今や推測の域を出ないが、中断がこの作品にもたらした価値は明確である。創造の一環として敢えて採られる未完と云う行為を考えてみたい。
■空白の断章
『源氏物語』「幻」の巻は、この前年最愛の紫の上を喪った主人公光源氏の最晩年の日々を描く。翌年に出家を考える彼は世俗の人として送る最後の年の暮れ、暗示的な一首を詠む。最後に明くる年の様子が数行ごく簡単に触れられ、この深い嘆息に満ちた巻は終わる。1巻おいて「匂宮(におうのみや)」の劈頭(へきとう)では「光かくれたまひしのち・・・・」と源氏の死後の事である旨が語られ、更に読み進むに連れて彼と同世代の関係者は大半が死んでいる事が明らかになってくる。算定してみると「幻」と「匂宮」との間には8年間の空白の期間があり、源氏はその間に死を迎えた事が後に会話の中に語られる。出家から死に至る部分の空白を埋めるべき巻は「雲隠(くもがくれ)」と名付けられている。ところがこの巻は名前だけ伝えられて本文が無い。古来この事は様々な説を生みだしてきた。
今ここにその諸説と論点を挙げて紹介する余裕は無いが、要するに根本はその巻の実在性に対する疑問である。時代が下って本居宣長が著書『源氏物語玉(たま)の小櫛(をぐし)』でその巻の存在そのものを否定して以来、現在では後世巻名のみが挿入されたとする説が有力である。学説とは味気ないものだ。しかし「雲隠」は確認し得る限り既に平安時代の末期(12世紀中頃)には知られていた事実もあり、僕個人はこの巻が物語の成立当初から存在し、その時点で既に本文を欠いていたと想像したい。
長大な「若菜」の巻を頂点として、その後は巻が進むに連れて物語は下り坂に入ってゆく。読む人はやがて来るであろう主人公の死を予感する。前述の「幻」で主人公は亡き紫の上の手紙を全て焼く。彼の魂はすでに限りなく死者に近い。そして「雲隠」の巻を経て「匂宮」。ここでその間に起こった事の断片が次第に判明する。だがその細部は「雲隠」の空白に象徴的に表されるのみで永遠にわからない。確かに、この巻が無くとも物語の展開に無理はない。だが、場面の転換の妙味を引き出す上でこれほどの効果的な手法を他に知らない。これは模倣しても何ら意味のない、まさに1回限りの方法である。
更に、当初は本文があったのかも知れないという想像にも駆り立てられる。その上で最終的に作者自身が本文を削り、巻名のみを残した。1巻が文字通り1つの巻子或いは冊子として伝えられてきた時代、同一の装幀でありながら中身が白紙の巻。僕はこの何も書かれていない1巻の存在を幾度となく想像しては、密かに心の戦慄を感じている。敢えて無言と空白に帰する創造の在り方をこれほど実感させてくれる例はなかなか見当たらない。
■『未完成』の周辺-錯誤の軌跡-
『未完成』に於いてシューベルトが第3楽章以降を放擲(ほうてき)した姿勢と結果としての効果とを、上の事象に僕はかねてより重ねて考えていた。ただここで注意すべきことがある。こと交響曲について言えば、この作曲者にとって創造の中断はそれ程特別なことではないという点だ。1813年(16歳)以来彼は全部で13曲の交響曲を書いたが、4楽章までオーケストレーションの調った「五体満足」な作品は7曲しかない。シューベルトの交響曲創作の足跡を『未完成』前後に焦点を絞って年代順にまとめると以下のようになる(*印は未完結作品を示す)。
1818年 交響曲ハ長調(第6)『小ハ長調』
1818年 *交響曲ニ長調(スケッチのみ2楽章)
1821年 *交響曲ホ長調D729(スケッチを含む4楽章)
1822年 *交響曲ロ短調(第7)『未完成』(2楽章 第3楽章はスケッチのみ)
1828年?*交響曲ニ長調(スケッチのみ3楽章)
1828年 交響曲ハ長調(第8)『グレート』
上記のうち、D729の作品番号を持つホ長調の交響曲は20世紀に入り、ヴァインガルトナーの補筆により完成している。かつてはこの曲を「第7番」とし、8番を『未完成』9番を『グレート』とする数え方があった。『未完成』を第8番と記憶されている方々は、この時代の反映である。(注)新響も前回1998年に『未完成』を取上げた際は、これを「第8番」としている。
ところで、こうしてみれば1818年の第6交響曲から第8番の『グレート』までに10年の時間が経過し、しかもその間に数多の未完に終わった交響曲が創られていた事に改めて驚かざるを得まい。31年という作曲者の生涯を考えれば、この10年間が如何に長い時間であるかは理解されよう。これが何を意味するのか。第6番には既に『グレート』への萌芽が見られる。その飛躍の為の助走の期間と考えるべきなのか?或いはさしもの早熟な天才もこの時期挫折し、錯誤の中で時を浪費していたのだろうか?
そこで『未完成』の事だ。この作品の成立に関して今日我々が知り得ることは極めて僅かである。 1822年の7月に彼は後世の我々にとって貴重な、ある文章を書いている。9月、3年の時間を費やした『ミサ曲変イ長調』(D678)を完成させる。翌月末の10月30日からロ短調交響曲の総譜を書き始めた(と云う事は既にスケッチは出来ていたのだろう)。12月以降彼は病床に就き、翌年の春までは創作活動に専念できる状態ではなくなった。
1823年4月に彼はグラーツに設立されたシュタイアーマルク協会の名誉会員に選ばれた旨の書簡を受け取る。9月20日付けで作曲家は「返礼」として自作の交響曲の中から1曲の総譜を贈る旨を書き送った。そして明くる1824年(この年の5月にベートーヴェンの『第9』が初演されていることには注目すべきだろう)になって送付された交響曲が、第2楽章まで完成したロ短調の作品だ。ここまでは確かな事である。
だがここからは推測する他はない。この間の協会側と作曲者とのやり取りも今となっては知りようがないが、受け取った側はこの作品を未完結なものと考えたのかも知れないという事は想像できる。そうでなければ『未完成』が1860年に「発見」されるまで沈黙を余儀なくされる結果を生んだと云う事実とつながりようがない。その後シューベルトは1827年にグラーツの協会を訪ねているが、その際両者間でこの作品の事について取り沙汰された様子もない。不可解この上ないが、この時何らかの話題になっていれば、この作品は別の道を確実に歩んだ筈である。その唯一の好機は永遠に去ってしまった。
■失われた楽章-創造的未完-
シューベルトの残した数少ない文章のうち、1822年7月の日付をもつ最も著名な自叙伝的短文<Mein Traum-僕の夢->は、同時期に書き始められたであろうロ短調の交響曲との関係を考える上で、重要な示唆に富んでいる。
・・・・・・・長い年月、僕は歌を歌った。愛を歌おうとした時、愛は苦しみになった。そして苦しみを歌おうとすると苦しみが今度は愛になるのだった。愛と苦しみとは、こうして僕を2つに裂いた。・・・・・
これは奇跡である。『未完成』を取り巻く極めて深い霧の中で、作品の底流に流れる作曲者の内面を語る彼自身の言葉が忽然と現れるのだ。実はこの文中にある愛とは精神的に相克する父親に対するそれなのだが、こだわる事もないだろう。この愛憎の交錯とそれに伴って絶え間無くたゆたう哀歓の精神を知れば、それが作品にどれほど緻密に結実しているかに改めて驚くほかあるまい。と言うよりむしろこの感情そのものが既に詩であり、その詩にふさわしい音楽が『未完成』となって顕れたと考えたほうが自然なのかも知れない。これはシューベルトの短い生涯に産みだされた夥(おびただ)しい作品の過半数を占めた歌曲(リート)の世界の次元である。
彼がこの作品を“Sinfonia”と題しながら、第1楽章もそれに続く緩徐楽章も3拍子の音楽にしてしまったのもその一例だろう。詩的な世界と音楽との融合に心を奪われた天才の、天衣無縫とも言うべき所行。だが彼のこの余りに詩的な世界は、荘厳な構築物たる交響曲として扱うには余りに脆弱に過ぎる印象を否めない。何故なら交響曲の形に固執する限り、続く第3楽章としてはスケルツォかメヌエット以外に選択肢はないからだ。またしても3拍子である。3拍子の楽章が3つ続く交響曲は独創には程遠い。事ここに至ってシューベルトも進退窮まったに違いないが、とにかくスケルツォを書き出した。
映画『未完成交響楽(1933年・オーストリア)』はその120小節余りのスケッチ(その内9小節だけはオーケストレーションされている)に基づく音楽を余さず伝え、この楽章が未完結に終わった「ある理由」をテーマとするが、理由はともあれ作曲者の苦渋は歴然としている。もしこのスケルツォをとにかく書き通し、続く最終楽章に長大なフィナーレを完成させ得たとしても、傑作を期待する事は不可能だったろう。そこそこの作品には仕上がったかも知れないが、『グレート』への捨て石に終わった可能性も充分あり得る。
残された道はひとつだ。彼は敢えて2楽章までで中断し、第3楽章は白紙に戻してこれで「完結」と捉えた。彼は強い意志を以ってこれを行なった。他の未完結な交響曲と一線を画すのはまさにこの点である。だからこそグラーツの協会にもスコアを贈った。これが僕の結論だ。期限(というものがあったとして)に間に合わせるために未完結を承知で、出来ている部分だけをとりあえず提出したと云う考えもあろうが、「返礼」として贈呈すべき作品という位置付けを思えばそれは極めて異質な行為に映る。しかもそうした考えが成り立つには、いずれその後の楽章も書くつもりだった=完結が可能だったと云う事が前提になるわけだ。が再度言うが、緩徐楽章を前の楽章に引続き3拍子で書き始めた時点から、この作品はもう一般的な意味での交響曲としては完成の見込みのない形になってしまっているのだ。この先に何を書き加えられたろう。
■同時代人としてのベートーヴェン
「この音楽は2つの楽章であまりにも完成しているので、あえて先を続けなかったのだろう」
とはブラームスのこの作品に対する解釈だ。至言であるが、彼のこの言葉には単なる批評以上の重みがある。「交響曲に於いてベートーヴェンの後で何が出来るか?」というシューベルトの独白に象徴される焦燥を、ブラームスほど切実に感じていた人あるまい。ベートーヴェンという眼前に立ちはだかる崇高な絶壁を、如何に乗り越えるかに腐心する人生を彼らは余儀なくされた。だが、ブラームスにはそれでもまだ救いがある。
シューベルトの場合は、ベートーヴェンより27歳遅れて生まれながら、1年しか長く生きられなかったと云う現実がある。彼が最初の交響曲を書いた1813年にはベートーヴェンは第8交響曲を既に完成させていたが、この偉大すぎる先達は、シューベルトの享年である31歳と云う年齢では『英雄』すら書いていなかった。本来次世代の人として生まれ生きながら、同時代人として死んでゆかざるを得なかった処にシューベルトにとっての悲劇があったかも知れない。比肩する位置を占めるためには時間が足りなすぎた。
技法上の問題とは別に、前述の「愛」をひとつのキイワードとして両者の違いを考えるのも面白いかもしれない。
ベートーヴェンがひとたび「愛」を語るとそれは人類愛に直結し、全世界を相手に回して葛藤と闘争と勝利というドラマトゥルギーを繰り広げ、長大な交響曲が産み出される(先にも述べたが『第9』と『未完成』はほぼ同時期の作品だ)。社会の流れにも敏感であり、感情の振幅と相俟(あいま)って作品に反映された。これは年齢によるものではない。この人は生来「疾風怒濤」の時代精神を体現したような性格の人だった。
同時代に生きたシューベルトの作品にもそうした社会の反映があっただろうか。彼にとっての「愛」は言うなれば家族愛である。よろこびや哀しみもホームドラマの規模だ。そして『未完成』が出来た。どちらの出来がどうのと言う問題ではなく、これは両者の音楽の本質的な違いである。だが交響曲と云う分野にこだわる限り、この差異がシューベルトの眼にはどうしても乗り越えなければならぬ障壁として映った筈である。彼は敢えてそれに挑んだ。煩悶と錯誤が繰り返され、絶えず挫折と隣り合わせであったろう。未完に終わった夥しい交響曲がその証左とも言える。
交響曲の大家に対する畏怖と憧憬は『未完成』の様な性質の音楽でさえ、彼をして交響曲の形式に固執させたのだ。この場合も危うく挫折に終わりかけたが、中断が彼を救った。この中断の効果も1回限りのものだ。この限られた手段を、彼の作品中でも異例の高い純度と独創と完成度とをもった2つの楽章の後という、最も適切な機会に使い得たことで『未完成』は交響曲として永遠の生命を得られたのである。
1828年3月。1,150小節を超える長大なフィナーレをもつ大交響曲『グレート』が、2年以上の時間をかけて完成した。この瞬間作曲者の脳裏に去来したものは、苦節を乗り越えたとの安堵か。或いは死屍累々たる未完結の作品への愛惜か。いずれにせよ苦悶と錯誤の時代は終わったのである。ベートーヴェンは前年既に他界している。次世代の交響曲作家としての自負も当然あった筈である。
だが畏怖と敬愛の対象であったこの大作曲家の傍らに自身の骸(むくろ)を埋めるまで、彼に残された時間はあと7カ月を切っていた。
大抵の人生は死がもたらす中断により未完結なものに終わる。それを半ば諦念から敢えて「完結」と捉えざるを得ないのが人の宿命だ。『未完成』にともすれば死の影を感じるのは、夭折した作曲者への想いのみならず、我々自身の生の宿命をそこに見るからではあるまいか。
ブルックナー三昧だったあの頃
思えば、貴重でかけがえのない大学時代は、高校3年の時に入部した部活を通してチューバと合唱にのめりこみ、とにかく演奏する楽しみに埋没していた。
音楽部は1922年頃創立、オケと合唱が一緒に活動しており、200名を越える大所帯で当時規模の小さい大学としては歴史と人数を誇るクラブである(学内の文科系部活の合計人数より大きかった)。混声合唱団・大学男声合唱団・大学女声合唱団・短大女声合唱団(現在は女子大合唱団)・管弦楽団があり、混声合唱団は各単声の合唱団が集まって構成されていた。春はオケと合唱が個別に、秋は音楽部としてまとまって演奏会を実施している。
大学3年目の1978年は、なぜかブルックナーの作品を部活以外も含めて3曲続けて演奏する機会に恵まれた。
■交響曲第7番
3年生になると、担当学年制といってクラブの運営を仕切らなければならない。ということは2年生のとき、来年に向けて指揮者とか曲目について学年皆で検討、ということになる。春のオケの演奏会にむけ、オケの同級生(確か13名ほど?)が集まって2年生の秋から役員の人選とともに、どうしようか、と検討が始まった。指揮者は前年初めてこの大学オケを指揮していただいた高関健さんにお願いすることで満場一致したが、我々の中で曲がなかなか決まらない。当時、部員の一部でブルックナーを話題にする雰囲気が多少あった。他の大学オケでも、例えば隣のW大を始めレパートリーとして演奏されることが多くなってきたこと、音楽ファンの間でブルックナーの人気が徐々に浸透して、ちょっとしたブームになってきたこともあるだろう。藝大の院生だった三番目の兄が持っていた交響曲のスコアを何冊か持ち出して、やれハース版だノヴァーク版だ、クナッパーツブッシュだシューリヒトだ、とか、部室や部活の友人の下宿で皆でレコードを聴いたり、スコアを見ていたりしていた。いずれにせよ、ブルックナーをよく知る部員はわずかであった。
とにかくメインだけでも曲を決めるリミットが近づいてきた。同級生には女子学生が多かったせいか、大学キャンパスのすぐ近く、当時目白駅前にあった喫茶店『ルノアール』の個室にて、いろいろなスコアを持ち寄って話をすることになった。時間だけが過ぎていき、時間制限が2時間とかで延長するには何か注文しなきゃいけないと店の人に言われ、各自また何がしか注文して時間いっぱいまで粘った。結局ブルックナーが最後まで話題に上り、とっても難しいけどと、皆でため息つきながら交響曲第7番に決まったことを覚えている。当時現役でオケの団員は60名弱くらいしかおらず、しかも交響曲第4番でなくて、よりによってワグナーチューバがある第7番をなぜ取り上げることになったのか、今もって経緯につきよくわからない。他の有名大学オケでも最近演奏しているから、ワグナーチューバを何とかすれば、みたいな、後は勢いで決まってしまったのだろうか。兄からは、「W大ではワグナーチューバではなくてユーフォニウムでやってたぞ」とか言われ、その話を皆にして、たぶん私も何とかなるだろう、と思っていたかもしれない。
問題はワグナーチューバである。奏者については、人数の少ない大学オケなので、どうせいろいろとエキストラをいれなければならないから何とかなるだろう、という気持ちが皆にあったに違いない。楽器もその勢いでといったところだ。同級生のヴィオラのCさんから、「私と同姓のハトコがN響でホルンを吹いているらしく、会ったことないけど親に連絡先聞いてみようか?」と話があり、「え?もしかしてトップのC先生?ほんと?スゲー!」と皆でその話にとびついたのは当然。話がついたとのことで、私が直接C先生に電話することになった。
おそるおそるC先生に電話すると、話は聴いているよ、楽器あるから家にいらっしゃい、貸してあげる、とのことで、ホルンの先輩たちとお宅に伺った。すごく緊張している私たちを温かく迎えてくださり、ワグナーチューバ4本をその場で吹いてお借りすることができた。先輩たちが悪戦苦闘しながらワグナーチューバを吹いているのを見て「楽しそうだねえ」と、ニコニコされていたことをよく覚えている。(ところでなぜこの楽器がC先生のところにセットであったのか、については話が長くなるので、割愛させていただきたい。)
後日、C先生宅に楽器を返却に伺った時かその後かは覚えていないが、せっかくだから皆で遊びにこない?とのことで、何人かでお酒を持って訪問、C先生からあれこれと酒と食事をご馳走になりながら楽しいお話を伺い、また奥様のH先生も加わって、「こういう楽器もあるのよ」と、初めてツィンバロンに触ってみたりとか、とにかく盛り上がり、結局徹夜で飲み明かした。
そのご縁からか、卒業後もずっとチューバを演奏する機会に恵まれたこともあって、C先生とはお亡くなりになるまで思わぬ場所でお会いする機会が多く、面白いエピソードもある。いずれの機会に記載したい。
さて、前プロもモーツァルトの交響曲第36番『リンツ』で決定。悪戦苦闘の半年にわたる練習の末、1978年5月30日に杉並公会堂で第17回の演奏会を迎えることになった。実はこの年の春にヴィオラに入部した1年生のことでマスコミが大きくとりあげ、3回生で音楽部総務委員長となった私は連日連夜の取材対応に奔走、演奏会直前までホールとか大学を含む関係各位との打ち合わせで多忙を極め、当日は本人がステージに登場するのではとの期待から観客と取材陣が殺到、ホール側と取材側がもめたりして会場の内外で騒然となった(本人は上手だったので、前プロにステージデビュー、上下関係が厳しい音楽部ではあくまでも後輩なので当日は下級生の常として男性の楽屋番を担当)。とにかく満員御礼にて無我夢中のまま、演奏内容はそれなりに、異常な熱気に包まれた演奏会であった。
高関さんはこの後、日本でのカラヤン・コンクールで1位になり、ベルリンへ行かれることになったが、箱崎のターミナルでお見送りがてら皆で押しかけ、ブラームスについてアドヴァイスをもらうとか、今思えば厚かましいことをやったものだ。
■交響曲第9番
この年の春、NHKがバックアップしていたJMJ「青少年音楽祭」、通称ジュネスのオーケストラに参加することになった。これは夏に年1度NHKホールで行なわれて全国放送されるという演奏会で、都内を中心に近郊の大学オケから参加者を募り、オーディションを経て3ヶ月近く毎週日曜日に渋谷のNHKのスタジオにて練習をするのである。オーケストラの曲はブルックナーの交響曲第9番、合唱曲としてラフマニノフの『鐘』、それとマンドリンオーケストラがあり、私はブルックナーに出演することになった。指揮者は山岡重信先生である。当時は各大学オケの名手が揃い、前年にマーラーの『復活』をNHKホールで聴いて、来年は是非とも出たいと思っていたのでエントリーしたのである。そして当時のアマチュアオケではまずとりあげることのない、というかありえない彼岸の響きに満ちた神秘の曲を演奏できるというすばらしいチャンスに恵まれた。
とにかく難しい曲だったが、若さゆえバリバリと怖いものなしで演奏したことを思いだす。思いつくままに当時のメンバーをあげてみると、コンサートマスターはW大のSさん、オーボエの1番はR大のDさん、フルートの2番にW大のM氏、トロンボーンは1番にW大のTさん、2番は前年のマーラーにてすばらしいソロを聞かせてくれたJ大のNさん、3番は大学の先輩Iさん、ホルンの1番はH大のSさん、2番はD大のFさん、3番は大学の先輩Iさん、5番ホルン(ワグナーチューバ1番)はW大のI君、トランペットの1番はH大のNさん、ティンパニーはJ大のSさん・・・などとよく覚えている。
ジュネスに出演したことで、学外での交友関係が一挙に広がり、他の大学オケからエキストラに呼んでいただいていろいろな音楽経験を積むことができたし、その後の金管アンサンブルの結成(現在もこのアンサンブルで活動している)、特にJ大のNさんからは親しく音楽面で教えていただき、後に新響の団員になられたことから新響を紹介され、入団のきっかけを作っていただいた。新響には元団員で当時のメンバーが多かったし、現在も何人かは在籍している。
またこの時のメンバーとは思いがけない所でお会いしたりすることも多い。お互い顔を覚えているもので、例えばティンパニーのSさんとは、10年前に新響が福岡で演奏した時に地元のオケの方と合同演奏したが、打楽器として出演され、20年ぶりに再会、ということもあった。
本番の演奏で印象に残っているのは、第3楽章の終わり。ホ長調のやわらかい響きがホールに残り、指揮者の山岡先生の手がまだ完全に降ろされていないのに、突然「ブラボー!」の声が掛かって、山岡先生がガクっと体を動かされたことを覚えている。
この年の春は、第7番と第9番を一緒に演奏するという、実に貴重な経験をした。今回新響で第9番を演奏するのは、このとき以来であり、練習していると当時のNHKでのスタジオの練習風景はもちろんのこと、NHKの食堂の風景とか、そこで見かけた芸能人の方々とか、いろいろと余計なことまで思い出す。
■『テ・デウム』
秋の音楽部の演奏会に向けて、確か6月から選曲が始まったと思う。秋は管弦楽団と合唱団が一緒になるため、選曲も合唱の担当学年が加わり、大掛かりである。短大の2年生も担当学年として加わっての話し合いが続く。指揮者は音楽部の常任指揮者でいらした前田幸市郎先生であり、とにかく演奏会のメインとなる曲がブルックナーの『テ・デウム』になった。ブルックナー晩年の作品で神に捧げられた大曲である。演奏時間は25分くらいの曲だが、ブルックナーの宗教曲の中でも最高傑作のひとつであり、とても力強くオルガン的な響きがする。合唱がこれまた大変で音域が広く、ソプラノやテナーには音がめちゃくちゃに高いところがあり、バスやアルトも低い音があって、とにかく難しい。なんでこの曲に決まったのかこれまたよく覚えていない。それにしても合唱もオケもチャレンジである。たぶん指揮者の前田先生が宗教音楽に造詣が深く、ブルックナーの三大ミサ曲を本邦初演されたことと、春に演奏した交響曲第7番の第2楽章アダージョと同様の音型があることが、刺激となった要因のひとつかもしれない。オケの学生指揮者と合唱の学生指揮者が、本当に合唱できるのか?そういうオケはどうなのよ?とお互いにやりあい、侃侃(かんかん)諤諤(がくがく)だった。
当時、合唱はオケより人数が少なく、大音量のオケに打ち勝つためにも必死だった。ブルックナー特有の金管の強烈なユニゾンとハーモニーでどうしてもオケの音量はでかく、オルガンも入る大規模な讃歌でソロも4人必要だ。オケと合唱の合同練習の時、合唱のテノールで同期のやつなんか、譜面台を前に置いて、「とにかく吼えるぞ!」と身構えているくらいである。
私は、特にバス・パートを集めるために合唱団のOBに個別に出演を依頼したり、合唱とは前田先生の関係で親しかった東大の男声合唱団にも声をかけたりと人集めに奔走した。
オケの先輩で合唱でもよくバス・パートを歌っておられた大学院生のK先輩は声がとても低く、ヘ音記号で五線から下の声がよくでるので、合唱の静かなアカペラの部分に登場する低いDの音のため、この曲に限ってはオケでなく合唱に出てください、と懇願した。ソロは高校の合唱部の先輩で(高校は大学と同じ敷地にある)大学に進まれたあと、藝大の大学院に入学されたテノールのH先輩に頼み込み、先輩のソロはもちろん、他の3名については同じ院生の仲間でお願いすることになった。
オケの前プロが、ベートーヴェンの序曲『フィデリオ』とブラームス交響曲第4番である。新響でも考え付かない?何かすごいプログラムになった。実は『テ・デウム』の弦楽器は、延々とユニゾンでド・ソ・ソ・ド、ド・ソ・ソ・ドと、労多くして何とか、といった感もあり、弦楽器が納得するプログラムでこうなったかもしれない。とにかく練習するしかない。第22回の音楽部としての演奏会は1978年11月14日、学校に新しくできたばかりの創立百周年記念会館の「正堂」と名づけられたホールで行うことになった。客席は補助いすをいれても1400にも満たないが、ステージが大きく響きも良い。何しろ初めてのできたばかりのホールの演奏会、山台の設置や照明の操作を全て自分たちでやらなければならない。
そして春に話題になった1年生のご両親がお見えになるとのことで、これまた演奏会直前まで大学や関係各所との打ち合わせで多忙を極めた。自分の出番は『テ・デウム』のチューバのみだが、この演奏のためにF管のチューバを手に入れたこともあり、その楽器で初めての演奏だったのでそれだけでも興奮している。そして本番当日、とにかく無我夢中でホール内を走り回っていた。とにかくばたばたして落ち着きなく動き回っていたので、副部長の先生達から、「君はもっとどっしりと構えていなさい」と注意を受けたことを思い出す。休憩時間の時に、ホール内の貴賓室に前田先生と一緒に伺い、来賓へのご挨拶の際、音楽の持つ素晴らしさについて滔々としゃべる自分に対して、何であの時にこんなことしゃべったのだろう、と後悔したりしたものだ。
休憩の後、いよいよ『テ・デウム』である。満席の客席で演奏が始まった。すさまじい音量と気合の入った壮大な響き。合唱もがんばって張り叫んでいる。自分自身も異常に興奮している。終曲の圧倒的な二重フーガを経て、例の第7番のアダージョと同様の音型で盛り上がるコラール風のところで、ふっと客席を見たら、なんと1Fの後ろにあのC先生が立っておられるではないか!ドア係の1年生がC先生に気がつき、既に満席でありもしない座席の方へ誘導しようとしていたが、いいよと手を振っておられる。すごく驚いたのと同時に、曲のボルテージがあがるにつれとても嬉しくなり、感動で涙が溢れそうになった。演奏会の前にC先生には招待状を発送していたが、わざわざいらしてくださったのである。
終演後、ステージで後輩たちに後片付けを指示していたら、C先生がステージにひょっこりといらして、ニコニコしながら、「今日は暇だったから新しいホールの見学に来てみたんだ、ところで指揮者の前田先生とはY大学にてお付き合いがあってねえ、さっき挨拶にいってきたよ、それにしてもいいホールだねえ」とのこと。思わず、「ありがとうございました!」と大声で最敬礼した。
その晩は、目白の喫茶店でのレセプションの後、とにかく飲み歩いて徹夜し、早朝に学校の部室に行って昨日の録音テープを、ボーっとしながら何回も聴いていた。
こうして、ブルックナーの傑作にどっぷりと浸った1年は終わった。
第209回演奏会ローテーション
| ウェーバー | シューベルト | ブルックナー | |
| フルート1st | 藤井 | 兼子 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 藤井 | 丸尾 |
| 3rd | - | - | 丸尾 |
| オーボエ1st | 山口 | 堀内 | 亀井淳 |
| 2nd | 桜井 | 横田 | 亀井優 | 3rd | - | - | 岩城 |
| クラリネット1st | 中條 | 品田 | 高梨 |
| 2nd | 石綿 | 大藪 | 進藤 |
| 3rd | - | - | 末村 |
| ファゴット1st | 長谷川 | 浦 | 田川 |
| 2nd | 田川 | 田川 | 長谷川 |
| 3rd | - | - | 浦 |
| ホルン1st | 鵜飼 | 大内 | 箭田 |
| 2nd | 市川 | 比護 | 大内 |
| 3rd | 園原 | - | 大原 |
| 4th | 大原 | - | 鵜飼 |
| 5th | - | - | 山口 |
| 6th | - | - | 園原 |
| 7th | - | - | 比護 |
| 8th | - | - | 市川 |
| トランペット1st | 小出 | 小出 | 野崎(アシ小出) |
| 2nd | 北村 | 北村 | 倉田 |
| 3rd | - | - | 青木 |
| トロンボーン1st | 志村 | 志村 | 牧 |
| 2nd | 牧 | 小倉 | 小倉 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 大内 |
| テューバ | - | - | 土田 |
| ティンパニ | 浦辺 | 今尾 | 桑形 |
| 1stヴァイオリン | 堀内(長沼) | 堀内(長沼) | 前田(田川) |
| 2ndヴァイオリン | 小松(大隈) | 小松(大隈) | 大隈(小松) |
| ヴィオラ | 石井(柳澤 | 石井(柳澤) | 柳澤(石井) |
| チェロ | 柳部容(光野) | 柳部容(光野) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 中野(植木) | 中野(植木) | 中野(植木) |
第209回演奏会のご案内
飯守泰次郎 ~ ドイツの響き
飯守は2つのプロオケの常任指揮者を務める日本を代表するマエストロです。様々な賞を受賞するなど社会的にもその活躍が認められており、円熟したタクトから出される「何か」がオーケストラをひとつの有機体にし音に命を与えます。新響は1993年以来、年に1~2回のペースで共演しその音楽に魅せられてきてました。ドイツでの活動歴が長い飯守との2年ぶりの共演となる今回のプログラムには、ドイツ・オーストリアのロマン派の名曲をそろえました。
特にブルックナーは初共演で交響曲第4番を演奏し、その後第8番、第7番、第8番と共に演奏してきた大切なレパートリーであり、いよいよ「とっておき」の第9番を取り上げます。
ブルックナー ~ 神に捧げられた第9番
オーストリア・リンツ近郊に生まれたブルックナーは、修道院に学んだ後、教師をしながら研鑽を積み、オルガン奏者として大成します。並行して38歳まで作曲のレッスンを受け続け、教会のための作品の数々を残す一方でオルガンの響きを連想させる壮大な交響曲を書きました。44歳でウィーン音楽院教授となり、60歳で交響曲第7番の成功によりようやく認められた遅咲きの作曲家でした。
交響曲第9番はブルックナー最後の作品です。62歳から書き始められましたが、直前に完成した第8番や過去の作品の改訂に手間取り、本格的に作曲に取り組む頃には病気で体調が悪化、70歳の時ようやく第3楽章まで完成します。その前年に遺言書を作成しているのに加え、「生からの別れ」と自ら呼んだテーマが第3楽章に登場するなど、迫り来る死が確実に意識されています。72歳で亡くなる日の朝まで最終楽章の作曲を続けましたが、未完に終わりました。
残された資料から第4楽章の補作が試みられたり『テ・デウム』が代用されることもありますが、完成している3つの楽章で内容の充実したひとつの作品となっており、美しく神々しいアダージョで静かに終わります。
『未完成交響曲』と言えばシューベルト
シューベルトの交響曲第7番『未完成』は、親しみやすく美しい旋律の有名曲で、ご存じの方も多いでしょう。
ウィーンに生まれたシューベルトは、13歳で作曲活動を開始、19歳で自作が出版され作曲料を得るようになりました。26歳の時にシュタイアーマルク音楽協会の名誉会員に推薦されたお礼として贈ったのが第2楽章までの第7番でした。しかしこの曲はその後発表されることなく、シューベルトは31歳の若さで病気で亡くなります。楽譜が発見され初演されたのは、作曲者の死後37年も経ってからでした。
未完のまま次の第8番「グレート」が作曲されていますから、絶筆でありません。なぜ未完のまま放置されたのか理由は諸説ありますが、完成された第1、第2楽章だけでも十分に存在感があり、残された第3楽章のスケッチを見る限り、素晴らしい2つの楽章に釣り合う続きを書くのが困難になったのかもしれません。
2つの未完成交響曲。創造の過程も未完に終わった事情も全く異なりますが、どちらも美しく感動的な傑作です。飯守+新響の演奏に、どうぞご期待下さい。
特別インタビュー 曽我大介氏にきく
今回、新交響楽団と初共演となる曽我大介氏。曽我氏が指揮者になるまでの意外なエピソードと今回のプログラムにまつわるお話をしていただきました。
―ルーマニアでの活動が長いそうですね
曽我 もともとルーマニアに留学していましたからね。先日(11月)も国際交流基金の助成を受けて、デビュー20周年ツアーに行ってきました。よく勘違いされるのですが、僕が卒業したのはルーマニア国立音楽大学で、桐朋学園大学は卒業していないのですよ(笑)。卒業論文はルーマニア語で書きました。そもそも指揮科ではなく、コントラバス科で勉強をしていました。桐朋の3年生が終わるときに休学して、ルーマニア国立音楽大学に編入したのです。本当は桐朋に復帰するつもりだったのですが、そのままフェードアウトしちゃった。ちなみに留学のきっかけは、桐朋で師事していた先生に、「ルーマニアに素晴らしい先生がいらっしゃるからぜひ行ってみなさい」と勧められたからです。当時ブカレストにはイオン・ケプテア教授というコントラバスの世界的権威がいらっしゃって、彼の教え子達は優秀なコントラバス奏者として世界中に広がっていたのです。ちょうど先日のツアー中に、この先生の80歳記念演奏会を振ってきました。ブカレストにあるアテネ音楽堂という、日本でいうサントリーホールにあたるようなホールで行われ、ドイツやアメリカで音楽教授をしているかつての教え子が、なんとハイドンの「チェロ協奏曲第1番」とチャイコフスキーの「ロココの主題による変奏曲」をコントラバスで技術的にも音楽的にも完璧に演奏しました。ちなみに後半は総勢34名のコントラバスオーケストラによる演奏で、この日のために僕が書き下ろした編曲もの3曲とオリジナル1曲の計4曲のステージでした。
―作曲もなさるのですか?
曽我 そもそも指揮科にいたら、作曲の勉強は必要ですからね。近年頻繁に作曲をするようになり、演 奏家の視点のみならず、作曲家の視点で演奏する作品がより深く見られるようになりました。特に気づかされたのは、演奏者や聴衆にとって 「曲」とは、“淀みなく作られたもの”と思われがちですが、実際はどの曲にも“継ぎ目”があるんです。例えば、作曲中に来客があったり、休憩を取ったりするたびに作曲の作業が物理的に中断されているわ けですからね。
―どのようなきっかけで指揮者になられたのです か?
曽我 先ほども申し上げましたが、もともと指揮者を目指してはいなかったんですよ。ルーマニアで魔が差しちゃったのです(笑)。ルーマニアでちょっとだけ指揮を習ってみて、卒業する年に“間違って” デビューする機会があって、音楽院のオーケストラを振ってみたら「いいんじゃないの」と認めてくれる人達がいたのです。ちなみに最初に振ったのは、ものすごく渋いプログラムで、ワーグナーの「ジークフリート牧歌」、シュターミッツの「ヴィオラ協奏曲」、ベートーヴェンの「交響曲第4番」でした。それからどんどんプロのオーケストラを振るようになって…。ここで魔が差さなければ、今頃コントラバス奏者になっていたでしょうね。桐朋で同期の池松さん(ニュージーランド響首席コントラバス奏者・元N響首席)は指揮をやりたくて、僕はコントラバスをやりたくて音大に入ったのだけど、結果的に選んだものは逆になってしまいましたね(笑)。
ルーマニアに2年半留学した後は、ウィーン音楽大学の指揮科に進みました。ウィーンでは2年間勉 強したのですが、その間にもイタリアにあるシエナ・キジアーナ音楽院の夏期講習会にも参加しました。いろいろなコンクールやタングルウッドを始めとする世界中の音楽祭にも参加して。とにかくあちこちで勉強していましたね。
―先生と関わりの深いタングルウッドでの思い出をお聞かせください。
曽我 今回のプログラム(バーンスタインとバルトーク)の発端は、まさにタングルウッドの絡みです。タングルウッド音楽センターはいわばコンクールのようなもので、まずボストンでオーディションを受 けなくてはいけません。そこで特待生として選ばれて、2ヶ月間タングルウッドに滞在しましたが、休みはたったの一日だけ。とにかく毎日音楽漬けの日々でしたが、音楽にも自然にも恵まれた素晴らしい環境でしたよ。そもそもタングルウッドにしろボストン交響楽団にしろ、“歴史”を作ったのはシャルル・ミュンシュであり、クーセヴィツキーであり、小澤先生ですが、“伝説”を残したのはバーンスタインです。タングルウッドの地に立ったとき、そこら中にバーンスタインの息吹が残っていました。僕たち指揮科の学生はクーセヴィツキーの住んでいた家でレッスンを受けるんです。丘の上からタングルウッド湖が見渡せて、ものすごく眺めの良いところでした。そこにはゲストブックが置いてあって、若き日のバーンスタインや小澤先生の写真が置いてありました。バーンスタインはクーセヴィツキーの影響を受けて指揮者を目指し、彼のアシスタントを経て、初期のキャリアを積みました。その地がまさにこのタングルウッドです。バーンスタインとタングルウッドは切り離せないのです。
僕は今まで指揮者として色々な素晴らしい先生に巡り合えて、若いうちからたくさん良い経験をさせ てもらいましたが、カラヤンとバーンスタインに師事できなかったことが、とても残念です。もちろん、聴衆という立場では彼等の演奏を何度も聞いていますし、歴史的な演奏会にも足を運んでいます。けれども直接対話できる機会がなかった。あと5年早く生まれていれば、違ったと思います。そういう意味では、一つ上の世代の方たちが本当にうらやましい ですね。
クーセヴィツキーの誕生パーティで、 ケーキの最初のひときれををもらうバーンスタイン(1942年)
―バーンスタインがタングルウッドで活躍したちょうどその頃に、クーセヴィツキーがバルトークに「管弦楽のための協奏曲」を委嘱したのですよね。
曽我 まさに第二次世界大戦のゴタゴタのときですよね。当時アメリカに活動の場を移していたバルトークは白血病を患い、経済的にも支援を必要としていました。クーセヴィツキーは病床のバルトークを見舞い、破格の見舞金をもって依頼。これが命尽きようとしていたバルトークを奮い立たせ、傑作を残 す源になりました。みすず書房から『バルトーク晩年の悲劇』という本が出ていますが、彼の晩年はまさに激動の時代でした。
―バルトークはアメリカに“亡命”したのでしょうか。それとも“移住”だったのでしょうか。
曽我 一応“移住”ということになっていますが、戦争やナチスの難を逃れてアメリカに渡った、ということは事実だと思います。あの時代は本当に難しいですよね。リヒャルト・シュトラウスも“亡命”ではありませんが、やはり戦争を逃れて一時期アルプスのガルミッシュ・パルテンキルヒェンに避難していましたしね。
有名なバルトークの民俗音楽研究も二度の世界大戦によって中断されてしまいました。彼はエジソン が発明した蓄音機を背負って東欧の山中を歩き回り、流行歌に染まっていない生粋の民謡を収集・研 究していたことでも知られています。それこそ村のおばあさんが心を許して歌ってくれるまで、何日も村に滞在して根気強く集めていたそうです。数々の民謡がバルトークの中で昇華して作品の中で使われ ています。第1楽章冒頭の低弦から始まるメロディー(譜例1)。実はあれも民謡の調べなのです。日 本人にとって理解しにくいのが、第3楽章(エレジー)でしょうね。オーボエやピッコロに出てくる、音高の変わらない音型(譜例2)のどこにアクセントを置くかがポイントです。ここには民族の言葉の語感が必要なのです。
バルトークが実際に使用したフォノグラフ(蝋管式蓄音機) 撮影:曽我大介氏
譜例1(第1楽章冒頭)
譜例2(第3楽章)
よくバルトークはストラヴィンスキーと比較されることがありますが、大きく異なる点が二つあります。まず第一点目はリズムです。バルトークのリズムは作為的な“変拍子”ではありません。民俗音楽を源泉としたリズムなのです。二点目の違いはメロディーです。ストラヴィンスキーにもロシア民謡はありますが、ことさらバルトークには旋律を謡い上げる、歌心が必要です。例えばバルトーク作品によく見られる、高い音から始まって下降していく独特の音型は中欧からトルコに至る民俗音楽でも使われているパターンです。ブラームスのハンガリー舞曲第5番の冒頭にも同じ動きが出てきますね。
バルトークはハンガリー人ですが、生まれたのは現在のルーマニア領で、両大戦のさなか彼の周囲に は様々な東欧文化がひしめきあっていました。彼はその源泉を求めて各地を踏破していったのです。
―ルーマニアは人種のるつぼなのでしょうか?
曽我 ルーマニアは母国語だけでも大きく分けて、ルーマニア語、マジャール語(ハンガリー語)が使用されています。さらに細かく分けると、ドイツ系、セルビア系、トルコ系、ギリシャ系、ロシア系など に分かれます。ルーマニアに限らず、東欧諸国の国境線はいまだに実際のカルチャーと合致していると は言いがたいですね。バルトークの家系はハンガリー人ですが、東欧諸国でいろいろ勉強して民謡を収 集し、マジャール語地域ではマジャール語を話し、ルーマニア語も完璧に話し、トルコ語を始めとする各国語を話しました。
―当時のバルトークの写真を見ると、確かに民族衣装を着た人と一緒に写っているものがありますね。
曽我 今でも日常生活で民族衣装を使用している地域はありますよ。先日ルーマニアの地方を巡った時も、刈り入れの済んだ農地の落ち穂を求めて移動する数百頭の羊を連れた羊飼いや、馬車などを頻繁に見かけました。ある意味バルトークが見たであろう、現代生活とかけ離れた営みがいまだに残っています。
―我々日本人にとっては東欧諸国の区別がなかなかつかないのですが。
曽我 オーストリア人ですらきちんとついていないかもしれませんね。特にブルガリアとルーマニアはよく混同されがちですが、そもそも使っている文字からして違う。ブルガリアはキリル文字、ルーマニ アはラテン文字(ローマ文字)を使っています。かつてルーマニアにフランス人が入植したときに、ルーマニア語が自国の言葉に近いということが分かり、それから西欧化が進んでラテン文字を使うようになりました。ルーマニアでもかつてはキリル文字を使っていましたが、これはギリシャやコンスタンティノーブルの影響を受けていた名残なのです。一部地域では未だに使われていますよ。
常々思っているのですが、言葉を勉強するということは文化を勉強するということです。これはルーマニアでロシア語教師に言われたことなのですけどね。
―ちなみに先生ご自身は何ヶ国語お話になるのですか?
曽我 普通に話せるのは日本語以外に、ルーマニア語、英語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語です。仕事や日常会話でフランス語、ロシア語も使っていますので、合計8ヶ国語は話せます。ちなみにルーマニア語はどちらかというとイタリア語に近いです。イタリア語はポルトガル語とも近いですね。逆に似すぎていて、何語を話しているのか混乱することがあります(笑)。
―改めて今回のプログラムについてお聞かせください。
曽我 バーンスタイン作品はとにかく曲がよくできています。譜面どおりに演奏するだけで、きちんと聞けるようになっている素晴らしい曲です。ジャズやビッグバンドの要素はまた別に織り込まなくては いけませんが、こちらはブランデーでも飲みながらスイングするような感じで入れてほしいですね(笑)。
バーンスタインはミュージカルでも非常に成功しましたが、やはり彼の作品は西欧音楽の伝統に根ざ していることには違いありません。エッセンスとしてオペラの要素を非常に感じます。ミュージカルとはまた違うレヴェルの作品と言えるでしょう。
あの当時いろいろなミュージカルが流行りましたが、「ウエスト・サイド・ストーリー」は音楽面だけではなく、ストーリー性でも突出した素晴らしい作品です。これは僕が実際アメリカに行って感じたことなのですが、アメリカ人は「ウエスト=西」に特別な感情を持っているのではないでしょうか。開拓時代、東海岸から入植してきた移民達は、夕日を追って西へ西へと進んでいきました。「西」は移民達の行き着く先で、いわばフロンティア精神の「望郷の地」でもあり、様々な民族の交わる地でもあるようです。実際アメリカ西海岸ではヒスパニック(スペイン語系)の影響が大きいですし。この「西」という言葉がまさにウエスト・サイド・ストーリーにとって重要な意味を成しているのだと思います。もちろんウエスト・サイドという言葉自体はニューヨークのウエスト・サイド地区を差す言葉ですし、またバルトークが亡くなったのもニューヨークのウエスト・サイドの病院。ちょっとだけ今回のプログラムを結ぶ見えない糸みたいなものもあります。
話は少し変わりますが、6年位前にロサンジェルス・フィルハーモニックの「シンフォニック・ダンス」を見て感動したことがあります。冒頭プロローグの指パッチン(Finger snaps)を行う弦楽器奏者達の所作がぴったり揃っていたのです。弓の下ろし方から指を鳴らすタイミングまで全てが完璧に揃っていました。でもすごくさりげなくやっていたのです。日本人だとこういうとき気合を入れてやってしまうのだろうけど、彼らはまさにクールにやっていましたよ(笑)。
―「管弦楽のための協奏曲」には特別なエピソードがおありだとか。
曽我 この曲はキリル・コンドラシン国際指揮者コンクールで優勝したときの曲でもあるので、いろいろ思い出があるのですが、一つ忘れられないエピソードがあります。以前、オーストリアのリンツに住 んでいたときのことなのですが、のどかな金曜の午後に洗車をしていたら、急にマネージャーから電話 がかかってきて、「明日からのスケジュールは空いているか?」と呼び出されました。当初予定してい た指揮者が急病になった為、代役としてお呼びがかかったのです。オーケストラはオランダのネザーラ ンド・フィルで、曲目は前プロがフォーレの「ペレアスとメリザンド」とラフマニノフの「ピアノ協奏曲第2番」。ここまでは良かったんですが、メインがなんと「管弦楽のための協奏曲」だった。「こりゃ大変だ!」ということになって、それから大慌てで荷造りして飛行機でアムステルダムに向かいました。機内ではいつも休むようにしているのですが、ここまで機内でスコアを勉強しまくったフライトは後にも先にもないでしょうね(笑)。現地にはその日の夜に到着したのですが、翌日の朝にリハーサルを行って、夜にはもう本番でした。しかもこれで終わりではなくて、その後にはコンセルト・ヘボウでの3日間連続定期演奏会、という怒濤の演奏会でしたが、無事成功に終わりました(笑)。
今回はどの曲も魅力的かつ盛りだくさんで、とてもおいしいプログラムです。演奏する側は大変?か もしれませんが、お客様にはきっと喜んでいただけると思います。ぜひ皆様に楽しんでいただきたいで すね。
写真撮影:桜井哲雄(オーボエ)
構成・まとめ:柳部容子(チェロ)
〈追記〉
このインタビューの後、再びルーマニアのオーケストラに客演し、念願だったバルトーク生誕の地、スンニコラウマーレ(マジャール語:ナジセントミクローシュ)を訪ねることが出来ました。悲しいことながら、民族の軋轢の中、この地でバルトークの名前を高めようとしているのはたった一人の愛好家の情熱だけなのです。バルトークは7歳にして父をこの地で無くし、移住を余儀なくされましたが、晩年にして幼年期のこの地での悲しい体験を生々しく語っています。
バルトークの父の墓がある村外れの淋しい墓地、喪服に身を包んだ老女達と小さな教会を見かけたと き、バルトークの死の体験がこの地に根ざしていることが思い出されました。
「エレジー」へのアプローチが根本的に変わりそ うです。
バルトーク生家の跡地前で
バルトーク:管弦楽のための協奏曲
「……バルトークその人こそ、他に例のないほどの警戒心と感受性とをもって世界の一切の動きを見張り、絶えず変化し、形づくられていく宇宙の声と、苦闘し続ける人類の声とに、自らのうちにあって形を与えていく人である」(ベンツェ・サボルチ)」
アメリカ移住
バルトークが前年の母の死を機に、ディッタ夫人とともに着の身着のままの状態で渡米したのは、1940年10月30日のことであった。
この頃、彼以外にもナチスから身を守るためにアメリカへ移住した音楽家に、ヒンデミット、ストラヴィンスキー、シェーンベルク、ミヨーなどがいた。このため当時のアメリカ音楽界の活況は大変なものであった。これらの音楽家たちはいずれもそれぞれの才能にふさわしい地位を得て、安住することができた。
ところが、ことバルトークに関してはこの移住は苛酷なものであったと言わざるを得なかった。なぜなら、彼だけは一向に安定した職を得ることができなかったからである。
―1881年3月25日、ハンガリー(現.ルーマニア領)のナジセントミクローシュで生まれた彼は、8歳で作曲を始め、10歳でピアニストとしてデビュー、18歳でブダペスト音楽院(現.リスト音楽院)に入学して、作曲とピアノを学んだ。26歳から同音楽院で三十数年間教授を務め、作曲家としても名声を得ていたほか、ピアニストとしての実力もあった。また、盟友の作曲家コダーイとともに行ったハンガリーやルーマニアの民謡の収集・研究は、広く世界各国の学者や音楽家からも注目されていた。―そのような名声と実力から考えるとまったく信じがたい状態であった。
もちろん、これには彼自身にも原因がないわけではなかった。元来、彼は人付き合いのよいタイプではなく、他人から同情されるのを嫌い、自己の意思に反して時流に迎合することができなかった。当初は演奏家として生計を立てるつもりもあったが、彼の演奏スタイルは聴衆を熱狂させるような派手なものではなく、彼が最も演奏したがっていた自作のピアノ曲がアメリカの大衆や評論家の好みに合わなかったので、演奏家としての道は閉ざされてしまったのである。他方で、音楽学校の教授の口は彼が音楽学校の授業のために作曲活動が制限されるのを嫌ったため、すべて断ってしまっていた。ようやく、コロンビア大学で民族音楽の名誉博士号を得て、嘱託講師の地位を受け入れた彼は、民謡の録音からの採譜と分類に従事しながら、不安定な収入でかろうじて生活をしていた。
アメリカへ移住して約1年半後の1942年3月、彼はかつてのピアノの弟子宛に、次のような書簡を送 っている。
「私たち二人の状態は日ごとに悪化しています。耐えられないといえば誇張になりますが、ほとんどそれに近いものです……。私は、かなりの悲観論者になりました。どんな人をも、どんな国をも、またどんなことをも信じられません……」
それに加え、彼の体は白血病に冒され始め、次第に衰弱していくのであった。
作曲の委嘱
そんな彼の窮状を見かねた同郷の友人、指揮者のフリッツ・ライナーとヴァイオリニストのヨーゼフ・シゲティは、アメリカ作曲家協会(ASCAP)に働きかけ、その援助でバルトークが安心して療養できるように取り計らった。1943年夏、こうして彼は、ASCAPの世話でニューヨーク北部の山中にあるサラナック湖畔で療養生活をすることになった。
ヴァイオリニストのヨーゼフ・シゲティとジャズ・クラリネット奏者のベニー・グッドマンとともに(1943年、ニューヨーク)
その出発の直前、当時ボストン交響楽団の音楽監督であったセルゲイ・クーセヴィツキーが彼を見舞 い(実はこの時、クーセヴィツキーはライナーとシゲティの二人から依頼を受けてやって来ていた)、クーセヴィツキー財団からの委嘱として、自身の70歳記念とボストン交響楽団指揮者就任20周年記念演奏のための作品を書いてほしいと切り出し、バルトークをいたく感激させた。彼にとっては、渡米後初めての作曲の委嘱である。
バルトークは体力に自信が持てなかったため、この申出をいったんは断ったが、クーセヴィツキーは 期限を設けなくてもよいからと彼を説得し、作曲料の半額に相当する額面の小切手を彼の枕元に置いて 席を立ったといわれている。
その後、バルトークは信じられないスピードで委嘱された作品を仕上げる。彼は同年8月15日、作曲 に着手し、同年10月8日には作曲を完了している。こうして作曲されたのが《管弦楽のための協奏曲》 であった。そして翌年の12月に初演されている。初演後、クーセヴィツキーは「過去の50年を通じて最 高の傑作だ」と彼を讃えた。
彼の晩年はこの曲とヴァイオリニストのユーディ・メニューインの委嘱で作曲した《無伴奏ヴァイオリン・ソナタ》の成功のおかげで、経済的にも精神的にも充実した日々を送ることができた。だが、病魔は既に彼の体を蝕んでおり、1945年9月26日、バルトークはニューヨーク市内のブルックリン病院で息を引き取った。
管弦楽のための協奏曲
バルトークは初演時の演奏会プログラムに次のように書いている。
「作品全体の雰囲気は、―第2楽章を除くと―第1楽章の厳粛さと第3楽章の死を悼む歌から終楽章の生への肯定へと移行する漸進的な推移を示す。……この交響的なオーケストラ曲にこのような題をつけたのは、諸楽器を協奏的及び独創的に使用する傾向からきている……」
この曲は名人ぞろいのボストン交響楽団の各プレイヤーの優れた腕前を発揮させるために作曲された だけあって、バロック時代のコンチェルト・グロッソ(合奏協奏曲)を思わせる内容となっている。なお、この曲の発想には、彼の楽譜を出版しているブージー・アンド・ホークス社の社主ラルフ・ホークスが彼に宛てた「バッハのブランデンブルク協奏曲集のような作品を書いてみたらどうでしょう」という書簡や、コダーイの同名作品の影響を指摘する声もあるが真相は定かでない。
第1楽章「序奏」
曲の冒頭で低音弦の進行上に表れる弦楽器の神秘的な音色や、その動機を発展し微妙に発想を変化させていく導入部は、バルトーク独特のものである。続いて、伝統的なソナタ形式の主部に入る。主部では、弦楽器が第1主題を示し、それと対照的な楽想の第2主題をオーボエが出す。
第2楽章「対の遊び」
二対の管楽器がファゴット、オーボエ、クラリネット、フルート、トランペットの順に次々に登場し、独立した旋律を歌い活躍する。スケルツォのような雰囲気を漂わせるが、中間部では一転、金管楽器の静かなコラールが聞こえる。
第3楽章「悲歌(エレジー)」
バルトークの典型的な「夜の歌」。中間部にハンガリー民謡風の旋律が使われているほかは、いずれ もその主題は第1楽章と強いつながりを持つ。
第4楽章「中断された間奏曲」
軽い気分の楽章で、民謡風の主題を中心に書かれている。「中断」とは曲の中盤で乱入してくる騒々 しい旋律のこと。ショスタコーヴィチの第7交響曲第1楽章、いわゆる「戦争の主題」のパロディとい われる。トロンボーンのグリッサンドによる「ブーイング」と木管楽器による「嘲笑」が特徴的である。
第5楽章「終曲」
ジグザグに音階を行き来する無窮動風の旋律が流れ、音楽は次第に高揚する。やがてトランペットが 新しい主題を演奏するが、各種の楽器でこれを対位法的に展開し、コーダで力強く再現して曲を閉じる。
コーダの部分は、バルトーク自身の「エンディングが唐突過ぎる感がある」との反省を基に改訂がな されている。本日の演奏ではこの改訂版を使用している。
ニューヨークのカーネギーホールで行われた バルトークの自作演奏会を描いた戯画
参考文献
『クラシック音楽史体系第10巻 Heritage of Music』ウィルフリッド・メラーズ監修(金澤正剛監修(日本語版)、パンコンサーツ、1985年)
『最新名曲解説全集第6巻』柴田南雄「バルトーク」音楽之友社編(音楽之友社、1980年)
『バルトーク音楽論集』バルトーク・ベーラ(岩城肇訳、御茶の水書房、1992年)
『バルトーク物語』セーケイ・ユーリア(羽仁協子・大熊進子共訳、音楽之友社、1992年)
『管弦楽のための協奏曲(ポケット・スコア解説)』 青島広志(日本楽譜出版社、2006年)
『名曲ものがたり(上)』 志鳥栄八郎(音楽之友社、1987年)
『オーケストラ名曲大全』 志鳥栄八郎(音楽之友社、1994年)
初 演:1944年12月1日、ニューヨーク・カーネギーホールクーセヴィツキー指揮、ボストン交響楽団
日本初演:1951年10月2日、日比谷公会堂上田仁指揮、東京交響楽団
楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ3(3番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット3(3番はバスクラリネット持ち替え)、ファゴット3(3番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、小太鼓、大太鼓、タムタム、シンバル、トライアングル、ハープ2、弦5部
バーンスタイン:「ウエスト・サイド・ストーリー」よりシンフォニック・ダンス
新響メンバーの中にはオペラファンは沢山いるようであるが、ミュージカルファンはきわめて少数派のようである。実は私はミュージカル大好き人間で、特に好きな「レ・ミゼラブル」は昨年の帝劇公演で観劇20回を超えた。ミュージカルが好きになったきっかけは映画で見た「ウェストサイド物語」の素晴らしい歌とダンスである。なかなか実演に接する機会がなかったが、昨年夏に50周年記念ツアーの公演をオーチャードホールで、秋には念願のブロードウェイのパレス劇場(写真参照)で本場の公演を、年末には劇団「四季」の公演を堪能でき、本日この曲を演奏できることは感無量である。なお、本稿では映画との関係もあり、「ウェストサイド物語」と表記させていただくことにする。
パレス劇場(筆者撮影)
最初は「イーストサイド物語」だった。
1949年1月、レナード・バーンスタインは、それまでにバレエ「ファンシー・フリー」とそのミュージカル化「オン・ザ・タウン」で一緒に仕事をして気心が知れている振付家のジェローム・ロビンスからシェークスピアの「ロミオとジュリエット」を現代ニューヨークに場面を移したミュージカルを作るというアイデアの提案を受けた。早速、脚本家のアーサー・ロレンツを引き込み、イタリア系カトリックのトニーとユダヤ教徒のマリアが宗教上の対立の中で悲劇的結末を迎えるという基本構想ができ、「イーストサイド物語」と仮に題名がつけられた。
関係者の忙しさのため、なかなか進まなかったが、1955年にバーンスタインがロレンツと再会したとき に、その当時ニューヨークのウェストサイドで社会問題となっていたプエルトリコ移民と白人の不良少 年グループを対立団体として描くことに方針変更され、題名も「ウェストサイド物語」となった。
原作との関係を見ると、モンタギュー家のロミオは白人不良少年グループであるジェット団の創立者 の一人で今は脱退しているトニー、キャピュレット家のジュリエットはプエルトリコ人不良少年グループであるシャーク団の団長ベルナルド(ティボルトに相当)の妹のマリアとされ、マーキューシオはジェット団の現団長リフに相当する。「ロミオとジュリエット」のような仮死状態になる薬は登場しないが、ロレンス神父に当たるのが、ドラグストアの親父(ドク)という設定がおもしろい。
ミュージカルのウェストサイド物語
このような詳細なプロットが決定された後、作詞にスティーブン・ソンドハイムという最適任者を得て、多忙なバーンスタインにより音楽がつけられ、構想から実に9年近くの歳月を経て初演にこぎ着けていった。バーンスタインは純粋なオペラも作曲しているが、ミュージカルの作曲に当たっては、筋や場面の雰囲気に関係なく声を張り上げるオペラの悪習に陥らないように気をつけたことを語っている。
ミュージカルの「ウェストサイド物語」は1957年7月8日にリハーサルが始まったが、ジェローム・ロビンスの振付けは役者の身体能力の限界に挑戦する難しいもので、完璧を目指す彼の過酷なトレーニングは連日誰かが故障するまで続いた。9月26日にニューヨークのウィンター・ガーデン劇場でブロードウェイ初演されると、これまでになかった新しいミュージカルとして高い評価を受け、全米ツアーを挟んで千回を超えるロングランとなった。
ジェット団のダンス
シェークスピアを現代のニューヨークに移したユニークなプロット、青少年の非行や人種差別、貧富の差などの社会問題を取り入れた斬新さ、才人バーンスタインがラテン音楽やジャズを素材に使い、激しいリズムや変拍子を取り入れて全力投球した質の高い音楽などが歓迎されたものであろう。
ウェストサイド物語での音楽の白眉は決闘に向かう前のジェット団、シャーク団、トニー、マリア、シャーク団団長のベルナルドの恋人アニタによるクインテット(五重唱)で「トゥナイト」(アンサンこの曲の中のトニーとマリアが歌う「トゥナイト」を「ロミオとジュリエット」のバルコニーシーンに当たる非常階段のシーンに移して独立の曲としたのが、有名な「トゥナイト」(バルコニーシーン)で、ミュージカルでも映画でも最高の見せ場となっている。
バルコニーシーン
また、ロバート・ワイズとジェローム・ロビンス(途中で解雇された)の共同監督で映画化されたが、映画 でのマリア役のナタリー・ウッドの声は吹き替えで、「マイフェアレディ」でオードリー・ヘップバーン、「王様と私」でデボラ・カーその他多数の吹き替えをしたマーニ・ニクソンが担当している。彼女は「サウンド・オブ・ミュージック」の尼僧役で出演したときに初めて名前がクレジットされた。
昨年から90歳を超えたアーサー・ロレンツが演出に加わった新演出による公演がブロードウェイで始まり、衣装やセットが一新され、スペイン語の台詞や歌の比重が増すなどの変更が行われているが、ダ ンスナンバーはジェローム・ロビンスの振付のままで、今見ても全く古さを感じさせない完璧なもので ある。
シンフォニック・ダンス
ミュージカルの評価も固まった1960年、バーンスタインはシド・ラミン、アーウィン・コスタルの協力を得て、ミュージカルの中のダンスナンバーを中心にオーケストラのための演奏会用組曲を作り、シンフォニック・ダンスと名付けた。バーンスタインの代表曲になるとともに、今や各オーケストラの主要なレパートリーになっている。
全曲が切れ目無く演奏されるが、次の部分から成り、最初と最後以外はミュージカルの進行に沿って はいない。
1.プロローグ ミュージカルや映画の導入部とほぼ同じで、ジェット団、シャーク団が登場してけんかを始め警官の笛で制止される。始まってすぐアルトサックスがスイング風の旋律を吹くのがいかにも ブル)の曲名がつけられた曲ではないだろうか。決闘を前にしてそれぞれの心情を語る複数の歌が対位 法を駆使して絡み合い、盛り上がるこの曲はそれまでのミュージカルでは無かった高みに達している。ニューヨークの雰囲気を醸し出している。映画では、ベルナルド役のジョージ・チャキリス(アカデミー賞助演男優賞受賞)を含む3人のシャーク団が左足を高く上げる場面が有名だが、本場の公演での左足 はほぼ垂直まで上がっていたのに感心した。
最初の「ソドー♯ファ」に含まれる増四度音程は不安感を感じる「悪魔の音程」と言われ、全曲を通じて何度も出てくるので、注目願いたい。また、全員でのフィンガースナップ(指パッチン)が出てくるが、これは良い音を出すのはなかなか難しい。ブロードウェイの公演ではフィンガースナップの音が大きく、切れの良い音であることに感心した。新響メンバー各自の自主特訓の成果はいかに。
2.どこかに ヴィオラソロで始まり、ホルンやヴァイオリンに引き継がれる美しい音楽である。オリジナルのミュージカルでは、登場人物ではない女性の声で歌われる。決闘で殺人犯人となったトニーと マリアがどこかへ行って幸せに暮らそうという希望に満ちた曲で、これが実現しないことがわかっているだけに悲痛である。
映画では流れを重視した結果、独立した場面としてはカットされたが、決闘の結果を聞いて動転して いるマリアの部屋に忍んで来たトニーとマリアにより歌われる。また、現在行われている新演出の公演 では、キッドと名付けられた男の子が登場してボーイソプラノで歌い、トニーとマリアの手を引いて舞 台から消えるという演出がされている。
3.スケルツォ ミュージカルでは「どこかに」の前に置かれ、トニーとマリアが、ジェット団とシャ ーク団を含む皆が仲良く踊る夢(現実から逃避したい願望を象徴)を見るダンス場面の音楽で、小さな 編成で演奏される。決闘の直後でリアリティに欠けるため、映画ではカットされている。
4.マンボ 体育館でのダンス場面の音楽。沢山の打楽器が効果的に使われ、楽しく、パワフルな音楽でバーンスタインの面目躍如といったところである。特にトランペットはシェイクやフラッターなど、 ジャズで使われる奏法を使って大活躍する。映画ではアニタ(リタ・モレノ アカデミー賞助演女優賞受賞)の華麗な踊りとリフ(ラス・タンブリン)の宙返りを含むアクロバットダンスが目立つ。この曲ではオーケストラ全員が2回「マンボ」とシャウトしなければならないが、恥ずかしがらずにとにかく大きな声を出したいものである。
,b>5.チャチャ ダンスパーティ会場で偶然出会って一目惚れしたトニーとマリアがチャチャチャのリズムで簡単なステップを踊る場面である。バスクラリネットの魅力的な前奏に続き、弦楽器のピチカート とフルートにより演奏される。
6.出会いの場面 トニーとマリアが言葉を交わすシーン。4本のヴァイオリンのソロが雰囲気を盛り上げる。
7.クール~フーガ ミュージカルでは決闘の前にドラグストアに集まった白人のジェット団のメンバーに団長のリフが冷静になるように諭し、激しく踊ることで興奮を収める曲である。静かな部分から強 奏になり、また静かになる対比が見事で、シンフォニック・ダンスの中でも最も魅力的な音楽ではない だろうか。この曲には「スウィングせよ」との作曲者指示がある他、ドラムス、アルトサックス、ビブラフォン、トランペットなどがジャズの雰囲気を出している。なお、映画では、二人が殺された決闘での興奮をガレージの中で狂ったように踊ることで収めるように変更されており、成功している。リフは死んでいるので、ミュージカルでは存在しなかった副団長格のアイス(いかにも冷たい名前でクールにふさわしい)が歌うが、この役を演じたタッカー・スミス(リフの歌の吹き替えもしている)のかっこ良さは何度見てもほれぼれする。
8.決闘 ジェット団とシャーク団が対決し、シャーク団団長のベルナルドによりジェット団団長のリフが刺殺され、仲裁のために来たトニーがベルナルドを刺殺してしまう悲劇的な場面を表す、激しく迫 力のある音楽となっている。
この場面の振付での一人一人の動きは計算し尽くされており、カウントをしながら練習が行われたが、 激しい踊りのため、特に初演時にはけが人が絶えず、代役が何人も準備され、公演中も毎日のようにメンバーが交代したそうである。
9.フィナーレ トニーが撃たれ、トニーとマリアが最後の会話を交わし、マリアをはじめ出演者全員がトニーの葬送を見送る荘厳な音楽。最後に「どこかに」の断片も顔を出して希望も感じられ、「ロミ オとジュリエット」の結末とは違い、マリアはこれからも力強く生きていくことが予感される。
ミュージカルのプログラム (左よりオーチャード、パレス劇場、劇団四季)
初 演:1961年2月13日ニューヨーク・カーネギーホールルーカス・フォス指揮 ニューヨーク・フィルハー モニック
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、Esクラリネット、クラリネット2、バスクラリネット、アルトサックス、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3(1番はD管持ち替え)、トロン ボーン3、テューバ、ティンパニ、打楽器(ボンゴ、タンバリン、ティンバレス、トムトム、スネアドラム2、コンガドラム、テナードラム、バスドラム、音程のあるドラム4、ドラムセット、トライアングル、シンバル、フィンガーシンバル、カウベル3、タムタム、ビブラフォン、グロッケンシュピール、チャイム、ウッドブロック、ギロ、マラカス(大小)、シロフォン、警官の笛)、ハープ、ピアノ/チェレスタ、弦5部
演奏時間:21分
バーンスタイン:「キャンディード」序曲
屋根裏で見つけた魔法の箱
指揮者、ピアニスト、教育者、そして作曲家。20世紀を代表する音楽家、レナード・バーンスタインは、1918年8月にアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン郊外のローレンスという静かな町に生まれた。化粧品店を営む父は、ウクライナ系ユダヤ人移民二世で、敬虔なユダヤ教徒。家族に演奏家や音楽愛好家がいるといった音楽的環境ではなかったが、両親に連れられて通っていたユダヤ教会で奏でられるオルガンや合唱に魅了されるようになる。そして10歳の時、屋根裏部屋で見つけた埃を被った古いピアノの鍵盤に触れた瞬間から、「音楽」は彼の人生のすべてとなり、病的でやる気のなかった子供を、生を渇望するエネルギッシュな子供に変貌させた。彼はそのときの出会いを「雷に打たれたようだった」と回想している。古いピアノは、まさに「魔法の箱」だったのである。
やがて少年はプロの音楽家になることを志し、父親の強い反対を押し切って音楽の道に進む。ニュー イングランド音楽院からハーバード大学、カーティス音楽院に学び、作曲をウォルター・ピストン、ランドル・トンプソン、指揮をフリッツ・ライナー、セルゲイ・クーセヴィツキーに師事した。
セルゲイ・クーセヴィツキーと(1949)
余談であるが、音楽教育を受けないまま、誰も使っていない古いピアノで遊んでいるうちに音楽に目覚 め、後に指揮者・作曲家として大成した点は、グスタフ・マーラーと非常によく似ている。
ブロードウェイの救世主
以後、彼の指揮者としての華々しい活躍はここで述べるまでもないが、作曲家としても非常に優れた 作品を世に送り出している。彼はこの『キャンディード』の他に、代表作である『ウエスト・サイド・ストーリー』、『オン・ザ・タウン』といったミュージカル、3曲の交響曲、『オーケストラのためのディベルティメント』*をはじめとする管弦楽曲、バレエ音楽、オペラ、合唱曲『チチェスター詩篇』、ミサ曲など、多彩な分野に数多くの作品を作曲した。
特に1950年代、彼はミュージカルの世界において精力的な活動を行う。53年『ワンダフル・タウン』、 56年『キャンディード』、57年『ウエスト・サイド・ストーリー』と立て続けに初演。ミュージカルの作曲にエネルギーを注ぎ込むことに、師のクーセヴィツキーは「君は才能を無駄遣いしている」と声を荒げたという。しかし、彼はそれをやめなかった。バーンスタインは言う。「けれども、誰かがアメリカの音楽のために、ブロードウェイで何かをしなければならなかったのです」。
*新交響楽団では2003年4月に演奏
ただいま作曲中キャンディード?それともウエスト・サイド?(1955)
天真爛漫な青年の世界冒険譚
『キャンディード』は、18世紀に活躍したフランスの思想家ヴォルテールの『カンディード或は楽天主義説』を原作とした、2幕のミュージカル。物語では、登場人物を通して、楽天主義の哲学や生きることの意味などが語られる。バーンスタインは、終生この作品のことを「靴の中の小石」と形容して気にかけており、1989年に本人も加わって大幅な改訂を行っている。あらすじは、以下の通り。
ドイツのウェストファリアの城に、領主の甥にあたるキャンディードという青年がいた。「考えうるこの世界において、すべての事柄は善である」という楽天主義を教え込まれて成長した彼は、善良で天真爛漫。しかし、領主の娘、クネゴンデと接吻をして結婚の約束をしたために、住んでいた城から追放されてしまう。そこからは、ヨーロッパから南米まで、世界を股にかけた荒唐無稽なストーリーが展開される。軍隊への入隊、戦争、脱走、船の沈没、大地震などなど、波瀾万丈を経て、キャンディードはクネゴンデと再会。最終的に「労働こそ人生を耐えうるものにする唯一の方法である」ということに思い至り、日々の仕事とその成果の中にささやかな幸福を見出す。
キャンディードの舞台(Walnut Creek Festival:2005)
舞台のフィナーレでは、キャンディードがクネゴンデの手を取り、あらためて求婚。「Make Our Garden Grow(さあ私たちの畑を育てよう)」と歌う。歌は独唱から二重唱、さらに出演者全員の合唱へと広がり、壮大かつ感動的に曲が閉じられる。
なお、当初ブロードウェイで上演されたため、ここでは「ミュージカル」とご紹介したが、歌手に高い歌唱技術が求められ、本格的な管弦楽や合唱が必要であるため、現在では「オペレッタ」または「オペラ」という位置づけで上演されるケースも多い。
ワクワクが疾走する
『キャンディード』上演に先立って演奏される序曲は、沸き立つように躍動的で、否応なしに舞台幕開けへのワクワク感が高まる曲である。速い2/2拍子で、輝かしい変ホ長調。ティンパニの強打と金管楽器のファンファーレで華々しく始まり、一度もテンポを緩めることなく、終結部でさらにスピードを上げ、一気呵成に終わる。曲中では、キャンディードとクネゴンデの二重唱「Oh, Happy We(幸せな私たち)」の旋律[譜例1]が繰り返され、後半ではコロラトゥーラ・ソプラノの超絶技巧ピースとしてしばしば単独で歌われるクネゴンデのアリア、「Glitter and Be Gay(着飾って浮かれよう)」の旋律[譜例2]が軽快に奏でられる。
キャンディードの舞台(Arden Theatre Campany:2008)
演奏時間が4~5分と比較的短いこともあり、親しみやすいメロディーに聴き入っているうちに、あっという間に駆け抜けて行ってしまう。オーケストラの小品として、単独で演奏会の冒頭やアンコールによく演奏される、名序曲の一つである。
譜例1
譜例2
レニーよ、永遠なれ
開放的な性格で人懐っこいバーンスタインは、友人や音楽仲間、そして世界中の音楽ファンから「レニー」と呼ばれ、愛されていた。しかしそんな人気者も、彼を生涯苦しめた肺気腫の悪化により、1990年10月にニューヨークで72年の生涯を閉じる。
自分に残された時間が少ないことを悟ったとき、彼が選んだ道は、作曲家として遺作を書くことでも、一流オーケストラの指揮台に立つことでもなかった。彼は「教育」という道を選択し、亡くなる年の夏、札幌にやって来る。残された時間とエネルギーを若い音楽家たちと分かち合うために。
この第1回パシフィック・ミュージック・フェスティバル(PMF)の模様は、当時テレビでも放映され、苦しそうに声を振り絞って若者たちに語りかかけるバーンスタインの姿は、多くの人々に深い感動を与えた。その中で、彼は自分と音楽の関わりについて、こうコメントしている。
「私には愛しているものが二つあります。音楽と人です。どちらが好きだとは言えません。私は人を愛しているから、人のために曲をつくり、演奏するのです。そして、心の深い場所で音楽と会話します。人と関わらない人生など考えられません。私は普段一人で何かをすることは殆どなく、夕食も映画も一人では行きません。人も音楽も、私にとって絶対に欠くことができないものです。人を愛することと音楽を愛することは同じで、私には一つのことなのです」。
札幌でバーンスタインが一緒に土を耕し、種をまいた若者たちの「音楽」という「畑」は、きっといま世界中で緑の葉を繁らせ、豊かな実をつけているに違いない。また、彼の提唱で始まったPMFは、その精神が受け継がれ、今年で21回目の開催を迎える。
早いもので、彼がいなくなってから20年近くの月日が流れたが、彼が遺した数多くの曲や数えきれな い演奏の記録、そして後進に託したメッセージは、これからも決して色あせることはないだろう。私にとっても、彼はいつまでもスターであり、ヒーローである。
レニーよ、永遠なれ。
レナード・バーンスタイン(1988)
参考資料
『バーンスタイン音学を生きる』青土社
『バーンスタイン最後のメッセージ』NHK
初 演:1956年12月1日、ブロードウェイ
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、Esクラリネット、バスクラリネット、ファゴット2、 コントラファゴット、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、大太鼓、トライアングル、小太鼓、グロッケンシュピール、木琴、テナードラム、ハープ、弦5部
亡命者とその芸術~バルトーク『管弦楽のための協奏曲』によせて~
東京駒場深夜0時。時折鈍い音を立てて通過する京王井の頭線に呼応するかのように、どこからか低く響いてくるハンガリー女性の独り言…。何も都市怪談などではなく私の学生時代の夜のひとコマである。当時私は外国人寮の住み込みチューターとして1年間留学生と生活を共にしていた。向いは中国人とマレーシア人、右隣はギリシャ人、そして左隣がハンガリー人。金髪の巻き毛から真っ赤な頬っぺたを覗かせて「ハンガリーはワインが美味しいのヨ」という時の可愛らしい声からは想像できない、真夜中のハンガリー語での怒涛の長電話は、意味が取れないため余計に音声としてのみ耳に伝わり、部分的に1オクターブ程の抑揚を伴うフランス語を学習中の私に、ヨーロッパにも日本語のように平坦な言語が存在し、そしておそらくそこには私が知っている「主要な国」とは違う何かがあるということを予感させた。しかしその女の子がこんなにも複雑な運命を辿ってきた国からやってきたということは想像しようともしなかった。
■亡命作家、アゴタ・クリストフ
大学ではフランス語を専攻していたが、東京の西の果てにあるキャンパスには辿り着かずに、気がつけば手前の映画館で一日が終わってしまうことも少なくなかった。そうは言っても入学してからの2年間は専攻語を強制的に叩き込まれる。忘れもしないマダムM。机に浅く腰掛け長い足は椅子に投げ出し顔はまるで魔女のようだ。Alors…(さて…)の一言で背筋が凍る。無慈悲にもひとつでも単位を落とせば容赦なく落第となるので、泣きそうになりながら授業に出た。3年に上がってからも幾つかは専攻語の授業を取らなければならない。晴れて魔女から解放された私は迷わず一番優しそうなN先生の授業を選んだ。その内容は、先生による日本語訳も多いミラン・クンデラを始めとして、イオネスコやシオランなど、第二次大戦後東欧からフランス語圏に亡命しフランス語で執筆した作家の作品を、テクスト講読だけではなく舞台作品や映画を交えて味わうというもので、今であれば何が何でも取りたい授業である。午後の柔らかい日差しに包まれながら先生の柔らかい声をBGMにウトウトとまどろんでいるあの時の私が恨めしい。
その授業で題材となった作家の一人がアゴタ・クリストフ。1935年にハンガリーのオーストリアとの国境近くに生まれる。ナチズムからスターリニズムという歴史の急変に伴い、9歳でドイツ語を押し付けられ、11歳にはロシア語を強制される。1956年のハンガリー動乱の折、夫と共に生後4ヶ月の乳飲み子を抱えて命がけで国境を超えスイスへ亡命。フランス語圏の町に住み時計工場で働きながら執筆を続け、母語を殺しつつあるという意味でこれもまた「敵語」であるフランス語で書かれた問題作『悪童日記』で衝撃的なデビューを飾る。この小説は、タイトルからわかる通り子供の書いた日記という形をとり、そこには無垢で残酷で聡明な双子の子供が、疎開先の祖母の家で数々の非行を重ねながら逞しく生を切り開いてゆく様子が淡々と語られている。時代や場所の設定は意識的に避けられているが、作家自身の体験がもとになっていることは明らかだ。
昨日は、すべてがもっと美しかった
木々の間に音楽
ぼくの髪に風
そして、君が伸ばした手には
太陽
この詩は、『悪童日記』から始まる三部作の後に書かれた『昨日』の冒頭に置かれているが、もとは14歳で独り入れられた知らない街の寄宿舎のベッドの中で悲しみの涙と共に生まれたものだという。幸福な時代への郷愁、そしてそれがもう決して戻らないことへの絶望。以来クリストフには書くことだけが別離の悲しみに耐える手段となった。国家・民族・国語・公用語の説明が大概「日本」という言葉で済まされてしまう世界的にも珍しい国に四半世紀も居座ってしまった私には、その悲惨さは想像もつかない。常に近隣の国に脅かされ続けたハンガリーという小国。今でもその傷を背負っているのだろうか。駒場のハンガリー人の女の子とは、隣に住んでいながら大事な話は何ひとつとしてしなかった。
■亡命作曲家、ベーラ・バルトーク
ハンガリーに生まれ政治的理由により亡命する運命を辿った芸術家はクリストフだけではない。ベーラ・バルトークもその一人。1881年生まれなのでクリストフよりは二世代程上にあたる。晩年いよいよ進むナチズムの台頭。ユダヤ人ではないバルトークは盟友コダーイのようにハンガリーに留まることもできたが、「死に優る苦悩の選択こそが、自らの土に加えられる暴力に対してとり得る最も激しい抵抗のかたちである」ために、ナチのハンガリー侵攻前の1940年59歳のときに引き裂かれる思いで祖国を後にした。亡命先のアメリカに着くとすぐに白血病の種子が宿り、残り少ない余命という定めに付き纏われる。加えて素朴な生活を愛した作曲家にとって、機械化・画一化の進んだ文明都市での生活は苦痛以外の何物でもなく、人工的な加工の施された机や止まぬ騒音を嫌悪した。思いは祖国の戦争に及ぶ。
「戦争は続行中だ。悪魔の力は速度を上げ、妨げるものもないままに私の慣れ親しんだところへ突入していくのだ。(中略)なんらかの方法で祖国に行き着くことができたとしても、非常に変わり果てた状況下にあり、もはや私はそこに属するものではない。」
自分がヨーロッパにいないという負い目を、受難を持って支払おうとするかのようであったという。医師には「一層の休養」をとるように言われるが、その言葉さえもが失意に響く。「安全」「何もしないこと」に伴うこのような亡命者の苦痛は、前出のクリストフが亡命先のスイスで「もうここにはロシア人は追ってこない、安全だから心配するな」と言われたのに対して綴った次の一文が物語っていよう。
「自分はロシア人が怖いわけではない、わたしが悲しいのは、それはむしろ今のこの完璧すぎる安全のせいであり、仕事と工場と買い物と洗濯と食事以外には何ひとつ、すべきことも、考えるべきこともないからだ、ただただ日曜日を待って、その日ゆっくりと眠り、いつもより少し長く故国の夢を見ること以外何ひとつ、待ち望むことがないからだ。」
そんな絶望のさなか魔法使いのごとく現れたのが当時ボストン交響楽団の音楽監督だったクーセヴィツキー。亡き夫人を記念するオーケストラ曲を、自らの基金から1000ドルの契約金で、しかも時間の制限や強制力を与えることなく依頼したのである。バルトークは高揚した。作曲に取り掛かると床中に本と楽譜の山が散らばり、アメリカ到着直後はあんなに悩まされていた周りの騒音も全く気にしていられなくなった。作曲中のスコアを見ながらこう言っている。
「この総譜に誰も読み取ることができないのは、この協奏曲をつくることを通じて、自分自身を回復に向かわせるのに必要としていた妙薬を発見したことだよ。これは発見というものがほとんどそうであるように、ほんの偶然のことなのだ。」
このようにして奇跡のごとく生まれたのが、今回私達が演奏する『管弦楽のための協奏曲』。作曲家がアメリカへ来て成し遂げた最初の作品だ。『悪童日記』にしても『管弦楽のための協奏曲』にしても、その産みの親の辿った運命は決して幸福なものとは言えないが、その傷を癒すように書かれたそれらの作品は多くの読者や聴衆に恵まれた。N先生の言葉を借りれば、どちらも「政治的亡命というきわめて不幸な二十世紀的現象が生み出した幸福な奇蹟」であると言える。
■いつか東十条駅で
「音楽の歴史を駆けめぐる彼の旅の始まりは、彼にとってもはや祖国が存在しなくなった時期にほぼ一致している。他のいかなる国も祖国に取って代わることができないと理解した彼は、唯一の祖国を音楽のなかに見いだした。(中略)彼の唯一の祖国、唯一の我が家、それは音楽、あらゆる音楽家たちの音楽すべて、音楽の歴史だった。そこにこそ彼は落ちつき、根づき、住もうと決意した。(中略)彼はそこを我が家だと感じるためにあらゆることをした。その家のすべての部屋で立ち止まり、部屋のすべての隅に触れ、すべての家具を撫でてみたのである」
ここに引用したのは、先に名前を挙げたクンデラの著作『裏切られた遺言』の一部で、「彼」とはストラヴィンスキーを指しているが、バルトークにも同じことが言えるであろうし、文中の「音楽」を「小説」と言い換えれば、クンデラ自身やクリストフにも当てはまるだろう。
偉大な芸術家の話の後で自分のことを引き合いに出すのは恐縮だが、私にとってはオーケストラが故郷のような存在になるのかもしれない。かつて独りになった時に何よりも求めたのは音楽であり、そして子供の頃から文句を言いながらも身を置いてきたオーケストラであった。それゆえ、こうしてまたその一員となることができて大変助かっている。しかし一方でオーケストラという集団的行為に対する苦手意識が未だに抜けきらないなど、その愛し方も決して真直ぐなものとは言えない。そんな私が懲りずにまたその集団に加わろうと思い、運よく新響入団に至ったのはなぜだろう。
私が新響に入団したのは2年ほど前。初めて練習に参加した日のことは良く覚えている。練習場があるのは北区十条。20年そこらの歴史しか持たない無味無臭の新興住宅地に育った私は、京浜東北線東十条駅の改札を出た瞬間に、まずこの十条という土地の持つ匂いに圧倒された。また丁度その頃、十条の隣町王子を舞台にした堀江敏幸の小説『いつか王子駅で』を読んでいたので、作品中の風景がそのままそこにあることに驚き、思わず物語の途中で姿を消した印鑑職人の正吉さんの姿を探した。興奮覚めやらぬまま改札を後にし、高架下を流し素麺のごとく滑ってゆく新幹線や辺りに生息する無愛想な猫に気を取られて、2回ほど道を間違えながらやっとのことで練習場に辿り着いた私を迎えたのは、長年日本経済を支えてきたであろう団員達の顔、顔、顔。クラクラする頭を必死で支え、自分の過去を知る人のいないここで全てをやり直そう、と気を取り直した矢先、見覚えのある顔が視界に入ってきた。パニック状態の私を面白がるかのように、寛いだ様子で「よう、吉田」と声を掛けてきたのは、子供の頃叱られ続けた苦い思い出のあるオーケストラで指導をして下さっていたYさん。私にとってYさんはあくまで「先生」であったので、団内では別の愛称で呼ばれているのを知った時は、何だか親の青春時代の写真を見てしまった時のような恥ずかしさを覚えた。同じ団員として演奏できるのは大変光栄ではあるが、一から出直す計画は、練習場に足を踏み入れたその瞬間にこうしてあっさりと断念された。その日、自分の父親ほどの年齢のベテラン団員に挟まれ、のぼせた頭で演奏したニールセンの出来が散々であったことは言うまでも無い。前途多難なスタートであった。
もう一人入団以前に会ったことのある人がいる。この原稿の依頼人でもあり、我らがフルートパート首席奏者のMさん。正確に言えばその分身に会っているのだ。大学からの帰り道、いつものように丸の内丸善本店に立ち寄り、岩波文庫の棚で肌色とピンク色の背表紙とにらめっこしていると、後ろからMさんの5分の3ほどの背丈のおじさんが近づいてきて、ある本の背表紙を指差し、
「この本、面白いんですよ、ひっひっひ」
とだけ言い残して去っていった。薄気味悪く思いながら小一時間ほどかけて店内を一周し、再び岩波文庫の棚に戻ると、また同じおじさんがやってきて、先ほどと一字一句違わぬフレーズを繰り返し去っていった。当時は他と比べて少々値の張る岩波文庫一冊買うのも一大決心だったので、見ず知らずのおじさんの薦めに従うのもためらわれ、その日は何も買わずに書店を後にした。そんなことはすっかり忘れた頃、たまたま通り掛かった古本屋で、あの時おじさんが指差した背表紙が目に飛び込んできた。ここに至ってようやく150円で購入したその本が、11世紀ペルシャの詩人オマル・ハイヤーム作『ルバイヤート』。おじさんは嘘をついていなかった。本当に面白くて、今でも夜中に「酒と楽の音と恋人と、そのほかには何もない!」などと諳んじては一人ふふふと楽しんでいる。
後日、新響の定期演奏会終了後のレセプションの席で学生時代のことに話が及び、Mさんがこの詩人のことを本格的に勉強されていたということがわかったとき、確信した。あのおじさんはMさんの分身であり、おじさんこそが私を新響へと導いたのだと。そんなわけで、私が新響に入団したのは8割がそのおじさんの仕業、残りの2割は屈折しながらも抱いている私の音楽そしてオーケストラへの愛ゆえだと思いたい。
■主な参考文献
アガサ・ファセット『バルトーク晩年の悲劇』(野水瑞穂訳、みすず書房:1973年)
アゴタ・クリストフ『文盲:アゴタ・クリストフ自伝』(堀茂樹訳、白水社:2006年)
第208回演奏会ローテーション
| キャンディード | ウェストサイド | オケコン | |
| フルート1st | 藤井 | 岡田充 | 松下 |
| 2nd | 丸尾 | 新井 | 吉田 |
| 3rd | - | - | 兼子 |
| Picc | 岡田充 | 藤井 | 兼子 |
| オーボエ1st | 横田 | 亀井優 | 亀井淳 |
| 2nd | 亀井優 | 亀井淳 | 横田 |
| 3rd | - | - | 岩城(C.A.) |
| コールアングレ | - | 桜井 | - |
| クラリネット1st | 高梨 | 末村 | 中條 |
| 2nd | 大藪 | 大藪 | 高梨 |
| 3rd | - | - | 石綿(Bs Cl) |
| Es Cl | 進藤 | 高梨 | - |
| BsCl | 品田 | 品田 | - |
| アルトサックス | - | 進藤 | - |
| ファゴット1st | 田川 | 田川 | 浦 |
| 2nd | 浦 | 浦 | 田川 |
| コントラファゴット | (*) | (*) | (*) |
| ホルン1st | 箭田 | 箭田 | 大原 |
| 2nd | 大内 | 大内 | 市川 |
| 3rd | 山口 | 山口 | 鵜飼 |
| 4th | 大原 | 大原 | 園原 |
| トランペット1st | 倉田 | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 北村 | 北村 | 青木 |
| 3rd | - | 倉田 | 中川 |
| トロンボーン1st | 武田 | 武田 | 牧 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 | 志村 |
| 3rd | 大内 | 大内 | 岡田 |
| テューバ | 足立 | 足立 | 土田 |
| ティンパニ | 皆月 | 中川 | 桑形 |
| 大太鼓 | 桜井 | 桜井 | 中川 |
| シンバル | 中川 | 田中 | 中川 |
| タムタム | - | - | 今尾 |
| トライアングル | (*) | - | 今尾 |
| 小太鼓 | 今尾(テナードラム) | - | 今尾 |
| 鉄琴、木琴 | 浦辺 | - | - |
| Perc. I | - | 中川 | - |
| Perc.II | - | 桑形 | - |
| Perc.III | - | 浦辺 | - |
| Perc.IV | - | (*) | - |
| Perc. V | - | 今尾 | - |
| Perc. VI | - | 皆月 | - |
| ピアノ | - | 藤井 | - |
| チェレスタ | - | 藤井 | - |
| ハープ1st | (*) | (*) | (*) |
| 2nd | - | - | (*) |
| 1stヴァイオリン | 前田(小松) | 前田(小松) | 前田(小松) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(田川) | 大隈(田川) | 大隈(田川) |
| ヴィオラ | 石井(柳澤) | 石井(柳澤) | 柳澤(石井) |
| チェロ | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) | 柳部容(光野) |
| コントラバス | 中野(加賀) | 中野(加賀) | 加賀(中野) |
I:マラカス大・小、鉄琴
II:ボンゴ、タンブリン、トライアングル、鐘、小太鼓2(623-672)
III:木琴、ギロ
IV:ヴィブラフォン、ティンバレス、コンガ、小太鼓1(660-683)
V:4 pitched drum、カウベル(一部を除く)、タムタム、テナードラム(635-652)、フィンガーシンバル
VI:ドラムセット、ウッドブロック、太鼓類[トムトム、テナードラム(一部を除く)、小太鼓(一部を除く)]、吊シンバル(一部)、カウベル(一部)
(*)はエキストラ
第208回演奏会のご案内
曽我大介 初登場
今回の指揮者は、新響初登場となる曽我大介です。1965年生まれの曽我は、桐朋学園大学(コントラバス専攻)を経てルーマニアに渡り、その後ウィーン音楽大学指揮科、シエナ・キジアーナ音楽院指揮科、タングルウッド音楽センターなどで研鑽を積みます。1993年ブザンソン国際指揮者コンクール優勝など数多くのコンクールで賞を得ており、世界各地のオーケストラで指揮をしています。中でもルーマニアではほとんどの国立オーケストラと共演し現在も関係を深めています。2001年には大阪シンフォニカーの音楽監督に就任、日本のプロオケで最も若い音楽監督として活躍しました。現在は東京ニューシティ管弦楽団首席客演指揮者を務め、近年は作曲家としても活動している新進気鋭の音楽家です。
バルトークのオケコン
新響は東欧でのキャリアの長い曽我との初共演に、ハンガリーの作曲家バルトークの作品を選びました。バルトークの生まれたナジセントミクローシュ村は実は現在のルーマニアにあります。バルトークはハンガリーの民謡を採取するなど、ハンガリーの作曲家として独特な作品を残しました。
アメリカ移住後、体調を崩し作曲もせず収入が途絶えたバルトークを支援するため、クーセヴィツキーが委嘱して完成したのが「管弦楽のための協奏曲」です。交響曲のような大作ですが、各楽器がソリストの様に活躍するコンチェルト風の色彩豊かな名曲です。
クーセヴィツキーとバーンスタイン
クーセヴィツキーはボストン交響楽団の指揮者としてアメリカで成功をおさめたユダヤ系ロシア人。同楽団を一流オーケストラに育て、タングルウッド音楽祭で若い音楽家を育成し、また同時代の作曲家のスポンサーとなり多くの作品が彼の委嘱により誕生しました。
20世紀後半の偉大なスター指揮者だったバーンスタインはクーセヴィツキーの弟子でした。同じユダヤ系ロシア人を父に持つアメリカ人の彼は、ピアノを学んでいた15歳の時にボストン交響楽団の定期会員となりクーセヴィツキーの指揮に夢中になります。その後タングルウッドでクーセヴィツキーの下で働くなど、多大な影響を受けます。後継者としてボストン交響楽団の音楽監督になることを望むも果せませんでしたが、彼の最後の指揮はタングルウッド音楽祭におけるボストン交響楽団との演奏でした。
ウエストサイド物語=アメリカ版ロミオとジュリエット
指揮者として活躍したバーンスタインですが、作曲家としても一流でした。交響曲をはじめとするクラシック音楽作品を数多く残していますが、何と言っても代表作はミュージカル『ウェストサイド物語』でしょう。映画化されアカデミー賞を総なめする世界的大ヒットしたことでバーンスタインの名は国際的なものになりました。今回演奏するのは、ミュージカルの音楽をオーケストラ演奏会用にバーンスタイン自身が編曲・再構成したものです。サウンドトラックとは違うシンフォニックな音楽をお楽しみください。『キャンディード』はブロードウェイでは興行的に今一つでしたが、その後改訂され組曲でも演奏されています。中でも序曲は楽しく躍動感溢れる曲です。
サウンドトラックとは一味違うシンフォニックな音楽をお楽しみください!!(H.O.)
ショスタコーヴィチ:交響曲第5番
ドミトリー・ドミトリエヴィッチ・ショスタコーヴ ィチは、1906年から1975年までの69年間の生涯に、 合計15の交響曲を作曲しました。但しこの全部をし っかりと聴いた事のある人は世の中に余りいない筈 で、クラシックおたくの精鋭が集う我が新交響楽団 でもせいぜい数人程度と思われます。
その中でこの第五交響曲は1937年に初演されて以 来今日に至るまで、世界中の交響楽団の主要レパー トリーの一つとして頻繁に演奏されてきました。特 に旧ソ連時代には「苦悩を通じての勝利・歓喜」「悲 劇の解決により導かれた明るい人生観・生きる喜び」 を表した社会主義リアリズムを体現する曲として喧 伝されたものです。
しかし実際にはこの曲を作った時のショスタコー ヴィチ(以下「作曲家」)は、芸術家として考え得 る限り過酷な状況にありました。それは前の年 (1936年)にソビエト共産党の機関紙「プラウダ」 が突然、彼の前衛的なオペラ作品を「支離滅裂・反社会主義リアリズム」であると紙面で非難した事か ら始まりました。翌々週にも同様の非難記事が続い て掲載されました。
この頃、ソ連の最高指導者ヨシフ・スターリンに よる大規模な政治弾圧(通称「大粛正」)は最高潮 に達していました。まず多くの共産党幹部や軍高官 を逮捕・処刑して独裁体制を固めた上で、更に科学 や芸術の分野でも「国民の指導者にして教師」とし て綱紀粛正に乗り出したのです。自ら現場に足を運 ぶ事も多く、上記の非難記事は彼が作曲家のオペラ を観に劇場に来て途中で気に入らず退席してしまっ た、その数日後に掲載されたものです。
作曲家はソビエト若手芸術家の中でもっとも輝け るスターの座から、文化を堕落させる有害人物とい うどん底に一気に引きずり下ろされ、あらゆる公式 の場で糾弾され自己批判を強いられる身となっただ けでなく、さらなる危機が目前に迫っていました。
当時、政治犯の逮捕はたいてい夜中に自宅で行わ れました。アパートの前に止まった車から数人の男 達が降り立ちエレベーターで昇ってきます。そして 目的の部屋のドアを静かにノックし、中から恐怖に 凍りついた人の両脇を支えて連れ去るのです。この 一部始終を同じアパートの人たちは自分が標的では ないかと怯えながら寝床で聞いていました。職場で は次々と同僚が消えていく中、人々は何もなかった かの様に黙々と仕事を続けるしかありませんでし た。この様にして1937年と1938年だけで少なくとも 135万人が逮捕され処刑或いは強制収容所に送られ、 その多くが亡くなったと言われています(信頼でき る統計は今なお無いのですが)。
周囲の友人や支援者たちが次々と逮捕されていく 中、作曲家が生き残るチャンスはただ一つ…自身が 更生したと認められる作品を書き、スターリンとそ の取り巻きに差し出す事でした。この途方もないプ レッシャーの下で作られた第五交響曲の初演は、 1937年11月、革命20周年記念と銘打たれたソビエト 芸術祭で行われました。聴衆の誰もが、この演奏会 に作曲家の命運がかかっている事を知っていまし た。そして結果は…圧倒的な成功でした。出席者の 回想によれば、既に第3楽章の途中に多くの聴衆が 涙を流しており、フィナーレの途中で一人また一人 と立ち上がり、曲が終わると嵐の様な喝采が何十分 も続きました。「(やがて作曲家が)真っ青な顔で唇 をかみながら舞台にあらわれた。思うに彼は泣くの をこらえていたのだ」。
当局の役人達は、この聴衆の熱狂はサクラの仕業 か或いは作曲家に同情しての(当局への)抗議行動 ではないかと最初は疑っていた様ですが、やがて再 演を経てこの曲は「正当な批判に対する芸術家の創 造的回答」であると認められ、作曲家への包囲網は ひとまず解かれました。彼は辛くも危地を脱したの です(この10年後にまたもや同様の危機を迎えるの ですが)。
この様にして作られたこの第五交響曲を、冒頭に 述べたような勝利・歓喜の曲と捉える事に対しては、 ソ連/ロシア国内外の多くの人から異論が出されて きました。特に長調のフォルティッシモで終わるフ ィナーレについては、実は「命令され強制されて必 死になって喜んでいる様子」なのだと作曲家自身が 秘密裏に告白したとか、或いは秘密のメッセージ (ビゼーのオペラの一節「信じるな!」の音階)が 埋め込んであるとか、その他かなり怪しげなものも 含めて今日でもなお、諸説が乱れ飛んでいます。
本人は存命中に公の席や手記でこの曲について 色々述べているのですが、残念ながらこれらが本当 に作曲家の考え意図するところであるとは単純には 信じられません。ここに作曲家と彼の時代の悲劇が あります。
ショスタコーヴィチの曲は、どれも「痛々しい」 としか言い様のない独特の雰囲気を湛えています が、これはまた筆者が80年代末から数年間仕事で滞在し、その最中に脆くも消滅してしまったソ連と言 う国の、今なお生々しい印象でもあります。
芥川也寸志とショスタコーヴィチ(1954年モスクワにて)
●演奏時間:約45~50分
・第1楽章:約15分、モデラート(中庸の速度)~アレグロ・ノン・トロッポ(快速に速過 ぎず)~モデラート
・第2楽章:約5分、アレグレット(やや快速に)
・第3楽章:約15分、ラルゴ(幅広くゆっくりと)
・第4楽章:約12分、アレグロ・ノン・トロッポ
参考文献
『ショスタコーヴィチ、ある生涯』Laurel Fay
『ショスタコーヴィチ』千葉潤『名曲解説全集3』音楽之友社
『ショスタコーヴィチの証言』Solomon Volkov
Wikipedia(英・日・露)、Yandex(露)
初 演:1937年11月21日 レニングラード(現サンクト・ ペテルブルグ)にて、ムラヴィンスキー指揮 レニングラード・フィル
楽器編成:フルート2、ピッコロ、オーボエ2、クラリネット2、 Esクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、 ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、 ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、タムタム、 トライアングル、木琴、グロッケンシュピール、ピ アノ、チェレスタ、ハープ、弦5部
新響のショスタコーヴィチ交響曲演奏記録
1969年 第5番(指揮:芥川也寸志)
1974年 第5番(指揮:芥川也寸志)
1977年 第7番「レニングラード」
1977年 第7番(指揮:芥川也寸志)
1981年 第11番「1905年」(指揮:芥川也寸志)
1984年 第5番(指揮:芥川也寸志)
1986年 第4番(指揮:芥川也寸志)日本初演
1990年 第1番(指揮:高関 健)
1994年 第10番(指揮:小泉和裕)
1996年 第9番(指揮:小泉和裕)
1997年 第5番(指揮:井﨑正浩)
2000年 第7番「レニングラード」(指揮:小泉和裕)
2006年 第8番(指揮:小松一彦)
2006年 室内交響曲Op.110a(指揮:高関 健)
2009年 第4番(指揮:小松一彦)
貴志康一:交響組曲「日本スケッチ」
Ⅰ 貴志康一について
今年は“夭折の天才”と呼ばれる関西の生んだ貴 志康一(1909~1937)の生誕百年にあたり、全国で 顕彰のイベントが催されているが、当団でも演奏・ 紹介できる運びになった事は、1983年以来貴志康一 作品の伝道師を自認し世に広めてきた私にとって大 変嬉しく、この楽団の邦人作品に対する積極的な姿 勢を改めて高く評価したい。
さて、貴志家は元来紀州の武家であったが、祖父 が大阪の船場で財を築き、裕福で恵まれた環境の下 で康一は伸び伸びと育った。その一例が“日本人で 初めてストラディバリウスを買って国内に持ち込ん だ人”として時の人となった事であろう。これの購 入には流石に祖父もなかなか首を縦には振らなかっ たそうである。それはそうだろう、当時でなんと6 万円(現在の数億円!)もしたと言うのだから。
しかし、その活動は“浪速のぼんぼんの道楽”で は終わらなかった。「大正モダニズムを代表する文 化人」として“祖父の財と父の智”を受け継ぎ欧州 で華々しく活躍したのも功績のひとつであり、社会 学的見地からもそこから現代人が学び「現在・未来 の日本」というものを考える、よいモデルとして彼 の研究が、音楽以外の分野でも今年始まった(東大 大学院)事は特筆されよう。
Ⅱ その音楽的バックボーンと活動について
康一は小学校5年生の時に芦屋の別荘に移った。 その「子どもの家」と名付けられた洋館では毎週土 曜日に家庭音楽会やワーズワース(英国の詩人)の 朗読があったなどの素晴らしい家庭である。
それには、日本が第一次世界大戦やロシア革命の 戦禍を幸いにして受けずにそこそこ富裕になったこ とが大きな要因としてあり、そのまた結果として 「習い事」も大いに促進され、それに加えて阪神間 には亡命ロシア人を初めとする多くの優れた外国人 音楽家が流れつき、定住した事が幸運であったと言 えよう。私の考えでは、「阪神間のクラシック音楽 の受容の歴史」にはスラブ系音楽・音楽家の影響が 強いという特徴があると思う。
康一は、亡命ロシア人ヴェックスラーに師事して ヴァイオリンを本格的に、また熱狂的にさらいはじ めた。また当時宝塚交響楽団(大阪フィルはまだ存 在しない)の常任指揮者に赴任していたチェコ人の ヨゼフ・ラスカに音楽理論の手ほどきを受けた。
そうこうしているうちに、康一は遂にヨーロッパ 留学を考えるようになる。第一次渡欧(1926)、17 歳である。スイスのジュネーブ音楽院に入学し研鑽 を積み、意気揚揚と帰国してヴァイオリンリサイタ ルなどを開く。
1923年 叔父良雄・ヴェックスラーと共に
第二次の渡欧(1930)は今度はドイツのベルリン に向かう。その頃から康一はヴァイオリニストから、 作曲家・指揮者への転身を考えるようになる。又も や帰国して日本に住みついていたユダヤ人のピアニ スト、レオ・シロタ(今年「シロタ家の20世紀」と いうこのユダヤ人一族の数奇な運命を描いた、ノン フィクションドキュメンタリー映画が日本でも公開 された記憶は新しい)などとのコンビは注目と賛辞 を浴びた。
1930年頃 レオ・シロタと
さていよいよ本命の第三次渡欧(1932~35 ベル リン)であるが、当時のベルリンの音楽界はかつて ない栄華を誇っていた。フルトヴェングラー率いる ベルリンフィルをはじめ、ブルーノ・ワルターの市 立歌劇場、エーリッヒ・クライバーの国立歌劇場、 そして1928年にブレヒト/ヴァイルのジャズオペラ 「三文オペラ」が初演されヨーロッパ中に一大ショ ックを与えた、クレンペラー率いるクロールオペラ 劇場などが競いあっていた夢のような時代。
1931年3月30日フルトヴェングラー宅での記念撮影
康一は持ち前の社交性も武器に先ず作曲家のヒン デミット、そして指揮者の近衛秀麿を通じてフルト ヴェングラーとも知遇を得て活動の基礎を築いて 行く。
しかし1933年、ヒトラー・ナチスが政権を握ると 悪名高い「ユダヤ人の迫害」が始まり、フルトヴェ ングラー以外のユダヤ人指揮者そしてユダヤ人音楽 家は皆いなくなってしまう。康一はそれを横目に見 ながら活動を続け、1934年にまず映画のウーファ交 響楽団、そして遂にベルリンフィルの指揮台に登場 し、テレフンケンレコードに自作自演をベルリンフ ィルで録音してレコードを作るという快挙までやっ てのけたのであった。
1934年11月18日ベルリンフィルを指揮し、「日曜コンサート」を開催
1935年に帰国した康一は、先ず宝塚交響楽団を指 揮して関西デビュー、次いで東京に進出してNHK 交響楽団を指揮してベートーヴェン「第九」演奏会 や、初来日した巨匠ピアニスト、ウィルヘルム・ケ ンプなどと共演し話題と人気を攫(さら)ったが、1936年6 月、病を得て僅か28歳でこの世を去った。 華麗にしかし束の間で活動を閉じた生き様はあま りにも哀しく、「彗星の音楽家」と呼んで冥福を祈 りたい。
Ⅲ 交響組曲「日本スケッチ」と貴志の音楽について
貴志康一の音楽は一言で表現するなら「旧くて新 しい」。毎回、演奏者の心をときめかせてくれるエ ネルギーを持っているのが素晴らしいのだ。「スラ ブ民族も羨む情熱」とベルリンで評された、指揮台 の上狭しと動きまわるエネルギッシュな指揮振りや 少年のような心の憧れをもつ瑞瑞しい感受性と抒情 性は、彼の作曲にそのままフィードバックされてい る。
1936年 帰国後、W.ケンプと共演
それに加えて管弦楽法の師であり、大きくアドヴァイスを受けたモーリス譲りのオーケストレーショ ンが何といっても素晴らしい。
日本的な古謡・俗謡・民謡などを素材に使うのは 「ヨーロッパの人々に日本の心・文化を『分かり易く 伝える』」ためであり、その上に優れた管弦楽法の中、 ヨーロッパの近代音楽(フランス近代音楽やヒンデ ミットの新音楽)のエッセンスがスパイスとして振 り撒かれているのである。
第1楽章「市場」
先ず市場の賑いが描かれ、その後人が絶えた気怠(けだる) さをサキソフォンが奏するのが、フランス近代音楽 やジャズの影響を感じさせ先進的で新鮮。
第2楽章「夜曲」
導入部と結びに昭和初期大流行した歌謡曲「君恋 し」の旋律と歌詞が使われており、これは「夕闇が 迫ってきたからこれから夜曲を聞きましょう」とい う貴志康一一流の洒落である。主部の旋律はメラン コリックで切ないもの。
第3楽章「面」
この時代には珍しい変拍子で、おどけた「お面」 を表現する。中間部は対照的に、神秘的な「能面」 を表す。
第4楽章「祭」
この曲を私が持参し、世界中で受けに受けた貴志 らしいエネルギッシュな楽章。中間部では、再び登 場するサックスの豪快さとオーボエやヴァイオリン の繊細な独奏などが心地よいコントラストを形造る。 再び遠くから祭りが戻ってきて最後は華やかに曲 を結ぶ。
写 真:学校法人甲南学園(貴志記念室)所蔵資料
初 演:1934年11月18日 作曲者指揮ベルリンフィルハーモニー管弦楽団
楽器編成:フルート3、ピッコロ、オーボエ2、クラリネット2、 バスクラリネット、アルトサックス、ファゴット2(2 番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トラ ンペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、 小太鼓、大太鼓、シンバル、カスタネット、トライ アングル、タンブリン、鞭、ウッドブロック、鉄琴、 木琴、弦5部
ヒンデミット:ウェーバーの主題による交響的変容
ヒンデミットは極めて多才な音楽家であり、作曲 家としてのみならず、指揮者、ヴィオラ奏者、音楽 理論家、教育者として精力的で幅広い活躍を行った 人である。通常のオーケストラに定席を持つほとん どの楽器のための独奏曲を残したことで、特に金管 楽器奏者にとっては非常にありがたい存在と思われ ているようだ。また、大学等で音楽を専攻した者が 必ずお世話になる「音楽家の基礎練習」~決して喜 ばしい内容ではない!~の著者であり、その他いく つかの重要な理論書を残した。極めて速いスピード で曲を書くことで知られており、生涯に600以上も の曲を残した。ヴィオラ奏者としては弦楽四重奏の 奏者、ソロ奏者として時代を代表するヴィルティオ ーゾであり、ヴィオラの独奏楽器としての価値を大 いに高めた。1929年にはウォルトンのヴィオラ協奏 曲を初演している。また、1956年にウィーンフィル ハーモニー管弦楽団が初来日した折の指揮者がヒン デミットであった。このように色々な顔を持つヒン デミットであるが、作曲家として見た場合、今日 我々が抱いているヒンデミット像は、どうしても 1950年代のトータルセリエリズムの隆盛を透かして 見てしまうため、「時代から取り残された作曲家」 というのが一般的な評価であろう。しかし第1次大 戦後から1950年頃までは、ヒンデミットは間違いな く時代の最先端を行き、ドイツ現代音楽を代表する 巨匠とみなされていた。
パウル・ヒンデミット(左端)と兵士の弦楽四重奏 第1次世界大戦中
生涯と音楽的変遷
パウル・ヒンデミットは1895年11月16日、ドイツ のハーナウで生まれた。早くから楽器に対する卓越 した才能を示し、二十歳前にしてヴァイオリン、ヴ ィオラ、クラリネット、ピアノなどいくつかの楽器 の優れた演奏家であった。弦楽四重奏やオーケスト ラのヴァイオリン奏者として活躍し、のちにヴィオ ラやヴィオラ・ダモーレの名演奏家として広く知ら れるようになった。若い頃は先行する巨匠たち(ド ビュッシー、シェーンベルク、バルトーク、ストラ ヴィンスキーなど)の様式の影響を受け、ダダイス ティックで激しい表現主義的な力強い作品を書い た。そこには「狂気を振りかざす煽動家としての前 衛」を自負する若き作曲家としての気概が感じられ る。1923年頃から彼の音楽は転換期を迎え、和声的 な荒々しさを持った新バロック様式を完成し、当時 流行であった新古典主義の旗手の一人と目されるよ うになった。1927年にベルリンの音楽大学で作曲の 教授となり、音楽学生やアマチュア演奏家たちと接 触した経験から、理論書の執筆やアマチュアのため の作品を手がけるようになり、作品はより抒情的で、 耳に快い印象を与えるものになっていった。1930年 代のナチス台頭によりしだいに「退廃音楽」とみな されるようになり、フルトヴェングラーの擁護(有 名なヒンデミット事件)などもあったが、結局1938 年にスイスへ亡命し、さらに1940年にアメリカへ亡 命した。ちなみに代表作である交響曲「画家マティ ス」の初演を指揮したのがフルトヴェングラーであ った。「画家マティス」以降、ヒンデミットは自ら 作り上げた音楽語法の体系化を目指し膨大な数の曲 を書き続けたが、もはやその作品が興奮を生み出す ことは少なく、音楽史の背後に沈潜していくことと なる。1963年12月28日、膵臓病のためフランクフル トにて死去した。ヒンデミットの音楽はその独創性 にもかかわらず、あるいはそのためか、後の作曲家 たちに何ら重要な影響を与えなかった。しかし、そ の非の打ちどころのない完成された作曲技法と音楽 全般への情熱の大きさにより、20世紀の新古典主義 の理想に合った不朽の名作として独自の位置を確立 したといえる。
ウェーバーの主題による交響的変容
この作品は交響曲「画家マティス」と並んでヒン デミットの作品の中では最もよく演奏される曲であ るが、音楽史や20世紀音楽の解説書などでは完全に 無視されている不思議な作品である。1943年にアメ リカで書かれ、老練な職人的技巧の見事さと、彼の 独自の和声理論(和声的勾配と呼ばれる)に基づく 協和音と不協和音の交差が印象的な曲である。
第1楽章
主題はウェーバーの四手ピアノのための「8つの 小品」作品60の中の第4番「Allegro, tutto ben marcato」から採られている。全体の構成はほとん ど原曲に従って進行していくが、聴く印象としては 全く似ても似つかぬ音楽となっている。原曲の素朴 さは微塵も残っておらず、ヒンデミット独自の世界 がこれでもかと言わんばかりに展開される。構成の 極端な明確性、主要旋律の音楽形式への凝集、打楽 器の豊富な使用などである。和声的には長調と短調 の区別が曖昧で頻繁に転調を繰り返す独特の方法が 繰り広げられる。
第2楽章
この楽章は特に印象深いもので、劇音楽「トゥー ランドット」作品37の中のスケルツォが主題となっ ている。巧みな対位法的処理と打楽器の効果的な使 用の目立つ楽章である。中間部では主題は当時流行 であったジャズ風のリズムを伴って変奏され、非常 に興味深い。ラヴェルやミヨーを思わせるミクスチ ュアや打楽器のみによるアンサンブルなどもみら れ、やりたい放題という感じである。
第3楽章
緩徐楽章で、主題は四手のためのピアノ曲「6つ の小品」作品10の中の第2番「Andantino con moto, Marcia maestoso」から採られている。再現部での フルートの細かいオブリガードが印象的である。
第4楽章
主題は四手のためのピアノ曲「8つの小品」作品 60の第7曲「Marcia maestoso」から採ったもので ある。原曲はやや重々しい感じの行進曲であるが、 ここでは華やかで輝かしい響きへと変えられてお り、爽快な疾走感溢れる楽章となっている。
参考文献
『最新名曲解説全集第7巻』音楽之友社
『ニューグローヴ世界音楽大辞典』より 講談社
『前衛音楽の漂流者たち』長木誠司 筑摩書房
『大作曲家の和声』ディーター・デ・ラ・モッテ(滝井敬子訳)シンフォニア
初 演:1945年1月20日アルトゥール・ロジンスキー指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック交響楽団
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、 クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コ ントラファゴット、ホルン4、トランペット2、トロン ボーン3、テューバ、ティンパニ、小太鼓、テナード ラム、タムタム、タンブリン、トライアングル、小 ゴング、シンバル、小シンバル、鐘、鉄琴、弦5部
小山 清茂氏を偲ぶ
去る6月6日、作曲家の小山清茂氏が亡くなった。享年95。最近公の場に出る事も少なく、やや忘れられた感が無いでもなかった。が、代表作である『管弦楽のための木挽歌(こびきうた)(1957)』は、今では小学校の音楽の教科書に鑑賞教材としても載る、すなわち日本の初等教育を受けた者は誰しも耳にした事のある、日本の管弦楽作品となっている。
俗に「木挽きの一升飯」と言われた、木を挽く重労働(と僕は想像している)と共に、口をついて出た彼らの即興歌が、やがて村の盆踊りの節となり、更には歌い継がれ、口ずさまれて都会に於いても人口に膾炙(かいしゃ)するという、音楽(民謡)の生成過程を辿るこの作品は、その冒頭の木を挽くのこぎりの音の描写からして、その複雑なハーモニーをものとせず、印象深い。「盆踊り」の楽章も素材となる旋律は素朴そのものなのだが、その切れ目にその都度入る合いの手は、よく聴くと非常に斬新な和声に満ちている。そして大団円に至った後に残るバスクラリネットによる最初の旋律のつぶやき・・・素朴な素材と斬新極まりない技法。「よく出来ているなぁ」と何度聴いても唸ってしまう。事実この曲の人気は初演以来高まり、作曲者自身によって吹奏楽用にも編曲(1970)されている。今では吹奏楽版の演奏頻度の方が、その演奏人口の裾野の広さを反映して、遥かに高い。
新響が「日本の交響作品展9」として小山氏の個展(1985年4月。第107回定期演奏会)を取上げたときの事だ。芥川氏は敢えてこの『木挽歌』を候補から外し、氏の作品の中では比較的演奏頻度の低いものを選定すると共に、新響のために作品を委嘱した。作曲者は、邦楽器を用いた旧作をベースに短時日のうちに1曲を完成させている。今日『管弦楽のための「うぶすな」』として記録されているものがそれである。
「うぶすな」とは産土。すなわち自分の生まれた土地の事であり、その語にはわが遠い祖(おや)たちから連綿と続く、風土への愛着が籠(こ)められている。人智の及ばぬ荒ぶる自然のもたらす音は言うに及ばず、辛うじて手なづけうる自然との共生の中で営まれてきた様々な年中行事や、死と再生の折々に行なわれる産土神への祭礼などに於いて耳にする様々な歌や楽の音・・・神主の上げる祝詞(のりと)の抑揚までも・・・20世紀の初頭、「文明」の入り込む以前の信州の里に生まれた小山氏にとって、それが親しむ事が可能な「音楽」のすべてだった。この音こそが氏にとっての「うぶすな」であり、作品の基調となっている(これはこの作品に限った事ではないが)。
さて1985年1月下旬のある晩、東久留米市のご自宅に単身伺った。委嘱されていた作品が完成し、沿線を通勤路にしていた僕に、そのスコアを受領するという大命が下ったためである。小山清茂というと、何となく「吹奏楽側の人」の印象が強かった。前述の『木挽歌』の吹奏楽版に続いて、吹奏楽用の作品を数々出しており、例えば『バンドジャーナル』誌上にも氏自身による自作の解説や、演奏への鋭い批評が載っているのをよく目にしていたせいでもある。1980年にはコンクールの課題曲も作曲している。
考えてみればこの時点で小山氏は古希を迎えており、流布されていた往時の肖像の印象は消えていた。物腰の柔らかい老人であって、その訪問の折も、信州の田舎から送られてきたという林檎をご馳走になりながら、幼年期の話や上京して教員によって結成されたオーケストラでフルートを吹いていた頃の話などを伺った。
肝腎の用件を忘れていた訳ではない。新作のスコアを渡されると、自身で装丁したとしか思われないその冊子の表紙には、毛筆で「うぶすな」と毛筆で自書された題簽(だいせん)が貼られていた。そして
「こうやって依頼された作品の場合、ほかの 人(作曲家)は、そちらのオーケストラに 総譜を奉納しているかね?」
と質問があった。
なるほど「奉納」か。いかにもこの作曲家らしい言葉に思われた。そこには自分の作品に対する愛着と謙遜があり、それを音として表現してくれる相手に対する深い感謝と畏敬の念に溢れている。そして更にはそれを言葉としてこの世の中に伝えるにふさわしい朴訥(ぼくとつ)な人格があった。時を経て、世の人として慌しく生活に追われ続ければ、そうした感情や人性を保つ事が、如何に難しいかを知った今、その時の事を想い出して殊更に胸が熱くなる。
が、厚顔無恥な当時の僕は、実態を良く知りもせず、そうですねそういう人もおいでです程度の情けない返事をその場でしたような気がする。世の中の権利意識が肥大した現在では、この人のように献呈のためにスコアを作成する作曲家はまずいないと言って良い。
2ヵ月後にこの『管弦楽のための「うぶすな」』は初演された。そしてその後他で再演された話を聞かない。新響に「奉納」されたスコアは、死蔵されたままになっているのではなかろうか?
またこの個展の録音は「小山清茂管弦楽選集(FONC-5062)」として市販されたが現在は廃盤となっており、この録音自体が今では全く知られていない。つまり『うぶすな』は初演以後、音として全く聴けない作品となっているのである。作曲者の死を契機にするのは不本意ではあるが、この作品の再演は検討の俎上(そじょう)に乗っても良いように思う。
小山清茂氏は1914年の生まれ。伊福部昭・早坂文雄両氏と同年である。早世した早坂氏の「晩年」の肖像と、ふたりの老大家のそれとを比較しても、なかなか同年のイメージは抱きにくい(中島敦と太宰治と松本清張が同年生まれと言われてもピンと来ないのと同じだろう)。
だが3人の残した仕事を想えば、小山氏の死によって「ひとつの時代の終わった」などという表現が如何に皮相的で何も語っていないか、改めてわかろうというものである。
魚沼市小出郷文化会館 榎本広樹氏にきく
新響が小出郷文化会館の柿(こけら)落し公演で、ベートーヴェンの『第九』を演奏したのが1996年6月9日です。この度は、新響とのパイプ役の榎本氏に、当時のことやホール運営に関して熱く語っていただきました。
― 今日は1996年杮落し公演の時の録音したCDを持って参りました。今聴くと凄まじいものがありますが・・・(笑)。ホールのオープニングイベントでしたね。
ええ、こうしたホールのオープンは魚沼では初めてで、プロジェクトはいろいろな企画が並行して動いていたし、誰も何もわからず大変でした。
― ところで新響を初めてお聴きになったのはいつですか。
1988年第118回演奏会で、ヤマカズさん(故・山田一雄)が振ったマーラーの4番を新宿文化センター大ホールの2階席から聴いたのが初めてです。87・88年ごろは都内のコンサートによく通っていましたので、それで公演のチラシを見て行ったんだと思います。それまでは新響のことは知らなかったのですが、行ってみてびっくり。こんなアマチュアオーケストラがあるのかと。アマオケなら普通は年1回の演奏会なのに4回もやっていて、しかもルーティン・ワークに堕したときのプロオケより感動したクオリティの高さ。本当に驚きました。
その後、95年4月に小出郷文化会館の開設準備室に入りました。すでに柿落しに何をするかの準備が進んでいて、住民が参加した委員会の中から地元の魚沼和太鼓と『第九』をやりたいとの声があがっていました。行政側の方ではお金が無いからプロオケは呼べないと。では近場のアマオケにという話になったので、新響の名前を出したんです。「アマオケで『第九』をやるんだったら、『新交響楽団』もオケの候補に入れていただけませんか? 私の知る限り、最高のアマオケです。」と。まさか実現するとは思わなかったんですが。
― 指揮者は大町陽一郎先生でしたが、よく来てくださいましたね。
この話はもう時効だと思うので話しますが、魚沼在住で医師の庭山先生のご紹介で、長年のお知り合いだった東京藝術大学の日本画の大家、堀越教授にホールの緞帳(どんちょう)の原画を描いていただくことが決まっていたんです。それで、大町先生も藝大の教授でしたから、庭山先生が「大町先生を口説こう」と。藝大では年一回、美術と音楽の合同の教授会が開かれる、その直前に着くように大町先生あてに情熱に満ちた手紙を出したんです。「ホールの杮落しのとき、緞帳が開くと大町先生が指揮台に立って『第九』を振っているといいなあと、堀越先生が夢を語った。それを聞いた魚沼の若者たちは、もうすっかりその気になってしまった。私たちにはお金も何もないけれど、情熱だけはある。どうか先生から『第九』を指揮していただきたい。」というような内容です。もちろん、堀越先生はそんなこと、一言も語っていません(笑)。なのでどうにか口裏を合わせていただくようお願いをし、合同教授会の日がやってきて・・・。
その後、大町先生ご本人から合唱団事務局をやっていた青年会議所の伊藤さんのお宅に電話がかかってきて「詳しくお話をうかがいたい。」と。それからですよ、大騒ぎになったのは(笑)。当時の私の認識では、大町先生は現役バリバリの指揮者というより、すでに名を遂げられて藝大の教授をなさっている方という程度だったのですが、私の20年くらい上の世代にとってはスターなんですね。うわさが広まると、「本当にあの大町陽一郎氏が指揮を?」との問い合わせがたくさんありまして、私の認識はまったくの誤りだったと感じました。
― 当時の合唱団の意気込みは本当に凄かった! 合唱指導の先生方も大町先生にハッパをかけられていましたね。みんなプレッシャーがあったし緊張もしていました。
合唱団に参加した地元の人で、『第九』を歌ったことがある人はほとんどいませんでしたから、指導した講師の先生方や、合唱団事務局を引き受けた小出青年会議所の方々は、本当に大変な苦労をなさっていました。「第4楽章だけでこんなに大変なのか」とか「日本語じゃないのか」とか、とにかく皆が知らなかったからできたのでしょうね。柿落しだし大町先生は呼んでしまうしということで、降りるに降りられない状況になってしまったんです。
大町先生は合唱団に対して三つの条件が出されました。「練習は50回以上」「暗譜」「全員が第1楽章からいること」(途中入場しない)。練習場の設営だけでも地域のあちこちで延べ百数十回あったと思います。
本番では、高齢の方もいましたから救急車を待機させていました。何せ第1楽章から入っていますから。私は本番ではステージ・マネージャーをしていました。第4楽章の舞台裏でついに合唱団が立ち上がったとき、青年会議所の方がモニター画面をチェックして、「榎本さん、350人全員立ち上がりましたぁ!」と報告してくれたのですが、その声はもう号泣していて(笑)。まだ合唱団は一言も歌っていないのに(笑)。事務局の人たちがどれだけ精魂を傾けたかが、この一事でも伝わってくるように思います。
― こちらも打合せの時など、事務局の皆さんからいつも熱いものを感じておりました。
ホールオープン5周年のとき、数人のホール関係者にお集まりいただいて、座談会を行ったんです。そこで『第九』の合唱に参加していた年配の方が、「先人たち、私の父母も、この魚沼でずっと泥だらけになって働いてきた。私は今、こうしてこのステージの上でベートーヴェンを歌っている。私はこの喜びを、彼らに聴かせてあげたいと思った。これが私の歓喜よ! と。」と語っていました。地域に根ざしたアクティブな活動をしていこうという文化ホールとして、このようなスタートが切れたことは本当に幸福なことだったと思います。
客席誘導のスタッフや「友の会」、資金応援団体「サポーターズクラブ」などがいずれも市民が自主運営する団体としてその後に誕生していくのですが、それらの全ての起点が1996年6月9日(オープンした日)に行き着くんです。『96.6.9』がなかったら今のホールの姿はなかったと思います。
― 魚沼は当時地方にできたホールのトップモデルとして、いまだに独自の活動を続けているからすばらしいですね。ホームページを拝見して驚きましたが、ロビースタッフだけでなく、ステージスタッフとして照明や音響もボランティアでなさっているんですね。
ただ、開館して13年たち、これまでずっと関わってきた人と、そうでない人との温度差がはっきりしてきてしまった部分があります。地方のホールの成功例として、市民と行政のパートナーシップを美談のように語られていますが、実際はいつもギリギリでやってきて、今も瀬戸際の綱渡りが続いていると思います。
― 魚沼の皆さんの活動をみて、ボランティアの本当の意味を強く実感しました。とかくボランティアは「無償で行う」方を見られがちですけれども、語源の通り「自分の意志で動く」ことなのだと。本当に熱心で、新響のメンバーはそういうことに敏感ですから、合唱団との練習の時すぐに感じました。
全てを掌握しているプロデューサーというのがいなくて、オケや指揮者などいろいろなことが後から決まっていきました。今から考えると、失敗する企画の典型例なんですけど(笑)。関わっている人たちは自分で自分を追い詰めた形になってしまい、どんどん必死にならざるを得なかったんですね(笑)。青年会議所の方々は本業もそっちのけで朝な夕なに集まっていました。
― ところで、2004年の新潟県中越地震の影響はいかがでしたか。
ホールはいたるところでかなり傷みました。館長は早く直してほしいと行政に要望し、当時の行政トップが大変理解のある方で、そのおかげもありほぼ1ヶ月で復旧して11月末にはコンサートを開くことができました。
ただ、現在は表面的には回復しましたが、魚沼市に限らず震災がひどかった地区の人口は、半数程度しか戻ってきていません。天災とは地域をこうして急激に衰退させるものなのだなぁ、と感じました。
また、ホールは、今もたくさんの市民の皆様が屋台骨となってくださっていますが、マネジメントとしてはたくさんの失敗をしてきました。これからは、もっと全体を見据えた中で、さらに多くの方々が情熱をかたむけてくださるようなホールになっていけるかが課題だと思っています。
― そうですね同感です。私たち新響もこの13年間にいろいろなことがありましたが、演奏や運営の質的レベルは確実に上がったと思います。
ところで、今回は最近取り上げた曲を同じ指揮者で演奏します。新響では同じ曲は原則として10年は演奏しないという暗黙のルールがあるのですが、一つの曲を何度もやることによる積み上げ感・ステップアップが経験できるのも事実です。ですから魚沼と新潟の「りゅーとぴあ」での二回の演奏会はとても楽しみです。
「りゅーとぴあ」は素晴らしいホールです。ハード的にもそうですが、マネジメントが素晴らしい。舞台芸術の愛好家を増やしていくところから始める、というホールとしてのあり方がはっきりしています。ジュニアのオケや合唱団、邦楽、演劇団体がありますし、ホール専属のダンスカンパニーがあるのは全国で唯一です。公立ホールでは間違いなく日本のトップランナーのひとつだと思います。
以前、ある公演をこのホールで拝見したのですが、お客様の熱狂ぶりはそれまでの新潟にはなかったもので、ああ、このホールは新潟の劇場文化を変えたのだなあと思いました。
― 魚沼の演奏会は新響主催であると同時にホール主催になっています。
ホール主催のシンフォニーオーケストラ公演は柿落し以来なんですよ。やはり演奏旅行で楽団が主催をするというのは大変でしょうから、ホールが主催することにより集客面などのお手伝いができれば、と思っています。
あと最後にひとつ。新潟のお客様は、東京と違ってとってもあったかいですよ
(2009年7月22日)。
聞き手:土田恭四郎(テューバ)
まとめ:田川暁子(ヴァイオリン)
ヒンデミットとナチス
ヒンデミットは1895年にドイツのフランクフルト近郊の町ハーナウで生まれました。ヴァイオリン奏者として音楽活動を始めた後ヴィオラ奏者として活動し、また多くの作品を作曲しました。1927年からはベルリン音楽大学の教授(作曲科)にもなり活躍していたのですが、このあとドイツではナチズムが台頭してきていました。1933年にヒトラーが政権を握りましたがその年ゲッペルスが全国音楽院を設立し、R.シュトラウスがその総裁になりました。
翌1934年3月ベルリンフィルの定期演奏会でヒンデミットの交響曲『画家マチス』が初演されました。この曲がナチスの望む保守的な作品ではなかったため7月から反ヒンデミットキャンペーンが始まったのでした。雑誌『音楽』(1934年7月号)には
「パウル・ヒンデミット。能力と芸術 家精神は同じものではない。ヒンデミット の能力は疑いなく偉大であるが、この模倣 者には神聖な専心などありえないのだ。 もし国民が彼の能力を拒否するとすれば、 それはこの新参者が新しい手段を用いて いるからではなく、彼の能力にはあの無 条件の真実味が欠けているためである。」
と書かれました。このようにヒンデミットに対する攻撃は激しくなっていきましたがこれに対してベルリンフィルの指揮者フルトヴェングラーは11月にドイツ一般新聞にヒンデミット擁護の記事を載せました。そのため彼は12月にはベルリンフィル等を辞職することになります(翌年には和解)。
R.シュトラウスも『無口な女』をユダヤ人と一緒に仕事をした、ということでナチスに責められ、追従的な態度を取るようになりましたが、これは息子の嫁がユダヤ人であったため家族を守るのに必死だったからです。 私は昔、その嫁であるアリーチェさんにお会いしたことがありますが、「シュトラウスは私達の命を守るためにナチスに協力せざるを得なかったのです」と強く訴えていたのを覚えています。
このような状況でヒンデミットも1938年にはスイスに亡命、1940年にはアメリカに亡命しています。その後市民権も取得しエール大学の教授になりました。そして1943年にウェーバーのピアノ連弾曲などからの主題を使って作曲したのが今回演奏する『ウェーバーの主題による交響的変容』です。アメリカでの生活も落ち着いて安心して作曲に取り組んだと思いますが、故国ドイツの1世紀前の作曲家による主題を使ったのはやはり望郷の思いもあったからではないでしょうか。
ところでこの曲の第3楽章の後半には主題の再現のバックで延々とフルートがオブリガートを演奏します。大変難しいのですが、実は最近の新響のオーディションでは必ず課題になっているもので、従って最近入団した人はみんなこれを吹いて入ってきているわけです。私が入団した約20年前にはオーケストラスタディは課題になかったので私はやっていませんが、今回この曲を吹くことになり「もう一回オーディションを受けている」ような気分でがんばりたいと思います。
第207回演奏会のご案内
夭折の天才音楽家
1934年(昭和9年)25歳の日本人がベルリンフィルハーモニー管弦楽団を指揮し、自作を含むコンサートは大成功を収めます。
その青年の名は「貴志康一」。ストラディヴァリウスを所有するヴァイオリニストにして作曲家、指揮者。映画製作や小説を書くなどマルチな芸術家でした。大阪の資産家に生まれ、甲南高等学校からジュネーヴ音楽院に留学。卒業後はベルリンで学び作曲をヒンデミットに師事、フルトヴェングラーとも親交がありました。帰国後は新交響楽団(現NHK交響楽団)を指揮するなどスター指揮者として注目され、また日本文化とヨーローッパ文化の掛橋として活躍しました。多忙な音楽活動の中で虫垂炎を悪化させ、1937年28歳の若さでこの世を去ります。
第二次世界大戦後、貴志の活躍が脚光を浴びることは少なかったのですが、指揮者小松一彦により貴志の作品が演奏され高い評価を受けるようになりました。今年は貴志の生誕100年にあたります。今回の演奏会では、ベルリンフィルで自作を演奏した中の1つである「日本スケッチ」を演奏します。市場、夜曲、面、祭りという日本の風景にまつわる4曲からなる組曲で、豊かなメロディと洗練されたハーモニーを持ち、日本的な要素と西洋文化が融合した曲といえるでしょう。
いっしょに演奏するのは、貴志のベルリン時代の師であるヒンデミットの作品です。「交響的変容」は、ウェーバーの4つの作品から主題が採られ、形を変えて展開して行く楽しい曲で、ヒンデミットの交響作品の中でも最も演奏される機会の多い作品です。
ショスタコーヴィチの「第五」
新響はショスタコーヴィチの交響曲を小松一彦の指揮で、50周年記念演奏会で第8番、芥川没後20年記念演奏会で第4番と演奏してきましたが、いよいよ今回はもっとも人気のある代表作、第5番の登場となります。ベートーヴェンの第5番「運命」と同様に、この第五も特別な意味のある存在かもしれません。
作曲された1937年、スターリン独裁体制の旧ソ連では大粛清が行われていました。身の危険を感じたショスタコーヴィチは、交響曲第4番を初演前に撤回します。その直後に作曲された第5番は聴衆を熱狂させ大成功を収め、ショスタコーヴィチは名誉を回復します。
体制に迎合したとも実は批判や皮肉が込められているとも言われますが、古典的な構成の中に人間の内面が表現されたこの曲は、美しく壮大、そして聴く者の魂を揺さぶります。
どうぞご期待下さい!
新潟演奏旅行ローテーション
| 芥川 | 黛 | ショスタコーヴィチ | |
| フルート1st | 藤井 | 岡田 | 松下 |
| 2nd | 吉田 | 兼子 | 兼子 |
| Picc | 丸尾 | 松下 | 岡田充 |
| オーボエ1st | 岩城 | 岩城 | 堀内 |
| 2nd | 横田 | 横田 | 岩城 |
| 3rd | - | 桜井(CA) | - |
| コールアングレ | 桜井 | - | - |
| クラリネット1st | 末村 | 品田 | 品田 |
| 2nd | 品田 | 進藤 | 末村 |
| EsCl | - | - | 進藤 |
| BsCl | 石綿 | 石綿 | - |
| ファゴット1st | 長谷川 | 長谷川 | 浦 |
| 2nd | 浦 | 浦 | 長谷川 |
| コントラファゴット | 田川 | 田川 | 田川 |
| ホルン1st | 園原 | 大原 | 箭田(アシ比護) |
| 2nd | 比護 | 比護 | 園原 |
| 3rd | 大内 | 箭田 | 大内 |
| 4th | 大原 | 大内 | 大原 |
| トランペット1st | 倉田 | 小出 | 野崎(アシ北村) |
| 2nd | 北村 | 北村 | 小出 |
| 3rd | 中川 | 中川 | 青木 |
| トロンボーン1st | 志村 | 牧 | 志村 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 | 牧 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 大内 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 浦辺 | 桑形 | 皆月 |
| 大太鼓 | 中川 | 今尾 | 浦辺 |
| シンバル | 桜井 | 中川 | 桜井 |
| 鈴 | - | 中川 | - |
| タムタム | - | 田中 | 田中 |
| トライアングル | - | - | 田中 |
| 小太鼓 | 今尾 | - | 中川 |
| 鉄琴 | - | 浦辺 | 浦辺 |
| 木琴 | - | 皆月 | 浦辺 |
| ピアノ | 藤井 | 藤井 | 藤井 |
| チェレスタ | - | - | 藤井 |
| ハープ1st | - | (*) | (*) |
| 2nd | - | - | (*) |
| 1stヴァイオリン | 前田(田川) | 前田(田川) | 前田(田川) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(小松) | 大隈(小松) | 大隈(小松) |
| ヴィオラ | 柳澤(石井) | 柳澤(石井) | 石井(柳澤) |
| チェロ | 日高(光野) | 日高(光野) | 柳部容(光野) |
| コントラバス | 中野(関口) | 中野(関口) | 関口(中野) |
第207回演奏会ローテーション
| ヒンデミット | 貴志 | ショスタコーヴィチ | |
| フルート1st | 岡田充 | 吉田 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 丸尾 | 兼子 |
| 3rd | - | 藤井 | - |
| Picc | 藤井 | 藤井 | 藤井 |
| オーボエ1st | 亀井淳 | 横田 | 堀内 |
| 2nd | 桜井 | 亀井淳 | 岩城 |
| コールアングレ | 亀井優 | - | - |
| クラリネット1st | 高梨 | 中條 | 品田 |
| 2nd | 大藪 | 大藪 | 末村 |
| Es Cl | - | - | 進藤 |
| BsCl | 石綿 | 石綿 | - |
| アルトサックス | - | (*) | - |
| ファゴット1st | 田川 | 田川 | 浦 |
| 2nd | 浦 | 長谷川(Cfg) | 長谷川 |
| コントラファゴット | 長谷川 | - | 田川 |
| ホルン1st | 大内 | 比護 | 箭田(アシ比護) |
| 2nd | 市川 | 市川 | 園原 |
| 3rd | 大原 | 園原 | 大内 |
| 4th | 比護 | 箭田 | 大原 |
| トランペット1st | 倉田 | 北村 | 野崎(アシ北村) |
| 2nd | 中川 | 中川 | 小出 |
| 3rd | - | 青木 | 青木 |
| トロンボーン1st | 武田 | 武田 | 志村 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 | 牧 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 大内 |
| テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 桑形 | 桑形 | 皆月 |
| 大太鼓、鉄琴、木琴 | - | - | 浦辺 |
| シンバル | - | - | 桜井 |
| タムタム、トライアングル | - | - | 田中 |
| 小太鼓 | - | - | 中川 |
| Perc. | - | 中川、浦辺、皆月 | - |
| Perc.I | 皆月 | - | - |
| Perc.II | 中川 | - | - |
| Perc.III | 桜井 | - | - |
| Perc.IV | 田中 | - | - |
| Perc.V | 浦辺 | - | - |
| ハープ1st | - | (*) | (*) |
| 2nd | - | - | (*) |
| 1stヴァイオリン | 前田(田川) | 前田(田川) | 前田(田川) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(小松) | 大隈(小松) | 大隈(小松) |
| ヴィオラ | 石井(柳澤) | 石井(柳澤) | 石井(柳澤) |
| チェロ | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) | 柳部容(光野) |
| コントラバス | 中野(関口) | 中野(関口) | 関口(中野) |
Perc.I:小太鼓、鐘
Perc.II:大太鼓、ウッドブロック
Perc.III;シンバル、小シンバル、タムタム
Perc.IV:トライアングル、タンブリン
Perc.V:鉄琴、トムトム、中太鼓
・貴志打楽器
小太鼓、大太鼓、シンバル、カスタネット、トライアングル、タンブリン、鞭、ウッドブロック、鉄琴、木琴
(*)はエキストラ
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」<音楽史上の革命性>
「英雄」作曲当時(1803年頃)のベートーヴェン
「革新」「雄大」「壮快」「躍動」「飛躍」「雄弁」 「荘厳」「大胆」「強靭」「入念」「緻密」「巧妙」「驚 嘆」「高貴」「自由」…、まだまだ書き足りない。 “エロイカ(英雄)”として広く親しまれているこの 作品は、ベートーヴェン(1770~1827)が独自の音 楽語法と作曲技法を確立し、交響曲という領域にて ヴィーン古典派の表現を格段に広げ概念を変えた、 音楽史上転換点を迎えた金字塔ともいえる傑作とい えよう。
1792年に生地ボンから、マクシミリアン・フラン ツ選帝侯の命により、宮廷音楽家ベートーヴェンは 研鑽のため再びヴィーンに赴いた。その時、友人た ちから門出を祝うための記念帳が贈られている。そ の中に重要な後援者であるヴァルトシュタイン伯爵 から寄せられた一文の最後「たゆまぬ努力によって、 モーツァルトの魂をハイドンの手から受け取るの は、あなたなのです。」に表されるように、18世紀 後半にハイドンとモーツァルトによって熟成された ヴィーン古典派の音楽様式を継承しつつ、自己の探求を積み重ねて個性を確立し新境地を切り開いたモ ニュメンタルな曲として、ベートーヴェンという巨 大な宇宙の中でシリウスのような輝きのごとく、交 響曲第3番「英雄」が出現した。
ヴィーンの社交界にピアニストとして活躍し、音 楽愛好貴族たちの注目を集めて名声を確立したベー トーヴェンは、交響曲第1番や6曲からなる弦楽四 重奏曲のセットを完成、作曲家としての不動の地位 を構築していた。この時代、音楽家として致命的な 難聴と耳鳴りの苦悩の中で、死後、遺品の中から発 見された「ハイリゲンシュタットの遺書」が書かれ ていることはよく知られている。耳疾からの絶望と いうよりはその克服を表現したものとして、すなわ ち、芸術は危機を乗り越える手段として、爆発的な 創造力により、次々と作品が生み出されていく、世 に言う中期の「傑作の森」時代に邁進していく。交 響曲第5番「運命」や第6番「田園」、ピアノ協奏 曲第5番「皇帝」に代表される数多くの作品の出発 点のひとつとして、けたはずれな作品として、交響 曲第3番「英雄」はベートーヴェンの生涯の中でも 重要な位置にあるといえよう。この作品が生み出さ れた当時の肖像画を見ると、後世のイメージとはだ いぶ異なる最先端のファッションに身をつつみ、み だしなみのよい上品な姿にて、まるで「英雄」を意 識しているかのような独特の輝きが感じられる。
その後、耳疾で社交界から遠ざかり、スランプと ロマン主義への接近、孤高様式の完成(交響曲第9 番や5曲の弦楽四重奏曲に代表される晩年の大作 群)へと向かっていくが、創作過程が複雑で作曲の 過程で常に発展し、また生存していたときから神格 化されて特別な崇敬によるさまざまな評伝が錯綜 し、「楽聖」としてその後の芸術家たちに影響を与 えてきたことは、ベートーヴェンに関する研究の広 さと複雑さにつながっている。この部分に関しては 新交響楽団第183回演奏会でのプログラムに掲載さ れている「答えはひとつではない。」を参照してい ただきたい。 (新響ホームページから「過去の演奏会」を選択し 第183回演奏会の詳細にあり) http://www.shinkyo.com/concerts/p183-1.html
■様式=交響曲第3番の解説
この作品が生まれた時代のヨーロッパ社会は、フ ランス革命後の変動による価値観の変化、ナポレオ ン・ボナパルトの出現、神聖ローマ帝国の消滅、と いった激動の中にあった。文学と哲学への探求、政 治的展開への関心を持って、職人としてではなく自 立した音楽家として、ベートーヴェンは、あらゆる 社会的な境界を越えて自己を確立すべく活躍した。
スコア筆写本の表紙。写譜者の他、ベートーヴェン自身による 書き込みや、削除のあとがある。
前項で述べた彼に関する研究の広さと複雑さとし て、この作品には数多くの逸話や伝説が存在してい る。ナポレオンに対する複雑な感情(例えばナポレ オンへの尊敬と関心、皇帝の座についたことでの激 怒による献呈の破棄といった説話、“ボナパルト” という標題へのこだわりと“シンフォニア・エロイ カ-ある偉大な人物の思い出を記念して”としてロ プコヴィッツ候に献呈された経緯)、当時のベート ーヴェンによる一連の「プロメテウス」音楽との関 連性、「英雄」の本質的意味等、ここでは詳細な解 説はあえて省き、ベートーヴェンの作品に共通した 要素を列挙してみよう。
「長さと編成」
当時の交響曲というスタイルからかけ離れた50分 近い長さであること。今まで同じパートとして譜面 に書かれていたチェロとコントラバスが分離されて いること。ホルンが3本という特殊な編成であるこ と。以前の交響曲と比較してほとんど二倍の規模と して意図された長さによる効果と意欲的な楽器法 は、より充実した響きを表現し、音楽表現の拡大と 想像力の進化につながっていく。
「モティーフ」
メロディーとしては、三和音を基礎とした単純明 快なモティーフで、しかもそれを多相的に発展させ、 自己完結した旋律ではなく常に反復や変容を持って 造形されている。そして、重要なのはメロディーだ けでなくリズムパターンを加えて、多相的変化の手法による内的な統一感を生み出している。これは第 1楽章に顕著な要素であり、リズムとして一定の拍 子に変化を与えスピード感をつけるシンコペーショ ンを用いて、小節をまたいで本来の拍のとり方を変 化させ強拍をずらして独特のリズムを生み出してい る効果としてのヘミオラを誘発し、リズムを今まで 従属的地位から引き上げている。調性や和音とメロ ディーだけでなく、強拍記号を多彩に使用してダイ ナミックな表現を創出している。
「調性と和音」
変ホ長調は「英雄的」な性格を持つことで後世に 影響を与えている。例えばR.ワグナー「ニーベルン グの指環」に登場する英雄ジークフリートの動機と か、R.シュトラウス「英雄の生涯」も同じ調で表現 されている。和声としては大胆且つ効果的に不協和 音を使用し、増六和音や減七和音をたびたび登場さ せて緊迫感と劇的な表現を生み出している。先述の リズムパターンと同様、この作品以外にも見られる ベートーヴェン作品の重要な特長といえよう。
「構成」
第1楽章:
音楽用語として“アレグロ・コン・ブリオ”とい えば、“エロイカ!”と出てくるほど有名な標記。 4部分からなるソナタ形式だが巨大な展開部とコー ダが特長。最初にチェロで登場する「英雄」のテー マは、その後の他のテーマとも関連性を持っており 重要。展開部の後半オーボエによる哀愁を帯びたメ ロディーが秀逸。再現部の直前、ヴァイオリンが属 和音で二度音程を奏しているところで突然ホルンに テーマを吹かせ、ロプコヴィッツ侯爵邸での試演の ときにホルンが拍を取り違えたかと弟子のフェルデ ィナンド・リースが思ったという有名な箇所があ る。当時の和声上の反則で記譜上の誤りと考えられ ていたが、この劇的な仕掛けは作曲者が意図してい るものである。
第1楽章再現部直前の部分(草稿)
試演されたロプコヴィッツ侯爵邸
第2楽章:
「葬送行進曲」という名称を与えたのは初めての こと。三部形式を複合的に変化させたものといえよ う。葬送の主題とともに小太鼓の音形が登場する。 トリオに相当する部分はハ長調となり英雄の偉大さ を賛美、この後のへ短調による二重フガートが苦悩 を表現しているようでドラマ性に富んでいる。最後 はため息のような嘆きと、遠くに去るように終結 する。
第3楽章:
本格的な“スケルツォ”。複合三部形式にてスピ ード感あふれ、トリオに三本のホルンによるアンサ ンブルが効果的。出版社であるブライトコプフ&ヘ ルテル宛の手紙の中にも、わざわざ「三本のオブリ ガート(独奏)ホルン」と書かれており、まさしく その真価が発揮されている。
第4楽章:
変奏曲だが、先例を破る規模の大きさがある。ベ ートーヴェンが同時期に作曲したバレエ音楽「プロ メテウスの創造物」に代表されるメロディー主題と バス主題が対置されており、特にバス主題が前面に でている。これら2つの主題は巧みに組み合わされ て大きな流れを構築している。
■“B to C”から“B to B”へ
バッハは「バッハ」(小川)ではなくて、「メーア」 第1楽章再現部直前の部分(草稿) (大海)という名であるべきであった、という言葉はバッハの音楽の果てしない広大さと深さをたとえ たものとして、ベートーヴェンの有名なしゃれとい われている。ベートーヴェンは、若きころボンにて、 クリスチャン・ゴットロープ・ネーフェよりバッハ の平均律クラヴィーア曲集を通して学び、当時の和 声や音楽構成に対する理論的秩序に関する問題を通 して音楽理論を認識した。ベートーヴェンは終生バ ッハの作品に親しんでいたという。
長年テューバを演奏している筆者にとって、テュ ーバはベートーヴェンの死後に開発された新しい楽 器とはいえ、バッハ(Bach)から現代(Contemporary) へというテューバの持つレパートリーの広さと演奏 表現の可能性としての概念を認識しているが、時代 を超越した精神世界の奥深くへいざなう音楽の流れ として、バッハ( B a c h ) からベートーヴェン (Beethoven)という大きな概念を感じている。「英 雄」をはじめとするベートーヴェンの音楽は、バッ ハという大海の流れのうえで、後世のあらゆる作曲 家の作品と生き様に多大な影響を与え続けている。 ベートーヴェンの作品から受けたプレッシャーの大 きさと、その意義を継承する責任も含めて、特に表 現様式として交響曲を選択したブラームスやブルッ クナーはもちろんのこと、伝統的なソナタ形式によ る作品ではベートーヴェンを凌駕することが困難で あるといった感覚が存在していたのは確かであり、 ベートーヴェンの確信に満ちた先駆性が改めて感じ られる。
初 演:1804年5月末、ヴィーンのロプコヴィッツ侯邸に て作曲者自身の指揮により試演。1805年4月7日、 ヴィーンのアン・デア・ヴィーン劇場にて作曲者 自身の指揮により公開初演。
日本初演:1909年11月28日東京音楽学校にて第1楽章のみ。 A.ユンケル指揮。1920年12月4日東京音楽学校に て全曲。G.クローン指揮。
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、 ホルン3、トランペット2、ティンパニ、弦五部
R.シュトラウス:交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」
「英雄の生涯」、「アルプス交響曲」あるいは「家庭交響曲」といったR.シュトラウスの交響詩を聴いたり演奏したりするときにいつも感じるのだが、作曲家がこういった標題音楽に対して与えている音楽の各部分の説明は、むしろ音楽にとって邪魔なものかもしれない。確かに、そういった説明を通じて作曲家が何を描こうとしているのか、そしてそれぞれの部分が何を表しているのか、明確に思い描くことができる。しかし、それによって逆に、われわれは与えられた説明から生み出されたイメージとしてしか音楽を捉えることができなくなってしまう。「英雄の生涯」のさまざまな主題は、もっと自由に、音楽そのものとして聴くとき、はるかに豊かなものとして受け取ることができるのではないだろうか。
とはいえ、われわれにとって、作曲家が語る言葉が作品を理解するための重要な手助けとなるというのも間違いないことだ。「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」に関しても、R.シュトラウス自身、ある音楽学者の求めに応じてこの曲の標題的内容をかなり詳細に総譜に書き込んでおり、それによってわれわれはこの交響詩の表現する具体的情景を知ることができる。ここでもそのシュトラウス自身の言葉を紹介することにしたいが、その前に、そもそもティル・オイレンシュピーゲルとは何者なのか簡単にふれておく方がよいだろう。
おそらく多くの日本人にとって、「ティル・オイレンシュピーゲル」という名前は、クラシック音楽が好きであれば、このR.シュトラウスの交響詩によって知られているか、さもなければほとんど馴染みのないものといえるだろう。しかし、ドイツ、オーストリアをはじめヨーロッパのいくつかの国では、ティル・オイレンシュピーゲルは、知らない人はまずいないほど有名なキャラクターである。ティル・オイレンシュピーゲルの物語は、16世紀初頭に書かれた「ディル・ウーレンシュピーゲルの退屈しのぎ話」(ブラウンシュヴァイクの徴税書記ヘルマン・ボーテの作と考えられている)によってヨーロッパ各地に広がっていった。
16世紀初頭の民衆本の挿絵
主人公のティル・オイレンシュピーゲルは悪戯者の放浪人で、生まれたときから死んだ後まで、人々 に悪戯を仕掛けて楽しませたり、激怒させたりし続けた道化タイプの人物である。実は、「原作」といえるボーテのテクストでは、手工業の親方や聖職者・王侯といった権力者をからかう愉快な話だけでなく、とてつもない糞尿譚(スカトロジー)がしつこいほど繰り返され、また弱者をいたぶる話も含まれている。しかし、現在多くのドイツ人が思い描くティルのイメージは、おそらくこの16世紀初頭の民衆本に描かれたものというよりも、むしろ絵本など、子ども用に書き直されたものによって生み出されたものといってよ い。ちょっと調べてみるだけで、ドイツ語圏、英語圏など、実に多くのティル・オイレンシュピーゲル の絵本が(アニメのDVDやビデオ、朗読CDも!)出版されているのがわかる。なかでもケストナーによる再話(1938年)は、ヴァルター・トリアーによる挿絵とともに、多くのドイツ人の「ティル」のイメージを作り上げてきたといえるだろう。
ケストナー作/トリアー絵によるオイレンシュピーゲル
1895年に作曲された「ティル」は、もちろんそういった現在のドイツ人のイメージとはある程度異なる文化的環境の中で生まれたものだが、楽しく反抗的なキャラクターという点では基本的に一致する。R.シュトラウス自身があとから総譜に書き込んだティルの物語は、まさに昔話の書き出しから始まる。「むかしむかしあるところに、いたずら者の道化がいました。」続いて、軽やかなホルンのソロによってティルが登場する。「名前はティル・オイレンシュピーゲル。」この旋律(の断片)は「ティルの主題」として、いろいろな姿をとって全曲に繰り返し現れることになる。ここから基本的に6/8拍子となるのだが、実はこのティルの主題は7/8拍子のようなリズムとなっており、ここにも世間的な枠組みからはみ出すティルの姿を見て取ることができる。
「それはひどいいたずら者(コボルト)だった。」オーケストラの強奏に次いで現れるひょうきんなクラリネットのソロによる主題は、もうひとつのティルの動機としてやはり曲全体のいたるところにちりばめられている。この動機は、冒頭の「昔々」の旋律が形を変えたものである。
そして、6/8拍子の軽やかなギャロップとともに、ティルは「新しい悪戯のために出発。――待ってろよ、この嘘っぱち野郎ども。」これから、ティルの悪戯の犠牲となる者たちに楽しく宣戦布告をした後、ここからかなり具体的な4つのエピソードが音楽によって描かれてゆくことになる。
一つ目の話は、女たちでにぎわう市場の中へと馬で突っ込み、市場を大混乱に陥れるという悪戯である。「そらっ! 馬で市場の女たちの真ん中へ。」しかしその大騒ぎはあっという間に終わり、ティルはその場から「七里靴ですたこら逃げ出す。」そして、「ネズミの巣穴に隠れて」やりすごす。
二つ目のエピソードは、「僧侶に化けてさもえらそうにお説教。」比較的穏やかなテンポのユーモラスな旋律である。「しかし、悪戯者の姿が足の親指からちらりとのぞいている」(クラリネットのソロ)。そのように悪戯を楽しみながらも、ティルは「キリスト教を侮辱したかどで恐ろしい末路をたどることになるのではないかという思いに捉えられる」。この箇所は、ミュートをしたトランペットとホルンによる不安げな旋律で表現されている。
ヴァイオリン・ソロによる細かい下降音形に続く三つ目のエピソードでは、「騎士に姿を変えたティルが美しい娘たちとやさしく洗練された挨拶の言葉をかわす」(オーボエなどによるやさしげなティルの動機)。ティルは「娘たちに求愛する」が(管楽器の上昇音形の繰り返しが感情の高まりを表現)、娘たちに体よく拒絶される。「やさしくても、肘鉄は肘鉄。」ティルは怒り狂い、「全人類に復讐することを誓う」(ホルンのユニゾンによる強奏)。
しかし、すぐに気を取り直したかのように現れるふざけたティルの動機に導かれて、第四のエピソードのための「俗物学者のモティーフ」が現れる。これは、ファゴットに始まりさまざまな楽器がぶつぶつ言うかのように折り重なる主題である。ティルは「俗物学者たちにとてつもない難題をつきつけたあと、目を白黒させている連中をほったらかしにする」ので、学者たちはしばらく喧々諤々と混乱した議論を続ける羽目になる。ティルはそんな学者たちを尻目に、「遠くからしかめっ面」(ffによるふざけたティルの動機。最後は木管楽器のトリル、ホルンとトランペットによるストップ音)をしてみせる。
余談だが、道化の「しかめっ面」(難しい顔をするしかめっ面ではなく、むしろ「あっかんべー」のほうが近い)には独特の文化的伝統がある。自分を笑いものにすることで相手に取り入り、持ち上げながら、心を許した次の瞬間にはその相手にしかめっ面をして見せることで、その上下関係をあっという間に逆転して見せるのだ。(ヴィスコンティの映画「ベニスに死す」には、それが見事に凝縮されたシーンがある。)音楽では、ホルンの金属的なストップ音はこういった意味合いをもつことがある。
そしてその場を後にすると軽やかで楽しい「ティルの鼻歌」とともに、ティルは何事もなかったかのように歩いてゆく。その後、ソナタ形式の再現部のように、冒頭と同じくホルンによるティルの主題が現れると、二つのティルの主題の断片が気まぐれに、そして次第に混沌とした様相を帯びながら、ほとんど大騒ぎになるまで高まってゆく。と、突然、ティルのこれまでの悪戯に対する「裁判」の物々しい響きが鳴り響く(小太鼓と金管楽器)。ティルはしかし、「どうでもいいこととばかりに口笛を吹く」。だが、結局はこの裁きの手から逃れることはできない(ここで「恐ろしい末路」の予感を表していた旋律が再現する)。ティルは処刑台の「はしごのうえへ! ティルの身体はだらんとなり、息はこと切れる。最後の痙攣――ティルのはかない命は終わった。」しかし、冒頭と同じく物語の語り手によるエピローグによって、処刑によって死んでもなお、ティルのはちゃめちゃな物語は楽しく締めくくられることになる。
実は、シュトラウスが標題的に描き出したこのティルの物語は、物語の筋そのものとしては、ヘルマン・ボーテの「原作」のうちにそれに当たるエピソードをほとんど見出すことができない。俗物学者を煙に巻く話が多少素材的に重なるくらいだ。確かに、度重なる悪戯のためにすんでのところで縛り首になりそうになった話はあるが、ティルの最期は処刑によるものではない。シュトラウスによるティルの物語は、作曲者のかなり自由なイメージによって作り出されたものといえそうだ。
しかしさらにいえば、われわれ自身、作曲者による標題的な言葉を念頭に置きつつも、もっと自由な イメージでこの音楽を捉えてよいのではないか。R.シュトラウスは、「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」を初演した指揮者フランツ・ヴュルナーが曲の内容についてあらかじめ尋ねたところ、次のように答えている。「オイレンシュピーゲルに対する標題を与えることは私にはできません。言葉に表現してしまうと、私がそれぞれの箇所で考えたことは、とてつもなくおかしな印象を与えてしまうことになるでしょうし、いろいろと軋轢を生むことになると思います。今回は聴衆の皆さんにご自分で、この悪戯者の差し出す胡桃の殻を割って[難題に取り組んで]いただくということにしませんか。」ティル・オイレンシュピーゲルの標題的内容についてこのように答えておきながら、シュトラウスはさほど時間を置かずして先に紹介したような「ティル」の標題について具体的に書き記しているわけだが、それでもなお、標題について語ることはできないというシュトラウスの言葉は、やはり力をもち続けている。この演奏会でも、一方ではシュトラウスによって与えられた解説を楽しみながら、もう一方で、「聴衆の皆さんにご自分で、この悪戯者 の差し出す胡桃の殻を割っていただく」ということでいかがだろうか。
主要参考文献:
『Till Eulenspiegels lustige Streiche』Hans-Jörg Nieden(München(Fink)1991)
Wikipedia:Till Eulenspiegels lustige Streiche(http://de.wikipedia.org/wiki/Till_Eulenspiegels_lustige_Streiche)
音楽之友社版スコア『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』解説(三宅幸夫)
『R.シュトラウス(作曲家別名曲解説ライブラリー)』音楽之友社(門馬直美氏による解説の部分)
『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』(阿部謹也訳)岩波文庫
『Till Eulenspiegel』Erich Kästner(Hamburg(Dressler), 2000)
初 演:1895年11月5日 フランツ・ヴュルナー指揮 ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団
楽器編成:ピッコロ、フルート3、オーボエ3、コールアングレ、小クラリネット、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン8、トランペット6、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太 鼓、シンバル、トライアングル、小太鼓、ラチェット(ガラガラ)、弦五部
デュカス:交響詩「魔法使いの弟子」
デュカスは1865年にパリで生まれたフランスの作曲家であり、31歳の時に作曲したこの曲で一躍その名を高めた。この曲は、ドイツの文豪ゲーテが1797年に書いた同名のバラード(物語詩)のフランス語訳に基づいて作られている。ちなみに、ゲーテの詩は紀元二世紀のシリアの風刺作家ルキアノスの「嘘つき、または懐疑者」にヒントを得て書かれたといわれている。どのような物語なのか、ゲーテの書いた物語にルキアノスの短編を織り交ぜて脚色してみた。
序 奏
今日は魔法使いの先生がお出かけで留守。静かな屋敷には僕ひとり。(ヴィオラとチェロのフラジオレットにのって弦楽器やこれに続く木管楽器が遅いテンポで静かな屋敷内の水や箒のテーマを奏でる)僕は箒(ほうき)を手に取り、先生の真似をして着物をきせてみた。(速いテンポで演奏される木管楽器による弟子のテーマ)このあいだ盗み見たあの魔法がうまくいけば、箒に買い物へ行かせたり、料理を作らせることだって出来るんだ。これで仕事や家事が楽になりそう。でも先生、僕に魔法をたくさん教えてくれたのに、あの魔法だけは教えてくれなかった。何故だろう?(急にテンポが速くなり、弱音器をつけたトランペットの魔法使いのテーマは、まるで弟子が先生の真似をして呪文を唱えているよう)さあ、例の呪文を唱えるのだ。この僕が奇跡を起こして見せようではないか。渾身の力を振り絞り、僕は呪文を叫んだ。「モビリコーバス!箒よ動け!」(ハリーポッターに出てくる呪文だそうで…失礼。ティンパニの一打で突然ファルマータ休止、魔法が効いた?)
スケルツォ
固唾を飲んで見つめる僕の前で、箒は二本足でむっくり起き上がったかと思うと、よちよち歩き出したではないか。(箒のテーマはファゴットによるこっけいなスケルツォ)ようし、今からは僕の言うとおりに動くのだ。「バケツを持って川から水を汲んでこい!」箒のやつ、川辺にすっ飛んでった。水を汲んだかと思うと電光石火で戻ってくる。そして水槽に水をざあっとぶちまけた。ほら、もう二度目だぞ。水槽も水がめも、あの水盤にもこの水盤にも水がなみなみ溢れてる。目にも止まらぬ早わざで、水はどんどん増えてくる。(箒のテーマ、水のテーマが繰り返し演奏される)どんなもんだい、僕の魔力は先生に負けてないぞ。
でも、もうそろそろやめてくれ!お前の働きは存分にわかったから!えい、しまった。もとの姿に帰す呪文を覚えてなかった。これじゃあ部屋は水浸し。あいつめ、つぎつぎ新しい水を運んでくる。水がどんどん僕に襲いかかる。もうこれ以上ほってはおけん。先生に見つかったら叱られる。斯くなる上は、この斧で箒を叩き割ってくれよう。「えいやーっ!」(短い休止)ほれみろ見事に命中、箒は真っ二つ。これで一安心…と思ったら。割れた箒の一方がむくりと起き上がり、また水を汲みはじめた。(ふたたびファゴットによる箒のテーマ)かと思うともう一方も起き上がり、とうとう二人の召使いが出来上がってしまった。こいつらのまあよく働くこと!広間も階段も水浸し。なんともすさまじい大洪水!先生、大先生、どうかおろかな私を助けてください!(箒、弟子、水のテーマがますます入り乱れる)
コーダ
(金管楽器のファンファーレにのせて)魔法使いの大先生のお出ましだ。そして最後に、師曰く『隅に退け、箒よ、箒!汝ら本来、箒なり。何故ならば汝らを霊として呼び出し、その目的に供し得るは、ただ練達の師あるのみなれば』
日本の昔話の似た話を思い出した。道に迷った旅の老人を泊めた親切な若者は、お礼に老人から何でも希望のものが出せる石臼をもらう。若者は村人のみんなに石臼を使ってご馳走をふるまった。しかし、悪い村人に石臼を盗まれてしまう。悪い村人は、これさえあれば金持ちになれると船で海へ逃げる。途中でおむすびを食べようと石臼に塩を出させるも、止め方がわからず、あふれ出た塩の重みで臼は海の底に沈んでしまう。臼は塩を出し続け、そのために海の水は塩辛いというお話。
また西洋では神の言いつけを守らず禁断のりんごを食べ、エデンの園を追放されたアダムとイブの話や、天まで届くバベルの塔を作ろうとしたため神の怒りを買い、異なる言語を話すようになった人々の話などがある。神様だけではなく、自然などに対しても畏敬の念を忘れ、それを真似しようとしたり、支配しようとまでする人間のおろかな行為に対し、大先生の最後の言葉は、わたしたちが越えてはならないものの存在を教えてくれる。
ドイツ人の知人に聞いたところ、『魔法使いの弟子』の話はドイツの小学校の教科書に載るくらい誰もが知っているそうだ。かわいらしくユーモラスで含蓄のあるこの物語を、デュカスは音楽によって見事に映像化している。
ファゴット吹きからひとこと。箒の役を演じるファゴットは、楽器の見た目も箒の柄に似ている。重い水をふらつきながらも黙々と運ぶ姿をぜひご想像ください。また、斧で真っ二つにされたあとゾンビのようにムクムクと起き上がる様子は、コントラファゴットが不気味に演じます。
初 演:1898年、パリにて作曲者自身の指揮による。
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン4、トランペット2、コルネット2、トロンボーン3、ハープ、ティンパニ、大太鼓、シンバル(合わせ・吊り)、トライアングル、グロッケンシュピール、弦五部
新潟に演奏旅行に行きます!!
今年の秋に5連休(9/19土~23水)があるのをご存じですか?1985年に制定された国民祝日法「二つの祝日に挟まれた平日を休日とする」が5月4日(みどりの日制定以前)以外に適応されるのは今年が初めてなのだそうです。この5連休を利用して、新響は演奏旅行に出かけます。
新響の活動を維持発展させるために、広く活動の場を求めることになっているのですが、団員の多くは仕事を持っているため土日祝日以外での活動は難しく、依頼演奏会(楽隊用語でお座敷といいます:アゴアシ枕付き=交通費と宿泊費食費が付くという意味です)もそうあるわけではありません。今年はせっかくの5連休ですので、自主演奏会を地方で開くことにしました。
旅行先は新潟県です。13年前に新響は新潟県魚沼市(当時は北魚沼郡小出町)の小出郷文化会館のこけら落としでべートーヴェンの第九を地元の合唱団と共演をしました。担当者の方が東京に住んでいた頃によく新響の演奏会を聴いて下さっていたそうです。最初はN響を呼ぼうと思ったが、あまりに高額で別のプロオケを紹介されたのだけれど、それだったら新響の方がいい演奏をする(こともある)ということで新響に声をかけていただきました。350名の大合唱団は数多くの練習を積み大変感動的な演奏で、私たち新響にとって思い出深い演奏会になりました。東京から約200Km、高速道路を降りてすぐの所にあります。地域に根ざした文化芸術活動の拠点として、全国的にも注目されているホールです。
もう1か所は新潟市です。10年前に完成した新潟市民文化芸術会館のコンサートホールは音響が良いことで有名で、見た感じはサントリーホールにそっくりです。その素晴らしいホールを東京では考えられないくらいの安い料金で借りることができます。ホールの名称となっている「りゅーとぴあ」は、新潟は川に囲まれ堀が多く柳が植えられていたので「柳都(りゅうと)」と呼ばれることに由来しています。
演奏する曲は邦人作品とショスタコーヴィチ、まさに「新響らしい」プログラムとなりました。演奏旅行のメリットは、良い音響環境で演奏ができること。また同じ曲を繰り返し演奏することで、より充実した演奏を実現できるメリットもあります。東京以外の方に新響の演奏、邦人作品を聴いていただきたい。そして団員の親睦の場になり益々新響が結束して良い演奏ができればと考えています。
宿代や交通費は団員が個人で負担しますが、指揮者の出演料や楽譜レンタル料、楽器運搬、各種印刷代など350万円ほどの費用がかかります。その一部に維持会費を使わせていただく予定でいます。そこで、維持会員の皆様(+同伴の方)に小出、新潟での演奏会のご招待券を差し上げたいと考えています。
新潟県は今年のNHK大河ドラマ『天地人』の主人公直江兼続ゆかりの土地です。ドラマの舞台を巡るのもよいですが、ご飯もお酒もお魚も美味しく、たくさんの温泉がありますので、のんびりするのも楽しいかと思います。
もし、5連休の予定が決まっていないようでしたら、新響と一緒に新潟に行きませんか?招待券のお申込み方法につきましては次回維持会ニュースでご案内いたします。宿や新幹線の予約にお困りの際はご相談ください。
また、新響に演奏会のご依頼があれば(日時等の条件があえばですが)どこにでも参じます。通常のコンサート以外の合唱やオペラの伴奏、ミニコンサートなども承ります。よろしくお願いします。
インスペクター事始(ことはじめ)~『魔法使いの弟子』に寄せて~
演奏会プログラムの団員名簿の一画には「インスペクター」という役職がある。運営委員長・演奏委員長と並ぶ謂わば「三権の長」の印象さえあるが、新響に於けるこの役職は練習に関する一切を統括する役職として名実ともに重要な位置づけである。それは新響の活動の主体が3ヶ月に1度の定期演奏会だけでなく、週1回の練習そのものにあるという、最も根本的な理念に基づくものだからにほかならない。
■新響にとっての練習とは
ひと口に「アマチュアオーケストラ」と言うがその活動のあり方は多彩である。概観すると、その主体とする「活動」によって以下のような分類は可能だろう。
①ある演奏会企画のために「その都度」メンバーが募集され、毎回の演奏会ごとに集合・離散を繰返す「団体」。
②永続的な活動を続けてはいるが、自団体だけでは必要な人員を確保できず、毎回の練習に際しては欠員が生じる。演奏会を開催するにはエキストラが不可欠となる。
③自集団のみで演奏に必要となる人員を確保でき、演奏会のみならず毎回の練習そのものを活動の柱として確立し得る団体。
大別すればこの3つで、それぞれに長所はある。アマチュアオーケストラの裾野が拡がり、そこで活動する人々の価値観も自ずから多様になった現在、様々なあり方があって然るべきで、どれが優っているという比較は何も意味しない事は当然である。そしてそれを享受する聴衆の側も、自らの価値観によってどのような活動形態のアマチュアオーケストラを聴き、楽しむかも多様化している。今はそうした時代である。
①の団体は、特定のプログラムを志向するメンバーが集まるため、その完成度は期待できる。が、永続的な団体ではないため、練習場や大型楽器などの手配に絶えず悩まざるを得ない。なまじ共有の資財などを持ってしまうと、その帰順を巡って争論が起こる場合もあるし、1回ごとの演奏会で収支を誤る事が絶対に出来ない。
②の団体・・・というのが所謂「アマチュア・オーケストラ」の大半を占めているのではないだろうか?そこでは常にメンバーの確保に頭を悩ませ、その時々の各人の出席状況によって、練習の「質」が大きく影響される。でもいずれメンバーを揃えて何とか演奏会は実現したい。そこで演奏会の直前から、大量のエキストラが投入され、何とか演奏を披露するまでにこぎつける。
こうしたオーケストラにとっては、そのようにして実現する演奏会こそが、「活動」の根幹と認識される。但し、エキストラという団外人員への依存度が高ければ、財政的にも頻繁に大がかりな演奏会を開く事は難しくなる。年に2回の定期演奏会開催の団体が圧倒的に多いのは、この様な事情が根底にある場合が多い。またそうした満を持した開催の演奏会であるだけに、活動の中心たる位置づけが強まるのである。
③のケースに新響は該当する。新響にとっては毎回の練習そのものが活動の主体である。そのためには各パートに必要となる人員が揃っており、且つそのメンバーが各回の練習に確実に出席する事が前提になる。これを可能にするにはその練習自体が魅力的なものである必要がある。
新響には活動全体の理想を示した「新響総括図」というものがあって、ここに活動のあるべき全容が凝縮されて伝えられている。
そこに練習のあるべき姿(「良い練習とは」)として「充実感・緊張感がある」とか「日々の進歩が感じられる」とか「(新響は)『自分のオケ』であるから積極的に(練習に)参加するという意識の確立」が必須などといった明確な言葉で表現されている。その場限りの脚光を浴びて終わらせる事が可能な「演奏会」ではなく、毎回の「練習」の充実を活動の根幹と考えた芥川先生と先人たちの智慧と炯眼(けいがん)によって、新響は今も磐石な活動理念を保ち得ているのである。
■インスペクターの職務
その練習の要となるインスペクターは、まず練習計画の立案を行うという重要な職務を負っている。立案の為には本番の指揮者は勿論、各トレーナーのスケジュールを確認し、ハープなど特殊楽器のエキストラ奏者がいつ練習に参加できるか?も押さえる。そして練習会場の確保状況を踏まえ、各曲の難易度を勘案して練習内容の比重を考た上で、まとめ上げた計画案を演奏委員会に提示する。
演奏委員会はオーケストラ全体の錬度向上の見地から、その計画の妥当性を検討し、必要に応じて修正を加えて、練習計画が晴れて完成する事になる。この結果次第では新たな練習指導者手配の必要が生じるが、それもインスペクターが行う。現在インスペクターと演奏委員会がこのようにして検討を進めているのは2010年1月のシーズン(本年10月以降)に関する練習計画。3ヶ月に一度、十数回の練習で定期演奏会が巡ってくる新響にあっては、練習計画も常に先々のサイクルで回していかねばならないのである。
インスペクターの職務には、ひとたび完成した計画が円滑に実行されるよう諸事を運ぶ事も当然含まれる。毎回の練習の開始に当たっては、メンバーの出欠その他の状況を把握した上で、その日練習しなければならない内容と時間配分とを指導者と打合せる。この予め打合せられた時間配分は厳密に守られなければならず、いかなる大指揮者が新響の練習に臨み、興が乗ってもう少しこの曲の練習時間を延ばしたいと懇願したとしても、インスペクターが認めなければ、そこであえなく打切りとなる。こうした事を現在はチェロの安田氏が執り行っているが、彼のような緻密な頭脳と性格を持った人格者にして初めて可能な事で、僕が指揮者に役務上とは言え物申せば、大抵はけんかになってしまうだろう。
ともあれこれは練習計画に関する権限が、指揮者ではなく、オーケストラの側にあるというある種の伝統の端的な例であり、その象徴がインスペクターという職務にある事を物語っているとも言える。
■インスペクター事始
さて、そのインスペクター制度だが、これほど「練習」に活動の主体をもつ新響に於いてその歴史は意外に浅い。正式に制度として発足し機能し始めたのは第122回定期演奏会(1989年1月22日)のシーズンからだ。このシーズンで僕はインスペクターとして練習に携わった。そしてこのコンサートの劈頭(へきとう)演奏されたのが『魔法使いの弟子』だった。その意味でこの曲は思い出深く、当時の昔語りをお許しいただきたい。
それまでの新響の練習は芥川先生が音楽監督として仕切られていた。その過酷とさえ言える練習は、まさに「聴衆・指導者・団員の精神力の燃焼を喚起する」と前述の「総括図」に載る先生の言葉そのものだったが、その時間配分も基本的には先生に委ねられており、例えば3曲練習する計画を立てても、2曲で終わってしまうケースが無いとはいえなかった。すると3曲目しか出番の無い管楽器奏者は無駄足になってしまう。そして来るか来ないかわからない出番のために、ひたすら練習場外で待機する団員の存在を産み出す結果をもたらす場合があった。
当時の練習は上野の東京文化会館地下のAリハーサル室で行なわれていた。その部屋前の廊下で、いつ来るともわからない練習に備え、楽器を抱えて待機していた日々を想い出す。隣の空調室に入るとそこで音が出せたので、ウォームアップに余念が無かったが、大ホールで演奏会が行われていれば、音が漏れると言われてそれもかなわなかった。突然リハーサル室内が騒がしくなってメンバー入れ替えの気配がドア越しに伝わってくる。出番が巡ってきたのだ・・・と時計を見ると終了時刻まであと15分!これでは時間的にはもちろん、何ひとつ満足な練習にはなり得ない。
さすがにこれは問題視され、技術委員会(現在の演奏委員会)内で練習内容を管理していこうとの機運ができた。そこで初めて「インスペクター」という名称が新響内でも取沙汰されるようになった。当初ヴィオラ首席奏者の柳澤氏がその任に当たった。指揮者の傍にいて対話し易いという条件もあったろう。
数シーズンでこちらにお鉢が回ってきた。前述のような「待機」を日常体験し、練習内容についてもあれこれケチをつけていたせいだろう(苦笑)。首席奏者でも何でもない一介の団員に話が来るからには、「うるさいあいつにやらせて黙らせよう」との意図が必ずやあった筈である。こちらとしては新響の維新を叫ぶ憂国の「青年将校」(死語でしょうか?)くらいのつもりでいたが、周囲は中味の無い野次ばかり飛ばす初当選の「陣笠代議士」(これも死語?)くらいの目で見ていたに違いない。この時僕は入団6年目、30歳になったかどうかの若造だったが、この役職を経験する事で、当たり前のように行なわれている毎回の練習が、多数の努力の寸分違わぬ組合せの末に成立つ奇蹟と知る事となった。
1988年10月からの新響の練習は、独立したインスペクター制度の下にスタートした。最初にやった事が、個々の練習に於ける内容の詳細時間配分を記した計画表を作成し、それを全団員と指導者とで共有だったのは、これまでの経緯からの当然過ぎる帰結だった。そして自らの職務の基本を、運営委員会と技術委員会とのすり合わせと位置づけた。新響の全活動の両輪となるべきこのふたつの委員会は、その構成員の成立ちの相違もあって、例えば練習の実施に当たっても音楽の理想を追う技術委員会が、それに必要となる実務を把握しているとは限らず、練習の現場には齟齬(そご)が生じがちだったのだ。故に両者の事情の落としどころを調整する役割は、どうしても必要だったという訳である。
この制度も役職も、規約の上では何ら規定が無かった。つまり規約上は存在せず、従って何ら権限を保障されないものだったのだ。故に既存の組織のすきまを縫い合わせ、欠落部分を補足するような役回りに徹する事は、むしろ当たり前と理解していたと言って良い。規約上にインスペクターの名称と役割、そして選出の方法が載ったのは6年後の1994年12月の事と記憶する。この間に毎シーズンの試行錯誤を繰返しながら、インスペクターの職務が次第に確立されて行ったのである。
■結果や如何に=ある時代の終焉=
さて、そのように意気込み盛んに臨んだシーズンだったが、本番の結果は散々だった・・・と思う。当時の新響は本番に於ける成功と失敗の落差が激しかった。そしてしばらく良い結果が続くと思い出したように「フランスもの」のプログラムを掲げ、やると毎回上手くいかないという事を繰返していた(フランスの作品をやって何とかものになってきたのは、2003年1月のプーランクやドビュッシーの演奏からからだろう)。このシーズンは『魔法使いの弟子』のような難曲(という意識さえ無かった)から始まりメインが『幻想交響曲』とあって、老練な山田一雄氏の指揮によってしても御しがたい難物だったのだ。
練習計画がいきなり「改善」された事も団内には動揺があったと今にして思う。社会の大多数の人は一見不合理を感じる事があっても、その改善に向けての急激勝つ大胆な変革を好まない、と知る結果となった。
更に重大な要素があった。それは芥川先生の病状だった。1988年4月に奏楽堂で行なわれたコンサートを最後に先生は体調を崩され、年の後半からは入院中の身だった。病状は新響に伝わらず、何よりも翌年4月に先生の指揮で行なわれる定期の計画をどうしたものかの判断がつかずじまいだったのである。当人から不可能との申し出が無い限り、新響サイドから代わりの指揮者を人選する訳にもいかない・・・時間はどんどん経過してゆき、にもかかわらず何も決まらない・決められない不透明感は、やはり団内にも目に見えぬ影響を与えていたように思う。1988年という年はこうして暮れていった。
明けて1989年1月7日早朝、昭和天皇崩御の報が伝わる。この日は土曜日で、新響の初練習に当たっていた。演奏会を2週間後に控えた最後の仕上げ段階にあったが、昨秋以来続いていた、運動会をはじめとした音響を伴う行事を含め、歌舞音曲を「自粛」する動きの中で、この報に飛び起きると練習会場や指揮者及び団内の幹部に電話をかけまくり、この日の練習を実施するかどうかを検討した。昼までに「実施」の結論を得、閑散とした都心の練習場に団員は揃ったが何となく「こんな日に練習を続けて良いのだろうか?」という気分を引きずった、中途半端なものとなってしまった。
新響はこのような内憂外患を抱えて演奏会に臨む事になってしまった。『魔法使いの弟子』の最初の音が鳴るまで、不安が尽きなかった記憶がよみがえってくる。そしてインスペクターとして終演後の忸怩(じくじ)たる想いもまた。
惨憺たるシーズンが終了した9日後の1月31日の午後、芥川先生の訃報が伝わってきた。いまそれがどのようにしてもたらされたかの記憶がない。覚えているのはその晩、外出先から帰宅途上のタクシーの中で、ラジオから先生死去のニュースが流れてきた事である。その後まっすぐ帰れず、独り呑んだ。
20年という時間が経過し、改めて芥川時代の新響の風景と、昭和という時代の遠さが想い起こされてくる。
ベートーヴェン交響曲第3番「英雄」
維持会の皆様、はじめまして。
昨年8月にオーボエパートに入団しました横田尚子と申します。
大学を卒業し、社会人二年目に入ります。
私は両親が邦楽(尺八、琴)、兄姉も楽器を演奏する環境の中で育ちました。私自身も3歳からピアノを始め、中学高校では、吹奏楽でサックスに没頭し、音楽が生活の大半を占めるという毎日を過ごしてきました。大学では、オーボエの音色に魅かれ、早稲田大学交響楽団でオーボエを始めました。そして、大学オケでのヨーロッパ演奏旅行の体験が、オーケストラへの関心をより深めるものになりました。
憧れの新響に入団することが出来、学生時代に何度も新響の演奏会に足を運んだその舞台に自分が立っているのが夢のようです。
入団して10ヶ月余り、レベルの高さに圧倒されそうな毎日ですが、素晴らしい環境で精進し、技術を磨いていけたらと思います。
今回はベートーヴェン交響曲第3番に乗らせていただきます。
ベートーヴェンの生きた背景を考える上で重要になってくるのが、晩年はほとんど聴こえなかったといわれている耳の障害。先の見えない絶望からハイリゲンシュタットの地で遺書を書いたのです。自身に降りかかる運命に絶望を感じながらも、その壁に立ち向かい、乗り越えるという強い意志が生まれ、ベートーヴェンの中に新しい音楽が湧き上がりました。そして1804年に交響曲第3番を完成させたのです。
題名となっている「英雄」は、この時代の歴史的背景にあるフランス革命でのナポレオンであるとされています。自身の運命との葛藤と、社会に起きている革命の中にある強いエネルギーを、今までにない新しい構成を使って表現しています。
この曲を演奏するにあたって、いくつかの課題がありました。あまりにも有名な曲であるため、自分の中のイメージが先行してしまい、表情をつけ過ぎてしまうということです。
余計な先入観を捨て、楽譜に忠実にというのが難しく、とても重要な課題となりました。また、曲の背景を知ることで、曲に寄り添いながら演奏することの大切さも実感しました。今後、多くの曲に出会っていく中で、それぞれの曲へのアプローチを大切に考え、レベルアップしていけたらと思います。
今後ともご指導の程、宜しくお願い致します。
2009年新潟公演のご案内
新響、再び新潟へ
1996年6月、現在の魚沼市にある小出郷文化会館のオープニングコンサートにおいて、新交響楽団(新響)は縁あって地元の合唱団とベートーヴェン交響曲第9番を共演しました。350名もの大合唱団とそれを支える地元の皆様と共に響き渡った「歓喜の歌」は、大変感動的なものでした。
あれから13年、小出郷文化会館は地域文化の拠点として全国的にも注目される存在となりました。新響もまた首都圏のアマチュアオーケストラを代表する存在として着実に成長を遂げています。今回の公演は新響にとって、新潟の皆様と音楽の喜びを共有できる素晴らしい機会です。
音楽はみんなのもの
新交響楽団は1956年に故芥川也寸志により創立されたオーケストラです。年4回の東京での定期演奏会を中心に、様々な職業・年齢の130名に及ぶ団員により自主運営されています。芥川の「音楽を愛する事にプロもアマチュアもない。音楽はみんなのもの。」という理念に支えられ、意欲的に活動をしてまいりました。演奏する作品に深い共感と探求心を持ち、時間と愛情をかけてアプローチしていくことを信条としており、その演奏は多くのお客様に支持されています。
芥川は作曲家として魅力的な作品を残す一方、指揮者や音楽番組の司会者として、また様々な活動を通して音楽を広め、戦後日本の文化の発展に大きく貢献しました。さらには戦前・戦中の日本人作曲家の作品を、新響との演奏によって復活させ、再評価につなげる功績も残しています。
その没後20年目の今年行われることとなった新潟公演では、芥川の代表作と、彼と同年代人である黛敏郎の作品、そして終生敬愛していたソ連の作曲家ショスタコーヴィチの交響曲を演奏いたします。
指揮は国内外で活躍する小松一彦氏。サンクトペテルブルグ・フィルハーモニーでも指揮をする氏にとってショスタコーヴィチの交響曲第5番は最も得意とする曲のひとつです。また、芥川作曲賞の指揮者を長年務めるなど、日本人作曲家の作品に造詣が深い指揮者でもあります。今回で新響との共演は13回目、息の合った熱い演奏をお届けします。
芥川と黛
「交響管絃楽のための音楽」は1950年芥川25歳の時の作品で、NHK放送開始25周年懸賞募集管弦楽曲に特賞入賞し、出世作となりました。哀愁のある第1楽章と明るく躍動的な第2楽章からなり、どことなく懐かしいけれどおしゃれで在りし日の芥川を思わせる魅力的な曲です。新響はこの曲をこれからも大切に演奏し続けていくでしょう。
黛敏郎は芥川と同じ伊福部昭の弟子で東京音楽学校(現東京藝術大学)の後輩でした。芥川、團伊玖磨と「三人の会」を結成し活動、「題名のない音楽会」の司会を務めるなど芥川と同様に世の中に大きな影響を与えた作曲家でした。
「BUGAKU(舞楽)」はニューヨーク・シティ・バレエの委嘱により1962年に作曲されました。黛は日本古来の文化をテーマにした曲を多く残していますが、舞楽とは舞を伴う雅楽のことで、この曲では笙(しょう)や篳篥(ひちりき)などの伝統的な雅楽器を用いず通常のオーケストラ編成で雅楽特有の響きが表現されています。雅楽の形態を踏襲しながらも前衛的でエネルギッシュな曲です。
ショスタコーヴィチの最高傑作
ショスタコーヴィチは20世紀を代表する大作曲家で15曲もの交響曲を残していますが、その中でも最高傑作とされるのが1937年に作曲された第5番です。人気があり、吹奏楽でもアレンジして演奏される機会が多いようです。
古典的な構成の中に人間の内面が表現されたこの曲は、美しく壮大、そして聴く者の魂を揺さぶります。「革命」という副題で呼ばれることもありますが、そういった政治的背景を抜きに、音楽を楽しんでいただきたい名曲です。
皆様のご来場をお待ちしています。
第206回演奏会ローテーション
| デュカス | シュトラウス | ベートーヴェン | |
| フルート1st | 兼子 | 岡田澪 | 松下 |
| 2nd | 新井 | 藤井 | 丸尾 |
| 3rd | - | 吉田 | - |
| Picc | 岡田充 | 岡田充 | - |
| オーボエ1st | 山口 | 亀井淳 | 堀内 |
| 2nd | 亀井優 | 岩城 | 横田 | 3rd | - | 亀井優 | - |
| コールアングレ | - | 桜井 | - |
| クラリネット1st | 中條 | 中條 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 大藪 | 進藤 |
| D Cl | - | 末村 | - |
| BsCl | 高梨 | 高梨 | - |
| ファゴット1st | 浦 | 浦 | 田川 |
| 2nd | 田川 | 田川 | 長谷川 |
| 3rd | (*) | (*) | - |
| コントラファゴット | 長谷川 | 長谷川 | - |
| ホルン1st | 大原 | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 鵜飼 | 比護 | 園原 |
| 3rd | 比護 | 鵜飼 | 大内 |
| 4th | 市川 | 市川 | - |
| 5th | - | 箭田 | - |
| 6th | - | 大原 | - |
| 7th | - | 大内 | - |
| 8th | - | 園原 | - |
| トランペット1st | 北村 | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 倉田 | 倉田 | 青木 |
| 3rd | - | 中川 | - |
| 4th | - | 北村 | - |
| 5th | - | 野崎 | - |
| 6th | - | 青木 | - |
| コルネット1st | 小出 | - | - |
| コルネット2nd | 中川 | - | - |
| トロンボーン1st | 武田 | 牧 | - |
| 2nd | 志村 | 志村 | - |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | - |
| テューバ | - | 足立 | - |
| ティンパニ | 中川 | 桑形 | 桑形 |
| 大太鼓 | 桑形 | 中川 | - |
| 吊りシンバル | 浦辺 | - | - |
| 合わせシンバル | 桜井 | 桜井 | - |
| トライアングル | 今尾 | 皆月 | - |
| 小太鼓、ガラガラ | - | 今尾 | - |
| グロッケン | 皆月 | - | - |
| ハープ1st | (*) | - | - |
| 2nd | (*) | - | - |
| 1stヴァイオリン | 前田(小松) | 前田(小松) | 堀内(田川) |
| 2ndヴァイオリン | 藤本(大隈) | 藤本(大隈) | 大隈(藤本) |
| ヴィオラ | 柳澤(石井) | 柳澤(石井) | 石井(柳澤) |
| チェロ | 光野(日高) | 光野(日高) | 柳部容(光野) |
| コントラバス | 中野(関口) | 中野(関口) | 関口(中野) |
第206回演奏会のご案内
クラシック音楽は楽しいデスヨ
今回の演奏会は、色彩豊かな交響詩2曲とベートーヴェンの傑作、交響曲第3番です。指揮者は7月の登場が3回目となる山下一史氏。華麗にして明快な棒から繰り出されるエネルギッシュな音楽は、新響にとって大切な存在となっています。
最近はコミック『のだめカンタービレ』が国民的人気となり、クラシック音楽に興味を持たれる方も増えて来ているのではないでしょうか。今回のプログラムはすべてこのコミックに登場する名曲ばかり。クラシック音楽にあまり馴染みのない方も是非生演奏をお楽しみください。
それぞれの主人公
「魔法使いの弟子」は近代フランスの作曲家デュカスの代表作。魔法使いの先生は弟子に雑用を言い渡して出かけ、弟子は見よう見まねの魔法で箒に水汲みをさせるが、魔法を止める方法がわからず水浸しになっていく。いろいろ試してみるも駄目、斧を箒に投げつけて割るが、それぞれが水汲みを続けかえって水が溢れかえる。助けて!その時先生が帰り魔法でおさめ弟子は怒られる、というお話です。ウォルト・ディズニーの音楽映画「ファンタジア」で魔法使いの弟子に扮したミッキーマウスがこの曲に乗ってユーモラスに動く様はご記憶の方も多いでしょう。
リヒャルト・シュトラウスの交響詩の主人公「ティル・オイレンシュピーゲル」は、ドイツに実在したとされる人物。彼の冒険談はおとぎ話となって伝えられています。いたずらをして空飛ぶ長靴で逃走したり、僧侶に扮して人々を説教したり、美しい娘に恋をして騎士の変装で口説くも振られると世の中に復讐を誓い、衒学者(知識や学問をひけらかす人)を相手に難問をふっかけ大論争をくりひろげたり。最後はそれまでの不品行がたたり逮捕され絞首刑となってしまう、というお話です。
ベートーヴェンの交響曲第3番は、当初「ボナパルト」(ナポレオン)と題され、後に作曲者自身により「英雄交響曲、ある英雄の思い出のために」と改められました。この「英雄」が誰であるかは諸説ありますが、雄大で壮快、時には荘厳に、交響曲の中で英雄が語られます。作曲当時、その斬新さゆえ周囲を驚かすほど革命的な存在でした。二百年を経過した今も私たちをワクワクさせる作品であり続けています。
どうぞご期待ください!!
マーラー 最も挑戦的なレパートリー ― 高関健氏にきく
2007年第199回演奏会でのマーラー交響曲第9番の大成功に続き、高関=マーラー第2弾として今回は第6番を取り上げます。徹底した楽譜研究と、入念で緻密な音楽作りで壮大な世界を構築する高関先生は、その誠実な人柄もあって、日本楽壇のリーダーとしての期待が高まっています。今回はお忙しい中、新響との初練習が終わった直後にお話を伺いました。
― 前回高関さんに指揮していただいたマーラーの交響曲第9番は、新響の歴史に残る演奏だったといえます。またこうして第6番で指揮して下さることを非常に嬉しく思います。
高関 ありがとうございます。
― 今回のプログラムを練習してみて、ウェーベルンとマーラーの組み合わせのよさを実感しました。
高関 やっぱりいいですね。作曲時期がほとんど同じ、数年しか違わないわけですから。
■新響初の試み~対向配置
― 今回はオーケストラの配置が対向配置(注1)になっています。これは新響の定期演奏会では初めての試みとなりますが。
高関 私がお願いしましたが、いかがでしょうか(笑)。
― 個人的には、特にマーラーは面白いと思いました。主要テーマや動機がいつもとは違う場所から聴こえたりして移り変わりがよくわかります。対向配置についてこだわりとかありますか。
高関 私がまだ学生で指揮をまじめに勉強し始めた頃に、ふたつの素晴らしいオーケストラが来日したのです。ひとつはムラヴィンスキーとレニングラード・フィル(現在のサンクトペテルブルク・フィル)、もうひとつがクーベリックとバイエルン放送交響楽団でした。この二つのオーケストラが対向配置で演奏していました。その時クーベリックがマーラーの9番を演奏したのです。特に弦楽器の立体的な響きに驚きました。対向配置がこんなに面白いものなのかと、初めて知ったわけです。それ以来、いつかは自分でもやりたいと思っていました。
その後ベルリンへ留学をしたのですが、1982年のベルリン芸術週間でマーラーの全曲演奏が行われて、交響曲も全曲演奏されたのです。1番がムーティとフィラデルフィア、2番がクーベリックとバイエルン放送、3番と7番がハイティンクとアムステルダム・コンセルトヘボウ、4番はユンゲ・ドイチェ・フィル、5番がアバドとロンドン響、8番はベルリン・フィルでテンシュテットの予定だったのですが病気でキャンセルになって、アツモンが振りました。6番と9番がカラヤンとベルリン・フィル、10番のアダージョがバーンスタインとウィーン・フィルでした。どれも素晴らしい演奏で、今でも良く記憶に残っていますが、クーベリックの2番だけが対向配置で演奏され、その効果は圧倒的でした。
マーラーの交響曲では、テーマが第2ヴァイオリンから始まることが多いのです。対向配置では現代の一般的な配置とは逆側の上手(みてか)ら聴こえてくるわけです。そこに下手(しもて)の第1ヴァイオリンが乗ってきて一つ上のパートを演奏する。特に9番ではその傾向が顕著に表れています。左右両側からヴァイオリンが対話するように演奏する対向配置の効果は絶大で、それを使わない手はないと学生時代からずっと思っていたわけです。オーケストラというものは、それこそモンテヴェルディ以来20世紀前半まで、ヴァイオリンはずっと対向に配置されてきました。バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、マーラー、シェーンベルク、バルトーク、すべての作曲家が対向配置を前提に作品を書いています。第2ヴァイオリンが第1の隣に移ったのは1945年以降で、実はここ70~80年の歴史でしかありません。いつか必ず対向配置で演奏したいと思っていたところ、群響や新日本フィルで実現の機会が出てきました。結果的にですが、私は日本では対向配置をかなり早くから取り入れた一人だと自負しています。最初はオーケストラ側の抵抗も大きかったですけれどもね。幾つかのオーケストラからは、はっきりと「いやだ」と言われたこともありました(笑)。最近は理解が進んできたので、やりやすくなりましたね。
― マーラーに限らず、どんな時代の音楽でも対向配置であるべきだとお考えでしょうか。
高関 歴史的な観点からも作曲家が違う配置を指定していない限りは、対向配置で演奏した方が良いと考えています。しかし一晩の演奏会の中でオーケストラの配置が変わるということは、オーケストラにとって非常に負担の大きいことだと思いますから、対向配置にするのだったら一晩を通じて対向でする、それが不可能な場合はしない。たとえばプログラムの中に現代作品が1曲あって、それが通常の配置という指定があれば、対向配置にしないということです。
― オーケストラの配置が対向配置から現在の一般的な配置へ変遷した理由はどのようにお考えでしょうか?
高関 二つあると思います。一つは録音におけるステレオの登場です。ステレオ録音を行った場合、サウンドの方向性を誇示させたいがために高音で軽量の楽器を左に、低音で重量の楽器を右へと配置したのです。その方が音の方向性がわかりやすいですから、当時のレコード会社がこぞって採用したのです。もう一つは第1ヴァイオリンのオクターヴ下や三度下など、同じ動きを取る第2が近くなったことにより、ヴァイオリン間ではお互い演奏しやすくなったことがあります。
ただこれはオーケストラにおける宿命なのですが、第1ヴァイオリンの対向にくるパートはお互いが遠くなってしまい、絶対に合わせにくいのです。合奏で必ず苦労するのが上手のパートで、現代の配置ではヴィオラ、またはチェロにあたります。けれども対向配置にすると、例えば古典派の作品で第1ヴァイオリンがメロディを弾いている時に、中央にいるチェロ(とコントラバス)が低音でアンサンブルを支え、和音を刻むことの多い第2ヴァイオリンとヴィオラがチェロ・バスに合わせて、しかも並んで弾けるという利点があります。
― 最近は日本のオーケストラでも対向配置をよくみかけるようになりました。
高関 そうですね、ずいぶんと増えましたよね。みんなでやろう、やろうと言い始めました。我々にとっては追い風になっています。
■原典版で演奏する意義~ウェーベルン
― ウェーベルンの「6つの小品作品6」、今回は原典版を使いますが如何でしょうか。
高関 私は改訂版で良いと言ったのですよ(笑)。
― ウェーベルン自身による1928年の改訂版では、編成がかなり縮小されているだけでなく、各曲につけられたテンポ・発想標語・標題的なもの(4曲目)が大きく異なっています。こういった変化については、どのようにお考えでしょうか。編成を縮小したことについては、例えば後期ロマン派の流れをそのままひきずった肥大化したオーケストレーションに対して、1928年時点でのウェーベルンにとっては、もっとコンパクトで透明なテクスチュアに対する志向が強まったとも考えられるのですが。
高関 コンパクトで透明なテクスチュアに対する志向が強まった、という観点には大いに賛成します。しかし、もっと現実的な話をしますと、編成を縮小しないと演奏される機会がないからなのです。原典版ではトロンボーンが6人、ティンパニ奏者は3人必要ですが、現実問題として普通のオーケストラの編成ではあり得ない話だと思います。また打楽器はティーフェ・グロッケン(低音の鐘)、ドラ、大太鼓、小太鼓、シンバルが同時に演奏して、その上ティンパニに3人ですから、少なくとも8人必要になってきます。演奏時間が短いにもかかわらず本当に巨大な編成になっています。おそらく「この編成では演奏できない」と言われ続けたことでしょう。1928年の改訂ではトランペットこそ4人必要ですが、トロンボーンも4人に減りましたし、ティンパニは1人、木管は2管編成になりました。これはストラヴィンスキーが「ペトルーシュカ」や「火の鳥」を書き直したことと同じ理由だと思います。
― 編成が大きい原典版を演奏してもらえないから書き直したということであれば、原典版で演奏する価値はあると思うのですが、如何でしょうか。
高関 もちろんあります。
― テンポの設定が変わっていることはどのように考えられるでしょうか。発想標語が大幅に変わっていることも、作曲者が見直したということでしょうか。
高関 指示がより具体的になったということです。ウェーベルンもストラヴィンスキーと同じように自作を良く指揮しました。演奏を繰り返すうちに自然にテンポが上がったり、遅くなっていったりするようになっていったのだろうと思うのです。その結果改訂版ではここは速く設定しようとか、こちらはゆっくりしようとか、そういうことになったのだと想像しています。しかし2曲目の最後のメトリークを例にとりますが、原典版と改訂版でここは発想自体が変化しているのですね。だからその違いをきちんと意識して演奏しなければなりません。
私が作品6をはじめて原典版で演奏したのは1987年11月、サントリー・ホールの作曲家委嘱シリーズでの演奏会です。テーマ作曲家はルイジ・ノーノで、演奏会にあわせて来日されました。サントリー音楽財団がノーノに委嘱した新作を世界初演したのですが、演奏会の最後を飾る曲がウェーベルンの作品6だったのです。その際ノーノは、作品6は絶対に原典版でやりたいと主張されました。ノーノが私のリハーサルを聴いていましてね、先ほどの2曲目の終わりの所で「そこは楽譜ではテンポは変わっていないはずですが。そこのテンポは変えなくてよいのです」と言ったのです。メトリークの読み方は改訂版と違わなければいけないということを、私はノーノから教わりました。因みに、ノーノの奥さんはシェーンベルクの娘さんです。
― では今回は意義がある、ということですね。
高関 大いにあります。
― 今回の演奏では、1928年の改訂版との違いを念頭において、とくに原典版の性格を意識しながら演奏されるということはあるのでしょうか。演奏においての原典版と改訂版との違いは出されますか。
高関 もちろん違いを明確に出します。言い換えれば1928年版の影響を受けないように演奏します。それは例えば「ペトルーシュカ」を演奏する時でも、「火の鳥」の場合でも同じです。楽譜の読み方を峻別しないと、結局は両者を混同してしまいますし、しっかりした演奏にならないと思っています。ですから両版をそれぞれの立場で、違う作品として演奏するようにします。
■マーラーの最終判断を探る~交響曲第6番
― さて話題をマーラーに移します。第6番はダイナミックで精緻なオーケストレーションで力強く生命力に満ち、大胆な対位法と和声を駆使した傑作だと思います。
高関 やはりマーラーの作曲活動の中期を代表する5番、6番、7番の交響曲群は凄い迫力ですよね。5番は対位法を駆使した多声的な書法が顕著に表れていて、実験的なところがあります。対位法に限って言えば、5番が指揮者にとって一番やっかいです。6番の方が古典への回帰が強いと思います。例えば古典的な4楽章構成になっていたり、第1楽章の提示部に繰り返しがついていたりなどです。一方7番になると表現主義が先走ってくるわけです。そういう意味では6番が一番均整のとれた完成度の高い作品だと思います。でもまあ随分規模を大きく書きましたね(笑)。マーラー自身にとっても生涯の絶頂期だったのでしょうね。
― 交響曲第6番に限らず、マーラーの楽譜には多くの版が存在します。また中間楽章である第2楽章と第3楽章の配置についてはどのようにお考えでしょうか。今回は第2楽章=アンダンテ・モデラート、第3楽章=スケルツォという順で演奏しますが。
高関 第6交響曲の校訂に関する重要な資料としては①自筆原稿、②版下(写譜師による筆写譜)、③初版のための校正刷り、④初版(大型および小型スコア)、⑤初版小型スコアの重版、⑥改訂新版、⑦その改訂新版にマーラー自身の訂正の入ったコピー(指揮者メンゲルベルク所有)、⑧初演に先立つウィーンでの試演(1906年5月1日、ウィーン・フィルによる)および初演(1906年5月27日、エッセン)で使われた管打楽器のパート譜(手書きのパート譜で、マーラー自身の手による書き込みが多数含まれる)、⑨そして1963年出版の第1次全集版、エルヴィン・ラッツ(Erwin Ratz)校訂、以上の9つが挙げられます。
初演は全ドイツ音楽協会音楽祭のフィナーレを飾る公演として、マーラー自身の指揮によって行われました。聴衆の大部分が音楽家だったこともあり、演奏会にあわせて大型および小型スコア(上掲の④にあたる)、ツェムリンスキー編曲によるピアノ連弾版と、音楽学者シュペヒトによる詳細な曲目解説が事前に出版されたのです。つまり聴衆は初演に先立って勉強することができたわけです。これは6番に限って行われたことです。初演には友人であったリヒャルト・シュトラウスも立ち会っています。
さて第2、第3楽章の演奏順についてですが、マーラー自身中間楽章の演奏順については何度か逡巡していたようです。初版(④)では、第2楽章=スケルツォ、第3楽章=アンダンテの順で印刷されています。しかしマーラーは既に楽譜が出来上がっているにもかかわらず、練習の間に、どうも最終日の練習のようですが、楽章の順番を入れ変えてしまいました。初演当日のプログラムには「第2楽章=アンダンテ、第3楽章=スケルツォの順で演奏することに決定した」という内容のメモが挿し込まれ、実際に初演はその通りの順で演奏されたことが確認されています。
小型スコア、初版、カーント出版、ライプツィヒ、1906年、楽章の入れ替えについての作曲家の希望が書き込まれた紙片がはさみこまれている(ウィーン楽友協会所蔵)
― なぜそのようなことをしたのでしょうか。
高関 まずマーラーが作曲をした時点で構成がはっきりしなかった事があります。両端の楽章があまりに確固としているので、中間については、ある意味どちらでも良かったのだと思います。演奏してみて決めたい、という部分があったようです。その後、マーラーは第6番を2回指揮しましたが、ともに「アンダンテ―スケルツォ」の順で演奏しました。また出版の上でも、初版小型スコアの重版(⑤)と改訂新版(⑥)では「アンダンテ―スケルツォ」の順に入れ替えられています。
作曲者の死後、1919年にウィレム・メンゲルベルクがアムステルダムで第6番を演奏することをアルマ・マーラーに知らせたところ、アルマから「まずスケルツォ、その後にアンダンテを。」という電報が入り、メンゲルベルクはそれを作曲者の最後の意向と受取って、楽章順を入れ替えて「スケルツォ―アンダンテ」の順で演奏しています。それから、ラッツ校訂の第1次全集版(⑨、1963)では初版の形「スケルツォ―アンダンテ」に戻されましたが、これはラッツが当時健在であったアルマと個人的にも親しく、アルマに意見を求めたことに原因があるようです。
ところでアルマ・マーラーは思い込みの強い、はっきり言って勘違いの多い人格のようです。彼女は自分にとって都合のよいようにしばしば事実を意図的に改変していると指摘されていますし、晩年に書いた「回想録」も脚色だらけと言われています。アルマの証言は間違っているという研究書もたくさん出つつあります。マーラーとリヒャルト・シュトラウスの交換書簡はもう出版されていますし、マーラーの書簡全集もこれから出版されますので、事実関係についてはこれから徐々に真実が明らかにされてくると思います。
楽譜の校訂の問題についてですが、ご存じの通りマーラー自身が卓越した指揮者でもあったので、演奏の度に自分の理想とする響きをめざしてどんどん改訂を重ねていくわけです。しかしこうした改訂は出版の段階から始まっていて、第6番においても、すでに版下(②)および校正刷り(③)にも数多くの変更がマーラー自身の手によって書き込まれています。その後いよいよリハーサルの段階に入り、本格的な変更が加えられていきます。ウィーンでの試演とエッセンでの初演に使われた管打楽器のパート譜(⑧)にはそうした変更がマーラー自身、あるいは助手の手によって書き込まれています。先ほどの校正刷り(③)をマーラーは初演の指揮で実際に使った形跡もあるようで、リハーサル時の変更も多く書き込まれています。
1931年に来日し東京音楽学校(現東京藝術大学)の作曲教師に就任したクラウス・プリングスハイムは、第6番の初演時に23歳でマーラーのアシスタントを務めました。彼は初演時の変更の過程を全部知っていて、後に回想を書き残しています。特に6番は出版を初演前に間に合わせるという時間的な制約が課せられたため、限られた時間の中での改訂作業は煩雑を極めたそうです。そしていよいよウィーンでの試演に入ると、マーラーは休憩中には直し、食事をしていても直すといった具合に、文字通り寝る間も惜しんで、初演の本当にぎりぎりまで改訂を加えたそうです。ですが例えば訂正をパート譜に書きこんだにもかかわらず自分のスコアに書き入れるのを忘れた、などということがとても多かったのです。それをプリングスハイムが懸命にまとめたのですが、結局まとめきれずに終わってしまった部分もあったようです。しかしこうした改訂の多くは改訂新版(⑥)に取り入れられ、ラッツ校訂の第1次全集版(⑨)の基になったわけです。
― そのプリングスハイムはマーラーの重要な作品の本邦初演を手掛けることになりますね。昭和9年(1934年)第6番の日本初演資料として「東京藝術大学百年史:演奏会篇第二巻」を持参しました。日比谷公会堂で行なわれた東京音楽学校の第70回の定期演奏会で、メンバー表が記載されており、ティーフェ・グロッケンを山田一雄先生が叩いています。
高関 これは面白い資料ですね。しかもこのメンバー表は凄い、ほんとうに「山田和男」としてお名前が載っていますね。金子登さんがファゴットで、安倍幸明さんがチェロを弾いていたり。ヴァイオリンには兎束龍夫先生のお名前も載っていますよ。
― その時の舞台写真がこの資料にありまして、やはり対向配置なんですよ(笑)。
高関 ほら、そうでしょう?(爆笑)
― それと面白いのは、第2楽章がアンダンテなのです。
高関 やっぱりそうだ!(笑)。マーラーを演奏するために楽譜を研究し続けているうちに、国際グスタフ・マーラー協会と仲良くなってしまいましてね(笑)。特に主任研究員のラインホルト・クビーク(Reinhold Kubik)博士(国際グスタフ・マーラー協会副会長)と親しくやり取りを交わすようになりました。第2番、7番、そして先日の9番でもそうでしたが、昨年群響で6番を演奏する際に、博士から「一番新しい版を持っているか」と尋ねられたので、「もちろん持っている」と答えました。続けて博士から「1998年版のカテゴリーⅢ」というのが大事だから、これは今回スコアには直接書き込まなかったけれどもぜひやって欲しい」と言われたのです。それで実際に「カテゴリーⅢ」を書き込んで演奏してみたのですが、ここはちょっとおかしいのではないかと思った点がいくつか出てきました。そこでその部分を指摘したところ、今後新しい校訂版を出す際の校訂報告の下書きを送ってくれたのです。まだゲラの状態で、譜例は書かれていませんでした。たとえば「ここは初版と同じ」とか、「ここは改訂新版と同じ」などと、文字でしか書かれていなかったのです。博士は「譜例がないから判りにくいとは思うけれども」と言ってくれたのですが、初版(④)と改訂新版(⑥)を持っていれば判ることなので、それを参考にして私が自分で全部パート譜に書き込みました。
― それでは今回、最も新しいとされている版に、さらに新しい情報をプラスアルファしているというわけですね。
高関 そうです。クビーク博士からの最新情報を反映させているのですから、今回が更に最新版となるわけです。このように6番の第2次全集版は現在クビーク博士を中心に校訂作業が進んでいます。新しい校訂では特にメンゲルベルクが演奏に使っていたマーラーの改訂の書き込み入りのスコア(上掲の⑦)と初演に使われたパート譜(⑧)の研究が要点とされているようです。
メンゲルベルクはマーラーの作品を何度も演奏して、また個人的にも親交を深めたので、彼が使ったスコアにはマーラーの意思が相当反映されていると言われています。6番でも初演からそう時間を経ないうちに、マーラーにアムステルダムでの自作自演を依頼しています。結局多忙のため実現しませんでしたが、後にメンゲルベルク自身が演奏を計画し、そのためにマーラーから訂正の入ったスコアを2度にわたって借り受けています。2回目に借りたのが1907年の1月末ですが、これはマーラー自身がウィーンで演奏した直後で、自作自演の最終回にあたります。メンゲルベルクはマーラーを心から尊敬し、しかも非常に誠意あふれる人だったそうで、マーラーの改訂を綿密に自分のスコアに書き込んでいます。また他の作品で、マーラーがアムステルダムで自作自演を行った折には、すべての練習から本番に出席して、特にマーラーが練習で指示したことを、テンポや表情を含め具体的な形でスコアにメモしています。ですから、メンゲルベルクのスコアにはマーラーの最終判断がそのまま書き込まれている、ということもできるのです。しかしマーラー自身の初演に使われたパート譜との間に違いが多く見られるようで、現在はその点を中心に研究が進んでいます。
それから中間楽章のことに戻りますが、私も資料を持ってきています。マーラー協会のホームページからもアクセス出来る資料(注2)ですが、これは「第2楽章にはアンダンテをもってくるべきだ」という論文です。最近の研究成果をまとめたもので、クビーク博士の論文も掲載されています。国際マーラー協会の最終判断として、ラッツの第1次全集版を批判し、「アンダンテ―スケルツォ」の順で演奏してほしいということがホームページ上で掲示されています。この論文はそれを補強するためにカプラン財団の協力の許に公開されています。
― この論文が発表された後でも、相変わらず通常通り演奏されていますが。
高関 1998年に最新版が出た当時は前任者との共同作業だったので、楽章を入れ替えることまではできなかったようです。来るべき第2次全集版では「アンダンテ―スケルツォ」の順で出版されるので、その後はこの順番が定着していくでしょう。
― アルマ・マーラーの回想にある第4楽章に使用されるハンマーに関しての記述に「英雄は運命の打撃を3度受ける。最後の一撃が、木を切り倒すように彼を倒す」とあります。これも嘘かもしれないということですか。
高関 かなり脚色があると思います。ハンマーの打撃についてですが、作曲当初は第4楽章が始まってすぐの9小節目、それから再現部の冒頭にあたる530小節目にも入っていたので、問題の最終回、783小節とあわせて5回あったのです。そのうちの2回を削って3回になったところで出版して、そして練習の段階で最後の3回目をやめたのです。一般的に3回目をものすごく強く演奏することが多いですが、あそこは実は、管打楽器に対して改訂後はフォルテ1つですね。最初はフォルテ2つだったところを、フォルテ1つに直しています。ですから最後は弱々しく演奏しないといけない、「もう立ち向かう気力もない」というように演奏しなければならないのです。それからマーラーは改訂の段階で打楽器のパートを徹底的に削っています。今回クビーク博士の新しい校訂報告に基づいて削った分を別にしても、初版から改訂新版までに全体の3分の1近くを削っています。初版を参照していただくと打楽器パートの異様さにむしろ驚かれるはずです。
― 例えばハンマーのように楽器以外のものを打楽器として使うという発想は、どこから生じたのでしょうか。
高関 作曲当初の自筆原稿にはハンマーは書かれてはいないのです。最初はイメージとしてはっきりしたものは無かったらしいです。その代りに色鉛筆で星印が書いてあるのです。それがだんだんとイメージが固まってきて、最初は鈍い音とか書いて、そのあとハンマーを加筆したのです。ですがハンマーというと金槌のような金属的な音が出てしまうので、nicht metallischem Charakter(金属的ではない)という言葉を書き入れ、しかも後に括弧付きで“(wie ein Axthieb)”(斧の一撃のように)と補強しています。
― 一般的に日本では「悲劇的」と副題がついておりますが、どのようにお考えですか。
高関 マーラーは最初に表題を書いて、最後にそれをはずすことが多いのです。1907年の1月にウィーンで初演した時のプログラムには、確かに“Tragische”(悲劇的)という副題がついています。ですがスコアには一度も表題としては印刷されませんでした。でもそうした発想自体が存在したことは確かにあったのだと思います。
― 「悲劇的」という言葉の感じ方についてはどのようにお考えですか。
高関 日本人の我々が思う悲惨なイメージの「悲劇」というよりも、「劇的」に近い印象ではないでしょうか。例えばギリシア悲劇のような、演劇的な発想だと思います。
― 高関さんにとってマーラーはライフワークですか。
高関 そう思います。マーラーはオーケストラを指揮する人間なら誰でも一度は振ってみたいはずです。合わない人もいるかもしれませんが、オーケストラで演奏会をするとすれば、最もチャレンジングなレパートリーだと思います。第6番よりもさらに編成の大きな曲もありますし、また演奏時間の長い曲もあるのですが、構想の壮大さや幅広いダイナミクス、そして心情の克明な描写などマーラーほど魅力的な作品を書いた人はいません。また指揮者に対する要求も大変厳しいので、私みたいなものにとってもそれがどこまで実現できるのか、非常に興味があるスコアとなっています。そういった意味でも非常に好きですよね、やっぱり。そしてこうして皆さんと演奏出来ることは何よりも楽しいのですけれどね。
― 今回、新響に期待することがありましたらお願いします。
高関 今日の初練習でもう全楽章通っちゃったからね(爆笑)。本当に素晴らしいな、と思います。これからもっと先へ練習を進めて行くことができますね。
(注1)本日の演奏会における配置(対向配置)
(注2)http://posthorn.com/Mahler/Correct_Movement_Order_III.pdf
写真撮影:桜井哲雄(オーボエ)
まとめ・構成:藤井 泉(ピアノ)
マーラー:交響曲第6番
■ハンマーを巡って
『悲劇的』が演奏されるとなると、そこには必ずそのオーケストラ独自のハンマーが登場する事になる。楽員そして聴衆の感嘆・呆然・失笑が渾然一体となった束の間の賞賛を浴びては忘れ去られるこの「楽器」は、言うなれば死と再生を繰返しながら、着実に巨大化の道を歩んできた。
確かに最終楽章の大音響の中でこのハンマーの効果を引き出す事は難しい。そこで音量を補強する手段としてハンマーの質量増大が図られる。これは人類の限りない欲望の肥大と同様に、不可逆的な道筋となって久しい。前回よりサイズを小さくしましょうという声は、世界中の核兵器を廃絶しましょうというに等しく、誰もその実現を信じていない。どこのオーケストラがどんなハンマーを使い、いかなる末路を辿 たどったかも耳に入る。かくしてハンマーの大型化は更に加速され、それはひとたび振り下ろされるや、人間の運命の変転よろしく奏者のコントロールを離れてしまい、指揮者はひたすら落下するハンマーの到達点を見定めて、オーケストラに出を合図せざるを得ないという段階にまで、今や事態は深刻化しているのである。今世紀中には人力の及ばぬところまで極大化するだろう。
マーラーはこのハンマーのパートを、総譜を脱稿した後に書き加えた。「金属的ではない性質の音。(斧を打ち込むように)」との指定がある。言うまでもなくハンマーは楽器ではない。打楽器として転用するにせよ、それは叩く為の道具であって、叩くべき発音体がなければならない。鐘を撞(つ)いて鳴るのは鐘であって撞木(しゅもく)ではない道理である(そしていくら撞木を大きくしても、鐘の音量は上がらない)。ところが作曲者は何を叩くかを指定せず、ただ音のイメージのみ示す。そこで一応は叩くべき対象について打楽器奏者は思案する。が、結局それよりは前述の通り、作曲家が指定しているハンマーの、サイズや仕様に帰着させてしまう傾向がある。基本的には指揮者も彼らの自主性に任せ、既存の楽器と組合せて現実の音を補強する挙に出る。と、その時点でハンマーは聴衆に対し、聴覚よりは視覚に訴え、彼らに実際以上の音を連想させる効果をもたらすべき象徴へと変質を遂げる。ここに於いてハンマーの無軌道且つ無謀とも見える巨大化は、音量を拡大する手段としては間違っているが、作曲者の意図を象徴する道具立てという意味では極めて正しいという結論が導き出される訳である。
では新響のハンマーはどうか?というと、巨大化路線には与(くみ)せず、叩くべき発音体の追求に力点が置かれている。所詮ハンマーは叩くための道具に過ぎぬという方針は、『悲劇的』を初めて演奏した1980年以来30年間、一貫して冷徹なまでに堅持されているのである。さすがというべきであろう(ちょっと 淋しい気もするが…)。
ハンマーによる打撃は当初5回書き入れられていた。その後3回に減らされ、初演では最終的に2回となった。だから妻であったアルマの語る、初演翌年の1907年に訪れるマーラーの人生への3つの打撃(長女の死・死病となった心臓病の判明・ウィーン宮廷歌劇場との訣別)の暗示とこれを解するのは、あとづけの理屈にもなっていない。この作品を書いた1903~4年はマーラーの人生に於いて順風満帆の時期だった。いま思えばあの時がピークだったとその後の結果を知る人は、そこに何らかの衰微の兆しを見出す事でひとつの物語を完結させようと努めがちである。マーラーの死後30年を経て語られたアルマの回想が、そうした「因果」の物語に満ちている事には、よくよくの注意を払わねばなるまい。
■『悲劇的』の誕生
グスタフ・マーラーは1911年に51歳を目前に死んだ。その生涯に生み出した作品数は決して多くはない。音楽大事典に載るその全作品リストは2ページに満たない(「M」つながりで言えば同書に見えるモーツァルトのそれは25ページに及ぶ)。彼はウィーンの音楽院で作曲を学んだものの卒業時のコンクール選考に落ち、指揮者としてスタートした。ヨーロッパ各地の劇場を転々とし、37歳(1897年)でウィーン宮廷歌劇場の音楽監督の地位に登りつめる。この悲願の実現に際し、ユダヤ人たる彼はカトリックへの改宗に踏み切っている。ヨーロッパ最高峰、という事は世界最高峰の指揮者としての多忙な日々…年間に100回もの演奏会(勿論練習は別にある)…の中で、2ヶ月弱の夏の休暇期間だけが自らの創作に許された時間だった。
限られた時間の中で彼の創作の主体となった交響曲は、最初期段階から従来このジャンルの作品が持っていた「時間の経過に伴う発展と終結」にこだわらぬスタイルを持っていた。それは例えばテーマの発展性に対する無関心であり、ソナタ形式からの離脱であり、楽章間の調的な連続性を含めた関連性の否定といったものある。卑俗な音楽をも採りこんだ作品は、ベートーヴェン以来の交響曲になじんだ聴衆に「つぎはぎだらけ」の印象をもたらし、故に指揮者の余技に過ぎぬとの非難も受けた。そうして最初の4曲の交響曲は書かれた。これらは並行して創作された彼の歌曲と密接な関係がある。20世紀を迎えて以降に書いた3曲の交響曲群は、様々な特殊楽器と前世紀に発達を遂げた管楽器を含んだ大編成の純器楽作品で、ウィーン宮廷歌劇場のオーケストラを掌中にしたマーラーにして、初めて完成し得た世 界だった。
さて第6交響曲である。マーラーの全11曲の交響曲中ちょうど中間に位置するこの作品は、ソナタ形式(もちろん極度に複雑化している)による両端の楽章を備え、全曲に一貫するテーマをもつなど、ほぼ唯一古典的スタイルを保ち、彼のそれまで「交響曲」とは一線を画している。
イ短調で書かれた交響曲は何故かこの作品以前には余り例がない(『スコットランド』くらいだろうか)が、それに加えて他の主要楽章もその調性に基づいているという一貫性。楽章間の調的関係についてこだわりを見せなかった作曲者が、こうしたスタイルを堅持している事はもっと注目されて良いだろう。この調性の持つ色調(トーン)が作品全体を覆い、交響曲としての統一感をもたらしている事は間違いないのだから。
そしてこの色調ゆえに『悲劇的』の名も定着している。作曲者による命名ではないが、初演時のプログラムの表紙に既にそれは明示されており、指揮をしたマーラーもこれに頓着しなかった。聴衆は新しい音楽に込められている意味を見出すためのヒントを常に求める。それが片言であっても構わない。むしろ作品全体のムードを象徴する、気の利いたひと言を好む。そんな手垢じみた空疎な一言で作品が表現され得るものなら、作曲家は複雑で長大な音楽など書く必要もないのだが。マーラーは最初の交響曲に『巨人』の標題を用いたが、その標題と音楽の細部との関連について説明を求められる煩雑さ故に、これを撤回している。第3交響曲には楽章ごとに標題を付したが、やはり後に全て取り去った。このように標題によって作品の持つ多面性が損なわれる事を避けようと行動した同じ人物が、第6交響曲のみ看過した真意は最早わからない。
「私の『第6番』は、私の最初の5つの交響曲を吸収し、それを真に消化した世代だけが、その解決を企てうる謎を提供するだろう」とはマーラーの書簡にある言葉である。晦渋(かいじゅう)な言葉だが、これまでの自身の交響曲の集大成を産み出した自信が伝わる。それが『悲劇的』の名を敢えて黙認するだけの余裕を、作曲者に与えていたと解すべきだろうか。
■第1楽章
マーラー特有の行進曲風の出だし。やがてこの作品に一貫する長和音→短和音のハーモニーの変転と打楽器による示導動機=「モットー」が現れる。次いでノスタルジックな旋律が提示される。アルマはこれを作曲者が与えた自分へのテーマと回想しているが、ソナタ形式の各主題としての対照性を際立たせている事の方がよほど重要だ。この2つの主題の提示部はマーラーの交響曲としては例外的に繰返される。
途中チェレスタを伴ってカウベルが彼方から響く。作曲者はこれを「非音楽的な日常の響きの断片」となるように奏者に指示する一方で、「この演奏上の注意は、決して標題的な意味をもたらさないということ、その事ははっきり釘を刺しておきたい」と、具体的な情景と無縁である事を強調している。
イ長調(同主調)に転じた第2主題を以って楽章は締めくくられる。
■第2楽章
楽章配置に最後まで迷ったものの、初演を含めマーラー自身が指揮をした演奏は全てここに緩徐楽章を置いている。古典的な楽章配列に落ち着いたわけである。
特徴のある跳躍の音型が動機となって、楽章全体を覆う。めまぐるしい転調の中で音響の色彩変化が繰返されるが、主調に戻り静謐(せいひつ)の中で終結する。
■第3楽章
激情・無邪気・グロテスクといったあらゆる感情の錯綜する楽章と言える。スケルツォと題されてはいるが、激情の部分については第1楽章に通じる部分を持っている(同じイ短調)。続けて演奏されれば楽章の転換の気分は表れにくく、作曲者が配置を変えた理由のひとつと言われる。トリオにあたる部分は長調に転調し、拍子もめまぐるしく変わる。アルマは、マーラーとの間に設けたふたりの娘がよちよち歩く様の描写であり、やがてそれが長女の死に向かう楽想であると回想しているが、次女はこの作曲の最中に生まれたばかりであり、「ふたりの娘」の描写と矛盾する。ここにも彼女の牽強付会(けんきょうふかい)がある。
モットーの長和音→短和音が繰返し現れながら次第に弱まって終わる。
■第4楽章
マーラーの書いた最長の楽章のひとつ。ここだけで約30分かかる。長い序奏が入る最終楽章も彼の交響曲にはあまり無いスタイルである。このテーマは都合3回現れ、その都度モットーにつながっていく。
ハンマーの打撃は、速度を速めた音楽の最高潮に1度、そして退潮の兆しが明確になった曲調を再度奮い立たせるために1度加えられている。当初考えられていた最後の打撃は3度目に楽章冒頭のテーマが現れる箇所であり、既に全体の音量も下がっている。これを「英雄への最後の一撃」と解する向きもあるが(作曲者がそうコメントしたという)、この部分にのみそうした具体性を追っても他の楽章から一貫したテーマが見えてくる訳ではない。せいぜいがこの楽章に限定された「気分」にすぎない。
楽章冒頭の葬送的な旋律が金管群によって奏されたのち、打楽器を含むモットーが短和音のまま現れ て、断ち切られたように突然終わる。
主要参考文献
『音楽大事典』(平凡社)
『マーラー 全作品解説事典』長木誠司(立風書房)
『マーラー-音楽的観相学』アドルノ(法政大学出版局)
『グスタフ・マーラー 愛と苦悩の回想』アルマ・マーラー 石井宏訳(中公文庫)
『グスタフ・マーラー 生涯と作品』クルシェネク/レートリヒ 和田旦訳(みすず書房)
『ウィーン音楽文化史』渡辺護(音楽之友社)
『文化史の中のマーラー』渡辺裕(ちくまライブラリー)
『音楽の現代史』諸井誠(岩波新書)
『マーラー』村井翔(音楽之友社) 他
初 演:1906年5月27日エッセン 全ドイツ音楽連盟音楽祭にて作曲者自身の指揮による
楽器編成:ピッコロ、フルート4(3・4番はピッコロ持替)、オーボエ4(3・4番はコールアングレ持替)、コールアングレ、Esクラリネット(クラリネット持替)、クラリネット3、バスクラリネット、ファゴット4、コントラファゴット、ホルン8、トランペット6、トロンボーン3、バストロンボーン、バステューバ、ハープ2、チェレスタ、ティンパニ(奏者2人)、大太鼓、シンバル(合わせ-複数・吊り)、トライアングル(複数)、小太鼓2、タムタム、ハンマー、ルーテ(ムチ)、ヘルデングロッケン(カウベル・複数)、低音の鐘(複数)、シロフォン、グロッケンシュピール、弦五部
ウェーベルン:管弦楽のための6つの小品
ウェーベルンの「オーケストラのための6つの小品」は、今からちょうど100年前にあたる1909年に作曲された。この時期は、彼が生きていた世紀転換期ウィーンの文化にとって、大きなターニングポイントにあたり、その意味でも非常に興味深い作品である。
1890年頃から第一次世界大戦が始まる1914年頃のウィーンの文化・社会は、一般に「世紀末ウィーン」という言葉で言い表されている。この時代には、それまでの貴族や富裕な市民層の文化・価値観に対して、文学・美術・工芸・建築・音楽などさまざまな領域で、相互に密接にかかわりつつ、この時期に集中して革新運動が展開されていった。画家のグスタフ・クリムト、作曲家グスタフ・マーラー、あるい はウィーン観光の目玉の一つである「分離派館」の設計者オルブリヒなどは、「世紀末ウィーン」の最 初の世代の芸術家たちである。
それに対して、それらを乗り越えていこうとする、さらに革新的な芸術家たちが20世紀にはいって躍進してくる。強烈にデフォルメされた表現で内面を赤裸々に描出する画家のココシュカ、エゴン・シーレ、 装飾を廃し機能性・構造性そのものの表現のうちに現代の建築の価値を求めたアドルフ・ロース、そして、「不協和音の解放」を推し進めることによって、伝統的な音楽における中心的な基盤である調性を解体したシェーンベルクとその弟子たち(ウェーベルン、ベルクら)は、そのもっとも代表的な芸術家である。こういった転換を考えるとき、1908年という年は特に重要な意味をもっている。建築家アドルフ・ロースが、装飾批判の姿勢を明確に打ち出すエッセイ「装飾と犯罪」を発表したのが1908年であり、またウェーベルンの師シェーンベルクが、いわゆる「無調性」へと移行したのも1908年だった。マーラーがウィーン宮廷歌劇場の監督を1907年に辞任したのも象徴的な出来事といえるかもしれない。ウェーベルンも、シェーンベルクと同じ時期に調性を放棄した作品を作曲し始める。「6つの小品」も、ウェーベルンの無調性の時代における最初の重要な作品の一つである。今日演奏される二つの曲は、ウィーンという街に生きた二人の作曲家のほぼ同じ時期の作品でありながら、1904年に完成されたマーラーの交響曲第6番と、1909年に作曲されたウェーベルンの「6つの小品」のあいだに、どれほど大きな隔たりがあるかを感じ取っていただけるのではないだろうか。
「調性」を放棄することによって作品の構成原理を失うことになり、無調期のシェーンベルクには、緊張が保たれる短時間のうちに表現が完結する作品か、あるいは時間的持続をテクストに依拠する作品かのいずれかの可能性しか残されていなかった、ということが一般にいわれている。そういったとらえ方に立てば、ウェーベルンの「6つの小品」も、短い時間のうちに表現が収束する代表的な作品の一つということになる(とくに短い第3曲は、たった11小節しかない)。しかし、しばしば「アフォリズム的様式」という言葉を当てはめられるこれら小品は、そういった消極的な理由による創作の結果といったものをはるかに越えて、まさに「アフォリズム」という凝縮された文学形式に対応するような強力で緊張感に満ちた表現様式をもっているといえるだろう。
「6つの小品」を実際に耳にすると、かなり抽象的な作品であるという印象を受けるかもしれない。しかし、このそれぞれの曲には、きわめて具体的なウェーベルンの個人的体験によって与えられたイメージがかかわっているということを、作曲者自身が語っている。今日演奏される1909年の初版では、第4曲目に「葬送行進曲(marcia funebre)」という標題が添えられているが、これは直接的には、この曲が作曲される3年前(1906年)の母の死と結びついている。ウェーベルンは、1906年に母親が亡くなった後、折にふれその悲しみについて言及しており、この「6つの小品」に限らず、彼の作品の多くには、母親の死という奥深い体験の影がつきまとっているようだ。「6つの小品」は、この経験がもっとも直接的なかたちで現れている作品で、初演の数週間前の1913年1月13日にシェーンベルクに宛てた手紙の中で、ウェーベルンは、それぞれの曲の根底にある心的状態や出来事について次のように述べている。
「第1曲は、私がまだウィーンにいた時の私の心情を表現しようとしています。そのとき私は、不幸を予感しながらも、生きているうちに母に会えるのではないかとそれでも希望を抱いていました。その日は天気の良い日で、一分間ほどは、何も起こってはいないのだと確信していたのです。(第2曲)ケルンテンへ汽車で向かう途上、それはまさにその日の午後のことだったのですが、その事実を知ることになりました。第3曲は、エリカの香りの印象です。このエリカの花は、森の中の私にとってとても意義深い場所で摘みとったもので、私はこれを棺架の上に置いたのです。第4曲目には、あとになって「葬送行進曲」という標題を与えました。私は今でもまだ、棺の後ろを墓地へと歩いて行ったこの時の私の感情を理解できません。わかっているのはただ、そのあいだずっと、背筋をぴんと伸ばして歩いて行ったということだけです。それはもしかすると、広い範囲にわたってあらゆる低俗なものの力を退けるためだったのかもしれません。私の申し上げることを正しく理解していただきたいのですが、私はこの独特な状態について明らかにしたいと思っているのです。私はこのことはまだ誰にも話したことがないのですが、埋葬が終わった晩はほんとうに不思議でした。(第5・6曲)私は妻[当時の妻ヴィルヘルミーネ]と連れだってもう一度墓地へと足を運び、埋葬された塚に供えられた花環や花束をきれいにととのえました。私はいつも、母と身体的に近いと感じていました。わたしには母がやさしく微笑んでいるのが見えました。それは一瞬のことでしたが、至福の感覚でした。その後、2回の夏[実際には、3回の夏]がすぎて、ようやくまた自分の家に戻ることになりましたが、その夏の終わりにこれらの曲〔「6つの小品」〕を書いたのです。私は毎日、夕方頃に墓を訪れました。もう夕暮れですっかり暗くなっていることもよくありました。」
さらに1933年、1928年に改訂されたこの曲が演奏される機会に、ウェーベルンは次のような短いコメ ントをある音楽雑誌に書いている。
「この曲は、その多くが3部形式だという意味で、短い歌曲の形式を取っている。主題的な連関は、それぞれの曲の内部においても存在しない。そういったものを与えなかったのは、意識的に行ったことでもある。次々に変化してゆく表現を求めていたからだ。これらの小品――純粋に抒情的性質をもつ――の性格を簡単に述べると、第1曲はある不幸の予感を、そして第2曲目はそれがほんとうにそうなったという確信を表している。第3曲は、きわめて繊細な対立・コントラストを表す。それはある意味で、第4曲、葬送行進曲への導入となっている。第5曲、第6曲はエピローグ――回想と諦念――である。この作品は1928年に、新しく楽器編成を行った稿を重ねることになった。この改定稿は、初稿に対してきわめて簡潔なものとなっており、唯一有効なものと考えている。」
1933年に書かれたこのコメントは、十二音技法時代のウェーベルンによって書かれたものだということをまず念頭においておく必要がある。このときのウェーベルンにとっては、無調性の時代に入ったばかりの1909年のこの曲の巨大なオーケストレーションに対して、より簡潔で透明性を増した改訂版が正しいものと考えられていたということになる。しかし、逆にいえば、無調性の時代の初稿は、改訂版とはまったく異なる志向を持つ作品として独自の価値を持つということもいえるだろう。
それはともかくとして、作曲家自身によるこれら二つのコメントから、この「6つの小品」を形成しているある明確なイメージ、あるいは母親の死にまつわる「物語」が浮かび上がってくる。それは、確かに、そのとき体験されたさまざまな心情や出来事が、6つの曲においていわば時系列的に並べられることによって出来上がる物語である。しかし、それと同時に、1933年のコメントでこれらの小品が「純粋に抒情的性質をもつ」と述べられていることを見逃すべきではないだろう。「抒情的」とは、「叙事的」に対置される言葉として、「物語」として語られるものではなく、ある感情や印象そのものの表現にかかわる。この作品の各曲に仮に標題が与えられることになったとしても、それらは、R.シュトラウスの交響詩にしばしば見られるように、ある種の物語を紡ぎだすものではなく、あるイメージに対してそれを何らかのかたちで呼ぶために名前がつけられたと考えられるだろう。「6つの小品」が作られたとき、そこには確かにウェーベルン自身が語っているような物語的な流れが存在していたかもしれない。しかしそうだとしても、それぞれの曲が「純粋に抒情的性質をもつ」ということは、これらの小品によって与えられるものは、出来事の描写ではなく、出来事によって生み出されたウェーベルンのイメージそのもの、つまり音楽そのものということになるだろう。
6つの曲のそれぞれには、次のような速度・表情の指示、標題が与えられている。
第1曲 ある程度動きをもった♪(八分音符)
第2曲 動きをもって
第3曲 繊細に動きをもって
第4曲 ゆっくりと(♪) 葬送行進曲
第5曲 非常にゆっくりと
第6曲 繊細に動きをもって
主要参考文献
『Anton von Webern.Chronik seines Lebens und Werkes. Zürich』Hans und Rosaleen Moldenhauer(Atlantis 1980)
『ヴェーベルン西洋音楽史のプリズム』岡部真一郎(春秋社2004年)
初 演:1913年3月31日 シェーンベルク指揮 ウィーン「私の師であり、友であるアーノルド・シェーンベルクに、この上ない愛情を込めて」献呈
楽器編成:フルート4(ピッコロ2、アルトフルート)、オーボエ2、コールアングレ2、クラリネット3(Esクラリネット)、バスクラリネット2、ファゴット2(コントラファゴット)、ホルン6、トランペット6、トロンボーン6、テューバ、ハープ2、チェレスタ、ティンパニ(奏者3人)、大太鼓、シンバル、トライアングル、小太鼓、タムタム、グロッケンシュピール、低音の鐘、ルーテ(ムチ)、弦五部
悲劇的は運命的(英雄に関する一考察)
指揮者の高関さんとプログラム掲載のため、今回いろいろなお話を伺う機会があった。その際「悲劇的」という言葉の印象について、日本人が思う悲惨なイメージというよりも、「劇的」とか「ドラマチック」という意味に近い印象ではないだろうか、高関さんから伺い、なるほど、例えば「ギリシャ悲劇」といった演劇的な意味と同じ感覚では、と感じ入った。マーラーの交響曲第6番は、英雄の悲劇の象徴化として長3和音から短3和音への変化、その下で刻まれるリズムが運命的とか、特に終楽章では「英雄は敵から3回攻撃を受け、3回目に木のように倒れてしまう。」とマーラーが言ったとかでハンマー・ストロークが有名であり、所謂「英雄の悲劇」というイメージが付きまとっていると思われる。そこで、いろいろと思いつくまま述べてみたい。
印象として最初に浮かんだ「ギリシャ悲劇」は、古代ギリシャの神話や英雄伝説をベースにした神話世界という宗教性と、当時の都市国家(ポリス)という社会的政治的な時代背景が相まって、人間とは何か、というテーマに、ギリシャ哲学の生成・発展とともに、深い洞察力と創造力に満ちた質の高い悲劇として総合的舞台芸術が形成されてきた。その絶大な影響力は、後世の西欧文化において哲学、音楽、精神医学などの多方面への足跡に及んでいる。
いくつか代表作を観てみると、アイスキュロスは『縛められたプロメテウス』で近代以降の芸術家・思想家に人類の恩人として影響を与え、文明の推進役として人間に味方し密接な関係を持つ巨人族の神プロメテウスを通して、運命に翻弄され苦しみの中から悟って得るものこそ真に価値のあることを表現している。また『オレスティア』三部作は、トロイア戦争終結後の壮大な物語で、男の正義と女の正義が激突(言い換えれば国家の法と家族の法の対立)、ギリシャ軍総大将のアガメムノンと復讐を胸に秘すその妻クリュタイメストラの対決、息子オレステスと娘エレクトラによる母への憎悪と復讐、そして神による審判を通して避けられない運命と根源的秩序たる正義とは何かを問いかけている。ソポクレスは、アリストテレスが『詩学』にて真実の「発見」と運命の「逆転」が必然として同時に起こるすぐれた悲劇として激賞している代表作『エディプス王』にて、世界の不条理、人生の不可解、運命の非常を訴えている。さらに、エウリピデスは『トロイアの女』にてトロイア陥落後の戦争の暴虐と惨禍を通してトロイア王妃ヘカペに次々と襲いかかる絶望という極限の中での生きることへの強さを表現。また『バッコスの信女たち』では、テーバイの若き王ペンテウスと若き神ディオニソスとの対決とディオニソスによる恐るべき復讐とペンテウスの残酷な死を通して、為政者として権力で風紀の秩序を保つ知の人ペンテウスが、自然の恩恵と暴威を象徴するディオニソスにより、人間として究明しなければ気のすまないという深層の欲望が暴かれることで、文化的な人知の深層部に潜む暗闇と欲望という狂気を通して、人知・賢(ソフォン)は知恵(ソフィア)にあらず、では知恵とは何であろうという問いかけがなされ、神とはなにか、人間とはなにか、そして人間はどうあるべきかを問題提起し続けている。
注目したいのは、ギリシャ悲劇のベースにある神話世界で、古代ギリシャの神々は、実に現実的で何より人間くさいが、しかしその本質は、人知の及ばぬはるか遠い高みにあって人間界の出来事に煩わされることの無い、非人間的な距離と無関心が存在し、すなわち非常な性格があること。その中で、ペルセウス、ヘラクレス、テセウス、アキレウス、ヘクトール、オデュッセウスといった英雄達が、過酷な運命、例えば「ヘラクレスの12の功業」といった理不尽な課題と運命、しかもそのことを従要として忍ぶ主人公の痛ましい姿を通して、所謂ドラマチックに我々の深層に直接訴えかけてきているに違いない。 他の説話、例えば旧約聖書の『ヨブ記』で、悪魔が神の前でこの世で最も正しい義人であるヨブの信仰を試みようとして、神がその試みを許したから彼もまた不条理な理由から様々な災厄に見舞われるが、かれの信仰はゆらぐことがない、という話もそうだし、北欧神話『ヴォルスンガ・サガ』等に登場する英雄達、ジグムント、シンフィヨトリ、龍殺しのシグルド(『ニーベルンゲンの歌』ジークフリート)も同様といえよう。 いかにも西洋的な原初の狩猟社会という構造のうえに、はじめに権力闘争、すなわち戦いがありその後の秩序が保たれるという神話構造は少なからず影響を与えている。ギリシャローマ神話しかり、北欧神話しかり、全てに戦いがあって、巨人族との戦い(ギガントマキア)神々のたそがれ(ラグナロク)という戦いの世界観や終末観は興味深いし、その中に出てくる前述の英雄達は、大体共通して単純率直で無私直情という、純真と底知れない獣力のある人物として描かれている。
例えば、日本でも西洋文化とは異なる農耕社会の土壌で、同様な英雄達の伝承を垣間見ることができよう。所謂「貴種流離譚」という、やんごとなき方が父権との対立・葛藤というテーマを底流に、英雄として受難と漂白の伝説が数多く存在している。スサノオとかオオナムチ(大国主命)、特に明治浪漫主義を代表する青木繁の絵画『日本武尊』で荒涼たる大地にたたずむ若き英雄のイメージが強烈なヤマトタケルに代表される多くの説話、近代では曽我五郎時致の曽我兄弟もの、『平家物語』の方々や源九郎判官義経、『太平記』の大塔宮護良親王、小倉宮に代表される後南朝の皇子達の伝承、見方をかえれば忠臣蔵といった赤穂浪士や、西郷隆盛とかも同様であろう。時の権力者が、闘争によって勝利した後、その正当性を示すため相手を英雄化していくこと、また鎮魂の意味で成仏させるため(祟りや怨霊)として、そして所謂「判官びいき」といった感情の上に、日本特有の悲劇的像を構築していったのではないだろうか。
このような運命(神々の意志)という不条理を扱った題材、人間の深層心理を切り取った最古のドラマ、翻弄される英雄達の生涯に、我々は共感し哀れみと恐れを通して日ごろのストレスを放出して身も心も開放され、安らぎ、浄化されているのであろう。それは音楽という表現を通しても同じことである。
今回演奏するマーラー交響曲第6番では、一般的に『悲劇的』という記述が商業主義的に扱われ、演奏上ではハンマー・ストロークという特異な演奏方法が音楽的意味から切り離されて取り上げられている感がある。単音から発生した音楽は、それだけでもドラマチックであるものの、やがてハーモニーへ移行し、対位法を駆使してロマン的絢爛と複雑さへ向かってきた。ただ『悲劇的』とか『英雄』の言葉にとらわれるのではなく、マーラーの古典的な様式の中にある大胆な和声と圧倒的な対位法技術による音楽表現、緊密なオーケストレーションの持つ力強さ、その生命力に満ちた壮絶さを楽しんでいきたい。
アイスキュロスの『縛められたプロメテウス』のゼウス賛歌に、古代ギリシャの重要な倫理観である「苦難によりて学ぶ」という言葉がある。(圧倒的・緻密な音楽の中で我々の練習も苦難の連続だが)音楽を通して身も心も浄化されていきたいものである。
『悲劇的』日本初演考
新響でマーラーといえば、故・山田一雄の指揮で交響曲全曲に挑戦したことが歴史に刻まれている。今回マーラーのパート譜を受け取ったとき、そういえば、と、以前に東京芸大在職の兄から交響曲第6番日本初演時のプログラム資料をさらっと見せてもらったことを思い出した。確かヤマカズが打楽器で参加していたはず。早速兄に連絡したところ、『東京芸術大学百年史』という本に掲載されている、とのこと。調べてみた。
東京音楽学校管弦楽部第70回定期演奏会にて指揮はクラウス・プリングスハイム、昭和9年(1934年)2月17日(土)日比谷公会堂で初演したプログラム資料の内容が『東京芸術大学百年史 演奏会編 第二巻』にそのまま掲載されている。曲目は、マーレル作曲『大管絃樂のための第六交響曲』1曲のみ。演奏者のリストを視ていると、なんと!打楽器「テイーフエグロッケ」に当時の名前「山田和男」とあるではないか。また出演者にはこれまた錚々たるメンバーが掲載されている。ざっとみただけでも、ヴァイオリンにはトップに作曲の橋本國彦、教本でおなじみ兎束龍夫、ヴィオラに元武蔵野音大学長の福井直弘、チェロに作曲の呉泰次郎と安部幸明、ハープには声楽家として高名でハーピストでも活躍した荻野綾子、ファゴットにのちの芸大指揮科教授の金子登、ティンパニに戦前の新響から戦後のN響まで長年活躍した名物団員“ハゲドン”こと小森宗太郎、などなど。きっと音楽学校の先生や生徒で当時あるいは後世著名になっておられる多くの方々が奏者としてこの初演を体験されたに違いない。
山田一雄『一音百態』(音楽之友社)によれば、当時、山田一雄は東京音楽学校に入学2年目の昭和7年2月、マーラー交響曲第5番初演に接して深い感銘を受け、プリングスハイム先生に傾倒し個人授業を通して計り知れない影響を受けたとのこと。いろいろと調べてみると、昭和9年10月第72回定期演奏会では、R.シュトラウス70周年記念で『ツァラトゥストラはかく語りき』や『アルプス交響曲』のプログラムでチェレスタ、昭和10年2月第74回定期演奏会マーラー交響曲第3番初演でハープ、同年6月第75回定期演奏会ではバッハ生誕250年記念として『ブランデンブルグ協奏曲』やカンタータの他シェーンベルク編曲の『前奏曲とフーガ 変ホ長調』でチェレスタ等々、音楽学校でプリングスハイムの指揮にて多くの演奏を経験されたことがその後の音楽人生に多大な影響を与えたにちがいない。(因みに昭和9年12月第73回定期演奏会で東京音楽学校はヴェルディの『レクイエム』を演奏しているが、バスのソリストとして増永丈夫、後の藤山一郎が出演している。当時東京音楽学校を首席で卒業、クラシック(バリトン・増永丈夫)と流行歌(テノール・藤山一郎)で活動していた。)
演奏者のリストで他に注目されるのは、東京音楽学校の先生や生徒、卒業生はもちろんのこと、海軍軍楽隊から弦楽器を習いに毎週来ていたとのことで、コントラバスや管打楽器には海軍軍楽隊の奏者をフルに導入している。当時はプロのオーケストラとして現N響の新響が発足した頃であり、演奏技術も含め音楽の環境が現在とはかけ離れたものであることは言うまでもない。
メンバー表以外にもいくつか興味深いことがあるので列挙してみよう。当時の初演の写真が掲載されているが、「対向配置」であり、演奏者も多く未曾有の大編成にて舞台が狭いのか指揮者の目の前に木管楽器が配置されている。それと、曲目解説に『悲劇的』という記述がすでに散見されること。作者の『悲劇的』心境としてその特性と思われる点として、動機上:長から短への三和音、音色上:意欲と現実、孤独と物質の対立、その克服は音色的象徴として「畜群の鈴」と「槌」としていること。この曲目解説が詳細に亘っているが、どうも当時の研究書に基づいていろいろな説を取り込み、日本語に訳しているのではないかと思われる。それと楽式上通例として二部に分けて観られるとしていること。前の3楽章を第1部とする説と、プリングスハイムの説として第1楽章のみを第1部とする説を紹介しており、休憩が第1楽章の後に入っている。それと最も興味深いのは、第2楽章がアンダンテとなっていること。これはマーラーの直弟子ともいえるプリングスハイムの考えが顕著に現れているといえよう。
当時の高名な音楽評論及び作曲家による批評をまとめてみると(今回紹介の資料に掲載されている)、確かに欧州でも聴けないマーラーを上演することは音楽学校としては意義があるが、オケの音が不揃いで殆ど聴くに耐えず、最後の1楽章を残して退出、音楽学校だからまずくても差し支えないと思うが一般に公開しない方が得策、とか、面白くなかった(というよりわからなかったという方が良いかも知れない)、ベートーヴェン以上の大交響曲の建築ができると思ったマーラーの自負心による誤算ではないだろうか、とか、結構辛辣である。演奏技術もさることながら、マーラーの音楽が当時の音楽界では未だ特殊な存在であったと思われる。音楽評論で若き山根銀二が、こういう企ては非常に結構だと思う、とだけ言っているのはどういう真意であろうか、興味がある。
今から70年も前、現在とは比較にならないほど貧弱だった日本の「洋楽」の未だ黎明期という時代、このような編成が膨大で難解な大曲を初演するこの情熱は計り知れないものがあったに違いない。山田一雄が昭和12年(1937年)東京音楽学校研究科を修了する年まで続いたプリングスハイムの献身的とも熱狂的ともいえるマーラーの交響曲の連続初演は、東京音楽学校の「洋楽」への取り組みとして実に大変なものだったに違いない。このエネルギーの大波は戦争という社会情勢で中断はされるものの、その後の日本の洋楽発展に多大な貢献をしたことは間違いないだろう。
■参考文献:
『東京芸術大学百年史 演奏会編 第二巻』(音楽之友社)
『一音百態』山田一雄 (音楽之友社)
第205回演奏会ローテーション
| ウェーベルン | マーラー | |
| フルート1st | 岡田充 | 吉田 |
| 2nd | 藤井(+Picc) | 新井 |
| 3rd | 兼子(+Picc) | 松下(+Picc) |
| 4th | 丸尾(+Alto) | 岡田澪(+Picc) |
| Picc | - | 藤井 |
| オーボエ1st | 岩城 | 亀井淳 |
| 2nd | 横田 | 亀井優 |
| 3rd | - | 山口 |
| 4th | - | 横田(+C.A.) |
| 1st C.A. | 桜井 | 堀内 |
| 2nd C.A. | 堀内 | - |
| クラリネット1st | 品田(+Escl) | 高梨 |
| 2nd | 大藪 | 大藪 |
| 3rd | 石綿 | 石綿 |
| EsCl | - | 末村(+4th) |
| 1st BsCl | 進藤 | 中條 |
| 2nd BsCl | 中條 | - | ファゴット1st | 田川 | 長谷川 |
| 2nd | 星(+Cfg) | 星 |
| 3rd | - | 田川 |
| 4th | - | (*) |
| コントラファゴット | - | 浦 |
| ホルン1st | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 比護 | 山口 |
| 3rd | 大内 | 園原 |
| 4th | 園原 | 比護 |
| 5th | 箭田 | 大原 |
| 6th | 大原 | 鵜飼 |
| 7th | - | 大内 |
| 8th | - | (*) |
| トランペット1st | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 北村 | 青木 |
| 3rd | 倉田 | 倉田 |
| 4th | 中川 | 小出 |
| 5th | 野崎 | 北村 |
| 6th | 青木 | 中川 |
| トロンボーン1st | 牧 | 武田 |
| 2nd | 小倉 | 牧 |
| 3rd | 志村 | 岡田 |
| 4th | 大内 | 大内 |
| 5th | 武田 | - |
| 6th | 岡田 | - |
| テューバ | 土田 | 土田 |
| ティンパニ1st | 浦辺 | 桑形 |
| ティンパニ2nd | 中川 | 浦辺 |
| ティンパニ3rd | 皆月 | - |
| 大太鼓 | 今尾 | - |
| シンバル | 桜井 | - |
| トライアングル、タムタム | 田中 | - |
| 小太鼓、グロッケン | (*) | - |
| 鐘、ルーテ | 桑形 | - |
| Perc. I | - | 中川 |
| Perc. II | - | 今尾 |
| Perc. III | - | (*) |
| Perc. IV | - | 田中 |
| Perc. V | - | 桜井 |
| Perc. VI | - | 皆月 |
| チェレスタ | 藤井 | 藤井 |
| ハープ1st | (*) | (*) |
| 2nd | - | (*) |
| 1stヴァイオリン | 前田(小松) | 掘内(藤本) |
| 2ndヴァイオリン | 岸野(田川) | 大隈(久保田) |
| ヴィオラ | 石井(柳澤) | 柳澤(石井) |
| チェロ | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 中野(関口) | 中野(関口) |
Perc. II:小太鼓1、内カウベル、外カウベル、シンバル3、ハンマー、トライアングル3
Perc. III:合わせシンバル、木琴、鐘2
Perc. IV:タムタム、シンバル2、トライアングル2、内カウベル、鐘1
Perc. V:吊シンバル
Perc. VI:トライアングル1、小太鼓2
(*)はエキストラ
第205回演奏会のご案内
高関健とマーラー
新響は2007年10月の第199回演奏会で高関健を指揮に迎え、マーラーの交響曲第9番を演奏し好評を博しました。今回の演奏会では、その高関=マーラーの第2弾として、彼の交響曲の中でも最もドラマティックな第6番を取り上げます。
高関のマーラー演奏には定評があり、細部を丁寧に作り上げることで壮大な世界が構築されます。大きな特徴は原典主義ともいえる徹底した楽譜へのこだわりです。交響曲第6番は初演前にスコアが出版されていましたが、最高の完成度をめざして楽章配置をも対象としたさまざまな変更が続けられた結果、多くの版が存在します。今回は最新の校訂版(1998年版)に変更を加えたものを使用します。
運命の打撃
ウィーン音楽院を卒業したマーラーは、1881年に21歳でライバッハ(現スロヴェニアの首都リュブリャナ)市立歌劇場の楽長に就任したのを皮切りに、各地の歌劇場を遍歴します。指揮活動で多忙なマーラーは、夏休みに保養地の静かな作曲小屋に籠り、集中的に作曲に取り組みました。第6番が作曲されたもの1903年と1904年の夏です。当時のマーラーはウィーン宮廷歌劇場監督として仕事にも恵まれ、結婚して2人の娘を授かり幸せの絶頂の時期でした。
作曲者自身により「悲劇的」という副題を付けられたこの曲は、巨大な編成に加え、珍しい打楽器が数多く使用されています。中でも床を叩くハンマーが有名です。マーラーはハンマーについて「主人公は運命の打撃を3回受ける。その3回目が木を切り倒すように、彼を打ち倒してしまう。」と妻のアルマに語ったということですが、これから少しして本当に3回の打撃がマーラーを襲います。ウィーン宮廷歌劇場辞任、長女の死、および自身の心臓病の発覚であり、まさに彼自身の悲劇を予知した曲となってしまいました。
新ウィーン楽派〜ウェーベルン
マーラーがウィーンで活躍していた頃に台頭してきたのがシェーンベルクらの新ウィーン楽派で、マーラーの影響を少なからず受けています。ウェーベルンの曲は極端に短いものが多いですが、凝縮し洗練された美しさがあります。第二次大戦後の現代音楽に大きな影響を与えており、そのルーツのひとつに位置づけられるでしょう。
今回取り上げる「6つの小品」はウェーベルンの代表作で、彼の作品の中では比較的わかりやすくポピュラーなものです。無調音楽というと難解で堅苦しいと考えられがちですが、ぜひ楽しんで聴いてみてください。この曲は2管編成の改訂版で演奏される機会が多いですが、今回は編成の大きな原典版を演奏します。
ショスタコーヴィチ:交響曲第4番
ショスタコーヴィチとその作品
1906年9月25日に生まれ、1975年8月9日に亡くなったロシア~ソ連の作曲家。第1回ショパンコンクールに入賞するなど、ピアノも上手だった。それぞれ15曲ずつの交響曲と弦楽四重奏曲を始めとして、歌劇、交響詩、協奏曲、カンタータ、映画音楽など、あらゆるジャンルの作品を遺している。作品1は、オーケストラのための「スケルツォ第1番嬰へ短調」(1919)、最後の作品は、「ビオラ・ソナタ作品147」(1975)である。
現在、ショスタコーヴィチの諸作品は、演奏会のレパートリーとして完全に定着している。「大作曲家」としての評価が固まったと言ってよいだろう。CDは多数発売されており、インターネットではいろいろな情報を検索することができる。
また、死後出版された書籍が物議をかもしたり、その真贋論争が起こったりするなど、音楽以外の面でも話題が多い。
「交響曲第4番」※について ※以下「4番」と表記
まず、作曲の経過や初演などについて、「通説」を簡単に整理してみたい。
1935年~36年にかけて作曲。同年12月(4月とする文献あり)のレニングラードでの初演に向けてリハーサルが行われていたが、突如作曲者の意向で初演は中止された。はっきりとした理由は定かではな いが、ソ連当局からの批判や粛清を恐れたためと言われている。
その後25年間、「4番」は謎に包まれた作品であったが、パート譜からスコアを作成して、1961年(60年とする文献あり)12月30日、モスクワでコンドラシン指揮のモスクワ・フィルによって初演された。ちなみに、1961年には交響曲第12番が完成されている。
初演の中止にあたっては、そのこと自体が呼び起こすであろう疑惑、演奏会のドタキャンによって生じる社会的信用の下落など、様々な懸案事項を勘案したうえで、ぎりぎりの判断を下したのであろう。超大物や有力な組織からの助言やフォローがあったとも想像することができる。
「ソ連」の作曲家ショスタコーヴィチの作品は、政治・社会情勢とリンクして語られてしまうことが多い。交響曲第10番でも、同様の傾向が見られる。
しかしながら、「4番」は表題がない「絶対音楽」であることを忘れてはならない。先入観をなくして「ショスタコーヴィチの音楽」に耳を傾けることも大切であろう。
どんな交響曲?
「4番」の特徴を、私見ながら5点掲げてみたい。
①大編成
ウィキペディアの「巨大編成の作品」にも登場するほどの大編成であり(次回の定期演奏会で演奏す るマーラーの交響曲第6番も載っています)、作曲者指定の演奏者人数を合計すると、最少でも113人に達する。ステージ上のオーケストラだけで見れば、「4番」は、ショスタコーヴィチの作品中、最も編成の大きい曲であろう。使われていない楽器は、ピアノくらいのものである。盛り上がると大音響で迫力充分、室内楽的な個所では繊細さが際立っている。各楽器のソリスティックな扱いも目立っており、長いソロを受け持つ奏者も多い。
②盛り沢山な内容
手持ちのあらゆる素材を楽譜にしたのではないかと思われるくらい、様々なエキスが詰まっている。そのために統一感に欠けるとの指摘もあるが、逆に、これだけの内容をよく1曲にまとめ得たものと思う。消化すべきことが多いうえに、全曲に渡って緊張感が張り詰めているため、演奏していると、実際の演奏時間(約60分)よりも長い時間が経過しているように感じる。また、練習を行うたびに新しい発見があり、心踊らされている。
③マーラーの影響
ほとんどすべての解説で語られていることだが、曲の素材、雰囲気、楽器編成(オーケストレーション)等において、マーラーの影響を見過ごすことはできない。実際に、マーラーの交響曲第1番とそっくりな動機や旋律が登場する。
④出発点
「4番」以後の作品、例えば交響曲第5番、8番、10番、13番、15番、チェロ協奏曲第2番、祝典序曲などに、「4番」からの引用と思われる旋律や書法が見られる。また、透明で叙情的な雰囲気、最高潮に向けての盛り上がり方などには、以後のショスタコーヴィチ作品の原型を聴き取ることができる。新たな出発点ともなっている曲なのだ。
⑤全楽章弱音で終わる
ショスタコーヴィチの交響曲中、全楽章弱音で終わるのは「4番」のみである。この他にも、3楽章構成であることが特徴と言えなくもないが、伝統的な4楽章構成の交響曲は、15曲中7曲しかない。
各楽章について
第1楽章
自由な形式だが、主題の展開や再現が聴かれるため、複雑なソナタ形式とも考えられる。大迫力のプ レストの部分を始めとして、各パートの演奏難易度は高い。最後は、これまでのことを回想しながら、深く息を吐き出すようにして終わる。
第2楽章
間奏曲風の楽章。目まぐるしく展開する長大な両端楽章とは対照的に、演奏時間は短く、最初から終 わりまで拍子(3/8)とテンポが全く変わらない。音楽は流れるようにたんたんと進んで行き、あっけなく終わる。
第3楽章
組曲風の楽章。葬送行進曲風の部分、映画音楽風の部分、舞曲風の部分、テンポは速いが耽美的な部分、コラール風の部分などが次々と登場する。終結部では、チェレスタが満を持して久々に登場。天国 的な美しさに彩りを添えている。
最後に少し寄り道をさせていただき、新響による日本初演時の個人的思い出をひとつ。第3楽章最後のクライマックスであるコラールの直前、ティンパニ2名と大太鼓が、9小節間の大クレッシェンドをして盛り上がりのきっかけを作りますが、ある日の練習時、芥川先生はこの部分を「5番のフィナーレの最後のようにやるよう」指示されました。本番でその通りにできたかどうか、芥川先生に伺い忘れたことが今では悔やまれます。
主要参考文献
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
「巨大編成の作品」
「交響曲第4番(ショスタコーヴィチ)」
『作曲家別名曲解説ライブラリー⑮/ショスタコーヴィチ』
音楽之友社編(音楽之友社1993)
『ショスタコーヴィチ』ホフマン著
清水正和・振津郁江共訳(音楽之友社昭和57年)
初 演:1961年12月30日K.コンドラシン指揮モスクワ・フィル
日本初演:1986年7月20日芥川也寸志指揮新交響楽団 於新宿文化センター
楽器編成:フルート4、ピッコロ2、オーボエ4(4番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット4、Esクラリネット、バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン8、トランペット4、トロンボーン3、テューバ2、ティンパニ2名、大太鼓、小太鼓、シンバル2名、木琴、鉄琴、ドラ、トライアングル、カスタネット、ウッドブロック、ハープ2、チェレスタ、弦5部
芥川也寸志:チェロとオーケストラのためのコンチェルト・オスティナート
〈作曲者の言葉〉“コンチェルト・オスティナート”は、おそらく、現代にあってはきわめて古典的な風貌をそなえた、チェロのための協奏曲で、譜例1のような進行に固執したオスティナートを中心にして書かれている。
F・メンデルスゾーンは、手紙のなかでこう書いている。〈……きっとあなたは私のことを、いつも不平をブツブツつぶやき続けている、バッソ・オスティナートのようだと思いはじめるに違いありません。そしてついには、うんざりしてしまうのでしょう。〉(Grove)
オスティナートによる、不朽のシャコンヌや、パッサカリアを書いたJ・S・バッハの、深い理解者であった彼でさえ、オスティナートは〈うんざりする〉ような存在であった。ロマン派の作曲家たちに見はなされていたオスティナートは、I・ストラヴィンスキーを筆頭とする二十世紀の作曲家たちによって、一応、復活の場を与えられた。しかし、かってJ・S・バッハによって、たとえば〈パッサカリア、ハ短調〉において用いられたように、作曲家の論理を強め、完結させるための名誉あるオスティナートの地位は、いまだに回復されてはいない。現代にあって、私はオスティナートに、単なる修辞学的技法以上の意味を与え得ると思っている。
この曲は、日本の素晴らしき才能、岩崎洸さんの依頼によって作曲された。かつて、コンチェルトを書いた作曲家の多くが、魅力的な独奏者に創造力を駆り立てられたのと同じように、私もおそらくそれと似た興奮を味わったことを、今もなお鮮かに記憶している。
このコンチェルトは、1969年12月16日、東京交響楽団定期演奏会で、岩崎洸さんによって初演された。
譜例1
譜例2
譜例3
〈解説〉
曲は、譜例1に示したオスティナーテ・モティーフを中心に、単一楽章で作曲されているが、形式的には、大きな2つの部分から作られている。第Ⅰ部は比較的ゆっくりとした部分で、A.B.A´.B´の2部形式でできている。まずAの部分は、ハープシコードとコントラバスのユニゾンによるオスティナーテ・モティーフの提示に始まる。このオスティナーテ・モティーフは、譜例からもわかるように、明確、単純で、下行音型、上行音型による、非常にシンメトリックな音型によっている。前にも述べたように、オスティナートとして使われるモティーフは、このように明確で単純なものの方が、聴くものの意識の根底に焼きつき、効果的なのである。さて、このオスティナーテ・モティーフは、リズムのみを固執しながら、ほかの楽器を加えていく。やがて独奏チェロが、オスティナートの上に、新しい主題a(譜例2)を奏する。この主題aは、発展的な要素を持ち、重要なものである。これをもう一度くり返して、Aの部分を終わる。Bの部分は、テンポが若干速くなり、譜例3の主題bが、弦の伴奏の上に、独奏チェロによって提示される。この歌謡的主題bは、シンメトリックな構造を持っており、あきらかに、オスティナーテ・モティーフから派生されたものである。この主題bにより、ひとつのクライマックスが作られたあと、A´の部分に入り、再びオスティナーテ・モティーフを伴奏に、主題aをくり返す。そしてこの主題aが、いろいろと展開され、変形され最高潮に達し、B´に入る。B´の部分では独奏チェロと打楽器を除いた全オーケストラによって、主題bが再び奏される。やがて、これは第Ⅱ部への推移部分に受け渡される。この推移部分は、主題aを中心に構成されている。まず、独奏チェロとオーケストラのかけ合いがしばらくあった後に、主題aは、トランペット、オーボエ、フルートへと移され、装飾的に奏される。そして、b主題の一部が再現されたあと、ハープシコードと弦楽によるオスティナーテ・モティーフは、テンポが漸次速くなり、アレグロに至って第Ⅱ部になる。
第Ⅱ部は、C.B″.C´の3部形式でできており、独奏チェロが、第Ⅰ部からの余勢をかって、オスティナーテ・モティーフを奏することから始まる。このCの部分は、オスティナーテ・モティーフを、さまざまに変容することに終始する。やがて、ゲネラル・パウゼがあり、中間部B″に入る。B″の部分では、一変してテンポが遅くなり、主題bが独奏チェロによって奏される。しかし、それは主題aにとって変わり、しばらくしたところで独奏チェロのカデンツァになる。カデンツァではオスティナーテ・モティーフ、主題aなどが、技巧的に展開され静寂にむかう。そして、その直後、ハープシコードにより、オスティナーテ・モティーフがユニゾンで奏され、この静寂は打ちこわされ、C´部分が始まる。C´部分は、C部分同様、一貫してオスティナーテ・モティーフの展開、変容に力が注がれる。それは、時には、独奏チェロだけで、時には、独奏チェロとオーケストラとのかけ合いで、時には、全オーケストラでと、巧みに構成されながら高潮していき、終結部に至る。終結部もまた、オスティナーテ・モティーフを中心に、独奏チェロによるグリッサンド、主題a.bの縮小形などを織りなしながら(sff)で終わる。
初 演:1969年12月16日秋山和慶指揮東京交響楽団(第173回定期演奏会)
チェロ独奏 岩崎 洸
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、トロンボーン2、テューバ1、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、鞭、鉄琴、マラカス、ハープ、チェンバロ、弦5部
チェンバロという楽器
「チェロとオーケストラのためのコンチェルト・オスティナート(1969)」は独奏チェロとオーケストラのための作品であるが、オーケストラの楽器編成にチェンバロが含まれていることもこの曲の大きな特徴のひとつとなっている(作曲者自身による曲目解説にはハープシコードとなっているが、同一の楽器を指す)。
チェンバロはグランドピアノとよく似た外観、そして鍵盤を持つことから鍵盤楽器の一種に分類されることもあるが、発音原理がピアノとは大きく異なる。ピアノはフェルトで被われたハンマーが弦を叩く打弦楽器であるのに対して、チェンバロはプレクトラム呼ばれる小さなツメが弦をはじく撥弦(はつげん)楽器であ る。撥弦楽器というと聞きなじみがないかもしれないが、何らかの方法で弦をはじくことによって音を出す楽器の総称で、代表的な楽器としてはギター、ハープがあげられ、日本の琴もこれらに分類される。
チェンバロはバロック時代において幅広く用いられたが、18世紀後半以降のピアノの発展とともに人気が衰え、19世紀に入ってからは歴史から忘れられた存在となった。しかし19世紀後半から始まった古楽の復興運動とともにチェンバロを復活させる動きがはじまり、博物館に残された楽器を参考にして、さらに当時のピアノ製作の技術を用いて重い弦を金属製のフレームに張ったモダンチェンバロが新しく開発された。このモダンチェンバロは20世紀前半まで頻繁に使われることとなる。この楽器を主に使用した代表的な演奏家としては、カール・リヒター、ヘルムート・ヴァルヒャなどがあげられる。
そして20世紀半ば頃からバロック時代の製作方法を復元しようとする試みが始まり、当時と同じ素材、設計で楽器を忠実に再現することに努めたヒストリカルチェンバロが生まれた。現在ではこのバロック最盛期の製作方法を尊重したヒストリカルチェンバロが主流となっている。一方ピアノの長所を応用したモダンチェンバロは、本来のチェンバロとは別物だという批判も生まれ、表舞台から消えつつある。20世紀以降、近現代オーケストラ作品でチェンバロを使用した代表的な曲(チェンバロ協奏曲は除く)としては、ショスタコーヴィチの映画音楽「ハムレット(1963―1964)」、シュニトケ「室内協奏曲」「ヴィオラ協奏曲(1985)」などがある。芥川作品の中ではNHK大河ドラマ「赤穂浪士」のテーマ音楽(1964)や、NHK新時代劇「武蔵坊弁慶」のテーマ音楽(1986)にもチェンバロが使用されている。
さて本日の「チェロとオーケストラのためのコンチェルト・オスティナート」のチェンバロは、オーケストラの総譜に記載されている頻繁なストップ操作の指示から、足のペダル操作によってストップを切り替えることができるモダンチェンバロを想定して作曲されたと推察される。しかしながら本日は現在の状況を鑑み、東京芸術劇場所有のヒストリカルチェンバロ「アトリエ・フォン・ナーゲル製フレンチダブルマニュアル型」を使用し、その上で作曲者の意図に沿った演奏に努めたい。
芥川也寸志:絃楽のための三楽章 ―トリプティーク
芥川也寸志(1925―1989)は22歳の時作曲した「交響三章」で注目を集め、25歳の時の作品「交響管絃楽のための音楽」がNHK放送25周年記念管弦楽懸賞で特選入賞を果たし、作曲家としての知名度を上げていった。1953年(28歳)、オーストリア出身でN響常任指揮者だったクルト・ヴェスの委嘱により作曲したのがこの「トリプティーク」で、同年12月ヴェス指揮、ニューヨーク・フィルによりカーネギー・ホールで初演され、芥川が弦楽器の扱いについても並々ならぬ力量を示した作品である。
芥川は翌54年10月ソ連に非合法に入国、ショスタコーヴィチ、ハチャトリアン、カバレフスキー等に会って親交を結び、その半年後この「トリプティーク」がモスクワで演奏され、翌56年にはソ連国立出版局から楽譜が出版された。これら芥川とソ連の密接な結びつきが67年の新交響楽団・訪ソ親善演奏旅行へとつながった。
この「トリプティーク(三連画)」という曲名は芥川の愛聴曲の1つだったアレクサンデル・タンスマン(1897―1986、ポーランド出身の作曲家・ピアニスト)の「トリプティーク」にちなんで名付けられた。
第一楽章 アレグロ
全弦楽器のユニゾンによる冒頭6小節の躍動感溢れる旋律の後、2度音程や上昇・下降の動きが絡まりあった混沌の中を突き抜けて冒頭部の旋律を約2オクターブ上げたヴァイオリン・ソロが現れる。第2ヴァイオリンとヴィオラによる溌剌とした第2主題の後、低音部のオスティナート・リズムに乗って第1ヴァイオリンがゆったりした中間部の旋律を奏で、これに第2ヴァイオリンが絡んでしばらく進んだ後、再び活気づいて前半部を部分的に繰り返してキッパリと終わる。
第二楽章 〈子守歌〉アンダンテ
作曲当時5歳だった長女、麻美子のためのために書かれた5/4拍子の子守歌。弱音器をつけたヴィオラが奏でる息の長い旋律を第1・第2ヴァイオリンが受け継ぐ。中間部は3拍子になり、チェロとヴィオラにノック・ザ・ボディー(楽器の胴体を拳で叩く)という珍しい奏法を要求、生命感を出しているのも聴きもの。再現部もヴィオラが主題を奏でるが、第2ヴァイオリンが8分音符の伴奏をつける。感傷的で叙情性に溢れた楽章。
第三楽章 プレスト
ヴァイオリンとヴィオラのサルタート(投弓)による祭の太鼓を思わせる変拍子の主題は次第に和音の音域を広げて行き、低弦に引き継がれる。第2主題は薄い響きの諧謔的な旋律で、コルレーニョ(弓の棹で弦を叩く)で冒頭の旋律を一瞬奏でたあと、テンポをあげて急停止する。静かでまどろむような中間部のアダージョはつかの間で、すぐ冒頭部分に戻り、ffで一瞬アダージョの旋律を回顧した後、fffのユニゾンで曲を閉じる。都会人・芥川の手になる祭は江戸っ子らしく粋で、泥臭さとは無縁である。
ところで私は約40年前に新響に入団し、芥川先生が亡くなられるまで20年間先生にお世話になった古参団員である。還暦を迎えた5年前にコンマスを引退したのだが、「今回の『芥川也寸志没後20年』のコンサートの意義は特別」という余り訳の分からない理由でまた「トリプティーク」のコンマスに引っ張り出されることになった。永年の不摂生や加齢による生活習慣病や関節痛等で棺桶に片足をかけているような私は固辞したのだが、恐喝まがいのあの手この手の圧力に屈してしまった。現在の新響のヴァイオリン・セクションには素晴らしいコンマスや優秀な若手が大勢いるのに、腕が落ちた前期高齢者に老醜を晒させるとは何とも迷惑な話である。「トリプティーク」のソロは数回弾かせていただいた記憶があるのだが、ドタキャンした苦い思い出もある。芥川先生の発案による「新響創立20周年記念・日本の交響作品展」(1976年9月)がサントリー音楽賞を受賞、翌年3月の授賞式での記念演奏で「トリプティーク」のソロを受け持つことになっていたのだが、その2日前に行った日帰りスキーで怪我をし(滑降中にビンディングが外れて空中に投げ出され、アイスバーンに左肩をしたたか打ちつけた)コンマスを交代して貰って、芥川先生から大目玉を食ったのだ。この左肩の古傷は5年前にまた疼きだし(60肩?のせいもあったのかもしれない)、苦痛に顔を歪めながら弾く状況がしばらく続いたのだが、整形外科医の白土先生(新響チェロ団員白土さんのご主人)のリハビリ指導でここ1年何とか小康を保っている。本日の本番を無事乗り切れることを祈るばかりである。
初 演:1953年12月4日K.ヴェス指揮 ニューヨ-ク・フィル
日本初演:1954年10月15日作曲者指揮東京交響楽団(東京労音創立2周年「森の歌大合唱 と交響曲のつどい」)
楽器編成:弦5部
小松先生からのメッセージ
“芥川也寸志没後20年”。もうそんなになるのか……。晩年(とは言っても60才代だった)の芥川氏とお会いするために、日本音楽著作権協会の理事長室に数回足を運んだ。「すみませ~ん、つまらない曲で!」が氏の口癖であった。何と謙虚な……。そして私の質問にいつもていねいに答えて下さったのだ。“音符の根っこから掘り起こす”事をモットーとする私は、ベートーヴェンに直接話を聞く事は叶わないが、ご存命の作曲家には、一音一音の持つ意味まで確かめたくて、面談に伺う。私が質問を向けると、音楽の深いところの話なので、どの作曲家も“活き活き・嬉々・沈思・困惑”などが交差する表情で応答して下さる。最晩年の伊福部昭氏や髙田三郎氏、團伊玖磨氏、黛敏郎氏、武満徹氏、松村禎三氏などなどと随分親しくさせて頂いたのが、今となっては素晴らしい思い出である。曲・作風についてのお話を伺っている間にその作曲家の個性的なパーソナリティに触れられる事になり、自分の貧しい人間性が少しでも豊かになる幸せを私は感じ、かみしめていた。優れた芸術家というものは、個性的でありながら、 豊かな人間性を持っているとつくづく思う。
今回の芥川作品「絃楽のためのトリプティーク」では、新響のお手曲であるという美点を生かしつつ、これまで無かったテクスチュアの立体的な明視度とクオリティの高さを目指し、「コンチェルト・オスティナート」では芥川の情念に“女流”チェリストの向山さんがどのようにアプローチし、そして表現して下さるのかが大変楽しみである。
さて前記のような“作曲家との禅問答的な対話”をもしも私がショスタコーヴィチと実現できていたらどんなことになっただろうと空想するだけでも楽しくなるというものだ。“二枚舌”“イソップ言語”と云われる彼の音楽語法の中の“本音”の部分をどこまで私に話してくれたのかと……。いや、多分ほんのごくごく少しだけしか明かしてくれなかっただろうと思う。何故なら、いつ自分がお上(当局)に引っぱられていくか判らない状況の中に常に彼は在ったのだから。
しかし、はっきり言えることは“雪解け(フルシチョフ政権)”以前と以後では明らかに身の周りの“空気の硬さ・緊張感の高さ”が目に見えて変わった事だろう。それ故、長年封印されてきたこの交響曲第4番もようやく雪解け後に初演されたのだから。
本日演奏する第4番は、第5番、第8番と密接な関係を持つ。そして又この三つの交響曲は共に難解な内容を持つが、その深層心理クイズ的なものを苦労して解くのが楽しくもある。
それにしてもこの第4番は演奏が大変に難しい。技術的には勿論の事、内容的に第5番のような構成のしっかりとしたまとまりの良さには欠けるし、第8番のような熟成・老成も無いからだ。しかし問題作・意欲作である事は確かで、第1番から受け継いだコラージュ、パロディ的な作曲法と、作曲者の強い創作欲が4管編成のオーケストラを媒体とする巨大なエネルギーとなって結実している。第1楽章後半部開始部部分の“ベートーヴェンの引用のお化け”とも云うべきすさまじいエネルギーと推進力を持つフーガの個所や、フィナーレでのマーラーの葬送行進曲の投影、そしてコーダ(結尾)部分でのチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」のフィナーレの重々しく引きずるような足取りのリズムの引用など、そのどれもが“歪められて”おり、音楽においては珍しい「シュールレアリズム」的な作品として、その新鮮さは貴重なものであろうと思う。
しかし上記のすべてのものを「死に向かおうとさせられている人間を救う」(ベートーヴェンの歌劇「フィデリオ」のレオノーレの引用)「自分自身への葬送行進曲」「死の足取りの上での残された不条理・未解決の部分」などと私は解き明かす事によって、ショスタコーヴィチが生涯つきあわざるを得なかった「死を見つめる・死との隣り合わせ」「自問自答」の命題がこの交響曲以降、最後の第15番まで続くこの作曲家 の“アイデンティティ”のスタートとなった事に注目したい。
この大変な曲を22年前に日本初演した芥川/新響に敬意を表しつつ、本日も渾身の指揮を念じて私は指揮台に登る。 有難うございました。
芥川也寸志没後20年に際して 小松一彦
団長あいさつ
今、芥川先生がここにいらしたら新響のことをどのように想われるだろう、どのようなお話をされるだろうか、と、ふっと想いがかきたてられることがあります。芥川先生への思慕という単純なものではなく、新交響楽団がアマチュアの音楽団体として冷静に自己の存在と活動を見つめる時、また未来に向けていろいろな夢を思い描くとき、湧き上がってきます。芥川先生は新交響楽団創立以来、音楽を愛してやまないその情熱で、アマチュアだからという甘えに妥協せず、団員の自覚を促すべく音楽の指導のみならず運営に関しても深く関わり、常に団員を叱咤激励されておりました。まさしく「芥川也寸志と新交響楽団」は常に一体でした。指導者として数多くのメッセージを残され、新響にとって大きな財産となっております。そのような状況の中、指揮者で音楽監督という立場の芥川先生と新響とは一定の緊張感が存在していたといえます。先生と教え子、というよりは父と子という関係でお互いに共感を持ちつつも時には抵抗することもあり、新響は父親である芥川先生の深い愛情と薫陶により成長し続けてまいりました。
芥川先生が1989年1月31日に63歳で亡くなられてから20年という歳月は、新響を取り巻く社会環境・音楽環境はもちろんのこと、芥川先生を直接知る団員も三分の一になって運営形態も団員の価値観も変化しております。必ずしも順風満帆でなく、多くの問題にぶつかり学ぶことによって新響は常に純粋な音楽団体としての自覚を持ち続けてきております。錚々たる指揮者・指導者の先生方に恵まれ、刺激に満ちたさまざまな音楽体験と経験を積み重ねて、独自の企画を展開することにより、質的向上を目指して大きく発展してきております。
このように、世代交代をしながらも、常に前向きにアマチュアとしての誇りを持ってその可能性を追求していく信念と、多くの夢を追い求め、独創性を持って音楽に対する情熱をエネルギーとして失うことなく持ち続けていることは新響の大きな力です。「今」を活きている新交響楽団、その根底に流れている大きな力は、芥川先生の「音楽はみんなのもの」という強い信念に支えられたものであり、先生と団員の音楽への熱い想いが情熱となって、脈々と途絶えることなく流れています。芥川先生の存在は目に見えない形で新響に影響を与え続け、一つ一つの演奏会を通して音楽に全力で集中していく新響の演奏に、先生の熱い想いが重なって表現されているものと信じております。
芥川先生は、作曲家として戦後の日本に影響を与え続けてきた作品を残されており、新響が演奏を積み重ねていくことは、指導者としての先生の側面とは別の新たな発見と新響の発展につながっていきます。父と子という関係に加え「芥川也寸志」という音楽に対する緊張感を持続することで、新響は先生と直接向き合っているのです。いつまでも団員名簿に先生のお名前が記載されていることも、具現化しているものの一つといえましょう。芥川先生は新響の中で現在も活きていらっしゃいます。
本日はご来場誠にありがとうございます。
第4交響曲をめぐって 『ショスタコーヴィチの証言』の事と
新響が芥川也寸志指揮でショスタコーヴィチの交響曲第4番を日本初演したのは1986年7月。22年前の事だ。20世紀を代表する作曲家の、比較的初期の交響曲が、1961年の初演以来四半世紀もの間、日本で手つかずになっていたという事実に、既にして隔世の感がある。
*日本初演のころ
この当時ソビエト社会主義共和国連邦という国家はまだ健在で、米ソを主軸とした東西の冷戦構造は厳然と続いていた。得体の知れない大国の不気味さは、現在半島の某国に我々が抱くそれとは比較にならない大きなものだった(ソ連領空に迷い込んだ大韓航空機が撃墜されてから、3年と経っていない)。日本では戦後40年を経て社会主義も当初の輝きも勢いも失っていたが、わずか3年後にベルリンの壁が破壊され、況してやその後超大国ソ連が消滅する事を想像できた人は皆無だったろう。記録されるべきこの曲の本邦初演は新宿文化センター大ホールで行われた。サントリーホールも東京芸術劇場も未だ無かったのだ。世の中は「バブル時代」の前夜であり、現在とは比較にならぬ活気があったが、その享楽の裏には冷戦の影が潜んでいた。東西の核傘下の平和・・・そうした時代である。
インターネットの概念さえ人々には無かった当時、情報を集める事自体が大変だった。ハイティンク指揮コンセルトヘボウによる交響曲第4番の音源(勿論レコードである)が得られたのだが、スコア(総譜)は当時神田にあったロシア語文献の専門店(これは2軒しかなかった)の「日ソ図書」を通じて、ソ連で出た全集版を新響で共同購入する事になった。値段こそ安かったが交響曲第3番《メーデー》とペアになった、百科事典1冊分のサイズと重量のいかつい装丁は、運搬の不自由をいや増しにした。これを鹿島での合宿や梅雨時の練習の度に持ち歩いていた事を、第4交響曲の無機質な曲想と共にまず想い出す。今日では日本の出版社から出たポケットスコアが容易に入手できる。「百科事典」を持ち歩く気力も体力も失せたので、今回の再演に際してつい買ってしまった。極めて個人的な些事(さじ)ながら、この一事は22年間の社会環境の激変と相俟って、この作品に対峙するに心理に少なからぬ差異をもたらしているように思える。
*『ショスタコーヴィチの証言』の世界
さてここに『ショスタコーヴィチの証言』という本ある。作曲家の死後に国外で公表する事を条件に、タジク共和国(当時)出身の少壮の音楽学者ソロモン・ヴォルコフ(Solomon Volkov:1944~)に対して口述された回顧録・・・という事になっており、その通り1975年の死を待って出版されている。1980年に邦訳も出ており、作曲家の死後ようやく我々に届いた肉声とも言うべきもので、当時の乏しい情報の中では注目すべき一書だった。
読みやすい本ではないが、一貫して流れているのがスターリンへの呪詛(じゅそ)である事は容易に解る。何故そうなったのか?作曲者が語ったあまたある逸話のひとつを紹介しよう。
自らの容姿に劣等感を抱いていたこの専制君主は、画家に肖像画を描かせるに当たって、ある遠い昔に実在した東洋の権力者と画家にまつわる寓話を聞かせていた。厄介な事にこの東洋の王は隻眼で片脚が不自由だった。
第一の画家はありのままの姿を描いて不興を買い、死を賜った。「中傷家など必要ない」という事だ。
第二の画家は王を健常者に仕立て上げて同じく死罪になった。「おべっか使いなんかは必要ない」
第三の画家は、狩りで岩に座り、弓を引く王の姿を描いた。これによって不自由な片脚は岩に隠れ、つぶれた片眼は獲物に狙いをつけるものとして糊塗された。この画家は賞を得て天寿を全うし得た。
権力者の肖像を描くとはそういう事なのだと示唆した訳である。そしてソ連の画家はこぞってその意を汲み、現代の王の言に従おうとした。
それでも・・ショスタコーヴィチは続ける。「スターリンは多くの画家を銃殺した。」
この「指導者にして教師」の些細な気まぐれによって死んだ芸術家は画家だけではなかった。権力者が文化への理解と寛容を外部に示そうとの意志から、自ら芸術への介入を図った時、多くの人々が収容所に向かい、死に追いやられたのである。いちいち批判などする必要は無い。作品や場面に対し一見差し障りの無い「疑問」を呈する事で充分だった。するとそれに関係した画家・作家・詩人・劇作家・・・そして作曲家のドアが深夜ノックされる。あとの事はわからない、恐らく永遠に。
ショスタコーヴィチは、舞台に於いて長年共に仕事をしてきた天才的な演出家メイエルホリド(Karl Kasimir Theodor Meyerhold:1874~1940)への回想を反芻(はんすう)する。彼は1938年、稽古の最中に逮捕された。その後の姿を見たものはいない。後年処刑されていた事が判る。『ショスタコーヴィチの証言』の記述。
演出家は逮捕されたが、なにもなかったように仕事はつづいた。これはあの時代のもっとも恐ろしい特徴のひとつである。・・・メイエルホリドという名前が一瞬のうちに会話から消えてしまった。それですべてである。
誰もが深夜のノックに怯えていた時、ショスタコーヴィチを震撼(しんかん)させる記事が『プラウダ』に出る。1936年1月28日の事だ。メイエルホリドとの仕事として、それまで何の問題もなく上演を繰返し、好評を得ていたオペラ『ムツェンスク郡のマクベス夫人』を批判する『音楽のかわりの荒唐無稽』なる論文である。
現在この論文はネット上で露文・英訳共に読む事が出来る(便利な世の中になったものだ。無論これらの言語が理解出来ればだが)。そこではこのオペラが「形式主義」に陥っており、ブルジョア的であると批判されている。無署名ではあったがショスタコーヴィチはこれをスターリンの意思と直感する。確かに国家の民衆に対する「教化の手段」としての音楽から彼の作品はかけ離れており、それは作曲家も自覚(自負)するところだった。批判の種は常に抱えていたのだ。
だから作品のどこが「形式主義」か?を問う事には余り意味が無い。スターリンが形式主義と言い出せば、それは形式主義である。それで充分だった。政治的な空気はいつの時代も、目障りなものを退けるための口実となるスローガンを求め、ひとたび見出せば何に対してもそれを用いる。同様の事がその後の中国でも日本でも起こった事を我々は記憶していよう。更に数日後、今度はバレエ音楽『明るい小川』に対する批判記事が出る。10日間にふたつの攻撃的な社説が『プラウダ』上に載ったのだ。「一人の人間としてじゅうぶんすぎるくらいではないか。いまや誰もがわたしの破滅を正確に知るにいたった」・・・何に対する批判にも使える武器がある事を明示されたショスタコーヴィチは「人民の敵」となり、孤立無援の状態に陥った。誰も最早彼の作品に手を出そうとはしない。前年から創作されていた第4交響曲が完成したのはそうした最中だった。不幸な生い立ちである。
初演に向けての準備は一応進められた。だが今や札付きとなった作曲家との関わりを避けたい一心から、みな腰が引けていた。不幸なくじを引き当てたのはシュティードリー(Fritz Stiedry:1883~1968)というオーストリアからの亡命指揮者だったが、彼は「人民の敵」の手になる作品を演奏する事で累が自分にも及ぶのではないかと怖気づいていた上に、不勉強で作品に対する誠実さに欠けていた。この指揮者に対する作曲者の怒りは終生止んでいない。
第4交響曲は作曲家の名を世界に広めた最初の交響曲以来の「個人的な」作品だったが、そこには西欧の作曲家・・・例えばマーラー・・・の作品から取込んだ様々な要素が随所に散りばめられており、「赤軍合唱団と踊り」程度しか理解できないスターリンにとっての「音楽」とは全く別ものに仕上がっていた。何をやっても咎められそうな圧縮された空気の中で、既に批判された作風の交響曲は破滅的な爆発をもたらすに充分な火種であった。危機は足元まで迫っていたのである。結局ショスタコーヴィチ自身がこの初演を取り下げた。そしてこの曲はその後実に25年の沈黙を余儀なくされたのだった。
翌年第5交響曲を書く。それは「強制された歓喜」だった。人々に鞭打ち「さあ喜べ。それが仕事だ」という訳である。普通の人間ならこれを契機に転向するところだ。事実そうする事で辛うじて命脈を保った芸術家が、この時代のこの国家では殆どだったのだから。
しかしながらこの作曲家はしたたかだった事が『ショスタコーヴィチの証言』によって判明する。ひとつの例として《レニングラード》と題された第7交響曲が、ナチスドイツとの攻防をテーマとする「戦争交響曲」と捉えられている事を彼は挙げる。この曲を《レニングラード交響曲》と呼ぶ事に異は唱えない。但しそれは包囲下のレニングラードではなく、スターリンが破壊し、ヒトラーがとどめの一撃を加えたレニングラードを主題にしているとまず言う。
更にこの大作は戦争の始まる前に構想されていた為、ヒトラーの攻撃に対する反応としてみるのはまったく不可能であり、冒頭の楽章で執拗に繰返される「侵略の主題」は実際の侵略とはまったく関係がないと述懐している(柴田南雄氏によればこの主題はレハール(Franz Lehár:1870~1948)のオペレッタ『メリー・ウィドウ』からの引用であるという)。
僕はここで「音楽は絶対的ななにものをも表現しない」とするハンスリック(Eduard Hanslick:1825~1904)の思想を思い起こす。言うなればこれは、音楽という本来抽象的な芸術によって初めて可能となる「だまし絵」のようなものだ。全く異なる意図を以って創られていても、違う角度から違う意図を盛り込んだと言いくるめて示せばそれはそう見える。例の「形式主義」を逆手にとった保身策だったと言えようか。彼はある時期から、全ての作品のあらゆる細部にこうした仕掛けを盛り込み、その仕掛けに一向に気づかぬ「指導者にして教師」とその取巻きを密かに冷笑していたのかもしれない。事実交響曲に於いてさえそれはあったのだ。この本を読む誰もが目を留めるであろう、おそらく最も有名な一節。
私の交響曲の大多数は墓碑である。わが国ではあまりにも多くの人がいずことも知れぬ場所で死に、誰ひとり、その縁者ですら、彼らがどこに埋められたかを知らない。私の多くの友人の場合もそうである・・・・わたしは自分の音楽を彼ら全員に捧げるのである。
作曲家が作品に対し、何を託しているかは本人にしかわからない。そしてそれは言葉として残されない限り、永遠にわからぬままである。『ショスタコーヴィチの証言』の言い知れぬ不気味さの一端はこうした箇所に宿ってる。
*偽書説をめぐって
『ショスタコーヴィチの証言』には出版された当初から偽書説・・・すなわちヴォルコフの捏造(ねつぞう)ではないかとの噂が絶えない。それはこの本が出版されるやその衝撃的な内容ゆえ、ソ連政府は即座に「偽書」と表明した事に端を発している。未亡人をはじめとした遺族もこれに賛同した。遺族がソ連内にとどまる限り、保身の為にもこれは当然の表明である。そしてその対抗処置として作曲家が生前に『プラウダ』『イズヴェスチャ』『文学新聞』などソ連の出版物に発表した論文とそれに対する注釈を集めた『時代と自分自身について語るショスタコーヴィチ』が編集されている。年代順に配置され、作曲家の回顧録として扱える構成になっているが、不思議な事に『ショスタコーヴィチの証言』各章にもそれと全く同じ文章が散見されるのである。これが偽書説を採る側にひとつの根拠を与える結果となっている。出版から20年に及ぶ論争を経て、現在では偽書との見方が定着していると言ってよい。
手元に邦訳の文庫初版本(水野忠夫訳・中公文庫:1986年1月出版)があるが、本文だけで450ページを超える大冊である。過去に公表されている記事や余り上等とは言えない、ソ連時代の逸話を散りばめた産物としても、偽書とするにはいかにも手が込みすぎている印象を否めない。勿論贋作はそうしてこそ迫真のものになるとも言えようが。
個人的には真贋いずれの説にも与(くみ)さない。はっきり言えるのは、この書物が「出るべき時機に、出るべくして出た」ものであったという事だ。「指導者にして教師」たるスターリンの暴虐の最中に痛烈な批判まで受けたにもかかわらず、また実際周囲に累々とした犠牲者を重ねた中にも生き残り、天寿を全うし得たショスタコーヴィチ。この作曲家が激動の時期に何を考え、どう行動したか?は当然関心の的であった。そこに死後でなければ公表できない内容と銘打ったものが出た。そしてそれは多くの人々が想像した通りの徹底した圧政者への批判、そして国家に尾を振った同時代の芸術家に対する悪口雑言が連ねられていたのだ。この本は人々の期待の産物である。偽書であったとして、我々にこれをとがめる資格があるだろうか。
*再演の機会を得て
第4交響曲再演の機会が巡ってきて、いま幸運にも初演の時と同じ席に座っている。まだ20代だった22年前の自分を思い出す。将来に対する希望を全く抱けない状況にあり、人生にはうんざりするほど長い時間が残されていると感じていた。肉親も健在で、「死」に対する現実感は皆無だった。当時出たばかりの『ショスタコーヴィチの証言』から、死を自覚した作曲者が語る、様々な人々の死のあり様を読み取ったはずなのに・・・。芥川先生と新響とが共有できる時間が、その後わずか2年ほどしか残されていないとも想像出来なかった。今ある状況はずっと続いていくものと、根拠もなく信じ込んでいたのだった。若さ故の、健全すぎる生のもたらす無知と無恥とは恐ろしいものである。
無知と無恥は50代にさしかかった今も変わらぬが、流石に自分の生の行く末は漠然とながらも見えてきている。10年間は同じ曲を演奏しない新響に於いては、次にこの曲が取り上げられる時には、自分がこの席に座っている事はあるまいと思う事も増えた。勿論ショスタコーヴィチのこの交響曲然りである。 第7交響曲についてもそうであるが、彼は作品全体の構想が確固とするまでは、決して譜面に落としこまない作曲家だった。それだけに、構想をまとめるまでの時間は長い。彼が30歳の時に書いたこの意慾的な作品も、当然ながらスターリンが芸術全般に対する支配力強める以前からずっと作曲家の内側で練られ続けられていた。だから後年の交響曲のような「墓碑」では本来ない筈なのだが、その後の彼の人生を暗示させる何かが宿っているように感じてしまう。
わたしは思うのだが、もしも人がもっと早くから死について考えはじめていたなら、もう少し愚かでない振舞いができることだろう。
『ショスタコーヴィチの証言』を再読して、改めて心に働きかけてくるのは、一見ありきたりとも思われるこんな言葉であったりする。
第204回演奏会ローテーション
第204回演奏会のご案内
新響の音楽監督であった芥川也寸志が亡くなったのは1989年1月31日、20年が経とうとしています。芥川也寸志は1925年(大正14)文豪芥川龍之介の息子として生まれ、東京音楽学校(現東京藝術大学)作曲科に進みます。作曲家として魅力的な作品を残す一方、指揮者として音楽番組の司会者としてまたさまざまな音楽活動を通して音楽を広め、日本の戦後の文化の発展に大きく貢献しました。
今回の没後20年の記念演奏会では、芥川の功績を記念して設立された芥川作曲賞の指揮者を長年つとめている小松一彦を指揮に迎え、前半では芥川作品を、後半は指揮者としての芥川を偲んでショスタコーヴィチの交響曲第4番を演奏します。
芥川也寸志とソヴィエト
幼少の頃にストラヴィンスキーの「火の鳥」を愛聴していたという芥川は、次第にソヴィエトの音楽に興味を持ち、1954年にウィーンまでの片道切符のみを持って当時国交のなかったソヴィエトに行きます。ショスタコーヴィチなど著名な作曲家の方々と会う機会に恵まれ、持っていった「交響三章」がソヴィエト国立出版所から出版され、その印税で無事帰国します。
ソヴィエトから帰国した1955年(昭和30)、この年に結成されたばかりの労音アンサンブルに招かれて指導を始め、翌年その団体は新交響楽団となります。1967年、新響は日ソ青年友好委員会の派遣により芥川の指揮でソヴィエト各地で演奏会を開きました。その後も芥川=新響は、チャイコフスキーやショスタコーヴィチなどのロシア音楽を取り上げ、主要なレパートリーとしてきました。
ショスタコーヴィチの問題作
ショスタコーヴィチの交響曲第4番が作曲されたのは1936年。第3番から6年を隔て満を持して作曲された4管を超える大編成の意欲作で、高度な芸術的要素を持ちあわせマーラー的とも呼ばれます。リハーサルは行われましたが、その後自ら楽譜を回収し初演は中止されました。この頃書かれたオペラとバレエ作品を「西欧的形式主義的作品」として厳しく批判され、「人民の敵」の粛清が進むソヴィエトで命の危険を感じたのかもしれません。改めて作曲された第5番は政府の求めた「社会主義リアリズム」的作風で大成功します。第4番が初演されたのは25年後の1961年、スターリンの死後ソヴィエトの社会主義体制が軟化してからでした。
1986年(昭和61)の新響創立30周年企画としてショスタコーヴィチの交響曲第4番を日本初演しました。これが新響で芥川が大好きなロシア音楽を振った最後の演奏会となりました。
芥川作品のオスティナート
新響は芥川の初期の作品をたびたび取り上げていますが、「トリプティーク」もまた28歳の若い作品。当時NHK交響楽団常任指揮者だったクルト・ヴェスの委嘱によるものでニューヨーク・フィルで初演されました。明瞭で美しい旋律と明快なオスティナートリズムのこの曲は、芥川作品の中でも最も人気のある曲の一つでしょう。
芥川は、オスティナートにこだわる作曲家でした。オスティナートとは音楽的なパターンを続けて何度も繰り返すことを指します。芥川は心臓の鼓動を例に挙げ、肉体的な喜びとして働きかけることが音楽の高まりであると述べています。オスティナートと名付けられたチェロ・コンチェルトは44歳の時に書かれた中期の傑作で、チェロがオーケストラとともに朗々と歌います。
芥川が新響に残したもの
芥川は指揮者として音楽の指導をするだけではなく、運営に関しても新響と深くかかわり、オーケストラの在り方を常に提示してきました。存命中からの団員は3分の1になりましたが、アマチュアであることに誇りを持ちその可能性を追求をしていく、つねに「よい演奏」を目指して活動をするということは、今も変わりません。
さて、天国から「新響もなかなかやるじゃないか」と言ってもらえるでしょうか。
新響行きつけの飲み屋「八起」閉店
新響団員の行きつけの飲み屋である、東十条の「八起(はっき)」がこの8月一杯で惜しまれつつ閉店となった。八起のママさんの娘さんが妊娠中で、これを機に店をたたむことをこの5月頃から決めていたのだ。八起は新響メンバーの練習終了後の飲み場の定番であったので、落胆している団員は多い。
十条、東十条は飲み屋が多い所として有名であるが、団員の行く飲み屋はほぼ毎回決まっている。「ヴァイオリンはここ」、「木管はここ」とほぼ固定されたメンバーで押しかけるのがお決まりのパターン。「八起」は金管、特にホルンの人たちの溜まり場となっていた。
「八起」は91年4月に現在の東十条の地に開店した。いつもはママさんと娘さん(お姉さん)とその後主人(若)の三人でお店に立っていた。店内はそれほど広くはなく、カウンターに10席くらい、座敷に20名くらいしか入れない。昔はあまりに来すぎて席がなくなり、店の外に追い出されたこともあったという。
ママさんの話によると、94年頃ホルンの団員がたまたま発見したのが常連客となるきっかけとなったそうだ。残念ながらそのきっかけを作った団員は既に退団しているので、当時の話は聞けなかった。それ以降、ホルンの人たちを中心として金管の皆さんが集まって飲む場となったようだ。
土曜の夜の八起は事実上新響の貸し切り状態となっていた。たまにカウンターに他のお客さんがいると、なんとうるさい団体客に迷惑であっただろうと思っていたに違いない。新響の練習が終わると、常連の皆さんは自然と東十条方面に歩いていき、八起ののれんをくぐっていく。新入団員が入ると、最初に誘われるのがだいたいこの店だ。
皆さんがお店に着く頃にはテーブルにはすでにお通しの刺身が準備されている。まずは皆さんジョッキビールをもれなく注文され、乾杯。八起の料理はすごく量が多い。お通しの刺身も結構な量があり、これだけでも満足かもしれないが、それからいつもお任せの料理が数点でてくる。最後の飲み会で出てきたメニューは刺身、ポテトサラダ、ローストビーフ、鶏肉の唐揚げ、ゴーヤー炒めなどであった。日本酒の品揃えは豊富であったが、新響の注文するのはいつも「〆張鶴」と決まっていた。たまに「立山」を頼むときもある。焼酎は「黒霧島」のロックである。水割り、お湯割りはまず出たことがない。料理が出終わると、最後には蕎麦か平打ちうどんが出てくる。興がのってくると、この辺でホルンの某団員が「ノメノメ節」という歌を歌うこともある。「ノメノメ節」とは新響伝統?の歌なのだが、調は毎回違い、歌詞の意味は誰もわからないというもので、たまに演奏会の打ち上げで歌われることがある。これを歌うのが好きな団員も結構多いと思う。私もその一人だが、なにせ歌詞が不明瞭なところがあるので、歌うに歌えない。さて皆さん食べきれないほど食べて飲んでも、だいたい一人3,000円くらい。この安さと料理のうまさで常連になってしまった人もいるのではないか。
八起閉店の知らせを聞いたのは今シーズンの初練習の日。いつも初練習で指揮を振ってくださる柴山先生もご一緒で、新入団員の歓迎会も兼ねていて盛り上がっていたところにママさんの衝撃の一言。最近は常連団員の退団等々、様々な理由で八起離れが進んでいて、かつてはいつも満員だった席が今日は5名ほどしかいないということがこの頃続いていた。このことは今回の廃業とは関係ないようだが、常連だった私は少々心が痛む。団員みんなで飲んだ最後の日は本当に店内満席で、みんなで飲む最後の機会を大いに楽しんだ。
八起のみなさまには心からお疲れ様と言いたい。長い間お世話なりました。本当にありがとうございました。
■補遺 松下俊行(維持会マネージャー)
オーケストラの奏者は基本的に個人主義者なので、練習後どうするかは皆まちまち。呑みにいきたい人は行くし、誘われても行かない人はいかない。誘った方も「俺の酒が呑めないのか」とか「つきあいが悪い」など一般の社会にありがちな酒の態はまず無いと断言できます。だから新響でも「八起」に1度も行ったことがない団員がいても不思議でもなければ、それを非難される事もない・・・けれど、新響に身を置いていればやはり「気になる店」として団内には浸透していました。お店の方々にコンサートにおいで戴いた事も度々です。
音楽への、演奏への抱負や練習での失望と愚痴、演奏する喜びと失敗に対する怨嗟と反省・・・と、酒と共に様々な言葉が飛び交い、悲喜こもごもの言動が渦巻いていた店でもありました。要するに演奏団体が常連となれば巻き起こるであろう全ての事が起こり、その全てを許容して戴いていた類(たぐい)稀なる店・・・こうした店は庶民的な十条の街といえども、昨今はなかなか見出し難くなっています。
どなたか「次の店」を御紹介下さいませんか。JRの東十条駅と十条駅の間にあって、最低でも10人以上収容できる上に他に客はおらず、一升瓶がキープできて、揚げ立てのものや切り立ての刺身が供される上に、「こちら~の方になります」という不思議な日本語と共に料理が運ばれて来ない事が、ささやかな条件ですが・・・。
ディーリアスとグレ=シュール=ロワン
維持会員の皆様こんにちは。前回の演奏会から入団しました岡田澪と申します。都内の音楽高校の2年生です。両親ともに新響の団員なので、実は最近まで維持会員でした。今回はディーリアスを吹かせていただきます。
「ブリッグの定期市」を作曲したフレデリック・ディーリアスはイギリスの作曲家です。ディーリアスは1862年にイギリスに生まれ、この国で育ちましたが、実はこの作曲家は生涯イギリスに住んでいたわけではありません。音楽家になることを反対した父から自由になるためにアメリカへ渡り、その後なんとか父の同意を得てライプツィヒ音楽院に在学。1888年からパリに移り住み、1897年から亡くなるまでパリ郊外にあるグレ=シュール=ロワンという村で過ごしました。
グレ=シュール=ロワンはパリ市街から南東に64kmほどの所にあり、中世の建造物である石橋や塔、そしてのどかな田園風景が残る静かな田舎町です。ディーリアスはパリでラヴェルやムンク、ゴーガン、ストリンドベリなどと親交を結んでいました。なぜ彼はパリから離れた、今日でも人口1300人ほどの小さな村に移り住むことにしたのでしょうか。
実はこのグレの村、19世紀後半からさまざまな国から芸術家が集まった芸術家村で、画家のカミーユ・コローやフランク・オマラ、スウェーデンの劇作家のアウグスト・ストリンドベリ、そして日本からは黒田清輝や浅井忠、美濃部達吉、梅原龍三郎、藤田嗣治などの人達が訪れています。日本人の画家で最初にグレを訪れたのは黒田清輝と思われますが、彼がこの地で描いた「読書」や「婦人図」などの作品のうち、「読書」はパリのサロンで入選しています。
このように、この村に来た画家達はこの村の自然や前述のロワン川に架かる橋、北のフォンテーヌの森などを描きながら、お互いに影響を与え合っていました。ディーリアスの妻であるイェルカ・ローゼンも画家であり、イェルカはグレで絵を描くために家を購入します。そのため、ディーリアスもこの村で作曲活動をするようになりました。ディーリアスが移住したのはコローや黒田清輝がグレを訪れた時期よりもあとですが、この村でたくさんの芸術家と交流を持ちました。パリ時代から親しい間柄のムンクも、1903年にグレのディーリアスの家を訪れています。
「ブリッグの定期市」もグレに移り住んでから作曲されました。イギリスの民謡をもとにした曲ですが、少なからずグレの村のディーリアス邸の庭園、村をゆるやかに流れるロワン川などの情景の影響を受けていると思われます。
~参考文献~
荒屋鋪透「グレー=シュル=ロワンに架かる橋」
ドヴォルザーク:交響曲第8番
1 生誕~ブラームスとの出会い
アントニーン・ドヴォルザークは1841年にチェコのネラホゼヴェス村(首都プラハから30kmほどの小さな農村)にて生まれた。このチェコという国の歴史の中では、大都市ではなく田舎の農村部から優れた作曲家を輩出することが多い。(他にもスークやヤナーチェクなどが挙げられる。)ドヴォルザークもその例に漏れず、音楽好きな家族、そして音楽が盛んな土地柄にも恵まれ、幼少の頃から音楽に親しみをもち学んでいくようになった。
もっとも、若い時分(1860年代)には作曲家としてすぐには芽が出ず、研鑽を積む日々を送った。作曲の勉強をしつつ、地元のカレル・コムザーク楽団でヴィオラ奏者として生計を立てていた。なお余談であるが、1866年からチェコ音楽界の先達、スメタナが指揮者に迎えられていた。作曲家として、そしてチェコ人の一芸術家として大成していく上で、大きな薫陶を受けたであろうことは想像に難くない。
1870年代に入り、下積みの時代から抜け出すきっかけとしては、ブラームスの影響が非常に大きい。1875年から5年間にわたり、ドヴォルザークはオーストリア政府の国家奨学金に応募し受賞していたが、その審査会の一員としてブラームスが参加していた。ブラームスはこの若きチェコの作曲家の才能にいち早く目をつけ、その作品を自分の楽譜の出版社であるジムロック社に紹介していった。こうして出版された諸作が評価されたことから、同出版社からは「スラブ舞曲第1集」の作曲が依頼されることとなった。1878年に作曲されたこの曲は、彼の出世作(と同時に、ご存知のとおり彼の生涯の中でも代表的名作の一つ)として好評を博し、チェコ国外においてもその名が広く知れ渡るようになった。
このように、ブラームスはドヴォルザークの国際的な名声を上げていく上で非常に重要な役割を担ったといえよう。後にドヴォルザークはブラームスとより密接に親交を深めていき、作曲技法など多くの点で影響を受けることとなった。
2 作風の確立~交響曲第8番の誕生
さて、ドヴォルザークの活躍していた19世紀の後半、チェコはオーストリア帝国からの独立を求め、民族運動に揺れ動いていた。そういった時勢の中で、多くのチェコ人芸術家たちは民族的かつ郷土愛に満ちた作品を次々と発表し、こぞって創作の腕を競い合っていた。
大作曲家としての道を歩み始めていた1880年代、ドヴォルザークは「民族的闘争の中で芸術家が果たすべき役割」に苦慮する日々が続いていた。ちょうどこの時期に、民族ドイツ・オペラ(内容的に、民族運動に逆行する内容と受け取られてしまう)の作曲を依頼されたことも、一因としてあったであろう。自分が進むべき道についての苦悩の果て、やがて彼も他の多くの芸術家と同様に、チェコ人として生き抜く決意に辿り着いたのである。彼は生涯にわたってチェコ国内に居を構え、作曲活動に専念した。
ドヴォルザーク独自の作風は、こういった背景によるところが非常に大きい。彼は古典・ロマン派の伝統的な様式(=西欧的な要素)に基本的には則り、9曲の交響曲を始めとした絶対音楽に重きを置いた。この辺りは、チェコの歴史的主題等をモチーフとした標題音楽(歌劇等)を数多く残したスメタナとは、非常に対照的である。前述のブラームスとの親交の中で、その技法や構成力など多くの影響を受けたこともあったであろう。しかし、西欧の伝統的な技法に留まらず、ドヴォルザークはその枠組みの中でスラブ的・チェコ的な民族舞曲・民謡などを積極的に取り入れていったのである。
こういった要素の集大成とも言えるのが、今回演奏する交響曲第8番(1889年作曲)である。以下、曲について簡単に紹介する。
3 曲目解説
前述のとおり、古典派の様式の枠組みの中での構成の自由化、及び所々に見られるボヘミアの民族色、この2点を主な特徴としている。
構成の自由化という点では、例えば1楽章の冒頭では、ト長調を主とした楽章にも関わらず、優美な旋律(第1主題)はト短調にて始まる。3楽章もスケルツォではなく、優雅で旋律的な舞曲となっている。4楽章はソナタ形式をとっているものの、全体としては主題の様々な変奏が登場していく。
ドヴォルザーク特有の民族色も曲中で鮮やかに彩られている。ボヘミアの自然や「民衆の声」といったものがイメージされる曲である。中でもそれが顕著であるのが2楽章である。おちついた田舎を思わせるような、冒頭の弦のメロディ、小鳥の鳴き声を連想させる、木管楽器の穏やかな響き。全曲を通しても最もドヴォルザーク的であり、独創性に満ちている。他にも3楽章のトリオ(自作の喜歌劇「がんこ者たち」からの引用)や、4楽章の第1主題(スコチナー舞曲というボヘミアの民族舞踊)や中間部の原始的な響きの和音・リズムなど、ドヴォルザークらしさが随所に散りばめられている。
4 イギリスとドヴォルザーク
さて、この交響曲第8番は、「イギリス」という副題で度々呼ばれることがあるが、これは何故であろうか?答えの前に、まずはチェコの国民的大作曲家ドヴォルザークと、エルガーやディーリアスといった、ドヴォルザークとは全く作風の異なった作曲家を生み出したイギリスという国との、意外な接点について簡単に述べておきたい。
1880年代、イギリスでは一般的に聴衆に認知されていない作曲家の作品を積極的に取り上げ上演するなど、外国の芸術家を暖かく受け入れる土壌が整っていた。その中でドヴォルザークの作品も度々イギリス各地で演奏され、好評を得るようになっていた。1884年3月にはドヴォルザーク自ら初のロンドン訪問を行い、自作「スターバト・マーテル」を指揮した。これはロンドンの聴衆の熱狂的ともいえる大絶賛を受け、彼のそれまでの人生において最高ともいえる公的な成功となった。イギリスでの活躍は、ドヴォルザークの作曲家人生において大きなステップアップになったといえるであろう。
またこれをきっかけに、当時のイギリスが「ドヴォルザーク贔屓」の国になったともいえる。ドヴォルザークはこの後も生涯において計9度に亘りイギリスを訪問し、その度に暖かい歓迎を受けた。国外での成功は、彼により大きな自信を与えていったことであろう。特に1885年4月にロンドンにて初演された交響曲第7番においては、イギリスの批評家に過大ともいえる好評(シューベルトの「ザ・グレート」やブラームスの4曲の交響曲と肩を並べるものと評されていたらしい。)でもって迎え入れられた。
話を冒頭の問いに戻すと、残念ながら交響曲第8番の曲の中身そのものはイギリスとは全く関係はない。「イギリス」という副題は、むしろ出版のときの諸事情によるものである。それまでドヴォルザークの作品の出版を主に受け持ってきたベルリンのジムロック社とは金銭面などで折り合いがつかず、確執が目立つようになっていた。そこで、ロンドン訪問当時に親交を深めたイギリスの出版社ノヴェロ社に楽譜を渡したことで、「イギリス」という副題でしばしば呼ばれるようになったのである。
そうとはいえ、これを単なる「出版社の問題」と片付けてしまうのは、少々味気ない。ドヴォルザークという作曲家を評価し、大作曲家として成長していくための土壌を提供した、イギリスという国。イギリスでの成功があってこその交響曲第8番という名曲の誕生、とまで言い切るのはさすがに乱暴すぎるかもしれない。が、少なくとも「イギリス」という副題が、この作品には中々洒落たネーミングとなっているように筆者個人としては感じられるのである。
参考文献
有坂愛彦他「作曲家別名曲解説ライブラリー6 ドヴォルザーク」(音楽之友社)
内藤久子「作曲家 人と作品シリーズ ドヴォルジャーク」(音楽之友社)
初演:1890年2月2日 ドヴォルザーク指揮の国民劇場管弦楽団によって行われた。
楽器編成:フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2(1番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、弦5部
エルガー:エニグマ変奏曲
イギリス、正しくは大ブリテン王国は僕の大好きな国のひとつです。とくに田舎はすばらしい。どこに行っても汚いところはいくら探してもありません。緑がいっぱいで、家並みは美しい、羊がたくさんいて、幸せそうな丘陵地帯がどこまでも続きます。エルガーはそういった田舎のモルバーンというロンドンの西140キロのウースターのすぐ南西にある小さな町の楽器屋さんの息子として生まれました。1857年のことです。ペリーが下田に来たのが54年ですから、57年は日本では安政4年、幕末の大混乱期です。そのころイギリスは、ヴィクトリア女王時代の最盛期で、東アフリカのほとんど、インド全土(いまのパキスタンやバングラデシュを含む)マレーシア、ビルマ、オーストラリアなど広大な植民地を支配し、それら植民地から得られる豊富な資源により世界一といっていい強国でした。19世紀のイギリスは絵画では、ターナーやミレー、ホイッスラーと言った有名な画家が、また小説ではディッケンズやコナン・ドイル、オスカー・ワイルドほか多数の天才達が活躍して華やかな時代でしたが、どういうわけか音楽に関しては全くといってよいほど衰微した時期でした。そんな時現れたのがエルガーです。17世紀のパーセル以来200年ぶりのイギリス待望の作曲家として人々から喜んで迎えられたのです。(ヘンデルはドイツ人で42歳の時イギリスに帰化したので、イギリスではドイツ人の作曲家とみなされている)
エドワード・エルガーの父親は教会のオルガン奏者だったことから音楽の才能があったようですが、貧しい楽器屋で、エドワードに専門的な音楽教育をうけさせることはできませんでした。それでもエドワードはピアノやヴァイオリンが上手で独学で作曲もできるようになりました。13歳のころ教会のオルガン奏者になり教会音楽を作曲しています。また仲間たちと始めたアンサンブルのためにも何曲か作曲しました。彼が大作曲家としてイギリス中に知られるようになるのは40歳を過ぎてからですが、それまで彼はピアノとヴァイオリンの個人教師として生活していました。そんな彼のところにアリス・ロバーツという女性が弟子になったのが1886年で2年後の1889年に二人は結婚します。アリスはその時40歳。エドワードは32歳。その1年前に婚約のお祝いとしてアリスに捧げたのがあの有名な『愛の挨拶』です。最近の若者は彼女の前でギターをジャラジャラ弾きながら愛の告白をするらしいですが、彼女ははなはだ迷惑ですよね。でも『愛の挨拶』みたいな曲だったら誰でもいちころではないでしょうか。名曲だと思います。じつは僕も昔(若い頃ですよ)彼女を家に連れてきてこの曲をチェロで弾いたことがあります。いま考えてみるとご迷惑をかけたのかも。
僕は今度の定期にエルガーのエニグマをやると聞いたとき、「へーそうなの。でもエルガーは新響で初めてやるのになぜ『謎』をやらないの?」と思いました。でもエニグマとは謎のことと判明して納得。謎なら有名なのにエニグマとは聞いたことがないなと思ったのは僕だけでしょうか?(そうだ、お前だけだ)
ある日、エルガーがピアノにむかってなにげなく指を動かして適当なメロディーを弾いていた時、そばを通りかかったアリスが「なーにいまのメロディー?」と聞いた。エルガーは「たいしたものじゃないよ。でも、これでなにかできるかも」と言って、そのメロディーをもとに親しい友人達を思い浮かべながら「彼はこんな感じ、彼女ならこうだね」といいながらいろいろな変奏を作ってみたのがこの曲ができたきっかけでした。エルガーはそれを主題と14の変奏曲にまとめ、各変奏曲に友人達のイニシアルをつけて、かつ全体を『エニグマ』と命名して発表しました。なにが謎なのかというと、第一にイニシアルが誰を指すのかということですが、これはエルガーが詮索好きの友人達によって問い詰められた結果、第13変奏を除いて解明されてしまいました。しかしこの曲には第二のもっと大きな謎があるらしい。エルガーによると「曲全体をより大きな主題が貫いているのだが、その主題は決して演奏されることはなく、その後の展開においても登場することはなく、主要な性格は表舞台には現れることはない。これはメーテルリンクの『闖入者』や『7人の王女』の主役が決して舞台上に現れないのと同じである」といっています。(メーテルリンクの戯曲は明治から大正にかけて日本でも非常に多く上演されていたが、昭和にはいって突然上演されなくなった。いまでは、青い鳥という童話の作者としてわずかに記憶されるに過ぎない)この第二の謎については、多くの研究がなされ、英国国歌が隠されているのではないか、いやAuld lang syne(蛍の光)だとか、英国愛唱歌のルールブリタニアだ、などいろいろな説がありますが結局いまだに解明されておらず、現在ではあきらめられているようです。エニグマが初演されたのは1899年ロンドンのセント・ジェームズ・ホールでハンス・リヒター(当時の一流指揮者で後にエルガーの擁護者となる、当時56歳)の指揮で行われ大成功をおさめました。曲としての完成度もさることながら、成功の鍵はやはりその題名とエピソードによるところが大であったと思われます。第14変奏の終曲は初演のときはもっと短かったらしいが、エルガーの親友であり後援者であり、また第9変奏の主人公である楽譜出版社の編集者だったJaegerのアドバイスにより100小節が書き足されました。この追加部分にはオルガンが参加しますが、スコアーには「ad lib」(随意)すなわち、無しでもいいと書いてあります。今日は無しです。
エニグマの成功に気をよくしたエルガーは1900年にオラトリオ『ゲロンティアスの夢』1901年に彼の代表作である軍隊行進曲『威風堂々』を発表する。即位したばかりの英国王エドワード7世は威風堂々がすっかり気に入り、「世界中の人に愛されるメロディーになるだろう」といい、翌年の戴冠式の頌歌に引用されることになりました。エルガーはこの功績により1904年にナイトの称号を送られ一生の生活が保証されることになったのです。ちなみに、日本は1902年に日英同盟を結び、それを支えに1904年日露戦争に突入しました。
エルガーは数多くの名曲を残しましたが、彼の最高傑作(私見)であるチェロ協奏曲は1919年彼が62歳の時の作品です。翌20年に妻アリスを亡くし、彼自身は1934年(昭和9年)に76歳で亡くなりました。
主題
ヴァイオリンによって奏される第一主題とクラリネットによって奏される第二主題で構成されるが、たったの17小節と短くすぐ第一変奏にはいる。
第一変奏:「C.A.E.」 Caroline Alice Elgar
最愛の妻アリス。主題から同じテンポで入るので、いつ始まったのか気をつける必要がある。ゆったりしたAdagioで、やさしさが表現されている。エルガーは「この変奏は主題の延長であり、ロマンティックで繊細な要素を加えたかった。C.A.E.を知っている人なら誰だかわかるだろう」といっている。
第二変奏:「H.D.S.-P.」Hew David Stewart-Powell
アマチュアのピアニストでエルガーの室内楽仲間の一人。彼が演奏の前に音階練習をする様子をパロディー化している。
第三変奏:「R.B.T.」 Richard Baxter Townsend
アマチュアの俳優でパントマイムも得意だった。声域や声質を自由に変える特技があり、それがこの変奏の主流となっている。
第四変奏:「W.M.B.」 William Meath Baker
ハスフィールドの大地主で育ちがよく学のある人。この変奏は彼がパーティーの準備のため紙片を手に当日の準備事項を力をこめて読み上げると、扉をバタンと閉めてあわてて出てゆくところを描写している。 第五変奏:「R.P.A.」 Richard P. Arnold
1888年に没した詩人Matthew Arnold の三男、父親譲りの文芸家だが音楽好きでもありピアノを独習していた。ヴァイオリンのG線で奏されるゆったりしたメロディーから彼の穏やかで重厚な性格が想像される。真面目に話していたかと思えば、突然奇抜でしゃれたことを口にする、笑い声がオーボエで奏される。
第六変奏:「Ysobel」 Isabel Fitton
ウースターに住む音楽一家の令嬢で、アリスとエドワードを結んだ恩人でもある。エルガーにヴィオラを習っていた。だから、この変奏はヴィオラが主役で、初心者が苦心する移弦の練習のパロディーである。 第七変奏:「Troyte」 Arther Troyte Griffith
モルバーンに住む建築家。エルガーの遊び友達で凧あげやハイキングをして楽しみ、一生を通じて親交があった。また、エルガーにピアノを習っていたが、下手だったらしい。プレストの指示があり非常に早いテンポで奏されるところから、かなり早口でせっかちだったと思われる。
第八変奏:「W.N.」 Winifred Norbury
ウースターフィルハーモニー協会の事務員だった彼女は、モルバーンの北にあるシェリッジという18世紀に建てられた古い邸宅に住んでいた。この曲はその邸宅と彼女ののんびりした笑い声を表している。 第九変奏:「Nimrod」 August Johannes Jaeger
楽譜出版社ノヴェロの編集者でエルガーの擁護者でありかつ親友だった。エニグマの楽譜の初版は当然ノヴェロ社から発行された。彼がベートーヴェンの緩徐楽章についてエルガーと話し合っている様子を表すといわれている。エルガーは3歳年下の彼を尊敬していたらしく、この変奏曲は非常に荘厳な感じになっている。よほど世話になったらしい。
第十変奏:「Dorabella」Dora Penny
第四変奏に登場するウイリアムベーカーの姪でエルガーにたいへん可愛がられていた。彼女は後に第二変奏のスチュアートパウエルと結婚することになる。おとなしくて控えめな女性で少しどもるくせがあったらしい。それが全曲に表れている。
第十一変奏:「G.R.S.」George Robertson Sinclair
友人が「G.R.S.というのはヘレフォード大聖堂のオルガン奏者のジョージのことだろう?」と聞くとエルガーは「その通り。でもこの曲は大聖堂やオルガンとは関係なく、彼が飼っているダンというブルドッグが散歩の途中ワイ河におっこち、流れに逆らって必死に泳いで岸にだどりつき、うれしそうに吠えるところを表しているんだ」と言った。大変ユーモラスな曲である。ちなみに「ユーモア」はイギリス紳士の大事な条件のひとつです。

前列左から、第11変奏のシンクレア、河に落ちたダン、エルガー
第十二変奏:「B.G.N.」Basil G. Nevinson
パウエルとともにエルガーの室内楽仲間でチェリスト。チェロが主役でメロディーを奏するがヴィオラがそれを助ける。
第十三変奏:「***」
問題の第十三変奏である。エルガーの初稿ではL.M.L.とされていたが、それを消して***となった。L.M.L.はLady Mary Lygonで当初は彼女を念頭に置いていたことは間違いなさそうだ。彼女はその時オーストラリアに向けて航海中で、曲は船のエンジンの音や波のうねる様子を表しているように聞こえる。また、メンデルスゾーンの序曲「静かな海と楽しい航海」のメロディーがクラリネットで奏される。彼女は1869年生まれで当時30歳、航海の目的はなんだったのだろう。当時のオーストラリアはまだイギリスの「流刑地」という印象が強く、殖民が始まっていたとはいえ、エルガーの周囲の友人達のような階級の人が殖民するとは思えず、単なる観光旅行ではありえない。イニシアルを消してしまった理由はいまだに解明されていない。また、この曲はエルガーが1883/4年に婚約していたHelen Weaverだという説をとなえる人もいる。彼女は婚約が破れてライプツィヒに行ってしまった。
第十四変奏:「E.D.U.」Edward Elger
妻アリスは彼女の年下の夫をエドゥーと呼んでいた。すなわちこの曲はエルガーの自画像である。しかしこの変奏は具体的にはなにを表しているというものではなく、自由奔放に作曲されており、全曲を通して一番エルガーらしさがでている。図らずして、まさにE.D.U.になっている。
参考文献
『エルガー/エニグマ変奏曲(独創主題による変奏曲「謎」)(ポケット・スコア )』(日本楽譜出版社)
日本エルガー協会公式HP
初演:1899年 ハンス・リヒター指揮ハレ管弦楽団 ロンドンのセント・ジェームズ・ホールにて
楽器編成:フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、小太鼓、トライアングル、大太鼓、シンバル、オルガン(任意)、弦5部
上品なイギリス音楽と人間愛に満ちたドヴォルザーク
我が愛する新響と、イギリス音楽とドヴォルザークを初めて共演する喜びを胸に本日の指揮台に上ろう。
あのバロックのヘンリー・パーセル以来、長らく不毛であったイギリスの芸術音楽作曲を200年の眠りから目覚めさせた、対照的な両雄ディーリアスとエルガー。近代イギリス音楽作品の代表作であり、初の国際的評価を確立した曲と謳われるエルガーの「エニグマ変奏曲」。一方、今年丁度初演百年を迎えるディーリアスの「ブリッグの定期市」。二人の作風は全く異なるが、共通するのは“上品さ”。そして二人共独学に近いというから恐れ入る才能だ。
そのディーリアス(実は北部イギリスで生れ育ったドイツ人)は、実は私の最も好きな作曲家の一人なのだが、日本では十分に理解されているとは言い難いのでその特徴を少々述べておきたい。
フランスのドビュッシーとモネをそれぞれのジャンルの典型的な“印象派”とするなら、イギリスのディーリアスとターナーは“印象派の先駆”あるいは“印象派的ロマン詩人”と私は位置づけている。ドビュッシーの“放置された(・・・・・)和音のひびきの美しさ”(それは後の武満徹につながって行くのだが)に対して、ディーリアスの音楽は、最終的には和音の“連結(カデンツァ)”により“解決(・・)”に向う。それが私をしてディーリアスを“印象派的ロマン派”と呼ばせる理由である。ターナーの絵と同じようにディーリアスの音楽を正しく味わうためには、聞き手に“大気・靄(もや)・蒸気”などの密やか(・・・)な(・)息遣い(・・・)を感じとれる繊細な感受性が必要とされる。それらが瑞瑞しさや、半音階進行によるデリケートでセンシティヴな“水彩画的色彩のグラデーション的変化の妙”となって表現される音楽故に、通俗的なポピュラリティを得る事は無い宿命を持つ。今後もディーリアスの音楽は、繊細で豊かな音楽性を持つ人間だけに扉を開いてくれるのであろうし、しかしその素晴らしさを知った者には至福の時間を与えてくれるであろう。
さて、今回のドヴォルザークでは、新響から“音楽性に溢れた演奏”を引き出してみたい。音楽をするには何より“感受性豊かで強い表現意欲を持つ音楽性”が大事な事の再認識であり、それが特にドヴォルザークのような“人懐こく温かいアナログ的良さ”と“土のついた野菜の持つ力強さと香り・味わいの深さ・濃さを享受する喜び”に喩えられる音楽の魅力を引き出し、聞き手に伝える基となるからである。
乞う御期待!
ディーリアス:ブリッグの定期市
Delius in 1912 Jelka Delius (ディーリアス公式HPより)
それは8月5日のことだった
天気はすばらしく晴れていた
ぼくはいとしい恋人に逢うために
ブリッグの定期市に出かけていった
ディーリアスの作曲した<ブリッグの定期市>は、同名のイギリス民謡をテーマとする変奏曲ですが、その民謡は、こんな歌詞で始まる優しくて柔らかい歌です。< br> ディーリアスはイングランド北部ヨークシャー州ブラッドフォードの生まれ。ブリッグ(Brigg)という街からおよそ70㎞西北西という近さから、幼い頃に耳にした民謡をモチーフとして取り上げて作曲したのかな?と思ってしまうのですが、彼がこの素敵な旋律に出会えたのは、グレインジャー(Percy Grainger, 1882~1961)という優れたピアニスト&作曲家がいたからでした。
オーストラリア(当時イギリス領)出身のグレインジャーは、ノルウェーに晩年のグリーグを訪ね、民俗音楽に関心を持つようになります。そして、イギリス各地で民謡を収集して回り、エジソン発明の蝋管蓄音器を用いて数多くの歌を記録しました。このため、集めた歌の一つである民謡<ブリッグの定期市>も、幸いなことに地元の老農夫ジョゼフ・テイラー(Josef Taylor)の艶やかな声による録音が残っています。グレインジャーはこの民謡に和声づけし、合唱曲にアレンジして発表しました。
1906年、グレインジャーとディーリアスは病床にあったグリーグの紹介で知り合い、親交を深めるようになります。ディーリアスがグレインジャーを自宅に招いた際に、グレインジャーが<ブリッグの定期市>を弾いて聴かせたところ、ディーリアスはすっかり魅了され、この旋律を作曲に使う許可を求めました。翌年、書き上げられた<ブリッグの定期市>はバーゼルの音楽祭で初演され、好評を博します。この頃から、イギリス人指揮者のビーチャム(Sir Thomas Beecham, 1879~1961)がディーリアスの才能に惚れ込み、イギリスで彼の作品を盛んに演奏したため、彼の音楽が母国で高く評価されるようになりました。
ちなみに、グレインジャーは、ジョゼフ・テイラーが歌の第2節までしか覚えていなかったため、他のイギリス民謡("Low down in the broom" と"The Merry King"の2曲)から歌詞を取り、付け加えました。その後録音された民謡<ブリッグの定期市>には様々なバージョンがありますが、グレインジャーがまとめたのは次のバージョンだといわれています。
It was on the fifth of August, the weather fine and fair,
Unto Brigg Fair I did repair, for love I was inclined.
I rose up with the lark in the morning, with my heart so full of glee,
Of thinking there to meet my dear, long time I'd wished to see.
I took hold of her lily-white hand, O and merrily was her heart:
"And now we're met together, I hope we ne'er shall part".
For it's meeting is a pleasure, and parting is a grief,
But an unconstant lover is worse than any thief.
The green leaves they shall wither and the branches they shall die
If ever I prove false to her, to the girl that loves me.
(第2節以降の日本語訳(例))
ぼくはよろこびに胸をふくらませて
朝早くひばりとともに起きた
ずっと逢いたいと願っていた
あの娘に逢えるのだと思って
ぼくは彼女の白百合のような手をとった
すると彼女の心もときめいていた
「ようやく逢えたのね
もう決して離れたくないわ」
逢っているときは楽しくて
離れているときは悲しい
けれども心変わりするような恋人は
どんな盗人よりもひどいもの
緑の葉はしおれ
枝は枯れてしまう
もしぼくを愛してくれる恋人を
ぼくが裏切ったりしたら
ところで、ブリッグは、イングランド中東部リンカンシャー州北部の、海辺から約20㎞離れた場所にあるほんとうに小さな街です。英国政府観光庁の説明によると、ブリッグはグレインジャーとディーリアスにより有名になった街とのこと。古くから、聖ジェイムズの祝祭日(旧暦7月20日)から数えて5日間、定期市(縁日)が開かれていました。暦が変わり開催日が8月5日に移りましたが、いずれにしても年に1回しかない催し物だったわけです。定期市に行かないと逢えない恋人だったのでしょうか…。なお、現在も、8月5日に夏祭りのようなBrigg Fairが開催されており、ダンスショーや手工芸品や美術品の店といった出し物があるようです。
この辺でディーリアスについても少し触れておきたいと思います。彼は裕福なイギリスの羊毛商人の家庭に育ち、ロンドンのカレッジ卒業後、一旦は父親に従い家業の羊毛会社に入りました。しかし、幼い頃からヴァイオリンやピアノを習い音楽に親しんでいた彼は、どうしても音楽の道に進みたかったため、当時盛んになっていたフロリダ州でのオレンジ栽培を口実にして父親を説得し、自由と資金を獲得します。案の定オレンジ栽培は放ったらかし。彼は音楽の勉強や作曲に積極的に取り組み始めました。農園で働く黒人労働者たちの音楽にも夢中になったといいます。
そのうち父親が諦めてライプツィヒ音楽院入学を許可し、1886年、晴れて音楽の道に。在学中に出会ったグリーグからは、音楽的に強い影響を受けただけでなく、卒業後もグリーグの口添えによりパリで作曲活動を続けられることになるなど随分と世話になりました。
1897年、ディーリアスは女流画家のイェルカ・ローゼンとともに、パリ近郊の村、グレ=シュール=ロワンに移り住み、結婚します。グレでの生活は、家の庭やすぐ近くを流れるロワン河など、その後のディーリアスの楽想を刺激するものに満ち溢れており、アメリカで触れた黒人音楽や、パリで出会ったゴーギャンやムンクといった後期印象派あるいは象徴主義と呼ばれる画家たちとの交流などとともに、彼の作品に大きな影響を与えました。
ディーリアスの音楽は、他の誰とも違う、独特の個性を持っているといわれています。19世紀後半の後期ロマン派に属しているものの、自由にしなやかに移ろうハーモニーの変化が、ディーリアスらしさを表しています。
また、音楽が絵画に喩えられることがよくありますが、ディーリアスはイギリス史上最も偉大な画家と呼ばれるターナー(Joseph Mallord William Turner, 1775~1851)に喩えられることが多いようです。ターナーは、特に水彩画の分野で高い業績を残したロマン主義の風景画家です。絵の多くは明るく透明感のある微妙な色彩で満たされており、物の輪郭ははっきりしていません。霧の中のような、まるで風景のなかの空気が描かれているように見えるのです。ディーリアスの描くハーモニーの移ろいは微妙で、ちょうどターナーのとらえた光や色彩の変化を想い起させるようです。
■序奏(ゆっくり、牧歌的に)
フルートがハープのアルペジオに乗って牧歌的な旋律を奏でる。夏の朝、まだ靄がかかる頃の田舎の空気の感じ。湿度や温度さえ肌に感じられるような美しい旋律である。
■主題(軽く楽な速さで)
オーボエがクラリネットとファゴットの作る独特の和声の上で、イングランド民謡<ブリッグの定期市>の主題をやわらかく歌う。
この旋律が和声、リズム、テクスチュアを変化させながら各楽器へと受け継がれる。木管楽器、弦楽器からホルン、そして最後にトランペットへ。トランペットによる第六変奏の頃にはだいぶ盛り上がってくるので、大きな楽器編成にも納得いただける…と思う。
■間奏(ゆっくりときわめて静かに)
フルートが序奏の旋律を回想し、弱音器をつけたヴァイオリンが美しい旋律を歌う。少し悲しげな旋律はコールアングレやホルンに引き継がれていく。
■第七変奏~(やや速く、しかし慌てずに)
少しだけ速度があがり、クラリネットやフルートが主題の変奏を奏でる。
■第九変奏~(ゆるやかなテンポで)
木管楽器の変奏に対してヴァイオリンが副主題を奏でる。この副主題は少しワーグナーを想起させる旋律。
■第十一変奏~(ゆっくり荘厳に)
トランペットとトロンボーンが荘厳な主題の変奏を奏した後、木管楽器とホルンに旋律が受け継がれ、周りで様々な楽器が八分音符の後打ちを入れ、めまぐるしくハーモニーを変化させながら曲が進む。この曲の中で一番混沌としている箇所。市の雑踏を複数のカメラで撮影し、素早く切り替えながら見せ、所々恋人たちの映像がちりばめられているような感じ。
■第十三変奏~(陽気に)
フルートとクラリネットによる変奏。恋人たちの楽しげな様子。さまざまな楽器による変奏が続き、曲は最高潮に。打楽器が明るい色彩感を与える。
■コーダ(きわめて静かに)
オーボエが再び静かに主題を奏で、ゆっくりと消え入るように終わる。
参考文献
「ディーリアス<ブリッグの定期市>(ポケット・スコア)」日本楽譜出版社
「ディーリアス管弦楽曲集 バルビローリ指揮 ロンドン交響楽団」CD曲目解説
ディーリアス公式HP、英国政府観光庁HP
初演:1907年10月23日、バーゼルにて。指揮はズーター(Hermann Suter, 1870~1926)。イギリスでの初演は翌年1月11日、リヴァプールにて。バントック(Granville Bantock, 1868~1946)指揮。
楽器編成:フルート3、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット3、バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン6、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、チューブラベルズ(チャイム)、トライアングル、ハープ、弦5部
第203回演奏会ローテーション
| ディーリアス | エルガー | ドヴォルザーク | |
| フルート1st | 岡田澪 | 岡田充 | 松下 |
| 2nd | 藤井 | 吉田(Picc) | 丸尾(Picc) |
| 3rd | 丸尾 | - | - |
| オーボエ1st | 山口 | 亀井淳 | 堀内(C.A.) |
| 2nd | 亀井優 | 岩城 | 横田 |
| コールアングレ | 桜井 | - | - |
| クラリネット1st | 高梨 | 品田 | 中條 |
| 2nd | 進藤 | 大藪 | 末村 |
| 3rd | 末村 | - | - |
| BsCl | 石綿 | - | - |
| ファゴット1st | 田川 | 浦 | 長谷川 |
| 2nd | 浦 | 田川 | 古川 |
| 3rd | 長谷川 | - | - |
| コントラファゴット | 古川 | 古川 | - |
| ホルン1st | 比護 | 園原 | 箭田 |
| 2nd | 山口 | 大内 | 山口 |
| 3rd | 大原 | 大原 | 鵜飼 |
| 4th | 箭田 | 市川 | 比護 |
| 5th | 大内 | - | - |
| 6th | 園原 | - | - |
| トランペット1st | 倉田 | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 北村 | 北村 | 青木 |
| 3rd | 中川 | 中川 | - |
| トロンボーン1st | 武田 | 小倉 | 志村 |
| 2nd | 牧 | 武田 | 牧 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 | 大内 |
| テューバ | 足立 | 足立 | 足立 |
| ティンパニ | 桑形 | 桑形 | 中川 |
| 大太鼓 | 桜井 | 桜井 | - |
| シンバル | - | 中川 | - |
| トライアングル | 田中 | 今尾 | - |
| 小太鼓 | - | 今尾 | - |
| 鐘 | 今尾 | - | - |
| ハープ | 堀米(*) | - | - |
| 1stヴァイオリン | 堀内(岸野) | 堀内(岸野) | 前田(岸野) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(笠川) | 大隈(笠川) | 大隈(田川) |
| ヴィオラ | 柳澤(石井) | 柳澤(石井) | 石井(柳澤) |
| チェロ | 柳部容(安田) | 柳部容(安田) | 光野(日高) |
| コントラバス | 中野(加賀) | 中野(加賀) | 加賀(中野) |
第203回演奏会のご案内
●今回は小松氏の十八番
新響の定期演奏会において小松一彦氏の登場は9回目となりますが、創立50周年記念シリーズや第200回演奏会といった節目での共演を経て、新響との関係を深めています。今回は、プラハ交響楽団の常任客演指揮者として度々チェコで演奏をしている小松氏が、得意中の得意とするチェコの大作曲家ドヴォルザーク交響曲第8番をプログラムしました。
●エルガー=イギリス近代音楽の父
前半にはイギリスの作曲家の作品を2曲を演奏します。
「Brigg Fair(ブリッグの定期市)」とは、イギリスのリンカーンシャー州北部のブリッグに伝わる民謡のことです。羊毛業の後継ぎであったディーリアスの生まれたヨークシャーとブリッグは近く、フランスに移り住んだディーリアスは故郷を懐かしみこのラプソディーを作曲したのでしょうか、郷愁を感じる美しい曲です。
もう一曲はエルガーの出世作、エニグマ変奏曲です。“エニグマ”とは謎あるいは謎解きという意味で、元々の題名は「創作主題による変奏曲」でしたが、スコアの1ページ目に”Enigma”と印刷されていたのでこう呼ばれるようになりました。この曲は主題と14の変奏曲からなり、各変奏曲にイニシャルまたはニックネームがつけられていて14人のエルガーの友人たちの特徴が表現されていますが、それらが誰なのかというのが1つ目の謎。しかしこれは現在解明されています。もう一つ、全曲を通じての大きな主題が隠れているがそれは何でしょう、というのが2つ目の謎で、諸説あるがこれは未だに謎のようです。「愛の挨拶」で知られるエルガーは愛妻家で、この曲も妻のリクエストに応じてピアノを弾いていて生まれました。ちなみに1番目の変奏曲はエルガー夫人で、最後がエルガー自身です。
●ドヴォルザーク「イギリス」交響曲
ドヴォルザークの交響曲第8番には「イギリス」という副題が付くことがありますが、イギリスの出版社から楽譜が出版されたというだけの理由で、イギリスというよりボヘミアののどかな風景を想像させ、ドヴォルザークの田園交響曲とも言われます。ドヴォルザークのそれまでの交響曲はワーグナーやブラームスの影響を残していますが、この第8番はまさにチェコの音楽であり、有名な第9番「新世界より」にアメリカの要素が入っていることを考えると、この第8番は国民楽派ドヴォルザークの真の代表作なのかもしれません。この曲は譜面が比較的簡単なためか学生オーケストラで演奏されることが多いのですが、その音符からは豊かな自然と人間の感情が湧き出てきます。小松氏のタクトに導かれる新響の熱い演奏にご期待ください!
ドビュッシー/交響詩「海」
クロード・アシル・ドビュッシーは、1862年パリ郊外のサン・ジェルマン・アン・レーにて生まれた。小さな陶器店を営む家庭内に、特別な音楽的環境は用意されていなかった。彼にとって初めての音楽体験は、伯母クレマンティーヌの住む南仏カンヌに一時身を寄せていた際であるが、彼はイタリア人のヴァイオリニストにピアノの手ほどきを受けた。この8歳でのカンヌの滞在は彼に鮮烈な印象を残した。約40年後、楽譜出版業者ジャック・デュランに宛てた手紙で当時を回想している。
「私は家の前の鉄道と地平線の奥の海を思い出しますが、それは、時として、鉄道が海から出てくる、あるいはそこに入ってく(あなたの好きな方を選んで下さい)ように思われたものでした。
それから、また、アンティーブの街道、そこにはたくさんのバラが咲き乱れていましたが、私の生涯を通じて、私は一度にあれだけたくさんのバラを見たことはけっしてありません。あの街道の香りはたしかに陶然とさせるものでした・・朝から晩まで歌-ひょっとしてグリーグの歌?-を歌っていたノルウェー人の大工を含めて・・」
この少年時代の美しい思い出は、詩的で感受性の強い作曲家の片鱗を感じさせる。また彼にとっての最初の「海」の記憶かもしれない。そして彼の父親マニュエルは、息子の将来を船乗りにと考えていたが―おそらく父親が若い頃海兵隊に勤務していたことに起因する―、カンヌでのレッスンの結果、次第に音楽家にしたいと考え始めた。パリに戻り本格的なレッスンを受けたドビュッシーは、1972年若干10歳にしてパリ国立高等音楽院に入学。彼は後年次のようにも語っている。同世代の作曲家であり指揮者のアンドレ・メサジェに宛てた手紙である。
「おそらくあなたは、私が船乗りとしての素晴らしいキャリアを約束されていたこと、そして生活上の様々な偶然が私の進路を変えさせたにすぎないことをご存じないでしょう。それでも、私は彼女(=海)に対する情熱を持ちつづけてきました。」
「海 三つの交響的素描」は1903年から作曲され、1905年3月5日に完成された。前作のオペラ「ペレアスとメリザンド」が賛否両論あったもののひとまずの成功に終わり、音楽家として社会的地位を得てからの最初の重要な作品がこの「海」であった。彼の他の管弦楽曲に比べて完成まで1年半という非常に短い期間で書かれた作品であるが(「夜想曲」は約5年、「映像」3部作に至っては7年を要する)、この期間彼はその人生の中でも最も辛い苦境の中にいた。1899年にリリー・テクシエと結婚するが、3年も経つと下町娘的であった彼女とうまくいかなくなり、1903年頃には自らの生徒の母親エンマ・バルダックとの関係が始まっていた。彼女は社交界でも有名な歌い手であり、リリーとは対照的な教養を身に付けた女性であった。夫婦仲は冷めていたものの、ついに彼に別れ話を切り出されたリリーは、絶望しピストルで自らの胸を撃ってしまう。幸い未遂に終わったが、エンマが裕福な未亡人であったことが、金目当てに伴侶の許を去ったというゴシップを増幅させ、騒動はパリ中が注目する一大スキャンダルに発展した。リリーとの離婚調停は結局1905年8月まで続き、このことは彼に多大な疲弊と孤独をもたらしたが、このような状況下でも「海」のオーケストレーションは続けられた。
作曲家は「海」という作品について多くを打ち明けてくれてはいない。故に完成から1世紀が経過した今でも、多様な解釈を可能にしている。ここで再度アンドレ・メサジェに宛てた手紙を取り上げよう。
「あなたは前述の作品(=「海」)に関連して、大西洋は必ずしもブルゴーニュの丘に打ち寄せはしないと私におっしゃるでしょう!・・そして、それはまさに(画家の)アトリエで書かれた風景画に似たようなものだと!でも私には無数の思い出があります。私の考えでは、そちらの方が現実よりましです。」
また固有の作品について述べられたものではないが、1911年のある談話は「海」を理解する上で参考になるだろうか。
「誰が音楽創造の秘密を知るだろうか?海のざわめき。海と空とをへだてる曲線。葉陰をゆく風。鳥の鳴き声。こういったすべてが私たちのうちに多様な印象をもたらします。そして突然、こちらの思いとはおよそなんのかかわりもなしに、それらの記憶のひとつが私たちの外にひろがり、音楽としてきこえてくるのです。それは、おのれのうちにみずからの和声をひめています。」
もう一つ重要な事実がある。ドビュッシー本人の希望により、「海」の初版の表紙に葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」(「富獄三十六景」の第二十八景)が採用されたのである。当時、主にフランスの芸術界に広がっていたオリエンタリズム、ジャポニズムへの関心―ドビュッシーの自室には「海」のスコアの表紙と同じ絵が飾られていた。彼のピアノ作品「映像」第2集の3曲目「金色の魚」は、同じく自室にあった日本風の蒔絵の箱の蓋に描かれた、柳の下を泳ぐ鯉から霊感を得たと言われている。しかしながら、ドビュッシー自身の口から日本美術の影響について具体的に語られたことはなく、これらの情報は、確実に無関係ではないだろうが、北斎の浮世絵が「海」という作品の内部にまで影響を与えている証明にはならない。同じく画家からの影響という意味では、イギリスの画家ターナーについて次のような逸話もある。同時代のピアニスト、リカルド・ビニェスの1903年6月13日の日記である。
「ドビュッシーの家に行った。彼は新たにピアノのための新作(=「版画」)を聞かせてくれた・・何たる偶然か、それらの曲はターナーの絵を思わせると彼に言うと、自分はまさに、それらを作曲する前、ロンドンのターナーの間で長時間過ごしたんだ、と彼は私に答えた!」
1905年10月15日、ベートーヴェンの交響曲第7番、ダンディ、ベルリオーズの作品と共に「海」は初演された。ドビュッシーが「猛獣使い」と酷評したシュヴィヤールの指揮に責任の一端があることに疑いの余地はないが、それにしても好意的な批評や作品の独創性を認めるそれはわずかであった。ドビュッシー研究の第一人者フランソワ・ルシュール曰く、
「このスコアの特殊性が読み取れるようになるには、数世代必要だった。それほど、「海」のスコアは、伝統的な分析には捉え難いのだ。1905年には、革新に最も注意を払っている聴衆にとってですら、「海」は「ペレアス」よりもはるかに途方に暮れてしまう作品だった。」
批評家ピエール・ラロは「海」の初演直後に出た『ル・タン」紙の批評欄で、次のように評した。
「はじめて、ドビュッシーの絵画的な作品に耳を傾けながら、私は、自然を前にでは全然なく、自然の複製を前にしているという印象を持った。素晴らしく繊細な、創意に富み、器用に細工された複製だが、それでも複製に変わりない・・・。私には海が見えず、聞こえず、感じられない。」
ドビュッシーは反論する。
「私は海を愛していて、海に払うべき情熱的な畏敬の念を以て、海に耳を傾けてきました。海が私に書き取らせるものを私が下手に書き写したとしても、私たち相互のどちらにも関係のないことです。そして、すべての耳が同じように知覚しないということでは、あなたは私たちの意見に同意なさるでしょう。」
―すべての耳が同じように知覚しない―ドビュッシーが我々に与えた、僅かであるが必要十分な情報 をガイドに、思い思いの「海」を感じていただければ幸いである。また彼が言った「自分にとってパンとぶどう酒の代わりとなる、つねに一層先に進みたいという、欲望」の下、強固な意志を以って、自らの芸術的な理想を追い求めた姿に思いを馳せていただきたい。
曲は3つの楽章から成る。
1.海の夜明けから正午まで
2.波の戯れ
3.風と海との対話
参考文献
『伝記 クロード・ドビュッシー』フランソワ・ルシュール著 笠羽映子訳(音楽之友社)
『ドビュッシー書簡集1884-1918』フランソワ・ルシュール編 笠羽映子訳(音楽之友社)
『作曲家◎人と作品シリーズ ドビュッシー』松橋麻利著(音楽之友社)
『作曲家別名曲解説ライブラリー ドビュッシー』(音楽之友社)
『ジャポニズム入門 ジャポニズム学会編』(思文閣出版)
『ジャポネズリー研究学会会報2』
初 演:1905年10月15日カミーユ・ジュヴィヤール指揮コンセール・ラムルー管弦楽団
楽器編成:フルート2、ピッコロ、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、コルネット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、トライアング ル、シンバル、タムタム、グロッケンシュピーゲル(またはチェレスタ)、ハープ2、弦5部
イベール/交響組曲「寄港地」
■海と作曲家
「海」は作曲家にとって特別な存在のようです。時には穏やかに時には激しく荒れ狂い、人間と言う存在の小ささと自然の偉大さを思い知らされます。そこは、生命の源であり、神秘的な青い星を形作る 源として、古くから芸術家の心を捉えて放しませんでした。
この時代、海に魅せられた作曲家はとても多く、有名なところでは12歳で海軍兵学校に入ったリムスキー=コルサコフ(後に「シェヘラザード」で波の情景を見事に描写した)や、「作曲家になれなかったら船乗りになっていただろう」と語ったドビュッシー(結局彼は船乗りにはなれず「海」や「小船にて」などの曲を書いた)などが挙げられます。生粋のパリジャンであるイベールも、大海原に対する憧れはひとしおで、パリ音楽院在学中に勃発した第一次世界大戦に乗じて、自ら志願して海軍に入り、地中海各地の港を巡り異国の印象を心に刻むこととなります。
また、バレエ組曲「三角帽子」などで有名な、スペインの作曲家ファリャはイベールのいとこで、時々、イベールはマドリッドのファリャの家を訪れています。この旅行の際に、海沿いのバレンシアに立ち寄った可能性も大いにあります。多くの国の港に立ち寄った経験のあるイベールにとって、「寄港地」とは単なる港町や陸地というよりも、もっともっと深い意味を持つ言葉だったのでしょう。
交響組曲「寄港地」の原題が「Escales...」と意味深な「...」が付いていることからも、寄港地に対す る彼の特別な思いを察することができます。
■パリからローマへ、そして各地へ
イベールが「寄港地」を作曲したのは30歳~32歳の頃。1919年に29歳でローマ大賞を受賞し、その副賞として翌年から3年間、住み慣れたパリからローマ音楽院へ留学していた時期でした。この頃のイベールの作品には学校への提出用の課題やデッサンなどが多数含まれており、「寄港地」もその中の作品の一つです。
ローマ留学中、イベールは地中海各地を旅行し、さまざまな異国の印象をスケッチに残します。以前、海軍士官として各地の航行した経験とあいまって、地中海のきらびやかな印象と異国情緒あふれる風景を美しく鮮明に記した作品ができあがりました。
■日本とイベールの意外な関係
ところで余談ですが、日本とイベールには意外な関係があります。昭和15年に開催された「紀元二千六百年記念行事」のための祝典曲を、日本政府は欧米の6カ国に依頼しました。このうちフランス、ドイツ、ハンガリー、イタリアの4ヶ国から奉祝曲が寄せられましたが(イギリスのブリテンの作品は「レクイエム」だったため日本政府が受け取りを拒否)、その時フランス政府が国を代表する作曲家として選任したのがイベールでした。
当時、イベールは50歳。ローマのフランスアカデミーの院長であるとともに、後のフランス国立歌劇場連盟総長候補としてフランス随一の実力と人気を博しており、友人のミヨー、オネゲルを差し置いての抜擢でした。
ちなみに、この時寄せられたイベールの「祝典序曲」は、昭和15年12月に東京歌舞伎座で山田耕筰指揮により演奏されています。
■交響組曲「寄港地」
さて、今回演奏する「寄港地」には「三つの交響的絵画」と副題が設けられ、それぞれの曲に地名が 付いていますが、これは後にイベール自身が付け足したものです。しかし、イベールの曲に寄せる思い を感じるための重要なヒントになっています。
第1曲 ローマ―パレルモ
ローマからパレルモに至るティレニア海は、今も昔も穏やかで豊かな、真っ青な海が広がっています。パレルモは、シチリア島北部にある港町で、古くから貿易による富と太陽に恵まれて、ギリシャ、ローマ文化が栄え、特にイベールが立ち寄った20世紀初頭は国際都市として栄華を極めた時期でした。
曲は、6/8拍子の穏やかなフルートに始まりますが、次第に沖合いに出てうねりも高まり、パレルモが近づくと、シチリアの陽気な舞曲タランテラがトランペットと打楽器により描かれます。シチリアに降り立つと南国の喧騒と情熱的なリズムに包まれますが、それも次第に静まり、冒頭の穏やかな海の情景が戻ってきます。(ちなみに毒グモの「タランチュラ」は、噛まれるとタランテラを狂ったように踊り続けるという伝説から名づけられたそうです。)
第2曲 チュニス―ネフタ
チュニスは古代ローマ時代のカルタゴの衛星都市として栄えた、古代遺跡が今になお残る、人口80万人あまりの都市です。16世紀にはオスマントルコに支配されたものの、19世紀にはフランス領となるなど、さまざまな文化が融合した街で、メディナと呼ばれる旧市街地はユネスコの世界遺産にも登録されています。
ネフタは、北アフリカの砂漠のオアシスの街で、古くからの観光名所です。イスラムの影響を強く受けたネフタはヨーロッパの人々にとって特に異国情緒を感じられる場所で、映画「インディージョーンズ」のロケ地にも使われました。そう言えば写真の市場の風景にはどこか見覚えがありませんか? 4/4拍子と3/4拍子を組み合わせた7拍子の曲で、チェロのリズムに乗って、オーボエがアラビア風のエキゾチックな旋律を奏でます。長い砂漠の旅の先にあるオアシスは、水と食料が待つだけでなく、酒と女と金と、さまざまな欲望の渦巻く土地でもあります。さて、今日のオーボエはどれほど妖しい響きを奏でるのでしょうか。
第3曲 バレンシア
3曲目は、スペインの東側に位置する港町バレンシアの「火祭り」をテーマにした楽章です。バレンシアの火祭りは、毎年3月1日~19日の間繰り広げられる伝統的な祭りで、数百のファラス(木と布でできた張りぼて人形)が街中を練り歩きます。祭りの最大の見所は3月15日から19日のハイライトで、大きなファラスに火が放たれ、メラメラと盛大に燃え上がるとともに大きな花火が街中で上がります。この祭は別名「サン・ホセの祭り」とも呼ばれます。マリアの夫であるヨセフ(スベイン語でサン・ホセ)の職業が大工であったことから、昔からこの地方の大工の間ではサン・ホセの日に木屑などを燃やして焚き火をする習慣がありましたが、いつの間にか飾り付けが派手になり、人形を燃やすようになりました。
3/8拍子の活気あふれるリズムにより、スペイン舞曲セギディーリャが始まります。カスタネットの軽快な響きに乗って時には洒落た踊りをみせ、また5/8拍子の緩やかな旋律を経て、次第に祭りは盛り上がり、打楽器を加えて曲は佳境へと展開していきます。
さまざまな主題が交錯しながら興奮は最高潮に達し、スペインの熱い夜を象徴するかのような管楽器の盛り上がりと激しいリズムのうちに幕を閉じます。
参考文献
『ファリャ生涯と作品』興津憲作著(音楽之友社)
『最新名曲解説全集7 管弦楽曲IV』(音楽之友社)
『バレンシア観光協会ホームページ』
初 演:1924年1月6日ポール・パレー指揮コンセール・ラムルー管弦楽団
楽器編成:ピッコロ、フルート2(1番は第2ピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット3、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、大太鼓、小太鼓、 タンブリン、カスタネット、ドラ、トライアングル、木琴、チェレスタ、ハープ2、弦5部
ニールセン/交響曲第2番「四つの気質」
クラシック音楽にある程度詳しい方でも、ニールセンという作曲家は、名前は聞いたことはあるけれどもあまり馴染みはなく曲も知らない、という人が多いのではないだろうか。かくいう私もニールセンの曲は過去1曲、それも30年近く前に演奏したことがあるだけであり、交響曲は初めての経験である。ここでは知られざる巨匠ニールセンをまずは近代音楽史の中に置いてみることから始めてみたい。
この交響曲第2番が初演された1902年、ニールセンは37歳、同じ年齢のシベリウスは有名な交響曲第2番を作曲、ドビュッシーは40歳で、歌劇「ペレアスとメリザンド」の完成間近、同じく40歳のマーラーは交響曲第5番をこの年に発表、R.シュトラウスは38歳、名だたる交響詩を書き終わり、これからオペラを書こうという時期、ラヴェルは27歳で初期のピアノ曲「水の戯れ」以外まだ有名な曲は書いていない。28歳のシェーンベルクは前回の定期演奏会で新響が取り上げた交響詩「ペレアスとメリザンド」を執筆中であった。ストラヴィンスキーやバルトークはまだ20歳前の若者で、ロマン派の巨匠たちの中ではサン=サーンスが67歳で健在であった。まさにロマン派音楽の終焉を間近に控え、新しい音楽がこれから生まれようとしているときである。ニールセンの音楽は、今名前を挙げた同時代の作曲家たちのいずれのものとも似ていない。だが彼もまた、何か新しい音楽を模索し、生み出そうとしていたのである。
ニールセンの音楽の印象は、重厚でごつごつした感じがあり、当時の主流であった半音階的な書法や 色彩的な和声を駆使した音楽とは趣がかなり異なる。後期ロマン派特有の仄暗いところは全く見られず、筋肉質で力強く前進していく音楽である。初めて接した時は耳慣れない転調やリズムが非常に耳に付くが、それらはニールセン独自の理論に基づくものであり、やがて3番以降の交響曲をはじめとする彼の代表的な作品の中で花開いていくこととなる。
■生涯
カール・ニールセンは1865年6月9日に、デンマークのノーレ・リュンデルセという農村地帯に生ま れた。父はペンキ職人で、子沢山ゆえ大変貧しい生活だったが、ヴァイオリンとコルネットをたしなみ、 村の楽隊を組織して結婚式やお祭りで演奏をし、評判となっていた。ニールセンは6歳から父の手ほど きでヴァイオリンを始め、やがて父のバンドに入って村の行事などで弾くようになった。14歳のとき、故郷から7マイルほどの小都市オーデンセの軍楽隊に入り、ホルンとコルネットを担当し、4年間務めた。1884年にコペンハーゲン音楽院に入学し、音楽史、音楽理論、作曲法、ヴァイオリン奏法等を本格的に学んだ。この時期の作品はヴァイオリンソナタ、弦楽四重奏曲など、すべて弦楽器を使った習作である。1889年から王立劇場オーケストラの第2ヴァイオリン奏者となり、彼の作曲も管弦楽へと向かっていく。1890―1891年に政府から奨学金を得てドイツ、フランス、イタリアへ遊学、ワーグナーの「指環」の上演を見た。また、デンマーク人の女性彫刻家アンネ・マリー・ブロデルセンと会い結婚。この旅行の翌年に交響曲第1番が完成し、交響曲作家としてのニールセンのスタートが切られた。そして、1901年からオペラ「サウルとダヴィデ」と平行して交響曲第2番「四つの気質」が書き始められ、1902年に完成した。1908年から6年間王立劇場の音楽監督を務め、この間に声楽入りの交響曲第3番「広がり」、ヴァイオリン協奏曲が書かれた。1914―1918年は第1次世界大戦下であるが、彼は1915年から音楽協会と王立音楽院での教育の仕事に精力を傾けた。交響曲の方も1916年に第4番「滅ぼし得ざるもの」、1922年には代表作第5番、1925年に最後の交響曲である第6番「シンプル」と傑作が生み出された。晩年にはフルート協奏曲、クラリネット協奏曲がある。1930年王立音楽院院長に就任。1931年心臓発作のため66歳で死去。
彼はあらゆるジャンルに多くの作品を残したが、とりわけ交響曲と、デンマーク語による素朴な歌曲 が高い評価を得ている。
なおわが国では一般的に「ニールセン」と表記されることが多いが、デンマーク語の発音は「ネルセ ン」に近い。
■「四つの気質」という標題について
この標題がついていることがこの曲を非常にユニークなものにしているといえる。この発想はニールセンが田舎の居酒屋で壁にかかっていたコミカルな絵を目撃したことによる。その絵は4部からなり、人間の4つの気質、すなわち胆汁質、粘液質、憂鬱質、多血質の人間をそれぞれ描いていた。この分類は古代ギリシャのヒポクラテスやガレノスに由来し、血液型発見以前はこの分類が西洋では一般的通念であった。これらの絵に描かれている人間の気質、性格への興味が作曲のきっかけになったのだが、曲は伝統的な交響曲の形式で手堅く書かれ、単なる描写音楽ではない。
■各楽章の解説
普通であれば、ここで音楽形式を中心にお話しするところであるが、ここではニールセンが各楽章に割り当てた気質と音楽の関係に注目してお話ししたい。
第1楽章 アレグロ・コレリーコ
「コレリーコ」とは胆汁質で怒りっぽい、という意味で使われている。胆汁質とは、愛憎が激しくて怒りっぽく、誠実で決断力に富み、明晰な概念付けを行うことを好み、結論を出したがる、という気質である。冒頭で示されるテーマ(譜例1)がこの胆汁質の象徴として示される。これに対して第2主題(譜例2)はテンポを落として穏やかに歌われるが、転調を繰り返し、その移りやすい性格を暗示する。
譜例1

譜例2

第2楽章 アレグロ・コモド・エ・フレマティコ
粘液質を表す。「鈍く、そして冷静に」という発想で、穏やかな落ち着いた音楽である。粘液質の特徴は、慎重で好き嫌いを表に現さず、思考力があり冷静、滅多にやる気を起こさない、というものである。この楽章も、とりとめもない伴奏音型に、あまり主題らしくない主題(譜例3)が乗り、最後はとりとめもなく消えていく。
譜例3

第3楽章 アンダンテ・マリンコーリコ
「憂鬱なアンダンテ」という意味で、憂鬱質を表している。憂鬱質の人は独創性豊かで探究心が強いが懐疑的で固定観念にとらわれがち、非社交的で孤独な性格といわれる。第2楽章と同様のモティーフで始まる主題(譜例4)をもち、短調と長調の間を浮遊してメランコリックな気分をかもし出すが、やがて劇的で起伏に富んだ音楽となっていく。
譜例4

第4楽章 アレグロ・サングイネオ
サングイネオとは「血」を意味する言葉から転じた形容詞で、「多血質」を表している。
多血質の特徴は、明るくユーモアを持ち、思いつきで行動し、気分や印象に左右されやすいが、感じがよく優しい人が多い、というもので、この楽章も最初の主題(譜例5)から明るく飛び跳ねるような活気に満ちたものである。平和で穏やかな中間部をはさんで曲は行進曲風に盛り上がって熱烈なクライマックスを築く。
譜例5
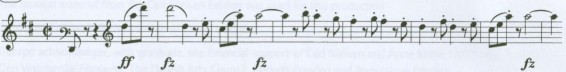
ニールセンについての印象を何人かの団員に聞いてみたところ、なかなか具体的な答えが返ってこなかった。やはり、皆私と同様に馴染みがなく分類しにくい個人様式に戸惑っていたのかもしれない。ただし、練習を重ねるうちにだんだん好きになった、という人がほとんどであった。人間の気質も音楽の内容も簡単に分類できるものではなく、奥深いものだが、真摯に付き合い愛情を持って接することで新しい地平が開けるのだと、今回この曲に取り組んであらためて感じた。そういった歓びを皆様に伝えることが出来れば幸いである。
参考文献
『作曲家別名曲解説ライブラリー2「北欧の巨匠」』より
「ニールセン」菅野浩和著(音楽之友社)
『最新名曲解説全集 補巻第1巻
「交響曲 管弦楽曲 協奏曲」』より
『ニールセン 交響曲第2番』菅野浩和著(音楽之友社)
『ニューグローブ世界音楽大辞典』(講談社1996)
初 演:1902年12月1日、コペンハーゲンにて。デンマーク・コンサート協会主催のコンサートにおいて、作曲者自身の指揮によって行われた。
楽器編成:フルート3、オーボエ2(2番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、弦5部
4つの気質と体液病理学 ~自分の気質を知ろう~
ニールセン(1865-1931年)はデンマークの作曲家です。シベリウスの次くらいに有名な北欧の作曲家なのですが、意外と演奏機会が少なく新響は初めての挑戦となります。なぜ今回の演奏会でニールセンかというと、指揮の山下氏は若い頃にデンマークの指揮者コンクールで優勝しており、その縁で振ったヘルシンボリ交響楽団(スウェーデンの南部ほとんどデンマークの近く)ではニールセン交響曲全曲を演奏しているのです。ニールセンを全部やったことのある(しかも北欧で!)日本人の指揮者はそうはいませんから。
ニールセンの交響曲は6番までありますが、山下氏によれば1番は習作に近いし2番が一番ニールセンらしいんじゃないかということで、比較的メジャーな「不滅」ではなくまずこの曲に取り組むことになりました。
さて、この交響曲第2番には「四つの気質」という標題がついています。1楽章:胆汁質、2楽章:粘液質、3楽章:憂鬱質、4楽章:多血質といった具合に、各楽章がそれぞれの気質を表現しています。
名曲解説辞典によれば『「四つの気質」という表題の所以は、彼がゼーランド(デンマークを構成する島の一つでコペンハーゲンもその上にある)の田舎を訪れたとき、ある所で「気質」をテーマとした水彩画を見て感興を覚え、やがてこの交響曲を作曲したことによる。しかし彼は音楽をもって水彩画をなぞったのでもなく、特定の人物の性格を描写したものでもない。水彩画に描かれている人間の気質、性格への興味が、このような作品を書かせるに至ったものである』とあります。
●体液病理学について
この「水彩画」というのがはたしてどんな物だったのかわかりませんが、気質に関してこのような図を見つけました。
体液病理学は古代ギリシャ時代から19世紀にいたるまで信じられてきました。「人間の体液は血液、粘液、黄色胆汁、黒色胆汁からなり、その体液のバランスによって病気が引き起こされる」というものです。(病理学とは文字通り病気の原因やメカニズムを解明する学問のことです。)ギリシャ哲学では4元素(空気、水、火、土)、4元性(冷、熱、乾、湿)であり、これらとの類似性で4体液が考えられたのです。空気のように温かく湿った血液、火のように温かく乾いている黄胆汁、水のように冷たく湿っている粘液、土のように冷たく乾いている黒胆汁、4つの体液が正常に混和していれば健康で、そのバランスが失調すると病気になる、というわけです。
古代ギリシャでは、体液病理学のほかに固体病理学(病気の所在は身体の固体部分、つまり臓器にある)の学派がありましたが、ヒポクラテス(紀元前400年頃)のいたコス派の体液説の方が大勢だったようです。この頃の治療は瀉血(皮膚を切開して毛細血管から血液を抜く)や下剤によって悪い体液を排出することが中心でした。方法学(体内の空隙の緊張と弛緩により病気が起こる)中心であった古代ローマにもガレノス(紀元130-200年)によって体液病理学が伝えられました。こうして体液病理学は17世紀までヨーロッパ医学に影響を与えました。
18世紀になってモルガーニ(1682-1771年)によりようやく体液病理学の4体液説が論破され固体病理学の基礎が固まり臓器病理学へと発展します。顕微鏡が発明され18世紀後半には病理学に使用されるようになりました。その後ロキタンスキー(1804-1878年:当時の高名な病理学者)が体液病理学を復活させますが、現代病理学の父といわれるウィルヒョウ(1821-1902年)によって細胞病理学(病気は細胞の質的・量的変化によって生じる)が誕生し、体液病理学の幕は閉じます。
ちなみに、モーツァルトが35歳の若さで病死したのはご存知と思いますが、当時主流であった体液病理学の医師によりモーツァルトの治療に瀉血が行われました。ウィーンのモーツァルトハウスには同時代に用いられていた瀉血の器具が展示されています。瀉血のしすぎで体力が弱ったのが死因ではないかという説もあるようです。
●シュタイナーによる「4つの気質」
現在の病理学では4体液説は誤ったものとして認識されていますが、教育学の世界ではシュタイナー(1861-1925年:思想家、哲学者)の教育論により4つの気質について知られているようです。子供や教師、親を4つの気質で分類し教育に活かそうというものです。
日本では血液型による性格分析がもてはやされていますが、血液型は骨髄移植でもしない限り一生変わらないのに対し、誰もが4つの気質をすべて持っていてどれが強く出るか状況や年齢により変化するとされています。シュタイナー教育で各気質がどういう傾向ととらえられているかまとめてみましょう(この表は大人の場合です)。
| 外へ | 内へ | |
| 多血質 | はつらつ、感じがいい、好印象、積極的、行動的、外向的、幅広い、気軽、気さく、親しみやすい、人付き合いがよい、社交的、柔軟、思いつく、アイディアがある、発想の転換が出来る、偏見がない、他人の考えを理解、自由な感じ、開放的 | 思いつき、軽い、深まらない、広く浅い、表面的、軽薄、軽率、移り気、当てにならない、責任を持たない、中途半端、持続・長続きしない、完成が苦手、くよくよしない、落ち込まない、楽天的、楽観的、おめでたい |
| 胆汁質 | 積極的、行動的、活動的、エネルギッシュ、自己主張する、自己顕示欲が強い、騒々しい、自信に満ちている、指導者、他人に押し付ける、高圧的、反発を受けやすい、攻撃的、横暴、暴力 | 意思が強固、信念を持つ、不屈、剛穀、理論的、論理的、論理明晰、素早い判断、決断が早い、やさしさ・思いやり・気配りに欠ける、感情の細やかさ・繊細さに欠ける |
| 粘液質 | ふくよか、動作が遅い、緩慢、受身的、消極的、控えめ、無関心、怠惰、怠け者、穏やか、温厚、円満、信頼される、せっかちでなく待てる、激しない、大らか、包容力がある、些細なことに動じない | 鈍い、鈍感、やり続ける、やり抜く、粘り強い、伸張、熟考、正確、確実、着実、几帳面、意志が強い、屈強、芯が強い、柔軟性・融通性に欠ける、頑固、固執する、執念深い、繊細でない、平静、冷静、自制的 |
| 憂鬱質 | 小心、臆病、心配性、非外交的、非社交的、控えめ、遠慮がち、無口、寡黙、懐疑的、否定的、悲観的、たまに別人のように活発 | 敏感、神経質、気難しい、不機嫌、内向的、ふさぎ込む、洞察力がある、語学力、美的センス、芸術的、理想や真実に従う、思慮深い、慎重、冷静、思い込みが激しい、柔軟性に欠ける、頑固、厳格、固定観念、自己中心的、被害者意識が強い |
●健康を支配するもの
細胞病理学から発展した現在の医学は、いわゆる対症療法が中心です。発熱や痛み、かゆみといった不快症状があれば消炎鎮痛剤やステロイド、副交感神経遮断剤などで症状を抑えますが、それらの症状は生体の治癒反応であるのにそれを阻害しさらに血行を悪くして症状を悪化させてしまうこともあるのです。数多くの患者をこなし薬を処方しないと成り立たない現在の医療制度ではしかたがないのかもしれませんが、最近免疫力や東洋医学が注目されているのは、そういう治療に疑問を感じるようになったからでしょうか。
免疫の立場から病気をとらえると、白血球(防御系)、自律神経(調節系)、体温(循環系)がキーポイントのようです。
血液中の白血球は、主に細菌や真菌を処理する顆粒球とウィルスなどの微小異物を処理するリンパ球からなり、顆粒球が54-60%、リンパ球が35-41%でバランスがとれているのを免疫力が高い状態といいます。免疫は自律神経(生体調整機能を制御する神経でそれぞれの臓器に対し交感神経と副交感神経が拮抗して働く)と連動しており、活発な生き方をすると交感神経が優位となり顆粒球が増加し、おだやかな生き方をすると副交感神経が優位となりリンパ球が増加します。年齢によっても変化し、子供時代はリンパ球が多いのですが15-20歳で逆転し加齢により顆粒球が増加していきます。また、ストレスや心の悩みで顆粒球が増加し甘い物の食べ過ぎや運動不足でリンパ球が増加します。顆粒球過多では胃腸炎といった組織破壊の病気に、リンパ球過多ではアレルギー性疾患になることが多いのです。
体温もまた自律神経と関係があります。健康な人は体温(平熱)が36度以上ありますが、体温が十分ある人でも、活発な人は高め体を動かさない人は低めになります。しかし交感神経が過度に緊張すれば血管が収縮して体温は低下し、不整脈、高血圧、高血糖、筋緊張、便秘といった症状が出てきます。逆に副交感神経過剰優位でも活動量や代謝が低下して低体温となり、徐脈、低血圧、低血糖、疲れやすい、むくみといった症状が出てきます。
鍼灸治療の作用機序は自律神経を整え血行をよくすることですし、有名なにんじんジュース断食は老廃物を排泄し免疫力を高めるのが狙いです。ヒポクラテスの時代に排泄と自己治癒力が重視されたことを考えると、体液病理学的な考えと共通しています。
●本当に4体液説は間違っているのか
それでは白血球、自律神経、体温で4つの気質を考えてみるとどうなるでしょうか。縦軸に体温は4体液の図と同様ですから、横軸を自律神経と白血球にして同じように気質を当てはめることができます。
多血質:体温が高く副交感神経優位の人は行動的でおだやか、血行がいいから多血質ですね。
胆汁質:体温が高く交感神経優位だと活動的で激しい。肉を多く食べると交感神経優位になるのでこういった人は消化のために胆汁が多く出るのでしょう。
粘液質:体温が低く副交感神経優位の人はあまり動かず穏やか、さらに副交感神経過剰優位になると疲れやすくアレルギー性疾患になりやすい。4体液説の白色粘液は脳を取巻く髄腔から流れるとされ、骨髄で作られるリンパ球による炎症反応で生じる粘液と考えれば当たっています。
憂鬱質:体温が低く交感神経優位だと行動的でなく敏感、さらに交感神経が緊張するとイライラして神経質になり血管収縮や組織破壊性疾患を起こしやすい。4体液説の黒色胆汁は脾臓にあって粘調で黒褐色といわれ現在でも正体不明。顆粒球による炎症反応で膿が生じ血液が混ざって赤黒くなったものかと想像するのですが、顆粒球は骨髄で作られますし脾臓はリンパ球の産生と古くなった赤血球の破壊を行う所なので残念ながら該当しません。しかし黒色胆汁は災いの原因としてはもっとも強力とされており現在は多くの病気(7割)が交感神経緊張側で起こると考えられているので、その辺は共通しています。
以上を図にすると次のようになります(私の説なので信憑性はありません)。
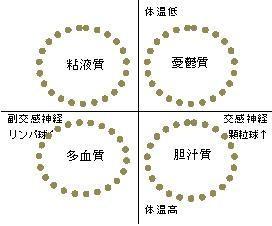
体液病理学には2000年もの歴史があります。誤りはありますが考え方には学ぶことも多いはずです。「4つの気質」は迷信ではなく、実は医学的な根拠があるのだと思います。自分の「気質」が何かを知ることは、生き方を見直し健康に過ごせる機会になるかもしれません。
<参考文献>
・西洋医学史ハンドブック ディーター・ジェッター著 山本俊一訳 朝倉書店
・病理学の歴史 エズモンド R.ロング著 難波紘二訳 西村書店
・気質でわかる子どもの心 シュタイナー教育のすすめ 広瀬牧子著 共同通信社
・免疫進化論 安保徹著 河出書房新社
(安保徹先生の著作には一般向けの物も多いです。どんな生き方をすれば免疫力が高くなるか興味のある方は読んでみてください。)
行き着く先を実感したい ― 飯守泰次郎氏にきく
2006年の新交響楽団・創立50周年シリーズにおいて、ワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」で圧倒的な音楽性と指導力でもって演奏会を大成功に導いた飯守先生。あれから約1年半ぶりの登場となります。飯守先生と共演したシューマンの交響曲では4度目で今回最後になる第1番「春」と、初挑戦で更なる新境地を開拓されるシェーンベルク「ペレアスとメリザンド」について、その魅力を中心にお伺いしました。
-まずはシューマンの交響曲の魅力についてお伺いします。
飯守 シューマンの本質をはっきりと言い切ることは出来ませんが、彼のパーソナリティから考えるとシンフォニーを作曲するには向かない作曲家だったと思います。ご存知のようにシューマンの場合は「ピアノの年」「歌曲の年」「室内楽の年」など、年代よって同じジャンルの作品を大量に集中して作曲していく傾向がありました。まず最初にピアノ曲から始まるのですが、次の歌曲まではとても素晴らしかったのです。その次に1841年の「交響曲の年」へと続きます。とはいっても第4番は既に第1番の時に作曲され、第2番は1846年、第3番は1850年というように、4つのシンフォニーはいくつかの年に分散して作曲されています。また草稿もいくつか残されていています。ヘ短調とかト短調、ハ短調、イ短調など、いろいろと修作の跡があるのです。ではなぜそのように試したかと言うと、彼はものすごく苦労していたんですね。やはりシンフォニーには向かない作曲家だったと思うのです。ピアノ曲や歌曲に向いていた、そういうパーソナリティなのだと思います。
ところが彼はドイツの作曲家としてバッハをとても研究し、次にベートーヴェンも研究しています。その結果、自分はこれらの偉業を継承する責任があると覚悟し、全身全霊を傾けてシンフォニーに取り組んだのです。ですからシューマンのシンフォニーの最大の魅力は、向いていないジャンルに本気で取り組み、苦労して作り上げ練り上げたところにあると思います。だけれどもその中にちょっとした未完成な部分や、出来の悪さが見受けられる、そこにもものすごく魅力があると思うのです。ちょっと良くない言葉ですが歪んだ魅力というか、苦労の跡がうかがえる魅力と言ってもよいでしょう。例えばベートーヴェンとかブラームスはもう完璧なわけです。同時代のメンデルスゾーンにしても同じです。ただシューマンの場合にはその中にちょっと無理がある。たとえばオーケストレーションひとつとっても何かそこに苦労の跡が見られて、もう少し違うやり方が出来たのではないかなと思うことがあるのです。弦楽器がなぜあれだけ細かい音符を刻まなければならないのだろうかとか、管楽器が浮き立ってこないなど。ただしその音楽性や音楽的発想が、本当に素晴らしいんですよ。
-初演当時のホルン奏者は当時の楽器では冒頭の部分を吹けなかったそうですね。
飯守 あの頃のオーケストラの実力というのは今では知る由もないですが、当時の交響曲の初演というのはかなり貧弱なものだったらしいです。またドヴォルザークあたりまではとても小さなオーケストラで演奏していたようです。随分前に聞いたシューマンのオーケストレーションの話ですが、当時のセカンドヴァイオリンが上手く弾けなかったため、その部分を管楽器で補ったそうです。それでどんどん楽器が重なってしまったとか、聞いたことがあります。ところどころに変な部分があるのは、弾けない箇所を補って書かなければならなかった当時の事情があったのかもしれません。
-交響曲第1番を作曲したときはちょうどクララと結婚した時になりますね。
飯守 彼が一番幸せな時です。
-その一方シューマンの音楽の中には精神的な悩みのようなものを常に感じます。
飯守 そのとおりです。またシューマンの精神的な悩みというのは、シューマンの魅力と見事に直結していると思います。それはピアノ曲や歌曲のとても幸せな曲の中にも出ています。例えば交響曲第1番の冒頭ではホルンとトランペットが春の到来を告げます。それはまだ発病していない時の幸せに満ちているのだけれども、オーケストラ全体で繰り返した後、急にニ短調になってハ短調になってしまう。そうすると単なる幸せな春の到来ではなくなり、その先のシューマンの鬱がもうすでに表れているような気がするのです。彼の音楽的な魅力は、彼の血の中に存在する精神病的な不安定さにあると思います。
-またシューマンは批評活動を通して新しいものを次々と紹介していきました。彼の活動には休むことを知らないという感を受けます。
飯守 ショパンの才能をいち早く告げた有名な言葉「諸君、脱帽したまえ、天才だ!」などの論評活動が有名ですね。しかしこれまた彼のパーソナリティから考えると雑誌の編集者なんて出来るわけが無いんです。なのにそれらを自分の任務だと思ってやっている。論評活動は彼にとってはものすごく負担だったと思います。そして先ほど申し上げたドイツの作曲家としてシンフォニーを継承するという責務を感じていたわけで、まさに苦しみの連続でした。それで精神的にだんだんひどくなっていきます。そういった苦しみがシューマンの作品には常にあり、またそこが魅力の一つだと思うのです。こういう傾向は他の作曲家にはあまり無いです。
一方そういった病的な魅力はマーラーの作品の中にもあります。ただマーラーの場合は見事なまでに現代人の精神的矛盾まで繋がっていきます。例えば「やがて自分の時代が来る」と言っているように、もう予測してやっているわけです。マーラーは自らそこに入り込んでいって、ある意味「苦しみの特権階級」みたいに自分をしてしまったのです。だけどシューマンの場合は違います。そこから必死に抜け出そうとする、あがく苦しさが見えてくるのです。必死にもがき苦しんでいる魅力といってもよいでしょう。
-クララとの結婚も大変でしたね。例えば夫婦でロシアへ演奏旅行した際、クララの成功がものすごかったのに対して彼は全然認められていなくて、「クララのご主人」と言われていたそうですが。
飯守 そうですね。そのロシアへの演奏旅行の後でだんだんと彼は落ち込んでいくわけです。まずもともと血の中にあった精神病的なもの、次にはクララの父親を含めた問題がありました。クララの父親は最初から彼の本質を見抜いていたのです。そして夫婦としてのキャリアのぶつかり合いですね、まあこれはよくある問題ですが。
それからもう一つ大事なことは、若きブラームスの登場です。シューマン自身「新しい道」という表題でその若者を強く賞賛して音楽界に迎え入れて、家庭にまでも迎え入れて友人として付き合っていたのだけれど、クララと非常に親しくなっていきました。逆にシューマンが入院してしまった時など、ブラームスが家族の面倒などもみています。そのあたりが精神的な病を早めた、ひどくしたのではないかとも考えられます。ラインに身を投げる前に結婚指輪を投げたりしていますね。クララとブラームスの間では300通を超える手紙のやりとりがあったそうですが、そのうちのかなりの部分が削除されたり、破棄されたので本当のところはよくわかりません。
-シューマンは一番正直に自分の病気に悩んだ人だといえるのでしょうか。
飯守 作曲家が悩み始めたと頃というのは、ちょうど作曲家が教会や王侯貴族などから独立し始めた頃から始まります。例えばハイドンやモーツアルトは貴族に仕えていたけれども、ベートーヴェンは完全にそこから抜け出して自立しました。そういったしがらみから抜け出したあたり、だいたい1800年くらいから個人の悩みや苦しみというものをぶつけて、それらを材料として作曲していくという動きが出てきました。もちろんハイドンだって勝手をやっているし、バッハだって随分ときかん坊でわがままで好き放題やっていたらしいけれども、一応社会人としての枠の中には収まっていたわけです。それがモーツアルトやベートーヴェンあたりから収まらなくなってきました。シューベルトなどもそうです。一方メンデルスゾーンは病弱でお金持ちだったこともありきちんとした社会人だったようですが、これは例外だと思います。シューマンになると完全に精神病の傾向が顕著になってきます。
そして音楽の中にもロマン性と同時にちょっとづつ毒が入ってきました。ワーグナーやリヒャルト・シュトラウス、そしてマーラーなどはその毒を非常に上手く利用した作曲家だといえます。逆にシューマンの場合は違います。だから彼の場合よくぞ交響曲を4曲も作曲できたと思うのです。しかも4曲とも名曲で後世まできちんと残っている。一種の奇跡ともいえます。よく勉強した上で、自分の性格に反してまでも懸命に取り組んだこともありますが、やはり音楽的な発想というのが素晴らしかったのだと思います。
-さてシェーンベルクへ移ります。まずテキストとなったメーテルランクの戯曲「ペレアスとメリザンド」はリヒャルト・シュトラウスが勧めたときいていますが。
飯守 シュトラウスはシェーンベルクに仕事が無くて娘も生まれて困窮していた頃、写譜の仕事などもあげたりしていました。そしてメーテルランクの戯曲を勧めたのですね。
-まったく同時期にフォーレやドビュッシー、シベリウスなどがこの戯曲を取り上げたというのも面白いと思うのですが如何でしょう。
飯守 流行とでもいいますか、象徴派(注1)の詩人がものすごく魅力を引きつけた、ちょうどそういう時代だったのです。
-世紀末という時代背景も関係するのでしょうか。この後に第一次世界大戦が勃発し、いままでの価値観が崩れ去った時代といえます。
飯守 もちろんです。世紀末というのは毎世紀あるわけですけれど、あの世紀末はもの凄かった。政治的にもそうですが、例えばシェーンベルクやマーラーなどの作曲家をはじめ、画家、建築家なども含めてその退廃の度合いが凄まじい。もう今後もあれ程まで行くことはないでしょう。本当に大変な時代でした。我々現代人はそれを通り抜けてきたから達観したところがありますが、あの頃はどろどろと燃えたぎっていました。それであまりに生々しくなってしまったので、ベルギーやフランスなどは象徴主義や印象主義などへすっと脱却していったのです。
-メーテルランクはこの頃のどろどろしたものを浄化しようとして作った戯曲なのだけれども、シェーンベルクはこれを使ってどろどろの極致を開拓したということでしょうか。
飯守 それはあたっていますね、どろどろを引き戻してしまったというやつです(笑)。
-他の作曲家はメルヘンのような綺麗な仕上がりですが、シェーンベルクはなぜこのような音楽をつけたのか、ちょっと理解しがたいのですが。
飯守 そうですね、他の作曲家の表現は大人か子供かわからないような神秘性に包まれているところがあるわけですよね。ところがシェーンベルクの作品だけはぐんと熱い。ペレアスが殺されるところなど凄いではないですか。フォルティッシモの打楽器と金管楽器でもってあんな殺し方ですよ。また冒頭の陰鬱な森のテーマは非常に「トリスタンとイゾルデ」的ですし、その他にもいたる所に「トリスタンとイゾルデ」を思わせる響きを見つけることができます。
その一方シェーンベルク自身が劇音楽として忠実に書いたと言っているように、メーテルランクの書いてある筋とおりに音楽は進行していきます。この作品の面白いところは、まず言葉が無いこと、そしてアクションもない、けれども戯曲に起きていることがかなり忠実に描写してあることです。あともう一つの特徴としては、示導動機(注2)と言ってもよいくらいに多くの動機が張り巡らされていることです。
-この作品についてアルバン・ベルクがアナリーゼ(楽曲分析)をしていますが。
飯守 シェーンベルク自身の解説によると、ペレアスとメリザンド、ゴローとあと運命などの動機は意識しているけれども、あくまで劇音楽として忠実に書いたとなっています。けれどもベルクがよくよくアナリーゼしてみたら、思っていた以上の示導動機が出てきたのです。またこれによると楽章などのシンフォニックでクラシカルなフォームまできちんと入っています。一方ワーグナーはそこまではやっていないわけで、それがとても面白いと思います。
シェーンベルクはこの作品の中で、非常に抽象的な美観の中にクラシックの要素を入れています。ベルクの解説はちょっとこじつけくさいところもありますが、確かに彼の構造の中に存在するのです。逆にシェーンベルクはあまり意識していなかったようだけれども、ベルクはそれを完全に掘りおこしています。最初に示導動機を提示したところが第1楽章、そして第2楽章がスケルツォ、中間部のゆっくりしたところが緩徐楽章で、そしてペレアスが殺された後冒頭に戻ってくるところがフィナーレになっていく、という具合にです。そう言われれば確かにそうなっています。この点は演奏する側は知っておいてもよいかと思います。
-シェーンベルクはきちんとした音楽の勉強はしたことがない、と伝記等に書かれています。ですがこれだけ数学的に作曲出来て、なおかつ大変ロマンティックです。どこで勉強したのでしょうか。
飯守 ツェムリンスキー(1871年~1942年 オーストリアの作曲家)がシェーンベルクに対位法の指導を行なっていますが、これがシェーンベルクの受けた唯一の音楽教育と言われています。またこの時代にツェムリンスキーも同じ努力をしていたわけですが、あくまでも調性から離れなかった、そして不幸な死を迎えてしまいました。逆にシェーンベルクの場合はもう完全に調性に行き詰ってしまったのです。そして改革してしまった。
-この作品の魅力は何でしょうか。
飯守 私が「ペレアスとメリザンド」をやりたくて仕方がなかった理由の一つとして、調性のある曲としてはシェーンベルクの最後の作品になることです。次の作品からは12音技法などの新ウィーン楽派に移行します。「グレの歌」は作品番号では後になりますが、実はこの前に書かれています。
調性の崩壊についてですが、例えばワーグナーでいうと「トリスタンとイゾルデ」よりも後の作品にあたる「神々の黄昏」の中、例えば第2幕でブリュンヒルデが怒りに狂ってものすごく盛り上がるところや、アルベリヒがハーゲンの夢に現れるところなどで、ほとんど調性がわからなくなっています。あと「パルジファル」の中の官能性を表しているところでも調性が極端に不安定になっているところなどがあります。ただしワーグナーの場合はその不安定さを最大限まで利用しているわけです。
それに対してシェーンベルクの「ペレアスとメリザンド」は明らかにその先を行っています。つまり調性が崩壊するぎりぎりまで行き詰っているのです。示導動機を張り巡らしたりしていますが、その変奏の手法とか、調性の乱高下の仕方とかがものすごく入り組んでいて、その先の12音技法のシェーンベルクを予想させるところまで行っているのではないかと思うのです。じつはこの辺りに調性が崩壊するちょうど前後の境目があるのではないかと思っています。だからその行き着く先を目撃したい、実感したいのです。もちろん皆さんと一緒にね。
-こういう異常なものをやってしまうと、シューマンの病気はもう普通の病気のように思えてしまうわけで(爆笑)。最後に今回の演奏会に向けてのメッセージをお願いします。
飯守 シューマンとシェーンベルクという、とても良いプログラムになったと思います。この二人に共通する異常さ、常識からはずれたところを述べましたが、そこにものすごく魅力があります。新響はそれらを正面から、また内面から取り組むオーケストラだと思いますので、本当に楽しみにしています。オーケストラと指揮者はギブアンドテイクというのか、お互いに教え教えられるところがあるというような演奏会になりそうです。これだけの重厚なプログラムになると、ただレパートリーをこなすというだけでは絶対に足りないのです。今回はそれが出来そうな気がします。
2008年3月10日
(注1)象徴派:象徴主義に属する詩人の一派。言語のもつ音楽的・映像的な側面に着目し、直接にはつかみにくい想念の世界を暗示的に表現しようとした。ボードレールを先駆者とし、マラルメ・ヴェルレーヌ・ランボーらが継承した。
(注2)示導動機(ライトモティーフ):オペラ・標題音楽などの曲中に繰り返し現れる特定の楽句で、楽曲の主要な想念や感情・物事・特定の人物などと結びついているもの。特にワーグナーが楽劇中に活用した。
聞き手:土田恭四郎(テューバ)
構成・まとめ:藤井 泉(ピアノ)
シェーンベルク:交響詩「ペレアスとメリザンド」
1.後期ロマン派作曲家シェーンベルク
アーノルト・シェーンベルクほど曲のスタイルが激しく変化した作曲家は珍しいでしょう。いわゆる“ゲンダイオンガク”の祖ともいえる「12音技法」の創始者なのですが、大変にロマンティックな曲も残しています。本日演奏する「ペレアスとメリザンド」はそれにあたります。
シェーンベルクはウィーンの靴店に生まれ、特別に音楽的環境の家庭で育ったというわけではありませんでしたが10歳に満たないうちにヴァイオリンの演奏や作曲をはじめたとのことです。16歳のときに父を亡くしたため中等学校を中退し銀行に勤めます。しかし長続きせず、弦楽器が十人足らずの小さなオーケストラのチェロ奏者になります。そこの指揮者がツェムリンスキーというウィーン音楽院を修了したばかりの若い音楽家で、シェーンベルクは彼から音楽に関するあらゆることを学んだと言っています(ツェムリンスキーはマーラーより少し後の後期ロマン派の作曲家として最近見直されています)。
シェーンベルクが最初に認められた作品は弦楽六重奏曲「浄夜」作品4です。その音楽はワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」をさらに推し進めた半音階的和声により、単に濃厚なロマンティシズムだけでなく異様な緊張感と美しさを漂わせています。
さて、本日演奏する「ペレアスとメリザンド」は作品5、すなわち「浄夜」の次の作品です。この曲はフル編成のオーケストラを使っていますから、前作同様のロマンティックな半音階的和声に加えて、複数のメロディーを同時に多数の楽器で演奏することによる屈折した感情表現や、弦楽器や木管楽器のソロおよびハープによる繊細で儚(はかな)い美しい響きなど、息を呑む場面が数多くあります。
2.曲の進行とストーリー
「ペレアスとメリザンド」は、日本では「青い鳥」で有名なベルギーの劇作家 メーテルランクの戯曲です(昔はメーテルリンクでしたが最近は原語読みに近いメーテルランクとよぶのが一般的です)。
シェーンベルクの「ペレアスとメリザンド」は劇音楽ではなく交響詩なのですが、劇の筋をかなり忠実に追っています。またワーグナーの楽劇と同様に登場人物や事物に固有のメロディーを割り当てた、いわゆるライトモティーフ(示導動機)により曲が構成されています。加えて4楽章の交響曲のような構成にもなっています。
ここでは音楽と劇の進行、そこに現れるライトモティーフについて解説していきましょう。これらを事前に理解しておくだけでこの曲をより深く楽しめるようになると思います。便宜的に四つの部分に分けて説明しますが楽譜にはそのような区切りは一切記載されていません。なお、特に聴きどころの部分はゴシック太字で表記しました。
■登場人物
原作の戯曲にはもう少し多くの人物が登場しますがこの交響詩では以下の三人を知っておけば十分でしょう。
・ゴロー:没落しつつある小国アルモンド王国の老王の孫。数年前に妻をなくしており、小さな子供がいる。
・メリザンド:正体不明の不思議な女性。一説では水の精であるとのことだが戯曲の中にほのめかしてあるだけで最後まで正体はわからない。
・ペレアス:ゴローの異母弟。若くて繊細な性格。
■第一部
ゴローが狩の獲物を追って森の奥深くに入ってゆく(「陰鬱な森」譜例1)。「トリスタンとイゾルデ」前奏曲の冒頭を憂鬱にしたようなこのテーマ(譜例1)がヴィオラ、コールアングレとファゴットを中心に繰り返される。
そこへ印象的な暗いメロディーがバスクラリネットによって二度奏される(譜例2)。これが「運命」と名づけられている、この曲の中心をなすライトモティーフである。
そのとき美しい若い娘が森の中に一人佇んでいるのが見える。オーボエを中心にメリザンドのテーマが現れる(譜例3)。美しいが生気の乏しい下降音型のテーマである。
ゴローがメリザンドを見つける。ゴローのテーマは最初ホルンでその後ヴィオラ、チェロが重なり、弦楽器群で美しく繰り返される(譜例4)。
敵(かたき)役のライトモティーフであるにもかかわらずそのメロディーは悲劇的でかつ美しい。ゴローの問いに対して要領を得ない答えしかしないメリザンド。ゴローはメリザンドの美しさに惚れ、妻にするため城に連れ帰る。悲劇の始まりである。運命の動機が金管楽器と打楽器により冷酷に繰り返される。
王国の没落を象徴するように覇気のない城の中でメリザンドは塞(ふさ)いでいる。そこへペレアスが現れる(譜例5)。
トランペットがリズミックに無調的な跳躍をする前半部と悩ましい響きの後半部からなる長いライトモティーフである。ペレアスの若々しくかつ憂いを持った二面的な性格を表現している。すると、クラリネットが非常に官能的なメロディーを奏で、後半にはヴァイオリンのソロが重なる(「愛に目覚めたメリザンド」譜例6)。ペレアスに出会って愛に目覚めたメリザンドは急に生気を帯び、艶かしく変貌するのである。
■第二部(スケルツォに相当)
急に早い三拍子となって、フルートが活躍する楽しげな音楽になる。この場面はメリザンドがペレアスと小さな古い井戸のそばで遊んでいる場面である。メリザンドはゴローからもらった結婚指輪をはずして弄(もてあそ)んでいるうちにその井戸に落としてしまう。このような情景がフルート、ピッコロを中心とした木管楽器で表現されている。ちょうどその頃、ゴローは森に狩に出かけて落馬する。井戸の傍らで無邪気に遊ぶペレアスとメリザンドの描写からゴローの落馬を表現する音楽に瞬時に移行する作曲技巧は目を見張るものがある。この、指輪紛失のできごとからゴローとメリザンドの悲劇が本格的に始まる。
落馬のけがを癒すためベッドで休むゴローをいたわるメリザンド。そのとき、メリザンドの指に指輪が無いことをゴローが発見する。「ゴローの疑いと嫉妬」のモティーフ(譜例7)がコントラバスにより“どす黒く”奏される。ゴローにきつく問いただされたメリザンドは海辺の洞穴で波にさらわれたと言い逃れをする。
「ゴローの疑いと嫉妬」(譜例7)の後、ヴィオラとチェロのソロによる儚(はかな)く美しい経過部(ほんとうに美しいです!)があり、いよいよ有名な「城の塔」の場面になる。これはメリザンドが城の二階の窓から身長ほどになる長い髪を垂らし、その下でペレアスがその髪を愛撫しながら語らうと言う、なんとも“フェチ”な場面である。ペレアスは、「明日旅に出なければならない」とメリザンドに伝える。直接的に愛を語る事はなく暗示的な会話であるが、髪を愛で、そして撫でるという行為によってメリザンドに対するペレアスの愛を表現している。この部分の音楽は繊細さを極めている。フルート、クラリネット2,3番のゆっくりしたアルペッジョとソロヴァイオリン、チェロの「メリザンド」、さらにクラリネット1番が「愛に目覚めたメリザンド」のテーマを、メリザンドの髪をまるで愛撫するかのように繰り返し奏する。
そこへゴローがやってきてペレアスを咎める。官能的な音楽が終わりを告げ「運命の動機」や「ゴローの疑いと嫉妬」などによる切迫した音楽に変わる。ゴローの二人に対する疑いが決定的なものとなる。
ゴローはペレアスを城の地下にある洞穴につれて行き、穴底を覗かせることでこの城から姿を消さないと命はないと暗示する。そこでは底なしの溜りからよどんだガスが沸いてきている。2本のクラリネットがオクターブで不気味なパッセージを繰り返し、トロンボーンのグリッサンドがその雰囲気を助長する。そして、木管楽器のフラッタータンギング※による上向音型の後、「運命の動機」が爆発する。
※:巻き舌または喉を震わせてtrrrrと発音する奏法
■第三部(緩徐楽章に相当)
音楽は急に甘美な響きに包まれ「愛に目覚めたメリザンド」(譜例6)のテーマが繰り返される。ペレアスは城から立ち去ることを決め、メリザンドに別れを告げるために夜に城外の泉の傍らで最後の逢引きをする約束をしたのである。ハープのアルペッジョと一瞬の休止の後、ヴァイオリンとチェロによりゆっくりした三拍子の甘美なテーマ(譜例8)が現れる。メリザンドはこっそり城を抜け出して来る。初めてお互いが好きだと言うことを口にし、これまで躊躇していた感情を爆発させる。原作では、愛の場面ではあるものの可憐で清純な愛の場面である。しかし、音楽の方はひたすら濃厚、爛熟、官能を極めてゆく。まさに「トリスタンとイゾルデ」第二幕をさらに濃縮したような音楽である。
甘く幸せな時間は短かった。ゴローがメリザンドの後を追ってきていたのである。メリザンドがそれを見つけ悲鳴をあげる。この悲鳴をピッコロや高音のクラリネットが表現する(芸が細かい!)。嫉妬の怒りが爆発したゴローは、ペレアスを剣で何度も突き刺して殺害する。
■第四部(フィナーレ楽章に相当)
これまでの悲劇を回顧するように冒頭の森の音楽が戻ってくる。ここで新しいテーマである「死の場面」(譜例9)が現れる。
またメリザンドが憔悴(しょうすい)している姿も表現される。その後、嫉妬と後悔で錯乱したゴローが音楽により表現される。ゴローはメリザンドにペレアスとの関係を執拗に問いただす。メリザンドは、ペレアス殺害直後のゴローによって城に連れ戻されていたのである。音楽はゴローが嫉妬に狂っている姿を激しいフォルティシモで表現してゆく。クライマックスの後にクラリネットのみが残り、それに続くコールアングレがメリザンドの悲劇的な運命を表現する。そして息を呑むようなハープのグリッサンドに導かれ、フルートとピッコロで美しい下降音型が、クラリネットで「死の場面」が奏される。メリザンドが死の床についているのである。メリザンドの死期が迫ってきた。ゴローの執拗な問いかけに対して「本当は、本当は・・」と言ったきり答えない。美しい和音が響いてフェルマータとなったところでメリザンドは息絶える。真実は謎のままゴローは独り残されてしまったのだ。
このあとはこれまでのテーマを用いてこの悲劇を総括してゆく。そのなかでもメリザンドの死の後、ゴローのテーマが万感の思いを込めて奏される箇所が印象的である。最後も「ゴローのテーマ」と「運命のテーマ」によって締めくくられる。
3.シェーンベルクの「ペレアスとメリザンド」が表現しているものとは?
このように原作の筋書きと音楽を比較してゆくと原作に比べて音楽があまりにも濃厚でエロティックなのが気になります。同じ題材を用いたドビュッシー、フォーレそしてシベリウスも美しく儚い音楽を付けているのに比べてあまりにも“濃すぎる”のです。これについては次のように考えられませんでしょうか(あくまで仮説です)。シェーンベルクはゴローから見たペレアスとメリザンドを表現したのではないかということです。そう考えれば敵役であるゴローにあれだけ重要な美しいテーマを与えたということも納得できますし、異常に濃厚な音楽も全て説明がつきます。ペレアスとメリザンドの間には実際はゴローが考えるようなことは無かった(あったのかもしれませんが字面を読む限り無かったことになっています)にもかかわらず、ゴローの頭の中では、「あんなこと」や「こんなこと」をしているに違いないと妄想が膨らみ、嫉妬を燃やしていたということです。
シェーンベルクがこの曲を作曲した1903年頃は長女が生まれ、家族円満な幸せな時代だったと思われます。にもかかわらずこれだけ深くて憂いを持った曲を書いてしまうというのは天才ゆえなのでしょうか。実は「ペレアスとメリザンド」の作曲から4年後、シェーンベルクに絵を教えるため出入りしていた若い画家ゲルシュトルがシェーンベルク夫人と駆け落ちするという事件が起きています。夫人は結局シェーンベルクのもとに戻り、ゲルシュトルは20代の若さで自殺するという結末を迎えます。なにか「ペレアスとメリザンド」を髣髴とさせる出来事です。あのマーラーが、二人の幼い娘が元気で幸せの絶頂のとき「亡き子をしのぶ歌」を作曲し、その後に娘を亡くしてしまうという有名な話のように、未来を予見しそしてそれを呼び寄せてしまったのでしょうか。
ゲルシュトルに指導を受けたシェーンベルクは多くの絵画も残しています。そこにはゴローの狂気の世界にも共通する暗い感情が潜んでいるように思えます。
参考文献
『"PELLEAS und MELISANDE" von ARNOLD SCHOENBERG Thematische Analyse』
Alban Berg (Universal Edition)
『“Arnold Schönberg Center” web site』
http://www.schoenberg.at/6_archiv/music/works/op/compositions_op5_e.htm
『〔大作曲家シリーズ〕シェーンベルク 』
フライターク著、宮川尚理訳(音楽之友社)
『岩波文庫 対訳「ペレアスとメリザンド」』
メーテルランク作、杉本秀太郎訳 (岩波書店)
『名曲解説全集第6巻 P182-184』(音楽之友社)
挿絵:『"PELÉAS ET MÉLIANDE"』より Carlos Schawb (Piazza社1924)
初演:1905年1月25日 シェーンベルク指揮Orchester des Wiener Konzertvereines (ウィーン楽友協会大ホールにて)
楽器編成:ピッコロ、フルート3(3番は2番ピッコロ持ち替え)、 オーボエ3(3番は2番コールアングレ持ち替え)、コールアングレ、クラリネット3(3番は2番バスクラリネット持ち替え)、Esクラリネット、 バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン8、トランペット4、アルトトロンボーン、トロンボーン4、テューバ、ティンパニ、シンバル、トライアングル、タムタム、テナードラム、大太鼓、鉄琴、ハープ2、弦5部
第202回演奏会ローテーション
| ニールセン | イベール | ドビュッシー | |
| フルート1st | 松下 | 岡田充 | 兼子 |
| 2nd | 吉田 | 丸尾(Picc) | 新井 |
| 3rd | 藤井 | - | - |
| Picc | - | 岡田澪 | 岡田澪 |
| オーボエ1st | 堀内 | 亀井淳 | 亀井淳 |
| 2nd | 桜井(C.A.) | 亀井優 | 山口 |
| コールアングレ | - | 岩城 | 岩城 |
| クラリネット1st | 末村 | 高梨 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 大藪 | 進藤 |
| ファゴット1st | 浦 | 田川 | 田川 |
| 2nd | 星 | 古川 | 古川 |
| 3rd | - | 浦 | 星 |
| コントラファゴット | - | - | 浦 |
| ホルン1st | 大内 | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 園原 | 比護 | 山口 |
| 3rd | 鵜飼 | 大原 | 比護 |
| 4th | 市川 | 箭田 | 大原 |
| トランペット1st | 小出 | 倉田 | 野崎 |
| 2nd | 北村 | 北村 | 青木 |
| 3rd | 中川 | 青木 | 倉田 |
| コルネット1st | - | - | 小出 |
| 2nd | - | - | 中川 |
| トロンボーン1st | 武田 | 志村 | 志村 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 | 武田 |
| 3rd | 岡田 | 大内 | 大内 |
| テューバ | 足立 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 桑形 | 中川 | 桑形 |
| 大太鼓 | - | 桑形 | 桜井 |
| シンバル | - | 皆月(*) | 中川 |
| トライアングル | - | 恒広(*) | 桜井 |
| タムタム | - | 田中 | 田中 |
| 小太鼓 | - | 浦辺(*) | - |
| タンブリン | - | 今尾 | - |
| カスタネット | - | 佐藤(*) | - |
| 鉄琴 | - | - | 今尾 |
| 木琴 | - | 桑形 | - |
| チェレスタ | - | 藤井 | - |
| ハープ1st | - | 佐々木(*) | 佐々木(*) |
| 2nd | - | 篠田(*) | 篠田(*) |
| 1stヴァイオリン | 前田(大隈) | 堀内(大隈) | 堀内(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 岸野(長沼) | 岸野(笠川) | 岸野(笠川) |
| ヴィオラ | 柳澤(石井) | 石井(柳澤) | 石井(柳澤) |
| チェロ | 日高(光野) | 光野(柳部容) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 加賀(中野) | 中野(加賀) | 中野(加賀) |
第202回演奏会のご案内
ニールセン=北欧の巨匠
山下一史氏2回目の登場となる今回は、デンマークの作曲家ニールセンの作品を取上げます。山下氏は1986年デンマークでの「ニコライ・マルコ国際指揮者コンクール」で優勝後、北欧の多くのオーケストラと共演をしています。中でもつながりの大きいスウェーデン南部のヘルシンボリ交響楽団とはニールセン交響曲全曲を演奏しています。
ニールセンはシベリウスと同じ1865年生まれ。今回演奏する交響曲第2番は、6つの交響曲の中でも最もニールセンらしい曲かもしれません。ニールセンが旅先で気質をテーマにした絵を見て興味を持ち作られた曲で「四つの気質」という副題がついています。古代ギリシャ時代から、人間には4つの体液がありそのバランスで病気が起こると考えられ、それによって性格の分類もされてきました。各楽章はそれぞれ胆汁質、粘液質、憂鬱質、多血質を表しており、4つのキャラクターを楽しむことができます。
「海の日」のコンサートに
後半はフランス印象派の作品から海にちなんだ2曲-イベール「寄港地」、ドビュッシー「海」を演奏します。
イベールは6人組(ミヨー、オネゲル他)と同世代ですが、第一次世界大戦勃発時に志願して海軍士官となったため6人組に参加しませんでした。大戦後にパリに戻りローマ大賞を受賞してローマに留学中に書いたのが「寄港地」です。イベールは海軍士官として地中海を航行し沿岸各地に寄港しており、その時各地で受けた印象から、イタリア・アフリカ・スペインの港町の情景を美しく鮮やかに描いています。
「海」は幼い頃船乗りになるのが夢だったドビュッシーの代表作。海の様々な表情が多彩な音色とリズムで表現されています。初版の楽譜の表紙には、ドビュッシーの要望により葛飾北斎の「冨嶽三十六景~神奈川沖浪裏」をモチーフにした海が描かれており、北斎の絵に霊感を得て作曲されたとされています。当時のパリでは、ジャポニズム(日本趣味)が流行しており、多くの芸術家が浮世絵に影響を受けました。「海」の中にも日本的な音がところどころ聞こえてきます。
山下氏の華麗なタクトでどのような色彩の音楽が繰り広げられるでしょうか。どうぞご期待ください!
シューマン:交響曲第1番
クララ、ライプツィヒでの創作、そして「春」
ロベルト・シューマンの交響曲第1番は1841年3月31日、当時ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者であり、シューマンの親友であったフェリックス・メンデルスゾーンにより「最大の愛情と心遣い」で初演された。この前年1840年9月12日、ロベルト・シューマンは苦難の末にクララ・ヴィークと結婚し、1841年は幸福と創作の絶頂にあった。交響曲第1番は、2番以降の交響曲のように15年後に訪れる「死に至る心の病」を予感させない、「春の訪れを歓ぶ」明るい作品に仕上がっている。クララの存在無しに交響曲第1番は生まれ得なかったし、それに続く3曲の交響曲も存在しなかったかもしれない。シューマンの作品が後世に残ったのも、夫の遺作の演奏に心血を注いだクララの偉業によるところが大きい。
ロベルト・シューマンは1810年にライプツィヒから70km南のツヴィカウで生まれた。出版商であり著述家でもあった父親は、早くからロベルトの音楽的才能に気がつき音楽教育を受けさせていた。母親は声楽家であり、この両親の才能を受け継いだロベルトは、その後、文筆活動と作曲で音楽界に入ることになり、ロベルト・シューマンの音楽は、「詩的なものから霊感を受けて音にしていく」というスタイルで作曲されていった。父親の死後、ロベルトは安定した生活を願う母の希望で法学を学ぶことになり1828年ライプツィヒ大学に入学したが、音楽家への夢を捨てることができず、ライプツィヒの音楽界に足を運んでいた。
クララ・ヴィークは、1819年ピアノ指導者フリードリッヒ・ヴィークの次女として生まれ、幼少の頃から父親の英才教育を受け、1828年10月20日、9歳にしてゲヴァントハウスでデビューした。
ロベルトとクララの最初の出会いは、クララがゲヴァントハウスにデビューした年の3月31日、ライプツィヒの有力者邸での音楽会であったが、お互いの存在を知るに至ったのは1830年10月、ロベルトが弟子としてヴィーク家で生活を始めた時である。子煩悩なロベルトはたちまちヴィーク家の子供達の人気者となる。11歳のクララは9歳年上のロベルトを「ヘル・シューマン」と呼び、常に好意を持って見ていた。彼女の感じやすい心は、ロベルトの詩的な音楽の美を捉えていたが、カフェに入り浸ったり酒に酔ったりするのは気に入らなかった。ヴィーク家は、ライプツィヒの音楽社交場のようなありさまで、いつも音楽家達が出入りしており、クララは青年音楽家達が語る哲学的、美学的な言葉を理解することは出来なかったが、作品を披露する場面では必ずピアノを弾いていた。クララにとってあまりにも難解でアンバランスな状態であったため、これを紐解く役回りのロベルトといつしか精神的な深いつながりを持つことになっていった。1831年パリ演奏旅行からクララが帰宅し、次第にロベルトの作品も演奏するようになり、1833年にロベルトは「クララ・ヴィークの主題による変奏曲」を作曲すると、クララは自作の「ロマンス」をロベルトに捧げる。1834年、クララは音楽理論と声楽を学ぶために、単身ドレスデンで生活するが、その頃ロベルトはエルネスティネという別の女性に夢中になっていた。この境遇は14歳のクララの心にロベルトへの思慕の情を育むことになった。結局エルネスティネはライプツィヒを去り、クララは自宅に戻る。15歳のクララは子供から大人へと脱皮する過程であり、ロベルトはエルネスティネとの嵐の後に、クララに心の平安を見いだすのである。そして、ロベルトからクララへの手紙は「貴女が私にとってどんなに大切な人か、ご存じでしょう。」という一節で結ばれる。
クララの父親フリードリッヒ・ヴィークは、二人の親密な交際に大反対であった。ヴィークはロベルトの才能は認めていたものの、作品はピアノ曲など小品ばかりなので、経済的に不安定だったのである。ロベルトはヴィーク家に出入り禁止の状態の上、ヴィークはロベルトがヴィーク家に現れたら射殺するとまで公言している。ヴィークはクララがロベルトの作品を演奏する事も禁じていたが、クララはロベルトの作品を絶えず研究し、作曲者の精神性に没入してロベルトの存在を身近に感じる事が心の慰安であった。ロベルトにとっても、クララが弾くことを前提として作曲に没頭することが心の救いであり、1839年まで数多くのピアノ曲を生み出す源になった。
ロベルト&クララと、フリードリッヒ・ヴィークは、お互いを訴訟するという、行き着くところまで行き着いてしまった。1840年8月20日に勝訴し、二人は結婚できることになったが、その後1843年、ヴィークからの和解の申し出により邂逅した。
ロベルトとクララは、1840年9月12日、クララ21歳の誕生日に、ライプツィヒ郊外のシェーネフェルト教会で結婚し、ライプツィヒ市街地から東へ10分ほどのインゼル通りに居を構えた。ここからライプツィヒ郊外南東に在るメンデルスゾーンの家までも10分ほどである。インゼル通りのシューマン邸には、メンデルスゾーンをはじめとした仲間達が集まり、彼らの作品を演奏したり音楽談義などで親交を深めていた。
1839年までロベルトは多数のピアノ作品を作曲してきたが、1940年になると歌曲の創作に没頭する。クララへの手紙には「書けて書けてしかたがない。」とある。リュッケルトの詩篇「恋の春」からの12曲の歌曲では、ロベルト9曲とクララ3曲を共同で作曲した。
そして1841年になって、ロベルトはいよいよ念願の交響曲に着手する。ロベルトは1839年にフランツ・シューベルトの兄を訪ね、遺稿の中から交響曲「ザ・グレート」を見つけ出し、ライプツィヒでメンデルスゾーンが初演を果たしたことから霊感を受けて交響曲を作曲する決意を固めた。更にアドルフ・ベッドガーの詩「汝、雲の霊よ」が作曲の機縁になったと言われている。このベッドガーの詩は、「冬の風景と自身の悩む心を重ね合わせ、春と悩みの昇華を重ね合わせて、春の到来に確信を持つ」といった内容のものである。詩的なものと音楽的なものを一体として捉えるロベルトは、いわば詩の続編とも言う形で、春の到来を音楽として生み出していった。1841年1月23日の日記に「春の交響曲を開始」、26日の日記には「万歳!交響曲が完成した!」とある。この4日間ロベルトは書斎に引き籠もり、クララとも殆ど語ることはなかった。この頃のクララはロベルトの作曲を邪魔しないように、自身でピアノに触れることを自制していった。しかしながら、26日のクララの日記には「私はすっかり幸福です。ああ、ここにオーケストラがあったら!・・・貴方はいつも感嘆の思いで私の心を満たしてくださいます」とある。交響曲第1番に引き続き、後にピアノ協奏曲の第1楽章になった「ピアノと管弦楽のための幻想曲」などの交響作品が生まれた。長い期間で育まれたクララとの愛情、苦難の末に得た幸福な家庭生活により、ロベルト・シューマンの才能は絶頂期を迎えていたのであった。
このように、「春」のあらゆる背景が揃って交響曲第1番は創作されるに至り、当初ロベルトは、交響曲第1番に「春の交響曲」という表題を付け、さらに各楽章にも
第1楽章「春の始まり」、
第2楽章「夕べ」、
第3楽章「楽しい遊び」、
第4楽章「たけなわの春」
という表題をつけていた。しかしながら、詩的で精神の内面を追求する為に、表題によって聴衆に先入観を与えることが無いように、全ての表題を消し去ってしまった。現在は「春の交響曲」という表題だけが残っている。
今でこそ、クララはロベルト・シューマンの妻として知られている。しかしながら、交響曲第1番が作曲された1841年頃の音楽界では今と逆で、ロベルト・シューマンは天才女性ピアニストであるクララ・シューマンの夫という存在であった。ロベルトは、クララの夫として相応しい芸術家であるべく作曲活動に没頭していたわけである。本拠地ライプツィヒ周辺では妻や友人達の愛情こもった演奏に支えられ、シューマンは大作曲家への道を歩み始めることができた。しかし、演奏旅行に出ると様相は一変する。妻クララは演奏家であり自らの力で聴衆の評価を手中に収める事が出来るが、これに対して夫ロベルトの作品は、妻の演奏によるピアノ作品を除くと、準備も充分でないまま初対面の演奏家によって聴衆に晒されてしまう。これでは、「天才女性ピアニスト」と「夫は売れない作曲家」という構図は容易に覆せない。この葛藤がシューマンを精神的に追い詰めていった。1844年1月に出発した冬のロシア演奏旅行も、ロベルトの役回りはクララの付き添いであった。この旅行でロベルトの感性はロシアの風物によって異常なまでに刺激され、冬のロシア旅行による体力的な消耗などから、ついに体力と精神のバランスを崩し、躁鬱病が発症した。親友のメンデルスゾーンがベルリンに去ったこともあり、シューマン一家は環境の変化による病状回復に望みをかけてドレスデンへ転居することにした。1844年12月、クララはライプツィヒ生活最後の演奏としてロベルトのピアノ四重奏曲を初演し、そして創作の絶頂期を過ごしたインゼル通りの家を引き払っていった。
シューマン夫妻が新婚時代を過ごしたインゼル通りの家は、当時の建物がシューマン博物館として公開されている。ここは「静的な博物館」ではなく、子煩悩なシューマン夫妻の意を汲み、「クララ・シューマン音楽学校」として160年の時空を超えて児童音楽教育に使用されており、子供の歌声や歓声が聞こえている。
かつて、ユーロ紙幣に移行する前の100ドイツマルク紙幣に印刷されていた肖像はクララ・シューマンであった。作曲家ロベルト・シューマンの妻として夫の亡き後、7人の子供を抱えながら、夫が残した作品の価値を高める為に献身した良妻賢母として、今でもドイツ国民に敬愛されている。
初演:1841年3月30日
フェリックス・メンデルスゾーン指揮
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス・オーケストラ
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、トライアングル、弦5部
ウィーンとシェーンベルクの想い出
私が大学1年生の時、とある弦楽アンサンブル団体の演奏会を聴きに行った。まだオーケストラを初めて間もなかったせいか、一曲目の「リュートのための古代 舞曲とアリア第3組曲」の冒頭の美しさに驚いたことは今でも思い出すほどであった。その演奏会のメインがシェーンベルクの「浄められた夜」(以下「浄夜」)であった。シェーンベルク若書きの調性時代の作品、トリスタンの影響が強いという知識は知っていたが、実際は全く聴いたことのなかった曲だった。そして実際聴いてみて、極めて退屈であった。序盤のクライマックスでワーグナー風にH-durの和音を響かせるところは鮮明に覚えているが、それ以外は全く曲の内容がつかめず、20数分間がとてつもなく長く感じてしまった。最悪の第一印象の後、浄夜には全く縁がなかった。
約1年後の2年生の時、大学OBオケがウィーンに演奏旅行に行くことをOBから聞いた。話によるとコントラバスが足らないようで、団員でもない私もついていくことができたのだ。かのムジークフェライン大ホールでの演奏そのものについては、しかし今回のテーマではない。
ヨーロッパには高校時代に家族でパック旅行で行ったことはあったが、本格的に行動を一から決める海外旅行は初めてであった。早速仲間との観光予定を立てるためにガイドブックを買って読んでいると、ウィーンという街は音楽の街ならず世紀末美術の街でもあることが詳しく紹介されていた。そこに出ていたクリムト、シーレ、ココシュカというウィーン分離派を代表する絵画作品を見て大いに興味を引かれた。
当時美術には関心がなかったわけではなかったが、分離派は縁がなく不勉強であった。昔たまたまテレビで見た「ユディトI」の艶かしい表情は一目見て以来強く印象に残っていたが、その作品名と作者がクリムトということはウィーン旅行がきっかけでわかった次第であった。分離派などの世紀末絵画についてはガイドブックで下調べをしはしたが、やはり現地で本物を見るという経験は、ウィーン世紀末絵画をより身近なものにしてくれた。厳密に言えば私にとって絵そのものを「見る」ことよりも絵が存在する場を「体験する」という経験のほうが重要であった。ベルヴェデーレ宮殿で見た「接吻」、「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像I」(*)の巨大な金ぴかの絵画そのものには確かに圧倒されたものだ(件の「ユディトI」は想像よりずっと小さい作品であった)。しかしウィーンの街が持つ言葉では言い表せない「雰囲気」を肌で味わったことが、私の感受性を変えたのでなはいかと思う。確かにマーラーもシェーンベルクもあの時代、あの街にいたのだ!黄金のムジークフェライン大ホールとクリムトの金箔の絵画は確かにウィーンという街の美意識を表しているものだ。
帰国後しばらくして、不思議とシェーンベルクの「浄夜」は身近なものに感じられるようになった。ブーレーズ指揮ニューヨークフィルの名盤 (ジャケットはあの「接吻」!)を購入し、全曲何度もリピートして聴くほどはまりこんだ。あれほど退屈に思えた「浄夜」が一転大好きになったのも、クリムトの絵画を通じて体感したウィーン世紀末の雰囲気を味わったウィーン旅行のお陰だと感じている。
もうひとつウィーンで印象深かった経験として、ザッハートルテで名高いホテルザッハーのカフェでザッハートルテを賞味したことを挙げたい。一緒に食した団員の方々はその日本人の標準的味覚を越えたあまりの甘さに辟易してしまっていたが、お一人(男性)だけがおいしそうに召し上がっていた(他の人が残した分まで!)。彼は「この甘さこそブラームスのドルチェ!」などとのたまっていた。なるほど西洋クラシック音楽を演奏するには日本人の感性を超えたものを受け入れるだけの度量が必要ということであろうか。それ以来あのザッハートルテは食する機会はないが、再び食する機会があればあの暴力的なまでに 甘いチョコレートケーキがかつてとは違ったように感じられるかもしれない。
新ウィーン楽派が苦手な人は、回り道をしてでも他の角度から世紀末ウィーンにアプローチしていくものよいかもしれない。ウィーン旅行はなかなか適わないにしても、ザッハートルテなら日本でも味わえる。ザッハートルテの濃厚さはシェーンベルクの濃厚さに繋がる…かも?
(*)「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像I」は現在はニューヨークのノイエ・ギャラリーに所蔵されている。)
禁断のR指定音楽へようこそ
シェーンベルクというとメロディーも協和音も無い、砂を噛むようないわゆる“ゲンダイオンガク”の創始者と考えている方も多いのではないでしょうか。しかしながら、20代までの彼の曲は爛熟を極めたロマンティシズムにあふれています。それはワーグナーやマーラーをもはるかにしのぐ濃厚さです。今回取り上げる交響詩「ペレアスとメリザンド」もその時代の傑作です。転調を繰り返しながらつながってゆく長い旋律線はワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」を、また、一見脈絡のなさそうな複数の旋律を重ねることで屈折した感情を表現するあたりはマーラーの交響曲第9番の第1楽章を思い起こさせます。そして、それらの中にシェーンベルク独特のキラキラと光る宝石のような、そして思わずため息が出てしまうような美しい瞬間がちりばめられています。
この交響詩で取り上げている題材は、フォーレの劇音楽やドビュッシーの有名なオペラにも取り上げられているベルギーの作家メーテルランクの戯曲です。「王子ゴローはあるとき森にいた謎の娘メリザンドを見つけて城に連れ帰り妻にするが、メリザンドはゴローの弟ペレアスと惹かれあってしまう。ゴローはそれに気づき嫉妬に狂い、ペレアスとメリザンドの逢引きに乱入してペレアスを刺殺、メリザンドは城に連れ戻されるが傷心のうちに亡くなる.」 という粗筋です。全体を貫く雰囲気は大きく異なりますが、道ならぬ恋愛という点では「トリスタンとイゾルデ」に共通する要素を見出すことも可能でしょう。シェーンベルクはフォーレやドビュッシーとまったく異なる雰囲気の響きを作り出し、清純な雰囲気のペレアスとメリザンドの恋愛がまるでトリスタンとイゾルデの恋愛のように濃厚かつエロティックに、また最後は弟を殺してしまうゴローの苦悩と嫉妬を執拗に表現しています。
ここまではチラシの裏面に書いた文章とほとんど同じですが、ここではこの少々難解だがエロティックな大人向けの音楽をしゃぶり尽くしていただくための「傾向と対策」を掲載いたしましょう。
シェーンベルクの「ペレアスとメリザンド」は交響詩なのですが、かなり忠実に劇の筋を追っています。またワーグナーの楽劇と同様に登場人物、事物や感情に固有のメロディーを割り当てた、いわゆるライトモティーフにより曲が構成されています。加えて4楽章の交響曲のような構成にもなっています。
ここに掲載したのは音楽と劇の進行、そこに現れるライトモティーフと演奏する楽器について解説してあります。(ネタ本はアルバン・ベルクのテーマ分析(ドイツ語)です。)また代表的なCDのトラック番号も記しておきますのでぜひ事前にCDで予習しておかれることをお奨めいたします。場面が目に浮かび、それぞれのライトモティーフを聞き分けられるようになってくるとこの危険な魅力一杯の禁断の世界に足を踏み入れることになるでしょう。
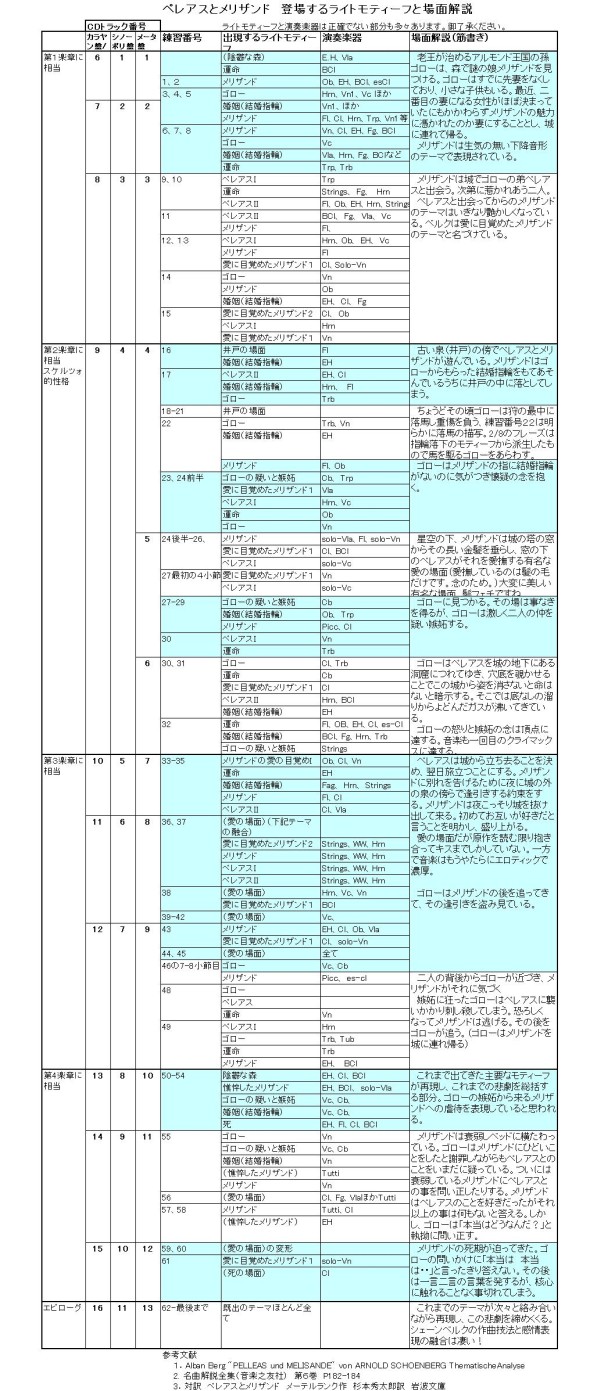
ロベルト・シューマンの交響曲第1番(フロレスタンとオイゼビウスとの対話)
ロベルト・シューマンの父は文学愛好から出版を生業としてしまった人物で、ロベルトは「音楽新報」という同人誌で音楽評論家として活動していました。この活動は、1833年から、病に冒されてライプツィヒを去った1844年まで続きます。この期間は、作曲家シューマンにとって最も充実した活動が出来ていた期間でもありました。数多くのピアノ曲、歌曲、そして交響曲1番「春」を生み出し、J.S.バッハの作品の再評価を世に問い、シューベルトの「ザ・グレート」を発掘した時期です。クララ・シューマンとの結婚もこの時期でした。
「音楽新報」では、「ダビッド同盟」という組織の同盟員が投稿するという形がとられていましたが、実は「ダビッド同盟」は架空の組織で全てシューマンの頭の中にあったのです。彼は、様々な音楽観を表現するために、芸術観や性格の異なった「オイゼビウス」と「フロレスタン」という架空の人物を作り、シューマン自身と共に3名の人物が主になって音楽作品論を展開していました。1841年にメンデルスゾーンの指揮で初演された交響曲1番「春」は大成功だったわけですが、「音楽新報」に取り上げられることはありませんでした。もし、「音楽新報」に取り上げられていたならば・・・・・
1841年*月*日
ロベルト・シューマンの交響曲第1番
フロレスタンとオイゼビウスの対談
フロレスタン:ショパンは「作品2」を以て、オイゼビウスに「諸君、帽子をとりたまえ、天才だ」と言わしめた。私は、今、「諸君、帽子をとりたまえ、ベートーベンの後継者が現れた」と言いたい。ダビッド同盟の同志であるロベルト・シューマンの交響曲第1番が初演されたのである。一貫したモットーを展開した中に、詩的、精神的な深みがある、ベートーベン後を立派に継いだ傑作であろう。
オイゼビウス:シューマンによると、ウィーン旅行で発見したシューベルトのハ長調交響曲に触発され、ベッドガーの詩が機縁になったという。
フロレスタン:ベッドガーの詩が機縁とはどういう事だ?
オイゼビウス:ベットガーの詩、交響曲1番の導入たる
「おんみ雲の霊よ、重く淀んで 海山をこえて脅かすように飛ぶ
おんみ灰色のヴェールはたちまちにして 天の明るい瞳を覆う
おまえの霧は遠くから湧き そして夜が、愛の星を包む
おんみ雲の霊よ、淀み、湿って 私の幸せすべてを追い払ってしまった
お前は顔に涙を呼び 心の明かりに影を呼ぶのか?
おお、変えよ、おんみの巡りを変えよ 谷間には春が花咲いている」
の後に、交響曲第1番のモットー
が続くと考えればよい。このモットーは「待ち焦がれる春」への「春の訪れ」を表す。
そしてこのモットーは終始作品の中で展開されていく。
つまり、シューマンの頭の中では、詩と音楽が渾然一体と鳴っているのだ。
ロベルト・シューマンの音楽は、POETIC「詩的」で精神の内面を追究した音楽である。これは、初期の1839年までに23曲連続して作曲されたピアノ曲や、その後の歌曲に於いて余すところ無く発揮されている。しかしながら、彼はベートーベンの後継者たらんとするところから、何としても交響曲を作曲しなければならないと考えていたようだ。
フロレスタン:ウィーン旅行で、ベートーベンとシューベルトの墓参をした時に、その墓の脇でペンを拾った。その後、フランツ・シューベルトの兄であるフェルナンド・シューベルトを訪れ、未整理の遺作の中から偉大な交響曲ハ長調を発見したのである。そして、ライプツィヒに持ち帰りメンデルスゾーンに初演を託したわけだが、その拾ったペンで交響曲1番の冒頭のモットー3小節を書いた。偉大なる先駆者の祝福を受けたモットーである事に疑う余地はない。
オイゼビウス:彼は始め、交響曲1番に「春の交響曲」という表題を付け、さらに各楽章にも
第1楽章「春の始まり」、
第2楽章「夕べ」、
第3楽章「楽しい遊び」、
第4楽章「たけなわの春」
という表題をつけていた。
しかしながら、POETICで精神の内面を追求する為に、表題によって聴衆に先入観を与えることが無いように、全ての表題を消し去ってしまった。春のイメージが溢れ出る演奏によって、聴衆の心が内面から「春」のPOEMの感覚で満たされることを理想としたのである。
フロレスタン:ピアノ作品「クライスレリアーナ」に似ているところが有ったように思うが?
オイゼビウス:その通り。交響曲1番の第2楽章にはクライスレリアーナの6曲目、第4楽章には8曲目のモットーが使われている。1841年1月23日の日記に「春の交響曲を開始」とあり26日の日記には「万歳!交響曲が完成した!」とあるので、僅か4日間で作曲した事になっているが、実は、クライスレリアーナが作曲された1838年頃、シューマンは少しずつではあるが交響曲のスケッチを始めていたようだ。この頃シューマンは、クララの父親フリードリッヒ・ヴィークにクララとの交際を禁止され、クララは父親と共にウィーンへ旅立ち、文通もままならぬ状態にあった。彼は、クララが演奏することを前提に、愛の葛藤をピアノ曲に託したのであった。結婚後の作品となった交響曲1番では、そのモットーが見事に昇華している。
フロレスタン:1840年の初夏に結婚して「人生の春」の中で、1841年新婚生活で初めての春の訪れに、「大作曲者としての春の訪れと」言える交響曲1番を創り出したということだね。
オイゼビウス:ロベルト・シューマンの音楽は、「詩的なものから霊感を受けて音にしていく」というスタイルで作曲されているから、あらゆる「春」の詩が重なり合い、それが霊感となって音になったと言うことだろう。
フロレスタン:ところで、「カフェ・バウム」の新しいメニューがとても良い。あのコーヒーを飲むと冷えた体の中に染み込んでいくようだ。
オイゼビウス:あの特製アップルパイも絶品だ。
フロレスタン:そろそろ、ロベルト・シューマンが「カフェ・バウム」に現れる時間だね。丁度、小腹も空いてきたし、アップルパイとコーヒーをいただきに行くとしよう。
もちろん、これは筆者の想像による架空の対談であり「音楽新報」に掲載されたものではありません。
(注)カフェ・バウム 当時ライプツィヒの音楽家達が良く利用していたカフェ。ロベルト・シューマンも入り浸っていた。今も、当時のまま営業中。写真は現在のメニュー。
1957年~1965年の自主演奏会の記録
(指揮は特記なしは芥川也寸志)
1965年
12/6 第8回定期演奏会 日比谷公会堂
ワーグナー:歌劇「ローエングリン」第3幕の前奏曲
ベートーヴェン:交響曲第8番
ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」
9/26 日立労音9月例会 日立市民会館
ワーグナー/歌劇「ローエングリン」第3幕への前奏曲
シューベルト/交響曲第8番「未完成」
ベートーヴェン/交響曲第5番
8/23 サマーコンサート 東京文化会館
ウェーバー/歌劇「魔弾の射手」序曲
ベートーヴェン/交響曲第6番「田園」
ベルリオーズ/歌劇「ファウストの劫罰」よりハンガリー行進曲
ドヴォルザーク/スラブ舞曲第10番、第1番
ラヴェル/ボレロ
7/24・25 浜松労音7月例会 浜松市民会館
ウェーバー/歌劇「魔弾の射手」序曲
ベートーヴェン/交響曲第5番
シューベルト/交響曲第8番「未完成」
4/22~28 労音4月例会
松山女子商講堂(22日)
宇和島市公会堂(23日)
新居浜市民文化センター(24日)
高知中央公民館(25日)
中村高校講堂(26日)
徳島市民会館(27日)
高松市民会館(28日)
スメタナ/歌劇「売られた花嫁」序曲
ハイドン/交響曲第94番「驚愕」
ベートーヴェン/交響曲第3番「英雄」
4/10~18 東京労音4月例会
東京文化会館(10日)
共立講堂(14日)
渋谷公会堂(18日)
スメタナ/歌劇「売られた花嫁」序曲
ハイドン/交響曲第94番「驚愕」
ベートーヴェン/交響曲第3番「英雄」
3/28 東京労音(千葉)3月例会 新宿小学校講堂
スメタナ/歌劇「売られた花嫁」序曲
ハイドン/交響曲第94番「驚愕」
ベートーヴェン/交響曲第3番「英雄」
2/3 第7回定期演奏会 日比谷公会堂
スメタナ/歌劇「売られた花嫁」序曲
ハイドン/交響曲第94番「驚愕」
チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」
1964年
8/31 サマーコンサート 東京文化会館
J.シュトラウス/喜歌劇「こうもり」序曲
同/皇帝円舞曲
チャイコフスキー/舞踏音楽「白鳥の湖」より
レーウェ/マイ・フェア・レディ
ロジャーズ/回転木馬
ロジャース/南太平洋
合唱:東京プリマ・ヴォークス
合唱指揮:岡田和夫
5/25 第6回定期演奏会 日比谷公会堂
シャブリエ/狂詩曲エスパナ
ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番
ブラームス/交響曲第1番
ピアノ:井内澄子
1963年
12/16~27 東京労音12月例会
東京文化会館(16日)
厚生年金会館(22・25~27日)
バッハ=ストコフスキー/トッカータとフーガニ短調
ベートーヴェン/交響曲第9番
6/16・17 水戸労音6月例会 水戸市民会館
ウェーバー/歌劇「魔弾の射手」序曲
J.シュトラウス/皇帝円舞曲
シューベルト/交響曲第8番「未完成」
ベートーヴェン/交響曲第5番
4/21 両毛労音4月例会 両毛小学校
ウェーバー/歌劇「魔弾の射手」序曲
J.シュトラウス/皇帝円舞曲
シューベルト/交響曲第8番「未完成」
ベートーヴェン/交響曲第5番
3/10~19 東京労音3月例会
日比谷公会堂(10日)
東京文化会館(16・18日)
産経ホール(19日)
グリンカ/歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ベートーヴェン/交響曲第7番
同/交響曲第5番
1962年
5/19・20 栃木労音5月例会 中央公民館
シベリウス/交響詩「フィンランディア」
同/カレリア組曲
モーツァルト/交響曲第40番
4/23~30 東京労音4月例会
文京公会堂(24日)
厚生年金会館(26日)
文京公会堂(29日)
日比谷公会堂(30日)
シベリウス/交響詩「フィンランディア」
同/カレリア組曲
モーツァルト/交響曲第40番
1961年
11/22 熱海労音11月例会 熱海市観光会館
シューベルト/交響曲第8番「未完成」
ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」
チャイコフスキー/交響曲第5番
11/19 秩父労音11月例会 秩父高校体育館
シューベルト/交響曲第8番「未完成」
ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」
チャイコフスキー/交響曲第5番
11/2 第5回定期演奏会 文京公会堂
シューベルト/交響曲第8番「未完成」
ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」
チャイコフスキー/交響曲第5番
4/25 第4回定期演奏会 共立講堂
ビゼー/「アルルの女」第2組曲
メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲
シベリウス/交響詩「フィンランディア」
ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」
1960年
11/28 第3回定期演奏会 大田区民会館
バッハ/組曲第3番
モーツァルト/交響曲第40番
5/15 熊谷労音例会 富士見中学校
ベートーヴェン/交響曲第1番
J.シュトラウス/皇帝円舞曲
イッポリトフ=イワノフ/酋長の行列
シューベルト/交響曲第8番「未完成」
1/12 上田労音例会 上田市公民館
モーツァルト/歌劇「劇場支配人」序曲
グルック/アウリスのイフゲニア序曲
シューベルト/交響曲第8番「未完成」
ベートーヴェン/交響曲第5番
1959年
5/17 会津労音例会 謹教小学校
ベートーヴェン/エグモント序曲
J.シュトラウス/ラデツキー行進曲
シューベルト/交響曲第8番「未完成」
ベートーヴェン/交響曲第5番
1958年
11/12 第2回定期演奏会 日本青年館
モーツァルト/歌劇「劇場支配人」序曲
同/アイネ・クライネ・ナハトムジーク
同/ピアノ協奏曲第26番「戴冠式」
同/交響曲第41番「ジュピター」
1957年
11/21 第1回定期演奏会 日本青年館
I 管弦楽
J.シュトラウス/ラデツキー行進曲
同/芸術家の生涯
グリーグ/ペールギュント第1組曲より「オーセの死」
II 合唱と管弦楽 世界民謡めぐり
III 管弦楽
ベートーヴェン/交響曲第5番
1966年~1975年の自主演奏会の記録
(指揮は特記なしは芥川也寸志)
1975年
12/8・9 第九特別演奏会 郵便貯金ホール
シベリウス/交響詩「フィンランディア」
ベートーヴェン/交響曲第9番
10/19 第30回定期演奏会 日比谷公会堂
ブラームス/大学祝典序曲
モーツァルト/ファゴット協奏曲
ブルックナー/交響曲第4番「ロマンティック」
指揮:山岡重信
ファゴット:前田信吉
8/9 サマーコンサート 東京文化会館
J.シュトラウス/喜歌劇「こうもり」序曲
同/「おしゃべり」ポルカ(トリッチ・トラッチ・ポルカ)
同/円舞曲「ウィーンの森の物語」
同/ポルカ「狩」
グールド/ラテンアメリカシンフォニエッタ
ムソルグスキー=ラヴェル/組曲「展覧会の絵」(*)
吹奏楽:瑞穂青少年吹奏楽団(*)
ツィター:河野保人
6/1 第29回定期演奏会「ストラヴィンスキー三部作」 渋谷公会堂
ストラヴィンスキー/舞踏組曲「火の鳥」(1919年版)
同/舞踏組曲「ペトルーシュカ」(1911年)
同/舞踏組曲「春の祭典」
ピアノ:渡辺達
4/23 新響鯨特別演奏会 文京公会堂
シューベルト/交響曲第8番「未完成」
モーツァルト/レクイエム
1974年
12/15 ペトルーシュカ(第28回定期演奏会) 東京文化会館
ベートーヴェン/交響曲第8番
芥川也寸志/絃楽のための三楽章
ストラヴィンスキー/舞踏組曲「ペトルーシュカ」
ピアノ:渡辺達
8/10・25 サマーコンサート 東京文化会館(10日) 神奈川県立音楽堂(25日)
ハチャトゥリアン/ガイーヌより第1組曲
ビゼー/カルメン第1組曲
同/「アルルの女」組曲よりファランドール
チャイコフスキー/舞踏音楽「白鳥の湖」より(ナレーション付)
おはなし:黒柳徹子(東京公演)、芥川也寸志(横浜公演)
5/17 芥川也寸志と弘中孝(新響名曲コンサート) 杉並公会堂
ベルリオーズ/ローマの謝肉祭序曲
ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第4番
ドヴォルザーク/交響曲第8番
ピアノ:弘中孝
3/31 新響とショスタコーヴィチ(第27回定期演奏会) 東京文化会館
モーツァルト/交響曲第35番「ハフナー」
ドビュッシー/牧神の午後への前奏曲
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番
1973年
12/19・21 新響第九特別演奏会 中野サンプラザホール
ワーグナー/楽劇「トリスタンとイゾルデ」より前奏曲と愛の死
ベートーヴェン/交響曲第9番
11/5 第26回定期演奏会 中野サンプラザホール
メンデルスゾーン/交響曲第4番「イタリア」
モーツァルト/ピアノ協奏曲第26番「戴冠式」
ストラヴィンスキー/舞踏組曲「火の鳥」
ピアノ:小栗豊
8/18 サマーコンサート 東京文化会館
ベートーヴェン/交響曲第6番「田園」
プロコフィエフ/ピーターと狼
ガーシュウィン/パリのアメリカ人
指揮:芥川也寸志、小林研一郎
語り手:浪花千栄子
3/24・25 チャイコフスキーの夕べ(第25回定期演奏会) 東京文化会館(24日) 神奈川県立音楽堂(25日)
チャイコフスキー/イタリア奇想曲
同/ヴァイオリン協奏曲
同/交響曲第6番「悲愴」
ヴァイオリン:徳永二男
1972年
12/15・17 新響・鯨特別演奏会”第九” 日比谷公会堂
ベートーヴェン/交響曲第9番
指揮:小林研一郎
11/12 第24回定期演奏会 東京文化会館
ベルリオーズ/劇的物語「ファウストの劫罰」より
モーツァルト/2台のピアノのための協奏曲
ベートーヴェン/交響曲第7番
ピアノ:池場文美、中井正子
4/2 第23回定期演奏会 東京文化会館
モーツァルト/交響曲第36番「リンツ」
ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第4番
ベルリオーズ/幻想交響曲
指揮:小林研一郎
ピアノ:遠藤郁子
2/7 新響新春特別演奏会 日比谷公会堂
バッハ=ストコフスキー/パッサカリアと小フーガ
メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲
マーラー/交響曲第1番
1971年
12/15・17 第九特別演奏会 日比谷公会堂
バッハ=ストコフスキー/パッサカリアと小フーガ
ベートーヴェン/交響曲第9番
10/28 第22回定期演奏会 厚生年金会館
芥川也寸志/交響管絃楽のための音楽
モーツァルト/フルート協奏曲第2番
マーラー/交響曲第1番「巨人」
フルート:澄川千津
8/10 サマーコンサート 東京文化会館
タイケ/旧友
メンデルスゾーン/結婚行進曲
チャイコフスキー/「くるみ割り人形」から行進曲
エルガー/威風堂々
ブリテン/青少年のための管弦楽入門
リムスキー=コルサコフ/交響組曲「シェエラザード」
指揮:芥川也寸志、小林研一郎
4/18・22 第21回定期演奏会 千葉県文化会館(18日) 虎ノ門ホール(22日)
バッハ/管弦楽組曲第3番
ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲第3番
ブラームス/交響曲第3番
ヴァイオリン:徳永二男
1970年
12/21・23 新響第九特別演奏会 共立講堂
バーバー/弦楽のためのアダージョ
ベートーヴェン/交響曲第9番
11/4 第20回定期演奏会 共立講堂
モーツァルト/歌劇「後宮よりの逃走」序曲
シューベルト/交響曲第5番
チャイコフスキー/交響曲第4番
指揮:外山雄三
8/20 サマーコンサート 東京文化会館
スッペ/喜歌劇「軽騎兵」序曲
オッフェンバック/喜歌劇「天国と地獄」序曲
ニコライ/喜歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
リスト/ハンガリー狂詩曲第2番
ヘンデル/「水上の音楽」組曲
グローフェ/組曲「大峡谷」
4/13 第19回定期演奏会 日比谷公会堂
リスト/交響詩「前奏曲」
ハイドン/交響曲第101番「時計」
ムソルグスキー=ラヴェル/組曲「展覧会の絵」
1969年
12/21 鯨・新響特別演奏会“メサイア” 厚生年金会館
ヘンデル/オラトリオ「メサイア」
10/27・11/2
熊本市民会館(10/27)
福岡市民会館(11/2)
J.シュトラウス/喜歌劇「こうもり」序曲
チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲
ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」
10/26~11/4 第1回九州沖縄芸術祭参加演奏旅行
琉球大学ホール(26日)
佐賀市民会館(29日)
長崎市民会館(30日)
大分文化会館(11/1日)
北九州市小倉市民会館(2日)
都城市民会館(3日)
鹿児島文化センター(4日)
J.シュトラウス/喜歌劇「こうもり」序曲
シューベルト/交響曲第8番「未完成」
ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」
8/4 サマーコンサート 東京文化会館
J.シュトラウス/喜歌劇「こうもり」序曲
同/円舞曲「ウィーンの森の物語」
チャイコフスキー/舞踏組曲「眠りの森の美女」から
グローフェ/組曲「ミシシッピ」
ロジャース/南太平洋
ポーター/カン・カン
レーウェ/マイ・フェア・レディ
合唱:東京混声合唱団
4/1 第18回定期演奏会 東京文化会館
J.C.バッハ/シンフォニア変ロ長調
ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第1番
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番
ピアノ:岡村梨影
2/2 特別演奏会(石岡) 石岡市市民会館
J.C.バッハ/シンフォニア変ロ長調
モーツァルト/交響曲第40番
ベートーヴェン/交響曲第5番
1968年
12/23・26 第九特別演奏会 日比谷公会堂
10/14 第17回定期演奏会 虎ノ門ホール
モーツァルト/歌劇「魔笛」序曲
同/交響曲第40番
同/モテット「おどれ、喜べ、なんじ幸いなる魂よ」
同/交響曲第41番「ジュピター」
指揮:近衛秀麿
ソプラノ:常森壽子
4/8 第16回定期演奏会 厚生年金会館
ブラームス/大学祝典序曲
メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲
ベルリオーズ/幻想交響曲
1967年
12/14 第15回定期演奏会 日比谷公会堂
コレルリ/合奏協奏曲ハ長調作品6の10
ドビュッシー/小組曲
ブラームス/交響曲第2番
9/25~10/3 ソビエト演奏旅行
ハバロフスク(25日)
イルクーツク(27日)
モスクワ(29、30日)
レニングラード(10月3日)
8/17 訪ソ記念新交響楽団特別演奏会 東京文化会館
伊福部昭/交響譚詩
カバレフスキー/組曲「道化師」より
芥川也寸志/絃楽のための三楽章
チャイコフスキー/交響曲第5番
4/17 第14回定期演奏会 日比谷公会堂
ベルリオーズ/序曲「ローマの謝肉祭」
ハチャトゥリアン/舞踏組曲「ガヤネー」第1番
レスピーギ/リュートのための古風な舞曲とアリア 第3番
ブラームス/交響曲第4番
1966年
12/19 創立10周年記念ベートーヴェン・チクルス第4回 虎ノ門ホール
ベートーヴェン/交響曲第8番
同/交響曲第9番
独唱:S常森壽子 A福島久貴子 T金谷良三 B常森闘士
合唱:東京プリマ・ヴォークス 日本合唱団
合唱指揮:岡田和夫 芥川也寸志
11/7 創立10周年記念ベートーヴェン・チクルス第3回 虎ノ門ホール
ベートーヴェン:序曲「エグモント」
同/交響曲第6番「田園」
同/交響曲第7番
10/2 創立10周年記念ベートーヴェン・チクルス第2回 虎ノ門ホール
ベートーヴェン/「レオノーレ」序曲第3番
同/交響曲第4番
同/交響曲第5番
9/5 創立10周年記念ベートーヴェン・チクルス第1回 虎ノ門ホール
ベートーヴェン/交響曲第1番
同/交響曲第2番
同/交響曲第3番「英雄」
4/4 第9回定期演奏会 日比谷公会堂
ボロディン:交響詩「中央アジアの草原にて」
伊福部昭:交響譚詩
芥川也寸志:絃楽のための三楽章
シベリウス:交響曲第2番
第201回演奏会のご案内
飯守—シューマン交響曲全集完結
シューマンはピアノ曲、歌曲および室内楽曲などにおいて健全なロマンあふれる多くの傑作を残していますが、晩年(と言っても40歳台で亡くなったのですが)は精神を病んで悲惨な最期を遂げたことでも有名です。そんなことからも、もえたぎる情熱を内に秘めた多面的性格の持ち主だったことが想像されます。完成された交響曲は4曲あり、若さあふれる第一番「春」、狂気が垣間見られる第二番、自由奔放な第三番「ライン」そしてベートーベンの交響曲第五番を思わせる緊密な構成の第四番とそれぞれ個性の異なる傑作ぞろいです。
新交響楽団では、シューマンに関して深い見識を持つ飯守氏のもと、これまでに第三番、第二番そして第四番の順番でとりあげてきました。どの演奏もシューマンの感情の襞を見事に表出した名演として聴衆の皆様から高い評価をいただいています。今回取り上げる第一交響曲は「春」と名づけられているように大変に明るい気分の交響曲です。シューマンの苦悩や狂気はほとんど感じられず、若々しい情熱がほとばしっています。まさに春の季節にふさわしい曲と言えましょう。飯守-新交響楽団におけるシューマン交響曲の締めくくりです、どうかご期待ください。
爛熟!究極のロマンティシズム
シェーンベルクの「ペレアスとメリザンド」
シェーンベルクというとメロディーも協和音も無い、砂を噛むようないわゆる“ゲンダイオンガク”の創始者と考えている方も多いのではないでしょうか。しかしながら、20代までの彼の曲は爛熟を極めたロマンティシズムにあふれています。それはワーグナーやマーラーをもはるかにしのぐ濃厚さです。今回取り上げる交響詩「ペレアスとメリザンド」もその時代の傑作です。転調を繰り返しながらつながってゆく長い旋律線はワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」を、また、一見脈絡のなさそうな複数の旋律を重ねることで屈折した感情を表現するあたりはマーラーの交響曲第9番の第1楽章を思い起こさせます。そして、それらの中にシェーンベルク独特のキラキラと光る宝石のような、そして思わずため息が出てしまうような美しい瞬間がちりばめられています。
この交響詩で取り上げている題材は、フォーレの劇音楽やドビュッシーの有名なオペラにも取り上げられているベルギーの作家メーテルランクの戯曲です。「王子ゴローはあるとき森にいた謎の娘メリザンドを見つけて城に連れ帰り妻にするが、メリザンドはゴローの弟ペレアスと惹かれあってしまう。ゴローはそれに気づき嫉妬に狂い、ペレアスとメリザンドの逢引きに乱入してペレアスを刺殺、メリザンドは城に連れ戻されるが傷心のうちに亡くなる.」 という粗筋です。全体を貫く雰囲気は大きく異なりますが、道ならぬ恋愛という点では「トリスタンとイゾルデ」に共通する要素を見出すことも可能でしょう。シェーンベルクはフォーレやドビュッシーとまったく異なる雰囲気の響きを作り出し、ペレアスとメリザンドの恋愛をまるでトリスタンとイゾルデの恋愛のように濃厚かつ官能的に、また最後は弟を殺してしまうゴローの苦悩と嫉妬を執拗にそしてどす黒く表現しています。
前回新響に登場した2006年11月には驚異的なカリスマ性で新響を導き、トリスタンとイゾルデでの名演を成し遂げた飯守氏のもとで再びどんな名演奏が生み出されるのか、ぜひともご期待ください。
曲目解説プログラムノート
芥川也寸志:交響三章
「第200回演奏会の曲目は芥川、黛、そしてストラヴィンスキー作品に決定」と聞いた時、芥川也寸志先生に20年間お世話になった古参団員の私は、「黛もストラヴィンスキーも新響創立者の先生に密接に関係があった作曲家だから記念碑的演奏会にふさわしいプログラミング、ただ、来年の『芥川没後20年』プロの選択肢が狭まるな」と感じた(以下、敬称略)。
黛敏郎は東京音楽学校(現東京藝術大学)で芥川の1年後輩で共に伊福部昭の弟子。この二人は芥川の1年先輩だった團伊玖磨と「三人の会」を結成、プロ・オケを使って自作を自ら指揮する演奏会を5回開いた。(二人ともに名声を確立した後、政治的には、芥川は社会党を支持し反核運動を指導した左派、黛は三島由紀夫と親交があった右派だった、というのが興味深いが)。
ストラヴィンスキーについては、芥川は幼少の時「火の鳥」と「ペトルーシュカ」のSPレコードを何度も聴き、「火の鳥」の子守歌を口ずさみながら幼稚園に通ったという、芥川音楽の原点ともいうべき作曲家である。芥川は新響で、1973年にまず「火の鳥」を取り上げ、翌年「ペトルーシュカ」、そして1975年には「春の祭典」を加えて、念願だった「ストラヴィンスキー三部作一挙上演」を3年がかりで果たした。
私が40年前に新響に入団したとき先生は43歳の若さだったが、音楽家の枠を超えた文化人としてすでに超有名で、その後も超人的な活動を続けられた。没後20年が近づいた今、芥川先生を直接知る新響団員は少なくなり、マスコミで取り上げられることも殆どなくなってきた。「交響三章」解説のあと、彼の著書を引用しながら波乱の生涯と豊かな人間性の一端を紹介させていただきたい。
「交響三章」について
芥川は1941年16歳の時、音楽の道に進むことを決め、東京音楽学校教授だった橋本國彦に作曲を師事した。43年同校に入学するが、翌44年学徒動員で陸軍戸山学校軍楽隊に入隊、終戦後の翌年学校に戻り、作曲科講師として赴任してきた伊福部昭に心酔して弟子入りする。1948年(23歳)にこの「交響三章」を作曲、翌年自ら東京フィルハーモニー交響楽団を指揮して放送初演した(舞台初演は1950年の尾高尚忠指揮NHK交響楽団)。橋本の叙情性、伊福部やストラヴィンスキーのオスティナート(短い動機の執拗な繰り返し)趣味と野性味、そして芥川特有の明るさを兼ね備えた彼の「青春交響曲」である。1950年作曲の「交響管絃楽のための音楽」、53年の「絃楽のための三楽章」とともに、いずれも若々しさに溢れた初期の三部作と言える。1954年、29歳の彼はこれら3曲の楽譜を携えて国交がなかったソビエトへ不法入国し、ショスタコーヴィチ、ハチャトゥリアン、カバレフスキー等の知遇を得る。この時、「交響三章」は当地で初演され、楽譜も出版された。
第1楽章
カプリッチョ(奇想曲)2/4拍子 アレグロ 約5分
ファゴットの8分音符の刻みにのってクラリネットが16分音符中心の軽妙・流麗で狭い音域でしか動かない愛らしい主題を提示する。この主題はその後フルート、ヴァイオリンに受け継がれた後、シンコペーションが印象的な、躍動感溢れる第2主題がヴァイオリン、木管によって示される。展開部はピアノが口火を切り、リズム遊びの様相を呈し、ファゴットとチェロによる第3主題がヴァイオリンに受け継がれる。再現部はピアノ伴奏にのってフルートが第1主題を奏し、幾度か盛り上がった後、木管楽器だけになってさりげなく終わる。
第2楽章
ニンネレッラ(子守歌)4/4拍子 アンダンテ 約11分
ファゴットが第1の子守歌を吹き、この主題はクラリネット、フルート、ヴァイオリンに移調しながら受け継がれる。中間部はオーボエが第2の子守歌を奏し、ヴァイオリンや他の楽器も加わって盛り上がっていく。再現部はトランペットが第1主題を奏し、他の楽器に綿々と引き継がれ、やがて消えていく。長女誕生の喜びを歌った楽章、という説がある。
第3楽章
フィナーレ(終曲)4/4拍子 アレグロ・ヴィヴァーチェ 約6分
冒頭2小節の6つの音は全楽器による派手なテュッティー。その後、脳天気ともいえる明るい流麗な主題が木管、ヴァイオリンで奏され、この旋律は何度も繰り返される。やがて第1楽章のリズム遊びを彷彿させる5/8拍子の強烈なリズム動機が現れ、中声部の軽快なリズムが発展した第2主題をヴァイオリンが奏する。これらの主題や動機はその後執拗に繰り返され、陶酔的熱狂で曲を閉じる。
芥川也寸志の生涯とエピソード(「」内は著書より引用)
幼少時
1925年(大正14年)7月12日、文豪・芥川龍之介の三男として東京田端に生まれる。1927年の父の自殺後、長兄・比呂志(後に俳優)、次兄・多加志(1945年ビルマで戦死)と「火の鳥」のレコードをBGMに、「アマゾン河の探検」という寸劇を演じた。
「幕に見立てた襖が開けられてレコードが鳴り出すと、いつも母はお義理でパチパチと手を叩いた。八畳の間の中央には座蒲団が三枚ほど並べられ、これがアマゾン河に浮かぶ探検隊の舟である。もちろん、兄は舳先に立って、槍か何かのつもりで、いつも箒を右手に持っている。次男の多加志はどんな時も地味な役回りで、一生懸命舟を漕ぐしぐさをする。そうこうするうちに私の出番がやってくる。私の役はいつもワニである。ストラビンスキーの音楽にのり、腹ばいになって座蒲団の舟の方に近寄っていく。やや間があって、兄は『ヤアッ』と言って箒の柄を私の背中に突き立てる格好をする。間髪を入れず、私は『ギャーッ』と言って今度は仰向けになり、手と足をバタバタとやって瀕死のワニを演じ、この芝居ごっこは幕となる。」
音楽学校・軍楽隊
16歳の時、音楽の道に進むことを決め、橋本國彦の紹介で井口基成にピアノをバイエルから習う。1943年、東京音楽学校に合格(18歳、晩学だったので成績はビリだった)するが翌年、学徒動員で陸軍戸山学校軍楽隊に入隊、あらゆるビンタを体験した。
「始めのうちは殴られる毎に口から血を吐いて、ろくに食事も出来なかったものが、日を追って殴られ方が上手になり、しまいには、どんなに殴られても痛みを感じなくなった……(略)……。私にとってビンタは、勿論厭なものではあったが、何百回と殴られていくうちに、少なくともこわいものではなくなった。」
終戦直後の苦労
1945年4月軍楽隊を首席で卒業後、終戦で家に戻った芥川は生活のため(龍之介の作品の印税収入が途絶え、母の生活は苦しかった)ヴァイオリンを担当して友人と小さなバンドを作り、進駐軍キャンプ等でアルバイトをした。
「初めて自分で稼いだ金で買ったのは、母に食べさせようと思ったシューマイ三個であった。忘れもしない、有楽町のガード下、露店商人の景気のいい呼び声に誘われたのだが、当時のこととて、包み紙などなく、新聞紙に直接くるんであったので、車庫を降りるまでは確かに温もりを感じていたのに、家に着いてみると、持っていたのはヴァイオリンのケースと穴のあいた新聞紙だけで、肝腎のシューマイがない。私は蝋燭を頼りに駅から家までの路を探し、とうとう三個とも見つけた。そのシューマイを洗って食べた母は涙を流したが、多分うれしかったのではなく、悲しくて仕方がなかったのだろう。」
ストラヴィンスキーとの唯一の(?)対話
芥川は「肉体的欲望と精神的欲望が同時に高進するタイプの作曲家の書斎は明るく窓が大きいが、そうではないタイプは部屋全体が暗く、窓は小さいか全くない」という私見を持っていた。二十世紀最大の作曲家、ストラヴィンスキーが1959年に訪日した時、機会を見計らってこの巨匠に尋ねた。
「『先生の書斎は大きな窓があって、とても明るいでしょう?』
『私の仕事部屋はサンルームで、壁も天井もみんなガラス張りです。』
高校野球と校歌
芥川は高校球児のひたむきさを愛した。校歌を作曲した高校(彼は校歌や社歌を100曲近く作曲した)が甲子園に出場したので、自分の曲が演奏されるかもと期待していたのに初戦で負けてしまった。NHKの番組でパートナーだった作詞家なかにし礼にこの口惜しさをぶつけると、「負けた方の校歌をやるべき」と事もなげに言った。
「これはいい。確かにいい。健闘を讃え、敗者の歌をうたう。そうすれば、出場校全部の校歌が聞けるし、決勝戦の試合終了後だけ、敗者の歌の後に、優勝校の校歌をスタンド全員の大合唱で歌って、ともに祝ってあげればいい。」
ワイン通・食通・女性通(?)
「フランスでは、よくワインを女性にたとえて批評するが……(略)……、若さを通り過ぎて老けに入る一歩手前のところが絶妙だと言われる。」
「魚の料理に限らず、牛肉にしろ、果物にしろ、この理屈は同じことで、素材の味を本当に味わうためには、煮ごろ、焼きごろ、食べごろが何より大切である。」
「美貌と言われる女性をよくよく観察すると、ただ単に目鼻立ちが整っておる、というだけの場合は、ほとんどないと言っていい。凄い美人になると、むしろどこか狂っていて、もう少し狂いそうなものなら、とんでもないことになる、という寸前でとまっているのがほとんどである。」
1989年(平成元年)逝去
肺癌のため1月31日逝去、享年63。大正・昭和・平成を駆け抜けた(昭和は1926年12月25日―1989年1月7日)短かすぎる一生で、黛は「芥川也寸志の最後は壮烈な文化への戦死であった」と述べた。
参考文献
『ぷれりゅうど』芥川也寸志著(筑摩書房 1990年初版)
初 演:放送初演 1948年9月26日、NHKラジオ「現代日本の音楽」芥川也寸志指揮 東京フィルハーモニー交響楽団(初演時タイトル「交響的三楽章」)
ステージ初演 1950年10月26日、尾高尚忠指揮日本交響楽団(現NHK交響楽団)
楽器編成:フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン2、ティンパニ、小太鼓、大太鼓、ピアノ、弦5部
黛 敏郎:バレエ音楽「舞楽(BUGAKU)」
■左と右の話
秦の都だった咸陽、九つの王朝が都とした洛陽や旧奉天の瀋陽のように、中国の地名に良く見かける「陽」の文字。この字には「川の北側」の意味がある。古来人々が住みやすい地の条件は、水の便があって日当たりが良いところと決まっている。この条件を満たす地は、突き詰めて考えてみれば「東西に流れる川の北側」となる。それが「陽」である。
この陽に人々が集まりやがて街ができる。権力を持つものが居と定めるのはこの街で最も日当たりが良いところ、すなわち北側の奥。北に居を定めるものは臣下に閲するとき、必然的に南を向く。「天子は南面す」……『易経』にある言葉がこれである。
臣下は左右に分かれて控える。南面する天子から見て左側が東。日の昇る方角であり、こちらが上席なのは現代の相撲の世界をみても解ろう。すなわち東と左が一体となり、西と右の結びつきに対して優位となる。例えば左大臣の方が上席である。
この考えは日本にも制度・文物共々そのまま伝わっている。雅楽の世界も勿論例外ではない。ここに「左楽・右楽」という一対のものがある。左楽は中国からダイレクトに伝わってきた音楽であるのに対し、右楽は朝鮮や渤海を通じてわが国にもたらされた。更には日本で独自に発達した音楽も、右楽に入れられている。中国より伝えられたものを「正式・正統なもの」として左に位置づけ、右楽はそれに比べ、ややくだけたものとの感覚があるのかもしれない。
この音楽に合わせての舞が生まれる。この場合「左舞・右舞」となる。右といい左といっても、これは相対的な位置関係に過ぎない。すなわち両者が対になって初めて成立する関係であるから、いずれかの一方のみの舞で終わるということはなく、必ず左右一対の舞となって構成されるのである。古来舞楽はこうした由来も性格も異なるふたつの世界を一対に置き、対立ではなく対比の妙を以って演じられ続け、伝えられてきた。黛敏郎の『BUGAKU』を考える上で、この事はまず念頭におく必要がある。
■バランシンの事
ここでバランシン(George Balanchine 1904・サンクトペテルブルク~1983・ニューヨーク―注1)なる稀代の振付家に触れなければならない。バランシンは革命前のロシアに生まれ、母親の影響下にあった幼児期よりピアノに習熟し(地方廻りであまり家にいない父親は作曲家だった)、10歳で舞踏学校へ入学したのを契機に、バレエ界の人となる。舞踏そのものの成績はぱっとしなかったが、ある機会に振付けを任されて、自己の才能を知ることになる。13歳で革命に遭い、20歳の折り(1924年)に曲折を経てパリに出る。斯界の大立役者たるディアギレフに出遭う事で、その後の人生が決定づけられたと言ってよい。彼の主宰するロシアバレエ団(バレエ・リュス)のバレエマスターとして斬新な振付けを以って一世を風靡する事となった。ストラヴィンスキーの『アポロの率いるミューズ』がバランシンの出世作となり、以後この作曲家との根強い交流の契機となった。
ディアギレフの死後渡米。ハリウッドでミュージカルの振付けで成功するが、「純粋な」バレエを目指すこの振付家にとっては不本意な日々と言えた。1944年その彼にニューヨーク・シティ・バレエ設立の話が持ち上がり、ここで初めてアメリカでのバレエの基盤を完成させた。爾後米国に於けるバレエの発展はこの振付家の貢献による。ストラヴィンスキーの渡米後のバレエ音楽は、全てバランシンとの仕事の成果であり、『オルフェウス』や『アゴン』はとりわけ名高い。
その赫々たる経歴によって米国舞踏界の重鎮となったバランシンが、ふたつの条件をつけて黛敏郎に作品を委嘱した。1960年の事である。それは雅楽の響きを主体とした作品である事と、ストーリーを持つ必要はない事の2点である。雅楽の響きを求めるという点については、バランシンの発案というよりは、渡米当初からの彼の援助者であった、リンカーン・カースティンの日本趣味によるものと言えなくはない。事実この企画は彼が推進した計画だった。(注2)
ストーリーを伴わないバレエとは、謂わば「純粋な」舞踏となるが、若い時分には作曲家を志望さえした自らの素養から、音楽に於けるストーリー性や絵画的要素による制約を極力排除し、舞踏の純粋性を常に追及していたこの振付家にとっては、至極当然の事だった。「努めてバレエ的な音楽でなく、純粋な演奏会用の音楽のつもりで」「雅楽にみられるような、非常にデリケートな音と音とのからみあう、対位法的な音楽」にして欲しいというのが、米国滞在中の作曲者に直接伝えられた要望だった。
■作曲家と振付家の領域
熟慮の末、黛敏郎がこの条件下で行き着いたのは、雅楽と舞踏との融合である舞楽だった。舞楽としての性格を考えれば左舞と右舞という、伝統的な構成による対照を際立たせたいと企図した筈である。先達である早坂文雄の作品『左方の舞と右方の舞』も当然念頭にあったろう(1958年に初演された彼の『涅槃交響曲』が早坂氏に捧げられている事を忘れてはならない)。
雅楽といい舞楽と言うが、室内での演奏を基本とした純音楽的な雅楽と、屋外での舞を主体とする舞楽では、楽器の編成をひとつみても異なる。後者の場合は音量の無い絃楽器は用いられない。「管絃」のうち絃を欠き、左舞の場合は篳篥・龍笛・笙と打楽器のみで演奏される。更に右舞になると笙も省かれる。ここまで徹底して「伝統」を踏襲してしまうと、依頼者の意図した雅楽のデリケートな響きは勿論失われてしまう。とすれば、舞楽に於ける左右の舞という二部構成のスタイルを採用しつつ、雅楽の楽器編成を保って玄妙な響きを再現するという選択に至らざるを得なかった。だが、この選択によって作品は伝統的な制約を超えた普遍性持ち得たと言えるだろう。作曲者が『舞楽』ではなく、敢えて『BUGAKU』と名づけた意味もそこにある。
第一部は雅楽に於ける音合わせに当たる「音取」の様式(注3)によって開始される。かなり忠実な再現と言えるが、5音音階(ペンタトニックス)こそ東洋の音との固定観念のある彼の地での評では、サイレンだとか猫の鳴き声だと書かれたと言う。現地のオーケストラが単に譜面を追って演奏しただけでは、本当にそんなものにしかならなかったかも知れない。その後は楽器が重なり、ピアノと打楽器による特徴的な旋律によって左舞的な要素(早拍子)が散りばめられた末に、楽筝の手である「閑掻」に基づくと思われるモチーフが現れる。高潮の果てにやがて次第に楽器が減り、開始の音量まで退潮して終わる。
第二部は右舞の楽器編成を踏襲し、打楽器を主体として音楽が進む。やがて笛(オーボエやピッコロ)による旋律が繰返されるが、これは本来右舞ではなく、左舞に属する『蘭陵王』に由来し、原曲をかなり忠実に再現している。例えば突然ピッコロに現れる諧謔的なフレーズは、非常に現代的な印象を与えるが、これは原曲を忠実に模した結果である。このように作曲者は素材となる音楽が「左舞」「右舞」いずれに属するかにはこだわっていない。むしろそうした音楽の再現からは離れ、一対のスタイルの対照と雅楽の響きこそが関心の的であった事の証左と言えよう。
もちろん第二部の音楽は第一部に比較すると、テンポや曲想にも「序破急」の要素が明確に示され、「右舞」的な要素に満ちている。締めくくりには第一部にあった「閑掻」の旋律が再現され、雄渾な終局を迎える展開となっている。
さて、この音楽に対するバランシンの「作品」はどのようなものであったか? 万難を排して初演の前夜にようやくニューヨーク入りした黛敏郎は、文字通りのぶっつけ本番でそれを目の当たりにする事になる。
朱と緑とで彩って単純化した舞楽の舞台は、音楽が始まっても暫しの間無人のまま。やがて現れたのは白タイツに唐傘型に広がったピンクのチュチュを着て、髪を東洋風に結い上げて簪をさした5人の女。そして同じ白タイツに直垂風の上衣をまとい、丁髷のカツラを乗せた5人の男である。「日本人が見れば、いろいろ文句も出てくるが、伝統的なバレエコスチュームと日本趣味とを、これだけ違和感無く調和させる事は並大抵ではなかったろう」と作曲者は書いている。
実際の振付けはというと、例えば第二部の「急」では、女が片脚を男の肩の上まで上げたまま抱き合って傾斜したり、男にかかえられた女が観客の方に向かって両脚を大きく開いたり……といった場面が現れるなど、かなり思い切ったものだった。「思い切った」は「官能的な」と言えばまだしも品位を保てるが、いっそ「きわどい」の語に置き換えても良いだろう。これはこの作品に限った事ではなく、ストーリーに依存しないバランシンの振付けの特徴のひとつではあった。とはいえ、ニューヨーク・シティ・バレエに新作が乏しかった1963年のシーズン、『BUGAKU』の上演は毀誉褒貶に満ちたものとならざるを得なかったのである。
黛敏郎はこうした振付けが自分の作品から導き出されるとは全く予期していなかった。そして「私たちが静謐の美と感じていたものに、思いもよらぬ官能の匂いを嗅ぎとったバランシンの鋭敏な感覚に、あらためて何か貴重なものを教えられた気がする」と述懐している。
これを作曲家の真意と受け取るべきかどうかは難しい。生み出した作品が異国のオーケストラの演奏に委ねられ(既にここに違和感が生じる可能性は充分すぎるほどある。『BUGAKU』のようなデリケートな作品が、譜面だけで伝えられる情報には限りがあり過ぎる)、況してや異国趣味の衣装とこれ見よがしの露骨とさえ言える振付けとを突然見せ付けられれば、清浄な神域を土足で踏みにじられたと感じる事さえ想像に難くない。況してやそれは1200年以上も前に日本人が採り入れ、咀嚼し、ずっと磨き上げてきた左舞・右舞という、実際に神事にさえ深く関わってきたスタイルに基づく作品である。それを浅薄な「官能性」などで片付けられたくはないと考えても不思議はない。もしリハーサルに立会い、この実態を事前に知り得ていれば抗議もし、修正も試みたかも知れない。だが全ては後の祭りだった。作品はこの初演の3年後の1966年に第15回尾高賞を受賞しているが、バランシンの振り付けを含めた作品として捉えれば、日本での評価とは裏腹に、作曲者の胸中には忸怩たる思いがあっても不思議はない。
彼はバランシンとの間で次なるバレエ……ことさらに日本的ではないバレエ……が計画されており、どんな振付けがなされるかが楽しみだとほのめかしている。だがこれが実現する事は結局なかった。
一方の振付家はどうか? バランシンは死後すぐに伝記がまとめられている。400ページに上る浩瀚なその書にMayuzumiの名が登場するのは1回、しかも『BUGAKU』に関する記事ではない。振付家志望の若いダンサーが、自分の振付けに際して黛敏郎の曲を使った。バランシンにその感想を求める。
「ひどいよ。あの曲はだめだ」「でも、あなたはマユズミがお好きなんじゃないんですか?」「そう昔はよかった。でも、もう彼の時代は終わったんだ」(注4)
これは1973年、すなわち『BUGAKU』初演から10年後の会話である。この時対象となった黛敏郎の作品は不明だ。但し両者の亀裂が決定的であった事は容易に伺えよう。ふたりの間に何があったのか?は書かれていない。だがその齟齬の直接の契機が、10年前の『BUGAKU』初演時に既にあったと僕は考える。(注5)
本来生まれも伝来のルートも異質な両者を、左右に分けつつも対比の妙によってひとつの世界を創り上げた日本人の智慧は、黛敏郎とバランシンという強烈な個性の間には、所詮成り立つものではなかったのだ。
(注1)バランシンはパリへの亡命後、ディアギレフの要請による改名で、本名はゲオルギイ・バランチヴァゼ(Georgy Balanchivadze)という。グルジア系の姓。
(注2)この前年の宮内庁楽部による雅楽の公演がニューヨークで行われており、バランシンやカースティンが雅楽を直接に知る契機となった。
(注3)雅楽の音取は演奏される曲目の調子によって、厳格なスタイルが決められており、これから奏される音楽の序曲にも相当する。舞楽の場合は舞人の入退場の際に奏される。この場合は「調子」と言う。
(注4)原文は以下の通りである。“Awful!”replies Balanchine.“The music is awful.”“But I Thought you liked Mayuzumi.”In 1963Balanchine had used mayuzmi's music for his ballet,Bugaku.“He used to be all right. Now he's passé”With a sniff and wave of the hand, Balanchinedismisses Mayuzmi.
(注5)因みに言えば、1983年に出版されたこの伝記のくだりを黛敏郎が生前に読む可能性は充分にあった。作曲家のコメントは残っていない。
参考文献
『雅楽入門』増本伎共子著(音楽之友社)
『Balanchine, a biography』
Bernard Taper(University of California Press)
『バランシン伝』長野由紀訳(新書館)
『バランシンとバレエ“BUGAKU”』
黛敏郎(音楽芸術1963年6月号)
『名曲解説全集7』“BUGAKU”の項
布施芳一(音楽之友社)
『音楽大事典』「雅楽」の項(平凡社)
初 演:1963年3月20日 ロバート・アーヴィング指揮 ニューヨーク・シティ・バレエ
楽器編成:フルート2、ピッコロ、オーボエ2、コールアングレ(3番オーボエ持ち替え)、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、シンバル、タムタム、木琴、鉄琴、鈴、ピアノ、ハープ、弦5部
ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」
「春の祭典」(Le Sacre du Printemps(仏)、The Rite of Spring(英)、通称:ハルサイ)は、ロシアの作曲家イーゴリ・ストラヴィンスキーが作曲したバレエ音楽である。「春の祭典」という言葉の響きからは、華やかで賑やかなイメージが連想されるところだが、その内容は「春の祭祀」と訳したほうが適切ではなかろうかというくらい、「クラシック音楽」の枠からはみ出そうなほどセンセーショナルなものとなっている。私も、初めてこの曲を聴いたときの衝撃をはっきりと覚えている。そして、今ではハルサイを聴くと身体が勝手に反応してしまう、そのくらいこの曲に魅了されている。
以下では、この「春の祭典」について、「楽しく、わかりやすく、そしてためになる(?)曲目解説」をめざして進めていきたい。
1 はじめに
バレエ音楽「春の祭典」について
「春の祭典」は、1913年に完成し、同年5月29日にパリのシャンゼリゼ劇場にて初演された。
この初演時の“大騒動”は今日でもよく知られており、これまでのバレエ作品とは全く異なる過激な内容に対し、パリの聴衆は激怒した。当時の新聞には「春の虐殺」(Le“Massacre”du Printemps)という見出しが躍るなど、一大スキャンダルにまでなったのだが、それはこれまでのバレエの伝統を破壊するものだと受け止められたからである。しかし、翌年の演奏会形式での再演では、純粋な音楽作品として大成功を収め、評価を確立するに至った。
このバレエのあらすじは、以下に引用するようなストラヴィンスキー自身のアイディア(霊感とも言っている)を友人である画家ニコラス・レーリッヒに伝え、共に作り上げたものである。
「突然、荘重な邪教徒の祭典という構想が頭に浮かんだ。輪を描いて座った長老たちがひとりの若い娘が死ぬまで踊るのを見守っていた。彼らは春の神の心を和らげるために彼女を犠牲にしていたのである……。」(ストラヴィンスキー『自伝』より)
スコアには、「ストラヴィンスキーとレーリッヒによる2部からなるロシアの異教徒の情景」という副題が記されており、前半(第1部 大地礼賛)と後半(第2部 いけにえの儀式)の二部で構成されている。
ストラヴィンスキーについて
ここでは、ストラヴィンスキーという人物を理解するに当たり、3つのポイントを挙げることにしよう。
(1)3つの作風
ストラヴィンスキーは、ちょうど画家ピカソにおける「青の時代」、「バラ色の時代」といったように、人生の中で「原始主義時代(=肉感的な音響で、聴く者に興奮を喚起)」、「新古典主義時代(=バロック音楽へ回帰し、新しい普遍性を創造)」、「十二音技法時代(=オクターブ内の12の音を均等に使用)」という3つの作風を築いている。例えば、彼の作品でも「ペトルーシュカ(原始)」と「管楽器のための八重奏曲(新古典)」では、本当に同じ作曲家の作品なのか?と思ってしまうくらいに違っており、多彩で多様な作曲様式を持つ作曲家であったことが分かる。
「春の祭典」は、このうち「原始主義時代」の末期頃に創作したもので、まさに原始主義音楽の頂点に位置するような“血沸き肉踊る作品”である。
(2)ディアギレフの存在
ディアギレフ(1872―1929)は、ロシア・バレエ団の創設者として名高い芸術プロデューサーであり、名だたる作曲家に歴史に残るバレエ音楽の傑作を委嘱した。
ストラヴィンスキーのバレエ三部作「火の鳥」「ペトルーシュカ」「春の祭典」は、いずれもディアギレフが彼に対し委嘱したものであり、まさにディアギレフあっての作品だといえよう。(ちなみに、ラヴェル「ダフニスとクロエ」、プーランク「牝鹿」もディアギレフの委嘱作品である。)
(3)師匠リムスキー=コルサコフ
リムスキー=コルサコフ(1844―1908)は、「色彩的な管弦楽法の大家」と言われており、多くの作曲家から模範として称えられている存在である。管弦楽法とは、オーケストラの楽譜を書くための技法のことであり、例えば「かえるの歌」でも、管弦楽法の大家がオーケストラ用に編曲すると、驚くほど感動的な作品になる(はずである)。
ストラヴィンスキーは、師匠の影響を非常に強く受けており、特にバレエ「火の鳥」においてそれを垣間見ることができる。しかし、この「春の祭典」では、さらにそこから一歩踏み込み、ロシアの民族音楽を取り込みながら、独自の世界を表現している。
2 「春の祭典」をもっと楽しむために
さて、以下では「春の祭典」をよりいっそう楽しく聴いていただくための、いわば道案内的な内容で進めていくことにしたい。
~ 観て楽しむ~
「春の祭典」の大きな特徴は、まず「楽器編成が巨大なこと」、そして「特殊楽器が活躍すること」ではないかと思う。舞台をご覧いただきたい。前半の2曲に比べ、ステージ上の人口密度も急激にアップしていることがお分かりいただけるだろう。そして、普段は見慣れないような楽器があることに気付かれるだろう。
この「春の祭典」では、アルトフルートやバストランペットなど、一般には珍しい楽器が力強く印象的なソロを奏でるほか、バスクラリネットやコントラファゴットといった、普段は1本で十分な楽器が2本も使用されており、この曲の複雑な響きに一役買っている。特殊楽器に注目しながら聴くのもこの曲の楽しみのひとつである。
そして、これら大編成オーケストラを束ねる指揮者にぜひご注目いただきたい。この複雑怪奇な曲をうまく“交通整理”するためには、高度な技術を要する。変拍子における指揮棒さばきは、まさに見モノである。近年、この「春の祭典」は、演奏時間も約33分と適当なことから、指揮者コンクールの課題曲に選ばれることもあるらしい(『のだめ』に登場する千秋真一もきっと振ったことだろう)。
~ 生演奏を楽しむ~
「春の祭典」は、自宅のスピーカーで聴くよりもコンサートホールで生演奏を聴くことをぜひお薦めしたい曲である。本日は、怒涛の大爆音から静謐な弱音まで、オーケストラも頑張って演奏するので、どうかご堪能いただければと願っている。
曲の詳細な構成と目安時間、聴きどころは、次のとおりである。
第1部 大地礼賛(16分)
1. 序奏(3分30秒)
ファゴットの怪しげな旋律から始まり、特殊楽器を含む様々な管楽器のソロが異様な雰囲気を醸し出す。
2. 春のきざし(3分20秒)
弦楽器による強烈な刻みから始まり、躍動感あふれる音楽が春のきざしを表現する。
3. 誘拐(1分15秒)
突如速い3拍子となり、変拍子も入り乱れる激しい音楽となる。演奏困難箇所のひとつ。
4. 春のロンド(3分45秒)
大小2つのクラリネットが「出た出た月が~♪」の歌に似た旋律を歌う。太古の春の雰囲気が漂う音楽である。
5. 敵の部族の遊戯(1分50秒)
春の雰囲気から一転して、胸騒ぎのするような音楽となる。雰囲気が異なる2つの旋律が、絡み合いながらも面白く展開されていく。
6. 長老の行進(1分)
低音のリズムに乗って、テューバが重々しい旋律を演奏する。
7. 長老の大地への口づけ(10秒)
突然静けさが訪れる。ここは長老(賢人)たちが大地を称えて拝むシーンである。
8. 大地の踊り(1分10秒)
ストラヴィンスキーの「生命が脈拍のある時存在するように、音楽はリズムのある時存在する」という言葉を端的に表した曲。静けさを打ち破る大太鼓のソロにつづいて、力強い3拍子のテンポに乗って大きなクライマックスを築く。
第2部 いけにえの儀式(17分)
1. 序奏(4分15秒)
極めて神妙で意味深な曲の始まりが、陰鬱な異教徒の夜を暗示する。大地が呼び覚まされ、いけにえの乙女をこれから選びださねばならないというシーンである。
2. 乙女の神秘的な踊り(3分15秒)
乙女たちが集まって、いけにえを選び出すシーン。ヴィオラによる美しい旋律にご注目を。終盤に登場する、弱音器をつけたトランペットの旋律が、いけにえが誰に決まったかを告げているかのようだ。
3. 選ばれしいけにえへの賛美(1分30秒)
11発の強打音の後、リズムと拍子が激しく変化し、恐怖に満ち満ちた曲が始まる。華麗なる指揮棒さばきにご注目いただきたい。
4. 祖先の召還(30秒)
いけにえを祭るために祖先の霊を呼び覚ますシーン。一種不気味なコラールである。
5. 祖先の儀式(3分15秒)
けだるく、ミステリアスな音楽が展開されていく。コールアングレ、アルトフルート、バストランペットのソロが、この曲の雰囲気を絶妙に醸し出す。
6. いけにえの踊り(4分15秒)
バスクラリネットのソロが呼び水となり、いけにえの苦悩と興奮を表現するような切迫したモチーフが奏される。最後は、一瞬の沈黙の後、踊り倒れたいけにえの乙女が神にささげられるシーンで幕を閉じる。
~ 演奏会後、ご自宅でも楽しむ~
もし、この演奏会で「春の祭典」が気に入ったら、もしくはあまりにひどくて口直ししたい(!)という場合は、ぜひご自宅でも鑑賞してみてはいかがだろうか。
巷には、「春の祭典」の名盤があふれているが、個人的には色彩豊かなピエール・ブーレーズ指揮クリーブランド管弦楽団のCDをお薦めしたい。また、映像資料としては、「Keeping Score」というシリーズで、ティルソン・トーマス指揮サンフランシスコ交響楽団のDVDが頒布されている。詳しい解説もあり、楽しめる1枚である。
~ 最後に~
200回の節目の演奏に「春の祭典」を取り上げることとなり、演奏者冥利に尽きるというものである。
今日は、精一杯努めたい。本日の演奏をきっかけに、「春の祭典」とストラヴィンスキーにご興味を持っていただければこの上ない幸せである。
参考文献
『作曲家別名曲解説ライブラリー25 ストラヴィンスキー』(音楽之友社)
『ストラヴィンスキー 二十世紀音楽の鏡像』船山隆著(音楽之友社)
『ストラヴィンスキー』ヴォルフガング・デームリング著・長木誠司訳(音楽之友社)
初 演:1913年5月29日 ピエール・モントゥー指揮ヴァーツラフ・ニジンスキー振付によるロシア・バレエ団公演(パリ・シャンゼリゼ劇場にて)
楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、ピッコロ、アルトフルート、オーボエ4(4番はコールアングレ持ち替え)、コールアングレ、クラリネット3(3番はバスクラリネット持ち替え)、Esクラリネット、バスクラリネット、ファゴット4(4番はコントラファゴット持ち替え)、コントラファゴット、ホルン8(7番・8番はワーグナーテューバ持ち替え)、トランペット4(4番はバストランペット持ち替え)、ピッコロトランペット、トロンボーン3、テューバ2、ティンパニ2、大太鼓、トライアングル、タンブリン、タムタム、ギロ、アンティークシンバル、弦5部
熱いハートとクールな頭脳で―― 新響万歳!
1913年の衝撃的な「春の祭典」初演から既に百年に近く、そして團伊玖磨、芥川也寸志、黛敏郎の才気煥発な(「昭和一桁世代」の)三人の作曲家グループが、颯爽とそれぞれの意欲溢れる作品を携え日本の楽壇に登場してから六十年余り。その三人共すでに他界……。
今回、本日演奏する三曲を“アヴァン・ギャルド(前衛)”という生乾きの状態のものとしてではなく“古典”として冷静な視点からスコアを洗い直し、精度が高く中身の濃い演奏に導いて行こう! と私は考えた次第。芥川、黛の両作品に漲る強いエネルギーは、二人の共通の師、伊福部昭の土俗的なヴァイタリティから受け継いだDNAがそれぞれの中で変異したものに他ならないし、「舞楽」の第2楽章には先駆「春の祭典」と全く同じリズムが現れる。即ち、ストラヴィンスキーやバルトーク等に見られる、19世紀には存在しなかった先鋭的で複雑なリズムと強烈なエネルギー・生命力(バーバリズム)の洗礼を、20世紀の作曲家たちは例外なく受けているのだ。そして「交響三章」の第2楽章中間部の、オーボエから始まる寂寥感に満ちた哀切極まりないメロディが、なぜか團伊玖磨の歌劇「夕鶴」にも殆ど同じ姿で現れるのは、日本人が“哀”を表現するときのアイデンティティを確しかと裏付けるものなのか!?
それらを全て包括・咀嚼し、アマチュアらしい“共感度に満ちた”(それが何より大事なのだ)しかし、曲の理解、演奏の意欲・熱気・勢いだけに止まらない、クオリティーアップを図った演奏を今回目指した。特に昔の演奏ではそこまで追求できなかったであろう、艶めかしい音色・音質(特に「春の祭典」)の獲得だ。
それらの成果を投影した“新しい新響像”は今日のステージの演奏から自ずと明らかになるだろう。 これからも私は、心から愛す新響と熱い演奏を積み重ねて参る所存ですので、どうぞ皆様、このオーケストラに一層のご支援をお願いいたします。
ありがとうございました。
団長あいさつ
1956年3月1日に発足した新交響楽団が、1957年11月21日に第1回の演奏会を開催してから51年目にして第200回という記念すべき演奏会を本日迎えることができました。
200回に亘る演奏会の企画・選曲はその時代のオーケストラの思想を表現しています。世代交代をしながらも常に純粋な音楽団体の立場として多くの夢を限りなく追い求め、一つ一つの演奏会に全力を集中しながら、その時の「今」を創造し、常に独創性を持って音楽に対する情熱をエネルギーとして失うことなく発展し続けてきた証といえます。
半世紀に及ぶ長い時間、新響の活動はあらゆる面で順風満帆であったわけではありませんでした。しかしながら、新響を取り巻く社会環境・音楽環境の大きな変化の中で、新響の活動の根底に流れているものは、創立指揮者で音楽監督であった故・芥川也寸志先生の「音楽はみんなのもの」という理念に支えられたアマチュアとしての誇りを持って、その可能性を追求していくという強い信念に支えられたものであり、新響は時代と共にその信念をアレンジして発展させながら、アマチュアだからという甘えに妥協せず、新響の特色を生かしたプログラムを模索し追及してきたことといえましょう。常にその時代のオーケストラの実力と団員の技術レベルを判断し、可能性を追求するために、時には技術レベルを上回る曲目で演奏会を企画し、それを乗り越えるべくオリジナリティを発揮して、地道な練習の充実と団の運営および演奏の質の向上を目指してきたのです。200回の演奏会を通して、数多くの団員が新響でしか味わえない音楽体験を通して刺激を体感し、積極的かつ幅広い音楽活動を発揮してきました。音楽を愛し、とにかく良い音楽をしたい、という熱い想いが情熱となって、そして活動の原動力として脈々と途絶えることなく新響には流れています。
本日の演奏会は第200回という節目を具現化するものとして、「今」の新響を創造し持てるパワーを発揮するべく企画致しました。新響が創立以来活動を続けてこられたのは、数え切れないほど多くの方々が新響の活動をさまざまな形で支えてくださり、ご協力とご支援あっての賜物と感謝しております。
この世に音楽がある限り、新響は「今」を活きることで多くの夢と素晴らしい音楽が創る楽しさと喜びをこれからも創造していくことでしょう。多くの課題に直面していく中で、その時にできることを地道に行うことで課題を乗り越え、魅力あるオーケストラとして、音楽への情熱を持って未来に向けて更なる飛躍をし、新響はあらゆる機会を通してその魅力を最大限に発信し続けていきます。
本日はご来場誠にありがとうございます。
第201回演奏会ローテーション
| シューマン | シェーンベルク | |
| フルート1st | 藤井 | 松下 |
| 2nd | 兼子 | 新井 |
| Picc(3rd Fl) | - | 岡田充 |
| Picc | - | 丸尾 |
| オーボエ1st | 岩城 | 亀井淳 |
| 2nd | 桜井 | 亀井優 |
| 3rd(2nd C.A.) | - | 岩城 |
| コールアングレ | - | 堀内 |
| クラリネット1st | 末村 | 品田 |
| 2nd | 大藪 | 石綿 |
| 3rd(2nd Bcl) | - | 高梨 |
| Es | - | 進藤 |
| 1st Bcl | - | 中條 |
| ファゴット1st | 田川 | 長谷川 |
| 2nd | 長谷川 | 田川 |
| 3rd | - | 所(*) |
| コントラファゴット | - | 星 |
| ホルン1st | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 比護 | 比護 |
| 3rd | 園原 | 鵜飼 |
| 4th | 大原 | 山口 |
| 5th | - | 大原 |
| 6th | - | 園原 |
| 7th | - | 大内 |
| 8th | - | 市川 |
| トランペット1st | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 北村 | 青木 |
| 3rd | - | 倉田 |
| 4th | - | 中川 |
| アルトトロンボーン | 志村 | 志村 |
| テナートロンボーン1st | 武田 | 武田 |
| 2nd | - | 小倉 |
| バストロンボーン1st | 岡田 | 岡田 |
| 2nd | - | 関田(*) |
| テューバ | - | 土田 |
| ティンパニ1st | 桑形 | 中川 |
| 2nd | - | 桑形 |
| シンバル | - | 桜井 |
| 中太鼓 | - | 浦辺(*) |
| 大太鼓 | - | 今尾 |
| トライアングル | 今尾 | 田中 |
| 銅鑼 | - | 田中 |
| 鉄琴 | - | 浦辺(*) |
| ハープ 1st | - | 佐々木(*) |
| 2nd | - | 篠田(*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(荒井あ) | 前田(堀内) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(岸野) | 岸野(大隈) |
| ヴィオラ | 柳澤(石井) | 柳澤(常住) |
| チェロ | 柳部容(光野) | 光野(日高) |
| コントラバス | 中野(関口) | 中野(関口) |
演奏する側から見た『春の祭典』
『春の祭典』の経済学
いささか堺屋太一めくが、ここで『春の祭典』を演奏することによって我が国にもたらされる経済的波及効果について考察してみたい。
1)特殊楽器市場の活性化
コントラファゴット、コール・アングレ、バスクラリネットが各2本。その他バストランペット、アルトフルートなどなどとにかく特殊楽器の総決起集会的様相を呈するため、これらの楽器の調達にメンバーは腐心せざるを得ない。この調達の労苦から普段滅多に使われることの無いこれらの楽器の重要性が再認識されたり、団所有の楽器の「耐用年数切れ」が明確になったりする事により、特殊楽器市場に例外的な需要をもたらす。これを「春祭特需(はるさいとくじゅ)」とよぶ専門家もいる。
2)人の動きに伴う需要の喚起
『春の祭典』は5管編成。管楽器だけで40人もの人数になってしまう。これに打楽器を加えて45人以上。全日本吹奏楽コンクールに行けてしまう人数だ。新響の管セクションの定員は各パート6名(ホルンは8名)を原則としているので、頭かずは足りる見当だが、一身上の都合でどうしても出られない人もいる。そこでエキストラのメンバーが必要になる。外の世界との交流が活発になり、ヒトとカネの流れが変化する。
具体的には、ノーギャラで出て戴いている(!) エキストラの方々を毎回の練習後に呑みに連れてゆくことで、練習場のある東京都北区十条近辺のアルコール消費量を前年同月比で8ポイントも底あげし、税収増と地域経済の活性化に貢献しているとの報告がある。
*アルコール消費量拡大の因子については『春の祭典』 の変拍子との関連を指摘する心理学・社会学的考察もあることを付記しておく。
3)楽譜の出版・販売業界への影響
『春の祭典』の出版元であるBOOSEY&HAWKES社は、ここ20年程の売上実績を分析した結果、奇妙な事実に気づいた。それは極東地域に於て『春の祭典』のスコアが爆発的に売れる年があり、しかも或る周期をもって繰り返されているという事であった。詳細な調査の結果、それが日本のさる学生オーケストラの海外公演の周期と一致することが判明し、以後はこの情報をいち早く取り込むことが同社の歴代極東支配人(そんな人いないか?) の最重要職務のひとつとなった。
新響が『春の祭典』を取り上げることは既に版元の知るところであるのは間違いない。おまけに(失礼)上記の某大学のオーケストラの海外公演も来年ある。出版社はこのスコアの大増刷を完了しているはずである。というのもかつてはこの曲を演奏すると決まるや東京中の楽譜屋からこのスコアが消えてしまうという状況が繰り返されてきたからである。頼んでも半年侍ちといわれてすごすご引き返した経験のある身にとっては、二つのオーケストラが『春の祭典』を演奏するという惑星直列的な珍事(! !)にも関わらずスコアが手に入るという状況に、どちらかと言えば保守的な楽譜出版・販売業界のマーケティング能力の向上を見ることが出来よう。
『春の祭典』はアマチュア・オーケストラという有望かつ無限の市場があることをこの業界に認識させた一点に限っても、感謝されて余るものがある。
かくなる上は、BOOSEY&HAWKESには一刻も早くパート譜の間違いを直して欲しいよ。
4)ハイテク応用機器のニーズ
「はるさい(春祭)の枕詞はと人問はば、言はずとも知れ変拍子なり─詠み人しらず」と古来歌にも詠まれた(!?) 「名所」は曲の後半のその又後半の部分でしかないが、この難所を切り抜けるときの緊張感はただものでない。
この曲の変拍子たる所以は、次の予測がまるで立たない事。「悲槍」の第2楽章の5拍子だって立派な変拍子なのだが誰も変拍子だとは気づかない。一定の予測可能な拍子だから。『春の祭典』の場合も慣れてくるとリズムのパターンが見えてくるのだが、人間は錯誤の動物。必ず誰かが何かやってくれる。そしてオーケストラは阿鼻叫喚の無間地獄へつき落とされるのであります(悪くすると止まってしまう)。
そうならないためには、とにかく練習あるのみ。と云っても普通の道具立てではなかなか困難。相手は拍子となればこれは「変拍子対応のメトロノーム」の様なハイテクノロジー応用機器開発の契機となるはずなのだが、なかなか実用化されない(余り欲しくもないが)。
ただ、こと拍子・テンポ関連周辺機器についてはハイテク応用の分野として有望ではあるまいか。
5)総論
『春の祭典』がもたらす効果の代表的なもの4点を以上に述べたが、この曲はそのオーケストラの技術的な水準にとどまらず、ヒト・モノ・カネ或いは運営・企画等あらゆる「力」を評価する尺度として、極めて有用である。こうした「総合力」とこの曲を演奏することによる周辺への広範な波及効果を考えると、一国の経済にたとえるなら、「自動車の国産化」程のインパクトはあろう。
尤も新響の場合、今までにも『春の祭典』を演奏したこと自体はあり、その時点で「先進工業国」の仲間入りは果たしている訳なのだが、既に20年近くを経過しており、そろそろもう一度車の造り方をおさらいしておく時期にさしかかっていた。そして実際に練習してみて、きれいさっぱり忘れ去っている現実に愕然としている。
保守的な姿勢に固執し、無事これ名馬的な「老大国」に新響が堕する事を僕は最も忌避し且つ恐れる。
『春の祭典』を演奏することによって、ともすれば我々の精神に溜りがちになる澱(おり)を浚い出せるとすればこれに優る効果はあるまい。
これはそうした力を持った音楽である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
タネを明かせば以上は97年に『春の祭典』を取上げた際に書いた維持会ニュースの記事。あれから10年が経過して、新響もずいぶん変わった・・・と思いきや、『春の祭典』を相手にするとなると、「相変わらず」という状態である。敢えて変わった事を探せば使用する譜面はBOOSEY&HAWKESからKalmus版になった位か。だが、この版も遺漏だらけという点では変わらない。『春の祭典』の変拍子に対応可能なメトロノームも実用化されてはいない(ま、あっても売れないだろうが)。
ただこの作品に対峙する際に持つべき「畏れ」のようなものは、変わるべきではないと感じる。僕は『春の祭典』を30年前に初めて演奏して以来、ずいぶん様々な処で、様々な出来の演奏を繰返してきた。その経験から言えば、「慣れ」が生じてしまうと大抵は上手くいかない。絶えず誰かが何かをしでかすのではないか、それはもしかすると次の瞬間の自分かもしれない・・・という危惧を抱きつつ、しかも萎縮せずに演奏する。これがこの作品を演奏する際の、ひとつの「奥義」とも言えるし、演奏者の心がけとすべきものと信じている。
『春の祭典』をやすやすと演奏するようなオーケストラに、新響はなってもらいたくない。それは人間の創造した音楽という宇宙に対する冒瀆とでも言うべきである。
このごろそれを特に強く思う。
芥川也寸志さんと新響の最後の演奏会
ヴァイオリンの川辺(1981年から在籍)と申します。新響の演奏会も遂に200回になりました。芥川さん指揮で第九を演奏した第100回記念演奏会から、ちょうど25年。そして1989年に亡くなられてから19年。改めて時間の流れの早さを感じます。今シーズン、久しぶりに「交響三章」を弾いていると、芥川さんの事が想い出されるので、私的な思い出で恐縮ですが、ここで少しその話をさせて下さい。
まず1楽章。新古典的なクールさ・スマートさ、というのが我々当時の若手団員が芥川さんから感じていたイメージでした。私はその頃運営委員長をして居り芥川さんのご自宅で会合を持つ事が時々ありました。他の運営メンバー達と成城の駅から会議の作戦を練りながら歩いて数分でたどり着くご自宅は、コンクリート打ち放し・地中海風(?)タイルの敷かれた玄関・3階までの吹き抜けの下でグランドピアノが光っている、まさにご本人のイメージにぴったりの建物でした。冬にお邪魔すると、少し底冷えがしたところなども・・・(?)。
次に2楽章。この楽章の泥臭いまでのセンチメンタルさが、当時の私にはちょっと作り物くさく感じられたのですが、その後他の芥川作品の演奏(例:映画音楽「八甲田山」など)を体験するにつれて、この音楽は作曲家の心の底から出てきているのだなと感じられる様になってきました。我々中高年おじさんの寂しい心に浸み通る作品です。
さて3楽章。作曲家の中の、ラテン的な熱い部分を感じさせる曲です。底抜けに明るいメロディーが寄せては返し延々と続く楽章を弾いていると想い出されるのは、ファリャの「三角帽子」を指揮している芥川さんの嬉しそうな表情です。新響との最後の定期演奏会になってしまったのは、88年4月3日のファリャ作品展(第119回・上野)でした。これはご本人が上述の会議でやや照れくさそうに提案してきた企画で、昔から好きでたまらなかったのだそうです。特に三角帽子の最後の大団円の踊り(この第3楽章に似ていますよね)がお好みだったようで、毎回の練習が終わる5分位前になると、他の部分を練習していても必ずここを(強引に)取り上げて、実に楽しそうに指揮していました。
このファリャ作品演奏会のすぐ後、4月の末に行われた、東京芸大の奏楽堂の移転保存記念演奏会が芥川・新響の最後の共演となりました。保存活動の中心としてご苦労された後の晴れ舞台であり、オーケストラ側は練習不足でお粗末なモーツァルトでしたが(申し訳ない)、ご本人は大変満足そうでした。この年は春の到来が遅く、打ち上げレセプションの席から見える上野公園の桜がまだ満開でした。私は翌月から仕事で海外に転勤する事になっており、そのご挨拶をしたところ、「ちょうど自分も6月に新聞社の依頼で現地に行くので是非会おう」とのお返事でした。それでは連絡先を、と紙に書いて振り返ると、もう既にお帰りになった様で、そこにご本人の姿はなく窓の外の桜だけ・・・、というのがあれから20年近くを経た私的記憶です。
その後体調不良という事で現地にも来られず、どうしたものかと訝っていたら、翌89年初めに、3日遅れで届く新聞で芥川さんが亡くなられた事を知りました。(インターネットなど無かった昔ですので)。
当時の新響運営メンバー達は、定期演奏会への芥川さんの登場回数を減らすなど独立色を強めようとしており、上述の会議では、ちょうど反抗期の子供とそれに苛立つ父親、といった様な場面も結構多かったのです。今になって想い出してみると、あまりうち解けた話をする機会がなかったのが、ちょっと悔やまれますが、最後の演奏会は2回とも、ご本人が喜んでもらえて幸いだった・・・・。 やっぱり芥川さんは新響の父親的存在だったんだな、と交響三章を弾きながら改めて感じています。
第200回演奏会ローテーション
| 交響三章 | 舞楽 | 春の祭典 | |
| フルート1st | 丸尾 | 岡田 | 松下 |
| 2nd | 藤井 | 新井 | 新井 |
| Picc(2nd) | - | 松下 | 丸尾(3rd Fl) |
| Picc(1st) | - | - | 岡田 |
| Alt | - | - | 藤井 |
| オーボエ1st | 山口 | 亀井(淳) | 堀内 |
| 2nd | 桜井 | 亀井(優) | 山口 |
| 3rd | - | 桜井(CA) | 亀井(淳) |
| 4th(CA 2nd) | - | - | 亀井(優) |
| CA 1st | - | - | 岩城 |
| クラリネット1st | 品田 | 高梨 | 末村 |
| 2nd | 大藪 | 石綿 | 品田 |
| 3rd | - | - | 石綿 |
| BsCl(1st) | - | 進藤 | 中條 |
| BsCl(2nd) | - | - | 進藤 |
| EsCl | - | - | 高梨 |
| ファゴット1st | 浦 | 長谷川 | 田川 |
| 2nd | 星 | 田川 | 星 |
| 3rd | - | - | 所(*) |
| コントラファゴット(2nd) | - | 星 | 浦(4th Fg) |
| コントラファゴット(1st) | - | - | 長谷川 |
| ホルン1st | 鵜飼 | 大原 | 箭田 |
| 2nd | 市川 | 比護 | 山口 |
| 3rd | 大内 | 山口 | 大内 |
| 4th | 園原 | 箭田 | 大原 |
| 5th | - | - | 園原 |
| 6th | - | - | 鵜飼 |
| 7th(1st ten. Tu) | - | - | 比護 |
| 8th(2nd ten. Tu) | - | - | 市川 |
| Piccトランペット | - | - | 北村 |
| トランペット1st | 倉田 | 小出 | 野崎 |
| 2nd | 中川 | 北村 | 青木 |
| 3rd | - | 中川 | 小出 |
| 4th | - | - | 倉田 | Bassトランペット | - | - | 岡田 |
| トロンボーン1st | 志村 | 志村 | 武田 |
| 2nd | 岡田 | 武田 | 小倉 |
| 3rd | - | 大内 | 大内 |
| テューバ(1st) | - | 足立 | 本橋 |
| 2nd | - | - | 土田 |
| ティンパニ(1st) | 中川 | 中川 | 桑形 |
| 2nd | - | - | 中川 |
| 3rd | - | - | 田中 |
| トライアングル | - | - | 桜井 |
| シンバル | - | 桜井 | 桜井 |
| 小太鼓 | 今尾 | - | - |
| 大太鼓 | 桑形 | 桑形 | 今尾 |
| タムタム | - | 田中 | 由谷(*) |
| 木琴 | - | 今尾 | - |
| 鉄琴 | - | 由谷(*) | - |
| 鈴 | - | 桜井 | - |
| ギロ | - | - | 中川 |
| アンティークシンバル | - | - | 中川 |
| タンバリン | - | - | 田中 |
| ピアノ | 藤井 | 藤井 | - |
| ハープ | - | 佐々木(*) | - |
| 1stヴァイオリン | 前田(堀内) | 前田(堀内) | 堀内(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 岸野(荒井あ) | 岸野(荒井あ) | 岸野(荒井あ) |
| ヴィオラ | 柳澤(常住) | 柳澤(常住) | 柳澤(佐々木) |
| チェロ | 日高(光野) | 日高(光野) | 光野(柳部容) |
| コントラバス | 加賀(中野) | 加賀(中野) | 中野(加賀) |
第200回演奏会のご案内
第200回演奏会
1955年(昭和30)に結成された労音アンサンブルは作曲家・芥川也寸志を指揮に迎え、翌56年に東京労音新交響楽団として発足しました(66年労音より独立)。そして1957年11月21日に第1回定期演奏会を開催します。NHK交響楽団の前身と同じ名前を付けることについては団員に照れもあったようですが、芥川の「世界一のアマチュアオーケストラにする」という目標の下、希望に満ちた出発でした。
以来50年間、ほぼ年に4回のペースで演奏会を開催してきました。第200回の演奏会を迎えるにあたり、1回1回の演奏会を大切にする活動の通過点として、何か特別なことをするわけではなく、しかし、より「新響らしい演奏会」にしたいと私たちは考えました。
芥川也寸志:交響三章
創立指揮者であり演奏の指導のみならず運営の道筋を作った芥川にちなんだ企画にしたいという思いから、多くの芥川作品の中でも新響の団員が最も親しみを持つ曲のひとつであるこの曲を選びました。弱冠23歳、東京音楽学校在学中の作品で、躍動するリズムと叙情的なメロディーの生き生きとした曲です。かつて電機メーカーのCMにも使われたので、聴けば懐かしく思い出されるかもしれません。
黛敏郎:バレエ音楽「舞楽」
新響は創立20周年での「日本の交響作品展」によりサントリー音楽賞を受賞し、その後も日本人の作品を積極的に演奏してきました。今回は創立50周年での涅槃交響曲に続き黛の作品を取り上げます。黛は日本古来の文化をテーマにした曲を多く残しています。舞楽とは舞を伴う雅楽のことで、この曲では笙(しょう)や篳篥(ひちりき)などの伝統的な雅楽器を用いず通常のオーケストラ編成で雅楽特有の響きが表現され、かつての宮廷の雰囲気が描かれています。ニューヨーク・シティ・バレエによる委嘱作品。
ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」
1913年パリでの初演時、あまりの斬新さに大騒動を巻き起こしたこの作品も今や「クラシックの名曲」となりつつありますが、強烈なリズムと土俗的なメロディーは何度聴いても新鮮です。幼少の頃にストラヴィンスキーのレコードを喜んで聴いたという芥川の企画で、新響は75年にストラヴィンスキー・バレエ3部作一挙上演を行いました。練習量を多く要求されるこのプログラムは、練習時間を豊富に持てるアマチュアの強みを活かした絶好の企画と考えたようです。現在でも難曲であることには変わりませんが、練習時間をかけ曲に対する愛情と理解を持って、アマチュアだからこそできる演奏をしたいと意気込んでいます。
特別寄稿 マーラーの交響曲 -残された楽譜と演奏の実際についての考察
ダイナミックな表現、精密なオーケストレーション、複雑で長大な構成、合唱を含む多くの演奏者など、スケールの大きさにおいて、マーラーの交響曲は他に全く類を見ない。オーケストラのそれぞれのパートにも難しいパッセ―ジがたくさん与えられているが、指揮者に対する要求も大変に厳しい。大編成のオーケストラや合唱を掌握する事自体とても難しいのだが、作品に込められた誇大妄想的なイメージを、大いなる共感を持って再現する事こそ、与えられた最大の課題であると思う。自分がそれを実現できたと感じたことはもちろん一度もないが、演奏のたびに予感することはできる。他の作曲家には決して感じられない、特別な熱気が会場全体を包む。いずれにしても、マーラーを演奏する事は私にとって必ず特別な体験となる。
当代一流の指揮者でもあったマーラーは最高の演奏をめざして、歌手やオーケストラに対し常に容赦ない要求を突きつけたと伝えられる。このような厳しい態度は、当然ながら自らの作品に対しても徹底的に貫かれた。作品の完成から演奏、その後の出版にいたる数々の段階でより精密な表現をめざし、多くの変更と更新が行われた。しかしながら、私たちが手に入れることができるマーラー作品の楽譜について、作曲者の最終的な意思を必ずしも反映しない複数の出版が現在にいたるまで行われており、作品に対する誤解を生じさせているようだ。音楽学の基礎知識を持たない私がこの問題に言及するのは僭越なことはではあるが、マーラーの音楽を愛して止まない聴衆の皆さんに少しでもご参考になればと思い、これまでの経験を基にこの稿を進めてみることにする。
作曲から初演まで
交響曲の作曲にあたり、多くの場合マーラーは楽想をスケッチした後、 ①4段に拡大した大譜表により曲の構成を決定し、(Particell) ②横長の五線紙にスコアを下書きしてオーケストレーションをほぼ確定して、(Partiturentwurf) ③最後に縦長の大きな五線紙を使い浄書、作品を完成させる、(Partitur-Reinschrift) という順で筆を進めていった。特に後期の作品では、それぞれの段階での作曲者のイメージはより明確になっているので、作曲の過程をはっきりとたどることが出来る。
出版社は原稿(Partitur-Reinschrift)を基に写譜師により版下(Stichvorlage)を製作、その後製版に入り、完成したところで試し刷り(Bürstenabzug)が行なわれる。版下および試し刷りは校正のために作曲者に届けられるが、マーラーは誤植のチェックだけでなく、この段階で早くもオーケストレーションの改良に取りかかり、時には旋律線の変更さえ行なっている。度重なる改訂の結果、試し刷りが数回繰り返される事もあった。校正ならびに改訂を受け、正式なスコアとパート譜の印刷(初版=Erstfassung)に取りかかる。初演の際には、パート譜についても手書きではなく、印刷された初版が使われたようである。楽譜の準備ができた後、いよいよオーケストラとの練習に入るわけであるが、練習中に実際の響きを聴きながら、マーラーはさらに改良を繰り返していくのである。
出版
練習から初演にいたる段階での変更や改良の結果は、初演の後にスコアやパート譜が重版されるか、あるいは研究用の小型スコアを新たに出版する際に取り入れられた。しかし、残念ながら作曲者が意図したすべてを含んだ万全なものとはならなかった。
一般論ではあるが、新作の初演では、限られた時間の中でテンポの決定、音の確認、表現の実際、特殊奏法の検討など、いろいろな事柄で作曲者、指揮者、オーケストラの相互間で議論が行われ、リハーサルは実に煩雑な作業となる。マーラーの場合は作曲と指揮を兼任して、しかも完全主義者であったので、その作業のめまぐるしさは想像を絶するものであったに違いない。自分のスコアにメモしながらも時間の制約で実現しなかったところ、練習中に新たなアイディアを思いついてオーケストラに注意をし、楽員はパートに書き込んだがマーラー自身がそれをスコアにチェックし忘れたところなど、かなりの錯誤が使われたスコアやパート譜に残されたままとなってしまった。
マーラーの逡巡が相当激しかった様子について、決して正確とは言えないようではあるが、第6交響曲の初演におけるアルマ・マーラーの記述によって、私たちも実感することができる。
初演後の状況
作曲者による再演は期日とオーケストラを変えて度々行なわれた。しかし再演のための練習においても、もとより不完全な楽譜の状態にマーラーが満足できるわけもなく、前述のような改訂や変更が同じように繰り返された。再演に使用され、変更されたパート譜の多くはオーケストラのライブラリーにそのまま残されるか、あるいは出版社によって回収された。例えば第5交響曲の場合、演奏の度に新しいパート譜が準備され、マーラーはそこに改めて変更や改良を容赦なく加えたので、結果として一つの交響曲に異なる変更が加えられた複数のヴァージョンが残っている。このようなパート譜の状態を統合する作業は、マーラーが活躍していた当時はまったく行なわれなかっただけでなく、実際の出版にほとんど取り入れられていない。またマーラー自身が演奏に使用したスコアにも多くの変更が記入されたが、これもまた省みられることはなかった。
以上の改訂の結果は、マーラー自身の演奏に立ち会ったか、あるいは助手を務めた指揮者などにより部分的に継承されたが、個人的な範疇を超えるものではなく、一般化するには至らなかった。時にはこうした改訂が一部の演奏用の貸し譜スコアおよびパートのみに書き込まれており、一般に手に入る研究用スコアと大きく違っていることもあった。
もう一つ触れておかなければならないことは、マーラーの場合、単独の出版社と専属契約を結ぶまでには至らず、それぞれの交響曲について異なる出版社に交渉し、演奏が決まった段階で出版を契約していた。現在では第1から第4交響曲までは、版権を受け継いだUniversal Editionが出版しているが、初版の段階ではそれぞれ異なる出版社が担当した。(Universal社がマーラーと専属契約を結んだのは第8交響曲以降のことである。)またマーラーの先進的な書法は、当時の出版社にとって理解し難い点も多かったようで、出来上がった楽譜の精度は作品ごとにかなり異なってしまった。例えば第7交響曲においては、初版の段階からすでに多くの誤植が指摘され、慌てた出版社が「訂正表」を別に刷ってスコアに添付するような状況であった。また第1および第4交響曲では、Universal社が1940年代に小型スコアを重版したが、当時ナチス・ドイツの占領下にあったヴィーンにおいてマーラーの作品は出版不可能だったので、ロンドンにあった支社が代行した。その際どうした理由か、改訂前の初版をそのまま印刷してしまった。 やむをえない事情もあったが、以上のような状況から演奏の現場での混乱は最近にいたるまで時々引き起こされていた。メンゲルベルク、ヴァルター、クレンペラーなど作曲者と直接の交流を持った指揮者たち、またバーンスタインによる1回目の全曲録音を聴けば、このような混乱は明瞭に判別できる。なお、最近容易に手に入るようになったリプリント版のほとんどは、改訂前の初版のコピーである。研究用資料としての価値はあるものの、作曲者の最終意図からは大きくかけ離れているで、実際の演奏には使われないものと考える。
マーラーの交響曲が正しく理解されるまでには、相応の時間が必要であったが、演奏される機会がなかなか増えなかった理由の一つとして、楽譜の不備があったことは指摘せざるを得ない。
国際マーラー協会による批判全集版
このような楽譜の状態を改善することを目的の一つとして1955年、ヴィーンに国際マーラー協会が設立された。各所に散らばった資料を統合し校訂作業が行なわれ、作曲家の生誕100周年にあたる1960年に批判全集版として、それまでもっとも問題の多かった第7交響曲が最初に発表される。この画期的な出版によりマーラーの交響曲のあるべき姿が初めて提示された、と言っても過言ではない。以後マーラーの作品が演奏される機会は格段に増えることとなる。エルヴィン・ラッツ(Erwin Ratz)がほとんど一人で校訂作業にあたったと言われているが、1970年代の終わりまでに全交響曲の批判全集版が揃った。
国際マーラー協会は批判全集版の一応の完成を機に、その後に判明した事実や出現した資料の検討を含めた「改良版」”Verbesserte Ausgabe”の校訂に着手、カール・ハインツ・フュッスル(Karl Heinz Füssl)が主な校訂者として、第1、第4、第5、第6、「大地の歌」、第9交響曲までが出版された。ただし「改良版」における改善点はあまり多くはない。
フュッスルの死後、ラインホルト・クビーク(Reinhold Kubik)が校訂作業を引き継いだが、クビークは研究チームを増強し、これまでの研究に加え、初演や再演の折に使われた更に多くのパート譜やマーラー自身の書き込みの含まれたスコア、メンゲルベルクとアムステルダム・コンセルトヘボウオーケストラが演奏に使った楽譜など、新発見を含むさらに幅広い資料を基に、マーラー自身が最終的に頭の中に持っていたイメージに迫ろうとする「新批判版」”Kritische Neuausgabe”を計画し、2002年にまず第5交響曲が出版された。発表と同時に指揮者サイモン・ラトルが取り上げ、第3楽章のホルン・ソロの演奏位置などが話題になったが、内容的に素晴らしい出版であり、これまでとはまったく一線を画したものになっている。批判全集版においても、スコアとパート譜との不統一がなお指摘されていたが、製版のコンピュータ化により、不統一は解消された。またパート譜も正確で読みやすい版組みとなった。(それまでは初版を版下に、変更部分のみを手作業で追加していたので錯誤は免れなかった。)さらにこれまでに比べ格段に多くの資料に当たった結果、初めて詳細な充実した校訂報告が添付され、指摘されていた数多くの疑問点についても解答が与えられている。
「新批判版」は現在、レナーテ・シュタルク=フォイト(Renate Stark=Voit)とギルバート・カプラン(Gilbert Kaplan)の共同校訂による第2交響曲の出版準備がほぼ整い、スコアと校訂報告の二分冊により、まもなく刊行される。また第7交響曲についてもクビークがすでに校訂を終えており、2007年3月にはマリス・ヤンソンス指揮のバイエルン放送交響楽団により試演が行なわれた。「新批判版」の出版はクビークを中心に今後も続けられる予定で、第9交響曲の校訂作業に現在入っているとの事である。
ここで第2交響曲について、私の経験を記しておきたい。2006年3月に群馬交響楽団と共に演奏した際に、上記の「新批判版」をUniversal Editionのご好意により試用版の形で使うことができた。演奏会の2週間ほど前に届いたスコアを一読した私は、長年持ち続けた疑問に対する明快な回答を得て、文字通り目から鱗が落ちる思いであった。批判全集版との違いは細かい点ばかりで、音程の違いなど聴いてはっきり認識できるものはごく限られているが、響きをより明確にするために必要な楽器間のバランスの操作、強弱およびフレージングの徹底、細かな奏法の指定など、全体として500ヵ所を超える更新が行われている。
読み進めるにしたがい、新たな出版においてどうしても逃れることのできない誤植と思われる個所や、不明な点も見つかった。そこで国際マーラー協会に連絡を取ってみたところ、直接クビーク博士およびシュタルク=フォイト博士から問題点をリストにまとめるよう要請された。時間も差し迫っていたので十分とは言えないものの、スコアの熟読にすぐに取りかかり、急ぎ質問リストを作成した。その際、カプラン財団が1985年に出版した交響曲全曲の自筆原稿ファクシミリ、初版(1899)および批判全集版(1970)、第1楽章の初稿である「葬送」”Todtenfeier、そして歌曲集「子供の不思議な角笛」の批判全集版を参照している。フォイト博士の対応は誠意あふれるもので、質問項目の一つひとつに赤で訂正を入れるような形で細かく答えていただいた。さらにオーケストラとの練習に入ると、楽員からも多くの指摘を得て、その後は公演直前までフォイト博士とのやり取りが続いた。もう一人の校訂者であるカプラン氏からも連絡が入り、すでにこの新版による演奏を重ねているカプラン氏とは、演奏面を含め有益な議論を繰り返すことができた。私が挙げた質問は140ヶ所を超えたが、そのうちの30数ヶ所については誤植、またはもう一度検証が必要な個所であることが判った。
楽譜の校訂という現場に図らずも立ち会うことになったが、この経験により残された楽譜から作曲家の意図をどこまで読み取り、どのように演奏に反映することができるかについて、多くの示唆を与えられた。マーラー自身による初演までの過酷な作業を、わずかながら追体験する機会に恵まれたのかもしれない。
「大地の歌」および第9交響曲における楽譜の状況
「大地の歌」と第9交響曲については、作曲者が初演を果たす機会がもう与えられなかったが、写譜師が作成した版下にはマーラーによる校正が行われていた。すでにこの段階でオーケストレーションの変更なども見られるようである。作曲者の死後、ブルーノ・ヴァルターによる初演のためにスコアとパート譜が急いで準備されたが、出版社の不理解による多くの誤植がそれぞれの初版(1912)には認められる。批判全集版(ラッツ校訂1964、1969)により誤植はかなり修正されたが、表現上の錯誤、矛盾している所などはそのままに残された。「改良版」 (1990、1998)においても、編集のスタンスに大きな違いはない。 両交響曲のスコアを比較検討してみると、作曲者のイメージは第9交響曲に較べ「大地の歌」でより明瞭で確固として、完成度が高いように見受けられる。「大地の歌」では、表現上の錯誤などの疑問点は非常に少なく、問題点のほとんどは、独唱とオーケストラとの音響上のバランス(特に第1、第4楽章において)に終始する。マーラーが初演を行うことができれば、第4および第8交響曲のようにオーケストレーションの無駄を削り、独唱がたやすく聴き取れる配慮がなされたに違いない。また第6楽章の数ヶ所については、さらに演奏しやすい具体的な形へ変更されたことであろう。
それに対し第9交響曲では、疑問の残る音程のみならず、コントラファゴットとバステューバなど同一の声部進行をするはずのパートにおいて、リズムが異なっている点が多く見受けられる。また強弱の不統一、時にはあるパートについて表情記号が全く脱落している個所、多過ぎる5連符のモルデントなど現実的とは言えない譜割りや不徹底がスコアに残されている。オーケストラとの共同作業を通じての改訂が行なわれた第8交響曲以前の作品と比較して、スコアの状況はかなり異なる。
先にも述べたように批判全集版では、矛盾点について基本的に作曲者の記譜のままとし、編集者独断による追加や変更は一切行っていない。こうした事情から、第9交響曲について、批判全集版の校訂者ラッツは、残された第1~3楽章のスコア下書き原稿(”Partiturentwurf”-前述作曲段階の②)をファクシミリの状態で特別に出版、演奏者に対しファクシミリを参考にスコアを検討し、各々が結論を出した上で実際の演奏に当たることを、批判全集版の前書きの中で薦めている。
演奏について-私の姿勢
20世紀前半は指揮者という演奏分野が確立した時代であったが、当時の指揮者たちの多くは「より良く」、あるいは「より饒舌に」自分を表現するために、特に古典的な作品に対し、容赦なくオーケストレーションを含む変更を加えて演奏していた。これは残された録音などを聴けば明らかであり、私たちの世代も少なからず影響を受けている。マーラー自身もモーツァルトやヴェーバーのオペラ、ベートーヴェンやシューマンの交響曲について大胆な変更を加えて演奏していたことが良く知られている。こうした変更は演奏解釈と隣接したものであるが、時には作品の本質から逸脱して、演奏家の独善に陥ることもあった。 これまで述べてきたように、マーラーは自身の作品について、可能な限り正確な記譜を試み、後の世代に対しても正確に演奏されるよう、最大限の努力をした。楽譜の改訂だけでは満足できずに、欄外に「指揮者への注意」として特殊奏法やテンポの設定、指揮の方法論にまで言及しているが、マーラーの細心さを端的に表したものと言って良い。しかし一旦作品を完成した後に、演奏のため、あるいは演奏の度に繰り返した加筆や改訂は、作曲者としての観点ではなく、むしろ演奏する立場からなされたと理解するべきである。作曲と演奏とがまさに専門分化していく時代に、マーラーは才能に秀でた一流の音楽家であったからこそ、相対する観点から自分の作品に批判を加えていく宿命を背負わされた。この点は注目しなければならない。
マーラーが行なった改訂の目的は、楽器間のバランスの調整と、主要主題や動機の詳細な表現、の二つに大きく分類できる。そのうちバランスの調整については、全曲を通じて遺漏なく行なわれているが、詳細な表現については徹底されていると認めるのは難しいようである。むしろ作品のあまりにも大規模な構成と膨大な音譜の量から、作品をすべて管理する事はできなかったと言わざるを得ない。スコアを読み進めるに従って解ることであるが、繰り返される主要なモティーフにおいても最初の部分のみ正確に記譜され、途中からは改訂を放棄しているところが見られ、また強弱や表情がスコアの上下や前後の関係での錯誤が多く残されている。
私自身は演奏に際し、作曲家の書いた楽譜を最も尊重し、余分な変更など行なわずに作曲者の持つイメージに迫ることを基本方針としている。しかしマーラーのスコアに残された不明瞭な部分に限っては、作曲者の真意を出来る限り忖度して、必要ならば加筆を行った上で、演奏に具体的に反映させるべきと考え、これまでも第10番を除くすべての交響曲について実行してきた。ただしこのような変更と加筆は、作曲者の意図から外れて独善的になることがないよう、あくまで慎重にされなければならない。そのために私は、自筆原稿のファクシミリ、初版から批判全集版に至る各段階の出版の収集、交響曲に関連する歌曲の研究など、手に入る限りの資料を基に比較検討し、変更の根拠を得るように努力している。 第9交響曲は私が指揮者を目指す原動力となった作品である。すでに1999年に群響と共に演奏しているが、事前に批判全集版の編集方針に従い、出版された下書き原稿(Pariturentwurf)のファクシミリを最も重要な資料としてスコアを詳細に検討、変更点をパート譜にチェックした上で演奏に使用した。オーケストレーションの変更など不合理なことは一切行なわなかったが、響きの明瞭さを得るために、強弱ならびにフレージングの錯誤については統一を試みた。また楽器間のバランスについても変更を行なったが、いずれもマーラー自身が第8交響曲以前の作品について各段階で演奏を通じ書き加えた改訂の状況を参考とし、拠りどころとしている。新交響楽団との本日の演奏のためにも、手持ちの資料を改めて検討し直し、新たに変更が必要と思われる点についてさらにパート譜に加筆を実施している。なお今回判明したもののうち大きな疑問点について、国際マーラー協会のクビーク博士に直接照会して、ご教示を仰いでいる。
マーラーの交響曲を演奏する機会に恵まれることは、私にとってはこの上ない喜びである。許されるならば、自分のライフワークとして、これからも演奏を積み重ねていきたいと考えている。今回の楽譜についての考察も、私のマーラーへの私淑と敬意の表れと理解していただければ幸いに思う次第である。 (2007年8月)
曲目解説プログラムノート
武満 徹:トゥイル・バイ・トワイライト
Twill:あや織り Twilight:たそがれ ――――
武満徹は、1930年10月8日東京生まれ。奇しくも本日が77回目の誕生日となる現代日本を代表する作曲家。
いきなり個人的な話になるが、打楽器奏者としての私の武満作品との出会いは、大学時代、オーケストラが『スター・アイル(星・島)』を演奏しており、そのときであった。早稲田大学100周年を記念して書かれたこの作品は、単純な音楽的ユニットを複雑に展開させる、いわゆる「武満ワールド」が存分に展開されており、かなりの衝撃を受けたことを覚えている。私自身も「いつかはこの作品を演奏してみたい!」と思っていたが、4年で全員が交代してしまう学生オーケストラには、ゼロからこの曲を練習するだけの技術的余裕がなく、結局憧れだけを持ったまま、残念ながら演奏する機会がなかった。
新響では、過去に、弦楽のための『ホゼイトレス』(作曲1959年)、『鳥は星型の庭に降りる』(同1977年)が演奏され、今回が3回目の演奏となる。個人的な印象では、作曲年代が後になればなるほど、より精緻で無駄の省かれた音楽になっていくような気がする(そして技術的な難しさも!)。
『トゥイル・バイ・トワイライト』は、読売日本交響楽団の25周年のために委嘱・作曲された(初演は、本日のプログラムと同じ、マーラーの9番との組み合わせだった)。
同楽団ではこの他にも、新響でも昨年演奏した2人の作曲家、三善晃(『アン・ソワ・ランタン』)や猿谷紀郎(『ここに慰めはない(尾高賞受賞)』)らに委嘱・初演を行っている。
この曲の作曲前年には、ギター曲「すべては薄明かりの中で All in Twilight 」が作曲されており、その曲の延長線上として、さらに友人モートン・フェルドマンの追悼の意味を込めて書かれたと言われる。モートン・フェルドマンは、武満と同じ時代を生きた現代アメリカの作曲家で、作曲前年の1987年に亡くなった。ジョン・ケージらと共にアメリカ前衛音楽の旗手を務め、彼の作品にも大きな影響を与えたという。
曲は、As-Bの2音で表される「ユニット」と呼ばれる音楽の一要素が、終始あや織りのように重ねられ、それが感情的にうねりのような起伏を作りながら展開していく。盛り上がりは大変に詩情豊かで、武満自身が「日没後の一瞬の華やぎ」と表現した「たそがれ」を表している。どこか映画音楽やドビュッシーの印象派の音楽のような感じがする。武満が後期作品の作風として特徴としていた、繊細で静謐でありながらも感情の起伏の激しい音楽の極致と言えるのではないだろうか。
自身の初期の代表作でもある『弦楽のためのレクイエム』の響きの引用もところどころ聴かれ、友人であったフェルドマンへの追悼の意を表している。最後の、ジャズ風のコラールを連想させる大きなうねりで曲が盛り上がった後、かすかに聞こえる鍵盤打楽器が添えられた和音には、武満による祈りが込められているかのようである。
ところで、私ども打楽器奏者としては、音程やリズムなど、特別に正確さを要求される武満作品は、非常にプレッシャーのかかるものである。この曲でも、奏法にはバチの種類や叩き方などに細かい指定があり、正確に演奏するためには、特別な練習や「慣れ」(=イメージトレーニング)が必要となる。また、特にこういった曲の場合、他のパートにとっても、打楽器がどこで鳴るかが自分の出るところのキッカケとなっている(「ガイド」と言います)場合が多いため、間違っても違うところで音を出してはならず、特に責任重大である。またこの曲にも、様々な打楽器が登場するが、特に写真のような「アンティーク・シンバル(クロタル)」が活躍する。新響でも、新たに2オクターヴの楽器を購入し、本日の演奏がデビューとなる。(維持会費による積立金を活用させていただきました。皆様ありがとうございました。)
最後に武満の言葉。「正確で美しくて、心を込めた演奏が、一番嬉しい」
―――生誕77年のお祝いとして、本日はそのような演奏ができることを祈りつつ・・・。
初 演:1988年3月8日 ハインツ・レーグナー指揮、読売日本交響楽団
楽器編成:フルート4(2番ピッコロ持ち替え、3番4番アルトフルート持ち替え)、オーボエ3(3番コールアングレ持ち替え)、クラリネット4(2番Esクラリネット持ち替え、4番バスクラリネット持ち替え)、ファゴット3(3番コントラファゴット持ち替え)、ホルン4、ピッコロトランペット、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、打楽器5名(シンバルを載せたティンパニ、大太鼓、吊りシンバル3枚、グロッケンシュピール、アンティーク・シンバル、ヴィブラフォン、チャイム、タムタム3枚) 、チェレスタ、ピアノ、ハープ2、弦5部
マーラー:交響曲第9番 ニ長調
特別な交響曲
交響曲第9番は、しばしばグスタフ・マーラーの最高傑作と評されます。曲想の斬新さ、他の何物にも似ていない独自性、そして例えようのない深さと美しさ。怒ったかと思えば泣き、泣いたかと思えばせせら笑う。また怒鳴ったかと思えば、深い祈りに頭を垂れる。そんな多面性や複雑さを強固な意志が串刺しにして、長大な曲に見事な統一感が与えられています。なんとも不思議な、そして「凄い」曲なのです。
また、この曲は何か「特別な」思いを演奏者にも聴衆にも抱かせる力を持っています。曲の複雑さ、難易度の高さゆえに、指揮者も楽員もしかるべき覚悟をもって演奏に臨まなければなりませんが、自分が聴衆としてコンサートホールに足を運ぶ時、演目がマーラーの9番であると、他の曲とは違う何か緊張感や高揚感のようなものを覚えるのも事実です。その特別さが何なのか?ひとことで言い表すことは非常に難しいですし、感じ方も人それぞれだと思います。それが何だったのか、皆様お一人お一人が終演後にもう一度思い起こしていただけると幸いです。
ちなみに、作曲家で高名な評論家でもあった柴田南雄氏は、「マーラーの全交響曲、全歌曲集の中にあって、群を抜いた存在である。単に異彩を放っているという以上のものであり、これによって彼の創作活動の画竜点睛が成ったといっても過言ではない。その独自性に満ちた構造、大胆きわまる書法は、まさに大芸術家の生涯の絶頂期にのみ可能なものである」と、この曲へ惜しみない賛辞を贈っています。
グスタフ・マーラーとアルマ・マーラー
マーラーの後期の交響曲を語る時に、妻アルマの存在を抜きにすることはできません。彼は19歳年下の若くて美しい妻を愛しており、彼女はマーラーの創作意欲の源でした。
アルマ・シントラー(後のアルマ・マーラー)は1879年8月31日にウィーンで画家の娘として生を受けました。実父は早く亡くなりますが、継父も画家で、アルマは芸術的環境の中で自由に伸び伸びと成長。その美貌と才気で少女時代からウィーンの若い芸術家たちの心を捕らえてしまいます。その相手には彼女の作曲の師でもあったツェムリンスキーや画家クリムトの名前も挙がっています。
一方、グスタフ・マーラーは1860年7月7日、ボヘミア、イーグラウ近郊のカリシュトという小さな村に生まれました。兄弟が15人(といわれている)という大家族でしたが、兄弟のうち6人が病気のため早世しています。父は馭者から身を起こし、酒の蒸留所を営んでいました。知識欲旺盛な野心家で活力にあふれた人でしたが、病弱な妻を虐待し、暇さえあれば女中の尻を追いかけまわすという男でもありました。こうした多くの兄弟の夭折や複雑な家庭環境は、マーラーの人格や死生観に大きな影を落としているといわれます。そのマーラー少年は幼い頃から音楽的才能を発揮。それを知った父はすぐに専門的な音楽教育を受けさせます。彼の才能はすぐに開花し、めざましい速さで成長して、15歳でウィーン音楽院に入学しています。そんな天才的な能力を持ったマーラーでしたが、森の中をさまよって忘我状態になってしまうような、夢見がちで多感な少年でもあったようです。
さて、この二人が出会ったのは1901年11月、ウィーンのとあるサロンの夕食会でのこと。当時マーラーは指揮者として既にウィーン宮廷歌劇場の音楽監督の座に就いていたので、アルマは彼のことを知っていました。ただし個人的な興味や関心は全くなく、紹介された時も別段「ときめき」を感じることはなかったようです。しかし、マーラーは若くて美しく、しかも才気溢れるアルマに一目惚れ。すぐにその席で歌劇場のリハーサルに彼女を招待します。
初対面では小柄で偏屈そうなマーラーに特別な想いを抱かなかったアルマですが、まず歌劇場のリハーサルで彼の並外れた才能に驚嘆。音楽の才能や力量のみならず、あらゆる芸術に対する高い見識などに惹かれていき、彼の求愛を受け入れることになります。こうして彼女の気持ちを捕まえたマーラーですが、彼は彼で若いアルマとの結婚に不安を抱いていました。妹ユスティーネに「秋は春を手元に引きつけておく力があるのだろうか?」と漏らしていたように。
そして、二人は1902年3月に結婚。マーラー41歳、アルマ22歳でした。すでにこの時アルマは第一子を身ごもっており、10月に長女を出産します。
9番目の交響曲と「第9交響曲」
マーラーは結婚後、第6番以降の交響曲を作曲。その苛烈な性格ゆえウィーンの楽壇からは少しずつ疎んじられていくものの、妻と二人の幼子に囲まれ、しばし幸福な年月を過ごします。その幸福だった時間をとめてしまったのは,1907年7月の娘の死でした。毎年夏に訪れていた避暑地のマイエルニッヒで、ジフテリアのため、長女マリア・アンナを失ったのです。マーラー夫妻の悲しみと落胆は、いかばかりであったでしょうか? その上、娘を診た同じ医師から診察を受けたマーラーは、心臓に重大な疾患があることを宣告されます。
この時、彼は「千人の交響曲」といわれる交響曲第8番の作曲をほぼ終えていましたが、巨大なエネルギーが外へ向かって放射される第8番と、それ以降の「大地の歌」、第9番などの内へ向かう曲想の違いを考えると、娘の死が作曲家マーラーにもたらした影響の大きさがうかがい知れます。またこの年は、ウィーン宮廷歌劇場の音楽監督を辞任し、メトロポリタン歌劇場からのオファーを受け、新天地ニューヨークへ渡った年でもありました。1907年はマーラーにとって大きな転機の年となったのです。
以後マーラーは秋から冬をニューヨークでの指揮活動、春から夏をヨーロッパでの作曲というライフサイクルで過ごします。翌1908年に9番目の交響曲として「大地の歌」の作曲に着手しますが、尊敬するベートーヴェンやブルックナーが第9番を最後の交響曲としていることにただならぬジンクスを感じたマーラーは「大地の歌」から第9番という番号を消してしまいます。ただし、この曲は青年期に書かれた歌曲の作風にかなり回帰しており、交響曲として番号が与えられなかったことが結果的に妥当だったかもしれません。
こうして10番目に書かれた「第9番」は1909年の夏に南チロルのトブラッハで作曲されます。マーラーは前年に亡き子の思い出が残るマイエルニッヒを引き払い、夏の作曲に充てる避暑地をここへ移していました。第8番と「大地の歌」は声楽を伴う交響曲でしたが、この曲は純粋な器楽のみの世界へ戻っています。もちろん誰が見ても純然たる交響曲ですから、マーラーも第9番という名前を与えざるを得ません。
そしてわずか2ヶ月ほどで、マーラーはそのスケッチを終えます。曲の複雑さや独創性、完成度などを考えた時に、このわずかな期間で作られたことには誰もが驚くのではないでしょうか? その後、スケッチを持ってニューヨークへ戻ったマーラーは過酷なスケジュールの間を縫って仕上げと浄書に励み、1910年4月1日に完成させました。1909年11月から翌年3月までに40回以上の演奏会を指揮したことや彼の健康状態を考えると、その作曲は、まさに命を削るものだったと思います。
4つの楽章について
この曲を構成している4つの楽章は「緩—急—急—緩」というシンメトリカル(対称的)に配置されており、第1楽章:ソナタ形式、第2楽章:スケルツォ、第3楽章:ロンド…といったそれまでの古典的な形式を踏襲しているように一見思われますが、踏襲したのは形式だけで、その内容は新ウィーン楽派へつながる斬新さに満ちています。新たな境地を拓こうとする意欲があふれています。
■第1楽章 ニ長調 アンダンテ・コモド
どこからともなく聴こえてくるチェロのAの音とそれに呼応するホルンに導かれるハープで曲は始まる。さらにヴィオラのさざ波に乗って、第2ヴァイオリンがためらうように、そして夢見るように第1主題を奏でる。こうして静かに始まるが、曲は次第に高揚し、中間部では「最大の暴力をもって」と記されているように、最後の審判を想起させるような激しさでオーケストラが咆哮する。そして曲はまた静けさを取り戻し、静かに終わる。
■第2楽章 ハ長調 レントラー・スケルツォ
ユーモラスでありながら非常に不気味な3拍子の舞曲。サン・サーンスの「死の舞踏」、すなわち骸骨の踊りを思わせる。本来明るく輝かしいはずのハ長調をこういう曲想で用いているのがいかにも皮肉っぽい。曲は、骸骨なら骨が外れてしまいそうなテンポに速度を上げるが、紆余曲折を経てまた元の少しゆったりしたテンポに戻り、最後はピッコロとコントラファゴットがすべてあざ笑うように締めくくる。
■第3楽章 イ短調 ロンド・ブルレスケ
ブルレスケとは道化芝居のことであるが、「きわめて反抗的に」と記されているように、暴力的で激しい楽章。4楽章で弦楽器により深く感動的に奏でられるモチーフが、ここでは諧謔的に速いテンポで用いられているのが印象的である。このモチーフはトランペットに受け継がれ、慰めをもって美しく奏でられ、4楽章への布石となる。しばしの慰めと嘲笑が入り交じった後、また凶暴性を取り戻し、加速を続け、すべてを断ち切るように激しく終わる。
■第4楽章 変ニ長調 アダージョ
この曲の白眉ともいえる楽章。この楽章が持っている深さや美しさは比類がない。第1・第2ヴァイオリンの緊張感をもったユニゾンで始まるが、すべての弦楽器が慈しみをもってこれを優しく迎え入れる。この楽章はただ美しいだけではなく、大きなエネルギーを持っている。曲は途中激しくうねり、何度かのクライマックスを経て、次第に安息へと向かう。そして最後のかすかな息づかいのように、ヴィオラがG-A♭-B♭-A♭という音型を奏で、彼方へ消え去って行く。
曲に込められた想い
この曲は全体的に死のイメージが根底に流れていると思われていますが、作曲者の真意はわかりません。マーラーの信奉者であり積極的に彼の作品を取り上げ続けた指揮者、ウィレム・メンゲルベルクはマーラーのこの世への別れであると解釈していますが、本当にそうなのでしょうか? 当時マーラーには心臓の疾患もあり、死への不安があったことは事実でしょうが、彼はまったく生を諦めていなかったと思います。確かに健康状態は悪化していましたが、創作意欲はまったく衰えることなく、この曲の完成後、すぐに第10番の作曲に取りかかっています。結局、第10番は未完に終わり、完成した交響曲としては先人のジンクス通り、第9番が最後の曲となるのですが、それはまったくマーラーとしては不本意なことだったでしょう。ですので、第9番に関していえば、この世への決別という思いはなく、5番~6番~7番~8番~大地の歌…と作曲してきた帰結として、このような曲にならざるを得なかったのではないでしょうか?
また、この曲が向かう先は「終わり」ではなく、「始まり」であると私は思っています。先に述べたシンメトリーな楽章の構成を考えた時、第2楽章と第3楽章の間で折り返したとすると、第1楽章の冒頭と第4楽章の最後が重なり合うことになりますね。この楽章配置が意味すること、最後のヴィオラのモチーフが冒頭にハープで奏でられたものの変形であることを考えると、そう思うのも不自然ではないでしょう。ヴィオラの最後の音が虚空へ消え去った後、遥か彼方から冒頭のチェロのAの音がかすかに聴こえてくるような気がするのは私だけではないと思います。
しかしマーラーはこの世ではなく、他のものに別れを告げていました。この曲のスコアには自筆の書き込みがあります。まず、スケッチには「ああ、消え去った若き日よ! ああ、破れた愛よ!」と記されており、完成したスコアには「おお、美よ!愛よ! さらば!さらば!」と五線譜に書き綴っています。そう、彼がこの時別れを告げていたのは他ならぬアルマだったのです。マーラーにとってアルマは美の象徴であり、愛の対象でした。彼はアルマのことを本当に深く愛していたようですが、1907年の長女の死を境にアルマの気持ちは次第にマーラーから離れていったといわれています。実際にアルマが年下の若い建築家ワルター・グロピウスと恋に落ちるのは、第9番が完成した後の1910年夏のことですが、既にこの時マーラーは近い将来アルマが自分のもとを去って行くことを予感し、断腸の思いで別れを告げていたのです。
その後のこと
引き続き並々ならぬ創作意欲を持っていたマーラーですが、彼の身体がそれを許してはくれませんでした。喉を細菌に侵されていたマーラーの健康状態は1911年が明けると、かなり悪化。細菌学の権威による治療を受けるため、4月にニューヨークからパリへ渡りますが、そこでは満足な治療が受けられませんでした。そこで、ウィーンから最も著名な医師を呼び寄せ、医師と共にウィーンへ帰ります。しかしマーラーの健康が回復することはありませんでした。1911年5月18日、ベートーヴェンと同じ激しい嵐の夜、モーツァルトの名前を二度呼んで、その音楽家はこの世を去りました。アルマの手記には臨終の床で「一本の指が掛け布団の上で指揮をしていた」と書かれており、彼が最後まで音楽家であり続けようとした執念が伝わってきます。そして、その亡骸は生前の希望通り、娘マリア・アンナの隣に埋葬されました。「大地の歌」と交響曲第9番の初演も果たせぬままに。
一度グロピウスとの恋に落ちたアルマですが、マーラーへの愛情が冷めてしまったわけではなく、彼に最後まで付き添っていました。彼女の手記は次のように結ばれています。「私には彼の最後の様子は決して忘れられないし、死が近づいた時の彼の顔の立派さも瞼に焼きついている。彼の、永遠の価値あるものを求めるための闘争、俗事からの超越、真理に対する不退転の献身などは、いずれも聖者の生涯の生きた範例であった」。
その後、アルマはさらに「恋多き女」としての人生を歩むことになります。1915年にグロピウスと再婚しますが、その2年前には画家のオスカー・ココシュカと熱愛。彼の代表作「風の花嫁」はアルマとココシュカ自身を描いたものといわれています。結局アルマはココシュカよりグロピウスを選んだわけですが、その関係も破綻し、離婚。11歳年下の作家、フランツ・ヴェルフェルと再々婚しました。
アルマは非常に長命で、1964年12月にマーラーとの思い出の地、ニューヨークでその生涯を終えます。85歳でした。彼女は終生、アルマ・ヴェルフェル・マーラーと名乗っています。偉大な音楽家マーラーの妻であったことは生涯変わることなく、彼女の大きな誇りだったのでしょう。
最後にまたマーラーに話を戻しましょう。彼自身が「やがて私の時代が来る」と予言したという話はあまりにも有名ですが、彼の音楽は生前から親交の厚かった、ブルーノ・ワルター、ウィレム・メンゲルベルク、オットー・クレンペラーらの大指揮者に受け継がれ、一時のナチからの弾圧を耐え忍び、1970〜1980年代に「マーラー・ブーム」として大輪の花を咲かせました。今ではブームも沈静化しましたが、オーケストラの重要なレパートリーとしてマーラーの作品は確固たる地位を得ています。
少々気の早い話かもしれませんが、3年後の2010年はマーラーの生誕150年、翌2011年は没後100年にあたります。この2年間は「マーラー・イヤー」として、また世界中で彼の作品がたくさん取り上げられることになるのでしょうか? 天上のマーラーは「よしよし」と、ほくそ笑んでいるのか、はたまた「まだ俺の曲をやってるのか?古いなぁ」と顔をしかめているのか、ちょっと興味があります。
参考資料
アルマ・マーラー:グスタフ・マーラー~愛と苦悩の回想~(中公文庫)
船山 隆:マーラー(新潮文庫)
Frank Scheffer:I have lost touch with the world(JUXTA POSITIONS)
初演:1912年6月26日、ブルーノ・ワルター指揮 ウィーン・フィルハーモニー
楽器編成:ピッコロ、フルート4、オーボエ4、コールアングレ(4番オーボエ持替え)、クラリネット3、Esクラリネット、バスクラリネット、ファゴット4、コントラファゴット(4番ファゴット持替え)、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ(2奏者)、大太鼓、小太鼓、シンバル、トライアングル、タムタム、グロッケンシュピール、低音の鐘3(音程指定)、ハープ、弦5部
コントラファゴットのボーカル購入しました
7月に維持会費でコントラファゴットの「ボーカル」を購入させていただきました。ありがとうございます。ボーカルというのは音の震動源であるリードを装着する金属の曲がった管で、リードの振動を本体である木の管体へ伝える非常に重要なパーツです。当団のコントラファゴットは非常に古く由緒あるものなのですが、そのボーカルに長年の金属疲労(勤続疲労)のせいでしょうか?ヒビが入ってきたこともあり、思いきって新品を購入することに致しました。楽器全体の管長から考えると、短いこの金属の管ですが、これをいいものに替えることで楽器のレスポンスや安定感が格段に向上します。
いつもはコントラバスの陰に隠れて、その生の音がなかなか聴こえづらいコントラファゴット。しかしながら、マーラーの交響曲第9番には「聴かせどころ」がいくつもあるのです。10月8日の演奏会にぜひお出かけいただき、木管セクションはもとより、オケ全体を支える「縁の下の力持ち」の音にも耳を傾けていただけるとありがたいです。
超個人的マーラー観
前々号のニュースに引続き、個人的な回想に基づく原稿である事を、お許し願いたい。
僕は1982年9月の入団なので、新響に籍を置く事とうとう25年になった。普通の勤め人なら永年勤続で少なからぬ金品をともなう表彰の対象となるところ。実際昨年勤め先からは休暇と旅行券を戴きました(本来は堅気の社会人なのです)。そこで新響でも「1年間団費免除」の恩典とか、「秘湯のペア宿泊券」謹呈とかの配慮があるといいなぁと思うのだが、これが何ら音沙汰無い。アマチュア・オーケストラの範たる事を自他共に認める団体として、これは恥ずべき事ではないか!?と心では「強く」思っているが、生来の小心ゆえに何も言えぬまま、悶々とした日々を過ごしておるのです。かと言って自分に対するご褒美・・・なるものをこの歳になって考えるのも、何かちょっと情けないし。
■僕はマーラーが嫌いだった!
さて、その25年前に初めてこのオーケストラの一員として演奏した曲目が、マーラーの「第九番」だったという事実は、振り返ってみればその後の音楽人生に大きく影を落としたと言って良い。今だから白状すれば、僕はマーラーが嫌いだったのだから。
新響をその歴史と共に見守って戴いている維持会員の方々には自明の事ながら、改めて説明すれば、かつての新響は山田一雄氏の指揮によるマーラーの交響曲全曲演奏(所謂(いわゆる)「マーラーシリーズ」)に取り組んでいた。これは’88年に終了するまで足掛け10年の時間を要したのだ。’79年から始まったシリーズは’83年初に「第九番」を演奏する事で佳境に入りつつあった。その真只中にマーラー嫌いが跳び込んでしまったのだから、これはもう結果は知れていると普通は思う。すなわち単なる「食わず嫌い」なのだから、新響にいる限り更正される・・・というところだ。が、僕の場合この病気は容易には治らなかった。
何が理由?ひとことで言うならマーラーの音楽を受け容れるには、心・技・体全てに未熟だったからだ。すなわちこうした複雑な含みを持つ音楽を容れる余裕のない心、それを演奏するに必要となる技術の未熟、そして彼の作品を演奏していた当時の新響の演奏形態への疑問・・・こんなところだろう。
今だからこのように冷静且つ分析的な言い方になるが、彼の作品はひどく子供じみた、若しくは狂気を交えた支離滅裂な音の集積に過ぎず、謂わば「音楽以前」のものにしか当時は思えなかった。生理的に受付けない。それは確かにマーラーに出会う以前の、個人的な音楽体験の乏しさに因る。それまで僕が「音楽」として理解できたものは、整然と均衡のとれた秩序ある世界のみだったのだから。それがいきなり4度音程のティンパニ連打の上に、人間離れしたテンポで旋律が展開されたり(『巨人』の第1楽章の最後)、次ぐ楽章ではどう考えても芸術的とは言えぬメロディがコントラバスから「輪唱」のように続くといったものにつき合わされる。或いは「陰惨」の印象しか残らないトロンボーンの蜿蜒(えんえん)としたソロとその後の馬鹿騒ぎ(4本のピッコロが高音域のユニゾンを合わせられると本気で思ってるのかよ→第3番)を聴かされたり、どんな音をイメージしたら良いのか皆目不明のハンマーが振り下ろされる茶番部分(第6番)を見せ付けられれば・・・純真無垢な感性には拒絶以外の反応はあり得ない。これが「心」の部分。
演奏体験のある人にはすぐに理解してもらえるのだが、彼のオーケストレーションは同じ旋律を重ねているにもかかわらず、強弱を交叉させている部分が多々ある。すなわち同旋律を演奏しているふたつのパートが、片方はクレッシェンドしつつあるその時、他方はディミヌエンドが求められているという状況である。「ほう面白いじゃないか」と思うのは、これを聴いて愉(たの)しむ立場にある人である。演奏する側はひとつの常識として、自分の見ている譜面にある強弱記号が全てのパートに共通していると考え、また皆が同じ方向を指向していこうとする。それが演奏者の生理と言うものである。事実、彼以前の音楽は基本的にそのようなものだった。勿論そうした音楽にも楽器の特性上避けられない音量の差異があり、バランス調整が必要ではある。そしてそれをするのは全体の音を俯瞰(ふかん)する指揮者の仕事だった。マーラーは自らの作品でこの調整を極限まで進め、それを演奏者に強いる。これは自分の音量を、他とのそれとの比較によって相対的に決めるのではなく、ある基準で絶対化する事を意味する。お蔭で演奏する側は絶えず総譜と首引きになり、他者が何をしているかを常に認識した上で、その関係に於いて己の「絶対化された」音量を行使しなければならなくなった。これを実現するには相当の演奏経験を積む必要があるが、駆け出しの若造(無論僕の事だ)には望むべくもなかった。言うなればこれが僕にとっての「技」の部分だ。
「体」についてはやや事情が複雑だ。当時の新響の状況に関わる話である。この団体に入って驚いたのはとにかく全員が「全力投球の音」を出している事だった。オーケストラは緻密な組織であり、各パートは出るべき時に出、退く時は退くべきものであると、学生時代に散々叩き込まれてきた思想はここでは全く通用しなかった。こうした事を酒の席ででも言おうものなら「新響はそんなサラリーマンのような演奏を目指す団体ではない!」と一蹴されるのが常だった。「遅れず・休まず・働かず」に表わされたように、与えられた目先の仕事だけをさしたる情熱もないままこなす・・・それが「サラリーマン」の語に含まれた意味である。「気楽な稼業」のイメージが人々の心にまだあった時代の話としても、ひどい譬(たと)えである。
更に言えばこのサラリーマンとは(日本の)プロオケの楽員を指していた。彼らは音楽という仕事に愛情を持っていない。だから「冷めた演奏」を平気でする。新響はそうではない。我々は愛情に根ざした「熱い演奏」をするのだという理屈である。流石にこういう意見は今の新響ではなりをひそめた。日本のサラリーマンの置かれる環境も激変し、決してお気楽な稼業ではなくなっているし。
確かに愛情は大切である。ただそれは他者との比較に於いて論ずるものではないし、それが押し付けがましい「音」となって表わされる事とは本来全く別物である。根拠のないこうした論理に、かつて日本社会を席巻していた「プロへのアンチテーゼとしてのアマチュアリズム」の典型を見る思いだった。新響には様々な美点があるのだが(だからこそ四半世紀も在籍している)、当時あったこの考え方にだけは、今思い起こしてもついていけない。
そのような思想の団体が、前述のような微妙な強弱の指定されているマーラーを、しかも「第九番」をやる場に飛び込んだのだ。マーラーの責任ではないけれど、こうした環境の中で、神経を逆撫でされるような彼の作品を合宿までして練習した事は、決して僕の心証にプラスには働かなかった。翌年初めの本番の出来は案の定と言うべきだろう、余り良いものではなかった。終楽章で山田先生が絃楽器群に向かって「叱咤」しているのを、3番フルートの席から醒めた目で眺めていた。但しこの交響曲そのものは、僕のマーラーに対する印象に僅かながら変化をもたらしていた。これに自分が気づくまでに少なからぬ時間を要したが。
■「マーラーブーム」を通じて
ひとことお断りしておけば、マーラーの作品は既に1970年代からブームを呼び起こしてはいた(新響のマーラーシリーズもその一画と言えなくもない)。今ここで取上げるブームはより狭義の、’80年代の後半、所謂「バブル」と言われた時代に、とある洋酒メーカーのCMを契機として突如沸き起こり、瞬時に消え去ったあのブームの事である。これ自体がバブルの申し子と言うべき異常なものだっただけに、今ではほぼ忘れ去られているようなので、敢えて書き留める事にした。異常と言えば当事の世の中自体が異常だったのだから、これは時代の正直な反映と捉えるべきなのだろう。
このブームのキイワードは「世紀末」と「メセナ」だったように今は思う。バブル景気に浮かれながらも「こんな時代が長く続くわけがない。だからこそ今を謳歌しよう」という、来たるべき時代に対する不安と、それを直視したくないために目先の現実だけを無批判に肯定しようとの刹那的な感情に、世の中全体がとり憑(つ)かれていた。それは企業も同じで、持ちなれないカネを「文化の貢献」に使おうと、競合する企業のメセナ活動を睨みながら結局皆が同じバラマキを行ない、殆ど全てが何も実を結ばなかった(そして景気後退と共に、皆が横並びで中断した。如何にも日本的である)。
懺悔(ざんげ)するほかないが、そうした中で最も異常だったのはこの僕だ。マーラーについてむしろ嫌悪感さえ抱いていたにもかかわらず「東京マーラー・ユーゲント・オーケストラ(TMJ)」なる団体を拵(こしら)え、祭り上げられた結果とはいえ、あろう事かその代表になったのだから。これは山田一雄氏の指揮でマーラーの交響曲第9番を演奏する、それだけを目的として在京のアマチュア演奏家有志によって結成されたオーケストラだった。念の為に言うが発起人は僕ではない。ただ1987年の初秋という初期段階で僕のところに企画が来た時、ふたつ返事で参画を承諾してしまったのは、本番会場がサントリーホールで、しかも1番フルートの席が用意されていたからだった。我ながら情けない気もするが、3年ほど前の新響のこの曲の演奏に満足できなかったために、謂(い)わば意趣返しのような心積もりを固めた。もうひとつ。新響の「アマチュアリズム」から離れた団体で、自分が考えるオーケストラのあり方を実現したいとの野心があった(まだ30歳になるかならぬかの若気の至りである)。演奏会を1度開けばそれで解散の宿命は、勿論計画性や長期的な視点を欠くものではあったが、このオーケストラがマーラーの演奏水準としてはトップにあった事だけは間違いない。
前述のブームの到来はこのオーケストラ結成の直後だった。マーラーに対する関心は増し、企業から寄付を募るには苦労はなかったし、チケットも右から左に捌(さば)け、1988年2月に行なわれたコンサートではサントリーホールを満席に出来た。確かに時宜を得ていたのだ。ただその客層・・・というべきだろう・・・は従来のコンサートのそれとは明らかに違っていた。演奏が進行するにつれてお行儀の悪さが目だった末に、こんなに長い曲だとは知らなかったとのアンケート回答が多かったのには、苦笑を禁じ得なかった記憶がある。「寝ている人も多かったようですね」とは、とある出版社系の週刊誌からの取材を受けた際、開口一番の質問だった。ブームに乗って会場に足を運んだ皮相な人々の様子を、揶揄(やゆ)を含んだ目で伝えようとの記者の意図はみえみえだったが、そもそもこの程度の演奏会に音楽関係以外の雑誌から取材が入る事自体が、特異な事だった。
この前後、特に’88年の前半は、日本中のあちこちのホールでマーラーの作品が鳴っていた。そして大抵の場合、何ら関係なさそうな企業が争って協賛した(因みに新響が「マーラーシリーズ」の最後を『巨人』で締めくくったのもこの年の7月だった。このタイミングは絶妙だったと言える)。ブームは所詮ブームでしかない。これによってマーラーの音楽の何たるかを初めて知った人々から熱病が去るには、さしたる時間を要しなかった。とにかく不思議な時代だったのだ。
一度解散したTMJは次の演奏会に向けてすぐ始動し、最終的には1994年まで毎年活動し続けた。その間に山田先生は亡くなり('91年)、井上道義氏や十束尚宏氏によってマーラーの他の作品も含めて演奏が継続されたが、既に時代は変わりつつあった。バブルの時代は終焉し、資金的な目処も立ちゆかなくなっていたにもかかわらず、一部の暴走メンバーによって海外公演の企画が立てられ、やがて当然のように行き詰まった。関係者の音信は今もって不明であるし、個人負担となった莫大な借金も残った。TMJ自体がバブルのあだ花のような存在として終わった事は、アマチュアに於けるマーラーの演奏史に残した足跡に比して、今も残念に思う。
■マーラーのある人生
個人的にはこのTMJでの活動を通じて、マーラーの作品に対するアレルギーから概(おおむ)ね脱却した。新響以外のオーケストラでマーラーを演奏する事は、ある種の転地療養の結果を生み出した。その後の新響で取上げたものも含め僕は、『巨人』から第10番及び『大地の歌』に至る全ての交響曲と、『嘆きの歌』『さすらう若人の歌』まで殆ど全てのオーケストラの作品を演奏する機会を得た。白状するが、僕はベートーヴェンの交響曲でさえ全ては演奏していないのだ(第1番をやる機会がない)。ところがマーラーに関しては繰返し演奏したものさえ多々あって、中でも「第九番」は今度で5度目になる。他のパートならいさ知らず、彼の交響曲の首席フルートのパートをこれだけ吹いている人間もアマチュアでは珍しいだろう。そしてこれだけ経験していて尚且つマーラーが嫌いだと言い続けたら、罰が当たろうと言うものだ(笑)。
僕はごく近々、「知命」と呼ばれる年齢になる(でも一向に己の使命が見えてこない。きっとこのままだろう)。だから人生の半分は新響というオーケストラで演奏してきた訳だ。僕などより遥かに在籍年数が長い「大家」の面々を差し置いて、明言してよいものかの逡巡はあるのだが、新響の演奏は変わっている。音楽への愛情こそ不変である(これは断言出来る)が、それを表現すべき方法論に対する考え方が明らかに変化したのだ。それはすなわち我々が作品に対する愛情を外の世界に発信するためには、「組織としてのオーケストラ機能」と「プロと同様に技術の追求」が不可欠だとの共通認識が確立されたという事である。これは新響を取り巻く環境・・・例えばプロのオーケストラのレヴェル向上やアマチュアの活動に対する考え方・・・の変化がもたらしたものでもあり、この団体がそれを敏感に察知し、順応し乗越えてゆくための適切な方策を選択した事を意味する。25年ぶりにこの団体で「第九番」の音を出し、その変貌を目の当たりにして感慨を禁じ得ない。またそれは前記のTMJで体験した演奏をも確実に凌ぐものとなっているのは間違いない。
これから同じ事を繰返せと言われてもうんざりするほかない25年の中で、マーラー作品に関わってきた時間は自ずから莫大な集積になった。だから自分の人生の節目となる各段階でマーラーの演奏をしていた印象がある。だから「あの時にどの作品を演奏していた」と体験によって作品を想起するのはたやすい。だがマーラーの作品群は、それ自体が彼自身の人生のその時々の心象を反映しているように思える。僕には彼の作品をよすがとして、個人的な記憶を呼び起こす必要など無い。大抵の作品を聴けば、そこから人生のある段階が抽象化された(でも確実に自分に生々しくかかわりのある)「心象」・・・とでも言うべきものが、自分の裡のどこかに潜んでいるに違いないその狂気を含めて、たちまちに引き起こされて来るのだから。こうした普遍的でありながら、どこかで個人的な体験に結びつく不思議な心象世界というものを、マーラーの作品は備えていると考えるようになった。これは独特のものである。
今では更に、彼の交響曲そのものが自身の人生を刻む尺度であったように、それに接する自分の人生の段階の尺度として捉えてしまう。だからこの年齢になって「第九番」を演奏するという意味合いは、個人的に時宜を得ていると感じている。こんなものを若いうちに繰り返し演奏し、心得顔をしていた自分を想い、実は密かに苦笑している。
「生・老・病・死」に代表される人生の各要素に密着しており、複雑に錯綜していながら、ある時はそれ以上にあり得ぬほど露骨にそれが顕れる音楽。実に生々しいものだ。ずいぶん慣れたが、その生々しさには未だに僕は完全にはついていけていない。これを克服する事は今後の人生に於ける課題のひとつなのかも知れない。だが、それを許容できるようになる事がマーラーの作品への真の理解につながるとすれば、それはそれで面白みに欠けるようにも思えるのだ。彼の作品の奥深いところである。
なるほど人生の悩みは容易には尽きぬものなのだ、と改めて思う。
第199回演奏会ローテーション
| 武満 | マーラー | |
| フルート1st | 岡田 | 松下 |
| 2nd | 藤井(Picc) | 新井 |
| 3rd | 新井(Alt) | 丸尾 |
| 4th | 兼子(Alt) | 岡田 |
| Picc | - | 兼子 |
| オーボエ1st | 堀内 | 亀井(淳) |
| 2nd | 亀井(優) | 山口 |
| 3rd | 桜井(E.H.) | 亀井(優) |
| 4th | - | 岩城(E.H.) |
| クラリネット1st | 末村 | 品田 |
| 2nd | 大藪(Es.Cl) | 進藤 |
| 3rd | 進藤 | 大藪 | 4th | 石綿(Bs.Cl) | 中條(Es.Cl) | Bs.Cl | - | 高梨 |
| ファゴット1st | 田川 | 長谷川 |
| 2nd | 長谷川 | 田川 |
| 3rd | 星(C.Fg) | 野本(*) |
| 4th | - | 星(C.Fg) |
| ホルン1st | 園原 | 箭田(アシ比護) |
| 2nd | 市川 | 山口 |
| 3rd | 比護 | 大原 |
| 4th | 大原 | 鵜飼 |
| Piccトランペット | 北村 | - |
| トランペット1st | 倉田 | 野崎 |
| 2nd | 小出 | 青木 |
| 3rd | 青木 | 小出 |
| トロンボーン1st | 武田 | 志村 |
| 2nd | 小倉 | 武田 |
| 3rd | 大内 | 岡田 |
| テューバ | 足立 | 土田 |
| ティンパニ1st | - | 桑形 |
| 2nd | - | 古関 |
| Perc. 1 | 古関 | - |
| Perc. 2 | 今尾 | - |
| Perc. 3 | 桑形 | - |
| Perc. 4 | 中川 | - |
| Perc. 5 | 田中 | - |
| 大太鼓 | - | 中川 |
| 小太鼓 | - | 今尾 |
| トライアングル | - | 桜井 |
| シンバル | - | 今尾 |
| タムタム | - | 田中 |
| 鉄琴 | - | 古関 |
| 鐘 | - | 今尾 |
| チェレスタ | 藤井 | - |
| ピアノ | 柳澤(*) | - |
| ハープ1st | 堀米(*) | - |
| 2nd | 操(*) | - |
| 1stヴァイオリン | 前田(田川) | 堀内(荒井あ) |
| 2ndヴァイオリン | 大隈(岸野) | 岸野(大隈) |
| ヴィオラ | 柳澤(田口) | 柳澤(田口) |
| チェロ | 光野(日高) | 光野(安田俊) |
| コントラバス | 中野(村山) | 中野(村山) |
第199回演奏会のご案内
新響とマーラーと高関健
新響は1979年から10年にわたって山田一雄の指揮でマーラー交響曲全曲シリーズに取り組みました。当時のアマチュアオーケストラにとってはかなり挑戦的なことでしたが、「一音百態」の指揮者がもたらした奥深い音楽的体験は新響の血肉となり、団員の半数が入れ替わった現在でも「新響のDNA」として受け継がれており、マーラーへの共感、そして音楽への愛情は変わりません。
指揮者・高関健にとってもマーラーは特別な作曲家です。中学3年の時に初めてマーラーの交響曲第9番を聴いて以来その魅力に取りつかれたまま、という氏は、高校時代には毎日のようにスコア片手に頭の中でこの曲を鳴らして通学したとのことです。今回の演奏会のために、指揮者は新響と通常の倍のリハーサル量を確保し、お互いにとって特別なこの曲に臨みます。
マーラーの「第九」
ベートーヴェンやブルックナーなど数々の巨匠たちが「交響曲第9番」をラストナンバーとしたため、マーラーは「第9番」を書くことを恐れ、9曲目となる交響曲に番外の「大地の歌」とした、というエピソードは知られています。しかし次に書いた作品は純器楽曲のため第9番と呼ばざるを得ず、第10番を未完のままマーラーは逝去、やはりジンクス通りとなりました。ウィーン宮廷歌劇場と決別し、娘を亡くし心疾患を指摘された頃に書かれたこの曲は「死」を濃厚に意識しており、その深さ、美しさから、マーラーの最高傑作とも称されていますが、それと同時に、ベートーヴェンの時代から連綿と続いたドイツ・ロマン派交響曲の時代の終焉を飾る曲と言えるのかもしれません。
武満の音の世界
もう1曲は、日本を代表する作曲家・武満徹の作品です。トゥイル・バイ・トワイライトは「黄昏の綾織」といった意味ですが、各楽器の音色を交互に織り上げたような静謐さのある繊細な響きが味わえます。どうぞご期待ください!
曲目解説プログラムノート
ブラームス:悲劇的序曲
ヨハネス・ブラームスは、1833年ハンブルクで、コントラバス奏者の父と、元貴族の娘だった母のもとに、長男として生まれる。彼に最初の音楽的手ほどきを行なったのは父であり、その楽器はヴァイオリンと言われているが、少年ブラームスの関心はピアノに強く向けられていった。そのピアノ教育の最初の師である、当時ハンブルクを代表する音楽家マルクスセンとその弟子コッセルに、正統的ドイツ音楽教育を受けつつ、11歳でピアノ・ソナタを作曲している。また、当時盛んな音楽活動が繰り広げられていたハンブルクでは、ベートーヴェンの交響曲、ヘンデルのメサイア、ハイドンの合唱作品など古典的なレパートリーの演奏会が多く、これらがブラームスの音楽観の基本を形成したとも言われる。
1853年、彼の生涯に最も大きな影響を与える3人の人物に出会うことになる。生涯の友であり音楽的理解者となるヴァイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒム、シューマン、そしてその妻クララである。20歳のブラームスはシューマン家を訪れ、自作のピアノ・ソナタ1番と2番を演奏し大歓迎を受け、その後すぐにシューマンは音楽雑誌にブラームスを絶賛する批評を載せる。そこには19世紀後半のドイツ音楽界において、確かな古典的教養に裏付けられた独創的作曲家を待望するシューマンの期待に満ちたメッセージがこめられていた。これは、ブラームスにとって未来を切り開く輝かしい賛辞であると同時に、世の中が待ち焦がれる「第二のベートーヴェン」として、自身がなすべき交響曲作曲へのプレッシャーともなっていったのである。一方、当時ブラームスは合唱指揮やピアノ演奏で、バッハを主要な演奏レパートリーとしていた。バッハ研究の密度は同時代の作曲家中群を抜いていたようだ。さらにヘンデル、クープラン、モーツァルトの作品校訂も数多く手がけ、それらが彼の創作活動にも反映されている。さらに同時代に活躍しながらも、音楽は対極的といわれたワーグナーの曲にも触れ、16~19世紀全体のヨーロッパ音楽を摂取していくことになる。
1862年(29歳)以降、ウィーンに移り住み、ウィーン楽友協会音楽監督就任など名声が高まる中、1876年(43歳)に構想から20年を費やした「交響曲第1番」を完成。その翌年には「交響曲第2番」を作曲し、1885年頃まで極めて平穏で充実した作曲活動が続く。そのような時期に、本日演奏する「悲劇的序曲」も作曲されている。やがて、尊敬するシューマンの妻であり、40年以上も敬愛に満ちた交際を続けたクララ・シューマンの死の悲しみに憔悴したブラームスは、1897年(64歳)、近づきつつある20世紀のモダニズムの響きの中で、19世紀ドイツ・ロマン派の幕が下りるのを感じつつ、その生涯を終える。
「悲劇的序曲」は、1880年(47歳)「大学祝典序曲」と対をなして作曲されている。後者はブレスラウ大学からの名誉博士号授与に対する返礼として4曲の学生歌を織り込んだ陽気なもので多彩な打楽器も用いられている。一方前者は同時期に演奏会用として作曲され、友人に宛てた手紙に「プログラムに〈劇的〉、〈悲劇的〉あるいは〈葬送〉序曲を加えるだろう」とあり、標題については迷いがあったようだ。では、何故この時期に対照的な作曲がなされたのだろうか。この2曲の創作は、彼が静けさを求めていつも訪れる、オーストリアの美しい保養地イシュルで、絶賛された交響曲第2番を完成した直後の、幸福と安定の中で行われた。だがその時期、愛するクララの息子フェリックスの死、親友の画家フォイアバッハの死、親友ヨアヒムとの不仲、そして一時的ながら難聴という恐怖が、立て続けに彼を襲ったのも事実だった。この「悲劇的序曲」には「幸福」と「不幸」、「喜び」と「悲しみ」という避けられない人生の「表裏」を敏感に受け止めた、ブラームスの思慮深くも激しい情熱を感じずにはいられない。
曲は、厳格なソナタ形式で、冒頭に力強い2つの和音、次に弦楽器による静かな第一主題、管楽器によって増幅される緊迫感、柔らかい第二主題、再び登場する激しい跳躍による力強い第一主題、そして最終音は全員によるffで終わる。主題は入念に作られ、密度の高い労作と言われている。一貫して流れる骨太の響きは、さめざめとメランコリックな「悲しみ」に打ちひしがれるのではなく、人生に立ち向かう意思の強さに満ちている。
参考文献
『作曲家◎人と作品 ブラームス』西原稔著(音楽之友社)
『ブラームス』三宅幸夫著(新潮社)
初 演:1880年12月26日
ハンス・リヒター指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
楽器編成:フルート2、ピッコロ、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、弦5部
ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲
ハイドンの主題による変奏曲は、「ハイドン変奏曲」という略称や「聖アントニウスのコラールによる変奏曲」の別称が有名であるが、新響団員の中ではハイドンバリエーションを「ハイバリ」と略す人もいる。私の好みであるが、本文では「ハイドン変奏曲」の略称を用いることにする。
ハイドン変奏曲が作曲された1873年、ブラームスは指揮者としても活躍中であると同時に、交響曲第1番の構想中でもあり、管弦楽に強い関心を抱いていた頃である。彼はそれまでに数々の歌曲やピアノ曲を作曲していたが、管弦楽曲としては1859年に作曲しているセレナード第2番以来14年ぶりの作品である。また、彼は変奏曲に強い関心を抱いており、ハイドン変奏曲以前にはピアノ曲として、「ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ」、「パガニーニの主題による変奏曲」などを作曲している。
まず、ハイドン変奏曲の主題を譜例1に示す。この主題はハイドンが18世紀末に作曲したとされるディベルティメント(フェルトパルティエン)第6曲の第2楽章に見られるものである(原曲の編成は2本のオーボエ、ホルン、ファゴット、セルパン。後に第6曲のみが“ディベルティメント”という名称で一般化した)。実は、このディベルティメントが本当にハイドンによるものかどうかは議論が分かれている。これはディベルティメントのオリジナルの草稿が見つかっていないためで、出版譜は誰かの手による写譜稿(パート譜)が元となっている。また、ディベルティメントの第2楽章の冒頭には作曲者自身によって「コラール聖アントニー」と記されていることから、たとえディベルティメントそのものがハイドン作であったとしても、第2楽章の主題自体は古い巡礼歌からの引用である可能性が高いようだ。
ブラームスがディベルティメントの第2楽章の主題(ハイドンの主題)を取り上げたのは、彼が1871年にウィーン楽友協会の芸術監督に就任したことが大きなきっかけであった。それは、当時楽友協会の司書であり、音楽学者でハイドン研究家でもあったフェルディナント・ポールと親密な関係になったためである。
ポールは、以前からディベルティメントの写譜稿に目をつけており、そのパート譜から総譜を独自に書き上げていた。既に彼と知り合いだったブラームスは、1870年頃にこの総譜を見ており、そのときからハイドンの主題に大きな興味を持っていたようだが、楽友協会でのポールとの再会により、ハイドン変奏曲の構想を拡大させたと言われている。
個人的なことではあるが、このハイドンの主題は私にとって思い出のある旋律である。私が学生時代に所属していたオーケストラでは、木管セクションのオーケストラ・スタディーとして、ハイドンのディベルティメントを半年かけて勉強する。編成は一般的な木管五重奏で、フルート、オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットであり、イギリス人のハロルド・ペリーによる編曲のものである(現在ハイドンのディベルティメントはこの編成で演奏されることが最も多いようだ)。第2楽章のハイドンの主題は一見簡単なフレーズではあるが、そこから一つ一つの音の扱い方、音のスピードや表現方法など、演奏方法の基本を学んだ。
私にとっても印象深いハイドンの主題だが、ブラームスはハイドン変奏曲冒頭の「主題」で原曲の響きを忠実に再現するよう努めている。しかし、そのあとに続く変奏は、主題を基本にしながらも、ブラームス独特の構成と色彩で書き上げられている。
主題 Andante 変ロ長調
原曲の響きに近づけるため、木管を主体とした楽器編成であり、弦は低弦のみでしかもピッチカートである。旋律は原曲どおりオーボエによるものであり、またセルパンの代わりとしてコントラファゴットを用いている。主題の最後には変ロ音(B♭)が5回連続して響き渡るが、この音こそ、第1変奏以降に繰り広げられる変奏の基となる。以降は、それぞれの変奏の変ロ音にも注目して聴いて頂きたい。
第1変奏 Poco più animato 変ロ長調
三連符を豊かに使用した旋律に八分の三拍子の効果を付している。変ロ音の連続で始まり、弦が対位法的に新しい旋律を二つの声部に分かれて演奏する。
第2変奏 Più vivace 変ロ短調
短調の変奏曲で、暗く寂しい感じであるが、情熱的である。強弱の変化が繰り返され、最後にはやはり変ロ音が重要な役目をしながら終わる。
第3変奏 Con moto 変ロ長調
明るく、ロマン的な曲想。旋律は繰り返されるごとに新しく変奏される。オーボエとファゴットが弦による対位法を伴って、新しい旋律を奏でる。旋律が弦に移行すると、木管が十六分音符のアルペジオで軽やか且つ愛らしい彩を加える。
第4変奏 Andante con moto 変ロ短調
前の変奏を受けて緩徐楽章のクライマックスを築き上げる。オーボエとホルンの旋律で始まり、ヴィオラが対位法的旋律を奏でる。その後、弦と管で旋律が入れ替わり演奏される。第5変奏 Vivace 変ロ長調急速、快活な曲想であり、次の変奏と共にスケルツォ楽章に当たる。弦が軽快な動機と変ロ音を用いた節を、また木管が主題に基づく軽快な旋律を奏す。その後、ホルンの出す断続的な変ロ音と、八分の六拍子と四分の三拍子との複合拍子に印象付けられる。
第6変奏 Vivace 変ロ長調
弦がピッチカートで主題を拡大し、管が主題の展開動機を奏する。さらに続くアルペジオの動機で次の変奏へとつなぐ。
第7変奏 Grazioso 変ロ長調
曲想が変化し、牧歌的なものとなる。前変奏に由来する動機がこの変奏を統一し、同様に管から弦へと旋律が移行される。後半は複合拍子へと展開され、変ロ音が低音のほかにクラリネット、ホルン、2番フルートに暗示的に表れる。
第8変奏 Presto non troppo 変ロ短調
神秘的な響きの変奏曲。ヴィオラとチェロの旋律に続き、ヴァイオリンそして木管が対位法で加わる形式が展開されて繰り返される。最後にはやはり変ロ音がシンコペーションで表れる。
終曲 Andante 変ロ長調
前からの変奏であると同時に、この曲だけで一連の変奏曲をなすパッサカリアを構成している。主題は低弦で奏でられる冒頭の5小節であり、その後18もの変奏が次々と展開される。曲の終わりに向けて徐々に「聖アントニー」の主題が明らかに示される。第18変奏では主題を示した上に木管が輝かしいグリッサンドを重ね、壮大な曲想となる。その後、変ロ音の節は弦及びピッコロ、コントラファゴットに示され、力は次第に弱まるが、最後は力強い和音で輝かしく曲が終結する。
参考文献
『ブラームス』門馬直美著(春秋社)
『作曲家◎人と作品 ブラームス』西原稔著(音楽之友社)
初 演:1873年11月2日 ブラームス指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
楽器編成:フルート2、ピッコロ、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット2、ティンパニ、トライアングル、弦5部
リヒャルト・シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」
リヒャルト・シュトラウス(1864~1949)が前半生に集中的に書いた7曲の一連の交響詩の中の最後の作品であり、ウィレム・メンゲルベルクとアムステルダム・コンセルトヘボウ・オーケストラに献呈されている。ミュンヘンの宮廷歌劇場の首席ホルン奏者であり名人として遍く知られていた父フランツ・シュトラウスの熱心な教育の元に育った早熟の天才シュトラウスは、大学での学業を中断し、マイニンゲン、ヴァイマール、ミュンヘンなどドイツ各地の宮廷歌劇場を渡り歩き指揮者・作曲家としてのキャリア形成を積んでいたが、その過程で、ブラームスの薫陶を受け(シュトラウスは1894年マイニンゲンにおけるブラームス自身の指揮による第4交響曲初演の演奏会に参加し、その際大学祝典序曲で大太鼓を叩いている)、一方で彼に終生最も大きな影響を与えることになったもう一人のリヒャルト、当時既に巨匠となっていたワーグナーの作品を深く識り、次第に独自の作風を築き上げて行き、今日のオーケストラコンサートのレパートリーとして欠くことの出来ない、『ドン・ファン』作品20(1888)、『死と変容』作品24(1889)、『ツァラトゥストラはかく語りき』作品30(1896)、『ドン・キホーテ』作品35(1897)等の傑作交響詩を次々に作曲していった。この曲は1898年、ミュンヘンに於ける2度目の宮仕えの間に着手し、翌年フェリックス・ワインガルトナーの後任としてベルリンの宮廷音楽監督になって間もなく完成した。規模的にも楽器編成的にもこれまでの作品を凌ぐものであり、交響詩作曲家としてのシュトラウスがその頂点に達した作品であるが、それはそのまま19世紀を通じて発達してきた管弦楽曲というジャンルが1世紀をかけて辿り着いた一つの頂点とも言えるものである。
『英雄』というタイトルと変ホ長調という調性は、当然約100年前に書かれたベートーヴェンの英雄交響曲を意識していたものであるが、ベートーヴェンにとっての英雄がナポレオン・ボナパルトという歴史的・政治的に偉大な人物であったのに対し、ここで描かれているのは、ビスマルクやヴィルヘルム2世ではなく、批評家や世間の嘲り・無理解と戦う芸術家の姿である。後述するように英雄が自らの業績を振り返る場面で、シュトラウスが自作の引用を行っていることから、初演当時からこの英雄はシュトラウス自身であり、自らを英雄に擬えるとは臆面もないとの非難があったが、この点につきシュトラウス自身がロマン・ローランなど何人かの人々に語った言葉が伝えられている。それによると、あるときは、自分自身に関する交響曲をなぜ書いてはいけないのか私にはわからないと言ったり、また別の場ではとくに曲自体にプログラムがあるわけではなく、戦いの場で敵と戦う一人の英雄を描いているということを知れば十分だと言ったり、必ずしも一貫しておらず、一体どちらが本音なのかと悩むところではあるが、後世の我々がこの曲を聞く際には、シュトラウスの自画像と思って聞くもよし、世間の無理解と戦う孤独な芸術家の姿を思い浮かべて聞くもよし、どのように聞いてもこの曲の価値が減ずることは無かろう。ただ、やはり、第5部が自作の引用で成り立っていること、第2部の英雄の伴侶が結婚して間もないシュトラウスの愛妻パウリーネを描写していること(この点についてはシュトラウスは明言している)などからすれば、英雄には作曲家自身の姿が色濃く投影されていると言わざるを得ないであろう。
この曲を書いたあとシュトラウスはオーケストラ作品としては、『家庭交響曲』作品53(1903)と、先日当団も取り上げた『アルプス交響曲』作品64(1915)という2つの大曲を書くが、後半生はもっぱらもう一人のリヒャルトの後を追って(あるいは越えようとして)、最後の楽劇『カプリッチョ』作品85(1941)に至るまで歌劇・楽劇作曲家としての道を歩んでいくことになる。(『英雄の生涯』を作曲した時点では、楽劇『ばらの騎士』作品59はおろか、この分野で初めて世に認められることになった、『サロメ』作品54すら書かれていなかった。)
全曲は切れ目無く演奏されるが、便宜的に6つの部分に分けられる。もともと各部に標題はなかったが、初演に際し主催者より聴き手の手引きとなる様、標題を付すことを求められ、シュトラウスが已む無く便宜的に付けたタイトルが残っている。楽譜出版に際してはこれらの標題は付されなかったが、曲の理解のためには便利なので、現在でも一般的に使われることが多い。以下それに従って各部の概要を見ていくこととする。
第1部 英雄
冒頭いきなりホルンとチェロがこの曲の基調である変ホ長調の分散和音を駆け上がり、ほとんど3オクターブにわたる堂々たる英雄のテーマを提示する。引き続きかなり遠い調性であるシャープが沢山付いたロ長調の優美な主題が直ぐにあらわれ、この英雄の持つさまざま側面が描かれていく。
第2部 英雄の敵
ほとんど調性感のない木管楽器による特徴的な音型、テューバによる5度音程の特徴的なリズムを持った音型などが、英雄の敵=批評家の嘲りや無理解・敵意を表す。あまりに執拗に繰り返されるこれらの攻撃に、英雄が苦悩し落胆する様がチェロ、バスクラリネット等の低音楽器で描かれ、英雄はこれに立ち向かっていこうとするが、対立が頂点に達したところで、突如として英雄を救うかのように、独奏ヴァイオリンによる英雄の妻が登場し、第3部に移行する。
第3部 英雄の妻
前半は独奏ヴァイオリンによる英雄の妻と、低音楽器による英雄との対話によって進められる、最初は英雄が妻をなだめたりすかしたりする様が描かれるが、途中から二人は寄り添い、全オーケストラによって二人の間の細やかな愛情が描かれる。(後半、第2ヴァイオリンには最低音(ソ)より半音低い音(♭ソ)が要求され、途中で調弦を変更しなくてはならないが、次の第4部ではまた元に戻さなければならず、これがなかなか厄介である。独奏ヴァイオリンについては、後で再述する。)
第4部 英雄の戦い
舞台裏のトランペットによるファンファーレが遠くから聴こえ、戦闘開始を告げる。チャイコフスキーの『くるみ割り人形』や『1812年』における戦闘場面でも聴かれるような、大砲や機銃の響き、奔走する兵士たちの足取り等がちりばめられているが、なぜかこの部分は3拍子で書かれていて、優雅なワルツに乗って踊るように英雄の妻が現れたりもする。敵との戦いは一進一退を繰り返すが、最終的には英雄の主題が圧倒し勝利を収める。
第5部 英雄の業績
英雄=シュトラウスがこれまでに作曲した数々の曲からの引用によるコラージュが織り成され、英雄の業績が回顧される。『ドン・ファン』、『死と変容』、『ツァラトゥストゥラ』、『ティル・オイレンシュピーゲル』、『ドン・キホーテ』等からお馴染みの旋律が次々に繰り広げられる。他に楽劇の処女作である『グントラム』、『マクベス』や自作歌曲からの引用もなされるが、これらは、余程のシュトラウス好きでもないとなかなか判り難いのではないか思われるので、末尾の譜例をご参照されたい。
第6部 英雄の引退と成就
英雄の敵がなおも現れ、英雄もそれに立ち向かいはするが、長くは続かず、やがて『ドン・キホーテ』からの引用を思わせる牧歌的なイングリッシュ・ホルンの響きが聴こえてくると、音楽はしだいに穏やかになり、過去を振り返りながら残りの人生を伴侶とともに平穏に暮らす英雄の姿が描かれる。独奏ヴァイオリンとホルンの対話により英雄は大往生を迎えるが、最後に金管楽器と打楽器により英雄に対する弔砲が高らかに奉げられ、その響きが消え去るとともに全曲は幕を閉じる。(初稿では、独奏ヴァイオリンにより静かに終わることになっているが、どちらの終わり方も捨てがたいものがある。)
さて以下は私事で恐縮ではあるが、今回の演奏会では前述の第3部英雄の伴侶における素敵なヴァイオリンソロを弾かせて頂けるという光栄に浴することになったのだが、とにかくこのソロはオーケストラ史上空前絶後の大ソロといっても過言ではなく、聴かせどころであるばかりではなく、曲全体の出来を左右することにもなりかねない箇所であるだけに、弾く者にとっては重責を感じざるを得ない。(技術的にもっと難易度が高い、あるいは時間的により長いソロは他にいくらでもあるかもしれないが、いろいろな意味でこのソロに匹敵するのは、ベートーヴェン『荘厳ミサ曲』ベネディクトゥスのソロくらいではないかと思う。コンサートマスターのオーディションなどでは必ず弾かなくてはならないという点でも。)
先述したように、この独奏ヴァイオリンは英雄の伴侶=作曲者の良き理解者であった妻パウリーネの描写であるのだが、新旧併せて30数種類の録音を聞いた中で、女性が弾いているものは1種類しかなかったのはやや意外な感じがする。私は今回このパートを弾くにあたって、パウリーネのことをよく知ることが演奏への手がかりになるのではないかと思い、いろいろと調べてみたのだが、シュトラウスや周囲の人々によるコメントもさることながら、やはり一番参考になったのは、シュトラウスの書いた音楽そのものであった。優れた歌手であった彼女のために、シュトラウスは彼女が演奏することを想定し
て実に様々なタイプの歌曲を書いているが、そこで要求される表現の幅の広さは、ヴァイオリンソロに非常に細かくつけられた表情指示(わざとらしくうな垂れて、陽気に、軽々しく、少しセンチメンタルに優しく、怒って、荒れ狂って、突然再びおとなしく情感に満ちて等々)と通ずるものがある。また、二人の間に本当にあった夫婦喧嘩をシュトラウスが自ら台本を書いてコメディに仕立ててしまった歌劇『インテルメッツォ』作品72では、宮廷楽長シュトルヒ夫人としてパウリーネそのものが登場するが、そこでの彼女の振る舞いはあるときはわざとらしくうな垂れ、媚を売ったかと思うと、突然陽気になり、その次の瞬間には激しく怒っているという様に、まるで、『英雄の生涯』のヴァイオリンソロそのものの様であり、上記の独奏ヴァイオリンに対する表情指示は、シュトルヒ夫人(=パウリーネ)の舞台上での一挙手一投足に対するト書きではないかと思われるほどである。
本日は、愛妻パウリーネ夫人の姿を、シュトラウスの書いた音符から音として蘇らせて、聴いて頂く方々に少しでも感じとって頂く事が、筆者に課せられた大きな課題であるが、それには私が女性であることを上手く活かすことができるのではないかと思っている次第である。
参考文献
“Richard Strauss” Kennedy Michael著(Shirmer, 1976 ; rev. 1995)
“Richard Strauss: Man, Musician, Enigma” Kennedy Michael著(Cambridge, 1999)
“Richard Strauss, An Intimate Portrait” Willhelm Kurt著(Rizzoli, 1989)
“Richard Strauss” Deppish Walter著(Hamburg, 1968)村井翔訳(音楽之友社1994)
作曲家別名曲解説ライブラリー⑨『R.シュトラウス』(音楽之友社1993)
初 演:1899年3月3日 リヒャルト・シュトラウス指揮フランクフルト・アム・マインに於ける博覧協会演奏会にて
被献呈者、メンゲルベルクとコンセルトヘボウオーケストラによる初演は1899年10月26日於アムステルダム
楽器編成:フルート3、ピッコロ、オーボエ3、コールアングレ(4番オーボエ持ち替え)、クラリネット2、Esクラリネット、バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン8、トランペット5、トロンボーン3、テナーテューバ、バステューバ、ティンパニ、シンバル、トライアングル、大太鼓、小太鼓、中太鼓、ドラ、ハープ2、弦5部(作曲家の指定では第1ヴァイオリン16、第2ヴァイオリン16、ヴィオラ12、チェロ12、コントラバス8)
第5部英雄の業績における自作引用(一部)
○歌劇『グラントラム』作品25より
○交響詩『マクベス』作品23より
○歌曲『解き放たれて』作品39-4より
○戯曲『たそがれの夢』作品29-1より
山下さん、初登場!
今回、指揮に初めて山下一史氏をお迎えいたします。カラヤンのアシスタントを務め、コンクール優勝を経てから現在に至るまでのご活躍ぶりは広く知られているところですが、ここではプロフィールだけではわからない“素顔の山下さん”をご紹介いたします。指揮者を目指していた少年時代や海外での貴重な経験、作品に対する熱い想いなどを大いに語っていただきました。
■ 「指揮者になりたい」
- 月並みな質問ですが、なぜ指揮者になられたのですか?
もともと音楽を始めたきっかけが「指揮者になりたかった」なんです。多分N響のコンサートのテレビ中継を見てだったと思うけど、ものごころがつく頃にはもうなりたいと思っていました。だってやっぱり指揮者が一番格好いいじゃない。一番後から出てきて一番大きな拍手をかっさらって。まだいろんな裏のことなんか知らないからね。(笑)最初はヤマハ音楽教室へ通いました。しばらくして広島にも東京と同じような桐朋学園の子供のための音楽教室ができたので、そこへ行くようになってピアノだけでなくソルフェージュなども教わりました。それで、「指揮者になりたい、なりたい」って言っていたんだけどオーケストラの中の楽器もやったほうがいいということで、小学4年からチェロを習い始めました。
その当時広島には優秀なチェロ弾きがたくさんいてね、山崎伸子さん、秋津さん(大フィル)、銅銀さん(N響)もみんな広島の出身なんですよ。それに、安田謙一郎さん、藤原真理さん、木越さん(N響)など錚々たる方たちが夜行電車に乗って教えに来てくださっていました。3ヶ月に1回くらいのペースで斎藤秀雄先生直々のレッスンもあり、本当に恵まれた環境でしたね。
中学2年のときに斎藤先生が亡くなられました。で、山崎さんが円光寺(雅彦)先生に「指揮者になりたい子がいるから」と僕を紹介してくれたんです。でも、円光寺先生は僕のことなど知らないからとりあえず左利きを理由に断ろうとしたんですよ。それで「高校から桐朋に行くつもりだから高校生になったら教えてほしい」とお願いすると、「それでは遅い」と円光寺先生に言われてしまいまして、それなら中学3年で上京しようかと考えました。山崎さんのお母さんにもハッパをかけられましてね。「伸子は小学生で斎藤先生に引っ張られて東京に行った。あなたは中学生でしかも男の子なんだからしっかりしなさい。」と。でも親にうちあけたらびっくり仰天しましたね。そして親父と「高校に入れなかったら音楽の道は一切諦める」と約束して、仙川のトイレも共同で風呂もないようなぼろいアパートに住むことになりました。調布の中学校に通いながら藤原真理さんのレッスンを受けたり、円光寺さんに教えていただいたりしました。高校2年からは円光寺さんが尾高(忠明)さんの一番弟子だったこともあって、尾高さんのレッスンを受けるようになりました。
だから大学では指揮科に行きたかったんです。桐朋のチェロ科はご存知のように指揮との二足のわらじをはける雰囲気ではないでしょう。一日もはやく指揮の勉強をしたかったし。それに何よりも中途半端にチェロをやることは許されないと思いました。一生懸命やっていましたけどね。それで尾高先生に相談に行ったら、一言、「とにかく大学を出るまではオーケストラの中で楽器を弾きながら指揮者のことを客観的に見なさい。」
たしかに高関(健)さんもヴァイオリン、大友(直人)さんもコントラバス。桐朋にはいいシステムがあったんですね。授業でも試験でも、指揮科だからチェロ科だからというわけ隔てがなかったんです。楽器をずっと弾いていたことは結果的にとてもよかったことだと思っています。
■ カラヤンのもとで
― 卒業後はベルリンに行かれましたね。
ベルリンはなんとなくだったんですよ。世界で最高のオケがあるから。カラヤンとかじゃなく。というか、最初はカラヤンに会えるとも思っていませんでした。高関さんみたいにカラヤン指揮者コンクールジャパンで優勝し招待されてベルリン・フィル・オーケストラ・アカデミーに行ったのと僕は全然違います。僕の場合は少ない奨学金をもらって何のあてもなく行ったんですよ。その頃ベルリン芸術大学から田中良和さんが帰国することになって、ちょうど席が空いたのでその後釜で入ることができました。
そのうち高関さんに連れられてベルリン・フィルの練習を聴きに行くようになりました。サラリーマンのように毎日朝から晩まで。よかったことは、高関さんはカラヤンの練習を見ることができたんですよ。普通はカラヤンの練習を見ちゃいけないんです。コントローラーがいて知らない人はつまみ出されるの。僕もつまみ出されていましたよ。(笑)高関さんとは同じ学校(桐朋)とは言っても年も離れているし師匠も違うから最初はそうでもなかったけど、ベルリン時代にとても親しくなりましたね。高関さんの家になかば居候していた時期もありました。(笑)
そしたら、1985年に高関さんが広響の音楽監督になるため帰国することになって、僕はその頃民音のコンクールに落ちてしょげかえっていたんだけど、「カラヤンのアシスタントをやってみる?」という話がありました。高関さんがそんなこと言わなかったら僕は今ここにいなかったですよ。(笑)
そのアシスタントの仕事というのはベルリン・フィルのVTR撮りのカメラリハーサルなんです。カラヤンが振った音楽に合わせて寄せ集めのオケを僕が振るんですよ。そのことについてはいろいろ言う人もいましたが、カラヤン本人が必ず立ち会っていましたから、彼は(カラヤン役の)僕が振っている姿をずっと見ているわけです。もちろんカラヤンは暗譜で指揮をするのでこちらも暗譜しなくてはならない。学校へもどこへも行かずに一日中本当に勉強しました。コンクールに落ちてどん底でまさに蜘蛛の糸にすがるようでしたね。ここから抜け出るにはこれしかないから本当に必死にやりましたよ。
初めてベルリン・フィルを振ったのは1985年の大晦日のコンサートのためのアシスタントをしたときでした。その時にカラヤンが気に入ってくれて、いきなり次はベルリン・フィルのカメラリハーサルということで、「魔弾の射手」の一部と「ボレロ」全部をやりました。その後すぐにカラヤンのマネージャーからこれから先のスケジュールに全部同行するよう言われました。また、ザルツブルク音楽祭は特別に契約をするから何かあったときのためのスタンバイでいるようにと。しっかりお金も出たし家も借りてくれましたよ。オペラの方は見学だけでしたが、その年(1986年)は「ドン・ジョヴァンニ」でね、「門前の小僧習わぬ経を読む」じゃないけど終わったころには全部覚えてしまいました。そういえば僕のオペラデビューは奇しくも「ドン・ジョヴァンニ」なんですよ。
- ベルリン・フィルの下振りみたいなことはいきなり言われるんですか?
そうですね。カメリハのとき限定ですけど。普通はベルリン・フィルは振れません。だってそこにカラヤンがいるわけですからね。
皆さんはカラヤンの代わりに振ったこととかに興味があるかもしれないけど、そのことよりも、ずーっと練習を聴けて、演奏会も録音も全部を見られて、その時の雰囲気をすごくよーく覚えている。生の現場に接したことが一番ですね。小泉(和裕)さんも高関さんも表面的には人それぞれ違うけど、カラヤンから非常に大きな深い影響を受けていると思います。本人にも計り知れない部分があるんじゃないかなぁ。
- カラヤンから直接指導を受けたことはありますか?
「第九」の第3楽章です。リハーサルの後にカラヤンが「山下を呼べ」ということで、音楽監督の楽屋に行きました。ソファに並んで座ってカラヤンが歌ったりしながら、最初から最後まで教えていただきました。結局手取り足取りみたいのはそれ一回きりでしたけどね。
■ ヘルシンボリへ
- プロとしてのデビューはどちらですか?
1986年のニコライ・マルコ国際指揮者コンクールで優勝したので、その関係で同年8月にチャイコフスキーの「悲愴」と「ロココの主題による変奏曲」を南ユトランド交響楽団と演奏したのが初めてです。日本では1987年に広島出身だという事で広島交響楽団が声をかけてくれて、その後札幌交響楽団は定期で呼んでいただいて「幻想交響曲」と「第九」を指揮しました。翌年1月には「若い芽のコンサート」でN響を振りました。
― 北欧でのご活躍もコンクールによるものですか?
そうです。コンクールの優勝記念コンサートがいくつかあって、デンマーク放送響とか振りました。で、その一環として行ったのが後に首席客演指揮者になったヘルシンボリ交響楽団です。ヘルシンボリはスウェーデンといってもデンマークに近くて、ストックホルムから入るよりも、コペンハーゲンからの方が便利な場所です。最初行って次の年も行ったらいきなりニールセンのシンフォニー。しかも6番。あのややこしい曲ですよ。それまでニールセンなんかまったく振ったこともなかったけれど、大きなチャンスだったし、北欧のオケで彼らの大切なレパートリーを任されたという大きな責任感を感じながら引き受けました。で、それ相応の結果が出たら、「今回はとてもよかった、君自身興味があれば毎年1曲ずつニールセンをやらないか?」というオファーを受けました。これは、6年はこのオケと付き合うということで、当然他の演奏会もやることになりました。日本とヘルシンボリとの行ったり来たりでしたがやっぱりやっていれば惹かれていきます。それで、結局常任のオッコ・カムの次に一番振っているから首席客演指揮者になってしまったというわけなんです。ヨーロッパのオケって指揮者とこういう仕事の仕方をするんだ、と思いました。日本だと最初にポジションありきで、良い時はワーッと使って、その後は・・・ということがあるけど、この人はいいなと思ったら、大事に6年間成長を期待するみたいなところがある。だって当然(年齢が)二十いくつの指揮者なんかいいわけがないじゃない。それでもどこかに良さを感じて、こいつの6年間を一緒に見てみたい、時間をかけて育てよう、というところがあるんですよね。
■ 現代曲は嫌い?
- ところで、プロフィールを拝見すると、現代曲もずいぶん振っていらっしゃるようですが。
デビューしたてはまったくダメでした。僕自身好き嫌いが激しくて本当に嫌いでしたね。音楽を苦しめているようで。例えば、これがオーボエではなくてクラリネットである理由を聞きたい。だってブラームスなら絶対あるわけじゃない。オーボエならオーボエの、クラリネットならクラリネットの必然性が。弦だってそうでしょう。ヴィオラでしか出せない音色とかブラームスだとある。でもひどい曲だと音域だけで楽器を使っている。楽器の生理みたいなものを無視しているんじゃないかと思うんですよ。
で、最初のうちは断っていたんだけどだんだんそんなことも言っていられなくなってきて。そんな時、渡邉曉雄先生の話を人づてに聞いたんですよ。「新しい作品を演奏するのは同時代に生きる我々演奏家の責任だ。我々が演奏しなかったら日の目を見ない、音にならない楽譜がある。世に出るチャンスがあるんだったらそれに協力する責任がある。」本当に目から鱗が落ちたとはこのことでそれから意識が変わってきました。結果的には淘汰されるにしても最初のチャンスがないと。もし良ければ再演されていくわけですからね。で、たくさんやってくると譜面を見ただけで良し悪しがわかるようにはなりました。去年も作曲家のコンクールみたいなものがあって20数曲の楽譜を読んで選定したりしましたね。
- 今回の新響のプログラムはまさにクラシックの王道を行くような曲目ですが。
僕自身現代作品もやっていきたいと思うんだけど初めて会うオケとはどうかな、と思って。やっぱり現代曲はまず音にするだけで大変だし、なかなか普段話しているような言葉やセンテンスのようにするのは難しいじゃない。やったことに意義があるだけでは最初の演奏会としてはどうかなぁ。現代曲でも自分の中で再演を続けてきた曲でないととりあげられないですよね。
■ さあ、「英雄の生涯」
- 今回のメインの曲目については、新響の意見として最初ブラームスの4番(交響曲)ということで先生にお伝えしていました。でも初めてお会いした時に、白紙の状態だとしたら先生は何がよろしいですかと「仮に」お聞きしたところ・・・。
仮に、だったんですか?(笑)是非ともリヒャルト・シュトラウスをやりたいと言いました。
言わずと知れたあの時代のカラヤンとベルリン・フィルの十八番で、右に出る人はいなかった!晩年のカラヤンの「アルペン・シンフォニー」を聴いたんだけどぶっ飛びましたね。もうその頃だいぶ足が悪くなっていて歩くのも大変そうでした。実は指揮台の背もたれに自転車のサドル状のものがついていて、もちろん客席からは立っているように見えるんですが、そこにまたがって指揮をするんです。そもそもカラヤンは指揮をするとき下半身は動かさない人でしたから。で、いったんそこにセットされてオケを振り始めたら、あのよぼよぼしていた人のどこにそんなパワーがあるのかと、そりゃあもう驚きました。まるでいい意味でのサイボーグのようでした。そういうのを目の当たりにしました。
リヒャルト・シュトラウスの作品はカラヤン自身が本当に好きだったんですよ。オケもよくそのことをわかっていました。ザルツブルクでの「英雄の生涯」のリハーサルで、カラヤンが終わったとき泣きはしなかったけど特別な雰囲気があって、それをオケも感知して自然とこう何というか・・・。カラヤンとベルリン・フィルとは仲違いしたという情報のみが独り歩きしている感があるけれど、勿論そういう部分もあったけれど、皆が思っているような完全に亀裂が入っていたわけではないと思うんですよ。夫婦がそうであるようにうまくいかないところもあるけど、こういう気持ちにさせてくれる人はこの人しかいないとか、そういったどうしようもない部分、「業」のような部分でものすごく固く繋がっていたんじゃないかと思います。カラヤンではないと出せない音、他の人では逆立ちしても絶対に出せない音があった。それが一番リヒャルト・シュトラウスの作品に表れていました。その音を僕も高関さんも小泉さんも聴いているから、どんな音かは言葉で説明できないけれど、不思議なもので相手がどんなオケであれ、指揮者がそこに思い描いて振っているとその片鱗が表れてくる時があるんですよ。魔法のようなことなんだけどね。だから安易なプログラミングと思われるかもしれないけど、だからといって僕も「英雄の生涯」は何度も振ったことがないから本当に大切な一回です。
「ハイドン・バリエーション」は、新響でもこれまで何度も挙がっていたけど、なかなか実現しなかったと最初お会いしたときに聞きました。「僕もそれはよくわかります」と答えたのを憶えています。あんな難しい曲はないですからね。でもそれをわかった上であえて取り上げます。そうしたらもう1曲(悲劇的序曲)はある程度必然的に決まりましたね。
- また「英雄の生涯」に話は戻りますが、新響では1978年に演奏して以来になります。先生からご提案を受けて団員の意見を聞いたんですけど、反対が多いかと思ったら意外とそんなこともなくてすんなり決まってしまいました。実は皆やりたかったのかと・・・。
誰かが言うのを待っていたんじゃない?(笑)まあ、こういうことはタイミングの問題もあるでしょうね。
「ツァラトストラ」だと別の難しさがあって、でもここのオケならパズルを組み立てるようにぱっとできあがると思うけれど、「英雄の生涯」はそうはいきません。よりリヒャルト・シュトラウスの世界があると思います。まぁ、実際凄い曲ですよね。晩年のリヒャルトは「オーボエコンチェルト」や「メタモルフォーゼン」みたいに室内オーケストラのような方向に進んでいくようになったけれど、そんなことになるとはまったく考えられない。三十何歳でこれを書いているんだから、ある意味絶頂期でもあり驕りも表れていますよね。それがまたものすごく魅力的です。「ここまで俺はできるぞ」みたいなね。
2007年5月8日
聞き手:土田恭四郎(テューバ)
撮影:桜井哲雄(オーボエ)
まとめ:田川暁子(ヴァイオリン)
昔も今も、パワフル山下さん
維持会員の皆様、いつもご支援ありがとうございます
今回の演奏会では新響の指揮台に初めて山下一史さんが登場します。
プロ・アマを問わず数多くのオーケストラを振っていらっしゃいますからご存知の方も多いことでしょう。山下さんは桐朋学園大学をご卒業後にベルリン芸術大学に留学し、カラヤンの最晩年にアシスタントをされていました。1986年に急病のカラヤンに代わってジーンズ姿で急遽ベルリン・フィルの第九を指揮し大喝采を浴びたエピソードはあまりにも有名です。
さて、私事で大変恐縮いたしますが、ちょうど同じころ私は都の西北にある某私立大学に入学しそこの交響楽団に入りました。オーケストラの中で弾くのはまったくの初めてで、とにかくわからないことだらけで不安なことばかり。ひとり飛び出したり落ちたりしないよう、練習中は怖い指揮者や先輩からいかに目をつけられずにすむかで必死でした。(私にもこんな初々しい時期がありました。懐かしい・・・。)そんな私の頭の中では、指揮者といえば「白髪・巨体・威圧」というイメージがいつしか出来上がっていました。 2年生になってしばらくすると初めての指揮者が練習にやってきました。
「うわぁっ、若い!」(怖くなさそう、よかった~♪)
そうです、それは当時まだ20代半ばの山下さんでした。髪は黒いし、お腹も出ていないし、偉そうでもない。目がくりっとして元気ハツラツのお兄さんではないですか!私の指揮者イメージ払拭です。練習はとにかく熱心で時には厳しく(“プルト弾き”なんてのもありましたっけ)、学生たちは一気に引き込まれていきました。
それ以来、演奏旅行も含めて卒業までに山下さんの棒では十数曲を演奏しましたが、得意とするリヒャルト・シュトラウス(ドン・ファン)とブラームス(第2交響曲)が私の学生演奏活動の締めくくりとなりました。カラヤン譲りの壮麗で輝かしい部分はもちろんパワー全開ですが、ただ大味なのではなく、緻密さ、正確さも同時に求め、学生相手だからと手を抜くことはなかったと記憶しています。そういえば、「ドン・ファン」では再現部直前のあのチェロのパッセージも最後まで妥協しませんでした。(ちなみに山下さんはチェロ弾きです。)
実はプログラム用のインタビューのため、すでに山下さんには一足お先にお目にかかりました。(プログラムのインタビュー記事をお楽しみに!)最初にお会いしてからなんと20年(!)になりますが、あまりお変わりなくパワフルで明るい山下さんは健在でした。いろいろなお話を伺いましたが、やはりカラヤン=ベルリン・フィルの話になると止まりません。特にリヒャルト・シュトラウスに関しては、何度も生で見聴きしていないとわからない貴重な経験や面白い話が次から次へと出てきて興味は尽きませんでした。当然ながら、山下さんご自身、体にしみついたリヒャルトの作品の中でも大切な「英雄の生涯」を取り組むことに並々ならぬ意欲をもっておられます。ブラームス2曲を含めてこの難曲を仕上げることは私たちにとって並大抵なことではありませんが、きっと充実した演奏会になるものと信じております。どうぞご期待ください!
ブラームスとの「悲劇的」なエピソード
維持会員の皆様、いつも新響を応援してくださってありがとうございます。以前維持会の係をしていたときは皆様の暖かい励ましのお言葉を直接お聞きすることができ大変うれしく思いました。今回は音楽とはあまり関係ない非常に私的な話ばかりで申し訳ありません。
高1の時ブラームスの第1交響曲に夢中になってからは、毎日ブラームスの交響曲を聴いて過ごす3年間でした。(ちょっと暗い女子高生?)大学以降も、ブラームスはずっと大好きな作曲家でした。曲がすばらしいだけでなく、実際に演奏してみてもフルートは1番だけでなく2番もとても面白く、何度でも演奏したい曲ばかりですし。そして就職してしばらくして初めてヨーロッパを訪れ、ウィーンに出かけた時のことです。ウィーンの中央墓地には有名な作曲家のお墓が集まっている場所があります。もちろん我が愛するブラームスも。私は張り切って墓地に出かけ、まず赤いバラをブラームスのお墓に捧げました。中央墓地のブラームスのお墓には彼の胸像がついています。肩肘をついて視線を斜め前方に向けている像です。この前に立って写真を撮ればあこがれのブラームスとのツーショットが撮れる!!私は喜び勇んで墓石の前方に並んで写真を撮りました。帰国後わくわくしながら現像してみると、なんと!!ブラームスの視線は私とまったく逆方向に向いていて、これでは「ブラームスに無視されている写真」ではありませんか!!
その年の冬、その頃所属していた関西の某アマオケのメンバーと一緒にウィーンで年越しをすることになりました。みんなと中央墓地に出かけた私はもう一度ブラームスとのツーショット写真に挑戦しました。今度は反対側に立ち、胸像の視線もよ~く確認してから撮影。安心してウィーンのワインとフォルクスオパーのこうもりを楽しみながら新年を迎え、今度こそ、と帰国後いそいそと現像してみたら、なんと!!ブラームスの視線は確かに私の方を向いているのですが、その表情はなんだかさえなくてこちらをちらっと見ている・・・これでは「ブラームスにあきれられている写真」ではありませんか!!今のようにデジカメが普及している頃だったらこんなことはないかもしれませんね。
その後もウィーンは何度か訪れましたがまだブラームスとのツーショット写真には再挑戦できていません。どなたか成功された方がいらっしゃいましたらぜひ方法を教えていただきたいものです。ところで翌年私はそのアマオケのトロンボーン奏者と結婚することになったのですが、結婚式の前の演奏会で吹いたのがマーラーの交響曲第6番「悲劇的」。結婚式直後の演奏会で吹いたのが今回演奏するブラームスの「悲劇的」序曲。なんとなくその後の生活に不安を抱いた私でしたが、なんとかずっと一緒にオーケストラを続け来年20周年を迎える予定です。久々の「悲劇的」序曲、演奏は悲劇的にならないようにがんばります。
「英雄の生涯」と偉大なるホルン奏者
R.シュトラウスの作品全てにおいてホルンは活躍の場が与えられていますが、特に「英雄の生涯」では主役である「英雄」としての役割を担いホルン奏者にとって特別重要なレパートリーとなっています。冒頭より弦楽器と共に演奏するテーマからホルンの音色を印象付けます。途中8本のホルンセクションによる咆哮から最後の弱音でのソロまで、ホルンという楽器の持つ表現力を最大限に引き出しています。従って「英雄の生涯」の演奏においては独奏ヴァイオリンと共にホルンの演奏が注目されるところとなります。そこで「英雄の生涯」の演奏に絡めて、20世紀の偉大なるホルン奏者についてご紹介させて頂きます。
1 ゲルト・ザイフェルト(1931-)
ザイフェルトはカラヤン時代のベルリン・フィルのサウンドを支えた偉大な奏者であり、多くのオーケストラのホルン奏者にとっての理想、目標となっています。全てのオーケストラ曲の演奏においてザイフェルトの演奏は規範となるものですが、特にカラヤンの最も得意とするR.シュトラウスにおいて、広い音域、極限まで抑えられた弱音から、ベルリン・フィルの大音量の全奏をも突き破る強音まで完璧にコントロールされた演奏には驚嘆させられます。EMIにより1974年に録音された「英雄の生涯」でカラヤン/ベルリン・フィルの全盛期の記録を聴くことができます。また1986年のサントリーホールのオープニングシリーズにおいて、カラヤンの代理として小澤征爾がベリルン・フィルを指揮した「英雄の生涯」の演奏はサントリーホールの誕生と共に多くの日本人の記憶に残る演奏でしたが、テレビで放送されたこの演奏会でのザイフェルトの演奏は特に素晴らしいものであり、ビデオに記録されたこの演奏は私にとって永遠のスタンダードとなっています。
ここで雑誌「パイパーズ」2005年5月号に掲載された元ヤマハの技術者であり、現在ベストブラス社長である濱永晋二氏のコラムよりザイフェルトに関する記述をご紹介いたします。『20年位前の東京でのことです。当時のベルリン・フィルのホルンセクション全員とソリストの故アラン・シビル氏が同席した貴重な試奏会での出来事でした。試奏会は通常生産品です。まず、メンバー全員が自由に試奏を開始しました。みんなの音が入り混じる中、少し遅れてザイフェルト氏が到着。そのうるさい(失礼)音の中で、ザイフェルト氏が英雄の生涯のフレーズを本番さながらの勢いで吹いた途端、周りの音が全く無くなり、彼の音だけが部屋中に鳴り響きました。このときの音が私の耳には、まるでオーケストラが一緒に鳴っている音に聴こえたのです。生涯忘れられない思い出の一つです。』
2 ローラント・ベルガー(1937-)
ウィーン・フィルは世界で最も統一された演奏スタイルと独自の音色を共有するオーケストラです。中でもウィーン式の楽器を用いるオーボエとホルンはその特徴的な音色が大きな魅力となっています。独特な構造を持ったウィンナ・ホルンは通常のホルンに比べて演奏困難な楽器ですが、ウィーンのホルン奏者達はその伝統の音色を守るべく切磋琢磨し、素晴らしい演奏を聴かせています。ウィーンの名手達の中でも60年代、70年代に首席奏者として活躍したローラント・ベルガーは偉大なる奏者として知られています。一部の室内楽演奏以外でソリストとして名前が出ることが少ない奏者ですが、多くのウィーン・フィルの演奏においてベルガーの名演を聴く事が出来ます。例を上げればショルティによるワーグナーのリングでのジークフリートの角笛、カール・ベームのブルックナー「ロマンティック」、ブラームスの交響曲、バーンスタインとのマーラーなどでしょうか。その魅力はまさに「朗々たるホルンの響き」であり、鳴り響く大音響は強い印象を残します。R.シュトラウスとも関係深かったウィーン・フィルはシュトラウスの演奏において多くの名盤を残しています。ベルガーによる「英雄の生涯」の録音も複数あるものと思いますが、確実にベルガーの演奏であろうものとして1977年のカール・ベームによる録音があります。晩年のベームによる重量級の演奏ですが、ウィーン・フィルの音色の魅力に溢れた演奏となっています。
3 デニス・ブレイン(1921-1957)
「英雄の生涯」の歴史的録音として作曲者の自演も残っておりますが、ホルン奏者にとっての遺産というべき録音に1947年11月トーマス・ビーチャム指揮によるロイヤル・フィルの演奏があります。この録音において伝説の名手デニス・ブレインによる演奏を聴く事ができます。デニス・ブレインは1945年にウィルター・レッグにより創設されたフィルハーモニアの首席奏者として活動し、特にカラヤンと多くの録音を残しています。フィルハーモニアはトーマス・ビーチャムにより最初の演奏会を行い、ビーチャムはこのオーケストラを自分のものとしたいと申し出るものの、常任指揮者を置かない方針のレッグに断られ、1946年に自分のオーケストラとしてロイヤル・フィルハーモニック(RPO)を結成します。デニス・ブレインは二つのオーケストラの首席奏者をかけもちすることになります。
デニス・ブレインとR.シュトラウス、ビーチャムについて興味深い逸話がありますのでスティーブン・ベテット著山田順訳「奇跡のホルン デニス・ブレインと英国楽団」(春秋社)から引用してご紹介します。
『リヒャルト・シュトラウスの作品は常に独奏ホルンのための豊麗なパートを含んでいるが、ビーチャムは、1947年秋ドルーリィ・レインのサター・ロイヤルで開始されたRPO演奏会の新シリーズを、この作曲家を讃えるフェスティヴァルの一環とすることを決めた。この企画は大成功であったが、既に84歳を迎えようとしていたシュトラウスが自らフェスティヴァルに臨席し、さらには演奏会の指揮も引き受けるに及んで、一層の盛り上がりを見せることになった。もっともシュトラウスが実際に指揮をしたのはRPOではなく、フィルハーモニアであった。10月19日、ウォルター・レッグもやはりシュトラウス・フェスティヴァルに参加する演奏会をロイヤル・アルバート・ホールで催し、作曲者自ら「ドン・ファン」「ブルレスケ」「家庭交響曲」を指揮したのだった。シュトラウスはこれより先、10月初めにビーチャムがRPOと行ったリハーサルと本番にも立ち会っていた。10月5日にはポール・トルトリエが「ドン・キホーテ」のチェロ独奏をとつとめ、その一週間後にはデニスが「英雄の生涯」を吹き、特に終曲の崇高かつ困難なホルン・ソロにおいて素晴らしい演奏を聞かせた。評論家の一人はデニスのカーマニアぶりを念頭に、「英雄の生涯」の冒頭を評して「彼はギアを三回シフトさせたようであった!」と書いている。』
この演奏会の後の11月にアビーロードスタジオにて行われた録音が上述したものです。古い録音ですがデニス・ブレインの気品ある音色を感じ取ることが出来ます。この翌年にデニスとRPOの関係に「英雄の生涯」を発端とするトラブルが発生します。
『ウォルター・レッグもトーマス・ビーチャムも、デニスのような奏者がこうした形でかけもちを行っていることを決して快くは思っていなかったが、本番がかち合わない限りにおいて、このシステムは何とか機能していた。両人とも、特定の奏者から全面的な忠誠を得ようと努め、例えばビーチャムはデニス、ジェイムズ・ブラッドショー、レジナルド・ゲルといった奏者については報酬を上乗せした。しかし、1948年12月には危機が訪れた。RPOはブラッドフォード、リーズ、マンチェスター、ハンリー、ウルヴァーハンプトンへの演奏旅行を行うことになり、プログラムにはリヒャルト・シュトラウスの「英雄の生涯」が含まれ、12月15日にはロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでも同じ曲目が演奏される予定であった。デニスはフィルハーモニアへの出演の関係で演奏旅行には参加出来なかったが、ロンドンの演奏会だけは出られる状況にあった。ここに到って、RPOの三番ホルンでデニスが不在の時は一番を吹いていたロイ・ホワイトが、憤然として抗議の声を上げた。演奏旅行の間中、「英雄の生涯」のきついソロを吹かされたあげく、最後のロンドンの演奏会ではデニスが戻ってくることに我慢がならなかったのである。ビーチャムは、人々が持つ印象とは異なり本来気楽な性格の持ち主であったが、問題の重大性を認識すると、直ちにデニスにメッセージを発した。すなわち、演奏旅行とロンドンの演奏会の両方に参加するか、さもなければRPOと袂を分かつかのいずれかにせよ、と。デニスは即座に退団を決め、残る1949年の間中、ロイ・ホワイトがRPOの首席ホルンを務めることになった。この間には、ビーチャムの70歳記念演奏会やリヒャルト・シュトラウス追悼演奏会も行われたが、当然ながらビーチャムは不満であった。彼は「聴衆は小利口な若いホルン奏者ではなく、この私を目当てにやってくるのである」と強がりを言った。それでも、フィルハーモニアとレッグへの対抗意識から、自分が重大な判断ミスを犯してしまった点は認めざるを得なかった。』
なおこの後の1950年にデニスはRPOに復帰しています。
デニス・ブレインは1957年9月1日未明に自身の運転する自動車事故により36歳という若さで帰らぬ人となりました。
第198回演奏会ローテーション
| 悲劇的序曲 | ハイドン変奏曲 | 英雄の生涯 | |
| フルート1st | 岡田 | 兼子 | 松下 |
| 2nd | 藤井 | 藤井 | 新井 |
| 3rd | - | - | 丸尾 |
| Picc | 丸尾 | 丸尾 | 岡田 |
| オーボエ1st | 岩城 | 亀井淳 | 堀内 |
| 2nd | 桜井 | 亀井優 | 山口 |
| 3rd | - | - | 岩城 |
| 4th(CA) | - | - | 亀井淳 |
| クラリネット1st | 進藤 | 中條 | 品田 |
| 2nd | 末村 | 末村 | 大藪 |
| EsCl | - | - | 高梨 |
| BsCl | - | - | 石綿 |
| ファゴット1st | 長谷川 | 浦 | 田川 |
| 2nd | 田川 | 長谷川 | 星 |
| 3rd | - | - | 浦 |
| コントラファゴット | - | 星 | 長谷川 |
| ホルン1st | 鵜飼 | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 山口 | 大原 | 山口 |
| 3rd | 園原 | 比護 | 大原 |
| 4th | 比護 | 箭田 | 鵜飼 |
| 5th | - | - | 園原 |
| 6th | - | - | 比護 |
| 7th | - | - | 大内(*) |
| 8th | - | - | 金城(*) |
| トランペット1st | 北村 | 北村 | 野崎 |
| 2nd | 中川 | 小出 | 青木 |
| 3rd | - | - | 小出 |
| Es1 | - | - | 倉田 | Es2 | - | - | 中川 |
| トロンボーン1st | 志村 | - | 志村 |
| 2nd | 佐藤(*) | - | 佐藤(*) |
| 3rd | 大内 | - | 岡田 |
| テナーテューバ | - | - | 武田 |
| テューバ | 本橋 | - | 土田 |
| ティンパニ | 古関 | 中川 | 桑形 |
| トライアングル | - | 今尾 | - |
| シンバル | - | - | 古関 |
| 小太鼓 | - | - | 今尾 |
| 中太鼓、Tri、Tam | - | - | 桜井 |
| 大太鼓 | - | - | 中川 |
| ハープ 1st | - | - | 佐々木(*) |
| 2nd | - | - | 太田(*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(田川暁) | 堀内(田川暁) | 前田(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 岸野(宇佐美) | 岸野(宇佐美) | 岸野(荒井あ) |
| ヴィオラ | 柳沢(小野崎) | 柳沢(小野崎) | 柳沢(田口) |
| チェロ | 日高(光野) | 日高(光野) | 光野(柳部) |
| コントラバス | 村山(中野) | 村山(中野) | 中野(村山) |
第198回演奏会のご案内
山下一史 初登場
今回の演奏会では、指揮に山下一史氏を迎えます。カラヤンの助手をつとめていた1986年、急病のカラヤンの代役としてジーンズ姿のままベルリンフィルの「第九」を振り話題となりました。以後国内外で活躍しており、情熱的なタクトと緻密なアンサンブル作りに定評があります。新響は初共演にあたり、山下氏がライフワークとしているリヒャルト・シュトラウスの作品を選びました。
英雄の生涯=R.シュトラウスの「自伝」
リヒャルト・シュトラウスは、ミュンヘン宮廷歌劇場の首席を45年間つとめた名ホルン奏者を父に持ち、古典派音楽の教育を受けて育ちますが、大のワーグナー嫌いだった父の意に反しワーグナーやリストに傾倒していきます。若い頃に交響詩を7曲書いており、この「英雄の生涯」は最後の交響詩作品です。
「ドン・ファン」や「ツァラトゥストラはかく語りき」といった彼の他の交響詩が文学作品をテーマにしているのに対し、「英雄の生涯」には文学的なモデルがなく、自伝ではないかといわれています。リヒャルト・シュトラウス=英雄が輝かしく成功し、妻をめとり、敵に叩かれながらも立ち向かい勝利して、業績を残して静かな余生を送るという一生を、4管編成ホルン8本の大オーケストラで楽しく描かれます。当時既に指揮者としても作曲家としても人気を博していたとはいえ、まだ34歳で自伝とは、ユーモアなのか自己顕示欲が強いのか・・・。いずれにせよ作曲家はその後50年生き、「英雄の生涯」のような人生を過ごしました。
R.シュトラウスとブラームス
リヒャルト・シュトラウスが21歳の時、ブラームスにアドヴァイスをもらっています。ワグネリアンであったとはいえ、30歳年上の巨匠との出会いは嬉しかったことでしょう。
コンサートの前半では、意外に数の少ないブラームスの管弦楽曲の中から、明るい「大学祝典序曲」と対で作られた「悲劇的序曲」と、古い賛美歌がテーマとされる「ハイドンの主題による変奏曲」を演奏します。
ブラームスは、ワーグナーやリストといった同時代の作曲家が扱っていた標題音楽には手をつけず、絶対音楽にこだわっていました。同じドイツロマン派でも、古典主義的で室内楽的に美しいブラームスの作品と、一歩先を行っていた壮大な響きのリヒャルト・シュトラウスの作品の組み合せで、オーケストラの2つの顔をお楽しみください。
特別寄稿 二つの名交響曲徒然(つれづれ)
リズムのルーセル(1869-1937)対メロディーのラフマニノフ(1873-1943)!?―なんと短絡的な位置付けよ!!
音楽の始まりは原始人の叩く太鼓のリズムからだったのか、それとも歌からだったのか、これは永遠に尽きない議論だが、それぞれの作品・作曲家にはバランスの違いはあるにせよ、その両者共に必要不可欠のものであり、それが「音楽」というものなのだ。
確かにこの二人の作曲家の“歌”の部分は全く対照的と言えるだろう。古今東西一、二を争うメロディーメーカーであったあのチャイコフスキーの後継者を自他共に認めるラフマニノフの旋律は、演奏の質・性格によっては映画音楽かと思わせる危うさを孕んでいるものだ。演奏の格調の高さを保ち、センチメンタルなだけの印象を聴衆に与えないよう、演奏者は心しなければならない。とは言うものの、喩えるならば、美味なるミルクチョコレートの誘いのようなラフマニノフの甘美で切なく、憧れに充ちたメロディーに対して、ルーセルのそれは滑らかではあるが、カカオ85%のビターチョコレート、或いは辛口のキリッとしたフランスの白ワインのような、甘ったるさとは無縁の独特な趣を持つ。(余談だが、個人的には、リハーサルの合間に元気を回復させるために摂るチョコレートはカカオ75%ぐらいのものが自分には丁度よい感じと結論づけているし、フランスの白ワインでは少し生臭い感じのあるミュスカデも好みである)
さて次に、この二人の作曲家の精神風土の違いの面に目を向けてみよう。私見ではルーセルは心身共に非常に健全な人間であったように思える。 その音楽・音符の持つエネルギーに満ちた表現意欲は健康そのものの人間にしか書けない音楽であろう。私には彼の音楽は大変によく理解できる。(実は私もオーケストラから「いつも元気でエネルギッシュですね!」と言われており、最近は“ターミネーター小松”というニックネームを頂いているのです?!) 聴いている人に元気を与える音楽という意味ではベートーヴェンに匹敵するかもしれない。そしてその中にフランス人らしいエスプリが点滅する。 「剛毅の中に遊び心」-これがルーセルの本質だろう。
一方ラフマニノフは基本がスラヴである故、根本的な性格はメランコリー(哀愁)であり、その上に交響曲第1番の不評から精神障害を起こし、医者の暗示によってようやく立ち直り、有名なピアノ協奏曲第2番(1901年)やこの交響曲第2番を作曲したという経歴を持つのがルーセルと対照的であり、見逃してはならない点である。しかしロシアシンフォニズムの流れを受けつぎ、それまでのどの交響曲よりも“悠久の流れ”を感じさせるこの曲の特質は特筆に価するものであり、小刻みに時間に管理される現代人に人気が高いというのも、音楽というものの持つ“癒し”の効果を考えると納得がいく。
以上、今回は対照的な性格を持つ名交響曲をお楽しみいただければ幸いです。 本日も私は入魂・渾身の指揮を念じて指揮台に登りたいと存じます。ありがとうございました。
197回演奏会曲目解説
ルーセル:交響曲第3番
アルベール・ルーセル Albert Charles Paul Marie Rousselは1869年4月5日、フランス北部トゥールコアンで生まれた。両親共に彼が子供の時に亡くなり、祖父や叔父と叔母の下で育てられた。彼は母からピアノとソルフェージュの基礎を教わっており、この頃から音楽に興味を持ってはいたが、その時点では音楽家になろうと決意していたわけではなかった。彼は元々体が弱く海沿いのリゾート地でよく療養しており、これがきっかけで彼は海に興味を持つようになり、18歳の時に海軍に入ることを決意し、パリの海 軍兵学校へ入学した。
ところがルーセルは海軍で成功しようとしつつも、音楽への興味は強まる一方だった。友人やルーベ音楽院長ジュリアン・コシュールの勧めもあり、本格的に音楽家になることを決意し、1894年には海軍を辞職しパリへ渡り、ウジェーヌ・ジグーの下で、また1898年には新しくできたスコラ・カントルムへ入学しヴァンサン・ダンディの下で学んだ。さらに、まだ学生ではあったが1902年には同校で対位法を教授し始めた。1908年、ルーセルは全ての科目を修了し、正式に学校を卒業することができた。
1908年4月7日、ルーセルはブランシュ・プレザッシュと結婚し、夫婦で4ヶ月間クルーズへと出かけインドなどを旅した。この旅行がよく反映されている作品に、交響詩《エヴォカシオン》、舞台音楽《パドマヴァティ》等がある。しかし、この後第一次世界大戦が勃発し、彼は陸軍の救急車の運転手として召集されたが、結局体調を崩し1918年に復員した。
1921年にはノルマンディーのヴァランジェヴィルにヴァステリヴァルという海沿いの別荘を購入し、彼のほとんどの作品はここで作曲された。同年10月には交響詩《春の祝祭のために》が、また1922年3月には交響曲第2番が初演され、これら数々の作品によってルーセルの評判はヨーロッパ全土、またアメリカでも急上昇することとなった。クーセヴィツキーはルーセルの交響曲第2番に対し賛辞を送っており、一方ルーセルは次の管弦楽曲《ヘ調の組曲》をクーセヴィツキーへ献呈している。
今回演奏する交響曲第3番は、1930年、ルーセル61歳の時にボストン交響楽団50周年を記念してクーセヴィツキーの委嘱により作曲された。この初演のために彼は夫婦で初めてアメリカへと渡り、その初演に立ち会った。ちなみにこの時の委嘱によって他にストラヴィンスキーの詩篇交響曲、オネゲルの交響曲第1番が作曲されている。
その後、ルーセルは心臓発作によって1937年8月23日にロワイアンで没した。
交響曲第3番 ト短調 作品42
これは4楽章から成る交響曲であり、フランス音楽の雰囲気を持ちつつも非常にリズミックな曲となっている。それぞれの楽章は第1楽章の展開部終盤で現れる5音のモットーによって支配されている(譜例1)。
第1楽章Allegro vivo
第1楽章は複雑なソナタ形式で構成されている。
提示部は3拍子の激しいリズムで始まる。この上に飛び跳ねるような高音楽器を伴い、モチーフは何度も繰り返される。この第1主題が弱まってくると、フルートによって第2主題が示される。
展開部では木管楽器とホルン、ハープによってやわらかな主題が奏されるが、次第に調性は失われ不協和音によって音楽が強まり、Tuttiで展開部の頂点を迎え、5音のモットーを繰り返す(譜例1)。
再現部においては、まず第1主題がほぼ元の通りに現れる。第2主題がオーボエによって再現された後にこれまでのテーマの断片が現れ、ト長調のフォルティッシモで終わる。
第2楽章Adagio
第2楽章は大きく3つに分けることができる。
第1部は5音のモットーを元にしたモチーフで、アダージョで始まる(譜例2)。これは対位法的に拡張され、ティンパニが加わったところで二度頂点を迎える。
第2部は生き生きとしたフーガとなっている。5音のモットーに基づいた主題と対旋律(譜例3)が繰り返された後に、フーガの主題が引き伸ばされた形でヴァイオリンに現れ、第2楽章の頂点を迎える。
第3部は再びアダージョとなり、冒頭のテーマが再現され、一度クライマックスを迎えるがその後は徐々に緩んでいき、最後は変ホ長調の和音で終わる。
第3楽章vivace
第3楽章はにぎやかな3拍子で古典的なスケルツォとなっており、形式的には変形されたソナタ形式のように見られる。
提示部では、まず弦楽器によってニ長調の第1主題が提示される。Tuttiで譜例4のモチーフが奏され、さらに展開され8小節間の特徴的なテーマが現れる。軽く踊るような第2主題は、その後木管楽器によって提示される。
展開部ではまずヘミオラのリズムに乗って前進し、第2主題がTuttiで奏される。展開部では提示部と比べ、楽器の音域・音量・編成等の面でよく対比されている。
再現部ではまず第1主題が低弦に現れ、第2主題は弦楽器によって柔らかく再現される。8小節のテーマとその断片が現れ、ピアニッシモで終わる。
第4楽章Allegro con spirito
第4楽章はソナタ形式、もしくは自由なロンド形式で構成されている。
提示部ではまずフルート・ソロで第1主題が示される。これは木管楽器によって展開され、3/4と4/4拍子が交互に現れ活気のあるモチーフがTuttiで奏される。第2主題は高音楽器によって示される。
展開部では徐々に音楽が静まっていき、アンダンテとなる。ここでは5音のモットーに基づいたメロディーがヴァイオリン・ソロによって展開される。
フルート・ソロの駆け上がりを合図に再現部となり、テンポは加速しアレグロ・モルトとなる。変拍子が調性を変えながら4回現れると音量は頂点に達し、5音のモットーがTuttiで壮大に繰り返され、最後はGのユニゾンで曲を閉じる。
参考文献
B. Deane, “Albert Roussel”, Barrie and Rockliff, London (1961)
J. M. Eddins, “The Symphonic Music of Albert Roussel”, フロリダ州立大学博士論文 (1966)
初演:1930年10月24日 ボストン
セルゲイ・クーセヴィツキー指揮 ボストン交響楽団
楽器編成:フルート3(ピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット4、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、トライアングル、大太鼓、小太鼓、ドラ、タンバリン、ハープ2、チェレスタ、弦5部
ラフマニノフ:交響曲第2番
作曲から長い年月が経ってもなお感動を与え続ける音楽を生み出した人間は、間違いなく天才である。一言に天才と言っても、モーツァルトのような神から才能を授けられた者もいるが、挫折や苦悩を乗り越え、努力を重ねて傑作を生み出す者もいる。ラフマニノフは圧倒的に後者である。
ラフマニノフは、モスクワ音楽院ピアノ科を過去最高の成績で卒業、同音楽院作曲科でも優秀な成績を修める。発表する作品は激賞され、特に初めて取り組んだオペラ「アレコ」は尊敬するチャイコフスキーから高い評価を受けるなど、20歳を過ぎたばかりのラフマニノフの前途は洋々であった。
ところがある時、彼の輝かしい音楽歴は一変する。満を持して取り組んだ交響曲第1番の初演が大失敗に終わってしまうのである。原因は曲に対する指揮者の理解不足と練習の不手際にあったのだが、新聞に載った批評の内容は「地獄に音楽院があったら、こんな作品が生まれるだろう」と作曲者への手厳しい批判だった。
24歳のラフマニノフ青年が受けた精神的ショックはあまりに大きく、その内向的な性格も災いし、強度の神経衰弱・自信喪失に陥る。以後数年もの間、作曲のためのペンを握ることさえ殆ど出来なくなってしまう。音楽教師、歌劇場の第二指揮者という職に就いて生計を立てるも、自分の天分は作曲だと信じるラフマニノフにとっては手足をもがれたに等しく、長い苦悩の日々を過ごすことになった。
しかし、彼は甦る。精神科医ニコライ=ダーリの尽力により徐々に自信喪失状態を克服し、チェーホフら文学者との交友から創作意欲を刺激され、作曲活動を再開する。そうして書き上げたピアノ協奏曲第2番が大成功を収め、その評判に手応えを感じたラフマニノフは、トラウマとなっていた交響曲の分野に再び挑戦。チャイコフスキーなど偉大なるロシアの先人達の作風を踏襲したこの曲の初演は大好評、ロシア音楽界で最も栄誉ある賞の1つであるグリンカ賞を授与される。ラフマニノフ34歳、交響曲第1番の挫折から10年あまりの月日が経っていた。
ラフマニノフの作品は、映画のワンシーンが思い浮かぶようなロマンティックなメロディーの宝庫である。交響曲第2番も例外ではない。1990年代にフジテレビで放映されたドラマ「妹よ」で、唐沢寿明演じるイケメン御曹司の好きな曲がこの交響曲の第3楽章であった。この楽章の持つ甘美な雰囲気は、主演の和久井映見が憧れる存在という設定にリアリティを与え、演出効果抜群であった。
そういった特徴があまりにも印象深いのか、しばしば映画音楽的と評され、約1時間という比較的長い演奏時間も手伝って「ただそれだけで、内容が薄い」と批判されることも少なくない。
しかし、ただそれだけの音楽と言い切るのは早計ではないだろうか。彼が作ったのは、いたずらに扇情的なだけのスクリーンミュージックのようなものなのであろうか。
ここで交響曲第2番作曲当時のラフマニノフの心情に思いを馳せて欲しい。交響曲第1番初演の悪夢が脳裏に焼き付いている彼は、自分の判断は間違っているのではないか、また失敗して酷い目にあうのではないかとくじけそうになる自分を叱咤して机に向かわなければならない。ごく親しい人にさえ交響曲を作っていることを口外せず、ただひたすら孤独な戦いをする彼の生みの苦しみは、想像を絶する。ラフマニノフは後年、「あくまで自分の美意識に従って作曲するだけだ」と作曲家としての信念を語っているが、精神的ショックから立ち直りかけだった当時の彼にとって、「自分の美意識」を音にして世間の目に晒す作曲という行為は、ともすれば自分を10年前に巻き戻しかねない、恐ろしいことだったに違いない。それでもラフマニノフは五線譜と向き合い続けた。この曲の美しい旋律の奥には、常に己の弱さと戦い続ける彼がいるのである。
標題やテーマを持たない純音楽である交響曲は、作曲者の内面がよりダイレクトに表現されることが多い。まさに人生をかけて作曲に取り組んだラフマニノフの交響曲があらわすものが彼自身だとしたら、この曲が表現しているのは、薄っぺらな感傷ではなく、打ちのめされても這い上がって己と戦い自分の信念を貫き通す彼の心意気ではないだろうか。
音楽とは面白いもので、聴く側の主観によって随分印象が変わる。この曲についても、人間ラフマニノフの辿ってきた道程をこうして念頭に置くと、この曲の美しさに、より深さと広がりが感じられるのである。
第1楽章 Largo-Allegro moderato
沈鬱だが美しい序奏を経て、コールアングレの独奏の後、主部に入る。主部では、ヴァイオリンとクラリネットが主題をかけ合い、その後展開部で、主部の主題がドラマティックに展開する。途中の金管による不安な響きは、ラフマニノフが終生モチーフにしていたロシア正教の鐘の音を模している。
第2楽章 Allegro molto
雪道を疾走するトロイカを思わせる軽快な主題と、広大な大地を思わせる情感豊かな主題が交互に登場する。緊迫した雰囲気の中間部分は、雪嵐、吹雪の情景を連想させる。この部分は演奏の難易度も高く、実際にオーケストラも緊迫する。満足に練習せずに演奏すると、音符の大吹雪に見舞われ遭難する奏者が続出する。
第3楽章 Adagio
緩徐楽章。ヴァイオリンによる短い序奏の後、クラリネットが「この世に存在する最も美しい旋律の一つ」で入ってくる。美しい響きの中でじれったいまでに引き伸ばされる旋律の魅力は、「ラフマニノフ節」の真骨頂である。
第4楽章 Allegro vivace
躍動感に溢れ、金管楽器の活躍するエネルギッシュな主題と、弦楽器による大らかな主題が絡み合って進展する。一時第3楽章を回想するが、すぐに前の主題に戻り、激しいフィナーレへとなだれ込む。
参考文献:
「ラフマニノフ その作品と生涯」
(ソコロワ著 佐藤靖彦訳)
「伝記 ラフマニノフ」
(ニコライ=バジャーノフ著 小林久枝訳)
初演:1908年1月26日 サンクトペテルブルク
作曲家自身の指揮にて
楽器編成:フルート3(ピッコロ持ち替え)、オーボエ3(コールアングレ持ち替え)、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、大太鼓、小太鼓、グロッケンシュピール、弦5部
小松先生からのメッセージ
● 小松一彦 プロフィール
桐朋学園大学指揮科卒業。齊藤秀雄氏に師事。
日本を代表する国際的指揮者の一人である。現在、チェコの名門プラハ交響楽団の常任客演指揮者を務め、2005年6月プラハ響日本ツアーのタクトをとり成功に導くと共に、CD「新世界より、モルダウ」もリリースされた。これまでイタリア放送協会賞、大阪府民劇場奨励賞などを、また2001年、現代音楽・邦人作品での長年の優れた業績に対し、第19回中島健蔵音楽賞を受賞した。2004年1月には世界最高のオーケストのひとつ、名指揮者ムラビンスキーが育て、テミルカーノフにひきつがれているロシアの名門サンクト・ペテルブルグ(旧レニングラード)フィルへのデビューで成功を収め、直ちに2005/6のシーズンに再び出演が決定、世界第一線で活躍・評価されるマエストロの仲間入りを果たす。2008年にはハンガリー国立交響楽団定期演奏会を指揮してハンガリーデビューが決定している。座右の銘のひとつが「プロの技術・アマチュアの心」。
新響とは1994年「芥川也寸志メモリアル・コンサートⅡ」(映画音楽の夕べ)以来共演を重ねており、今回で8回目(定期では6回目)の共演となる。
●小松先生のご趣味について伺いました。
私は楽天的な性格からか“人生を楽しむ”のが趣味です。
よく冗談に言うのですが私の第一の趣味は車、第二はお酒です。この順序は時々逆転しますが‥。3番目はなく(皆さんのご想像にお任せします)、4番目がスキー、5番目が音楽です。
アマチュアの皆さんによく申し上げているのは、“趣味と道楽は違う”ということです。お酒にもさまざまな文化があり歴史があり、国民性があります。それぞれの地域を知る上の手がかりでもあります。しかし、飲むという行為自体は難しくない、ですからお酒は私にとって道楽であり趣味なのです。
それに比べ、趣味というものは向上心を持ちある程度の努力を伴って自分が満足していくというものだと思います。ですから自分にとっての趣味はスキーです。少しでも上手くなりたいと思っていますし、時にはインストラクターに指示を仰ぎ、ゲレンデに立ち止まって考えたりもします。新響の皆さんは全員そういうお考えだと思います。オーケストラプレーヤーを生業としていないだけで、120%素晴らしい趣味としてやっていらっしゃると信じています。ですから私は新響が大好きなのです!
私は指揮者になっていなかったら、デザイナーかレーシングドライバーになっていたと思います。やはりイタリアのデザインと色のセンスは素晴らしいですよね。車はもう40年運転しています。今日も大阪から500キロ運転して帰ってきました。疲れないかとよく聞かれますが、体に良いリズム感がでます。ちょっとスポーティーな運転をすればアドレナリンが出て練習会場に着いたときは120%のハイテンションになっています。ポルシェなどは特にそうです。でもポルシェはブレーキ(車を止める性能)も世界一なのです。筋肉の固まりのようなこの車を運転すると運動神経と反射神経が全開になります。
車にもまた文化があります。北欧の車はボルボやサーブに代表されますが、何より安全性を追及しています。厳しい自然の中で生きていく民族はお互いにいたわり助け合い、ひとりひとりの命を大切にしているので福祉も充実しているわけです。ですから車の安全性も特に重要視されているわけです。ボルボの企業理念が安全性を目指しているということは周知です。ここにもその国の文化が表れています。
イタリアの車は、以前はやたらエンジンが熱く、ブレーキがあまり利かない(!)という特徴がありました。情熱的なイタリア人らしいと思いませんか?
フランスはシトロエンに代表されるようにエレガントな乗り味で、おしゃれな色使いです。僕が一時買おうと思ったルノー・メガーヌのクーペという車は、シートの背中の部分になんとモネの「睡蓮」の絵が描かれています。そんなセンスはフランス車にしかありませんね。
ドイツの車は一番優秀な車でありたいという意地とテクノロジーが見えます。頑丈でかのヒットラーが残した唯二の良い遺産と云われる高速道路(遺産のもうひとつはポルシェ博士にフォルクスワーゲンを作らせたこと)を走る事が主体の堅実な造りです。ベンツにしてもポルシェにしてもそうですが、昔から金庫のような車を作る上に速さも追求した優越性を出そうとするところはドイツ民族的です。数年前、速度無制限のドイツアウトバーンを最高速度130kmにしようという法案が議会に提出されましたが、結局否決されました。
イギリス車はジャガーとかランド・ローバーに代表されるようにやや日本車に似ているところがあります。あまり高速道路主体ではないし、当りが柔らかく穏やかと言えるでしょう。私には足まわりが柔らかすぎて個人的にはあまり好きではありません。日本とイギリスは共に島国であり音楽的環境も似ているといえます。
アメリカの車はアメリカン・ドリームを連想させる豪快さとやや大味な造りがあります。
このように文化と密接に結びついているので勉強になるし、それぞれの国の車を運転すると、その国の音楽にも結びついていきますね。
車のクラクションひとつにも文化があります。フランス車とドイツ車の違いですが、フランス車は単音で高めのファンファンという音です。鼻にかかったような音で、フランス語の鼻音と通じるところがあります。ドイツ車はだいたい二つの音でハーモニーができるようになっていて厚みがあります。クラクションひとつとってもこのように文化の違いがはっきり現れます。フランス車のクラクションがガーシュイン作曲の「パリのアメリカ人」の最初にでてきます。私の長年の夢だった企画が、1回だけ実現したことがあります。横浜の「子供の日のコンサート」で、私のプジョーのオープンカーがステージに載り、司会の女性に車の中に座ってもらい私の指揮でクラクションを鳴らしてもらいました。普通は打楽器奏者がお豆腐屋さんのラッパのようなものを持って演奏し、それでも面白いのですが、実際の車とは大分違いますね。オケがターリーラーとやったあと司会の女性がパパパとクラクションをならし、僕がそれに答えパパパと鳴らす。子供の日のコンサートなのでバカウケでした。フランス音楽では鼻音の響きがだせなければ、音楽の重要な要素が欠落してしまします。ドイツ音楽をやるときは音の厚み、クラクションも単音では満足しないというような三度の響きの重厚感のようなものが大切です。
一時期どこの国の車もグローバリゼーションやコスト削減のための世界規格で同じようになってつまらない時期もありましたが、今はルノーやシトロエンに代表されるように特にルノーは斬新なデザインです。メガーヌの新型はでっちりがボコーンとでているような誰が見ても一回で覚えるような強い「個性」を持っています。このような特徴やアイデンティティをまた出すようになり、1960年代位の形をもう一回リニューアル、それぞれが先祖還りしています。まあ、中身はイタリア車も現在ではコンピューターはドイツのボッシュを使っていますが。
次にお酒と食のお話をしましょう。タバコは有害といわれていますが、お酒は適度であれば健康によいとか、リラックス効果が認められていますよね。ただ、この“適度”が難しい。(笑)私は毎晩晩酌をし、皆さんともよく飲みにいったりするわけですが、その中に文化があり、それが音楽に通じてくるのです。味覚というのは音楽の味を出すのに非常に重要な要素を受け持っています。毎日コンビニのレトルト食品を食べている人には中身のある味のある演奏はできない。そういうものを食べる場合もあるでしょうが、時々は色々な味の真髄を味わっていないと音楽でも味を出せない。なんでも醤油をかければいいというものではありません。プロの料理人は調理方法を駆使し、いろいろな隠し味、スパイスを吟味し作っているわけですから、それを味わい、わかって音楽に生かせるかということが重要な要素だと思っています。僕はグルメにはなりたいとは思っていないし(鴨肉を毎日食べていたらダイエットできません!)、とてもそんなお金はないですが、いろいろな味はわかるようでいたい。音楽にはその国の国民性、民族の血、地域性、気候風土、言語全部が譜面のなかに滲みこんでいる、練りこまれ、すり込まれているわけです。もちろん短絡的に音楽の「楽」の部分だけが強調されたマーチのような楽しい曲もあります。しかし内面的な深い内容を持った曲であれば、作曲者の個人的な強い、切ない思いまで含めて全部練りこまれているわけですから、それを読み取るという能力はまさに「感性」(音楽脳=右脳)が研ぎ澄まされていないとだめなのです。音楽はなによりも自分の感性が大事ですから。よく音楽がわからないという人がいますが、音楽は感じるか感じないかです。聴衆も演奏者も上級者になれば勿論楽曲のこととか背景とかを研究し、事前に調べて曲を聴こうとするでしょうから、それはそれで大変重要なことです。(言語脳=左脳のバックアップという)けれども、まずは心で感じるか感じないかということです。感じない人にとっては音楽というものはあまり意味のないものではないでしょうか。音楽をあまり知らない人でも、ドヴォルザークの「新世界交響曲」の第二楽章のコールアングレの独奏の部分を聞いたら、普段はクラシックはそんなに聞かないのに涙が出てきたという人がいます。私達にとって西洋音楽は基本的には異文化なのにいったいなぜでしょう。これを題材にレクチャーをすることもあります。感じる心を広げる為にお酒と肴は大切です。拙宅にはお酒のコレクションはホテルのバー位ありますね。色々な味わいから文化を感じようと思っています。最近はダイエットに励んでおりますのでアルコールはワインと焼酎を好んで飲みます。ダイエットは三進二退、時には二進三退になることもありますが(笑)、ようやく完成に近づきあと2キロやせればいいかなというところまで来ました。現在一日1.75食に挑戦中です。これは1回はしっかり食べ、あと0.25と0.5にするということです。朝と夜とでどうバランスをとるかということです。ワインも焼酎も香りがとても大きな要素です。最近気に入っているのはある黒糖焼酎です。黒糖の甘い香りがし、その上米麹で仕込んであるので、麹の香り、醤油の様な匂いが甘い黒糖の香りと絶妙に二本立てで、時にはミックスされて立ち上ってくるのは、この焼酎だけです。名前がまた、いいんだな。“ほどほど”といいます。適度のアルコールは云々の効用に嵌る訳でございます。それに対してワインは同じものであってもボトル一本ずつ全部違う、日本酒もそうですね。色も香りも重い、軽い、コクにしても。音楽に共通してますね。譜面の上に書いてない部分、たとえば音符の重い軽い、温かい冷たいなどというのは感じ取らなければならない。ですから、車、お酒、食事からその国の文化を感じることを大切にしています。それが人生を楽しむことにもつながっています。
ところで一つの曲を最後まで無事に演奏し終えるということは、スキーでゲレンデを滞りなく転ばないで下まで滑り降りるのと同じです。何百回もやっているような曲、「運命」でも「第九」でも時にはオーケストラがなんでもないところで事故を起こすことがあるかもしれません。スキーで言えば全てわかっているつもりのゲレンデが、その時の雪質やちょっとしたギャップがあってオッと思って転びそうになる、それをリカバリーできるか出来ないかということで、オケの事故も一つのことがきっかけで立ち直る方向に行くのか崩壊に向かうのか、これには鋭い反射神経と運動神経が必要です。そのためにもこれからも私は、健康に気をつけて出来るだけ滑り続けたいと思っています。いつも家内に言われていますが、怪我をして皆様にご迷惑をお掛けしたりしないように気をつけながら続けたいと思っています。
さて、私はその時手掛けている曲に肉迫し、その曲の内容を抉る事を信条としていますので、演奏者の皆さんがそれに応えてくださることを期待しています。それがあってこそ聴衆にとってインパクトのある演奏となるのです。音楽の演奏というのは“アナログの極致”です。二度と同じ演奏はありません。これを「演奏の一回性の尊さと新鮮さを大切にする」という心根に繋げて行って頂きたいものです。しかも、あの練習の時の演奏が一番良かったとはならない事を念じつつ‥。
私は、いつも熱く燃える演奏を目指しています。(私の座右の銘のひとつに「熱いハート(右脳)とクールな頭脳(左脳)」というものがあります。また車の話になりますが、所有はしていないけれど、アルピナという車に喩えられるでしょう。)しかし指揮者だけが踊り、また舞い上がるのではなく、オーケストラ・演奏者と強い一体感のある、集中力に満ちたエネルギーが客席に放射される演奏になることを常に心掛けています。
新響のメンバー・ファンとの新たな、本命的なお付き合いが始まる今回のシーズンを私もとても楽しみにしています。というのはここ数年、半ば意図的に、新響がこれまであまり取り組んでこなかった曲目にも挑戦してもらうプログラムを組み、このオーケストラの表現力の幅・引き出しの数を増やし、成長を促す方向性を打ち出してきたのですが、私がロシアのオーケストラをよく指揮しに行っているという事で、今回のメイン曲に皆様からもご提案のあったラフマニノフの交響曲を一緒に演奏できるのが本当に嬉しいのです。ロシアの空気を吸ってきている小松と重厚な曲の演奏を得意とする新響の組み合わせにご期待下さい。
ルーセルと海、そして音楽
アルベール・ルーセルはフランスの作曲家です。北部フランスのトゥールコワンという町の裕福な家の生まれでした。1歳のときに父親をそして、8歳のときに母親を亡くす悲劇を味わったものの、その後彼の祖父に引き取られ順調に育っていきました。ルーセルの母は彼の音楽的素養の高さを見抜き、幼少のころからピアノを習わせたのでそれが功を奏したといえます。ルーセルは両親も兄弟もなく、市長である祖父の名誉を汚さないためにも身を慎ましやかに生きていかねばならず、オペラの楽譜などと親しく過ごしました。やがて、「神童」ルーセルは市庁舎に保管されていたオペラ「ポプリ」や小曲のすべてを弾きつくし、自分は音楽家になるのか、といったほのかな未来の自分像を見出します。やがて、その祖父も亡くなり、母方のおばの家で生活しながら音楽を勉強する準備を進めていました そんな折、病弱な彼の体のためにと連れ出されたベルギーの海を見てルーセルの考えが変わります。これまで、孤独で禁欲的に生きていかねばならないと思っていた彼に、海が誘います。明るい日差しにきらめく青い海面、その先になにがあるのか想像の彼方にある水平線。世界はもっと果てしない、遠い見知らぬ地にあなたを育む何かがある・・・とでも聞こえたのでしょう。18歳になったルーセルは海軍兵学校に入学。2年後には士官として砲艦スティックス号の乗組員になっていました。この軍船は現在のタイ辺りに赴く任務につき、ルーセルもそれに従事しました。
同じ海沿いでも東南アジアの空気は地中海のそれとは違い、重くまとわりつくような鬱陶しさがあるのですが、ルーセルにとってはそれがかえって心を奮い立たせ感性を磨いてくれたようです。目に突き刺さるような強い陽射し、なんの衒いもなく天に伸びる樹木、生命力溢れる人々の喧騒、故郷とはまた違った活力にルーセルは引き付けられたことでしょう。
音楽とは無縁の軍隊生活の中でもルーセルは音楽とのつきあいを忘れずにいたようです。機会があればピアノに向かい、先人たちの作品も勉強していました。
たとえば・・・
将校クラブの午後はけだるい。客である砲艦スティックス号の乗組員の姿もまばらで、現地人のボーイたちも暇そうにしゃべりあっている。
ルーセルの正面には同じ部隊の大尉がつまらなそうに髭をいじっていた。籐椅子は彼の大きな身体を軋みながら支えている。現地の政情不安は多少の緊張をここへ運んでくるが、そんなものは心身の弛緩したこの大尉には何の役にもたたない。
「ルーセル中尉、君はピアノの名人だそうだな。気持ちよく昼寝でもできる曲を何か1曲やってくれたまえ」
大尉は顎だけしゃくってピアノを指し、ルーセルを促した。
長旅に揺られてきた上にこの気候ではまともなピアノであるわけがない。ルーセルはここにピアノのあることはわかっていたが、これまでとても触る気にはなれなかった。彼はおもむろにピアノの前に座り、キーにそっと触れてみた。上品な冷たい感触が指先から伝わってくる。意を決してキーを押す。湿り気を含んだ鈍い音が抜けていった。さらに隣にキーを押してみた。やはり同じだ。でも、ルーセルの音楽家魂を呼び起こすにはそれで十分だった。
次から次へと音を紡ぎだす魔法に聴衆はあっけにとられた。
大尉は昼寝を忘れてしまったようである。
ボーイたちも思わぬ暇つぶしに機嫌がよかった。
当のルーセルはといえば、やはり自分には音楽しかないのかと改めて考えさせられた。
砲艦スティックス号の寄港地ではさながらこんな光景が見られたのではないでしょうか。
ルーセルは健康のこともあり、海軍兵学校に入学してから7年後の1894年に軍籍を離れました。その後、本格的に音楽の勉強を行い、1897年に最初の作品4声のための二つのマドリガルを発表いたします。
彼の作風である、ドイツ的なかっちりとした構成は幼少のころの規律正しい生活の影響で、色彩の豊かさは東南アジアで刺激を受けたものともいわれています。
1930年に書かれた交響曲第3番はこうした作品群のなかで最高峰のものと評価されています。
譜面の思い出
ヴァイオリン・パートの笠川と申します。新響には入団6年目になりますが、昨年まで3年間ほど団のライブラリーを担当しておりました。ライブラリーとは、演奏会で使用する譜面を調達・管理する役目のことです。公演回数の多いプロオケでは専任のライブラリアンが置かれているのが普通ですが、新響を含めアマチュアの場合、団員が交代で担当する「係」のひとつであることがほとんどかと思います。新響では、年4回の演奏会に合わせて、譜面の手配、団員への配布、トレーナーの先生へのスコア(総譜)の送付、使用後の譜面の回収・保管といったところが主な活動となりますが、それらを通じて、50年という新響の歴史を感じることが幾度もありました。
新響では、演奏会で使用した譜面は整理したうえで倉庫会社に預けて保管しています。以前、預けている譜面すべてを確認する「棚卸し」の作業を行ったときのことです。団員の厚意により自宅の20畳ほどの部屋を提供してもらい、取り寄せた百数十個の段ボール箱を部屋中に広げて、一箱ずつ中身をすべてチェックしたのですが、興味深い譜面をたくさん見ることができました。パート譜一式が布貼りの箱の中にうやうやしく収められたチャイコフスキーの交響曲は、新響がソビエトに演奏旅行(1967年)した際に現地で購入したものだったり、邦人作品のスコアの中には天地1メートルを超える巨大なものがあったり、思わず譜面整理の手を止めて見入ってしまうことがしばしば…。また、前回の演奏会でも取り上げた伊福部先生の「シンフォニア・タプカーラ」など、作曲家のスコアをもとに団員が手作りで作成したパート譜を目にして、「作品への愛情」や「譜面に対する思い入れ」のようなものを感じることができたのも、自分にとって貴重な体験でした。
ところで私の場合、譜面といえば思い出すのが、今回演奏するラフマニノフの交響曲第2番です。以前大学オケでこの曲を演奏した際に使用した譜面は、出版社から正規にレンタルで調達したうえで、それとは別に当時トレーナーでお世話になっていた先生(新響にもたまに指導にお見えになる)が所属するプロオケのライブラリアンから、「弦楽器のボウイング(弓遣い)などを勉強するため」という口実でコピーさせていただいたものでした。譜面にはそのプロオケの楽団員が書き込んだユーモラスなイタズラ書きがあって、オーケストラ初心者の自分にとっては結構楽しかった記憶があるのです。2楽章最初のページの余白には、冒頭のリズムが連想させるのか『ヤギブシ』の書き込み、また4楽章の中ほどには、徳利とお猪口のイラストが器用に描かれ下に、(飲みに)『イコウヨ』の文字が…。ちなみにこの譜面(2ndヴァイオリン)は、全体で29ページありますが、そのうち10ページ分が4楽章で占められていて、しかも「休み」の部分は少なく、ほぼ弾きっぱなしです。「この楽章、ちょっと長い」と感じながらページをめくると、徳利とお猪口が目に入り、訳もなく元気が湧いてくることがあったのを思い出します。そういえば、今回新響で配られた譜面は何の書き込みもない「まっさら」なものだったので、受け取ったとき自分の中では何か物足りないような気持ちになりました。(だからといって、これからイタズラ書きをしようと思っている訳ではありませんが…)
第197回演奏会ローテーション
| ルーセル | ラフマニノフ | |
| フルート1st | 岡田 | 松下 |
| 2nd | 丸尾 | 新井 |
| Picc(3rd Fl) | 藤井 | 兼子 |
| オーボエ1st | 堀内 | 亀井(淳) |
| 2nd | 山口 | 亀井(優) |
| コールアングレ | 桜井 | 岩城(3rd Ob) |
| クラリネット1st | 中條 | 高梨 |
| 2nd | 大藪 | 末村 |
| バスクラリネット | 進藤 | 石綿 |
| ファゴット1st | 田川 | 浦 |
| 2nd | 星 | 星 |
| コントラファゴット | 浦 | - |
| ホルン1st | 山口 | 箭田(アシ比護) |
| 2nd | 比護 | 市川 |
| 3rd | 鵜飼 | 園原 |
| 4th | 大原 | 大原 |
| トランペット1st | 中川 | 野崎 |
| 2nd | 倉田 | 青木 |
| 3rd | 北村 | 小出 |
| 4th | 小出 | - |
| トロンボーン1st | 武田 | 志村 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 |
| 3rd | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 足立 | 土田 |
| ティンパニ | 桑形 | 桑形 |
| シンバル | 中川 | 中川 |
| 小太鼓 | 今尾 | 今尾 |
| 大太鼓 | 桜井 | 桜井 |
| トライアングル | 田中 | - |
| タンバリン、銅鑼 | 古関 | - |
| 鉄琴 | - | 古関 |
| チェレスタ | 藤井 | - |
| ハープ I | 神谷(*) | - |
| ハープ II | 高橋(*) | - |
| 1stヴァイオリン | 堀内(大隈) | 前田(奥村) |
| 2ndヴァイオリン | 村井美(笠川) | 岸野(宇佐美) |
| ヴィオラ | 柳沢(小野崎) | 柳沢(田口) |
| チェロ | 柳部容(光野) | 光野(日高) |
| コントラバス | 加賀(中野) | 中野(加賀) |
第197回演奏会のご案内
小松一彦の熱き想い
今回の指揮者は、昨年の創立50周年シリーズで2回共演して新響との関係がさらに近くなった小松一彦氏の登場です。最近では日本での活躍にとどまらず、プラハ交響楽団やロシアの名門サンクト・ペテルブルク・フィルハーモニー管弦楽団の客演指揮者を務めていますが、氏のチェコ・デビュー、モスクワ・デビューを飾った曲が今回とりあげるラフマニノフの交響曲第2番です。
ラフマニノフ--ロシアの魂
ラフマニノフといえばピアノ協奏曲第2番が有名ですが、3つの交響曲も残し、その中でも今回演奏する交響曲第2番はもっとも人気の高いロマンティックな曲です。この曲をご存知ないという方でも、耳にしたことのあるパッセージがいくつかあるかもしれません。
新響は6年前にロシア人指揮者ヴィクトル・ティーツ氏(ハバロフスク・ロシア極東交響楽団芸術監督)を招き、「オール・ラフマニノフ・プログラム」を演奏する機会がありました。氏のラフマニノフに対する思い入れは非常に深く、「ラフマニノフの楽譜の音譜ひとつひとつには、ロシアの魂が込められている」と語られていました。その時は交響曲第3番を演奏しましたが、「今度は第2番を」という話もあり次の機会を楽しみにしていたのですが、悲しいことに氏は昨年3月に亡くなり、叶わなくなりました。
この曲は「ロシア抒情交響曲」とも称され、ロシア固有の旋律こそ使われてはいませんが、ロシアの風景や民族の心情が音楽の中に主観的に表現されています。だからこそロシア人に愛され、私たちの心にも沁みるのでしょう。
ルーセル--近代フランスのシンフォニスト
ルーセルは、ドビュッシーやラヴェルと同じ世代の作曲家です。印象派と新古典主義音楽の移行期のパリにおいて、独自のスタイルの作品を残しています。日本では演奏される機会の少ない作曲家ですが、フランスでの評価は高いものがあります。交響曲第3番はルーセルの代表作ですが、鮮烈なリズムとしっかりとした形式の中にもフランスのエスプリが見え隠れします。いわゆる「フランスもの」と思って聴くと驚かれるかもしれません。
新響がルーセルの作品をとりあげるのは今回が初めてですが、これまで小松氏とはプーランクやフランク、ベルリオーズなどのフランスの作品を数多く演奏してきました。その蓄積を活かしてよい演奏ができればと思っています。どうぞお楽しみに!!
第196回演奏会ローテーション
| ボロディン | コダーイ | 伊福部 | |
| フルート1st | 丸尾 | 松下 | 藤井 |
| 2nd | 新井 | 岡田 | 新井 |
| Picc | 藤井 | 丸尾 | 松下(アシ岡田) |
| オーボエ1st | 亀井(淳) | 亀井(淳) | 岩城 |
| 2nd | 桜井 | 亀井(優) | 亀井(優) |
| コールアングレ | - | - | 堀内 |
| クラリネット1st | 品田 | 末村 | 中條 |
| 2nd | 大藪 | 進藤 | 高梨 |
| バスクラリネット | - | - | 石綿 |
| アルトサックス | - | 鈴木(*) | - |
| ファゴット1st | 田川 | 田川 | 長谷川 |
| 2nd | 長谷川 | 長谷川 | 田川 |
| コントラファゴット | - | - | 稲田(*) |
| ホルン1st | 箭田 | 山口 | 鵜飼 |
| 2nd | 比護 | 比護 | 園原 |
| 3rd | 大原 | 大原 | 箭田 |
| 4th | 市川 | 市川 | 山口 |
| トランペット1st | 倉田 | 中川 | 野崎(アシ小出) |
| 2nd | 北村 | 小出 | 北村 |
| 3rd | - | 青木 | 青木 |
| コルネット1st | - | 野崎 | - |
| 2nd | - | 青木 | - |
| 3rd | - | 倉田 | - |
| トロンボーン1st | 志村 | 志村 | 武田(アシ志村) |
| 2nd | 武田 | 小倉 | 小倉 |
| 3rd | 大内 | 岡田 | 岡田 |
| テューバ | 本橋 | 足立 | 土田 |
| ティンパニ | 桑形 | 桑形 | 古関 |
| 大太鼓 | - | 古関 | - |
| シンバル | - | 桜井 | - |
| 小太鼓 | - | 中川 | - |
| トライアングル | - | 田中 | - |
| 木琴・鉄琴 | - | 由谷(*) | - |
| 鐘・鉄琴一部・Tamb-b | - | 今尾 | - |
| Perc. I | - | - | 今尾 |
| Perc. II | - | - | 桜井 |
| ツィンバロン | - | 中川(*) | - |
| チェレスタ | - | 渡辺(*) | - |
| ピアノ | - | 藤井 | - |
| ハープ | - | - | 佐々木(*) |
| 1stヴァイオリン | 前田(宇佐美) | 前田(宇佐美) | 堀内(大隈) |
| 2ndヴァイオリン | 岸野(田川) | 岸野(田川) | 村井美(奥村) |
| ヴィオラ | 柳沢(小野崎) | 柳沢(小野崎) | 柳沢(内田) |
| チェロ | 日高(光野) | 光野(日高) | 光野(柳部) |
| コントラバス | 藤澤(中野) | 藤澤(中野) | 藤澤(中野) |
追悼 ヴィクトル・ティーツ先生
ティーツさんのこと
昨年は新響創立50周年という記念の年であったのだが、我々の敬愛する伊福部昭氏、7月の194回演奏会を指揮していただく予定だった岩城宏之氏と訃報が続いた。記念シリーズの一連の演奏会は成功だったように思うが、それを支えたテンションは、おまつり気分というよりも、むしろ何か厳粛な緊迫感、悲壮感が底流にあったよう感じたのは、私だけの思い過ごしだろうか。
そんな中、私たちはもう一つの訃報に接しなければならなかった。指揮者のヴィクトル・ティーツ氏が昨年の3月に亡くなった、という情報が我々の元に届いたのである。
ティーツ氏は、ロシア、ハバロフスクの極東交響楽団の芸術監督・指揮者で、私たち新響の演奏会では、1999年10月11日の第167回演奏会、2001年7月28日の第174回演奏会、2004年10月17日の第187回演奏会、と3回の演奏会を指揮していただいた。
1938年のお生まれだから、まだ67歳だったはずで、2004年にご一緒したときも、エネルギッシュな精力的で厳しい練習であったし、とてもお元気だったので、急な訃報に私たちは大変驚いた。
ふとしたご縁から、私たちがはじめてティーツ氏にお会いしたのは1997年6月のことであったから、足掛け10年に近いお付き合いをさせていただいたことになる。
マネージメント会社も介さず、事前交渉や来日中のアテンドも全て団員があたったので、演奏会の回数こそ3回だが、その割にとても濃密な交友をさせていただいたように感じる。
在ハバロフスク日本領事館の方のお話では、以前から心臓の調子はよくなかったが、一昨年(2005年)晩秋頃から入退院を繰り返すようになっていたそうだ。それでも、2006年3月8日に予定されていた、ティーツ氏の念願だった日本の邦楽器演奏家との共演コンサートに向けて、ご自身がタクトを振るおつもりで、領事館の担当者とも演奏会準備の打合せをしていらしたそうだ。
しかし、2006年の年が明けると病状が進み、病院から退院することが難しくなった。奥様のジャンナさんは、付きっきりで看病にあたられたそうだが、残念ながら病状は好転せず、3月に亡くなられたそうだ。
葬儀はモスクワで行われたそうだが、ハバロフスクでも氏の功績と人柄を慕う人々は数多く、お別れの会が催された。
ティーツ氏の真摯な人柄は、理想の音楽に近づくためには妥協をせず、こと音楽、練習に関しては例えようもなく厳しいのだが、ひとたび指揮台を降りると、決して偉ぶらず謙虚で、日本の暑さや食事や送迎などのアメニティについて不満をおっしゃることはなく、チャーミングでユーモアのセンスのあふれた、魅力的なおじさんになる。
ティーツ氏との最初の共演に向けて、プログラムのメインとなる候補曲をあげていただいた。それは次の5曲だった。チャイコフスキーの4番、5番、6番の交響曲、ラフマニノフの2番、3番の交響曲である。ティーツ氏はロシアの作曲家の中でも、「人間の内側から湧き出る深いテーマ性を持つ」作曲家として、まず第一にチャイコフスキーを、そしてそれにほとんど並んでラフマニノフを敬愛されていた。
最初に示された「メイン候補曲5曲」のうち、チャイコフスキーの第6番「悲愴」は最初の共演の167回演奏会で、174回演奏会ではラフマニノフの交響曲第3番を、そして187回演奏会ではチャイコフスキーの第4番を指揮していただいた。
残るはチャイコフスキーの第5番とラフマニノフの第2番。…なかなか良い曲が残ったなあ…などと考えていた。
ティーツ氏と演奏会プログラムの案をやり取りする課程で、ボロディンの「イーゴリ公」序曲は、何度も候補にあがったことがあって、私は「イーゴリ公」序曲を聞くと、ティーツ氏のことを思い出す。本日の演奏会の「シンフォニア・タプカーラ」は伊福部昭氏の追悼演奏なのだが、私個人の気持ちとしては「イーゴリ公」序曲はティーツ氏の追悼演奏という感じがする。そして、次回の演奏会のラフマニノフの交響曲第2番も…。
自分で自分の歴史を書く新響に期待
新響の演奏会はほとんどいつも聴かせてもらっている。
一番最近きいたのは第195回。演奏会形式によるワーグナーの 楽劇「トリスタンとイゾルデ」、指揮は飯守泰次郎。これは、自分でも驚くくらい感動し、一瞬の沈黙ののちの万雷の拍手に加わった。
演奏会曲目が外国曲ばかりのとき、帰りぎわにお客さまの「今日は日本のものはなかったね。」などのつぶやきを耳にすることもあるが、それでも、新響ではなんでもきいてみようと私が思うのは、彼らの演奏からは、演奏する彼ら自身が作品をかみくだいた上で本番にのぞんでいるその成果がきこえてくる気がするからである。この日もそうであった。
このワーグナーの演奏会は、2006年を通じて行われた創立 50周年4回シリーズのしめくくりで、初回は1月、三善晃の「交響三章」からだったが、そのとき私は病院にいて、病室の窓から見える南の富士、北の八ヶ岳、西の南アルプスの氷壁に慰められていたのだった。
だから、せっかくの50周年シリーズのうち、満足にきけたのは半分しか、「涅槃交響曲」のあった3回からだが、せっかくだから、三善晃にはじまりワーグナーで終わった50周年企画全体を私なりに考えてみたくなった。
そこでやむなき事情によりということで、三善さんには申し訳ないが、当日の音をいただいた。1回目、そして2回目、最初の出だしのチェロの一音にまぎれもなく私たちの音を感じる。そして、緩急自在、ゆっくりとした動きが音色の変化につれていつのまにか速まっていくところなど、まぎれもなく私たちの音楽、という気がしてくる。
いわゆる旋律らしい旋律を主題とするのではないため、ちょっととらえにくいのだが、そういえば、『作曲家との対話』(新日本出版社、1982)のなかで、三善さんが、「(曲の)発想というものはすごく具体的なんです。オーボエでもなんでもいい、とにかく音があるんだからしょうがない、聞こえているわけですから。それは、自分が書かなくてはいけないもののどこかの部分であるということが非常にはっきりしているんです。聞こえててゆるがせにできないものなんです、書く書かないは別にしてあるんですから。」と説明しておられたことを思い出した。まさに納得である。
作曲家には、ピアノで作曲する人と、ピアノを使わないで作曲する人との2種ある、といわれている。清瀬保二はピアノで作曲した。亡くなる日の朝もピアノの即興演奏をしていたことでもわかる。三善さんの作曲は後者のタイプ、いわば頭のなかですべてできあがっていく。そうとわかれば譜面を眺めるのも、きくのもたのしくなる。
そうしている折りもおり、日本現代音楽協会から、〈現代の音楽展2007〉のチラシとともに、三善さんが、現音創立75周年、2006~7年度のその催しの芸術監督を引き受け、テーマとした「未来をつむぐ、受けてつないで渡す」の趣旨をのべた文章が送られてきた。その後半の一部分をまず原文どおりに紹介しよう。
日本人は自己決定をためらう、ということがあります。一言で言えば、「私は私」ということをひとまず避ける傾向があります。この傾向のために、逆説的なことですが、ほんとうの協調をしないことが見受けられます。私はよく「日本人は共同はするが協同はしたがらない」と言うのですが、このことは既に政経の外交面では、日本人という人種の定評になっていますね。これはしかし、21世紀の新しい世代では、通用しない、させたくない事です。現に、色々なことを知りたがっている世代があり、上の世代がそれに応えられない。逆に、ある世代がやりたがっていることに違う世代は関心がない。両方とも不満で孤独です。この両者をつないで協同させる。とりあえず一つの地域、一つのイヴェント、一つのプログラムのなかで二つの世代を「つなぐ」。
すなわち、それが「未来をつむぐ」の意味で、作曲家にもそうできる場面がたくさんあるのではないか。そして、現音の存在感もそこにかけられているのではないか、と三善さんは提起しているのだ。
私は、三善さんとはこれまでほとんど親しく言葉をかわしたことはなかったのに、ちょうど3年前の12月、思わぬことで手紙を出しお返事をいただいている。
それは、ブッシュのイラク戦争開始前日の、2003年3月19日、三善さんが現音として反対の意思表示を出せないだろうかと問題提起したのにたいして、会側が驚くほど消極的な対応をした。そのことを『NEW COMPOSER』4号誌上で知って、びっくりした私が、思わずひろく友人たちに知らせるべく声をかけたことにたいしてのもの。
いまやイラク戦争が内戦状態にあることは誰の目にも明らか、この数年の日本の政治が、まさに「私は私」を主張することなく、共同はするが協調はしてこなかった、それがいまの情況の根本にあることも、痛いほど知らされている。
同文の前半で三善さんが言っているのは、伊福部昭のことばとしても多くの人にも繰り返されている、固有な価値こそグローバルな価値の基、あらゆる芸術はみなローカルだ、ということで、それを前提として、日本語の歌は世界中で理解され愛される価値がある、それも声楽曲に限っていうのではなく、「自分で自分の歴史を書いてみよう」というよびかけだ。
これは、民族的といわれる作曲家の作品についていうとき、まず民族的あるいは日本的特徴にとらわれてしまうのをいつも私が残念に思っていることとも共通する。
たとえば伊福部昭が、アイヌの生活には音楽が生きている、そこで学んだのは、自分の書いたものを発表するということになんら抵抗感を持つ必要はない、思ったように書けばいい、ということなのだ。
ところが、これだけ音楽がさかんなこの國で、そのだいじなところが案外忘れられている。
「自分で自分の歴史を書いてみよう」というよびかけは、作曲家に限らず、日本の演奏家たちにも、聴き手たち全体にも向けていわれているのだということを、あらためて認識したいと私は思う。
ところで「交響三章」は、東京交響楽団と日本作品のシリーズに続いて、日本フィルハーモニー交響楽団がはじめた委嘱シリーズの第4作目、初演は1960年の10月14日、指揮渡邊暁雄。ことあらためてここに記すのは、私の『受容史ではない近現代日本の音楽史』(音楽の世界社、2001)の年表1960年のところで記載もれしているから。
これは単なるミスだが、ここで、日本の管弦楽作品年表でながらく漏れていた橋本国彦の戦後に書かれた交響曲について書きたい。
橋本国彦作曲「交響曲 第2番 ヘ長調」。
第1楽章 ソナタ形式
自筆譜末尾には、
「於 鎌倉極楽寺108、1947年3月4日起稿、
同年3月25日脱稿(Beethovenの命日)」
第2楽章 フィナーレ、変奏曲
自筆譜末尾には、
「1947年4月16日、於 鎌倉」
初演は、同年5月3日、帝国劇場、演奏は東宝交響楽団、指揮は作曲者自身。
この初演記録がこれまで不明だった理由は、普通の音楽会ではなかったこと、憲法普及会主催の「新憲法施行記念祝賀会」のプログラムのひとつとして入っていた、という事情もありそうだ。
東宝交響楽団(のちの東京交響楽団)はすでにこの名称を名乗っていたとはいえ、第1回定期演奏会が行われるのは、まだそれから半年後の10月のことである。
それに、祝賀会全体は、第1部にヴァイオリン独奏などの音楽演奏、第2部は歌舞伎舞踊「京鹿子娘道成寺一幕」の上演といった内容のものなのだから。
ただ、音楽はその後放送も行われているので、だれか、記憶しておられないかと思っているのだが、いまのところ、情報は得られていない。
私自身のその当時といえば、大学入学を機に疎開先から東京へ移ってきたばかり。吉田隆子に師事することになるのはもう少しあとのことになる。
2005年春、吉田隆子のオペラ台本「君死にたもうことなかれ」を安部幸明先生との対談なども加えて復刻(新宿書房)したが、そのあとになって、吉田隆子の遺品のなかから、橋本国彦が滞在中のオーストリアから愛弟子吉田たか子に寄せた手紙が、私の手元にもたらされた。
投函の日付は1935年7月16日。
70年も前の手紙である。
前記、「交響曲 ヘ長調」自筆譜に記されたのと同じく女文字のようにも見える細い字でびっしり書かれている。 おそらく渡欧にあたってひきついでいった曙会の舞踊のための音楽のこと、そのオーケストレーションについて、たいへん具体的なアドヴァイスを与えている。
ついでに橋本は、ヨーロッパから眺めると日本の楽壇のいろいろの原因がどうも島国根性からきているらしい、などといい、「日本ではミジメなオーケストラを考慮して仕事をしなければならない。皇太子のカンタータを書いたときのように、自分の芸術としてでないときは、公然と手をかえられるけれど、自分の作品として公開する場合にはこまるのです。」などといっている。
つまり彼の地にいて、フルトヴェングラー指揮の場合(リハーサルにもぐりこんで聴いたのだそうだが)のように信頼できるオーケストラならいいが、日本ではとてもそうはいかないのが「こまる」というのだ。
「けれど、そんなことはおいて、思い切ってよいものをお書きください。何より、自分の芸術的良心を満足さすために。」と、励ましの言葉で手紙を結んでいる。
この手紙からなお数年たって橋本が帰国したとき、すでに日中戦争は押しとどめられなくなっていた。さらに母校東京音楽学校教授に就任した1940年は紀元2600年の年。あの戦争の時代、橋本はまさに矢面に立たされていたのだ。
安部先生からの、結局、最後のものとなったお手紙に、橋本国彦にふれて、次のようにあった。
橋本さんの交響曲、確か私は初演の時に奏いているはずです。あの人なかなかの才人で、当時のオケの力ではあの程度の事しか出来ませんでした。欠点を挙げると、紀元節の歌とか妙にこだわるところがあったのが、惜しまれるのでないですか。
ここにあげられたのはもちろん、戦後のでなく、「交響曲ニ調」のこと。新響40年シリーズでとりあげられたものである。
果たしてこれは作曲者が「自分の芸術的良心を満足さすために」「思い切って」書いたものだろうか。
それにくらべて、楽章を書き上げるごとに、筆をおいたときの思いがなまなましく記された自筆楽譜をみればみるほど、橋本がほんとうに、自分のことばで書いたのは、「交響曲 第2番」、と思うゆえに、第1番の「交響曲ニ調」だけでは片手落ちではないか、と私は思うのである。
「交響曲第2番」の第1楽章、かなり長い旋律主題は、それこそ、はじめて橋本が、「自分で自分の歴史を書く」よろこびをいっぱいにくりひろげたように、のびのびしたテーマだ。
ソナタ形式の第1楽章と変奏曲、形式としては、その後の作曲家たちが挑んだ交響曲とくらべれば、保守的ということになるだろうが、そんなことよりもっと大事なのは、この「第2番」が全楽章を通じて、橋本のほんとうに「自分が思ったもの」だけであらわした交響曲だと思えることである。
そしてもうひとつ全体に明るいところがいい。その明るさは、敗戦からまだ2年もたたないあのころ、衣食住すべてまだ満足ではなかったのに、なぜか希望があった、その未来の明るさをだれもが感じた時代だったと思う。橋本のこの交響曲からはそれがはっきり感じられる気がするのである。
50周年企画からすっかり脱線してしまったが、ワーグナーにもどってみれば、ライトモティーフも、半音階的な傾向も、そして、トリスタン和音というものがあって、それがいわゆる調性破壊へのきっかけになったなども、多くの聞き手のみなさんにもよく知られてきていると思う。
そしてその後、調性崩壊の結果のようにいわれる12音や無調その他の前衛技法が編み出されたとはいえ、むしろ現在にいたるまで、依然として調性は健在、という歴史の方がよほど確かに見えるのではないか。
もちろん、いわゆる長短調調性に限ってでなく、ひろく旋法的調性を含めて考えればの話、である。
「涅槃交響曲」では、たとえば梵鐘の「唸り」。その余韻嫋々のひびきは私たちにはごく親しい。それを、作曲者はこの曲で鐘そのものによるではなく管弦楽で再現しているのだということが、新響では楽員の解説によって案内される。
つまり、管弦楽という表現手段は、それこそ「なんでもできる」演奏手段なのだということをごく、具体的に教えてくれるのだ。
50周年企画のなかではもっとも若い世代の猿谷紀郎まで含めて考えるとすれば、新響は、ワーグナー以来の管弦楽の表現力のそれこそ無限の可能性を、これからもきっとどこまでも展開していくであろう。それは、「自分で自分の歴史を書く」ことにみごとに参加していくことだと思う。
西欧近代ではなく、日本近代のベート―ヴェンであろうとした作曲家たちの、そして、さらに現代へと続く作曲家たちの作品を、どうぞこれからも聴かせてください。
伊福部昭先生の思い出
巨星墜つ
昨年2月、伊福部昭先生が91歳で逝去された時は「ついに巨星墜つ」と悲しんだのだが時がたつにつれ、「長寿を全うされて幸せな人生だったのでは」との思いの方が勝ってきた。先生と同じ1914年生まれで互に親しかった作曲家、早坂文雄は41歳の若さで亡くなった。芥川也寸志、黛敏郎、石井眞木、池野成といった優秀な弟子達も先生より先に逝ってしまったが、先生は古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿等人生の節目を弟子達や新響を含む演奏家、ファンからコンサートやパーティーで祝福され、膨大な業績と偉大な功績に対しては紫綬褒章、勲三等瑞宝章、そして文化功労賞まで授与されたのだ。
私が初めて伊福部作品に触れたのは新響創立20周年の1976年に芥川先生が発案された「日本の交響作品展」での「交響譚詩」で、伊福部先生に初めてお会いしたのは1980年4月「伊福部昭個展」のための練習に立ち会われた時(当時65歳)と記憶している。長身でステッキを持ち、蝶ネクタイ、黒い帽子、黒マント姿の「怪傑ゾロ」スタイルにびっくりした(晩年の先生は限りなくゴジラに似てこられたのだが)が、弟子の芥川先生に敬語を使うという暖かいお人柄に感激した(スコアの受け渡し等で尾山台のお宅に伺った新響団員達もご夫妻から丁重なおもてなしを受けたそうだ)。この27年前のコンサートで初演した「シンフォニア・タプカーラ(1979年改訂版)」には新響全団員が深く共感し、今まで14回も演奏してすっかり新響の「持ち曲」になった。
その後、先生の古希、喜寿、傘寿、米寿等の折々に度々お会いしたが、2004年2月の文化功労賞受賞をお祝いするパーティーでの先生のスピーチは今でも鮮明に残っている。「昔、お上の命令で出征兵士を鼓舞する曲を書いた。今回、文化庁から『近々責任者が伺うのでよろしく』との電話があったので時節柄、イラクに出征する自衛隊員を鼓舞する曲を書けというのだな、困ったことになった、と眠れない夜が数日続いた。結局は『文化功労賞をお受け頂けないでしょうか?』との話でホッとした」というユーモア溢れるものだった。同年5月31日の「90歳『卒寿』を祝うバースデー・コンサート」(本名徹次指揮・日フィル@サントリー・ホール)が先生にお会いした最後になってしまったのだが、先生はプログラムの謝辞に「1935年作曲の日本狂詩曲は海外では評価されたが国内では国辱的と非難され、その後も私の作品は『時代遅れで純音楽には遠い』と酷評されてきた。しかし、1980年頃から何故か事情は少しづつ変わってきた」と書かれている。1980年といえばまさに、芥川・新響が「伊福部昭個展」を開催した年で、これをきっかけに先生の作品を数多く演奏するようになった。新響は伊福部作品の真価を世に知らしめるのに貢献した、と自負してよいのではないだろうか。
葬儀後、ご遺族から香典返しとして送られてきたのは、4匹のかわいいゴジラの砂糖菓子と、側面に先生の筆跡で「日本狂詩曲・伊福部昭」と刻まれた花瓶で、我が家の家宝になっている。先生には、先に逝った弟子や新響団員達と天国で酒を酌み交わして楽しく過ごされ、地上であくせくしている我々を暖かく見守って頂きたい、と思う。
「はあ、どうぞお好きなように」
伊福部先生は北海道ご出身ですが、以前「先祖は鳥取県の神社の禰宜だった」と先生から教えていただいた記憶があります。甥御さんの、東大教授の伊福部達さんによれば、「正確には先祖は因幡(現:鳥取県)の宇部神社の宮司です。伊福部家は1500年以上前からの因幡の豪族でした。伊福部家系図によりますと、初代は大国主命で、その後天皇家の釆女の家もつとめ勤め、日本国家の制定に尽くした武内宿禰などを輩出し、大和時代に繁栄したとのことです。伊福部昭は67代目になります。明治維新の後、当主の祖父(注:伊福部昭先生のお父様)が訳あって宮司を捨てて北海道に移り住みました」ということです。大国主命の子孫だなんて、すごいですね。
近年にも伊福部家には多くの人材がおられます。お父上は北海道音更村の村長さんでした。一番上のお兄様は北海学園大学の建設工学科の教授でしたが、一方では『アイヌの熊祭り』を著すなどアイヌ文化への造詣も深かった方です(この本は絶版で、以前、出版元に問い合わせたところ、残りは3部しかないから手放せない、と断られてしまいました)。その息子さんが上記の伊福部達東大教授で、日本の福祉工学の第一人者で私も親しくさせていただいています。次兄でやはり科学技術者だった伊福部勲さんは早世されました。先生はこのお兄様のことはあまりお話になりませんでしたが、あるときぽつりと「兄はギターが上手くてね」とおっしゃったのを覚えています。名曲「交響譚詩」の第2楽章は、追悼として書かれたもので、二人で遊んだ夏祭りのお囃子が遠くから来て去っていく様子など、敬愛するお兄様への思い出にあふれる、哀しくも美しい曲です。
先生の曲はどれも私たちの心に深く残ります。「伊福部昭には上記のような歴史的な背景があることから、日本を強く意識した作品がたくさん生まれたような気がします」とは、伊福部達さんの述懐です。
さて、新響は先生の曲を芥川先生の指揮で何度も演奏させていただいていましたが、先生にはその練習にもよくおいでいただきました。いつもスーツに蝶ネクタイで、背を丸めて入ってこられました。私たちはそのときの伊福部先生と芥川先生の次のようなやり取りを忘れられません。
芥川 ここのところの弾き方、これでいいですか。
伊福部 はあ、大変結構でございます。
芥川 もう少し大きい方がいいかな、と思うんですが。
伊福部 いや、皆さんがおやりになりたいように。
芥川 でも、作曲者として何かおっしゃってくださいよ。
伊福部 はあ、どうぞお好きなように。
芥川 ・・・・。
その後に「それが指揮芸術というものですから」という一言が続いたと覚えている団員もいます。弟子の芥川先生にも、子供のような年齢の私たちにも、にこにこと一言一言、丁寧な言葉でお話になる伊福部先生でした。
196回演奏会曲目解説プログラムノート
ボロディン:歌劇「イーゴリ公」序曲
―再放送番組―
真面目で温厚な性格のアマチュア作曲家ボロディン
皆さんこんばんは、アルベルト本橋です(以下A)。今夜も「クラシックナイト野郎倶楽部」の時間がやってきました。毎回先生をお迎えして様々な角度から独断と私見によるホットでマニアックなクラシック曲をお伝えしていく、先週から始まった話題の新番組です。先週は第一回目としてゲオルグス・ペレーティスの弦楽合奏とピアノのための協奏曲「ビアンコ」をお届けいたしました。正真正銘ぜんぶ白鍵で弾かれる協奏曲です。すごかったですね~。さて今週はアレクサンドル・ポルフィーリェヴィチ・ボロディン(以下ボロディン)の「イーゴリ公」序曲です。これは歌劇「イーゴリ公」に含まれている曲として知られています。さあ、今週も素敵な先生をお呼びしています。音楽評論家の羽亜摸煮 熊三郎(はあもにいくまさぶろう)さん(以下熊)です。先生どうぞ!!
A さて羽亜摸煮さん。今夜はボロディンの「イーゴリ公」序曲ですね。よろしくお願いします。
熊 よろしくお願いします。
A このボロディン、1833年にサンクトペテルブルクで生まれ、1887年2月16日に心臓病で亡くなっているのですが、彼もともとはプロの音楽家ではなく医者で化学者だったといいますね。
熊 そうなんです。そういう意味ではボロディンはアマチュアなのです(笑)。しかし彼は13歳でフルート協奏曲を作曲したり、家族や学校の友人等あちこちのアマチュア室内楽団でチェロを弾いたり、おまけにピアノの腕は玄人はだしだったり等、音楽の才能に秀でていた少年でした。しかし彼はあくまでも音楽は趣味と割り切り、大学では化学を修め、卒業後は陸軍病院の薬剤師などを経て、サンクトペテルブルクにある大学病院に勤務し、また学者としても母校をはじめ医科大学の教授として教鞭もとっていました。そして並行して同じくアマチュア作曲家であるムソルグスキー、まぁ本業は陸軍将校なんですが…、などと親交を深め、徐々に作曲家としても頭角を現していったのです。
A なるほど作曲家と医者ですか…、多芸多才というかすごいですね。さて歌劇「イーゴリ公」についてお伺いしたいのですが、ズバリどんな曲なのでしょうか?
熊 う~ん、難しい質問ですが一言でいうなら時代劇スペクタクルでしょう(笑)。当時のロシア国民楽派の作曲家は、音楽を題材としてロシアの歴史や人物を扱う事が多かったようです。まぁ、いわば時代劇ですね。ボロディンもその一人でロシア建国時代の英雄・イーゴリ公を題材にしたオペラに着想し、1869年に書きはじめました。これはこの年の4月にロシア五人組の理論的指導者であったウラディミール・スターノフのすすめによったものだといわれています。彼はロシアの叙情詩「イーゴリ軍譚」と「イパテフスキー年代記」とから筋書きをつくってボロディンへ送ったところ、ボロディンはこれに大いに満足し、自分でリブレットを作成して同年の9月に作曲にとりかかったといわれています。
A 時代劇ですか…、今回イーゴリ公特集という事で私も曲を聴いたのですが、何というかロシア大地、壮大な風景と厳しい冬の景色というかロシア土着の香りがすごく漂っていいですね~(笑)。
熊 そうですね~。ボロディンの作品は力強い抒情性と豊かな和声が特徴ですね。息の長い中間部が存在していることが特徴で、明るい旋律がふっと寂しさを誘ったり、時に荒荒しい金管のメロディーあったりと非常に変化に富んでいるのも魅力的ですよね。この情熱的な音楽表現や比類のない和声法は、ドビッシ-やラヴェルといったフランスの作曲家にも影響を与えました。
A なるほど。で、序曲なのですが、何といいますか、「イーゴリ公」というとパッと思い浮かぶのは「ダッタン人の踊り」というイメージが強いですよね(笑)。
熊 そうなんですよね…。正直私も序曲は聴いた事なかったんです(笑)。何故か演奏される機会も少ないんですよね。説明いたしますと、この序曲は歌劇の中のいくつかの旋律をもとにして作られており、ボロディンはそのだいたいのプランを作成し友人達の前でピアノを演奏しただけで亡くなってしまったのです。その後グラズノフが暗譜していたメロディーやボロディンの草稿に基づいて作曲したといわれています。
A そうなんですか! ではこの曲は合作ということですか? それに手元の資料によりますとボロディンはものすごく作曲が遅いんですよね。代表作の歌劇「イーゴリ公」さえも1869~1887の19年間かかってますよね(笑)。しかも本人が書き上げた部分は非常に少ない。残りは友人のグラズノフやリムスキー・コルサコフが仕上げたようですね。初演も作曲者の死後3年経った1890年という…。有名な「だったん人の踊り」は本人が書いていますよね。
熊 まぁ、合作というか序曲はほぼグラズノフが作ったと言えますね(笑)。先ほど述べましたように、ただでさえ本業で多忙を極めていたボロディンですから、もとの歌劇「イーゴリ公」もいざ手がけてみたものの、完成までの道のりは相当長かったそうです。一つ面白いエピソードがあるんです。ボロディンは曲を作るにあたって台本用の歴史文献・考古学資料の下調べに時間をかけすぎて早々に作曲の情熱をなくしてしまい、書きかけの楽譜は置きっ放しになってしまったのです。友人のリムスキー・コルサコフは、何とか完成させようと考え、「イーゴリ公」の一部を演奏会にかけることにして先輩ボロディンにはっぱをかけるんです。
「お書きになりましたか?」
リムスキー・コルサコフの矢の催促に、ボロディンは答えました。
「ああ、書いたとも」
リムスキー・コルサコフが喜び勇んで行ってみると、書いたのは手紙でありました。また、なかなかスケッチを総譜(スコア)に書き写さないので、リムスキー・コルサコフがやきもきして、
「そのー、何でしょうね、あのオペラの総譜の例の曲は、もう写したでしょうね?」
と聞くと、
「うん、もちろん」
「ああ、助かった、やっと---」
「総譜はちゃんとピアノから机の上に移しましたよ」
と、ボロディンは大真面目に答えるんです。
A なんか落語みたいな話ですね(笑)。
熊 ですよね(笑)。 でもリムスキー・コルサコフが自伝にそう書いていているのだから仕方ないんです。で、いよいよ演奏会直前に合唱の練習をする段になったというのに、楽譜も出来ていなくて、とうとうリムスキー・コルサコフは弟子のリャードフと一緒に、ほとんど徹夜でボロディンを手伝うことになったんです。時間を節約するため、インクでなく鉛筆で書き、後でスコアをゼラチン液で濡らして、鉛筆の跡が消えないようにします。部屋の中には、ゼラチン液で濡れた楽譜が洗濯物のように並べて干されたのであります。 こうしてコンサートにはなんとか間に合ったのでありますが、この1879年の編曲を最後に、「イーゴリ公」は完全にほっぽり出されたのです。で、結局先ほども言いましたが序曲はグラズノフが記憶をたどって再現しました。第2幕はリムスキー・コルサコフが修正し、第3幕はグラズノフが完成させました。そしてほとんど真っ白だった第4幕は、リムスキー・コルサコフが事実上一から書き上げたものであります。従って、ボロディンの“代表作”とされる「イーゴリ公」は、実は半分くらいは他人の作品なのです。まぁこれが後々問題になるのですが…。
A 確かに「ダッタン人の踊り」や「イーゴリ公」がポピュラーなタイトルとして私たちが楽しむことができるのは、間違いなくグラズノフとリムスキー・コルサコフの功績といえるでしょうね。しかしどこかにボロディンの意図とは違ってしまったのではないかという一抹の不安も残ってますよね。実際一番有名な「ダッタン人の踊り」は本人が書いているわけですし。現在では上演される際には新たな解釈、アレンジが加えられることが多いようですね。それにしてもボロディン、代表作を未完成のままほったらかし、人に完成してもらう大作曲家なんて、なんだかある意味素敵ですね(笑)。
熊 彼が作曲が遅かったのは、決して怠惰とかぐうたらだからではありません。 彼がなかなか作曲を進められなかったのは、彼があまりにもいい人過ぎたからです。どういうことかと言いますと、つまり、人のためにばかり働いて、自分の作曲のための時間を取れなかったのです。 彼はそもそもプロの作曲家ではありません。先ほども言いましたが元来は化学者であり、長年女学校で教えていました。真面目で温厚な性格の彼は、友人や生徒から頼まれると嫌とは言えず、過大な仕事を抱え込みました。また、夜中に素晴らしい楽想が浮かんでも、ピアノに向かうことはありませんでした。安眠している家族を起こしたくなかったからであります。そして、朝になると大抵、前の晩の楽想は散ってしまっておりました。そんな方なんです。
A なるほど。もし彼がもっと作曲に集中していればどんな素晴らしい傑作を生み出したことかと、少し残念な気がいたしますね。実際、同時代のプロ作曲家であったバラキエフよりも数段ポピュラーですしね(笑)。
熊 本当です。私も是非聴いてみたいです。
A はい、今回はイーゴリ公特集という事で音楽詳論家の羽亜摸煮 熊三郎さんをお迎えしてお話してまいりました。先生ありがとうございます。
熊 ありがとうございました。
A さぁ~て、来週の「クラシックナイト野郎倶楽部」は~、Ullmann,Viktor(ウルマン)特集です。ウルマンは、アウシュヴィッツの収容所のガス室で生涯を閉じた不幸な作曲家です。しかしその人生からは想像もつかない曲の雰囲気を素敵な先生と見ていきましょう。お楽しみに!…じゃーん・けん!グー!(笑)。それでは今回はこれで失礼いたします。
注)この番組はフィクションです。
参考文献:最新 名曲解説全集 音楽之友社 ほか
初演:歌劇「イーゴリ公」 1890年11月4日(旧暦10月23日)
サンクトペテルブルク・マリインスキイ劇場
バレエ振付 レフ・イヴァノフ
編成:フルート2 、ピッコロ1、オーボエ2、クラリネット2、、ファゴット2、ホルン4 、トランペット2 、トロンボーン3 、テューバ1、ティンパニ、弦5部
コダーイ:組曲「ハーリ・ヤーノシュ」
コダーイ・ゾルターン(1882-1967)はバルトーク(1881-1945)とならんで20世紀を代表するハンガリーの作曲家です。コダーイとバルトークは共に王立音楽アカデミー(ブタペスト音楽院)で学びますが、在学中に二人の交流はありませんでした。しかし1905年にたまたま出会った二人は意気投合し共に活動を始めました。当時ハンガリーで盛んだったのは後期ロマン派風の音楽でしたが、熱烈な愛国者だった二人はこれに反発して真のハンガリー国民音楽を作る決心をします。そのためにはハンガリー民謡の研究が第一と考え、ハンガリー民謡の収集とその編集に没頭します。同時にコダーイは子供の音楽教育に心血を注ぎました。第二次世界大戦が始まりナチスドイツが近隣諸国へ侵攻すると、バルトークはアメリカへ亡命しました。しかし、コダーイは幾多の妨害に遭いながらも祖国に残り創作、演奏と教育に生涯を捧げました。大戦後には彼を大統領に推す動きも出るほど国民的象徴となりました。
私が初めて「ハーリ・ヤーノシュ」に出会ったのは小学校の時に親に連れて行ってもらった「子供の為のクラシックコンサート」でした。このコンサートでは落語家の方が物語を面白おかしく話し、その合間にオーケストラの演奏が入るという構成でした。当時落語家の語りもオーケストラもあまり生で聴いたことが無かったせいもあり、とても楽しかった記憶があります。もしかするとコダーイのおかげで私は今も音楽を楽しんでいるのかも知れません。
1926年に作曲された「組曲ハーリ・ヤーノシュ」はオペラと呼ばれるものの、実際にはモーツァルトの「魔笛」と同様に「ジングシュピール」(音楽付きの芝居)です。「ハーリ・ヤーノシュ」とは主人公の名前で、日本と同じようにハーリは姓、ヤーノシュは名前です。あらすじは、初老の農民ハーリがかつて軽騎兵であった若い頃、ウィーンに攻めてきたナポレオン軍と戦い、ついには撃退して英雄になってしまうというホラ吹き話です。
6曲の中の第3曲、第5曲ではハンガリーの代表的な民族楽器ツィンバロンが活躍します。また全般にわたり吹奏楽器が活躍するため、吹奏楽でもよく取り上げられます。
第1曲 前奏曲
まず最初にオーケストラの壮大な「くしゃみ」から始まります。ハンガリーでは昔から聞き手がくしゃみをすると、その話は本当であると言い伝えられており、コダーイのユーモアぶりがうかがえます。
第2曲 ウィーンの音楽時計
ハーリが兵隊となってウィーンに進駐したときのシーン。ウィーンの音楽時計が時刻を告げると、小さな機械仕掛けの兵隊たちが現れて行進を始めます。
木管楽器、金管楽器、打楽器、ピアノで演奏され、弦楽器はお休みです。
第3曲 歌
故郷の村を旅立つハーリが恋人のエルジュと一緒に「いつでも心は故郷のことを、そしてあなたと二人でいる事を願っている」と歌う歌です。ここでは民族楽器ツィンバロンがどこか懐かしいような響きを聴かせてくれます。
第4曲 合戦とナポレオンの敗走
ハーリの出世をねたんだ騎士の悪巧みでフランス軍が攻めてきました。しかし、ハーリは一人でフランス軍を倒し、ナポレオンはハーリに命乞いをします。木管楽器、金管楽器、打楽器のみで演奏されます。また、ジャズでよく耳にするサックスフォーンが加わります。
第5曲 間奏曲
昔から伝わるジプシーの民謡。ハンガリーでは昔から兵隊が町や村で飲食をしながらお祭りのようなものを催して、若者に軍隊生活の快適さを喧伝して入隊をうながしたそうです。この際に使われたのがヴェルブンコシュという募兵舞曲でした。
第6曲 皇帝と延臣たちの入場
今や皇帝以上に有名になった英雄ハーリが表彰される時の祝宴の音楽です。コルネットが加わり、ファンファーレも飛び出し賑やかなフィナーレとなります、めでたし、めでたし。
初演:歌劇「ハーリ・ヤーノシュ」 1926年 ハンガリー国立歌劇場
楽器編成:ツィンバロン、フルート3(ピッコロ持ち替え)オーボエ2、クラリネット2、アルトサックス1、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、コルネット3、トロンボーン3、テューバ、ピアノ、チェレスタ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、トライアングル、木琴、鉄琴、チューブラベル、弦5部
伊福部昭:シンフォニア・タプカーラ
「タプカーラ」の意味は、アイヌの「足を踏みしめる動作」の立ち踊りである。悪霊を追い払い良霊を招く動作で、相撲の四股もこの動作と言われている。伊福部昭は、1914年に釧路で生を受け道内で育った。小学校時代を過ごした十勝地方の音更の風景、そして幼年期に接したアイヌ民族の歌や踊り、これらへのノスタルジアが「シンフォニア・タプカーラ」創作の動機である。成長の後、北海道帝国大学に入学して林業を学び、卒業後は道東の厚岸で森林事務所に1939年まで勤務したが、独学で作曲を志し、1935年には「日本狂詩曲」がチェレプニン賞を受賞して作曲家としての道を歩む事になった。「シンフォニア・タプカーラ」は1954年に初稿が完成され、1955年1月26日に、インディアナポリス・シンフォニー・オーケストラ、フェビアン・セヴィッキーの指揮で演奏された。その後、1979年12月に改訂版が完成され、それ以降再演されているのはこの改訂版である。今回、新響は改訂版初演を含めて15回目の演奏
という事になる。
新響のタプカーラでは、いつも2名のピッコロ奏者が演奏する。第3楽章の練習番号43以降、下記の譜例で示すとおりピッコロの最高音付近で非常に効果的なフレーズ続く。この音域では、非常に早い息のスピードと高い息の圧力が必要であると共に、運指も複雑である。おまけに、このフレーズではブレスの位置も無いという、体力的にも演奏テクニックでも演奏不可能なのである。1935年に作曲された日本狂詩曲の第2楽章でも同様な手法でピッコロが効果的に使用されているが、こちらはタプカーラに比べて平均的な音域が三度低い事と、オーケストラ全体の響きに隠れる音も有るので隠しブレスも可能であり、演奏不可能ではない。しかし、タプカーラのこのフレーズは、どんな名人・銘器を以てしても演奏不可能なのである。1980年改訂初演から3回の演奏は、原譜の通りピッコロ奏者は1名で演奏していたが、ピッコロの音が聞こえてこなかったり、5度下の音が聞こえたりと、作曲者が意図した効果は全く実現できていなかった。譜例の通り、1番フルートの記譜はピッコロと同じであり、実音はピッコロより1オクターブ低いので、ピッコロが記譜通り演奏されれば殆ど聞こえなくなる。(ピッコロの譜面は実音より1オクターブ低く記譜される)そこで1984年10月の第3回の演奏からは、第3楽章の練習番号42以降、1番フルート奏者がピッコロに持ち替えて演奏するようになり、作曲者の意図した効果が出るようになった。このとき、演奏者の席順はピッコロ持ち替えの1番フルート、2番フルート、ピッコロという順番になるので、2番フルートはフォルテシモでオーケストラ最高音に近い音を出し続ける2本のピッコロに挟まれることになり、2番フルート奏者は毎回の練習の度に耳鳴りと頭痛に悩まされた。これでは、2番フルートの団員があまりに可哀想なので、1985年の第5回目演奏以降は2名のピッコロ奏者で演奏する現在の演奏様式になった。それでも、一番端に座る奏者には隣の奏者のピッコロの音が直撃するので、一番端の奏者は左耳に耳栓をして演奏している。第3楽章クライマックスでのピッコロの音響効果は、憑かれたように無心に踊りに没頭している曲想に素晴らしく効果的であるが、ピッコロ奏者は貧血直前で頭の中が真っ白になり、まさに憑かれたように無心でなければ演奏できないのである。
今回のタプカーラは伊福部先生が天に召されてから新響では始めての演奏である。伊福部先生は、先
に天に召された弟子の芥川也寸志先生や石井眞木先生と共に、天上の観客席からご覧になっているに違いない。3人のこんな会話が聞こえてきそうである。
石井 いつもの事ながら、新響のタプカーラはピッコロ2本で、迫力があって良いですなー。
伊福部 いつもピッコロ2本で演奏してくれて、申し訳ない事です。
芥川 申し訳ないことなんか無いですよ。なるべく多くの団員が演奏に参加した方が良いんです。みんな、この曲を愛していますから。
新交響楽団「シンフォニア・タプカーラ」演奏記録
(演奏年・演奏会タイトル・指揮者・演奏会場 の順)
1987 日本の交響作品展4 芥川也寸志 東京文化会館
1981 福生ニューイヤーコンサート 芥川也寸志 福生市民ホール
1984 アマチュアオーケストラ連盟フェスティバル 芥川也寸志 東京文化会館
1984 伊福部昭古希記念交響コンサート 芥川也寸志 東京文化会館
1985 MRKコンサート 芥川也寸志 新宿文化センター
1987 東京第三友の会演奏会 芥川也寸志 杉並公会堂
1987 サントリー音楽賞受賞演奏家シリーズ 芥川也寸志 サントリー・ホール
1990 アマチュアオーケストラ連盟フェスティバル 石井眞木 東京文化会館
1994 第145回演奏会 原田幸一郎 東京芸術劇場
1999 第165回演奏会 井﨑正浩 東京芸術劇場
1999 九州演奏旅行 井﨑正浩 アクロス福岡シンフォニーホール
1999 九州演奏旅行 井﨑正浩 熊本県立劇場
1999 九州演奏旅行 井﨑正浩 九州厚生年金会館
2002 伊福部昭米寿記念演奏会 石井眞木 紀尾井ホール
改訂初演:1980年4月6日 芥川也寸志指揮 新交響楽団
楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トムトム3、小太鼓、キューバン・ティンバレス、ギロ、ハープ、弦5部
196回演奏会のご案内
シンフォニア・タプカーラ
2006年2月8日に伊福部昭先生が亡くなってから、196回演奏会当日でほぼ1年となります。今回は先生の1年祭ということもあり、これまでに何度も演奏してきた「シンフォニア・タプカーラ」をメインとしたプログラムを組みました。
「この曲の初稿は1954年に完成したが後に改訂を施し1979年12月に脱稿した。作者によれば主たる改訂は、1楽章の冒頭、2楽章の中間部、3楽章の結尾部に行われたという。改訂版の初演は1980年4月6日、芥川也寸志指揮により、当団第87回演奏会「日本の交響作品展-4 伊福部昭」で行われた」(第145回演奏会プログラムより)
伊福部作品を新響は数多く演奏しており、創立50周年記念シリーズでも7月に「管絃楽のための日本組曲」を取り上げました。しかし、上記のプログラムの文章にあるように、伊福部作品の中でも「シンフォニア・タプカーラ」は新響のために改訂版を作っていただいた記念すべき作品として、今なお新響団員の一つの拠りどころとなっています。
タプカーラとは、アイヌの足を踏みしめる動作を意味しており、悪霊を追払い良霊を招くものとされています。この日本の古い信仰に根ざした動作が各地の民族芸能や宗教儀式に今も多数見られ、身近なところでは相僕の四股(しこ)もこれにあたると言われています(同上より)。
今回の演奏は2002年5月の伊福部昭米寿記念演奏会以来となります。また、指揮の井﨑正浩氏とは1999年の165回演奏会でこの曲を演奏しており、その際、伊福部先生にリハーサルに来ていただきました。約8年経った196回演奏会で、その時の経験がどのように発揮されるか、ご期待ください。
「イーゴリ公」と「ハーリ・ヤーノシュ」
プログラムの前半はロシア・東欧作品です。指揮の井﨑正浩は海外での拠点をハンガリーに置き、これまでにハンガリー国立響(現、ナショナル・フィル)、ブダペスト放送響、マターヴ響、マーヴ響、ハンガリー国立歌劇場管弦楽団(ブダペスト・フィル)などを始めハンガリーの主要なオーケストラのほとんどに客演指揮し、高い評価を受けています。
井﨑にとって第2の故郷ともいえるハンガリーを代表する作曲家、コダーイの組曲「ハーリ・ヤーノシュ」はオペラというよりも「歌つき芝居」の原曲から、作曲者自身が編曲したものです。ハーリ・ヤーノシュは、ハンガリーでは知らない人がいないほど有名な伝説上の人物であり、退役軍人の彼が若い頃、ウィーンに攻めてきたナポレオン軍と戦って撃退したというホラ話が内容になっています。ツィンバロンが曲の中で効果的に使われており、マジャール(ハンガリー)の郷愁を効果的に表しています。
1曲目のイーゴリ公もルーシ(現在のウクライナにあたる地域)の英雄の物語で、ロシア文学の草創期を代表する叙事詩を基にしたオペラの序曲です。
196回演奏会当日は東京でも寒さが最も厳しい時期ですが、ルーシ=マジャール=アイヌの熱い思いを込めた演奏会にしたいと思います。
オーケストラへの扉 =『ハーリ・ヤーノシュ』をめぐる個人史=
■出発点としての吹奏楽
新響の管楽器奏者でも、吹奏楽と全く無縁で来た人はそれほど多くはあるまい。そして縁がある場合、吹奏楽を自らの「音楽人生」の出発点にしている・・・のではないかと思う。概して言えば、余り音楽や楽器の演奏に縁が無い境遇に育ち、初めて接した音楽環境が中学校で入った吹奏楽部。しかもそこでは必ずしも自分の希望する楽器を割り当てられず(一例だが1970年代からフルートは既に男子禁制のパートだった)、不本意ながらもあてがわれた楽器(因みに僕の場合はテューバ)とそのパートを黙々と続ける、それだけが音楽・・・特に合奏という場・・・を体験できる唯一の道だったというケース。だからいずれその集団から抜け出て、その楽器を続けなければならない必然性がなくなると、他の楽器に転向する事はむしろ自然だった。という訳で新響内部でも、誰が「転向組」で元々何の楽器をやっていたか?は時々話題になるばかりでなく、本当にその「古巣」の楽器の演奏を聴く機会さえある(大抵上手い)。
さて、30年以上前の自分の体験を書き記す事をお許しいただきたい。まぁ昔語りも多少は許される程度には枯れてきた・・・と思うので(苦笑)。
僕の高校時代は1973年から76年までだ。荻窪のさる大学附属校で送った3年間の演奏活動も、楽器こそフルートに変わっていたが、吹奏楽以外の選択肢は無かった。そもそも全日本吹奏楽コンクールの全国大会常連校であった事が、この学校への進学を決めた最大の理由だったのだから仕方が無い。今もそうだろうが、吹奏楽とコンクールとは不可分の関係だ。コンクールで優秀な成績を収める団体に身をおくことが、より質の高い「演奏」に参加できる唯一の手段であり、且つ当時は僕の出身県である埼玉県下の如何なる高校に進んでも、全国大会に出られる目は全く無かったのだから、質を求めればどうしても県外に出るほかは無かったのだった。
このコンクールに対する諸々の体験や感想については、いずれ別の機会を得て書く事もあろう。今ここでは3年間一度も全国大会に行く事が無かったという事実だけを書くにとどめる。この事は当時の僕にとっては人生の根幹に関わるような事であった訳だが、今になってみればどうという事は無い。以下に書く『ハーリ・ヤーノシュ』に関わる一連の事に比べれば・・・だが。
■吹奏楽をめぐるふたつの志向
様々なジャンルの作品を演奏の対象とする吹奏楽の団体は、大まかにふたつの志向をもっている。それは「古典的」若しくは「伝統的な」スタイルの音楽を志向しようとする流れと、よりなじみの深い、一般にいう「軽音楽」に傾倒しようとする流れである。前者は吹奏楽の為に書かれたオリジナルの作品を演奏する事にとどまらず(何故なら吹奏楽の歴史そのものが浅いので、オリジナル作品そのものが質にも量にも恵まれていないのだ)、オーケストラ作品を吹奏楽用に編曲したものを厳格に演奏する事をまず考える。吹奏楽の真骨頂たる行進曲もこちらに入るだろう。後者はそれに比べると遥かに柔軟なレパートリーでよしとする。
これらは各奏者の嗜好に基づいており、そのバランスの違いはあっても両者は必ず団体内に並存する。だから一般に吹奏楽団体のコンサートは2部構成で、第1部はクラシカルなお堅い選曲で固め、第2部はポップス系の作品メドレー・・・大抵はこちらの方がメンバーは生き生きと演奏する・・・というものになりがちだ。そうでなければ最大多数の最大幸福が保たれないのだ。これは前述したとおり「音楽をする唯一の手段」として吹奏楽を選ばざるを得ない人間がいる限り、今後もあり続けるだろう。このあたりがオーケストラと大きく異なる点である。僕が高校在学中の1974年に初めてコンクールの「課題曲」がスタイルの異なる2種類の曲に分かれたが、これとてそうした背景を考えればごく自然な帰結と思えてくるのである。
■『ハーリ・ヤーノシュ』への道
我々の吹奏楽団(僕らの学校では他のクラブと異なり「吹奏楽部」ではなく「吹奏楽団」が正式な名称だった)内部でもその拮抗は絶えずあり、運営を支配するその時々の上級生の意向により方針は年々大きく振れた。僕は当然「正統派」だったので、最上級生として所謂「練習指揮者」となると、それまで傾斜しすぎていたポップス路線をゆり戻すべく、あらゆる試みをした。例えばシェーンベルクが吹奏楽の為に書いた作品(というものがあるのだ)『主題と変奏(作品43-a)』の譜面を、本郷三丁目のアカデミア・ミュージック・・・当時の同店は、現在の場所より駅寄りにあった・・・の薄暗い書棚から探し出して強引に練習にかけたが、そもそもこうした音響に慣れていない団員間では不評だった。今でも良い曲だと思っているのだが、これは流石に劇薬に過ぎたようだ。
この時の団員数は僅かに35名だった。この人数の少なさが、コンクールでのハンディキャップとなったが、僕の1学年下には現在広島交響楽団でオーボエ奏者を務める柴滋氏、更に下にはNHK交響楽団クラリネット奏者となった加藤明久氏がおり、それ以外の奏者も含めて今考えても人材的にはひとつのピークを迎えていた。何でもやってみようとする意慾が横溢しており、そこで出てきたのがコダーイの『ハーリ・ヤーノシュ』の編曲構想だった。
『ハーリ・ヤーノシュ』なる作品が、我々のようなともすれば偏った音楽体験しか得られぬ高校生にまで知られるようになった理由にも、コンクールが関わってくる。前年の全国大会で、この曲(のごく一部)を自由曲に取り上げた団体があったのだ。こうしたものはすぐ伝染する。それは『戦争とナポレオンの敗北』と終曲『皇帝と廷臣の入場』の2曲だけだったが、その後あらゆる吹奏楽団にとって、重要なレパートリーになった。いま聴いてみても上の2曲は、ハーリの語る荒唐無稽な内容をそのまま音にしたようなある種不思議な部分だ。僕は『戦争と~』中にあるトロンボーンの旋律末尾に現れるF→Hという増4度の跳躍が、しばらく頭から離れなくなった。因みに言えば増4度(減5度)の音程は、ヨーロッパの音楽では「悪魔の音程」と言われて忌避される作曲上の禁じ手である。こうした奇抜さに当時の僕らは魅了されてしまったのだ。
で、当然の事だが全曲を聴いてみた。巨大な「くしゃみ」の描写から音楽が始まるのも奇抜だが、これは物語りの最中に聞き手の誰かがくしゃみをすると、その話は現実のものとなるというハンガリーの言い伝えに基づくものだ(『ハンガリー民話集(岩波文庫)』には編者である同国の民俗学者オルトゥタイにより、民衆間に於けるこうした語り手・聞き手の実態や慣習が詳述されているが、どうした訳かこのくしゃみの件は書いていない)。いずれにせよ、もうここまで来ると機は熟していたと言って良い。自分らの手を以って、何とかこれを全曲演奏してみようとの野心が沸々と起こるまで、さしたる時間を必要とはしなかった。
1975年5月2日金曜日・・・行動を起こした。まず再びアカデミア・ミュージックに行き、スコアを探し出した。2,400円の大枚をはたいて購入。次に池袋のヤマハで34段の大型五線紙を大量に買いこんだ。あとはひたすら「作業」である。
作業の基本はオリジナルのオーケストレーションを、吹奏楽にある楽器のパートに割り振る・・・という事だが、当然の事ながら吹奏楽には無く、しかもオーケストラでは主体になっている絃楽5部のパートをどこにどう割り振るか?が難しい。最も安直なのは人数も多く、高音部から低音部までの楽器が充実しているクラリネットを充てるという方策。実はこうした凡庸極まりない「編曲版」が市販されている譜面の大半を占めていた。だがこれでは絶えずクラリネットが鳴っている印象しか与えられないので、他の楽器を重ねて音色に変化を与える・・・という仕掛け作りが必要になるのだ。
また、同じ楽器を使用していても、管絃楽と吹奏楽では求められる音色や使われる音域など、楽器の用法が異なる場合が多々ある。例えばホルンの扱い方は、その記譜法を含めて違いが顕著なひとつだ。だからオリジナルのパートと同じ楽器だからといって、その譜面をそのまま転記しても吹奏楽では音に出来ないというケースもある。
それから山のようにある移調楽器への対処。「inE♭」で記譜されているアルト・サクソフォーンに実音のニ長調を吹かせるには、譜面に何の調号をいくつ付ければ良いか?(答えは#5つ=♭7つ)という変換を頭の中で行ない、ダブルシャープやダブルフラットなど、日頃はあまり目にする事の少ない記号を思い浮かべながら実際に移調をさせて34段の五線を埋めてゆく・・・という訳で、結構複雑な作業を伴う。この原稿を書くにあたり、久々にそのスコアを出して一覧したが、各曲とも大抵4日ほどで仕上げている。これ以前にも何曲か同様の事を手がけてはおり、ある種の慣れは身についていたのだろうが、17歳当時は頭も手も存分に機能していたのにわが事ながら驚く。勿論・・・これは学業の合間にやっていた(筈だ!)。
■17歳の挫折と転機
さて、その結果だが第3曲目の『歌』(これが表題である。余談だが、由緒ある居酒屋の品書きに、銘酒であってもただ「酒」とだけある潔さをいつも想い浮かべてしまう)は編曲を断念せざるを得なかった。僕はこの曲に最も強い印象と、郷愁のようなものを感じ取っていたので、何とかならないかと知恵を絞ったが、どうやっても35名の編成では無理だった。
そもそも前面に出てくるツィンバロンというハンガリーの民族楽器のパートは他の楽器で代替する事が不可能だったし、厳密に言えば冒頭のヴィオラのソロも、管楽器では表現し難いニュアンスを含んでいる。それ以上に問題だったのは絃楽器群に最弱音で出てくる高音域のトレモロだった。吹奏楽器の宿命であるブレスの問題はさておくとしても、高音域を最弱音で、且つ霞むような質感を出せる管楽器は、残念ながら存在しない。だからマーラーの『巨人』やブルックナーの交響曲第7番を吹奏楽でやろうとすると(そんな野望を抱くところはないだろうが)、その冒頭から行き詰まってしまう事になる。
身もふたも無い言い方をすれば、最もハンガリー的な色彩の強いこの『歌』の部分を欠いている事で、既に編曲は失敗だった。コンサートのプログラムにするにしても、あくまで「抜粋」とせざるを得ないのだから。それでも一応パート譜を作り、音にはしてみた。悪くは無い出来だったが、「やはり何かが足りない」という欠落感は拭えなかった。考えてみればこれは当然の事だ。『ハーリ・ヤーノシュ』6曲の編成にはサクソフォーンやコルネットや多彩な打楽器群など、吹奏楽で使用されている楽器の殆どを含んでいる。だからその音響は多分に「吹奏楽的」で、実際『ウィーンの音楽時計』や前述の『戦争とナポレオンの敗北』は管打楽器だけの曲である。そしてその上に絃楽器が加わって前述の『歌』や『間奏曲』のような世界を作り上げる。この音響的な対比こそがこの組曲のひとつの魅力であり、作品の深みに結びついている。だが当時はこうした事を分析的に考える力は無く、やみくもに音にしてみてただ「何かが足りない」と首をかしげるだけだった。やはり気力と体力はあっても思慮には欠ける高校3年生だったのだ。最近は気力と体力さえ欠けてきて、いささかうんざりしているが(苦笑)。
この失敗から得たものは詰まるところ、「オーケストラの作品はオーケストラの為に書かれ、オーケストラでなければ再現は出来ない」という至極単純な真理だった。オーケストラならではの音域や音色や音量の多彩さ。その精緻な表現力とそれを活かした作品の多様性。そうした世界がこの世にあるのだと気づいた瞬間、僕はオーケストラへの扉を開けた訳で、それは確実にその後の人生の転機になった。こんな簡単な事が転機になってよかったのだろうか?との思いは今もあるが、とにかく「これからは何が何でもオーケストラだ!」となって、それまで漠然としか捉えていなかった進路を急にすっきりさせた。すなわち附属大学への進学を捨て、「しっかりしたオーケストラ」のある大学に入ろうと考え直したのだ。これは当時としては、結構勇気の要る選択だった。音大への興味が湧かぬでも無かったが、オーケストラで演奏する機会を得る事を優先すればこれはむしろマイナスの要因となり得たし、そもそも音大進学を考えるには成績が良すぎた(冗談です)。
いずれにせよ、いくつかの紆余曲折を経て大学入学と同時にオーケストラに籍を置き、所謂「カラヤンコンクール」での演奏と優勝を体験し、最盛期のジュネス(この時のメンバーの多くは、新響を含め今も主要なアマチュアオーケストラの中核として活動を続けている)での演奏機会も得た。卒業後1年して新響に入り、退団に追い込まれる事も無く(2007年9月で在団25年)、ずっとオーケストラに関わって来られたのだから、僥倖としなければなるまい。その契機に『ハーリ・ヤーノシュ』があり、それをオーケストラで演奏する機会を遂に得た事に、殊更の感慨を禁じ得ない。
「心血を注いで仕上げた」手書きのスコアは僕の譜面棚に放置されたまま、その後全然日の目を見ていない。僕自身がその後吹奏楽から離れてしまったから、演奏される機会はついに巡っては来なかったのだ。冷めてしまえばあれは一体何だったのかと苦笑するほかない一時の熱情だったのかも知れない。が、びっしり書き込まれた音符群を眺めていると、吹奏楽という唯一の窓から、音楽の宇宙を何とかして覗こうとした若き日の無謀の軌跡にも見え、その後の音楽体験を経るうちに自分の中から喪われて久しいものに思い至るのである。
歌劇「イーゴリ公」の思い出
○20年来の思い
私ごとで恐縮ですが、ボロディンの歌劇「イーゴリ公」は私にとって、もっとも思い出深い曲のひとつです。今から二十年ほど前、私は所属している大学の吹奏楽団で学生指揮を務めていたのですが、当事はちょうどバブルの絶頂期。学生も合コンやディスコに忙しく、地味に毎日練習をしているような音楽系のクラブは敬遠されて、団員減少の一途を辿っていました。一時は存亡の危機にまで立たされましたが、学生時代最後の演奏会を、何とか想い出に残る演奏会にしたいと、夜を徹して侃々諤々、選曲について議論しました。
そして少人数でも、編成やアンサンブルに無理が無く、かつ親しみやすく、難易度的にも比較的やりがいのある曲という条件でいろいろ探し回って、やっと選曲したのがボロディンの「イーゴリ公」でした。
ところが、スコアを入手してみるとその厚さ約10cm。どこを抜粋するかで、また散々悩み、結局、だったん人の踊りやホロヴィッツの娘たちの踊りなど、よく演奏される箇所を選んだのですが、最後までプログラムに入れるかどうか迷ったのが、今回新響で演奏する「序曲」でした。
遥か彼方から続く地平線をイメージさせるような冒頭の弦楽器、草原を駿馬が疾走するような躍動感溢れる金管楽器のベルトーン、そして、「だったん人の踊り」の有名なフレーズを連想させるホルンと弦楽器の流れるような美しい旋律、次から次へと歌劇の有名なシーンが繰り広げられます。この序曲を聴くだけで、イーゴリ公の英雄伝とそれにまつわる数々の美しいシーンが思い浮かぶかのようです。しかし、結局プログラム構成の都合で当事は演奏することができず、それ以来20数年間ずっと心の中に私の名曲としてしまい込んでいたのでした。
○「イーゴリ公」の魅力
今回、演奏する機会に恵まれて、あらためて「イーゴリ公」のストーリーを読んでみたのですが、この歌劇の元となった「イーゴリ遠征物語」は小説として読んでもとても面白い物語です。(日本語版は、岩波文庫から「イーゴリ遠征物語」の題名で出版されています。)
物語の詳細はプログラム解説に譲りますが、主人公が囚われの身となるが敵はイーゴリの勇敢な戦いを讃え寛大にもてなすシーンや、イーゴリの息子が敵方の美しい娘と恋仲になる話など、イタリアオペラなどにはあまり見られない、ロシア的な人間味溢れる物語も、この曲の魅力の一つです。
さて今回の新響は、イーゴリ公の舞台となったウクライナに近い、東欧で指揮の研鑽を詰まれた井崎先生による演奏です。雄大なロシアの大地と勇敢な騎馬兵士たち、そして敵・味方を交えた深い友情や愛情がどのように表現されるか、私たちもとても楽しみにしています。
井﨑正浩先生のこと
リコーフィルハーモニーオーケストラという、今年創立20周年を迎えたアマオケがある。主な演奏会は、定期とサマーコンサートなど、これまで42回行なっているが、その第1回定期と94年のサマーコンサート以外はすべて井﨑先生に振っていただいている。私は5年前まで(株)リコーに勤務していて、創立以来ずっと在籍し、転職した現在も常任・トラ代なしの主要(?)エキストラである。井﨑先生によれば、上京して初めて聞いたオケが新響、初めて振った本格的(?)オケがリコーフィルだということで、両方に関わっている私としてははなはだ縁が深い。
1995年、リコーフィルの練習で歓声が上がった。ハンガリーでのブダペスト国際指揮者コンクールの予選に井﨑先生が通った、というニュースが入ってきたのである。そして次の練習では、優勝したというニュースに大騒ぎになった。「あの時と同じだ・・・」私は1974年の新響の練習を思い出していた。当時、芥川也寸志先生の弟子としてときどき新響の練習を振り、コンクールのための指揮練習にも新響が付き合った小林研一郎氏が、ブダペストのコンクールの予選を通った、優勝した、というニュースが練習のときに入ってきて、芥川先生と共に喜んだのである。新響はこのコンクールの優勝者の小林研一郎氏、本名徹次氏にも振っていただいており、井﨑先生も含めてこのコンクールには結構縁があるといえるだろう。
私は井﨑先生の優勝記念のパーティの祝辞で、二つの生意気な、しかも相矛盾することを言った。「井﨑先生はリコーフィルでスタートしたのだから、偉くなっても恩知らずにならないで、いつまでも指導してください」、「いつまでもリコーフィルを振れるような時間が余っている指揮者ではいけません」。
さて、井﨑先生は今もリコーフィルは必ず振ってくれている。新響もお願いしたときは必ず振っていただいている。時間が余っているからではない。律儀な井﨑先生ならではのことである。しかし、もう一つ生意気なことを言わせていただくと、その律儀さを抑えてでも、指揮者としてのカリスマ性をもっと出してもらっていいと思っている。世の中で偉くなっている人柄の悪い人、恩知らずの人はたくさんいるではないか。前回の「トリスタンとイゾルデ」の作曲者ワーグナーもとんでもない人柄だったそうだし。と、いいながら、私は井﨑先生に性格の悪い人になってもらいたいと思っているのではない.その良さを保って,さらに巨匠といわれるようになっていただきたいし、なれる人なのである。新響では思いっきり厳しく指導していただき、井﨑音楽を作っていただけるものと楽しみにしている。
ホルツトランペットについて
「トリスタンとイゾルデ」には、ホルツトランペットという楽器が登場します。実はこの楽器、ワーグナーが想像上の不思議な音を出す楽器として使用したのですが、実存する楽器ではありません。スコアには「アルペンホルンのように木でできたトランペットで吹く。」と書いてありますが、この曲のためだけに作られた楽器は世界で数台しかないため、今回、ベル部分が木製の「ホルツトランペット」を自作しました。
恐らく日本では1台限りの楽器です。第三幕第一場の終わりにファンファーレとして登場しますので、どうぞお楽しみに。
マエストロ 飯守の誌上講義
「トリスタンとイゾルデ」について
今回この偉大なる作品に取り組むにあたり、演奏者一人一人が深い理解と共感を持って曲に臨むべく、飯守先生との初リハーサルの日に先生にピアノを弾きながら解説をしていただきました。文章ではその内容を十分にお伝えすることはできませんが、「誌上講義」という趣でお読みいただければ幸いです。
(この場では先生のピアノ演奏を表現できないことが誠に残念です。)
ワーグナーと示導動機
ワーグナーというのは説明しだすと本当にきりがありません。それほど表現の内容が入り組んでいて、いろいろ絡み合っているのです。特に「示導動機(ライトモチーフ)」についての問題はいろいろあって名前の付け方すら一致しないことがありますが、それは曲全体に網の目のように張り巡らされていて、全体としてひとつの大きな作品を構成しています。とはいえ、ワーグナーは自分から示導動機を名付けていないし、システマティックに作り上げて作曲していったわけではないんですね。彼としては、何というか一つの「思い入れ」としての動機のつもりだったのですが、後世の人たちが研究した結果、あまりにもうまくできていたため、いろいろな理論がそこから取り出せるということになったわけです。ですから、ちょっと誇張されてしまい、示導動機が一人歩きしてしまったり、あるいは示導動機でなんでも理論付けてしまうようなことが起こりがちです。しかし実際のところワーグナーはそこまで考えていなかったのではないでしょうか?
示導動機は「リング」*1の場合は非常に明確な具体性をもっています。「ラインの黄金」の動機だとか「ジークフリート」の動機だとか。明らかに物体や物事、例えば殺しとか勝利や敗北といった、かなりはっきりした具体性をもっているのですが、「トリスタンとイゾルデ」の示導動機には「暗示」と「象徴性」が入ってくるのです。おそらくすべての音楽の中で最も内面性を深く表していて、人の心の内面、感情表現、つまり言葉では表せないようなことを象徴しています。しかし、内面性を表すとどうしても具体性に欠けてしまう。これがこの作品に対して第一に言えることで、そういう内面の音楽を作ったという意味で「トリスタン」は革命的だったのです。
革新的な半音階の用法
そしてその「革命」がどのように行われたかというと、半音階を中心に使い、全音階から遠ざかるということでした。つまり、そうすることで調性が不安定になり、和声が複雑になっていく。半音階を駆使することにより人間の内面を深く表現できたわけです。その結果、これはよく言われることですが、「トリスタンとイゾルデ」という音楽が作曲の面で大きな革命を起こした -ここから調性が崩壊し始めたひとつの出発点である、と。後にシェーンベルクがそれをさらに推し進めて「調性の否定」「12音技法の確立」へともっと先へ行くことになります。これをワーグナーに責任がある、と唱える人がいますが僕はそう思わない。調性の崩壊に導いたのが「トリスタン」であるというのは、それを理由に、これ以上できないということを感じた人たちが崩壊、つまり新しい方向へ行くということを自ら望んだのでしょう。フルトヴェングラーが言っていますが、「トリスタンこそ、調性を否定したのではなく、最大限まで使いこなした」ということなんです。半音階をどんどん使って非和声音をたくさん入れると調性は不安定になる。そこに言葉では言い表わせない内面の暗示や象徴的表現が生まれる。そのような点でいえば、「トリスタン」を超えるものはないのではないでしょうか?
それではさっそく音を出しながら説明しましょう。
前奏曲・第一幕
 有名だから皆さんご存知だと思いますが、これが前奏曲のいわゆる「トリスタン・アコード(和音)」です。(譜例1の2小節目最初の音)これは「憧憬の動機」または”Liebestrank”(愛の魔酒)と言われています。最初にチェロのものすごいクレッシェンドがあります。ここの音の跳躍は次の下降音型を強調するためのものであって、その長い下降音型(半音降りること)が「痛み」を表現しています。そして次の和音で調性が壊れたと言い切る人がいるくらい、曰くつきの和音です。3小節目の最後の和音は解決感がありますが、属7の和音*2ですから解決にはなっていません。
有名だから皆さんご存知だと思いますが、これが前奏曲のいわゆる「トリスタン・アコード(和音)」です。(譜例1の2小節目最初の音)これは「憧憬の動機」または”Liebestrank”(愛の魔酒)と言われています。最初にチェロのものすごいクレッシェンドがあります。ここの音の跳躍は次の下降音型を強調するためのものであって、その長い下降音型(半音降りること)が「痛み」を表現しています。そして次の和音で調性が壊れたと言い切る人がいるくらい、曰くつきの和音です。3小節目の最後の和音は解決感がありますが、属7の和音*2ですから解決にはなっていません。
この動機は「普通ならこうなる」という音を半音上げたり下げたりして手を加えたわけですが、これはまさにワーグナーのインスピレーションですね。理屈じゃない。なぜ彼はこんなことを思いついたのか?とにかくすごい発明です。
そして譜例2の2小節目で和音が解決します。欲求が満たされた感じがしますが、これは「愛への欲求」でトリスタンの「渇望の動機」または「愛の動機A・愛のまなざし」といわれています。ここでもまた半音が使われていますね。
次に、譜例3「愛の動機」にも半音があります。そしてトリスタン・アコード。内声にご注意ください。他にもあちこちに半音が内在しています。
譜例4ですが、実は対旋律がファゴットとホルンにあります。愛の動機が変形されたり、一方で死の動機が出てきていろいろと絡み合ったり、織り込まれたりして、それが一つになって進んでいきます。そうして譜例5が木管楽器に出てきます。
さらに変形を繰り返しつつ、また一方で譜例6「運命の動機」も現われます。このように、いろいろな動機が変奏され、絡み合いながら、前奏曲のいわゆるクライマックスを迎えますが、これもまたトリスタン・アコードです。
「運命の動機」といえば譜例7もあってこれは第五場の最初にも現われますが、トリスタンが登場するまさに運命的瞬間を表しています。
「トリスタンとイゾルデ」は内面を表現した音楽ですが、憎悪と愛、痛みと快楽、渇望と絶望、そういう相反するものが両方成り立っているのです。「リング」の場合は、「立派な人には立派なアコード、悪人は不協和音」と明確なパターンがありますが、ここでは共存しています。
譜例8「心の動揺」は怒りやフラストレーションを表す動機で、あちこちに登場します。トリスタンが毒薬を飲むという時や第二幕でマルケ王が怒る場面でも、やり場のない気持ちを表現しています。
譜例9「死の動機」でも半音が使われています。最後の部分の半音の動きが譜例11「宿命の動機」と同じです。譜例10の「死の動機」は、なかなか気づきにくいのですが、よく現れます。チェロ、コントラバス、ファゴットが下からクレッシェンドして浮き上がってドーンと落ちる。これが「死」を象徴した動きなんです。
それから「病めるトリスタン(タントリス)」という動機も半音が活躍します。瀕死のトリスタンがここでは下降形の半音階で表現されています。実は、トリスタンはイゾルデの許婚のモロルトと闘って殺すのですが、そのときに自分もモロルトの剣に塗ってあった毒で致命傷を負ってしまいます。それを治療できるのはイゾルデしかいなかったので、瀕死の状態で「タントリス」とう偽名を名乗ってイゾルデの元へたどり着きましたが、彼女は許婚を殺した相手だと見抜いていました。・・・これはどこにも出てこない場面だけれども、大事な話なんです。
譜例12は「イゾルデの嘲弄」です。トリスタンが自分のことをマルケ王に嫁がせることについて、トリスタンを嘲り皮肉りながら歌う場面です。この辺はわりと調性があるところですね。
第二幕
 まず第二幕で重要なことは、ここで二人がついに逢引きをすること、そしてそれは「夜」だということです。ロマン派文学の作家がすべて一致することですが、愛が満たされるのは夜である、ということ。昼間はその反対で、嫌悪や破壊の対象であり、敵なのです。第二幕はショッキングな音楽で始まります(譜例13)。この忌々しい「光の動機」は倍の速さになったりして形をいろいろ変えて、その後数限りなく出てきます。
まず第二幕で重要なことは、ここで二人がついに逢引きをすること、そしてそれは「夜」だということです。ロマン派文学の作家がすべて一致することですが、愛が満たされるのは夜である、ということ。昼間はその反対で、嫌悪や破壊の対象であり、敵なのです。第二幕はショッキングな音楽で始まります(譜例13)。この忌々しい「光の動機」は倍の速さになったりして形をいろいろ変えて、その後数限りなく出てきます。
トリスタンが現われる場面で「愛の歓喜A」(譜例14)が出てきます。「愛の歓喜D」(譜例17)は「愛の歓喜B」(譜例15)の変形で、何度も繰り返されてどんどん盛り上がり、そしてついに「Tristan!」「Isolde!」と叫び、二人はついに抱き合うのです。これがいかに激しいか、渇望していたか、というのがよくわかります。それにしても狂ったような逢引きですね。「愛の歓喜C」(譜例16)が何度も出てきます。そして「憎むべき光よ」と歌い、昼と夜の哲学を延々と語ります。ここはあまりに長いので、ドイツでもよくカットをされます(今回もカット)。
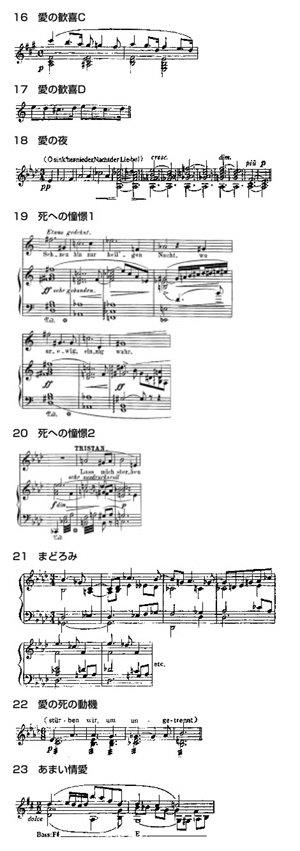 第二幕で一番大事なのは、本当の愛の恍惚です。どの本にも出ていなくて僕が非常に大事だと考えているところがあるんですが、それが「愛の夜」(譜例18)の直前に現われる「死への憧憬」です。(譜例19、20)曲にはたくさん出てくるけれども、どの本にもない。他にもいっぱいありすぎて、取り上げるのが面倒くさいのかもしれませんが。抱き合っている時にトリスタンが「私を死なせてくれ」と言うんです。そこにはこれが必ず出てきます。
第二幕で一番大事なのは、本当の愛の恍惚です。どの本にも出ていなくて僕が非常に大事だと考えているところがあるんですが、それが「愛の夜」(譜例18)の直前に現われる「死への憧憬」です。(譜例19、20)曲にはたくさん出てくるけれども、どの本にもない。他にもいっぱいありすぎて、取り上げるのが面倒くさいのかもしれませんが。抱き合っている時にトリスタンが「私を死なせてくれ」と言うんです。そこにはこれが必ず出てきます。
譜例18の部分は変わったシンコペーションですが(オーケストラの譜面はシンコペーションになっている)、どういうリズムかわからないように、わざとぼかしています。非常に単純ですが、全部非和声音です。これくらい深い感覚を表現するものは他にないですね。そしてまた「光の動機」が出てきたりして、その後の盛り上がり方もなんともいえません。これで本当に二人の愛が結ばれたという充足感があります。このあとブランゲーネが見張り台から「もうすぐ夜が明けます、気をつけてください」と歌いますが、これもまた夜の音楽ですね、実に美しい。
前に調性の話をしましたが、第一幕の最後でマルケ王の登場する場面はC-dur(ハ長調)です。栄光に称えられた王様、現実の世界。そこから一番遠いのはGes-dur(変ト長調)あるいはFis-dur(嬰ヘ長調)です。「死への憧憬」あるいは「まどろみ」(譜例21)。ゆりかごのような本当に甘い音楽ですね。最も愛に満たされた至福の瞬間ですが、そこから愛は必然的に死の動機へと移行します(「愛の死の動機」譜例22)。そうして、愛の悦びがどんどん高まっていきます(「あまい情愛」譜例23)。先程の「愛の歓喜」がいろいろな形で出てきます。そして二人の情事の最高潮。
しかし愛の夜も突然終わります。メロートの密告によって皆が踏み込んできます。今までの恍惚の音楽が乱暴で粗暴な音楽に断ち切られる。夢がふーっと飛んでいってしまった様子も描かれています。照明がぱっと明るくなり、二人は皆に取り囲まれている。そこでトリスタンは「忌まわしい日がもう一度最後にやってきた」と言うのです。するとマルケ王が綿々と悲しい心情を訴えます。非常に低いバスです。メロートはトリスタンに決闘を申し渡しますが、トリスタンは剣を捨ててわざと傷を負います。トリスタンが死を望む場面は全部で三回あります。まず第一幕で毒薬と思って媚薬を飲むところ、第二幕のここ、さらに第三幕でもう一回(自ら包帯をはずす)。
そして最後にマルケ王のテーマが出てきて第二幕は終わります。やはり一番悲しんでいるのはマルケ王だったのですね。
第三幕
冒頭は絶望の音楽ですね。苦しみと痛み、そして空虚。傷ついたトリスタンはクルヴェナールによって故郷のカレオールに連れてこられています。遠くから聴こえるイングリッシュホルンの旋律がなんとももの悲しい。これほど鬱をうまく表現した音楽はないのではないでしょうか?
トリスタンは瀕死の状態でイゾルデの舟を今か今かと待っています。「まだか?舟はこないのか?」トリスタンは自分の欲求を抑えきれなくなる。やがて喜びを知らせる牧笛が聴こえてきます。「イゾルデがついに来た!」笛吹きの羊飼いも興奮しているのです。トリスタンは自ら包帯をむしりとって「我が血よ流れろ」という場面になります。変形した「まどろみ」が繰り返し出てきて、トリスタンが一種のトランス状態になっている感じを表しているようです。激しく盛り上がったところでイゾルデがついに登場します。彼は彼女のもとに倒れこむと最初のテーマ(「憧憬の動機」)が流れイゾルデが深い悲しみを歌います。
そしてマルケ王の最後の嘆きを経て「愛の死」が始まります。「愛の死の動機」が現われ、やがて「愛の歓喜B」の落ち着いた変形が何度も繰り返されます。だんだん盛り上がり「愛の死」の最後となります。至福の愛、トリスタンのテーマ(「憧憬の動機」)が最後にもう一回現われますが、今度は和音が解決されて終わります。
2006年9月10日 労音十条会館にて
*1 「ニーベルングの指環」。四つの楽劇からなる壮大な作品。
*2 属音上の7の和音(長調ではソシレファ)。不協和音なので解決のため主和音へ向かうのがもっとも自然である。
まとめ:田川(ヴァイオリン)
曲目解説プログラムノート
ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」
「トリスタンとイゾルデ」への誘い
ワーグナーの最高傑作とも言われる「トリスタンとイゾルデ」は、前代未聞のエロティックな音楽と言ってよいでしょう。全曲約4時間のうちの大部分が、主人公であるトリスタンとイゾルデの心理的駆け引きと性愛の場面に費やされ、音楽は二人の心理状態や行為をこれでもかと言わんばかりに深く、そして執拗に表現していきます。まさに全てが聴き所と言ってよいほど充実した音楽で、一度嵌ると抜け出せない魅力にあふれています(なお本日は抜粋でおよそ2時間の演奏となります)。
しかしながら一方では、なかなかとっつきにくいと思われているのも事実です。 「いつ終わるとも知れぬ音楽を聴いているうちに熟睡し、一眠りして目がさめたが、まだ同じ歌手が同じような歌を歌っていた。」などと揶揄されることもあるようです。せっかく極上の音楽のご馳走を目の前にしながら、睡眠不足解消でお帰りになるようなことにならないように、この解説がお役に立てば幸いです。
「トリスタンとイゾルデ」は他のワーグナーの作品と同じように多数の示導動機と呼ばれる旋律の組み合わせにより作られています。示導動機は歌やオーケストラに変幻自在に現れて、劇の進行や登場人物の心理状態を表現します(詳しくは飯守氏の講義記事をご覧ください)。いわゆる普通の歌劇にある「アリア」というものがありませんから、はじめて聞くとつかみどころがない印象を受けるかもしれません。しかし、最初に述べましたように一度この音楽の魅力を知ってしまうと抜け出せません。そこでこの魅力を味わうための“コツ“をご紹介しましょう。
まずは、主要な示導動機(旋律)を覚えることです。有名な前奏曲に出てくるもののうち、譜例に示した2個の旋律、「憧憬の動機」、「愛のまなざしの動機」、そして第一幕で出てくる陰鬱な「運命の動機」と「死の動機」さらに、甘美な「愛の死の動機」を覚えればとりあえずはOKです。その旋律がどのような場面でどんな風に出てくるのかを感じ取ってください。
そしてなによりも、登場人物に感情移入することです。物語の背景や、登場人物の置かれている状況をよく理解することでワーグナー音楽の真髄を深く味わえることでしょう。というわけで少し長くなりますが、以下にトリスタンとイゾルデ入門編とでも言うべき解説を書いてみました。
1.「トリスタンとイゾルデ」の背景
時代は中世。マルケ王が治めるコーンウォールは戦争に敗れて以来、アイルランドに租税を納めねばならない状況にあった。あるとき租税を取り立てに来たアイルランドの勇者モロルトとコーンウォールの勇者トリスタンが決闘してトリスタンが勝利、モロルトは殺される。これを機に両国の関係は緊張した状況となるが、マルケ王の妃としてアイルランドのイゾルデ姫を迎えることで両国は和解することとなる。そして、トリスタンの操る船に乗せられ、イゾルデ姫がコーンウォールに向かっている。このような状況で幕が開く。
2.主要登場人物の紹介とその心理状態
■トリスタン
マルケ王の甥であるトリスタンはフランスのブルターニュ地方のカレオール出身で、今はコーンウォール一番の勇者。王が最も信頼する家臣である。彼はアイルランドのモロルトとの決闘で勝利するが傷も負っていた。モロルトの剣には毒が塗られていたため瀕死の状態で、それを直すには特別な医術を持つイゾルデに直してもらう以外に助かる見込みはなかったのである。そのためタントリスという偽名(そんな偽名ではばれて当然と思うが)を名乗って、単身敵国のイゾルデのもとに行き治療してもらった。イゾルデはトリスタンであることを見破ったのだが命を助ける。このときにトリスタンとイゾルデは、実は惹かれあったのだった。にもかかわらず、イゾルデをマルケ王の後妻にする計画を奨めたのもトリスタンであった。この理由について、悲劇的な出生(父親は戦死、出生後すぐに母親も死んだ)から自己犠牲的な性格を負わされていること、また身分の違いや政略結婚のためやむを得ず などいろいろな解釈が可能である。死への願望が強く、劇中でも各幕で一回ずつ自ら死を選ぶような行為を行う。
■イゾルデ
アイルランドの王女であり、モロルトの許婚者であった。しかし、モロルトの仇であるトリスタンの素姓を知りながらトリスタンと目を合わせた瞬間に(ビビッときた)特別な感情を持つに至り、そのまま治療して返してしまった。そしていずれトリスタンと結ばれると思い込んでいたのだと考えられる。ところが、マルケ王に嫁がねばならないということになり、しかもよりによってあのトリスタンがまるで貢物を運ぶかのように自分を迎えにきたことで逆上している。
■マルケ王
コーンウォール王でトリスタンの伯父にあたる。とにかく「人格者」である。最初の妃には先立たれ、その後は独身であった。ということからそれなりの年齢であることが推察される。トリスタンに全幅の信頼を寄せており、最初は乗り気でなかったイゾルデとの結婚もトリスタンの強い勧めで承諾した。にもかかわらずトリスタンに裏切られることになる。最後には全てを許して二人を結婚させようとするのだが・・・。登場すると嘆いてばかりである。
■ブランゲーネ
イゾルデの従者であり、ずっとイゾルデの身の世話をしている。年齢はイゾルデとさほど変わらないように思われるが詳細は不明である。第一幕では死の薬を用意するようにイゾルデに言われるが、動揺のあまり媚薬を用意してしまう。第二幕の逢引きの場面では見張り(全曲中でも特に美しい箇所)をしているのだが、結局マルケ王に踏み込まれてしまう。第三幕ではマルケ王に全てを打ち明けて許してもらうのだが、時すでに遅く・・・など、やることが全て裏目に出てしまう。
■クルヴェナール
トリスタンの忠実な家臣である。少々お調子者でもあり、トリスタンの本当の苦悩などは理解できていないようであるがトリスタンに最期まで仕え、メロートを討つ。
■メロート
トリスタンの元親友(ということになっている)だが、トリスタンとイゾルデの仲をマルケ王に密告、逢引きの場面に踏み込んでトリスタンを刺す。本日の公演では登場しない。
3.「トリスタンとイゾルデ」の聴き所
ここでは各幕についてそれぞれ、つぼを押さえた聴き方の一例をご紹介します。
<第一幕>
第一幕の聴き所は二つ、第一は、トリスタンとイゾルデの駆け引きです。前奏曲の後しばらくの間は、字幕で二人が何を言っているのか追ってみてください。オーケストラはあくまで伴奏として聴くというのがお奨めです。音楽が二人の心理状態を克明に表現していきます。「運命の動機」や「死の動機」が頻繁に現れます。
第二は、トリスタンとイゾルデが死の薬のつもりで媚薬を飲んでしまうあたりからです。ここは何といっても音楽が聴き所。字幕にあまり気を取られずに緊迫した音楽をお楽しみください。今日の演奏では前奏曲の終わった後20分くらいから第一幕終結までの部分です。
<第二幕>
「トリスタン」の第二幕はほとんど長大な愛の場面に費やされます。どっぷりと夜の世界に浸って戻って来られないほどの、麻薬的な「媚薬」音楽体験、いわゆるワーグナーの毒をたっぷり抽入されるひとときでしょう。
ただし、恋人たちが語り合っている歌詞はかなり哲学的です。無理をして字幕をまじめに追わなくても、大きな流れをつかんでいろいろと想像をたくましくしながら音楽だけ聞いているのでも十分に魅力を味わえるでしょう。
<第三幕>
第三幕はトリスタンの一人舞台である狂乱の場とイゾルデの船が到着してからの劇的な展開、そしてあの有名な「愛の死」で構成されています。本日の公演では、前奏曲の後、第一場を大幅にカットし、イゾルデ到着の少し前からの演奏になります。 「イゾルデの船が見えてトリスタン狂喜-イゾルデ到着-トリスタンの死-マルケ王一行の到着-クルヴェナールの死-イゾルデの愛の死」とめまぐるしく劇が進行します。とりあえず何がおきているのかだけ字幕で確認しつつ、後は変化に富んだ緊張感あふれる音楽をお楽しみください。最後の「愛の死」では、「前奏曲と愛の死」だけを聞いたときとは比較にならない、感動体験が得られるでしょう。
4.物語の進行
ここでは少し詳細に物語の進行を追ってみましょう。太字部分は本日の演奏箇所に相当します。斜体部分は本日の演奏ではカットいたします。
1)第一幕
【前奏曲】
前奏曲にはこの楽劇の魅力が凝縮されている。終止和音なしの旋律が連なって何度も繰り返され、トリスタンとイゾルデの飽くことなき憧憬と張りつめた心理状態が表現される。冒頭に流れるのは「憧憬の動機」、刷り込まれるくらい聴かされるのは「愛のまなざしの動機」だ。
【第一場】
幕が開くとそこは船の上、イゾルデはマルケ王に嫁ぐためコーンウォールへ向かっている。その船を操るのは、あのトリスタンである。同じ船に乗りながらトリスタンはイゾルデに会おうともしない。トリスタンに惹かれ命を救ったにもかかわらず、なぜマルケ王の妃とならねばならないのか、なぜトリスタンに無視されるのか、イゾルデは激しく苛立つ。
【第二場】
窓の向こうにはトリスタンと従者クルヴェナールの姿も見える。イゾルデはその姿を素早く見つけて陰鬱にトリスタンへの恨み言をつぶやく。
直前まで猛り狂っていたイゾルデの言葉はここでは謎めいて少々狂気じみている。ここでイゾルデが口にする旋律は、重要な「渇望の動機」と 「死の動機」だ。トリスタンが自分を選ばなかったことに対する屈折した感情がイゾルデの怒りの根本にある。そして、今すぐトリスタンをこの部屋に連れて来るようにと侍女ブランゲーネに命令する。
ブランゲーネはトリスタンのもとに行きイゾルデが呼んでいることを伝えるが、トリスタンも複雑な心境を覗かせつつ核心に触れない返事で逃げようとする。しかしトリスタンの従者クルヴェナールはトリスタンの心境を察することなく調子に乗り、『モロルトの歌』をうたう。貢物をめぐってアイルランドのモロルトとトリスタンが小島で決闘し、トリスタンが見事に勝ってモロルトの首をアイルランドに送りつけたと。「・・・われらが勇士トリスタン、貢物のなんとみごとな納めぶり!」とうたう。
このイゾルデを嘲笑する『モロルトの歌』がトリスタンの本意ではない。トリスタンはこれを叱り、静止する。
【第三場】
クルヴェナールに笑いものにされたイゾルデは、激怒する。そして『タントリスの歌』を歌い、ブランゲーネに(観客に)向けて、トリスタンとの因縁を解き明かす。「」内がその内容である。
「アイルランドの岸辺に瀕死の一人の男が流れ着いた。男は「タントリス」と名乗り、イゾルデは医術の業を用いて男の傷を癒した。イゾルデはタントリスの剣に刃こぼれを見つける。その形状はモロルトの頭蓋に残っていた剣の欠片と一致した。タントリスこそ婚約者モロルトを殺した仇、トリスタン。イゾルデは復讐のためにそのままその剣を持って病床の傍らに立つ。剣を振りかざすイゾルデにトリスタンは正体がばれたと、たちどころに事情を察知した。しかし命の危険が迫っているにも拘らず、ただイゾルデの目だけを捉え続ける。トリスタンは常に死への願望に身をさらさずにはいられない自己破滅的な男。イゾルデはトリスタンの「哀れなさま」に「同情」を感じて剣を手放す。イゾルデはトリスタンのけがを治療し、そして故郷に帰してやる。イゾルデにひたすら感謝し、まごころを尽くすと誓ったタントリスは今度トリスタンとして再びアイルランドに戻ってきた。コーンウォールのマルケ王とアイルランドの王女を結婚させるために。あのときに剣を振り下ろしていればこんなことにはならなかった。」とイゾルデは後悔する。
ブランゲーネはその話を聞いてもさほど気にもせずに、夫になるマルケ王は素晴らしい方だと説得をはじめる。イゾルデ様を一目見て夢中にならない男などいるはずがない。それにイゾルデの母が持たせた各種の秘薬がある。そのなかの媚薬を使えば大丈夫とうたう。しかしイゾルデは媚薬ではなく、死の薬を指し示す。驚くブランゲーネ。そのとき水夫たちの歌が聞こえてくる。
【第四場】
クルヴェナールが到着の準備を急がせるためにイゾルデの部屋に入ってくる。イゾルデはクルヴェナールに、トリスタンが赦しを求めに来るようにと伝える。
クルヴェナールが退場すると、イゾルデはブランゲーネに死の飲み物を用意するよう命じる。動揺するブランゲーネ。そこへトリスタンが登場する。
【第五場】
トリスタンがついに姿を現す。イゾルデはそんな姿を興奮して見つめ、しばらく無言となる。オーケストラには印象的な「運命の動機」が現れる。その後、トリスタンとイゾルデの間でかなり回りくどいやり取りが続く。イゾルデの本心はトリスタンの口から愛しているという言葉を聞きたいのだろうが、ストレートに聞き出さず、トリスタンが殺したモロルトがいいなずけであった事、にもかかわらず命を救ったこと、その仇を誰がとればよいのかと言って責め立てる。トリスタンは動揺し、それならこの剣で仇を討てばよいと言って渡す。しかしイゾルデはそれを否定し、和解の償いの盃を二人で飲み干そうと盃を差し出す。このあたりから音楽はしだいに緊張感を帯び、「死の動機」「運命の動機」などが繰り返される。それが死の飲み物であることをトリスタンが悟っていることを暗示するようである。一方、このやり取りとは別世界にいる上陸準備をする船員たちの合唱が重なることで、延々と登場人物二人だけで続くこの場面にアクセントを加える。
トリスタンとイゾルデはすでにどうしようもないほど惹かれ合い、愛し合っている。只、お互いそれを禁句にしているだけである。表面的には憎悪をたぎらせているようでいながら、ことばの裏では感情を確かめ合っている。ここでイゾルデは、マルケ王にイゾルデのことを娶るよう勧めるトリスタンの様子をからかってうたう。このあたりは「イゾルデの嘲弄の動機」が何度も繰り返される。イゾルデが心理的に優位に立っていることをあらわしている。
トリスタンには「和解の盃」の中身が何であるか既に察しがついている。しかし「死の飲みもの」を「心やさしい忘れ薬」とさえ述べて、進んで盃をあおる。トリスタンの歌詞やその行動を見てみると、いくつも死への願望をもっている事がわかるのだが、この行動もそのひとつである。イゾルデはトリスタンから飲みかけの盃を奪い取って競うように飲み干す。ともに死へ突き進むことで二人の思いは成就し、一気に燃え上がる。しかし実は、ブランゲーネが恐ろしさのあまり死の飲み物ではなく愛の飲み物〔媚薬〕を入れてしまっていたのだ。恐ろしいほどの沈黙の後に前奏曲冒頭と同じ「憧憬の動機」が現れる。この場面の音楽は、全曲中の白眉とも言える切迫感、最大の聴き所のひとつである。
一旦決壊した感情の堰の流れは最早留まるはずもなく、二人は「愛のまなざしの動機」に乗ってお互いの名前を震える声で呼び合う。こうなってしまえばただの男と女、愛の歓喜に酔い熱烈な抱擁を交わす。船室の外でマルケ王を歓呼する声も、部屋の中でブランゲーネが大げさに嘆いているのにもまったく気がつかない。しかしこの二重唱はすぐに到着の歓声にさえぎられる。ブランゲーネはイゾルデを正装に変え、クルヴェナールはトリスタンを讃えるために部屋に飛び込んでくる。この部分「二人の世界(夜)」と「それ以外の常識的な世界(昼)」という対立する二つの世界を劇的に表現する。ワーグナー的カタルシスを味わえる瞬間である。最後にマルケ王が船に到着し、別働隊のラッパがファンファーレを奏で、唐突に第一幕が終わる。
2)第二幕
【第一場】
第二幕の前奏曲は、恋の気持ちが溢れて浮き立つような、馬が駆け足で通り過ぎていくような調べを持っている。国王一行は夜の狩に出かけ、角笛が遠くに近くにこだましている。庭園でイゾルデとブランゲーネがそわそわと振舞っており、扉には目立つように松明が掲げられている。
第一幕の冒頭と同じように、舞台上に立っているのはイゾルデとブランゲーネ二人だけだ。イゾルデはまさに文字通りの「恋は盲目」状態に陥っている。
松明を消すのがトリスタンへの合図となっているようで、イゾルデは早く松明を消すようにブランゲーネに迫るが、ブランゲーネは、今日の狩は仕組まれたものであり、二人の逢引きを取り押さえるための陰謀だと警告する。消せだの消さないだのの一悶着の後、最終的にイゾルデが松明を手にして、その火を消す。この辺りから第二場へ向けてトリスタンが登場して抱擁に至るまでの音楽の盛り上がり方は、ものすごい。
【第二場】
ここからがいよいよ愛の場面だ。松明を消して、逢引きが発覚するまで、劇進行は止まり、恋人たちだけの特別な場所が用意される。
イゾルデの合図からほどなく、トリスタンが庭に飛び込んでくる。オーケストラが雄弁に二人の固い抱擁と燃え盛る情熱の激しさを物語る。
「あなたは私のもの?」
「きみはまたぼくのもの?」
「あなたを抱けるのね?」
「夢ではないか?」
「やっと、やっとだわ!」
「ぼくのこの胸に!」
「本当にあなたに触れているのかしら?」(以下延々としばらくこんな調子が続く。)
待ち焦がれていたことが実現したが未だに信じられない様子が良く出ている。二人は逢引きを邪魔していた昼の光に対する憎しみを歌う。そして音楽は次第に静かになり、えもいわれぬ甘く気だるい雰囲気をかもし出してくる。二人は昼への決別を終え、本格的な夜の賛歌へと移動する。ここからが本格的な愛の場面であり、音楽による性愛描写が続く。ここまでエロティックに愛の場面を表現した音楽は他にないだろう。
しばらくすると見張り台のブランゲーネが警告の声を発する。「お気をつけください! お気をつけください! まもなく、夜が去っていきます」ここがまた大変に美しい。この警告の最中、二人は黙ったままである。この陶酔的な音楽の後は一時的に緊張が緩んで、気だるい雰囲気となる。トリスタンは「このまま死なせてくれ」などと言う。
その後しばらくは恋人同士の哲学的なやり取りが続く。トリスタンは愛に耽る真っ最中でもやはり「死」を考えている。イゾルデは、あなたが死んだら愛も終わってしまうのでは?と問い掛ける。それに対しては
「それならば、ともに死のうではないか。・・・中略・・・、ただ愛に生きるために!」
ここではじめて「愛の死の動機」が現れる。再び性愛の音楽が盛り上がる。一緒に「死んでもいい」と思わせるだけの妖しい魅力に満ちている。イゾルデはこの死の宣誓に「身も心もあずけ合って」同調する。
ブランゲーネの警告の歌が再び響く。 夜は白々と明け染め始めている。今度はイゾルデが「私を死なせて」と呟く。二人がしだいに興奮に駆られ熱中していくのは、危険を察知するからこそ燃え上がるためなのか。刹那の想いが二人を更なる衝動へと駆り立てる。
これ以上ないくらいの絶頂を迎えた瞬間に破局を迎える。「愛の夜」は突然終焉のときを迎える。
【第三場】
「逃げなさい、トリスタン!」慌てて飛び込んできたクルヴェナールは既に遅し、マルケ王とメロートたちがその場に踏み込んでくる。侍女が心配したとおり夜の狩は罠だったのだ。二人の関係は公に露見した。
マルケ王は、信頼していたトリスタンが自分を裏切ったことを嘆く。「このマルケのために数々の武勲や手柄を立ててくれたトリスタンに対して、感謝の気持ちを表そうとトリスタンを世継ぎにしたかった。妻など娶りたくなかったのに、宮廷も国も捨てていくとトリスタンが脅して、先頭に立ってまでイゾルデを迎えに行ったのではないか。それなのに何故だ。」(本日はこの部分の一部をカットして演奏します)。
しかしトリスタンは一切弁解をしない。「昼」の世界にいる者には「夜」の世界のことなど理解できるわけがないということであろうか。トリスタンはイゾルデの方へ向き直ると「これからトリスタンが行く先へついてくるか? そこは陽の光の射さぬ国。・・・」と歌う。トリスタンは第一幕でイゾルデの盃を受けたときから死を覚悟していたと考えられるがここでも暗示的に死への願望が現れていると言えるだろう。
イゾルデはこの申し出を受ける。しかし、トリスタンがイゾルデに接吻を与えているときにメロートが無粋にも剣を抜いて挑発してくる。トリスタンも剣を抜いて応戦するかと思ったその瞬間、トリスタンはわざと自分の剣を落とし、メロートの刃中に飛び込んでいく。一同がトリスタンの自傷行為に呆然としているうちに第二幕が終わる。
第二幕終結後幕間のできごととして、トリスタンはクルヴェナールによって故郷のカレオールに連れ帰られる。トリスタンは深手を負っており、ほとんど回復の見込みがないような状況である。イゾルデはその後を追うことができず、事情は明らかではないがコーンウォールにとどまる。第三幕はそのような状況で始まる。
3)第三幕
【第一場】
第三幕への前奏曲は、トリスタンの心境を表した、絶望のどん底に叩き落されるような暗いものである。
幕が開くと男が二人。クルヴェナールと羊飼いだ。トリスタンは、瀕死の重傷を負って昏睡状態に陥っている。ようやく目覚めたトリスタンにクルヴェナールが、故郷カレオールに来た経緯を話す。その後しばらくはトリスタンの一人舞台、いわゆる「狂乱の場」に相当する場面である。トリスタンは、「夜の闇の国」に、イゾルデはまだ「昼の世界」にいる。イゾルデに会いたいという強い欲求を延々と狂ったようにうたう。クルヴェナールは、イゾルデに来てもらえるようコーンウォールへ使者を送っており、今到着を待ち焦がれているところだと話す。その言葉にトリスタンは我を忘れて叫ぶ。「イゾルデが来るのだ!」トリスタンはいまだ来ないイゾルデの船を待ち焦がれ、これまでの出来事を回想し、最後には媚薬を呪って狂乱し失神する。
再び昏睡状態に陥った主人を、クルヴェナールは親身になって気遣う。その献身的な介護にトリスタンは再び不死鳥のごとく息を吹き返す。「船は? おまえにはまだ見えぬか?」
意識を取り戻したトリスタンは、再び船に乗ったイゾルデの幻影を見る。音楽はイゾルデに対する美しい調べから、しだいに狂気と激情をはらんだものに変わっていく。そこへようやく到着の合図が鳴り響く。今までの暗い空気を吹き飛ばすような、明るい陽気な節だ。ここまで、半音階だらけの音楽を散々耳にしているので、整った長調を聞くと安心する。船が到着するとの知らせに、トリスタンは飛び上がらんばかりの勢いで喜ぶ。 しばらくの間、物見台に立って海を眺めるクルヴェナールと寝台に寝ているトリスタンとのやり取りが続く。それを通じて、聴衆は船が近づいてくる様子を間接的に知ることができる。
【第二場】
トリスタンは、当然じっとしていられない。「おお、この太陽! ああ、この真昼! ああ、歓喜にまばゆいばかりのこの日」と、早速寝台の上で喜びの気持ちを旋律に託し始める。そして 「ようこそ、わが血よ! 楽しく流れるがいい!」トリスタンは寝台から立ち上がり、包帯をむしりとる。おびただしく血がしたたりおちる。トリスタンは血染めの包帯を誇示し振りかざす。トリスタンの意識は明らかに高揚している。しかし自傷的行為によって生命力は残り少なくなっている。自分で傷口を広げるなど狂っているとしか言いようのない行動だ。音楽は急上昇、急降下の繰り返し、長調に忍び寄る半音階、それにめまぐるしく変わる拍子によって、劇的な効果が生まれる。
「トリスタン! いとしい人!」 異様な興奮にかられたトリスタンの耳にイゾルデの声がようやく届く。イゾルデの姿をついに認める。そして身体を恋人に投げ出すようにあずけ、崩れ落ちる。この部分、まるでトリスタンの血しぶきが飛び散るかのような凄惨な響きの迫力、その後に続く「憧憬の動機」の切実さと寂寥は、筆舌に尽くしがたいものがある。
再会した二人は媚薬を飲んだ直後のように見つめあう。しかしトリスタンは「イゾルデ!」と一声発して、息絶える。
メロートと剣を交えた際も、同じようにイゾルデが見守る中、トリスタンは先に死のうとした。「共に死のうではないか」と誘った本人が二度までも裏切っているのだ。当然イゾルデは骸をかき抱いて大いに嘆く。
【第三場】
羊飼いがもう一隻船が着いたことをクルヴェナールに告げる。マルケ王とメロート、ブランゲーネがやってくる。クルヴェナールは剣を片手に戦い始めるが、多勢に無勢だ。主人の恨み、メロートだけは何とか倒して復讐を果たす。やがてクルヴェナールもトリスタンのもとに倒れる。マルケ王がこの様子を見て嘆き、ブランゲーネは必死でイゾルデに呼びかける。媚薬の秘密をマルケ王に打ち明けたところマルケ王は急いで船を出したのだ。イゾルデをトリスタンと結婚させようと。しかし、そんな周囲のもろもろの出来事からはイゾルデはもはや超越している。いよいよクライマックス、「愛の死」だ。
「やさしく、おだやかな彼の微笑み、その目を柔和に開く、そのさま、ごらんになれますか、みなさん? しだいに輝きをまして彼がきらめくさま、星の光にとりまかれて昇って行くさまを? ごらんになれますか?」 文章だけでは気がふれてしまったようにしか思えないが、ここまで通して音楽を聞いてくると本当に「やさしく、おだやかな彼の微笑み」が見え、イゾルデが確実に昇天していくさまが聴こえてくる。ここがワーグナー魔術の最たるものだと思う。 「この高まる大波の中、鳴りわたる響きの中、世界の呼吸の吹きわたる宇宙の中に―― 溺れ―― 沈み―われを忘れる―このうえない悦び!」 と「愛の死」を歌い、イゾルデはトリスタンのなきがらの上に斃れる。
「トリスタンとイゾルデ」誕生のエピソード
ワーグナーは、畢生の大作「ニーベルングの指環」四部作の作曲途上にあった1857年2月、第三作目となる「ジークフリート」の途中で作曲を中断してしまう。その理由のひとつは、上演に四晩かかるような破格な曲を上演するめどがまったく立っていなかったということであった。おまけに金もなくなっていた。そこでワーグナーは上演の簡単な、小規模な作品を作曲し売り込もうと思い立つ。それがこの「トリスタンとイゾルデ」であった。ヨーロッパに古くから伝わる恋愛物語である「トリスタンとイズー物語」を題材にしてどの歌劇場でも上演できるようなものを作る構想であったようだ。 (ちなみに最近封切られた「トリスタンとイゾルデ」という映画はこの伝説を題材にして作られたもので、ワーグナーのものとは大幅にストーリーが異なるようです。) ところが作曲が始まったら、後述する不倫体験のせいなのか、ワーグナーの天才の性(さが)か、有数の規模の大曲が出来上がり、上演の機会はずっと先になってしまうのであるが。
話を戻すが、トリスタンの作曲を思い立ったちょうどそのころに絶好のパトロンが現れた。オットー・ウエーゼンドンクという富豪である。オットーは、チューリッヒにある豪邸の敷地内の離れをワーグナーに提供し、多額の金銭的な援助もした。
ところが、よりによってワーグナーはオットーの妻であるマティルデと恋愛関係になってしまう。二人は秘密裏に逢引きしては芸術を語り合ったと言われている。実際、マティルデの詩による歌曲を作曲し、マティルデにささげている。両人の関係は精神的なもののみであったとする説もあるが、いずれにしろオットーの恩を仇で返す行為ではあった。別居同然のワーグナーの妻ミンナがこの関係に気づいて大騒ぎするという事件もあった。しかし、オットーはこのことを表ざたにせずワーグナーを責めることもなかったようで、まるでマルケ王のように寛大であった。さすがの自己中心的なワーグナーもウェーゼンドンク家との破局を避けるためにチューリヒを離れ、美と頽廃の街であるヴェネツィアに移る。そこで館を借り切って第二幕の作曲に没頭するのだった。
しかし、イタリアの政情が不安定となり、以前より政治犯としてお尋ねものでもあったワーグナーは身の安全を図れるスイスのルツェルンに移る。そこで「トリスタンとイゾルデ」を完成させた。1859年8月のことであった。
この話で驚くのは、凡人では考えられない自信、才能、金銭感覚と運の強さである。そもそも、「金が足りないので短いオペラを作曲しようと思い立った人間が、タイミングよく富豪に助けられ、その妻にインスパイアされて世紀の傑作を生むインスピレーションが生まれる」なんていう話、これだけでも奇跡的な強運である。なのに、不倫も許されておとがめなし。しかも、その後この曲を作ったのは(おそらくとてつもなく高価な)ヴェネツィアの館を借り切ってのことなのである。金が底をついたので作曲をはじめたなどという「けちくさい話」は完全に吹っ飛んでいる。この後もワーグナーは、借金を重ねては踏み倒したり、著名な指揮者で、自分の弟子でもあり支持者でもあった人の奥さんを略奪したり、バイエルンの国王というこれ以上はないパトロンを捕まえて国庫から資金援助させたりしながら名作を生み出し続けるのであった。まるで「自分は全人類のための至高の芸術を生み出すのであるから、他人は自分のために奉仕して当然である」と考えていたかのように思える。そしてそれを実行してしまった。なんともすごい人生である。そして1883年69歳、心臓発作によりヴェネツィアで最期を迎えた。
そして今、ワーグナーが創設したワーグナーの曲だけを上演するための劇場(ベートーヴェンの第九など別の曲もたまには上演するようですが)であるバイロイト祝祭劇場で催される音楽祭には、公演を聞くために毎年世界中から多数の観客が集まる。チケットは申し込んでから何年も待たねば入手できないとのことである。
ワーグナーの「傍若無人な振る舞い」の根拠とも言える「才能」と「自信」が本物であったことが、没後120年以上経過した現代においても実証され続けているのである。
【謝辞】
本解説は、参考文献1より多くの部分を引用しています。快諾いただいた城後麻美氏に感謝します。また、写真を提供いただいた中島幹夫氏に感謝します。(都合によりHPでは写真を省略しました。)
参考文献:
1. 城後麻美著「トリスタンとイゾルデ論」http://www3.pinky.ne.jp/~pippo/page/tristanundisolde1.htm
2. 高辻知義著「ワーグナー」 岩波文庫
3. ベディエ編 佐藤輝夫訳「トリスタン・イズ-物語」岩波文庫
4. スタンダードオペラ鑑賞ブック[4]ドイツオペラ(下) 音楽之友社
初演:1865年6月10日 ハンス・フォン・ビューロー指揮 ミュンヘン宮廷劇場
楽器編成:フルート3(3番奏者ピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ1、クラリネット2、バスクラリネット1、ファゴット3、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ1、
ティンパニ、シンバル、トライアングル、ハープ、弦5部
その他に舞台上に(あるいは その他に別働隊として)
トランペット3、トロンボーン3(以上第一幕)、ホルン6(以上第二幕、今回はカット)、コールアングレ(後半はホルツトランペット)(以上第三幕)
第195回演奏会ローテーション
| 1幕 | 2幕 | 3幕 | |
| フルート1st | 松下 | 兼子 | 岡田 |
| 2nd | 新井 | 藤井 | 新井 |
| 3rd | 丸尾 | 丸尾 | 藤井 |
| オーボエ1st | 山口 | 亀井(淳) | 堀内 |
| 2nd | 岩城 | 亀井(優) | 亀井(優) |
| コールアングレ | 堀内 | 桜井 | 岩城 |
| クラリネット1st | 高梨 | 品田 | 品田 |
| 2nd | 石綿 | 末村 | 大藪 |
| バスクラリネット | 進藤 | 中條 | 進藤 |
| ファゴット1st | 長谷川 | 田川 | 田川 |
| 2nd | 浦 | 浦 | 浦 |
| 3rd | 田川 | 長谷川 | 長谷川 |
| ホルン1st | 大原 | 山口 | 箭田 |
| 2nd | 市川 | 比護 | 大原 |
| 3rd | 園原 | 箭田 | 山口 |
| 4th | 鵜飼 | 市川 | 比護 |
| トランペット1st | 北村 | 野崎 | 野崎 |
| 2nd | 倉田 | 青木 | 青木 |
| 3rd | 中川 | 中川 | 中川 |
| バンダ | 野崎、青木、横原(*) | - | - |
| ホルツトランペット | - | - | 倉田 |
| トロンボーン1st | 志村 | 武田 | 武田 |
| 2nd | 小倉 | 小倉 | 志村 |
| 3rd | 岡田 | 大内 | 大内 |
| バンダ | 武田、福澤(*)、大内 | - | - |
| テューバ | 本橋 | 土田 | 土田 |
| ティンパニ | 桑形 | 中川 | 古関 |
| トライアングル | 古関 | - | - |
| シンバル | 中川 | - | - |
| ハープ | 神谷(*) | 神谷(*) | 神谷(*) |
| 1stヴァイオリン | 堀内(岸野) | 前田(岸野) | 前田(岸野) |
| 2ndヴァイオリン | 村井美(奥村) | 村井美(奥村) | 村井美(奥村) |
| ヴィオラ | 柳沢(田口) | 柳沢(田口) | 柳沢(田口) |
| チェロ | 光野(日高) | 光野(日高) | 光野(日高) |
| コントラバス | 中野(木田) | 中野(木田) | 中野(木田) |
50年後の新響<新響の過去・現在・未来>
今まで3回連続で寄稿してきたが、いよいよ未来というキーワードに突入することになった。新響が創立100年を迎える50年後、はたして新響はどうなっているのだろうか?過去や現在のことを語るのは容易でも、未来どうなっているかは、どこに話の軸を置くかによってその内容は大きく変わってくる。
少なくとも、芥川也寸志先生や山田一雄先生のことを直接知っている団員がたぶんこの世に存在していないこと。また現在の新響に係わっておられる多数の錚々たる音楽界の先生方を直接知る団員が限りなく少なくなっていることは間違いない。新響が創立して50年間にあった出来事はもちろんのこと、サントリー音楽賞を取ったことや、ベルリン芸術週間に招聘されたこととかもうたくさんの思い出とともに、現在の活動も全て資料として過去のものとなって、こんな時代があったんだなあ、と言われているに違いない。日本の古典芸能じゃないが、口伝として、あの時はこんなことがあったらしい、運営はこうだったらしい、とか、なんでこんな曲演奏したんだ?いやあの時はかくかくしかじかあって、なんて多少なりとも尾ひれが付いて噂だけが残っているに違いない。
もちろん運営の体制も方針も変わっているだろうし(もしかして自主運営でなくなっているかもしれない)音楽監督とか常任指揮者が存在していて、活動の内容も大幅に変わっているに違いない。維持会もどのように展開していくことだろうか?
国内のみならず海外にも演奏活動の場を拡大し、維持会も現在では考えられないほど大きく発展しているとなればうれしい限りである。
ネガティブに考えていけば、もしかして団の名前も変わっているかもしれない。全てが過去の栄光としてのみ残り、長いディミヌエントの末、やがては消え果てしまうカゲロウの如き影のうすい存在でしかないかもしれない。すなわちもはや新響が存在しているという保障はない。維持会もどうにかなっちゃったりして、そうなっては欲しくないのはもちろんで、たとえ活動の規模が縮小しても新響としての活動の火だけは、燃え続けて欲しいものである。
世の中の経済や環境がどのように激変しようとも、新響がその時代にあった文化的に意義の高い企画、すばらしい演奏をしている限り、新響はその価値を高めつつ存在していくことを信じている。たとえ運営体制が変わろうと、団員の意識や価値観が時代と共に変わろうと、常に前向きに質的向上を目指し、今を活きている、という認識があれば順調な変遷と発展をとげていくだろう。新しい時代の流れに乗っていかないと発展はない。しかしここで大切なのは、今まで築き上げてきたものを改めて認識し、土台にした上で常に前にチャレンジして行く、ということといえよう。そのベースとなっているのは、いつの時代において変わることのない「音楽が好きだ。」という情熱と新響に対する思いが全てだと思う。
最近、音楽性の高さとその実力において認知されている優秀な合唱団とお付き合いする機会があり、「過去に学び、現在(いま)を活き、未来を創る」精神を大切にしていくことが合唱団のモットーであることを伺った。新響も同じだと感じた次第である。常に新響は現代を活きているのであり、そこで得た蓄積が将来の糧となっていることは間違いない。これからの新響はどのような運営、演奏会企画を立案していくのかが重要なことであり、また楽しみでもある。どうか、維持会の皆様には今後ともサポーターとして新響を見守っていただきたい。
ワーグナーの魔力
維持会の皆様こんにちは。ここ数年維持会ニュース編集を担当していますが、こうして原稿を執筆するのは今回が初めてです。なぜ裏方の私が表舞台(?)に立つ羽目になったのかここで少し説明させてください。説明など聞きたくないわい!などとおっしゃらず、どうかしばらくおつきあいください。
ニュース作成の仕事はまず、原稿執筆者を決めることから始まるのですが、これが今回とても難航しました。通常なら演奏曲目が2,3曲なので、それぞれの曲に思い入れがありそうな、あるいは作曲家について詳しいと思われる団員に(担当の独断と偏見で)原稿を依頼します。原稿執筆のお願いをしますと、誰でもとりあえずちょっとだけいやそうな顔をします。皆忙しい毎日ですし、おまけに楽器もさらわなくてならないし、しかたありません。でも担当の必死の表情を見ると、「仕方ない、書いてやるか」という気持ちになり、わりとスムーズに契約(と言っても何も出なくて、原稿料は担当の心からの感謝とスマイルだけ)にこぎつけることができます。コレが通常の場合。
しかし、しかし、ですよ。今回は事情がちがいました。ことはそんなに甘くはなかったのです。毎日かなりの数の団員に直接、あるいはお願いメールを書いては断られてしまったんです。そして不思議なことに皆せりふがおんなじ…。
「今回だけはかんべんしてください」「えぇ~~(ほんとうにいやそう)ワーグナーはちょっと…」「他の人を当たってよ。ほら詳しい人いるじゃない。Sさん*とか。」etc.etc.
そこで、もうこうなったら自分で書いた方が早い、とばかりに、この危険な世界に足を踏み入れることにしました。
なぜ危険かといいますと。私の場合ワーグナーに関わったがさいご、身も心も捧げてにわかワグネリアンと化し、寝ても覚めてもあの魔力的な和音が頭の中で鳴りひびき、熱に浮かされたようになってしまうからなんです。過去に新響で「ワルキューレ第1幕」「指輪抜粋」「ファウスト序曲」を演奏したときも同じ状態で、3ヶ月間ほかのことが手に付かなくなりました。「魔力に屈する」とはまさにこのこと…といった感じです。
そう、ワーグナーには「魔力」ということばがぴったり。なにしろびりびりきます。しびれます。文字通り、背筋がゾクゾクします。鳥肌も立ちます。特にこの「トリスタンとイゾルデ」は官能の極地、と言ってもいいでしょう。「憧憬」「歓喜」「孤独」といった内面的な動機が複雑に絡み合った音楽は難解とも言われますが、逆にとてもわかりやすいとも言えます。心を空にして音楽に身をゆだねれば「うわぁ~怒ってる」「絶望の淵に立ってる」とか、「幸せの絶頂なのね」などと自然にわかるので、頭ではなく身体が直接に反応し、しまいには溺れてしまいます。(ああアブナイ…)。私のお気に入りは、なんと言ってもイゾルデの「愛の死」。シャープが5つもあってすごく音程がとりにくいんですけど、なぜか幸せ。聴いていても弾いていても、この箇所にさしかかるといつも、心のたががはずれてしまったようになります。自分をコントロールできないような不思議な感じに陥り、涙腺までゆるんで来ちゃいます。なんだろう、この感じ…楽しいとか嬉しいとかではない、舞いあがっちゃって、まるで別世界に行ってしまいそうな感じ…。ああなぜ?どうして?なんでこんなに気持ちいいんだろ?…といつも不思議だったのでした。そんなある日、数年前飯守先生のレクチャーを聞いたときにとったノートを開いてみました。すると。「H-dur:至福」の文字が目に飛び込んできたではありませんか!ああ、これだ!これだったんだ、このゾクゾク感は!!
初めてこの音楽を聴いたのは渋谷の映画館でした。映画「アリア」のなかの一話「トリスタンとイゾルデ」。赤茶けて乾いた風景の中、一本道を走る一台の車。乗っているのは若い男女、というよりは、まだあどけなささえ残る、少年と少女といった面もちのふたり。突如スクリーンに映し出されるけばけばしいネオンの洪水。夜だというのに昼間のごとく絢爛たるラスベガスの目抜き通り。そして安ホテルの一室。愛し合うふたりは、まるで明日という日が来ないかのように激しく求めあうのですが、究極は手首の傷から止めどなく流れる血…。あまりにも愛し合うふたりにはもう、「死」しか残されていないのです。そんなせつなく激しい愛の物語にぴったりはまったワーグナーの音楽!この世にこれほど美しく狂おしい音楽があるのかと私は圧倒されました。それから20年近くの月日が流れましたが、まさかこの音楽を演奏する機会がやってくるなんて。それこそ至福の3ヶ月です。皆様にもこのゾクゾク感を味わって頂ければ幸いです。どうか魔の音楽に酔いしれていただけますように。
*註:当団きってのワグネリアン、クラリネットの品田氏。すばらしい解説をプログラムに執筆していますので、どうぞお楽しみに!
我が青春の想い出
今を去る事40年程前私は一人の女性を好きになりました。今以上に純情だった私は「まず、何かすごい事に誘わなければ成らない」と思って、銀座のフランス料理に誘うくらいにしておけばいいのに「トリスタンとイゾルデ」に誘いました。1967年(昭和42年)の夏、バイロイト・ワーグナー・フェスティバルが例外的特別出張公演で大阪国際フェスティバル・ホールに来たのです。東京には来なかったのです。知る人ぞ知る公演で、ヴィーラント・ワーグナー演出、ピエール・ブーレーズ指揮。歌手はヴィントガッセン、ビルギット・ニルソン、ハンス・ホッター、オケはN響と言うものでした。チケットは2万円を超える。フランス料理とチューリップにしておけば良かった。見事に断られました。良家の子女はそんなものには行きません。で、ひとりで新幹線に乗って大阪へ。忘れられない一夜を過ごす事に成ったのです。ぼけ始めた脳がいまだに覚えてる事をいくつか。
1.ビルギット・ニルソンのソプラノ。恋するには媚薬の助けが必要な女丈夫でしたが、声は素晴らしかった。3管編成のN響がフォルテで演奏しているその頭上を神の声のように隅々まで届いてくる。3時間も歌い続けているのに。
2.長過ぎる休憩。2回の休憩の合計が1時間以上あって、恋に破れて代役を現地調達出来ない純情青年には長過ぎた。ひたすらビールを飲んでトイレに通った。オペラに一人で行くのはやめた方がいいという事を彼女のおかげで学んだ。特に失恋中の男にとっては、目に入った女性、誰でも良くなり始める。
3.似鳥健彦のコール・アングレ。長く、とても難しいソロが有るのです。今回の演奏会では少し短くしますがとても印象的なソロです。それを似鳥健彦は表情豊かに歌い上げたのです。2000人が聞き惚れました。あまりのすばらしさにブーレーズは賞賛と感謝の手紙を似鳥先生に送ったそうです。先生はそれに感動して宝物にしているとおっしゃっていました。
4.ヴィーラント・ワーグナーの舞台。最近では当たり前になった現代的象徴的な一見簡素化された舞台装置。手前に傾いた舞台。照明でやりくりする舞台。バイロイトも破産寸前と思いました。でも本当はお城仕立てにするより大変なんです。
5.字幕の無いワーグナー。何が何だか。
これで私の青春は終りました。ところでその好きになった女性ですが、誰だったかどうしても思い出せないのです。多分、あの女性かあの女性、どっちかだと思うんですが、気の弱い僕は聞く事が出来ないでいます。
ルートヴィヒ2世-熱烈なワグネリアン
バイエルン国王ルートヴィヒ2世とワーグナーの関係はあまりにも有名です。ワーグナーは敵対者も多く、経済的に困窮していました。ワーグナーを崇拝していたルートヴィヒ2世は1865年ミュンヘン近郊のシュタルンベルク湖畔の邸宅を彼に提供します。このまさに同じ年に初演されたのが今回演奏する「トリスタンとイゾルデ」です。ルートヴィヒ2世は3つの壮麗な城を建てました。現在バイエルン州の主要な観光資源となり、多くの日本人も訪れるこれらの城はワーグナーを知らない人にも充分楽しめますが、各部屋の壁や洞窟などに彼のオペラの場面を描いたものが多くあり、ファンにはたまらないものとなっています。昨今は世界遺産を訪れる人も年々増えていますが、ヨーロッパの豪華絢爛な城は人気も高く、皆さんもさまざまな場所を訪れているでしょう。なんと言っても人気のあるのは、ディズニーランドのシンデレラ城のモデルともなったノイシュヴァンシュタイン城、緑と湖に囲まれたこの城は季節や天候を問わず様々な幻想美を楽しませてくれます。絶好のポイントは城の裏手にあるマリエン橋から見た姿。ただし、高所恐怖症の方にはちときついかもしれません。山の気まぐれな天候もあり、なかなか雲ひとつない快晴には恵まれないようですが、我々がベルリン演奏旅行の後、何人かの団員で訪れた際にはまさしく空は真っ青で日頃の行いの良さが証明された気になって喜んだものでした。絵葉書やガイドブックで見る雪の中の城も、仄暗く憂鬱に立ち籠める霧にまかれた風景もいいですが、自分がそこにいることを考えるといい天候に恵まれるに越したことはありませんよね。日本名「白鳥城」がまさにぴったりくるとても美しい城です。まだ行ったことのない方はすぐにでも旅行を計画すべし。ユーロディズニーランドが受けない理由がわかります。ヨーロッパには正真正銘の古城がたくさんあるんですから。このノイシュヴァンシュタイン城のすぐ下には黄色いホーエンシュヴァンガウ城もあり、一箇所で二度おいしい場所です。
さて、二番目の城はリンダーホーフ城。ノイシュヴァンシュタイン城の建設中にとりかかりましたが、実はこちらが先に、しかも王の存命中に完成した唯一の城です。こちらは、オペラの一場面を再現した人造の鍾乳洞があります。ルートヴィヒ2世は人間嫌いで、湖に金色の会の小舟を浮かべ、白鳥をはべらせ、まさに「ローエングリン」の白鳥の騎士の気分を味わっていたのでしょうか。
最後の城は、ヘレンキームゼー城。名前の通り、キーム湖に浮かぶ島にあります。多少行きにくいのですが、太陽王ルイ14世のヴェルサイユ宮殿をまねて作ったことで有名です。プリーンという駅から湖畔の遊覧船乗り場で島に渡ります。島についてからもすぐに城があるわけではなく、森の中を歩いていかなければなりません。案内図にしたがって歩いていくと、突然開けた場所に庭園が現われ、美しいヘレンキームゼー城が見えます。中は未完なこともあって、国庫を枯渇させるほどに豪華な鏡の広間から、順路をたどっていくと最後にはがらんとした部屋もあり、国を傾けた王の行く末を見るようで複雑な気分になりました。王はさらに第4の城ファルケンシュタイン城までも計画しており、この城の絵はノイシュヴァンシュタイン城のある部屋で見ることができます。王位を追われたルートヴィヒ2世は前に述べたシュタルンベルク湖で謎に満ちた非業の死を遂げます。これほどまでに王が心酔したワーグナーの音楽、そのある意味での頂点とも言える「トリスタンとイゾルデ」を抜粋ではありますが、是非演奏会にお越しになり、楽しんでいただきたいと切に願うものです。
聴いてなんぼのトリスタン
トロンボーン吹きには、トリスタンとイゾルデってやっぱ聴く曲だと思います。出番は極端に少なく、それでいて和声のつながりが難しいので音程が悪いと一発でばれてしまう、ホントやな曲です。何度か「前奏曲と愛の死」は演奏したことありますが、まさか演奏会形式で上演することになろうとは…。演奏するという立場ではこんなにブゥたれている私ですが、「トリスタン」を聴くのはとっても好きです。
大学時代にクライバー&ドレスデンの「トリスタン」の録音(*レコード*5枚組ですよ)が出た、とFM雑誌に載ったのを見ると、すぱっと買っちゃいましたし(そのすぐ後にバーンスタイン&ベーレンス版が出たのだが、必死に思いとどまった)。全曲のスコアも今からざっと20ウン年前に買って持ってましたし、多分、私が持っているオペラ全曲のスコアの中でも最も早い時期に買ったものだと思います。どうして買ったんでしょう?
記憶が定かでありませんが、友達がオケで「トリスタン」をやるというのでライトモチーフのチェックをしようと思ったのでしょうか(失念)、その友達にしばらく貸していたような記憶もあります。あっ、一つ思い出しました。それより前から持っていた「前奏曲&愛の死」のスコアの解説に、「トリスタン」の調性の話が載っていたからでした。それによると、「トリスタン」の理想の主調は「ホ長調」らしいですね。でも、理想の(というかあこがれの、というか)調ということで、全編で「ホ長調」はほとんど出てこないとのこと。聴音のできない私はスコアを見てそれを確かめたかったのでした。確かにシャープ4つの箇所はなかったですねぇ…1カ所を除いては。三幕で傷ついたトリスタンが夢とも現実ともわからない状態でまどろんでいるところにだけ出てきます。結局、現世では「ホ長調」にお目にかかることはできないんですね。最後の「愛の死」の場面でクライマックスに達するところの和声はE-dur→H-dur→E-dur→H-durで、やっと「ホ長調」の和音は出てきますが(ただし、ロ長調のドファラとしてですが)、トリスタンはもう死んでいますし、二幕で実際に2人が逢い引きしている場面では「ホ長調」の和音に達する直前にメロートたちが乱入してきて曲が中断しています。
「ホ長調」といえば、「トリスタン」より少し前に書かれた「ワルキューレ」の最後の部分とは好対照です。なんか「トリスタン」と同じようなフレーズが出てきたり(逆か…)もしますが、「ワルキューレ」の最後はずっとずっと「ホ長調」です。舞台上ではウォータンがブリュンヒルデに罰として、彼女を次に目覚めさせた男に彼女をくれてやる、ことにするわけですが(さぞかし悲嘆にくれているかと思えばさにあらず)、音楽は来るべきジークフリートとの出会いを先取りして祝福しているんですね。
「目は口ほどにものを言い」ではないですが、音楽は劇の「影の語り手」になっています。書き出すときりがないですが、例えば、ストーリーは「愛の媚薬」で図らずも2人が愛し合うことになってますが、解説本など読まなくても、その前から2人は強く互いを意識し合っています(と音楽は語っています)。2人はそれが愛だと気づいていないだけなんですね。
多分他の方もお書きでしょうからこの辺でやめときますが、今からソリスト合わせやゲネプロ、本番が楽しみです(「聴ける」という意味で、ですが)。あまりに聴き入りすぎて休みを数え忘れるのだけは避けたいと思います。
ワーグナー雑感
私とワーグナーの出会いは中学生の時に、我が家にステレオが入ったときに最初に買ったレコードの中に「タンホイザー」の巡礼の合唱が入っており、それがえらく気に入ってしまったことに始まるようである。
大学でオーケストラに目覚めたものの、演奏経験は「マイスタージンガー」前奏曲ぐらいしかなかったが、その後に収集したレコード、CD、LD、DVDではワーグナーの作品はかなりの比率を占めている。中でもショルティ指揮による「ニーベルングの指輪」、特にライトモチーフ集のレコードはワーグナーを理解する上で大変役に立った。重要な人物、物、感情などにそれを表すテーマミュージック(ライトモチーフ)を全曲を通じて統一的に使う作曲技法の見事さに大変なショックを受けた。
その後、新響ではいくつかのワーグナーの曲をやる機会があったが、飯守先生の棒の下でのワーグナー体験は何にも増して貴重なものであった。例えば「タンホイザー」序曲は前述の巡礼の合唱のテーマで始まるが、これは重い荷物を背負って疲れ切った体で歩いているので絶対に等間隔の3拍子にはならない事を強調された。また、「ワルキューレ」第1幕を演奏会形式でやったときには、ワーグナーの精緻で効果的な作曲技法に感心するとともにその難しさに閉口した。個人的にはあれほど真剣に練習した演奏会は後にも先にもなく、その成果が現れた演奏会は今でも新響のベスト5に入るのではないかと思っている。
今回の「トリスタンとイゾルデ」については、最初の先生の練習時間の半分以上を使って先生のビアノによる楽曲解説の時間があり、「トリスタン和音は調性を破壊したと言われるが、そうではなく、調性の機能を最大限活用したものである」など目からうろこが落ちる思いで拝聴した。
海外出張などで夜の自由時間があるときにはオペラを最優先で探すようにしているが、結構当日でも切符を入手でき、演目としてはワーグナーに当たる確率がかなり高いように思う。それだけ世界中で人気があることの証拠であろう。最近では、昨年11月にパリ・バスチーユオペラで「トリスタンとイゾルデ」(ピーターセラーズ演出のわけのわからないもの。ゲルギエフ指揮で演奏は良かった)を、今年の9月にはウィーン国立歌劇場で「ローエングリン」(ペーター・ザイフェルトがローエングリン役)を楽しむことができた。バスチーユオペラでは数年前に「さまよえるオランダ人」も観ているが、このときの合唱団は子音が弱く、母音も鼻にかかったりしてとてもドイツ語には聞こえず、やはりフランス人にはワーグナーは向かないのかと思ったが、今回は違和感はなかった。余談ながら、KLMオランダ航空のマイレージプログラムは「さまよえるオランダ人」の英語訳と同じFlying Dutchmanで、空を飛ぶ(fly)をひっかけたしゃれたものであったが、エールフランスとの合併でFlying Blueというつまらないものになってしまったのは残念である。
さて、ワーグナーの人間性についてであるが、これははっきり言って最悪で、あまりお付き合いしたくない。情熱的で、革命家ではあるが自己チューでわがまま、尊大、嘘つきでもあり、女性関係は華々しかった。有名なのは、スイスの商人ヴェーゼンドンクの妻マティルデを誘惑したことで、このときの体験が「トリスタンとイゾルデ」を作曲するきっかけになったと言われ、歌曲集「ヴェーゼンドンクの5つの歌」も生まれている。もう一つはワーグナーの支持者であった指揮者ハンス・フォン・ビューローの妻であり2人の子持ちであったコジマ(リストの娘)を誘惑して、不倫関係のまま娘「イゾルデ」をもうけ、後にコジマを正式に妻にした事件であろう。コジマは後に息子「ジークフリート」を産んでおり、このことにより名曲「ジークフリートの牧歌」も誕生しているが、妻を取られたハンス・フォン・ビューローがワーグナーに敵対するブラームス支持派に移ったのには同情したい。
ワーグナーの書いた音符の量はとてつもなく多い。彼のオペラは上演に4晩を要する「ニーベルングの指輪」をはじめ、単独で4時間以上かかるものも多く、そのスコア(総譜)は大きく、厚く、重く、パートの数も多く、パート譜に書かれた音符の数も半端ではなく、とても人間技とは思えない。例えば、「ワルキューレ」第3幕の「魔の炎の音楽」などは効果音として4つに分かれたヴァイオリンに細かく速く動く音符が延々と書かれ、これを楽譜上に書くだけで通常はかなりの日数を必要としそうだ。「トリスタンとイゾルデ」もスコアは650ページ以上あり、勉強熱心な多くの新響メンバーはこれを練習の度に運んで腕の筋力の強化に努めている。
ワーグナーの楽劇の世界は異常である。「指輪」では古代の北欧神話、「ローエングリン」と「パルシファル」では聖杯伝説、「トリスタンとイゾルデ」ではケルト伝説などをもとにしつつもワーグナー流に自由に変えているので、登場人物の行動や言動は我々の理解を超えることが多い。「トリスタンとイゾルデ」におけるトリスタンはかなり異常であり、やはりワーグナーの異常性格が反映しているとしか思えない。しかし、音楽は、登場人物のすべての行動を赦し包み込む素晴らしいものであり、ついハマってしまう。麻薬のよう、とは良く言ったもので、私も脱出不可能な迷宮に入り込まないよう、必死に抵抗しているところである。