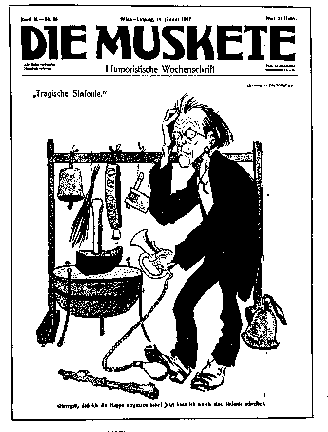 交響曲第6番がウィーンで初演(1907年1月5日)された2週間後、ご覧のような漫画が週刊誌に掲載されました。「チクショウ、警笛を忘れてた!これでもう1曲交響曲が書けるぞ」とつぶやくマーラーの周りには、6番で使われた様々な、およそ楽器とはいえない代物がころがっています。また『MAHLER』という題の写真集に載せられた6番の自筆総譜の写真には、「当時としては異常な打楽器の用法は嘲笑を買った」といった意味の説明が添えられています。さらに「いっそのこと大砲や爆弾を並べればよかったのに、それらの力強さに比べてゴングやハンマーは見劣りし、悲劇的な品位を高めるのに何の役にも立たない」といった批評もありました。このように当時のマーラーは、芸術の前には決して妥協を許さない厳格な姿勢を貫いて、破竹の勢いの出世と熱狂的な信奉者を得た反面、あまりの厳格さと強い自己主張に手強い敵をも増やし続け、さらに彼がユダヤ人であったための中傷が輪をかけました。
交響曲第6番がウィーンで初演(1907年1月5日)された2週間後、ご覧のような漫画が週刊誌に掲載されました。「チクショウ、警笛を忘れてた!これでもう1曲交響曲が書けるぞ」とつぶやくマーラーの周りには、6番で使われた様々な、およそ楽器とはいえない代物がころがっています。また『MAHLER』という題の写真集に載せられた6番の自筆総譜の写真には、「当時としては異常な打楽器の用法は嘲笑を買った」といった意味の説明が添えられています。さらに「いっそのこと大砲や爆弾を並べればよかったのに、それらの力強さに比べてゴングやハンマーは見劣りし、悲劇的な品位を高めるのに何の役にも立たない」といった批評もありました。このように当時のマーラーは、芸術の前には決して妥協を許さない厳格な姿勢を貫いて、破竹の勢いの出世と熱狂的な信奉者を得た反面、あまりの厳格さと強い自己主張に手強い敵をも増やし続け、さらに彼がユダヤ人であったための中傷が輪をかけました。しかし、この6番を作曲した1903〜04年頃のマーラーは、ウィーン宮廷歌劇場の芸術監督の地位にあって次々と斬新な改革を断行し、聴衆の圧倒的な賞賛を得ていました。なにしろ歌劇場の栄光ある伝統を「怠惰」と公言したのですから、その緊張と闘いは並大抵のことではありません。こうした激務の無い夏休み、彼はお気に入りのオーストリア南部イタリア国境近くのヴェルター湖畔の小さな作曲小屋に篭り、大自然の懐に抱かれて人間社会のすべての「いやなこと」から開放されて、現実には遂げられることのない心の本音を作曲に注ぎ込んだのです。
マーラーの人と作品を語るとき、しばしば“相反する二面”ということが言われます。“静と動”“生と死”“聖と俗”などですが、私はこの6番の打楽器に“慰めあるいは安息”と“叱宅激励”という二面を感じます。
それではもう1度先ほどの漫画を見ながら、それらの駄楽器(?)をご紹介しましょう。
まず"Rute"(笞:ムチ)です。ムチといえば音楽では、馬の“鞭”を模して細長い板を蝶番でV字型につなげ、打ち合わせるものが使われます。(先の160回では“シンフォニア ダ レクイエム”で使いました。)しかしこのRuteは細い枝を束ねたもの、つまり折濫のムチなのです。マーラーが自らを笞打つことを意味しているのかと思いましたが、今回改めて辞書を引いたところ、比喩として“厳重な監督”という意味が載っていました。もしかしたらマーラー自身が密かに"Rute"とアダ名されているのを知っており、「何が悪い」と居直っているのでは、というのは考えすぎでしょうか。
次は"Tiefes Glockengelaute"と"Herdenglocken"です。前者は「低い鐘」とでも言うのでしょうかスコアには「お互いに異なった定まらない音程の非常に低い鐘は、遠くに置いてかすかに不規則に打つ(意訳、以下同じ)」とあり、後者は「家畜のベル」で「遠くから草を食べながらやってくる家畜の群れを思い浮かべるように」といった指示があります。「低い鐘」は教会の鐘を模したもので、ヨーロッパの小さな町でその位置も人々の心にとっても中心となる、穏やかで心を洗われるような音色を思い出させてくれます。「家畜のベル」はスイス・オーストリアの山間部で耳にすることができるカウベルです。人間社会の醜さをいやと言うほど味わってきたマーラーにとって、これらの音は人間と家畜と自然がいたわりあいながら生きる田舎での安らぎを象徴するものであり、さらに教会の鐘は“聖なるもの”(彼にとっては芸術でしょうか)ヘの畏敬、憧憬、そして田舎で聞いてこそ感じられる親近感が耳に快い、嬉しいものであったに違いありません。
最後は極め付き、"Hammer"です。スコア指示は「短く力強い、しかし陰にこもって響きわたるような響き、金属的な音色は厳禁」とあります。大きな木槌が2回、舞台に振り下ろされます。これは最初の稿では3回で、マーラー自身が「3回目が英雄を倒す」と語ったそうですが、後に2回に変更されました。英雄は彼自身であり、決して倒されないと言いたかったのでしょうか。
当時と比ベ、はるかに複雑な現代社会にあって、“激情の人”マーラーの魂の吐露は、私たちにも共感できるものです。