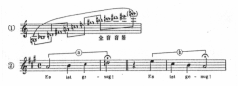 譜例-1
譜例-1第161回演奏会(1998年4月)維持会ニュースより
新響フルート奏者 松下俊行
旋法−音階−音列
誰かアルバン・ベルクの『ヴァイオリン協奏曲』のコラールを聴いて心動かされぬ人があろう。錯綜する不安定な旋律群の中からそれは忽然と現れ、その後に続く変奏曲の動機として、またこの曲の生み出されるに至った契機(それはG.マーラー未亡人の再婚相手との間に生まれた娘の夭折である)と、そして作品の完成後時を経ずして訪れた作曲者自身の死と密接に結び付き、聴く人の魂の深淵で響く。
同時にこのコラールの辿ってきた長い道のりについても考えてみるべきだろう。巷間この旋律はJ.S.バッハのコラール作品に由来するものとして知られているが、旋律自体の作曲者は別にいる。本来は第4音まで全音程で進む教会旋法(リディア旋法)に因っている。バッハはこの旋律にイ長調の和声を施し、調性音楽としてひとつの形を作り上げたのである。(譜例−1-2) ベルクは前述の『ヴァイオリン協奏曲』を創造するに当たり設定した音列(譜例−1-1)の最後の4つの音がこの旋律の開始と終止の4音の音程が同一である事に着目し、彼自身のレクイエムとなったこの作品に取り入れた。和声は勿論ベルク独自のものだ。
即ちベルクの作品に於けるこの旋律は、「教会旋法」「長音階」そして無調音楽の基礎となる「音列」と云う3段階の系統発生を繰り返した結果として我々の耳に今届いていると言えよう。これはそのままヨーロッパ音楽の凝縮された歴史である。
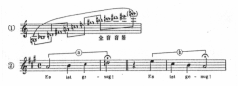 譜例-1
譜例-1
グレゴリオ聖歌以来中世まで教会音楽に用いられた旋法は、全て同一の全音階系の上に置かれており、開始する音から並ぶ7つの音の全音と半音の組合せ方で規定されるだけであるから、どこの音から開始してもよい。だから基本的に12種類ある各旋法は17世紀以降急速に発達を遂げた、後述する長・短音階に於ける「調性」とは別物である。元来教会旋法は単旋律から起こったものであるだけに、その後の多声化の潮流の中で、和声的にも、対位法的にも旋法本来のスタイルを保ち得ず、次第に変化を遂げざるを得なくなった。こうして幾世紀もの淘汰を経て産み出されたのが長調・短調の2種類の音階である。これらも旋法の一種には違いないが、従来のそれと異なって「調性」が確立し、ヨーロッパの音楽はより和声的な展開が可能となった。バッハはそれまでの旋法による旋律と「調的和声」とを融合させ、近代音楽の基礎を作り出した。彼が後世に伝えた偉大な遺産のひとつはまさにここにある。
以後ヨーロッパの音楽はこの基盤(バッハによる12平均律の採用も忘れてはなるまい)の上に急速な発展を遂げるのだが、この進化の根底にあったのはあくなき転調の可能性への追及であった。
その後の西欧の音楽の確固たる土台となった調性の崩壊は思いの外早く訪れた。無限とも言える転調への執着の結果がR.ヴァーグナーの『トリスタン』を生み出すに至り、バッハ以来の確固たる調的世界は瀕死の状態となったのである。同時にそれは音楽に於ける神の喪失を意味した。今世紀に入り主にヴィーンを中心に無調或は十二音という端的なスタイルが出現するのは決して驚くに値しない。独創を追及すればやがてひとつの意匠は変容を迫られる。それが世に受け入れられるかどうかは別にして、そうした方向に奔らざるを得ない。冒頭のベルクもそのひとりであった。
一方C.ドビュッシーを筆頭とする「印象派」の作曲家たちは長・短音階に代わる秩序の確立に腐心した。その方策の中心のひとつが「旋法への回帰」とも云うべきものであった。例えば彼は1オクターブ内の6個の音を全音程で結んだ「全音階」を創始して実際に作品を書いた。前述の「教会旋法」への再認識もあった。
「印象派」以降のフランス音楽にはこの「旋法への回帰」が色濃く見られる事を認識する必要があろう。
ふたたび旋法へ
O.メシアンの殊に初期の作品の土台は独自に創造された旋法にある。この意味で彼は確固たるドビュッシーの継承者である。1930年22歳の時に書かれた『忘れられた捧げもの』についての或るCDの解説。
「この標題音楽の音楽動機シグナルの変質は以下のとおりである。つねに『移調の限られた旋法(M.T.L.)』第2番の中に横たえられてはいるが、そのアイディアはまずリズミカルで柔軟な半音階から野性的な同類へと移動し、さらに休止に至るというものである−−−」
読んでいて頭が痛くなった。レコードからCDの時代となって、ジャケットの解説の質についてはもうとうに諦めてはいたがそれにしても、である。M.T.L.などと云う未知の記号を何の前触れもなくいきなり出してきて、何 ら説明もしないという態度は許し難い。実際の演奏に多少なりとも関わっている我々だって知らないのだ(尤もこれまでメシアンの作品を演奏したことがないからかも知れないが)純粋なリスナーがこうした語句を理解し得るとは到底思えない。演奏に関わる以上無視はできないので調べてみた。
M.T.L.は les mode a transposition limiteesの略号。まさに「移調の限られた旋法」ではある。メシアンはこれを1〜7番まで創り作品を書いた。今ここに2番の旋法を示す。(譜例−2)
 譜例-2
譜例-2
移調の形として第1から第4までが考えられるが、第4移調形は第1のそれと重複するので実際の移調は3種類のみとなる。これが「限られた」移調である。メシアンの音楽の構造を知る上で不可欠とも言えるこうした情報がともするとなおざりにされたまま日々の練習が進んで行くとしたら、空恐ろしい。新響の団員各位は本番を迎えるまで、日々この旋法を浚い続ける必要があろうと云うものだ。
信仰・色彩・秩序
閑話休題。「旋法への回帰」が印象派以来のひとつの潮流であったとしても、メシアンが旋法に固執した理由は彼独自の信仰に由来すると考えても良いように思える。彼の信仰の根源は幼児期の環境に因っている。詩人であった母親は彼の受胎を知ると『芽生える魂』なる一篇の詩を作った。この時既に彼女は生まれてくるのが男の子であり、将来音楽と深い結び付きを持った人生を歩む出あろう事を予知していたと云う。誕生からして神話的だ。シェークスピアの研究者であった父親を通じて知った様々な伝承は、カトリック信仰の世界を謂わば「現実化したおとぎ話」として極めて自然に受容する契機となった。
音楽院に入学した10歳の折パリの教会で見た、ステンドグラスの色彩から受けた印象も彼には鮮烈だった。爾来音そして和音(音群)によって様々な色彩がはっきりと見えると彼は言う。作品の中でも色彩を添える為に敢えて取り込む和音(これを色彩和声とよんでいる)が駆使されることが創作の上でひとつの重要な条件だった。前述の『忘れられた捧げもの』の冒頭と末尾の絃楽器群の旋律に対する自身の注釈にも色彩の語彙が溢れている。それは赤や金、ふじ色と云った具体的な色である。この様な音に対する色彩感覚を持ったメシアンにとって、所謂「現代音楽」は黒と白のみの組合せによって形成された世界にしか映らず、苦渋を覚えざるを得ぬものだった。こうしてみると彼の作品に於ける色彩感と旋法は自身の宗教観の象徴に思えてくる。旋法はこの世界の秩序であり、色彩は神の恩寵の表出であると言っては穿ちすぎか。
更に、メシアンがその作品の中で「偶発性」や「即興性」を完全に排除していたことには注目して良かろう。ひとつの作品に於て、美の秩序の形成が偶然に委ねられ得ると云うのは作曲家の思い上がりであり、神への冒涜である。神による秩序が存在するのみで、世界の事象は全て調和的に完結するという考え方は徹底している。10年に亙る音楽院での研鑽(その間5つのクラスを全て1等賞を得て修了している)の後、彼は長く教会のオルガニストを務めた。そこでは数限りない即興演奏が求められたが、彼の言う「即興」とは予め緻密・周到に考えられ、用意されたものでなければらず、一般に行なわれている「即興的演奏」とは一線を画すものだとも語っている。
調性の崩壊は今世紀に入り、音楽からその独自の色彩感を奪った。無調の世界はともすれば無機的な、敢えて言えば無神論的な方向に傾斜せざるを得ない宿命を持つ。そうした無機質の気分の蔓延する中で聴くメシアンの作品には明かな救済の響きが感じられよう。勿論この世界は救済だけではない。人間の神に対する罪(神の忘却)も重要なテーマである。そこには過激な情動も存在する。ただ、こうした具体的な事柄に余り拘泥するのも考えものだ。先程の即興演奏観の言を借りれば、彼の初期作品は「宗教的音楽」ではあっても「宗教音楽」ではない。ひとつの破壊の時代が去り、何もかもが混迷の黒の闇の底に沈んだ果てから幽かに漏れてきた光の色を、我々は想えば充分だろう。
和音の解決に神の救済を見いだしていたかつての人々の健全な精神が、メシアンの音楽に形を変え脈々と息づいている事に僕は深い安堵を覚えるのである。
主な参考文献「音楽大事典」 平凡社
「音楽の不思議」 別宮 貞雄 音楽之友社
「創意と創造」−現代フランスの作曲家たち− 丹波 明 音楽之友社
「私の好きな曲」 吉田 秀和 新潮文庫
他